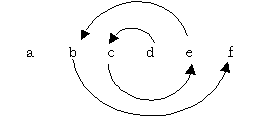چ‚‘ٍŒِگM"Critique"/2002.1.20 |
|
پ@ چl‚¦‚é‚ئ‚ح‚ا‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚© پ@
پ@‘O‰ٌ‚ةڈq‚ׂ½‚و‚¤‚ةپCژvچl‚حپC پ@پEŒ»ژہ‚جٹضŒWگ«‚ج“à–ت‰»پپک_—“Iژvچl پ@‚ج‚S‚آ‚جژ²‚ھ‚ ‚éپB‚»‚ج‚¤‚؟پCٹ´ٹo‰^“®“Iژvچl‚â•\ڈغژvچl‚حپC‚ي‚ê‚ي‚ê‚ة‚ح‘ه‚«‚ب“‚«‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚ئ‚è‚ي‚¯ژq‹ں‚إ‚حپCگ¬گl‚ئˆظ‚ب‚èپCƒ‚ƒm‚ج–¼‘O‚âˆس–،‚ً’m‚ç‚ب‚¢•ھپCƒ‚ƒm‚ًگà–¾‚µ‚½‚èچl‚¦‚½‚è‚·‚é‚ئ‚«پCƒ‚ƒm‚ج“®‚«‚إ•\Œ»پiƒuپ[ƒ“‚ئ”ٍ‚ٌ‚إ‚¢‚éژd‘گپj‚µ‚½‚èپCƒ‚ƒm‚ًگ¶‚«•¨‚إپCƒRƒgƒKƒ‰‚ً•ت‚جƒ‚ƒm‚إڑg‚¦‚½‚èپi“¥گخ‚ً‹T‚ئŒ©—§‚ؤ‚½‚èپCژ¼گ]‚ًƒTƒCƒ_پ[‚ج–A‚ئڑg‚¦‚½‚èپj‚·‚éپB‚±‚ê‚ھگ¬گl‚ب‚çپCٹبŒ‰‚ةƒ‚ƒm‚âƒRƒg‚ج–¼‘O‚ًŒ¾‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤڈI‚ي‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚µ‚©‚µ‚»‚ج’ê‚إپCŒ¾—t‚جژہ‘ج‚ًپC‚»‚¤‚¢‚¤‹ï‘ج“I‚ب‘جŒ±‚ھژx‚¦‚ؤ‚¢‚邵پCƒCƒپپ[ƒW‚à“à–ت‰»‚µ‚½’mٹoپEŒoŒ±‚ھژx‚¦‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حپCگ¬گl‚à•د‚ي‚è‚ح‚µ‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ھپCژq‹ں‚ةŒہ‚炸پCگ¬گl‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚à’mٹoڈم‚جچِٹo‚ة–‚؟‚ؤ‚¢‚é——R‚إ‚ ‚éپB—ل‚¦‚خپC‰؛گ}‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ًژ¦‚³‚ê‚é‚ئپC‰E‚ج–î‚ج•û‚ھ’·‚¢‚ئٹ´‚¶‚½‚èپiƒ~ƒ…پ[ƒ‰پ[ƒٹƒ„پ[‚جچِژ‹پjپC
ڈo“T;ژي‘؛‹GچO¥چ‚–ِ“ؤپw‚¾‚ـ‚µٹGپx(‰حڈo•¶Œة) پ@‚ـ‚½پC‘Oڈq‚ج‚و‚¤‚ةپCچׂ¢ƒRƒbƒv‚ة“ü‚ء‚½‚à‚ج‚ج•û‚ھ—ت‚ھ‘½‚¢‚ئ’¼ٹد“I‚ة‚حچِٹo‚µ‚½‚è‚·‚é‚ج‚àپCگ¬گl‚µ‚ؤ‚©‚ç‚àˆêڈu‚جچِٹo‚ةٹׂéپB‚µ‚©‚µپC‚»‚ê‚حپCƒ}ƒCƒiƒX‚ئ‚ج‚فچl‚¦‚é‚ׂ«‚إ‚ح‚ب‚پC—ل‚¦‚خ‰؛گ}‚ج‚و‚¤‚ةپC
پ@”wŒم‚ً‘z’è‚إ‚«‚é‚ج‚àپC‚±‚جƒCƒپپ[ƒW‚ج“‚«‚ج‚¹‚¢‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ‚»‚ج‚½‚ك‚ةپC‰؛گ}‚ج‚و‚¤‚ب‘خڈغ‚إ‚حچِٹo‚ًگ¶‚¸‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é(‡@‚حپCƒlƒbƒJپ[‚ج—§•û‘جپC‡A‚حپC‚q.ƒyƒ“ƒچپ[ƒY‚جپCپuچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢گ}Œ`پvپC‚¢‚ي‚ن‚éپgˆ«–‚‚جƒtƒHپ[ƒNپhپjپB
پ@پ@پ@ ڈo“T;ژي‘؛‹GچO¥چ‚–ِ“ؤپw‚¾‚ـ‚µٹGپx(‰حڈo•¶Œة) پ@‡@‚إ‚حپC‰œچs‚ًژ¦‚·—إگü‚ھ‘OŒi‚ئ‚ب‚ء‚½‚èپC‘Oڈo‚جگ}‚ج“_گü‚ج‚و‚¤‚ةŒم”w‚ةˆّ‚ءچ‚ٌ‚إŒ©‚¦‚½‚è‚·‚éپB‚±‚ê‚حپC’mٹoŒoŒ±‚©‚çپC‚ي‚ê‚ي‚ê‚ھ”wŒم‚جڈَ‘ش‚ًٹù‚ة’m‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚ة‚ظ‚©‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپC‹t‚ةپgˆ«–‚‚جƒtƒHپ[ƒNپh‚إچ¬—گ‚·‚é‚ج‚حپC‚»‚ج’mٹoŒoŒ±‚ج“–‚ؤ›ئ‚ك‚ھŒّ‚©‚ب‚¢‚©‚ç‚ة‚ظ‚©‚ب‚ç‚ب‚¢،
پ@‚ي‚ê‚ي‚ê‚ة‚¨‚¢‚ؤپC‚±‚¤‚µ‚½’mٹoŒoŒ±‚ھپCژq‹ں‚ج‚و‚¤‚ة’P‚ب‚éگ}•؟‚جچ·‚إ”»’f‚·‚é‚ظ‚ا’Pڈƒ‚إ‚ح‚ب‚¢‚ھپC‘S‘ج“I‚ة”cˆ¬‚·‚éڈم‚إپC”ٌڈي‚ة‘ه‚«‚ب—ح‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚éپB—ل‚¦‚خپC پ@پ@پ@‚پ‚„‚‡‚پ‚ƒ‚‡‚پ‚…‚‡‚پ‚‚‚‡‚پپ پ@‚ئ‚¢‚¤•¶ژڑŒn—ٌ‚ً‰ً‚‚ج‚ةپCƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^‚ح•s“¾ˆس‚¾‚ھپC‚ي‚ê‚ي‚ê‚حپCˆêڈu‚ج‚¤‚؟‚ةپCƒpƒ^پ[ƒ“‚ًŒ©‚آ‚¯پC‚پ‚‡‚حŒJ‚è•ش‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپCژہژ؟“I‚ة‚حپC پ@پ@پ@‚„‚ƒ‚…‚‚پ پ@‚ج•¶ژڑŒn—ٌ‚ً‰ً‚¯‚خ‚¢‚¢‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‹C‚أ‚¯‚éپB‚»‚µ‚ؤپC‚»‚ê‚حپC—ل‚¦‚خپC
پ@‚ج‰Qٹھ‚«‚ج‚و‚¤‚بƒCƒپپ[ƒW‚ً•‚‚©‚ׂ邱‚ئ‚إپC•¶ژڑ‚ج—ٌ‚ج“ءگF‚ً‚آ‚©‚ق‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邵پC‚ƒ‚ئ‚„پC‚‚‚ئ‚…‚ھŒü‚«چ‡‚ء‚½”½ژث‚جٹضŒW‚ئƒCƒپپ[ƒW‚µ‚½‚è‚à‚إ‚«‚éپi‘ٹ—اپE‘OŒfڈ‘پjپB‚»‚جˆس–،‚إپC‚±‚ج’¼ٹ´‚ئ‚إ‚à‚¢‚¤‚ׂ«‚à‚ج‚حپCƒCƒپپ[ƒW‚ً‘z’è‚·‚邱‚ئ‚إ‘S‘ج‘œ‚ً‚آ‚©‚ـ‚¦‚â‚·‚‚·‚邱‚ئ‚حژ–ژہ‚إ‚ ‚éپB پ@ٹm‚©‚ة‚±‚¤‚µ‚½‰f‘œ“I‚بژvچlپC‚آ‚ـ‚è‚¢‚ي‚ن‚é‰E”]“Iژvچl‚حپCƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^‚جچإ‚à•s“¾ˆس‚ئ‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚èپC‘S‘ج“I‚ب”»•تپC”F’m‚ئ‚¢‚¤ŒoŒ±‚ة‘¦‚µ‚½‚ي‚ê‚ي‚ê‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ح—ک“_‚ئ‚¢‚¤‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپC‚»‚ê‚ھ‚¢‚ي‚ن‚é‰E”]ک_ˆب—ˆ‰ك‘ه•]‰؟‚³‚ê‚·‚¬‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةژv‚ي‚ê‚ؤ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‹َٹشڈî•ٌ‚جڈˆ—‚ً‰E”]‚ھ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤ڈيژ¯‰»‚µ‚½Œ©‰ً‚ة‘خ‚µ‚ؤپC‘S‘ج‚ً‚آ‚©‚قƒCƒپپ[ƒW‚جŒ`گ¬‚ة‚حچ¶”]‚ھ‘ه‚«‚ٹض—^‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚·‚éژہŒ±Œ‹‰ت‚àڈ‚ب‚¢‚ھ‚ ‚邵پC’mژ¯‚جکg‘g‚ھ‘S‘ج‚ًˆêٹ‡‚µ‚ؤ”cˆ¬‚·‚é‚ج‚ًڈ•‚¯‚é‚ئ‚·‚éپCŒمڈq‚جƒnƒ“ƒ\ƒ“‚جژw“E‚à‚ ‚éپB‚±‚¤‚µ‚½ژ‹ٹoƒCƒپپ[ƒW‚ً“à•”‹L‰¯‚ة‚و‚ء‚ؤ‘چچ‡‚·‚邽‚ك‚ة‚حپCچ¶”]‚ج‹@”\‚ھ‘ه‚«‚چى—p‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپC‚ـ‚½“–‘Rچl‚¦‚ç‚ê‚锽ک_‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB پ@‚ق‚µ‚ëپC‘هژ–‚ب‚ج‚حپC‰Eچ¶‚إ”]‚ج‹@”\‚ً‚Q•ھ‚·‚锑zژ©‘ج‚ھ–â‘è‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB‚ي‚ê‚ي‚ê‚ھƒCƒپپ[ƒW‚ً•‚‚©‚ׂؤ‚¢‚é‚ئ‚«پC”]‚جٹˆ“®•”ˆت‚حپC‰Eچ¶‚ئ‚¢‚ء‚½’Pڈƒ‚ب‹و•ھ‚إ‚ح‚«‚©‚ب‚¢‚‚ç‚¢پCŒم“ھ—tپC‘O“ھ—tپC‰؛•”‘¤“ھ—tپC“ھ’¸—tپC‘S‘ج‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤ‚¢‚éپC‚ئ‚¢‚ي‚ê‚éپB‚µ‚©‚àپCƒCƒپپ[ƒW‚حژَ“®“I‚ة‰و‘œ‚ًژv‚¢•`‚‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پC”\“®“I‚ةپiگو‚ً“ا‚ق‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةپj“‚©‚¹‚ؤ‚¨‚èپC‚»‚جˆس–،‚إ‚حڈيژ¯“I‚بچ¶”]‚جپuکg‘gپv‚âپuƒpƒ‰ƒ_ƒCƒ€پvپu—\ٹْگ}ژ®پv‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ً‚à‚ء‚ؤپC—\‘ھ“I—\ٹْ“I‚ة•`‚¢‚ؤ‚ف‚¹‚é‚ئ‚¢‚¤–ت‚à‚à‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًŒ©“¦‚¹‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپBپu’m‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ًŒ©‚éپvپuŒ©‚½‚¢‚à‚جپi‚µ‚©پjŒ©‚¦‚ب‚¢پvپuŒ©‚½‚¢‚à‚ج‚ً‚ف‚و‚¤‚ئ‚·‚éپv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپC‚±‚¤‚µ‚½’mٹoƒCƒپپ[ƒW‚à‚ـ‚½پC‚ي‚ê‚ي‚ê‚ة‚ئ‚ء‚ؤڈK“¾‚³‚ꂽ‚à‚ج‚¾‚©‚炾پB‚»‚جˆس–،‚إ‚حپC’¼ٹ´‚à‚ـ‚½پCˆêژي‚جژvچl‚جٹµگ«‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB پyˆب‰؛‘±‚پz |
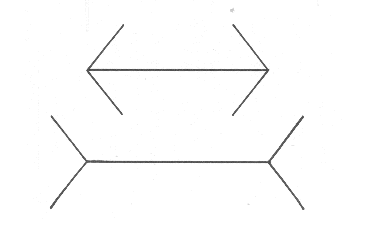
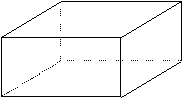
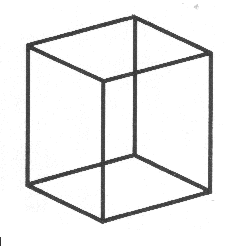 پ@
پ@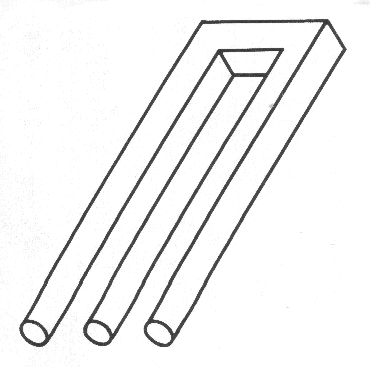 پ@پ@
پ@پ@