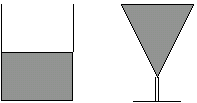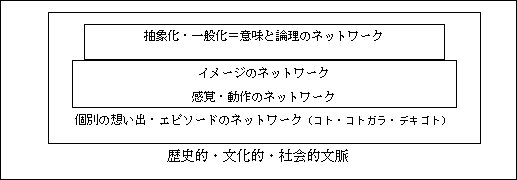������M"Critique"/2001.12.20 |
||||
|
�@
���E�l����Ƃ͂ǂ��������Ƃ� �@ �@�������F���́C�l����Ƃ́C�u�Ƃ߂����ɑ��āC���˓I�E���^�ɔ�������C������Z�������I�Ȑ��_�����ł͂Ȃ��B�ݒ肵�����̉����C���Ă��ڕW�̎�����B���̂��߂ɁC�ߋ��̂��낢��Ȍo���⌻�݂����m�������낢��g�݂��킹�Ȃ���C�V�����S�̓��e�ɂ܂Ƃ߂����Ă䂭���_�����ł���B���Ȃ킿�C�v�����߂��炵(�A�z�C�z���C����),�l��(�v�l�C�H�v),�����Č��f����(���f)�Ƃ������Ƃł���v(�w�l�Ԃł��邱�Ɓx)�ƒ�`���Ă���B �@�������C���ꂾ���ł́C���_�����̒��g�ނ��āC�l���邱�Ƃ̒��g�ɂ́C����������ނ̂��̂�����Ɛ������Ă��邾�������āC���ꂼ��̎d�g�݂��ǂ��Ȃ��Ă��āC�ǂ����Ă��̂悤�ɍl���邱�Ƃ��ł���̂��܂œ��ݍ���ł��Ȃ����߁C�l����Ƃ͂ǂ��������Ƃ����邱�ƂȂ̂��������Ă��Ȃ��悤�Ɏv����̂��B��������������˂�����ł݂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��
�@����ꂪ���m���l����Ƃ��������́C�ʏ�͍s���̂悤�ɊO������͎f���Ȃ��قǂɓ��ʉ�����Ă��邪�C���߂��炻���Ȃ̂ł͂Ȃ��B���̓��ʉ��̃v���Z�X�𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁC�v�l�̔��B�̃X�e�b�v�𖾂�ɂ��邱�Ƃ��ł���B���������_����C�v�l�̎d�g�݂𖾂炩�ɂ����̂��C�i.�s�A�W�F�ł���B����ɂ��C�v�l���B�́C �@���o�^���I�m�\�̒i�K�i�O�`�Q�j �@�O����I�v�l�̒i�K�i�Q�`�U,�V�j �@��̓I�ȑ���I�v�l�̒i�K�i�U,�V�`�P�P,�Q�j �@�`���I�ȑ���I�v�l�̒i�K�i�P�P,�Q�`�P�S,�T�Ő��l�ɋ߂Â��j �@�̂S�i�K�����Ƃ����B�N��͌l�������㍷������̂Ŗڈ��ɂ����Ȃ����C���̃X�e�b�v�̏����́C���̒��Ԃɗl�X�ȃ��x���̈ڍs�]�[���������Ȃ�����C�ς��Ȃ��Ƃ���Ă��� �@���o�^���I�m�\�Ƃ́C�܊��⓮���ʂ��ĊO���Ƃ̊W��̓����Ă��������ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����ł́C�u�Ώە��̕s�ϐ��v�܂�C�����Ɍ�������̂́C�z�ŕ����悤�ƎՂ��悤�Ƃ���C�Ƃ������Ƃ�m���Ă����i�K���Ƃ������Ƃ��ł���B���̎�����ʂ��āC�����͎����������ƌ��������ς�邱�ƁC�����������߂��Ȃ艓������Ώ������Ȃ邱�Ƃ��C�Öق̂����ɐg�ɂ��Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B����ɂ���āC�����̂Ƃ��Ɋ�u���Ȃ����Ȃ��C���v�ɂ͔������Ȃ��Ȃ�B�����ɂ�����̂������Ȃ��Ȃ��Ă��C�����ɂ��邱�Ƃ��킩���Ă���C�Ăь��ꂽ���Ƃɖʔ����������������͂��Ȃ����炾�B �@���̎����̖��ɂ́C�Ⴆ�C��̕��̃R�C�����悹�C�����z�c�̉��ɓ���ĉB���C��̎��������ƁC�q���͂����ɃR�C�����Ȃ��Ƃ킩��ƁC�����ɕz�c�����s�����Ƃ�C�Ƃ������Ƃ��s�A�W�F�͎������Ă���B���Ɏq���́C�ڂɌ����Ȃ��Ƃ���i�z�c�̂����j�Ń��m���ڂ��āi�B����j���C�����ǐՂ��Ă������Ƃ��ł���B���̂Ƃ��C�����I�Ȑ��_�����Ă���̂ł���B�������C�q���͌��t�ł͂Ȃ��C���o�^���I�Ȋ����i�s���j�ɂ���Ă�����m�F���Ă�����̂ł���B �@�O����I�v�l�Ƃ́C�\�ۓI�v�l�C�܂�����ł͂Ȃ������̃C���[�W��`�����Ƃ��ł��邱�ƁC���t���g���ă��m��R�g��\���ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B����́C�^�����o�I�����̓��ʉ��Ƃ����Ă����i��X�s���Ŏ����Ȃ��Ă��C�O�q�̗�Ȃ�C���t�ł��̐���������ł���悤�ɂȂ��Ă���j�B����́C�܂܂��ƗV�тŁC�͂��ς��D�Ƃ݂Ȃ�����C�������V�тȂǂŁC�V���{�������R�Ɉ�����悤�ɂȂ��Ă���Ƃ���ɓT�^�I�Ɍ����������Ƃ��ł���B�����ł́C�����ɕ�e�����Ȃ��Ă��C��e��\�ۂ��Ȃ���C��e�̂���ɂȂ��āC���̍s�����Ȃ��邱�Ƃ��ł���B���o�^���I�����ł́C���̏�₻�̃��m�Ɉˑ����Ă����̂ɂ���Ȃ��ŁC���ɓ��̒������ŁC�������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B����͕`��C�H��Ƃ��������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�����C���t�ɂ���Ă̕\�����\�ƂȂ�i�K�ł���B �@�������C�܂����t�͓��ʉ�����Ă��Ȃ�����C�V��ł���Ƃ��C�N�ɘb��������Ƃ����̂ł��Ȃ��Ƃ茾������ׂ��Ă���B �@�S�Ώ��̎q�u���̖ɂ͂ˁC���T�������̂�B���T�����킢���ˁC�������Ɠo���Ă������Ƃ����̂�v �@�S�Βj�̎q�u�n�C�E�F�[�����B�����Z�f�X�x���c��������C�傫�����v �@���݂��ɒN���Ƙb�������Ă���킯�łȂ����C�l�ɕ�����Ă���Ƃ���������Ȃ��B���������Ŏ������l���Ă��邱�Ƃ��ǂ�ǂƂɂ��āC������h���ɂ��Ă܂�����ׂ��Ă���B������v�l�v���Z�X���̂��̂��O�ʉ����Ă���Ƃ݂邱�Ƃ��ł��邾�낤�i���ǎ玟�ҁw�w�K�Ǝv�l�x�j�B �@�����Ńs�A�W�F������I�Ƃ����Ă���̂́C���t��L���𑀍삵�Ďv�l�ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B���𐔂���̂Ɏw��m�Ő�����̂ł͂Ȃ��C�����𑀍삷�邱�Ƃ��ł��邱�ƁC���邢�̓X�Y�������������������Ƃ������ށi�N���X�j�̊W�̒��ŊT�O�I�ɗ����ł��邱�Ɠ��X�C����ꐬ�l����Ȃ����Ȃ��Ă���v�l�ɂ�����C���ۓI�T�O�I�ȓ������Ӗ����Ă���B���������āC���̒i�K�ł́C�C���[�W��\�ۂ͂܂����m��R�g�Ƃ�������̓I�Ȃ��̂�}��ɂ��Ȃ��ƕs�\���Ȃ̂ł���C�܂��m�o�C���[�W�i�m�o�I�}���j�ɍ��E����Ă��܂��B
�@�Ⴆ�C�����ʂł��C�E�̕��������Ɠ�����B�܂�������瑼���ֈڂ��ƁC�������ɍ��E����āC�ʂ��ς�����Ɣ��f����B�����ƑS�̗ʂ̊W�Ƃ���������I�v�l���ł��Ă��Ȃ�����C���o�I�ȓ��l���������Ȃ��ƁC���l�ƔF�߂Ȃ��̂ł���B �@��̓I����v�l�̒i�K�ł́C��̓I�Ȏ����ɂ��Ă̊T�O���ł��C���m�������舵���Ă������C�_���I�Ȏv�l������������悤�ɂȂ�B���������ĕ��ނ�z�ł��C�����ł͑���I�v�l�Ƃ��āC�X�Y�������������������Ƃ������ށi�N���X�j�̊W�̕��ނ�O�q�̃R�b�v�̌������ɍ��E���ꂽ�肹���ɁC�S�̗ʂ̓��ꐫ�𗝉��ł���悤�ɂȂ�B �@�������C�Ⴆ�T�̎q�ɐ�����ꂽ�R�b�v�ƌ��̊J�����T�O�~�ʂ������āC �@�u���̂�������ꂽ��C�������C���ނ��v �@�ƕ����ƁC �@�u���ށv�Ɠ������B���̗��R���ƁC���炭�T�O�~�ʂ����l�߂āC �@�u�����J���Ă��邩��v�Ɠ������B�ŁC���Ɍ��̊J���Ă��Ȃ��T�O�~�ʂ����o���āC���l�̎��������ƁC �@�u���ށv �@�u�����J���Ă��Ȃ�����v�Ɠ�����B��ȗ��������C�����łł������̂̒��ޒm�o�o����������ۂÂ����Ă��āC����ɍ��E����Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B�������C���R�͐����ł��Ȃ��̂ɁC����I�T�O����ɓ��ꂽ�W�̎q���ɂȂ�ƁC��������������ƁC�u�������S�݂����Ȃ��̂͒��ށC�̖_���łł��Ă�����̕����v�Ƃ�������������B�d���y���Ƃ����T�O�ŋ�ʂ��Ă���B�������܂�����͖@���I�Ȑ������ł��Ă��Ȃ�����C�u�S�łł��Ă���D�͕����ł͂Ȃ����v�Ɩ₤�ƁC�u�D�̌`�ɂ���ƊF�����v�Ƃ����`�œ�����B����ɓ����邽�߂ɂ́C���̂��Ƃ��I�ɐ������C�������牉㈓I�ɐ��_����_���̌n���w�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�܂����̒i�K�ɂȂ�ƁC�ʏ�͓Ƃ茾�͏��Ȃ��Ȃ��āC�u�c�c�c�����͂���Ɓc�c�c�v�i�ԂԂ��̒��Ō����Ă��邯��ǂ��C���܂蕷�����Ȃ��j�C�Ƃ����悤�ɁC�Ƃ茾������ɕ������Ȃ��Ȃ��Ă����B����́C�����̂��߂ɂ���ׂ��Ă���̂ł����āC�ʂɕ����������Ă���K�v���Ȃ�����ł���C���ꂾ���C�����̓��I��b�Ɛl�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����i�Љ�I��b�j�Ƃ��������Ă����Ƃ������Ƃł�����B�������Č��ꂪ���ʉ�����Ă����i���Ǔ��E�O�f���j�B �@�����ŁC�`���I����v�l�̒i�K�ł́C��̓I�������Ȃ��Ă��C���̒��Ř_�����삪�ł���悤�ɂȂ�B�Ƃ��ɑO�i�K�łł��Ȃ������C�u�����C�����Ȃ����炱���Ȃ�v�Ƃ������`�Ő����ł���C������㈓I�Ȏv�l���ł���悤�ɂȂ�B���ɐ��l�̎v�l�̒i�K�ɂ���C�Ƃ������Ƃ��ł���B����ΐl�ԂƂ��Ă̎v�l�̘g�g���ł�������̂ł���B �@�������C���������_���I�v�l�́C�������܂ł̊��o�^���I�m�\�C�\�ۓI�v�l�C�`���I�v�l�ƁC�����C���ꂾ���łȂ��C����E�s����m�o�C���[�W�C�f������ʉ����Ă������̐ςݏd�˂̌��ʂƂ��Č`������Ă���Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u����Ƃ́C���ʉ����ꂽ�����ł���v�Ƃ����̂́C���̂��Ƃł���C�����̒��ɂ́C���o�^���I�������Ђ傢�ƊO�ʂ���邱�Ƃ�����̂��B�Ⴆ�C�S���t�̃X�C���O��z�肷��Ƃ��C�n�̊��D�⍘�̐��������C�v�킸������Ȃ���C���ꂱ��l���Ă���B����́C�����̋�̓��������̒��ɂ��܂��Ă���(���ʉ�����Ă���)���̂����݉������ƍl������B�܂��C�\���o����肪�ÎZ�ɍۂ��āC����Ȃ��Ă��C���ɂ����̃C���[�W�����܂�����i�C���[�W�̓��ʉ��j���C�����Ɏv�킸�E��ŋ��e���悤�Ȏd��������i����̓��ʉ��j�B�����́C���ʉ����ꂽ���삪�C��u�O�֟��ݏo����Ƃ������Ƃ��ł���B�����܂ŁC����I�v�l�́C�u���ʉ����ꂽ�����v���Ƃ����̂́C�����������Ƃ��Ӗ����Ă���B �@���̖ʂŁC���ɕt�������Ă����K�v������̂́C����̓��ʉ��ɂ͏d�v�Ȗ�肪�܂܂�Ă���Ƃ����_�ł���B�u���Ȃ����Ȃ��C���v�ɂ͔������Ȃ��Ȃ鎞����ʂ��āC�����͑Ώۂւ̋����ƈʒu���w��ł����B����́C���������ς���Ă��Ώۂ����݂��Â��邱�ƁC�������������͌����ɂ���ĕς�肤�邱�ƁC�����C���_�̖��ł���B��������C�u�����������̂Ƃ����l���́C�l�Ԃ������邩�瑶�݂���킯�ł��B�������Ƃ��Ύ����A���Ƃ��Ă��̏ꏊ�ɗ����Ă����������Ƃ�����C�܂莄�����܂�Ă��̂������܂܂őS�R�ړ����Ă��Ȃ��Ƃ���ƁC���ɂ͗��̂Ƃ����ϔO�͂Ȃ��킯���B���̂́C�����Ɨ��̂Ƃ̊Ԃɑ��ΓI�ȉ^�����\�ŁC���̂��㉺�C���E�C�O�ォ�猩�邱�Ƃ��ł��āC�͂��߂Ă킩��v�i�X���O�j�ƁC������̂ł���B �@���o�^���I�m�\����ɓ��ꂽ�Ƃ��C����ꂫ�́C�����ɂǂ����猩����ǂ����������ς��i������ς���ƌ��������ς��j���C�Ƃ������Ƃ������Ƃ������Ƃ��B���ꂪ�C���̓C���[�W�����E����d�v�Ȗ��ł��邱�Ƃ́C�J��Ԃ��܂ł��Ȃ����낤�B�Ɠ����ɁC���邱�ƂɎ��_�������Ƃ��C�����ɍ��[���Ɋւ���Ă��邩�������Ă�����̂ł���B
�@�ȏ�C�S�i�K�̃X�e�b�v��ŁC�v�l���l�����Ă������ƂɂȂ邪�C�����, �@�@����C�s�ׂ���т����̓��ʉ������ߒ�(�����̌����������o) �@�A�m�o�C�o������т��̓��ʉ������C���[�W(�S�ۂƂ��Ă̌��������C���[�W) �@�B���ꂨ��т��̓��ʉ������ے��ߒ� �@�C�����̈��ʊW�̓��ʉ������@���I�_�� �@�ƁC�������邱�Ƃ��ł���i���Ǔ��E�O�f���j�B �@��l�ɂȂ�ƁC����I�v�l�܂茾��Ƙ_���ɂ��v�l�������ڂɂ����C���ꂵ���g��Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�O�q�����悤�ɁC�_���I�v�l�́C���o�^���I�m�\�C�\�ۓI�v�l�C�`���I�v�l�ƁC�����C���ꂾ���łȂ��C����E�s����m�o�C���[�W�C�f������ʉ����Ă������̐ςݏd�˂̌��ʂƂ��Č`������Ă���̂ł���B���̂��ׂĂ̎v�l���C�����̒��őw�ƂȂ��Ă���ƍl���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���m���l����Ƃ��C�����́C�ȏ�̂S�̎����ׂĂ�g�ݍ��킹�Ă���̂ł����āC���̂S���͎v�l�`���̃v���Z�X�ł���Ɠ����ɁC�v�l�͂̂S�̗v���ł�����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���i���x�C�}�Y���[�̗~���T�i�K���ŁC�����I�~�������S�~���������̗~�������F�̗~�������Ȏ����̗~���̂T�̗~�����C�~���̏��ʂ̃X�e�b�v�ł���Ɠ����ɕ�������~���̃��x�����������̂ł���悤�Ɂj�B �@����͉��}�̂悤�ɍ\�������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�@����́C�ʂ̌�����������ƁC�����ɂ͌ʋ�̓I�ł��������̂��C���t�◝����ʂ��āC�ǂ�ǂ�܂Ƃ߂����ۉ��E��ʉ��������̂ɏ����Ă����Ƃ������Ƃł�����B���ꂪ�m����Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B �@����������̓��탌�x���ł̎v�l�̎d������݂�ƁC�����́C�ǂ������`�ł����̒��ɒ~�ρi�L���j����C������C���̂ǂǂ������ӂ��Ɏ��o���Ă��邩�Ƃ������_����l���Ă݂邱�Ƃ��ł���B�ЂƂ̍l�����́C
�@�Ƃ��������ނƂȂ�C�菇���Ӗ����G�s�\�[�h�̏��ɉ��ʃV�X�e�����`�����Ă���Ƃ���Ă���(�d�D�^���r���O)���C��������ꂸ�ɁC���̋L���̊K�w��O�q�̂S�w�ɓ��ěƂ߂āC�����ɒP���Ȑ}���ɂ��Ă��܂��C
�@�Ƃ������ӂ��ɑw���Ȃ��Ă���Ƃ����ӂ��ɂ݂邱�Ƃ��ł���B�܂�C�����̊��o�^��������C���[�W�́C�ʂ̑z���o�Ɏx�����C�ʂ��Ă���̂ł���B�������C�e�w�͑����̌����荇���͂����Ă��C���ꂼ�ꂪ�o���o���̃l�b�g���[�N�ƂȂ��Ă��āC�Ӗ���H���Ă��K���������̃G�s�\�[�h�ɂȂ���Ƃ͂����Ȃ��B �@�G�s�\�[�h�L���́C����̎����Ɍ��肳�ꂽ�Ɠ��̎��ԓI�ȑg�D���ɂȂ��Ă��āC�����̌O�肩�炠��z���o��������C���銴��i��������{��j�ɂ���āC�ӂ��ɐ̂̒p���������̌����v���o���ꂽ�肷��i�|�b�v�A�b�v���ہj�B���錾�t����C��u�̏o�������C���[�W���ꂽ��Ƃ������Ƃ�����B���邢�͈ӎ����Ȃ��œƎ��̌��t��F�ւ̚n�D������Ă���Ƃ������Ƃ�����B���̈Ӗ��ŁC�G�s�\�[�h�L���̑����͖��ӎ���Ԃɂ���Ƃ݂Ȃ����B�Ƃ����Ă��C���ӎ��Ƃ����̂́C�������炱���܂łƂ����悤�ɁC��ΓI�ȗ̈�Ƃ��Ċm�肵�Ă�����̂ł͂Ȃ��C����Ƃ��͈ӎ�������Ă��C�ʂ̂Ƃ��ɂ͈ӎ��̊O�ɂ������肷�鑊�ΓI�Ȃ��̂ł���C�Œ肳�ꂽ�ꏊ�i�t���C�g���\�������g���݈ӎ��h��g�ӎ��̒�h�g�ӎ��̉��h�Ƃ����̂͂����܂Ŕ�g�ł���j�Ƃ��Ď��̓I�ɂƂ炦��ׂ��ł͂Ȃ��C���ɂ�������(as if)��i�����O�j�Ƃ��Ă��������ł��Ȃ��C���̂Ƃ��ǂ��̈ӎ��ɂ̂ڂ�Ȃ����̂��C���ӎ��Ƃ݂Ȃ��悢�B �@�_����Ӗ����l���Ă���Ƃ��ɂ́C���ڂɂ͌ʂ̑̌��Ƃ͐ڑ����ɂ������C���ӎ��œƓ��̈Ӗ��i�j���A���X�j�����Ă��邩������Ȃ��B���邢�́C�����ł͘_���I�ł��C���̍����ɂ��Ă���̂́C�@����[��������ʂ̑̌������͂ɍ�p���Ă���̂�������Ȃ��B���m�̌����Ɍʂ̃G�s�\�[�h����̏�I�c�݂����邱�ƂɋC�Â��Ȃ��ł��邩������Ȃ��B����Ӗ��ŁC�G�s�\�[�h�L���́C�l�b�g���[�N�S�̂ɐZ�����Ă��āC�G�s�\�[�h�L���͈Ӗ��L���ňӖ��Â����C�Ӗ��L���̓G�s�\�[�h�L���G�s�\�[�h�Ŋ���I�ɐF�t�����Ă��邪�C���̂��Ƃɂ����͎��o�I�łȂ�����C�Ǝ��̍ʂ�ɂ͋C�Â��Ă��Ȃ����C�܂����̌ʂ̍��s�ƂȂ��Ă���G�s�\�[�h���ӎ����Ă��Ȃ������Ȃ̂��B�G�s�\�[�h�L���́C�m����Ӗ��I�ȂȂ����ǂ������Ă��钆����͌����Ă��Ȃ��B����ɂ͎��o���Ă��Ȃ����炾�B�ɂ�����炸�C���L�C���[�h�i���邢�̓L�C�ƂȂ�Ό��ዾ�j�̂悤�Ȃ��̂ɏo��ƁC��u�̂����ɉ�H���ς��C�Ɠ��̃G�s�\�[�h�L���Ɛڑ����Ă��܂��i���銆�D�������Ƃ���ɁC���w�Z�̂Ƃ��̖Y��Ă������i�ƂȂ���C�Ƃ����悤�Ɂj�C�ɂ߂ċ߂��Ƃ���ɂ���B �@���̂悤�ɁC�G�s�\�[�h�L���̂قƂ�ǂ́C�Ƃ��ƂƂ���ɂ���ĕ����蒾�肵�Ă�����̂ł���C���ӎ��̃l�b�g���[�N�Ȃ̂ł���B�������C���̐l�Ƃ��Ă̓Ǝ����́C�l�Ƃ��Ă̌o���̒~�ςł���G�s�\�[�h�L���̒��ɂ�������̂�����C�����ɂ����C�ǂ����������C���̐l�̃I���W�i���e�B������ƍl����ׂ��ł͂���܂����B���ꂱ�����C�{���̎����̒m���E�o���i���邢�͌l�I�o���ɍʂ�ꂽ�m���j�ł���C���Ƃ��펯���ɂƂ��ꂽ���̂ł������ɂ���C���̓Ǝ��̍ʂ�̒��ɁC���z�̃I���W�i���e�B�̊�Ղ�����B�����͂���ȊO�ɓƎ��̂��̂������Ă��Ȃ��̂�����C�Ǝ��̃G�s�\�[�h�ɍʂ�ꂽ�m����o���C�C���[�W�C���o���C�ǂ����������C�ǂ������o�������d�v�Ȃ̂�� �y�ȉ������z
�����怃y�[�W�� |