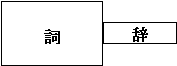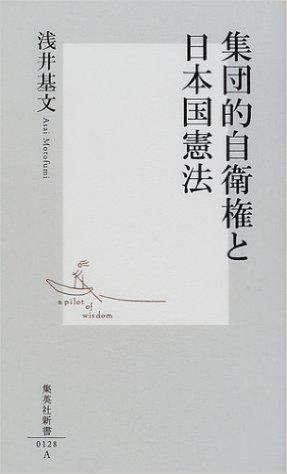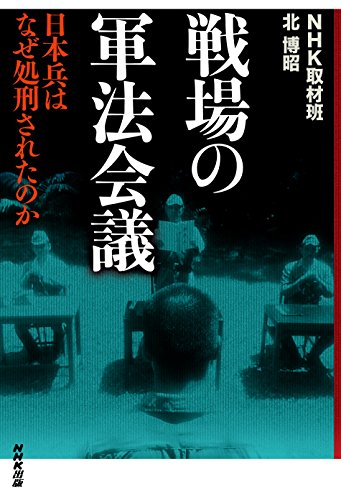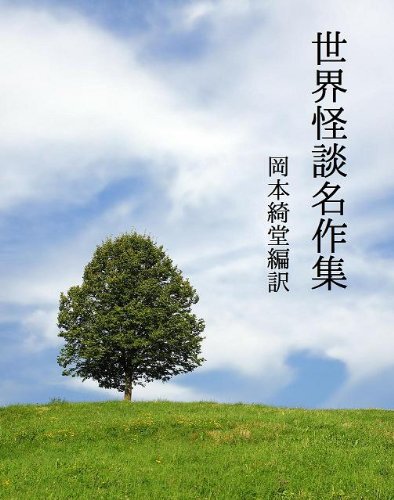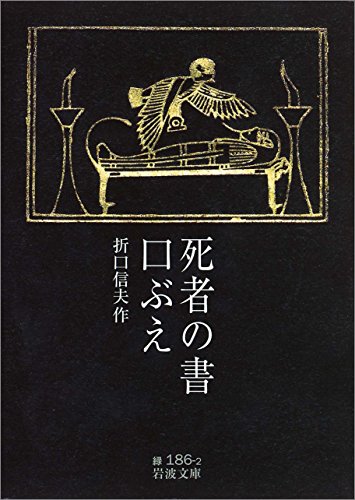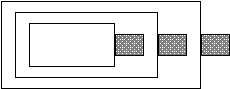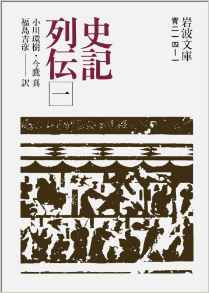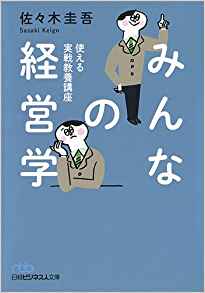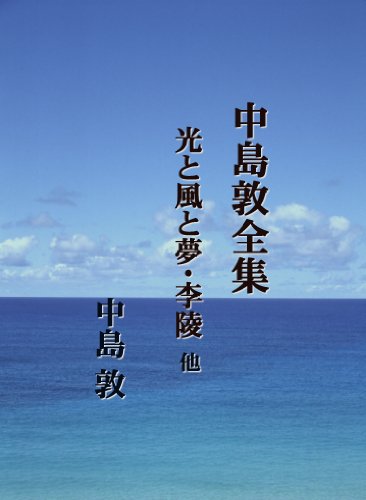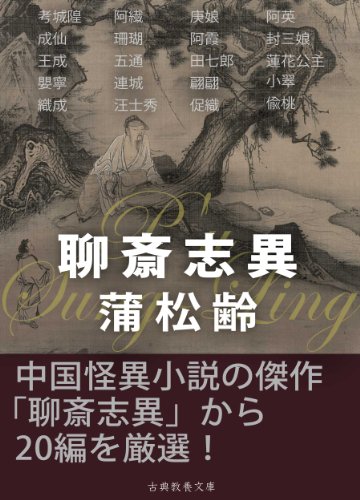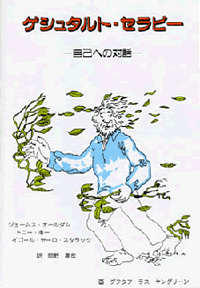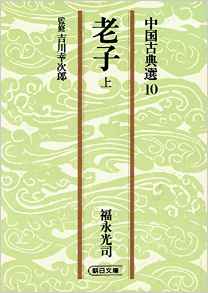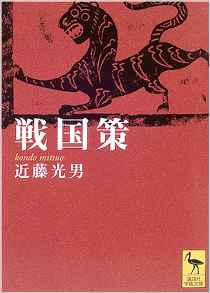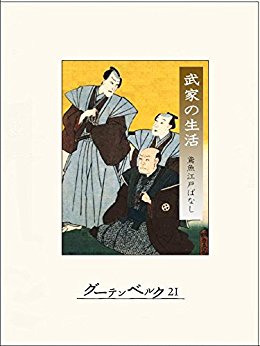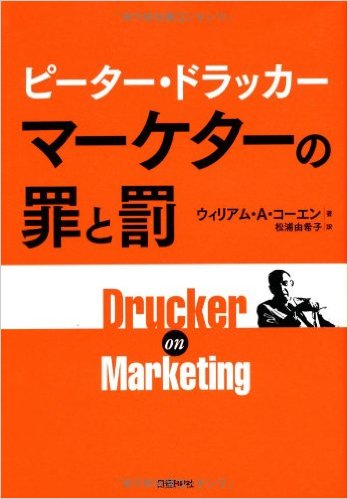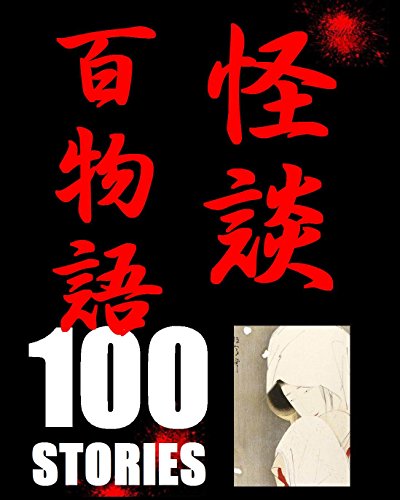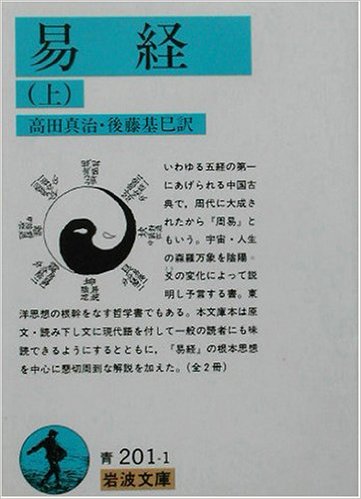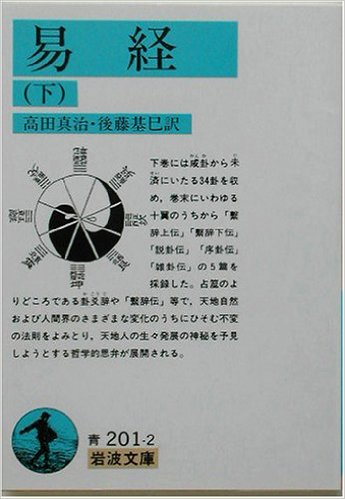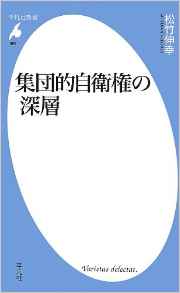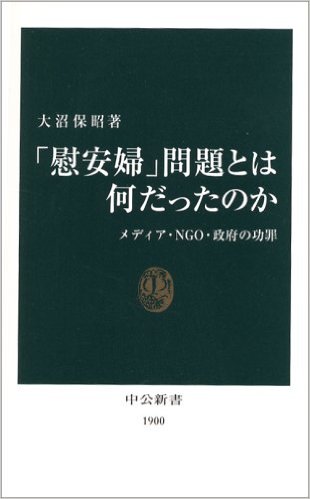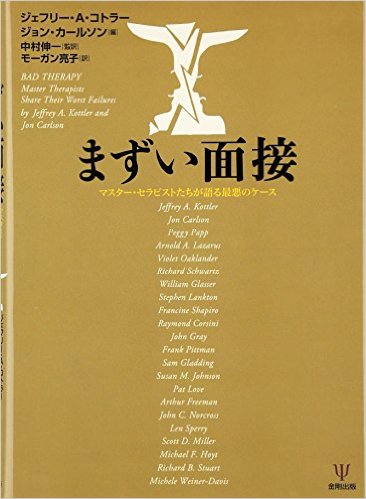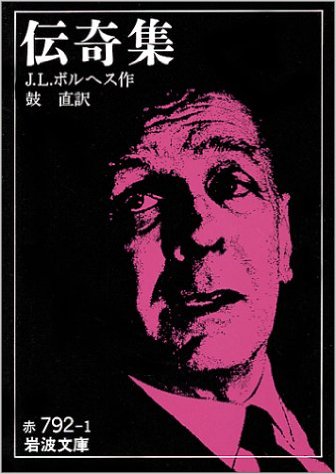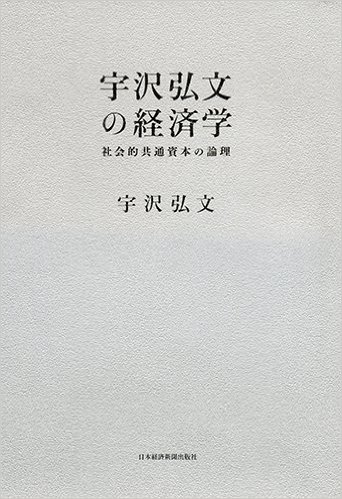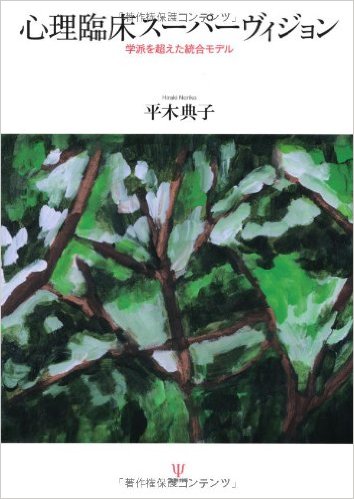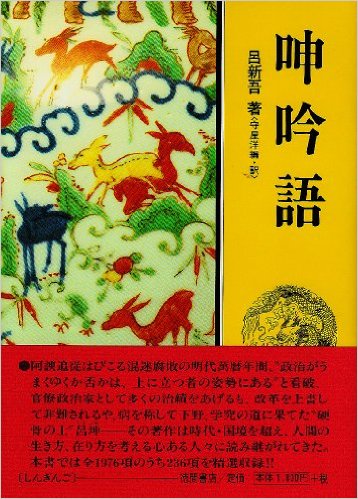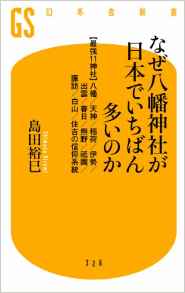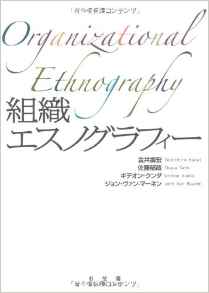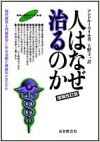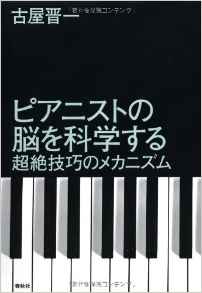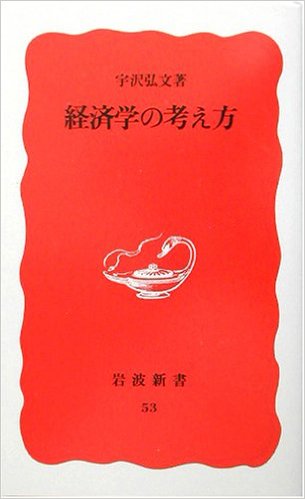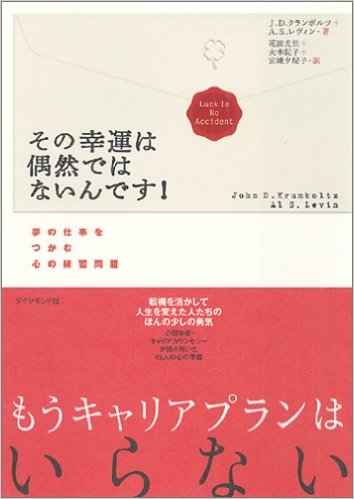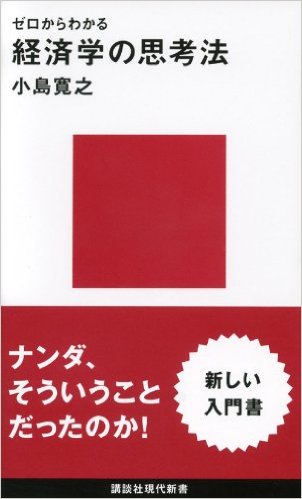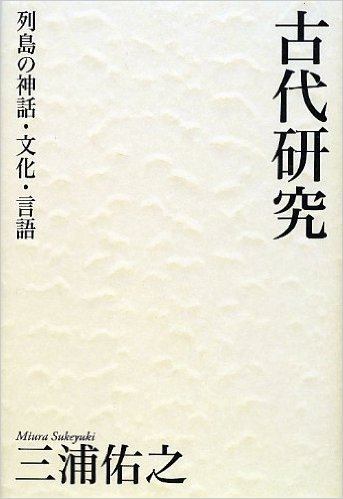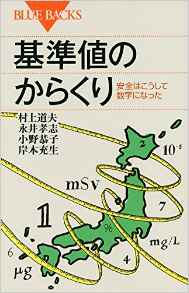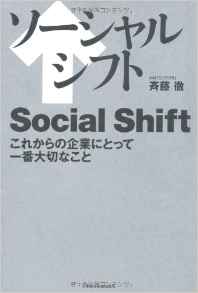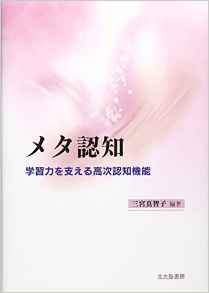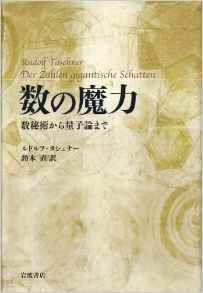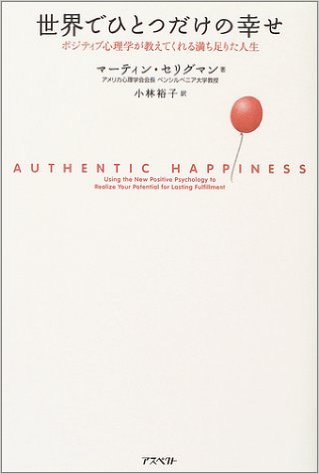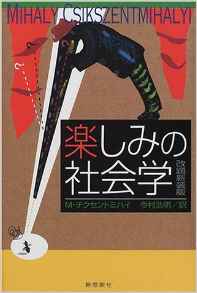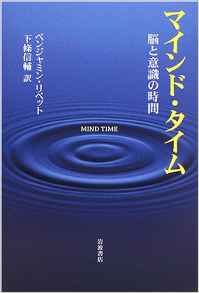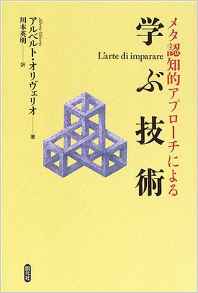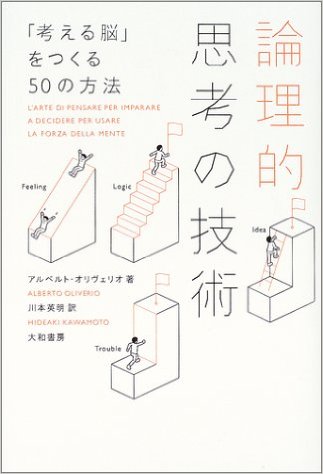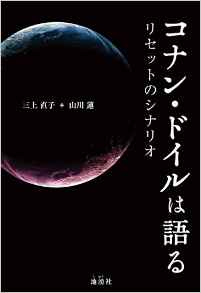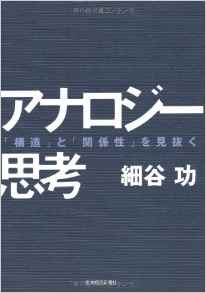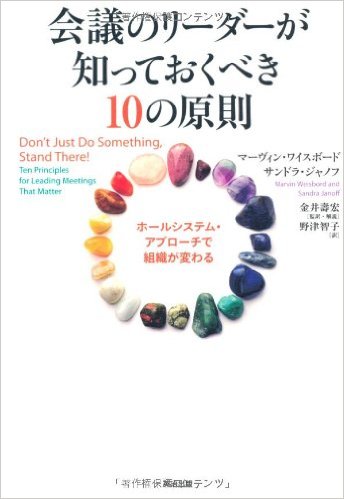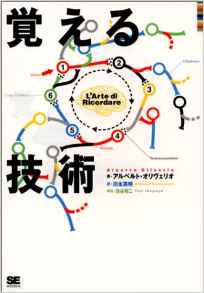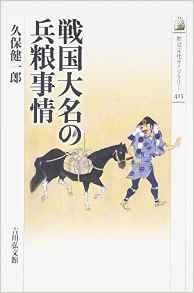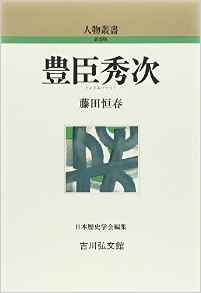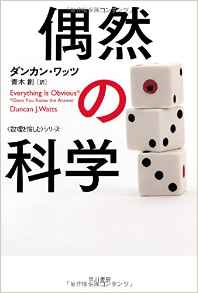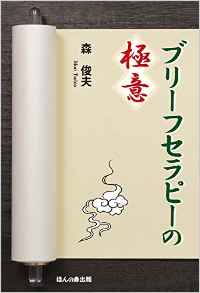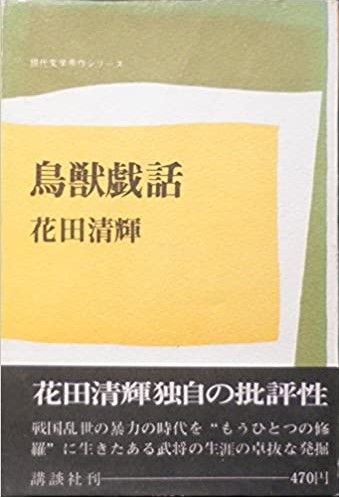|
空洞化 |
|
浅井基文『集団的自衛権と日本国憲法』を読む。
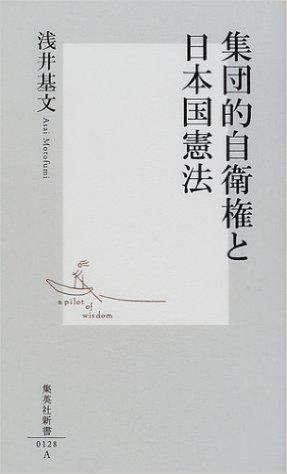
本書は,ブッシュ政権,小泉政権の成立という,今から16年も前の時代状況を背景に,タイトルになっている,
集団的自衛権,
をめぐる論議を取り上げている。にもかかわらず,先年集団的自衛権を巡って論議されたことを映し鏡のように,炙り出している。結局,日本の政府は,対米関係に振り回されているのである。
その時点で,ブッシュ政権は,
日本が集団的自衛権を行使することに踏み込む,
ことを求めている。それを著者は,
「一つは,ブッシュ政権が進める軍事戦略の見直しとのかかわりです。この軍事戦略の見直しを進めていくうえでは,日本がきわめて重要な要素となるのです。
つまり,アメリカがこれからおこなうことがある戦争に日本が全面的な協力体制をとるようにすること,言いかえれば,集団的自衛権を行使することに踏み込むことが,欠くことができない前提条件になる,ということです。日本がどう出るかによって新しい戦略の行方が決まる,といっても決して言い過ぎではありません。
もう一つ実際的な問題として,これまでの日米軍事関係,とくに日本のこれまでの対応に対する不満がブッシュ政権の内部で強まってきたことも無視できません。日本の集団的自衛権の行使に踏み込まない限度での対米協力に終始してきたことを,ブッシュ政権はもはやこのままにしておくことはできないと考えるのです。」
とし,そして,こう書き加える。
「以上二つの事情に共通することがあります。つまりいずれの場合にも,ブッシュ政権は日米軍事関係のあり方を,集団的自衛権を軸にして根本的に変えようとしているということなのです。」
この帰結が,自衛隊のイラク派兵,に行き着くのである。
国務省の副長官アーミテージは,
「アメリカと日本―成熟したパートナーシップに向けて」
という,いわゆる「アーミテージ報告」を,ブッシュ政権成立前に出してる。
「改訂された日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)は,(日米)同盟において日本が役割を拡大するうえでの出発点(フロア)であって最終目標(シーリング)ではない…。(中略)日本が集団的自衛権を禁止していることは,同盟の協力にとって制約であり,この制約を除くことによって安全保障上の協力がより緊密かつ効果的になる」
今回の安倍政権の集団的自衛権をめぐる法制化は,ほぼこの報告の敷いた路線に応える対応ということがわかり,
「九・一一事件がおこった後,特に国務省のアーミテージ副長官…が『旗を見せろ』とせまってから,小泉首相は血相を変えて動き始めました。アメリカの報復戦争を無条件で全面的に支持しただけではありません。自衛隊を海外派兵して,アメリカの軍事行動を支援する方針を追求したのです。それが特措法であり,この法律を根拠にした自衛隊の海外派兵でした。」
という経緯は,今日見るとき,著者の,
「特措法と海外派兵は,事件に対処するための例外的なもの,と受け止めるとしたら,それはとんでもない間違いです。それは,集団的自衛権行使というアメリカの対日要求を実現し,憲法九条の枠組みを最終的にとりはらうための布石です。」
という言葉は,集団的自衛権法制化の露払いだったということがはっきりわかるのである。
「集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は,一見明確です。それは,他衛を本質とするいわゆる集団的自衛権の行使は,憲法九条のもとでは認められない,とするものです。この解釈は,集団的自衛権の本質…を踏まえたもの,といえます。
しかし実際には,アメリカが対日軍事要求をエスカレートするにしたがって,保守政治は,集団的自衛権を禁止する憲法第九条をなんとかしたい,と動いています。」
そして,「特措法」では,
武力行使にあたらない,
戦闘行為がおこなわれておらず,活動期間を通じて戦闘行為が行われないと認められる地域に限定する,
という方針で,
「日本は武力行使しないんですよ。個別自衛権,集団自衛権の問題は,武力行使する場合のことでしょう。(中略)テロ根絶,テロ抑止のために支援,協力態勢をつくるというのが今考えている新法の考え方である。」
「アメリカは個別自衛権でこのテロとの闘いに向かっている。日本は集団的自衛権でもない,個別自衛権でもない,国際協調だ」
等々と詭弁で潜り抜け,まさに集団的自衛権行使の露払いを果たしたことになる。
「つまり,武力行使はしないということによって,特措法は憲法違反という批判を入り口で封じる。また,集団的自衛権の問題も武力行使とのかかわりあいで問題になるわけだから,武力行使はしないと言い切ることで,特措法を集団的自衛権とのかかわりで批判する動きに対抗する。特措法では海外出動する自衛隊は武力行使することも予定しているが,その問題については,…自然権的権利の行使としての武器使用ということで言いぬける,ということなのです。」
このやりとりを見ると,集団的自衛権法制化で,意識的に集団的自衛権を個別自衛権と混同させることで誤魔化した経緯を思い起こさせる。著者は,
「憲法違反のことをやろうとしながら,そういう批判を言いのがれるだけのために,政府がいかにごまかしの議論をすることにきゅうきゅうとしているか,…。こういうやり方がまかり通ってしまったことが,戦後日本の安全保障のあり方について,私たちの健全な思考をさまたげてきたと思います。」
と書く。それは,16年たっても,いささかも変わらず,対米重視とは聞えがいいが,アメリカ政府の意向にふりまわされている姿勢だけが際立つだけである。当時,自由党の党首小沢一郎は,
「反テロのムードに便乗して,なし崩しに既成事実をつくろうとしている。その体質と手法は戦前の昭和史と同じ」
と喝破している。そのなし崩しは,ほぼ憲法九条を空洞化するところまできた。それは,九条にとどまらず,
基本的人権,
も,何よりも,
議会制民主主義,
も,さらには,
三権分立,
までも,ほぼ空洞化しつつある,憲法九条の空洞化は,
戦後日本の空洞化,
そのものの象徴である。
参考文献;
浅井基文『集団的自衛権と日本国憲法』(集英社新書) |
|
法務官 |
|
北博昭・NHKスペシャル取材班『戦場の軍法会議:日本兵はなぜ処刑されたのか』を読む。
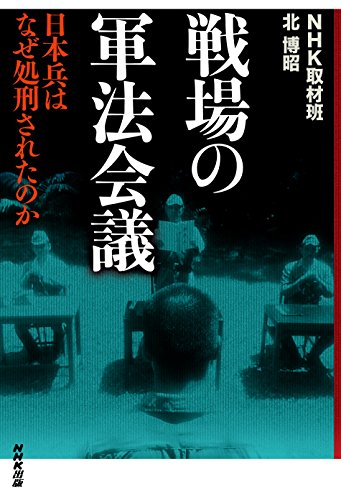
本書の中心になっている取材は,ある兵隊を,
逃亡罪
で,処刑した事件である。
「その事件が起きたのは,1945年(昭和二十年)2月のフィリピン。米軍から激しい攻撃を受けた日本軍の部隊が,ルソン島北部にある山岳地帯に追い込まれ,食糧も弾薬も底をついたため,兵士たちは飢えや病気に苦しんでいた。こうした中,悲劇は起きた。中田富太郎という二二歳の海軍の上等機関兵が,食糧を求めて周辺をさまよい,部隊を離れたため『逃亡罪』の容疑で逮捕された。『軍法会議』と呼ばれる軍の法廷が屋外で開かれ,裁判官を務めた上官たちが,中田に死刑判決を下す。そして,銃殺刑によって若い命が失われた。」
その軍法会議に立ち会った法務官は,メモを残していた。
「中田富太郎はの死刑宣告あり。これは犯罪事実自体としては死刑宣告に値せざるやに認めらるるも(中略)遂に処刑を選ぶこととしたるものなり」
中田は,奔敵未遂・略奪・窃盗の容疑で,死刑に処せられる。
「軍法会議では,通常五人いる裁判官のうち,四人を軍人…,さらに軍人の中でも階級が一番上の兵科将校が裁判長を務めていた。(中略)五人の裁判官のうち必ず一人は,『軍人』ではない『文官』の『法務官』が担当することが法律で定められていた。」
後に法改正がなされ,法務官も武官とされることになるが,戦時下での臨時軍法会議(では控訴審はない)で,法務官がこう記録しているのである。その法務官のメモには,
犯罪犯行表,
があり,その供述調書には,
「空腹に耐えかね,部隊から逃走す」
という記述がいっぱいある。
「おそらく中田も食糧をとりに部隊を抜け出して捕まったのではないか」
と,取材の過程で,体験者が語る。その人は言う。
「日本軍上層部の『現地調達』というバカな考え。これがすべての敗因ですよ。食糧を送り込まずに,現地で調達せぇ,って無茶で無謀な戦略です。それも日本軍は,前線へ行けば行くほど食糧が無いんです。米軍は逆ですよ。前線に行けば行くほど,豪華なレーション(軍に配給される食糧パック)が飛行機でばらまかれる。それに日本軍の上官連中は,食糧を独り占めにしていた。」
現地にいたもう一人の目撃者は,
「バヨンボンでおかしなことがあってな。ある戦友が突然処刑されたんや。藪の中で。」
と,
語る。法務官と同行していた録事(事務官)は
「裁判は,屋外で行われ,米軍の飛行機が頭上を通過する度に木陰に隠れて中断したこと,中央に三人の裁判官が座り,向かって上手に録事,下手に検察官が座っていたこと。そこで裁判官から罪状を告げられたこと,一一人を裁いた裁判は一時間程度で終わった」
と語り,中田上級機関兵について,
「今度逃亡したら,向こうに入ってこちらの様子がみんな分かるから処刑にされたんだ」
ということを,誰かから聞かされたことを覚えていた。中田は英語が堪能で,
「これは逃亡したら日本の軍隊の情報がみんなアメリカにつうじちゃうんじゃないか…。(中略)中田は死刑にしないとマズいという“空気”が流れたんです。」
と。
「“空気”という責任が極めて曖昧なものによって『法の正義』がねじ曲げられ,軍隊という“大の虫”を生かすために,一人の兵士という“小の虫”の命が奪われる。」
しかし,これは,ほんの一例に過ぎない。メモにはこうある。
「16名密に準備の上兵器食糧携行二月一八日逃亡せり。外に一二名は正に非ざることを知り帰隊せしをもって厳重告諭の上総員特攻に使用。国賊の汚名をそそがしめんとす。」」
つまり,
「逃亡兵を軍法会議にかけることなく,代わりに自らの命と引き替えに,敵に体当たりをする特攻作戦に使われた」
のである。体験者は,
「私はそれを逃亡だと思ってないんですよ。(中略)食うもの食わせて,飲むもの飲ませとったら,にげやしませんよ。」
そして「特攻」について,
「切り込みのことですよ。決死隊ですよ。もう行って死んで来いって。生きて帰ってくるなということですよ。これで帰ってくれば,今度はもう味方にやられるわけですよ。」
といい,そしてこう付け加える。
「上官にとって,兵隊の数が減れば“口減らし”にもなる。酷いものですよ。(中略)だけど,食べ物がないから,人を減らすしかないんですよ。(中略)食糧を捜しに部隊から一時でも離れた兵隊を,『敵前逃亡』だという罪をなすりつけ,決死隊に送れば,…責任をとがめられることもない。」
しかし,そういう汚名を着せられた,遺族は汚名を雪ぐ機会もないまま,しかもある時までは,年金までも支払われなかった。唯一の名誉回復の裁判(吉池裁判)も,請求を棄却された。
戦後軍の法務官だった人たちは,多く法曹界において大きな影響力を発揮した。そして,
「複数の元法務官は,戦争被害を受けた一般の人たちによる賠償請求を国が斥ける根拠になってきた『受任論』という考え方の形声に関わっている」
という。判決文に曰く,
「戦争犠牲,戦争損害は,国の非常事態のもとでは,国民の等しく受忍しなければならないところ」
と。法務官は,自分の責任も放棄し,責任を取るべき人間をも免責し,国をも免責するという,二重三重に,無任性を発揮したというべきである。
「軍法会議で不当に処刑された兵士の遺族は未だに苦しんでいて,名誉の回復がなされていない。…そもそも検証すること自体が不可能になっているのは事実である。“国家の非常事態だったから”,“当時の法律にもとづいてやっていたから”などの理由で,戦時中に行われたことを戦後検証することさえ避けてきた」
というより,逃げてきた法曹界である。
「誰ひとりとして,軍法会議の実態に真摯に向き合った元法務官はみあたらなかった。」
このことは,当時しかるべき地位にいたほとんどすべての人間に当てはまる。
参考文献;
北博昭・NHKスペシャル取材班『戦場の軍法会議:日本兵はなぜ処刑されたのか』(NHK出版) |
|
避決定 |
|
森山優『日本はなぜ開戦に踏み切ったか―「両論併記」と「非決定」』を読む。

本書の意図を,著者が「あとかぎ」で,
「これは,大本営政府連絡懇談会(連絡会議)における『国策』策定という当該期の意思決定の『制度』を対象に,開戦過程に対して筆者なりの説明を試みたものである。しかし『非決定』というネーミングのインパクトが強かったためか,『非決定』なのに開戦を決定したではないか,という批判も受けた。今にして思えば,『避決定』としたほうが実態に近かったかもしれないと反省している。このため,本文中では『非(避)決定』としている。」
と書く。本書のサブタイトルにある,
「両論併記」と「非決定」
とは,「明確な意思決定が困難な場合の国策」決定プロセスの,
「コンセンサス方式による文案の決定のありよう」
を指す。それは,
「①『両論併記』=一つの『国策』の中に二つの選択肢を併記する。二つどころか,多様な指向性を盛り込み過ぎて同床異夢的な性格が露呈する場合もある。
②『非(避)決定』=『国策』の決定自体を取り止めたり,文言を削除して先送りにすることで対立を回避する。
③同時に他の文書を採択することで決定された『国策』を相対化ないしは,その機能を相殺する。」
と,著者は,整理する。そして,
「となると,なぜ日米開戦のような重大問題で,これら当事者全員の意思決定が可能となったのだろうか。それは,日米開戦が,それ自体を目的として追求された結果,選択されたわけではなかったことも一因である。」
そのプロセスを見ていくのが本書の狙いになる。
「その中で明らかになってくることは,むしろ,効果的な戦争回避を決定することができなかったために,最もましな選択肢を選んだところ,それが日米開戦だったという事実である。」
1940年以降,政府と統帥部との関係緊密化の試みとして設けられた,
大本営政府連絡懇談会 ,
で,国家の方針を定める「国策」が決定されることになったが,そこで41年7月から42年の「対英米蘭開戦の件」まで,10件以上の「国策」が決定される。しかし,
「たとえば,…1941年7月2日に御前会議で決定された『情勢ノ推移ニ伴フ帝国国策要綱』…は,対英米戦に関する重大な文言が認められた『国策』であった。ここでは,仏印とタイへの進出による南方進出態勢の強化がうたわれたが,そのためには『対英米戦を辞せず』とされていた。日本は,この決定に従って南部仏印に進駐し,英米蘭の対日全面禁輸を招来した。『対英米戦を辞せず』と大見得を切ってまで決定された『帝国国策要綱』だったが,つきなる措置を決めた…『帝国国策遂行要領』(9月6日)では,外交交渉と戦争準備を並行して進め(『両論併記』),開戦の判断は10月上旬まで先送り(『非(避)決定』)されていたのである。
ところが,近衛内閣は期限が過ぎても判断をなし得ず,10月中旬に崩壊した。そして新たに組閣した東条には『白紙還元の御諚』が下され,『国策』は反故となった。八月末から十月までの間は,国際情勢が激変した時期ではない。つまり,日本はいったん決定されたはずの政策を実行に移すまでの間に,内閣の崩壊と更なる根本的な政策内容の検討を余儀なくされたのである。このような『国策』とは,いったい何なのであろうか。」
この「避決定」たるゆえんを,こう「あとがき」で書く。
「後世の目から冷静に評価すれば,,戦争に向かう選択は,他の選択肢に比較して目先のストレスが少ない道であった。海相の任命,被害船舶の算定,海軍の開戦決意,『聖断』構想,天皇の作為,いずれもが,もし真剣に実行しようとしたら,それまでの組織のあり方や周囲との深刻な軋轢が予想された。実は,回避されたのはそのような種々の係争が予想される選択肢だったのである。つまり,内的なリスク回避を追求した積み重ねが,開戦という最もリスクが大きい選択であった。にもかかわらず,当事者にとっては,開戦は三年めの見通しのつかないあいまいな選択肢だった。ようするに,目の前の軋轢を回避し,選択の結果についても判断を避けることが可能になる。開戦決定は,一見非(避)決定から踏み出した決定に思えるが,非(避)決定の構造の枠内にとどまっていたのである。
全く逆の発想もある。それは何もしないという選択,意図的な非(避)決定の貫徹,つまり臥薪嘗胆である。しかし,これは受苦の連続となることは必定だった。確実に国力が低下して行くなかで,状況の好転をひたすら待ちつづける。小役人的に目先のリスクを回避するのに汲々としていた当時の指導者層に,あえて『ジリ貧』を選ぶというような,そんな肝が据わった行動が期待できただろうか。」
と切り捨てる。ここで言う臥薪嘗胆とは,アメリカの石油禁輸措置を受けて,東条首相が示した,
戦争することなく臥薪嘗胆,
直ちに回線を決意し戦争によって解決,
戦争決意の下に作戦準備と外交交渉,
という選択肢の,「臥薪嘗胆」つまり,石油禁輸に堪える,ということを意味する。しかし,陸軍が,中国よりの撤兵を拒む以上,対米交渉も先行きの見通しは立たない。
「浮き彫りになったのは,結局どんな選択肢をとるにせよ,日本に明るい未来は来そうにないということであった。種々の限定付きであるにせよ,最も希望の持てそうな選択肢が南方資源確保のための開戦であった。しかしそれは,希望的観測に根拠を置く,粉飾に満ちた数字合わせの所産だったのである。日本の選択が『ベスト・ケース・アナリシス(全てが良い方向に転ぶことを前提とした分析)』に依拠していたと指摘される所以である。」
「非(避)決定」の一例は,対米戦の主たる戦力となるはずの海軍自体が,
「成算があるのは緒戦の資源地帯占領作戦のみであった。長期戦の見通しは『不明』」
「開戦三年め以降の見通しは不明という態度をとり続けていた」
(中国からの)「撤兵問題だけで日米が戦うなど『馬鹿なこと』という立場」
であった「海軍が戦争やむなし」と決意したのは,「開戦三年め以降の戦局に対する判断を放棄したことと同意義だった」にもかかわらず,結局,
「英米可分論や船舶損耗量の見通しのような,それまでの海軍の立場を揺るがしかねず,かつ周囲との軋轢が予想される戦争回避策を避けた,ということである。つまり決定回避の対象が開戦ではなく,目前の重圧(しかも海軍にとっての)に向けられたのである。そして三年め以降は不明という戦争見通しは,海軍の立場を守るうえでも有効だった。開戦という選択肢の評価は,三年め以降にしか判明しないからである。海軍は組織的利害を優先し,自らが戦争の行方を判断することを放棄した。」
というていたらくなのである。多くの軍人は,たとえば,参謀本部の中堅幕僚は,ぎりぎりまで戦争回避を画策する重臣を,
「皇国興亡の歴史を見るに国を興すものは青年,国を亡ぼすものは老年なり。(中略)若槻,平沼連の老衰者に皇国永遠の生命を託する能わず」
と,冷ややかである。しかし著者は,
「この後,わずか四年を経ずして,永遠の筈の皇国の生命を断ち切ることになる選択をしたのは彼らのほうであった」
と切り捨てる。この間の決定の過程をみるとき,
「そもそも,何故に両論併記や非(避)決定を特徴とする『国策』が必要とされたのであろうか。それは,強力な指導者を欠いた寄り合い所帯の政策決定システムが,相互の決定的対立を避けるためであった。そのための重要な構成要素が,『国策』の曖昧さであった。それでは,臥薪嘗胆,外交交渉,戦争という三つの選択肢から,なぜ臥薪嘗胆が排除されたのだろうか。それは臥薪嘗胆が,日本が将来に蒙るであろうマイナス要素を確定してしまったからであった。これに比較して,外交交渉と戦争は,その結果において曖昧だった。つまり,アメリカが乗ってくるかどうかわからない外交交渉と,開戦三年めからの見通しがつかない戦争は,どうなるかわからないにもかかわらず選ばれたのではなく,ともにどうなるかわからないからこそ,指導者たちが合意することができたのである。」
結局,結果として,
「何のための戦争だったのだろうか。即物的な観点からすれば,石油のためであった。…結果的に,石油のための戦争となったのである。」
ということになる。著者は,陸軍が,中国からの撤兵に反対したのに象徴されるように,
「日本は,自らの政策が破たんしたツケを,自らが傷ついてまで支払う責任感に欠けていた。最低限度の現状維持すら確保できなくなった日本は,それまでの『成果』を無にしないため,」
対英米戦に突入することになる。
こうした意思決定システムの原因は,明治憲法体制にある。著者は,明治憲法体制における政治システムを,図のようにまとめているが,
「明治憲法体制において,天皇は統治権の総攬者の大元帥という絶対的な立場にあったが,同時に責任を負わないことにもなっていた(天皇無答責)。政治的選択には,必ず結果責任がつきまとう。それを担ったのが内閣や統帥部(陸軍は参謀本部,海軍は軍令部)やそれ以外の超憲法機関(枢密院など)だったのである。」
とし,問題は,
「これらがビラミッド型の上下関係ではなく,それぞれの組織が天皇に直結して補佐するようになっていたことである。たとえば,戦争指導については大元帥である天皇に直属している統帥部が輔翼…し,内閣は軍政事項(軍の行政事務。軍の規模や,それを支える予算措置など)を除いてこれにタッチできなかった。」
上記の大本営政府連絡懇談会は,こうした横並びの弊を打破するための策ではあった。
結局こういうシステムを見ていると,明治維新のツケが,結局戦争へと突入させるに至ったとみることができる。とするなら,今日,再び,戦後体制を覆して,明治体制へと戻そうとする試みは,再び,結果として,日本の壊滅へと至るのが必然であるように思える。これは,見事なループ構造に見える。しかし,一度目は,悲劇だが,二度目は,喜劇でしかない。
参考文献;
森山優『日本はなぜ開戦に踏み切ったか―「両論併記」と「非決定」』(新潮選書) |
|
怪を志す |
|
岡本綺堂編訳『世界怪談名作集』を読む。
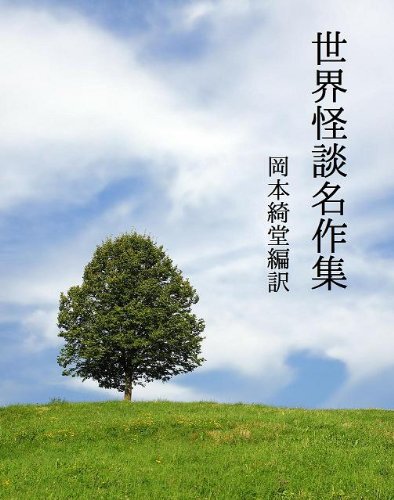
編者の綺堂は,
「外国にも怪談は非常に多い。古今の作家、大抵は怪談を書いている。そのうちから最も優れたるものを選ぶというのはすこぶる困難な仕事であるので、ここでは世すでに定評ある名家の作品のみを紹介することにした。
したがって、その多数がクラシックに傾いたのはまことに已む得ない結果であると思ってもらい たい。
怪談と言っても、いわゆる幽霊物語ばかりでは単調に陥る嫌いがあるので、たとい幽霊は出現しないでも、その事実の怪奇なるものは採録することにした。」
として,以下の17編を採録している。
「貸家」エドワード・ブルワー・リットン
「女王」アレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン
「妖物」アンブローズ・ビヤース
「クラリモンド」ピエール・ジュール・テオフィル・ゴーティエ
「信号手」チャールズ・ディケンズ
「ヴィール夫人の亡霊」ダニエル・デフォー
「ラッパチーニの娘 アウペパンの作から」ナサニエル・ホーソーン
「北極星号の船長 医学生ジョン・マリスターレーの奇異なる日記よりの抜萃」アーサー・コナン・ドイル
「廃宅」エルンスト・テオドーア・アマーデウス・ホフマン
「聖餐祭」アナトール・フランス
「幻の人力車」ラドヤード・キップリング
「上床.」フランシス・マリオン・クラウフォード
「ラザルス」レオニード・ニコラエヴィッチ・アンドレーエフ
「幽霊」ギ・ド・モーパッサン
「鏡中の美女」ジョージ・マクドナルド
「幽霊の移転」フランシス・リチャードストックトン
「牡丹燈記」瞿宗吉
たとえば,ポーが入っていないのについては,
「アラン・ポーの作品──殊にかの『黒猫』のごときは、当然ここに編入すべきであったが、この全集には別にポーの傑作集が出ているので、遺憾ながら省くこと
にして、その代りに、ポーの二代目ともいうべきビヤースの『妖物』 を掲載した。」
とあるので,何かの全集の一巻として編集されたものらしい。
この中に,「牡丹燈記」が入るのは,小説といっても,
志怪小説,
であって,今日言う小説ではないので,いささか不釣り合いかもしれない。「志怪」つまり,「怪を志(しる)す」とは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/434978812.html
で触れたように,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
であり, ここで言う,「小説」は,
「志怪小説、志人小説は、面白い話ではあるが作者の主張は含まれないことが多い。」
とされるが,中国明代の小説集『剪灯新話』に収録された『牡丹燈記』は,志怪小説であるのだから,である。
プーシキン,
モーパッサン,
ディケンズ,
というビッグネームも並ぶ中で,何より圧倒的な筆力を見せるのは,プーシキンの,
「女王」
だと思う。「女王の遊び(
骨牌戯の一種)」の必勝の秘策を巡る,一種の怪異譚であるが,主人公(ヘルマン)はそれを手に入れるために,それを知る伯爵夫人に近づくために付き添いの女(リザヴェッタ・イヴァノヴナ)を欺き,それを知る伯爵夫人を脅して知ろうとし,死なしめてしまう。その伯爵夫人の幽霊が訪れ,
「わたしは不本意ながらあなたの所へ来ました」と、彼女はしっかりした声で言った。「わたしはあなたの懇願を容れてやれと言いつかったのです。
三、七、一の順に続けて賭けたなら、あなたは勝負に勝つでしょう。しかし二十四時間内にたった一回より勝負をしないということと、生涯に二度と骨牌の賭けをしないという条件を守らなければなりません。それから、あなたがわたしの附き添い人のリザヴェッタ・イヴァノヴナと結婚して下されば、私はあなたに殺され
たことを赦しましょう」
と言って去る。もとろん,主人公(ヘルマン)は,約束を守らず,三回目に勝負に入った日,
右に女王が出た。左に一の札が出た。「一が勝った」と、ヘルマンは自分の札を見せながら叫んだ。「あなたの女王が負けでございます」と、シェカリンスキイは慇懃に言った。
ヘルマンははっとした。一の札だと思っていたのが、いつの間にかスペードの女王になっているではないか。
と,大敗し,発狂する。
次は,ディケンズの,
「信号手」
を取る。そして,意外にも,こう並べてみても,
「牡丹燈記」
がいい。圓朝が惚れ込んだだけのものはある。その次に,ジョージ・マクドナルドの,
「鏡中の美女」
がいい。
これらのが他の作品と何が違うのか,と考えてみた。大きいのは,
作品の構造の奥行,
ではないか,と思う。それは,作品の主人公のいる世界の更に奥の世界を感じさせるものだ。「女王」だと,
伯爵夫人の過去,
と,
ヘルマンの欺き,
と,
付添女の戸惑い,
と,
ヘルマンの挫折,
とが,別々の世界として同時進行で重なり合う。「牡丹燈記」でいうなら,
主人公,
と
幽霊,
と,
法師,
と
道人,
であり,それぞれ,並行宇宙のように,同時に存在している世界があり,それを自在に行き来する道人が,最後,
九泉の獄屋,
つまり,
地獄,
へと,迷う三人を送りつける,という意味ではさらに向こうに世界がある。重なる世界は,それぞれ異にしても,でも,それが作品に奥行を与える。「信号手」で,「私」がこう書く。
この物語の不思議な事情を詳細に説明するのはさておいて、終わりに臨んで私が指摘したいのは、不幸なる信号手が自分をおびやかすものとして、私に話して聞かせた言葉ばかりでなく、わたし自身が「
下にいる人!」と彼を呼ん
だ言葉や、彼が真似てみせた手振りや、それらがすべて、かの機関手の警告の言葉と動作とに暗合しているということである。
このとき,予兆の世界と実現の世界の重なり合い,ということになる。
怪異は単純ではない。多重宇宙や並行宇宙を挙げるまでもなく,たとえば,この世とあの世は,次元を異にして,同時に存在している,という(メタ化された)目から,見ることなしに,物語世界の奥行が広がることはない。
参考文献;
岡本綺堂編訳『世界怪談名作集』(Kindle版) |
|
孝明天皇 |
|
家近良樹『幕末の朝廷―若き孝明帝と鷹司関白』を読む。

本書は,幕末という大きな転換点で,歴史を変える役割を果たした孝明天皇に焦点を当て,
「通商条約の勅許問題を契機に,江戸期を通じて朝幕間最大の政治対立にまで発展した安政五年政変に至る過程を分析しようとする」
ものである。結果,
「本人の意思とは裏腹に重要な役割をはたすことになったのが,孝明天皇であった。ペリー来航に代表される未曾有の対外危機に遭遇した彼は,広く知られているように,安政五年(1858)の時点で,幕府が推し進めようとした開国路線の前に立ちはだかることになる。
もし彼がこうした姿勢を貫かなかったならば,その後の歴史は,我々の知るそれとは相当程度異なるものとなったであろうことは間違いない。だが,孝明天皇は,この時点で,開国路線に待ったをかけ,ここに幕末日本の運命は事実上決した。これ以降,朝幕関係は悪化し,それに伴って日本は動乱の時期に突入する。その結果,最終的には,幕府支配が倒され,長い歴史を誇った摂関体制も一気に廃止されることになる。そして,平安時代より続いてきた伝統的な朝廷のあり方を否定したうえで,天皇を国家元首とする新しい政府(近代天皇制国家)が創出された。」
という,この時期の孝明天皇の揺れ動く意思決定プロセスをつぶさに分析していくのである。
「まず,政変前の平穏であった朝幕関係や朝廷社会の内部」
「つづいて,その後,どう政変が発生したのか」
「そして最終的には,その後の天皇および朝廷社会のあり方にいかなる影響を及ぼしたのか」
を展開する。そこでは,著者は,三点に留意したという。
第一に,
「政変に至る過程を分析するにあたって,孝明天皇の動向を軸にしながらも,従来はほとんど本格的に取り上げられることのなかった一連の人物(関白の鷹司政通など)にも焦点をあてて,じっくり公家社会のじっくり解明する」
サブタイトルに「若き孝明帝と鷹司関白」とある所以である。孝明帝の父,仁孝帝以来三十年関白職にとどまった関白との関係は,なかなか一筋縄ではいかない。本人自身が病弱で,再三辞意を表明しながら,慰留され続けてきた。しかも仁孝帝より一回り以上年上で,しかも,
鷹司家と仁孝・孝明両天皇が同じ血脈(政通の祖父輔平の実兄は,光格(孝明の祖父)天皇の父閑院宮典仁親王),
であったことも,
「両天皇(仁孝・孝明両天皇)にとって,政通は血縁的に親しい感情を持てる相手であり,その分政通には,天皇の支持が当初から獲得しやすかった」
ということも,さらに,鷹司関白が,
「周到な配慮のできる,真に『大人』の関白であった」
からこそ,人心を掌握できた,その人と孝明帝との確執が,大きな作用をしていくことになるらこそである。
第二は,通説となっている,
「孝明天皇は,長期間にわたって朝廷を支配してきた摂家(関白の鷹司政通)に対抗して,天皇権(天皇の権勢)の回復に努めた豪胆な性格の天皇であったこと,その背景に祖父光格天皇の存在が大きく影を落としていることを力説する」
評価に対して,
「安政五年の時点で彼を豪胆な君主に変貌させたのが,すぐれて幕末期に特有の事情によったことを明らかにしようとする」
という本書の狙いは,ほぼ達成されている。気弱で,やさしい配慮(鷹司関白に,辞任後,異例の太閤の称号を贈る)の孝明帝が,どうして頑なに開国を拒むに至った彼の経緯は,説得力がある。そのことが,逆に,合理的で,迷信を排する鷹司関白との対立をもたらすことになっだけである。
第三は,
「幕末期の天皇や公家については,漠然たる形であれ,世界史の流れを理解できない頑迷固陋な人間集団(閉鎖的で狂信的な攘夷主義者の集まり)といった評価が定着しているようだが,この点の再評価を試みる」
とする。
「彼らの主張には,変革を拒否する守旧主義や,欧米諸国の文物・宗教に対する偏見と誤解が色濃く見られた」
ことは確かだが,
「アメリカ等が強制してきた,いわゆる『グローバル・スタンダード』(それは『世界通商の仕向』『万国共通の常例』『世界普通の御法』といったお題目のもと,文化・文明の両面で欧米的価値観を日本側に強引におしつけようとするものであった)への鋭い批判が見られたのも事実である。すなわち,健全なナショナリズムの萌芽がそこには含まれていた」
とも見なし,時代状況の中で,守旧となることが,ある意味を持つことも的確に分析されている。
さて,本書を通読して,つくづく感じたのは,,リーダーが,下々に広く意見を求めることは,多く,責任放棄か,バックアップを求めてということになる,という点である。それは,リーダーが,意思決定することに揺らいでいることが多い。意思決定した後にその是非を求めるのと,その前に意見を求めるのとでは雲泥の差だ。
老中阿部正弘は,ペリー来航後,それまでの意思決定システムを崩し,
「上は天皇・諸大名から,下は幕臣に至るまで,国内の広い層の同意を得て,幕府の方針を決定檣とはかった」
結果,多くは,「存念なし」と,意見すら表明し得ない有様で,
「幕府首脳は,自分たちを援護してくれる筈の『世論』づくりに失敗した」
が,同じことは,老中堀田正睦に勅許を迫られ追い込まれた孝明帝が,取ったのも,
「多くの人々の意見を聴いて,それを参考にする手法(口実)」
であった。
「もし仮に,孝明天皇が,いくら自分は開国に反対すると叫んでも,それが即,朝廷の方針とはならなかったのである。すなわち,長年にわたって,朝廷の方針は関白−両役(武家伝奏と議奏,なかでも武家伝奏)ラインによって決定されてきた。そこで,開国路線にとりあえず待ったをかけるためには,従来の朝廷の最高意思を決定するあり方を,一時的にせよ停止する必要が出てくる。そして,このために天皇が採ったのが,開国に反対する圧倒的な世論を朝廷内に形成し,それでもって開国を阻止する作戦であった。」
一旦開けたパンドラの箱は,元へは戻らない。阿部正弘は,朝廷の意見を聴取するにあたって,
「叡慮に,かよう遊ばされたくと申す思し召しもあらせられ候はば,ご遠慮なく仰せ出され候よう,左候はば,その思し召しにて御取計らいも仕るべく儀と申すことに再応申し述べらる」
と,リップサービスで言ったことが,朝廷側に,
「国家の御大事は公武御一体の御義」
と受けとめさせ,以後,朝廷側に強く意識させることになる。ここでもパンドラの箱を不用意に開けたのである。
リーダーが意思決定に当たって,広く意見を求めることが,結果として,リーダーの思惑通りにはならないことは,今日でも,国民投票に振り回された例で見ることができる。それは,意思決定の先送り以上の悪夢しか生まないようである。
参考文献;た
家近良樹『幕末の朝廷―若き孝明帝と鷹司関白』(中公叢書) |
|
ポー |
|
エドガー・アラン・ポー『エドガー・アラン・ポー完全版』を読む。

何十年ぶりかで,再読した。やはり,圧倒的に,『うづしほ』あるいは『メールストロムの旋渦』と題される作品がいい。Kindle版のせいか,森鴎外の訳が載っていて,対比することができる。まず鴎外訳。
「船は竜骨の向に平らに走つてゐます。と申しますのは、船のデツクと水面とは并行してゐるのでございます。併し水面は下へ向いて四十五度以上の斜な角度を作つてゐる船の中で、わたくしが手と足とで釣合を取つてゐますのは、平面の上にゐるのと大した相違はないのでございます。
多分廻転している速度が非常に大きいからでございませう。
月は漏斗の底の様子を自分の光で好く照らして見ようとでも思ふらしく、さし込んでゐますが、どうもわたくしには
その底の所がはつきり見えませんのでございます。なぜかと申しますると、漏斗の底の所には霧が立つてゐて、それが何もかも包んでゐるのでございます。その霧の上に実に美しい虹が見えてをります。回教徒の信ずる所に寄りますると、この世からあの世へ行く唯一の道は、狭い、揺らめく橋だといふことでございますが、丁度その橋のやうに美しい虹が霧の上に横はつているのでございます。この霧このしぶきは疑もなく、恐ろしい水の壁面が漏斗の底で衝突するので出来るのでございませう。併しその霧の中から、天に向かつて立ち昇る恐ろしい叫声は、どうして出来るのか、わたくし
にも分かりませんのでございました。
最初に波頭の帯の所から、
一息に沈んで行つたときは斜な壁の大分の幅を下りたのでございますが、それからはその最初の割には船が底の方へ下だつて行かないのでございます。船は竪に下だつて行くよりは寧ろ横に輪をかいてゐます。それも平等な運動ではなくて目まぐろしい衝突をしながら横に走るのでございます。或るときは百尺ばかりも進みます。又或るときは渦巻の全体を一週します。そんな風に、ゆるゆるとではございますが、次第々々に底の方へ近寄つて行くことだけは、はつ
きり知れているのでございます。
わたくしはこの流れている黒檀の壁の広い沙漠の上で、周囲を見廻しましたとき、この渦巻に吸ひ寄せられて動いているものが、わたくし共の船ばかりでないのに気が付きました。船より上の方にも下の方にも壊れた船の板片やら、山から切り出した林木やら、生木の幹やら、その外色々な小さい物、家財、壊れた箱、桶、板なんぞが走つています。」
次いで佐々木直次郎訳。
「船はまったく水平になっていました、―というのは、船の甲板が水面と平行になっていた、ということです、―がその水面が四十五度以上の角度で傾斜しているので、私どもは横ざまになっているのです。しかしこんな位置にありながら、まったく平らな面にいると同じように、手がかりや足がかりを保っているのがむずかしくないことに、気がつかずにはいられませんでした。これは船の回転している速さのためであったろうと思います。月の光は深い渦巻の底までも射しているようでした。しかしそれでも、そこのあらゆるものを立ちこめている濃い霧のためになにもはっきりと見分けることができませんでした。その霧の上には、マホメット教徒が現世から永劫の国へゆく唯一の通路だという、あのせまいゆらゆらする橋のような、壮麗な虹がかかっていました。
この霧あるいは飛沫は、疑いもなく漏斗の大きな水壁が底で合って互いに衝突するために生ずるものでした。―がその霧のなかから天に向って湧き上がる大叫喚は、お話ししようとしたって、とてもできるものではありません。
上の方の泡の帯のところから最初に深淵のなかへすべすべりこんだときは、斜面をよほど下の方へ降りましたが、それからのちはその割合では降りてゆきませんでした。ぐるぐるまわりながら船は走ります、―が一様な速さではなく―目まぐるしく揺れたり跳び上がったりして、あるときはたった二、三百ヤード―またあるときは渦巻の周囲をほとんど完全に一周したりします。
一回転ごとに船が下に降りてゆくのは、急ではありませ
んでしたが、はっきりと感じられました。こうして船の運ばれてゆくこの広々とした流れる黒檀の上で、自分のまわりを見渡していますと、渦に巻きこまれるのが私どもの船だけではないことに気がつきました。上の方にも下の方にも、船の破片や、建築用材の大きな塊や、樹木の幹や、そのほか家具の砕片や、こわれた箱や、樽や、桶板などの小さなものが、たくさん見えるのです。」
どちらがいいとは言えないが,好みで言うと,(原作がそうなのだろうが)ハイフンを省いた鴎外訳の方が,完結でいい。
それにしても,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%A0
で,
「メイルストロム(ノルウェー語: malstrøm
[発音の仮名転写例:メルストロム]、英語: maelstrom
[発音の仮名転写例:メイルストラム])は、ノルウェーのロフォーテン諸島はモスケン島周辺海域に存在する極めて強い潮流、および、それが生み出す大渦潮を指す語(慣習的な日本語音訳)。
ノルウェー語で「mosk (意:sea splay、波飛沫) + -n
(定冠詞)」の意からなる最寄りの島名 "Mosken" (モスケン)と同じく(あるいは、これを語源として)、現地語(および、英語等)では
Moskenstraumen
(ノルウェー語発音の仮名転写例:モスケンスラウメン)など(その他は#呼称を参照のこと)とも呼ばれ、これを日本語ではモスケンの渦潮(モスケンのうずしお)と訳す(モスケンの大渦巻[モスケンのおおうずまき]などとも呼ぶ)。」
という大渦巻を,スローモーションのように描きだす筆力は,最初に読んだときも,再読,再々読したときも,変らず,圧倒される。
ポーの描く世界は,
「アッシャー家の崩壊」
「黒猫」
「ウィリアム・ウィルソン」
「落穴と振り子」
等々の恐怖小説,あるいは,
「モルグ街の殺人」
「盗まれた手紙」
「マリー・ロジェの怪事件」
「黄金虫」
という,いわゆる,ポー自身が「推理物語(the tales of rasiocination)」と呼んでいた作品群,あるいは,
「十三時」
のようのユーモアもの,いずれも,特異なシチュエーションの作品世界であるためか,昔語りでいう,
むかしむかし,あうるところに,おじいさんとおばあさんが住んでいました,
という,イントロというか,作品世界へのつなぎが必ずある。あるいは,
能のワキ,
シテが登場するための舞台装置を,必ず設えている。あるいは意識的なのかもしれないが,僕には,直接作品世界の中から始めないのが,結構まだるこしかった,というのが正直な感想である。さて,推理小説の嚆矢とされる作品を読みながら,
「マリー・ロジェの怪事件」
の中で,C・オーギュスト・デュパンの,
「もしも理性が真実なものを探して進むのならば、常套なものの面から突き出たものを手がかりにすることによってであって、また、こういった事件についての正しい質問は、『どんなことが起ったか?』ということよりも、『起ったことのなかで、いままでぜんぜん起ったことの
ないのはどんなことか?』ということなんだ。」
というセリフに,物を見るときの鍵が示されている。ポーの推理場面は,たまに現場へ行くこともあるが,多くは,新聞情報,あるいはそこに示される目撃情報から,推測していく。そのプロセスは,まさに情報分析と仮説を立てていく作業そのものだと,感心させられる。デュバンの言う,
「『どんなことが起ったか?』ということよりも、『起ったことのなかで、いままでぜんぜん起ったことの ないのはどんなことか?』」
とは,問題解決手法のEM(飯久保廣嗣)法が,
原因分析(PA:Problem Analysis),
において,
トラブル発生時の「原因究明」において、問題の対象と現象を特定し、発生事象(IS)と比較事実(IS
NOT)の情報収集を行い、その特異性と変化から原因を推定し、対策を講じる思考プロセス,
そのものと同じである。その視点で見るとき,小説的興味とは別に,デュバンの推論は,なかなか興味深いのである。
参考文献;
エドガー・アラン・ポー『エドガー・アラン・ポー完全版』(Kindle版) |
|
死者の書 |
|
折口信夫『死者の書・口ぶえ』を読む。
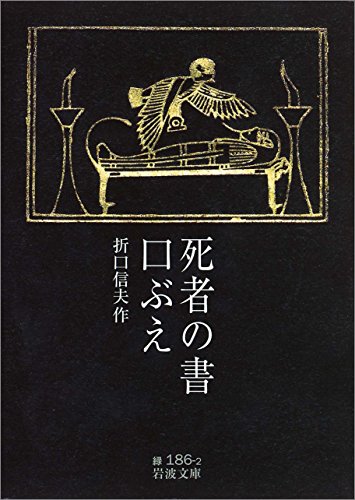
解説によると,「死者の書」は,単行本として上梓される際,雑誌連載時の第一回目と第二回目とは入れ替えられているらしい。つまり,
「彼(か)の人の眠りは、徐(しず)かに覚めて行った。まっ黒い夜の中に、更に冷え圧するものの澱んでいるなかに、目のあいて来るのを、覚えたのである。
した した した。耳に伝うように来るのは、水の垂れる音か。ただ凍りつくような暗闇の中で、おのずと睫と睫とが離れて来る。膝が、肱が、徐(おもむ)ろに埋れていた感覚をとり戻して来るらしく、彼の人の頭に響いて居るもの――。全身にこわばった筋が、僅かな響きを立てて、掌・足の裏に到るまで、ひきつれを起しかけているのだ。
そうして、なお深い闇。ぽっちりと目をあいて見廻す瞳に、まず圧(あつ)しかかる黒い巌(いわお)の天井を意識した。次いで、氷になった岩牀いわどこ。両脇に垂れさがる荒石の壁。したしたと、岩伝う雫しずくの音。」
と始るのは,連載時は,単行本で「六」にあたる,
「門をはいると、俄(にわ)かに松風が、吹きあてるように響いた。
一町も先に、固まって見える堂伽藍がらん――そこまでずっと、砂地である。
白い地面に、広い葉の青いままでちらばって居るのは、朴(ほお)の木だ。
まともに、寺を圧してつき立っているのは、二上山(ふたかみやま)である。其真下に涅槃仏(ねはんぶつ)のような姿に横っているのが麻呂子山(まろこやま)だ。其頂がやっと、講堂の屋の棟に、乗りかかっているようにしか見えない。こんな事を、女人(にょにん)の身で知って居る訣(わけ)はなかった。だが、俊敏な此旅びとの胸に、其に似たほのかな綜合の、出来あがって居たのは疑われぬ。暫らくの間、その薄緑の山色を仰いで居た。其から、朱塗りの、激しく光る建て物へ、目を移して行った。」
が冒頭であった,という。おそらく,これによって,死者である滋賀津彦(大津皇子)の思い人である耳面刀自(みみものとじ)と,万法蔵院に入り込んだ郎女(藤原豊成の娘)とを重ねようという意図からだったと想像される。
作品の構成というなら,むしろ,僕は,「三」の,
「万法蔵院(まんほうぞういん)の北の山陰に、昔から小な庵室(あんしつ)があった。昔からと言うのは、村人がすべて、そう信じて居たのである。荒廃すれば繕い繕いして、人は住まぬ廬に、孔雀明王像(くじゃくみょうおうぞう)が据えてあった。当麻(たぎま)の村人の中には、稀(まれ)に、此が山田寺である、と言うものもあった。そう言う人の伝えでは、万法蔵院は、山田寺の荒れて後、飛鳥の宮の仰せを受けてとも言い、又御自身の御発起からだとも言うが、一人の尊いみ子が、昔の地を占めにお出でなされて、大伽藍(だいがらん)を建てさせられた。其際、山田寺の旧構を残すため、寺の四至の中、北の隅へ、当時立ち朽(ぐさ)りになって居た堂を移し、規模を小くして造られたもの、と伝え言うのであった。そう言えば、山田寺は、役君小角(えのきみおづぬ)が、山林仏教を創はじめる最初の足代(あししろ)になった処だと言う伝えが、吉野や、葛城の山伏行人(やまぶしぎょうにん)の間に行われていた。何しろ、万法蔵院の大伽藍が焼けて百年、荒野の道場となって居た、目と鼻との間に、こんな古い建て物が、残って居たと言うのも、不思議なことである。
夜は、もう更けて居た。谷川の激たぎちの音が、段々高まって来る。二上山の二つの峰の間から、流れくだる水なのだ。」
と,女人結界を破ったとして,万法蔵院の庵室に謹慎したところから始めてもよかったのではないか,と思う。
折口信夫という巨人に申し上げるのも,僭越の極みだが,最初に,滋賀津彦の思いを出してしまったために,それが全体の翳としておおいかぶさるようにはならず,途中で消えていく印象がある。むしろ,郎女が結界を犯して,謹慎しているという背景に,その翳が滲み出てくる方が,完成版のもつ,滋賀津彦が,庚申で尻切れトンボのように消えていくのに比べれば,いいように思う。
ま,しかし,大事なのは,どうも構成ではなく,
語りの構造,
なのではないかと思う。作者は,語りを,滋賀津彦についての,
「おれは活(い)きた。
闇(くら)い空間は、明りのようなものを漂していた。併し其は、蒼黒い靄の如く、たなびくものであった。
巌ばかりであった。壁も、牀(とこ)も、梁(はり)も、巌であった。自身のからだすらが、既に、巌になって居たのだ。
屋根が壁であった。壁が牀であった。巌ばかり――。触っても触っても、巌ばかりである。手を伸すと、更に堅い巌が、掌に触れた。脚をひろげると、もっと広い磐石(ばんじゃく)の面(おもて)が、感じられた。
纔(わず)かにさす薄光りも、黒い巌石が皆吸いとったように、岩窟(いわむろ)の中に見えるものはなかった。唯けはい――彼の人の探り歩くらしい空気の微動があった。
思い出したぞ。おれが誰だったか、――訣(わか)ったぞ。
おれだ。此おれだ。大津の宮に仕え、飛鳥の宮に呼び戻されたおれ。滋賀津彦(しがつひこ)。其が、おれだったのだ。」
と,郎女についての,
「南家の郎女の神隠しに遭ったのは、其夜であった。家人は、翌朝空が霽れ、山々がなごりなく見えわたる時まで、気がつかずに居た。横佩墻内(よこはきかきつ)に住む限りの者は、男も、女も、上の空になって、洛中洛外を馳はせ求めた。そうした奔(はし)り人(びと)の多く見出される場処と言う場処は、残りなく捜された。春日山の奥へ入ったものは、伊賀境までも踏み込んだ。高円山(たかまどやま)の墓原も、佐紀の沼地・雑木原も、又は、南は山村(やまむら)、北は奈良山、泉川の見える処まで馳せ廻って、戻る者も戻る者も、皆空足からあしを踏んで来た。
姫は、何処をどう歩いたか、覚えがない。唯家を出て、西へ西へと辿たどって来た。降り募るあらしが、姫の衣を濡した。姫は、誰にも教わらないで、裾を脛はぎまであげた。風は、姫の髪を吹き乱した。姫は、いつとなく、髻(もとどり)をとり束ねて、襟から着物の中に、含(くく)み入れた。夜中になって、風雨が止み、星空が出た。
姫の行くてには常に、二つの峰の並んだ山の立ち姿がはっきりと聳(そび)えて居た。毛孔(けあな)の竪(た)つような畏(おそろ)しい声を、度々聞いた。ある時は、鳥の音であった。其後、頻(しき)りなく断続したのは、山の獣の叫び声であった。大和の内も、都に遠い広瀬・葛城あたりには、人居などは、ほんの忘れ残りのように、山陰などにあるだけで、あとは曠野(あらの)。それに――本村(ほんむら)を遠く離れた、時はずれの、人棲(すま)ぬ田居(たい)ばかりである。」
と,大伴家持についての,
「兵部大輔(ひょうぶたいふ)大伴家持は、偶然この噂を、極めて早く耳にした。ちょうど、春分から二日目の朝、朱雀大路を南へ、馬をやって居た。二人ばかりの資人(とねり)が徒歩(かち)で、驚くほどに足早について行く。此は、晋唐の新しい文学の影響を、受け過ぎるほど享(う)け入れた文人かたぎの彼には、数年来珍しくもなくなった癖である。こうして、何処まで行くのだろう。唯、朱雀の並み木の柳の花がほほけて、霞のように飛んで居る。向うには、低い山と、細長い野が、のどかに陽炎かげろうばかりである。資人の一人が、とっとと追いついて来たと思うと、主人の鞍に顔をおしつける様にして、新しい耳を聞かした。今行きすごうた知り人の口から、聞いたばかりの噂である。
それで、何か――。娘御の行くえは知れた、と言うのか。
はい……。いいえ。何分、その男がとり急いで居りまして。
この間抜け。話はもっと上手に聴くものだ。
柔らかく叱った。そこへ今も一人の伴(とも)が、追いついて来た。息をきらしている。」
という語りを並行させている。それぞれを並べ替えたと解説の言う,
「時間の経過通りに進行していた物語をいったんばらばらに切り離して,あらためて映画のモンタージュのように自由につなぎ合わせたのだ。物語を流れる時間は錯綜し,物語の筋は混乱する。その結果,作品は謎に満ち,複雑な陰影をもつことになった。」
とあるのは,推測だが,こうした語りの対象をつなぎかえた,ということだ。しかし,これは,作家の仕事というより,学者が,素材(あるいは伝承の資料)を,矯めつ眇めつして,並べ替えている作業のように見える。
それは,作家自身の博識の広がりの中,いくつものイメージを重ねて,読み手をその広大な奥行へといざなう。しかし,それは,作家のそれだろうか。むしろ,折口自身が,おのが掌にある世界を,カードのように並べて見せているだけだ。
作品は,語りである。能において,シテが演じるさまざまなものを,ワキは,目撃者として,あるいは,語り手として,語る。そのとき,語りは二重になる。シテは,ワキから見た時,語られているものであると同時に,語る者でもあり,その語りは,幾重にも,重ねられていくことができる。時間軸を重ねることで,幾重にもときとところは,重なり合い,混淆しあって,幻想の世界の奥行になる。
僭越ながら,語りとして言うなら,郎女に語りかける姥の語り,
「郎女は、御存じおざるまい。でも、聴いて見る気はおありかえ。お生れなさらぬ前の世からのことを。それを知った姥でおざるがや。
一旦、口がほぐれると、老女は止めどなく、喋しゃべり出した。姫は、この姥(うば)の顔に見知りのある気のした訣(わけ)を、悟りはじめて居た。藤原南家にも、常々、此年よりとおなじような媼(おむな)が、出入りして居た。郎女たちの居る女部屋までも、何時もずかずか這入って来て、憚(はばか)りなく古物語りを語った、あの中臣志斐媼(なかとみのしいのおむな)――。あれと、おなじ表情をして居る。其も、尤(もっとも)であった。志斐老女が、藤氏とうしの語部の一人であるように、此も亦、この当麻(たぎま)の村の旧族、当麻真人の「氏の語部」、亡び残りの一人であったのである。」
で始まり,
「藤原のお家が、今は、四筋に分れて居りまする。じゃが、大織冠(たいしょくかん)さまの代どころでは、ありは致しませぬ。淡海公の時も、まだ一流れのお家でおざりました。併し其頃やはり、藤原は、中臣と二つの筋に岐(わか)れました。中臣の氏人で、藤原の里に栄えられたのが、藤原と、家名の申され初めでおざりました。
藤原のお流れ。今ゆく先も、公家摂籙(くげしょうろく)の家柄。中臣の筋や、おん神仕え。差別(けじめ)差別(けじめ)明らかに、御代御代(みよみよ)の宮守(みやまもり)。じゃが、今は今、昔は昔でおざります。藤原の遠つ祖(おや)、中臣の氏の神、天押雲根(あめのおしくもね)と申されるお方の事は、お聞き及びかえ。」
という語りこそ,能のワキに近い,語り手ではないのか。だから,語りの構造から言えば,「死者の書」は,
「郎女さま。
緘黙(しじま)を破って、却(かえっ)てもの寂しい、乾声(からごえ)が響いた。
郎女は、御存じおざるまい。でも、聴いて見る気はおありかえ。お生れなさらぬ前の世からのことを。それを知った姥でおざるがや。」
という姥の語りから始まってもいいのだ,とすら思う。僕は,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic2-2.htm
で書いた中上建次の『千年の愉楽』のオリュウノオバの語りを,あるいは,『奇蹟』の語りを思い描いている。
「どこから見ても巨大な魚の上顎の部分の見えた。その湾に向かって広がったチガヤやハマボウフウの草叢の中を背を丸めて歩いていくと、いつも妙な悲しみに襲われる。トモノオジはその妙な悲しみが、巨大な魚の上顎に打ち当たる潮音に由来するのだと信じ、両手で耳を塞ぐのだった。指に擦り傷や斬り傷がついているせいか、齢を取って自然にまがり節くれだったためか、それとも端から両の手で両の耳を完全に塞ぐのをあきらめてそうなったのか、指と指の隙間から漏れ聴こえる潮音はいっそう響き籠り、トモノオジの妙な悲しみはいや増しに増す。
トモノオジは体に広がる悲しみを、幻覚の種のようなものだと思っていた。日が魚の上顎の先にある岩に当たり水晶のように光らせる頃から、湾面が葡萄の汁をたらしたように染まる夕暮れまで、ほとんど日がな一日、震えながら幻覚の中にいた。幻覚があらわれ、ある時ふと正気にもどり、また幻覚に身も心も吸い込まれてゆく。」
こう語り始められたとき、語り手が向き合っている(語ろうとしている)のは、現のトモノオジかトモノオジの思い出か、あるいはトモノオジの幻想のはずである。
現と幻とかが交錯させるには,語り手をぼかさなくてはならない。作家の知識もいらない。作品自体が,
幻想化,
するとは,幻想を語ることではなく,語りそのものが幻想化することでなくてはならない。それは,語り手自体を,現ともゆめともわからぬものにしていく必要がある。究極イメージしているのは,古井由吉の『眉雨』の語りである。
たとえば、次のような、時枝誠記氏の風呂敷構造の日本語の,「詞」と「辞」になぞらえるなら
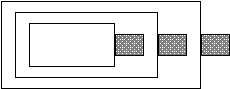
辞をもたない語り,零記号化した語りの入子を重ねた語りならどうか。そこには語っている“いま”も
“ここ”もない,幻想も現実も区別する指標はない。「誰がしゃべっているのか。(中略)ディスクールが、というよりも、言語活動が語っている」(バルト)ことになる,そういう語りである。時枝誠記説の,日本語の風呂敷構造では,
辞において初めて、そこで語られていることと話者との関係が明示されることになる。
第一に、辞によって、話者の主体的立場が表現される。
第二に、辞によって、語っている〃とき〃が示される。
第三に、辞の〃とき〃にある話者は、詞を語るとき、一旦詞の“とき”と“ところ”に観念的に移動して、それを現前化させ、それを入子として辞によって包みこんでいる。
辞において,語られていることとの時間的隔たりが示されるが,語られている“とき”においては、“そのとき”ではなく、“いま”としてそれを見ていることを,“いま”語っていることになる。零記号化するとは,その“いま”が消されることで,時間は無限に重ねられ,いつともどことも辿れない中を漂う。
そういう語りこそ,死者の書にふさわしい語りなのではないか。そのとき,もはやワキすらいない。いきなり,幻想そのものが,幾重にも語り重ねられていく。
参考文献;
折口信夫『死者の書・口ぶえ』(岩波文庫)
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0924.htm
http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm
http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-3.htm
時枝誠記『日本文法 口語篇』(岩波全書 |
|
ソフト・テクノロジー |
|
D・A.・ノーマン『人を賢くする道具―ソフト・テクノロジーの心理学』を読む。

原題は,
Things That Make Us Smart;Defending Human
Attriyutes in the Age of the Machine
である。著者は,「日本語版の読者へ」で,
「今日の問題は,テクノロジーのデザインを技術信奉者に任せきりにしてきた点にある。今こそ,日常を生きている人間の側が,コントロールの主体となるべき時である。目標は高いところにある。すなわち,我々が,我々の生み出した機械仕掛けのあるいは電子式の道具とより調和のとれたやり取りができるようになること,である。機械が,人間のニーズに自らを適応させなければならない。今はまだ,人間の側が,機械の気まぐれにつきあわなければせならないことがあまりにも多すぎるのである。」
と述べる。つまり,それは,「まえがき」で述べることにつながっていく。
「我々の社会では,人の生き方に対して機械中心の態度を知らず知らずのうちにとるようになってしまった。人間側よりテクノロジー側の要求に重点をおき,われわれの方が機械のサポート役となることを強いる。これは人間が最も不得意としていることだ。さらに悪いことに,機械中心の見方では,人間は機械と比べて,精密さや繰り返しや正確さが必要な行動が苦手な欠陥品ということになる。こういうことはよく言われるし,社会にも広まっているが,それは人間に対する最も不適切な見方である。」
だから,
「今はわれわれがテクノロジーに仕えてしまっている。われわれは機械中心の見方を覆し,人間中心の見方に変えなければいけない。テクノロジーがわれわれに仕えるべきなのである。これは,テクノロジーの問題であると同時に社会の問題でもある。」
と。これは,一度大学を辞めてコンピュータ業界に入った著者ならではの,
「何よりもわれわれの社会構造こそが,テクノロジーの進む方向と生活へのインパクトの両方を決めている」
という問題意識で,単なる反科学技術としてではなく,
「テクノロジーと人間との関わりを社会問題として捉えなければならない」
という考えに基づく。サブタイトルとなっている,
ソフト・テクノロジー,
とは,ハード・テクノロジーと対比させて使われている。
「精密で正確な測定に頼る科学を『ハード』サイエンスと呼ぼう。観察や分類,主観的による測定や評価に頼らなければならない科学を『ソフト』サイエンスと呼ぼう。そしてこの二つの科学の上に築かれ,これらを活かすテクノロジーをそれぞれハード・テクノロジー,ソフト・テクノロジーと呼ぼう。さて,ハード・サイエンスやハード・テクノロジーは,それ自体が悪いわけではない。問題は,それが置き去りにするものの中にある。ハード・サイエンスは,測定できるものだけを測定し他を無視する。ソフト・サイエンスはこうした忘れ去られている部分を救おうとする。」
今日起こっているのは,
「テクノロジー…が,生活のある一面を意図的に重視し他の面を無視する考え方をもたらす。重視するかどうかはその真の重要性によるのではなく,今日のツールで科学的,客観的に測定できるかどうかという恣意的な条件によるのである。」
ということによる偏りである。これでは,「人を賢くする」道具になりきっていない,というわけである。機械の機能で,人間の機能を測るというのは本末転倒だが,しかし,多く,機械に慣れているか(機械に適合しているか)どうかで,人を測っている。機械をコンピュータに置き換えれば,そういう評価の仕方を当たり前にしている。しかし,それは機械基準で考えているのであって,人のもつ能力を活かしたり,伸ばしたりするように,機能しようとしていない。それでそれでいいのか,そういう社会のあり方でいいのか,という問いが,著者の問題意識であり,本書を貫くテーマである。
著者は,人の認知を,
体験的認知(experimental cognition),
と
内省的認知(reflective cognition)
の二つに分けて考える。
「体験モードにおいて,我々は特別な努力なしに効率良く周囲の出来事を知覚したりそれに反応したりできるようになる。これはエキスパートの行動モードであり,効率的行動のキーとなる要素である。内省モードは比較対照や思考,意思決定のモードである。このモードにより新しいアイデア,新たな行動がもたらされる。それぞれのモードはどちらも人間の行動には重要なものであるが,まったく異なったテクノロジーの支援を必要とするのである。人間の知覚と認知に結びついたこれらのモードの違いに対する十分な理解なしには,テクノロジーに手綱をつけること,つまり製品を人間に適合させることは不可能なのである。」
しかし,現状,どちらかというと,体験モードに偏っている,と著者は見る。
「テレビや他の娯楽メディアの価値に関する意見の対立はこれらの二種類の認知の性質を混同することから起こっている。現在の多くの機械とその使い方がうまくいっていないのは,体験的状況に対して内省のためのツールを,内省的状況に対して体験ツールを与えてしまっていることによる。」
と。確かに,ゲーム感覚で学ぶ等々という体験型のツールは増えている。体験を入口にして誘おうとする傾向は強まっている。まさに,器械に使われている。体験モードは,
「新しい体験を得ることができても,人間がものごとを理解するうえでの新しいアイデア,新しいコンセプト,進歩をもたらすことはできない―そうするためには内省が必要なのである。」
今日,それが使えてもそれ自体がブラックボックスになっているモノが圧倒的に増えている。それは,あるいは人間の退化なのかもしれない。ふと,
「学びて思わざれぱ則ち罔(くら)く,思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し」
という孔子の言葉を思い出した。体験と内省は,両輪である。
(メタ化かしなければ)体験しただけでは,自分のスキル,ノウハウにはならない,
というのも同趣旨である。そのためのツールがなにほどあるのか,という著者の問いは,20年以上前なのに,未だ生きていると思う。
参考文献;
D・A.・ノーマン『人を賢くする道具―ソフト・テクノロジーの心理学』(新曜社認知科学選書) |
|
列伝 |
|
司馬遷『史記列伝』を読む。
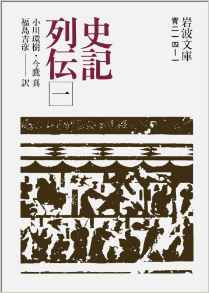
本書は,司馬遷が『史記』において創始した歴史叙述の一形式,紀伝体の,
列伝,
の訳である。『史記』は,
中国の二十四史の一つ,黄帝から前漢武帝までの二千数百年にわたる通史,
であるが,紀伝体は,班固の『漢書』以降の歴代の正史はみなこの形式を踏襲する,とされる。『史記』は,
本記12巻,
世家 30巻,
表 10巻,
書8巻,
列伝 70巻,
からなる。本記,世家は,『春秋』『左伝』に倣う部分があるが,年表,『列伝』は,司馬遷が創り出した。ちなみに,我が国の『日本書記』も,『日本書』か『日本書紀』かの論争はあるが,
『日本書紀』は「紀」にあたる,
ので,紀伝体全体の,『日本紀』の部分のみ,つまり未完,とされる説もある。
列伝とは,
人々の伝記を連ね記したもの,
だが,訳者(小川環樹)は,「伝」について,
「『伝』という語の本来の意味は広義の伝承であり,経書の注釈などが『伝』とよばれるのも,師から門人(たぶん口づたえ)次つぎに語りつがれたからであろう。司馬遷がただ『伝』とは言わず『列伝』の名称をことさら選んだ理由は,いくつかの解釈があるが,私の臆説を言えば,かれはある個人の性格やその一生を叙述することに特別の意義を見出したからであって,単に伝承されたことを転述するのではないと考えたからであろうと考えられる。そうでなければ,『商君列伝』その他ただ一人のことをしるしながら『列伝』というのは奇異である。」
と書く。
それにしても,列伝記載中,生をまっとうしたものは数えるほどしかいない。暗殺されるか,処刑されるか,牢死するか,自決するか,いずれも王や競争相手によって振り回されていく。いやいや王自体が,秦の二世,三世皇帝のように,佞臣に追い詰められていく。斯く言う,司馬遷自身が,匈奴に降伏した李陵を擁護して,武帝の怒りを買い,宮刑(腐刑)という屈辱を味あわされた。
本書の中で,列伝と言いつつ,
ただ一人だけを叙述,
する場合と,
数人併せて一群の伝記,
とする場合があり,後者は,
合伝,
と呼ばれる,「長耳・陳余列伝」のような組み合わせたものと,さらに,
雑伝,
と呼ばれる。テーマで寄せ集めた,例えば,循良な官吏の,
循吏列伝,
漢代儒者の,
儒林列伝,
孔子の高弟七十数人の,
仲尼弟子列伝,
等々がある。訳者の言うように,
「雑伝の中に司馬遷の独特の歴史観または人間観をあらわすものがある。」
ので,たとえば,
刺客列伝,
の,秦王政(始皇帝)の暗殺をねらった荊軻の,有名な,
風蕭々とふきて易水寒(つめ)く
壮士一たび去(ゆ)かば復(ふたた)び還(かえ)らず
歌う場面は印象深いが,秦王暗殺の場面は詳細を究める。そのことについて,司馬遷は,「太史公曰く」として,
「世間では,荊軻といえば,太子丹の運のこと,つまり『天が穀物を雨とふらせた,馬に角がはえた』などの話をひきあいに出す。それは度がすぎる。また『荊軻は秦王に負傷させた』とも言う。すべて正しくない。ずっと以前公孫季功(こうそんきこう)と董生(とうせい)は,夏無且(かぶしょ 御典医。その場に居合わせて薬箱を荊軻に投げつけ,秦王を助けようとした)とつきあったことがあり,彼の事件をくわしく聞き知っていた。わたくしのために話してくれたのが,以上の如くなのである。」
と書く。秦から前漢へと,秦滅亡後,高祖,恵帝,文帝,景帝を経て,武帝の世となっても,見聞の実話が残っている,そういうリアリティを感じさせる。
あるいは,「游侠列伝」も,こういう史書には珍しい。太史公自序は言う。
「苦難にある人を救い出し,金品に困っている人を援助することでは,仁者も学ぶ点があり,信頼を裏ぎらず,約束にそむかないということでは,義人も見習う点があろう。ゆえに游侠列伝第六十四を作る」
と。冒頭に,司馬遷はこう書きだす。
「韓非子は述べている。
『儒は,文の知識によって法律を乱し,そして侠は,部の暴力を用いて禁令を破る』と。」
そして,游侠について,
「游侠とは,その行為が世の正義と一致しないことはあるが,しかし言ったことはぜったいに守り,なそうとしたことはぜったにやりとげ,いったんひきうけたことはぜったいに実行し,自分の身を投げうって,他人の苦難のために奔走し,存と亡,死と生の境目にわたったあとでも,おのれの能力におごらず,おのれの徳行を自慢することを恥とする,そういった重んずべきところを有しているものである。」
と書く。さらに,
「古(いにし)えの游侠については,なにも(伝わらず)知るすべはない。
近世では,延陵(の季子)や孟嘗君・春申君・平原君・信陵君たちは,いずれも国王の親族で,領地をもち大臣の位をもって裕福であったため,天下の人材を招き集め,その名声は諸侯の間にも鳴りひびいていた。かれらも,すぐれていない,とは評することのできない人たちであった。しかしかれらは,たとえば追い風にのって叫びをあげたようなものであって,その声そのものが速さを増したわけではなく,(声を運んだ)風(財産や地位)の勢いがはげしかったのである。
ところが,民間の裏町に住む侠客について言えば,おのれの行いをまっすぐにし,名誉を重んじた結果,評判は天下にひろがり,りっぱだとほめない者とてなかった。これこそ困難なのだ。それなのに,儒家も墨家もどちらも游侠を排斥し棄てさって,かれらの書物に記しとどめはしなかった。秦より前の時代では,民間独行の游侠の事蹟は埋没して伝わっていない。わたしはそのことをきわめて残念に思う。」
とまで書く。あるいは「貨殖列伝」では,おのれの才覚で巨大な富を築いた庶民を書く。太史公自序に,
「官位をもたない全くの平民でも,政治の害にはならず,人びとの活動をさまたげることもなくて,うまい時機を見はからい物の売買をし,それでもって富をふやす。知あるひとは,そこから得るところがあるだろう。ゆえに貨殖列伝第六十九を作る。」
と。
「雑伝の多くは,後世の歴史家といえども,取り上げない人物を主人公とする。」
訳者は,司馬遷の思いをこう仮託する。
「四十八歳で宮刑を受け,不具者とされて以後,かれが歩いた人生の裏側が顔を出しているのだとも言える。かれは否応なしに正字の世界の裏面を考えさせられた。そのことが皮肉な形で,通常は高く評価されない人びとの伝記をも作ることを可能にしたのであった。」
司馬遷の知識の深さ,見識の広さ,と同時に,対象とする歴史を俯瞰しようとする問題意識に,ただ圧倒される。しかも,列伝中の人々の,歴史に振り回され滅びていく悲劇の描写は,生き生きとしているのである。
参考文献;
小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳『史記列伝』(岩波文庫)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E9%81%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%8A%E8%BB%BB |
|
マネジメント |
|
佐々木圭吾『みんなの経営学―使える実戦教養講座』を読む。
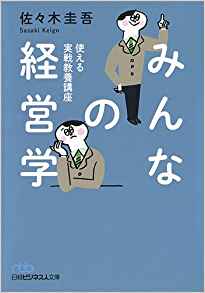
本書の「まえがき」で,著者は,ドラッカーの,
「マネジメントとは,伝統的な意味における一般教養である。」
を引く。経営学があって,企業経営があるのではなく,企業経営という現実があって,経営学がある。経営学は,だから,後追いでしかない。過去の知恵と知識と経験を整理したものだ。ドラッカーの意味は,そういうことではないか,と僕は思う。僭越ながら,歴史学に近い。しかし過去から学ばないものは,何度でも同じ轍を踏むことになる。そういう意味でも,教養である。だから,未来については,教養として以上の役には立たない。
マネジメントのマネージとは,
何とかすること,
であるが,それは,むろん,精神論でも,努力論でも,行動論でもない。いかに,
(誰でも,いつでも,どこでも,何とかできる)仕組み,
をつくるか,ではないか。著者は,「部下が言うことを聞かない」という愚痴を言う上司について,
「直接動かすことのできない他人をいかに動かすか(動いてもらうか)が,マネジメントを考える際の最重要ポイントになります。」
と言っているのは,そういう意味でなくてはならない。だから,
個々の能力発揮の有無,
個々のやる気の有無,
個々のコミュニケーションの是非,
という個人レベルのことを言っているのは,マネジメントではない。
どういう仕組みにすれば,
能力を発揮しやすくなるか,やる気を高めてくれるか,コミュニケーションの齟齬を生まないか,を考えることが,マネジメントでなくてはならない。それは,
仕組み,
や
仕掛け,
や
システム,
を考えることに他ならない。バーナードが,
「権限が委譲されるなんてフィクション(作り話)で,権限が部下によって受容されて初めて成り立つものだ」
というのは,上司と部下の個々人の意思や関係性を言っているのではない。それもまた,
仕組み,
の観点から考えなくては,意味がない。
成果主義,
は,結局業績というカネの面だけで「働き方」の仕組みを作ることで,組織としての仕組みをシンプルにした。しかし,それだけで「働く」仕組みが成り立っていたわけではないために,マイナスだけが目立つ。僕には,マネジメントの,手抜き,怠慢にしか見えない。目に見えるところだけで測るなら,そこだけにしか注力しなくなる。その付けは,マネジメントにとって小さくないはずである。
著者は,フェッファーとサットンの,イノベーティブな企業かどうかの,キークエスチョン,
「失敗した人はどうなりましたか?」
を紹介している。それに対して,
「周囲に失敗した人がたくさんいますよ」
「このヒット商品は大失敗に続く三度目の正直だったんです」
という答えが返ってくるヒット商品連発の企業を挙げ,
「失敗する確率が高い挑戦を自発的に行っていく意欲を高めるためには,組織的な『支え』が必要ではないでしょうか」
と言っているが,この「支え」こそがまさに,
仕組み,
であり,それがトップマターであること,つまり,
マネジメントそのもの,
であることは明白である。あるいは,リーダーシップ(本書でも,リーダー論とリーダーシップ論を混同しているのは気になるが)についても,著者は,
ピーターの法則,
を挙げる。つまり,
人は無能と呼ばれるまで出世する,
である。つまり,その職位に求められる成績を上げられなくなるまでは,出世する,ということだ。これも,実は,
仕組み,
そのものでしかない。当該職位での成績を基に昇進させていく,という仕組みの結果である。それは,育成と評価の仕組みそのものの結果でしかない。
バーナードは,組織が生成・存続していくための要因を,
協働意志,
共通目的,
コミュニケーション,
を挙げたが,目的があって,協働意志とコミュニケーションが必要となる。つまり,
共通目的,
があってこそである。とすると,組織の問題が生まれた時,
「組織的視点を持った人は,組織の具合がおかしくなったとき,『犯人捜し』ではなく,…『やる気はあるのか(協働意志)』『全員が目的を理解し納得しているのか(共通目的)』『メンバー全員のコミュニケーションがとれているか(コミュニケーション)』といった眼鏡で組織を見直す…。」
と著者は書くが,それはマネジメントの視点ではない。僭越ながら,それは傍観者視点である。マネジメントの当事者なら,
やる気があるか,
ではなく,
やる気を高める仕組みはきちんとあるのか(あるいはそれが機能しているのか),
でなくてはならないし,
目的を理解し納得しているか,
ではなく,
目的を理解し納得させる仕掛けはあるのか(あるいはそれが機能しているのか),
でなくてはならないし,
コミュニケーションはとれているか,
ではなく,
コミュニケーションがとれる仕組みはあるのか(あるいはそれが機能しているのか),
でなくてはならない。この発想こそが,
マネジメントは仕組みを考えること,
の肝のはずである。
バーナードが,組織が生き延びるには,有効性と能率が必要であり,それには,
「組織メンバーが従うべき規範や価値基準である道徳準則を創造する必要があり,道徳準則の創造こそが経営者のやそくわりである」
と言っているのは,「経営準則」つま経営ビジョンという目的が明確になってこそ,そのためにどうメンバーのやる気を高め,コミュニケーションが取れるようにするか,というその仕組みを考えていくことになる。まさにそこにこそマネジメントそのものの背骨があるからにほかならない。
参考文献;
佐々木圭吾『みんなの経営学―使える実戦教養講座』(日本経済新聞出版社) |
|
中島敦 |
|
中島敦『中島敦全集』を読む。
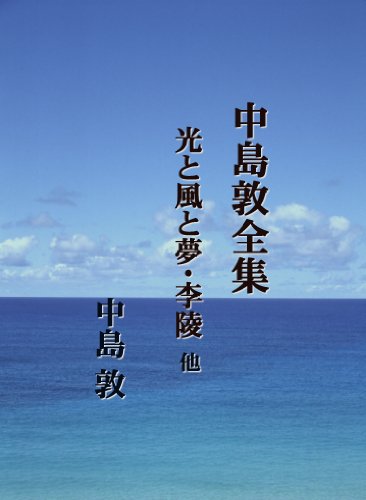
久しぶりに,「李陵」「山月記」を読み直して,改めて,その硬質な文章に感嘆した。若いころ読んだのとは別の感慨もある。本書の中では,『古譚』の,「狐憑」「木乃伊」「山月記」「文字鍋」がいいが,やはり,
「山月記」
が群を抜く。「山月記」の,李徴の語り,
「何故こんな運命になったか判らぬと、先刻は言ったが、しかし、考えように依れば、思い当ることが全然ないでもない。人間であった時、己は努めて人との交を避けた。人々は己を倨傲だ、尊大だといった。実は、それが殆ど羞恥心に近いものであることを、人々は知らなかった。勿論、曾ての郷党の鬼才といわれた自分に、自尊心が無かったとは云わない。しかし、それは臆病な自尊心とでもいうべきものであった。己は詩によって名を成そうと思いながら、進んで師に就いたり、求めて詩友と交って切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって、又、己は俗物の間に伍することも潔しとしなかった。
共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心との所為である。己の珠に非ざることを惧れるが故に敢て刻苦して磨こうともせず、又、己の珠なるべきを半ば信ずるが故に、碌々として瓦に伍することも出来なかった。己は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤悶と慙恚とによって益々己の内なる臆病な自尊心を飼いふとらせる結果になった。人間は誰でも猛獣使であり、その猛獣に当るのが、各人の性情だという。己の場合、この尊大な羞恥心
が猛獣だった。虎だったのだ。」
これを何のメタファと見てもよい。いずれ,この固執は,歳を経て顕在化する。虎になるとは限らない。ある意味で,年を経て図に浮かび上がる部分が違うことに気づく。
「山月記」の
「隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。いくばくもなく官を退いた後は、故山、虢略に帰臥し、人と交を絶って、ひたすら詩作に耽った。下吏となって長く膝を俗悪な大官の前に屈するよりは、
詩家としての名を死後百年に遺そうとしたのである。」
あるいは,
「李陵」の,
「漢の武帝の天漢二年秋九月、騎都尉・李陵は歩卒五千を率い、辺塞遮虜鄣を発して北へ向かった。
阿爾泰山脈の東 南端が戈壁沙漠に没せんとする辺の磽确たる丘陵地帯を縫って北行すること三十日。
朔風は戎衣を吹いて寒く、いかにも万里孤軍来たるの感が深い。漠北・浚稽山の麓に至って軍はようやく止営した。すでに敵匈奴の勢力圏に深く進み入っているのである。」
と,中島に漢文の素養があるせいもあり,その文体の作り出す凛とした雰囲気が,中国に題材を取ったものに合っている。『古俗』の,
「盈虚」の,
「衛の霊公の三十九年と云う年の秋に、太子蒯聵が父の命を受けて斉に使したことがある。途に宋の国を過ぎた時、畑に耕す農夫共が妙な唄を歌うのを聞いた。
既定爾婁豬
盍帰吾艾豭
牝豚はたしかに遣った故
早く牡 豚を返すべし
衛の太子は之を聞くと顔色を変えた。思い当ることがあったのである。」
「牛人」の,
「魯の叔孫豹がまだ若かった頃、乱を避けて一時斉に奔ったことがある。途に魯の北境庚宗の地で一美婦を見た。俄かに懇ろとなり、一夜を共に共に過して、さて翌朝別れて斉に入った。斉に落着き大夫国氏の娘を娶って二児を挙げるに及んで、かつての路傍一夜の契などはすっかり忘れ果ててしまった。」
さらに,「名人伝」。子路を主人公にした,
「弟子」の,
「魯の卞の游侠の徒、仲由、字は子路という者が、近頃賢者の噂も高い学匠・陬人孔丘を辱しめてくれようものと思い立った。似而非賢者何程のことやあらんと、蓬頭突鬢・垂冠・短後の衣という服装で、左手に雄雞、右手に牡豚を引提げ、勢猛に、孔丘が家を指して出掛ける。雞を揺り豚を奮い、嗷しい脣吻の音をもって、儒家の絃歌講誦の声を擾そうというのである。」
もいい。しかし,意外に『南島譚』の「幸福」「夫婦」の,のびやかな作品も,作家の気質に合っているような気がする。『南島』の「幸福」の,
「昔、此の島に一人の極めて哀れな男がいた。年齢を数えるという不自然な習慣が此の辺には無いので、幾歳ということはハッキリ言えないが、余り若くないことだけは確かであった。髪の毛が余り縮れてもおらず、鼻の頭がすっかり潰れてもおらぬので、此の男の醜貌は衆人の顰笑の的となっていた。おまけに脣が薄く、顔色にも見事な黒檀の様な艶が無いことは、此の男の醜さを一層甚だしいものにしていた。此の男は、恐らく、島一番の貧乏人であったろう。」
「夫婦」の,
「今でもパラオ本島、殊にオギワルからガラルドへ掛けての島民で、ギラ・コシサンと其の妻エビルの話を知らない者は無い。ガクラオ部落のギラ・コシサンは大変に大人しい男だった。其の妻のエビルは頗る多情で、部落の誰彼と何時も浮名を流しては夫を悲しませていた。エビルは浮気者だったので、(斯ういう時に「けれども」という接続詞を
使いたがるのは温帯人の論理に過ぎない)又、大の嫉妬家でもあった。己の浮気に夫が当然浮気を以て酬いるであろうことを極度に恐れたのである。」
は,中国素材のものと比較すると,語彙はさほどに違わないが,印象が変わるのは,中国素材の作品は,自分の素養で書いているのに対して,『南島譚』などは,ひとつ立ち位置を挙げて,メタ・メタ・ポジションに立っているからではないか,という気がする。
他方,作家とおぼしい人物主題の,「カメレオン日記」の,
「博物教室から職員室へ引揚げて来る時、途中の廊下で背後から『先生』と呼びとめられた。
振返ると、生徒の一人――
顏は確かに知っているが名前が咄嗟には浮かんで来ない――が私の前に来て、何かよく
聞きとれないことを言いながら、五寸角位の・蓋の無い・菓子箱様のものを差出した。」
や,「斗南先生」の,
「雲海蒼茫 佐渡ノ洲
郎ヲ思ウテ 一日三秋ノ愁
四十九里 風波悪シ
渡ラント欲スレド 妾ガ身自由ナラズ
ははあ、来いとゆたとて行かりょか佐渡へだな、と思った。題を見ると、戯翻竹枝ととある。
それは彼の伯父の詩文集であった。」
や,「虎狩」の,
「私は虎狩の話をしようと思う。虎狩といってもタラスコンの英雄タルタラン氏の獅子狩のようなふざけたものでは
ない。正真正銘の虎狩だ。場所は朝鮮の、しかも京城から二十里位しか隔たっていない山の中、というと、今時そんな所に虎が出て堪るものかと云って笑われそうだが、何しろ今から二十年程前迄は、京城といっても、その近郊東小門外の平山牧場の牛や馬がよく夜中にさらわれて行ったものだ。」
は,ちょうど中国ものと南洋ものとの中間に位置する。作品に対する印象の違いは,作品と作家の向き合い方の差のように思われる。素養で書くというのは,漢文の素養で,自家薬篭中のものの如く書く,ということを意味する。そこに硬質の緊張感はある。それは,あるいは漢文というものの,独特の読み下し文の緊張感に依存する。しかし物語世界との距離は小さい。南洋ものは,ある程度の距離があり,その分余裕というか,ユーモアが出る。中間の「三造」ものや「わたし」ものも,ユーモアはなくはないが,どこか自虐的というか,被虐的な翳がつきまとう。
わずか33歳で亡くなった作家の,これを使い分けて書く,才能に驚く。ふと,発想は,
知識と経験の函数,
という言葉を思いだした。意外と,いいのは,ロバート・ルイス・スティーヴンソンのサモアでの晩年を描いた,
『光と風と夢』
だ。日記による自身の独白と,客観部分とを使い分けながら,二面から
スティーヴンソン像,
を描きだそうとする。それは,「彼」として,
「小説(ロマンス)とはcircumstanceの詩だと、彼は言った。事件(インシデントよりも、それに依って生ずる幾つかの場面の効果を、彼は喜んだのである。ロマンス作家を以て任じていた彼は、(自ら意識すると、せぬとに拘わら
ず)自分の一生を以て、自己の作品中最大のロマスたらしめようとしていた。(そして、実際、それは或る程度迄成功したかに見える。)従って其の主人公たる自己の住む雰囲気は、常に、彼の小説に於ける要求と同じく詩をもったもの、ロマンス的効果に富んだものでなければならなかった。雰囲気描写の大家たる彼は、実生活に於て自分の行動する場面場面が、常に彼の霊妙な描写の筆に値する程のものでなければ我慢がならなかったのである。傍人の眼に苦々しく映ったに違いない・彼の無用の気取(
或いはダンディズム)の正体は、正しく此処にあった。)
の文を地とすることで,「日記」の文が図として浮かび上がる。
「性格的乃至心理的小説と誇称する作品がある。何とうるさいことだ、と私は思う。何の為にこんなに、ごたごたと性格説明や心理説明をやって見せるのだ。性格や心理は、表面に現れた行動によってのみ描くべきではないのか?(中略)
さて、又一方、ゾラ先生の煩瑣なる写実主義、西欧の文壇に横行すと聞く。目にうつる事物を細大洩らさず列記して、以て、自然の真実を写し得たりとなすとか。その陋や、哂うべし。文学とは選択だ。作家の眼とは、選択する眼だ。絶対に現実を描くべしとや?誰か全き現実を捉え得べき。現実は革。作品は靴。靴は革より成ると雖も、しかも単なる革ではないのだ。」
「自己告白が書けぬという事は、人間としての致命的欠陥であるかも知れぬことに思い到った。(それが同時に、作家としての欠陥になるか、どうか、之は私にとって非常にむずかしい問題だ。或る人々にとっては極めて簡単な自明の問題らしいが。)早い話が、俺にデイヴィッド・カパァフィールドが書けるか、どうか、考えて見た。
書けないのだ。何故?俺は、あの偉大にして凡庸なる大作家程、自己の過去の生活に自信が有てないから。単純平明な、あの大家よりも、遥かに深刻な苦悩を越えて来ているとは思いながら、俺は俺の過去に(ということは、現在に、ということにもなるぞ。しっかりしろ!
R・L・S・)自信が無い。幼年少年時代の宗教的な雰囲気。それは大いに書けるし、又書きもした。青年時代の乱痴気騒ぎや、父親との衝突。之も書こうと思えば書ける。むしろ大いに、批評家諸君を悦ばせる程、深刻に。」
「三造」ものは,ひいき目にみても,後世には残らぬが,この作品の持つ厚みは,今日読んでも,新たな驚きがある。ただ,この手法が,好いかどうかは好みが分かれようか。
中島敦については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E6%95%A6
に詳しい。ロバート・ルイス・スティーヴンソンについては,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3
に詳しい。
参考文献;
中島敦『中島敦全集』(Kindle版) |
|
志異 |
|
蒲松齢 『聊斎志異』を読む。
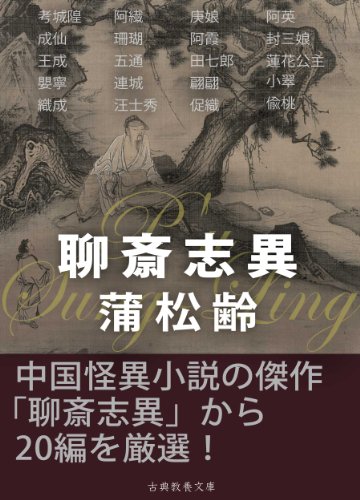
本書は,怪異文学の最高峰と言われる『聊齋志異』の,490余篇に及ぶと言われる作品の中の,21作のみの,いわば,『聊斎志異』の触りにすぎない。ほとんどが,田中貢太郎訳であるが,最後の一作,『石清虚(せきせいきょ)』のみが,国木田独歩の訳である。
作者は蒲松齢,聊齋は作者の号および書斎の名であり,書名の,『聊齋志異』とは,
「聊齋が怪異を記す」
の意味である。
志怪
http://ppnetwork.seesaa.net/article/434978812.html
で触れたように,これも,
志怪小説,
に入る。「志怪」とは,
「怪を志(しる)す」
という意味であり,「志」という字は,
「士印は,進み行く足のかたちが変形したもので,之(いく)と同じ。士女の士(おとこ)ではない。志は『心+音符之』で,心が目標を目指して進み行くこと」
とある。意味には,「しるす」「書き留めた記録」という意味もある。「怪」の字は,
「圣は,『又(て)+土』からなり,手でまるめた土のかたまりのこと。塊と同じ。怪は,それを音符とし,心を添えた字で,丸い頭をして突出したいような感じを与える物のこと」
とある。で,「あやしい」「見馴れない姿をしている」「不思議である」という意味になる。ついでに,
「志異」
の,「異」の字は,
「『大きなざる,または頭+両手を出したからだ』で,一本の手のほか,もう一本別の手をそえて物を持つさま,同一ではなく,別にもう一つとの意。」
とある。だから,「異類」「異端」「異様」等々,
普通とは違った奇妙な事がら,
といった意味になる。「怪異」ともいうので,
志怪,
と,
志異,
との差はないようだが,敢えて差異を言えば,
怪しい,
より,
異なる,
と言うところなのではないか。「志異」と敢えて,言ったのには,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/444432230.html
で触れた「怪奇」とは異なる,という意味が含まれているのか,と想像する。
ここで言う,「小説」は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/432692200.html
で触れたように,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
であり,
「志怪小説、志人小説は、面白い話ではあるが作者の主張は含まれないことが多い。」
とされる。しかし,本書の巻末には,
「鄒濤の『三借廬筆談』によると彼は茶とパイプを傍ら置いて大通りに座し、道を通った者をひき止めては語らって奇異な事柄を収集し、気に入るものがあればそれを粉飾して文にしたという(ただし魯迅はこの話を疑っている)。こうして40歳の時には12巻・490余篇に及ぶ志怪小説『聊斎志異』が完成された。聊斎志異の完成後も蒲松齢は同郷
の王士禎の協力を得て文章の改易を続け、死の直前まで行っていた。 聊斎志異は蒲松齡の死後刊行された。」
とある。「小説」の,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
でいう,稗史とは,
「昔、中国で稗官(はいかん)が民間から集めて記録した小説風の歴史書。また、正史に対して、民間の歴史書。転じて、作り物語。転じて,広く,小説。」
であり,それが転じて、作り物語。転じて,広く,今日言う,虚構としての小説になっていくが,ここに登場するものは,
「面白い話ではあるが作者の主張は含まれないことが多い。」
という結構を保ち,
「内容は神仙、幽霊、妖狐等にまつわる怪異譚で、当時世間に口伝されていたものを収集して小説の形にまとめたものである。」
さて,だから,本書の第一話,
考城隍(こうじょうこう),
は,
「予(聊斎志異の著者、蒲松齢)の姉の夫の祖父に宋公、諱を鎞といった者があった。」
と始る。聞き書きのスタイルを取る。「小説」の結構とは,このことである。
おもしろいのは,第十五話,
促織(そくしょく),
である。「促織」とは,
こおろぎ,
とルビがふられている。
「明の宣 宗の宣徳年間には、宮中で促織あわせの遊戯を盛んにやった」
ので,民間から献上させた。貧しい主人公は,ある知らせで知った場所で,促織を捕まえる。
「それは大きな尾の長い、項(うなじ)の青い、金色の翅をした虫であった。」
しかし,それを息子が誤って殺してしまう。叱られた子供は井戸に落ちるが,意識がもうろうとしている。そんな時,小さな虫を捕まえる。
「それを見ると
促織の上等のものとせられている土狗(どこう)か梅花翅(ばいかし)のようであった。それは首の角ばった長い脛をした 虫」
であったが,小ささいわりに強く、
「宮中に入ると、西方から献上した蝴蝶、蟷螂、油利撻、青糸額などいう有名な促織とそれぞれ闘わしたが、その右に出る者がなかった。そして琴の音色を聞くたびにその調子に従って舞い踊ったので、ますます不思議な虫とせられた。天子は大いに悦ばれて、詔をくだ」
され,献上した撫軍(ぶぐん),邑宰(むらやくにん)を介して,主人公にも巡り巡って恩賞があり,
「数年にならないうちに田が百頃、御殿のような第宅、牛馬羊の家畜も千疋位ずつできた。で、他出する際には衣服や乗物 が旧家の人のよう」
になった。 意識朦朧とした息子は,
「後一年あまりして成の子供の精神が旧のようになったが、自分で、
『私は促織になってすばしこく闘って、捷(か)って今やっと生きかえった。』」
不思議ではあるが,志怪と志異の差は,こんなところにあるのかもしれない。
参考文献;
蒲松齢 『聊斎志異』(Kindle版) |
|
気づきトレーニング |
|
J・オールダム,T・キー,I・Y・スタラック『ゲシュタルト・セラピー−自己への対話』を読む。
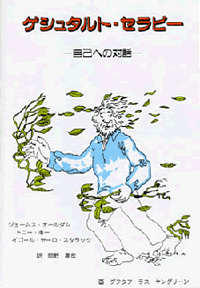
原題は,
Risking Being Alive,
「ゲシュタルト・セラピストによって研究開発された心理学的な道具を紹介する考え方,そして,読み物を集めたものです。」
と「はじめに」に,ある。ゲシュタルト・ツール集なのか,と読み終わって,この一文の存在に気づいた。確かに,全15章の各章ごとに,気づきを確認する「実験」4〜11が設けられ,一人で,あるいはパートナーと,15のテーマについて「気づき」トレーニングの実践をしながら,読み進めていく仕掛けにはなっている。
もちろん,
地と図,
のどこ(何)を図とするかに正解があるわけではない。著者の一人,イゴール(Y・スタラック)は,
「今これを書きながら,『私は今どこにいるのだろう』と自問しています。そして,『私は過程の中にいる』というのが答えです。私の一生が終る日まで,私は過程の中にあるでしょう。今の中に存在し,生きているということがもたらす違いは,はっきり反応することができるということです。」
と書く。
いま・ここ,
にあるとは,そういうことなのだろう。それは,自分が,何を図として見ているか,に気づいていること,でもある。
「『ゲシュタルト』とは,ドイツ語で『かたち,全体のかたち,全体性』を意味する言葉です。(中略)どのような物体,かたち,あるいは形状を認識するば場合でも,まず最初にその物体を周囲から区別するという過程が必要です。つまり,物体は『地』の上に浮かび上がる『図柄』として見られなければなりません。物体に焦点が定められ,『地』との間の境界がはっきりと識別されると,ゲシュタルトが形作られたといわれます。(中略)私たち一人一人は,自分の意識の全体という地の中から,……明確で変化の可能性に富んだ図柄の実体をつくり出す能力を持っているとゲシュタルト・セラピストは考えています。」
この瞬間瞬間の気づきを広げることが,自分自身を理解するよう助ける,とする本書は,
気づきのトレーニング,
の書でもある。気づきの対象は,
外側の領域(感覚的な気づき),
と
内側の領域(感覚的な気づき),
だけではなく,
中間の区域(抽象的な気づき),
にも向けられる。つまり,
思考,夢想,空想,過去の思い出,将来への計画,
等々,多くこうした認知が気づきを妨げる。ゲシュタルト・セラピーの創始者フリッツ・パールズは,
「神経症的な苦しみというのは,想像上の苦しみ,空想上の苦しみです。」
というが,不安,恐れ,怒りの多くは,自分の思いが引き起こす。
「私たちは自らの考えと空想の世界に閉じ込められていると,危険を冒して,実際に起こることを体験しないかぎり,自分が考え出した悲観的な予想を試したり,それが正しくないと説明することができなくなります。」
そして,
「ゲシュタルトの気づきのトレーニングは,私たちがある瞬間に感じることそのものと,外の世界で起こっていることそれ自体に私たちの気づきの焦点を合わせることをうながして,固定化した行動様式を崩すことを目的としています。私たちはある特定の瞬間に自分が誰であるかを見るだけでなく,その瞬間に自分がどのように万物の体系に組み込まれているかをも見なければなりません。このようにして初めて,私たちは自分自身と周りの世界にはっきりと反応することができます。しかし,これには危険が伴い,私たちは自分の行動の責任をとらなければならないのです。」
さらに,
「ゲシュタルト・セラピーでは,『責任』という言葉がしばしば『反応能力』を意味するものとして使われます。
普通,日常用いられる『責任』という言葉には,社会から与えられる道徳的,または倫理的な要求という意味を付近でいます。(中略)こうした一般的な意味では,『責任のある』という言葉は,私たちの自然のままとは関係のない一連の期待に対する反応という意味を含んでいます。それに対して反応できる能力を持つということは,私たちが゛どのように選択するかを選ぶという意味を持っています。(中略)重要なことは,私たちは選択することができる,と認識することなのです。」
気づき,
図柄と図,
責任,
反応する能力,
接触,
三つの回避,
等々,と続く各章の流れは,なかなかよく出来ている。気づきの実験を重ねていくことが,
「私たちの生きる世界全体は絶え間なく変化し,私たちはその変化に遅れないように,意識的に気づきを用いなければなりません。世界がいつも新しいと気がつくことは,心をワクワクさせ,本当の喜びにつながることがありますが,私たちは変化が私たちのためのなるようにしなければなりません。変化から常に自分を守ろうとしてはいけません。私たちが好むと好まざるとにかかわらず,世界は変化し続けているのですから。
変化が私たちの役立つためには,『今,この瞬間』に生きていることができる必要があります。『今,この瞬間』は,他のどの瞬間とも違う時であり,『今,この瞬間』に私たちが話している人は,一瞬前に話していた人とは違うのです。この瞬間に生きるためには,私たちはその時に何が起こっているかを決定しなければなりません。それをするためには,瞬間的に,見,触れ,感じ取る選択の自由をもち,そして,ほんの少し前の過去に見たことの記憶にとらわれないようにしなければならないのです。気づきの実検は,手っ取り早い方法です。」
と,有効なのだ,と。で,
「この瞬間に生きることによって,私たちは自分の運命をコントロールすることになる」
と。ある意味,何気なく流さない,という意識,メタ化を重視するところは,西欧的であるが,どこか禅に通じることを,パールズが(どこかで禅を)けなしていた以上に,強く感じさせられる。
参考文献;
J・オールダム,T・キー,I・Y・スタラック『ゲシュタルト・セラピー−自己への対話』(社会産業教育研究所) |
|
老子 |
|
福永光司訳『老子』を読む。
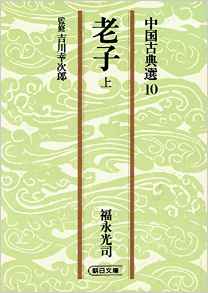
第一章の,
道可道非常道,名可名非熱名,
道の道とす可きは常の道に非ず,名の名とす常の名にあらず,
から,
第八十一章の,
信言不美,美言不信,
信言は美ならず,美言は信ならず,
までの五千余字の老子の思想は,中国思想(だけでなく東洋思想全般)の底流で,広く社会の考え方のみならす,禅にも,毛沢東にも,連綿と通底するものがある。それは,親鸞の「自然(じねん)」にも,道元の「無為」にもつながる,という。訳者は,その無為の思想は,
「(その)無為の政治哲学を法による無為の政治哲学に改編し,絶対権力の座に専制の無為を構想する法家」
と
「『天下を用(も)って為す無し』と揚言する荘子の真人」
とに二分する,という。それは,
法家の法による無為の権力政治,
と
「天下を用って為す無き」真人の道の哲学,
とに分極する。このことは,「徳」の項,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/445836790.html
で,いくらか触れた。『韓非子』に,
「君,其の欲する所を見(しめ)す無かれ。君,其の欲する所を見せば,臣まさに雕琢(ちょうたく)せんとす。」
「其の跡を函掩(おおいかく)し,其の端(きざはし)を匿(かく)せば,下原(たず)ぬる能わず」
とある,『老子』の,
「国の利器は以て人に示すべからず」
という考え方は,法家にこのように引き継がれる。その種は,「無為」とする『老子』にある。
われわれにとっても,『老子』,あるいは道教の影響は深く大きく,たとえば,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/438205191.html
で触れた,
天網恢恢疎にして漏らさず,
というような,言い回しを無意識で耳に覚えているほどに,我々の心に深く浸透している。もとは,
天網恢恢疎にして失わず,
にある。
天の道は,争わずして善く勝ち,言わずして善く応じ,召かずして自ずから来たり,繟然として善く謀る。天網恢恢,疎にして失わず,
に載る。和光同塵は,
和其光,同其塵,
其の光を和らげ,その塵れを同じくす,
である。あるいは,「足るを知る」も,
故知足之足。常足矣。
足るを知るの足るは,常に足る,
と。
『老子』の無為は,
何もしない,という意味ではない。
無為の為,
である。あるいは,
無以為,
以て為す無し,
作為を弄しない,という意である。その背景には,親鸞の言う,
はからい,
を棄てる,ということがある。
皆我を自然と謂う,
とは,その謂いであろう。しかし,『老子』は,
道常無為,而無不為,
道の常は無為にして,而も為さざるは無し,
と転ずる。
上徳は無為にして以て為す無く,下徳は之を為して以て為す有り,
と対比されることで,
無以為,
が何もしないだらけた状態ではないことは明らかである。
「為さざること無き無為」
なのである。といって,凡人によく出来ることではないが。
孔子の,
「之を知るを之を知ると為し,知らざるを知らずと為す,是れ知るなり」
に対比して(随所に対比しているところがあるが),
知不知上,不知知病,夫唯病病,是以不病。
知って知らざるは上なり,知らずして知るは病(へい)なり,夫れ唯病を病とす,是を以って病あらず,
と,
無知の知,
へとシフトさせる。おのれの知っていることなどたかが知れている,という思いである。孔子の,
「『之を知る』をも老子はなおも之を知らざる者として否定することを教える」
と。
其の愚を知る者は大患にあらず,其の惑いを知る者は大惑にあらず(『荘子』),
に通じるようである。
天は道に法(のっと)り,道は自然に法る,
なのである。
なお,老子自身については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E5%AD%90
に詳しい。
参考文献;
福永光司訳注『老子』(朝日文庫) |
|
戦国策 |
|
近藤光男編『戦国策』を読む。
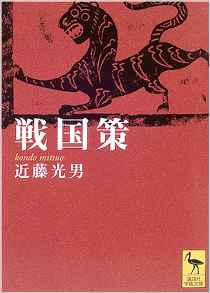
「まえがき」によると,
「前漢末に,学者劉向(りゅうきょう 前七七−前六)が命ぜられて天子の書庫の整理をしたとき,『国策』『国事』『探長』『事語』『長書』『脩書』などという錯乱した竹簡があった。みな戦国のとき(春秋以後の二百四十五年間)の遊説の士が国々の政治への参与を企てて,その国の為に建てた策謀であったので,劉向は国別にしているものに基づいて,それぞれほぼ年代順に整え,重複を刪(けず)り,三三篇として『戦国策』と名づけた。」
と,本書『戦国策』の由来を説明している。本書は,
「三三篇四八六章から,百章を選んで,それを新たに物語りの内容によって類別し」
直したものだ。約五分の一の分量ということになる。それでも,この時代の権謀術策の雰囲気はつかめるが,編者は,こう書いている。
「多く蘇秦・張儀らに託して記述されている権謀術数は,必ずしも歴史的事実を述べているとは限らなくて,むしろ奇知縦横の言論や説得の技法の習練を意とするもののようで,小説的でさえある。」
あるいは,
「『戦国策』に登場する説士(ぜいし)が本当にこれほど活躍したのかどうかは疑わしい。同じような場面での登場人物が異なるからである。」
と。つまりは,縦横家,遊説の士にとっての教科書と見なせばよい。こんな口説の徒に翻弄されるようなアホな君主ばかりではやっておられない。しかし,本書から出ている成語・熟語はかなり多い。ざっと拾ってみる。
「士は己を知る者の為に死し,女(じょ)は己を悦ぶ者のために容(かたちづ)くる」
豫譲は知伯のために,名を変え衆人に成りすまし,趙襄子を刺さんとして失敗て捕らわれるが,一度は豫譲を義士と見なして,趙襄子は解き放つ。再度豫譲は趙襄子を狙うが,また露見し,「臣は,『明主は人の節義を覆い隠すことなく,忠臣は師を惜しまずして名分を成し遂げる』」といい,趙襄子の上着を借りて,これを撃ち,『而(すなわ)ち以て知伯に報ゆべし』といい,自ら剣に伏して死んだ。
「伯楽一顧」
蘇代が自分を売り込むためのたとえ話。駿馬を売ろうとしていたものが,伯楽に頼んで,「馬の周りをぐるっと一回りしながらよく観察し,立ち去り際にふり返ってもらうと,馬の値は一朝にして十倍になった」という喩えをあげて,燕の淳于髠(じゅんうこん)に自分の伯楽になるよう頼む。
「狡兎三窟」
孟嘗君の食客馮諼(ふうけん)が,孟嘗君に説いた説の喩え。「狡兎は三窟有りて,僅かに其の死を免るるのみ。今君は一窟有るのみ。未だ枕を高うして臥するを得ざるなり。請う君のために復た二窟を鑿たん」と建策する。
「遠交近攻」
范雎(はんしょ)が秦王に説いた策。「遠く交わりて近く攻めんには如かず。寸を得れば則ち王の寸なり。尺を得れば亦王の尺なり。今此れを捨てて遠く攻む,亦た繆(あやま)らずや。」
「禍を転じて福と為す」
斉の宣王は燕の喪に乗じて十城を奪った。蘇秦は斉王をいさめた。「聖人の事を制するや,禍を転じて福と為し,敗に因りて功を為す。」城を返せば,燕の先王の義父の秦にとっても,燕の現王からも徳とされる,と。「燕の十城を帰し,辞を低くして以て秦に謝するに如くは莫し。秦王の己の故を以て燕に城を帰すを知らば,秦必ず王を徳とせん。燕故無くして十城を得ば,燕も亦た王を徳とせん。是れ強仇を棄てて厚交を立つるなり。且つ夫れ燕・秦俱に斉に事(つか)えば,則ち大王の号令天下皆従わん。」
「将に之を敗(やぶ)らんと欲せば,必ず姑(しばら)く之を輔(たす)けよ」
この語は「『戦国策』の根本理念のひとつ」であるらしい。『老子』にも似たこ とばで,「将にこれを奪わんと欲せば,必ず固(しばら)く之を与えよ」というのがあるらしい。ここでは,周書に曰くとして,「将に之を敗らんと欲せば,必ず姑く之を輔けよ。将に之を取らんと欲せば,必ず姑く之を与えよ。」という。
「人を使うて能(あた)わざれば,則ち之を不肖と謂う」
人には適材適所。「猿・獮猴(びこう)も,木を錯(お)きて水に拠らば,則ち魚鼈(ぎょべつ)に若かず。険を歴(へ)危うきに乗らば,則ち騏驥(きき)も狐狸に如かじ。」にもかかわらず,「今,人を使うて能(あた)わざれば,則ち之を不肖と謂い,人に教えて能わざれば,則ち之を拙と謂い,拙なれば之を罷(や)め,不肖なれば則ち之を棄て,人をして棄逐(きちく)せらるるあり」と。
「隗より始めよ」
人材を集めたいのであれば,と郭隗が,燕の昭王に説いた。「王誠に士を致さんと欲せば,先ず隗従り始めよ。隗すら且つ事(つか)え見(ら)る。況や於(よ)り賢(まさ)れる者をや。豈(あに)千里を遠しとせんや。」
「蛇足を為す者は終に其の酒を亡う」
蛇足の出処である。これもたとえ話で,楚の将昭陽を戒めたもの。大杯の酒を競うて蛇の絵を早く書き上げたものが飲むことにした。真っ先に描き上げたものは,足を書き足そうとして,その隙に次のものに敗れた。その例えば,連戦連勝している将への戒めである。「今君楚に相として魏を攻め,軍を破り将を殺し,八城を得て兵を弱めず,斉を攻めんと欲す。斉公を畏るること甚だし。公是を以て名と為さば足れり。官の上(かみ)に,重(くわ)う可きに非ざるなり。戦って勝たざる無くして,止まるを知らざる者は,身且(まさ)に死せんとし,爵且に後に帰せんとす。猶蛇足を為すがごときなり」と。
「猶薪(たきぎ)を抱きて火を救うが如し」
これも「喩えば猶薪を抱きて火を救うが如きなり。薪尽きずんば,則ち火止まじ。」と喩えを用いて,魏王を諌止した。
「魚者得て之を幷(あわ)せ禽(とら)う」
いわゆる「漁夫の利」「鷸蚌(いっぼう)の争い」の出処。蘇代が,趙の恵王を戒めた。今燕を攻めれば,秦が漁夫の利を得る,と。
思うに,話のうまさは,例え話と喩え話の挙げ方のうまさ,ということを感じる。ミルトン・エリクソンがよくアネクドート(逸話)やメタファー,たとえ話を使って,勝手にクライエントに考えさせる中で答えを見つけさせていたが,遊説家がしていたこともそれと似ているようだ。
参考文献;
近藤光男編『戦国策』 (講談社学術文庫) |
|
武士道 |
|
三田村鳶魚『武家の生活』を読む。
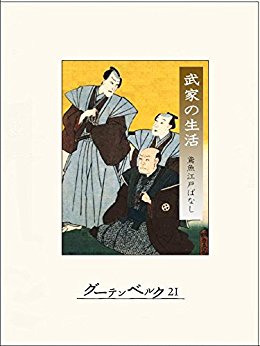
「武士道とはいかなるものか」
と言われれば,
「『それは義理ということだ』と私は思う。これが最も直截簡明だと思うのである。」
と,著者,三田村鳶魚は言い切る。義理については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/441727637.html
で触れたが,本来の意味は,
善悪の心の道筋,
日本でも,
「古くは,物事の正しい筋道の意で,《今昔物語集》や《愚管抄》にその用例が見える。また,文章やことばの〈意味〉という使われ方もあった。中世末期の《日葡辞書》には,すでに,〈良い道理〉とともに〈礼儀正しさ,律義さ〉という意味があげられているが,この言葉が,対人関係上,守り実践しなければならない道義をさすものとして特に重んじられるようになるのは,近世社会においてである。近世初めの儒者林羅山は,〈人ノ心ノ公平正大ニシテ,毛ノサキホドモ人欲ノ私ヲマジヘズシテ,義理ヲ義トスルハ,義ゾ〉(《春鑑抄》)といい,〈義理〉を儒教の〈義〉と結びつけ,世俗的な人間関係における絶対的な道義とした。」(『世界大百科事典
第2版』)
とあり,それが,「義理を欠く」という意味に変って,
「村社会における相互関係を維持するために定められた行為。この義理を欠く者は,村八分という制裁を受けることもあった。親戚の間で果されるものと,村社会に対して果さなければならないものとに大別される。」(『ブリタニカ国際大百科事典』)
ということになる。ほぼ,個人から見れば,しがらみ,と同じに変わった。
著者は,武士道について,
「戦国時代の末期における、軍書・戦記・随筆などの中には、『武辺吟味』とか、少し遅れて『男の道』というような
言葉が散見されるが、『武士道』なる言葉は全く見当らない。仁斎・闇斎時代にも、まだ『武士道』なる成語は生れて
いなかった。室鳩巣が赤穂浪士の快挙を初めて執筆したが、鳩巣も、赤穂浪士のことを『義人』と呼び、その著書の標題を、『義人録』と命名した。武士道という言葉は用いていない。一般がボツボツと『武士道』という言葉を用いだしたのは、元禄以後であって、普遍的に『武士道』という言葉が一般の用語として認められだしたのは、享保以後のことである。」
と書く。それは,武士がただ農工商のうえに乗っかって惰眠をむさぼり,経済的に困窮化し始めた時期と重なる。たぶんに,自己弁護,自己正当化として,武士道を言い立てているように見える。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163232.html
でも取り上げたが,氏家幹人は,
「戦乱の世が終わり,武将が大名に昇華して,徳川体制に組み込まれた。その過程で,戦士の作法であった男道はすたれ,治者あるいは役人の心得である武士道へと様変わりする。爾来,武士は総じて非武闘化し,代わって,武家屋敷側が傭兵のように雇った,供回り,駕籠かきに委託した。次第に彼らは武士を軽視し,武家も彼らの命知らずの行動に危機感を抱きながら,ある種賞嘆の感情を抱くようになる。」
ここで言う,「男だて」の「男」とは,「士」のことである。いつの間にか,その男立が,ヤクザもどきの方に転移し,滑稽なことに,その堕落した武士に変わって,馬鹿な男伊達を競う連中の侠気を,侍が真似る,という事態にいたる。
幕末の開明的官僚,川路左衛門尉聖謨は,こう日記に書いている。
「一体無宿又は非人等関東の博徒は可惜(おしむべき)もの多,上(かみ)かたの盗賊は,死するといふことはしりながら網のかかるまで先(まず)甘美軽暖の事によを過すか,百年生て乞人たらむよりは盗人と成てわかくして被殺(ころさる)かましといふかこときもの共にて,入墨後の盗なと少しもおしつつますみないふ也,死をみる如帰(きするがごとく)に人とは不思議也。」
鳶魚も,武士道の謂れについて,
「戦国末期の『武辺吟味』というのは、弓馬・剣槍、あるいは鉄砲等の武器に関することで、主として戦場における働き、すなわち、軍事上における働きの場合に用いられたものであって、今日いうところの武士道ではなく、むしろ、
兵書・兵学に属するものであった。吟味は今でいう研究という言葉に相応するものだ。それよりも、『男の道』の方が『武士道』には近い。『そうしては男の道が立たない』というようなことは、『武士道が立たない』というのと同一の意味で用いられた言葉だ。故に、もし『武士道』なるものの語原的詮索をするとしたならば、武士道の母胎は『男の道』であって、これから、武士道なる言葉が転化し発生
したもの だ、ということが出来る。」
男立が,いまや侠気にしか使われないのなら,
「武士が単なる偶像化されたる『人間の見本』であったり、あるいは、『人間の理想化』であっては、『武士道』甚だ愚なるものである。」
と鳶魚も断定する。そして,
「古歌にこうしたものがある。
船の道 船の道とて道もなし船 ゆく道が船の道 なり
ひきよせて結べ ば草の庵 にてほどけ ばもとの野原なりけり
ひきよせて結べ ば草の庵 にてとかね どもとの野原なりけり
実に味わうべき意味深い歌である。
武士道詮索も、まずこの『道』より出発しなければいけない。そして、武士道
というその道も、結局この古歌のごときであると、私は断じたい。武士道という道はない。しかし武士道は厳存する。(中略)『道』とは、『万人が踏んでゆくところの道』であらねばならない。武士道もまたしかりである。武士道という道があって武士道が生じたものではない。武士道もまた、この道路のごとき、あるいは『船の道』『草の庵』の古歌
のごときものである。」
と。だから,武士道とは,
義理,
すなわち,
善悪の心の道筋,
なのであろう。
では,本来の武士の道とはどんなものだったのか。鳶魚は,
戦国時代と戦国以後,
戦国以後でも、直後から江戸の初期 に至る間と、後期 ,
と分けて,武士道の変遷を書く。戦国時代は,
「屍山血河の中に生れ、そこに育ち、そこで成長した。故に、絶えず心に不安があった。(中略)戦国時代の武士道は、
禅味を帯びていた。宗教心が強く、彼等を支配した。生きるも死ぬるも義理からであり、武士を捨てれば生きていられないというように 宗教
的であった。それが戦国武士の武士道であり、信念であった。」
戦国時代以後、徳川の初期時代においても,この武士道信念は,伝統的に当時の武士の心理を支配したが,江戸時代、殊に中期より後期にかけては、平和時代がずっと打ち続いたために,
「刀は鞘に納まった。武張ったことよりも、人心は享楽を追うことに忙しくなった。尚武の気風は衰えて、元禄時代の華美な世界が展開され、両刀は武士の表道具にほかならなかった。実に泰平の謳歌時代である。故に、武士道でも、『武士なるが故に武士道を立てる』、あるいは伝統的にこれを墨守するというようになった。すなわち、よくいうところの『
刀の手前』であった。『刀の手前、武士道 が相立たぬ』というようになった。更に換言すれば、『武士としての栄誉のため に』であった。」
と変る。つまり,
「全く武士という名のために、看板のために、武士道というものが必要であり、その必要から強調された。そこに戦国時代と江戸時代との
間に、深い溝渠がある。」
最早,ただの看板,武士の自己正当化のために必要な道具に変わった,ということになる。本来の,義理,つまり武士道の例を,鳶魚は一杯あげているが,一例は,
「戸次紹運という九州豪傑が、名嶋の城にいて、薩摩の兵を受けたことがあります。その時に紹運が、自分の墓所はこの城である、お前達の中で、年取った親が立花におり、他に養うものがない者は立花に帰れ、兄弟ともにここにあるものは、
一人だけ帰って父祖の姓を絶さぬようにしろ、どうせ薩摩の大軍を相手にするのだから、討死するにきまっている、遠慮なく帰ったがいい、と言った。立花というのは立花城のことで、ここには養われた紹運の息男飛騨守宗茂がおったのです。ところが、この下知を聞いて、それでは私は帰ります、という者は一人もない。三百人もいたのが、ことごとく討死
してしまった。
この下知の裏は、一人でも帰るな、ということなのですが、もしその通り、帰るな、討死しろ、と言ったらどうなるか。放ったようで捉えるのがここなので、頼んでいる人が討死するという場合に、これを見捨てて行くことはどうも出来ない。そこが義理です。これが武士道の一道の光明となってゆくところのものなのです。
名嶋の城にいた者は、皆討死したのですが、紹運はその中の一人を呼び出して、お前はこれから立花に帰って、この有様を話せ、名嶋が落ちれば、敵はすぐ立花へかかるに相違ない、
急いで行け、と言って命じた。どうしたものか、
この人の名が知れませんが、これが立花へ駆けつけて、名嶋の状況を報告しました。波のごとくに押し寄せる大軍を相手に、存分の働きをして死ぬことでしょう、もう間もなく薩摩の兵は御城下まで迫ってまいりまする、と言って使命を果した後、今討たれようとする主を捨て、共々に討死と覚悟した友達を振り捨てて、ここまで来るべき心もないが、軍事上の大事は伝えなければならぬ、その道理に迫ってまいりましたが、役目を果してしまえば、何の未練もない、逃れることの出来ぬ中を逃れて来るのさえ、面目ないと思うのに、その上にまだ生きているわけにゆかぬ、と言って、旅装束も解かず、すぐ
自殺してしまいました。これ が武士の義理であります。」
あるいは,
「摂津国に割拠しておりました和田伊賀守が、五六の要害に立て籠って、荒木村重に対抗している。村重の方は、もう信長についてしまったので、隣同士で戦争しているのですが、元来荒木の方が大きな身分で、三千五百くらいの兵がある。和田は僅かに八百くらいしかないけれども、地の利を得ているために、いつでも少い兵をもって、多い荒木の兵を困らしておりました。あまりいつも勝つので、いい気になって、もう少し押し出そうというので、三里ばかりある馬塚というところまで出て来た。その時に、斎藤道三の甥で、和田の客分になっておりました永井隼人が、馬塚へ出張るというのを聞いて、大変に諌めた。三里だけれども、馬塚までお延びになれば、もうそうは行かない、お止めなさい、と言って止めたのですが、和田には驕る心持が出て、敵を甘く見ているから、なかなか聞かれない。そこで永井は和田と一緒に行って、あれだけ言葉を尽して利害を説いても、お聞きなさらぬ上は、何とも仕方がない、私も身を避けようとは思わ
ぬ、年来お世話を受けたあなたに一命を与えて、これままでの恩誼に報いるほかはありませ
ん、といって永井はここで討死した。和田も勿論敗死したのです。さんざん諫めても言うことを聞かぬのだから、一応義理が立ったようなものだが、これまで永いこと世話になったというところに、義理を持つ。これが義理なのです。」
もちろんこれは,選択である。おのれの
善悪の心の道筋,
として,もう少し突っ込めば,
倫理,
としてである。倫理とは,
いかに生きるか,
である。だから,武士道とは切腹と短絡するのは笑止である。
「武士が切腹をするということには、二通りの意味がある。その一つは、自分の犯した罪科とか過失とかに対して、自ら悔い償うためには、屠腹するということであり、今一つは、申し付けられて、その罪を償うということである。そして、そのいずれにしても、切腹は自滅を意味する。(中略)切腹は、…武士に対する処決の一特典にしか過ぎない
のである。ただ自らその罪に対する自責上、切腹して相果てるというその精神だけは武士道に咲いた一つの華と言っ
てもよいが、武士道の真髄ではあり得ない。」
したがって,他人の忖度とは無縁である。しかし,では,これが男だけか,と言えばそうではない。吉宗の時代,松平(浅野)安芸守吉長の夫人,つまり,
「御内室は、加賀宰相綱紀卿の御息女也、生得武勇の心ある女性にて、乗馬打物に達し、殊に長刀鍛錬の聞えあり、召仕はるゝ女まで皆々勇気たくましく、殊に一騎当千の女とも
いうべし」
という女性だったが,安芸守吉長が,吉原に通い,
「三浦屋四郎右衛門抱えの太夫花紫、同孫三郎抱えの格子歌野を落籍させて、屋敷へ引き取られました。その上に、 芝
神明前の陰間を二人までも請け出されました。(中略)請け出された遊女二人、陰間二人を、御帰国の節は、お供に召し連れられることにきめられました。(中略)こうなっては、夫人も、重ねて強諌なさらなければ済まない、と思し召したものか、外君に御対面なされ、大名が遊興のあまり、遊び者を請け出さるることも、あるまじき次第とはいわれまじけれども、永々の道中を国許まで召し連れらるることは、世間の耳目といい、殊には幕府への聞えもいかがなれば、これだけは何分にもお取止めなさるように、と切に進言されました。吉長朝臣は、この進言が大不機嫌であったという。」
結局夫人の諫言を聞き入れず,
「遊女・陰間が美々しい行装で、お供 する」
ことになって,夫人は,
「お居間に夜闌くるまで燈火あかあかと照して、御弟加賀中将へのお文細々とお認めなされ、 五十
一 歳を一期として、腹一文字に掻き切りて」
割腹するのである。その間のことを,鳶魚は,こう書く。
「武士の家では、自由恋愛などいうことはなく、それは不義者で成敗されます。決して、好いたの惚れたのという話はない。勿論、生理上必至なものとして婚姻するのではありません。夫婦は生活を愉楽するためではない。人道を行うために夫婦になったので、それはその家門を維持し、かつ繁昌させるため、当面に親を安んじ、子を育て、九族を和し、家風を揚げ、家名を輝かせる大切な戮力なのです。(中略)恋愛から出来た夫婦でなく、義理が仕立てた夫婦で
あった。互いにその一分を尊重する。それを蹂躍することは、他身を踏み潰すのでなく、 自身を破毀するのだと思っ ておりました。
吉長夫人前田氏も、外君の内行について、至当な進言が棄たるようになった時、婦道が立たなくなり
ます。もし特別な秘密があってのこととしても、何とか夫人からの進言の出ぬように打ち開けられないにもせよ、相応な工夫がなければなりません。一旦進言が出ますと、一般に至当と見られることだけに、是非とも聴納されなければなりません。悋気とか嫉妬とか、そんなこととは違う。一身一己からのことでない。
天下に公然たる婦道を行うの
です。夫婦の間に局限した事柄ではありません。人間を維持する道義です。至当なことさえ聞かれない。それでは婦道が行えないとすれば、この頃しばしば承る面子などということとも違う。妻の一分が立たないとは倫理がすたること、女に生れて妻となる、夫にはなれない、そこに動かし難いものがあって、
妻としてなすべきその職事は、天に受けた私ならぬ務めなのです。これを真ッ正直に考える、それを少し考え、あるいは全く考えない、時世の人は、少し考える者よりも、全く考えない者の方
がはるか に多かったのです。」
武士道とは,
義理である,
とはこのことである。
武士の一分がたたない,
のと同じである。
この武士道でいう「義理」は,「義」とは違う。『孟子』に,
惻隠の心は,仁の端(はじめ)なり,善悪の心は,義の端なり,辞譲の心は礼の端なり,是非の心は,智の端なり」
とある。「善悪の心は,義の端なり」には,武士道の「義理」の関係性とは違う。似ているようで違う,と思う。
士は己を知る者のために死す,
の「士」と「侍」が微妙に違うように,それについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/411864896.html
で触れた,文天祥の,
天地に正気あり,
雑然として流形を賦す
下は則ち河嶽と為り
上は則ち日星と為る
人に於いては浩然と為る
沛乎として滄溟に塞つ
皇路清く夷(たい)らかに当たりて
和を含みて明庭に吐く
時窮まれば節乃ち見(あら)われ
一一丹青に垂る
という「正気の歌」にある,おのれ一個の気概の担うものの大きさの差かもしれない。しかしそれは個としての私的な気概ではない。『論語』の,
士は以て弘毅ならざるべからず。任重くして道遠し。仁以て以て己が任となす。亦重からずや。死して後已む。また遠からずや。
の「士」もまた然りである。関係性としての「心の筋」は,「私」である。「士」の背後にあるのは,『孟子』の,
「惻隠の心は,仁の端(はじめ)なり,善悪の心は,義の端なり,辞譲の心は礼の端なり,是非の心は,智の端なり」
と,一貫する「公」の思想である。「公」とは,「志」である。「志」とは,すなわち,目的の謂いである。この差は,大きい。
参考文献;
三田村鳶魚『武家の生活』 [Kindle版]
氏家幹人『サムライとヤクザ』(ちくま文庫)
小林勝人訳注『孟子』(岩波文庫)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)
冨谷至『中国義士伝』(中公新書) |
|
マーケティング |
|
ウィリアム・A・コーエン『ピーター・ドラッカー−マーケターの罪と罰』を読む。
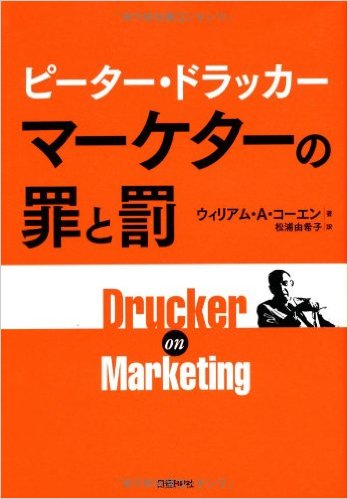
本書の原題は,
Drucker on Marketing
である。序文で,コトラーが,
「ピーター・ドラッカーは現代経営学の父として広く認められている。世間には時折,不用意にも私のことを現代マーケティングの父と呼ぶ人がいる。もしそうだとすれば,ドラッカーは現代マーケティングの祖父と称されるべきだろう。」
と述べている。本書は,そのドラッカーのマーケティングに関する考察を集めたものだ。コトラーは,
「ピーターはマーケティングに関する系統だった論文を書いていないが,顧客第一主義の企業の目的や,利益とリーダーシップの役割,イノベーションと企業家精神の決定的な重要性などについて論じる時,彼の念頭にはマーケティングがあったのだ。」
という。ドラッカーは経営トップに質問を投げかけた。例えば,
われわれのビジネスとは何か?
われわれの顧客は誰か?
顧客は何を価値と見なしているか?
われわれの事業は何であるべきなのか?
等々。ジャック・ウェルチは,GE史上最も若いCEOに就任した時,ドラッカーに二つの質問を投げかけられた。
「もしGEにある既にある特定の事業を手がけていなかったとしたら,今,その事業に進出するか?」
「もしその答がノーであれば,どうするのか?」
それを受けて,
「利益は出ているが業績が標準に及ばない事業の廃止を決断した。この経営判断がGEをスリム化させて,成功に導いた。ウェルチは当該市場で首位または2位でない事業は売却ないし清算することを命じた。」
これが,GEの市場価値を就任時の120億ドルから25倍以上にしていく成長の端緒となった。ドラッカーは,
企業の目的は,顧客の創造,
とする。なぜなら。
「顧客は企業の基盤であり,顧客が企業を存続させている。顧客のみが雇用を生み出してくれる。顧客の欲求と要求を満たすために,社会は企業に富を想像する資源を委ねている。」
と。である以上,企業の基本的な機能は,
マーケティング,
と
イノベーション,
の2つしなない,と言った。
「マーケティングとイノベーションは成果を生み出す。その他すべてはコストだ」
と。そして,著者は,こう付け加える。
「販売とマーケティングはほぼ同義だと考えているなら,間違っている。なぜなら,答えの一部しか得ていないからだ。ドラッカーは,販売とマーケティングが別物だということだけでなく,優れた販売は実は優れたマーケティングと対立し得るということを知っていた。
なぜそうなるのか。その答を理解するためには,販売は自分が既に持っているモノを見込み客に買うように説得することと関係しているという事実を思い出す必要がある。これに対して,マーケティングとは,すなわち,潜在顧客が求めているモノを既に持っていることだ。別の商品ならば格段に少ない努力でもっと大量に売れる時に,採算ぎりぎりの商品を売るために販売員を動かすことは,マーケティングと敵対する。」
だから,われわれにはマーケティングは機能と見がちだが,ドラッカーは,
基本的なコミットメント,
として,あるいは,
大きなものの見方,
として捉えていた。だから,こういう問いがなされる(「経営者に贈る五つの質問」)。
①我々のミッションは何か?
②我々の顧客は誰か?
③顧客にとっての価値は何か?
④我々の成果とは何か?
⑤我々の計画は何か?
全てマーケティングに関わる。ドラッカーは皮肉を込めてこう書く。
「もう10年にわたって『マーケティング観』が広く喧伝されてきた。『トータル・マーケティング・アプローチ』という派手な名称を得るまでに至った。この名前で通っているすべてのものが,その名にふさわしいとは限らない。『マーケティング』は流行語になった。しかし,たとえ『葬儀屋』と呼ばれても,墓掘りが墓掘りであることに変わりはなく,埋葬費が高くなるだけだ。多くの営業部長の役職が『マーケティング担当バイスプレジデント』と改名されたが,結局は経費と給与が増えただけだった。」(1964)
だからこそ,
リーダーシップの本質とはマーケティングである,
というドラッカーの視点でみると,上記の五つの質問の意味が新たになるはずである。そして,
マーケティングを組織のすべての階層に浸透させる,
マーケティングと販売の違いを理解する,
教育して指導する,
顧客の観点からビジネスに取り組む,
という,ドラッカーの4つの指示から鑑みるなら,
リーダーシップの本質とはマーケティングである,
は,
マーケティングとはリーダーシップである,
とも言い換えることができる。著者は書く。
「リーダーシップはマーケティングであるというドラッカーの前提を受け入れたら,同じようにマーケティングはリーダーシップだということが事実であることは,驚くにあたらない。」
顧客第一主義とは,スローガンではない。例えば品質も,そうである。
「ドラッカーは,…製品・サービスの品質は,サプライヤーが盛り込んだものではない…。ドラッカーいわく,品質とは,買い手がその製品・サービスから得るものであり,それにお金を払ってもいいと考えるものだという。顧客は自分たちが使えるもの,自分たちに価値を与えてくれるものにだけお金を出すのだ。
ここで『自分たち』というところを強調しておきたい。価値というものは,サプライヤーが考えているものではなく,顧客が考えるものだ。そして品質は価値の一部だ。このため,買い手が同じように定義しないのであれば,売り手が勝手に品質だと考えているものを築くのにお金や時間や労力を注ぎ込むのは愚かなことだ。
さらに言えば,顧客が望むもの,あるいは,望ましいものとして評価しているものでなければ,製品の耐久性やサービスのスピードをマーケターが喧伝するのも同じくらい愚かなことだ。」
こう見ると,まだドラッカーは,まだまだ時代の先にいるようである。
参考文献;
ウィリアム・A・コーエン『ピーター・ドラッカー マーケターの罪と罰』(日経BP社) |
|
怪談 |
|
田中貢太郎『怪談百物語』を読む。
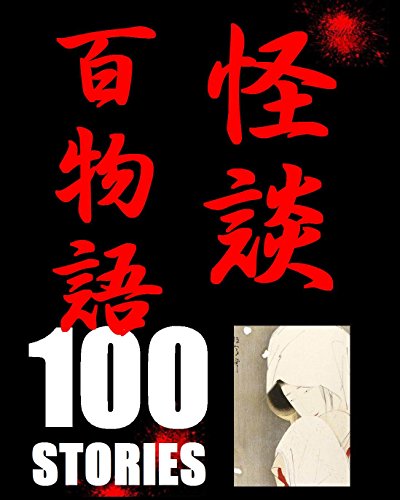
ここで取り上げているのは,いわゆる,
志怪小説,
の類である。志怪小説は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/434978812.html
で触れたように,
中国の旧小説の一類,不思議な出来事を短い文に綴ったもの。また創作の意図はなく,小説の原初的段階を示す。六朝東晋の頃より起こった。「捜神記」など,
と言われるものだ(『広辞苑』)。志怪小説は,
「面白い話ではあるが作者の主張は含まれないことが多い。志怪小説や伝奇小説は文語で書かれた文言小説であるが、宋から明の時代にかけてはこれらを元にした語り物も発展し、やがて俗語で書かれた『水滸伝』『金瓶梅』などの通俗小説へと続いていく。」
という。そもそも「志怪」とは,
「怪を志(しる)す」
という意味で,
『列異伝』曹丕の作として伝えられるが、現存するものには後人の作品が混入しており、成立の経緯は不明。
『捜神記』晋の干宝作。
『捜神後記』晋の陶淵明作。「桃花源記」が含まれる。
『述異記』斉の祖冲之作。同題の任鈁作の書は地理書的作品。
『異苑』宋の劉敬叔作。劉は江蘇省銅山の人で、東晋の劉毅、劉裕に仕えた。
『漢武故事』作者不詳。班固の作として伝えられて来たが、六朝の作品と見られる志人小説。
『聊斎志異』清の蒲松齢作。
等々と挙げられるが,たとえば,
『捜神記』の『むじな』や『ろくろ首』は,小泉八雲『怪談』の原典
となっていると言われるし,『剪燈新話』の『牡丹燈記』は,
三遊亭円朝の『怪談牡丹燈籠』
の元になっており,上田秋成は『剪燈新話』の構成を借りて,
『雨月物語』の『吉備津の釜』
を著している,という。すでに,江戸時代(寛文年間1660年代)には,
『伽婢子(おとぎぼうこ)』
『狗張子(いぬはりこ)』
が,志怪小説の翻案として,出されている。そもそも,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/432692200.html
で触れたように,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
で,稗史は,
「昔、中国で稗官(はいかん)が民間から集めて記録した小説風の歴史書。また、正史に対して、民間の歴史書。転じて、作り物語。転じて,広く,小説。」
を言う。語源を見ると,こうある。
「中国の『稗史』からでたものです。『小(とるに足りぬ)+説(議論)』が語源です。市井の出来事や話題を,書き記したものです。」
日本語では,
物語
咄(囃)
があり,両者の違いは,近世の俳人高田幸佐によると,
「首を斬られた盗人が自分の首を懐に入れて逃げ去った話」
は,「世に噂にもまことしからぬ儀」は,「咄とこそいうなれ」と定義する。他方,
「朱雀院の御宇に起きた平将門の乱の折,将門の獄門首が歯がみをなして声をあげた怪異談」
は,「出書正しき物語」の典型としている。堤邦彦氏は,
「ここにいう『物語』とは,史実と認められる出来事や,原拠の明らかな故事をもとに創り出された話」
を指す。従って,
「それらは時・人・所を明示しえる内容でなければならない」
ということになる。逆に言うと,それを明示して見せることで,「噂」ではないかのごとく見せることができる。
本書の過半は,著者の田中貢太郎が,
物語風,
に,つまり,
時・人・所を明示しえる内容,
に仕立てたものになっているが,正直のところ,全体の一割程度だが,中国由来の作品が,圧倒的に,奥行,スケールともに面白い。中国の「小説」については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/444432230.html?1480364327
で触れた,
岡本綺堂『中国怪奇小説集』
に詳しいが,多くは,それとは重ならない。自分の好みでいえば,神をたばかって,寿命を延ばそうとした,
「北斗と南斗星」
「沒くなっ て二十三年も経った」女性と「交往」した男の,
「黄金の枕」
岩見重太郎の狒々の元ネタになったらしい,
「殺神記」
美女を盗んで囲う大猿の話,
「美女を盗む鬼神」
等々,面白い話がいっぱいである。それに引き換え,日本のものはスケールが小さく,
怨み,
だの,
遺恨,
だの
怨恨
といったものに起因するものが多くて,因果を辿りたくて仕方がないらしい。その中では,暴漢を智慧で驚かせた,
「女の怪異」
得体の知れない怪僧の不気味さが残る,
「竈の中の顔」
理不尽な為政者の犠牲の,
「八人みさきの話」
はおもしろい。どうも,
うらみ,
つらみ,
という個人の我執の怪異は,いただけない。
参考文献;
田中貢太郎『怪談百物語』(Kindle版)
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社) |
|
易経 |
|
高田真治・後藤基巳訳『易経』を読む。
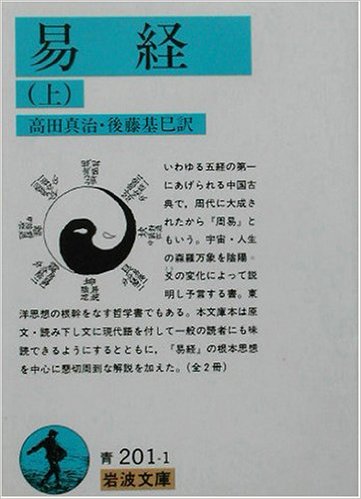 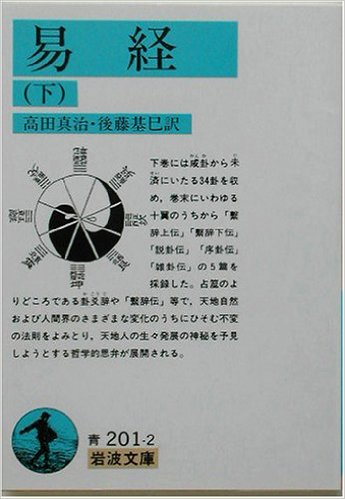
四書(『大学』『論語』『孟子』『中庸』)五経(『詩経』『詩経』『礼経』『易経』『春秋経』)の一つ,『易経』の訳である。かつて,荘子が,
「詩,書,礼,楽,易,春秋」
を六経と挙げ,
「詩はもって志を道(い)い,書はもって事を道い,礼はもって行いを道い,楽はもって和を道い,易はもって陰陽を道い,春秋はもって名分を道う」
といったように,
「詩,書,礼,楽,易,春秋を王道の基づくところ,儒家の経典としている。」
とある。礼記には,
「孔子曰く,その人となりや,温柔敦厚なるは詩の教えなり,疎通知遠なるは書の教えなり,広博易良なるは学の教えなり,隩静精微なるは易の教えなり,恭敬荘敬なるは礼の教えなり,属辞比事なるは春秋の教えなり」
と。本書は,
「易はまたは周易といい,これを経典とし尊んで易経と称する」
もので,
「陰陽八卦を基本として成る六十四卦をもって構成されたものを二経に分かち,さらにこれを十翼すなわち彖伝(たんでん)上・下,象伝(しょうでん)上・下,繋辞伝(けいじでん)上・下,文言伝(ぶんげんでん),説卦伝(せっかでん),序卦伝(じょかでん),雑卦伝(ざっかでん)の十篇を加えて一書としたものである。」
易と孔子との関係については,『論語』に,
「我に数年を加し,五十にして以て易を学べば,以て大過なかるべし」
とある如く深い関わりがあり,十翼が孔子によって書かれたとする説は今日否定されているが,
「中庸にいたっては十翼の思想に類するものがはなはだ多く,…趙岐の孟子章句序に依れば,孟子は最も易に深い者と称せられ,荀子にいたっては易に論及することがはなはだ多く,かつ易の伝播が孔子の門流によってなされたこと等を思えば,孔子ならびにその門流によって研究せられて,古来占筮の書であった易が,漸く義理修養の書として重んぜられるに至った経路を想像するに足りるのである。十翼の思想の中には孔子の思想と相一致するものがあり,また相類するものも少なくないのであって,たとえ十翼が孔子自ら筆を下して作ったものでないとしても十翼は孔子門流,特に子思,孟子の学派の手によって成り,その中には孔子の思想が含有せられているものとみてさしつかえないであろう。」
と。そして,
「十翼のうち彖象二伝の文が最も簡奥で,春秋,論語の文に近く,繋辞,文言がこれに次ぎ,その文章内容は中庸,孟子に類し,その製作年代は,おそらく中庸と相前後する戦国の時にあるであろう。序卦,説卦,雑卦等はずっと下って漢初の易学者の作ともいわれている。」
と(以上本書解説(高田真治)による)。
確かに,易に不案内のせいもあるが,読んでいて,その世界観が面白く展開されているのは,繋辞伝上・下である。たとえば,
「易は天地を準(なぞら)う。故に能く天地の道を弥綸(びりん)す。仰いでもって天文を観,俯してもって地理を察す。この故に幽明の故を知る。始めを原(たず)ね終りに反る。故に死生の説を知る。精気は物を為し,遊魂は変を為す,この故に鬼神の情状を知る。
天地と相似たり,故に違わず。知万物に周(あまね)くして道天下を済(すく)う,故に過たず。旁(あまね)く行きて流れず,天を楽しみ命を知る,故に憂えず。土に安んじ仁に敦(あつ)し,故に能く愛す。
天地の化を範囲して過ぎしめず,万物を曲成して遺さず。昼夜の道に通じて知る。故に神は方なくして易は体なし。」
と。その天地は,
「天は尊く地は卑しくして,乾坤定まる。卑高もって陳(つらな)り,貴賤位す。動静常ありて,剛柔断(わか)る。方は類をもって聚(あつ)まり,物は群をもって分かれて,吉凶生ず。天に在りては象を成し,地に在りては形を成して,変化見(あらわ)る。」
ということだが,乾坤は,男女に準えられる。
「乾道は男を成し,坤道は女をなす。乾は大始を知(つかさど)り,坤は成物を作(な)す。乾は易(い)をもって知(つかさど)り,坤は簡をもって能くす。易なれば知り易(やす)く,簡なれば従い易し。知り易ければ親しみあり,従い易ければ功あり。親しみあれば久しかるべく,功あれば大なるべし。久しかるべきは賢人の徳,大なるべきは賢人の業なり。易簡にして天下の理得たり。天下の理得て位をその中に成す。」
このメタファは,例えば,
「戸を闔(とざ)ざすこれを坤と謂い,戸を闢(ひら)くこれを乾と謂い,一闔一闢(いちこういっぺき 一たびは闔じ一たびは闢く)之を変と謂い,往来窮まらざるこれを通と謂い,見(あら)わるるはすなわちこれを象と謂い,形あるはすなわちこれを噐と謂い,制してこれをもちうるはこれを法と謂い,利用出入して民みなこれを用うるはこれを神と謂う。」
の,戸の闔闢は,『老子』にある,
「天門,開闔(かいこう)して,能く雌と為らんか。」
を思い起こさせる。孔子門下にとって,易は,
「夫れ易は,聖人の徳を崇(たか)くし業を広むる所以なり。知は崇く礼は卑(ひく)し。崇きは天に効(なら)い,卑きは知に法(のっと)る。天地位を設けて,易その中に行わる。性を成し存すべきを存するは,道義の門なり。」
と述べた孔子の言葉によって代表されるように,是非判断のよりどころであったらしい。なぜなら,
「天下の賾(さく)を極るものは卦に存し,天下の動を鼓するものは(卦爻の)辞に存し,化してこれを栽する破片に存し,推して之を行うは通に存し,神にしてこれを明らかにするはその人に存し,黙してこれを成し言わずして信(まこと)あるは,徳行に存す。」
「賾」すなわち錯雑とした複雑さをほどき,変を見通していく,儒者にとって,易は,一種の天下の趨勢をみるシミュレーションツールのようなものといってもいいのかもしれない。
参考文献;
高田真治・後藤基巳訳『易経』(岩波文庫)
福永光司訳注『老子』(朝日文庫) |
|
集団的自衛権 |
|
松竹伸幸『集団的自衛権の深層』を読む。
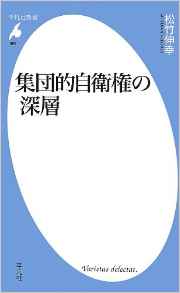
同じ著者の,『憲法九条の軍事戦略』は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/402074073.html
で触れたことがある。そこで,九条のもと,専守防衛を旨としたきたが,それは,
「専守防衛とは相手からの武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し,その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ,また保持する防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど,憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略をいう…」(大村防衛庁長官 参議院予算委員会 81.3.19)
つまり,
日本側が反撃を開始するのは相手から武力攻撃を受けたときであり,
その反撃の態様は,自衛のための必要最小限度の範囲にとどめ,
その反撃をする装備も自衛のための必要最小限度
というものである。これに合わせて,自衛権発動の三要件というのがある。
「憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については,政府は,従来からいわゆる自衛権発動の三要件(我が国に対する急迫不正の侵害があること,この場合に他に適当な手段のないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られると解している」(参議院決算委員会提出資料 72.10.14)
「他に適当な手段がない場合」を除くと,専守防衛の要件と重なっている。この趣旨は,
「外交交渉とか経済制裁などで相手国の侵略をやめさせることができるならそうすべきであって,武力で自衛するのはそういう手段ではダメな場合に限る」
という意味である。
こういう専守防衛の考え方を覆す安保法案が昨年国会を通ったが,そこでの議論が,いかに尽くされていない(あるいは,尽くす気がなかった)かが,本書を通して見えてくる。
安全保障関連法案(安保法案)は,新しくつくられる「国際平和支援法案」と自衛隊法改正案など10の法律の改正案を一つにまとめた「平和安全法制整備法案」からなる。
集団的自衛権を認める
自衛隊の活動範囲や、使用できる武器を拡大する
有事の際に自衛隊を派遣するまでの国会議論の時間を短縮する
在外邦人救出や米艦防護を可能になる
武器使用基準を緩和
上官に反抗した場合の処罰規定を追加
などが盛り込まれた。歴代内閣が否定してきた集団的自衛権の行使容認には「合憲性を基礎づけようとする論理が破綻している」(長谷部恭男・早稲田大学教授)など,法学者らから疑問の声も強かったものだ。
本書は,2013年上梓なので,本書での対象になっているのは,「安全保障の法的基盤再構築に関する懇談会」と,13年秋の報告書をベースに議論している。そこで,
「どんな集団的自衛権を行使できるようにしたいのか」
として上げているケースが,
①自衛隊の知覚にいる米艦船が攻撃された場合,
②米本土に向かうミサイルが発射された場合,
③PKOで仲間の他国兵士が攻撃を受ける場合や任務遂行に必要な場合,
④PKO等で武力行使と一体化した後方支援が必要な場合,
である。しかし,国会審議中もそうであったが,敢えて,個別的自衛権と集団的自衛権をあいまい化したり,ぼかす意図か,必ず関係ないケースを挙げる。ここでも,敢えて混同している。
「後者のふたつは,国連平和維持活動(PKO)の問題であって,集団的自衛権とは直接関係がない。…集団的自衛権自衛権とは,国連として何らかの軍事的措置をとるという合意ができるまでの間,各々の国家が国連とは無縁に独自の軍事的措置を行使する権利のことである。国連軍や国連PKOに参加した際の自衛隊による武器使用は,武器の行使という範疇に入る問題ではあるが,国連の合意にもとづく活動であって,個別国家による集団的自衛権とはまったく異なる概念である。したがって『報告書』が,そういう国連の活動を日米同盟にかかわる問題と同列に論じているのは,集団的自衛権がPKOと同様,国際社会によってオーソライズされているかのように描きだそうとするものであってここにも虚構がみられる。」
と本書の指摘する通りである。
集団的自衛権の根拠になっている国連憲章51条には,
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
とある。ただし,2条4項に,
「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」
とあり,「武力行使」は,「いかなる」ものも禁止されている。それを破って武力行使された場合,
「国連憲章は,ふたつの例外をもうけた。ひとつは,侵略に対して国連が制裁をくわえる場合である。もうひとつは,そうやって国連がのりだしてくるまでの間,各国が独自に自衛権を発動する場合である。このうち後者を規定したのが,憲章第五一条だということになる。」
本書の特徴は,国会審議でほぼスルーされた,集団的自衛権がどのように行使過去の例をつぶさに検討しているところだろう。
1956年ソ連のハンガリー介入,
1958年米英のレバノン・ヨルダン介入,
1964年イギリスのイエメン介入,
1966年アメリカのベトナム介入,
1968年ソ連のチェコスロバキア介入,
1980年ソ連のアフガニスタン介入,
1983年アメリカのグレナダ介入,
1984年アメリカのニカラグア介入,
1986年フランスのチャド介入,
集団的自衛権を行使したのは,四か国の大国だが,これが,
「この権利は世界のどの国もが保有しているものであって,それを行使する国こそが普通の国」
だと主張した根拠である。しかも,
「どの国も『武力攻撃』をうけたわけでもないのに」
集団的自衛権を名目に,軍事的介入をしているという,「現実と建前の乖離」である。要するに,
「集団的自衛権というものの実態は,『自衛』とは何の関係もないのはもちろん,二重にも三重にも違法な武力行使だったということである。国際法に対する重大な違反だったのだ。」
にもかかわらず集団的自衛権をもとめる「本音」は,第一に,
自衛隊の軍事能力である,
と著者は見る。
「集団的自衛権というのは,海外にまで出向いていって武力を使うということだから,並大抵の軍事能力では行使することができない。普通の国は,集団的自衛権を行使したくても,その能力をもたないのだ。だからこれまで軍事大国しか集団的自衛権を行使してこなかった。
実際,ミサイル防衛システムにしても,昔だったらアメリカだけでシステムを構築しただろう。ところが,海上自衛隊の能力が飛躍的に向上し,アメリカを防衛する能力を獲得したからこそ,ミサイル防衛システムの一部を日本が分担することになったのである。また,海上自衛隊の護衛艦は,性能の向上と長年の訓練の積み重ねによって,アメリカの艦船を守るために不可欠の能力を身につけることとなった。集団的自衛権の行使を求めるのは,世界の環境が変わったからではなく,日本の軍事能力がかわったからなのだ。」
第二は,
「明示はされていないが,想定する『敵』との軍事能力の違いである。さらには,それと対抗する日米共同の軍事作戦の違いといってもよい。
冷戦期は,世界のどこかでアメリカとソ連が戦端を開くようなことがあったら,米ソは世界規模で戦争する態勢がつくられていたので,ソ連はただちに在日米軍基地に対して空と海から攻撃をしかけてくること,さらには北海道を皮切りに大規模な陸軍も上陸させてくることが想定されていた。つまり,米ソの戦争のなかでは,日本もまたソ連の武力攻撃を受けるのであって,…集団的自衛権の発動などしなくても,個別的自衛権で十分説明できるものだったのである。」
それと比較して,
「アメリカと日本の軍事能力が『敵』より優位にあるということが前提にされている。」
だから,集団的自衛権というわけである。
第三は,
「集団的自衛権の具体的な必要性というよりも,日米同盟絶対化の思想とでもいうべきものだ。
集団的自衛権を行使する国になるということは,きわめて重い決断である。なぜなら,アメリカの艦船が攻撃されたら日本も一緒に反撃するとか,アメリカに向かうミサイルを日米が協力して撃ち落とすなどというが,その時点において,アメリカの相手国は日本を攻撃対象にしていないのである。…ところが,日本が集団的自衛権を行使し,その国の艦船を攻撃したり,ミサイルを破壊したりしたとたん,日本もまた相手国の敵になる。その国のミサイルは,今度は日本に向かってくることになる。(中略)安倍首相は,集団的自衛権が日本を守ることにつながると勇ましく発言するが,実際は日本人の命を軽んじているから,そういう発想が生まれるのである。」
なのにである,この報告書には,
「どんな戦争がこの地域で起きるのか,起きるにしても,日本の集団的自衛権の行使が正しい選択肢なのか…,それがはたして,日本と地域の平和にとって大事なのか…。」
を検討していないのである。つまり,はじめに結論ありき,なのである。こうした検討抜きの法制化は,既に現実である。この付けは,安倍首相やその取り巻きではなく,国民が払わされることだけは間違いない。
参考文献;
松竹伸幸『集団的自衛権の深層』(平凡社新書)
松竹伸幸『憲法九条の軍事戦略』(平凡社新書)
http://www.huffingtonpost.jp/2015/07/15/security-law-wakariyasuku_n_7806570.html |
|
「慰安婦」問題 |
|
大沼保昭『「慰安婦」問題とは何だったのか―メディア・NGO・政府の功罪 』を読む。
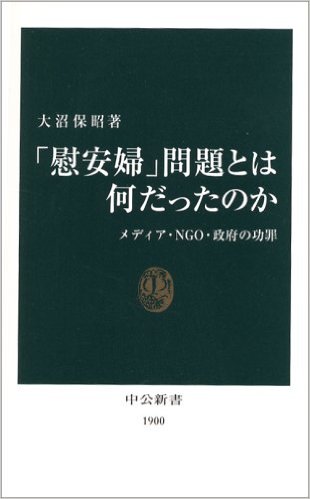
本書は,アジア女性基金の設立とその経緯に終了までずっと携わった著者の総括の書である。
「わたしは,1995年に村山内閣の下でアジア女性基金の設立にかかわり,それ以来元『慰安婦』の償い事業に与ってきた。本書でわたしは,『慰安婦』問題をテーマとして,公共性の担い手としてのメディアとNGOの意義と問題性,そして歴史認識をめぐる韓国や中国とのつきあい方について,読者とともに考えたい。『慰安婦』問題と歴史認識をめぐるメディア,NGO,関係国政府,アジア女性基金の絡み合いを,こうした視角からできるだけ醒めた目をもって再現したい。」
とし,その動機を,
「1995年,村山富市内閣が『慰安婦』問題解決の一環としてアジア女性基金を設立したとき,わたしはそれに深くかかわり,基金の呼びかけ人,理事として,『慰安婦』問題の解決のために時間と精力を費やしてきた。基金が日本国民からの償い金,総理のお詫び手紙,医療福祉支援費を個々の被害者に届けるというかたちで被害者への償いを実施ているあいだは,一人でも多くの被害者に日本国民のお詫びと償いの気持ちを伝え,被害者のいくばくかの支えとなることが,わたしにとってもっとも重要な課題であった。
この間,日本でも韓国でも,また他のアジア諸国や欧米でも,『慰安婦』問題について事実を歪曲した報道や主張,わたしからみて疑問と思われる議論が横行した。元『慰安婦』の意思や希望についてきわめて一面的な主張がなされ,それがそのまま『被害者の意思』として報道された。アジア女性基金はしばしばそうした誤った主張,偏った報道にもとづいて非難され,それが被害者への償いをさらに困難なものにした。(中略)
アジア女性基金の償い事業が終了し,2007年三月に基金が解散して,状況がかわった。元『慰安婦』のプライバシーにかかわる問題を除けば,これまでメディアで報道されてこなかったことをあきらかにし,これまで有力に主張されてきた見解の誤りを指摘し,『慰安婦』問題に当事者としてかかわり,同時に現代史の観察者として目の前で観てきた『慰安婦』問題の像をわたしなりに示すことができる,そういう時期がきた,とわたしは考えた。その結果が本書である。
本書は,このようにアジア女性基金の一員として元『慰安婦』への償いに携わった過程で体験し,考えたこと,またひとりの国際法学者,現代史の観察者,日本の戦後責任を考えてきた者として見聞きし,考えてきたことにもとづく現代史の覚え書である。本書を通して読者に『慰安婦』問題の複雑な諸相を提示するとともに,将来こうした深刻な問題が生じた場合,すこしでもましな対応をとることができるように,一人ひとりがじっくり考えていただきたい。それが本書を執筆した動機である。」
だからこそ,著者は,
「本書でわたしがめざしているのは,『慰安婦』問題をめぐる日本と韓国双方の政府,NGO,主に日韓の新聞やテレビなどのメディア,さらにアジア女性基金がやってきたことややらなかった,あるいはやれなかったことを示し,そうした作為・不作為のなかで問題の解決に役立ったこととマイナスに働いたことをありのままに提示し,それへのわたしの評価をあきらかにすることである。それによって,将来日本に再び『慰安婦』問題のような重大な政治・社会・外交問題が生じた場合,日本の一員として取るべき態度について考える手がかりを読者に提供したいと思う。」
と,その意図を明確に書いている。その背景にある,著者の,
「『慰安婦』問題をつくりだしたのは過去の日本だが,日本という国は政府だけのものではない。国家とは,国民の一人ひとりが過去を引き継ぎ,現在を生き,未来を創っていくものである。戦後五〇年という時期に全国民的な償いをはたすことは,現在を生きるわたしたち自身の,犠牲者の方々への,国際社会への,そして将来の世代への責任ではないか。」
という覚悟を重く受けとめる。この覚悟を,今やほとんどの人が失っている。過去からは,絶対に逃げることはできない。安倍談話にあった,
「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」
という言葉ほど,過去を背負うという覚悟からいかに遠い言葉であることが,よく分かる。
歴史認識,
と責められるとき,過去の重荷や過去の罪科を背負うのを逃れたり,言い訳したりしていると見えた時であるに違いない。われわれは,日本国民である限り,永遠に,過去から逃れることはできないと思う。だから,著者が,
「左右いずれであれ,実証的な研究を顧みず,みずからの思い込みにもとづいて煽動的な議論を重ねる人々とは対話と議論が成り立たない。その意味で,『慰安婦』問題について,実証的基礎もないまま元『慰安婦』を売女呼ばわりする『論客』は,まともな議論の対象にならない。本書で『慰安婦=公娼』論への言及と反論がすくないのは,それをよしとしているからではなく,およそ学問的議論の対象にならないと考えているためである。」
と述べた,一笑に付すべきそうした論が,二〇年後,上記の文言を談話として口にした首相が公然とすることになる。メディアも,また同然である。村山内閣という,いま考えると奇跡のような,自民・社会・さきがけの連立内閣という政権だったからこそ,できたことだし,まだしもまともな議論ができた時代なのだと,つくづく思う。いまや,こうした議論さえ,はるかな奇跡に見える。
その著者が本書で展開した論旨は,
「『慰安婦』問題は,戦争,性,政治,法,道義など,人間の多様な面とかかわり,多様な視点から捉えることができる。書かれた本も多い。ただ,これまでこの問題について書かれた本は,ひたすら日本の政府や社会を告発・批判するか,『慰安婦は公娼だった』といった立場からそれに反論するタイプのものが大部分を占めていた。」
それに対して,第一に,
「『慰安婦』問題には,二一世紀の日本が政治,経済,教育,環境など,さまざまな問題に立ち向かっていくうえできわめて重要な問題が隠されていた。それは,こうした問題を解決するうえで,日本がメディアやNGO…など,二〇世紀後半に大きな影響力をもつようになった主体を通して,どのような姿勢で社会問題や政治問題にかかわるべきか,という問題である。」
世論を左右するメディアやそれに係るNGOのあり方に踏み込んでいること(それがサブタイトルの主旨だ),そして,
「みずからが政治に関与する主体であり,政治では結果責任が問われるという意識が希薄だった」
と,厳しく批判し,そうした,
「公共性の担い手のあるべき姿は何か」
と問いかけていること。第二に,
「『歴史認識』をめぐって中国,韓国といった,日本の侵略戦争,植民地支配の『被害国』とのつきあい方はいかにあるべきか,という問題である。」
特に,
「韓国では,『慰安婦』問題は日本への不信と猜疑という反日ナショナリズムの象徴と化した。」
ここで,メディア・NGOは,
「韓国と日本の多くのNGOは,問題の本質は人間の尊厳の回復であってお金ではないという『正論』をひたすら主張した。…マスメディアによって単純化され,聖化された被害者像が日韓の社会を支配し,こうした像と異なる解決は聖なる『被害者の声』に反するとして排除された。他方,『何度謝ってもまだ足りないと言われる』ことに苛立つ日本の一部のメディアは,元『慰安婦』を『売春婦』呼ばわりする感情的な議論を爆発させた。そうした感情的な議論は韓国に大々的に伝えられ,韓国国民の感情をさらに硬化させた。
こうして,韓国の反日ナショナリズムと日本の嫌韓感情の悪循環が日韓関係を覆った。」
二〇年後も,一向に変らぬ悪循環は,続いている。「結果責任」とは,これをいう。マイナスイメージの日本像は,払拭されるどころか,何かことがあるたびに,
「政府部内では『負け戦は戦わない』という『大人の知恵』論が主張され,…弥縫策の積み重ねでは,将来また問題が再発した時,また同じような対応をしなければならない。それでは,『「慰安婦」問題の解決を怠った日本』というマイナスイメージは永久に改善されることはないだろう。」
という十年前の予言は,そのままいつまでも予言であり続けるようだ。
参考文献;
大沼保昭『「慰安婦」問題とは何だったのか―メディア・NGO・政府の功罪 』(中公新書) |
|
失敗した面接 |
|
ジェフリー・A. コトラー&ジョン
カールソン編『まずい面接―マスター・セラピストたちが語る最悪のケース』を読む。
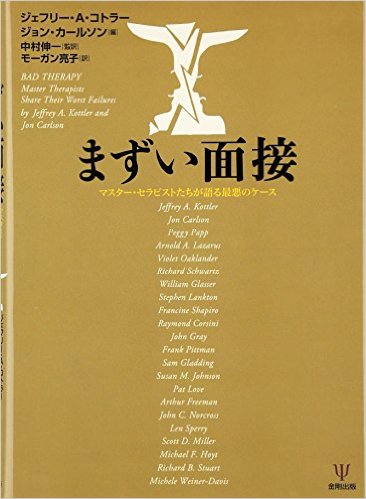
本書の原題は,ずばり,
Bad thrapy
である。著名な,「マスター・セラピスト」が,自分の最悪の失敗を語っている。著者二人を除くと,選択理論のグラッサー,EMDRのシャピロ等々を含めた,
ペギー・パップ,
アーノルド・A・ラザラス,
バイオレット・オークランダー,
リチャード・シュワルツ,
ウイリアム・グラッサー,
スティーブン・ランクトン,
フランシーン・シャピロ,
レイモンド・コルシーニ,
フランク・ピットマン,
サム・グレイディング,
スーザン・M・ジョンソン,
パッド・ラブ,
アーサー・フリーマン,
ジョン・C・ノークロス,
レン・スペリー,
スコット・D・ミラー,
マイケル・F・ホワイト,
リチャード・B・スチュアート,
ミシェル・ワイナー・デイヴィス,
という著名なセラピストである。著者は,
「トップレベルのセラピストが自分の最悪なまちがいについて打ち明ける。あまりの正直さに驚くほどである。」
と書く。
「これまで長い間,セラピストの誤った判断や間違いは,セラピスト自身には関係がないものとするさまざまな解釈方法が生み出されてきた。たとえば,クライアントの努力やモチベーションが足りないということ。また,望ましくない結果の原因を,どうしようもない状況―お節介な家族,器質的または環境的要因,時間の制限など―のせいだとする。さらにクライアントの言動に境界例,妨害,抵抗などといったひどいレッテルを貼る。」
つまり,クライアントがセラピストの機体に応えていない,ということをそう言っている。しかし,と著者は書く。
「今まで助けることのできなかったクライアントのことを思い出しては胸の痛む思いをする経験は,誰にでもあるだろう。特に自分の手落ちのせいでまずい面接となった(願わくば)数少ない症例については思い悩むものだ。手落ちの例はさまざまだ。押しが強すぎた。ペースが速すぎた。状況を読み違えた。重大な情報を聞きもらした。自分のプライベートな問題が浮上してしまった。気転に欠けていた。誤診断した。介入を行う技術が欠けていた。クライアントを追っ払ってしまった。もちろん,この他にも数えきれない程さまざまなタイプの手落ちがあるだろうが,要するに私たちは面接を台無しにして,クライアントは退散してしまったのだ。治療を後退させてしまった可能性もある。こうした状況にあって,しかも誰にも知られないで済むなら,私たちはこうした経験をなかったことのようにふるまうことを選ぶ。否認と自己防衛という非常に便利な手段がこういうときには役に立つ。私たちの間違いを記憶の奥底にしまい,そもそも,そうした経験など無かったことにするような役割を果たすのである。」
寝た子を起こすような,本書に応え,
「オープンに話すにはかなり勇気のいるもので,決して簡単なものではない。だいたい自分のこれまでの臨床経験で出くわした失望を招く最悪な大失敗について進んで話したい人なんているわけがない。」
そこで,
「ただなにかなにか゛うまく行かなかったのかだけではなく,間違いから何が学べるかということに焦点を当てた。結局,何がうまく行かなかったのか納得することで,そこから何かを学んで成長していくものなのだ。この成長過程の鍵となるのは,一連の出来事を体系的に一つ一つ分析して反省し,納得していくことである。こうした作業は,私たちとの面接を通してクライアントが行う取り組みとなんら変わらない。」
インタヴューの対象者は,
「『著名』であること」
だが,その定義を,著者は,
①これまでに相当数の文献を発表していて,それが多くの臨床家に知られていること,
②長年にわたる臨床経験が土台にあること,
③積極的な参加意思があること,
とする当然ながら,著者たちが,
「コンタクトをとったうちの約3分の1の人が辞退したことは,不思議ではない。それよりも,残りの3分の2の人が乗り気で応じてくれたことのほうが驚いた。」
と。著者は,あらかじめ,次の質問項目を送付している。つまり,
①今回のインタビューを迎えるにあたって,どのような考えが浮かびましたか?
②あなたにとって,まずい面接とはどのようなものですか?
③これまでで最悪の面接をきかれて,真っ先に頭に浮かぶのはどのようなものですか? 何が起きたか詳細にお話しください。
④その面接がそれほどひどい結果(あなたとクライアントの一方,または両方にとって)になってしまった原因は何だと思いますか?
⑤その経験をいま振り返って公の場で話すことは,どのような感じがしますか?
⑥あなたの行ったこと,もしくは行わなかったことに対して,後悔したり他の対応をすればよかったと感じる経験は,どのようなものですか?
⑦その経験から学んだことは何ですか?
⑧その出来事そのものと,それに対するあなたの向き合い方から,他の人が学べることはどのようなことですか?
⑨より率直にオープンに自分の最大の失敗について話すことは,一般的にいってどのような望ましい効果があると思いますか?
詳細は,読んでいただくほかはないが,監訳者中村伸一氏は,
「『身につまされる』ことしきり」
と,あとがきで書かれる。ベテランであるほど,深く感じることが多いのではないだろうか。
参考文献;
ジェフリー・A. コトラー&ジョン
カールソン編『まずい面接―マスター・セラピストたちが語る最悪のケース』(金剛出版) |
|
ボルヘス |
|
J・L・ボルヘス『伝奇集』を読む。
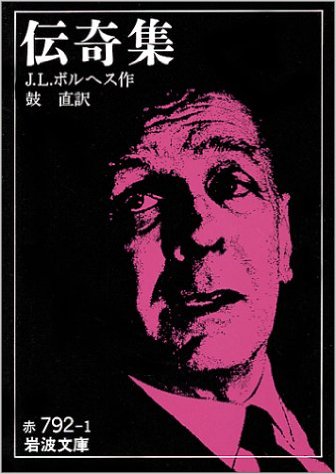
作家に読まれる作家,
らしいのだが,正直,博識と言うよりも,
ペダンチック(pedantic),
の匂いがして,好きになれなかった。読むたびにこっちの無知を思い知らされるせいかもしれない。
架空の小説についての評論をする,
というスタイルや,
架空の地域を推理していく,
というスタイルや,
喩の喩を積み重ねていく,
という寓意スタイルや,
小説の方法そのものについて書いていく,
スタイル等々,その方法そのものが作品世界になっているものが多い。その意味で,たぶん,
メタ・ポジション,
から眺めるのが好みなのだと,その知的奥行に圧倒されながら,思う。例えば,著名な,
『バベルの図書館』
は,いろんな読み方ができるだろうが,さながら,キアヌ・リーブス主演の『マトリックス』のように,ハイパー空間そのものにいるように感じさせる。そこでは,すべてがメタ化されている。いや,すべては,どこまでも,
メタメタメタメタ…化,
される。そういう空間に入り込んだが最後,
メタ化,
の誘惑から逃れられなくなる。
「図書館は全体的なもので,その書架は二十数個の記号のあらゆる可能な組み合わせ―その数はきわめて膨大であるが無限ではない―を,換言すれば,あらゆる言語で表現可能なもののいっさいをふくんでいると推測した。いっさいとは,未来の詳細な歴史,熾天使らの自伝,図書館の信頼すべきカタログ,何千何万もの虚偽のカタログ,これらのカタログの虚偽性の証明,真実のカタログの虚偽性の証明,パシリデスのグノーシス派の福音書,この福音書の注解,この福音書の注解の注解,あなたの死の真実の記述,それぞれの本のあらゆる言語への翻訳,それぞれの本のあらゆる本のなかへの挿入,などである。」
「他のすべての本の鍵であり完全な要約である,一冊の本が存在していなければならない。」
「本Aの所在を突き止めるために,あらかじめ,Aの位置を示す本Bにあたってみる。本Bの所在を突き止めるために,あらかじめ本Cにあたってみる。」
マトリックスというか,すべてデジタル化された0と1が浮遊し,随時に組み合わされていく。当然要約も目次も,自在である。
全てがある,
と同時に,それは,
すでに書かれてもいる,
というわけである。
『円環の廃墟』は,
「おのれもまた幻にすぎないと,他者がおのれの夢をみているのだと悟った。」
入れ子の夢,夢の夢の夢…であるが,これは,作家によった紡がれる作品世界そのものの喩でもある。
『死とコンパス』は,犯罪を追っかけている刑事が,犯罪者の描いた筋書き通りに辿り着いて,挙句,犯人に殺されるストーリーの経過,つまり推理のプロセスは,中井英夫の『虚無への供物』の,アンチ推理小説のようなおかしさがある。それを謎解きしていく理屈をあざ笑うように,犯人が辿り着いた地で待ち伏せている。ここにも,
メタ推理小説,
の視点がある。僕は,『隠された軌跡』が面白いと思う。戯曲を執筆中,ゲシュタポに逮捕された主人公は,神に,「一年の猶予」を乞う。銃殺刑で,銃殺隊の前に立たされ,
「軍曹が大きな声で最後の命令をくだした。
物理的な世界が静止した。
銃の先はフラディークに集まっていたが,彼の命を絶とうとする人間たちは動かなかった。軍曹の腕は動作の途中で止ったままだった。中庭の敷石のひとつに,一匹の蜜蜂が動かぬ影を投げていた。風はやんでいた,絵のなかのように。フラディークは試しに叫び,一個のシラブルを発音し,手でひねってみた。麻痺状態にあることがわかった。不動の世界からは,かすかな物音ひとつ彼のところへ達しなかった。私は地獄にいる,死んだのだ,と彼は考えた。狂ったのだ,と考えた。時間が止まったのだ,と考えた。だが,すぐに,それならば,自分の思考も停止しているはずだと思いなおした。」
そしてただ,記憶をたよりに,
「彼はその戯曲を結末まで持っていった。あとは,ただ,ひとつの形容詞をどうするかという問題だった。ついにそれを見つけた。水滴が彼の頬からすべり落ちた。もの狂おしい絶叫が口をついて出,顔をそむけた。四重の斉射が彼を倒した。」
「アキレスと亀」ではないが,一瞬が,一年にのびたような時間感覚の中で,主人公は,作品を完成させて,殺された。
参考文献;
J・L・ボルヘス『伝奇集』(岩波文庫) |
|
社会的共通資本 |
|
宇沢弘文『宇沢弘文の経済学 社会的共通資本の論理』を読む。
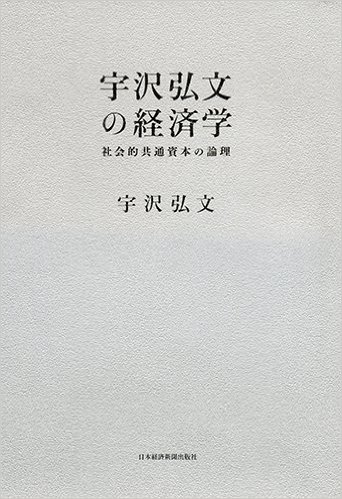
本書の著者について,解説の小島寛之氏は,
「一般には,アメリカ時代と帰国後では別種の経済学を展開したと評されることが多い。アメリカ時代は,経済学の主流派である新古典派と呼ばれる学派の方法論を用い,帰国後は制度学派と呼ばれる学派の方法論に転じたということである。
前者は,数学モデルを用いて,いわば物理学のような方法で経済現象の法則を解明する。他方,後者は,歴史学・文化論・社会思想などの総合的な観点から,主に人文学的な手法を使って,経済のあり方を分析するものである。この二つの方法論は,ある意味では相容れない水と油のような関係にある。」
と。本書は,帰国後の,
社会共通資本の理論,
についての解説書になる。本来は,生前私家版として刊行されたものを,再編集して上梓されたものになる。
アダム・スミスから書きはじめる本書で,
「スミスは,『道徳感情論』で,ハチスン,ヒュームの思想を敷衍して,共感(sympathy)という概念を導入し,人間性の社会的本質を明らかにしようとしたのであった。人間性のもっとも基本的な表現は,人々が生き,喜び,悲しむというすぐれて人間的な感情であって,この人間的な感情を素直に,自由に表現できるような社会が新しい市民社会の基本原理でなければならないと考えた。しかし,このような人間的な感情は個々の個人に特有なもの,あるいはその人だけにしかわからないという性格のものではなく,他の人々にとっても共通のものであって,お互いに分かち合うことができるようなものである。このような共感の可能性を秘めているのが人間的感情の特質であって,人間存在の社会性を表現するものでもある。」
そして,「市民社会を,このような共感の可能性を秘めた社会的人間の集団としてとらえようとする」のが,スミスの考え方の基礎にあった,と。それは,
「一人一人の市民が,人間的な感情を素直に,自由に表現し,生活を享受することができるような社会,それが新しい市民社会の理念であるが,そのような社会を形成し,維持するためには,経済的な面で十分にゆたかになっていなければならない。健康で文化的な生活を営むことが可能となるような物質的生産の基礎がつくられていなければならないというのがスミスの考え方だった。」
その考え方の上に,
「『国富論』は,このような意味で,『道徳感情論』を基礎において,新しいリベラルな市民社会の経済原理を明らかにしようという意図をもって書かれたものであった。」
と。この中に,著者の思いもまた詰まっているように見える。なぜなら,ジョン・スチュアート・ミルは,それを受けて,
Stationary state
つまり,
「マクロ経済的にみたとき,すべての変数は一定で,時間を通じて不変に保たれるが,ひとたび社会の中に入ってみたとき,そこには,華やかな人間的活動が展開され,スミスの『道徳感情論』に描かれているような人間的営みが繰り広げられている。新しい製品がつぎからつぎに創り出され,文化的活動が活発に行われながら,すべての市民の人間的尊厳が保たれ,その魂の自立が保たれ,市民的権利が最大限に保証されているような社会が持続的(sustainable)に維持されている。このようなリベラリズムの理念に適ったstationary
stateを古典派経済学は分析の対象にしたのだとミルは考えたのである。」
果たして,ミルのいうような,
「国民所得,消費,投資,物価水準などといあうマクロ的諸変数が一定に保たれながら,ミクロ的にみたとき,華やかな人間的活動が展開されているという」
Stationary state
は,現実に実現可能なのか,この設問に答えたのが,著者の依拠するソーンスティン・ヴェブレンの,
制度主義の経済学,
だからである。それは,
「さまざまなsocial common
capital(社会的共通資本)を社会的な観点から最適なかたちに建設し,そのサービスの供給を社会的な基準にしたがっておこなうことによって,ミルのstationary
stateが実現可能になるというように理解することができる。」
言い換えれば,
Sustainable development(持続的開発),
の状態を意味する。
著者は,ヴェブレンを,
「ヴェブレンがリベラリズムというとき,それは,人間の尊厳と自由を守るという視点に立って,経済制度に関する進化論的分析を展開する…。」
と評する。ヴェブレンは,女性のドレスをめぐって,
「経済学でふつう想定されている,効用最大化を求めて各人が合理的に選択するという理論的前提では,…女性のドレスについては適用することができない。ヴェブレンは,女性のドレスを論ずることによって,当時支配的であった新古典派経済学(こう表現したのもヴェブレンが最初である)の考え方を批判し,否定しょうとしたのであった。」
と。制度派の考え方は要約すると(アーロン・ゴードンによると),
「すべての経済行動は,その経済主体が置かれている制度的諸条件によって規定される。と同時に,どのような経済行動がとられたかによって,制度的諸条件も変化する。この,制度的諸条件と経済行動との間に存在する相互関係は,進化のプロセスである。環境の変化にともなって人々の行動が変化し,行動の変化はまた,制度的環境の変化を誘発することになり,経済学に対して,進化論的アプローチが必要になってくる。」
そして,それを担う人間像は,
「進化論的立場に立ちとき,人間のとらえ方は180度転換する。人間の本性は,行動するということにある。たんに,外部的な力を受けて,喜びや苦しみを味わう,受動的な存在ではない。人間は,たんなる欲望の塊として,環境の影響を受けて,その力に翻弄されるにまかせるという受動的な存在ではない。絶えず新しい展開を求めて,夢をもち,その夢を実現しようとする本源的な性向と,歴史的に受けついできた習慣とをもった,一個の有機体的存在である。人間の活動,特に経済活動は,所与の欲望を最大にするようなものではなく,行動自体が,このプロセスにとって本質的なものである。このような行動を誘発する満足ということは,このような行動によって各人の気質的(テンペラメントな)環境がどのように変化するかということの結果にすぎない。」
という高らかな人間のイメージがいい。そこでの経済活動は,「それぞれの社会の基本的条件を規定する」,
社会的共通資本,
によって左右される。社会的共通資本とは,
「1つの国ないし特定の地域が,ゆたかな経済生活を営み,すぐれた文化を展開し,人間的に魅力ある社会を持続的,安定的に維持することを可能にするような自然環境,社会的装置を意味する。社会的共通資本は,たとえ私有ないし私的管理が認められたとしても,社会全体にとって共通の財産として,社会的な基準にしたがって管理・運営される。」
それは,
「土地をはじめとする,大気,土壌,水,森林,河川,海洋などの自然資本だけでなく,道路,上・下水道,公共的な交通機関,電力,通信施設などの社会的インフラストラクチャー,さらに教育,医療,金融,財政制度などという制度資本も含む。」
その観点から,
都市,コモンズ(入会制のような),
地球環境(温暖化),
学校教育,
医療,
金融制度,
等々が各論で論じられていく。
「社会的共通資本は,官僚的な基準ないしルールにしたがって行われるものではない…。(中略)各機構はそれぞれ該当する社会的共通資本の管理を社会から信託されているのであって,その基本的原則はフィデュシアリー(fiduciary)の概念にもとづくものでなければならない。」
今日わが国の,豊洲市場の経緯や水道事業の私企業への売却等々の制度のありようを観るとき,もはや何をかいわんや,である。随所に著者の憤りが,生の声で聞えてくる。
参考文献;
宇沢弘文『宇沢弘文の経済学 社会的共通資本の論理』(日本経済新聞出版社) |
|
怪奇 |
|
岡本綺堂『中国怪奇小説集』を読む。

これはいわば,志怪小説集とも言うべきものだ。「志怪」とは,
「怪を志(しる)す」
という意味である。
三遊亭圓朝の創作した怪談噺「牡丹灯籠」は、中国明代の小説集『剪灯新話』に収録された小説『牡丹燈記』に着想を得ている,というように,中国から翻案したものが少なくない。
志怪小説については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/434978812.html
で触れた。「小説」は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/432692200.html
で触れたように,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
であり,『日本大百科全書(ニッポニカ)』には,
「中国、六朝(りくちょう)時代にもっとも盛んに記録された説話の名称。「怪を志(誌)(しる)したもの」という意味の命名で、この種の話には怪奇な内容をもつものが多いところから、近代中国の文学史家によって名づけられたものである。志怪小説ともよばれ、特異な人物の事跡を記録した志人小説という説話群と相対する説話群の呼称でもある。六朝も早期の三国・晋(しん)のころの志怪には、昔話や伝説など、民間伝承の記録とみられるものが多いが、劉宋(りゅうそう)以降、六朝期後半の志怪書には、仏教や道教の功徳(くどく)を説く宗教説話がしだいに数を増してくる。しかし今日原形をとどめる志怪書は1本もなく、いずれも後人が『太平広記(たいへいこうき)』や『太平御覧(たいへいぎょらん)』などの類書に引かれ残っていた六朝志怪書の断片を拾い集めて作り直したようなものばかりである。また原話の筆録に忠実でなく、話の骨子だけを記したようなものも多い。」
その意味で,いま言う小説のはしり,ということになる。ただし,
「昔、中国で稗官(はいかん)が民間から集めて記録した小説風の歴史書。また、正史に対して、民間の歴史書。」
であり,それが転じて、作り物語。転じて,広く,小説になっていくが,ここに登場するものは,
「面白い話ではあるが作者の主張は含まれないことが多い。」
のである。その意味で,後に,
「俗語で書かれた『水滸伝』『金瓶梅』などの通俗小説へと続いていく。」
が,それとは一線を画す。取り上げられているのは,
捜神記(六朝)
捜神後記(六朝)
酉陽雑爼(唐)
宣室志(唐)
白猿伝・其他(唐)
録異記(五代)
稽神録(宋)
夷堅志(宋)
異聞総録・其他(宋)
続夷堅志・其他(金・元)
輟耕録(明)
剪灯新話(明)
池北偶談(清)
子不語(清)
閲微草堂筆記(清)
である。清の時代の頃のものは,書き手自体が,話を信じておらず,安っぽい種明かしをしたりするので,かえって興醒めである。たとえば,
『閲微草堂筆記』の「木偶の演戯」
では,
「わたしの先祖の光禄公は康煕年間、崔荘で質庫を開いていた。沈伯玉という男が番頭役の司事を勤めていた。
あるとき傀儡師が二箱に入れた木彫りの人形を質入れに来た。人形の高さは一尺あまりで、すこぶる精巧に作られ
ていたが、期限を越えてもつぐなわず、とうとう質流れになってしまった。ほかに売る先もないので、廃り物として空き屋のなかに久しく押し込んで置くと、月の明るい夜にその人形が幾つも現われて、あるいは踊り、あるいは舞い、さながら演劇のような姿を見せた。耳を傾けると、何かの曲を唱えているようでもあった。
沈は気丈の男であるので、声をはげしゅうして叱り付けると、人形の群れは一度に散って消え失せ
た。翌日その人形をことごとく焚いてしまったが、その後は別に変ったこともなかった。
物が久しくなると妖をなす。 それを焚けば精気が溶けて散じ、
再び聚まることが出来なくなる。また何か憑る所があれば妖をなす。それを焚けば憑る所をうしなう。それが物理の自然である。」
と,まるで高みから見下しているかのようである。いわゆる,
付喪(つくも),
の謂いである。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163408.html
で書いたように,日本の民間信仰において,長い年月を経て古くなったり,長く生きた依り代(道具や生き物や自然の物)に,神や霊魂などが宿ったものの総称で,荒ぶれば(荒ぶる神・九尾の狐など)禍をもたらし,和(な)ぎれば(和ぎる神・お狐様など)幸をもたらすとされる。
「付喪」自体,
長く生きたもの(動植物)や古くなるまで使われた道具(器物)に神が宿り,人が大事に思ったり慈しみを持って接すれば幸をもたらし,でなければ荒ぶる神となって禍をもたらすといわれる。親しみ,泥んだものや人や生き物が,邪険にされて妖怪と化す,というそれである。
しかし,こういう訳知り顔の語りは,「牡丹灯籠」の元になった,明代の『剪灯新話』「牡丹燈記」にはない。
http://www.aozora.gr.jp/cards/001078/files/4999_12230.html
を読んでいただくと,三遊亭圓朝が「牡丹燈籠」で,どう変えたのかもよくわかる。
宋代の,『夷堅志』「餅を買う女」も,おなじみだ。
小夜の中山の夜泣石の伝説も、支那から輸入されたものであるらしく、宋の洪邁の「夷堅志」のうちに同様の話がある。
「宣城は兵乱の後、人民は四方に離散して、郊外の所々に蕭条たる草原が多かった。
その当時のことである。民家の妻が妊娠中に死亡したので、その亡骸を村内の古廟のうしろに葬った。その後、廟に近い民家の者が草むらの間に灯のかげを見る夜があった。あるときはどこかで赤児の啼く声を聞くこともあった。
街に近い餅屋へ毎日餅を買いにくる女があって、彼女は赤児をかかえていた。それが毎日かならず来るので、餅屋の者もすこしく疑って、あるときそっとその跡をつけて行くと、女の姿は廟のあたりで消え失せた。いよいよ不審に思って、その次の日に来た時、なにげなく世間話などをしているうちに、隙をみて彼女の裾に紅い糸を縫いつけて置いて、帰るときに再びそのあとを附けてゆくと、女は追ってくる者のあるのを覚ったらしく、いつの間にか姿を消して、赤児ばかりが残っていた。糸は草むらの塚の上にかかっていた。
近所で聞きあわせて、塚のぬしの夫へ知らせてやると、夫をはじめ一家の者が駈けつけて、試みに塚を掘返すと、女の顔色は生けるがごとくで、妊娠中の胎児が死後に生み出されたものと判った。
夫の家では妻のなきがらを灰にして、その赤児を養育した。」
この手の話は,日本では,
飴を買う幽霊,
等々という呼ばれ方をして,
子育て幽霊,
として知られている。その辺りは,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E5%B9%BD%E9%9C%8A
に詳しい。
たとえば,
「ある民家で、妻が妊娠中に死亡し、埋葬された。その後、町に近い餅屋へ、赤ちゃんを抱えた女が毎日餅を買いに来るようになった。餅屋の者は怪しく思い、こっそり女の服のすそに赤い糸を縫いつけ、彼女が帰ったあとその糸をたどってゆくと、糸は草むらの墓の上にかかっていた。知らせを聞いた遺族が墓を掘り返してみると、棺のなかで赤ちゃんが生きており、死んだ女は顔色なお生けるがごとくであった。女の死後、お腹の中の胎児が死後出産で生まれたものとわかった。遺族は女の死体をあらためて火葬にし、その赤児を養育した。」
と。まあ,上記「子育て幽霊」では,
「この手の話は日本各所にあるが色々と考察できる。
説法による真実性を増すためにでっちあげ説
飴の販売促進のための飴屋による宣伝説
禁忌を破り子を生した僧の外分を保つための保身説
墓場に捨てられた赤子が拾われた場合の出所説
なお、幽霊の墓と寺、子供の引き取った寺・その後の進退の寺、飴屋の場所と屋号、全て揃って伝わっているのは京都の話だけである。」
とするが,江戸時代(寛文年間1660年代)に,
『伽婢子(おとぎぼうこ)』
『狗張子(いぬはりこ)』
が,志怪小説の翻案として,出されている。中国で志怪小説『夷堅志』に取り上げられたのが,宋代なので,日本で流布する600年前になる。あるいは,中国伝来なのではないか。
参考文献;
岡本綺堂『中国怪奇小説集』Kindle版
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E6%80%AA%E5%B0%8F%E8%AA%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E6%9C%88%E7%89%A9 |
|
スーパーヴィジョン |
|
平木典子『心理臨床スーパーヴィジョン−学派を超えた統合モデル』を読む。
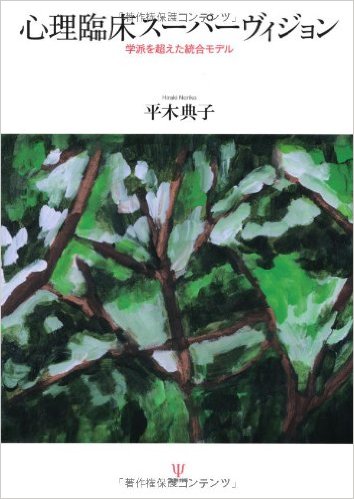
本書は,「はじめに」と「おわりに」で,つぶさに,著者の問題意識が説明されている。
「心理臨床におけるスーパーヴィジョンについては,これまで個々の心理臨床職やその指導・訓練に携わる専門家,あるいは各学派内でさまざまな形で検討されてきた。しかし,その検討は主として学派内あるいは個人内に止まっており,スーパーヴィジョン全般,あるいは個人や学派を超えたスーパーヴィジョンについて検討されたものは非常に少ない。
そのような現状を背景にして1991年に心理臨床職専門の養成を開始した大学院修士課程で,スーパーヴィジョンに力点を置いた訓練を開始することになった筆者は,個人・学派を越えた汎用性のある,あるいは統合的なスーパーヴィジョンの必要性を切に感じていた。
それまで筆者が行っていたスーパーヴィジョンは,個人的に求められて行うものであったため,個人の志向性,学派の特徴はスーパーヴァイジーとスーパーヴァイザー双方の選択と契約の中に含まれていることで,ほとんど問題にならなかったのだが,心理臨床の初心者にそれは適応できないという基本問題に直面したのである。
個人技と言える境地に達している心理臨床家であれば,相手の特徴に応じた臨機応変のスーパーヴィジョンができるだろう。ところが,臨床家の成長の歩みの途中に居る指導者が,とりわけ初心者に適したスーパーヴィジョンを行うには,相応の視野と訓練が必要なのではないか,ということでもあった。」
「おわりに」にこう書いた問題意識の背景にあるのは,スーパーヴィジョンには,
視点の多様性,
がいるということのようなのである。たとえば,
ケースに登場するクライエントの立場に立った時は,
「その苦しみや人間関係を味わい,またクライエントに同一化してセラピストの言動に安堵したり,反発を感じたりする。」
自分をセラピストの位置に置いた時は,
「アセスメントや介入を思案し,セラピーの進行やセラピストとしてのあり方などをふり返り,クライエントの状態に思いを馳せるだろう。」
スーパーヴァイジーの立場に立った時は,
「その不安や緊張がひしひしと感じられ,スーパーヴァイザーの一言一句に抵抗や感動を味わったり,自己の未熟さに恥いったりする…。」
スーパーヴァイザーの立場に立った時は,
「セラピストとクライエントの関係やその関係におけるセラピストの支援のポイントに関心が向き,スーパーヴァイザーとして必要な動きや介入に心を砕く。」
観察舎の立場に立つ時,
「異なる視点と立場を持った登場人物の知りえない体験と関係を思い,人間模様の多様性と複雑さを俯瞰することの難しさに目がくらむ。」
という視点を挙げて,スーパーヴァイザーには,
「ケースの中の①クライエント,②カウンセラー,スーパーヴィジョンにおける,③スーパーヴァイジー,④スーパーヴァイザー,そしてそれらすべてを総合した⑤観察者という5つの視点」
が必要なのだと,言う。しかし,日本には,北米で進められているような,
スーパーヴィジョン独自の理論モデル
もなく,
理論横断的なスーパーヴィジョン・モデルの開発,
もなく,個人技に委ねられている。そこには,
「スーパーヴィジョンを受けた経験,あるいは臨床実践経験があれば,スーパーヴィジョンができるといった思い込みがあったと思われる。しかし,指導者各自の臨床実践領域(教育,産業,医療など)における長年かけて身につけた独自の心理臨床モデル(たとえば精神分析,家族療法,コミュニティ心理学など)の活用と工夫は,即初心の心理臨床家の養成・訓練に適用できるとは限らない。また,それは臨床現場のセラピストに対する訓練やスーパーヴィジョンとも同じではない。」
だから,
「指導者が,スーパーヴァイザー・トレーニングを受けていない」
ことと,
「心理臨床モデルを超えたスーパーヴィジョン・モデル」
がないことによる,現在の我が国の指導層の抱える問題は,
第一に,スーパーヴィジョンを受けた経験はあっても,スーパーヴァイザー訓練を受けていないこと,
第二に,心理臨床理論の多様なモデル間の相互交流が少ないこと,
第三に,スーパーヴィジョンの基本理論,特に訓練生に対するスーパーヴィジてョンと現場のセラピストに対するスーパーヴィジョンは異なることに配慮を欠き,さらに,スーパーヴィジョン,カウンセリング,コンサルテーションの区別が不明確なままで,実践指導をしていること,
と指摘する。サブタイトルが,
学派を超えた統合モデル,
とある所以である。
さて,スーパーヴァイザーは,上述のように5つの視点を駆使するのだが,
「スーパーヴァイザーとは,スーパーヴァイジーセラピストのとしての発達やつまずきの様相,特定のクライエントの理解や関係の力動などの相互作用を受けとめながら,適切な場面とタイミングを選択して介入できる人である。そのような指導が訓練生を専門職として出立させ,同僚の臨床に磨きをかけていく。あらためて,スーパーヴィジョンとは,する側と受ける側の現実の可能性が結果として現れる畏るべき事実に気づかされる。」
と,著者の述懐する通り,だからこそ,特別なスーパーヴァイザーの訓練数不可欠なのである。
スーパーヴィジョンの普遍的な原則を5つ挙げている。
1.スーパーヴィジョンには,同時進行する重層的人間の相互作用とその文脈を理解するメタ知識が必要である。
2.スーパーヴィジョンは,スーパーヴァイザーとスーパーヴァイジーの「スーパーヴィジョン同盟」とも呼ぶべき安定した関係の上に成り立つ。
3.スーパーヴィジョンの介入は,スーパーヴァイジーのセラピストとしての発達に応じて行われる。したがって,スーパーヴァイジーの発達段階に応じた検討内容とプロセスが必要である。
4.学びと成長が醸成されるスーパーヴィジョンでは,スーパーヴァイザーとスーパーヴァイジーのアサーティヴなコミュニケーションがある。
5.スーパーヴィジョンは,セラピーの質を高めるためのふり返りと評価を含む指導から成り立っており,その目的は,スーパーヴァイジー自身が頼れる内的スーパーヴァイザーを自己内に育てることである。
これを踏まえた,スーパーヴィジョンの理論とプログラムモデルが,
第2章 心理臨床スーパーヴィジョンの基本,
第3章 スーパーヴィジョンの統合モデル,
第4章 さーパーヴィジョンの形式と方法
第5章 スーパーヴィジョンの実際
と展開される。いまのセラピスト育成システムと育成プログラムがどうなっいるかわからないが,寡聞にして,そうしたシステムが横断的にできたという話は聞かない。
参考文献;
平木典子『心理臨床スーパーヴィジョン』(金剛出版) |
|
臨床実習 |
|
友久久雄・吉川 悟編『臨床心理実習マニュアル』を読む。

本書は,臨床心理士養成課程の大学院生のために,
「実習の場に学生が赴く前段階で,最低限の座学の延長として『実習先が実習生に知っておいてもらいたい』と考えておられる内容を整理したもの」
である。本来,学内向けの,
実習マニュアル,
ベースにしている。
本書中にもあったが,
「現在の大学院生に見られる特性として,『教わることはできるものの,学ぶことができない』『自ら進んで自己研鑽のために,自ら研修会,研究かいに参加する力が弱く,いわゆるハングリー精神に欠ける』」
という指摘がある。よく言われることだ。しかし,僕はそうは思っていない。昔だって,そんなに学ぶ力があったとは思わない。むしろ,社会が,受け入れる企業が,即戦力を求めるためだ,と思う。要は,寛容さというか,余裕というか,懐が浅くなったにすぎない。実習で,試行錯誤すること自体が,スキルだけではなく,精神を鍛えていくために不可欠な学びの場だという受け入れ側の姿勢の欠如が,結局芯のある人材を育て損なっているとしか思えない。それと,根本的には,平木典子先生が,『心理臨床スーパーヴィジョン』で指摘しておられるが,我が国には,個々のセラピストや教員に依存するのではない,公的な育成の仕組みと育成プログラムが確立していないせいでもあるようだ。
臨床心理実習は,
クリニック実習に適応していくため,社会的な常識を身につける,
クリニックで求められている治療者との関係,他のスタッフとの関係,あるいは実践の場面に触れることなとで,自ら身につけるべき資質・能力・知識について気づく,
現実の社会的なニーズの一部をクリニックで体験し,それに向けての自己研鑽の場とする,
心理担当者に要求される資質を知ることで,現在の自己に目を向け,柔軟性,臨機応変さを身につける,
というならなおさらだ。しかし,大事なことが抜けている。自分が向いていないと思ったら,転身するための最後のチャンスであるかもしれない,ということだ。上記のようなことを,改めて言い聞かせられなければならないのだとすると,そんなことすら,学んでいないのかもしれないからだ。
本書は二部構成になっていて,第一部は,
「実習のための基本」」
として,
臨床心理実習に当たっての心得,
臨床心理実習の領域別基本事項,
等々,実習のための基本的なガイドラインであり,
「臨床心理學的実践においては,多様なオリエンテーションが存在するとともに,多様な現場があり,それぞれに臨床心理士に対する要請は異なるものとなっています。それらに共通する基本中の基本ともいえる部分だけを取り出し,整理した内容」
になっている。
第二部は,
「実習のための臨床メモ」
として,
妄想と幻覚,
うつ病,
パーソナリティ障害,
発達障害,
心身症,
自傷行為,
摂食障害,
強迫性障害,
ひきこもり・不登校,
トラウマ,
虐待やDVなどの家族の問題,
症例を病名の区分によってだけではなく列挙しているところが特徴で,
「学生が実習先で出会うであろういくつかの疾患について,基本的な立場から解説を行っています。ここでは疾患や行動障害だけでなく,事例の理解に結びつくためのクライエントの背景にある家族に対するアセスメントを含めています。個々の疾患を理解するためのガイドラインはいくつも存在していますが,実質的な事例を理解し対応するために必要なことは,現場で要請されるクライエントからのさまざまな訴えをどのように把握しておくべきか,日常的な影響を与えている家族をどのように面接の中に位置づけるべきか,そして,事例の全体像をどのように理解すべきかなどを示しています。」
となっており,
事例の背景にある「家族」を考慮すること,
という項目にウエイトをおいていることが,編者たちの立場をよく示しているが,この部分は,実習生のみならず,実践的に非常に参考になる。
参考文献;
友久久雄・吉川 悟編『臨床心理実習マニュアル』(遠見書房)
平木典子『心理臨床スーパーヴィジョン』(金剛出版) |
|
新吾 |
|
呂新吾『呻吟語』を読む。
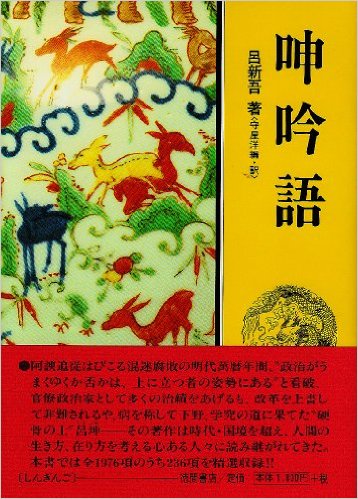
呂新吾は,名を坤,字を叔簡,新吾は号である。
「吾を新たにする」
である。どうやら硬骨の人であったらしい。
「吏治,良なきは,いまだ大吏より治まらざるものにあらず」
と,上に立つものの姿勢にあるとして,
「およそ事,皆自ら責め自ら任じ,饋遺贖羨,尽くこれを途絶す」
というほど,おのれの身を律した。だから中央に出ても,同じ姿勢を貫き,
「大臣,交わりを内侍(宦官)に結ぶば,律に明筋り。いわんや素いまだ面を識らざるをや」
と,実力者(宦官)の贈り物すら突っ返した。しかも,朝廷の乱れに,数千言から成る上書を奉り,ために,身を引くこととなる。
「先生,憂危の疏数千言を草してこれを上(たてまつ)る。これを悪(にく)む者,中(あ)つるに奇禍を以てす」(『呂新吾伝』)
で,自らも,墓誌銘に,こう記す。
「性,直にして委婉なし。厳毅にして温燠少なし。官に居りては法を持して情涼(ひややか)に,家に居りては義勝ちて恩薄し。事に当たりては過激にして涵養の功疏(うと)し」
と。だからこそ,誰ぞのアフォリズムのように,偉そうではなく,内々の葛藤が忍ばれる文言が少なくない。
だから,自序に,
「呻吟は,病声なり,呻吟語は,病む時の疼痛の語なり。病中の疼痛は,ただ病者のみ知る。他者と与(とも)に道(い)い難し。またただ病む時のみ覚ゆ。すでに愈(い)ゆれば,施(たちま)ちまた忘る。」
と,「呻吟語」の謂れを書き,
「余矍然(かくぜん)として曰く,『病者は狂なり,またその狂なる者を以て人の聞聴を惑わすは,可ならんや。』因ってその狂にしていまだ甚だしからざる者を択びてこれを存す。」
と認める。今やわが国にも本家中国にも消えた,
修身斉家治国平天下,
つまり,
「天下を平らかに治めるには,まず自分のおこないを正しくし,次に家庭をととのえ,次に国を治めて次に天下を平らかにするような順序に従うべきである。」(『大学』)。
の思想の血肉である。その葛藤であり,その自問自答である。
たとえば,
「天下国家の存亡,身の生死は,ただ敬怠の両字に係る。敬すれば則ち慎む。慎めば則ち百務修まり挙ぐ。怠れば則ち苟(かりそ)めにす。苟(かりそ)めにせば則ち万事隳(やぶ)れ頽(くず)る。天子より庶人に至るまで,かくの如くならざるはなし。」
と。しかし,他人事としてそう言っているのではない。
「その行わざるを得ざる所に行い,その止まらざるを得ざる所に止る。言に於けるや,その語らざるを得ざる所に語り,その黙せざるを得ざる所に黙す。尤悔(ゆうかい),寡(すくな)きに庶幾(ちか)し。」
とある背後に,山のように悔いがあったに違いないのである。
「事に当たらざれば,自家の才を済(な)さざるを知らず。遇に随い識を長じ以て精を窮む。坐談先生はただ好みて理を説くのみ。」
「公論は衆口一詞の謂いに非ざるなり。満朝皆非にして一人是なれば,則ち公論は一人にあり。」
「愈いよ上れば則ち愈いよ聾瞽(ろうこ)なり。」
「人を恕するに六つあり。いまだ真ならざる処あらん。或いは彼の力量,及ばざらん処あらん。或いは彼の心事,苦しむ所の処あらん。或いは彼の精神,忽(ゆるがせ)にする所の処あらん。或いは彼の微意,在る所の処あらん。この六つを先にし,而してこれに命ずれども従わず,これに教うれども改めずして,然る後に罪すべきなるのみ。」
等々。葛藤が見える気がする。それにしても,
「貧しきは羞(は)ずるに足らず,羞ずべきはこれ貧しくて志なきなり。賤(いや)しきは悪(にく)むに足らず。悪むべきはこれ賤しくて能なきなり。老ゆるは嘆くに足らず,嘆くべきはこれ老いて虚しく生きるなり。死するば悲しむに足らず,悲しむべきはこれ死して聞ゆるなきなり。」
はかなりきつい。
参考文献;
呂新吾『呻吟語』(徳間書店)
金谷治訳注『大学・中庸』(岩波文庫) |
|
神社 |
|
島田裕巳『なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか』を読む。
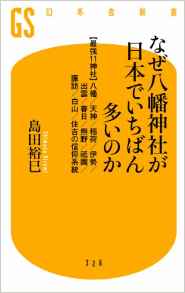
本書では,代表的な神社の祭神の由来を解きほぐしていくが,ほぐせばほぐすほど,由来がはっきりしなくなるのが特徴と言えば特徴で,しかも神仏習合が信仰の中で根付いていたものを無理やり,明治政府が剥離したために,どこかいびつなものになっていることもよくわかる。取り上げているのは,
八幡,
天神,
稲荷,
伊勢,
出雲,
春日,
熊野,
祇園,
諏訪,
白山(日吉),
住吉(宗像,恵比寿,金毘羅),
だが,この理由の多くは,神社数の多さからきているようだ。神社本庁調べでは,
一位は,八幡信仰に関わる神社7817社(八幡神社,八幡宮,若水緒神社など),
二位は,伊勢信仰に関わる神社4425社(神明社,神明宮,皇大神社,伊勢神宮など),
三位は,天神信仰に関わる神社3953社(天満宮,天神社,北野神社など)
四位は,稲荷信仰に関わる神社2970社(稲荷神社,宇賀神社,稲荷社など),
五位は,熊野信仰に関わる神社2693社(熊野神社,王子神社,十二所神社,若一王子神社など),
六位は,諏訪信仰に関わる神社2616社(諏訪神社,諏訪社,南方神社など),
七位は,祇園信仰に関わる神社2290社(八坂神社,須賀神社,八雲神社,津島神社など),
八位は,白山信仰に関わる神社1893社(白山神社,白山社,白山比迠神社,白山姫神社など)
九位は,日吉信仰に関わる神社1724社(日吉神社,日枝神社,山王社など)
十位は,山神信仰に関わる神社1571社(山神社など)
と続いて,春日進行,三島・大山祇信仰,鹿島進行,金毘羅信仰,と続くらしい。
日本の神々は,
神話に根ざした神々,
記紀神話に登場せず,歴史の中で新たに祀られた神々,
人を神として祀ったもの,
の三種があり,しかも,神々は,
「誰を神と祀ろうと,それは祀るものの自由で,どこかの許可を必要とするわけではない。その点で,日本の神の数は常に増え続けていくわけで,今後も増えていくものと考えられる」
ということで,実は神社の総数を数えることが難しい。しかも,神の祀り方も数え方を難しくしている,という。
「同じ祭神を祀っている神社であっても,個々の神社の名称には地名などがついていて,それぞれが区別されている。
たとえば,…荒川区では,稲荷社として,西日暮里の向陵稲荷神社,東日暮里の隼人稲荷神社,南千住の豊川稲荷社,荒川の宮地稲荷神社,町屋の原稲荷神社と,5社が祀られている。どれも祭神は,稲荷神,つまりは宇迦之御魂神(別名・倉稲荷魂命)である。
その点で,どれも同じ神を祀る神社ということになるが,地域の人たちはそれぞれの稲荷社を区別しており,別々の名称で呼んでいる。つまり,宮地稲荷神社と原稲荷神社は,別の神を祀る神社としてとらえられているわけだ。となると,現実的には,荒川区内には,一つではなく5つの稲荷神が祀られていることになる。」
しかも,神社へ参詣に行くとわかるが,
「一つの神社には,本殿のほかに境内社があり,そこには,本殿の祭神とは別の神々が祀られている。」
数を把握することのむつかしさがわかる。例えば,稲荷系は,一応,4位ということになっているが,江戸に多いものとして,
火事喧嘩伊勢屋稲荷に犬の糞,
と言われたように,稲荷社は数が多いが,さらに,
「ほかの神社の境内に摂社や末社として稲荷社が祀られている事例がかなり見られる。…かえって稲荷社がない神社の方が珍しい。…街角に小さな稲荷社が祀られていることも多い。…屋敷神として祀られている稲荷社もかなりの数にのぼるが,企業が本社のビルの屋上に稲荷社を祀っている例もある。」
ということで,稲荷社と名乗る神社以外の,摂社末社や街中の小詞を数え上げれば,膨大な数の稲荷社が存在することになる,ということらしい。
「数としては,稲荷社が実際には一番多いはずだ。」
と,表題とは矛盾する,結論になる。ことほど左様に,神社を数えることのむつかしさであろう。
本来,仏教と神道は分かちがたく結びついて,信仰を形作ってきた。それを無理やり,分離し,廃仏毀釈をした結果,庶民は,別のことを考える。伏見稲荷の千本鳥居は有名だが,実は,明治以降のことらしい。
「伏見稲荷に残された絵図に,『稲荷山寛文之大絵図』…には,稲荷山全体が描かれ,社殿なども記されているのだが,鳥居はいくつかあるものの,千本鳥居にはなっていない。(中略)また天保年間に…刊行した『江戸名所図会』には,江戸の市中にあったいくつかの稲荷社について,その絵図を掲げているが,どれを見ても,千本鳥居は見いだせない。」
実は,千本鳥居は,お塚の信仰と関係がある。稲荷山に無数に祀られている石碑のことである。これも,『稲荷山寛文之大絵図』には載らない。お塚は,明治政府の「神仏判然令」に基づいて,
「神社に祀られていた仏教関係の仏像を撤去したり,境内にあった神宮寺を廃止」
することとなり,
「伏見稲荷では,神号が稲荷大明神に統一され,他の神名を使うことができなくなった。そこで,自分たちで独自の神を祀っていた人々が,稲荷山の山中に勝手に石碑を建て,それを私的な礼拝施設にした。それがお塚のはじまりだったのである。」
それが明治以降急速に増え,その正確な数は分からない,という。庶民の信仰の抵抗である。
「千本鳥居も,このお塚の信仰の高まりの影響で生まれたのであろう。お塚を建てることは神社側によって規制されている。ならば,鳥居を奉納することでその代りにしよう。それについては,神社側もコントロール可能なので,許容されたのではないだろうか。」
と。
「日本の神々の正体を知ることは,日本人の本当の姿を知ることに結びつく」
のは,廃仏毀釈でぶち壊されたかつての神社のことであって,明治政府による官制神社ではない。
参考文献;
島田裕巳『なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか』(幻冬舎新書) |
|
エスノグラフィー |
|
金井壽宏・佐藤郁哉・ギデオン・クンダ・ジョン・ヴァン-マーネン『組織エスノグラフィー』を読む。
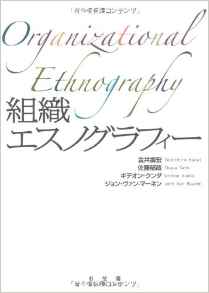
本書は,
金井壽宏,
佐藤郁哉,
ギデオン・クンダ,
ジョン・ヴァン−マーネン,
という四人の(エスノグラフィーの可能性を追及してきた)執筆者による,
組織エスノグラフィーの入門書,
である。エスノグラフィーとは,
民族誌,
と訳されるように,
「人類学におけるフィールドワークおよびその報告書を指す言葉として使われてきたものであるが,次第に社会科学一般におけるフィールドワーク的な作業とその報告書を指す用語として使われるようになってきている」
というものであり,
「他の方法よりも深く調査対象に入り込み,参加者として観察することによって,内部者の見解を解明するためのフィールドワークの報告書(モノグラフ,論文,著書などの作品)のことである。また成果となる作品を指すばかりでなく,フィールドワーク的な調査プロセスそのものを指してエスノグラフィーということもある。この場合の訳語としては『民族誌的調査』というものがある。」
確かに,民族誌というと,人類学者マリノフスキーなどの著作が思い浮かぶが,
「人類学者ロイド・ウォーナーが,シカゴ郊外のホーソン工場に招かれて,働く人の文化や規範に関する調査方法を始動したホーソン実験での観察研究の開始は,1931年であるので,元祖マリノフスキーの著書から10年もたたずに,エスノグラフィーは,近代組織に適用されたことになる。組織エスノグラフィーの起源の古さは,意外に見逃されている。」
というように,未開地の民族誌だけではなく,工場にこの方法が使えると気づいたのは意外と早く,本書の著者たちは,
警察,ハイテク企業,ハイテクベンチャーの企業家の集う場,暴走族,劇団と演劇界,
等々でエスノグラフィーを実践してきている。
そういう著者たちは,本書の特徴を,
「自らの調査を手本,見本として行儀良く提示するのではなく,苦労した点も正直に描いたこと」
「エスノグラフィーの書き方にもこだわったこと」
「『組織』エスノグラフィーに究極の焦点を合わせている点」
の三つを挙げる。金井氏は,組織エスノグラフィーの特徴を,
内部者(現地人,住民)の見解に迫る,
フィールドに住む(長く居るか,少なくとも足繁く通う),
参与観察という方法を重視する,
を挙げている。これは,
フィールドワーク,
という言葉ではなく,
エスノグラフィー,
という言葉が使われている理由とも関わる。それは,
「社会や文化を対象とした現場調査(フィールドワーク)と他の学問分野(たとえば,地学や動物学)における野外調査(フィールドワーク)と明確に区別する」
ということであり,
「同じ社会調査としてのフィールドワークでも,文献研究や資料調査などのようなデスクワークと対比させるためにサーベイのような調査であってもフィールドワークと呼ぶことがある。したがって,これらの調査と参与観察法(一種の『体験取材』)やインフォーマル・インタビューによる密着取材的な現場調査(他のタイプのフィールドワークと区別するために,『民族誌的フィールドワーク[ethnographic
fieldwork])』と呼ばれることも多い)とを区別する」
ために,エスノグラフィーと名づけていることと深くかかわる。
「知らない世界なのに,内部者の考えがわかるためには,そこに入り込むしかない。中に入り込んでそこに住むか,澄むに匹敵するぐらい通って,参与観察を重ねる。その結果,元の目的である,内部者のものの見方まで見えてくる。それは,文化の理解にも近づいているということである。」
しかし,金井氏は言う,
「作品としてのエスノグラフィーを,『読ませる』『読者をうならせる』レベルに熟成させるためには,これら3点は必要条件にすぎない。つまり,『書き方』『物語り方』『読ませ方』にも工夫がいるのである。」
本書が,書き方にこだわっている理由である。
金井壽宏,
佐藤郁哉,
ギデオン・クンダ,
の3氏による,
「研究課題を見つけて,特定の調査対象にアクセスし,中に入り込んでフィールド調査を実施し,フィールドノーツから意味を見出す分析や解釈の作業を行い,その結果を書いていく執筆段階までの,喜びも苦労も,告白を混じえながら描かれている」
第Ⅱ部の「三つの告白」は読みごたえがある。しかし,佐藤氏が引く,
「何にもまして,フィールドワークというのは一つの技芸(わざ)なのであり,本を読むだけで学べるようなものではないということを肝に銘じておく必要がある。ブロック工の修行のようなものである。コツをつかむためには,まず自分の手でやってみなければならない。試行錯誤もあれば,事前に練習しておかなければならないことが多く,また徒弟修業の期間もある。この技芸の多くの部分は口伝や模倣を通して教えられるものであるし,いまだ明らかにされていない部分もかなりある。」
というジェラルド・サトルズ教授の言葉が印象的である。
参考文献;
金井 壽宏・佐藤 郁哉・ギデオン・クンダ・ジョン・ヴァン-マーネン『組織エスノグラフィー』(有斐閣) |
|
治る |
|
アンドルー・ワイル『人はなぜ治るのか―現代医学と代替医学にみる治癒と健康のメカニズム』を読む。
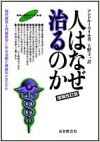
同じく,アンドルー・ワイルの『癒す心、治る力―自発的治癒とはなにか 』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/427491650.html
で触れたことがある。著者は,「日本の読者へ」で,
「私たちに必要なことは,…自分を頼みにする習慣を身につけてもらうことだ。すなわち,何かあってから医者に頼るのではなく,ふだんの食事・運動・呼吸・仕事・ストレスマネジメントに気を配り,それを健全な方法で行うようにすることである。また,起こりやすい病気に対処する,簡単で安価な方法を知ってもらうことである。
私は読者に生得の自然治癒力を正当に認め,現状に替わる新しい医学の方法を理解し,精神・身体・霊性の相互作用にかんするホリスティック(全体的)な思考を育んでいただくための一助として『人はなぜ治るぱらのか』を書いた。」
と述べている。そして,序文で,
「私は個々の患者に合った食生活・運動・リラクセーションをはじめとするセルフケアの方法を指導する。またもっぱら生薬を患者にすすめている。私の生薬の処方量は製薬会社の薬剤の処方量を大きく上回っている。ハーヴァード大学で医学の前に植物学を修めた私は,いまでも薬草の研究が主要関心事のひとつになっているのだ。セルフケアの指導と生薬の処方が終ったら,最後に患者を他の治療家に差し向ける。その中には現代医学の専門家はもちろん,シャーマン,鍼師,催眠療法家,整骨治療家をはじめ,この本で紹介した治療法のほとんどの実践家が含まれている。したがって,私の治療哲学を一言でいうならば,つぎのようになる。『害にならないかぎり,効くと思われる妥当な方法は何でも使うこと』」
と書き,「奇々怪々諸治療法総覧」として,現代医学(本書ではホメオパシーの創始者ハーネマンが,『その病気とは別のもの』という意味のギリシャ語で,当時の医学を名づけた『アロパシー医学』という表現を使っている)から,にせ医療まで,治療法を列挙し,冷静に是非を論じている。
例えば,こんな具合である。
アロパシー医学(内科。外科)
アロパシー医学(薬物)
アロパシー医学(怠慢の罪)
三大異端医学(オステオパシー,カイロプラクティックス,ナチュロバシー)
東洋医学
シャーマニズム,マインド・キュアー,信仰療法,
心霊療法
ホリスティック医学
クワッカリー(にせ医療)
等々。そして,すべての治療に共通するものとして,六つの結論を挙げている。
①絶対に効かないという治療法はない,
②絶対に効くという治療法もない,
③各治療法は互いにつじつまが合わない,
④草創期の新興治療法ほどよく効く,
⑤信念だけでも治ることがある,
⑥以上の結論を包括する統一変数は治療に対する信仰心である,
と。そして,イボの例を挙げている。
「疣贅(ゆうぜい イボ)は機能的な疾患ではない。ウイルス感染による組織の異常を伴う,実体のある,分離性の,角質増殖の強い器質性の皮疹である。にもかかわらず,ウイルスや異常組織になんら直接的作用のない,イボとり法に対する信念のみによって,事実上,瞬間的治癒に近い治り方をすることが多い。
効果が著しく予後もきわめていいイボの民間療法に比べると,現代医学による科学的治療法は見るも無残だ。医師がイボをとるときは,メスで切るか,電気メスで焼灼するか,液体窒素で冷凍するか,周囲の皮膚を傷つけないように細心の注意を払いつつ酸で腐食させるかといった方法を使う。これらの方法は粗野で,痛みもあり,余計な傷をつくるばかりではなく,無効例が非常に多い。少なくとも手術例の半分はイボが再発し,かえって増やしてしまう結果になりがちだ。」
として,こう述べる。
「私は,このテーマ以上に研究されてしかるべき医学的現象を,ほかに思いつかない。何ヵ月も何年も存続していたイボが,ジャガイモのかけらでこすって何時間かするとポロリととれる。…決して超自然的なものではない。神経とか血液といった,よく知られているからだの構成物を使った,何らかの分析可能なメカニズムが,背後で必ず働いているはずだ。…それは,きわめて短時間の活動で,強力,正確,かつ効果的に,病変組織の切り捨て(と再発防止)を行うからだ。そのメカニズムを悪性腫瘍や冠動脈をふさぐ栓子,あるいは関節中に蓄積したカルシウムに向けて働かせることができたら! イボとりが広く行なわれているということは,誰もがそのメカニズムをもっているということだといっていい。明らかに,そのメカニズムを作動させるスイッチは,心の中にある。」
それは,プラシーボ効果とつながる。
「イボとりは,プラシーボ反応の一例だ。それはまた,生まれつきからだに備わっている治癒力―それにくらべると外部から施す治療措置が不器用かつ無力にみえるほど効率のいい能力―の存在を明白に証明するものでもある。」
人の心のもつ機能について,
プラシーボ効果,
という言い方を著者はしない。
「これは正しい言葉の使い方とはいえない。好結果はにせ薬の効果ではなく,それを服用した患者の反応である。正しくは,『プラシーボ反応』と呼ばれるべきであり,私もそう呼びたい。」
と。次の言葉が印象深い。
「最良の治療とは医師と患者の双方が心から信頼できる貴重な固有の効果があり,したがって,それがからだに直接作用すると同時に,心が介在するメカニズムによって生来の治癒力が発動されるような,よき活性プラシーボとして機能する治療である。それこそが真の心身医学であり,またいかなる判定基準によってもすぐれた医学であって,決してクワッカリーや詐術ではありえない。事実,真の医術とは,個々の患者に内部からの治癒力を最もうまく生じさせる治療法を選択し,提示する,治療家の能力のことなのだ。」
参考文献;
アンドルー・ワイル『人はなぜ治るのか―現代医学と代替医学にみる治癒と健康のメカニズム』(日本教文社) |
|
ピアニストの脳 |
|
古屋晋一『ピアニストの脳を科学する:超絶技巧のメカニズム』を読む。
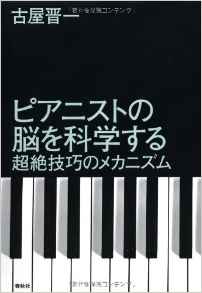
本書は,
「ピアニストの脳と身体が,いったいどのような働きをしているのか,さまざまな実験と調査を駆使して探求した本」
である。
「感性豊かな芸術家であるとともに,高度な身体能力を持ったアスリートであり,優れた記憶力,ハイスピードで膨大な情報を緻密に処理できる,高度な知性の持ち主」
であるピアニストの,
「脳と身体」
を明らかにしようとしている。著者自身が,
「いわゆる理系人間として工学,医学の道に進みましたが,ピアニストを夢見た時期もあっ」
て,ずっとピアノを弾き続けてきた,という経験をもち,
「練習をして弾けなかった曲が弾けるようになると,脳や身体はどう変わるのか。『脱力』とは,どの筋肉をいつ弛めることなのか。指や腕や肩をどう動かせば狙った効果があるのか。」
等々,どの解剖学や運動学の教科書に載っていない,
「ピアノを弾く身体の動き」
を明らかにしようとしたものでもある。
たとえば,
「ピアニストが指をあれほど速く動かせるのはなぜでしょうか?」
その答は,
脳にある,
らしい。しかも,
「ピアニストの脳は,たくさん働かなくても複雑な指の動きができるように,洗練されている」
という省エネできる脳らしいのである。
「音楽家ではない人は,指の動きが複雑になればなるほど,高次運動野の神経細胞をもっとたくさん使わなければいけないが,ピアニストはこの部位をあまり働かせなくても,複雑な指の動きが可能である」
のである。それは,
「ピアノの演奏に必要な,複雑な指の動きをしやすいように,神経細胞の機能を特別に変化」
させている結果らしいのである。具体的には,
「ピアニストの脳の運動野の体積…は,音楽家でない人よりも…大きい」
だけでなく,運動の学習や力やタイミングの調節に関わっている,
「脳部位(小脳)の体積…が5%ほど大きい」
ことも分かっている。
「5%と聞くと,少ないと思われるかもしれませんが,小脳には一般に約1000億個の神経細胞があると言われています。ということは,ピアニストは音楽家でない人よりも,単純に計算すると,小脳の細胞が50億個近く多いということになる」
さらに,「大脳基底核の『被殻』」が,小さくなっている,という。
「この部位が大きい人ほど,演奏するときの動きが不正確で,バラつくことが報告されています。『バラつく』というのは,『正確なリズムで弾けない』ということです。」
訓練を積んだバレーダンサーの被殻も小さいそうで,
「この脳部位は,巧みな動作を生み出すうえでは『大きくないほうが良い』」
らしい。では,英才教育ではないが,はやく訓練を始めた方がいいのかどうか。
「(神経細胞(灰白質)の下の)脳の岩盤部分には,『白質』といって,脳の神経細胞同士が情報のやり取りをするために必要な,何百万本もの白いケーブルが詰まった部分があります。このケーブルは鞘(ミエリン)に包まれていて,20歳頃までに少しずつ発達していきます。…この鞘の発達のしかたが,運動能力や認知能力に影響を及ぼすことがわかっています。(中略)指を独立に動かしたり,両手の動きを協調させたりするときに使われるケーブルの周りの鞘は,11歳までの練習時間に比例して発達していました。(中略)これはつまり,11歳までにおこなう練習は,すればするほど鞘を発達させるが,12歳以降は,練習をたくさんすれば鞘が発達する,というわけではない」
と。しかし,指が早く動かせれば優れたピアニストかというと,そうとは限らない。
「指を動かす速さは,数ある表現手段の1つにすぎないからです。」
とも。
こう見ると,ピアニストはピアニストになるように,必要な脳機能を発達させているのだとすると,それはすべてのプロフェッショナルな職業に就いて当てはまるはずだ。僕が一番知りたいのは,
政治屋,
の脳の構造だ。
鉄面皮,
厚顔無恥,
嘘つき,
等々という機能は,脳のどこに現れているのだろうか。
参考文献;
古屋晋一『ピアニストの脳を科学する: 超絶技巧のメカニズム』(春秋社) |
|
「『社会』科学」としての経済学 |
|
宇沢弘文『経済学の考え方』を読む。
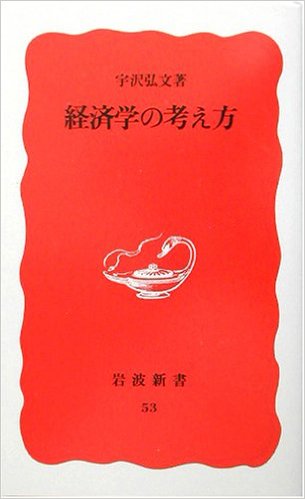
冒頭に,こうある。
「経済学は,人間の営む経済行為を直接の対象とし,現実の経済現象の根底にひそむ本質的な諸要因を引き出し,経済社会の基本的な運用法則を明らかにすると同時に,貧困の解消,不公平の是正,物価の安定,さらには経済発展の可能性を探ろうという実践的な意図をももつ。経済現象は,一つの社会あるいは複数の社会において,大勢の人々が,お互いに深い関わりをもちつつ,それぞれの置かれた歴史的,文化的,技術的,制度的な制約条件のもとで,どのような経済的行動を選択するかということによって,その特質が定まってくる。経済学はこのような意味で,『社会』科学である。と同時に,それぞれの社会のもつ制度的諸条件を明らかにし,そこに置かれた人間がどのような行動をとるかということについて,科学的な方法によって,その法則性を解明しようとする,そのような意味で,『社会』科学である。」
と。これを,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/443043807.html
で取り上げた,小島寛之氏の,
「経済活動の運動法則を,物理学と類似した形で解明しようと試みるのが経済学である。」(『経済学の思考法』)
という定義と比較すればその違いが,歴然としている。経済法則を,社会的,制度的な背景,つまり文脈抜きで,自己完結させられる,と考えているらしいのである。そう考えるから,「経済学がなかなか進歩できない理由」として,
「第一の理由は,経済に関しては実験がままならない,ということだ。」
「第二の理由は,物質は観測者の意志によって行動を変えないが,人間は行動を変える,ということだ。」
と挙げ(この考え方はニュートンの世界観しか反映していない。今日の量子論の世界観は,観察によって変わるのだが),
「経済学の致命的な弱点」として,
「経済活動は,『歴史的事象』,『一回性のできごと』であり,『実験がままならない』という弱点」
を挙げていた。しかし,それはおかしい。それを所与して考えるのが経済学ではないのか。発想が逆転している。その可笑しさは,著者の,次の言葉を読めば明らかである。前述の「『社会』科学」に続いて,
「しかし,経済学は普通の意味における科学とは異なる面をもつ。それは,経済学が対象とする経済現象はあくまでも,歴史的過程のもとにおける人間の社会的行動に関わるものであって,繰り返しを許さない歴史的な現象であるということである。そこでは,自然科学にみられるような実験をおこなうということは許されないし,また天文学のように,同じ条件のもとで多くの観察をおこなうということもごくまれにしかできない。したがって,経済学の研究にさいしては,とくに深い洞察力と厳しい論理力とが必要になってくる。」
と書く。上述の小島氏は,経済学の前提が異なっている。経済学の足枷は,そもそも経済学の前提なのではないのか。しかし,著者は同時に,
「経済学はまた,すぐれて実践的な面をもつ。経済学者がなにゆえ,経済学に関心をもち,経済学の研究を一生の仕事としようと決意するのかというと,貧困と分配の問題にその原点をもつことが多い。」
と付言し,川上肇の『貧乏物語』を,
「日本での経済学の入門書としてもっともずぐれた書物のひとつ」
として挙げる所以である。
本書は,1988年,バブルのはじける直前に書かれたものだ。著者自身が,「あとがき」で,
「本書は,経済学史の書物ではない。経済学の考え方がどのように形成され,発展してきたのかという面に焦点を当てた。経済学者が,その生きたときどきの時代的状況をどのように受けとめ,経済学の理論の形に昇華させていったのかという面を強調したかった。」
と述べる通り,人に焦点が当たっている。多くは,平坦だが,時に,辛辣になる。特に,70年代のマネタリズムに代表される「反ケインズ経済学」対する口調は厳しい。
「1970年代の経済学は,一言でいえば,反ケインズ経済学といってもよいように思われる。七〇年代に流行した経済学の考え方がいずれも,ケインズ以前の新古典派経済学の考え方ないしはそのバリエーションを基礎として展開されたものであって,しかも,その生成が,ケインズ経済学に対するアンチテーゼを形成するという明示的な意図でもってなされてきたからである。反ケインズ経済学は,合理主義の経済学,マネタリズム,合理的期待形成仮説,サプライサイド経済学など多様な形態をとっているが,その共通の特徴として,理論的前提の非現実性,政策的偏向性,結論の反社会性をもち,いずれも市場機構の果たす役割に対する宗教的帰依感をもつものである。」
その代表的な経済学者フリードマンの,
「ある一つの経済理論にかんして,その前提条件について,その当否を問うことはできないし,すべきではない。その前提条件から演繹され,導き出された理論的あるいは政策的命題が,現実の状況を適切に説明し,望ましい政策的な帰結をもつか,否かによってのみ,その理論の当否を問うべきである…。」
に対して,
「フリードマンの主張は,ケインズが『一般理論』の冒頭で展開した考え方とまさに対照的なものである。ケインズは,経済理論の当否は,その理論前提が,対象とする現実の経済制度の,制度的,社会的,技術的な条件を的確に反映したものであるか,否かということによって決まるものであり,そこから導き出される理論的,政策的命題が望ましいか,否かということとはまったく無関係なものであるということを強調したのであった。」
と批判した。前提条件を立てて,「望ましい製作的な帰結」をもたらすものは,政治的経済であって,経済学ではない。
今日,レーガン,ニクソンの系譜につながる,「前提条件から演繹され,導き出された理論的あるいは政策的命題が,現実の状況を適切に説明し,望ましい政策的な帰結をもつ」らしい日本の経済政策をみるとき,70年代のアメリカの経済政策についての,以下の言及が,シンクロするのは当たり前のように見える。
「社会的不均衡というとき,…社会的共通資本と私的資本の相対的バランスを維持するようなメカニズムを内蔵していないような状況を指す。政府の政策的対応が,市場経済に内在する不安定的要素を相殺することができず,私的資本と社会的共通資本の間の相対的バランスが崩れて,しかもそのバランスを回復するメカニズムが,政策的な対応も含めて考えたときに,すでに失われているような状況を社会的不均衡と呼ぶわけである。」
「政府が中立的な立場に立って,有効需要のファイン・チューニング(微調整)をおこなうことがはたして可能であろうかという問題である。ここで,政府の中立性というとき,二つの側面をもつ。まず第一に,政府のおこなう財政・金融政策ないし経済政策一般について,その効果が市場経済における経済循環のプロセスに対して中立的であるか,否かという問題である。第二の問題は,政府の選択する経済政策が,市場経済の制度的諸条件から中立的でありうるか,否かという問題である。資本主義的な市場経済制度自体,ある一つの社会体系のなかで歴史的過程を経て形成されてきた一つの歴史的段階であるが,政府の経済政策決定のメカニズムもまた,同じ社会的,歴史的条件のもとで形成されるものであって,とくに政治的民主主義をたてまえとするときに,政府の行動が市場経済制度を特徴づける諸条件と無関係に,中立的な立場にたって策定され,実行に移されてゆくという前提条件が妥当しているとは考えにくい。政府の行動も究極的には,資本主義的な市場経済制度を支えている歴史的,社会的,文化的な諸要因によって規定されるということが当然の帰結となるであろう。」
参考文献;
宇沢弘文『経済学の考え方』(岩波新書) |
|
財政再建 |
|
田中秀明『日本の財政』を読む。

本書は,第二次安倍内閣発足当時に上梓されたが,以来三年,財政は,改善どころか,ますます悪化して,赤字は膨れ上がり,誰も当事者意識をもって(とは責任を取る形で),国家財政の運営をしていない時代が,続いている。
著者は,「はじめに」で,少なくとも(財政破綻かどうかは別として),
「日本の経済や財政について信頼性が高まっていると主張する者はいない。1990年代の財政悪化から二〇余年が経過し,リスクが確実に高くなっている。」
と述べる。にもかかわらず,政治・経済に携わるものは,手を拱いているのか。それどころか,悪化に拍車をかける行為をし続けるのか。その,
無責任体制,
は,何に由来するのか。安倍内閣のし続けているのは,デフレ脱却し,景気を好転させれば,財政赤字や借金は解消する,という路線である。著者は言う。
「日本経済がデフレ脱却し,成長路線に戻れば,財政赤字や借金の問題はすぐに解決するだろうか。
残念ながら,それほど単純にはかんがえられない。これまでも幾度となく財政再建が試みられているが,そのほとんどは成功していないからだ。いままでできなかったことが,景気が上向けば可能になるとはにわかには信じられない。1990年代以降現在に至るまでの間には,好景気があったが,財政赤字は生じている。財政赤字は景気だけの問題ではない。」
「財政再建には,一定の経済成長が必要であることは,論を俟たないが,景気対策で経済は上向くと言い続けた結果が今の日本財政の姿である。巨額の財政赤字を目の前にして,国内金融機関は日本の国債の保有リスクを気にし始めている。仮に経済が成長し,税収が増えたとしても,財政の健全化はそれほど進まないだろう。景気は常に一定の周期で循環しており,好景気はそれほど長く続かないからである。そのときには,再び景気対策となり,赤字は拡大する。日本の予算制度は,支出のコントロールに弱く,また透明性もきわめて低い。こうした状況を放置したままでは,いくら増税しても,また経済が成長しても,財政は期待したほど健全化せず,世代間の問題も解決しないだろう。」
と,予測通り,三年間じゃぶじゃぶと紙幣を印刷しまくり,ミニバブルを醸し出させ,円安誘導したが,デフレは脱却どころか,また下がり始め,政策自体が破綻をきたし,借金はさらに膨らみ続けている。
著者は,
「財政再建に失敗している本質的な理由は予算制度にある」
と考えており,こう問題意識を語っている。
「それは単なる制度や法律の問題ではない。予算とは,希少資源の配分をめぐる政治的な調整システムである。市場で提供できない財・サービスの供給を決めるのが民主主義であり,予算は政治そのものであるといってもよい。つまり,予算制度改革は,政治改革と同義である。したがって,日本の財政を立て直すためには,政治・行政システムの転換が必要である。端的にいえば,豊富な税収を分配するためにつくられた高度成長期の分配型システムから資源制約下での優先順位を決める戦略型システムへの転換である。
だが,日本の経済社会にとっては,財政再建が最終的な目標ではない。日本における当面の最大の課題は,少子高齢化をどうやって乗り切るかである。少子高齢化を乗り切るためには,持続的な経済成長(特に一人当たりのGDP)を維持するとともに,財政を通じて効率的かつ効果的な資源配分を達成する必要がある。
残念ながら,日本の財政はそうなっておらず,むしろ,破綻という時限爆弾を抱えている。今後,財政収支の黒字の減少が予測されている。高齢化により貯蓄率が低下し,政府部門の赤字を国内で賄うことが難しくなるからである。」
既に一人当たりのGDPは下がり続け,危機は高まっているが,政権にその危機感はまるでない。
本書のテーマは,従って,
「少子高齢化を乗り切るためには日本経済をどうやって立て直すかである。それは政治・行政システムと密接にかかわる問題である。」
として,
「歳出・歳入といった財政の中身にとどまらず,予算をつくる仕組みや制度,政治の意思決定システム,政治の統治機構の問題を対象」
とし,今日の財政破綻は,
制度改革,
ぬきではないと主張している。
「中身(社会保障や税制)をよくするためには,それをつくるための器(予算・政治制度)が重要である。」
逆に言えば,今のままの制度でいけば,破綻は必須ということを意味する。本書は,そのために,
バブル経済崩壊以降,民主党政権までの財政の軌跡,
財政赤字の理由の整理,
諸外国の財政再建の成功と失敗,
日本の予算制度改革,
公務員制度を含む政治改革,
を順次展開する。財政破綻は,つまるところ,
日本というシステムの制度疲労,
そのものということになる。提案は多岐にわたるが,
三つの課題,
として,整理している。
財政再建の第一歩,
は,危機感の共有,という。
「財政赤字は,言い換えると,政治家,官僚,そして国民が改革を回避してきた結果である。いまの日本で最も欠けていることは,危機感の共有である。」
いまだけ・金だけ,自分だけ,という風潮で,そうできるかどうかは,かなり厳しいが。
財政再建の第二歩,
は,予算制度や公務員制度の改革,であり,
「第一に,拘束力のある中期財政フレームと支出ルールであり,これに基づき毎年の予算を編成する。複数年にわたり支出にシーリングを設け,財源の手当てを義務付けるルールを課す。」
「第二に,独立財政機関の設置である。財政規律を維持することが難しいのは,楽観的な成長率,会計上の操作など,政治的なバイアスが働くからである。これを是正するため,専門家で構成される委員会や行政組織を設置する。」
「第三に,…財政運営の枠組みを規定する財政責任法の制定である。」
と。
財政再建の第三歩,
は,社会制度改革,である。
さて,この提案が三年前に上梓されて,この間,まったく逆の方向に運営され,恐らく,借金は嵩み,破綻するか,戦前と同じく,戦争に踏み切るか(財界人の中には「このままだとどこかに戦争が起きないと」と発言していた),いずれかが早晩やってくる。たぶん,自力で改革できない民族なので,破滅を待つほかないのではないか,と悲観的になる。
参考文献;
田中秀明『日本の財政』(中公新書) |
|
計画された偶発性 |
|
J・D・クランボルツ&A・S・レヴィン『その幸運は偶然ではないんです!』を読む。
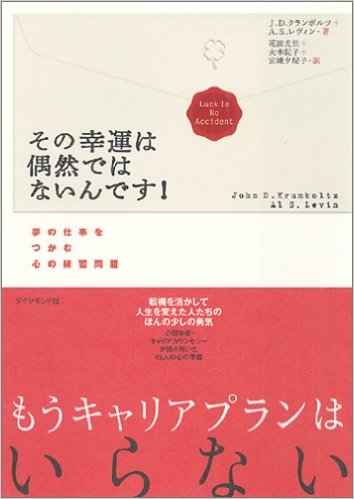
本書の原題は,
Luck is No Accident
である。つまり,
「幸福に偶然はない」
である。これは,著者の一人,J・D・クランボルツ教授が提唱したキャリア論(1999),
プランド・ハップンスタンス(planned
happenstance)理論(「計画された偶然」「意図された偶然」とも訳される),
に基づく実例集,それも偉人や特別な有名人のそれではなく,ごくごく普通の人のキャリアを巡る,失敗と成功(途上)の話である。
その理論は,数百人に及ぶ成功したビジネスパーソンのキャリアを分析したところ,そのうちの8割は『いまある自分のキャリアは予期せぬ偶然に因るものだ』と答えた,という。そのデータをきっかけとして構成された。その理論は,
●個人のキャリアは、予期しない偶然の出来事によってその8割が形成される,
●その偶然の出来事,予期せぬ出来事に対し,最善を尽くし対応することを積み重ねることでキャリアは形成される,
●偶然の出来事をただ待つのではなく,それを意図的に生み出すように積極的に行動したり,自分の周りに起きていることに心を研ぎ澄ませることで自らのキャリアを創造する機会を増やすことができる,
という3つの骨子から構成される。そして,そのためには,
○好奇心(Curiosity):新しい学習機会を模索すること
○持続性(Persistence):失敗に屈せず努力をすること
○楽観性(Optimism):新しい機会が「必ず実現する」「可能となる」と捉えること
○柔軟性(Flexibility):信念、概念、態度、行動を変えること
○リスク・テイキング(Risk-taking):結果が不確実でも行動を起こすこと
という特性が必要らしい,というものだ。つまり,
偶然が起きた後も,そして偶然が起きる前も,それをもたらす準備を当人はしている。そこに,「プランド」すなわち「計画された」という含意がある。
本書は,45人の,普通の人のキャリア選択における,
プランド・ハップンスタンス(planned happenstance),
が示されている。各章の,
「想定外の出来事を最大限に活用する」
「選択肢はいつもオープンに」
「目を覚ませ!夢が現実になる前に」
「結果が見えなくてもやってみる」
「どんどん間違えよう」
「行動を起こして自分の運をつくりだす」
「まず仕事に就いてそれからスキルを学ぶ」
「内なる壁を克服する」
というタイトルに随所にそのマインドが見られる。
「私たちは,自分自身の経験から,キャリア開発とはいかに想定外のチャンスをつくりだし,いかにそれを活用するかの問題だと気づいたのです。」
と著者は書く。それには,
先ず動かくなくては何も始まらない,
ということたが,ソリューション・フォーカスト・アプローチの原則,
もしうまくいっていないのであれば,(なんでもいいから)違うことをせよ,
を思い起こさせる。著者は,
「人生の目標を決め,将来のキャリア設計を考え,自分の性格やタイプを分析したからといって,自分が望む仕事を見つけることができ,理想のライフスタイルを手に入れることができるとは限りません。
人生には,予測不可能なことのほうが多いし,あなたはあなたは遭遇する人々や出来事の影響を受け続けるのです。」
「想定外の出来事は,生涯にわたって起こり続けます。あなたの人生に影響を与える出来事の多くは,実際にはあなたが生まれるよりずっと前に起きています。たとえば,自分の親や,母国語,人種や出生地などを自分で選ぶことはできません。(中略)キャリア構成理論はどうでしょう?(中略)
自分がコントロールできるなんてことが存在するのだろうか?とあなたは思うかもしれません。幸いなことに,私たちは自分の行動と,さまざまな経験に対する自分の反応をコントロールすることができます。この二つは,人生の方向を決める重要な要因です。」
と書く。しかし,もちろん,
「結果をコントロールすることはだれにもできません。しかし,あなたの行動次第で望ましい結果が起こる確率を高めることができるのです。人生には保証されているものは何ひとつありません。唯一確かなことは,何もしないでいるす限り,どこにもたどり着かないということでしょう。」
と,そして,
「あなたは人生の目標を持ち,それを実現するために計画を立てるべきだと信じているかもしれません。私たちは,計画を立てることが正しいことだとずっと教えられてきました。でも,私たちはそうは思いません。計画を立てること自体には反対しませんが,意にそわないことが明らかになった計画に固執することに,私たちは反対なのです。」
とも。さらに,
「将来の夢を描くことは素晴らしいことです。夢を見ることを大いに楽しみ,実現するように努力してください。でも,もし夢が計画通りに実現しなかったとしても,がっかりしないでください。よくも悪くもあなたの人生には予測不可能なことのほうが多いのです。『夢はきえてしまった』と考えるのではなく,『状況が変わった。さらに自分にとってよいチャンスを探すにはどうしたらいいだろう!』と考えましょう。」
と。なぜなら,
「思い通りにならないことをやるのは,楽しくはないかもしれませんが,貴重な学びの体験になる可能性があります。失望する方で,何かをえることができるのです。」
「私たちが言いたいのは,時々失敗してしまうことは必ずしも致命的なことではなく,予想外の状況に前向きな方法で対応することもできるということです。」
と。「あとがき」に,並ぶポイントは,従来のキャリア開発に対する見事なアンチテーゼになっている。曰く,
将来何になるかを決める必要はない,
想定外の出来事があなたのキャリアに影響を及ぼすことは避けられない,
現実は,あなたが想定している以上の選択肢を提供しているかもしれない,
いろいろな活動に参加して,好きなこと,嫌いなことを発見する,
間違いを犯し,失敗を経験しよう,
想定外の幸運な出来事をつくりだそう,
どんな経験も学びへの道,
仕事以外でも満足感を得られる活動に携わる,
内面的な障害を克服するために,新しい考えや経験にオープンであり続ける,
まさに,
「神さまを笑わせたいのなら自分の人生計画を話すといい」
という格言通りである。変化はチャンス,ということだろう。それには,
いつも学び,いつも挑戦し,いつも好奇心をもつ,
に尽きるようだ。そうして,本書の45人の人生を垣間見た時,
「人生とは,なにかを計画している時に起こってしまう別の出来事のことをいう。結果が最初の思惑通りにならなくても,…最後に意味をもつのは,結果ではなく,過ごしてしまったかけがえのないその時間である。予期せぬ出来事の中で全身全霊を尽くしている時,予期せぬ世界が開けてくる。」
という,龍村仁の『ガイアシンフォニー第三番』にある言葉を思い出させる。それには,人生のそのときそのときを必死で生きることがなければ生まれては来ない。
予期せぬ出来事,
が,
プランド・ハップンスタンス(planned happenstance)
を指す。
参考文献;
J・D・クランボルツ&A・S・レヴィン『その幸運は偶然ではないんです!』(ダイヤモンド社)
龍村仁『魂の旅 地球交響曲第三番』(角川ソフィア文庫)
http://allabout.co.jp/gm/gc/441716/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%94%BB%E7%9A%84%E5%81%B6%E7%99%BA%E6%80%A7%E7%90%86%E8%AB%96
http://www.educate.co.jp/2008-10-05-11-32-19/64-2009-03-06-08-11-14.html |
|
:経済学 |
|
小島寛之『ゼロからわかる 経済学の思考法』を読む。
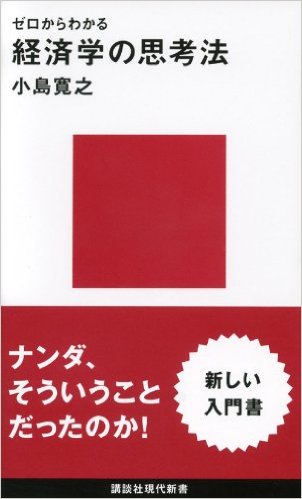
随所に,経済学の現状への批判がみられる。たとえば,あとがきで,
「経済学者の著作のほとんどには,『経済学が現実を説明できている』という大前提が見られる。新聞記事などで経済について語る経済学者もみな自信満々だ。
はっきり言って,僕にはそういう態度は理解できない。そういう人たちが,本当にそう信じて言っているのか,職業的立場からわざとそういうスタンスをとっているのかはわからないが,僕の感覚とは大きく異なる。…現実の理論としては,経済学は物理学から数百年分遅れた段階にしかないというのが,僕の正直な認識なのである。」
それはそうだろう。
「日本では1990年代から継続的なデフレに見舞われており,歴史的に珍しい経験を余儀なくされている」
にもかかわらず,それを説明できていない。説明できているなら,処方箋が出せるはずだ。経済学は,ままごとにすぎないか,歴史学と同じく過去の分析をする,後出しじゃんけんの学問でしかない,という証拠のように僕には見える。
著者は,
「宇沢先生の講義で,人生最大級の衝撃を受けた。」
という出会いから経済学の世界に足を踏み入れ,そこで講義を受けながら,
「数学としての経済学はとてつもなく面白い」
「経済学は現実説明力はがっかりするほど乏しい」
と感じ,数学科で学んだキャリアから,前者に向かう。
「宇沢先生は数学的方法に批判的であったが,それは先生の主張したいこと(人権的な問題)が数学と不調和であって,経済学が数学によって現実を解明すること自体は,きっとある程度はできるのだろう」
と考えて,
「宇沢先生の経済学に魅せられてこの道に入ったが,先生のような方法で,経済学にアプローチする道はえらばなかった。社会観の点でも人間的な洞察力の点でも先生に比べてずっと未熟で非力だと感じたからだ。(中略)
他方,伝統的なミクロ経済学にはある程度の適性があった。数学的なモデルを精緻に操作することが,面白くこそあれ,苦痛でなかったからだ。」
しかし,
「経済学は,現実解析の学問としては,まだ完成からほど遠い状態であり,社会設計や政策選択の科学としては無力にも近い状態だ。世の中には,経済学的な主張をあたかも『科学的真実』かのように堂々と語る経済学者も多いが,きっとそういう人たちは,ある種の社会的な立場からうそぶいているか,あるいは,物理学を勉強したことがないせいで『科学的真実』とは何であるかがまったくわかっていないのであろう。」
と。経済学が物理学のような法則を目指す,という志向は,
「経済活動の運動法則は,物理学と類似した形で解明しようと試みる」
というものだが,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/438821677.html
で批判していた,同じく物理学の法則をモデルにした「社会心理学」が,
「矮小な学問になったしまった」
のと同じ隘路に,経済学も入り込んでしまったようにしか思えない。結局著者は,
ゲーム理論,
にいきつくのだが,現在主流の「非協力ゲーム」については言及していないのでわからないが,かつて主流だった,「協力ゲーム」について,
「実証的な研究はほとんど存在しない」
が唯一の例として,「空港の滑走路を協力ゲームと見なし」た例を挙げる。これが経済学なのか。こうした,自己完結した閉じられた世界の分析に向いていても,著者自身が言うように,
実験ができないこと,
人間は行動を変えること,
一回性の出来事であること,
によって,物理学のようにはいかない。それにしても,ほぼ30年日本の不況を解明できず,有効な処方箋が出せないのでは,ままごと遊びをしている場合ではないのではないか,と僕には思えるが,著者は強気である。
「経済学は数理科学であるべきだと思っているし,それしか成功の道はないと信じている。」
「経済学はじわじわ進歩している。その歩みはゆっくりすぎるかもしれないが,しかし着実に新しい境地にむかっているのである。このような小さな全身の積み重ねが,それだけが,遠い将来に,経済学を本物の科学に成長させるのであろう。」
と。どうやらこの失われた30年は当分克服される見込みはなさそうである。
参考文献;
小島寛之『ゼロからわかる 経済学の思考法』(講談社現代新書) |
|
列島の古代 |
|
三浦佑之『古代研究−列島の神話・文化・言語』を読む。
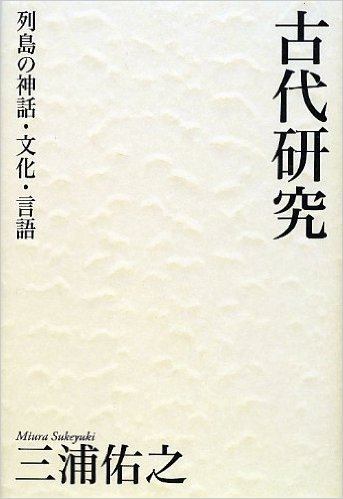
サブタイトルに,
列島の神話・文化・言語
とあるのは,「まえがき」にある,
「たしかに古事記という作品はおもしろい。しかしわたしは,(中略)どちらかといえば,かなりうさん臭い書物ではないかと考えている。そして,だからこそ古事記はおもしろいのだ。
古事記を読んでいると,いろんなことが見えてくる。いや見えなくなってしまう。古事記のことばを追いかけていると,その表現の奥に引き込まれてしまうからではないかと思う。結局あれこれと考えながら,いつのまにやらわき道へ迷いこんでゆくことになる。するとそこには,また得体のしれない神話があり,生活や思考があり,ことばがある。だから,そこでの遊びに夢中になってしまう。…。
作品のなかに閉じこもるのではなく,作品から外の世界へと放り出され,それによって新しい何かに気づかされる。わたしが古事記という作品を好きなのはそういうところだ。そして,この本にはそうした古事記から放り出された旅の記録が集められている。」
その通りに,古事記をめぐっての旅である。
「基本スタンスは,このわたしたちの住む列島を広がりのある世界として眺めてみようとしているのだ。律令国家ができて以来,一つにならなければいけないように仕向けられてきた思考を,いちど解放して解体してみたらどうなるか。」
という姿勢である。たとえば,
「古代についての文章を書くとき,わたしは二つのことを意識している。それは,神武とか仁徳とか天武とかの漢風諡号の使用をできるだけ避けること,七世紀半ば以前をいう場合には『天皇』および『日本』という称号の使用を必要最小限におさえること,この二点である。」
という。ここに,著者の我が国に奥行と多様性を見ようとする視点がある。
「ほとんどの古代史や古代文学の研究者なら,『古事記』という作品には,『天皇』という語は多用されているが,『日本』という語は一度も使われておらず,ヤマトは『大和』ではなく『倭』と表記されているということは知っている。もちろん,八世紀後半にならないと漢風諡号の使用は認められないというのも常識である。でありながら平気で,雄略天皇とか天智天皇とか表記したり,六世紀の日本と呼んだりする。」
この問題意識は,すごく重要である。その当時,日本とか韓国があったのではない。倭があり新羅があり,百済があった。それは,そのまま今日の日本でも韓国でもない。しかし,
「それに慣らされてしまうとどうなるか。極端な言い方になるが,神武や仁徳や雄略や天智や天武が自明の存在になってしまい,本当は存在しない『仁徳天皇』を,五世紀初頭に実在したと思い込んでしまうことになる。そうした思考回路をいったん中断して,『オホサザキ』と表記し,天皇ではなく大君とか大王とか呼んでみると,『仁徳天皇』と呼んでいた時とは別の,五世紀初頭に難波を中心とした地域を支配した王を想像できるようになる。それは古代を考えようとする場合にとても重要なことだ…。」
八世紀に,大和朝廷が作り出した天皇像に基づいて歴史を見ることは,そのままその虚像を肯うことになる。もっと多様で,各地に大王がおり,多様な古代があったことを,一色に塗りつぶしてしまう。その目で見れば,すべてが,そうしか見えなくなる。
『万葉集』の山上憶良の歌に,
いざ子ども 早く日本へ 大伴の 御津の浜松 待ち恋ひぬらむ
があるが,この「日本」は,「にほん(にっぽん)」と読むらしい。多くの『万葉集』の「日本」は「やまと」と訓ませるが,この歌の成立期,七世紀末には,「日本」という国名が成立した傍証になる。
「『日本』はそこではじめて誕生したのであり,それ以前に『日本』は存在しないのである。」
そして,
「『天皇』と『日本』とはセットになった呼称であり,(中略)681年に編纂が開始されたのは,『日本書紀』によれば律令だけではない。二月に律令の編纂が命じられ,三月には史書の編纂が命じられたと『日本書紀』は記している。そして,この時に開始された歴史書の編纂事業が720年(養老四年)の『日本書紀』に結実することになった。…そのとき完成したのは『「日本書」紀』であり,完成形として目指していたのは,紀・志・伝のそろった『日本書』であった。そしてその書名には,国名としての『日本』が用いられたし,『「日本書」紀』の本文にも,『日本』が溢れている。
それに対して,『古事記』には『天皇』は存在するが,『日本』は存在しない。そこに『古事記』と『日本書紀』との歴史認識の違いが如実に表れている。」
こう考えると,次の指摘は首肯できる。
「古代の日本列島を考えようとして『日本』と発想してしまった途端に,日本列島は単一の国家に塗り込められてしまうのである。それを,ヤマトと言い換えた時,ヤマトの隣にはキビがあり,その向こうにイヅモがあり,遥か北には,エミシと呼ばれる人たちが自分たちの世界を営んでいたはずだと想像することができるのだ。」
その視点で見るとき,
「ヤマト(邪馬台)国が九州説と大和説に分かれて決着がつかないのは,どちらにしても,一つの起源を欲しいからにほかならない。
ヤマト国はヤマト(倭・大和)にあったのだということを認めたうえで,そのヤマトとは別に,九州の北部にも日本海沿岸の弐氏のほうのイヅモに東のほうのコシ(高志)にも,瀬戸内海沿岸地域にも伊勢湾沿岸にも,さまざまに王権の萌しがあって相互に対立し繋がり,海彼の世界とも交流しながら存在したのだと考えることから出発するのがいいのではないか。」
という主張は,今日,アイヌの存在を否定し,少数民族としての琉球の存在を認めない状況では,特に重要に思える。では,仁徳天皇ではなく,オホサザキと表記してみると,そこから何が見えて来るのか。
「オホサザキという音だけをたよりに連想をはたらかせれば,サザキは,(通常言われているような鳥の名の)ミソサザイである前に,『陵墓』という意味を引きだしてくる。『日本書紀』の『陵』は『山陵』という漢字は,『日本書紀』の古訓や平安時代の古辞書などをもとに,ミサザキ(ミササキ)と訓読される。(中略)
語構成は,『ミ(御)+サザキ(陵)』で,サザキが陵墓を表す言葉であったらしい。(中略)当然それは,オホサザキが葬られているとみなされている大山(仙)古墳(大阪府堺市大仙町)を想起させる。(中略)とすれば,その呼称は死語に生じたのかもしれないし,生前から墓が造りはじめられたからそう呼ばれることになったのかもしれない。」
ここに見えるものの方が,はるかに豊かで奥行があるように,僕には感じられる。
参考文献;
三浦佑之『古代研究−列島の神話・文化・言語』(青土社) |
|
イノベーターのジレンマ |
|
クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』を読む。

同じ著者の『経営論』について,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163444.html
で触れたが,
「本書の面白さは,設問の鋭さ,問題設定の鋭角さにある,と感じた。それがクリエイティブであるかどうかは,その問いの新しさ,斬新さにある。まさにその典型といっていい。」
と書いた。本書は,まさに,その延長線上にあり,通常のマネジメント論が,
マネジメントの失敗,
と断ずるところを,
優れたマネジメントであるが故に失敗する,
という。原題は,
The Innovator’s Dilemma
である。邦題「イノベーションのジレンマ」だと,主語が消えてしまう。主体は,イノベーターなのではないか。業界をリードしている企業か懸命にイノベーションしているつもりが,持続的技術でしかなく,結果として視野の外の破壊的技術(必ずしも持続的技術より上とは限らない)によって追い落とされてしまう。そのジレンマである。
著者は,日本語版への「日本語版刊行にあたって」で,
「本書には,経営者にとって重要な教訓が盛り込まれている。なかでも注意すべき点は,『優良企業』のパラダイムの多くが,実は優良企業を失敗に追い込みかねないことだ。これは欧米の企業はもちろん,日本企業にもあてはまる重要な教訓である。
その一つは,六〇年代,七〇年代の日本の驚異的な経済成長を支えてきた産業のほとんどが,欧米の競合相手にとって破壊的技術であったことだ。当時の状況は,本書に示したパターンにあてはまる。日本の鉄鋼業界は,欧米の鉄鋼市場のなかでも,本書で実績ある企業が最も打撃を受けやすいと述べた低品質,低価格の分野に攻め込んだ。その後,日本の鉄鋼業界は容赦なく上位市場へ移行しつづけ,日本の鉄鋼メーカーは世界最高の品質を誇るようになった。トヨタ,日産,ホンダ,マツダなどの日本の自動車メーカーは,欧米の自動車市場の最下層にある低品質,低価格の分野に,破壊的技術をもって攻め込んだ。…各社はその後も容赦なく上位市場へ移行し,世界最高の品質を誇る自動車メーカーとなった。ソニーをはじめとする日本の家電メーカーは,低価格・低品質の携帯用ラジオ・テレビによってアメリカ市場の最下層を攻撃した。その後も容赦なく上位市場へ移行しつづけ,世界最高の品質を誇る家電メーカーになった。セイコー,シチズンなどの時計メーカー,ヤマハなどのピアノ・メーカー,ホンダ,カワサキなどのオートバイ・メーカーにも同じことが言える。これらの企業はすべて,同様の戦略によって欧米の市場を下部から『破壊』した。(中略)
…もう一つの日本特有の問題は,ここ数年日本経済が停滞している理由に関係している。その理由は,右に揚げたな日本の大企業が,本書で取り上げた各業界と同様の力に動かされていることである。優れた経営者は,市場の中でも高品質,高収益の分野へ会社を導くことができる。しかし,会社を下位市場へ導くことはできない。日本の大企業は世界中の大企業と同様,市場の最上層まで登りつめて行き場をなくしている。」
と述べる。これがイノベーターのジレンマである。技術を向上すればするほど,持続的な技術の向上にしかならず,破壊的な技術の前に,為すところがない。しかも著者は,本書が刊行された十五年前,
「米国経済がこういった問題をどのように対処してきたかを紹介している。各企業が行き詰まるなか,社員は業界をリードする大企業を辞め,ベンチャー・キャピタルから資金を調達し,市場の最下層に攻め込む新企業を設立し,徐々に上位市場へ移行し,こうして歴史は繰り返している。個々の企業が市場の最上層で行き場をなくし,やがて衰退するとしても,それに代わる企業が現れるため,米国経済は力強さを保っている。これは日本では起こりえないことである。企業の伝統市場のしくみができていないからだ。本書の理論から考えて,現在のシステムが続くなら,日本経済が勢いを取り戻すことは二度とないかもしれない。」
と予言し,著者の理論を実証したことになっている。いまや,過剰品質(市場の求める品質を超えている)のガラパゴス化が,全体をおおい,窮余の一策,軍事シフトし始めている。衰退は確実である。必要なのは,新たな市場を開く破壊的技術だからだ。
本書には,破壊的技術をもって切り込んだ日本企業の例も,注に,いくつか紹介されているが,たとえばソニーの例では,AT&Tからトンジスター技術の使用権をえると,
「米国市場で,最初の携帯用トランジスター・ラジオを発売した。主流市場のラジオの主な性能指標からみれば,この初期のトランジスター・ラジオは,最悪の代物だった。当時の主流だった真空管卓上ラジオに比べて,忠実度がはるかに低く,雑音がひどかった。しかし,盛田(昭夫)は,大手の電機メーカーのほとんどがトランジスター技術にとった行動とは異なり,トランジスター・ラジオが主要市場で性能競争力を持つまで研究室に閉じこもらず,当時存在した技術の特性を評価する市場,携帯用パーソナル・ラジオ市場を見いだした。卓上ラジオの主力メーカーが一社も携帯用ラジオの主力メーカーにならず,その後一社残らずラジオ市場から撤退したことは,驚くにあたらない。」
本書の言う持続的技術と破壊的技術とは,
「漸進的変化と抜本的変化の区別」
とはまったく異なる。
「新技術のほとんどは,製品の性能を高めるものである。これを『持続的技術』と呼ぶ。持続的技術のなかには,断続的なものや急進的なものもあれば,少しずつ進む者もある。あらゆる持続的技術に共通するのは,主要市場のメインの顧客が今まで評価してきた性能指標にしたがって,既存製品の性能を向上させる点である。個々の業界における技術的進歩は,持続的な性質のものがほとんどである。…もっとも急進的で難しい持続的技術でさえ,大手企業の失敗につながることはめったにない。」
しかし,破壊的技術は,
「少なくとも短期的には,製品の性能を引き下げる効果を持つイノベーションである。…大手企業を失敗に導いたのは破壊的持術にほかならない。」
「破壊的技術は,従来とはまったく異なる価値基準を市場にもたらす。一般的に,破壊的技術の性能は既存製品の性能を下回るのは,主流市場での話である。しかし,破壊的技術には,そのほかに,主流から外れた少数の,たいていは新しい顧客に評価される特徴がある。破壊的技術を利用した製品のほうが,通常は低価格,シンプル,小型で,使い勝手がよい場合が多い。」
いままで多くの衰退した企業は,マネジメントの失敗で片づけられてきた。しかし,本書は,
「優れた経営こそが,業界リーダーの座を失った最大の理由である」
ことを,競争激しいハードディスク業界を中心に,さらに,掘削機業界他の例も交えながら,具体的に検証してみせる。
「技術革新のペースがときに市場の需要のペースを上回るため…,企業が競争相手よりすぐれた製品を供給し,価格と利益率を高めようと努力すると,市場を追い抜いてしまうことがある。顧客が必要とする以上の,ひいては顧客が対価を支払おうと思う以上のものを提供してしまうのだ。さらに重要な点として,破壊的技術の性能は,現在は市場の需要を下回るかもしれないが,明日は十分な競争力を持つ可能性がある。」
しかも,
「安定した企業が,破壊的技術に積極的に投資するのは合理的でないと判断することには,三つの根拠がある。第一に,破壊的技術のほうがシンプルで低価格,利益率も低いのが通常であること,第二に,破壊的技術が最初に商品化されるのは,一般に,新しい市場や小規模な市場であること。第三に,大手企業にとっても収益性の高い顧客は,通常,破壊的技術を利用した製品を求めず,また当初は使えないこと。概して,破壊的技術は,最初は市場で最も収益性の低い顧客に受け入れられる。そのため,最高の顧客の意見に耳を傾け,収益性と成長率を高める新製品を見いだすことを慣行としている企業は,破壊的技術に投資するころには,すでに手遅れである場合がほとんどだ。」
と。つまり,
「優良な企業が成功するのは,顧客の声に鋭敏に耳を傾け,顧客の次世代の要望に応えるように積極的に技術,製品,生産設備に投資するためだ。しかし,逆説的だが,その後優良企業が失敗するのも同じ理由からだ。」
では,経営者にどんな選択肢があるのか。
新しい仕事に適したプロセスと価値基準を持った別の組織を買収する,
現在の組織のプロセスと価値基準を変えようと試みる,
独立した別組織を新設し,そのなかで新しい問題を解決するために必要な新しいプロセスと価値基準を育てる,
の三つである。異なる目的を一つのプロセスで行おうとすることには,無理があり,一番成功しやすいのは,
スピンアウト組織によって能力を生み出す,
方法のようだ。 しかし,
「CEOがみずから注意して監督しないかぎり,主流の価値基準を破壊するような変化に対応できた企業は一社もない。これはまさに,プロセスと価値基準の力,特に通常の資源配分プロセスの論理が強力であるためだ。新しい組織が必要な資源を確保し,新しい課題に取り組むために必要なプロセスと価値基準を自由に作れるよう指示できるのは,CEOだけである。スピンアウトを,破壊的技術の脅威を問題リストから取り除くための手段としてしか見ていないCEOは,まちがいなく失敗する。これまで,この問題に例外はない。」
と。まさに,マネジメントの問題である。
参考文献;
クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』(翔泳社) |
|
基準値 |
|
村上道夫・永井孝志・小野 恭子・岸本 充生『基準値のからくり』を読む。
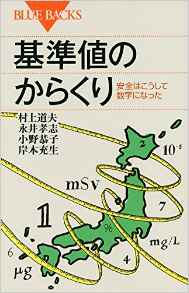
サブタイトルは,
「安全はこうして数字になった」
である。数字になると,独り歩きを始める。本書に,
Standards are devices to keep the lazy mind
from thinking.
という,アメリカの疫学者ウイリアム・セジウィックの言葉が引用されている。
「基準というものは,考えるという行為を遠ざけてしまう格好の道具である。」
と。本書は,工学系二人,理学系一人,経済学系一人による,基準値のからくりを明らかにするものである。範囲は幅広く,奥が深い。最近でいえば,被爆線量の基準値がどうやって定められたのか,未成年の飲酒禁止が二十歳なのはなぜか等々,ざぐっていくと闇の中に紛れてしまうものも少なくない。欧米ではその経緯が公にされているのに,我が国ではブラックボックスになっているものも少なくない。
安全の基準を考えるヒントは,国際的な安全規格に関する「ガイド51」(ISO/IEC
Guide 51)に,
「受け入れられないリスクのないこと」
という定義がある。この定義は,
「安全とは『リスクゼロ』,つまり絶対安全という状態を意味しない。さまざまなリスクについて,それを社会が受け入れられるか,受け入れられないかを判断し,『受け入れられないリスク』がない状態を安全とする。『受け入れられないリスク』がどれくらいかについて社会が合意をもつことで,安全という抽象的な概念が具体的・定量的に議論できるようになる。これに基づいて基準値が定められ,守られることで,社会は安全を確保することができる。そのような考え方である。」
この前提は,設定プロセスとその根拠が,オープンでなくてはならない。でなくては,社会的合意にはならない。ということは,
「放射能汚染について,政府関係者や有識者がいう『基準値以下だから安全』とは(彼らが安全の意味を正しく理解していると解釈すれば)『受け入れられないと社会が合意したリスク』よりも低いから安全,という意味である。これに反発する人たちのいう『基準値以下でも安全とは思えない』とは(実際のリスクの程度を知ることの難しさはおいて),『自分にとっては受け入れられないリスク』だから安全ではない,と言っているのである。」
というやりとりが「かみ合うはずがない」のは,そもそも「リスク」について,ほぼオープンな議論がなされてきていない,というわが国の設定結果をあらわにしているとも言える。たとえば,水道水質基準は,1995年に,
「WHOの飲料水質ガイドラインにならい,生涯発がん率が『10万人に1人』というレベルで設定され,こうしたリスクレベルにもとづく基準値設定をしたことを国民に公開するか否かが議論されたが,『時期尚早』と判断され,明示されなかった。」
この経緯は,国民の無関心,お上に委ねる志向にもよるが,基準値の設定プロセスが公開されない背景を象徴している。アメリカやイギリスでは,1970〜80年代,
「受け入れられないリスクについての研究や社会調査・議論が熱心になされてきた。
たとえば米国では,食品中の発がん物質がどの程度までなら安全と見なすかについて論争が巻き起こり,何度も裁判が繰り返されているうちに,一つの化学物質について発がんリスクとして受け入れられるレベルは,生涯でがんが生じる割合が『1万人に1人』から『100万人に1人』くらいという範囲に落ちついた。(中略)
これらに対し,残念ながら日本では,…『受け入れられないリスクの水準はどれくらいか』という議論はほとんどなされていない。(中略)たいていの場合,海外で使われている数字をそのまま輸入している。」
基準値には,「受け入れられないリスク」という考え方の以前にあった,
環境基準型の基準値,すなわち無毒性換算型(NOAEL No Observed Adverse
Effect),
残留農薬型の基準値,ALARA型(As Low As Reasonably Ach
ievable),
があり,前者は「無毒性=ゼロ」であり,ゼロリスクを目指す考え方,後者は,「できる限り低く」する努力をするという考え方であり,特に前者は,
「化学物質の毒性を基準に決められているので一見,根拠はわかりやすい。」
が,しかしそんなにクリアではない。たとえば,水俣病の原因になったメタル水銀。
「厚生省(当時)は1973年,魚介類の水銀について暫定的規制値として0.4mg/kgを設定した。この基準値は,水俣病患者の調査結果から導出されたものである。…導出法は,環境基準型と同じ無毒性換算型である。
ところが,この基準値にはからくりがある。マグロ類(マグロ,カジキ,カツオ),深海性魚介類(メヌケ類,メンメダイ,ギンダラ,ベニズワイガニ,エッチュウバイガイ,サメ類),河川産魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)などについては,適用除外とされたのである。
その理由として,高級魚類のため摂取量が少ない,含有される水銀が天然由来である,健康被害の懸念がない,という説明がなされていたが,これはかなり違和感を覚えるものだ。マグロは日本人の食卓になじみが深いものであるし,天然由来の水銀だから健康被害が起こらないというのは論理的ではない。
では,実際にこれらの魚類は水銀をどのくらい含んでいるのだろうか。2003年に厚生労働省が公開した,これらの魚介類の水銀濃度は,…なんと,のきなみ暫定規制値を超えてしまっている。」
本書では,
飲食物に関する基準,
環境にまつわる基準,
事故に関する基準,
を取り上げていく。プロローグで,基準値の特徴を,
①従来型の科学だけでは決められない(「予測・評価・判断をともなう科学を…『レギュラトリーサイエンス』と呼ぶ」),
②数字を使いまわする(欧米や関連する基準値,他国基準をベースに定めていく),
③一度決まるとなかなか変更されない(日本では科学的判断を加えて定期的に改定する手続きの制度がない),
④法的意味はさまざまである(「規制知」「指針値」「目標値」さまざまに呼ばれ,罰則規定のない基準値もある),
と挙げている。それにしても,恣意的だったり,欧米の焼き直しだったりしても,数値は独り歩きする。そもそも基準値は何のためのものか。
「安全やリスクをどのように管理すべきか,という問いは,つきつめれば,どのような環境や暮らしを求めているのか,という価値観の問題になる。さまざまな価値観をどのように,どこまで安全管理に反映させるのか,私たちはどのような世界をめざしているのか。そのような問いを私たちに突きつけたのが,第一原発の事故だったのではないだろうか。基準値設定において前提になる『受け入れリスク』には,本来そこまでの考えが求められるはずだ。」
というプロローグの言葉が皮肉である。何一つ合意形成もないまま,リスクの見積もりもそこそこに原発を再稼働させようとする政権には,
どんな社会を目指すか,
よりも,
誰が得するか(誰が損するか),
という(為政者と官僚と関係者の)目先の利益しかないように見える。そのとき,基準値は,
自己弁護と合理化の道具,
にしかならない。何の(誰の)ための基準値かは,置き去りにされたままである。
参考文献;
村上道夫・永井孝志・小野 恭子・岸本 充生『基準値のからくり』(ブルーバックス) |
|
ソーシャルシフト |
|
斉藤徹『ソーシャルシフト―これからの企業にとって一番大切なこと』を読む。
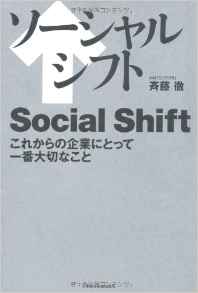
本書の,ソーシャルソフトの意図を,著者は,「はじめに」でこう書く。
「この書籍では,ソーシャルメディアが社会にもたらす本質的な変化,企業と生活者との新しいコミュニケーションのカタチ,すべての顧客接点で素晴らしいブランド体験を提供するための仕組み,それを実現するためのリーダーシップや組織のあり方,具体的に企業を変革するためのステップに言及し,新しい時代の『あるべき企業像』を追及する。タイトルとした『ソーシャルシフト』とは,ソーシャルメディアが誘起する,不連続で劇的な変化,そしてマーケティング,リーダーシップ,組織構造にまで及ぶビジネスのパラダイムシフトをあらわしたものだ。」
この高らかな宣言には,大きな新たな変革への期待が垣間見える。本書は,
2011年,
あの大震災直後である。あれから五年,日本社会には,こういう前向きのシフトはまったく起きておらず,いえそれどころか起きる気配すらなく,秘密保護法,原発再稼働,安保法制等々,むしろ逆回転が起きつつあり,変革の兆しであったはずの,SNSは,今や監視の,さらには炎上という形で政権擁護側からのすさまじいプレッシャーの場と化しつつある。民主党政権時代は,震災直後でも,まだこういう未来を期待できる雰囲気があったのかと,逆にこの五年の停滞に思いがゆく。こういう変革の動きが消え,重い,逆バネがきく時代とは,停滞と抑圧の時代なのだと,改めて思い知らされる。
本書の構成は,
第1部では,「金融危機や大震災,そしてソーシャルメディアが誘発した社会全体の価値観変化にフォーカスする。」
第2部では,「企業と生活者の関係性にフォーカスし,新しい時代のマーケティングのあり方を掘り下げる。」
第3部では,「企業の内部にフォーカスし,どのようなステップで企業をソーシャルシフトしていくべきかを考察した。」
となっている。
第1部に,
「企業は生活者とあらゆる接点で,今までの考え方を大きく変革しなければならない。透明性の時代,ソーシャルメディアが誘起したパラダイムシフトを,この書籍では『ソーシャルシフト』と呼ぶ。ソーシャルシフトの背景にあるのは,驚くべきスピードで世界に広がりつつある新しい習慣『シェアの文化』だ。」
とある。しかし,いまその自由は,削除というカタチで,投稿者の意思とは関係なく,SNS自体が自己規制ないし,権力の圧力に従容として従っている。時代の変化に驚くほかはない。本書の意とする社会こそが,本当は,日本の未来を開くはずなのだが。
いま日本の企業自体が,透明性とは逆回転しつつある間は,電力会社を見ればわかるし,本書が取り上げた,ソーシャルメディア活用企業の,たとえば,
NHK
は,視聴者の声に耳をふさぎ続けている。
透明性の時代の新しいリーダーシップについて,著者は,
オープン・リーダーシップ,
という。それを,
「従来のような統制の関係性ではなく,信頼を基礎とした乱験的な関係性」
そして,シャーリー・リーの五つの原則を,
オープン・リーダーシップのゴールデン・ルール
として,こう挙げる。
顧客や社員のもつパワーを尊重する,
絶えず情報を共有して信頼関係を築く,
好奇心を持ち,謙虚になる,
オープンであることに責任を持たせる,
失敗を許す,
と。しかし,国のトップをみれば,そのリーダーシップスタイルは,隠し,ただ盲目的に従うとのをよしとしているようで,明らかに背反している。大企業のリーダーシップも,財界のそれを見る限り,オープンというより,隠して,密かにことを進めようとしているとしか見えない。それで,ユニクロのつい最近の値上げという意思決定は,惨憺たる結果を招いた。
このオープン・リーダーシップを前提にしなければ,企業のソーシャルシフトのステップ,
①まずソーシャルシフトの必要性をトップに認知してもらい,プロジェクトを発足させる,
②ブランドとして「あるべき姿」を部門横断で検討,ブランドの哲学を練り上げる,
③ブランドの顧客接点を調査し,優先度の決定。「あるべき姿」に従い,現場を改善する,
④ソーシャルメディア運用の組織を立ち上げ,生活者とオープンに対話できる場をつくる,
⑤顧客の声に基づき,全社的なフィードバック・ループを構築,弛まぬ改善活動を行う。
⑥社員の幸せと顧客の感動を尊ぶ社風を醸成する。そのための仕組みを構築する,
で,
「ポイントは『現場の力』を結集し,そして『顧客の真実の声』の力を最大限に活用すること」
として,6つのステップは,次のように展開される。
ステップ1 プロジェクトのコアをカタチづくる
ステップ2 ブランドコンセプトを練り上げる
ステップ3 すべての顧客接点を改善する
ステップ4 オープンに対話できる場をつくる
ステップ5 顧客の声を傾聴する仕組みを構築する
ステップ6 社員の幸せと顧客の感動を尊ぶ社風を育む
を見れば,逆回転した五年後のいまが見えてくる。賃金の実質低下は目を覆うばかりである。企業は,特に大手企業は,人為的な政権の円安誘導に助けられて,土木中心の公共投資に縋り,労働法制を骨抜き化し,そのため必要な自己改革を免れ,安易な軍事シフトに乗って,軍事産業化に向かっているように見える。それは,
重厚長大化,
の再来であり,それ自体が,自殺行為にしか見えない。この五年で,日本は確実に本書の目指した未来の芽を摘み取ってしまった。別の意味のパラダイムシフトを起こしてしまったようだ。
参考文献;
斉藤徹『ソーシャルシフト―これからの企業にとって一番大切なこと』(日本経済新聞出版社) |
|
よい製品とは |
|
ジェイムズ・L・アダムズ『よい製品とは何か』を読む。

原題は,ずばり,
Good Products Bad products
サブタイトルは,
Essential Elements to Achieving Superior
Quality
邦題のサブタイトルは,
「スタンフォード大学伝説の『ものづくり』講義」
である。まさに,本書が,著者がスタンフォード大学大学院で教えてきた「良い製品・悪い製品」という科目の講義メモをもとにしたものだからである。著者曰く,
「本書の内容は,品質という問題について私が長年積み上げてきたものの集大成だ。私は,究極の品質を目指した会社(ジェット推進研究所/JPL)や,そうすべきなのにそうしなかった会社(ゼネラルモーターズ)でエンジニアとして働き,また,大学でデザイン・設計,創造性,美学,組織行動,エンジニアリングや技術の本質に関わる科目を教えてきた。機械(クルマ,バイク,古いトラクターほか)を愛し,そういうものを手に入れていじることにかなりの時間を費やし,裏庭にレストア(復元,修理)を待つマシンを増やしているが,なぜそれほど好きなのか,今でも自問している。そして数多くのものづくり企業の相談に乗るたび,いつも品質の問題にぶつかっている。さまざまな活動を通して気づいたことは,多くの人が品質問題を部分的に見ており,総合的に見ていないということだ。
本書が目指しているのは,これまでほとんど注視されてこなかった全体品質のいくつかの側面をよく知ってもらうことだ。」
と。当然,著者の「個人的な価値観や偏った見方が反映されている」。著者はこう付け加える。
「意見の相違は大いに歓迎,代わりに自分の考えを入れてもらって構わないし,なんなら異論を本にまとめて私の考えを正してほしい。品質を理解するカギは対話にある。」
後述するように,品質のなかには美意識に関わる部分がある。著者は,カリフォルニア工科大学で工学を勉強していたころ,UCLAの美術学部に入学して,一年間学んでいる。
「美の世界についてだいぶ理解することができた」
背景は,品質の要件に反映されている。
「良い製品の特徴である『エレガンス』や,優れた製品に対する感情である『愛着』といったものは言語で伝えるのは難しく,数字でも表せない。それに,明確に定義できてこそ改善もしやすいが,定義することは難しい。(中略)美しさや知覚品質は確かに一般化するのは難しいが,製品がヒットする最大の貢献者であることがよくある。私がこれまで仕事で出会った製造関係者の多くが,測定不能なもの,プロット図にできないものにアレルギー反応を示している」
と述べた後,本書を象徴するようなことにこう言及する。
「マーケティングは,前例のない商品には滅法弱い。人は,経験したことのないものについて,どうこういえないのだ。たしかにマーケティングは役立つが,それよりも優先される大原則がある。フォーカスグループのトピックにしようとしまいと,製品は人に適合しなければならない。たとえ言葉で表しにくくとも,洗練すべきだ。」
「優れた設計者は,優れたエンジニアであると同時に優れた芸術家でもあり,ビジネスを理解し,チームワークに長けた人だ。専門スキルだげてなく,大人スキルも要求される。」
と。そして,品質の鍵を握る「七つ領域」を詳述していく。
第一は,パフォーマンスとコスト(生産者にとっては「コスト」,消費者にとっては「価格」)
「パフォーマンス,コスト,価格は,切っても切れない関係にある。消費者は,『いいコーヒーメーカーだね』とはいわず,『三〇ドルにしてはいいコーヒーメーカーだね』という。価格は安く,パフォーマンスは高く,を求める。かたや生産者は,コストは安く,価格は高く,パフォーマンは他社より少し上,を望むだろう。」
「製品が真新しいうちは,生産者も消費者も性能に注目すれば物事は簡単に済むが,品質が高いというには長持ちしなければならず,その製品寿命を通したパフォーマンスを考慮する必要がある。パフォーマンスには信頼性,耐久性,サービス性,メンテナンス性などの要素が含まれる。なぜなら不具合が起きれば,直接生産者の落ち度によらなくても,製品性能に対してマイナスイメージとなるからだ。」
等々。「携帯電話をつかいながら,はたしてこんなにたくさんの機能が必要か」と言いつつ,こういう例を挙げる。
「人々は,コンピュータ,OS,アプリケーションソフトのアップグレードという無限ループに陥っているようだ。使用中のアプリケーションが古すぎて,メールの添付ファイルが開けないとする。そこでアップグレードしようと思ったら,OSが古くてできない。最新のOSと新しいアプリケーションをインストールしたらコンピュータが遅くなってしまった。次にすることは,コンピュータを買い替えてすべてをアップグレードすることだが,結局新しい機能が使いこなせない。そして慣れたころに再びサイクルが始まる。私や友人たちは,『パワーアップした』ソフトを覚えることより,コンピュータを活用することに専念したいので,頻繁なアップグレードは避けたいのだが,世間とのしがらみがあってそうもいかない(これでも私や友人たちはおそらくコンピュータに通じた部類に入るから不思議だ)。」
そして,付け加える。
「技術が高度に進んだ今,『我々は製品にしてほしいこと』だけでなく,『してほしくないこと』も考えなければならない。」
と。
第二は,人になじむ製品(人と製品の適合性=ヒューマンフィット)
「人になじまなければ,良い製品とは呼べない。…身体感覚,考え方に合わないものがすぐに思い浮かぶだろう。世の中には,人がものすごく不便を感じながら使っている製品は山のようにある。」
「物を作る人は,そのほかのことに気をとられてヒューマンフィットに十分注意を向けていないのが実情だ。頭の中は製品の機能,コスト,外観,信頼性のことでいっぱいなのだ。厳しい日程と予算では,試作や使用テストがなかなかできない。さらに良くないことに,自分を基準にものをつくっている。…それに,人がもつ非常に優れた対応力や柔軟性に頼ることに慣れている。人は,呆れるほど粗悪なつくりの製品にも順応するし,信じられないくらい短期間でほとんど文句もいわずにそれを成し遂げる。」
等々。製品の適合には,
身体(骨,筋肉,心臓,肺などとの間のインタラクション),
感覚(視覚や聴覚,嗅覚等々),
知覚(脳と機械のインタラクション),
複雑なシステムとの適合,
がある最後のそれは,
「長い時間をかけて使い方を覚えたり,メンテナンスしたり,お金を払って専門家の助けを借りなければならないのなら,それは違うと私は思う。技術は我々が満足のいく生活を送る助けになるべきで,その操作や維持に時間や労力を割くべきものではないはずだ。」
という意味だ。
第三は,クラフツマンシップ(職人技,職人魂),
「優れたクラフツマンシップは,美的喜びと誇りを作り手と使い手の両方にもたらす。」
「クラフツマンシップは,表面仕上げのことだけをいっていると思われがちだ。だからこそ,どんなものであれ,手がけるものすべてに関わろうとする姿勢が必要なことを強調したいのだ。もっとも表面仕上げであっても機能的な効果が見られる場合がある。故障はしばしば構造的ストレスの集中に関連して起こり,それは,製造中や組み立て中に発生した局所的な損傷や,熱処理や部品同士のこすれによる摩耗が要因となる場合が多い。熱効率は,たいてい流体通路の滑らかさや,細かなバーナー形状といったものに依存する。耐食性を支えるのは,厳密な表面被膜制御だ。挙げだしたらきりがない。品質は確実にディテールに依存し,ディテールはクラフツマンシップに依存する。
また優れたクラフツマンシップは,製造がしやすい設計がなされていることを示唆し,言い換えれば,優れた設計だということもできる。」
等々。
第四は,感情に訴えているか,
「アップルの成功の一因は,機能とは別に,人に好まれる(情動反応)ルック・アンド・フィール(見た目や操作感など)を実現したことにある。理屈は,感情の二の次になることが多い。」
「人間の感情―自分自身の,製品の販売・製造・サービスに関わる人々の,一緒に働く人々や従業員の感情―に配慮すれば,品質の高い製品をつくる上で必ずプラスの影響がある。この感情を育てるには,単純に人間の重要な特質としての感情にもっと興味をもつことだ。」
「ヒューマンフィットに関する問題の原因は,情報やツールの不足ではなく,生産消費プロセスにおける相対的な優先順位の低さだ。なぜか。それはたぶん,つくり手の感情がエンドユーザーの感情よりも強く働いているからだ。設計者にとっては,人の手になじむかどうかを心配するより,小型化を追及するほうが楽しいかもしれないし,新しい機能を追加することに夢中になるあまり,ユーザーが使い方を理解できるかどうかまで頭が回らない可能性がある(だが好都合なことに,消費者もヒューマンフィットよりも,多機能の小型製品を好む傾向が強い)。」
等々。
第五は,美,エレガンス,洗練,
「ものづくりに関わる人の短期的思考やセンスの偏りと欠如のために,その多くが美的要素よりも重視されている。製品企画や生産に関わる大半の人は,芸術家に関心がない。」
「工業製品の美しさには多くの要素が絡んでいる。ライン,フォルム,色,テクスチャー,重量などのほか,工業製品に特有の留め具の使用や,接合部の処理,製造の仕上がり(たとえば,成型や溶接によるヒケやバリ)などがある。アートには,デザインの指針となるものがいろいろある。画家は,スケールやバランス,統一感,強調,対比,リズム,変化にこだわる。彫刻家は,見た目の面白さや,どこから見ても立体的に見える(アーティキュレーション)を重視する。こうしたことが製品デザインや設計に当てはまる場合も当てはまらない場合もあるが,設計者は頭の片隅に置いておかなければならない。(中略)しかし,美的配慮に関する限り,製品設計者は,…制約が多い。(中略)マーケティングや,社内の製品部門,組織の慣習,会長から生産ラインの担当者に至るあらゆる人の意見といった制約を受けて仕事をしている。((中略))そこに美的要素を入れ込むのは難しい。美しい製品をつくることによって得られるかもしれない長期的な利益よりも,美しさを無視して節約できるイニシャルコストのほうが簡単に数値化できる。
そのため,採算性が怪しくなると,企業は現行製品の改良や次世代製品の品質を損なう危険性があっても,短期的なコストカットを選ぶ傾向がある。」
等々。しかも,美的判断力には訓練,経験,センスがいる。
「『エレガント』と『洗練』は,言葉そのものの意味はわかりにくくても,人間にとって大事なものだ。ものをつくる人は,エレガントで洗練された製品をつくるために,デザイン的に研ぎ澄まさる必要がある。そうやってつくられたものは,たとえ受け手がデザイン的に洗練されていなくても,誰にも愛される製品になると私は信じている。デザインする上での『洗練』には,訓練,接触,そしてセンスが求められる。何を訴求しているのかをわからずに,エレガントな設計をすることはおそらくできまい。もし私が,エレガントで洗練された製品はどうしたらつくれるようになるのかと聞かれたら,私は,そういう製品を愛し,そういう製品にどっぷり浸かることだと答えるだろう。」
第六は,象徴性と文化的価値を表す,
「個々の製品から連想する象徴性は,歴史的なものであると同時に,その製品がもつ役割の作用でもあり,つくり手や売り手の努力の結果でもある。」
「ものをつくる企業は,自社製品が何を象徴するのかを理解し,それが顧客に合っているのかを確認しなければならない。」
「長期的観点で人類が繁栄するには,グローバル思考を身につけるしかない。しかし,人類のサブセットを象徴する多様化した製品は生き残るだろう。私はもっと多様化してほしいと思う。簡単に欠点や欠陥が見つかる製品が多いのは,大量生産という今のシステムに内在する妥協のせいだ。製品のカスタマイゼーションの強化については二〇年前から議論されているが,ほとんど何も変わっていない。人間の嗜好に合わせて多様化するよりも,集約化を納得させるほうが安く済むからだろう。人は多様性にしがみつき,市場はそれに従うと私は見ている。」
等々。
第七は,地球という制約。
「アメリカのビジネススクールの学生たちはよく『トリプルボトムライン』について議論している。企業は経済的利益(ボトムラインは財務諸表の最終行,つまり利益や損失を示す)だけでなく,人類や地球のことも考えなければならないというジョン・エルキトンが提唱した概念だ。国民の多くは,温室効果ガスの排出量を低減するための国際的合意である京都議定書にアメリカが参加しなかったことを恥ずかしく思い,アメリカが環境保護において足を引っ張るのではなく,リーダー的立場をとるべきだと考えている。」
「企業は昔から環境保護のための規制や費用に反対する立場をとっているが,それはおかしなことで,生態圏へのアプローチを方向転換すれば,いくらでも利益を上げる方法はある。」
等々。
著者の問題意識の対象は,アメリカ企業だが,その多くは,今日の日本企業にも当てはまる。
「論理的に議論し,定量的に扱うことが難しい品質の側面」
を取り上げようとする,著者の意図はよく伝わってくる。
「良い製品は善である(Better Quality is Good)」
と述べ,
「ぜひ,『いい仕事』をしてください。」
とは,著者の本音である。
参考文献;
ジェイムズ・L・アダムズ『よい製品とは何か』(ダイヤモンド社) |
|
メタ認知 |
|
三宮真智子編『メタ認知―学習力を支える高次認知機能』を読む。
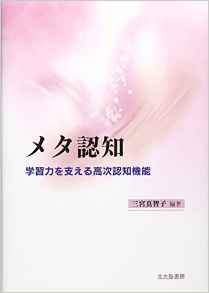
本書は,「はじめに」の劈頭,
「人間には,認知活動それ自体を対象として認知する心の働きがある。これがメタ認知とよばれるものである。」
で始まる。
自分自身をメタ・ポジションから見る,
と言ってもいい。当然,その自分自身をもメタ化することができる。
メタメタ認知,
もあるし,
メタメタメタ認知,
もありえるが,実感では,堂々巡りの言い換えのようなところに陥る。メタ化には限界があるはずである。ちょうど,鏡で自分の目の中に映る自分の目を見るのに似ている。当然視界の限度がある。
メタ認知が話題になっているのは,
「メタ認知を働かせることにより,私たちは,自分の判断や推理,記憶や理解など,あらゆる認知活動にチェックをかけ,誤りを正し,望ましい方向に軌道修正することが可能になる。また,自分の認知的な弱点を補い,パフォーマンスを向上させることができる。」
という機能を持っているからだが,これが重要になってくるのは,
「学習活動を効果的に行うために欠かせない」
からだし,
「学ぶ力すなわち学習力を考えるとき,メタ認知こそが,この学習力を支えてくれる。」
からだ。本書では,
「認知心理学,教育心理学,学習心理学,発達心理学,言語心理学,臨床心理学,障害児心理学,神経心理学といった多岐にわたる研究領域を視野に入れ,特に学習に関連するメタ認知研究の現状と課題を論じる」
ものになっている。当然研究途上のものもある。しかし,本書は,
「学習に関連したメタ認知の理論研究から応用研究までを幅広く網羅し,…最新のメタ研究の成果を系統的に紹介する」
ことを目指している。
第一章 メタ認知研究の背景と意義
で,かつては,
省察(reflection),
あるいは,
省察的思考(reflective thinking),
あるいは,
内観(introspection),
と呼ばれてきた先史から,ピアジェの,
認知の自己調整(self-regulation),
を経て,
心の理論(theory of mind),
や,ヴィゴツキーの,
外語(external speech)から内語(inner speech)へ,
等々を経て, 1970年代以降,
メタ認知(metacognition)
という言葉が使われ,現時点での,
メタ認知知識,
と
メタ認知活動,
を整理している。メタ認知知識は,
Knowing that,
メタ認知活動は,
Knowing how
と喩えると,僕にはわかりやすい。メタ認知活動は,
メタ認知的コントロール
と
メタ認知的モニタリング,
と分けられるらしい。そして,こう整理する。
「日常の学習場面においても,自分が学習内容を理解できていないことがわかったり(メタ認知的モニタリングの失敗),目標設定が高すぎたり低すぎたりする(メタ認知的コントロールの失敗)など,…メタ認知を修正するためには,メタ認知そのものを認知の対象とすること,すなわちメタメタ認知を働かせることが必要である。」
Knowing howについてのKnowing that,
の蓄積ということになる。さて,そうやって,メタ認知の研究を俯瞰した後,
第2章 学習におけるメタ認知と機能,
第3章 知識の獲得・利用とメタ認知,
第4章 学習方略とメタ認知,
第5章 学習における動機づけとメタ認知,
第6章 文章の理解におけるメタ認知,
第7章 数学的問題解決におけるメタ認知,
第8章 科学的思考と科学理論の形成におけるメタ認知,
第9章 談話の産出・理解におけるメタ認知
第10章 学習の障害とメタ認知
第11章 認知行動療法とメタ認知
第12章 メタ認知の神経科学的基礎
と各論に入る。特に,学習の,
自己調整,
つまり主体的に学習していくためには,
自己効力感(ある課題に対する自分にはできるだろうという自分への期待),
に支えられる,ということは,動機づけにおいての,
自己決定性,
自律性,
に繋がり,それが,原因帰属において,
自分以外の事柄(外的)
自分(内的)
に起因させるかにつながり,自尊感情を左右するところにもつながっていく。
最後に,
「前頭連合野はメタ認知的知識を利用したメタ認知的モニター,メタ認知的統御に最も重要な役割を果たしている…・前頭連合野損傷の患者が,『どのようにすべきかという知識については,正しく保持しているのに,それを場面に即して利用することができない』という事例が数多くあげられている。メタ認知の知識は意味記憶として海馬の働きで後連合野に,あるいは手続き記憶として大脳基底核に蓄えられていると考えられている。ただそうした知識を身につける過程では,『何をどのように身につけるか』という点で前頭連合野は重要な役割を果たしていると考えられる。」
どう身につけるかというプロセスをモニタリングした経験が,どうするかの実践のコントロールに活かされる,という意味で,実体験の感覚と合致する。それをコントロールし支えているのが,前頭連合野ということになるらしい。
参考文献;
三宮真智子編『メタ認知―学習力を支える高次認知機能』(北大路書房) |
|
数の影 |
|
ルドルフ・タシュナー『数の魔力―数秘術から量子論まで』を読む。
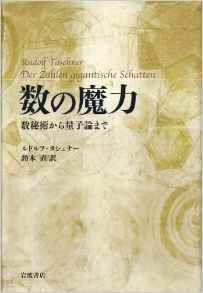
原書のタイトルは,直訳すると,
『数たちの巨大な影』
で,サブタイトルには,
「時代の兆しの中の数学」
とあるらしい。著者は,「まえがき」で,
「数というものが,存在の多様な側面にいかに深く浸透しているかは,ほとんど知られていない。そして,数が投じる長い影がどれほど果てしない遠方にまで延びているかを調べた人は,これまでほとんどいなかったように思える。本書はその影をたどり,そして思いがけず,世界についての驚嘆すべき奇想天外な諸見解に出くわすことになった。それらは,とことん考え抜く気構えさえあれば,ありふれたSFが提供するいかなる仮説やシナリオも軽く凌駕するものだ。とはいえこれは決して,(中略)主役は数そのものではなく,あくまでその『巨大な影』の方だ。(中略)だから本書では『数とは何か』ではなく,『数とは何を意味しているか』を語っていきたいと思う。」
と書く。本書の,劈頭は,
「ありとあらゆるものは,われわれ自身を含めた全宇宙は数である」
というピタゴラスの思想から始まり,巻末は,
「無限なるものに適切に対処するには,無限なるものがあたかも整数と同様に,数学の対象としてすでに与えられ,全体として支配できるものであるかのように錯覚に陥らないようにする必要がある。無限なるものはむしろある種の境界概念であり,基本的に人間の知的好奇心の網の目からは逃れていく。無限なるものは,デーデキントのあらゆる幻想(『πのような値の計算と,3のような整数の計算とを区別する境界線は,もはやまったく認められない』と言ったとされる)とは逆に,つかみどころのないものだ。しかしそれにもかかわらず,パスカルが言うとおりの意味で,われわれはそれについて考えるように促されているのを感じる。なぜなら無限なるもののうちには『バベルの図書館』が,宇宙が潜んでいるからだ。」
で締めくくる。因みに,「バベルの図書館」とは,ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編小説で,そこに登場する架空の図書館である。そこには,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8
によると,
「全て同じ大きさの本であり、1冊410ページで構成される。さらにどの本も1ページに40行、1行に80文字という構成である。また本の大半は意味のない文字の羅列である。また、ほとんどは題名が内容と一致しない。
全ての本は22文字のアルファベット(小文字)と文字の区切り(空白)、コンマ、ピリオドの25文字しか使われていない。
同じ本は2冊とない。
それゆえ司書たちはこの図書館は、この25文字で表現可能な全ての組合せを納めていると考えている。すなわち、これまでに書かれたすべての本の翻訳、これから書かれるすべての本の翻訳、それらの本の落丁・乱丁・誤訳版、および不完全な版を指摘した解説書、解説書の偽書、解説書の偽書一覧目録(これにも偽書あり)等のすべてを含む。つまり本作『バベルの図書館』自体がバベルの図書館に所蔵されている。序章でボルヘスはこの作品自体、すでに書かれていたものであるとしている。」
のだそうである。だから,我々の知的探求は,とどまらない,ということだろう。で,各章は,
1.ピタゴラス 数と象徴,
2.バッハ 数と音楽,
3.ホーフマンスタール 数と時間,
4.デカルト 数と時間,
5,ライプニッツ 数と倫理,
6.ラプラス 数と政治,
7.ボーア 数と物理,
8.パスカル 数と精神,
というちょっと魅力的なタイトルがついている。しかし,簡単には噛み切れない手ごたえ満載である。いくつか「影」を拾ってみる。
たとえば,第一章では,創世記にまつわって,
「創造の過程は,文字から単語を作る過程の中に映し出される。22のヘブライ語文字から二つの文字を選んで並べる並べ方は何通りあるだろうか。(中略)合計は以下のようになる。
2×21+2×20+2×19+……+2×3+2×2+2×1
これらの総計は四六二通り。すでに述べたように,冒頭の基本文は『はじめに神は天と地とを創造された』の七つの語は,折句を通じて22のアルファベッドの各文字を示唆していた。創造物語からこの最初の文章を取り除くと,全創造物語の残りの(ヘブライ語)単語数は全部で四六二語となる。こうなるとほとんど有無を言わさず,次のことを認識させられる。つまり創造物語の作者は,光の創造から人間の創造に至るまでの物語をわかりやすく語ろうとしていただけではなかった。この作者はテキスト構成の際に,数秘術の立場から世界をアルファベッドの展開として,また同時に―ヘブライ語では数字と文字は同じものなので―多くの単語を用いて,世界を数の展開としても説明しようとしていたのだ。」
と。第二章では,バッハの『平均律クラヴィーア曲集』について,
「このフーガの主題が音階に含まれるすべての音をめぐっていることで,そこでは,十二音すべてが使われている。12という数は半音階の音の総数を象徴しているだけではなく,『完全性』の象徴でもある。なぜなら12=3×4であり,3は空間の三次元を,4は東西南北の方角,あるいは土,火,水,空気の古代の四元素を表しているからだ。同時に12は黄道十二宮の数であり,一年の月数でもある。」
と。さらに,ゼノンをめぐって,第三章では,
「ゼノンの論理は,矢が(ゼノンにとってはただ見かけ上)動いている時間を無限に多くの時間に分割できるということを,また同じように,矢が(ゼノンにとってはただ見かけ上)動いている距離を無限に多くの点に分解できるということを前提にしている。というのも,この前提があってはじめて矢が『すべての瞬間』に『特定の』場所にとどまっているという言い方ができるからだ。しかし論理の中に無限なるものの存在を前提にすることは,いかようにしても正当化できない。(中略)現実にはいかなる場所においても,われわれは無限なものに出会うことはない。微視的にみれば,世界は有限なものであることが立証される。ある区間は無限に多くの点に分割できるというアイデアには,量子力学的な不確実性が立ちふさがる。巨視的にもまた無限性の実在という観念は,宇宙の地平の存在によって頓挫する。この地平の『かなた』にはいかなる信号も届かず,したがってこの『かなた』なるものはわれわれにとって意味をなさないからだ。」
と。第四章では,デカルトをめぐって,
「広がりをもつ対象と思考する主体とをそもそも区別しうるようにするために,デカルトは当然のことながら,空間は思考とは独立に存在するという仮定から出発した。デカルトの世界観を要約すれば『空間と思考は対立項である』ということになるであろう。しかし実際には,(中略)空間は思考の対立項ではなく,思考の対象なのだ。デカルトが提案したように,世界を対立項に分けねばならないとしても,それは広がりをもつ対象と思考する主体の間の対立ではなく,むしろ…『思考された対象』と…『思考する主体』の間の対立であるべきだ。そして空間とは,数によって把握可能な『思考された対象』なのだ。果たしなく巨大な宇宙(中略)の距離が『存在している』のは,ひとえにわれわれがそれを計算できるからだ。数よりほかには何一つ,宇宙のうちには見いだせるものはない。そして,宇宙の広さは,数学的思考の深さによってきめられているのだ。」
と。第五章では,チューリング,ゲーデルをめぐって,
「0と1による思考の形式論理学に不具合などありえない。そしてこのことは『無限ループ発見プログラム』など存在しえないという認識にたどりつかざるをえない。論理学者とコンピュータの専門家たちはこの認識を,彼らの用語でゲーデルの不完全性定理,あるいはチューリングの停止性問題の決定不可能性問題と呼んでいる。それによれば,すべてのコンピュータプログラムに対して,そのプログラムがいつか停止するのか,それとも無限ループの中で永遠に走り続けるのかを決定できるような,万能かつ計算機によって実行可能な手順というものは存在しえない。」
と。第六章で,全宇宙は魂なきマシンであり,不確実なものはない,とした「ラプラスの悪魔」について,それを打ち砕いた,
「決定的な一歩は,ヴェルナー・ハイゼンベルクによって立てられた不確定性原理によって踏み出された。ある特定の瞬間における位置座標と速度座標とが―少なくとも原理的には―好きなだけ正確に記述できる点状の『原子』というイメージが,これによって破壊された。簡単にいえば,ラプラスが依拠していたニュートンの公式は,まったく存在していない対象についてしか成り立たないということだ。ニュートンの数学体系は,たとえば天体力学のように,互いに結合した多くの原子の巨大な塊を観察するといった単純化された前提条件のもとでしか成立しない。それ以外のときには,はるかに複雑な量子論の数学体系を代用する必要があり,この理論はラプラスの悪魔を無力な怪物に変えてしまった。」
と。円周率をめぐって,現在一兆二四〇〇億桁以上に達していることについて,第八章で,
「計算をかりに一〇京桁にまで延ばしてみても,そこからはほとんど何もえられないだろう。なぜなら,正確な値はそれでもまだわからないからだ。いかにコンピュータが巨大な計算能力を備えていたとしても,われわれらはπの無限桁のすべてを明かすことは絶対にできない。」
このπについて,
「πの小数展開の中に出現する00という数字列を空白に置き換え,01という数字列をaに,02という数字列をbに,03という数字列をcに置き換えるというふうに進めていく。アルファベッドが尽きたら,また空白から始め,最後は99も一つのアルファベッドに置き換える。こうすれば,最新世代の最強のコンピュータによって計算されたπの少数展開を収めた図書館は,ボルヘスが…描いた,考えうるあらゆる書を収めた図書館に変貌する。」
と。影は,我々自身も含めた全宇宙に及ぶ。
参考文献;
ルドルフ・タシュナー『数の魔力―数秘術から量子論まで』(岩波書店) |
|
ポジティブ感情 |
|
マーティン・セリグマン『世界でひとつだけの幸せ―ポジティブ心理学が教えてくれる満ち足りた人生』を読む。
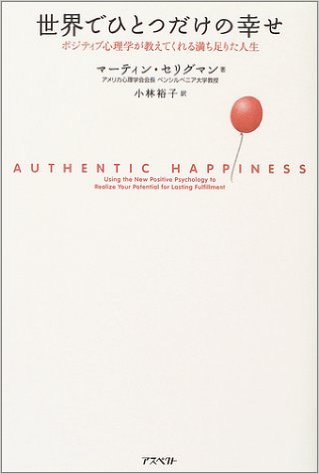
正直,このタイトルには引いた。ポジティブ心理学のセリグマンの著作でなければ,手にすることもなく,無視したであろう。原題は,
Authentic Happiness
である。邦題との乖離は大きい。ぶっちゃけいえば,
幸せを目指す,
などということを聞くと,浮世離れした人だと思うことにしている。幸せは目的ではない。それについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/429261226.html
で触れた。著者は,
「私の関心事は,幸福を定義することではなく,ポジティブな感情と強みを分析し,どうすればその感情と強みを増やすことができるかという『幸福の構成要素』をあなたに教えることだ」
という。それは,「学習性無力感」を研究するなかで,
「最悪の状況におちいっても,快復のきざしを見せる患者たちの存在」
に気づき,
「無気力感に屈しない人たちがもつ弾力性のある強さ」
に着目し,ポジティブな感情に焦点を当て,
「本書の最大のテーマは,心の病を和らげる精神病理の知識に,人々の備えもつ強みと美徳,そしてポジティブな感情についての知識をプラスして,今までの心理学のバランスを修正し,ポジティブ心理学を発展させることにある。」
と,冒頭で書く。そして,こう加える。
「それにしても,既存のポジティブ心理学の本は,どうしても刹那的な『幸福論』や『快楽論』の域をでないのだろうか?幸福をもたらす質の良い生活とは,単純に,良い時間の総量から悪い時間の総量を差し引いたものだと,快楽主義者は指摘する。事実,大多数の人たちが,このゴールに向かって生活を営んでいる。しかしこの論理は,まったく浮世離れしている。刹那的な感情の合計とは,映画や休暇,結婚といったエピソードが,その人にとって良かったか悪かったか判断しただけの,欠陥だらけの論理に過ぎないからだ。」
そこで,パート1では,ポジティブな感情の,
進化の過程でポジティブな感情を得た理由は何か,
ポジティブな感情を多く持つ人と持たない人の差は何か,
日常生活で,ポジティブな感情を持続させる秘訣は何か,
の答えを,調査結果に基づいて出し,パート2では,
心身ともに健康な状態とはどういうことか,
を知るために,自分の強みや美徳を理解する必要がある,これがテーマになる。強みについて,こう著者は書いている。
「強みには,性格と深くかかわるものと,あまりかかわれりのないものがある。私は,性格と深くかかわる強みのことを『とっておきの強み』と呼んでいる。あなたが,『とっておきの強み』と『性格とは関係のない強み』とを区別できるようになることも,本書の目的のひとつである。」
と。それは,
「良い人生とは,毎日の生活の主要な領域で,自分の強みを使うことによって引きだされる幸せの中にある。有意義な人生とは,人生を豊かにするのと同じ強みを使って,さらに知識や力,善良さを促進することだ。そういった人生は意義深いものになるだろう。」
と,末尾の結論に書いていることとも関わっている。そしてパート3では,
豊かな生活とは何か,
について応えていく。ここにあるのは,目的化した「幸せ」ではなく,
どう生きるか,
についての,ポジティブ心理学からの提案なのである。随所にセルフチェックを交え,自分の強み発見へといざなっていく。有名なのかどうか知らないが,
H(永続する幸福のレベル)=S(あらかじめ設定された幸福の範囲)+C(生活環境から得られる幸せ)+V(自発的にコントロールする要因),
という数式を示す。遺伝的要因,環境的要因はあるが,掛け算ではない。自発的な要因というのは,
ポジティブ感情次第,
という含意である。たとえば,
「楽観的な人は,良い出来事が起きた要因を『能力』や『特性』といった永続的な言葉で説明し,悲観的な人は,『気分』や『努力』といった一時的な言葉で説明する。」(逆に「悪い出来事については一時的で特定的な説明をする」)
それは,自分がコントロールできる力があると思えているかどうかを左右する。
だからといって,
「もし人生のすべてがポジティブな感情の追求だけにささげられるとしたら,本物の幸せやその意味は見つからないだろう。…アリストテレスが提示したごとく,『どうしたら幸福になれるか』ではなく,『充実した人生とは何か』と問うべきなのだ。」
と著者は,釘を刺すことを忘れていない。ここが,ポジティブ心理学をまがいものにしない所以だと,思う。
因みに,著者は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/442342315.html?1475092111
で触れたフロー体験についても,強みがいるとして,
とっておきの強みを意識する,
日々その強みを活用できる仕事を選ぶ,
とっておきの強みをもっと発揮し,現在の仕事への取り組み方を見直し,改善する,
等々を挙げている。
参考文献;
マーティン・セリグマン『世界でひとつだけの幸せ―ポジティブ心理学が教えてくれる満ち足りた人生』(アスベクト)
|
|
フロー体験 |
|
M・チクセントミハイ『楽しみの社会学』を読む。
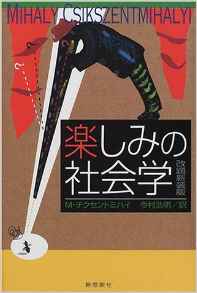
本書の原題は,
Beyond Boredom and Anxiety
である。これは,行動主義のB・F・スキナーの,
Beyond Freedom and Di gnity,Bantam
のパロディとされる。訳者(今村浩明)は,あとがきで,
「スキナーは,同書の中で一種の人間機械論…を展開し,人間へのオペラント条件づけを重視」
したらしいが,まさに本書は,スキナーがスルーした人の内発的動機づけに焦点を当てていることの高らかな喧伝でもある。
本書は,既に著名な,
フロー体験,
を発見するに至る経緯を著わしたものだ。本文中で,
「不安と退屈という二つの変数の彼方にある行為の経験」
と,著者は,書いている,
「内発的報酬を得る行動の,新しいモデル」
をつくるために,
「我々が最初この研究に取り組んだ方法は,できるだけ多くの,オートテリック(ギリシャ語のauto=自己とtelos=目標,目的との合成語)活動を行っている人々と会い,なぜ彼らがこれらの行動を行っているのかをたずねるという単純なことであった。その活動がある型に従った大きなエネルギー消費を必要とし,もし世俗的な報酬が与えられるとしても,それがわずかなものであるならば,その活動をオートテリックなものと仮定した。最初に我々は大学のホッケーとサッカーの選手,洞窟探検家や探検家,国際的に著名な一人の登山家,ハンドボールの優勝チームの一選手,それに一人の水泳長距離世界記録保持者を含む,約六十名に対して予備的面接を行った。更にこれらの面接の結果から,質問紙と,より精密な面接を行った。
これらを用いて,自己目的的活動を行っている他の数多くの人々を調べた。その中には,次のような人々が含まれている。即ち熟達者と若干の初心者を含むロック・クライマー三〇名,初心者から名人までを含む男性チェス・プレイヤー三〇名,合衆国で一流の女性チェス・プレイヤー二三名,現代音楽の職業作曲家,初心者とプロを含む女性モダン・ダンサー二八名,ボストン地区の選手権を獲得した二校のハイスクールのバスケットチームのメンバー四〇名である。」
この他,本書には,二一名の外科医の調査に基づく結果もある。
「フロー」ということば自体が,こうした面接の中で,ロック・クライマーが,
「ロック・クライミングの神秘で崇高な雰囲気は,登るということの中にあります。頂上について終ったと喜ぶ。しかしほんとうは永遠に登り続けることを望んでいるのです。…クライミングを意味づけるものは登るということなのです。自分自身の内にあるもののほか,征服すべきものなど何もありません…。…自分が一つの流れ(フロー)であることの認識ですね。フローの目的は流れ続けること,頂上やユートピアを望むということではなく,流れの状態を保ち続けるということです。登るということではなく,絶え間のない流れなのです。この流れを保つために登っているにしかすぎません。クライミングにとって,登るということ以外に考えられることはありません。それは自分との対話なのです。」
という面談での話から「借用したもの」なのである。本書では,
チェス・プレイヤー,
ロック・クライマー,
ロック・ダンサー,
外科医,
についてそれぞれ章を立てて,詳述しているが,フロー体験(特に,深いフロー体験)は,次のように特徴が整理されている。
第一は,行為と意識の融合。
「通常,人はわずかの間しか意識と行為との融合を維持できない。その融合は彼が外からの視点を採るという幕間をいれることによって壊されてしまう…。」
第二は,その活動は実行可能で手頃なものでなければならない。
「フローは遂行すべき課業が,人の遂行能力の範囲内にある時にのみ生ずるようである。」
第三に,限定された刺激領域への,注意集中から生ずる。
「自分の行為への注意の集中を確かなものにするためには,邪魔になる刺激を注意の外に留めておかねばならない。」
第四に,自我の喪失,自我忘却,自我意識の喪失。
「『個の超越』『世界との融合』とすら表現されてきたものである。」
第五に,自分の行為や環境を支配している。
「多くの場合,フロー状態が続いている場合,自分の技能は環境の求めるところと一致していた…。…環境を支配しながら,同時に環境に融合しているという感じ…。」
第六に,首尾一貫した矛盾のない行為を必要とし,個人の行為に対する明瞭で明確なフィードバックを備えている。
「フロー体験という人為的に単純化された現実においては,何が『正しい』か『間違っている』かが明確にわかり,目的と手段が論理的に整理されており,現実での生活のように両立しないものごとの遂行を期待されることもない。」
第七は,自己目的的である。
「明らかにそれ自体のほかに目的や報酬を必要としないということである。」
そして,これらのフロー体験の特徴は,
「互いに結びつきあい,依存しあっている。フロー活動は刺激の領域を限定することによって,人々の行為を一点に集中させ,気持ちの分散を無視させるが,その結果,人々は環境支配の可能性を感ずることになる。フロー活動は明瞭で矛盾のないルールを持っているところから,その中で行動する人々は,しばしの間,我を忘れ,自分にまつわる問題を忘れることができる。」
である。ポジティブ心理学のセリグマンは,
その任務は困難であり,技能が必要である,
集中できる,
はっきりしたゴールがある,
すぐにフィードバックが得られる,
たやすく深くかかわれる,
コントロールする感覚がある,
自己意識が消滅する,
時間が停止する,
と,ちょっとニュアンスを変えてまとめている。こうしたフロー体験の構造は,
「人々の行為の機会を自分の能力にちょうど適合したものとして知覚した時,フローは経験される」
ものであり,
「行為への機会が自分の能力よりも大きければ,結果として生ずる緊張は不安として経験される。挑戦に対する能力の比率がより高く,しかも依然として挑戦が彼の技能よりも大きいならば,その経験は心配である。フローの経験は,行為への機会が行為者の技能とつり合っている時に感じられ,従って,その経験は自己目的的である。技能が,それを用いる機会よりも大きい時には退屈状態が生じる。技能の挑戦が大きすぎると,退屈は次第に不安へと手効する。」
と。そして,
「フローを経験する手順は…,現実世界を,ある範囲に限定すること,現実世界のいくつかの局面を支配すること,フロー活動に無関係なものを排除する注意の集中によってフィードバックに反応することなど」
は同一過程らしい。それにしても,注意散漫な,僕らのような人間には,
深いフロー,
に代わって,「テレビを見る,腕を伸ばす,コーヒーを飲みながら歓談する等」の
小さなフロー(マイクロフロー),
というものがあり,それは,
ウィンドウショッピング,買い物をする,
画廊へ行く,
他者と無駄話をしたり冗談を言う,
社交的行事に参加する,パーティに出る,
性的活動,
等々という,「社交的」領域が28.6%を占めている,という。考えれば,
現実世界を,ある範囲に限定すること,
現実世界のいくつかの局面を支配すること,
というフロー体験の要件に合うことを考えれば,
散歩,
ウォーキング,
一人でゲームする,
等々も,
鼻歌を歌う,
心の中で妄想する,
独りごと,
等々も,
プチ集中,
プチ熱中,
といってよく,その意味で,軽いフローのない生活はないのかもしれない。
参考文献;
M・チクセントミハイ『楽しみの社会学』(新思索社)
マーティン・セリグマン『世界でひとつだけの幸せ―ポジティブ心理学が教えてくれる満ち足りた人生』(アスベクト) |
|
サイエンス・ウォーズ |
|
ジェームズ・ロバート・ブラウン『なぜ科学を語ってすれ違うのか――ソーカル事件を超えて』を読む。

原題は,
Who Rules In Scienc?
である。曰く,
誰が科学を支配するのか?
である。著者は,最後に,その答えを,こう書く。
「誰が支配するべき何のだろうか? もちろん大衆が支配するべきだ。ただし,大衆は情報に通じた声を聞く必要がある。もしもソーカル事件が,分析的思考力をもち,科学に共感する人たちを触発して,社会にとって建設的な行動をとらせるのであれば,それこそは彼の真の遺産となるだろう。」
と,本書のきっかけでもあり,全体に強い影を落としている,
ソーカル事件,
とは,物理学者アラン・ソーカルが,
「境界を侵犯すること―量子重力の変形解釈に向けて」
と題するパロディ論文を,1996年,『ソーシャル・テクスト』誌に投稿し,編集者をまんまと欺いて掲載させてしまった。
「ソーカルの論文は,ポストモダンのジャーゴンで巧妙に塗り固めたでっちあげ」
だったのである。その紹介の中で,二つの文章を掲げる。
「二つの文のうち一方は,物理学者たちに広く受け入れられている内容である。他方は,安っぽいナンセンスだ。
どちらがどちらかわかるだろうか?
a.今後は,たんなる空間とたんなる時間は,影にすぎないものとして消え去る運命にあり,それら二つがある種の結びつきをしたものだけが,独立の実在性をたもちつづけるだろう。
b.球の一次のホモロジー群はトリビアルだが,他の面のホモロジー群は深い。そしてこのホモロジーは,ひとつまたはそれ以上の,切断を入れたあとの,その連結性,非連結性とつながっている。さらに,物理的世界の外的構造と,結び目理論として見たときの,それの内的な心理学的表現とのあいだには密接な関係がある。
どちらがナンセンスか,わからなくとも無理はない。」
確かに,編集者もころりと騙されたのだから(前者は,ヘルマン・ミンコフスキーからの引用と,著者は後で明かしている)。ソーカルのこのパロディは,デリダやラカンいったポストモダンを標的として,
「ものごとには特定のありようというものがある。科学者はそれを理解しようとし,そのためにさまざまなテクニックを身につけ…,多大な成功をおさめてきた」
という,まあ,オーソドックスな,
「正統的科学観」
を擁護しようとした,というように見える。ということは,その背景に,われわよれにとって当たり前の科学常識が,西欧では,論争の素材であったということでもある。そのこと自体が,羨望に値する。今日の我が国のズタボロの知的状況は,これまで怠って知的議論の付けでもある,と思い知らされるのである。
しかし,ソーカルの動機は,本人が明かしているところでは,科学の擁護ではないところが,また面白い。
「ソーカルは,ポストモダン派の連中の手から科学を救出しなければならないなどというつもりはこれっぽっちもなく,むしろ左派の政治運動をお粗末な思想から奪還しなければならないといっているのである。多くの先人たちと同じく,ソーカルもまた,相対主義や,非合理主義や,ずさんな議論などは,進歩主義的な政治目標の基礎をゆるがすと考える。左派には,やりたいことをやり抜くための金もなければ,銃もない。明晰な思考こそが,左派にとっては最強の武器だ。その武器を捨てることは,まさしく愚かなおこないである,と。」
つまり,ソーカルの意図は,政治的である。
「彼の標的となったポストモダン主義者たちとの真の争点は,『量子重力をどう考えるべきか?』ではなく,『社会をより良いものとするには,どうすればいいのか?』という問いだ。」
しかし,このソーカルの投げた−石は,ポストモダン派,アンチ・ポストモダン派にとどまらず,マスメディアを巻き込み,科学者,科学哲学者,社会構成主義者,知識社会学者,政治的な右派左派,と広がり,アメリカ,フランス,イギリスと飛び火し,ついに,
サイエンス・ウォーズ,
という言葉が独り歩きし始めるに至る。バブル崩壊後の混乱の中,知的荒廃している日本は,蚊帳の外である。
著者は,参陣した論者を,政治的右派,左派,正統的科学観に反対,正統的科学観を支持,の四軸で分けて見せるほど,この論戦の戦場は広く深い。
著者は,冒頭で,タイトルについて,
「この表現は,いまどきの若者たちのあいだでは,『誰が一番?』という意味だが,わたしはこの表現の多義的なところが気にいっている。政治的文脈では,『誰が支配しているのか?』という意味にもとれるし,『誰が支配するべきなのか?』ともとれる。本書は,まさにそれについて書かれた一般向けの入門書―それも,ニュートラルな解説書ではなく旗幟鮮明な入門書だ。」
と述べ,その旗幟を,
「そのテーマを,いささか素朴ながら,ひとことで表現すれば,『優れた科学と社会正義は結びついている』ということになるだろう。そして知性と高潔の灯がどこかにともれば,その光はいたるところにひろがっていく。」
と。本書には,科学をめぐる成否の論争を通して,
科学とは何か,
科学者はどうあるべきか,
の図を,地から際立たせていくところがある。こういう科学者と社会科学者との論争の土俵があってこその,西欧の文化なのだと思い知らされる。そこにタブーはない。
だから,
「サイエンス・ウォーズの全貌をとらえるためには,まずはじめに,本書で論じる客観性と価値と社会的要因にまつわる問題を,しっかり掘り下げておく必要があるのだ」
というところから,本書は始められる。科学者の経験として,
新奇な予測をして的中した理論はいい線をいっている,
多くの現象を統一的に説明できる理論には見込みがある,
正確な予測をする理論は有望,
思考実験を賢く利用すれば,概念がはっきりするし,そこから発見に結びつくことさえある,
反証を重く受け止める,
いかに学ぶかを学ぶ,
科学的方法は改良される。
等々を挙げ,ではそれに批判的な各派の論点を一つ一つ整理し,批判していく。まず,
科学哲学は何を問題にしてきたか,
の章では,
ポパーの科学と非科学との線引き問題,
例の反証可能性が取り上げられ, 著者は,ポパーについて,こう書く。
「科学は革命的である,とポパーはいう。科学は安全確実な事実ばかりを慎重に溜めこむことではない。また,科学は,観測可能な事柄をただたんに組織化していくことでもない。ポパーによれば科学とは,実在を説明し,理解しようという,大胆かつ終わりのない探求なのである。」
というポパーの描く科学者像を,
ロマンチック,
と言い切り,こう著者は書く。
「反証可能性という考え方は,科学と非科学とを区別してくれたが,知の営みとして優良なものとガラクタとの違いを教えてはくれなかった。これについてポパーにできたのは,一般原理に訴えることだけだった。この場合は,その学問分野に批判精神があるかどうかを見るのだ。ダーウィンの進化論にはそれがあるのにたいし,創世記の天地創造の記述を文字通りに受けとる宗教的根本主義者たちにはそれがない。しかし,この基準はあまりにもあいまいで使いものにならず,キリスト教根本主義者たちによってあっさり逆手にとられてしまった。キリスト教根本主義者たちは,『著名な科学哲学者のポパーが,ダーウィンの進化論はほんものの科学ではないといっている』といいだしたのである。」
さらに,社会構成主義,ポストモダン等々,と科学の批判の論点をひとつひとつつぶさに見ていく。その論争の論点を,
実在論,
客観性,
価値,
の三つに絞って検証していく。これを中心として論じる「第五章 三つのキーワード」が,サイエンス・ウォーズの主戦場であるらしいのである。著者は,実在論については,
「独断的な意見を求められれば,わたしは喜んでこういおう。実在論者は正しく,それ以外はみんな見当違いをしていると。」
と言い切った上で,
「ほんとうの争点は,実在論ではない。(中略)擁護すべきは客観性という概念なのだ。」
として,主観的,客観的,存在論,認識論の四軸で整理し,
「存在論的意味において,ある命題が客観的であるといえるのは,その命題の真偽がわたしたちとは独立な場合である。」
と述べる。しかし,著者が公正なのは,
「客観的であっても誤りは起こるという点は,いくら強調しても協調しすぎることはない。客観的だから真実だ,という話にはならないのだ。証拠はときに人を欺く。」
と強調するところだろう。価値については,価値命題(であるべき)と事実命題(である)がそれほどクリアに区別できないし,またできるはずもない。著者は,
「科学は価値にとらわれていると主張する人たちは,実は次のようなことをいいたいのではないだろうか。『科学はたくさんの価値を体現しているが,それらの価値は,客観的知識を増進するために役立つようなものである。科学がとらわれないのは,真理の探究という科学の目標を損なうような価値である』。このように限定することにはたしかに難点もあるが,科学はいかなる価値にもいっさいとらわれないという,子どもじみた戯言に比べれば大きな前進だろう。」
と書くときのリアリティは現実的に思える。
あくまで,著者は,科学の側に立つので,
なぜ,現代思想が科学を相対化しようとするのか,
という哲学側の根本的な論点が必ずしも鮮明に伝わってくるわけではないが,単なる科学信仰のように,原発神話を信じて,それについて哲学的,社会思想的な論争をほとんどスルーしてきたわが国の貧弱な思想状況に較べるなら,その幅と奥行きに,ただ圧倒されてしまう。
参考文献;
ジェームズ・ロバート・ブラウン『なぜ科学を語ってすれ違うのか――ソーカル事件を超えて』(みすず書房) |
|
マネジャー |
|
ヘンリー・ミンツバーグ『マネジャーの実像』を読む。

本書の原題は,ずばり,
Managing
である。現実のマネジャーが,何を考え,どう行動しているかを, 30年前の,
『マネジャーの仕事』
という土台の上に,さらに,
「さまざまなタイプの29人のマネジャーの日々を観察した研究結果」
を加えたものだ。この29人は,
「民間企業のマネジャーもいれば,政府機関,医療機関,非政府機関・非営利機関のマネジャーもいる。金融,警察,映画製作,航空機製造,小売,通信など業種もさまざまだ。小さな組織のマネジャーもいるし,大きな組織のマネジャーもいる(スタッフの数は,最小で一八人,最大で八〇万人)。組織内での階層もまたまちだ。トップマネジャーに始まり,ミドルマネジャー,さらに最底辺の現場レベルのマネジャーもいる。ロンドンやパリ,アムステルダム,モントリオールなどの都会で働いている人がいる一方で,タンザニアのンガラ,ノバスコシア(カナダ)のニューミナス,カナダ西部のバンフ国立公園など,人里離れた土地で働いている人もいる。」
それぞれの一日に密着し,それを理論的に読み解くことを試みたのが本書である。
「大切にしたのは,一人ひとりのマネジャーに自分の言葉で語らせること。」
だという。マネジャーを,本書では,
「組織の全体,もしくは組織内の明確に区分できる一部分(ほかに適切な言葉がないので『部署』と呼ぶことにする)に責任を持つ人物のこと」
と定義する。そして,マネジャーは,
「主としてほかの人たちの行動を通して仕事を成し遂げる」
この「ほかの人たち」とは,部下とは限らない。それ以外の人も含まれる。だからこそ,リーダーシップが不可欠になる。そして,
「この本のテーマは,マネジメントという営みそのものである。」
と,著者は語る。
「難しいのは,マネジャーがどういう行動を取っているのかを明らかにすることではない。問題は,マネジャーが取っている行動をどう理解するかだ。マネジメントを構成する多種多様な活動をどのようにかいしゃくすればいいのか。」
その視点からみたとき,リーダーとマネジャーを別物とみなす昨今の流行に,著者は異論を唱える。
「率直に言って,組織の現場でこの区別にどの程度の意味があるのか理解しかねる。なるほど,理窟の上でリーダーシップとマネジメントを区別することは可能だろう。しかし,現実にそれを区別することなどできるのか。もっと言えば,そもそも区別するのが正しいことなのか。
あなたは,リーダーシップを振るわないマネジャーの下で働きたいだろうか。そのような人物は部下の士気を鼓舞できない。では逆に,マネジメントを行なわないリーダーについていきたいだろうか。そのような人物は現場をあまりに知らなすぎる。マネジメントをおこなわなければ,現場で何が起きているのか把握できるわけがない。」
だから,
「マネジャーはリーダーでもあり,リーダーシップはマネジャーでもあるべきだ」
という至極当然の理解に至る。そして,こう書く。
「本当に必要なのは,リーダーシップを強化することではなく,自然にものごとに取り組める主体的な個人からなるコミュニティを築くこと。そしてリーダーシップをマネジメントと一体化させることだ。そこでこの本では,マネジメントを最も重視し,マネジメントとリーダーシップの両者をいわば『コミュニティシップ』の一部をなすものと位置づける。」
コミュニティシップは,あるいは,「チームシップ」とでも言い換えられる。マネジメントの目的とは,
「組織の中でものごとを成し遂げる後押しをすること」
と考えれば,それを推進するチーム構成員を一つにまとめていくことが求められる。それに,マネジメントとリーダーシップの両輪が不可欠なのは理の当然なのである。では,今日,マネジメントは変わったのか。著者はそうは考えていない。
本書が『マネジャーの仕事』を土台にしているという構成から見ると,著者は,
マネジメントの基本,
は,本質的に変わらない,と言いたいのであると,ぼくは思う。
「マネジメントの仕事はずっと変わっていないのだ」
だから,旧著の,マネジメントの仕事の,
過酷なペース,頻繁な中断,守備範囲の広さ,書面以外のコミュニケーションの多さ,行動志向の強さ,ヨコ関係の重視,主導権を握りづらい状況での苦心,等々というマネジャーという仕事の面,
と,
看板役,トラブル処理役,他の役割への越境など,マネジャーの基本的役割の面,
については修正すべき材料はない,と言い切っている。
マネジメントのモデルを,
情報次元のマネジメント,
人間次元のマネジメント,
行動次元のマネジメント,
に分けて,
「情報の次元で,現場から距離を置いて,言葉を使ってマネジメントをおこなう。人間の次元では,情報の次元より現場に近づいて,影響力を用いてマネジメントをおこなう。そして行動の次元では,行動を直接的にマネジメントする。」
マネジャーは,ある業務を完了させるために必要な行動を自分自身でも取る。この場合の,行動は,プレイングマネジャーのそれでは,もちろんない。
「これらの活動は,すべてコントロールの一種だ。コントロールをおこなうときと異なり,ものごとを実行する役割を実践するとき,マネジャーは組織の任務を成し遂げるための活動にじきじき携わる。組織が成果を生み出すために直接的に必要な行動の一翼を担うのである。」
違いは,全体視点を失っていないことだ。そう考えると,マネジャーの評価は,
「トラブルが発生したかどうかではなく,トラブルにどう対処したかを基準に考えるべきだ」
というのはよくわかる。それも,全体の視点からである。そこで著者が導入しているのが,
スコープ(マネジャーの仕事の範囲,裁量の及ぶ範囲)
と
スケール(マネジャーがマネジメントする部署の規模)
という視点だ。とりわけ,スコープの,
タテ方向のスコープ(組織内の階層の上下に及ぶ裁量権の大きさ)
と
ヨコ方向のスコープ(部署や組織の外に及ぶ裁量権の大きさ)
である。この視点抜きで,マネジメントを語ることにはほとんど現実的な意味はない。ただし,僕は,これを規定された裁量権という意味だけには取らない。タテでいえば,課長であっても,部長や本部長や,トップを動かす力があれば,その動かせる人の分だけ,裁量権は大きくなる。ヨコも同じである。組織横断的な影響力,あるいは組織を越えた影響力というものを考えたとき,リーダーシップ抜きのマネジメントなど,ありえないということが見えてくる。
そのときのマネジャーのマネジメントスタイルには,
アート(ビジョン 創造的発想)
クラフト(経験 現実に即した学習)
サイエンス(分析 体系的データ)
のバランスだと,著者は言う。少し矮小化するようだが,
発想力
と
現実力
と
論理力
と言い換えることもできるかもしれない。しかし,マネジメントは,
文脈依存型,
であり,環境や状況抜きに,一般論があるはずはない。
「マネジャーには,自分で自分の仕事をつくり出すだけでなく,与えられた仕事が求められる。したがって,環境を度外視してマネジメントスタイルを論じることには意味がない。」
とは正論である。第五章の「マネジメントのジレンマ」にある,
思考のジレンマ,
情報のジレンマ,
行動のジレンマ,
全体的なジレンマ,
には,マネジメントのリアリティがある。そして著者は,
マネジャーにはみな欠陥がある,
と言い切る。
「致命的な欠陥を抱えているのは,マネジャーに要求される超人的な資質のリストのほうだ。あまりに現実離れしているし,リストに掲げられている資質が好ましい結果を生まない場合も多い。」
と。著者は,マネジメントのマインドセット(思考様式)を挙げる。それを糸とと呼ぶ。
エネルギーの糸,
振り返りの糸,
分析の糸,
広い視野の糸,
協働の糸,
積極行動の糸,
これは資質ではなく,仕事を指していて,それぞれがからみあって一体となる,という意味だ,と著者は説く。マインドセットという意味は,ここにある。
「マネジメントの最大の眼目は,合成を目指して,休むことなく奮闘し続けること,いつまでもゴールにたどり着かなくても,それどころか自分がどの程度ゴールに近づいているかすら見当がつかなくても,その努力をつづけなくてはならない」
と。
「マネジメントの仕事はなまけ者にはつとまらない」
とは,正解かも知れない。
参考文献;
ヘンリー・ミンツバーグ『マネジャーの実像』(日経BP社) |
|
マインド・タイム |
|
ベンジャミン・リベット『マインド・タイム−脳と意識の時間』を読む。
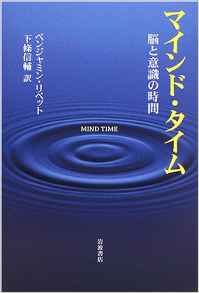
リベットの研究とは,
何かしようと意思決定するより前に,無意識レベルで意思決定が起動している,
ということを実証した研究で知られる。本書は,その仮説,実験,検証,仮説,実験,仮説のプロセスを書いたものだ。序文を書く,S・M・コズリンは,
「この本は,大多数の類書とある一点で決定的に異なっている。それは,推測や議論ではなく,実証的な発見に的を絞っている点だ。」
と言っているが,随所で,著者自身も,カール・ポッパーを引き,
「もし,ある理論なり仮説なりが,それを否定する可能性が,ある方法で検証不能なのであれば,提言者は理論が反証されるおそれなしに,どのような意見でも主張することができてしまいます。」
と,自分の主張は,実験を経て発見したものだということを,強調している。それは,反論は,実証をもってなされるべきだ,という主張でもある。
本書では,著者は,三つのことを述べている。
第一は,感覚か脳で意識されるまでに時間差があるということ,
第二は,自由意思に先立って,無意識レベルで神経活動が始まっているということ,
第三は,脳の活動から生じる精神場(CMF)というものを仮説として提示していること,
この三点である。「マインドタイム」という本書の題名は,ここで見られる意識されるまでの「時間差」を指している,と思われる。この意識を,著者は,
アウェアネス(気づき),
と呼び,
「何かに気づいている状態」
とする。
「外界と(感覚入力を介した)身体内部の世界へのアウェアネス,自己の感情(怒り,喜び,鬱)のアウェアネス,自己の思考と想像力へのアウェアネス,そして,自己へのアウェアネスといった,非常に多岐にわたる経験の内容を包括して,人間は気づいて(アウェアネスを持って)います。」
で,まず,感覚的なアウェアネスについて,結果として,
「短いパルス電流(実験によってそれぞれ約0.1〜0.5ミリ秒間持続する)による刺激を,一秒あたり20パルスから60パルスの範囲で反復します。その結果,…閾値レベルの微弱な感覚を引き出すには,反復的なパルスを約0.5秒間継続しなければなりません。(中略)連発した閾値の刺激を0.5秒以下に短縮すると,感覚が消失します。」
という結果になる。しかし,
「無意識の精神活動は,ほんの0.1秒かそれ以下の非常に短い神経活動でも現れ」
るのに,である。500ミリ秒持続しなければ意識されないが,
「主観的には,私たちは皮膚刺激に対して感知可能な遅延なしにほとんど即座に気づくようです。個々で,奇妙な逆説が生じます。脳内の神経活動の必要条件は,500ミリ秒程度経過しなければ皮膚刺激の意識経験またはアウェアネスが現れることができないことを示しています。その一方,このような遅延なしに経験したと私たちは主観的に信じています。」
この持続時間あるいは,言い換えると遅延しての知覚を,
タイム−オン(持続時間),
と呼ぶ。この無意識と意識の遅延が,有名な実験結果につながる。これがもたらすことの意味と効果は,すなわち,コズリンの整理に従うなら,こうである。
「リベットは人々に,彼らが選んだ任意の時間に手首を動かすことを求めた。参加者は,時間を示す動く点を観て,彼らが手首を曲げようと決めた正確な瞬間(に点がどこにあったか)を心に留めておくように求められた。彼らは実際に運動を始める約200ミリ秒前に意図をもったと報告した。リベットはまた,脳内の『準備電位』を計測している。これは(運動の制御に関わる)補足運動野からの活動記録によって明らかにされた。この準備電位は実験の行為開始のおおよそ550ミリ秒も先立って生じる。したがって,運動を生み出す脳内事象は,実験の参加者当人が決定を下したことに気づくよりも約350ミリ秒前には起こっていることになる。(中略)
この知見が重要なのはなぜか。二つの理由を考えてみてもらいたい。まず率直に事態を眺めると,意思決定を意識することというのは,決定に至る事象の因果的連鎖の一部というよりはむしろ,その行為を実際に行う脳過程の結果として考えるべきだということを,これらの知見は示唆している。第二に,もし仮に運動が無意識の力によって起動されているとしても,ひとたび人が自らの意図に気づくやそれを拒否するのに十分な時間があるということを,リベットは指摘している。」
「脳過程の結果」としての意思決定,というのは結構衝撃的だが,リベットが例を出すように,スポーツ選手や演奏家の多くが,
意識する前に動いている,
という例は枚挙にいとまがない。例えば,野球のバッターの場合,145キロのボールなら,
「ボールは450ミリ秒でバッターに届く。バッターはおそらく…200ミリ秒まで待つことになる。最後の150ミリ秒前くらいになると,スイングすべきかを決定しなければならない。つまり,150ミリ秒とは,運動皮質を活性化させるために必要な最小限の時間である。というのも,神経メッセージを脊髄の運動神経細胞へと下行させ…適切な筋肉を活性化するまでには,およそ50ミリ秒かかるからである。バットのスイングを生み出す実際の筋肉の収縮は約100ミリ秒の間に生じる。」
筋肉の起動は,既に無意識ではじめていなくては間に合わないのである。リベットの発見は,ある意味常識と合致していると言えるのである。
もうひとつ,リベットが出している仮説は,精神活動は,
「脳のニューロン活動によって生じる場」
である,とするものだ。
「意識を伴う精神場(CMF)は,神経細胞の物質的活動と主観的経験の創発との間で媒介作用をする」
と,リベットはいい,このCMF理論は,ロジャー・スペリーの,
「『精神』は『物質』である脳の創発した属性である」
という理論の延長戦上にある,と自ら認めている。
「磁界は導線の中を流れる電流によって生じますが,いったん生じれば今度は電流の流れに影響を与える」
という譬えで,「場」を説明する。むろん,仮説である。しかし,僕は,意識は,ニューロン活動のもたらす,
ホログラム,
のようなものと考えているので,リベットの仮説がすんなり入る。
それにしても,改めて,無意識が表面化し,著者も,再三フロイトの名を挙げているが,優れた仮説は,いつか,実証の中で蘇る。
仮説構想の大きさ,
というものを再認識させられた著書でもある。著者の
「提案されたモデルまたは理論は,データの解釈に役立てられるときに限って価値があるのであって,データを反証するときに価値があるのではありません。」
という言葉は,常に有効である。
参考文献;
ベンジャミン・リベット『マインド・タイム−脳と意識の時間』(岩波書店) |
|
学習方法の知 |
|
アルベルト オリヴェリオ『メタ認知的アプローチによる学ぶ技術』を読む。
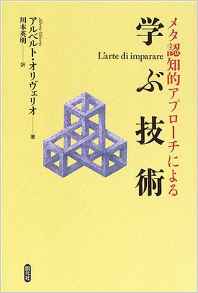
同じ著者,アルベルト オリヴェリオの,
『覚える技術』
『論理的思考の技術』
について,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/441242881.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/441581523.html?1472846643
で,それぞれ触れた。その「技術」シリーズの一冊である。
「何かを学習することは別の状況で役立てることができ,それを応用することが可能」
で,次の経験に活かすことができるが,それは,
「何かを経験することは,それに続く経験に活かされるのです。というのは,以前の経験の特殊な側面を利用するのではなく,それを異なる経験に応用したり,必要不可欠な情報を捜したり,より上手な方法を見につけたりして,『学習方法を学んだ』」
ことになる。この,
学習方法を学ぶ,
というのは,「生まれつきの能力ではなく,後天的な能力」であり,その認知能力を,
メタ認知能力,
と呼ぶ。つまり,
自分の認知をメタ化する能力,
である。たとえば,
「自分の考えの矛盾に気づいたり,課題の特性を把握したうえで解決方法を選択するなど,通常の認知より高次の」
省察とか反省とか,という言い方をすることもある,メタ・ポジションから自分を見る視点に立つ,という言い方もできる。いい例かどうかわからないが,知には,ライルの言う,
Knowing how(いかにやるかを知っている)
と
Knowing that(そのことについて知っている)
という二面があるが,Knowing howだけではなく,Knowing
howについてのKnowing thatを高めていくことで,自分の「どうやるか」をメタ化した方法として意識することができる。その意味で,
「『メタ認知』というのは私たちが知能やその機能,問題解決法などについてもっている知識を示す言葉なのです。私たち人間がどのように考えるのかという働きを知ることは,認識能力を高めることにつながっていて,学習にとって不可欠な知能のプロセスを知ることにもなるのです。つまり,私たちの知能がどのような機能をもち,学習のメカニズムとはどんなものなのかを知ることが,学習方法を学ぶための第一歩となるわけです。」
と,著者は「はじめに」で書く。本書のタイトルに,「メタ認知的アプローチによる」がついている所以である。つまり,
「私たちの認知活動,つまり思考力を上手に用いること」
で,学びの効果を高めようとするのが狙い,というわけである。その点で,学習プロセスをクローズアップした,
第三章 学習の方法
第四章 最初の発見から学習方法を学ぶまで
は,なかなか面白い。学習とは,
「人の知能に修正を加えることであり,その修正は外部環境と自らの行動に左右され,さらには記憶,理解,思考といった学習レベル,すなわち成長とともに実現される体験や学習のレベルと深い関わりがある…。」
のであり,そのつどその学習体験を一般化して,応用しようとする能力は,
転移(トランスファー),
と呼ばれる。それは,
第一に,学習の「陳述記憶」力
つまり,
「新たな学習体験が連続的な動作などのプロセスを伴い具体的な物であっても,それを論理的に(抽象的に)説明する能力…,つまり,一連の概念や出来事を言葉で明確に表現できる(陳述できる)」
ことが重要になる。つまりは,言語化すること自体が,メタ化することなのだから,それが明晰であるほど,経験を対象化できていることを意味する。
第二は,学習の「状況設定」力,
つまり,
「可能な限り行動を状況に当てはめ,特定の場面や前後関係(コンテキスト)と関係づけようとする能力」
である。文脈抜きではあり得ない,というあたりまえのことだが,学習とは取り巻く環境との関係,つまり,グレゴリー・ベイトソンが言う,
相互作用のダンス,
なのであり,そのためには,
①学習課題に関する知識は,なるべくそれを実践する必要のある状況と関連していること,
②学習課題に関する諸要素は,どんな状況にも応用できるものではなく,特定の状況でのみ利用できるものであること,つまり抽象的ではなく具体的な場面で利用できるものであること。
③理屈っぽく抽象的な学習はほとんど役立たないこと。
と,著者は整理する。
かつては, 脳については,
青年期から老年期にかけて,ニューロンが減少していく,
誕生後,ニューロンは増殖しない,
というのが常識であった。しかし,この説は覆されつつある。むしろ,
ニューロンの刈り込みがあるからこそ,神経回路が形成されるし,
刺激のあ環境であれば,ニューロンは増殖する,
と言われる。それは,この変化の時代を生き抜くためには,
「青年期から老年期にかけても,ずっと学習を続ける必要がある」
ということでもある。その意味で,
学習方法の学習,
は一生続くのである。
参考文献;
アルベルト オリヴェリオ『メタ認知的アプローチによる学ぶ技術』(創元社)
三宮真智子編『メタ認知―学習力を支える高次認知機能』(北大路書房)
ギルバート・ライル『心の概念』(みすず書房) |
|
思考の技術 |
|
アルベルト オリヴェリオ『論理的思考の技術―「考える脳」をつくる50の方法』を読む。
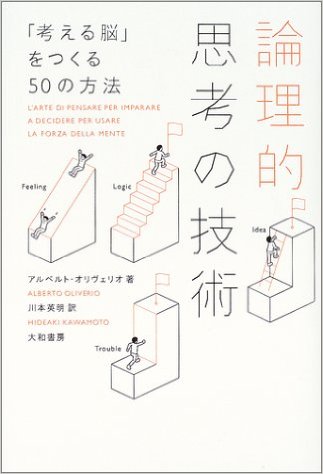
同じ著者,アルベルト オリヴェリオの,
『覚える技術』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/441242881.html
で触れた。その「アート」シリーズの第一作らしい。原題は,「Arte」とある。技術である。しかし,邦題の,
論理的思考の技術,
というのはいかがなものか。
Pensare
とは,「思考」であり,推薦のことばで,池谷裕二氏は,
「いかに考えるか」
ではないか,と書き,
「思考(神経情報処理)は,あえて脳科学的に説明すれば,『アトラクター・ダイナミクス』によって遂行されている。つまり,『帰納法』である。いかに少ない情報で全体を把握するかという能力であり,進化論的にみれば,動物が大自然の中で効率よく生き抜いていくために必要に迫られて発達させた機能である。」
と説明するとおりである。しかし,帰納法は,黒鳥が見つかるまで,「白鳥は白い」という結論は,それまで知られている範囲で(つまりは北半球で)しか帰納させられなかったように,既知の範囲で結論を出すという,一種の限界があり,その中で結論へと飛躍させるところに,勘違いや思い込みが入る余地がある。本書が,
「論理のワナ」にだまされてはいけない
という第一章から始めている所以である。
著者は,「はじめに」で,
「たいていの人は,論理的な思考力や,上手に考え,画期的な答えを出してくれる類推能力,創造力を高めようとしていません。その必要に迫られていないのです。」
しかし,「私たちの脳は,筋力と同じように訓練(経験や教養)によって鍛えることができる」。なぜなら,「『考えられる能力』とは人間の頭脳に初めから備わったものではなく,自分で身につけ,磨いていかなければ」いけないものだからである,と述べています。そして,
「『考える脳』は『意思決定できる脳』に結びついています。」
とも。本書は,
「私たちがなんらかの意思決定を下すときも,認識のワナや感情のワナ,社会のワナなどに陥る可能性はあるわけです。
本書は,そんなワナにはまりたくないと考える人,あるいは理性による論理的な思考だげてなく,水平思考や拡散的思考など,新たな創造的思考を実践してみたいと思う人たちの容貌にお応えしたものです。」
とある。
典型的な認識のワナは,本書で再三出る,
フレーミング,
である。著者は,こう説明している。
「『枠組み(フレーム)』が現実の世界とは異なる絵の『世界』を私たちに見せてくれる…」
と。この「枠組み」が,でっち上げの意味の,
フレーミング,
に通じている。ミュラー・リアーの矢をはじめとする錯視は,われわれの認知に,フレーミングが存在していることを示している。別の言い方をすれば,
バイアス,
である。そして,帰納法(特殊から一般へ)や演繹法(一般から特殊具体例へ)を,われわれは気づかず使っているらしい。
「意識しているか否かにかかわらず,ほとんど自発的に私たちが理論を組みたてる際の基本的な方法になっているのです。たとえどんなに簡単なものであっても,演繹的な考え方は,ほとんどの場合,三段論法を基本としています。それは私たちの知能が現実の枠組みを正しくとらえ,導き出した結論の正当性を『保証する』ためにつくりあげるものです。
私たちの知能が処理する大部分の情報は,論理の追求がなく,『自発的に』処理されているようにみえても,実は三段論法の鎖をかいくぐり,類推のふるいにかけられているのです。」
多くは,社会的常識に基づくが,その論理の組みたてが必ずしも有益な結論に至るとは限らない。たとえば,
①どんな政治家も嘘をつく。
②マリオは政治家である。
③マリオは嘘をつく。
という例を挙げる。一般論から演繹しているが,これが正しいとは限らない。しかし,こうしう常識を前提にして,論理を組み立てることはよくある。
論理の組み立て
や
枠組み
に,つまり粉飾に丸め込まれ,そのフレームの世界の中で,あやまったものを見させられる,とはこのことである。そのためにどうしたらいいかは,
考える脳の「プロセス」
や
「あいまい問題」
の読んで戴くほかはないが,個人的には,創造的思考や直観との絡みで,
類推思考,
の言及に興味がわく。なぜなら,著者は,本書の最後で,
「どんな意思決定においても,その基本となるべき論理・合理主義的な判断基準を『直観に基づいて(アプリオリ)』見極めることが大切なのです。
また,多くの影響力をもつ他の『論理』を基準に,すでに実行している選択を正当化するために『経験に基づいて(ポステリオリ)』,それらを調べることを忘れてはならないでしょう。」
と。結論づけているのだから。
著者は,類推的思考を,こう述べている。
「類推的思考は,いわゆる(演繹的な論理に基づいているという意味で)『論理的』ではありませんが,未知の対象物を認識しようとする試みに対して『強制』したり押しつけたりする論理(類推 アナロジー)が伴っているのです。そして,類推には典型的な強制ともいえる次の3つの点が必然的に存在しています。
1.いくつかの要素が類似していること。
2.種々の役割における構造的な類似点を探求すること。
3.類推的な思考を導くための目的や対象物が存在すること。」
通常,比喩を使って,類推と同じ思考スタイルをとるが,
「類推の働きについては,まだ第一に寓話や比喩を通じて,考え方を間接的に表現できる…。さらに,類推にはもう一つ重要な働きがあり,それは,『うまい駆け引き』ができることです(直接的な表現を使うことができなかったり,危険が伴ったりする場合,類推することで事実を暗示的に伝えられるからです)。(中略)
さらに,類推にはことばを飾る修辞的な働き(よりわかりやすく具体的なことばで,抽象的な世界を『視覚化』させながら対手を納得させる働き)もあります。」
といった利点があるが,類推的思考のプロセスを,著者は,
①(自分の記憶や知識の中から)情報源としていくつかの類似点を選択する。
②その類似点を対象物に応じて図式化する(類似点をさまざまな側面にあてはめる)。つまり,新しい視点を通して,既知の事実や可能性を未知の事実や自分の予想にまで拡大して考える。対象物のもっている新たな特性を明らかにしていく。
③対象物のもつユニークな側面を見極める。
④類推の結果,成功例や失敗例から多くのことを学び取る。
この能力を,強化するには,意識的に,
①対象物の相互関係を読み取る。
②類推的思考の対象となるべきものを図式化するために,記憶をたどって役に立つ情報源を引きだす。
③知能の論理的なプロセスを通して,類推を働かせる。
をしてみることだ,と著者は,説いている。僕は,鍵は,
図式化,
であり,これは,
モデル化,
象徴化,
ともなっていると思う。この積み重ねが,個人的には,
直観,
つまり,
パターン認識,
を醸成していくのだと感じている。
「直観とは,実はほとんど無意識下の思考力であり,意思決定能力です。それは知能が感知できないほど素早く行なわれる一種の価値判断や即座の連想に基づいているものなのです。」
そして,その,
「ほとんどが類推思考です。」
と,著者は書いている。もちろん,その危険も含めて承知しておく必要はある。
参考文献;
アルベルト オリヴェリオ『論理的思考の技術―「考える脳」をつくる50の方法』(大和書房) |
|
ドイルのメッセージ |
|
三上直子・山川蓮『コナン・ドイルは語る―リセットのシナリオ』を読む。
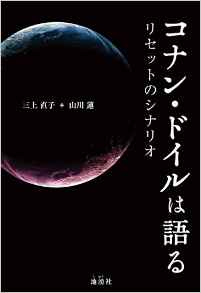
本書は,コナン・ドイルの霊的メッセージをまとめたものだ。たぶん,それだけで引く人がいることが予想できる。ただ,本書を読みながら,多次元宇宙論を思い出していた。超ひも理論では11次元(空間次元が10個、時間次元が1個)が折り畳まれているという説さえある。
コナン・ドイルについては,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%AB
に譲るが,コナンドイルが,第一次大戦後,スピリチュアリズムにのめり込み,大概は揶揄の対象として,
コティングリー妖精事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%A6%96%E7%B2%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
について語られることが多い。
「1916年7月、妖精がフランシスと一緒にいる写真をエルシーが撮った。彼女たちは妖精が踊っている様子が写っている写真を、1916年から1920年の間に全部で5枚撮影した。写真に写った妖精は、小さい人の姿で、1920年代の髪型をし、非常に薄いガウンをはおり、背中には大きな羽があった。
1枚の写真にはノームが写っていた。そのノームは身長12インチ(約30cm)ぐらいで、エリザベス朝時代の格好をして、背中には羽があった。」
完全な偽造写真に,妖精の実在する証拠として,コナン・ドイルが信じたと言う一件である。ドイルがこれを信じたのは,「少女に偽造写真を作る技術などあるわけがないと考えた」のもあるし,コナン・ドイルの娘によれば,「父はこの事件を完全に信用していたのではなく、二人の少女達が嘘をつき続けているという事が信じられなかった」ということもあるかもしれない。この件で,ドイルとスピリチュアリズムは,揶揄の対象とされてしまった。
しかし,ドイルの霊的メッセージは,第二次大戦を予言したとか,死後も,スピリチュアリズムの世界では,名を成していたらしい。本書は,ホームズの作者としてではなく,
スピリチュアリズムのパウロ,
と呼ばれ,スピリチュアリズムの著作が十冊を超え,他界する直前,
「何より偉大で輝かしい冒険がこれから私を待っています。」
と書いた,スピリチュアリズム普及活動に尽力した側面に焦点を当てながら,生前のメッセージ,死後のメッセージを紹介しつつ,最新のメッセージ,
リセットのシナリオ,
を伝えようとしているものである。もちろん,大真面目である。メッセージのいくつかを紹介してみる。
「私たちが最終的に焦点を当てているのは,〈リセット〉です。霊的循環の回復により,天と地をつなぎ直すことです。そのための素地として,スピリチュアリズムがもたらされ,いよいよその知識を総動員したところで〈リセット〉がいま語られるということです。
スピリチュアリズムの要点は,あらゆるものに霊は宿り,それらは因果律(因果応報の法則)から逃れることはできない,ということでした。この因果律は,リセットを理解していただくための下地でした。
現状の認識と,そしてそれがなにゆえそうなったのか,という原因分析がなされないことには,この大転換に際しての人類の大きな学びは見いだせないからです。
〈リセット〉では,地球の周期にのっとり,それまで人類が行ったことが結果として返ってきます。物質的な見地から言えば,地上のあらゆる文明が破壊される大参事となるでしょう。それはもはや避けられない事態です。
一方,…〈アセンション〉とは,次元が変わるということにフォーカスした,事態を部分的にとらえた概念です。もちろん次元が変わることを選択する霊もいます。みなさんは実感がないかもしれませんが,この地球,そして宇宙はあらゆる次元にいて存在していますので,霊的に進化した方たちは次の次元という現実の中に生きることも可能なのです。異なる次元にはこれまで消滅したとされる文明も存続していますし,あらゆる可能性の一つ一つが違った現実として同時進行しているという複雑な多次元世界を知覚できるようになれば,その中のどの現実を選択するかもきめられます。」
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416694519.html?1428004473
で紹介したように,たとえば,「シュレディンガーの猫のパラドックス」というのがある。
放射性物質と猫を入れて,一定時間後に蓋を開けて中を見る,
「人が蓋を開ける前に猫の生死が決まっているのか(決定論),箱を開けた瞬間に決まるのか(確率論),そのいずれが正しいのかを問う」
というものである。シュレディンガーは,量子論への反対の立場からこの思考実験を提示した。しかし,ヒュー・エベレットの「並行世界説」,多重宇宙論からの解釈では,
「〈生きている猫の宇宙〉と〈死んでいる猫の宇宙〉が〈共存している宇宙〉を考え,その宇宙が観察を繰り返すごとに〈生きている猫の宇宙〉と〈死んでいる猫の宇宙〉に〈分岐〉し,〈生きている猫〉と〈死んでいる猫〉とがそれぞれ〈別の宇宙〉に〈重ね合わせ〉の状態で並存している」(『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」
』)
というのである。つまり,人間が観察するまでは,〈生きている猫の宇宙〉と〈死んでいる猫の宇宙〉が共存していたのに,観察によって,分岐した,ということになる。しかも,
「観察によって分岐した複数の並行多重宇宙は,互いに関係が断ち切られ影響し合うことがなくなるので,それらの宇宙を観察する人間もまた分岐して複数存在する。」(『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」
』)
こういう量子の世界が,開く新しい視界と通じるところがあるのである。別のメッセージ(「そのビジョン通り」とドイルが肯定したビジョン)には,
「宇宙の中に左と右の両方の地球が見える。ちょうど真ん中の視点。境界ラインは,画像を二つ並べた時に,その真ん中にうっすらと線があるように感じる。そのような透明な線で左右が区切られている。『左右は何が違うんだろう』と思い,その境界の所に行って,左と右にそれぞれ手を出してみる。比べると,左手は普通の物質性がある手で,右手は霊的な手に見える。ざっくり言えば,左が地(物質世界)で,右が天(霊的世界)のようだ。(中略)右の天で起こることは,左の地に反映されるということのよう。
ところが境界に灰色の雲がかかりはじめると,それが上手く反映しない。連動できずに地は勝手に動き始める。元々天と地が一体となって,天の意志が通る連動関係だったけれど,その境界が覆われると,天と地が連動できなくなり,バラバラになる。」
あるいは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163082.html
で触れたように,こういう宇宙像ともつながるのかもしれない。
「三次元空間のある領域で起きる重力現象は,すべてその空間の果てに設置されたスクリーンに投影されて,スクリーンの上の二次元世界の現象として理解することができる…。」
のであり,ブライアン・グリーンは,
「ひょっとすると私たちは,今このときも,3ブレーン(ブレーンとは膜braneのこと)の内部に生きているのではないだろうか?高次の宇宙(三次元のドライブイン・シアター)の内部に置かれている二次元スクリーン(2ブレーン)の中で暮らす白雪姫のように,私たちの知るものすべては,ひも/M理論(5つのひも理論を統合するマスター理論の意味)の言う高次元宇宙の内部にある三次元スクリーン(3ブレーン)の中に存在しているのではなかろうか?ニュートン,ライプニッツ,マッハ,アインシュタインが三次元空間と呼んだものは,実は,ひも/M理論における三次元の実体なのではないだろうか?相対論的に言えば,ミンコフスキーとアインシュタインが開発した四次元時空は,実は,時間とともに展開していく3ブレーンの軌跡である可能性はないのだろうか?つまり,私たちの知るこの宇宙は,一枚のブレーンなのではないだろうか?」(『宇宙を織りなすもの』)
と述べている。マルチバース論(多宇宙あるいは並行宇宙あるいは多元宇宙と言われる宇宙論)では,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416793184.html?1428175950
で触れたように(『隠れていた宇宙』),
・パッチワークキルト多宇宙 我々はそのパッチの一つである
・インフレーション多宇宙 永遠のインフレーションが泡宇宙のネットワークを生む。われわれはその泡宇宙の一つ。
・プレーン多宇宙 ひも理論が行き着いた,一切れの食パンのような宇宙が並んでいる。
・サイクリック多宇宙 プレーンワールド間の衝突がビッグバンをもたらす。いくつもの並行宇宙が始まりうる。
・ランドスケープ多宇宙
ひも理論の余剰次元が,インフレーション宇宙とプレーン宇宙を合体させる。
・量子多宇宙 確立派が具体化されるたびに世界が分岐して並行して存在する。
・ホログラフィック多宇宙 この宇宙は,遠くの境界面で起きていることを映し出しているだけである。
・シミュレーション多宇宙 宇宙のシミュレーションの中の世界でしかない。
・究極の多宇宙 ありうる宇宙はすべて実在するという包括の宇宙
等々想定されており,霊的世界像も真っ青である。そこで,もうひとつ,ドイルのメッセージ。
「文明が破壊される大参事(中略)はどのようにして起こされるのかですが,今のところ隕石が落ちる可能性が高いです。次に地軸が反転するポールシフト。このどちらかもしくはその両方です。」
なおここで言う,ポールシフトは,
「地磁気の磁極は、頻繁に変化していることが観測されている。また、海洋プレートに記録された古地磁気の研究(古地磁気学)によって、数万年〜数十万年の頻度でN極とS極が反転していることも知られている。」
ではなく,よくオカルトなどで言われている,
「自転軸上の北極と南極が(何らかの要因で、短時間のうちに)反転する」「自転軸の北極・南極が瞬間的ないし短時間で入れ替わる」
を指しているらしいが,現在の地軸が,原始地球に火星大の原始惑星が衝突したことにより,月ができ,現在の地軸が確定したとする説があるので,(反転かどうかは別に地軸のずれを伴い)両方起きる可能性はある。
大栗博司氏は,「わたしたちが暮らしているこの空間そのものが,ある種の『幻想』」だとして,
「私たちは縦・横・高さという三つの情報で位置の決まる三次元空間を現実のものだと感じていますが,ホログラフィー原理の立場から見れば,それはホログラムを『立体』だと感じるのと同じことに過ぎません。空間の果てにある二次元の平面上で起きていることを,三次元空間で起きているように幻想しているのです。」(『重力とは何か』)
と言っている。どちらが霊的でどちらがリアルかなど区別はつかない。
参考文献;
三上直子・山川蓮『コナン・ドイルは語る―リセットのシナリオ』(地湧社)
ブライアン・グリーン『隠れていた宇宙』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)
ブライアン・グリーン『宇宙を織りなすもの』(草思社)
ブライアン・グリーン『エレガントな宇宙』(草思社)
岸根卓郎『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」 』(PHP)
大栗博司『重力とは何か』(幻冬舎新書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/M%E7%90%86%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 |
|
アナロジー思考 |
|
細谷功『アナロジー思考』を読む。
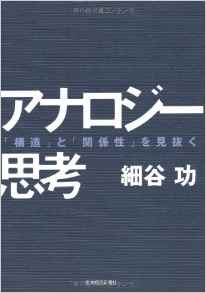
著者は,「はじめに」で,ウィリアム・ジェームズの,
「才能の最良の指標はアナロジーに気づく能力である」
という言葉を引用し,
「アナロジー思考の強い人はありとあらゆることを関連付けて考え,すべての事象を学びの対象にすると同時にすべての事象をアウトプットの対象にする。それに対して,アナロジー思考の弱い人は,『これはこれ,あれはあれ』とすべての事象を別々に考えるためのまったく応用が利かない。」
と書く。しかし,人は,おのれの知識と経験を参照にしながら,それをヒントに,あるいはそれからアイデアを得て,日々の問題解決をしている。その意味で,大なり小なり,アナロジーなしに生きている人はいない,と僕は思う。
著者は,アナロジー思考力は,
抽象化思考力,
と呼ぶ。しかし,そうだろうか。アナロジーとは,
パターン認識,
だから,抽象化とは重なるけれども,イコールではない。棋士は,パターン認識が優れていると言われる。それは型やタイプで盤面を認識することだが,それを抽象化と言ってしまっては,微妙に違う気がする。
のっけから,著者の言わんとするところが,僕の認識するアナロジーとは,微妙に違う。
著者は,アナロジー思考を,
「日本語でいえば『類推』あるいは『類比』」
であり,文字通り(類推に即して言えは),
「『類似のものから推し量る』ということである」
として
「もともと知っている領域(『ベース』と呼ぶ)を基にして,類似の関係にある対象領域(『ターゲット』と呼ぶ)に関する知見を推論するというものである。」
と定義し,
たとえ話,
や
メタファー(隠喩),
も,アナロジー思考である,という。
細かいことにこだわるようだが,ぼくは,まず,
類推
と
類比
とは,厳密に言うと,違うものだと思っている。それは,
・類似性に基づくアナロジーを,「類比」
・関係性に基づくアナロジーを,「類推」
と区別している。くわしくは,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/view24.htm
に譲るとして,そこをきちんと区別しておかないと,比喩における,メタファーの位置づけがきちんとできなくなる。類似性と関係性に対応させるなら,
直喩,隠喩が《類似性》の言語表現,
換喩,提喩が《関係性》の言語表現<
なのであり,類比と類推をひとくくりにしてしまったら,換喩と提喩が見えなくなってしまう。
著者は,「かばん」を「喩え」にして,「予算管理」を説明して見せた。しかし,あくまで,「カバン」を例示したのであって,それが引出でも,ファイルでもなんでも,予算を具体的に見える化できれば,好かったのではないか。これをアナロジーの例とされてしまったのでは,
例(例え(れ)ば)
と
アナロジー(喩え(れ)ば)
が区別がついていないことを,著者自身が露呈してしまったように見えてしまう。皮肉なものである。
例(え)は,ある概念(モノでもコトでもコトバでも構わない)の下に,ツリー状にぶら下がっている。その下にも,より具体化してぶら下がるかもしれない。だから,よりツリーを上へ行けばいくほど抽象度が上がる。
喩(え)は,そのぶら下がったツリー全体の構造ないし,そのカタチと似たものと対比する。だから,抽象力ではなく,似たモノ,似たコトに「なぞらえる」想像力や直観力(パターの発見力)が必要であって,抽象化したら得られるものではない。
だから,「例え」たものは,もとの概念を,具体化するものだから,概念の意味の内包をはずれてしまっては,例えた意味をなくす。しかし,「喩え」たものは,概念の意味の外延を広げるものだから,内包を外すことはある,というか,全く新たな視点を見つけるために,喩える。例えば(「喩えば」ではない),百貨店の「例え」は,伊勢丹や丸井や雑貨店かもしれないが,「喩え」は,バザールとするか,縁日とするかで,百貨店が変わる。そのたてめに喩える。
著者が,予算管理のアナロジーにカバンを使ったが,むしろ,「区分け」という概念の下に,カバンや,予算管理,引きだし等々の,区分の具体例がぶらさがっている,と見える。むろん具体的なものの例示を参照することはあるが,アナロジーは,その全体像と対比して(その関係か構造かで)何かに見立てるのでなくてはならない。たとえば,ハチの巣とかブドウの房とか,あるいは,データファイル(のフォルダ)の記録とか,脳の記憶等々。
アルキメデスは「ヘウレーカ(わかったぞ)」と叫んだのは,王冠の混ぜ物の比重は,
「流体中の物体は、その物体が押しのけている流体の重さ(重量)と同じ大きさで上向きの浮力を受ける」
ということを,湯船に入った時にあふれたお湯から類推したのだ。これが喩え,である。王冠の比重を,具体的に,ありうる混ぜ物別に枚挙して,一つ一つどうなるかを確かめていく,というのが例である。
著者は,アナロジーの4つのステップとして,
①ターゲット課題の設定
↓
②ベース領域の選択
↓
③ベースからターゲットへのマッピング
↓
④評価・検証
を挙げる。このとき,「どこから借りて来るか」が鍵と言ったが,
例え
と
譬え,
の区別がつかなければ,具体事例を挙げるにとどまる。もちろん,具体例に照らし合わせることが,発想に無意味と言っているのではない。それが有効なことも,もちろんある。
例えば,シュレッダーを発想するとき,
情報の破棄
を
製麺機からカットされた麺が切り出されてくる状態,
に喩えて発案した。そのとき,破る,焼く,切り刻む,という具体例を考えることも,役立ったには違いないのだ。しかし,ここでは,喩え,つまりアナロジーを問題にしているのである。
アナロジーは,別の言い方をすれば,
見立て,
である。ままごとで,泥をご飯に見立てるように,
〜として見る,
である。正確には,
「〜と見る」見方,
「〜にする」仕方,
「〜になる」なり方,
の3つがある,と考えている。大事なことは,その瞬間,現実の視界ではなく,
別の視界が開く,
のである。泥をご飯として見立てて,初めて,ご飯を食べているシーンが見えてくる。これが,アナロジーが発想に寄与するところだ。これの区別がつけられなければ話にならない。
類推については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/405217646.html
で,喩えについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/401399781.html
で。見立てについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/408700916.html
で,アナロジーについては,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/prod0213.htm
で,すでに触れた。
参考文献;
細谷功『アナロジー思考』(東洋経済新報社)
高沢公信『発想力の冒険』(産能大出版部) |
|
ホールシステム・アプローチ |
|
マーヴィン
ワイスボード&サンドラ・ジャノフ『会議のリーダーが知っておくべき10の原則――ホールシステム・アプローチで組織が変わる』を読む。
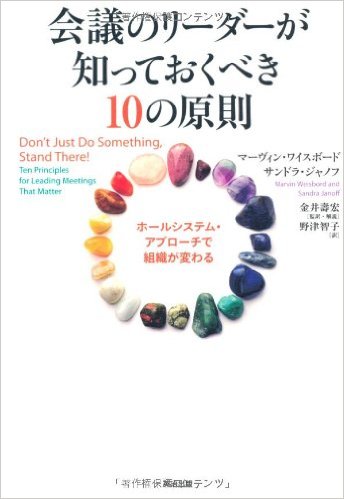
著者たちは,ホールシステム・アプローチと呼ばれる組織開発の手法のひとつフューチャーサーチの提唱者にして,実践者・普及者である,とこの本の監訳者,金井壽宏氏は,言う。実は,この本は,監訳者の持ち込み企画らしい。それだけ金井氏が,内容に入れ込んでいるものらしい。
フューチャーサーチについては,著者らの『フューチャーサーチ』を,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163468.html
で,取り上げた。
「本書は,会議についてのありがちな本とはまったく違う。これは読者のみなさんが会議をひらくたびに着実にリーダーシップを発揮できるようになるのを手助けする本なのだ。そのための手段として,私たちは一般によいとされる方法のほとんどを根底から覆す。人間同士の交流という難しい問題について万事心得ておかなければという重圧を逃れる手助けもしたいと思っている。」
本書は,冒頭こう始まる。たしかに,原題は,
Don’t Just Do Something,Stand There
で,サブタイトルは,
Ten Principles for leading Meetings That
Matter
なのである。金井氏は,
「とにかくしゃしゃり出ないで,どんと構えて立て―大切な会議をリードする10の原則」
と訳し,その象徴として,現著の表紙には,イヌクシュクが使われている,という。
「表紙にあしらった石のオブジェ…は,本書の柱となる内容を象徴している。このオブジェを,高緯度北極に暮らすイヌイットはイヌクシュクと呼んでいる。数世紀の昔から,イヌイットはこれを,不毛の凍土を進むときの道しるべとして使ってきた。」
と,著者は書くが,金井氏は,
「『どんと構える』とは具体的には,『会議の参加者がすべきことをやってくれているときには,目に見えるような行動は何もしないということ』を指している。」
と解く。
本書のいう会議とは,
「目的が明確で,じかに会って対話がなされる会議である。…その会議とは,さまざまな人が集まって,問題を解決し,意思決定をし,計画を実行に移す会議のことなのだ。それは集まった人たちが,積極的に参加し,自分の意見を聞いてもらい,影響を及ぼすことを期待できる会議,ひとことで言えば意義ある会議のことだ。そして,進行の仕方がまずければ,皮肉と無関心ばかりが生まれることになる。」
であり,本書は,
「どんな会議でも価値あるものにできる」
をテーマに,
「リードする会議を通して,あなたが世界にもっとも影響を及ぼせるようになるのを手助けする」
ことを目的に,
会議を運営する人,
向けに書かれている。そのために,
「出席者の行動を管理するのではなく,構造,すなわち人々が話し合いをする状況を管理する」
ことを目指し,そのために,
「自分たち自身を変えること」
を真っ先に始めた,という。その目指すのは,
「ただそこに立っていられるようになる」
こと,つまり,これが,イヌクシュクが本書の象徴である所以なのである。
「すべてに答を出したり,グループそれぞれに抱える問題の障害物を片付けたり,全出席者を常に満足させたりする必要がある,と思うことをやめた。私たちのやり方は,注意深く『ただそこに立っている』ものとなった。それは観察すること,耳をすませること,そして人々に対して彼らみずから選ぶもの以外のいかなる態度も促すことなく,彼等の心の内にあることを話すよう導くことである。」
本書は,
会議をリードする六の原則,
と
自分をマネジメントする四の原則,
で成り立つ。原則をそのまま書き出しても意味はないが。前者は,
①ホールシステムを集める,
②コントロールできることをコントロールし,できないことは手放す,
③全体“象”を探求する,
④人々に責任を持ってもらう,
⑤コモングラウンドを見つける,
⑥サブグルーピングを究める,
後者は,
⑦不安と仲良くなる,
⑧投影に慣れる,
⑨頼できる権威者になる,
⑩Yesを異議深いものにしたいなら,Noと言えるようになる,
である。最後にある「六つのテクニック」が,なかなか含蓄がある。
①全体の感じをすばやくつかむために,人々の間を歩いて,それぞれの立場をはなしてもらう(「分化」)
②グループがばらばらにならなしいようにするために,孤立しそうな人が出てきたら,「ほかにいませんか」と尋ねて支持者を見つける(原則⑥)
③二極対立を阻止するために,衝突したりダイアローグするなかで,人々がサブグループを意識するのを手伝う(原則④)
④独創的なアイデアやより幅広い参加を促すために,なんらかのテーマについて少人数のグループで話し合い,その後どんな話をしたか全体に報告してもらう。「近くにいる人と(あるいは三人/四人で)〇〇分話をして,どんな考えをもっているか確かめてください」。(原則④)
⑤次に何をしたらいいかわからなくなったら,グループの人たちに意見を求めよう。どうすべきか知っている人は必ずいる(原則⑦)
⑥進展が見込めないと人々が思う場合は,会議を終了することを提案する。「話し合いを続ける必要はないと思います。このまま話し合いを続ける価値があると思うかどうか,みなさん一人ひとりの意見を聴かせてください」(原則⑦)
個人的には,
ほかに誰かいませんか,
という問いは,新鮮だし,「混乱している」とか「不満だ」とか「時間の無駄」とか,参加者から出た声を,
「ほか誰か時間の無駄(混乱している,不満だ)と思う人はいませんか,
と,
ダイアローグの一部として受け入れる,
という考え方である。そして,
「『ほかに誰かいませんか』と尋ねてからたっぷり20秒くらい待つ。永遠よりも長く思えるその時間をまってなお何の返答もないと,緊張が生まれ,私たちはみずからの経験をもとに正直な感想を述べることになる。
リーダー:実は私も,今日のミーティングは時間の無駄だと何度も感じています。
みずからをサブグループにいれなかったらどうするか。つまりその会議が,私から見て素晴らしいものである場合だ。
リーダー:現時点では,あなた一人のようですね。先へ進んでいいですか。」
参考文献;
マーヴィン
ワイスボード&サンドラ・ジャノフ『会議のリーダーが知っておくべき10の原則――ホールシステム・アプローチで組織が変わる』(英治出版)
マーヴィン・ワイスボード&サンドラ・シャノス『フューチャーサーチ』(ヒューマンバリュー) |
|
記憶 |
|
アルベルト・オリヴェリオ『覚える技術』を読む。
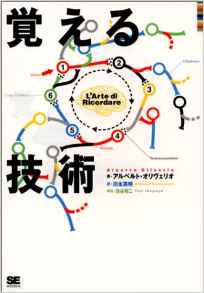
訳書名『覚える技術』だと,
記憶術,
の本のように見える。そのことに言及がないわけではないが,いささか全体の印象とは異和感がある。訳者の池谷裕二氏によると,
『La Arte di Ricordare』
で,直訳すると,
『記憶の技巧』で,
「『効率よく記憶するためのノウハウ』といった意味であろう。しかしイタリア語のArteには,『芸術』という意味も含まれている。」
とする。英語のArtと同じと見ると,記憶というものの驚異を込めた含意に思える。それは,同時に,脳というものの持つ潜在力といってもいい。
脳の力,記憶には,
陳述記憶(意味記憶),
エピソード記憶(自伝的記憶),
手続記憶,
というのがあるが,
「手続き記憶は進化の流れからいえば,かなり古風なもので(つまり,カタツムリや他の無脊椎動物などの原始的生物にもある),人間にも発祥初期に胚の時代があるように,進化の過程でいえば,初期の形態」
であり,逆に,認識に関わる,
「意味記憶的タイプの記憶は,進化の段階では後期の形態で(高等なホ乳類だけに備わっている),手続き記憶に較べるとその発達も遅く,幼児期になってやっと発達がはじまります。社会的なタイプの手続き記憶は高齢になるまで持続し,老人に見られる脳の老化現象…がはじまるまで続きます。」
別の記憶の分類,つまり脳の機能による,
短期記憶(作業記憶),
長期記憶,
という区分の仕方もある。一度に6,7の情報源を短期間記憶にとどめ,それが貯蔵庫に移されて,長期記憶となる。
「短期記憶から長期記憶へ移行する,つまり,記憶が定着するためには,新しくシナプスが形成され,それが安定する必要があります。もし,シナプスが安定しなければ,そのまま排除されることになります。」
それを,
ヘブのモデル,
と呼ぶらしい。カナダの神経学者ドナルド・ヘブは,こういう仮説を立てた。
「短期記憶とは,一群の神経細胞やそのネットワークが神経細胞のつくる『輪(ループ)』,つまり,神経回路…を通る活動電位の影響を受けて,電気的に変化することではないかと考えたのです。そして,…その回路に何度も繰り返し情報が通過することを示すために,それが『反射回路』であると定めました。(中略)この段階で,(電気ショックのように)強い放電があったり,(脳の外傷による後遺症のように)神経機能の変化があったり,あるいは(多くの記憶の干渉現象に見られるように)ライバルの『神経回路』があったなら,不安定な反射回路である短期記憶が,安定したシナプスによって結びついた神経細胞のネットワークである,本物の神経回路へ変化することを妨げられる…。」
それは,庭師の,余分な葉や枝を刈り込む,剪定に喩えられる,という。たとえば,エピソード記憶を例に,脳の機能をみれば,
「側頭葉は扁桃体や海馬と結びつき,海馬は脳弓を介して間脳と結びついている…。それは,まるで記憶回路を形作っているように見えます。もちろん,その回路には側頭葉や海馬,間脳とも直接結びついている,すべての大脳皮質が関与しています。…この働きによって,経験したことを意識下で認識し,それを自分の意志で思い出したり,自発的に心に思い浮かべたりするわけです。感情や経験は外面的な記憶に形を変えるために,側頭葉の神経組織を通過しなければなりません。これは一種の漏斗のようなもので,すべての感情や認識がいったんここでフィルターに掛けられ,さらにここから海馬や扁桃体を通って,その特徴によって細かく分類され(空間的記憶,感情的記憶など),間脳に到達し,様々な経験が『集められ』,そして脳の神経回路に安定した記憶として登録されるわけです。これが,『側頭葉―海馬―間脳』という記憶回路…であり,日常生活のさまざまなエピソードの要素(感情,知的なエピソード,情緒,価値観など)を互いに結びつけて,個々人の思い出に残る出来事として,エピソード記憶に形を変えるわけです。」
通常,脳は,目覚めている状態で,一秒間の振動数が,
12〜14ヘルツ,
と,言われる。しかし記憶力の高い人は,
8〜10ヘルツ,
の目をつむって休憩している状態にまで抑え込み,さらに,
5〜7ヘルツ,
という眠っている状態まで,抑えることができる,という。そうすることで,神経を高ぶらせる刺激を断ち切っている,ということらしい。情緒のコントロール,ストレスの解消,注意力の涵養,によってそれができる,らしいのである。
J・フォン・ニューマンによると,
「人間が一生のうちに脳に貯えることのできる記憶量の総計は,平均して情報の基本単位で28×1020に達するそうです。これは280×10億×10億ビット,つまり3000億ギガビットに相当します。」
という。その中には,
覚えのない記憶,
も含まれる。M・ミシュキンによると,
記憶には,異なる二つの機能,
が存在する,という。
「一つは本来の意味で使われる『記憶』で,情報をそのまま写し取る機能です。もうひとつは,『刺激・反応に結び付いた機能』で,習慣的な記憶や暗黙の記憶などと呼ばれているものです。」
だから,何かを学ぼうとする時,記憶の無意識的な側面」,潜在的記憶が,その前提になっていることがある。逆に言うと,それを利用すれば,もっとうまく上達したりするかもしれない。それを呼び起こすことを,
プライミング,
あるいは,
プライミング効果,
と呼ばれる。それは,ローレンツの,
刷り込み,
と似ているとされる。予想されるように,プライミングは,
手続き記憶,
に属している,とされる。プライミングは,
「本質は『視覚』なのです。したがって,この記憶は視覚をコントロールする後頭葉に存在するわけです。…同じ領域には,言葉を視覚的な側面から捉えようとする,言葉のイメージが貯えられています。一方,言葉を考えることは,言葉の意味を考えることであり,この働きは,より複雑な『意味記憶』に頼っています。そして,それは側頭葉や前頭葉の活動によるものなのです。…『プライミング』が機能している間は,脳の後頭葉が活性化されていますが,意味記憶が活動している時には,脳の中部や前部が活性化されているのが確認されます。ふつうの状態では,これらの記憶システムは協力し合って働くのです。」
最後に,ボケを防ぐには,という五項が出ているが,かつてNHKで,
脱メタボ,
有酸素運動,
コミュニケーション,
と三条件を挙げたが,「コミュニケーション」を条件に入れていないことが気になる。脳への刺激は,ひとり暮らしにとって,人からの刺激のないことだ。コミュニケーションこそ,その意味で最大の刺激のはずだから。
参考文献;
アルベルト・オリヴェリオ『覚える技術』(翔泳社) |
|
こつ |
|
諏訪正樹『「こつ」と「スランプ」の研究−身体知の認知科学』を読む。

著者は,「はじめに」で,
「本書で論じるのは『こつ』の体得や『スランプ』を内包する学びです。(中略)サブタイトルにある『身体知』とは,身体と頭(ことば)を駆使して体得する,身体に根ざした知のことです。身体知の学びにおいて,スランプは必要不可欠なできごとです。身体で実践し,ことばで色々考えて試行錯誤することを通じてスランプから抜け出したときに,身体知で学んだ状態(『こつ』の体得)に辿り着けます。新しい『こつ』を体得することで,真新しい風景が見えるようになるのです。」
と書き,身体知とは,
「環境と,自分なりの意味・解釈と,そのときの身体の立ち居振る舞いの三つからなるもの」
で,
身体知の形成過程では,
ことばが重要な役割を果たすこと,
身体は計測機械で客観的に観察できるばかりではなく,自身が内側から感じ,考えることができる,
として,それを,
一人称研究,
と呼び,著者自身の内角打ちを例に,「こつ」を内側(体感)から明らかにしようとする試みを,本書では随所に披瀝している。
「身体知の学びとは如何なる事象なのか?学びを促すために効果的な手法はあるか?これらの問いの答えを探ることが私の研究テーマです。現在私が抱く仮説は以下のとおりです。身体知をうまく学ぶには,身体と環境の相互作用で生まれる体感に向き合い,それをことばで表現しようと努め,体感の微妙な差を感じとって比較し,体感を制御したりつくりだしたりする生活習慣をもつのがよい。
同じ行為を繰り返していても,…身体も環境も実は知らぬ間に変化しています。したがって,体感も変化しているはずです。体感を感じとってことばで表現しようとする努力がない場合は,いつのまにか相互作用が変容していても自覚できないものです。」
このことばで表現するのを,
体感と言葉のマッピング,
と呼び,その身体知の学びを促す,
身体とことばの共創を生むメソッド,
を,ことばシステムとからだシステムが共存している,
からだメタ認知,
として理論化している。これを,マイケル・ポランニーの暗黙知の近位項・遠位項と対比して,
「身体が物理的な環境に遭遇することによって生じる関係や相互作用の一部に対して,私たちは心の働きによって自分なりの意味を生み出す」
という身体知の,
「身体と物理的な環境の間に成り立つ関係や相互作用は,…近位項…,『自分なりに生み出した意味』…が近位項」
と類推し,
「近位の方向に眼差しを向ける領域を拡げ,個々のモノ,モノの性質や位置関係,自分の身体の各部位,そして体感へと,より身体に近い領域を丹念にことばで表現してみるというメソッドを,わたしは〈からだメタ認知〉と呼んでいます。」
という。この〈からだのメタ認知〉は,いわゆる,ブラウンやフラベルらの提唱した,
メタ認知,
とは違う,とこう説明する。
「認知の認知であるメタ認知とは,自分が『何を考えているか』をことばにして明確に捉える行為であると定義されたのも不思議ではありません。また〈メタ認知〉という概念が登場した当時は,…逐次的な情報処理モデル(知覚→思考→行動)で知能が理解され,環境は認知の外側に位置するものでした。したがって,認知=頭のなかで言語的に考えていること,という図式だったのです。しかし…認知とは,単に頭のなかで生起している思考だけではなく,環境からの知覚,環境に対する働きかけとしての身体動作も含む,主体のからだと環境のインタラクションの総体を意味する。」
したがって,〈からだメタ認知〉は,
身体と環境のインタラクション(体感を含めて)をことばで表現する,
として,ことばで表現(ことば化)するべきものとして,
①自分は環境を構成するどういうモノの存在に気を留めているか,
②自分はモノのどういう性質や関係を認識しているのか,
③自分の身体はどう動いているか,
④自分はどのような体感を得ているのか,
⑤自分は知覚したモノ世界にどのような意味を与え,解釈しているのか,
⑥自分はどんな問題意識や目的をもっているか,
を挙げている。
「ことばという外的表象化を行う前には漠としていたのに,語ることを通して,そのときどきの選択/分別に自己が現れ,それを自覚し,次第に自己が確立するのです。」
一方では,新しいことばがうまれたとき,それに応じて,身体の御し方が変わり,逆に,からだが摑んだことをことばの変化につなげることもあり得る。
「からだメタ認知の実践において,体感に必ずことばを貼り付け,様々な体感に留意していると,以下のことが可能になります。それは,『体感の類似性や連動性に気付く』という現象です。」
ことばと身体の共創,とはこういうことを指しているのだろう。
以上,「こつ」については,「whatの研究」ではなく,
「howの研究」
と著者自身が言っているように,実践的に示されているが,「スランプ」については,少し異論がある。著者が,
「スランプとは,現状の問題点を発見し修正して,新しい『こつ』を体得するための準備期間」
「スランプとこつの体得(パフォーマンスの急激な向上)の繰り返しです。」
で使っている,
スランプ,
と呼んでいるのは,学習曲線の,
踊り場,
をそう呼んでいるのではないか。素人に,あるいは初心者に,
スランプはない,
という名言(誰が言ったのだったか,野村克也氏かも)は当たっていると思うのだが。
参考文献;
諏訪正樹『「こつ」と「スランプ」の研究−身体知の認知科学』(講談社選書メチエ) |
|
兵粮 |
|
久保健一郎『戦国大名の兵粮事情』を読む。
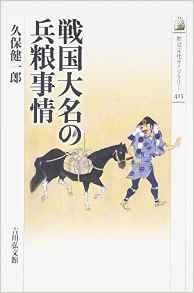
冒頭,著者は,
「食料である兵粮」を,
「モノとしての兵粮」,
「売買における代価」としての兵粮を,
「カネとしての兵粮」
と区別し,兵粮とひとことで言うものの背後の歴史を探る,という問題意識で,本書を始めている。思えは,
兵粮攻め,
という今に残る言葉は,確かに,
「経済的に追いつめる方策」
を意味し,「カネとしての兵粮」の意味で使われている。
従来,戦国大名の軍隊は,
「兵粮自弁」
の軍隊とされ,戦争の最中,
作薙(さくなぎ),
稻薙(いねなぎ),
麦薙(むぎなぎ),
と称する,
「敵地において収穫前の作毛=農作物,稲や麦などを刈り取ってしまう行動」
が見られ,これは,
「稻・麦の奪取より敵を兵粮攻めにする意味」
と同時に,
「その刈り取った『兵粮』を…味方の兵粮へ転用する」
という狙いもあった,とされる。関ヶ原合戦図屏風では,刈田して米を精米している光景が描かれていた。しかし,一方で,前線に送る兵粮を調達するため,大名が,
大量買付,
する例や,家臣に,
用立て,
を依頼するケースもある。この場合は,
「れっきとした利息をともない貸付」
として,家臣は,用立てたのである。その多くは,
「商人」
であり,
「商人として活躍を見込まれて家臣に取り立てられたのか,家臣として戦功をあげたり,領主として経営を拡大するなかで,商業活動でも台頭したのか」
は,はっきりしないが,いずれ,御用商人役を果たし,大名の兵粮調達を支えている。
兵粮の調達・搬送は,
持参,
両国内から現地への搬送,
現地調達(略奪・徴発,買付),
現地での貯蔵,
等々があるが,大規模に搬送するには,人手もかかり,大掛かりになれば,敵の妨害を受けやすい。その意味で,兵粮は,
「お荷物」
なのである。だから,
「大規模な搬送が見られるのは,戦闘状況が固定化・膠着化して,長期戦の様相を呈してから,というのが基本である。」
とすると,常日頃から,備蓄に供えておかなくてはならない。しかし,
「大名の蔵には物資が十分にあったというよりは不足がちだったのではないか」
と,著者は見る。蔵から流出していくのは,
家臣への扶持給・褒賞,
である。戦功に加増で報いるにも,戦国半ばを過ぎると侵略地の獲得は難しく,蔵から支給することが多くなる。また,
困窮する家臣の救済,
のための扶助がある。この時期武士は困窮していたらしいのである。それは,
軍役負担,
に起因する。自身の兵粮,軍装以外に,
従者の扶持,
馬の飼料,
武器・武具・軍装の準備,整備,
等々,戦争が続き,かつ長期化すれば,負担は重くのしかかる。多く,軍役は,そのものの知行に応じて,従者の数,整えるべき武器・武具・軍装が決められており,軍役に応ずることのコストはばかにならなかった。
蔵から兵粮が出ていく理由には,大名自身が,
御蔵銭,
公方銭,
と称して,家臣への兵粮貸しとは別に,特定の者に預けて,
郷中へ貸す,
という行為をしていた。もちろん利息を取る。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/438705830.html
で取り上げた,『落日の豊臣政権』が触れていた,豊臣秀長の行っていたらしい,
ならかし,
もその延長線上のものだろう。この場合,もはや,
兵粮はカネ,
であり,
「通常『兵粮』とされるものは米」
であるから,米を価値基準とする,
石高制,
への移行の地ならしができていたことになる。その統一的な石高に応じて,全国統一の,
城普請,
軍役,
等々を大名に賦課することになる。それは,徳川政権へと引き継がれ,明治維新まで続くことになる。
参考文献;
久保健一郎『戦国大名の兵粮事情』(吉川弘文館)
桑田忠親他編『関ヶ原合戦図』(中央公論社)
河内将芳『落日の豊臣政権:』(吉川弘文館)
日本史史料研究会『秀吉研究の最前線』 (歴史新書y) |
|
類比 |
|
井上寿一『第一次世界大戦と日本 』を読む。

本書は,第一次世界大戦(1914〜1918)をはさんで,関東大震災(1923)後までの大正時代(1912〜1926)を中心に,
外交,
軍事,
政治,
経済,
社会,
文化,
を輪切りに,大正時代という,日本史の中では,比較的影の薄い時代の雰囲気を伝える。しかし,この時代,
国際連盟設立メンバーとして,常任理事国として,国際舞台で西欧列強に伍し,
人種平等事項の実現をはかろうとし,
他方,国内では,
政友会,憲政会の二大政党制の時代であり,
普通選挙法(1925年,男子のみだが)成立するが,
大戦景気の反動の不況がつづき,昭和の金融恐慌の兆しの中,貧富の格差が拡大し,
その最中,関東大震災が起きる。そして,
安田善次郎,原敬がテロに倒れる,
という,テロとクーデターの昭和を予兆させる出来事が頻発してもいた。
著者は,「大正時代と今との間に時代状況の類似点がある」と,類似点を三点挙げる。
第一は,「大衆社会状況下の格差の問題である。第一次世界大戦とその後の関東大震災(1923〈大正一二〉年)は,日本社会に平等と共同の意識をもたらす。しかしそれも長くは続かなかった。大震災直後の昂奮は弛緩が取って代わる。日本は社会的な格差の問題の過酷な現実に直面する。」
今日,日本の総資産の41%を上位10%の人が独占し,他方六人に1人の子供が貧困にあえぐ。大正時代にも,それが目立ち,
「誰もが『細民』生活に転落するおそれがある。そのような危機が日本全国に広がっていた。」
との本書の記述は,「細民」をホームレスと置き換えれば,そのままこんにちの現状を指摘していると言ってもいい。
第二は,「長期の経済停滞です。第一の社会的な格差の問題は経済停滞に起因している。第一次大戦後の戦争景気は長続きしなかった。戦後の反動不況が深刻化する。大正時代は,バブル経済崩壊後の『失われた二〇年』の今日と共通するような経済停滞が長期化していた。」
今日,「失われた二〇年」は「失われた三〇年」となりつつある。
IMF(国際通貨基金)が公表したGDP推移見込みでは,バブル崩壊があった1990年代初頭からIMF予測の最終年2019年まで30年間、日本のGDPは5兆ドル前後に張り付いたまま,となる。一人当たりGDPにいたっては,26位,惨憺たる状態である。
第三は,「政党政治システムの模索である。この世界大戦前の第一次憲政擁護運動から始まり,大戦後の第二次憲政擁護運動に終る大正時代の日本は,戦前昭和の二大政党制の確立に至る政党政治システムを模索していた。」
とあり,民主党と自民党の政権交代は,「本格的な複数政党制への過渡期」として,当時と今の同時代性を感じさせる,と著者は言う。
「二大政党制が短期間に崩壊したのは,大正時代にあらかじめ準備されていたかのよう」な,いわゆる,
茶番劇,
と言いたげである。大正時代と平成時代のシンクロは,ネット上で,
1923年 関東大震災
1925年 治安維持法
1940年 東京オリンピック
1941年 太平洋戦争
2011年 東日本大震災
2013年 秘密保護法
2020年 東京オリンピック
2021年 ?
と,対照されていたような,不気味なシンクロを感じさせる。
日本は,1930(昭和五)年,ロンドン軍縮条約を,「米英と信頼関係のなかで調印をめざし」調印する。しかし,翌年,満州事変を起こし,国際連盟は,対日非難勧告を,四二対一で採択,日本は,連盟を脱退する道を選ぶ。
今日,財界人の一人が,
「戦争でも起きないと日本経済も立ちゆかなくなってきますなあ」
といい,武器輸出を解禁し始めている。公然と,「支那を叩く」などということを公言する政治家までいる。
本書は,こう締めくくられている。
「東京オリンピックは戦局の悪化を理由に返上された。他方で1940年の日本は紀元2600年記念行事で沸いた。何百万もの人々が汽車やバス,飛行機さえ使って,皇室関連史跡観光に訪れた。植民地観光も盛況だった。大衆消費文化を背景に,帝国観光で日本はにぎわっていた。真珠湾攻撃の前年のことだった。」
参考文献;
井上寿一『第一次世界大戦と日本 』(講談社現代新書)
http://blogos.com/article/104198/ |
|
和語 |
|
熊倉千之『日本語の深層:〈話者のイマ・ココ〉を生きることば』を読む。

同じ著者の,
『日本人の表現力と個性─新しい「私」の発見』(中公新書)
を,ずいぶん昔に読ませてもらった記憶がある。それについては,
http://www.d7.dion.ne.jp/‾linkpin/critique102.htm
で使わせていただいた。
本書で,著者は,
「『イマ』起こっていることを,ぼくたちの五感によって取り込んで,それをそのまま音声に換え,直接的・具体的なことばとして誰にも直感的にわかる表現にしています。たとえば『S』音は,スレル音(摩擦音)ですから,ただ『すー』ッと伸ばして発音しただけで,狭いところを何かが通る現象が表現できます。『すらすら・するする・すれすれ・すかすか・すくすく・すいすい・すべすべ』などなど,聞いただけですぐ具体的な何かがイメージできるのは,日本語がぼくたちの感性をとおして現実を捉まえる機能を持っているからです。」
という日本語の特性を,その音韻の発生にさかのぼりながら,丁寧に辿っていく。その説は,今日の国語学の主流とは異なり,多数に受け入れがたいものがあるに違いないが,僕には,首肯出来る部分が多々ある。傍らに,ぼくの依拠する,
日本語は文脈依存である,
という考え方と,時枝誠記の,
風呂敷型統一形式,
を念頭に置きながら,読ませてもらった。文脈依存については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/402221188.html
で,風呂敷型統一形式については,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/prod0924.htm
で触れた。いずれも,客観化,というかメタ・ポジションからの発話ができない日本語の特徴を示している。本書も,
「『イマ・ココ』の『現実』がよく見えるのですが,『イマ・ココ』から離れた時間・空間の扱い方には問題が生じます。(中略)日本語には,抽象的・間接的な事象・現象をうまく処理できないところがあるのです。それは『やまとことば』と言われる古い日本語が,文字をもたない言語だったことが一つの理由です。」
と,その特徴を書く。それは,
擬音語・擬態語,
と言われる表現の多種多様さに,よく現れている。たとえば,
イライラ,
について,
「『/iraira/』とは,/i/と表現すべき『存在』が,まだ『未然/ra/』形であることを繰り返す(強調する)表現でした…。実現すべき事象がなかなか起こらない状況が,この『いらいら』という感情を起こす基です。擬態語の音声としてムダなものが全くない見事なことばです。」
と,通常の「イライラ」の語源(イラ(刺)イラ(刺))とは別に,言葉の成り立ちから迫っていく。この,
イライラの「イ」,
は,「イマ」の「イ」に通じると,著者は説く。
「『イ』は口を横に引いて発音し,舌の位置がほかの四つの母音よりも相対的に前にくるので,一番鋭く響きますし,時間的にも口の緊張が長く続かない,自然に短い音なので,『イマ』という『瞬間』を表現できるのです。」
と言い,
「やまとことばの『音声』と『意味』には,ソシュールの説に反して,『恣意的』ではなく,密接なつながりが感じられるのです。」
として,「イマ」の「マ」について,こう触れていく。
「『イマ』の『マ』は,実は/i/という一瞬の時間的な間隔なのです。『マをとる』とか『マをおく』とか,何もないように見える時間・空間が,演劇でも絵画でも日本文化では大切な意味をもっています。/a/は一般的に『開かれた』時間や空間の表現に使われます。『開かれている』時間・空間『マ』は,何もないように見えますが,そこに何かが生まれる可能性を孕んでいます。/m/音が何かを『生む/umu/』特性をもつからです。…/m/音は,唇を閉じて発音するので,内にこもった語感があり,何かが『内包』された事態に使われます。」
日本語は,ウラル・アルタイ語系といわれ,
膠着語,
とされる。その例に,「もつ(縺)る」を例に,こう述べる。
「日葡辞典…の説明に,『ユクミチニカヅラガシゲツテアシニモツルル』とあります。『モツルル』は『裳(も)+蔓(つる)+ル』,つまり『着物のすそが蔓にからまっている』ことですが,『裳』と『蔓』の二つのイメージが,その順序でつながっているところに,『膠着語』としてのやまとことばの『特質』がはっきり見えています。」
この膠着語の特性のひとつは,
「抽象的なことばを文の初めに使えないことです。『雨が降る』を英語の〈It
rains.〉のように,抽象的な〈it〉から始めることがありません。」
であり,いまひとつは,
「/r/という流音(はじき音)がけっして語頭には来ないことで,(中略)この/r/音は,…日本語で『最重要な動詞』だとした,『ある』という動詞の根幹を担う音で,実際やまとことばでは,/r/音は,『存在』を意味する以外に使われることはありません。」
和語のことばの特性を,たとえば,
「『来(く)』(現代語の『来る』)は,話し手のいる場所へ何かが向かって『来る』ことです。『行く・往く』とし対照的な動作です。…『来』の未然形は/kö/で,現代語でも『コない』ですが,(中略)何かが出来するまでの現象として認識できないので,『未然(まだ起こっていない)』形には,特殊な音声が必然的に求められます。『変格活用』と言われる特殊な動詞の変化です。このあたりの音声の論理性は,目を見張るばかりですが,日本語の音声と認識の緊密な関係は,ぼくたちの感性を支えて,日本文化の生成に深くかかわっています。」
と書く。ここからも知れるように,
「体験を経て自分の語彙となるやまとことばは,否応なしに『主観』性をおびます。(中略)つまり日本語では,すべてのことばの意味は,厳密には,話し手・書き手でなければ判らない『主観』性を,他人とのコミュニケーションの問題点として抱えることになります。」
したがって形容詞は,西欧語のように,
モノの属性を表現することば,
ではなく,
話者の感性がモノに反応して発することば,
でしかない。
イマ・ココの言語,
と言っているのは,その意味で,話者のいる,
イマ・ココ
へ必ず戻ってくる,ということを意味する。たとえば,僕の理解では,
This is a pen.
を日本語に訳すと,
これはペンです,
となるが,それは,そう日本語表記した瞬間,これは客観描写ではなく,そう語っている話者が,そう言っているという含意を必ず持ってしまう,ということだ。著者が,
翻訳不能,
と言っているのは,このことを指す。その日本語の特色を具体化した,
能のワキ,
と
浄瑠璃の太夫,
のもつ意味,更に三人称小説と悪戦苦闘した,
夏目漱石の『こころ』,
と
中島敦の『古譚』(「狐憑」「木乃伊」「山月記」「文字禍」),
を例にとり,どう取り組んだかを分析してみせる。ちょっと視界が開くこと請け合いである。
参考文献;
熊倉千之『日本語の深層: 〈話者のイマ・ココ〉を生きることば』(筑摩選書) |
|
秀次 |
|
藤田恒春『豊臣秀次』を読む。
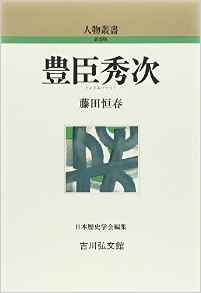
秀次には,二点の肖像画が残されている。一点は,一般によく知られている瑞泉寺所蔵のものだ。

豊臣秀次像/瑞泉寺蔵(部分)
著者は,こう書く。
「冠に直衣(のうし)姿で,切れ長の目に鼻の下と顎に少し髯をたくわえた少し傲岸不遜な雰囲気をたたえたものである。揉上(もみあげ)が特徴的,やや釣り上った両眼,固く結んだ唇がきつい印象を与えている。
作者がどのような意図で描いたものかわからないが,後世喧伝された『摂政関白』像に沿うような意図で画かれたものではないかと推察される。近世以降の秀次像形成に大きな役割を果たしたと思われる。」
もう一点は,京都地蔵院に伝来したもので,賛がある。

豊臣秀次像、高厳一華賛(京都地蔵院所蔵)
「赤い唇が印象的である。冠をつけ束帯に太刀を佩び,右手に笏を持ち,やや面長な容貌は,穏やかな青年武将の風貌をたたえているように見える。」
と著者は書く。賛には,
文禄四年七月十五日
同示不悟
東假図畫
海和尚之
前関白高巖一峯御影
とある。「十五日」とすると,
「切腹した日であたり,死の直前に画かれたものとなろう。いずれにせよ,死の直前か直後に描かれたものであり,秀次肖像画として信憑性は高い」
として,著者は,両者の印象が,ずいぶん違うが,
「真贋は問わないが,賛のある地蔵院の肖像画が,秀次の姿に近いものではなかったかと考えている。」
と書く。秀次は,
「子供のときから叔父秀吉の政略のため最初は宮部継潤へ,二度目は三好康長のもとへ養子に出され,天正十三年(1585)の四国攻めの前には,三好氏から離れ,羽柴孫七郎として秀吉の麾下に属するようになり,このときの論功行賞として一躍近江で四十万石を宛行(あてが)われ,八幡山城主となった。(中略)天正十八年七月,尾張国清州へ転封となって以降も,尾張の支配は父親の三好吉房へ任せ,自らは聚楽第にいることが多かった。
このような状況に変更を余儀なくさせたのは,秀吉の弟秀長の病気と死去という現実であった。秀長にかわり北条を攻め,ついで奥州仕置に従軍せざるをえなくなった。しかのみならず,天正十七年五月二十七日に生まれた,秀吉の鶴首の実子,鶴松が二年後の八月五日に亡くなり,…三度目の養家先として秀吉に迎えられたのである。」
その一生は,
「叔父の意のままに操られていた観すらあり,一青年の人生を考えるとき,自らの意志を表現できなかったものかと怪訝に思われるところもある」
にしろ,
叔父秀吉に振り回された28年の一生,
ということになる。その秀次が,関白という位に就くことによって,
「公家や桑門の人びとを宰領するようになるに及んで政権側に危機感を募らせるようになったのではないか」
と,著者は推測する。少なくとも,「関白」職を通さなければならないという制度上の権威と権力はついてくる。秀次事件について,
「秀次が謀叛といっても,秀吉を圧倒する軍勢を持たないことに鑑みれば,また,秀次附属の池田・山内などの軍勢も動いていないことをも勘案するとき,『謀叛』との言葉は軍勢を動かすようなものではなく,単純に秀吉の意向あるいは命令に,真っ向から背く回答をすることによって引き起こされた混乱と考えるべきであろう。すなわち,両者の不和の内実は,直接的であれ間接的であれ,自明の問題である。豊臣家家督を巡る問題である。」
と語り,秀次追放に当たり,明智光秀・柴田勝家・佐々成政・北条氏政にしたように,明確に罪状を書いていないことから,
「甥子とはいえ,関白職を剥奪し高野山へ追放するにしては,その理由を不届とだけ記すのは,いかにも奥歯にものの挟まった物言いである。秀次に非があるとすれば,もっと断定的に断罪できたのではないだろうか。」
と秀吉サイドの謀略を暗示する。江戸時代,秀次像ができあがった時代に,松浦静山は,『甲子夜話』で,
「新関(秀次のこと)は桀紂の如き独夫とも聞こへず,全く石田が讒侫と太閤の不明とに出るなるべし」
と書くように,政権側の危機感の反映である。高野山へ追放した折,秀吉は,身の回りのものだけの供を認める条書を出し,その文面だけを見れば,高野山軟禁を意図していたように見え,切腹を命じていない。しかし,それをもたらした,福島正則ら三名は,結果として検死役となった。この経緯を,
「秀次の切腹については,秀吉の命によるものとする考え方に対し,秀次自身が雪冤のため腹を切ったとする見方がある。秀吉が当初より秀次へ死を与えるなら,右の条書など必要ないものである。秀次謀叛を呼ばわっているうちに話が嵩じ,条書の旨趣を伝える前に一気に死を賜う方向へと行ってしまった。いわばもののはずみ的現象である。」
と書く。秀次二十八歳である。
「秀次は,山本主殿・山田三十郎・不破万作の介錯をしたうえで,自らは雀部重政をたのみ生害した。」
という。しかし,だとすると,この後の妻子を何十人も,三条河原で殺戮したのは何であったのか。秀吉の死の三年前である。
「秀次を葬り去ることにより,一番の痛手を蒙ったのはほかでもない秀吉自身であったと商量するものである。」
という著者の言葉が印象深い。それは,
「小牧長久手での失態に対する譴責,北条攻めに際して与えた覚書,関白職就任に対して与えた戒めなどを勘案するとき,十六世紀末期の政治社会の大きな変革のうねりが,まだ収まりきらない状況のなかで,政権を託せるような『器用』さを持ち合わせた人物であったようには思われない。にもかかわらず,秀吉のまわりには人材がいなかった。天下人秀吉をもってしてもこのことばかりは如何ともしがたかった。甥っ子秀次を一軍の将として,豊臣氏の後事を託せる人物として訓育しきれなかったところに秀吉の限界があったのかもしれない。」
と,秀吉につけが返ってくる。著者は,
「たとえ秀次が優れた人物であっても秀吉自身の血肉をわけた実子に豊臣家を継がせたかった」
と著者は書くが,仮に,養嗣子として迎え入れた,
織田信長の四男,秀勝(於次丸),
が存命であったとしても,やはり,秀吉は実子のお拾(秀頼)に継がせようとしたのであろうか。
参考文献;
藤田恒春『豊臣秀次』(吉川弘文館) |
|
ナショナリズム |
|
大澤真幸『近代日本のナショナリズム』を読む。

本書の冒頭,
「ナショナリズムの謎」
の章は,レーニンのショックから書きはじめられる。
「ナショナリズムの謎は,第一次世界大戦勃発の直後にレーニンが受けた衝撃の中に集約されている。世界大戦が始って間もない頃,第二インターナショナルに参加していた,ヨーロッパ各国の社会主義政党は,ほぼ一斉に,自国の戦争の支持にまわった。」
レーニンに与えた「驚倒」は,
「ナショナリズムは,特定のネーション(国民・民族)に愛着し,これを優先する特殊主義の一形態であるように思える。他方,社会主義やマルクス主義は普遍主義的な思想である。普遍主義者の特殊主義への突然の折れ曲がり,ここに,この出来事の驚きの中心がある。」
というものである。なぜなら,
「ナショナリズムは,特殊主義の一形態であると見なされ,これを批判したり,乗り越えようとする者は,コスモポリタニズムのような何らかの普遍主義的な思想に立脚しようとする。」
それが,大戦勃発で,ナショナリズム克服になりえないことを明らかにしたからだ。それは,
「ナショナリズムは,特殊主義と普遍主義の交叉,特殊に限定された共同性への志向と普遍的な社会への志向との接続をこそ,その本質としている」
からだ,と著者は書く。例えば,「背反するポテンシャルを有している」民族自決と民主主義とを例に,著者は,
「民主主義を特徴づけているのは,諸個人の属性についての『にもかかわらず』という非限定・脱限定の表現である。納税額にかかわらず,身分にかかわらず,人種にかかわらず,性別にかかわらず…といった否定によって,個人の具体的な属性を還元し,抽象化することで,政治への参加の可能性を普遍化すること,これが民主主義あるいは民主化ということだ。とすれば,民主主義は,特定の民族を他から区別し,それに自決の権利を与えようとする思想とは,少なくとも,その基本的な精神において背反するはずだ。両者が国際政治において同等に重視され,ときに同時に要請されても,誰もとまどったり,たじろいだりしないのは,この一見明白な矛盾を不可視化する,何らかの社会的なメカニズムが働いているからである。それこそが,ナショナリズムである。」
と,ナショナリズムの,
「普遍性への志向と特殊性への志向,真っ向から対立するこれら二つのベクトルが,いかにして,どのようなメカニズムに媒介されて接続することができるのか。普遍性への志向が,どうして,特殊性への志向へと反転するのか」
という問題意識を,本書の通底するテーマとして,戦前の,
ナショナリズムからウルトラナショナリズムへの変化,
更に現代の,
靖国問題,
おたく問題,
を例示として,展開している。発表場所が違う論文を集めているために,正直,文体が異なって文の難易に差があるという難はあるし,かつ,問題提起だけで終わっていて,
で,どうするの?
と問いたくなる箇所もある。しかし,今日わが国の脱知性というか反知性というか,ずたぼろな知的状況の中では,ある意味,こうした思想のフレームを明確にしておくことは,大事だと思う。第一章の,
「ナショナリズムの謎」
が,やはり読みごたえがある。ベネディクト・アンダーソンの,
ナショナリズムの三つのパラドクス,
を手掛かりに始められる。三つとは,
「第一に,ナショナリティ(国民的帰属)という社会文化的概念は,形式的には普遍的なのに,それが具体的にはいつも,手のほどこしようがないほど固有性を持って現れ,そのため,定義上,たとえば『ギリシャ』というナショナリティは,完全にそれ独自の存在になってしまう。」
「第二に,歴史家の客観的な目には国民(ネーション)は近代的現象に見えるのに,ナショナリストの主観的な目にはそれはきわめて古い存在と見える。」
「三つ目のパラドクスとは,…ナショナリズムは,近代のどのような『イズム(主義)』よりも大きな政治的影響力をもったのに,哲学的には貧困で,リベラリズムやマルキシズム,フェミニズム等の他の『イズム』と違って偉大な思想家を生み出さなかった。」
である。しかし,明らかに,
ネーションは近代の産物,
にもかかわらず,
「どうしてナショナリストの目にはネーションがそれより遥かに古いものに見えるのか。」
著者は,アントニー・スミスの,
「固有の意味でのネーションは近代に成立したのだが,ネーションの素材とも言うべきエスニックな共同体―これを『エトニー』と呼ぶ―は,はるかな古代から存在していたのだ」
という説は,逆立ちしている,という。三角形を例に,
「個々の具体的な三角形は,決して概念としての『三角形』ではないが,それなしに『三角形』という概念を理解することはできない。同様に,市民の抽象的な共同体は,エトニーの具体的で有機的な繋がりとは異なるが,それなしには構成されえないのである。」
として,
「エトニーがネーションの起源なのではなく,ネーションこそがエトニーの(論理的な)起源だ」
と。それは,ネーションが,アンダーソンの言う,
「想像された共同体」
つまり,「想像においてのみ実在的」であるからにほかならない。しかし,今日吹き荒れているナショナリズムは質的に異なり,
「国民を民族化する運動として生起している。かつて,ナショナリズムは主として,局地的な共同体…を『国民』という広範で包括的な単位へとまとめ上げていく圧力として作用していた。だが,今日のナショナリズムは,この人民の国民化とちょうど反対方向への圧力を加えてくる。それは,国民を,『民族(エスニシティ)』というより小さな単位へと分解していく圧力として作用しているのだ。」
と。いま,国内で起こっているヘイトスピーチは,まさにそういう反応に見える。しかし,なぜ,
「古典的なナショナリズムは,特殊主義と普遍主義の背反するベクトルの均衡点において…ネーションを結節させることで成り立ってきた。それに対して,特殊主義と普遍主義が,ともに,この均衡点の位置を超えて強化されたときに現れるのが,現代のナショナリズム」
なのか,の答は,出されていない。あるいは,本質的にナショナリズムは,変っておらず,この分析が間違っているのかもしれない。そもそも,特殊主義が,
普遍主義を凌駕しようとすること自体,
が,ナショナリスティックな表れではないのか,という気がしないでもない。
普遍主義と特殊主義の相克は,そのまま,靖国問題の象徴的対立と重なってくる。それを,著者は,こう整理する。
一つの立ち位置は,「死者のまなざし」である。つまり,
「戦後の『日本人』が自らの現在を肯定し,規範的に承認するためには,今日の『日本』をもたらすのに貢献した―あるいは少なくともその『原因』となった―死者のまなざしを必要とする。死者たちが欲望し,願望していたことの現実化(の過程)として,自らの現在を意味づけることにおいて,『日本人』としてのアイデンティティを全的に確立することがかなうのである。そのためには,まずは,『死者』そのものが肯定的に措定されなくてはならない。しかもその『死者』は,特定の希望や願望をもって,能動的に社会に変化をもたらそうとした者でなくてはならない。つまり,(中略)靖国参拝は―非業の死を遂げた軍人・軍属を靖国神社で追悼し,ときには検証することは―,われわれの『(日本人としての)現在』を承認する,超越的な他者を措定する操作そのものなのである。」
一方は,普遍的な立ち位置である。
「歴史は,そしてまたわれわれの『現在』は,死者たちが保持してきた共同体の『善』によってではなく,歴史の終局に仮想的に置かれた救済者の判断によって,つまり『普遍的な正義』によって裁かれることになるだろう。裁き手とその判断基準が異なるのだから,当然,その『判決』も,したがって歴史の『勝者』も異なってくる。第二次大戦でアジアに侵出した日本の軍人は,右派から見れば,無罪でなくても,情状酌量の余地が出てくるが,左派から見れば,決定的に有罪である。いずれにせよ,現在の日本社会は,自らに承認を与える,超越的な第三者の審級を,『戦後六〇年』の時間幅の内部に見出すことに,困難を感じているように思える。それを過去の方に,つまり『六〇年』の以前に求めれば,右派に,逆に,未来の方に,『六〇年』の以降に求めれば,左派になる。」
普遍主義と特殊主義の綱引きを乗り越える第三の道は,
「神(第三の審級)が可謬的であることを認めるところ」
と,著者は言う。しかし,それは,今日のずたぼろの知的状況では,
東京裁判の否定,
更には,
ポツダム体制の否定,
に,シフトさせることになるだけのような気がするが,いかがであろうか。
参考文献;
大澤真幸『近代日本のナショナリズム』(講談社選書メチエ) |
|
偶然 |
|
ダンカン ワッツ『偶然の科学』を読む。
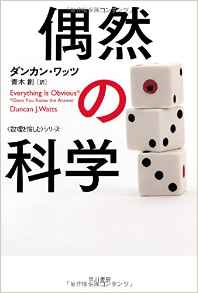
原題は,
Everything is Obvious
であり,さらに,
Once You Know the Answer
とある。そう,
そんなの当たり前じゃないか,
と口走ることがある。それがまあ,常識,である。更にタイトルには,
How common Sense Fails Us
とある。だから,本書は,
第一部 常識
第二部 反常識
と分けて展開される。しかし,本書のテーマは,社会学,あるいは広く社会科学の有用性への著者なりの解答なのである。だから,「まえがき」に,
「社会科学の考え方を学ぶのは,物事の仕組みについておのれの直観そのものを疑い,場合によってはそれらを完全に捨ててしまうことを学ぶに等しい。だから,この本を読んでも,皆さんが世界についてもう知っていることを再確認する役にしか立たなかったのなら,お詫びする。社会学者として,わたしは自分のつとめをはたせなかったのだから。」
と,挑戦的なことが書かれる。そして,巻末に,こう書いているのである。
「望遠鏡の発明が天空の研究に革命をもたらしたように,携帯電話やウェブやインターネットを介したコミュニケーションなどの技術革命も,測定不能なものを測定可能にすることで,我々自身についての理解や交流の仕方に革命をもたらす力がある。
マートンのことばは正しい。社会科学はいまだに自分たちのケプラーを見いだしていない。しかし,アレグザンダー・ホープが人間の適切な研究課題は天上ではなくわれわれのなかにあると説いてから三〇〇年後,われわれはようやく自分たちの望遠鏡を手に入れたのである。
さあ,革命をはじめるとしよう……」
と。これは,マートンが,
「多くの社会学者は,物理学の業績が自分を評価するときの基準になるととらえている。兄と力比べをしたがっている。自分も一目置かれたいと思っている。そして兄ほどのたくましい体格も強力なパンチ力もないのが明らかになったとき,絶望する社会学者もいる。そしてこんなふうに問いはじめる。社会学の総合体系を作らずに社会の科学などというものがほんとうに可能なのか?」
「おそらく,社会学は自分たちのアインシュタインを迎える準備がまだできていないのだろう。いまだに自分たちのケプラーを見いだしていないのだから―ニュートン,ラプラス,ギブス,マックスウェル,ブランクは言うまでもなく。」
と嘆いたことへの,著者なりの解答なのである。
著者の名を高からしめた,ミルグラムの三百人によるボストンの一人を目指した,いわゆる,
六次の隔たり,
実験を追試し,二万人以上の鎖が,最終的に六万人,166か国を経由してターゲットに行きつき,
「鎖のおよそ半分が,七つ以下のステップでターゲットにたどりつけた」
ことを発見した。しかし,ミルグラムが,
「一握りの個人にメッセージが集中していた」
とする,
「伝達過程での『ハブ』はなんら見いだせなかった。メッセージをターゲットに届けた人の数は,鎖の数にほぼ等しかった。(中略)つまるところ,スモールワールド実験の被験者はたいていの場合,最も地位の高い友人や最も親しい友人にメッセージを伝えるわけではない。そのかわり,地理的に近いとか,似た職業に就いているといったターゲットと何かしら共通点がありそうな人々に伝えるか,単にメッセージの伝達をつづけてくれそうな相手に伝える。言い換えれば,ふつうの人でも特別な人々と同じように,社会集団や業種,国家,居住地などのあいだにある大きな溝に橋を架けることができるということだ。」
この実験は,「特別な人がいるはずだ」という常識,
スーパープレッダー,
あるいは,
インフルエンサー(影響者)
に起因させようとする常識についてのいくつかの実験につながっていく。そのひとつは,ヒット曲やヒット本には,
特別な人が介在している,
という常識を検証する,「音楽『市場』の再現を目的」に,ティーンエイジャー向けの初期のソーシャルネットワーキング・サイトであるボルト」での,
ミュージック・ラボ,
実験である。数週間でおよそ一万四〇〇〇人の会員が実験に参加し,
「実験サイトを訪れた会員は,無名のバンドの曲を聴いて,採点し,望むならダウンロードするように依頼される。一方の被験者には曲名しか示されないが,他方の被験者には以前の被験者がダウンロードした回数も示される。後者の『社会的影響あり』のカテゴリーの人々はさらに八つの並行『世界』に分けられ,その世界でのダウンロード回数しかたしかめられない。」
結果,
「明らかになったのは,他人がなにをダウンロードしたかについての情報があると,人々は累積的優位の理論が予測するとおり,たしかにそれからの影響を受けることだった。『社会的影響あり』のどの世界でも,自己判断のみの条件下に比べ,人気のある曲はいっそう人気があった(人気のない曲はいっそう人気がなかった)。
だが同時に,…社会的影響を人間の意思決定に持ちこむと,不均衡性だけでなく予測不能性も増していた。…予測不能性は市場そのもののダイナミクスにもとから備わっていたのだ。
注意すべきなのは,社会的影響が質の優劣まで完全に消し去ってしまったわけではないことだ。『すぐれた』曲(自己判断のみの条件下での人気度から判定できる)は『劣った』曲よりも平均して結果が良かったのも事実だった。(中略)別の言い方をすると,最もすぐれた曲でも一位になれないときがあり,最も劣った曲でも健闘するときがあった。そして並みの曲,つまり最もすぐれてもいないし最もおとってもいなかった大多数の曲は,ほぼどんな結果でもありえた。(中略)全体を見ると,質の点で上位の曲の五曲が結果の点でも上位の五曲になる可能性は五〇パーセントしかなかった。」
著者は,これを,
「個人が他人の行動から影響を受けるとき,似たような集団であってもやがて大きく異なる行動をとりうる」
とまとめ,そして,
「これは常識に基づく説明を根底から揺るがす」
と言う。つまり,こういう常識に,である。
「常識に基づく説明は,集団を代表的個人に単純に置き換えることにより,個人の選択がどう積み重なって集団の行動になるのかという問題をまるきり無視してしまう。そしてわれわれは,個々の人びとの行動理由はわかっていると思いこんでいる。そのため何かが起こったとたん,それは架空の個人,つまり『人々』なり『市場』なりがのぞんだことなのだと主張することができる。」
また,インフルエンサ―の実験では,
「二カ月の期間をとり,のべ160万人以上のユーザーからはじまった7400万本以上の拡散の鎖」
を辿って,ツイッターによる情報の拡散を実験してもいる。結果は,
「7400万本の鎖のうち,リツィート数が1000回に達したのはわずか数十本だったし,一万回に達したのは,一,二本にすぎない。」
という。これは,
「数百万の人々の複雑なネットワークがどうつながっているのか―そしてこれはもっと厄介なのだが,影響がそこでどう広まるのか―を想像しようとしたとたん,われわれの直観は打ち負かされる。少数者の法則のような『特別な人々』説は,事実上あらゆる働きをわずかな個人の手に集中させることで,ネットワークの構造は結果にどう影響するのかという問題を,特別な人々を動かすものは何かというずっと単純な問題にすり替えてしまう。
常識に基づく説明の例に漏れず,これも理にかなっているように聞こえるし,正しいのかもしれない。だが,『Xが起こったのは少数の特別な人々がそれを起こしたからだ』と主張するのは,循環論法を別の循環論法で置き換えるのに等しい。」
と。
ミュージック・ラボ実験,スモールワールド実験等々を通して,今日,
測定不能なものを測定,
するツールが手に入ったことを,著者は証明している。しかし,
「電子データがいくらあろうと,そこから社会学的に意味のある推測を引き出すわれわれの能力は制限されている。」
が,
「われわれはこれらすべてのアプローチを同時に進め,人々の行動と世界の仕組みを上からも下からも理解することに集中し,利用できるすべての手段と資源をつぎ込む必要がある。」
そういう時代になったのだ,著者は言いたいらしいのである。僕には,著者自身も認めていたが,
「社会学者は人間の行動の大理論や普遍法則を探求するのではなく,『中範囲の理論』を発展させることに集中すべきだとマートンは説いた。中範囲の理論とは,孤立した現象以上のものを説明できるほどに適用範囲が広いが,具体的で有用なことが言えるほどに限定的な理論を意味する」
でいう「中範囲の理論」を実現しつつあるのだ,とは感じる。
読み終えてみると,『偶然の科学』という訳書のタイトルへの違和感は,
当たり前とする常識を検証し,偶然でしかないことを実証しようとする,
という意味で少しは薄らいだか,少なくとも,
当たり前に見える「偶然」を検証しようとする,
著者のマインドを正確に反映しているとは思えない気がした。
参考文献;
ダンカン ワッツ『偶然の科学』(早川書房) |
|
極意 |
|
森俊夫『ブリーフセラピーの極意』を読む。
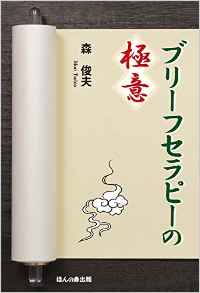
昨年亡くなられた森先生の最後の著作である。黒沢先生の「森先生を偲んで」には,
「二年をかけて『極意』を書き切られました。それから,本書の第一校の著者校正を集中して終えられたのが2014年六月。森先生の軽妙な文体からは想像がしづらいことですが,一言一言,徹底的に吟味される方ですので,この段階で完成度はほぼ完璧でした。そして,第二校の校正の最中にご病気になられてしまいました。最期は『極意』を私たちに託し,2015年三月,本書の完成を見ることなく,旅立たれました。森先生の生き様そのものが究極のブリーフセラピストでした。」
とある。何度も何度も,そう数えれば,何十回と,研修やセミナー,吉祥寺でのKIDSの連続講習等々で,直接学ばせていただく機会があり,産業カウンセラー協会の最後のセミナーが中止になって,ご病気を知ったという御縁もあり,本書をつい手にした。
いつもあの独特の息継ぎの,癖のある喋り方を思い出しながら,読ませていただいた。
『極意』は,たぶん,『五輪書』に書かかれている,何気ない言葉が,実際にやってみると限りなく奥が深いように,そうそう簡単ではない。たとえば,著者が,エリクソンに触れて,
「心理療法とは,クライエントが持っていないものを与えることでも,持っているものを矯正することでもない。持っているにも関わらず,使われていないものを引きだすことである。」
という言葉を引用し,森先生は,「これ,極意」と書く。それと同じように,ソリューション・フォーカスト・アプローチの『極意』も,たとえば,
ものすごく基本的なこと(極意)四つ,
として,
ブリーフなかかわりをしようと思うこと,
ラポール形成を素早く,
面接(かかわり)は,明るく,楽しく,楽に,
これから(未来)のことに,明るい展望が持てる面接に,
を挙げる。言葉を換えて,僕流に言い換えると,
ブリーフをやろうとしないとブリーフはできない,
共通点や一致点を見つける気になれば見つかる,
喜びや楽しさ,安心感に焦点を当てれば,その部分が膨らんでいく,
自分に力があると思えれば未来が思い描ける,
ということになる。その「スタンス」を遂行していくには,練達のスキルがいる。しかし,森先生は,
「方法論なんて,なんだっていい。目指すところは何なのかというお話です。『あとはお好きにどうぞ』。あああ,話終っちゃった。」
と言われる。まるで,(本書で引用されている)エリクソンの,
「人は皆,一人一人ユニークな存在です。したがって,心理療法はそのユニークさに合わせて,一人一人に仕立てられるべきであって,人間行動に関する仮説理論という“プロクルステスのベッド”に寝かせて,人を切ったり伸ばしたりしてはいけません。」
「もし私が理論をつくるとしたら,患者一人一人に対してつくります。」
の言葉のようである。神業である。
でも,本書では,四つの「達成目標」に対する,「ブリーフセラピーの方法論の極意」も,ちゃんと教えてくれている。
ソリューション・フォーカスト・アプローチの解決志向,
つまり,
「『解決(より良き未来)』を手に入れること」
に役立つものは,
リソース(資源・資質),
解決像(良い未来像),
アクション(何かをすること),
であり,四つの基本にもかかわるが,
リソース,
こそがすべてである。リソースとは,
「ある個人の中にある力(能力)・興味や関心(好きなこと)・すでにやれていること(これらを『内的リソース』と呼ぶ),および,ある個人の周囲にあって,その個人を支える人々・生き物(ペットや植物など)・物(これらを『外的リソース』と呼ぶ)」
のことである。それは特別なものではない。
「やれている分だけをリソースと考えれば,さらにまだ実際にやれていなくても,その潜在能力はあるなと感じられるのであれば,それもリソースである」
として,森先生は,
「私の好む『リソース』の定義とは,『今,ここにあるもの』です。『ないもの』は『リソース』ではないですが,もし『ある』のだったら,その内容が何であれ,それは『リソース』です。」
と定義する。たとえば,「場面緘黙」(しゃべれるのに,ある状況下では何も言葉を発しない)ですら,
「すごい『能力』」
リソースと言い切る。その意味で,神田橋條治さんの,
「『問題』の言葉が浮かんだら,その下に『能力』という言葉を付けなさい」
という言葉を引用する。
問題もまたリソースである,
というのが,リソースに対する方法論でもある。
ソリューション・フォーカスト・アプローチでは,
ミラクル・クエスチョン,
が有名だが,これもまた,解決像をつくる方法である。そのバリエーションに,
どこでもドア
や
ドラえもんのポケット,
や
変身クエスチョン,
や
タイムマシン・クエスチョン,
という方法がある。定型ミラクル・クエスチョンとタイムマシン・クエスチョンの使い分けについて,
「判断基準の一つは,『問題』の存在がクライエントさんから明確に表明されているかどうかです。定型ミラクル・クエスチョンには『今日お話された問題が奇跡によってすべて解決したとすれば』という文言が入っていますので,クライエントさんがはっきりと『これが問題です』と語っていることが前提となります」
「一方現在の『問題』について,クライエントさんがはっきりと(あるいは,まったく)語っていない場合とか,すぐにこうしたいというよりも,将来のことに対する不安が話のテーマであったりする場合は,タイムマシン・クェスチョンのほうがいいでしょう。」
と書く。ここにも,練達の技がある。
「『ゴール』というのは,あくまで一歩踏み出せたときの『状態』」
であり,課題とは別とか,スケーリング・クェスチョンにおいて,0点だとしても,
「ええっ,0点の状況の中で,どうやって毎日やっているの?」
とコーピングクェスチョンで切り返したり,スケールの向きについて,
「学習障害(LD)のある子の中には,横軸スケールをイメージできない子がいる」
とか,些細ながら,練達の技の中で気づくことが,随所にちりばめられる。極意は,そうした積み上げの,
氷山,
でしかない。読み返すほどに,また,森先生の声とともに,いろんな発見がありそうである。
参考文献;
森俊夫『ブリーフセラピーの極意』(ほんの森出版) |
|
虚実皮膜の隙間 |
|
花田清輝『鳥獣戯話』をめぐって。
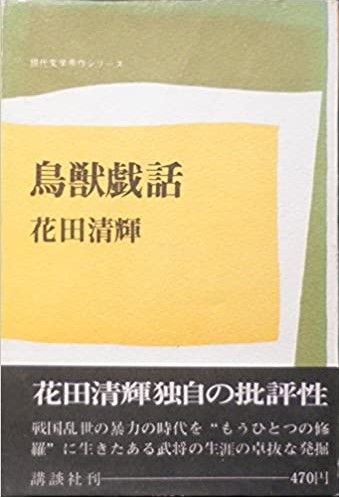
私のように武骨で,律儀だけが取り柄の男には,なかなか花田清輝のような,洒脱で,人を食ったようなアイロニー,あるいは意地の悪さといってもいいようなものにはついていけないところがある。ただ,記憶では,花田清輝が,自殺した田中英光のことを書いていた文章を読んだことがあり,その誠実さにひかれた覚えがある。
皮肉たっぷりの表現に,かつてすごく魅力を感じたものだ。たとえば,こうだ。
そもそもあの「風林火山」という甲州勢の軍旗にれいれいしくかかれていた孫子の言葉そのものが,孫子よりも,むしろ,猿のむれに暗示されて,採用されたのではなかろうかとわたしはおもう。「動かざること山のごとく,侵掠すること火のごとく,静かなること林のごとく,はやきことかぜのごとし。」−などというと,いかにも立派にきこえるが,つまるところ,それは,猿のむれのたたかいかたなのである。
猿知恵とは,猿のむれの知恵のことであって,むれからひきはなされた一匹もしくは数匹の猿たちのちえのことではない。檻のなかにいれられた猿たちを,いくら綿密に観察してみたところで,生きいきしたかれらの知恵にふれることのできないのは当然のことであり,観察者の知恵が猿知恵以下のばあいは,なおさらのことである。
なるほど,かれは,甲斐の国の統一にあたって,ほとんど連戦連勝の記録をのこしているが−しかし,それは,かれが勇敢だったからではなく,むしろ,卑怯だとみられることをおそれなかったからかもしれないのである。猿のむれの示すところによれば,戦場のかけひきとは,要するに,すすむべきときに,いっせいにすすみ,しりぞくべきときに,いっせいにしりぞくことを意味する。ところが,その当時の武士たちは,「ぬけがけの功名」が大好きであって,全体の作戦など眼中になく,ただ,もう,むれを離れて,おのれの勇敢さをひけらかす機会のみをうかがっている阿呆らしい連中ばかりだったから,ひとたまりもなく,すすむことともに,しりぞくことを知っていた信虎のために,ひとたまりもなく,一敗地にまみれ去ったのはあやしむにたりない。
武田の軍法を定めたが,わが子信玄によって追放され,京で足利義昭のお伽衆に加わり,無人斎道有として生きた,武田信虎を中心に設えながら,当時の信玄,信長を玩弄している。
たとえば,信長が,義昭のために二条城普請をするために,毎日石運びさせられているというので,こんな落書があった。「花より団子の京とぞなりけるに今日も石々あすもいしいし」。動員された近江の百姓の怨嗟の声を読み取り,婦人の面帕を上げて顔を見ようとして足軽を一刀のもとに首をはねた,というエピソードがある。それを桑田忠親氏が,「黙って首を刎ねるとは,凄い」と評したことに対して,「強すぎたる大将のふりをした,臆病なる大将のすがたをみるだけであって,すこしも凄いとはおもわない。」と言い切る。そして,こう付け加える。
もしも凄いという言葉が,非情ということを意味するなら,わたしには,それらの落書の作者であることを,ちゃんと承知していながら,平気で,無人斎道有を,おのれのお伽衆のなかへ加え,一緒になって信長の器量のちいささをせせら笑っていた将軍義昭のほうが,信長よりも,はるかに凄い性格の持ち主だったような気がしないこともない。
そして,こう皮肉るのである。
戦国時代をあつかう段になると,わたしには,歴史家ばかりではなく,作家まで,時代をみる眼が,不意に武士的になってしまうような気がするのであるが,まちがっているであろうか。時代の波にのった織田信長,豊臣秀吉,徳川家康といった武士たちよりも,時代の波にさからった−いや,さからうことさえできずに,波のまにまにただよいつづけた,三条西実隆,冷泉為和,山科言継といったような公家たちのほうが,もしかすると,はるかにわれわれに近い存在だったかもしれないのである。それとも延暦寺の焼き討ちを試み,一山の僧侶の首ことごとくはねてしまった信長のほうが,薬用のため庭でとらえて殺した一匹のむぐらもちをあわれみ,慙愧の念にたえないといって,わが身を責めている実隆によりも,われわれの共感をさそうものを,より多くもっているのであろうか。
この高角度で,細部までつぶさに焦点を当てた書き方を,野口武彦氏は,パンフォーカス(全焦点)というたとえをしているが,その時代のあらゆるところに焦点を当てて,信長どころか,信玄も,信虎をも,相対化していく書き方には,魅力を覚える。
しかも,うっかりその話法にのると,とんでもないことになる。
確かかどうか記憶が定かではないが,『甲陽軍鑑』『三河風土記』『犬筑波集』『弧猿随筆』『武田三代軍記』『甲斐国志』『言継卿記』『老人雑話』等々に交じって,『逍遥軒記』という偽書を混じりこませ,高名な評論家がころりとだまされた,というのをどこかで読んだ記憶があり,うかつに読むと,その術中にはまりかねない。しかしこういう高度なエンターテインメントこそが,知的な遊びに思えてしまう。これも術中にはまった結果か。
わたしは,信長が,徹底した合理主義者だったというような伝説をすこしも信じない。『醒睡笑』や『昨日は今日の物語』のなかに登場する信長は,たえず前兆のようなものを気にして,びくびくしている。
ただどうだろう。こういう相対化した話は,世には受けない。受けない話は伝搬せず,沈殿していく。それが惜しくて,ここにちょっと紹介してみた。へそ曲がりなので,世の中に受ける話には乗らない。今や時代遅れの(とは思わないからこそ),花田清輝をあえて紹介するのも,その性分から来ている。
昨今侍だの武士だのを吹聴する傾向がある。あえてへそ曲がり流にいうなら,侍はおのれを侍などとは言わない。なぜなら,そんなにことを言わなくても侍なのだから。わざわざおのれが侍だなどという必要はない。そう自らいわなければならないとしたら,侍ではないのだ。外目からも,生きざまからも。自分で侍などという手合いは,信じないことだ。ましてや,それをほめそやす輩からは,そっと離れるにしくはない。 |