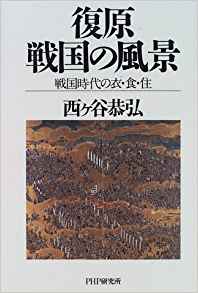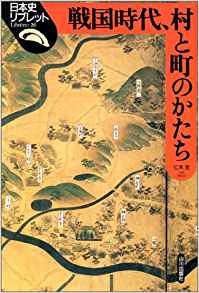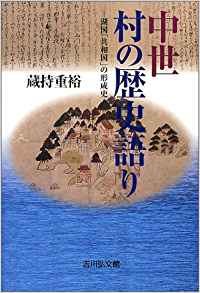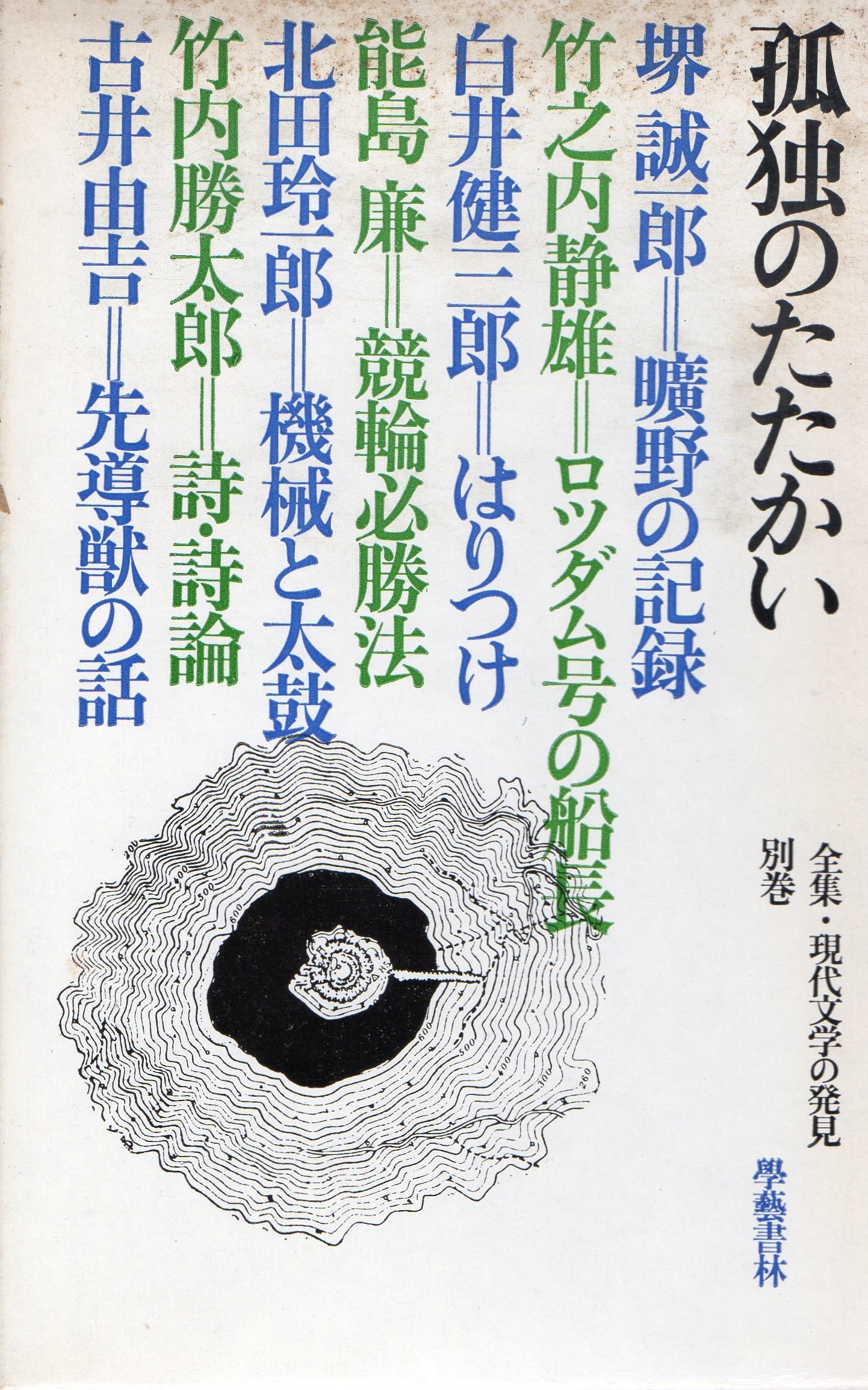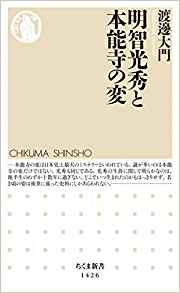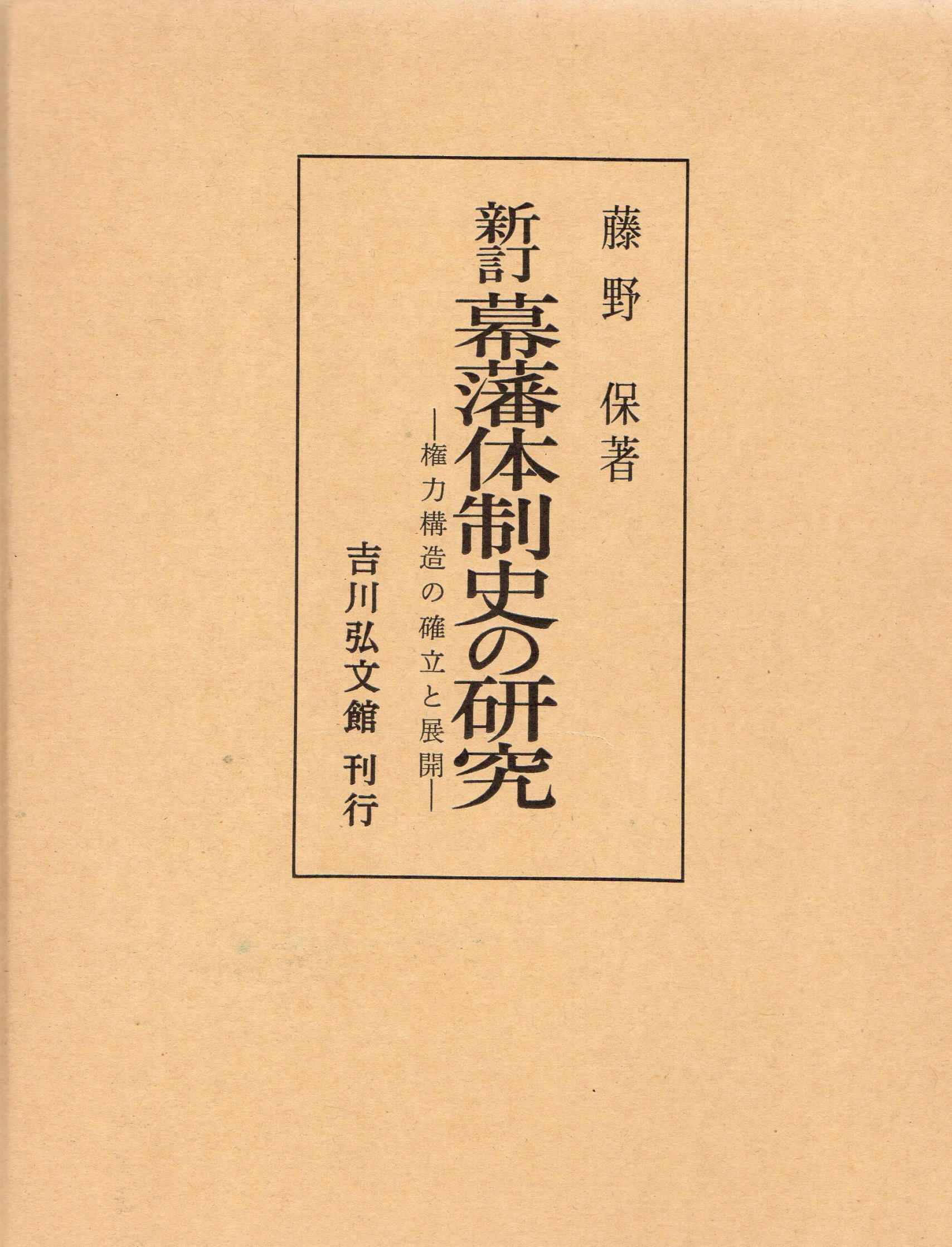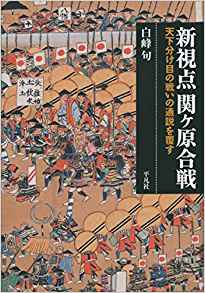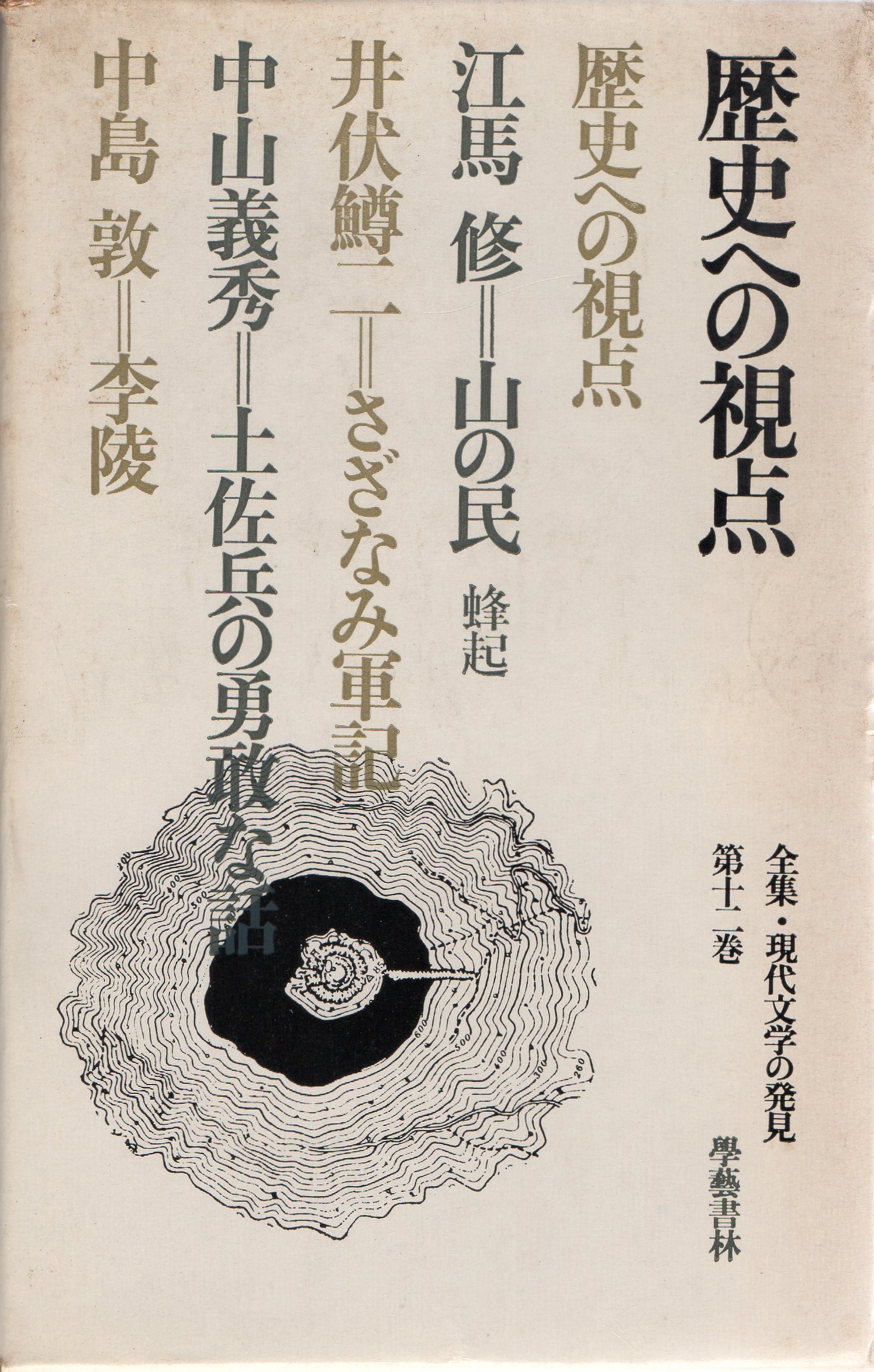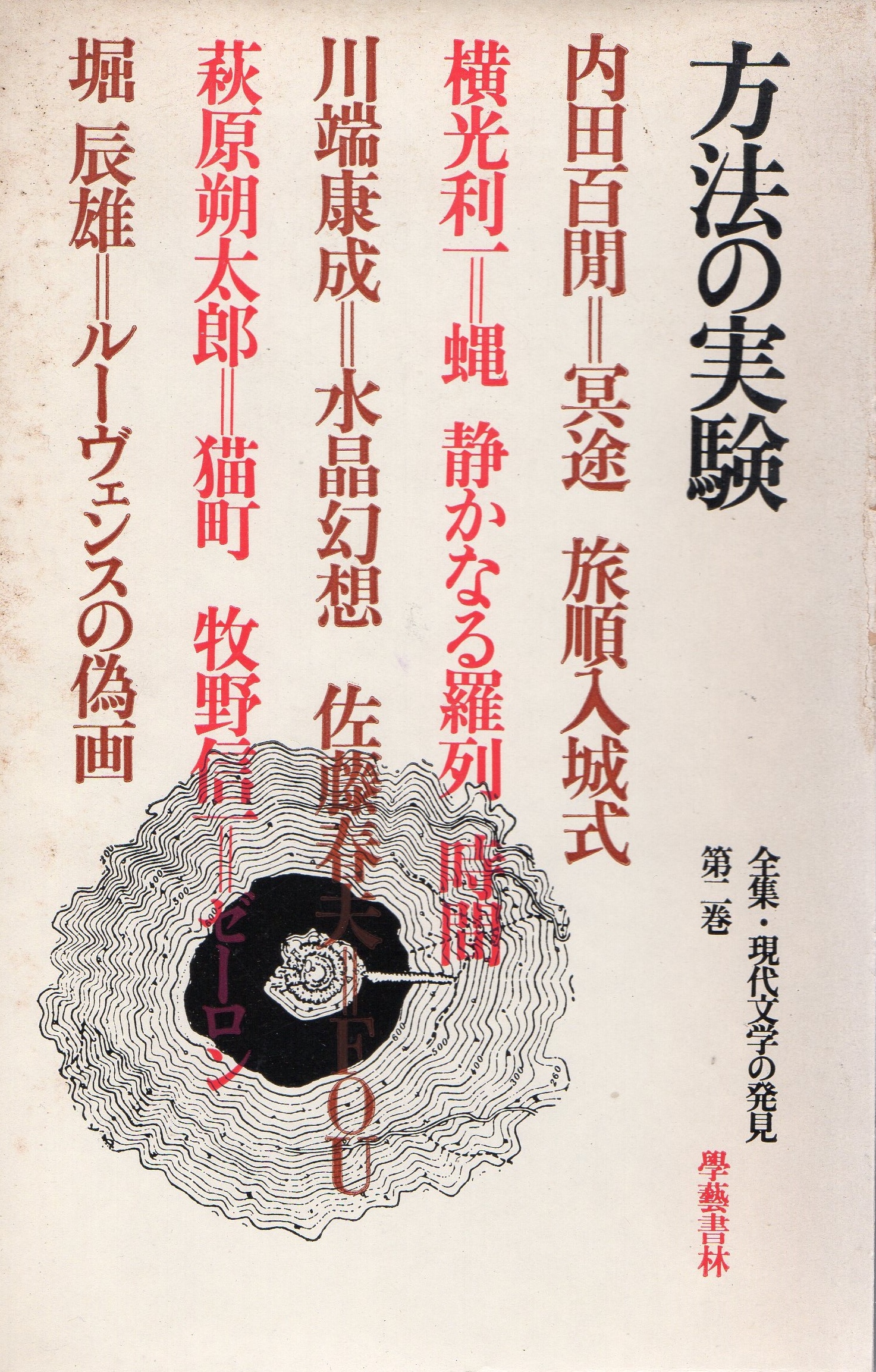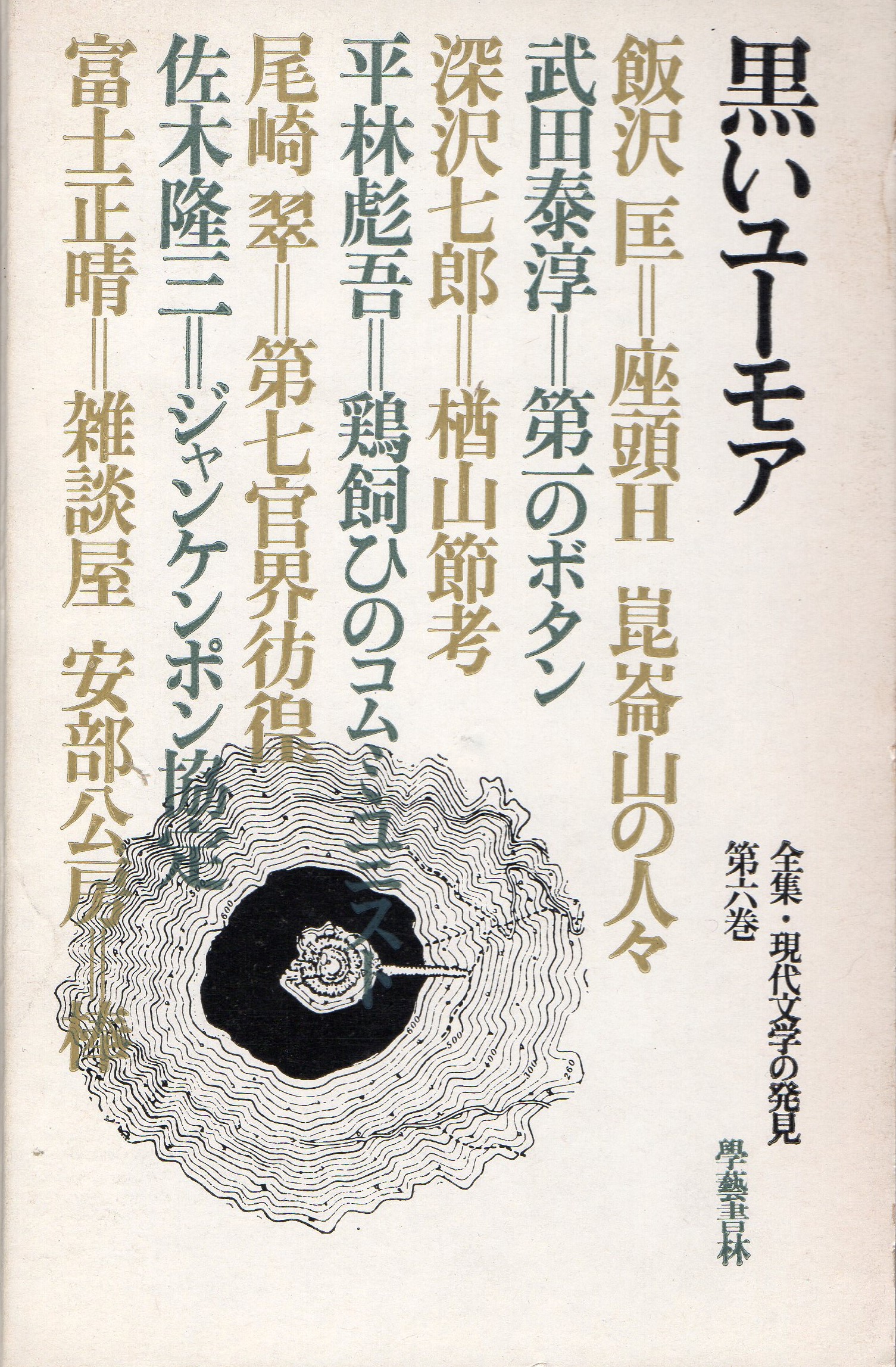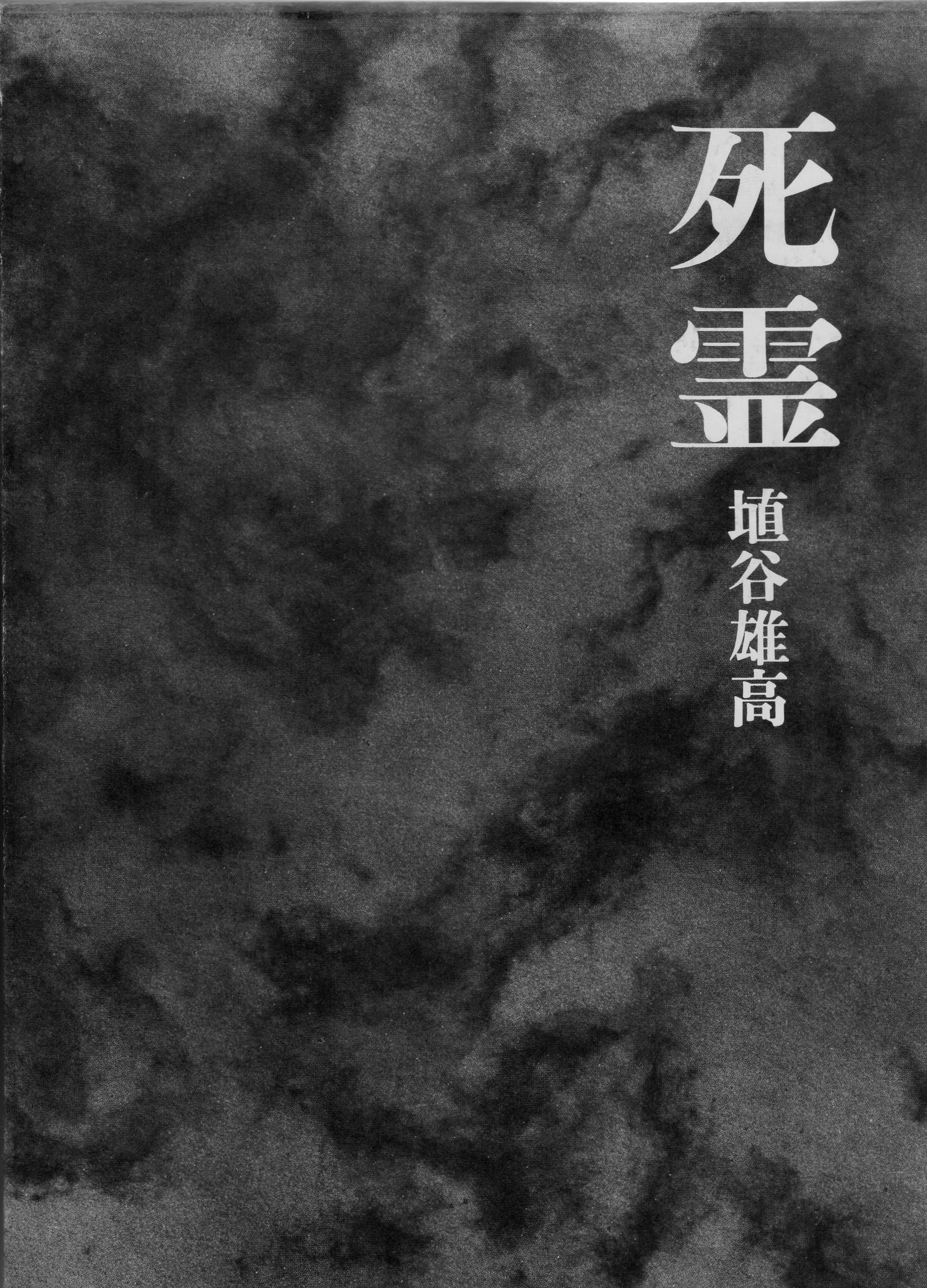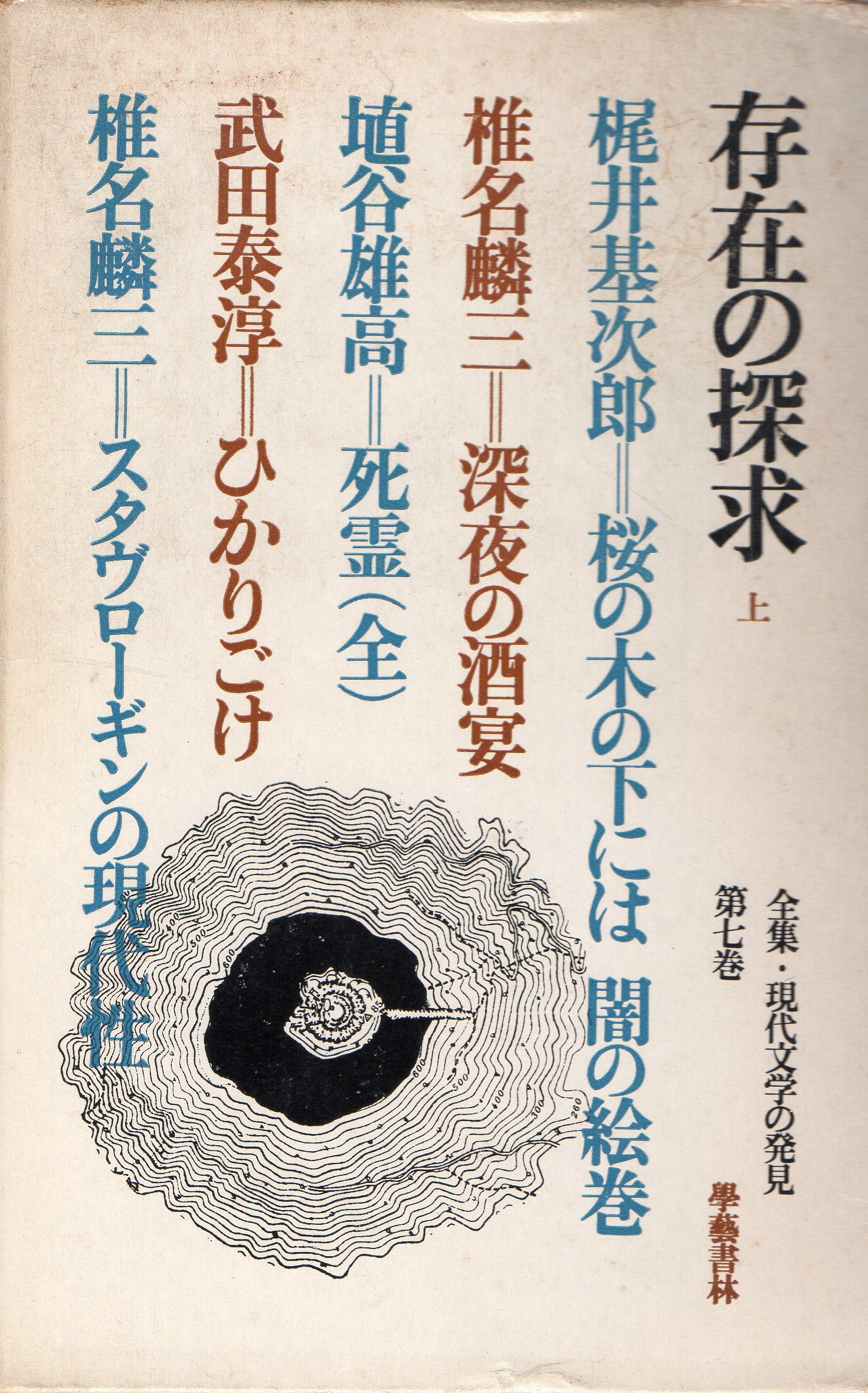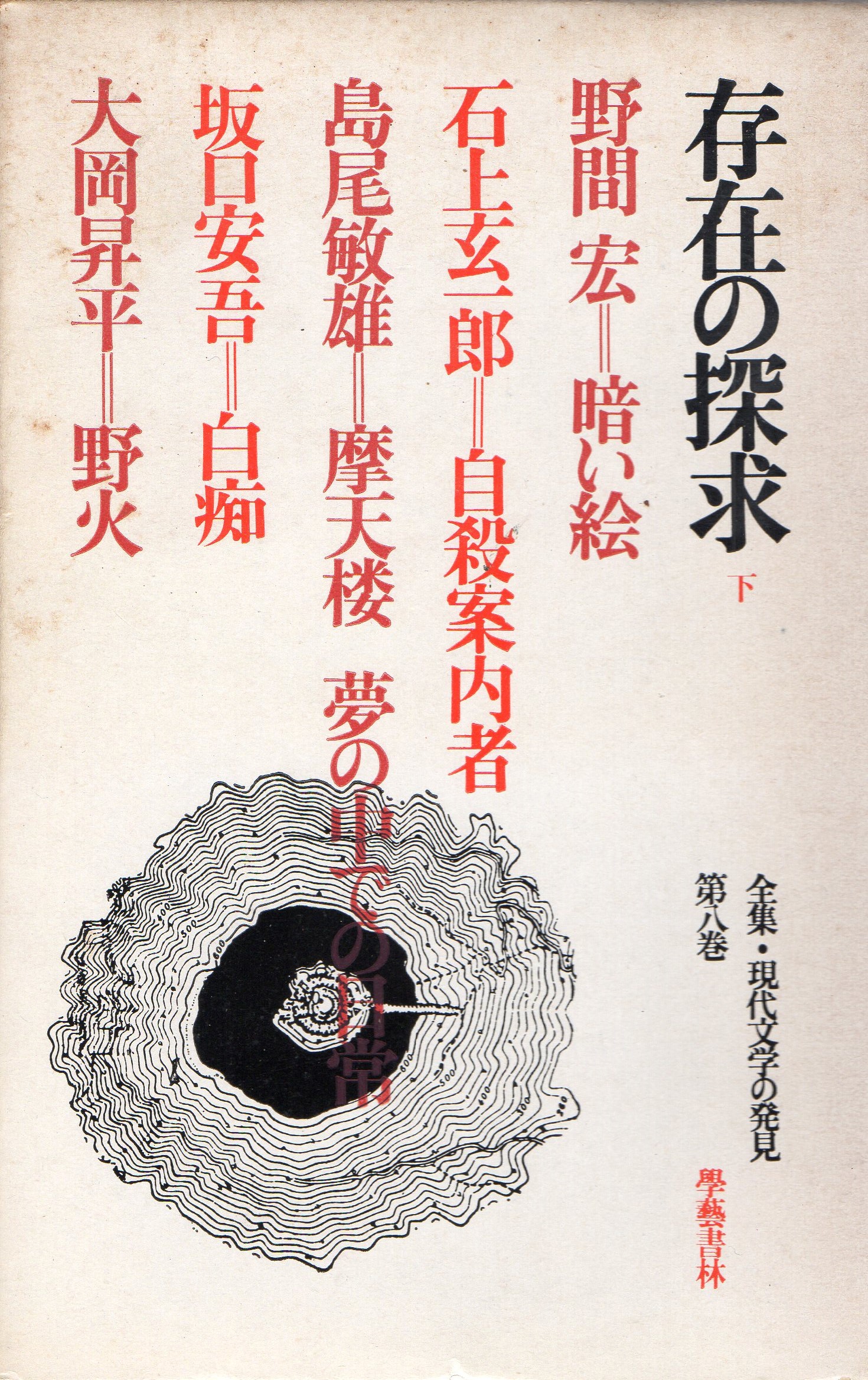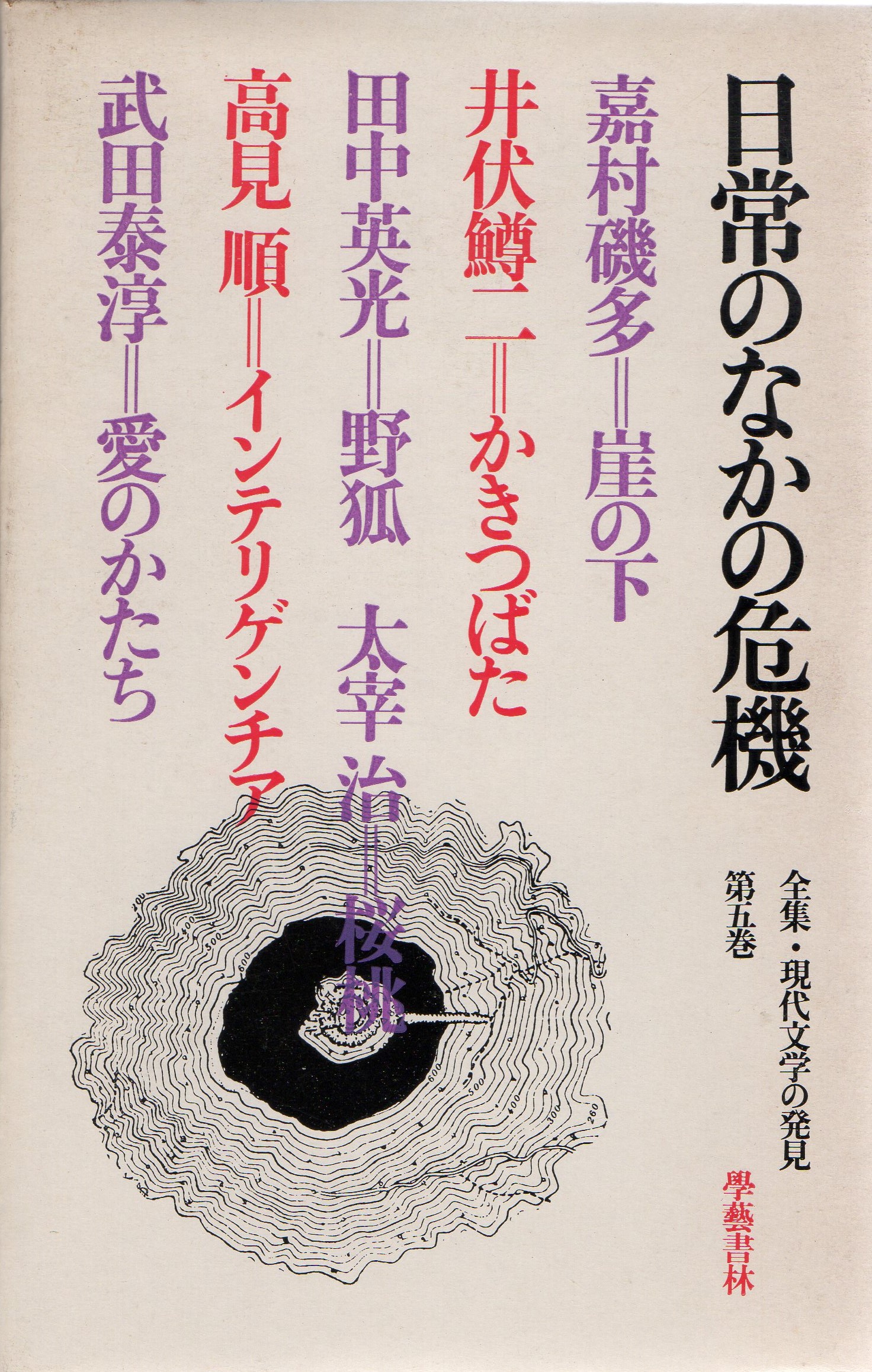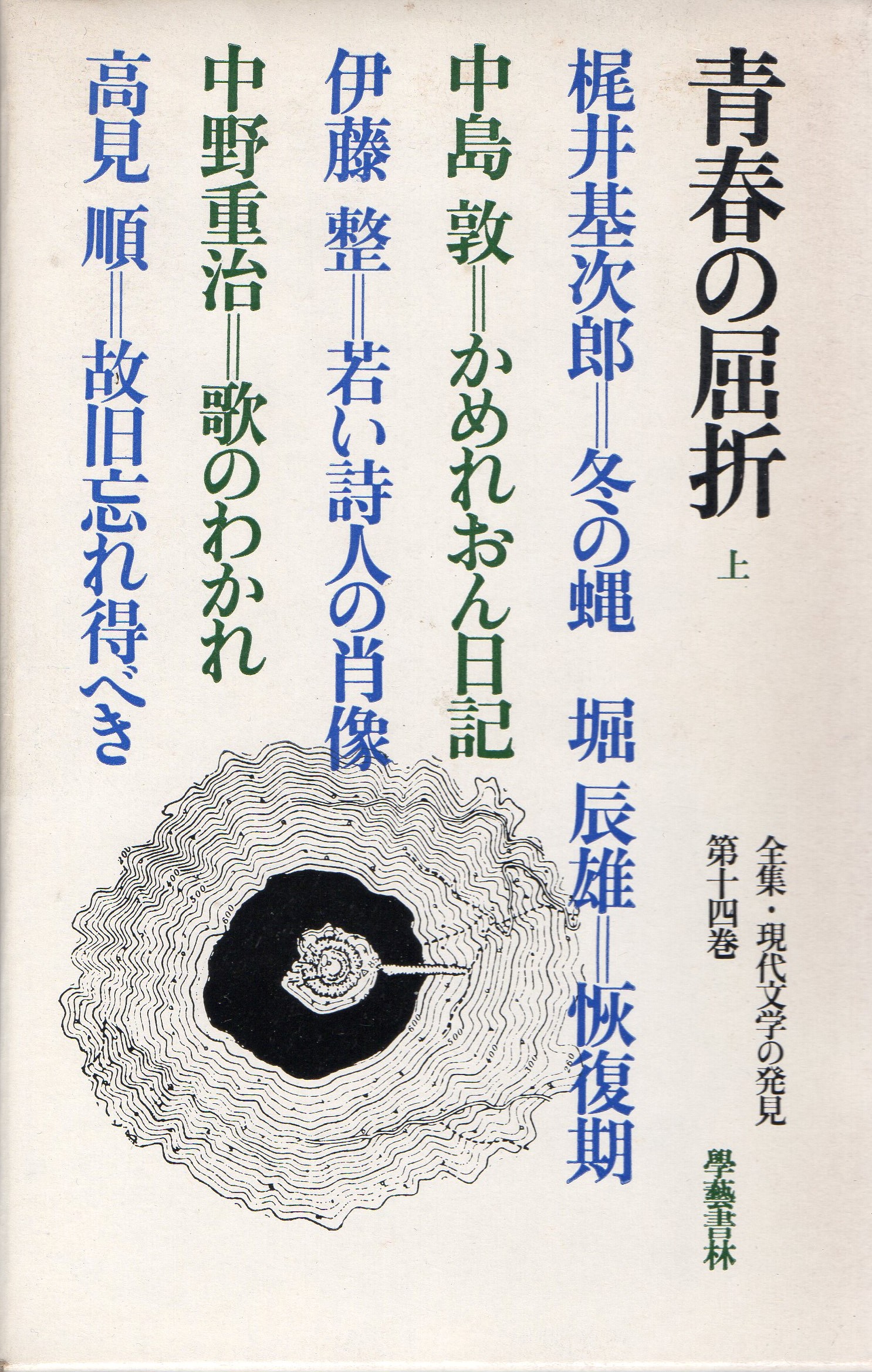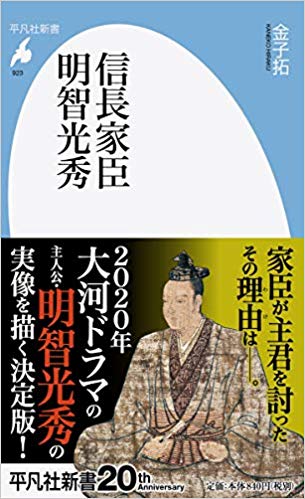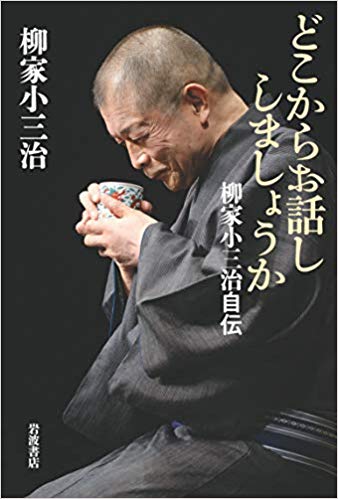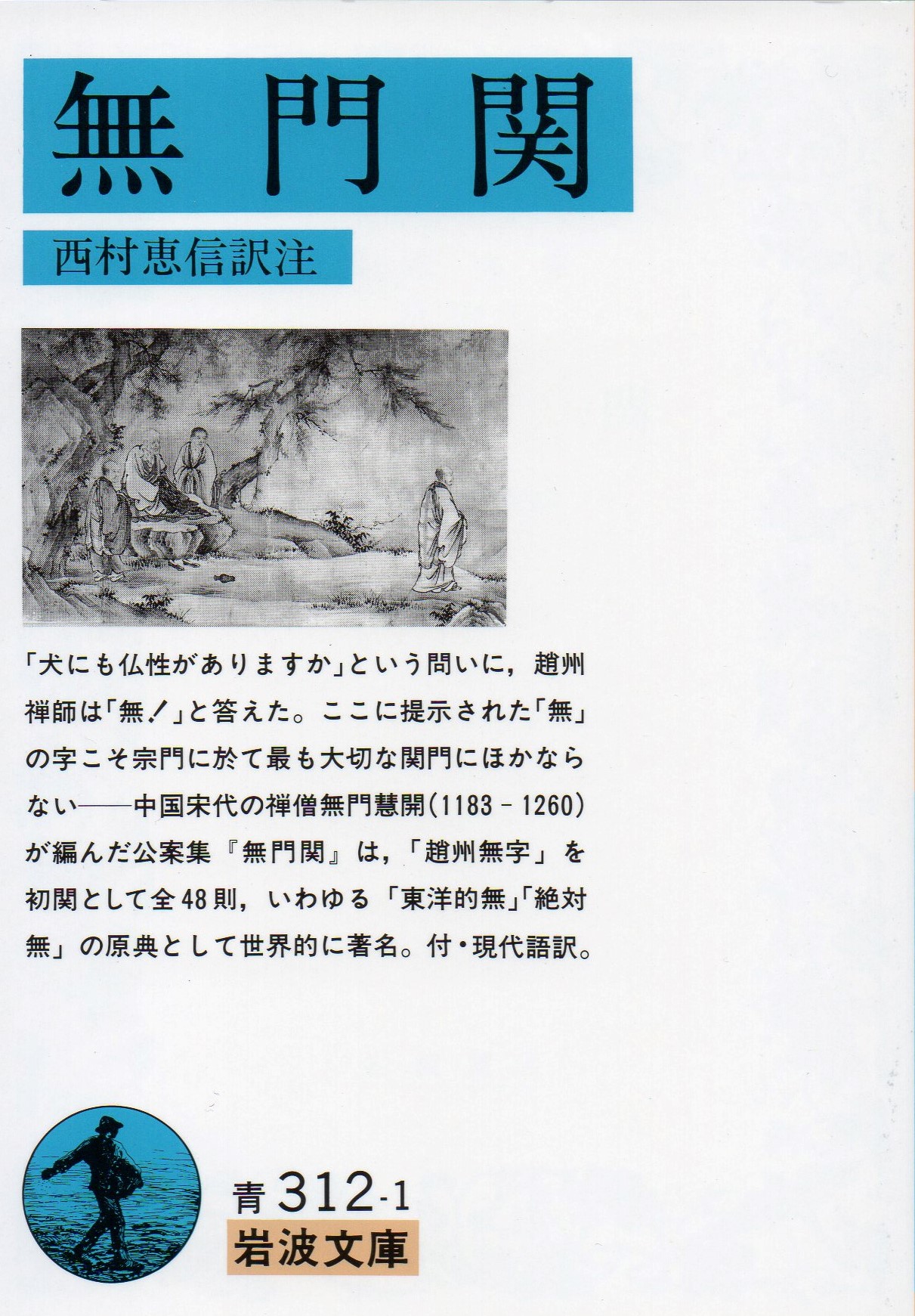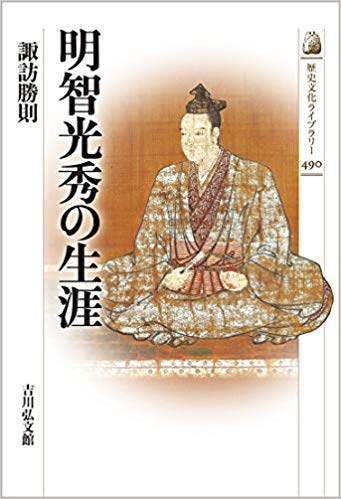|
戦国風景 |
|
西ヶ谷恭弘『復原 戦国の風景―戦国時代の衣・食・住 』を読む。
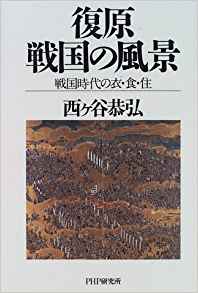
同じ著者(「城の西ヶ谷」といわれるらしい)の,
『城郭』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/463419410.html)
については触れたことがある。本書は,戦国時代を,
武器・戦術,
食文化,
服飾,
風俗・儀礼,
に分けて紹介する。しかし,「城」を外したのはわかるにしても,甲冑,小具足等々の「武具」についての言及がないのは,「戦国の風景」としては,いささか物足りない。それと,連載の寄せ集めらしく,大事なものが抜けていて,些末なところがページが割かれているアンバランスな感じが否めない。個人的には,この時代の地下の人びとの実態,例えば,まだ兵農未分化の時代の村落の,武士と農民の風俗や生活実態を知りたいと思ったが,ほとんど言及がないのは,落胆した。
たとえば,「鑓」の項で,
「鑓は槍,鎗とも記すが,槍は縄文時代の骨角器に代表される狩猟道具として発達したもので,鑓とは異なる。槍はのちに棒術と呼ばれるものに相当する。鑓の祖素形は,長刀で,古代の鉾と中世の剣刀が改良されたものである。」
という記述がある。「槍」と「鎗」は違う,というのは読んだことがある。この記述だけでは消化不良を起こしそうである。別に,
「木篇を用いたのは木の柄のついた武器で,倉が音を表し突く意の衡からきている。鑓は本来は金属の触合う音から来ているから鎗鎗(錚鎗)などと表現したが,日本では槍と同じに用いられた。鑓は繰り出して遣の武器であるから金篇を用いた国字である。その『やり』の当字が『也利』『矢利』である」
とある(日本合戦武具事典)。かつて「槍」「鎗」は,「ほこ(鉾)」と訓ませていたようであるので,「槍」と「鑓」は別物ということになる。ただ,
「槍の本来の用法は鉾と同じで剣突が主であり,手鉾・薙刀のように両手で操作する。しかも突出し,手繰り寄せ,後世は柄が長いので,撲ったり払ったり」
した(仝上)。その鑓は,戦国時代,長柄鑓となる。
「竹鑓にて扣き合ひを御覧じ,兎角,鑓はみじかく候ては,悪しく候わんと仰せられ候て」(信長公記)
織田家では,
三間長柄,
三間半長柄,
が家風となったらしい。次第に戦力の主体が鑓となり,この長い鑓が城の構造も変える。
「谷を利用していない人工の堀幅は,八メートルから一四メートル平均である。(中略)これら空堀数値は,鑓の長さを意識しており,鉄炮はあまり考慮されていないと思える。というのは,籠城戦となった場合,守城軍は,攻城軍に打撃を充分に加えなければならず,堀幅を広くして,いたずらに攻撃をかわしていたならば,兵糧が尽きて陥落するからである。守城軍と攻城軍が相方ともに長柄鑓で穂先を突きあわす距離,鑓二本の長さが,空堀幅の数値と合致するのである。同様なことは,側壁高にもいえ,(中略)(逆井城本丸は)矩高は七・五メートルと長柄の長さで,,堀底に立つ人に攻撃を加える長さに合致するのである」
本書の中で面白いのは,酒に関する部分である。戦国期「柳」は,酒の代名詞であった。柳小路,柳ヶ瀬,柳川,と地名に残る。
「『柳』とは戦国時代には酒の代名詞であった。柳町とは酒の集まる街という意味,柳ヶ瀬とは,酒が陸揚げされる河岸のことである」
とし,この「柳」は,
「日本ではじめての商品名すなわち銘がつけられた『大柳』という酒に由来する」。
そして,著者は,
「この柳酒が清酒であった」
と推定しているのである。
「というのは,戦国期の城や館を発掘して,出土する盃に代表される器をみると,いわゆる濁酒では不必要な陶磁器の模様や,土器の雲母分が強調されて施されているからだ」
しかし,そこまでしか説明がない。「鑓」の説明と同じである。雲母文をまぜてキラキラさせるのは,縄文土器にも見られる。研究書でないにしても,着想をもう少し丁寧に展開してほしい。
参考文献;
西ヶ谷恭弘『復原 戦国の風景―戦国時代の衣・食・住 』(PHP研究所) |
|
自力救済 |
|
仁木宏『戦国時代、村と町のかたち』を読む。
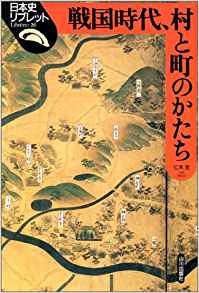
本書は,京都西南の山城國西岡地域と大山崎における,地域住民に視点を置いて,室町末期から織豊期にかけての地域社会の変化を追う。
「従来,重視されてきた領主・百姓や村の『経営』についてはほとんどふれない。そうした視点に立つかぎり,村落や地域社会を再編成するダイナミズムを解明することはむずかしい。むしろ,土豪やその連帯組織が地域においてどのような社会的存在であったかに注目したい。こうした方法が『下から』と『上から』の視点のズレを解消する有効な分析方法であると考えるからである」
という問題意識で,地下人に視点を置く。この場合,地下は,文字通り,在地の土豪を指す。地下(じげ)人は,
凡下,
甲乙人,
重複する呼称で,「凡下」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/463837199.html)で触れたように,地下(人)は,室町末期の『日葡辞典』には,
土着の人,
の意となる。本来五位以下を指したが,そこにも至らぬ公家以外を指し,対に,庶民を指すようになった。武家も,公家から見れば,地下である。しかし武家の隆盛とともに,地下は,
土着の人,
つまり,
地元の人,
という意になった。土豪は,
「在地の数村を支配する小規模の豪族である、地頭やその系譜をひく国人領主の家臣或いは被官たる者で地侍の主筋になる在地領主をも含む概念」
とある。本書の主役は,このレベルの土豪である。
室町末期,室町幕府,それを駆逐した三好長慶政権,織豊政権と,支配層の変遷に伴って,右往左往しつつ,しぶとく生き残っていく。
西岡地域は,
「十四世紀半ば以降,史料にみえる山城國『西岡』地域は,向日市・長岡京市の全域と,京都市南区・西京区,大山崎町の一部からなる。桂川の右岸(西岸)にあたるが,嵐山と松尾社までは含まない。…ほぼ山陰道以南を範囲とし,久我縄手・西国街道に沿った地域にあたる。」
大山崎は,それに含まれず,
「山城國と摂津國にまたがって立地した。(中略)権門の支配からの自立をめざした山崎の住民たちは,十三世紀以降,石清水八幡宮に仕える神人(じにん)の身分を共通して獲得…1392(明徳三)年には,将軍足利義満より,『神人在所』であることを理由に守護不入特権をさずけられ」
たが,大山崎の領域は,円明寺(大山崎町)から摂津の水無瀬川(島本町)までと確定された。この地域は,まさに,後年,東上する羽柴秀吉と明智光秀がぶつかった山崎の合戦の主戦場にも重なる。
大山崎は,
「『神人』という社会的身分をもつ住民によってなりたつ『神人在所』として,その領域を確定した都市・大山崎」
として,油商人,米商人,土倉・酒屋等々の拠点であった。彼らは十五世紀半ば,
惣中,
という自律的組織(「所」と呼ぶ)をつくる。西岡の土豪たちは,連帯組織,
国,
をつくる。国衆と呼ばれるようになるが,それは,時の権力者との関係で,
土豪たちが半済を給付されることで公的な地位を獲得した,
ことによる。ときに幕府や有力武家(細川・畠山等々)の被官として,社会的身分として,
御被官人,
と呼ばれ,軍事動員を受ける立場でもあったのである。しかし,重要なのは,
「土豪たちがみずからを『国』と名乗ったことである。『国』が地域の公権としての立場を示し,自分たちの政治的な正統性を主張する」
に至るのである。
「こうして『国』も『所』も,みずからの領域内の諸問題を自律的に解決する能力を獲得し,構成員からも,外部勢力からも『公』的な存在と認められるようになった。」
こうした戦国的自立性の転機は,織田政権下,細川藤孝が西岡の一職支配を得たことにある。土豪に本領安堵や新恩給与を行ない,それに抵抗した土豪は亡ぼされる。
「藤孝は,信長の家臣として各地を転戦したが,これには西岡の土豪たちも従軍した。」
後に,細川が丹後へ国替えを命じられた折,土豪の中には従わず在地に残ったものが少なくない。彼らは,もはや「国衆」という自律性はもちえず,豪農として生き残っていく。
大山崎も,自立都市堺がそうであるように,織豊政権は,直轄都市として掌握する志向を持ち,
「羽柴秀吉による山崎城築城,大山崎の城下町化による,強力な統制へとつながっていく」。
戦国の終りとは,土豪だけでなく,百姓・町人の,
自力救済,
の剥奪でもある。
参考文献;
仁木宏『戦国時代、村と町のかたち』(山川出版社) |
|
小さな共和国 |
|
蔵持重裕『中世村の歴史語り―湖国「共和国」の形成史』を読む。
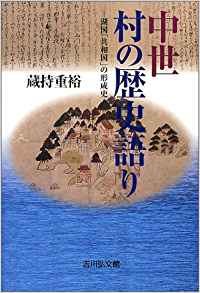
本書は菅浦という,琵琶湖北岸,竹生島の対岸にある,七十戸ほどの小さな集落の「菅浦文書」にもとづく,生き残りの歴史である。この文書は,
「中世の『村の歴史』を書き残した唯一と言ってよい」
史料である。これが残ったのは,
「西北となりの大浦庄と『日差』『諸河』という葛籠尾崎(半島)の緩斜面の耕地を争った」
訴訟を繰り返した,
「死者数・動員軍勢・その組織性・戦術・戦争法(ルール),近隣への影響,費用の大きさから,戦争とでも表現したほうが適当な大騒動であった」
からである。本書は,その「村の歴史」を記した「置書」を読みながら,
「生存をかけて,京と比叡山という中央に関わりを持ちながら,また山と港の湖北地域という社会環境の中で,ひとつの『共和国』を形成して,生き延びた菅浦惣村の姿をあきらかにしよう」
とした。この集落を「共和国」というのは,
「この集落が,乙名を指導者とする行政組織を持ち,在家を単位とする村の税を徴収し,若衆という軍事・警察組織を持ち,裁判も行い,村の運営を寄合という話し合いで進め,そのため構成員は平等な議決権を持つ,自治の村落だからである。」
史料の言葉で,これを,
惣村,
と呼び,
「惣の目的は住民の家を保護することで,平等観念は一揆の原理」
と同じである,という。組織は,大浦との戦いの中で,調えられ,
乙名(20名),中老(2名×東西),若衆,
という年齢階梯組織になっていく。まさに,中世の村の,
自力救済,
という原理の見本であり,
領主−村関係,
の在り方自体が,従来の支配関係ではなく,
契約関係,
であることの見本を見る。つまり,
在地の選択で領主を変更し得る,
ということなのである。菅浦では,
我々為地下改分致奉公之時ハ,年貢ハ可有沙汰事候,
という。つまり,地下(じげ)とは菅浦村民を指す。
「領主が地下のために“奉公”した時は地下は年貢を納めるべきである」
と言い切る。つまり,
「中世の紛争解決の基本は自力救済である…。それはその通りなのであるが,自力の道はリスクが大きいことも認識しているのである。平和確保の“しんどさ”,それが有償でも武士を雇う関係を時に生み出すのである。在地の人々にしてみればそうした保護機能こそ領主に期待した。領主がそれに応えてくれるからこそ年貢も出すのである」。
菅浦は,訴訟に勝つために,複数のルートを確保する。著者は,それは,
「情報ルートの結節点・プロバイダーにアクセスする回路を開いておくことなのだ。したがって,地下からみれは領主を一つに固定する必要はないのである。その例を菅浦は示している」
と喩えている。
「最終的な高家・権門である朝廷・幕府こそ日本のあらゆる地域・階層へのコンタクトをもつ家・機関であり,国家とはそうしたコトなのである。どこの誰と紛争を起こそうと,情報ルートさえあればともかくも平和への糸口があるのである。領主−地下・領民という上下の支配関係とは結局こうした『頼み』の関係の固定・定期契約なのである」。
こうした訴訟は,金がかかる。結局,
訴訟経費は二年で二百貫文,
地下兵粮五十石,
酒代五十貫文,
「此入目ニ五六年ハ地下計会して借物多く候也」
と「置書」は書く。著者は,
「この経費は,手に入れたもの=日差・諸河の田地に見合うのであろうか。」
と問う。
ただここで,一貫文 = 一石としている概算はちょっと疑問だ。たとえば,
1貫文 = 2石(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AB),
とすると倍だし,
「一貫を米五石とする」(日本戦陣作法事典)
とすると,五倍になる。
「貫高を石高に換算すると全国的に1貫文=2石であったが、一部の地域では差異があり、江戸時代も貫高制を続けた仙台藩では1貫文=10石であった」
となる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AB%E9%AB%98%E5%88%B6)と,十倍になる。まあそれを勘案するとして,著者は,こう結論する。
「菅浦の負担する年貢は応永年間(1394−1428)以降,年に二十石・十貫文,他に麦・枇杷等で推移する。文安三年(1446)当時京都での和市(わし)は一石当たり九八六文であったという。ほぼ一貫文と考えると,米錢合わせ年貢は三十貫文になるから,トータルで三百貫文(二百貫文+五十石+五十貫文)の経費は年貢十年文であった。訴訟費用だけで約七年間分である。これを騠いと見るかどうかである。菅浦は採算を見てとったはずである。だからこそ戦った。」
と。
参考文献;
蔵持重裕『中世村の歴史語り―湖国「共和国」の形成史』(吉川弘文館) |
|
帰農した土豪 |
|
牧原成征『近世の土地制度と在地社会』を読む。

本書は,
「近世の百姓たちは,いかなる社会構造や諸条件の中で,それらにいかに規定されて,どのように再生産や生活を成り立たせていたのだろうか。本書はこうした素朴な問題関心から出発しているが,土地制度や金融・流通,共同体などの観点から,近世の在地社会について」
の考察をしている。その主張の素描は,
「中世後期,(中略)多くの土地片で,地主と作人が分離して,前者が後者から加地子(カジコ,カジシ 地代)を収取する関係が一般化していたと考えてよい」
「地主権(加地子)や名主得分を集積した階層は,(中略)抗争・戦乱の中でその土地所有を維持・拡大するために,被官を従え,戦国大名などのもとに被官化(結集)した。これは戦国社会の基底的な動向であり,彼らを『小領主』と呼ぶことができる」
「16世紀の江北地域では,戦国争乱が激化し小領主が滅亡したり牢人したりするなかで,彼らのもとで制約されていた作人の土地に対する権利が強まった(一職売券の出現)。それによって土地を家産として継承するイエが,作人レベルにおいて成立しはじめた」
「江北の一大名から出発・成長した豊臣政権は,領主(給人)が収穫高の三分の二を年貢として収取するという理念を示し,また検地を広範囲に行なって地積掌握を深化し,加地子を吸収した高額の年貢・分米を打ち出した。村にとどまった旧小領主(地主)は百姓身分とされ,それまで得ていた中間得分・剰余をかなりのていど否定された。加地子得分権の形で留保されていた惣有財産も同様である。こうした点では領主『反動』と評価することもできる。しかし一方で,年貢収取に際して,百姓に収穫高の三分の一の作得を公認・保障し,…江北でようやく16世紀に萌芽・展開しつつあった作人レベルにおける土地所持権を,検地の結果,公認・保障する姿勢を示した」
「そのようにして成立した近世の年貢村請制の下では,農業経営の集約化という生産力条件にもよって,村=百姓たちは,一定数以上の経営を維持することを要求された。そのため百姓相互の融通関係が必然化され,そのなかから土地を集積する地主が出現する場合があった。彼らは村請制と小農経営の展開に基礎をおき,それに規定される点で『村方地主』という範疇で捉えるのが適当である」
等々と,在地の土地制度と社会の変化を描こうとしている。
僕個人の関心は,土豪,地侍という在地の有力層が,国人や戦国大名の被官となった後,豊臣政権の政策で,徳川家康が,三河・遠江から関東へ家臣まるごと移封されたように,被官化した土豪・地侍が,鉢植えのように転封される大名に従わず,在地に残った場合,その後,幕藩体制下で,どのような変化を蒙ったのか,という点にある。いわゆる兵農分離に従わず,在地に残った旧大名被官たちは,百姓身分になるが,村ないし,その地域に大きな影響力を保っていたはずである。
そのひとつの転機は,太閤検地である。検地では,
「一筆ごとに年貢を負担すべき責任者,請負人(百姓)を一名書き載せる」
が,
「あらゆる土地片で唯一単独の所持者・所持権が定まっていたわけではなく,太閤検地開始時にも依然として,地主と作人とが加地子収得関係などを結んでいた土地片もあった。そうした地主・作人関係は,作人から得分を収取するだけで年貢も作人が直納するといった作人の権利が強いケースから,一年季契約による小作関係のように地主の権利が強いケースまで,非常に個別的で多様であった。前者では作人が名請されるのが自然であるが,後者(一年季小作)の場合,地主がその土地を名請しようと望めば,小作人が容易に名請しえたとは考えにくい。この点で,直接耕作者を一律に名請したとする見解には無理がある。ただし,侍身分の地主たちがみずから名請しようとしたかどうかは問題である。検地で名請することは百姓になることを意味するのだから,あくまで仕官をめざし,名請しようという志向をもたないか,あるいは名請を拒む者もいた」
その結果,
「検地帳に名請した者には,年貢諸役負担と引き換えに,その土地の所持権が保障・公認されることになった」
石田三成の掟条条(文禄五(1596)年)には,
「田畠さくしきの儀は,此のさき御検地の時,けんち帳にかきのり候者のさハきにつかまつり,人にとられ候事も,又むかし我さくしきとて人のとり申事も,ちやうしの事」
とあり,土地の実質所有が移ることになる。その結果,かつての土豪の中には,土地を取り戻そうとし,敗訴する例も少なくなかった。
「検地帳名請の意義は大きく,被官たちのなかには,井戸村氏(旧土豪)が土地所持権を確認しようと迫った際にも拒否する者もむ現れた。訴訟の際にも,名請と代々の所有を根拠にしとて自己の所持権を主張し,それを勝ち取ることもあった」
のである。公儀レベルの理念としては,
「検地帳名請人に所持権を認めるのが原則であった」
からである。結果として,
小農自立,
がもたらされたが,その結果,「高持百姓」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/464612794.html)で触れたように,
「近世の土地台帳である検地帳や名寄帳,あるいは免割帳などに記載された高持百姓あるいは本百姓のち所持石高や田畑の反別が一石未満,また一反未満を中心に零細な百姓が圧倒的に多い」
こととなり,一年の決算毎に質屋を利用して,
「不勝手之百姓ハ例年質物ヲ置諸色廻仕候」
というように,それは,
「春には冬の衣類・家財を質に置いて借金をして稲や綿の植え付けをし,秋の収穫で補填して質からだし,年貢納入やその他の不足分や生活費用の補填は再度夏の衣類から,種籾まで質に入れて年越しをして,また春になればその逆をするという状態にあった」
ことの反映で,
「零細小高持百姓の経営は危機的であった」
近世慢性的に飢饉が頻発した背景が窺い知れるのある。
五反百姓出ず入らず,
という諺がある(臼田甚五郎監修・ことわざ辞典)。五反でトントンの意である。それ以下は,危険水域なのである。
近世の飢饉については,
「飢饉」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/462848761.html),
で触れた。
参考文献;
牧原成征『近世の土地制度と在地社会』(東京大学出版会) |
|
発掘 |
| 大岡昇平他編『孤独のたたかい(全集現代文学の発見・別巻)』を読む。
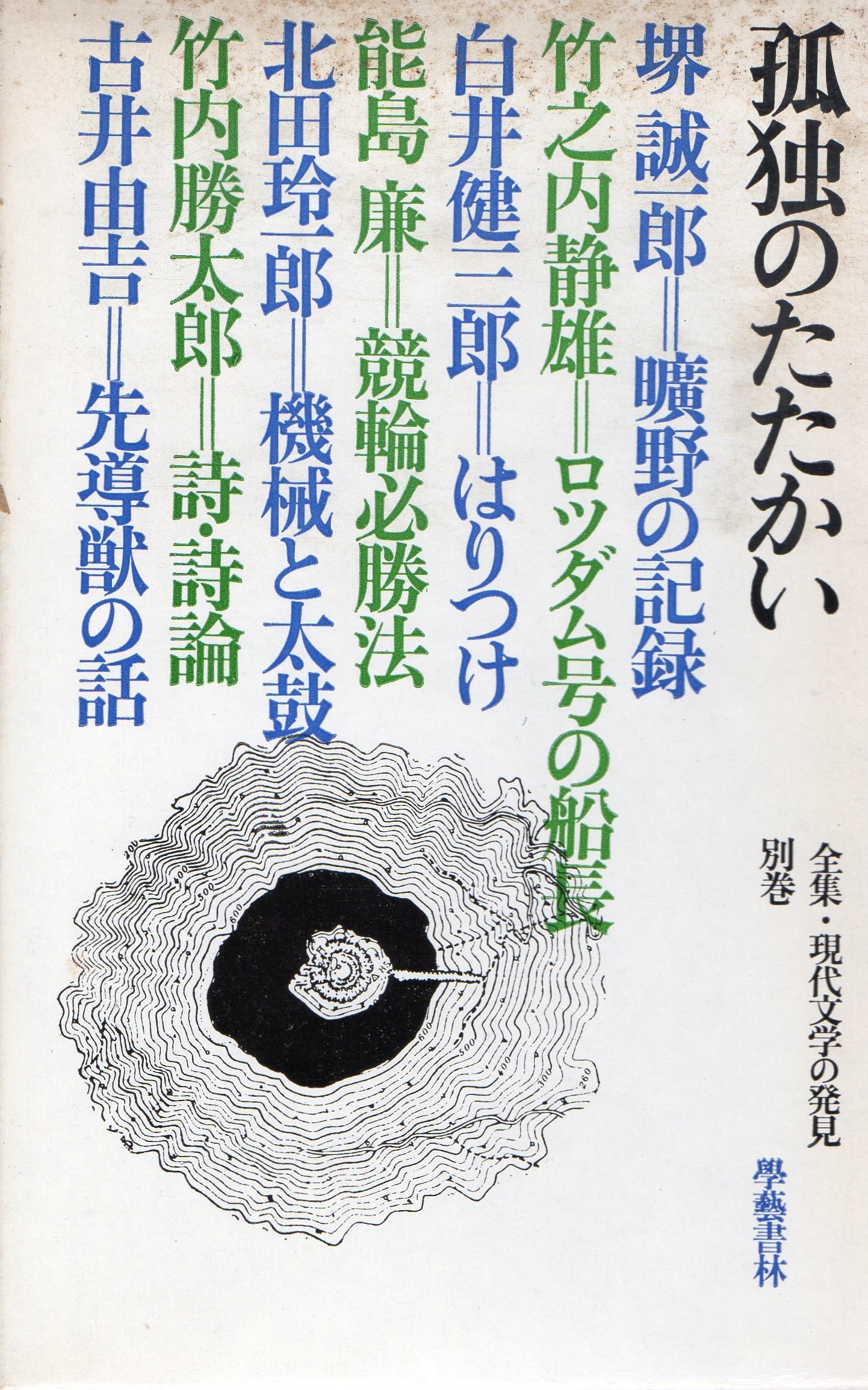
半世紀も前の,昭和四十年代にまとめられた,
現代文学の発見,
と題された全16巻の別巻としてまとめられたものだ。この全集自体が,過去の文学作品を発掘・位置づけ直し,
最初の衝撃,
方法の実験,
革命と転向,
政治と文学,
日常の中の危機,
黒いユーモア,
存在の探求,
性の追求,
証言としての文学,
日本的なるものをめぐって,
歴史への視点,
言語空間の探検,
青春の屈折,
物語の饗宴,
と,テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーで,この時代の文学市場もあるが,編集者,文学者の知的レベルを彷彿とさせるものだ(全集の責任編集は,大岡昇平,埴谷雄高,佐々木基一,平野兼,花田清輝。編集は,別巻の解説を書く,八木岡英治)。その別巻として,「埋もれたるものの巻」として,多ぐの人々の推薦を得た中から,選ばれた作品集になっている。ほぼ無名の人が多数を占める(このための公募作品の帯正子「可愛い娘」をのぞくと)。今日,名を残すものは数少ない。むしろ編集者(竹之内静雄・堺誠一郎・能島廉),サルトルなど実存主義の翻訳で知られる学者(白井健三郎),司法書士(北田玲一郎),大学教授(田木繁),政治家(犬養健)等々と,詩人(竹内勝太郎・秋山清・荒津寛子)を別にすると,作家として生きた人は少なく,その中に,まだ当時同人誌に作品を発表していた古井由吉が入っている。確か,発売当時読んでいるはずである。読んでいるが,半世紀近く前なので,ほぼ記憶にない。覚書が書き込まれていたり,線が引かれているが,その意味さえ覚束ない。初めて読むのと同じである。
いま思えば,僕には,無名の古井由吉が入っていることが奇跡に思える(『杳子』で芥川賞を受賞するのは二年後のことになる)。八木岡は,その選を,
「文句のない作品である。送ってもらった同人誌『白描』の中から飛びついて来た。それぐらい際立っていた。作品が読者の内部に掻き立て,引き出してゆく想像力というものが,豊かで快い」
とし,
「これはまだ出来たての作品で,これから評価をかちとり,時流に乗っていきそうに思える。ここに取りあげなくても,という意見もきかれたが,逸する気にはなれなかった」
と書く。編集者の慧眼である。そして,
「自己はここでは個であることをやめ,群衆の中に拡散され,雨滴となって飛んでいる。肉質を失い,現代というおそろしいものを運動においてとらえるための装置と化している。しかし作者は物質化されているように見えながら,ちゃんと元の場所静かな眼をひらいている。すべてのことは作者の内部でおこっている」
と古井由吉のスタイルを見ぬいている。
「スタイルというものが形ではなく,内的必然の掘進でありその軌跡であることが,ここによく示されている」
と。この内的運動は,処女作『木曜日に』の,
「それは木目だった。山の風雨に曝されて灰色になった板戸の木目だった。私はその戸をいましがた、まだ朝日の届かない森の中で閉じたところだった。そして、なぜかそれをまじまじと眺めている。と、木目が動きはじめた。木質の中に固く封じこめられて、もう生命のなごりもない乾からびた節の中から、奇妙なリズムにのって、ふくよかな木目がつぎつぎと生まれてくる。数かぎりない同心円が若々しくひしめきあって輪をひろげ、やがて成長しきると、うっとりと身をくねらせて板戸の表面を流れ、見つめる私の目を眠気の中に誘いこんだ。」
という内的運動に通じ,芥川賞受賞作の『杳子』の冒頭ともつながっていく。そこでは,二人の見方が重なり,対立し,重ねられていく相互運動が,語られる。
「女が顔をわずかにこっちに向けて、彼の立っているすこし左のあたりをぼんやりと眺め、何も見えなかったようにもとの凝視にもどった。それから、彼の影がふっと目の隅に残ったのか、女は今度はまともに彼のほうを仰ぎ、見つめるともなく、鈍いまなざしを彼の胸もとに注いだ。気がつくと、彼の足はいつのまにか女をよけて右のほうへ右のほうへと動いていた。彼の動きにつれて、女は胸の前に腕を組みかわしたまま、上半身を段々によじり起して、彼女の背後のほうへ背後のほうへと消えようとする彼の姿を目で追った。
女のまなざしはたえず彼の動きに遅れたり、彼のところまで届かなかったり、彼の頭を越えて遠くひろがったりしながら従いてくーきた。彼の歩みは女を右へ右へとよけながら、それでいて一途に女から遠ざかろうとせず、女を中心にゆるい弧を描いていた。そうして彼は女との距離をほとんど縮めず、女とほぼ同じ高さのところまで降りてきて、苦しそうに軀をこちらにねじ向けている女を見やりながら、そのままあゆみを進めた。
その時、彼はふと、鈍くひろがる女の視野の中を影のように移っていく自分自身の姿を思い浮かべた。というよりも、その姿をまざまざと見たような気がした。
(中略)彼は立ち違い舞った。足音が跡絶えたとたんに、ふいに夢から覚めたように、彼は岩のひろがりの中にほっそりとたっている自分を見出し、そうしてまっすぐに立っていることにつらさを覚えた。それと同時に、彼は女のまなざしを鮮やかに躯に感じ取った。見ると、荒々しい岩屑の流れの中に浮かぶ平たい岩の上で、女はまだ胸をきつく抱えこんで、不思議に柔軟な生き物のように腰をきゅうっとひねって彼のほうを向き、首をかしげて彼の目を一心に見つめていた。その目を彼は見つめかえした。まなざしとまなざしがひとつにつながった。その力に惹かれて、彼は女にむかってまっすぐ歩き出した。」
後の古井由吉を知る者にとって,当時の編集者の慧眼と見識にただ驚倒させられるばかりである。その他,掲載候補の中に,小川国夫『アポロンの馬』,丸谷才一『笹まくら』,秋山駿『想像する自由』,佐江衆一『無邪気な狂気』等々が入っていたらしい(月報)。
「『埋もれたるもの』の巻を編むに当たって,非情にも,今日われわれに資すること篤きもの,という規準に合わせて選択し,歴史的顧慮をふくめなかった。はずれるものはすべてスこれを捨てた。われわれは今日生き今日考えねばならぬ。博物館をここに建てるわけではない」
と,編集者八木岡氏は「この本のなりたち」で書く。しかし,それなら,埋もれたものは,過去ではなく,そのときの「いま」埋もれているものを見つけるべきではなかったか(編者の同時代と,読者の同時代は異なるのでやむを得ないかもしれないが)。過去の中に,未来はない。本書に掲載された竹内勝太郎が,
「詩でも絵でも,吐き出すことに意義がある。出してしまえば,捨てて省みない。」
と書く如く,書いた時,作家はそこにはいない。とすれば,過去に「埋もれている」ものではなく,いま,機を待つものを掘り出すべきではなかったのか。しかし,全集自体が過去の文学作品を発掘・位置づけ直すという意図に立つ以上やむを得ないのかもしれない。僕には,皮肉にも,戦前の,
堺誠一郎『嚝野の記録』
犬養健『明るい人』
よりは,その時に無名に近かった,
古井由吉『先導獣の話』
浅井美英子『阿修羅王』
の方が光って見える。
参考文献;
大岡昇平他編『孤独のたたかい(全集現代文学の発見・別巻)』(學藝出版)
http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm#%E8%AA%9E%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96 |
|
光秀 |
| 渡邊大門『明智光秀と本能寺の変』を読む。
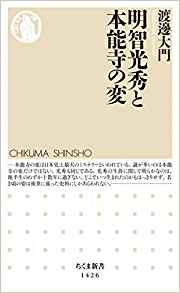
来年の大河ドラマの主人公だけに,これから柳の下を狙う類似本が一杯上梓されるだろう,おそらくその嚆矢か。しかし本書はその種の際物ではない。
「本書は光秀の生涯を軸としながら,信長,足利義昭,朝廷などの動向を交えつつ,本能寺の変に至る経過および結果」
を述べているが,その根本姿勢は,一次史料(古文書−書状など,記録−日記など)を重視し,二次史料(軍記物語,系図,家譜など)を副次的に扱う。
「二次史料を使用する際は,史料批判を十文に行う必要がある」
とする。なぜなら,
「こと本能寺の変に関しては二次史料への批判が甘く,特に歴史史料に適さない二次史料であっても『この部分だけは真実を語っているはずだ』という思い込みで,安易に使用されるケースが散見される」
からである。明智光秀の出自を,土岐明智の流れを汲むとする見方がある。しかし,身分が高い,例えば,
幕府の随分衆,
あるいは,
幕府の奉公衆,
であるとする史料はない。あるのは,
「『明智なる人物が『光源院殿御代当参衆幷足軽以下衆覚』に『足軽衆』として記載されて」
いることであり,しかも,
「『光源院殿御代当参衆幷足軽以下衆覚』は,足利義輝の時代の奉公衆のなどの名簿と考えられていた。しかし,,近年の研究により,前半部分が義輝段階のもので,後半部分が義昭段階のものであることがあきらかになった」
のである。この「明智」は,
「当該期に明智姓の者が光秀以外に候補がいないことを考慮すると,やはり光秀とみなさなくてはならないだろう」
とされる。光秀初見文書が確認できるのは,この後半部分の成立の一,二年後,永禄十二年(1569)二月十九日である。
実名が記されていないほど,ほぼ無名であったと見られる。足軽とは,
普段は雑役を務め、戦時には歩兵となる者。弓組・鑓組・鉄炮組などの諸隊の歩卒,
つまり,かなり身分が低い。光秀が小栗栖で一揆に殺されたとき,
「惟任日向守ハ十二日勝竜寺ヨリ逃テ、山階ニテ一揆にタタキ殺サレ了、首ムクロモ京ヘ引了云々、浅猿々々、細川ノ兵部大夫ガ中間にてアリシヲ引立之、中國ノ名誉ニ信長厚恩ニテ被召遣之、忘大恩致曲事、天命如此」
と,多聞院日記英俊(えいしゅん)は冷笑するように、切り捨てた。「中間」とは,武家奉公人のうち,地位の高い者を,
郎党(郎等)、
その下に,
若党(わかとう)、
悴者(かせもの),
がいる。若党は、主人の側近くに仕えて雑務に携わるほか、外出などのときには身辺警固を任とする。悴者(かせもの)は賤しい者の意で、姓をもつ侍身分の最下位。この下に,
中間、小者、あらしこ、
といった武家奉公人がいる。足軽は,中間よりはましで,姓をもつ。しかし,下層の武士である。
光秀の初見文書は永禄十二年の,村井貞勝らとの連署奉書である。以降光秀は急速に出世し,元亀二年(1571)までには,大津の宇佐山城を与えられ,歴史上に名を刻み始める。
本書の結論は,
「本能寺の変後の光秀の右往左往ぶりをみれば,とても政権構想や将来構想があったとは思えず,突発的な単独犯と言わざるを得ないのである。現段階おける一次史料からは,少なくとも黒幕うの存在を裏付けるものがない」
としている。当たり前の結論かと思う。変後,細川藤孝に三カ条の覚書を送り,藤孝の助勢を乞うているが,光秀自身,
不慮の義,
と書いている。計画的ではなく,咄嗟の思いつきであったことを白状している。
足利義昭黒幕説,
があるなら,毛利の鞆にいた義昭の動きを知らず,秀吉と和睦するはずはない。
朝廷黒幕説,
四国政策の転換,
怨恨説,
等の諸説を,史料と研究成果を踏まえつつ,ひとつひとつつぶしていく。
「光秀はなぜ本能寺の変を起こしたのか。さまざまな黒幕説が成り立たない以上,現段階の結論としては,光秀の単独犯ということになる。光秀の単独犯といえば,『つまらない結論』ということになるが,前提として言えることは,光秀が信長に対して何らかの不安や不満を抱いていたのは確かである」
それは,どこか摂津一職支配を委ねられた荒木村重の謀反を思い起こさせる。
「信長は軍功を挙げた者には恩賞で報いるが,そうでなければおしまいである。光秀がその重圧に耐えることは,非常に苦しかったと推測される。従来の二次史料に基づく不安説は誤りであるが,実態に即した信長や光秀の関係を勘案すると,光秀は将来に漠然とした不安を抱いていたことは容易に想像される」
村重も,光秀も,外様であった。
それにしても,光秀の変後の行動は,悠長である。
六月二日の変当日から,ほぼ九日まで安土にとどまり続けている。細川父子(藤孝・忠興),筒井順慶の参陣に拘泥し,十日には洞ヶ峠に出向いて順慶を待つ。黒幕がいるなら,この間動きがあるはずだが,まったくなく,落胆したように下鳥羽へ下り,そこに本陣を設置するのが,十一日である。既に,秀吉は,六日姫路に達し,九日には姫路を立ち,十一日には尼崎に達し,翌十二日には摂津富田に着陣している。その動きを,光秀はほとんど摑んでいない。翌日,両軍の間に小競り合いが生じている。既に,戦いの帰趨は決していたと思われる。とうてい光秀に事前に周到な準備があったとは思えない。
参考文献;
渡邊大門『明智光秀と本能寺の変』(ちくま新書) |
|
幕藩体制の確立 |
|
藤野保『新訂幕藩体制史の研究―権力構造の確立と展開』を読む。
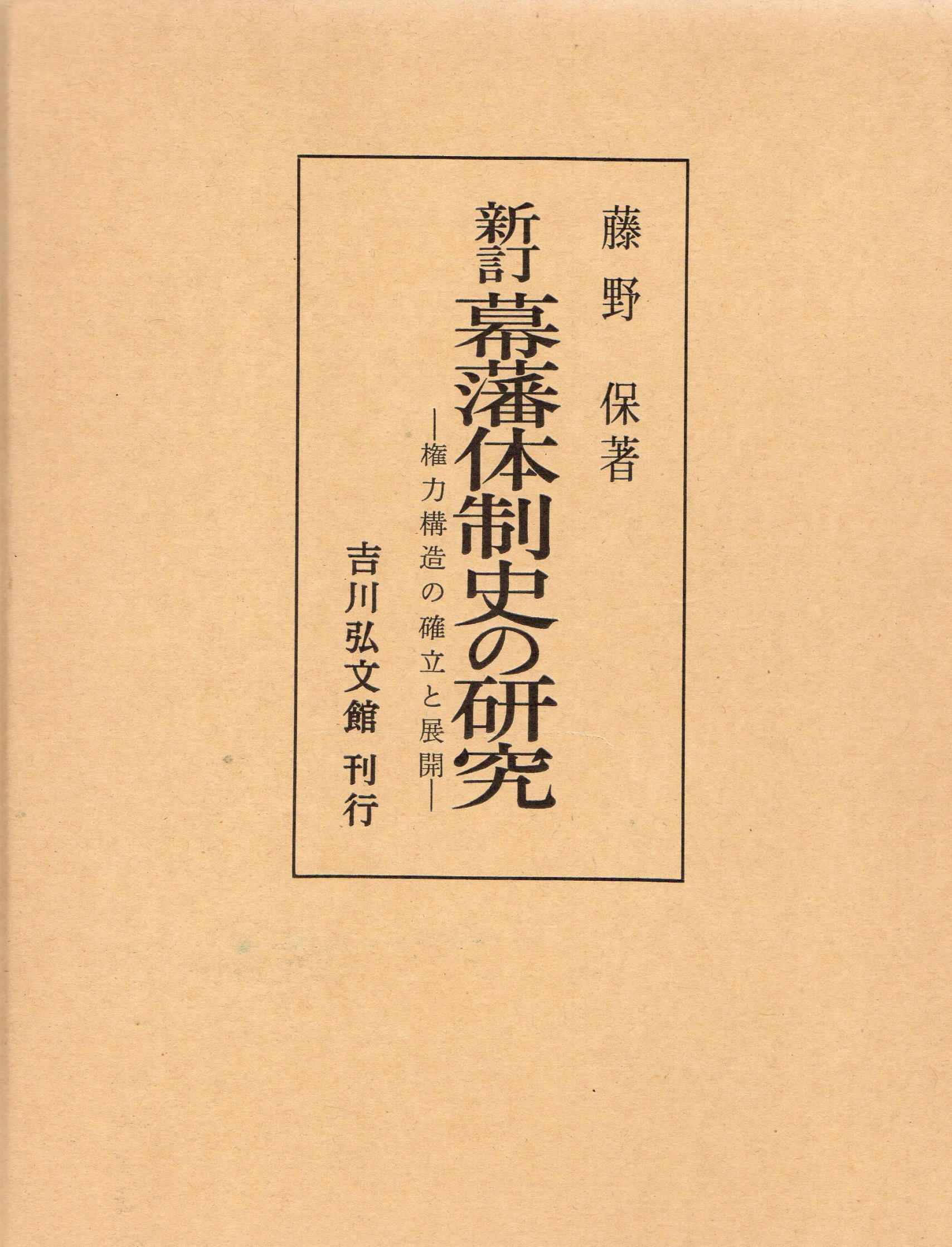
徳川にとっての故地三河,遠江・駿河から,秀吉によって,旧北条領地へ移封されて以降,関ヶ原,大阪の役を経て,幕藩体制を確立していくプロセスを,家康―秀忠―家光―家綱―綱吉―家宣―家継,と初期三代と,その一門の将軍から,紀州から入った吉宗までを,精緻にたどった大著である。
本書は,中村孝也『徳川家康文書の研究』中の,
「寛政重修諸家譜を逐一検討するだけでも,関東入国当初における諸将士分封の状況は一層明らかになり,徳川氏家臣団の成立過程・その性格・その構成などを知ることができると思ふけれども,今は其の暇がない。よつてただその志向だけを記しておく」
という言葉を導きに,各藩別の家臣団の成立過程を検討してきた著者が,それを徳川家に当てはめ,
徳川幕藩体制の綜合研究,
に足を踏み込んだ,研究成果である(はじがき)。そして,本書の狙いは,第一に,幕藩体制成立の基礎過程として,
「一方において,太閤検地等の基礎過程に関する豊かな個別研究の成果の上にたって,これを太閤検地施行段階および幕藩体制第一段階における政策構造との有機的関連のもとに統一的把握を試みるとともに,他方において,検地帳が存在する当該地域の検地施行者たる,あるいは個々の幕藩法令を発布する幕府権力および相互に政治条件が異なり,かつ一定の独自性を有する個別大名権力を幾つかの段階に区分しつつ,具体的分析を行なうことによって,権力と政策構造および政策施行の結果を示す小農民の存在形態を総合的に理解し,さらに幕藩体制第二段階への身通しをたてようとするものである」
とする。第二段階とは,吉宗の時代が,各藩の定着にともない,分権化がすすみ,幕藩体制の転換点と目されることをいっている。
さらに,本書は,幕藩体制成立の政治過程として,
「戦国大名徳川氏が近世大名へと発展し,さらに全国統一者として,あるいは前史として徳川氏自身の三河以来の発展過程を追及するとともに,徳川氏の覇権確立以降のいわゆる幕政史においては,徳川幕府権力の拡大過程が,実は徳川一門=親藩・譜代大名の創出・増強の過程であるという理解の上にたって,徳川幕府権力拡大の各段階に応じて,それら徳川系譜大名の創出・増強の過程を,徳川幕藩体制確立との関連において詳細に検討し,かつ幕府機構の整備過程を幕閣内部の権力後世を通じて分析し,各段階における幕政の意義・内容を究明しょうとする」
徳川一門=親藩・譜代大名の創出・増強の過程と表裏一体なのは,改易・転封であるが,それは,
「一方において,幕藩封建社会における封建的ヒエラルヒーの形成が,将軍の大名に対する。大名の家臣に対する圧倒的優位という形で出現する事態を具体的に検討し,終局において幕藩領主的土地所有権が将軍へ帰属する事態を明らかにするとともに,他方において,この編成原理が将軍の外様大名に対する改易・転封を通じて遂行される徳川一門=親藩・譜代大名の全国への転封・配置という形で現象する事態を明らかにしつつ,それが徳川幕府権力拡大の各段階に応じて,具体的に如何なる形をとりつつ如何に遂行されるかを精密に検討し,かつそれを通じて幕府と諸大名が『幕藩体制』のなかで如何に定位せしめられるか,大名類別(旧続大名・織豊大名・親藩・譜代大名)に全国的展望を試み,それが諸大名の土地所有構造および7発展段階差に如何なる影響をおよぼしたかについて」
解明している。いわば,殆どの大名が,植え替え可能な鉢植化するということは,大名家臣もまた,主の転封にともなって鉢植化していくことを意味する。その移封・転封を通して,豊臣体制から,漸次織豊系大名が消され(改易),かわっって,一門が配置されていくことになる。
更に,幕藩体制成立に伴う,流通過程についても分析をし,
「第一に,徳川幕藩体制の確立過程を貨幣の統一・確立の視角から問題とし,戦国大名の貨幣鋳造に系譜を引く近世大名の独自の貨幣鋳造および領内流通,その結果としての独自の領内地域市場が,幕府の貨幣鋳造の独占による統一貨幣の流通によって,漸次それに代位され,その結果,幕府の掌握する全国市場に連携していく過程として把え,これを農民的貨幣経済の前進のなかで把握し…,藩の再生産構造から追求し,第二に,徳川幕藩体制確立との関連において領主的商品流通機構を問題とし,(一)諸大名城下町の形成過程についての全国的展望を試みつつ,これを幕藩領主的土地所有の展開の視角から分析して,その地域差と分業関係の進展度を明らかにし,(二)特に地域差については,譜代小藩(非領国型)と外様大名(領国型)を具体的に比較検討しつつ,(中略)統一権力との対応関係から分析し,さらに近世大名領相互の地域差・発展段階差から,全国諸藩の再生産確保条件の相違と全国市場に対する対応の仕方を追及し,第三に,幕府の都市および門閥商人に対する諸政策を検討しつつ,貿易・市場をめぐる幕藩間の対抗関係
を追及し,鎖国を契機として諸藩の再生産確保条件が,幕府の流通機構に従属せしめられていく過程を明らかにしょとする」
と,その狙いは,権力構造成立過程を中心に,農民政策,流通政策にまで及ぶ。
その過程の分析は,著者自身が,
「寛政重修諸家譜の全面的分析を志向し…ついで徳川実紀・藩翰譜・譜牒余禄・寛永諸家系図伝等の分析に入り,数百枚におよぶ大名カードを作成する一方,御触書集成・徳川禁令考・御当家令条・徳川十五代史等から幕府の法令を,各藩法令集・県郡市町村史等から藩の法令を検索して,これを時代別に配列し,同じ題名を持つ三上参次・栗田元次ぐ両氏の『江戸時代史』を片手に,戦後の活発な社会経済史に関する個別研究を片手に,それらの成果を検討批判しつつ」
書き上げたというように,確かに,関東移封から,家康・秀忠,家光,家綱,綱吉,家宣,家継と続く政権下の,諸大名の改易,減封,移封,転封は,聖地を極める。
しかし,本書末尾で,吉宗時代に触れる中で,その画期とも言える変化について,
殿様は当分之御国主,田畑は公儀之田畑,
という,
「徳川幕府体制確立期における大名領主の封建的土地所有に対する思想の変革を意味する」
と述べる。つまり,徳川幕府が,諸大名を意のままに,鉢植え化できるのは,
天下の土地は,公儀のもの,
という考え方に基づくはずである。秀吉は,全国の土地を,一旦収公し,その上で,旧領を安堵したり,家康を関東に入封したり,政宗を仙台に移封したりした。一番問題なのは,徳川家康は,ただ秀吉の収公の延長線上で,
田畑は公儀之田畑,
としたのか,それとも,秀吉が天皇の権威に依拠したように,天皇に依拠したのか,それとも,全く別の考えに基づくのか,本書では,その徳川幕藩体制の権力の根拠が,僕が読んだ限り,明確ではなかった。
確かに,徳川政権の強化のために,たとえば関ヶ原後,六十八名の徳川一門・譜代大名を創出し,全国に配置しているが,それを遂行しうるのは何に基づいているのか。
大名を改易し,一門大名を増やしていくことは,権力の行使ではあるのだが,その細部が精緻に解き明かされるほど,それを可能にするものは何なのか,ただ徳川氏が相対的に強大であったので,それに従わざるを得なかったということだけでは納得できない何かが残る。鉢植化した大名は,仮にその領地の統治を認められているだけだとして,それを認めさせる徳川政権の権威はどこからくるのか,という問いに代えてもいい。そこが自明のまま議論が進められているように思えたのは,素人の僻目だろうか。たとえば,専門用語でいえば,
将軍の強力な土地所有権=全封建土地所有権,
とある。しかしそれは何に基づくのか。軍事的に秀吉のように,全国を制圧したわけではない。まだ大阪の役の前,
「徳川氏の覇権確立以降において,九州の大名領主相互間の争いが秀頼に持込まれ,その裁定に片桐且元・黒田長政が当たっていることは,西国諸大名がなお徳川氏の権力外にあったことをしめしている」
とある。このとき,秀頼の権威は何に基づくのか。大阪の役後,徳川に移った権威は,何に基づくのか。これは,僕には,大事なことに見えるが,専門的には,
一笑すべき問いなのか。
参考文献;
藤野保『新訂幕藩体制史の研究―権力構造の確立と展開』(吉川弘文館) |
|
関ヶ原の合戦 |
| 白峰旬『新視点関ヶ原合戦:天下分け目の戦いの通説を覆す』を読む。
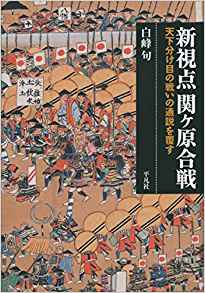
本著者の『新解釈 関ヶ原合戦の真実
脚色された天下分け目の戦い』(宮帯出版社)、『新「関ヶ原合戦」論―定説を履す史上最大の戦いの真実』(新人物ブックス)で展開された主張の補綴の役の本と見られる。従って、全体像よりは隙間を埋めるテーマが多いのは致し方ない。
主眼は、江戸時代の『慶長軍記』をはじめとする軍記物によって形成された、数々の家康目線で語られてきた伝承、さらにそれにのっとった参謀本部が編纂した『日本戦史 関ケ原役』の記述を、一次史料によって見直す作業である。
明治になって、『関原合戦図志』をあらわした神谷道一は、その緒言で、
「幕府ノ世ニ在リテハ人皆忌諱ニ觸レンコトヲ恐レ實記アリト雖モ秘シテ世ニ示サズ、今ヤ皇政開明復囁嚅ノ憂ナク正ニ是レ直筆ニ記載シ得ルノ日ナリ」
と記した。しかし、
「嘘も百回言えば、真実になる」
ではないが、
「一次史料による史料的根拠のない話が通説に化けた」
影響は大きく、
豊臣七将襲撃事件、
小山評定、
小早川秀秋への問鉄炮、
などが史実であるかのように思い込まされてきている。
本書では、著者の主著の補綴なので、一番の見どころは、第一章の、
豊臣七将襲撃事件はフィクションである、
が、読みごたえがある。七将については、
福島正則、池田照政、黒田長政、加藤清正、細川忠興、浅野長慶、加藤嘉明(関原始末記)、
福島正則、黒田長政、加藤清正、細川忠興、浅野長慶、加藤嘉明、脇坂安治(慶長年中卜斎記)、
福島正則、黒田長政、加藤清正、細川忠興、浅野長慶、蜂須賀家政、藤堂高虎(関原始末記)、
等々と異同はあるが、この七人が石田三成を襲撃・暗殺せんとしたとするものである。しかし、著者は、
「当時の人物が記した記録から三成襲撃事件をみた場合、襲撃・暗殺計画といった性格ではなく、七将が家康に三成の制裁(切腹)を訴えたもの」
と断定する。その意味で、三成が佐和山へ「隠居」あるいは「隠遁」と、関係資料で記されていることとつながる。それは、この騒動の責任をとって、
「中央政界から一時的に失脚したものの、問題の本質としては、佐和山に一時的に謹慎したにすぎないのであり、豊臣政権(豊臣公儀)の奉行職への復帰(政治的復権)の余地は十分のこしていた」
しかも、佐和山へ入るにあたって家康と三成は、相互に自分の子を人質としてとっている。この時点で、
「三成と家康は対等の関係であった」
のである。
本書の特徴は、
「公儀」という言葉の使い方である。たとえば、関ケ原で勝利した家康は、征夷大将軍となり、江戸に幕府を開く。しかし、だからと言って、天下が定まったわけではない。著者は、
二重公儀論(笠原和比古)、
に依拠しつつ、
「家康は慶長八年(1603)に征夷大将軍に就任して、徳川公儀の主催者になったが、このことは、この時点で豊臣公儀が消滅したことを意味せず、豊臣公儀のスキームはそのまま継続した(秀頼は死去するまで点火人という位置づけは変わらなかった)」
とする。たとえば、まだ大阪の役の前,
「徳川氏の覇権確立以降において,九州の大名領主相互間の争いが秀頼に持込まれ,その裁定に片桐且元・黒田長政が当たっていることは,西国諸大名がなお徳川氏の権力外にあったことをしめしている」
とある(藤野保『新訂幕藩体制史の研究―権力構造の確立と展開』)。このことは、
「幕藩体制の確立」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470099727.html?1568502090)、
で触れたが、このとき,この秀頼の権威は何に基づくのか。大阪の役後,徳川に移った権威は,何に基づくのかという視点抜きでは、これは理解できない。だからこそ、
家康は関ケ原合戦直後の時点で、前田利長宛ての手紙で、「すぐに(大阪城を)乗り掛けて攻め崩すべきであるが、(大阪城は)秀頼様の御座所であるので(大阪城攻めを)延期した」という趣旨のことを述べている。
「そもそも、なぜ徳川家康は、豊臣秀頼を改易できなかったのか、改易で済めば、わざわざ戦争(大坂の陣)をする必要はなかったははずである。現在の通説的見方では、大坂の陣は、徳川が主、豊臣が従という見方であるが、徳川と豊臣を対等の関係で見ないと、大坂の陣というのは政治的に正しく理解できない」
著者は言う。
「一方の公儀(徳川公儀)が他方の公儀(豊臣公儀)を改易することはできなかった」
のである。秀吉は、旧主君の子信雄は家臣であったから改易したが、家康は、改易できなかった。なぜなら、
「天下人として独裁者であった秀吉が後継指名した時点で次期天下人は(秀頼に)確定したのであって秀吉死去(慶長三年(1598))後は、即時に、豊臣公儀の主催者として天下人になったのである。独裁者であった秀吉が、独裁国家の後継者として実子の秀頼を指名した以上、(中略)諸大名はもちろん、豊臣政権下で当時、最大の大名であった家康でさえ、覆すことはできなかった。」
つまり、
徳川公儀と豊臣公儀の決戦、
で決着をつけるしかなかった、のである、とする。「公儀」という言い方は、
豊臣の体制対徳川の(幕藩)体制、
ということである。徳川政権にとって、豊臣家は、意のままに改易したり、移封したりできる相手ではなく、それ自体が、政治体制だという意味で、
公儀、
という言い方は、至当に思える。秀吉は、信長が本能寺で死んだ後も、信長を、「惟任退治記」や手紙で、
公儀、
と呼んでいたが、それは、織田体制という含意を持たせていたのもかもしれない。
参考文献;
白峰旬『新視点関ヶ原合戦:天下分け目の戦いの通説を覆す』(平凡社)
藤野保『新訂幕藩体制史の研究―権力構造の確立と展開』(吉川弘文館) |
|
歴史小説 |
|
大岡昇平他編『歴史への視点(全集現代文学の発見・12巻)』を読む。
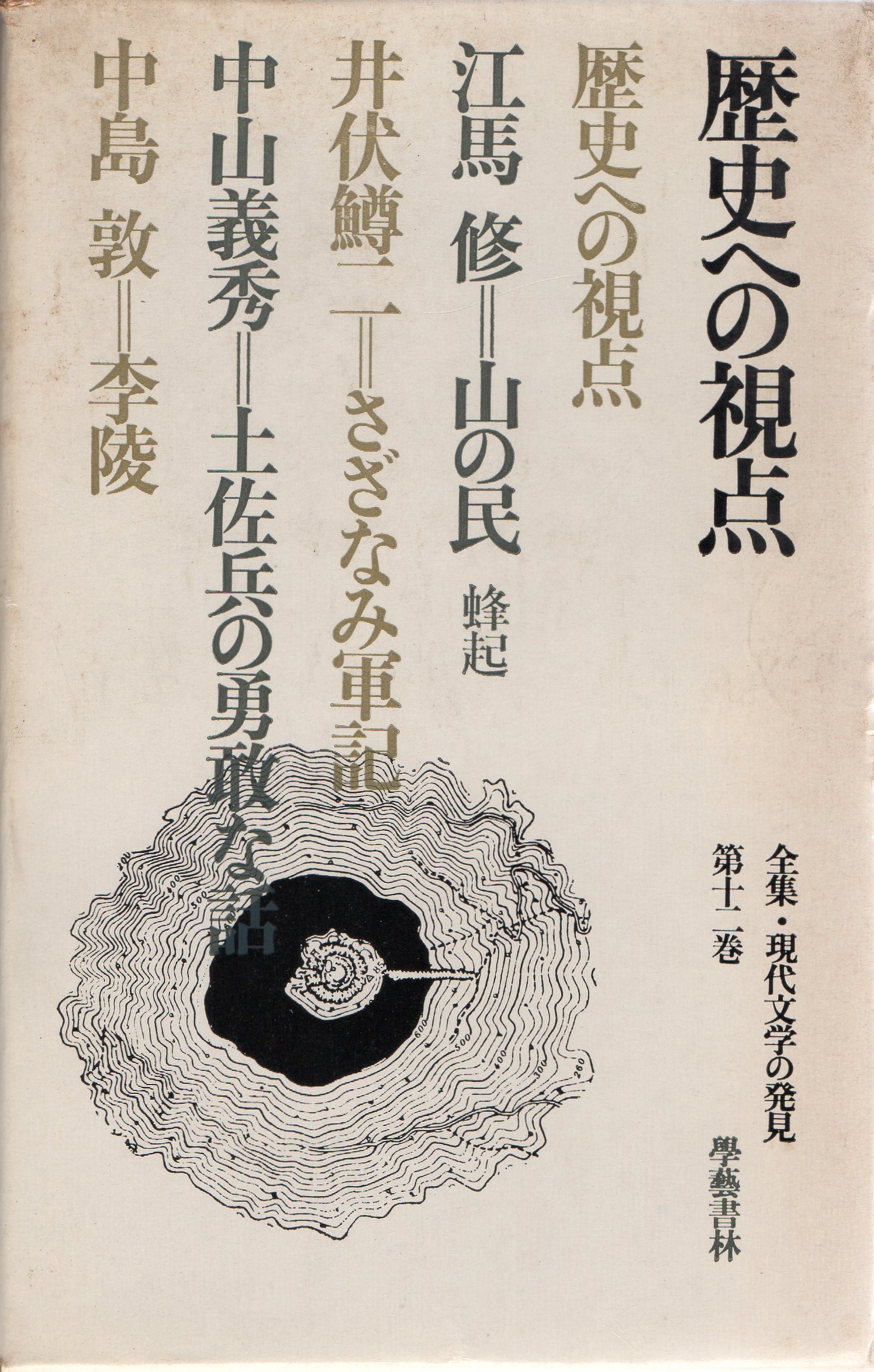
本書は、
現代文学の発見,
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し,テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、
歴史への視点,
と題された「歴史小説」を収録している。収録されているのは、
江馬修『山の民』(蜂起)、
井伏鱒二『さざ波軍記』
中山義秀『土佐兵の勇敢な話』
中島敦『李陵』
坂口安吾『二流の人』
田宮虎彦『落城』
井上靖『楼蘭』
杉浦明平『秘事法門』
大原富江『婉という女』
である。世情、歴史小説は、歴史小説とは区別されている。歴史小説は、
主要な登場人物が歴史上実在した人物で、主要な部分はほぼ史実の通りに進められる、
のに対して、時代小説は、
架空の人物(例えば銭形平次)を登場させるか、実在の人物を使っても史実と違った展開をし(例えば水戸黄門)、。史実と照らし合わせるとかなり荒唐無稽である、
とされる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%B0%8F%E8%AA%AC0)。いわゆる、
史伝小説、
も、
歴史上の事実に基づいて書かれた伝記、
で、歴史小説に入る。本書で「歴史小説論」を解説として書く大岡昇平は、歴史小説は、
題材を歴史に取った小説、
であると同時に、
歴史感覚、或いは歴史意識というものが、作品を支えているか、どうか、どうかというところを一応の目安としたい、
と述べ、
「ただ面白い話を語り、現代では不可能な刺激的シチュエーションを作る便法としたり、過去の王侯貴族の生活に対するスノッブ的郷愁に溺れたり、既成の通念を、小説家の自由によって引っくりかえす、スキャンダル趣味に頼ったり、なんらかの政治的先入見によって宣伝的な効果をねらう、という特徴を持つもの」
は対象外、としている。そのうえで、
「歴史小説には歴史それ自身としての評価と、文学作品の芸術的価値の二つの軸」
で、評価し、本巻収録の中で、
「二つの価値の調和という観点から」
山の民、
が最も欠陥のない作品と結論付けている。鴎外が、
述べて作らず、
という孔子の言を引き、
史実の作者の恣意による変更を述べていたが、鴎外のたどり着いたのは、世情、
史伝、
の範疇に入れている、
澀江抽斎、
以後の伝記物において、
史伝を書くことを書く、
というメタ化によって、「述べる」ことと「作る」ことの二項対立を解決し、石川淳の言う、
「小説概念を変更するような新課題」
を提出したのである。
「澀江抽斎」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/457109903.html)で触れたように、それを石川淳は,
「作者はまず筆を取って,小説とはどうして書くものかと考え,そう考えたことを書くことからはじめている。ということは,頭脳を既成の小説概念から清潔に洗っていることである。(中略)前もってたくらんでいたらしいものはなに一つ持ちこまない。…味もそっけも無いようなはなしである。…しかし『追儺』は小説というものの,小説はどうして書くかということの,単純な見本である。これが鷗外四十八歳にして初めて書いた小説である。」
と評していた(森鴎外)。
しかし、もはやこれは歴史小説ではなく、小説とは何かについての模索そのものである。
鴎外が、「述べて作らす」について、煩悶し、「阿部一族」「大塩平八郎」などから史伝といわれるものに移ったような、「述べることと」「作る」ことを、中島敦は、『李陵』の中で、司馬遷に仮託して、こう書く。
「彼も孔子に倣って、述べて作らぬ方針を執ったが、しかし、孔子のそれとは多分に内容を異にした述而不作である。司馬遷にとって、単なる編年体の事件列挙は未だ『述べる』の中にはいらぬものだったし、又、後世人の事実そのものを知ることを妨げる様な、余りにも道義的な新案は、寧ろ『作る』の部類に入るように思われた」
そして、
「初めの五帝本紀から夏殷周秦本紀あたり迄は、彼も、材料を塩梅して記述の正確厳密を期する一人の技師に過ぎなかったのだが、始皇帝を経て、項羽本紀に入る頃から、その技術家の冷静さが怪しくなって来た。ともすれば、項羽が彼に、或いは彼が項羽にのり移りかねないのである。
項王則チ夜起キテ帳中ニ飲ス。美人有り。名は虞。常ニ幸セラレテ従フ。駿馬名ハ騅、常ニ之ニ騎ス。是ニ於テ項王乃チ悲歌慷慨シ自ラ詩ヲ為リて曰ク『力山ヲ抜キ気世ヲ蓋フ、時利アラズ、騅逝カズ、騅逝カズ奈何スベキ、虞ヤ虞ヤ若奈何ニセン』ト。歌フコト数闋、美人之ニ和ス。項王泣数行下ル、左右皆泣キ、能ク仰ギ視ルモノ莫シ…。
これでいいのか? と司馬遷は疑う。こんな熱に浮かされた様な書きっぷりでいいものだろうか?
彼は『作ル』ことを極度に警戒した。自分の仕事は『述ベル』ことに尽きる。(中略)彼は時に『作ル』ことを恐れるの余り、すでに書いた部分を読返して見て、それがある為に史上の人物が現実の人物の如くに躍動すると思われる字句を削る。すると確かにその人物はハツラツたる呼吸活動を止める。之で、『作ル』ことになる心配はない訳である。しかし、(と司馬遷が思うに)之では項羽が項羽ではなくなるのではないか。項羽も始皇帝も楚の荘王もみな同じ人間になってしまう。違った人間を同じ人間として記述することが、何が『述ベル』だ?
『述ベル』とは、違った人間は違った人間として述べることではないか。そう考えてくると、やはり彼は削った字句を再び生かさない訳にはいかない。元通りに直して、さて一読して見て、彼はやっと落ち着く」
と書く。「述べる」ことと「作る」ことの葛藤は、そのまま『李陵』という作品に向き合う中島敦の心の動きでもある。これだけで、僕は『李陵』を推す。
かつて述べたことだが、基本的に、何かを「述べる」ことは、それ自体、なにがしか「作る」ほかない。いや、「述べる」ことは、「作る」ことなしには成り立たない(孔子の春秋自体がその例証である)。そう考えれば、あとは、それが、
文学作品の芸術的価値、
があるかどうかではあるまいか。僕は、小説は、
何を書くか、
ではなく、
どう書くか、
にのみ焦点があると思っている。大岡昇平の言う、
歴史感覚、或いは歴史意識、
はどちらかというと、「何を書くか」の側の問題ではあるまいか。近松門左衛門の、
虚実皮膜、
は、歴史小説にも当てはまる。
参考文献;
大岡昇平他編『歴史への視点(全集現代文学の発見・12巻)』(學藝出版)
石川淳『森鷗外』(ちくま学芸文庫)
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0924.htm#%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0%E3%81%A8%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0 |
|
太閤検地 |
|
中野等『太閤検地−秀吉が目指した国のかたち』を読む。

本書は、秀吉の織田政権下での羽柴領検地から始まって時系列に、豊臣政権下で行われた検地を詳細に検討し、
「豊臣政権が創り上げようとした近世社会あるいは近世国家像」
に迫ろうとする。この検地によって、米の容積を示す単位を「石」を基軸としたため、
「国内の生産力が『石高』によって表示されるにいたる。すなわち、太閤検地によって田畠には等級が設けられ、土地の面積は町・段(反)・畝・歩という単位体系によって把握され、生産力の指標となる米の容積も基準となる統一の枡によりつつ、石・斗・升・合・勺という単位体系に整理された。田も畠もさらには屋敷地まで米を生産するものと想定され、その収穫高が米高として算出された」
これを前提として、村々の境界線を確定し、地域を明確にして、
「村々の石高が算出され、さらにそれを基準として郡の石高(郡高)や国の石高(国高)が算出される」
こととなり、これによって、
「大名の領地高や給人(知行地を与えられた大名家臣)の知行高はもとより、村々の規模や百姓が所持する高知の規模、さらには年貢として収奪される生産物の多寡も石高によって表示されることとなった」
村の確定は、村単位として年貢を納める責任を負う、
「村請制』が機能しはじめることである。『村請制』のもとでは、村のみが法人格を付与されて年貢や諸役の責任を負う。仮に、個々の百姓に年貢の滞納(未進)があったとしても、その責めは村全体に帰する」
ことになる。つまり、検地により、
村の境界を画し、
当該地域の土地面積を測量し、
田地の品位を定め、
石盛(一反当たりの収穫量)を定め、
石高を定め、
一村当たりの総地積、総石高を決定する、
ことによって、太閤検地は、
「在地秩序を再編し、社会の新たな基本単位を設定する」
ことになり、この結果、近世の村が成立する。
さらに在地の一元化に伴い、
主を持たず、田畠を作らざる侍、
は村々から放逐される。つまり、
「豊臣政権が目指した在所のありようは『百姓』『諸職人』『商売人』と、武具類の所持を認められた主人をもつ『奉公人』からなるもの」
であった。
「豊臣政権下の『在所』は給恩をもって主人の役を務める『諸奉公人』と田畠開作を専らに仕る『百姓』および『町人』すまなわち諸職人や商売人から構成されることになる」
したがって、大名は、国替えで移封される場合、
「『家中』『侍』のことは申すに及ばす、『中間』『小者』に至るまで『奉公人』は一人も残さず連れていく」
ことを命じられる。これを、
「『兵農分離』ではなく『士農分離』という概念こそがふさわしい」
とする。それは、中世以来の、地侍、土豪という所有地を持った侍の在り方の解体、士・農の分離を意味する。在地に残った地侍。土豪は、百姓となることを意味した。
この検地は、土地から離された侍側にも大きな変化をもたらす。
「検地の結果として機能する石高制によることで、秀吉は臣下の領知を容易に異動する環境を獲得する。前後の知行規模が数値化されており、知行加増や減封といった主従関係の変化も容易に具現化されることとなるが、領知内容の互換性を図るうえで石高のもつ客観性や合理性は大きな意味を持つ」
その結果、豊臣政権末期になると、
戦国以来の故地にいたのは中国毛利氏と九州・奥羽など遠隔地の諸大名」
のみになり、
「薩摩・大隅・日向の一部を領した島津氏の場合も、給人レベルでみれば文禄四年検地ののち、ほとんどが本来の領地から引き離された地に転封を余儀なくされている」
ありさまで、これを、確か荻生徂徠は、
鉢植化、
といったと思うが、
「原理的にすべての『国土』は天皇あるいは秀吉の手に帰し、以後江戸時代を通じて大名・給人は在地性を否定された「鉢植え」の領主として存在することとなる。こうした世界史的にも稀有な『封建制度』を可能にし、それを根本で支えたのが一連の太閤検地と称される政策であった」
この太閤検地の成果の上に、徳川幕藩体制は成り立つ。幕藩体制の成立しについては、
「幕藩体制の確立」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470099727.html?1568502090)
で触れた。
参考文献;
中野等『太閤検地−秀吉が目指した国のかたち』(中公新書) |
|
方法の実験 |
|
大岡昇平他編『方法の実験(全集現代文学の発見第2巻)』を読む。
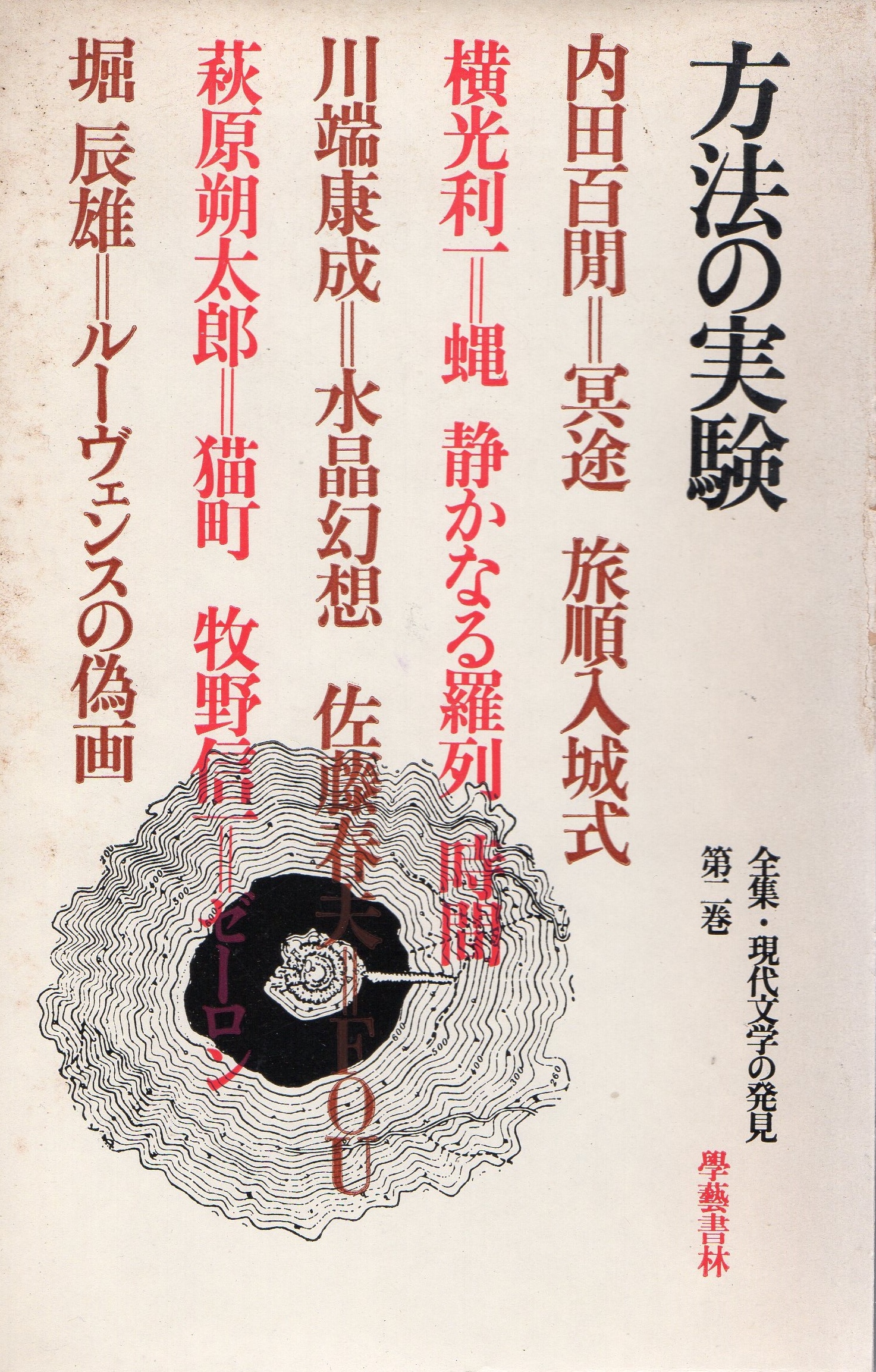
本書は、
現代文学の発見,
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し,テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、
方法の実験,
と題された「方法」を自覚した実験作を収録している。収録されているのは、
内田百饟『冥途』『旅順入城式』
佐藤春夫『F・O・U』
横光利一『蠅』『静かなる羅列』『時間』
川端康成『水晶幻想』
萩原朔太郎『猫町』
牧野信一『ゼーロン』
堀辰雄『ルウヴェンスの偽画』
中野重治『空想家とシナリオ』
伊藤整『幽鬼の街』
石川淳『鷹』
埴谷雄高『虚空』
神西清『月見座頭』
安部公房『赤い繭』
福永武彦『飛ぶ男』
井上光晴『地の群れ』
花田清輝『大秘事(「小説平家」より)』
である。僕は文学史に博識ではないので、この選集上梓以後五十年の間に、他にどんな「方法の実験」に値する作家が入るのか、わからないが、私見では、これに、
古井由吉『眉雨』
中上健次『奇蹟』
は確実に入ると思われる。
本書の中で、注目すべきことは、
実験、
ではない。実験は、実験であって、いわば、
習作、
に過ぎない。実験は作品ではない。その意味で横光以下、ほとんどは、
実験、
の域を出ない。実験そのものが、方法として確立し、その方法で自覚的に、
作品世界、
を構築し、その上で、作品としての評価に耐えうるのは、ぼくは、
石川淳『鷹』
井上光晴『地の群れ』
花田清輝『大秘事(「小説平家」より)』
であると思う。埴谷雄高『虚空』、安部公房『赤い繭』も挙げたいが、埴谷雄高『は虚空』よりは、やはり『死霊』だろう。安部公房は『赤い繭』より他に採るべき作品(例えば『壁』)があるように思える。
ぼくは、小説とは、
何を書くか、
ではなく、
どう書くか、
がテーマであるべきだと思っている。その時、方法は、
主題、
である、と思う。そのことを、伊藤整は、芥川龍之介に擬した塵川辰之介に、
「『何を書くか』ではないのですよ。…如何に美しく書くか、ですよ。」
と語らせている。プロレタリア文学の脅威に立ち向かっている芥川にとって、それは伸るか反るかの一大事であった。しかし、芥川は、「何を書くか」主義の潮流に抗えず、自刃した。今日もなお、
何を書くか、
という主題主義は、巨大な壁である。石川淳は、
「森鴎外」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/456849243.html)
で触れたように、『澀江抽斎』は、
「小説家鷗外が切りひらいたのは文学の血路である」
と言い切っている。それは,
「出来上がったものは史伝でも物語でもなく,抽斎という人物がいる世界像で,初めにわくわくしたはずの当の作者の自意識など影も見えない。当時の批評がめんくらって,勝手がちがうと憤慨したのも無理はない。作品は校勘学の実演のようでもあり新講談のようでもあるが,さっぱりおもしろくもないしろもので,作者の料簡も同様にえたいが知れないと,世評が内内気にしながら匙を投げていたものが,じつは古今一流の大文章であったとは,文学の高尚なる論理である。」
「『抽斎』『蘭軒』『霞亭』はふつう史伝と見られている。そう見られるわけは単にこれらの作品を組み立てている材料が過去の実在人物の事蹟に係るというだけのことであろう。いかにも史伝ではある。だが,文章のうまい史伝なるがゆえに,ひとはこれに感動するのではない。作品の世界を自立させているところの一貫した努力がひとを打つのみである。」
と。この小説は、
メタ小説(http://ppnetwork.seesaa.net/article/457109903.html)、
で触れたように、
書くことを書く,
を方法とした、
メタ小説、
である。それは、
「作者はまず筆を取って,小説とはどうして書くものかと考え,そう考えたことを書くことからはじめている。ということは,頭脳を既成の小説概念から清潔に洗っていることである。(中略)前もってたくらんでいたらしいものはなに一つ持ちこまない。…味もそっけも無いようなはなしである。…しかし『追儺』は小説というものの,小説はどうして書くかということの,単純な見本である。これが鷗外四十八歳にして初めて書いた小説である。」
石川淳の評した短編『追儺』の方法意識で、
書くとはどういうことかを書きながら,書いていったのである。本巻に、
澀江抽斎、
をこそ、納めるべきであった。
参考文献;
大岡昇平他編『方法の実験(全集現代文学の発見第2巻)』(學藝出版) |
|
ガルゲン・フモール |
|
大岡昇平他編『黒いユーモア(全集現代文学の発見第6巻)』を読む。
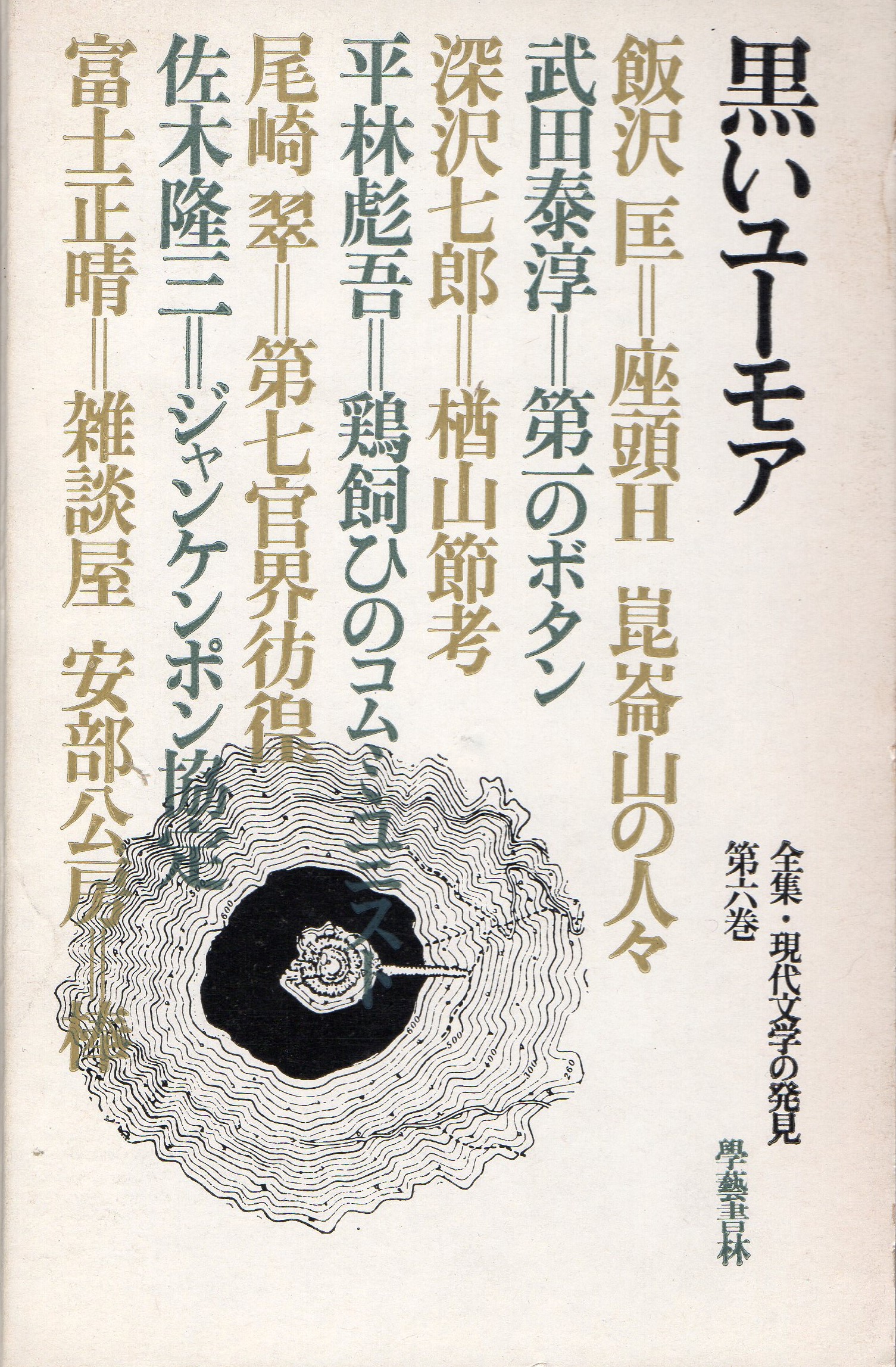
本書は、
現代文学の発見,
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し,テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、
黒いユーモア,
と題された「ユーモア」に関わる作品を収録している。収録されているのは、
内田百饟『朝の雨』
石川淳『曽呂利咄』
井伏鱒二『白毛』
飯沢匡『座頭H』『崑崙山の人々』
深沢七郎『楢山節考』
武田泰淳『第一のボタン』
富士正治『雑談屋』
織田作之助『世相』
安部公房『棒』
平林彪吉『鶏飼ひのコミュニスト』
尾崎翠『第七官界彷徨』
佐木隆三『ジャンケンポン協定』
泉大八『アクチュアルな女』
坂口安吾『あヽ無情』
野坂昭如『マッチ売りの少女』
花田清輝『鳥獣戯話』
今村昌平・山内久『果てしなき欲望』
である。花田清輝は、本巻の解説で、「黒いユーモア」、すなわち、
ガルゲン・フモール(Galgen humor)、
「ガルゲンは絞首台、フモールは諧謔。窮余の諧謔。曳かれ者の者の小唄」
とする。とすると、このアンソロジーに、
井上光晴、
の作品がないのは、いささか画竜点睛を欠くかに見える。この意味の「黒い」と題されたユーモアに値するのは、本巻掲載作品の中では、
井伏鱒二『白毛』
深沢七郎『楢山節考』
武田泰淳『第一のボタン』
安部公房『棒』
平林彪吉『鶏飼ひのコミュニスト』
野坂昭如『マッチ売りの少女』
花田清輝『鳥獣戯話』
かと思われる。特に、
野坂昭如『マッチ売りの少女』
は、アンデルセンの童話の、寒空の下でマッチを売っていた少女のラスト、マッチの炎に現れた祖母の幻影が消えるのを恐れた少女は、急いでマッチ全てに火を付け、自身も火と燃えるストーリーを頭の片隅に置くと、一層その「窮余の諧謔」ぶりが目立つ。
がさつな僕には、
尾崎翠『第七官界彷徨』
の繊細な少女の揺れる、
第七官、
はうまくつかみ取れない。少女の微妙な心情を描く環境として、特異な環境を設定した意図は、よく見えなかった。結果からみて、本当に、このシチュエーションが必要だったのだろうか、という疑問はぬぐえない。ガサツなせいかもしれないが。
やはり本巻の中で出色なのは、
花田清輝『鳥獣戯話』
である。巻末の解説を書く花田清輝自身が、この作品についての平野謙の、
「『群猿図』においてすら、あれの終わったところから小説ははじまるというような感想をいだかされた私としては、『孤狐紙』はますます後退してしまった、と思わざるを得ない。小さなことをいうようだが、作者は〈ないでもない〉とか〈らしい〉とか〈のようである〉というような言葉をさかんに使っているけれど、そういう作者自身のコケンのようなものをかなぐりすてたところに、小説世界はそれみずからを全肯定的によみがえらすのではないか」
という文芸時評の一説を引き、
「いくぶん、ほめかたがたりないような気がしないでもなかった」
と嘯く。おそらく、平野謙の小説観そのものと対峙するところに、花田清輝の小説世界はある。
〈ないでもない〉
〈らしい〉
〈のようである〉
という仮説というか、推測というか、曖昧化、によって事柄の中に多様な像を多重写しにして、その中の一つを可能性として取り上げ広げていく、この筆法自体が、小説世界になっている、ということを平野謙は認めなかったのである。例は悪いが、
春秋、
は、孔子の正邪の判断を加え、
些事をとりあげて、間接的な原因を直接的な原因として表現する、
ところから
春秋の筆法、
と言われる。しかし、それも歴史記述の一つである。事実の選択一つ、書き手の判断に俟たないものはないのではないか。
メタ小説(http://ppnetwork.seesaa.net/article/457109903.html)
で触れたように、鴎外の『澀江抽斎』は、
史伝、
という範疇に入れるしかなかったが、
「著者はこの伝記の稿に筆を下すに当たって,先ず如何にして自分がこの作品の主人公とめぐりあったか,どうしてその人に関心をいだき,伝記を立てる興味をおこしたか,そしてこの著述に如何にして着手し,史料は如何にして蒐め,また如何にして主人公に就いての知識を拡大して行ったか,その筋みちを詳しく説明してゐるのである。言ってみれば著者はここで伝記作者としての自分の舞台裏をなんのこだわりもなく最初から打ち明けて見せてゐるのであり,著述を進めてゆく途上に自分が突き当たった難渋も,未解決の疑問も,一方探索を押し進めてゆく際に経験した自分の発見や疑問解決の喜びをも,いささかもかくすことなく筆にしてゐる。これは澀江抽斎といふ人の伝記を叙述してゐると同時に,澀江氏の事蹟を探ってゆく著者の努力の経過をもまた,随筆のやうな構へを以て淡々と報告してゆく,さうした特異な叙述の方法にもとづいて書かれた伝記である。」
と、解説者(小堀桂一郎)自身が説明しているように、まさに、平野謙の言う、
あれの終わったところから小説ははじまる、
という作品である。しかし、
小説とはどうして書くものかと考え,そう考えたことを書くこと、
自身がテーマなのである。卓見の石川淳は、それを、
「小説概念に変更を強要するような新課題が提出」
「小説家鷗外が切りひらいたのは文学の血路である」
と評した(http://ppnetwork.seesaa.net/article/456849243.html)。
花田清輝の作品は、ある意味で、鴎外の切り開いた血路の先にある。しかし、鷗外自身はその新地平について気づいていなかったらしい。
「鷗外自身は前期のいわゆる小説作品よりもはるかに小説に近似したものだとは考えていなかったようである。たしかに従来の文学的努力とは性質のちがった努力がはじめられていたにも係らず,そういう自分の努力と小説との不可分な関係をなにげなく通り越して行ったらしい点に於て,鷗外の小説観の一端がうかがわれるであろう」
と石川淳は評した(仝上)。花田清輝は、それを意識的に切り開いている。だからこそ、平野謙の、
あれの終わったところから小説ははじまる、
を、
ほめ方が足りない、
と嘯いたのである。
参考文献;
大岡昇平他編『黒いユーモア(全集現代文学の発見第6巻)』(學藝出版)
石川淳『森鷗外』(ちくま学芸文庫) |
|
死霊 |
|
埴谷雄高『死霊』を読む。
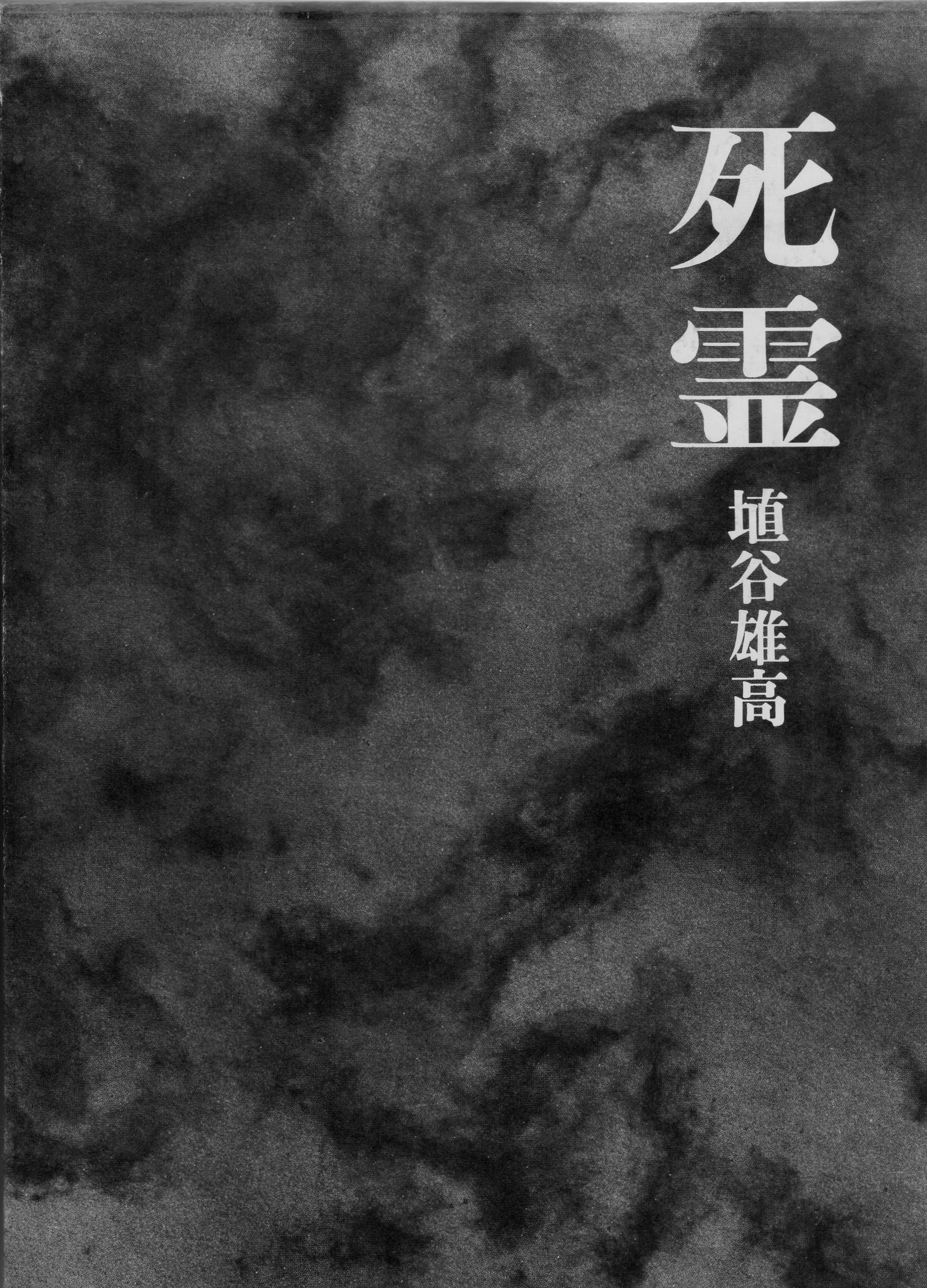
『死霊』の一〜三章までは、何度も読んだ記憶がある。その後、四、五章が二十数年ぶりに執筆され、一巻にまとめられた時、各章にタイトルがついた。
第一章 癲狂院にて
第二章 《死の理論》
第三章 屋根裏部屋
第四章 霧のなかで
第五章 夢魔の世界
さらに、その後、
第六章 《愁いの王》
第七章 《最後の審判》
第八章 《月光のなかで》
第九章 《虚體》論―大宇宙の夢
と書き継がれ、一応未完ながら、死の直前書き終えられた。今回、改めて、全部を読み通してみた。率直な感想を言うなら、文庫では、第一巻が、
第一章 癲狂院にて
第二章 《死の理論》
第三章 屋根裏部屋
第二巻が、
第四章 霧のなかで
第五章 夢魔の世界
第六章 《愁いの王》
第三巻が、
第七章 《最後の審判》
第八章 《月光のなかで》
第九章 《虚體》論―大宇宙の夢
と分けられているのに倣っていうと、
第一巻(一〜三)は、快作、
第二巻(四〜六)は、怪作、
第三巻(七〜九)は、懈作、
という印象である。特に、
七〜九
は、作家自身が死期を意識してか、言いたいことを言い急ぐ感じで、小説としての結構を崩してしまっている。『死霊』は、基本、
対話、
を中心にして成り立っている。しかも、会話の主張の多くは、
喩え、
や
たとえ話、
や
アネクドート、
で語られる。それ自体が閉鎖的である。あるいは、
自己完結
したものである。それは、
自己意識の妄想、
にふさわしいのかもしれないが、僕には新しさを感じなかった。書評家の大森望氏が,
「現実的で論理的なのがミステリー、非現実的で論理的なのがSF、現実的で非論理的なのがホラー、非現実的で非論理的なのがファンタジー」
と定義したのに倣うなら、『死霊』は、一種、
ファンタジー、
である。ある意味、自己意識の語る、
壮大な自己実現の夢想、
である。埴谷は、「不可能性の作家」で、「吾思う故に我あり」の「思う」に、
「理解する、欲する、想像する、知覚するなどの広い意味」
で理解し、その思惟作用に、
推理する、
も加え、
「幾段かのより高くなりゆくその種の推論を飛躍している裡に、想像力はもはやまったく客観的な対応物を自身のなかに失って…これまで嘗てなく、またこれからも決してないだろうところの唯一無二の事物に到達した不可能性の作家」
は、ドストエフスキーとポーしかいないとし、そのボーの『メエルストロームの渦』について、
「そこに夢より幻想、幻想より想像力、想像力より推論が打ち勝ち…、そこに在るものを描くのではなく、そこに決してないものを創り出してしまう」
衝迫力について書いていた。言葉を換えれば、非現実の中に描き出した世界である。
その意味で、僕から見れば、
存在のホログラフィー、
でしかない自己意識の身もだえに近い、『死霊』の、
儚い夢物語、
の世界は、やはり、
ファンタジー、
である。その意味で、
喩え、
で語るのはふさわしいのかもしれない。しかし、「喩」は,所詮、
何かのアナロジー、
である。その何かを直截語れないので、メタファーや逸話で語るしかないのである。それは,語れない時点で、方法の敗北ではあるまいか。
世界を「喩え」で語っても,世界は語り尽くせない。いや語れないから、喩えたのである。しかし,それで完結させようとしている,というふうに見える。だからこそ、また、
ファンタジー、
である。『死霊』とほぼ同時期に出た、『嘔吐』で、サルトルは、
ロカンタンの日記、
のスタイルをとり、ラスト、
一編の小説、
を書こうと決意するところで終わる。その一片の小説が、
嘔吐、
という作品である、というように受け止められる。この方法自体を別段斬新とは思わないが、方法としては、二十世紀的である、と僕は思う。
小説は、何を書くか、
ではなく、
どう書くか、
こそが主題である、と僕は思うが、対話と喩えで終始する『死霊』は、僕には、十九世紀的であると思えてならない。多くの論者が、この中で論じられている「何」を中心に語り過ぎでいる。小説は別に、思想を述べる手段ではない(そんな議論はプロレタリア文学論争で疾うに終わっている)。何が書かれているかは、本来どうでもいい、それがどう書かれようとしているかこそが、問われるべきなのではないか。
対話で成り立っている全体のうち、一〜三は、対話となっている。両者が絡み合い、響きあいながら、世界が描けている。しかし、四〜六になると、それが怪しくなり、七〜九になると、ほぼ一方的な語りに終始する。それは、既に、対話を方法としたこの作品の結構が破綻しかけている証である。僕には、
神格化の一〜三、
に対して、地に降りた、
普通化の四〜六、
であり、ついに、
破綻化の七〜九、
に見える。大江健三郎は、この作品は、
「三輪与志と津田安壽子の愛の物語」
だと主張した、という。それに倣うなら、いささか古風なところの垣間見える埴谷雄高の男女感からみれば、僕には、
津田安壽子の恋、
という方が叶っているとも見える。未完の九章のラスト、
―ほう、何が、はじめて全宇宙に創出されるのでしょう……?
―与志さんの、虚体、です!
と、さっと頬全体に紅い帯を掃かせながら、津田安壽子は鋭く叫んだ。
の、一言に安壽子の思いが籠り、作品全体と釣り合っているように見えるから。
ちなみに、「死霊」は、
シリョウ、
とは訓ませず、
シレイ、
と訓ませる。埴谷雄高自身が、
「日本語は怨霊のリョウなんだけれども、そうすると恨めしやという感じになっちゃうんだよ。日本の怨霊は全部或る個人に恨めしやという感情をもって出てくるんだね。ぼくのあそこに出てくる幽霊はみんな論理的な、しかも一見理性的で全宇宙を相手にするような途方もない大げさなことばかりしゃべる。そうした理性的幽霊しか出てこないから、いわば『進歩した』現代の語感をもってシレイと読ませているんだ」
と語っている(『二つの同時代史』)し、
「死霊」は革命で死んだ死者、
の意であり、主人公は、
五章(夢魔の世界)で出てる、
という発言(仝上)から見ても、
死霊(しりょう)、
のことのようだが、僕には、それぞれの自己意識の妄想は、
死霊、
ではなく、三輪与志、高志、首猛夫、矢場徹吾等の
生霊(いきりょう)、
のように見える。そして、当たり前だが、ここでの宇宙論は、
人間原理、
そのものである。
参考文献;
埴谷雄高『死霊』(講談社)
大岡昇平・埴谷雄高『二つの同時代史』(岩波書店) |
|
証言者 |
|
大岡昇平・埴谷雄高『二つの同時代史』を読む。

戦後派の巨人二人の、1982年の一年余にわたる対談である。当時、埴谷雄高は72歳、大岡昇平は九ヶ月年長の73歳。いわゆる文士という言葉が当てはまる最後の世代である。すでに、椎名麟三、武田泰淳、竹内好もないが、まだ『死霊』を書き継ぐ埴谷、森鴎外の『堺事件』に対する批判の『堺港攘夷始末』を始めようとしている大岡昇平と、七十を過ぎてなお、現役であり続けていた二人の対談は、埴谷自身が、
「後世の史家からいえば、とにかく日本が近代化していく過程においてインテリゲンチャがどういう境遇に上以降まれ、そのなかでどういうことを考えてきたかということがこの対談のなかに象徴的に反映しているのではないかと思う」
というように、戦前、戦中、戦後と、文学者がどう生き抜いてきたか、の証言者となっている。
一人は、刑務所に、一人は捕虜収容所に、それを「ゼロ時点」として、それぞれの文学的スタートとしたという意味で、面白い企画の対談である。
小林秀雄に近く、鎌倉派にいたはずの大岡が、戦後、いつのまにか左翼の埴谷と近い位置になるほど、日本が右傾化し、大岡が左翼と目されるほどに、社会が変化した流れは、今日もっとひどくなり、いまやいっしょくたにパヨクとひとくくりにされる時代になっているのを見ると、戦後一貫した時代の右傾化の中で、今日の位置があることに、改めて気づかされる。日本は、戦後から、終始一貫して、戦前回帰をめざしてきた、と。
時代の証言者としての面で面白いのは、記録の中だけではわからない体験談だ。たとえば、埴谷が、「新経済」という雑誌を作った経緯が面白い。
「昭和十六年に……偶然、経済連盟の調査課長をしていた帆足計が統制会というものを作ろうと言い始めたんだよ。彼は郷誠之助の子分みたいなもんだが、やはり旧左翼だよ。その彼が『統制会の理論と実際』という本を書いた。それが『新経済』社の最初の出版物で、あたかも『新経済』社は統制会の宣伝機関みたいになったわけだ。われわれもそれなら統制会の応援をしようというんで、初めは会と二人三脚のようにして出発したんだよ。唐島基智三、帆足計、郷司浩平、島田晋作、奥村綱雄、工藤昭四郎、野田信夫などが『新経済』社の顧問だった。また木村禧八郎も顧問だったことがある。その九人の顧問のうち、奥村綱雄は、戦後野村證券の社長兼会長になったし、工藤昭四郎は都民銀行の頭取、郷司浩平は生産性本部の親玉になったから、要するに、半分は戦後、資本主義の主要人物になったわけだ。それから帆足計と島田晋作と木村禧八郎は、戦後社会党の代議士になったし、野田信夫は成蹊大学の学長、唐島基智三は政治評論家になったから、もう半分は幾分社会党系といってもいいかもしれない。とにかく自由派も社会派も全員厭戦家だった」
その彼らは、「経済」を隠れ蓑に、外務省の短波情報を得て、スターリングラードの攻防の結果や、ノルマンディ上陸成功、アトミック・ボム投下の情報をも、的確につかんでいた。終戦の詔勅については、
「木原(通雄)が書いたんだよ。あれは安岡正篤が後で見たんだけど、原文は木原が書いている。彼は国民新聞にいて、おれたちの『新経済』の顧問だった唐島基智三のすぐ下のきれものの部下だった」
とも語っている。さらに、戦後のGHQの検閲についても、埴谷は、『近代文学』に掲載予定の原民喜『夏の花』の事前検閲をめぐって、こう証言している。
「GHQといったって内閣も検閲もアメリカ人が読むわけじゃないんだよ。GHQの下には日本人の事実上の検閲係がいて、それで、読んだあと、こんな原子爆弾のことを書いたらとうていだめだって、返されちゃった。日本人が日本の作品を『自己規制』してるんだよ。アメリカの占領方針をすっかり自分が体しているつもりになっているんだが、日本人は茶坊主型が実に多いんだよ。あとで問題が起きたとき責任が自分にかからないように、これはアメリカの占領方針に反するだろうと、できるだけ拡大解釈して、ほんとに小さなことでもチェックして、これはだめだと返してくる。そして、上のアメリカ人に尤もらしく報告するんだな。仮に、日本がアメリカを占領して、アメリカの新聞や雑誌を検閲するためにアメリカ人を使ったとしても、その使われたアメリカ人が、占領軍の方針を勝手に忖度し拡大解釈して『上官の日本人の気にいられる報告』ばかりこれほど出そうとはおそらくしないと思うな。おれは、権力者に対する茶坊主ぶりでは、日本人は世界のベストテンのなかにはいると思っているよ」
まさに「忖度」とは、茶坊主の心性ということだ。七十年たっても変わっていないのである。
文学者の証言でも、なかなか鋭いものが随所にある。たとえば、大岡は、梅崎春生をめぐって、
「梅崎も武田(泰淳)も吉本隆明や高橋和巳と同じ伏目なんだよ。ぼくはそういうのを全部、“伏目族”と名付けている(笑)。“伏目族”は本来全部弱者で、その弱者であることによって逆に強者になるというタイプなんだよ。
つまり全部見るのはいやだけれども、見た瞬間にその見た瞬間にその見たものの何か本質をつかまなくちゃいけないという感じになるらしいんだな。この弱者が強者に転化するいちばんいい例は、武田の例の『風媒花』で、竹内毛沢東に対して、自分は人民裁判にかけられる小毛で、武田小毛はせいぜい小毛なりに精一杯生きている、何も竹内毛沢東だけが偉いんじゃないんだというふうに言って、武田は最底辺の弱者を頂上にいるもの以上の強者に転化させたわけだ」
と語る。その鋭い観察に敬服する。
また酔っぱらうと「バカヤロー」が口癖の石川淳のエピソードも笑える。
「(中薗英助が)石川淳が『バカヤロー』といったとき、『あのバカヤローといったジジイをおれがやっつけてやる』といって石川淳の前に座って、『わたしはどうですか』っていったんだよ。そうしたら石川淳は『おまえもバカヤローだ』といった。そこで中薗が『きさまもバカヤローだ』って怒鳴ったとたん、石川淳はぱっと立ち上がってサーッと玄関へ出ていっちゃった。あわてて送っていった安部公房がびっくりして『ああ、石川さんはけんかがうまい、逃げるのが』といっていたね。中薗が怒鳴った途端にサッと立ち上がると、靴をはいてスーッと出て帰っちゃった。すごいもんだよ」
と。小柄の石川淳の逃走姿が、目に見えるようで可笑しい。
政治的な発言も随所にあるが、こんなやり取りもある。
大岡 …日本という国は韓国とも中国とも接し、ソ連とも接している。海はいまはなんでもないから、アメリカとも接しているんで、こういう国は珍しいんだ。ここで第九条というSF的な理想を掲げて永遠に貫くのはいいと思うよ。
埴谷 それはいい。これは自縄自縛に役立っている。ただ僕は必ずしも憲法改正に反対ではないんだよ。僕は天皇制を廃止するというのをまず入れた憲法にする改正なら大賛成なんだ。そういう廃止をやってもらいたい。ロベスピエールがフランス革命のときにつくったのは、『政府が人民の諸権利を侵害した場合、蜂起は人民にとって、また人民の各部分にとって、その諸権利のうちもっとも神聖な権利、その諸義務のうちもっとも不可避なぎむである』という憲法なんですよ。」
硬骨な二人は、
大岡 人間はだいたい二十五までに考えいたことからでられない、とベルグソンがずっと前に言っているな。
埴谷 着想は全部そうだ。
大岡 それを仕上げるのに一生かかっても足りないという。われわれは随分長く、七十何年も生きて来た。むかしより平均寿命が延びているから、やりとげられるさ」
と言い合った通り、埴谷は1997年、八十七歳まで生き、『死霊』を曲がりなりにも完成させて往った。大岡は、その十年前1987年に亡くなっているが、『堺港攘夷始末』をほぼ完成させて往った。成し遂げていったのである。
二人が終始嘆いていた、「時代がどんどん悪くなる」は、もはやティッピングポイントを越えてしまった。この現状にお二人はどんな顔をしておられるやら。
参考文献;
大岡昇平・埴谷雄高『二つの同時代史』(岩波書店) |
|
戦いの痕 |
|
大岡昇平他編『存在の探求(上)(全集現代文学の発見第7巻)』を読む。
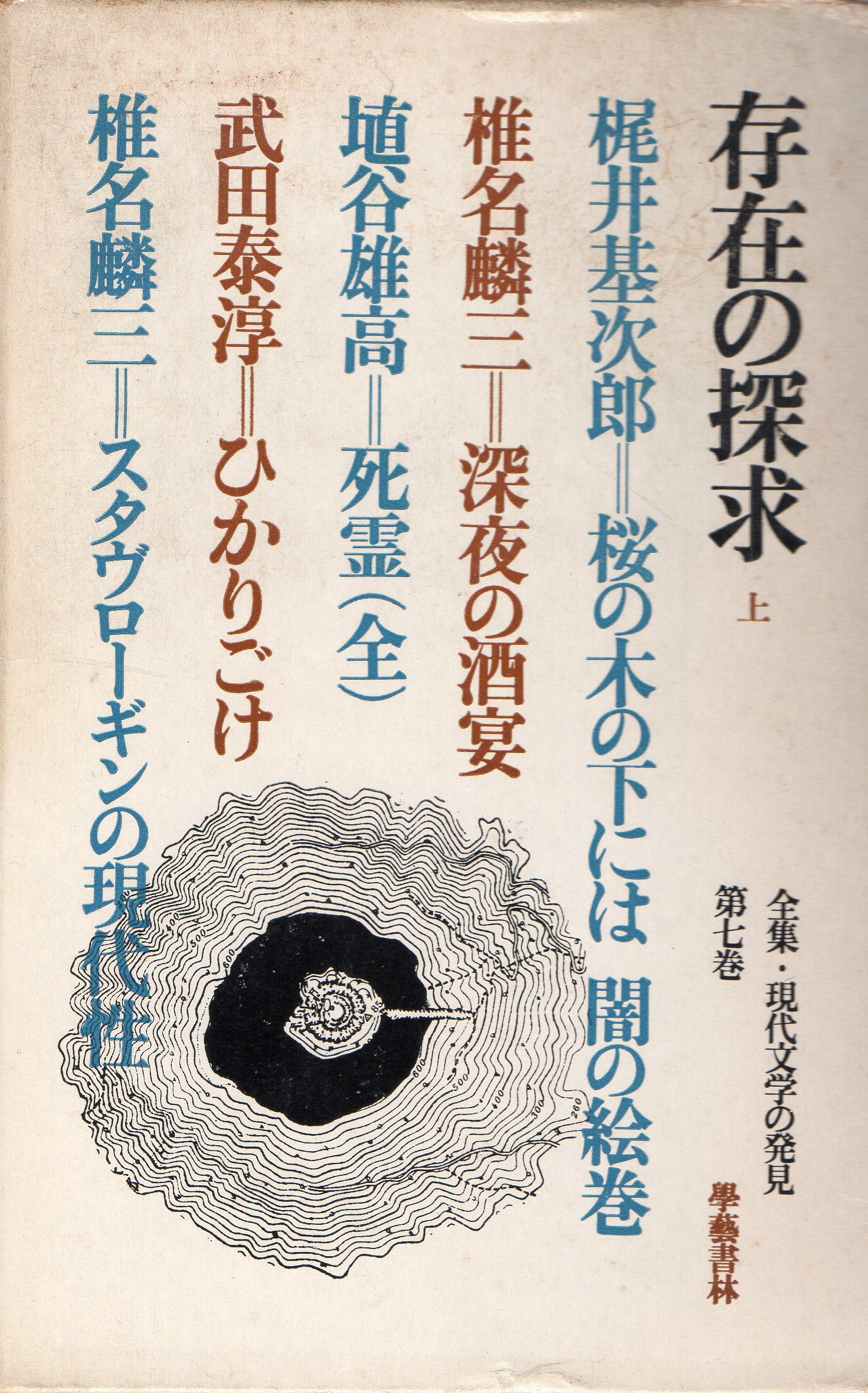
本書は、
現代文学の発見,
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し,テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、二巻に分かれた、
存在の探求,
と題された前半である。収録されているのは、
梶井基次郎『櫻の木下には』『闇の繪巻』
北條民雄『いのちの初夜』
中島敦『悟浄出世』『悟浄歎異』
稲垣足穂『彌勒』
椎名麟三『深夜の酒宴』『スタヴローギンの現代性』
埴谷雄高『死霊』『存在と非在ののっぺらぼう』『夢について』『可能性の作家』『不可能性の作家』
武田泰淳『ひかりごけ』『滅亡について』
である。いずれも、何回か読んだことがある。この中で、群を抜くのは、
埴谷雄高『死霊』
である。これについては、別途触れた(http://ppnetwork.seesaa.net/article/471454118.html?1574308068)が、存在とのかかわりを、自己意識側から、広げるだけ広げて見せたというところは、他に類を見ない。特に、本書に納められた、一〜三章は、文章の緊張度、会話の緊迫度、無駄のない描写等々、のちに書き継がれた四章以降とは格段に違う、と僕は思う。
俺は、
と言って、
俺である、
と言い切ることに「不快」という「自同律の不快」とは、埴谷の造語であるが、少し矮小化するかもしれないが、
自己意識の身もだえ、
と僕は思う。埴谷は、自己意識の妄想を極限まで広げて見せたが、「存在」との関わり方には、
自分存在に限定するか、
世界存在に広げるか、
その世界も、
現実世界なのか、
或いは、
自然世界なのか、
で、方向は三分するように思う。『いのちの初夜』は、自分の癩に病にかかったおのれに絶望して、死のうとして死にきれず、
「ぬるぬると全身にまつわりついてくる生命を感じるのであった。逃れようとしても逃れられない、それはとりもちのような粘り強さ」
の生命を意識する。そして同病の看護人の佐柄木に、
「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです」
と言われる。その生命そのものになった己を受け入れよ、と言われる。
「あなたは人間じゃあないんです。あなたの苦悩や絶望、それがどこからくるか、考えてみて下さい。ひとたび死んだ過去を捜し求めているからではないでしょうか」
似た発想は、稲垣足穂『彌勒』にもある。主人公、
「江美留は悟った。波羅門の子、その名は阿逸多、いまから五十六億七千万年の後、竜華樹下において成道して、さきの釈迦牟尼の説法に漏れた衆生を済度すべき使命を託された者は、まさにこの自分でなければならないと」
ここにあるのは、自己意識の自己救済の妄想である。しかし、それは、叔父の用意した紅白の、輪を作った綱を示されて、
「咄嗟に思いついて、その綱の輪を首にかけた。そしてネクタイでも締めるようにゆるく締めてから二、三度首を振った」
主人公の、現状の悲惨な状況を無感動に受けいれているのと、実は何も変わってはいない。
「そのとき、突然僕は時間の観念を喪失していた。僕は生まれてからずっとこのように歩きつづけているような気分に襲われていた。そして僕の未来もやはりこのようであることがはっきり予感されるのだった。僕はその気分に堪えるために、背の荷物を揺り上げながら立止った。そして何となくあたりを見廻したのだった。すると瞬間、僕は、以前この道をこのような想いに蔽われながら、ここで立止って何となくあたりを見廻したことがあるような気がした。……この瞬間の僕は、自分の人生の象徴的な姿なのだった。しかもその姿は、なんの変化も何の新鮮さもなく、そっくりそのままの絶望的な自分が繰り返されているだけなのである。すべてが僕に決定的であり、すべてが僕に予定的なのだった。……たしかに僕は何かによって、すべて決定的に予定されているのである。何かにって何だ―と僕は自分に尋ねた。そのとき自分の心の隅から、それは神だという誘惑的な甘い囁きを聞いたのだった。だが僕はその誘惑に堪えながら、それは自分の認識だと答えたのだった」
「認識」と己に言い切らせる限りで、自己意識は、まだおのが矜持を保っているが、それはそのまま今のありように埋もれ尽くすという意味では、より絶望的である。それは、
絶望を衒う、
といってもいい。
それにしても、しかし、いずれも、『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャのように、
神の作ったこの世界を承認することができない、
という、
「僕は調和なぞほしくない。つまり、人類に対する愛のためにほしくないというのだ。僕はむしろあがなわれざる苦悶をもって終始したい。たとえ僕の考えが間違っていても、あがなわれざる苦悶と癒されざる不満の境に止まるのを潔しとする」
境地から後退してしまうのだろう。埴谷も椎名も、ともに投獄の経験を持ち、そこから後退したところで、身もだえしているように見える。確かに、
戦いの痕跡、
はある。しかしそれで終わっていいのだろうか。そこには、日本的な、余りにも日本的な、
自己意識の自足、
か、
自然への埋没、
か、
しかないのだろうか。今日の日本の現状を併せ考えるとき、暗澹たる気持ちになる。
参考文献;
大岡昇平他編『存在の探求(上)(全集現代文学の発見第7巻)』(學藝書林) |
|
皮膜の広がり |
| 大岡昇平他編『存在の探求(下)(全集現代文学の発見第8巻)』を読む。
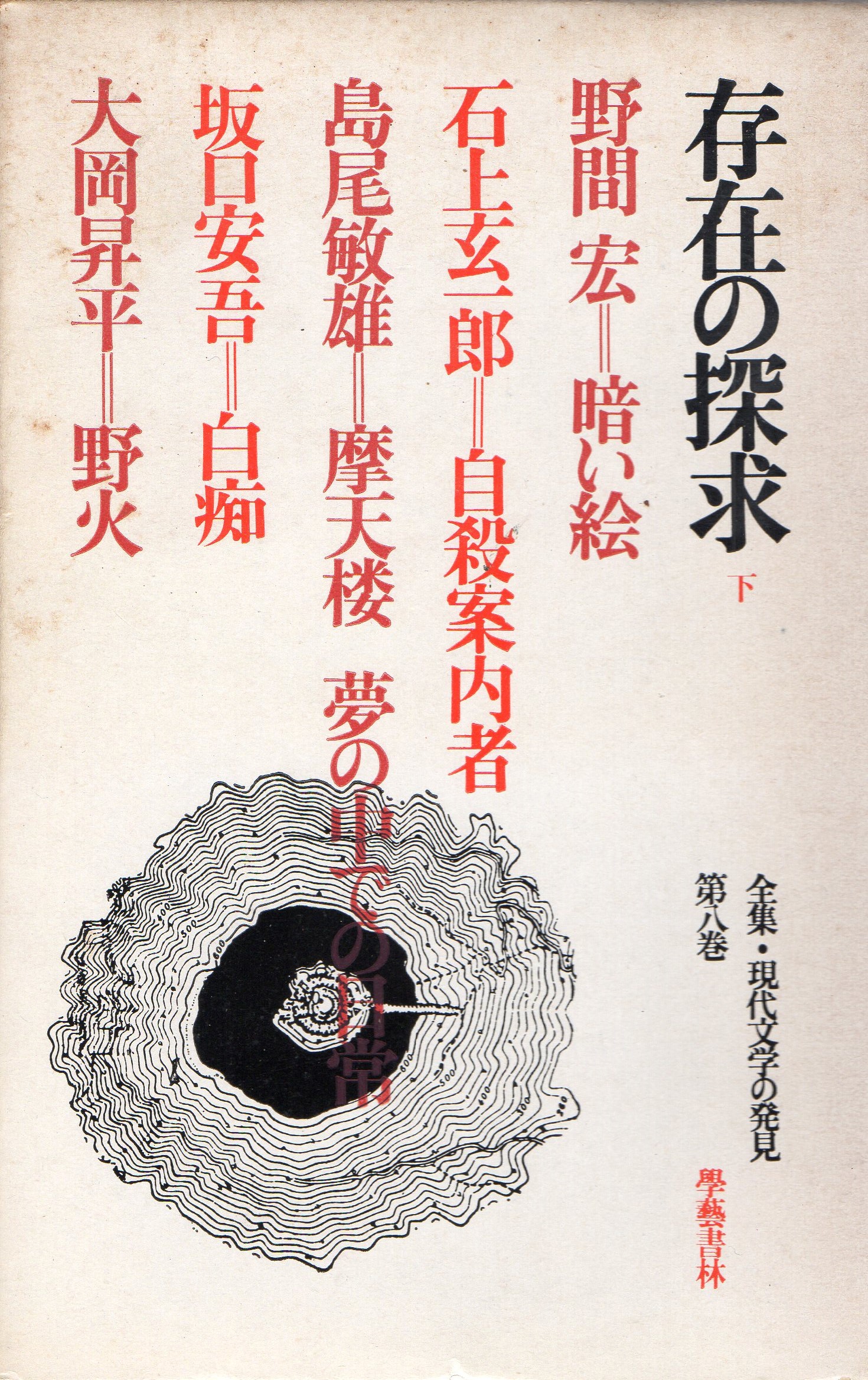
本書は、
現代文学の発見,
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し,テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、二巻に分かれた、
存在の探求,
と題された後半である。収録されているのは、
石上玄一郎『自殺案内者』
野間宏『暗い絵』
島尾敏雄『摩天楼』『夢の中での日常』
坂口安吾『白痴』『堕落論』
大岡昇平『野火』
安部公房『S・カルマ氏の犯罪―壁』
石川淳『無盡燈』
三好十郎『胎内』
吉田一穂「極の誘い」「穀物と葡萄の祝祭」「野生の幻影」
花田清輝「沙漠について」「楕円幻想」
である。
『自殺案内者』は、僕には作意が過ぎ、それが透けて見えるようで、とても好きになれない。小説は虚構だが、その結構が作為的では、ちょっとついていけない、と思った。あくまで憶説だが。これを「ゆたかな虚構」という評価もありえるが、僕は採らない。戦争文学の金字塔とされる『野火』は、敗走する日本兵の無残さを余さず描く。230万の戦死者の六割とか七割が餓死者といわれる、戦争指導者そのものの失策の附けを、兵卒が荷わされた惨状を、象徴的に描くのは、人肉を食うというシーンだ。捕虜となった主人公は、
「彼らを殺したけれど、喰べなかった。殺したのば、戦争とか神とか偶然とか、私以外の力の結果であるが、たしかに私の意志で喰べなかった。」
と言う。そう言わしめたのは、この国の指導者である。十分の補給も確保できないまま、机上で戦線を拡大した連中の無為無策、無能ぶりを、後に、大岡は、『レイテ戦記』でその実態を詳らかにした。
ただ、僕は、この小説の結構を、狂人日記としたのは不満である。「三七 狂人日記」以降は、蛇足ではないか。もちろん、時代の制約はある、と認めたうえで、なお小説の結構としては、斜めに逃げず、真正面から描くべきではなかったかと、惜しむ。
花田清輝の『復興期の精神』からとられた、二編は、戦争中に書かれたという点でも、出色である。精神は自在に、虚実の皮膜の隙間を泳ぎ回っている気配である。すでに、戦後の活躍の胚珠を抱えている。
島尾敏雄の『夢の中での日常』の、
「私の頭にはうすいカルシウム煎餅のような大きな瘡が一面にはびこっていた。私はぞっとして、頭の血が一ぺんにどこか中心の方に冷却して引込んで行くようないやな感触に襲われた。私はその瘡をはがしてみた。すると簡単にはがれた。しかしその後で急激に矢もたてもたまらないかゆさに落込んだ。私は我慢がならずにもうでたらめにきかきむしった。始めのうちは陶酔したい程気持がよかった。しかしすぐ猛烈なかゆさがやって来た。そしてそれは頭だけではなく、全身にぶーっと吹き上って来るようなかゆさであった。それは止めようがなかった。身体は氷の中につかっていた首から上を、理髪の後のあの生ぬるい髪洗いのように、なめくじに首筋を這い廻られるいやな感触であった。手を休めると、きのこのように瘡が生えて来た。私は人間を放棄するのではないかという変な気持の中で、頭の瘡をかきむしった。すると同時に強烈な腹痛が起こった。それは腹の中に石ころをいっぱいつめ込まれた狼のように、ごろごろした感じで、まともに歩けそうもない。私は思い切って右手を胃袋の中につっ込んだ。そして左手で頭をぼりぼりひっかきながら、右手でぐいぐい胃の中のものをえぐりだそうとした。私は胃の底に核のようなものが頑強に密着しているのを右手に感じた。それでそれを一所懸命に引っぱった。すると何とした事だ、その核を頂点にして、私の肉体がずるずると引き上げられてきたのだ。私はもう、やけくそで引っぱり続けた。そしてその揚句に私は足袋を裏返しにするように、私自身の身体が裏返しになってしまったことを感じた。頭のかゆさも腹痛もなくなっていた。ただ私の外観はいかのようにのっぺり、透き通って見えた。そして私は、さらさらと清い流れの中に沈んでいることを知った。」
という体感覚と、一瞬で裏返る自分という、我々のありようの別の貌を意表を突く形で現出してみせた。ここには、作家が、夢の文脈をなぞりながら、ただ、「私」の体感覚に一体化しているのではなく、その「私」をも、突き放す視点を持っている証である。それは、安部公房『S・カルマ氏の犯罪―壁』の、
「不意に舞台の両袖で気負い立った足音がしました。どこから現れたのか、グリーンの服の大男たちでした。立直るまもなく二人は左右から襲いかかり、力いっぱいぼくの背中を突きとばしました。ぼくはスクリーンの中に顔からつっこんでいきました。
と、ぼくは―というよりももはや彼はと言わなければならないでしょう―そのままスクリーンをつきぬけて画面の中にはいりこみ、部屋の中に倒れているのでした。」
と、映画のスクリーンの中に入り込むシーンとつながる。この時、作家は、「ぼく」も「彼」も、等間隔で眺める視点で、ずっと描いてきていることが、ここでわかるのである。それは、作家の、虚実皮膜の、皮膜の拡大と言ってもいい。そして、ひっくり返った「私」を見る位置と、スクリーンを通り抜けた「彼」を見る位置とは、ほぼ同じである。
解説で、埴谷雄高が、
「この方法的な領域において私達はまだ極めて僅かな歩幅の踏み出ししか行っていないのである。(中略)仮象の体操法とでも名づけるべき領域において、より僅かな踏み出ししかおこない得ないことに比例するかの如く、さて、さらに視点を遠くに投げて、存在の変容といった課題へ目を移せば、まことに寥々たる仕事しか見当たらないのである。」
と嘆いているのは、なにも、島尾や安部の試みた、変身や時空移動を指しているのではない。それは、作家の前の皮膜の幅の拡大である。かつて、
「世界像」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/456849243.html)
や
「メタ小説」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/457109903.html)
で触れたように、鴎外は、
小説を書くことを書く、
ことによって、格段に皮膜の世界を広げた。そのことを言及した石川淳は『無盡燈』で、
「そこで、弓子の心願の正體を突きとめにかかるとすれば、わたしはわたしといふ質點に於て傾斜して來たところの、ひとりの女の心情曲線を微分して行くことになるだろう。そして、わたしが無藝の一つおぼえにもつている思考の方法は散文よりほかは無いのだから、この微分の操作をつづけて行つた揚句はしぜん小説の形式に出來上つてしまふかもしれないだらう。」
と書き、それが『無盡燈』という作品であるかのごとき体裁をとっている。むろん、それは、
「どこまで行つても地上のくされ縁がたたき切れずに、行つたさきから振出しに跳ねかへつて來るやうなぐあひに、所詮作者の生活に還元されてしまふことを見越しながら、書かれるであらう作品としいふものはむ、わたしの小説観にとつてぞつとしないしろものである。」
と書くように、作家自身を「私」とするような、皮膜が虚ではなく、実によりそうような、狭苦しい作品世界でなく、このために設えられた世界であることは、当然である。
そして、この各自分を書く位置と、ひっくり返った「私」、スクリーンを通り抜けた「彼」を見る位置とは、重なるのである。皮膜の奥行きとは、このことである。
参考文献;
大岡昇平他編『存在の探求(下)(全集現代文学の発見第8巻)』(學藝書林) |
|
危機 |
| 大岡昇平他編『日常の中の危機(全集現代文学の発見第5巻)』を読む。
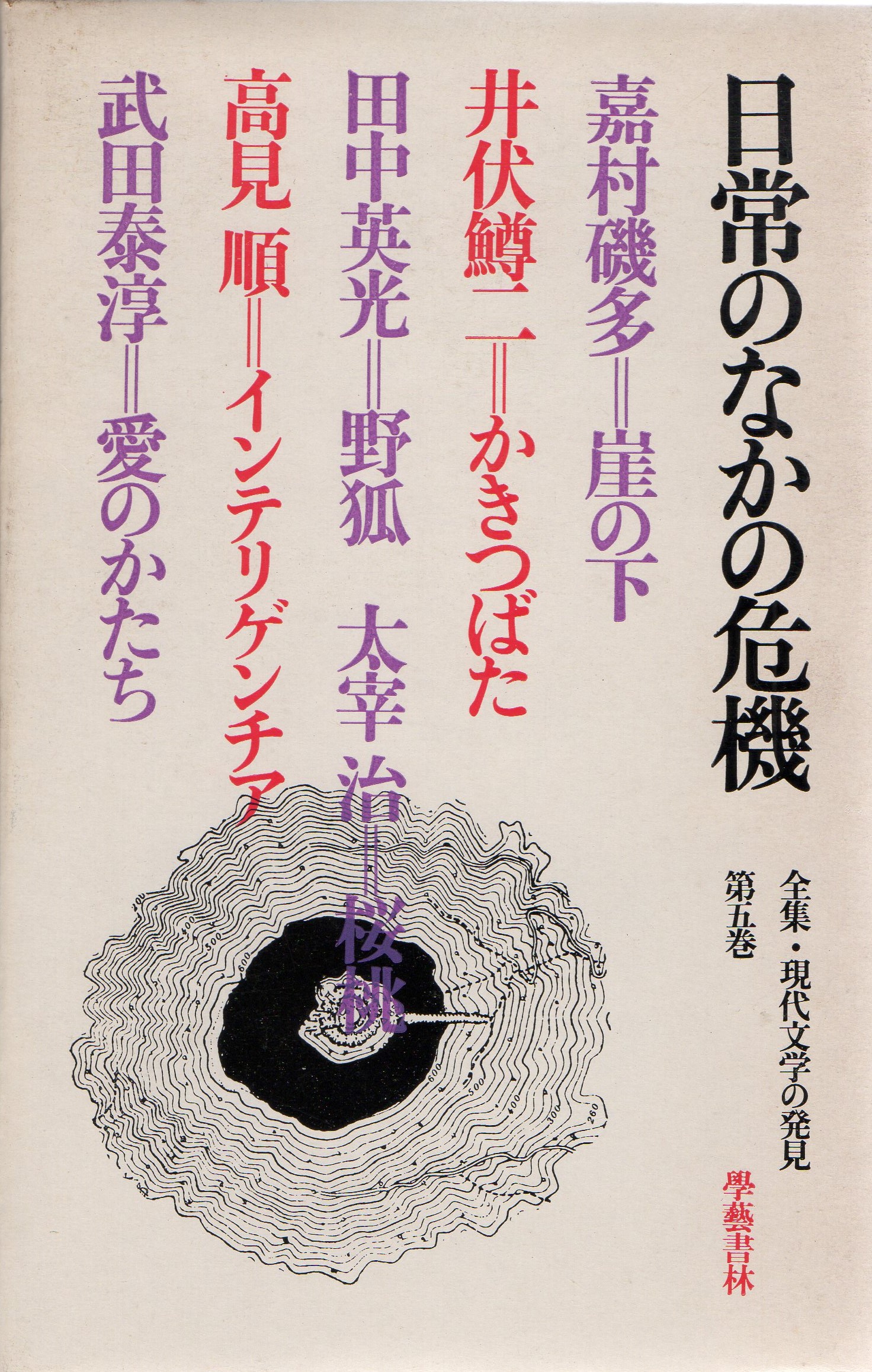
本書は、
現代文学の発見、
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し、テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、
日常の中の危機、
と題されている。収録されているのは、
嘉村磯多『崖の下』
井伏鱒二『かきつばた』
太宰治『桜桃』
高見順『インテリゲンチァ』
武田泰淳『「愛」のかたち』
田中英光『野狐』
小山清『落穂ひろい』
椎名麟三『神の道化師』
島尾敏雄『死の棘』
安岡章太郎『海辺の光景』
庄野潤三『プールサイド小景』
小島信夫『返照』
永井龍男『青梅雨』
梅崎春生『幻化』
である。しかし、解説の松原新一も言うように、大半が正常成らざる男女関係のもつれを扱うのである。それを日常の中の危機ではないとは言わない、しかし、どこかずれている気がする。日常の中の危機が、本書の帯のフレーズのように、
足元にひらく亀裂、
なら、普通に歩いていたら砂の穴に押し込められた(砂の女)、突然棒になった(棒)、目が覚めたら虫になっていた(変身)、といったたぐいの、
ただ普通に生活していたのに、いつの間にか迷路に踏み迷った、
突然発病して、見える世界が変わった、
理不尽にある日逮捕された、
冤罪で置換と名指しされた、
等々、といったありきたりの生活と思ったものが、いつの間にか、本線から引き込み線に、あるいは脱線に、陥ることではないか、という気がする。
もし、不倫が、危機というなら、不倫自体ではなく、ちょっとした浮気心で崩壊した普通の家庭、という意味で、
死の棘、
は、もっともありうる「日常の中の危機」に違いない。子供たちが、カテイノジジョウという「夫婦の葛藤」の中で、子供たちが荒れていくさまが、既に危機である。
「『ウチデハ、オトウシャンハオカアシャンヲオコラナイノニ、オカアシャンハオトウシャンヲオコッテバカリイル。ソンナオトウシャンハ、キライニナッチャオカナ』マヤは父親をまっすぐに見てそう言い、父親の私は伸一が近所の遊び友だちのあいだで荒れて行くすがたが目に残ってはなれない。
伸一が、いきなり大きな叫び声を出し、小石をつかんでふりあげると、とりまいていた年上のこどもらが一目散に逃げ出し、それを路地の奥の方に追いこんだあと、つかんだ小石をそのあたりの塀になげつけながら、戻ってくるひとりぼっちのすがた。「親がカテイノジジョウをすると、おかあさんが逃げないかしんぱいで、けんかに負ける」とませた口をきいた伸一。」(死の棘)
あるいは、
「青木氏の家族が南京はぜの木の陰に消えるのを見送ったコーチの先生は、何ということなく心を打たれた。
『あれが本当にせいかつだな。生活らしい生活だな。夕食の前に、家族でプールで一泳ぎして帰ってゆくなんて……』」(プールサイド小景)
という青木氏の家庭は、夫が会社の金の使い込みで会社を馘になり、二週間分の生活費しかないのである。
「起こった事を冷静に見てみれば、これは全く想像を絶したことではないのだ。給料では、自前で飲むにしてもたかが知れているのだ。それを何となく安心して、一度も疑ってみたことのない自分の方が、迂闊であね、
夫の方にしてみても、大事に到るとは思ってもみなかったのだろうが、そういう風に物事を甘く見るところに、既に破綻が始まっていたのだ。本当に埋め合わせる気があれば、何とかできた金額である。」(仝上)
危機のさなかを、しかし、深刻ではなく、どこか突き放したように、逆に言うと、高をくくっている感じの夫婦の様子が、危機の深刻さを、ひとごとに見ている雰囲気を、よく出している。妻は、偽装出勤の夫について、
「(……夫は帰ってくるだろうか。無事に帰って来てくれさえすればいい。失業者だって何だって構わない。この家から離れないでいてくれたら……)」(仝上)
と、 気遣うのである。そんな突き放した感覚は、妻の死の後、後添えをもらうかどうかの話に終始する『反照』にもある。危機を危機と感ずるかどうかは感性だが、当人がどこかひとごとに見ている雰囲気というのは、人から見ると、確信犯に見える。
「あなたはどんな女が来ても、けっきょくおんなじじゃないのかな。そのことをあなたは、自分で知っているんですよ。その女が気に入らなければ、かえってあなたは、やっぱりそうだった、そうだったと手を打っていいますよ。あなたがもともとそうなのか、途中からそうなったのか、僕には分からないが、やがてあなたは吹聴しますよ。(略)」
『青梅雨』は、一家心中の記事(?)の、
「十九日午後二時ごろ、神奈川県F市F八三八無職太田千三さん(七七)方で、太田と妻ひでさん(六七)養女の春枝さん(五一)ひでさんの実姉林ゆきさん(七二)の四人が、自宅六畳間のふとんの中で死んでいるのを、親類の同所一八四九雑貨商梅本貞吉さん(四七)がみつけ、F署に届けた。」
その夜を描く。しかし、危機というよりは、危機の決算というかんじではあるまいか。『幻化』は、神経を病んで入院先から脱走した主人公の、戦時中駐屯した鹿児島への旅を描く。確かに、戦争の心の傷を描く。しかし、これを日常の中の危機と括っていいのだろうか。ちょっと違和感がある。それは、『かきつばた』の、原爆投下後の異変についてもいえる。戦争下の話で、やはり、僕には、「日常の中の危機」とはずれる感じがしてならない。『神の道化師』も、父母の離婚で、世間に放り出された少年の苦労だが、やはりこのテーマの中に入れるのは、無理があると思う。
嘉村磯多『崖の下』
高見順『インテリゲンチァ』
武田泰淳『「愛」のかたち』
田中英光『野狐』
島尾敏雄『死の棘』
と、男女間の葛藤を描くものは、確かに、日常の中の危機といえばいえるが、僕には、これも少しずれている気がしてならない。これが過半を占めるというのは、選の間違いというより、我々は、眼下の日常の危機を描く作品(『変身』や『審判』)を、いまだ手元に持っていない、ということの表れのような気がする。
なお、太宰については、「太宰」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/451454488.html)で触れたが、同じ理由で、『桜桃』は買わない。
参考文献;
大岡昇平他編『日常の中の危機(全集現代文学の発見第5巻)』(學藝書林) |
|
青春時代 |
| 大岡昇平他編『青春の屈折下(全集現代文学の発見第15巻)』を読む。
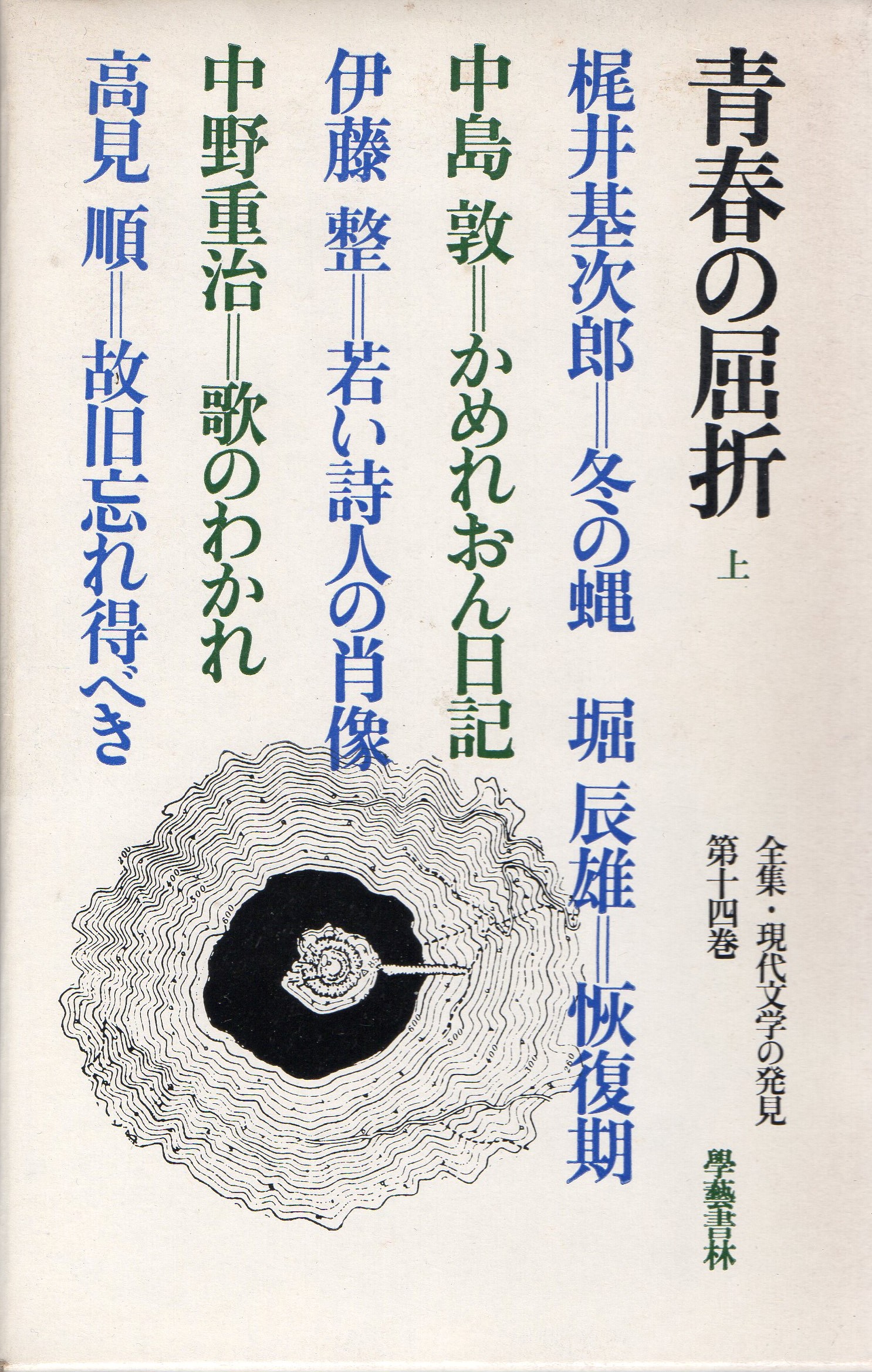
現代文学の発見、
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し、テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、
青春の屈折、
と題された、二分冊の前半である。収録されているのは、
梶井基次郎『冬の蠅』
中島敦『かめれおん日記』
堀辰雄『恢復期』
伊藤整『若い詩人の肖像』
中野重治『歌のわかれ』
高見順『故旧忘れ得べき』
坂口安吾『古都』『真珠』
太宰治『ダス・ゲマイネ』
檀一雄『花筐』
立原道造『萱草に寄す』
井上立士『編隊飛行』
田宮虎彦『琵琶湖疎水』
西原啓『焦土』
日本戦没学生の手記『きけわだつみの声」
である。時代の背景もあり、「わだつみの声」が掲載されているのが異色だ。
これを読みながら、ふと思い出したのは、「青春時代」という歌謡曲の、
青春時代が夢なんて
あとからほのぼの 想うもの
青春時代の 真ん中は
道に迷って いるばかり(作詞・阿久 悠、作曲・森田 公一)
というフレーズであった。
なぜなら、本巻のほとんどの作品が、何年、何十年たってから振り返る作品だからだ。
夢は そのさきには もうゆかない
なにもかも 忘れ果てようとおもひ
忘れつくしたことさへ 忘れてしまつたときには
夢は 真冬の追憶のうちに凍るであらう
そして それは戸をあけて 寂寥のなかに
星くづにてらされた道を過ぎ去るであらう(「のちのおもひに」)
けふ 私のなかで
ひとつの意志が死に絶へた…
孤独な大きい風景が
弱々しい陽ざしにあたためられやうとする
しかし寂寥が風のやうに
私の眼の裏にうづたかく灰色の雲を積んで行く
やがてすべては諦めといふ絵のなかで
私を拒み 私の魂はひびわれるだらう(「初冬」)
二十五歳で死んだ立原道造は、まさに、青春の真っただ中で、しかし一言も「青春」を言わず、その心性を詠った。
解説の長田弘は、武田泰淳が、「かめれおん日記」の中島敦を、
「中島ははげしい狼疾をわずらってゐる。彼は指のために肩を失わんとしてゐる」
と、評したという。そひれは、まさに「道に迷っている」時代のただなかだということではあるまいか。
「何事に就いても之と同様で、竟には、失望しないために、初めから希望を有つまいと決心するようになった。落胆しないために初めから慾望をもたず、成功しないであろうとの予見から、てんで努力しようとせず、辱めを受けたり気まずい思いをし度くないために、人中へ出まいとし、自分が頼まれた場合の困惑を誇大に類推しては、自分から他人にものを依頼することが全然できなくなって了った。外へ向って展かれた器関を凡て閉じ、まるで堀上げられた冬の球根類のようになろうとした。それに触れると、どのような外からの愛情も、途端に冷たい氷滴となって凍りつくような石・となろうと、私は思った」(かめれおん日記)
は、中島敦(http://ppnetwork.seesaa.net/article/446642719.html)で触れたように、『李陵』の硬質施な文体と比べると、中国素材の作品が自分の素養である距離を取って書けているのに対して、自分を描くとき、自分との距離が定っていない。この違いは、作品と作家の向き合い方の差のように思われる。素養で書くというのは、漢文の素養で、自家薬篭中のものの如く書く、ということを意味する。そこに硬質の緊張感はある。それは、あるいは漢文というものの、独特の読み下し文の緊張感に依存する。しかし物語世界との距離は小さい『かめれおん日記』は、どこか自虐的というか、被虐的な翳がつきまとう。それが、ある意味、「指のために肩を失わんとしてゐる」ということなのではないか、と勝手に解釈する。
梶井基次郎『冬の蠅』は、自分の振幅、揺れ幅をきちんととらえている。だから、自虐的にも諧謔的にもならない。その視点がぶれていないからではないか、と思う。生き残っていた蠅がいなくなったことについて、
「私が鬱屈した部屋から逃げ出してわれとわが身を虐んでいた間に、彼等はほんとうに寒気と飢えで死んでしまったのである。私はそのことにしばらく憂鬱を感じた。私が彼等の死を傷んだためではなく、私にもなにか私を生かしそしていつか私を殺してしまうきまぐれな条件があるような気がしたからであった。私は其奴の幅広い背を見たように思った。」(『冬の蠅』)
視点のぶれない文章は、対象との距離をあやまたない。
後世に書かれた作品の中で、高見順『故旧忘れ得べき』は、自虐的に書くことで、その自分を許そうとするような甘ったれを感じた。この距離感は、太宰のそれとともに、僕はあまり好かない。
伊藤整『若い詩人の肖像』と中野重治『歌のわかれ』は、好対照に思える。『若い詩人の肖像』は、実名を出し、丹念に「若い詩人」としての自分を、一定の距離で、価値観、つまり、不当な卑下も傲慢にも堕さない、視点を保ち続けている。作品の結構は、十分に練り込まれ、作り込まれている。なのに、作為を感じさせない。他方、『歌のわかれ』は、穿ちすぎかもしれないが、最初から、「歌」との離別を考えられたものに見える。しかし、前半、自分との距離が保てず、自虐や諧謔に振れて来たのに、最後になって、
「彼は袖を振るようにしてうつむいて急ぎながら、なんとなくこれで短歌ともお別れだという気がしてならなかった。短歌とのお別れということは、このさいに彼には短歌的なものとの別れということでもあった。それが何を意味するかは彼にもわからなかった」(歌のわかれ)
という決意が、作為的に見えて仕方がなかった。
「きけわだつみの声」を読みながら、不意に、京五輪男子マラソン銅メダルの円谷幸吉の遺書、
父上様 母上様 三日とろゝ美味(おい)しうございました。干し柿 もちも美味しうございました。
敏雄兄 姉上様 おすし美味しうございました。
父上様 母上様 幸吉は、もうすっかり疲れ切ってしまって走れません。
何卒(なにとぞ) お許し下さい。
を思い出していた。川端康成は、円谷の遺書について、
「相手ごと食べものごとに繰りかへされる〈美味しゆうございました〉といふ、ありきたりの言葉が、じつに純ないのちを生きてゐる。そして、遺書全文の韻律をなしてゐる。美しくて、まことで、かなしいひびきだ」
と語ったという(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E8%B0%B7%E5%B9%B8%E5%90%89)。哀切な文章に違いないが、それは、遺書ということを知っているからだ。それがなければ、ありふれた日記ととらえてもいい。
原爆投下直後に、広島近くに動員されていた経験を描いた、西原啓『焦土』に、被爆して死んだ友人について、
「新井はもはや正視することができなかった。恐らく山崎が意識を失う以前に書いたと思われる数枚の大学ノートの切れはしが枕辺に散っていた。新井はあたりを憚りながらその一枚を手にしてみた。月見れば乳千々にものこそ悲しけれ わが身一つの傷にはあらねど。涙がとめどもなく新井の頬を流れ始めた。患部の痛みに苦しみぬいた山崎を想ったのではない。ついに死なねばならぬ山崎の無念を想ったのではない。他人の歌に自分の思いを託さねばならなかった山崎のエネルギーの衰弱が痛ましかったのだ」(『焦土』)
と書き、「山崎を単なる記憶に終わらせまいとする意志」が、この作品だ、というように読める。
自分の言葉で、自分を描くためには、自分に対する冷静な距離が必要なのかもしれない、と思いつつ、自分の言葉て、自分の思いを語り得る人間の能力に嫉妬した。
なお、太宰治(http://ppnetwork.seesaa.net/article/451454488.html)については、触れたことがある。
参考文献;
大岡昇平他編大岡昇平他編『青春の屈折上(全集現代文学の発見第14巻)』(學藝書林) |
|
信長殺害 |
| 金子拓『信長家臣明智光秀』を読む。
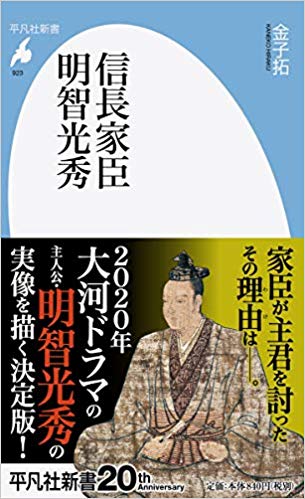
本書の特徴は、第一に、
信長家臣、
とタイトルにある通り、まず、はっきりしない、信長に仕える以前の、
「前半生のには謎が多く、出自や信長に仕えるまでの経歴がわかるような良質な史料はほとんど残っていない」
部分には踏み込まないことだ。光秀討死の報を聞いた、奈良興福寺の塔頭多聞院主英俊が、
「惟任日向守ハ十二日勝竜寺ヨリ逃テ、山階ニテ一揆にタタキ殺サレ了、首ムクロモ京ヘ引了云々、浅猿々々、細川ノ兵部大夫ガ中間ニテアリシヲ引立之、中國ノ名誉ニ信長厚恩ニテ被召遣之、忘大恩致曲事、天命如此」
と切り捨てた多聞院日記に。
細川ノ兵部大夫ガ中間、
つまり細川藤孝の家臣であったということ、あるいは、「永禄六年(一五六三)諸役人付」(光源院殿御代当参衆幷足軽以下衆覚)に、
足利義昭の足軽衆の一人、
として明智の名がある、という程度にしか、前半生はわかっていないのである。
第二の特徴は、
明智光秀と吉田兼見、
と、一章を設けて、吉田神社の吉田家当主との関係を掘り下げたことである。吉田兼見は、細川藤孝の従兄弟に当たる。
本能寺の変当日、兼見は、六月二日、
「本應寺・二条御殿等放火、洛中・洛外驚騒畢、悉討果、未刻大津通下向、予、粟田口辺令乗馬罷出、惟日対面、在所之儀万端頼入之由申畢」
と、惟日(惟任日向守、つまり明智光秀)に会いに出かけている。後に、やばいと思ったのか、粟田口辺にまで赴いて光秀と対面した部分を削除し、こう他所事のように書き換えた。
「戊子(つちのえね)、昊天(ごうてん)當信長之屋敷本應寺而放火之由告來、罷出門外之処治定也、卽刻相聞、企惟任日向守謀叛、自丹州以人數取懸、生害信長、三位中将為妙覺寺陣所、依此事取入二条之御殿、卽諸勢取懸、及數刻責戦、果而三位中将生害、此時御殿悉放火、信長父子・馬廻數輩・村井親子三人討死、其外不知數、事終而惟日大津通下向也、山岡館放火云々、右之於二条御殿双方乱入之最中、親王御方・若宮御两三人・女中各被出御殿、上之御殿へ御成、中々不及御乗物躰也」
しかし、兼見と光秀の関係は、ただならぬものがある。三日、四日、近江を抑えた光秀は、五日に安土城に入り、八日京へ戻る。兼見は、日記に、
「八日、甲午、早天發足安土、今日日向守上洛、諸勢悉罷上、明日至攝州手遣ひ云々、先勢山科・大津陣取也、
九日、乙未、早々自江州折帋到来、唯今此方へ可來之由申了。不及返事、飛脚直出京、即予為迎罷出白川、
未刻上洛、直同道、公家衆・攝家・清華、上下京不殘為迎至白川・神楽岡邊罷出也。向州云、今度上洛、諸家・地下人礼之義堅停止之由被申、於路次對面勿論、於此方無對面之義也、次至私宅、向州云、一昨日自禁裏御使忝、為御礼上洛也、随而銀子五百枚進上之由、以折帋予に相渡之、卽可持参候由申訖、次五山之寺へ百枚充各遣之、大徳寺へ百枚、予五十枚、為當社之御修理賜之、五山之内依不足、賜予五十枚之内廿枚借用之、次於小座敷羞小漬、相伴紹巴、昌叱、心前也、食以後、至下鳥羽出陣」
とある。この関係は、ちょっと不思議であった。本書で、光秀は、兼見の父兼右とも懇意な関係にあり、それが兼見とも続くことを解き明かす。兼見室のきょうだいである、佐竹出羽守は、光秀に従い、
「『明智』の名字と『秀』の諱を許され、明智秀慶と名乗った」
ともある。光秀の年齢は、
五十五歳、
五十七歳、
等々があるが、『当代記』には、
六十七歳、
とする。吉田兼右との親交について、
「光秀はもともと兼見の父兼右と親交があった…。実は兼右は、永生十三年生まれなのだ。光秀六七歳説を採ると、まったくのおない年ということになる」
と、このことは、光秀の没年齢とも関わってくる。
第三の特徴は、「本能寺の変」という言葉を使わず、「あえて即物的に」
信長殺害事件、
としたことだ。ここで、この件は、
歴史的事件、
としてよりは、
個人的事件、
としての含意を持たせたのだと、僕は推測する。それは、殺害動機と絡んでくる。著者は、
「結論から先に述べておこう。
最近特に注目されるようになってきた、信長の四国政策転換(長曾我部氏の処遇)問題や、美濃稲葉氏と光秀の間に起きた斎藤利三・那波直治の召抱えに関する確執といった、天正十年になってから起きた光秀の活動に深く関わることがらについて、信長とのあいだに生じた思惑のすれちがいを根底に、それが原因となったらしい信長による光秀の殴打、さらに秀吉支援のための出陣命令による家康饗応役の突然の変更が直接のきっかけとなり、面目をつぶされた光秀が信長を討った、というものである。」
と、動機を書く。詳しくは本書を読んでいただくしかないが、
四国政策の変更は五月七日、
饗応役を解かれて出陣命令は五月十五日前後、
斎藤利三・那波直治の召抱えの裁定は五月二十七日、
と続く。
召抱え問題では、那波直治を稲葉家に戻し、利三は切腹させるというものである。光秀が承知せず、
「髪束をつかみ、膝本へ引きよせ、頭を二つ三つはり給いし」
とある(宇土家譜)。この件は、
「有力家臣同士の紛争にあたり、信長が双方を納得させる裁定を下せなかったのは、体系的な国法をもたず、彼の上意がすべてを優先する政治のあり方に問題があった」
帰結でもある。ひとつひとつは些細なことだが、光秀の面目失墜の積み重ねが、爆発した、という見方である。
変の後、勅使として安土城へ赴いた兼見は、光秀と面談するが、日記に、
今度謀叛の存分雑談(ぞうだん)なり、
と記した。
「『雑談』とひと言で片づける程度の、たいした動機ではなかったのかもしれない」
と著者は書く。細川藤孝に宛てて協力を求めた手紙では、
不慮の儀、
と書く。特段の大義名分がなかった証かもしれない。
本能寺の変、
と書くより、
信長殺害事件、
と書くことで、かえって事は見やすくなったのかもしれない、という気がする。
光秀については、
「謀叛」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/399629041.html)、
「光秀」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/469748642.html)、
でも触れたことがある。
参考文献;
金子拓『信長家臣明智光秀』(平凡社新書) |
|
気っ風 |
|
柳家小三治『どこからお話ししましょうか‐柳家小三治自伝』を読む。
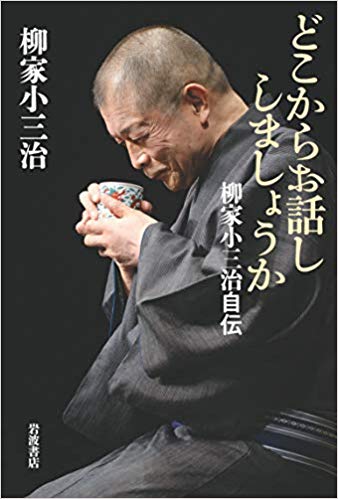
10代目柳家小三治の自伝、というか自分史語り、である。別に小三治(師匠、といちいちお断りしないが、その含意で書いています)の追っかけでもないし、落語通でもないので、あくまで通りすがりにちょっと読んだ感想を述べてみたい。
前に、広瀬和生『なぜ「小三治」の落語は面白いのか?』で、小三治に触れているが(http://ppnetwork.seesaa.net/article/405538611.html)、それと重なるところが少なかった気がする。
まくらの小三治、
という異名があり、「まくら」だけを集めたわけでもなさそうだが、小三治のトークを録った『ま・く・ら』『もひとつ
ま・く・ら』という書籍化されたものまである。たしか、
「まくら」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/421083802.html)、
で触れたことと重なるが、
まくら、
は、その演目に合ったものをするが、基本的には、
演じる落語の演目に関連した話をする、
現代ではほとんど使われなくなった人、物、様子などの解説をする、
2種類が骨格で、それにいろいろまぶす結果、いろいろな話が加えられるらしい。小三治のように、
まくらだけで高座が終わる、
ということもあるが、そこまで行くと、本題に入らなくて(そこで終わらないで)、このまま続けてほしい、と(観客側が)いうほどの、まくら自体が、
エンターテイメント、
になっているからかもしれない。
「マクラは、噺の本題とセットになって伝承されてきているものが少なくない」
という。しかし、素人ながら、マクラの果たす役割は、ただ、
現実(この会場のこの時、この場)と噺の世界、
をつなぐ、
回路
というか、
異次元を開くまじない(「開けゴマ」みたいな)、
というだけではない気がする。もちろん、そういう意図があるにはあるが、僕は、いま、噺をしようとしている噺家その人が、その導き手で、その人の口先に乗って、一緒に噺の世界へ入って行くための、
協約関係、
というか、
共同作業関係、
というか、
同盟関係、
というか、
違う言い方をすると、
この(噺の)船頭の船に乗ってついて行っても大丈夫、
という見立ての位置づけにあるのではないか、という気がする。しかし、『ま・く・ら』に載る、
めりけん留学奮闘記、
玉子かけ御飯、
駐車場物語、
他の「まくら」をみると、巧まず飾らず、
どうだいこんな自分だが、
と、おのれ自身を自己開示して見せている感がある。ある意味、そこに、個性があり、人柄が出る。というより押し出す。独特の場づくりになっている。
さて『どこからお話ししましょうか‐柳家小三治自伝』である。このタイトルが、たまらなくいい。本書そのものの自然体を象徴する表現になっている。
その自然体の背後に、とてつもない努力の跡があるはずである。誰かが、
努力できるのも才能、
といった。それを随所でさりげなく語っている。読むうちに、我身を振り返って、思わず、背中に冷や汗が出る。身もだえするほど、脂汗が出る。とても評ずるどころではないのである。で、そんなところをピックアップしておくにとどめる。
お客さんに受けることについて。
「『粗忽長屋』をやってみると、最初からおしまいまで、お客さんに受けるための仕掛けが次々と出てくるんです。くやしいから全部受けようと思って、かなり完成させたんですけどね。そうしたら、師匠にピシッとやられた。噺ってものは最初ボソボソやってても、一番最後、ウワーって盛り上がっておしまいになるもんだ。お前の噺は最初から盛り上げ盛り上げしている。あれじゃあ、自分もくたびれ、客もくたびれちゃうじゃないか、と。(中略)全部うけようとしちゃあいけない。ちょっと受けたなと思ったら、次、ここは受けるはずだと思うところは受けないようにスーッと通り過ぎろとか、結構、技術的なことも言われましたね。それまでは全部受けさせていたんです。『お前のは受け過ぎだ。ただのまんだんになっちゃう。どういう噺か、なぜこの噺がおもしろいのかっていう、一番肝心なことをお前は飛ばしてしまう』って…。」
まくらが変化するきっかけについて。
「この対談(ナベサダとの)をやるまでの私は、高座では決まったマクラしかやらなかった。きちんと、どこからでも文句を言われないようにやっていた。だんだん、これでいいのかよって思うようになった。外側をつくろって、うまく聞こえるのは恥ずかしいことだっていうのは、その後、ほんとうに私のきほんですね。芸、芸術、人の生き方でもなんでも、いいじゃないの、つまずいたって。その人がなにをしようとしているのか、目指していることが素敵だったら、拍手したいよね。また、拍手できる人間になりたいと思う。それにはまず自分の側を取り去ることしかない。結局、そこに行き着いちゃった。」
「私のマクラがだんだん長くなったのは、ラジオの『小沢昭一的こころ』の影響もあるでしょうね。小沢さんの『明日のこころだあー』っていう言葉で番組が終わった途端、一緒にタクシーに乗っていた、私の師匠の小さんが『これが現代の落語っていうもんだよ』ってつぶやいたのを、私は忘れません。(中略)こういう切り口でいいんだ、っていう気持ちになったかもしれません。(中略)私のマクラはなんにでも影響受けてますね。いいと思うものはなんでもいいな、って首つっこんで行っちゃう。
だから、(入船亭)扇橋がぐだぐだ言っているのを聞いて、私のマクラが長くなったっていうこともあるでしょう。若いころから、私よりマクラが長かった。(中略)主に自分のことなんでしょうけど、なにを言ってたんでしょうかねぇ。あいつはきっと、ほんとうのことを言ってたんでしょう。わざわざおもしろい、ギャグのようなものを並べて喜ばせようっていう漫談じゃなくて、『そんなんで、おもしれえのかよ』って思うんだけど、聞いているとなんかおもしろいような気がするんですね。だから、『こんなんでいいのかい』って私もやりだしたのかもしれません。そしたら、私のほうがながくなったちゃった。」
入船亭扇橋について。
「私が『千早ふる』っていう噺をやったときのことです。(中略)私がはなし終えて頭下げて高座をおりてくると、楽屋で障子越しに聞いていた扇橋がぽろぽろって涙をこぼして『落語ってかなしいね』って言ったんです。なにがかなしいってことは言わない。だけど、五年後ばったり出会う男と女の人生を考えると、『人生はかなしいね』ということにもつながっていくし、それを理解しながら、『噺の中に入り込んで、一生懸命はなしていくのはかなしいね』ということの、ひとつの美的表現かなあ。
噺に出てくる人の心に寄り添わないと噺はできないって気づいたのかもしれない。それに、かなしさを笑いでまぎらしてしまおうっていう、落語そのもののかなしさっていうものもあるかもしれない。(中略)
なんかあいつは、おれのそばにいた。なんだったんだろう。やっぱりおれのこと好きだったのかな。そう思うと、おれもあいつのこと好きだったんだねえ。まあ、困ったやつです。」
バイクから学んだこと。
「自分がいっぺんその中へ飛び込んでみると、暴走族がいいっていうわけじゃないけど、そうしなきゃならない人にはなにか理由があるんだって考え始めます。すると、世の中のどんな罪をおかした人でも訳があるんだろうって考える。人間が根本的に変わっちゃったんです。
落語をやるときでも、そういう人間に変わっちゃった人の噺と、変わっていない人の噺では違うと思う。(中略)世の中の人を悪い人といい人に分けて、自分はいつもいい人の側にいる。その考えは違うなって思ってくると、落語も世間の人を見る目も変わってきた。
そう見ようとするっていうより、そう見えちゃう。見えなきゃ、人間は理解できない。人間を理解できなきゃ、落語はできない。落語は、人生の、社会の縮図ですから。いつの間にか人が生きるということの根本までかんがえるようになる。」
「小言念仏」をめぐって。
「(金馬師匠の『小言念仏』からの)抜け道のひとつが、三枡家勝太郎さんです。そのやり方は、金馬師匠とはまったく違う。金馬師匠のは、エンターテインメント。いってみれば、シネラマを見ているような、会場中に小言をまき散らすようなやり方です。勝太郎さんのは、ほんとに高座の前にまあ多くても五人、三人ぐらいの家族がいるだけで、それに向かってぶつぶつぶつ言う。それ以上、声を遠くに張りはしない。その景色がおかしかった。
私がとるのはこっちだなと思って、それをめざしてやったんですけとじ、結局は金馬師匠みたいな形になってきちゃった。そこがまことにくやしい。残念だ。(中略)ほんとうはもう誰も聞かないぐらいの声で、いちばん前の席の人に向って話しかける。いや、話しかけるっていうのがもう違う。話しかけちゃあ、いけないんですよ。」
古今亭志ん朝について。立川談志について。
「志ん朝・小三治」の落語会をやりたいっていうのは、会をやるひとたちにとってはひとつのステイタスだったみたいですけど、なかなか実現しないんです。志ん朝さんのとこへいっても。小三治のところへいっても、なかなかイエスって言わない。だれかがあるとき、マネージャーをやっていた志ん朝さんのカミサンに『どうして志ん朝さんは、小三治さんと一緒に会をやってくれないんですか』ってたずねた。そしたら『きっと、あの二人は芸が似てるから、二人ともいやなんでしょう』って言ったっていうんです。これは言い得て妙ですねえ。」
「みんなは志ん朝さんの口調に注目するけど、私は口調の奥にあるものを見ようとした。これは、だんだんその後になって気がついていくことですけど、芸の本域、芸の奥の院、神髄っていいますか、中身は結局、そこなんです。表面に表れているところより、その奥にあるものがなにかっていうことです。表面に見えているものだけで世間は評価して、感心したりしなかったり、で終わってしまうんだけど、そうじゃなくて、そのむこうにある奥でどんな会話を登場人物がしているのか。まあ、最後はそこじゃないですかねえ。そうすると、そこに演者の個性っていうものが、いつのまにか感じられるようになる。演者の個性が好きだからっていうんじゃなくて、その奥をのぞこうとしていると、いつのまにか演者の個性に動かされているっていう……ちょっと難しいですけど、これは。
私はやっぱり口調じゃなくて、中に秘められている人柄、立場、そういうもので噺をしていかなきゃあ、人を動かんすことはできないんだなってことに、まあ、気づくことは気づいたんです。(中略)
志ん朝さんは、若いころのテンポのいい口調のままでは、いつかいけなくなるだろうということに、晩年、ちょっと気がついてきたようでした。どうすればいいのかわからないけれども、これじゃダメだなってことを、感じ始めていました。それだけでも私は、えらいなと思いました。闘ってるなって。闘っていれば、そのうち答えがでてくるんですよ。闘わないやつにはなにも出てこない、と私は信じてるんですけどねえ。
口調だけに頼らずにといっても、ほとんどかわらないんです。でも、なんか噺の中の人物のこころで噺を進めていくってことが見えてきた。(中略)
談志さんには、これは言ってもわからないんじゃないかなあ。あの人を心底ひっくり返して説得しなきゃなんない。有名になりたいとか、議員になりたいとか、小三治になりたい、小さんになりたいって、そういうことがなかったら、あの人はとんでもない人になってましたね、あの先、どうなったんだろうって思いはあります。若いときから口調もしっかりしていたし、言うことや考えてることもはっきりしてたから、まともにやってまともにおもしろいひとだった。落語がおもしろいんですから。」
「青葉」をめぐって。
「受けるところは受けたいとか、短い間でわっと笑わせるとか、というもんじゃないんだということは、私がこの世界へ入ったころから言われてました。『そこがおかしいから笑うんじゃなくて、その前があるからおかしいんだ』っていうのは、いまだにこの世界に入ってきた人たちはわからないんでしょうか。…もったいないですねえ。
伏線を敷くのも、順序だった言葉とか、そういうことではないんです。それより、自分のお庭のデザインなり、吹いてくる風の匂いなり、色なりがちゃんと見えていれば、自然にそういうものが噺に出てくる。そういうものがちょっと見えただけで、庭全体が見えてくる。そのためには、庭の設計図が自分の頭の中に出来てなきゃいけない。どこかへ行って『ここみたいなお庭かな』とか、ふだんからそういうものを拾い集めて、頭の中に入れておく。それを思い出そうとすると、その景色がふわー、ふわーって出てくる。(中略)
ぽつ、ぽつって言ったなかで、そのぽつぽつの間を埋め尽くしていく景色がお客さんの頭の中に自然に広がっていけば、最高でしょう。お客さんと演者との間合いと間合いがうまく合ったら、そういう景色がみえてくるんじゃないですか。」
この話ぶりに見える気っ風が小気味いい。その人柄と心映えを映している。
本の帯に、こうある。
「噺家になってよかった。一歩、一歩……来ました。」
こう言いたい。
「噺家になってもらってよかった」
と。
参考文献;
柳家小三治『どこからお話ししましょうか‐柳家小三治自伝』(岩波書店)
野村雅昭『落語の言語学』(平凡社選書)
http://allabout.co.jp/gm/gc/207062/ |
|
大道無門 |
|
西村恵信訳『無門関』を読む。
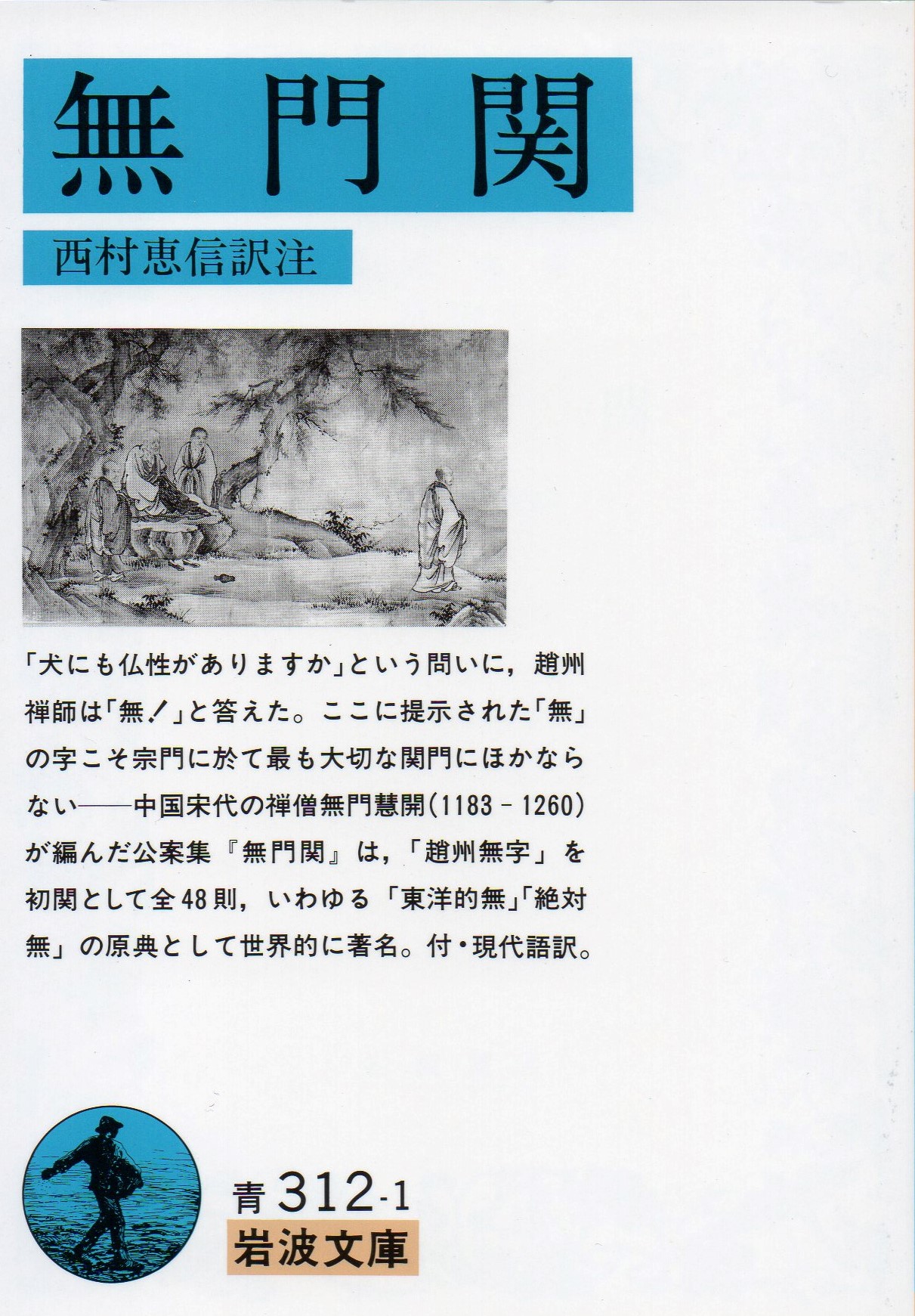
読んだ程度で何かが会得できるわけではないし、浅学の者の生悟りが叶うわけでもない。無門は、
何ぞ況や言句に滞って解会(げえ)を覓(もとむ)るをや、
と戒めている。
通りすがりに、いくつか感じたことがある。それを書き留めておく。
大道無門、千差路有り、
此の門を透得せば、乾坤に独歩せん、
とある。しかし、
参禅は須らく祖師の関を透るべし、
ともある。そして、祖師は問う、
趙州和尚、因みに僧問う、狗子(くす)、還(は)た仏性有りや、州云く、無。
と。
如何が是れ祖師の関。只だ者(こ)の一箇の無字、乃ち宗門の一関なり、遂に之れを目(なず)けて禅宗の無門関と曰う、
そして、
平生の気力を尽くして箇の無の字を挙せよ、
と。本書の編者無門慧開(1183〜260年)自身が、自著で、
老拙もまた一偈有り。諸人に挙示(こじ)せん。敢えて道理を説かず。若し也(ま)た信得及(しんとくぎゅう)し挙得(ことく)熟せば、生死(しょうじ)岸頭(がんとう)に於いて大自在を得ん。無無無無無、無無無無無。無無無無無、無無無無無」
と書いているように、この「無」の字に苦しんだ、とか(本書解説)。無門は、
狗子仏性、全提正令、
纔(わずか)に渉れば、喪身失命せん、
と曰う。有無どちらかに偏ることを嫌うと見た。
本書には、四十八の公案が載るが、その多くは、答えを出そうとしても出せない。般若心経の、
色不異空、空不異色、色即是空、空即是色、
ではないが、一種矛盾、二律背反の中に、答えを求めるものが多い。
声、耳畔(にはん)に来るか、耳、声返(しょうへん)に往くか、(中略)若し耳を将(も)って聴かば応に会し難かるべし、眼処に声を聞いて、方始(はじ)めて親し。
語黙離微に渉り(語れば微に陥り、黙すれば離に陥る)、
口を開けば即ち失し、口を閉ずれば又喪す、
是れ風の動くにきあらず、是れ幡の動くにあらず、是れ心の動くにあらず、
即心即仏、非心非仏、
是れ一か是れ二か、
語黙対せざれ、
言、事(じ)を展(の)ぶること無く、語、機に投ぜず、
言を承(う)くるものは喪し、句に滞(とどこお)るものは迷う、
有語なるを得ず、無語なるを得ず、速かに道(い)え、速かに道え、
你(なんじ)に拄杖子(しゅじょうす)有らば、我你に拄杖子を与えん。你に拄杖子無くんば、我你が拄杖子を奪わん、
百尺竿頭に須らく歩を進め、十方世界に全身を現ずべし、
等々。この中では、「百尺竿頭」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/426438375.html)で触れた、
百尺竿頭に坐する底の人、然も得入すと雖も、未だ真を為さず。百尺竿頭に須らく歩を進め、十方世界に全身を現ずべし、
が、強く心に残る。理屈ばっているせいかもしれない。
心は是れ仏ならず、智は是れ道ならず、
といい、
若し心を認(と)めて決定(けつじょう)すれば、是れ仏ならず、若し智を認めて決定すれば、是れ道ならず、
というとある。無門の言う、
是れ一か是れ二か、
つまり、
一でもあり、二でもある、
ということは理屈ではない境地なのだろう。ちょっと僕には分からない。
ところで、
雲門、因みに問う、如何なるか是れ仏。門云く、乾屎橛。
という乾屎橛は、通常、「べらぼう」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/421256499.html)で触れたように、クソ掻き箆とされてきたが、本書では、棒状のまま乾燥したクソそのものをいう、としている。たいして意味は変わらないが。。。
参考文献;
西村恵信訳『無門関』(岩波文庫) |
|
不慮の儀 |
|
諏訪勝則『明智光秀の生涯』を読む。
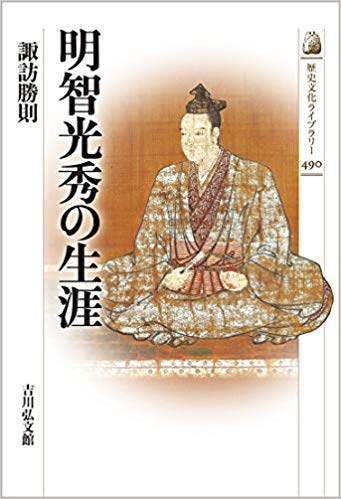
相次いで、何匹目かの泥鰌を狙って、光秀ものが上梓されている。その中で、陰謀論を主張する著者は避けたら、
「黒田官兵衛」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163528.html)、
「古田織部」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/435235025.html)、
を書いた著者のものがあったので、取り上げてみたい。
何か特徴を出さないと、ということだろうか、
「既出の史料をもとに新たな史料を加味して光秀の履歴を再検討することにした。あまり顧みられることのない文芸の側面からも光秀の立ち位置を探ってみようと思った」
と述べる。その高い素養は、
「一朝一夕に身につくものではなく、…幼い頃から、教養高き知識層の許で育ち、文芸に関する修養に努めたとみて間違いないであろう。決して低い階層の出身ではない」
その光秀の教養は、
「光秀が美濃土岐氏の文化圏にその淵源が求められると思料する。…土岐氏は、清和源氏の頼光流で鎌倉末期に土岐頼貞が美濃守護に補されてから、同国の文芸活動の中核として歴代土岐当主が牽引役を果たした。…頼貞は、玉藻・風雅・新千載・新拾遺・新後拾遺の各勅撰和歌集に入集するなど、『歌人、弓馬上手』と伝えられる。…政房の代には、中世随一の文学者である公家の三条西実隆との交流がみられるなど文芸活動が活発に行われた。(中略)また、守護代斎藤一族の文芸活動も看過できない。(中略)
かくして、美濃国において土岐・斎藤氏により文芸活動が盛んに行われ、家臣たちもこぞって嗜んだのである。」
そして光秀は、美濃出身なのである。『兼見卿記』に、
「明智十兵衛尉折帋を以て申し来りて云く、濃州より親類の方申し上ぐる也」
とあり、また、『立入左京亮入道隆佐記』にも、
「美濃国住人、ときの随分衆也」
とあり、さらに、光秀室も美濃妻木氏出身で、
「美濃出身で土岐氏の家臣であったことを補う情報といえる。また、光秀の重臣斎藤利三が美濃出身ということから、光秀も美濃国に縁があって利三との関係が成り立っていると考えて間違いないであろう」
と、著者は見る。また、『光源院殿御代当参衆幷足軽以下覚』の「永禄六年初役人附」に、足軽衆の中に、明智の名があることについて、
「足軽衆として『山口勘介・三上・一卜軒・移飯・沢村・野村越中守・内山弥五太兵衛尉・丹彦十郎・長井兵部少輔・薬師寺・柳本・玖蔵主・森坊・明智』の名が列記されている。ここにみられる『明智』を光秀に捉えて間違いないと思われる。足軽といっても、下級の武士層を指すものではない。
たとえば、山口甚介(勘介)は、諱を秀景と称し、もともと公家の葉室家の侍で、その後将軍義昭に仕えた人物である。『言継卿記』元亀元年(1570)九月二十七日条には、『武家御足軽山口甚介』と記されており、甚介のように公家に奉公するなど相応の立場の者が足軽衆に名を連ねていたことがわかる。(中略)そうなると、光秀はこれらの人々に交じって名を連ねるからには、将軍の側近になるのに相応しい資質・素性であったと思料される」
とする。「足軽」とは、
平時は雑役、戦時には歩兵となり、足軽組(足軽大将の下に鉄炮足軽、弓足軽、鑓足軽に編成)に属する最下層の武士、
である。武士というのは、主人持ちであるが、
武家の従者は、
地位の高い郎党(等)、
地位の低い従類、
に分ける。主人と血縁関係のある一族・子弟は、
家子(いえのこ)、
と呼ぶ。
家子・郎等・従類などを合わせて、
郎従(ろうじゅう)、
という。郎党(ろうどう)は相伝の所領を持たない家臣。家子は自己の所領を持ち独立の生計を営みながら、主家と主従関係で結ばれている。従類は、郎党の下の若党、悴者(かせもの)を指す。家子・郎等・従類は、皆姓を持ち、合戦では最後まで主人と運命を共にする。この下に、戦場で主人を助けて馬を引き、鑓、弓、挟(はさみ)箱等々を持つ下人(げにん)である、
中間、小者、あらしこ、
がいる。身分は中間・小者・荒子(あらしこ)の順。あらしこが武家奉公人の最下層。姓を持たない。中間の上が、悴者(かせもの)、若党(わかとう)、その上が郎党(ろうどう)となる。つまり、光秀は、最下層に近い位置にあったといえる。将軍直属の足軽衆である。いわゆる「足軽」よりは高い地位にあるとみていい。
ちなみに、同じ義昭の家臣であった細川藤孝は、
相伴(しょうばん)衆、
である。格段の差がある。
しかし、光秀は、
「美濃国で培った教養人としての素養」
があったから、朝倉氏に受け入れられたし、義昭にも受容されるだけ資質があった、と著者はみなす。たしかに、その教養は、信長にしたがって入京した直後、「中央における蓮歌会の総帥里村紹巴とその一門を中心とした」蓮歌会に参会しているのである。そこには当代最高の武家文人細川藤孝も出席している。この会で発句を詠んだのは、明院良政、信長の祐筆である。その素養を武器に、光秀が、中央文人の中に地位を占めていく、ともいえるのである。この蓮歌会の意味について、著者は、こうまとめている。
「一点目は、上洛後間もない段階において、中央文人と交流をしていることである。蓮歌を詠むためには、高い教養が必要である…。光秀は、この段階ですでに蓮歌に関する知識・技量を身につけていたことになる。朝倉氏のもとに逗留していた際には、さまざまな蓮歌会に出席していたとみて間違いないであろう。その基礎は、美濃で育ちその幼少期に育まれたと考えられる。
二点目は、信長の祐筆として、この時期に庶政に当たった良政と交流するからには、光秀も織田政権においては早い頃から相応の立場につき、職務を遂行していたことがわかる。」
いま零落しているが、それなりの素養を積める環境で育った、ということである。この点は、ある面、光秀像の一つのイメージとも重なる。光秀の出自を教養面から補強したのが、本書の特色といっていい。
さて、信長の命で、秀吉救援のために中国出陣に先立ち、光秀は、五月二十八日蓮歌を催し、有名な、
ときは今あめが下知る五月哉、
と発句を詠み、
国々はなほ長閑時、
と挙句を詠んだのは、光秀嫡男光慶である。
それにしても、この謀叛は、杜撰である。本能寺襲撃後、信忠をも殺害した直後、光秀は、
「瀬田を本拠地とする山岡景友・景猶兄弟に同心を求めるが、拒絶された。山崎兄弟は、瀬田の橋に火をつけ山中に退いたのである。光秀にとって誤算というより、最初から計画性がなかったことがわかる」
直後、細川藤孝に与同を求めた手紙を書くが、そこに、
吾等不慮の儀、
と書いた。
おもいがけない、
とか
意外、
の意である。自分で起こしながら、意外とは、とぼけているというか、随分無責任な言い条である。突発的な、あるいは発作的な決断に見える。理由はいろいろあるかもしれないが、大義名分があってのことではなさそうである。著者は、四国政策の転換を一応のきっかけとみなしている。
著者は謀叛を考えるためのキーワードを、この、
不慮の儀、
の他に、
謀叛随一、
を挙げる。『言経(ときつね)卿記』に、
日向守内斎藤内蔵助、今度謀叛随一也、堅田ニ窂籠、則尋出、京洛中車ニテ被渡、於六条河原ニテ被誅了、
とある、山科言経が「謀叛随一」とみなしていた、ということである。
「公家衆の記録には、『かれなと信長打談合衆也』『今度謀叛随一也』ときされていて」
公家社会では利三を首謀者としている。
当初長宗我部氏との取次をしたのは光秀である。
「光秀の重臣斎藤利三の兄石谷頼辰の義妹が長宗我部元親の性質という関係から担当したのであろう」
しかし、前年位から四国政策が変化する。「信長主導のもとに三好康長を中核として四国政策を推進」し、本能寺の変直前には、信孝を総大将とする四国侵攻が決定している。光秀は、信長の四国政策の「蚊帳の外」におかれている。この少し前、信長は老臣佐久間信盛らを突然粛清した。
「粛清には、主君として、台頭してくる者の排除と不要な家臣の処分がある。…信長は猜疑心が強く猜疑心が強いとされる。それが故、粛清と反逆が繰り返された。(中略)信長の家臣たちはそれぞれ処分されることを想定していたことは間違いない。天正八年の佐久間信盛ら主要家臣の粛清後、四国政策と秀吉の実力の伸長があり、光秀の心は動揺していたと思う。おびえていたのかもしれない。」
「計画性のない無謀な戦いを強力に推し進め、光秀の気持ちを後押ししたのは、斎藤利三ではないかと考えられる。利三としても、兄石谷頼辰を保護するためにも信長の排除が必要になったのであろう」
と推測する。是非はわからないが、その決断を促す要因に、
「洛中近辺には、光秀の軍勢以外に、織田軍の主力部隊がいない…空白の状況」
が、あった。戦国武将なら、天下取りの野望はある。これを奇禍として、不意に決断された、と見る。計画性が欠けている所以である。
本書で、もうひとつ面白いのは、光秀と秀吉を随所で比較しているところである。
「秀吉は気性が激しい信長に対して、危機を回避する対処能力に優れていた。」
とし、例えば、勝家と対立し、独断で戦線離脱し、信長に激怒されながら、
「『播磨国中、夜を日に継いで懸けまはり、悉く人質執り固め、霜月十日比には播磨表隙明申すべきの旨』と(信長公記に)記録されていて、秀吉は、播磨侵攻に際し、昼夜を分かたず奔走し、播磨の諸将から人質を集めたとある。この秀吉の尋常では考えられない迅速な活きに対して信長は秀吉を認め、播磨から一時、離れて帰国するように朱印状をもって伝えた。しかし、秀吉は、まだ働きが足りないとして但馬方面を攻め、山口岩淵の城を陥落させ、竹田城を攻略させている」
という、「猛烈な行動力のアピール」というか、パフォーマンス力は、到底光秀にはない。それは、毛利と和睦して上洛するとき、摂津の中川清秀に、
「仍ただ今、京より罷下候者慥申候、上様并殿様何も無御別儀、御きりぬけなされ候、ぜゝか崎へ御退きなされ候内ニ、福平左三度つきあひ、無比類動にて、無何事之由、先以目出度存知候、我等も成次第、帰城候状、猶追々可申承候、云々」
と、平然と信長存命の手紙で嘘八百を並べ立てていく。
「瞬時の対応には、感服せざるをえない。秀吉は行動が迅速であり、即座に何をしなければならないか分析し対応する能力に長けている」
と。すでに、山崎での合戦の前に勝敗は決していたようである。
光秀については、
「謀叛」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/399629041.html)、
「光秀」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/469748642.html)、
「信長殺害」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/472831218.html?1578548959)、
等々でも触れた。他の書に比べると、本書は、書き急いだせいなのか、少々粗笨なのが目に付いたのが気になった。
参考文献;
諏訪勝則『明智光秀の生涯』(吉川弘文館) |