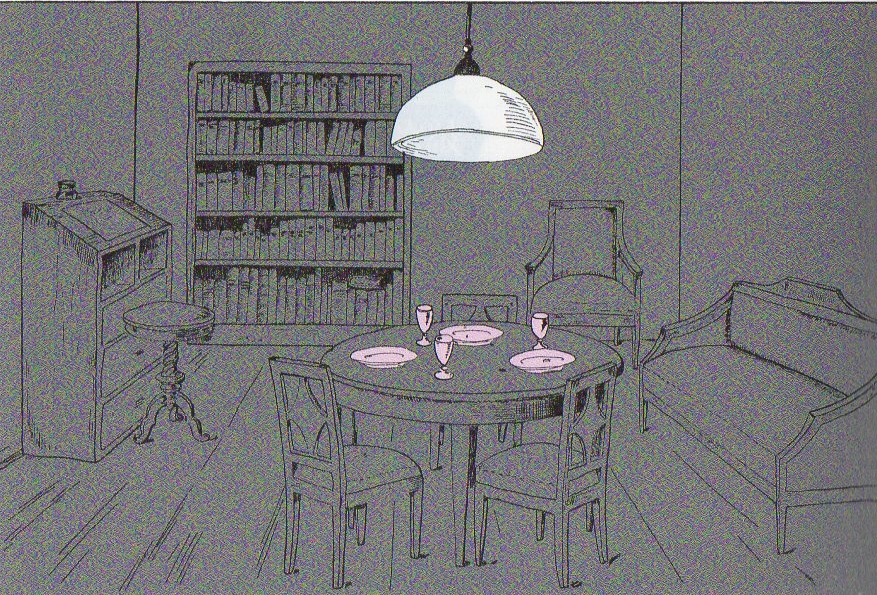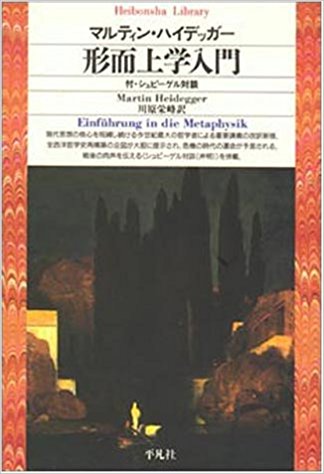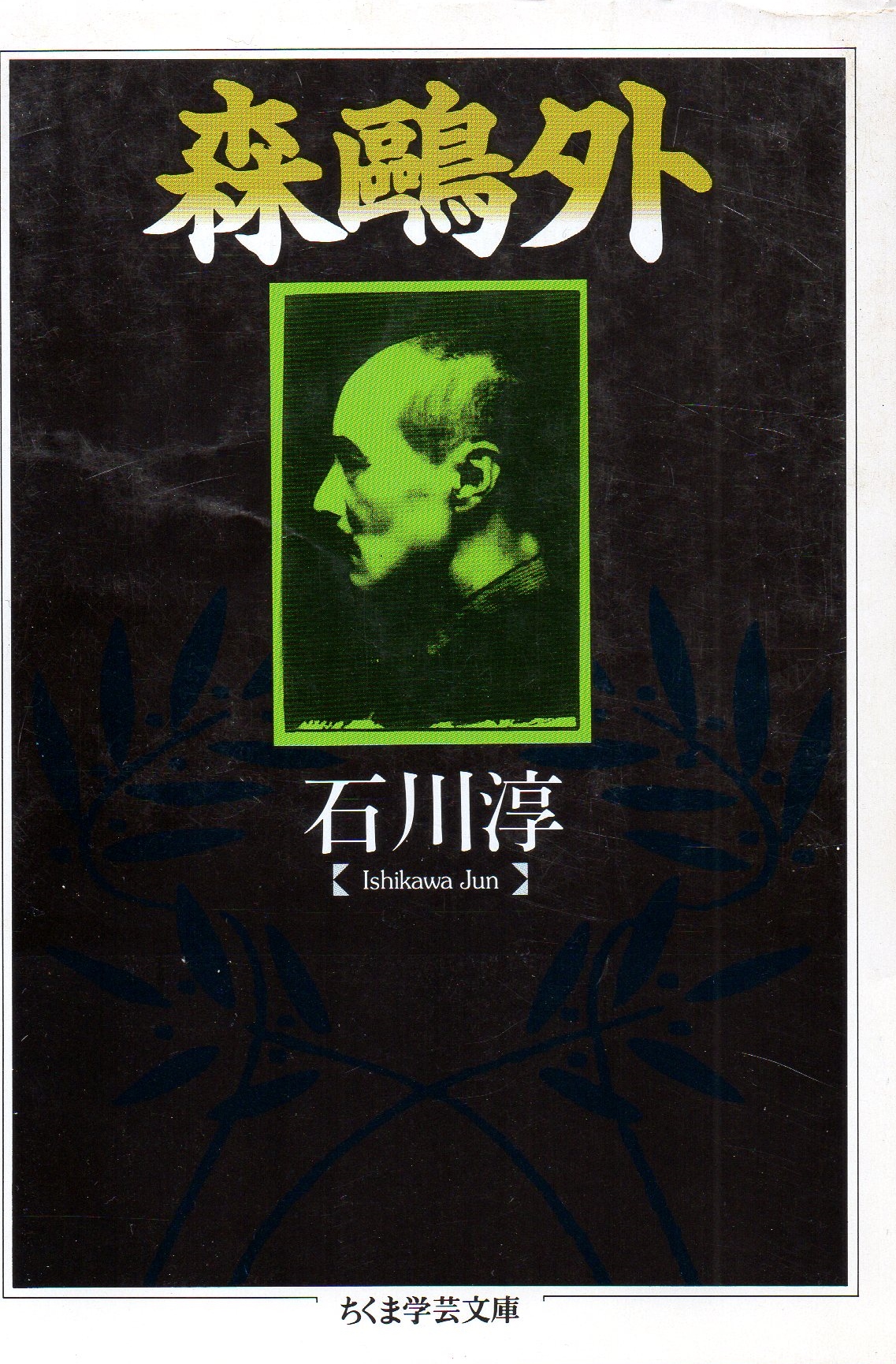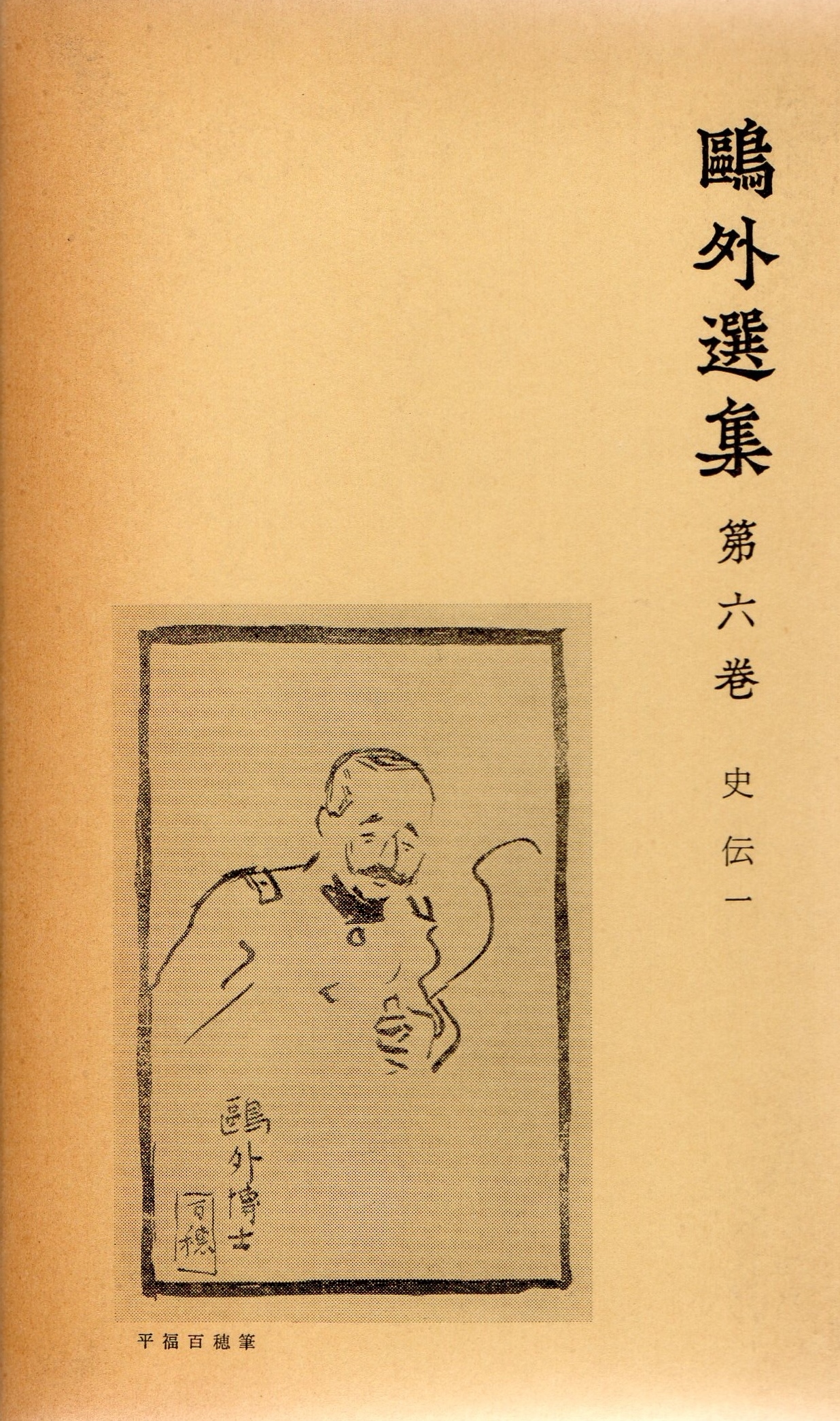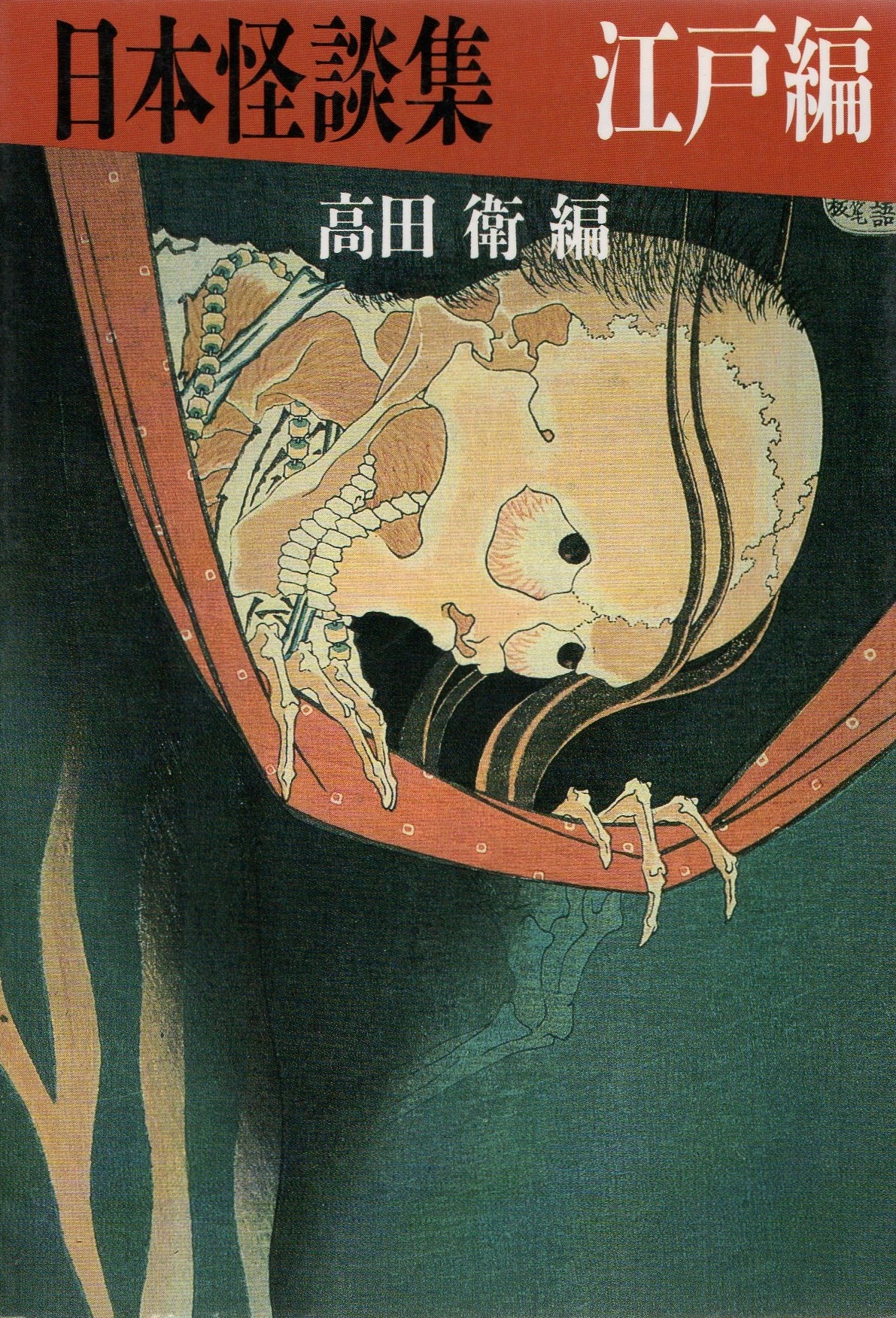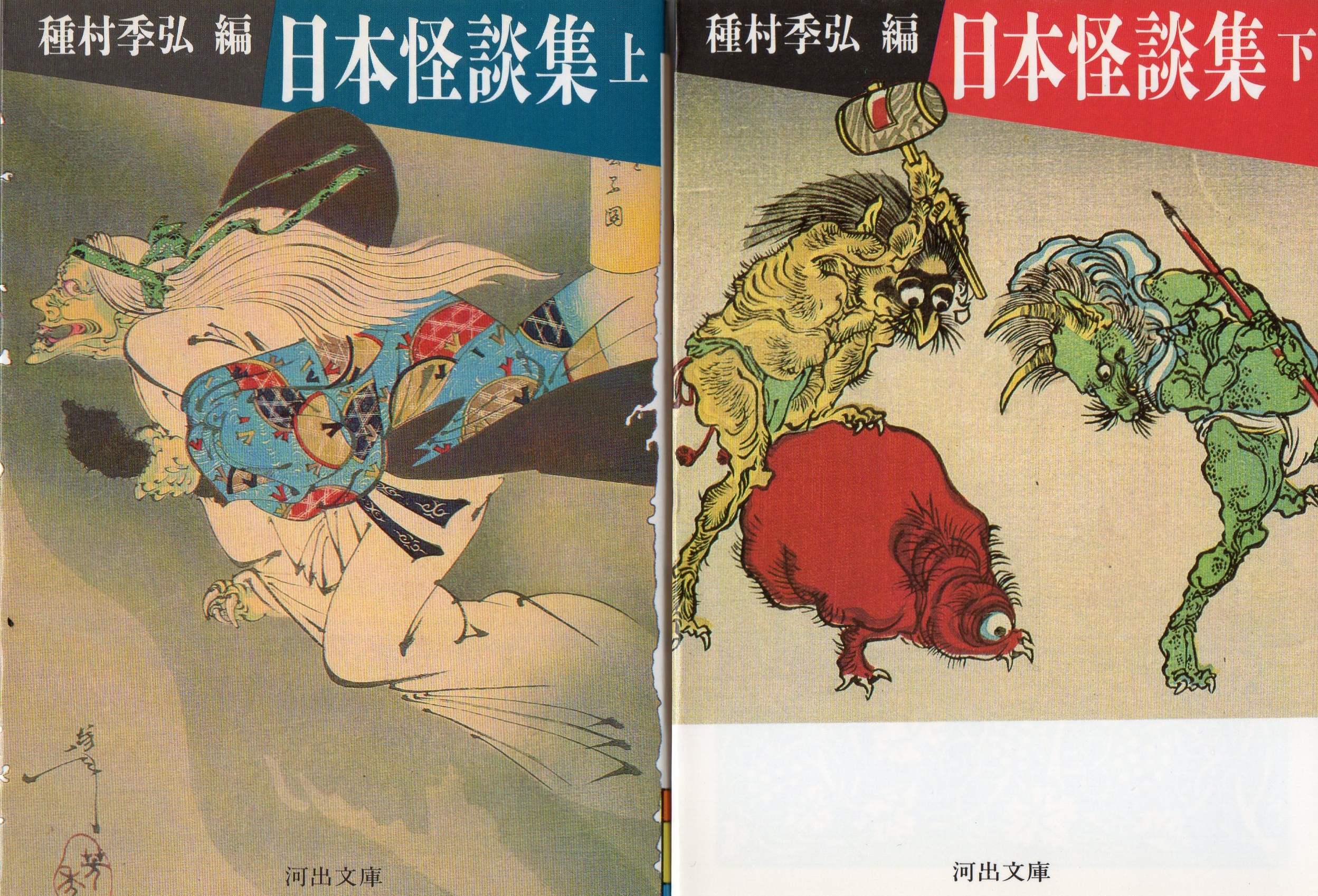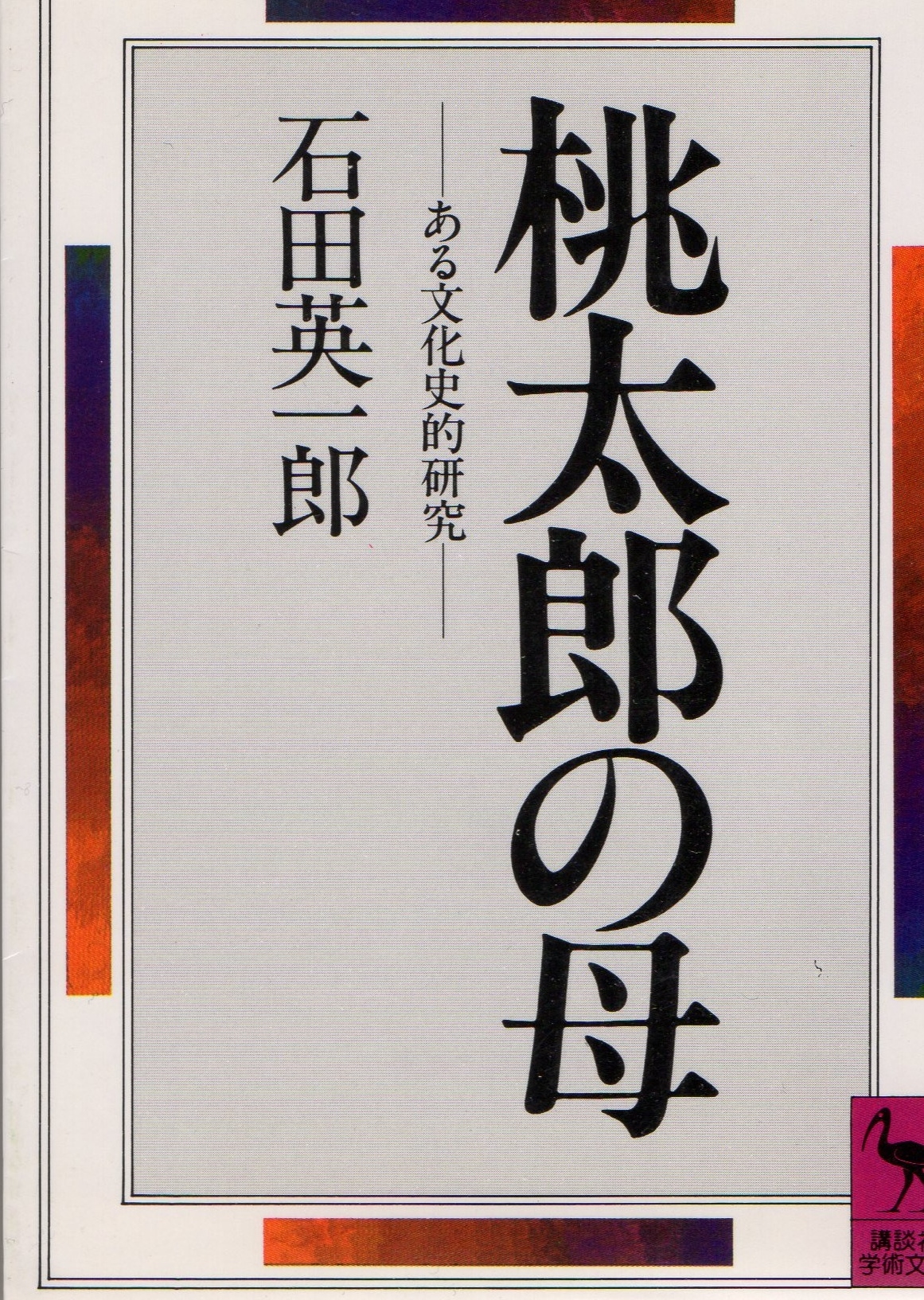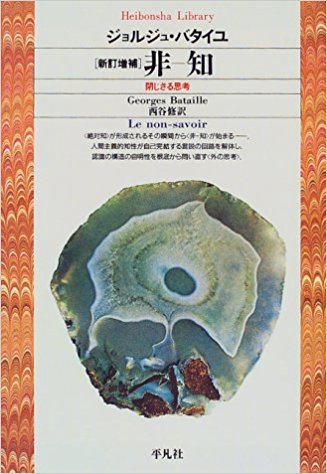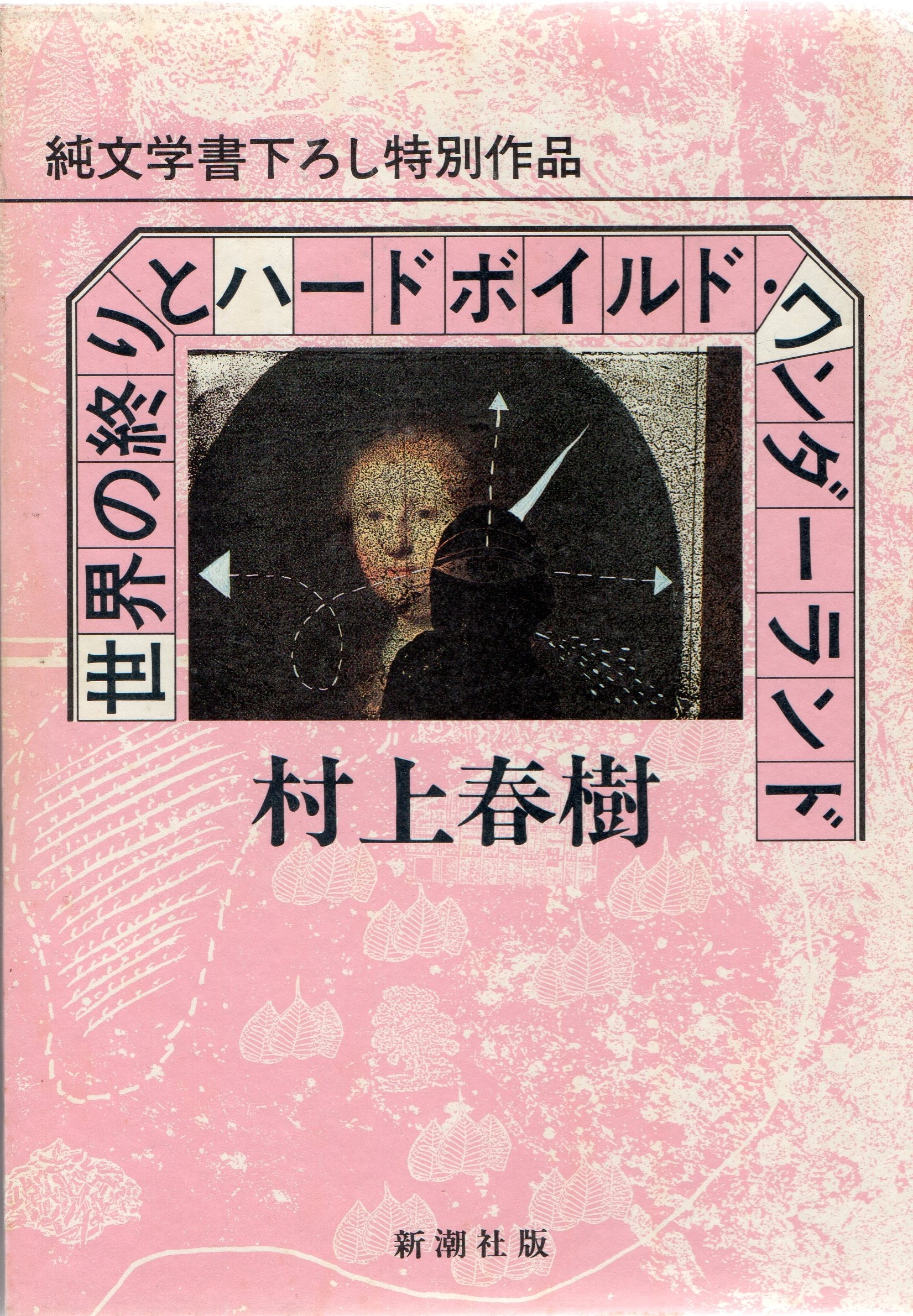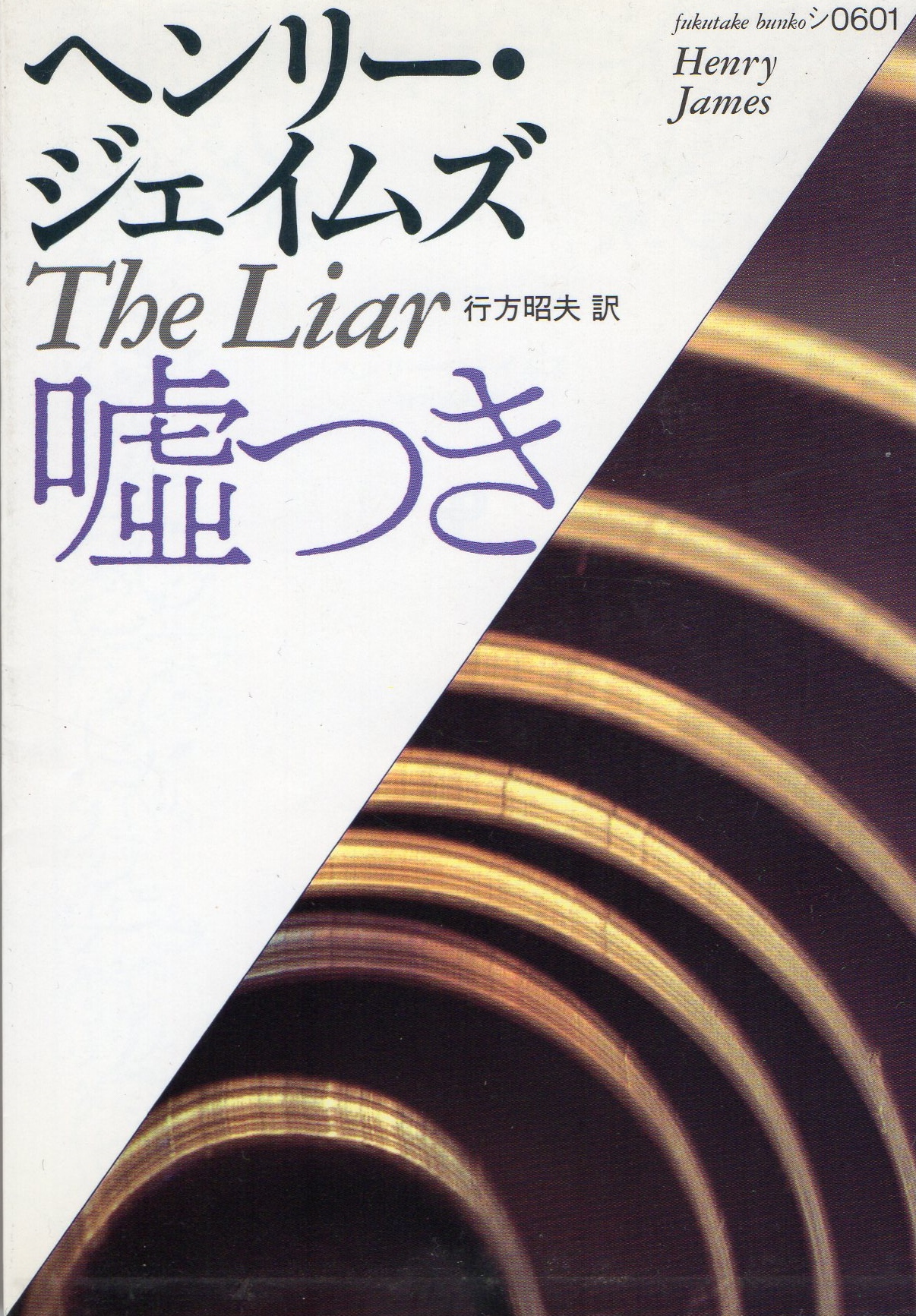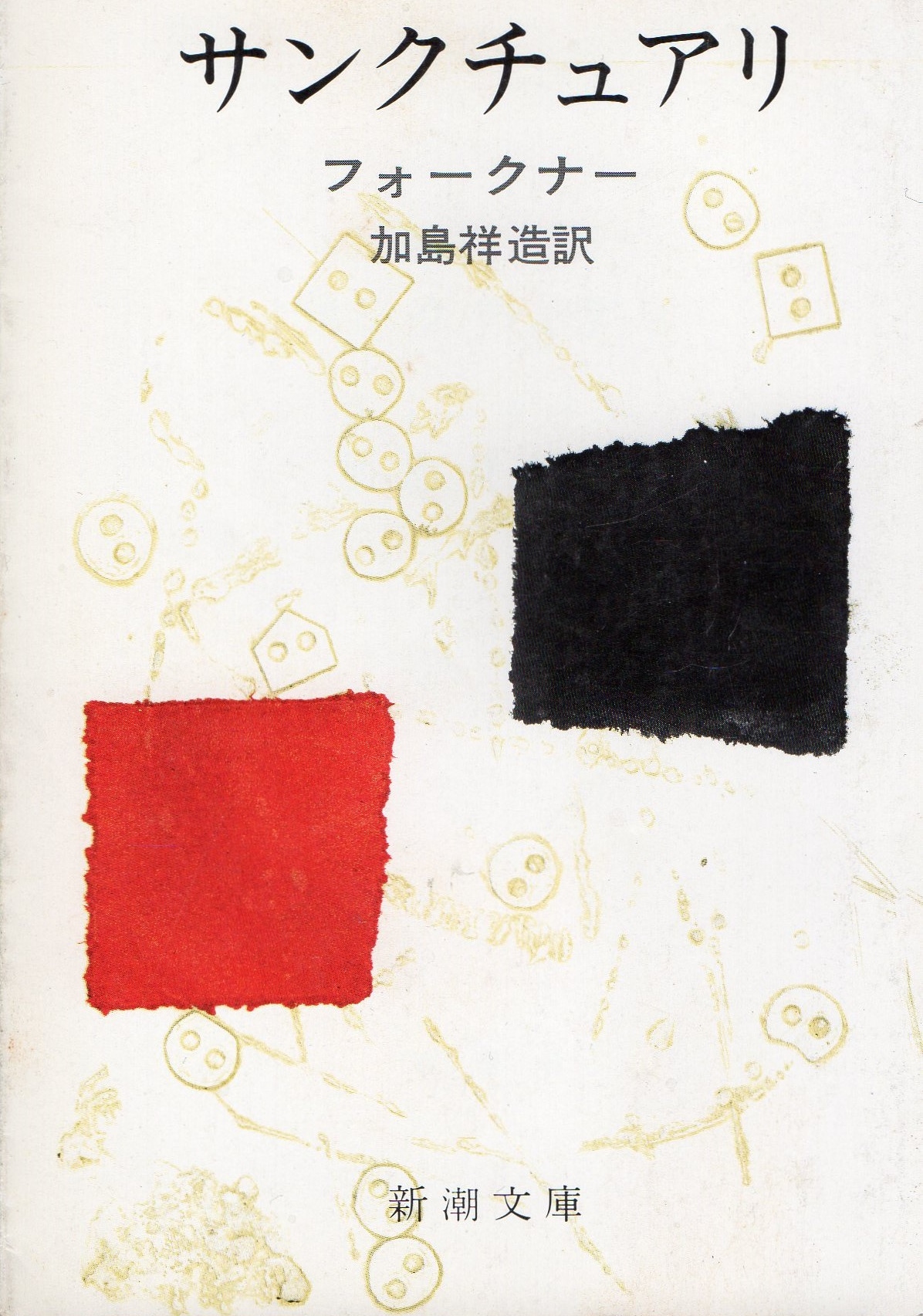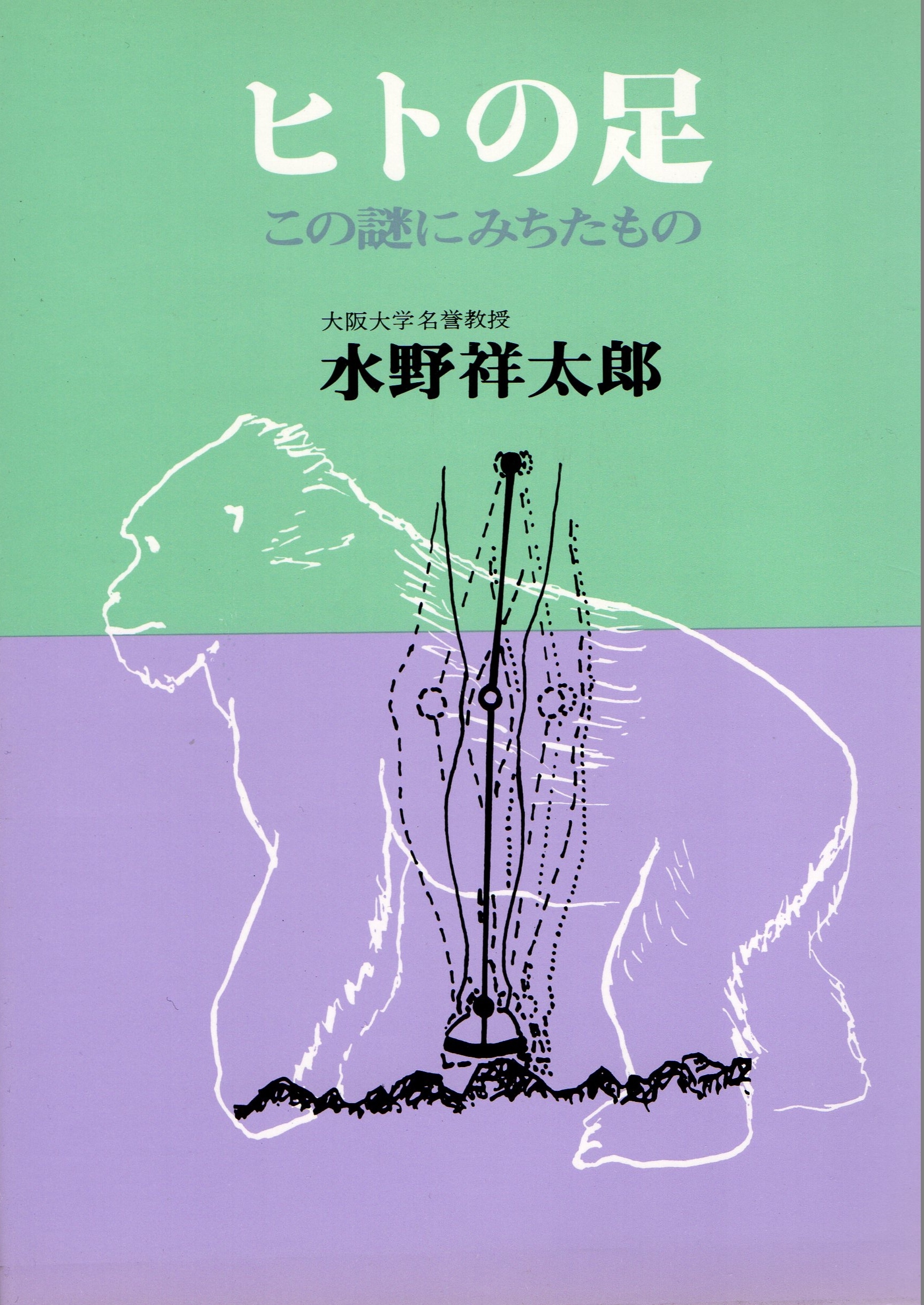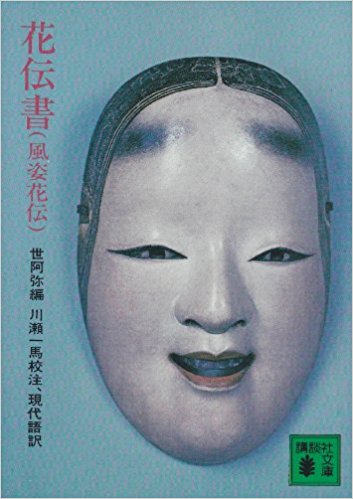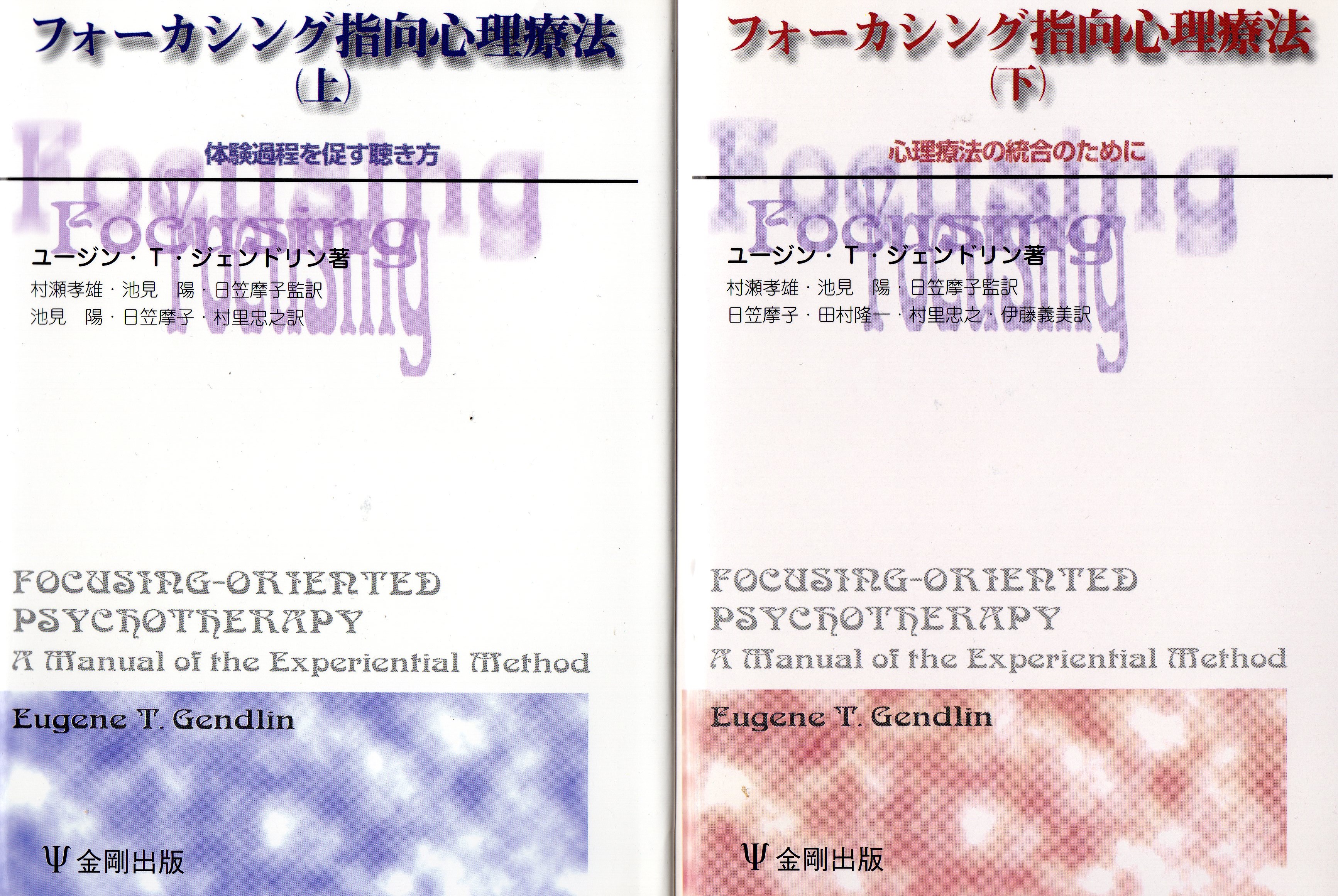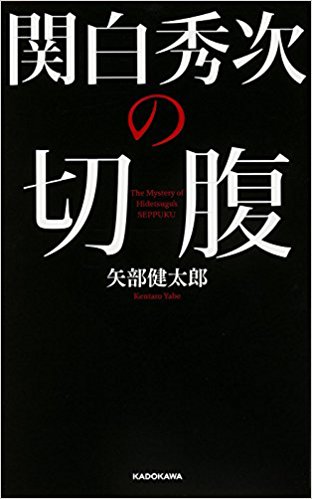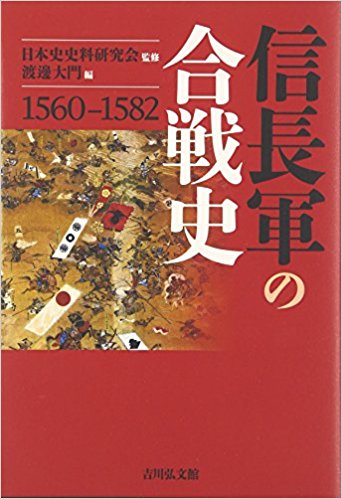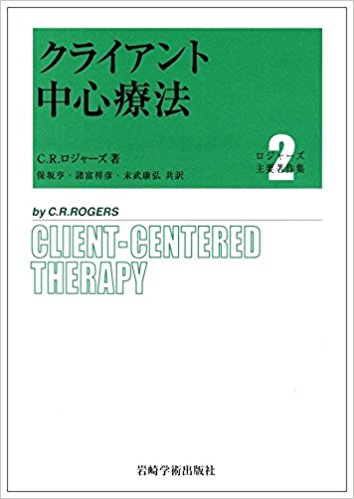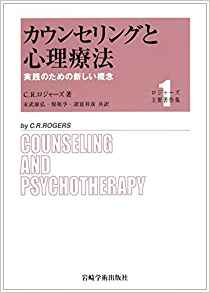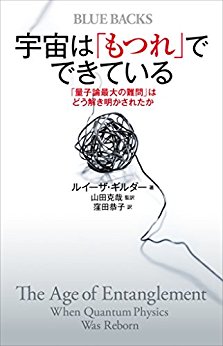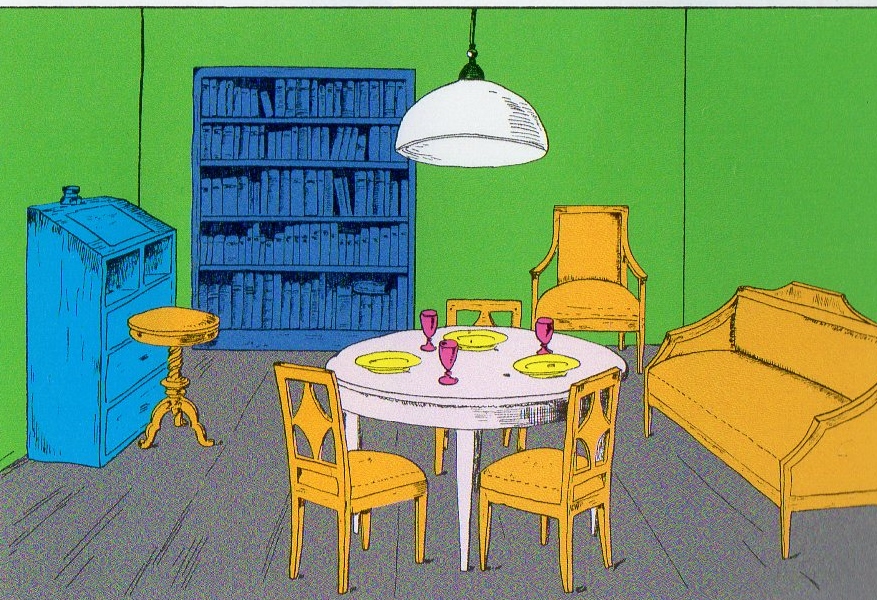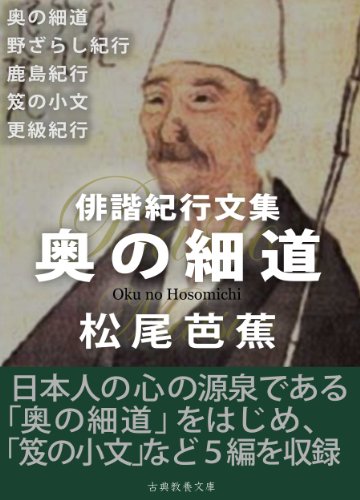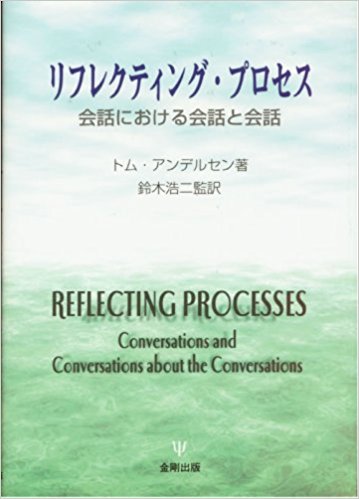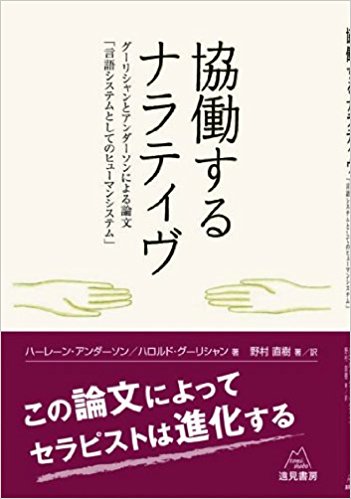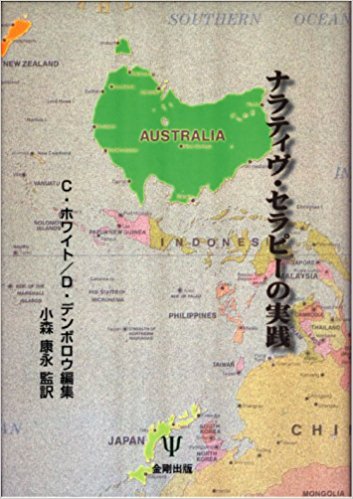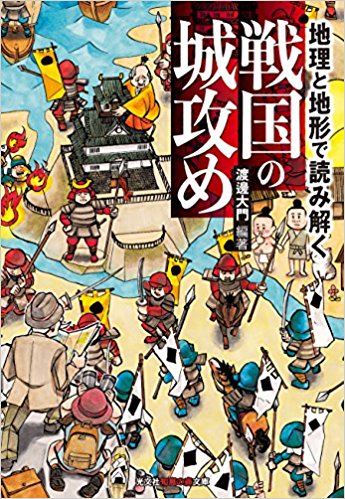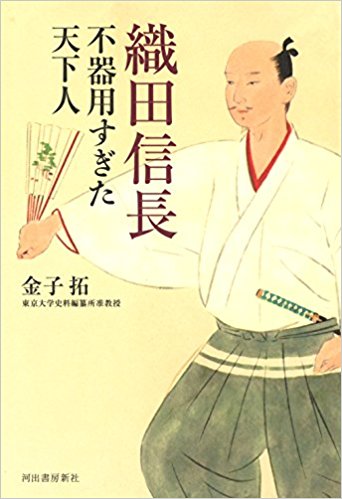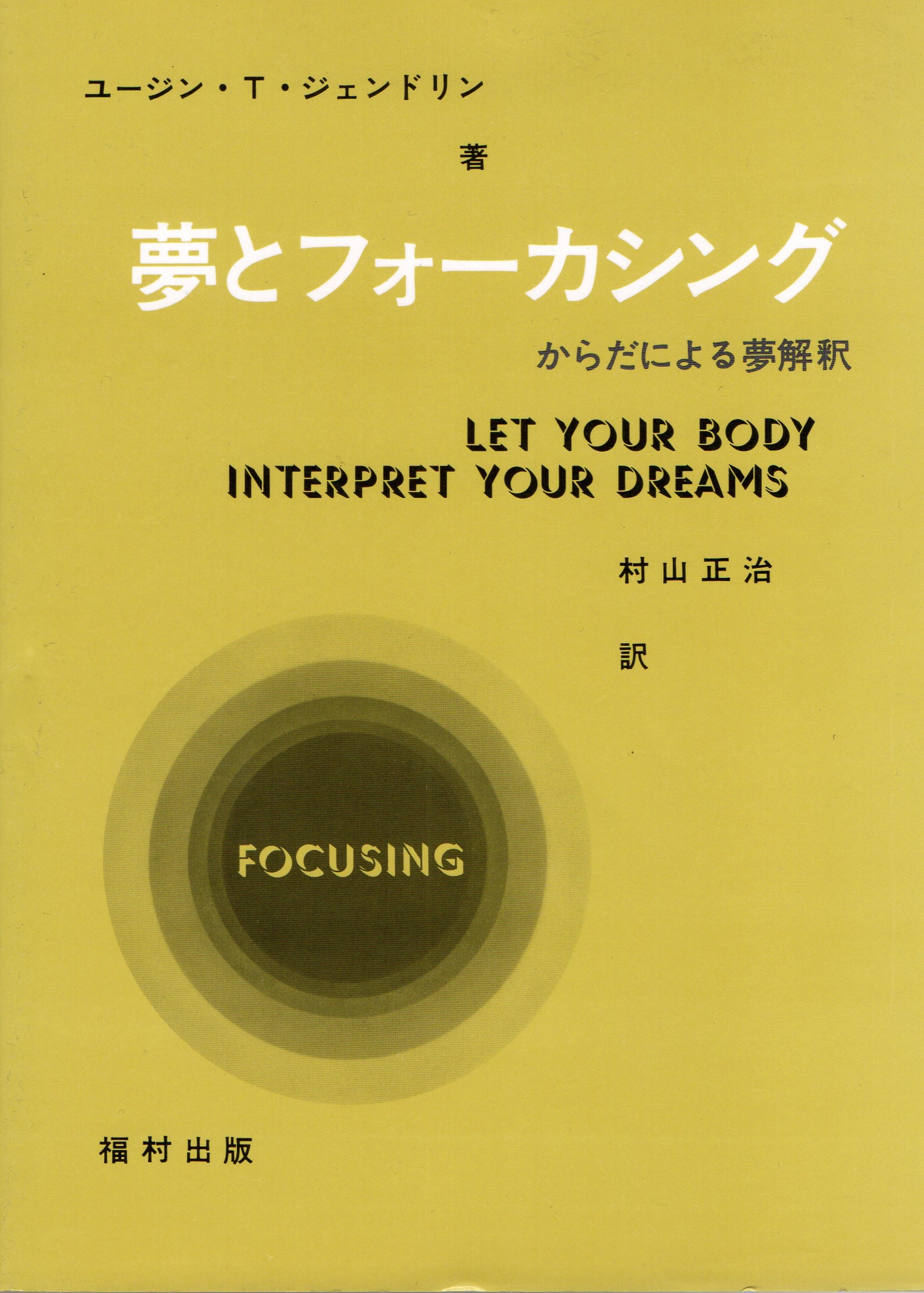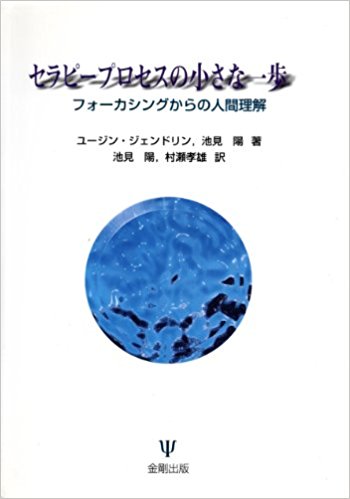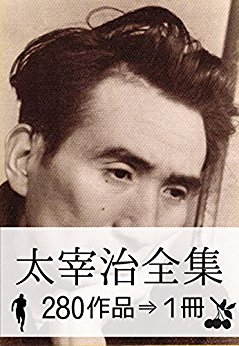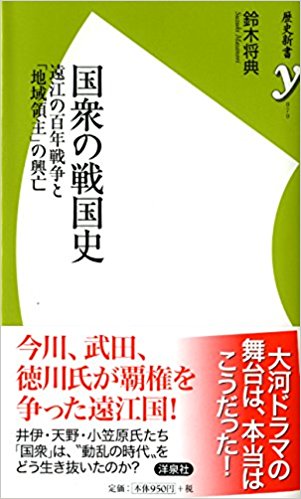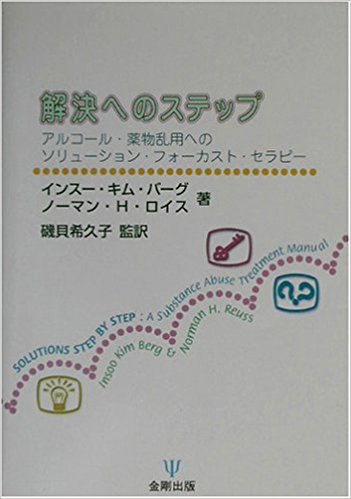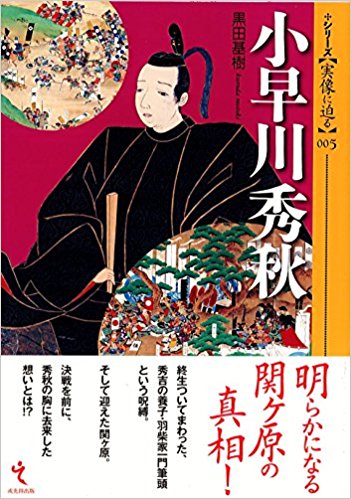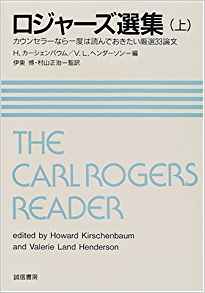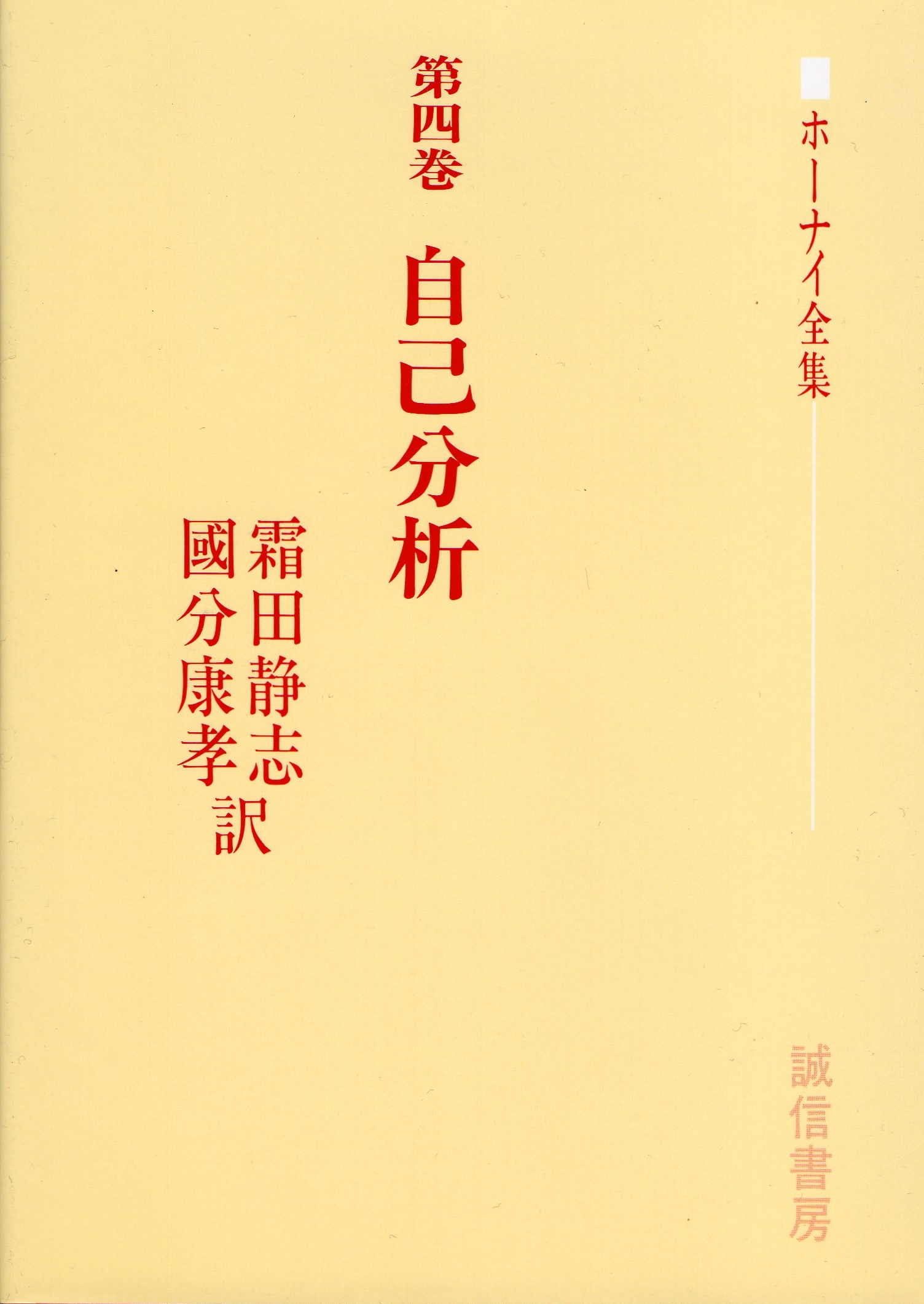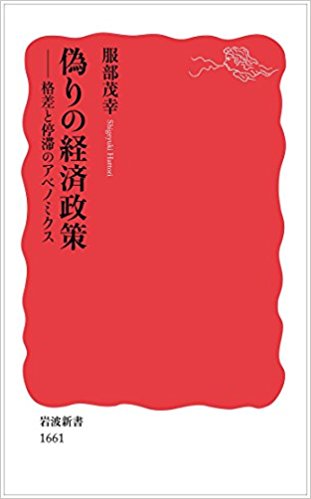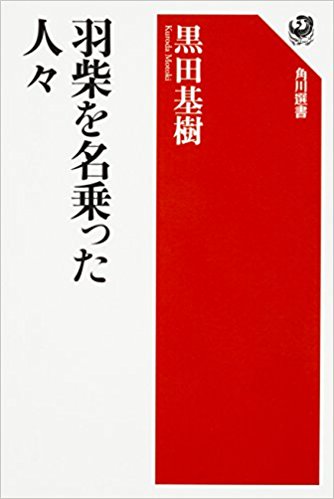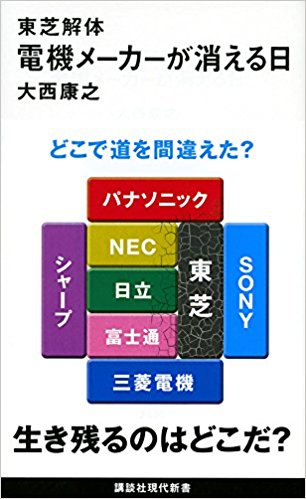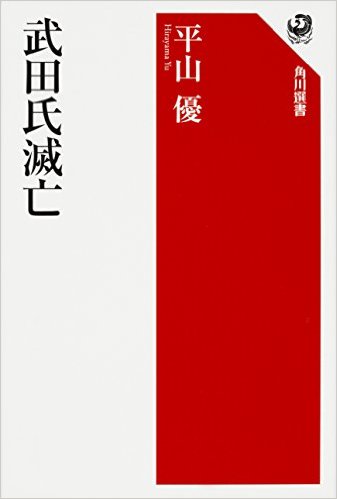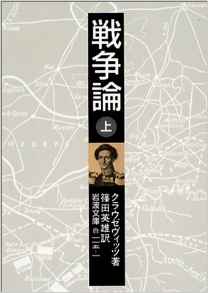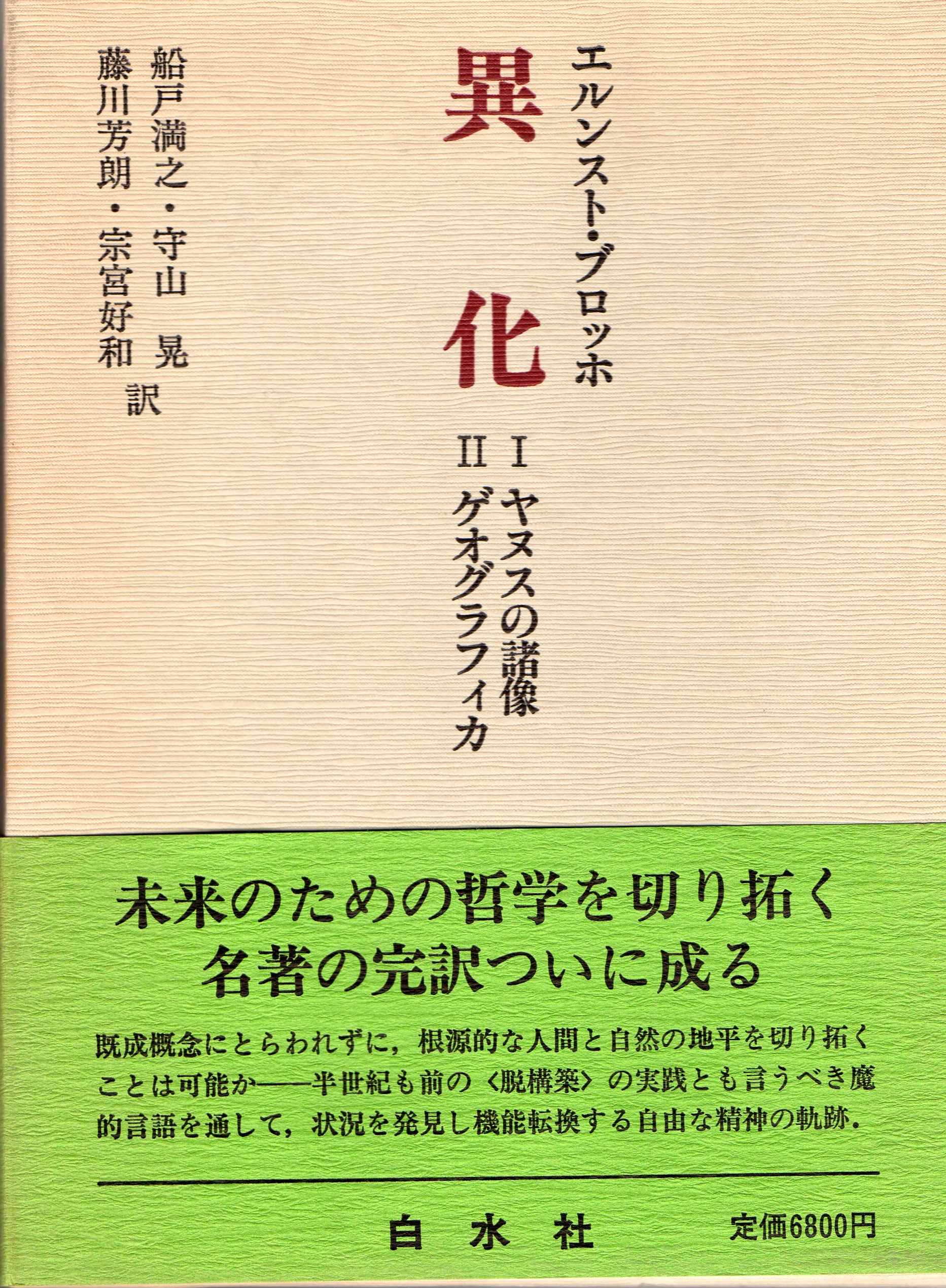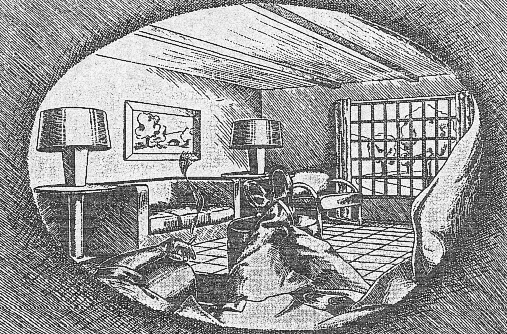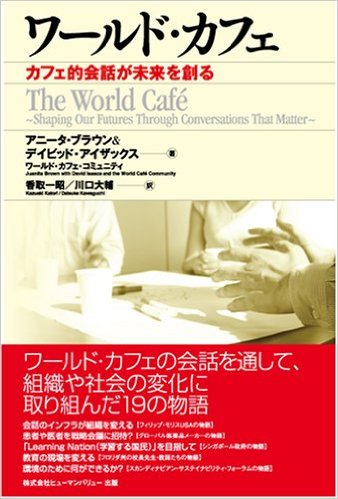|
ポリフォニー |
|
ミハイル・ミハイロヴィチ・バフチン『ドストエフスキーの詩学』を読む。
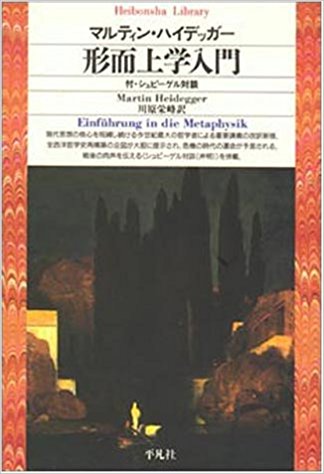
著者は,ドストエフスキーの小説を,
ポリフォニー小説,
と名づけたことで知られている。ポリフォニー (polyphony) とは,音楽用語で,
「複数の独立した声部(パート)からなる音楽のこと。ただ一つの声部しかないモノフォニーの対義語として、多声音楽を意味する。(中略)ポリフォニーは独立した複数の声部からなる音楽であり、一つの旋律(声部)を複数の演奏単位(楽器や男声・女声のグループ別など)で奏する場合に生じる自然な「ずれ」による一時的な多声化はヘテロフォニーと呼んで区別する。」
で,それに準えて,
「それぞれ独立して互いに融け合うことのないあまたの声と意識,それぞれがれっきとした価値を持つ声たちによる」
ドストエフスキーの小説の多声性をそう名づけた。あるいは,同じことだが,
対位法,
にも準える。つまり,ポリフォニー音楽についての理論である「対位法」とは,
「ポリフォニー音楽においては、それぞれの声部が奏でる旋律は独立性を持っている。そのため、和声法によるホモフォニー音楽よりも各声部の旋律の流れに重きを置いている。和声法が主に、楽曲に使われている個々の和音の類別や、それらの和音をいかに経時的に連結するかを問題にするのに対し、対位法は主に『旋律をいかに同時的に堆積するか』という観点から論じられる。」
であり,ドストエフスキーの小説の構造である,
多声性,
多重性,
多元性,
と,リンクしている,という考え方である。そこには,従来の小説を,
モノローグ小説,
として,対比させるというところにも通じる。
ドストエフスキーの小説は,対話で成り立つ。
「実際ドストエフスキーの本質的な対話性は,けっして彼の主人公たちの外面的な,構成的に表現された対話に尽きるものではない。ポリフォニー小説は全体がまるこど対話的なのである。小説を構成するすべての要素間に対話的関係が存在する。すなわちすべてが対位法的に対置されているのである。そもそも対話的関係というものは,ある構成のもとに表現された対話における発言同士の関係よりももっとはるかに広い概念である。それはあらゆる人間の言葉,あらゆる関係,人間の生のあらゆる発露,すなわちおよそ意味と意義を持つすべてのものを貫く,ほとんど普遍的な現象なのである。」
そして,ドストエフスキーの
「小説においては,その外面と内面の部分や要素の関係すべてが対話的な性格を持っている。つまり小説全体を彼は《大きな対話》として構成したのである。この《大きな対話》の内部では,構成的に表現された主人公たちの対話が,《大きな対話》を照らし出すとともに,凝縮するような形で響いている。そしてついにはこの対話は作品の奥深く浸透してゆく。それは小説の一つ一つの言葉に浸透して,それを複声的なものとし,また主人公たちの個々の身振りや表情の物真似に浸透して,それがぶつぶつ切れた,ヒステリックなものとするのである。これこそがドストエフスキーの言葉のスタイルの特性を規定する《ミクロの対話》である。」
と要約してみせる。そこにあるのは,外的な人との対話だけではなく,内的に,その人の身振りや口ぶりをなぞっての,内的な対話(自己対話)での内なる他人との対話という,対話の多重性なのである。その時ドストエフスキーにとって関心を引くのは,主人公の持つ
「世界と自分自身に対する特別の視点であり,人間が自身と周囲の現実に対して物意味と価値の立場」
であり,さらに,ドストエフスキーにとって大切なのは,
「主人公が世界において何者であるかということではなく,…主人公にとって世界が何であるか,そして自分自身にとって彼が何者なのか」
なのである。そして,ドストエフスキーが,
「そこで解明し性格づけるべきものは,主人公という一定の存在,彼の確固たる形象ではなく,彼の意識および自意識の総決算,つまり自分自身と自分の世界に関する主人公の最終的な言葉なのである。
したがって主人公像を形成する要素となっているのは,現実(主人公自身および彼の生活環境の現実)の諸特徴ではなく,それらの諸特徴が彼自身に対して,彼の自意識に対して持つ意味なのである。主人公の確固とした客観的な資質のすべて,すなわち彼の社会的地位,社会学的・性格論的に見た彼のタイプ,習性,気質,そしてついにはその外貌まで―つまり通常作者が《主人公は何者か?》という形でその確固普遍のイメージを形成する際に役に立つすべての事柄が,ドストエフスキーにおいては主人公自身の内省の対象となり,自意識の対象となる。いわば作者の観察と描写の対象とは,主人公の自意識の機能そのものなのである。通常の場合には,主人公の自意識は単に彼の現実の一要素,彼の全一的な形象の一要素に過ぎないのだが,ここでは反対に現実のすべてが主人公の自意識の一要素となるのだ。そこでは,…作者…はすべてを主人公自身の視野に導入し,その自意識の坩堝に投げ込む。そして主人公の純粋な自意識もそっくりそのまま,作者自身の視野の内に観察と描写の対象として残るのである。」
そのとき,「描写される人物に対する作者の位置関係が根本的に新しいもの」となる。
「主人公自身の現実のみではなく,彼を取り巻く外的世界や風俗も,この自意識のプロセスに導入され,作者の視野から主人公の視野の中へと移し換えられる。それらはすでに,作者の単一の世界の中で,主人公と同じ平面上に,彼と並んで,彼の外部に置かれているのではなく,したがって主人公を規定する因果律的・発生論的要因でもあり得ず,作品の中で説明的機能をを担うこともできない。具象世界のすべてを自らに取り込む主人公の自意識と同じ平面にあって,それと並んで存在し得るものは,別のもう一つの意識のみであり,彼の視野に対しては別のもう一つの視野が,彼の世界への視点対しては別のもう一つの視点が,それぞれ併置できるのみである。すべてを飲み込む主人公の意識に作者が対置し得るのは,ただ一つの客観世界,すなわち主人公と同等の権利を持った別の意識たちの世界のみである。」
このことを,ドストエフスキー自身は,
「人間の内なる人間を見出す」
とし,それを「完全なリアリズム」と呼んでいる。それに向き合う作者は,語り手をも,その意識たちと併置される位置におく対話の相手でもある。それは,
「ひたむきに実践され,とことん推し進められれた対話的立場であり,それが主人公の独立性,内的自由,未完結性と未決定性を保証しているのである。作者にとっての主人公とは《彼》でも《我》でもなく,一人の自立した《汝》つまり(《汝あり》という言葉で語られる)もう一人の完全な権利を持つ他者の《我》なのである。主人公は,きわめて真剣な,本当の対話的呼びかけの主体であって,修辞的に演じられる,あるいは文学的な約束事としての対話的呼びかけの主体ではない。そしてこの対話―小説の《大きな対話》の全体―は,過去に起こったことではなく,いま,すなわち創作過程の現在において起こっていることなのである。(中略)
ドストエフスキーの構想の中では,主人公とは自立した価値を持った言葉の担い手であって,作者の言葉のもの言わぬ客体ではない。そして主人公についての作者の言葉は,言葉についての言葉なのである。作者の言葉は,言葉を扱うのと同じように主人公を扱う。つまり彼に対して対話的に向けられるのである。作者はその小説の全構成をもって,主人公について語るのではなく,主人公と語り合う。」
多少,作家と書き手,書き手と語り手をごちゃごちゃにしている嫌いはある(ドストエフスキーは,書き手の位置も,語り手の位置も意識的であるし,いま進行しているように現在進行形で,そこにいる,という設定を意図している[作品は書き終わったところが「いま」であるのだから])が,この作品世界への向き合い方は,的確である。(作家ではなく)語り手は,
主人公について語るのではなく,主人公と語り合う,
は,ドストエフスキーの小説の語りについて的確な言い方である。
対話の歴史的系譜を,もうひとつの概念である「カーニバル文学」を説明するために,「ソクラテスの対話」「メニッポス風刺」と言ったギリシャ由来の経緯をたどって見せるたあと,本書の圧巻は,「第五章 ドストエフスキーの言葉」において,自意識の自己対話,自意識の中の他者との対話,他者そのものとの対話へと転換していく,語りの重層性と,そこでの語りの転位についての分析である。先ず自己対話について,
「主人公の自分自身に対する関係は,彼の他者に対する関係および他者の彼に対する関係と不可分に結びついている。自意識はいつも自分自身を,彼についての他者の意識を背景として知覚する,つまり,《自分にとっての私》は《他者にとっての私》を背景として知覚されるのである。したがって主人公の自分自身についての言葉は,彼についての他者の言葉の間断なき影響のもとで形成されるのである。」
その対話は,
「主人公の自意識の中に彼についての他者の意識が入り込み,主人公の自己言表の中に彼についての他者の言葉が投げ込まれる。次に他者の意識と他者の言葉が,一方では主人公の自意識の主題論的発展やその逸脱,逃げ道,反抗を規定し,他方ではアクセント上の中断,統辞論的逸脱,繰り返し,留保,冗長性を伴った主人公の発話を規定することになるような,独特の現象を引き起こす」
その場合,ポリフォニーとは,自己対話に入り込んだ他者の言葉だけではない。その口ぶりや口癖,喋り方,といった意味でも,多層的なのであり,
「対話は自分自身の声に他者の声による代替を可能」
にしてしまう。たとえば,『分身』のゴリャートキンについて,
「ここでの対話的展開は,(『貧しき人々』の)デーヴシキンの場合より複雑である。デーヴシキンの発話では《他者》と論争していたのは首尾一貫した一つの声であったが,ここで《他者》と論争しているのは二つの声,自信のある,過剰なほど自信たっぷりな声と,過剰なほどびくついた,何事においても譲歩し,全面降伏しようとする声という二つの声だからである。
他者を代替するゴリャートキンの第二の声,それに,初めは他者の言葉から身を隠そうとするが,(『俺だってみんなと同じさ』『俺は何でもない』),後になってその他者の言葉に降伏してしまう(『俺がどうしたって,そういうことなら,俺にも覚悟はあるさ』)彼の第一の声,そして彼の中で絶えず鳴り響いている純然たる他者の声―この三つの声は,非常に複雑な相互関係にある」
とし,この三つの声,つまり,
「他者と他者の承認なしにはやってゆけない《私のための私》の声であり,虚構としての《他者のための私》(他者の中に投影された私)の声,つまり他者を代替しようとするゴリャートキンの第二の声であり,そしてゴリャートキンの存在を承認しようとしない他者の声」
に加えて,語り手自身が,
「ゴリャートキンの言葉と思想を,つまり彼の第二の声と言葉を借用し,それらの中に装填されている挑発的で嘲笑的な調子を強化しながら,その強化した調子でゴリャートキンの言動の一挙手一投足をえがいている」
のである。語り手の声が,第二の声と融合してしまうことで,
「叙述は,形式的には読者に向けられているにもかかわらず,あたかもゴリャートキン自身に対話的にむけられており,ゴリャートキン自身の耳の中で彼を挑発する他者の声として,彼の分身の声として響き渡っているかのような印象が生まれることになる」
まさに,そこでは,ただ語り手の言葉が主人公に向けられているのではなく,
「叙述の志向性そのものが,主人公に向けられているのである。」
こうした自己対話は,他者との対話として,客体化されたときも,複雑な多声性を醸し出す。たとえば,『カラマーゾフの兄弟』のイワン・カラマーゾフとアリョーシャを例に,
「二人の主人公がドストエフスキーによって導入されるときはいつでも,彼らは,お互いがお互いの声の直接的な化身になることはけっしてないとはいえ…,お互いに相手の内なる声と密かに親密の応答の急所を衝いたり,また部分的にはそれと重なり合ったりするのである。一方の主人公にとっての他者の言葉と,もう一方の主人公の内に秘めた言葉との間の深く本質的な関係あるいは部分的な一本化―それこそが,ドストエフスキーの本質的な対話すべてに不可欠の契機であり,基本的な対話はこの契機を土台として組み立てられている。」
と述べる。
この対話の関係性の中に現実があり,この対話の中にこそ自己がある,ということを,(社会構成主義という)時代に先駆けて,バフチンが,ドストエフスキーの中から探り出した,時代を切り開く視界,といってもいい。
「世界について語っているのではなく,世界を相手に語り合っている」
かのようなドストエフスキーの開いた世界は,いわゆる現実の世界ではない。
言葉のみで成り立っている対話の世界,
である。まさしく,バフチンが掘り起こしたのは,
会話が世界をつくる,
という時代の最先端である。
参考文献;
ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』(ちくま学芸文庫)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%83%BC |
|
世界像 |
|
石川淳『森鷗外』を読む。
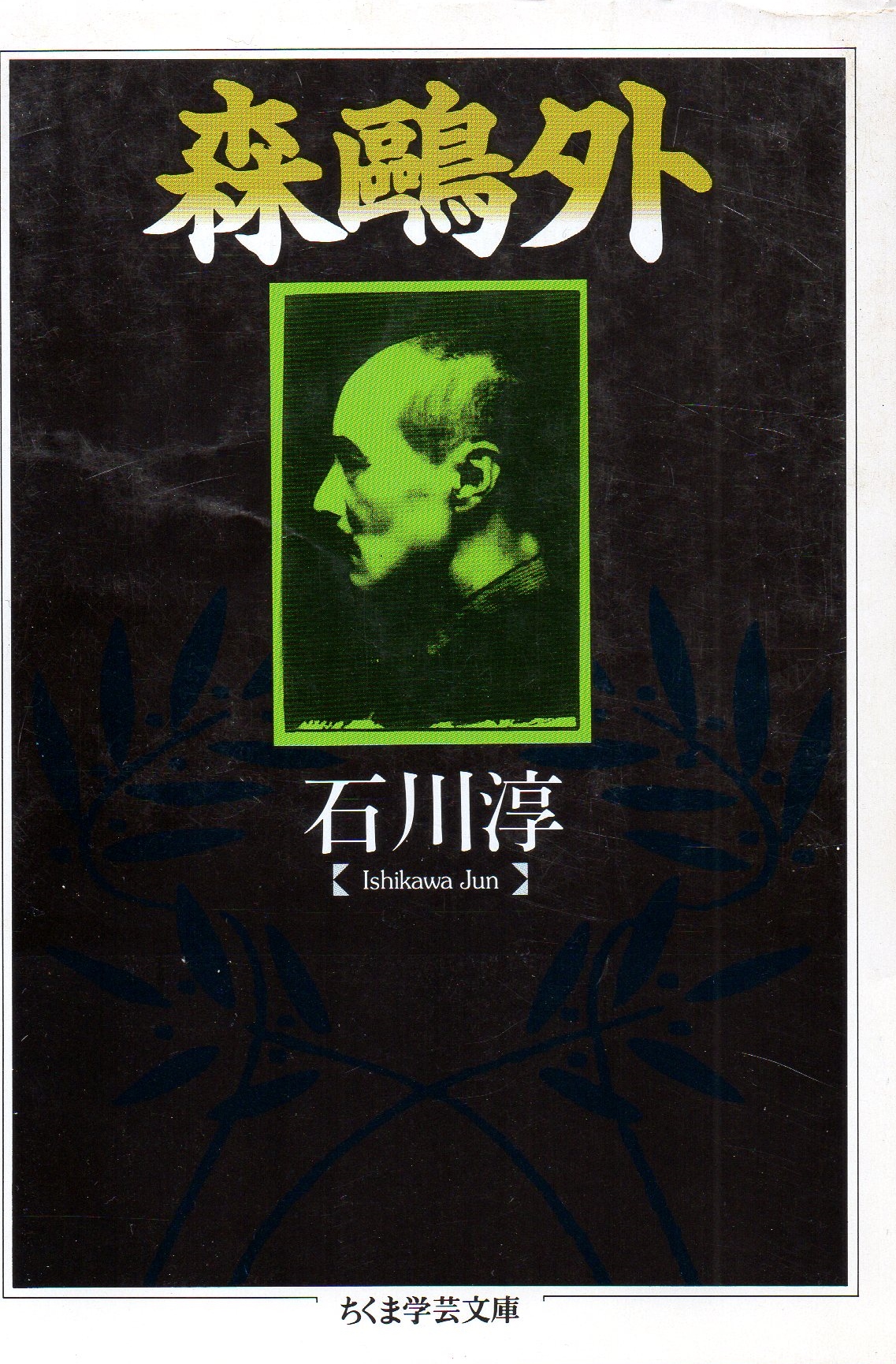
本書では,
「人物を論じない。伝記にたらない。官人としての事績をさぐらない。時代に係合を附けない。文学史に触れない。衛生学の仕事に係らない。芝居の仕事を追わない。美術の仕事を述べない。翻訳の仕事を記さない。」
と著者は書く。書いたのは,「小説とは何か」である。それは鷗外を語りつつ自らのそれを語っているかの如くである。
冒頭は,有名な書き出しである。
「『抽斎』と『霞亭』といずれを取るかといえば,どうでもよい質問のごとくであろう。だが,わたしは無意味なことはいわないつもりである。この二編を措いて鷗外にはもっと傑作があるとおもっているようなひとびとを,私は信用しない。『雁』などは児戯に類する。『山椒大夫』に至っては俗臭芬芬たる駄作である。『百物語』の妙といえども,これを捨てて惜しまない。詩歌翻訳の評判ならば,別席の閑談にゆだねよう。
『抽斎』と『霞亭』と,双方とも結構だとか,撰択は読者の趣味に依るとか,漫然とそう答えるかもしれぬひとびとを,わたしはまた信用しない。この二者撰一に於いて,撰ぶ人の文学上のプロフェッシオン・ド・フォアが現れるはずである。では,おまえはどうだときかれるであろう。ただちに答える。『抽斎』第一だと。そして附け加える。それはかならずしも『霞亭』を次位に貶すことではないと。」
これは,
「『澀江抽斎』に引きつづき『伊沢蘭軒』『北條霞亭』の三篇は一個の非凡の小説家の比類なき努力の上に立つ大業であって,とても傍観者などというなまぬるい規定をもって律しうるようなものではない。(中略)ひとが鴎外に期待したであろうとはちがったところに,努力が突き抜けて行った。したがって『澀江抽斎』以後の仕事に対して当時の世評は香しくない。青山胤通は『つまらぬものを書く』といったそうである。青山ばかりではなく,新聞社宛には悪罵の投書が殺到したという。肝腎の文壇批評家諸君は手のつけようを知らず,そっぽをむいていたかと見える。中には,あれは小説ではないといって,眼をつぶって安心していた小説家先生もあったかもしれない。おおかた自分の書くうすぎたない身上噺のほうがよほど斬新で深刻な芸術だとでも思っていたのであろう。」
等々という,ある意味鷗外の『澀江抽斎』以降の「世評は香しくない」鷗外観への挑戦状である,とも言える。それはまた,「小説とは何か」ということを問いかけてもいる。そして,言う。これは,
「小説概念に変更を強要するような新課題が提出」
されており,
「小説家鷗外が切りひらいたのは文学の血路である」
と。それは,
「鴎外の感動は怒号をもって外部に発散していく性質のものではない。それはひとに知れたとき云訣しなくてはならなかったほど,ひっそりと内部に沈潜する底のものであったが,そこからおこった精神の運動が展開して行ったさきは小宇宙を成就してしまった。なにか身にしみることがあってたちまち心あたたまり,からだがわれを忘れて乗り出して行き,用と無用とを問わず,横町をめぐり溝板をわたるように,はたへの気兼で汚されることのない清潔なペンがせっせとうごきはじめると,末はどんな大事件をおこすに至るか。仕合せにも『抽斎』一篇がここにある。出来上がったものは史伝でも物語でもなく,抽斎という人物がいる世界像で,初めにわくわくしたはずの当の作者の自意識など影も見えない。当時の批評がめんくらって,勝手がちがうと憤慨したのも無理はない。作品は校勘学の実演のようでもあり新講談のようでもあるが,さっぱりおもしろくもないしろもので,作者の料簡も同様にえたいが知れないと,世評が内内気にしながら匙を投げていたものが,じつは古今一流の大文章であったとは,文学の高尚なる論理である。」
鍵は,作品の「世界像」である。こう続けている。
「鴎外みずから『敬慕』『親愛』と称しているところの,抽斎という人間への愛情が作品においてどんなはたらきをしているか。鴎外はその愛情の中に自分をつかまえることによって書き出したのではあったが,またその中に自分を取り落すことに依って文章の世界を高次に築き上げている。(中略)
抽斎への『親愛』が氾濫したけしきで,鷗外は抽斎の周囲をことごとく,凡庸な学者も,市井の通人も,俗物も,蕩児も,婦女子も,愛撫してきわまらなかった。『わたくし自身の判断』を支離滅裂の惨状におとしいれてしまうような,あぶない橋のうえに,おかげで書かれた人物が生動し,出来上がった世界が発光するという稀代の珍事が現出した。そして,このおなじ地盤のうえに,鷗外は文章を書く新方法を発明したはずである。」
しかし面白いことに,鷗外自身はその新地平について気づいていない。
「鷗外自身は前期のいわゆる小説作品よりもはるかに小説に近似したものだとは考えていなかったようである。たしかに従来の文学的努力とは性質のちがった努力がはじめられていたにも係らず,そういう自分の努力と小説との不可分な関係をなにげなく通り越して行ったらしい点に於て,鷗外の小説観の一端がうかがわれるであろう。それはまたこの偉大な功業を立てた文学者の論説中小説論の見るべきものがない所以であろう。」
著者は,こう評する。
「『抽斎』『蘭軒』『霞亭』はふつう史伝と見られている。そう見られるわけは単にこれらの作品を組み立てている材料が過去の実在人物の事蹟に係るというだけのことであろう。いかにも史伝ではある。だが,文章のうまい史伝なるがゆえに,ひとはこれに感動するのではない。作品の世界を自立させているところの一貫した努力がひとを打つのみである。」
その小説観の一端は,「追儺」という作品について,こう書くところに表れている。
「作者はまず筆を取って,小説とはどうして書くものかと考え,そう考えたことを書くことからはじめている。ということは,頭脳を既成の小説概念から清潔に洗っていることである。(中略)前もってたくらんでいたらしいものはなに一つ持ちこまない。…味もそっけも無いようなはなしである。…しかし『追儺』は小説というものの,小説はどうして書くかということの,単純な見本である。これが鷗外四十八歳にして初めて書いた小説である。文豪の処女作たるに恥じない。」
そして,鷗外の小説は,『追儺』から数える,という。そう考えて初めて,最後の作品『北條霞亭』について,こう評することと対になる。
「鷗外六十歳,一世を蓋う大家として,その文学的障害の最後に,『霞亭生涯の末一年』に至って初めて流血の文字を成した。作品の出来ばえ,稟質才能の詮議は別として,右は通常これから小説に乗り出そうというすべての二十代の青年が立つであろう地点である。」
それにしても,石川淳は,鷗外に対する敬愛なみなみならない。かつて,その愚作ぶりにあっけにとられた『大塩平八郎』についても,
「『大塩平八郎』は低級無力なる作品である。それにしても,不思議なことに,鷗外のような高い意識と強力な手腕とをそなえた傍観者の著実な仕事に俟たなければ,こう別誂えに低級無力には出来上らない。これは漫然と不思議だということにしておく。」
と評する。「低級無力」とは最大限の罵倒であるが,どこかでその底をみきわめたやさしさがある。かつて,
「むかし,荷風散人が妾宅に配置した孤独はまさにそこから運動をおこすべき性質のものであった。これを芸術家の孤独という。はるかに年をへて,とうに運動がおわったあとに,市川の僑居にのこった老人のひとりぐらしには,芸術的な意味はなにも無い。したがって,その最期にはなにも悲劇的な事件は無い。今日なおわたしの目中にあるのは,かつての妾宅,日和下駄,下谷叢話,葛飾土産なんぞにおける荷風散人の運動である。日はすでに落ちた。もはや太陽のエネルギーと縁が切れたところの,一箇の怠惰な老人の末路のごときは,わたしは一燈をささげるゆかりもない。」(「敗荷落日」)
と,痛罵したのと対比すれば,明らかである。著者は,リルケに準えて,
「鷗外もまた手の甲の強靭な,てのひらの柔軟な抒情詩人」
というのが,著者の鷗外像らしい。死の直前まで,おのれの血を流す羽目になりながら,「小説の血路」を開き続けた鷗外へのオマージュである,だけでなく,鷗外を出汁にして,石川淳自身の小説観そのものを再構築していくプロセスでもあるように見える。突飛なことを言うようだが,石川淳の『佳人』『普賢』は,どこやら,『澀江抽斎』のパロディにも見えなくもないのである。
参考文献;
石川淳『森鷗外』(ちくま学芸文庫) |
|
メタ小説 |
|
森鷗外『澀江抽斎』を再読。
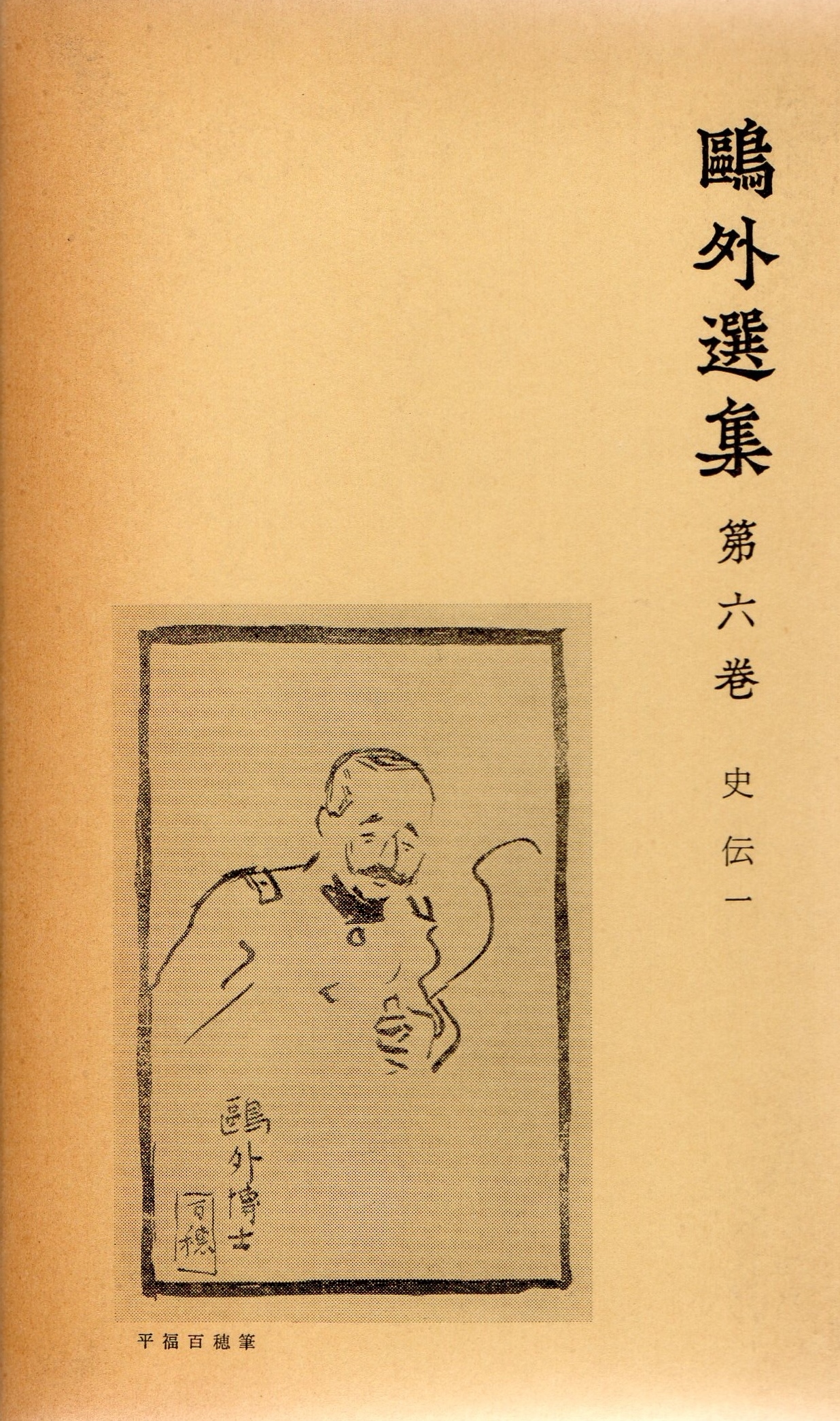
以前読んだとき,恥ずかしながら,人の死が連ねられているという印象が強く残っていた。人との関わりのネットワークよりは,その終末に強く印象づけられていた。世の中では,この作品が,史伝の中にカテゴライズされているらしいことを,ほぼ疑わなかった。しかし,今回,ひどく面白く読んだ。前回とは全く印象が違う。これは,
書くことを書く,
というメタ・ポジションからのものだと,気づいたからだ。今日なら,おのれが書いているものについて,書くなどということは,奇異でも特異でもない。しかし鷗外が新聞連載(これが新聞連載されていたことに驚くが)当時はどうであったか。困り果てて,史伝とするしかなかったのではないか。
本巻の解説(小堀桂一郎)は,こう書いている。
「著者はこの伝記の稿に筆を下すに当たって,先ず如何にして自分がこの作品の主人公とめぐりあったか,どうしてその人に関心をいだき,伝記を立てる興味をおこしたか,そしてこの著述に如何にして着手し,史料は如何にして蒐め,また如何にして主人公に就いての知識を拡大して行ったか,その筋みちを詳しく説明してゐるのである。言ってみれば著者はここで伝記作者としての自分の舞台裏をなんのこだわりもなく最初から打ち明けて見せてゐるのであり,著述を進めてゆく途上に自分が突き当たった難渋も,未解決の疑問も,一方探索を押し進めてゆく際に経験した自分の発見や疑問解決の喜びをも,いささかもかくすことなく筆にしてゐる。これは澀江抽斎といふ人の伝記を叙述してゐると同時に,澀江氏の事蹟を探ってゆく著者の努力の経過をもまた,随筆のやうな構へを以て淡々と報告してゆく,さうした特異な叙述の方法にもとづいて書かれた伝記である。」
伝記という概念から脱せられないから,「特異」といい,「特異の研究方法」(永井荷風)ということになる。しかしこの解説者自身がすでに書いている,
「澀江抽斎といふ人の伝記を叙述してゐると同時に,澀江氏の事蹟を探ってゆく著者の努力の経過をもまた,随筆のやうな構へを以て淡々と報告してゆく,さうした特異な叙述の方法」
こそが,書くことのメタ化ではないか。つまり,
書くことを書く,
である。これが鷗外の発明かどうかは知らない。しかし,鷗外は,短編『追儺』,未完の『灰燼』で,既に,小説を書く(書こうとすること)を書く,ことを試みている。だから,石川淳は,
「作者はまず筆を取って,小説とはどうして書くものかと考え,そう考えたことを書くことからはじめている。ということは,頭脳を既成の小説概念から清潔に洗っていることである。(中略)前もってたくらんでいたらしいものはなに一つ持ちこまない。…味もそっけも無いようなはなしである。…しかし『追儺』は小説というものの,小説はどうして書くかということの,単純な見本である。これが鷗外四十八歳にして初めて書いた小説である。」
と書いている。石川淳が,これを処女作としたのは,いかに書くかをめざして初めて書いた小説からだ。小説という既成の概念を前提に,物語を語るのではなく,
書くとはどういうことかを書きながら,書いていった,
という意味で初めての小説だ,という意味だ。『追儺』で,
「小説といふものは何をどんなふうに書いても好いものだといふ断案を下す」
と。それは,鷗外が,初めて自分の書く世界を,『追儺』で手掛りをえた,と言い換えてもいい。その先の試みの『灰燼』は失敗した。しかし,その上に,『澀江抽斎』がくる。
『澀江抽斎』を読んで,何気なく見過ごしていけないのは,鷗外は,初めから,シーケンシャルに,抽斎について調べていくプロセスをそのまま書くことを通して,澀江抽斎という世界を描こうと意図していたということだ。この方法は,意図されている。調べ終わってから,抽斎について書くことを書く,などという書き方ではないのである。最初から,抽斎を書こうとする自分自身を書き,そこで調べている自分を書き,さらに,調べ上げた抽斎について書く,ということ意図して,第一行から書き始めている。でなくて,こういう世界を描くということは,ほぼできないのである。鷗外は,意識して,書くことを書くとしたのかどうか,その方法を意識していたかどうかはともかくとして,『追儺』の方法をなぞるようにして,「書くことを書く」(書くを書く)を始めるつもりで書き出しているのである。
書くを書くとは,小説を書く書き手を書きつつ,作品世界の語り手をも書く,ということだ。そこでは,作家は,小説世界を構築する書き手を対象化しつつ,その書き手をして,小説世界を語らせる,そこまでを書く。それは,中里介山が,『大菩薩峠』の作中で,自分の小説が世界一の長さだなどと,ポロリをおのれの自慢を書きつらねたこととは,天と地ほどに,根本的に違う,小説をいかに書くかという小説の方法そのものを書くことなのだ,と僕は思う。しかし,
「鷗外自身は前期のいわゆる小説作品よりもはるかに小説に近似したものだとは考えていなかったようである。たしかに従来の文学的努力とは性質のちがった努力がはじめられていたにも係らず,そういう自分の努力と小説との不可分な関係をなにげなく通り越して行ったらしい点に於て,鷗外の小説観の一端がうかがわれるであろう。それはまたこの偉大な功業を立てた文学者の論説中小説論の見るべきものがない所以であろう。」
石川淳が書くように,鷗外自身は,史伝を書いていたつもりかもしれない。しかし,少なくとも,
澀江抽斎を調べている自分をも描くことを通して,明らかになっていく澀江抽斎像を書いていく,
ということを,方法論としては意識化しないまま,無意識のうちに,ある閾を,
なにげなく通り越して行った,
らしいのである。
『澀江抽斎』の冒頭は,こうである。
「三十七年如一瞬。学医伝業薄才仲。栄枯窮達任天命。安楽換錢不患貧。これは澀江抽斎の述志の詩である。想ふに天保十二年の春に作つたものであろう。弘前の城主津軽順承の定府の医官で,当時近習詰になつてゐた。しかし隠居附にせられて,主に,柳島にあつた信順の館へ出仕することになつてゐた。父允成が致仕して,家督相続をしてきから十九年,母岩田氏縫を喪つてから十二年,乳を失つてから四年になつている。」
この時,この文の語り手は,鷗外の設定した書き手である「わたくし」の設定した語り手である。このとき,
(鷗外→)書き手→わたくし→語り手,
と,語りの構造(次元)は,厳密には,四層になっている。つまり,語られている中味から言うと,
語られている澀江抽斎←を語っている語り手←を語っている「わたくし」←を書いている書き手(←を書いている鷗外),
となる。鷗外は,自分の書こうとする世界を,
澀江抽斎の史伝的世界を語る「わたくし」と,その「わたくし」を語る書き手,
を,設定しているのである。書くということについて,そこまで自覚的であったかどうかは別にして,書く世界に向き合った時,作家と,大なり小なり,自分が向き合う「世界」をどう語るか,逆に言うと,「世界」とどう向き合って,その「世界」を独立した対象とするかを工夫する。鷗外は,この世界のあり方を,冒頭で,既に顕現しているのである。
石川淳は,こう評している。
「『抽斎』『蘭軒』『霞亭』はふつう史伝と見られている。そう見られるわけは単にこれらの作品を組み立てている材料が過去の実在人物の事蹟に係るというだけのことであろう。いかにも史伝ではある。だが,文章のうまい史伝なるがゆえに,ひとはこれに感動するのではない。作品の世界を自立させているところの一貫した努力がひとを打つのみである。」
「作品の世界を自立させている」仕掛けこそが,まさに,この語りの多次元化である。
他方,書き手が対象化した「わたくし」について書くとき,
「わたくしが抽斎を知ったのは奇縁である。わたくしは医者になって大学を出た。そして官吏になつた。然るに少い時から文を作ることを好んでゐたので,いつの間にやら文士の列に加えられることになつた。其文章の題材を,種々の周囲の状況のために,過去に求めるやうになつてから,わたくしは徳川時代の事蹟を捜つた。そこに武鑑を検する必要が生じた。」
となる。あくまで,過去を題材に小説を書こうとする流れの中で,鷗外は,『澀江抽斎』を書いた。しかし,鷗外は,『興津彌五右衛門』『阿部一族』等々とは異なり,いきなり「物語世界」を現在化させる語り口を取らなかった。このときは,
(鷗外→)語り手,
という物語でしかない。しかし,そうして語るには,語りようのないほど複雑で錯綜した関係そのものが面白いせいかもしれない。このとき,書き手は,作家鷗外に設定された書き手が語っている「わたくし」である。このとき,
(鷗外→)書き手→わたくし
と,書く次元(構造)は,三層になっている。書き手(鷗外自身ではない)は,「わたくし」として,自己を対象化している。「わたくし」について語るところが,一見,史伝の書き手自身の随筆のように見えるが,そうではない。鷗外自身が,自ら書いているには違いないが,この『澀江抽斎』という作品世界に向き合っているのは,鷗外が立てた書き手である。その書き手が,自らを対象化して,「わたくし」をして語らしめていく。
「わたくしは直に保さんの住所を訪ねることを外崎さんにな頼んだ。保と云ふ名は,わたくしは始めて聞いたのでは無い。是より先,弘前から来た書状の中に,かう云ふことを報じて来たのがあった。津軽家に仕へた澀江氏まったく当主は澀江保である。保は広島の師範学校の教員になつてゐると云ふのであつた。わたくしは職員録を検した。しかし澀江保の名は見えない。それから広島高等師範学校長幣原坦さんに書を遣つて問うた。」
「わたくし」は,あくまで作家が立てた「書き手」の立てた「語り手」にすぎない。あるいは,少し約めれば,作家が立てた語り手としてもよい。小説とは,
別の世界への視界を開くこと,
言い換えると,作家が拵えた世界を,目前に見ることである。本書のラストは,
「牛込の保さんの家と,其保さんを,父抽斎の後嗣たる故を以て,終始『兄いさん』と呼んでゐる本所の勝久さんの家との外に,現に東京には第三の澀江氏がある。即ち下渋谷の澀江氏である。
下渋谷の家は侑の子終吉さんを当主としてゐる。終吉は図案家で,大正三年に津田駙楓さんの門人になつた。大正五年に二十八歳である。終吉には二人の弟がある。前年に明治薬学校の業を終へた忠三さんが二十一歳,末男さんが十五歳である。此二人の生母福島氏おさださんは静岡にいる。牛込のお松さんと同齢で,四十八歳である。」
これを語っているのが,全体の語り手である,書き手の立てた「わたくし」である。
なお本巻所収の他の作品,『寿阿弥の手紙』『細木香以』『小嶋宝素』は,『澀江抽斎』の作品世界の衛星群である。もちろん方法は,『澀江抽斎』と同じである。
参考文献;
森鷗外『澀江抽斎』(鷗外選集第六巻 岩波書店)
石川淳『森鷗外』(ちくま学芸文庫) |
|
江戸怪談 |
|
高田衛『日本怪談集〈江戸編〉』を読む。
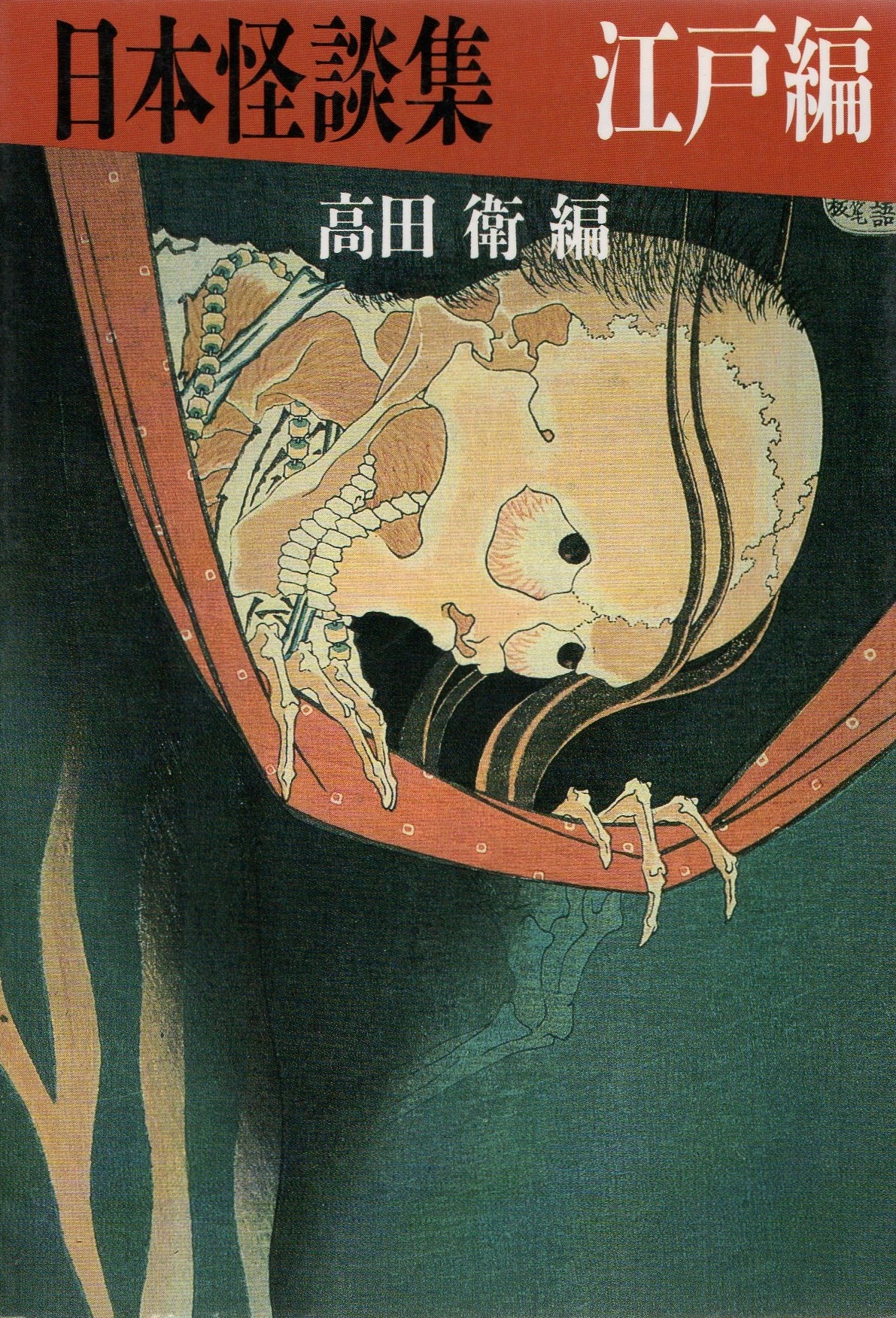
江戸の怪異譚の系譜については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/432575456.html
で,
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』
を紹介したが,そこで,そのの特色を,
ひとつは,仏教唱導者の近世説教書(勧化(かんげ)本)のなかに類例の求められる,仏教的な因果譚としての側面,
として,
「檀家制度をはじめとする幕府の宗教統制のもとで,近世社会に草の根のような浸透を果たした当時の仏教唱導は,通俗平易なるがゆえに,前代にもまして,衆庶の心に教義に基づく生き方や倫理観などの社会通念を定着させていった。とりわけ人間の霊魂が引き起こす妖異については,説教僧の説く死生観,冥府観の強い影響がみてとれる。死者の魂の行方をめぐる宗教観念は,もはやそれと分からぬ程に民衆の心意にすりこまれ,なかば生活化した状態となっていたわけである。成仏できない怨霊の噂咄が,ごく自然なかたちで人々の間をへめぐったことは,仏教と近世社会の日常的な親縁性に起因するといってもよかろう。」
そうした神仏の霊験,利益,寺社の縁起由来,高僧俗伝などに関する宗教テーマが広く広まり,
仏教説話の俗伝化,
を強めて,宗教伝説が,拡散していった。
他方で,怪異譚は,結果として一族を滅ぼし,法力の霊験が効果がなかったことをも示しており,ある意味,宗教的因果譚の覊絆から離れていく傾向が,
「もはや中世風の高僧法力譚の定型におさまりきれなくなった江戸怪談の多様な表現を示す特色」
であり,説話の目的と興味が,
「高僧の聖なる験力や幽霊済度といった『仏教説話』の常套表現を脱却して,怨む相手の血筋を根絶やしにするまで繰り返される亡婦の復讐劇に転換するさま」
がみられ,それが怪異小説に脚色され,虚構文芸の表現形式を創り出すところへとつながっていくことになる。
本書は,その江戸怪談の中から,
『狗張子』『怪談登志男』『金玉ねじふくさ』『太平百物語』『御伽厚化粧』といった怪異小説集からの小品集,
と,いわゆる四谷怪談の種本となった,
『四谷雑談集』,
清玄・桜姫の怪談を清水寺子安観音の本地に結び付けて説いた勧化本の,
『勧善桜姫伝』,
いわゆゆる大南北の鶴屋南北の,
『怪談岩倉万之丞』,
初世林家正蔵の浄瑠璃『お半長右衛門』を取り入れた怪談咄,
『林乃河浪』,
そして上田秋成の『雨月物語』から,
「吉備津の釜」。
やはり,「吉備津の釜」の完成度が高いが,一番面白いのは,
『四谷雑談集』
である。この本は,作者不詳の実録小説とされたものだが,写本の奥付に,享保12年(1727年),元禄時代に起きた事件として記されている,という。これが鶴屋南北の『東海道四谷怪談』(初演 文政八年(1825))の原典とされた話でだそうだが,この話を下敷きにした作品としては、曲亭馬琴『勧善常世物語』(文化3年(1806年))や柳亭種彦『近世怪談霜夜星』(文化5年(1808年))があるという。
編者が言うように,内容は南北の芝居のようにおどろおどろしくはなく,もっと細かく江戸は御先手組組屋敷のあった四谷左門町を中心に,貧窮の与力・同心などの下級武士たちの生態を描いている。
話は,田宮伊右衛門だけではなく,御先手与力,伊東喜兵衛,同組秋山長右衛門の三家の絶滅までの因果話で,事は,
御先手同心田宮家の一人娘お岩の婿取り話から始まる。お岩は,疱瘡を患い,眼病も患ったため,
「かろうじて命はとりとめたものの,ひどいあとが残って,顔は渋紙のようにざらざらになり,髪は年(二十一歳)にも似ず白髪まじりに縮みあがって枯野の薄のようになり,声はなまって狼が友を呼ぶような音になり,腰は曲がって松屋叢考の枯れ木のようで,その上片目がつぶれて,たえず涙をながし,かわいそうだが,その見苦しさはたとえるものがないほどであった。」
とさんざんである。そのため,なかなか婿がきまらない。そこで伊右衛門という牢人を,半ば騙すようにして婿に仕立てる。伊右衛門は,三十一歳,
「すらりとした身体つきの,顔だちのよい男」
と,いわゆる四谷怪談とは筋立てが違う。伊右衛門は,伊東喜兵衛の妾の一人が懐妊したが,それを(その妾に惹かれている)伊右衛門におしつけるために,秋山,伊右衛門と語らい,お岩を自分から離縁を申し出るように仕組んで,まんまとお岩を追い出す。それを知ったお岩は,狂乱し失踪する,ということで,遺恨を返すという,件の怪談話になるが,しかし,お岩の幽霊も,亡霊もほとんど出ない。ただ,次々と病や不幸に見舞われ,結句,田宮,秋山,伊東三家は絶滅する。
しかし,四谷怪談の基本的なストーリー,
「貞女・岩が夫・伊右衛門に惨殺され、幽霊となって復讐を果たす」
というものとはまったく異なる。むしろ,それなりに,伊右衛門は,若い妾に惚れ,伊東喜兵衛は懐妊した妾を厄介払いしたく,秋山長右衛門は金に目がくらんで加担するという,人間の欲からでた話として,むしろ通常の怪異譚よりは,何がしか身に覚えがあり,怖い。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%B0%B7%E6%80%AA%E8%AB%87
によると,
「田宮家は現在まで続いており、田宮家に伝わる話としてはお岩は貞女で夫婦仲も睦まじかったとある。このことから、田宮家ゆかりの女性の失踪事件が、怪談として改変されたのではないかという考察がある(小池壮彦「お岩」『幽霊の本』学研、平成11年)。」
という説もあるので,あくまで,これも志怪小説にすぎないのかもしれない。『四谷雑談集』のラストは,
「そもそもお岩の怨念というのは,伊東土快(喜兵衛)が妾の容色に迷い,邪を企てたことから発し,伊東,田宮,秋山,三人の家を絶やすことになった。その上多くの人の命がお岩のためにとり殺されて,後世の語り草となったわけだが,あながちお岩の怨みばかりでなく,この三人の心がけが邪であったからこんな事になったのである。」
と締めくくる。
小品集の中では,
「藪を借りた老人の話」
という,老人,つまり京都の古狐の話が,ほっとする。初世林家正蔵の『林乃河浪』は策に溺れて冗長,つまらない駄作である,と見た。
参考文献;
高田衛『日本怪談集〈江戸編〉』(河出文庫)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%B0%B7%E6%80%AA%E8%AB%87 |
|
パラレルワールド |
|
種村季弘編『日本怪談集』をよむ。
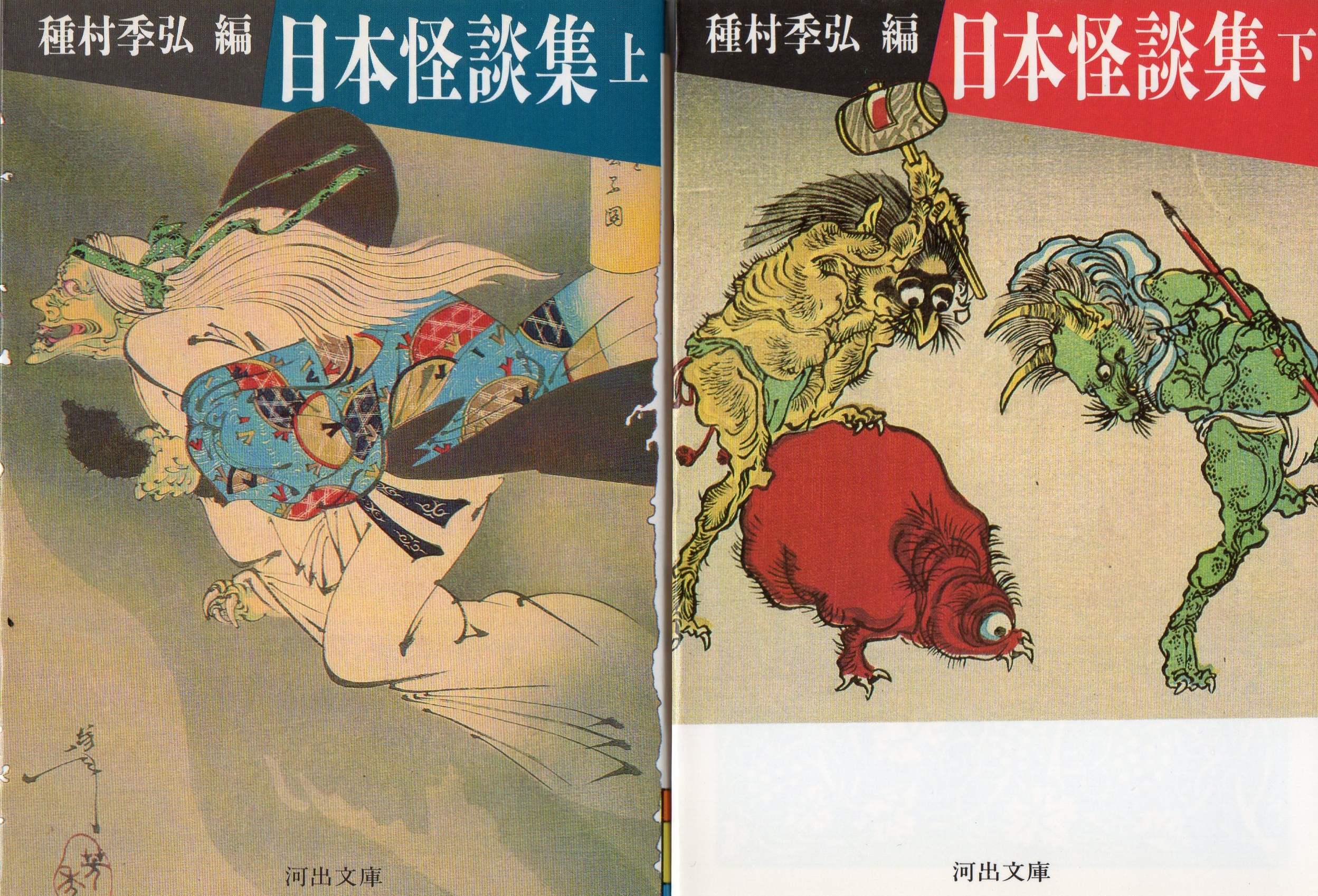
本書は,折口信夫から,森鴎外,三島由紀夫,芥川龍之介,泉鏡花,正宗白鳥,岡本綺堂,佐藤春夫,森銑三,吉田健一,澁澤竜彦,吉行淳之介,柴田錬三郎,筒井康隆,半村良,藤沢周平等々明治以降の作家の怪異小説を集めたものだ。
「怪を志(しる)す」
のは,中国伝来で,以来,様々な妖怪譚がある。
「妖怪の基本は,…二種類以上の動物が一つになった場合で,《鵺(ぬえ)》にその一典型をみる。」
という説もあるが,幽霊,妖怪,魔物などを含めて,「妖怪」は,
「日本で伝承される民間信仰において、人間の理解を超える奇怪で異常な現象や、あるいはそれらを起こす、不可思議な力を持つ非日常的・非科学的な存在のこと。妖(あやかし)または物の怪(もののけ)、魔物(まもの)とも呼ばれる。」
と一括りにしておく。僕は,怪異との出会いは,
接近遭遇,
であり,異界は,
パラレルワールド,
だと思っている。宇宙論が,あの世や幽界・霊界とつながることについては,コナン・ドイルのスピリチュアリズムについて触れた,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/441553477.html
や,あの世を量子論からアプローチした,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416694519.html
で触れた。なお宇宙論のパラレル・ワールドについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416793184.html
で触れている。
異界がパラレルワールドであることを示すのは,筒井康隆の「母子像」だろう。異界へ連れ去られた妻と子を,そこから引き出したのだが,身体だけは,こちらへ取り戻したが,首だけが異界に残り,
「妻の首は,そして赤ん坊の首は,ついに戻ってくることはなかった。首のない妻は,首のない赤ん坊を抱いたまま,一日中あの薄暗い茶の間で,今もひっそりとすわっている。もちろん,そとへでることもない。」
正確には,
「パラレルワールド(parallel
world)とは、ある世界(時空)から分岐し、それに並行して存在する別の世界(時空)を指す。並行世界、並行宇宙、並行時空ともいう。
『異世界(異界)』、『魔界』、『四次元世界』などとは違い、パラレルワールドは我々の宇宙と同一の次元を持つ。SFの世界でのみならず、理論物理学の世界でもその存在の可能性について語られている。」
だそうだが,宇宙論の相互の宇宙は,出会うことはない。一説には,人が,何かをして,選択する度に,別の選択をした世界とは,平行線世界として分岐するという。これは,異世界とも同じだ。
吉田健一「化けもの屋敷」は,パラレルワールドそのものだ。同じ屋敷に,以前の家族と同居している。
「日が暮れると木山がゐる所にだけ電気を付けてさうすると電気が付いていない座敷の方で人の話し声が殊の外賑やかになるやうだつた。或は確かに賑やかになつてそこまでせ行つてみれば電気も付いてゐるのではないかといふ感じがした。併しそれで木山はその家にゐる何かとの最初の問題にぶつかつてそれは木山はその家にゐるのが自分だけではないことを知ってゐてもその何かの方は木山がそこに移つて来たことに気が付いてゐるのだらうかといふことだつた。もし気が付いてゐなければ他人でそれが集まつてゐなければ他人でそれが集まつてゐる中に挨拶もしないで入つて行くのは遠慮しなければならないことだった。又挨拶をするとしてその時に何と言つたらばいいのか。木山はそれまでただ簡単に人間か人間と見ていいものと考へてゐたのだつたがまだ木山はさういふものと付き合つたことがなかつた。」
この主人公の構えの何というか,ユーモラスさが,全体の特徴で,そこで老人を見かけるのだが,
「そこの家の家の人達は先づ眼に見えないでゐるのが普通のやうでその一人が木山の前に姿を現したのは好意からのこととしか思へなかつた。」
という感慨は,ちょっとユニークといっていい。それが「化けもの屋敷」というタイトルとは異なる和やかな雰囲気を醸し出している。
このアンソロジーの中の傑作は,稲垣足穂の「山ン本五郎左衛門只今退散仕る」であろう。この元となったのは,堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/432575456.html)でも触れた,
「江戸時代中期の日本の妖怪物語『稲生物怪録』に登場する妖怪。姓の『山本』は、『稲生物怪録』を描いた古典の絵巻のうち、『稲生物怪録絵巻』を始めとする絵巻7作品によるもので、広島県立歴史民俗資料館所蔵『稲亭物怪録』には『山ン本五郎左衛門』とある。また、『稲生物怪録』の主人公・稲生平太郎自身が遺したとされる『三次実録物語』では『山本太郎左衛門』とされる」
話が基ネタである。まだ元服前,十六歳の「稲生平太郎」が,我が家に出没する妖怪変化に対応し,大の大人が逃げたり寝込んだりする中,「相手にしなければいい」と決め込んで,ついに一ヶ月堪え切り,相手の妖怪の親玉,山ン本五郎左衛門をして,
「扨々,御身,若年乍ラ殊勝至極」
と言わしめ,自ら名乗りをして,
「驚かせタレド,恐レザル故,思ワズ長逗留,却ッテ当方ノ業ノ妨ゲトナレリ」
と嘆いて,魔よけの鎚を置き土産に,供廻りを従えて,雲の彼方へと消えていく。この,肝競べのような話が,爽快である。
その他,「くだん」
http://ppnetwork.seesaa.net/article/456407720.html
で触れたように,小松左京「くだんのはは」,内田百饟「件」と,妖怪「くだん」をめぐる話も面白い。掉尾を飾る,折口信夫の「生き口を問ふ女」は,未完ながら,関西弁の語り口が生き生きとして,さてどうなると,気にかかる。
参考文献;
種村季弘編『日本怪談集上・下』(河出文庫)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E4%BA%94%E9%83%8E%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%96%E6%80%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89
阿部正路『日本の妖怪たち』 (東書選書 )
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%B6 |
|
パースペクティブ |
|
石田英一郎『桃太郎の母―ある文化史的研究』を読む。
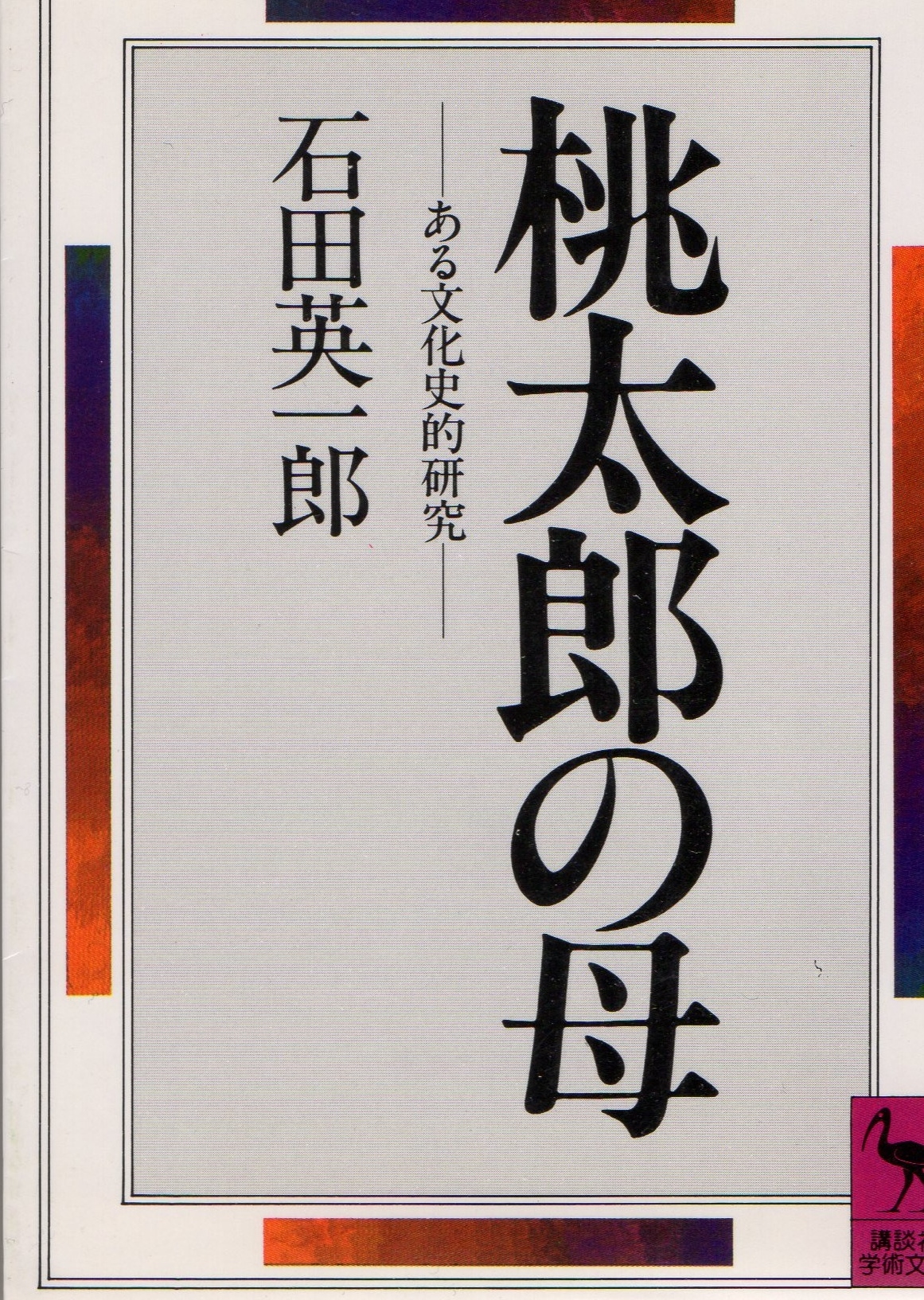
本書の今日的な評価は知らない。しかし,そのパースペクティブの射程の深さは,圧倒される。たとえば,タイトルになっている「桃太郎の母」は,その端緒を,柳田國男が,
小さ子(ちいさご),
と名づけた説話の系列,つまり,
「古くはスクナヒコナの神の神話をはじめ,一方で赫奕姫(かぐやひめ),瓜子姫,桃太郎,一寸法師等々,人口に膾炙するお伽ばなしに発展し,他方では奥州の座敷ワラシ,スネコタンパコ,カブキレワラシ,ウントク,ヒョウトク,信州の小泉小太郎,泉小次郎,鳥取の五分次郎などのような種類の地方的俗信や昔ばなしにのこる一連の伝承」
を端緒に,小童と水界とのつながり,その母神を糸口に,朝鮮半島を経てユーラシア大陸まで,さらに太平洋の島々の母子相姦による民族起源譚,豊穣神としての母像から,母子像を経て,ついに幼子キリストを抱くマリア像までたどりつく,その射程の幅と奥行きに驚かされる。
「わが国の一寸法師をはじめ,各種の小サ子物語の意義は,その背後にひそむ母性の姿を,消えゆく過去の記憶から引き出してこれと結びつけることによって,その隠微な一面が解明されていくのではあるまいか。私はここで文化の伝播とか,独立起源とかいう,言い古された用語を用いて問題をあげつらおうとするものではない。ただ,少なくとも本稿で取り扱った一群の信仰の根底には,かつて地球上ある広大な区域を支配した母系的な社会関係や婚姻の形式が,共通の母胎として横たわっていることを,今後の研究のための初次的な作業仮説として想定すればたりるのである。」
と締めくくる。その余韻で見ると,
「戦国時代に輸入されたキリスト教の聖母が《マリア観音》の称呼をもって迎えられたのも,悠遠の過去の共同の母胎から相分かれたまま,それぞれ別個の発達をとげた二つの信仰が,ふたたび文化の接触によってたがいに相結ぶにいたった一例を示すものとして興味深い。」
という一文は,なかなか意味深である。
方法は同じだが,個人的には,「桑原論」が面白い。「くわばら」については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/412748051.html
で触れたが,雷など怖いものにであった時,
「くわばら,くわばら」
と,呪文のように唱える,あの「くわばら」である。今日では,あるいは死語に近いのかもしれない。その謂れは,
ひとつには,菅原道真の領地「桑原」にあるらしい。都には落雷が多かったが,この地だけは,被害がなかった。で,落雷除けのマジナイに使った,というのである。
ふたつには,大阪和泉軍の桑原の井戸に落雷後,すぐに蓋をして雷を出られなくしたので,雷神が「自分は桑の木が嫌いなので,桑原と唱えたなら二度と落ちない」と誓った,という伝説によるともいう。この説には,異説もある。和泉の西福寺には雷井戸と呼ばれる井戸があるらしい。このお寺には奈良時代に道行と言う修行僧がいて,雷に遭遇したとき,慌てずに大般若経を浄写したところ雷がピタリとやんだという伝説があり,それ以来ここにある井戸には雷を封じ込める力があると言われるようになった。「くわばら くわばら」と唱えることで「ここは雷を封じ込めた雷井戸のあるクワバラですよ」と雷に教えると言うことになった,というもっと詳しい説明がついたものもある。
三つには,説話的な説で,桑原という人が落ちてきた雷さまを助けたという。そこで雷さまが「おまえとおまえの子孫の住む場所には雷を落とさない」と約束をしたのです。それ以来雷が落ちそうになると,誰もが桑原さんの子孫だと「くわばら くわばら」と言うようになったというものである。
四つには,昔から雷は何故か桑畑に落ちないといわれていて,そのために,雷がなると昔は桑畑に逃げたと言われている。そこから,雷が鳴り出すと「くわばら くわばら」と言って,雷を避けるようになったと言われています。
いずれも,「桑原」という言葉に関わる。「雷」と「桑」とのかかわりは,
「桑樹もしくは桑葉の呪能にもとづく」
とし,
「桑を何らかの形で霊怪視する思想は古くから分布する」
という。中国民間では,雷のみならず,
「古来山中より出没する独脚反踵(どくきゃくはんしょう)の怪山魈(かいさんしょう)も,また『最も桑刀を怕(おそ)れ,老桑を以て削って刀と成し,之を斫(き)れば即ち死す。桑刀を門に懸くるも亦避けて去る』といわれている。」
と,魔よけの効力をもつ。これは,桑を聖樹とする中国のきわめて古い信仰に起源があり,
「先秦以来の諸書に見える扶桑(榑桑)は,太陽の出入する所の神木と信ぜられた。『山海経』に,『湯谷(とうこく)の上に扶桑り,十日(じゅうひ)の浴する所,…大木有り,九日(きゅうひ)は下枝に居り,一日は上枝に居る』(海外東経)と言い,また,『湯谷の上に扶木有り,一日方に至れば一日方に出づ,皆烏を戴く』(大荒東経)とある」
ことから,
「古代の中国人は,一種の桑樹によって太陽の運行を考える《世界樹》的な信仰を有していたことがそうぞうせられないだろうか。」
とし,『呂史春秋』の,高誘注,
「桑林は,桑山の林,能く雲を興し,雨を作(おこ)し」
と,桑樹の霊能が水界と関係あるところへと至る。その桑樹神聖化の思想は,中国を故地とする養蚕へとさかのぼっていく。そして,殷墟の出土品と伝えられる,骨の蚕に行き着く。さらに,
中国で馬と蚕の,
「馬頭娘,馬鳴(ばめい)菩薩などの蚕の神として民間に祀られ,『蚕は馬と神を同じゅうす。本竜精にして首馬に類す。故に蚕駒と曰ふ』などともいわれている。」
という中国の俗信や説話は,そっくりそのままわが国各地の民間に広く分布している。
「両者が無関係に発達したものとはどうしても考えられない。常陸をはじめ関東一円から以西にかけては,養蚕の守護神としての馬鳴菩薩や馬頭娘信仰が普及している」
つまりは,
「わが『桑原々々』の呪語や俗信が,けっして単なる地名や人名にからんだ伝承ではなく,遠く禹域桑土の野の養蚕習俗から生まれた,ある種の呪的な信仰にその濫觴を有する」
とまとめる。語源的な「ことば」レベルの奥に,生活史があり,そこを手繰り寄せていかない限り,言葉の背景は見えてこない,とつくづく思い知らされる。
参考文献;
石田英一郎『桃太郎の母―ある文化史的研究』(講談社学術文庫) |
|
非‐知 |
|
ジョルジュ・バタイユ『非‐知―閉じざる思考』を読む。
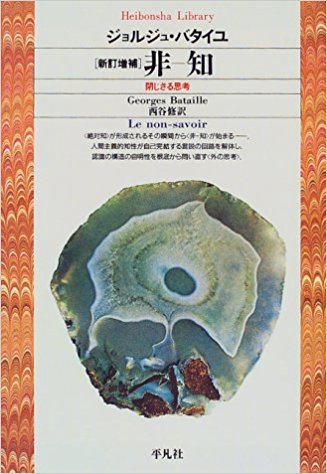
本書自体が,講演速記,草稿,等々からなる断片の寄せ集めのせいか,全体像を摑むのが実にむつかしい。「非‐知」について,バタイユは,こう述べる。
「この非‐知という言葉でわたしが言おうとしていることをもう少し厳密な言えば,ある命題の内容を根底まで掘り下げようとするとき,そしてそのことに何かひっかかりを感じるとき,こうしたすべての命題から結果するもののことを言っているのです。」
バタイユは,A=J・エアー,メルロ=ポンティらとの議論の中で,「人間が生存する以前に太陽はすでにあった」という命題を巡って,物理学者(アンブロジーノ)が「太陽は世界より先には存在しなかった」と言い,エアーが「人間が存在する以前に太陽はすでにあった」と言う,そういう発言に対して,
「どうしてそういうことが言えるのかわかりません。この命題は,道理に敵った命題が完全な無-意味を呈することがありうる,ということを示すものです。誰しもが共有しうる真理は,発せられている命題には原則として主題と対象とが潜在的にふくまれているという意味での,全体的意味を備えていなければなりません。ところがこの命題では,太陽はあったけれども人間はいない,つまり主題はあって対象がないわけです。」
ここでバタイユが言っている「ひっかかり」は,
「どこか精神的にひっかかり,不安定な気分にさせる。」
というものを指す。
このとき,バタイユがひっかかっているのは,訳者(西谷修氏)が,ヒロシマをめぐって(バタイユの『性の苦悩からヒロシマの不幸へ』を引きつつ)こう言っていることと照応する。
「核兵器についてもちうるさまざまな知識,それを生み出した知,その効能について,用途について,さらにその惨禍についての知と,実際には『ヒロシマ』を生きた人びとの置かれた『動物的な無知』(世界了解の構造が解体され,もはや,『人間的』反応を維持することさえ難しくなる)との暴力的な懸隔の前に茫然自失している。…ひとは何でも知的に理解することはできるが,それは極端な『無知』をともなって実現され,生きられるこの『無知』の闇の前には知は完璧に無力なのだ。
非-知とはそういう事態であり,現代の知の,常に隠蔽される根本的な条件なのである。」
人のなかにある「ひっかかり」を無視すれば無視できる。しかし,その翳を,バタイユは徹底的に追い詰めようとしているように見える。
「わたしはかの問い,いうなればハイデガーの建てたあの問い(なぜ存在があって,無があるのではないのか?)の前に立たされるのです。わたしとしては,この問いは不十分だとずっと以前から考えていたので,もうひとつ違うかたちで問いを発してみようとしました。つまり,なぜわたしの知っていることがあるのか,という問いです。最終的にはこのことを完全なかたちで言葉にすることはできないと思っています。とはいえ根本的な問いは,いかなる定型表現も不可能となるそのときから,人が沈黙のうちに世界のうちに世界の不条理を聴きとるそのときからしか提起されえないものだと思います。
わたしは何が認識可能かを知るためにあらゆる手立てを尽くしましたが,私が求めたのはわたしの奥深くある言い表わしえないものなのです。私は世界の中のわたしですが,その世界はわたしにとって気の遠くなるほど近づきがたいものだと認めています。というのも,わたしが世界と結ぼうとしたあらゆる絆の中に,何か克服できないものが残っており,そのことがわたしをある種の絶望にとり残すからです。」
それを,
「鍵をかけたトランクの中に何があるかを知らない,その鍵を開けることもできない者の立場」
になぞらえた。しかしサルトルは,
「何も知らないのなら,知らないと一度言えばそれでたくさんだ」
というだけだと,バタイユは,サルトルとの差を表現する。それは,
「何かを求めながらそれが手にはいにらないだけの絶望とは較べようのない完璧な絶望のうち」
と喩える。
「それはわれわれが通常味わう絶望,何かの企てが念頭にあってそれが実現できないとか,本質的には欲求の対象に執着するあまり欲求不満に苛まれるといったことに由来する通常の絶望より,遥かに深い絶望です。」
なぜなら,
「わたしが何も知らないと主張しうるのは,ただわたしがいっさいを知り尽くしたと仮定した場合だけであり,わたしが非‐知に辿り着いたと決定的に主張しうるのは,この言説的知(絶対知)をわたしが所有したときだけでしょう。事物を不正確にしか知らないうちは,いくら非‐知だと言い張っても,それは空疎な主張にすぎません。私が何も知らないのであれば,言うべきことは何もないわけです。わたしは口を閉ざすでしょう。」
であり,サルトルの言っている「知らない」とはこれを指す。これは,死,笑,戯れ等々に喩えられる。
「死を思い描いてみることはできます。思い描きながら同時にその表象が正確でないと意識することもできます。死に関しては,われわれが何を言おうとも何がしかの錯誤がついてまわります。とりわけ死に関する非‐知も,一般的な非‐知と同じ性質をもっているのです。」
「死にうるために生きる。歓ぶことを苦しみ,苦しむことを歓ぶ,もはや何も言わないために語る。『非』とは,知らないことの情熱的受苦を目的とする―ないしはみずからの目的の否定とする―ある認識の媒介項である。」
「大いなる戯れとは非‐知だということ―戯れは定義できない,思考の崩壊しえないものだ。」
「われわれが笑うのは,ただ情報や検討が不十分なためにわれわれが知るに到らないといった性質のもつ何らかの理由のためではなく,知らないものが笑いを惹き起こすからこそ笑うのです。」
「ただ少なくとも,笑うときにはいつでも,われわれは知っているもの,予測可能なものの領域から,知らないもの,予測不可能なものの領域に移行しているときだということを示すことはできるでしょう。」
等々,そしてバタイユは,
「まず笑いの体験から出発し,この特殊な体験からそれに隣接する聖なるものや詩的なものの体験に移るとき,笑の体験を手放さずにいることができるのです。そう言ってよければそれは,笑いという与件の中に,哲学の中心的与件,第一の,そしておそらくは最後の与件を見出す」
として,自分のやっているのが哲学とすれば,
笑の哲学,
だと言い切る。その背景にあるのは,
「知はわれわれを隷属させるもの」
「意識は限定された対象についての意識であり,したがって対象の限界が否定(あるいは破壊)されてしまえば対象意識はあり得ない。対象の限界,あるいは対象としての主体の限界が否定されてしまうと,そのときから意識は夜に入る。あるいはむしろ,意識は,対象の限界の否定(ないし破壊)を限界(定義)としてもつ対象意識となる。つまり,意識の作用が限界の不在を新たな限界に,対象の破壊の起こる場である対象を新たな一種の対象に,非‐意味を新たな意味に,取って代えるのだ」
「意識とは他でもない限界の意識だからだ。意識はまるまる規則の側にある。意識が欠落すれば,そのときはじめて哲学は端緒につくことができるだろう。」
だから,
「神,聖なるもの,エロティックなもの,笑いを惹き起こすもの,詩的なもの,等々未知のものと同一視することが,いっさいの哲学的困難を解く鍵である。」
とするのである。それにしても,
「わたしの言う非‐知の体験の中に宗教的体験が残っているとしても,それは将来への配慮からはまったく切り離されており,その体験が命ずるような起こりうる威嚇的な苦痛からもまったく切り離されており,それはもはや戯れでしかないのです。」
とあるのを読むと,次元は異なるかもしれないが,どこか最後,非‐知は,知を突き抜けた愚になっていくように見える。そのとき,良寛のことを思い出した。しかし,バタイユは,
「(照らされた)明るみと(照らす)光の地帯について語ること,それが知と非‐知とを乗り越えること」
というような,メタ哲学を手放してはいない。そして,良寛は知を閉じて完結させているとすれば,バタイユのそれは,けっして閉じない,あるいは諦めない知,ではあるけれど。
参考文献;
ジョルジュ・バタイユ『非‐知―閉じざる思考』(平凡社ライブラリー)
|
|
喩 |
|
村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読む。
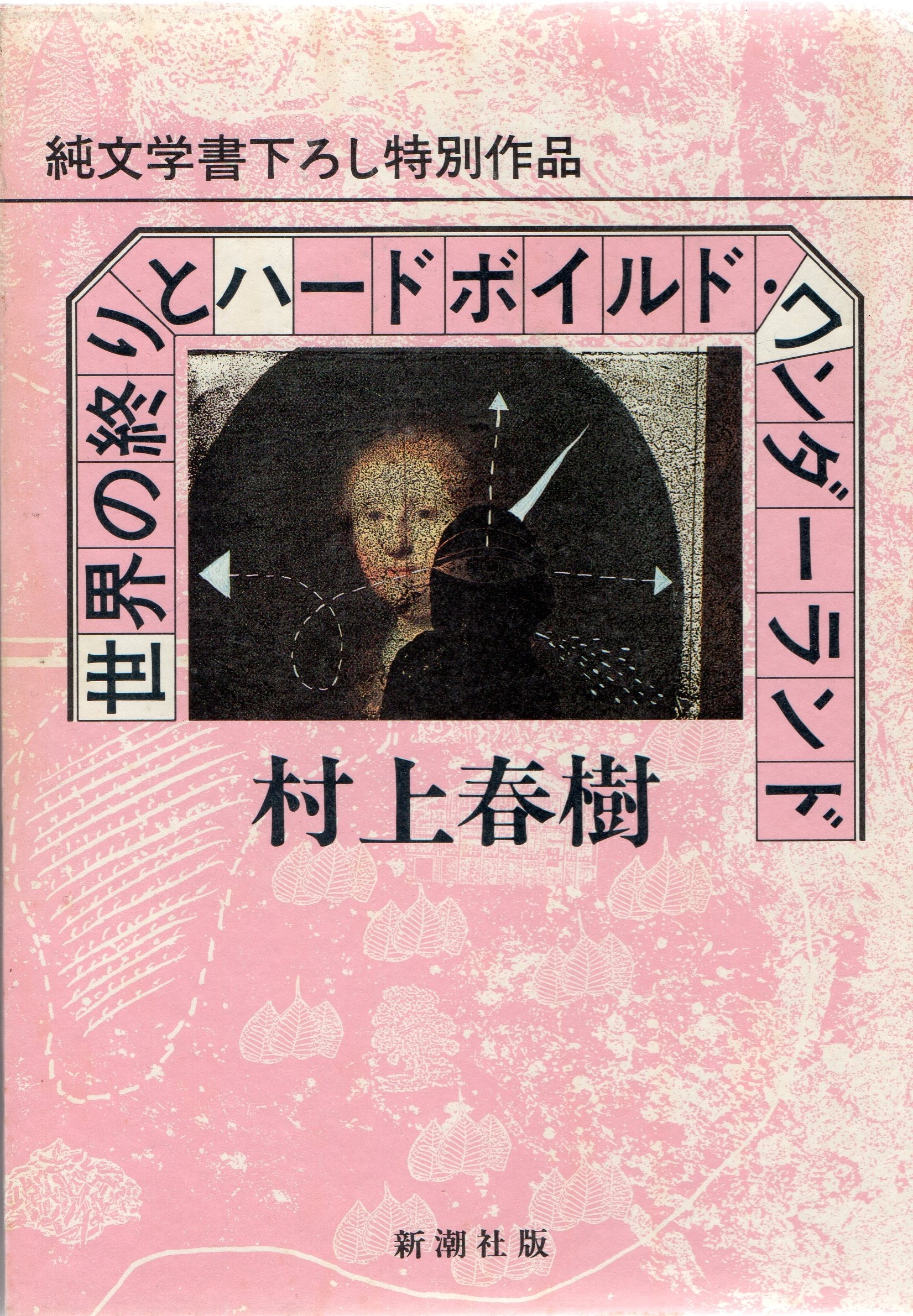
何の間違いが,書棚の本を順次廃棄している中に,本書が出てきた。随分昔,『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』と,初期の作品を読んだ記憶があり,その軽快さと,反面のうすっぺらさが嫌で,以降読むのをやめたつもりだったが,調べると,本書は,その次の作品らしい。ずいぶん間を置いて,気まぐれに買ったものだと勘違いしていたが,三作読んで,その次というつもりで購入したまま,放り出していたものらしい。
かなり前なので,或は評価が確立しているのかもしれないが,今日どんな評価になっているのか,僕は村上をほとんど読まないので,全く知らない。知らない上で,自分なりの感想を勝手に述べて見る。
正直,くどいところもあるが,ストーリーはおもしろい。ときにハードボイルド,ときにSF,ときにファンタジー。しかし,それだけだ。やはり,うすっぺらな気がしてならない。蟹はおのれに似せて穴を掘る,というから,結局自分が薄っぺらだけなのかもしれないが,何か薄い,という印象をやはり拭えない。それと,どこかで見たような既視感がつきまとう。
基本的にファンではないので,斜に構えて読んだせいかもしれないが,あまりにも,
閉鎖的な,
そして,
自己完結した世界観,
に思える。要は,自分の中を,
メタメタメタ…化,
して見せた感じである。だから,
喩の上に(の中に)喩を載せ(あるいは容れ),さらにその上に(の中に)…,
という感じである。それは,ある意味,
ファンタジー,
であるし,
メルヘン,
である。書評家の大森望氏が,あるところで,
「現実的で論理的なのがミステリー、非現実的で論理的なのがSF、現実的で非論理的なのがホラー、非現実的で非論理的なのがファンタジー」
と整理されているとか,というのを目にしたが,その意味で,
夢,
と同じなのかもしれない。だから,筋自体は破綻していても構わない。構わないが,こう自分の中に,メタメタと入り込んで行ってしまうと,読者はおいてきぼりを食う。
この小説世界に浸れる人と,すっと身を引く人とに分かれるに違いない。僕は,後者だろう。僕には,誤解を恐れず,あえて言うなら,
何か高を括っている,
というふうに見えて仕方がない。社会とはこんなもの,人生とはこんなもの,自己とはこんなもの,心とはこんなもの等々,僕も多少高を括る癖があるので,偉そうには言えないが,何に対してかは分からないが,
見縊っている,
ように見える。それは傲慢というのではない,そういう感じは一切しない。それよりは,
自己完結,
させていることが,そう見えるのかもしれない。その外の世界について,
その喩,
で語り尽くせるはずはない。「喩」は,
メタファー,
である。世界を「喩え」で語っても,世界は語り尽くせない。しかし,それで完結させようとしている,というふうに見える。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163200.html
で触れたが,茂木健一郎氏は,村上春樹に言及して,
「双方向の行き来が盛んになるにつれて,翻訳可能なものだけが事実上の普遍性を帯びていくということは実際的な意味で不可避のダイナミクスだといってよい。村上春樹の作品が,最初から翻訳可能な文体で書かれていることは,意識されたものであるかどうかは別として高度に戦略的である。」
と言っていた。その真偽は知らない。また,その当否は,ここではどうでもいい。しかし,あの頻度の高い直喩は,たとえば,
「彼女の体には,まるで夜のあいだに大量の無音の雪が降ったみたいにたっぷりと肉がついていた。」
「進化途上にある魚のような気分で暗闇の中を上流へと向かった。」
「ひきちぎられた空の切れはしが長い時間をかけてその本来の記憶を失くしてしまったようなくすんだ駙だ」
「重機関銃で納屋をなぎ倒すような,すさまじい勢いの食欲だった。」
「彼女が一枚ずつ服を身にまとっていく様は,ほっそりした冬の鳥のように滑らかで無駄な動きがなく,しんとしたと静けさに充ちていた。」
「沈黙が銃口から出る煙のように受話器の口からたちのぼっていた。」
「インカの井戸クライアント深いため息をつき,」
「ウエイターがやってきて宮廷の専属接骨医が皇太子の脱臼をなおすときのような格好でうやうやしくワインの栓を抜き,」
「日曜日の朝の公園は飛行機が出払ってしまったあとの航空母艦の甲板みたいにがらんとして静かだった。」
等々,実に具象的なイメージが湧くように書かれている。それは,何語に置き換えても,クリアなはずだ。しかし,中には,その喩のイメージとその描写のシチュエーションがマッチしないものもある。あっても,たぶん気にならない。なぜなら,
喩の中の喩,
つまり,
現実からは切れた喩の中の喩,
でしかないからだ。それは,
現実の捨象の仕方,
と言ってもいい。
高を括る,
とは,この捨象の仕方を言っている。「計算士」「記号士」「組織(システム)」「工場(ファクトリー)」もすべて,喩である。その文脈の中では,「コンピュータ」も喩であり,「私」も「僕」も喩である。「博士」も「孫娘」も「図書館の女」も喩でしかない。何かについての喩えでしかない。しかし,喩えは,現実にフックがかかっていない限り,ただの抽象であり,肉体をそぎ落とした洗い晒した骨にすぎない。その意味で,
頭骨,
は象徴的である。しかし,そこに何かを深読みしても無駄である。すべては,洗い晒されているからだ。その意味でも自己完結している。それは,ある意味,
無国籍化した文体,
そのものが象徴している(この作品の文章を「文体」という言葉で表現するにはひどく抵抗あるが「文章」とは言えないので仕方ない)。
参考文献;
村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(新潮社)
茂木健一郎『思考の補助線』(ちくま新書)
|
|
噓 |
|
ヘンリー・ジェイムズ『嘘つき』を読む。
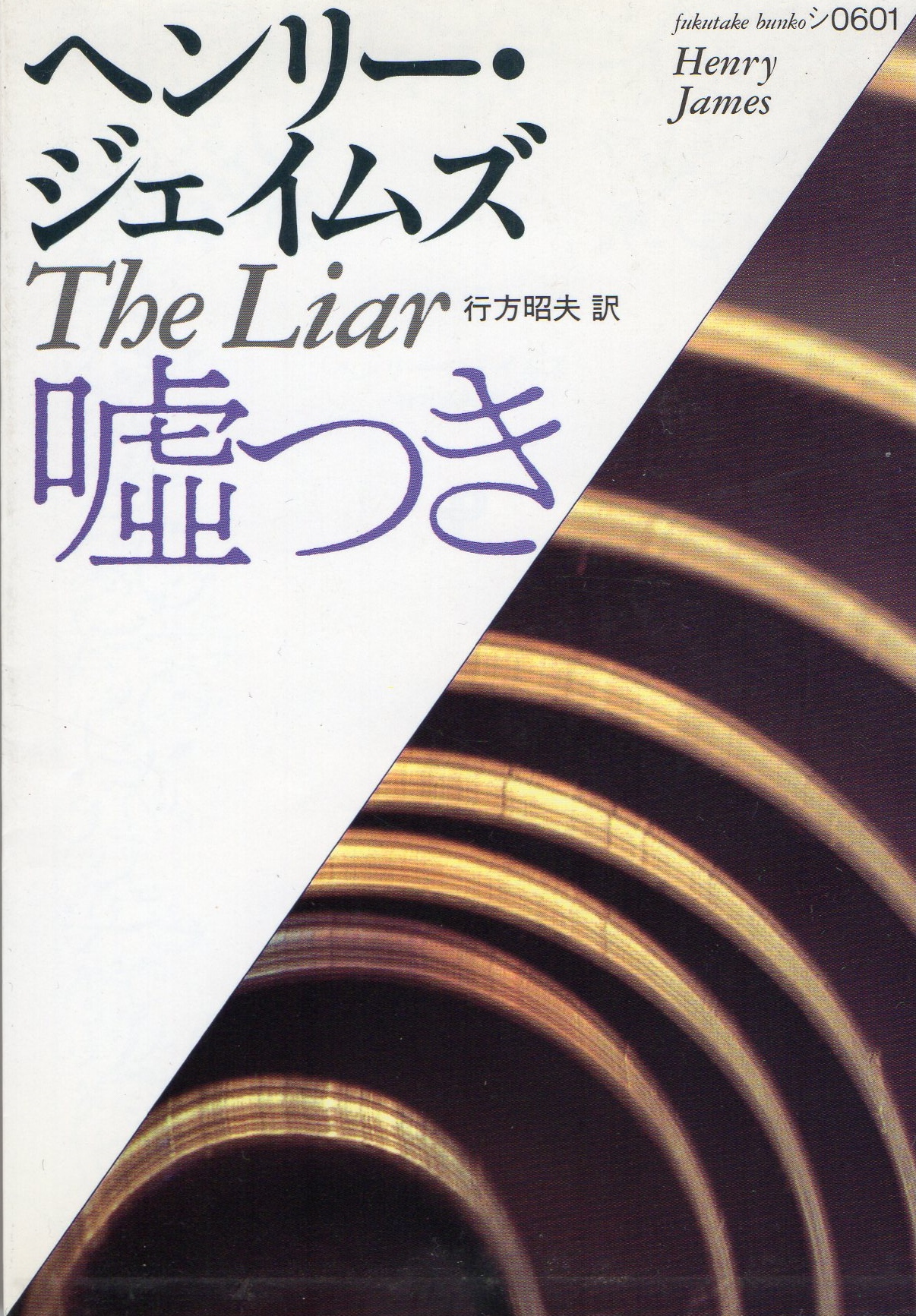
「噓」とは,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%98
によると,
「嘘とは事実に反する事柄の表明であり、特に故意に表明されたものを言う。
アウグスティヌスは『嘘をつくことについて』(395年)と『嘘をつくことに反対する』(420年)の二論文において、嘘について「欺こうとする意図をもって行われる虚偽の陳述」という定義を与えている。」
とある。その場合,「噓」つまり「事実に反する事柄の表明」だと,誰が認知するのか,ということで,話が違ってくる。神の位置から,真偽を判定するのでなければ,「噓」であるかどうか,誰に分かるのか。
本書は,「噓」について,考えさせる三作が載っている。
『五十男の日記』
では,書き手が,相手を魔女だと決めつけて,相手から身を隠した二十七年後,その娘と同じような関係にある青年を通して,自分が二十七年前,自身の思い込み(自分で信じた「噓」と言ってもいいし,先入観と言ってもいい)によって,目をくらまされたことに気づく。そして,ラスト,
「いやはや,なんと多くの疑問が次々と湧いてくることか! たとえわたしが彼女の幸福を損なったとしても,わたしだって幸福にはならなかったのだ。だがそうなれたかもしれないではないか。この年になってそんな発見をするなんて何ということだ!」
と述懐する。でもまだ,自分が決めつけた相手象から自由にはなっていない。
『嘘つき』
は,嘘つきだが,
「大佐の噓はさまざまな種類があったが,どれにも共通の要素があり,それは徹底的な無用性であった。それ故にこそ腹立たしかった。それは普通の会話の場に割り込んできて,貴重なスペースを占領し,その場を実体のないゆらめく蜃気楼のようなものにしてしまうのだ。これがやむを得ずつく噓であれば,丁度芝居の初日の夜,原作者から貰った無料入場券を持って劇場に現れた人に対してのように,それなりの場所が与えられよう。しかし無用な噓は入場券なしで現れた客のようなもので,通路に補助椅子を置いてもらう以上の扱いは受けられないのだ。」
という類で,その大佐の妻が,主人公がかつてプロポーズした女性であるだけに,彼女がどこまでそれを承知しているのか,を確かめたく思い,無理やり,大佐の肖像画を画くことを申し入れ,その大佐の本性を描きだそうと企む。
「大佐の本性を引き出して,…全体像を余すところなく描いてやろるのだ。凡人にはそれが分からないだろう。分かる者には見抜ける筈だ。柄を解する人びとは,きっとその肖像を騠く評価するだろう。それは意味深長な作品で,微妙な性格描写の傑作であり,合法的な裏切りともなるだろう。ライアンは,もう何年も前から,画家と真理研究家と両方の手腕を示すような作品を描いてみたいと望んでいたが,ようやくその機会が面前にあらわれたのだ。」
ほぼ完成したが,見せるのは休暇後と約束したが,旅先で,
「ふと,その絵を再び見て,二,三筆を加えたいという欲求」
にかられて急いで旅を切り上げて帰宅すると,そこに大佐夫妻が来訪し,絵を見ようとしているのに遭遇し,その様子を盗み見る。夫人は,叫ぶ。
「全部出てしまっているわ! 出てしまっていする!」
「一体,何が出ているっていうのだ?」
「あってはならぬものが全部ですよ。あの人が見たもの全部が出てしまっている!ああ,恐ろしい!」
「あいつが見たもの全部だって? それでいいじゃないか! 僕は好男子だものな。どうだい,いい男に描けているじゃないか」
(中略)
「あなたを変人にしてしまったのですもの! あの人は発見したんだわ! これでは誰にでもわかってしまう。」
そうした帰りかけて,大佐は戻ってくると,キャンバスを切り裂いていった。その一部始終を目撃したが,後日再会した折,二人は,作品が切り裂かれたというライアンに,
「何だって!」大佐が叫んだ。
ライアンは微笑を浮かべて視線をそちらに向けた。
「まさかあなたがやったのではないでしょうね?」
「もう駄目ですか?」大佐は尋ねた。彼は妻と同じく何の疚しいところもないという顔をし,ライアンの質問を冗談と見なしているようだった。「わたしがやったとすれば,またはじめから描いてもらうためですね? それを思いつけば,きっと,やったところですよ!」
「まさか奥さまでもありませんね?」ライアンは尋ねた。
夫人が答える前に,夫はとてもよい答えを思いついたというように妻の腕をつかんだ。
「きっとあの女がやったんだよ!」
ライアンが,夫人が夫の嘘つきであることを知っているかどうかの答は出た。しかし,肖像画家として,本人は,かつて愛した女性の本音を引き出そうとしたのは,あるいは,ライアン自身の自分に対する嘘でもあるかもしれない。本音は,
「ヨーロッパ全体で,半ダースばかりのライアンが最高傑作と折紙をつけている肖像画」
の一翼に加わる絵を描くというのが,本音なのかもしれない。その意味で,『嘘つき』は,正真正銘の嘘つきである大佐を対象にしながら,その実,その嘘つきの,
「どんな鈍い人にも分かるよう,画の中ではっきり出るようにしよう」
という意図にあり,それは達成されたのである。
「彼は一部始終を目撃しながら絵を失いつつあるとは感じなかったし,たとえ感じても気にしなかった。それ以上に,確証を得たことを強く感じていたからだ。彼女はたしかに夫を恥じている。そしてこのぼくが恥じるようにさせたのであり,その意味で,たとえこの絵は切断されてしまっても,大成功を収めたのだ。」
ラストで,
「何しろ,彼女は今でも大佐を愛しているのだ。何とよく飼いならされてしまったことだろうか!」
とライアンは嘆くが,それは多分違うのだろう。ライアンは,画家であり,結局,「対幻想」の土俵に乗り,その幻想を共有するのではなく,それをメタ・ポジションから見る,ということしかできなかった,ということでもある。ここでは,ライアン自身が,自分の噓には気づけていない,と作家は描いているようにみえる。
『モード・イーヴリン』
は,その意味では,死んだ娘イーヴリンと共に生きる夫婦の幻想の世界に取り込まれた若い男女を描いている。その幻想を共有する土俵に乗らなければ,見えないものがある。語り手のエマ夫人は,徹頭徹尾部外者であり,その批判者であるが,その幻想についてのさまざまな思いを聞いてやる立場でもある。それを聞くものがいなければ,その幻想は自己完結しているので,外には漏れ出ない。エマ夫人は,意図せず,うつつと幻の橋渡し役になっている。
ここで,「噓」というものが,当事者にとって真実である限り,それを噓と決めつける根拠が失せるということを示している。
本書の著者は,『ねじの回転』等々で知られているが,丁度神の視点から,作中人物の視点へと,作品のパースペクティブを転換する先駆者と言われる。その意味では,「噓」という私的なパースペクティブで語るには,絶好の素材に見える。しかし,ところどころ,上の視点の作者がポロリと出てくるのはご愛嬌だろう。『嘘つき』の中に,
「この点についてのライアンの関心は愚かしくも独りよがりだと読者の目に映るかも知れないが,心に傷を受けている者はある程度大目に見てやらなくてはならない。」
とある。書き手(作家ではない)の声に聞こえる。
参考文献;
ヘンリー・ジェイムズ『嘘つき』(福武文庫) |
|
concept of mind |
|
ギルバート・ライル『心の概念』を読む。

今日のライルの評価は分からないが,ヴィトゲンシュタインと並ぶ,
日常言語学派,
に位置づけられる,という(訳者解説)。ライルは,本書の意図を,
「われわれが心についてもっている知見について,その論理的地図の改訂を試みようとするもの」
とし,
「心的行為の諸概念(memtal-conduct ckncepts)の論理的な振る舞いを吟味」
していく。それに,
カテゴリー錯誤(category-mistake),
と,ライル自身が呼ぶ概念によって,過去の哲学の理論構成を打破していく。対象となるのは,ライルの,
機械の中の幽霊のドグマ(the dogma of the Ghost in the
machine),
と名づけた,デカルト流の心身二元論である。その誤りを,
「たんなる個々の誤りの集まりであるのはなく,一つの大がかりな誤りであり,同時にまた,ある独特な種類の誤りなのである。その意味において,これは『カテゴリー錯誤』(category-mistake)とがふさわしいと思う。」
と。そして,
「根本的なカテゴリー錯誤が二重生涯理論double-life
theoryの源泉となっている」
と。それは,
「結局,デカルトは問題の論理を誤ったのである。彼は理知的な行動が現実にはすかなる規準によって非理知的な行動と区別されているかということを問うことをせず,むしろ『機械論的因果の原理がその両者の相異を明らかにすることができないとするならば,そもそも他のいかなる因果的原理がその差を明らかにすることができるのか』と問うたのである。彼はそれが力学の問題でないということは十分理解していた。そこで彼はそれが力学に対応する他の何ものかでなければならないと仮定した。(中略)
ある二つの名辞が同じカテゴリーに属している場合には,その両者を含む連言的な命題を構成することは適切である。たとえば,買い物客が右手袋と左手袋を買ったと述べることは可能である。しかし,彼は右手袋と左手今日も袋と,そして一対の手袋とを買ったとのべることは出来ない。(中略)機械の中のドグマはまさにこの種の馬鹿げたことを現実に行っているのである。それは,身体と心との両者が存在し,物体的過程と心的過程との両者が生起しつつ,かつ,身体的な運動には機械的な原因と心的な原因との両者が存在することを主張するものである。(中略)私の主張は,『心的過程が生起する』という表現は『物的過程が生起する』という表現と同じ種類のことを意味しているのではないということであり,したがってその二つを連言ないし選言の形で結合させることには意味がないということである。」
ということである。そのことを,象徴的に示すのは,
knowing that(内容を知ること),
と,
knowing how(方法を知ること),
に分けた,「理知」(intelligence)の概念についての説明である。
「『愚かである』stupid
ことと無知であることとは同じことではないということ,あるいは同じ種類のことではないということに注意することははわめて重要である。『物事をよく知っている』well-informed
ということと『ばかな』silly
ということは両立可能でありまた逆に議論や冗談に長けた人が案外事実を正しく知っていないということもありうるのである。」
それは,
「理知的であるということと知識を所有していることの区別が重要である」
ということでもある。その背景にあるのは,
「知識という概念によって他のすべての心的行為の概念を定義する傾向がある」
からである。要するに,
「そこでは理性的 rational
であるということは真実を認識しうることであり,そしてさらに諸真理間の関連を認識しうることであると考えられたからである。」
しかし,とライルはも皮肉な言い方で批判する。
「『真理を理解すること』を理知によって定義するという方法をとらずに,逆に理知を真理の理解によって定義しようと試みる」
から,
「理論化という作業が心の主要な活動であるという仮定と,その作業が本来は私的で無言のあるいは内的な作業であるという仮定とは今日もなお機械の中の幽霊のドグマの中心的な支柱の一つとなっている。われわれは心というものが自分たちがひそかに思考を遂行している『場所』であるとみなしがちである。われわれは,自分の思考内容を胸の中に秘めておくためにこそ特殊な技巧を使用しているのであるということを理解せず,むしろ逆に,われわれが自分の思考内容を他人に知らせる方法に特別な神秘性があると考えるのである。」
で,ライルは言う。
「ある人が理知的であるか否かを表すために『鋭敏な』 shrewed あるいは『間抜けな』
shilly,『慎重な』 prudent,『軽率な』 imprudent
などという形容詞が使われる。しかし,この場合,その人が何らかの真理を知っているということや知っていないということをわれわれは述べているわけではない。その記述は,その人にはある種の事柄を行う能力があるかないかということを述べているのである。」
それは,理論の本性,源泉,資格などにとらわれて,
「ある事柄を遂行する仕方を知っている knowing
how ということはいかなることであるのかという問題をほとんど無視してきた」
からだ,と。
「日常生活においては,…われわれは,…人々の知識の貯蔵量に対してよりもむしろ彼らの認識の能力に対してより多くの関心をもっており,また人々が習得する真理そのものに対してよりもむしろそれを得るための作業に対してより多くの関心をもっているのである。事実,ある人の知的卓越や知的欠陥を問題にしている場合においてさえも,その人がすでに獲得し所有している真理の貯蔵量の多寡はあまり問題ではない。むしろ,みずからの真理を見出す能力,さらに真理を見出した後にそれを組織的に利用する能力こそがはるかに重要なのである。われわれはときにある人がある事実に関して無知であることを嘆く。しかし,それは実はたんにその無知を結果としてもたらす愚かさを嘆いているのである。」
当然,「機械の中の幽霊」の考えるような,
「自分が何ごとかを行うということはつねに二つの事柄を行うことなのである。すなわち,何らかの適切な命題ないし処方を考察することと,次いでこれらの命題ないし処方が要求するところのものを実行に移すことの二つを行うこと」
ではなし,
「外部に現れた行為はその心的過程の結果」
なのでもなく,
「何ごとかを理知的に行っているとき,すなわち自分の行っていることについて考えながらそれを行っているとき,私は唯一つのことをしているのであってけっして二つのことをしているわけではない。」
日常的な言葉によって分析していくライルのアプローチは,たとえば,思考 thought
と考えること thinking の違いについて,
「ある人が何かを案出する think out
ことに従事していると述べる場合と,これこれしかじかが彼の考えている内容であると述べる場合とにおける『考える』の意味を明確に区別しなくてはならない。すなわち,『思考』には熱心な
hard,長引いた protracted,中断された interrupted,不注意な careless,成功した
successful,効果のない unvailing,などと形容することが出来るような意味と,真の true,偽の false,妥当な
valid,誤った fallaction,抽象的な abstract,退けられた rejected,共有された shared,公表された
published,未公表の
unpublished,などと形容することができるような意味とがあり,両者を明確に区別しなければならない。前者の意味における思考について語る場合には,われわれはある人がある時期においてある期間従事している作業について語っている。また,後者の意味における思考について語る場合には,そのような作業の成果について語っている。」
というような類別の仕方をする。これは,
われわれは持っている言葉によって見える世界が違う,
という,確か,ヴィトゲンシュタインの言葉を思い起こさせる。言葉をどう使っているかに徹底的にこだわるライルの手法は,ある意味,その言葉によって何が見えるかで境界線を引こうとしている,とも言えるのかもしれない。
参考文献;
ギルバート・ライル『心の概念』(みすず書房) |
|
意識 |
|
ダニエル・C.・デネット『解明される意識』を読む。

二段組,六百頁を超える大著である。
少し前の本なので,本書の主張が,現在どの程度の位置を占めているかは分からないが,著者が,言うほど,明晰に意識が解明された,とは到底思えない。それにしても,この本はどうしてこんなに読みにくいのか。かつて,誰かが吉田拓郎のめんどくささを評して,手旗信号に準えて,ただ赤(旗)揚げる,と言えば済むところを,
赤揚げないで,白揚げないで,赤揚げる,
と言う,と言っていたのを思い出した。白挙げる,と言えば済むのを,
白揚げないで,赤挙げないで,白揚げないで…,
と延々と続け,その間にもさらに入子になった説明が入る。しかもその説明がまだるっこしくて,ついには,何を説明しているのかが,僕のような浅学の徒には,迷路に入り込むように,分からなくなる。
その迷路の果てに,著者は,最後の最後,掉尾に,こう書いている。
「意識についての私の説明は,とても完全なものとは言われない。それは,説明の手始めでしかなかったと言ってもよいだろう。けれどもそれが手始めであるのは,意識の説明を不可能と思わせた,魔法にかかった観念群の呪縛が,それによって断ち切られるからである。わたしは『カルテジアン劇場』という比喩的理論を,一つの〈非〉比喩的な(つまりは,『字義通りの,科学的な』)理論によって置き換えたわけではない。実際のところ,私がしたのは,『劇場』,『証人〔目撃者〕』,『中心の意味主体』,『空想の産物』などの観念を下取りに出して,その代りに『ソフトウエア』,『ヴァーチャル・マシーン』『多元的草稿』,『ホムンクルスたちのパンデモニアム』などの観念を立てることによって,一群の比喩とイメージに置き換えたことでしかない。それでは比喩同士の戦いにすぎないではないかと,あなたは言われるかもしれないが,比喩というのは,『単なる』比喩に『すぎな』いわけではない。それは,思考の道具だからである。誰も,比喩なくしては,意識について考えることは出来ないのだから,手に入る一式のもっとも優れた道具をそろえておくのが,肝腎である。私たちが自分の道具をつかってつくりあげてきたものに注目したらよい。はたしてあなたには,道具がなくても,それらを思い描くことが出来るだろうか。」
この一文に,この著者のめんどくささと,微妙に話をずらしていく手際がよくみてとれるだろう。「比喩」は自分が持ちだした。そのくせ,比喩なしで意識は語れない,と話をずらし,比喩の話へとずれていく。そして,何か肝腎なことが,ずらされていく,というか,ずれている,という感じを抱かせる。ここで問題にしていたのは,この本で意識が解明できたかどうかではないのか。
この一文に,象徴的に,読み手に苛立ちを与える一端が見える。
正直のところ,かつて,『脳のなかの幽霊』(
V・S・ラマチャンドラン)等々,いくつもの脳に関わる本を読んだが,本署ほど,一向にワクワクもドキドキもしない本はない。なぜなのかは,上の一文に見える。本書は,ある種,
メタ哲学,
というか,さまざまな理論ををメタ・ポジションから,論ずるメタ理論というやり方のせいなのかもしれないが,それにしても,説明過多,,贅言が過ぎる。
著者の本書での方法は,
ヘテロ現象学,
と名づけた,
「客観的物理科学と三人称的視点へのこだわりから出発して,このうえもなく私的でこのうえもなくいわく言い難い主観的体験(原理的な)の公平を期しながらも,科学の方法論的疚しさをも同時に貫くことが出来るといった,そういった現象学的記述にまで到る〈中立的な〉道」
をとる。つまり,現象学の,
一人称パースペクティブ,
だけでなく,
三人称的パースペクティブ,
からも,併せて見ていこうとする。まさに,主観的アプローチ,客観的アプローチをも,メタ視点から見ようとするものである。
そこで槍玉に挙げられるのは,
究極の観察者,
を措定する,著者の言う,
カルテジアン劇場,
である。著者は繰り返し,
「脳は,究極の観察者がひかえる本部ではあるが,脳そのもののなかにも,そこに達することが意識体験の必要条件であったり十分条件であったりするような,何かさらに密かな本部やさらに内なる聖域があるのだと信じなければいけない理由は,どこにもはない。つまり脳のなかには,観察者などどこにもいないのである。」
と言い,脳の中にある最終的な集中するポイント,という考え方を否定し,代わりに,著者は,
多元的草稿モデル,
という仮説を提起する。それは,
「知覚をはじめ思考や心的活動はどのようなものも,脳のなかの,感覚インプットを解釈したり遂行したりする多重トラック方式にもとづくたがいに並行したプロセスによって,遂行されている。神経系統にに入ってくる情報は,絶え間なく『編集・改竄』に付されているのである。(中略)
このような編集プロセスは一秒間の何分の一という時間の幅で起こっており,その間には,内容の付け足し,合体,修正,重ね合わせなどが,様々な形で,様々な順に生じることが,可能である。私たちは,自分の網膜,自分の耳,自分の皮膚の表面で起こっていることがらを,直々に体験しているわけではない。私たちが現実に体験しているのは,多くの解釈プロセス―実際には多くの編集プロセス−から生まれた,一つの帰結にすぎない。そうした編集プロセスは,比較的生で一面的な表象を取り入れて,それらに照合と改竄とレベルアップをほどこしているのであるが,それらの営みは,脳の多様な部分で生じている活動のの流れ全体を通じて行われている。(中略)ここで私たちは,特徴発見や特徴弁別は〈一度行われるだけでよい〉という,『多元的草稿』の新しい特徴に立ち合うことになる。つまりこれは,ある特徴についての個別的な『観察』がひとたび脳の特定の一部によって行われれば,そこで定着した情報内容は,さらにどこか別のところへ送られて,誰か『支配者づらした』弁別者の手で再び弁別されたりする必要はない,ということを意味する。」
と,「カルテジアン劇場」の観察者は存在しないことを強調している。しかし,それが,脳に構造として,臓器として特定の箇所がなかろうが,意識のポイントは,かつての,
即自・対自,
といったような,メタ構造を持っていると感じさせるところに本質があると思っている。意識の本質は,ここではないのか。その情報処理が,並行的になされていようと,それをメタ・ポジションで見るような感じを抱かせるのは,人類にとって,何か必要があったからこそなのではないか。そこを,否定してしまっても,何の解決にもならない気がする。そもそも,言葉は,意識のメタ化がなくては,生み出せないのではないのか(進化の部分で,自問自答に触れていたが,それがメタ化の話とはつながっていかなかったと,感じる)。
「意識というのは,何かがある一点に到達する,ということをめぐる問題であるのではなく,むしろ何かが,大脳皮質全体もしくはその大部分にわたって活性化の閾値を越えることによって,表象となる,ということを巡る問題であるのではなかろうか。」
この言い換えて,僕には,何かがすり替えられて,その一点への集中の代替案として可なのか非なのかが曖昧のまま,ずるずると,贅言に引きずられてしまう感覚だけが残る。そのことは,人の,
「内的識別状態〈もまた〉,何か特別の『内在的』特性を,つまりは〈ものが私たちに見えたり,聞えたり,味を与えたりす〉るときのその見え方〈聞こえ方,味の仕方など〉を構成する,主観的で,私的で,いわく言い難い特性」
つまり,
クオリア,
についての,著者の見解にも,つながる。クオリアは,ない,と著者は断言する。そして,
「機械と人間という経験主体(…私が想像したワインの質を見分ける機械のことを思い起こされよ)の間に人々があると想像している〈ような〉違いを,私は断固否定しているのである。」
と。メタ化を否定するなら,当然の帰結かもしれない。そして,その究極は,意識の,
バーチャル・リアリティ仮説,
である。
「人間の意識という現象が『ヴァーチャル・マシーン〔仮想機械〕』の働き」
なのであり,つまりは,
「人間の脳の働きを形づくるある種の進化した(そして今なお進化し続けている)コンピュータ・プログラムの働き」
である,というのが結論である。
今日,どう評価されているかは分からないが,脳の活動=発火にともなう,ホログラフィックなものが,意識ではないか,と思っているので,別に脳がソフトウエアに準えられても驚かないが,肝腎のメタ構造を,説明してもらわないと,いまひとつ納得できない。
参考文献;
ダニエル・C.・デネット『解明される意識』(青土社) |
|
サンクチュアリ |
|
ウィリアム・フォークナー『サンクチュアリ』を読む。
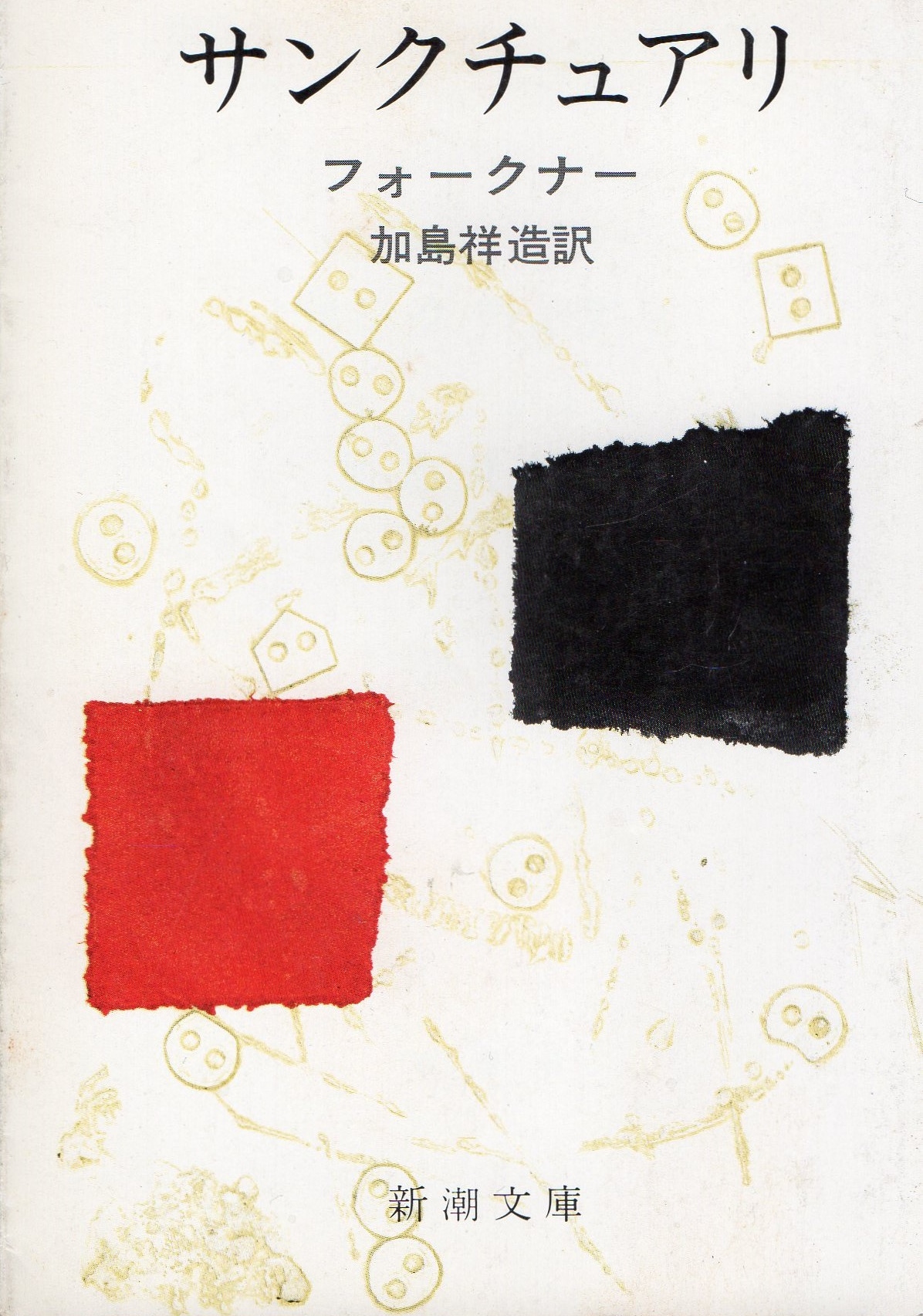
表題である,
サンクチュアリ(sanctuary),
は,訳者(加島祥造)によると,
「『聖所』『聖域』『逃げ込み場所』などといった意味をもっているが,ここでは後者の『隠れ家』という意味が強い。」
とある。それは,
密造酒をつくっていたグッドウィン一家たちの住んでいた場所,
を指すとも言えるし,
17歳の女学生テンプルを連れ込んだ曖昧宿,
を指すともいえるし,
冤罪で収監されたグッドウィンのいた刑務所の監房,
を指すともいえるし,
無実のグッドウィルを裁判で救えずリンチで焼き殺されるのを手を拱いているしかなかった弁護士ホレスが逃げ込んだ(そこから逃げ出したはずの)家庭,
を指すともいえる。あるいは,
グッドウィンを陥れる偽証をして父とともに逃げたテンプルのいるパリ,
を指すともいえる。さらには,
自分がしたのではない殺人の罪で処刑されたポパイの死そのもの,
を指すとも言えるのかもしれない。客観的なものではなく,主観的なそれ,あるいは,本人自身は気づいていないが,結果としてのそれ,という意味も含む。
本書を読みながら,対比のように,何十年も前に読んで圧倒された,ドス・パソス(ジョン・ロデリーゴ・ドス・パソス(John Roderigo
Dos Passos)の『U・S・A』3部作を思い出していた。『U・S・A』3部作は,
「新聞の切り抜き(『ニュース映画』)・作者の意識の流れ(『カメラの目』)・登場人物たちそれぞれのドラマで、20世紀初頭の『アメリカ合衆国』を、虚実織り交ぜて、実験的手法で、眺望したもの」
とされ,ちょうど,1930年代のアメリカを俯瞰したものになっている。その実験的な手法に魅了された記憶がある。
対するフォークナーは,
「フォークナーが創造したヨクナパトーファ郡(ミシシッピ州)を舞台にし、時代設定は禁酒法(1933年)時代の1929年5月と6月」
と,アメリカ南部の(架空の)小さな町での出来事を,虫瞰的に稠密に,描く。その状況描写は,緻密な西陣織のように微に入り,細を穿つ。しかし,それに比べて,登場人物は,ちょうど,細密画の背景の前でヒラヒラおどる紙人形のように,ペラペラである。そのギャップに,驚く。存在感のなさを描いたという強弁もあるかもしれないが,僕には,そうは見えなかった。主役は,その背景の時代と,密閉された南部の街の気質,雰囲気そのものなのではないか。だから,登場人物は,その状況の付けたし,添え物にすぎないのかもしれない。
本書は,フォークナーの傑作には加えられない作品らしい。『怒りと響き』『八月の光』に比べると,作家自身も,
「私としてはこれは安っぽい思いつきの本だ。なぜならこれは金がほしいという考えから書いたものだからだ。」
と書いていたという。もっとも,
「初校の校正刷りを見て,これはひどい作品だと知り,(中略)書き直した。組み直し料を払わなければならなかったが,とにかく『響きと怒り』や『死者の床に横たわりて』をあまり辱めぬように努力し,その仕事はかなりうまくいったと思う」
と書いてはいる。しかし,筋の粗っぽさと,人物のぺらぺらさ(人物像だけではなくその行動の突飛さ),は救われていないと僕は見た。ただ,人物の空虚さ,存在感のなさが意識的なら,その意識的であることが文学空間に表現されているとは思えなかった。その証拠に,取ってつけたように,ラストでポパイの生い立ちの悲惨さを描きだす。それも唐突に,だ。
参考文献;
ウィリアム・フォークナー『サンクチュアリ』(新潮文庫)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%83%BC |
|
四次元 |
|
ルディ・ラッカー『四次元の冒険―幾何学・宇宙・想像力』を読む。

通常四次元と言うと,三次元空間プラス時間軸の意味で受け取られる。しかし,しかし著者は,冒頭で,
「実在レベルや色や時間によって第四次元を表現しようとするのは見当違いである。ここで実際に必要なのは第四次元空間の概念なのである。」
と言う。確かに,今日の「超弦理論」では,十次元だの六次元だの二十六次元だのと,折り畳まれた次元の話が出てくる。そのとき,次元は,時間ではない。その辺りは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/441553477.html
等々で触れたことがある。
しかし,そのような次元を「視覚化するのは難しい」ということで,著者は,
「その主要なアイデアはアナロジーによって推論することである。つまり三次元を二次元空間で表すのと同様に四次元を三次元空間で表せばよい。4D:3D::3D:2D。この独特のアナロジーは人類に知られた最も古い頭のトリックである。プラトンは,有名な洞窟の比喩でそれを表現した最初の人であった。」
と言い,二次元世界の『フラットランド』というビクトリア時代の二次元世界の話を例に説明に入る。
「フラットランドは平面で,そこに住む動物は平面を這い回っているのである。それを机上に置かれたコインのようなものだと考えてもらってもよい。あるいは,シャボン玉の膜の虹色の模様だとか,紙面上のインクのシミだと考えることもできる。」
しかし,二次元にいる限り,三次元は理解できない。
「君が超空間(ハイパースペース)に引き上げられたものと想定しよう。この有利な地点から私たちの世界を見るとどのように見えるだろうか? 始めに,0Dの点が1Dの線分を二分し,1D線は2D平面を二分し,二D面は三D面空間を二分すると同じように,3D空間は4D超空間を二分することに注目しよう。ちなみに,点のことを零次元=0次元と称している。全空間が一点にかぎられる所では,運動の自由度は存在しないからである。
私たちの空間によって二つに確定された超空間の各領域を何と呼ぶことができるだろうか。チャールズ・H・ヒントンは,ほぼ上と下という言葉のように使うアナ(ana)とカタ(kata)という言葉を提案している。アナを私たちの空間の上にあるものとして天国とし,カタを下にあるものとして地獄とすると考えやすいかもしれない。」
この時,視点は,超空間にある。あるいは,
「高次元空間のアイデアをまじめに心に抱いた最初の哲学者は,例の大イマヌエル・カントであった。(中略)カントは,晩年になって第四次元の着想に関係した有名なパズル,つまり,人間の片方の腕のほかには全空間が空っぽのとき,この腕が右腕であると明言することは意味をなすかどうか,というパズルを提案した。はっきりしていることは,答えがないということである。左とか右という概念は空虚な空間では意味をなさないからである。
なぜかを理解する糸口として,そこが手相見の店であることを示す大きなプレキシガラスの看板を想像していただきたい。…手のひらの輪郭とシワが透明なプレキシガラスに描かれている。そこでその看板を一方の側から見れば右手に見えるだろうし,反対側から見れば左手に見えるだろう。ところがこの看板の二次元平面を外から眺めることができることを一度了解してしまうと,手のひらが本当は右手の方だというのは意味をなさないということに気づくはずである。
同様のことは三次元空間でも正しい。四次元のどちら側から見るかによって,右手に見えたり,左手に見えたりする。別の表現をすれば,右手を四次元空間に引き上げてそれをひっくり返せば左手に変えることができるのだ。」
その意味で,次元は,人の視点を示している。
「空間は位置からできているのだ。そして時空は事象からできているのだ。事象とは,与えられた時刻における与えられた位置といったようなものだと考えられる。個々の感覚の印象はささやかな事象なのである。僕らが経験する事象は,自然な四次元的序列,すなわち東西,南北,上下,遅速といった序列に並ぶ。自分の人生をふり返ってみるときは,実際には四次元的時空パターンを見ていることになるのである。だから,内部から時空を見ているかぎりは,それに不案内だとかいって混乱することはない。」
では,外から見たらどうなるのか,著者はこんな説を提起する。
「普通,誰も,世界は時間の推移とともに変化する三次元空間であると考えている。過去は去り,未来はまだ存在せず,現在だけが現実のものである。しかし世界を見るもう一つの方法がある。すなわち,世界をブロックになった宇宙と見なすことができる。世界を一つのブロック宇宙と考えると,時間と空間が一緒になったものすべてが一つの巨大な物象となる。ブロック空間は一つの時空(spacetime)からなる空間の三次元と時間の一次元を加えたものだ。外から時空を眺めるということは,歴史の外に立って,永遠の相の下で事物を見るということなのだ。(中略)
つまるところ,僕の世界は僕の感覚の総体である。こういった感覚は,四次元時空におけるパターンとしてごく自然に並べてみることができるものだ。僕の人生は,ブロック宇宙に閉じ込められている一種の四次元の虫というわけだ。(中略)永遠は当然,時空の外にある。永遠とは当然“いまただち”のことである。」
それは,
「ブロック宇宙には客観的に存在する現在がないという点である」
ということだ。だから「感覚の総体」なのである。しかし,それを外からの視点に切り替えたとき,別の世界が見える。
「地上の2D表面は私たちの3D宇宙の部分である。3D宇宙は4D超球体の表面であるかもしれない。4D超球体は,湾曲した5D時空のパターンの断面である。湾曲した5D時空は,たぶん空間と時間が交互に堆積した山の一層にすぎない。6Dの山はそれ自身歪んで,7D空間に織り込まれているかもしれない。さまざまな山の型はともに8D空間の入子になっているかもしれない。たぶん8D空間全体は九次元超時間軸に展開されることができる等々。」
つまり,第四次元は時間とは限らない。
「常に広さと呼んでいる空間の中に,一つの決まった方向があるわけではないのと同様,常に時間と呼んでいる一つの決まった高次元かある必要はないのである。第四次元について語ってきたことすべては,多様な高次元,たとえば空間から跳び出すことができる方向とか,空間が湾曲している方向とか,別の宇宙に達するために通るとかについて考えることを可能にしてくれる。(中略)時間は第四次元だというよりは,時間は高次元の一つであるという方が図と自然である。」
こうしてある種ペダンティックな知的な次元旅行の末,著者は,こう結論づける。
「私たちはなぜ私たちがここにいるか知らない―私たちが何であるかさえ知らないのである。しかし私たちは存在し,世界はこれからも存在し続けていく。私たちの通常の空間と時間の概念はただ便利な虚構にすぎないのである。いたる所が高次元なのである照明をあてる必要もない。第四次元ほど密着した,ただいまここが証明しているのである。」
とは,あまりにも大山鳴動してネズミ一匹に過ぎまいか。冒頭の方にあった,
「類推によって考えれば,四次元生物はどのようにしっかり施錠されたかにはかかわりなく,私たちの部屋であれ密室であれ入り込めることがおわかりいただけるであろう。」
は,ついに腑には落ちなかった。
参考文献;
ルディ・ラッカー『四次元の冒険―幾何学・宇宙・想像力』(工作舎) |
|
ヒトの足 |
|
水野祥太郎『ヒトの足―この謎にみちたもの』を読む。
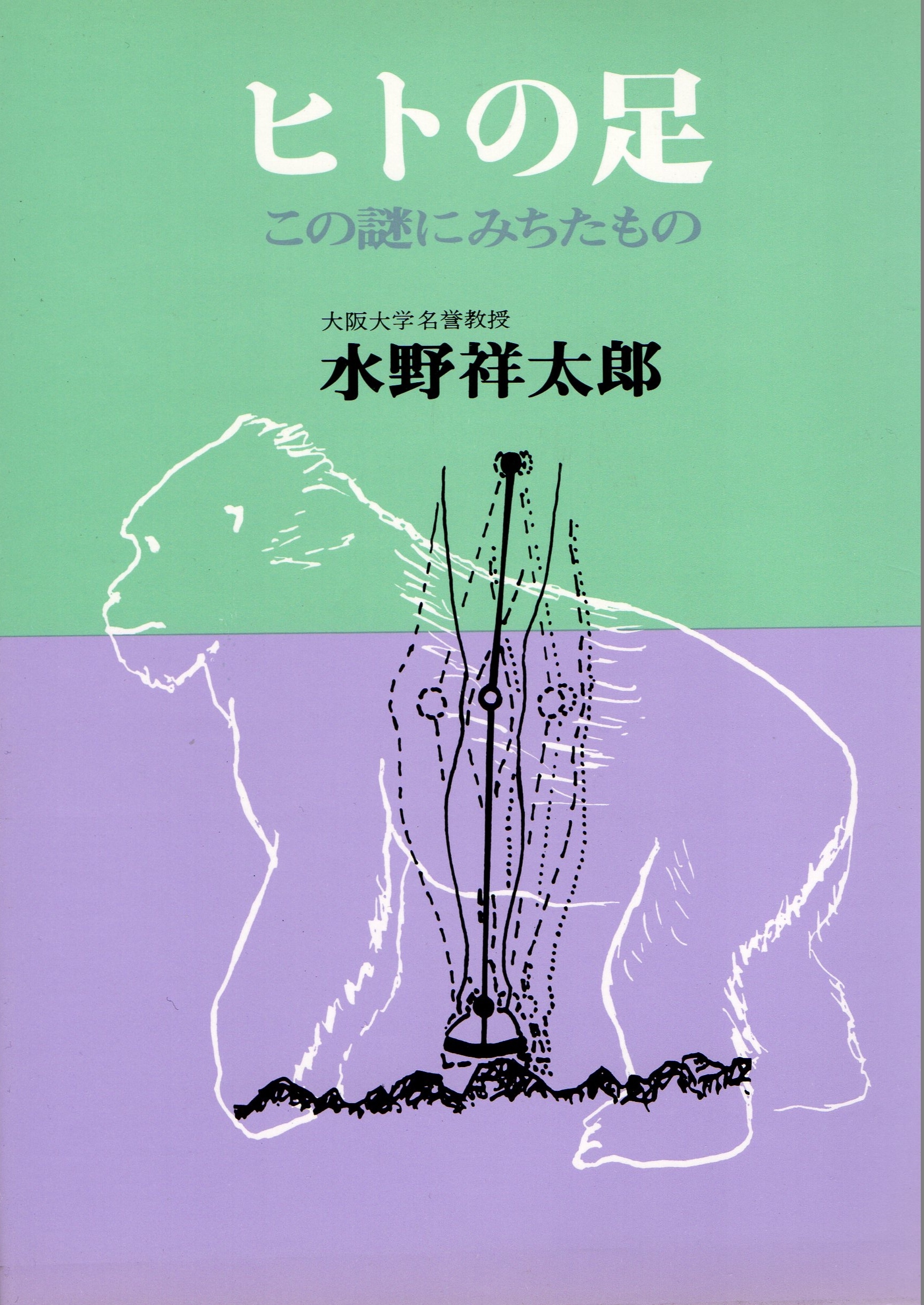
この本の目的は,「木に登るための足から,地面を走る足に変ろうとしている」という人類学者の主張に対し,整形外科医として,
「『走る』ためより『立つ』ためのヒトの足」
であることを主張するためと著者の言うように,その主張は,通奏低音のように,本書を貫いている。
その主張は,ルイス・リーキーの発見した「ジンジャントロープス」の化石(OH-8)の足に対しても,人類学者を批判して,
「この踝関節の内がえしに有利な距骨部の構造も,中足骨の外側に片寄ったヒトにはない大きな動き方も,なるほど木登りには適しているとしても,足をもって立ち,歩くうえでは,どういったものなのであろうか。このように動きやすい足は,荷重を受けたときにも動きやすく,形を保つのには適していない弱い足ということにも連なる。これはしたがって歩くときにも,硬い棒のような梃子としてよりは,力を受けたときに多少なりとも曲りやすくて弱い,能率のわるい梃子ということになりそうである。ヒトの足は固くて,強い足であって,…いくら長い距離を長い時間,あるいは長い年月のあいだ,歩き通すということもできるのであって,ケニアの原人には,それができるはずがなかった,ということになる。(中略)つまり,ケニアに見られる原人は,木の幹をかかえての木登りにはヒトよりもずっと上手であったにちがいないが,長くは立っておれなかったし,歩かせても走らせても,すぐに足に痛みが出やすくて,参ってしまうような状態であったであろうということなのである。」
そして,こう付け加える。
「足アーチがヒトの構造上の特徴として,たいへん重要なものであるにもかかわらず,解剖学のうえでも整形外科学のうえでも,その発育成長の道筋や,それを保ち,また作り育てるエージェント(作用力)についてはなんら記されていないか,漠然とよりほかは書かれていない。ヒトがヒトになってきたうえで,これこそもっとも重要なところであると思われるにもかかわらず。」
さらに,
「一日何時間も働いて,足にはほとんど何の変化も起こらないのである。これを驚きをもって迎えられない人は,よほど鈍感といおうか,分かりの悪い人なのである。
これこそ足のアーチの潜め持った本当の意味なのであった。これこそがヒトがヒトとして地球のうえで存在を主張できることになった本当の理由なのであった。」
そして,こう皮肉まじりに書く。
「ヒトの足のアーチ構造は,地面に固定されているのではなく,いわば浮いており,単に立つばかりではなく,歩いたり,走ったり,跳んだりするのに,テコとして剛体のはたらきもしなければならず,凹凸不整の地面に対しても,三次元的にうまくなずませながら,重心の位置や,あらゆる運動にも妨害をあたえないための調整機能をはたしていくという重要な役割を仕遂げていくのである。
不思議なのは,二本で立っているのを,ただちに『直立』と『歩行』とに結びつけるよりほか,考えられないらしい研究者のいることである。そういう研究者にかぎって歩行の研究といえば,矢状面内に投影された歩行(まっすぐに前にむかって歩いていくのを,単に横からのみ眺めた形にあたる―本当ははるかに複雑な三次元の運動をしているのに)のことに終始しているのである。近視眼といってよいのか,視野狭窄症といえばよいのか,これには少々ならず,おどろかされよう事実ではなかろうか。英語では『二本足の地上での生活 bipendal
terrestrial』と,はっきり書かれる慣わしであるのに,日本語に直すときには,,奇妙にもすぐに『二足直立歩行 bipedal
upright…』に化けてしまう。『歩行』にあたるところを,わざと…としたのは,ふつう英語ではここはlocomotionを使って,gaitとかwalkingを用いないからで,『移動』の意味はあっても,『歩行』の意味はちっともないからである。Loco-は場所を示しており,motionはいうまでもなく『運動』であって,ある場所から移動する運動,または力をさすと,辞書にははっきりでている。どうして日本中の研究者がみなlocomotionを『歩行』にしてしまって,そういう漢字をつかったばかりに,『まっすぐに前に向かって歩く』ことばかりをヒトの特徴と考えてしまうようになったのか,私にはどうしても分からない謎の一つではある。」
というのも,
「ヒトは一日の生活の中では,あまり『二足直立歩行』している時間のないことにも注意しなければならない。もちろん,ここで括弧でくくったような『歩行』は,『歩行研究』と称して行われてきたような『歩行』ということであって,一定の歩幅をそろえて,一定のリズムをもって,ただまっしぐらに,まっすぐにのみ歩くという動作を意味している。一日二十四時間中,起きている間の大きい部分は,そういう歩き方によってではなく,むしろ『立っている時間』によって占められている。座ったり,横になる時間をのぞくと,あとは立つか,歩くかと考えられがちであるが,実はこれは,完全な静止を意味する立ち方ではなく,何となしの立ち方,いわばブラブラ立ちと,ブラブラ歩きの時間が多い。二足生活ではあっても,二足直立歩行というほどのものではなかったのである。」
そして。こう結論づける。
「アーチの存在がヒトの足の特徴であり,ヒトそのものの特徴である以上は,ヒトの足の特徴を簡単に二足直立歩行などとは言って欲しくはないように思う。立つことの方がどう見ても重要であると考えられるからである。」
物を具体的に事実に即して考えるとは,「歩行」と「移動」を丸めたりすることではないはずである。言葉は見ている世界を,分化しているはずである。言葉を大切にするとは,見ている世界の分化にこだわることであると,つくづく教えられる。
参考文献;
水野祥太郎『ヒトの足―この謎にみちたもの』(創元社) |
|
認知的不協和 |
|
レオン・フェスティンガー『認知的不協和の理論―社会心理学序説』を読む。

「個人は自分自身の内部に矛盾がないようにと努力する。」
と書きだされた本書で,著者は,
「<矛盾>という言葉を,論理的内包の少ない言葉,すなわち不協和(dissonance)という言葉に置き換えよう。同様に,<無矛盾>という言葉をもっと中立的な言葉,すなわち協和(consonance)という言葉に置き換えよう。」
と述べ,さらに,類語「葛藤」との違いを,
「決定にいたるまえには,人は葛藤の状況におかれている。しかし,ひとたび決定を下せば,かれはもはや葛藤の状態にはいない。かれは選択を終え,いわば,葛藤を解決したのである。かれは二つあるいはそれ以上の方向へ同時に突き動かされることはない。そこでかれは自分の選んだ行程を進んでいこうとする。このときはじめて不協和がうまれるのである。この不協和を低減しようとする圧力は,その個人を同時に二つの方向へと突き動かしてはいない。」
と書く。で,「認知的不協和」とは,
「二つまたはそれ以上の選択肢の取捨について行われた後には,ほとんどつねに不協和が存在する。選ばれなかった選択肢のポジティヴな性質に対応する認知要素と,選ばれた選択肢のネガティヴな性質に対応する認知要素とは,その行為〔決定〕を行ったという知識と不協和である。選ばれた選択肢のポジティヴな性質ならびに選ばれなかった選択肢のネガティヴな性質に対応する認知要素は,その行為を行ったということに対応する認知要素と協和的である。」
とある。そして,
「不協和の存在は,その不協和を低減させる圧力を生ぜしめる。」
「不協和を低減させる圧力の強さは,既存の不協和の大きさの函数である。」
と。しかし,
「二つまたはそれ以上の選択肢の取捨について行われた後には,ほとんどつねに不協和が存在する。」
という前提が正しいのかどうか,僕には疑問である。この前提が崩れると,実は,この仮説は意味をなさないのではないか。だから,本書の末尾で,著者は,急に,パーソナリティの問題を持ち出す。
「不協和の存在に反応する程度,および仕方について,人々の間にはたしかに個人差が存在する。ある人々にとっては,不協和は極端に苦しく耐え難いものであるが,他方,非常に大きな不協和に耐えることができる人々もある。<不協和へのトレランス(耐性)>の差異は,少なくとも大ざっぱに測定可能であるように思われる。不協和へのトレランスの低い人は,トレランスの高い人とくらべると,不協和の存在に対してより多くの不快を示し,不協和を低減させるためにより大きな努力を払うはずである。不協和を低減させる努力にこのような差異があるところを見ると,トレランスの低い人はいつも,かれと同等な,不協和へのトレランスのかなり高い人とくらべて,実際上相当少ない不協和しか持っていない,と考えるのはもっともなことである。不協和へのトレランスの高い人が,かれの認知のなかに<灰色>の部分を残しておくことができるのに対して,不協和へのトレランスの低い人は問題をよりいっそう<白か黒か>という言葉で理解する傾向があると期待してもよいであろう。」
これは,無残な仮説の破たんではないのか。結局認知的不協和はは,パーソナリティによって顕在化したりしなかったりする,ということなのではないのか。現在この仮説が,どの程度影響力を持っているのかどうかわからないが,決定の後の迷いを,あえて,認知的不協和と呼んだにすぎない気がしてならない。
人は,決定に当たって,いつも選択肢を明確に吟味するのではなく,ほぼ直観でする,とは,よく言われていることだ。つまり,
「目的を明示し,選択肢を探索し,妥当する目的に応じて選択肢の順位を位置づけ,そして好ましい選択肢を選ぶ」(『決定の本質』)
というようには,意思決定されない。だから決定後に迷う。だからといって,認知的不協和に立ち止まるとは思えない。一旦意思決定された時点で,既に現実は動いており,暇人でなければ,決定後の事態に対応するアクションに余念がないからだ。でなければ,決定自体がふいになる。それを,「不協和の低減」と呼ぶのはいささか,理解不能である。もし,決定が誤っているとするなら,不協和の低減ではなく,決定自体の取り消し以外にはない。
僕には,本書の仮説は,非常に狭い個人の中に閉じこもった,密室の仮説に思えてならない。たしか,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/438821677.html
で取り上げた,『社会心理学講義−〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉』(小坂井敏晶)は,
「閉じたシステムとして社会を把握したフェスティンガー」
と,呼んでいた気がする。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163239.html
でも取り上げたが,社会心理学という学問が,基本的に,どうにも好きになれない。
参考文献;
レオン・フェスティンガー『認知的不協和の理論―社会心理学序説』(誠信書房) |
|
花 |
|
世阿弥編『花伝書(風姿花伝)』を読む。
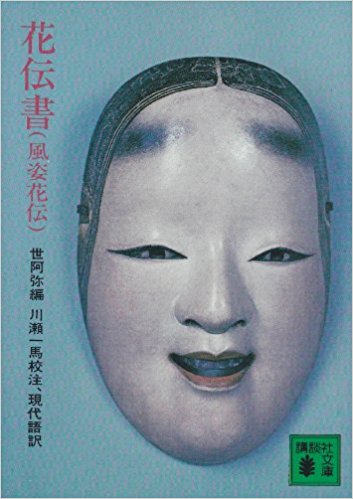
「そもそも、花といふに、万木千草において、四季をりふしに咲くものなれば、その時を得て珍しきゆゑにもてあそぶなり。申楽も、人の心にめづらしきと知るところ、すなはち、おもしろき心なり。と、これ三つは同じ心なり。いづれの花か散らで残るべき。散るゆゑによりて、咲くころあればめづらしきなり。花と、おもしろきと、めづらしき能も住するところなきを、まづ花と知るべし。住せずして、余の風体に移れば、めづらしきなり。」
にある,
「花と、おもしろきと、めづら しきと、これ三つは同じ心なり。」
が気になる。「花」については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/449051395.html
で触れた。『大言海』は,「はな(花)」について,
「端(はな)の義。著しく現れ目立つの意」
とし,「はな(鼻)」も,
「端(はな)の義」
とし,「はな(端)」つにいて,
初,
とも当て,「物事の最も先なるところ。まっさき。はじめ」と意を載せる。『古語辞典』も,「鼻」と「端」を同源としている。つまり,「はな(花・華)」は,
「著しく目立つの意のハナ」
で,「はな(鼻・端)」は,ともに,
「著しく目立つ意の,ハナ」
で,顔の真ん中で著しく目立つ,ところからということになる。つまり,
「花と、おもしろきと、めづらしき」
の意は,「花」の原意からみても,通じるのである。
しかし,
「様あり。めづらしきといへばとて、世になき風体をしいだすにてはあるべからず。」
とある。見るものに「めずらしい」と感じさせるのであって,奇をてらうことではない。それは,
「花伝にいだすところの条々を、ことごとく稽古し終わりて、さて、申楽をせん時に、その物数を、用々に従ひてとりいだすべし。花と申すも、万の草木において、いづれか四季をりふしの、時の花のほかに、めづらしき花のあるべき。そのごとくに、
習ひおぼえつる品々をきはめぬれば、時をりふしの当世を心得て、時の人の好みの品によりて、その風体をとりいだす。これ時の花の咲くを見んがごとし。」
と。
「物数をきはめつくしたらんしては、初春の梅より秋の菊の花の咲きはつるまで、一年中の花の種を持ちたらんがごとし。いづれの花なりとも、人の望み、時によりて、とりいだすべし。物数を究めずば、時によりて花を失うことあるべし。たとへば、春の花のころ過ぎて、夏草の花を賞翫せんずる時分に、春の花の風体ばかりを得たらんしてが、夏草の花はなくて、過ぎし春の花を、また持ちていでたらんは、時の花に合ふべしや。
」
と。意表をついて珍しいことをすればいいのではない。
「花とて別にはなきものなり。物数をつくして、工夫を得て、めづらしき感を心得るが花なり。」
と。それを,
巌に花の咲かんがごとし,
とも喩える。
「花といふは、余の風体を残さずして、幽玄至極の上手と、人の、思ひなれたるところに、思ひのほかに鬼をすれば、めづらしく見ゆるところ、これ花なり。しかれば、鬼許りをせんずるしては、巌ばかりにて、花はあるべか
らず。」
と。
「そもそも、因果とて、善き悪しき時のあるも、公案をつくして見るに、ただめづらしき・めづらしからぬの二つなり。同じ上手にて、同じ能を、昨日今日見れども、おもしろやと見えつることの、いままた、おもしろくもなき善きのあるは、昨日おもしろかりつる心ならひに、今日はめづらしからぬによりて、悪しと見るなり。その後、
また善き時のあるは、さきに悪かりつるものをと思ふ心、また珍しきにかへりて、おもしろくなるなり。 」
そして,
善悪不二、邪正一如。
に譬える。
「本来より、善き悪しきとは、なにをもて、さだむべきや。ただ時にとりて用足るものをば善きものとし、用足らぬを悪しきものとす。この風体の品々も、当世の衆人・所々にわたりて、その時のあまねき好みによりてとりいだす風体、これ用足るための花なるべし。ここにこの風体をもてあそめば、かしこにまた余の風体を賞翫す。これ人々心心のはななり。いづれをまこと
とせんや。ただ、時に用ゆるをもて花と知るべし。」
それは,
「幽玄と強きと、別にあるものと心得るゆゑに、迷ふなり。この二つは、そのものの体にあり。たとへば、人においては、女御・更衣、または、優女・好色・美男・草木には花のたぐひ。か様の数々は、その形、幽玄のものなり。また、あるは、武士・荒夷、あるひは、鬼・神、草木にも、松・杉、か様の数々のたぐひは、強きものと申すべきか。
か様の万物の品々を、よくし似せたらんは、幽玄のものまねは幽玄になり、強きはおのづから強かるべし。この
分見をばあてがはずして、ただ、幽玄にせんとばかり心得て、ものまねおろそかなれば、それに似ず。似ぬをば知らで、幽玄にするぞと思ふ心、これ弱きなり。されば、優女・美男などのものまねを、よく似せたらば、おのづか
ら幽玄なるべし。また、強きことをもよく似せたらんは、おのづから強かるべし。
ただし、心得うべきことあり。力無く、この道は、見所を本にするわざなれば、その当世当世の風儀にて、幽玄をもてあそぶ見物衆の前にては、強きかたをば、すこしものまねにはづるるとも、幽玄の方へはやらせたまふべし。」
と通じる。
「同じ能を、昨日今日見れども、おもしろやと見えつることの、いままた、おもしろくもなき善きのあるは、昨日おもしろかりつる心ならひに、今日はめづらしからぬによりて、悪しと見るなり。」
にも通じる。申楽は,当時,時代の観客と真剣なキャッチボールをしていたことがよく分かる。
「珍しき、花ぞと、みな人知るならば、さては、めづらしきことあるべしと、思ひ設けたらん見物衆の前にては、たとひめづらしきことをするとも、見手の心にめづらしき感はあるべからず。見る人のため、花ぞとも知らでこそ、しての花にはなるべけれ。されば、見る人は、ただ思ひのほかに、おもしろき上手とばかり見て、これは、花ぞとも知らぬが、しての花なり。さるほどに、人の心に思ひもよらぬ感を催すてだて、これ花なり。」
まさに,
秘すれば花、秘せぬは花なるべからず,
である。
芭蕉『笈之小文』の,
「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休が茶における、其貫道する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。見る処花にあらずといふ事なし。おもふ処月にあらずといふ事なし。像花にあらざる時は夷狄にひとし。心花にあらざる時は鳥獣に類ス。夷狄を出、鳥獣を離れて、造化にしたがひ、造化にかへれとなり。
神無月の初、空定めなきけしき、身は風葉の行末なき心地して、
旅人と我名よばれん初しぐれ」
とあるのと,通じるところが,もちろんある。しかし,造花に従い,造花にかえるだけでは,花ではない。その時々の目の付け所は造花をメタ化する目がいる。その「公案」こそが,「花」の鍵,と見たが,僻目か。
「いづれの花なりとも、人の望み、時によりて、とりいだすべし。物数を究めずば、時によりて花を失うことあるべし。」
「この道を究め終りて見れば、花とて別にはなきものなり、奥義を究めて万に珍しきことわりを、われと知るならでは、花はあるべからず」
に謂い尽くされている気がする。
参考文献;
世阿弥編『花伝書(風姿花伝)』(講談社文庫) |
|
夢の利用 |
|
W・ボニーム『夢の臨床的利用』を読む。

フロイトの『夢判断』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/452252107.html
で触れたが,著者は,「まえがき」で,
「私は,パーソナリティを基本的に対人関係のかかわり合いの中で発達していくものと見なしている点で,伝統的な精神分析的見解とはちがっている。人のパーソナリティは,性的あるいはその他の本能の表れであり,本質は本能であり,その発達したものであるとは考えない。むしろ反対に,この性的行動は他の行動と同様に,根本的に社会的に生み出されたパーソナリティを反映している。」
と,ホーナイの流れを汲んで,
「自己との対決」
という中で,夢を分析していく。因みに,カレン・ホーナイについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/450812938.html
で触れた。
本書は,タイトルに,「臨床的利用」とある以上,「序章」で,
「本書の目的は,夢の資料を実際に役立てるための作業仮説や,その仮説から導き出される諸技法を系統だてて紹介することである」
というように,基本,
「専門家のために書かれたものであり,また実際的な本」
である。それは,
第一に,夢を四種類の要素(活動性,人格像,周囲の状況,感情)に分類して考える,
第二に,連奏活動についてのアプローチ,
第三に,解釈活動についての考察,
という三つの基本的アプローチからなされている,と著者はいう。著者の夢の考え方は,四つの要素に,象徴されている。
たとえば,「(夢の)活動性」とは,「パーソナリティの働きの重要な面を映し出」し,それは,
「治療や夢が関与する事柄全てには,変化のプロセスが,必ず本質的に存在しているものである。」
として,
「分析治療全体を通して,次のような問題意識をいつも持ち続けている必要がある。それはまず,患者に特徴的な動きとして,どのようなものがみられるだろうか。こうしたことは,どれも似かよった動きなのだろうか。あるいは調和した,協応的な動きなのだろうか,それとも葛藤的な動きなのだろうか。その方向や強さは,どうなっているのだろうか。また患者の思考の働きや感情の動きは,どのような性質を備えており,患者は,他者に対してどのように働きかけ,どのように応じているのだろうか。さらにて病理性は,消失していきつつあるのだろうか。それとも,古い病理が,顕在化してきているのだろうか。また,健康になってきているのだろうか。それとも患者は,変化することに抵抗し,逆らっているいるのだろうか。あるいはその両方が,ともに起こっているのだろうか。さらに患者は,分析家の治療に協力的なのだろうか,それとも妨害的なのだろうか。あるいは,その両方の動きが含まれているのだろうか。以上あげたようなことが,治療における動きの問題であり,こうしたことが,夢の中の活動性によって反映され,強調されているプロセスなのである。」
と書く。今日読むと,クライアントの見方も,セラピストの姿勢も,隔世の感がある。
さらに,「(夢の)人格像」は,
「夢の中の登場人物の正体を明らかにするのに役立つだけではなく,具体的なパーソナリティ特性を明らかにしていくのにも役立つ」
もので,
「夢における人格像は,人それ自体というよりもむしろ,人びとの持っている諸々重要な属性を表してることの方が多い。この属性は,患者自身の属性ということもあれば誰か他の人物の属性ということもある。このようにして描きだされた属性は,(一),覚醒時に患者が考えていることとは本質的に異なっているが,的確な知覚であることもあるし,(二),患者が気づいていなかったり,認めたくないと感じている患者自身や他の人(特に分析家)についての歪んだ知覚のこともある。」
とし,夢の中の人物が誰にしろ,
「患者,あるいは別の人のある属性として」
表れてくる,という。経験の反映だから,それはあるのだろうが。。。
「(夢の中の)周囲の状況」とは,
「夢の中で活動がなされたり,人格像が登場する場面はもちろんのこと,自然を形作っているすべての風物や,文明の諸産物のこと」
で,「活動性や,人物像や,感情といった夢の各要素をみきわめたり,その意味を明確にしてゆく上で助けになる」
とされる。
「(夢の中の)感情」には,
「象徴化された感情と,体験された感情」
とがあり,
「象徴化された感情というのは,夢を見ている時には実際に感じられていないけれども,活動性や,人格像や,周囲の状況といったような夢の要素のいずれかによって推測される感情的な構成要素である。それに対して体験された感情というのは,夢を見ている間に,現に体験されている感情的な構成要素のことである。」
そして,感情が鍵らしいのである。
「分析家と患者が協力して,覚醒時と夢に見られる感情を可能な限り詳しく探り,そして評価する努力を傾けるならば,他の方法ではとても手に入らないような患者に関する情報が,新たに見つけ出される。見い出された感情に注意を集中させながら連想活動を行うことによって,その感情と関連のある思考や行動の意味を,深く理解することができるようになる。こうした感情に焦点を当てる手続きを取らない限り,患者の思考や行動は,自己欺瞞と混乱の渦の中に落ち込んでしまい,どうしようもないままになってしまう。こうした感情に焦点をあてようという努力は,しばしば夢を探求していくことによってうまく促進されるし,成果があがるものである。事実,夢が臨床的に役立つかどうかということは,夢の中の感情にどれだけ注意が払われているかということと正比例しているのである。」
それにしても,回り道をしながら長い長い時間がかかる分析治療の,分析家と患者の忍耐には感嘆させられる。
よく,「フロイト派の分析治療を受けている患者はしばらくすると,フロイト派の言う象徴のゆめをみ」,「ユング派の分析家に分析を受けている患者はユング派の象徴の夢をみ」ると言われる。それは,夢が経験と学習の記憶の整理のためだという近年の説を象徴するように思える。だから,夢に本人の人生や生き方が反映していることは間違いはない。しかし,それに意味づけをすることの効果について,僕には,是非を言う資格はない。
今日夢を扱うセラピーの中で,どう取り上げられているのかは知らないが,本書を,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/452252107.html
で取り上げたフロイトの『夢判断』と,さらに,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/451725678.html
で取り上げた,ジェンドリンの『夢とフォーカシング―からだによる夢解釈』とを読み比べると,夢がセラピーの中で位置づけを小さくしていく様子が見える。夢は,実体験をなにがしか反映している。そこにある事柄の意味よりは,感情に意味があるに違いはない。しかし,今日のセラピーは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/453570328.html
で取り上げたように,ほぼ夢は,取り上げない。ある意味,夢は,
ドミナント・ストーリー
に拘束された意識のものでしかないからなのかもしれない。
参考文献;
W・ボニーム『夢の臨床的利用』(誠信書房) |
|
心理療法の統合 |
|
ポール・L.・ワクテル『心理療法の統合を求めて―精神分析・行動療法・家族療法』を読む。

同じ著者の『心理療法家の言葉の技術―治療的なコミュニケーションをひらく』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/450411722.html
で触れたが,本書は,精神分析の流れ(著者は,特にホーナイ,サリヴァン等の対人関係モデルの流れ)をくむ立場から(本書では,「心理力動的アプローチ」という表現をする),行動療法,家族療法との統合を目指したプロセスを描く。著者は,
心理療法の統合を探求する学会(the Society for the Exploration
of Psychotherapy Integration SEPI),
の設立者の一人であり,その実践として,
循環的心理力動アプローチ,
を唱道する。しかし,彼の立場は,
「現在の循環的心理力動アプローチは,…『同化的統合』…の諸特徴を備えている。今日までの間に,循環的心理力動的観点には行動論的概念とシステム的概念とが極めて実質的に浸透してきたけれども,それにもかかわらず,明らかにこのアプローチは,何よりもまず精神分析的な考え方の発展として,つまり精神分析に積極介入,文脈への注目,あらゆる関係性の特徴である相互性を導入する試みとして理解されるものである。」
というもので,だから,飽くまで,精神分析(フロイト主流とはかなり隔たっているにしても)という療法を崩さず,たとえば,
「行動論的方法を精神分析的な治療の中に統合することが私にとって魅力的であった理由の一つは,前者が後者をより体験的なものにすることにあった」
というように,その理論的な実践の方法として精神分析的治療に同化するという発想である。家族療法との統合も同じで,
「(家族療法との)統合に向けた最近の努力の多くは,両者を結ぶ架け橋として特に対象関係論に注目し,精神分析家の関心の焦点である内的な対象関係と,家族療法家の関心の焦点である顕在的な対象関係とを,投影同一視の概念によって結びつけようとしてきた…。循環的心理力動アプローチは,個人的な心理力動的思考と家族システム的思考とを,これとは違った道筋によって統合しようとするものである。(中略)循環的心理力動論の視点に根ざした統合のアプローチは―悪循環と皮肉ironiesの強調によって―統合に対してより十全で啓発的な枠組みを提供するものだと私は信じている。」
この著者の立場は,心理療法統合の三つのアプローチ,
技術的折衷主義(technical electicism),
共通要因アプローチ(the common factors approach),
理論的統合(theoretical integration),
のうち,理論的統合の立場である。その考え方は,次の言葉で説明されている。
「確かに,現在の行動療法を構成している手続き,理論,哲学的前提のセット全体は(認知行動療法のそれでさえ),精神分析を構成している手続き,理論,哲学的前提のセット全体とは両立不可能である。(中略)しかし,それぞれから重要な要素を選択的に抽出し,それらを結合して,その源である諸アプローチのそれぞれと重要な(おおむね重複しない)特徴を共有しているものの,独自の構成と内容一貫性を備えた新しい統合を生み出すことは可能である。その新しい統合は,ほぼ間違いなく,もともとのアプローチ同士が似ている以上に,もともとのアプローチと似ているだろう。」
と。それには,
「それぞれのアプローチのどの側面を取り生けるかは,さまざまな諸要素が共同して働く新しい方略を構成するうえで,何を取り入れれば有効である可能性が高いかという判断」
に基づく。つまり,理論的統合とは,
自分の理論の文脈にそぐうように位置づけていく,
ということなのだ。違う言い方をすると,
意味づけとして合うものを取り入れる,
と言ってもいい。その意味で,本書の著者は,理論的に意味づけに徹底的にこだわる。たとえば,
「循環的心理力動的観点が,来談者中心療法,ゲシュタルト療法,実存的・現象学的な諸療法…といった体験的な視点を考慮することによってさらに発展させられうる可能性については,これまであまり探索されてこなかった。しかしながら私は,心理療法の統合を探求する学会(SEPI)のミーティングでの多くのやり取りから,こうした方向での重なりについてヒントを得て,そこに興味を抱くようになった。体験的アプローチの多くは精神分析的方法とも行動論的方法とも違う『第三の流れ』として描かれることが多いが,本質的には心理力動的な基礎から発展した多様な発展形であるというのが私の個人的見解である。したがってそれらは,…両立可能であり,このアプローチに寄与しうるものであると私は考えている。」
と,さりげなく書くが,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/453353253.html?1505091112
で見たロジャーズの悪戦苦闘を思うとき,なかなか意味深くはある。しかし,逆な言い方をすると,精神分析の流れも,ここまで変わったということなのかもしれない。著者のその試みは,『心理療法家の言葉の技術―治療的なコミュニケーションをひらく』,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/450411722.html
で触れたが,それには,
「心理力動アプローチこそ最も典型的に『談話療法』であるアプローチであり,かつまた,心理力動アプローチこそ,逆説的なことに,ある面で治療者の言葉のインパクトが最も検討されてこなかったアプローチだからである。」
という言葉が,背景にある。
「循環的心理力動論は,悪循環への焦点づけ,自己実現する予言,対人的な期待の喚起的効果といった諸概念を中心に統合を取り組む」
というとき,ふと,ローゼンツヴァイクが心理療法の効果に学派間の大きな優劣はないという意味で,
「ドードー鳥の裁定」
と呼んだり(ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』のドードー鳥のエピソードで,かけっこの後,「みんな勝ったんだよ。だから全員が賞品をもらうんだ」という裁定),ランバート(Lambert,
1992)のメタ研究,「心理療法に共通する因子(common factors)についての研究」のいう,
「患者側の因子」(環境因や本人の資質など)40%,
「治療者−患者関係の因子」(共感的な関係や相性など)30%,
「治療に対するプラセボや期待の因子」15%,
「治療技法の因子」15%,
を思い起こす。ほぼ同じ所へ,到達しようとしている,と。しかし,社会構成主義にはわずかに言及があるが,ミルトン・エリクソンには全く言及がない。統合というとき,結局,セラピストの視野の独自性を思わざるを得ない。
参考文献;
ポール・L.・ワクテル『心理療法の統合を求めて―精神分析・行動療法・家族療法』(金剛出版)
ポール・L.・ワクテル『心理療法家の言葉の技術―治療的なコミュニケーションをひらく』(金剛出版) |
|
フォーカシング指向 |
|
ユージン・T・ジェンドリン『フォーカシング指向心理療法〈上〉体験過程を促す聴き方』,『フォーカシング指向心理療法〈下〉心理療法の統合のために』を読む。
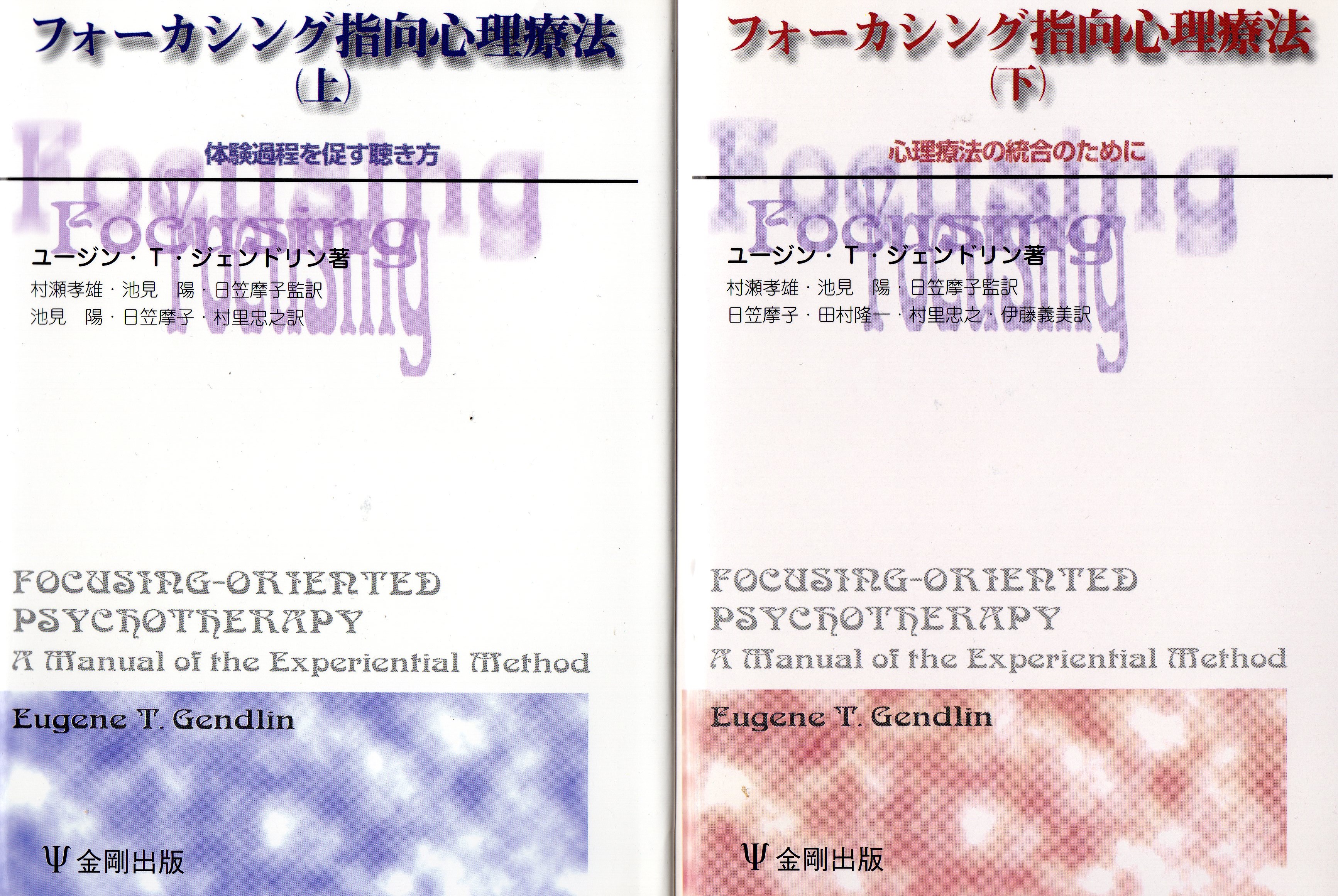
既に,フォーカシングについては,ユージン・T.・ジェンドリンの,『夢とフォーカシング』『セラピープロセスの小さな一歩』について,それぞれ触れたことがある。本書は,
「『心理療法ではフォーカシングはこのように用いるのです。』という答えである」
と,監訳者の一人池見優氏は説明する。それは,こういう意味である。
「フォーカシング自体は治療法(エンジン)ではないので,ジェンドリンは『フォーカシング療法』という名称には『うん』と言えないのである。しかし,その種々の心理療法では必要なものなので,種々の心理療法を行うセラピストたちには,その重要性を認識してもらいたいのである。本書の下巻で見ていくように,種々のセラピーに,少しだけでもフォーカシングを取り入れることで,セラピーは変わってくるのである。だからこそ,フォーカシング指向心理療法なのである。」
と。本書の特色は,下巻の,フォーカシングを媒介とした種々の療法との統合の実践例である。だからこそ,監訳者は,「本書はプロ向き」と呼んだのである。
ジェンドリンは,「臨床心理の統合的視点」で,こう書いている。
「諸流派の枠や流派ごとの説明を取り除くと,諸技法の本当の違いが見えてくる。つまり,セラピーを構成しているのは,まったく種類の異なる多様な体験なのである。私はこれを治療の『道筋』(therapeutic
avenues)と呼ぶ。治療場面に登場しうるものには,イメージ,ロールプレイ,言葉,認知的信念,記憶,感情,情動的カタルシス,対人的相互作用,夢,ダンスの動き,筋肉運動,習慣的行動がある。これらの道筋には,セラピーを構成している材料そのものが異なっているという意味で実質的な違いがある。
流派の違いは道筋の違いではない。(中略)それぞれの技法は,理論的背景を異とする別な流派に属していても,それらをまとめた道筋という観点から再分類することができる。」
そして,
「流派や技法はすべて,硬くこだわればこだわるほど,心理療法の妨害になる。常に優先されるべきは,クライエントその人,その人とセラピストの今ここでの関係なのである。(中略)人は,誰か(who)なのであって,何(what)ではない。この一人の人間は,ここに生きている存在,私たちの目の前にいるその人なのである。そして,その人は,一刻一刻新たにそこにいるのであり,理論や技法ではとらえきれない存在なのである。
理論の間違った使い方はもう一つある。体験過程の分化の次の一歩は予測できないという点を見逃してしまうことである。…感じられた辺縁(edge)の中に1,2歩踏み込むことで,一見おなじみの体験や出来事から予測もつかない新しい発見がもたらされるのである。」
と。大事なのは,
「内面で流れている体験過程である。」
だからこそ,
「クライエントに『自分のからだで…感じる』ことを求めることで,セラピーで用いる別の道筋の意義も深まる」
と。ジェンドリンは,「日本語版への序」で,身体とのかかわりについて,こうポイントを書いている。
「気をつけて見ておきたいことは,『からだ』に入っていくというときに,すべてをバイパスして平和なところ,瞑想的な『からだだけ』といったところに入っていくことがあるが,フォーカシングはそこまではいかない。フォーカシングは中間にある。それは確かに『からだ』を扱っているのだが,ここで言う『からだ』は状況を抱えたからだ,問題を抱えたからだ,状況を生きているからだなのである。…フォーカシングでいう『からだ』は,状況−内のからだである。」
もうひとつ,
「フォーカシングは本当は二つのことなのである。それは,私たちの中に『からだ』が,たった今の生の感覚を浮かび上がらせてくれるような,深いところがあることへの気づき(アウェアネス)であり,また人にその気づきを持つことを援助することなのである。それはいつも現在形なのである。(中略)さらに,そこには,たった今の状況や目の前にいるこの人,といった新しい状況もあり,そこから新たな体験的な一歩が開かれてくる。…もしも,このレベルの気づきが人の中で解放され,そこから語ることができるようになれば,それが深い意味でのフォーカシングなのである。(中略)フォーカシングは人を,概念の下にある,あるいは言葉の下にある,あるいは言葉の周りにある深い部分に導いてくれる。そこには常にもっと広いものがある。『からだ』が語り始めてくる下の方の部分には,常に(言葉や概念的理解)『〜より以上』のものがある。」
ただし,ジェンドリンは,繰り返し留意を求める。
「フォーカシングを神秘的なものにしてはならない。『フォーカシング』が意味するのは,ある問題についての最初のはっきりしないからだの感覚のそばに居続けることであり,その目的と結果はそこから新たな体験的一歩が生まれることである。フォーカシングは小さな扉である。この扉を通して自分が見つけたものすべてに『フォーカシング』という名前を与えたがる人がいる。しかしそれは違う。フォーカシングとは,問題に関してからだで感じる違和感に注意を向けること,それだけなのである。これはこのまま単純にしておかなくてはならない。そのほうが誰にでもわかりやすい。」
そうした「からだを感じる」フォーカシングを接点に,セラピーの道筋に沿って,
ロールプレイ,
体験的な夢解釈,
イメージ,
情動的カタルシス,
行動ステップ,
認知療法,
超自我,
価値観,
とたどって行く。特に,
クライエントとセラピストの関係,
それを「セラピー」と呼ぶべきかどうか
の最後の二章は,セラピープロセスを,微に入り細に穿って,セラピストとクライエントとの関係の機微にわたって詳細である。根幹は,
相互作用,
である。ひとつは,
クライエントとクライエントのからだとの,
いまひとつは,
セラピストとクライエントとの,
である。だから,そこに,フォーカシングが機能する。ジェンドリンは,
「問題が奥深いほど,…フォーカシング指向療法はクライエント中心療法である。」
とし,その相互作用を,
「体験された関係は,身体的で具体的なものである。それは関係について語られる内容ではない。また,二人の人がお互いをどう感じ,どう思っているかでもない。関係とは,それぞれの時点で具体的に進行している相互作用なのである。」
とし,そのために,次のように,ポイントを挙げている。
(セラピストとクライエントとの)間に何も挟まない,
セラピストが関わるのは「その中にいる人」である,
その人の奥深くに流れている連続性がある,
セラピーは二人の人間の間の率直で本物の関係である,
相互作用の中で,(セラピストとクライエントは)それぞれ別個の任怨気である,
そして,セラピーと呼べるかどうかは,
「クライエントにとって,治療(セラピー)的過程がおこっているかどうか」
であると。
参考文献;
ユージン・T.・ジェンドリン『フォーカシング指向心理療法〈上〉体験過程を促す聴き方』(金剛出版)
ユージン・T.・ジェンドリン『フォーカシング指向心理療法〈下〉心理療法の統合のために』(金剛出版) |
|
2.5人に一人は高齢者 |
|
河合雅司『未来の年表〜人口減少日本でこれから起きること』を読む。

「少子高齢化」と言われて久しいが,高齢化と少子化は別の問題にもかかわらず,絡み合って,著者の言う,
静かなる有事,
がやってくる。2015年に1億2700万人の総人口は,40年後9000万人を下回り,100年経たないうちに5000万人を下回る,と予測される。
「こんなに急激に人口が減るのは世界史においても類例がない。」
だけでなく,
「高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)7%を超えると『高齢化社会』,14%を超えると,『高齢社会』とされる。(日本の)高齢化率が7%から14%に達するのに24年というのは,実は世界史的に見ても極めて速い。ドイツが40年,イギリスがは48%,アメリカは72年,スウェーデンでは85年を要し,フランスに至ってはなんと115年である。」
と,高齢化も群を抜いて急速なのである。
著者は,「静かなる有事」の課題を,
「1つは,…出生数の減少…。2つ目は高齢者の激増。3つ目は勤労世代(20〜64歳)の激減に伴う社会の支え手の不足。…4つ目は,これらが互いに絡み合って起こる人口の減少…。」
と挙げる。人口は,机上の計算では,
200年後1380万人,
300年後450万人,
そして,
西暦2900年6000人,
という。石器時代の列島人口へと逆戻りとなる。それは,国家の消滅である。著者が,
「静かなる有事」
と呼ぶ所以である。著者の「人口減少カレンダー」が衝撃的である。
2015年 65歳人口が総人口の26%超,4人に1人が高齢者。出生数は100万人を切った,
2017年 日本人女性に3人に1人は高齢者。「おばあちゃん天国」化,
2018年 18歳人口が減り始め,全体の半数近い大学が定員割れし,国立大学も倒産の危機,
2019年 社会インフラの老朽化,維持管理の技術者も高齢化し,技術継承が困難に,
2020年 女性人口の50歳以上が0〜49歳人口を抜き,2人に1人が5o歳以上に,
2021年 団塊ジュニア世代が50代に突入,介護離職が増大,
2022年 人口減少なのに,独居世帯が増え,ひとり暮らし老人が急増,
2023年 労働力人口が300万人減り,騎馬戦型(3人で高齢者1人を担ぐ)から2人で1人,さらに肩車型へ,
2024年 3人に1人が65歳以上,6人に1人が75歳以上の超高齢者社会へ,
2025年 団塊世代が全員75歳超,東京都の人口がピークとなり,人口減少に転ずる,
2026年 65歳以上の5人に1人が認知症に,
2027年 必要量のピークを迎えるが,545万人の献血を必要とするが,86万人分不足となる,
2030年 存在確率(立地に必要な需要規模)が人口減で成り立たず,百貨店も銀行も大学も老人ホームも存続不可能,
2033年 全国住宅の3戸に1戸が空き家になる,
2035年 男性の3人に1人,女性の5人に1人が,生涯未婚,
2039年 国内死亡者数が168万人とピーク,火葬場不足が深刻に,
2040年 人口が40%以上減る自治体が全体の23%に。自治体消滅の危機,
2042年 高齢者人口が約4000万と,ピークになる,
2045年 東京都民の3人に1人が高齢者に,
2050年 人口減少で農業人口が減り続け,世界人口は100億となり,食糧危機に,
2065年 2.5人に1人は高齢者,現在の居住地の20%が誰も住まない土地になる,
と。著者は,2042年こそが最大の危機,と見ている。一般には,団塊ジュニアが75歳以上となる2025年を,
2025年問題,
とするが,2042年は,高齢者の数が,3935万人と,2016年を500万人上回り,高齢者の絶対数がピークになるこの年が,同時に,支える,勤労世代が,2025年と比較して,1256万人も減る,と。
出生率が下がり続け,高齢化が進むことは,そのまま,人口の老齢化を意味し,勤労世代は減り続ける。今のままの国のあり様を維持できるはずはない。著者の言う,
戦略的に縮む,
という方向性しかないことは確かだ。しかし,著者の示す処方箋,
高齢者の区分を75歳以上に引き上げて,高齢者を減らす,
24時間社会からの脱却,
居住エリアと非居住エリアの明確化,
都道府県を飛び地合併,
国際分業の徹底,
匠の技を維持,
国費学生制度で人材育成,
中高年の地方移住,
セカンド市民制度,
第三子以降に1000万円給付,
はどうであろうか。抑々どういう国になるのかというビジョンが先である。まだ,大国意識をもつ夜郎自大な指導者の下では,張子の虎の大国意識ばかりが先行し,軍備優先の国づくりになること請け合いである。まずはひとづくり,とするなら,教育の無償化をはからなくてはならない。そうすれば,優れた子弟は,貧しくても,学ぶ機会を得る。まずは,人ではあるまいか。
参考文献;
河合雅司『未来の年表〜人口減少日本でこれから起きること』(講談社現代新書) |
|
日本の支配構造 |
|
矢部宏治『知ってはいけない〜隠された日本支配の構造』を読む。

著者の『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/411281361.html
で触れた。本書は,日本の支配構造全体に,迫ろうとする。僕自身の異和感のきっかけは,2010年,普天間基地の県外移設を唱えて,失脚させられた鳩山首相の件である。著者もこう書く,
「誰が見ても危険な人口密集地の外国軍基地(普天間基地)を,『県外または国外』へ移そうとしたところ,官僚や検察,大手マスコミから激しいバッシングを受けて,あっけなく政権が崩壊してしまった」
ことがきっかけで,沖縄米軍基地のガイドブックをつくった,という。鳩山首相は,
「このとき官僚たちは,選挙で選ばれた首相鳩山ではない,なにかほかのものに忠誠を誓っているのではないかという思いがしました。」
と語っている。それはいったい何なのか。本書は,次の九つの視点から,今日,真に日本を支配しているのは,何(誰)なのかを明らかにしようとしている。各章が,それを示している。
第一章 日本の空は,すべて米軍に支配されている
第二章 日本の国土は,すべて米軍の治外法権下にある
第三章 日本に国境はない
第四章 国のトップは『米軍+官僚』である
第五章 国家は密約と裏マニュアルで運営する
第六章 政府は憲法にしばられない
第七章 重要な文書は,すべて英訳で作成される
第八章 自衛隊は米軍の指揮のもとで戦う
第九章 アメリカは「国」ではなく「国連」である
既に,国内の空域制限や日米合同委員会については,著者らによって,他でも触れられつつあり,目新しいものではないかもしれないが,驚くべきことは,
「まず,多くの官僚たちが『横田空域』の存在そのものを知らない。ごくまれに知っている人がいても,なぜそんなものが首都圏上空に存在するかについては,もちろんまったくわかっていない。
これほど大きな存在について,国家の中枢にいる人たちが何も知らないのです。日本を普通の独立国と呼ぶことは,とてもできないでしょう,」
という一文だ。さらに,基地だらけの沖縄では,
嘉手納空域,
がある。
「嘉手納空域とはつまり,沖縄本島の上空はすべて米軍に支配されているという意味なのです。」
そして,航空法特例法の適用除外によって,米軍は,
離着陸する場所,
飛行禁止区域,
最低高度,
制限速度,
飛行計画の通報と承認,
が適用されないことになる。なぜなのか,それは,
「日本政府は,軍事演習を行う米軍機については,優先的に管制権を与える」
という日米合同委員会での「密約」に基づくものらしいのである。しかも,
「日本国の当局は,所在地のいかんを問わず米軍の財産について,捜索,差し押さえ,または検証を行う権利を行使しない」(日米合同委員会・公式議事録)
という治外法権も与えている。さらに,
「平和条約および安保条約の効力が発生すると同時に,米軍を日本国内およびその周辺に配備する権利を,日本は認め,アメリカは認める」(旧安保条約第1条)
によって,
「米軍が日本の国土のなかで,日本の憲法も国内法も無視して,
『自由にどこでも機智を置き』
『自由に軍事行動をおこなう』
ことを可能にする法的しくみ」
がつくられ,これによって,「国内および周辺」にもとづき,
「米軍とその関係者は,日本政府から一切チェックを受けることなく,いつでも首都圏の米軍基地に降り立つことができ…,到着後,米軍基地からフェンスの外へ出て日本に『入国』するときも,日本側のチェックは一切はいっさいありません。」
と,それは日本の国境を越えて自由に軍事行動ができることを意味している。その運用を支えているのが,
日米合同委員会,
ということになる。その異様さは,外交ルートを通さないという意味で,アメリカ大使スナイダーが,
「ようするに日本では,アメリカ大使館がまだ存在しない占領中にできあがった,米軍と日本の官僚とのあいだの異常な直接関係が,いまだ続いていることなのです。」(アメリカ外交文書)
と,言っているほどのことなのだ。著者は,それを,
「つまり『戦後日本』という国は,
『在日米軍の法的地位は変えず』
『軍事面での占領体制がそのまま継続した』
『半主権国家』
として国際社会に復帰したということなのです。」
とまとめる。一番衝撃的なのは,
憲法九条は,太平洋憲章第8項がルーツとし,
太平洋憲章
↓
連合国共同宣言
↓
ダンバートン・オークス提案
↓
国連憲章,
という連合国の一連の文脈の上で,憲法九条「戦争放棄」になるとし,
「ですから憲法九条とは,完全に国連軍の存在を前提として書かれたものなのです。」
と,著者は断定するところだ。彼らの視点に沿ってみたところが,新鮮である。そして,朝鮮戦争を介して,二つのことが,決められる。
戦争になったら自衛隊は米軍指揮下に入る(旧安保条約),
日本中どこにでも,必要な期間,必要なだけの軍隊を置くことができる(国連安保理に基づく二国間協定),
その結果,
占領下での米軍への戦争協力体制,
が生まれることになる。それが,以降60年も継続している。著者は言う,
「だから現在,私たちが生きているのは,実は『戦後レジーム』ではなくて,『朝鮮戦争レジーム』なのです。」
と。奇しくも,日本と韓国だけが,米国軍を国内およびその周辺に配備する権利を与えている。だから,ライス国務長官は,回顧録で,
「太平洋軍司令官は昔から植民地総督のような存在」
と称していた。
こんないびつな独立国はない。そのことを多くの国民が知らないこと,無関心なことが,一番の問題なのではないか。著者が,
「すべてのポジショントークを一度やめて,遠く離れた場所(沖縄・福島。自衛隊の最前線)で大きな矛盾に苦しむ人たちの声に真摯に耳を傾け,あくまで事実に基づいて,根本的な議論を行うときにきていると私は考えます。」
という言葉が響く。
著者の『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/411281361.html
で触れた。
参考文献;
矢部宏治『知ってはいけない〜隠された日本支配の構造』(講談社現代新書) |
|
秀次の切腹 |
|
矢部健太郎『関白秀次の切腹』を読む。
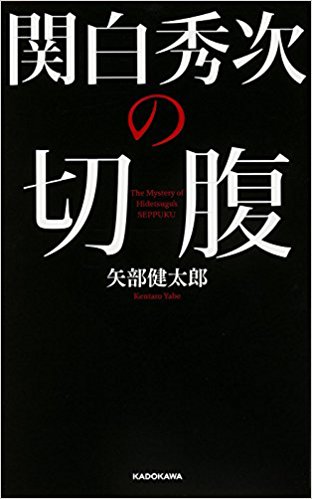
秀次については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/440783746.html
で,藤田恒春『豊臣秀次』を取り上げた。そこでも秀次が自裁なのか賜死なのかが問題になっていたが,本書は,「秀次の切腹」そのものに迫る。
「『秀次事件』の全体は一ヶ月に及んでおり,少なくとも三つの大事件,具体的には,『秀次失脚事件』『秀次切腹事件』『妻子惨殺事件』が連続して発生している。」
これまでは,この連続性は,
「秀吉の怒りが増幅した結果」
として処理されてきた。この流れは,本書で,史料に基づき,次のように整理されている。
七月三日 石田三成ら四名,秀次謀反について尋問(『大かうさまくんきのうち』)
八日 秀次出奔(『御湯殿上日記』『言経卿記』)
十日 秀次高野山到着(『島津家文書』『吉川家文書』)
十二日 「秀次高野山住山」令が発給される(『佐竹家旧記』)
十三日 「秀次切腹命令」が発給される(『甫庵太閤記』)
十四日 三使(福島正則,福原正堯,池田秀雄),高野山到着(『甫庵太閤記』)
十五日 聚楽第の秀次妻女居所の取り壊しが発令(『賀茂別雷神社』)
木村常陸介,秀吉の命により切腹(『言経卿記』『兼見卿記』)
同巳刻,秀次切腹
二十日 諸大名血判起請文作成,秀次遺領配分に関する朱印状作成(『木下家文書』『佐竹記旧記』)
二十五日 三成書状発給「今度関白殿御逆意顕形ニ付而,御腹被召」(『伊達家文書』)
八月二日 秀次妻子ら三十余名,三条河原にて処刑(『御湯殿上日記』『言経卿記』『兼見卿記』『大かうさまくんきのうち』『甫庵太閤記』)
実は,『甫庵太閤記』の切腹命令には,一次史料はなく,信頼できる一次史料は,秀次切腹の3日前の秀吉の文禄四年七月十二日付朱印状,
「秀次高野山住山」令
のみである。それは,
高野山側に秀次の住山(高野山で生活する)について命じた法令
で,
秀次高野山住山之儀ニ付被仰出条々,
として,口語訳で,次のような指示がなされていた。
一、召し使うことのできる者は、侍十人〔この内に〔坊主・台所人(料理人)を含む〕、下人・小者・下男五人を加え、十五人とする。この他に小者を召し仕うことは一切禁止する。ただし、出家の身となり袈裟を着ている以上は、身分の上下にかかわらず、刀・脇差を携帯してはならない。加えて、奉公する者の親類を召し置いてはならない。)
一、高野山全山として、番人を昼夜問わず堅く申し付けるように。もし下山させるようなことがあれば、高野山全山に成敗を加える。
一、高野山の出入口ごとに番人を置き、秀次を見舞う者は固く停止させること。
史料で,明確なのは,秀次切腹の日時である。
七月十五日巳刻(『兼見卿記』)
十五日よつ時(『御湯殿上日記』)
つまり,十五日午前十時頃,である。それを基点に,一連の時系列を,検証した結果,筆者は,
「十三日付『切腹命令』は実在し,十四日夜に高野山に届けられたという『甫庵太閤記』の描写はフィクションであって史実ではないと結論づけられる。『五奉行』による『秀次切腹命令』は,文禄四年七月十三日の時点では存在しておらず,甫庵が江戸期に創作した『偽文書』として判断してよいだろう。」
と結論を下す。その上で,上記,「秀次高野山住山」令にあるのは,
「文禄四年七月十二日時点での秀吉の『真意』を朱印状として成文化したもの」
であり,
「それを持参した『三使』が高野山に到着した時点で秀次に命じられたのは『高野山住山』=『禁固刑』だったといってよい。逆にいえば,秀吉は秀次に『切腹』=『死刑』を命じたわけではなかったのである。」
筆者は,秀次が切腹した,
清巌寺,
は,秀吉が大政所の菩提弔うために建立した寺である。
「秀次がこの清巌寺の一室・柳の間で切腹したこと自体に不可解さを感じていた」
と書くが,当時の人にとって,高野山へ追放された人が,切腹させられること自体にも衝撃を受けたらしいのである。
「当時の人々の感覚として,高野山への『入山』とは『世俗社会からの死』と同義であった。それゆえ,高野山に入山した人物が切腹したことは,かつてない衝撃」
だった。『御湯殿上日記』には,
「くわんはくとのきのふ十五日のよつ時に御はらきらせられ候よし申,むしちゆ(無実)ゆへかくの事候のよし申なり」
とある。
秀吉の命令で,
秀次失脚→秀次切腹→妻子惨殺
が進んだとする視点で,この流れを視るのと,切腹自体が,秀次の意思という視点で,見るのとでは,一連の意味のつながりがまったく変わる。そもそも,
秀次失脚,
は,
関白殿御遁世,高野へ御発可有之好有之(『言経卿記』)
くわんはくとのかうやへ御のほりのよし(『御湯殿上日記』)
もとゆいきり御はしり候ふんにて(『大外記中原師生母記』)
等々,どうやら「追放」ではなく,共通するのは,
「彼自身の意志に基づく『出奔』とする認識」
であり,だからこそ,これで,
「まつしつまり候まま,めでたく候」(『大外記中原師生母記』)
というように,一件落着したという雰囲気だっのである。それを一変させたのが,
秀次自裁,
である。
「秀次の切腹は秀吉や三成らの意志に反する出来事であり,関白職を世襲する『豊臣摂関家』に大きなダメージを与えた。」
その衝撃の大きさが,その報が伝わって以降,二週間後,
「文禄二年八月二日,混乱を極めた『秀次事件』の幕を引くために政権側がなした行為は,いつまでも語り継がれる凄惨な悲劇となった。」
そして,それは豊臣政権のたそがれの始まりでもある。筆者は,最後に,
「結局のところ,この事件には『二つの冤罪』があった。
一つは,『秀吉が秀次を切腹させた』という認識,そしてこの事件が秀吉個人による暴走行為であったという評価である。そしていま一つは,秀次には切腹に相当する罪があったという評価である。」
と締めくくる。しかし,どんなにダメージがあろうと,
秀次妻子三十余人の惨殺,
は,理解を超える。その政権防衛の意思決定プロセスは,まだ藪の中である。
参考文献;
矢部健太郎『関白秀次の切腹』(KADOKAWA)
藤田恒春『豊臣秀次』(吉川弘文館)
http://koueorihotaru.hatenadiary.com/entry/2017/01/22/151052 |
|
信長戦史 |
|
日本史史料研究会監修・渡邊大門編『信長軍の合戦史』を読む。
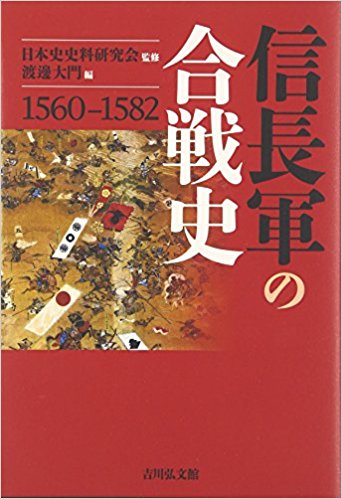
本書は,桶狭間の合戦の奇襲とか,長篠の合戦の三千挺の鉄炮による三段撃ち等々,『甫庵信長記』などの軍記物によって語られてきた信長神話を,一次史料に基づいた精緻な研究調査により,「従来とは違ったイメージ」を提供しようとしている。既に,周知になりつつあることも含め,本書では,
「できるだけ良質な史料,つまり一次史料を中心に用いて執筆」
することを意図している。
「一次史料とは,同時代に書かれた書状や日記など」
であり,重要な点は,本書は,
「最新の良質な研究成果に基づいて」
執筆されている,というのが売りである。対象は,
桶狭間の戦い,
美濃斎藤氏との戦い,
本願寺・一向一揆との戦い,
姉川合戦,
三方原合戦,
長篠の戦い,
有岡城の戦い,
三木合戦,
鳥取城の攻防戦,
備中高松城の戦い,
本能寺の変,
である。つぶさに見ていくと,信長の,
革新性,
とか,
革命性,
というのが神話に過ぎず,人の使い方,軍の戦略性など,結構同時代と比較して,先へ行っているとばかりはいえない面が見えてくる。さて,この中で,一番に取り上げたいのは,
奇襲の成功例,
として,喧伝された桶狭間の合戦が,実は,正面からの攻撃なのであると明らかにされつつある点だろう。
「義元は,桶狭間山に,北西に向かって仁を布いた。(中略)早朝であろう。義元の布陣は,丸根・鷲津両砦を攻撃する今川軍の背後に位置し,中島砦あるいは善照寺砦からの(信長の)援軍を遮断することを目的としていたと考えられる。その時は,主に南西を向いていたのではなかろうか。丸根・鷲津両砦を陥落させたので,攻撃目標を中嶋砦あるいは善照寺砦へと移した。そのため布陣替えを行い,北西に向けて陣を布いたのであろう。」
そこに,織田方の抜駆け佐々隼人正,千秋四郎らの三百が中島砦から桶狭間山へ向かい,今川側は,それを迎え撃つために前進し,平地へと降りていた。善照寺砦にいた信長は,それを見て,中嶋砦へと兵を動かす。二千弱である。今川方は,鳴海城,大高城に入れた人数も含めて,総勢二万弱。桶狭間山に布陣しているのは一万余。
『信長公記』によれば,信長は,家老たちがすがりついて止めるのをふりきり,
「皆の者,よく聞け。あの敵兵は夜行軍を行い,大高城に兵粮を入れ,鷲津砦・丸根砦で奮闘して疲れ切っている兵である。こちらは新手だ。そのうえ,小勢でも大軍に怖れることはない。運は天にあるという言葉を知っているか。敵が攻めてきたら退け,敵が退いたら引っ付いて攻撃せよ。そうすれば,きっと多くを倒し,追い崩すことができるであろう。分捕りをしてはならない。打ち捨てよ。この軍に勝ったならば,参戦した者は家の面目であり,末代までの高名となろう。ひたすら励めと訓示した。」
とある。
「今川軍は,桶狭間山から降りて平地にいたと思われるので,信長はこれがチャンスとみたのであろう。信長は,義元が再び要害の地へ移動する前に攻撃を仕掛けたかったのではなかろうか。」
実は,このとき,
「にわか雨が降ってきた。雹を含んでおり,投げつけるように今川軍の顔に打ちつけた。織田軍には背中に降りかかった。(中略)中嶋砦を出陣した信長は,山際へと進んだ。雨で楠が東へ倒れたとあり,今川軍の顔に,織田軍の背中に降りかかったというので,信長は東向きに進撃したと考えられている。桶狭間山から降りた今川軍であるので,中嶋砦からは東方に陣を布いていたと推測される。
そして雨は投げつけるように今川軍の顔に打ちつけたというので,風も強かったのであろう。今川軍は前を向いていられない状況だったと推測される。織田軍の動静を監視し続けることが困難な状況だったかもしれない。それに対して織田軍は,前を向き続けられた。」
そして,空が晴れる。『信長公記』は,こう書く,
「空が晴れるのを見て,信長は槍を取り,大声をあげて,さあ懸れ懸れと命じた。織田軍が黒煙を立てて懸ってくるのを見て今川軍は,水をぶちまけたように後ろにどっと崩れた。弓・槍・鉄砲・幟・指物などが散乱した様子は,算木を乱したように無秩序に散らばっているようだ。義元の塗輿も捨てた。総崩れになって敗走した。
信長は,旗本はこれだ。これへ懸れと命令した。未の刻に東へ向かって攻撃した。今川軍は当初,三〇〇騎くらいが,まん丸になって義元を囲み退却したけれど,二度三度,四度五度と,踏みとどまって戦っているうちに,次第に人数が減っていき,ついには五〇騎くらいになった。信長も馬から下り,若者たちと先を争って槍で敵を突き伏せ,突き倒した。」
『信長公記』の記事を,どう奇襲と読み替えたものか,今考えると,不思議ではある。
いま一つ姉川の合戦は,後世の記事とは異なり,完全に,信長側が虚を突かれ,本陣が急襲されたようだ。
「浅井長政が横山城包囲網の最後尾(最北端)にいた織田信長・徳川家康本陣に『奇襲』をかけた」
のは,
「信長や家康は横山城を包囲するに当たり,浅井の居城小谷や,浅井・朝倉軍が横山救援のために陣を置いた大依山に最も近い,龍ケ鼻に陣を敷いていた。これは龍ケ鼻が横山城と小谷城の状況を一望するために,最適の場所と判断したからと見られる。信長・家康としては,大依山との距離も約五キロあり,万が一『奇襲』を受けても対処できる安全圏と考えていたのであろう。」
しかし,地形から見ても,信長本陣が,
「姉川の河原であった部分のすぐ南に位置し,本陣の前は決戦地の河原で,信長の馬廻り以外の武将が並ぶ余地がないことがわかる」
そこを衝かれたのである。つまり,浅井側にそこを衝かれるということは,
「信長の見込みの甘さを露呈するもの」
ということだろう。最後にもう一つ。既に,知られているが,家康の,
しかみ像,
と言われるものがある。三方原の合戦で鎧袖一触,大敗した家康が,浜松に逃げ帰って従軍していた絵師に描かせたもので,家康が,みずからの戒めとしてきたという伝説があった。しかし,
「最近この画像が江戸時代中期に描かれ,尾張徳川宗睦の養嗣子治行の妻である従姫が嫁入り道具として持参し,伝承されたものであることが判明した。さらに,それまで描かれた背景が不明で,明治から昭和初期には,『長篠敗戦』(実際には勝利している)後のものと伝えられていたらしい。肖像画が三方原合戦直後に描かれたものと紹介されたのは,何と昭和十一年だという。つまり,『しかみ像』に描かれた人物は家康ではないかもしれないのである」
と。
肖像画は,武田信玄像,源頼朝像等々もそうだが,伝承とは異なることが多いということか。
参考文献;
日本史史料研究会監修・渡邊大門 編『信長軍の合戦史』(吉川弘文館)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E4%B8%89%E6%96%B9%E3%83%B6%E5%8E%9F%E6%88%A6%E5%BD%B9%E7%94%BB%E5%83%8F |
|
自分になる |
|
カール・R.・ロジャーズ『自己実現の道(ロジャーズ主要著作集3)』を読む。

本書は,ロジャーズの著作の中でもっとも読まれたものとされるが,日本では,部分が紹介されることはあっても,全体として一冊として訳出されたのは,初めてらしい(二章,九章以外はすでに紹介されている)。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/450874048.html
で取り上げた,H・カーシェンバウム&V・L・ランド
ヘンダーソン編『ロジャーズ選集』にもかなりかなり重なるものがある。
本書の原題は,
On Becoming a Person,
である。訳者(諸冨祥彦氏)は,
「本書でロジャーズが読者に伝えようとしているメッセージは,原題のOn Becoming a
Personに,おおよそ示されています。うまい日本語が思い浮かびませんが,あえて意訳するとすれば,『人が,“ひと”になるということ』となるでしょうか。その意味するところは,『ひとが自分自身になっていくこと』―言ってみれば,『自分が自分になるということ』です。(中略)
原題のOn Becoming a
Personにぴったりの日本語訳が見あたらなかったことから困惑しました。あえて直訳すると『人間になること』となってしまいます。…先に述べたようなニュアンスが含まれていることから,悩みに悩んだ末にタイトルは『自己実現の道』としました。そして,それがマズローやユングの言う自己実現とは異なるロジャーズ固有の考えであることを示すためにあえて,『ロジャーズが語る』と付したのです。」
と語り,On Becoming a Personの含意を強く強調している。確かに,本書は,
On Becoming a Person
を通奏低音のように,響かせ,繰り返し,語られている。しかし,ここで言う,
自分になる,
とは,何か固定したものになる,という意味ではない。ロジャーズは,
第六章「人が“ひと”になるとはどういうことか」
で,
仮面に気づき,
感情を体験し,
体験の中に自分を発見し,
自分自身になる,
というプロセスを描き出しながら,
「自分自身を発見し,自分自身になろうとしている人間の最後の特徴…とは,その人が一つの結果であるよりも,一つのプロセスとなることに,より大きな満足を感じるようになるということである。」
と述べている。そして,
「人間は,一定量の特性などではなく,絶えず変化し続ける可能性の布置(constellation)である。」
とも。Constellationは,星座とか,一群,配列といった意味である。ここには,一点に収斂するのではない自分という含意がある。ふと,ハイデッガーの,
人は死ぬまで可能性の中にある,
という言葉を思い出す。ロジャーズには,実存主義の翳がある。これが,本書の結論であると言ってもいい。
もっとも個人的なものが,最も普遍的なものである,
という言葉をロジャーズは記しているが,そのように,本書は,
自分を語る,
の第一部第一章は,
これが私です,
から始まる。そして,「私が学んできた大切な教訓」を挙げていく。たとえば,
「他者との関係において,私があたかも私自身でないかのように振る舞っても,それは結局援助にはなりえない」
「自分が自分自身に受容的に耳を傾けることができるとき,そして,自分自身になることができるとき,私はより効果的でありうる」
「私が自分自身に他者を理解することを許すことができるならば,そのことはとても大切な価値を持つ」
「他者を受け容れることができれば,多くのものが得られる」
「私は,自分や他者のうちなるリアリティに開かれていればいるほど,急いで物事を処理しようとしなくなるようである」
等々。ここでも,
「人生は,その最善の状態においては,流れゆき,変化していくプロセスである。そこでは固定されたものは何一つない」
を結論としている。
つとに紹介される,第七章「心理療法の過程概念」にある,
心理療法の過程の七段階,
は,何度読み直しても,発見があるほど,凝縮されたエッセンスである。しかし,そのプロセスで「援助関係を作り出す」ためには,前提となることがある。
「クライアントが,自分は十分受け容れられていると体験していると仮定しておこう。つまり,たとえクライアントの感情が恐怖,絶望,不安,怒りなど,どんなものであろうとも,また彼の表現の仕方が沈黙,身振り,涙,言葉など,どんなものであろうとも,あるいはこの瞬間に彼が自分自身をどんなふうに見せていようとも,クライアントが自分がまさにあるがままにセラピストから心理的に受け容れられていると感じていると仮定しておこう。この言葉には,共感的に理解されているという考えや,受容(acceptance)という考えが暗に含まれている。この条件が最適かどうかを決めるものは,単にセラピストにこの条件が存在しているということではなく,クライアントがこの条件を体験しているということである」
と。ロジャーズは,
私はいかにして援助的関係をつくり出すことができるか?
とこういう問いを投げかけている。
①私は他者から信頼に値すると受け取られるようなり深い意味で,頼りになるとか矛盾なく一貫していると受け取られるようなあり方でいることができるだろうか?
②私は,自分がこのような人間であることが相手に明らかに伝わるように,自分を十分に表現できるだろうか?
③私は目の前にいるこの他者に対して,温かさ,配慮,好意,関心,尊重といったポジティブな態度を経験することができるだろうか?
④私は一人の人間として,他者からまったく別個に存在できるほど強くいることができるだろうか? 他者の感情や要求を尊重するのと同じように,自分自身の感情や要求をしっかりと尊重することができるだろうか?
⑤私は,相手が私とは別の存在であることを許せるほど,自分の中が十分安定しているだろうか? 私は,相手が正直だろうが噓をついていようが,子どもであろうが大人であろうが,絶望していようが自信過剰であろうが,その人自身であることを許容できるだろうか? 私は相手があるがままである自由を提供することができるだろうか?
⑥私は,相手の感情や個人的意味の世界の中に十分入っていくことができ,そして相手が見ているがままにその世界を見ることができるだろうか? 私は,自分が相手の私的な世界を評価しようとか判断しょうとまったく思わなくなるほど,その中に完全に入ることができるだろうか?
⑦相手が私に表すさまざまな側面のどのようなものに対しても受容的であることができるだろうか? 私は,相手の人そのものを受けとめることができるだろうか? そうした態度を相手に伝えることができるだろうか? それとも相手の感情のある側面だけを受容し,それ以外の面については暗に,あるいは公然と認めないような条件つきの受容しかできないだろうか?
⑧私は,関係の中で相手に脅威を感じさせないような十分な感受性をもって行動することができるだろうか?
⑨私は,外的な評価の脅威からクライアントを解放することができるだろうか?
⑩私は,この他者が生成しつつある過程にある人だということを前提にして,その人と出会うことができるだろうか? それとも私は,その人の過去や私自身の過去に束縛されてしまうだろうか?
問いこそが創造的な答えを産み出す,という。この問いあって,
セラピストの備えておくべき条件,
として,
①一致
「セラピストがその関係の中でひとつにまとまった,統合された,もしくは一致した人であることが必要である。私が言いたいのは,その関係の中でセラピストが,仮面や役割や見せかけなどから離れて,まさしくありのままの自分であるということである。私は,体験と意識とが正確に合致しているという意味で『一致(congruence)』という用語を使っている。セラピストが完全に一致しているのは,その関係におけるこの瞬間に,自分が体験していることを十分にそして正確に意識している時である。」
②無条件の肯定的配慮
「セラピストがクライアントに対して温かい配慮の体験をするということである。その配慮は,相手を支配するようなものでもなければ,個人的な満足を求めようとするものでもない。それは,『もしもあなたが〜といった行動をするなら,私はあなたに関心を寄せます』というあり方ではなく,『私はあなたに関心を寄せています』ということを真に表すような雰囲気のことである。」
③共感的理解
「セラピストはクライアントが自分の世界を内側から見ているとおりにその世界について正確で共感的な理解を体験している,ということである。クライエントの私的な世界をあたかも自分自身のものであるかのように,しかもこの『あたかも』という質を決して失うことなく感じることである。」
へと集約される。大事なことは,
「共感的に理解されているという考えや,受容(acceptance)という……条件が最適かどうかを決めるものは,単にセラピストにこの条件が存在しているということではなく,クライアントがこの条件を体験しているということである」
からこそ,
「セラピストの一致と受容と共感を,クライアントがある程度体験もしくは知覚する,ということである。これまで述べてきた条件がセラピストの中に存在するだけでは十分ではない。これらの条件はクライアントに対してある程度十分に伝えられなければならない。」
なぜなら,その相互の関係は,
「私がある種の関係を提供できるならば,相手は自分が成長するためにその関係を用いる力が自分の中にあることを見出すであろうし,そこで変化と人間的な成長が生じる」
ものだからだ。それは,ミルトン・エリクソンが,
「自らを変える力があることを相手自身が気づけるような状況をつくること」
といった,その状況づくりそのものでもある。
参考文献;
カール・R.・ロジャーズ『自己実現の道(ロジャーズ主要著作集3)』(岩崎学術出版社) |
|
クライアント中心療法 |
|
カール・R.・ロジャーズ『クライアント中心療法(ロジャーズ主要著作集2)』を読む。
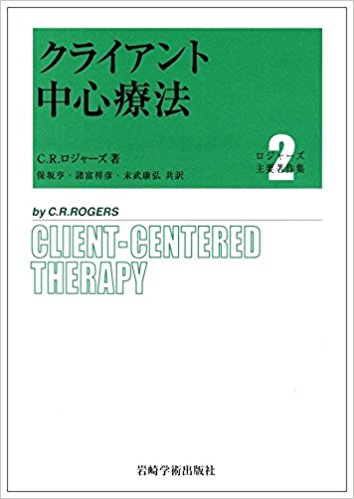
本書は,“Client‐Centered Therapy:Its Current
Practice,Implication,and theory”のうち,ロジャーズ自身の執筆論文の全訳である。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/453353253.html?1504987804
で取り上げた,『カウンセリングと心理療法』では,クライアント中心療法の宣言という部分が強かったが,本書は,実践でどれだけ効果があるか,というクライアント中心療法の検証も含めた,クライエント中心療法をより深化させた応用編という色合いがある。ロジャーズは,「はしがき」で,
「本書は,カウンセリングルームに充満した苦しみや希望,不安や喜びについて書かれています。それぞれのカウンセラーがそれぞれのクライアントと織りなす唯一無二の関係についてであり,同時にこうした関係すべてに見られる共通な要素についてであります。私たち一人ひとりが体験するきわめて個人的な体験について書かれているのです。」
とあり,「第一章 クライアント中心療法の現在」の冒頭で,「本書の目的」を,
「固定し硬直した考え方を示すことではなく,発達途上の心理療法分野の理論と実際を含めた現時点での断面図を示すことにある。はっきりしている変遷と動向を示し,以前の定式化と比較し,限られた範囲であるが他のオリエンテーションの見解との比較を行う。
その際,クライアント中心療法に従事する者の臨床上の考え方をまとめることが一つのねらいとなる。(中略)
さらなるねらいは,心理療法における明確な仮説,あるいは暗黙の了解となっている仮説に関して,既に収集されつつある研究証拠を再検討することである。心理療法の各方面での客観的証拠は少しずつ蓄積されているので,こうした研究努力の成果を分析・検討したい。」
随処で出てくるこの時点での心理療法の効果の検証が,今日見てどうなのかはわからないが,ある面,クライエント中心療法が,心理療法の確実な地歩を固めつつある自信のようなものが,うかがえる記述がしばしばみられる。
本書の中で,最も興味深かったのは,
第三章 クライアントにより体験される心理療法の関係
で,
「個々のケースの心理療法が進展する可能性は,カウンセラーの人格に依存するものではない。させにカウンセラーの態度に依存する者でさえない。これらの要素すべてがその関係の中でクライアントがどのように体験されるかにかかっているのである。面接中にクライアントの認知を中心に据えれば,そのことが自ずと認識される。葛藤,再編成,成長,統合―に対する解決をみるか否かの決め手となるのは,クライエントがどのように感じるかである。クライアントがある関係を心理療法の関係として体験することはなにを意味するのか? いかにしてある関係を心理療法の関係として体験できるように援助すればいいのか? もしこれらの質問に対する答えがわかれば,心理療法についてのわれわれの理解は格段に進歩するだろう。」
と書き,例として,あるカウンセリングで,クライアント自身が自分のカウンセリング体験を,セッションごとに手記を残した例を取り上げている。そして,八回のセッションが終った三カ月後の手記の末尾に,
「ほとんどのクライアントに共通する特徴がここにいくつか明かされている。まず第一に,行動の変化があまりに自然発生に起こり,現行の態度の編成からあまりに自然に脱却するために,なにか外的な事情により注意が向けられるまでそれに気づかないということである。もうひとつは,人格変化は,不慣れで,たよりない,『生まれたて』の感覚がつきものであることだ。そして最後に,特徴として興味深いのだが,クライアント中心療法は,心理療法の扱う自己に神経を張りつめて集中し,最終的には,自意識を強めるのではなく,自意識を弱めるという結果をもたらすことである。…別の言葉で表現すれば,自己が内省の対象になるのではなく,体験の中で円滑に機能するということである。あるいは,あるクライアントが心理療法終結後一年経ってから行われたフォローアップ面接で述べたように,『かつてのように自意識が強いということはなくなりました……。自分自身らしくいるということに集中することはありません。ただ,我は我なりなのです』ということである。」
しかし,大事なことは,「典型的体験として」伝えているのではなく,著者は,
「クライアントにとって,すべての心理療法は完全に唯一無二の体験であり,この事実をより完全に感じ取れれば感じ取れるほど他のクライアントがこうした唯一無二の体験をする援助が可能になるであろうということだ。」
と付け加えている点にある。少なくとも,クライアントが何を感じ,何を体験したかが,クライアント自身によって語られていることを紹介した,この章は,今も昔も,さほど例は多くはない。ロジャースは,クライアントの体験とそれをカウンセリングしたカウンセラーの体験とをセットで対比することを,将来への期待として述べている。
さて,もうひとつ,
第四章 心理療法の過程
の,「価値を認める過程における特徴的な心の動き」の節で,
「心理療法面接の録音を聞くにつけ,文字化された資料を研究するにつけ,『良い』あるいは『悪い』,『正しい』あるいは『間違っている』,『満足』あるいは『不満足』と認識されるものと心理療法との間には密接な関係があることがいよいよはっきりする。心理療法はどういうわけか個人の価値体系を巻き込み,その体系に巻き込まれて変化する。」
として,まず,
「心理療法の初期において,クライアントは他人や個人的な文化環境から植えつけられた価値観を人生の指針としていると言ってよいだろう。」
「心理療法が進むにつれ,クライアントは,自分が他人の考えていることに従って行動しようとしており,真の自己になっていないことに気づくようになり,こうした状況にますます不満を抱くようになる。」
「もしクライアントがこのような他人から植えつけられた価値感を棄てるとしたら,その代りになるものはなんであろう? 後に続くのは,価値感に対する混乱と疑いの過程であり,正誤や善悪の判断の基準を失ったことによる必然的な不安感である。」
「クライアントが価値判断を下す際に基礎となる拠り所が,自分自身の感覚や自分自身の体験によって与えられるということを徐々に理解することにより,この混乱は次第におさまる。」
「人間は,体験に基づいた証拠事実を検証し,長期にわたって自分自身を向上させるもの…を決定する能力を,自分自身の内に備えていることに気づく。」
「他人や個人的な文化環境から植えつけられた価値観を人生の指針としている」とは,今日のナラティヴ・アプローチの「ドミナントストーリー」そのものと言ってもいい。しかし,クライアント中心療法は,別のアプローチをとる。」
「心理療法の初期段階には,評価の位置はクライアントの外側にある傾向がある。これは,両親,文化,友達,…(中略)クライアント中心療法では,評価の位置をクライアントの側に保ち続けることがカウンセラーの行動の一つであると説明している。これはカウンセラーの応答方法からも明らかである。『あなたは―に腹を立てているのですね』,『あなたは―のせいで混乱しているのですね』,『―であるとあなたは思われるのですね』,『あなたは―であると感じているのですね』,『あなたは自分が―だから自分が悪いと思うのですね』。それぞれの応答に見られる言いまわしはもちろんのこと,その態度に示されていることは,受け入れられているのは状況に対するクライアントの下した評価だということである。自分自身の中にある評価の位置を受け入れることは,単に可能であるばかりではなく,満足できる健全なものであることにクライアントは徐々に気づき出す。」
等々。これは,明らかに認識の変化である。
「クライアントは一枚の地図を指針として生きていると言えるかもしれない。心理療法を受けている間,クライアントがまず第一に気づくのは,その地図がそのものを表しているわけではないということである―体験に基づいた領域はまったく異なり,ずっと複雑である。さらに,自分の地図は,地図であるにもかかわらず,重大な誤りを含んでいることに気づく。」
ロジャーズの例は,しかしあくまで個人の認識上の「地図」である。同じことを,マイケル・ホワイト&デビット・エプストン『物語としての家族』では,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/452653318.html?1502568827
で触れたように,
「ゴルジブスキーの格言である『地図は領土ではない』を参照にして,彼(ベイトソン)は,出来事に対する私たちの理解や私たちの出来事に対する意味は,出来事を受け取る文脈,すなわち,私たちの世界の地図を構成する前提や予測のネットワークによって決定され拘束されているのである,と提案した。彼は,地図のパターンにたとえて,全ての出来事の解釈は,どれくらいその解釈が出来事の知られているパターンに適合するかによって決まると主張し,それを『部分が全体のコードになるpart
for whole ckding』と呼んだ(ベイトソン,1972)。彼は,出来事の解釈は,それを受け取る文脈によって決められると述べただけではなく,パターン化されえない出来事は,生き残りのために選択されないと主張した。つまり,そのような出来事は,私たちにとって事実としては存在しないのである。」
われわれの社会全体の認識がわれわれの認識を拘束している,という視点からアプローチする。時代の差が,如実に表れていて興味深い。
参考文献;
カール・R.・ロジャーズ『クライアント中心療法(ロジャーズ主要著作集2)』(岩崎学術出版社) |
|
カウンセリングと心理療法 |
|
カール・R.・ロジャーズ『カウンセリングと心理療法(ロジャーズ主要著作集1)』を読む。
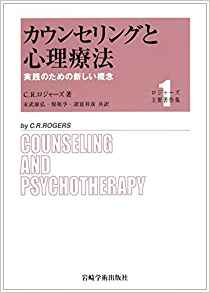
本書は,カール・ロジャーズの初期の代表作,counseling and
psuchotherpy(1943)の全訳である。本書のタイトル自体が,象徴的である。「訳者あとがき」で,
「アメリカにおけるガイダンス(その後のカウンセリング)とヨーロッパにおける精神分析(あるいはそれを中心とした心理療法)…の創造的な合流のあり様を示したのがロジャーズであった」
と書く。そして,「今となっては一見平凡な印象しか懐かせない『カウンセリングと心理療法』」というタイトルには,
「深い意味が込められている」
と。フロイトの亡くなったのが1939年,その三年後に,本書が刊行されている。
本書の中で,三,四回しか,
クライアント中心の心理療法,
という言葉を使っていないが,「序文」で,ロジャーズは,満々たる自信を吐露している。
「この本において筆者にはゆるぎない信念があることをお伝えしようと思う。それは,カウンセリングとは明確に理解することができるものであり,またどのように進むのかを予測できるものでもあり,またカウンセリングとは,学習され,検証され,より洗練されうる過程であるはずだ,という信念である。」
ロジャーズのめざすカウンセリングの全体像が,余すところなく,本書には詰まっている。そして,これが,今日のセラピーの底流にあることを感じさせるものでもある。ロジャーズは,本書の目的を,
「この本では,カウンセリングについての検証され考察されうるような仮説を,理解できるかたちで明確に提示する。それを検証し,それをさらに吟味することができるように示すのである。学生のためには,カウンセリングの実際の手順についての具体例をあげながら,一貫した考察のための枠組みを提供することをめざす。また,研究者のためには,どうすれば心理療法がうまくいくのか,その仮説を筋の通ったかたちで示すことをめざすことを目的とする。実験的検証によって,こうした仮説はそのとおりだったと分かるかもしれないし,まちがいだったと分かるかもしれない。そして本書は,臨床家のためには,既存のものに代わりうるより正確な仮説を臨床家自らが創出するという課題を提供することになろう。」
と書く。そして,
「本書は心理療法のあらゆる見解をすべて提示しようとはしない。相容れないさまざまな見解の混沌を示して混乱を増幅してしまうよりも,一つの見解をあますところなく論じることで,カウンセリングの分野をよりすっきりと整理する方が賢明であろう。したがって,本書は,カウンセリングに関する一つの方法と理論を提示するものである。」
とし,その基本的な仮説を,
「カウンセリングが効果的に成立するために必要なのは,ある明確に形作られた許容的な関係であり,その関係のなかで,クライアントは自分自身に気づくようになり,新たな方向をめざして,人生を前向きに進んでいけるようになる。この仮説に従えば,カウンセリングの技術とはおのずと,自由で許容的な関係の醸成,クライアントの自己理解の深まり,そしてその前向きで自己主導的な生き方の促進のためにこそ用いられるものであるといえる。」
として,本書全体は,
この仮説を説明したり,
定義づけたり,
拡充したり,
明確化したり,
するためにある,と。で,本書の構成は,
カウンセリングの初期,
カウンセリングの過程,
カウンセリングの終結,
をつぶさに辿り,
実践上に生じる問題,
では,たとえば,
面接時間はどれくらいがいいのか,
カウンセラーは面接中にノートを取るべきか,
クライアントが面接中に虚偽のはつげんをしたらどうするのか,
カウンセラーの資質とは,
料金はカウンセリングに影響するか,
等々といった微に入り,細を穿つような細部を具体的に解説して,最後に,第四部では,たぶん(セラピー史上)初めて,
ハーバート・ブライアンのケース,
として,カウンセリングの第一回面接から終結までの全逐語記録を載せている。そして,各回ごとに,
全般的なコメント,
具体的なコメント,
をつけて,そのやりとりの意図と意味を解説しつつ,自分のカウンセリングの全体像を披露している。ある意味,本書は,ロジャーズのカウンセリングとはどういうものかを,丁寧に,詳細に展開する,いわば,ロジャーズの,
カウンセリング宣言,
とも言うべきものだ。その意味で,今日,改めて,原点に立ち返ることで,今日常識になっていることが,ロジャースの汗と努力で,明確化されたことを知るよすがになり,この原点の仮説の論拠を見直すことで,セラピスト,カウンセラー自身のカウンセリングを点検することにもなるのではあるまいか。
従来の心理療法と対比して,ロジャーズは,この心理療法は,
「もしカウンセラーが問題解決の手助けをするならば,これこれの結果が生じるだろうと期待するよりもむしろ,人間がより大きな自立と統合へと向かう方向を直接的にめざすもの」
であり,
第一に,「人間の成長や健康,適応へと向かう動因にっいて,きわめて大きな信頼をよせている。」
第二に,「知的な側面よりも,情緒的な要素や状況に対する感情的な側面に,より大きな強調点をおいている。」
第三に,「人間の過去よりも,今ここでの状況により大きな強調点をおいている。」
最後に,「心理療法的接触それ自体が成長の経験である。個人はここで,自分自身を理解し,重要な自律的選択を行い,より成熟したやり方で他者とかかわることなどを学ぶのである。」
とその特徴を強調している。そして,「心理療法的接触」によって,
何が進行しているのか,
カウンセラーは何をしているのか,
クライアントは?
と,そのプロセスの概略を次のように整理する。
①「個人が援助を求めて来談する。このことは当然ながら,心理療法のもっとも重要な段階の一つである。ここで個人は,いわば自分に働きかけ,最初の重要な行動を責任をもってとったといえる。彼は,これが自立した行為であるということはまだ認めたくないかもしれない。しかし,こうしたことが育まれるならば,それはそのまま治療へと向かっていくものになりうるのである。」
②「通常,援助場面は明確に設定される。クライアントは来談当初から,カウンセラーが解答をもっているのではなく,カウンセリング場面とは,クライアントが援助によって問題に対する自分なりの解決を見いだすところである,という事実に気づかされる。」
③「カウンセラーは問題に関する感情を自由に表現するように促進する。このことはある程度まで,カウンセラーの親しみをこめた,相手に関心を寄せる受容的な態度によってもたらされる。…もし私たちが,その時間が本当にクライアントのものであり,その人の望むように使うことのできる時間であることをクライアントに実感させることができるならば,こうした感情は自由に流れ出てくるのである。」
④「カウンセラーは,否定的な感情を受容し,理解し,明確化する。…カウンセラーがこうした感情を受容しようとするならば,相手が話していることの知的な内容ではなく,その底にある感情に応答する構えがなくてはならない。ときとしてその感情は,とても両価的なものであったり,憎悪の勘定であったり,不全感であったりする。しかしその感情がどのようなものであっても,カウンセラーは言葉や行為によって,ある雰囲気をつくり出すよう努力する。」
⑤「その人の否定的な感情がまったく十分に表現されたとき,それに続いて,かすかに,またためらいながらではあるが,成長へと向かう肯定的な衝動が表現される。…この肯定的な表現は,心理療法全体の過程においてもっとも確実に生じる,予測可能な局面の一つである。否定的な表現が激しく,深いものであればあるほど(それが受容され理解されるならば),愛情,社会的交流への衝動,根本的な自己尊重,成熟したいという欲求などの肯定的表現が,より確かなものとして生じてくる。」
⑥「カウンセラーは否定的な感情を受容し理解したのと同じように,肯定的な感情の表現を受容し理解する。こうした肯定的な感情は,賛同や賞讃によってカウンセラーに受け入れられるのではない。道徳的な価値判断は,この種の心理療法のなかには入ってこない。肯定的な感情は,否定的な感情とまったく同じように,その人の人格の一部としてそのまま受容される。…その人は,自分の否定的感情について防衛的になる必要がない。また,自分の肯定的感情を過大評価する機会を与えられるわけでもない。しかもこうした場面では,自己洞察と自己理解が自発的に湧き出てくるのである。」
⑦「この自己洞察,利己理解,自己受容は,心理療法の過程全体のなかで二番目に重要な局面である。それは,人が新たな統合の段階へと前進する基礎を与えるものである。」
⑧「この自己洞察の過程と混ざり合って,可能性のある選択や行為の方向を明確化していく過程が生じる(ここでもう一度,これまで記述してきた各段階は互いに排他的なものではなく,また番号通りの順番で進行していくものでもないということを強調しておきたい)。このとき,いくぶん失望したような態度がみられることも多い。本質的には,その人はこのようにいっているのだ。『これが私自身です。そのことがとてもはっきり分かりました。でもどうすれば,私はこれまでと違うふうに自分自身を作りかえることができるんでしょうね』と。ここでのカウンセラーの役割は,いろいろな選択の可能性が明確になるように援助し,その人が経験している恐れの感情や,前進する勇気の欠如などについて理解できるように助けることである。」
⑨「引き続誣いて,かすかにではあるがとても意味のある肯定的な行為がはじまるという,心理療法の魅力的な局面の一つが起こってくる。」
⑩「その人がひとたびかなりの自己洞察を達成し,おそるおそる,ためらいながら肯定的な行為を試みるようになると,そこに残された局面は,もっと成長していくという要素だけである。何よりまず,そこには自己洞察のいっそうの発展がみられる。すなわち,個人が自分の行為をより深く見つめる勇気を獲得するにつれて,より完全で正確な自己理解が発展する。」
⑪「クライアント側の肯定的な行為はますます統合されたものになる。選択することについての恐れが減少し,自分が決めた行為への信頼が増大する。カウンセラーとクライアントは,今や新しい意味で協働しているのである。二人の人間的な関係はもっとも強いものになる。」
⑫「援助を求める気持ちが減少し,その関係が終らなければならないことをクライアントが認識する。」
このプロセスについて,ロジャーズは,
「ケースはどれも違うものだ」
という一般的な見解を,「日和見的な見解」と,一蹴する。
「ここで述べた心理療法は,秩序的な一貫した過程であり,その主な道筋においては予測可能なかていである。」
と。
かつて,すぐれたカウンセリングの逐語を読むと,カウンセラーはほとんどしゃべっていない,ということを言われたことがある。ロジャースは,非指示的な特徴は,
クライアントの発言だけを読んで,その面接の全体像が把握できる,
と指摘している。ここに淵源があったらしい。
参考文献;
カール・R.・ロジャーズ『カウンセリングと心理療法(ロジャーズ主要著作集1)』(岩崎学術出版社) |
|
秀吉像 |
|
堀新・ 井上泰至編『秀吉の虚像と実像』を読む。

本書は,
実像,
と
虚像,
を対比しながら,
秀吉の生まれと容貌,
秀吉の青年時代,
浅井攻め,
秀吉の出世,
高松水攻めと中国大返し,
清州会議と天下簒奪,
秀吉と女性,
秀吉と天皇,
秀吉はなぜ関白になったのか,
文禄・慶長の役/壬辰戦争の原因,
秀次事件の真相,
豊臣政権の政務体制,
関ヶ原の戦いから大坂の陣へ,
秀吉の神格化,
という14のテーマについて,対比的に掘り下げている。今までなかった試みといっていい。「実像」は,第一次史料,つまり,
書状,
知行宛行状,
武将や公家の日記,
検地帳,
分国法,
宣教師の記録,
李朝実録等の外国史料,
等々の古文書,古記録をもとに分析する。従来,多用されてきた,
小瀬甫庵『太閤記』,
『川角太閤記』
等の軍記物は二次史料として,余り重んじない。しかし,他でも触れたことがあるが,小瀬甫庵は,ほぼ同時代人であり,
寛永11(1634)〜14年,
という刊行時期は,まだ存命の人もいたり,直接見聞した人もいたりで,そうそう軽んずべきではないところがある。『川角太閤記』(1621〜23)も似た事情である。
『虚像』が,成り立つのは,秀吉ほど,物語化された人物はいないからだ。上記『太閤記』以外にも,江戸時代は太閤ブームというほど本の刊行,歌舞伎化,浄瑠璃化が続いた。竹中半兵衛の子息,竹中重門『豊鑑』,土屋知貞『太閤素性記』,白栄堂『太閤真顕記』,武内確齊『絵本太閤記』,栗原信充『真書太閤記』等々。
実は,厄介なのは,『信長公記』のように,部下の太田牛一のような人物が記録として残したのではなく,秀吉の祐筆である大村由己が,ほぼ同時期に,
『天正記』
という記録を残していることだ。つまり,秀吉自身が,演出・主演の物語を書かせている,ということだ。秀吉は,類稀な,
自己演出家,
でもあった。『天正記』は,
「天正8年(1580年)の三木合戦から天正18年(1590年)の小田原征伐まで、天正年間の秀吉の活躍を記録する軍記物。別名を『秀吉事記』とも。」
であり,具体的には,
『播磨別所記』(三木合戦の様相を記述する)
『惟任退治記』(惟任謀反記)
『柴田退治記』(柴田合戦記)
『紀州御発向記』(紀伊攻めの記録)
『関白任官記』(秀吉の関白就任の正当性を主張する)
『四国御発向並北国御動座記』(長宗我部元親ら(四国征伐)、および越中国の佐々成政らとの戦いの記録)
『聚楽行幸記』(後陽成天皇の聚楽第への行幸の有様を記録した)
『小田原御陣』
等々で(賤ヶ岳七本槍と喧伝したのは秀吉自身である),しかも,『播磨別所記』については,
「貝塚で蟄居中の本願寺顕如・教如親子の前で由己本人が朗読した」
と伝わっているなど,どうやら,この記録は,軍記物のように朗読された気配がある。『信長公記』も太田牛一自身が朗読したと言われているので,それにならったのかも知れない。
この『天正記』自体が,小瀬甫庵『太閤記』など、後の秀吉主役の軍記物語に大きな影響を与えている,と言われているのだから,虚像は,まず秀吉自身が演出した,といってもいい。
その意味では,『太閤記』類が,虚説ではない,という一例が,秀吉糟糠の妻の名前である。
かつては,『太閤記』などによって,
ねね,
とされたが,桑田忠親氏が,
「北政所宛秀吉消息の宛名は『おね』であり,北政所自筆書状には『ね』と署名されているから…『お』は敬称であるから『ね』が北政所の実名」
と主張し,近年は,
おね,
とされるようになっていた。しかし,
「女性が署名する際に,名前の頭文字一時たけ記すのは通例である。そのうえ,室町〜安土桃山時代に『ね』という一字の女性は,北政所を除けば,一人もいない。そして『ねね』という女性名は一般的だったので,やはり『ねね』が正しい」
と角田文衛氏が反論したようである。ただ直接的根拠がなかった。(甥にあたる)木下家の「系図」は,
子為(ねい),
(実家の)『平性杉原氏御系図附言』には,
於祢居(おねい),
(実兄の)『足守木下家譜』には,
寧子,
とあり,定まらない。しかし,
「『ねい』が複数あることは無視できない重みがあろう。」
ということで,近年は,
ねい,
あるいは,
寧,
と当てることが多くなっていた。だが,天正十三年十一月二十一日付「掟」が残されている,という。これは,
「秀吉と北政所の間の取り決めを記した三ヶ条であるが,その最終条に『ひでよしおねゝニくちこたへ候ハゝ,いちにち(一日)・一や(夜)しばり(縛)可申事』とある。北政所に口答えすれば一昼夜縛り付ける」
という内容で,そこに,
おねゝ,
と秀吉自筆であるのである。とすると,軽んじられてきた,『太閤素性記』が「祢ゝ(ねね)」と記していたことが正しかった,ということになる。
秀吉,自己演出の影響は端倪すべからず,というべき案件かもしれない。
参考文献;
堀新・ 井上泰至編『秀吉の虚像と実像』(笠間書院)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%94%B1%E5%B7%B |
|
会話 |
|
ルイーザ・ギルダー『宇宙は「もつれ」でできている−「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』を読む。
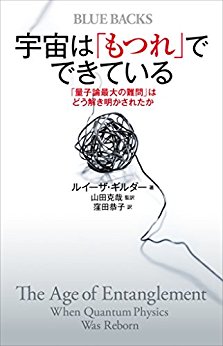
本書は,著者が,「読者のみなさんへ」で,ハイゼンベルクの,
「科学は実験に基づく」が、「科学は対話に根差している」
という言葉を引いているが, その通りに,
「量子力学の完成は必然的に、
彼ら当時の物理学者たちが互いにコミュニケーションを取り合わないかぎり、ありえなかった。アインシュタインやボーア、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、パウリ、ボーム、ディラックら、錚々たる物理学者たちが直接会って会話をしたり、手紙のやり取り(当時は電子メールなどあろうはずがない!)をしたりすることで侃々諤々の議論が闘わされ、20世紀の初頭から約30年の歳月をかけて、1930年代に量子力学が完成
したのである。」(監訳者(山田克哉))
との,「侃々諤々の議論」を,まるで見てきたように,再現して見せる。著者は,
「長年にわたって彼らが交わしたさまざまな形によるコミュニケーションを、あたかも彼女自身が直接、見聞したかのような鮮やかな〝口調〟で語っている。本書の執筆にあたり、ギルダーは8年半もの歳月をかけて、先人たちが執筆した論文や書簡、公の場での発言や討論の記録などを渉猟したという。史実に裏打ちされた再現ドラマは実にヴィヴィッドに描かれて」
いる。著者自身,
「本書は『会話』から成り立っている。会話によって、我々が日々暮らし、体験する世界がさりげなく、あるいは劇的に変わることがあるように、物理学者たちの活発な会話によって、いかに量子力学の発展の方向性が繰り返し変わってきたかについて語った本
である。本書で描かれる会話会話はすべて何らかの形で、本文に明記された日付に交わされたものであり、その一つひとつの要旨を完全に記録したものである」
と述べ,1923年夏にコペンハーゲンの市電で量子論の創始者の二人、アルベルト・アインシュタインおよびニールス・ボーアと、量子論の偉大な教師であっ
たアルノルト・ゾンマーフェルトとの 間で交わされた会話が,実際の手紙ややり取りを繋ぎ合わせたものであることを明かしている。
本書の,「量子論最大の難問」とは,監訳者(山田克哉)は,「まえがき」で,こう説明する。
「『量子』とは、ときに〝 波〟のごとくふるまったり、ときに〝
粒子〟のごとくふるまったりする物理的な『実体』
で、光子や電子が典型的な量子である。一般に、量子は内部構造をもたないが、エネルギーや運動量、スピン(自転)などの 物理量を有している。
二つの量子のあいだでいったん相互作用が生じると、その二つの量子は『相関』をもつと言われる。相関をもった二つの量子がどんなに離れていっても─たとえ互いに100兆㎞
離れても─ 、その相関性は完全に保たれる。二つ
のうち、一方の量子の物理状態(たとえばスピン)だけを実際に測定器を使って測定し、その値をはっきりと確定してしまうと、その瞬間(同時に、すなわちゼロ秒間で!)、100兆㎞のはるか彼方にあるもう一方の量子の物理状態が、いっさい測定することなく自動的に決定してしまうのである。このような意味で、二つの量子の間の相関性は『量子のもつれ』とよばれるよう
になった(名付け親はシュレーディンガー)。」
因果を破るこの考えに,強く反対したのは,アインシュタインである。「神はサイコロを振らない」と言って,量子力学が「不完全な理論」であると主張した。対して,徹頭徹尾,
量子力学を支持 したのは,ニールス・ボーアである。量子力学が完成を見たとされる1930 年から5年後の1935年,
「EPR論文(アインシュタイン(Einstein)・ポドルスキー(Podolsky)・ローゼン(Rosen)の共同執筆)」
が出る。
「EPR パラドックス」
とも呼ばれるこの論文から端を発した,長い論争が続くのである。
「二つの電子を選ぶ。電子にもまた内部構造がなく、粒子としてふるまうときは点のごとくふるまうのだが、スピンしている。電子は2回転して初めて元の状態に戻るような量子であるため、1回転では『半分』まで戻るという意味で『スピン』とよばれている。…スピンの電子の『自転軸』には『上向き』と『下向き』の
二つの方向がある(前者 を『スピン・アップ』、後者を『スピン・ダウン』とよぶことにする)。実際に、相関をもって
いて100兆㎞離れた電子Aと電子Bとからなる系に測定器をかけて、それぞれの電子の状態を測定してみるとどうなるだろうか。たとえば、測定器を電子Aに向けた結果、電子Aのスピンがアップであると測定されたとする。電子Aがスピン・アップと観測されたその瞬間(そう、まさにその瞬間、ゼロ秒間で!)、100
兆㎞離れた場所にある電子Bのスピンは自動的に(観測することなしに!)スピン・ダウ に決定する。相関をもつ(
つまり、もつれた)二つの電子の合計スピンは、必ずゼロにならなければならないからだ。」
EPR論文が提起したのは,100兆㎞も離れた二つの量子の相関関係は崩れることなく完全に保たれることに対して
の疑問である。アインシュタインは,因果律を破るこの現象を,
幽霊による遠隔作用,
と呼び,この問題の解決に(つまり因果律をまもるために)持ち出したのが,後に,ボームが固執することになる,
「隠れた変数」理論,
であった。これをもって,古典物理学の決定論へと回帰させようとするのである。この最終決定は,デヴィッド・ボームを経て,1964年,ジョン・ベルの,
ベルの不等式,
によって理論的に決着がつく。
「二つの相関している電子が100兆㎞も離れているのに、一方の電子の測定結果が瞬時にもう一方の電子の状態に影響を及ぼすということは、二つの電子の相関関係は局所的ではなく、『分離不可能』な一つの系(そう、全体で一つ!)
を成していて、その系の中で起こることは部分から部分へと伝わるのではなく、系全体に瞬時に影響を及ぼすと考えたのだ。すなわち、すべては系内の全範囲にわたって『非局所
的』に起こる。」
ベルの不等式が成り立てば「隠れた変数」の必要性が生じ、『非局所性』や『
分離不可能性』は現われない。「その場合には、系の部分部分を考えねばならず(局所的)、すべては決定論に従うこととなって、量子力学は不完全な理論」となる。それが実証されるのは,1980年代,
ベルの不等式が成立しない( 破れる),
ことが実験で確認される。この長い道のりを,本書は,会話と対話で追っていく。とくに,ボームが,孤立無援で
「隠れた変数」理論,
を固執するところから,ベルの思考実験までは,推理小説を見るように,ハラハラさせられる。
アインシュタインとボーア,
シュレーディンガー,ハイゼンベルク,パウリ,
フォン・ノイマン,
ボーム,
ベル,
とそれぞれがかみ合いながら,あるいはすれ違う会話は,読み応えがある。
本書は,最後に,若き物理学者ルドルフを登場させ,
シュレーディンガー
の孫だという落ちをつけている。
参考文献;
ルイーザ・ギルダー『宇宙は「もつれ」でできている 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』(ブルーバックス) |
|
環世界 |
|
ヤーコブ・フォン・ユクスキュル『生物から見た世界』を読む。

訳者である日高敏隆氏は,「環世界」という訳語に付いて,
「客観的に記述されうる環境(英語のenvironment,ドイツ語でこれに相当する語は,Umgebung)というものはあるかもしれないが,その中にいるそれぞれの主体にとってみれば,そこに『現実に』存在しているのは,その主体が主観的につくりあげた世界なのであり,客観的な『環境』ではないのである。
それぞれの主体が環境の中の諸物に意味を与えて構築している世界のことを,ユクスキュルはUmweltと呼んだ。それは客観的な『環境Umgebung』とはまったく異なるものである。
じつはドイツ語では昔から,客観的な『環境』のことをUmweltといっている。いわゆる環境問題はUmweltproblemeである。その一方,英語にはユクスキュルのいうUmweltに相当する語はない。
…Umweltということばは,ドイツ語を使うデンマーク人の詩人バッゲンセン…が,身のまわりの環境を意味するものとして,1800年に造語したものらしい。その後このUmweltという語はフランス語のミリュー(milieu,やはり同じような意味での環境)の訳語として使われたり…してきた。しかし,Umweltに明確な概念を与え,新しい無認識を打ち立てたのはユクスキュルである。
このUmweltは日本語としては従来『環境世界』と訳されてきたが,…環境とUmweltとは対立するものとユクスキュルはとらえている。そこでぼくは,環境という語を含む『環境世界』はUmweltの訳語としては適切ではないと思い,『環世界』という語に変えることにした。
…『環境』はある主体のまわりに単に存在しているもの(Umgebung)であるが,『環世界』はそれとは異なって,その主体が意味を与えて構築した世界(Umwelt)なのである。」
と説明し,ユクスキュルの「環世界」が「環境世界」とは異なる謂れを説いている。「まえがき」で,ユクスキュルは,主体と環世界との関係について,(行動主義を批判しつつ)こう書くところから始めている。
「われわれの感覚器官がわれわれの知覚に役立ち,われわれの運動器官がわれわれの働きかけ役立っているのではないかと考える人は,それらの器官の組み込まれた機械操作系を発見するだろう。われわれ自身がわれわれの体に組み込まれているのと同じように。するとその人は,動物はもはや単なる客体ではなく,知覚と作用とをその本質的な活動とする主体だとみなすことになるであろう。
しかしそうなれば環世界に通じる門はすでに開かれていることになる。なぜなら,主体が知覚するものすべてその知覚世界になるからである。知覚世界と作用世界が連れだって環世界という一つの完結した全体を作り上げているのだ。」
それは,人には人の環世界があり,ハエにはハエの,犬には犬の環世界がある,ということを意味する。
「つまり,動物主体は最も単純なものも最も複雑なものもすべて,それぞれの環世界に同じように完全にはめ込まれている。単純な動物には単純な環世界が,複雑な動物にはそれに見合った豊かな構造の環世界が対応しているのである。」
ユクスキュルは,ダニを例にして,
「哺乳類の皮膚腺は最初の回路の知覚標識の担い手である。なぜなら酪酸という刺激が知覚器官の中で特異的な知覚記号を解発し,それらが嗅覚標識として外へ移されるからである。知覚器官の中のこの出来事は,誘導(これがなにかはわからないが)によって作用器官に相応のインパルスを生じさせ,これが肢を離して落下することを引き起こす。落下するダニはぶつかった哺乳類の毛に衝撃という作用標識を与える。これがダニの側に触覚という知覚標識を解発し,それによって酪酸という嗅覚標識が消去される。この新しい知覚標識はダニに歩きまわる行動を解発し,やがて毛のない皮膚に到達すると温かさという知覚標識によって歩きまわるのは終り,代わりに食いこむ行動がはじまる。(中略)哺乳類の体に由来するあらゆる作用のうち三つだけが,しかもそれらが一定の順序で刺激になるのである。ダニをとりまく巨大な世界から,三つの刺激が闇の中の灯火信号のように輝きあらわれ,道しるべとしてダニを確実に目標に導く役目をする。これを可能にするために,ダニは受容器と実行器をそなえた体のほかに知覚標識として利用できる三つの知覚記号が与えられている。そしてダニはこの知覚標識によって,まったくきまった作用標識だけを取り出すことができるよう行動の過程をしっかり規定されている。
ダニを取り囲む豊かな世界は崩れ去り,重要なものとしてはわずか三つの知覚標識と三つの作用標識からなる貧弱な姿に,つまりダニの環世界に変る。」
と,ダニの環世界を描いてみせる。こうした環世界の違いを,ハエ,イヌ,人間で,象徴的に説明する。
「われわれは自分の環世界の対象物で行うあらゆる行為について作用像を築きあげており,それを感覚器官から生じる知覚像と不可避的にしっかり結びつけるので,その対象物は,その意味をわれわれに知らせる新たな特性を獲得する。これを簡単に作用トーンと呼ぶことにしよう。(中略)
作用像を利用して人間と類縁の遠い動物の環世界を描きだそうとするとき,常に肝に銘じておかなければならないのは,作用像とはその動物の環世界に投影された働きであるということである。」
例えば同じ部屋が,人にとって,ハエにとって,イヌにとって,
「自分と結びつける作用トーンの数に応じて異なるようにあらわされている」
図で,環世界の違いを,象徴的に示してみせる。
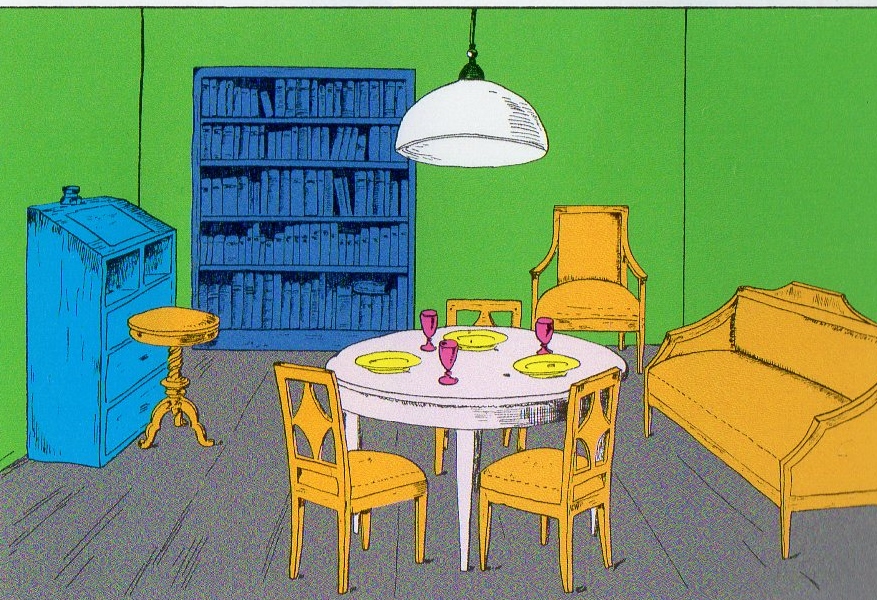
(人間にとっての部屋)
「人間の環世界では部屋の中の対象物の作用トーンは,椅子は座席のトーン色(オレンジ),テーブルは食事のトーン色(ローズ色),グラスや皿はまた別のしかるべき作用のトーン色(黄色と赤=食物トーンと飲み物トーン)で表されている。床は歩行のトーン色をもつが,本棚は読書のトーン色(藤色),机は書き物のトーン色(駙)を示す。そして壁は障害物のトーン色(緑)をもち,電灯は光のトーン色(白)をもっている。」
(イヌにとっての部屋)
「イヌの環世界では,人間の環世界のものと同じ作用トーンのものは同じ色で示してある。だが,そのようなものは食物のトーン色や座席のトーン色くらいで,そのほかはすべて障害物のトーン色を示している。」
(ハエにとっての部屋)
「ハエにとっては,電灯とテーブルの上のものを除いてすべてのものが歩行のトーン色しかもっていらわかないのがわかる。」
このことからわかることは,盲導犬というのは,
「イヌの利益になる知覚標識ではなくて盲人の利益になる知覚標識を,イヌの環世界に組み込まなくてはならない」
という調教のむつかしさであると,ユクスキュルは指摘している。
ユクスキュルの描く環世界をイメージしながら,片隅で,アフォーダンスのことを考えていた。ギブソンは,
「環境のアフォーダンスとは,環境が動物に提供するもの,よいものであれ,悪いものであれ,用意したり備えたりするものである。(中略)この言葉は動物と環境の相補性を包含している。」
といい,佐々木正人氏は,
「『すり抜けられるすき間』,『登れる桜』,『つかめる距離』はアフォーダンスである。アフォーダンスとは,環境が動物に提供する『価値』のことである。」
と説く。しかし,ユクスキュルの環世界から見ると,アフォーダンスは,人間の環世界のアナロジーにしかなっていないように見える。つまり,人の環世界を当てはめているのではないのか,という疑問がわく。
参考文献;
ヤーコブ・フォン・ユクスキュル『生物から見た世界』(岩波文庫)
J・J・ギブソン『生態学的視覚論』(サイエンス社)
佐々木正人『アフォーダンス』(岩波書店) |
|
おくの細道 |
|
松尾芭蕉『奥の細道 俳諧紀行文集』を読む。
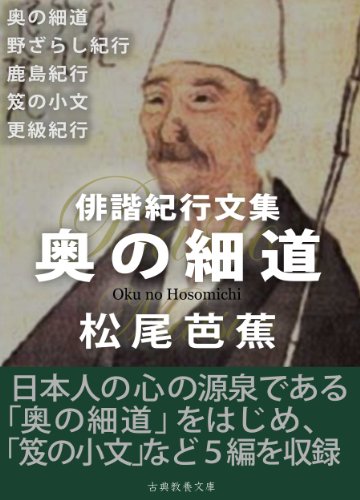
昔,読んだとき,殺生石を見物したあと,西行ゆかりの遊行柳のもとで詠んだ,
田一枚植ゑて立ちさる柳かな
という句が強く印象に残った。やはり今回も,
時間を折り畳んだ,
ようなこの句に,惹かれる。「おくのほそ道」本文は,
「清水ながるるの柳は、蘆野の里に有りて田の畔にのこる。この所の郡守戸部某の、この柳みせばやなど折々にのたまひ聞こえ給ふを、い
づくの程にやと思ひしを、今日この柳の蔭にこそ立ちより侍りつれ。」
とあり,上記の句がつづく。田一枚植え終るまで佇んでいた時間が,一瞬に折り畳まれている。思い込みかもしれないが,こうした時間の折り畳み方をした句は,あまりないように思う。
この柳は,
道のべに清水流るる柳陰しばしとてこそ立ち止まりつれ ,
という西行の歌で知られるらしいが,この西行の柳を主題にして、謡曲「遊行柳」によって,「遊行柳」として広く世に知られるところとなり,歌枕の地となった,と言われる。
もうひとつ,「おくのほそ道」ですきな句は,旅立ちの,
行く春や鳥啼き魚の目は泪,
という句で,物の本には,
鳥啼き魚の目は泪
は常套句と評していたが,
https://blogs.yahoo.co.jp/yan1123jp/16244088.html
によると,いくつか出典と想定されるものがあるらしい。
感時花濺涙
恨別鳥驚心(杜甫)
王鮪懐河岫
晨風思北林(文選古詩)
枯魚過河泣
何時還復入(古楽府)
羈鳥恋旧林
池魚思故淵(陶淵明「帰田園居」)
春眠不覚暁
処処聞啼鳥(孟浩然「春暁」)
千里鶯啼隳映紅
水村山郭酒旗風(杜牧「江南春」)
等々。しかし,僕は,この句を見ると,
月落烏啼霜満天
江楓漁火対愁眠手いる。
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘声到客船(張継「楓橋夜泊」)
を思い出す。たしか,もう30年以上前になるが,長安(西安)に旅行した時,ホテルで店を開いていた書家に,隷書で,この詩を扇に書いて貰った記憶がある。もちろん,
月落ち烏啼いて霜天に満つ
だから,季節も,時間も違うし,「鳥」ではなく,「烏」だ。でも,他の出典に比べて,句の調子が合う,と勝手に思っている。
幾つか心に引っ掛かった句を拾っておく。
眉掃(まゆはき)を俤(おもかげ)にして紅粉(べに)の花(おくの細道)
馬に寝て残夢月遠し茶の煙(野ざらし紀行)
死にもせぬ旅寝の果よ秋の暮(野ざらし紀行)
僧朝顔いく死 にかへる法の松(野ざらし紀行)
旅人と我が名よばれん初ぐれ(笈の小文)
冬の日や馬上に凍る影法師(笈の小文)
言葉の陰翳が,背後に,どれだけの時間と空間を想定させるか,言葉の向こうに見るものは,おのれ自身でしかない。とつくづく思う。メタファというかアナロジーというか,それは,詠む人ではなく,読む人次第ということかもしれない。
この道や行く人なし秋の暮(元禄7年)
参考文献;
松尾芭蕉『奥の細道 俳諧紀行文集』( Kindle版)
http://www.bashouan.com/pbYugyouyanagi.htm |
|
宇宙の終り |
|
吉田伸夫『宇宙に「終わり」はあるのか−最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで』を読む。

本書は,ビックバンから,「10の100乗年」後の,ビッグウィンパーと呼ばれる,宇宙の終焉までを描く。その意味では,
「ビッグバンから138億年後の現在は,宇宙が誕生した“直後”にすぎない」
のだそうだ。僕の理解では,急膨張の直前の,急拡大,爆発のイメージに近いが,著者は,
「ビッグバンは,巨大な爆発などではない。異常な高温状態にある一様な空間が整然と膨張を始めたものであり,生前とした膨張だからこそ,その後に続く宇宙の進化が可能になったのである。」
と書く。つまり,
「最初に膨張を始めたきっかけが何もない」
のである。著者は,さらにこう付け加える。
「これは,答える必要のない謎なのかもしれない。膨張が始まらなければ天体も形成されず生命も登場しないので,なぜ宇宙がかくあるのかなどと誰も悩まないからである。もしかしたら,宇宙は無数に存在するのかもしれない。その中に,何の理由もなく全くの偶然で膨張を始めた宇宙があり,そこに発生した生命の一つである人類が,『なぜ宇宙空間は膨張を始めたのか』と無駄に悩んでいるだけということもあり得る。」
しかし,「なぜ膨張を始めたか」について,現代物理学は,こういう説明をしている。
「現代物理学では,空間は物質を入れる容器ではなく,物理現象の担い手である『場』と一体化した物理的実在と見なされている。暗黒エネルギーが,こうした場が有するポテンシャルエネルギーだとすると,押し込められたコイルバネと同じように,蓄えられていたエネルギーが何らかのきっかけによって外部に放出されることも起こり得る。
暗黒エネルギーの担い手となる場があるとして,それがどんな性質を持つのかはほとんどわかっていない。取りあえず,インフラトン場という名前だけが与えられている。ポテンシャルエネルギーの大きさは,インフラトン場の強さ(電場や磁場の強度と同じような場の値)の関数になるはずだが,関数形は不明である。インフラトン場の値が常に一定ならば,ポテンシャルエネルギーも不変で,新たな現象は何も起きない。しかし,マザーユユニバースのどこか一部でインフラトン場の値が変動し,それに伴ってポテンシャルエネルギーが減少するような事態が生じたとしよう。このとき,エネルギー保存の法則に従って,インフラトン場以外の場にエネルギーが供給され,場が激しく震動することでさまざまな物理現象を引き起こす。」
と。この前提は,
「暗黒エネルギーが常に一定の値ならば,マザーユニバースでは,物質的な現象が何も生起しないまま永遠に時が過ぎていくだけである。しかし,暗黒エネルギーがポテンシャルエネルギーの一種であるならば」
ということから想定されている。
「宇宙に内在するエネルギーによって加速膨張する宇宙は,膨張すること自体がアインシュタイン方程式から導かれる自然な過程であり,地上から打ち上げる物体のように,最初に速度を与える必要がない。つまり,ド・ジッター宇宙は,ビックバンが持つ不自然さの多くを回避している。」
因みに,ド・ジッター宇宙とは,物質のない宇宙で,「物質同士が引きあう重力がないので」一貫して膨張し続ける宇宙である。
「アインシュタイン方程式を信じると,ド・ジッター宇宙は,ある瞬間に誕生するのではなく,…永遠の過去から膨張し続ける…。加速度自体が増えるために,宇宙は指数関数的に巨大になっていく。物質がないので,天体が形成されることはなく,もちろん,ブラックホールも存在しない。…どこを見ても一様に何もない虚無の世界となる。」
だから,
「この宇宙が絶対的な虚無の世界であるマザーユニバースから生まれたというアイデアが正しいとすると,物質は初めから存在したのではなく,インフラトンのエネルギーが解放されて高温状態になったビッグバンの際に,何らかのメカニズムによって生まれたと考えなければならない。」
そのメカニズムは,こうである。
「量子論によると,結晶の振動エネルギーや原子の内部エネルギー,電子の角運動量などの物理量が,それまで考えられていたような連続的な値ではなく,とびとびの値しか取れない…。例えば,固体比熱の理論によると,結晶内部で原子が振動するときのエネルギーは,基準となるエネルギーの整数倍にしかならない。この基準エネルギーは,『エネルギー量子』と命名された。結晶全体の振動エネルギーは,エネルギー量子というエネルギーの“塊”が何個あるかという形で表現できる。振動が波の形で伝わるときは,エネルギー量子が移動することになり,その際,移動に伴う運動エネルギーが付け加わる。
こうした性質は,結晶に限らず,振動するあらゆるものに共通する。したがって,電磁場のような振動する場に量子論を適用すると,エネルギー量子があたかも粒子のように振る舞うことが示される。これが,場から“粒子のようなもの”が生み出されるメカニズムである。こうした粒子的なものは,素粒子と呼ばれる。」
つまり,
「質量が『物質の量』ではなく『内部エネルギー』だと考えると,物質のないマザーユニバースから物質を含む我々の宇宙が誕生したことが,すんなり納得されよう。この宇宙が誕生したのは,インフラトン場がポテンシャルエネルギーを解放した結果だと考えられる…。このとき,解放されたエネルギーによって物質の場が激しく震動し始めたため,膨大な数の素粒子が生まれてきたのである。この見方によれば,物質はビッグバンにおけるエネルギーの残滓であり,物質現象は全て,始まりの瞬間にもたらされたエネルギーが引き起こしていることになる。」
と。こうして本書は,
始りの瞬間,
宇宙歴10分まで,
宇宙歴100万年まで,
宇宙歴10億年まで,
宇宙歴138億年まで,
と現時点に到達し,そこから,「研究者が自信を持って語れるのは数百億年先まで」を超えて,
宇宙歴数百億年,
宇宙歴1兆年まで,
宇宙歴100兆年まで,
宇宙歴1垓(10の20乗)まで,
宇宙歴1正(10の40乗)まで,
宇宙歴10の100乗以降,
と,最後は,ビッグウィンパーへと至る。さすがの中国の単位も,
1正(10の40乗)
1載(10の44乗)
1極(10の48乗)
1恒河沙(10の52乗)
1阿僧祇(10の56乗)
1那由多(10の60乗)
1不可思議(10の64乗)
1無量大数(10の68乗)
までしか,数の単位を想定していない。その先の10の100乗年先の話である。
すでに1兆年先には,ビッグバンの証拠も,膨張し続けた証拠,
ハッブルの法則(「他の銀河が,距離的にはほぼ比例する後退速度で天の川銀河から遠ざかる」),
ビッグバンの核融合理論値(宇宙に存在する元素のわりあいは,水素全体の3/4,残りの大半をヘリウムが占める),
宇宙背景放射(ビッグバンの余熱が宇宙歴38万年の熱放射という形で残っている),
その痕跡はまったく消えてしまう。そして,宇宙歴10の100乗年以降,
ビッグウィンパー,
と名づけられた,永遠の静寂を迎える。
ビッグウィンパーとは,エリオットの詩からとられている,という。
「全てのブラックホールが蒸発し,物理現象がほとんど何も起きなくなった熱死に近い状態」
である。ビッグウィンパーとは,
すすり泣きの声,
であり,エリオットの「うつろな人間」の,
これが世界の終わり方だ。
これが世界の終わり方だ。
これが世界の終わり方だ。
轟音(bang)ではなく,すすり泣き(whimper)とともに。
から来ている。
ビッグウィンパー,
とは,なかなか知的な命名である。
参考文献;
吉田伸夫『宇宙に「終わり」はあるのか−最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで』(ブルーバックス)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%90%E3%83%B3 |
|
孫子 |
|
金谷治訳注『新訂 孫子』を読む。

本書は,
「兵とは国の大事なり」
と,「五事七計」から論じはじめる。「五事」とは,
「一に曰わ く道、二に曰わく天、三に曰わく地、四に曰わく将、五に曰わく法なり。」
とし,「七計」とは,
「主 孰れか有道なる、将 孰れか有能なる、天地 孰れか得たる、法令 孰れか行なわる、兵衆 孰れか強き、士卒 孰れか練いたる、賞罰 孰れか明らかなると。」
である。ふと,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/449836582.html
で取り上げたクラウゼヴィッツを思い起こす。
「戦争は政治的交渉の継続にほかならない,しかし政治的継続におけるとは異なる手段を交えた継続である」
「戦争は,とうてい政治交渉から切り離され得るものではない。もしこの二個の要素を分断して別々に考察するならば,両者をつなぐさまざまな関係の糸はすべて断ち切られ,そこは意味もなければ目的もないおかしな物が生じるだけだろう。」
兵の強さは,国のありようの延長にある。兵力のみを問題にする愚は,今日の北朝鮮を見れば一目瞭然である。その上で,
「兵とは詭道なり。」
と説く。しかし,「五事七計」によって,
「算多きは勝ち、算少なきは勝たず。」
と。既に,
「夫れ未だ戦わずして算して勝つ者は、算を得ること多ければなり。」
目算も立たず,戦を決意する者は,第二次大戦の我が国の指導者以外にはない。その愚行は,『日本はなぜ開戦に踏み切ったか』
http://ppnetwork.seesaa.net/article/448110449.html
で触れた。だから,孫子は言う,
「凡そ用兵の法は、国を全うするを上と為し、国を破るはこれに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るはこれに次ぐ。旅を全うするを上と為し、旅を破るはこれに次ぐ。卒を全うするを上と為し、卒を破るはこれに次ぐ。伍を全うするを上と為し、伍を破るはこれに次ぐ。是の故に百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり。」
因みに,
「軍は一万二千五百人の部隊、旅は五百人、卒は五百
人から百人、伍は百人から五人までの軍隊編成。」
とか。どのレベルでも同じで,
「百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり。」
と。まさに,「兵とは詭道なり」とはこのことであり,政治が主であり,兵は従である。だから,孫子は,はっきり言う。
「故に上兵は謀を伐つ。其の次ぎは交を伐つ。其の次ぎは兵を伐つ。其の下は城を攻む。攻城の法は已むを得ざるが為めなり。」
と。
「故に勝を知るに五あり。戦うべきと戦うべからざるとを知る者は勝つ。衆寡の用を識る者は勝つ。上下の欲を同じうする者は勝つ。虞を以て不虞を待つ者は勝つ。将の能にして君の御せざる者は勝つ。此の五者は勝を知るの道なり。故に曰わく、彼れを知りて己れを知れば、百戦して殆うからず。彼れを知らずして己れを知れば、一勝一負す。彼れを知らず
己れを知らざれば、戦う毎に必ず殆うし。」
まさに,「戦うべきと戦うべからざるとを知る」ことのできるものが指導者でなくてはならない。いまだに,平気で,「中国に勝ちたい」などとほざく指導者を持つ国につける薬はない。それが民力の反映だけに,なおさら絶望的である。
「故に兵は拙速なるを聞くも、未だ巧久なるを睹ざるなり。夫れ兵久しくして国の利する者は、未だこれ有らざるなり。故に尽く用兵の害を知らざる
者は、則ち尽く用兵の利をも知ること能わざるなり。」
と。だから,
「昔の善く戦う者は、先ず勝つべからざるを為して、以て敵の勝つべきを待つ。勝つべからざるは己れに在るも、勝つべきは敵に在り。故に善く戦う者は、能く勝つべからざるを為すも、敵をして勝つべからしむること能わず。故に曰わく、勝は知るべし、而して為すべからずと。」
まさに,クラウゼヴィツの言う,
「戦争によって,また戦争において何を達成しようとするのか,という二通りの問いに答えずして,戦争を始める者はおるまい。また―当事者にして賢明である限り―戦争を開始すべきではあるまい。この問いの第一は戦争の目的に関し,また第二は戦争の目標に関する。,
これら二件の主要な思想によって,軍事的方向の一切の方向,使用さるべき手段の範囲,戦争を遂行する気力の程度が規定されるのである。そして戦争計画は,軍事的行動の極く些細な末端にまでその影響を及ぼすのである。」
戦争は政治の外延であり,軍人のものではなく,政治家のものでなくてはならない。有名な,武田信玄の,
風林火山,
も,
「故に兵は詐を以て立ち、利を以て動き、分合を以てを以て変を為す者なり。故に其の疾きことは風の如く、其の徐なることは林の如く、侵掠することは火の如く、知り難きことは陰の如く、動かざることは山の如く、動くことは雷の震うが如くにして、郷を掠むるには衆を分かち、地を廓むるには利を分かち、権を懸けて而して動く。直の計を先知する者は勝つ。此れ軍争の法なり。」
単なる戦術と取れば,誤る。信玄が誤ったように。あくまで,戦略の一環でなくてはならない。
なぜならば,クラウゼヴィツの言う如く,
「第一は,政治的交渉は戦争によって断絶するのでもなければ,またまったく別のものに転化するのでもない,たとえこの場合に政治的交渉に用いる手段がいかなる種類のものであるにせよ,依然としてその本質を保持する,ということである。また第二は,戦争における一切の事件の辿る主要な線は,取りも直さず戦争を貫いて講和に至るまで不断に続く政治交渉の要綱にほかならないということである」
これを過てば,戦うこと自体を自己目的化して,無意味な戦いを継続することになる。
『孫子』は,かかって,戦略の書である。つまり,クラウゼヴィツ『戦争論』と同様政治の書である。これを見誤ってはならない。
参考文献;
金谷治訳注『新訂 孫子』(Kindle版 岩波文庫)
クラウゼヴィッツ『戦争論』(岩波文庫)
森山優『日本はなぜ開戦に踏み切ったか―「両論併記」と「非決定」』(新潮選書) |
|
半島から見る |
|
高田貫太『海の向こうから見た倭国』を読む。

本書は,
「おおむね三世紀後半〜六世紀前半の日朝関係を描くことを目的とする」
が,もちろん日朝関係と言っても,
日本列島と朝鮮半島に生活する人々の交流の歴史,
である。舞台は,
「むろん日本列島と朝鮮半島だ。けれども,この両区域の間にくっきりとした境界をひいてしまっては,いきいきとした描写は出来ない。それよりも半島と列島の間の海を,…人びとが往来した場ととらえて,日本列島と朝鮮半島を,対馬(大韓・朝鮮)海峡や日本(東)海,黄海,玄界灘,瀬戸内海,ひいては太平洋を媒介として人びとが活発に交流を重ねてきたひとつの地域,『環海地域』と認識してみたい。」
どある。本書は,
「最も根本的な問題として,これまでの研究では朝鮮半島からの視点が欠けている」
という問題意識に立つ。
「日本列島の古墳時代と同じころの朝鮮半島は,北に高句麗,東に新羅,西に百済というように三国が割拠した時代,三国時代だった。また,新羅と百済に挟まれた南部には,加耶と総称される,金官加那・大加耶・小加耶・阿羅加耶などのいくつかの社会が群立していた。さらに,西南部の栄山江流域にも,独自の文化を有する社会が位置している。」
という半島の状況の中で,
「おもに新羅,百済,伽那,栄山江流域など半島南部に位置した社会が,倭と盛んに交渉を重ねていたことが,これまでの研究でわかっている。けれども,これらの社会がどうしてさまざまな先進文化にかかわるモノ,人,情報を倭へ伝えたのか,その目的は何か,という問いに対して,倭の立場からだけで描かれた関係史では,あまり答えることができない。ここに研究の盲点がある。」
一方,中国や朝鮮半島から,
倭人,
倭,
と呼ばれた日本列島に住む人々やそこに成立した社会は,
古墳時代,
にある。
「十六万基という膨大な数の古墳が,日本列島の各地で築かれた。地域を代表する大首長から,それにしたがう中小の首長,集落や家族の長,時には一般の民衆にいたるまで,実にさまざまな人びとが古墳に葬られた。その中で,首長たちが葬られた大きな古墳の多くは前方後円墳で,岩手県から鹿児島県にかけて広がる。(中略)古墳の大小や,前方後円墳・前方後方墳・円墳・方墳などというその多様な形から,列島各地の地域社会の間で政治的な秩序が形成されていた,と考えられている。筑紫地域・吉備地域・出雲地域・毛野地域などが大首長を擁する有力な地域社会であり,その頂点に立つのが,多くの巨大古墳が集中する畿内地域に本拠地を置いて倭王を擁する社会だった。(中略)当時の倭は,列島各他のさまざまな地域社会と畿内の倭王権で構成されていた。」
倭の立場から見ただけでは,日朝関係は,所詮,倭の立場から(希望的に)描いたものにすぎない。
「倭に先進文化の受容という目的があるのと同じように,百済,新羅,伽那,栄山江流域それぞれにも,倭と交渉する目的があったはずだからである。その交渉の目的は何か,実際どのように交渉がおこなわれたのかについて,具体的に明らかにしていく必要がある。そして,それぞれの社会にとって倭とは一体どのような存在だったのか,についても考えなければならない。」
し,その交渉の担い手は,王権に一元化されていたわけではない。
「倭と新羅,百済,伽那,栄山江流域の間では,いうなれば王権による外交だけではなく,それぞれに属する地域社会も主体的に交渉を行っていた。そして実際の交渉にたずさわっている集団や個人が存在していた。」
交渉,
つまり,
「人。モノ,情報をめぐる交易や使節の派遣,時には武力の行使などを通して,社会や集団が何らかの利益を得るように,相手側に働きかけること」
は,半島側にもあった。
「半島のそれぞれの社会は,半島情勢をみずからが有利な方向へ動かしていく策のひとつとして,倭とつながろうとしたのであり,一方,倭のほうにも先進文化を安定的に受容するという目的があった。」
つまりは,半島と列島を囲む,広い社会の中での,
倭と新羅,百済,伽那,栄山江流域,
とのダイナミックな三百年の関係を描きだす。その象徴は,いわゆる,
磐井の乱,
と呼ばれる出来事にみることができる。それは,新羅の加耶侵攻に始まる。加耶は倭にとって重要な交渉相手であった。その流れは,
①524年に新羅は加耶への侵攻を本格化させる。この時におそらく加耶が倭王権への軍事的な支援を要請した。
②倭王権は要請を受け入れ,「近江毛野臣」を将軍として,対新羅戦のための派兵を計画する。
③倭王権は北九州の大首長だった磐井に,磐井が管理する玄界灘遠雅言考の港を倭王権の直属とすること,中北部九州への軍事動員をかけるみと,の要求をする,
④磐井は,それに応ずるかを迷っている中,新羅はひそかに「貨賄(まいない)」を贈り,倭王権の加耶派兵阻止を要請した。
⑤磐井は,倭と朝鮮半島を繋ぐ海路を遮断し,近江毛野臣軍の渡海阻止のために挙兵する。
結果として,磐井は鎮圧されるが,新羅の倭の派兵阻止のもくろみは成功したことになる。磐井の意図は何であっか?
「朝鮮半島とのつながりが成長の背景にあった磐井にとって,玄界灘の港を倭王権に接収されることは,みずからの地位や権益が大きく損なわれることだったろう。倭王権の…要求に応じるかそれとも反発するか迷いを重ねていた磐井に,新羅が派兵阻止を要請してきたのである。この時,磐井の中では,百済―加耶―倭王権に対峙する新羅―九州という展望が開けたのだろう。そして倭王権を見限り,戦争へと踏み切った。磐井自身にはそれなりの勝算があったのかもしれない。」
新羅が,列島の社会情勢に通じていた,ということができる。磐井は,
「(当時としては列島第四位の規模の)岩戸山古墳の位置する八女地域に本拠地を置いた地域首長であったことはむろんのことだが,大王墓に準じる古墳の規模や膨大な数の石製表飾の出土からみれば,九州各地の有力首長間の連携をリードした大首長だったと評価できる。」
という位置や,倭王権との微妙な関係にくさびを打ち込む新羅の政治的手腕もなかなかである。
半島と列島との,政治的な関係,繋がり,文化的な交流等々,この時代の日朝は,まさに,
一衣帯水,
というより,著者の言う,
環海地域,
と見ることが,正鵠を射ている,とつくづく思う。
「三世紀後半から六世紀前半の朝鮮半島には,高句麗,百済,新羅,加耶,栄山江流域などの社会が割拠し,遠交近攻のような関係でしのぎを削っていた。特に,高句麗が朝鮮半島中南部への進出をもくろむようになると,百済,新羅,加耶,栄山江流域などの社会は,国際情勢を有利に展開させていくために,さまざまな対外戦略を取る必要があった。
その戦略のひとつに,海をへだてて位置する倭との通交があった。さまざまなモノ,人,情報を倭へ提供することで,みずからの側へ引き入れ,その関係を他の社会に誇示することで,情勢の安定に努めようとした。すなわち,百済,新羅,加耶,栄山江流域社会それぞれにとって倭は,戦略的に重視しなければならなず,友好関係の確立が必要な『遠くて近い』社会だったのだ。」
朝鮮側にとって,倭との結びつきが,重要な外交的な意味を持っていた。だからこそ,倭は,
先進文化を受け入れ,自らのものとすることができた,
ということができる。
参考文献;
高田貫太『海の向こうから見た倭国』(講談社現代新書) |
|
物語 |
|
マイケル・ホワイト&デビット・エプストン『物語としての家族』を読む。

否応なく,われわれは,自分人生の舞台に立っている。問題は,自分の物語をどう演ずるか,である。
「はしがき」で,カール・トムは,ホワイトとエプストンの特徴を,
第一に,問題の外在化(externalizing the problem),
第二に,書き言葉を治療目的に多様な方法で使うこと,
と挙げている。「問題の外在化」とは,
「家族のメンバーの人生や人間関係に関する『問題のしみ込んだproblem‐saturated』描写から彼らを引き離すことを援助するための仕掛け」
であり,それは,
「私たちの個人的アイデンティティーは,私たちが自分たち自身について『知っているknow』ことや,私たちが自分たち自身を人間としてどのように描写するかによって構成されます。しかし,私たちが自分たち自身について知っていることは,その大部分が,私たちが組み込まれている文化的実践(描写することや,ラベルを付けること,分類すること,評価すること,隔離すること,それに排除することなど)によって定義されているのです。言葉を使う人間として,事実,私たちは,前提的言語実践と暗黙のうちの社会的文化的共働パターンの目に見えない社会的『コントロール』に服従しているのです。」(カール・トム)
という文脈に埋め込まれている。だから,
「人々が問題から離れることを学ぶと,彼らは,人々や人々の身体を『客体化objectification』あるいは『物化thingrification』する,文化にその起源をもつ他人の実践に挑戦するかもしれない。これらの実践の文脈には,人々は,客体として構成されており,人々は,自分自身や身体,そして他人に対しても,客体として適応するよう励まされている。これは,人々の固定化であり,公式化である。西洋社会においては,この客体化の実践が浸透している。
問題の外在化の実践は,人々や人々の身体,そしてお互いの『脱客体化』に彼らを従事させる対抗実践と見なすことができる。これらの対抗実践は,常に人々に大きく訴えかける。人々は,これを情熱的に受け入れ,自分たちが救われる。」
まさに,訳者(小森康永)の言われる通り,
「外在化とは,ひとつの技法に留まらない。ひとつの認識論といわざるをえない。」
のである。文化的・社会的な文脈に埋め込まれ,おのれのストーリー(ドミナント・ストーリー)に苦しんできた者は,それを突き離すことで,自分自身の地に埋もれていた図(ユニークな結果)を拾い上げていく。
ベイトソンについての,
「ゴルジブスキーの格言である『地図は領土ではない』を参照にして,彼(ベイトソン)は,出来事に対する私たちの理解や私たちの出来事に対する意味は,出来事を受け取る文脈,すなわち,私たちの世界の地図を構成する前提や予測のネットワークによって決定され拘束されているのである,と提案した。彼は,地図のパターンにたとえて,全ての出来事の解釈は,どれくらいその解釈が出来事の知られているパターンに適合するかによって決まると主張し,それを『部分が全体のコードになるpart
for whole ckding』と呼んだ(ベイトソン,1972)。彼は,出来事の解釈は,それを受け取る文脈によって決められると述べただけではなく,パターン化されえない出来事は,生き残りのために選択されないと主張した。つまり,そのような出来事は,私たちにとって事実としては存在しないのである。」
という考え方の紹介は,そのまま,問題の外在化→ユニークな結果→オルタナティブストーリー,へとつながる大きな思想のバックボーになっていることがわかる。なぜなら,
「人々が治療を求めてやってくるほどの問題を経験するのは,彼らが自分たちの経験を『ストーリング』している物語と/または他者によって『ストーリーされて』いる彼らの物語が,充分に彼らの生きられた経験を表していないときであり,そのような状況では,これらのドミナント(優勢な)・ストーリーと矛盾する彼らの生きられた経験の重要な側面が存在するであろう,というものである。」
「人々が治療を求めるような問題を抱えるのは,(a)彼らが自分の経験をストーリングしている物語/また他人によってストーリーされた彼らの経験についての物語が充分に彼らの生きられた経験を表しておらず,(b)そのような状況では,その優勢な物語と矛盾する,人々の生きられた経験の重要で生き生きとした側面が生まれてくるだろう」
ということで,
「人々が治療を求めてやってきたときの容認しうる結果とは,オルタナティブ(代わりの)ストーリーの同定と誕生ということになる」
のである。それには,
「パターン化されえない出来事は,生き残りのために選択されないと主張した。つまり,そのような出来事は,私たちにとって事実としては存在しない」
とされた経験を拾い集めなくてはならない。この,
「ドミナント・ストーリーの外側に汲み残された生きられた経験のこれらの側面のことを『ユニークな結果unique outcome』と呼ぶ」
そして,
「ユニークな結果が見つかれば,これらに関連した新しい意味の上演に従事するよう励ますことができる。ユニークな結果は人生におけるオルタナティブ・ストーリーとなるまで引き続きプロットされる必要がある。私は,このオルタナティブ・ストーリーを『ユニークな説明unique
account』と呼び,ユニークな結果が『意味をなすmake
sense』ようなオルタナティブ・ストーリーを位置づけ,生み出し,復活させるよう人々を励ます…。」
実は,本書の大半は,特徴の第二の,
書き言葉を治療目的に多様な方法で使うこと,
の実践例で占められている。
招待状,
予言の手紙,
対抗紹介状,
特別な機会のための手紙,
独立宣言,
等々,これらはある意味で,
オルタナティブ・ストーリー,
という新たな舞台の上で,自分の人生を意味づけ直す(という仮説)を強化するための手段と見なすことができる。オルタナティブ・ストーリーを生み出す以上に,それを引き続き生きていく方が,遥かに,難しいからだ。ここに,本書の大きな仕掛けがある。
それにしても,フロイトもそうだが,ロジャーズも含め,セラピー理論が,いかに認識の革新をはかろうとする結果の中から生まれてきている,ということを,つくづく思い知らされる。翻って,わが国のセラピーは,技法の真似は出来ても,こうした認識論の革命にまでいたっているのかどうか,ふと疑問を感ずる。いつまでたっても,所詮キャッチアップとうわべの模倣だけなのではないか。
参考文献;
マイケル・ホワイト&デビット・エプストン『物語としての家族』(金剛出版)
|
|
リフレクティング |
|
トム・アンデルセン『リフレクティング・プロセス―会話における会話と会話』を読む。
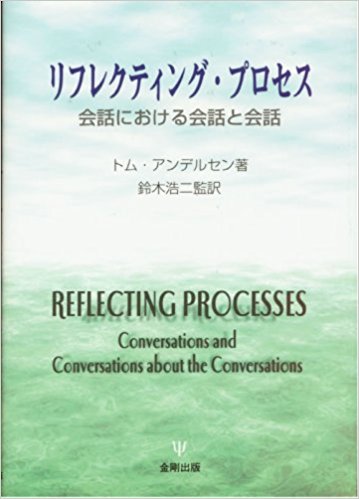
アンデルセンのリフレクティング・チームの特徴は,監訳者(鈴木浩二)が言うように,
「鏡の裏側にいるリフレクティング・チームメンバーが面接の途中,それぞれ熟考した面接場面に対する考えを面接者と家族のいるところで披露し,面接者と家族の思考の転換を促し,新たな物語を構成し,自らの解決方法を共働して産み出すところ」
にあるが,正確には,面接者と家族が,今度は逆に,リフレクティング・チームメンバーが話す場面を,鏡の後ろで聞く側になる。それを交替しつつ,話が深まっていく。
アンデルセンは,それを,
「明かりと音声の切り換えは,我々と家族を驚くほど自由にした。われわれはもはや責任をもつ側にあるだけではなく,2つの側面の片側に(すぎなく)なった。」
という言い方をしている。この考え方について,
「我々はこの言葉を英語ではなくフランス語の意味で考えた。それは我々の理解ではreplicationに近いものであった。フランス語のréflectionはノルウェー語の“refleksjon”と同じ意味をもつ。すなわち聞いたことを理解し,反応はする前に考えることを意味する。明かりと音声の切り換えもまた思考をより自由にしてくれたので,我々は我々が従っているさまざまな概念やルールがどのように我々に影響しているかを問い直すことになった。」
と述べている。それは,
「我々はリフレクティング・チームの代わりにリフレクティング・ポジションという用語を好んで用いている。」
ということにも表れている。家族と面接者,リフレクティング・チームメンバーとか,交互に聞く側に回り,その都度聞きながら考えたことを披歴し合うのには,ある意味で,自分の問題を,
メタ・ポジション,
で聞くという効果があるような気がするが,アンデルセンは,たとえば,
「参加者たちが一つあるいはそれ以上の問題について積極的に発言する立場と,同じ問題に関する他者の発言に耳を傾ける立場を相互に交換する機会を面接の中に作るという…ように,立場を変えることによって,外的(outer)対話と内的(inner)対話の間を行きつ戻りつすることができるようになる。これら二つの異なった種類の対話は,私たちが物事の新しい記述と理解の仕方を求めている時に,同じ事柄について二つの異なる展望を与えてくれ,さらに異なる二つの出発点を備えてくれる。(中略)ある場合にはチームを使い,ある場合には同僚1人だけの協力で,またある場合にはクライエントたち,すなわち家族メンバーだけしかいないところでも同じやり方をすることができるわけである。この最後の場合は,治療者が家族の1人と話している間に,それに聴き入っている他の家族メンバーはリフレクターとなり,のちには一つの“リフレクティング・チーム”となることもあろう。」
と,その効果を説明する。それは,治療者とクライエントとの間には,
「三つの並行する会話―2つの内的対話(inner talk)と1つの外的対話(outer
talk)―が進行していると考える」
からである。同時に,聞く側の時,鏡の外から,見てもいる。
「聴いている人は話されたことすべてに耳を傾けているだけでなく,それがどのように発語されるかを見てもいるわけである。」
からでもある。その意味でも,
メタ・ポジション,
である。いわば,
メタ化,
の具現化,見える化である。
このリフレクティングに意味があるのは,
「私たちが対話を変化のための“方法”として用いているこの世界は,生きている人々と彼らの意味づけから成り立っている世界である。この世界には,彼らが自分とその周りの世界とをどのように理解できるかということと,その世界にどのように関与しうるかという意味づけとが含まれている。人々と,とりわけその意味づけは常に変化しており,その起こりは急速である。意味づけは多様であり,文脈の転換に伴って変更される」
ものだからである。自分の文脈に縛りづけた意味は,メタ化した視点から聞くことで,リフレーミングされる。なぜなら,
「人はそれぞれ,自分が『属している』状況を知覚している(我々はそれを構造化された知覚と呼んでいる)。この知覚はその人の『現実』である。同じ状況にある別の人もまた『現実』を知覚しているが,その『現実』はその人特有の『現実』である。『現実』は知覚する人の『現実』としてのみ存在するのである。同じ『外的』状況は多数の『現実』となる可能性がある。他よりよいといえる『現実』はない。それらは全て等しく『実在』するものである」
し,
「多角的理解は,ひとつの同じ現象,例えばある問題が幾通りにも記述され,理解されることがあることを意味している。人はいずれもある状況に関する自分なりの解釈を創り出すという構成主義的な考えは,行き詰まったシステムに遭遇したときに非常に役に立つものである。…どの解釈も正しいわけでも間違っているわけでもない。我々の課題は,さまざまな人がどのように自分の記述や説明を作り出しているかを理解するために,できる限り多く対話するよう心がけることである。それから,我々は彼らがいまだかつてみたことのない別の記述があるかどうか,まだ考えたこともない別の説明があるかどうかを論じる対話へと導く」
からである。この背景には,グリーシャンが,ヴィトゲンシュタインの,
「我々の言語の限界が我々の世界の限界を設定する」
に基づいて,
「我々の有するあらゆる理解,この世に関する我々のあらゆる記述,我々が社会組織を観察するその方法,問題を理解するための手段,我々が治療を行う際のモデルが我々の言語の使用法と語彙と物語の表現以上の何ものでもない,ということができるのでしょうか?我々の行動が意味を成就するのは,我々の意味体系のなせるわざなのでしょうか?もっと恐ろしいのは,我々が人生において理にかなった行動を自らを他者と協和させ,組織づける複雑な一連の操作であるところの我々人間の営為が,実は我々が相互に形成した叙述が行動へと変形した以上の何ものでもない,という意味が含まれていることです。」
という考え方がある。ぶっちゃけ,
人は持っている言葉によって見える世界が変わる,
とも言う。ならば,同じことを,言い換えてもいいと分かった瞬間,
意味も,
見える世界も,
変るかもしれない。それが,内的対話と外的対話の交替のもたらすものだ。このバックボーンは,ベイトソンの,
差異を作り出す差異(the difference that makes
difference),
である。そこには,
空間的差異(区別),
時間的差異(変化),
いつもと異なる(例外),
の3つがある。文脈の中の,地と図の違い,時間経過が生む違い,いつもから浮きだす違い(例外),それは,文脈に埋もれ,視界が閉ざされている時には,別の見え方ができない。メタ・ポジションに立つ時,視界が変わり,違いが見えてくる。
なお,グリーシャンについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/452599306.html?1502395255
で触れた。
参考文献;
トム・アンデルセン『リフレクティング・プロセス―会話における会話と会話』(金剛出版) |
|
ナラティヴ |
|
ハーレーン・アンダーソン,ハロルド・グーリシャン『協働するナラティヴ』を読む。
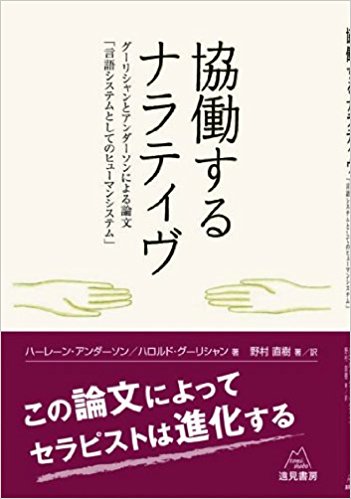
本書は,グーリシャンとアンダーソンによる論文「言語システムとしてのヒューマンシステム」の訳書である。ハーレーン・アンダーソンは,「日本の読者のみなさま」で,
「私が日本に来た最初の頃,あるパネルに招待された時のことです。隣に座った精神科医が私に質問しました。『すぐれたセラピストとしての条件とは何ですか?』と。そのとき私は,『それはマナーのよさ』と答えました。それは彼には生意気に響いたかもしれません。でも,これは彼のまじめな質問に対する私のまじめな答えだったのです。それは今日でも変わりません。創造的な会話と発展性のある関係へと他者をいざなうために最も必要なことは『よいマナー』であることを私はいつも強調しています。」
と書いている。意外ではない。人との関わりの節度というか,自制というか,抑制というものが,当たり前のことだか,不可欠だということだ。それは,人と関わるときの基本と言ってもいい。この言葉がさりげなく出るところに,この著者の人柄が出ている気がする。
冒頭,自分たちの立ち位置を,
「人が関わってできる組織や制度(ヒューマンシステム)を,社会組織(役割や構造)によってできているとする立場から,言語的,コミュニケーション的な標識によってできあがっているとする立場への移行である。治療(セラピー)という場において,私たちが相手にするのは,問題について語る人々によって定義される言語システムという単位(ユニット)であって,社会組織として一般に認識されたもの(例えば家族とか裁判所)という社会的単位ではない。私たちはそのようなわけからセラピーにおけるシステムを,『問題によって編成され(集められ),問題を解決するより解消していくシステム』(a
problem-organizing,problem-solving system)と呼ぶことにした。」
と宣言する。そして,
「この新たな方向に沿っていくと(あるいは会話のしかたをすると),人がかかわってできる(いわゆる機械ではない)システム,つまりヒューマンシステムは,意味という領域においてのみ,また相互に変化しあう言語リアリティとしてのみ,存在する。」
「私たちが言語と言った場合,それは言語によって仲介された文脈と関連した意味のことであって,言葉の交換とコミュニケーション的行為によって生み出された意味のことである。このような一定の社会的文脈の中で生成された意味は(それは理解と言ってもいいのだが)対話と会話というダイナミックな社交のプロセスをとおして進化していく。(中略)言葉の中で私たちは他者との触れ合いに意味をもち,言葉をとおして現実を分かち合う。『ことばの中にいる』,それはたんなる言語行為ではなく,ダイナミックな社会活動なのだ。」
と。この中心にあるのは,
「現実とは協働で制作されるものだ」
「言語でもって,言語をとおして,この世界を産出している」
「言葉は世界を映し出しているのではなく,言葉はそれぞれが知るべき世界を創り出している」
という考え方(社会構成主義)である。それは,
Here and now
いま・ここで取る「待ったなしの姿勢」(訳者=野村直樹氏)である。そこでは,セラピーとは,
「対話コミュニケーションの場づくりである。会話の空間を広げてゆくプロセスである。問題によって召集され,問題を解消するシステムのメンバーたちは,そのコミュニケーション空間において,意味と理解を新たにする作業に取り組むが,それは言い換えれば,『未だ語られていないこと』を探し当てていくことに他ならない。その意味では,セラピーは,これまでと違う会話をし,新しい言葉遣いを覚え,現実を違う角度から眺めてみるという,普段の私たちの行為とさほど変わらない。新たな経験に即して異なる意味をお互いが獲得していくことは,私たち人間としての資質にかなったことだからである。システムは私たちが取り組む対象ではあるが,それは言葉の中に存在するということをしっかり覚えておこう。」
と言うものである。「未だ語られていないこと」とは,通常,
リソース,
という言い方をする。これについて,マイケル・ホワイトは,
「ぼくらは個人が自己というものをもっているとか,リソースをうちにひめているとは考えない。自分もリソースもむしろ今ここで創り出していくもので,この場で発見し育て上げていくものだから」
という。それはこういうことだ。
「意味は一つだけ,なんてことはないということだ。すべての表現が,まだ表現されていない部分をもち,新たな解釈の可能性をもち,明確にされ言葉にされることを待っている。…すべてのコミュニケーション行為が無限の解釈と意味の余地を残しているということなのだ。だから対話においては,テーマもその内容も,意味をたえず変えながら進化していく。(中略)私たちがお互いを深く理解するというのは,相手を個人(という抽象物)として理解するのではない―表現されたものの総体として理解するのである。この過程に対話が変化を促していくからくりがある。
そこで私たちは,この『語られずにある』部分を言葉に直し,その言葉を拡げていくことがセラピーだと考える。そこでは,対話を通して新しいテーマが現れ,新しい物語が展開されるが,そうした新しい語りはその人の“歴史”をいくぶんでも書き換えることになる。セラピーはクライエントの物語の中の『未だ語られていない』無限大の資源に期待をかけるのだ。そこで語られた新しい物語を組み入れることで,参与者たちはこれまでと異なる現実感を手にし,新しく人間関係を築いていく。これらは『表現されずにあった領域』に埋蔵された資源,リソースからでてきたものではあるが,その進展を促すためには,どうしてもコミュニケーションすること,対話すること,言葉にすることが必要となる。」
つまり,
「セラピーにおける変化とは,対話や会話から生じた意味の変化」
なのであり,だからこそ,
「問題は言葉と会話を通過することにより,新たな意味,解釈,理解を獲得していく。治療的会話とは解決を見つけるための会話ではないのだ。解決は見つかるのではない―問題が消失するのである。」
そして大事なことは,
「この過程を経てセラピストが変わるのである。私たちの治療倫理のエッセンスは,セラピスト自身が変化するリスクを承知でそれを覚悟するその姿勢にある。」
という点だ。セラピストもまた,対話の当事者であり,こうした,
インターサブジェクティヴな(双方向に思いが交差してできる)
を通して,セラピーの基本は,
「行き交う理解,互いへの敬意,耳を澄まし相手の言葉を聴こうとする意思である。病理から離れて,語られたことの『真正さ』へと重心を移すことができる偏見のなさと自由さである。これが治療的会話のエッセンスであろう。自分が誰でまた将来どのような人になっていくかは,対話がその基点にあるのだ。(中略)セラピストの専門性は何に根ざしているかと言えば,対話や会話への参加にあえて賭けていくという“能力”にである。また自分も変化するリスクを負うということに根ざしているのである。」
ということになる「マナー」という言葉が生きてくる。
ちなみに,こうした治療的会話の特徴を,次のように列挙している。
①セラピストは,検討する問題の範囲をクライエントが言った問題の範囲内にとどめる。
②セラピストは,多様な考え方や相矛盾する考え方を同時に受け入れる。
③非協力的ではなく協力的な言葉を選択する。
④セラピストはクライエントの言葉を学習する。
⑤セラピストは敬意をもって聴き,あまり急いで理解してしまわない(すぐさま理解してしまうことがたとえ可能であったとしても)。
⑥セラピストは質問を発し,クライエントはそれに応えるが,重要なのはクライエントの応えは,セラピストからさらに新たな質問を投げかけられるのを待っているということだ。
⑦セラピストには,会話のための環境をととのえるという責任がある。
⑧セラピストは,自分自身と対話しそれを維持していく。
そこで,「当面の課題や検討事項に対して新しい見方を可能にする方向に…いつも目をむける」
開いていく会話,
をしていくことになる。訳者は,
無知の姿勢(not-knowing)
と
会話への信頼(trust)
を,本書のキーワードとされた。僕は,
「未だ語られていないこと」を探し当てていくこと,
の方に着目したい。
参考文献;
ハーレーン・アンダーソン,ハロルド・グーリシャン『協働するナラティヴ』(遠見書房) |
|
瓦版 |
|
森田健司『江戸の瓦版−庶民を熱狂させたメディアの正体』を読む。

著者は,「はじめに」で,
「現在,『瓦版という情報媒体』は存在しない。しかし面白いことに,現代の日本に生きる人々の多くは,『瓦版という言葉』を知っている。新聞の『号外』に近い意味で,今も頻繁に使われているからである。…ところが,瓦版の実像が知られないまま,虚像のみが複製され,増幅されていっている。」
で,本書は,瓦版の実像を知ることができるように,
第一に,史料に残る瓦版に関する資料,
第二に,実際に残されている瓦版,
から,
瓦版とは何か,
とともに,
残された瓦版を読む,
という二部構成で,瓦版像を知ろうとするものである。
瓦版を辞書で引くと,例えば『広辞苑』には,
「粘土に文字・絵画などを彫刻して瓦のように焼いたものを原版として一枚摺りにした粗末な印刷物。江戸時代,事件の急報に用いた。実際は木版のものが多い。」
とあるが,著者は,
「粘土版によって摺られたと思わしき瓦版は,一枚も現存していない。」
という。しかし,黙阿弥の『歳市廓討人』で,瓦版を,
「読売―そりゃあいつもの敵討でござります。瓦版とは違います。今日版行が改まって知行高から姓名まで委しく記してござりますから,十六文ぢゃあお安うごさせります」
という台詞で,
「まるで瓦の原料である粘土で原版を作ったように劣悪な品質の摺物というニュアンス」で,言わせている。あくまでたとえだが,そこで,著者は,瓦版を,
「江戸時代に始まった印刷物体。天災の速報や娯楽性の高い情報を,一枚から数枚の紙に木版で摺って作られた。市中で読みながら売られ,明治に入ってからはもしばらくは,新聞と並行して存在した。」
と,瓦版の定義を提示している。
瓦版は,
読売,
一枚摺り,
絵双紙(草紙),
とも呼ばれたが,基本,
非合法な存在,
であった。印刷物を販売する場合,版元を明示することを,享保七年(1722)に義務付けた。つまり,
「内容を事前に届け出て許可がない限り,版行できなかった」
にもかかわらず,
「瓦版は,従来同様,版元も明記もせず,許可も取らず,版行が続けられた。」
しかし,
「瓦版は,法的には禁止されていた。これは間違いない。だが,幕府は本気ではなかった。役人たちも,全力で彼らを追ったりはしなかった。逃げれば多くの場合,それで黙認されていた。」
という。あくまで,
黙認,
である。だから,読売(瓦版の売り子)は,頬被り,編笠など,
「ほとんどは,顔を隠して活動していた」
という。しかし,
「読売は,ただ瓦版を抱えて立ち尽くしていたわけではない。彼らは自慢のダミ声で瓦版の一節を調子よく語り,客寄せをしていた。三味線の伴奏がつく場合もあり,よみうりは一種の芸人だったのである。瓦版は紙でありつつ,肉声を伴ったメディアであった。このあたりに,江戸の庶民を夢中にさせた秘密がありそうである。」
と。
それにしても,瓦版の隆盛の背景には,驚異的な識字率がある。だから,
「当時の日本において,文字の書かれた出版物が,『庶民の娯楽を提供するものだった』」
ということがありうる。
「日本人の識字率は,…『世界の他のどこの国』より高かった。武士階級はもちろん,それ以外の庶民もほとんどが文字を読み,書くことができたのである。」
さらに,
「江戸時代の彫師の技術は世界的にも注目されるほどのレベル」
で,江戸時代,版木彫師は,
「一時間に二十二字〜二十三字を彫刻できた」
ので,瓦版制作には,一日程度といわれる。この技術的背景もまた,瓦版から見えてくる。さらに,幕末,仮名垣魯文は,安政江戸地震に際し,その翌日には,
「翌早朝一人の書肆来たり何ぞ地震の趣向にて一枚摺りの原稿を書いて貰ひたしと頼みければ魯文は露店にて立ちながら筆を取りて鯰の老といへる趣向を附け折よく来合わせたる画師狂斎に魯文下画の儘を描かせて売出せしに此の錦絵大評判となりて売れること数千枚,他の書肆よりも続いて種々の注文あり,魯文は五六日の間地震当込み錦絵の草稿書くこと二三十枚に及び皆売口よくして鯰の為めには思はぬ潤ひを得たりと云ふ」
とあり,この場合は鯰絵だが,瓦版の作られる速効性が伺える逸話である。
「瓦版は紙だけであっても十分鑑賞に耐え得るものが多い。それは,瓦版があくまで『商品』だったからだろう。瓦版屋たちは,日々『どうすれば売れるか』をたんきゅうしていたに違いない。そこから,様々な創意工夫が生まれたのである。デザインや絵図,摺り色の数まで,瓦版は時代と共に進化している。幕末になると瓦版は長大化するが,それね同業他社との競争に起因するものだろう。」
まるで今日の週刊誌,タブロイド紙,写真週刊誌を思わせる。かつての木版刷に比べて,圧倒的な技術革新を経ているのに,内容だけではなく,表現スてタイルに,どれだけの創意工夫があるのか,と気になる。サラリーマン化した大新聞に,もはやジャーナリズムも瓦版屋根性もないのなら,せめて他の媒体に頑張ってもらわねば,江戸時代の読売屋に嗤われるのではないか。
参考文献;
森田健司『江戸の瓦版‾庶民を熱狂させたメディアの正体』(歴史新書y)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%93%A6%E7%89%88 |
|
ナラティヴ・セラピー |
|
シェリル・ワイト編『ナラティヴ・セラピーの実践』を読む。
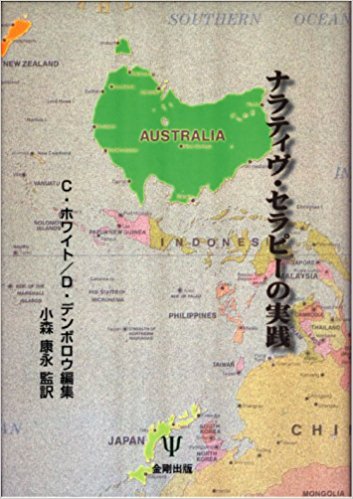
本書のねらいについて,「序文」で,
「私たちは,トレーニングやワークショップ,それにカンファレンスに参加した人たちからいつも必ず,ナラティヴな考え方やナラティヴな仕事の仕方についての入門書として何がいいのだろうかと尋ねられてきた。これでようやく,その質問に答えることができるわけだ。つまり,この本を読めばいいのだから!」
とあり,本書は,マイケル・ホワイトの主宰するダルウィッチ・センターの季刊誌『Dulwich
Centre Newsletter』に発表された,
「実践に基づいた論文」
が集められている。そして,
「ナラティヴ・セラピーをもっと理解したいと願う人々や仕事の仕方を探求し実験していくさまざまな方法について知りたいと願う人々にとって,この本は読みやすいながらも完全なイントロダクションとなるだろう。」
とある。しかし,正直,ナラティヴ・セラピー,あるいは,ナラティヴ・アプローチについてある程度承知したうえで読まないと,ここでの実践の位置づけがきちんとできないのではないか,というのが,読んだ感想である。実践報告ということは,現実のナラティヴ・アプローチによって,何をしているか,が中心なので,なぜ,ナラティヴは,こういう活動をするのかは,きちんと伝わりにくい,と感じた。
本書は,活動を,
個人との仕事,
グループとの仕事,
コミュニティとの仕事,
とにわけ,その他共同研究,マイケル・ホワイトの覚書などが付加されて,構成されている。その中身は,
幻聴や幻から人生を取り戻していく様を描く「パワー・トゥ・アワ・ジャーニー」の取り組み,
性的虐待やアノレキシア・ネルボーザ(摂食障害)の影響,
アフリカのマラウィ村での仕事,
自己虐待を繰り返している若者との対話,
糖尿病や悲しみについてのアボリジニとの仕事,
亡くなった人との再会の誘い,
等々。ここにあるのは,
「カウンセラーの役割というものを,…(相談者自身と)その人生についての問題のしみ込んだドミナント・ストーリーから離してやり,オルタナティヴ・ストーリーを共著できるよう援助する存在だと考えている」
という,ホワイトの言葉に象徴されるナラティヴの思想を実践しているということだ。
だから,ときに,
「セラピー文化がドミナントな文化をどの程度再生産しているかに気づくことで,これと完全には共犯しない治療的態度を求める私たちは援助される。」
として,たとえば,
a 特権化された知識とドミナントな文化に関わる力の実践が,諸個人の人生と人間関係にどのような現実的影響をもつのか探求するよう諸個人を援助すること
b そのようなドミナントな知識と力の実践の煽動に対する抵抗を賞讃し採用するよう諸個人を励ますこと
c オルタナティヴな知識とこの抵抗に関連する意味の枠組みを特権化すること
d セラピーの実践において現実に虐待したり,虐待の可能性のある力を露呈するようなアカウンタビリティの構造を確立すること
e サイコセラピー文化における知識のヒエラルキーを転覆させること
f 社会におけるその人の位置づけ(ジェンダー,人種,社会階級,エスニシティー,性的嗜好等々)を認め,その位置づけが暗示するさまざまなことがらを認めること
g その人自身の人生を形作る上での治療的相互作用の貢献を認めること
h セラピーに関する経験について,そして,私たちの動機やふるまいについて家族がどのように解釈するのかという点について,たえず家族をインタヴューすること
i 治療的文脈を完全に平等な文脈にすることは不可能であるという事実を認め,尊重すること。ただし,より平等な文脈となるよう努力すること
と,ホワイトが,したためた「力とセラピーについての覚え書き」に,その姿勢は象徴的に示されている。だから,
「引っかき傷が自己虐待になるとき」
という章で,自傷行為をする十代の若者たちとの対話において,こう書いている。
「私たちは,この過程が共同研究よりもむしろセラピーめいたものにならないよう全体的に気を配る必要があることを学んだ。前もって用意した質問を後から見直してみたら実際にいくつかの《セラピー》的な質問があったことに気づいたからである。しかしグループをしているあいだに,私たちはそれらの質問を自動的に《共同研究》的なものに変えていた。たとえば,《自己虐待をしている時,あなたたちに何がいるのですか?≫という質問を用意していたが,実際には《私たちが誰かのセラピーを担当しているとしましょう。その人たちが自己虐待を始めたとしたら,一体彼らに何がおこっている可能性があるのかしら?》と尋ねていたのである。それでもついセラピー・モードに戻ってしまったことが,確かに一度あった。私たちと全く同じ意見をスーザンがはっきり(自傷行為が友達ではなく敵)と発言しているのがわかったので,私たちは興奮して我を忘れ,つい彼女にもっと意見を言わせようとして《あなたはいつから(自己虐待が)友達ではなく,敵だと思うようになったのか?》というような質問をしてしまったのである。この個人的な質問によって即座に彼女の気持ちが萎えてしまったのは明らかで,私たちが間違いを犯したのは,はっきりしていた。」
こうした一連の姿勢と方向の中で,
「問題の外在化は,問題が人々の中にあるとか人間関係の中にあると考えることを拒否することが含まれている。人が問題ではなく,問題が問題なのである。『外在化する会話』とは,人々が自分たちの人生に影響している問題から自分たち自身を分離して考えることができる空間を創造する会話である。ある問題が,その人のアイデンティティないし,ある重要な人間関係のアイデンティティから分離されて見られるようになると,その人は,新しい行為に出る立場くる。彼/彼女は,問題に抗議,ないし抵抗する,そして/あるいは,問題との関係に何らかの方法でもう一度折り合いをつけ直す機会を得る。」
というホワイトの言葉は生きてくる。
参考文献;
シェリル・ワイト編『ナラティヴ・セラピーの実践』(金剛出版) |
|
面接プロセス |
|
H・S・サリヴァン『精神医学的面接』を読む。

本書は,「精神医学的面接」のタイトルで行われた連続講義をもとにしている遺著である。そのせいか読みやすいが,それ以上に,
「実践家サリヴァンの面接に臨んでの具体的な処方が随所に顔を出している。…せっぱつまった時にはっと思い出すと有用な助言が多い。やろうとしてできない建て前的なことは一つも書かれていないと言ってよい。」
と訳者・中井久夫氏が指摘している通り,実に実践的である。例えば,同氏は,
「面接の場の基礎を『専門家(エクスパート)=依頼者(クライエント)関係』と定義し,場の目的を『依頼者の対人的相互作用の個人的パターンの明確化』とする。はっとするのは,のっけに精神医学的面接におけるコミュニケーションは何よりも音声的であって,言語的コミュニケーションではないという箇所であろう。サリヴァンは,本書では言っていないが,患者に,『きみのレーニングの声(建て前の声か)とデザイアの声(本音の声)とがあるのを,聞き分けるようにしなさい。今はどっちの声かな』と言っていたそうである。前者はうすっぺらいフラットな声,後者は倍音の多いディープな声である。ここではそれにかぎらず,音声の変化が発語の内容より多くを語る」
と指摘している。
サリヴァンは,本書の意図を,
「私の意図は一つである。ある人とある人が出会って真剣に議論をする場面を想定し,そこに望ましい最終目標に到達する確率が最大となる経路(コース)を考えて,その際に踏むべき段階を明確な文言をもって定式化したいということである。これから述べる事項は,患者を相手にしても有効である。患者とは,自分の特殊なところや奇妙なところ,あるいは他の人間におかしい扱いをされるためにわれわれに助けを求めてくる人のことである。求職者にも役に立つだろう。雇い主から,『どうしてうまく仕事ができないのか調べてもらってこい』といわれてやってきた人のためにもなるだろう。ある基準を満たす程度によく計算された面接であれば,,精神科医が用いるのと同じ技法を用いてよいのである。それは精神科医が,患者が求める専門的な内容(の問題)になんとか応える道を発見しようと苦心しているうちに使うようになった技法である。」
とし,「話の中心を医学の領域に限るというつもりは全然ない」と,強調する。そして,こう始まる。
「『精神医学という分野は対人関係の学である』という定義が下され,『精神医学とは科学的方法を適用する根拠を有する領域である』と見なされるようになって以来のことであるが,われわれは『精神医学のデータは関与的観察をとおしてのみ獲得できるものである』という結論に達した。」
そして,上記の「コミュニケーションの音声的性質」について,こう触れている。
「精神医学的面接についての私の定義はまず,『精神医学的面接とはすぐれて音声的(ヴォーカル)なコミュニケーションの場である』と述べる。『もっぱら言語的(ヴァーバル)なコミュニケーションの場だ』と述べていないのに注目してほしい。(中略)イントネーション,話す速さ,あることばにくるとつかえることなどには話し手(の意図)を裏切って,(そこのところの)秘密を明かすという面があるだろう? これに非常に注意していると得るところがあるはずだ。こういう因子は,…すぐわかる。話す単語の意味だけに注意していてもしかたがない。それよりも,今言ったことのほうが,サインとしては,つまり意味のリトマス試験紙としては,重要だ。」
そして,こう付け加える。
「実は,人間が心底からほんとうに言いたいことの手がかりはたいてい耳経由で届くものだ。声の『音調変化』(tonal
variation)ということばがあるが,このことばの私の用法はとても広い。一切合財前部を含めていう。つまり音声言語(スピーチ,発話)を構成するにはいろいろ複雑なものがあって,それがまたグループをなしているが,そういうグループの全部を洩れなくひっくるめて,その変化のことをいうのだ。これは実に頼りがいのあるもので,コミュニケーションの場の変化の確実な手がかりはこれだ。」
そして,こういう例を挙げる。
「ある人が自分は電気技師で,電気技術者組合員だという話をしはじめるとしよう。話はあるところまで円滑に進む。ところが,それは,あることを話そうとして声が喉を出かかるまでなんだ。仕事に関することだが,組合にはっきりと不義理を働いた箇所さ。その箇所にさしかかると男の声の響きが変わる。まだ『組合員の電気技師はかくあるべし』とか『かくかくすべきだ』とかいうような話をつづけるかもしれないが,その話の音(サウンド)はすっかり別物になっているわけだ。
精神医学的面接ですこしずつ積み重ねてきた経験を生かす手始めは,ここだ。つまり,音調の変化が起こりだした時点で,そうっと(マイルドに)関心があることを示してみせる。面接者はこんなことをいってみる。『あ,うん,えーと,きっかり2.5パーセント支払うのだね。収入の中からだね。傷病基金に。あたりまえの組合員ならまず忘れぬことだね』。こう言われると相手はどう答えるだろう? 音調は,その直前とまた変わった響きになる。『もちろん! 組合員たることの重要資格ですからな!』面接者が,この対人のばにおける感覚に自信がもてれば,こういってよいかもしれない。『なるほど,あなたがけっして反則を犯したことのない部分ですな!』こうなると相手の音調はぐっと変わる。たぶん怒りをかろうじて我慢しながら言うだろう。『むろな,してなんかいませんぞ』。面接者が事態の真相に十二分の確信がもてれば,『なるほど,むろん,君はわかってくれていると思うが,ぼくは君を疑っちゃいないよ。しかし,その箇所に触れた時の君のことばの調子は,ありゃあ変だったぜ。あの話が君の心をいためつけているのではないかな。どうもそう考えないではおれないのでね』。こう聞かされた男は,さらにまたちがった音調を出してこんな話をするかもしれない。『はあー,まあー,じつは―,正式に技師になったばかりの頃,ほんのちょっとポケットに入れてしまって…,ごくわずかなパーセントですが,…そいつがそれから私の良心の上に乗っかってしまって,その重いこと,ああー,重くて…』。」
この関わり方は,別のところで,
「患者の話を聴く際にはすべて『批判意識を伴う関心』(クリティカル・インタレスト)持つべきだと言いたいだけである。(中略)いつも心に『果たしてそうか』という単純な問い(『私はわかっていないことを即座に言わんとしているのではないか,私の受け取ったままで相手の言っていることがわかったとしてよいのか』)―を持ちつづけてほしい。」
という。別のところで,
「精神科医の持てるものは,せいぜいのところいくつかの『どれかわからないがその中のどれかであるだろうという確率的可能性』(alternative
probabilities)を持つ仮説」
といっているのとも符合する。この場合,あくまで,初対面の時の第一印象のことを指しているのだが,姿勢としては同じである。そして,
「最低二つの可能性を仮説すること」
という。
「一つしか仮説を持っていない人はいわば信仰を実践しているのである。(中略)そういう連中の場合,一つだけの仮説は結局“確実性”なのだ。しかし,面接者の心中にあれかもしれないこれかもしれないという複数の可能性が存在しているならば,面接者は,さらに深く探求するように誘われていき,その結果,可能性の確率が増大するものや減少するものがあるようになる。面接者はこの単純なやり方で充分な確実性をめざして進むのがよい。」
こうしたサリヴァンは,面接中のメモについては否定的である。それは,精神医学的面接者の仕事と両立しない,という。精神医学的面接者の仕事とは,
第一に,「患者の言っていることにもとづいていわんとしていることが何かを考える人」であり,
第二に,「患者へとコミュニケートしたいことをいちばんうまく言い表す文句を自分で考えつく人」であり,
第三に,「目下コミュニケートしつつあること,あるいは話し合いつつあることの一般的パターンを観察している人」であり,
このこと以上に値打ちのあるノートをとることは,「たいていの人間の能力を超えている」とみる。音調を重視する以上,当然,逐語録には,それは反映されないのだから,今日のように,音も映像も記録できる時代とは違うので,サリヴァンの言わんとすることは重要だ。そのとき,その場,その瞬間に,目の前で起きていることに注目しなければ,面接という場は,創造できまい。
本書は,サリヴァンの面接過程についての,
第1段階 正式接遇(the formal inception)段階
第2段階 偵察段階(the reconnaissaance)段階
第3段階 詳細問診(the detailed inquiry)段階
第4段階 終結(the termination)段階
の仮説に基づいて,語られていく。その場は,両者で創造される場(状況 situation),と見なされる。だから,
「医師患者間の相互作用は,必ず二人の人間のする営みであるから,患者の言動は『この精神科医はどういう人か』という,患者の能力と手持ちの情報を尽くして推測したものに合わせたものになっている。だから,精神科医の感想や質問や合いの手や『あてこすり』の効果は,精神科医が自分にたいする患者の態度を意識し,患者の出自や経験を知り,患者がどういう種類の人かを知っている程度に応じて変わる。精神科医は,全力を尽くして,自分と相手との間で進行中の過程―自分と相手を巻き込んでいる過程というべきか―に注意を集中しなさい。」
だから,
「精神科医が,患者はほんとうは何を語っているのかを知ろうと努めると,結局患者も『自分が考えていること,伝達しようとしていること,隠蔽しようとしていることは何か』ということが少しずつはっきりしてくるようになり,人生の把握も少しはしっかりしてくる。自分の心の中で起こっていることを非常によく把握している人間で重症を抱えている人間などはいない。」
と。どうやら,常に面接一般についてのことがサリヴァンの頭にはあるらしく,面接をこう整理してみせる。
「『面接は一つの過程である』あるいは『過程のシステム』であるということではなかろうか。この過程(プロセス)ということばには変化という含意がある。(中略)一つは被面接者の態度の変化である。同じく対人の場で起こる別の変化(中略)は,面接の場において『面接者の態度の変化が被面接者によって照らし返されること』である。すなわち面接者は自問しなければならない―,『私の態度の何がいま被面接者から照らし返されているのか』『私の態度をどういうものとして経験しているように思えるか』『私が今していることを何と考えているのだろうか』『私が彼にどういう感じを向けていると彼は思っているのだろうか』である。こういうふうに面接者が考え始めると,面接というものを構成している複雑な諸過程を解くのに有用なカギがはじめてたくさん現れるようになる。面接者の熟練という物の一部は『面接者の態度についての被面接者の感じは確率的にどれが正しいか』ということをある程度自動的に観察できるようになることである。」
実践の場で培われてきたノウハウは,実は,細部にあることをうかがわせる記述は,尽きないが,
「精神医学的面接をやっている精神科医でもっとも頼りになる態度の人間は,どんな人間だと思う? 単純な話だ。『自分の日々の糧を自分で稼がなければならない』ことがわかっていて,そのために働いている人間だ。」
と言ってのけるサリヴァンという人に達人の域を感じさせる。中井久夫氏も挙げているが,神田橋條治氏の著作(「コツ」シリーズ)をつい思い浮かべてしまう。
参考文献;
H・S・サリヴァン『精神医学的面接』(みすず書房) |
|
城攻め |
|
渡邊大門編『地理と地形で読み解く 戦国の城攻め』を読む。
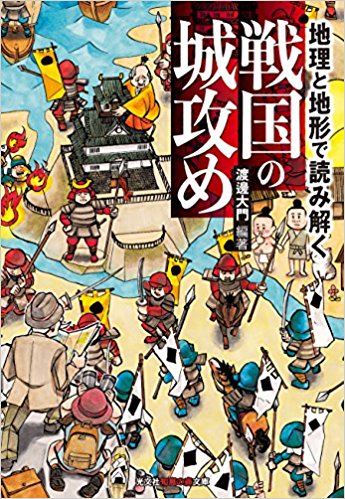
同じ城攻めをテーマにした伊東潤『城を攻める 城を守る』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/397675168.html
で触れたことがある。今回は,戦国期(織豊期まで)の,籠城した城の攻防に焦点を当てて,25例載せている。そのために,それぞれの攻防両者の事情,経緯,背景にはあまり紙数を避けず,奥行がないのは,やむを得まい。
「はじめに」で,
「城攻めの成否を握るのが地理と地形である。いうまでもないが,城は場所を十分に考えて築城されている。(中略)必要である。イントであった。周囲に構築された,砦などとのネットワークも攻守に必要である。それゆえ,難攻不落の名城は多い。
いわば,戦国時代の城郭とは,当時の人々の英知の結晶であるゆえ,それを攻め落とすことは並大抵ではなかった。本書は,単に城攻めの経過をたどるだけではなく,…城郭の築かれた場所(周辺地域も含めて)の地理的な条件や地形に留意して,検討を行ったものである。」
と述べ,城の特徴に合わせた攻め手の工夫が見物である。本書は,中央に偏り,
織田方武将の城攻めが,
高天神城,
観音寺城,
魚津城,
八上城,
有岡城,
信貴山城,
小谷城,
が,次いで,秀吉の城攻めが,
鳥取城,
備中高松城,
三木城,
紀伊太田城,
長水城,
忍城,
と多い。あとは,関ヶ原と関連した,
長谷堂城,
上田城,
大津城,
安濃津城,
岐阜城,
が続く。ほぼ日本の中央を制した織田・豊臣方の城攻めが多いのは,やむを得ないかもしれないが,それにしては,小田原城攻めがないし,数少ない,籠城からの起死回生の勝ちをえた佐嘉城攻めが抜けている。完全孤立した竜造寺隆信五千を包囲した大友宗麟六万が,竜造寺側の夜討ちという奇策に大敗するに至る戦いは,籠城戦には珍しい逆転勝ちなのだが。
城攻めは,守る側,つまり籠城から見ると,後詰の援軍がなければ,ほとんど勝ち目はない。大体,籠城側が寡兵,攻め手が大軍なのだから追いつめられての籠城と決まっている。松平容保の会津城,豊臣秀頼の大阪城,荒木村重の有岡城,浅井長政の小谷城,石田三成に水攻めされた忍城,毛利に追い詰められた尼子義久の月山富田城,信長を再度裏切り包囲された松永久秀の信貴山城,さらに島原一揆の原城も加えてもよい。そうならざるを得ない仕儀にて,孤城の籠城になる。追い詰められてか,やむを得ずかはともかく,籠城の瞬間,自らの手足を縛るに等しい。孤軍では勝負は決している。その前に,切所はある。寡兵での籠城を嫌った信長が,倍する今川義元の本陣を突いたのは,その意味で,まだ勝負を捨てていないという意味になる。そこに,将の器量の差が出る。
城攻めには,追い詰められた相手を更に追いつめるために,
城内への(内応を働きかける)調略,
水の手を断つ,
糧道を断つ,
坑道を掘る,
等々が常套手段だが,包囲した城の周囲に,
付城,
を構築して,包囲を固めていく。別所長治の三木城,荒木村重の有岡城なども,そうやって攻囲し,糧道を断った。糧道を断つために,糧食を高値で買い取って兵粮のたくわえを得にくくすることで,攻囲の効果を挙げ,結果として,「餓え殺し」といわれる鳥取城攻めは,三木城とともに,秀吉の得意の戦法である。秀吉の戦法で有名なのは,備中高松城,紀伊太田城,忍城の水攻めだろう。地形を利用し,川を堰きとめて城を水没させる。
しかし,多くの城は,境目(敵味方の境界)で,両軍のせめぎあいの中で,攻囲される。たとえば,高天神城が,徳川家康に包囲されたとき,勝頼は,後詰をせず,結果として,勝頼の威信は地に落ちた。逆に,柴田勝家に包囲された魚津城を,後背から織田勢に迫られて,上杉景勝は,後詰したくてもできず,結果として,魚津城兵二千は全滅するに至る。
他の戦線との兼ね合いで,籠城し,結果として開城した,京極高次は,籠城の間,西軍の立花宗茂らの一万五千を釘づけにすることで,主戦場の関ヶ原合戦から引き離し,結局開城した時点では,関ヶ原は開戦しており,これが東軍勝利に貢献した,という籠城戦もある。城の攻防という局地戦のみを観ていると,大局としての戦局を見失う,という例かもしれない。この一万五千が,関ヶ原に到着していれば,関ヶ原の勝敗の行方は,また変わったかもしれない。
徳川秀忠を足止めし,翻弄した真田昌幸の上田城籠城戦も,関ヶ原の戦局を直接左右した訳ではないが,徳川本隊である秀忠軍が合戦に間に合わないという大恥をかかせたのも,大津城とは立場が逆ながら,籠城が,他の戦線と連携していればこそ効果があるいるということを示す例と言えるかもしれない。
魚津城も,そうかもしれないが,籠城自体に,城兵に意味があるとすると,名を残す,という,一点かもしれない。景勝の救援は当てにできず,糧道も尽き,守る上杉方三千八百,攻める柴田勝家二万数千,劣勢の中,
「一人として寝返りなどの脱落者がいなかった」
という。
「籠城戦に付き物ともいえる調略による裏切りがなかったばかりか,『滅亡』を覚悟で戦い続けた戦いというのは,極めて珍しいケース」
という。最終的には,三月から六月三日まで持ちこたえ,残った二千余人が全員討たれた。しかし皮肉なことに,この前日織田信長は,本能寺で横死しているのである。
たぶん,こうした攻城戦のハイライトは,二十万対十万の大阪冬の陣の真田丸だろう。孤立した難攻不落の大阪城とはいえ,籠城の先に光明があるとは言えない。まさに局地戦中の局地戦である。その中で,ただおのれの才覚ひとつで,時間を延ばすだけの闘いに過ぎない。しかし,その局地だからこその極致,前田勢,井伊勢,松平勢を翻弄した真田丸での闘いは目立つ。しかし,それはあくまで,局地戦に過ぎない。
結局攻城も,他の戦線と連携していてこそ,意味がある。結果は裏目に出たが,武田勝頼は,長篠城を攻囲しつつ,織田・徳川連合軍を誘い出した。これは,信玄が二俣城を落とさず,家康を三方ヶ原におびき出したのと同様の,武田流の戦法だともいわれる。長篠城を囮にして信長と家康をおびき出し,「無二の一戦」に及ぼうとした,という。結果は,設楽ヶ原で惨敗することになるが,これは意味のある城攻めだ。しかし,数年後,今度は逆に,武田軍が籠城する高天神城が徳川軍に包囲されたとき,後詰をせず,落城させた。この落城は,勝頼の威信を失墜させる効果があった。
参考文献;
渡邊大門編『地理と地形で読み解く 戦国の城攻め』(光文社知恵の森文庫)
伊東潤『城を攻める 城を守る』(講談社現代新書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E4%B8%B8%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84 |
|
裏切り |
|
金子拓『織田信長−不器用すぎた天下人』を読む。
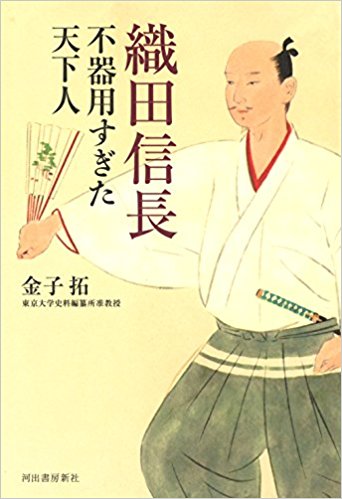
「はじめに」で,下克上の時代,この時代を代表する信長も,
「彼の一生が,家臣・惟任(明智)光秀の謀叛(本能寺の変)によって,劇的なかたちで幕を閉じるということを考えたとき,やはり信長は,この時代の風潮を体現していると考えてもゅ禰されるのではあるまいか。」
と書く。だから,信長だけが特異だったという訳ではない。斉藤道三は,息子義龍に背かれ,武田信玄は嫡男義信に背かれている。
「あとがき」で,キーワードを,
裏切られ信長,
だと書いていた。取り上げているのは,
浅井長政,
武田信玄,
上杉謙信,
毛利輝元,
松永久秀,
荒木村重,
明智光秀,
である。
松永久秀,荒木村重,明智光秀,百歩譲って,義理の弟になる,浅井長政,までは,「裏切り」という言葉が妥当かもしれないが,武田信玄,上杉謙信,毛利輝元は,あくまで外交上,誼を通じたにすぎず,外交上の友好関係がくずれたのをもって,「裏切り」とするのはどうであろうか。
また取り上げた人物の中に,弟・信勝が入っていないのはなぜだろう。信勝は,信長が家督相続後,最初の謀叛,弟信勝(信行)が林秀貞(通勝)・林通具・柴田勝家に擁立されて,挙兵。敗れた後許されても,なお信勝は,再度謀反を企て,謀殺されるに至っている。この信勝を取り上げていないのはなぜだろうか。
家臣の裏切りで,信長の特徴的な対応は,松永久秀,荒木村重ともに,言い分を聞こうとしていることだ。例えば,久秀の再度の裏切りに対しても,
「何篇(いずれへん)の子細候や,存分に申ウォーキング・近所そし上げ候わば,望みを仰せ付けよう」
伝者の松井友閑に伝えたし,荒木村重には,
「早々出頭もっともに候。待ち覚え候。そこもと様躰(ようてい)言語道断是非なくそうろう。誠天下の面目を失う事どもにそうろう。存分の通り両人に申し含め候・かしく。」
と,使者に申し開きさせようとするる姿勢は同じである。後世,大坂の陣で,片桐勝元が徳川に通じているといううわさがあったとき,下問された浅井一政の回顧録に,
「側近少々を召し連れて勝元のところへいらっしゃり,説得されるのがよろしいのでは」
と助言したとある。一政は,その際,
「昔信長様おとなむほんを仕る時,か様に成されたる由承り及び候」
と,信長を引き合いに出した,とある。著者は,その真偽は別として,
「ほぼ同時代に,家臣の謀叛に遭遇した信長の行動が,このように伝えられていることは注目してよいかもしれない。」
と書く。上記浅井一政は,近江・浅井氏の一族なのである。家臣に対するこういう行動は,外交関係については,難しい。状況が,生き残りをかけた戦国大名自身の意思決定に基づくからだ。やはり,家臣と,同列に論ずるのは無理があるのではないか。
いまひとつは,例の,本能寺の変での,信長の一言,
是非に及ばす,
である。この意味は,
是非を論じている場合ではない,
という意味に取られるが,村重への手紙でも,
是非なし,
という文言がある。著者は,
良い悪いの判断をしても仕方がない,
つまり,
「しかたがない,やむをえない」
の意味を取っている。まあ,ぶっちゃけ,
しゃあない,
という言葉だろう。外交関係の破綻では,そういう言い方はしないだろう。武田信玄の遠江侵攻に,是非なし,などとは言わないだろう。上杉,毛利との敵対化にも,そんなことは言うまい。お互い,利害での結びつきなのだから。
僕は,この,
是非なし,
という言葉に,下克上を,尾張一国から初めて生き抜いてきた信長の,
性根,
心ばえ,
をみる。そういう時代に生きている,ということに覚悟があったのではないか。
参考文献;
金子拓『織田信長 不器用すぎた天下人』(河出書房新社)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7 |
|
夢判断 |
|
フロイト『フロイト著作集 2 夢判断』を読む。

いまさら,フロイトの『夢判断』でもないのかもしれないが,読みそびれていたので,改めて通読し直した。フロイトの夢判断についての仮説が今日の脳科学からみてどうなのかは,知らない。しかし,仮説を構築していくその構想力は,驚嘆するほかない。性に偏りすぎている等々といったことは,瑣末なことだ。こういう構想力だけは,どうやら,とうていわれわれは敵わない。仮説の是非を後知恵でとやかく言うのは,愚かである。
フロイトは,ちゃんとこう言っている。
「ある仮説を,未知の現実によりよく接近しているところの,ある別のものに変えるべき時がきたと考えられる場合は,われわれはいつでもそれまでの補助的見解を棄て去るだけの心構えをしていなければならないからである。」
と。大事なことは,フロイトにとって,夢判断は,あくまで,精神分析の一環として,必要に迫られてきた,ということだ。
「夢というものは,ある病的な観念から逆に記憶を遡って追尋することのできる心的連鎖の中に組み入れられるものだということがわかった。すると,夢そのものを一病的症状のごとくに取り扱い,精神病のために編み出された解釈の方法を夢に適用してみたらどうかと考え始めた次第である。」
そして,
「私の意図するところはむしろ,夢の分析を通じて神経症心理学のもっとも困難な諸問題のための予備的な仕事をするという点にある。」
そのために「千以上の夢を判断しときあかした」と。フロイトにとっては,基本,夢は,
「間然することなき一個の心的現象,しかも願望充足である」
ということを一貫して証明する。その出所は,第一に,
「日中時にかきたてられることがある。そして外的諸事情のために充足させられないでいる。すると,夜のために,承認されたけれども,しかし充足されなかった願望が残ることになる。」
第二に,
「ある願望が,日中すでに浮かんでいたのだが,われわれの意識から非難を浴びせかけられる。すると夜のために,充足されていず,かつ抑圧された願望が残される。」
第三に,
「願望は覚醒時生活と無関係のものでありえる。そして夜になって初めて抑制されていたものの中から動き出すような,かの諸願望のひとつでありうる。」
第四に,
「夜中頭を擡げるところの,積極的な願望衝動(たとえば喉の渇きの刺激,性欲欲求など)を加えなければならない。」
と。しかし,見る夢の多くは,とうてい願望充足とは思えないものが多い。しかし,それにも,フロイトは,
不快夢もまた願望充足である,
刑罰夢もまた不快夢の一種である(つまり願望充足夢),
と言い切る。「不快夢」も,
(a)「すべての苦痛な観念を反対の観念で代理させ,それに属する不快感情を抑えつづけることが夢作業に成功するという場合。この場合には純粋の充足夢,それ以上何の論ずべき点もないように見えるところの,はっきりとした『願望充足』が結果として出てくる。」
(b)「苦痛な観念は多かれ少なかれ変更を加えられ,しかしよくそれと見わけられる状態で,顕在的夢内容中に顔を出す。…苦痛な内容を有するこういう夢は,何でもないように感じ取られるか,あるいは不快感情をそっくりそのまま携えて現れるか(この不快感情はその表象内容のために正当なものであるかのごとく思われる),あるいはまた,不快感をさえ醸成させて,ついには人を覚醒に導くかの,いずれかである。」
と分類し,フロイトは,
「分析は次のような事実,すなわちこの不快夢もまた願望充足であることを証明する。その充足が夢を見ている本人の自我からは苦痛としか感ぜえられないような,無意識の,抑圧された願望は,苦痛な日中残滓物の居坐りによって提供される機会を利用し,それらの残滓物を支持し,この支持によってそれらの残滓物が夢の中へ採用されうるようにする。しかし上記aの場合には無意識的願望が意識的願望と合致するのに,上記bの場合市場には無意識的なものと意識的なものとのあいだの分裂―抑圧されたものと自我との乖離が露呈され,そして,妖精が夫婦者に自由に選びとらせた三つの願い(詰まらぬ願いとその取り消しで,結局三つの願いを使ってしまう)という童話の状況が実現されるのである。抑圧された願望の充足に対する満足感はきわめて大きなものでありうるから,それは優に日中残滓物に付着している苦痛感情と釣合いをとることができる。その場合,夢はその根本的な色調において無関心なものになる。もっともその夢は一面においてはある願望の充足であり,他面においては懼れの充足なのであるが。あるいはまた,ねむっている自我が夢形成にかなり自由に参画して,夢が結果する抑圧願望の満足に対して烈しい反抗を以て反応し,不安恐怖感によってこの夢を終らせてしまうことさえする。だから,不快夢および不安恐怖夢が理論的には,円滑な満足夢と同様の願望充足であることはこれを容易に認めうるのである。」
なぜなら,その夢判断そのものが,分析治療そのものだからだ。それにしても,夢の検閲,加工,二次加工,移動,抑圧,象徴的表現等々,とフロイトが苦心した夢解釈の仮説は,有効なのだろうか。僕には,夢は,
経験の記憶化作用,
そのものでしかないと思えてならない。刺激的な経験をしたときは,ものすごい夢を見る。その経験を記憶のリンクにつなぎとめていくための作業が,過去の記憶や経験を引っ張り出したりするのかもしれない。現代の神経生理学では,夢は,
「睡眠中は感覚遮断に近い状態でありながら、大脳皮質や(記憶に関係のある)辺縁系の活動水準が覚醒時にほぼ近い水準にあるために、外的あるいは内的な刺激と関連する興奮によって脳の記憶貯蔵庫から過去の記憶映像が再生されつつ、記憶映像に合致する夢のストーリーをつくってゆく」
と考えられている、と言う。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/399405380.html
で触れたが,夢は,
レム睡眠というごく浅い眠りに随伴する内的体験,
で,夢を見ている最中は,
脳の奥のほうにある記憶に関連した大脳辺縁系と呼ばれる部分が活発に活動し,同時に大脳辺縁系で情動的反応に関連した部位も活発に活動している,とされる。そして,他方で,記憶の照合をしている,より理性的な判断機能と関連する前頭葉の機能は抑制されている,という。
人は,睡眠中,
記憶の整理と定着がされている,
とも言う。
「浅い眠りの時には,『海馬』がシータ波という脳波を出し,上方の脳内再生を行っています。逆に,深い眠りの時には大脳皮質がデルタ波を出し,記憶として保存する作業を行っています。」
フランスの脳生理学者ミッシェル・ジュヴェは,
レム睡眠中には,動物も人間も危機に対処する行動をリハーサルし,いつでも行動できるよう練習している,
ともいう。つまりは,イメージ・トレーニングである。レム睡眠は朝に向かって増える。夢は,
脳の機能から考えると,ノンレム睡眠の時に休んだ脳機能を朝の覚醒にむけて,外界の変化から離れた夢を見ながら徐々に働かせている。つまりはオフライン状態のときに,ウォーミングアップしているのだという。
フロイトの考察は,理論的な裏付けの得られるものもあるし,仮説として捨てられるものもあるのだろう。しかし患者の夢の分析を通して積んだ実践的な慧眼は,なかなか侮れるものではない。本書の掉尾では,こう言いきっているのである。
「夢には未来を予知するというような能力はあるのであろうか。夢による未来予知というようなことはむろん考えられない。その代わり,夢は過去について考える。なぜなら夢というものは,あらゆる意味において過去に由来するものだからである。夢はひとに未来を示すという古い信仰にもまたなるほど一面の心理は含まれていよう。とにかく夢は願望を満たされたものとしてわれわれに示すことによって,ある意味ではわれわれを未来の中へと導いていく。しかし夢を見ている人間が現在だと思っている未来は,不壊の願望によって,彼の過去の模像として作り上げられているものなのである。」
なお,現代の「夢の理論」は,
http://jssr.jp/kiso/hito/hito10.html
に整理されているし,夢の機構については,
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E5%A4%A2
に詳しい。
参考文献;
フロイト『フロイト著作集 2 夢判断』(人文書院)
内山真『睡眠の話』(中公新書)
池谷祐二『脳には奇妙なクセがある』(扶桑社)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A2 |
|
夢解釈 |
|
ユージン・T.・ジェンドリン『夢とフォーカシング―からだによる夢解釈』を読む。
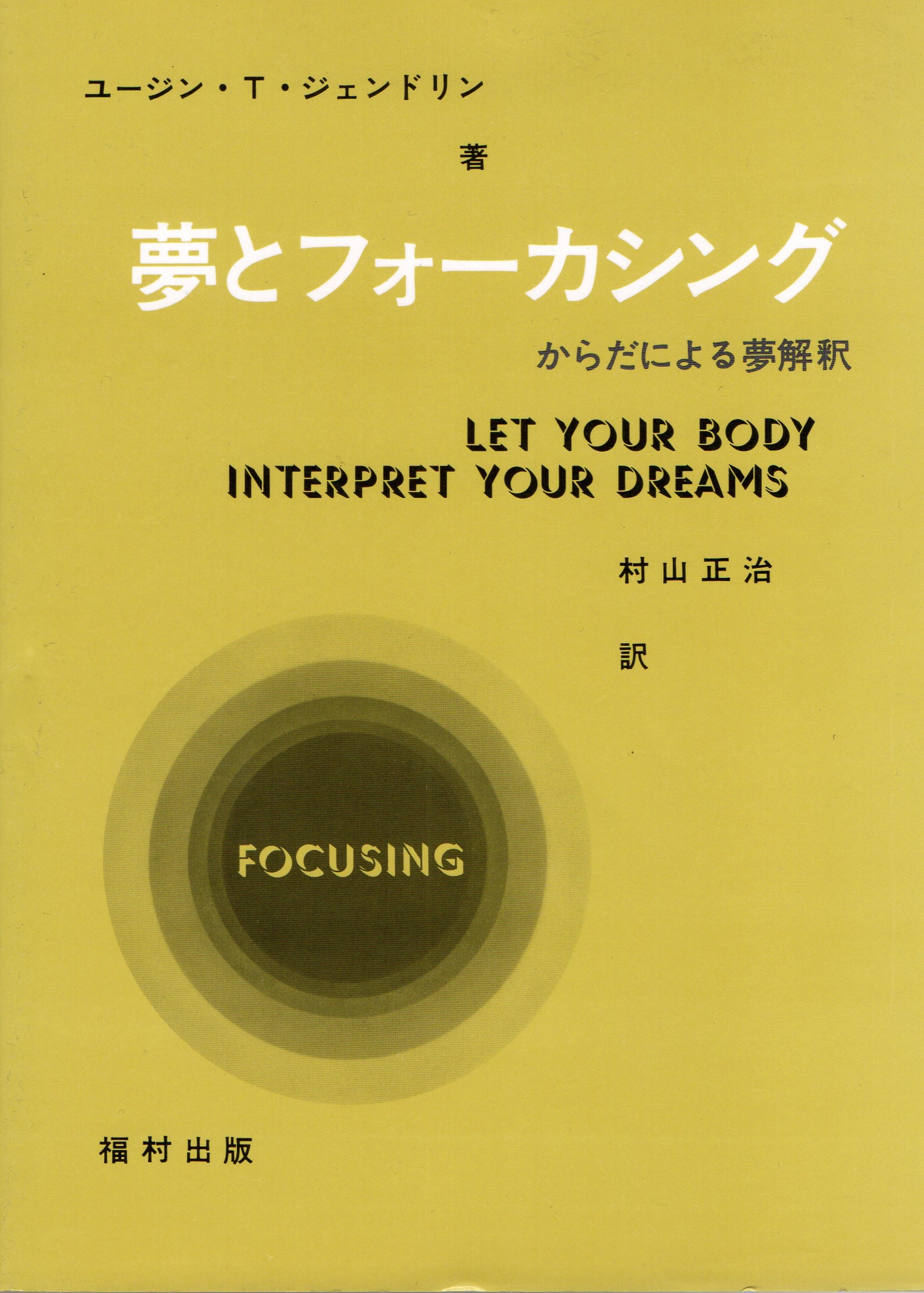
サブタイトルに,「からだによる夢解釈」とあるのが,本書のすべてを説明している。
「本書のねらい」で,著者は,
「伝統的な夢『解釈』の方法は,1つの理論を応用してある結論に達するのです。私はこのような夢解釈の方法を否定します。出てきた結論は,仮説にすぎません。その仮説に応じて,夢を見た人に具体的に,体験的に何かがひょいと出てこないかぎり,解釈にしたことにはなりません。そこで,私はこうしたさまざまの異なった視点を質問形式に組みかえました。ゆっくりとからだのフェルトセンスに問いかけてみます。何も出てこなかったら,次の問いかけへと進むのです。
フェルトセンスそのものが反応したときは,からだからの信号があり,緊張がほぐれ,フェルトシフトが起こります。こうして起こったからだのシフトは具体的では実感できますので,私がその解釈は本当なんですよ,あなた自身が夢を解釈したんですよ,とことさら説明する必要もありません。」
と述べ,ここでの夢に対するフォーカシングは,一人でもできるように工夫されている。
「フェルトセンスは,怒り,恐れ,悲しみといった普通の感情ではありません。こうした見覚えのある感情に加えて,夢は分類できない,独特の感じをあなたに残してくれます。そのことを頭で考えることはできません。フェルトセンスは漠然とした,全体的な,わけのわからない,奇妙な,気にかかる,ぼんやりしたからだの感じです。
私たちの方法は,そこに,つまりフェルトセンスに直接問いかけるのです。そして新しいものが浮かんでくるかどうか待ってみるのです。」
この方法には,
第一に,「1つの理論や信念の体型に限定されていないことです。」
第二に,「この方法の根本的な基準はあなたの中に何かが開かれてくる,あなたの自身のからだの感じにあることです。解釈は,あなたが気づき,つまり,からだのフェルトシフトを感じたときにだけ確かなものになるのです。」
第三に,「この方法は教えることができ,また,学習することができることです。」
という特徴がある,と著者は自信ありげである。確かに質問は,定式化されている。質問は5段階に分かれる。
◆連想を捉えるための方法
①何が心に浮かんできますか(夢にどんな連想をしますか,何が心に浮かんできますか等々)
②どんな感じがしますか(夢の中でどんな感じがしましたか,夢にもった感じは等々)
③きのうのことは(昨日何をしましたか,昨日のことを思い出してください等々)
◆場所・あらすじ・登場人物という物語をつくる3つの要素
④場所は(夢に出てきた主な場所は,そこから何を思い出しますか等々)
⑤夢のあらすじは(あらすじを要約,生活のどんなところと似ているか等々)
⑥登場人物は(夢の中の知らない人物は,その人物から何を思い出しますか等々)
◆登場人物と係るための3つの方法
⑦それはあなたの中のどの部分ですか(夢の中の他人はあなたの中のある部分を象徴しています,それは何等々)
⑧その人になってみると(その人物になってみる等々)
⑨夢の続きは(夢の最後の重要と思える光景を思い浮かべ,それを感じてください等々)
◆象徴・身体のアナロジー・反事実性など夢の(暗合を)解読するための3つの方法
⑩象徴は(夢の中のモノやコトの象徴,メタファーを考える)
⑪身体的なアナロジーは(身体に準えてみると等々)
⑫事実に反するものは(夢は何を変えたのですか等々)
◆成長における4つの次元
⑬子どものころのことは(夢に関連して,子どもの頃のどんな思い出が出てきますか等々)
⑭人格的な成長は(どんなふうに成長しつつありまいか,どんなふうに成長しようとしていますか等々)
⑮性に関しては(夢を,性的なものについてしたり,感じたりしていることの物語と考えると等々)
⑯霊性に関しては(夢は,創造的あるいは霊的な可能性について何か語っていませんか等々)
しかも,この質問は,
「夢をみた人が自分のからだに聞くためのものです。質問がからだの内部に届くようにしてください。質問はそこに向けてされるのです。1つの質問について,1分ほどかけてください。」
と,著者は言う。
「ただ,夢をみた人のからだだけが,夢を解釈できるのです。」
そのために,
「(質問によって)あなたの注意をからだの中へ向け,曖昧な感覚を感じてください。それを感じられたら,静かにその質問を内側に向けて問いかけ,待ってください。何が浮かんでくるかを見てください。」
この質問ステップは,ただ夢を解釈するだけではなく,自分自身の次への成長ステップにつながるものを見つけ出すところに主眼がある。
「何についての夢かを知るだけでは,まだ十分な解釈ではありません。私たちは,さらに先へ進むことができます。
第2段階の目的は,夢から何か新しいものを得ることです。」
そういう著者自身は,
「すべての夢には,本当に役割があって新しいことを生み出すとは,私たちも科学的に確認したわけではありません。しかし,私はそう考えています。
として,
「夢解釈には2つの段階があります(ときには2つが一度に起こることもあるし,そうでないときもあります)。気づきが起こるとその夢が何について語っているか知ることができますが,それは,みんな以前から知っていたことかもしれません。それは,夢解釈の第1段階にすぎないのです。…第2段階…はどんな夢にも成功するとは限りません。それがうまくいくと,あなた自身の成長にとって新しい発見になるでしょう。」
なぜなら,
「有機体は,物質的なものだけを必要とする生物学的な機械ではありません。からだはコスミック・システムであり,概念を超えたいろいろな意味合いや,多様な方向性に富んでいます。人生の中では,私たちは『私たち自身であること』のほんの一部を成長させるにすぎません。
成長していく方向は,あなたのからだでかんじられるものです。あなたが成長の方向を感じとり,その方向に沿って進むのに夢は役立つでしょう。」
ねらいは,
「目的は,あなた自身についていろいろ知ることではなく,成長すること」
であり,そのための夢フォーカシングであること,ここはぶれない。
著者自身は,このステップについて,
「このステップに理論は必要ありません。理論がここでは付録になっているのはそのためです。」
と,付録の「生きているからだと夢の理論」で述べている。あくまで,実践の書である,と言いたいらしいのである。
本書を通読して,正直のところ,物足りないと感じるところがある。それは,果たして,夢は,自分の人生について,何かを象徴したり,何かのアナロジーであったりするのか,という疑問である。所詮,夢は,自分の体験を記憶するための脳の機能に過ぎないのではないか,という思いがあるからだ。
しかし,反面,本書に惹かれたのは,あくまで,夢そのものではなく,夢を通して,
自分の中で起きている感じ,
あるいは,
起こっていた感じ,
に焦点を当て,自分自身がそこから何を得るか,というところにポイントを置くなら,それは,また別の,自分の今の感じ(フェルトセンス)を通して,自分自身を知り,そこに目覚めている意識していない自分の方向性を顕在化させる,という意味が見えてくる。そのとき,夢は,ただの自己理解と,自分の潜在的な方向性を感じとるための素材に過ぎなくなる。
それは,エリクソンが,クライエントに,
アネクドート(逸話),
を伝え,それをクライエント自身が勝手に解釈し,理解し,おのずと問題を解決していった,というそのアネクドートと似た役割を,夢に果たさせている,と解釈できなくもない。
参考文献;
ユージン・T.・ジェンドリン『夢とフォーカシング―からだによる夢解釈』(福村出版) |
|
通底 |
|
倉本一宏『戦争の日本古代史−好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで』を読む。

本書は,四世紀末から五世紀にかけての,高句麗との戦いでの大敗らか始まり,さらに七世紀の唐との白村江での大敗を経て,古代の日本の戦争史を繙く。実は,明治以前は,この後,十六世紀の秀吉の朝鮮侵攻を加えて,三回しか日本は対外戦争を経験していない。いずれも朝鮮半島でであったが,しかし明治政府が,維新後早々から朝鮮半島侵略に踏み切ったのには,明治政権の特質ももちろんある(僕自身はテロリスト集団が政権奪取してしまったと認識している)が,それ以上に根深いものがある,と著者は説く。正直,これは衝撃であった。
「(朝鮮侵略は)もちろん,直接的には藩閥政府の帝国主義への志向と,帝国陸海軍の内包した矛盾に解明の道があるのであろう。しかし,さらにその淵源は,古代倭国や日本にあり,そして長い歴史を通じて醸成され,蓄積された小帝国志向,それに対朝鮮観と敵国視が,幾度にもわたって記憶の呼び戻しと再生産をもたらし,近代日本人のDNAに植えつけられてしまっていたことにあるのではないかと考える。」
そのキーワードを,
東夷の小帝国,゛
と,著者は見る。「中国に倣った中華思想を基軸に据え」た大宝律令が完成した大宝元年(701)の元日,
「文武天皇は大極殿に出御し,朝賀を受けた。その眼前には前年新羅から遣わされた『蕃夷の使者』も左右に列立した。」
という。この中華思想「東夷の小帝国」は,
「日本(および倭国)は中華帝国よりは下位だが,朝鮮諸国よりは上位に位置し,蕃国を支配する小帝国」
を主張するというものだ。これが,
荒唐無稽で,笑止千万な主張,
とは言い切れない,「その根拠とされた歴史的事実も,それなりに存在した」として,次のように,列挙し,
「第一に,四世紀末から五世紀初頭にかけて,百済(ひゃくさい)・伽耶(かや)・新羅(しんら)を『臣民』としたという認識である。実際には,百済の要請を受けて半島に出兵し,百済(や伽耶)と一時的に軍事協力関係を結び,新羅に攻め入っただけなのであろうが,その過程において,百済や伽耶・新羅を『臣民』にしたという主張は,倭国の支配者層のあいだに根強く残った。
この出兵(と白村江の戦い)が神功皇后の『三韓征伐』説話のモチーフとなり,それがはるか後世までくりかえし歴史の表面に現われ出ることになることを思うと,倭国最初の海外出兵が日本史に与えた影響は,我々の想像以上に大きいものであったと考えるべきであろう。」
「第二に,五世紀に宋から朝鮮半島南部六国(伽耶諸国と新羅)の軍事指揮権(『六国諸軍事』)を承認されれたという事実である。(中略)もちろん,倭国は半島南部において実質上の支配権は有していなかった。しかし中国皇帝から認められたことは,この国の支配者の記憶に刻印され,後世にまで大きな影響を及ぼしたはずである。」
「第三に,六世紀までは『任那』を支配していたという主張である。『任那』というのは金官国のことで,実際には倭国が支配した事実はない。(中略)『日本書記』が氏族伝承や百済系外交史料といった原史料を,そのまま本分としてしまった結果,あたかも倭国が朝鮮半島南部に統治権を有していたような記述となってしまったのである。」
「第四に,『任那』滅亡後,六世紀から七世紀にかけて,倭国は新羅や百済に『任那の調』の貢進を求めたが,新羅や百済は外交的・軍事的に苦境に立つと,倭国に何度も『任那の調』を送ってきた。実際には新羅や百済の特産物を贈っただけのことでことは言うまでもないし,新羅や百済の側にはこれが『調』であるとの認識はなく,あくまで外交上の口頭によるやりとりに過ぎなかったと思われる。
しかし,倭国側にとっては,この事実が,七世紀までは新羅や百済,それに『任那』が倭国に『朝貢』してきたという主張につながったのである。」
「第五に,遣隋使と遣唐使の問題である。600年に第一次の使節が派遣された遣隋使は,これまでの倭国の志節とは異なり,また他の周辺諸国(『蕃国』)とは異なり,中国の皇帝に冊封を求めなかった。
倭国の大王は,隋から冊封された朝鮮諸国の国王より優越した地位と認識されることを欲したのである。『随書』東夷伝倭国条に記されている,『新羅と百済は,皆,倭を大国であって珍物が多いとして,幷にこれを敬仰し,つねに使者を通わせて往来している』という記事は,ある程度,倭国の主張が隋に認められたことを示すものであろう。
これも倭国の主張を助長させる結果につながったことは,もちろんである。」
「第六に,七世紀後半に百済遺臣の要請を受けて,白村江で唐と戦ったという事実である。その際に,倭国に滞在していた百済王族の余豊璋を新しい百済王として,それに倭国人の妻を与え,倭国の冠位を授けていることは,重要である。この戦いに勝利し,倭国人妻が生んだ王子が即位したならば,百済は倭国の属国として位置づけられるであろう。」
「第七に,八世紀初頭に成立した律令制において,新羅を『蕃国』として設定した地理認識である。また,東北地方の『蝦夷』,九州南部の『隼人』,南島という『異民族』を設定し,位階と官職を授けて河内に住まわせた百済王氏(くだらのこにしき)と合わせて,これを支配していいるという主張によって,『小帝国』世界観念を構築していった。」
こうした歴史における「事実と主張」によって,
「日本(および倭国)の支配者層はは,自国が朝鮮諸国よりも優越した存在の『大国』であると認識した」
というのである。それと同時に,
「朝鮮半島諸国に対する敵国観も,日本人の意識の奥底に深く刻まれた。もともと,交戦国であった高句麗や新羅に対する敵国視は古い時代から存在していたのであるが,(中略)その後新羅に替わって半島を統一した高麗は高句麗の後継者と自称したが,日本ではこれを新羅の後継者と見なした。そして新羅に対する敵国視もまた,高麗に対しても継承させたのである。」
この対朝鮮観の根深さは,ちょっと衝撃的である。われわれの夜郎自大ぶりには,われわれの1500年に及ぶ年季が入っているのである。一方の,朝鮮は,
「『自己(朝鮮)は中国よりは下位にあるが日本(倭)よりは上位である』と思いつづけてきた」
のに,それが,
『自己(日本)は中国よりは下位にあるが朝鮮よりは上位にある』と思いつづけてきた日本の植民地支配を受ける。これ程の屈辱感は,その国の人でないと,我々日本人にはとうてい理解しがたいことだったであろう。」
いま,近隣諸国で,日本を指す,
倭奴,
小日本,
日本鬼子,
という言葉が使われ続けていると,著者は締めくくる。相手は,おのれの写し鏡である。日本の他国観は,そのまま他国の日本観に反映する。
参考文献;
倉本一宏『戦争の日本古代史−好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで』(講談社現代新書 |
|
小さな一歩 |
|
ユージン・ジェンドリン『セラピープロセスの小さな一歩』を読む。
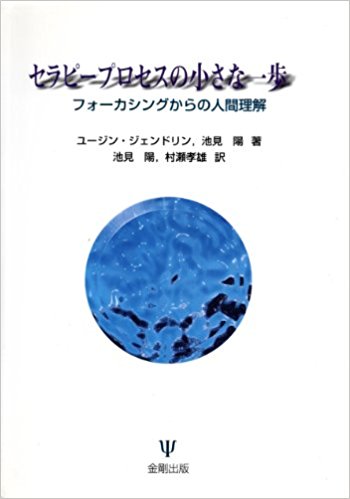
本書は,フォーカシングの創始者ジェンドリンの,
「セラピープロセスの小さな一歩」(講演速記)
「体験過程療法」
「人格変化の一理論」
を,訳者でもあり,編者でもある池辺陽氏が,解説をつけた書である。本書の狙いを,池辺氏は,フォーカシングの技法についての翻訳はあるが,哲学者でもあるジェンドリンの理論書が,
『体験過程の意味の創造』
しかないことから,「本来,哲学者であり,理論家であるジェンドリンの技法だけが紹介され,その優れた理論が日本語になっていない」ことを惜しみ,訳者(池辺陽・村瀬孝雄)が,「歴史的と思われる」代表的論文を集約したと,「本書の特徴」で述べている。
小さな一歩とは,セラピストとクライエントとの間で起きる,
クライエントの変化,
を指している。ジェンドリンは,
クライエント・センタード・セラピーには,
あるリズムがあります。
まず初めに,クライエントが何か言います。
あなたはそれを言い返すのですが,
それはどこかはずれています。
それからクライエントはそれを修正するのです。
あなたは修正を受け入れ(言い返します)。
それでも彼らは言います。
「ええ,そう,…でもピッタリじゃない」
彼らは次の絞り込みを示してきます。
あなたはそれも取り入れます。
それから彼らは一息ついて,
「そうです」といいます。
そのあと独特の沈黙がそこにあります。
その沈黙の中から次のことが浮かんできます。
通常,次に浮かんでくることは,
もっと深くなっています。
あなたはそれをリフレクトし,
また彼らはそれを修正します。
あなたは修正を取り入れます。
彼らはさらに特定の条件を加えます。
あなたはそれも取り入れます。
再び一息ついて,そしてあの沈黙。
あの沈黙はとても独特です。
(中略)
話そうと準備してきたものは,
傾聴され,応答されました。
もう話すことはなくなっています。
にもかかわらず,その問題は感受できます。
もちろんそれは解決されていません。
あなたはそのその事柄の不明瞭な実感,
不明瞭な縁(edge)をもっています。
すぐそこに。
あなたはそれをからだで実感します。
言葉はそんなにいらないのです。
(中略)
もしもセラピストという相手と一緒にいるときは,
その沈黙の中にいてほしい。
すぐそこに,
不明瞭な実感から次のものが現れるまで。
「フォーカシング」という言葉は,
あの内面に感じられた縁に注意を向けるために時間をかける
ということを意味します。
それが沈黙の中で起こるとき,
次なるものが,そしてさらに,その次なるものが,
深いところから,さらに深いところから,
徐々に表れるのです。(「セラピープロセスの小さな一歩)
と,それを表現する。本書は,その沈黙を通過して,何が起きているのかを,明らかにしようとする試みといっていい。大事なことは,この一歩は,
相互作用のプロセス,
だということである。だから,
あの縁が一歩を生み出すのに必要なものは,
ある種の非侵襲的な接触,あるいは共にいることなのです。
(中略)
あなたがそこにいること,
それだけを必要としているのです。(仝上)
と。そのプロセスを,
体験過程(experiencing),
と名づけ,それについて,「体験過程療法」では,
「ある瞬間において人が感じることは,いつも相互作用的で,それは無限の宇宙や状況の中で他の人々や,言葉やサイン,物理的な環境や,過去,現在,未来の事象とのかかわりの中でのひとつの生きる過程である。体験過程は『主観的』でなく,相互作用的なのである。それは精神内的世界(intrapsychic)でもなく,相互作用的なのである。それは内側ではなく,内側−外側なのである。からだとこころと同じように,体験過程論は単に内側−外側のこの統一を主張しているのではない。それは気持ちに対しては内側の用語を使い続け,物事や人々に対しては外側の用語を使い続けるのではないのである。相互作用を示す言葉が基本であり,第一である。それは,あたかも外側で何かが起こって,それについての気持ちをということではない。むしろ,『起こる出来事』はすでに相互作用的なのである。それは人をすでに変えており,その人がなぜ,どのようにその状況にあるかが重要であるからこそ,それはその人にとって『出来事』なのである。ひとがどのように感じるかは,起こることの上にやってくる後の出来事ではなく,それは起こる出来事そのものなのである。(中略)出来事はひとがその出来事を生きる過程なのである。(中略)体験過程は常に内的に感じられ,状況的に生きられ,そしていつも相互作用として参照される。」
と述べられる。そして,
「このような一歩にはからだで感じられた継続性(bodily felt
continuity)がある。(中略)からだのプロセスにおけるこの変化―内―継続の特徴(continuity―in―change
characteristics)を突然の変化や変化がないことと区別するために,それを推進(carrying forward)と呼ぶ。
文化,歴史,思想や個人的生活の複雑さにもかかわらず,状況に対するからだで感じられた実感(フェルトセンス)(bodily felt
sense)はこの過程-進展(process
movement)の特徴を保持しており,あるフェルトセンスはある特定の出来事や次の行動,言葉や他の象徴によって『推進』されたり,されなかったりする。からだで解放が感じられるあの特徴的な変化による継続性は起こるか,起こらないかのどちらかなのである。
例えば,今『へんな感じ』(認知的に不明瞭)があるとすれば,感じられるものについて述べてみることができる。『へんな感じがします』と言ってみるかもしれない。『妙な感じがします』と言い換えてみても,たぶんその感じは変わらないであろう。もしも『いい気分で,何か面白いことをしてみたい』と言ってみると,これは望ましいことであったとしても,『へんな感じを推進』するには,あまりにも突然の変化となるであろう。かなりの努力を要して,わりと特殊な言い回しを思いついたときにのみ,あの変化―とともに―継続(change-with-continuity)が体験され,『あぁ,そうだ,私が感じていたことはこれでピッタリだ!』と言えるであろう。その中核は,言語化されなくても,そのいくつかの側面はとらえられ,『それが何だかかよくわからないけど,何か怖い感じがする』というようになるかもしれない。その場合,大きく流れ出るような解放や一息つくことはなくても,もっと小さなスケールの『…そう…ええ…そう…それは確かに,この〔気持ちの〕一部なんだなぁ』といった実感がある。シフト〔変化〕が感じられ,からだの何かが解放される。明らかにただの言葉だけではないのである。それを言うことによってからだへの効果があり,その効果が異なったものへの,ただの突然の変化ではない。したがって,人がその体験過程を(言葉や他の象徴によって)象徴化すると,それ自体がさらに進んだ体験過程で,それは象徴化される体験過程の推進とそれによる変化なのである。感じることを話すことは感じることを変えるのである。」
そしてその瞬間のことを,
ひらけ(unfolding),
と名づける。僕は,ひらめいた瞬間を「視界が開く」と呼ぶが,それと似ているかもしれない。
「直接感じられたリファレント,すなわち感じられた意味に(中略)焦点を合わせていくと,時にそのレファレントが何であるかを一歩一歩次第に明白に知るようになる過程が見られることがある。しかしそのことがある瞬間に劇的に『ぱっと開く』(open
up)こともある。」(「人格変化の一理論」)
こうした背景を意識して,技法としてのフォーカシングのプロセスを改めて見直してみると,ジェンドリンが,体験過程を,
現在を生きる過程の中で自分自身を築き上げ,変えていく,
と実存的な意味を負荷した意図がよりわかるのではないだろうか。
参考文献;
ユージン・ジェンドリン『セラピープロセスの小さな一歩』(金剛出版) |
|
太宰治 |
|
太宰治『太宰治全集』を読む。
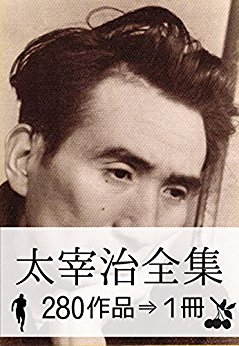
何十年ぶりかに,太宰を読み直した。Kindle版で,簡単に手に入るようになったせいだ。かつて,なぜあんなに熱中したのか,と不思議な気持ちで読み通した。正直,
つまらない,
と感じた。
文学としての巧拙は知らない。しかし,いつも同じテーマが通奏低音のように流れる。言い方が悪いが,それは,
言い訳,
あるいは,
弁解,
に見える。というか,それを意識してテーマとして書いている,と見えた。あるいは,
生きている理由,
を捜す,という言い方でもいい。ただ,良さは,
自己正当化,
には堕していない,というところだと思う。少し乱暴な言い方をするなら,通底する弁解は,ときに,
諧謔,
ときに,
被虐,
あるいは,
衒学,
となる。それは自分との距離の取り方に起因する。たぶん,おのれの生き方,あり方については,疑い,狐疑逡巡するが,
筆の世界,
つまり,書かれた小説世界には,揺れ動くおのれとの距離をとりつつ,それを描く世界そのものへの確信は揺るぎはないように見える。
自分
と
それへの距離の取り方,
と
それを描く作品世界,
とのバランスで成り立っていた,と見える。それが,
自分自身か,
おのれとの距離の取り方か,
それを描く世界か,
そのいずれかに僅かな齟齬が生まれれば,たちまち崩れる危うさ,でもある,と見える。
ヴィヨンの妻,
も
斜陽,
も
走れメロス,
も,
竹駙,
も
魚服記,
も,
人間失格,
も,
グッド・バイ,
も,
同じテーマだ。同じ事件(といっていいか),経験を,異なる視点から,たぶん,しっくりこないのだろう,いろいろ書き直す。その筆力には驚くが,今日読み直して,僕には,今に堪えうるものは,どれほどだろうか,と疑問に思う。
いま,手許に唯一残っているのは,新書版の太宰全集(筑摩書房)第一巻のみだが,その『晩年』で,その巻頭の「葉」のエピグラフに,ベルレーヌの,
選ばれてあることの
恍惚と不安と
二つわれにあり,
がある。太宰を象徴するフレーズだとずっと思ってきた。この『晩年』に出会ってしまって,僕の小説観が歪んでしまったと常々思ってきた。しかし,いま思うのは,自惚れと自嘲との振れ幅,自己意識の振り子に堪えきれず,煩悶するというのが,正しいのかもしれない。
有名かどうか知らないが,『川端康成へ』と題された文章は,ある意味太宰の煩悶を象徴するように見える。
「前略。――なるほど、道化の華の方が作者の生活や文学観を一杯に盛っているが、私見によれば、作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾みあった。」
という川端康成の,(たぶん芥川賞の)選評に,太宰は,異常に反応し,川端を罵倒する。
「川端康成の、さりげなさそうに装って、装い切れなかった嘘が、残念でならないのだ。
こんな筈ではなかった。 たしかに、こんな筈ではなかったのだ。
あなたは、作家というものは『間抜け』の中で生きているものだということを、もっとはっきり意識してかからなけれ ばいけない。」
ここで問題になっている,『道化の華』を壇一雄が,
「これは、君、傑作だ、どこかの雑誌社へ持ち込め、僕は川端康成氏のところへたのみに行ってみる。川端氏なら、きっとこの作品が判るにちがいない、と言った。」
ということで,事前に川端が目を通していた経緯があるなのか,太宰の私生活をあてこすっていると受けとめたのか,いずれにしても,太宰は,川端の一文に,異常な反応をした。この『道化の華』は,
「三年前、私、二十四歳の夏に書いたものである。『海』という題であった。友人の今官一、伊馬鵜平に読んでもらっ
たが、それは、現在のものにくらべて、たいへん素朴な形式で、作中の『僕』という男の独白なぞは全くなかったのでのである。物語だけをきちんとまとめあげたものであった。
そのとしの秋、ジッドのドストエフスキイ論を御近所
の赤松月船氏より借りて読んで考えさせられ、私のその原始的な端正でさえあった『海』という作品をずたずたに切りきざんで、『僕』という男の顔を作中の随所に出没させ、日本にまだない小説だと友人間に威張ってまわった。」
という。太宰としては技巧を駆使した作品だ,という。僕は,この,何回か素材として使われる,例の心中未遂を素材にした,この作品を,傑作とは思えず,どこか,
後ろ暗さ,
というよりも,言い過ぎかもしれないが,
薄汚さ,
を感じた。川端の感じたものが同じかどうかは知らない。しかし,ここでは,
言い訳,
は,あるいは,
正当化,
の翳を感じた。たぶん,むかしは,熱中した彼の作品に,好意よりは,嫌悪を感じ始めているのは,太宰ではなく,いまの自分を反映している。若いときにおのれの写し鏡のように受け取った太宰は,いま,同じ写し鏡でも,厭うべき何か,のようだ。たぶん,それが,老いる,ということなのだろう。
太宰よりも倍生きたせいか,太宰の身もだえが,滑稽に見える。いま,若い人にとって,太宰はどう読まれるのだろうか。
参考文献;
太宰治『太宰治全集』Kindle版 |
|
国衆 |
|
鈴木将典『国衆の戦国史』を読む。
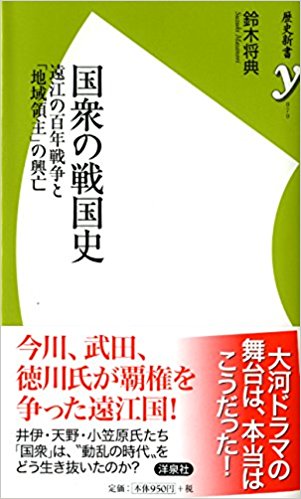
「国衆」とは,
「戦国時代に一定の領域(おおむね一郡から数郡程度)を支配した領主」
を指す。現代の学術用語では,
戦国領主
地域領主,
と呼ばれる。多くは,
「戦国大名の傘下に入ることで家の存続を図り,もし戦国大名が弱体化するなどの理由で,家の存続が保障されなくなった場合は,他の戦国大名に従属したり,複数の戦国大名に『両属』したりすることもあった。」
とされる。本書では,徳川家康の例を挙げて,
「家康は西三河を支配する国衆・松平氏の惣領家(安城松平氏)に生まれたが,父の松平広忠(1526〜49)が駿河の戦国大名今川氏に従属したことにより,人質として今川氏の下に送られ,成人後は今川義元(1519〜60)から『元』の偏諱(実名の一字)を与えられて『元信』(後に『元康』)と名乗った。
しかし,永禄三年(1560)五月に義元が尾張・桶狭間(名古屋市緑区・豊明市一帯)で戦死し,今川氏の勢力が衰えると,家康は今川氏から独立して他の国衆たちを従属させ,三河を制圧して永禄九年(1566)に『徳川』へと改姓し,戦国大名化を果たしている。」
本書は,遠江の国衆の戦国時代の興亡を描く。「遠江」とは,「うみ」
http://ppnetwork.seesaa.net/article/448421529.html
で触れたように,琵琶湖が,
「都から近い淡水の海として近淡海(ちかつあふみ、単に淡海とも。万葉集では『淡海乃海』(あふみのうみ)と記載)と呼ばれた。近淡海に対し、都から遠い淡水の海として浜名湖が遠淡海(とほつあふみ)と呼ばれ、それぞれが『近江国(おうみのくに、現在の滋賀県)」と遠江国(とおとうみのくに、現在の静岡県西部)の語源になった。別名の鳰海(におのうみ)は、近江国の歌枕である。」
とある。「遠江」を,
とおとおみ,
と呼ぶのは,浜名湖が遠淡海(とほつあふみ)と呼ばれていたことに由来する,現在の静岡県西部(大井川以西)を指す。端緒は,
「文明五年(1473)に駿河の今川義忠(1436〜76)が遠江へ侵攻したのが始まり」
で,
「天正十年(1582)三月に甲斐の戦国大名武田氏が滅亡したことによって,遠江は徳川氏と武田氏が争う『境目』(紛争地域)の状態から解放され」
で,終る。全国的には,
「戦国時代は,天正十八年(1590)に秀吉が関東・奥羽の戦国大名を従属させて,『天下一統』を成し遂げた」
時に終る。この間百年余,
今川,
北条,
武田,
徳川,
という戦国大名に翻弄され,あちらにつき,こちらについて,生き残りを図り続けた。今話題の大河ドラマの「直虎」の井伊谷は,三河と接する地域で,まさに,今川,徳川,更に武田に翻弄され続ける。
本書では,「直虎」について,「次郎直虎」と署名し,花押を据えている書状等々から,
「『次郎法師』と『二郎』『井次』『次郎直虎』が同一人物であることは確実だろう。だが,戦国時代に女性が花押を用いた例はなく,…寿桂尼(今川氏親の後室)のように,印判を用いて仮名書きの文書を発給するのが一般的である。また,直虎が女性であったことを示す証拠は,後世の系図や『井伊家伝記』のような編纂物に基づいており,逆に同時代の史料ではまったくみられない。」
と否定的である。そして,
「直虎は永禄十一年(1568)十二月に(徳川の侵攻を受けて)本拠の井伊谷を追われ,後に直政が徳川家康の家臣に取り立てられて再興を果たしたが,『国衆』としての井伊氏は没落している。」
ということになる。
では家康に与し本領を安堵された他の国衆はどうなったのか。
「天正十八年(1590)七月に家康は羽柴(豊臣)秀吉によって関東へ転封され,徳川氏に従属する国衆たちも本領を離れたことによって,家康から領地を与えられる家臣(大名・旗本)として転身せざるをえな」
くなる。この背景には,
「国衆に対する豊臣政権の政策があった。近年の研究によれば,大名に従属しながら自立的に領域を支配する領主(国衆)の存在を秀吉は認めず,以下の三つの選択肢を彼らに強いたとされる。
①豊臣政権に直接従属して,秀吉から領地を安堵される存在(豊臣大名)になる。
②豊臣大名の家臣になる。
③豊臣政権に従わず,改易される。」
豊臣大名に成れたのは,真田昌幸などわずかであり,ほとんどの国衆は,家臣として生き残るか改易されるかの選択を迫られた。
「そもそも『国衆』という存在は,日本全国で起こった戦乱の中で,地域の平和を維持する『秩序』として成立したものであった」
以上,「天下一統」され,戦国時代が終るとともに,消滅せざるを得なかった,ということだろう。それにしても,戦国時代は,面白い時代であったということだろう。
参考文献;
鈴木将典『国衆の戦国史』(歴史新書y)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%BC%8A%E7%9B%B4%E6%94%BF |
|
SFT |
|
インスー・キム バーグ&ノーマン・H.
ロイス『解決へのステップ―アルコール・薬物乱用へのソリューション・フォーカスト・セラピー』を読む。
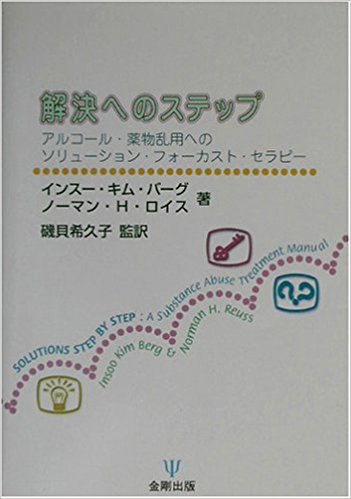
同じソリューション・フォーカスト・アプローチによるDVへのセラピーについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163302.html
で触れたことがある。今回は,ソリューション・フォーカスト・セラピー(SFT)による,アルコール・薬物乱用者へのセラピーである。
本書の特徴は,監訳者(磯貝希久子)のあとがきで,
「『臨床現場からの質問』『臨床現場からのヒント』には,私がワークショップやレクチャーしている時によく受ける質問と同じような問い(SFTを学び始めた方が抱く疑問は世界各国共通のようです)に対する具体的なアドバイスが記述されています。くしくも,インスーの日本語版へのまえがきにもあるように,これらはインスーとノームから,ソリューション・フォーカスト・セラピーを学ぼうとする読者の皆様へ贈られた『宝物』です。これらを何度も目を通されると,SFTの哲学を理解する助けになると思います。」
と述べた通り,随所で,「キーポイント」「臨床現場からのヒント」「臨床現場からの質問」が示される。たとえば,冒頭の「キーポイント」は,
治療前の変化を逃さないこと,
というタイトルで,
「予約の電話の際には,クライエントの生活の中で今起こっていることで,これからも続いてほしいと彼らが思うことを見つけ,それに注意を払うようにたのみましょう。クライエントとの初回面接では,これからも続いていく価値あることを詳細に見つけ出すのを忘れないでください。」
とある。解決志向の出発点である。同じ「スタート」のところでの「臨床現場からのヒント」には,
幸先のよいスタート,
と題して,こうある。
「クライエントが初回の予約のために電話をかけてきたときに,インスーの受付には次のように伝えます。『ご予約は水曜日の午後2時で,インスー先生の担当になります。インスー先生から,今から今度お逢いするまでの間,あなたの生活でうまくいっていることに,注意を払っていてくださいとのことです。』」
このことの背景は,冒頭の,本書の書き出しに明らかである。
「ほとんどのクライエントが,酒をやめなくてはと毎日自分に言い聞かせている。(中略)ある女性が,今日我々に援助を求めて電話をかけてきた。彼女にはそうしようと思ってもできなかった日々があったからこそ,今日それができたのである。回復というのは,クライエントが我々のオフィスを訪れた日に始まるのではないし,ましてその人が実際に酒を飲むのをやめた日から始まるのでもない。回復は,その人が『お酒を飲むのをとにかく何とかしなければ』と初めて考えた,まさにその日に始まる。この変化は,援助を求める電話をかける前にすでに起きていることなので,これを活用しない手はない。たとえクライエントが強制されて面接を受けに来たとしても,あるいは彼女は誰かをなだめるため,例えば夫が彼女を非難するのをやめさせるだけの目的で電話をしてきたに違いないと考えたくなるような時であってもである。彼女が電話をかけようと考え,実際にこの電話をかけてきたということは,今までとは違うことをしたことになる。そして彼女は,今までの試みがうまくいかなかったことを認めたからこそ,そうしたのである。今や行動は起こされたのだから,我々は彼女が回復に向けて既に歩み出したこの重要な一歩を活用する方法を考えなければならない。我々は,この最初の一歩を“治療前の変化”と呼び,クライエントがどうやってこの第一歩をふみだせたのかを,できるだけ知りたいと望んでいる。」
そんな大変な状況で,どうやって電話をしようという気持ちをふるいおこしたのですか?
などといった,例のコンプリメントの質問から,面談が始まるのだろうということが,目に見える気がする。この一文の中に,ソリューション・フォーカスト・アプローチのエッセンスがつまっている。
「臨床現場からの質問」の最初は,
「ソリューション・フォーカスト・セラピーはケア・マネジメントの要請に合うように発展したのですか?」
という問いである。それに対して,
「ソリューション・フォーカスト・セラピーとブリーフ・セラピーとの区別を注意深く付けてください。多くのブリーフ・セラピーは,ケア・マネジメントの要請に合うように発展してきました。ソリューション・フォーカスト・セラピーは,ブリーフ(短期)になるために発展してきたものではありません。このモデルには25年以上の歴史があります。私たちは自分たちのアイデアをいろいろ試してきましたが,そうするとクライエントの回復が早くなっていったのです。技法が洗練されていくにつれ,面接回数が減っていきました。ソリューション・フォーカスト・セラピーの発展のある時点では,意図的に治療を長引かせようともしてみました。この実験は裏目に出て,実際には治療はさらに短くなったのです。ソリューション・フォーカスト・セラピーの手法に従えば,わざわざブリーフ・セラピーを自らに強いなくても,治療は自然に短期になることでしょう。」
と。こうした質問は,もっと切実に,たとえば,
「望んでいるのは運転免許証を返してもらうことだけ,というクライエントが言う時には,どうしたら良いのでしょう?」
という問いに,
「そう望むのは良いことだと考えましょう。運転免許証を取り返すために,州が要求する面倒なことをやろうという人ばかりではないからです。このクライエントは,返してもらうためには何でもしようという動機づけが強いのです。クライエントがこんなふうに言う時には,免許証を返してもらうということについて,カスタマー・タイプの関係性にあります。もちろん,目標を達成するためには,酒をやめるための行動を起こすということを含んだ大変な課題を成さなければならないのですが。」
と応える。そこには,明確に方法の確立したソリューション・フォーカスト・アプローチがある。これと比較して,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/451280217.html?1498593150
で取り上げた,ソリューション・フォーカスト・アプローチの開発者スティーヴ・ド・シェーザーの,手法確立前の試行錯誤のプロセスと比べてみると,その一貫した姿勢と方向性が確立しているのがよく分かる。
本書の前半は,アルコール乱用者へのソリューション・フォーカスト・セラピーによる基本的な対応を整理し,セッション例で,まとめている。このパート1だけで,アルコール乱用者に対しても,いつものソリューション・フォーカスト・アプローチと変らず,コンプリメントがあり,例外探しがあり,ミラクル・クエスチョンがあり,スケーリング・クエスチョンがあり,それでアルコールにも薬物にも対応して解決していく。
後半は,共依存,常習再発者,リソースとしての家族との関係,命令されてきたクライエント等々の特別な治療例を展開する。
たとえば,「命令されてきたクライエント」の章の「臨床現場からの質問」には,
「まったく信じられないデタラメ話を語る,命令されてきたクライエントにどう対処しますか?」
「クライエントがあなたに嘘をつく時にはどうしますか?」
といった興味深い質問にも,ソリューション・フォーカスト・アプローチならではの答えが出る。前者には,
「こんなふうに,止めるのがとても簡単だった(という噓をついているのだが)ということが,あなたにはどうやってわかりますか?」
「あたなにとって止めることがそれほど簡単だということを,(あなたの奥さん,保護観察官)はどんなことから気づくでしょうか?」
という質問で向かう,という。ソリューション・フォーカスト・アプローチらしい対応である。後者だと,
「嘘をつくことで得たいとのぞんでいること,彼らのその望んでいる意を共有するように促す」
という。噓もまた,使えるリソースなのである。
参考文献;
インスー・キム バーグ&ノーマン・H.
ロイス『解決へのステップ―アルコール・薬物乱用へのソリューション・フォーカスト・セラピー』(金剛出版)
|
|
短期療法 |
|
スティーヴ・ド・シェーザー『短期療法 解決の鍵』を読む。

本書を読むと,今日のソリューション・フォーカスト・アプローチを知っているものから見て,ソリューション・フォーカスト・アプローチを確立するまでの,スティーヴ・ド・シェーザーの,エリクソンを出発点として,そのへその緒を引きずりつつ離陸していく様子がよく見える気がする。ときに,MRIの色合いが見えたり,家族療法のシステムズ・アプローチの翳が見えたり,と,さまざまな試行錯誤が垣間見える。
しかし,まえがきで,
「クライエントがセラピストにもちこむ主訴はドアの錠前である,(中略)介入は,解決をひきだすかたちでフィットしさえすればよい。錠前の複雑にところにぴったりと合う必要はないのだ。主訴がこみいっているからといった,解決もこみいっている必要はない。」
と述べ,さらに,
「本書で述べる(中略)モデルは過去に対してはほんの限定された注意しかはらわない。そのすこしの注意は,ほとんどもっぱら過去の成功にむけられる。他の短期療法のモデルとは異なり,このモデルは主訴の細部には,わりに少ししか注意をはらわない。そのかわり,問題が解決したとき,クライエントはどのようにそれがわかるのか,に焦点をあてる。焦点はほかにもあてられる。クライエントがどんな『自分のためによいこと』をしているかに,である。『うまくいっていないもの』に,ではない。」
と,まだそう名づけられてはいないが,ソリューション・トークへと強く意識的に方向づけられている。
本書は,まず,エリクソンの引用から始まる(のもまた象徴的である)。
「エリクソンは,59歳の男の治療について述べている。このひとは右腕のヒステリー性まひで,ついに職を失い年金ももらえなくなるという関連した脅威に直面していた。エリクソンはこの患者につぎのように話した。『あなたの病気は進行性の症状群で,このまま右手を使っていると結局右の手首が凝ってきますよ』。予言のとおり,このマヒは手首がわずかに凝るところまで進行し,男は職場に復帰することができた。エリクソンによれば,このケースや他の似たケースでは,
『じっさいに存在する神経症的能力低下のかわりに,べつのものをもってきた。つまり種類としては比較可能で,能力低下のない性質で,かつ症状的には,建設的に機能するパーソナリティとしてのかれを損なわせないもの,をもって代理させたのである。結果的にはどちらも,その援助と刺激をうけいれ,良好な現実適応が可能になった』
思うに,これこそ短期療法である。≪クライエントがもたらしたものを利用して,その欲求にあわせて,自分で満足できる生活をつくれるようにすることである≫。エリクソンが述べているように,なにか『底にあって原因になっている非適応』を矯正しようとくわだてたわけではないし,なにも必要としなかった。」
こんなエリクソンを手掛かりに,随所で,試行錯誤しつつ,仮説を得ては,それを検証し続けていく。たとえば,
「次のような着想をえた。必要なのは小さな変化。したがって小さな,ほどよい目標だけ,それのみがセラピストとクライエントの協力関係をはるかに容易に発展させるのだ,と。短期療法の他のモデルとのちがいは,短期療法の発想にある。つまり,『どんなにおそろしい状況,どんなに複雑な状況であろうとも,ひとりの行動に一つの小さな変化がおきればよい。それによって,関係するすべての人びとの行動に深い広範な変化を産み出すことができる』という考え方である。(中略)解決が解決であることが解決なのだ。システム内に変化をひきおこすには小さな変化しかいらないのだから,問題と解決をうまく構成するさい人数は関係ない。短期療法家にとっては『患者』が問題なのだ。」
と。これもまた,エリクソンの次の言葉と,反照し合っている。
「あなたのもとへやってくる患者は,自分が『なぜ』きたのか,ほんとうは知らない。だから,くるのだ。かれらは問題をもっている。またもし自分がなんであったか知っていたら,こなかったであろう。自分の問題が『ほんとう』はなにか,知らないから,あなたにも言えない。自分が考えた,ごたごたした説明を述べるしかしようがない。そしてあなたは,『あなた』の背景のもとにそれをきく。だから,かれらの言うことがわからない。しかし,わからないということがわかるだけ,まだましだ。そこで,患者に変化をひきおこす『なにか』をしなければならない…。どんな小さな変化でもかまわない。なぜなら,患者は変化を望んでいる。どんな小さなものでも,変化がほしい。だからそれを『変化』としてうけいれるだろう。かれはその変化の『程度』を,はかることをやめないだろう。それを変化としてうけいれ,その変化に従い,その変化は自分の欲求にしたがって発展するだろう。…あたかも雪玉がころがりおちるようなものだ。小さな雪の玉がころがるにつれて大きくなり…ついにはなだれになって,その山のかたちにおさまる。」
そして,いくつかソリューション・フォーカスト・アプローチの技法として知られるものの端緒も,随所に垣間見える。たとえば,例外。
「新たな反応を選択するさい,この法則の例外を見つけると役立つことがわかった。『なにか別のことなんてまったくない』と言うのは,あまりにも鈍感なようだ。仮にその子のベッドが昨夜もぬれており,一昨夜もまたその前の晩も,となると,『この子は毎晩おねしょする』と,言われてしまう。たくさんもらした晩もあれば,少ししかもらさない夜もあった,というのに。また日によってちがった時刻にもらしたかもしれないし,たぶんシーツがいつもおなじということはなかったろう。いつもおねしょすると見られているけれど,もらさない夜だって時どきはあるだろう。法則の例外である。(中略)これらの例外はしばしば見のがされてしまう。ちがいがあまりに小さく,またあまりにおそいので,変化などもたらすはずがない,と思われているからだ。」
また,今日だと,イエスセットやコンプリメントとして知られるものについても,エリクソンを導き手に,
「治療的暗示の導入を容易にするために,セラピストはほめことばを言う。あなたがしていることは自分のためにとてもいいことですよ,という趣旨を伝えるのである。主訴にかかわることでも,無関係なことでもかまわない。ほめことば,あるいは『おせじ』の目的は,『「はい」の構え』をつくることである。…これは治療的課題や指示のような,新しいものをうけいれる心の枠組みのなかに,クライエントをみちびくのに役立つ,これらの課題,指示,および暗示は,本質的には後催眠暗示として構成されており,避けがたい出来事と,むすびつけられていることが多い。避けられない出来事なので,それが『ひきがね』のはたらきをして,クライエントになにかちがったことをさせることになる。」
と。あるいは,過渡だと感じさせるのに,エリクソンの,
水晶球テクニック,
と呼ぶものがある。著者は,「自己流にこのテクニックを用い」て,
「クライエントに,成功した未来(つまり主訴が解決したとき)の自分の姿を見せる」
ということを試みている。
「わたしは,クライエントをトランスにみちびいて,一つまたは複数の水晶球のなかに自分の未来を見せるだけでも,十分行動の変化をもたらし,解決にみちびきうることを知った。(中略)水晶球テクニック…によって,クライエントは,問題が解決したのちの自分の世界がどんなふうに見えてくるかを知ることができる。『こんなことがおきるといいな!』という期待が,いま進行中のことやこれからはじまろうとしていることを潤色,または『決定』する。(中略)変化がおきるというのは,条件があるかたちで変わる,ということであろう。けれどもその過程自体が期待維持の行動をひきおこすのである。期待はあとにつづく出来事の性質を決定するのに役立つ。したがって,期待が変われば行動が変わることはあきらかだ。」
次の言葉は,実に象徴的である。
「短期療法家は,変化についてクライエントに語るとき,変化がおきるということに関しては疑問の余地を残さない。
これは単純なことばのおきかえの問題である。…『もしも』のかわりに『いつ』を,もってくるのである。『もしおふたりが喧嘩をやめたら,どんなことがおきると思いますか』ではなく,むしろ『おふたりが喧嘩をやめたとき,どんなことがおきると思いますか』なのだ。」
あとは,どうノウハウをスキルとしてメタ化するかだけのように見える。ソリューション・フォーカスト・アプローチは,もうすでにある。
参考文献;
スティーヴ・ド・シェーザー『短期療法 解決の鍵』(誠信書房) |
|
秀秋 |
|
黒田基樹『小早川秀秋』を読む。
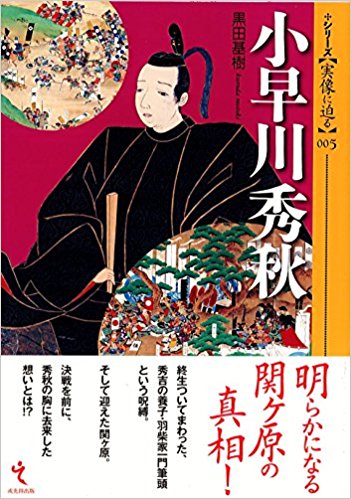
わずか百ページに満たない本である。小早川秀秋(と称したことはなく,羽柴姓でありつづけた)という,僅か二十一歳で世を去った男の人生の薄さのように見える。
著者は,「はしがき」で,「小早川秀秋」について語られるとき,
「そこでの語られ方は,ほぼ一様に,ひ弱で,関ヶ原合戦では江戸方(徳川家康方)と大坂方(石田・大谷方)のいずれに味方するか迷い,あげくには合戦当日に大阪方から江戸方へ寝返り,しかもその寝返り方にすら優柔不断さを発揮し,家康から『問鉄砲』されて漸く実行した,というようなものであろう。
ところが,こうした秀秋に対するイメージは,江戸時代中期以降に成立した軍記物などによって創りだされたものといってよく,それが戦後の歴史小説などで増幅されてきたものであった。」
その秀秋の実像を,明らかにしようというのが本書である。
「秀秋は,秀吉の妻北政所(浅野寧々・高台院,杉原定利の娘・浅野長勝の養女)の実兄木下家定の五男とされる(『藩翰譜』など)。これについては,家定の三男延俊が,秀秋の兄であったことが確かなので,(『兼見卿記』 文禄三年十二月三日条),信用してよいと思われる。
生まれ年には諸説があり,慶長七年に死去したときの没年齢について,『小早川系図』などに二十六歳,『藩翰譜』などに二十三歳,『落穂集』などに二十二歳,『沼田小早川系図』などに二十一歳,などと見える。それぞれ逆算すると,生まれ年は天正五年(一五七七),同八年,同九年,同十年という具合になる。
かつては天正五年説が有力であったが,近年は同十年説が有力になっている。これに関しては,天正十年生まれであることを示す明確な史料がそんざいすることから,同年で確定される。」
と,生まれた年ですら,こんな具合である。
「秀秋が史料に初めて登場するのは,天正十三年(一五八五)閏八月のことである。すでに羽柴(豊臣)秀吉の養子になっていたから,苗字は『羽柴』を称していたとみていい。その後,文禄三年(一五九四)十一月に筑前小早川隆景の養子になって,『小早川』の名字を称することになる。ただし,羽柴政権のもとでは,国持大名・公家成大名は『羽柴名字』を称したので,秀秋は小早川家に養子入りし,翌年家督を継ぐものの,実際には名字は羽柴名字のままであった。」
つまり,「小早川秀秋」と呼ばれているけれども,
「正確にいうと,『小早川秀俊』(と四年半ほど名のっていた)や『小早川秀秋』(後に秀詮と変えているが)と称した人物は存在しない」
のである。存在したのは,
羽柴中納言,
である(所領に応じて羽柴丹波中納言,筑前中納言,備前中納言と称した)。
また,たとえば,よく「金吾(金五)」という秀秋の呼び名についても,
「通称は,仮名と官職名によるものとがあった。元服前から元服後を通じて称していたのが『金吾(金五)』である。『金吾』や『金五』の名は,衛門府の唐名であることから,江戸時代から,右衛門尉ないしは右衛門督に任官したことにともなうものと考えられてきた。しかし,わずか三歳の時点で,しかも元服前の任官は考えられないので,これは幼名もしくは仮名とみるべきであろう。元服前の呼称は幼名として名乗ったと考えられ,それを元服後も称していることから,そこでは仮名として称したと考えられる。」
三歳のとき,秀吉の養子となり,秀吉書状で,
「養女豪姫(宇喜多秀家の妻・前田利家の娘)に続いて,『きん吾も事って申し候』とみえる…。このとき,秀秋はわずか四歳であったから,むしろここにみえる『金五』(金吾)こそが,幼名であったとみられる。」
天正十六年,わずか七歳で元服。従五位下・侍従に叙任され,公家成となっている。
「公家成とは,武士が同官位に叙任され,公家の身分になることをいう。そして,それにともなって『金吾侍従』と称されている。同十七年十一月に丹波国亀山領(京都市亀山市)を与えられて大名となり,同二十年(文禄元年・一五九二)正月に従三位・権中納言に叙任されると,以後は『羽柴丹波中納言』を称している。羽柴政権では,公家成大名の場合,羽柴苗字・領国名・官職名を合わせた呼称をするのが通例となっていた。」
この任官は,織田秀信,羽柴秀長の養子秀保と同時であったが,
「翌(四月)十五日には,諸大名から秀吉に対して,秀吉への忠誠を誓約した連署起請文が提出されるが,その宛名は『金吾殿』とされていて,秀秋に宛てたものとなっている。このことは秀秋が諸大名の秀吉への忠誠を受けとめる立場にあったこと,すなわち,叔父秀長を含む諸大名とは異なる立場にあったことを示している。」
この秀秋の立場は,実子が生まれた後,後継者の地位からははずれても,秀吉の養子として特別な扱いを受け続ける。
「たとえば,(同十八年)五月十四日付で秀吉が北政所にあてた消息(手紙)では,『わかきみ(鶴松)・大まんどころ殿(秀吉母)・五ひめ(豪姫)・きん五・そもじ』と(『小山文書』『太閤書信』),別の消息では『大まんどころ殿・そもし・わかきみ・おつめ(養女,織田信雄の娘・徳川秀忠の妻)・きん五』と(『篠崎文書』),家族を列挙したなかに必ず入っているのである。」
また小早川への養子となるについても,通説とは異なり,著者は,
「この件は隆景から申し出たものであったろう。というのは,秀秋の養子化が決まると,清華衆であった秀秋を養子に迎えるにふさわしく,隆景自身の家格が清華衆に上昇しているからである。すなわち,文禄四年正月までに参議に昇進し,翌慶長元年(一五九六)二月に秀秋同官の中納言に昇進,そして同年五月には清華衆に加えられている。このことをみると,隆景は本来,秀秋を養子に迎えることができるような家格にはなかったことがわかる。また,独立した領国大名であったとはいえ,毛利家の一門にすぎなかった隆景が,秀秋を養子にするのも不釣り合いなことといえる。」
と書く。その秀秋が,関ヶ原で寝返った経緯については,
「毛利勢の中心人物の一人であった吉川広家が,関ヶ原から二日後の九月十七日に記した書状案に,『筑中(秀秋)の御逆意がすでにはっきりした,そのために大柿衆も山中に移り,大谷吉継の陣が心配なため,(これを)引き取った』と記していることが注目される。
これによれば,大柿城にいた石田三成らは,松尾山城に在陣する秀秋が,江戸方の立場を明確にしたので,大谷吉継を守るために関ヶ原に陣を移したのだという。」
とする。とすると,合戦最中に翻意したというのは後世の創作ということになる。
「むしろ当時の史料からは,開戦とほぼ同時に,秀秋は江戸方の立場をとって,大阪方を攻撃したことが明らかになっている。」
約束通り,宇喜多秀家の旧領備前・美作の二国四十万石に加増転封されたが,関ヶ原の二年後,秀秋は,病死する。飲酒によって体を病んでいた,と言う。
それにしても,秀吉の甥秀次といい,北政所の甥秀秋といい,巨大な叔父秀吉によって振り回された一生であった。秀次については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/440783746.html
で触れた。
参考文献;
黒田基樹『小早川秀秋』(戎光祥出版) |
|
ロジャーズ |
|
H・カーシェンバウム&V・L・ランド ヘンダーソン編『ロジャーズ選集』を読む。
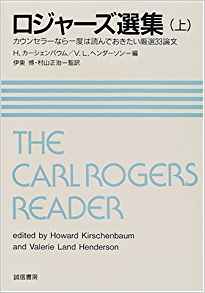
本書は,カール・ランソン・ロジャーズ(Carl Ransom Rkgers)の著作集である。サブタイトルに,「カウンセラーなら一度は読んでおきたい厳選33論文」とある。上巻は,カウンセリング関係の主要論文,下巻は,サイコセラピーで培った科学的研究を,行動科学が適用されている社会的・政治的文脈であり,そこにはスキナーとの長い対話も含まれる。いまひとつは,ハードサイエンスに対する「もっと人間的な人間科学にむけて」という死の直前に書かれた論文に見られるような,人間科学の新しい方向性である。
しかし,こう言っては何だが,やはり上巻のセラピーに関する予見ともいうべき数々の見識には圧倒される。そうか,ロジャーズがとうの昔に言っていたのか,ということに気づかされることが度々あった。
たとえば,ロジャーズは,さりげなく,
「自分自身に他人を理解することを許すことができるならば,それはたいへん価値があることがわかった。こういう言い方は奇妙に聞こえるかもしれない。他人を理解するように自分を許すなどということが必要なのだろうか。私は必要だと思う。私たちが他人の言葉を聞いたときの最初の反応は,たいていの場合,最初は,それを理解することよりも,すぐに評価したり,判断を下したりするものである。誰かが,その感情,態度,信念を述べると,たちまち,『それは正しい』『それは馬鹿らしい』『それは異常だ』『それはおかしい』『そいつは不正確だ』『それは良いことではない』などと私たちは反応する傾向がある。彼の言葉が彼自身にどんな意味があるかを正確に理解しようと自分に許すことはほとんどない。私は,その理由は,理解することが危険なことだからだと思う。他人を本当に理解しようとすると,理解することによって私が変化するかもしれない。私たちは誰でも変化を恐れている。したがって私が述べるように,他人を理解することを自分に許し,他人の照合枠(frame
of reference)のなかで十分に共感して入り込むのは容易なことではない。またそれは稀なことである。」(「私を語る」)
と書く。たしかに,
「他人を理解することを自分に許し,他人の照合枠(frame of
reference)のなかで十分に共感して入り込むのは容易なことではない。」
だからこそ,自らの価値基準を脇に置いて,相手の枠組みの中で相手が考え,見ているものを見ようとする姿勢がなければ,共感はあり得ない(エリクソンは,「相手の枠組み」という言い方をしていたが)。自らに許す,というよりは,覚悟という言葉がふさわしいのかもしれない。
さらに,同じところで,
「人間ひとりひとりが,きわめて現実的な意味で,自分自身という島である。人はみずからすすんで自分自身になろうとし,自分自身であることを許されるならば,そのときはじめて他の島に橋をかけることができるのである。そこで,私が他人を受容するとき,それをもっと具体的にいえば,彼の感情や態度,信念などを彼の生きている現実のものとして受容できるならば,私は彼がひとりの人間になる援助をしているのである。このことにはとても大きな価値があると思われるのである。
次の経験はとても伝えにくい性質のものである。私が自分自身や他人のなかの現実にひらかれていればいるほど,ことを急いで『処理』しようとしなくなってきている。私が自分の内部に耳を傾けようとし,私のなかに進んでいるその体験過程に耳を傾けているとき,そしてまた,その同じ傾聴の態度を他人にも広げようとするとき,それだけで私は,複雑なプロセスを尊重するようになってきている。私は,ただ自分自身になること,他人がその人自身になるように援助することに満足するようになった。(中略)この複雑な人生のなかで,ただ自分自身になろうとすればするほど,自分自身や他人の現実を理解し受容しようとすればするほど,それだけ変化が起こりだしてくるように思われる。非常に逆説的なのであるが,誰でも進んで自分自身になろうとすればするほど,自分が変化するばかりでなく,自分と関係している人たちもまた変化していくのである。少なくともこれは私のもっとも生々しい経験であり,私の私生活や専門職の生活から学んだ最も深い経験のひとつである。」(仝上)
とも書く。この一文の中に,我々のなかで常識としていることが,彼個人の経験のメタ化されたものであることを知らされるのである。あるいは,
「個人が援助を求めにやってくる。正しく認識されるならば,これはセラピーの最も重要なステップのひとつである。その個人はいわば,自分自身にとりかかったのであり,第1に重要な責任ある行為をとったのである。彼は,これが自律的な行為であることを否認したいかもしれない。しかし,もしこの自律的行為が育っていくならば,それはそのままセラピーへと進展していくことができる。それ自体としては重要でない出来事も,セラピーにおいてはしばしば,もっと重要な機会と同じように,自己理解や責任ある行為に向かう基盤を提供することが多い…。」(「より新しいサイコセラピー」)
もまた,ここでも,さりげなく,語られているが,セラピーへくること,あるいは行こうと決意すること自体で,既に大きな変化が起きることは,今日常識である。
あるいは,
「もしクライエント自身が来談した責任を受容しているならば,彼はまた,自分の問題に取り組む責任をも受容しているのである。」(仝上)
「少しずつ,私たちは,敵意や不安の感情の流れ,ひっかかりの気持ちや罪悪感,両価的な感情や決断できない感じ,を阻止しないでいることを学ぶのだが,こうした感情は,もし私たちが,その時間を本当にクライエントのものであり,その人の望むように用いることができる時間であることを,クライエントに感じさせることができるならば,それは自由に流れ出てくるものである。」(仝上)
「カウンセラーの仕事は,さまざまな選択の可能性を明確にするように援助し,その人が経験している恐怖の感情や,前進する勇気の欠如を認識することである。ある行為の方向を強制したり,助言を与えることがカウンセラーの仕事なのではない。」(仝上)
あるいは,
「クライエントの意味づけを『理解する』(understanding)ということは,本質的には理解『しようとする』(desiring to
understanding)態度にほかならない…。」
「信頼されるためには,頑なに一貫した態度をとるのではなく,信頼に足るほどリアルである(dependably
real)ことが必要であることを認めるようになったのである。『一致している』という言葉は,私がそうありたいあり方を表現するものである。この言葉は,私がどのような感情や態度を経験していても,そのことに私自身が気づいていること(awareness)を意味している。」
「私は『気持ちのリフレクション』をしようとは努めていないのである。私はクライエントの内的世界についての私の理解が正しいかどうか―私は相手がこの瞬間において体験している(experiencing)がままにそれをみているのかどうか―見極めようと思っているのである。私の応答はいずれも言葉にならない次の質問を含んでいる,『あなたのなかではこんなふうになっているんですか。あなたがまさに今経験している個人的意味(personal
meaning)の色合いや手触りを私は正確にわかっていますか。もしそうでなければ,私は自分の知覚をあなたのと合わせたいと思っています』と」(「気持ちのリフレクション(反映)と転移」)
等々。それらを整理した,
「セラピーによるパーソナリティ変化のための必要にして十分な条件」
「クライエント・センタードの枠組みから発展したセラピー,パーソナリティ,人間関係の理論」
の二論文は,やはり重い。そして,
セラピー過程の6条件は,いまも厳然として生きている。
①二人の人間が接触(contact)をもっていること。
②一方のクライエントと呼ばれる人間は,不一致(incongruence)の状態にあり,傷つきやすい(vulnerable)か,あるいは不安(anxious)な状態にあること。
③他方のセラピストとよばれる人間は,2人の関係(relationship)のなかで一致の状態にあること。
④セラピストは,クライエントに対して無条件の肯定的配慮(unconditional
positive regard)を経験していること。
⑤セラピストは,クライエントをその内的照合枠(internal frame of
reference)から共感的に理解する(empathic understanding)という経験をしていること。
⑥クライエントは,条件4および,5,すなわち自分に対するセラピストの無条件の肯定的配慮および共感的理解を,少なくとも最低限に知覚していること。
それにしても,ロジャースは,自分の考えを「仮説」と呼んだ。ロジャーズの,
「すべての人間は,自分自身のなかに,個人的にも満ち足りた,社会的にも建設的な方向に,自らの人生を導いていく能力をもっている。」
「「個人は自分自身のなかに,自分を理解し,自己概念や態度を変え,自己主導的な行動をひき起こすための巨大な資源をもっており,そしてある心理的に促進的な態度について規定可能な風土が提供されさえすれば,これらの資源は働き始める」
という,彼の「仮説」を,彼は57年間にわたって,自ら検証したのだと,つくづく納得させられる。
参考文献;
H・カーシェンバウム&V・L・ランド ヘンダーソン編『ロジャーズ選集上下』(誠信書房) |
|
自己分析 |
|
K・ホーナイ『自己分析』を読む。
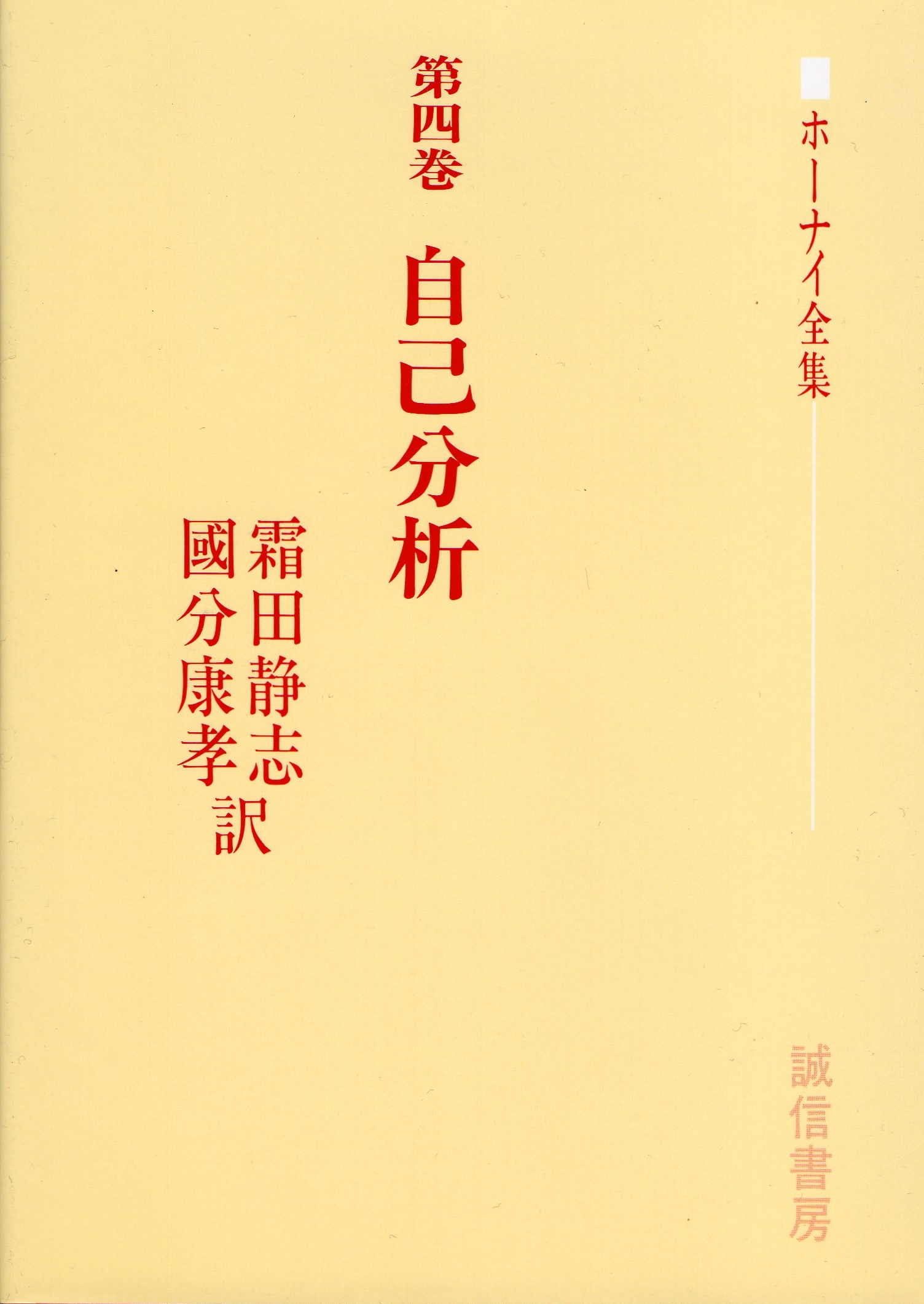
本書の自己分析とは,セルフ精神分析を指す。いわゆる「自分を知る」という類の自己分析ではない。
著者は,「まえがき」で,精神分析の必要性が高まっているが,精神分析の専門的援助をすべての人にはカバーできない,とした上で,
「自己分析が重視されるのはこのためである。『自分を知る』ということは,ただ結構なことであるというだけにとどまらず,それはまた可能であると,これまで考えられてきた。その努力が分析的諸発見によってい大いに助けられたことは否めない。一方,精神分析の発見こそが,自己を知るという精神分析的な自己検討の可能性を論ずるには,楽観と同時に謙虚さが要求されるのである。」
と述べて,
自己分析の手順,
を提起する本書の試みを位置づけている。そして,冒頭で,(精神分析的な)
自己分析は可能か,
という問いに,
「分析とは個人を内なる束縛から解放させて,彼自身の潜在能力を最高度に発揮させることである。(中略)以上のように精神分析の積極的な目標を立てることは,患者に次のような意欲がありさえすれば確かに実際的な価値がある。すなわち,自分の有する才能がたとえどんなものであろうと,それを伸ばそうとするきわめて旺盛な意欲である。つまり天与の才を具現させていく意欲,きびしい試練にときには出会うであろうが,それでもなお,自己を把握理解しようとする意欲,要するに成長しようとする意欲,これである。」
というのが,「分析を促進させる原動力」となる,と著者は書く。さらに,専門的分析者には,
第一に,無意識的欲求の性質,無意識的欲求の顕現法,無意識的欲求の原因,無意識的欲求の影響,無意識の解明など,心理学知識が必要,
第二に,一定の訓練を経た技能,
第三に,分析者自身の徹底的な自己認識が必要,
の資格が要ると,著者は挙げるが,自己分析の場合,他人を分析するのとは違い,
「われわれ一人ひとりの世界は,われわれにとって未知のものではない,という事実である。実際われわれが本当に知っているのは唯一人だけである。たしかに神経症者は現実の世界の大部分から隔たり,現実の世界を見まいとする気持ちにかられている。さらにまた神経症者は自分について熟知しているので,ある重要な要因を重視しすぎる危険がある。しかしそれは彼の世界であり,それについては彼は多少なりとも知っており,その世界に近づくために彼は観察し,この観察を利用するという事実は変わりがない。もし彼が自分の障害の原因を知ることにも興味があり,それを知る際の抵抗を克服できれば,ある点では第三者よりも上手に自分を観察できる。結局彼は自分自身と朝晩つき合っているわけである。それ故,自己観察は,ちょうど頭のいい看護婦が終始患者と一緒にいるのにたとえられるだろう。」
として,専門分析者の資格のうち,第一を軽視し,第二を廃止できる,という。
「自己分析の非常なむずかしさは,これらの知識や技術にあるのではなく,無意識的欲求に対してわれわれを盲目にしてしまう感情的要因にある。つまり,自己分析の主な障害物は知的なものよりは感情的なものである。」
だから,自己分析の障害は,
理論的,
でもないし,
危険性,
でもない。むしろ,
「自己分析実施中の人がまだ自分の耐えられないほどの洞察を引き出すような自己観察をしないことがある。あるいはその観察の中心点のはずれた解釈をあたえることもあろう。あるいはまた自分がまちがっていたと感じた態度を手早く表面的に訂正しようとするだけで,それ以上の自己探究は放棄してしまうこともあろう。つまり,自己分析における実際の危険性は,分析者による分析よりは少ないのである。というのは,分析者,しかも敏感な分析者が,まちがって時期尚早の解釈を患者に与えるのにくらべれば,自己分析では患者は直観的に何をさけるべきかをしっているからである。」
と,分析が浅いとか,中途半端とか,といった限界の方が大きい,と著者は言う。そして,多く成功した自己分析は,多く,
「自己分析を試みる前に分析を受けていたということである。ということは,彼らは分析方法に通じており,また自分に対し容赦なくかつ忠実なことが効果があることを経験的に知っていたことである。そのような前経験なしに自己分析は可能かどうか,またその程度はどうかが,未決の問題としてのこされなければならない。しかし,次のような勇気づけられる事実もある。それは分析的処置を受けにくるまでに自分の問題に正確な洞察を得ている人がたくさんいるということである。」
と。で,一番効果ある自己分析は,
精神分析過程に生じる長期の休止期間中,
だと,著者はいう。専門家による,精神分析とセットの自己分析が,もっとも効果がある,ということになる。自己分析手順の,
臨時的自己分析,
と
系統的自己分析,
と紹介された方法の中では,前者は,
「健全と神経症的との間には,画たる境界線があるわけではないから」
機能性頭痛,
不安発作,
機能性胃痛,
恐怖,
立腹,
といった,強度の神経症ではない,日常起きるちょっととしたトラブルは,
自己理解の一歩,
として有効であるように見える。著者は,
「自分の能力を最高度に伸ばそうとする深い,もっと積極的な意欲とは異なる」
とはいうが,起こっている自分を通して,自分の怒りの対象が,相手ではなく,自分自身(の性格や隠れた要求)であることに気づくなど,それなりの自己理解の一助にはなる。
しかし,終始気になったのは,自己分析例の中で随所に出てくる,自己分析に対する,浅いとか,見落としたとか,といった評である。その著者の姿勢にほの見える,アドラーに感じたのと同じ,自分に正解がある,という姿勢である。
アドラーについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/395411257.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/437675329.html
で触れた。もちろん時代の制約もあるが,ロジャーズの次の言葉が,反照のように浮かんでくる。,
「『それはこうである』と言うよりも,私たちは『それはこうだと思う』という言い方をしたいと思っている…。」
「自分自身に他人を理解することを許すことができるならば,それはたいへん価値があることがわかった。こういう言い方は奇妙に聞こえるかもしれない。他人を理解するように自分を許すなどということが必要なのだろうか。私は必要だと思う。私たちが他人の言葉を聞いたときの最初の反応は,たいていの場合,最初は,それを理解することよりも,すぐに評価したり,判断を下したりするものである。誰かが,その感情,態度,信念を述べると,たちまち,『それは正しい』『それは馬鹿らしい』『それは異常だ』『それはおかしい』『そいつは不正確だ』『それは良いことではない』などと私たちは反応する傾向がある。彼の言葉が彼自身にどんな意味があるかを正確に理解しようと自分に許すことはほとんどない。私は,その理由は,理解することが危険なことだからだと思う。他人を本当に理解しようとすると,理解することによって私が変化するかもしれない。私たちは誰でも変化を恐れている。したがって私が述べるように,他人を理解することを自分に許し,他人の照合枠(frame
of reference)のなかで十分に共感して入り込むのは容易なことではない。またそれは稀なことである。」
参考文献;
K・ホーナイ『自己分析』(誠信書房)
H・カーシェンバウム&V・L・ランド ヘンダーソン編『ロジャーズ選集下』(誠信書房) |
|
破綻 |
|
服部茂幸『偽りの経済政策―格差と停滞のアベノミクス』を読む。
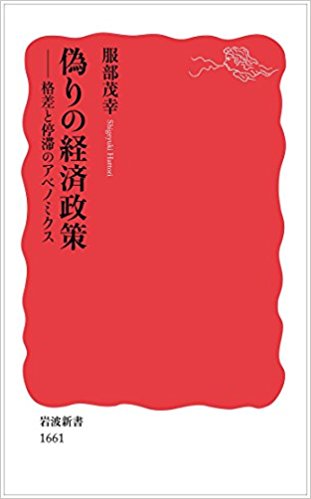
現在の日銀の金融政策を遂行しているのは,これまで日本銀行が積極的に金融緩和を行わずデフレを放置したとする,いわゆるリフレ派の経済学者による(黒田=岩田)体制である。しかし,四年が経過しても,デフレ脱却の公約は果たされていない。そこには,政策の破綻と,彼らの理論の破綻がある。しかし,恥ずかしげもなく,目標期限が来るたびにそれを先延ばしするのを五回も繰り返し,外的要因に責任転嫁している。これについて,
「黒田=岩田日銀はデフレ脱却に失敗した。しかし,これでは国民に嘘をついたことになる。そこで,物価が上昇していないのは,外的要因の結果であって,異次元緩和は成果を上げていることにした。ここでも,政策の正当化に反事実的推論が使われているのである。」
と皮肉る。反事実的推論とは,
「相関関係や事象の同時性は因果関係を意味しないことは科学の基本である。例えば,ある政策を実施した時に,経済が10%も落ち込んだとしよう。しかし,ある政策がとられなければ,経済の落ち込みが15%だったとすれば,政策は経済を5%も改善したことになる。反事実的推論自体は科学的な方法である。
しかし,管理された実験が行われない限り,反事実的推論は単なる推論でしかあり得ない。実際のアメリカ経済の回復が遅くても,ある意味政策が実施されなければ,もっと回復が遅れたと主張することによって,どのような政策でも正当化できるだろう。」
というものだ。どこか,安倍首相の使う論理に似ている。
本書の著者は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/405050518.html
で触れた前著『アベノミクスの終焉』で
「アベノミクスの下で経済が順調に成長していると思われていた。けれども,経済成長を支えているのは,政府支出,耐久消費財と住宅投資にすぎない。2014年4月に消費税増税が行われた後,反動減で耐久消費財と住宅投資が急減するのは目に見えている。政府投資も14年度には横ばいと,日本の政府自身が見込んでいる。14年度には経済成長が挫折する。消費者物価上昇率もプラスに転じたが,これは円安による輸入インフレの結果に過ぎない。円安が止まれば,デフレに戻る。」
と見通した。そして,
「今では消費者物価上昇率はほぼゼロか,マイナスに転じ,経済も停滞している。」
「アベノミクスが消費税増税のために挫折したという責任転嫁の議論は正しくない。(中略)消費税増税が経済の回復に水を差したのではない。駆け込み需要と政府支出でかさ上げされていた経済が,元に戻っただけである。」
として,こう結論づける。
「アベノミクスと日銀の金融緩和の物語は単純である。それは,デフレ脱却にも,実体経済の復活にも失敗した。けれども,それでは国民をだましたことになってしまう。そこで,彼らはデフレ脱却に失敗した責任を消費税増税後の需要の弱さ,原油価格の世界的急落,2015年夏以降の新興国の経済の減速に押しつけた。
筋の通らない話である。金融政策が適切に行われていれば,デフレが回避できるし,デフレが解決できれば日本経済は復活できるとして,彼らは現在の地位につくまで,日銀を批判してきた。その彼らがデフレと経済停滞の原因を外的要因に押しつけている。これまでの批判は何だったのだろうか。彼らは責任転嫁によって,自らの理論を否定しているのである。」
つまりは,リフレ理論の破綻とその理論に基づく金融政策の破綻である。それはアベノミクスの破綻の露呈でもある。著者は,
アベノミクスの成果と言えるものは存在しない,
と断言する。
消費者物価上昇率はゼロか,マイナスで,アベノミクス以前と同じ状況,
雇用の回復も,実際に増加しているのは短時間就業者で,長時間就業者は逆に減少している,
企業の利益も,生産も売り上げもその増加はわずかで,円安や原油安による名目的な要因に過ぎない,
と。さらに,
「政府・日銀の認識では,現在の日本経済は緩やかな回復過程にある。経済成長率は,1%程度で低いが,プラス成長だから,この認識は間違っているわけではない。しかし,一部の時期を除くと,アベノミクス前の日本経済もこの程度の成長は実現できていた。だから,ゆるやかな経済回復がアベノミクスの成果だとは思わない。」
では成果は何か。
富裕層の所得と富の拡大,
である。アベノミクスによる株価上昇により,
「純資産一億円を超える富裕層・超富裕層の世帯は,2011年の81万世帯から,15年には122万世帯に増加した。純金融資産総額も188兆円から272兆円へと急増した。その結果,世帯数では2%の富裕層・超富裕層が純金融資産の二割を占めることになった。『もともと富裕層および超富裕層の人々の保有資産が拡大したことに加え,金融資産を運用(投資)している準富裕層の一部が富裕層に移行したため』と野村総合研究所は述べる。」
つまり,
「アベノミクスは富裕層の所得と富の拡大に大きな貢献をした」
のである。で,結論は,
「アベノミクスが始まってから,どの世論調査でも景気回復の実感がないという回答が一貫して七割かそれ以上を占めている。大部分の家計は労働をして,給与を受け取り,生活をしている。物価上昇に給与が追いつかない状況では,多くの国民の生活は改善するはずもない。大多数の国民の実感は実態を反映しているのである。
アメリカに倣った政策がアメリカと同じような賃金停滞と,所得と富の集中を作り出すのは不思議なことではない。」
この政権下,紙幣を刷りまくり,膨大な政府支出を繰りだしても,実体経済は,その前の民主党政権時代を超えていない。この四年余はいったい何であったのか。このつけは,後の世代につけ回される。既に,滅びの予感がしてならない。
参考文献;
服部茂幸『偽りの経済政策―格差と停滞のアベノミクス』(岩波新書) |
|
羽柴 |
|
黒田基樹『羽柴を名乗った人々』を読む。
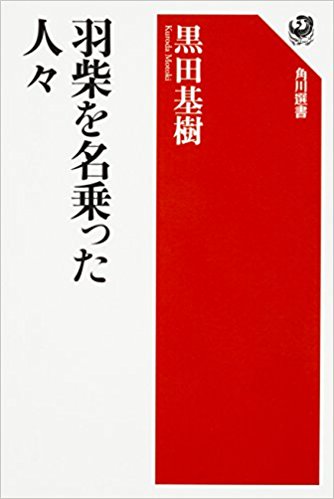
この十年,羽柴政権(と著者は命名する。その理由は後述)に関する政治史研究が本格的に進められるようになった,と著者は別のところで書いていた(『小早川秀秋』)。本書はそういう中の一つと見ていい。
著者は,「はしがき」を,
「羽柴(豊臣)秀吉の政権時代,有力な大名たちの名字(苗字)はすべて『羽柴』であった」
と書きはじめ,そして,
「秀吉の死後,政権の執政に関わった,いわゆる『五大老』たちは,一般的には徳川家康・前田利家・宇喜多秀家・毛利輝元・上杉景勝と表記されているが,当時は正式には『羽柴家康』『羽柴利家』『羽柴秀家』『羽柴輝元』『羽柴須景勝』と名乗っていたのである。」
と述べる。つまり,羽柴の名字は,一門だけではなく,
「姻戚関係にあった大名(親類大名),織田家出身の大名,旧織田家家臣の大名,さらには旧戦国大名の有力者も,相次いで秀吉に服属した後に,秀吉から『羽柴』の名字を与えられ,それを名のっていた。そのため秀吉の政権時代,それら有力大名を列記した史料をみると,まさに『羽柴だらけ』の状態にあったのである。」
このことと,「豊臣」姓を与えられたこととの関係は,次のようになる。
「秀吉は関白に任官すると,天皇から新たに創始された『豊臣』姓を与えられた。(中略)一般には,『豊臣』姓を与えられたことは,『羽柴』から『豊臣』への『改姓』といわれているが,これは正しくない。『豊臣』は『氏(あるいは姓)』であり,名字である『羽柴』とは性格が異なっている。(中略)したがって秀吉の『改姓』は,『藤原』姓から『豊臣』姓へのものであり,名字である『羽柴』からのものではない。そしてその後も,秀吉が『羽柴』の名字を改めたというような事柄はみられていないので,彼の名字は死ぬまで『羽柴』であったのであり,その後継者である秀次や秀頼も,同様であった,と考えるべきなのである。」
いうまでもなく,この「羽柴」という苗字は,秀吉の創ったものである。俗に,
「織田家の重臣である丹羽長秀と柴田勝家にあやかり、丹羽の『羽』と柴田の『柴』を1字ずつもらってつけたという話は有名であるが、史料的な根拠は何もない。
井沢元彦は『柴田と丹羽の当時の織田家内の立場からしても、2人を同格としてそれぞれから一字ずつもらうというのは、あり得ない。これは『羽柴=端柴、つまり自分は柴の木の切れ端のような取るに足らない存在です』ということを主張し、自身の出世への周囲の嫉妬を避けるための改名ではないか』と推測している。」
いずれにしても,秀吉が勝手に作り出したものに過ぎない。秀吉の名が,
「現れた最初の史料は、永禄8年(1565年)11月2日付けの坪内利定宛て知行安堵状であり、『木下藤吉郎秀吉』として副署している(坪内文書)」
さらに,それが羽柴と,改める,
「最初の例は、元亀4年(1573年)7月20日付で大山崎惣中に縄の供出を求めた書状(『離宮八幡宮文書』)であり『羽柴藤吉郎秀吉』と署名している。『信長公記』では、元亀3年7月24日条に近江一向一揆掃討の指揮官として『木下藤吉郎』の名を記し、同年8月条では虎御前山に建設された砦の『定番(じょうばん)』として『羽柴藤吉郎』の名を記す。」
ところからだ。「豊臣」は,源平藤橘の四姓と同じく姓という訳である。だから,徳川家康なら,
源家康,
であり,織田信長なら,
平信長,
となる。だからは,羽柴秀吉は,初め平氏を自称するが,近衛家の猶子となり藤原氏に改姓した後、豊臣氏に改め,
豊臣秀吉,
となった,ということになる。
で,著者は,
「本書では,秀吉らの名字は,あくまでも『羽柴』で表記する。また秀吉の政権については,学術的には『豊臣政権』の呼称が定着しているが,…本書においては『羽柴政権』と表記することにしたい。」
と述べる。本来なら,「豊臣政権」という呼び方とレベルを合わせるなら,「平政権」と呼ぶべきを,「徳川政権」と呼ぶ以上,著者の主張は,首肯出来る。
「羽柴苗字を称している大名たちは,いずれも『○○侍従』『○○少将』というように,官名でよばれている。『侍従』は天皇の居所に出入りして,天皇に対面できる官職であり,そうした立場になることを『昇殿』といっていた。そしてこの『昇殿』できる身分を『公家』といった。すなわち『侍従』以上の官職にあるものが『公家』と呼ばれていたのである。したがってこれらの大名は『公家』でもあったのである。ただし彼らは武家の大名であつたため,本来の公家衆とは区別されていて,そのため『新公家衆』とか『武家公家衆』などと呼ばれていた。」
このように,侍従以上の官職に任官して,公家になることを,
公家成,
と呼び,公家成した大名を,
公家成大名,
と称した。これを始めたのは,関白になった秀吉が,
「初めて参内する際に,大名たちを供奉させるにともなって,主要な大名たちを侍従以上に任官したことに始まっている。」
そして,それと同時に,
「公家成大名に羽柴苗字を与えて,『羽柴』を名のらせていったのである。これは羽柴政権が,関白職によって表現されたことに基づいて,官位序列を政権内の政治序列に適用したためであった。これによって秀吉は,全く新しい武家の政治序列の方法を創り出し,前代の織田政権以来の政治秩序の改編を行ったのである。」
と。この秩序見ることで,各大名の位置づけが見直される。後に,羽柴後継者を抹殺することになる徳川家康について,
「文禄三年二月から九月までの間に,秀吉から羽柴名字を与えられて,『羽柴武蔵大納言』『羽柴江戸大納言』と称した…。そして羽柴名字の性は豊臣姓であったから,羽柴名字を与えられたと同時に,豊臣姓を与えられて,それを称したと考えられる。」
そして嫡子秀忠は,秀吉の養女小姫(織田信雄の娘)と婚約し,秀吉の秦類聚名物考として扱われることになった。こうした経緯から,
「家康・秀忠父子は,羽柴一門衆に匹敵する政治的立場を認められていた存在,とみることができる。(中略)慶長三年(1598)の秀吉死去時,羽柴家の一門衆は小早川秀秋一人を残すのみとなっていた。しかし家康・秀忠父子は,それに準じた存在であったとみることができる。」
と。この秀吉の政権秩序から,従来とは違った,公的な序列が見えてくるような気がする。
本書は,羽柴名字を名乗った大名を,
・秀吉の一門大名(羽柴秀長・秀保/羽柴秀次/羽柴(小吉)秀勝/羽柴秀俊(小早川秀秋))
・秀吉の親類大名(宇喜多秀家/結城秀康/前田利家・利長(利勝)利政/徳川家康・秀忠/京極高次/京極高知(生双)/木下勝俊/某 秀弘/青木重吉/福島正則・正長・忠清(忠勝))
・織田家(織田秀信/織田秀雄/織田信兼/織田長益・頼長/織田信秀/織田信高/織田信吉)
・旧織田家臣(堀秀政・秀治・秀隆(忠俊)/堀秀家(秀成・親良)/滝川雄利・正利/丹羽長重/長岡(細川)忠興・忠隆/蒲生氏郷・秀隆(秀行)/蜂屋頼隆/毛利秀頼/稲葉貞通・典通/津川(斯波)義康/長谷川秀一・秀康/前田秀以・茂勝/佐々成政/筒井定次/池田照政(輝政)・照直(利隆)/森忠政)
・旧戦国大名の人々(上杉景勝/大友吉統(義統)/長宗我部元親・盛親/島津義弘・忠恒(家久)/立花統虎(親成・宗茂)/龍造寺政家/毛利輝元・秀元/小早川隆景・秀包(秀直)/吉川広家/宗吉智(義智)・義成/佐竹義宣/最上義光・義康/伊達政宗/里見義康/宇都宮国綱)
と辿る。豊後国の戦国大名・大友義統を,羽柴名字,豊臣姓にしたことについて,
「公家に迄させられ,御一門に仰せ付けられ候」
と述べているように,それは,
「旧戦国大名を,羽柴名字を与えることで『御一門』に位置づけて,いわば羽柴家の論理によって秩序化しようとしていた」
ものであり,それは,徳川政権になって,松平姓を与えることにつながっていく。
参考文献;
黒田基樹『羽柴を名乗った人々』(角川選書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E6%9F%B4%E6%B0%8F |
|
落日 |
|
大西康之『東芝解体−電機メーカーが消える日』を読む。
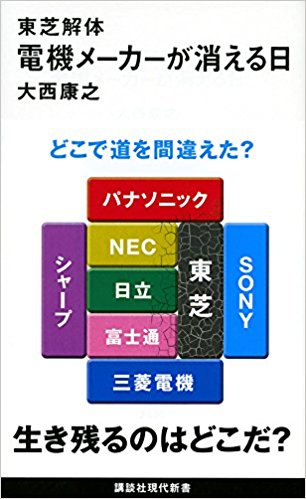
モノづくり大国という言葉が空々しくなったのは,いつからだろうか。半導体で起きたことは,携帯電話で置き,携帯電話で起きたことは,家電で起き,それはやがて,自動車でも起きるのではないか。本書の中で,シャープを買収したホンハイと日本電産の関係について,こんなことを書いている。
「仮に(ホンハイと日本電産が)手を組んだとしたら,2人はどこへ向かうのだろう。(中略)現時点でもっとも可能性が高いのは電気自動車(EV)ではないか。日本電産のもつモーター技術とホンハイの生産力,そこに電子部品,通信,液晶といったシャープの技術力を加えれば,価格競争力の高いEVの量産が可能になる。
内燃機関を持たないEVの生産工程は,ガソリン車よりはるかにシンプルだ。床の下に電池を貼り,車輪の周りにモーターをつければ走り出す。組み立て工程は,自動車というよりスマホに近い。ガソリン車に比べ,新規参入のハードルははるかに低い。
それでもホンハイと日本電産だけでは自動車事業を立ち上げるのは難しいかもしれない。そこで生きてくるのがテリー(ホンハイ会長)の人脈だ。
「iPhoneの次は車を作ってみないか。」
2015年,EV大手テスラーモーターズの創業者,イーロン・マスクがテリーにこう持ちかけたことが米国の新聞紙上で報じられた。『冗談半分で』というニュアンスだったが,あながちそうとも言い切れまい。(中略)
テスラが加われば,EVに欠かせない電池の問題も解決する。テスラはパナソニックと合弁で米国に巨大なリチウムイオン電池工場,ギガファクトリーを立ち上げつつあるからだ。
テリーの人脈から推測されるもう一つの可能性はアップルだ。アップルはiPhoneの限界を突き破るべく,2019年からEV市場への参入を目指している。」
グーグルが自動運転車で自動車産業への進出を進めている。これから必要なのは,モノづくりではなく,ITとネットである。
「日本のIT,ネット産業における最大の問題は,先行する米国勢を追撃する企業がないことだ。」
と。
本書は,エピグラフに,
Survival of the Fittest(適者生存)
という言葉(ハーバート・スペンサー)を載せる。日本企業は,最先端部門ですでに敗退している,と僕も思う。それは,
変化する力
の欠如だ。日本企業の惨状を尻目に,生き残りを果たした企業の例を,たとえば,ノキア。
「2011年まで従来型携帯電話で世界シェア1位だったフィンランドの通信機器大手のノキア。同社はスマホへのシフトが遅れて2013年に経営危機を迎えた。2014年には主力の携帯端末事業を米マイクロソフトに54億4000万ユーロ(約6500億円)で売却し,事業領域を通信インフラに絞り込んだ。この時日本では『ノキアは終った』とまで言われた。
しかしノキアはその後,シーメンスとの通信インフラ合弁会社を完全子会社化し,2016年には最大のライバルである仏米合弁のアルカテル・ルーセントを156億ユーロ(約2兆円)で買収した。現在ノキアは世界最強の通信インフラ企業」
であり,
「同市場で世界ナンバーワンに浮上した。世界の通信インフラ市場は,ノキア,エリクソン(スウェーデン),華為技術(中国)の3強」
なのである。また,かつてはCDの規格をつくったオランダの電機大手フィリップスは,
「1990年代に経営危機を迎え,2000年代初頭には半導体やテレビから撤退した。(中略)だがフィリップスは死んではいなかった。デジタル機器の事業を売却して得た資金で医療機器メーカーを次々に買収し,今や『医療のフィリップス』に生まれ変わり,電機メーカーだった頃よりもはるかに高い利益率を叩き出している。(中略)2013年5月,フィリップスは正式にロイヤル・フィリップス・エレクトロニクスからロイヤル・フィリップスに変えた。」
一方,日本の家電メーカーはどうかというと,いまの東芝のように,切り売りしつつ縮小再生産をし続け,消滅しつつある。ただ,わずかに生き残りの可能性のあるのを,
ソニー,
と
三菱電機,
と,本書は言う。
「世界にはプレステのユーザーが数千万人いる。その数千万人がネットを介してソニーのプラットフォームにつながっているという事実は大きなアドバンテージである。VR,AI(人工知能)など持ちうる全ての技術をそそぎ込み,世界をアッと言わせるリカーリングビジネスを生み出せば,物づくりの呪縛から解き放たれたソニーは再び輝きを取り戻すかもしれない。」
リカーリングビジネスとは,
「『商品を打って終り』のメーカーから,利用者・へのサービスを通じて継続的に利益を上げる」
ビジネスを指す。
「ネットを使ったリカーリングで薄く広く稼ぐ企業を『プラットフォーマー』と呼ぶ。代表的なプラットフォーマーはアップル,グーグル,フェイスブック,ツイッター,アマゾン・ドット・コムなどだ。
三菱電機は,
「デジタル分野での消耗戦を避け,得意のFAに資源を集中した」
ことで,「世界では当たり前」の経営で生き残りを果たしている。そして,結果として,「機械メーカー」に変身した。この電機メーカーから転身しつつある二社を除くと,結果として,日本の電機メーカーは,ほぼ絶滅しつつある,ということになる。
本書は,「おわりに」で,
「お気付きの方もいると思うが,本書のモチーフは第二次世界大戦における日本の敗北の原因を組織論で解き明かした『失敗の本質−日本軍の組織論的研究』である。」
と述べているように,日本企業の組織論的研究にもなっている。恐竜が絶滅,というより鳥に進化していったように,日本企業も生き残りをかけて,変身しない限り,生き残る可能性はほとんどない。
東芝の章で,本書は,
「戦後の高度経済成長期に水俣病を引き起こした『チッソ』が公害の代名詞として記憶されたように,『東芝』の名は原子力ムラの墓標として歴史に残るだろう。」
と締めくくる。
参考文献;
大西康之『東芝解体−電機メーカーが消える日』(講談社現代新書) |
|
メタ・メッセージ |
|
ポール・L.・ワクテル『心理療法家の言葉の技術―治療的なコミュニケーションをひらく』を読む。

著者は,「訳者(杉原保史)あとがき」によると,
「ニューヨーク大学で教鞭をとる臨床心理学者であり,心理療法家である。心理療法家として彼は対人関係論的な精神分析の立場から出発したが,早くから行動療法や家族療法に対しても開かれた態度を取り,これら多学派の心理療法をも真剣に考察する中で,もはや自学派の伝統にとどまることができなくなり,循環的力動論という新たな治療体系を提唱するに至っている。」
とある。本書の意図は,明確である。『日本語版』への序文で,著者は
「本書のかなりの部分は,微妙な言葉のあやについて論じています。つまり,何かを言葉にする際のちょっとした違いが,その治療的影響力(非治療的影響力)に大きな違いをもたらしうるということを論じています。また同様に,本書のかなりの部分は,同じ内容のメッセージでも,違った形で伝えられると,その情緒的なトーンは大きく異なってくる,ということを論じています。」
と述べ,本書の焦点が,治療的コミュニケーションにおける,治療者の言葉のもつ,
焦点メッセージ(focal message),
と
メタ・メッセージ(meta-message),
にあることを明確にしている。「焦点メッセージ」とは,
治療者が自分が伝えていると考えているもの,
つまり,
メッセージの内容である。それに対して,「メタ・メッセージ」と著者が呼んでいる概念は,メタ化されたメッセージではなく,
治療者がしばしば知らぬうちに,あるいは,無意識のうちに伝えているもの,
つまり,
メッセージの情緒的で関係的な側面,
を指している。それは,たとえば,
治療者がその患者を好きかどうか(尊重しているかどうか),
その患者がしたことや言ったことを承認しているか不承認か,
患者の変化の可能性について楽天的か悲観的か,
その患者に情緒的に関与しているか距離があって情緒的に関与していないか,
等々を含んでいるという。セラピスト―クライエント関係でのコミュニケーションと言えども,
相手に伝わったことが自分が伝えたことだ,
という原則は変わらない。治療家が自分のコミュニケーションおいてどうすれば,伝えるべきことを伝えられるか,伝えるべきでないことを,伝えないようにするか,というとき,
何を,
に焦点が当たるが,
どのように伝えるか,
どういう言い回しにするか,
が重要になる。僅かの言い換えで,ニュアンスが大きく変わる。本書は,事例に基づいて,具体的に展開される。ただ,精神分析出自であるために,精神分析を強く意識し,正統はからの批判に対する反論を縷々展開する部分は,時に,煩雑という印象を受ける。
当然,メタ・メッセージには,言葉だけではない。ノンバーバルの,声や振る舞い,表情なども含まれる。
「タイミング,声のトーン,ボディランゲージ,これらすべてが治療者の言葉かけの影響力に実質的に寄与している。(中略)しかしその中でもわれわれが最もコントロールしやすいのは言葉である。われわれにとって,声のトーンについて気づいたり検討したりするよりも,言葉について気づいたり検討したりする方が容易である。」
本書では,メッセージの伝え方に焦点が当てられている。
ところで,著者は,セラピストが使う,
クライエント,
という表記をしない。「患者」とするに至った理由を,
「患者という言葉のラテン語の語源は『苦しむ者』であるが,クライエントという言葉の語源は『依存する者』」
だとワークショップの参加者から示唆されたからだという。
「『クライエント』という用語は,その関係の職業的な側面を強調しすぎる…。たとえば公認会計士はその取り組みの相手をクライエントと呼んでいる。心理療法家がそれと同じ言葉を用いるのは,私には満足のいかないことと感じられる…。(中略)患者という言葉が相手の品位を傷つけたり見下したりするような意味合いを帯びているかもしれないという理由からこの言葉を避けるのであれば,それに代わってクライエントという言葉を選択するのはあまり適切とは言えない。」
ここにも,著者の「本書のテーマ」である言葉の内容とそれのもたらす陰翳についてのひとつのこだわりが見受けられる。たしかに,来談者は,クライエント(依頼人)ではないし,クライアント(顧客)でもない。
著者が示す例を見ていくと,興味深いことに気づく。たとえば,「患者」の,
強さ認めようとするところ,
小さな変化を認めて伝えるところ,
僅かな変化を言語化するところ,
等々で,
何がそれを可能にしたのでしょうね?
という問いなど,
そんな大変な中で,どうしてそんなことができたのですか?
というソリューション・フォーカスト・アプローチのコンプリメントですることとほとんど同じである。あるいは,
患者の物語をリフレーミングして見せるところなどで,
「もしそれが患者にとって説得力があり,患者の一貫性の感覚を増大させ,人生の物語を見直させて新しい可能性の扉を開くような,患者の人生についての新しい理解を伝えているなら,それはよい解釈なのである。」
というところは,ナラティブアプローチと差はない。あるいは,
「患者の生活体験を形成し媒介している,感情を帯びた表象を患者が再構築するのを助けることがいかに重要だとはいえ,この道筋からだけでは持続的で意味のある変化は得られない。内的表象の変化と並行して,患者の顕在的な行動が変化しない限り,つまり患者の困難の中心を占めてきた悪循環が変わらないかぎり,どのような内的表象の変化も不安定かつ束の間のものにとどまるであろう。」
と,悪循環を断とうとするところなどは,MRIと指向は変わらない。結局,セラピーの最前線での問題意識は,ほとんど変わらないのだ,ということに気づかされる。
さてしかし,言葉の技術にのみ力点を置けばいいのか,ということについて,捕逸の著者(エレン・F・ワクテル)は,末尾で,こう釘をさすことを忘れない。
「結局のところ,いかかなる心理療法的アプローチもそれを行っている治療者次第なのである。心理療法は厳密科学ではない。心理療法においては,完全に明瞭に説明することなど不可能なニュアンスに対する感受性が要求される。また,どの学派のそれであれ,心理療法というものは広大でまだほとんど探究されていない領域についての非常に暫定的な地図にすぎない,ということを進んで認める姿勢が要求される。本書に記述されている治療的コミュニケーションの諸原理は治療実践家にとって非常に有用なものであり,幅広い事例において治療者の能力を高めてくれるものだと私は信じているけれども,それらは決して優れた治療家を特徴づける個人的な諸特性の代わりになるものではない。」
参考文献;
ポール・L.・ワクテル『心理療法家の言葉の技術―治療的なコミュニケーションをひらく』(金剛出版) |
|
武田氏滅亡 |
|
平山優『武田氏滅亡』を読む。
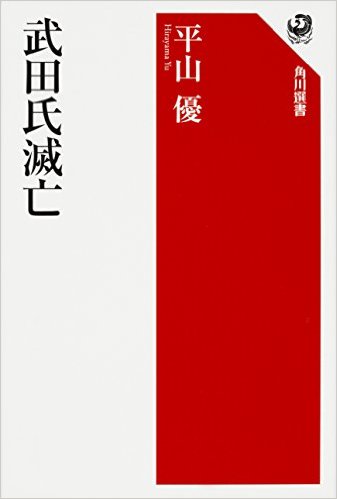
本書は,長篠の合戦から,勝頼の自刃までの,滅亡の過程を,詳細に辿る。同じ著者の,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/409410768.html
で触れた,『長篠合戦と武田勝頼』と,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/409358085.html?1416602810
で触れた,『検証 長篠合戦』につづく著作になる。著者は,本書の意図を,
「なぜ武田氏は滅亡したのか。私は,勝頼が長篠敗戦後どのような動きをしていたかを詳細に探ることで,彼の成果と蹉跌を見極めようと考えた。」
とする。そのプロセスを,日を追うように,つぶさにフォローしていく。本書は,八百ページに及ぶ大著である。
従来,織田側中心,つまり勝者の視点で見られた同時代を,勝頼側,つまり敗者側から見てみると,まったく風景が変わる。歴史は,当たり前のことだが,ひとり勝者のためにのみあるのではない。しかし,滅亡へのプロセスを読むのは,結構しんどい。
追い詰められた勝頼主従は,(織田方に勝頼に味方したと認められて討伐対象になるのを恐れた)その一帯の天目山の地下人らに入山を拒まれて,麓の田野で自刃する(戦死とする説もある)。
「(勝頼に)殉死した人々を見ると,勝頼の高遠時代以来の家臣が多く,その他諏方衆とみられる人々も見受けられる。これに対し,武田の譜代では土屋・秋山兄弟が目立ち,跡部・河村・安西氏がいるだけである。小山田一族にも,勝頼に殉じた者がいたようだが,山県・内藤・馬場・春日などの上級譜代の縁者は一人もいない。高遠城の奮戦といい,殉死者の構成といい,勝頼はやはり武田勝頼ではなく,どこまでも諏方勝頼としての運命を背負っていたとの印象が強い。」
と著者は書く。このことは,信玄と嫡子義信の確執による,義信廃嫡がなければ,勝頼は,あくまで,
諏方(すわ)四郎勝頼(俗に「伊那四郎」),
であって,「武田勝頼ではな」く,武田を継ぐようには位置づけられていなかった(信玄と諏方頼重息女との間に生まれた)。
「勝頼は生まれながらにして諏方家の通字『頼』を頂く,諏方氏の家筋の人物として遇されていたのであり(信玄の息子たちのなかで,武田氏の通字『信』を頂いていないのは勝頼だけである),長じて伊那郡高遠城主に就任したのも伊那の統治に勝頼を登用することでその地域(もともと諏方氏の地盤)の安定が期待できると,信玄が考えたためであろう。」
その意味では,義信の謀反・廃嫡は信玄自体にも誤算であったが,武田家全体にとっても,想定外であった。
「諏方勝頼が武田家の家督を相続すること」
の意味することは,かなり重要である,と著者はこう書く。
「南北朝動乱期に,南朝方となった武田政憲(まさつな 石和流武田氏)が没落して以降,武田信武(安芸守護)以来,甲斐守護武田氏の家督を連綿として継承してきた信時流武田氏の家系が,初めて他国の一国衆出身の男子によって継承されることを意味したからである。
武田氏はそれまで,甲斐源氏の支流,傍流を問わず,家督の簒奪を目論む勢力(逸見・今井・油川など)と激しく戦い,それらを排除することで家系を維持してきた。ところが今回,武田氏にとってかわってかつての宿敵諏方氏の当主を,信玄の男子とはいえ惣領として迎え入れることになったわけであり,それは諏方の家系による争いなき武田総領家の簒奪を意味するともいえる事態になったのである。」
その勝頼の微妙な立ち位置は,不安定で,重臣との間の確執があったとされる。それに輪をかけたのは,信玄の遺言である。それは,
「①勝頼は嫡男武王丸信勝が成人したら速やかに家督を譲ること(勝頼はそれまでの陣代(中継ぎ)である),②勝頼が武田軍を率いる時には,『武田家代々の旗』『孫子ノ旗』など武田家当主を象徴する一切の事物をの使用を禁ずる。勝頼はこれまでも彼が使用していた『大』の字の文字をあしらった旗(長篠合戦図屏風などでよく知られる旌旗)のみを掲げるようにせよ。③ただし諏方法性の兜の着用は認める」
というものである。これでは,勝頼の地位は不安定であり,その中で,おのれを示すために,勝頼が葛藤したであろうことは,想像に難くない。そんな中での長篠の合戦であった。
武田家を滅ぼした張本人として,世上勝頼は評判が悪い。しかし,
「武田氏は,長篠敗戦後も,必死に立て直しを行い,御館の乱終結直後は,武田信玄時代よりも広大な領国を誇るに至った。とりわけ北条氏は,勝頼による北条包囲網に苦しみ,関東の領国を侵食され,悲鳴をあげていた。
天正十年の織田侵攻が始った当時,北条氏は勝頼が滅亡するとはまったく思っておらず,天正十年一月から二月の戦局を誤報だと信じて疑わなかった。織田信長もまた,勝頼はどこかで乾坤一擲の決戦を挑んでくるに違いないと信じ,息子信忠では荷が重いと焦慮していた。信長もまた,勝頼があっけなく滅亡するとは思っていなかったのだ。」
事実,同時代の人々には,有能な人物であり,その滅亡は「運が尽きた」と認識されていた,という。
では,なぜあっけなく亡んだのか。著者は言う。
「勝頼には,幾つかの転機がったと思う。それは大きく,甲相越三国和睦構想,御館の乱,高天神城の攻防戦であろう。それらへの対応が,勝頼の生き残りの可能性を狭めていったといえるだろう。
だが勝頼の対応や判断は,流動的であり,かつ多様さが縺れあう当時の情勢に規定されており,彼だけの問題ではなかった。上杉,北条,徳川,織田,毛利,本願寺などの大名や,中小国衆,足利義昭らの思惑に規定され,勝頼自身が予想もしなかった展開をもたらしたこともあった。そうした意味で,滅亡の要因を勝頼の個人的資質にすべて押し込めて説明できないことだけははっきりしたであろう。調査,分析を行う過程で私が感じたことは,信長がいみじくも勝頼の首に語りかけたように,彼には『運がなかった』ということである。」
と。信長は,『三河物語』によれば,
「日本に隠れなき弓取りなれ共,運尽きさせ給ひて,かくならせ給ふ者かな」
と言ったとある。しかしその信長も,二ヵ月後,本能寺で倒れる。その原因は,武田攻略戦の最中の,光秀との確執にあるらしい。
さらに,一族で早くから徳川に内通していた穴山梅雪も,堺で家康とともに本能寺の変に遭遇し,帰る途中で,殺される。
参考文献;
平山優『武田氏滅亡』(角川選書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%8B%9D%E9%A0%BC |
|
戦争論 |
|
クラウゼヴィッツ『戦争論』を読む。
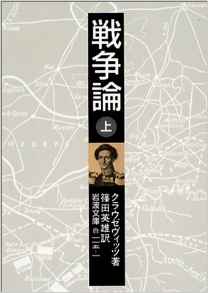
クラウゼヴィッツの主張は,実にクリアであり,論理的である。
「戦争は政治的交渉の一部であり,従ってまたそれだけで独立に存在するものではない」
とするクラウゼヴィッツの「戦争」は,あくまで政治的目的達成の手段である。間違っても,戦争が目的化されることはない。だから,戦争になったからといって,
「交戦両国間の政治的交渉が断絶し,これとはまったく別の状態が現れる,そしてこの新奇な状態は,それ自身の法則に従う」
などとは考えない。
「戦争は政治的交渉の継続にほかならない,しかし政治的継続におけるとは異なる手段を交えた継続である」
と見なす。なぜならば,
「第一は,政治的交渉戦争によって断絶するのでもなければ,またまったく別のものに転化するのでもない,たとえこの場合に政治的交渉に用いる手段がいかなる種類のものであるにせよ,依然としてその本質を保持する,ということである。また第二は,戦争における一切の事件の辿る主要な線は,取りも直さず戦争を貫いて講和に至るまで不断に続く政治交渉の要綱にほかならないということである」
からだ。だから,
「戦争は,とうてい政治交渉から切り離され得るものではない。もしこの二個の要素を分断して別々に考察するならば,両者をつなぐさまざまな関係の糸はすべて断ち切られ,そこは意味もなければ目的もないおかしな物が生じるだけだろう。」
という。そう考えれば,
「戦争によって,また戦争において何を達成しようとするのか,という二通りの問いに答えずして,戦争を始める者はおるまい。また―当事者にして賢明である限り―戦争を開始すべきではあるまい。この問いの第一は戦争の目的に関し,また第二は戦争の目標に関する。,
これら二件の主要な思想によって,軍事的方向の一切の方向,使用さるべき手段の範囲,戦争を遂行する気力の程度が規定されるのである。そして戦争計画は,軍事的行動の極く些細な末端にまでその影響を及ぼすのである。」
というのは当然なのである。しかし,『日本はなぜ開戦に踏み切ったか』
http://ppnetwork.seesaa.net/article/448110449.html
で触れたように,大戦への意思決定をした連中は,目的と目標,戦略と戦術の見極めもつかず,
「成算があるのは緒戦の資源地帯占領作戦のみであった。長期戦の見通しは『不明』」
「開戦三年め以降の見通しは不明」
であるにもかかわらず,終着点もないまま開戦に踏み切り,果ては,目的も目標も見失い,戦うこと自体を自己目的化して,カミカゼというような自爆テロの嚆矢となる愚行を考案し,ついに全国民を道ずれに破滅に突入した。恐らく,今も,戦略と戦術,目的と目標の区別がつかない為政者が国の舵を取り,それを半数以上が支持し,地獄へと向かっている。一度目は悲劇だが,二度目は喜劇というか,お笑い草である。
クラウゼヴィッツ自身,
「通説となっているようなものはすべて排除した。二年か三年たてばすぐに忘れ去られるような書物を創ることは,私の自尊心が許さなかった」
と自ら述べるように,戦争手段は圧倒的に変化し,大量破壊兵器は破滅的になったにしろ,戦争をどう位置付け,どう戦争を終結するか,ということについての基本思想において,その理論的骨格はいまだ十分に有効である(もちろん,一旦始まってしまうと,それを忘れて,戦争自体が自己目的化することは,あるにしても)。
「戦争は一種の強力行為であり,その旨とするところは相手に我が方の意を強要するにある。」
「戦争においては,かかる強力行為,即ち物理的強力行為は…手段であり,相手に我が意を強要することが目的である。…この目的を達成するためには,まず敵の防御を完全に無力ならしめねばならない,そして強力行為という建前から言えば,このことこそ一切の軍事行動の目標なのである。」
等々という書き方をする。特徴は,目的と,その手段としての目標という,目的−目標のツリー構造を決して外さない,論理的な論旨であるところにある。それは,戦略と戦術の区別と置き換えてもいい。
たとえば,
クラウゼヴィッツは,
「およそ戦争は,盲目的な激情に基づく行為ではない。戦争を支配するものは政治的目的である。それだから政治的目的の価値が,この目的を達成するために必要な犠牲の量を決定せねばならない。そしてこの量は,犠牲の大小だけに関するのではなくて,犠牲を払う時間の長短にも関係するのである。それだから戦力の消費が増大して,政治的目的の価値がもはやこれと釣合わなくなれば,この目的は放棄され,けっきょく講和が締結されざるをえなくなるのである。」
とし,その目的とそのための手段たる目標は数多くあり,さらに,その目標に達する道は数多い。たとえば,末端の戦術でも,
「或る歩兵大隊が,敵を或る山地或は橋梁その他から駆逐せよという任務を受領したとする,その場合にはこれらの対象の占領が本来の目的であって,該地における敵戦闘力の撃滅は単なる手段であるか,或は付帯的な任務に過ぎない。もし敵が我が方の陽動だけで駆逐されるとしたら,それでも当面の目標は達成されるのである。…我が方がこの山地,この橋梁を占領するのは,…これによって敵戦闘力の撃滅を促進するためにほかならない。」
のである。しかも,戦争行為が,
「第一は,ここの戦闘をそれぞれ按排し指導する活動であり,また第二は,戦争の目的を達成するためにこれらの戦闘を互いに結びつける(組み合わせる)活動である。そして前者は戦術と呼ばれ,後者は戦略と呼ばれる。」
からなっていると見るなら,上記の例は,戦術の一端に過ぎない。しかし,それぞれの戦術をどう組み合わせて,目的達成へとつながっているという意味では,その戦術は,戦略達成の意味のある手段でなくてはならない,という訳である。
「目的が,講和に直接つながるものでない限り,つまり従属的な目的に過ぎなければ,やはり手段と見なさざるを得ない。」
「戦略の旨とするところは,戦争の目的を達成するために戦闘を使用するにある。」
「戦闘は,戦争における唯一の有効な手段である。そして戦闘においては,現に我が方の戦闘力に対峙する敵戦闘力の撃滅こそ,目的を達成するための手段なのである。」
「戦術は,戦闘において戦闘力を使用する仕方を指定し,また戦略は,戦争目的を達成するために戦闘を使用する仕方を指定する。」
「戦略の旨とするところが,戦争の目的らを達成するために戦闘を使用するにあるとすれば,戦略は全軍事的行動に対して,戦争の目的に相応するような目標を設定せねばならない。」
「現実の戦争は,戦争そのものの法則に従うのではなくて,或る全体の一部と見なさねばならない。そしてその全体というのが,取りも直さず政治なのである。」
等々。今日でも,
「政治は,戦争を道具として使役する。」
という原則は,厳然として生きている。僕個人は,
戦いになったら,政治の失敗,
と思っているが,そうではなく,政治目的利用のために,「戦争を使役する」政治家は後を絶たない。
参考文献;
クラウゼヴィッツ『戦争論』(岩波文庫)
森山優『日本はなぜ開戦に踏み切ったか―「両論併記」と「非決定」』(新潮選書) |
|
方面軍 |
|
和田裕弘『織田信長の家臣団―派閥と人間関係』を読む。

「織田信長の最晩年には,天下統一を目指して各地の戦国大名と戦う『方面軍』ともいうべき軍団が編成されていた。それぞれ万単位の軍勢を擁し,当時としては大軍団である。これらの軍団は一朝一夕にして出来上がったものではない。信長の手足となって各方面で敵軍を破り,敵将の旧臣を家臣化するなどして拡大していった。また,大敵に対しては信長から与力を付けられて軍団を補強していた。軍団は脹れ上がっていったが,中枢部は軍団長の一族や同郷出身者が占めていた。」
こういう背景を踏まえて,本書では,
「前半は時系列で信長軍の拡大を追いかけ,後半では信長の支配領域の拡大とともに増強されていった方面軍の成長過程を,地縁・血縁関係を横軸に交えながら眺めていきたい。軍団を構成した有力武将と軍団長との地縁・血縁を確認していくことで,その軍団の強さの秘密を知ることができる。」
とその趣旨を述べている。地縁・血縁は,
「戦国時代は,地縁・血縁の紐帯によって堅く結びついていた時代だったと言われる。…成り上がり者の戦国武将などは,自分と同じ出身地の者を家臣化していった。最も信用できるからである。血縁についてはそれ以上に重きをなした。敵対する戦国大名同士が和睦する時には,婚姻関係を結ぶことがあるが,婚姻が最も手っ取り早く効果があったからである。」
武田―織田,織田―浅井,織田―徳川等々,織田信長も積極的に使っていた。
本書は,方面軍を,
織田信忠軍,
神戸信孝軍,
柴田勝家軍,
佐久間信盛軍,
羽柴秀吉軍,
滝川一益軍,
明智光秀軍,
と順次紹介しているが,突如追放された重臣・佐久間信盛軍の特徴を,
「信長と直接縁戚となることもなく,有力武将とのつながりも薄く,追放処分の抑止力となる人的ネットワークを持たなかったため,簡単に追放されてしまった。」
と書く。では,柴田勝家はいうと,信盛が家督相続時の苦境でも見捨てず支持し続けたのに対して,信長の弟信勝をたてて信長廃嫡を謀っていたのに,たとえば,
「滝川一益に嫁した(勝家の)妹もいる。一益の娘「於伊地(おいち)」は勝家の子権六に嫁しているので,柴田家と滝川家は重縁で結ばれていることになる。…ルイス・フロイスの書簡には,天正九年にフロイスが当時の勝家の居城だった越前北の庄を訪問した時のことが記されており,それには,『信長は彼(勝家の嫡子)に嫁がせるため娘を一人与えた』とあり,勝家嫡男に信長の娘が嫁していることを記している。一益の娘を信長の養女として嫁がせたのだろう。」
という勝家の人脈,あるいは,卑賤の身から身を起こした秀吉には,譜代の家臣はおろか,一族も少ないため,
「地縁・血縁を頼ったのはもとより,同じ織田家中に『兄弟の契り』を結ぶ武将を求めて人的ネットワークを拡大したり,さらに主君信長の御曹司を養子に貰い受けて一門衆にも連なり,その地位をより安泰ならしめた。」
という秀吉の人脈づくり,と比べても,信盛軍が自己完結した軍団だったことが浮びあがる。
「織田家最大の佐久間信盛の軍団を解体することで,与力の近江衆は信長の直臣に組み入れ,尾張衆は信忠に附属させた」
が,それが追放の動機だったとしても,人脈強化が,生き残りの戦略に不可欠だったことをうかがわせる。たとえば,秀吉は,
「譜代の家臣を持たないことに加え,朋輩との姻戚関係もないことから,これと見込んだ人材には,とことん密着した。その一人が黒田(官兵衛)孝高であり,中川清秀だった。ともに義兄弟の契りを結んでいる。黒田孝高宛の書状には,『我ら弟小一郎め同然に心安く存知候』と伝え…」
ている。中川清秀は,
「(信長が清秀の)嫡子秀政に息女『鶴』を娶せ,一門衆として待遇」
されている。さらに,
「信長時代の秀吉は,譜代家臣をもたないために与力(蜂須賀正勝,竹中重治など)や新参の家臣も大事に扱い,合戦を経るごとに,秀吉への従属度を増していった。荒木村重旧臣の荒木重堅(木下半大夫)や津田左馬允(盛月)など信長から睨まれている武将も秘密裏に助けて家中に取り込んでいる。」
明智光秀の軍団も,特徴がある。
「光秀軍の家臣団構成は,…他の方面軍に比べて異質なのは,光秀と同郷の美濃出身者はいるが,尾張衆が皆無に近いことである。信長の目付の存在も知られていないし,変直前の謀議に加わった五人の家老衆も尾張出身ではない。家臣団自体も近江志賀郡や丹波を領地にしたことで,西近江衆や丹波衆が中心である。また,旧幕臣衆も配下に加えている。旧幕臣衆は,信長を恐れて義昭を離れたに過ぎず,信長から見れば敵性勢力ともいえる。光秀が信長を討つと打ち明けても,反対するどころか賛成したかもしれない。ただし,光秀もそこまでは信頼していなかったと思われ,内談した形跡はない。もし,事前に相談していれば,毛利に庇護されている義昭の担ぎ出しを積極的に進め,大義名分を含めて大戦略を打ち出せただろう。」
しかし,こうした,
目付がいない,
尾張衆がいない,
という光秀軍の特徴が謀叛を成功させた要因になる。
「光秀軍に有力な尾張出身者がいれば,信長に対する謀反であると知れたときは,どうなっていたか分からない。逆に光秀を討ち取っていたかもしれない。光秀はクーデター最中にどういう異変が起こるかもしれないと用心し,本陣は本能寺から距離を隔てていたのもそういう配慮からだろう。」
結局,謀反成功の要因は,直接の動機は別として,畿内が真空地帯となっていたことに加えて,明智軍自体が,外様(旧敵性部隊)中心で,他の部隊と切れた自己完結した部隊であったこと等々が見えてくる。
参考文献;
和田裕弘『織田信長の家臣団―派閥と人間関係』(中公新書) |
|
異化 |
|
エルンスト・ブロッホ『異化』を読む。
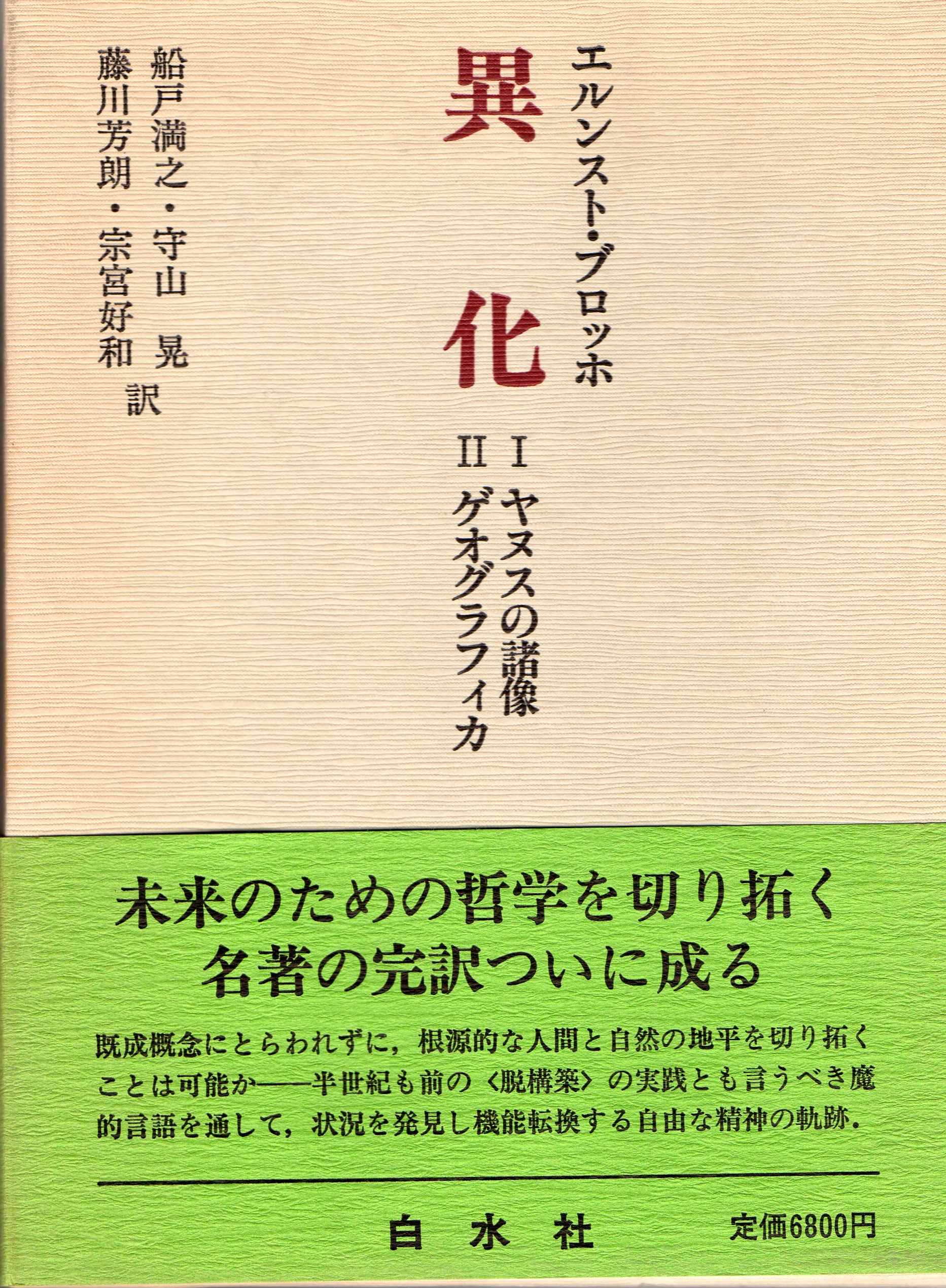
エルンスト・ブロッホの『異化』(本書は,船戸満之・守山晃・藤川芳朗・宗宮好和訳)には,現代思潮社(1971年)がある(片岡啓治・種村季弘・船戸満之共訳)。本書の「異化Ⅰ ヤヌスの諸像」のみを訳したものだ。若い頃,それを読んだ記憶がある。だから,全体の訳が出た時すぐに入手したが,そのまま今日まで,数十年も書架の風景になっていた。本書は,
異化Ⅰ ヤヌスの諸像
異化Ⅱ ゲオグラフィカ
の全訳である。これで,若いころの積み残し,長年の未完了を,漸く完了させたことになる。
ところで,現代思潮社版は,箱に,マッハの自画像を載せている。寝椅子に横たわる自分が,自身にどう見えるかを示している。マッハはこの奇妙なデッサンを,「自我の自己観察」と名づけた。鼻の左側に開けた視界に,肩の突端になびく髭,下方にむかって短縮された遠近法で,胴,肢,足と順次つづいていく。
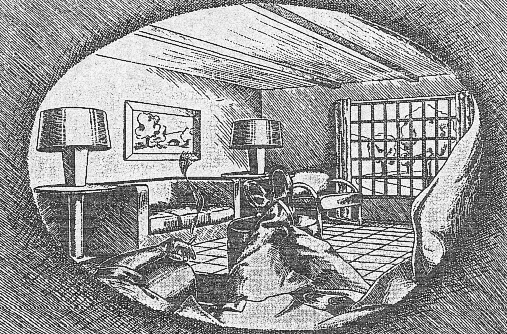
(出典;マッハ『感覚の分析』(法大出版局))
原画は,マッハの『感覚の分析』に載る。そこでマッハは,こう書いている。
「例えば,私が安楽椅子によこたわって右の眼を閉じると,左の眼に,上図のような映像が映る。眉毛半弓,鼻,および髭からなる枠の内に,見える限りでの私の身体の一部とその周囲が現れる。私の身体は他人の身体から次の点で区別される。すなわち,活発な運動表象が直ちに私の身体の運動となって現れ,それに触れると他の物体に触れた場合に比べて一層目立った変化が生ずるということのほかに,自分の身体はただ一部分しか見えず,とりわけ頭が見えないことによってである。」
ブロッホは,「鏡なしの自画像」で,
「この自画像は見るものから隔たっていない。ただまさに主体が,その自画像の中心においてまったく姿を現さないのだ。首なし,それが自分で自分を見たときの人間というものである。」
とした上で,
「書き手自身のこの首なし像は,自画像の歴史におけるひとつの新事象」
と評した。そして,それは,人間の自己意識の象徴ですらある。対自も即自も,所詮自分自身でしかない。そして,
「人間は一日中そのように―首はなく,胸と肩はまじかに接し,その他は下方に縮小して遠ざかっている―自分を見ているにもかかわらず,それは,私たちにとってあたりまえすぎる所与の事実であり,そしてことさら…マッハは,それを『反形而上学』のために,まぎれもない表面として描いて見せたのだ。にもかかわらず,この絵はマックス・エルンストのものであるかのように,シュルレアリスムそのもののごとくに,働きかける。その表面はひとつの深淵なのだ。」
として,鏡に映る自分と対比しつつ,こう結論づける。
「真の人間は,いまだこの鏡に映る姿の外にある。苦しみも,希いも,生産も,享受も,いまだ真にふさわしいものとなってはいないし,自分の名さえいまだ正確には知らない。人間存在のこの真の主体は,外から見たときの姿としてあるというより,むしろ,自分で自分で見たときのあの姿なのだ。すなわち,首は見えず,根本思想は凝集されえず,中核としてただやっと大脳の知覚思考だけはあるが,視覚も自分自身との出会いも実現しえていないのである。物を見る眼は,眼それ自体を見るに至っていない。歴史を創りだす人間も,まだ自分自身を創りだしていない。自己という意味をどんなに単純にとるにしろ厳密にとるにしろ,これが真の自画像である。」
と。そして,これは,本書の冒頭の,「呼びさます」の,
「人は,とにかく,ある。〈私はある〉(ダス・イッヒ・ビン)も,ときにはそこにあるように思われる。しかし,つねに中途にあるにすぎず,あまりにも自分に近すぎる。〈(私は)ある〉(ビン)は,けっして自分の外へ出ることはない。」
と共鳴し合う。そして,「鏡なしの自画像」の末尾につながる。
「もちろん,このポートレートを出来上がりとするためには,首の部分を白紙のまま放っておくことはできない。そこは,希望の置かれるべき場所であり,首なしのままでいるわけではなくて,まさにそこでは希望が自らを創造しているさなかなのである。」
こうした表現スタイルが,ブロッホの言う,「異化」に他ならない。「異化」については,「疎外,異化」の項で,
「『異化効果』は,事件の過程や人間の性格が自明のものと見なされることのないよう,それらを慣れ親しんだものかずらすこと,置き換えることとして現れている。」
とする。つまり,ありふれた地に別の輪郭を描きだすことで,同じものに異なる図を際立たせること,と言い換えてもいい。マッハの絵を,マッハの文脈から切り離し,新たな自画像として,そう,まだ描かれていない,これから描きだされるべき主体として,図化して見せたということになる。
僕には,博覧強記なブロッホの,屈折した陰翳のある含意を到底読み解き切れないが,たとえば,「大いなる瞬間,きづかれずに」の項で,
「重大な意味をもつ〈いま〉と〈ここ〉とが現れているときですら,それはめったに気づかれることがないのである。歴史はこの種の例をつぎつぎと積み重ねてきたが,誰もそこから学んだ者はいない。しかし,これはみなかつて起こったことなのだ。つまり,誰の注意も惹かない人間が目立たずに入ってきて,そのときは何も予期していなかった人々が,あとになってはじめてここで何が起こったかを知るのである。ルターが提願を貼り出していたあいだに,城内教会の広場の上にその槌音が響いた瞬間があった。むろん,誰もその音に耳をそばだてていたわけではない。若き日のベートーヴェンはモーツアルトの前で演奏し,またヘーゲルはベルリン大学の一室でショーペンハウアーの教授資格試験を行った。これを人は見ることができた。実際,耳で聞き,目で見た人もいたのだ。この驚くべき瞬間を,その〈いま〉ならびにとりわけまだまったく未展開の内容を,理解しながらその場に臨んでいた人は一人もいなかったのである。リヨンでのある夜会の折に,若い少尉が出版業者に原稿を渡そうとしていた。出版業者は以前からその原稿に関心を示していたのだ。しかし,その夜会にはあるテノールも出席しており,自分の作品を提供しようとしていた若い少尉よりもずっと注目を集めていた。少尉はたしかに名前を名のったのだが,そうしたことはみんな,ヴィッテンベルクで鳴り響いていた鎚の音にも劣らず,何の意味ももたなかった。すなわち,こうしてユリウス・カエサルを描いたナポレオンの著作は日の目を見ることなく終わったのである。これらすべてのケースでは,〈いま〉と〈ここ〉の闇に,いずれにせよまだ瞬間的である,人生行路の始まりというものが付け加わっていた。しかし,まさにその始まりにあっては,視線の軌道が人生行路の中へ進行することは皆無といってよい。実際また,どうすればその時点ですでに核心において知ることができるというのか。闇の中では―これこそ意識のこうした特別の狭隘さにおけるキーポイントであるが―ライオンの鉤爪すら見えなかったのだ。
ほかの点ではすでに十分ライオンになっていたが,それでも闇の暗さは変わらなかったということがある。侍従たちの前だけではない。英雄たちのあいだでもそうだったのだ。英雄同士はお互いにそれを認めることはないのである。あるとき,シラーのところを若い同郷人ヘルダーリンが訪ねた。訪問の終るころ,ずんぐりした体格の男が一人その席に加わった。この男は簡単な挨拶のあと,部屋の隅に坐って邪魔にならないようにしていた。ヘルダーリンは,いよいよ辞去するときになってはじめて,どこか地主のように見えたこの男が,シラーで部屋での予期せぬ〈いま〉と〈ここ〉,そればかりかまさに邪魔な印象を与えていた〈いま〉と〈ここ〉が,ゲーテであったことを知らされたのである。」
と,あとになって気づく〈いま〉と〈ここ〉について書くくだりがある。訳者は,その文章の中に,いろいろなもじりが埋め込まれている,という(「侍従たちの前だけではない」は「侍従たちの前ではナポレオンも英雄ではない」という格言らしい)。ただものの見方を示す,文章自体が異化であるばかりではなく,埋め込まれた博覧強記の文脈自体が,また異化されている。そして,全体として,物の見方を異化させる,という何重にも折り畳まれた仕掛けがあるということは,到底非才の眼には見抜けない。
ある意味,本書の文章そのものもまた,文体の異化に他ならない。例えば引用した文章は,その地に異質な図をいくつも折り畳んでいる。それは,読み手の知力に挑戦しているように見える。(竜馬の西郷を喩えた言い回しに準えるなら)読者の知に応じて鳴る鐘のようである。凡庸非才の我身には聞こえる音はわずかであった。
参考文献;
エルンスト・ブロッホ『異化』(白水社)
エルンスト・マッハ『感覚の分析』(法政大学出版局) |
|
ワールド・カフェ |
|
J・ブラウン&D・アイザックス『ワールド・カフェ〜カフェ的会話が未来を創る』を読む。
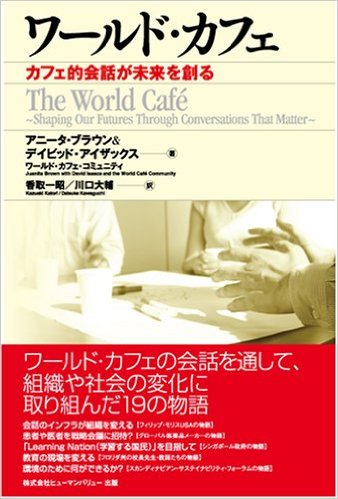
量子物理学者ハイゼンベルクは,
「科学は実験にもとづくが,…科学は対話に根ざしている」
と,言っているという。物理学者が熱い対話を通して,自分の理論を固めっていた,ということはつとに有名だ。昨今,改めてダイアローグについて注目されることが多いが,ブレインストーミングを始め,キャッチボールのもつ創造的効果について,改めて贅言を費やす必要はあるまい。本書の主題であるワールド・カフェは,そうした対話の効果的な手法として,夙に有名だし,何回か,僕自身も参加してみたことがある。
ワールド・カフェもそうだが,組織改革などを進める際に,関係者が一同に会して会話する手法が数々ある。これ等を,
ホールシステム・アプローチ,
と呼ぶそうだが,ホールシステム・アプローチについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/441302507.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163468.html
で,それぞれすでに触れた。特徴を,訳者の香取一昭氏は,
社会構成主義に基づき,会話を大切にする,
組織も生命体と見なし,自己組織化を起こしやすい環境を作る,
テーマに関わる全てのステークホルダーが参加する,
ポジティブ発想に基づく,
と,まとめている。思えば,誤解を恐れずに言えば,
ブレインストーミング,
も,
エンカウンターグループ,
も,
Tグループ,
も,
会話(沈黙も含めて)で成り立っていた。その会話を,対話,ダイアローグとして意識することで,それを図として,そのもつ機能を最大限に活かそうとする仕掛けのひとつ,とワールド・カフェを位置づけてもよいのかもしれない。
本書の中で,マーガレット・J・ウィートリーは,
「ワールド・カフェのプロセスでは,人々は一般的にテーブルからテーブルへと移動しますが,それは物理的に移動すること以上に意味があることです。私たちは,自分たちの役割や,先入観,確信をもっている考え方を背後に置きながら,移動していきます。そして,新しいテーブルに移動するたびに,私たちは自我を捨てて,より大きな存在になるのです。つまり,そのときには,私たちは,すでに何人かの人々の間で行われた会話を代表する存在になっているのです。私たちは,自己と小さな確かさという限定的な感覚から解き放たれて,新しいアイデアが生まれる広々とした空間へと移動します。ある参加者は次のように語っています。『それはあたかも,その考えがどこから来たのかわからないという感じです。なぜなら,その考えは何度も結合され,新しい物差しによって形づくられ,転換させられたものだからです。人々はお互いに話し合い,どこかほかのところで使われ始めた新しい言葉を使いますが,その言葉は,それまで自分では考えたこともなかった言葉なのです。』
キーワードは,ダイアローグである。ダイアローグについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163119.html
で,また,デヴィッド ボーム『全体性と内蔵秩序』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/421586313.html
で触れた。
本書は,ワールド・カフェのホストを果たした人たちの物語で成り立っている。
上述のマーガレット・J・ウィートリーは,
「ワールド・カフェで行われる話し合いのプロセスは,人間の本質に関する2つの基本的信念についての深い『種の記憶』を呼び覚まします。それは第一に,『人間は自分たちにとって大切なことについて,本当は共に話し合いたいのだ』ということです。実際に人生に満足感と意味を与えてくれるのは,この本質なのです。そして第二に,『共に話し合うにつれて,私たちは,集団の中にのみ見い出せる,より偉大な知恵にアクセスすることができる』ということなのです。」
と述べている。対話の重要性は,疑わない。ロジャーズが,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/410724005.html
で触れたように,果敢にチャレンジした,プロテスタント4名,カトリック4名,英国陸軍退役大佐1名との,3日間に亘るエンカウンター・グループによる「鋼鉄のシャッター」は,人の対話の威力を思い知らせるが,いま,
パレスチナ人
と
ユダヤ人,
とのワールド・カフェを,仮に試みたとして,その土俵に乗る意思がなければ,そもそもスタートしない。ワールド・カフェのコンテキストの要素として,
目的,
参加者,
パラメーター(時間・予算・場所),
が不可欠だが,目的は共有できるのだろうか。
「カフェの目的を検討するための1つの方法は,『何が人々を結びつけているのか?この会話によって,どのようなニーズが足されるのか?』という質問をしてみることです。」
とある。しかしそもそもその質問が成立しないところで,どうやって,目的を設定していくのか。結局「鋼鉄のシャツター」では,アイルランド紛争は解決できなかった。その意思決定は,政治であった。政治解決で必要な対話は,この種の対話スキルで可能なのか。組織の問題でもそうだが,組織の問題を解決する土俵を決めるのは,会話ではない。その意思決定である。それがあって初めて,土俵ができる。
多少悲観に過ぎるのかもしれない。しかし,コミュニケーション・スキルでは解決できないものがある,ということを逆に,このワールド・カフェは照らし出してくれるように思える。
参考文献;
J・ブラウン&D・アイザックス『ワールド・カフェ〜カフェ的会話が未来を創る』(ヒューマンバリュー出版)
ルイーザ・ギルダー『宇宙は「もつれ」でできている』(ブルーバックス) |
|
主体幻想 |
|
ダニエル・C・デネット『スウィート・ドリームズ』を読む。

本書は,サブタイトルに,
Philosophical Obstacles to a Science of
Consciousness
とあるように,『解明される意識』以後十年,著者がこれで解決したと考えていた意識問題が「哲学的」に議論され続けている状況が科学の進展を阻害するものとして批判・糾弾する内容になっている。タイトルの,
「スウィート・ドリームズ」
とは,クオリアをはじめとする意識の特徴が実体のないものであり,「甘い夢」に過ぎないことを揶揄する挑戦的なタイトルになっている。『解明される意識』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/455379804.html
で触れたように,そこで,著者は,
多草稿モデル(multi-draft model)
を提案していた。これはその後,
脳内の名声(あるいは「脳内の有名人」)モデル,
と改められ,さらに,
意識の「ファンタジー・エコー」理論,
と名づけられることになる。それは,
「意識はテレビではなく,名声に似たものである」
というもので,
「意識とは,内容を担う出来事が意識になるために『変換され』なければならない特別な『表現媒体』ではないのであり,むしろ,意識とは,脳の中の内容を担う出来事が名声を求める(あるいは,ともかくも,潜在的に名声を求める)他の出来事と競争して名声のようなものに到達することである。」
そして,脳内の小人(ホムンクルス)を出汁に,こう展開して行く。
「しかし,もちろん,意識は脳の中の名声ではありえない。なぜなら,名声があることは,多くの人々の意識を持つ心の中で共有される志向的対象であることだからである。そして,脳が無数の小人たちで構成されているものとして理解することは有用であるが,小人たちが一部の同胞を脳内有名人へ昇格させるために必要がある程度に,その小人たちを意識をもつものであると想像しようとするならば,私の意識の理論に明白な無限後退を組み込むことになってしまう問題が生じるだろう。この無限後退の可能性は,しばしばこのような前兆をうまく封じる方法,すなわち,基本的な考え方を放棄するのではなく,それを柔軟にすることによって止めることができる。そのような小人たちが,それが一部となって構成する知的媒体よりも愚かで無知である限り,小人の中の小人の埋め込みは有限で,機械に置き換えられる程度に,たいしたことのないエージェントの段階でそこを打つことがあり得る。
したがって意識は,名声というよりは影響力,すなわちその時点において身体を制御する対立する諸過程における一種の相対的な政治力というようなものである。(中略)私たちの脳は民主的であり,実際は無政府状態ですらある。脳の中にはいかなる王も国営テレビ放送の公式視聴装置もデカルト劇場も存在しないが,内容が長期にわたって行使する政治力には,今もまだかなり際立った差異がある。意識の理論が説明しなければならないのは,比較的少数の内容がこの政治的力に高められ,その他のほとんどの内容が脳の中で展開するプロジェクトの中でささやかな役割を果たしたあと,雲散霧消し忘れ去られるのはなぜかということである。
なぜこれが意識の理論の課題なのか? なぜなら,それこそが意識的なった出来事がなすことだからである。意識的な出来事が停滞し,『脚光を浴びて』時間を独占する。しかし,私たちはこの魅力的な比喩とその類縁である注意のサーチライトという考えを説明して消し去らなければならない。そのためには,注意を向ける単一の原点を前提にしないで,注意をつかむという機能的な力を説明しなければならない。」
ここにあるのは機能主義で,
「昨日主義とは,行いの立派な人が立派な人であるという古い諺にも奉られた考え方で背ある。つまり,物質は物質がなし得ることのみゆえに重要である。」
という立場であり,その意味では,どこかに中央集権的な主体というものがある,という古くはデカルト流の二元論を徹底的に批判する。しかし,たとえば,
「反省に関する反省状態であるメタ状態と,メタメタ状態に置かれるこれらすべての能力傾向とメタ能力けいこうといったもののすべてを…ある種のロボットに作り込むことは可能だろう。私は,この内部状態切り換えの軌跡は,私の意識の流れを説明する際の『一人称的』説明に驚くほど似ているようにみえると思う。しかし,ロボットのそういう状態には,実在する感触,現象的特質がいっさいふくまれていないだろう! 」
と,「クオリア」が抜けている,という批判はしつこくついて回る。それに,著者は,
「あなたがクオリアを,論理的にはあらゆる能力的性質と無関係に,すべての因果関係から切り離して考慮された経験の内容的性質として定義するなら,それらは,広義の機能主義のすべてを回避することが論理的に保証される。しかし,それは空しい勝利である。このような性質の存在を信じる理由がまったくないからである。」
と断言する。脳の機能の外に,それを置くことは,二元論の「われ」を無限後退させていくのと同じである。主体も,クオリアも,脳の機能として説明できる日が来るのではないか。著者は,
「意識状態には多くの性質があり,それらは今後の科学的調査の対象とすることが可能でもあり,また,対象とすべきである。そして,準備が整って私たちが説明を受けるならば,ただちにそれらの説明が,意識とは何であるかを説明するものとして満足すべきものとして判断してもおかしくないだろう。結局,これはかって生命とは何かに関する不可解性の場合に起きたことである。」
と締めくくる。生命と同じように,説明できる日がくる,ということである。
それにしても,この活発な議論は何だろう。議論の中から,真理が創り出される,を地でいくこの環境にただ羨望するのみである。問いと問いとのぶつかり合いのないところに,けっして真理は拓かれない,とつくづく思う。
参考文献;
ダニエル・C・デネット『スウィート・ドリームズ』(NTT出版) |