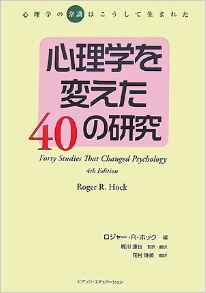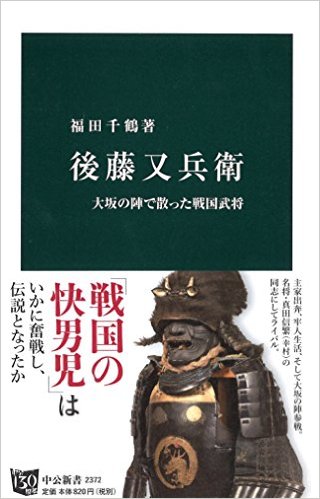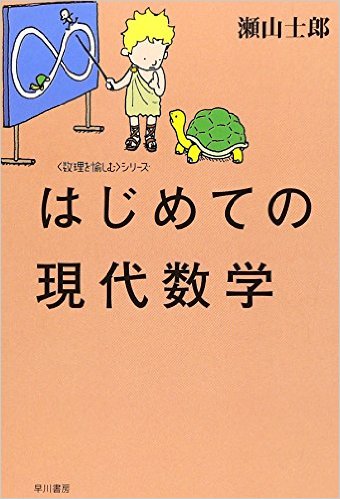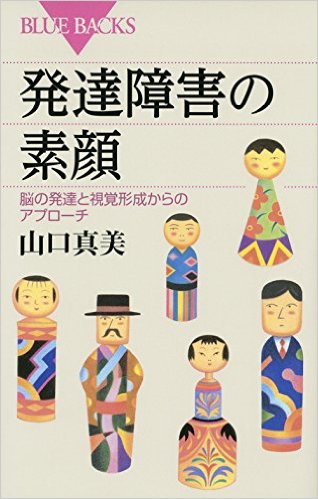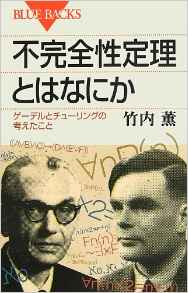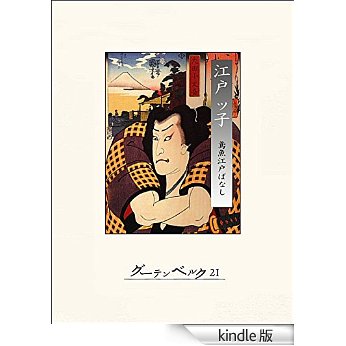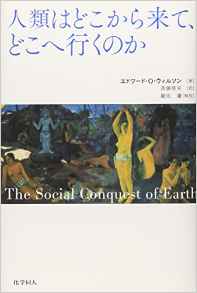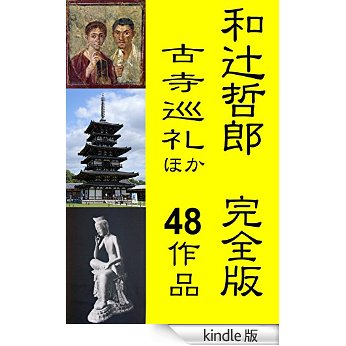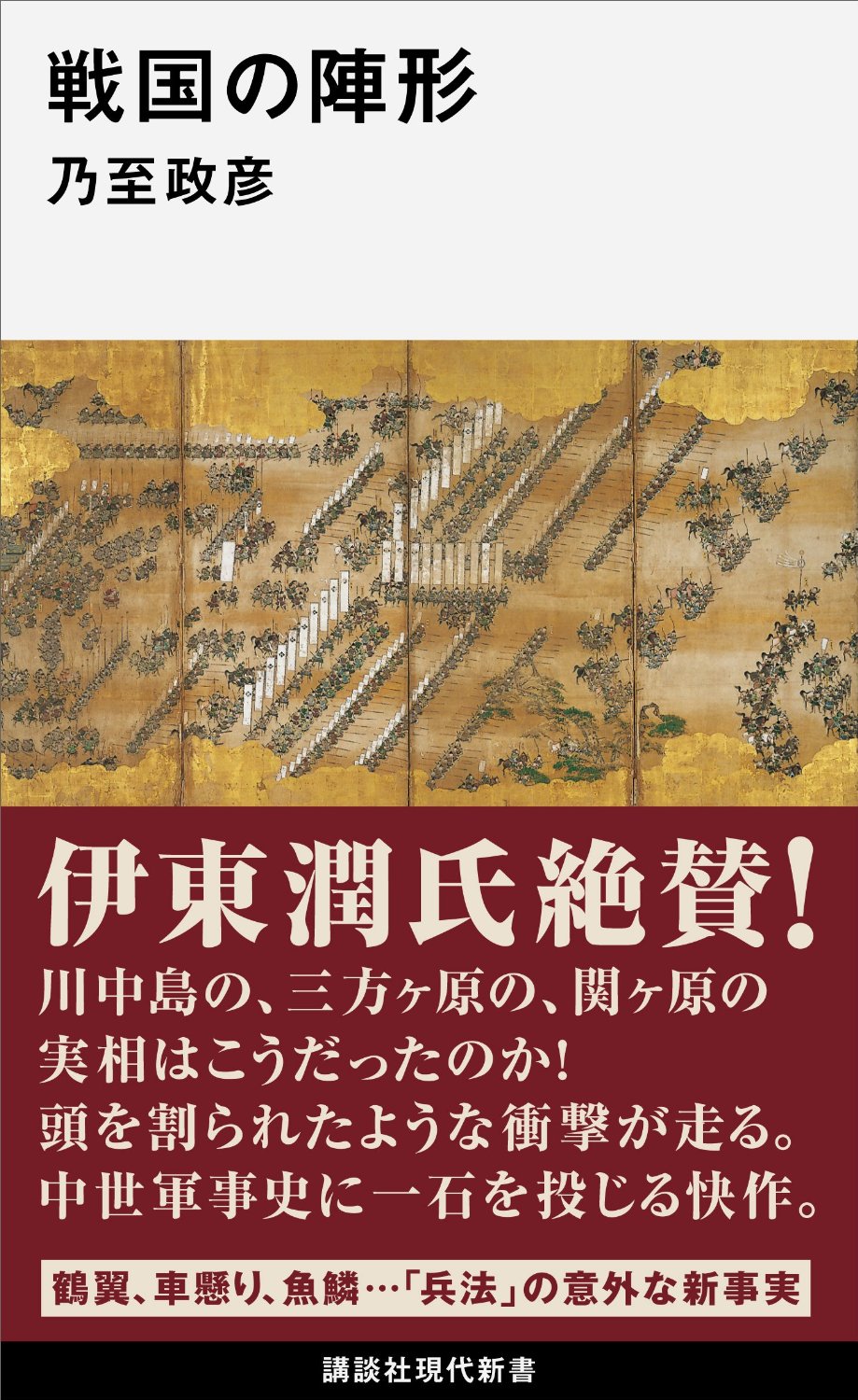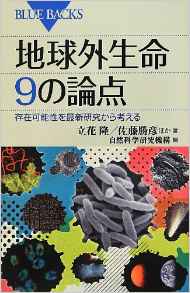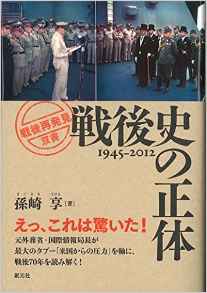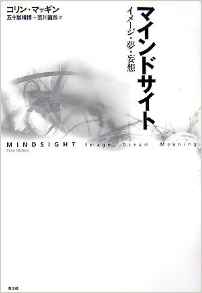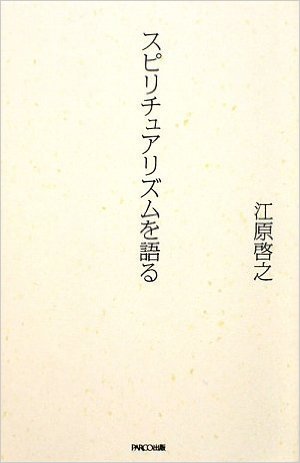|
マーケティング3.0 |
|
フィリップ・コトラー他『コトラーのマーケティング3.0−ソーシャル・メディア時代の新法則』を読む。

ずいぶん昔,コトラーの,
『[新版]マーケティング原理』
や
『マーケティング・マネジメント[第4版]』
という大著を読んだ記憶があり,その流れで,「3.0」が気になって,数年前に買ったのに,積読になっていた。2010年上梓なので,少し現在の危機的状況とは乖離があるかもしれないと思って読み始めたが,それをあまり感じさせなかった。
おもしろいのは,
マーケティング3.0
の基本コンセプトが,
「2005年11月,ヘルマワン・カルタジャヤ率いる東南アジアのマーケティング・サービス会社,マークプラスのコンサルタント・グルーブによって生み出された。二年間の共創作業でそのコンセプトを強化したのち,フィリップ・コトラーとヘルマン・カルタジャヤが,ジャカルタで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)40周年記念セミナーで思案として発表した。…マーケティング3.0は東洋で誕生し,形づくられたもの」
と,「本書が生まれた経緯」にあることだ。それを,日本語訳本としてわれわれは知る破目になっている。
僕は,日本は自画自賛し,円安誘導という短期の恩恵に浴しているうちに,企業も,社会も,国自体も,自己革新を怠り,世界の流れから,周回遅れどころか,何週も立ち遅れてしまったという危機感を持っている。本書を読んで,ますますその感を強くした。
「マーケティング3.0に進んでいる者となるとごく少数」
だそうだが,日本はおそらくその中に入らないだろう。
マーケティング1.0は,製品中心の段階,
マーケティング2.0は,情報化時代の段階,つまり情報技術がコア・テクノロジーになった時代,
マーケティング3.0は,価値主導の段階。消費者としてのみとらえるのではなく,全的存在として捉えて働きかける,
という。端的に,
マーケティング1.0は,製品中心のマーケティング,製品を販売すること,
マーケティング2.0は,消費者志向のマーケティング,消費者を満足させつなぎとめること,
マーケティング3.0は,価値主導のマーケティング,世界をより良い場所にすること,
と,整理している。
「消費者思考のマーケティング2.0と同じく,マーケティング3.0も消費者を満足させることをめざす。だが,マーケティング3.0を実行している企業は,より多きなミッションやビジョンや価値を持ち,世界に貢献することを目指している。社会の問題に対するソリューションを提供しようとしているのである。マーケティング3.0は,マーケティングのコンセプトを人間の志や価値や精神の領域に押し上げる。消費者を全人的存在としてとらえ,消費者としての一面以外のニーズや願望もおろそかにされてはならないと考える。それゆえマーケティング3.0では,感情に訴えるマーケティングを,精神に訴えるマーケティングで補うのである。」
なぜなら,
「世界的な経済危機の時代において,マーケティング3.0は消費者の生活により大きな意味を持つ。社会や経済や環境の急激な変化や混乱に,消費者はこれまで以上にさらされているからだ。病気は世界的に流行し,貧困は増大し,環境破壊は進んでいる。マーケティング3.0を実行する企業は,そのような問題に直面している人びとに解決策と希望を提供するのであり,より高い次元で消費者を感動させるのである。マーケティング3.0における差別化は,企業の価値によって進められる。」
だから,マーケティング・コンセプトは,
マーケティング1.0は,製品開発,
マーケティング2.0は,差別化,
マーケティング3.0は,価値,
であり,マーケティングのガイドラインは,
マーケティング1.0は,製品の説明,
マーケティング2.0は,企業と製品のポジショニング,
マーケティング3.0は,企業のミッション,ビジョン,価値,
となる。そして,今日の,
参加の時代,
グローバル化のパラドックスの時代,
クリエイティブ社会の時代,
という三つの力の中,マーケティング3.0は,
協働マーケティング,
文化マーケティング,
スピリチュアル・マーケティング,
の融合だと,本書は主張する。そして,
「マーケティング3.0では,マーケティングはブランドとポジショニングと差別化のバランスのとれた三角形として定義し直される必要がある。」
として,
「3i」
というコンセプトを打ち出す。つまり,
Brand identity
Brand integrity
Brand emage
である。つまり,
「消費者が喩横につながっている世界では,ブランドはポジショニングを明確にするだけでは価値がない。ポジショニングを明確にすれば,ブランドは消費者のマインド内で明確なアイデンティティを持つだろうが,それは必ずしも好ましいアイデンティティではないかも知れないからだ。ポジショニングは本物ではないブランドにだまされないよう,消費者に注意を促す言葉にすぎない。つまり,この三角形は差別化なくしては完全なものにならないのである。差別化は当該ブランドの真のインテグリティ(完全性)を反映したブランドのDNAだ。それは,そのブランドが約束を果たしている確かな証拠であり,約束された性能や満足を顧客に届けるということだ。ポジショニングとの相乗効果を持つ差別化は,自動的に好ましいブランド・イメージを生み出す。」
「ブランド・アイデンティティとは,ブランドを消費者のマインド内にポジショニングすることだ。…消費者に知られ,関心を引くためには,ポジショニングはユニークでなければならない。また,消費者の合理的なニーズや欲求にとって意味を持っていなければならない。それに対しブランド・インテグリティは,ポジショニングと差別化によって主張されていることを実現することだ。誠実であること,約束を果たすこと,そして当該ブランドに対する消費者の信頼を醸成することだ。ブランド・インテグリティの標的は消費者の精神である。」
このとき消費者を「全人的存在としてとらえる」というのは,
マインド,
と,
ハート,
と
精神,
を持つ人間として,という意味になる。マーケティング3.0は,
「消費者のマインドと精神に同時に訴えかけて,彼等のハートを動かす必要があるということだ。ポジショニングはマインドに買うべきかどうかを判断させる。ブランドが本当に差別化されていれば,精神が買うべきだという判断を強化する。最後にハートが消費者に行動させ,購買の決定を下させるのである。」
価値主導のマーケティング,
においては,企業の
ミッション(なぜ),
ビジョン(何を),
価値(どのようにして)
が問われる。ミッション,つまり,
「その企業がなにをするために存在しているのか」
という「その企業の存在理由」と,ビジョン,つまり,
企業をミッションの未来の状態へと導く羅針盤,
と,価値,つまり,
企業組織の行動規範,
何を大切にしているか,
である。そして,マーケティング3.0では,
「企業のミッションやビジョンや価値に組み込まれた意味をマーケティングすることである。」
前述の,
「ブランドの真のインテグリティ(完全性)を反映したブランドのDNAだ」
とは,ここと関わる。具体例や企業例は,本書をお読みいただくとして,
マーケティング3.0の10原則
を挙げる章で,
マーケティングと価値の関係には三つの発展段階,
があるとして,
第一段階は,マーケティングと価値が分離している(崇高な価値は必要ない),
第二段階は,フーリエ機の一部を社会的コーズ(大義)のために寄付する,
第三段階は,企業は価値通りに行動しようとし,その価値が企業にパーソナリティと目的を与える,
として,2000年の国連ミレニアムサミットで掲げた八つの目標を挙げている。
①極度の貧困と飢餓の撲滅,
②普遍的初等教育の達成,
③ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上,
④乳幼児の死亡率の削減,
⑤妊産婦の健康の改善,
⑥HIV/エイズ,マラリア,その他の疾病の蔓延防止,
⑦環境の持続可能性の確保,
⑧開発のためのグローバル・パートナーシップの推進,
本書で「価値」との統合と言っているのは,地球規模の社会的問題のソリューション,ということなのである。その点から見ると,あるいは,我が国のトップ,企業は,周回遅れどころか,逆走していることにすら気づかないでいるのではないか,と思えてくる。杞憂でなければいいが。
参考文献;
フィリップ・コトラー他『コトラーのマーケティング3.0 ソーシャル・メディア時代の新法則』(朝日新聞出版) |
|
戦国大名 |
|
鍛代敏雄『戦国大名の正体 - 家中粛清と権威志向』を読む。

「はしがき」で,戦国大名について,
「戦国の世に生きる大名との意識はあったろうが,『戦国大名』というレッテルを貼られた武将の誰一人として,自分が戦国大名と呼ばれていることを知らない。…戦国大名とは戦国時代に使われていた用語ではなく,歴史用語としての造語である。その本質と考えられる要素で構成された概念であって,厳密に言えば,戦国大名という大名は存在しない。」
と書く。著者は,戦国時代を,
「応仁・文明の大乱(応仁元年(1467))から,室町幕府の滅亡(天正元年(1573))までの約百年間」
とする。ただ,戦国期の始まりとされる応仁の乱の戦国始期には,戦国大名は存在しないので,戦国大名の登場(北条早雲など)期以降,四期に分けて,戦国大名を分類する。
第一世代 十六世紀第一四半期 北条早雲,今川氏親,大内義興
第二世代 十六世紀第二四半期 尼子晴久 毛利元就 北条氏綱,伊達稙宗,大内義隆
第三世代 十六世紀第三〜第四四半期 北条氏康,北条氏政,武田信玄,上杉謙信,伊達晴宗,今川義元,朝倉義景,大友宗麟,長宗我部元親,島津義久
第四世代 十六世紀第四四半期〜十七世紀 伊達政宗,毛利輝元,佐竹義宣,島津家久,上杉景勝,北条氏直
信長,秀吉,家康は,第三世代と同時代に当たることになる。宣教師は,戦国大名を,
「山口の国王(大内義隆),豊後の国王(大友宗麟)」
と,大名を国王と呼び,その領国を,
王国,
と呼び,
「全支配権と命令権を掌握した『屋形』と呼ばれた戦国大名たちは,国の領主であり国王にほかならず,その国は屋形―国衆―小領主−農夫の身分階層と土地の分配によって構成されている」
と見ていた。しかし,第四世代は,
「前半生は戦国・織豊時代の戦国大名だが,天下人の時代に『仕置』と称した領地宛行(あてがい),すなわち安堵の朱印状によって領地に封じこめられた。」
そうした戦国大名の,
「実像を観察し戦国乱世を生きた彼らの行動規範や思考回路を探索する」
のが本書の目的である。
「大名家中における権力闘争や家臣団の内部紛争,および領域的な支配権を持つ譜代の家臣や独立性の強い一門一族との抗争など,家中の粛清」
による権力掌握プロセスを,
「粛清と王殺し」
として,第一章を始めている。下剋上,つまり,「下が上に克つ」の意味を,著者は,
「いつの時代にもある,権力闘争としての下剋上が,ことさら戦国・織豊の大名や武将の個性として解かれる理由」
を,
「毛利元就のように,守護大名と闘争して地域国家を成立させた非守護系の地頭国人らの下剋上を,戦国大名の典型とする考え方」
と,
「織豊期の下剋上(立身出世・人材登用)の代表が太閤秀吉だったように,信長・秀吉・家康らの家臣も主人にともない身分的上昇が顕著だった…。儒学者・林羅山に系図の真偽を疑われた福岡藩主黒田家にしても叱り,ほとんどの近世大名のルーツが判然としない」
と,
「十五世紀前半はに飢饉の頻発したことから,一揆の時代だった。山科本願寺の一向一揆…,対抗した法華宗の一揆が,…京中の一向宗の御堂を焼き払い,更に山科は灰燼と化し,本願寺は大阪へ移った。このような宗教一揆,宗教戦争の様相について,鷲尾隆康が『一揆の世』と嘆いた」
と,
「『俗姓凡下』と呼ばれた地侍・足軽・土豪商人ら地下人による,自由な『主取り』(主従関係を結ぶこと)や,複数の主人を仰ぐ複線的な主従関係も想定できる。ただし彼らは領主側からは,名字を持って『侍分』を自称しても,所詮『凡下』だと見下されていた。そのような身分上のボーダーラインに生きる人々が一揆の主力だった」
等々という,一種の階層のガラガラポンの様相にあることを挙げている。
そんな中で,戦国大名として権力を掌握していくプロセスを,
父子相克として,武田信虎・信玄,信玄・義信他,伊達家,島津家の内訌,
兄弟内訌として,織田信長・信勝等々,
家中粛清として,毛利元就の井上元兼一族の粛清,尼子等々,
王殺しとして,松平,大友,大内,斉藤等々,
を挙げて,
「戦国大名の軍事国家は,主に家中粛清によって構築された。『王殺し』も含めて,粛清は戦国大名の権力や権威の源泉となった。」
という。「家中」とは,
「大名の家族・親族衆,譜代・外様の家臣を大名の『家』として包括するもので,血縁・姻戚関係と主従関係,および家臣団の横の連帯によって構成された大名家の権力構造」
のことであり,だからこそ,この粛清は,
「家中や分国内で評価され認知されてこそ,権力の安定をみることができた。戦国大名の分国は,あくまでも正当な武威に支えられた軍事優先の主権国家だったのである。」
そういう戦国大名は,毛利元就の遺訓に,
「『天下御競望(ごけいもう)』など決して思ってはいけない」
とあるように,多く,
「家中と自らの領国たる『分国』を死守することに努め,天下の野望はほとんど抱いていなかった」
とされる。分国内では,戦国大名は,自らを,
公儀,
と称し,
「分国中では,戦国大名の公儀以外を排除して,大名の自力で地域国家を統治し,国家主権を形成した。」
しかし,豊臣政権が,全国制覇すると,
「豊臣政権では屈服した大名に対して,秀吉の領地朱印状をもって知行国を宛行(あてが)い,大名としての国主と領土としての分国が,列島規模の上級権力である豊臣公儀によって保証された。このような日本の国家体制のもとでは,戦国大名の自主独立した公儀は存在できない。大名間の戦争は,喧嘩と同様に私戦として断罪され,天下静謐の大義名分を掲げた統一戦争の攻撃対象となった。」
北条家は,その大義の元,二十万の豊臣軍に攻囲,押し潰された。
参考文献;
鍛代敏雄『戦国大名の正体 - 家中粛清と権威志向』 (中公新書) |
|
ヘイト・スピーチ |
|
師岡康子『ヘイト・スピーチとは何か』を読む。

最近ヘイトスピーチ対策法案が,実効性の是非はあるものの,ようやく国会で成立したが,本書(2013年刊行)は,「ヘイト・スピーチ」という言葉が,
「2013年に日本で一挙に広まった『ヘイト・スピーチ』という用語は,ヘイト・スピーチ・クライムという用語とともに1980年代のアメリカで作られ,一般化↓意外に新しい用語である。」
と冒頭で紹介する。そして,その言葉の成立経緯,
「ニューヨークを中心にアフリカ系の人々や性的マイノリティに対する差別主義的動機による殺人事件が頻発したことから,…ヘイト・スピーチ・クライムの調査を国に義務付ける『ヘイト・スピーチ・クライム統計法案』が作成された。これが『ヘイト・スピーチ・クライム』という用語の始まりと言われている。」
から見て,
「ヘイト・スピーチ・クライム・もヘイト・スピーチもいずれも人種,民族,性などのマイノリティに対する差別に基づく攻撃を指す。」
とし,本書の狙いを,
「現在最も焦点化している新大久保,鶴橋などにおける排外主義デモに代表される人種主義的ヘイト・スピーチracist hate
speechについて中心的に取り上げるそれは『人種的烙印の一形態としての攻撃』であり,標的とされた集団が『取るに足らない価値しか持たない』というメッセージであり,それ自体が言葉の暴力であると同時に,物理的暴力を誘引する点で,単なる『表現』を超える危険性を有し,『人種的偏見,偏見による行為,差別,暴力行為,ジェノサイド』の五段階の『憎悪のピラミッドとしてしばしば説明される。」
とする。その意図を慮る前に,具体的にヘイト・スピーチを紹介して見れば,一目瞭然。たとえば,
「不逞鮮人追放」「韓国人を絞め殺せ」「うじ虫韓国人を日本から叩き出せ」「寄生虫,ゴキブリ,犯罪者。朝鮮民族は日本の敵です」「よい韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ」「くそ喰い土人撲滅」「害虫駆除」「韓国人売春婦五万人叩き殺せ」等々(新大久保)
「ゴキブリチョンコを日本から叩き出せ」「二足歩行で歩くな,チョンコ分際で」「いつまでも調子に乗っとったら,南京大虐殺じゃなくて,鶴橋大虐殺を実行しますよ」等々(鶴橋)
という具合である。
人を呪わば穴二つ,
という,人への罵詈雑言は,そのまま天に唾するものだが,こういう手合いには,効かない。しかし,日本政府は,基本的に人種差別に消極的だ。それどころか,石原慎太郎をはじめとして,公人自体が,平然とヘイト・スピーチをして憚るところはない。たとえば,慎太郎の発言は,
「不法入国した三国人,外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している。」
「女性が生殖能力を失ってもまだ生きているってのは,無駄な罪です。…もっとも悪しき有害なものはババァ」
「同性愛の人間ってのはかわいそうなんだよ,…遺伝工学の先生に聞いたら,人間に限らず哺乳類ってどんな世界でも必ず何パーセントかは純粋なホモができちゃうんだと」
等々,こういうのを放置できる日本の危険性は,
「偏見を拡散しステレオタイプ化し,差別を当然のものとして社会に蔓延させ,差別構造を強化することである。社会心理学者のゴードン・オルポートによれば,それは憎悪を社会に充満させ,『暴力と脅迫を増大させる連続体の一部』であり,究極的にはジェノサイドや戦争へと導く。」
ドイツでは,ユダヤ人に繰り返したヘイトスピーチが数百万人単位のホロコーストに直結した。ルワンダにおけるフツ族によるツチ族の数十万人の虐殺は,フツ族高官のラジオ報道での「ツチ族はゴキブリだ,叩き殺せ」などのヘイト・スピーチが引き金になった。我が国の関東大震災での虐殺事件も,「朝鮮人が来襲する」「朝鮮人が井戸に毒を投げた」と権力の捏造したデマとヘイト・スピーチが引き金になった。
本書では,「マイノリティ」を,
①一国においてその他の住民より数的に劣勢な集団で,
②非支配的な立場にあり,
③国民の残りの人たちと異なった民族的,宗教的または言語的特徴を有し,
④自己の文化,伝統,宗教または言語を保持することに対して,連帯意識を黙示的であるにせよ示しているもの,
とし,
「例えば,日本における米兵は,②の要件を満たさないのでマイノリティとはいえず,米兵に対する非難はヘイト・スピーチにはあたらない。」
とする。ヘイト・スピーチに曝された人は,
「性暴力の被害者と同様,PTSDに苦しみ,魂の殺人にまで至り,自死にまで追いつめられる」
という。そして,
「私が本当に許せないのは(在特会ではなくて)このような事態が許されているこの社会の規律と良識です」
という。その通り,我が国は,人種差別にも,民族差別にも,規制に,消極的というか,むしろ抵抗し続けている。
「1979年,自由権規約を批准し,20条によりヘイト・スピーチを禁止する法的義務を負ったが,30年以上その義務を怠ってきた。」
他の人権諸条約に較べると,人種差別条約への取り組みの消極姿勢が際立つ,と著者は言う。
「人種差別禁止法もヘイト・スピーチ・クライム法もヘイト・スピーチ法もないにもかかわらず,法整備を一切行わなかったのである。日本政府の人種差別に対する特異な姿勢がここでもみてとれる。」
国内のヘイト・スピーチの放置は,言ってみれば,そういう為政者の姿勢を反映している。そして,日本政府の,
「現状が,既存の法制度では差別行為を効果的に抑制できず,かつ立法以外の措置によってそれを行うことができないほど明白な人種差別が行われている現状にあるとは考えていない」
との態度は,まさしく現行のヘイト・スピーチを助長するものでしかない。意図的であるとしたら,醜悪である。
本書は,ヘイト・スピーチに法的規制に取り組む欧米,カナダ,法規制に消極的なアメリカ,日本を取り上げつつ,表現の自由を持ち出す慎重論に,
「想像してみてほしい『うじむしゴキブリ朝鮮人』と言われ,どのような対抗言論が成り立つだろうか。…『でていけ』『叩き出せ』という表現も,マジョリティがマイノリティ,とりわけ外国籍者に対して言うからこそ社会からの排除を意味し,生活基盤を失う恐怖につながる攻撃になるのであり,マイノリティの側がマジョリティに対し,『出ていけ』ということは,何ら反撃とはなりえない。」
と述べ,さらに,
「法規制するとヘイト・スピーチとして表れていた勢力が潜在化し,より危険な暴力行為に走るとの主張は,主観的にはどうあれ,表現の自由を社会防衛機能の観点からとらえ,そのためにマイノリティらに言語の暴力のサンドバッグに耐えろと主張しているに等しい。」
少なくとも,国際基準から見たとき,
「人権基準の求める制度のほぼすべてが存在しない」
という現状は,そのまま,ヘイト・スピーチの保護と同じである。恥ずかしいことは,他にも一杯あるが,これが,
美しい日本,
と自画自賛する,我が国の実態である。
参考文献;
師岡康子『ヘイト・スピーチとは何か』(岩波新書) |
|
40の仮説 |
|
ロジャー・R・ホック編『心理学を変えた40の研究―心理学の“常識”はこうして生まれた』を読む。
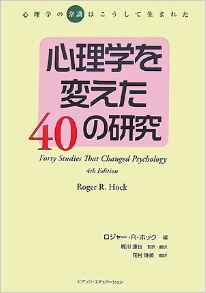
心理学といっても,本書で取り上げているのは,生物心理学,認知心理学,学習心理学,発達心理学,人格心理学,異常心理学,臨床心理学,社会心理学等々と多岐にわたり,生物学,行動科学,認知科学,精神病理学,精神医学と境界線を接している分野も多い。この中から,40の研究を取り上げているが,編者ロジャー・R・ホックは,本書のコンセプトをこう述べている。
「本書のコンセプトは,私の長年にわたる心理学講義から生まれた。心理学の教科書は,その比較的短い歴史において,心理学という科学を育ててきた中核となる研究を基本としている。しかし,教科書では,そういった独創的な研究に対して,その研究が享受すべき関心が払われることはめったにない。研究の過程は,そうした研究による発見がもつ本質,その発見にともなう高揚感がほとんど残っていないくらいまで,要約され内容が薄められている。研究方法や研究による発見についての記述のされ方のせいで,読者が研究の持つ本当の影響力について誤解することさえもときどき起る。(中略)心理学すべての基礎は研究にあり,私たちの人間行動に関する知識・理解が,今日に見られる高度のレベルまで質量ともに発展してきたのは,一世紀に渡る独創的で素晴らしい研究があったからこそであることを考えると,この状況は不幸であると言える。
本書は,心理学教科書と,心理学を成立させた研究との間にある,かなり大きなギャップを埋めようとする試みである。」
40の選択は,編者自身,
「議論の余地はあるが,心理学の歴史において,もっとも有名で,重要で,影響力があると言ってもよい者たちである。」
と述べるように,異論はあるかもしれないが,
「本書で取り上げた研究は,もっともひんぱんに引用され続けており,発表時に多くの論争を巻き起こし,多くの関連研究が続くきっかけを作り,心理学研究の新分野を開拓したのである。」
取り上げ方は,
1.オリジナルの研究はどこで手に入れられるかがわかるように,入手しやすく,しかも正確な参照先
2.取り上げた研究が生まれることになったこの分野における背景や,研究者が研究プロジェクトとを実行するにいたった理由をまとめた簡潔な紹介
3,研究が依拠する仮説
4.被験者はどういう人物であり,その被験者はどのように選ばれたかなど,必要に応じて,研究プロジェクトで採用された実験の設計や実験の方法の詳細な説明
5.明確で,わかりやすい,専門知識や統計データを使わない,専門用語を避けた言葉による研究結果の要約
6.オリジナルの論文における著者自身の考えをもとにした,研究による発見がもつ意味
7.心理学の専門分野における同研究の意義
8.同研究を支持したり,反駁したりする研究結果やこの分野における同研究に対する疑問や批判に関するまとめ
9.同研究が引き続き影響を及ぼしていることを示す,最近の展開や他の研究者の論文における同研究の引用から一部を紹介
10.同研究に関連している祭神論文の参照先
と,その論文のポジショニングをはかると同時に,
「こうした重要な発見がもつ高揚感やドラマ性を感じ取ってもらう」
ねらいで,委曲を尽くしている。とりわけ,
仮説―実験―結論−支持・反駁
という流れは,各紹介論文ごとに徹底している。さらに,当時は議論にならなかったであろう,動物実験や被験者への研究倫理上の問題にも,いちいち触れて検討を加えている。ただ,論文を取り上げるという制約から,たとえば,フロイトは,
アンナ・フロイト,
の論文「自我関与と自己防衛」で代替せざるを得なかったような部分はある。
心理学百年余の中で,
古典的条件反射のパブロフ,
オペラント条件付けのスキナー,
認知発達段階のピアジェ,
印象形成プロセスのアッシュ,
心の中の地図(認知地図)のトールマン,
奥行認知能力のギブソン&ウォーク,
期待効果(ピグマリオン効果)のローゼンソール,
レム睡眠のアゼリンスキー,
顔表情の共通性をざぐったエクマン,
社会的再適応評定尺度(SRRS)ノホームス&レイ,
タイプAタイプBのフリードマン&ローゼンマン
異常と正常診断の不可能さのローゼンハン,
服従に関する研究のミルグラム,
認知的不協和のフェスティンガー,
左脳右脳の分業につてのザガニガ,
目撃証言の不確かさを証明したロフタス,
母と子のカンガルーケアの重要性を発見したハーロウ,
性行為の実態に迫ったマスターズ&ジョンソン,
学習性無力感のセリグマン,
セラピー理論の効果についてのスミス&グラス,
系統的脱感作法のウォルピ,
同調圧力についてのアッシュ,
責任分散で傍観するダーリー&ラタネ,
等々,懐かしいのもあれば,知らなかった研究もある。
本書を読んで感心するのは,当たり前だが,
仮説,
を一項目必ずおいていることだ。仮説とは,
現状への疑問,
に他ならない。実験プロセスや人となりの是非だけで,おもしろい仮説を葬り去るSTAP細胞騒動の,この国の,独創性とは何か,創造性とは何かという基本風土がなく,ただ結論だけを追い求める野次馬根性とのあまりの差に,愕然とする(一方,STAP細胞と名づけるかどうかは別にこの仮説を特許申請するアメリカの学者のチャレンジ精神に感心する)。
例えば,ホブソンとマッカレーは,フロイトの精神分析的夢解釈に疑問を持ち,結果として,
「生理学上の夢睡眠に,人間とその他の動物に違いはない」
「眠っている間,感覚入力(外界から脳に入ってくる情報)はブロックされている。」
「レム睡眠中に脳は活性化され,独自の情報を自ら生み出し,レム睡眠中に夢を作っている」
として,
「夢睡眠は純粋に生理的なもの」
と結論を出した。大事なのは,仮説であり,それを立証するための実験方法の構想である。その(今日では批判があるが)出色なのは,ミルグラムの服従実験である。
なお,他にもこの40から洩れているものはあるだろうが,個人的には,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/436714013.html
で取り上げたザイアンスの,
単純接触効果,
が入っていないのは,ちょっと残念である。
参考文献;
ロジャー・R・ホック編『心理学を変えた40の研究―心理学の“常識”はこうして生まれた』(ピアソンエデュケーション) |
|
社会心理学 |
|
小坂井敏晶『社会心理学講義−〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉』を読む。

社会心理学に関する書籍は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/398486307.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163239.html
等々,何冊か読んだが,どれも薄っぺらな感じがして,不満であった。そのわけを,本書を読んで,何分かわかった気がする。それは,今日の社会科学,あるいは広く科学そのものの陥っている陥穽でもあるように見える。
著者は,「あとがき」で,
「本書を綴り始めた頃,『社会心理学の敗北』というタイトルを考えていました。」
と書くほど,現在の社会心理学の「矮小な学問になったしまった」現状に批判的である。
「人間という存在を理解するために社会と心理の知見の統合をするという最初の野心を忘れ,心理学の軒を借りて営業する小さな屋台になり下がりました。自然科学に憧れ,模倣するうちに技術的細部にばかりこだわり,本来の使命を忘れたのです。」
と書く。本書は,著者が,「はじめに」で,
「勤務するパリ第八大学で修士課程の学生を対象に行った講義を基に構成しました。社会心理学講義とはいえ,概説や入門書ではありません。影響理論を中心に話を進めますが,個々の内容よりも社会心理学の考え方について批判的に検討します。」
と,書く通りの展開である。
「二つの重心を選びました。生物や社会を支える根本原理は同一性と変化です。ところで,この二つは矛盾する。あるシステムが同一性を保てば変化できないし,変化すれば同一性は破られる。同一性を維持しながら変化するシステムは,どのように可能なのか。」
このテーマを軸に,
認知的不協和理論のレオン・フェスティンガー,
と
少数派影響理論のセルジュ・モスコヴィッシ,
という二人の社会心理学者を中心に,その「発想」を学びながら,著者の問題意識を展開する。そこには,サブタイトルの,
「〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉」
が関わる。
「閉じたシステムとして社会を把握したフェスティンガーと,開かれたシステムとして理解したモスコヴィッシ。普遍的価値に支えられた〈正しい世界〉という全体主義,システムを内部から切り崩す少数派の存在意義…。」
精しくは,本論を読んでいただくほかはないが,
「科学においても哲学においても大切なのは疑問を提示し,それに何らかの答を与えることです。」
という著者らしく,著者の強烈な疑問で,本書は成り立っている。
「本書は社会心理学を俯瞰する教科書ではありません。人間を理解するために,どのような角度からアプローチすべきか。それを示唆するのが本書の目的です。」
「人間を知るためには心理と社会を同時に考慮する必要がある。というよりも,社会と心理とを分ける発想がすでに誤りです。問いの立て方や答の見つけ方,特に,矛盾の解き方について私が格闘した軌跡をなぞり,読者と一緒に考えたい。」
疑問,
とは,
「ふつう信じて疑わない常識の見直し」
であり,当たり前としていることを疑うことである。著者は,
「答より問いの立て方」
である,という。それは,
どう仮説を立てるか,
ではないか。仮説とは,
「暫定的な説明」
であり,
実験結果の予測ではない,と著者は言う。僕は,仮説を,
仮の説明概念,
と呼んでいる。STAP細胞騒動で露呈したのは,日本は,
仮説のもつ重要性,
逆に言えば,
問いを立てること,
の重要性にはほとんどか関心がない,というあきれ果てた現状だった(確かめられないままに終るのかもしれないが,小保方氏の仮説は面白いと思っている。だからこそ,検証されないうちに,ハーバード大は特許申請に動いた。彼らは仮説の持つ重要性に気づいている)。
「私の立ち位置についても少し説明します。科学的思考は客観性を重んじますが,それは中立性とは違います。学問においても政治においても中立な立場は存在しない。」
だから,著者は,こう書くのである。
「学問の背景には人生がある。考察の陰に感情や苦悩あるいは叫びが隠れている。テーマの選択にもそれは表れるし,自らとの対話を通して出てくる疑問と,それに対する答とを昇華した形で書かれる文章の行間には研究者が悩んだ軌跡が読みとれるはずです。当人の実存に無関係なテーマで人文・社会科学の研究が可能だとは私には信じられません。」
その著者は,フランスで勉強し始めた頃,
「何を研究しているかではなく,誰を研究しているのか」
と,日本の学者や学生から聞かれて当惑したと書く。そこには痛烈に批判が込められている。
「デカルトやウィトゲンシュタインに向かって,『先生は誰の専門家ですか』と尋ねるでしょうか。…あなたにとって,主体とは,時間とは,責任とは何なのか。これらの問いに対して,あなたはどうアプローチして,どのような答えをだすのか。本当に大切なのはそれだけです。」
この背景には,当然多くの日本の,人文・社会科学系の学者が,「誰かについての研究者」であり,哲学者ではなく,(カントやヘーゲルなどの)哲学者研究者でしかないという現状がある。
久しぶりに,肉体のある,というか,肉声のある論説を読んだという印象がある。こういう一節がある。
「モスコヴィッシはなぜ少数派影響理論を考えついたのでしょうか。…モスコヴィッシは構成主義的な発想をし,世界や歴史の根元的な恣意性あるいは虚構性を熟知していた点がその理由のひとつだと思います。つまり世界に普遍的な真理はない。我々の目に映る真理は人間の相互作用が生み出すという世界観です。真理だから同意するのではない。悪い行為だから非難するのでもなければ,美しいから愛するのでもない。方向が逆です。同意に至るから真理のように映る。…共同体での相互作用が真・善・美を演出するのです。
社会心理学者は集団現象を,個人の心理メカニズムに還元して把握する。それどころか,社会状況におかれた個人心理の分析のみが社会心理学者の仕事だと考え,集団現象を研究対象に含めない学者がほとんどです。モスコヴィッシの反論を聴きましょう…。
『もっともよくある研究アプローチは,まず個人の表象を個別に分析する。そして次の段階として,集団内におかれた個人の表象を検討する。しかし集団から隔離された個人などは抽象的に考えられるだけで実際には存在しない。だから,これでは問題から逃げているだけだ。もちろん二種類の事象を区別する必要はある。しかし往々にして信じられるように,(a)個人表象と,(b)集団表象に分けるのではなく,(a)集団表象と,(b)集団におかれた個人の表象とに区別すべきである。』」
こんな当たり前のことを,と思いつつ,不意に,花田清輝が,武田戦法について書いていたことを思い出した。
「そもそもあの『風林火山』という甲州勢の軍旗にれいれいしくかかれていた孫子の言葉そのものが,孫子よりも,むしろ,猿のむれに暗示されて,採用されたのではなかろうかとわたしはおもう。『動かざること山のごとく,侵掠すること火のごとく,静かなること林のごとく,はやきことかぜのごとし。』−などというと,いかにも立派にきこえるが,つまるところ,それは,猿のむれのたたかいかたなのである。(中略)
猿知恵とは,猿のむれの知恵のことであって,むれからひきはなされた一匹もしくは数匹の猿たちのちえのことではない。檻のなかにいれられた猿たちを,いくら綿密に観察してみたところで,生きいきしたかれらの知恵にふれることのできないのは当然のことであり,観察者の知恵が猿知恵以下のばあいは,なおさらのことである。」
妙に,この痛烈な皮肉が響きあうのである。
参考文献;
小坂井敏晶『社会心理学講義−〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉』 (筑摩選書)
花田清輝『鳥獣戯話』(講談社) |
|
アルゴリズム |
|
デイヴィッド・バーリンスキ『史上最大の発明アルゴリズム:
現代社会を造りあげた根本原理』を読む。

本書の原題は,
The Advent of the Algorithum
「出現」というか,どうやら「降臨」という含意らしい。副題が,
The Idea That Rules the World
世界を制御する,というより,規定するというか,世界を解くための手順,ということになる。しかし,思うに,それをするには,それ自体をメタ化するポジションに立たなければ,それを解くことはできない。
本書の冒頭は,
「60年以上前,数理論理学者は,アルゴリズムの概念を精密に定義して,効率的な計算という古来の概念に実質のある内容を与えた。その定義がデジタルコンピューターの創造につながった。思考が自らの目的に物質を従わせた興味深い例である。」
で始まる。しかし,
「物理法則は時空のなかには存在しません。世界を記述するのであって,世界のなかにあるわけではありません。」
と言わしめているように,最後の方で,こう述べている。
「アルゴリズム,情報,記号のパターンが,とくに分子生物学的レベルで繰り返し現れるのを見ると,わが意を得たりという感じがするが,このパターンがどうしてここまで増えたのか,一般的に私たちにはわかっていないという,往々にして忘れがちな事実を心にとどめておくことが大切だ。…生物はなんといっても具体的で複雑で自律的な三次元物体であり,自活できる何か,あるいは誰がだ。生物は,…好きなように動きまわる世界―私たちの世界―に属している。一方,アルゴリズム,情報,記号は,抽象的,一次元,完全に静的なものであり,先の世界とは大きく異なる記号世界に属しているのだ。こうした記号が有機体を生み出し,その形態と成長を支配し,自らのコピーを未来に残すなかで,分子生物学の核心にどんと腰をすえている大きな謎に私たちは気づかされる。いま述べた過程には,命令が与えられて実行され,問いが発せられて,その答が出され,約束が成されて守られる,そういう世界に特徴的ではあるものの,純粋に物理的な客体にはけっして見られない一つのプロセスが隠れている。コンピューターが唸り,人間がそれを見守るという相互作用のあるその世界では,知能は常に知能自身に依存しており,記号体系が目的達成するというのは,目的を達成することでなされるのである。これはパラドクスではない。…200年前,スイスの生物学者シャルル・ボネ―ベイリーの同時代人―は,『脳,心臓,肺その他多くの器官の形成を支配する機構』についての説明を求めた。それに応える,力学による説明はまだ得られていない。情報がゲノムから有機体に移るとき,何かが与えられ,何かが読まれる。また,何かが命じられ,何かがなされる。しかし,誰が何を読んでいて,誰が命令を実行しているのかは,依然さだかでない。」
と。だから,
「アルゴリズム,情報,記号の概念は生命の核心にある」
けれども,
「この三つがどのように有機体を形成するのかは,知能がどのように効果を現すか」
は謎の一部であると。
「物理法則でプレートテクトニクスの複雑性は説明がついても,リボゾームの生成は説明がつかない」
つまり,まだ,
「物理法則から私たちを取り巻く世界…にいたる推論の階段」
は組み立てられていない。で,
「ステーヴン・ワインバーグの忘れがたい言明を修正しよう。科学に期待できることは,せいぜい,物理の基本法則と偶然,それに計算方法,アルゴリズム,専門化されたプログラム言語,数値的統合の手法,巨大なお決まりのプログラム(マテマティカやメープルといったもの),コンピューターグラフィクス,内挿法,コンピューター理論の近道,さらには数学者と物理学者がシミュレーションのデータを一貫したパターンや示唆に富む対称性と連続性を具えたストーリーに変換しようとする,精一杯の努力の寄せ集め等々の手段に基づいて,あらゆる自然現象を説明することくらいだ。」
と,皮肉を込めて結論づける。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/437240511.html
で触れたように,ゲーデルのしたことは,
「基本的には,数学におけるメタフィクションに他ならない。」
のであり,「数学の『外』に出て,…数学の全体像を眺める」ことである。そして,テューリングは,公式や推論規則といった道具の代わりに「計算する機械」,「テューリング機械」を考えた。その視点の問題に行きつく,と思い知らされる。
著者は,西洋世界での偉大な概念を,
微積分,
と
アルゴリズム,
と言い,「三つめは現れていない」という。そして,
「アルゴリズムは,一組の規則であり,規定であり,行動規範であり,指針であり,結びつけられ制御された指令であり,規約であり,生命がさえずるカオスに複雑な言葉のショールを掛けようとする努力」
であり,その努力のプロセスを,ライプニッツから始める。
ペアノ,
ブルーノ,
フレーゲ,
ラッセル,
ヒンベルト,
と経て,ゲーデル,チャーチ,テューリング,と列伝が続く。しかし,著者は,
「ゲーデルは,成果を生むのに必要なエネルギーを得るために強い向精神薬を服用し,1930年代を通じて各地のサナトリウムを転々とせざるを得なかった。チャーチ自身は自分の生活を記号の追求に従属させ,自分の記号論理研究の一環として人生をおくった。“単純さ”ということについて急進的な意識を持ち,孤独に生きたテューリングは,最後には,生きるより死ぬほうが単純であることを受け入れた。深遠かつ強力で,論理を引き起こす学問分野として数理論理学が誕生しようとしていた時期を調べると,論理学をつくった人々は,ほとんど例外なく,生みの苦しみを人格に反映させていた。神経衰弱になる者もいれば,完全に狂ってしまう者もいたし,…酒や薬に逃避するものもいた。」
と,しかし,その結果,
「世界各地の論理学者が々概念領域を探った結果,アルゴリズムを体系化する作業はわずか数年で完了」
するに至る。そこから,
エミル・ポスト,
が,
ポスト生産方式(プロダクション)
と呼ばれる仕事をなす。テューリングマシンとの違いを,著者は,
「テューリングマシンは理想化されたコンピューターであり,テューリングマシンにはハードウエアとソフトウエアのあいだにはっきりした区別がある。テープ読み取りヘッドはハードウエア,指示はソフトウエアだ。しかし,ポストの機械は全く象徴的なものである。ハードウエアは極限にまで縮小してしまっている。人間の作業者は指示にしたがうためにだけいる。この点から考えれば,ポストはデジタル・コンピューターよりむしろそのプログラムを先取りしたものをつくりだしたのだ。」
とし,「記号で表される規則にしたがって記号が記号によって衝き動かされる宇宙にある」機械を創造したとする。そして,
ゲーデル,
チャーチ,
テューリング,
にポストを加えた四人を,
アルゴリズムの定義,
を四通りで与えた人物,とした。
「この四つの定義は“四つの言い回しによって一つの概念を定義している”
という意味で等価であることに気付いた時点で,『劇的な統一』をはたした,と。それを,デジタルコンピュータ―として完成させたのが,『その深みのなさを速さと守備範囲の広さと数学上のテクニック』で補った」,
フォン・ノイマン,
ということになる。
ボルツマン,
シャンクン・マ,
シャノン,
を経て,ニューラルネットワークまで至る。しかしいまだ,
心のアルゴリズム,
は見つかってはいない。ペンローズは,
「意識は計算的なものではありえない」
という結論を下しているという。しかし,著者は,
「心に属する概念と数学上の概念をへだてる石だらけの土地は,不毛なものだと思われがちだが,現代数学はアルゴリズムの概念のなかで知能の概念そのものの存在証明を示す。」
といい,現時点の到達点を,こうまとめている。
「アルゴリズムは記号を操作するための方法である。だが,これは,アルゴリズムがなにをするかを言っているにすぎない。記号は,…世界を反映するためにある。情報を伝える手段なのだ。(中略)クロード・シャノンが情報を非公式な概念から数学上の第一級の概念に格上げしたことは,…別の目的にも役立った。複雑性を,測定可能であるため基本的なものとみなされる属性の一つとすることを可能にしたのである。(中略)ロシアの大数学者グレゴリー・コルモゴロフと,当時ニューヨーク市立大学にいた学生グレゴリー・チェイティン(中略)は同時期に,ランダムさと複雑性の間に親和性を認めた。(中略)事物の複雑性は事物が記述される状況によって測ることができるのだ。(中略)そこで,…二進数(バイナリ―)数列―0と1の列―に注目する。『ある記号列がそれより著しく短いコンピュータ―プログラムによって生成できる場合,その記号列は単純であり,そうでなければ複雑である』と…。(中略)
いま述べた定義づけが劇的な印象を与えるのは,そこに二重の還元手続が含まれているからだ。事物のなかに潜む情報は,二進法数字の列によって,それらを制御する記述はコンピュータ―プログラムによって書き表される。しかし,コンピュータープログラム自体も,記号列として書き表すことができるのだ。今や,宇宙に存在するお馴染みのものは取り去られ,ランダムさと,複雑性,単純性,情報が,…記号列の穴の上で踊る。
この複雑性という概念によって,ある程度まで,数理科学が陥っている普通の人の興味との乖離の説明はつく。」
さて,ここで,求めているのは,やはり,
「私どもは根究極的な統一理論を探し求めているのです。」
なのである。乞うご期待,である。
参考文献;
デイヴィッド・バーリンスキ『史上最大の発明アルゴリズム:
現代社会を造りあげた根本原理』(ハヤカワ文庫 NF ) |
|
秀吉像 |
|
日本史史料研究会『秀吉研究の最前線』を読む。

本書は,最新の秀吉像を,
第1部 政治権力者としての実像
では,
秀吉と朝廷との関係,
秀吉と武家官位の問題,
秀吉の大名統制策,
五大老・五奉行の機能と意義,
政権初期の知られざる家臣たち,
というテーマで,特に,
「関白になった意義,および官位を用いた大名統制」
「五大老・五奉行…も,五大老が上,五奉行が下…という尺度では測れないこと」
等々は,余り知られていない面だが,新たな側面に光を当てている。秀吉の官位制度は,
「それまでの中世の武家官途による秩序とはまったく異なるもので,秀吉によって創出され,それを継承した徳川政権によって近世武家官位制として確立されることになる。なお天正十三年九月に秀吉は豊臣姓を賜っており,秀吉の家臣・臣従大名は,官位の叙任を受ける際,当初は元々の本姓(藤原,源など)で受けていたが,聚楽第行幸後の天正十六年(1588)七月以降,豊臣政権に属する者は,叙任の際に必ず豊臣姓を与えられて用いるようになっている。」
官位は,臣従したものの忠誠を獲得するために,秀吉が与えた恩恵であって,
「秀吉の政治的意図により創出された」
と見なされている。つまり,
「諸大名に豊臣姓を授与すると同時に,苗字である羽柴を与えることにより,擬制的な血縁関係をもって,『豊臣一門』と見なすことで大名統制策のひとつとした。さらに,諸大名の家臣(陪臣)にまで豊臣姓が授与されることとなる。」
第2部 誰もが知っている秀吉が命じた政策,
では,秀吉の重要な政策である,
太閤検地,
刀狩,
惣無事,
天下統一船,
朝鮮出兵,
の見直しはかなり知られてきたが,特に,「惣無事」の可否について真のホットな論争は,ある意味秀吉像を真逆にするものだけになかなか面白い。
第3部 秀吉の宗教・文化政策の実像
では,
秀吉と寺社との関係,
キリスト教政策,
茶道との関わり,
の切り口から取り上げているが,茶道の政治的利用に焦点を当てた分析は,利休の主体的なかかわりの部分も含めて,改めて戦国期の茶道イメージを確認させられる。キリスト教禁止令については,わずか一日で,不況への規制令から,翌日には禁止令に,がらりと方針転換する背景に,何があったかの部分が,秀吉の貿易政策を象徴しておおり,なかなか興味深い。
第4部 秀吉の人生で気になる3つのポイント
では,
秀吉の出自,
清州会議以降のどこで統一に転じたのか,
家康との関係,
を取り上げている。出自では,縁者が少なく,母方の姉や弟や,母とつながる加藤清正等々は重視している。しかし,
「実父さえわからない秀吉が,竹阿弥は言うに及ばず,実父の菩提寺を建てたり,位牌を追贈したりすることをおこなっていない…し,実父や養父の系統に連なる親族が,秀吉の家臣に含まれていない」
ことから,秀吉の出自の想像がつく。さらに,
「なかには数人の子が存在した可能性」
があり,
「フロイスの『日本史』に見える記述から,生活を維持するために大政所は不特定の男性と関係を持ったのは確実であり,当時は珍しいことではなかったこと,母の大政所は貧苦にあえぐなかで,複数の男性と関係を持ち,子を産んだ可能性が高いこと…。ただし彼らは,いずれも秀吉によって殺されてしまったらしい。」
との記述に,秀吉が,どういう来歴だったかを如実に語っている。その中から,おのれの才覚ひとつで,史上初の「武家関白」として,天下人に昇り詰めるというのが,いかほど至難なことかは,想像に余る。
「秀吉は信長の小者として出発し,一代で権力を掌握し,大家臣団を築きあげた傑出した人物である。ゆえに,秀吉あっての家臣団と言い換えることも可能であろう。ここに,秀吉の家臣団の特徴がある。(中略)しかし,このいっけん頑強で一枚岩のように見えた家臣団も,秀吉というカリスマがあってのものであった。…秀吉亡き後にそのもろさを露呈する。」
秀吉ひとりの政権であり,制度としての政権には至らなかった,ということなのだろう。
参考文献;
日本史史料研究会『秀吉研究の最前線』 (歴史新書y) |
|
恠異 |
|
河内将芳『落日の豊臣政権: 秀吉の憂鬱、不穏な京都』を読む。

本書は,文禄五年(1596)閏七月十二日(から十三日の深夜)の,文禄大地震から書きはじめる。小田原攻めから六年後,関ヶ原合戦まで,あと四年の時期である。
この地震は,
「有馬―高槻断層帯,さらに,淡路島では東岸の複数の活断層や先山断層が活動」
したもので,その規模も,
「内陸の活断層が引き起こした地震としては最大級に近く,マグニチュード七・五以上でマグニチュード八近い値と推測」
される大規模なものであった。しかも余震が翌年まで続くのである。この地震で最も大きな被害を受けたのは,
伏見城(指月城),
で,醍醐寺三宝院門跡義演の『義演准后日記』によれば,七月十三日の条に,
「伏見のこと,御城御門・殿以下大破,あるいは顛倒す,大殿守(天守)ことごとく崩れて倒れえわんぬ。男女御番衆数多(あまた)死に,いまだその数知れず,そのほか諸大名の屋形,あるいは顛倒,あるいはあい残るといえども,かたちばかりなり,そのほか在家のていたらく,前代未聞,大路も破裂す,ただごとにあらず」
と記す。また,吉田社の梵舜という僧侶の『舜旧記』には,
「大地震,子の刻で数万人死す,京中寺々所々崩れ倒る,第一伏見城町已下転倒しおわんぬ,大仏築地・本尊破裂しおわんぬ,北野経堂・東寺金堂(食堂カ)以下倒れると」
とあり,
「もっとも大きな被害を受けたのが,当時豊臣秀吉(羽柴秀吉)が主要な虚点のひとつとしていた『伏見城町』(伏見城(指月城)とその城下町)と,秀吉によって造立された『大仏』(東山大仏)の『築地』(築地塀)や『本尊』だった」
のである。
社会を震撼させたこの地震が引き金で,「地震大凶ゆえ」と,文禄から,
慶長,
へと年号が改元される。著者は言う。
「これからわずか三年後に秀吉も亡くなってしまうことを考えたとき,この地震による『伏見城町』と『大仏』『本尊』の崩壊は,秀吉とその政権,いわゆる豊臣政権の崩壊のはじまりを暗示するものになったであろう。」
と。そして,
「そのような崩壊は,この地震によってのみ突然はじまったわけではなく,それを準備する時代の動きも徐々に用意されていったのではないかと考えられる。本書は,そのような時代の動きを文禄元年から五年という,文禄の年号を冠する時期にあえて限定してみようとするものである。」
と意図を説明する。
天正から文禄に改元された天正二十年(1592)は,小田原北条氏が滅亡し,奥羽仕置も終り,
「もはや秀吉とその政権に歯むかう敵は存在せず,天下統一がなしとげられた時期にあたる。つまり,権力としては絶頂期をむかえていたころだが,しかしながら,絶頂期こそ,崩壊の序曲がはじまるというのも世の常であろう。」
と,本書が,文禄年間(1592−96)というかぎられた時期に注目する理由を述べている。ちょうど文禄の役という対外戦争が始まるが,本書は,
「そのような対外戦争や,あるいは政権そのものに焦点をあわせるのではなく,むしろ,その外側にいる人びと,とりわけこの時期,秀吉とその政権下にあった京都という都市に住む人びとに焦点をすえて,時代の動きというものを見ていきたいと考えている。」
と述べる。いわば,
時代の雰囲気,
というものをつかんでみようとする試み,といっていい。その反照になっているのは,
桃山の京都,
を,
弥勒の世,
とした,林屋辰三郎氏の言葉にある,
豪華絢爛な桃山時代,
というイメージや,『大かうさまのくんきのうち』(太田牛一)の自画自賛するような,
ありがたき御代,
ではなかった時代の雰囲気を,伝えようとしている。
象徴的なのは,文禄四年(1595)十月の,宇喜多秀家女房(前田利家の娘)の,
狐憑き,
騒動と,秀吉政権による,
野狐狩り,
である秀次切腹,秀次妻子の処刑から二カ月後のことである。この翌年六月二十七日,京都周辺で,
降砂,
あるいは,砂ともされるが,
「土器(かわらけ)の粉のごとくなるもの」(『義演准后日記』)
「こまかな灰」(イエズス会宣教師)
が,「四方曇りて雨の降るがごと」くに降り,七月十二日に,
大地震,
が起こり,翌々日十四日には,
降毛,
が起きる。
「白くて長い毛髪の大量の雨が降った…老婆の毛髪と何らかわっていない」(『義演准后日記』)
ものが,正午まで降り続いた(この砂と毛は浅間山噴火が原因らしいが)。こうした,
「恠異(かいい)」
について,義演は,
「不可思議なる恠異,ただごとにあらず」
と,日記に書く。そして,
「まことに百姓の労苦このときなり,地検をせられ,あまつさえ昼夜普請に責めつかわれ,片時も安んずることなきなり,よって土を雨(ふら)すは余儀なきか,ついでに去年関白秀次謀反,誅せられ,今が数万人をもって,伏見山を開く,衆人群集す,まことに毛を雨するゆえなり」
と,秀吉と政権への批判を書きとめている。秀吉は,地震直後にもかかわらず,大破した伏見城を指月山から別の木幡山へと移し再建しようとしていたのである。しかも再建を思い至ったその日に,
降毛,
という恠異が起きたことについての上記義演の解釈は,ひとり彼のみではなく,
「『東寺寺僧』による『太平御覧』や『随書』など漢籍を『選出』しての解釈」
であり,多く共有されていたらしいのである。その解釈は,
「秀次事件や伏見城再見などに対する『天』のふるまいにほかならないと解釈されていたことをふまえたとき,人びとのなかで,秀吉やその政権が『天道,すなわち神様』や『天』から見放されつつあるのではないかという思いはもはや押さえがたいものになっていたことであろう。」
と,著者は書きとめる。秀吉死去の二年前である。『当代記』の,
「太閤秀吉公,日本小国には不相応の才人たり,しかるところかくのごとくの人の苦労を顧みたまわざること,ときの人不審」
という記述が象徴している。
「資料の表側にはなかなか出てこない闇の部分に焦点をしぼった」
本書は,確かに,政権末期の豊臣時代の暗い破滅の兆候を,のぞき見させてくれている。
参考文献;
河内将芳『落日の豊臣政権: 秀吉の憂鬱、不穏な京都』(吉川弘文館 歴史文化ライブラリー) |
|
小田原攻め |
|
中田正光『最後の戦国合戦「小田原の陣」』を読む。

秀吉の「関東惣無事令」,再三の上洛要請,北条氏直の舅に当たる家康からの要請に,迷い続けた北条が,
氏政の四男氏規の上洛,出仕を経て,天正十七年(1589)極月(十二月)上旬に,氏政・氏直が,上洛出仕するという誓約,
御請一札,
を秀吉に届け,落着する運びになっていた。懸案の,
沼田領問題,
も秀吉による,
上野の中で真田の知行地の三分の二を,沼田城とともに北条領地とし,三分の一は真田領とし,家康支配下の信州伊奈郡を真田に引き渡す,
という裁定で決着したはずであった。しかし,名胡桃城事件が起きる。このいきさつは,沼田領の三分の一の真田領にある名胡桃城を,11月3日,
「相模(北条)が信濃の真田の城を一つ取った」(松平家忠日記)
という事件が起きる。つまり,名胡桃城の城代鈴木主水が猪俣邦憲に城を奪われる事態が起きる。それを聞いた秀吉は,11月21日
「この上は,北条出仕申すにおいても,彼のなくるみへ取り懸け討ち果たし候者どもを成敗せしめざるにおいては,北条赦免の儀これあるべからず候。その意を得て,境目の諸城共へ来春までに人数を入れ置き,堅固を申し付く」
と指示した,という。しかし,この名胡桃事件,いささかきな臭い。森田善明氏も,秀吉の謀略と言っていたが,氏直は,こう弁明している。
「名胡桃城はすでに真田から北条へ渡されたものなので,奪い取る必要がない。中山の書付をみればわかる」
と。中山とは,
「中山城(群馬県東郡高山村)の城主で真田昌幸の家臣だった中山右衛門尉か,あるいは弟の中山九兵衛のどちらかである。中山城も名胡桃城とおなじように,沼田・岩櫃の中間にあり,越後道(旧三国街道)を抑えていた。
中山城主の中山右衛門尉は,天正十年(1582)秋に北条方となっていた津久田城(群馬県渋川市)を攻めたが,伏兵によって殺害された(『加沢記』)。これにより,主人を失った地侍の中山衆と他の侍衆57名は北条方に属した。
こうして天正十年以来,中山城が存在する吾妻郡高山村周辺は北条に押さえられていたが,天正十四年九月七日に真田昌幸が奪還に成功してからは,兄を失っていた中山九兵衛尉も再び真田に属した(『沼田根元記』)。
しかし,北条軍の勢いが増してくると,九兵衛尉は再び北条軍に追われ,やがて天正十六年11月22日名胡桃城へと逃亡し,当時の城代とかっていた妹婿の鈴木主水(重則)に介抱を受け食客の身となった。
この九兵衛尉が,やがて天正十七年に猪俣邦憲の家臣にそそのかされ,名胡桃城代だった鈴木主水を城から追い出し,追い出された主水は沼田の正覚寺で自刃して果てたというのが『加沢記』の『名胡桃事件』といわれるものである。」
と,著者は書く。当然猪俣邦憲の独断でできるはずもなく,この背後には,北条の意志,小田原城の氏政・氏直親子の意志がある,と著者は見る。これを,
「中山右衛門尉が北条に攻めたてられた天正十年の春,名胡桃城主でもあった中山氏は北条との間で名胡桃城を引き渡すという合意を交わしていた可能性がある。」
それを証にして,「奪い取ったのではない」と弁明していたことになる。確かに,北条方には,
「名胡桃城を奪い取ったという認識はなかった」
のかもしれないが,事実上,秀吉の沼田裁定を反古にしようとしたことになる。
しかし,裁定で沼田問題が落着したはずの十月,秀吉は,大規模な軍事作戦を指示しているのである。
「一,兵糧奉行に長束正家,ならびに小奉行十七人を命じる,
一,年内に代官潟り二十万石を受け取り,来春早々ねで駿州江尻・清水へ運送してくらを建てて入れ置き,惣軍勢へ配分すること,
一,黄金二万枚を受け取り,勢州・尾州・三州・駿州で八木(米)を買い調え,小田原近辺の舟着へ届け置くこと,
附(つけたり),馬二万疋の飼料を調え置き,滞りなく与えること」(『碩田叢史』)
さらに,軍役定書があり,
「一,来年の春に関東に攻め込むための軍役のこと,
一,五畿内は半役,中国地方は六人役のこと,
一,四国地方から尾張までの間は六人役のこと,
一,三河・遠江・駿河・甲斐・信濃は七人役のこと,
右,軍役書付けのように,来三月出陣して,小田原北条を攻め滅ぼす,忠勤に励むように」
と定めている。これを,著者は,
「これを北条を滅ぼすための戦争準備だったと解釈するのは早計ではないだろか。長年の懸案だった沼田問題を解決して北条氏政の上洛が決定し,いよいよ関東の統治上の処置に取り掛かろうとする準備だったのではないだろうか。
この軍事行動は『北条を攻め滅ぼす』と強圧的に表現しているものの,内実は沼田領を含めた関東の今後の統治上の政策を平和裏に確実に進めるための軍隊派遣であり,北条攻略を目的とした軍隊派遣ではなかったと思われる。」
と書く。是非はわからぬが,素人ながら,
「秀吉の関白就任後に行われた四国・九州への出兵と国分けで,一貫して共通していたのは,当事者の意見を聞き届け,最低によって平和裏に解決しようとした」
という「惣無事」の概念にとらわれ過ぎているように見える。敢えて,氏政の上洛前に軍令を出すという意図は,少し違うのではないか。少なくとも,家康が,氏政に上洛を促す手紙の中で,
「北条領を望んでいない」
と言い訳するほどに,天正十六年段階で,
「坂東の北条殿(の領地)が家康の領国」(ルイス・フロイス)
になると噂さされていたこともあり,家康移封は既定路線だったとみるのが順当ではないのか。だからこそ,本来沼田城の付城として作られた名胡桃城は,北条にとって戦略上重要な意味,つまり,
「北条方の沼田城を監視する付城の役目をしていた名胡桃城を抑えることにより,それまで越後道への警戒が手薄状態だった状況を克服し,三国峠を越えてくると予想されていた北国勢(上杉・前田を主力とする軍勢)の最前線となることを回避する作戦だった。」
ということになる。いずれにしろ,秀吉方に口実を与えるという行為が持つ,重要性と,秀吉の動員する軍事的・経済的力量を見積もりそこなった,という意味では,この段階で,北条方は戦術にこだわって,戦略を誤った,というべきなのかもしれない。
では,なぜ,秀吉は,北条を打ち滅ぼす,という選択をしたのか。
「小田原攻めを通し,秀吉が民衆に対して取りつづけた対策があった。それは,『奴原』と呼ぶ侍たちに対しては容赦しなかったが,非戦闘員の一般民衆に対しては寛大な姿勢だった。
たとえば,天正十三年(1585)紀州・太田城(和歌山市)を攻めたとき,『各地にいる悪人の主だった奴らを選んで首を切り,残った百姓やそのほかの住民の妻子以下は助命するように』と,侍たち五十人以上が打ち首となり,百姓の家族は助命された(『太田文書』)。
これはあたかも中間搾取層(棟梁の奴原,侍衆)の否定と同時に,平百姓といった土地を所有する農民の救助を意味した。
戦国大名の家臣たちは,その大部分が郷村に居住して,直接的に村人たちを支配していた。彼らは在地領主として,農家(名子と呼ぶ反自立的な農民を従えた一軒の農家であったが,税収取の中に組み込まれていた。)とは徴税関係によって結ばれていた。
大名たちは,こうした家臣(在地領主・中間搾取層・奴原)と,農家との徴税関係をみとめていた。
ところが秀吉はそうした関係を断ち切り,家臣たちを郷村から切り離し,それまでの領主的権限を剥奪しようとした。」
この延長に,各大名に課す軍役の基準となる「太閤検地」,さらには,戦国大名の鉢植大名化がある。父祖伝来の土地にいる諸大名,特に,家康を北条の関東に,上杉を会津に,伊達を仙台に,と鉢植えのように戦国大名を移封していくためには,北条が攻め滅ぼされなければ,大名の鉢植化の将棋倒しが始まらなかった。僕はそう見たが,如何か。
参考文献;
中田正光『最後の戦国合戦「小田原の陣」』(歴史新書y)
森田善明『北条氏滅亡と秀吉の策謀』(歴史新書y) |
|
七将 |
|
三池純正『大坂の陣 秀頼七将の実像』を読む。

取り上げている七将は,
真田信繁,
長宗我部盛親,
毛利勝永,
後藤基次,
明石全登(たけのり),
木村重成,
大野治房,
である。多分馴染みが一番薄いのは,大野治房かもしれない。大野治長は有名だろう。その実弟である。また,大坂城落城後,脱出し生き延びたことが確かなのも,治房のみである。
七将の中で,最も若く,この冬の陣が初陣なのが,木村重成である。夏の陣で,戦死したが,わずか二十二歳である。秀次事件に連座して父常陸介切腹したのが三歳の時,以後,母の宮内卿局とともに淀君に引き取られ,母は秀頼の乳母となり,重成自身秀頼の小姓として,秀頼とともに成長,慶長十年(1605)に秀頼が右大臣になるとともにね重成も,諸大夫長門守に任じられ,初陣ながら,冬の陣では,三千の兵を率いた。
基次の家臣,長沢九郎兵衛の『長沢聞書』には,
「秀頼公と木村長門守は同年にして乳兄弟」
とある。
冬の陣では,重野・今福の戦いで,佐竹義宣に柵を占領され,その応援に駆け付けた重成は,佐竹隊を押し戻して追撃,鴫野からの上杉景勝隊の援護で分断され,孤立した際,救援の後藤基次に,交替を申し出られ,
「初陣の今日,途中で戦場を引き渡しては何の面目がたちましょう。」
と,言い切ったと言われる。夏の陣では,若江で,井伊直孝隊と激突,終に討死する。もともと討死を覚悟で,髪に香を焚いておいたとされる重成は,唯一,家康の首実検が行われた武将だが,重成の首からも微かに項の香りがした,という。著者は,家康が,
「大阪にも,見事な心がけを持った武士がいたものか。重成は稀代の勇士である」
といったという言葉を伝える。
天王寺の戦いで,家康本陣に突入し,二度本陣を突き崩して,あと一歩まで迫った真田信繁については,有名だが,最後数名にまで追いつめられ,安居神社で,松平忠直の配下,西尾仁左衛門に打ち取られる。それについて,細川忠興は,
「信繁は負傷した上,疲労して倒れていたところを討たれただけで,何の自慢にもならない。」
と書き,島津家には,
「真田日本一の兵(つわもの),いにしへよりの物語にもこれなき由」
と絶賛されている,という。まさに,死して名を残す,である。
後藤又兵衛については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/438599575.html?1464982607
で触れた。
明石全登は,キリシタンとして有名だが,宇喜多家のお家騒動直後,多くの家臣が去った後の宇喜多家を支え,関ヶ原では八千の大軍を率いて福島正則と対峙,小早川秀秋の秀家の裏切りで敗北した後,主君秀秋が戦場を離脱するまで敵兵を一身に受けて,踏みとどまり,秀家の離脱を見届けて,脱出した。
大坂入城に際しては,二千人のキリシタン武士とともに,七人の神父も大坂城に入ったとされる。夏の陣では,生国魂辺りから,精兵三百とともに押し出し,藤堂孝高虎隊を撃破,その後方の水野勝成隊,松平忠直隊を突き崩して,家康本陣に突入を試みるが,阻まれて,包囲を破って城東へ退いて行った,とされる。。諸説あるが,全登の行方は分からないままである。
毛利勝永は,関ヶ原で西軍につき,改易された。土佐の山内一豊に預けられたが,秀頼の要請を受けて,息子勝家ともども,密かに土佐を脱出,入城した。夏の陣では,真田信繁とともに,家康本陣に迫った。最後は,本丸に戻り,秀頼の介錯をし,嫡男勝家とともに,自刃する。
これら七将の中心にいるのは,豊臣秀頼である。秀頼については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/408642088.html
で触れた。家康は,豊臣家に大坂城から退城を促し続けた。
「少なくとも,秀頼の母淀殿や秀頼の側近大野治長らは,最後は家康の意向を汲み,大坂城を出ることで,豊臣家の存続を目指そうとしていた」
が,それを拒み,家康に挑んだについては,秀頼の強い意志が,一貫して貫いている。
参考文献;
三池純正『大坂の陣 秀頼七将の実像』(歴史新書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9D%91%E9%87%8D%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%85%A8%E7%99%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E5%9F%BA%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%B9%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E9%A0%BC |
|
後藤又兵衛 |
|
福田千鶴『後藤又兵衛 - 大坂の陣で散った戦国武将』を読む。
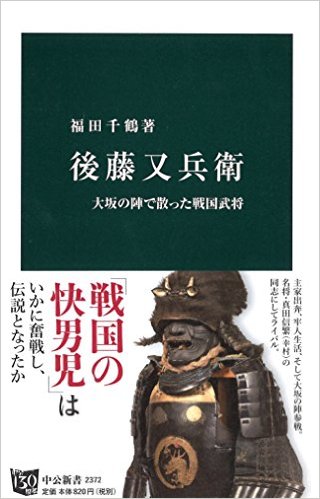
著者は,「あとがき」で書く。
「いざ調べ始めると,案の定,わからない。というより,納得いかないことばかりだった。特に播磨後藤氏と又兵衛との関係について,通説で言われていることは江戸時代になってから創られたものと確信するにいたった。諱からして,又兵衛が生存していた時期に基次を名のった形跡はない。」
つまり,
後藤又兵衛基次
といわれている,「諱」すら確かではないのである。しかし読みながら思ったことは,この時代,
来歴,
など無用の時代だったのではあるまいか。その人本人の器量だけが重要で,どこの由来で,どういう出身なのかが問題にされたのは,平和な江戸時代であり,二世三世が跋扈し,どういう家柄かだけが問われる今日は,個々人の才能にとっては,生きづらい時代なのかもしれない。思えば,徳川家だって辿れば,どこぞの乞食坊主まがいであったと言われる。この時代,すべてが「どこの馬の骨」か,という時代だった。
大坂城落城後,細川忠興は,その様子をこう手紙に書いている。
「さなだ・後藤又兵衛手がら共古今これなき次第に候」
本人は大坂冬の陣直後に,
「けふニあす替候浮世之習,面白候,大身小身も分別之仕置はむし口ニて候との申事候」
という文意の手紙を残している(ここで又兵衛の諱は「正親」となっている)。
「むし口」とは,「無口」の意で,著者は,
「目の前のいつ変るともしれないことをとやかく言ったりせず。『無口』で済ませておくことが,大身であろうと小身であろうと,武士にとって分別のあるしかたではないか」
と意訳する。
『豊内記』を例に,侍を,
「品々ある国とともに栄え,国とともに滅びるを社稷の臣」
「国の事はともあれ,善にも悪にも主君次第に成りゆくを譜代の臣とも,重代の家人」
「渡り者にて善き国へ身を寄せ,悪しき主君を去るを渡り奉公とも客臣」
とにわけ,
「又兵衛は故郷の播磨を去ったことで社稷の臣としての道を失い,悪しき主人長政のもとを去ったことで譜代の臣として生きる道をも否定した。残る生き方は,渡り奉公人の世界のみであった。そうした渡り奉公人の世界に生きればこそ,その渡り奉公人の『花時』が終焉を迎えようとしているなかで,又兵衛は最後の大きな夢を託せる人物として豊臣秀頼を選んだのである。」
その秀頼はというと,徳川側が流した虚像を剥がすと,
「最終決戦である五月七日未明に秀頼が先手に出陣して下知すれば軍勢の勇みとなり,たとえ敗軍しても秀頼が天王寺を墓所とする覚悟を究めていれば,如何なる弱兵といえども秀頼を観てて逃げたりはしないので,比類なき前代未聞の一戦を遂げるべき」
と真田信繁が主張したのも,
「勝ち負けではない。比類なき前代未聞の一戦を遂げ,色あせることのない名を末代まで残すことにこそ,定めなき浮世を生き,戦場を死に場所と思う中世人(戦国武将)にとっての最後の夢があった。命を預ける。そして,その命を預かる。これをつなぐものが『器量』である。そして,最後まで運命をともにする。そのような人物に出会えたことに生きていた証をみるのである。」
とされる秀頼は,最後に,
「運命早究りたり,ながらへてわが世の衰えを見玉わんより,同じ道に急ぎ後世を楽しみ玉ふべし,百年の栄華も一睡の夢と成り果てる習いなり」
と,自害を引きとめる母(茶々)に言ったとされる。秀頼像については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/408642088.html
で触れたように,
大坂夏の陣で,細川忠興は,
「秀頼は大阪小人町近辺まで出陣し,先手は『伊藤丹後・青木民部組中』であった」
と書状で伝えている。この地は,
「徳川方の小笠原秀政・忠脩父子が討死し,弟の忠政…も瀕死の深手を負った激戦区である。物語を辛口で評することで知られる忠興が,激戦区への秀頼の出陣を疑わなかった点は,秀頼が大阪城本丸の奥に隠れて何もしなかった軟弱者であるかのようなイメージを否定する…」
と,見直されつつある。つまり,
「秀頼は自己に一命を預けた者たちを見捨てるような武将ではなかった。かような武将だからこそ,又兵衛は大坂城に入り,和議後も大坂城を去ることなく,夏の陣を死に場所に選んだのである。」
翻って,又兵衛が,黒田長政のもとを去ったのは,
「主君長政に一命を預けられない,と考えたのではないだろうか。なぜなら,長政は器量のある戦国武将―預かった命を見捨てない―から,処世術にたけた近世大名―黒田家存続のためなら家臣の命も見捨てる―へと,自己のありようを変えようとしていた。それを大きく促したのは,天下泰平,徳川の世への移り変わりである。」
そのような変化は,「軽薄そのもの」と又兵衛には見えた。
又兵衛は,六尺以上あったとされる。その具足が,五男爲勝が受け継ぎ,菩提寺の景福寺(鳥取市)に納められた,
日月竜文蒔絵仏胴具足,
が伝来し,現在大坂城天守閣にある。
大坂陣中では,
「白黒段々の筋の幟,指物は黒に半月を描き,具足も黒で,兜の立物は獅噛(しかみ),武者羽織は,表を白色の熊皮,裏は玉虫色の大緞子,見送りに鉞を白糸にて大紋とし,纏は二重の鳥毛,上は角取紙があった。(中略)馬印は大ホオズキの提灯,使番は黄色の四半旗,家中の指物は黒一本撓い。」
又兵衛は入場に際して,中国の諸大名から三千余騎を借用した,と言う。黒い撓にそろえた兵団は,真っ赤の撓にそろえた,真田信繁と好対照であった。
最後にいくつか誤植に気付いたが,
「市川歌右衛門」
とあるのは,
「市川右太衛門」
の誤りである。
参考文献;
福田千鶴『後藤又兵衛 - 大坂の陣で散った戦国武将』(中公新書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E5%9F%BA%E6%AC%A1
http://www.sankei.com/west/photos/150314/wst1503140006-p2.html
福田千鶴『豊臣秀頼』(吉川弘文館) |
|
歴史認識 |
|
東郷和彦『歴史と外交─靖国・アジア・東京裁判』を読む。

著者は,終戦時外務大臣であった東郷茂徳の孫にあたる。その来歴を,日韓問題の章で,著者はこう書く。
「東郷茂徳は,鹿児島市から車で約一時間ほどの距離にある日置郡東市来街美山という村(現・日置市)の出身だった。美山は慶長三(1598)年,朝鮮戦役の最後に,半島から撤退する豊臣秀吉軍に拉致された朝鮮の陶工たちが,居を構えた場所である。この村で,朝鮮の陶工たちは,薩摩藩の独特の保護と隔離の政策下で,当時は世界の最先端技術による陶器を製産,世に知られる薩摩焼となった。
茂徳の父寿勝はこの村の陶工のひとりであり,明治維新のとき,旧姓朴を捨て,東郷姓を名乗った。茂徳は,明治十五(1882)年,この村に生まれ,この村からやがて,東京帝国大学に学び,外交官になった。」
以来三代続く外交官の家系である。
本書は,
靖国神社,
慰安婦問題,
日韓関係,
台湾関係,
原爆投下問題,
東京裁判,
と,いずれも「歴史認識」「戦争責任」に関わる,戦後70年もたっていながら,いまだ何一つ国家として主体的に,まともに解決できていない実にホットな問題を,冷静に腑分けし,論点整理をしている。個々に異論はあっても,必要なのは,こういう論点整理,つまり,
メタ・ポジション,
からの俯瞰だということをつくづく感じさせる。本書は,2008年,第一次安倍内閣当時に上梓されたが,以降,事態は一向に改善されていない。いや,改善どころか,悪化の一途をたどり,政権自ら歴史の全否定をし始めている。その意味で,本書の冷静な腑分けが,いまなお際立っている。
「あとがきにかえて」で,
「歴史に関心を寄せない民族に,おおきな将来性があるとは思えない。
だが,わが民族の,歴史に対する関心を見ていると,もうひとつ,そこに,猛烈な内部対立があり,巨大なエネルギーが,その内部対立に割かれていることを感じざるをえない。
歴史と民族のアイデンティティに関するわが国内の議論は,相互尊重にもとづく対話というよりも,人格攻撃を含む,猛烈な相互攻撃の渦のように感ぜられるのである。とくに,最近の出版の中には,右から左に対する猛烈な批判の書があふれているように思われてならない。
そういうことは,もうそろそろ,終りにしないといけない。」
と書く言葉が,切実である。幕末の,攘夷派と佐幕派のテロに見まがう口撃が,ネット上で,炎上という形で発生する。とても筆者の願いとは反する方向へ,その後さらに進んでいるように見える。
「日本自身として,戦争責任の問題をどう考えるのか。日本自身でこの問題について考え,結論を出し,それをサンフランシスコ条約第十一条との関係も十分に考えたうえで,受け入れていく」
というあなた任せの東京裁判以外に,戦後唯一,戦争責任の問題について,自分で判断したのが,
村山談話,
である,と著者は見る。
「閣議決定によって採択されたこの談話こそ,それまでの戦争責任に関する議論を総括し,政府として,自発的に下した,最も重要な意思決定だったと思う。」
著者は,慰安婦問題については,河野談話を,
「私自身は,明確に,“河野談話派”だった。私の年代の外務官僚としては,それは,一般的な立場だった。」
と語る。いまの世代の外務官僚とどの程度の認識さがあるのかは知らないが,漏れ聞こえる昨今の外交官の言動は,そこからは大きくずれ,夜郎自大化しているかに見える。印象深いのは,
「トーゴーさん,あなたは納得できないかもしれない。しかし,いまのアメリカ社会における,性(ジェンダー)の問題は,過去十年,二十年前とはまったくちがった問題になっている。
婦人の尊厳と権利を踏みにじることについては,過去のことであれ,現在のことであれ,少しでもそれを正当化しようとしたら,文字どおり社会から総反撃を受けることになる。(中略)
要するに,慰安婦の問題を考えるとき,多くのアメリカ人は,いま現在,自分の娘がそういう立場に立たされたらどうかということを本能的に考える。ましてや,それが,少しでも『甘言によって』つまり『だまされて』連れてこられ,そのあと,実際に拒否することができなかったというのであれば,あとは,もう聞く耳もたずに,ひどい話だということになる。
あなたが言われるように,そういう甘言でもって強制された人は全員ではなかったかもしれないし,軍の本旨としてはそういう事態を抑制したかったとしても,それが徹底して厳密に抑止できなかった以上,結果責任は免れないということになる。
(中略)日本全体が,今述べたアメリカ社会の現状を知ったうえで,議論しているだろうか。」
著者はアメリカでの慰安婦セッションの後,参加者から言われたことを書きとめている。この意味を弁えた議論がなされているとは,今日到底思えない。「朝日新聞が…」といい,言い訳し,正当化しようとした瞬間,そっぽを向かれている,ということが認識できているとは思えない。それは,著者の言う,
「情報戦で,極めて深刻な立ち遅れに至っている」
というレベルの問題ではない。集団拉致が誤報であることを言いことに,慰安婦問題自体を,公娼の問題にすり替えようとしている,というその姿勢そのものに問題がある。僕は個人的に,何千人単位で,インドネシアから徴用された人が,戦後多く行方不明となり,その帰還に尽力された日本人を知っている。ことは,慰安婦問題だけではない,占領地の人々を勝手に強制的に徴用するばかりか,シンガポールの華人虐殺のように公にならない虐殺,暴行,拉致は数知れず,そのいっさいに頬被りし続けているという態度そのものが問われている。「責任を取る」と二言目には言うどこやらのトップ同様,責任を取るとはどういうことかを,日本は国家として,本当にほとんど世界に,アジアに発信していないのである。慰安婦は,その象徴に過ぎない。
ところで,日韓問題で,著者は,安重根に言及し,彼の,
「いまは韓日は非常に不幸なかたちで袂をわかってしまった。しかし,いずれの日にか,韓日清はともに手を携えて,北東アジアの平和と繁栄をつくっていかなければならない。」
という言葉を載せる。僕はそこに,勝海舟が,(ということは,多分横井小楠も)三国連携を言っていたことを思い出させ,当時のトップクラス(維新の遂行者のほとんどはそこに入れない)の知性が抱く構想を共有する,安重根の人物とその無念さが見える気がする。
著者は,どの問題でも,常に,
「日本国および諸外国が受け入れられるような最善のかたち」
を,独自に提案する。その冷静なメタ・ポジションからの整理は,得難い。その上で,
「先の大戦にかかわる歴史認識の問題は,日本がいずれかの時点で克服すべき課題である。しかし,そのためには,戦略と情報が必要である。戦略とは,一番重要なのはなにかを識別し,選択し,他の重要なものとのあいだに優先順位をつけて,一つひとつ時間差をつけて解決していくことである。また,情報とは,相手側がなにを考えているかを知悉することである。」
開戦前に似て,自己に都合のいい情報のみを入れて自画自賛し,自己正当化し,相手を矮小化する今日のありようは,著者の考えとはあまりにも乖離している。
参考文献;
東郷和彦『歴史と外交─靖国・アジア・東京裁判』(講談社現代新書) |
|
間違い |
|
キャスリン・シュルツ『まちがっている―エラーの心理学、誤りのパラドックス』を読む。

本書の原題は,
Being Wrong
であり,サブタイトルが,
Adventures in the Margin of Error
となっている。邦語のサブタイトル「エラーの心理学、誤りのパラドックス」だと,間違いではないかもしれないが,焦点がずれる。
本書は,通常の「エラー」「錯覚」「勘違い」の本と違うのは,人が「間違った」と,認めないときも,認めたときも,その状態で起きる内的反応に焦点を当てていることだ。その意味で,
Being Wrong,
とは言い得て妙,「間違っている」と訳すと,微妙にずれる。多く,間違うことを,
「ただ恥ずかしい愚かなこととされるだけではない。無知で,怠惰で,精神的に可笑しくて,道徳的に堕落しているとみられることもある。」
しかし,
「間違いをそんなふうに見ることこそが,何より間違いなのかもしれない。それは私たちのメタミステーク(誤りに関する誤り)だ。私たちは,間違っているということの実態について誤解してしまっている。間違うというのは,頭が悪いことのしるしどころか,人間の認知能力の要にあることだし,道徳的な欠陥どころか,思いやり,前向きの姿勢,想像力,自信,勇気といった,最も人間的でほめられるべき性質とも切り離せない。間違いは,無知や頭の固さのしるしなのではなくて,私たちが学習して変わっていくことの根幹にある。間違えばこそ,私たちは自身についての理解をバージョンアップし,世界についての考えを修正することもできる。」
と,それが本書の底流に流れる通奏低音である。
「人の間違いがどんなに的はずれで,苦しく,つまらなくても,自分が何者であるかを教えてくれるのは,つまるところ,正しいところではなく,間違っているところなのだ。」
と。「Adventures」とあるのは,そういうところを狙うという含意がある。その意味で,著者の引用する,アウグスティヌスの,
「私は『もし私が間違っているのなら,私は存在する』と答える。存在しないものは間違いようがない。したがって私が間違っているなら,私は存在せざるを得ない。そして,私が間違っているということが私の存在を証明するなら,自分の間違いを見ることが,私の存在を確かめるのであって,私が存在すると考えることは間違いようがないではないか。」(『神の国』)
を引用する。しかし,それは間違いを認めたときだ。誤っている時,
「誤りが見えない(エラー・ブラインドネス)」
状態にある。間違いが何であれ,自分には見えない。しかし,誤りに気づいた時,
「一人称単数現在形では,誤りは文字どおり存在しない」。
自分が間違ったと気づくとは,自分では,
「I was wrong」
としか言えない。なぜなら,
「現在進行中の誤りは知覚できない」。
だから,誤りを,認めない。
「あることを,それが正しくないのに正しいと信じることだ―あるいは逆に,それが正しいのに正しくないと信じることだ。」
あるいは,
「私たちが正しいと感じるのは,自分が正しいと『感じる』からだ。私たちは正確さの指標として,自分自身の確信を使う。…私たちの確信は,内面にとくに鮮明な像が存在することを反映する」
から。そして,著者は,「間違っているのは,…必ず何かの信念」だと言い切る。さらに,
「自分が抱く信念は,自分の正体と不可分のこと」
であり,そこには,その人の振る舞い,知識,経験を含める。著者は,
「私は『信念』という言葉と『理論』という言葉を,…ほとんど同じものとして使っている。」
というとき,人の言動・意思決定を左右するものも,結局「信念」(違う言い方をすれば先入観)と言っているのに等しい。そこで,例に引いているのは,グリーンスパンの間違いの原因なのである(グリーンスパンは「世界のモデル」という言い方をしているらしいが)。そして皮肉を込めて,こう言う(これはそのまま黒田日銀総裁にも,アベノミクスを喧伝するわが国の首相にも当てはまる)。
「それはすべて,グリーンスパンの自由市場哲学と同じく,世界に関するモデルなのだ。…世界のモデルとは地図であり,基本的には信念もそういうもの,つまり,私たちの物理的,社会的,感情的,精神的,政治的地形を頭の中に再現したものだ。」
しかし,著者の関心は,その是非を言うことにはなく,
「思想としての間違い,経験としての間違い」
であり,本書では,間違いを,
「外部の現実からの逸脱か,自分が信じていることの内側からの逆転か」(あるいは「内面にある世界像と実際の世界とのずれ」「何かについて自分のもっているイメージと当のものとのずれ」)
を軸にしながら,
「何かの痛い思いをした人の話を中心にして構成されている。そこには,錯覚,手品師,コメディアン,薬物による幻覚,常時,海辺での不慮の事故,奇妙な神経学的現象,医療事故,司法の失態,娼婦との結婚がもたらしうる結果,なげかわしい世界的な失敗,アラン・グリーンスパンなどの話がある。」
それを,
第1部 私たちが間違いについてどう考えているか,
第2部 誤りの起源,
第3部 どうして間違うのか,間違ったときどう思うのか,
第4部 誤りの受け入れ
と追っていく。そして最後に,
「誤りをまさしくギフト―豊かで他に代えがたいユーモア,芸術,ひらめき,自分らしさ,変化の元―とみることを促す。」
そして
「間違っていることの快感でしめくくる」
と著者は言う。しかし,
「私たちは文化として,『私は間違っていました』と言うための基本的な技能を身に着けていないのだ。(中略)逆に,私たちは自分の間違いを認めることに対する代替手段を二つ修得する…。一つはささやかながらも巧みな追加条項。『私は間違っていましたけれど…』―この『…』は,自分が実はそれほど間違っていないことを言う,見事に想像力あふれる説明で埋められる―…。もう一つは(リチャード・ニクソンがウォーターゲート事件で,あるいはロナルド・レーガンがイラン・コントラ事件で用いたことで悪名高いが),もっと効果がある。『いくつかの誤りが犯された』と受動態で言うのだ(誰が犯したかは伏せられる)。このいつまでもすたれない言い方が見事に明らかにするように,誤りを処理する方法は,それを自分のものとは認めないことなのだ。」
その言わんとするところは,
(誤りを)認めるときには,新たな視界が開くのに,
である。著者の示す「誤りを認める」処方箋は,著者自身がありふれたと言う通り,ささやかなものだ。
「聞く耳をもつことは,自分の間違いやすさを自分の生活の中に入れる余地を作る。…しゃべるのをやめることで,十分,他の人の見方や自分の考え方についての見方を変える」
「自分が間違っている可能性を認める唯一の方法は,しばらく自分を強硬に弁護するのをやめることなのだ。」
しかし,誤りをガンディの,
「自由はそれが過誤を犯す自由も含んでいなければ,もつに値しない」
という言葉を,
「自由は,過誤を犯す権利を含んでいなければ自由ではない」
と言い替える。そして,
「誤るとはさまようことで,さまようことは世界を発見する方法であり,…思索にふければ自分自身を発見する方法なのだ。」
という著者の言葉は印象的だ。だから,
「へまをするとは冒険を見いだすことだ。」
と,ある意味,
「間違うことは,自分が自分から疎外される」
ことだとするなら,それは,自分自身の発見にもつながっていくはずである。
参考文献;
キャスリン・シュルツ『まちがっている エラーの心理学、誤りのパラドックス』(青土社) |
|
内発的動機づけ |
|
エドワード・L・デシ&リチャード・フラスト『人を伸ばす力―内発と自律のすすめ 』を読む。

本書は,内発的動機づけ研究の第一人者,エドワード・L・デシの著作である。原題は,
Why we do what we do
「人を伸ばす力」という邦題とは少しニュアンスが違う。
著者は,「人が何かに動機づけられるとはどういうことなのか,をこの本では考えてゆこう。」と述べている。で,
「そのとき,行動が,自律的(autonomous)か,それとも他者によって統制されているかという区別が大変重要である。自律ということばは,もともと自治を意味している。自律的であることは,自己と一致した行動をすることを意味する。」
著者は,内発的動機づけを,
「活動することそれ自体がその活動の目的であるような行為の過程,つまり,活動それ自体に内在する報酬のために行う行為の過程を意味する。」
とし,リチャード・ド・シャームの,
自己原因性(personal causation),
「『チェスのコマ』のような存在ではなく,自分自身の行為の『源泉(origin)』でありたいという欲求」や,チクセントミハイの「フロー体験」との類似性を挙げつつ,その内的動機づけの背景に,人が本来持つ,
自律性,
有能感(competence),
関係性(relatedness),
という三つの欲求(need)を想定している。それは,言い換えると,
行為の選択において,自己決定できるということであり,
それができる自分の有能感(それができるという感覚)をもてることであり,
そういう自分でありつつ他者と結びつきたいという欲求をもつこと,
である,といっていい。「関係性への欲求」について,著者は,
「偽りのない自分であること,自分らしくあること,そして自分自身のペースとリズムで歩んでいくことが重要であるというヒューマニスティックな信念を重んじている。しかし同じように明らかなことは,責任を引き受けることの重要性にも重きをおいているということである。自律性を主張することは,自分だけの世界に浸ることを求めているわけではない。なぜなら,真に自分らしくあるということには,他者の幸福に対する責任を受け入れることも伴うからである。他者とつながっていると感じていたいという欲求が,人に文化の諸側面を自然に身につけさせ,あるいは同化させ,その結果創意あふれる社会的貢献をするようになる。」
この三つの欲求の前提にされているのは,
「自己とは,真の意思にもとづいて偽りのない時分にもとづく行動を行う統合された心理的な核である。」
という考えである。だから,
「偽りのない自分を生きるためには,自律的にふるまわなければならない。なぜなら,偽りのない自分を生きるということは自らが行為の主体であるということであり,ほんとうの自分にもとづいて行動することだからである。自律性,偽りのない自分,そして自己ということを理解する鍵は,統合と呼ばれる心理的プロセスである。心のさまざまな局面がどの程度統合されているか,その人の偽りのない本来的な中心的自己とどの程度調和しているかは,さまざまである。ある行動が自律的だ,その人が偽りのない自分を生きていると言えるのは,その行動を開始して調整してゆくプロセスがその人の自己に統合されているときだけである。」
というわけである。しかし,今日,この「偽りのない自分(authentic)」「真の自己」という表現に違和感を覚えるのは,僕だけであろうか。社会構成主義,あるいは,以前触れた,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/436220288.html?1459800911
で,マーク・L・サビカスが,
人生コースの個別化,
と言っていたのは,言葉は似ているが,まったくの背中合わせである。その意味は,本書の言うような,
「人の内に備わっている中核となる自己を実現する」
という近代的考え方ではなく,
「自己の構成は一生を通じたプロジェクト」
という考え方であり,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/425774541.html
で,平野啓一郎が,「分人」という概念で言っていたのも,それだと思うが,
確固とした自己,
あるいは,
コアとしての自己,
というものがあるのではない。人は,文脈の中で生きる。文脈に合わせて生きる,と言い換えてもいい。その時の自分も,あの時の自分も,いまの自分も,同じ自分であり,その振幅の中に,自分がある。僕は,その考え方がいいと思う。その振幅が,自分を苦しめるとき,自分を見失っているのだ。それは,どこかにある,
「偽りのない自分」
を見失っているのではない。自分という一貫したストーリーを見失っているのである。
アイデンティティを作り直す,
とはそういう意味であった。その意味で,本書は,いささか時代性を感じさせるように僕には思える。
本書を読みつつ,もう一つ気になった(というかよく分からないという方が正確かもしれない)ことがある。
自我関与(ego-involvement),
の概念(の外延)である。浅学非才故かもしれないのだが,自律性との関連で,
「自我関与…は,自分に価値があると感じられるかどうかが,特定の結果に依存しているようなプロセスのことを指す。採り入れられた規範に縛られていて,しかもその規範が随伴的な自己価値感によって強化されているとき,その人は自我関与しているという。もしある男性の自己価値感が仕事にはげんで財産を築くことに依存していれば,彼は仕事に自我関与しているのであり,もしある女性の自己価値感が,健康クラブでの競争に勝つことに依存していれば,彼女はエクササイズに自我関与してるのである。」
と説明する。あるいは,
「人々が多くの出来事を脅威だと解釈する一つの理由は,自我関与を発達させているからである。…自我関与しているとき,自分には価値があるという気持ちが何らかの結果に依存している。価値があると感じるためには知性的だと見られる必要があるかもしれないし,女性らしいとか,強いとか,芸術的とか,ハンサムだとか見られ必要があるかもしれない。人はあらゆることに自我を関与させる可能性があり,そうなったとき,知性的だとか女性らしいと見られようとして,自分自身に対して非常に厳格で統制的になる。そして,自我関与した状態になったとき,簡単に他者に脅かされるようになる。自我関与があると,感情の人質になってしまう。」
で,その状態の自尊感情は,
随伴的な自尊感情,
であり,
真の自尊感情,
ではない,というのである。「真の自己」ということを軸にすることで,自我関与自体が,「真の自分」ではない,他者や状況に捉われている,としているように見えてならない。著者らは,実験で,
「ひとつのグループは自我関与,すなわち自己を脅かすような圧力によって動機づけられており,他のグループは課題関与(task
involvement),すなわち活動そのものに対する興味や価値によって動機づけられている」
によって,「自我関与が課題に対する内発的動機づけを低め,被験者は多くの圧力や緊張,作業のできばえへの不安を報告する」とし,
「自我関与とは希薄な自己感覚のうえに構築されるものであり,自律的であることを妨げるように作用する。」
「自我関与は内発的動機づけを低減するだけでなく,…学習や創造性を損ない,柔軟な問題解決を必要とするあらゆる課題での作業成績を低下させる傾向がある。」
等々とする。しかし,
(何かに)とらわれる,
という言い方をするか,
(何かに)こだわる,
という言い方をするか,
(何かに)気を取られる,
という言い方をするかの違いは,「真の自己」というものを仮定するせいではないのかという疑問を拭えない。心理学に造詣がある訳ではないので,自我関与の定義をいくつか拾ってみる。
「特定の作業,状況ないし対象を自我にとって重要なものとみなす態度,またそのような態度を生じさせるようななんらかの事態ないしは関係をさす。このような関係が存在するとき,人はその作業を遂行し,その状況を維持し,ないしはその対象との接触を保つように努めかつ行動する。」(『ブリタニカ国際大百科事典』)
「われわれが行動する場合,しばしば自分の責任だ,自分の仕事だ,という意識をもつことがあり,自分の身内だ,自分の家だ,という態度を示すことがある。このように,私が,私の,と考える態度を《自我態度》といい,行動にこの態度がふくまれているとき,〈自我関与〉と称する。〈自我関与〉の概念によって,人間の行動には自我が入っているときとそうでないときとでは甚だしい差があること,物事の判断には自分に関係があるときには純粋に客観的に行われないという事実を説明することができる。」(『心理学小辞典』)
「個人がある問題,人物などについて心理的に深くコミットしている状態。対象が自己の中心的価値と関わっていたり,対象との同一視が行われている場合に自我関与が生じているという。自我関与の対象が人である場合,その相手の自分に対する言動や,相手に対する第三者の言動などが,自らの自尊心や感情などに深く影響する。…社会心理学の態度理論の文脈では,態度対象への自我関与は態度と行動の一貫性を高め,説得への抵抗を強める。」(『心理学辞典』)
ある面,さまざまな事柄に関して,「自分の責任」「自分の仕事」「自分の問題」と,自身に関わるものとみなす,というのを,自我関与とすると,コミットメントそのものは自我関与なくしては成り立たないのではないか。(ある文脈のなかで)それに深くコミットメントするのもまた自己の一面であるとみれば,自我関与はマイナスとは限らない。第一,役割意識というか当事者意識(あるいは目的意識,問題意識を加えてもいいが)というものは,客観的ない意味ではなく,主観的な意味づげによる,目的や目標への自我関与がなければ成り立たない。あるいは,
有能感,
というか,
自己効力感,
そのものが,自我関与なくして成り立つものなのか。しかし,行きついた,
http://cocoru.jp/archives/560
に,こうあった(この他にもいろいろ設定の仕方はあるようだが)。
「目標の設定の仕方は、大きくわけて3つ。
1、自我関与的目標
2、課題関与的目標
3、課題回避的目標
1の自我関与的な目標を持つ人は、人からの高い評価、好ましい評価に焦点を当てます。その逆にある低い評価、好ましくない評価は得ないよう努力します。このような人は自分がいかに賢いかを示すことに関心が高まります。
2の課題関与的な目標を持つ人は、課題の達成自体に関心がある為、課題をどれだけこなせたか、課題から何を学んだかに意識が向きます。
3の課題回避的な目標を持つ人は、努力することを惜しみ、何もしないでおこうという意識が働きます。
この3つの中で最も好ましいとされる目標設定は、課題関与的目標だとみなされています。」
これが,心理学の世界では常識らしい。つまり自我関与的であることで,「おれがおれが」と,おのれの(他者からの)評価や(他者との)位置づけにこだわり,課題そのものによる自分の学習や成長にコミットメントしない,というところから内発的動機づけではなく,随伴的というのだろう,とは不承不承納得するがいまひとつ腑に落ちない(とは,思わず,僕自身が自我関与が強いと言っているようなものだが)。
どうしても,こういう考え方の背景自体に,デシ的な(自律的)自己の中心は変わらないという牢固とした概念の前提があり,人は,文脈次第で変わる,つまり関係性の中で,自我関与的目標を持ったり,課題関与的目標を持ったり,場合によっては課題回避的目標ををもったりするものだという,当たり前の振幅ある人間像のほうに,今日的には真実があると思えてならない。
参考文献;
エドワード・L・デシ&リチャード・フラスト『人を伸ばす力―内発と自律のすすめ』(新曜社)
宮城音弥編『心理学小辞典』(岩波書店)
中嶋義明他編『心理学辞典』(有斐閣)
宮本美沙子扁『達成動機の心理学』(金子書房)
宮本美沙子他編『達成動機の理論と展開』(金子書房)
http://cocoru.jp/archives/560
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/40046/1/Honbun-6228.pdf |
|
メタシステム |
|
瀬山士郎『はじめての現代数学』を読む。
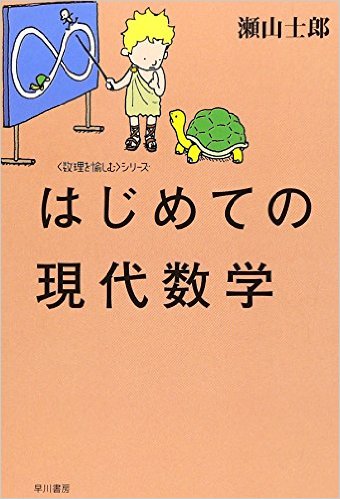
http://ppnetwork.seesaa.net/article/437240511.html
で取り上げた,
竹内薫『不完全性定理とはなにか−ゲーデルとチューリングの考えたこと』
を読んでいて,その参考図書として,著者が薦めていて,興味をそそられたのが,本書を繙くきっかけである。文系の自分には,数学への特別の憧憬があり,時々思いついては,読むが,身についたためしがない。
本書に通底するキーワードは,「モノ」と「コト」である。
「数学全体の流れは一貫していて,現代数学の主題も19世紀までの古典的な数学のなかで育まれてきたものである。にもかかわらず,古典的な数学の方法論や主題と現代数学の方法論や主題には,はっきりとした違いもあるように思われる。それは一言で『モノ』と『コト』との違いというとはっきりする。」
この場合,「モノ」は具体的な実体を指し,「コト」は,出来事であり,「モノ」と「モノ」の関係を指すが,著者は,
「この『モノ』から『コト』への主題の変化が現代数学を特徴づけ,それを古典的な数学から区別する一つの大きなポイントである。」
と書く。その転換点に当たる,
代数方程式の解法についての構造主義的方法,
非ユークリッド幾何学の発見による別世界への旅,
解析学における無限の取り扱いマニュアル,
から,話を始めている。
「作図可能な場合には『モノ』を離れることはない。(中略)しかしながら,作図が不可能であるという場合には,この『モノ』的問題設定と『モノ』的視点は大きな手かせ足かせとなった。なぜなら作図不能であるという『コト』は,文字通り『コト』であって,これを捉えるためには,『モノ』的視点を超えて,作図できるということの構造を知ることが不可欠だからである。そして,この『作図できる構造』は『方程式が解ける構造』と本質的に同一なのである。(中略)したがって直線や円の交点を求めて作図を行うということは,結局,いくつかの一次方程式,二次方程式を順に解いて得られる数を求めていくことと同じであり,そのようにして得られる数だけがコンパス,定規だけで作図可能である。」
つまり作図できる「コト」とは,
「その数が,与えられた数(長さ)から四則演算と開平算を有言回数繰り返して作れ」
るという作図の構造を発見し,三次方程式,四次方程式,五次方程式と,「作図」から「方程式を解く」ことへと「モノ」的視点から「コト」的視点へと転換するまでに,二千年を費やし,ガロアの群論へと行きつく。
「ここに代数学は方程式の解法の探求という古典的『モノ』的主題を離れて,代数的構造の探求という現代的『コト』的主題を研究する数学へと変貌を遂げ」
るに至る。これが,
「作図問題という『モノ』の背後に隠されていた,拡大体による数拡張という『コト』である。」
こうして,どうやら,現代数学が,モノという実体に即したものから,そのメタ・ポジションへと移行していくことなのだ,とわかってくる。
「モノ」「コト」の視点で見ると,ユークリッドの平行線の公理,
「二直線に他の一直線が交わってできる同じ側の内角の和が二直角よ小さいなら,この二直線を延長すると,二直角より小さい側で交わる。」
ここに,著者は,
「平行線という『モノ』と二直線が平行であるという『コト』の微妙なニュアンスの差が顔をのぞかせている」
という。そして,ガウスを経て,ボヤイ,ロバチェフスキーの非ユークリッド幾何学へと至る。著者は,こう書くのである。
「図形という『モノ』に関わっている間は幾何学の土台に想いをめぐらすことはなかったのかも知れないが,平行線公理の成立という『コト』に関わり始めたとたん,論理は空間そのものの成立基盤に直結してしまい,それこそ『コト』の重大さを知らされることになるのである。
かくして…幾何学は二つの方向へと向かう。一つは大域的な空間そのものの研究であり,これは20世紀に入って抽象空間論として結実する。もう一つは公理の無矛盾性を問題とする幾何学基礎論の方向であり,これはヒンベルトを…経て幾何学と離れ,集合論と結びつき,数学基礎論という現代数学の一大潮流を形作るにいたったのである。」
ギリシャ数学は,ある意味,
「『モノ』としての無限を暗黙の了解のうちに図形という容器の中に閉じ込めて置き,無限が暴れ出さないようにしていた。」
しかし,たとえば,ゼノンの「アキレスと亀」「飛矢の静止」というパラドックスのように,
「無限を図形という容器からとり出し,完結した『モノ』ではなく,運動という『コト』に関連させたとたん,無限はその牙をむきだした」
が,コーシーのイプシロン・デルタ法,によって無限という「コト」を手なづけることに成功する。こうした(代数方程式,非ユークリッド幾何学),
「記号化による統辞体系の完成」
が,数学全体を大きく変化させていくことになる。ここから,
集合論,
トポロジー,
命題の記号化,
を経て,ゲーデル,さらに,
ファジー理論,
フラクタル理論,
カタストロフィー理論,
四色問題,
へと展開されていく。その都度,「モノ」「コト」が,視点として通底する。たとえば,集合をめぐって,
「『モノ』としての無限を『コト』としての無限として捉えなおし,その『コト』的無限にあきたらず,再び『モノ』としての完結した無限に果敢に挑戦し,緒戦に大きな戦果を上げながら,後半戦,『モノ』的無限の反撃に遭い,傷つき敗れ去ったのがカントールであった。やはり,『モノ』としての無限は,コーシーのプロセス主義の陰に隠れながら,巨大化していたのである。」
と,さらには,ゲーデル(の不完全性定理)について,
「われわれの見たのは,“形式の限界”であって“証明の限界”ではないことには十分注意を払う必要があろう。不完全性定理は『正しいけれども証明できない定理』という形で流布しているが,その内容はこのように理解されるべきである。」
と,メタ・ポジションで,メタ化(メタメタ…化)された記号という,数学の埒の問題なのではないか。そのことについて,
「あるシステムについて語るためには,そのシステムを外側から眺める立場,いわゆるメタシステムが必要である。たとえば『リンゴは赤い』という文章と『「リンゴは赤い」は肯定文である』という文章と比べてみると後者はメタシステムに属する文章となる。…本来は前者と同じシステムの中では扱えない性格のものだったのである。
ところがゲーデルのコード化による数の三通りの解釈法によって,本来メタシステムの中でしかとり扱えないはずの文章を,システム自体の中でとり扱えるようになった。ゲーデルの不完全性定理はこのようにも解釈できる。この場合,形式化の限界が見えたという側面より,形式化による新しい数学が拓けたという側面を強く感じる」
とも付け加える。そのゲーデルの拓いた形式主義数学の世界の先を見るには,
「その形式が持つ意味を理解することこそが,数学がわかることの最初の一歩であり,かつ最後の一歩に他ならない。」
と。いやはや,元へ戻ってきてしまった。
参考文献;
瀬山士郎『はじめての現代数学』(ハヤカワ文庫NF) |
|
人生の意味 |
|
アルフレッド・アドラー『人生の意味の心理学(上下)』を読む。
 
アドラーについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/395411257.html
で,『個人心理学講義』を取り上げた。そこで,アドラーは,
「個人心理学が目指すのは,
「社会」適応である,
と言い切る。それが,目的である,と。本書の『意味』もその延長線上にある。
本書は,
「人間は意味の領域に生きている。われわれは状況をそれ自体として経験することはない。いつも人間にとって意味がある物だけを経験するのである。われわれの経験は,その根元においてすでに,人間的な目的によって規定されている。『木』は『人間との関係における木』という意味であり,『石』は『人間の生活における要素であるかぎりのものとしての石』という意味である。意味を排除して事実だけを考えようとする人がいれば,そのような人は非常に不幸になるだろう。自分を他者から切り離すことになり,行動は自分にも他人にも役に立たなくなり,一言で言えば,無意味になるだろう。しかし,人間は意味を離れて生きることはできない。」
という文章で始まる。この文章を読みながら,
アフォーダンス,
ということを連想した。意味は,人間だげにあるわけではない。ジェームズ・J・ギブソンは,
環境が動物に対して与える「意味」
を,アフォーダンスと名づけた。それは,関係性を言う。それは,また情報,つまり,対象にこちらが付加した意味によって,それが情報になる,ということでもある。しかし,ここで,アドラーが言っている意味は,もっと限定されているようだ。続けてこう言っている。
「『でも,なぜ生きるのか。生きることの意味は何か』…こんな質問をするのは,何かでつまずいている時だけだといっていい。何もかもうまくいっていて,難しい問題にぶつかっていなければ,そのような問いが口にされることはない。むしろ,人がこのようなことを問い,それに答えるのは,行動においてである。(中略)人が固有の個人的な『人生の意味』を持っていて,意見,態度,動き,表現,癖,野心,習慣,性格特性のすべてが,この意味に一致していることがわかるだろう。」
これが本書のテーマである。人は,「自分の意味」(あるいは目的と言い換えてもいいが)をもち,そのための手段を選択して生きている。だから,手段の過ちを見れば,その人の躓き(犯罪や心の病や挫折等々)の意味の錯誤がわかる,というわけである。だから,
「人生に与えられる意味は,人間の数と同じだけある。そして,おそらく…どの意味も,多かれ少なかれ,誤っている。人生についての絶対の意味を知っている人はいない。したがって,役立ちうるどんな意味も,絶対に誤っているとは言えない。すべての意味はこれら二つの限度間の差異である。しかし,意味は多様であっても,ある意味はうまく機能し,あるものは,あまり効果的ではない。…われわれは,よりよい意味が共通して持っているものは何か,より満足できない解釈に欠けているものが何かを見つけることができる。」
そこから引き出された,共通の意味は,
人生の三つの課題(タスク),
と名づけられている。「それが人の現実を構成する。なぜなら,人が直面するすべての問題や問いは,そこから生じるからである」と。それを,
三つの絆,
とも言う。一つは,
仕事,
である。それは,
「われわれがこの小さな宇宙の殻,つまり,地球の上で生きている…。(中略)われわれは地球上で個人として生きるためにも,人類が存続することを保証するためにも,身体も心も発達させなければならない。これは,すべての人に答えることを挑む,逃れることのできない問題である。われわれが何をしても,われわれの行為は人間生活の状況へのわれわれ自身の答である。」
という意味づけを与えられている。ふたつは,
対人関係,
である。
「われわれは誰も人類のただ一人の成員ではないということである。われわれのまわりには他者がいる。そしてわれわれは他者と結びついて生きている。(中略)われわれは常に他者を考慮に入れ,他者に自分を適応させ,自分を他者に関心を持つようにしなければならない。この問題は,友情,共同体感覚,協力によってもっともよく解決される。」
とくに,「共同体感覚」の不足が,あるいは人への無関心が,人の不適応(心の病,犯罪,問題行動等々)の背景にある,というのが,しはしばアドラーの下す診断に見られる。三つ目は,
性,
である。
「人間がふたつの性でできているということである。個人と共同生活の維持は,この事実も考慮に入れなければならない。愛と結婚の問題はこの三番目の絆に属する。」
アドラーは,交友(第2の課題)と労働(第1の課題)の,
「最善の仕方で成就する解決は,一夫一婦制である。」
と繰り返している。アドラーは,人が,この三つの課題にどう対応するかに,「人生の意味の解釈」が明らかになる。それが,世界ついて,自分の経験について,自分をについて,どう意味づけるか,につながる。その総体を,
ライフスタイル,
と名づけた。そのスタイルに基づいて,目的を立て,手段を選んで,行動する。アドラーは,その手段から,目的を推測し,ライフスタイルを推定する。その意味では,
因果律,
という仮説で成り立っている,といってもいい。だから,二つの例示を対照的に提示する。
「例えば,性生活が不完全な人,仕事で努力しない人,あるいは,友人がほとんどいなくて仲間と接触することを苦痛だと思うような人を仮定しよう。そのような人は,人生において自分自身によって課された限界と制限から,生きていることを好機がほとんどなく失敗ばかりの困難で危険なことと見ている,と結論づけてよい。そのような人の行動範囲が狭いことは,次のような考えを表現していると解釈できる。『人生は,危害に対してバリケードで自分を守り,無傷で逃れることによって自分自身を守ることである』」
「他方,次のような人を観察すると仮定しよう。その人は親密で協力に満ちた愛の関係を持っており,仕事は有益な成果へと結実し,友人は多く,人との結びつきは広く豊かである。このような人は,人生に多くの好機を提供し,取り消しの出来ない失敗をもたらすことのない創造的な課題と見ている,と結論づけてよい。その人の人生のすべての課題に直面する勇気は次のようにいっていると解釈できる。『人生は仲間に関心を持ち,全体の一部であり,人類の幸福に貢献することである』」
そして,前者のような「誤った『人生の意味』とあらゆる真実の『人生の意味』の共通の尺度」を,
共同体感覚,
と呼ぶ。しかし,そうやって因果で整序したぶん(それをドミナント・ストーリーと考えれば,),そこからこそぎおちていく部分に,別の物語(オルタナティブ・ストーリーが一杯)がある,とナラティヴ・アプローチなら,いうのではあるまいか。
「すべての誤り―神経症者,精神病者,犯罪者,アルコール依存者,問題行動のある子どもたち,自殺者,倒錯者,売春婦―が誤りであるのは,共同体感覚を欠いているからである。彼(女)らは,仕事,友情,性の問題に取り組む時,それらの問題が協力することによって解決できると信じていないのである。彼(女)らが人生に与える意味は,私的な意味である。つまり,自分が行ったことから益をうけるのは自分だけである,と考え,関心は自分にだけ向けられているのである。彼(女)らの成功の目標は単なる虚構の個人的な優越性であり,勝利は自分自身に対してしか意味をもっていない。」
ここに,少なくとも,アドラーの考えている(彼の現実がどうだったかどうかは知らないが)ライフスタイルが反映していることだけは間違いない。
それにしても,「人生の意味」に正誤をつけ,「すへきである」と断言すること自体の是非については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/395411257.html
で触れたので,ここでは問わないにしても,少なくとも,アドラーが自分自身だけがすべてに正解をもち,それを基に人を判断する,という過去のセラピストのスタイルの典型をここに見るような気がすることだけは確かだ。
個人的には,
器官劣等性
劣等コンプレックス
優越性
優越コンプレックス
と言った独特の用語からも,何となく,正解を持つ者の(上からの)視点を感じ,いま流行っているらしいのだが,
強者の論理,
の匂いが,そこここにして,ちょっと好きになれない
参考文献;
アルフレッド・アドラー『人生の意味の心理学(上下)』(アルテ)
ジェームズ・J・ギブソン『生態学的視覚論』(サイエンス社) |
|
自己語り |
|
ジョン・マクレオッド『物語りとしての心理療法―ナラティヴ・セラピィの魅力』を読む。

著者は,
「〈新しい〉セラピィといったものは,存在しません。」
という一文から書き始める。昔からあったさまざまな実践を無視しているだけだ,と。目新しいものがあったとしても,それは,「より広範な,より豊かな文化の伝統から引き出されたもの」だ,と。
しかし,同時に,
「あらゆる心理療法は,〈新しい〉セラピィでもある。」
とも書く。それは,仮に最新のマニュアル化されたトレーニングを受けたとしても,「セラピストは誰でも,その人に特有な経験や価値観を自らの実践に持ち込」み,心理療法モデルは,「個々の世界観やスタイルに統合」され,結局,
「クライエントとの出会いは個別的になるのです。」
だから,「あらゆる心理療法は『新しい』セラピィでもある」と。本書は,
「心理療法におけるストーリーの役割と意義について検討する。」
と書く著者自身,ストーリーの必要性を,クライエントから教えられたとして,
「クライエント…らは,悲劇的で,しかも絶望的な内容の自己語り(self-narrative)を抱えて,私のもとを訪れました。これらの人びとは,自己のストーリィを語るなかで,やがて奮い立ち,それまで甘んじてきた人生のあり方に対して異を唱えることができるようになりました。そして,辛いと感じられていた出来事が,実は,より大きな人生のストーリィが展開するなかで起きたエピソードであるとの見方ができるようになりました。より大きな人生のストーリィが見えてくることは,そこに含まれている人生の意味と目的も感じられるようになることです。」
と書く。そこで,
「心理療法をナラティヴののプロセスとして理解することが理にかなっていることに気づきました。つまり,心理療法の過程は,自らの行動をストーリィとして語り,その内容を編集し,書き換えるというナラティヴのプロセスとして理解するようになったのです。」
と。だから,本書は,
「『あらゆる心理療法は,ナラティヴ・セラピィである』ということです。あなたがセラピストであれ,クライエントであれ,あなたが心理療法においてしていること,あるいはしていると思っていることは,語ることと語り直すことという観点から理解できるのです。」
ということについて書いたものだ,と。その背景にあるのは,
社会構成主義,
である。したがって,著者は,
「私は,心理療法を,単にクライエントとセラピストとの間で起きるプロセスとしてだけではなく,研究,研修,組織などを含めて心理療法活動を取り巻く文化的様式とみなしています。そうした広範な領域に対してナラティヴ理論が持つ意義を検討することを本書の最終目標とします。」
と,宣言する。そのために本書では,
「なぜ,心理療法が現在のような形をとるに至ったか」
について,著者自身の答を提示する,と。だから,心理療法の歴史を文化的観点から検討し,
心理療法を一種の文化形態,
とみなし,「ストーリィや物語ること」の意味を,
「心理療法と文化をつなぐ結節点」
として,明らかにしようとしていく。
社会構成主義については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/390438872.html
で触れが,ポストモダンの時代の特徴を,
「自己の断片化」
であり,他者や他の集団から,
「一貫した全体像」
を把握されることのない時代,つまり,
部分自己,
がテーマとなる,ということである。そのとき,
「物語行為の実践の場」
である心理療法では,何をすべきなのか。
「視点を内部から外部へとずらすこと」
という。つまり,
「哲学者マッキンタイアーは,人間が『本質的に物語る動物』で…『〈私は何を行うべきか〉との問いに答えられるのは,〈どんな(諸)物語のなかで私は自分の役を見つけるのか〉という先立つ問いに答を出せる場だけである』と…書いています。私たちの生を構成するストーリィの大部分は,私たちが生まれる前から,そして死んだ後も〈そこにある〉のです。文化のなかで,人間として生きるための課題は,個人の経験と〈自己を見いだすことのできるストーリィ〉との間に,十分な調整を加えることです。セラピストの仕事は,特にこの調整がうまくいかなくなったとき葛藤に際して,再調整を促すことです。ナラティヴの観点に立つと,…一人ひとりの個人的な経験へと〈内向する〉のではなく,文化のストーリィへと〈外向〉することが迫られるのです。」
である,と。このことは,ストーリィの意味の機能の面と,ポストモダンという時代の意味,との二つの面から,言及されていく。
先ずは,ストーリィについては,前に触れたことがあるが,ブルーナーが,人間が世界を認識する方法として,
物語的認識 ストーリー・モード(Narrative Mose)
と
パラディグマ的認識 パラディグマティック・モード(Paradigmatic Mode)
があるとし,前者は,「人びとが自らの経験を語るストーリィを通じて」,後者は,「科学的な思考モードに端を発し,抽象的で命題的な認識を通じて」,表象される。ここでナラティヴというのは,「ある特定の出来事の説明」というストーリィとは異なり,
「単なるストーリィの提示だけではなく,それに加えて〈物語る〉というコミュニケーション形態も含まれています。」
従って,たとえば,語り手や聴き手としてストーリィに参加することができる。そして,この能力は,人が,言語習得とほとんど同時期に,語る能力を獲得するらしい。そこで,
経験を順序立てて再現し,
物語化は,日々の生活の中の逸脱した経験を説明したり,対処したりする,
ストーリイの伝える情報には,語り手の内的世界の表明を含んでいる,
経験を物語ることで,ジレンマや緊張状態を解決する手段になる,
無秩序な経験を因果的な筋道に当てはめて理解するのを促す,
ナラティヴには,関係的世界が含まれている,
物語ることで,一人の人間を,誰かに知らしめるという社会的機能をもつ,
ストーリィは,語り手が社会や文化の中で,どのように位置づけられるかの情報を伝達している,
等々,ストーリィを語ることは,
「単に情報や経験の表象であるのみならず,社会的・対人的な行為の形式でもある…。(中略)ストーリィを語っているクライエントは,ただ単に一連の出来事を報告しているだけではないのです。同時に社会的なアイデンティティを構築しているのです。…自己を語り,そしてそれを価値あるものとして聴いてもらえるという経験は,まさに,自分の存在の新たな意味の創造に向けた一つのステップなのです。」
「現在に至るまでの人生の道のりには,(終着点についての将来的な予期まで含めると)さまざまなエピソード,出来事,人間関係が存在します。それらの多様性に一貫性をもたらすのが,自己語りなのです。」
しかし,そこには,自己を語る時の限界もある。
「自己語りという概念が暗々裏に前提にしているのは,自己がまとまりのある何かとして存在し,さらに一貫した自己感に到達することを望ましいとみなす考え方です。また,自己が内外をわける境界をもった自律的存在であることも前提とされています。」
つまり,
一貫した自己感という個人神話,
単純に一元的に語られる自己概念,
である。むしろ,
多元的に語られる自己,
という観点で見るならば,
「自己は,多様なナラティヴ群に囲まれ…,さまざまに異なる状況,人間関係,場面,人びとと結びついています。」
これを,著者は,
単一化した自己感,
と
散在し,インデックス化された自己感,
と区分し,単一のストーリーによって人生の特徴を意味づけるのを,
単一解的,
という考え方を紹介し,そうではない解を取ろうとしている,と見なすことができる。たとえば,ホワイトとエプソンの,「外在化」について,
「『外在化』の…『外部』という概念が表しているのは,自律的な内面をもつ自己を具えた人間という,近代のイメージからの脱却と,新たなイメージへの移行です。近代的な人間の概念においては,内面の自己に対しての絶え間ない探索と注意が求められていました。それに対して,新たに移行の先にあるのは,『文化に埋め込まれた行為をなす人間』というイメージです。あるいは,『語りを生き,語りを紡ぐ存在としての人間』というイメージです。」
それは,
社会に孤立した,自己完結した自律的自己,
ではなく,
自己の概念の広範な多様性,
に着目することであり,同時に,
「構成主義的なナラティヴ・セラピィでは,個人的な自己という概念は,人間(person)という概念に取って代わられます。その意味するところは,(中略)『人間』について語ろうとすれば,おのずと意図的な活動に携わる能動的な主体としてのあり様や,関係的なあり様を意味することになります。」
静的で,単位としての自己概念は,
能動的な社会的な存在,
に変る。とすれば,自己のストーリィは,
「どのようにしてここに至り,どこに向かおうとしているのか」
ということである。例のポール・ゴーギャンの大作,『我々は何処から来たか、我々は何者か、我々は何処に行くのか』が示しているのは,そういうストーリィである。
外へ,というのは,自律した固定的自己概念から出ることであり,自己を語るとは,単一のストーリィを,
著者として,再著述すること,
である。
「ひとたびストーリィが語られたなら,そのストーリィは改訂の機会に開かれたものとなり,異なるバージョンが生じる可能性が出てきます。(中略)社会構成主義的セラピストは,この『著述』という語を『会話』に近い意味に用います。そのために,『著述』とは,それが語られるたびに,新たな意味の地平が見出されるプロセスとなります。過去の語りと照合されつつ,新しいバージョンが生み出されていくのです。
そのときセラピストの目標は,
「『あるストーリィを他のストーリィで置き換えること』ではなく,『意味を創出し,変容する絶え間ないプロセスに関わるようにクライエントをいざなうこと』です。言い換えれば,伝統や文化を形成する協同的なディスコースや会話に加わり,寄与することなのです。こうした観点にもとづく心理療法は,『自己』についての最終的で決定的かつ固定的な理解に到達するためのものではありません。そうではなく,『理解の途上にとどまり続ける』ためのものとなります。」
ここでセラピストがすることは,クライエントを治療したり改善することではなく,こうした「共同構成」を通して,
「単に自らのストーリィを語る場があり,そこでそのストーリィを尊重され,受け止められることが計り知れない自己肯定感を得る経験」
となる,ということであり,これが,
「心理療法と文化をつなぐ結節点」
ということの意味でもある。ただし,ナラティヴは,自己完結したものではない。
絡み合ったナラティヴ群の一部,
であることを忘れてはならない。社会性つまり,
能動的な社会的な存在,
とはそういう意味でなくてはならない。
参考文献;
ジョン・マクレオッド『物語りとしての心理療法―ナラティヴ・セラピィの魅力』(誠信書房) |
|
発達障害 |
|
山口真美『発達障害の素顔−脳の発達と視覚形成からのアプローチ』を読む。
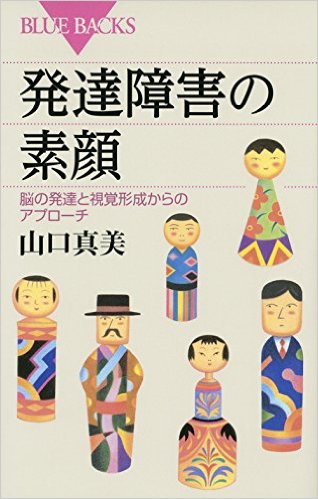
「乳幼児の心と脳の発達を研究する」心理学者が,我々にとって,当たり前に見え,聞える世界が,発達障害,つまり,
ASD(自閉症スペクトラム障害),
ADHD(注意欠陥多動性障害),
ディスレクシア,
ウイリアムズ症候群,
アスペルガー症候群,
サヴァン症候群,
等々の知的認知はどう違うのか,を見ていく。思うに,「普通」というのは,何を指すのか,それは,個性とどう違うのか,人は発達プロセスに微妙な差がある,それと,発達障害とはどう違うのか。著者が,「あとがき」で,
「本書で語るひとつひとつのエピソードは,私たちとは別次元の話ではなく,自分の心の中に,あるいは周囲の人々の心の中に,それぞれのタイプは隠れているのかもしれない。」
と書く,違いは,地続きの中にある,と僕も思う。本書は,
「これまで社会性の障害といわれたきた発達障害の原因を,近年の脳科学と認知科学からわかった成果を基に説明していく。発達障害の問題は,発達の出発点における,ほんのわずかな認知のちがいにある。認知の基本であるモノの見え方や聞え方が平均的な人たちとちがうだけで,コミュニケーションのすれちがいが生じ,社会性がないというレッテルを貼られることになる。
現代社会の中では,発達障害は特殊な問題ではない。中でも自閉症においては,同じ傾向をもつ人々はすそ野を広げ,社会の中でひとつの個性となりつつある。」
しかも,「小児医療の進展に伴い,発達障害と診断されるケースは増加傾向にある」中で,その「特殊性」をどう理解するか,という問題意識で,脳の発達と絡めながら,具体的に紹介される。「素顔」とあるが,発達障害児の見え方,聞え方,考え方,感じ方を比較していく。
発達障害は発達の過程で問題が明確になっていく。しかし,
「発達障害がやっかいなのは,単純に発達が健常者に比べて劣っているかいないかという問題に帰結できないことにある。それは発達が平均通りに進まない,この先どうなるかの予測がつかないということだ。」
平均との差もまちまち,発達とともに平均との差が広がることもあれば,急速に縮まることもある。
「実際の発達障害の診断は,…3歳(36ヵ月)程度でなされる。」
診断は,観察中心に,
「対人相互反応における質的な障害,コミュニケーションの質的な障害,行動・興味や活動の限定された反復的で情動的な様式という3種類の基準によって行われる。具体的には名前を呼ばれても気にしない,遊んでいるときに母親に得意げに玩具を見せない,遊びの途中で母親の存在を確認するといった社会的な反応の欠如,特定の事象への固執傾向,視覚や聴覚・嗅覚といった特定の感覚の過敏さなどから気づくことが多い。」
とされる。厄介なことに,その独自性のために親をはじめとした周囲とぶつかり,
「それがまた,脳に別の障害を残す可能性がある」
ということだ。確か,コミュニケーションを拒絶されると,脳は,なぐられたのと同じくらいのダメージを受ける,と聞いたことがある。その意味で,「独自性」は,とりわけ,同調圧力の強い日本では生きにくいのではないか,と想像させる。
自閉症の感覚世界は,たとえば,自閉症スペクトラム(ASD)児者の聞こえ方を疑似体験は,
https://www.youtube.com/watch?v=MKeiCZWvZaA
http://maminyan.com/asd/autism/post-22.php
等々でできる。
「まず,そのざわめきの大きさに驚かされる。突然現れる雑音が,とても大きく感じられる。思わず,耳をふさぎたくなる。それとは反対に,人の声を聞きとることが難しい。」
と,その特徴は,
「感覚そのものをフィルターに通すことなく,直接受け止めることにある。彼らの感覚は非常に過敏で,その範囲が狭いという特徴をもつ。」
すべてが同じレベルで耳に入ってくる。それは,視覚についても同じで,
「あらゆるものを分け隔てなく,見てしまう,聞いてしまう」
のである。それは,シナプスの「刈り込み」と関係がある。
「シナプスは生まれてから8ヵ月まで急峻な発達を見せる。…その後,シナプスの数は減り続ける。『刈り込み』と呼ばれる状態だ。8ヵ月までは神経細胞同士の結合が大量に増加するのに対し,その後は不要な結合を減らし,より能率的な結びつきになるように,神経細胞の活動の頻度や細胞同士の連携も進み,トップダウンな思考(全体を見わたせる能力)の獲得を可能にしていく。ところが発達障害者では,健常者に比べこの能率化が遅れたり,うまく進まなかったりする(中略)。この刈り込みに問題があるとされるのが,自閉症児だ。自閉症児は刈り込みが少なく,多くのシナプスをもち続けるのではないかといわれている。(中略)その証拠に,自閉症児の生後半年から1歳代の時期の頭周が,普通の子供よりわずかにおおきいといわれている。」
トップダウンとは,カクテルパーティ効果が象徴するように,
「見るときや聞くときに,トップダウンによるフィルターごしに,意識に入るべき情報と不要な情報をえり分けている。このフィルターで使われるのが,蓄積された知識や記憶である。」
すべての情報が,先入観や常識抜きで,優劣つけず入ってくる。どうしても,全体ではなく,細部に目が行き,統合が苦手ということになる。それは,
「表情と声色から感情を読み取ったりすることができない。たとえば笑いながら否定的な口調で皮肉をいってみたり,苦しい実情を吐露しながら笑ってみたり…。…そうした場面の意味が理解できないとしたら,他人との関係を円滑に作り出すことができず,苦労すると」
推測される。ところで,人の,
「視覚情報は大脳半球の両側の基底部にあたる下部側頭皮質へと続く腹側経路と,後部頭頂皮質へと続く背側経路の2つの経路がある。背側は動いているものを見ることに,腹側は静かに形を観察することにかかわっている。(中略)自由自在に動き回れるヒトは,背側経路で『空間』を正確に見ている。逆に,背側経路で空間を正確に見ることができなければ,自由に動き回ることができなくなる。(中略)発達障害の中でもウィリアムス症候群は,…決定的な視空間能力の欠如という特徴を持っている。(中略)背側経路は腹側経路より先に発達するにもかかわらず,発達障害の過程では背側経路の方が壊れやすく,ウィリアムス症候群の問題から発達障害の『背側経路の脆弱性仮説』が唱えられている。…背側経路は壊れやすく,その結果,自閉症児の多くは腹側経路が正常に成長できない可能性がある。」
自閉症児は,顔を見ることが苦手であるが,これは,トップダウンとも関係がある。目・鼻・口の位置(「トップヘビーと言われる」)さえ保たれていれば,新生児はまず顔に注目する。この顔検出は,「一次処理」と呼ばれる。知っている顔を区別できるようになるのは「二次処理」と呼ばれる。パターン認識である。しかし,
「自閉症になりやすい子どもの特徴は,視力がよすぎることである。…視力を支えに細かい部分で顔を見る癖がつき,その結果,顔を全体で見ずに部分に注目する傾向ができあがった…。とりわけ腹側経路の発達が早すぎた自閉症児に多く見られる。幼いころ視力が極端によいため部分に着目してしまい,全体をパターン認識することができなくなる…。」
視力がよすぎることは,相手とのコミュニケーションに支障が出る。一般に,
「親と子が見つめ合えるようになった後,生後6ヵ月頃になると,視線追従が生じるようになる。興味の対象は,相手の目から視線の先へ移っていく。それはコミュニケーションの発達障害からいうと劇的な変化である。やがて生後9ヵ月頃になると,親と子とで互いにひとつのものをみつめ合う『共同注意』,他者との世界の共有がはじまる。(中略)共同注意の生起率は,指差しや言語産出に相関がある。共同注意をしている時間の長い子どもほど,言語理解と産出が優れており,子供が注意を向けている対象に母親が追随する傾向が高い子どもも,言語理解や産出の能力が高い傾向がある。」
しかし自閉症児では共同注意は観察されない。目に注目する効果が見られない,という。そのため,
「発達障害の問題の基本は,コミュニケーション能力にあった。」
ということになる。
「皆が話題にしていることに的確に注意を向け,視線を合わせ,言葉を発すること,それが試金石になる。…そのいずれにも強い影響を与えるのが,顔である。顔のもつ視線に注目し,皆がなにに注目しているかを理解する。相手の口から発せられる言語(音)に注目して,言葉を獲得する。」
しかし,自閉症状というのは,グラデーションではないか。どこかで境界線が引けるわけではない。昨今,コミュニケーションに躓いて,会社を辞めたり,引き籠ったりする若者が少なくない。だが,著者が,「はじめに」で,
「赤ちゃん実検の立場からすると,発達障害に見られる個性的な認知とその脳の発達は,『脳の発達と進化』から鑑みて,より進化した形態である可能性も考えられる。」
と書く言葉は象徴的ではある。
参考文献;
山口真美『発達障害の素顔−脳の発達と視覚形成からのアプローチ』(ブルーバックス) |
|
不完全性定理 |
|
竹内薫『不完全性定理とはなにか−ゲーデルとチューリングの考えたこと』を読む。
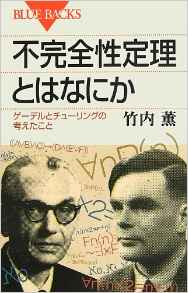
本書は,「各章は,不完全性定理の歴史の順に」並んでいる。著者曰く,
「革命的な理論が『わからない』と感じたときは,…『歴史』を書いた本を読むと,目から鱗が落ちることがある。なぜなら,歴史的な視点で学問の発展を追うことにより,革命前夜の混乱と,革命後の整理整頓された知的状況が俯瞰できるから。」
と。で,ペアノ算術の公理から,多宇宙仮説までをフォローする。それは,著者の言う,
(理数系)3わからん,
つまり,
アインシュタインの相対性理論,
量子論(不確定性定理),
ゲーデルの不完全性定理,
をカバーしている。ゲーデルのしたことは,
「基本的には,数学におけるメタフィクションに他ならない。」
という通り,「数学の『外』に出て,…数学の全体像を眺める」ことである。たとえば,例の,
(嘘つきのクレタ人が)「クレタ人は嘘つきだ」と言った,
という文章について,
「意味論の範囲にとどまるかぎり,…循環は無限に続いてしまう。(中略)ゲーデルは,この嘘つきのパラドックスにヒントを得て,意味論から構文論へと舞台を変え,証明できることと真であることは別であることを示すために,『この命題は証明できません』ということを証明」
した。ゲーデルのメタ化は,こんな手続きである。
「「『この命題は証明できません』は証明できません」は証明できません」
という自己言及の無限後退を避けるために,
「ゲーデルの天才は,とんでもないことを思いついた。…『この命題』に数字の番号を付けて,(中略)『符号化』(coding)もしくは『コード化』(中略),ようするに,同じ機能をもった別の記号におきかえよう」
ということをした(ゲーデル数化)。この時点で,メタ・ポジションに立っている。
「この方法の素晴らしいところは,あらゆる命題だけでなく,あらゆる証明も背番号で呼ぶことができる点。なぜなら,証明というのは,…命題がずらずらと並んだもののことだから」
で,
「証明は必ず有限個の命題の集まりである。ところが,素数は無限個あるので,ゲーデル数に置き換えると,すべての命題,つまり過去に証明されたすべての命題から,これから未来永劫にわたって証明されるであろうすべての命題も,それぞれ固有のゲーデル数で表現することがかのうになるのである!」
そこで,著者は,不完全性定理の証明のあらすじを,次のように説明する(数式をカットした)。
ステップ1 1変数の命題F(y)を網羅した一覧表をつくる。Fの下添え数にゲーデル数をいれる
ステップ2 「Fk(l)」の形式証明のゲーデル数xが存在する」という命題を考える。数式略記する。
ステップ3 命題のkとlを変数yに置き換え,否定した命題を,数式化する。此の数式は,ステップ一の一覧表のどこかにあるはずである。それがn番目だったとする。
ステップ4 変数yに自分自身背番号,すなわちゲーデル数nを代入する。
ステップ5 ステップ4でつくった命題の右辺は,「Fn(n)の形式召命のゲーデル数が存在しない」となる。対応するゲーデル数が存在しないのだから,それは,Fn(n)が証明できない
と。Fn(n)=の右辺が証明できないという命題ができた,ということになる,というプロセスである。
「形式証明は規則的な式の変形に過ぎない。真理関数のような外部殿関係性は出てこない。それなのに,なぜ,『真だけれど証明できない命題』というような意味論的な説明がなされているのか?(中略)
実は,ゲーデルの考察にペアノ算術が入ってくるため,このような混乱が起きてしまうのだ。たしかにゲーデルの証明は純粋の構文論の世界である。だが,『ペアノ算術を含むシステム』を考え,ゲーデル数の方法により,システム内の式のすべてを『数』に翻訳してしまう。そうなると,算術はすなわち数同士の関係にほかならないから,算数の式として,『真』であるにもかかわらず証明できない,という気持ち悪い状況が出現するのだ。(中略)そもそも『意味』とは,記号と記号外部との関係性にほかならない。で,ゲーデルの不完全性定理は,ゲーデル数によつて,システム内部に含まれる算術との関係性が生じるので,意味が『自然と湧き出てくる』…。自分自身について考えるシステム,すなわち超数学ならではの不可思議な現象だといえるだろう。」
チューリングは,決定問題を考えていく過程で,ゲーデルの不完全性定理と同じことを別の視点から証明することになる。
「決定問題とは,数学の個々の問題が真か偽かを決定する手順のことだ。たとえば命題論理は真偽表の方法が存在するから決定可能だ。でも(ふつうの)述語論理は決定可能ではない。」
チューリングは,公式や推論規則といった道具の代わりに「計算する機械」,「チューリング機械」を考えた。問題は,
「実用的な計算につきものの『計算は終るか』,あるいは『プログラムは停止するか』という,切実な問題だったのである。」
停止問題の証明のあらすじは,次のようなステップで説明される。
ステップ1 あらゆる計算にそれぞれ特化したチューリング機械Tに背番号(添え字)をつけて縦に並べる。
ステップ2 Tに入力できるデータ(1,2,3…)を横に並べる。
ステップ3 各チューリング機械に1,2,3…を入力した出力結果を一覧表化する。この表は,あらゆる可能なチューリング機械にあらゆる可能な値を入力した結果であり,機会が停止して具体的な数値を出力するか,停止せずに走り続けるかは決まっていると仮定。
ステップ4 出力の対角線をまるで囲んで,各出力を替えてしまう。たとえば,「1を足す」。この結果を与えるチューリング機械をDと呼ぶ。
ステップ5 ステップ4で作ったチューリング機械も,チューリング機械である以上,一覧表のどこかにあるはずだが,どこにも載っていない。
ステップ6 一覧表に載っていないということは,そもそもの過程,任意のチューリング機械が停止するかしないかは決められない。
コンピュータ科学者のG・チャイティン(「ゲーデルの証明は好きになれなかった」と言ったそうだ)は,ゲーデルとチューリングの差を,
「ゲーデルの場合は,公理系の内部構造,原始帰納定義スキーマ,および,かれの番号付が複雑なのでした。チューリングの場合は,彼の万能チューリングマシンのインタープリタープログラムが複雑でした。」
と,そのわかりにくさは,ブラックボックスの内部構造にある,ということらしい。いずれにしても,記号論理学になじみのないものにはわかりづらい。
さて,こうした数学上の「不完全性定理」は,物理学にどんな影響を与えたのか。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416793184.html
で触れた,ブライアン・グリーンは,マックス・テグマークの「数学宇宙仮説」を紹介している。それは,
「この宇宙は数学により記述される。宇宙のあらゆる物理法則は数字なのだ。」
ということになる。
「もしこの考えが正しいなら,この宇宙は単なる数学シミュレーションだ,という結論にならざるをえない。そして,数学シミュレーションであるならば,それが描き出す宇宙の姿はひとつとはかぎらない。数学シミュレーションはパラメーターや初期値や方程式を変えるだけで,別の宇宙を創りだすだろう。つまり,もし宇宙が数学シミュレーションにすぎないのであれば,宇宙は,われわれの宇宙だけであるはずがない。」
と,今日の多宇宙仮説へとつながっていく。
「そもそもゲーデルやチューリングが発見したことは,『システム内で〜』という点が重要なのだ。個々の宇宙のシミュレーションが個々のプログラム,いいかえるとチューリング機械に相当するなら,すべての宇宙のシミュレーションは万能チューリング機械に相当するだろう。(中略)この宇宙全体をひとつのシステムとみなし,あらゆる物理現象の背後に『計算』が存在する,と仮定して,ゲーデルの定理やチューリングの定理を当てはめることも可能だろう。しかし,最近の物理学では多宇宙の存在がふつうに論じられている。それは厳密に形式的に論じられているわけではない。だから,この宇宙内では証明できない物理法則(?)があるとしても,それを別の宇宙から見ている観測者がその物理法則を『あの宇宙ではこんな物理法則が成り立っている』と証明することは可能だろう。」
結局,視点というか,同じことだが,立ち位置の問題に行きつく。
「相対性理論と量子力学(不確定性原理)と不完全性定理に共通するわからなさは,『視点を意識しないといけない』ということなのだと思う。相対性理論では,『誰が何を観測しているのか』,(中略)量子力学についても,観測装置の向きによって,観測される数値が変ってしまうのだ。(中略)ゲーデルの俯瞰是正定理も,メタな視点から数学を考察する以上,誰が何を計算(証明)しているのかが決定的に重要になってくる。」
と,著者が最後に指摘することは印象深い。更に敷衍すれば,視点は,
誰が,
という主体によって,
そのパースペクティブ,
が決定づけられる,それを決するのは,あえて言えば,
位置が,どこか,
が鍵になる。このことは,敷衍できる,ものの見方の鍵になりそうである。
参考文献;
竹内薫『不完全性定理とはなにか−ゲーデルとチューリングの考えたこと 』(ブルーバックス) |
|
脳の機能 |
|
マーヴィン・ミンスキー『心の社会』を読む。

本書は,「人工知能の父」と呼ばれるマービン・ミンスキー(Marvin Minsky,
1927〜 2016)の,
「心がどうはたらくかを説明しよう」
と意図した本である。そして,冒頭,
「知能は,知能でないものからどのようにして現れてくるのだろうか。この問いに答えるために,この本では,心がたくさんの小さな部分を組み合わせて作れることを示そうと思う。ただし,それぞれの部分には心がないものとしようと思う。
このような考え方,つまり,心がたくさんの小さなプロセスからできているという考え方を,《心の社会》と呼ぶことにする。また,心を構成する小さなプロセス一つひとつを,エージェントと呼ぶことにする。心のエージェントたちは,一つひとつとってみれば,心とか思考をまったく必要としないような簡単なことしかできない。それなのに,こうしたエージェントたちがある特別な方法でいろいろな社会を構成すると,本当の知能にまで到達することができるのである。」
と述べる。この背景には,著者が,
「コンピュータ科学者であり、認知科学者。専門は人工知能 (AI)
であり、マサチューセッツ工科大学の人工知能研究所の創設者の1人。初期の人工知能研究を行い、AIや哲学に関する著書でも知られ、現在ダートマス会議として知られる、"The
Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (1956)"
の発起人の一人」
であり,
「世界初のヘッドマウント型グラフィックディスプレイ(1963年)と共焦点顕微鏡(1961年、今日よく使われている共焦点レーザー顕微鏡の原点)がある。また、シーモア・パパートと共にLOGO言語を開発した。その他にも、1951年、ミンスキーは世界初のランダム結線型ニューラルネットワーク学習マシン
SNARC を製作している」
という特許をも取得しているという,長年培ってきた人工知能研究がある。
「あとがき」で,著者は,
「心は果たして機械であろうか? この問いに対しては,私は一点の曇りもなくイエスと答えてきた。むしろ,私が問題としてきたのは,どういう種類の機械なのか,ということだけであった。」
で,
「思考を作り出す脳という機械の性質」
を,劈頭,
「心とは何かを説明するには,心でないものから心がどのようにして作られるかをしめさなければならない。」
と始め,
「今でも世の中の人の大部分は,機械が意識を持ったり,野心嫉妬やユーモアのようないろいろな気持ちを感じたりすることなど,できるわけがないと信じている。実際,私たちはまだ,人間に可能などんなことでもできるような機械が作れたわけではない。しかし,このことは単に,思考のはたらきについてもっとよい理論が必要だ,ということを言っているにすぎない。これからこの本で示すのは,どうすれば《心のエージェント》と呼ぶ小さな機械が,長い間私たちの求めてきた理論の《基本的な要素》になれるかということなのである。」
と言い,部品(エージェント)をどうつなぎ合わせることで,どう働きどう働いて心が機能するのかが示され,思考や感情を産み出すという,
「心はたくさんの小さなメカニズムからなる社会」
の形成プロセスを具体的に展開して行く。そして同時に,この本自体も,この本の主張と同じように,
「小さな考えをたくさん集めた社会の形になっている」
ところが,みそである。
当然冒頭の文章にあるように仮説の積み重ねで,本書は成り立っている。それについて,「あとがき」で,
「この本で示されている考え方を組み立てるのに,私は,文字通り何百もの仮説を立てなければならなかった。一部の科学者たちは,これに対して反論を唱えるかもしれない。彼らの反論の根拠は,物理学や化学のように科学として成功している分野は,必要不可欠なもの以外はすべて取り除いて,最小限の仮説を立てるのに必要な理論だけを展開させることで,より実り豊かな成果をあげてきた,という考え方にある。しかし,心理学に対して,もっと筋の通った骨組みをうちたてられるまでは,まだはっきりと否定されていない仮説を排除したり,ある理論が別の理論より良いことを示そうとしたりするのは,早すぎるといえよう。なぜなら,現在私たちが知っているいろいろな理論が,たとえ一つでも,これから長い間生き残るということは,いずれにしてもありえないように思えるからである。」
今日,この「心の社会」理論が,どのような位置づけにあるかは知らない。しかし,「《心の社会》理論はフレーム理論と神経回路網理論の限界を乗り越えようとして出てきた」(訳者(安西祐一郎)あとがき)である以上,この延長線上に,今日のいくつかの成果が表れていることは疑いあるまい。
本書の特徴は,
「やさしいことはむつかしい」
と,随所で指摘していることだ。
「ロボットを動かそうとしているときに私たちが発見したのは,日常的な問題の多くが,おとなの考えるパズルやゲームのような問題よりもずっと複雑だということである。」
たとえば,積み木の世界について,
「簡単そうな世界でも,ふだんより注意深く見ざるをえない立場に立ってみると,思わぬ複雑な世界が至るところに見いだされる。たとえば,塔を作るのに使ってしまった積み木は二度と使わないようにするという,一見ごく単純な問題を考えてみよう。人間にとっては,これは次のような簡単な常識の問題に過ぎない。〈以前の目標を達成するのに使ったものは,新しい目標を達成するためには使わないこと。〉人間の心にどうしてこんなことができるのか。正確なことは誰も知らない。ただ,私たちが,やっかいなことが起こりそうな状況であることがわかると経験から新たなことを学習できることは明らかである。しかしまた,私たちにとっては,何がうまくいくかは前もってわかりえないのだから,不確定なことで対応できるような方策を学習する必要もある。どんな方策を試してみるのが一番良いのか,また最悪の誤りを避けるにはどうすればよいか。私たちが予期し,イメージし,計画を立て,予測を行ない,誤りの起こるのを防ぐことができるためには,何千,いや何百万もの小さなプロセスが必要である。しかも,こうしたプロセスはまったく自動的に実行されるので,私たちは,〈ふつうの常識〉と呼んですませてしまうくらいである。しかし,もしも思考というものがそんなに複雑なものなら,なぜこうも一見単純に見えるのだろうか。」
だから,
「一般に私たちは,自分の心の一番得意なことが一番わからない」。
本書で,フロイトとピアジェが頻繁に顔を出す所以であるが,著者は,
「私たちが《意識》と呼んでいるものに関係した特別なエージェンシーたちは,主として,他の機能がうまくはたらかなくなりだしたときにはたらき始める。だから私たちは,余計なことをせずきちんと動く複雑なプロセスよりも,うまく動かない単純なプロセスの方に気がつくことが多い。」
と。だから,
「ジャン・ピアジェの理論とジークムント・フロイトの理論は,表面的には別々の科学の領域にあるように見える。つまり,ピアジェの仕事はほとんどが知能に関係しているのに対して,フロイトの仕事は感情のメカニズムについて研究したもののように見える。しかし,実際には,この二人の理論が本当に違ったものかどうかは明らかではない。なぜなら,感情による行動が意識下のメカニズムに依存していることは広く認められているけれども,日常的な〈知的な〉思考もまた同じように,内省のできない隠れたメカニズムに依存している,ということについては,あまり認識されているとはいえないからである。」
と。つまり,感情も,思考も,「よくある日常の目的を達成するための手段」ということになるからだということになる。
それにしても,すぐれた科学者は,問いの立て方が独特だが,本書の著者も,随所に,はっとする問いを立てる。たとえば,
「〈自己とは何か?〉と問う代わりに,〈自己について我々が考えていることは何なのか?〉と問うことができる。そして次には〈そうした考えは,どんな心理的機能を果たしているのか?〉と問うことができる。」
自己を前提に考えるのではなく,「自己」というものどう考えるかから迫ることで,
「《自己》についての私たちの考えには,自分自身が何であるかについて自分が信じていることが含まれている。」
ことが見え,自己についての考えが多様であることがわかってくる。あるいは,
機械は創造的にはなれない,
という前提に立てば,機械に創造的なプログラムは出来ないという仮定になる。しかし,どうすれば創造的な答えを出せるようにできるか,と考えると,
「どんな問題でも,解けたときに解けたことがわかるような方法さえあれば,解き方が前もってわからなくても,試行錯誤によってコンピュータに解かせるようにプログラムすることができる。」
となる。あるいは,知能を持った機械は感情をもてるかという問いではなく,
「ここで問うべきは,実は知能をもった機械が何らかの感情を持てるかということではなく,機械は感情を持たずに知能を持てるかということである。あらゆる種類のチェック機構やバランス感覚を与えてやらねばならなくなるだろう。」
から,それは不可能と,言外に言っている。
「目標がどんなに中立的で合理的に見えても,長いこと続くと,結局は他の目標と争いを起こすことになる。長期的な計画は,互いに競合する関心事に抗するための何らかの防衛機構がなくては,実行することができない。そして,この防衛機構が,急を要する目標たちの間の争いに対して,感情的反応と呼ばれるものを惹き起こすのである。」
と。
著者の,
「私は,『機械は意識を持てますか?』と聞かれると,『人間は意識を持てますか?』と問い返したくなる。私にとっては,もとの問いへのまじめな答えなのである。というのは,私たち人間には,自分を理解するための装置があまりにも欠けているからである。人間が自分の脳のはたらきを理解したいと思うようになるよりずっと前から,人間の脳の構造は,すでに,進化による制約を受けてしまっている。一方,新しい機械のほうは私たちの好きなように設計できる。とくに,その機械の活動自体を記録し,それを機械が自分で調べることができるように,良い方法を機械に組み込むこともできる。そしてこのことは,機械のほうが私たちよりもはるかに多く意識を持てる可能性がある,ということを意味しているのである。」
という記述は,象徴的である。
マービン・ミンスキーについては,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC
に詳しい。
参考文献;
マーヴィン・ミンスキー『心の社会』(産業図書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%B3%E3%83%BB%E3% |
|
江戸ッ子 |
|
三田村鳶魚『江戸ッ子』を読む。
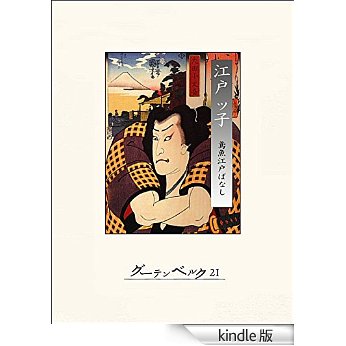
まずは,鳶魚は,「江戸ッ子」と表記する。これについて,
「江戸ッ子ということ、これは江戸子ではいけないので、どうしても『ッ』の字が中に割り込んでいないと具合が悪い。東京(とうけい)ッ子でもいけない。鶏が鳴くように聞えるからいけないのじゃないので、江戸を背負って生れた若い者、という意味にならないからです。」
という。ついでながら,これに続いて,「東京」の訓み方について,こう書く。
「明治のはじまりには、トウキョウとは申さないで、トウケイと申しました。」
なぜなら,
「これはどういうわけでそうなったのか、この心持はどういうものかと申しますと、西京と並ぶのが厭だったのです。
西京がもとから向うにありまして、サイキョウというところから、こっちはわざとトウケイといった。あっちではケイとは申しません。そのキョウを嫌って、ケイと申しました。西キョウに東キョウでなく、西キョウに東ケイという。」
と,何だか,「江戸ッ子」のような意地っ張りに聞こえる。しかし,「江戸ッ子」というのは一筋縄ではいかない。鳶魚に言わせると,「江戸ッ子」は,
「表通りには住んで いない。皆裏通りに住んでいた」
つまりは,
裏店(うらだな),
に棲む。では,裏店とは何か。鳶魚曰く,
長屋と裏店とは違う,
という。
「長屋というのは建てつらねた家ですから、どんな場所にもあった。
水戸様の百間長屋などというのは、今の砲兵工廠の所にあったので、その他大名衆の本邸には、囲いのようにお長屋というものがあって、そこに、勤番士もおれば、定府の者もおりました。長屋の方は、建て方からきている名称ですが、裏店の方は、位置からきている名称」
で,位置とは,場所を指す。
「裏店というのは、商売の出来ない場所」
で,ここに住んでいるのは,
「日雇取・土方・大工・左官 などの手間取・棒手振、そんな
手合で、大工・左官でも棟梁といわれるような人、鳶の者でも頭になった人は、小商人のいる横町とか、新道とかいうところに住んでおりますから、裏店住居ではない。」
では,裏店に対して,表店とは何か。そのためには,町人とは何かが,はっきりしなくてはならない。
「町人という言葉から考えますと、武家の住っている屋敷地に居らぬ人、市街地に住んでいる人を、すべて言いそうなものなのに、町人といえ
ば商人に限るようになっている 」
のであって,そこには,裏店の人間は入らない。
「都会の自治制の単位が一町一町になっておりまして、町の万端は地面を持ったものだけがする。地面を持つには、それだけの資力のある人でなければなりませんから、自然と銭のある商人が権利を得て銭のない、地面のないものは、そこから除外されることになる。したがって、町人といえば商人のことになって、町内費用の相談などという時にも、第一が地主寄合、その次が町内寄合――これは地面を借りて家作をした人――というふうになっております。とにかく、すべての町内費用は表店の人が出すので、裏店の人は何も出すわけじゃない。」
それは,たとえば,
「今日でいえば、地方税とか、市町村税とか、そんなもの」
も払っていない,ということで,裏店の人間は町人の員数に入っていない。逆に言うと,ここで鳶魚の言う「町人」は,「江戸ッ子」とは呼ばないし,自らもそう認識していない,ということにらしいのである。
では,いつから「江戸ッ子」という言い方をするようになったのか。
「この江戸ッ子という言葉は、いつ頃からいうようになったかと申しますと、寛政九年に出ました洒落本の『廓通遊子』というものにあるのが、一番古いようです。」
そして,
「江戸者という言葉は、もっともっと古くからありますが、(中略)寛政以来ズーッと江戸ッ子といっているわけでもないので、為永春水の書きましたもの、これは天保期でありますが、これには東ッ子といっております。元禄頃にいった『吾妻男に京女郎』というような気持になって、何だか間が抜けている。そこで、とにかく寛政以来、江戸ッ子という言葉が浮いて出ておりますが、この江戸ッ子という言葉は、気が利いているように、『おらア江戸ッ子だ』と、自称するものの多くなったのは、文化以来のことであります。」
しかし,それを,『飛鳥川』という 随筆の中で,
「近来は、棒手振の肴売りや野菜売りが、ばかに力み出して威張っているが、それがよっぽどおかしい、ということが書いてある。」
と,鳶魚は皮肉っている。この文化・文政期は,家斉の時代で,
「文政二年に小判が改鋳されて、草文小判といい、一歩判も同じく改鋳されて、草文歩判と称されております。文政三年には丁銀も改められ、十一年にはまた二朱銀も改められ…通貨膨脹ということで景気が立つのであります。家斉が近来で贅沢な羽振りのいい将軍だったということも、実はこの通貨膨脹のため」
ということで,「江戸ッ子」にもその余沢が来る。なぜなら,
「この頃は交通が不便でもありましたし、各藩に各々制度がありまして、出稼ぎ人を出すことをしませんから、江戸が景気がいいからといって、労働者を吸収するようなことはない。」
ということが背景にある。この頃,
大工の一日の手間が,四匁二分,
一年に一貫587匁6分,
という。夫婦に子供一人で,一貫514匁かかる,という。この頃,ようやく豊かになったと言って,これである。
本書で鳶魚が強調するのは,我々のなかにある「べらんめい」の,「巻き舌でまくしたてる」という「江戸ッ子」像は,造られたものだ,ということだ。そういうイメージを創り出したのは,
芝居,
であり,
滑稽本(『膝栗毛』『浮世床』『浮世風呂』『花暦八笑人』『七偏人』等々),
だ,と鳶魚は言う。
「芝居だと、江戸ッ子がいかにも活躍する。彼等が得意の痰火を切るということも芝居で聞けばおもしろいが、実際
の江戸ッ子には、あれだけの弁舌はありません。それはよく落語の中に残っていて、皆さんが寄席へ行ってお笑いなさる道具になっているのでも知れております。『金のしゃっちょこを横眼に睨んで、水道の水を産湯に浴び、おがみづきの米を食って、日本橋の真中で育った金箔付の江戸ッ子だ』というような、気の利いたらしい台詞は、実際彼等に言えやしない。皆狂言作者がそういうふうに拵えて、役者に言せるのです。」
しかし滑稽なことに,多くの「江戸ッ子」は本を読まないし,芝居も見ない。鳶魚は,「地主とゆかりのないものは立ち見もできない」という。それを観たり,読んだりするのは,町人なのである。そういう人たちが,「江戸ッ子」を観る。「江戸ッ子」は,芝居を真似て,イメージ通りに演ずる,と鳶魚う言うのである。
「小説でも読む人達は、多少銭のある人達ですから、自分と世界の違った連中が、とんでもないことをするのを、おもしろがって見る。
今日江戸ッ子をおもしろがるのも同じことで、江戸ッ子というものがなくなった後になればなるほど、そういう眼でみることになります。諸君も御自分の境涯におひきくらべになって、江戸ッ子というものをおもしろいと思われるかも知れませんが、いよいよ本当の江戸ッ子がやって来たら、多分諸君は逃げ出されるでしょう。」
と。「江戸ッ子」の風体は,
半纏着
で,
「もう一つ、明らかに江戸ッ子を語っているものは、半纏着という言葉です。半纏着では、吉原へ行っても上げない。
江戸ッ子というと、意気で気前がよくって、どこへ行ってももてそうに思われるが、半纏着だと銭を持っていても女郎さえ買えないんだから、ひどいものです。この連中は、普通の人の着物を長着という。羽織は見たこともない手合だから、長着は持っていない。持っているのは、半纏・股引だけだ。もし長着があるとすれば、単物に三尺くらいのものでしょう。」
と。いったいこの「江戸ッ子」は何人いるのか。
「大概 江戸の人口の一割くらい」
で,五万人,と鳶魚は見積もる。我々のイメージしているのは,町人かその使用人であったが,それを鳶魚は,「江戸ッ子」に入れない。
「町家でも 一軒の御主人は勿論、番頭や小僧に至るまで、 江戸ッ子だなんていってては
商内が出来ない。」
したがって,これを「江戸ッ子」には数えない。では,江戸の範囲は,というと,
「文化・文政の江戸は、ひろがっておりました。江戸という名称は下町のことで、下町というのは城下町の意味ですから、千代田城の前のところ、新橋から筋違見附まで――
筋違見附というのは、今日では少し曲っておりますが、まず万世橋のところです―― が江戸で、そのほかは江戸じゃない。」
と,そもそも江戸を限定する。で,
「芝へ行けば芝ッ子、外神田なら外神田ッ子で、浅草だの本所・深川は無論江戸じゃない、場違いの方です。また、(中略)江戸前というのはどこかというと、両国から永代までの間、お城の前面をいうのであります。文化・文政の江戸には、本所・深川も入っておりましたが、こういう場違いの江戸ッ子を差引きまして、本場物ばかりですと、まず二万五千くらいの数にしかならない。」
となる。「江戸ッ子」自慢の江戸弁は,というと,
「寛文年中の江戸の流行物を挙げた中に、『まづ年頃のかたがたは、立身せんと朝公儀、三河言葉をにせ廻り、そらいんぎんのきつとばる』という文句がある。これは、江戸のはじめ以来、三河の者が大勢入り込んで来て、それが主人になったわけですから、三河言葉が盛んになった。少し改まった言葉を言おうとすれば、京言葉が入る。三河と、京と、関東と、この三つがごっちゃになってゆくわけす。」
あるいは,
「西沢一鳳は、江戸の言葉は方々の寄せ集めみたいなものであるから、本当に江戸にもとからあった言葉は、甚だ少ない、江戸の言葉というものは、関八州の言葉を取り合せたもので、それを江戸言葉と言っているのだが、だいたいから言えば、京、大坂の言葉を詰めて短く言っているように思う」
と。「江戸弁」つまりは,「江戸なまり」だが,「江戸ッ子」が限定される以上,「江戸ッ子」以外は使わない。鳶魚は,こういうのである。
「一体、江戸言葉・江戸訛り・関東べい・東訛りというようなものは、中流以上の人の言葉には聞かれないもので、
これは早く昔の人も言っている。江戸だからといっても、上等の人々は、ちっとも言葉に変りがない。日本中押し通したものだ。殿様なんていう人達になれば、奥州大名も西国大名も、話がわからないようなことは決してない。それほどでなくても、中等以上の人であれば、武士にしろ町人にしろ、お互いにわからないような言葉は遣わない。」
少なくとも,本書を通して,「江戸ッ子」のイメージが完全に変わることは間違いない。
参考文献;
三田村鳶魚『江戸ッ子』(Kindle版) |
|
中世論 |
|
渡辺京二『 日本近世の起源』を読む。

誠に失礼ながら,本書を読んで,間違った使い方かもしれないが,思い浮かんだのは,
道を聞きて塗(みち)に説くは,これ徳を棄つるなり,
という『論語』の一節である。戦後左派歴史学者や網野善彦氏らへの罵詈雑言は,途中で本を投げ出したくなるほど読むに堪えず,その論拠は,しかし,近年の藤木久志氏らの戦国史の研究であり,さらに言えば,世評高いらしい,著者の,
『逝きし世の面影』
で示しているらしい,
徳川の平和(これに,「パックス・トクガワーナ」とルビを振っている),
を前提とするための中世論であるらしく,とりわけ,中世の,
自由だの,
自主独立だの,
というのが目障りだっただけなのではないか,と勘繰りたくなる。で思い立したのは,この著者が,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163207.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163449.html
の横井小楠で触れたように,著者は,神風連の生みの親,林櫻園と対比して,小楠をこう批判している。
「国民攘夷戦争(幕末の攘夷熱のときに決戦を唱えた)の主張から全人間界の出来事の放棄(晩年厭世的になり神事に専念するようになる)にいたる櫻園の思想的道すじは,彼がヨーロッパ文明の圧倒的な侵蝕力を鋭く感知し,この異種文明との出会いがわが国の伝統的文明を運命的に脅かさずにはいないことを見抜いていたところから,生まれたもののように見える。たとえば開国論者横井小楠には,『堯舜孔子の道を明らかにし/西洋器械の術を尽くさば/なんぞ富国に止まらん/なんぞ強兵に止まらん/大義を四海に布かんのみ』という有名な詩があるが,櫻園にいわせればこれはとほうもない誇大妄想というものであったろう。ヨーロッパ文明との接触はそれから『器械の術』だけをいただけばいいようなものではなく,小楠にとっての『大義』すなわち『堯舜孔子の道』を必然的に崩壊させずにすまぬことであることを,彼はおそら洞察していた。」
このとき櫻園をかように持ち上げる都合上,「とほうもない夢想家」小楠は格好の餌であった。いま本書では,
徳川の平和(パックス・トクガワーナ),
を唱導する都合上,中世に自由や安寧があってはならない,というようにしか,僻目でしかないかもしれないが,思えてならない。だから,最後で,こう書く,
「十六世紀という大転換のあの流血と騒乱は,もともと徳川の平和(パックス・トクガワーナ)をあがなうためのものだったと考えるしかあるまい。徳川の平和は武装した幕藩領主の連合によって実現した。しかしそれはいったん成立するや,武家社会の『兵営』的性格を骨抜きにし,あげくは払拭するような方向性を当初から備えていたというべきである。」
しかし,その論拠は,続いて引用する尾藤正英氏の仮説(『江戸時代とはなにか』)に基づく。
「秀吉や家康らの支配に人々が服従したのは,その指導のもとに形成された新しい秩序が,むしろ好ましいものとして受け入れられたからこそであろう。そうでなく,もしそれが権力による一方的な抑圧や共生の結果であったとすれば,そののちの二七〇年間にわたって国内の平和が維持されたという事実を,どのようにして合理的に説明することができるのであろうか」
こう言うに値する論拠があって言っているのであろう。しかし,それは,仮説である。突っ込もうと思えば一杯ある。「人々」で括れるものか,とか,「好ましてものとして受け入れられた」って何,とか,まあ,時代の変化を反映するので,それはそれでいいとして,それを仮説であるにもかかわらず,
「徳川の平和は,…十八世紀に確立して十九世紀を通じて存続した日本の前近代文明が成り立つための前提条件」
とまで言い切るのは,昨今の自画自賛の魁として,一種気持ちの悪さがつきまとう。だから,その前の中世は,混乱と騒擾の世界でなくてはならない,というように,最後をこう締めくくる。
「徳川期の社会は,今日極相にまで到達した近代を批判的に照らし出す豊かな啓示にみちている。そのような社会を可能ならしめた国家機構,さらにはそこに花咲いた文化は,批判以前にまず理解すべきものとしてわれわれの眼前に在る。…私はそのような語義通りにユニークな一文明が出現するまでの苛烈な道程を,従来の市民主義史学ないし左翼史学と全く反する視点で,しかし何人かの秀れた史家の助けを借りて読み解いてみようとしたにすぎない。」
ここに本書の意図が明確に示されている。つまり,先に結論ありきなのである。学問に右翼左翼は関係ない,その仮説が,どれだけ視界を開くに値するすぐれた仮説かどうか,というだけだ。それは,いずれ,検証の中で消えていく。罵倒すべきものではなく,検証によって乗り越えていくべきものではあるまいか。ある意味,著者自身がイデオロギーというものに,強い近親憎悪を懐き,別の意味のイデオロギーにとらわれているとしか思えない。
しかし,著者が引用しまくってくれることで,おかけで,ある意味,中世研究の最前線を総覧させていただくことになった。僕には,その意味で,
第二章 武装し自立する惣村
第五章 自力救済の世界
第七章 侍に成り上がる百姓
が,面白かった。惣村の力の背景には,中世の農業生産力があるのではないか,という気がするが,反イデオロギー(多く=反マルクス主義)というイデオロギーにとらわれている著者は,その辺りを完全にスルーしていて,なぜ農民が力を持ってきたのかは,本書からは読めない。
荘園制を内部から打ち崩していく流れを,勝俣鎮夫氏や黒川直則氏らの研究をもとに,こうまとめる。
「新しい共同体としての村落,いわゆる惣村は,惣有財産,惣掟(村法),あるいは自検断の存在と,年貢の村請の成立によってであり,(中略)村請とは,荘園領主が検注帳にもとづいて農民を個別直接的に把握し,毎年実検を行って年貢・課役を決定・徴収する従来のシステムに代わって,村が領主と起請契約して,一定額の年貢・課役の納入に責任をもつシステムである。したがって,…未進の追及や減免措置…(は)村請においては村を対象として行われ,未進の場合は領主は村の責任者を追及することになる。…
このシステムの画期的な意義は,…領主対個別農民の関係が領主対村の関係に変化したことになる。」
こうした惣村の力は,そのまま惣村の指導者層の力の背景になっていく。
「中世後期から近世への大転換を主導したのは,百姓地下衆の上層部,すなわち荘園公領的集落の名主層,いいかえれば惣村の指導者たる長百姓の動向だった。中世の社会身分は,聖俗の貴族を別とすると侍と凡下にわかれる。近世武家社会支配を実現した武士階級は,中世の侍身分だったのではない。彼らは中世の凡下,すなわち百姓地下衆だったものが朝尾直弘の表現を借りると,侍に成り上がったのである。」
この象徴は,秀吉である。
「徳川幕藩体制は秀吉の遺業のうえに成り立っている。その秀吉が尾張の平百姓の出で,草履取りという雑兵として閲歴の一歩を踏み出したことの意味は重大であるはずだ。宣教師カブラルが『百姓でも内心王たらんとおもわないようなものは一人もおらず,機会次第そうなろうとする』と言うのは,…当時の民心の一斑を察するに足る。…秀吉を好例とするように百姓が武将に成り上がったとしても,彼をその一員として迎い入れた武士団は土地領主としての長い伝統をもっている。…百姓の『身分変更闘争』としての武士化は,彼自身が伝統的武士団のイデオロギーに同化することでもあった。しかし,この場合肝心なのは,織豊武士団と伝統的武士団との異質さにあるだろう。頼朝や尊氏は源氏の棟梁であるからこそ,武士たちから主人としてあおがれた。ところが織豊武士団は,尾張の一平百姓であったものをおのれの棟梁に戴くことに,何の違和感も感じなかったのである。
つまり織豊武士団は…百姓を組織した軍隊だった。単に雑兵が百姓だったというばかりではない。将校クラスの武士から,軍団の長たる大名にいたるまで,百姓から成り上がった者は珍しくもなんともなかったのだ。惣村は中世後期に至って,数々のきびしい軍事的経験を積んできた。その期間は優に二百年にわたっている。…惣村の武力を把握できるかどうかは,すでに戦国大名時代から興亡の鍵をにぎる重大事だったのである。」
こうして,日本中世を掘り下げていくと,意外と,我が国の中世とヨーロッパ中世との同時代性が炙り出されてくる。そして,本書の著者の主張とは異なり,あらためて,和辻哲郎が,『鎖国』で嘆いていたように,著者渡辺京二の賛美する,
徳川の平和(パックス・トクガワーナ)
という三百年にわたる自己完結した閉鎖性の中で,せっかくもっていた世界との同時代性を失い,ヨーロッパのもつ,
世界的視圏,
という
視界の幅と奥行き,
視線の射程,
をついにもてない(ままだ),とつくづく思う。
参考文献;
渡辺京二『日本近世の起源』 (新書y)
渡辺京二『神風連とその時代』(洋泉社)
和辻哲郎『鎖国』(岩波文庫) |
|
マインドワンダリング |
|
マイケル・コーバリス『意識と無意識のあいだ 「ぼんやり」したとき脳で起きていること』を読む。

本書の原題は,ずばり,
THE WANDERING MIND
である。いわゆる,
マインドワンダリング,
ぼんやりした状態,
のことである。この現象は18世紀ころから知られていたが,その科学的研究の流れを創り出したのが,本書の著者とその教え子,トーマス・ズデンドルフが,1997年に発表した論文である。
ぼんやり空想に耽っている状態は,悪いことばかりではない,著者は,
「マインドワンダリングには多くの建設的で適応的な側面があり,たぶんそれなしでは生きていけないこと」
を示そうとしたのが,本書の意図だという。マインドワンダリングを,著者は別に,
メンタルトラベル
とも呼ぶ。この放心状態のとき,
「時間をさかのぼったり進めたりして,過去の経験から未来の計画を立てるとともに,連続した自己意識を得てもいるのだ。マインドワンダリングによって他者の気持ちになることができ,共感や社会的理解がうながされる。発明し,物語を紡ぎ,視野を広げられる。創造的にもなる。ひとひらの雲のごとく独りさまよう,イギリスの桂冠詩人ワーズワースのように,あるいは光速で旅する自分を想像するアインシュタインのように。」
著者らの実験では,
「過去のできごとを思い出すときに活性化する脳領域と,未来のできごとを想像するときに活性化する脳領域はほぼ重なっていた。脳にとって,この二つの行為のあいだにはほぼ違いというものがないようだ。」
という。
カリフォルニア大学の心理学者ジョナサン・スクーラーの実験では,トルストイの『戦争と平和』の冒頭部分を45分を読みながら,その間別の事を考えたのは,平均5.4回,
「私たちはみな集中し続けるのが苦手で,とりわけ読書や講義の最中に空想の世界に迷う込んでしまう。」
と,著者は書く。つまりは,それは,イレギュラーではない。むしろ当たり前,ということになる。だからこそ,
フェイルセーフ(エラーが起きても,エラーによる被害の拡大防止やエラー前の状態に回復するエラー対処)
や
フールプルーフ(エラーそのものが起きないよう対策をたてること,つまりエラーの未然防止),
が不可欠になる。
「心が休んでいるとき,つまり目の前の仕事からさまよい出ているときも,脳は活動している」のをはじめて明らかにしたのは,
1924年ドイツの精神科医ハンス・ベルガ―で,
患者の頭皮下に電極を指し込み,電波を検知した。目を閉じて安静にしているときの脳波が8〜13ヘルツであることを検出しベルガー波(いまでいうアルファ波)を検出した。
1970年代,スウェーデンの生理学者ダーヴィド・H・イングヴァル,デンマークの科学者ニルス・A・ラッセンが,
脳に放射性物質を注入し,それが脳内を流れる。様子を体外モニターで確認した。イングヴァルは,「安静時に脳の前部がとりわけ活発に活動していること」を発見し,
「目的不明で,自発的で,意識ある精神作用」
を示すと述べた,という。これが,本書の言う,
マインドワンダリング
である。いまや,ポジトロン断層法(PET)や機能的磁気共鳴画像法(fMRI)などによって,読書,顔認識,頭の中で物体を回転させる等々誠信書房作業に関わる脳内ネットワークの地図作成ができている。そうして,
「人が何かをしているときと,そうでないとき,どの能領域が活性化しているかがわかるようになった。当初,安静時の脳の活動は神経的な背景雑音で,…単語を読むなどの何か作業をしているときの脳活動を研究するには,作業中の神経的信号から安静時の信号を引けばすむと思われていた。ところが,何もしていない脳へ流れる血液の量は作業中の脳の場合よりわずか5〜10パーセント少ないだけで,作業中より作業中でないときのほうが脳内ではより広い領域が活性化していることがわかった。安静時に活動する神経網は『デフォルトモードネットワーク』(DNN)として知られるようになる。」
これで思いつくのは,
人が何かひらめいたとき,0.1秒,脳の広範囲が活性化する,
と言われていることだ。ひらめきは,多く,何かに根を詰めて考え込んでいた時ではなく,その後,リラックスしたとき,たとえば,アルキメデスが,浴槽に入っていて,
「浴槽に入ると、水面が高くなることに気づいたアルキメデスは、水は圧縮では容易に減容しない性質から王冠を水槽に沈めれば同じ体積分水面が上昇し、容易に体積を測ることができると考えた。」
こととつながるに違いない。
心の中で時間を行き来するとき活性化する脳領域は,MRIで調べると,
デフォルトモードネットワーク,
に対応するが,これが「マインドワンダリング」ネットワークで,
「前頭前野,側頭葉,頭頂葉をふくんでいる。被験者が過去と未来のどちらについて考えているかにかかわらず,活性化した領域はかなり重複していた。」
という。そのネットワークのグランドセントラル駅は,
海馬,
である。
「海馬は前向きの構造をしていて,前端が未来に,後端が過去に関わるらしい。私たちが行ったクルーとの実験では,未来のできごとを想像し,想像したできごとをあとで思いだすよう指示されると,被験者の海馬の両端が活性化する例が多かった。つまり,想像されたシナリオもまるで実際に起きたかのように思いだされることになる。」
このデフォルトモードネットワークは,夜眠っている間も働く。
神経科学者のレックス・ユングらは,
「脳イメージングで得られた証拠を創造的認知の各指標についてつぶさに調べ上げ,創造性がマインドワンダリングのメカニズム,すなわちデフォルトモードネットワークにほぼ依存すると結論づけた。」
という。今まで,漠然と想定されて,夜の睡眠も,夢も,いわゆる3B(bus,bath,bed),我々流儀で言うと,
三上(厠上,馬上,枕上),
というインキュベーションの環境は,脳の環境からいっても,当たらずと言えども遠からず,というところになるのか。
参考文献;
マイケル・コーバリス『意識と無意識のあいだ−「ぼんやり」したとき脳で起きていること』(ブルーバックス)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%B9 |
|
ザイアンスの法則 |
|
宮本聡介・太田信夫編著『単純接触効果研究の最前線』を読む。

いまから百年以上前からこうした現象は報告されていたが,1968年のザイアンスの論文(Attitudinal Effects of
Mere Exposure)に端を発した,
単純接触効果,
についての,最新研究事情である。単純接触効果とは,
「単に繰り返し見聞きするだけで知覚者にその対象への選好を形成させることができる」
つまり,「対象への単純な繰り返し接触がその対象に対する好意度を高める現象」のことである。従って,
ザイアンスの法則,
とも言われる。よくその例として教科書に載るのはこんな例である(僕も,この例から知った)。
「ある朝,仕事に向かう途中で一人の男とすれ違た主人公は,面識がないはずのその男に対して不思議な懐かしさ,親近感を抱いていることに気づく。その理由を考えながら歩いていると,毎朝通る交番の前でびっくりして立ち止まる。指名手配中の犯人の写真のなかに先ほどの男がいるではないか。実は主人公は毎日あの男の顔を交番の前で見ていたのである。」
ザイアンス以前にも,オールポートの,
「相手に対する知識の欠如が偏見形成に関わっており,偏見の解消には接触が必要」
とする,接触仮説や,フェスティンガーの,
「大学宿舎における,親密化過程に…,物理的に近接した相手(自分の部屋の隣室の学生)を友人として選択する」
といった,物理的近接効果等々があったし,これらの研究も,
「人との繰り返し接触が,相手への好意度を高める」
という意味で似ているが,決定的に違うのは,
「単純接触効果は単純(mere)と称されるように,強化を伴わない(unreinforced)単なる接触によって,当該刺激に対して好意的反応を示すことである。」
つまり,接触仮説や物理的近接性効果に見られるバーバル(挨拶やその他の会話)・ノンバーバル(表情,アイコンタクトなど)のやりとりがなく,単純に接触するだけで,好意度が上がる,という点である。
しかも,1980年のクンスト・ウィルソンとザイアンスが出した閾下単純接触効果研究(Subliminal Mere Expososure
Effect)では,「閾下」でそれが起こると報告し,研究のパラダイムを変えたと言われている。そこで,
「認知と感情が本質的に独立(認知‐感情独立説)であり,かつ感情は認知に先行する(感情先行説)とする挑戦的な仮説を提唱した。」
つまり,
「主観的には見えておらず,当然思い出せもしないにもかかわらず,単純接触効果は得られる」
のである。さらに,ザイアンスらは,その後,
「閾下単純接触効果に替えて閾下感情プライミング効果」
をとなえた。プライミング効果とは,
「先行の学習もしくは記憶課題が、後続の別の学習もしくは記憶課題の成績に、無意識的に影響を与えること」
を言うらしく,
「笑顔や怒り顔といった感情的な刺激をプライムとして閾下提示することでその直後に閾上提示される中性的な刺激への評価がプライムの感情評価の方向へ引きずられる」
ことになる,と言う。
このザイアンス仮説に伴い,「単純接触効果」は,実験社会心理学の心理現象のレベルを超えて,認知心理学から,学習心理学,広告効果をめぐるマーケティングまで,各界を巻き込んでいくことになる。
本書は,社会心理学の現時点までの,
「なぜ対象への単純な繰り返し接触が,その対象への好意度を高めるか」
の単純接触効果のメカニズムを説明するモデル,たとえば,
対立過程モデル,
覚醒モデル,
二要因モデル,
感情先行説,
非特異的活性化モデル,
知覚的流暢性誤帰属説,
等々を取り上げているが,なかでも,本書は,知覚的流暢性誤帰属説に,ページを割いている。それは,
「ある対象への反復接触によって,その対象を知覚するときにより流暢に処理がなされるようになる。この流暢性の起源は反復接触にあるのだが,しかしそれが誤って対象の印象や対象への好意,好みへと帰属される。すると,その流暢性が帰属された分,その対象によりよい印象や好意を感じるようになる。」
所謂サブリミナル効果とつながる効果ということになる。そこで,当然,
意思決定,
や
学習効果,
ともリンクしていくし,
広告効果,
言語学習,
衣服の流行,
音楽,
香り,
味覚,
等々の単純接触効果についても,本書では検討されている。まだまだ研究途上ではあるが,
「閾下単純接触効果の発見」
に端を発する意識・無意識にかかわる好意度の単純接触効果問題は,まだまだ,幅広い分野からの参入によって,ますます進化し続けていくようである。
参考文献;
宮本聡介・太田信夫編著『単純接触効果研究の最前線』(北大路書房) |
|
どこから来てどこへ行くのか |
|
エドワード・O・ウィルソン『人類はどこから来て,どこへ行くのか』を読む。
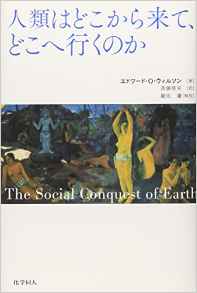
著者は,「プロローグ」で,フランスの画家ポール・ゴーギャンの話から始め,有名な,『我々は何処から来たか、我々は何者か、我々は何処に行くのか』に触れるところから始める。
ポール・ゴーギャン「我々は何処から来たか、我々は何者か、我々は何処に行くのか」(ボストン美術館)
(絵の左上にはフランス語で D'où Venons Nous Que Sommes Nous Où Allons Nous
と題名が書かれ、右上には P. Gauguin 1897 と署名および年が書かれている。)
「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか
その絵は,答ではない。問いなのである。」
と本書を書き始め,本書の掉尾を,
「ポール・ゴーギャン様,あなたについて質問ですが,なぜ絵にあの三行を書いたのですか?もちろん,私が思うに,タヒチのパノラマに描いた幅広い人間活動の象徴化についてはっきり伝えたかったから,という答えがすぐに返ってくるでしょう。万が一,その点を見落とす人がいるといけませんから。でも私には,それ以上の意図があるような気がします。もしかして,あなたが拒絶してあとにした文明社会にも,安らぎを見つけるために選んだ原始的な世界にも答えがないことを匂わせる一手として,三つの問いを発したのではないでしょうか。あるいはまた,芸術にできることはあなたのしたことが精一杯で,だからもうあの悩ましい問いを手書きで表現することしか自分にはできないと言いたかったのかもしれませんね。さらにもうひとつ,あなたがわれわれにあの謎を残した理由として,ここまでの推測と必ずしも矛盾しないものを提示させてください。あなたが書いた言葉は,勝利の叫びだと思います。あなたは遠くへ旅をしたい,視覚芸術の斬新なスタイルを見つけて採り入れたい,あの問いをこれまでにないやり方で発したい,またそうしたすべてのことから真に独創的な作品を生み出したいという情熱を実現しました。この意味で,あなたの画家としての生涯は,世代を超えた価値があります。無駄に費やされたのではありません。われわれの時代では,合理的な分析と芸術を結びつけ,自然科学と人文科学を協力させることによって,あなたが求めた答に迫っています。」
と,それへの答で締めくくっている。そう,その現代の答が,本書なのだということになる。
本書は,ゴーギャンの問い,
われわれはどこから来たか?
われわれは何者か?
われわれはどこに行くのか?
に答えるように展開するが,ただ人類発祥からの歴史をなぞっただけではない。それだけなら,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/419871878.html
で触れたように,ヒト族について書かれた本は無数にある。本書の特色は,
真社会性,
に焦点を当てたことだ。つまり,
「グループのメンバーが複数の世代で構成され,分業の一環として利他的行為に及ぶ」
アリやシロアリといった社会性昆虫と対比しつつ,(社会性昆虫であるシロアリは二億二千万年前,アリは一億五千万年前,ミツバチは七,八千年前なのに)わずか数十万年前に現れ,世界に拡散(出アフリカ)したのは六万年前にすぎないホモ・サピエンスの進化の謎に迫っている。
動物界の社会的行動には,「原因と結果によって結びつけられるふたつの現象」がある,として,
「第一の現象は,陸上環境の動物は最高に複雑な社会システムをもつ種に支配される,…。第二の現象は,そうした種が進化の歴史でまれにしか生れ出なかった…。」
と挙げ,ホモ・サピエンスは,
「何百万年にもわたる進化で数多くの準備段階を経て世に現れた」
ひとつである,と。たとえば,
「これまでに知られている二万種の真社会性昆虫は,ほとんどがアリやシロアリ,ハナバチ,狩りバチだが,およそ100万種に及ぶ既知の昆虫の二%に過ぎない。それでもこの小さなマイノリティが,数と,重量と,環境への影響という点で,他の昆虫を支配している。」
そして,
「アリとヒトは地上の世界のいわば二大覇権国家を代表している。違いは,アリやシロアリが自分たちの欲しいものをすべて一億年以内に手に入れ,ヒトがだんだん進化をとげ,ついに真社会性のレベルに達するまで世界は彼らの独壇場だった…」
のである。しかも,現時点でも,
「私は(非常に)大ざっぱにだが,現在生きているアリの数を,最も近い累乗のオーダーで,10の十乗すなわち,一京と見積もっている。平均的に見て,アリ一匹ヒト一人の百万分の一の重さだとすれば,アリの数はヒトの数…の百万倍なので,地球上に棲むすべてのアリの重さは,すべてのヒトの重さとおおよそ等しい。」
と。しかし,
「真社会性の獲得ほど重大な出来事が大型動物で起きる機会は,過去二億五千万年のうちでたくさんあった。(中略)それでも世界の霊長類以外の哺乳類ではデバネズミだけが,また熱帯から亜熱帯地域に数百万年暮らしてきた霊長類種ではただひとつ,ホモ・サピエンスの祖先であるアフリカの大型類人猿の一派が,真社会性への敷居をまたいだのである。」
では,ヒトだけが,その進化の鍵となる,真社会性をどうやって手に入れることができたのか。
真社会性誕生には,二つの段階があった,と,真社会性昆虫を例に,著者は書く。
「第一に,真社会性を獲得した動物種のすべて―例外は知られていない―で,利他的な協力が,長く使われて防御できるように作られた巣を,捕食者であれ,寄生者であれ,競合者であれ,とにかく敵から守る。第二に,この段階が達成されると,グループのメンバーが複数の世代をもち,グループの利益のために個体の利益の少なくとも一部を犠牲にするような形で分業をおこなうようにして,真社会性の準備が整った。」
たとえば,単独生のハナバチを無理やり一つの狭い部屋に押し込めると,
「ハナバチのペアは,自然界における原始的な真社会性のハナバチに見られるような序列を,自然に形成する。優位の雌である『女王』は巣にとどまり,生殖と巣の護衛をする一方,下位の雄である『ワーカー』は食料をあさる」
という自己組織化をする。そして,
「自然界では,同じ仕組みを遺伝的にプログラミングでき,母親の昆虫を巣に残る子が取り巻く結果,母親が女王となり,子がワーカーとなる。最後のステップをクリアするのに必要なただひとつの遺伝的変化は,一個の対立遺伝子―新しいタイプの単一遺伝子―の獲得であり,これによって移動分散するための脳のプログラムは働かなくなり,母親と子は新しい巣を作りに移動することがなくなる。
そんな結びつきの強いグループが現れると,そのグループのレベルで働く自然選択が始まる。つまり,繁殖できるグループに属する個体は,同じ環境でそれ以外の点ではそっくり同じである単独生の個体に比べ,うまくできたりできなかったりするのだ。結果を決めるのは,グループのメンバー同士の交わりによって発現する形質である。そうした形質には,勢力拡大にあたって協力する,巣を守り大きくする,食料を獲得する,未熟な子を育てるなどがあり,言い換えれば,このすべての行為を,単独生で生殖する昆虫は本来自分ひとりでおこなうことになる。
グループに発現するこうした形質を指定する対立遺伝子が,巣から個体が移動分散するように指定する対立遺伝子を圧倒したら,ゲノムの残りの部分に対する自然選択が始まり,より複雑な形態の社会組織が生み出される。」
これは,
「真社会性の種における分業の発生を説明する『固定閾値』モデルと合致する。」
という。それは,
「個体間の遺伝子に由来したりしなかったりするバリエーションが,特定のタスクにかかわる仕事の引き金を引くために必要な刺激の量にあらわれるとするものだ。二個体以上のアリやハチが,まだだれも手がけていない同じタスクに遭遇したら,刺激の量が少ない個体が最初に仕事をし出す。すると他の仲間は阻害され,何であれまだ手がけられていないタスクのほうへ移りやすくなる。」
というもので,
「神経系にたったひとつの変化―この場合は実質的にフレキシブルな結果をもたらす一個の対立遺伝子の置換による―が生じただけで,前適応した種が真社会性への敷居をまたげるようになる」
とする。ここで,著者は,40年来学界の主流である,
血縁選択説,
といわれる「包括的適応度の理論」を,「数学的にも生物学的にも間違っている」と,決然と異論を,述べている。
「(血縁選択説の)基本的な問題のひとつは,母親たる女王と子どものあいだの分業を『協力』,子どもが母親の巣から移動分散することを『離反』と見なしている点だ。これに対しわれわれ(著者とマーティン・ノヴァック,コリーナ・タルニタ)は,グループへの忠実さと分業は進化のゲームではないと指摘した。ワーカーはゲームのプレーヤーではない。真社会性が確立しても,ワーカーは女王の表現型の延長,つまり,女王自身の遺伝子と生殖相手となる雄の遺伝子が交互に発現したものなのだ。(中略)
この認識が正しければ,また論理的で証拠と合致していると私は思うのだが,真社会性昆虫の誕生と進化は,個体レベルの自然選択に突き動かされたプロセスと見なせる。」
そして,こう言い切る。
「必要な条件がすべて揃えば―つまり,しかるべき前真社会性(真社会性の前段階)の特徴を備え,集団内にきわめて低レベルではあっても真社会性の対立遺伝子が存在し,さらには集団での活動に有利となる環境的圧力も存在すれば―単独生の種は真社会性への敷居をまたぐことになる。この進化の段階で意外な点は,…既存の行動をやめさせ,それによって巣から親や成長した子が移動分散するのを押しとどめるだけでいい。(中略)
真社会性と,われわれが利他行動と呼びたがるものは,親がすでに巣を作り,わが子に餌を与えるようになっていれば,ひとつかひと組の対立遺伝子(遺伝子のタイプ)のフレキシブルな発現によって誕生しうる。唯一必要なのは,グループの形質に対して働くグループ選択で,これが巣にいる家族にも有利に働く。すると,生態系への支配に向けた歩みが始まり,生物の新しいレベルの組織に到達する。これは,新たに造られたワーカー階級を従えるひとりの女王にとっては小さな一歩だが,昆虫にとっては大きな飛躍なのだ。」
この仮説を展開する,18,19章はなかなか読みごたえがある。そこで,著者は,高度な真社会性へと進化する移行モデルを次のように整理して見せる。
第一段階は,利他的であるように分業をともないながら,他の点では単独生と言える個体が自由に混じり合う集団のなかに複数のグループが形成される。
「家族によるグループの形成は,真社会性の対立遺伝子の拡大を加速することがあるが,それだけで高度な社会的行動へ導きはしない。高度な社会的行動をもたらす要因は,防御可能な巣,特に作るのにコストがかかり,持続可能な食糧源の近くにある巣をもつという利点だ。昆虫ではこれが最初の要件なので,原始的コロニーの形成において,遺伝的近縁性は真社会性の行動の結果であって,原因ではない。」
第二段階は,真社会性への変化を起こしやすくする他の形質が偶然蓄積する。
「たとえば一部の種は,比較的捕食者がいない生息環境に棲むようになるかもしれない。すると子を守る必要が差し迫ったものではなくなり,彼らは社会進化の点で安定しやすくなったり,進化の道筋をすっかりはずれて単独生の生活になりやすかったりする。一方で別の一部の種は,危険な捕食者の多い生息環境では,真社会性の敷居に近づき,越えやすくなる。」
第三段階は,変異か外から変異した個体が入ってくることによる,真社会性の対立遺伝子が誕生する。
「少なくとも前適応した膜翅類(ハナバチや狩りバチ)の場合,この現象は単一の点突然変異で起こりうる。さらに,新しい行動の完成をもたらすのに変異は必要ではない。古い行動を取り消すだけでいいのだ。真社会性への敷居を越えるには,雌とその成熟した子が移動分散して新たな個々の巣を創始しないことが求められる。」
第四段階は,コロニーにメンバー間の相互作用によって新たな形質のみを対象とするグループ選択が進む。
「その選択の力が,きっと警戒音や化学的なシグナルによる警報システムを生み出すのだろう。そうした種は,自分達のコロニーと他のコロニーを区別するために,自分たちの体のにおいを作り出す。」
第五の段階は,コロニー間のグループ選択が,さらに高度な真社会性の種のライフサイクルや階級制度を形成する。
「最後のふたつの段階が昆虫などの無脊椎動物でしか起きないことを考えると,ヒトはどうやってみずからのユニークで文化にもとづく社会的条件に到達したのだろうか?」
と,ここまでが「われわれはどこから来たのか」への答だとすると,ここからが,「われわれは何者か」への解答となる。しかし,ここは,既に,文化的,言語的に,かなり議論が尽くされてきている部分でもある。著者は,その背景となる「社会的知能」について,
「第一に,…いろいろなできごとが起きている際に,他者と同じ対象に関心を払う傾向をもつようになった…。第二に,共通の目標を達成しようとして(またはそれを企てる他者を妨害しようとして)協働するのに必要な高レベルの意識を獲得した。そして第三に『心の理論』,すなわち自分の心の状態を他者も共有できるという認識を手に入れた。」
この進歩を出アフリカ以前に手に入れた,と。この後,文化,言語,倫理,宗教と,人間としての特性をフォローし,「われわれはどこへ行くか(どこへ向かうべきでないか)」について,
「人類は地球で孤独であり,それゆえ人類はひとつの種として我々の行動に全責任を負っている」
として,こう締めくくる。
「地球二二世紀になるまでには,われわれが望めば,人類にとって永遠の楽園になるか,少なくともその力強い兆しを見せうる。」
と。それがなるかならぬか,我々にかかっている,と言いたげである。
さて,本書は,主流の「血縁選択」(著者は,自説を「マルチレベルの自然選択」と呼んでいる)への批判で成り立っている。著者は,その理論は,
「多数の競合する仮説を考慮していない」
と鋭く批判している。ところが,本書の巻末で解説している巌佐庸(九州大学大学院理学研究院)教授は,
「血縁淘汰の否定は私には受け入れられない」
という立場から,著者の主張を,
「人を惑わす言説」
といい,「血縁淘汰によってなされている…と考えるべきだ」と,まるで,異端審問官のような口ぶりであり,素人の僕には是非を判断することはできないにしても,「血縁淘汰」説も,著者の説も,アインシュタインの相対性理論がそうであるように,真理ではなく,仮説にすぎないということを忘れて,血迷っているとしか言いようのない口ぶりには,開いた口がふさがらない。
参考文献;
エドワード・O. ウィルソン『人類はどこから来て,どこへ行くのか』(化学同人) |
|
アイデンティティ |
|
マーク・L・サビカス『キャリア・カウンセリング理論』を読む。

以前に,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/433426636.html
で触れた,平木典子先生の「ライフキャリア・カウンセリングへの道ーワーク・ライフ・バランスとは何だろう?」で出た,サビカスの近著である。
本書の問題意識は,「日本の読者の皆様へ」で,明確に示されている。いまや,
「学校を卒業して就職すること,あるいは仕事から次の仕事に移動することは,会社に依存するというよりは,個人に依存する度合いが大きくなっています。」
それが,ポストモダン社会の中核的な特色であり,
「人生コースが個別化される」
のだという。その時代には,ひとりひとりに,
「人生を個別に設計すること」
が求められる。本書で示すモデルや方法は,「一人ひとりが自叙伝的な物語と職業の可能性との間に意味あるリンクを構成するために」役立ち,「一貫性と継続性のある物語の構成は,自らの方向を決定し,個人的に責任を負うための内なるガイドを提供すること」になると,書く。
この背景にあるのは,時代の大きな変化である。著者はこう書く。
「いまでもフルタイム雇用が主要な仕事の形態であり,長期のキャリアも存在しているが,階層体系的な組織が壊れつつあるのに続いて,臨時の仕事やパートタイムの仕事がますます常態化しつつある。デジタル革命によって,組織はマーケット状況に合わせてより小さく,よりスマートに,より機敏になることが要求されている。」
「組織は,標準的な仕事に非標準的な契約を混入させている。仕事は消えていないが,雇用数は減らすという手法によって,プロジェクトの開始と共に始り,製品の完成と共に終了する契約に変えることによって,雇用形態が変化している。」
「33歳から38歳までの間に新しい就職先に就いた人の39%が,1年以内に離職し,70%が5年以内に離職している。労働者の4人に1人が,現在の雇用者の下で働き出してまだ1年もたっていない…。」
「組織の中核で働いている労働者にとってさえ,確実で予測できるキャリアの筋道は消えつつある。確立された路線,伝統的な筋書きは消えつつある。今日の多くの労働者は,安定した雇用に基礎を持つ堅実な生活を発展させるのではなく,生涯を通じた学習を通じて,あるいは誰かが言ったように『生きるための学習』を通じて,柔軟性のある能力を維持していかなくてはならない。安定した生活条件のなかで計画を立ててキャリアを発展させるのではなく,変化しつつある環境の中で,可能性を見いだしながら,キャリアをうまく管理していかなくてはならない。」
それは,仕事が非標準化され,そのことによって,人生も,非標準化され,
「それぞれが行う仕事によって自分の安定した居場所をこの世の中に見出すことができなくなっている」。こういう時代に必要なのは,
「企業の提供する物語を生きるのではなく,自分自身のストーリーの著者になり,ポストモダン世界における転職の舵を自分で取らなければならない。」
であり,
人生コースの個別化,
とはそういう意味である。それは,従来のように,
「人の内に備わっている中核となる自己を実現する」
という近代的考え方ではなく,
「自己の構成は一生を通じたプロジェクト」
なのであり,そういう新たな時代のカウンセリングは,
「人生の職業を見つけるという課題から人生の職業を創造する方法にカウンセリングの方向を転換させるためには,人生設計に取り組み,人生において仕事をどのように用いるかを決定する学問を必要とする。」
ものでなくてはならない。本書は,それを実例と共に,提示する,
キャリア構成理論
なのである(それに基づくカウンセリングを「構成主義的キャリア・カウンセリング」と呼ぶ)。キャリア構成理論においては,
「アイデンティティは,人が社会的役割との関係で自分自身をどのように考えているかということを意味する。役割における自己,あるいは役割アイデンティティとは,社会的状況または環境的文脈において,社会的に構成された自己の定義である。アイデンティティは,自己を社会的文脈の中に位置づけることによって,自己をスキーマとして位置づける。」
とされる。人がキャリア・カウンセリングを求めるのは,
「大きな職業上の発達課題,重要な職業の転機,あるいは深刻なワーク・トラウマに適応する必要が生じたとき」
である。そのとき,アイデンティティが揺らいだり,新しい適応には不十分になる。その解決ないしは,困難に適応するために,
アイデンティティを作り替える,
必要がある。それは,
アイデンティティにおけるナラティブのプロセス作業が必要,
と,本書では考える。なぜなら,
「アイデンティティはナラティブによって形づくられ,ナラティブのなかで表現される」
からである。そのナラティブのプロセス作業は,
「人が自分は変わりつつあるが誰になりつつあるかわからない,と感じるときに起こる。社会的な場に自分を再配置しようとするとき,人は,同一性を維持しながらも変化の理由を与えるナラティブ・アイデンティティを著述することが必要になる。人は,ナラティブの修正を行うことによって,アイデンティティの同一性の問題を解決し,いまあるズレの問題を解消するのである。」
そのナラティブは,重要な出来事やエピソードについての小さなストーリー(マイクロナラティブ)を,一つの織物に織り上げて,大きなストーリー(マクロナラティブ)が構成される。このプロセス作業,
アイデンティティ・ワーク
は,
自伝作業,
と呼ばれるが,この自伝的語りを通して,
「個々人が自己を参照する能力」
を再確認することでもある。現在の困難を,自分の伝記のなかに位置づけることで,その答が,
自分のなかにあること,
に気付いていくことになる。この間の機微は,次の言葉が象徴的に言い表している。
「構成主義的カウンセリングとは,語りを通じてキャリアを共に構成する関係のことである。ストーリーは,ナラティブ・アイデンティティの構成のための,そして複雑な社会的相互作用の中からキャリア・テーマを浮かび上がらせるための建築ツールとして働く。クライエントが自らのストーリーを語ると,そのストーリーはより現実的なものとして感じられるようになる。より多くのストーリーを語ればかたるほど,そのストーリーは,さらに現実的なものとなる。『自分』を眺めれば眺めるほど,クライエントは自身の自己概念をさらに発達させていく。ストーリーを語ることによってクライエントは,自分が自分自身をどのように思っているかを結晶化させる。…クライエント自身が自分とカウンセラーの間にある空間に出現する自分のライフテーマを聞くからである。」
そのとき,カウンセラーがするのは,
「(クライエントの語った中で)それまで語ってきたことの言外の意味を理解するよう支援することが大切である。」
と。本書では,キャリア構成のためのナラティブ・カウンセリングの進め方を,具体的かつ詳細に展開するが,それは,
「あなたがキャリアを構成していくうえで,私はどのようにお役に立てますか?」
という,「クライエントの自己呈示のスタイルや感情表現,他者との関係の結び方を観察する」という意図的な質問から始まる。そして,キャリアストーリー・インタビューで,
子供の頃に憧れ,尊敬していた人物
定期的に読んでいる雑誌
好きな本や映画のストーリー
好きな格言
幼少期の最初の思い出
という5つの質問をする。その上で,キャリアストーリー・アセスメントの8の手順でカウンセリングを進めていく。それは,
「クライエントのマイクロナラティブを,クライエントが過去を理解し,現在の状況を定義し,次に何をすべきかを見通すための包括的で一貫性のあるアイデンティティ・ナラティブへと再構成するための概念的枠組みを提供する」
ものでなければならない。それには,そのナラティブは,
クライエントの現在の経験を同化するものでなければならないし,
クライエントがカウンセリングの場に持ち込んだストーリーにあるズレを,一貫性のある方法で埋める新たな材料を提供するものでなくてはならないし,
新しい視点と深い意味をもつマクロナラティブによって,クライエントを元気づけ,行動に向かわせるものでなくてはならない。
8つの手順は,
①カウンセリングを訪れた目標の再確認し,キャリア全体を貫く(キャリア・アーク)パターンを認識すること。
②幼少期の思い出のなかにある特徴的な出来事を特定する。それをアナロジーに,いまの状況が理解できる。
③幼少期の思い出で提起された問題に対するクライエントの解決を明らかにし,現在の問題へのローモデルとする。
④雑誌,テレビ等々で明らかにされた教育的および職業的興味をアセスメントし,労働や職場への好みを炙り出す。
⑤クライエントの好みの場での自己の可能性をどのように活動させるか,場と自己の統合を図る(筋書きと台本)。
⑥クライエントの指針となる言葉を問うことで,自分の中で,何が行動を呼び起こすかを明らかにする。
⑦クライエントのめざす職場,学校を考える。
⑧当初の来訪の,何がクライエントを前へ進めさせるのをためらわせていたかを明確にする。
である。これを通して,カウンセラーは,「小さなストーリーを大きなナラティブへと変容させる」ライフレポートを描く。最終的には,そのカウンセラーのレポートを,クライエント自身が,自分が,
「生きるに値するものとするように,修正する」
のである。著者の次の言葉が印象的である。
「クライエントの言語の限界はクライエントの世界の限界である。クライエントの言葉を作り直すことによって,クライエントの世界を作り直すことができる」
まさに,ヴィトゲンシュタインの,
もっている言葉によって,見える世界が違う,
である。
だから,カウンセリングを通してしたことは,クライエントの人生を,語り直すことで,自分を再確認し,新たな言葉で,自分の意味と価値を定義し直した,ということである。
僕自身,読みながら,自分のキャリアを語り直してみた。手順が,マニュアルのようにすっきりしていない難はあるが,随所で自己発見があった。残念ながら,こういう時代を見据えたカウンセリング理論が,日本では生まれないだろうという絶望をも,しかし同時に感じていた。
参考文献;
マーク・L・サビカス『キャリア・カウンセリング理論』(福村出版) |
|
時間感覚 |
|
一川誠『大人の時間はなぜ短いのか』を読む。

本書は,
「物理的には同じ時間が経過しているのに,感じられる時間の長さが異なるのはなぜか」
に答えるのを目的の一つとしている,と冒頭で述べる。しかし,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416479966.html
で触れた,
ジャネーの法則
つまり,「感じられる時間の長さは,年齢と反比例の関係にある」という仮説を,
「同じ年齢でも人によって,年齢による時間の感じ方の変化は異なる。」
「同じ個人でも,色々な要因によって,感じられる時間の長さは変わってしまう」
ということから,「年齢は感じられる時間の長さを決定する唯一の要因ではない」として,一蹴してしまう。
では,何によって,時間の長さは変わるのか。著者はいくつか例示を挙げる(ただ,完全にはリストアップされていない,と断っている)。
「感じられる時間と物理的時間の進み方の違いは,心的時計,または内的時計(inner
clock)と実際の時計(物理的時計)の時間の進み方の違いとして考えることができる。(中略)この心的時計の進み方は身体的および心的な活性度に対応していると考えられる。つまり,身体や心が活性化しているときや代謝が激しいときは,心的時計が速く進み,場合によっては物理的時間よりも速くなる。他方,代謝が落ちているときは,心的時計がゆっくり進む。」
そこから,物理的時間の長さに比して,感じられる時間が短くなる理由としては,
第一は,加齢に伴う身体的代謝の低下。身体的代謝が落ちると,,それに伴って,心的時計の進み方も遅くなる。もちろん,個人差もあるし,同じ人でも,朝方は,心的時計がゆっくり進み,午後に向けて早くなっていく,あるいは発熱していると代謝が激しいので,時間の進み方がゆっくりになる,といった1日のうちでも違いがある。
第二は,感情状態によって,たとえば,恐怖を感じていると,時間の進み方がゆっくりと感じたり,交通事故の時など,緊張した状態だと,心的時間が速く進み,目の前の出来事がスローモーションのように見える,ということが起きる。
第三は,時間経過に注意が向くほど,時間が長く感じられる。著者は,これについて,
「時間の経過に注意が向けられるほど,時間経過が多くの部分に分節化され,その分節化された時間帯の数が多いほど,時間が長く感じられるとする仮説もある。時間の経過に注意を向ける回数に対応して,心的時間の目盛の数が増えるのに,一目盛あたりの針の進む速さはいつも同じであるため,時間の進行がゆっくり感じられるのかもしれない。」
と述べる。
第四は,空間感覚が時間の進み方をゆっくりにさせる。大きいと感じる場所での時間の方が狭いと感じさせる場所でより,時間が長く感じる,というのである。
第五は,映像のスローモーション再生の時間間隔は,通常再生より,短く感じる。
第六は,同じ長さの時間でも,その間に,刺激が多いほど,長い時間と感じる。それは,出来事が次々と起きる方が,時間を長く感じる,ということにあらわれる。
第七は,難しい課題に取り組んでいるほど,時間を短く感じる。これは日常感覚でもよくわかる。
第八は,動作ペースも時間に影響する。速いペースで歩くと,時間を短く感じる。
第九は,リラックスした状態だと,経過時間が過小評価(実際よりゆっくり進み)され,心的活性の程度が著しくなるにつれて,評価する時間が長くなる(時間の進み方が速くなる),傾向がある
第十は,加齢に伴い,心的時計がゆっくり進む。それは,
「身体運動能力が低下して,若いころであれば一日でできたことがこなせなくなる。このことも,加齢に伴い,一年や一ヵ月といった時間が思いのほか速くすぎるように感じられる(時間の長さが短く評価される)のに関係するものと推察される」
ためのようだ。著者は,加齢に伴う時間評価を,産出法(「無響空間」で,三分経ったと感じるところでストップさせる)によって実験したところ,
「年をとるほど,同じ時間をより短く感じる(時間があっという間に過ぎるように感じる)傾向があった。具体的には三分間をターゲットと考えた場合,2〜4歳年を取るごとに,評価時間が一秒長くなるという結論が出た。」
と,これは,結果として,ジャネーの法則を追認した形になる。ただし,
「この加齢効果の基礎にあるメカニズムはまだ特定されていない」
という。当然個人差はある。
個人の精神テンポは,歩くペースや会話の間合いの長さと正の相関がある。これは,年を経ても変わらないが,作業ペースが,自分のテンポと異なる場合,心拍数が上昇し,ストレスになる。或いは,正確分類で,タイプAの人は,時間に厳格であろうとするため,その分体に負荷がかかり,循環器系の疾患の発生と有意な関係にある,と言われている。自分の精神テンポを知ることは,大事かもしれない。それを測る簡単な方法は,
10回のタッビング(机を指で叩く)
に何秒かかったかを調べるといい。平均的には,一回当たりのタッビングはる0.4〜0.9秒の範囲に入る人が多いようである。
参考文献;
一川誠『大人の時間はなぜ短いのか』(集英社新書)
岸根卓郎『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」 』(PHP) |
|
古寺巡礼 |
|
和辻哲郎『古寺巡礼』を読む。
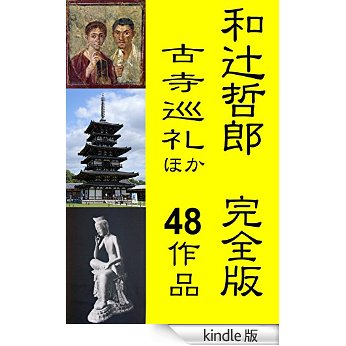
初版が,大正八年(1919)という年代を表しているのか,今と違い,諸仏にも,壁画にも,間近に対面し,矯めつ眇めつ出来ている,というのに,時代を感じる(改訂版になる,本書は,1947年)。
和辻については,敗戦後に書いた『鎖国―日本の悲劇』にあった,敗北によって,情けない姿をさらけ出した日本民族の,
科学的精神の欠如,
への反省のなかで,再三出てきた「世界的視圏」,特に「視圏」という言葉に,強く惹かれた記憶がある。その視線の射程の長さこそが,知的レベルを示す,というように受け止めた記憶がある。
本書は,戦後の改訂で,
「著者がこの書を書いて以来、日本美術史の研究はずっと進んでいるはずであるし、またその方面の著書も数多く現われている。この書がかつてつとめたような手引きの役目は、もう必要がなくなっていると思われる。著者自身も、もしそういう古美術の案内記をかくとすれば、すっかり内容の違ったものを作るであろう。つまりこの書は時勢おくれになっているはずなのである。にもかかわらずなおこの書が要求されるのは何ゆえであろうか。それを考えめぐらしているうちにふと思い当たったのは、この書のうちに今の著者がもはや持っていないもの、すなわち若さや情熱があるということであった。十年間の京都在住のうちに著者はいく度も新しい『古寺巡礼』の起稿を思わぬではなかったが、しかしそれを実現させる力はなかった。ということは、最初の場合のような若い情熱がもはや著者にはなくなっていたということなのである。」
と述べ,「文章は添えた部分よりも削った部分の方が多いと思うが、それは当時の気持ちを一層はっきりさせるためである。」と,意図を明確にしている。
この分野に疎いので,ここで書かれていることが,今日の常識とどの程度乖離しているかは読めない。しかし,昨年,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/413133184.html
で書いたように,たまたま奈良を訪れており,そのときの自分の印象と重ねながら,読んでいた。
聖林寺十一面観音に関する記述がいい。
「観世音菩薩は衆生をその困難から救う絶大の力と慈悲とを持っている。彼に救われるためには、ただ彼を念ずればいい。彼は境に応じて、時には仏身を現じ、時には梵天の身を現ずる。また時には人身をも現じ、時には獣身をさえも現ずる。そうして衆生を度脱し、衆生に無畏(むい)を施す。――かくのごとき菩薩はいかなる形貌を供えていなくてはならないか。まず第一にそれは人間離れのした、超人的な威厳を持っていなくてはならぬ。と同時に、最も人間らしい優しさや美しさを持っていなくてはならぬ。それは根本においては人でない。しかし人体をかりて現われることによって、人体を神的な清浄と美とに高めるのである。儀規(ぎき)は左手に澡瓶(そうへい)を把ることや頭上の諸面が菩薩面・瞋面(しんめん)・大笑面等であることなどを定めているが、しかしそれは幻像の重大な部分ではない。頭上の面はただ宝冠のごとく見えさえすればいい。左手の瓶もただ姿勢の変化のために役立てば結構である。重大なのはやはり超人らしさと人間らしさとの結合であって、そこに作者の幻想の飛翔得る余地があるのである。
かくてわが十一面観音は、幾多の経典や幾多の仏像によって培われて来た、永い、深い、そうしてまた自由な、構想力の活動の結晶なのである。そこにはインドの限りなくほしいままな神話の痕跡も認められる。半裸の人体に清浄や美を看取することは、もと極東の民族の気質にはなかったであろう。またそこには抽象的な空想のなかへ写実の美を注ぎ込んだガンダーラ人の心も認められる。あのような肉づけの微妙さと確かさ、あのような衣のひだの真に迫った美しさ、それは極東の美術の伝統にはなかった。また沙海のほとりに住んで雪山の彼方かなたに地上の楽園を望んだ中央アジアの民の、烈しい憧憬の心も認められる。写実であって、しかも人間以上のものを現わす強い理想芸術の香気は、怪物のごとき沙漠の脅迫と離して考えることができぬ。さらにまた、極東における文化の絶頂、諸文化融合の鎔炉、あらゆるものを豊満のうちに生かし切ろうとした大唐の気分は、全身を濃い雰囲気のごとくに包んでいる。それは異国情調を単に異国情調に終わらしめない。憧憬を単に憧憬に終わらしめない。人の心を奥底から掘り返し、人の体を中核にまで突き入り、そこにつかまれた人間の存在の神秘を、一挙にして一つの形像に結晶せしめようとしたのである。」
その上で,
「このような偉大な芸術の作家が日本人であったかどうかは記録されてはいない。しかし唐の融合文化のうちに生まれた人も、養われた人も、黄海を越えてわが風光明媚な内海にはいって来た時に、何らか心情の変移するのを感じないであろうか。漠々たる黄土の大陸と十六の少女のように可憐な大和の山水と、その相違は何らか気分の転換を惹起しないであろうか。そこに変化を認めるならば、作家の心眼に映ずる幻像にもそこばくの変化を認めずばなるまい。たとえば顔面の表情が、大陸らしいボーッとしたところを失って、こまやかに、幾分鋭くなっているごときは、その証拠と見るわけに行かないだろうか。われわれは聖林寺十一面観音の前に立つとき、この像がわれわれの国土にあって幻視せられたものであることを直接に感ずる。その幻視は作者の気禀と離し難いが、われわれはその気禀にもある秘めやかな親しみを感じないではいられない。その感じを細部にわたって説明することは容易でないが、とにかく唐の遺物に対して感ずる少しばかりの他人らしさは、この像の前では全然感じないのである。」
こういうのを視圏と言いたい。しかし,この視圏をもってしても,あの狂気の時代は止められなかったのである。
「きれの長い、半ば閉じた眼、厚ぼったい瞼まぶた、ふくよかな唇、鋭くない鼻、――すべてわれわれが見慣れた形相の理想化であって、異国人らしいあともなければ、また超人を現わす特殊な相好があるわけでもない。しかもそこには神々しい威厳と、人間のものならぬ美しさとが現わされている。薄く開かれた瞼の間からのぞくのは、人の心と運命とを見とおす観自在の眼(まなこ)である。豊かに結ばれた唇には、刀刃(とうじん)の堅きを段々に壊(やぶ)り、風濤洪水(ふうとうこうずい)の暴力を和やかに鎮(しず)むる無限の力強さがある。円く肉づいた頬は、肉感性の幸福を暗示するどころか、人間の淫欲を抑滅し尽くそうとするほどに気高い。これらの相好が黒漆(こくしつ)の地に浮かんだほのかな金色に輝いているところを見ると、われわれは否応なしに感じさせられる、確かにこれは観音の顔であって、人の顔ではない。
この顔をうけて立つ豊かな肉体も、観音らしい気高さを欠かない。それはあらわな肌が黒と金に輝いているためばかりではない。肉づけは豊満でありながら、肥満の感じを与えない。四肢のしなやかさは柔らかい衣の皺にも腕や手の円さにも十分現わされていながら、しかもその底に強剛な意力のひらめきを持っている。ことにこの重々しかるべき五体は、重力の法則を超越するかのようにいかにも軽やかな、浮現せるごとき趣を見せている。これらのことがすべて気高さの印象の素因なのである。
かすかな大気の流れが観音の前面にやや下方から突き当たって、ゆるやかに後ろの方へと流れて行く、――その心持ちは体にまといついた衣の皺の流れ工合で明らかに現わされている。それは観音の出現が虚空での出来事であり、また運動と離し難いものであるために、定石として試みられる手法であろうが、しかしそれがこの像ほどに成功していれば、体全体に地上のものならぬ貴さを加えるように思われる。
肩より胸、あるいは腰のあたりをめぐって、腕から足に垂れる天衣の工合も、体を取り巻く曲線装飾として、あるいは肩や腕の触覚を暗示する微妙な補助手段として、きわめて成功したものである。左右の腕の位置の変化は、天衣の左右整斉とからみあって、体全体に、流るるごとく自由な、そうして均勢を失わない、快いリズムをあたえている。
横からながめるとさらに新しい驚きがわれわれに迫ってくる。肩から胴へ、腰から脚へと流れ下る肉づけの確かさ、力強さ。またその釣り合いの微妙な美しさ。これこそ真に写実の何であるかを知っている巨腕の製作である。われわれは観音像に接するときその写実的成功のいかんを最初に問題としはしない。にもかかわらずそこに浅薄な写実やあらわな不自然が認められると、その像の神々しさも美しさもことごとく崩れ去るように感ずる。だからこの種の像にとっては写実的透徹は必須の条件なのである。そのことをこの像ははっきりと示している。」
ここまで書ききれる目と手を憧憬するしかない。その後,こんなエピソードを綴る。
「しかしこの偉大な作品も五十年ほど前には路傍にころがしてあったという。これは人から伝え聞いた話で、どれほど確実であるかはわからないが、もとこの像は三輪山の神宮寺の本尊であって、明治維新の神仏分離の際に、古神道の権威におされて、路傍に放棄せられるという悲運に逢った。この放逐せられた偶像を自分の手に引き取ろうとする篤志家は、その界隈にはなかった。そこで幾日も幾日も、この気高い観音は、埃にまみれて雑草のなかに横たわっていた。ある日偶然に、聖林寺という小さい真宗寺の住職がそこを通りかかって、これはもったいない、誰も拾い手がないのなら拙僧がお守をいたそう、と言って自分の寺へ運んで行った、というのである。」
廃仏毀釈の狂気が,興福寺をほぼ廃墟と化さしめた,その流れの中である。時代が,個々の視圏を押し流す奔流になったときの怖さを示す。
あるいは,薬師寺の薬師如来について,
「この本尊の雄大で豊麗な、柔らかさと強さとの抱擁し合った、円満そのもののような美しい姿は、(中略)それはわれわれがギリシア彫刻を見て感ずるあの人体の美しさではない。ギリシア彫刻は人間の願望の最高の反映としての理想的な美しさを現わしているが、ここには彼岸の願望を反映する超絶的なある者が人の姿をかりて現われているのである。現世を仮幻とし真実の生をその奥に認める宗教的な心情から、絶対境の具体的な象徴が生まれなくてはならなかったとすれば、このように超人間的な香気を強くするのは避け難いことであったろう。その心持ちはさらに頭部の美において著しい。その顔は瞼の重い、鼻のひろい、輪郭の比較的に不鮮明な、蒙古種独特の骨相を持ってはいるが、しかしその気品と威厳とにおいてはどんな人種の顔にも劣らない。……あの頬の奇妙な円さ、豊満な肉の言い難いしまり方、――肉団であるべきはずの顔には、無限の慈悲と聡明と威厳とが浮かび出ているのである。あのわずかに見開いたきれの長い眼には、大悲の涙がたたえられているように感じられる。あの頬と唇と顎とに光るとろりとした光のうちにも、無量の慧智えいちと意力とが感じられる。確かにこれは人間の顔でない。その美しさも人間以上の美しさである。
しかしこの美を生み出したものは、依然として、写実を乗り越すほどに写実に秀でた芸術家の精神であった。彼らは下から人体を形造ることに練達した後に、初めて上から超絶者の姿を造る過程を会得したのであろう。自然の美を深くつかみ得るものでなければ、――またそのつかんだ美を鋭敏に表現し得るものでなければ、内に渦巻いている想念を結晶させてそれに適当な形を与えることはできまい。もとよりこの作は模範のないところに突如として造られたのではない。その想念の結晶も初発的のものとは言えない。しかし模範さえあれば容易にこの種の傑作が造り出されるわけではないのである。これほどの製作をなし得る芸術家は、たとい目の前に千百の模範を控えているにしても、なお自分の目をもって美をつかみ、自らの情熱によって想念を結晶させたであろう。ローマ時代のギリシア彫刻の模作は、いかに巧妙であってもなお中心の生気を欠き表面の新鮮さを失っている。そのような鈍さはこの薬師如来のどこにも現われていない。これは今生まれたばかりのように新鮮なのである。」
と,像と像の向こうの作り手の精神にまで踏み込む。あるいは,東院堂の聖観音についてでも,
「美しい荘厳な顔である。力強い雄大な肢体である。仏教美術の偉大性がここにあらわにされている。底知れぬ深味を感じさせるような何ともいえない古銅の色。その銅のつややかな肌がふっくりと盛りあがっているあの気高い胸。堂々たる左右の手。衣文につつまれた清らかな下肢。それらはまさしく人の姿に人間以上の威厳を表現したものである。しかもそれは、人体の写実としても、一点の非の打ちどころがない。わたくしはきのう聖林寺の観音の写実的な確かさに感服したが、しかしこの像の前にあるときには、聖林寺の観音何するものぞという気がする。もとよりこの写実は、近代的な、個性を重んずる写生と同じではない。一個の人を写さずして人間そのものを写すのである。芸術の一流派としての写実的傾向ではなくして芸術の本質としての写実なのである。この像のどの点をとってみても、そこに人体を見る眼の不足を思わせるものはない。すべてが透徹した眼で見られ、その見られたものが自由な手腕によって表現せられている。がその写実も、あらゆる偉大な古典的芸術におけるごとく、さらに深いある者を表現するための手段にほかならない。もし近代の傑作が一個の人を写して人間そのものを示現しているといえるならば、この種の古典的傑作は人間そのものを写して神を示現しているといえるであろう。だからあの肩から胸への力強いうねりや、腕と手の美しい円さや、すべて最も人らしい形のうちに、無限の力の神秘を現わしているのである。」
と,作り手の心映えを通して,その時代の精神にまで透徹させていく。
しかし,本書の魅力は,薀蓄を語る部分ではなく,天平伎楽面についての,
「そのときH氏が、その仮面をとって自分の顔の上につけた。この所作によって仮面は突然に異様な生気を帯びはじめた。ことに仮面をかぶったH氏が少しくその首を動かしてみたとき、顔面の表情が自由に動き出したかと思われるような、強い効果があった。わたくしは予期しなかったこの印象に圧せられて、思わず驚異の眼をみはった。
仮面を畳の上に横たえ、または手にとって自分の膝の上に置いた時には、それはその本来あるべき所にあるのではない。われわれはこれまで仮面をその作られた目的から放して、それだけで独立したものとして観察するに慣れていたのである。普通人の顔の四倍もありそうなその仮面を、人体と結びつけて想像することは、この驚異の瞬間まではわたくしには不可能であった。しかしさてこの仮面が、仮面としてそのあるべき所に置かれて見ると、そのばかばかしい大きさは少しも大き過ぎはしない。むしろその大きさのゆえに人が仮面をつけたのでなくして、芸術的に造られた一つの顔が人体を獲得した、と言っていいような、近代人の想像をはずれた、おもしろい印象が作り出されるのである。ここではじめてわたくしは、仮面を何ゆえに大きくしたかを了解した。そうして、ギリシアの劇の仮面も同じくらいな大きさであったことを思い出し、この種の仮面の効用と大きさとの間に必然の関係のあることに思い到ったのである。」
という,著者の感覚的な印象にあるように思う。たとえば,中宮寺半跏像についての,
「この像は本来観音像であるのか弥勒像であるのか知らないが、その与える印象はいかにも聖女と呼ぶのがふさわしい。しかしこれは聖母ではない。母であるとともに処女であるマリアの像の美しさには、母の慈愛と処女の清らかさとの結晶によって『女』を浄化し透明にした趣があるが、しかしゴシック彫刻におけるように特に母の姿となっている場合もあれば、また文芸復興期の絵画におけるごとく女としての美しさを強調した場合もある。それに従って聖母像は救い主の母たる威厳を現わすこともあれば、また浄化されたヴィナスの美を現わすこともある。しかしこの聖女は、およそ人間の、あるいは神の、『母』ではない。そのういういしさはあくまでも『処女』のものである。がまたその複雑な表情は、人間を知らない『処女』のものとも思えない。と言って『女』ではなおさらない。ヴィナスはいかに浄化されてもこの聖女にはなれない。しかもなおそこに女らしさがある。女らしい形でなければ現わせない優しさがある。では何であるか。――慈悲の権化である。人間心奥の慈悲の願望が、その求むるところを人体の形に結晶せしめたものである。」
という文章よりは,
「わたくしはかつてこの寺で、いかにもこの観音の侍者にふさわしい感じの尼僧を見たことがあった。それは十八九の色の白い、感じのこまやかな、物腰の柔らかい人であった。わたくしのつれていた子供が物珍しそうに熱心に廚子のなかをのぞき込んでいたので、それをさもかわいいらしくほほえみながらながめていたが、やがてきれいな声で、お嬢ちゃま観音さまはほんとうにまっ黒々でいらっしゃいますねえ、と言った。わたくしたちもほほえみ交わした。こんなに感じのいい尼さんは見たことがないと思った。――この日もあの尼僧に逢えるかと思っていたが、とうとう帰るまでその姿を見なかったので何となく物足りない気がした。」
という感想に,惹かれる。
それにしても,百年近く前の文章なのに,まだ,生き生きとした息吹を伝えるのは,文章のなせる業か,それとも,観ている仏像・伽藍の醸し出す文化的な変わらぬ厚みなのだろうか。
参考文献;
和辻哲郎『古寺巡礼』(kindle版)
菊池章太『阿修羅と大仏』(幻冬舎ルネッサンス新書) |
|
古田織部
|
|
諏訪勝則『古田織部 - 美の革命を起こした武家茶人』を読む。

本書の口絵に,茶室『燕庵(えんなん)』の内部,が載っている。そこに,
「薮内剣仲(妻は古田織部の妹)を祖とする茶道薮内流宗家に伝わる茶室,三条の客坐,台目の点前座,一畳の相伴席からなっている。三畳台目は織部好みである。織部の創意による『色紙窓』など,窓が10ヵ所あり,明かりのもたらす様々な効果を狙っている。右手に見える茶道口に竹を用いているのも,また織部好みである。」
と,記す。ちなみに,台目とは,畳一畳の四分の三の規格のことをいう,そうである。また,「三畳台目に通イ一畳付タルヲ織部格ト云也」と織部の弟子上田宗箇の上田流の茶書にはある,らしい。
筑前国博多の豪商茶人神屋宗湛が,織部の茶会に赴いた際,
「ウス茶ノ時ハセト茶碗ひみつ候也。ヘウケモノなり。」
と書いた。
「ここでの『ヘウケモノ』は,『ひずんでいる』『ひしゃげている』という意味で使用されている。」
と,著者は書き,織部の特徴を,
第一に,織部が茶の湯を伝授した弟子たちが錚々たる人物が名を連ねていること(徳川秀忠,黒田官兵衛,伊達政宗,毛利秀元,小堀遠州等々),
第二に,師の利休は商家出身だが,織部はれっきとした武将であり,信長,秀吉に仕えて,各地を転戦し,武功を挙げ,秀吉時代は,三万石を領したともされていること。一説には,秀吉が,利休相伝の茶の湯は町人の茶である,武家流,大名風に,改革せよ,と命じられたとの説もある。この大名茶の湯は,遠州流,石州流に引き継がれていく。
第三に,大坂夏の陣に際して,師利休と同じく,切腹させられていること。
と挙げる。イエズス会宣教師ロドリゲスは,『日本教会史』で,織部と目される数寄者について,
資質とすぐれた習性をもっていること,
果断で確固たる勇気をもっていること,
物事を見て,その調和を見つける判断力と鑑識眼をもっていること,
時と場合に応じて,その目的を達成するために新たな考案をすること,
大小の壺,釜,陶器,絵画について,見誤ることのない知識と,器物の等級を定める責任がある,
と記している,と言う。著者は,
「織部は師に忠実であるとともに,積極的に情報を入手し,斬新なアイデアで新たな世界を創造しようとしていたと思う。」
と書き,『利休居士伝書』の,
「数寄というは,違ってするが易のかかりなり。これ故に古織は能し。細川三斎は少しも違わで,結句それほどに名を得取り給わずという。」
の一文を引き,
「易(利休)は『数寄というのは,人と違ったことを創造するものである』と唱えた。織部はこの考え方に適合している。細川三斎はすことも教えを変えることがなかったので名を残すことができなかったと伝えている。なかなか面白い比較である。」
と。
その織部が,大坂方に内通したとの罪で,師利休同様,慶長二十年(1615)切腹させられる。
「利休の弟子と言われた山上宗二は,天正十八年(1590),秀吉の逆鱗に触れ,耳と鼻を削がれ,斬首されている。利休はその翌年に横死した。当代における茶の湯の名人と言われた三名が夜を去ったのである。」
織部の家財は没収され,名物「勢高肩衝」は徳川家のものとなった。その半年後,織部の息子重広は,「伏誅」される。つまり,惨殺されている。
著者は,織豊時代を代表する文化人,利休,秀次(豊臣秀次),織部の死に共通するものとして,三人の深く広い人脈を挙げる。
「大阪の陣は,徳川政権の永続を願う家康にとって,危険因子を取り除く総決算の事業であった。
織部の弟子は,豊臣・徳川方に関係なく存在し,その繋がりの広さと深さは確たるものであった。依然として豊臣恩顧の武将とも親しかった。もちろん文化的なつながりであって,政治的なものではない。しかし徳川政権にとって,そのネットワークは排除しておくべき危険因子であったと思われる。」
その視点でみるとき,秀次,利休も,同じ視界のなかに見えてくる。
「秀次は文化の庇護者として,公家社会や五山(臨済宗の頂点に立つ諸寺院)と深い繋がりをもっていた。…秀次は特に五山に対して,経済的に扶助し和漢聯句会の開催を支援するなど,五山文学の復興を企図し,掌握下に置いていた。幼いお拾(秀頼)に豊臣家を託したい秀吉にとって,秀次が築いたネットワークは潜在的な脅威であった。」
利休は,大友宗麟が,豊臣秀長から,
「公儀のことは私に、内々のことは宗易(利休)に」
と耳打ちされたほど,政権中枢にいた。しかし,天正十九年(1591)に秀長が病死し,そのバランスが崩れ,翌二月,切腹させられる。
「利休。秀次の追放を目の当たりにしてきた織部は,権力者によって葬り去られる運命を覚悟していたのではなかろうか。」
と,締めくくる。
参考文献;
諏訪勝則『古田織部 - 美の革命を起こした武家茶人』 (中公新書)
http://www.yabunouchi-ennan.or.jp/pc/contents25.html
http://www.kyobunka.or.jp/tearoom/part_01/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E9%87%8D%E7%84%B6 |
|
陣形 |
|
乃至政彦『戦国の陣形』を読む。
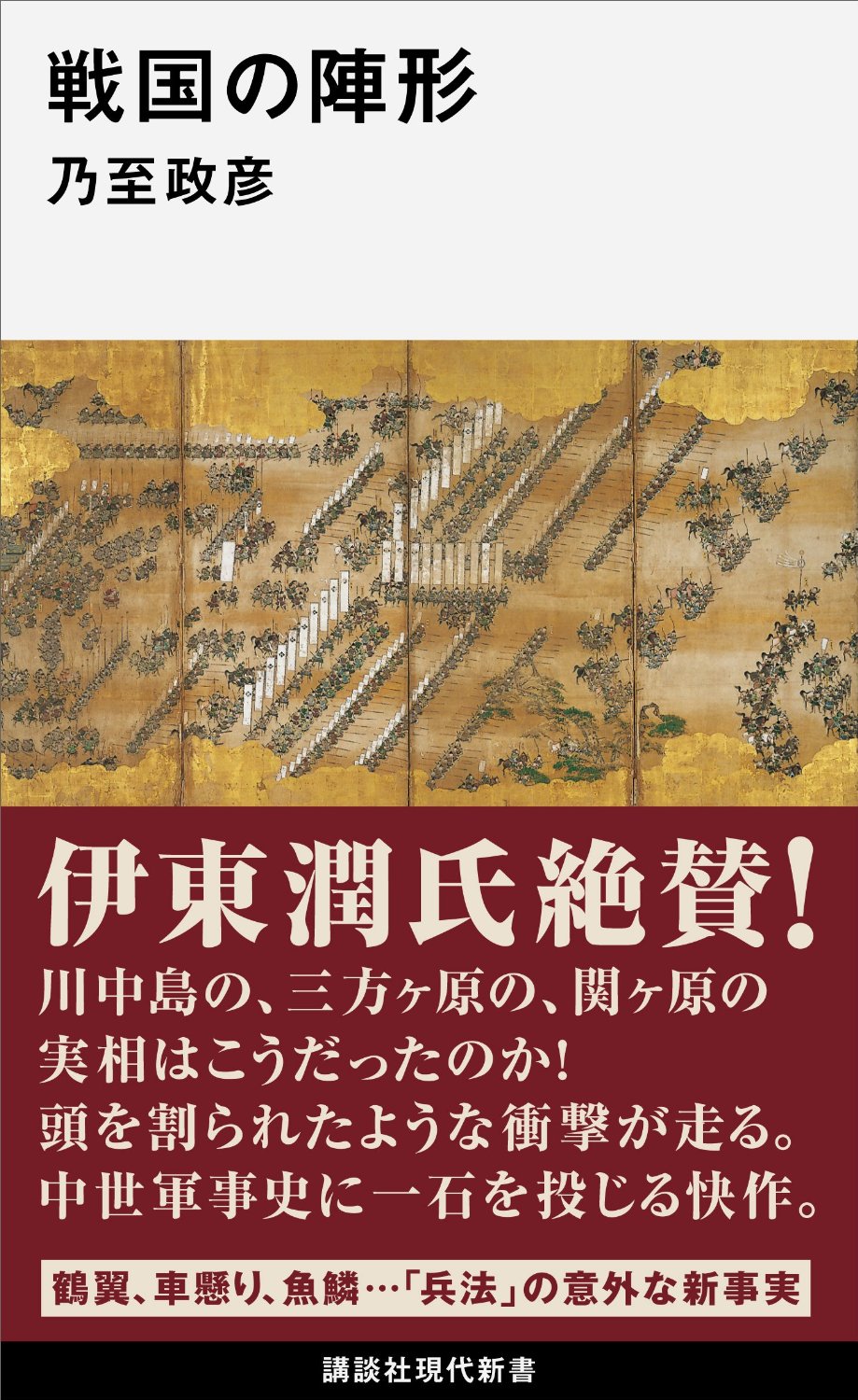
テレビや映画の合戦シーンやシミュレーションゲームに登場する「魚鱗陣」「鶴翼陣」の相性ルール等々に異和感を覚えた著者は,その理由を,
「戦国時代に長柄鎗や弓,鉄炮の兵種があったことは知っているが,兵種の性格や意義まで考えたことはあまりない」
という研究状況にある,と断じる。そして,
「『兵種とは何か』という素朴な問いかけ自体,中世軍事史ではほとんどなされてなく,兵種を考えるうえで必要不可欠であるはずの陣立・陣形についても基本的考察がない。」
そこで,「自からの手で陣形の変遷史をたどってみることにした」と。
本書は,意外とシステマチックだった律令制時代の,唐制を模倣した軍制から説き始め,武士勢力がどう陣形を考えていたかをたどる。エポックは,戦国時代である。そして大阪の陣で,終る。
陣形について,常識とされている「鶴翼」「魚鱗」について,
「中世から近世までの軍事史料を見てみると,…具体的な形状を示す同時代史料(いわゆる一次史料)に,こうした陣形の存在を裏付ける証拠がない」
という。そして,
「それらのものが登場するのは,戦国が終焉して何十年も経過した徳川時代になってから」
軍学者が言い出したものらしいのである。
「川中島で車懸りと鶴翼の衝突があり,三方ヶ原も鶴翼と魚鱗の激突図あったとされる。関ヶ原も鶴翼と魚鱗の対決だったという。」
その常識にある「鶴翼」「魚鱗」が,現実にどうであったかの根拠が薄いのである。
現実には,
「足利時代初頭,陣形はただの『言葉』でしかなかった。魚鱗の陣といえば,そういう形状があるのではなく,『魚の鱗がどういう形状だったか思い描いて,びっしり集まれ』と言う程度で,『ものの喩え』に過ぎなかったのではないか。言い換えれば『魚鱗の陣』とは『びっしり(集まれ)の陣』であり,『鶴翼の陣』も『ばっさり(広がれ)の陣』」
でしかなかったと断定する。つまり,中世の武士は,「中国にあるらしい陣形」をあいまいに認識していただけで,実形まで把握していなかったということになる。いわば,言葉だけの陣形である。
それが,戦国期,戦国大名への権力集中に伴って軍事編成の変化が現れる。『甲陽軍鑑』には,武田が初めて陣形を本格的に設計し始めたことが載る。山本勘介が,「唐の軍法」である「諸葛孔明八陣」を研究し,信玄に提案したのである。たとえば,世に知られる武田の八陣というものがあるが,著者は,それは「諸葛孔明の八陣」「李善の八陣」「長良の八陣」を折衷し,打ち出したもので,
「勘介は晴信(信玄)に『その方は物の本,四五冊もよみたるか』と聞かれ,『一冊も読み申さず候』と八幡宮に誓文を立てた」
と,『甲陽軍鑑』にある程度で,
「すべてが冗談のような代物」
なのである。しかし晴信は,勘介の進言を入れ,
「陣形の単純素朴なルールとシステムを作り,それぞれの部隊が定型の陣形を実用できるようにした」
という。これが,
定型に基づく,日本初の陣形,
ということになる,と著者は言う。そして,その陣形による合戦の嚆矢を,武田に追い詰められていた村上義清と信玄の,
塩田原の合戦,
である。村上勢は,総大将・信玄を負傷させたのである。村上の戦法は,
二百騎の騎馬隊(勝敗がどうあれ「晴信討つべし」との念を強める「武篇の者共」)を編成,
これに
徒歩の鎗持ちを二百人つける。そのうち百人は長柄の鑓を武装,
さらに,
足軽二百人,うち百五十人を弓隊(矢を十本ずつ所持),五十人を鉄炮隊(1人玉薬を三つずつ所持),
という計六百人の臨時編成で,武田・村上の合戦が始まると,その脇から,義清自ら上記六百余で,武田旗本に殺到させた。
「はじめに弓隊百五十人が矢を放ち,次に鉄炮隊五十人が銃撃した。矢弾が尽きるとかれら足軽二百人は抜刀して切り込みをかけた。義清自身も間髪を入れず精鋭の騎馬隊二百騎と長柄隊百人に号令をかけ,晴信に太刀打ちせんと猛進した。」
お気づきだろうか。まさに,上杉謙信と武田信玄の川中島合戦に瓜二つである。越後に遁れた村上を庇護した謙信は,信玄討ち取りに特化した旗本を編成する。
騎馬100
長柄鎗100
弓100
鉄砲100
の編成である。
「ここに見えてくるのは,村上義清が切り開いた臨時の兵種別編成からなる五段隊形が,謙信に受け継がれて常備の戦術隊形となり,対抗する大名たちがこれを導入して,…その後畿内・西国にも伝播している。」
この隊形は,文禄の朝鮮侵略時にも,緒戦段階では威力を発揮することになる。
さて,最後にひとつ。著者は隊形と陣形の区別を指摘していたが,関ヶ原で,東軍が赤坂に着いたとき,西軍は前進したが,霧が深かったため,二万五千は迂回して,駒野に布陣,主力は関ヶ原に布陣した。しかしその途中で小早川が離反し,あっけなく勝敗が決した,
こう著者は書く。しかし,これは,隊形を言っている。陣は,史料だけでなく,構造物の遺跡などをきちんと分析すれば,西軍の陣が強固な構造物を作っていたことがはっきりしているはずである。それを考慮に入れないで論ずるのは,はなはだ陣形を論ずる著者には似つかわしくない。
参考文献;
乃至政彦『戦国の陣形』(講談社現代新書) [Kindle版]
http://iwakuni-art-museum.org/collection/special/001.html
藤井尚夫『フィールドワーク関ヶ原合戦』(朝日新聞社) |
|
地球外生命 |
|
自然科学研究機構編『地球外生命 9の論点』を読む。
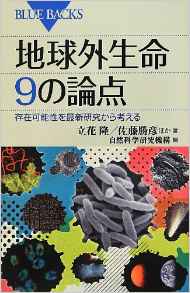
本書は,
自然科学研究機構の連続シンポジウム「宇宙に仲間はいるのか」の第一回目(2010年),
をベースに,地球外生命について,それぞれの立場から,9人の研究者が発言したが,それをもとに,「最新の成果も取り入れて」一冊の本にまとめたものである。内容は,
第Ⅰ部 地球外生命が射るとしたらそれはどのような生物か
論点1 極限生物に見る地球外生命の可能性(長沼毅)
論点2 光合成に見る地球の生命の絶妙さ(皆川淳)
第Ⅱ部 正命が誕生し,反映するには何が必要なのか
論点3 RNAワールド仮説が意味するもの(菅裕明)
論点4 正命は意外に簡単に誕生した(山岸明彦)
論点5 共生なくしてわれわれはなかった
第Ⅲ部 宇宙には生命誕生の条件はどれだけあるか
論点6 正命の材料は宇宙から来たのか(小林憲正)
論点7 世界初の星間アミノ酸検出への課題(大石雅寿)
第Ⅳ部 宇宙空間に生命を探す
論点8 太陽系内に生命の可能性を探す(佐々木晶)
論点9 宇宙には「地球」がたくさんある(田村元秀)
それに,
序論 「科学」になった地球外生命
を佐藤勝彦(自然科学研究機構長)東大名誉教授,
総説 いまわれわれはどのような地点にいるのか
を,立花隆が,まとめている。このタイトルを見ただけで,心がわくわく踊る。
序論の「科学になった」というのは,二人の先人の考え方から端を発している。ひとりは,アメリカの物理学者,フェルミ。彼の,
フェルミ推定,
によって,「知的生命体は必ず存在し,すでに何度も地球を訪れているはず」と,推定した。しかし,地球外生命体が存在する可能性の高さと一度もそれに遭遇していない事実とのギャップ,
フェルミのパラドックス,
に対する,科学者の答の出し方は,
①地球外生命体は既に地球に来ている(UFO伝説や人間わざと思えない古代遺跡等),
②地球外生命体はまだ地球に訪問できていない(星間距離,平均恒星間約3光年は克服できていない)
③地球外生命体は存在しない,
の三つ,と佐藤勝彦氏はまとめる。もう一人の科学者は,天文学者ドレイク。ドレイクは,
「直径26mの電波望遠鏡で,地球から約10光年離れたくじら座のタウ星とエリダヌス座のイプシロン星に向け,知的生命体が発信する電波信号をキャッチしようとのべ400時間に及ぶ観察を試みた。」
その,「地球外生命体からの通信探査」は,SETI(Search for Extra
terrestrial Intelligence)と名づけられ,ドレイクは,フェルミ推定から導き出した,
ドレイクの方程式,
を発表する。それは,
銀河系のなかで,地球外知的生命体による文明がどれだけあるか,を概算する公式である。佐藤氏は,
(公式の中にある)「問題はLです。」
Lは,高度な文明が存続する時間の長さ,である。電波通信技術を手にして,100年しかたっていない。そしてこの文明がどれだけ続くものか。立花氏は,前国立天文台長の海部宣男氏の発言を引用している。文明の寿命を一万年とすると,
「銀貨系内の文明の数は約1000個という答えが出ます。そこで,銀河系内に1000個の文明が均等にばらまかれているとします。すると,文明どうしの平均距離は1000光年となります。1000光年を光で通信するには,1000年かかります。どんなに文明が進んだとしても,1000光年という距離は,それを越えてであえるかどうかという点で非常にむずかしい問題です。」
と。だから佐藤氏は,
「このことは,我々人類の生き方にも関係してきます。つまり,知的生命体に出会いたいと思ったら,まずわれわれ自身が簡単に滅びないことです。」
と,意味深い発言をされている。さて,
地球外生命,
といっても,
そもそも生命とは何か,
その発生の仕組みは何か,
その発生条件は何か,
がわかっていなくては探しようはない。生命の定義は,
代謝,
自己複製,
外界との境界,
進化,
と定義されている。しかも,生命が存在するに必要な,
水が存在すること,
が必要である。
「惑星に水が存在するには,恒星から遠すぎて表面温度が低くなり過ぎない,逆に近すぎて表面温度が騠くなりすぎない」
という条件が必要になる。そういう生命の生存可能な領域を,
ハビタブルゾーン,
という。まさに,地球がそのど真ん中にある。その太陽系外惑星の数は,
2000個
を越えて,どんどん見つかっている。しかし,立花氏は,
「われわれがみれまでできたことは,きわめてプリミティブな方法(ドップラー法,トランジット法など)で,惑星がそこにあるということを発見したことだけで,バイオマーカーや文明マーカーの有無を云々できるようなレベルの解像度がある観測方法をもっていないのはもちろん,そのようなマーカーとして何があるかを議論するに十分な予備知識も持っていないのである。」
とまとめる。今やっているのは,関節観測であり,直截観測ができる望遠鏡の飛躍的解像度のアップには,まだ十年はかかる,と。
生命誕生については,地球自体に探そうとする,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/420205932.html
と地球外に探そうとする,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/423899201.html
とがあり,
地球外生命体については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/393613062.html
で(この著者の長沼毅氏は,本書の論点の著者でもある),太陽系外惑星探索については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163034.html
で,それぞれ触れた。
参考文献;
自然科学研究機構編『地球外生命 9の論点』 (講談社・ブルーバックス) |
|
対米路線 |
|
孫崎享『戦後史の正体』を読む。
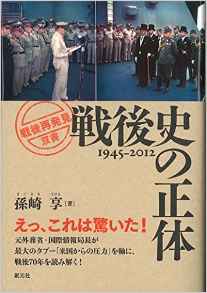
著者,孫崎享氏は,
「1966年に外務省に入り,…ソ連に5年,…イラクとイランにそれぞれ3年…,その間,東京では主として情報分野を歩き,情報分野のトップである国際情報局長もつとめた」
が,7年間の防衛大学校教授の間,戦後の日本外交しを研究する機会を得て,
「その中でくっきりと見えてきたのが,戦後の日本外交を動かしてきた最大の原動力は,米国から加えられる圧力と,それに対する『自主』路線と『追随』路線のせめぎ合い,相克だったということです。」
ということである。アメリカは,
「他の国をどう使うかをつねに考えています。当然,日本もその戦略のなかにふくまれます。(中略)
将棋の盤面を考えていただければよいと思います。米国は王将です。この王将を守り,相手の王将を取るためにすべての戦略が立てられます。米国にとって,日本は『歩』かもしれません。『桂馬』かもしれません。『銀』かもしれません。ときには『飛車』だといってチヤホヤしてくれるかもしれません。それは状況によって変わるのです。
しかしたとえどんなコマであっても,国際政治というゲームのなかで,米国という王将を守り,相手の王将を取るために利用されることに変りはありません。」
コマである日本の対処法は,2つである。
一つは,圧倒的に強い米国のいうとおりにしよう,そのなかで多くの利益を得よう,という追随路線,
もう一つは,日本独自の価値がある。どこまで自分の価値を貫けるか,それが外交だ,という自主路線,
著者自身は,後者の立場を取る,という。そして,
「戦後の日本外交は,米国に対する『追随』路線と『自主』路線の戦いでした」
と,さらに,
「『対米追随』路線と『自主』路線,もっと強い言葉でいえば,『対米従属』路線と『自主』路線,このふたつのあいだでどのような選択をするかが,つまりは戦後の日米外交だったといえます。」
といい,一つの例を示す。著者が駐イラン大使であったとき,イランのハタミ大統領訪日を計画し,あわせて,イランのアザデガン油田の開発権を得ることになった。推定埋蔵量260億バレルという世界最大規模の油田である。しかし当時イランと敵対的な関係にあったアメリカは,それ対して圧力をかけてきた。結果として,開発権を放棄することになる。その開発権は中国に渡る。イランのラフサンジャニ大統領は,著者に,こう言ったそうである。
「米国は馬鹿だ。日本に圧力をかければ,漁夫の利を得るのは中国とロシアだ。中国とロシアの立場を強くし,逆に同盟国である日本の立場を弱めてどうするのだ。」
しかし,
「多くの政治家が『対米追随』と『自主』のあいだで苦悩し,ときに『自主』路線を選択した。歴史を見れば,『自主』を選択した多くの政治家や官僚は排斥されています。ざっとみても,重光葵,芦田均,鳩山一郎,石橋湛山,田中角栄,細川護煕,鳩山由紀夫などがいます。意外かもしれませんが,竹下登,福田康夫も,おそらく排斥されたグループに入るでしょう。外務省,大蔵省,通産省などで自主路線を追求し,米国からの圧力をかけられた官僚は私の周辺にも数多くいます。」
と。そして,前記のアザデガン油田の開発をめぐっては,チェイニー副大統領みずから,先頭に立ち,開発権獲得に動いた日本人関係者をポストから排除している,という。
「日本の首相とか外相といった,自分と同じレベルの人物への圧力だけではありません。現場で動いていた人たちが,副大統領からの排斥の対象となっていたのです。
この事実を知ったとき,米国という国の凄さを感じました。」
その著者による,「1945−2012」とサブタイトルをつけた,本書は,
「米国からの圧力とそれへの抵抗を軸に」
「米国に対する『追随路線』と『自主路線』の対立という視点で」
戦後史全体をみようとするものである。その視点でみると,一種悪名高い,
岸信介,
も,自主路線の故に,政権を降りざるを得なくなった所以がよく見えてくる。逆に,戦後の対米従属路線を確定したものとして,
吉田茂,
の裏面が見え,田中角栄が,アメリカのから葬りさられたという視点から見れば,
三木武夫,
の別の顔が見えてくる。その意味では,最近の例でいえば,
鳩山由紀夫,
が,「最低でも(普天間を)県外」といったことで,よってたかって潰されたのが思い出される。このとき,急先鋒になった,大新聞社(朝日新聞と読売新聞)は,また,田中角栄追い落としの時にも,重要な世論作りを担っている。
著者は,ポイントを次の3点に絞って整理している。
①米国の対日政策は,あくまでも米国の利益のためにあります。日本の利益とつねに一致しているわけではありません。
②米国の対日政策は,米国の環境の変化によって大きく変わります。
③米国は自分の利益にもとづいて日本に様々な要求をします。それに立ち向かうのは大変なことです。しかし冷戦期のように,とにかく米国のいうことをきいていれば大丈夫だという時代はすでに20年前に畢っています。どんなに困難でも,日本の譲れない国益については主張し,米国の理解を得る必要があります。
日本の長期政権は,吉田茂,池田勇人,中曽根康弘,小泉純一郎,いずれも対米追随路線である。著者は,こういう。
「日本社会のなかに『自主派』の首相を引きずりおろし,『対米追随派』にすげかえるためのシステムがうめこまれている」
と。そのひとつは,検察。特捜部は,
「前身はGHQの指揮下にあった『隠匿退蔵物資事件捜査部』です。終戦直後,日本人が隠した『お宝』を探し出しGHQに差し出すのがその役目でした。したがって検察特捜部は,創設当時からどの組織よりも米国との密接な関係を維持していました。」
いまひとつは,報道機関。
「米国は政治を運営するなかでマスコミの役割を強く認識しています。占領期から今日まで,米国は日本の大手マスコミのなかに,『米国と特別な関係を持つ人びと』を育成してきました。…さらには外務省,防衛省,財務省,大学のなかにも,『米国と特別な関係をもつ人びと』が育成されています。」
だから,田中角栄の時も,小沢一郎の時も,鳩山由紀夫の時も,マスコミは連動して強力なキャンペーンを張り,追い落としに大いに役割を担っている。
しかし,著者は,カナダの例を,締めくくりに出す。
アメリカで北爆反対の演説をしたピアソン首相は,ジョンソン大統領につるしあられた。しかし,カナダ国民は,
外務省をピアソンビルと呼び,
国際空港を,トロント・ピアソン空港と名づける,
「米国へ毅然とものを言う」
という強いメッセージを込めている,と(恐らく願望を込めて)著者は言う。
参考文献;
孫崎享『戦後史の正体』(創元社) |
|
動物行動学 |
|
小林朋道『ヒトはなぜ拍手をするのか―動物行動学から見た人間』を読む。

「まえがき」で,動物行動学,人間比較行動学の著者は,
「私はこの本で,人間の日常的な生活のなかに見られる『動作』や『行動』『心理』』『感情』について頭に浮かぶものをいくつかあげ,進化の仕組みに照らして『なぜそうなのか』についてわかりやすく解説してみようと思う。解説といっても,科学的に十分証明された知見を並べたわけではなく,これまでの研究成果も踏まえた。現時点での私の推察をふんだんに入れた内容にした。」
と書き,「あとがき」で,
「私の大きな夢の一つは,動物行動学の知見をたよりに,現代の人間が抱えるさまざまな問題の改善につながる本質的なアイデアを提示することである。それらの問題の中には,『人間による自然の破壊』も含まれる。それは研究対象を広げることにもなり,ますます『専門性が薄い』と言われる場面も増えるかもしれない。でも,私は,自分自身は,人間と野生動物の両方を研究対象としているという意味での独自性を持った研究者でありたい,そうなりたいと思っている。」
と書いて,
「『なぜそうなのか』についの理解を深め,その知見をたよりに,この先,自然環境の保全も含めた現代の問題の改善について必要なことを考えてみたい。」
と結ぶ。この「なぜ」には,意味がある。著者は,「初期動物行動学の創始者の一人であるニコ・ティンバーゲン」が挙げた,
「動物行動学は,対象とする特定の動物行動について,『四つのなぜ』に答えるべく研究を進める学問である」
ところに根差している。「四つのなぜ」とは,
①「その行動は,どのような刺激によって,体内でどのような変化が起きて発現したのか」
②「その行動は,個体の生存や繁殖にどのように役立っているのか」
③「その行動は,その個体の成長の過程で,どのようにして発達してくるのか」
④「その行動は,それをまだ行わなかった祖先種の行動がどのように変化して,現在の種でおこなわれるようになったのか」
である。これを,それぞれ,
①至近的要因,
②究極的要因,
③発達的要因,
④系統進化的要因,
と呼び,いまでも,「動物行動を研究する者の指針」となっている,という。本書も,
「動作」
「行動」
「心理・感情」
について,「『四つのなぜ』を念頭に,人間は『なぜ,そう振舞うのか?』について解説している。」
書名になっている「ヒトはなぜ拍手をするのか」は,そのひとつとして,取り上げられているので,本書全体が,このテーマを展開しているわけではない。因みに,
「ヒトはなぜ拍手をするのか」
の問いは,実は,
「なぜ友好的な気持ちを示すとき拍手をするのか?」
と,微妙に変えられている(のが気になるが)。その答えは,
「拍手には,『ありがとう』『おめでとう』『そのとおりだ』『』がんばれよ』『よくやった』といったメッセージが込められている。これらのメッセージに共通しているのは,相手に対する友好や親和の気持ちである」
とし,
「このような相手に対する友好の気持ちと,拍手が作り出す音の特性―パチパチという音程が高い音―とがヒトの生得的な認知系の中で,無理なくつながるのではないかと推察している。」
と述べて,音程の持つ特性,,
「相手に有効的な信号を送ろうとするとき,知らず知らずのうちに声を高くする。(中略)相手に敵意を持っているときは,ヒトは声を低くする。」
と関連させて,
高音=親和
と関連づける。ただ,拍手と,どうつながるかは,突き詰められていない。で,関連する,
「なぜヒトは,リズム感があるのか?」
を追ってみると,
「リズムは,われわれの認知や運動に,切っても切れ離せない要素」
として,最近の脳生理学の研究経過から,
「脳内の情報処理では,一定の時間を単位として,外部からの聴覚や視覚の刺激が蓄積されて,まとめて情報処理され,また次の単位時間に,外部情報が蓄積・情報処理され,…という繰り返しが起こっているらしいのである。
また,動作についても,脳から筋肉への命令情報は,一定時間の“かたまり”になっており(そのかたまりのひとつは3秒であることが知られている),3秒なら3秒を単位として運動が構成されていることが明らかにされている。
これらのことは,『単位の繰り返し,すなわち“リズム”という現象は,脳の根元的な特性である』こと,そして『能は,外部の変化を単位の連続(リズム)としてつかみ取り,それを信号として体の各部の動きを統一的に同調させている』ことを示唆している」
とは述べているが,拍手との関連は言及がない。周囲との同期とか同調といった社会的要因もあるのだが,この点について言及はなく,「?」マークのついたままに終ってしまっているのが,気になって仕方がない。
ほかにも,
並んで歩くカップルは,なぜ女性が左側になることが多いのか?
なぜ振り込め詐欺にだまされるのか?
なぜ赤ん坊は「高い,高い」でわらうのか?
といった面白いテーマもあるが,動物行動学だけでは解けないな,と感じさせたのは,
スポーツの有名人に“品格”を求めるのはなぜか?
について,
「有名で影響力のある有名人に対して『自分だけの欲求にしたがって好き放題にふるまうのはやめよ』と思うのが(動物行動学的には)自然である。」
とし,その理由を,動物行動学の,
「個体は,自分の遺伝子を持つ個体(そういう典型的な個体は“子ども”や“兄弟姉妹”)がより増えるようにふるまう」
と同時に,人間のように,
「“他の個体と協力したり,助け合うような”行動が『自分の反映にとって利益』をもたらしやすい種がいる」
という原理に求め,
「有名人というのは他の人に対して大きな影響力を持つ場合が多い。その一方で,その“有名さ”はファンによって支えられている面が大きい。だとしたら,“一般の人”は,(意識するかどうかはまちまちだろうが)『その有名人が,自分を含めた他の人々に利益を与えるような行為をするように要求したい』と思うのが自然だろう。」
と説く。しかし,この説明よりは,これに続けて,「日本人の気質」に言及した,
「村社会の中だけで生きていくためには,自分の成功はつつましく話したり,自分の利益は独り占めせず,近所の人たちにおすそ分けしたり,…そんな気づかいが必要だったのである。これはまさに“品格”ある立ち居振る舞い方であり,日本という島国の農耕民で,“品格”が強く認識された理由でもある」
の方が説得力がある。人間は社会的動物であり,社会的・文化的文脈に強いられていることが多々ある。ある意味,その分析を抜いてしまう(あるいは,抜かざるをえない),動物行動学で分析する時の限界なのかもしれない。
それにしても,他のテーマは,行動。動作,心理なのに,
スポーツの有名人に“品格”を求めるのはなぜか?
というテーマの時だけ,価値観というものを前面に出している気がする,これを論ずるのは,動物行動学の閾値を越えているように見えた(失礼!)。
参考文献;
小林朋道『ヒトはなぜ拍手をするのか―動物行動学から見た人間』(新潮選書) |
|
謎解き |
|
木村泰司『謎解き西洋絵画』を読む。

ここで著者の言う,「謎」とは,こういう意味である。
「伝統的に西洋美術はある一定のメッセージを伝える手段として制作されてきました。」
だから,
「私たちが美術館で『美術品』として鑑賞する作品には,寓意を凝らして伝えている思想や観念,宗教原理,神話のエピソード,哲学的若しくは政治的な思想,美徳や悪徳,そしてモデルが観る者にアピールしたいメッセージなどが込められている」
しかし,それは,現代人にとって「謎」だという意味である。その謎を解くには,
「作品の持つ時代背景を理解しなければなりません。この時代背景を学ぶことも美術史の持つ奥行の深さの一つです。」
というわけである。そして,
「日本人が西洋美術を鑑賞する際,日本人の美意識がかえって鑑賞の邪魔をしてしまうことがあります。ましてや,現代の日本ではやたらと個人の感性を重要視し,好き勝手に絵画を鑑賞する傾向がありますが,それだけではもったいないと思います。作品の背景にあるメッセージを解読してこそ,作品を緩衝するだいご味が味わえるのです。」
と。仰せ御尤もである。
たとえば,ロベルト・カルピン『メロードの祭壇画』で,絵の中の,
「ネズミ捕りは。神が悪魔を欺くために人間(キリスト)の姿として地上に現れ,そしてそのキリストの十字架上の死は,結局悪魔の滅亡となったことを意味しているのです。」
とか,ラファエロ・サンツォイ『ガラティアの勝利』『サン・シストの聖母』を巡って,キューピットと天使は違うとして,
「キューピットは旧約・新約聖書の物語や成人を描いた宗教画には登場しません。キューピットは古代ギリシャの神々で,性愛の神様エロスの英語名です。(中略)一方,旧約・新約聖書を主題としたキリスト教関連の作品に登場する天使は,本来は純粋な精神体で肉体を持っていないのですが,地上においては物質化して人間のように見えるという考え方に基づいて表現されています。……本来天使は男性でも女性でもなく中性なのです。キューピットのように男性ではありません。」
とか,ベルト・モリゾ『ブージヴァルの庭のウジェーヌ・マネと娘』を巡って,印象派なのに,なぜ半径五メートル以内ばかりを描いたのか,
「(ブルジョワ階級という)彼女たちのような社会的階級に属していた女性には,なかなか好きな場所に一人で出かける自由がなかったからです。…当時は女性が戸外で制作することは罵声を浴びせられるくらいに,品のいいことと見なされなかったからです。」
等々,知らないことを知ることの意味はある。しかし,いま,我々が絵を観るのは,お勉強のためでも,教養のためでもなく,21世紀のいま生きる自分への刺激として,観る。すくなくとも,僕は,自分の,
視界を開く,
ために観る。それ以外で,観る必要はない。その時代に必要だったメッセージは,いま必要なメッセージではなく,いまの感性で,絵を観ながら,そこに,新たな視界を開く刺激があるかどうかで,いいのではないか。別に,お勉強として,美術品を観ることを否定はしない。われわれは,知っているものしか,見えない。だから,知識がなければ,おのれの知識でしかものは見えない。しかし,絵を観るのは,それでもいいのではないか,という気がしている。
著者は,ディエゴ・ベラスケス『ラス・メニーナス』について,
「この時代,王族夫妻の肖像画は基本的に一人ひとりで描かれるのが一般的でした。(中略)実際,……フェリペ四世夫妻が同じ絵に描かれているのはこの作品だけです。マルガリータ王女自身もまるでベラスケスに向かってポーズを取っているように見えますが,このカンヴァスは幼い王女を描くには大きすぎますから王女の肖像とは考えにくいのです。…それとも,夫妻だけでなく,『国王一家』という肖像の場合は国王夫妻と子どもたちが一緒に描かれたので,ベラスケスは複雑な構成のもと,家族の肖像を描いたのでしょうか?」
とか,
「鏡には,王女の両親であるフェリペ四世とマリア王妃が鏡に映っています。しかし,この国王夫妻は本人たちなのか,それとも画面左手に立つベラスケスの前にあるカンヴァスに描かれた姿が映っているのかはいまだになぞのままです。」
とか,
「当時,スペインでは画家の社会的地位は低い物でした。彼は宮廷画家としてだけではなく,宮廷の職員としてもフェリペ四世に仕え,王から絶大な信頼を寄せられてはいましたが,本来なら王家の人々と同じカンヴァスに描かれることなど許されませんでした。現代人が想像する以上に当時ではとても不敬なことでした。」
といった謎を挙げています。しかし,僕は,この文を読みながら,フーコーを思い出していた。
ディエゴ・ベラスケス『ラス・メニーナス』
なぜなら,この絵の中にいる自分を描いているベラスケスは,この絵の中で描こうとしている,こちらに立っているフェリペ夫妻と,同じ位置,架空の位置を想定しなければ,この絵の世界そのものが成り立たない,そのポジションについて,フーコーが書いていた記憶があるからだ。その位置は,また,まさに,鑑賞する我々が立っている位置でもある。
フーコーの『言葉と物』では,
「われわれは絵を見つめ,絵の中の画家は画家で我々を凝視する。」
という位置関係をしめし,さらに,
「画家が眼をれわれのほうに向けているのは,われわれが絵のモチーフの場所にいるからにほかならない。」
と書く。そして,画家とモデルとみえない描かれつつある絵との関係を,「潜在的な三角形」として,
「その頂点―可視的な唯一の点―に芸術家の眼,底辺の一方にモデルのいる不可視の場所,他方に,裏がえしにされた画布のうえにきっと素描されているに違いない形象がある」
と,その,いま描かれつつある絵を描いているその瞬間を,絵にしている,というこの絵を観ている鑑賞者も,
「鑑賞者をその視線の場に置いた瞬間に,画家の眼は鑑賞者をとらえてむりに絵のなかへ連れこみ,特権的であると同時に強制的な場所を指示したうえで,輝く可視的な形相を彼から先どりし,それを裏がえしにされた画布の近づき得ぬ表面に投射するのである。だから鑑賞者は,画家にとっては可視的だが,自分に取っては決定的に不可視的な像におきかえられてしまう。」
モデルと,同じ立ち位置に立つことで,鑑賞者は,絵の中の画家のモデルになっているかのような位置にいるのである。さらに,こう書く,
「オランダ絵画では,鏡が二重化の役割をはたすという伝統がある。つまり鏡は,絵のなかにひとたびあたえられたものを,変様され,縮小されたわめられた非現実の空間の内部で反復するわけだ。(中略)同じアトリエ,同じ画家,同じ画布が,鏡のなかに同一の空間にしたがってならべられることを期待するであろう。それは完全に模造となるはずなのである。」
そして,
「鏡のなかに映しだされているもの,それこそ,画面のあらゆる人物が視線をまっすぐに伸ばし凝視しているものにほかならない。つまり,画家のモデルとなっている人物をも含めるまで画面が手前に,すなわち,もっと下の方へ延長されれば見ることのできるはずのものなのである。けれども,それはまた,画面が画家とアトリエを見せるところで止まっているのであるから,絵が絵である限り,…絵の外部にあるものでもある。…思いがけず鏡が誰にも知られず,画家(仕事中の画家という,その表象された客観的実在性における画家)の見つめている諸形象ばかりか,画家(線や色が画面においてあの物質的実在性における画家)を見つめている諸形象をも,きらめかせている。」
絵画空間の外の、この絵を描く画家と,この絵のなかで国王夫妻を描いている画家のモデルたる,国王夫妻と,この絵の鑑賞者の立つ位置との三重の関係,それはまた,絵の中の人々が意識し,目を向けている位置でもある,
「描かれている瞬間のモデルの視線、場面を見つめている観賞者の視線、そしてその絵(表象されている絵ではなく、われわれのまえにあって、われわれがそれについて語っているところの絵)を創作している瞬間の画家の視線が,正確に重なりあう」
その位置は,画家ベラスケスの設定した,
描かれるべきものと向き合う仮設の画家,
である。本当の謎は,ここから始まるように思える。フーコーは,
絵を見つめ,あるいは制作するときの,画家と鑑賞者の空位,
と呼んでいた。この自覚的絵の,歴史的な意味をこそ,解き明かしてほしい。
参考文献;
木村泰司『謎解き西洋絵画』(洋泉社)
ミシェル・フーコー『言葉と物』(新潮社) |
|
マインドサイト |
|
コリン マッギン『マインドサイト―イメージ・夢・妄想』を読む。
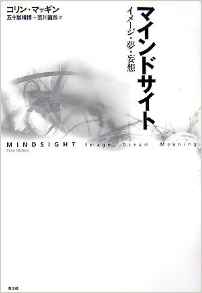
著者は,「まえがき」で,ウィトゲンシュタインとサルトル(『想像力の問題』)を刺激に,広範囲な想像力の問題を,
「体系的にアプローチし,さまざまな想像力の事例を秩序づける」
ことを試みたとし,
「全体として想像力がきわめて多様な心的現象に関わる能力だと示すことが私の目的である。想像力という主題を巡り,さまざまな心的現象の変奏が繰り広げられる。」
その,
「全体を結びつける糸は,想像と知覚の間の対比と,それが正確に何に存するのかという問題」
であると述べている。「はじめに」で,それを具体的に,
「心に描く想像は外に向けられた本物の目で見ることと同じではないが,まさに心の目で見ることだといえる。ここで私は,見ることは,二つの種類(身体の目で見ることと心の目で見ること)があるという考えを擁護する。両者は根本的に異なるのだが,ともにより一般的な『見る』という概念の事例なのである。だから私は本書のタイトルを『マインドサイト』としたのだ。」
と述べる。最終章で,全体像を整理し,
「私の考える『想像力のスペクトラム』とは,次のようなものである。
知覚……記憶イメージ→想像的感覚→生産的イメージ→白昼夢/夢→可能性と否定→意味→創造性
説明しよう。私たちは基本的な知覚から出発した。この知覚は想像によって汚染されていないもの(世界が乳児の感覚に与えるもの)である。この段階ではイメージのようなものは何もない。知覚と記憶イメージの間の「……」はこの明確な断絶を示す。記憶イメージは知覚に由来するが,知覚の一種ではない。」
云々と,述べ,初めて,知覚が仮説としての「知覚」ということを明かすのは,ちょっとルール違反のような気はするが,徹底して,知覚と想像力差異化にこだわり,巻末には,
意図 イメージ(意のままになる) 知覚(意のままにならない)
観察 イメージ(新しい情報を提供しない) 知覚(新しい情報を提供する)
視野 イメージ(視野を持たない,物理的に制約されない) 知覚(視野をもつ 物理的に制約される)
非決定性 イメージ(表現されない属性がある) 知覚(すべての属性が表現される)
注意 イメージ(注意を必要とする) 知覚(注意を必要としない)
不在 イメージ(現前を必要としない) 知覚(現前を必要とする)
思考 イメージ(他の志向により中断される) 知覚(他の思考により中断されない)
等々と,「知覚とイメージの相違点リスト」を挙げてみせる。
特に,注意と意図が鍵になる。
しかし,素人が言うのも,変だが,著者は,イメージと知覚との差異化にこだわるあまり,
「夢はイメージの範疇に入るのか,知覚の範疇にはいるのか」
との設問を立て,知覚ではなく,イメージであることを帰結するために,イメージが意図的,意識的であるという原則と整合性を持たせようとして,
「眠っている人が完全に受動的で,まったく行為の主体ではないと考えるのは間違っているだろう。(中略)夢が随意的な制御とまったく無関係というわけではなく,眠っている人は必ずしも単なる受動的な存在ではない。」
として,こういう(仮説の)提案をする。
「ここで,より過激な(聞いたこともないような)提案が必要だと私は思う。それは,夢の観客と夢の著者(夢の消費者と夢のプロデューサー)を区別する必要があるというものだ。つまり,夢を見る心における『精神の分離』,自己の分割を仮定する必要がある。…そこでは夢の著者は,夢の観客の知識と意識から切り離されて働くことができるため,夢を生成する意図や心的行為は消費者としての夢を見る人の意識には開示されない。夢のプロデューサーは夢の消費者からすると無意識的である。これは,心理的な受動性の錯覚をもたらす。観客は受動的で,意図的に夢を作り出してはいないので,その過程全体が受動的なように思えることになる。」
そして,結論として,
「夢のイメージは無意識的な意図の産物である。」
という。なぜ,夢が知覚かイメージかとの二者択一にしなくてはならないのか,その理由がわからない。少なくとも,夢は,
想像力のアナロジー,
とはなっても,想像的な心的機能とは別なのではないか。ここで,イメージの範疇に入れてしまったために,
(狂気としての)妄想,
も,夢とリンクさせなくてはならなくなっているように見える。想像力は,少なくとも,
意識的な心的操作,
であり,それは,ウィトゲンシュタインの言う,
「〜として見る」
と,ほぼ地続きのはずである。これを知覚の範疇として考えようするより,人の,
認知,
の問題として考えることで,創造力の問題の端緒になるはずなのだ。つまり,ウィトゲンシュタインが,三角形の図を例に,
「この三角形は三角の穴とも,物体とも,幾何学の図形とも見ることができる。土台の上に立っているとも,先端からぶら下がっているとも,山とも,矢印のない指示標識…」
と,人は,どのようにも見る。その内的な機制は別として,そこに,実は想像力の鍵があるのではないか。「穴として」とみたとき,三角形は認知されない。その想像力の独自の空間というものにこそ目を向け,知覚を著者のように限定しなければ,われわれが,物を見るとき,
自分の知っているもの,
を見ていて,「穴」とみたとき,紙に描かれた三角形は見(え)ていない。地と図という言い方をするが,物を認める時,現実のそのものとは別のものを認知することは多くある。
うつつを見ないで,見えた(と思うものを見ている),
この現実との差こそが,想像力につながる地平でなければならない。それは,限界まで行けば,
ストーカーの妄想,
につながっていく。しかし夢は,
自己完結し,
現実の認知機能は停止している。脳の機能としていろいろな仮説はあるが,少なくとも意識的コントロールはできない。夢をイメージに加えてしまうことで,何が得られるのか,僕にはわからなかった。
「想像力は広大な領域で現れている。心的イメージから夢や白昼夢まで,狂気,信念と意味,芸術と科学など,創造力はあらゆるものに係っている。」
として,厳密に,境界線を引こうとするよりは,その間の機能の連続性に着目した方が,もっと人間の豊かさが出たように思える。
参考文献;
コリン マッギン『マインドサイト―イメージ・夢・妄想』(青土社) |
|
ゆるす |
|
ロバート.D.エンライト『ゆるしの選択―怒りから解放されるために』を読む。

著者は,冒頭で,本書を,
セルフヘルプの本(他者による援助ではなく自力で自分を援助するための自助本)
とし,
「怒り,憤慨,終りのないように思える破壊的な人間関係というパターンの渦に巻き込まれ,そこから抜け出す方法を探している人のための本」
という。そして,本書は,著者のゆるしに関する科学的研究に基づくプログラムの紹介になっている。
「ゆるすというプロセスを選択すれば,怒り,憤慨,苦痛,そしてそれらの感情に伴う自己破壊の行動パターンから解放されて,自由になれるのです。」
と。そして,ゆるしを,
「他者によって不当に傷つけられた場合,その加害者に対する怒りの感情を乗り越えたときゆるすことができます。これは,怒りを感じる権利を否定するものではなく,その代りに,過ちを犯した行為者に憐憫,慈愛を提供するものです。加害者は必ずしもこのような恩恵に浴する権利はないことを了解しながら,ゆるしを実践します。」
と定義し,こう説明する。
「ゆるしのはじめには痛みを伴うこと,それに私たちには感じる権利があるということです。第一に,被害を与えることは不当であり,将来も不当であり続けることを承認すること。第二に,道義的にも怒る権利があり,人は私たちを傷つける権利がないという主張を支持するのは公正であること。私たちには,人として価値を認める権利があること。第三に,ゆるすことは,私たちの権利の放棄,つまり怒りや憤りの感情を放棄する必要があること。
ゆるしは,必ずしもそうすることに値しない加害者に対する慈悲の行いです。それは,加害者と私たちの間の関係性を変化させるために提供された贈り物です。加害者がどのような人かわからない場合でも,私たちはその人との関係の質を変化させることができます。というのは,私たちはこの人に対する怒りの感情によってコントロールされなくなるからです。」
と。「ゆるし」は,英語では,forgivenessである。その語源はともかく,
許す,
赦す,
という意味となり,本書の解説が言うように,
「『許可する』ように願いを聞き届ける」
という意味なのかもしれない。しかし,日本語の語源は,
「緩う+す」
で,かたく締めたものを緩くする,という意味という。相手との緊張関係を緩めることを,自分にゆるす,ということになろうか。漢字では,
許は,それでよしとゆるすなり,
赦は,罪をゆるしやるなり,
釋は,ときゆるすなり,
宥は,なだめゆるすなり,
聴は,先方の望みを聞ききいれるなり,
免は,ゆるして免れしむるなり,
容は,堪忍してゆるすなり,
等々とあるが,やはり,この場合,「許す」「赦す」が妥当のようだ。
さて,本書は,ゆるしのプロセスを,フェーズ1から4まで定め,以下のようなステップを示している。
フェーズ1 怒りの表出
・怒りに対処することを避けてきましたか。
・怒りに向かい合ったことがありますか。
・罪や恥を感じていることを人に知られるのが怖いですか。
・怒りによる影響があなたの健康面にありますか。
・受けた傷や加害者のことばかり考えていませんか。
・あなたの状況を加害者の状況と比較しますか。
・被害を受けたことであなたの人生は永久に変わってしまいましたか。
・被害を受けたことであなたの世界観は変わりましたか。
フェーズ2 ゆるすことの決意
・あなたがしてきたことは効果がなかったと認める。
・ゆるしのプロセスを自発的に始める。
・ゆるすことを決意する。
フェーズ3 ゆるしの作業
・理解するよう努力する。
・思いやるように努力する。
・傷ついて痛みを受け入れる。
・傷つけた人に贈り物をする。
フェーズ4 発見と,感情の牢獄からの脱出
・苦しむことの意味を発見する。
・ゆるしの必要性を発見する。
・あなたはひとりではないことを発見する。
・人生の目的を発見する。
・赦しは自由自在であることを発見する。
以上のプロセスを実践するために,道具は,
日記をつける,
プロセスを同伴してくれるパートナー,
である。何度か出る「努力する」の言葉が,すごく気になるし,むなしい気がするが,このプロセスの是非を,僕は判断できない。ただ,日記については疑問がある。
どんなに感情を書き付けても,それは,あくまで閉鎖された自己対話のなかに過ぎず,自己完結している。それでは,自己対話の地獄を脱することにはならない。そのくらいなら,同伴してくれるパートナーに,
怒りを語る,
ほうがいい。
怒ること
と,
「怒っている」と言うこと
とは,まったく違う。怒りを表現できず,最悪,怒っていること自体に気付いていない場合もある。そのためには,自分の思いを語ったほうがいい。日記では,
怒る,
だけだか,人に語ることで,
怒っている(かどうかわからない思い)を伝える,
ことになり,遥かに,感情の表現になっている。前にも,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163015.html
で触れたことがあるが,僕は,
バカヤロー,
と怒りを爆発させるのではなく,
「『バカヤロー』(ここは怒りの表出でいい)と,言いたい気分だ」
と言うことで,十分,怒りの表現になる,と思っている。この効果は,感情を言葉として表現したことで,
①自分の感情との間合いが取れる,
②相手の感情とも距離を取れる。感情のやり取りを感情のぶつかりあいでなく,言葉によるコミュニケーションの土俵ができる,
といっている。ゆるすとは,
相手の行為に反応している自分の感情の虜になっている状態,
つまり,同じ土俵上での綱引き状態から,
引っぱりあう綱を緩める状態,
あるいは,
その土俵から降りる状態,
だとすると,その土俵上での視点に立っ限り,絶対に相手への感情関係は緩められない。いわば,自分をも相対化する,
メタ・ポジション,
をとらない限り,綱引き状態を脱せられないのだと思う。それは,
どつぼ
にはまった状態に近い。「どつぼ」を脱するには,前にも,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/399787014.html
で,書いたが,
「どつぼにはまって,トンネルビジョンに陥っているとき,視野狭窄の自分には気づけない。自分がトンネルに入り込んでいること自体を気づかない。それに気づけるのは,その自分を別の視点から,見ることができたときだ。一番いい方法は,あえて,距離を取ることだ。それには,
時間的な距離化
空間的な距離化
の二つである。その場から離れるか,時間を置くか,だが,それを意識的にするには,立ち止まる,ことだと思う。そうすると,選択肢が生まれる。このまま続けるか,ここでいったん止めるか,思案し続けるか等々。選択肢が出たことで,自分に距離を置ける。
この自分の状態,あるいは自分の心理,自分の感情に距離を置いて,おいおい,嵌ってるぜ,という余裕が出れば,距離が持てたのと似ている。つまり,見る自分を突き放して,ものと自分に固着した視点を相対化することだ。そうしなければ,他の視点があることには気づきにくい。」
つまり,
メタ化
である。怒りを相対化する作業をする,つまりメタ・ポジションに立つためには,まずは,
怒りを語る,
ことではないか,と僕は思う。アサーティブが効果的なのも,
自分の気持ちを言語化し,伝えようとする,
ことに端を発する。
その意味で,(いくつか異論はあるが)本書が,自分の怒りを相対化するためのプログラム,であることは確かではある。
ゆるすのは自由であることを発見する,
ということであり,その視野の囚われを脱することで,
自分の人生の意味を見つけ直す,
というのも,確かである。
参考文献;
ロバート.D.エンライト『ゆるしの選択―怒りから解放されるために』(河出書房新社)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社) |
|
分裂病 |
|
中井久夫『分裂病と人類』を読む。

いまは,統合失調症というが,これについて,著者は,「新装版あとがき」で,
「統合失調症とは何かというのは,当時も精神医学の大問題であったが,私は人文科学の助けを借りてこれを解こうとしたのである。ことに精神分裂病は,その後,病名までが『統合失調症』と変り,私もそれを支持する一文を書いているが,復刊に当たっては編集者と話し合って,けっきょく昔の題を残すことにした。この本の『固有名詞』とおもっていただくとありがたい。」
と,書き添えている。その「分裂病」についての,著者の見解は,人というものを考えさせるところがある。たとえば,
「オランダの臨床精神医学者リュムケは,正常者もすべていわゆる分裂病症状を体験する。ただし,それは数秒から数十秒であると述べている。この持続時間の差がなにを意味するのか,と彼は自問する。」
と,
第一章 分裂病と人類
を書きだした著者は,
「私は一方では,分裂病になる可能性は全人類が持っているであろうと仮定し,他方では,その重い失調状態が他の病いよりも分裂病になりやすい『分裂病親和者』(以下,S親和者とよぶ)を考える。…分裂病親和性を,木村敏が人間学的に『ante
festum(祭りの前=先取り)的な構えの卓越』と包括的に捉えたことは私の立場からとしてもプレグナントな捉え方である。別に私はかつて『兆候空間優位性』と『統合指向性』を描出し,『もっと遠くもっと杳(かす)かな兆候をもっとも強烈に感じ,あたかもその事態が現前するごとく恐怖し憧憬する』と述べた(兆候が局所にとどまらず,一つの全体的な事態を代表象するのが『統合指向性』である)。」
と,分裂病,あるいはその親和性を分析する。ここにあるのは,気質の拡大化した見方である。つまり,極端化とみるということである。この先取り的構えを,微分回路(的認知),積分回路(的認知)のメタファで,
「入力の時間的変動部分のみを検出し未来の傾向予測に用いられる」「ノイズの吸収力がほとんどない」
微分回路的認識は,「系統発生的には」,
「過去全体の集積であり,つねに入力が出力に追いつけず,傾向の把握に向かないが,ノイズの吸収力が抜群」な,
集積回路的認識より古く,
「微分回路は見越し(リード)式ともいわれ,変化の傾向を予測的に把握し,将来発生する動作に対して予防的対策を講じるのに用いられる。まさに先取り的回路ということができる。またウォッシュ・アウト回路と言われるごとく,過渡的現象に敏感でこれを洗いだす鋭敏さがあり,t≒0において相手の傾向を正しく把握する。しかしこの“現実吟味力”は持続しない。すなわち出力が入力に追随するのは,t=0付近だけで,時がたつにつれて出力は入力に追随できず,すぐ頭打ちとなり漸次低下する。増幅力の意地も不能で不定となる。中程度の増幅力では突然入力にも漸変入力にも合理的に対応できるが,ある程度以上の増幅に弱い。また過度の厳密さを追求してt=0における完全微分を求めようとすると相手の初動にふりまわされて全く認知不能になるという。また…高周波ノイズが介入すると出力が乱れる。また未来指向的な回路であって過去のメモリーがいかされない。」
という,この気質は,分裂病親和者に重なる。
「(微分回路のメタファは)分裂病親和者の多くの局面を説明するもののように思われる(対人関係論的にみればすべては相互的なので,相手に波長を合わせて(チューン・イン)ている分裂病治療者のほうも面接時に微分[回路]的感覚に鋭くなるはずだ)。もし不安に駆られて完璧な予測を求めようとするならば,これはt=0における完全微分を求めることで,かえって相手の初動にふりまわされてしまい,発病の初期に見られるごとく身近な人物のほとんど雑音に等しい微表情の動きに重大で決定的な意味をよみとり,それにしたがって思い切った行動に出る。また入力の変化から将来の傾向を鋭敏に予測し,過渡的現象も見のがしはしないが,時とともに出力の変動は入力の変動を反映しなくなり(現実吟味性の低下),エネルギー的にも低下,増幅力も維持できず,不安定になる。この辺りは分裂病親和者の疲れやすさ,あるいは分裂病者のポテンシャル喪失を想わせる。晩発性治癒が問題となって以来…,分裂病的変化を,理論的には可逆的であるが,なかなか回復のエネルギーをとり出しにくい構造と考えねばならなくなってきたけれども,微分回路の欠点はおおむねこれに対応するモデルとなるように思われる。」
この「兆候空間=微分(回路)的認知」は,
「人類史においても最古の段階である狩猟採集民においてもっともその長所をはっきできたのではないか」
と,著者は想定し,ブッシュマンを例に,その認知特性を分析し,こう要約する。
「狩猟採集民においては,強迫性格もヒステリー性格も循環気質も粘着気質も,ほとんど出番がない。逆にS親和型の兆候性への優位(外界への微分[回路]的認識)が決定的な力をもつ。ここでは(中略)つねに現在に先立つ者であることだけが問題なのだ。」
しかしその気質は,「粘着質的職業倫理」に比して,
「ほとんど負(マイナス)の意味を帯びた形容詞でかざられる」
ばかりでなく,
「多くの社会復帰事業は,分裂病経過後の,いわば鎧の糸の(少なくとも一旦は)ほころびた分裂気質者を執着気質者に仕立て直すことをめざしている。」
と皮肉る。そこには,執着気質が,いまの時代に叶う気質であるという「社会的被規定性」を持っている,ということなのであろう。だから,
「分裂病者の社会『復帰』の最大の壁は,社会の強迫性,いいかえれば脅迫的な周囲が患者に自らを押しつけて止まないこと,である。…ただ言いうることは,私がかつて分裂病者の治癒は『心の生ぶ毛』を失ってはならないといったが,実はそれこそは分裂病者の微分(回路)的認知力であり,それが摩耗してはすべてがむなしい。」
と書く。「心の生ぶ毛」と「心のひげ根」という言い方で,分裂病者の気質にとって,その「高い感受性」こそがかけがえのないものだという,治療者としての著者の射程の深い眼差しを感じさせることばである。
そして,もし社会が,粘液気質のものばかりであったら,どうなるか,と問う。
「とくに木村のpost fesyum(事後=あとの祭)的な構えのゆえに,思わぬ破局に踏みいれてなお気づかず,彼らには得意の小破局の再建を『七転び八起き』と反復することはできるとしても,『大破局は目に見えない』という奇妙な盲点を彼らがもちつづけることに変りはない。そこで積極的な者ほど,盲目的な勤勉努力の果てに『レミングの悲劇』を起こすおそれがある」
から,人類において,いつも1%前後の統合失調症が現れる,意味があるのだろう,と述べる。
精神病と人類史,あるいは社会との関連性に注目して,第二章では,「粘着気質の歴史的背景」,さらに第三章では,「西欧精神医学背景史」と,視野を広げていく。その見識の深さと,射程の広さには,ついていくのでやっとであるが,前者で,分裂気質の世直し型に対して,立て直し型の粘着気質の仕事ぶりを,二宮尊徳を例に取り上げていく。後者は,精神病というものが,いかに被社会規定性かを,古代ギリシャからひもとき,
「市民社会の成立と近代精神医学のそれとのあいだには,きわめて密接な関連がある。」
として,フランス革命以降を丹念に追尾し,
「二十世紀初頭における最大の精神医学的発見は分裂病の発見であり,これは古代以来の躁病・うつ病の二大別をくつがえしただけでなく,精神医学それ自体の雰囲気を一変させた。」
そしてヨーロッパではアカデミズムに受け入れられなかったフロイトが,アメリカで,公式精神医学として採用され,
「治療者に医師資格を前提とする」
というアメリカ精神医学の独特の成り立ちまで追っていく。そこにあるのは,独特の西洋の文化史,宗教史と絡み合った陰翳で,一読だけでは,その含蓄を味わい尽くせないほどの深みがある。その動機を,1982年のあとがきで,
「私の意識には,自分の一応実践していることになっているが,ある距離と違和を感じてもいる西欧精神医学の正体を見きわめたいという強い底流が一貫してあり,さらにその底には,『近代西欧』という現象は何であろうか,という考えが底流しているのを感じる。『それは非常に特殊なものではないか』という感じが私にはつねに存在してきた。私が,日本その他の魔女狩りの不在に触れたのも,また『近代的自我』をわが国における一つの神話として彼地の『無垢なる乙女の神話』と対置させたのも,その線にそってのことである。」
という問題意識の奥行があってのことと納得させられるのである。その奥には,
「日本における近代精神医学が『近代西欧的な装備は何でも一揃い揃っています』という近代日本百年の至る所にみられるショウ的な存在でありつづけてはならないと思う。『ショウ的存在ではない』という反証の一つは底辺の充実であるのだが。」
という強いマインドが隠れている。
参考文献;
中井久夫『分裂病と人類』 (UP選書 221) |
|
妖怪 |
|
阿部正路『日本の妖怪たち』を読む。

妖怪というと,亡くなった水木しげるになるが,彼が依拠したのが,鳥山石燕の『画図・百鬼夜行』である。
(河童 川太郎ともいふ、『画図百鬼夜行』の内、一図「河童」蓮池の茂みから現れ出でた河童を描く。)
鳥山石燕(1712〜1788年)は,『今昔物語』や『宇治拾遺物語』が,
「〈さまざまの怖ろしげ〉とのみ帰した妖怪たちをみごとに視覚化」
した。『画図・百鬼夜行 前偏 陰』には,
「『木魅(こだま)―百年の樹には神ありてかたちをあらはすといふ』から『白沢(はくたく)―黄帝東巡し,白一たび見(あらわ)る,怪を避け害を除き,靡く所偏せず』に至るところ百五十五類に及ぶ視覚化された〈妖怪〉が並び,まことに壮観」
と,著者は書く。しかし,と,著者はこう書く。
「石燕の画図には,『今昔物語』や『宇治拾遺物語』が〈さまざまの怖ろしげ〉とのみ記した妖怪たちをみごとに視覚化しているものの,かえって〈さまざまの怖ろしげ〉なものから遠ざかっているようにすら思える。いや,正確には,石燕の画図に視覚化されたものは,『今昔物語』や『宇治拾遺物語』などが心にとめていた〈さまざまの怖ろしげ〉なるものとはまったく異なった他のあるものだというべきなのかもしれない。しかし,それ以上に,日本の妖怪たちは視覚化されることを根本から拒否しているのではあるまいか。日本の妖怪たちは,どこまでも観念的な実在としての〈希有希現〉なのであって,視覚的な存在としての〈毛羽毛現〉ではないのではあるまいか。」
さらに,草森紳一氏の,
「石燕は,妖怪を,あたかも檻に入れられた動物のように,封じこんでしまっているのである。これらの百鬼は,からめとられ,骨抜きにされた妖怪なのである。恐怖感は起きるはずもない。」(『お化け図絵』)
という言葉を引いて,著者は,
「『画図』の外に,常に〈妖怪〉は存在しているのであって,『画図』の中には決して閉じ込められることはない。」
と書く。
水木しげるの妖怪ワールド 妖怪大全集
http://www.top-page.jp/site/page/mizuki/complete_works/list/
を見ても,それは,わかる。しかし,である。本来,
〈さまざまの怖ろしげ〉
という言葉の向こうに,それぞれの人が見ていた恐ろしい視界を,
画図化,
することで,一つに強制することは,そういう意味を持つのではあるまいか。しかも,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/432575456.html?1452804830
で,取り上げたように,江戸時代は,「妖怪」を物語として楽しむ時代になっている。
「江戸期の巷間にいて,明らかに『世間話』として享受され,機能していたと考えられる場合が少なからず存する。」(『江戸の怪異譚』)
世間話とは,いまふうに言うと,「都市伝説」である。そういう時代背景の中で見れば,石燕は,時代の要請にこたえたのでもある。
本書は,鳥山石燕をはじめ,怪談研究の名だたる人を上げ,水木しげる,手塚治虫にまで言及している。まあ,妖怪研究の入門書と考えていいのではないか。
本書の巻末に,「妖怪出現略年表」があり,
「草木がものを言った。伊邪邦岐命が黄泉醜女に襲われる(『書紀』では,伊弉諾尊は,冥界の鬼女に襲われる)」
から始まって,慶応四年,
「明治天皇は讃岐の白峯山中の大魔王を鎮めた」
で終わっている。これは,崇徳上皇の怨霊を鎮めた,ということを意味する。この怨霊については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/407475215.html
で触れた。この時点で,一応公式には,
「妖怪たちを封じ込めた」
ことになる。しかし都市伝説としての「世間話」は生き続けているが。
「あとがきに代えて」で,こう締めくくっている。
「妖怪の基本は,…二種類以上の動物が一つになった場合で,《鵺(ぬえ)》にその一典型をみる。鵺に限らず,妖怪のほとんどは尻尾を持つ。尻尾は,動物が方向感覚のバランスを保つためのかけがえのない《舵》である。その舵を持たない人間は,実は妖怪にすら及ばないのではないのか。さらにいえば,尻尾を出すとは,化けの皮がはがれることをいい,尻尾は常に,ごまかしやかくしていたことが表面にあらわれるいとぐちになる。」
しかし,昨今,日本の妖怪たちは,化けの皮がはがれても,臆面もなく,平然としている。あれは妖怪ではなく,ひとだったということか。
参考文献;
阿部正路『日本の妖怪たち』 (東書選書 )
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%B1%E7%9F%B3%E7%87%95
水木しげる『妖怪事典 正・続』(東京堂出版)
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫) |
|
倫理 |
|
マックス・ウェーバー『職業としての政治/職業としての学問』を読む。

本書は,ウェーバーの二つの講演録である(バイエルン州の自由学生同盟主催,ミュンヘン大学で講演)。ウェーバーは,この講演を,1919年,ドイツ革命が起こり帝政が崩壊し,ワイマール共和国成立という動乱の時期に行っている。『職業としての政治』の終りのところで,
「わたしたちはみなさまと10年後,この問題について話し合いたいとおもっています。」
と語る。そして,こう予言めいたことを語っている(ウェーバー自身は,翌年亡くなっているが)。
「10年後にはおそらく,残念ながら様々な理由から,反動の時代がすでに始まっているという予感がしますし,みなさまの多くが期待しておられることは,そしてわたしもともに期待していることは,まったくでないにしても,ほとんど実現されていないのではないかと感じるのです(すくなくとも見掛けのうえではということですが)。これはかなりたしかなことで,それでわたしの心がくじけることはないとしても,気持ちが重くなるのは間違いありません。そこでわたしか知りたいのは,みなさまのうちで,いまは自分が純粋な『信条倫理に基づいた政治家』であると考えておられ,革命と呼ばれる熱狂に参加しておられる方々が,10年後等は精神的にどう『なっている』だろうかということなのです。」
と,そして,こう言うのである。
「一見すると現在は〈わが世の春〉を謳歌しているように見える人々のうちで,誰が生き延びているでしょうか。」
と。
1921年ヒトラーがナチ党の指導者となり,33年にヒトラー内閣が成立する。そういう時代を予期していたような言葉である。しかし,ウェーバーは,そういう事態にどう対処するかが,政治を仕事にする人間に問われる,として,最後をこう締めくくる。
「すべての希望が挫折しても耐えることのできる心の強靭さを,今すぐにそなえなければなりません。それでなければ,今可能であることさえ,実現できないでしょう。…世界がどれほどに愚かで卑俗にみえたとしてもくじけることのない人,どんな事態に陥っても,『それでもわたしはやる』と断言できる人,そのような人だけが政治への『召命』『天職』をそなえているのです。」
いまの日本の政治状況が,ナチ台頭で風前のともしびのワイマール共和国のドイツの状況とよく対比される。いま,このウェーバーの問題意識は,今日の我々の胸に,ずしりと響くのはそのせいだ。これは我々にも問いかけられていることでもうる,と。
さて,ウェーバーは,この講演で,政治史をひもときながら,ドイツとイギリス,アメリカを対照しつつ,
「権力を行使し,その権力の行使に伴う責任を担いうるために,職業的政治家」
に必要な資質として,
情熱
と
責任感
と
判断力,
を挙げる。そのカギは,メタ・ポジションであるように見える。
「それがどれほど純粋な情熱であってもたんなる情熱では十分ではないのは明らかなことです。情熱が『仕事』に役立つものとして,仕事への責任という形で,行動の決定的な指針となるのでなければ,政治家にふさわしいものではないのです。そしてそのためには,判断力が必要なのであって,これは政治家に決定的に必要な心的な特性です。この判断力とは,集中と冷静さをもって現実をそのままうけいれることのできる能力,事物と人間から距離を置くことのできる能力のことです。」
その距離は,
「自分のうちに潜んでいる瑣末で,あまりにも人間くさい〈敵〉と闘い続けねばならないのです。この敵とは,ごくありふれた虚栄心で,これはすべての仕事への献身の,すべての距離(この場合には,自分と距離をおくことですが)の不倶戴天の敵なのです。」
という,自分も含めた距離をおく,メタ・ポジションを意味している。そのための政治家の倫理として,
信条倫理
と
責任倫理
を挙げる(信条倫理は,従来心情倫理と訳されてきたものだが,訳者の中山元氏は,原語から考えると,心映え,心構えという意味であり,心情ではなく,信条を取ったとする)。
「信条倫理的な原則に這従って行動するか(宗教的に表現すれば,キリスト教徒として正しく行動することだけ考え,その結果は神に委ねるということです),それとも責任倫理的に行動して,自分の行動に(予測される)結果の責任を負うかどうかは,深淵に隔てられているほどに対立した姿勢なのです。」
僕は,信条倫理に基づいていると見える我が国の首相を思い浮かべながら,次の言葉を噛みしめる。
「わたしとしては,この信条倫理の背後に,どれだけ精神の重みがあるのかまず問いたいのである。…自分の追っている責任を実感しておらず,ロマンチックな情緒によっているだけのほら吹きだという印象をうけるのだ」
と(まさにその通りなのが笑えるが),そして,「息を吐くように嘘をついても平然としている」,責任感の完全欠如した御仁を思い浮かべつつ,次の言葉を胸に刻む。
「わたしが計り知れないほどの感動をうけるのは,結果にたいする責任を実際に,しかも心の底から感じていて,責任倫理のもとで行動する成熟した人が(若い人か,高齢の人かを問いません),あるところまで到達して,[ルターのように]『こうするしかありません,わたしはここに立っています』と語る場合です。これは人間として純粋な姿勢であり,感動を呼ぶのです。なぜなら精神的に死んでいないかぎり,誰もがいつか,このような場にたたされることがありうるからです。その意味では信条倫理と責任倫理は絶対的に対立するものではなく,たがいに補いあうものであり,『政治を職業とする』ことのできる真の人間を作りだすものなのです。」
以上は,『職業としての政治』だが,『職業としての学問』でも,自己抑制,というか学者の倫理を強調する。
「教師が学問的な姿勢で政治に取り組んでいる場合,…実践的に政治的見解を表明することと,政治組織や政党の姿勢について科学的に分析することは,まったく別の事柄」
であり,
「教室や講堂でたとえぱ民主主義について語るとすれば,民主主義の様々な形態を示し,それぞれの形態がどのように機能するか分析し,社会生活においてそれぞれの形態がどのように影響を及ぼすかを確認し,これを民主主義的でないその他の政治秩序と比較するのです。これによって聴講者は,自分が何を究極の理想とするかに応じて,民主主義について取るべき姿勢を決める拠り所をみいだせるようになるのです。そして真の教師であれば,明確に表現するか暗黙的に表現するかを問わず,教壇から自分の見解を押しつけるようなことは避けるでしょう。『事実をして語らしめ』るためにも,このような態度をとることが不誠実なものであるのは,明らかだからです。」
とし,それを,
価値判断
と
事実判断
と区別し,教師は,預言者でも指導者でもデマゴーグ(民衆政治家)でもなく,後者に基づく姿勢が,教師の自己抑制であることを強調している。
学問のもたらすものは,
技術についての知識,
であり,学問は,
物を考えるための方法を提示し,そのための道具と訓練を提供する,
のであり,それによって,
明晰さ,
をもたらすものなのであり,現実の中で,
「目的と,採用しなければならない手段とのあいだで選択を迫られることになります。そして目的が手段を『正当化する』かどうかが問われることになるのです。教師は諸君に,この選択が必然的なものであることを教えることができます。しかし教師が教師であって,煽動政治家になろうとしないかぎりは,教師はそれ以上のことを教えることはできないのです。(中略)私たち教師は,自分がどのような仕事を為すべきかを理解している限り(もちろんここではそれを当然のこととして前提にしなければなりません),個々の学生に対して,自分の行為の究極の意味に責任を負わせることができるのであり,あるいはそのための手助けをすることができるのです。」
確か,記憶で書くが,ミシェル・フーコーも,学者としてのそのような弁えを語っていた。結局,責任を取るとは,
(自らの立場と役割を)弁えている,
ことなのだ,とつくづく感じる。そして,それが,
その人の倫理,
なのである,と。言うまでもなく,倫理とは,この場合,その人が,人として,
いかに生きるか,
という生き方そのもののことである。
参考文献;
マックス・ウェーバー『職業としての政治/職業としての学問』(日経BPクラシックス) |
|
怪異 |
|
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』を読む。

「はじめに」で,
「江戸時代の怪異譚を特徴付ける時代特性とは何か。あるいは江戸期の人々の奇談語りに立ちあらわれる説話の志向性とは,いかなるものか。」
と設問し,それを考える糸口として,丹波国山家領の郷士楠数右衛門に起きた霊異を挙げている(越前若狭の博物地誌『拾遺雑話』)。
「妻のお梅が長煩いの末にみまかる。野辺送りの折,塚穴から沢山の蛇が湧き出し,皆人は不吉な兆しにおののいた。間もなく福知山より後妻を迎え,祝言をとり行うことになる。盃を取り交わすところに亡き妻が『挨拶に出』たので,宴客は驚き逃げ出してしまう。それからというもの,お梅の幽霊は化粧鏡の中にさえ影を映すようになり,憔悴しきった後妻を親元に返そうと駕籠に乗せるが,『お梅ものりて重くして舁く事』がかなわない。執拗な亡魂の発動を封じるために講じた真言僧や山伏の祈祷も効験なく,結局,『禅宗覚応寺』の『禅嶺和尚』の施餓鬼法要を受けて,やっと執念深い亡者を済度することができたという。この事件の後日談について,編者の木崎酡窓はこう付記するのであった。
『お梅が法名を妙善といふ。妙善が障礙やまず,終に数右衛門も自殺す。弟も江戸にて自害,その類族を亡す。皆人聞て恐る。元禄末の事なり。』
名僧の法力により一旦は成仏したかに見えた婦霊は,その後も侍の家筋に祟りをなし,ついに血族一門の滅亡に至る。皿屋敷伝説にも似た結末を示して,この地方奇談は畢るのであった。」
この例話には,
「近世の怪異譚を成り立たせている重要な文化背景の痕跡が見え隠れする。」
として,著者はいくつかの特徴を挙げていく。
ひとつは,仏教唱導者の近世説教書(勧化(かんげ)本)のなかに類例の求められる,
仏教的な因果譚としての側面,
をあらわしている。
「檀家制度をはじめとする幕府の宗教統制のもとで,近世社会に草の根のような浸透を果たした当時の仏教唱導は,通俗平易なるがゆえに,前代にもまして,衆庶の心に教義に基づく生き方や倫理観などの社会通念を定着させていった。とりわけ人間の霊魂が引き起こす妖異については,説教僧の説く死生観,冥府観の強い影響がみてとれる。死者の魂の行方をめぐる宗教観念は,もはやそれと分からぬ程に民衆の心意にすりこまれ,なかば生活化した状態となっていたわけである。成仏できない怨霊の噂咄が,ごく自然なかたちで人々の間をへめぐったことは,仏教と近世社会の日常的な親縁性に起因するといってもよかろう。」
そうした神仏の霊験,利益,寺社の縁起由来,高僧俗伝などに関する宗教テーマが広く広まり,
仏教説話の俗伝化,
を強めて,宗教伝説が,拡散していった。
その一方で,上記の怪異譚は,結果として一族を滅ぼした亡霊は,法力の霊験が効果がなかったことをも示しているのだから,そうした宗教的因果譚の覊絆から離れていく傾向もあらわている。それは,
「もはや中世風の高僧法力譚の定型におさまりきれなくなった江戸怪談の多様な表現を示す特色」
であり,
「中世曹洞禅の縁起伝承には,名僧を導師とする妖魔,幽鬼の鎮撫と禅寺開創の因縁譚がめずらしくない。…そのような仏教説話の常套話型に比べてみた場合,決して救われることのないお梅怨霊の風説が放つ説話伝承史的な特性と位相は明白であった。」
そこには,説話の目的と興味が,
「高僧の聖なる験力や幽霊済度といった『仏教説話』の常套表現を脱却して,怨む相手の血筋を根絶やしにするまで繰り返される亡婦の復讐劇に転換するさまを遠望することになるだろう。」
それは,怪異小説に脚色され,虚構文芸の表現形式を創り出すところへとつながっていくことになる。こうした,
「江戸怪談の宗教性と脱宗教性,もしくは物語の深層に沈殿した仏教的な思惟」
の解析が,「本書の第一の目的」と,著者は書く。そのために,
和漢の類書,
故事説話集,
民間説話,
口碑伝説,
市井の奇談雑筆,
地方奇談集,
地誌に載る山川草木の妖異,
古社名刹の故事,
等々も「江戸怪談の生成プロセスを解き明かすのに欠かせない」等々によって,「あとがき」にあるように,
「現今の文学史ジャンルに含まれる怪異小説,浮世草子,読本はもとより,民間伝承や仏教民俗,宗教思想を包括する広義の『江戸怪談』を対象とせざるを得なかった」
幅広い範囲を網羅している。
全体は,
第1部 仏教唱導と怪異譚(唱導と文芸の間;仏教説話の近世的位相)
第2部 怪異小説のながれ(初期怪異小説の成立;浮世草子・読本と説話・伝承)
第3部 江戸怪談の人間理解(富と怪異;産育と怪異;江戸時代人は何を怖れたか)
という構成なのだが,
それぞれで取り上げられる,たとえば,
『死霊解脱物語聞き』
『御伽人形』
『金玉ねぢぶくさ』
『世間子息気質』
『雨月物語』
が,全体のなかで,どんな位置づけで例示されているのか,門外漢には,わからないまま読まされることが多く,全体を俯瞰する流れがわからないままに細部に分け入っていく苦痛が付きまとった。非才ゆゑの苦痛かもしれないが。
参考文献;
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社) |
|
チョムスキー |
|
田中克彦『チョムスキー』を読む。

まさに一気呵成に読ませる。1983年に書かれた本書が,今どんなポジションにあるかどうかとは別に,チョムスキーを,言語学の歴史全体の中で,クリアに位置づけて見せていることは,今も変わらないはずである。
著者は,序論で,
「本書での役割は,チョムスキー学者としてその著作の数々を祖述することではないから,その理論構成の基本的な特徴のみに焦点をしぼって,かれの思想をあきらかにすることである。」
と書く,その意図は達成されている,といっていい。著者は,音もなく先住理論と後退して支配的位置を占めたチョムスキー理論は,日本では,
チョムスキー革命,
を起こさなかったと皮肉り,本書の動機をこう書く。
「私が本書を書くきになったのは次のようなちょっと困った人に出会う機会が多いからである。それは,チョムスキーが天才的な言語理論の開発者であるというふれ込みをすなおに受け入れ,その天才的,革命的なるもののなかみを問わず,単にその政治的批判の姿勢に共感して好意を抱いている人たちである。ほんとうはその人たちは,言語学名士であるチョムスキーの威光にすっかりまいってしまった,俗物の肩書き信者にすぎないにもかかわらず,チョムスキー思想の理解者であるかのような口ぶりをしている。これこそチョムスキーが批判した,専門テクノクラート信仰の実例そのものではないだろうか。現代の状況からすれば,チョムスキー自身が,無駄な探索だと斥けている,専門の分野における理論と,その一般的な思想的背景との関係を明らかにすることは,意味を失っていないばかりか,ますます重要になっているとさえ思われる。」
その状況は,おそらく,いまも,少しも変わっていない。そこで,本書は,
「私たちは,『革命』ということばにつられて,そのなかみまでわかってしまったような気になっては困る。チョムスキーが言語学において行なった『チョムスキー革命』は,いったい何を革命したのか。何を革命しなければならなかったのか。その革命を行うためにどんな装置を用いたのか。その装置はどこまで有効であったのか。それと同時に,革命が必要とするモデルの教条として,チョムスキーは何を盾にとったのか。その教条,およびその解釈は,我々にとって受け入れられるかどうかということを検討しなければならない。」
この冷静な,「革命の主体としてそこに参加する勇気も展望も持つ義理のない」立場から,いわば,メタ・ポジションから,
「それはわれわれにとってほんとうに革命なのか反革命なのか」
「この革命は学問の世界の中で,とりわけ政治がらみの学問のなかでどのような反応を引き起こしたか」
等々,を順序立てて展開していく。
まずは,その革命の装置は,次のようなものである。
「その装置の第一は,現実にある言語の外に別の言語―これは考え方によればすでに言語ではないのであるが―
を設け,言葉の現象は,すべてそこ(深層構造のこと)へもどして,あるいはそれと関係づけることによって説明することにした。」
それは,これまで「ことばの科学」たらんとして,ひたすら音や言葉,文字だけを対象としてきた言語学に,コトバを現象させるココロを持ち出したことになる。
「実際にあらわれた言語表現,すなわち『表層構造』(日本語の訳者によっては『表面構造』とする人もある。『表面』は『表層』よりも,直接目に見えるという感じを表している点ですぐれている。もとの英語はsurface
structure)は,その『深層構造』とは『一般に別物』であると言っている。それらが『別のものである』(distinct)として,別の二番目のことばを仮定した―それは仮定でしかない。なぜなら表にあらわれておらず,見ることも聞くこともできないのだから―これがチョムスキーに革命を可能ならしめた第一の,しかも最も重要な装置だった。」
言語しか対象にしない言語学は,実際に生じた発話を集める。
「手に入るかぎりの,ある特定社会,ある特定個人の言語から集めた,まとまった資料の総体をコーパス(corpus)と言い,それが記述言語の作業の対象となり,基礎となる。」
しかし,チョムスキーにとって,
「より本源的でかんじんなのは,実演によってコーパスを産み出すそのもとに,言語を使う人間の能力(competence)があるのだから,その根元にある能力を描きだすことの方がより本質的だと考えた。つまり,この能力がそなえている基本的な(言語)形式があらゆるじっさいの言語表現―つまり表層構造を作りだしているもとなのである。それぞれの言語は,この深層構造を,一定の規則にもとづいて変形し,表層構造において,いわゆる言語として実現する。」
この深層構造は,抽象的だが,ポール・ロワイヤルの文法理論から要約される。これも装置である。
「いくつかの命題(proposition)から成るひとまとまりであって,…その命題の基本系は単純な『主語+述語』である。」
深層構造を表層構造につなげていくための変形規則が文法となる。それは,深層構造で,
「ただナントナク,ココロのなかで思われるだけ」
のものが,
「『一定の精神的操作』によって表層構造として姿をあらわす。『この一定の精神的操作』は,きっとこんなぐあいに行われるにちがいないと見当をつけて,その深層(ココロのなかのオモイチガイ)が表層(現れたことば)へと行きつくさまをいくつかの規則として引き出し,それをまとめたものがチョムスキーの言う『文法』である。」
そうすると,語られている表層構造ではなく,十個ばかりのタイプに記せられる深層構造だけが対象になる。それは,
意味,
であり,
思考の形式の反映,
であり,
全ての言語に共通(あるいは同じ),
とされる。言語の違いを超えて深層構造が同一なのは,
人間という種に共通の器官の能力
だから,という。
「人間という生物のうちの特別の種が,種として授かった器官の能力として発生するものだと考える。この器官の中には,原語を組みたてる理論や文法がセットされている。」
つまり,チョムスキーは,
「言語理論(あるいは『普遍文法』)とは,ぼくたちが生物学的な所与であると仮定できるもの,つまり人類という種の発生学的に決定された特性だ。」
というのである。それは,
「後天的に,経験的に見につけるような能力ではなく,生まれながらにして,その種の特性として,もって生まれてくる能力」
らしいのである。そして,
「普遍文法を一つの臓器として内蔵してうまれてきている」
とし,それを,
言語獲得装置(language acquisition device),
略して,LAD,と呼ぶ。しかし,これは,「仮定」に過ぎない。その仮定のもとに組みたてられた,深層構造であり,表層構造ということになる。
「深層構造,言語能力(competence),普遍文法,言語獲得装置,心的器官等々」
の概念によって,「いわゆる近代言語学の方法を全く逆転させて」,つまり,現実の言語を通して一般化する作業ではなく,「見えないが,論理的に仮定される一般文法から,つまり普遍の方から出発すべき」としたということになる。
著者は皮肉を込めて,
「チョムスキーの言語理論の骨組みは,まずはこの深層構造なるものの存在を信ずるよう説き伏せ,認めさせたところで築かれ,それが確立されると,さらにそれを現実の言語へと変形させる(transform)規則を設けることになる。」
と。しかしである,変形を論じうるのは,
「常に深層構造というものが準備されているからで,表層構造同士の比較は,かならずこの深層を介して行われるのである。その深層構造は単純で,従ってそれ以上何かに還元できない構造をもち,一般的に主語+述語の形をとる命題である。その命題は,常に肯定文の形をとるものとされており,その命題に,否定変形規則,疑問変形規則,受動変形規則などをくわえて変形させることによって,一つの命題から,否定文,疑問文,受動文などが生成されて,表層に現れるのである。深層構造は,そうした操作を受けて具体的なことばとなる以前,心の中にだけ思い描かれる抽象的な構造である…。ところが,そのような心に描かれただけの言語以前の何かを言語学者は意味とは呼ばなかった。ふつう言語学では,ことばの形をとって具体的に言い表されたもののなかにだけ意味を認める。」
以上がチョムスキーの装置である。当然仮説に仮説を重ねている。その補強のために,ポール・ロワイヤルの文法理論以外にも,
デカルト,
フンボルト,
という古ぼけた権威を借りる。著者曰く,
「デカルトとフンボルトのかけあわせは,チョムスキーによる最大の発明品だったというべきであろう。…これらの思想的権威を味方に引き入れ,うしろだてにしたてあげることによって,基本問題が通過しなければならない難所をきりぬけた…。」
と。では,この「革命」で何をもたらしたのか。言葉は社会的なものであった。しかし,
「チョムスキーは言語のあり場所を,社会や大衆などではなく,生物的個体の中に閉じ込めたのである。」
そして,
「個々の言語の研究は,原語の本質の解明にとってはもはや無駄な骨折りであって,英語をしらべれば,すべての言語にもあてはまる一般理論が引き出せると信じている」
この言語の多様性の否定を巡って,著者はひとつの仮説を,さりげなく述べている。
「ザメンホフが,実用の領域でエスペラント語という普遍的な混成共用言語を思いついたのと全く同様,チョムスキーは,現実にある,個々の言語に手をつけることなく,理念の上で,普遍言語を作りだしたのであると。それがほかでもない深層構造であった。」
脳科学者からの生成文法の脳内根拠,つまり認知のシステムの研究プロセスについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163351.html
で,すでに触れたが,他の動物が生得的に鳴いたりするのと違って,人間は,社会的に学びつつ言語を得ていく。言語化の器官的な根拠があるとしても,チョムスキーの仮定したようなものではない可能性が高い。
日本語学者が,日本語の構造を通して,チョムスキーの仮説を立証したのか,反証したのか,知らない。文脈依存度が高い日本語に,文脈抜きで深層構造を想定するのには,少し無理があるような気は,素人ながら,推測できる。
著者の次の言葉の意味する射程は長く深い気がする。
「チョムスキーの言語モデルには,各人は,その言語能力に見合った言語運用をするものだという前提が含まれている。このモデルには,言語というものが,その他の表現行為ときりはなしてとらえられている。したがって,かれが考え出して示す,いわゆるあいまい文は,いっさい文脈ぬきの,意図して曖昧が起きるように作られた例文である。しかもその例文は,印刷言語のレベルだけで観察されている。
人間の表現手段は言語だけに限られてはいないのであって,その場に前提された言語外の状況や,表情,身振りなどと幾層にも組み合わさっている。
深層構造が表層構造に,有形なすがたをとって,かけねなくあらわされるかどうかは,言語ごとにいちじるしく異なっている。それは単に言語の構造によって異なるだけでなく,その言語が用いられる文化的環境の相異や,社会階層の相異によって異なるのである。」
参考文献;
田中克彦『チョムスキー』 (岩波現代文庫) |
|
統辞 |
|
ノーム・チョムスキー『統辞構造論』を読む。

「まえがき」で,著者は,
「言語構造に関する3つのモデルを考察し,それらの限界を明確にしていきたい。ある種の極めて単純なコミュニケーション理論に基づく言語モデルや,『直接構成素分析』として現在広く知られているものの大部分を組み込んだより強力なモデルが,文法記述のためには全く適正を欠いていることが判るだろう。これらのモデルを考察し適用することによって,言語構造に関するいくつかの事実に光が当たり,また言語構造におけるいくつもの欠陥が浮き彫りにされる。特に,能動−受動関係のような文同士の関係を説明することができないという欠陥である。そして言語構造に関する第3のモデル,即ち変換(transformational)モデルを展開する。このモデルは,或る重要な面において直接構成素分析よりも一層強力であり,今述べような文同士の関係を自然な形で説明できるものである。変換の理論を注意深く定式化し,それを広く英語に適用してみると,このモデルの設計にあたって特にその説明の対象とされた現象を超える広範囲の諸現象に対して多くの洞察を与えるということが判る。つまり,形式化を行うことによって,上述したとおりの消極的および積極的な貢献が実際になされ得るということが判るのである。」
と,ある意味,高らかに宣言している。そして,「統辞論」については,冒頭で,
「統辞論(syntax)は,個別の言語において分が構築される諸原理とプロセスの研究である。ある言語の統辞的研究は,分析の対象となっているその言語の文を産み出すある種の装置とみなせるような文法を構築することを目標としている。より一般的に言うと,言語学者は,文を産み出すことに成功した文法の根底にある根源的諸特性を決定するという問題に取り組まなければならない。こうした研究から最終的にもたらされる成果は言語構造の理論でなくてはならず,この理論においては,特定の個別言語に言及することなしに,個別文法で用いられる記憶装置が抽象的に提示され,研究される。そしてこの理論の1つの機能は,個々の言語のコーパス(発話やテキストの集積)が与えられた時に,その言語にとっての文法を選択できるような一般的方法を提供するということである。」
と,その研究者の奥行と広さを明言している。その「文を産み出す装置」を,「構造的に可能な化合物に関する化学理論」と類比して,こう喩えている。
「ちょうど文法が文法的に『可能な』発話を全て生成するのと同様に,この化学理論は物理的に可能な化合物全てを生成するとも言える。そして,個々の発話の分析と合成といった特定の問題を研究するためには文法に依拠しなくてはならないのと同じように,化学理論も,特定の化合物の定性分析および合成の技術に対する理論的基礎を与えるものとして機能するのである。」
その理論構造とその可能性を,本書の付録としてついている「『言語理論の論理構造』序論」で,著者は,こう述べている。
「Lの文法とはLの理論であり,この理論はLの要素や規則に関する言語学者の諸仮説を組み入れたものである。この文法は,Lを身につけた話者−聴者によって獲得されたLの知識というものに関する説明である。変換生成文法の理論(あるいは,他の一般言語理論)は,人間言語というものを定義付けるような諸特性,即ち『言語の本質』に関する仮説を表現する。このように解釈された一般言語理論は,原語知識の獲得のための基礎を与えるところの生得的で内在的な言語機能に関する理論と見なすことが出来る。子供はその『初期状態』においては自分が暮らしている言語共同体の言語に関して何も知らされていない。その言語を決定するための,つまりその言語知っているという『最終状態』に到達するための,一群のメカニズム(その子供の『言語機能』と呼べるもの)が子供に備わっていることは明らかである。一般言語理論は子供の初期状態を記述し,子供の文法はその子供の最終状態を記述する。ここで,一般言語理論は説明理論であると見なすのが妥当であろう。というのも,一般言語理論は,言語共同体において子供がどのようにしてその共同体の言語を知るようになるか,そしてある表現の形式や意味に関する無数の事実を知るようになるのか,等々の説明を追求しているからである。
これと完全に類比的な方法で,人間知性の他の側面を研究することが出来るかもしれない。人間がある種のデータを基にして発達させた知識や信念のシステムを考えてみよう。(中略)このシステムの獲得が―言語の獲得と同様に―人間の通常の生物学的な機能であるのならば,我々は全ての人間に共通の属性である初期状態を特徴付けようとするだろう。この特徴付けが満たすべき経験的条件というのは,所与の知識や信念のシステムを獲得する人間が利用できる類のデータが与えられた時に,初期状態における『装置』がこのシステムが表示されているような最終状態に到達できるということである。この初期状態を特徴付ける一般理論は,(中略)人間が持つある特定の認知機能(cognitive
faculty)に関する説明理論であると言える。」
言語は,一つのきっかけとして,「人間知性の一般構造の考察」へと広がっていく。脳科学者からの生成文法の脳内根拠,つまり認知のシステムの研究プロセスについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163351.html
で,すでに触れた。チョムスキーの構想の奥行の深さがわかるところでもある。
しかし,こうした生成文法の本書での結論は,
「句構造に基づく直接的記述の範囲を基本的な文の核(複合的な動詞句や名詞句を含まない,単文かつ平叙文かつ能動文)に限定し,これらの基本的文(精確に言うと,これらの文の基底にある連鎖)から他のあらゆる文を変換(の繰り返しの適用)によって派生させるようにすれば,英語の記述を大いに単純化できる上に,英語の形式的構造に対する斬新で重要な洞察を得ることが出来る。」
「(その)文法は,3部構成の内部構造をもつと考えられる。文法にはには,句構造を再構築することが出来る諸法則の列と,形態素の連鎖を音素の連鎖に換える形態音素規則の列があ。この2種類の規則の列を結びつけるものとして変換規則の列があり,変換規則は,句構造を伴う連鎖を形態音素規則が適用できる新たな連鎖に換える。句構造規則と形態音素規則は,変換規則とは異なり初等的であると言える。変換をある連鎖に適用するためには,その連鎖の派生の履歴を知っていなければならないが,変換以外の諸規則を適用するときには,その規則が適用される連鎖の形が判っていれば十分なのである。」
という説明になる。この「素描」だけでは,その具体的核心は,なかなか得られない。その意味で,本書は,訳者(福井直樹・辻子美保子)が,解説で,
「言語研究に広く深い影響を与え,しばしば学問上の『革命』と称される生成文法理論の誕生は,『統辞構造論』という一冊の小冊子によって告げられたとされることが多い」
と述べるように,名高い生成文法理論を世に問うた一書ということになるのは確かだが,しかし,著者自身も,
「ここでの大半の議論の基礎となっている変換の理論および英語の変換構造に関する研究は,本書では簡潔に素描されているだけ」
で,訳者が指摘するように,本『統辞構造論』(1957)は,
「『現代ヘブライ語の形態音素論』(1951),『言語理論の論理構造』(1955),「言語記述のための3つのモデル」(1956)のエッセンスを非常に凝縮した形でインフォーマルにまとめた著作」
であり,しかも,前二著は,長く未出版のままであって,実に読んでいても,意味のよくくみ取れない抽象度の高い著述なのである。
「『統辞構造論』に書かれていることを正確に理解するためには,これら3つの著作の大まかな内容およびそれが生まれて来る知的背景となった,さまざまな学問分野に於ける当時の展開をある程度知っていることが望ましい」
として,そのための解説を,
「『生成文法の企て』の原点」
として,本書成立までの理論形成の背景史を書き加えてくれている。しかし,それでもなお,素人には,隔靴掻痒,視界の開けないことおびただしい。
しかし素描だけでも,理論の是非判断は到底できないとしても,その構想に大きさは見えてくる。『統辞構造論』の注で,チョムスキーがこう述べていることは,実に含意が深い。
「言語理論は,文法を書いている言語に対するメタ言語で定式化されることになる。つまり,文法を構成する対象である(個別)言語に対してはメタメタ言語による定式化なのである。」
この,メタメタ言語による定式化,がまるで駄目なのは,ソシュールだのヤコブソンだのチョムスキーだの,一斉に靡くわが国の学者を見るとわかるが,それは(言語学だけにとどまらずニーチェだの,カントだの,ヘーゲルだの,ヴィトゲンシュタインだの,フーコーだのと靡くのも同じで),思想や哲学というもの(メタメタ言語による定式化そのもの)の欠如以外の何ものでもない。それは,今日,ソフト(これもまた,メタメタ言語による定式化)において完全に後れを取り(というよりコピーそのものになり),いまだ「ものづくり」しか自慢できないわが国の貧しさを示しているようで,悲哀というより,絶望感に駆られる。
ついでながら,チョムスキーはいまだ健在で,オリバー・ストーンやマイケル・ムーアとともに,普天間基地の辺野古移転に反対しているアメリカ文化人29人の一人であることも,付記しておきたい。
参考文献;
ノーム・チョムスキー『統辞構造論』(岩波文庫) |
|
スピリチュアリズム |
|
江原啓之『スピリチュアリズムを語る』を読む。
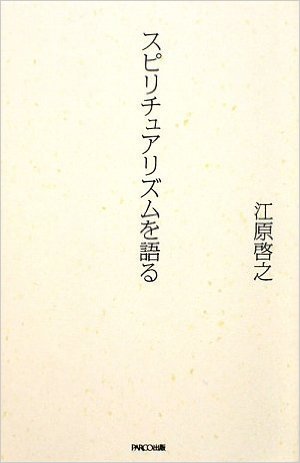
「出会いは『宿命』です。しかし結婚するかどうかは『運命』です。」
という著者の言葉がある。それは,
「『運命』を築くという自由が与えられている」
ということでもある。たましいにとってたいせつなのは,「生き抜く」こと,
「生き抜くことに価値がある。」
だから,「たましい」は,自分自身の成長のために,
「自分で超えられない課題は選ばない」
「自分自身に必要な出来事しか起きない」
のだという。
スピリチュアリズムというのは,
どう生きるかという哲学,
なのだとつくづく思う。それは,
人から見られていることを意識する,
というのと,
人から見護られていることを意識する,
というのとの,差のように見える。人を意識しないで自己完結している人生は,歪んでいるとは思うが,その人を誰とするか,で,少し変わる。別に神である必要はない。
スピリチュアリズムというのは,
「ひとりひとりのなかに崇高な神の部分=神我(しんが)が宿っている」
と,とらえることだと,著者はいう。それを仏性(ぶっしょう)と置き換えてもいいかもしれない。だから,
「その人の生き方は,死にあらわれる。最後に生きざまがあらわれるわけです。」
と。まさに,
人事蓋棺定,
つまり,人の行事の是非善悪は棺の蓋をして定まる,である。だから,
「自分自身が生まれてきた目的を理解して,それをちゃんと行っていく姿勢」
が必要になる。同じことかもしれないが,
「価値があるから生きるのではない。生き抜くことに価値がある。」
とも言う。ふと,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/410780513.html
で書いた,V・E・フランクルを思い出した。フランクルは問う。
人生が何を自分にしてくれるか,ではなく,自分が人生にどう応えるかだ,
と。そして,人間が実現できる価値は,創造価値,体験価値,態度価値,だと提唱した。
創造価値とは,人間が行動したり何かを作ったりすることで実現される価値である。仕事をしたり,芸術作品を創作したりすることがこれに当たる。
体験価値とは,人間が何かを体験することで実現される価値である。芸術を鑑賞したり,自然の美しさを体験したり,あるいは人を愛したりすることでこの価値は実現される。
態度価値とは,人間が運命を受け止める態度によって実現される価値である。
フランクルの,『夜と霧』を読むと,最後まで生き残るのは,
自分が生きる意味,
を意識している人々であった。
「なぜ生きるかを知っている者は,どのように生きることにも耐えられる」
と,そして必要なのは,
「生きる意味についての問いを百八十度転換することだ。わたしたちが生きていることから何を期待するかではなく,むしろ,ひたすら生きることがわたしたちから何を期待しているかが問題なのだ,」
それは,
何をするために自分はいるのか,
何をするために自分は生きているのか,
を意識しているということでもある。それを考えることこそが,
スピリチュアリティ
であるということなのではないか。マザー・テレサは,
祈りましょう,
と繰り返したが,著者は,
「祈りとは,『自分自身』という神を見つめること,つまり内観するということをいうのです。」
という。
内なる神と対話すること,である。それは,『論語』の,
日に三たび吾が身を省みる。人の為に謀りて忠ならざるか,朋友と交わりて信ならざるか,習わざりしを伝えしか,
であり,
一,至誠に悖る勿かりしか
一,言行に恥づる勿かりしか
一,気力に缺くる勿かりしか
一,努力に憾み勿かりしか
一,不精に亘る勿なかりしか
という五省にも通じるものがある(日本を占領したアメリカ海軍の英訳文がアナポリス海軍兵学校に掲示されたと聞く)。それは,
わたしはどうすべきか,
と,自らに問うことだ。答えは,おのれ自身の中にある。
「祈りとは自分自身に問いかけ,実践すること。決して神頼みすることでも,依存することでもありません。」
天については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163401.html
で触れた。
参考文献;
江原啓之『スピリチュアリズムを語る』(PARCO出版)
アン・ドゥーリー編『シルバー・パーチの霊訓』(潮文社)
ヴィクトール・E・フランクル『夜と霧』(みすず書房)
ヴィクトール・E・フランクル『それでも人生にイエスと言う』(春秋社)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫) |
|
ロボット |
|
浅田稔『ロボットという思想〜脳と知能の謎に挑む』を読む。

人間の知に迫るアプローチに,
脳科学や神経学などの自然科学的アプローチ,
哲学,心理学,社会学などの,人文科学的アプローチ,
以外に,第三の道として,
ロボットにより前二者のアプローチの統合を図る道がある,
と著者は書く。ロボットという考え方とは,
「ロボットという人工物を設計して作動させる…だけでなく,その過程を通じて,人間の知の発生の理解を試みる」
ものだという。そのためには,飛行機を開発した人々が,鳥の見かけにとらわれてそれに似た翼をつくるのではなく,鳥の飛行の根本原理を深化したように,
「知的行動発生の最も基本的な原理を見極め,それを実際の環境中に構築し,実験しながらスケールアップしていく」
という。重要なのは,
①設計の視点で「知の発生」にかかわる既存分野の知見を見直す。
②人工物としての知の発生モデルを構築する。
③設計・製作・作動のループを通して,知の発生モデルを精錬する。その際,作動結果から得られる事実を既存分野へフィードバックし,共有可能な新たな知の理解と創造をめざす。
として,ここに,
ロボティクス(ロボット学)の未来がある,
し,
「人間という謎の未来がある」
と,著者は書く。それは,ある意味,人間が生誕して知を得ていくように,ロボットが,そうやって知を自律的に得ていくプロセスを創り出そうという壮大なプロジェクトである。それを,
人間とロボティクスを融合するヒューマノイド・サイエンス
と呼んでいる。それをこう説明する。
「脳を扱う脳科学,心の発達を扱う心理学,ロボットを扱うロボティクスの三者ともに,人間の知的発達過程の理解と構築という共通課題を持っています。これらが結びつくことで人間とロボットの関わり方の本質に迫る学問領域―『認知発達ロボティクス』が確立され,人間社会に真に貢献しうる適応・発達ロボットの基本原理を世界に提供できるようになれるのではないか。」
本書は,「認知発達ロボティクス」の研究プロセスを介して,知の発生がどこまで,現実化しているか(ロボットとして作れているか)を,詳しく紹介している。
当然著者が目指しているロボットは,人間の代わりをする労働ロボットでも,兵器ロボットでも,エンターテインメントロボットでもなく,
人間を理解するためのロボット,
であり,そのためには,一番いいのは,
人間をつくってみる,
ことだが,それはできないから,
人間を映すロボット,
をつくるこことで,それを果たそうというのである。著者らの作っている,ヒューマノイドロボットCB2,については,
http://www.jst.go.jp/pr/info/info401/
http://robot.watch.impress.co.jp/cda/column/2007/08/03/584.html
にも詳しいが,
「人間が赤ちゃんから大人へとどのように発達していくか,その過程」
を調べ,カタチにしていくことで,
「ロボットを通じて人間を知る」
ことになり,同時にそれをまたカタチにし直していく。基本は,
自律的に行動するロボット
であり,それは,著者らが主催する「ロボカップ」によく表れている。「ロボコン」との違いを,
「ロボコンのロボットの多くがリモコンで操作するものなのに対して,ロボカップに出場するロボットはロボット自身が『自律』して動くのが基本」
であり,
「競技が始まったら,人間が外からリモコンで操作することは一切しません。すべてロボットが自分で判断し,ゴールを目指します。」
という,学習する機能を備え,成長するロボットなのであり,
「2050年『サッカーの世界チャンピオンチームに勝てる,自律型ヒューマノイドロボット(人間型ロボット)のチームをつくる』という夢」
に本気でチャレンジしているところにみることができる。そのとき,自律とは,
「ヘディングして人間が脳震盪を起こしてもロボットがケロッとしていたらまずいですね。やはり人間並みに傷ついたりするからだをつくろうとしたら,痛みを感じないといけないのです。」
という自律でもあるが,認知発達ロボティクスは,
「理解の対象となるヒトの発達モデルを人工物のなかに埋め込み,環境の中で作動させ,その挙動から,発達モデルの新たな理解を目指す」
という「構成論的ブローチ」であり,今までのように制作者のプログラミングを埋め込んで動かすというのとは違う発想であることを,著者はこう説明する。
「従来であれば,ロボットの設計者が明示的にロボットの行動を規定しプログラミングしてきたことに対して,ロボットが環境との相互作用をとおして,世界どのように表現し行動を確定していくかといったロボットの認知発達過程の設計と理解に焦点を当てるものです。」
だから,この自律は,
ロボットとして自己完結するのではなく,
環境との間で,相互作用し,行動するなかに,
「自分の行動をどのように規定していくかという過程のなかに,ロボットが『自我』を見いだしていく道筋が解釈できるのではないかという期待」
のもてる,
環境と相互作用する身体,
でなければならない,という開かれた,まさに人間と同じである,という意味でもある。
プロジェクト(浅田共創知能システムプロジェクト)は多岐にわたるが,
起き上がりロボット
空気圧人口筋の二足歩行ロボット
柔らかい指の内部に多くの感覚センサーを配置した柔軟ロボットハンド
等々では,人間に近い身体構造をしている。これについて,著者はこう語る。
「(これらは)人間の身体構造(筋肉や感覚器)からうまく学び,それを利用して,それぞれの行動を実現してきた…。そうした発想からロボットをつくった結果,あらかじめ人間が動きを考え,その通り動くようにプログラミングした場合に比べて,事前に決めておく部分の割合がすくなくてすみました。これは人間に戻して言えば,行動における脳にあたる部分の割合が少なくてすむということです。身体が脳の代わりをしていたと言えるかもしれません。
これを脳の発達という視点から考えてみると,興味深い仮説が成り立ちます。もしも脳が,身体から得た情報をもとに,一度行った動きを『学習』することができたらどうなるでしょうか。
わたしたち人間は,それと同じような経験をすることがあります。たとえば自転車の乗り方を身につけるとき,最初はなかなかうまくいきません。いろいろ意識して考えながら,なんとかぎこちなく練習を繰り返します。それが,何度も転びながら練習を繰り返すうちに,いつしか自然と身体が乗り方を学習し,上手に乗れるようになります。このとき,脳のなかに自転車を乗りこなすように身体を動かす回路ができたと考えられます。いわば,『身体が脳をつくった』わけです。
こうした自らが学習していく能力をロボットに与え,ロボット自身が教えられた内容について解釈し,賢くなっていく過程を知ろうというのが,私たちの研究の基本的な考え方です。」
これが,構成論的アプローチ,
「人間の知能に関する仮説を立ててロボットを作って動かし,そのロボットの成長していくさまを見ることで,先の仮説を検証していく」
プロセスなのである。これは,
胎児シミュレーション,
音声を模倣する音声模倣ロボット
母親の表情を読み取る共感ロボット,
認知発達の脳マップ,
等々,「心の理解とココロの創発に向けた発達モデル」の解明,へと進んでいく。
いやはや,いつの日か,ロボットと共生する社会が来ることを予感させる。現に,著者は,
「『ロボットを通じて人間を知る』課題から,さらにその先に人間がロボットと暮らす社会とはどのようなものか,という課題を見据えなければいけないのではないでしょうか。」
と言っているのである。
参考文献;
浅田稔『ロボットという思想〜脳と知能の謎に挑む』(NHKブックス) |
|
創造性 |
|
シャロン・ ベイリン『創造性とは何か―その理解と実現のために 』を読む。

まあ,創造性開発に関わる本は,最近はともかく,管見だけでも,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/prod0841.htm
と,すさまじいものがある。本書もそういう類いの一冊だが,特色は,
創造性,
というものを特殊な思考と見なす姿勢への批判だ。僕も同感だ。著者は,「序」で,
「“創造性”という概念は,その語源から離れてきたきらいがある。私たちが忘れてしまっているのは,“創造性”という言葉がもともと『創意工夫して造り出すこと』という意味で使われていたはずであり,すばらしい達成や成果と関係しているとしいう点だ。」
と述べる。でなければ,
創造性ごっこ,
発想ごっこ,
にしかならないと,僕も思う。著者は,創造性について見られる見解を次のように整理し,本書を通して,それを徹底的に批判している。
創造性についての見解の共通点は,
①「目新しいことを生みだすという言い方で使われる“独創性(オリジナリティ)”と,創造性との間に密接な関係があるという点だ。漸進で,拡散的だが,日常一般のことがらや,すでに容認されているものとは決定的に違うという意味が,“創造性”という言葉にこめられているようだ。」
②「創造性とは,過去と,また現存する伝統と完全に決別する,つまり枠組みを根本的に帰るという意味に受けとっている。」
③「創造性には飛躍があるという考え方の根本に,『創造的な成果の“価値”など,客観的に決められない』という,いまひとつの仮説がある。だが,若しも創造性が,過去の伝統と,それにともなう考え方の枠組みとの根本的な断絶に特徴ありとすれば,創造的な仕事を評価できる基準などありえないし,そうした評価など全く主観的なものとなる。」
④「こうした考えに従うと,創造的成果の価値が論じられるか否かの結論として,創造性に必要なのは,成果として製作したものにあるのではないという点に行きつく。」
⑤「創造過程は,『いままでの規則を打破しては,パターンを再構築する』というようなことを含めると,必然的に自由で,何ら拘束を受けるものではないはずという考えが強く出る。」
⑥「創造性は,技能以上のもの,即ち経験を越え,何かに原因を求めることのできない,元々説明の出来ない想像上のものという考えに落ちつく。」
とまとめ,こうした見解によれば,
「ふつうの思考は,論理,慣習,厳密さ,きちょうめんな判断,それに以前に確立され規則やパターンに固執する点に特徴がある」
ということになり,創造的思考は,
「想像力の飛躍,理性によらないプロセス,カタやぶりの判断停止,そして止めどなく湧いてくるアイデア」
というイメージになる,と。多少のカリカチュアはあるにしろ,本書で槍玉に挙げられている。
アーサー・ケストラー(『創造活動の理論』),
エドワード・デ・ノボ(『六色ハット』)
トーマス・クーン(『科学革命の構造』)
等々,の創造性論者たちだ。で,著者は,
「創造的な成果に見られる独創性は,伝統との関連を抜きにして理解できないこと」
「創造性を評価する客観的な基準があり,その基準は,作品が発展していく際に連綿と引きつがれる伝統によって,かなり明確に示せる」
「創造性をみる唯一筋の通った方法は,価値あるものを創り出すか否かという点にある。」
「創造性にとって,特殊な専門分野での知識や規則,技能,方法が最も重要」
「想像は技能に密接に結びついていて,それを理解すれば創造性の説明にもつながる」
という立論を,創造性論者の論点に添いつつ論じていく。その論点は,
芸術,
科学と技術,
数学,
日常生活での問題解決,
幅広い。僕は,発想とは,
知識と経験の函数である,
と思っている。過去から断絶しているように見えるのは結果であって,プロセスではない。
「独創性というのは,行き当たりばったりの目新しさではない。いわれのない目新しさでもない。いままでのものと差をつけるような,また,時代の要求に応えて,問題を解決し,芸術の進展に寄与するような,他と一味“違う”点にかかわっているのが独創性なのである。」
という著者の言葉に同感である。ベイトソンは,
情報とは差異である,
として,
「情報の1ビットとは,(受け手にとって)一個の差異(ちがい)を生む差異である。そうした差異が回路内を次々と変換しながら伝わっていくもの,それが観念アイデアの基本形である。」
といった。その差異は,顕在化しているとは限らない。誰にでも自明とは限らない。その僅かなその差異に気づいたものが,それをカタチにしていく。
「芸術の価値をみるのに関係しているのは,伝統を知ることであり,いかに作品が伝統と適合したり,はみだしたりしているかである。」
と,著者の言うのはその意味である,と思う。この辺りのことは,本書でも言及する,
ロバート・ワインバーグ(『創造性の研究』)
が,かなり掘り下げて,実証研究し,
「創造的思考は,増加した情報に基づいて従来の考えを一つひとつ修正しながら,増大していくという性質をもつ」
と述べていることと符合する。
参考文献;
シャロン・ベイリン『創造性とは何か―その理解と実現のために 』(法政大学出版局)
グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』(思索社) |
|
ミドルワールド |
|
マーク・ホウ『ミドルワールド―動き続ける物質と生命の起原』を読む。

著者が名づけたらしい,ミドルワールドという世界は,口絵で,
マクロワールド
ミドルワールド
ミクロワールド
と区分し,マクロワールドは,
ミクロン(1000分の一ミリメートル以上)以上の世界,
として,宇宙,蒸気機関車,自動車,自転車,バイク,大砲の弾,羽毛,動物,植物,微生物,
と例示し,ミクロワールドは,
ナノメートル(100万分の一ミリメートル)以下の世界,
として,
分子,原子,原子核,素粒子,光子,陽子,中性子,電子,
と例示する。そして,ミドルワールドを,
マクロワールドとミクロワールドの間の世界として,
細胞(DNA,RNA,タンパク質,ミトコンドリア,リボゾーム,分子モーター),ウイルス,バクテリア,筋肉(アクチン,ミオシン),天然樹脂,合成高分子(シャンプー,リンス,界面活性剤),石鹸,ミルクに浮かぶ脂肪の粒,
等々を例示する。
しかし,正直に言うが,本書の書き方が,「ミドルワールド」に関わった科学者の小伝を中心にするためか,ミドルワールドが何なのか,遂にわからなかった。「ミドルワールド」の定義も,口絵に掲げられた,三角形を三区分した以上にはなく,隔靴掻痒,わからないまま,命と生活に一番関わる世界だ,という以上の理解に出なかった。
で,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95#/media/File:Brownian_motion_large.gif
にある,この世界特有の,ブラウン運動,
「液体のような溶媒中(媒質としては気体、固体もあり得る)に浮遊する微粒子(例:コロイド)が、不規則(ランダム)に運動する現象」
から,想定するしかなかった。ブラウン運動とは,
「ロバート・ブラウンが、水の浸透圧で破裂した花粉から水中に流出し浮遊した微粒子を、顕微鏡下で観察中に発見し、論文『植物の花粉に含まれている微粒子について』で発表した。
この現象は長い間原因が不明のままであったが、1905年、アインシュタインにより、熱運動する媒質の分子の不規則な衝突によって引き起こされているという論文が発表された。この論文により当時不確かだった原子および分子の存在が、実験的において証明出来る可能性が示された。後にこれは実験的に検証され、原子や分子が確かに実在することが確認された。
この現象は,かなり広い意味で使用されることもあり、類似した現象として、電気回路における熱雑音(ランジュバン方程式)や、希薄な気体中に置かれた、微小な鏡の不規則な振動(気体分子による)などもブラウン運動の範疇として説明される。」
という定義を確認して,ようやくこの世界の概要がつかめた。
ブラウン運動,
の名のもとになった,スコットランドの植物学者ロバート・ブラウンが,顕微鏡で見た花粉の粒子の「ぴくぴくと動く」様子を始めて,世界に知らしめた,ところから,本書を描き始めている。
ブラウン,
の名から,(たぶんブラウン運動のことだろうなと)薄々は感じられたが,何の説明もないまま,次は,60年後の,
筋肉タンパク質
の動きに飛び,
「動きやまないのは,筋肉に限らない,化学物質を細胞内に運び込む分子とか,タンパク質をちゃんと機能する形に整える過程,酵素の働き,DNA分子がやるべき仕事をやっているときなど,細胞の中で起こる生命現象にはランダム性(変則性・無秩序性のことだが,本書ではこれを用語として使用する)や小刻みな動き,予測不能さがつきもののようだ。」
と書き,これが,生命の基本的メカニズムに関わる現象らしいとは推測がつく。こういう推測をしなければ読み解けない著作の追尾は,結構しんどい。
そして,
「動きやまない筋肉タンパク質と花粉の粒子の共通点は,何か?
―大きさ。
大きさの問題なのだ。ブラウンが明らかにしたように,出鱈目に,疲れを知らぬように踊るのは,花粉の粒子だけではなかった。鉱物の粒子も,年度も,踊ったのだ。石炭の粉塵…,砂鉄など,すべて踊った。ブラウンの踊る物体の共通点は,それらの大きさだった。
最大のものは,直径が1ミリメートルの5000分の一から10000分の一である。すべてが,人間の髪の毛の太さの100分の一から10分の一の範囲に収まった。これは独特のおおきさだ。この大きさの物体に起こる現象,このスケールの実体に起こる現象…によって,我々が何であり,我々に何ができるかが決まる。」
と書き,「ミドルワールド」と,これを著者が呼んでいるのである。
ブラウンの発見以降200年,この世界の広がりが拡大しつづけている。ブラウンは,「命の仕組みがどうなっているか」という疑問から,花粉の粒子を顕微鏡でのぞいたが,当時,
「彼の観察した現象が生命とは何の関係もないという結論になった」
が,皮肉なことに,彼の発見したブラウン運動こそが,
生命と物質の境界線の曖昧なグレーゾーン
の発見であり,
「原始のスープはブラウン運動の風味がした。」
という著者の言葉は,しかし,メタファとして,なかなか含意は深い,と感じた。
参考文献;
マーク・ホウ『ミドルワールド―動き続ける物質と生命の起原』(紀伊国屋書店)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95 |
|
神道 |
|
伊藤聡『神道とは何か ― 神と仏の日本史』を読む。

サブタイトルに,
神と仏の日本史
とあるのが肝,いま目にしている神道とは,明治に作り上げられたものだ。維新後の廃仏毀釈で,狂気のようにお寺が廃棄され,貴重な文化遺産が散逸した。まるで,ISと同じ行為が,日本を数年跋扈した。それを主導したのは,
平田派および津和野派の国学者・神職,
水戸学の同調者,
これらの影響を受けた新政府が派遣した行政担当者,
である。政府は,
神道を「神武創業之始」の「純粋」な姿に復すること,つまり神仏習合的信仰の排除,
を意図した。それは,明治元年から,四年まで全国を荒れ狂った。いまの神道イメージは,そういうISもどきの政権担当者が作り上げたものだ,と言っても過言ではない,と僕は思っている。そのとき,
「興福寺は,春日大社と一体だったために廃寺となり,僧侶全体が還俗させられた。五重塔が二十五円で売られたというのは有名な話はこのときのことである。結局,五重塔自体は残ったが,金堂・食堂などの多くの堂舎や一条院・大乗院などの院家は破却されてしまった。」
どんな過去であれ,おのれの過去の歴史と文化を破却し,破壊する権力は偽物だ。レーニンも毛沢東も,過去の主要文化遺産を破却していない。
「現代の私たちは,『神道』という語を,『日本の民俗宗教』の総称として理解している。ところが,歴史的に見た場合,この語は各時代を通じて,そのように理解されていたのではなかった。」
として,本書では,津田左右吉の『日本の神道』に上げている,「神道」の意味を,上げる。それによると,
①古くから伝えられてきた日本の民族的風習としての宗教(呪術も含める)
②神の権威,力,はたらき,しわざ,神としての地位,神であること,もしくは神そのもの
③民族的風習としての宗教に何らかの思想的解釈を加えたもの(例:両部神道,唯一神道,垂加神道)
④特定の神社で宣伝されているもの(例:伊勢神道,山王神道)
⑤日本に特殊な政治若しくは道徳の規範としての意義に用いられるもの
⑥宗派神道(例:天理教,金光教)
とあり,
「古代における意味は,①②のみであり,それ以降は中世以降に現れるという。今日,われわれが漠然とイメージしている『神道』は①に近い。これらーに日本人の精神の基底という意味あいを込めて,⑤を重ねて理解していることも多いと思う。③④は中世,近世,⑥は近世後期から近代に起こった神道流派・教派であるから,神道全体を指すものではない,」
という。「神道」という語の初見は,『日本書紀』で,本来は,(津田の指摘によると),「当時中国で使用されていた成語からの借用である。『神道』の語は,中国大陸では古くから使われてきた」もので,
「『霊妙』なる『理法』を意味し,そののち道教や仏教経典に取り入れられ,道・仏それ自体を指して使われている。また,より一般的には,神祇・神霊やその祭祀・呪法を意味するのである。」
『日本書紀』で,「神道」という言葉を使った意味は,道教の影響,神祇の意味の転用などいろいろあるが,津田は,
「日本固有の神祇信仰を仏教と対比するため」
用いたと解している。しかし,平安中期まで用例は少なく,そのほとんどが,津田の分類の②の意味で使われている。とするなら,
「『日本書紀』のみ,特殊な意味で用いられたとすることになり,…むしろ②すなわち『神の権威,力,はたらき,しわざ,神としての地位,神であること,もしくは神そのもの』という意味に解すべきではなかろうか。」
と,著者は述べる。1603年に完成した『日葡辞典』には,
「神々および神々に関する事柄」
と。定義している。このことは,
「日本の神信仰やそれにまつわる言説の総体を『神道』と呼ぶことは,解釈がわかれる『日本書記』の例を除くと,古代においては存在せず,中世,あるいは近世になって起こってきた」
と考えることができる,と著者は考え,
「現代の我々は,『神道』の語を,このような歴史過程のなかで見いだされたてきた呼称であるということを棚上げして,日本の民族宗教を指す語として使用している。しかし,『神道』の語をそのように用いることは,上代から現代に至るまで,一貫して『神道』なるものが存在していたかのような印象を与えかねない。…しかしながら,このような意識こそ,まさに近世の国学者等が唱えていたことであり,神仏分離を正当化する根拠となったものである。」
と書く。そういう意図から,本書は,
「日本の神信仰と言説の総体が『神道』の名で呼ばれるようになったのはいつからなのか,さらに道徳的・倫理的ニュアンスを含意するようになったのはいつからなのかという問題」
を追及する。
実は,「神」という漢字を当てているが,「カミ」の語源すらはっきりしていない。本居宣長も,
「迦微(かみ)と申す名の義はいまだ思ひ得ず」
と言うほどである。古代,霊的なものを示す言葉に,「カミ」「タマ」「モノ」「オニ」がある。「タマ」は,霊魂を指す,人のみならずすべての存在は「タマ」をもち,その霊威をおそれるものを「モノ」と呼び,「オニ」は,「隠」で,隠れて見えない存在を指す。
著者は,「カミ」の基本的性格を次のように整理している。
①霊的なものとして把握されており,実態的なものとみなされていない。ただ,すべての「タマ」が神なのではなく,強力な霊威・脅威をもつ「タマ」が「カミ」として祀られる。か「カミ」は「タマ」の一種なのである。
②「モノ」「オニ」も,「タマ」に属す。「カミ」が神となり,「カミ」の否定的な部分がモノ(名指し得ぬもの)は,後に怨霊的存在として,「モツケ」「モノノケ(物+気)」となる。「オニ」は「カミ」の最も荒々しい部分を取り出したもの。といって,「カミ」には,「モノ」「オニ」要素が消えたわけではない。
③「タマ」と同じく,「カミ」は目に見えないとされた。
④「カミ」は人と直接接触せず,意志を伝える時は,巫女や子供に憑依する。
⑤「カミ」の怒りは祟りという形をとる。
その「カミ」が,仏教伝来以降,神仏習合,本地垂迹を経て,神と仏は,いずれが裏か面か分かちがたくよじれていく。わずか四年弱で,廃仏毀釈が終焉したのは,仏教抜きでは,あるいは密教,修験道も含めた,仏教系抜きで,神道理論が成り立っていかないからにほかならない。
著者の立場は明確である。
「『神と仏の日本史』という副題が示すように,神道とは神祇信仰(あるいは神[カミ]信仰)と仏教(および他の大陸思想)との交流のなかで,後天的に作り出された宗教である」
である。そのことは,仏教と絡み合いながら思想化されていく神道の歴史が,おのずと証している。
参考文献;
伊藤聡『神道とは何か ― 神と仏の日本史』
(中公新書) |
|
恋愛 |
|
小谷野敦『日本恋愛思想史 - 記紀万葉から現代まで』を読む。

「比較恋愛思想史」が専門という著者の,日本のそれであるが,適宜他国と対比しつつ,わが国をポジショニングし直してくれている。ただし,彼我ともに,直接的資料があるわけではないので,文芸作品を通して見た,それであるということであるが。
著者の主張の特徴は,「序文」に,
「日本における恋愛思想は,谷崎純一郎が『恋愛及び色情』(1931)で述べている通り,女性崇拝的な平安朝文化と,女性蔑視的な武士および町人の文化とで違っていて,同じ『前近代日本』の『色』の文化などとくくることはできない。遊里を舞台とし,娼婦を恋の相手とするのは,近世町人の遊治郎の文化であり,一般的な倫理とは違うものであった。
1980年代以降の恋愛やセックスの研究は,一方で階層による違いを無視していた。徳川時代において性が自由であったかのように言うのはその最たるもので,武家,上層の農民,商人の家では,娘の貞操はそれなりに厳しく守られたものである。また西洋においても,近代的な恋愛は十七世紀辺りから市民階級を中心に徐々に広まったものである。近世日本では,遊里における娼婦相手の『恋』という概念が広まったりしていたので,明治の知識人青年は,あたかも西洋の小説に描かれるように『恋愛』を新しいものとみなしたが,中世以前の文藝には別種の恋が描かれていた。」
とあるように,その時代に,いまの世界を投影することへの戒めである。たとえば,滑稽なのは,
恋愛輸入品説,
である。これは,
「『恋愛』は,明治になって西洋から輸入されたしそうである,という説である。」
むろん「恋愛」という言葉は,明治になって造語されたが,「恋」はそれ以前からあったはずである。なのに,
「前近代の日本は,『色』の世界だった。」
というものである。それは,江戸時代の遊里を中心とする「洒落本」の遊里文化を指している。しかし,著者は言う。
「明治の文学者が,今の一般的知識人のように物を知っていたというわけではない。彼らは『源氏物語』を中心とする王朝女流文藝について,ほとんど知らなかった。『源氏』を読んでいたのは,尾崎紅葉,田山花袋,近松秋江,与謝野晶子などで,晶子は明治末に現代語訳を出したが,売れず,読まれなかった。『源氏』を一般の読書階層が読むようになったのは,実に昭和十四年に谷崎潤一郎の現代語訳がベストセラーになってからで,それはアーサー・ウェイリーが英訳を完成させた後だった。
漱石の時代の知識人は,英語が非常によく出来た。また,漢文を中心とした教育を受けた。世界各国の文学に『恋愛』は現れるが,漢文学だけは別である。漱石が,英文学というのを漢文詩のようなものだと思って専攻し,のちに失望したというのはよく知られる話だが,漢文学というのはいわゆる文学=リテラチュアではなく,漢詩と歴史,道徳などを中心とした『文』のことで,なかんずく漢文学は恋愛を軽視し,女性蔑視的だった。」
つまり,そうした明治期の文学者は,徳川期の軟文学はよく知っていた。だから,一方で,
「遊里での遊びを描いた洒落本や,男女の三角関係を描き,藝者などが登場する人情本,あるいは近松門左衛門の世話浄瑠璃の心中ものなどで,それらは娼妓,藝者が恋の相手だった。」
という世界がある。しかし著者は,それを一般化するのを否定する。
「娼婦相手に『恋』をするのは特殊である。それは近世後期,江戸,大阪の遊治郎の間に成立した特殊文化であって,とても日本の前近代の恋愛思想として一般化できるものではない。」
と言い切る。しかし他方,明治期,知識人は,
「西洋をあまりに理想化し過ぎ,日本について知らな過ぎた傾向があった。日本は遊郭や芸者があるみだらな国で,西洋はキリスト教の国々だから一夫一婦制で,清らかな恋愛をしている,というふうに過大に彼我の差をとらえ過ぎていたのである。」
著者は,
「近代恋愛は精神性を重視した,というが,それはある程度いいとしても,実際に西洋でも,そのようなものが広まったのは十九世紀半ば,女性を読者とする恋愛小説が普及してからで,明治維新は1886年だから,せいぜい二,三十年のずれしかない。なるほど,小説という形式は,西洋で発達し,日本へ持ち込まれたものである。そして,小説と恋愛が深い関係をもつのは事実だ。だから,たとえば中国やインド,東南アジアで,近代になった小説が輸入されたり,恋愛が広まったりした,というなら,まだ話は分かる。実は一番具合が悪いのが,古典若や平安朝物語で,さんざん恋愛が描かれた日本なのだ」
と,輸入品論者を,皮肉る。そして,
確かに,「恋愛」という言葉は,明治二十年頃定着したが,それまでは,
『日本情交之変遷』(宮崎湖処子)
というタイトルがあるように,
情交,
とか,
愛恋,
とされていた。「愛する」という言葉も,明治期以降に使われ出したと思われがちだが,
「徳川時代の文藝では,『愛する』というのは,目上の者が目下の者をかわいがる意味で使われていた」
というし,「愛敬(あいぎょう)法」という秘法が,平安から中世に行われていたが,まさに,
「『愛』は恋愛の愛で,むしろ政治的に,結婚したい相手の心がこちらへ向くように行われる法」
だという。
著者のものの見方を示す好例は,次のような分析である。
「当時の中産階級では,女の結婚適齢期は二十歳前後である。さらに,その相手は,家柄はもとより,資産や職業をもっていなければならない。だから十歳くらい上の相手と結婚させられた。…漱石の『三四郎』で,三四郎は二十三歳で,同年の里見美彌子に恋をするが,だから,美彌子は既に婚(い)き遅れであり,同年でしかも学生の三四郎と結婚できないのは当然なのである。」
「三四郎は下宿する学生ながら,下女がいる。つまり福岡の豪農出身の中産階級なのである。」
で,中流というのを,
「高度経済成長以後の日本人は,家政婦とか子守とか,他人を家に入れることを極端に嫌がるようになったため使用人がいるという条件を外すにしても,中流と言えるには,庭のある一戸建ての五百坪くらいの家を持ち,ほかにしかるべき財産がなければなるまい」
と厳格である。つまり,一億中流化などは幻想ということである。そして,恋愛というとき,そういう社会的背景抜きに,一般化してはならない,という考え方なのだ。で,
「平安文藝では,女に恋する男がヒーローたりえた,といえるが,徳川後期文藝では,女にもてる男が英雄となった」
と,時代の価値観の変化を,フレーズ化したが,現在について,
「恋愛思想の近代は終わってはいないのである」
と,本書を締めくくる。それは,過大な西洋の理想化と過小な日本評価が終わっていない,という意味を持含んでいるようである。
参考文献;
小谷野敦『日本恋愛思想史 - 記紀万葉から現代まで』 (中公新書) |
|
モティベーション |
|
ゲイリー・レイサム『ワーク・モティベーション 』を読む。

本書の監訳者金井壽宏氏が,
「ワーク・モティベーションの諸研究に造詣が深く,科学的な実証研究でもつねに最先端で,さらには,世界中の有力なワーク・モティベーション学者とつながり,そのネットワークの核に立つような人の体系的著作を日本に紹介したいと思い,そのような本を探し求めてきた。そのなかで,…本書『ワーク・モティベーション』は,実践的で科学的なワーク・モティベーション論であり,おそらく今後,経営学における定番,古典として,長く読み継がれることだろう。」
と紹介する。その意味て,本書は,現時点で,モティベーション論の百年以上の歴史を,「現存する諸理論を相互に関連づけながら,網羅し,理論を検証する調査研究の内容や方法にもふれ」て,概観し,今後をも展望して見せている大作である。
著者自身が,「科学者であるとともに実践者である」という,その言葉通り,ご自身の企業の現場での実践,実証がふんだんに盛り込まれている。
ホーソン実験,
欲求五段階説,
X理論Y理論,
動機づけ・衛生理論,
職務特性理論,
公正理論,
期待理論,
目標設定理論,
社会的認知理論,
内的モティへ―ジョンと外的モティベーション,
等々と,懐かしい過去の学説・理論を,25年刻みで,1900年から辿りつつ,二十世紀を総括し,21世紀を検証し,将来を展望して見せている。著者自身は,
「深く長期的にコミットしてきた目標設定理論への思い,こだわりは強い」
が,「ワーク・モティベーション論全体を渉猟しようとする意図,包括的理解を示す姿勢」があり,それぞれの画期毎に,著者自身が,「結論としてのコメント」で,その時代を,それぞれ総括している。
著者は,それを,
「第Ⅰ部は,職場のモティベーションに関する研究と理論を時系列で概説し,テーマの比較的ユニークな発展形態を強調している。職場のモティベーションに対するわれわれの理解をいかに深めたかという観点から,それぞれの研究や理論の長所,貢献,限界を論じる。」
「新しい千年期に入ると,モティベーションの研究で三つの移行が明らかになった。認知に加え,情緒,とりわけ感情が調査されるようになった。かつて回避されたパーソナリティの問題が,ふたたびモティベーションの文献のなかで圧倒的となり,意識に加えて前意識または下意識への関心が高まっている。そこで第Ⅱ部では,この分野の現状に焦点を当てた。」
「第Ⅲ部では,将来の理論の発展と実証研究の有望な道筋と私が思うものをはっきりと説明している。」
「第Ⅳ部のエピローグでは,モティベーションの行動科学的原則を実践に活かす技法について論じる。」
と,狙いを書いている。僕には,
期待理論,
目標設定理論,
社会的認知理論,
あたりが,近しく,特に,いちばん,
社会的認知理論,
とりわけ,
自己効力感,
は,深く感ずるところがあり,強く影響を受けている。
目標設定理論は,
①具体的で困難な目標があると,目標がない場合や,あったとしても「ベストを尽くせ」という抽象的な目標の場合より,高い業績が得られる,
②目標にコミットメントがあると,その目標が高いほど高い業績が得られる,
③金銭的インセンティブ,意思決定への参加,フィードバック。または結果の把握といった変数は,具体的で困難な目標の設定とそのコミットメントにつながる場合にのみ,業績に影響を残す。
というもので,以降のマネジメントに強い影響を与えたことが,よく分かる。著者は,
「要するに,目標は,その達成に向けて関心と行動を方向づけ(選択),活力をかき立て(努力),努力する時間を引き延ばし(持続),適切な戦略を立てるよう個人を動機づける(認知)ことに効果がある」
とまとめる。
社会的認知理論は,
①行動を認知的,行動的,環境的変数の継続的な相互作用として捉える。行動が環境によって決定され,同時に環境に影響する。環境は次に,その人の自覚する意思または目標に影響し,その逆も起きる。
②人は他者の行動とその結果を予測し,目標を設定し,それに応じて行動することができる。このような自己調整プロセスの結果として,人は目標達成に向けた報酬を通して,各々自己動機付けの担い手として機能することを学ぶ。
③個人差を示す,結果期待(必要な行動をとれば所定の結果が起きるという信念),自己効力感(所定の環境で所定の行動を実行できるという信念)が,重要な仲介的役割を果たす。
④結果期待によって行動を調整する際,人は+の結果を生みそうな行動をとり,報われない結果や懲罰的な結果につながる行動は通常とらない。
⑤自己効力感が強いと,苦労の多い状況でもストレスや落ち込みが少なくなり,逆境を跳ね返す力が強くなる。
等々であり,著者は,こうまとめる。
「業績への影響で能力より重要なのは,与えられた課題を実行できる能力が自分にあるという本人の信念だ。同じように業績が低い人でも,自己効力感が高い人は努力し,課題を修得できるまで努力を続ける。対照的に,自己効力感の低い人は,業績の悪さを理由に目標をあきらめようとする。…自分の行動によって目標を達成できると信じていないかぎり,困難に直面したときに行動を持続することは難しい。自己効力感は,結果的にモティベーションを左右する認知的判断だ。」
著者は20世紀を概括して,モティベーションの議論を,
ソーンダイクの職務満足効果,
金銭的インセンティブ効果,
リッカートの態度調査効果,
ホーソン研究効果,
マズローの欲求階層説効果,
ハーズバーグの動機づけ要因効果,
ヴルームの期待理論効果,
目標設定理論効果,
ヴァンデューラの社会的認知理論効果,
組織の公正の原則効果,
の10項目を,「激震的出来事」として挙げた。そして,ピンターの言を借りて,モティベーションを,
「個人の存在のなかで,また個人の存在を超えたところで生まれる,活力源となる力の集合であり,仕事に関連した行動を始動し,その形態,方向,強度,期間を決定する」
とし,こう付け加える。
「ワーク・モティベーションを予測し,理解するには,動機づけられたエネルギーの向かう具体的な目標を知らなければならない。モティベーションは目標が難しい時に喚起される。目標が達成可能であると知覚される(自己効力感)かぎりにおいて,継続や持続の力がうまれる。」
と,まとめる。最後に,
「私が掲げた大きな目標は,『無境界』心理学を構築することだ」
として,社会心理学,臨床心理学,生涯研究,進化心理学,神経科学の協調と交流によるシナジー効果による,
「人間行動における『不変要素』を発見できる」
のではないか,と提起する。そして,最後に,著者とエドウィン・ロックによる,モティベーション理論の統合モデルを示している。
「モデルは,欲求から始まり,獲得された価値と動機(パーソナリティを含む),目標選択,目標そのもの,自己効力感へと進む。ロックは,目標と自己効力感を『モティベーションの中心』とした。理由は,ほとんどの例において,この二つが従業員の業績を決定する直截的で意識的なモティベーションの決定要因だからだ。」
これは,メタ分析を統合することによってうまれた最初のモティベーション理論ということになる,と著者は語り,大事なことは,
「社会的普及に関する理論がぜひとも必要である」
と,社会のなかでの実効性からの評価を求めている。
私的なことだが,モティベーション理論の歴史を概観する最適な参考書が少なく,昔,自分で,システム手帳に,動機づけ理論の変遷としてノートを創っていた。そこは,テーラーの科学的管理法から始まり,マズロー,マクレガー,ハーズバーグから,バーナード,アージリス,リカート,を挟んで,ヴルームで終わっていた。これからは,インデックスの完備した本書が最適の参考資料となりそうだ。
参考文献;
ゲイリー・レイサム『ワーク・モティベーション 』(エヌティティ出版) |
|
批評 |
|
柄谷行人『トランスクリティーク――カントとマルクス』を読む。

著者は,冒頭で,
「本書は二つの部分,カントとマルクスに関する考察からなっている。この二つは分離されているように見えるけれども,実際は分離できないものであって,相互作用的に存在する。私がトランスクリティークと呼ぶものは,倫理性と政治経済学の領域の間,カント的批判とマルクス的批判の間のtranscoding,つまり,カントからマルクスを読み,マルクスからカントを読む企てである。私がなそうとしたのは,カントとマルクスに共通する『批判(批評)』の意味を取り戻すことである。いうまでもなく,『批判』とは相手を非難することではなく,吟味であり,むしろ自己吟味である。」
と書きはじめる。カントの,『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の「批判」であると同時に,マルクスの,『資本論』の国民経済学(ポリス的経済学)批判の批判でもある。文庫版のあとがきに,
「カントをマルクスから読むとは,カントをヘーゲルに乗り越えられた人ではなく,ヘーゲルが乗り越えられない人として読むことだ。マルクスをカントから読むとは,カントがもっていたがヘーゲルによって否定されてしまった諸課題の実現を,マルクスの中に読むことだ。」
と,その意図を説明する。陰の主役はヘーゲルということになる。なぜか,
「私の考えでは,資本・ネーション・国家を相互関連体系においてとらえたのは,『法の哲学』におけるヘーゲルである。それはまた,フランス革命で唱えられた自由・平等・友愛を統合するものである。ヘーゲルは,感性的段階として,市民社会あるいは市場経済の中に『自由』を見出す。つぎに,悟性的段階として,そのような市場経済がもたらす富の不平等や諸矛盾を是正して『平等』を実現するものとして,国家=官僚を見出す。最後に理性的段階として,『友愛』をネーションに見出す。ヘーゲルはどの契機をも斥けることなく,資本=ネーション=国家を,三位一体的な体系として弁証法的に把握したのである。
ヘーゲルはイギリスをモデルにして近代国家を考えていた。ゆえに,そこにいたる革命は今後においても各地にあるだろう。しかし,この三位一体的な体制ができあがったのちには,本質的な変化はあり得ない。ゆえに,そこで歴史は終わる,というのがヘーゲルの考えである。」
しかし,その後,(今日に至るまで)本質的な変化は存在しない,だから,いまヘーゲルを批判することは,いまも強固な資本=ネーション=ステートを超える方法を考えることである。
資本=ネーション=国家の流れについては,イントロダクションで,著者は簡潔にこうまとめているのがわかりやすい。
「国家,資本,ネーションは,封建時代においては,明瞭に区別されていた。すなわち,封建国家(領主・王・皇帝),都市,そして農業共同体である。それらは,異なった『交換』の原理にもとづいている。…国家は,収奪と再分配の原理にもとづく。第二に,そのような国家機構によって支配され,相互に孤立した農業共同体は,その内部においては自律的であり,相互扶助的,互酬的交換を原理にしている。第三に,そうした共同体と共同体との『間』に,市場,すなわち都市が成立する。それは相互的合意による貨幣的交換である。封建的体制を崩壊させたのは,この資本主義的市場経済の全般的浸透である。だが,この経済過程は政治的に,絶対主義的王権国家という形態をとることによってのみ実現される。絶対主義的王権は,商人階級と結託し,多数の封建国家(貴族)を倒すことによって暴力を独占し,封建支配(経済外的支配)を廃棄する。それこそ,国家と資本の『結婚』にほかならない。商人資本(ブルジョアジー)は,この絶対主義的王権国家のなかで成長し,また,統一的な市場形成のために国民の同一性を形成した,ということができる。しかし,それだけでは,ネーションは成立しない。ネーションの基盤には,市場経済の浸透とともに,また,都市的な啓蒙主義とともに解体されていった農業共同体がある。それまで,自律的で自給自足的であった各農業共同体は,貨幣経済の浸透によって解体されるとともに,その共同性(相互扶助や互酬制)を,ネーション(民族)の中に想像的に回復したのである。(中略)フランス革命で,自由,平等,友愛というトリニティ(三位一体)が唱えられたように,資本,国家,ネーションは切り離せないものとして統合される。だから,近代国家は,資本=ネーション=ステート(capitalist-nation-state)と呼ばれるべきである。それらは相互に補完し合い,補強しあうようになっている。たとえば,経済的に自由に振る舞い,そのことが階級的対立に帰結したとすれば,それを国民の相互扶助的な感情によって解消し,国家によって規制し富を再分配する,というような具合である。その場合,資本主義だけを打倒しようとするなら,国家主義的形態になるし,あるいは,ネーションの感情に足をすくわれる。前者がスターリン主義で,後者がファシズムである。
(中略)資本は,人間と自然の生産に関しては,家族や農業共同体に依拠するほかないし,根本的に非資本生産を前提にしている。ネーションの基盤はそこにある。一方,絶対主義的な王(主権者)はブルジョア革命によって消えても,国家そのものは残る。それは,国民主権による代表者=政府に解消されてしまうものではない。国家はつねに他の国家に対して主権者として存在するのである。したがって,その危機(戦争)においては,強力な指導者(決断する主体)が要請される。ボナパルティズムやファシズムにおいてみられるように。現在,資本主義のグローバリゼーションによって,国民国家が解体されるだろうという見通しが語られることがある。しかし,ステートやネーションがそれによって消滅することはない。(中略)資本=ネーション=ステート…のどれかを否定しようとしても,結局この環の中に回収されてしまうほかない。」
要するに,これは,思弁的な哲学的課題でも,遠い過去の歴史的課題ではなく,今日のわれわれの世界を変えるために何をすべきかを考える現代の課題そのものなのである。著者は,「まだ萌芽的なものでしかない」と,断っているが,著者なりの,資本=ネーション=ステートの回路の外へ出る処方箋を,本書の終りに提案している。
本書では,著者は,カントとマルクスに共通するキーワードを,
視差,
移動,
あるいは,
差異,
という言い方で表現しているように見える。
「カントの哲学は超越論的―超越的と区別される―と呼ばれている。超越論的態度とは,わかりやすくいえば,われわれが意識しないような,経験に先行する形式を明るみにだすことである。」
それは単なる反省ではない。
「カントの反省には,『他者』が介在している。」
ただし,それは,「自分の視点から見るだけではなく,『他人の視点』からも見よ」というようなありふれたことではない。
「もしわれわれの主観的な視点が光学的欺瞞であるなら,他人の視点あるいは客観的な視点もそうであることをまぬかれない。であれば,反省としての哲学の歴史は『光学的欺瞞』の歴史でしかない。カントがもたらした反省とは,そのような反省が光学的欺瞞でしかないことを暴露するような種類の反省である。反省の批判としてのこの反省は,私の視点と他人の視点の『強い視差』においてのみもたらされる。」
それは,カントにおいて,「テーゼとアンチテーゼのいずれもが『光学的欺瞞』にすぎない」という,アンチノミー(二律背反)として現れる。マルクスにおいても,
「『ドイツ・イデオロギー』の時期,彼は直前まで自身がその中にいたヘーゲル左派を批判した。(中略)ドイツのイデオロギーとは,先進国イギリスにおいて実現されていることを観念的に実現しようとする後進国の言説にほかならない。しかし,マルクスにとって,それは彼自身がはじめてドイツの言説の外に出ることによって得た,或る衝撃をともなう覚醒の体験であった。それは,自分の視点で見ることでも他人の視点で見ることでもなく,それらの差異(視差)から露呈してくる『現実』に直面することである。」
著者が,本書でしようとしたことは,要するに,
「重要なのは,マルクスの批判がつねに『移動』とその結果としての『強い視差』から生まれていることだ。カントが見出した『強い視差』は,カントの主観主義を批判し客観性を強調したヘーゲルにおいて消されてしまった。同様に,マルクスが見出した『強い視差』は,エンゲルスやマルクス主義者によって消されてしまった。」
その消されたものを,読み直すということだ。だから,
「私はカントやマルクスの,トランセンデンタル且つトランスポジショナルな批判を『トランスクリティーク』と呼ぶ」
のであり,ここでしようとしているのは,
「トラスヴァーナル(横断的)な,あるいは,トランスポジショナルな移動なしにはありえない」
という超越論的な批判なのである。要は,カントとマルクスがやっていた,トランスクリティークな批判を両者の読みに対して試みようとしている,ということなのであろう。
そのキーワードは,超越論的という言葉である。先の自分の視点,他人の視点,それぞれの光学的欺瞞をも暴くのもそれだが,著者は,「批判的場所(critical
space)」と名づけている。デカルトのコギトについて,
「デカルトのコギト(我疑う)は,システムとシステム,あるいは,共同体と共同体の『間』において見いだされる。この『間』は,たんに『差異』としてあり,実体的にあるのではない。」
と書く。この言い方は,そのまま,著者が,カントやマルクスのコペルニクス的転回を述べる時の,このコペルニクス的転回そのものの説明によく現れる。まさに,これこそが,コペルニクス的転回の超越論的な見方である。
「コペルニクスがもたらしたのは,それまでプトレマイオス以来の天動説においてつきまとう天体の回転運動のズレが,地球が太陽の周りを回転すると見た場合に解消されるということである。…天動説を指示する者もコペルニクスの計算体系を用いざるをえなかった。彼らは,本当は太陽が地球の周りをまわっているのだが,計算上においてその逆である『かのように』考えることができたのである。だが,『コペルニクス革命』はむしろそこにこそ存したというべきである。重要なのは,地動説か天動説かではなく,コペルニクスが,地球や太陽を,経験的に観察される物とは別に,或る関係構造の項としてとらえたということである。」
この超越論的構造が,カントにも,マルクスにも当てはまる,と著者は指摘している。ところで,
「カントが『実践理性批判』で最も批判したのは,『幸福主義』(功利主義)である。彼が幸福主義を斥けるのは,幸福がフィジカルな原因に左右されるからだ。つまり,それは他律的だからだ。その意味では,自由はメタフィジカルであり,カントが目差す形而上学の再建とはそのこと以外にはない。」
と書く。カントは,『実践理性批判』の中で,
「幸福の認識は,まったく経験的事実にもとづくものであり,また幸福に関する判断は各人の臆見に左右され,そのうえこの臆見なるものが,また極めて変り易いものだからである。」
という。カントがいうのはこういうことだ。
「われわれは自由意志などないと考えなければならない。われわれが自由な選択だと考えるものは,原因に規定されていることが十分にわからないからにすぎない。そう考えたとき,はじめて,『自由』はいかに可能かということが問われるのだ。(中略)カントは,自由は義務(命令)に対する服従にあるといった。(中略)それは,『自由であれ』という命令である。…カントがいう『当為であるがゆえに可能である』という言葉にも謎はない。それは,自由が『自由であれ』という義務以外のところから生じない(不可能である)という意味にすぎない。」
それは,他者に関わる。
「この『自由であれ』という義務は,むしろ。他者を自由な存在として扱えという義務に他ならない。カントがいう道徳律とは,『君の人格ならびにすべての他者の人格における人間性を,けっしてたんに手段としてのみ用いるのみならず,つねに同時に目的(=自由な主体)として用いるように行為せよ』(『実践理性批判』)ということである。」
それはそのまま,プルードンの次の言葉に重なる。
「汝が人にしてもらいたくないようなことを,他人に対してなすなかれ。汝が他人にしてもらいたいように,他人に対してなせ。」
という行動の準則に重なっていく(孔子も似たことを言っていた)。この道徳律は,
「根本的に経済的である。(中略)生産関係を前提にしている。それなしに成立するように見える『人格的』関係は僧院や学生寮において成立するような夢想にすぎない。(中略)カントがいう『目的の国』は物質的経済的基盤に置いてある。…かくして(新カント左派のヘルマン・)コーヘンは,カントを『ドイツ社会主義の真実の創始者』と呼んでいる。実際コミュニズムは,他者を手段としつつ,なお且同時に他者を目的として扱うような社会でなければならない。それは,『他者を手段としてのみならず目的として扱うこと』を不可能にする社会的システムを変えることによってしかありえない。」
だから,当然,この道徳律は,
「根本的に政治的である。(中略)カントが政治的次元を否定するどころか,道徳的なものの実現は政治的次元なしにはありえないと考えたことである。カントがいう『目的の国』は具体的には世界共和国として実現されなければならない。そして,それは,ネーション=ステートの集まりである国際連合のようなものとは根本的に異質であることに注意すべきである。」
として,カントはこう書いている。
「各国家をして,国内的に完全であるばかりでなく,さらにこの目的のために対外的にも完全であるような国家組織を設定する」
と。だから,著者は,
「カントの倫理学は,たんに道徳次元にとどまりえず,政治的・経済的なものとして,歴史的に実現されるべき理念(コミュニズム)をはらまずにはいないのである」
と。ここから,マルクスを照射していくことになる。その結果の著者の,
資本=ネーション=ステートの回路の外へ出る処方箋
は,本書を読む楽しみとして残しておくべきだろう。
参考文献;
柄谷行人『トランスクリティーク――カントとマルクス』 (岩波現代文庫) |
|
〈私〉 |
|
永井均『〈私〉の存在の比類なさ』を読む。

著者は冒頭でこう書く。
「それにしても,ある新しい問題提起が人々に理解してもらえるためには,どれほどの根気と労力と時間が必要であることか,この間の私は痛感せざるをえなかった。人々は,頑ななまでに新しい問題提起というものに鈍感で,かつ拒絶的である。そして,どういうわけか,問題が世の中で少しでも注目されるようになると,今度は精確に理解しようともせずに,さまざまな角度からその問題の悪口を言って,なんとかそれを旧来の枠組みに押し込めてしまおうとする人が,次々と現れるのである。自分にとって異質な問題が存在すること自体がたえがたいような人々が居るらしいのだ。これは私にとってまったく予想外のことであった。」
そして,こう付け加える。
「問題を感じない人は入ってこないでほしい。ひょっとすると,私はただ特殊な種類の錯覚にとらわれているだけかもしれない―それはありうることだ―が,たとえそうだとしても,それが如何なる錯覚であるかを解明できるのは,―同じ種類の錯覚に悩まされた経験のある人だけなのである。これは,誰もが問うべき人生と世界に関するもっとも重要な問題などではない。ある種の人間にとっては,それどころではない,人生と世界に関する他のさまざまな重要(とされる)問題が馬鹿馬鹿しくなるほどの,とびぬけて重大な,おそらくは唯一の問題であろうが,別の種類の人にとっては,意味さえわからない,とただ馬鹿馬鹿しいだけの愚問であろう。」
ここまで境界線を張られると,自分はどうやら境界外の人間らしいと感じるのだが,それはそれとして,関わったかぎりで,読み取ったものをまとめていくと,まず,著者が自分で書いた冒頭の文章を俎上にのせるところから始まる。
「自分と他人は違う。自分のことはよく分かるが,他人のことはよく分からない。いま自分が何を考え,何を感じているか,それは手に取るようによくわかる。しかし,いま他人が何を考え,何を感じているか,これは手に取るようにはわからない。この自他の非対称性は,誰もが知っている事実である。」
ここでいう「自分」という言葉を問題にする。
「この文章に登場する『自分』とは,すべての人にとっての自分自身を意味している。誰にとっても,自分が何を考え感じているかは手に取るようにわかるが,他人が何を考え何を感じているかはわからない,と言っているわけである。そして事実,この段落は『この自他の非対称性は,誰もが知っている事実である』という文で結ばれている。しかし,そうだとすると,少々奇妙なことが起こる。『すべての人』のほとんどは他人なのだから,この文章の筆者は他人にとっての他者問題と自分にとっての他者問題とを同時に提起していることになり,そのことの内で自他のある非対称性が,つまり一つの他者問題が暗黙の内にすでに乗り越えられてしまっている,ということである。」
僕は思うのだが,この文章をすっとスルーして行けるなら,たぶん,この問題提起とは無縁なのであり,ひとつのリトマス試験紙のような位置にあるのではないか。
少し前のところで,心を持った何某にそっくりのロボットと,心を抜き取られた何某という「ロボット問題」の思考実験を設定して,
「外部から窺い知ることができないはずのこの変化が,外部にいるものにとっても,有意味な変化であるように思えるのはなぜだろうか。」
と問い,こう考える。
「この問題には,私の考える真の他者問題へいたる二つの通路が,同時に示されている。第一は,『他者』とはもちろん外部から与えられる規定であるにもかかわらず,他者性のうちには外部からの接近を絶対的に拒絶する地点が必ずある,というパラドクシカルな事態である。(中略)
(更にそれを敷衍して,次に,仮に自分が心を抜き取られるという事態を想定して)もし,自分に起こるこの変化に意味を認めるならば,当然,他人に起こるこの変化にも意味を認めないわけにはいかない。その理由はかんたんである。他人もまたそれぞれ,この意味での『自分』,つまり『私』でありうるはずであるからである。そのことを前提にして,この『ロボット問題』は立てられていた。しかし,そうだとすると,問題は奇妙な様相を呈することになる。最初の問題は,この私ただひとりを別にして,他人とロボットの違いをめぐって立てられていた。誰もがそのつもりで問題の意味を理解する。ところが,誰もがそのように理解するというまさにそのことによって,しかもそのことが問題の提起に際しては実は暗に前提されているという事実によって,解答が問題の中にあらかじめ入り込んでしまうのである。(中略)これが他者問題にいたる第二の通路なのである。」
と。ここでも,暗黙の内に,共有化できる視点で見た「自分」「私」を前提にしている,その意味では,立てられた他者問題を,前述の記述と同様,乗り越えられている,と言うのである。この機微,
ある意味での主体,
のポジションの微妙さが,すべての前提になっている。で,冒頭の「自分」を「私」に置き換える,つまり,「自分」という言い方で,自分をメタ化かした視点から,発話主体の視点に置き換えるとどうなるか。
「この文章にも二義性はある。その『私』とは誰か? という問いがつねに立てられるからである。しかしこの問いには,それはこの私ひとりを指示する,と応えることがつねに可能なのである。もちろん,その『この私』とは誰か? という更なる問いがつねに立てられざるをえない,としてもである。
しかし,この更なる問いがつねに立てられざるをえないという事実は,他者問題に非常に特殊な問題性を与えている。すなわち,他者問題は,まさにこの事実によってこそ,他の人々と共有される問いとして,すなわち客観的な『問題』として定式化されうるにもかかわらず,同じその事実によって,当初の問題感覚は定式化された『問題』の内ではつねにすでに裏切られた形でしかあらわれない,という点である。(中略)問題として感じられた当初の他者問題が,はじめから万人にとっての他者問題という形をとっているなどということは,ことの本質上,本来ありうるはずのないことである。にもかかわらず,立てられた他者問題はもうすでに万人にとっての他者問題に変質してしまっているのである。」
にしても,著者のこだわりは,この変質にある。フッサールの『デカルト的省察』やメルロ=ポンティの『知覚の現象学』などでは,「ほぼ一貫して『私』という第一人称主語によって語られている。」。実際,われわれも私(僕)という一人称によって,文章を書くこともある。この「私」とは誰を指しているのか。
「もしかりに,彼らがそれぞれ自分自身だけを念頭においてその文章を書いたとしても,読者は(フッサールやメルロ=ポンティの書いた私小説を読むつもりでないならば)各自の『私』のこととしてそれを読み換えるはずである。そして実は,著者たちはその読者の立場を先取りしつつその文を書いたのである。読み換えはいつもすでに始まっているのだ。ここでの『私』は,だからすでに,みんなの『私』なのであり,論じられている問題は,それを論じる文の内で,あらかじめ暗黙の内に解決されているのである。」
そこで,「私」という表記について,
①著者自身とっての著者自身の「私」
②著者(一般的に,フッサールであったり,メルロ=ポンティであったりする等々)
③(読者それぞれの)各自にとっての自分自身を指す指示作用としての「私」
と区分して,
「問題は,(著者自身とっての著者自身の「私」という)指示作用は,他人(ここでは著者以外の人)に伝達される際には,(著者か読者の「私」)に読み換えられざるをえない」
と言う。著者は上記①〜③は図示しているが,ここでは便宜的に記述して表現しておくが,こういう転換を,著者側の例として,デカルトを引いて,
「欺くならば力の限り欺くがよい。しかし,私が私は何ものかであると思っているあいだは,彼はけっして私を何ものでもないとすることはできないでろう。こうして,すべてを存分にあますところなく考え尽くしたあげく,ついにこう結論せざるをえない。『私はある,私は存在する』というこの命題は,私によって言表されるたびごとに,あるいは精神によって把握されるたびごとに,必然的に真である,と。」
こう分析する。
「デカルトは明らかに…(①)の指示作用を遂行しているつもりで,『私』と発話していた。なぜなら,方法的懐疑のその段階においては,並び立つ他の人間(他の諸精神)はもはや存在せず,そのうえさらに,『デカルト』という固有名で指示される人格的同一性を具えた一人物もまた,すでに懐疑の対象となって廃去されていたはずであるからである。だから,もしこの段階で,デカルトとまったく同じ主張をおこなう別人がいたとしても,デカルトはその人物に賛成するわけにはいかなかったはずである。存在を疑いえない『私』とは,『私』一般ではなく『この私』ただひとりでなければならず,しかもそれはデカルトという一人物ではなかったはずだからである。ところが,引用文の後半で『「私はある,私は存在する」というこの命題は,私によって言表されるたびごとに,あるいは精神によって把握されるたびごとに,必然的に真である』と言われるときには,おそらくもうすでに…(②③)に変質してしまっているのである。デカルト的な省察を他人に伝達しようとする場合,これはおそらく避けることのできない変質なのである。そしてまたおそらく,その変質可能性こそが…(①)の指示作用をはじめて可能ならしめているのである。」
言表し,伝えようとする時,その変質作用抜きではないとしても,
「それを語ろうとするならば無理を承知で…(①)の「私」に固執せざるをえない,あるきわめて特殊な事情が存在するように思われる。」
だからこそ,デカルトの位置と意味がある,と著者は言いつつ,
「たまたま自分自身であるところの一人物でもなければ,誰にでも備わっている自我といったものでもない,〈私〉の存在,そこから出発するのでなければ,他者の問題の深みに達することはできない。」
著者は,〈私〉と表記することの意味は,「語の指示作用に関する意味論的な主張」ではなく,
「世界の構造に関する存在論的な主張のために導入」
されたものだ,と。では〈私〉とは何か。ここでも著者は,〈私〉の利用を図示していているが,
①は,世界として表示された中に人間がいる,
②は,〈私〉の前に広がる世界で,他人がその中にいるが(〈私〉はそこにいない)
③は,世界の中に他人たちがいる,
④は,世界の中に,私と他人たちが一緒にいる,
と区分する。
「私が存在している場合,世界は,…(②)のような形をしている(…③は私の視点から見たその断面図である)。…(②および③)は,しかし,私が永井均という世界内の一人の人間として同定されることによって,…(④)に転変する。」
この転変は,上記の①の指示作用が②に変るのに対応している。そして,③④は,私が世界を表象する二つの方式,を示している,という。そして,
「ここでまず気づくことは,私が生み出され,今ここに存在しているということは,まったく奇跡的な出来事だ,ということである。」
それを別のところで,こう書く。
「その驚きは,過去・現在・未来の無数の人間のうち,この人間が,そしてこの人間だけが,私であり,他はそうではない,という事実のもつ〈偶然性〉と,それら無数の人間のどれも私ではない(私は存在しない)ことできたはずなのに,実際にはそうなっていない,という事実のもつ〈奇跡性〉という,二つの驚きに分解することができる。」
ただしそれは,
諸々の性質を特定の仕方で束ねてできた一人の人間が存在していることでも,
それらの諸性質の基体たる永井均という個体が存在することでも,
ない。それは,①と②の世界の違いでもある。難しいことに,
「その明らかな差異は私以外の誰にとってもなんら差異ではないのである。」
という点なのだ。だから,その〈私〉を,
永井均を指示する「私」でも,
誰にとっても自分自身を意味する「私」
でもない。この〈私〉を説明するのに,解説の茂木健一郎氏が,「それは違う」と言いづけているように,差異で伝えるほかにない。人に伝えるようにした瞬間,それぞれが共有できる「私」に変換してしまうからでもある。だから,
認識上の「私」でもないし,
感覚上の「私」でもないし,
自我の「私」でもないし,
自己意識の「私」でもないし,
と言い続ける。それらは,多く,「単独性」ではあるが,「独在性」ではない。そこにあるのは,言表という共有化で失われてしまう何かである。
「『私…』と語りだすとき,われわれは自分が他人と同様に知覚し予期し意味するひとりの人間であることを前提している。『私』という概念もまた差異化的に構成されているのである。では『実質』は? これも同様であって,われわれはそもそもあの図の面(著者は,『実質を面で表現し,差異を線で区画』した図を示している)を表現する言葉を持たないのである。」
この表現する言葉を持たないことについて,この少し前で,ヴィトゲンシュタインの,
「見られたものから言葉へのこの私的な移行に対して,私は規則を適用することができない。ここでは規則が宙に浮いている」
を引用し,
「(線になされた差異という)戦による区分は…意味を与えることのできない私的な事実である。この私的な事実に固執すると,『赤』という言葉は〈私〉に赤く見える当のものを,『痛み』という言葉は私が今生々しく感じているこの痛みを,…表現しているかのような(またしうるかのような)錯覚が生まれる。」
と述べ,
そして,
「『体験』も『感覚』も『自我』も『この私』もそして『実質』も『面』も,差異を表現する公共言語である。しかし,そうしたあらゆる差異化の網打ちをのがれて,語りえぬ―その上示されもせぬ―何かが在る。それは,非言語的に最も真近であるがゆえに言語的に最も遠い―決して到達できぬ―世界である。」
そのことき「この私」(〈私〉)であり,この何某である,「この」としか言いようのない何か,である。
ヴィトゲンシュタインは,
「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」
と言ったが,それでは,〈私〉は伝わらない。「それは違う」「それは違う」と言い続ける,違いの中で,際立たせていくほかはないのかもしれない。だからこそ,〈私〉について,
「〈私〉であるという軌跡が〈人〉のもつ如何なる物理的・心理的諸性質によっても規定されえない…のと同様に,〈私〉であり続けるという軌跡は,〈人〉としてのいかなる物理的・心理的連続性によっても保証されない」
と書き,ヴィトゲンシュタインが「私の魂」とよんだそれを,〈私〉と同様,
〈魂〉
と名づけ,
「それは存在しないこともできたはずなのになぜか存在している,現実に『最も重要な意味において隣人をもたない』存在者を,すなわちこの〈私〉(しかし永井均ではない)」
と付言せざるを得ない,この〈私〉なのである。
参考文献;
永井均『〈私〉の存在の比類なさ』 (講談社学術文庫) |
|
行動経済学 |
|
依田高典『行動経済学―感情に揺れる経済心理』を読む。

冒頭にこうある。
「人々は限られた情報をもとに,限られた時間の中で,限られた能力を用いて,良かれと思って最善の行動を選びながらも,それでもしばしば後悔をしてしまう。そんな当たり前のことが,経済学の中で市民権を得るには随分と時間がかかった。人間の限定された合理性を中心に最適な行動からの乖離(アノマリー)を経済分析の核にすえる学問を,行動経済学と呼ぶ。」
合理的経済人(ホモエコノミクス)を前提にした新古典派経済学全盛期なかなか火の目を見なかったのが受け入れられるようになったのは,
「ダニエル・カーネマンが,実験経済学のバーノン・スミスと共同で,2002年にノーベル経済学賞を受賞した前後」
というから,ほんの最近のことになる。
従来想定していたホモエコノミクスは,
「意志決定を行うにさいして完全な情報を有し,完全な計算能力を持ち,自分の満足,すなわち効用(utility)を最大化できると仮定されていた」
それを,現代の主流派経済学の理論も立脚してきた。人間には限界がある,という当たり前のことを学問体系として完成させたのは,ハーバート・サイモンからのようで,それを限界合理性と名付けた。で,サイモンは,
「問題解決の可能な選択肢を発見する過程こそが研究すべき」
ことだと主張する。そこから,簡便な,
ヒューリスティクス,
と名付けられる,簡便な問題解決に焦点が当たる。それは,
「目の子算とか,親指の法則などともいわれる。人間の認知や情報処理能力には限界があるので,効用を最大化する最適な解を見つけ出す時間はない。せいぜい満足化原理に従い,理性的というよりは直感的に,限られた時間のなかで意思決定を行うしかない。そのときに用いるルール」
であり,ステレオタイプと言い換えてもいい。それには,
似ているとか典型的か(代表的ヒューリスティクス)
想起しやすさ(想起しやすさヒューリスティクス)
初期情報に依拠し引きずられる(アンカーヒューリスティクス)
があるらしい。つまりは,論理的であるよりは,ステレオタイプ的判断をしている,ということを回りくどく言っている。
どうやら経済学は,科学というものの進化を横にらみしながら,学問を作り上げているらしく,当初ニュートンの自己完結した物理学をモデルにしつつ理論化しようとしていたらしい,と窺わせる。
「近代経済学とニュートン力学は異同同型の理論体系を持っており,歴史的順序関係でいえば,科学に憧れた経済学が物理学を200年間横恋慕してきたともいえる。」
と,著者は書く。
「ニュートン的時間において論難された問題点は基本的に理論経済学上の困難としてそのままあてはまる」
とも。事実,ハイゼンベルグの不確定性原理,さらにマクスウェルの統計物理学へと,量子力学の主流派が確率論的解釈へ進む物理学の流れを横目に,経済学も不確実性を着目するようになる。それが,「確率的不確実性であるリスク下での意思決定論を期待効用理論」である。それは,
「ゲーム理論の創始者であるオスカー・モルゲンシュテルンとジョン・フォン・ノイマンによって創始された。」
そこからノイマンによって,ゲーム理論が体系化されていく。いまやゲーム理論全盛である。しかし,である。ゲーム理論には泣き所がひとつある,と著者は言う。
「実際に,実験や観察でゲーム理論の予想を検証したところ,必ずしも的中率が高くなかったのである。」
と。そして,
「ゲーム理論の重要な仮定は,①プレーヤーは完全に利己的であるり,②完全に合理的であるというものである。人間を完全に利己的,合理的とみなすのもナイーブ,完全に利他的,非合理的とみなすのもナイーブ,人間はそこそこ利己的であり,そこそこ合理的でもあるが,完全に利己的,合理的なわけでもない。これが行動経済学の取る立場である。」
で,ゲーム理論の解けなかった問題を解決しようとする立場を,「行動ゲーム理論」と呼んでいる。
こうした経済理論の変化には,最近の脳科学の進化が反映しているようである。
機能的核磁気共鳴画像(f-MRI)等々のニューロイメージング装置を通して,脳の働きのマッピングが可能となり,それに対応して,「脳科学と経済学の融合によって人間行動を解明しようとする」ニューロエコノミクスがあり,またアントニオ・ダマシオの意思決定に際して体感覚が重要な役割を果たすという,「ソマティック・マーカー仮説」にもとづいて,
「恐怖や不安は人間の基本的感情であるが,それらは危険を減らしたり,生存に有利に働いたりするように,人間の行動を方向づける」
という経済学が無視してきた経済行動における感情の果たす役割にも目を向けようとしている。
著者の最後の言葉は示唆的である。
「21世紀はバイオ科学の時代となろう。21世紀の経済学も物理学よりはバイオ科学の発達から大きな影響を受けることになる。とりわけ,脳機能の解明が進むにつれて,経済額の意思決定理論の無邪気な想定がそっくりそのまま生き残ることはできなくなる。」
意思決定ということで言うなら,意識が意志を意識するより,400ミリ秒前に,脳の関連部位の活動が始まっている,とされる。とすると,意思決定とは何であるのだろうか。意識する前に,意思決定はなされているのである。
参考文献;
依田高典『行動経済学―感情に揺れる経済心理』 (中公新書) |