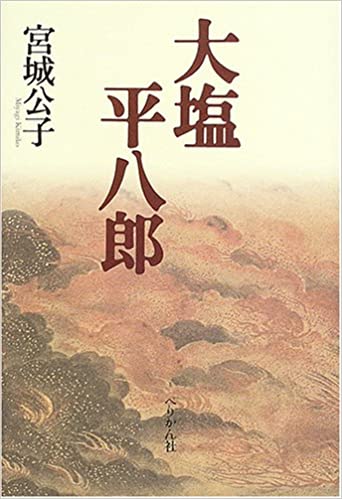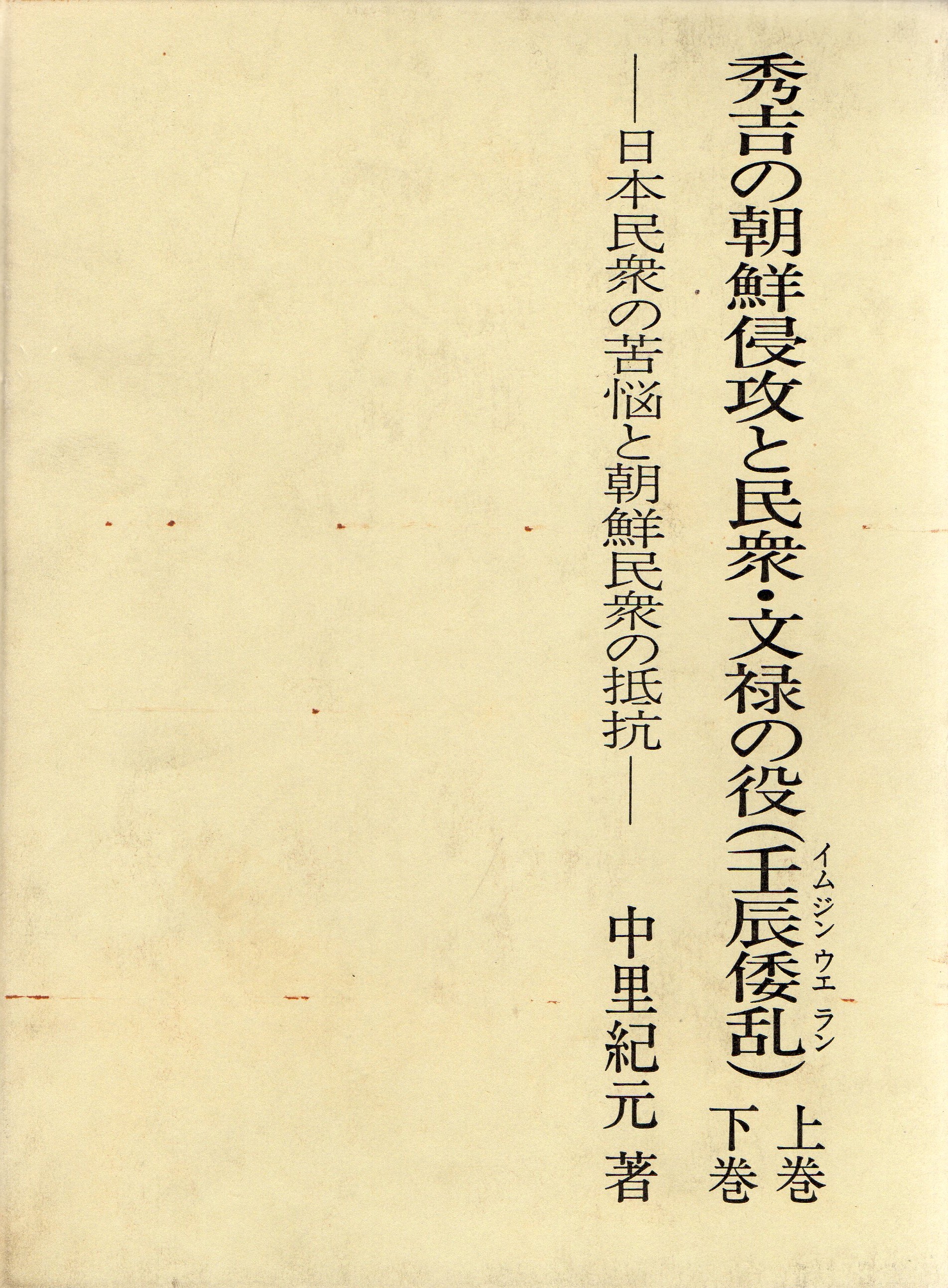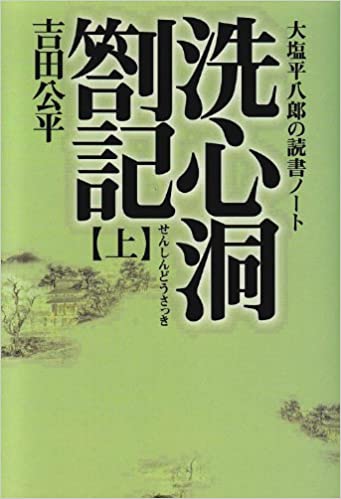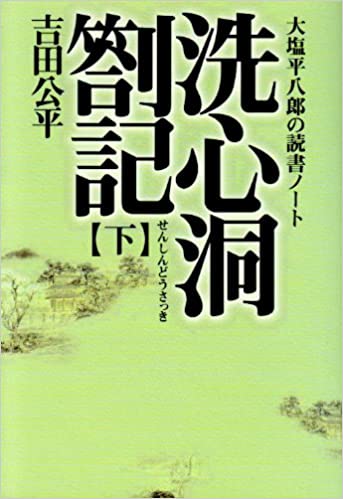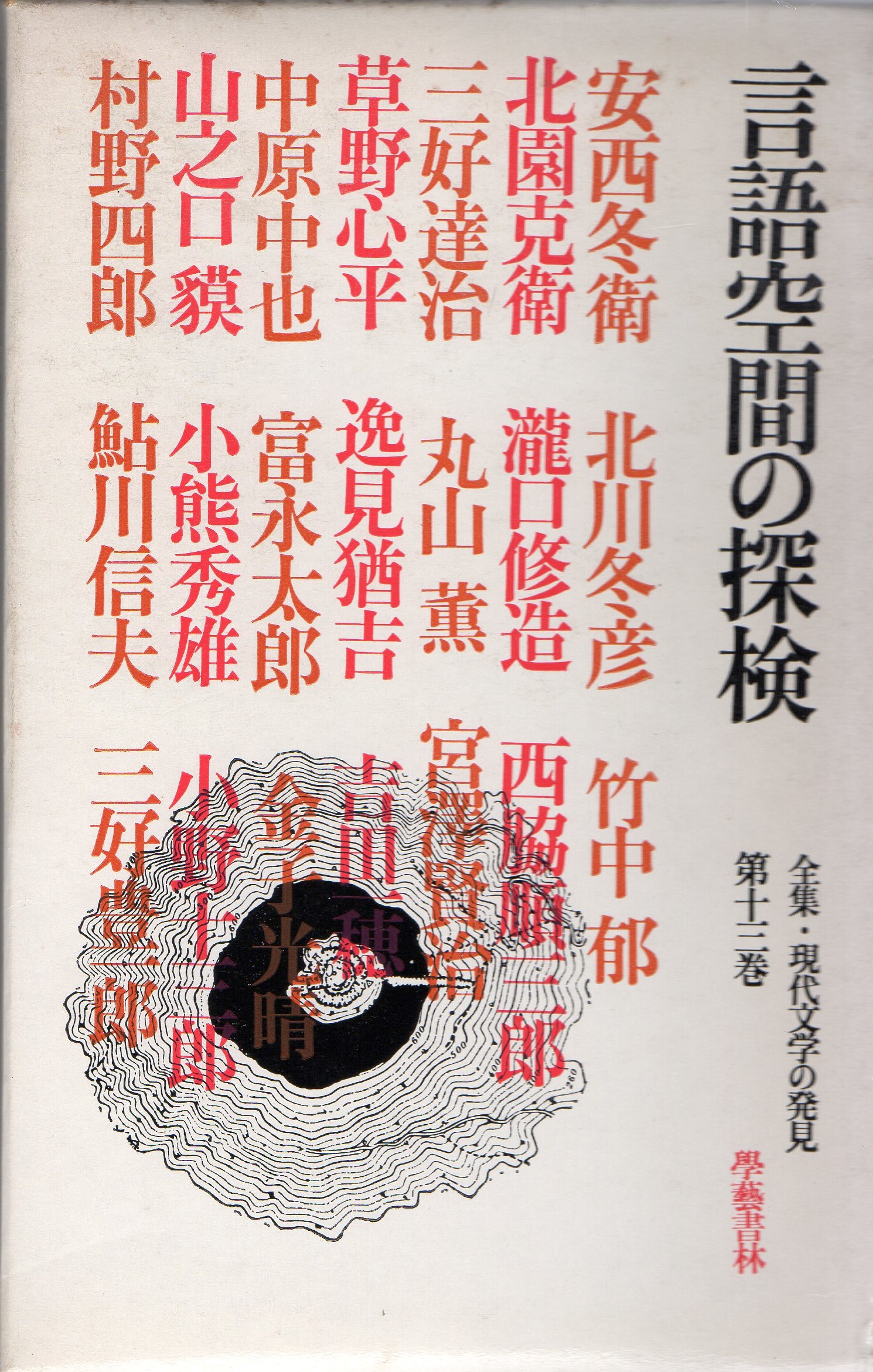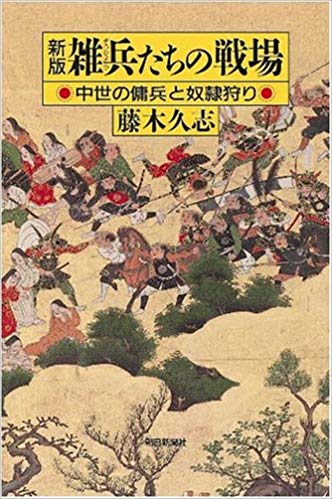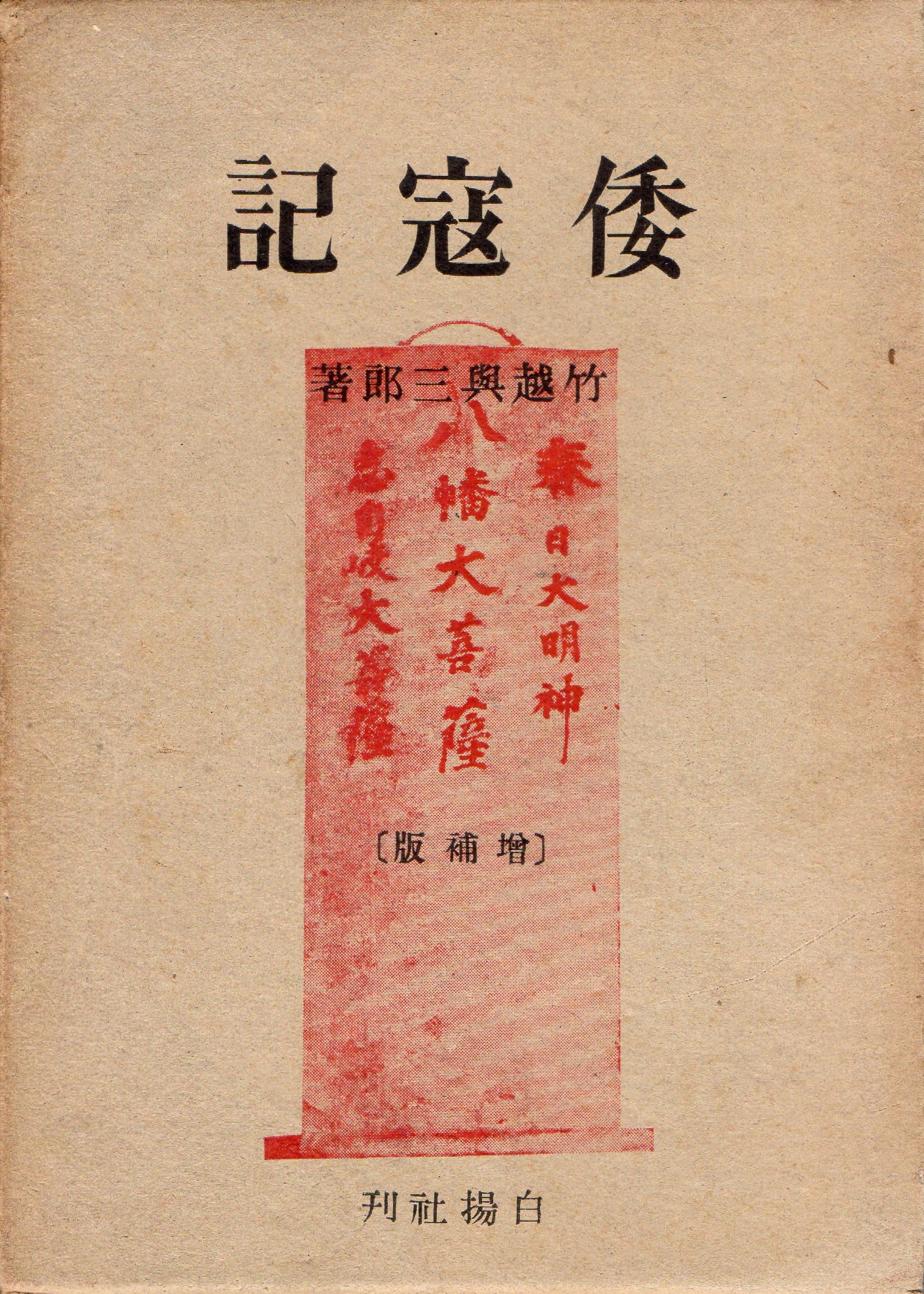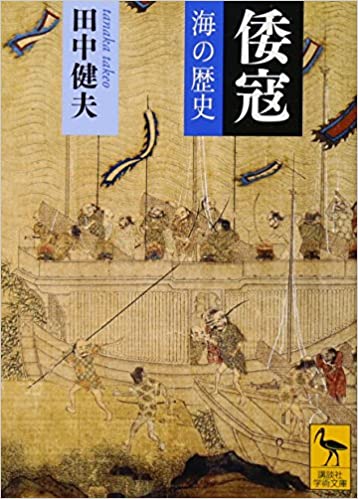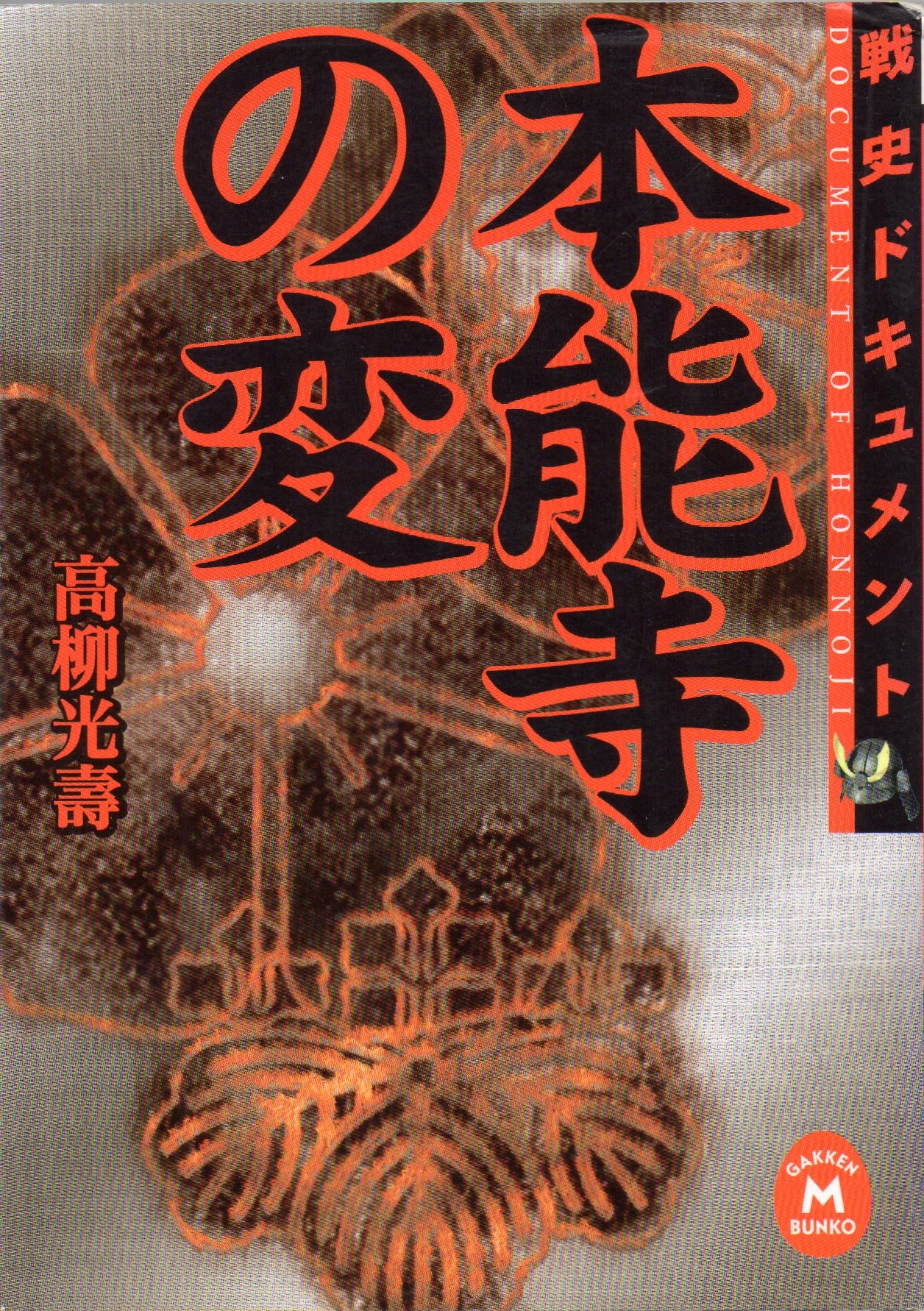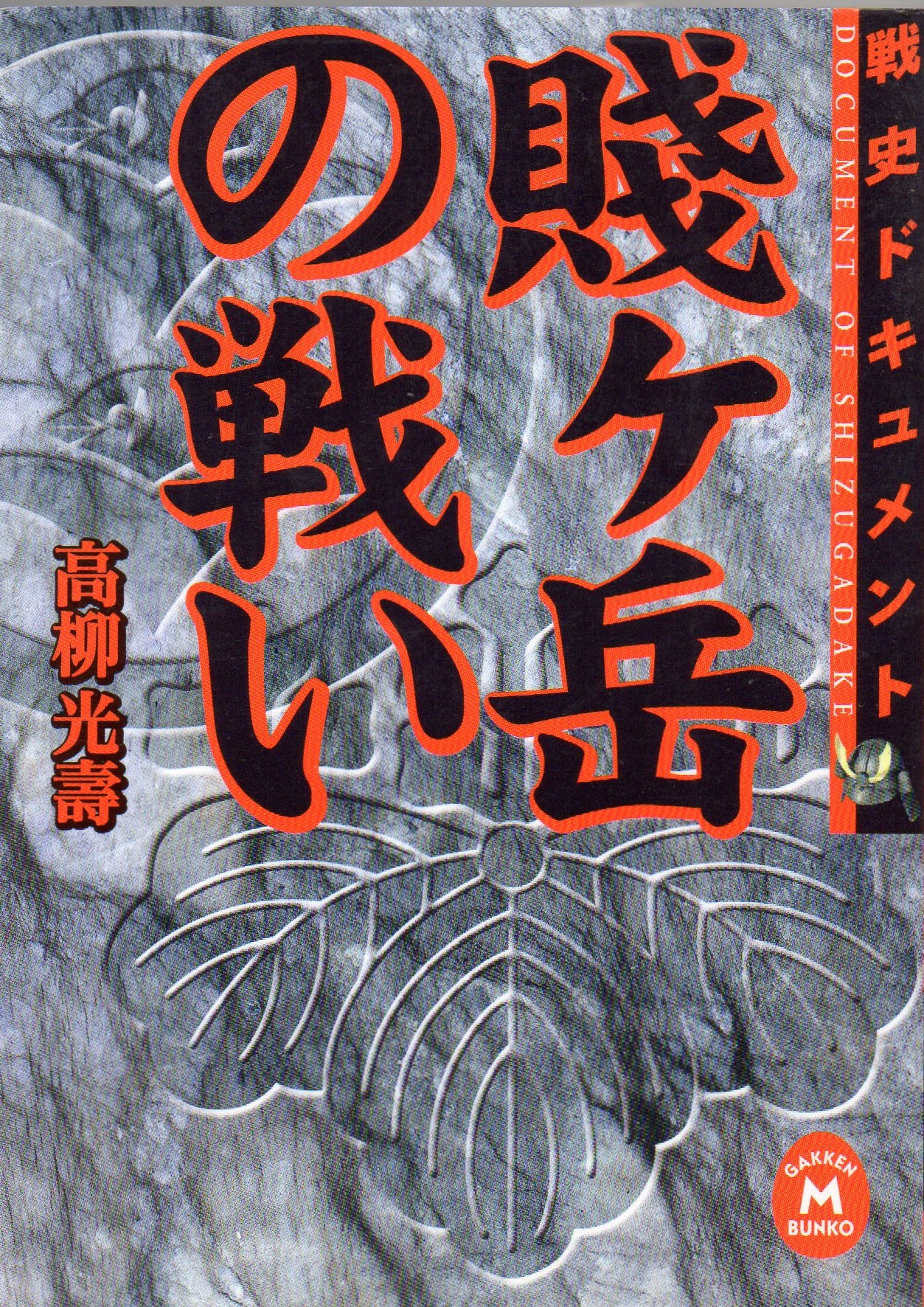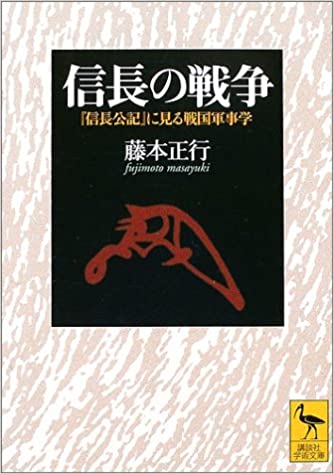| 粉川哲夫編『花田清輝評論集』を読む。
「1949年刊行の『二つの世界』から、遺著となった1974年刊の『箱の話』にいたる九冊の著書から、二九篇のエッセーを選び、ほぼ発表年次順に並べたもの」 であるが、それは、 「花田清輝の文体の多様さや思考の飛躍のあざやかさが端的に表れているものを優先した」 と「解説」で記す。理由は、 「花田清輝にとって、文体は、つねに『内容』と深く結びついているのだが、花田清輝の世界の魅力に接するには、『内容』からよりも文体から入る方がこの作者の流儀にかなっていると思うからである」 としている。そのせいか、僕には、『復興期の精神』『鳥獣戯話』『小説平家』『室町小説集』等々のフィクションに比べると、いまひとつのれなかった。大庭みな子氏が、いつも「くっ、くっ、くっ、」と笑いながら愛読した、というほどの切れ味を感じられなかった。 思うにそれは、編者言う、 「花田清輝の文章は、ことごとく、政治的・文化的な状況に触発されながら書かれている。文壇青磁から国際政治まで、書の文化からテレビ文化までのあらゆる日常的現象から刺激を受けながら、彼が『乱世をいかにいきるか』で言った『ちぎっては投げ、ちぎっては投げ』という批評活動」 の、肝心の文脈を共有できないからに違いない、という気がした。その点、フィクションは、そもそも共有できる文脈の上で展開されるのだから、格段に違うのかもしれない。それと、フィクションの中では、記憶で書くので間違っているかもしれないが、『鳥獣戯話』の中に、れっきとした史書にまぎれて偽書(『逍遥軒記』だったか)を史書の如くに引用して、煙に巻いていたようなことは、現実相手にはむつかしいせいかもしれない。 その中では、1959年刊行の 「柳田國男について」 は、出色であると思った。柳田國男の姿勢を、 前近代的なものを否定的媒介にして、近代的なものを超えようとする、 態度とみる。それはまた、花田自身の方法論とも重なる。だから、 「わたしは、どちらかといえば、柳田史学よりも柳田民俗学に―柳田民俗学によってあきらかにされたわが國におけるさまざまな芸術のありかたに、ヨリ多く興味を持つ。なぜなら、わたしには、それらの芸術のありかたを否定的媒介にしないかぎり、近代芸術をこえた、あたらしい革命芸術のありかたは考えられないからである」 と書いている。それは柳田國男が『藁しべ長者と蜂』で、 「國の文芸の二つの流れ、文字ある者の間に限られた筆の文学と、言葉そのままで口から耳へ伝えていた芸術と、この二つのものの連絡交渉、というよりも、一が他を育み養ってきた経緯が、つい近頃まで心附かれずに過ぎた。昔話のやや綿密なる考察によって、始めて少しずつ我々にわかってきたのである。いわゆる説話文学に限らず、歌でもことわざでも、もとは一切が口の文芸であり、今でもまだ三分の一はそうだ。現にカタリモノなどは、活字になってもなおカタリモノと呼ばれている。即ち少しも筆を捻らぬ人々の隠れたる仕事のあと始末だったのである。それが文人を尊敬するの余りに、悉く椽の下の舞になってしまった。読者という者の文芸能力を無視して、大衆はアレキサンドル大王の兵士の如くでどこへつれて行って討死させてもよいもののようになった」 と述べているのに触れて、 創造者としての大衆の主体性を過小評価、 しているとして、かつての「芸術大衆化論争」を批判しているのだが、それは、今日死語に近いので省くとして、柳田が、 「活字文化以前の視聴覚文化と、以後の視聴覚文化とのあいだにみいだされる対応」 に着眼し、 「前者を手がかりにして後者を創造することによって、活字文化そのものをのりこえていく」 「民間説話などに代表されるかつての視聴覚的表現を手がかりにして、ラジオやテレビなどの未来の新しい視聴覚表現をつくりだし、文学的表現の限界を突破していく」 という問題意識は、半世紀たった今日、確かに、今日、ネットやゲームを含めたデジタル映像文化や漫画が活字文化を凌駕しているのを見るとき、たぶん花田清輝が想定したものとは違ったものになっているはずである。花田の想定した「のりこえ」像はわからないが、活字文化は、(凸版印刷の時代の)「活字」という言葉自体が死語になりつつあるのを考えると、最早文字単独で世界をつくる文学以上のことが、視聴覚、あるいは視聴触覚で、表現できる、それが技術的に可能になっているということははっきりしている。そのコンテンツが、活字文化のそれを超えているかどうかは別だが。 花田は、この中で、桑原武夫の、 「日本文化のうち西洋の影響下に近代化した意識の層があり、その下に封建的といわれる、古風なサムライ的、儒教的な日本文化の層、さらに下にドロドロとよどんだ、規定しがたい、古代から神社崇拝といった形でつたわるような、シャーマニズム的なものを含む地層がある」 を紹介しているが、分解して見せた文化地層の、最下層のどろどろした地層こそ、柳田が探求し続けた世界である。今日でも、表層の積み重なりがあろうとも、突然何かの折に吹き出てくるようなマグマとして、あることは確かである。 2020年の春、コロナ禍の最中、疫病よけに効くとされる妖怪「アマビエ」がネットを中心に注目を集めたのも、文化地層の底からの蘇りの気配ではある。 しかし、そのマグマは、あるいは、視聴覚化した瞬間、例えば、鳥山石燕『画図百鬼夜行』や、水木しげるの『妖怪事典』のように見える化した瞬間、怖くもなんともなくなるということはある。そこに文学の可能性は、僕は残っているし、それは口承文芸と共通する、想像力に依拠した文脈だと感じているのだが。 ところで、もうひとつ本書で取り上げておきたいのは、 「ダイダラ坊の足跡」 ので触れている、南方熊楠である。その巨人ぶりは、今や知らぬ人はいないが、 「日本の学者、口ばかり達者で、足が動かぬを笑い、みずから率先して隠花植物を探索はすることに御座候」 と言いつつ、馬にけられて膝関節を痛めながら、歩くのを諦めぬ姿を書き記す花田には、イロニーも、皮肉もない。珍しいことである。 最晩年、遺著に納められた「箱の話」に、 ひるがえって考えるならば、ここに、こうして立っているわたし自身が、無数の先祖の『生きている墓』であって、べつだん、かれらは、石でつくった、墓らしい墓を欲しがってはいなかったのかもしれないのだ」 とある。それは服部之総の、 「子供のない夫婦はあるが、父と母をもたぬ子供はいない。そうだとすれば、鼠算というものは、子供に関するかぎり不確実であるが、祖先に関するかぎり確実にふえていくものである」 を受けてのものだが、不思議と印象深い。、 なお花田清輝の作品については、 「鳥獣戯話」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470946114.html)、 「復興期の精神」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/472034541.html)、 「小説平家」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470800504.html)、 についてそれぞれ触れた。 参考文献; 粉川哲夫編『花田清輝評論集』(岩波文庫) |
| 宮城公子『大塩平八郎』を読む。
何度目か、ふと気になって、また本書を開いた。大塩中斎に寄り添い、その思想の流れに則って、中斎の一生を追う。本書は、中斎の思想、陽明学というより、中斎自身が孔孟学と呼んだ、その思想の決算書のような性格を持つ。 |
|
中里紀元『秀吉の朝鮮侵攻と民衆・文禄の役』を読む。
本書は、所謂、文禄・慶長の役の、 天正20年(1592年)に始まって翌文禄2年(1593年)に休戦した文禄の役、 を描く。通常文禄の役、というが、文禄元年への改元は12月8日に行われたため、4月12日の釜山上陸で始まった戦役初年のほとんどは、厳密にいえば天正20年の出来事になる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9)らしい。 著者は、 「私の祖父は唐津藩御用窯の最後の御用碗師であった。文禄、慶長の役で唐津藩初代藩主寺沢志摩守広高によって連行されて来た朝鮮陶工又七(トウチル)が私たちの祖先にあたる」 いわば、略奪連行された朝鮮の人たちは、 薩摩藩だけで三万七千人、 といわれる途方もない数である。特に陶工の連行は、ために朝鮮の生産は衰微したといわれるほどの惨状となり、逆に有田焼、唐津焼といわれるものは、拉致してきた朝鮮人の手に始められたものである。その子孫の著作であることには、ちょっと感慨がある。ただ、問題意識が、侵略した日本軍の行状にあるのか、現地の人々の惨状にあるのか、焦点が定まらず、時系列に、日本軍の経路に合わせて叙述していく方式は、もう少し工夫があってよかったのではないか、という憾みがある。 この朝鮮侵略は、まさに、 無名之師、 である。「無名の師」とは、 おこす名分のない戦争、 の意であり、特に仕掛けられる側だけでなく、仕掛ける側においても必要がなくかつ勝算が確定的でない場合に独裁的な指導者によってなされるものを言う、 とある(https://ja.wiktionary.org/wiki/%E7%84%A1%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%B8%AB)。後漢書・袁紹劉表列伝に、 曹操法令既行、士卒精練、非公孫瓚坐受圍者也。今棄萬安之術、而興無名之師、竊為公懼之 とある。 名分の無い戦争、 である。 無名之兵(三国志・魏書)、 とも書く。まさに、秀吉の朝鮮出兵は、「無名之師」そのものであった。 秀吉の妄想とも言うべき、 唐入り、 という構想から、 ただ佳名を三国(日本、明、天竺)に顕さんのみ、 という朝鮮王への手紙にある、途方もない妄想の実現を目指すのである。そのために、朝鮮は、 仮道(途)入明、 つまり、 秀吉は朝鮮にみずからのもとに服属し、明征服の先導をするよう命じ、 それに応じないことを理由として、四月先手勢の小西行長軍は、釜山城を攻撃する。こうして、翌年まで続く戦争が始まるが、初期の快進撃は、朝鮮軍のゲリラ戦、李舜臣率いる朝鮮水軍による敗北、明軍の参戦などによって、補給線を断たれ、寒気と食料不足に悩まされた日本軍は、南部へ後退、恒久的な支配と在陣のために朝鮮半島南部の各地に拠点となる城の築城を開始し、日本・明講和交渉が始まったところで、文禄の役は終わる。 しかし、十五万余の渡海軍は、翌年には、七万四千余人の減員となっている。特に、先手勢の小西軍は、一万八千が、六千余に減っているし、加藤・鍋島勢も、二万二千から一万一千に減っている、という惨憺たるありさまである。もちろん、この減員は、戦国時代の軍隊が、
かりに百人の兵士がいても、騎馬姿の武士はせいぜい十人足らずであった。あとの九十人余りは雑兵(ぞうひょう)と呼んで、次の三種類の人々からなっていた。 という(藤井久志)編成から見て、雑兵の中には,侍(若党,悴者は名字を持つ)と武家の奉公人(下人)もいるが、人夫として動員された百姓が多数混在している。この構成の中で、多く、弱い立場のものが一番しわ寄せを受け、主従のつながりを持たぬ人夫たちの多くは逃亡している可能性があるので、すべてが戦病死者というわけではないが、その消耗はすさまじい。それにしても、異国の厳冬のさなか、どう生き延びたのだろうか。 本書は、時系列に追うために、こうした兵員各層の実像に迫りきれておらず、そのあたりも、事件を概括しているだけの恨みが残る。 それにしても、秀吉の朝鮮、明を侮る姿勢は、滑稽というよりも悲惨である。しかし、その姿勢は、西郷の征韓論、明治政府の朝鮮併合にまで、通奏低音のように続き、今日もまだ、どこかにいわれなき朝鮮蔑視が続くのが、やりきれない。 それで思い出すのは、西郷の征韓論に抗議、自裁した薩摩藩士横山安武(森有礼の兄)のことを思い出す。これについては、「異議」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-5.htm#%E7%95%B0%E8%AD%B0)でも触れた。 横山安武の抗議の建白書は、こう書く。安武の満腔の思いがある。全文を載せる。
朝鮮征伐の議、草莽の間、盛んに主張する由、畢竟、皇国の委糜不振を慷慨するの余、斯く憤慨論を発すと見えたり、然れ共兵を起すに名あり、議り、殊に海外に対し、一度名義を失するに至っては、大勝利を得るとも天下萬世の誹謗を免るべからず、兵法に己を知り彼を知ると言ふことあり、今朝鮮の事は姑らく我国の情実を察するに諸民は飢渇困窮に迫り、政令は鎖細の枝葉のみにて根本は今に不定、何事も名目虚飾のみにて実効の立所甚だ薄く、一新とは口に称すれど、一新の徳化は毫も見えず、萬民汲々として隠に土崩の兆しあり、若し我国勢、充実盛大ならば区々の朝鮮豈能く非礼を我に加へんや慮此に出でず、只朝鮮を小国と見侮り、妄りに無名の師を興し、萬一蹉跌あらば、天下億兆何と言わん、蝦夷の開拓さへも土民の怨みを受くること多し。 朝鮮を小国と見侮り、妄りに無名の師、 を起こした延長線上に、日清戦争があり、日露戦争があり、その権益を守るための太平洋戦争がある。この建白書は、現代日本をも鋭く刺し突く槍である。いまなお、嫌韓、ヘイトの対象にして、言われなく他国を侮蔑する者への、無言の刃である。 しかし、「通底」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-1.htm#%E9%80%9A%E5%BA%95で触れたように、 「中国に倣った中華思想を基軸に据え」た大宝律令が完成した大宝元年(701)の元日, 「文武天皇は大極殿に出御し,朝賀を受けた。その眼前には前年新羅から遣わされた『蕃夷の使者』も左右に列立した。」 という。この中華思想「東夷の小帝国」意識は, 「日本(および倭国)は中華帝国よりは下位だが,朝鮮諸国よりは上位に位置し,蕃国を支配する小帝国」 を主張するというものだ。それと同時に, 「朝鮮半島諸国に対する敵国観も,日本人の意識の奥底に深く刻まれた。もともと,交戦国であった高句麗や新羅に対する敵国視は古い時代から存在していたのであるが,(中略)その後新羅に替わって半島を統一した高麗は高句麗の後継者と自称したが,日本ではこれを新羅の後継者と見なした。そして新羅に対する敵国視もまた,高麗に対しても継承させたのである。」 この対朝鮮観の根深さは,ちょっと衝撃的である。われわれの夜郎自大ぶりには,われわれの1500年に及ぶ年季が入っているのである。この根の深さは、深刻である。 参考文献; 中里紀元『秀吉の朝鮮侵攻と民衆・文禄の役』(文献出版) |
|
大塩中斎については、「万物一体の仁」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/475454613.html?1591380773)で触れたが、大塩平八郎中斎は、天保八年(1837)二月一九日(三月二五日)に門人と共に蜂起する。その檄文に曰く、 四海こんきういたし候ハゝ天禄ながくたゝん、小人に国家をおさめしめば菑害并至と、昔の聖人深く天下後世、人君人の臣たる者を御誡被置候ゆヘ、東照神君ニも、鰥寡孤独ニおひて尤あはれみを加ふへくハ是仁政之基と被仰置候、然ルに茲二百四五十年太平之間ニ、追々上たる人驕奢とておこりを極、太切之政事ニ携候諸役人とも、賄賂を公ニ授受とて贈貰いたし、奥向女中之因縁を以、道徳仁義をもなき拙き身分ニて、立身重き役ニ経上り、一人一家を肥し候工夫而已ニ智術を運し、其領分知行所之民百姓共へ過分之用金申付、是迄年貢諸役の甚しき苦む上江、右の通無躰之儀を申渡、追々入用かさみ候ゆへ、四海の困窮と相成候付、……。
しかし、その日、中斎は、その高弟であり最愛の愛弟子宇津木靖を惨殺せしめた。宇津木靖、字は共甫。通称は矩之丞,。静区(セイオウ)と号す。静区は全力で中斎を諫めた。その思想的対立を、架空の問答としてまとめてみた。ただ、素人の悲しさ、二人の思想を十分理解し得ていたかどうかは、些か覚束ない。乞う、ご憫笑。。。
|
| 大岡昇平他編『言語空間の探検(全集現代文学の発見第13巻)』)を読む。
現代文学の発見、 |
| 松浦玲『勝海舟』を読む。
文政六年(1823)に生まれ、明治三一年(1899)に死んだ七十七年の生涯を、十八章に桁記述された、900ページを超える大著である。ふと思いついて、再読を始めた。この著者には、『勝海舟』『海舟と幕末明治』『明治の勝海舟』等々、海舟を論じた著作はあるが、『横井小楠』も忘れ難い。 |
|
藤木久志『【新版】雑兵たちの戦場−中世の傭兵と奴隷狩り』を読む。
何度目になるだろうか。読むたびに,戦国日本の風景が変わるのを実感する。信長,秀吉や,信玄や謙信といった戦国大名や武将を中心としてみる風景では,戦国期の実像は決して見えない。本書が与えた衝撃は,はかり知れない。 |
|
竹腰輿三郎『倭寇記』を読む。
「倭寇」という言葉が使われているが、明の文献にも、 大抵の倭寇は真の倭、十の三にして、従ふもの七、 其の倭は十の三にして倭に従ふ者十の七、倭戦へば則ち其掠むる所の人を駆りて軍峰たらしめ、法厳にして人皆な死を致す、 等々とあり、日本人だけではなく「異人種」が多数含まれている。そこには、中世の日本国内とは別の、ある種の国際的な海上世界がある。しかし、その特徴は、 日本流の紅柄染の大模様を染め出した衣服を着用、 し、また、 倭の旗號を用ひた、 とある。「倭寇」たる旗印である。 当時倭寇は、船先に八幡大菩薩の旗を立てて単に祈り、自ら安んじたもので、倭寇と云へば、必ず八幡大菩薩の旗を連想せしむるほどであるから、支那の海賊もまたこの旗を立てたものであろう。そして明人は八幡の二字を「バハン」と読むので、一転して、海賊の所業、若くは密貿易をバシンと號し、やがてそれが日本語となって、「バハンする」若くは「バハンしない」とも云ふ動詞となってしまったと云はれる、 とある。で、倭寇が用いる、 七十頓内外の船、 を、 バハン船(八幡船)、 と呼び、「バハン」は、 海賊、 を意味し、転じて、 密貿易、 を意味するようになる。 徳川氏の初、外国に航行することを許可せられた船長は、誓書に記して、「バハン致すまじく候」と書くようになった、 ともある。ただ、「バハン」の由来については異説があり、 バハンはむ支那音にあらず、配半の支那音であるとなし、昔し鎮西八郎為朝が宋の濱海を侵したとき支那の海賊から配半税(バハン)の方法に従って、収穫の山分を要求せられたことから、日本では此バハンと云ふ語を使用するようになった、 とする説もあるらしい。しかし「八幡」は、 奪販、 番舶、 破帆、 とも当てる(ブリタニカ国際大百科事典・百科事典マイペディア)らしいので、八幡大菩薩の「八幡」であるかどうかは、少しいかがわしいかもしれない。 確かに、「倭寇」は、 永正大永の頃より、伊予國海中因島、久留島、大島の地士、飯田、大島、河野、脇屋、松島、久留島、村上、北浦、等諸士共に相議して、外国に渡海し、海戦を働き各家を富さん事を謀り、野島領主村上図書を議主と定め、各其一族浮浪の人数を集め、都合三四百人大小十余艘の船に乗り、大洋を航行し、西は大明国の寧波、福建、広東、広西、等の諸州より、西南は印度の諸国、安南、広南、占城(チャンパン)、東坡塞(カンボヂャ)、暹羅、其他南海中の呂宋、巴刺臥亜(パラコヤ)、渤泥(ボルネオ)等の諸島に至り、近海諸邑を剽掠し、種々の財物器械を奪取し来たりて、其家を富せり、 とあるように、国内から出航した者たちがたくさんいたことは確かだが、明人の、 汪直、 徐海、 陳東、 鹿葉、 等々が倭寇と共謀するようになって、 倭寇の勢力が益増加、 した事実はある。後期の倭寇であるが、汪直は平戸に居を構え、 門太郎次郎史四助四郎等と結んで、方一百二十歩の巨船を作った。この船は二千人を容れ、木を以て城と楼とを船の上に立て、舟上、馬を走らせるといふ、 一大勢力を成し、1553年(明暦の嘉靖三十二)に、 數十種の倭寇を糾合して支那に侵入し、連艦数百をもって海を蔽ふて進み、……先づ昌國衛を破り、四月大倉を犯し、上海県を破り、揚子江を遡り、江陰を掠め、乍浦を攻め、金山衛を襲ひ、崇熟を攻め、翌年正月には、オオクラり蘇州を攻め松江を掠め、江北の通泰に迫り、六月には呉江より嘉興を掠め川沙窪拓林を以て巣窟となし、四方を侵掠した、 という。結局明の本軍と戦い、 死者千九百に及んだ、 というのだから、その勢力の大きさがうかがえる。しかし、豊臣秀吉の国内統一を機に、八幡の渡航を禁じたことから、さしもの倭寇は、終息したが、別の意味での海外渡航、海外貿易は、衰えず、山田長政のような、海外で活躍する者たちが続く。 参考文献; 竹腰輿三郎『倭寇記』(白揚社) |
|
谷口克広『秀吉戦記―天下取りの軌跡』を読む。
秀吉が信長に仕えてから賤ケ岳の戦いに勝つまでの二十数年間が、誰も真似できない彼の能力が最大限発揮された時期(おわりに)、 についての秀吉であり、 天下を平定した後の秀吉には傲岸な為政者の像が目立ち、さらに晩年には誇大妄想や惨忍さまで表れて(仝上)、 姿を隠した「かつての爽やかな姿」の秀吉像に焦点を当てている。 著者は、「一介の農民だった秀吉を天下人に押し上げたもの」は、 一にも二にもかれの精勤さ、 であるという。おそらく寝る間も惜しんで、 他の者の二倍は動いている、 と。自身が、小早川隆景に宛てた手紙で、 若い頃から、信長家中で、自分の真似のできるものはなかった、 と書くほど働いたのである。その上に、 他人の真似できない能力、 がある。その第一は、 現実を踏まえてきちんと計算できること、 を挙げる。 大ざっぱに何日行程とされているところでも、何キロメートルだから一心に飛ばせば何時間で行ける、と彼は計算する。そして、そのために必要な物資、馬とか食料とかを素早く調わせる、 という。 周りの状況を適格に読む力も、秀吉は他の者よりも抜きんでている。秀吉には、中国大返しをはじめ何度かいちかばちかの賭けがあるが、賭ける前に冷静な状況判断がある。これら徹底的に現実を踏まえた思考は、当時にあっては驚くべきものと言っていい、 と。そして、第二は、 相手をたちまちに心服させてしまう才能、 という。俗に、 人たらし、 といわれる能力である。梟雄といわれた宇喜多直家は、最晩年秀吉に心服し、毛利戦の最前線に立つ。賤ケ岳の戦いで、柴田勝家や織田信雄の配下をたちまちのうちに味方にしてしまう手腕など、 まるでマジック、 である、と。そして、 秀吉は、決して自分に付いてくる者を裏切らなかった。宇喜多に対して信長が赦免しなかった時でも、身をもってかばい、決しておろそかにすることはなかった、 と。 では、その秀吉が、天下取りに成功したのは才能だけか、というと、 何重にも重なった運の良さ、 があった、という。その一つは、 秀吉が仕えたのが能力尊重主義の信長だったということである。主君が信長だったからこそ、小者からはじまって方面司令官という家臣最高の地位まで昇進できた、 のである。第二は、 自他ともに認められた信長の後継者である信忠が、信長と一緒に倒れたことである。信忠が難を逃れていたらならば、秀吉には全くチャンスはなかったはずである。 第三は、 明智光秀と戦うことのできる軍勢を持った有力武将、柴田勝家、羽柴秀吉、滝川一益のうち、秀吉が京都から最も近い地点にいたことである。しかも秀吉は、敵の毛利氏と講和交渉の段階になっていた。本能寺の変を知った秀吉は、いち早く講和を結んで、弔い合戦に備えることができた。毛利氏が追撃してこなかったのも、大きな幸運であった。 第四は、 秀吉と一緒に弔い合戦を行ったのが三男の信孝の方であり、その功績によって、二男の信雄との差がなくなってしまったこと、後継者としての資格が互角になった二人が争ったため、一方を立てにくくなった。 第五は、 ライバルの一人滝川一益が没落しただけでなく、清須会議に間に合わなかったこと。おかげで、丹羽長秀・池田恒興を籠絡した秀吉は、勝家に対して三対一の優勢を保ったまま会議に臨むことができた。 第六は、 謀叛を起こして滅びてしまった明智光秀が、機内一帯に支配権をもつ「近畿管領」ともいうべき地位にあったということ。そのため秀吉は、その跡を取り込んで京都近辺を固めることができた。 もちろん、その幸運を生かすも殺すも、本人次第である。それについて、著者は、 これほどの幸運が重なるのだから、まさに秀吉は幸運の女神の寵児といってよいだろう。しかし、幸運を最大限に生かすものは、やはり当人の実力である。本能寺の変以後の秀吉の動きを見てみるがいい。毛利との交渉、中国大返し、山崎の戦い、丹羽・池田・堀(秀政)の取り込み、清須会議、畿内の掌握、いかに敏速でかつ適格であったか。秀吉の前には、優れた人材であったはずの明智や柴田さえ、のろまで能無しに見えてしまうほどである。 と書く。この時期の秀吉は、まさに絶頂である。 参考文献; 谷口克広『秀吉戦記―天下取りの軌跡』(集英社) |
|
田中健夫『倭寇―海の歴史』を読む。
著者は、本書の狙いを、 |
|
高柳光寿『本能寺の変』を読む。
|
|
高柳光寿『明智光秀』を読む。
明智光秀の言葉として伝わっているものがある。 |
|
高柳光寿『賤ヶ岳の戦い』を読む。
「この江北の一戦は、本来なれば、余呉庄合戦とか、柳ケ瀬の戦いとか呼ばれるべき筈である。現に『江州余呉庄合戦覚書』という本がある位である。それなのに、古くから普通に賤ヶ岳合戦といっている。そこにはそれだけの理由がなければならない。七本槍のあった地名によるなれば、飯浦山合戦といってもよい筈である。それを賤ヶ岳合戦というには、飯浦山の戦いを秀吉が賤ヶ岳の砦にあって指揮していたからではないかと思う。七本槍の感状には柳ヶ瀬表という言葉はあっても賤ヶ岳という文字は見えていない。理窟にならない理窟をつけるような気がするが、この一戦を賤ヶ岳合戦というのは、どうもそこで秀吉が指揮をとったからではないかと思う。そしてこの切通しの勝敗が全局の勝敗を決定したからであろう。」 と分析する。実はこのことは、大事な分析を前提にしている。大垣から、大返しで、十三里を五時間で駆け戻った秀吉は、大岩砦、岩崎砦陥落で動揺する味方の士気を鼓舞するため、自分の到着を諸軍に触れ、夜明けを期して攻撃開始を令し、賤ヶ岳の砦に入った、と著者は見る。しかし、 「秀吉が賤ヶ岳の砦に入ったと書いている史料は一つもない。丹羽長秀がこの砦に入ったということは、『太閤記』『志津ヶ嶽合戦小須賀久兵衛私記』『丹羽家譜伝』などに見えている。そして、『太閤記』には、秀吉は賤ヶ岳の砦の南に旗を立てたとある。しかし、砦は山巓にある。その南では山に遮られて指揮はできない。秀吉の七本槍の感状をみると、秀吉の眼前において槍を合わせたとある。七本槍のあったところはこの切通し付近である。それを秀吉は高い所、すなわち賤ヶ岳の砦から見ていた。それでなければ、この文字は使用できない。切通しを見通せるところは、秀吉からはこの賤ヶ岳の砦より外にない筈である。秀吉はこの砦にしいて切通し付近の勝政隊攻撃の指揮をしたとすることは誤っていない。」 という前提である。それはさらに、秀吉は攻撃の部署を決め、 「自分自身で(大岩砦に留まる)佐久間盛政に当たることにした。これは、結果は追撃となったのであるが、軍全体の配備からいえば三手にわかれ、自分が左翼に廻ったことになる。そして狐塚にある勝家に対して包囲の形成をとったのである。この秀吉が左翼に廻ったということは、全軍の把握が難しいように考えられるが、(中略)このときの作戦は右翼を移動させないで、それを軸として左翼から敵の右翼を打ちのめして、これが成功を待って中央を進出させ、右翼からも突撃させるという策をとったのであり、左翼が主動部隊であり、しかもその行動は峰筋で行われたので、中央からも、右翼からも望見され、それをはっきり知ることが出来るという状態にあった。だから、秀吉自身が左翼に廻ったということは最も適当した、最も必要な処置であった。」 という戦略とも合うのである。 秀吉帰陣の方を受けて、大岩山から退陣する佐久間盛政隊を援護していた柴田勝政隊三千は、賤ヶ岳の西北方約百メートルの切通しにあり、秀吉は、切通しの東南方の小平地、切通しまでは約五百メートル、俯瞰できる位置にある。 「秀吉は旗本をその真近に攻撃態勢を取って布陣させ、自分は高いところから、敵陣とこの兵とを見おろして、攻撃の機を待っていた」 のである。 「秀吉は柴田勝政隊攻撃の機会を待っていた。この敵部隊が退却を開始するであろうことは十分予想されるところである。われはこれに対して、兵力を集中し、包囲の姿勢を取り、監視を厳重にして敵の退却開始を待てばよい。そして退却開始と同時にこれを攻撃すればよい。退却開始は敵陣動揺の端緒である。それを秀吉は待っていた。」 そして、まさに柴田勝政隊の退却開始と同時に、待機の旗本部隊に攻撃を命じた。 「勝政の部隊は切通しの低地を挟んで、その両側に布陣していたらしい。そこでまず東南方の高みにある部隊を西北方の高みに収容しようとしたのであるこの東南方の部隊が低みにかかったところを、秀吉の旗本は東南方の高みから銃撃を加え、敵が動揺するに及んで、秀吉はこれに突撃をおこなわせた。」 柴田勝政隊は、峰筋を北方へ二キロ、戦いつつ権現坂付近の佐久間盛政隊に合流しようとする。 「佐久間盛政は退却して来る柴田勝政の兵を収容し、列を乱してこれを追ってくる秀吉の兵を迎えて、これに邀撃をくわえた。」 勝政の隊は総崩れになり、二十町ばかり敵味方一つになって追い立てられたが、峰筋の高みにある二千ばかりの盛政隊は備えを崩さず、『江州余呉庄合戦覚書』には、 「盛政は分目の戦いを快くやるだろう」 と書くほど、収容は成功するかに見えたが、 「このときに当たって、茂山にあった盛政の左側背の掩護に当たっていた前田利家は、その陣地を放棄して移動を開始した。それは敵と戦闘を開始した盛政隊の背後を遮って、東方から西方へ峰越に移動して塩津谷に下り、そこから北方の敦賀方面へ脱出したのである。」 前田隊の移動は、盛政の隊からは、 裏崩れ、 に見え、 「前田隊より後方に陣していた諸隊からは盛政隊の敗走のように見えた。そこで初めから戦意を有たない部隊は勿論のこと、その他の部隊にあっても戦意を失ったらしく、早くも戦場を脱走するものが少なくなかった」 という。 「このころになると、秀吉の兵力はますます増加し、(中略)南方及び東方から佐久間信盛の隊に強力な攻撃を加えた。これに対して、盛政方にあっては佐久間盛政・原彦次郎ら奮戦大いに努め、行市山の陣地へ峰筋をしだいに北方に退却したけれども、前夜からの疲労もあり、ついに力及ばず、盛政の兵は全く潰乱に陥り、一部は峰伝いに柳ヶ瀬方面へ、また一部は山を下って塩津谷方面へ敗走したのであった。」 そして、著者はこの戦闘の帰趨をこう断言する。 「この切通しから権現坂までの戦闘の勝敗は余呉湖を中心とする柳ヶ瀬一帯の戦争を決定づけたものであるが、それはまた全戦局の勝敗をも決定したものでもあった。そして権現坂における勝敗を決定した一番大きな原因は前田利家の裏切りであったのである。」 それは、クラウゼヴィッツの、 「戦争は政治的交渉の一部であり、従ってまたそれだけで独立に存在するものではない」 という「戦争論」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-1.htm#%E6%88%A6%E4%BA%89%E8%AB%96)を思い起こさせる。「戦争」は、あくまで政治的目的達成の手段である。間違っても、戦争が目的化されることはない。 「戦争は政治的交渉の継続にほかならない、しかし政治的継続におけるとは異なる手段を交えた継続である」 である、と。 利家に限らず、秀吉の切り崩しは、多岐にわたったが、同じことは、勝家側からも行われ、 「堂木山の守将山路将監……、賤ヶ岳の桑山重晴・岩崎山の高山重友にしても、勝家に通じていたと思われる節がないではない。」 だからこそ、敵の陣営に加えぬため、大垣からの帰還を急ぎ、それを、味方に知らしめようとしたのである。 「そこでその帰還を味方の諸将に知らせるという目的もあって、盛んに松明を焚いた…。賤ヶ岳をはじめとして田上山からも、北国脇街道のこの松明は良く見えた筈である。」 と。だから、 「勝家の政治力が秀吉のそれより勝れていたら、賤ヶ岳の戦いは佐久間盛政の大岩山攻略を機会として勝家の勝利に帰したであろう。(中略)勝家は盛政の大岩山攻略によって秀吉陣営の崩壊を期していたのではなかろうか。岩崎山の高山重友も、賤ヶ岳の桑山重晴も敗走した。堂木山の敵も動揺した。神明山の敵も動揺したであろう。けれども田上山の羽柴秀長の陣と左称山の堀秀政の陣は微動だにしなかった。そのために堂木山の兵も神明山の兵も敗走するに至らなかったのである。すなわち秀吉の陣は崩壊すべくして崩壊しなかったのであった。秀長は勝家方の盛政のような地位にあったから問題とすることはできないとしても、秀政を完全に掌握していたことは、秀吉の政治力でなければならない。」 と。すなわち、 「戦争は単なる軍事的行動ばかりではない。戦争は戦闘ではないのである。」 と著者は締めくくる。
参考文献; |
|
藤本正行『信長の戦争−「信長公記」に見る戦国軍事学』を読む。
本書は、 |
-
関連ページ
-
リーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
管理者のリーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
目標達成のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
-
リーダーシップに必要な5つのことについては,【1】【2】をご覧ください。
-
リーダーシップチェックリストについては,ここをご覧ください。
-
発想技法の活用については,ここをご覧下さい。
-
管理者の意味については,「中堅と管理者の違いは何か」をご覧下さい。
-
管理者は何を問題にすべきかについては,ここをご覧下さい。
-
「管理者にとっての問題」については,ここをご覧下さい。
-
-
管理者の役割行動4つのチェックポイントについては,ここをご覧下さい。
-
OJTのスキルについては,ここをご覧下さい。各論は,それぞれ下ページをご覧下さい。
-
OJTプランのプロセス管理【1・2・3】
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションスキルは,コミュニケーションスキル①とコミュニケーションスキル②をご覧下さい。
-
コミュニケーション力チェックリストは,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションタブーについては,ここをご覧下さい。
-
職場のコミュニケーションは,ここをご覧ください。
-
マネジメントに求められるコミュニケーションスキルについては,ここをご覧下さい。
-
-
自己点検チェックリストは,ここをご覧下さい。
-
-
アイデアづくりは,日々 1つずつを実践している。それについては,ここを見てほしい。