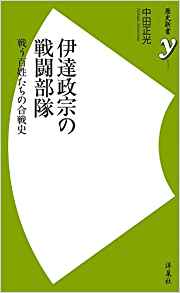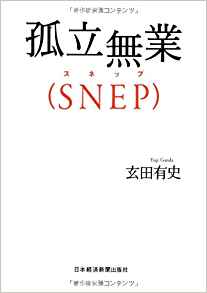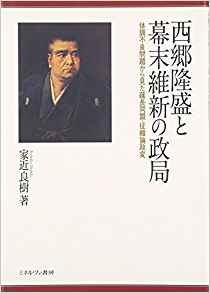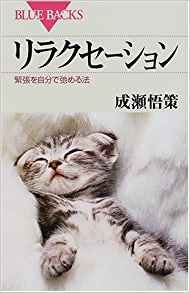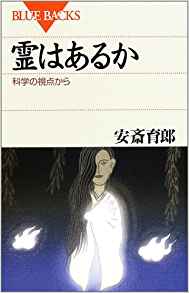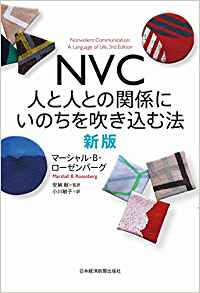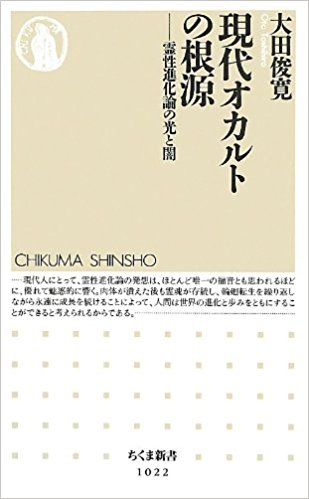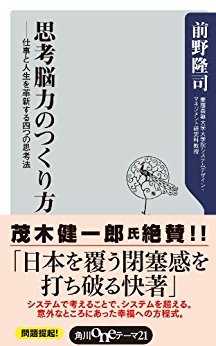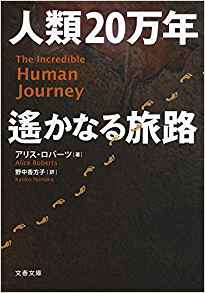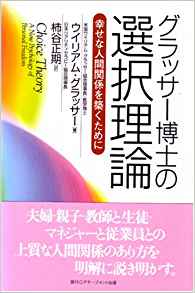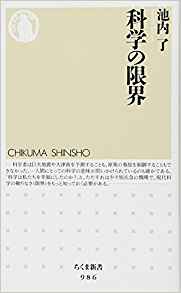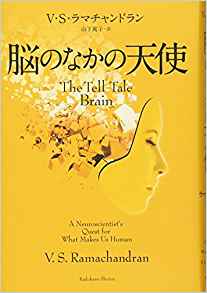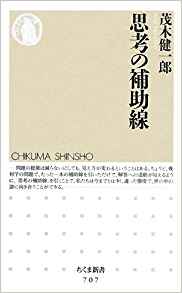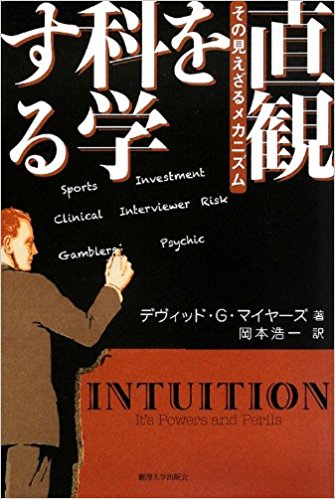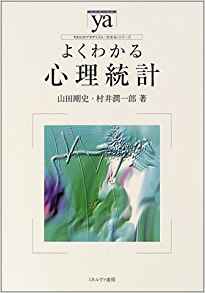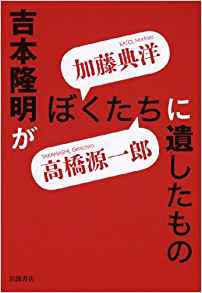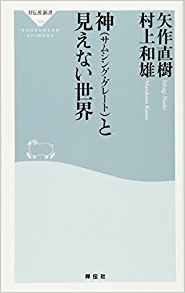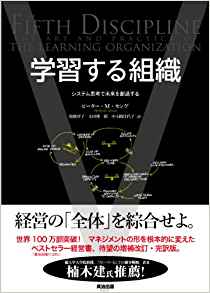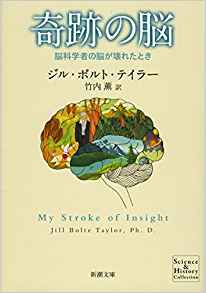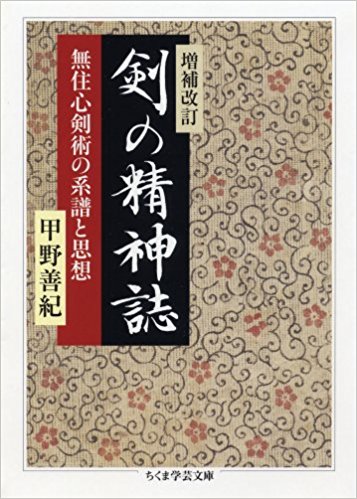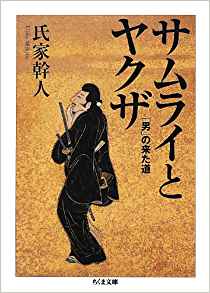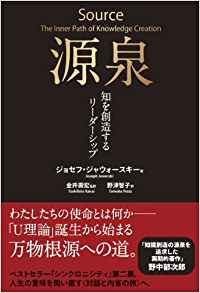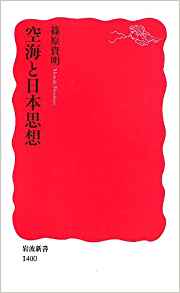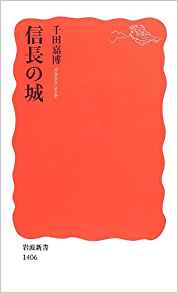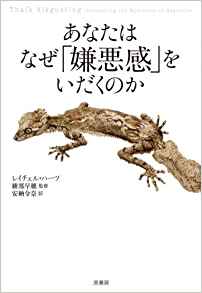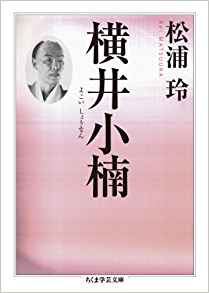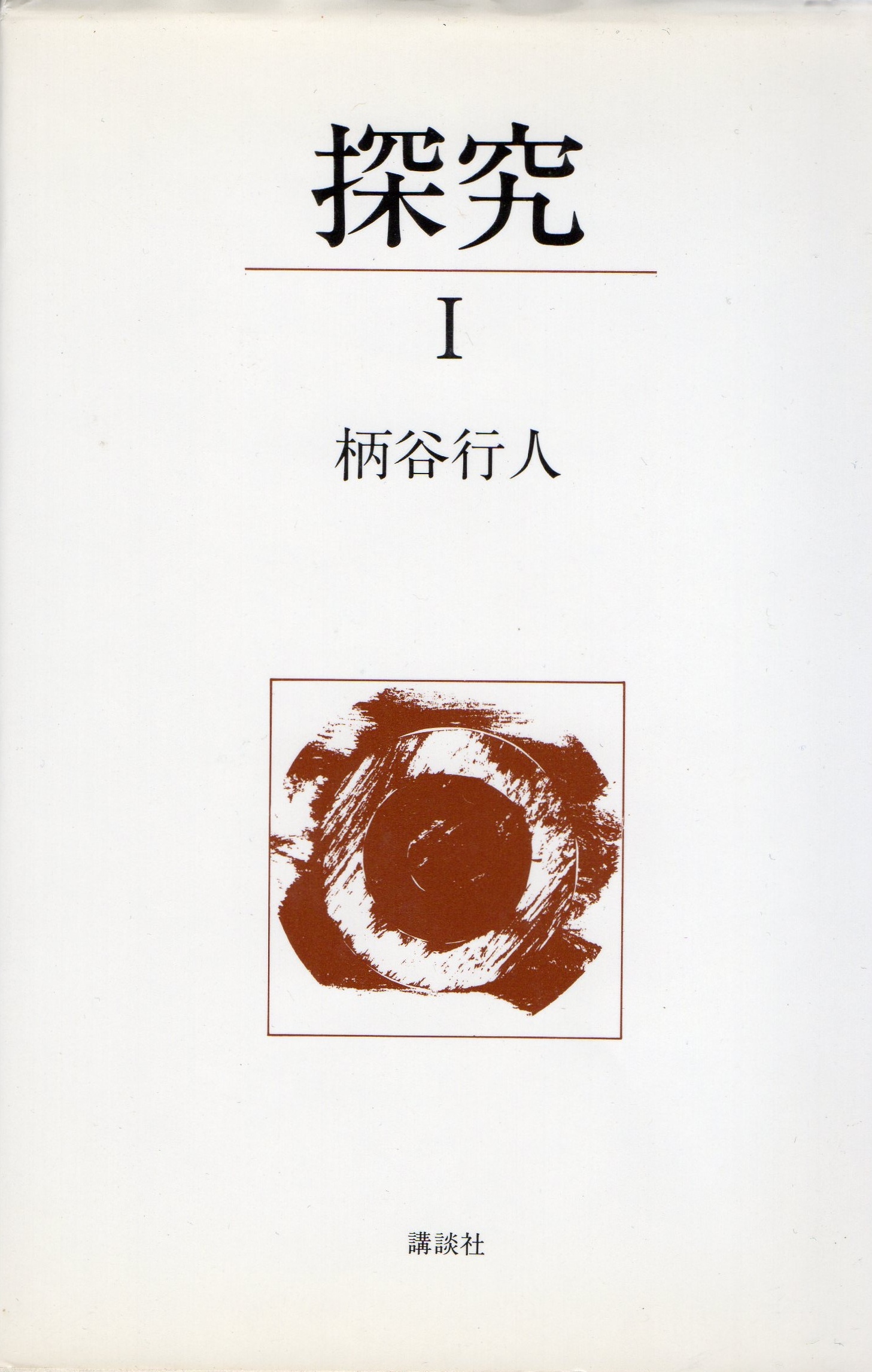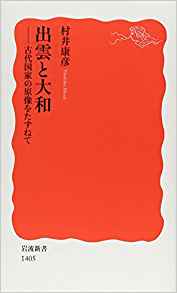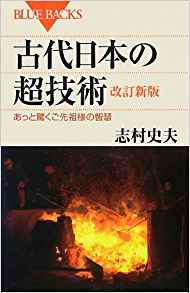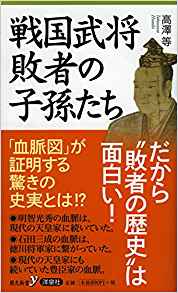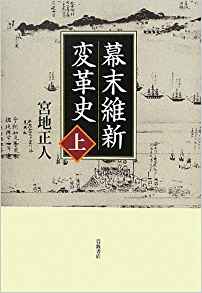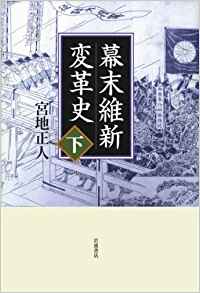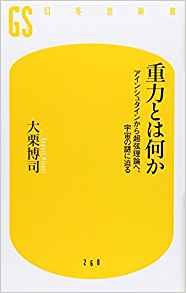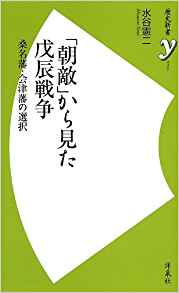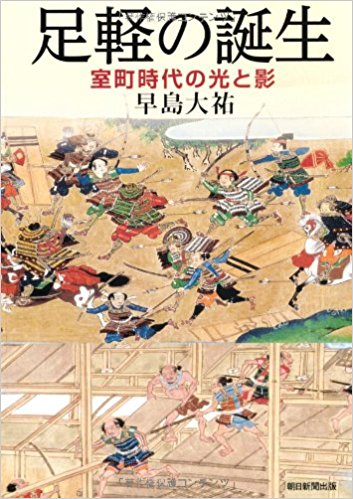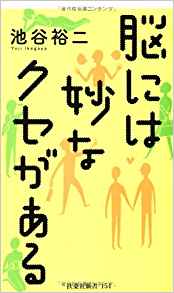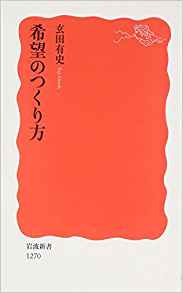|
野臥 |
|
中田正光『伊達政宗の戦闘部隊』を読む。
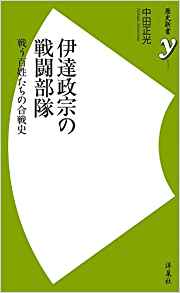
戦国大名の軍事力の基礎となる,戦闘部隊,兵站部隊の実像は,よく分かっていないこと言う。本書は,
後北条氏が豊臣秀吉に滅ぼされる一年前の天正十七年(1589)年,伊達氏が相馬攻めの為に領内一部郷村で陣夫動員調査を行った『野臥日記』をもとに,動員兵力の内実に迫ろうとした。
記録に残っているのは,現在の宮城県白石市の一部と刈田郡,福島県の信夫郡,伊達郡の一部で実施された記録である。
『野臥日記』では,当時郷村に住んでいる壮年男子をすべて書き記しているが,家族や女性,子供が記されていないため,村の住民数まではわからない。野臥とは,百姓たちが武装した状態をいうのだそうだ。「野伏」とも書く。
ただ記録には,比較的裕福な家主,半自立的で未だ自分の耕作地を持たない名子,家主に一生隷属している下人が記されており,煩い(病人),牢人,行人(修験者),中懸(なかけ=下層家臣組士)が記録されている。さらに,馬上の侍である「平士」(へいし)に相当する地頭(郷村の領主)としての地侍なでが記されている。
たとえば,こんなふうに記されている。
かぢや 大波分
上 や一郎
上 四郎兵へ 大分
上 藤十郎
上 与二郎
大なミ殿分
上 寺嶋二郎兵へ
上 大波与三さへもん
上 わく沢新兵へ
上 助ゑもん
上 たんは
山伏 大泉房
上 新さえもん
上 や一郎
上というのは,健康状態を上中下で区別したもの。「かぢや」は,農耕具や刀槍といった手工業的作業に従事していた非農業的存在の在家という意味。「大波分」とあるのは,大波玄蕃という地頭が知行していることを明記している。「大なミ殿分」は,山伏を含めた八人を,大波氏が扶持しているということであ。なお,大波氏は,伊達家の中で「召出」という,門閥的な存在であったと推測されている。これによって,鍛冶屋在家の四人と,大波殿分の八名が,陣夫として動員可能と判断されたことを意味する。
在家(ざいけ)というのは,本来は一軒の農家のことを言う。しかし実際には,数軒集まって在家と呼んでいることが多い。屋敷,菜園を含めてそう呼ぶ。屋敷の主人は家族兄弟のほか,名子,下人まで従え,農家とはいうものの経済的には恵まれている。本来,在家とは郷村に数人いた地頭地主(伊達氏と御恩と奉公の関係にあった家臣)が税を徴収する際の呼び名で,在家農民と直接相対していたのは地頭たちということになる。大名は,こういう地頭を介して,郷村支配を行っていたが,『野臥日記』は,直接把握しようとしたものと見ることができる。
郷村に根を張り,多くの耕作地や在家を所有し,自らも農耕に従事していたような地頭こそが伊達家家臣団のなかの「馬上の平士」に相当する(地侍・土豪)。もしその村が大名の直轄地の場合は,地頭的存在は,伊達政宗自身ということになる。
もう一例。小国郷の中島在家。
中島 大波分
上 十郎ゑもん
上 惣さへもん
上 助十郎
御なかけ てらさき弥七郎
同 かんのとさの守
ここには二人の「御なかけ」(名懸)というのは歩卒の足軽で,弓組,鉄砲組が主力となっていた。これは,伊達氏と「奉公と御恩」の関係にある給人(知行地を与えられている家臣)ではなく,単に伊達氏に抜擢された有力農民であり,地侍・土豪のように馬上は許されない。しかし,著者は言う。
伊達氏が有力農民たちを歩卒侍(中懸衆)として抜擢して,伊達氏直属の弓衆に仕立てることで,村では地頭大波氏との徴税関係を廃止し,地頭と有力農民の名懸たちを引き離す結果となったことを意味する。
つまり農から兵への分離のはじまりである。やがて名懸を城下に住まわせ,村から引き離そうという展望があったことを示している。
と。こういう軍勢構成から考えれば,
ある時期,伊達氏の軍勢一万のうち,直臣は500程で,残りはほとんどが郷村からの動員兵や臨時雇いであった,
という。つまり,
伊達氏は,重層的に直臣である家臣団を形成し,さらに,郷村の地頭領主を召出や平士として,さらに在家農民から多くの兵士を動員していった,
のである。となると,映画や小説のような激しい戦闘はしにくいはずである。なぜなら,
こうした兵を失うということは村の崩壊につながりかねなかった。つまり,耕作者を失うことを意味していたからである。ましてや,伊達氏の直轄地から集められた者たちが多ければ年貢が見込めなくなる…。だから合戦以前には必ず調略という誘いの手を伸ばし,戦わずして勝つことを℃の武将たちも求めていた。
それは当然,戦いになって,
撫で斬りその数を知らず,
と必ず戦勝報告に記す,常套句も信じてはいけないということを意味する。領有しても,村々に耕作者がいなければ,何のための戦いだったかがわからなくなる。
いまひとつは,最近は,「乱取り」が常識的に言われるようになったが,野臥主体の戦闘集団の狙いは,乱取りにある。
当時のおもな合戦のねらいは乱取りであって,村や町を襲って金目になる物を奪い取ることに主眼が置かれた。なかでも牛や馬は在家農民(野臥)たちの貴重な家財…,
であったらしい。それは伊達氏が,兵農分離が進んでいないせいだという常識を,著者は疑っている。基本的に,程度の差はあれ,伊達家の軍隊構造と変わらなかったのではないか。
現に,関ヶ原の合戦終了後,徳川軍の雑兵たちは引き揚げ途中で,牛馬の略奪に夢中になっていた,といわれる。実態は変わっていないのである。
こうした地頭と在家の関係を決定的に断ち切るきっかけになったのは,秀吉であり,惣無事令の儀の発令によって,大名間の私闘だけではなく,百姓・町人の自力救済の武装蜂起も否定した。やがて,支城廃棄,刀狩り,検地と,次々と全国均一の仕置きが進められ,兵農分離への本格的な一歩となっていく。
この後,帰農するか城下へと移り住むかの,一人一人の選択がやってくる。それは身分社会の確立への道でもある。
参考文献;
中田正光『伊達政宗の戦闘部隊』(歴史新書y) |
|
孤立無業 |
|
玄田有史『孤立無業』を読む。
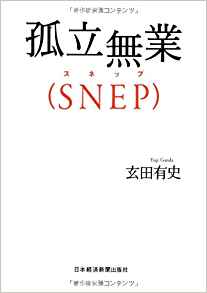
どこかで,ひきこもり,ニート,フリーターを含めて500万人という推測数値を聞いたことがある。ここでいう,孤立無業もこの中に入る。500万かというと,一世代200万人(もっと少なくなっているが)と見積もって,二世代半に当たる。それは,その人たちが,社会保険料をきちんと払う仕事をしていないということになる。それを聞いた時,足もとで,社会保障制度は崩壊している,と感じた。
「労働力調査」によると,2012年を平均すると,15歳以上の人口は1億1098万人,そのうち就業者は6270万人,その差が,無業者で,4828万人になる。
著者は,その無業者の中で,
20〜59歳で未婚の人のうち,仕事をしていないだけでなく,ふだんずっと一人でいるか,そうでなければ家族しか一緒にいる人がいない人,
を孤立無業者と呼び,それを研究してきた,という。本書は,
そんな無業者の実態をデータ(「社会生活基本調査」)に基づき,詳しく紹介している。
この,「孤立無業」とは,日本で開発された概念で,英語でSolitary
Non-Employed Persons を指す。2011年の調査では,162万人,10年間で80万人近く増加しているという。
孤立無業者を,
20歳以上59歳以下の在学中を除く未婚無業者のうち,ふだんずっと一人か,一緒にいる人が家族以外にはない人々,
と定義している。2011年時点で,60歳未満の未婚無業者は255.9万人,そのうち孤立無業者が162.3人,実に60歳未満の未婚無業者の63%を占める。このうち,家族型孤立無業は,128.0万人,8割弱を占める。そして,求職活動に消極的なのが,家族型で,29.3%は,仕事をしたいと思っていない。
では,これは,ニート(not in education, employment or
training)やフリーター,ひきこもりと,どういう違いがあるのか。
厚生労働省は,ニートを,
15〜34歳の非労働力人口のうち,通学,家事を行っていない者,
と提示しているが,労働力調査から,2011年時点で,約60万人になる。このうち非求職型と非希望型を合計すると,43.2%,そのうちニートであり,同時に孤立無業である人は,30.0%を占める。
同じく厚生労働省は,フリーターを,
15〜34歳の男性または未婚の女性(学生を除く)で,パート,アルバイトとして働く者,またはこれを希望する者,
と定義していて,やはり,2011年時点で,176万人になる。
厚生労働省は,ひきこもりを,「ひきこもりの支援・評価に関するガイドライン」で,
さまざまな要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学,非常勤職を含む就労,家庭外での交遊など)を回避し,原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしてもよい)
と定義している。ただ実態は把握しにくく,ガイドラインでは,ひきこもり状態の子供のいる世帯を26万世帯と試算しているが,内閣府(「若者の意識に関する調査」)は,「自室からほとんど出ない」「自室から出るが家から出ない」「近所のコンビニなどへは出かける」という狭義のひきこもりが,15歳以上39歳以下で23.6万人,「普段は家にいるが,自分の趣味に関する用事の時だけ外出する」準ひきこもりが46.0万人と試算している。著者は,
(いま)無業であることが,就職しないということを意味しないが,
孤立状態にあることは,仕事に就こうとする活動やそもそも働こうという希望を抑制することにつながる,
とし,さらに,
自分ひとりで考えているだけでは,かえって悩み過ぎてしまって,袋小路に陥ることもあります。結局,考え過ぎてしまって「自分には働くことは無理」と思い込み,就職を断念する,
ことになり,ニートになる原因の一つとなっている,と著者は分析し,
さらにいえば,ニートになることが,ますます無業者の孤立に拍車をかける,
という。そして,
ニート状態にある若者も,最初から働くことをあきらめていたわけではありません。かつては一生懸命就職活動をしていた人も多くいます。その方が言うには,ニートには「就職を求める人たちの長い行列の後ろのほうに自分は並んでいる」感覚があるそうです。そして「その行列は,前のほうだけ入れ替わっている様子は感じるけれども,少しずつでも自分の順番が前に繰り上がっていく気配がない」というのです。そして「このまま並んでいても希望は見えないし,かといって他の方法が思いつくわけではない。そのまましばらく並んでいたが,どう考えても自分の番がきそうもない」。そのなかで仕事に就くことを徐々に断念し,ニートになっていく,
という。そしていったんニートになると,ますます孤立化を深めていく。
孤立無業→ニート→孤立無業→ニート…
と負のスパイラルに落ち込んでいく。孤立無業では,一度も,仕事をしたことのない人が20%を超える。しかも孤立無業のうち,一人型では,4人に一人が,受けられるなら生活保護を受けたいと考えている,のである。
これは正直,心底日本の危機と思う。希望のない社会に,未来志向は生まれない。単なるポジティブシンキングのレベルの話ではないのである。
著者は言う。
政府の手で100人のニートを自立させることは難しい。むしろ100人のニートを支援できる10人の若者を育ててほしい。政府が若者を支援するのも重要ですが,若者を支援する若者を支援することは,もっと大事なことなんです。
と。なぜなら,
孤立無業者本人が自分の力だけでは踏み出すことができない以上,他者のほうから働きかける。つまり会うとリーチによって上手に「おせっかい」することが肝要,
だからなのだ,と。
僕は,こうした若者の現状は,社会の生み出したものであり,それが家庭に反映し,それが個人に反映すると思っている。いま日本の社会は病んでいる。一朝一夕に特効薬はない。しかし,いま動きはじめないと…という著者の危機感だけは,伝わってくる。
参考文献;
玄田有史『孤立無業』(日本経済新聞出版) |
|
ストレス |
|
家近良樹『西郷隆盛と幕末維新の政局』を読む。
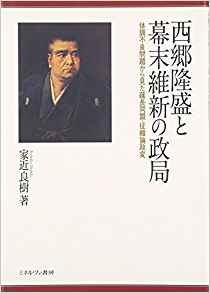
あとがきで,著者は,
従来の日本史研究者があまりにも健常者中心であること,
を問題意識に,西郷隆盛のストレスを,久光との葛藤を通して,幕末から,明治六年の政変まで辿る。是非はともかく,西郷隆盛の抱えていた桎梏が見え,それはまた同時に,西郷自身のものの考え方の一貫した軸のようなものまでをあぶりだすところが,いままでの史書にない,斬新さといっていい。
朝鮮へ政府要人を使節としてなにがなんでも派遣しなければならないほど,朝鮮問題が緊迫化していないなかで,
西郷が朝鮮使節志願を,突然,閣議で願い出た後,板垣(退助)に,協力を求めて,
是非,此処を以テ戦に持込不申候ては迚も出来候丈に無御座候付,此温順の論を以テはめ込み候へば必ズ可戦機会を引起し可申候付,只此一挙に先立,死なせ候ては不便杯と若哉姑息の心を御起し被下候ては何も相叶不申候間,只前後の差別あるのみに御座候間,是迄の御厚情を以御尽力被成下候へば死後迄の御厚意難有事に御座候間,偏ニ奉願候。最早八分通は参掛居候付,今少の処に御座候故,何卒奉希候…
という必死の手紙を認める。著者は言う。
この文面からは,当時の西郷が,まるで死神に取り付かれたかのように死に急ぐ姿が浮かび上がってくる。
と。この後,三条(実美)との会見を板垣に報じる,西郷の文面にも,
此節は戦を直様相始め候訳にては決て無之,戦は二段に相成居申候。只今の行掛りにても,公法上は押詰候へば可討の道理は可有之事に候へ共,是は全ク言訳の有之迄にて,天下の人は更に存知無之候へば,今日に至り候ては全ク戦の意を不持候て,隣交を薄する儀を責,且是迄の不遜を相正し,往先隣交を厚くする厚意を被示候賦を以,使節被差向候へば,必ズ彼が軽侮の振舞相顕候のみならず,使節を暴殺に及候儀は決て相違無之候間,其節は天下の人,皆挙て可討の罪を知り可申候間,是非此処迄に不持参候ては不相済場合に候段,内乱を冀ふ心を外に移して国を興すの遠略は勿論,旧政府の機会を失し無事を計て終に天下を失ふ所以の確証を取りて論じ候…
と,その動機を余すところなく語っている。
第一は,「使節を暴殺に及候儀は決て相違無之候間,其節は天下の人,皆挙て可討の罪を知り可申候」と,本来なら征韓するほどの理由がなかったにもかかわらず,それを強引につくりだそうとしている,
第二は,「内乱を冀ふ心を外に移して国を興す」と,不平士族の不満をそらそうとしている,
第三は,「旧政府の機会を失し無事を計て終に天下を失ふ所以」と,旧幕府が平穏節を計り,事なかれ主義に陥ったために滅んだが,新政府の現状はそれに近いという危機意識がある,
というのである。それにしても,と著者は言う。
西郷はひどく急いていたのである。ここには,余裕を失っている,それまでの西郷とはまったく異なる別人の姿が見られる…
と。そして,この時期,西郷は,極度の体調不良に陥っていた。
数十度の瀉し方にて甚以て疲労…
という状態なのである。これは,下剤を日常的に用いていたゆえに起きたことだが,それは,陛下から遣わされたドイツ人医師の,持病である「肩並びに胸杯の痛み」対策として,肥満解消のための瀉薬療法と食事療法という処方にもとづくが,このために,日に五六度の下痢に苦しめられることになる。
その原因となった西郷の持病に,著者は,ストレスを見る。
その一つは,西郷の性格である。一般には豪放磊落と受け止められているが,
ステレオタイプ化された西郷 隆盛像から離れて,西郷のありのままの姿を追う…,
として次のような特徴を上げた。
第一は,軍好き。単なる戦闘好きだけにとどまらず,戦に臨む前の緊張感を持って日常を生きるのを好んだ。
第二は,多情多感。目配り,気配りの凄い,きめ細かな感情の持ち主。感情の豊かな人間味あふれた人物であった。血気にはやり,自分の感情を率直に噴出させるタイプで,その分好き嫌いが激しい。「相手をひどく憎む」「度量が狭い」という藩内の評もある。
第三は,策謀家・政略家。緻密かつ論理的・組織的な頭脳の持ち主。あ相手との駆け引きを楽しむタイプ。無策な人間を軽蔑した。ただし策略家としては,失敗が多い。
そして,著者は,
こうした容易に他人に信をおけないタイプの人間は,当然相手の行為をめぐって憶測をたくましくし,そのことで強いストレスを受ける羽目になる。
というが,むしろ,西郷が矢面に立つほかない出色の人物である故に,というべきなのかもしれない。そして,西郷の特色は,常に死の意識が付きまとっていることだ。いつくかのエピソードで有名なのは,僧月照と入水自殺から,一人生き延びた後,大島に流罪になるが,このエピソードで,
南洲は此事あってより後は…終始死を急ぐ心持があったものとおもわれる,
という(重野安繹の)回想もあるが,西郷自身は,「土中の死骨」と自ら称し,
投身という「女子のしさうな」手段を講じ,しかも自分一人生き残ったことを悔いる言葉を吐いた,
という。それが強く西郷の中にあったらしく,それを象徴するのが,二度の流罪から赦免されて軍賦役になった西郷が,長州藩邸に乗り込み,長州藩を関係者を説得するとして,
迚も説得いたし付け候儀は六ケ敷候得共,承引致さず候迚空敷帰し申す間敷,殺し候えば長には人心を失い申すべし,
と,朝鮮使節と同じ発想,自分の死を持って,軍の名分を立てようという発想がみられる。
しかしそれ以上に,ストレスとなったのは,斉彬死後,国父として薩摩の実力者となった島津久光およびその近臣との間での葛藤として,現在化する。
とりわけ,「地ゴロ」(田舎者)発言以来,久光の憎悪を一身に受け,奄美大島,沖永良部島と二度の流人生活を余儀なくされ,軍賦役で復帰して以降は,久光を意識し格段に慎重になった,と言われる。
しかも慶応三年時点ですら,武力倒幕に傾く,「暴論派」は,藩内でも少数派で,小松帯刀も,慶喜の大政奉還以降,慶喜を新体制の中心に据えようという方向に転じ,京都藩邸ですら,武力討幕を志向するものは少数派であった。しかし,この時期に,久光は,体調不良に陥り,国元へ帰国,代わって,藩主茂久が上洛,以後,その機をつかんで,曲折を経ながら,鳥羽伏見で,戦端を開くに至る。
藩の大勢,当然久光自身も,倒幕を容認していない。そんな中で戊辰戦争に引きずり込まれ,薩摩藩は,多大の犠牲を払い,しかも人口の四分の一にまで達する,他藩と比較にならない20万人に及ぶ武士が,廃藩置県で路頭に迷うに至る。その憎悪とプレッシャーは,西郷に重くのしかかっていた,と言えるだろう。
それが病気の一因かどうかはどうかはわからないが,西郷という人間に大きなストレスを与えていたことだけは間違いない。少なくとも,ただ,西郷自身の志向だけから,征韓を急いだというより,薩摩の藩内事情(久光の反発を含めた)が,西郷にその善後策を強いたということだけは間違いない。その責めを一身に背負うタイプの人間でもあったということだ。
そうした西郷を取り巻く環境を,病気という切り口で,いままでは異なる歴史の断面を剔抉した手際は,鮮やかだと思う。
ところで,小松帯刀と島津久光の体調不良がなければ,鳥羽伏見に始まる戊辰戦争を経た明治維新への回路はよほど違ったものになったということを,感じる。著者は,小松が体調を崩して鹿児島から上洛できなくなったのを,
…このことが薩摩藩ひいては日本国そのもののその後の運命を大きく変えることになったと言ってよい。
と,述懐する。確かに,「たら」「れば」は歴史にはないが,こう思わせるのは,結局歴史を作るのは人間だからだとつくづ思う。
参考文献;
家近良樹『西郷隆盛と幕末維新の政局』(ミネルヴァ書房) |
|
リラクセーション |
|
成瀬悟策『リラクセーション』を読む。
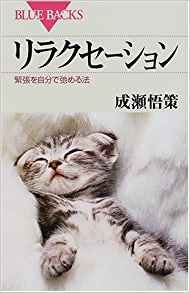
正直に言うが,リラクセーションは苦手である。だから,この本も,長く積読になっていた。ただ,不意に手に取って,読み始めてしまった。
本書について,著者は,
本書のリラクセーションは,巷間行われている筋の生理的な弛みを目的とするものではありません。自分の体の「緊張を自分で弛める」という本人自身の心理的な努力活動を目指しているのです。…からだの緊張という生理的な現象を手がかりとしながら,ご自身でそれをリラックスさせる努力と体験の仕方を模索し,有効なやり方を見出して,自らに適したものを見につけ,生活のなかで習熟していけるようになっていただくことです。
と言う。まあ,自分で緊張を見つけ,それをほぐす方法を見つける手がかりに,ということのようだ。
実のところ,リラクセーションの状態がわからない。だらけているせいか,いつも弛緩していると思いきや,とんでもない。弛めようとしても,どこかで身構えている緊張が残っている。たとえば,
何かをしようとする,しようとしない,いずれにしても,意図があり,意図があるところでは,筋緊張が伴う。
これから動作しようとする予期的な意図の仕方,その気になり方によって現れる準備緊張。
緊張が不全ないし残留して,慢性化する恒常緊張。
人前に出るとか,試験や面接をうけるという状況で起こる場面緊張。
翌日のことを考えて緊張が強くなるイメージ緊張。
等々,日常生活にストレスはつきものだが,
ストレスに対して自分のこころが緊張したというふうに感じているのですが,緊張したのは自分のからだであって,心ではありません。…こころは自分が緊張させた自分のからだの緊張を感じているだけなのです。
と。では,その緊張をどう弛めるのか。
筋の過剰な緊張に対処する仕方として,「弛む」と「弛める」があり,著者はこう言います。
「弛む」ことをよしとするのは,収縮・緊張している筋群の緊張水準が低下した状態であることを重視するからで…本人自身がその「弛む」プロセスそのものに直接関わるか否かに関係なく,どんな方法によつても筋緊張が低下した状態になりさえすればよしとします。
それに対して,
「弛める」ことを重視するのは,自分のからだの緊張レベルを高いところから低いところへ,自分自身の目的実現的な努力,即ち動作という心理活動を意識し,さらにはそれができるようになることを目指しているからです。
当然本書の目指しているのは,
本人自身が主体的に関わり,…自分で自分のからだを「弛める」自己弛緩という心理活動
である。
自己弛緩のプロセスでは,主体が自ら弛めようという意志をもって,ともすれば無用な緊張に走ろうとする自分のからだ,すなわち「身体」という自分自身に真正面から立ち向かいます。
ところで,
リラクセーションが難しいのは,自分が緊張していることに気づいていないからです。
その通りなのだ。そこで,
緊張を捨てなさいといっても,それが容易に務できるわけではありません。幸い緊張感は,その存在を肩の凝り,背中の痛み,頸の突っ張り,腰の痛み,股や膝の突っ張りなどの身体的緊張として,その所在を明らかにしています。それらの部位に本人自身が力を入れて緊張させているのが原因ですから,それを止めさえすればいいのです。
それがリラクセーションの基本は,入れた力を抜くことだが,自分の力を入れていることに気づいていないのだから,自分が緊張していることに気づくためのひとつの方法として,ジェイコブソンの弛緩方法を入り口として紹介している。
これについての評価ができるほど,リラクセーションに精通しているわけではないが,自分で筋肉をそらせることで,緊張する感覚を味わってみるには,いい方法のように思われる。
それは,緊張させながら,緊張を弛める,というもののようだ。
自分のからだに意識を向ける,と言うことの重要性は,ある意味,自分の凝っている,あるいは緊張している部分に注意を向けるということの,重要なのかもしれない。
自分のそれに鈍感だと,どうしても人のそれにも鈍感になる。まずは,自分のからだの好不調,緊張弛緩程度には敏感になりたいものだ。
参考文献;
成瀬悟策『リラクセーション』(講談社ブルーバックス) |
|
フューチャーサーチ |
|
マーヴィン・ワイスボード&サンドラ・ジャノス『フューチャーサーチ』を読む。

フューチャー・サーチは,もともと「ストラテジック・フューチャー・コンファレンス」と言っていたそうだ。そのままだ。未来への話し合いを構造化したものだからだ。
著者はこう書く。
フューチャー・サーチが効果的なのは,…私たちにとって大切ではあるが一人ではできない課題に取り組む中で,人間としての尊厳や意味,コミュニティを求める内なるニーズにアクセスすることができるからだと考えています。「全体
“象”」(whole
elephant)との関係から自分自身をみることで,過去に不可能だったアクションプランを生み出すことができるのです。
群盲象をなでる
のことわざがあるが,それぞれがそれぞれの経験でモノを見ている。それをもちよって,共通の現実,象を作らない限り,相手がどう理解しているかは見えてこない。「全体象」はそれを言っている。
そのために,フューチャー・サーチでは,
・ホールシステムが一堂に会する
・ローカル(検討対象とする組織やコミュニティ)での取り組みを,「全体象」(グローバル)の中でとらえる。
・未来に焦点をあて,コモングラウンドを明確化する
・参加者が自己管理し,行動に責任を持つ
の4つの基本原理に基づいて,三日間(正確には,初日午後から,三日目の午前まで)の日程で行われる。
初日午後は,過去を振り返る。現在と外部のトレンドに焦点をあてる
2日目午前は,トレンドの続き。現在に焦点をあて,自分たちの行動を認める
2日目午後は,理想的な未来のシナリオ,コモングラウンド(共通の拠りどころを)を明確化する
3日目午前は,コモングラウンドの明確化。アクションプランの作成。
活字の上だけではわからないが,広範囲なステークホルダーを集め,自分ちのコンテクストを確認して,未来像を描こうという流れは見えてくる。
成功の条件を,こうまとめている。
・ホールシステムが一堂に会する
・ローカルな行動を起こすコンテキストとしての全体象
・問題と対立に注目するのではなく,コモングラウンドと未来に焦点をあてる
・小グループによる自己管理
・全日程への完全な出席
・快適な話し合いの環境
・3日間の日程
・フューチャーサーチ終了後の活動についての責任を公にする
特に,問題に焦点をあてず,いまここにある現実と,未来を志向する姿勢が強調される。それには,
・意見はすべて正当なものと考える
・すべてをフリップチャートに書く
・お互いに耳を傾ける
・時間を守る
・問題と対立を扱うのではなく,コモングラウンドと行動を探求する
を原則とし,
私たちは,対立には目をつぶり,すでに決議されたことや,これまでがお互いに接することがなかったために行動を起こすことができなかったことを共に実行するために,対立を受け入れ,解決できないことは保留にすることを進めているのです。
その背景をこう説明している。
(すべての対立に取り組まなければならないという考えに)フューチャーサーチではそこにはまってしまうことは命取りになります。…もし私たちが最も深いところにある意見の相違について徹底的に検討し始めたなら,私たちは家族,同僚,…とですら一日を乗り切ることを難しくなってしまうでしょう。日常生活において,私たちはすべての問題に取り組んではいないのです。フューチャーサーチでも,合意したことに対して行動を起こす前に,対立しているすべての問題に取り組まなければならないということはありません。
妥当だと思う。未来に向かって,問題に焦点をあてるのではなく,解決状態(その時どういう状態になっていたらいいか)に向かって何をするかに焦点をあてようとしているのだから。
さてしかし,これは体験してみるべきものだから,この仕組みがいいものかどうかは,何とも言い難い。しかしそれとは別に,僭越ながら,違う感慨が起きる。
こうやって,次々アメリカのソフトを輸入し,お先棒を担ぐ連中がいっぱいいることに,辟易する。自分の頭で考えるものは,外に答えを探そうとはしないものだ。しかし,コーチングもそうだが,いつも答えを欧米に求める姿勢を,恥ずかしいと思わない限り,このいまの日本の体たらくは変わらない。
中国の偽造を言っている場合ではない。精神は,全く同じ構造だ。
日本に,こういうようなソフトがないのかと言えば,ある。たとえば,遠く,中世に,小さな共和国を維持した,70戸ほどの小さな村がある。そこでは,
乙名を指導者とする行政組織,在家を単位とする村の税を徴収し,若衆という軍事・警察組織をもち,独自の裁判を行い,村の運営を寄合という話し合いですすめ,そのために,構成員は,平等な議決権をもつ,
自治の村であった。それを惣村という。
あるいは,秩父事件でも,われわれのリーダーシップの根がある。
そこに,ソフトがある。しかし,
ひとつは,多くは歴史上,失敗とみなされるために,
さらにはわれわれが,答えを外に探したがるために,
いまも昔も,ないがしろにされてきた。おのれたちのリソースを大事にしないものは,根無し草である。
まあ,最後は愚痴になった。
参考文献;
マーヴィン・ワイスボード&サンドラ・ジャノス『フューチャーサーチ』(ヒューマンバリュー)
蔵持重裕『中世 村の歴史語り』(吉川弘文館)
長崎浩『政治の現象学あるいはアジテーターの遍歴史』(田畑書店) |
|
お伊勢参り |
|
鎌田道隆『お伊勢参り』を読む。

楽しさと学びとを深く広く定着させた江戸時代の旅,その代表がお伊勢参りではなかったか…
という著者の言い分も分からないではないか,少し楽天的すぎる。
抜け参り
という言葉がある。奉公人が主人に断りなく,家出する。主婦も家出する。そして,
伊勢神宮とさえ言えば家出も許される,
しかも,雇い主側も,
伊勢までの往復の日数を数えてまってみた,
という社会的な風潮があった。しかし無一文でも,沿道の人の施行を受けて,多くは,無事に帰ってこられる,という社会的基盤もあった。逆に言うと,伊勢参りは,封建時代の身分にしばりつけられた自分のありようを,一瞬解き放つ,絶好の機会となっていた,ともいえる。
一般に旅費は,一日当たり,四百九文,一文を二十円から三十円とすると,一日おおよそ一万円,これは普通の奉公人レベルで賄える金額ではない。それも,伊勢参りという名目があると,施行で支えてもらえる。
江戸時代,日常的な参宮とは別に,大規模な集団的参宮が,おおよそ,六十年に一度起こっている。
慶安三年(1650)江戸の商人たちが中心。白装束。
宝永二年(1705)京都の子供たちが発端,360万人。
享保八年(1723)京都の花街の遊女たち。派手な衣装・装束。
明和八年(1771)京都周辺から始まり,お札降りで拡大。
文政十三年(1830)阿波から始まる。450万人。
その他にも地域的に群参があったとされるが,時代が下るにつれて,施行や接待が拡充し,明和の大阪施行では,豪商たちが,競って施行したり,阿波藩や郡山藩の領主層も,施行に乗り出している。
こうした施行の基盤があることが,より誰でもが参宮にかこつけて抜け参りに出やすくしている,ということはいえるだろう。
こういう領主層の好意的態度こそ,おがげまいりの性格を示しているという考え方もあるが,藤田俊雄は,こう言っている。
「おかげまいり」とむすびついた「おかげおどり」にたいして,伊賀名張や大和俵本では,藩役人が必死になってこれを抑圧しようとし,領民と激しく対立した…,
という事実を上げ,政治的な集団運動ではなかったにしろ,必ずしも,領主にとって,全く危険のないものではなく,
(大名による)施行がおこなわれた反面には,無言の大衆的圧力がはたらいていることを見なければならない…,
としている。たとえば阿波藩の施行には,前年ぬけ参り禁止をした反動とみることができる,と。それだけ,伊勢参りという行為のもつ,社会的プレッシャーというものが相当に大きかったと,見ることができる。
確かに,伊勢参りには,参宮という信仰心とともに,一面日常を脱出する娯楽の側面があることを否定しないが,反面で,身分社会の下層の人々,奉公人,農民の,そうしたくびきからの解放という側面があったことも事実なのである。
伊勢参りを止めだてした主人に神罰がくだったという話がいろいろ伝搬しているということは,雇い主側へも強烈なプレッシャーとなっており,伊勢参りと言いさえすれば,突然の出奔も許さざるを得ない風潮があり,それを物質面で支える施行のバックボーンもあった。
この背景を考えるとき,幕末の慶応に大流行した「ええじゃないか」は,このおがけまいりの延長線上にありながら,ほとんど伊勢参宮や信仰とは関係なく,爆発的なエネルギーの解放という側面が突出した現象であったことがよく見えてくる。おかげまいりの流れをただの信仰と娯楽だけにみると,ええじやないかは異質のものに見えるが,エネルギーの解放という側面で見れば,見事につながって見える。
その面で,著者は楽天的にも,この面を全く見逃しているように見える。既にそのことは,江戸時代最後の「おかげまいり」である文政のおかげまいりにその兆しはあったのである。それを全く言及しないのは,意図があるのでなければ,少し杜撰ではないか。
文政のおかげまいりに際しては,続いて,地域によって,おかげおどりが流行る。
誰いうともなく,踊らないものは一族病死し,家が焼失するという噂が立ち,揃いの緋紋羽のぶっさき羽織をつくり,明け六つに氏神の杜に勢ぞろいし,踊り騒ぐうちに村役人に交渉して,年貢一石につき三斗の減免を要求し,ついに一斗の減免に成功したという。
ここには,慶応の「ええじゃないか」に直接つらなる,時代の変化を見抜いた,したたかな民衆の解放感がほの見える。
参宮にかこつけて抜け参りする民衆に,その兆しがずっとあったのである。それは,
伊勢参り大神宮にもちょっと寄り
のしたたかさ,なのである。
参考文献;
鎌田道隆『お伊勢参り』(中公新書)
藤田俊雄『「おかげまいり」と「ええじゃないか」』(岩波新書) |
|
差別 |
|
網野善彦『日本中世に何が起きたか』を読む。

著者が崩した常識は一杯あるが,本書は,そうした我々の常識崩しには格好の著作といっていい。
まず日本という国はいつ成立したのか。
「日本国」という国名は,七世紀末から八世紀初めに決まるのだと思います。浄御原令という令が決まった698年ごろだというのが今のところ,研究者の多数意見ですが,大ざっぱに言って,七世紀末から八世紀初めという点では一致していると思います。注意しておく必要のあるのは,その時点の日本国の領域には東北と南九州は入っていません。北海道,沖縄はもちろんです。
ということは,それ以前について,軽々に日本とか,日本人という言葉を使ってはいけない。日本人がずっといたかのようなイメージを懐きかねない危険がある,と指摘する。では倭人かというと,日本人と倭人は重ならないところがある。だから,
聖徳太子は倭人ではあるが日本人ではない,
と著者は言う。さらに,著者は,「列島東部人」「列島西部人」という言い方をしている。なぜか。埴原和郎氏の説を紹介しているが,
弥生文化が流入してから古墳時代まで,七,八百年から千年ぐらいの間に,百万人以上に及ぶ人が西の方から日本列島に入ったのではないかと言われています。
(「列島東部人」「列島西部人」)の間の差異,現代の東日本人と西日本人,とくに畿内人の差と,朝鮮半島の人びとと西日本人,とくに畿内人との差異とどちらが大きいかというと,前者の方がむしろ大きいのだそうです。
これは遺伝子レベルでの検討だと思われるが,日本が均一というあいまいな言い方は,ためにする場合を除くと,危険である,といっていい。関西人気質と関東人気質の差は,結構根が深い。
ところで,近世以前,百姓というと農民というイメージが強く,農業社会であった,と受け取られてきた。それについて,強烈に異質なメッセージを発し続けてきたのが著者だ。
近世においても「百姓」はその原義の通り,直ちに農民を意味するのではなく,実体に即してみても「農人」だけでなく,商人,船持,手工業者,金融業者等,多様な非農業民を含んでいること,また従来,貧農・小作農と見られてきた水呑,加賀・能登・越中の頭振,瀬戸内海地域の門男(亡土),越前の雑家,隠岐の間脇など,多様な呼称を持つ無高民のなかにも,土地を持てないのではなく全く持つ必要のない商人,廻船人,職人などの富裕な都市民が数多くいた事実を認識したのは,(中略)奥能登地域と時国家の調査を通じてであった。
いわゆる差別問題も,その視角から見ると,全く様相が変わる。転機は,十三〜十四世紀と見られる。
遊女・白拍子・傀儡の地位は,十四世紀ごろまでの日本の社会の中ではかなり高かったと思うのです。(中略)鎌倉時代のごく初めの『右記』という…記録にも,遊女・白拍子は,「公庭」―朝廷に直属するものだとはっきり書いてあります。ですから,遊女の和歌は,勅撰和歌集にたくさん出てきますし,十四世紀,つまり南北朝前期のころまで,貴族たちは自分の母親が遊女・白拍子出身であることについて,何らひけめを感ずることなく堂々と系図に書いています。
そして著者はこう言う。
私はいわゆる被差別部落の直接の源流がはっきりと姿を見せるのは,やはり遊女が差別され始めるのと時期を同じくしていると考えているのです。
奈良時代に悲田院が設けられ,身寄りのない病人や捨て子が収容されていた。これが被差部落問題と深くかかわっている,と言われている。九世紀ころまでは,成人した孤児は,戸主の養子となったり,独立した戸を作ったりと,平民と同じ扱いを受けている。しかし九世紀末ころには,律令国家自体が崩れ,悲田院も維持できなくなる。そこで,そこにいる人は,何か仕事を探さなくてはならなくなる。さらには,
穢れの「清目」を一つの仕事,
とするようになり,十一世紀から十二世紀にかけて,悲田院に収容できなくなった人々を救済しようとする,聖,上人といわれる僧侶が関与し,
非人,乞食といわれるような人々の集団が十一世紀半ばごろになると,畿内―京都,奈良を中心に,まず姿を現してきます。
そうして,西日本には十二世紀から十三世紀にかけて,各地にこういう非人の集団が見られるようになる,
という。そして,
この人々が,…浄め−清目,つまり葬送や清掃,さらに罪の穢れを浄める機能を持った刑吏としての仕事,罪人の宅を壊し,人を追放する,あるいは人を処刑するような仕事に携わっていたことも,確認できるようになります。
同時に牛や馬の死体処理,その皮革の加工,細工に携わる者は,河原者と呼ばれているが,非人や河原者は,
遊女の社会的な地位が高かった時期,つまり十四世紀までは,非人にせよ,河原者にせよ,まだ社会的に固定された差別,賤視を受けていない,
と著者は見る。なぜかというと,
これらの人は神社の神人,寺院の寄人という立場に立っていたわけです。さらにまた京都―洛中洛外の非人の集団は,検非違使庁という天皇直属の官庁を通じて,天皇にも直接統括されています。
つまり,聖なる存在であめ天皇と直接つながっているという意味で,聖視される存在だったと,著者は見る。
天皇や神仏そのものに直属する地位にあるという意味で,「神奴」「寺奴」と表記され,神仏,天皇の奴婢として,
神人,寄人,供御人(天皇の直属民)という称号を持っていた。
つまり一般の平民と区別され,平民にできない職能を持っており,鎌倉時代の非人の訴状では,
神仏に直属して,「清目」という大事な職能によって神仏に奉仕するのが自分たちの使命としている,
と堂々と書いているという。
供御人,神人,寄人―商工業者,芸能民から遊女,非人を含む天皇,神仏の直属民は,一般平民の負担する課役は免除されております。そのかわりに,それぞれの芸能を通じて天皇神仏に奉仕をすることになるのですが,関所や津泊などの港でも交通税を免除されて,諸国を自由に通行することが出来ました。
供御人,神人,寄人は,非農業民なので,津や泊に根拠を持つことが多いが,非人の根拠地は,宿と言われている。それが,南北朝の動乱を機に,十五世紀にはいると,
非人の宿についてみても,鎌倉時代までは「宿」という字を使っております。…十六世紀ごろから,「夙」という字を非人の「宿」に関しては使うようになっております。
という。そして,「穢多」という文字も一部で使われ始める。なぜそうなったのか。著者は,こう結論づける。
では一体なぜ南北朝の動乱以後,遊女や非人の地位が決定的に低落したか,なぜ賤視されるようになったか。それはこの動乱を境に天皇,神仏の権威が決定的に低落したことと表裏をなしていると考えられます。
鎌倉幕府とそれを倒した後醍醐天皇の建武政府の崩壊,
いわば当時の日本国を統合していた幕府と天皇の二つの大きな権威が,一挙に崩れた,
同時に,それはそれまで続いてきた神仏の権威の失墜をも伴い,その権威に依存して職能を発揮してきた人々が,
聖別された存在から賤視の方向に差別された存在への転落が葉きりここに現れてくる…
と著者は言う。しかしそれは同時に,秩序だって管理されてきたものの崩壊といってもいいのだと思う。
悪党
というものが同時に,その時代の中で脚光を浴び始める。悪という言葉は,
どうもこれが差別の問題とどこかで関わりを持っている,
と著者は言い,多く,神人,寄人,供御人,非人と重なっている。
人の予想のつかない,自分にはわからない何か否応のない力に動かされる行為…
を悪という意味でとらえていたのではないか,そして,
一遍が「悪党」と呼ばれる集団に支えられていたことは,『一遍聖絵』という絵巻物にも描かれています。その一遍は,
「身命を山野にすて,居住を風雲にまかせて」遍歴する遊行。信・不信,浄・不浄を問わず,広くすべての人びとに名号札を賦る賦算。そして念仏する喜びを身体そのものの躍動によって表現する踊念仏
であり,その悪人を肯定し,その中に自らをも置く姿勢は,そのまま親鸞の悪人正機につながっていくように見える。
著者は,高校教師であった時に,
なぜ平安末・鎌倉という時代のみにすぐれた宗教家が輩出したのか,
という問いに応えようとしたもののひとつ,という言い方をあとがきがしている。それは,どういう時代なら,傑出した人物を生み出せるのか,というふうに問いを変えてみると,別の答えが見えてきそうである。
網野善彦『日本中世に何が起きたか』(歴史新書y) |
|
生き残り |
|
渡邊大門『黒田官兵衛』を読む。

僕はそもそも黒田官兵衛という人物が,世に言うほどたいそうな人物とは思わない。講談じゃあるまいし,当時軍師などという存在はいない。所詮,信長,秀吉,家康の配下として力量を発揮しただけの人物だと思う。
多くは,黒田家の正史『黒田家譜』に因っているようだが,これがまた食わせ物だ。そもそも家譜とか家系図が正しいなどという思い込みは棄てたほうがいい。秀吉程でないにしろ,家康にしろ信長にしろ,戦国時代から出てきた武将,大名は,それほどの出自ではない。だから,江戸自体家系図づくりが盛んに行われた。平和な時代になると,武功で名を成せなければ,出自か先祖の武功を誇るしかない。
『黒田家譜』は,三代目藩主光之(官兵衛の曾孫)が貝原益軒に編纂を命じた。既に官兵衛死して八十年,官兵衛誕生から数えれば百四十年経過している。したがって,
黒田家の先祖が近江佐々木源氏出自,
という記述すら怪しい。しかも史料不足から,いまでは偽書とされる『江源武鑑』が多用されており,
有力な大名家の家譜は,正史と位置づけられ,そこには「真実」が記されていると考える向きが多い。しかし,実際には,一次史料を用いて子細に内容を検討する必要がある。特に……『黒田家譜』に動向が記されていても,裏付けとなる一次史料がない場合は,そのまま鵜呑みにすることはできない。伝承(口伝)などにより,不確かなまま記された可能性がある。
と著者は慎重な物言いをされている。しかし,僕は,家譜は,ただ正史を書くために記されたのではない,と考える。系図と同様,自らの出自と武功を顕彰するのが目的だと考える。不都合な部分はカットされるだろう。
著者はこう言う。
改めて,近世初期に期待された官兵衛像を考えてみると,名君像を提示したかったと推測される。それは,先見性に優れており,戦いの巧者であり,江戸幕府成立の立役者であり,質素・倹約を旨とする理想の君主像である。官兵衛の逸話が数多くさまざまな形で残っているのは,その証左と言えるであろう。
たとえば,『黒田家譜』によると,官兵衛は運命の岐路に立たされると,必ず正確な判断を行っている。…政局を見誤り,正確な判断を下せず没落した大名は数多い。官兵衛は,その都度判断を見誤ることなく,尋常ならざる出世を遂げた。先見性は,名君の重要なファクターであった。…藩祖ともいうべき官兵衛を名君に仕立てることは,長政(官兵衛の子)や福岡藩にとっても重要なことであった。それゆえ諸書を通じて,官兵衛の神憑り的なエピソードが繰り返し再生産されることになった。
と。ふと思い出すのは,二兵衛と並び称され,長政の命を救った竹中半兵衛の子,竹中重門が書いた,秀吉の伝記『豊鑑』である。祖先を顕彰することは,そのまま自らの家系を顕彰することになる。
その意味では,関ヶ原で下した判断が正しくても,加藤清正や福島正則は,家康にとって利用価値はなく,黒田や細川は利用価値があったということだ。関ヶ原で判断を誤っても,立花宗茂のように復権するものもあれば,,島津義久のようにしぶとく生き残るのもある。また毛利や上杉のように減封されて生き残った者もある。
あくまで,主導権はそのときの天下の実勢を握ったものの手中に,それぞれの命運はある。それがあの時代の厳然たる事実であるとするなら,生き残れた判断だけに,価値があるのではないだろう。
そのあたりは僕にはわからないが,少なくとも,石田三成のような,覇権に挑む生き方を,官兵衛が取らなかったことだけは確かである。その意味では,毀誉褒貶は別にして,官兵衛に,三成ほどの気概は感じられない。
著者はこう締めくくっている。
官兵衛の出自は播磨の一土豪であり,小寺氏の一家臣に過ぎなかった。しかし,官兵衛のすぐれた才覚は認めざるを得ない。(中略)官兵衛がいかんなく才能を発揮したのは,類稀なる交渉術を駆使する調略戦であった。敵方の領主を見方に引き入れたり,和平を結ぶ際に有利な条件のもとで締結に漕ぎ着けるなど,その役割には大きな重責が伴った。官兵衛は,秀吉の中国計略以後,北条氏討伐の小田原合戦に至るまで,その役割を全うしたといえる。
そして,官兵衛を軍師とするには無理があり,
官兵衛は数々の大名との交渉を担当したことから,「取次」などと称するのが無難なようだ。
と結論づけている。それは蜂須賀正勝も同様であり,毛利側の交渉窓口であった安国寺恵瓊もまた同じ役割を担っていた,ということができる。
参考文献;
渡邊大門『黒田官兵衛』(講談社現代新書) |
|
剣禅一如 |
|
渡辺誠『真説・柳生一族』を読む。

剣豪小説の中で,記憶に残る立会いのひとつが,吉川英治『宮本武蔵』での,柳生四天王と武蔵との戦いのシーンだが,それがフィクションとわかっていても,ついその眼で柳生一族を見てしまう。
いまひとつは,本書でも指摘しているが,五味康祐の『柳生連也斎』での連也斎と武蔵の弟子鈴木綱四郎との立ち会いシーンだ。
いずれにも,小説に過ぎない。本書は,戦国時代,織豊の戦乱を生き残り,家康に見出されることで地歩を固めて以降,柳生宗厳(むねよし)石舟斎,柳生宗矩,柳生十兵衛三厳(みつよし)を中心に,柳生家の歴史をたどる。
中心は,戦国時代を,松永,筒井,信長,秀長,家康となんとか生き延びようとする戦国の小領主でありつつ,しかし上泉伊勢守から新陰流の印可を受けた剣豪でもある柳生宗厳石舟斎。
戦国時代にもかかわらず,流祖伊勢守の新陰流の特色は,
戦国末期の諸流が一般に本源としていた,戦場における甲冑武者剣術―介者剣術刀法・理合を徹底的に革新して,人性に自然・自由・活発な剣術を創めた,
といわれるもので,その本質は,
敵の動きに随って,無理なく転変して勝つ刀法,
といわれ,
一方的に敵を圧倒し尽くして勝つことが能ではなく,敵と我との相対的な関係,千変万化する働きのもとに成り立っている,
とする。この兵法観の背後にあるのは,
禅の思想であり,石舟斎も参禅したし,宗矩も沢庵とも深い交わりがあり,
剣禅一如
の境地を進化させている。このあたり,武蔵の『五輪書』と読み比べると,「石火のあたり」「紅葉の打ち」というように,間合いにしろ,相手との駆け引きは同じでも,武蔵が,圧倒的な膂力を前提にしているということがよくわかる。
宗矩と武蔵は同時代人だが,武蔵は牢人であり続け,島原の乱では,養子伊織の仕える小笠原家に陣借りして,参陣し,石垣から転落して負傷したのに対して,宗矩は,家光政権の惣目付として,一万石の大名に上り詰め,家光をして,
吾,天下統御の道は,宗矩に学びたり,
と言わしめる幕閣のひとりでもあった。
勝海舟は,『氷川清話』で,宗矩について,
柳生但馬守は,決して尋常一様の剣客ではない。名義こそ剣法の指南役で,ごく低い格であったけれど,三代将軍に対しては非常な権力を持っていたらしい。…表向きはただ一個の剣法指南役の格で君側に出入りして,毎日お面お小手と一生懸命やって居たから,世間の人もあまり注意しなかった。しかしながら,実際この男に非常の権力があったのは,島原の乱が起こった時の事でわかる…。
と言っている。島原の乱のこととは,宗矩が,
一揆鎮圧軍の上使に,格の低い板倉重昌を任命したことに反対し,板倉は討ち死にする,
と予言したことを指す。宗矩は,その時,
一揆討伐は苦戦になることを,家康が一向一揆で苦しんだことを例に,攻めあぐねているうちに,諸大名は最初は従うが,そのうちに足並みが乱れ,再度上使が派遣されることになれば,板倉は面目を失い,例え一騎でも吶喊し討ち死にする,
と説いた。既に出立した後で,任命は取り消されず,結果,戦いが苦戦の中,再度上使派遣が,松平信綱と決まると,板倉は無謀な総攻撃を仕掛けて,討ち死にする。
僕は,宗矩のこの立場は,おそらく武蔵が願ってかなわなかったことなのだと想像する。城や街の縄張りまでやってのけた武蔵は,剣術家としてではなく,宗矩のような帷幄にいる役どころを望んでいたに違いない。
一介の牢人の子と小なりと言えど領主の子の,出発点のわずかな差は,大きい。それは度量,器量,技量の差では追いつけない隔てのようだ。
参考文献;
渡辺誠『真説・柳生一族』(歴史新書y) |
|
人間原理 |
|
佐藤勝彦『宇宙は無数にあるのか』を読む。

佐藤勝彦氏は,インフレーション理論の提唱者の一人だ。その彼が,宇宙論の潮流である,「人間原理」との対決をしているところが,見どころか。
イギリスの天文学者,マーティン・リースは,この宇宙を成り立たせている6つの数を挙げている。逆に言うと,その数値が違っていれば,宇宙のあり方がいまとは違っている,ということになる。
第一は,N。電磁気力を重力で割った比のこと。もしNが10の30乗,つまり重力が現実の100万倍だったら,天体はこれほど大きくなる必要はない。その場合,微小な虫でさえ,自分の体を支えるために太い脚を持たなければならない。それよりおおきな生物が生まれる可能性は皆無となる。つまり,われわれが存在するのは,重力が弱いおかげということになる。
第二は,ε(イプシロン)。太陽の中では,二個の陽子と二個の中性子が融合してヘリウムの原子核が作られる。融合の前後では質量が異なり,ヘリウムの方が軽い。この質量の軽くなる度合いを示すのがε。それは,0.007。しかしもしこれが,0.006未満なら,陽子と中性子がくっつきにくく,宇宙は水素だけの世界になる。0.008より大きかったら,中性子なしに陽子がくっつき,複雑な元素はできにくく,やはり生命は生まれない。人間が生まれる宇宙は,0.006から0.008の間に収まっていなければならない。
第三は,Ω。宇宙が減速膨張するのか,加速膨張するのかの鍵を握る数となる。現在宇宙は加速膨張しているが,やがて膨張から収縮することになる。そうなると,遠い将来,一点で潰れる(ビック・クランチ)ことになる。そうでなく膨張し続ければ,あらゆる物質が素粒子レベルでバラバラになり,引き裂かれる(ビック・リップ)。潰れもせず,引き裂かれず原則膨張し続けるには,宇宙の全物質の重力と膨張を後押しするエネルギーの力関係で決まる。重力が膨張エネルギーを上回れば収縮し始める。その境界線が臨界密度(Ω)。この密度は,宇宙が平坦になる密度ということになる。もしΩが1より大きければ(物質の密度が臨界密度より高ければ)宇宙の曲率は正になり,収縮を始める。逆に1より小さければ,初めから等速で膨張したので,ガスが固まらず,銀河や星ができない。曲率1だから,宇宙は平坦に保たれている。
第四は,λ。宇宙を押し広げる斥力として働く真空のエネルギーの大きさを示す。この数値が小さいために,現在の宇宙が成り立っている。
第五は,Q。銀河や星の集合体である銀河団などのまとまり具合を示す数字。現実の宇宙では,Qは,十万分の一となっている。これが100分の一といった大きな数値なら,ほとんどの構造がブラックホールになっている。十万分の一になっているので,銀河や星が存在する。
第六は,D。次元。われわれは,三次元に暮らしているが,もし二次元なら,生物は存在できない。三次元空間では重力の強さが距離の自乗に反比例するが,四次元なら距離の三乗に比例する。そうなると,銀河の中心程重力の影響が大きく,三次元では銀河の中心を回転している星々が,スパイラルを描くように中心部に堕ち,ブラックホールだらけの宇宙になる。
こういう奇跡のような数字をみると,人間が生まれるように,「ファイン・チューニング」されたようにみえる。
これを人間原理という。
スティーブン・ワインバーグは,マルチパース(多数宇宙)による人間原理を,こう主張する
宇宙は無数に存在し,それぞれが異なった真空のエネルギー密度を持っている。その中でも,知的生命体が生まれる宇宙のみ認識される。現在の値より大きな値を持つ宇宙では天体の形成が進まず,知的生命体も生まれない。認識される宇宙はいま観測されている程度の宇宙のみである。
無数の宇宙があり,その中で天体の形成が進み,知的生命体の生まれる宇宙がある。そこで観測される宇宙が,その知的生命体を生むのに都合よく見えるのは当たり前,…これが人間原理と呼ばれるものだ。
これより前,ロバート・ヘンリー・ディッケは,もっとはっきりした言い方をしている。
宇宙開闢の初期条件は人間が生まれてくるようにデザインされている…。
初めて人間原理という言葉を使ったのは,ブランドン・カーター。コペルニクス原理に対比させて人間原理と呼んだ。
まるで,せっかく人間中心からの転換を果たしたコペルニクス以前に,天文学者が回帰しようとしているような,異様な意見に見える。
著者は,人間原理を使うことなしに,宇宙の平坦問題を,インフレーション理論で,説明可能だという。
インフレーション理論は,宇宙がビックバンを起こした理由を説明し,真空の相移転による急膨張が終わったところで放出された膨大なエネルギーによって,宇宙が火の玉になったことを説明すると同時に,
宇宙が完全に均質な空間ではなく,星や銀河といった構造の「タネ」になるデコボコが生まれた理由を
明らかにしている,としてこう説明する。
…全体の構造を造るには「事象の地平線」を超える大きなスケールの密度揺らぎか必要です。ビックバン理論ではちいさなゆらぎしかできないのです。
事象の地平線とは,「そこまでは光が届く境界線」のことです。アインシュタインの相対性理論によれば,光速は宇宙の「制限速度」ですから,それよりも速く移動できるものはありません。したがって「地平線」の向こうには情報や物質が伝わらない。つまり,因果関係をもつことができないのです。
初期宇宙はこの地平線距離が短く,空間全体が因果関係をもつことができませんでした。全体の構造を作るほど大きな密度ゆらぎを作れないのも,そのためです。
まず「密度ゆらぎ」の問題は,微小なゆらぎが急速な膨張によって一気に大きく引き伸ばされたと考えれば説明がつきます。つまり現在の私たちが観測できる宇宙は,「地平線」の内側にあった領域が大きく拡大されたものなのです。
だとすれば,観測できる宇宙が「一様」になっているのも当然でしょう。インフレーション前に「地平線」の内側にあった領域は,因果関係があるので,物質やエネルギーを移動して均一な空間にすることができます。
そして,平坦問題も,
私たちが観測できる宇宙が初期宇宙の一部を拡大したものだとすれば,「一様性問題」と同様,これは不思議でもなんでもありません。
初期宇宙の曲率が大きく正か負の値を取っていたとしても,その一部がインフレーションによって巨大に引き伸ばされれば,そこは平坦に見えます。「地平線」の外側まで観測できれば,…大きく曲がっているのかもしれませんが…。
しかし人間原理は,天文学者を二分している。
スティーブン・ホーキングは,マルチバースの人間原理について,
マルチバース(多数宇宙)の概念は物理法則に微調整があることを説明できる。この「見かけの奇跡」を説明できる唯一の理論だ。物理法則は,われわれの存在を可能にしている環境因子にすぎないのだ。
と擁護する。しかし一方,デビッド・グロスは,
それはまったく科学ではない。科学の理論に必要な観測的実証性も反証可能性もない。結局,論理を詰めることによって究極の理論に到達するという物理学の目的を,放棄することになる。
と厳しく批判する。著者は後者の立場に立つ。こう締めくくっている。科学者の矜持というものだろう。
四半世紀前に人間原理を知ったとき,これはとうてい科学ではない,と強い嫌悪感を覚えたものである。物理学者の端くれとして,
論理を詰めて研究を進めるならば,私たちは,未定定数を一切含まない究極の統一理論に達するはずだ
そもそも,物理法則の美しさから考えても,物理法則はでたらめにサイコロを振ってきまっているようないい加減なものではなく,確かな原理で確定的に決まっているものだ
という信念を,貫いてほしい。コペルニクス的転換を逆回転させるのが,科学であるはずはない。
参考文献;
佐藤勝彦『宇宙は無数にあるのか』(集英社新書) |
|
霊 |
|
安斎育郎『霊はあるか』を読む。
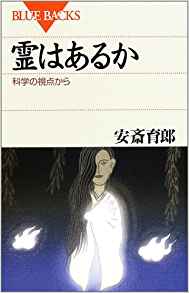
「霊魂不説」が,仏教の教義上の原則だそうだ。親鸞は,
悲しきかな道俗の,良時吉日を選ばしめ,天地地祗を崇めつつ,卜占祭祗勤めとす
五濁増のしるしには,この世の道俗ことごとく,外儀は仏教の姿にて,内心外道を帰敬せり
と,表向きは仏教の装いをしていながら,心は仏道を離れている,と嘆いている。
先日亡くなった市川団十郎の辞世,
色は空 空は色との 時なき世へ
は,そのあたりの仏教の本質をとらえている気がしないでもない。すなわち,色即是空・空即是色,形あるものはいずれ空になる,実体のない空がそのまま万物の姿でもある,と。
本来,仏教は,本来,霊肉二元観・霊魂不滅論を取らない。「霊魂不説」すなわち,霊魂と肉体の二元的考え方を否定し,
実践的主体ということから,心を重視するが,存在論としては,あくまでも心物相関にたち,一方を不滅の実体,他方を滅の仮象などとはみない。心物ともに空・無自性を基本とする…。
しかし,
輪廻転生説がとりいれられ,輪廻する主体が問題となり,その結果,輪廻主体が一種の霊魂のごとき色彩を呈するに至り,また祖先崇拝に結びつき,祖先の霊に対するまつりをおこなうようになった…。
と著者は,仏教事典から引用する。そしてこう言い切る。
われわれが人生で扱う命題群を「科学的命題群(客観的命題群)」と「価値的命題群(主観的命題群)」とに分類してきた。前者は,「事実との照合を通じて命題の真偽を客観的に決定できるような命題群」であり,後者は,「命題の真偽が価値観に依存するため客観的に決定できないような命題群」である。「霊は実体を持つ存在である」とか,「霊は祟る」といった命題は明らかに「科学的命題」であり,もしそのように主張するのであれば,その真偽は科学的検証の対象とされなければならない。
そして心霊写真のトリック,コナン・ドイルがお墨付きを与えた妖精写真のトリック,念写のトリック,霊感商法の詐術,神霊手術のトリックなどを例示しつつ,律儀にというか,大真面目に,真正面から,
霊が見えるとはどういうことか
を検討していく。なんだか,この辺りは,薪を割るのに,薙刀か太刀を取り出しているようで,ちょっとユーモラスではある。
まず何かが見えるには,自らが発光しているか,他の光源によって反射しているかのいずれかだ,として発光生物を検討していくが,それは無理として,反射しているのだとすると,
どう考えても霊は物質系だ,
とし,ではどんな原子で構成されているのか,そして,物質で構成されている霊が移動するには,移動のためのエネルギーを調達しなければならない,しかし,火葬された体から抜け出した霊が,
生きたままの元素組成で再構成されるなどということ自体,あり得ない…。
という調子である。たぶん霊を信ずる人間とは,すれ違うことになるだろう。なぜなら,著者自身も言うように,
一般に人間には,自分の尺度に合わないものは心理的に受け入れを拒否するような面があり,自分の考えを支持する情報には進んで耳を傾けるが,それを否定するような情報に接すると心理的な不快感を感じて,さまざまな理由をつけてその受け容れを拒否する傾向がみられる,
のは振り込め詐欺にあうトンネルビジョンと化した老人を見れはよくわかる。後は,それぞれの生き方の問題なのだろう。
加藤周一の5つの秘訣が少しは参考になる。
1.因果関係を速断するな
2.AとBの関係を論じるには,AB両概念を明確にせよ
3.枝葉を省き,本質を見きわめよ
4.主観的願望と客観的推論を峻別せよ
5.事実と照合して白黒のつく問題とそうでない問題とを区別せよ
まあ,著者自身も言っているように,白黒のつかない思い込みの領域に踏み込んでいるのかもしれない。
それだけに,著者の言う,次の言葉は説得力がある。
人生には,思い描く通りにはいかない困難がつきものだ。そんな時,人は「なぜ自分にはこんな困難がつきまとうんだ」と思い悩む。どんな事態にも,そうした事態がもたらされた原因があるはずだか,時には思いがけず降って涌いた災難が困難が原因となることもある。…そのような場合,少なからぬ人が自分の不運を嘆き,「どうして理不尽にもじぶんだけこんな不幸が降りかかるのか」と自問自答する。「霊」が心の隙間に入り込むのは,そんな時だ。人間の特徴は,自分の見聞きするもの,体験するものに原因を求めたがることだ。「なぜ」にこだわる心と言ってもいい。自分の納得のゆく理由が欲しい。(中略)そんな時,「霊」は便利なのだ。
それ自体は,心の安寧を求めるその人なりの選択だが,そこに付け込まれる余地がある。
科学的命題には科学的な思考を貫く,という著者の姿勢は,正しいが,なかなか難しい。しかし,あいまいなものをあいまいなままに受け入れるのだけはやめなくてはならない。
分からなければ,わかるまで,納得がいくまで,その案件を「宙」に浮かして,結論を出さない。
それくらいはできる。
参考文献;
安斎育郎『霊はあるか』(講談社ブルーバックス) |
|
NVC |
|
マーシャル・B・ローゼンバーグ『NVC』を読む。
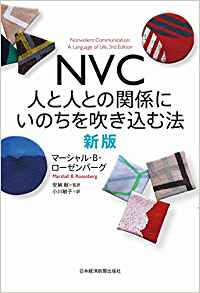
かつて我が国に,襲撃してきた軍人に,
話せばわかる!
と叫び,
問答無用!
と射殺された首相がいた。不謹慎ながら,ふいにそれを,思い出した。
基本,コミュニケーションで解決できるのは,コミュニケーションレベルに過ぎない,再三書いているのは,このイメージがあるからだ。政治的課題,社会的課題,地球規模の課題は,コミュニケーションの問題ではなく,仕組みやシステムや制度の問題だ。そのためにコミュニケーションが不可欠なのはわかっているが,それは,関係性の枠のなかでのコミュニケーションとは別次元の問題だ。
パレスチナ人とユダヤ人がコミュニケーションすることで,イスラエルという国とパレスチナという国の政治的課題が解決することはないし,未だかって解決できていない。それはレベルの違う話だ。
しかもそのコミュニケーションが機能するためにすら,曲がりなりにも,両者(あるいは関係者)がその土俵に乗るという意志と思いがなければ,成り立たない。土俵の有無が,コミュニケーションのスキルを論じる前に,コミュニケーションを機能させる前提になる。
『NVC』で語られている例は,ふたつの例外を除いて,ほとんどが,そういう土俵があるか,土俵が設えられるということが,暗黙のうちに前提にされている。問題なのは,その前提をどうつくるか,だ。それが,上記で言った,関係性の枠という意味だ。そのことについては,本書では一切語られていない。舞台の上で演じているのに,その舞台がないかのように,NVCのプロセスを語るのは,フェアではない。コンテクスト抜きのコンテンツは,黄身だけ剥き出された趣だ。
この本の枠組みについての印象から入ったのは,そこを抜きにしては,コミュニケーションレベルでさえ,解決できないと信ずるからだ。家族や友人,同僚は当然だが,ギャングだって,そこにコミュニケーションの土俵を設えている。設えてなければ,冒頭の「問答無用」になる。
そこで,具体的に考えるために,NVCプロセスを例示してみる。
NVCプロセスの構成要素は,次の四つだ。
・自分の人生のしつを左右する具体的行動の「観察」
・観察したことについて抱いている「感情」
・そうした感情を生み出している,価値,願望,「必要としていること」
・人生を豊かにするための具体的な行動の「要求」
これを,具体例を挙げて考えてみる。ただし,後でアサーティブ・アプローチと対比するために,例を,いつも厳しく叱責し,大声を出す上司に対するアプローチとしてみる。
●第一構成要素は,観察。評価を交えず観察する。
上司は,指示されたことを提出すると,間違いを次々と指摘し,赤字で訂正を加え,大声で,いったいいつまでこんな初歩的なミスを繰り返すのか,いい加減にしてくれ,と怒鳴る。指示された案件が,無傷でOKをもらえたことは一度もない。
●第二の構成要素は,感情を見きわめ表現する。
あなたに指示案件を提出するたびに,びくびく怯えています。たまた大声でどなられるのではないか,と提出する時間をぎりぎりまで先延ばししてしまいます。
●第三の構成要素は,自分の感情の底に何があるのか,を見きわめる。上司の否定的なメッセージを受け止めるには,4つの選択肢があると,NVCでは考えている。
1.自分自身を責める
2.相手を責める
3.自分の感情と,自分が必要としていることを感じ取る
4.相手の感情と,相手が必要としていることを感じ取る
ここで,自分の感情は,怯えと恐怖。再三の叱責で自己嫌悪に陥っている。
自分が必要としていることは,この間に自分が上司の求めているレベルの100とはいかないまでも,かなりの程度質が上がっている,その自分の成長を認め,君の仕事で助かっている,あるいは,役に立っていると,承認してほしいということ。
上司は,自分の仕事のレベルに苛立っている。上司が必要としていることは,いい加減,こんなことで俺に手間をかけさせないでくれ,早く一人前になって,俺を楽させろ,俺にはチーフとしてやらなくてはならないことが一杯ある,こんなことで俺のチェックリストが不要になるくらいの一人前に成長してくれ。
●第四の構成要素は,人性を豊かにするための人への要求である。
「チーフが僕の成長がのろいのに,いらだっておられるのはよくわかります。自分ももっと的確に指示を摑むよう,指示をいただいたその場で,指示内容をきちんと把握するようにして,指示についての遺漏をなくすように努力します。チーフにお願いは,より自分が成長し,チーフの手がかからないようにするために,前より少しでも良くなっている部分はお認めいただけると嬉しいです。それて,もう少し穏やかに教えていただけると,受け入れやすいのですが…」。
最後に,自分の要求について,上司に,伝え返しを求める。
「僕のリクエストについて,どのようにどのように受け止められたのか,率直にフィードバックをいただけると嬉しいです」。
以上が,僕の受け止めた,NVCのラフなステップだ。
アサーションでは,LADDER法やDESC法があるが,いずれも,事実を描写することが重視される。後述するアサーティブ・アプローチでも,事実を重視する。たとえば「傲慢」というのではなく,「いつ,どこで,何をした」ことが自分に傲慢に見えたかが語られること。その意味では,NVCも同じだ。
さて,次に,上記のNVCプロセスと対比するために,アサーティブプロセスを以下に紹介する。
アン・ディクソン『第四の生き方』,森田汐生『「NO」を上手に伝える技術』を参考に,あくまで,僕の理解に基づいてアサーティブ・プロセスとして展開したものだということをお含みいただきたい。
上位者にいつも厳しく叱責されている部下という立場での,僕流のアサーティブ対応プロセスは,
1.土俵を共有する
セットアップである。「ちょっとよろしいでしょうか」「少しお時間いただけますか」など,いまから話をしたいという土俵を相手と共有する。
2.自己開示する
自分の今の気持ちを正直に伝える。「言いずらいんですが……」「どう申し上げていいか迷っているんですが……」「どきどきしているんですが……」という言い方をすることで,相手の身構えを緩める。
3.事実を伝える
ここは,相手を持ち上げたり,感情を交えるのではなく,「いつも大声で叱責されるのですが」「いろいろ細かな気配りをいただくのですが」など,事実,起こっていることを表現する。ここで,「いやなんです」という感情から伝えては,相手は受け入れにくい。
4.感情を言語化する
ここは,その事実に対して,自分がどう感じてきたか,を率直に伝える。「大声を出されるたびにびくびくして
おびえていました」「ちょうど何かしょうとするたびに先回りされた気がしていやでした」等々。
5.望む変化をリクエストする
率直に,どうしてほしいか,どうなりたいかを伝える。「〜したい」「〜してほしい」「〜してほしくない」「〜してはどうでしょうか」。ただ,いくつも要求を羅列するのではなく,ひとつ,しかも的を絞る。あわせて,それを放置した自分の責任はきちんと伝える。「もっと早くお伝えしないでいた自分にも責任があります」「迷いに迷って言いそびれてしまった私も悪いと思います」等々。
6.相手の反応を求める
自分が言ったことについて,相手がどう受け止めたかをきちんと聞く。自分の主張を理解してほしいなら,相手も理解将とする姿勢がいる。
7.繰り返す
自分のしてほしいことをもう一度,きちんと整理して伝える。相手の反論や感情的反発にふりまわされることなく,自分の主張を繰り返す。
8.会話を終了させる
相手にうんといわせるまで主張するのが目的ではない。それでは,立場が代わっただけで同じコトをしていることになる。相手に考える時間を与え,選択の余地を残す。「聞いてくれてありがとう」「ぜひ心に留めておいてください」「2,3日後に話す時間をつくってください」
かなりNVCアプローチとアサーティブ・アプローチは重複している。重なる部分も少なくない。しかし微妙だが,両者には重大な差がある。その差は,
ひとつは,両者の間に土俵をつくろうとするかどうかだ。土俵がないところでは,共有も,共感も難しいと僕は思う。
いまひとつは,そのアプローチが,
人は分かりあえる,
ということを前提にしているのか,
人はわかりあえない,
を前提にしているのかの違いだ,と僕は思う。
わかる,というのはこちらがそう受け止めた,そう理解したということであって,言葉レベルでフィードバックしあったところで,相手のすべてがわかるわけではない。とりあえず,
仕事をうまく進めるために,
両者の関係を崩さないために,
両者のつながりを保つために,
等々限定はいろいろあるだろうが,「理解」するたびに,微妙にこぼれていくものがある。そのことを分かっているかどうかの差だ。
僕は,「わかる」とは,
お互いが分かりあえないことがあることを分かりあう,
ということだと思っている。あるいは,
自分にわかる部分しかわからない,
ということだと言ってもいい。
この差は大きい。傲慢さを感じたのはここだが,もっとあけすけに言うと,鈍感さといってもいい。
どんなに話しても,
どんなに言葉を交わし合っても,
お互いに分かりあえない部分があるという悲しみ,切なさがあるから,
話す,
のと,わかりあえると思い込んで,
話す,
のとでは違う。「わかりあえる」と思っていれば,なぜ分かりあえないか,わかりあえない原因を探していくことになるだろう。それはまた別の物語をでっち上げ,両者の齟齬を増やすだけだ。
それはつまらなくないか?いや,それよりなにより,
それでは人のもつ奥行きを軽視していないだろうか?
分かりあえない悲しみということがわからなければ,人というものがわかりっこない。
その眼で見ると,NVCのプロセスには,そういう鈍感さがある。まだしも,アン・ディクソンのアサーティブには,その心の陰影がある気がする。
分かりあえる部分でしかわかりあえない,
だからこそ,一生かけてお互いが分かりあおうとする。しかし,わからないことと,信頼は別だ。わからなくても,信頼はできる。言葉に尽くせなくても,その立ち居振る舞いだけで,十分信頼はできる。
なお,わかりあえないことについては,
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/10996546.html
ですでに触れた。
参考文献;
マーシャル・B・ローゼンバーグ『NVC』(日本経済新聞出版社)
アン・ディクソン『第四の生き方』(つげ書房新社)
平木典子『アサーション・トレーニング』(金子書房)
平田オリザ『わかりあえないことから』(講談社現代新書)
森田汐生『「NO」を上手に伝える技術』(あさ書房) |
|
オカルト |
|
大田俊寛『現代オカルトの根源』を読む。
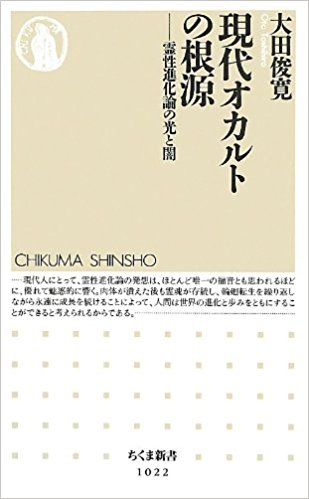
著者は,オウム事件の最期の指名手配犯菊池直子と高橋克也が逮捕された後,かつてのオーム真理教の幹部,いまはオームの後継団体のひとつである「ひかりの輪」の代表上祐史浩氏と対談したおり,
そもそもオウムという宗教団体は何を最終目標にしていたのか,
について,上祐氏が,
シュノイレカエ,
と言ったとき,意味が分からなかったと,ということから書き始めている。そして,それが,
種の入れ替え,
と思いいたるのに,しばらくタイムラグがあった,という。そして,こう書く。
言われてみれば確かに,オウム真理教の世界観をこれほどまでに凝縮して表現した言葉も,他に存在しないであろう。
として,オウムの世界観を,
オウム真理教の教義は,その根幹において,きわめて単純な二元論から成り立っていた。…すなわち,現在生きている人間たちは,霊性を高めて徐々に「神的存在」に近づいてゆく者と,物質的次元に囚われて「動物的存在」に堕ちてゆく者の二つに大別される。
人間の霊性は不滅であり,それは輪廻転生を繰り返しながら,永遠に存続する。また,人生における数々の行為は,すべて「業」として霊魂のうちに蓄積される。人間の生の目的は,良いカルマを積むことにより,自らの霊性を進化・向上させることにある。
現代における真の対立とは,…「神的種族(神人)」と「動物的種族(獣人)」のあいだにある。近い将来に勃発する最終戦争=ハルマゲドンにおいては,秘められていた両者の対立が顕在化し,それぞれがこれまで積み上げてきた業に対する審判がくだされる。真理の護持者であるオウムは,最終戦争を生きぬくことによって,世界を支配する主流派を,動物的種族から神的種族への「入れ替え」なければならない…。
と要約する。そして,大量のサリンを散布して日本を壊滅させ,「真理国」を創ろうとしていたオウムの計画は,阻止されたが,
しかしオウムという教団は,麻原が当初に抱いた「浄化」の手段としての最終戦争という構想,すなわち物欲に塗られた動物的人間を粛清し,超能力を具えた神的人間を創出するという「種の入れ替え」に向けて,着実に歩み始めていたのである。
とまとめる。そしてこの「霊的進化」源流を,
ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーの「神智学」という宗教思想運動から辿っていく。そこに,既に,オウムの思想の源流が胚胎している。ついで,チャールズ・リードピーター,ルドルフ・シュタイナー,ルシファー・キリスト・アーリマン,グイド・フォン・リストとランツ・フォン・リーベンフェルスの「新テンプル騎士団」,ルドルフ・フォン・ゼボッテンドルフの「トゥーレ協会」へと至る。この協会には,後のナチズムの重要な役割を担う,ルドルフ・ヘス,アルフレート・ローゼンベルクなどがいたのである。この「トゥーレ協会」が,国家社会主義ドイツ労働者党=ナチスへと改称されていく。
戦後は,ナチズムとの関係から,神智学の系譜は,下火になるが,「霊性進化論」の潮流はアメリカを中心に,オカルティズムと装いを変えて,広がっていく。
エドガー・ケイシーの超古代史と輪廻転生,
ジョージ・アダムスキーのUFOと宇宙との結合,
ホゼ・アグエイアスとマヤ歴,
デーヴィッド・アイクと爬虫類人類の陰謀
等々と脈々とつながり,日本の三浦関造,本山博,桐山靖雄(阿含宗)を経て,そこに入信していた麻原,さらに大川隆法へとたどっていく。
こうしたオカルティズムの系譜は,近代科学によっていったん打ち捨てられた宗教の知恵を,霊性進化として再解釈して,再発見してきた歴史といっていいが,著者は,こう締めくくる。
人間を単なる物質的存在と捉えるのではなく,その本質が霊的次元にあることを認識し,絶えざる反省と研鑽を通じて,自らの霊性を進化・向上させていくこと。それが霊性進化論の「正」の側面であるとすれば,…その裏面に強烈な「負」の側面を隠し持っている。端的に言えば,霊性進化論は,往々にして,純然たる誇大妄想の体系に帰着してしまうのである。
読んでいくと,そこまで妄想を広げていくのかというほど,気味の悪い部分がある。正邪対立の二元論は往々にして,陰謀説になり,人種差別につながる。それは,ある意味で,自分たちを「神の化身」としてエリート意識をもち,批判者を,「霊性のレベルが低い」「低級霊悪魔に憑りつかれている」「動物的存在に堕している」といった差別につながりやすい。オウムの暴走に,そういう選別意識が働いていたのではないか。
参考文献;
大田俊寛『現代オカルトの根源』(ちくま新書) |
|
大きなビジョンを描く |
|
前野隆司『思考脳力のつくり方』を読む。
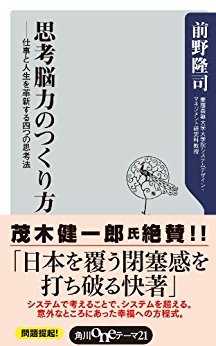
日本だけではなく,世界中が,部分最適思考が蔓延し,
とにかくどこにも大きなビジョンがない。理念がない。思想がない。ぶれない基準がない。
そう著者は慨嘆し,
大きなビジョンを描き,実行し,表現するための考え方のフレームワークを整理し,明らかにすること,
それが本書の目的だと,「大見えを切らせていただく」と,言い切った。
ではそのフレームワークは,何か。4つだ。
要素還元思考
システム思考
ポスト・システム思考
システム思想
一見して明らかなように,メタ化になっていることだ。要素還元思考をメタ化し,大きなフレームで見ることで,システム思考になり,それ自体の限界をメタ化することで,ポスト・システム思考となり,最後に,その全体を俯瞰するシステム思考へと至る。
要素還元的な思考は,部分部分を深く理解しさえすれば,あとはそれらを寄せ集めることによって,ものごとの全体も理解できるという(一足す一は二の)論理に基づいている。
システム思考とは,ものごとをシステム(要素間の相互作用およびその結果全体としての性質が部分の振る舞いに影響する創発が起きる)としてみることによって,システム全体の問題を明確にしたり,解決したりする思考法。
著者は言う。
システム思考の最も重要な点は,…要素還元の視点からひとつ視点をひろげることだ。要素還元思考では,ひとつの視点から物事を捉えている。
しかしシステム思考が有効なのは,線形相互作用の場合だ。
システムの要素間が非線形相互作用をする場合,…未来を予測することは不可能なカオス(混沌)が生じうる。システムの振る舞いは,ある臨界点を超えると急激に乱雑さを増し,予測不可能になる。
いわゆるバタフライ効果の,複雑系である。
システム思考は,システムの大雑把なモデル化には役立つ。特に,非線形が小さく,カオスが生ずる可能性が小さいときには,とても有効だ。
しかし複雑系の場合,
システムをロジックツリーのような形で論理的に分解して最適な答えを求めようとする発想から抜け出す必要がある。
と著者は言う。「目的・条件・手段が多様であったり時間とともに変動したりするために,目的・条件・手段の予測確定が困難」になる。その場合,答えは多様になる。
設計空間の自由度の方が解空間の自由度よりも大きいために,創造的に拘束を設けないと解が求まらないような悪設定問題,あるいは,そもそも問題定義を明確に行えない悪定義問題,問題解決手段を明確に定義できない悪構造問題,
においては,設計はアートとサイエンスの両方にまたがる。そこでは,
最適解ではなく,設計条件を満足する複数の「満足解」
が求める解になる,と。
こういうシステム思考とポスト・システム思考の関係は,ニュートン力学とアインシュタインの相対性理論に類比できる。
そして,システム思想は,
頭で考える思想ではなく,環境と身体と脳が接続された全体システムとして感じる思想だ。
という。そしてこうも言う。
矛盾を容認しないのがシステム思考,容認するのがポスト・システム思考なら,矛盾であるかどうか,容認するかどうか,という価値判断を超越するのがシステム思想だ。
と。正直言って,システム思考のメタ化であるポスト・システム思考まではわかる。そこでは,静的なモデルでは解けない複雑系,観察者自身をも巻き込んだ対象化がなされる。その主客分離が捨てられた世界をメタ化したとき,すべてが対象化される世界を,「悟り」と言われたのでは,ちょっとついていけなくなる。
システム思想とは,いつ死んでもいい覚悟がすでにできていて,そうだからこそ,もはや当然,利己への執着などという醜いレベルは超越している境地なのだ。
おいおい,と言いたくなる。問題なのは,ものを見る視点だったはずだ。境地など持ち出されては,もはや,単なる自己完結へともどっているとしかいいようがない。
ところで,
要素還元思考
システム思考
ポスト・システム思考
システム思想
の4つの関係は,包含関係という。まあ,入れ子構造というわけだ。
で,こういう。
現実的な問題関係をどこで行うかというと,直観的に言って,要素還元思考が四十パーセント,システム思考が三十パーセント,ポスト・システム思考が二十パーセントと,システム思想が十パーセント,
とみる。
メタ化かの究極が,「悟り」というのは,ちょっと思考停止に見える。著者が得意げなだけに,少し距離をおきたなる?
研究者なら,どうせ境地というなら,その境地をもっと具体的に,システム思考で,ツリー型,マトリックス型,ネットワーク型と詳細に分析したように,境地のものの見方を,詳細に分析すべきではないのか。
たとえば,著者の挙げていた例を借りるなら,釈迦型,老子型,荘子型,禅型等々。
「悟り」などと丸めるのは,僭越ながら,学者としての学究の放棄に見える。
参考文献;
前野隆司『思考脳力のつくり方』(角川書店) |
|
出自 |
|
渡邊大門『秀吉の出自と出世伝説』を読む。

蟹はおのれに似せて穴を掘る,というが誠に人は自分を語ってしまうというか,語るに落ちるというか,つくづく表現することは,自分をさらけだすことだ,と思わされる。
いまも昔も,極貧から,トップに上り詰めた人は本当に少ない。特に身分社会の中では,秀吉以外にはいない。しかも,源平藤橘と同様,「豊臣」姓を与えられ,しかも五摂家以外つけなかった関白職に就き,それを養子秀次に継がせたものは,歴史上秀吉以外いない。その故か,「太閤」というと秀吉のことを指すと相場が決まってしまった。
当然その異能の出世ぶりの原因を探りたくなる。著者は言う。
最近の秀吉の出自や職業をめぐる研究は状況証拠に頼っているので,肯定も否定もできない側面がある。ただ,秀吉の特殊性を極端に強調するのは,あまり不自然で現実的ではないと考える。
賛成である。因みに,出生をめぐる説には,本人の書かせたものを含め,一杯ある。
①信秀の鉄砲足軽 木下弥右衛門の子(『太閤素性記』)
②信秀の御伽衆 筑阿弥の子(『甫庵太閤記』)
③正親町天皇の御落胤(『関白任官記』)
④尾張の「あやし」の民(『豊鑑』)
⑤若いころは下っ端の小者に過ぎず,乞食をしたこともある(安国寺恵瓊の手紙)
⑥甚だ微賤に身を起こし(イエズス会1585年年次報告)
⑦きわめて陰鬱で下賤な家から身を起こし(ルイス・フロイス『日本史』)
⑧貧しい百姓の倅として生まれた。若い頃には山で薪を刈り,それを売って生計を立てていた。(同上)
⑨彼はその出自がたいそう賤しく,また生まれた土地はきわめて貧しく衰えていたため,暮らしていくことができず,その生国である尾張の国に住んでいたある金持ちの農夫の許に雇われて働いていたからである。このころ彼は藤吉郎と呼ばれていた。その主人の仕事をたいそう熱心に,忠実につとめた。(1600年&1601年耶蘇会の日本年報)
⑩薪を売って生計を立てていた。(『看羊録』)
⑪秀吉は十歳の頃から他人の奴婢とならざるを得ず,方々を流浪する身となった。遠江,三河,尾張,美濃の四か国を放浪し,一か所にとどまることはなかった。(『甫庵太閤記』)
⑫ミツノゴウ戸の生まれ(『祖父物語』)というところから,「都市民で,出自は職人ないし商人」(服部秀雄『河原ノ者・非人・秀吉)
⑬十五歳のとき,一貫文を与えられて家を飛び出し,その一貫文で木綿針を買い,それを売って生計を立てた。(『太閤素性記』)
⑭連雀商人(行商人)(石井進『日本の中世Ⅰ』)
秀吉の異能を,その出自と来歴に求めることについて,著者は,
このような出自を持ったため,秀吉は特殊能力を身につけたと考えられている。…しかし,…秀吉を語る史料で共通しているのは,「貧しい」の一言である。
その通りだ。そしてこう付け加える。
貧しい人間は,貧困から抜け出すため,さまざまな創意工夫を行うようになる。無論,秀吉もその一人であった。秀吉と同じような環境にあった人物は,ほかにも大勢いたはずである。その中から秀吉が抜けだし,信長に登用されたのは,卓抜した能力と粘り強く辛抱強い性格があったからであった。そして,秀吉自身の強い上昇志向である。
史料から確かに言えることは,
①貧しい百姓の子であること。
②若い頃,薪拾いをしていたこと。
③非常に厳しい生活を強いられ,乞食のようであったこと。
だと著者は言う。そしてこうまとめる。
秀吉に備わっていたのは,主人の言いつけを忠実に守り,任務を遂行するという勤勉さにあった。同時に創意工夫を凝らし,これまでの不合理性を改め,改革していくという能力である。信長に仕えて以後,秀吉は栄達を遂げるが,その原点はこの二つの能力がったと考えられる。
妥当だろう。同じ環境にいた人間は一杯いても,秀吉にはならなかった。なれなかった。その異能ぶりが突出しているから,環境に原因を求めたがるが,後にも先にもこんな人物が出ていないことを見れば,その能力の突出を見るだけでいい。
しかし,この著者も,結局,「貧しさ」「出自の賤しさ」故に,ということを再三強調する。「貧しさ」があったことは,異能の原因ではないし,出世意欲の原因でもない。残酷さも,猜疑心も,そこに起因させようとする。
出自の賤しい秀吉は,自らの残虐性を誇示し,伝説を作り上げることで,自身の姿を大きく見せようとしたのである。
と。これでは,ただ原因を「貧しさ」と「賤しさ」に丸め直しただけではないか。そして,著者は,
もしかしたら,秀吉は生涯を貧しさのまま過ごしたほうが幸せだったかもしれない。
とまでいう。おいおい,それでは,まるで秀吉の人生を認めないのと同じではないか。
参考文献;
渡邊大門『秀吉の出自と出世伝説』(歴史新書y) |
|
黄禍論 |
|
飯倉章『黄禍論と日本人』を読む。

黄禍論は,いわば白禍の裏返しといっていい。19世紀から20世紀初頭までの帝国主義的進出や植民地支配を正当化したのが,人種主義である。
自らを優秀であると信じた白人は,有色人種を支配することは理にかなっていると考えたのである。
しかしその論拠への不安が黄禍に違いない。著者はこう書く。
抑圧された有色人種が連合して白人支配に抵抗し,世界規模の人種間戦争が起きるのではないかと危惧する人々が白人のなかに現れる。そのような危惧のなかでも,とくに東アジアの黄色人種,日本人と中国人が連合して攻めてくる,といった脅威は「黄禍」と名づけられた。
本書は,それを欧米の新聞・雑誌の風刺画を通して,探っていこうとしているところが,ユニーク。ここでは,それを具体的に紹介できないが。
日本が,世界政治の舞台に登場するのは,日清戦争後の三国干渉の時期,三国干渉の当事者,ドイツ皇帝(カイザー)ヴィルヘルム二世が,黄色人種の勃興を脅威と説き,一幅の寓意画「ヨーロッパの諸国民よ,汝らの最も神聖な宝を守れ!」を創らせた。後に「黄禍の図」とも呼ばれ,黄禍思想が流布するきっかけとなったものである。
もっとも他の国々では,それに同調したという様子はなく,そこには,
黄禍を利用してヨーロッパの国際関係を,ドイツに有利な形で進めたい,というカイザーとドイツの意図が透けて見える。
その意味で,国際関係の中で,日本や日本人が,
時に極端に歪曲されて醜く描かれる…
一方で,日本を支持したり,頼りにした国々では,
「黄禍」をパロディ化して嘲笑ったり,批判している風刺画もたくさん描かれている…
つまりは,ドイツのように,自国の主張にとって使い勝手のいい批判ネタとして使われたといっていい。
たとえば,日本人学童に対する差別的措置から始まった,日系移民をめぐる日米対立は,排日移民法の成立をもってひとつの決着を見るが,人種主義による日米憎悪の増幅は,太平洋戦争の遠因の一つと言われるほどのものだが,著者いわく,
太平洋戦争は,白人のくびきから東南アジアが逃れるきっかけを作ったといえる。一方で,人種によって日米がお互いに対する憎悪を増幅したはての戦争であったといえる。
と。
面白いのは,第一次大戦後,設立される国際連盟の規約に,
人種平等条項
を入れるように,日本が提起した問題だ。
日本は会議で独自に提案をし,人種差別撤廃を「信教の自由」条項に盛り込もうとしたが,議長を務めていたイギリスやフランスの委員から反対を受けた。条項そのものも採択されなかった。その後も日本側は,人種平等という表現を国民平等という表現へトーンダウンして何とか連盟規約に盛り込もうとした。
結局採択されなかった。その時代の国際関係の主潮がよく見える。皮肉なことに,それは,第二次大戦後,敵側の国々よって規範化された。
国際連合設立時,主要連合国(米英ソ中)の間では,国連憲章に,人種平等を明示しないというコンセンサスがあったらしい。
それが覆るのは,国際連合を設立に導いた1945年4月から6月のサンフランシスコ会議において,フィリピン,ブラジル,ドミニカ,メキシコ,カナダといった中小の連合国が,人種平等条項の挿入を要求して交渉し,劇的ともいえる成果を上げたためである。
つまり,国連憲章第一条に,
人種,性,言語又は宗教による差別なく
と明示されることになった。
最後に著者は,こう締めくくる。
日本は,アジアにおける非白人の国家として最初に近代化を成し遂げ,それゆえに脅威とみなされ,黄禍というレッテルを貼られもした。それでも明治日本は,西洋列強と協調する道を選び,黄禍論を引き起こさないよう慎重に行動し,それに反論もした。また,時には近代化に伴う平等を積極的に主張し,白人列強による人種の壁を打ち破ろうとした。人種平等はその後,日本によってではなく,日本の敵側の国々によって規範化された。歴史はこのような皮肉な結果をしばしば生む。そう考えると,歴史そのものが一幅の長大な風刺画のように思えないでもない。
参考文献;
飯倉章『黄禍論と日本人』(中公新書) |
|
ホミニンの旅 |
|
アリス・ロバーツ『人類20万年 遥かな旅路』を読む。
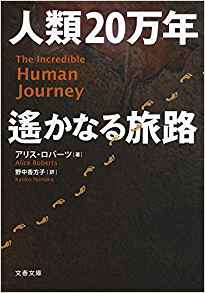
BBCのドキュメンタリーの書籍化ということを,購入してから知ったが,独立したものとして読んでも十分(というかEテレでの放送を観たが,本の方がはるかに突っ込んでいた),人類の系譜をたどる道が,シンプルではなく,いまだ論争の続いている領域であることが,よくわかって,面白い。特に,考古学者たちが,現場に立って,自説を語るところは,正解はないとはいえ,人の持つ先入観の強さを感じさせて,いろいろ考えさせられる。
著者は言う。
現生人類(ホモ・サピエンス)は,二足歩行する類人猿の,長い系譜の最後に遺された種で,「ヒト族(ホミニン)」に属する。…時をさかのぼれば,ホミニンの系統樹には多様な枝が茂り,同じ時代に複数の種が存在することも珍しくなかった。だが,三万年前までに,その枝はわずか二本を残すのみとなった。現生人類と,近い親戚のネアンデルタール人である。そして今日,私たちだけが残った。
そして,
奇妙に思えるかもしれないが,ホミニンが何種いたのかは,まだわかっていない。
とも。
600万年ほど前に,人類の祖先である猿人が類人猿とわかれて以来,200万年前に,ホモ・ハビリス(器用な人)が石器を使うようになり,ホモ・エレクトス(立つヒト)の時代に,第一次出アフリカが行われたとされる。100万年前には,ホモ・エレクトスはジャワ島や中国に達していた(ジャワ原人,北京原人)。60万年前,ホモ・エレクトスの系譜からホモ・ハイデルベルゲンシスがわかれ,30万年前,ヨーロッパに移住したホモ・ハイデルベルゲンシスから,ネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルタレンシス)が生まれた。
一方現生人類(ホモ・サピエンス)は,20万年前,アフリカに残った集団(ホモ・ハイデルベルゲンシス)から生まれ,地球全体に広がっていった。これを「アフリカ単一起源説」というが,ホモ・エレクトスやホモ・ハイデルベルゲンシスなどの古代種が,各地に拡散した後,それらの地域で現生人類に「進化」したとする「多地域進化説」もある。北京原人の研究者は,北京原人(ホモ・エレクトス)が直接中国人に進化したと主張している。
しかしDNAのmtDNA(ミトコンドリアDNA)によって,母方をたどっていくことができる。それによると,20万年前にアフリカにいた一人の女性に始まる,ということが明らかにされている。それを,「ミトコンドリア・イブ」あるいは「アフリカのイブ」と名づけられている。
だが,なぜ,その女性がアフリカにいたと言えるのだろう。それは,系統樹の枝が最も込み入っている部分,言い換えれば,mtDNAが最も多様な地域がアフリカにあるからだ。証拠となるのはmtDNAだけではない。Y染色体を含め,他の染色体の遺伝子も,アジアやヨーロッパに比べて,アフリカの人々の遺伝子のほうが多様なのだ。そうした遺伝的多様性のすべてが,アフリカがホモ・サピエンスの故郷であることを語っている。なぜなら,どこよりも多様な枝が茂ったのは,変異を起こすための年月がたっぷりあったからで,それはアフリカに他のどこよりも昔から人類が暮らしていたからなのだ。
現生人類最初の化石は,エチオピア・オモで見つかった。19万5000年前と結論付けられている。
ではいつ,現生人類は,出アフリカをしたのか。
遺伝子的には,mtDNAの系統樹から,アフリカから出る旅は,一度だけだった可能性が高い,そう遺伝子学者は言っている。
アフリカ外の人類は全員,約8万4000年前後にアフリカで生まれたL3と呼ばれる系統につながっている。L3の「娘」である「ハプログループ」MとNは,およそ七万年前に現れた。Mの系統が最も多様に枝を茂らせているのは南アジアで,それはこの「ハプログループ」が南アジアで生まれたことを示唆している。Mの枝の一つであるM1は南アフリカで見つかっているが,それは最終氷期極相期が終わった後に,外からアフリカにもどった集団だと考えられている。一方,Nの系譜はほぼすべてがアフリカの外にある。…このパターンを見たまま説明すれば,約8万5000年前から6万5000年前のある時期に,L3の枝の一本がアフリカから出て,その後,インド亜大陸あたりでNとMが芽を出した,と言えるのだろう。そして,ヨーロッパに現れた最初の現生人類は,北アフリカからレヴァント地方を通ってやってきたのではなく,インド亜大陸に定住した集団の一部が,西へ流れてきたことになる。
もちろん遺伝子でわかることは,系譜であって,具体的にどれだけが,どういうふうにたどって,地球上にちらばっていったかまではわからない。
だから,考古学が必死で発掘し続けている。しかし,
現生人類が移動した道筋をたどっていくのは難しい。後期旧石器時代,後期石器時代より前の時代の道具は,現生人類が作ったのか,それともネアンデルタール人など他の旧人類が作ったのか,判別しにくい。
しかも,頭骨の形状分析は,難しい。集団間で異なるだけではなく,個体間でも異なり,さらに,個体間の違いが集団間の違いよりも,大きかったりする。
著者は,アフリカから,インド,インドネシア,オーストラリア,東アジア,ヨーロッパ,アメリカと人類の拡散していった道筋を,考古学者を尋ねながら,辿っていく。
著者と明らかに違う見解も,たぶんテレビのドキュメンタリーだからだろうか,きちんと言い分を聞き,その反論を,別の考古学者にさせる。ホモ・エレクトスの地域進化したのが中国人だという説には,上海の遺伝学者に批判させる。
遺伝的証拠は,アフリカ単一起源説が正しいことを示しているのです。地域連続説は間違っていたのです。
と言わせている。そして著者は,こう付け加える。
タイやカンボジアなど,アジアでも南方の人々のY染色体の方がより多様であることは,人類が最初にその一帯に移住し,それから北へ広がっていったことを語っている。そしてY染色体の系統樹は,人類が東アジアに入ってきた時期は,六万年前から2万5000年前のいつかであることを示唆している。mtDNAも南方の人ほど多様であり,移住が南から始まり,北へ広がっていったことを支持している。
我々が皆,アフリカのイブの子孫である,ということは,
わたしたちは皆アフリカ人なのだ。
という著者のメッセージは,その言葉通りに受け取らなくてはならない。
参考文献;
アリス・ロバーツ『人類20万年 遥かな旅路』(文藝春秋)
池内了『科学の限界』(ちくま新書) |
|
ラノベ |
|
波戸岡景太『ラノベのなかの現代日本』(講談社現代新書)を読む。

ラノベ,ライトノベルの世界を知らなかったので,その意味では,著者が冒頭でこう書くのを,新鮮な視界が開けたような感じで読んだ。
ラノベ,という文芸ジャンルがある。正式名称は,ライトノベル。従来の文芸作品全般を「ヘビー」なものと考え,質量ともに「ライト」であることを追求した小説群のことを指す。読者層は主に中高生とされている。しかし,…平成生まれの世代は,そのほとんどが,何らかのかたちでラノベの影響下に(あるいは,ラノベを意識せざるを得ない状況下に)育ってきたといえるだろう。
だが一方で,昭和生まれの世代ほとんどにとって,ラノベはある日突然降ってわいた「よく分からないジャンル」である。
そう考えると,直木賞受賞作品が売れず,本屋大賞を設けざるを得なかった書店の危機感は,社会的な根拠があったと言うべきなのだろう。しかし,
ラノベという文芸ジャンルは,現代日本におけるひとつの「断絶」を意味している。
かつてそういう代表だったマンガやアニメは幅広いターゲット向けになったのに対して,ラノベは,
そのターゲットはあまりに限定的だ。なにより致命的であるのは,ラノベが若者向けの日本語で書かれている,という至極明快な事実である。…ましてや,ラノベのテキストに書き込まれているのは,日本の中高生がちょっとだけ背伸びしてほくそ笑みたくなるようなスラングであり,世界観である。「ぼっち」,「ジト目」,「リア充爆発しろ」…。
つまり,ラノベという「日本語で書かれた小説」は,若者たちにとっての「現代日本」を題材とし,彼らにとっての「現代日本」そのものを主題としている。
ということらしい。そこで,本書がしようとしていることは,SFやファンタジーやラブコメといった多彩なジャンルを取り込んだラノベについて,
「ライト」であることが,書き手と読み手のコミュニケーション効率を向上させるための「軽快さ」を意味している場合,ラノベのテキストが共通言語のように抱えている「現代日本」の姿を知ることは,やはり重要だと思われる。なぜなら,そこで得られるのは,昭和が青春だった世代と,平成の世に学生時代を過ごした世代のあいだに横たわる,「現代日本の断絶」を乗り越えるための教養であるからだ。
という。大学の教員であるゆえに「教養」とでるのだろう。しかし,別に断絶を乗り越えたいとは思わないし,文芸という共通の土俵に乗っていれば,後は,ただ中身ではなく,その表現としての力量,表現としての突出力だけが問題になるだけと考えている人間には,断絶という言葉は意味を持たない。
どうも,著者はそう考えないらしい。
いまどきの若者の書いた小説を読み,「俺たちの若い時はこんなんじゃなかった」とくちにしてしまう―まさにその刹那,読者はみずからが属すべき「世代」なるものを創出する。
という。だから,自分の代弁として,著者は,村上龍と村上春樹を対照として出している。どうも,それこそが,蟹はおのれの甲羅に似せて穴を掘る,に見えてくる。俺たちの若い時はこんなんじゃなかった,等々と口にしない僕には,この問題意識はさっぱり共有できない。そう言っている限り,相手ばかりか,自分自身をもステレオタイプでしかとらえられていないことの象徴のようにしか見えないと思うからだ。。
それに,小説を題材にして,その著者の描く「現代日本」を評論するというこの著者の手法が,なじめないのは,文芸という土俵に乗ったら,どの世代が描くものも,日本を切り取っているものにすぎない。それなら,もっと上の世代の切り取っている日本と対比しなくては,ラノベの世界を相対化できないのではないか,という疑問からくる。しかし著者は,そうは考えていないらしい。W村上を出したのも,対照としているだけらしいのだ。
たとえば,「ほっち」について,渡航(わたり わたる)の『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』から,
1987年生まれの渡が描く「ぼっち」とは,たとえば,遂にドラえもんがやってこなかった(高校生になった)「その後の野比のび太」を想像してみるといいかもしれない。
といい,入間人間(いるまひとま)の『ぼっちーズ』では,
大学生になっても,ついにのび太のままであった「ぼっち」は,
「独りぼっち」のぼっちは,「墓地」に通ずる
とつぶやき,
誰かと一緒にいても,自分は変わらない。
と言う。そこに,著者は,
オタク的な自己卑下はない。彼らは,明らかに,のび太のままに成長してしまった自分を嘆いてはいない。
と見る。そして,こう書く。
たとえば,1970年生まれの谷川流(ながる)による『涼宮ハルヒの憂鬱』(2004年)という物語は,実際は「ハルヒ」というツンデレ・キャラに萌えることが主眼なのではない。そうではなく,「アニメ的特撮マンガ的物語」に別れを告げたキョンと呼ばれる男子高校生が,いかにして「いつも眉間にシワ寄せている頭の内部がミステリアスな涼宮ハルヒ」という「ぼっち」に,我知らず仲間意識をいだくようになったのかを一人称によって述懐するものであった。
そして,
『涼宮ハルヒ』以後,多くのラノベは,「かつてのオタク/現在はフツー」という男子学生を語り手に起用すると同時に,「オタク嫌い」が「オタク好き」を憧れ半分自嘲半分に眺めやる,という一人称スタイルを採ることとなる。
ここに一つの鍵がある。どういう語り手を立てるかで,眺める世界が変わる。この瞬間,書き手が,自分の世界,「現代日本」を,どう眺めているかが,見えてくる。しかし著者は,スルーしてしまう。
ライトであるかどうか,どういうラベルが貼られているかどうかとは,関係なく,文学は文学の眼で見られなくてはならない。そのスタイルを確立した「谷川流」は,自分の時代を見る視点を確立したのであり,文学の表現スタイルを確立したとみる。表現は実物にあたってみるほかはない。
参考文献;
八十岡景太『ラノベのなかの現代日本』(講談社現代新書) |
|
キャリアポルノ |
|
谷本真由美『キャリアポルノは人生の無駄だ』を読む。

自己啓発本に「キャリアポルノ」と名づけたのは,この著者らしい。ネットには疎いので,そんなことが話題になったこと自体を,この本を通して知った。
自己啓発本とは何か。著者によると,ウィキペディアでは,
人間の能力向上や成功のための手段を説く書籍
のことと定義しているらしい。で著者が,それに,「キャリアポルノ」と命名したのは,
基本的に自己啓発書が「フードポルノ」と同じところに理由があります。
といい,こう言う。
アメリカではフードポルノは,栄養バランスが悪くて高カロリーで健康に悪い食べ物を,食品業界が広告やテレビではさもおいしそうに見せかけて消費者に売りつける行動のことをさします。
だから,
フードポルノは,食べ物を食べたり健康になることが目的ではなく,食べ物を見ることでストレスを解消したり,自分では作ることができないおいしい食べ物,自分では費用を負担することができない高い食べ物,自分では時間もお金もないので体験することができない外国の珍しくておいしい食べ物を食べたり体験することの代償行為です。
まあ,この書き方にも,著者は意識していないが,結構上から目線になっている,というより自分の価値の観点が是だという無意識(意識的かもしれない)の論調が出ているが,まあ,ここは省く。そして,こういう。
自己啓発書も基本的にはフードポルノと同じです。自己啓発書で描かれるような成功した人になるには,大変な努力が必要です。書いてあるノウハウを本当に実践するには努力が必要で,身につけるには手間も時間もかかります。読むだけではどうにもならないのです。(中略)フードポルノと同じように,自己啓発書というのは,目に見えない部分での努力や行動,勉強をすっ飛ばして,読むだけで自分の手に届かないもの,…を想像し,自分が求めている欲求を満たすだけの「娯楽」にすぎないのです。
そもそもここまで何が,この著者の正義感だか,義憤だかを駆り立てているのかが,さっぱり読めない。「娯楽」なら,ファッションヘルスへ行こうと,AVを鑑賞しようと,勉強をしようと,自己啓発本を読もうと,その人の勝手ではないか。
だいたい人が何を読もうと,それから何も学ばなかろうと,そのことをひと様がとやかく言うこと自体が,自分を特別視しているという矛盾に気づいていない。僕は著者を知らないが,終始,優越感をどこかに漂わせている気配があった。
僕自身は,基本的に自己啓発本もノウハウ書もあまり読まない。必要性があって,外観をつかむのに便利と思ったときだけ見る。しかし考えようによると,日本の書籍の大半は,欧米の本の翻訳か,解説か,入門か,言ってみればすべてが自己啓発の近接領域にある。おのれ一個の思想を掘り下げたオリジナルな本は,たぶん本当に数えるほどしかないだろう。それなら,まだしも自己啓発本の方がオリジナリティがある。翻訳しても,それは欧米の翻訳の翻訳と蔑まれることはない。
この著者自身が,そういうことに無自覚に,しかも,ご丁寧に,最後に,
「人生を楽しむための具体的な方法」
として,一章を立てて,教訓を垂れている。これ時代が,自己矛盾だと気づいていないの?それを箇条書きにして,列挙してみる。
私は私,あなたはあなた,制す校舎は成功者と自覚する
自分を受け入れる
キャリアポルノにはノウハウや努力のすべてが書かれているわけではない
出来ないのは当たり前
ポジティブシンキングを盲目的に信じるべきではない
人間はそもそも怠惰であると自覚する
不安や恐れを可視化する
不安や恐れを吐き出す
効率よく仕事人生を楽しめ
仕事は仕事と割り切れ
等々。というか,これってそのまま自己啓発ではないか。欧米視点から見たら,著者の指摘の通りかもしれない。しかし,その視点そのものを180度変えると,実は日本人は,江戸時代の貝原益軒の『養生訓』の例を出すまでもなく,ノウハウ本は大好きなのだ。考えたら,宮本武蔵の『五輪書』だって,ノウハウ本だし,有名な山本常朝の『葉隠』だって武士たるにはどうあるべきかを説く武士の処世術,つまりはノウハウ本ではないか。
そう考えると,日本的な自己啓発書,ノウハウ書には,独自の文化的ノウハウがある。西欧を是として観るのではない見方があっていい。第一,翻訳,翻案,入門等々,西欧書籍のそのまま垂れ流しの方がよほど恥ずかしい。そのことに知的優越を感じている連中のほうが,よほど,「西欧ポルノ」ではないのか。その本を翻訳して,出せるの?そう聞いて,出せないような本を書いている人こそ,恥ずかしいと言うべきではないか。
参考文献;
谷本真由美『キャリアポルノは人生の無駄だ』(朝日新書) |
|
選択 |
| ウイリアム・グラッサー『グラッサー博士の選択理論−幸せな人間関係を築くために』を読む。
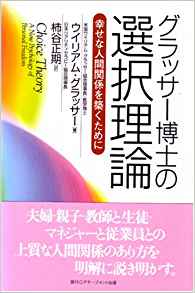
グラッサーは,ある日妻に突然去られて,落ち込むクライアントに,
奥さんが家を出てから,あなたは家にいて座ったままで,仕事に行かないという選択をしているわけですね
そして,
今日ここにくる選択をしましたよね。
と。ここに選択理論の中核がある。
彼は,自分の感じているみじめさを選んでいる。
すべては,自分が選択したということ,そしてその選択には意味がある,ということである。こういう場合,多くの古臭いセラピストは,感情を問題にするだろう。もっと古臭いセラピストは,過去に原因を探ろうとするだろう。しかしすでにE・F・ロフタフたちが明らかにしたように,記憶はうそをつく。書き換えられる。おおくの幼児虐待の記憶,性的虐待の記憶は,セラピストの問いによって,つくられた物語であることは明らかにされた。
過去はいまの状況がつくる物語に過ぎない。生い立ちや母子関係に原因を探っても,現状は動かせない。今落ち込んでいるのは,過去のせいではなく,いまの自分だからだ。感情を探ることも,あまり意味がない。感情は,たとえば,脳卒中で倒れた脳科学者テイラーが,
わたしは,反応能力を,「感覚系を通って入ってくるあらゆる刺激に対してどう反応するかを選ぶ能力」と定義します。自発的に引き起こされる(感情を司る)大脳辺縁系のプログラムが存在しますが,このプログラムの一つが誘発されて,化学物質が体内に満ちわたり,そして血液からその痕跡が消えるまで,すべてが90秒以内に終わります。
脳の化学的・生理的反応は90秒で終わるのである。
通常無意識で反応しているのを意識的に,90秒を目安に,自分で選択できるということです。例えば,90秒過ぎても怒りが続いていたとしたら,それはそれが機能するよう自分が選択し続けているだけのことだ,というわけです。
つまり,その感情を選択しているのである。なのに,その感情を取り出し注目すれば,ますますその感情にのめり込むことを選択し続けるだけだ。あるいはその感情と自慰しているに等しい。
そこから抜け出すには,3つの選択肢しかない,とグラッサーは言う。
①自分の求めているものを変える
②自分のしていることを変える
③両方を変える
上記のクライアントの例に即せば,
①妻への要求を変える
②妻に対して行っていることを変える
となる。そして,グラッサーは,
落ち込みを選択するということは,落ち込みがどれほど長引いても,精神病ではない。すべての行動と同様,これも選択なのだ。歩いたり,話したりするような直接の選択ではないが,全行動の概念を理解すれば,全ての感情は,快感であれ,苦痛であれ,間接的な選択であることがわかってくる。
として,全行動をこう説明する。
私の辞書によると,行動とは,体を動かし,何かをすることである。…選択理論の観点から言うと,体の動かし方が重要である。体を動かす方法には四つの不可分の要素がある。第一に行為。行動について考えるときに,ほとんどの人が歩く,話す,食べる,などの行為を考える。第二に思考。私たちはいつも何かを考えている。第三の要素は感情。私たちが行動するとき,いつも何かを感じている。第四は生理反応。何かをしているときにいつも生理反応が伴っている。例えば,心臓の鼓動,肺の呼吸,脳の働きに関係のある神経化学物質の変化。
行動するときこの四つが同時に機能している。そして,
あなたが全行動を選択するとき,常に四つの構成要素すべてが関与しているが,直接コントロールできるのは行為と思考だけである。
先のクライアントが選択したのは,落ち込の行為と思考なのである。そして,これを選択することで,他の選択肢を無意識で抑圧していることになる。
第一は,怒りである。落ち込むことで,相手への怒りが抑制されている。
第二は,人にお願いせずに,援助を求める方法になっている。
第三は,したいこと,恐れていることをしない言い訳にしている。
落ち込み,引き籠らせることで,激しい怒りに駆られて,妻を探し出し,強引に連れ戻そうとしたり,自暴自棄の行動を取ったりという他の選択肢をしないようにさせたということができる。
このバックボーにあるのは,人をコントロールすることではなく,自分をコントロールするという視点,自分の責任のとれることを自分でする,という視点だ。
何事でも自分にしてもらいことは,ほかの人にもそのようにしなさい。(マタイ伝)
孔子も同じことを言っている。
子貢問いて曰く,一言にして以って身を終うるまでこれを行うべき者ありや。子曰く,それ恕か。己の欲せざる所を人に施す勿れ。
記憶が不確かだが,ミルトン・エリクソンが,オネショの子に,あえて「今日はオネショをする日」と決めさせたことがあったと思う。それは,オネショが外的なものではなく,自分でコントロールできるものだということを,体得させていくことだったように思うが,それと同じことだ。
だとすると,まずは落ち込むことで,より悪い事態になるのを防ごうとする選択をしたのだ,とみなすと,次にすることは,自分自身の中で,
次に何をするつもりですか,
と問いかける。そこには,
①自分の求めているものを変える
②自分のしていることを変える
③両方を変える
の選択肢がある。何かをする,いつものやり方を変える,いつもと違う肯定的なことをする等々。ソリューションフォーカスト・アプローチの,
もしうまくいっていないのであれば,何でもいいから,(いつもと)違うことをせよ,
という原則が生きるかもしれない。グラッサーは言う。
私たちは,相と所属,力,自由,そして楽しみという四つの心理的欲求を満足させるように遺伝子によってプログラムされていると,私は信じている。すべての行動は選択時点では最善の選択であり,四つの欲求を満たすためのものである。
参考文献;
ウイリアム・グラッサー『グラッサー博士の選択理論−幸せな人間関係を築くために』(アチーブメント出版)
ロバート・ウォボルディング『リアリティ・セラピー』(アチーブメント出版)
E・F・ロフタフ&K・ケッチャム『抑圧された記憶の神話』(誠信書房)
E・F・ロフタフ『目撃者の証言』(誠信書房)
ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』(新潮文庫)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫) |
|
科学の限界 |
|
池内了『科学の限界』を読む。
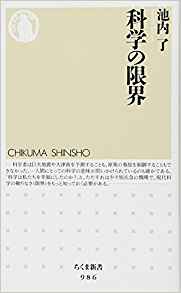
「何が科学の限界を決めているのか,それは克服できるのか,克服できるとすれば現在の私たちに何が欠けているのか,克服できないとすれば今後科学・技術とどう付き合っていくべきなのか」そんな問題意識で,書かれている。
いま一種の踊り場にある。ホーガンは,『科学の終焉』(1996)で,20世紀の前半で,相対性理論,量子論,DNAの二重らせん,ビックバン理論等々は,1950年代までに出され,その後50年それらと匹敵する成果は出ていない,といった。
では本当に限界に達したのか。著者は,いくつかの切り口から,整理しつつ,現在の科学の直面する課題をあぶりだしていく。
まずは人間の生み出す科学の限界。
人間の英知の進化は,600万年前人類の祖先が類人猿とわかれ,200万年前にホモ・ハビリスが石器を使い,60万年前にホモ・エレクトスが第一次出アフリカを行い,20万年前ホモ・サピエンスが出現し,6年前,第二次出アフリカとなって,この間,人類叡智は時間をほぼ三分の一に短縮して進んできた。では,技術(文明)はどうか。40万年前ホモ・エレクトスが火を発見し,一万年前に農業をはじめ,250年前に燃料革命と機会による産業革命となり,6年前情報革命…と,技術は時間を40分の一に縮めて展開してきた。つまり人間の英知の発達に比べて10倍以上の速さで進む。
もはや人間の英知が追いつかなくなる状況を迎えているのではないだろうか。
と著者は,「問題がより高度になり,より難解になったために,…なかなか打開の方向が見いだせず,人間の認知能力の限界に挑戦している状態」と言う。たとえば,
物理学で言えば,マクロ物質とミクロの原子との間には質的なジャンプがあり,ニュートン力学から量子力学への大きな変革の必要があったが,原子以下の原子核・核子(陽子と中性子)・クォークという下の階層ではそのまま量子論が通用している。力学構造が同じであるなら,実体の形状に階層の原因を求めなければならない。そこで点粒子の描像から弦(ひも)や膜のような形状を考えるようになった(超弦理論)。そうなると空間次元が九次元とか10次元となり,難解な理論にならざるを得ないのである。ひょっとすると袋小路に入り込んでいるのかもしれない。
次は社会が生み出す科学の限界。
19世紀以降,科学が国家の精度に組み入れられ,「科学のための科学」ではなく,「社会のための科学」に変質し,「社会に役立つ科学」であることを求められるようになる。結果として第一世界大戦の毒ガス,航空機から始まって,第二次世界大戦へと軍事技術として総動員されるようになる。その結果,爆弾は,殺傷能力で40万倍,爆発力で10億倍,飛翔距離で1000倍となる。そして,1990年代からは,グローバル化に伴って,科学の成果の商業化を強く求められるようになる。商業化に伴って,科学が社会に迎合する方向になびき,基礎から,改良主義に陥っていき,科学の多様性が失われていく。
そして科学に内在する化学の限界。
ミクロの世界では,位置と運動量やエネルギーとその常態にある時間は完全に決定できないという不確定性関係を受け入れると,
必然的に私たちが厳密に決定できる物理利用の値に制限がつく。完全に位置と運動量が決定できるなら不確定度はゼロなのだが,素粒子のようなミクロ物質では,サイズと運動量の不確定度の積はプランク定数程度のおおきさになり,ゼロではなくなるのである。速度の上限は光速だから,運動利用は質量に光速をかけた量が上限値となる。すると不確定性関係は,サイズと量の積がある一定の大きさ以上でしか決まらないことを意味する。つまり,サイズを指定すると質量の下限(それ以上の質量が許容範囲)が決まり,逆に質量を指定するとサイズの下限(それ以上のサイズが許容範囲)が決まる。それ以下の質量なりサイズでは,物質の状態は決定できなくなるのだ。
つまり研究範囲が,ある大きさ以上に限定され,物理量すべてを調べ尽くせなくなる。一方,マクロ物質においても,ブラックホールでは,光だけでなくいかなる信号も出てこられなくなるので,物体に対する情報が得られなくなる。つまり,
物質の質量やサイズに,量子力学から要請される不確定性関係と,一般相対性理論から導かれるブラックホール境界という二つの制限条件が課せられることになる。具体的には,サイズを一定にしたとき,私たちが認識できる質量範囲として,不確定性関係から質量の下限を与え,ブラックホール条件から質量の上限が決まる。
要は,物質の質量や密度のすべてを知ることができない。つまり,
科学自身に内在する法則によってある限られた範囲しか極められない,
という限界がある,ということになる。さらに,従来からの科学の方法は,要素還元主義で,
その系(システム)を部分(要素)に分け,あるいはより根源的な物質を想定し,それらの反応性や振る舞いを調べて足し合わせれば全体像が明らかになるという手法
であった。それは,
すべての過程を線形に帰着させることによって問題を簡明化し,その範囲で威力を発揮できたためである。別の言い方をすれば,線形として扱える範囲の問題に限り,非線形の問題は「複雑系」として後回ししてきたのだ。
しかし3.11と原発の事故は,典型的な非線形現象であり,科学者は巨大地震や大津波を予測することも,原発を安全に制御することもできなかった。
最後は現実社会で起こることと科学の限界。
エネルギー資源,地球温暖化,核エネルギー等々に対して,科学は社会の要請に応えるばかりでいいのか,という問題提起である。
こうした限界の中で,著者は,
①科学者は「社会のカナリア」であるべきだという。炭坑夫は行動へ入る時ガス感知としてカナリアを先頭にする。科学者はその役割を果たすべきだという。そのためには,科学者は,何があっても事実を正直に公開し,現実を直視し,真実に忠実でなくてはならない,という。
②等身大の科学。たとえば,地球温暖化の指紋として,世界各地の鳥や虫や植物がどれだけ移動したかを研究する。等身大の身近な現象は複雑系が多い,特に生態系はそうである。そこで確固とした事実が言えるためには,長年の観察が欠かせない。
③社会と向き合う。科学は無限ではないけれども有限でもない。その限界は時代とともに変化する。科学者と市民との連帯がそれを決める重要な要素である。
そう締めくくる。是非はともかく,いま科学そのものが,そして科学者そのものが問われている場面がいっぱいある。それをどう掣肘し,質すかは,まさに社会が問われているのではないか。そんな印象をもった。
参考文献;
池内了『科学の限界』(ちくま新書) |
|
コンテクスト転換 |
|
寺本義也『コンテクスト転換のマネジメント』を読む。

知識がネットワークを通じて,獲得され,創造され,活用される「知識ネットワーク社会」における企業経営課題は,
人々の行為を主体的な知識の創造と活用に向けて,いかに効果的に方向づけ(戦略創造),結合・連関づける(組織化)かにある…。
として,著者は,新しいマネジメントの目標は,持続的な「知的生産性の革新」にあるということができるとして,
あたらしいマネジメントの最大の条件は,創造的でかつ効率的なことであり,組織全体で多様でかつ変換効率の高い知識体系を構築していくことにある。すなわち,組織全体としていかに多様な知識を取り込んでいくか,その多様な知識をいかに変換効率を上げながら,あらたな価値や意味を具現化するすぐれた製品やサービスとして結実させていくか,という二つの課題の同時的な実現が要求される,
という。この場合,知識とは,次のような意味として整理されている。
知識は優れてそれぞれの主体や主体の置かれた文脈に依存した,あるいは関係づけられたものである。また知識は,すでにつくられたものとして,われわれの前に置かれているものではなく,われわれ一人ひとりが,それを解釈し,それに意味を与えるものである。言い換えれば,知識は他者から一方的に与えられるものではなく,個々人が自己の存在を賭けて主体的に創造し,活用するダイナミックな行為に関わるものなのである。
これは,かつて,
知識とは思いの客観化プロセス,
と語った野中郁次郎氏の言とつながるものだ。知識は,あるものではなく,主体的に作り出していくものだ。その意味で,その文脈(コンテクスト)によって,解釈が変わる。逆にいえば,
コンテクストとは,基本的には,ある情報や知識(コンテンツ)の意味に影響を与える(意味づける)ものである。
と言い替えることができる。情報で言えば,金子郁容氏のいう,コード化できるコード情報とコード化できないアナログなモード情報との対比で考えると,通ずるものがある。それは,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/prod05111.htm
で触れたところだ。
では,コンテクストの機能をもう少し整理してみるとどうなるのか。
第一は,コンテクストの表示性。人や組織がある情報・知識(コンテンツ)の意味・価値を解釈するときの枠組みとしてのコンテクスト。
第二は,コンテクストの再帰性。ある局面のコンテクストのなかで意味あるものとして行われた行為自体が,その直後の局面のコンテクストを形成する一要素となることを通して,引き続き起こる次の局面のコンテクストを規定する。
第三は,コンテクストの型式性。対話者の間のコミュニケーションにおける背後にある関係性のパターン。
つまり,コンテクストとは,ある情報・知識に特定の意味・価値を与えるための認知上の枠組みであり,結局一つの情報・知識(コンテンツ)は,受け取る人や組織の異なるコンテクストによって意味づけ,価値が異なるが異なれば,解釈が異なり,違う現実が見えるということになる。
そうなると上述のように,
組織全体としていかに多様な知識を取り込んでいくか,
その多様な知識をいかに変換効率を上げながら,あらたな価値や意味を具現化するすぐれた製品やサービスとして結実させていくか,
という課題の実現が企業の生死を決める時代には,コンテンツではなく,コンテクストに着目するのは,一つの慧眼に他ならない。
つまり,「コンテクスト転換のマネジメント」にとって,
まずは,コンテクストの表示性,コンテクストの再帰性,コンテクストの型式性の三つの機能は,二者以上のコミュニケーションにとって重要な要素になる。なぜなら,コミュニケーションにおいて,コンテクストは効率的,効果的なコミュニケーションを成立させる土台となる,「解釈の枠組み」として成立しているからである。つまり,コンテクストをどう共有するかが,鍵になる。つまり何を伝えるか(コンテンツ)ではなく,どう解釈するか,どう見ているかというコンテクストが重要になる。
しかも,マネジメントにとっては,
多様な参加者が既存のコンテクストを共有するだけではなく,さらに進んで,参加者の相互作用を通して,
異なるコンテクストを融合し,あらたなコンテクストを創造する(止揚的融合)するよう働きかけていくことが重要である。なぜならば,…コンテクストの転換による新たなコンテクストの創造は既存のコンテンツに対して,あらたな意味・価値を付与するものであり,そのことによって,組織の学習と知識の創造・活用を促進することにつながるからである。
言い換えれば,
組織が既存のコンテクストの共有化を超えて,参加者間の相互作用を通じて既存のコンテクストを転換し,あらたなコンテクストを創造することによって,より高度で多様な意味・価値をできる限り迅速に創出することこそが,コンテクスト転換のマネジメントの主要な目的なのである。
自己完結した知識・情報から,開放して多様な知識・情報を取り込む。それは人とセットになっている。そのとき,知識・情報というコンテンツではなく,背景になっているコンテクストを開示しあわなくては,コンテンツそのものの再構築にはならない。
コンテクスト転換を重視する著者の主張の背景は,「ネットワーク組織」「止揚的融合」「共進化」という概念にある。いわばこれからの企業のあり方を考えるキイ概念になっている。
特に,共進化。共進化とは,
複数の個体(ないし集団)が各々別個に進化を遂げるだけでなく,個体(ないし集団)間の自由でダイナミックな相互作用を通じて,お互いの進化を促進する状態,
を指し,それは生物学の,
それぞれの種の遺伝的特性の状態が,もう一方の種の支配的な遺伝的特性によってお互いに影響を受けあうような相互作用を持つ二つの種の進化的変化パターン
をから来ている。時間軸で見ると,共進化だが,空間軸で見ると共生になる。そのとき,コンテクストの共有を避けては通れない。
以上の本書の趣旨は大変よくわかる。しかし,事例は,ほぼ十年近く前のもので,仮説の検証としては,いささか説得力に欠けるのが惜しまれる。というか,むしろ今日の日本企業の体たらくをみると,相変わらず,コンテンツのみに走り,コンテクスト転換をなおざりにしたつけ,と見えなくもない。
それは,あるいは明治以来の日本全体の桎梏といえなくもない。そのくびきから,まだわれわれ一人一人が抜け出し得ていない。
参考文献;
寺本義也『コンテクスト転換のマネジメント』(白桃書房)
金子郁容『ネットワーキングへの招待』(中公新書) |
|
江戸の経済政策 |
|
山室恭子『江戸の小判ゲーム』を読む。

江戸幕府の経済官僚と承認との虚々実々の駆け引きと,奇妙な共存共栄関係が描かれる。言ってみると,いままでの先入観を拭い去ってみると,江戸幕府の経済政策は,独善的だったり,幕府や武家の利のみを計っているとは言えない,目から鱗の歴史が,現れてくるのが面白い。
焦点は,ふたつ。ひとつは,50年周期で繰り出される借金棒引きの政策。いまひとつは,小判の改鋳。世上いずれも,武家による武家のための施策に見える。しかしそうではない,と著者は言う。
武家と商人という,まったく編成原理の異なる二つの社会集団のあいだを取り持ち,互いが互いの長所と欠点を補いあっての集団相互の精妙なる均衡関係を維持する,というまことに崇高で困難に満ちた使命
を果たすべく,幕府の経済官僚は,知恵を絞っている。
両者をどう均衡させれば,どちらにも不満を発生させずに,商人に偏った富を再配分させるのか,
借金棒引き令も,貨幣改鋳も,同じ目的で実施されている。
公儀による借金棒引き令は,窮乏武家一般を救済するために無計画に繰り出されたのではなく,父祖以来の借財が累積し,余儀なき不幸によって当人の積でない自由で債務過多に陥った武家が多数を占めるようになる時期を見計らって,計画的に実施されたものであり,それが50年周期になっている。借金棒引きのその意味に光を当てると,有名な,享保の改革,寛政の改革,天保の改革,いずれもが,政治の偶然ではなく,経済の必然に導かれての政策だ…
と著者は分析する。
武家の窮乏は,ひとり武家だけの困難を招くのではない。武家の消費が冷え込めば,商人も苦境に陥る。なにしろ武家は江戸の人口の半分を占め,かつその日暮らしの零細民の多い町方とは異なり,確実な定収入のある大口の消費者である。その武家の購買力低下は,江戸の商人に深刻な営業不振をもたらすことになる。だから公儀は,借金破棄という荒療治をあえてしてでも,売れない/買えない,あるいは貸せない/借りられないという商人・武家双方の手詰まり状態を打開し,「融通」の回復を図ったのである。
いわば,富の再配分である。
武家から承認へと年々移動し固定化し流通しなくなってしまった富を,50年に一度,強制的に商人から吸い上げて武家に再配分することで,「世上不融通」を解消し,売買・貸借という両者間の経済活動を再び活性化する役割を公儀は積極的に担っていたのではないか。
もちろん,棒引きにされた札差側はたまったものではない。黙ってそれに従ったのではない。反発や異議申し立てを受けて,幕府側も,棒引きから,利下げへと譲歩したり,
損害により営業不振に陥った札差に資金援助をするため,江戸の豪商から7万3000万両を出仕させ,会所を設立させて,武家への融資の資金源としたが,それが天保になると,20万8200万両の上納金に,大阪商人からは,110万両が上納されたが,無論これは20年賦利子つきで返済される条件付きである。
といったバックアップ体制を取りながら,推し進めていくが,実は商人が受け入れざるを得なかったのは,「金銭訴訟」受付の絞り込みという幕府の締め付けであったからだ。年間200件以上の「借金払い」に関わる訴訟が奉行所に持ち込まれている。
それを審議し裁定し,さらにその裁定に強制力をもたせて債務を返済させるために,奉行から初期・執達吏にいたる膨大な人手が投入されていた…。
その機能が止まると,商人にとって公儀が金銀訴訟を裁定し,信用取引を保証してくれていることがいかに大きな,それこそ死活問題につながりかねないほど,公儀に依存している部分があったともいえる。
いまひとつは,小判改鋳だが,幕府は20年ごとに小判を改鋳し続けている。
改鋳の目的は退蔵貨幣の解消にあり,放っておくと滞留してしまう貨幣の流れに人為的な刺激を定期的に与えて回転を円滑にするため,わざわざ貨幣自体をリセットしたのである。
従来は,旧貨幣より品位を落とした新貨幣をリリースし,その差益=出目をえることとされてきたが,そうではない,と著者は言う。その理由を,こう分析する。
現代であれば貯蓄=投資,誰かが貯蓄した分は銀行等を通して別の誰かに貸し出され,投資として機能する。しかし,江戸の場合は貯蓄+投資=定数,誰かが貯蓄すると,その分の小判が世の中から消え,投資に回す分が減ってしまう。とりわけ札差や両替商のような大手の金融業者が貯蓄志向に走り,年貢米を買い叩いたり武家への貸し渋りをしたりして巨額の資金を抱え込んでしまうと,武家の購買力がもろに低下したりモノが売れなくなって商業界全体が沈滞してしまう。貯蓄ができない社会。そこから公儀の苦労が始まる。放っておくとみんながお宝を抱え込み,貨幣の過半が世上から姿を消してそこでしまいかねない。そこで頃合いを見はからって貨幣会知友という強硬手段を発動し,蔵にしまわれたままの旧貨幣を期限切れに追い込んで放出させる。
それについて,では商人はどういう反応をしたのか。
たび重なる改鋳に実施に対して,商業界からは指弾の声ひとつ上がらない。それどころか,両替商たちは手弁当で旧貨幣と新貨幣の引き換え実務を黙々と担い,全面的に公儀に協力している。
だから銭は230年一度も改鋳されていない。「寛永通宝」のまま通された。
意外と,江戸幕府の政策の細部は合理的なところとかゆいところに手が届くような繊細さがあった。再度見直されるべきなのかもしれない。で,ふと思い出すのは,幕府が森を維持するために努力し続けてきていたということを。明治新政府は,そこまでのきめの細かさはなかったために,森が荒れた,と。
しかし同時に思う。これは,幕藩体制という制度自体の矛盾でもある。横井小楠は言い切る。幕末3500万の人口中,まともに食べているのは,5〜600万人にすぎない,と。その矛盾を,その時代を維持するための荒療治だったにすぎない,という言い方もできる。
参考文献;
山室恭子『江戸の小判ゲーム』(講談社現代新書) |
|
発明家 |
|
橋本毅彦『近代発明家列伝』を読む。

「世界をつないだ九つの技術」とサブタイトルがついている。取り上げた発明家は,
ハリソン(世界時計の計測)→ワット(産業革命の原動力・蒸気機関)→ブルネル(鉄道建設と蒸気船)→エジソン(電球と発電)→ベル(電話)→デフォレスト(無線通信とラジオ放送)→ベンツ(自動車)→ライト兄弟(飛行機)→フォン・ブラウン(ロケット)。
近代の骨格となる発明といっていい。もちろん別の選択もありうるだろうが,「世界をつなぐ」に焦点をあてている。
ハリソンは,大航海時代の船載時計の開発。揺れる船に乗せて,精度を保つ機械時計の原点となったハリソンの塔時計は,
驚くことに現在に至るまで動き続けている。
という。
ワットと言えば,蒸気機関だが,ワットは蒸気機関の発明者ではない。ワット以前にすでに実用化されていた。彼がした功績は,それを改良し,格段に性能と効率を向上させ,汎用性の高い機会によって,産業革命の原動力となった。彼の蒸気機関は,大気圧程度で作動する低圧の蒸気機関で,後の蒸気機関車や蒸気船に搭載された高圧の蒸気機関とは異なっていたが,ワットは,
高圧の蒸気を扱うことは大変危険だと固く信じていた…。
という。その蒸気機関車の鉄道建設に関わり,世界一周航海が可能な巨大な蒸気船を建造したのが,ブルネルである。
エジソンについては言うまでもないが,彼は,
ちただ電球を製造するだけでなく,発電所と送配電用の伝染を建設し,電気を利用者に供給する事業を計画した。
というように,「システム構築者」であったところだ。
電話の発明者ベルは,一方で聾唖教育の実践者であり,ヘレンケラーとサリヴァンを引き合わせることになる。そして『ナショナル・ジオグラフィック』誌を支援した功績も大きい。
真空管の先駆けになる三極真空管を発明したデフォルトは,無線の用途として音楽やニュースの包装の事業化に関心を持ち続けた。
ガソリンエンジン搭載の自動車を開発したのがベンツ。それが一大産業として開花したのは,アメリカである。
アメリカの自動車産業を支えたのは,自動車が走行する舗装道路の建設と信号や標識の設置,ゴムタイヤの製造などの基盤技術の発展である。
という。
電話の発明酒ベルは,晩年飛行機の発明に関心をよせたそうだが,自家製のガソリンエンジンを搭載した飛行機械で初飛行に成功したのは,ライと兄弟である。
飛行機は第一次世界大戦に利用され,戦争の形態を一変させた。さらにそれを激変させたのが,フォン・ブラウンの開発したロケットであり,それを使ったV−2ミサイルはロンドンに降り注いだ。
そのミサイル技術が,別々にアメリカとソ連に運び出され,米ソの宇宙ロケット打ち上げ競争になり,スプートニク,ガガーリンの有人宇宙飛行とソ連に先んじられた宇宙競争で,アポロ計画が立案され,フォン・ブラウンが,それを担当した。
こうした発明史に,何を取り上げるかで,近代の見え方が変わる。これに,コンピュータを取り上げるか,交通システムを取り上げるか,によっても変わるだろう。
いまや個人の発明家の時代ではなくなった。エジソンが依頼されていた潜水艦探知機の開発に失敗した時,科学者中心の組織が,音響探知機を開発したのを例に,著者は言う。
時代はすでに,機械職人が創意工夫をしながら工作していく段階から,科学者たちが現象の分析を行い,科学理論を応用しつつ新しい装置を開発していく段階に移ろうとしていた。
いまは,さらにそういう様相を呈している。しかしシステムがあったら発明ができるわけでもない。田中耕一さんの例のように,やはり個人の着想と問題意識なくして発明はない。
最後に著者はこう書く。
10人の発明家の生涯を追って改めて気づくことは,彼らの多くが特許取得をめぐって苦労を重ねていることである。なかでも熾烈な特許係争に巻き込まれたのはベルである。発明家の思考と活動は,特許制度のあり方に色濃く特徴づけられている。特許取得に有利なよう,日々の思考や実験をノートに書きとめ,ライバルの動向に注意し,よき財政支援者と協力する。特許制度への対応は,産業革命以降の技術活動の非常に重要な側面を形成しており,そのことは特にアメリカの発明家たちにあてはまることだったろう。
そう思うと,ほぼ同じ地点にいたライバル,特許係争に敗れたライバルたちに焦点をあててみてみると,別の歴史があるに違いない。
参考文献;
橋本毅彦『近代発明家列伝』(岩波新書) |
|
言語を生み出す脳 |
|
酒井邦嘉『言語の脳科学』を読んだ。

問題意識は明確だ。
本書では,言語がサイエンスの対象であることを明らかにしたい。言語に規則があるのは,人間が規則的に言語を作ったためではなく,言語が自然法則に従っているためだと私は考える。
言語を心の外にある実態と考えるよりも,心のはたらきの一部と考えたほうが自然であろう。
つまり,「人間に特有な言語能力は,脳の生得的な性質に由来する」という問題意識だ。それは,言語習得を,単語レベルではなく,統語論・意味論・音韻論の三要素の言語知識を,幼児は並行して獲得していく,というところに端を発している。
所謂プラトンの問題と言われるものだ。
言語の発達過程にある幼児が耳にする言葉は,多く言い間違いや不完全な文を含んでおり,限りある言語データしか与えられない。それにもかかわらず,どうしてほとんど無限に近い文を発話したり解釈できるようになるのだろうか。
これがプラトンの考えた問題であり,
幼児に与えられる言語の刺激が貧困であるという事実を指して,「刺激の貧困」とも呼ばれている。
そして,プラトンの問題が示しているのは,
幼児が白紙の状態から言葉を話せるようになるのではない,という事実である。それを整理して,著者は三つの謎としてまとめている。
第一は,「決定不能の謎」である。これは,与えられる言語データだけから,幼児が言語知識のすべてを決定するのは不可能だという問題である。しかも,六歳頃までの幼児は,推理・類推・論理などの分析能力がまだ発達途上であり,部分的な言語データから帰納的に文法すべてを推理することなど,とうてい不可能だと考えられる。そもそも決定できないはずのものがなぜ決まってしまうのか。
第二は,「不完全性の謎」である。刺激の貧困から明らかなように,幼児に与えられる言語データは不完全である。しかも,どのデータが完全で,どのデータが不完全か,という手がかりすらもない。不完全なデータから,なぜ完全な文法データが生まれるのか。
第三は,「否定証拠の謎」である。文法的に誤った分のデータを否定証拠(負例)と言う。…否定証拠も十分に与えなければ,文法を決定することは不可能であることは理論的に証明されている。親は,子どもの言い間違いをすべて直すとは限らないし,あえて間違った例文を与えてくれるということもない。…それにもかかわらず,なぜ文法的に間違った文が間違っているとわかるようになるのだろうか。
この答えは,ひとつだけある,と著者は言う。
それは,いたって簡単。幼児の脳にはじめから文法の知識があると考えればよいのだ。
そうみなすと,類人猿も言葉を使うとか,手話(手話は左脳を使う言語であって,ジェスチャーとは違う)を使うとかということは,論外になる。すなわち,
第一に,類人猿は,人工的なシンボルとその意味を連想して覚える能力を持っている。ニホンザルも,たくさんの人工的なシンボル(図形)を連想して長期的に覚えられることは,私のかかわった以前の実験が証明している。このような連想能力は,一般的な学習のメカニズムに基づくものであって,言語を使うことに必要であるが十分ではない。ジェスチャーやシンボルと意味との連想関係を覚えたからといって,言語を使っているというのは間違いである。
第二に,類人猿がシンボルを使って解釈している意味が,人間の言葉と同じであるという保証は全くない。犬も人間の言葉を使って訓練できるわけだが,動物は人間の言葉に反応しているのであって,「理解している」とは限らない。
ここには,言語を使うということの正確な定義が抜けていところからくる勝手な解釈が横行している。著者は言う。
言語とは,心の一部として人間に備わった生得的な能力であって,文法規則の一定の順序に従って言語要素(音声・手話・文字など)を並べることで意味を表現し伝達できるシステムである。
こう見ると,逆に類人猿を,人間の眼を通して人間の都合よく解釈していて,
これまで忘れられているのは,むしろ類人猿本来のコミュニケーションを明らかにする研究であろう。動物同士がどのようなコミュニケーションを行うかがわからなければ,人間の言語と比較すること自体,無意味なのだから。
というのがむしろ驚きだ。いままで,科学者は何をしていたか(何をしていなかったか)が逆に照らし出されてくる。
著者は,チョムスキーの生成文法に,一つの方向性を見出している。
チョムスキーは,発生の仕組みで体ができあがるのと同じように,脳に「言語器官」があって,言語も成長に従って決定されると考えた。言い換えると,言語は,本人の努力による「学習」の結果生ずるのではなく,言語の元になる能力,即ち言語知識の原型がすでに脳に存在していて,その変化によって言語の獲得が生ずる…。
それにもとづく仮説が,言語のモジュール仮説である。つまり,
独立して仕事できるけれども,互いに補い合ってはたらくものを,認知科学では「モジュール」と呼んでいる。統語論・意味論・音韻論は,言語のモジュールであると考えられる。モジュールは,この「独立性」の他に,単独で処理が自動的に進むという「自動性」,そして必要な入力以外は受け付けないという「入力制限」といった特徴をもっている。言語が他の認知機能とは独立したモジュールであるという考えのことを,「領域固有性,領域特殊性」といい,学習のように一般的な機能のことを,「領域一般性」と言う。
まだ仮説にすぎないが,たとえば,文法処理について,ブローカー野が文法中枢として働くことが見つけられている。
文法の処理が脳の機能として局在しているという発見によって,「言語のはたらきは,一般的な記憶や学習では説明できないユニークなシステムである」という言語学の主張が裏付けられたことになる。
しかし,MITのオニールは,「脳科学が言語学の知見を実証するというのは誤りで,言語がどのように表現されるかという問題は,言語学者と脳科学者の共通の仕事なのだ」と言っているそうだ。
その道筋を,著者はこう言う。
二十世紀の物理学は,理論物理学と実験物理学の見事な融合によって,たくさんの発見をもたらした。…言語学と脳科学の関係は,この物理学の関係とよく似ている。言語学は言語の法則に関する理論を提供し,脳科学は言語のシステムの仕組みを実験的に明らかにする。しかも,両者の関係は両方向になり得る。言語学の理論的予想が脳科学によって実証され,脳科学が見つけた言語の現象に,言語学が説明を与える。こうなることが近い将来の理想である。
まだまだ「脳がどのように言葉を生み出すか」の探求は,緒についたばかりといっていい。
参考文献;
酒井邦嘉『言語の脳科学』(中公新書) |
|
シグナル |
|
アレックス(サンディ)・ペントランド『正直シグナル−非言語コミュニケーションの科学』を読む。

人と人との相互作用を,ソシオメーターをつかって,一度に何百人の行動を正確に測定できるらしい。それを装着した人の行動を分析することによって,どれだけ対面していたか,発話の特性から非言語の社会的シグナルを測定する,人と人との物理的距離を測る等々を知ることができる。『正直シグナル』(アレックス(サンディ)・ペントランド)はそうしたデータに基づいて,人の非言語コミュニケーションの特徴を検証した報告でもある。
人間には,言葉ではなく社会的な関係を軸とする第二のコミュニケーションのチャンネルがある。この社会的なチャンネルには互いに誰も気づいていないにもかかわらず,私たちが下す大切な決定はこのチャンネルに大きく左右される。
それが本書のテーマである。それは,
人間の行動のタイプには,生物学的基礎をもつ正直シグナリング行動から,かなり確実に予測できることが多いことがわかった。
という。本書は,人の相互作用は,
話し手の態度あるいは意図が,韻律と身振りの大きさや頻度の変化のような無意識の行動を通じて伝わる。
それわ,動物コミュニケーションや社会心理学に基づく,「非言語的な無意識のシグナル」に重点を置いた「正直シグナル」と名付けたものから明らかにしようとする。
そこでは,「対話の内容でなく,人間のあいだの関係」に着目するので,
なじみのない外国語での会話を観察していても,誰かが会話の主導権を握っていたり,友好的な相互関係を築いていたりするのが「わかる」ときに,知覚しているもの,
と同じなのだ,という。これは,カウンセリングやコーチングで,クライアントの言葉の中身や意味ではなく,その振る舞いやしぐさから見ようとしている姿勢と同じといっていい。
本書では,そういう正直シグナルを,
●影響力 社会的相互作用のなかで,各自が別の人に与える影響の大きさ。相手の行動をコントロールできる度合い,相手の言葉にかぶせるように話しあっているときはどちらの影響力も大きい。不規則な会話の中断があると,影響力は小さい。一方が質問しているときは,一方的な影響力が見られる等々。
●ミミクリ 会話の間,人がほかの人を反射的になぞること。無意識に相互で微笑んだり,相槌をうったり,頷いたりする。人が相手の行動をまねたり,なぞったりしているときは共感を示している,他人の行動の無意識なミミクリは社会的適応機能を果たしている。
●活動レベル レベルが上がるのは,関心を持ったり興奮したときだ。発話時間は関心のレベルや外向性と相関がある。
●一貫性 発話の韻律や身ぶり,手振りの変動の量,声の大きさやリズムの変動,身振りや手振りの大きさ速さで測る。協調やタイミングの一貫性は精神が集中しているシグナルで,逆に変動性は,感情的になっているしるしであることが多い。変動性は他人からのインプットに対する寛容性,それを受け入れる用意があると伝えるシグナルになる。
こうしたシグナルは,脳の構造や生物学的仕組みに根差している。
影響力は,注意や低位の神経系,感覚情報をまとめて,人に目を向けたり,音に反応したりする,定位反応を引き起こす,ミミクリはミラーニューロン,ほかの人の行動に反応しまねるフィードバック経路を提供する,活動レベルは自律神経系,闘争か逃避かを迫られたり,性的興奮状態にある時,神経エネルギーを提供する行動に現れる,一貫性は小脳,大脳基底核,大脳皮質に投射している神経経路の働きが表面化したもの,等々と考えている。
このシグナルは,人類の進化の古い遺産といえる。人類のシグナルは,類人猿のシグナルに似ているし,幅広い動物界のシグナルにも近い。例の飼い主の心を読んだ「賢いハンス」という馬の例や飼い主の心を読む犬の例は,無数にある。
面白いのは,このシグナルを意識的にでっち上げて,偽って伝えようとすることは難しい,ということだ。例外は,特定の社会的役割に完全に没入する「スタニスラフスキー方式」で,これは,うまくいくという。
ではそうしたシグナルは,どう社会的役割を伝えているのか。ここでは,それを,打診,傾聴,協調,主導にわけ,それらはいくつかの心の働きの組み合わせを仮定している。
たとえば,影響力は注意を,ミミクリは共感的な理解を,活動レベルは関心を,一貫性のある協調は精神的集中と決意を伝えると解釈すると,相手との関係を深める可能性を探りたい打診という社会的役割は,関心と影響力に対する寛容性(つまり受け入れる用意)のシグナルになる。
傾聴という役割は,注意と関心と新しい考えへの寛容性の組み合わせによって相手に示される。活動レベルは抑制される。
協調の役割は,注意と,共感的理解,集中した思考と目的という組み合わせの表出になる。強い影響力,ミミクリ,一貫した協調とのリズムが見られる。
主導の役割は,注意と関心,とても集中した思考と目的を示す。
しかも無意識で独立したこのコミュニケーションのチャンネルから,客観的行動と主観的な社会的印象をかなり正確に予想できるらしい。つまり,意識的に抑えようとしても,無意識はその覊絆を脱して,意図を表面化させてしまう。例えば,ポーカーフェイスを競うカードゲームでもパーティや会議でも,ソシオメーターを使うと,80%の精度で,行動が予測できた,という。
もともとわれわれは他人の心を即座に読み取って反応できる,「ネットワーキング・ハードウエア」をもっている。この鍵になるのがミラーニューロンで,相手の影響力やミミクリ活動レベル,一貫した強調などが伝える正直シグナルを読み取るための直接の神経経路をもっているので,相手の関心,決意,共感などのレベルを無意識に読み取っている。
それは,個人にとどまらず,社会的ネットワークを作り上げている人々とのつながりを通じて広まり,集団全体にも影響を及ぼす。人々の間のシグナリングのパターンによって形づくられる社会的回路もある。例えば,典型的なのは,気分の伝染だ。いまの「好景気感」という気分もそうだが,興奮した一人がいるだけでチーム全体のエネルギーレベルが上がったりする。それが自分にフィードバックされて,無意識のうちに興奮する。
意識的な言語と違うのは,シグナリングが当事者双方を変えることだ。たとえば,
だれかがあなたのまねをすると,あなたも相手の真似をしはじめる傾向がとても強い。その結果,ある種の社会的回路が生まれ,それが自己強化するようなかたちになり,二人はますます盛んに相手のまねに取り組み,それぞれ相手のことをますます好ましく思うようになる。
いわば,「自発的洗脳」という効果は,たとえば実験で,売り込みに,ともかく首を上下に振るように求めると,その売込みが気にいるようになる。脳は,怖いから鳥肌立つのではなく,鳥肌立っているから怖いと感じる,というのと同じで,首を振っていることから,気にいっている,と感じてしまう。
では,さらに突っ込んで,集団内の社会的役割では,正直シグナルはどう機能するのか。
社会学的には,チームのメンバーを,グループロール(攻撃者・主唱者・支援者・中立者)と任務としての役割であるタスクロール(授与者・探究者・中立者・先導者)という観点で分析している。
ソシオメーターを使った実験で,無意識の社会的シグナリングを分析することで,人がどんなグループロールとタスクロールを演じているかが,正確に読み取れ,参加者がグループロールやタスクロールを変えるたびに,無意識の社会的シグナリングも役割に応じて必ず変えている。
たとえば主唱者の役割を果たしているひとは,…(社会的役割の)打診のシグナリングをみせ,支援者の役割にある人は,…協調のシグナリングを見せ,中立者は,能動的傾聴のシグナルを発し…,攻撃者の役割を担ったときは,強い主導のシグナルを発した。
しかもグループロールとタスクロールは,リンクしていて,「どのタスクをしているかに応じて,特定のグループロールを演じていた」という。つまり,「無意識の社会的シグナリングのパターンを観察するだけで,その集団のダイナミックスについて」わかり,「各人のグループロールとタスクロールを正確に見きわめられる」ということだ。
しかし,単にそうした心理的葛藤やダイナミクスだけが見きわめられるだけなのか。本書では,新たなインテリジェンスのあり方を提案する。それは,集団のもつ声を見きわめる,ということに近い。つまり,
個人の知性が,脳内の多数の特化した中枢を神経回路を通して調整することから生まれるのとちょうど同じように,行動の選択が,多数の個人の心を社会的回路を通して調整することから生まれるという考え方だ。
という。そして,
人間の集団を,言語によって結びついた,個々の知性の集まりとして見ることから,太古のシグナリング・メカニズムによって結びついたネットワーク・インテリジェンスとして見ることへの移行は,必要不可欠だ。
と。ピラミッド型からネットワーク型のインテリジェンスへと移りつつある今の時代の中で考えれば,暗黙知と言われるものも,幅広く言えば,ここに加えてもいい。つまり,意識が判断する以上のことを,無意識,あるいは意識下では判断している,と。しかし,監訳者も指摘したように,この「声」が正しいとは限らない。衆愚という言葉があるように,日本が,第二次世界大戦へと突き進んでいったのは,国民自身の「夜郎自大」な「声」だったことも否めない。
その意味では,無意識にただ従うのではなく,無意識と意識の相互のフィードバックのあり方こそが,必要で,その意味で,暗黙知一辺倒ではだめなのと同じなのではないか。
参考文献;
アレックス(サンディ)・ペントランド『正直シグナル−非言語コミュニケーションの科学』(みすず書房) |
|
脳が教えること |
|
V・S・ラマチャンドラン『脳のなかの天使』を読む。
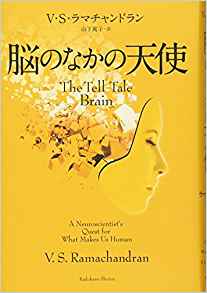
前作の『脳のなかの幽霊』に衝撃を受け,つづいて『脳のなかの幽霊、ふたたび』も読んで,三作目になる。今回の『脳のなかの天使』という訳題はどうも変だ。原題は『The
Tell-Tale
Brain』とある。まあ,脳が暴露することというか,脳の告げ口というか,脳が教えることという方が,原題のニュアンスに近いのではないか。
ラマチャンドランは,
進歩がいかにめざましくても,私たちは私たち自身に完全に正直でありつづけ,人間の脳について知るべきことのうち,小さな断片しかまだ発見できていないと認める必要がある。
といいつつ,本書の主題を,
まず,人間は心にユニークで特別な存在であり,「単なる」霊長類の種のひとつではない。
もうひとつ共通する主題は,全体にわたる進化的見地である。脳がどのように進化したかの理解なしに,脳が働く仕組みを理解するのは不可能である。
と述べている。ダーウィンのブルドックと称されたハクスリーとその論敵(神の)創造論者オーウェンの説を紹介しながら,ラマチャンドランは,こういう。
人間の脳は…実際にユニークであり,類人猿のそれとは大きなへだたりによって区別されるという主張において,オーウェンは正しかった。しかしこの見解は,人間の脳は,何百万年という年月によって少しずつ,神の介入なしに進化したというハクスリーやダーウィンの主張と完全に両立する。
そして,こう想定する。
そして今から15万年ほど前に,鍵となる脳構造と機能が爆発的に発達し,それらの幸運な組み合わせの結果として,私が論じている意味において人間を特別な存在としている精神的能力が生じた。私たちは誠信書房の相転移をくぐりぬけたのである。脳部位はすべてもとと同じままそこにあったが,それらがいっしょになって開始された新たな働きは,部分の総和をはるかにうわまわるものだった。
その基本姿勢は,上記からわかるように,仮説を立てるところだ。こう言っている。
科学は世界についての素朴な,偏見のない観察からはじまるという考えはよくあるまちがいで,実際はその反対である。未知の領域を探求するときはつねに,真かもしれない暗黙の仮説―あらかじめ考えた見解もしくは偏見―から出発する。イギリスの動物学者で科学哲学者のピーター・メダワーがかつて述べたように,私たちは「知識という牧草を食べる牛」ではない。発見の行為はすべて,決定的に重要に二つのステップをともなう。第一は,何が真であるかについての推量を明確に述べること,第二は,その推量を検証するために不可欠の実験を考案することである。
そして,ダーウィンを引用する。
誤って事実とされたことは,長くそのままになりがちなので,科学の進歩にとって極めて有害である。しかし誤った見解は,たとえなんらかの証拠によって支持されていようと,ほとんど害をなさない。誤りを立証するという有益なだれもが実行したがるからだ。
その意味で,本書は,神経科学者として接してきた様々な患者の症例をベースに大胆な仮説と大胆な実験に満ちている。例の,切断した手足が痛むという幻肢の話は,やはり衝撃的だし,それを鏡で脳を騙して,軽減させるという実践は,何度見ても,そのユニークな「実験の考案」には脱帽する。
さて,本書の肝は,「人間のユニークさ」にある気がする。それを失った症例から,ラマチャンドランは大胆に仮説を立てている。そのいくつかを紹介してみる。
自動車事故で頭部に重傷を負い,前部帯状回が損傷し,無動無言症と呼ばれる半昏睡状態になった患者は,歩くことも話すこともできない寝たきりの状態で,人を認識することもできなかった。驚くべきことに,
父親が隣の部屋から電話してくると,意識がはっきりして父を認識して話せる。しかし部屋へ戻ってくると父を認識できず,元の状態に戻る。ラマチャンドランは,こう推測する。
前部帯状回にいたる視角の経路のある段階だけが選択的に損傷され,聴覚の経路だけが健在だったとしたらどうか。(中略)ジェイソンの視覚運動システムは,それでもまだ,空間内の対象物を追い,自動的にそちらに目を向けることはできるが,彼は見ているものを認識できず,それに意味つげることもできない。ジェイソンは,父親と話しているときをのぞくと,意味のある豊かなメタ表象を形成する能力に欠けている。メタ表象は,わたしたち人間の生物種としてのユニークさのかなめであると同時に,個人としての独自性や自己感にとっても不可欠である。
そこからこう仮説を立てていく。
脳は,進化の歴史のごく早い時期に,外界の対象物の一次感覚表象を形成する能力を発達させた。この一次感覚表象が引き起こす反応の数は非常に限られている。たとえばラットの脳は,ネコの一次表象―具体的には,反射的に避けなくてはならない,やわらかな毛でおおわれた,うごいているものという表象―しかもてない。しかし人間の脳がさらに進化したとき,ある意味で古い脳に寄生する第二の脳(正確にいえば一セットの神経結合)が出現した。この第二の脳は,第一の脳からの情報を処理し,それを,言語野シンボル思考を含む幅広いレパートリーのより洗練された反応に使える,あつかいやすいチャンクにすることによって,メタ表象(表象の表象―高次の抽象)をつくりだす。
さらに,
メタ表象は私たちの価値観,信念,優先順位づけなどに欠くことのできない前提条件である。(中略)そうした高次の表象は,心のなかで,人間に独特のやり方でさまざまに操作することができる。それらは私たちの自己感と結びついて,私たちが外界…で意味を発見しそれに対する自分の立場を決定することを可能にしている。
その意味で上記症例の患者は「断片化された自己」しかもたない。そこから,ラマチャンドランはこう言う。
自己は自己自身が信じているような一枚岩的な存在ではない。(中略)自己は多数の構成要素からなっており,単一の自己という見解は幻想かもしれないと,神経科学は私たちに告げている。
しかし,別の言い方をすると,メタ化の中に自己の本質があり,キルケゴールが,
自己とはひとつの関係,その関係それ自身に関係する関係である。あるいはその関係においてその関係がそれ自身に関係するということ,そのことである。
という言葉につながる。単なるメタだけではなく,メタ関係のメタだから,そのリンクの一部でも切れれば,自己は一部消えて行く。
脳に,脳の構造に,その答えがある。
参考文献;
V・S・ラマチャンドラン『脳のなかの天使』(角川書店) |
|
集合知 |
|
西垣通『集合知とは何か−ネット時代の「知」のゆくえ』を読む。

人は,閉鎖システムであり,オートポエーシス理論の提唱者,フランシスコ・ヴァレラは,主体的個人の「自己(self/identity)」は五つのレベルの閉鎖システムで定義される,と言っている。
第一は,生命体の最小要素は細胞レベル。「生物的自己」
第二は,免疫レベル。身体的同一性を保つ。「身体的自己」
第三は,行動レベル。知覚器官をもとに行動するレベル。「認知的自己」
第四は,人間社会における個人のレベル。「社会的自己」
第五は,個人が組織化されたレベル。「集団的自己」
人間の想像力が,上位レベルへの創発の原動力だという。ここでは,作動することとそれを観察することとが同一に同時に行われている。つまり,自分のしていることを自分でモニタリングしている。そうすることで,自律性が保たれ,一貫性が保たれる。
生命体とは,機械と異なり,設計図なく自分で自己を創出していく自律的なシステムである。その作動の仕方は,外界に対して,自分の中から,その固有の歴史に依存して,対応していく。いわば,リソースは自分の中にある。それが生きるということだと言い換えてもいい。
西川アサキという人がコンピュータ・シミュレーションによって,面白い実験をした。閉鎖系システムと開放系システムで,集団がどう変化し,リーダーがどう出現するかをみている。
システムが他律的で,機械のように開かれていれば,適切な情報伝達と入出力操作によって,世界像を完璧に共通化し「客観化」していくことができる。しかし生命体のように閉じていれば,情報の意味を主観的に解釈するプロセスが入るので,どうしても差異や不透明さが残る。
結論を言うと,開放システムの場合は,リーダーが一人出現する場合もあるが,多数のリーダーが乱立したり,全くリーダーが出現しなかったりする。一方,閉鎖システムでは,必ずリーダーが安定して出現する。
この理由を,西垣さんは,こう整理している。
開放システムでは,各メンバーにとって世界があまりに「透明」に見えすぎ,瞬間的にせよ,そこには一元的で絶対的な価値観(世界観)が生まれる。わずかな周囲条件(外部環境)の変動に敏感に反応し,グローバルな状況が急変する。外部環境に他律的に依存するために,唯一のリーダー,複数のリーダー,リーダーシップなしの間を揺れ動く。
一方,閉鎖システムは,各メンバーにとって,世界は不透明であり,それぞれ保守的に自分なりの価値観を維持しようとする。その意味で安定している。グローバルな状況としては多元的で相対的な価値観が併存する。と同時に,一人のリーダー,つまり一元的価値も生成されやすい。そういう一元的な価値観のもとでこそ,集団における相対主義も存立しうる。
このシミュレーションが示唆するのは,こういうことだ。西垣さんは,オープンな社会が必ずしも望ましくないことを示している,と言う。つまり,
人間が自律性を失って開放システムに近づくと,社会がいわば透明になりすぎ,外部環境の変動にともなって,「絶対的リーダーへの一極集中/多極化/完全な無秩序」といった諸状態の間をぐるぐる彷徨することになりやすい。
これに対して人間本来の閉鎖性が保たれていれば,それぞれが自律的で唯一の尺度は存在しないにもかかわらず,社会のなかに一種の慣性力が働いて,安定したリーダーが生まれる。
こういったリーダーに対するほどほどの従属関係がある時の方が,世界の崩壊は起きにくい。逆に,メンバーにできるだけ透明な情報伝達と一元的な価値観を強制する独裁社会の方が,多様性に基づく値がまれず,世界は不安定になる。
実はこのリーダーシップとメンバーの従属関係に基づく階層構造は,ポラニーの暗黙知の構造と深くつながる。ポラニーの暗黙知の構造は,
「諸細目(particulars)」と「包括的存在(comprehensive
entity)」との二項関係からなるダイナミックスである。前者は近接項,後者は遠隔項にそれぞれ対応する。
たとえば,顔を認識する例で考えると,
まず,相手の眼,鼻,口,額,頬,顎などの「諸細目(近接項)」にちらっと目を向けるが,いつまでも続くことはない。われわれの注意はすぐに諸細目から離れ,顔全体という「包括的存在(遠隔項)」に移行する。といっても,諸細目は完全に忘れ去られるわけではない。相手の顔を認知識別しているとき,われわれは相手の眼や鼻などの諸細目を無意識に,「顔全体の姿」のなかにしっかりと感知しているのだ。それらは潜在化し,明示的に語られないものの,顔全体の「意味」を構成しているのである。
つまり,下位レベルの諸知覚器官による認知観察行動は自律的におこなわれ,脳はそれらを完全に統御しているわけではない。しかしそれなしでは「顔という全体」を認知できない。
こういうダイナミックスは,リーダーとメンバーも同じなのではないか。
リーダーは集団の代表であり,リーダーの言動は事実上社会組織の言動とみなされる。それは,暗黙のうちに集団個々の構成メンバーの言動によって支えられている。逆にいえば,個々のメンバーの主観を反映した対話や行動をもとに上位レベルのリーダーの言動が生成され,逆にリーダーレベルからみれば,個々のメンバーの言動は無意識のレベルにある。
いわば,個々のメンバーの「諸細目」とリーダーという「包括的存在」のセットで暗黙知を形成している。諸細目の無意識(メンバーレベルでは無意識ではない)とのダイナミックなやり取り抜きでは,組織の活力は生まれない,という当たり前のことを言っているのかもしれない。
参考文献;
西垣通『集合知とは何か−ネット時代の「知」のゆくえ』(中公新書)
西川アサキ『魂と体,脳―計算機とドゥルーズで考える心身問題』(講談社) |
|
補助線 |
|
茂木健一郎『思考の補助線』を読む。
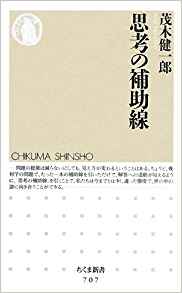
補助線というと,幾何の問題で一本補助線を引くことで,問題自体は変わらないのに,こちらのパースペクティブが変わり,解き方が見えてくることがある。どこに,何を引くかが,発想の肝になる。
しかし世の中の問題は,幾何の問題のように,全体像が見えているわけでもないし,補助線自体が物理的に見えるカタチで引けるものでもない。しかし,補助線を,足す線とばかりではなく,引く線であったり,リンクをつなげる,次元を畳む,次元を橋渡しすると考えていくと,補助線は,思考のトンネルに開ける選択肢に見える。選択肢が広いほど,発想が広がるのだから。
茂木さんが,生涯の目標となったクオリア(感覚質)との出会いを,こう書いている。
研究所からの帰り,夜。私は電車に乗っていた。無意識のうちにガタンゴトンという音を聴いていた。突然,その音が,周波数で解析しても,スペクトラムを眺めても決して解明しきれぬ生々しい「質感」として私の意識に到達していることに気がついた。私は感動と畏怖で青ざめた。車両と車両の連結部分の空気が一変した。その瞬間,わたしは,芸術を愛する経験的自然科学者から,現象学的経験をも視野に含めた「自然哲学者」へと変貌したのである。
そして,いま,
「クオリア」という補助線を精神と物質の間に引きたい。それで問題が解けるかどうかはわからない。しかし,明らかに不思議の質が変わる。
面白いことは,「クオリア」という補助線が,「地」から「図」になった瞬間,見える世界が変わり,パースペクティブが変質した。そのことによって,実はこちらも変貌していく。その精神のダイナミズムが面白い。それは,我々にも,日常的にある。
茂木さんの問題意識は,こんなところにも見える。
ニュートン力学から最近の超ひも理論に至る数学的形式に基づく自然科学の厳密さと,それを生み出す人間の思考の「あいまい」さ,
数学的心理や完璧な科学とそれを生み出す,ノイズだらけの脳のダイナミクス,
視野の中に複数のものが存在している状態を,並列的に「私」が見るという統合された並列性と,それを生み出す脳の大脳皮質の神経細胞の活動,
永遠を考え,宇宙を考え,孫嗄声しない正七面体を考えることと,いま,ここにしばりつけられた意識,
等々。この振幅にあるのは,この振幅を見極める補助線を引きたいという,茂木健一郎という学者が,サブカルチャー化し断片化した知を丸ごと引き受けたいという志向に他ならない。茂木さんは言う。
人としてこの世に生を受けた以上,単に世界の部分だけを知るだけでなく,全体を,そして普遍を志向したいという私たちひとりひとりの切ない思いについて考えたいのである。
そして,
どうあがいても有限の存在でしかない人生という泥沼からときには大輪の蓮の花が咲くことがあるのは,私たちの感情が「どうせできないとわかっているのに」悪あがきするからなのである。(中略)傍から見れば滑稽な大言壮語にすぎなくても,「今論文を書いている。大論文を書いている」と言い続けなければならない。
一見関係のないものの間に補助線を引くことで,世界の見え方を変える。世界の見え方を変えることで,見ているこちらも変わる。その変わった目線で見えるパースペクティブは,また変わるだろう。
ロジャー・ペンローズは,「創造することは思い出すことに似ている」といった。なぜなら,脳は何もないところから何かを生み出すのではなく,脳内のアーカイヴに依存している。自分のもっている者を組み替える。リンクを変える。それは,所蔵されている「知」を,別のパースペクティブで見直すことと言ってもいい。
川喜多二郎は,「本来ばらばらで異質なものを意味あるようにむすびつけ秩序付ける」ことを創造と呼んだ。だから補助線が生きる。見え方が変わることで,今まで当たり前に見えていたものが違って見える。違って見えることで,今まで全くリンクしなかった脳内のネットワークとつながる。そこで,異質な解が開けてくる。
参考文献;
茂木健一郎『思考の補助線』(ちくま新書) |
|
直観 |
|
デヴィッド・G・マイヤーズ『直観を科学する』を読む。
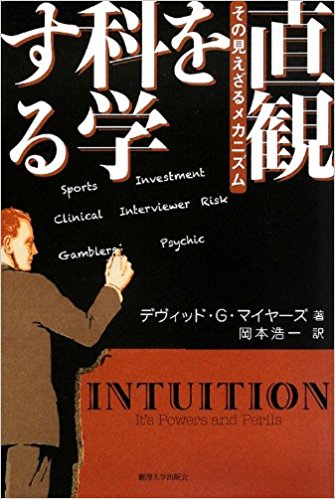
直観というと,パターンに認識で,将棋の羽生善治を思い出すが,通常直観とはあまりいい意味では使われないらしい。
例えば,マイヤーズは,こういう例を出す。
一枚の紙を100回折ると,その厚さはどのくらいになるか?
多くの直観は間違う。マイヤーズはこういう。
我々の直観は,たいてい間違いを犯す。紙の厚さが0.1ミリだとすると,折るたびに前の厚さの倍になって,100回折り畳んだ後の厚さは地球と太陽との間の距離の800兆倍になるだろう。
しかし,我々は直観で判断していることが多い。たとえば,
ヘッドホンをして,片方の耳で朗読を聞き,朗読のテキストと照合しながら,もう片方から音楽が聞こえている。意識して聞いているわけではないが,その音楽の間に,以前聞いたことのある音楽を挿入しておく。で,どちらが好きかを問われると,聞いたことのある方と,答えるらしい。意識的にはわからないことを好き嫌いの選考では,明らかにできる。
物体写真や顔写真を200ミリ秒見ただけで,ひとは直ちに良し悪しを判断する。対人関係では,最初の10秒で直観的に判断してしまう。
ザイアンスの法則と言われるのは,単純接触効果だ。よく知っているものほど好きになる。見慣れたものに近づき,見慣れないものを警戒する。
他者を観察するとき,素早くわれわれは何らかの判断を下す。そして後になってそのとっさの感情に理屈づけする。われわれはものを感じている時,なぜそう感じるかがわかっているわけではない。その感情の理由を探ると,もっともらしい間違った要因に目を向けることになる。意識しないでやった理由を,左脳は間違った解釈をする,という。
では,直観というのは記憶と同じなのか。記憶には,潜在記憶(手続き型記憶)と顕在記憶(陳述型記憶)という分け方もできるし,もう少し細かく,手続き記憶,意味記憶,エピソード記憶とわけることができる。意識化しないで,働くという面で言えば,手続き記憶とエピソード記憶が,直観,あるいは勘に機能しているということができる。
パターン認識を使う,将棋のような何十通りの手筋を思い描く場合とは違い,通常我々の直観は,あてずっぽうか思い込みのことが多い。盤面という限られた世界ではなく,複雑な人間関係や心理については,手筋は無数なのだ。
たとえば,自分の将来について,直観する場合,失敗する。
感情の持続時間を予測する場合は,失敗する。失恋した後の,選挙に敗れた後の,試合に勝った後の,侮辱された後の,感情の持続時間を間違って予測している,という。ネガティブな出来事に注目すれば,それ以外のあらゆることを軽視してしまい,みじめさはずっと続くと予測する。しかし,自分が注目しているものは,自分が思っているほど重要ではない。また自分の将来の行動についても,直観は間違える。自分の将来行動の予測よりは,他人の行動予測の方が当たる,という。
人の行動を解釈するとき,その置かれている状況を過小評価し,その人の内的要因を過大評価する。しかし自分の行動を評価するときは,これと逆に考える。自分が不機嫌なのはその日が不愉快だからで,他人が不機嫌なのは,その人が不愉快な気質だからだ。
関連ないことにパターン化する。たとえば,子供の無い夫婦は養子をもらうと妊娠する可能性が高くなる。目立つところに注目するために,パターンとして意識化されやすくなる。
しかし,直観のつけが自分にくるだけなら,別にたいしたことではない。そういう直観が試されるのは,象徴的には,心理臨床場面だ。
マイヤーズによると,セラピストは,自分の直観に味方する,という。しかし研究者たちは,直観と統計的予測とが競合した場合(たとえば面接者による生徒の学力予測と,成績や適性得点に基づいた客観評価とが食い違うような場合),たいてい客観的評価によって決定する,という。統計的予測が必ずしも正確ではないにもかかわらず。
臨床心理的直観は,過った関連付けや後知恵のバイアス,信念の根強さ,自己成就的診断などの弱みが現れている,とマイヤーズはいう。
心理臨床のクライアントの行動がそのセラピストの理論としばしば一致している,と言われる。
あなたの気持ちがそうならば
あなたの求めるものがそうなる。
自分の望むものをあなたは見つけるだろう。
自分の見たがっている関連性を見ようとし,それを後知恵で補強する。自分の理論や仮説を見てしまう。自分が正しいと思う質問をする等々。
他山の石だ。
たまたまをそもそもとしているのではないか,そういうチェックは欠かせない。
参考文献;
デヴィッド・G・マイヤーズ『直観を科学する−その見えざるメカニズム』(麗澤大学出版会) |
|
元勲 |
|
一坂太郎『山形有朋の「奇兵隊戦記」』を読む。

元勲というのは,
明治維新を実現し,明治政府の樹立・安定に寄与した一群のカリスマ的な人物たちが「元勲」と呼ばれた,
のだそうだ。しかし,薩摩で言えば,西郷隆盛は城山で自刃し,大久保利通は紀尾井坂で暗殺され,長州で言えば,大村益次郎は暗殺され,木戸孝允は病死し,前原一誠は萩の乱で死に,広沢真臣は暗殺された。
山形有朋は,最終的に生き残り,陸軍を牛耳り,長州閥のトップとして,明治維新から第二次大戦の敗戦へと導くに至った元凶だと思っていたし,いまも変わらない。しかも,成り上がりそのままに豪邸を造り,私財を蓄え,あまつさえ大和屋和助事件では,金にまみれて危うく失脚するところを,西郷隆盛に救われた,まあそういった,金と名誉と権力にまみれた,いわば藩閥政府の首魁(たまたま生きのこったから)として,元勲の象徴的存在として君臨した。
その山形の,奇兵隊と,戊辰の国内線の自伝的戦記(『懐旧旧事』『越の山嵐』)を元にした,狂介時代の事績を振り返る。狂介は,正確には,苗字も許されない,足軽の下の中間の出身である。
世に出る機会の第一は,松下村塾の入江九一らの推挙で京都へ藩命で出て,久坂玄瑞らに出会い,梅田雲浜にあい,時勢を肌で感じたことだ。これをきっかけに,松下村塾に入門する。わずか一か月しか松蔭と接する機会はなかったが,松蔭は,「気」があると,狂介の人材を認めた。以後60年,狂介は,「門下生」と言ってはばからず,自身を松蔭の後継者として信じて疑わなかった。
松蔭の言う「草莽」が,狂介を含む,軽輩,軽率の人材を想定した,「草莽崛起」であることを考えれば,後述するように,創設者の高杉晋作ではなく,軍監として実権を握った狂介に,本当の意味の「奇兵」の「奇兵」たるゆえんがわかっていたと考えることができる。
高杉晋作は,藩の正規軍の補佐として,奇兵隊を提案し,結成する。高杉の構想では,奇兵隊は,有志の集まりであり,藩士,陪臣,軽率を選ばず,もっぱら力量を重視し,堅固の隊にしたいと上申し,その後,百姓,商人も応募してきたため,認めている。最終的に,奇兵隊士823人,うち559人の出身がはっきりしており,士48.7%,農42.4%,町4.5%,社僧4.5%の構成になる。この後,遊撃隊,八幡隊,御楯隊,膺懲隊,集義隊,南園隊といった奇兵隊的なものが400ほど結成される。
大事なのは,高杉に平等意識があったのではない,ということだ。攘夷決行に当たり,外国襲撃に備える兵力不足を補うための動員に過ぎない。したがって,身分差は変わらず,袖章の素材一つとっても,士分は絹,足軽以下は晒と決められていた。が,応募する側は,栄達の機会と期待し,農家の次三男をはじめとして,藩内から野心に燃えて入隊希望が殺到した。
四国連合艦隊の襲来で,一敗地にまみれた経験が,奇兵隊の性格を変えていく。第一次長州征伐で藩論が変わり,実験を握った「俗論派」はひたすら恭順し,奇兵隊をはじめとする諸隊に解散命令を出す。しかし奇兵隊他主力はそれに応じず,狂介は,あくまで戦いによる政権交代を主張する。この間隊の軍規を独自に定め,藩命に逆らう非合法の諸隊は,山口に駐屯,諸隊幹部による独自の意思決定システムを築きあげていく。
しかし結果として藩内内戦の導火線を引いたのは,高杉晋作で,狂介ら諸隊指導部の逡巡や躊躇をしり目に,わずか80名を率いて,決起する。この辺りが,高杉の決断力のさえているところで,結局諸隊は引きずられるようにして,俗論派との決戦に踏み切り,絵堂急襲で口火を切り,大田で俗論派を破る。この大田・絵堂の闘いで勝利を導いた狂介には,この戦いが「維新の元素」を創ったとの自負があった,という。
一方高杉晋作は,あくまで正義派として奇兵隊他諸隊を政権奪取の軍事力として利用はしたが,諸隊の下級武士や庶民を新政権に加える気はない。しかし諸隊は,藩政府を監視したり,威嚇する勢力として,存在感を増す。高杉は,上士で構成する干城隊を結成して,諸隊の上におき,「諸隊の指揮号令も干城隊総督,政府より請け,…諸隊の総管を呼び申し合わす」ようにするのだという。しかし高杉の想定以上に,下級武士や民衆の勢いが強く,統括できなかった。そのエネルギーの中心に,狂介がいたとみることができる。
傑作は,萩へ進軍するにあたって,世子を押し立ててくる政府軍に,「洞春公(毛利元就)の神霊」と書いた紙切れ一枚で対抗しようとする狂介の発想だ。この発想は,既得権益や既得制度に胡坐をかく上士にはない,松蔭の期待した「草莽」の発想に他ならない。ここは,狂介の面目躍如といっていい。
こうした背景から,狂介は,戊辰前後,武力討伐へ変じる辺り,逡巡する藩上層部に反し,九州制圧,近畿制圧といった倒幕を堂々と藩に対して主張している。諸隊を牛耳る実力者として,その存在が大きくなっているのがわかる。藩首脳が逡巡し,決断しないのをみると,狂介は,諸隊の集団数百人規模での脱藩を計画する。
著者は言う。
山形は慎重な性格だったが,時に大胆な決断をし行動することがあった。この点高杉に通ずるものがある。自分たちの意見が通らないからといって,一度に数百人の兵士が脱藩するなど,史上類を見ないであろう。
こうして,戊辰戦役を戦い抜いた諸隊は,山口に帰還するが,山形は,軍功により永世禄600石を得,奇兵隊を離れ,海外巡遊の旅に出る。しかしその間,論功行賞も十分なされないまま,身分を重視した東京常備軍兵への選抜6-名以外は,「土民は農に帰り,商夫は商を専らに」と,解散させられる。
それを不満とする奇兵隊,鋭武隊,振武隊,遊撃隊,健武隊,整武隊などの諸隊1200名が山口を脱走,最終的には2000名に膨れ上がったが,木戸指揮下の軍に撃破され,最終的に,百名を超える隊士が処刑され,決着をつけられる。
結果的に,高杉晋作が,そして木戸孝允が目途したように,戦力として利用されただけで,奇兵隊と諸隊は抹殺されたといっていい。その血の上に,山形の栄達がある。
しかし,考えようによれば,西郷,高杉,大久保,木戸と40代で死んだのに比し,85歳の往生を遂げた山形の,生き残りがちといっていい。
参考文献;
一坂太郎『山形有朋の「奇兵隊戦記」』(歴史新書y) |
|
贔屓目 |
|
坂野潤治『西郷隆盛と明治維新』を詠む。

なぜ反乱したか,著者はこう言う。
西郷には内乱にまで訴えて実現しなければならないような『目的』は,もはやのこされていなかった。幕府を倒し,大名を倒し,近代的な中央集権国家を樹立するという西郷の夢は,すべて果たされてしまったのである。西南戦争は,西郷にとっては,大義なき内戦だったのである。
そして,桐野利秋ら急進派の暴発に引きずられたのだとする。だとすれば,長州の前原一誠,佐賀の江藤新平と同列の,いわゆる不平士族の乱の中に埋没していく。それが,西郷の虚像を崩し,「実像を再現する」という本書の趣旨からすれば,竜頭蛇尾に終わっていると言わざるを得ない。
更に最大の「征韓論」については,毛利俊彦『明治6年政変の研究』で論証された通り,「征韓」ではなく,「使節派遣」という傍証に,江華島事件に対する対応を,
是迄の友誼上実に天理に於いて恥ずべきの所為に御座候
何分にも道を尽くさず,只弱を慢り強を恐れ候神庭り起こり候ものと察せられ候
の手紙を引くというのでは,少し説得力に欠ける。当事者でない時は,岡目八目,正論を吐くことができる。人とはそういうものだ。
同時に,多くの根拠に,元薩摩藩士の勝田孫弥『西郷隆盛伝』に依拠していることも,いささか気になる。所詮伝記ではないか。上記江華島事件についての隆盛の手紙を載せたことについて,こう持ち上げる。
1895年といえば,日清戦争での日本の勝利はすでに決まっていた。そのような時,この西郷伝の著者は,西郷が「征韓」論者ではなかったことを強調しているのである。
さらに,勝と西郷の最初の会談について,
この会談の重要性を最初に指摘したのは,明治27(1894)年刊の勝田の『西郷隆盛伝』である。
として,そこに同席した吉井友美と西郷の大久保への書簡が収録されていて,最近まで両書簡の関係が明らかでなかった。もっと早くこの書に注目すべきであった,というのである。それは,こうした偉人伝をないがしろにした(?)反省と見れば,妥当なのだが。ただし,論証抜きに,これに依拠して,
西郷の復権と大久保の転換こそが,「維新の大業」の本格的な始動であるとする勝田孫弥の指摘は,的を射たものと思われる。
とするのは,いかがなものであろうか。
それでなくとも,随所に,新書とは言え,歴史家の物とは見えない筆の走りが散見される。たとえば,
1859年初めから丸5年間流刑に処した島津久光には嫌悪の情しか湧いてこないし,その久光に忠勤を励んだ5年間の大久保利通にも,筆者は好感を持てない。
西郷流刑の張本人である島津久光の幕政改革に興奮している勝海舟問いあう人物も,あまり好きにはなれない。
これ以後2年に及ぶ,徳之島,沖永良部島への西郷の流刑は,藩主の実父島津久光の無知と傲慢から出たもので,…とても許せる処置ではない。
等々,まあ私見を入れてはいけないとは言わぬが,あんまりである。それは,別のところにも現れる。たとえば,
ペリーの2度の来航に際して,「尊王攘夷」の本家とも言うべき水戸藩の態度が,攘夷の先送り,いわゆる「ぶらかし論」に転換したのである。
というのはいい,しかし,横井小楠も勝海舟も西郷も棚上げ論である,とまとめるのは,丸めすぎにもほどがある。少なくとも,西郷は知らず,小楠は,
応接の最下等は,彼の威権に屈して和議を唱えるもの。これは話にならない。結局幕府はこれを取った。次策は,理非を分かたず一切異国を拒否して戦争をしようとするもの。これが攘夷派の主張だ。長州が通告なく通過する艦船を砲撃したのはこれだ。これは天地自然の道理を知らないから,長州がそうなったように,必ず破れる。第三策は,しばらく屈して和し,士気を張ってから戦おうというもの。水戸派の主張だ。これは彼我の国情をよく知っているようだが,実は天下の大義に暗い。一旦和してしまえば,天下の人心怠惰にながれ,士気がふるいたつことなど覚束ない。最上の策は,必戦の覚悟を固め,国を挙げて材傑の人を集め政体を改革することである。天下の人心に大義のあることを知らせ,士気を一新することである。我は戦闘必死を旨とし,天地の大義を奉じて彼に応接する道こそが,義にかなうはずだ。
ということを言っている。そして,こういう詩もある。
守るに非ざれば戦う能わず
戦うに非ざれば和する能わず
和は豈に不利の事ならんや
戦守の如何なるかを顧みよ
我が武已に虜を呑めば
和は以て邦家を安んず
看(み)よ看よ今日の和
保たざるは明らかに河の如し
事実は細部に真実がある。細部をおろそかにするのは,真実を求める意思がないことの証明ではないか。まして,小楠,海舟を貶めることは,相対的に,結果として隆盛を貶めている。贔屓の引き倒しとはこのことである。
参考文献;
坂野潤治『西郷隆盛と明治維新』(講談社現代新書)
野口宗親『横井小楠漢詩文全釈』(熊本出版文化会館)
松浦玲編『佐久間象山・横井小楠』(中央公論社) |
|
要不要 |
|
山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』を読む。
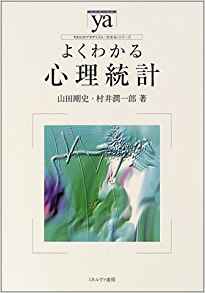
「心理統計」とは表現として矛盾している。心理は統計で測れるほどデジタルではない。では何の役に立つのか。
これについて,『よくわかる心理統計』(山田剛史・村井潤一郎)では,体重計を計るときに体重計に乗るように,心にも重さがあるとし,こう答えている。
たとえば,付き合っているカップルの片方が,「彼の気持ちが重荷になってきた」という場合,心にある種の重さを想定していることになるでしょう。それでは,「彼氏の恋愛感情の大きさ」はどのように測ったらよいでしょうか。(中略)心理学では,このような場合,たとえば,「心理尺度」というものを使ったりします。(中略)学術的には,ルビンという人が,愛情尺度を開発しているのですが,ここではその一部を紹介してみましょう。
これは明らかに論理的な飛躍がある。つまり立てた設問(「心理統計で数字を使う」こと,つまり心理統計の必要性について)の答えをはぐらかしている。もっとはっきり言うと,これでは論理が通らない。
第一に,心の重荷とは,比喩なのであって,それを実際の重さに置き換えて,答えている。まずここで第一のすり替えをしている。比喩で言っているからと言って,心を重さで測れる根拠にはならない。
第二に,第一での仮定(心の重さをはかる)を前提に,心の重さをはかる例として,恋愛尺度が測れる,としている。しかし,心の重さが測れるという前提が成り立たなければ,この仮定はそもそも成り立たない。
第三に,その心理尺度というものを,ルビン(ルビンの壺のゲシュタルト心理学者のことか?説明がないのでわからない)という人が,「愛情尺度」というものを開発している,という。外国の有名な学者が「尺度化」している,ということで,心理尺度をオーソライズしようとしているのだろうか。外国の学者が開発したからと言って,心理尺度が可能だということの証明にはならない。
推測するに,たぶんこの論理の組み立ては,執筆者の中では,逆立ちしている。まずルビンの「愛情尺度」がある,という認識から出発して,それがあるのだから,心理尺度があって当然で,その例として,心の重さを出した。これは,心理統計があることの説明にもなっていないし,その必要性を説明する論理も展開できていない。こんな非論理的な説明しかしないで,統計が利用できるのか。まずもって疑問である。
更に,では「愛情尺度」というのはどこまで有効なのか。結論から言うと,まず答えありきとしか思えない。「愛情を尺度化できる」という仮説(「仮説を仮の説明概念」としておく)を前提に,それを尺度として振り分けたはずなのに,その振り分けたものから結論を出して,「だから尺度化できる」と,仮説を証明しようとしている。つまりは自己撞着というか,論点先取りというか,話にならない。これを例にして,心理統計が必要という根拠にされたのではたまったものではない。
更に,この尺度設定の疑問は,第一に設問だ。この設問が,本当に「愛情(恋愛感情)尺度」をはかるのに妥当な項目なのかどうかが,説明されていて(証明されていて),その上で,その段階設定が妥当かどうかが検討されなくてはならない。その検討はスルーされている。そもそも説明が必要という問題意識すらない。
そもそもデジタル化に意味があるか,という回答としては,この「恋愛尺度」が例示されるにいたった自分の論理の展開を忘れてしまっているのではないか。こうやって尺度化すれば,心理も数値化できるという例のはずだ。それが心理の説明として有効という説明がなされないまま,「数値化」できたことでよしとしている。それは変だ。数値化するように振り分けたのだから,数値になるのは当たり前,問題はその数値が有効かどうか,妥当かどうかか問われている。それがなされなければ答えになっていない。
しかし,どうやら,「ルビンが開発した」というオーソライズで,証明が終わったつもりになっているらしい。
更におかしいのは,この5段階(9段階でも同じだが)に振り分けていくのは,回答者に振り分けさせているのであって,これが20段階でも100段階でも,本来グラデーションになっているはずの心理を,無理やりどこかに振り分けなくてはならないという無理については,一顧だにしていない。だから,繰り返すが,数値になるように振り分けているから,数値化の可否が問題なのではなく,そうやって振り分けることが,心理を正確に反映しているかどうかが検討されるべきなのだ。論点先取りとは,このことを言っている。
心理は尺度化できるという前提に立たなければ,こういうものをつくらない。だから,「愛情尺度」があることは,心理統計が必要だということの説明にも証明にもなっていない(ことに気づいていない?)。
たとえば,「心理統計」としての愛情尺度が使えるという「帰無仮説」を立て,対立仮説として「愛情尺度」は心理統計として使えない,を立てたとする。この仮説検定をするには,一定の検定統計量が必要になる。その母集団として,日本での婚姻組数はここ30年では平均して,年間70万組程度での推移をしている。そのうち標本として,海外なら旅行先ランキング別に,ハワイ,オーストラリア,イタリア,グアム,国内なら北海道,沖縄,京都,東京,大分,と行き先別に母集団を抽出してもいいし,ランキング1〜5位を,抽出してもいい。で,有意水準を,仮に5%としておく。ただこの数値には意味がなく,「根拠がはっきりしているわけではありません。いってみれば,慣習として利用されている」(『ウソを見破る統計学』)のであって,「偶然といえる確率がどれだけ小さいか」を示している。
ここまでやってみて,初めて,「心理尺度」の例としての,「愛情尺度」の有効性が一応言えるのではないか。過去の実績があるというのは,ここでは取らない。なぜなら,この紹介の論法では,「愛情尺度」があるということを前提に(それに疑いを向けることをしない),心理尺度の有効性を説明していたのだから。
必ずしも,統計が無効だと言いたいのではない。そもそも統計そのものが,問題を内包している。
統計はすべて人々の選択と妥協の産物であり,そうしたことによって形づくられ,制約され,ゆがめられている」(『統計という名のウソ』)。その理由として,数字として抜けるものがあるからだ,とジョエル・ベストは,以下のことを挙げている。
①数字に欠けているものがある。有名なコロンバイン乱射事件で,隠れていたのは,アメリカでは過去20年約80,000人の子供が銃の犠牲になっている。
②計算不可能のものがある。全米でいなくなる子どもは年間200万人に上る。しかしそこにいなくなっている期間も理由も隠されている。
③故意に数えられないものがある。アメリカでは憲法との兼ね合いから,宗教の設問がない。
④忘れられたものがある。かつては調べていたが,いまは関心のない,たとえば麻疹の死者。
⑤伝説的な数字で社会的に流布している。都市伝説のようなものだ。夫に先立たれる女性の平均年齢は56歳。
そして,こう付け加えている。
統計を用いるとき人々は,その数字に意味があると考えている―少なくとも,受け手にそう考えてほしいと思っている。つまり,最低限だれかが実際に何かを数えた,しかも,意味をなす仕方で数えたということだ。統計情報は,複雑な世界を理解する術,混乱のただなかにパターンを認識する術として,私たちが手にしているとりわけ優れたものの一つである。
だから,使い方だ,といっているのだ(何だか当たり前だが)。統計も,統計学も,使い方次第で,有効になる,そういう説明が必要で,あたかも万能の如く言うのは論外としても,統計が,一定程度数値を丸めたり,カットしたりしなければ,統計にならないということを自覚したうえで,どう使うかが問われる。
その例として,ここでは,直観と勘でやっている世界に,補助データとして使えるのではないか,という問題提起をして締めくくりとしておく。
人の直観は,ある意味パターン認識なので,将棋の羽生善治の手筋を読むパターンは,いわば直観と言われる。盤面はいざ知らず,人に関わることは,人事面接でも心理面接でも,その勘,専門的直観は,少々危うい。限定された盤面で読み切れる手筋の数とは圧倒的に差があるのだから。
マイヤーズは指摘している。「心と頭脳が格闘する中で,臨床医は時には,自らの経験のささやきに耳を傾け自分の直観のほうに味方する」と。しかし,研究者は,そうしない。「直観と統計的予測が競合した場合(たとえば面接者による生徒の学力予測と成績や適性得点に基づいた客観評価がくいちがう場合),驚くべきことに,たいてい客観的評価によって決定がなされる」という。「統計的予測は必ずしも正確ではない」にもかかわらず(『直観を科学する』)。
さらに,マイヤーズは書く。
いったん臨床医がありもしない問題に関する解釈を憶測でつくると,その解釈が一人歩きをはじめる。スタンフォード大学のリー・ロスと同僚たちは信念のもつ根強さに関する初期の実験において,被験者たちにある実際の患者の病歴を読ませた。それから一部の被験者に,自殺のような特異な出来事が後に起こったと伝え,病歴からその説明をしてほしいと求めた。最後に被験者たちは,その患者のその後のことはわかっていないと本当のことを教えられた。この類の出来事は起こりがちだと評価している,とその説明した出来事は本当にありそうに思えてくるのである。
いったん手にした直観を説明するために,臨床心理的直観は,過った関連付けや後知恵のバイアス,信念の根強さ,自己成就的診断などの弱みが現れている。しばしば補強する情報を探して,自分の勘を試す。ある人が外向的かどうかに疑問をもつと,外向性の質問をする。「パーティを盛り上げたかったらどうするか」等々,自分の見たがっている関連性を見ようとし,それを後知恵で補強する。自分の理論や仮説を見てしまう。自分が正しいと思う質問をする等々。
エリザベス・F・ロフタフが,セラピストによって促された子供の親による性的虐待記憶が,子供の想像によってつくられた偽記憶であることを暴いたように(『抑圧された記憶の神話』),セラピストを反映する。心理療法のクライアントがしばしばセラピストの理論に一致してしまう。
あなたの気持ちがそうならば
あなたの求めるものがそうなる。
自分の望むものをあなたは見つけるだろう。
それを回避するには,過小評価されている統計的予測を利用することだ,とマイヤーは言う。大学入学事務局が,合格者の統計的予測を判断材料にするように。ここに,心理統計の必要性がある。とすれば,まさに,「心理」統計でなくてはならないはずだ。ここで必要なのは,傾向値の閾値が示せれば,少なくとも,誤った勘を是正し,再確認させるきっかけにはなるはずだ。
だから,その限界を知っていれば,心理統計は,有効なのだ,と考える。
参考文献
山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』(ミネルヴァ書房 2004)
ダレル・ハフ『統計でウソをつく法』(高木秀玄訳 講談社ブルーバックス 1968)
ジョエル・ベスト『統計という名のウソ』(林大訳 白楊社 2007)
神永正博『ウソを見破る統計学』(講談社ブルーバックス 2012)
金子郁容『〈不確実性と情報〉入門』(岩波書店 1990)
デヴッド・G・マイヤーズ『直観を科学する』(岡本浩一 麗澤大学出版会 2012) |
|
後姿 |
|
加藤典洋・高橋源一郎『吉本隆明がぼくたちに遺したもの』を読む。
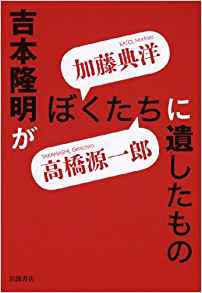
考えてみれば,十代から,ずっと,吉本隆明の著作に,つかず離れず,付き合ってきた。珍しくほとんどの出版物を読んだ作家の一人だが,とても僕のような非才には理解はでき兼ねるが,「世の中の正しい」ということに,いつも違う視点から異を唱えていた印象がある。
記憶で書くので間違っているかもしれないが,「吉本がいるなら日本は信じられる」といったような趣旨の遺書を書いて自殺した学生がいたと記憶している。
ぼくもまた,いつも,「吉本ならどう考えるのだろう」と,高橋源一郎がいっているような,「吉本さんは,ものを考えるときの『原器』のようなものだった」というところがある。その理由が,僕の中で見えた気がした。
加藤氏が言っている。
「正しいこと」って本当に不思議だよね。これが一人で言われるときはいい。特に大勢に対して言われるときにはもっといい。でも,たとえことばとしては同じでも,これが大勢として言われるときには何かが変わっている。
吉本の原点は,その違和感のようだ。そして,吉本にとっては,
「どちらもただしい」という解こそが,唯一,正しさへの抵抗になる。
その原点は敗戦にある。
自分はこの戦争は正しいと思った。そしてどこまでも遂行すべきだとその考えに穴がないかどうかは何度も検討した。それでも誤った。ではどこが間違いだったのか,と考える。他の人が,たとえ自分は戦争は正しいと思ったのだったとしても,それは十分に考えなかったからだ,ついうかうかと世の中の考え方に流されたからだ,というように簡単に反省して,戦後の民主主義につくところ,吉本さんは,自分は十分に考えた,それなのに間違った,なぜだろう,と立ちどまるのです。
その視点は,簡単に立ち直る戦後文学の担い手への違和感であり,そこから転向論があり,非転向への批判があり,さらに思想のあり方そのものへと踏み込んでいく。
その思想が自分の生きている現実から生まれたものでない場合には,思想は,それをもって生きる現実とのすり合わせのなかからその意味と価値を創りだす。
この課題は,いまも営々と移入された思想を信奉する者のあとを絶たない,というか,ほとんど自分で考えず翻訳するだけで思想家になったつもりのものだらけのわが国では,今も原則として生きている。そして,そんなすりあわせすらほとんどされない現状をみるとき,まだその意味は消えていない。
では吉本のしたことは何か。加藤氏はいう。
(3.11の原発事故の後)日本の多くの思想的な営為とことばが,日本と世界だとか,日本の未来だとか,自分と日本だとか,極めて中途半端な射程のうちに,無自覚に企てられ,発せられているものとして映ってきます。そういうなかで,何人か,いまの日本の場所から,直接,世界について考えている思想家のいることも見えてきます。そういうふうに,世の中がみえてくるようになってはじめてわかったことのひとつが,こうした思想的な企て,思想の源流に,日本語で書く思想家として,吉本隆明がいるということだったのです。
そして,こう続ける。
ここで日本という場所にいて世界のことを考えるというのは,これまで多く見られた海外の新たな思想を日本に移入する形で,日本で世界のことを語るというのとは全く違っています。(中略)そうした仕事は,翻訳されれば,すぐに海外にオリジナルがあるとわかってしまいます。そうではなくて,日本の現実に根ざして,かつ,そこから世界のことを考え,もしこれが世界に照会されれば,世界の人々にインパクトを与えるだろうというような仕事のことをここではいっています。
それは,国や民族の限界から離脱し,日本人ではなく,人間を単位とする思考をすることだ,そこに加藤氏は改めて吉本隆明を再発見したのだという。
世界と自分との間に「日本」という国単位の枠をおかない。そのだめさ加減に自分は,戦争で,つくづく懲りた,という吉本の徹底した自分への掘り下げがある。それを,加藤氏は,
腑に落ちる
という。同じ感覚を,高橋氏は,
浮かない感じ
という。そういう,自分の中の違和感を,吉本は常に大事にしている。右へならへすることにも,違和感を違和感として言語化する。「反反原発」も「オーム」も,吉本の中には,「原理としての軸がある。高橋氏はいう。
ほとんどすべての思想家,あるいはほとんどすべての作家,ほとんどすべてのことばをあつかう人たちの拠って立つものと,吉本さんが拠って立つ者との違いみたいなもの,それが…「腑に落ちるか」ということではないですか?つまり内臓言語で,「原生的疎外」のところまで下りていかなければだめだということと,大衆に向き合うということとは等号で結ばれるということで,吉本さんの思想みたいなものは成り立っているのかもしれない。
この原生的疎外とは,
生命体(生物)は,それが高等であれ原生的であれ,ただ生命体であるという存在自体によって無機的自然に対してひとつの異和をなしている。この異和を仮に原生的疎外と呼んでおけば,生命体はアメーバ―から人間にいたるまで,ただ生命体であるという理由で,原生的疎外の領域をもっており,したがってこの疎外の打消しとして存在している。
から来ている。内臓言語とは,『言語にとって美とはなにか』(日本語ではなく,言語そのものを対象にしていることに注意)での,指示表出,自己表出を三木成夫によって,自己表出を内臓系感覚,指示表出を神経系感覚に対応させたのによる。だから,「腑に落ちる」「浮かない」に対応する。
その意味で,吉本にはいつも二つのメジャーがある。
歴史は,外から見る外在史(文明史)として現れるが,内から見ると内在史(精神史)として現れてくる。(中略)外在史の視点から内在史を断罪しない。近代的倫理から悪を断罪するのではなく,悪の行為のうちに,近代的倫理を相対化するような内在性があると認められる場合は,足場の近代的倫理をいったん相対化する必要がある…。
あるいは,
「未来の何かに向かっていることへの追求」(外在史)と「人類の原型であるような段階を掘り下げること」(内在史)が同じ作業であるような場所で,いまかろうじて「歴史」の概念は成り立つはずで,これまでの世界史という考え方ではもはや「歴史」はとらえられないし,これを超えるには「原始と未確定の未来の二方向性」の探求が必要となる…。
あるいは,
たとえ,どんな外界のきっかけの結果として起こるのでも,あるいは(お腹が重苦しいというような)内的な生理過程の結果として起こるのでも,「個体はなお〈じぶんがいまこう心でおもっていることをだれも知らないし,まただれも理解することはできない〉という心的状態になることができる」。そのことは個体の「心的な現象」が自分自身の心的な過程,生理過程とじかに関係していることが,ありえることを語っている。そうだとすれば,「このような心的状態」をそれとして独立に考えることは,できるだろう…。では人間の個体が〈じぶんがいまこう心でおもっていることをだれも知らないし,まただれも理解することはできない〉と感じるとしたら,「その「感じる」とは何を内容としたものだろうか,というように広がり,(中略)最後に,もし単細胞のアメーバが〈じぶんがいまこう心でおもっていることをだれも知らないし,まただれも理解することはできない〉と感じるとしたら,それはアメーバがどう何を感じるということだろうか,というところまで行く…。
その先に,フロイトは,生命には生きていることへの違和感があるとし,それを「死への欲動」としたことを批判し,それは「変だと」感じ,フロイトのように人間的違和感に還元するのではなく,生命体としての違和感とすれば,前述の「原生的疎外」にいたる。つまり,人間には,人間であるほかに,生命体としての人間がある,ということになる。
ここにも,人間に還元しない,もう一つの視点を入れる,二元的指標がある。ここにあるのは,
生命種は永続するが人類はいつかほろびる,
という感じ方が入っている,と加藤氏はいう。このように,
吉本さんは異なったメジャーを用いて正しさに抵抗するということをやってきた。(中略)いまになって,吉本さん自身の考えていた以上に,彼の実践にはとても有効な部分があったことに気づいた。
そういう吉本の姿勢は,処女作である詩集にすでにある。
ひとつきりで耐えられないから
たくさんのひとと手をつなぐというのは嘘だから
ひとつきりで抗争できないから
たくさんのひとと手をつなぐというのは卑怯だから
ぼくはでてゆく(「ちいさな群れへの挨拶」)
そしていう。
ぼくの孤独はほとんど極限に耐えられる
ぼくの肉体はほとんど過酷に耐えられる
ぼくがたおれたらひとつの直接性がたおれる
もたれあえことをきらった反抗がたおれる(同)
そう振り返る時,高橋氏が言うのがひどく共感できる。
吉本さんは,「正面」だけでなく,その思想の「後ろ姿」も見せることができた。彼の思想やことばや行動が,彼の,どんな暮らし,どんな生き方,どんな性格,どんな個人的な来歴や規律からやってくるのか,想像できるような気がした。どんな思想家も,結局は,僕たちの背後からけしかけるだけなのに,吉本さんだけは,ぼくたちの前で,ぼくたちに背中を見せ,ぼくたちの楯になろうとしているかのようだった。
いつも先頭で,最前線で,思想としての旗を振る。前からどころか,集中砲火を,背後から浴びても,なお,考え続けることをやめない。知識人であるとは,どういうことか,常に市井で,どこかの大学教授なんぞにならず,ただ文筆家として,筆一本で戦い続け,老いてもなお,常識に背き,「正しいこと」に異を唱えた。
常に僕の理想であったことが,正しいと,再確認した。自殺した学生の確信は正しかったのだ。
参考文献;
加藤典洋・高橋源一郎『吉本隆明がぼくたちに遺したもの』(岩波書店) |
|
サムシング・グレート |
|
矢作直樹・村上和雄『神と見えない世界』を読む。
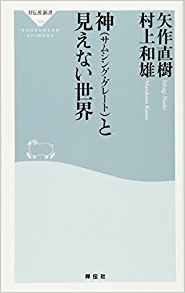
科学者だから許されるが,結構間違いや思い込みで語っているところがあり,そういうところを端折っても,科学者が真剣にサムシング・グレートに向き合っているのか,と疑問を感じた。思いつきでモノを言うのは,科学者のすべきことではない。
科学の研究を突き詰めていって,その先に畏怖を感じるというのはいい。しかし,それと宗教とは別だ。宗教心とも別だ,と僕は思う。正直言って,こんな程度を語っているから,科学者の中で,サムシング・グレートあるいは神秘さについて心を開く人が少ないのだと思う。雑に過ぎる。
たとえば,宇宙論に,「人間原理説」があるのは,僕も知っている。
もしビックバン時の物理定数が少しでも狂ったら,今の宇宙は生まれていません。宇宙では,引力を含めたさまざまな定数がビシッと決まっています。ある定数は,7.0000でないとダメで,6.9999でも7.0001でもダメ。では,この定数を決めたのは誰か?
「この定数を決めたのは誰か?」という問いは,科学者の問いではない。「誰か」と擬人化した瞬間,科学者であることを停止している。思考停止とは言わないが,「この定数を決めたのは何か?」という問いからしか,未知は開かない。
これらは,宇宙における偉大な法則です。素粒子みたいな極微の世界から,宇宙の生成と発展に至るまで,人智を超える「神の働き」があったとしか思えないというのが,私の考えです。
と村上さんが断言する。それが宗教心からではないのが,わからない。100年前もいまも,四割の科学者は神を信じている。その人の言う,「神の働き」とは違うことを村上さんは言っている。「サムシング・グレート」をそう呼んでいる。信仰心をもちつつ科学者であることと,科学者でありながら,サムシング・グレートを「神の働き」ということとは,似ているようで,すさまじい懸隔がある。だから,ここには,まっとうな科学者は近づかない。
アインシュタインが,
宗教心抜きの科学は足が不自由も同然であり,科学抜きの宗教は目が不自由も同然である。
を引用しているが,アインシュタインとご自分たちの立ち位置の違いに,全く無自覚である。
例えば,ゲノムについても,
DNAは命の設計図と言われていますが,あれは言いすぎです。そもそも命の設計図じたいがわからないわけですから。部品設計図としてのDNAという存在は理解できますが,命の設計図,つまり「魂の設計図」は科学ではまったくわかりません。
ちょっとまってよ,「魂」というものがあることを仮説として考えるなら,それを科学として解明したの?と聞きたくなる。「神」がいることを前提にしない限りできない議論をしている。つまり,論点先取りの議論をしている。これも,DNAを動かしている何かを想定しなければ理解できない,というサムシング・グレートを意識する畏怖心とは,別の理屈をここへもってきて,それで良しとしてしまっている。思考停止と言っているのは,ここなのだ。
アインシュタインの立脚点とは違うというのはここだ。畏怖心を持つことと,それを神の仕業としてしまうこととは別だ。そうした瞬間,人智を超えている,と手探りすることすらやめている。
ある部分がわかれば,また別の「謎」が出現する…。
だから,「魂」という表現で丸めてしまうのは,思考をそこでやめることではないのか?
体は60兆個の細胞でできており,それは一年くらいで一度ほとんど全部入れ替わりますから,…残っているのは魂しかありません。
ちょっと待ってくれよ,「魂」を勝手に仮定して話を進めないでほしい。全部すれ変わってしまってもなお,「私」であるのは,どういう仕組みなのか,を問うことの方が先なのではないか。
簡単な解決策が見つかったならば,それは神の答えだ。
というアインシュタインの言葉は,思考停止の言い訳に使ってはならない,とつくづく思う。
同じく,野依良治さんの,
科学者が次々と新しいことを発見するけれども,発見したと同時にさらに多くの疑問が出てくる。宇宙でも科学でも自分たちが知っていることは,まだまだごくわずか。その意味では,科学者は謙虚であらねば…。
という言葉も,アインシュタインの,
基本的な法則を発見するのに論理的なやり方など存在しない。ただ直感あるのみで,それを助けるのが,見かけの裏に隠れている秩序を感じ取る力である。
というのを神秘性というだけにとどめず,神につなげてしまっては,お二人が嘆く。それは,謙虚ではなく,神への平服でしかない。
参考文献;
矢作直樹・村上和雄『神と見えない世界』(祥伝社新書) |
|
遺伝子の開花 |
|
堀田凱樹・酒井邦嘉『遺伝子・脳・言語』を読む。

かつて,神田橋條治さんが,
ボクは,精神療法の目標は自己実現であり自己実現とは遺伝子の開花である,と考えています。「鵜は鵜のように,烏は烏のように」がボクの治療方針のセントラル・ドグマです。
と書いていた。遺伝子学の堀田さんは,
遺伝子で決めている範囲を逸脱することはできない。それは厳然たる真理だと思います。ただし,遺伝子が決めている範囲をすべて使っているかというと,実はほとんど使っていないとおもうんですよ。僕だって,もし優れた指導者に出会えれば,全然違う才能を発揮して,…いたかもしれません。そういう才能を発揮するような環境にいなければ,その才能が有ることも知らずに死んでいくわけです。(中略)自分が遺伝的にもらった才能というのは,自分が思っているよりはるかに広い。それを開拓するのが,学習するということです。
というふうに語っている。つまりは,遺伝子で決定論的に決まるのではなく,非決定論的な柔軟性がある,それは少し丸めた言い方をすると,どんな生き方をするかでその開花は変わる,といってもいい。
ところで,ハエのゲノム(一組の染色体)には,約一万五千の遺伝子があり,ヒトの遺伝子は三万程度で,その差が小さいように感じるが,一個の遺伝子を変えただけで大きなことが起きるのだから,数千個も変われば,全然違うものになる。しかし,
ひとつの幹に沿って生物が進化していって,最後に無脊椎と脊椎の二つの枝に分かれたんです。それもたかだか四億〜五億年前のことで,四〇億年近い生命の歴史を考えれば,別れてからの時間が全体の10パーセントなら,90パーセントは同じだということになります。
その意味では,ヒトとヒトの間の差は,平均0.1%,ゲノムとして0.1%の変動,チンパンジーとは1%の違い。10倍違う。わずか1%の差でも,
ヒトとヒトの間の距離の10倍くらいのところにチンパンジーがいるというようなイメージです。
こう空間的に示されると,不思議とイメージが鮮明になる。それもそのはずで,
脳の視角野といわれる部分は,実際に物体を見たときに働いている領域なんですが,イメージしただけでも同じように活動する…。
ことに起因している。
言語については,小さい時にある段階までに一番適応しやすい年齢があり,自然に言語を学んでいくが,
脳は,聞こえているものが言語なのか雑音なのかわかっています。赤ん坊がちゃんと言葉がわかるようになるということは,たくさんの聞こえている音の中から言葉を抽出して取り入れている…。
という。ここで不思議なのは,手話もそれと同じ自然言語なのだということだ。
アメリカの研究では,手話を第一言語として使っていたろうあ者が左脳のトラブルで手話失語になることを報告しています。
つまり,手話も赤ちゃんが自然に第一言語として覚え,手話を使っているときの脳を調べると,完全に左脳優位であるという。
ここから想像できることは,言語化する方法が何であれ,抽象化する作業は左脳が担う。必然的に,脳の機能としては同じだということだ。
では,そういう人間の脳とコンピュータを比較して,何がわかるのか。人がコンピュータをつくるので,コンピュータは人を超えられない,そういう常識は正しいのか。
たとえば,将棋のコンピュータでは,従来の,手をしらみつぶしに計算して,最も良い手を残すというやり方から,
最初に可能な手を絞り込んでしまうのです。つまり,手持ちのデータを使って,いくつかの手はありえないということで,落としてしまう。絞った手に関して深く読んで見込があるかどうかを判定して,その中で一番良いのを残すという方法を取っています。
という。「将棋のコンピュータは,捨て方を人間が教えてやった時点で,創造性に一歩近づいた」のだという。
この背後にあるのは,堀田さんの,
天才とは,ものを捨てる能力の高いひとじゃないか,…いろいろな可能性を考えるスピードが速くて,しかも,その可能性の中で,適切なものだけ残して,不適切なものを捨てる。
という考え方と照らしてみるとき,一歩人に近づいている。たとえば,
コンピュータが意志をもてるか,というのは本質的な問題です。「意志」とは,自分が自分に対して命令を出すことでしょう。…それら簡単にできます。つまり,コンピュータがある命令を別の命令で呼べばいいわけです。それは「サブルーチン」というプログラムの基本としてよく知られています。(中略)人間の脳もまさにそうなっているのでしょう。下位の命令は,脚を動かしなさい,…という「運動野」の命令なんですが,その上位の前頭葉のニューロンは,その命令に対してさらに命令を出す役割をしているのです。
本書でも言っているが,人間と同じものをつくっても仕方がない。何をするためのものなのか,というツールとして徹底するのか,人の代替をつくろうとするのか,そういう選択が現実的になってきた時代にいる,ということが実感である。
参考文献;
堀田凱樹・酒井邦嘉『遺伝子・脳・言語』(中公新書)
神田橋條治『技を育む』(中山書店) |
|
ソリューション・トーク |
|
モー・イー・リー&ジョン・シーボルト&エイドリアナ・ウーケン『DV加害者が変わる』を読む。

解決志向グループセラピー実践マニュアルと副題された本書は,DV加害者プログラムでのソリューション・フォーカスト・アプローチの実践記録である。
DV加害者に対する裁判所命令の一つとしてDV加害者プログラムへの参加が義務付けられているアメリカでは,様々な治療プログラムが試みがなされているにもかかわらず,再犯率は,15〜50%と言われている。このプログラムは,3カ月に8回のセッションを行うという,まさに短期プログラムにもかかわらず,再犯率は,16.7%であった。
特徴は,従来型のように,問題や原因に焦点をあてる「プロブレム・トーク」ではなく,どうなりたいか,どうしたいかに焦点をあてた「ソリューション・トーク」に集中し,次の原則に基づいて,治療に取り組んでいる。
①参加者が答えをもっている
②できないことではなく出来ることに焦点を絞る
③変化は絶えず起きている。参加者は問題や欠点があると思っているにもかかわらず,より満足のいく方法か違った仕方で対処できているときがある。
④部分の小さな変化は他の部分の変化を導く
つまり,「問題に深入りせず,目標と目に見える行動と進歩する生活を新しく有益な方法で描写することによって,意味と解決を構築することをめざす」。なぜなら,
病理や問題について話すことは自己成就的実現(言い続けると本当になること)になり,問題のある現実を維持したり解決したりしようとする私たちの注意をそらすことになる
からだという。そのために,ソリューション・トークの鍵は,ゴール設定である。
ゴールが使われ始めると,何ができないかから何ができるかに注意の焦点が移っていく。そうすると参加者は他人や自分をせめるのではなく,今とは違うより良い未来を作る責任を感じるのである。
そして,
ゴール作りの目的は変化が起きやすい状況を作ることである。参加者が自分のゴールと合致する行動をはじめたら,その行動がもたらす利点を参加者に気づかせる。ほんの小さな行動や考えの変化にも注目し,それが重要なものだと説明する。私たちの役割は,参加者が作り上げる目標とその結果としての行動が彼らにとって大きな利益であることを体験してもらい,そのための状況を作ることである。
それを,SFAの創始者,インスー・キム・バーグ,スティーブ・ディ・シェイザーは,「あたりまえのことを予想もしなかったことに変える」という。つまり,
小さな変化を見逃さない,
ことなのだ。そのため,ゴールは,6つの条件が説明されている。
①あなたの生活を改善するうえで役に立つゴールを作り出してほしい
②そのゴールは対人関係上のものでなければならない。つまり,あなたがゴールに向かって努力するときに,別の人があなたの変化に気づき,あなたの行動の変化から影響を受けるようなものでなければならない
③別の考え方では,あなたがゴールに向かって努力しているビデオテープをもってきたとすれば,あなたが「している」違ったこと,さらにはそれらが他の人にどう影響しているかをテープ上で指摘できるようなものでなければならない
④ゴールはあなたが普段していなかった何か「違う」ことでなければならない
⑤毎回ゴールへの努力を説明することになっているので,少なくとも週に2,3回は実行できるような行動でなければならない
⑥第3回のグループセッションまでに全員が承認されたゴールを作り上げていなければならないし,それに向かって努力していなければ3回目以降グループにとどまることはできない
では,セラピスト(ここではファシリテーターと呼んでいる)はどういう姿勢で取り組むのか。ソリューション・フォーカスト・アプローチのおなじみの原則といっていい。
第一は,知らない姿勢。
私たちは,参加者が彼ら自身の生活の専門家になれると信じている。(中略)変化の本質は,参加者自身が解決を創造したり見つけたりする努力のなかにあると私たちは信じている。解決は参加者の探求によってのみ得られるものである。(中略)私たちが彼らの能力を信頼していれば,彼らは自分に適した持続可能な解決に到達する…。
第二は,選択肢を作り出す。
参加者の多くは,自分の周囲の人々と出来事が,彼らの生活を支配していると感じている。彼らは周りから支配的だと言われているのに,自分では他の人々に支配されていると感じている。彼らは自分に無数の選択肢があるということを見落としている。その選択肢を自覚させ,彼らが自分の生活の専門家だという自覚を促すことがファシリテーターの重要な仕事の一つである。
第三は,変化は絶え間なく起こる。
ひとに「殴る人」「犠牲者」「うつ」「そううつ」などと分類されると,彼らが絶えず変わって変化している複雑な人だという事実を認識しにくくなる。実際にひとが「変わって」も,その変化は無視されやすく,(中略)「それは一時的なものだ」として片づけられてしまう。
第四は,あらゆるものは関連している。
小さな持続する変化は広範囲に影響する可能性がある…。小さな変化は一人の参加者の小さな持続する変化は広範囲に影響する可能性がある…。小さな変化は一人の参加者のゴール探求に活用されるものだが,グループ過程にも使われる。(中略)最も変化しそうな参加者から変化を追求し始めればよいことになる。それが変化の流れに他の参加者を引き込むからである。参加者が次々に引き込まれると,流れはさらに強くなり,人を惹きつける。流れが十分強力になったとき,グループ自体が前進し,参加者の報告に強い関心を示すようになる。
では実践としてどんな対話をするのか。
①傾聴
それは,聞いてますよ,というメッセージを伝えるだけでなく,あなたの話していることに興味があります,とかあなたの話していることは重要ですというフィードバックを参加者に伝えていることになる。
②承認
参加者の行動,感情,思考を支持し,参加者に希望を注ぎ込み,さらにゴールを追求しようという勇気を与える。
③繰り返し
参加者の説明した行動,意味,感情をさらに明確にして強化するフィードバックを与えるという意味で,鏡や反響板のような働きをする。
④拡大
参加者のゴール達成の努力に新しい意味と可能性を生み出すために,参加者の言葉を使ったり拡大したりする。
⑤評価的質問
・探索を助ける その中でどんな可能性がありますか
・計画を助ける このゴールをどうやって実行しますか,いままでとどんな違うことをしますか
・指標づくり それができたことがどうやってわかりますか
・例外探し できていたことはないですか
・スケーリングクエスチョン ゴール10のうちいまいくつ
・効果を考える それが出来たらどんなことが起きますか,それをしていたことを誰が知っていましたか
・有用性 それがどんな役に立ちましたか
・実行可能性 それをすることは無理のないことですか
・意味つげ どうやってそれが出来たんですか
・変化を起こしたのは本人 あなたはいつそれを決めたんですか
こう見てくると,ソリューション・フォーカスト・アプローチがコーチングと親和性がいかに高いかが改めて再認識できる。
参考文献;
モー・イー・リー&ジョン・シーボルト&エイドリアナ・ウーケン『DV加害者が変わる』(金剛出版) |
|
自己マスタリー |
|
ピーター・M・センゲの『学習する組織』を読んだ。
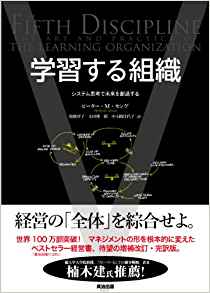
何年前か,『フィールドブック 学習する組織「5つの能力」』を読んだ時の,脳の発酵するような興奮はなく,正直に言うと,醒めて,眉に唾をつけつつ読んでいた。
それは単に自分の側の変化なのか,時代の変化なのか,僕自身には見極めがつかない。ただ,距離を置いて,それを計っている自分がいたことは確かだ。
学習する組織のディシプリンとして,
システム思考
自己マスタリー
メンタル・モデル
共有ビジョン
チーム学習
という中で,他のディシプリンは,当たり前で,最も気になるのは,自己マスタリーだ。
自己マスタリーとは,
自分たちにとって最も重要である結果をつねに実現することができる―要するに,芸術家が作品に取り組むがごとくに人生に向き合う。自身の生涯を通じた学習に身を投じることによってそれを実現するのである。
といい,このディシプリンは,
継続的に私たちの個人のビジョンを明確にし,それを客観的に深めることであり,エネルギーを集中させること,忍耐力を身に着けること,そして,現実を客観的に見ることである。
という。別にすべての人がスーパーマンになることを前提にしているのではないと思うが,「学習」に焦点を合わせることで,何かがずれているように思えてならない。もちろん,そういう人の成長を組織が促すのは大事だが,あくまで,組織でのかかわりの中であって,それ以上でも以下でもない。組織内人生=自分の人生ではないのだから。
そういう時に,清水博さんのモデルが思い出される。これについては,
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/11189806.html
で触れたが,サッカーの例を挙げている。
サッカーの選手たちが,サッカー場という居場所に自分で自分の役割を位置づけることができるようになると,はじめて立派にチームプレーをすることができる。
あるいはフランスのサッカーチームとの親善試合で負けたことについて,フランスの記者が,
フランスの選手はグラウンドを広く使っていたが,日本の選手は狭く使っていた。
と評したという。
まず,ふたつのことが言える。ひとつは,人がチームに入った状態を考える。その場に入って,自分の居場所を見つけるまでに,チームから学んだり教えられたりしながら,チーム自体の居場所を知り,その目的を知り,その意味を知り,そこでの自分のいる意味を知って,はじめて自分がそこで何をするかが見えてくる。そう考えれば,我々はいつもこれを繰り返している。それを僕は,「ポジショニング」と呼んできた。
自分の「ポジショニング」がわからない人は,自分の役割どころか,何をするためにそこにいるのかが,わからないので,チーム内で主体的に仕事に関わり,仕事を創り出していくことができない。それではチームの石ころ,つまり邪魔者にしかなれない。
いまひとつは,チームのいる場所を考える。チーム内的なポジショニングだけではなく,チームの置かれている組織全体との関係の中で,チームそのものをポジショニングする,チーム外的な視点を持てないと,チームの目標を目的化する。そうではなく,チームの目的を考える視点と言ってもいい。
人の成長をサポートするのは,この視点からでなくてはならない。たとえば「知れるを知るとなし,知らざるを知しらざるとせよ。これ知るなり」という,無知の知を自覚したとき,そのサポートをするというのはいい。しかしそれはあくまで実践との関連の中でなくてはならない。
もちろん,
個人が学習することによってのみ組織は学習する。
それはその通りだが,問題は,学習の中身だ。ここが,たぶん,この本に対する姿勢の分岐点のような気がする。
自己マスタリーは,能力やスキルを土台にしているが,それらにとどまるものではない。(中略)独創的な仕事として自分の人生に取り組み,受身的な視点ではなく,創造的な視点で生きるということなのだ。
自己マスタリーがディシプリン―自分の人生に一体化させて取り組む―の一つになれば,二つの根本的な動きが具現化する。一つは,自分にとって何が重要かを絶えず明確にすることだ。(中略)もう一つは,どうすれば今の現実をもっとはっきり見ることができるかを絶えず学ぶことだ。
ビジョン(私たちがありたい姿)と今の現実(ありたい姿の現在地)のはっきりしたイメージを対置させたときに「創造的緊張」(クリエイティブ・テンション)と呼ばれるものが生まれる。…自己マスタリーの本質は,自分の人生においてこの創造的緊張をどう生み出し,どう持続するかを学習することだ。
おいおい,と思わないのだろうか,それは,その人の人生そのものであって,そこに組織がどう介入しようというのか。どこかで逸脱している,としか思えない。これをありがたがる人は,僕には理解できない。組織学習,学習する組織は大事だが,それと個々人の人生そのものとは別だ。そういう言い方をすると誤解されるが,もちろんそういう人生創造をすることが前提かもしれない。しかしそれこそ自己責任ではないか。するもしないも自己責任,自由だ。
僕はこの本のように,個人の成長に組織が関与するのを是としない。はっきり言って大きなお世話だ。しかし,個人にとっての意味を組織の意味とつなげていくための架け橋を,組織がすることはむしろ大事だ。学習の中身は,それだと思う。僕は,それを旗と呼んでいる。組織の中で,
自分が何をするためにそこにいるのか,
それは自分にとってどんな意味があるのか,
そのために自分ができることは何か,
そこで自分がしたいことは何か,
を考えていく。その限りで,個々の成長のサポートを組織ですることは意味があるし重要だ。自分の旗を立てる意味については,
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/11129007.html
で触れたし,そもそも仕事で,「旗」を立てるについては,
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/11011724.html
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/10966920.html
で触れた。それを超えて個人の生き方まで踏み込むのは,本末転倒だ。センゲだからと言ってありがたがる必要はない。ダメなものはだめだ。
思い出すのは,清水さんの,「自己の卵モデル」だ。
①自己は卵のように局在的性質をもつ「黄身」(局在的自己)と遍在的性質をもつ「白身」(遍在的自己)の二領域構造をもっている。黄身の働きは大脳新皮質,白身の働きは身体の活(はたら)きに相当する。
②黄身には中核があり,そこには自己表現のルールが存在している。もって生まれた性格に加えて,人生のなかで獲得した体験がルール化されている。黄身と白身は決して混ざらないが,両者の相互誘導合致によって,黄身の活(はたら)きが白身に移る。逆もあり,白身が黄身を変えることもある。
③場所における人間は「器」に割って入れられた卵に相当する。白身はできる限り空間的に広がろうとする。器に広がった白身が「場」に相当する。他方,黄身は場のどこかに適切な位置に広がらず局在しようとする。
④人間の集まりの状態は,一つの「器」に多くの卵を割って入れた状態に相当する。器の中では,黄身は互いに分かれて局在するが,白身は空間的に広がって互いに接触する。そして互いに混じり合って,一つの全体的な秩序状態(コヒーレント状態)を生成(自己組織)する。このコヒーレント状態の生成によって,複数の黄身のあいだでの場の共有(空間的な場の共有も含む)がおきる。そして集団には,多くの「我」(独立した卵)という意志器に代わって,「われわれ」(白身を共有した卵)という意識が生まれる。
⑤白身が広がった範囲が場である。したがって器は,白身の広がりである場の活(はたら)きを通して。黄身(狭義の自己=自分)に「自己全体の存在範囲」(自分が今存在している生活世界の範囲)を示す活(はたら)きをする。そして黄身は,示された生活世界に存在するための適切な位置を発見する。
⑥個(黄身)の合計が全体ではない。器が,その内部に広がるコヒーレントな白身の場を通じて,黄身に全体性を与える役割をしている。現実の生活世界では,いつもはじめから器が用意されているとは限らない。実際は,器はそのつど生成され,またその器の形態は器における人間の活(はたら)きによって変化していく(実際,空間的に広がった白身の境界が器の形であるという考え方もある)全体は,卵が広がろうとする活(はたら)きと,器を外から限定しようとするちからとがある。
⑦内側からの力は自己拡張の本能的欲望から生まれるが,外側からの力は遍在的な生命が様々な生命を包摂しようとする活(はたら)きによって生まれる。両者のバランスが場の形成作用となる。
組織という器の中で,白身と白身の接点にチームができる。だからと言って,黄身のありようまで組織側から変えられてたまるか。とっさにそう感じた。
この本の「学習する組織」の肝は,「自己マスタリー」だ。それだけにいただけない。
参考文献;
ピーター・M・センゲ『学習する組織』(英治出版)
清水博『場の思想』(東京大学出版会) |
|
右脳左脳 |
|
ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』を読む。
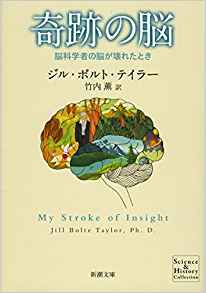
僕は基本的に右脳・左脳と区別して語る人を信じない。人は,両方合わせて僕なのであって,片っ方では,「僕」として存在しない。機能として僕を語ることは,御免蒙る。
しかし,30代半ばで,先天性の動静脈瘤奇形(AVM)によって,大量の血液が左半球のあふれ,左脳の思考中枢の機能を失った,脳科学者が,8年かけて脳卒中から回復した奇跡的な努力をまとめた本だとすると,まずはその先入観を捨てて,受け入れるところから始めなくてはならない。
僕はキャパを超えて努力した人しか,自分を超えられないと信じているのだ。
出血したのは,左脳の,方向定位連合野(からだの境界,空間と時間),ウェルニッケ野(言葉の意味を理解する能力),感覚野(皮膚と筋で世界を感じ取る能力),ブローカ野(文章をつくる能力),運動野(体を動かい能力)にかかわる分野が出血で沈んだ。その結果,順序立てて出来事を並べる左脳が機能不全に陥り,「内部に心地よい安らぎが訪れた」という。
解放感と変容する感じに包まれて,意識の中心はシータ村にいるかのようです。仏教徒なら,涅槃の境地に入ったと言うでしょう。
具体的にはこんなふうになっていく。
…左脳の言語中枢が徐々に静かになるにつれて,わたしは人生の思い出から切り離され,神の恵みのような感覚に浸り,心がなごんでいきました。高度な認知能力と過去の人生から切り離されたことによって,意識は悟りの感覚,あるいは宇宙と融合して「ひとつになる」ところまで高まっていきました。無理やりとはいえ,家路をたどるような感じで,心地よいのです。この時点で,わたしは自分を囲んでいる三次元の現実感覚を失っていました。
左脳は自分自身を,他から分離された固体として認知するように訓練されていました。今ではその堅苦しい回路から解放され,わたしの右脳は永遠の流れへの結びつきを楽しんでいました。もう孤独ではなく,淋しくもない。魂は宇宙と同じように大きく,そして無限の海のなかで歓喜に心を躍らせていました。
しかしそれは,本来の能力が意識があるのに,系統的にむしり取られていく状態なのである。
まず耳を通ってくる音を理解する能力を失う。
次に,目の前にある何かの物体のもともとの形を見る能力を失う。
更に,何でもなかった匂いがきつく,息をするのもつらくなる。
そして,温度も振動も苦痛も,あるいはどこに手があるのか足があるのかの知覚を失う。
そして,自分自身を宇宙と同じように大きいと感じる。自分がどこのだれかを思い出す内側の声が聞こえなくなる。
そこから天性の介護人である母親と二人三脚の回復をしていくことになる。著者はこう言う。
脳卒中で一命をとりとめた方の多くが,自分はもう回復できないと嘆いています。でも本当は,彼らが成し遂げている小さな成功に,誰も注意を払わないから回復できないのだと,わたしは常日頃から考えています。だって,できることとできないことの境目がハッキリしなければ,次に何に挑戦していいのか,わからないはず。そんなことでは,回復なんて気の遠くなるような話ではありませんか。
だから,
うまく回復するためには,できないことではなく,出来ることに注目するのが非常に大切。
頭のなかに響く対話,つまり独り言には要注意。なぜなら,ちょっと油断すると,1日何千回だって,以前の自分と比べて劣っていると感じてしまうからです。
わたしがきちんと回復できるかどうかは,あらゆる課題を小さく単純な行動のステップに分けられるかどうかにかかっていました。
それらを実践する母親の辛抱強い励まし,意志的に努力を積み重ねる介護が,少しずつ著者を回復させていく。
できるだけ早く神経系を刺激する必要があることを,二人は本質的によく理解していました。わたしのニューロンは「失神状態」でしたが,専門的にみれば,実際に死んだのはわずかなニューロンにすぎません。(中略)ニューロンは他のニューロンと回路でつながって育つか,そうでなければ刺激のない孤立状態で死んで行くかのどちらかです。GG(母親のこと)もわたしも,脳を取り戻すことに闘志を燃やしていました。ですから寸暇を惜しんで,貴重なエネルギーを全部残らず利用したのです。
回復は感情を感じるプロセスで見えてきたと言う。たとえば,
新しい感情がわたしを通って溢れ出し,わたしを解放するのを感じるんです。こうした「感じる」体験に名称をつけるための新しい言葉を学ばなければなりませんでした。そしてもっとも注目すべきことは,「ある感じ」をつなぎ留めてからだの中に長く残しておくか,あるいはすぐに追い出してしまうかを選ぶ力をもつていることに,自分自身がきづいたこと。(中略)どの感情的なプログラムを持ち続けたいのか,どんな感情的なプログラムは二度と動かしたくないのか(たとえば,短気,批判,不親切など)を決めるには,やきもきしました。この世界で,どんな「わたし」とどのように過ごしたいかを選べるなんて,脳卒中はなんてステキな贈り物をくれたのでしょう。
そうして著者は,自分の脳を自分でコントロールできる力を,同時に学び身につけていく。
知りたかったのは,左脳の機能を取り戻すために,せっかく見つけた右脳の意識,価値観,人格のどれくらいを犠牲にしなくてはいけないのか,という点でした。
しかし,
脳内の出血によって,自分を決めていた左脳の言語中枢の細胞が失われたとき,左脳は右脳の細胞を抑制できなくなりました。その結果,頭蓋の中に共存している二つの独特な「キャラクター」のあいだに,はっきり線引きできるようになったのです。
それは,誰にもできると著者は言う。
あなたが,左右それぞれの「キャラクター」に合った大脳半球の住み処を見つけてやれば,左右の個性は尊重され,世界の中でどのように生きていきたいのか,もっと主張できるようになります。(中略)頭蓋の内側にいるのは「誰」なのかをハッキリ理解することによって,バランスのとれた脳が,人生の過ごし方の道しるべとなるのです。
そのバランスを,こう著者はまとめている。
わたしはたしかに,右脳マインドが生命を包みこむ際の態度,柔軟さ,熱意が大好きですが,左脳マインドも実は驚きに満ちていることを知っています。なにしろわたしは,10年に近い歳月をかけて,左脳の性格を回復させようと努力したのですから。左脳の仕事は,右脳がもっている全エネルギーを受け取り,右脳がもっている現在の全情報を受け取り,右脳が感じているすばらしい可能性のすべてを受け取る責任を担い,それを実行可能な形にすること。
著者は,コントロールのコツをこう言っている。
わたしは,反応能力を,「感覚系を通って入ってくるあらゆる刺激に対してどう反応するかを選ぶ能力」と定義します。自発的に引き起こされる(感情を司る)大脳辺縁系のプログラムが存在しますが,このプログラムの一つが誘発されて,化学物質が体内に満ちわたり,そして血液からその痕跡が消えるまで,すべてが90秒以内に終わります。
通常無意識で反応しているのを意識的に,90秒を目安に,自分で選択できるということです。例えば,90秒過ぎても怒りが続いていたとしたら,それはそれが機能するよう自分数が選択し続けているだけのことだ,というわけです。
最後に,左脳が判断能力を失っている間に見つけた涅槃体験から,著者は,脳卒中から得た「新たな発見」を,こう言い切る。
「頭の中でほんの一歩踏み出せば,そこには心の平和がある。そこに近づくためには,いつも人を支配している左脳の声を黙らせるだけでいい」と。
それも,自分でコントロールできると,著者は言いたげである。
脳の可塑性によって,著者は8年後,失われた機能を回復したが,「わたしの脳の配線は昔とは異なっており,興味を覚えることも,好き嫌いも,前とは違ってしまっている」という。ひょっとしたら,別の人間に生まれ変わっている,と言えなくもない。
参考文献;
ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』(新潮文庫) |
|
命をつくる |
|
岩崎秀雄『〈生命〉とは何だろうか』を読む。

生命とは何かへの答え方として,冒頭に,リチャード・ファインマンの,
「もし自分につくれないのなら,私はそれを理解したことにはならない」
という発言をもってくる。つまり,生命とは何かへの答えは,それが作れるかどうかにかかっている。
第一線では,二つのアプローチがある。ひとつは,トップダウン型のアプローチ。ゲノムDNAを大規模に改変することで,新たな生命体を生み出そうとする試み。いまひとつは,ボトムアップ型アプローチ。研究者が簡単な見取り図を設計して,それに基づいて化学物質を試験管の中で混ぜ合わせて簡単な生命体をくみ上げる試み。
トップダウン型の人工細胞の場合,これが作ったものになるのか,という疑問が生まれ,ボトムアップ型の場合,これを生命体と呼んでいいのかという疑問がでる。両社は対極だが,「生命がどのような存在なのか,どのようにして生き物らしい振る舞いをするのか。その見取り図(設計図)を把握しようとする試みが,自然科学としての生命科学の本流」である,という。
「細胞が生命の基本単位であり,細胞というのは基本的に細胞が分裂して増える」という細胞説が,生物学の前提となっている。だから,細胞を創ることで,生命体を生み出そうとしていくことになる。
では,その人工細胞はどういう特性をもっている必要があるのか。研究者たちは,
「自己増殖すること,代謝機能をもつこと,遺伝子情報をもっていること」
を挙げる。それは人工細胞の源流,「トラウベの人工細胞」を考え出したトラウベは,市井の研究者であり,こんな言葉を残している。
「新たな発見を目の前にしながら,あらゆる進歩に目をつむり,市販することしか考えないたくさんの人たちがいた」
いわば,クーンのパラダイムではないが,要は,知識でものを見ている。だから知らないことを認めるのは大変難しい。しかしトラウベの成果に影響を受け,生命を物理化学的に解明しようとした,フランスのルデュックは,「生きていること」の3機能を,
・エネルギー変換器 外部からエネルギーを受けとり,外部に別の形で放出する
・物質変換器 環境から物質を受けとり,別の化学物質の形に変換する
・形態変換器 はじめはシンプルな形から次第に複雑な形態に変化していく
とした。日本の第一人者,柴谷篤弘は,生物モデルを,
エネルギー変換系であること
系は自己保存の機構を持つこと
系は自己増殖の機構ホ持つこと
とする。しかし,こういう発想からの転換になったのは,チューリング・テストだという。チューリングは,「機械が知性を持つかどうかをどう判断するか」という思考実験で,「やり取りしている相手が,人間なのか機会なのかが見分けられなかったら,機会が知性をもつとはんだんしてよい」という提案であった。
そこから人工物を細胞とみなせるかどうかは,,見分けられるかどうかで判断する,という,言ってみると客観的基準ではなく,「間主観的判定」によってしか,論じられないのではないか,と著者は言う。
江上不二夫は,地球外生物はタンパク質や核酸をもつとはかぎらない。その意味からも,生命の合成も,物質にとらわれず,物質は何でできていても,金属でも,プラスチックでも,生命の基本的な性格を示すものが作られれば,生命の合成といえないことはないだろう,という。
そしてさらに一歩進んで,情報論から,生命を要素間のネットワークの振る舞いと考えるという方向が出てくる。
そこでは,森羅万象が情報の流れ,あるいはダイナミックな制御ネットワークに満ちた世界として記述されます。「これが生命である」と定義を与えるのではなく,物質と生命現象と非生命現象とは切れ目なく連続的につながっていることを前提として,「僕らが知っている生物の中には,そのうちの特定の振る舞いが含まれる」という形で生命の理解が進んでいる。
そこでは,特性を列挙することで生命を定義する姿勢が無効化されている。境界がボーダレスであるゆえに,どこからが生命的な情報の状態なのかを指定できないからである。
そこから想定されることは,情報だけで生命現象を現出させることも可能かもしれない,ということになる。まるでマトリックスの世界である。
参考文献;
岩崎秀雄『〈生命〉とは何だろうか』(講談社現代新書) |
|
社会心理学 |
|
岡本真一郎『言語の社会心理学』を読んだ。

口幅ったい言い方になるが,社会心理学が,パターンを分類するだけのつまらない学問だということの再確認ができたという成果しかない。コミュニケーションが文脈に依存する以上,どんなに文脈を精緻にしても,そのアプローチでは,コミュニケーションは結局つかめないという見本のようなものだという気がした。つかめたとしても,上っ面をなぜているだけだ。
例えば,コミュニケーションを,道具的コミュニケーションと自己充足的コミュニケーションに分ける。情報を伝えて目的を達する道具的コミュニケーションに対して,感情を表明するコミュニケーションを自己充足的コミュニケーションという。
こんなバカげた分類に意味を見いだせるだろうか?人がコミュニケーションする実態を掘り下げるのではなく,表面的なかかわりを分類しようとするから,こういうことになる。
あるいはコミュニケーションのチャンネルを,言語的コミュニケーションと非言語コミュニケーションに分ける。で,非言語チャンネルを,音声,表情,視線,頭の動き,ジェスチャー,姿勢,対人距離と整理する。そう整理されると,言語以外が伝える情報というものが浮き上がっては来る。だが,有名な,メーラビアンの,7%が言語で,音声が38%,表情が55%という相手への影響力比率があるが,常識的に考えても,7%しゃべるだけで相手に伝わるとは思えない。もっともらしい調査の弊害だ。全体があいまって,相手に伝わっていく。恋人同士なら,もっと言葉は少ないかもしれない。見知らぬ他人なら,言葉なしでは何も伝わらない。文脈次第なのだ。
では,文脈を共有できれば,伝わるのか。それを,「共通の基盤」として,著者は4つに整理する。
第一は,会話の物理的状況
第二は,先行する会話。
第三は,共同社会の成員性。
第四は,聞き手側の推測
しかしこの分類は,基本的におかしい。会話している者同士が,共通の会話の基盤にいるかどうかは,二人(ないし何人か会話をしている者同士)の文脈だけであって,それが,同じ会社にいるかとか,それまでの会話の流れとか,レベルの違う条件を並べても,ほとんど意味がない。
僕は,これをコミュニケーションの土俵という。例えば,ジョハリの窓でいう,「パブリック(相手の知っている自分と自分の知っているいる自分の重なる領域)」も,その一つだが,土俵は,話し手同士で意識しないと,作れない。例えば,「ちょっといい?」「●●について話したいんだけど」というやり取りで,向き合って初めて,土俵ができる。そこでなら,「先行する会話」が意味を持つ。上っ面をなぜている,というのは,こういう分析を言う。
ポライトネス理論と言われるものも,似たようなものだ。対人配慮の先達理論というが,5つのストラテジーに分ける。
①あからさまに,何の対処もなしに言う。たとえば,「手伝え」
②積極的ポライトネス 主に付加的表現によって,相手との親愛感を強調しマイナスの影響を緩和する。「何々のご出身だそうで,私もそうです。では,手伝っていただけますか?」
③消極的ポライトネス 言動を和らげたりニュアンスを弱めて影響を緩和する。「忙しいので,手伝ってもらえないかもしれないけれど,どうかな」
④何も言わない
要するに,対人配慮をちょっとレベル差で分類して見せたというだけで,何の役にも立たない。それなら,どんな付加的言葉で,表現を緩和しようとするか,配慮言語を分類していった方が,行動パターンが見えるのではないか。
「ごくろうさん」という言葉を,いっとき若手が上司に使うというので,話題になったことがある。これも,文脈なのではないか。言葉は生き物なので,「ご苦労様」という労りを,
表現する場面の経験値がなかっただけに過ぎない。それが,すたれたのは,使い勝手が悪いだけだ。逆に,「お疲れ様」という,同じ労りの言葉は,上下の覊絆が薄らいでいる分,使い勝手がよく,次のように汎用化しているという。
①ねぎらうべき労働等の跡の別れのあいさつ
②職場,学校などでがんばるべきところですれちがいのあいさつ
③職場での呼びかけ
④電話での決まり文句
⑤どう利用へのメールへの件名や書き出し
⑥職場や学校での最初の挨拶
⑦自分が先に帰る時,仕事を続けている同僚にあいさつ
⑧行楽地での解散のあいさつ
⑨おしゃべりや食事の後の解散時のあいさつ
⑩理容院や美容院などの終了時の客へのあいさつ
⑪ウエブサイドでの書き出し挨拶
つまり,文脈を共有化しているというシグナルと言っていい。「ご苦労さん」には,上から目線が入りがちだが,それがないのが,いまのなんとなく文脈を共有しているようなふんわりした雰囲気には合う,ということなのだろう。
こう見ると,文脈依存のコミュニケーションを,文脈を精緻化しないところで,パターン分類しても,実はコミュニケーションについては何もつかめず,網の目のようなレッテルをいっぱい貼るだけで終わっていく。
そんなことを考えさせる本ではあった。
参考文献;
岡本真一郎『言語の社会心理学』(中公新書) |
|
神技 |
|
甲野善紀『剣の精神誌』を読む。
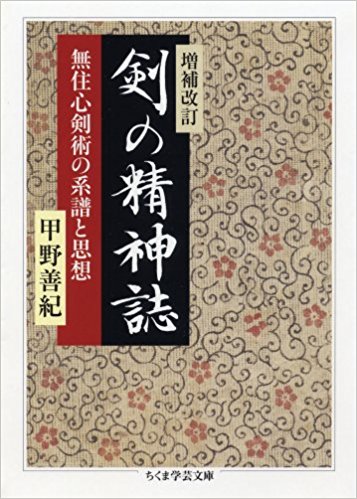
昔読んだ時代小説(というか剣豪小説というべきか)の世界で,決闘のシーンというか,果たし合いのシーンというので,印象に残っているのは,第一は,中里介山の『大菩薩峠』で,詳しいことは覚えていないが,土方歳三率いる新徴組の手練れが,清川八郎を襲撃しようとして,襲うべき駕籠を間違え,乗っていた島田虎之助に襲いかかり,結局島田一人に十数人の使い手全員が倒され,土方も翻弄される,すさまじい戦いシーンがあった。そのやりとりの迫力は,ずっと記憶に残っている。襲撃の一隊に加わった主人公,机龍之介は呆然,手をつかねて立ち尽くしていた,と記憶している。
ついでながら,第二に,指を折るのは,吉川英治の『宮本武蔵』で,確か武蔵が,柳生石州斎の屋敷に紛れ込み,柳生の四天王と,刃を交えるシーンであった。その気迫と,立ち会う面々との間合いは,一瞬で決着する吉岡兄弟との立ち会いも,一条下がり松のシーンも,般若坂の決闘も,かすむほどの緊迫したものだと記憶している。
ついでに思い出したのは,何の映画だったか覚えていないが,果たし合いの後,相手が,「急所を外した」というセリフを言った時,会場から失笑が漏れたことがあった。そういう神業を,ほとんどの人が知らないというか,小説の中のことと思っているらしい,とその時感じたものだ。
僕自身も,別にそういう神業に出会った経験はないが,技量を極めたときに,どんな状態になるかぐらいの想像力はある。難波走りと同様,かつての日本人の体の使い方は,明治以降の体育教育及び軍隊教練で,正座も含めて,創り出されてしまい,それが普通のように思ってしまっている。日本人本来の体の使い方,及びそんな日本人の知っていた身体を見失ってしまっているので,それを探るよすがもない。
甲野善紀氏は,江戸時代の剣客で,夢想願流の松林左馬助無雲のエピソードを紹介している。
ある夏の夕方,蛍見物に川べりを門弟とともに散歩していた無雲を,門人の一人が川へいきなり突き飛ばした。無雲は突き飛ばされたなりフワリと川を飛び越え,しかも,突き飛ばした門人も気づかぬ間に,その門人の佩刀を抜き取っていた…。
それは遠い江戸時代の話ではなく,現代の武道家にもいる,という。たとえば,柔術家の黒田泰治師範は,警察の道場で,寝転んだまま力士五人に体中を押さえさせ,よもやと思っていたら,あっという間に,いとも簡単に起き上ってみせた…。
あるいは,親戚男谷信友の弟子筋の島田虎之助の元で修業した勝海舟が,幕末の剣豪白井亨についてこんなことを語っている。
此人の剣法は,大袈裟に云えば一種の神通力を具えていたよ。彼が白刃を揮うて武場にたつや,凛然たるあり,神然たるあり,迚も犯す可からざるの神気,刀尖より迸りて,真に不可思議なものであったよ。己れらは迚も真正面には立てなかった。己れも是非此境に達せんと欲して,一所懸命になって修行したけれども,惜乎,到底其奥には達しなかったよ。己れは不審に堪えず,此事を白井に話すと,白井は聞流して笑いながら,それは御身が多少剣法の心得があるから,私の刃先を恐ろしく感ずるのだ。無我無心の人には平気なものだ。其処が所詮剣法の極意の存在する処だと言われた。己れは其ことを聞いて,そぞろ恐れ心が生じて,中々及ばぬと悟ったよ。
その白井は,平和時の武術を晴天の雨具にたとえ,なるべく目立たぬことを心掛けるように説いたという。
雨でもないのに,これみよがしに剣術家然として歩くのは,晴れているのに雨具をつけて歩くようなもので,人々の顰蹙をかうだけだ,と。
また坂本龍馬を斬ったという今井信郎は,北辰一刀流の皆伝,榊原健吉から直心影流を学んだが,片手打ちという我流の実践剣法で,ひと打ちで相手を倒したらしいが,その彼が,こう言っている。
免許とか,目録とかという人達を斬るのは素人を斬るよりははるかに容易,剣術なぞ習わない方が安全,と。
追い込まれた人が,窮鼠猫を噛む状態の予想外の膂力とスピードの方が,対応できないということらしい。つまり,並みのプロと格段のプロとの違いは,そんな心構えにあるらしい。
言ってみると,剣術というのは,一定の枠組みの中で想定された枠内でやっているということなのかもしれない。そういう通常の剣法に対して,いわゆる「相ぬけ」を究極の形として目指した異色の剣法が,「無住心剣術」という。頂点は,相打ちではなく,相ぬけという。
剣術の勝負は,勝か負けるか,相打ちになるか,そうでなければ意識的に引き分けるか以外ない武術の鉄則を超え,お互いが打てない,打たれない状態で,たとえば,一雲と巨雲の師匠と弟子では,一方は太刀を頭上に,一方は太刀を肩の上にかざして,互いにすらすらと歩み寄り,いよいよの間合いに入ってから,互いに見合って,「ニコッ」とわらってやめた,という。しかし他流には負けたことがない,という。
「他流を畜生心によるもの」と開祖夕雲がいう,
「無住心剣術」の稽古法は,片手打ちで,特有の絹布や木綿でくるんだ竹刀で,ひたすら相手に向かって真っすぐ入り,相手の眉間へ引き上げて落とす,相打ちから入る。
よく当たるものはよくはずれ,よくはずるるものはよく当たる,
という言葉があり,相手はこっちの姿をみて打ち込んでくるが,こちらは敵を敵として認識せず,敵の気からはずれて出ていくため,意識的に打ち込むものほどはずれてしまい,こちらは相手の気筋を外してでるため,相手には不意に目の前にあらわれるように感ずるらしい。
心にとかくの作為があって勝負に臨めば,勝負にとらわれて,足がなかなか進まず,立ちが相手に届かない,
ともいう。いわば,「常の気のまま」を尊重する流儀のようで,相手を打つも自分が相手を打つというよりも,自然の法則(天理の自然)が自分の体を通して行われた,という理法のようだが,その太刀の威力は,すさまじく,竹刀打ちを兜で受けたものが,吐血したというほどのものだ。従って,無敗の剣とも言われる。
双方に戦う気があれば,相抜けにはならず,相打ちになる。
それで思い出したのが,69連勝でストップした横綱の双葉山が「未だ木鶏たりえず」といったとされる「木鶏」である。「荘子」にこういう逸話がある。
紀子という鶏を育てる名人に鶏の要請を依頼する。王は,10日ほど経過した時点で仕上がり具合について下問する。すると紀渻子は,「まだ空威張りして闘争心があるからいけません」と答える。更に10日ほど経過して再度王が下問すると「まだいけません。他の闘鶏の声や姿を見ただけでいきり立ってしまいます」と答える。更に10日経過したが「目を怒らせて己の強さを誇示しているから話になりません」と答える。さらに10日経過して王が下問すると「もう良いでしょう。他の闘鶏が鳴いても,全く相手にしません。まるで木鶏のように泰然自若としています。その徳の前に,かなう闘鶏はいないでしょう」と答えた。
いわば,この心境である。これを,こういっている。
当流に奇妙不思議な教えや修行法があるのではなく,人々がほんらいもっている天心を日々常に養い育て,私心を払い,意識を洗い捨てるからである。人々がみな,幼児の頃にはもっていながら,成長するにつれて,いつの間にかなくしてしまった一物(本来の天心)が,次第に立ち戻ってきて,肉体に再び宿ってくるそうなれば,命がけの場でも自然と霊妙な働きが生まれて,自由に敵をあしらう。
老子の
知る者は言わず,
言うものは知らず
をふと思い出す。この剣法は,江戸中期門人一万人と言われながら,ついに,いまに伝わらない。
ところで,小林秀雄は,武蔵について言及し,
彼(武蔵)は,青年期の六十余回の決闘を顧み,三十歳を過ぎて,次の様に悟ったと言っている。「兵法至極にして勝にはあらず,おのずから道の器用ありて,天理を離れざる故か」と。ここに現れている二つの考え,勝つという事と,器用という事,これが武蔵の思想の精髄をなしているので,彼はこの二つの考えを極めて,遂に尋常の意味からは遥かに遠いものを摑んだ様に思われます。器用とは,無論,器用不器用の器用であり,当時だって決して高級な言葉ではない,器用は小手先の事であって,物の道理は心にある。太刀は器用に使うが,兵法の理を知らぬ。そういう通念の馬鹿馬鹿しさを,彼は自分の経験によって悟った。相手が切られたのは,まさしく自分の小手先によってである。目的を遂行したものは,自分の心ではない。自分の腕の驚くべき器用である。自分の心は遂に子の器用を追う事が出来なかった。器用が元である。目的の遂行からものを考えないから,全てが転倒してしまうのだ。兵法は,観念のうちにはない。有効な行為の中にある。(中略)必要なのは,子の器用という侮辱された考えの解放だ。器用というものに含まれた理外の理を極める事が,武蔵の所謂「実の道」であったと思う。
そしてこうまとめている。
思想の道も,諸職諸芸の一つであり,従って未知の器用というものがある,という事です。兵法至極にして勝つにはあらず,というのは思想至極にして勝にはあらずという事だ。精神の状態に関していかに精しくても,それは思想とはいえぬ,思想とは一つの行為である。勝つ行為だ,という事です。一人に勝つとは,千人万人に勝つという事であり,それは要するに,己に勝つという事である。武蔵は,そういう考えを次のような特色ある語法で言っています。「善人をもつ事に勝ち,人数をつかうことに勝ち,身を正しく行うことに勝ち,民を養う事に勝ち,世に例法を行う事に勝つ」,即ち人生観を持つ事に勝つ,という事になりましょう。
「未知の器用」とは神業といっていい。そこまで,技量を極限まで極める。「相ぬけ」もまたそれだ。技は,結局身体が覚える。しかし,それは伝わらない。その人に体現されたものだからだ。五輪書を百回読んでも,技にはならぬ。
僕は,これを修羅場をくぐるという。つまり,技量の極北へ行くために,血みどろの努力がいる。イチローは,それを,
小さいことを積み重ねるのが,とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています,
という。結局,
知る者は言わず,
言うものは知らず
なのだ。
参考文献;
甲野善紀『古武術の発見』(光文社文庫)
甲野善紀『剣の精神誌』(新曜社) |
|
サムライとヤクザ |
|
氏家幹人『サムライとヤクザ』を読む。
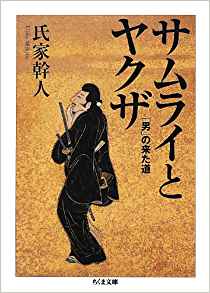
かつてもいまも,僕は,サムライを美化する連中を嫌いである。侍は,基本,社会の寄生虫である。穀つぶしである。ヤクザも同様だ。自閉し自己完結した世界に閉じこもり,それを完結させるために独自のしきたりと風儀を必要とする。
昔,博徒に仮託して,こう語らせたことがある。
「あっしはね,こう申し上げては失礼ながら,お武家様なんぞは,あっしら博徒同様,この世には必要のない,無職渡世ではないかと思いやすね,百姓衆にとっても,職人にとっても,ましてや商人にとっては,お武家さまなんぞは無用のものですよ,何かを生み出すわけではなし,ただ何の因果か上にたって威張ってお指図される。でも,その無用の方々がいなかったら,どれだけお百姓衆の肩の荷が軽くなることか,
お侍方は,仁とか義とか,仰ってますが,それは上に乗っかっておられる言い訳に聞こえます。理をこねくっておられる。いい迷惑です。いっそ,そこをのいてくれっていいたいですよ。あっしらにも,あるんですよ,仲間内の仁義ってやつが,杯かわした親分への忠,お互いの島への義ってやつですよ。でも,こんなのは,住んでいる人を無視して,勝手にあっしらが囲っただけですよ,これも似てるでしょ,お武家様のやり口に,まあ,真似たんでしょうがね。無職渡世は無職渡世なりに理屈がいるんですよ」
その通りなのだ。新渡戸稲造は,『武士道』で,こう書いた。
武士道精神がいかにすべての社会階級に浸透したかは,男達として知られたる特定階級の人物,平民主義の天成の頭領の発達によっても知られる。彼らは剛毅の男子であって,その頭の頂より足の爪先に至るまで豪快なる男児の力をもって力強くあった。平民の権利の代言者かつ保護者として,彼らはおのおの数百千の乾児(こぶん)を有し,これらの乾児は武士が大名に対したると同じ流儀に,喜んで「肢体と生命,身体,財産および地上の名誉」を捧げて,彼らに奉仕した。過激短気の市井の徒たるべき阻止力を構成した。
この愚かな文を読むだけで,『武士道』を読む気をなくすだろう。この「男達」を「暴力団」「ヤクザ」と置き換えればよい。第一,大正時代から,警察は,ヤクザを「暴力団」と措定し,その取締りを計っていることは,国立公文書館に当たれば,わかる。暴力団が男達(おとこだて)なんぞといわれたら,みかじめ料を拒んだがために殺されかけた人は何と言うか。
暴力団は勝手に,お互いの間で縄張りという自己の勢力範囲を設定し,縄張り内で風俗営業等の営業を行いあるいは行おうとしている者に対し,その営業を認める対価あるいはその用心棒代的な意味で,挨拶料,ショバ代,守料など様々な名目で金品を要求する。この要求に応じた者にこれを月々支払わせるが,これをみかじめ料と呼ぶらしい。
ともすれば,任侠道を表看板にし,暴力を武器としたアウトサイダーたちの反社会的行動であり,利権争いに過ぎない。任侠道などは,武士道同様,ないからこそ,あるいはすたれたからこそ,言挙げしなくてはならなかったまでだ。それが自己防衛というか,自分存在証明に他ならない。でなければ,存在する必要がないのだから。
ところで,明治期,『武士道』の英文が出た直後,こういう書評が出た。新渡戸が薩摩藩の若者が薩摩琵琶を奏でるのを「優美」と称賛したのに対して,
薩摩琵琶と関係の親密な『賤のおだまき』は之を何とか評せん。元禄文学などに一つの題目となれる最も忌まわしき武士の猥褻は,余りに詩的に武士道を謳歌する者をして調子に乗らざらしむる車の歯止めなるべし。
薩摩藩でとりわけ男色の習俗が顕著で,その事実を伝えず,美化するだけでは表面的だ,と言っている。ことほどさように,実は,実体としての武士とは別の世界を,虚構の世界を描いている,そう考えるほかない代物なのだ。
氏家幹人は,こうまとめている。
戦乱の世が終わり,武将が大名に昇華して,徳川体制に組み込まれた。その過程で,戦士の作法であった男道はすたれ,治者あるいは役人の心得である武士道へと様変わりする。爾来,武士は総じて非武闘化し,代わって,武家屋敷側が傭兵のように雇った,供回り,駕籠かきに委託した。次第に彼らは武士を軽視し,武家も彼らの命知らずの行動に危機感を抱きながら,ある種賞嘆の感情を抱くようになる。
結局平和ボケし,堕落した武士に変わって,馬鹿な男伊達を競う連中が出てきて,それがヤクザの精神の(いわゆる任侠の)淵源になっているだけだ。
幕末の開明的官僚,川路左衛門尉聖謨は,その一人。こう日記に書いている。
上かたの盗賊は,死するといふことはしりながら網のかかるまで先甘美軽暖の事によを過ごすか,百年生て乞人たらむよりは盗人と成てわかくして被殺かましといふかこときもの共にて,入墨後の盗なと少しもおしつつますみないふ也,死をみる如帰に人とは不思議也。
この畏怖の念に,すでに武士と盗人,ヤクザと区分けすることの無意味さが現れている。
結局大事なことは,もっともらしい看板や二本差しではなく,人としてどうなのか,ということが問われているだけだ。それに,任侠だの侍だの男だてなどの限定をする必要はない。
子曰く,暴虎憑河し,死して悔いなき者は,吾与(とも)にせざるなり,
である。
これでも三河武士の末裔だが,それでも,サムライであることを野放図に賛美する輩が信じられない。
参考文献;
氏家幹人『サムライとヤクザ』(ちくま文庫) |
|
リーダーシップの源泉 |
|
ジョセフ・ジャウォースキー『源泉』を読む。
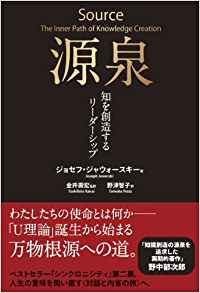
ジョセフ・ジャウォースキーは,こう言う。
数年にわたるリーダーシップ・フォーラムでの経験から,私は,人々の中には一体感を経験したい,自分より大きなものの役に立ちたいという強い欲求があることがわかってきた。そんなふうに役立つことが人間である意味だということも理解し始めた。だからこそ,個々のメンバーよりももっと大きなものと結びつき,一つの意識として行動するチームの一員であるという経験は,人々の人生においてたぐいまれな瞬間として光彩を放つことになるのだ。
それを場ができると呼んでもいい。その時,リーダーシップのあり方も変化している。ジャウォースキーは,リーダーシップを,四段階に分けた。
第一段階 自分が中心になるリーダー
この段階では,メンバーを大切にすることができない,信念がなく,自分の意思のほかは何にも左右されない未熟な段階。その時その時で変わる可能性があり,誠実さに欠ける。
第二段階 一定の水準に達しつつあるリーダー
メンバーを大切にする程度にまで成熟している。この段階にあるリーダーにとっては,安定性が大きな価値を持つ。彼らは公正さと礼儀とメンバーに対する敬意を大切にし,必ず組織の目標を達成する。この段階になると,性向は,メンバーとともに,そしてメンバーを通して成し遂げられる。
第三段階 サーバント・リーダー
帰属意識の範囲を広げ,あらゆる人を受け入れる。第三段階のリーダーは自分の権力を使ってメンバーの役に立ったり,メンバーを成長させたりする。この段階のリーダーは「強い達成欲求」を示すが,組織のメンバーや社会の誰かを犠牲にすることはない。
第四段階 新生のリーダー
昨今の山積する課題に対しては,サーバント・リーダーシップだけでは十分ではなく,サーバント・リーダーの特徴と価値観を持っているが,全体的なレベルが一段上がる。そして目を見張るような働きをし,業績を上げるその中心には,暗黙知を使う力がある。第四段階のリーダーは,宇宙には目に見えない知性があって,私たちを導き,創り出すべき未来に対して準備させてくれると確信している。
いまの場を,いまのチームを,より大きな広がりの中で,全体の中で,位置づけなおす,ということは,意味を変えることかもしれない。意味が変わると,現実の見え方が変わり,行動の意味も変わる。
ジャウォースキーは,最終的に4つの原理にまとめる。
①宇宙には開かれた,出現する性質がある。
一連のシンプルな構成要素が,新しい性質を持った新しい統一体として,自己組織化という,より高いレベルで突然ふたたび現れることがある。そうした出現する性質について原因も理由も見つけることはできないが,何度も経験するうちに,宇宙が無限の可能性を提供してくれることがわかる。
②宇宙は,分割されていない全体性の世界である。物質世界も意識も両方ともが,分割されていない同じ全体の部分なのだ。
存在の全体は,空間と時間それぞれの断片―一つの物であれ,考えであれ,出来事であれ―の中に包まれている。そのため,宇宙にあるあらゆるものは,人間の意思やあり方を含め,ほかのあらゆるものに影響を及ぼす。なぜなら,あらゆるものは同じ完全なる全体の部分だからである。
③宇宙には,無限の可能性を持つ創造的な源泉がある。
この源泉と結びつくと,新たな現実―発見,創造,再生,変革―が出現する。私たちと源泉は宇宙が徐々に明らかになる中でパートナーになるのである。
④自己実現と愛(すなわち宇宙で最も強力なエネルギー)への規律ある道を歩むという選択をすることによって,その道では,数千年にわたって育まれてきた,いにしえの考えや,瞑想の実践や,豊かな自然の営みに直接触れる事から,さまざまな教えを受けることになる。
本物のリーダーシップとは,出現する場をうまく使って,新たな現実を生み出す技術だという。そして,あらわれることになっているものは,何を成し遂げるかを決めたときに初めて現れる。だから,自分の中から現れようとするものに,この世界の存在の過程に,耳を傾ける。世界によって支持してもらうためでなく,世界が望むとおりに世界を実現するために。
では,どうすればいいのか。マイケル・ポラニーは,そのプロセスをこうまとめている,という。
①ふとした折に,それとなく示される
発見のプロセスは,見出されるべき問題がふとした折にそれとなく示されて,おぼろげに始まる。それは心の奥から沸き起こるぼんやりした声,すなわち「明確に言い表すことのできない衝動」であり,その衝動の中で,ほかの人が存在していることに気づきさえしない問題を感じ取ることになる。
②宇宙の意思によってヒューリスティックな情熱が引き起こされる
最初に起きるぼんやりした暗示は,発見者によって,探究しようという固い決意へと変わる。これは使命,すなわち宇宙の意思によって突き動かされるヒューリスティックな情熱,自分自身より大きなものに身をゆだねるという行為へと進化する。
③身をゆだねること,奉仕する気持ち
発見者は,現れようとしているものにいっそう近づくために,自分の現在の知から離れようとする。
④精力的に理解を深める人として内在する
発見者は労苦を重ねることによって,心が整い,自分ではコントロールできない源泉から真実を受け取れるようになると信じて行動する。
⑤一歩下がることと突然のひらめき―恩寵
探求は静かに時が流れたのちに終わりを迎える。ふいに恵治がって問題の解決策がもたらされる。
⑥試してみることと確認
こうした勝利の閃光によってもたらされるものは,普通の解決策ではなく,まだ試していない方法に思い当ったにすぎない。
まさに,U理論のステップの,Uの谷の底の,「内在ひらめき」プロセスで,源泉とどう意思疎通するか,だ。
①全体を見渡す力 他の視点からの見方に,つまり別の現実があり得ることに心が開く。
②メタファーの魔法 目の前の課題について認識される状況を,不可能と思われる状況から無可能な状況に変える。
③共鳴の役割 もともと別々だった二人の私が,共有される私になり,現実に対する認識や解釈を変えられるようになる。
④不確かさに身をゆだねる 不確定性とともに流れる。現実が望むように現実に現れさせる。
⑤概念的相補性についての論証 原子スケールでの波動・粒子の二重性が相補的であるように,その現実をその現実が望むように明らかにしなくてはならない。意識と源泉も相補的,相互重なりあって経験を生む。
⑥心のセルフマネジメント 心を鍛えるツールを使う。
ボームは,その人がたゆまぬ個人的鍛錬をするならば,人の肉体は,予期せぬ大量の情報の入り口になる,といっている。
ここでは,三つを挙げている。
ひとつは,世界はひらかれ,可能性にあふれていると考えることで,心のあり方が可能性へシフトする
いまひとつは,内面を鍛える。瞑想,観想,自然の中で過ごす等々
そして,即座に行動する勇気
結局,神秘的な「啓示」や個人的な瞑想的なものに丸められてしまっているのが気にいらない。それが大事だということは認めるにしても。
監訳者金井壽宏は,こうまとめる。
出現する未来を感じて,それを現実のものにしていく。そのような力が,ビジョンに向かって,人々を巻き込み,そのビジョンを実際に現実のものにしていくというリーダーシップの基盤にある。こうしたジャウォースキーのリーダーシップ論が通常のリーダーシップ論と大きく異なる点は,その一種の神秘的な性質にある。つながり合う人々の「出現する未来」への想いが強ければ,偶然も味方となり,いろいろな流れが絶妙のタイミングと組み合わせで合流する局面がある,とジャウォースキーは示唆している。
「源泉(ソース)」とは,ボームの言葉では,「内蔵秩序」である。リーダーシップ,チームワークがうまくいくとき,ひとつの意識として行動しているという感覚をもたらすものであり,個々のメンバーよりももっと「大きなもの」に結びついているという感覚をもたらすもの,と言えよう。
ボームの言う内蔵秩序というのは,境界や単独の存在を離れ,全体論や相互のつながりを指す。「非分離の分離」という。たとえば,音楽に夢中になっているとき,それを直接経験している。フロー状態もそれだ。バラバラでありながら,一つの感覚を同時に持つというのは,確かにまれだがある。
結局リーダーシップを,また特殊なものに還元しているとしか思えない。こんなことをしているうちに社会は動く。人は飢え死にする。リーダーシップをどこかカリスマ性へ戻そうとしているようにしか見えない。だとすれば,矛盾と腹立ちを覚えるだけだ。
参考文献;
ジョセフ・ジャウォースキー『源泉』(金井壽宏監訳 英治出版)
デヴィッド・ボーム『ダイアローグ』(金井真弓訳 英治出版)
マイケル・ポラニー『暗黙知の次元』(佐藤 敬三訳 紀伊國屋書店) |
|
空海 |
|
篠原資明『空海と日本思想』を読む。
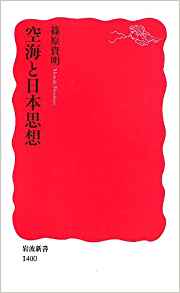
著者は,プラトンに西洋哲学の基本系として,美とイデアと政治,を見て,それを日本になぞらえ,空海の風雅・成仏・政治を仮定した。それに基づいて,日本思想の基本系を推し量ろうとしている。
その仮説の是非はともかく,ある意味では,芸術から宗教,政治に関わる幅広い空海の知的活動を網羅する試みであり,その巨大な思想の後世への影響を見積もろうとしている,ともとれる。空海の書は知られているが,現存する個人詩集のある,日本最古の詩人でもある。
①風雅について
ここでいう,風雅は,芭蕉の『笈の小文』にいう,
西行の和歌における,宗祇の連歌における,雪舟の絵における,利休が茶における,其貫道するものは一なり。しかも風雅におけるもの,造化に随い四時を友とす。
の意味になる。それを著者は,
和歌と連歌と絵と俳諧を統括するものが風雅に見出されていること。第二に,その風雅のありようが,自然に従い季節の運行を友とするものとして理解されていることだ。
とまとめ,風雅が芸術全般に及ぶ広い意味につかわれる遠因に,空海がいる,という。空海は言う。
目もて其の物を覩(み)れば,即ち心に入る。心に其の物に通じ,物通ずれば即ち言ふ。其の状を言ふこと,須く其の景に似るべし。語は須く天海の内を,皆な方寸に納むべし。
詩は志に本づくなり,心に在るを志と為し,言に発するを詩と為す。情(こころ)中に動きて,言に形(あら)はれ,然る後に之を紙に書くなり。(『文鏡秘府論』)
空海に心酔する京極為兼は,その歌論『為兼卿和歌抄』において,こう書く。「うちに動心をほかにあらわして,紙に書き候事」。芭蕉もまた,空海を意識して,こう風雅を語る。「古人の跡を求めず,古人の求めたるところを求めよ」と,南山大師(弘法大師)の筆の道にも見えたり。風雅も又これに同じ」と。
必ず須く心を境物に遊ばしめ,懐抱を散逸す,法を四時に取り,形を万類に象るべし。
と,心を自然のあれこれに遊ばせつつ,吸収し,それらを自分のうちからわきいずるように詩と書にあらわす,そう空海は言う。
しかし,その背後にあるのは,服部土芳が,「乾坤の変は風雅の種」と芭蕉の言葉を伝えつつ,「無常の観,なほ亡師の心なり」と付け加えざるを得ない心情である。空海は,長編詩「山に遊むで仙を慕ふ」で,
一身独り生歿す
電影是れ無常なり
とうたう。その背後にあるのは,金剛般若経の,
一切の有為法は,夢・幻・泡・影の如く
露の如く,また,電の如し
まさにかくの如き観を作すべし
ここで連想されるのが,「さび」だろう。その理解に必要なのは,草庵と隠遁という生活のありようだ,という。つまり,無常,離脱,大自然。その要件は,空海の,上記詩句の,「わが身はひとりぼっちで死んでいく,まさに稲光のように一瞬だ」の中に満ちている。
②即身成仏について
遮那阿誰(たれ)が号(な)ぞ
本是れ我が心王なり
空海のこの詩句を,前述した「語は須く天海の内を,皆な方寸に納むべし」と対比するとき,
仏も人も,六大,すなわち,地・水・火・風・空・識を共通要素とし,それ以外の非情と呼ばれる存在も含めてありとあらゆるものが六大からなる。地・水・火・風は物質要素,空は環境,識は心(『即身成仏義』)。この立場からすれば,法身大日如来と個々人との間に本質的違いはない。見方を変えれば,すべてが大日如来に通じている。だからこそ,大日如来の境地に立ちいたるのに,この身を捨てず,この身に即して大日如来になることができる,いやすでに,大日如来となっている。即身成仏とはこのことをいう。
誰もがあるがままにあらゆるものを知る智を備えている。とすれば,
五大には皆響き有り
十界には言語を具す
六塵悉く文字なり
法身は是れ実相なり
つまり,森羅万象が言語表現を行う。人がそれを友として,表現を行うことはありえる。古今集は言っている。「花に鳴く鶯,水に住むかはづの声を聞けば,生きとし生けるもの,いづれか歌をよまざりける」と。芭蕉も,「松のことは松に習へ,竹のことは竹に習へ」と教える。
③政治について
生けるものの世界,および生けるものが拠りどころとする自然世界をあわせて国と名づける。智慧は,よくこのふたつの世界を護って災難を払いのけ幸福を招く。それを護国と名づける。
そう空海は言う。一切衆生をしてみな歓喜を得せしむために,成仏がある。そのために高野山に伽藍を建立する。大日如来の悟りのいきわたる世界にするために。それを報恩という。
父母の恩,国王の恩,衆生の恩,仏法僧の恩。この四恩に報いる。
生きとし生けるものは,輪廻転生を繰り返すなかで,自分の父であったかもしれず,子であったかもしれず,王,さらには師であったかもしれない。だからこそ,衆生に報いるべきと,空海は説く。
最後に著者は,長編詩「山に遊むで仙を慕ふ」から,二行ずつ摘み取り,
一身独り生歿す
電影是れ無常なり
遮那阿誰(たれ)が号(な)ぞ
本是れ我が心王なり
四行詩にして,こうまとめる。
わが身は一人ぼっちで生まれては死んでいく。まさに稲光のように一瞬のうちに。大日如来とは,元はと言えば,自分の心のことだ。ここにある,「寂しさ」に,三つの段階をみる。
第一は,孤独感が無常観によって強められる
第二は,無常観の共有による孤独感がいやされる
第三は,無常とは,生成変化するものすべてに共通する
ここに,風雅の道がある,という。芭蕉の,
無常の観,なお亡師の心なり
千変万化するものは自然の理也
不易流行
乾坤の変は風雅の種なり
新しみは俳諧の花也
風雅には,芭蕉にとって,生成変化する自然に身も心も託しきる。そこに,寂しさと新しみがある。
とまあ,基本系という枠組みの中で,風雅をとらえ直す試みということができる。背景に,ここでは詳しく触れなかったが,本地垂迹つまり,密教に組み込まれた神道,アマテラスが大日如来を本地として日本に姿を現した等々をも併せ考えていくと,空海の巨大な影響力が見えてくる。
しかし本書は,最後に三島由紀夫になぞらえて,天皇に言及し,天皇によって執り行われる和歌とまつりごとは,自然を真ん中において,和歌・自然・まつりごととして構造化され,わが国の,風雅・と政治の雛形だと位置づけなおして見せた。ここは,異論の出そうなところかもしれない。むしろ,空海の掌の上に,すべて乗っている,と見たほうがスケールが大きくていいかもしれない。
参考文献;
篠原資明『空海と日本思想』(岩波新書) |
|
象徴 |
|
千田嘉博『信長の城』を読む。
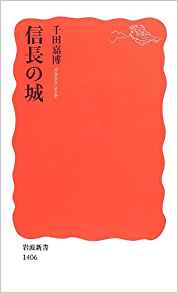
信長が館城とした,勝旗城,那古野城,清州城,小牧山城,岐阜城,安土城と,信長が住まった城の軌跡を通して,信長が,なそうとしたこと,めざしたものが見える,と著者はいう。
①近世城郭が獲得した強力な象徴性を創り上げたこと。これはいまでも受け継がれ,我々に影響を与えている。
②自分を頂点とした武士の権力構造を,城づくりの中につくりだしていった。
③信長を頂点とした秩序観は,城下一体にも城と町とが一体化させた,近世的な城下町を実現した。
その出発点は,父信秀から譲られ,初めて城主となった那古野城に見ることができる。信長は,林秀勝,平手政秀,内藤勝介という宿老がついた。那古野城の発掘でわかったことは,那古野城の周囲に,そうした宿老たちの,堀を備えた強固な館城群がみられたことだと,著者は言う。その周囲に,家臣屋敷を配置し,社寺や市町を再編して取り込んだ,室町時代から戦国期の城下町と変わらぬものであった。
那古野城下に凝集的に建設された館城群の堀は,強力な防御性をもち,那古野城と変わらぬ防備を施した館城を築いて,軍事力を分有し,相対的に高い自立性を持っていた,ということが,城から読めるのである。
実際林秀勝は,弟の信行を後継者として謀反を起こしたが,信長軍700に対して,柴田(勝家)・林の動員したのは,柴田1000,林700と,信長を凌駕していた。
著者は言う。
信長は生涯をかけて,大名と家臣たちの分立・連合的な権力構造を脱却し,大名を中心とした求心的な権力を生み出そうとしていきました。それは同時代のほかの大名より徹底し,また地域的な一揆体制による横並びの権力が各地に根を張った戦国期の社会構造とも異質なものでした。四方を敵に囲まれ,兄弟,一族,宿老からも背かれた若き日の過酷な経験が,信長に専制的な権力を目指す道を選ばせたのかもしれません。
次に入った清須城には,『信長公記』の記述によって,北矢蔵,南矢蔵と呼ばれる,櫓があったことがわかるが,「天主」と呼ばれるほどの櫓だった。著者は,当時の多くが山城に拠点を移していたが,当時の「大名の拠点変化に遅れた城郭形態だった」という。平らな清州周辺では,山はなく,そのために,「北矢蔵」「南矢蔵」という立派な櫓を備え,防御を重視した館城を建設したのは,尾張における戦国期拠点城郭への変化とみられる,という。ただ
清須城では館そのものが複郭化したのではなく,防御面から,館城を並列的に配置するにとどまったもので,清須城を中核として周辺の館城を階層的に再配置できる政治体制ではなかった。したがって,城の周囲には,直属の家臣や直属の商職人の住むエリアを堀で囲んだ惣構えがあり,その外にも,一般の商職人の住む市町とがある。
戦国時代の城下町は,城を中心に大名と武士・直属商工業者の住む惣構えで守られた町と,それから空間的に分離した市町という二元構造になっているが,清須城下はその構造になっている。
次の小牧山城へ移る前,二宮山へ移ると言ったが,家中の不満が大きいため,標高が三分の一の小牧山へ移ると言って,家中を納得させた。この時代は,重臣たちは,それぞれの領地に館城をもち,清須に出仕した時の屋敷を清須城下にもっていたが,妻子は本拠の館城に住んでいた。
信長は,直臣に対しては,屋敷の配置を直接指示し,信長を中心とした求心的な城下町を築こうとしたようだ。ただ,他の戦国大名に比べると,50年も遅れて山城の拠点化を始めている,ということを著者は強調している。
信長は,常に時代の先端を切り開いていたのではありません。それどころか,居城の選択という点では,大幅に遅れた大名であった。
にもかかわらず,古代以来の伝統的な都市設計ではなく,効率的な長方形街区と短冊形地割を組み合わせた,近世城下町の源流になっている,というところが面白い。しかもあらかじめ,長方形街区の街路を挟んで両側に立ち並んだ町屋の敷地奥の境界線にそって,南北に整然とした排水施設「背割り下水」が設けられていた。ここでも信長の合理性が垣間見える。
家臣との関係では,直臣はともかく重臣は,まだ別途に館城をもつという,並列的な関係が続いており,小牧山城は,先進的な街づくりと同時に中世的な面も強く残していたと言えるらしい。しかし,小牧山城の大手道をみると,山麓・山腹では,意図的に防御性の弱い,直線道にして,中心部だけを防御性を高めた曲線の大手道にするなど,信長は目指す方向に一歩歩みを進めていたようだ。
次の岐阜城では,家臣との間の絶対的な階層構造を実現しようとしている。それは裏を返すと,家臣に君臨する信長の権力基盤が圧倒的に強化され,重臣が相対的に下位になり,かつての重臣に支えられた構造ではなくなったことを反映している。
岐阜城は,大きく山上の城と山麓の館に分かれる。その間300mの比高差があり,山城には,信長家族と限られた家臣しか立ち入ることができない。一方山麓の館は,守護公権力を受けついだ公権力としての権威を象徴した,室町時代の武家儀礼にのっとった空間構成になっていたが,その構造は,七層もの曲輪を階層的に積み重ねた,しかも身分によって入り口や道が違うなど,家臣との横並びではなく,家臣の上に立つ権力者として臨んだ,という姿勢を明確に反映したものになっている。
信長の目指した圧倒的な上下関係を構造として構築した城の構造になっている。かつては,武家の一部が分散していた小牧山城に比して,劇的な変化をなし,それぞれが別個の館城を築いて分立的な面影は消え,柴田勝家も,木下藤吉郎も,一族の織田信広も,肩を並べた武家屋敷街を形成していた。城下町はやはり惣構えの内と外の二重構造にはなっているものの,惣構え外の市町には,楽市の制札を出し,市町へ引っ越すものに,特権を与えたのは有名な話であろう。
そしてその集大成が安土城ということになる。安土城は,最高所の天主を核として,山腹から山麓,周囲の平地にかけて,階層的な武家屋敷を計画し,そうした求心的な城郭構造を,実現するため,天主,高石垣,巧みな出入口,瓦葺で礎石建ちの建物群を揃えた,近世城郭を最初に実現した城となる。さらに,城下町は,城下の街全体を自由な楽市とする画期的な政策を実施し,城と町が一体化した一元的な城下町を実現した。しかし,実態は,武家屋敷は,妻子の居住する本宅ではなく,あくまで,安土に出する時の屋敷でしかなく,その意味では,まだ過渡的なものであったことがわかる。
他の戦国武将に比べると,信長は一貫して信長を頂点とした求心的な権力を目指した。他の城では,曲輪が横並びに連結した並列的な構造なのに,信長は,旧来の並列的な分立構造をリセットするように,城を建て替えるたびに,階層構造にこだわった。例えば,安土城では,信長の居所である城郭中心には瓦を用い,家臣の屋敷には瓦の使用を禁止するなどにも,典型的に意図を見て取ることができる。
信長が城下町を地域の経済・流通の拠点にしていくという,特に安土城で見せた城づくりが,近世へと受け継がれていく。その意味では,信長の目指した社会構造,自分を中心として,武家,商工業者,階層化させたものが,江戸時代の構造へとつながっていく,という気がする。
城づくりをただマニアックな構造にとどめず,信長の意図を,発掘と航空写真,絵図を対比しつつ総合的に示した本書の意図は,読後強く印象に残る。
参考文献;
千田嘉博『信長の城』(岩波新書) |
|
嫌悪感 |
|
レイチェル・ハーツ『あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか』を読む。
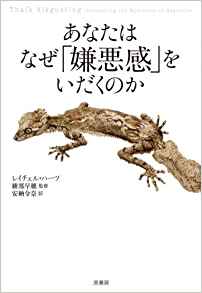
※
嫌悪感とは決して腹黒い感情ではない。嫌悪感とは,他者に共感できる文明化された人間であるがゆえの副産物である。
嫌悪感はきわめて社会的な感情である。
レイチェル・ハーツは,『あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか』で,こう書いている。
ただ,ハーツの言うのは,disgustのことで,むかつく,嫌気と訳されているが,監修者の綾部早穂さんは,
怒り(anger)は,頭や腹にきて,嫌悪(disgust)は胸に来るもののようである。「胸糞悪い」もdisgustに対応する。
と書いている。もともと日本人は,嫌悪の表情は,怒りや悲しみとまぎれやすいらしいので,日本人は嫌悪の表情を出すのが北米人に比して少ないとも言われているようだが,それは表情のことであって,感情としてはないわけはない。しかし,ハーツもこう言う。
嫌悪感とは,おおむね普遍的でありながら,生まれつき備わっている感情ではないことがわかった…。何を不快に思うかは人それぞれであり,時と場合によっても意味が異なる…。つまり置かれた状況,文化,そして生い立ちによって形作られるのである。また,嫌悪感には人間の感情でも独特の複雑さがある。
ふと連想したのは,ハンソンが,21世紀のわれわれと13世紀の人々とは、日々巡る太陽に同じものを見ているのだろうか?なぜ、同じ空を見ていて、ケプラーは、地球が回っていると見、ティコ・ブラーエは、太陽が回っていると見たのか?という問題意識だ。
たぶん,われわれは対象に自分の知識・経験を見ている。あるいは知識でつけた文脈(意味のつながり)を見ている。21世紀の我々には、宇宙空間の適当な位置から見れば、地球が太陽の回りに軌道を描いていると知っており、その知っている知識を見ている。13世紀の科学者は、太陽が地球の回りに描く軌道という知識、プトレマイオスの天動説を見ている。見ているのは知識なのだ。
アインシュタインは「われわれに刷り込まれたモノの見方の集合体」と呼ぶが、邪魔したのは、この「〜として見る」「〜としてしか見ない」われわれの知識である。ゲーテが,われわれは知っているものだけを見る,と言ったそうだが,それと同じことが,嫌悪感にも言えそうなのだ。嫌悪感には,こちら側の知識と経験がある。
西洋人には,納豆は,「アンモニア臭とタイヤを燃やしたにおいがマリアージュ,つまり組み合わさったように思える」という。しかし,そのハーツでさえ,「カース マルツゥはイタリアのサルディーニャ地方でよく食べられている羊のチーズ」は,苦手だという。「俗にうじ虫チーズと呼ばれていることからもわかるように,このチーズには文字とおり生きた幼虫がひしめいている」。そして「食べごろになったカース マルツゥには,通常,何千もの幼虫が宿っている。それどころか,地元の人々は,幼虫が死んでいるカール マルツゥは危ないと考えている。そのため,生きた幼虫が蠢いたままで,供される。」
で,こう言い切る。「もっとも原始的な嫌悪感情の生来の目的は,私たちが,腐敗して毒性をもつ食べ物を口にしてしまうのを避けるためにある」と。
ほとんどの場合,何かに嫌悪感をいだくか否かというのは,見る側の気持ちが決める。
その背景になるもののひとつが,文化だ。食べ物の価値が敵と味方を分ける。
文化を区分する際にもう一つ大切な目印は,…人間の体は,食べたものと同じにおいを発する。…これは,食べ物に含まれている臭気成分が,肌や汗を通して放出されるからである。こうしたにおいは,共通の食文化を有している限りは,「同じものを食べているからあなたが好き」と言う根拠になる。
つまるところ,
食べ物と,それを食べる人が不愉快かどうかをきめるのは,私たちの思考,つまり私たちの心なのである。
その嫌悪の感情は,人間の中枢神経システムを支配し,血圧を下げる。そのせいで発汗量が減り,失神,悪心,吐き気などが起こされる。…嫌悪感情からは,やんわりした反感から抑えきれない憎悪まで,さまざまな精神状態が引き起こされるが,これらにはすべて,その嫌悪感情の原因に対して,そこから逃げようとしたり,排除しようとしたり,そして多くの場合,避けようとする衝動感が中核にある。
予想されることだが,嫌悪感は,子供にはなかなか習得しにくい感情である。…子どもというものは幸福感を最初に覚え,次に悲しみと苦痛を覚える。…少なくとも,三歳になるまでは,どんな形の嫌悪感も経験しない。
子どもは怒りと嫌悪の表情の区別がつかないが,その区別の能力は,その子が何かについて嫌悪を感じるようになる能力と一致しているらしい。つまり,最初にトイレの躾をし終えて,「うんちでお絵かきしたりたべたり」しなくなり,嫌悪を理解するようになる。それは,
知的発達と同じ軌跡をたどるのである。
子どもたちは他のどの感情よりも,嫌悪感についての文化や社会の基準に触れ,そこから学ぶ必要がある。たとえ,それが何であろうとも,文化の違いは,不快なものへの態度の違いとなって現れる。
つまり,嫌悪感は生まれつき備わったものではない。人間は嫌悪感を経験できる唯一の生き物といえる。つまりチンパンジーやゴリラにはない文化的な背景が,嫌悪感と深く結びついていることを予想させるのである。
ではそれは脳とどうつながっているのか。
嫌悪感を示す顔を見せた時もっとも活性化するのは,側頭葉,前頭葉,頭頂葉の下に隠れている島皮質がもっとも活性化する。そのため,
嫌悪感を味わうには,損傷のない脳構造のネットワーク,特に島皮質が必要だ。ところが,そのほかにも必要なものがある。嫌悪感というのは,学習を経なければ身につかない唯一の感情だ。そして,それには複雑な思考と解釈も求められる…。言い換えると,嫌悪感にはあるレベル以上の認知能力と社会性が必要なのだ。さらに…他者の嫌悪感を正確に認識するためには,正常に機能する脳を持つことが必要であり,それとともに社会的な学習も求められる。
たとえば,大脳基底核の神経細胞が委縮するハンチントン病の人は,他人の嫌悪感を読み取れない。強迫神経症のひとも,嫌悪表情が読み取れない。ところが,ヘロイン中毒者は,嫌悪感情を理解できている。これは,
社会における暗黙の了解や経験が,嫌悪の解釈や経験にいかに欠かせないものであるかを示している。さらには,社会生活から受けるフィードバックにはあまりも大きな影響力があるため,あなたが抱いた嫌悪感が,そのまま私の嫌悪感になることすらある…。
嫌悪感は,社会文化的な反映であることが,はっきりしている。内に籠ったり,自閉状態にあると,社会的な感情経験と他者との交流の中で育まれる感情が育たず,脳としてのハードウエアが正常でも,嫌悪感情は育たない。外との間の中で,身に着けていくものであるらしい。
嫌悪感情をいだくか否かは,そのような感情をいだいてしまう可能性のある状況や対象についての判断できる能力によって左右される。
※※
ハーツは,面白いことを言う。
多くの感情には,ポジティブな気持ちよりもネガティブな気持ちが勝るほうが物事がうまく運ぶのだ。なかなかそんなふうには思えないかもしれない。しかし,ポジティブさよりもネガティブさの方が多めというアンバランスに基づいて行動した方が,生物学的に見ると生存適応性が高くなる。プラス面に近づくよりも,マイナスを回避する方が,生存にはずっと有利なのである。
世をあげてポジティブ思考なのだが,程度問題だ。能天気なのは,リスク対応ができない,それは人間の嫌悪感の存在理由とつながっている。嫌悪感の敏感なものが,生き残ってきた。
たとえば,ハーツは,「見るも恐ろしい」病もちの物乞いから逃げたがる衝動を嫌悪感と呼び,
嫌悪というのは,恐怖の一種,つまり病が招く緩慢で不確実な死から逃れさせるために進化した,特殊なタイプの恐怖だからである。…恐怖は衝動的で思考を伴わず湧き起こり,素早く激しく,そして差し迫った危険が招く死を避けるのに役立ってくれる。…これと対照的に,嫌悪感は学習され,熟慮的で,かなりゆっくり進行している。
一定の認知を経て理解するプロセスが介在しないと嫌悪が起きない,という。脳は,恐怖は扁桃体が活性化し,嫌悪感は,島皮質が活性化する。
嫌悪は,人間の感情をつかさどる六つの基本感情のなかでも,最新でかつ先進的であると私は確信している。(中略)人類はなぜ,恐怖というより基本的な反応から,嫌悪感を発展さ是なければならなかったのか。それは,人間の寿命が哺乳類のなかでも特別に長かったからだ。
と言う。つまり,嫌悪感の神経学的な基盤が,嫌悪感の基本的な特徴が人間を病気から守ることだ,として,ある実験の例を挙げる。
健康な被験者に無害な細菌を注射し,悪人たちがピストルで威嚇している写真か,あるいは発熱している人の写真,
咳をしている人の写真,痘痕だらけの人の写真のいずれかを見せた。次に被験者の血液を採取して,免疫反応の強さを測定したのである。その結果,病気の写真を見た人は,恐怖心をかきたてられる写真を見た人よりずっと免疫反応が強かったという。これは,病気にかかっている人を見ることで,体内の免疫システムが誘発されて,迫りくる病気と闘う反応を起動させることができることを意味する。しかし,病気の写真を見て,強い嫌悪感を感じた人は,特に感じなかった人に比べて,免疫システムの反応が低かったという。
これについて,ハーツはこう説明する。
私たちには生まれながらにバックアップシステムが備わっているからではないだろうか。嫌悪感を刺激しても病原菌から逃げたいという気持ちに心が向かわない場合には,身体が病原菌と闘おうとしてより激しく積極的に免疫システムが働く。逆にいえば,身体の免疫システムが十分にしっかりしていない時にこそ,心は嫌悪感をよりいだきやすくなるのだ。…免疫システムが危うくなると,健康そのものである時よりもよりたやすく,激しい嫌悪感を催すことが多い。
こう考えることができる。十分身体の免疫システムが働かない時は,嫌悪感で,それを回避して,「行動による免疫システム」を働かす。つまり回避して,避けようとする。
しかし醜いものや気持ち悪いものを回避することは,単に「行動による免疫メカニズム」と呼んでもいいのか?それとも,社会的差別や反感の正当化なのではないのか?そうハーツは問いかける。なぜなら,子どもはそれを避けたりはしない。だから生得のものではない。
むしろ,「不適応者」に対する嫌悪感情の根源にあるのは,もっと深いところに潜む懸念だと私は確信している。
それを「死」とハーツは言う。ある実験では,自分の死について心に浮かぶ感情をじっくり考えてもらい,死んだときに肉体に何が起こると思うかを書き留めてもらった。その結果,自分の死について考えると,嫌悪感受性が高くなった,という。だから,
いつか死ぬ運命だと想起させる他人や刺激を嫌がる気持ちは,そもそも自分自身の死への意識と,死に対していだく恐れだ。
嫌悪感をコントロールするのは,死への恐怖なのだ,と言う。そして,共感との関連で,こうまとめている。
結局,…嫌悪感は,どんな不愉快なことが我が身に起こるかについて知る,生き残るための直感だ。
その意味で,他の,喜び,悲しみ,怒り,恐怖,驚きは,嫌悪感と比べると,はるかに自動的,反射的で,しかも外から与えられる感情である。嫌悪感には,幼い子供や動物にはみられない,ある意味で自己中心的な思考と自覚が必要だ。基本的に嫌悪感は,本質的に自己焦点的であり,内省的だという。
ある意味嫌悪感が,社会的な産物なら,差別も価値観も,また内省によって崩すことができる。知識と経験が嫌悪をもたらすなら,知識と経験が嫌悪感を消してくれるはずなのだ。嫌悪感が,知的発達と同じ軌跡を描くのであれば,意味のない嫌悪は,知的レベルの低さを反映している。
参考文献;
レイチェル・ハーツ『あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか』(原書房)
ノーウッド・R・ハンソン『知覚と発見』(紀伊國屋書店) |
|
小楠論 |
|
松浦玲『横井小楠』を参考に小楠について考えてみた。
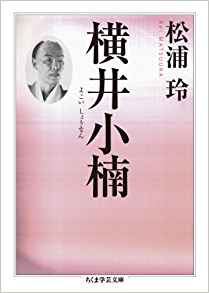
※
横井小楠については,概略は,
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E4%BA%95%E5%B0%8F%E6%A5%A0
で知っていただくとして,「今までに恐ろしいものを二人見た。それは横井小楠と西郷南洲とだ」と勝海舟は「氷川清話」で述べていることから紹介しておきたい。さらに「横井の思想を西郷の手で行われたら敵うものはあるまい」とも述べている。妹婿の佐久間象山ではなく,小楠を挙げているところが海舟らしい。
坂本龍馬の船中八策も由利公正(三岡八郎)の五箇条の御誓文も,元は横井小楠にある。坂本の師匠勝海舟とは,肝胆相照らす間柄で,坂本も勝の使いで何度も,熊本に蟄居中の小楠をたずねている。由利は,小楠が越前に招聘された折,立てた殖産興業策に触発され,横井から財政学を学び,藩札発行と専売制を結合した殖産興業政策で窮乏した藩財政を再建する。
その由利と龍馬は気が合い,2度目の福井来訪時,早朝から深夜まで延々日本の将来を語り合ったという。背後の小楠の思想が,生かされている。明治新政府に召されたのも故なしとしないが,ために暗殺されることになった。
ついでながら,横井小楠については,松浦玲『横井小楠』(筑摩学芸文庫)を読んでほしい。本文の倍の注が,この本自体のもつ,通常の伝記ものとは異なる破格の熱が伝わってくる。因みに,松浦の『勝海舟』もいい。海舟全集を編集しただけに,細部がよく見えている。それに『坂本龍馬』もある。
小楠は実践家なので,学問も,政治としての実践論になっている。ここでは,小楠の思想をふれるには力量不足なので,その講義の一端と,自分の好きな詩を紹介してお茶を濁す。一回でまとめようと思ったが,長くなりすぎたので,二回にわける。
学問の学び方が,実にユニーク。実学と称されただけのことはある。
学の義如何,我が心上に就いて理解すべし。朱註に委細備われとも其の註によりて理解すればすなわち,朱子の奴隷にして,学の真意を知らず。後世学者と言えば,書を読み文を作る者を指していうようなれども,古えを考えれば,決して左様な義にてはなし。堯舜以来孔夫子の時にも何ぞ曾て当節のごとき幾多の書あらんや。且つまた古来の聖賢読書にのみ精を励みたまうことも曾て聞かず。すなわち古人の所謂学なるもの果たして如何と見れば,全く吾が方寸の修行なり。良心を拡充し,日用事物の上にて功を用いれば,総て学に非ざるはなし。父子兄弟夫婦の間より,君に事え友に交わり,賢に親づき衆を愛するなり。百工伎芸農商の者と話しあい,山河草木鳥獣に至るまで其の事に即して其の理を解し,其の上に書を読みて古人の事歴成法を考え,義理の究まりなきを知り,孜々として止まず,吾が心をして日々霊活ならしむる,是れ則ち学問にして修行なり。堯舜も一生修行したまいしなり。古来聖賢の学なるもの是れをすてて何にあらんや。後世の学者日用の上に学なくして唯書について理会す,是れ古人の学ぶところを学ぶに非らずして,所謂古人の奴隷という者なり。いま朱子を学ばんと思いなば,朱子の学ぶところ如何と思うべし。左なくして朱子の書につくときは全く朱子の奴隷なり。たとえば,詩を作るもの杜甫を学ばんと思いなば,杜甫の学ぶところ如何と考え,漢魏六朝までさかのぼって可なり。且つまた尋常の人にて一通り道理を聞きては合点すれども,唯一場の説話となり践履の実なきは口耳三寸の学とやいわん。学者の通患なり。故に学に志すものは至極の道理と思いなば,尺進あって寸退すべからず。是れ眞の修行なり。
「朱註に委細備われとも其の註によりて理解すればすなわち,朱子の奴隷にして,学の真意を知らず」とは厳しい。誰それの解釈や解説を読んだのでは,その奴隷と言い切っている。
「後世の学者日用の上に学なくして唯書について理会す,是れ古人の学ぶところを学ぶに非らずして,所謂古人の奴隷という者なり。いま朱子を学ばんと思いなば,朱子の学ぶところ如何と思うべし。左なくして朱子の書につくときは全く朱子の奴隷なり」とも言う。これと同じことを,王陽明も『伝習禄』の中で触れていた。つながるのかもしれない。
彼は講義中にメモを取ることを禁じた。それは,小楠の言うことをそのまま書き取ったのでは,小楠の奴隷になるだけだ。その都度,自問自答しつつ,考えることを求める。
学ぶとは,書物や講学の上だけで修行することではない。書物の上ばかりで物事を会得しょうとしていては,その奴隷になるだけだ。日用の事物の上で心を活用し,どう工夫すれば実現できるのかを考える,そのまま書きとめるのではなく,おのれの中で,なるほどこのことか,と合点するよう心がけるが肝要だ。合点が得られたときは,世間窮通得失栄辱などの外欲の一切を度外視し,舜何人か,沼山何人かの思いが脱然としておこる,この学問にはまりこみ,日用実用の上でどう力行するかを工夫する,その修行なのだ,という。小楠の奴隷になのではなく,おのれの合点を得て,世の中に,おのれの工夫を実現せよ,それには日々,一刻一刻が,そのときだと心得よ,という趣旨であった。
「且つまた古来の聖賢読書にのみ精を励みたまうことも曾て聞かず。すなわち古人の所謂学なるもの果たして如何と見れば,全く吾が方寸の修行なり。良心を拡充し,日用事物の上にて功を用いれば,総て学に非ざるはなし」とは,実践家らしい。
朋有り(これは論語の「朋有り,遠方より来る」云々を指す),この義は学問の味を覚え,修行の心盛んなれば,吾がほうより有徳の人と聞かば,遠近親疎の差別なく,親しみ近づきて話し合えば,自然と彼方よりも打ち解けて親しむ,是れ感応の理なり。此の朋の字は学者に限らず,誰にてもあれ其の長を取りて学ぶときは世人皆吾が朋友なり。憧々として往来するの謂いにあらず今一際広めていえば,幕府より米利堅に遣わされし使節を米人厚くあしらいし其の交情の深さにても考え思うべし。是れ感応の理なり。此の義を推せば,日本に限らず世界中皆吾が朋友なり。
日本に限らず世界中皆吾が朋友なり。この言,二人の甥を龍馬に託して洋行させる折送った,有名な送別の詩
堯舜孔子の道を明らかにし
西洋器械の術を尽くさば
なんぞ富国に止まらん
なんぞ強兵に止まらん
大義を四海に布かんのみ
の満々たる楽観主義を思わせる。和魂洋才などという縮んだ諭吉の思想とは全く違う。「大義」と言っているところがポイントだ。「大義」を第二次大戦下のおためごかしのスローガンと同じにしてはならない。堯瞬の理想主義を高々と掲げてはばからない。彼には,国権主義とは無縁なのだ。だから楽観主義という。この高らかな楽観主義は,暗殺で,ついに政策に反映されることはなかった。この精神は,五箇条の御誓文の精神と通底している。因みに,五箇条とは,以下のものだ。
一,広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
一,上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一,官武一途庶民ニ至ルマデ各其ノ志ヲ遂ゲ,人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
一,知識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
長所短所についても,面白いことを言っている。
長所短所といっても,右と左というようにはっきり区別されたものならば,そういうやり方もあろうが,長所短所はつながりあっていて,しっかり区別はつかない。たとえば,火は燃えるが故に種々利用されるが,その長に任せて制するところがなければ,家も宝も焼き尽くしてときには人の命もそこなうことになる。水も物を潤す性あるものの溢れるときは害をなす。これ長に短あるところ,物みなそうである。人にありても進取的な人は退き守るに短なるがために,手前に過を取ることがあり,退守的な人は進み取るに短なるために機を失することが多い。
横井の「堯舜孔子の道を明らかにし」という楽天主義について,渡辺京二は,神風連の生みの親,林櫻園と対比して,こう批判している。
国民攘夷戦争(幕末の攘夷熱のときに決戦を唱えた)の主張から全人間界の出来事の放棄(晩年厭世的になり神事に専念するようになる)にいたる櫻園の思想的道すじは,彼がヨーロッパ文明の圧倒的な侵蝕力を鋭く感知し,この異種文明との出会いがわが国の伝統的文明を運命的に脅かさずにはいないことを見抜いていたところから,生まれたもののように見える。たとえば開国論者横井小楠には,「堯舜孔子の道を明らかにし/西洋器械の術を尽くさば/なんぞ富国に止まらん/なんぞ強兵に止まらん/大義を四海に布かんのみ」という有名な詩があるが,櫻園にいわせればこれはとほうもない誇大妄想というものであったろう。ヨーロッパ文明との接触はそれから「器械の術」だけをいただけばいいようなものではなく,小楠にとっての「大義」すなわち「堯舜孔子の道」を必然的に崩壊させずにすまぬことであることを,彼はおそら洞察していた。
しかしこれは本人の言うように,「深読み」に過ぎない。楽天家とは,小楠へのほめ言葉に過ぎない。
所詮シニカルな現実主義者は,神の世界に逃避し,途方もない楽天家は,最後まで現実的であった。シニカルな評論家が,自分の血を流すことは,決してない。櫻園は畳の上で往生し,小楠は,京都の寺町丸太町の路上で襲撃され,小刀の刃が刃こぼれするほど敵と戦い,首を刈られた。
僕はシニカルな現実主義者を信じない。恐らく評論家でしかない。それを擁護するものもまた評論家でしかないのだ,と経験則から学んでいる。
※※
僕の好きな小楠の言葉は,これだ。
本当の小人,姦人というのは百人にひとりもいない。その他は皆人としてたりないところがあるにすぎない。それをすぐ小人,姦人とけなし,よいところをみてやらず,欠点のみ責めるのは,その責めているほうこそが小人なのだと思い知らねばならぬ。小人をもって小人を責むるということです。
「小人をもって小人を責むる」とは,痛い。子曰く,君子は諸(これ)を己に求め,小人は諸(これ)を人に求む,と。おのれを知らないのと,相手を知らないのとは,丁度裏表ということか。そして,こう言う。
人材には、上中下とある。高い節操、篤行があり、才智が深く、道理を外さず臨機応変に対処できるものが上材、才識が秀で英邁豪俊ではあるが、行いを慎んだり、大事を取れぬものは中材、諄諄としてしきたり墨守し、智力で臨機応変に対応できぬものは下材、下材ではものの役に立てぬ。上材は、百世に一人現れるもので、中材の異能のものこそが役に立てるものだ。いまはその中材の抜擢すら慣例にとらわれていて、登用される道が閉ざされているが、この混迷の時代、中材こそが有用な人材になりうる,と。
こうした人材観の背景にあるのは,
人は三段階あると知るべし。天は太古から今日に至るまで不易の一天である。人は天中の一小天で、我より以上の前人、我以後の後人とこの三段の人を合わせて一天の全体をなす。故に我より前人は我前生の天工を享けて我に譲れり。我これを継いで我後人に譲る。後人これを継いでそのまた後人に譲る。前生今生後生の三段あれども皆我天中の子にしてこの三人あって天帝の命を果たすものだ。孔子は堯舜を祖述し、周公などの前聖を継いで、後世のための学を開く。しかしこれを孔子のみにとどめてはならない。人と生まれては、人々皆天に事(つか)える職分である。身形は我一生の仮託、身形は変々生々してこの道は往古以来今日まで一致している。故に天に事えるよりのほか何ぞ利害禍福栄辱死生の欲に迷ふことあろうか,
という,天を意識し,連綿と続く歴史の一端を担っているという自覚だ。先人の背に乗って,後世へとつないでいく。その眼から見れば,異国を「夷狄」と呼ぶ攘夷の風潮が,小楠には相対化される。
中国にとって我国が東夷とよばれたように、みずからを中華とみなさねば、そうは呼べない。では、彼らにとって、われらはどう見えるのか、大洋を押し渡ってきた彼らにとって、われらはちっぽけな島国でしかない。彼らにとって、われらこそが夷狄かもしれない。では、なぜ国を開くのか、国を開くことで、一国の中で堅持された仕組みは崩れる。いま起きていることは、いままでこの国を動かしてきた偉い人たちが、この事態に対処できない周章狼狽ぶりをさらけ出し、国の政事を果たしていけぬことを世間に知らしめたにすぎない。
道は天地の道なり。わが国の、外国のということはないのだ。道のある所は外夷といえども中国なり。無道になるならば、我国支那といえどもすなわち夷なり。初めより中国といい夷ということはない。国学者流の見識は大いに狂っている。だから、支那と我国とは愚かな国になってしまった。亜墨利加などはよく日本のことを熟視し、決して無理非道なことをなさず、ただわれらを諭して漸漸に国を開くの了簡と見えた。猖獗なるものは下人どもだけだ。ここで日本に仁義の大道を起さなくてはならない、強国になるのであってはならない。強あれば必ず弱あり、この道を明らかにして世界の世話やきにならにはならねばならぬ。一発で一万も二万も戦死するというようになることは必ずとめさせねばならぬ。そこで我日本は印度になるか、世界第一等の仁義の国になるか、この二筋のうちしか選択肢はない。
そして異国との対応のあり方を,こう説く。常に,天が意識されている。
天地仁義の大道を貫く条理に基づかねばならぬ。すなわち、有道の国は通信を許し、無道の国は拒絶するのふたつだ。天地には道理がある。この道理をもって説諭すれば、夷狄禽獣も従う。
応接の最下等は、彼の威権に屈して和議を唱えるもの。これは話にならない。結局幕府はこれを取った。次策は、理非を分かたず一切異国を拒否して戦争をしようとするもの。これが攘夷派の主張だ。長州が通告なく通過する艦船を砲撃したのはこれだ。これは天地自然の道理を知らないから、長州がそうなったように、必ず破れる。第三策は、しばらく屈して和し、士気を張ってから戦おうというもの。水戸派の主張だ。これは彼我の国情をよく知っているようだが、実は天下の大義に暗い。一旦和してしまえば、天下の人心怠惰にながれ、士気がふるいたつことなど覚束ない。最上の策は、必戦の覚悟を固め、国を挙げて材傑の人を集め政体を改革することである。天下の人心に大義のあることを知らせ、士気を一新することである。我は戦闘必死を旨とし、天地の大義を奉じて彼に応接する道こそが、義にかなうはずだ。
この第三策は,勝海舟の考えでもあった。家茂も慶喜も,幕閣もこ,徳川幕府という体制の維持に汲々として,国としての覚悟を決断しなかった。小楠は大政奉還を聞いて,松平春嶽に,こう建策している。
第一に、議事院を建てられるべきこと。上院は公武御一席、下院は広く天下の人材を御挙用のこと。第二に、皇国政府相立った上は、金穀の用度一日もなくてはすまぬ。勘定局を建てられ、五百万両くらいの紙幣をつくり、皇国政府の官印を押し通用するようにすべきこと。第三に、一万石につき百石の拠出を求め、新政府の収入とすること。第四に、刑法局を建てられるべきこと。第五に、海軍局を兵庫に建てられるべきこと。関東諸侯の軍艦を集め、十万石以上の大名から高に応じて人数を定めて兵士を出さしめ、西洋より航海師ならびに指揮官を乞い、伝習させる。第六に、兵庫開港期限が迫っている。国体名分改正の第一歩なれば、旧来の条約中適中せざるを一々改正し公共正大百年不易の条約を正むべし。第七に、外国は交易、商法の学があり、世界物産の有無を調べ、物価の高低を明らかにして広く万国に通商している。そうした熟練に対して、我国は拙劣であり、大人と子供のようなものだ。彼らが大奸をなす所以である。十余年来交易において我国大損たるは明らかである。これより外国に乗り出すにあたっては、まず魯、英、佛、墨、蘭に日本商館を建て、内治においては、商社を建て、兵庫港であれば、五畿内、四国、南海道は、大名ばかりでなく、小人百姓も共望によってその社に容れ、同心して共に舟を仕立てて乗り出し交易すべし。
小楠の中の,ありうべき国家像は,この後,さらにブラッシュアップし,実践される機会が与えられないまま,潰えた。しかしここにあるのは,清潔感だ。義であり,天であり,という言い方を今風に変えれば,絶対に譲れぬ価値を見据えているといっていい。それは徹底している。
その小楠に,こういう詩がある。小楠の判断の一端を知ることができる。
彼を是とし又此を非とすれば
是非一方に偏す
姑(しばら)く是非の心を置け
心虚なれば即ち天を見る
心虚なれば即ち天を見る
天理万物和す
紛々たる閑是非
一笑逝波に付さん
衆言は正義を恐れ
正義は衆言を憎む
之を要するに名と利
別に天理の存する在り
是非の二者択一ではない視点をいつも持つ,小楠はしたたかな政治顧問であった。小楠が,松平春嶽のブレーンであった時,最も松平春嶽が輝いていた。その間,藩レベルで,こうすれば民が肥え,結果として藩が豊かになるという殖産政策を実施した。なかなか端倪すべからざるコンサルタントでもある。ついに国レベルで,実践する機会に恵まれないまま殺された。
酒席に,肥後勤王派の襲撃を受けた折,士道に悖る行為があったとして,知行召し上げ士席剥奪の処分を受け,熊本郊外の沼山津に逼塞していた時,こう読んだ。
心事分明にして疑う所無く
四時佳(か)興(きょう)坐(そぞろ)に卮(さかずき)を傾く
此の生一局既に収め了(おわ)り
忘却す人間(じんかん)の喜と悲とを
なかなかどうして,こんな達観した御仁ではない。この間,井上毅と対話した(というより喧嘩別れした対談)で,こういっていた。「凡そ我が心の理は六合に亘りて通ぜざることはなく,我が惻怛の誠は宇宙間のこと皆是れにひびかざるはなき者」と,昂揚した言い方をしていた。まだまだ意気軒昂であった。
人君なんすれぞ天職なる
天に代わりて百姓を治ればなり
天徳の人に非らざるよりは
何を以って天命に愜(かなわ)ん
堯の舜を巽(えら)ぶ所以
是れ真に大聖たり
迂儒此の理に暗く
之を以って聖人病めりとなす
嗟乎血統論
是れ豈天理に順ならんや
と,あの時代に言い切れる人はそうはいまい。いまでも,なかなか難しい。だから「廃帝論」を論じたとして,暗殺者をかばう論調が高まり,危うく暗殺者が英雄になるところだった。これは将軍継嗣問題で,一橋慶喜か紀州の慶福かで対立している時に読んだとされている。
あえて深読みすれば,血統による世襲は天下を私物化することだ。天命をうけた天徳の人が天下のために政事をするのではなく,君主の血統を維持するために国天下があるかのごとくになる。開幕以来天下のためにする政事これなく,ことごとく徳川氏のため,また諸侯はおのが国のためになされている。これを逆転しなくてはならない。君子のために国があるのではなく,国を治めるために君主がある。政事の役に立たないなら,君主は取り替えなければならない,そう読める。
嗟乎血統論/是れ豈天理に順ならんや,こう言い切れる人こそ,真の民主主義者に他ならない。いまの日本は,二代目三代目だらけ,またそれをよしとする風潮がある。その踏襲主義で,自由闊達な風土の国々に太刀打ちできようか。
二人の甥を坂本龍馬に託して洋行させる折,送ったもうひとつの送別の詩,
心に逆らうこと有るも
人を尤(とが)むること勿れ
人を尤むれば徳を損ず
為さんと欲する処るも
心に正(あて)にする勿れ
心に正にすれば事を破る
君子の道は身を脩むるに在り
に彼の心意気がある。おのれを律することなきは,彼の眼中にはない。
参考文献;
野口宗親『横井小楠漢詩文全釈』(熊本出版文化会館)
山崎正董『横井小楠』(明治書院)
松浦玲『横井小楠』(ちくま学芸文庫)
松浦玲編『佐久間象山・横井小楠』(中央公論社),
渡辺京二『神風連とその時代』(洋泉社) |
|
沈黙 |
|
吉川悟『家族療法―システムズアプローチの「ものの見方」』を読む。
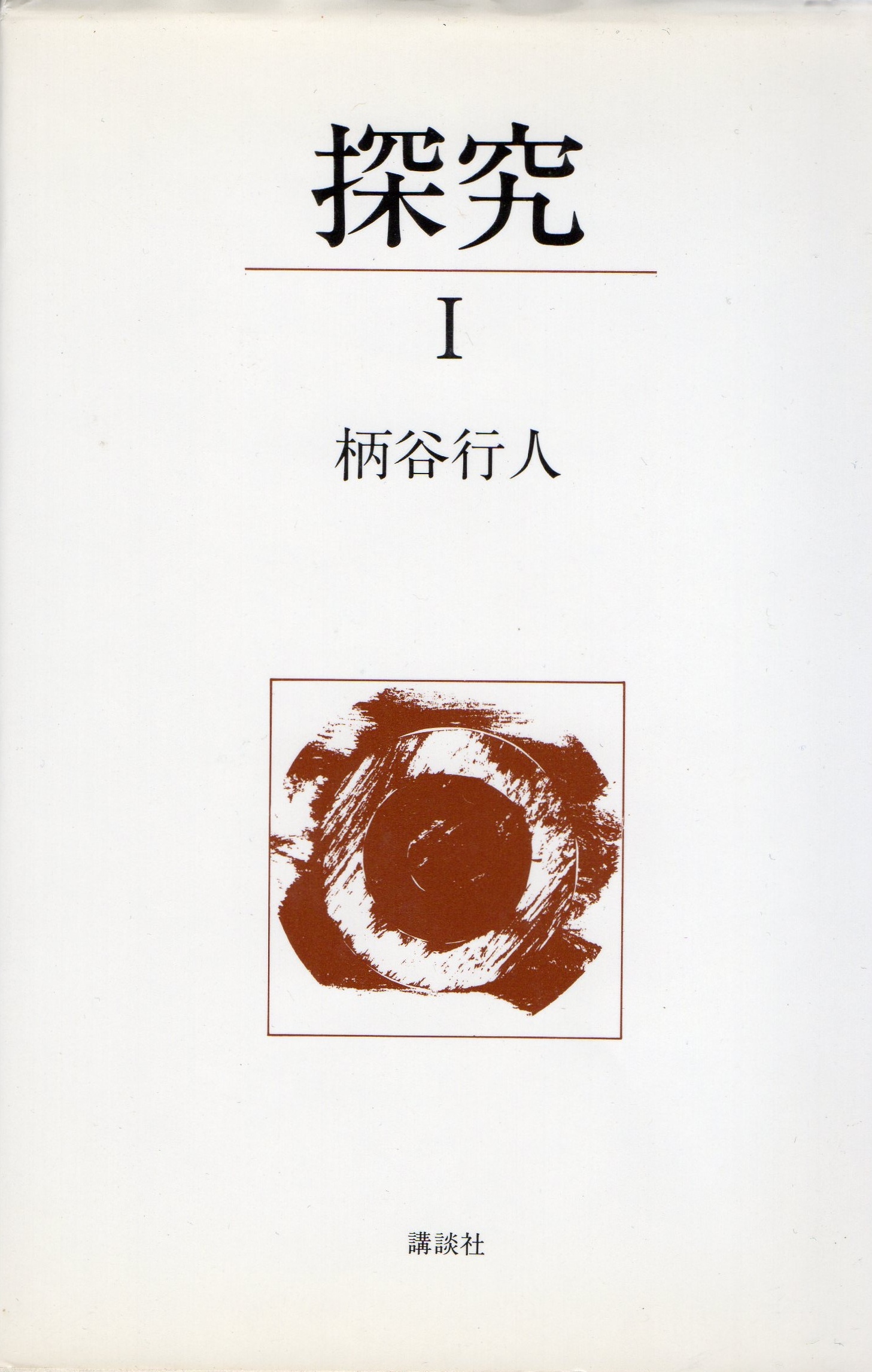
「赤ちゃん〜脳の成長の神秘」(NHKの再放送)の中で,こんなセリフがあった。
返事をしないからと言って,
赤ちゃんの中で何事も起きていない
と考えるのは間違っている(パトリシア・クール ワシントン大学教授)
耳の背後の言語野が活性化するという。言葉が変わると,それにも反応する。ならば,大人の場合の沈黙は,脳内活性化度は,赤ん坊の比ではあるまい。
コミュニケーションは自分の伝えたことではなく,相手に伝わったことが,伝えたことである,ということをよくいう。その意味では,言葉によるコミュニケーションだけではない,相手に伝わったことが,こちらが意図しようがしまいが,伝えてしまったことなのだ。あるいはこういう言い方もできる。僕のしゃべったことがどう伝わったかは,相手が何を返すかでわかる,と。
たとえば,
黙っていても
考えているのだ
俺が物言わぬからといって
壁と間違えるな(壺井繁治)
という詩から,相手が,黙っている壺井をシカとしたのだとも受け取れるが,ふてくされていると無視されたともいえる。そのメッセージを正確に受け止めているとは限らない。しかし,黙るということには,ひとつのメッセージが込められている。たとえば,
先生 どうして何も言わないんだ。
生徒 (無言)
先生 黙ったままでは,わからん。いったい何を考えているんだ。
生徒 (やはり無言)
という会話で,生徒は一見何も伝えていないように見えるが,この沈黙をどうとらえるか,だ。
吉川悟先生は,こう書いている。
たしかに,生徒は表面的に何も伝えていないのですから,従来の考え方では「コミュニケーションが成立していない」と考えがちです。こうした≪ものの見方≫は,会話の中にある言葉によって伝わる情報だけに目を向けているといえます。
しかし,別の面からも考えられるはずです。それは,「生徒が無言でいるという行動がコミュニケーションの一形態である」と考えることです。つまり,生徒が何もしないという行動は,先生から見れば生徒からのメッセージとして伝わるということです。生徒は「何もしていない」のではなく,返事をすべき時にはっきりと「無言でいる」という行動をとっているのです。この「無言でいる」という行動は,「返事をしない」という意志伝達の意味があると考えられます。つまり,無言で何も話さないという行動であっても,それが会話の前後関係によって異なる意味を持つと考えるのです。
情報には,コード化できるコード情報と,コードでは表しにくい,その雰囲気,身ぶり,態度,薫り,ニュアンス等々より複雑に装飾された情報である,モード情報があると言われている。
つまり,文脈によって言葉の意味はがらりと変わる。たとえば上記の例でいえば,死にたいと言って泣いていた生徒との会話とするか,万引きして問い詰められてふてくされている生徒との会話とするかで,ニュアンスはがらりと変わる。
吉川先生は,
コミュニケーションの前後関係や流れの違いによって伝達される情報は,会話の前後関係・脈絡・場面の状況などから伝えられている情報を含むものであり,表面に表れない意味が含まれています。この考えにしたがえば,(中略)コそのミュニケーションの文脈(前後関係・脈絡・場面の状況など)に関する情報を把握するためには,出来る限りコミュニケーションの全体の流れを理解しなければならないのです。
として,コミュニケーションによって伝達される意味の種類を,僕なりにまとめて,整理すると,こうなる。
①コミュニケーションに用いられているすでに共有されているという前提に立った単語で伝えていることの意味。ただこの場合も意味レベルでは一致しても,そこに描いているイメージが人それぞれのエピソード記憶によって,異なっていて,そこでずれを生ずることはあり得る。犬といっても,マルチーズなのか,シェパードなのか。
②コミュニケーションに用いられている単語の並び方,文法的な規則によって,生まれる意味。平田オリザが言うように,「その,竿,立てろ」というのと,「竿,竿,竿,その竿立てて」というのと,「立てて,立てて,その竿」というので,ニュアンスが違う。
③コミュニケーションによって用いられている文同士のつながりによって生まれる意味。結論を先に出して,経過を説明するのと,経過説明して,結論を言うのと,伝わり方が違うだろう。判決文で,主文を最後にするのと,最初にするのを使い分けているのは,裁判官の意図を伝えようとしているからだ。
④身ぶりや表情など,非言語レベルで伝えられる意味。言葉は明るくても,表情や手が別のことを伝えていることはある。
⑤コミュニケーションを行っている人の声の強弱やトーン,特殊なニュアンスなどによって伝えられる意味。ひそひそ声になることで,それ自体で秘密を伝えようとしていることが,伝わる。メラビアンの法則の言うとおり目に見えているものの,伝達力の方が強い。
⑥その場の状況や会話の前後関係など,文脈によって規定されている意味。会議で順番に発言させられるのと,手を挙げるのとでは意味が変わる。
文脈抜きの情報の危険性は,日々の新聞報道でも,ネット情報でも,いやというほど思い知らされている。情報の裏を取るとは,ある意味で,その具体的な場面について,確かめることを含んでいる。
コーチングでも同じで,文脈を共有できているかどうかは,絶えず確認し続けなくてはいけない気がする。なぜなら,文脈は,言葉出来なく,言葉の背景にあるエピソード記憶(自伝的記憶に重なる)に依存しており,言葉に張り付くモード情報だから,体験を共有していないと,ニュアンスが伝わりにくいからだ。
参考文献;
吉川悟『家族療法―システムズアプローチの「ものの見方」』(ミネルヴァ書房)
金子郁容『ネットワーキングへの招待』(中公新書)
平田オリザ『わかりあえないことから』(講談社現代新書) |
|
卑弥呼の影 |
|
村井康彦『出雲と大和』を読む。
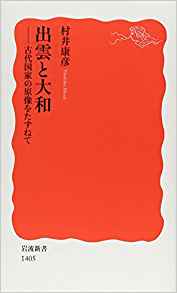
著者自身が,「古代の出雲世界とは何だったのか。本書はその答えを求めて各地をたずねた,文字通り遍歴の軌跡」と言うように,各地の神社の写真を織り交ぜながら語っている,「出雲理解のデータ」は三つである。
第一は,三輪山の存在である。本殿のない山そのものが神体とされた,その祭神・大物主神(大己貴神,大国主神と同神)が出雲系の神であること。大神神社には,神を祀る本殿はない。三輪山そのものがご神体であり,かつては全山禁足,いまも許可を得ないと入れないところがある。大神神社が今も本殿を持たないのは,由緒の古さだけではなく,この神社が最も古い祭祀=信仰の姿を残している証拠であり,その出雲系の神が,なぜ大和なのか,しかも大和の中心にあるのか,ということ。
第二は,八世紀初め,出雲国造が朝廷に奏上した神賀詞(かむよごと)の中で,貢り置くとした「皇孫の命の近き守神」が,三輪山の大神神社,葛城の高鴨神社など,いずれも出雲系の神々であったこと。そして,それが意味があったのは,「それらの神々が守神になりえたのは,大和朝廷以前から大和に存在していた神々であったから」であること。
第三は,『魏志倭人伝』で知られた倭の女王卑弥呼の名が,『古事記』にも『日本書紀』にも全く出てこないこと。しかも『日本書紀』の著者たちは,卑弥呼の内容も存在も知っていて,にもかかわらず名を出さなかったことは,卑弥呼が大和朝廷とは無縁の存在であること。従って,邪馬台国は大和朝廷とはつながらないということ。
そこから推論されることは,
①大和朝廷が出雲系であるか,
②大和朝廷が,出雲を取り込んだか,
③大和朝廷が,出雲を滅ぼしたか,
である。もし③なら,出雲系の神々は,別の伊勢系の神々に取り換えられているはずで,残るはずはない。①は,国譲りの神話や神武東征の神話から見て,矛盾が出る。で,著者は,②をとる。
そして,著者の立てたのは,邪馬台国は出雲勢力が(大和に)立てたクニであった,という仮説である。
そのカギになるのを,ひとつは,長髄彦(ながすねひこ)にとる。神武軍は,待ち構えた長髄彦にてこずり,手痛い敗北を喫している。奈良の富雄川沿いは,長髄彦の遺跡が点在しているが,その中で富雄地域の中心である,忝御県坐(ひうのみあがたにいます)神社は,祭神が武乳速命(たけちはやのみこと)であるが,地元の人は,武乳速命が長髄彦と信じ,「神武東征の折の孔舎衛坂(くさえのさか)の戦いでは,自分たちの先祖は長髄彦に従い,生駒山頂から大きな石を神武軍の軍兵に投げたものだ,と戦いのさまを昨日の事のように語ってくれる古老がいたとのことだ」と著者は書く。長髄彦が,祭神から消されたのは,明治になってからだという。「近代国家になった時期に消された,この種の祭神が少なくなかったことを記憶にとどめておきたい」とは,神社を丁寧にめぐっての,著者の実感だろう。
カギのもうひとつは,その長髄彦が仕えていたのが,饒速日命(にぎはやひのみこと)であり,その饒速日命が,抵抗し続ける長髄彦を殺し,「天津瑞(あまつしるし)」(天のしるしの神宝)を差し出した。この饒速日命の帰順を,著者は「国譲り」とみる。
苦労して大和へ侵攻した神武軍だが,生駒から桜井方面に回った長髄彦との戦いにどうしても勝てなかった。神武軍が圧倒的優勢というわけではなく,長髄彦側にも勝機があった。にもかかわらず,長髄彦を殺して,饒速日命は帰順した。だからこそ,「国譲り」だと著者は言う。饒速日命もまた,出雲系である。
そこで,著者は,邪馬台国を,出雲系の国と推定する。そして,邪馬台国の「四官」に注目する。『魏志倭人伝』では,四官,すなわち,
伊支馬
弥馬升
弥馬獲支
奴佳鞮
であるが,それぞれの字をあてる天皇名があることから類推して,弥馬升→生駒,弥馬升→みます(葛城一帯),弥馬獲支→みまき(三輪山のふもと,天理から桜井にかけて)と読み,奴佳鞮を「なかと」と読み,地域的に,生駒,みます,みまきに囲まれた「中央」ととらえた。奈良盆地の中央,「大字なし」のエリアになる。
この大胆な考えの是非はともかく,神社を徹底的に歩いた末にたどり着いたこの仮説は,大きな新しい視界を開いていることは間違いない。著者は,「はじめに」で,この本についての姿勢を,こう書いている。
(出雲系の神々をたずねた旅の軌跡を書くにあたって,)「心に決めたことがある。それは。これまでの通説にこだわらず自由に発想すること,であった。対象が対象であるだけに,しばしば神話の世界にも分け入り,古代人の思惟や行動について考えるところがあったが,そこは歴史研究者にとっては禁断の領域であるかもしれなかった。」
しかし,頭でひねり出しているのではない。足で神社をたずねまわり,その祭神,由緒を紐解くところから出た仮説なのだ。それを検証しないで,云々するものは,学問を知らぬものだ。まず大胆な仮説を,出す勇気がいる。
日本の社会科学系の学者が,ほとんど欧米学説の金棒引きか自己完結型が多いのは,実にこの点にある,と感じている。前例踏襲(師匠の学統)から出られない。その分絶対に世界に通用しない。なぜなら,何十年か前の欧米の学派の後塵でしかないからだ。こういう大胆な仮説があってはじめて,それを検証するに値する。そこから新たな学問の視界が開けていく。
老いてなお,新たな仮説に邁進する著者に最敬礼!こういう姿勢しか世界に伍す研究はない。
参考文献;
村井康彦『出雲と大和』(岩波新書) |
|
古代の技術 |
|
志村史夫『古代超技術』を読む。
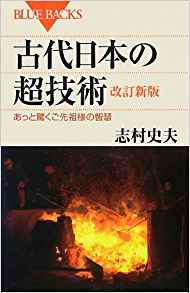
スカイツリーが,日本古来の五重塔のような木塔の工法を使っていることで有名だが,いわゆる木塔で,今まで地震で倒れた塔はないそうだ。あの関東大震災でも,25万戸の家屋が倒壊したのに,木塔は一基も倒れていない。台風で杉の大木が倒壊して一部壊れた室生寺の五重塔も持ちこたえている。地震に強いというそのカギは,二つある。
ひとつは心柱(しんばしら)による制振システム
いまひとつは,通し柱がなく,鉛筆のキャップを重ねたようなキャップ構造であること
心柱は,重要な柱だが,塔そのものの荷重を支えることにはまったく貢献していない。それどころか,宙刷りの心柱すらあるし,宙吊りになっていない,礎石の上に乗せられている場合でも,全体を支える役は果たしていない。では宙吊りでどう全体を支えるのか。こういう例がある。
宙吊り心柱構法で有名な大室勝四郎棟梁は,「地深夜大風に五重塔を造るには,心柱を宙吊りにするのが一番いい」という。そして,棟梁は子供の頃の体験をこう語っている。
小遣い稼ぎに乾燥する板の積み上げをやっていたが,井桁でくみ上げて行っても,風で倒されてしまう。あるとき,棒に錘を縄でくくり,井桁の塔の上にさし掛けておくと,風に対してのみならず,地震にも効果があったのだ,という。
大室棟梁は,こういう。「心柱を宙吊りにすれば,塔が出来上がった後,何年かして部材が乾燥したり変形したりしても,塔が壊されないからいいんだ」と。実際,再建された薬師寺の西塔は,東塔よりも高さが33センチ高い,屋根の反りも東塔に比べてかなり扁平につくられている。西塔を建てた西岡常一棟梁は,およそ200年後に,東塔と同じ高さ,同じ形になる,という。
繊維方向に伸びて塔の荷重を支えていない心柱の種粛・変形は小さいので,もし心柱が固定されていると,
五重塔の屋根との間に隙間ができ,激しい雨漏りを招くことになる。
建築家の石田修三さんは,心柱は,首ふりを含め,一般に層変位の集中を抑制する,と結論付け,五重塔の心柱は丁度観音開きの扉を固定する閂のような働きをして,耐震性を強めている,という。
ところで,法隆寺は釘が使われているが,西岡棟梁は,釘は,いまの建築の様に釘の力で抑えつけているのではなく,木を組んでいく途中での仮の支えとして使われているだけで,組み合わさってしまったら,各部材が,有機的に結合され,機能的に構造をささえ合っているから,釘は重要ではない,という。しかし,その釘が,砂鉄からつくった和鉄のものなら千年持つが,溶鉱炉で積み出した鉄はだめだという。法隆寺の解体修理の時飛鳥の釘,慶長の釘,元禄の釘と出てくるが,古いものはたたき直して使えるのだという。「いまの五寸釘など,10年もたたないうちに頭がなくなってしまう」と。
古来の釘はたたら製法で作られる。たたらの第一の特徴は,原料に砂鉄を使う。砂鉄は,鉄鉱石に比べると圧倒的に高純度だが,様々な種類の不純物がかなりの量含まれている。鉄のさびを助長するシリコンやマンガンも含まれている。逆に精錬された鉄はこれらの不純物はきわめて微量である。特に,かつてたたらは,砂鉄を多く含む山を見立てて掘り崩し,土砂に交じっている砂鉄を,長い水路を通過させて分離させてきた。したがって似た比重の遺物の混入は避けられない。しかし,
私は,砂鉄に混じったこの異物がたたら鉄の高純度化に一役買っていたと思う。
と,『古代超技術』の著者はいう。
溶鉱炉法で使われる石灰石は鉄鉱石の融点を下げ,さらに不純物を取り込む重要な役割を果たす融剤であるが,たたらの場合の主たる融剤は壁の粘土である。さらに,砂鉄中の遺物が融剤の一端を担っている。
実は奈良の大仏でも,理由は違うが,不純物が機能していたらしいのである。
銅像の銅は,一班には青銅であるが,奈良の大仏の銅は,鋳造された年代で多少差はあっても,濃度90%前後の,純銅に近い。しかも,時代が下がるにつれて,銅の純度が下がる。これは銅を溶かすことと関係がある。銅の融点は,1083度Cである。
大仏創建当時,燃料は木材,木炭に限られるので,融点は低い方がいい。そこで5%のヒ素を含む山口県美祢市美東町大田長登の銅が使われることになる。これだと1000度C前後で溶ける。しかも石灰分も含まれている。現在の製銅,製鉄では融剤に石灰が大量に使われるように,熔銅の粘度を下げる働きがあるのだ。
不純物という言い方は何だが,チームでも,組織でも,異端者がいたほうが,残りがまとまるという,媒介剤というだけの,せこい考えだけではなく,異質な考えをするものを交えていない成員は,もろいのではないか。接着機能があるに違いないと,信じている。まあ,大概異端児であり続け,「組織の風土に合わぬ」と上司に言われた,自分が言うのもなんだけれども。
最後に気になったのは,著者が意識的に「シナ」という言葉を使っていることだ。これは,差別とは,こちらの無意識(あるいは無知)が,相手に何を誘い出すかという,慮りや配慮がないところに生まれるということを改めて考えさせられた(これは構造として,無意識に使う「バカチョン」カメラと同じだ)。意識的ならば,もう論外だ。
参考文献;
志村史夫『古代超技術』(講談社ブルーバックス) |
|
錯覚 |
|
一川誠『錯覚学−『知覚の謎を解く』を読む。

正直言って,全くつまらない。つまらない本を書評するのか,というご批判が聞こえそうだが,僕はブレストの原則で行こうと思っている。
どんなくだらないアイデアも,それを生かせなければ,生かせない自分の力量が問われている。「くだらない」で切り捨てるのは簡単だが,それは自分の先入観がそうしているからかもしれない。そこで,自分なりに,何がつまらないかを,説明したいと思う。それが,どんな人とも共感性を持つことと通じると思うからだ。
著者自身も,言っているように,錯覚というのは,日常生活では,それ自体が問題にはならない。というと言いすぎで,錯視しやすい道路標識とか,道路の見え方が錯覚を起こすということはあるが,ここでそう言い切ってしまったのは,この本で紹介される錯覚は,例の,ミューラー・リヤー錯視のように,ほとんどが二次元画像で起こる錯視だ。それは,人間の知覚にはどういう錯視がありうるかを研究するために作られた二次元画像であることがほとんどだ。その紹介に大半がさかれている。けれども,こう書く。
実は,これまでの研究の中で,華完全に解明された錯覚はほとんどない。むしろ,ほとんどの錯覚については,どのようにして成立しているのか,いまも議論が続いている。
けれども,大事なことは,読者側に必要なのが,どういう錯覚があるかという,つくられた錯覚ではなく,どういう時に,どういう場所で,どういう状態の時,人に錯覚が起きやすいのか,という現実の中での錯覚だ。ひょっとすると,交通事故のいくつかは,そのために起きているのかもしれない。このことがあまり重きを置いているように感じられなかったこと,これが第一だ。
第二は,錯覚は,何が問題なのかが,ちっともわからない。伝わってこない(過去に読んだのでは,高野陽太郎『傾いた図形の謎』,今井省吾『錯視図形』,ニコラウス・ウェイド『ビジュアル・イリュージョン』,とコブ『錯覚のはなし』いうのがあるが,こんなに苛立たなかった記憶がある)。
進化の過程で,人は,そうなるように,極端に言うと,そう錯覚した方が生き残りやすいから,そういう錯視を手に入れたのではないのか。とすると,いまそれが問題なのは,わずか数千年の間に,人類が手に入れた錯視が,自分自身の文明で,人類を危険に陥れそうだ,というのなら,そこをこそ紹介してほしい。それについては,
人間は自分たちで生活環境を大きく変容させ,その環境が知覚や認知のシステムの限界を超えた判断をしないと致命的な問題を生ずるような潜在的危険性と日々接している。
といいながら,抽象的な指摘にとどまっている。現実のそういう潜在的危険についての実験結果を指摘してもらった方がわかりやすいし,面白いはずなのに。
一方では,ぱらぱら漫画から,アニメ,テレビ,映画まで,人間の錯視があるから成り立っているものがある。その意味では,錯覚があるから成り立っているという,錯視の効用はいっぱいある。若干の言及はあるが,この面にもっと誌面を割いてもいいし,錯覚があるから楽しめる面を,もっと突っ込んでほしい不満がある。これは錯覚のプラス面かどうかはわからないが,効用ではある。
つまり,錯覚の危険と面白さ,あるいは錯覚のリスクと錯覚だからこそ起こるエンターテインメントというか,そういう具体例を我々は聞きたいはずだし,それが新書という媒体の役割のような気がするのだ(誤解?)。
次から次へと,何々錯視という錯覚の例示をいっぱい与えられても,しかもそれが似ていて,現実にはありそうもない図柄解くると,退屈してしまうだけだ。著者も言うように,それが人間の錯覚というものをあぶり出すためにつくりだしたものなら,それを元に,現実では何が起きるかを,その次に,展開してもらわなくては,錯覚にリアリティ感がない。それくらいなら,だまし絵,例の老婆と娘のような,錯覚させるだまし絵のほうが,エンターテインメント性がある(板根厳夫『遊びの博物誌1・2』,種村季弘・高柳篤『だまし絵』等々)。それに,この手の絵は,人間の錯視の特徴も表しているのではないか(たとえば,老婆と娘では,人間の「いま」とは何かというのが現れているという指摘もある。エルンスト・ヘッペル『意識のなかの時間』)。
ハンソンは,ネッカーキューブについて,錯覚などという言葉を使わず,
この図の遠近法的逆転現象を経験しうる人のほとんどは,この図を植えないし下から眺められた三次元の箱としてみることができるほど十分な知識を持っており,十分なものを学んでいる…(『知覚と発見上』)
といい,それを「〜としてみる」と言った。我々の認識の特徴として,「知っているものとしてみる」という認知の特徴として言及している。遠近法という錯覚らみるのではなく,「知識を見ている」ともいえる側面がある,ということを忘れてはならない気がする。
もう一つ言っておきたいのは,人の認知形式,思考形式には,「論理・実証モード(Paradigmatic
Mode)」と「ストーリーモード(Narrative
Mode)」がある(ジェロム・ブルナー)があるとされていることである。前者はロジカル・シンキングのように,物事の是非を論証していく。後者は,出来事と出来事の意味とつながりを見ようとする。ドナルド・A・ノーマンは,これについて,こう言っている。
「物語には,形式的な解決手段が置き去りにしてしまう要素を的確に捉えてくれる素晴らしい能力がある。論理は一般化しようとする。結論を特定の文脈から切り離したり,主観的な感情に左右されないようにしようとするのである。物語は文脈を捉え,感情を捉える。論理は一般化し,物語は特殊化する。論理を使えば,文脈に依存しない凡庸な結論を導き出すことができる。物語を使えば,個人的な視点でその結論が関係者にどんなインパクトを与えるか理解できるのである。物語が論理より優れているわけではない。また,論理が物語りより優れているわけでもない。二つは別のものなのだ。各々が別の観点を採用しているだけである。」(『人を賢くする道具』)
要は,ストーリーモードは,論理モードで一般化され,文脈を切り離してしまう思考パターンを補完し,具象で裏打ちすることになる。
その意味では,物語として,錯覚を提示してもらう方が,インパクトがあったと思う。
最後に,ただひとつ心に残ったのは,例のペンローズの「考えられない三角形」への錯視は,視点を移動することで見破ることができる,という指摘だ。それは他の錯視でも,人間ならではの,視点を変える,視点を動かすことで,それが打ち破れるのなら,ただ一瞬の錯視だけで,錯覚を論ずるのではなく,錯覚を崩せる人間の可能性についても,もっと言及してほしいと思う。錯覚という人間の弱点(?)だけでなく,それを克服できる人間の持つリソースにも言及しなくては,いささか,公平性に欠く気がしてならない。
参考文献;
N・R・ハンソン『知覚と発見』(紀伊國屋書店)
一川誠『錯覚学−『知覚の謎を解く』(集英社新書) |
|
敗者 |
|
高澤等『戦国武将 敗者の子孫たち』を読む。
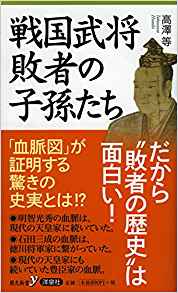
ここでは,武田勝頼,真田信繁,明智光秀,石田三成,豊臣秀勝,松平信康,今川氏真,
が取り上げられている。真田信繁は,いわゆる幸村のこと。秀勝は秀次の弟,松平信康は信長の娘と結婚し,若くして自死に追い込まれた,家康の長子,今川氏真は,義元の長子。
言ってみると,負け組戦国武将の子孫が,どういう血脈を残したかを,延々描いていくので,それ自体は,退屈なものだが,所々で,著者は,自分の読みを披歴する。
たとえば,明智光秀には,「ツマキ」という妹だか,側室の妹だかが,信長の側に仕えていたが,本能寺の前年,死んでいる。「多聞院日記」に,「惟任(光秀)ノ妹ノ御ツマキ死量,信長一段ノキヨシ也,向州(光秀)無比類力落也」とあるらしい。これが,光秀の織田家中での立場を弱体化させた,とある。
あるいは秀吉については,百姓出の武将というイメージが定着しているが,それを覆す。
母親仲は,中田憲信編の『諸系譜』によれば美濃関鍛冶の系譜を引き,父は関弥五郎兼員と称していたとされる。『祖父物語』では青木一矩は秀吉の従弟としており,引用元の不明だが『若越小誌』は「青木一矩は秀吉の従弟」としている。
一矩の父は青木重矩,母は関兼定の娘であり,青木氏が美濃安八郡青木を本拠地としていた地縁を考えれば,隣接する美濃赤坂の刀工であったという関氏の女を母としたことも自然なことであろう。(中略)家康の側室にお梅の方という女性がいる。(中略)このお梅の方の父は青木一矩であり,(中略)江戸時代の竹尾善筑が編纂した『幕府祚胤伝』には,……青木一矩の娘お梅の方は家康の外祖母華陽院の姪であると明記されているのである。(中略)
つまり秀吉が生まれる以前の話,秀吉の母仲の姉妹が青木氏に嫁いでおり,その青木氏は家康の祖母華陽院と血縁であったことを徳川の史料が認めていることになるのである。
秀吉の葬儀では,青木一矩が福嶋正則と供に秀頼の名代をつとめている,というのも,ここから推測すると,意味深に見える。さらに,『百家系図稿』によると,秀吉の養父となった竹阿弥という人物について,水野氏の支流である水野藤次郎為春の子であるとし,
その真偽を補完する一次資料はないが,ただ秀吉が織田家の一部将であった頃用いた家紋は沢瀉紋であり水野家の家紋と一致する。
沢瀉紋はその後,形を変えて秀吉と姻戚関係にある浅野家,福嶋家,木下家も用い,羽柴秀次も旗印としており,…さらに秀吉が作らせた世界最大の金貨とも言われる慶長大判にも沢瀉紋が刻まれている。それだけ沢瀉紋は秀吉にとって特別な家紋であったことは確かである。(中略)
そして「藤吉郎」というような,「藤」の文字を通称に用いるのは藤原氏系に多くみられ,この通称は,水野家でよく用いる藤四郎,藤七郎,藤九郎,藤次郎,藤太郎などにも符合するものである。
秀吉来歴の幅を再確認するだけで,通常のイメージが変わっていく。こうした箇所がいくつかあるのが,本書のもうひとつの面白さかもしれない。
こうした血縁のつながりは,敗者の血のつながりが,たとえば,石田三成の血脈が,「尾張徳川家に入り,さらに四代徳川吉通を通して公家の九条家にも渡っていった」ということを考えると,同じ家格の家同士が婚姻でつながっていく,特に戦国時代,生き残りの重要な結合手段であったことを考えると,そんなに不思議ではない。
また明智光秀の血脈は皇室に入っているが,その系譜は,
一本は細川ガラシャ→多羅→稲葉信通→知通→恒通→勧修寺顕道室→経逸→婧子→仁孝天皇となり,もう一本は細川ガラシャ→細川忠隆→徳→西園寺公満→久我通名室→広幡豊忠→正親町実連室→正親町公明→正親町実光→正親町雅子→孝明天皇という流れである。
光秀ですらこれである。同じ家格同士が縁組するとすれば,420あるといわれる大名諸侯の間を血が行ったり来たりし,それが皇室・公家にまで行くのは,江戸時代という閉鎖された社会では十分ありうる。
比較的確実な系譜をたどってもこれである,女系で先があいまいになった場合を含めれば,すそ野は広がる一方だろう。我が家のようにどこの馬の骨かわからないものにとっては,うらやましい限りだが,それでも,細君の母方は,新田義貞の直系らしいので,どんな馬の骨にも,血脈は流れている,らしい。当たり前のことだが,全人類は,アフリカのたった一人の女性へと辿れるのだから,負け惜しみかもしれないが,血脈の貴種を競うことに意味があるとは思えない。
確かに貴種へのあこがれはわからないでもないが,江戸末期,徳川家定の後継を巡る継嗣問題が,一橋慶喜と紀州徳川慶福で争われているとき,肥後の横井小楠は,
人君なんすれぞ天職なる
天に代わりて百姓を治ればなり
天徳の人に非らざるよりは
何を以って天命に愜(かなわ)ん
堯の舜を巽(えら)ぶ所以
是れ真に大聖たり
迂儒此の理に暗く
之を以って聖人病めりとなす
嗟乎血統論
是れ豈天理に順ならんや
と呼んだ。今日でも,こうはっきり言い切ったら,右翼に狙われるかもしれない。小楠は,明治初年,新政府に召しだされた直後,京都でテロに殺られた。はっきりものをいうことは,今も昔も,結構覚悟がいる。
参考文献;
高澤等『戦国武将 敗者の子孫たち』(歴史新書y) |
|
パースペクティブ |
|
宮地正人『幕末維新変革史』を読む。
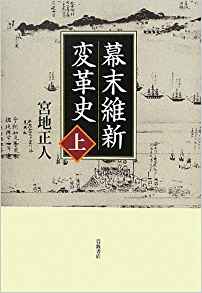 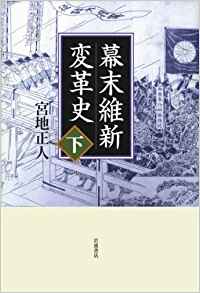
本書の中で,福沢諭吉が『西洋事情』を上梓する際,「天下にこんなものを読む人が有るか無いか夫れも分からず,仮令読んだからとて,之を日本の実際に試みるなんて固より思いも寄らぬことで,一口に申せば西洋の小説,夢物語の戯作くらいに自ら認めて居た」という,諭吉の述懐に,珍しくこういう私論を持ち込んでいる。
本物の著述というものは,人に読ませる以上に,なによりもまず自らの思考を筋道だたせるもの,自己の身体に内在化させるものなのである。(宮地正人『幕末維新変革史下』)
これが,そのまま,本書への著者の覚悟といったもののように受け止めた。
はっきり言って,こういう通史を読んだことはない。あえて言えば,大佛次郎の『天皇の世紀』が匹敵するか。でもあれは,人物中心の縦だけに視点が当たっていた。
本書の特色は,いろいろあるが,3つに整理できる。
第一は,世界史の中に突然投げ込まれる当時の日本の背景となる,欧米列強の東アジア進出から,「前史」として,書き始められる。
冒頭は,こう始まる。
マゼランが1519年,世界一周航海を行おうとした当時は,緯度だけが計測できた。
航海術の開発史は,そのまま世界へ欧米列強が進出する前提になる。つまり,日本史は,世界史レベルの中において位置づけなおされる。日本から見てわからないことが,世界史から見ると,よく見える。あの当時の日本のおかれているジレンマ,個人の有能無能,日本の有能無能だけでは測れない。自分ではコントロールできない時代の圧力といったものの中でしか見えないものがある。
第二は,この本の終りは,田中正造と幕末維新で,こう締めくくられる。
幕末期から明治初年にかけての政治体験から正造が導き出した政治原則は,反封建・反専制であり,法によって保障され,しかもその規模と大小によって決して区別されることのない私有権の擁護であった。彼はこの原則を堅持し貫徹していく中で,労働と生存権の思想にその後の闘いの中で接近していくのである。
すでにこの中に,明治の中期後期の芽がある,という考え方は,この直前の章,福沢諭吉と幕末維新の最後で,こう書くのとつながっている。
諭吉の「丁丑公論」での西郷擁護に触れて,
そのベクトルは大きく異なっていたにしろ,一貫して社会から国家を照射し,社会のレヴェルから国家のあり方を構想しようとする立場において,福沢と西郷は立場を共有していた。それだからこそ,西郷自刃の直後,公表を全く目的とせずひそかに福沢が草した「丁丑公論」こそが,最もすぐれた西郷追悼の言葉になったのである。
として,その引用の後,こう締めくくるのである。
福沢諭吉は国家に対峙する抵抗の精神を西郷に見出す。国家以前に社会があり,社会のためにこそ国家があるとの彼の思想が,自由民権運動の思想と行動にいかに多大な影響を与えたのか,その後の歴史が証明するだろう。
と。この著述全体は,地租改正と西南戦争で終わるが,そのパースペクティブは,もっと広く,自由民権運動にまで及んでいる。その締めくくりで,こう書く。
士族反乱に訴えることが不可能となった状況のもと,幕府の私政と秕政に対する新政府の正統性を保証するものとしての明治元年の五箇条の御誓文と新政府のスローガン「公議輿論の尊重」を前面に押し出し,自由民権運動によって国政参加を要求することになるのは極めて自然な流であった。しかも,新政府が掲げ,条約改正交渉出会えなくも失敗した「万国対峙」と国家主権の回復の実現,即ち不平等条約の廃棄を,自由平等運動の結果創設される国会に国民の総力を結集することによってかちとることを主要目的に構えるのである。士族運動は明治初年代の歴史動向の中から,そしてそこに根差して発展していくのである。
このことが国権拡張につながる芽も,僕はここにあると考えている。すなわち,条約改正が失敗するのは,不平等条約締結が単なる徳川政権の失政ではなく,世界側つまり欧米列強から見ると全く違うということだ。
欧米キリスト教諸国が日本に押し付けている治外法権と低率協定関税は,日本に対してだけのものでは全くなく,不平等条約体制という国際的法秩序そのものだ,という苦い真実を使節団は米欧回覧の中で初めて理解した。
そのなかから,
国家的能動性を誇示して国威・国権を回復するコースには,条約改正の早期実現による主権国家としての日本の確立という道とともに,日本を19世紀後半の世界資本主義体制に安定的に編入するため,東アジア外交関係の形成,国境画定という国際的課題で国家的能動性を顕在化させる道が存在していた。
その道が,民権・国権と対峙しながら,統一されていくのも,世界史レベルで見た日本の生き残りの,ひとつの途だったということが見えてくる。
本書の特徴の第三は,通史としての,一本道を,縦だけではなく,断面を層として膨らませていく手法がとられていることだ。
その中に,おなじみの吉田松陰,勝海舟,西郷隆盛,福沢諭吉等々とは別に,幕末期の漂流民(ジョン万次郎を含めて)のもたらす世界知識,蝦夷地に通じた松浦武四郎,町医師から奥医師となった坪井信良,
さらに,個人とは別に,幕末維新期に影響を与えた,平田国学,風説留という各地の豪農,儒者,医師が書き取った手記,手紙での同時代の意見や感想,『夜明け前』のモデルとなった信州の豪農たち,蘭学者たち,国学者たち,豪農・豪商,農民が,その時代どう考えていたのか,手紙,日記を駆使して,時代の横断面から,分厚い歴史の地層を描出している。
たとえば,平田国学について,
自然科学書は当時の知識人の必読文献であり,篤胤とその門弟たちは人を批判するのに,「コペルニクスも知らないで」と嘲笑している。
と,国学者レベルの持つ幅広い知識を紹介しているし,風説留では,
(ペリー)来航情報が瞬時にして全国に伝搬し,人々がそれを記録し,そして江戸の事態を深い憂慮をもって凝視するという社会が出現していた。
という。だから,ある意味で世論があった。「幕府を守ろうとする」私権で動いていることが,幕府・幕閣を除く有意の人々には見えてくる。幕府は,見限られるべくして,見限られていく。
著書は,前書きで,こう書く。
本書の基本的視角は,幕末維新期を,非合理主義的・排外主義的攘夷主義から開明的開国主義への転向過程とする,多くの幕末維新通史にみられる歴史理論への正面からの批判である。
たとえば,攘夷について,
狭義の奉勅攘夷期を,無謀で非合理主義的な排外運動と見るのが,明治20年代から今日までの日本の普通の理解だが,著者はそうは見ていない。
民族運動の中でも,その地域に伝統的国家が長期にわたって存続し続けていた場合には,必ず国家性の回復という性格がそこにはまとわりついてくる。特に日本の場合には古代以来の王権が武家の組織する幕府と合体して,日本人にとっての伝統的国家観念を形成していた。当時の日本人の全員が感じた危機感とは,この国家解体の危機感,このままいってしまっては日本国家そのものが消滅してしまうのではないかとの得体の知れない恐怖感なのである。幕府が外圧に押されて後退するたびに,この感覚は増幅され,それへの対抗運動と凝縮行動がとられていく。(中略)
吉田松陰は刑死の直前,「天下将に乱麻,此事不忍見,故に死ぬると,此の明らめ,大いに吾と相違なり,天下乱麻とならば,大いに吾力を竭すべき所なり,豈死すべけんや,唯今の勢いは和漢古今歴史にて見及ばぬ悪兆にて,治世から乱世なしに直ちに亡国になるべし」「何卒乱世となれかし,乱世となる勢い御見据候か,治世から直に亡国にはならぬか,此所,僕大いに惑う」と述べている。この乱世を起こす能力もない日本「亡国」化の危機感が彼をあのように刑死にまで突き動かした根源なのである。
と説明している。こういう言い方もしている。
攘夷主義としてレッテルを貼られている政治思想は,少なくとも日本の場合,外国嫌いだから,あるいは世界の事情に通じていない無知蒙昧だから形成されたのではない。国家権力が外圧に対して主体的に対応不可能に陥った時,国家と社会の解体と崩壊の危機意識から必然的に発生する。その条件が消滅すれば,当然存在しなくなるものである。すべてを世界史を前提とした政治過程として理解すべきだ,と著者は思っている。
そして,この通史全体を,こう概括する。
この世界資本主義への力づくの包摂過程に対し,日本は世界史の中でも例外的といえるほどの激しい抵抗と対外戦争を経,その中で初めて,ヨーロッパは17世紀なかば,絶対主義国際体制のもとで確立された主権国家というもの(著者はこれを天皇制国家の原基形態と考えている)を,19世紀70年代,欧米列強により不平等条約体制を押し付けられた東アジア地域世界に創りあげた。そしてこの主権国家がようやく獲得した自信をもって,上から日本社会を権力的につかみ直そうとするその瞬間,幕末維新変革過程でぶ厚く形成されてきた日本社会そのものが,自由民権運動という一大国民運動をもって,自己の論理,社会の論理を国家に貫徹させようとする。この極めてダイナミックな歴史過程こそが幕末維新変革の政治過程ではないだろうか。
その意図は,おおよそ達成されている。もちろん好みを言えば,勝のウエイトより福沢が重視されている,横井小楠が軽視されすぎている等々という個人的な憾みはあるが,初めて,幕末維新史が,イデオロギーではなく,内発する人々の動機とエネルギーに焦点を当てた感じがする。
本書読むうちに,いまの時代と重なる。幕末時代,外圧に対抗することで,自らのアイデンティティを確立していった。敗戦後もそうだ。しかし,いま日本は1000兆もの借金まみれの中,また政府は新たな借金を増やそうとしている。頼みの1500兆の個人金融資産も,個人債務,株式・出資金等々を除くと,ほぼ借金と重なりつつある,危険水域に達している。その危機に,政治家も,経営者も,自治体トップも,もちろん国民も,本気で臨むものはほとんどいない。何か,まだ国に頼めば何とかなる,とぼんやり期待している。土建屋はまた公共事業に蟻のように集まっている。地方自治体は国に頼めば何とかなると思っている,企業も国の補助金をあてにし,ちょっと具合が悪いと,働かなくても,年金より多い生活保護にすがる。惰性と,無気力というか奇妙な能天気で,この先に巨大な大瀑布があるとわかっているのに,流され続けている。あの時,幕府が,世界史のテンポに比べて緩慢であったように,いまわれわれも,世界史のテンポに比して,あまりにも緩慢で,のんびりしている。
参考文献;
宮地正人『幕末維新変革史』(岩波書店) |
|
重力 |
|
大栗博司『重力とは何か』を読む。
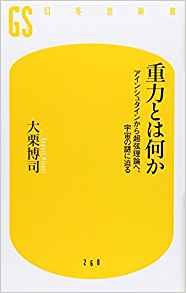
※
著者自身が超弦理論(超ひも理論)研究の最前線で,六次元空間から三次元素粒子の性質を導き出すトポロジカルな計算方法(「トポロジカルな弦理論」)を開発した共同研究者の一人であり,わくわくするような,ミクロからマクロにわたる宇宙研究の最前線への歴史を,数式を使わず読ませていく。ベストセラーだそうだが,なかなか面白いし,考えさせられる。
ただ,私の知識では,ここにあるすべてを解きほぐせないので,なぞるだけになるかもしれない。しかしそれにしては,一回では無理で,何回かに分けて,紹介したい。
京都市青少年科学センターに,朝永振一郎の色紙がある,という。そこにはこう書かれている,という。
ふしぎだと思うこと これが科学の芽です
よく観察してたしかめ そして考えること これが科学の茎です
そうして最後になぞがとける これが科学の花です
そのために,まず重力の7不思議から書き始めている。これが科学の芽にあたる。それがどう解かれてきたのかを説明して,最後に今の科学の到達点,まだ花開いていないけれども,そこを締めくくりとして,全体が構成されている。
第一の不思議は,重力は力である。ニュートンによって,りんごが地面に落ちる現象も月が地球の周りを回る現象も,同じひとつの理論,万有引力で統一された。
第二の不思議は,重力は弱い。重力はほんの小さな磁石の方が強い。電磁気力があるから,分子がしっかりくっついていて,物質もわれわれの身体もまとまっていられる。
第三の不思議は,重力は離れていても働く。磁石が鉄を引き寄せる時,両者の間では力を伝える粒子が行き来している。重力も,まだ発見されていないが,目に見えない粒子が重力を伝えていると考えられている。
第四の不思議は,重力はすべてのものに等しく働く。同じ大きさの鉄の玉と木の玉を落とすと,同じ速さで落下する。質量の大きい物体は,動かしにくい性質と重力に強く惹かれる性質があり,重いものと軽いものが同時に落ちるのは,プラマイゼロで相殺されていると考えられている。重力は質量が大きいほど強いのに,重力が運動に与える影響は質量と無関係になる。
第五の不思議は,重力は幻想である。飛行機の自由落下で無重力状態を作り出すことができる。逆にエレベーターで上昇するとき,強く重力を感じる。重力は消せるし,強さが変わる。見方によって姿を変える性質がある。
第六の不思議は,重力はちょうどいい。宇宙は137億年前に生まれ,現在のように銀河が生まれ,宇宙全体の構造が出来上がるまでに100億年かかり,その間に太陽系も生まれて,地球は46億もの時間をかけて人間を作り出している。しかしもし少しでも重力の働きが違っていたら,生まれた瞬間に重力の重みで潰れてしまうか,逆にあっという間に膨張して冷え切ってしまい,星さえできなかったかもしれない。その意味で,重力がちょうどいい強さだった,といえる。
第七の不思議は,重力理論は完成していない。重力の働きを説明する理論はまだ完成していない。身近なことなのに,なかなか説明できない。それは,宇宙の謎と深くつながっている。
科学史にあたる部分は,少し端折って,最近の解明に飛ばすと,「宇宙という玉ねぎ」はどこまで皮がむけるか,という問いが面白い。
いままで,原子→原子核→陽子・中性子→クォーク,と皮をむいてきた。「その先がある気がします」という。そして,
結論から申し上げましょう。それがクォークかどうかは別にして,この玉ねぎには必ず「芯」があります。物理学者の皮むき作業は,永遠に続くわけではありません。
ミクロの世界を観察する現代の顕微鏡は,「できるだけ波長の短いものを観察対象にぶつけなくてはいけません。対象のおおきさよりも波長が長いと,波が相手を回り込んで通り過ぎてしまいます」。しかし「『波長が短い』とは『エネルギーが高い』」ので,どれだけエネルギーをどこまで高められるかが解像度を左右する。
そのため粒子加速器は巨大化し,CERN(欧州原子核研究機構)のLHC(大型ハドロン衝突型加速器)は,一周27キロの装置が,地下100メートルに埋められている。その中で,陽子を回転させて加速し,反対方向からくる陽子と衝突させて,≪100億×10億≫分の一メートルというミクロの世界を観察する(ナノが10億分の一メートルなので,ナノ×名の10分の一)。
きわめて小さな領域に大きな質量が集中すると,ブラックホールが生まれる。ブラックホールができると,その質量に応じた事象の地平線ができ,そこより内側の領域を見ることができなくなる。だから,LHCを超える加速器をつくっても,ブラックホールが無視できない大きさになり,観測領域が覆い隠されてしまう。そのため,原理的には,≪1億×10億×10億×10億≫分の一,10ナノ・ナノ・ナノ・ナノメートルが限界とされている。これを「プランクの長さ」と呼ぶ。これが宇宙の玉ねぎの「芯」とされる。
原理的に観測できない以上,それより小さいものはありません。それが宇宙という玉ねぎの「芯」であり,そこから先は,もう皮をむくことができないのです。
だとして,
その「芯」を説明できる理論さえ築くことができれば,それ以上に理論を拡張する必要はありません。その先にフロンティアはないのですから,そこが理論の終着点です。そこまでたどり着けば,この世界の根源を統一的に記述する
「究極の理論」が完成することになります。
実は,すでにその目星はついています。その統一理論は,量子力学と一般相対論を融合したものになるに違いありません。というのも,まず「波長」をもつ粒子は量子力学の守備範囲です。一方,ブラックホールは一般相対論の世界。つまり,その両者が一致する10ナノ・ナノ・ナノ・ナノメートルの「プランクの長さ」は,量子力学と一般相対論がどちらも同じくらいの影響を及ぼす領域なのです。
しかしそれを統一するのは,大きな障害がある。ひとつは,計算に無限大が現れて物理的な意味をなさないことが一つ。さらに,
アインシュタイン理論では,重力の伝わり方を空間の曲り具合や時間の伸び縮みで説明します。そこでは時間と空間が混ざり合っているのですが,これに量子力学を当てはめると,時間と空間の構造そのものがミクロの世界で揺らいでしまう。空間が固定されないので,「長さ」という概念も成り立ちません。長さを決めようと思っても,揺らいでいる空間のどこを測定していいのかわからないからです。
この量子重力の無限大の困難を克服し,様々なパラドックスを解決することで,量子力学と一般相対論を融合すると期待されている理論,それが…「超弦理論」です。
超弦理論は,超ひも理論と表記されることもある,Superstring
Theory。ストリングとは,現在わかっている素粒子,クォーク,光子,電子,ニュートリノなどとしてあらわれてくる素粒子の基本単位,皮をもう一枚むいた,共通単位として,すべての粒子は同じストリングからできている,と考えている。
この超弦理論が,宇宙論(ミクロの世界とマクロの世界を統一する)のフロンティアなのである。この弦理論を,「素粒子が『点』ではなく,弾力のある『弦』でできていると考えれば,次々と見つかる粒子の性質をその公式で説明できることを発見」したのが,ノーベル賞を受賞した南部陽一郎であった。
このほかにも,素粒子論の湯川秀樹,朝永振一郎,益川敏英,小林誠,米谷民明から,インフレーション理論の佐藤勝彦まで,綺羅,星のような学者・研究者群の中に,日本人の多くの学者が数多くかかわっていることが,よくわかる。
その多くは,仮説の連続であり,ついこの間,アインシュタインの仮説が崩れたと大騒ぎになっていた。まだ仮説なのだと思い知らされた逸話だ。著者は,はじめにでこう書く。
科学的な発見は,最初は研究者の知的好奇心から生まれたものであっても,長い目で見ると,結果的に世の中の役に立つことが少なくありません。かつて「数学のノーベル賞」とも呼ばれるフィールズ賞を受賞した森重文は,自身の研究している基礎数学が,「いますぐには無理でも,5〇年先か,100年先かわからないが役に立つ。そのためには探究心が最高のコンパスだ」と語っています。
そうした余沢にあずかっている。GPSもニュートンがいなければ人工衛星を飛ばせず,アインシュタインがいなければ,距離を正確に測定できなかった。
物理学の歴史は,10億のステップで広がってきた,と著者は言っている。月の軌道の10億メートルの世界と地上の身の丈とが同じ原理で動いているのを発見したのが,ニュートンであり,10億の階段をもう一つ上がって,10億×10億の世界,銀河一つ分の世界になると,アインシュタインの理論が必要になる。
ところが,そのアインシュタインの理論も,10億×10億×10億より先の世界,宇宙の果ての距離,光で見ることのできる限界になると,遠くを見れば見るほど過去を見ていることになり,アンドロメダ銀河は250万年前であり,さらに遠くを見れば,137億年前の宇宙のはじまりを見ることになる。そこではアインシュタインの理論は破綻する。
逆にナノレベル,10億分の一,素粒子研究は,量子力学がなくてはならないものです。素粒子加速器は,≪10億×10億≫分の一の世界を観測できる。しかし≪10億×10億×10億≫分の一の世界では,新しい理論を必要とする。
いま,ミクロとマクロを統一理論する理論が求められているのは,ミクロの解明が,そのまま宇宙の解明につながっているからに他ならない。
その最前線,超弦理論と,それが描き出す驚天動地の世界については,次回,次々回にまとめたい。
※※
70年代からマクロとミクロを統合すると期待された超弦理論であったが,
困った問題が立ちはだかっていた。
そのひとつは,理論が成り立つためには宇宙が10次元(空間9次元+時間1次元)である必要があり,6つの余分な次元がなぜ必要なのかが,理論の欠陥とみなされたこと。
さらに,実験で見つかっていない奇妙な粒子が,理論に含まれていること。
後者は,ジョン・シュワルツと米谷民明によって,前者は,十年後の 1984年,
ジョン・シュワルツらによって,6つの余剰空間を小さな空間に丸め込むことで,通常の三次元を除く余剰空間が見えなくなるメカニズムを発見し,再び日の目を見ることになる。
当時の研究者たちにとって,それは奇跡的なことだと思えました。最初からそこを目指していたわけではないのに,たまたま最高の形であらゆるパーツが揃っていた。そのため多くの研究者が「これが最終解答に違いない」と考え,超弦理論に惹かれていったのです。
当時大学院に進んだばかりの著者自身も,この分野を主戦場にしょうと決めた,という。しかし,
一筋縄では理解できません。とくに,超弦理論に使われる「カラビ=ヤウ多様体」と呼ばれる六次元空間では,2点間の距離をどうやって測るかという単純なことさえわかっていなかったのです。
そんな超弦理論の行きづまりを打破したのは,10年後の1995年,エドワード・ウィッテンが,一次元の弦でなくてもいいという画期的な構想を発表した。
「点」でない粒子を考えるなら,一次元だけではなく,たとえば,「二次元の膜」や「三次元の立体」のようなものを考えてもいいはずです。なにしろ空間が九次元まであるのですから,素粒子が広がる次元にも選択肢はたくさんある。四次元,五次元,六次元…に広がった素粒子があってもいいでしょう。……アインシュタインの重力方程式から導かれるブラックホールの解は,質量がある一点(ゼロ次元)に集まってできるものでした。しかし超弦理論の方程式を解くと,ゼロ次元に質量が集まるブラックホール以外に,線(二次元),面(二次元),立体(三次元)…などに沿って質量が集まる解があることがわかります。それをすべて考えよう,というウィッテンが提案したところから「第二次超弦理論革命」が幕を開けました。
いままでもそれに近いアイデアはあったが,一旦,そこで新しいパースペクティブが開くと,クーンのパラダイム変革ではないが,一気に視界が広がっていく。一つの仮説が行き詰まり,それを諦めず追い詰めたものが,それを突破するアイデアを着想する。そういう繰り返しの中,螺旋階段を上る,というより,踊り場から数段ステージを一気に登る,今その時代の中にあるらしい。
想定するさまざまな「膜」のことを「ブレーン(brane)」と呼びます。これは,二次元の膜を意味する「メインブレーン(membrane)という英語からの造語です。…ゼロ次元の点を「0-ブレーン」,一次元の線を「1-ブレーン」,二次元の面を「2-ブレーン」…と呼び,一般にp次元の(pは0,1,2といった次元を表す整数)の膜を「p-ブレーン」と呼んでいました。
ちなみに,英語では,「pea」は「豆」のことで,「pea
brain」と言えば,「豆頭=お馬鹿さん」の意味もあり,綴りは違うが,「p-brane」は,それにひっかけたイギリス流のユーモアでもありました。
と著者は付け加えてる。そういえば,iPS細胞のiも,当時世界的に大流行していた米アップルの携帯音楽プレーヤーiPodのように普及してほしいとの願いが込められているそうだ。そういえば,最初になづけるには,それなりに発見者や発明者の思いがこもっている。
名づけるとは,物事を想像または生成させる行為であり,そのようにして誕生した物事の認識そのものであった。(中略)人間は名前によって,連続体としてある世界に切れ目を入れ対象を区切り,相互に分離することを通じて事物を生成させ,それぞれの名前を組織化することによって事物を了解する。(中略)ある事物についての名前を獲ることは,その存在についての認識の獲得それ自体を意味するのであった。(『「名づけ」の精神史』)
だからこそ,ヴィトゲンシュタインのいう,持っている言葉によって見える世界が違うことが起こる。それは別の話だが,ここでは,新たに視界に入った図,いままでは一様の地でしかなかったものに,図が見えたことを意味する。とすれば,その名づけには特別な意味がある。
この数か月後,ジョセフ・ボルチンスキーが,両端のある「開いた弦」のアイデアを提起する(この膜をD-ブレーンと呼ぶ。このDは,19世紀の数学者のグスタフ・ディリクレからとっているらしい)。それを,こう説明する。
ブラックホールの近くを閉じた弦がたくさん飛び回っているとしましょう。ブラックホールの表面は事象の地平線で,その中の様子は遠方からは観察することができません。そのため,閉じた弦の半分だけが,たまたま事象の地平線を越えて中に入ったとして,それを遠方からみると,「両端のある弦」がブラックホールの表面に張り付いているように見えます。このような考察から,ボルチンスキーは,ブラックホールの表面には開いた弦の端が張り付いていると考えました。
この結果,次のような視界が開けていく。
表面に張り付いた弦をブラックホールの「自由度」とみなせることがわかりました。物理学では,物の状態を表すのに自由度という概念を用います。たとえば,ある部屋の空気の自由度は,それぞれの分子の位置です。分子の位置をすべて決めれば,部屋の中の空気の状態が完全に決まります。
ブラックホールの場合には,その自由度が表面に張り付いた弦であることが,ボルチンスキーのアイデアによってわかったのです。自由度がわかれば,ブラックホールにどのような状態があるのかもわかり,その状態の総数(すなわち書き込める情報量)を計算することができるようになりました。
たとえば私のミクロな自由度は,私の体を構成する原子の配置にほかなりません。それになぞらえて言うなら,表面に張り付いた弦はブラックホールの「原子」のようなものだと言えるでしょう。
だとすれば,空気の分子によって熱や温度などの性質がミクロな立場から導き出せるのと同じように,「原子」である開いた弦によって,ブラックホールの発熱をミクロな立場から理解できるはずです。
その計算を最初に行ったのは,アンドリュー・ストロミンジャーとカムラン・バッファで,その結果ブラックホールが大きくなる極限ではホーキングの計算から期待された状態数(10の「10の78乗」)と一致し,質量の大きなブラックボックスでの問題を解決し,次は,ミクロの小さいブラックホールの状態をどう理解するかです。そこで,著者は,かつて三人の共同研究者と発表した「トポロジカルな弦理論」を使って,アンドリュー・ストロミンジャーとカムラン・バッファに呼び掛け,あらゆるサイズのブラックホールの状態数を計算できることを突き止める。
しかしブラックホール問題には,奇妙な計算結果が見つかる。
それは,ホーキングの計算と超弦理論の計算が一致したブラックホールの状態の数が,ブラックホールの体積ではなく,「表面積」に比例していることです。
この不思議な事実から,ひとつのアイデアが生まれる。ブラックホールの中で起きていることは,すべてその表面が知っているのではないか。つまり,
三次元空間のある領域で起きる重力現象は,すべてその空間の果てに設置されたスクリーンに投影されて,スクリーンの上の二次元世界の現象として理解することができる…。
これを,重力のホログラフィー原理と名付けられている,という。
この結果,奇妙な事態に陥るのだが,それは次回に譲る。しかし次々とアイデアに時代が開かれ,さらにまたそこから次のアイデアに導かれていく,その沸騰する雰囲気がうらやましい。もちろん,すべてが紳士的であるわけではなく,出し抜いたり,改竄したり,ねつ造したり,だましたり,人を追い詰めたり,といった,どの世界にもある葛藤,闘争もある。そのあたりは,アレクサンダー・コーンの『科学の罠』『科学の運』(工作舎)やアービング・M・クロツの『幻の大発見』(朝日新聞社)あたりに詳しい。
それでも,アイデアを競いあうという,いわばタイムラグのあるブレストというかキャッチボールは,いまや時々刻々,ネットを介して瞬時に行われている。著者が,ジョン・シュワルツらの論文を船便で待ち,スタートダッシュで三か月の遅れをとったという,焦りがよくわかる。
※※※
三次元空間のある領域で起きる重力現象は,すべてその空間の果てに設置されたスクリーンに投影されて,スクリーンの上の二次元世界の現象として理解することができる…。
これを,重力のホログラフィー原理と名付けられている,という奇妙な説について,ブライアン・グリーンは,『宇宙を織りなすもの』で,それをこうショッキングに表現している。
ひょっとすると私たちは,今このときも,3ブレーン(ブレーンとは膜braneのこと)の内部に生きているのではないだろうか?高次の宇宙(三次元のドライブイン・シアター)の内部に置かれている二次元スクリーン(2ブレーン)の中で暮らす白雪姫のように,私たちの知るものすべては,ひも/M理論(5つのひも理論を統合するマスター理論の意味)の言う高次元宇宙の内部にある三次元スクリーン(3ブレーン)の中に存在しているのではなかろうか?ニュートン,ライプニッツ,マッハ,アインシュタインが三次元空間と呼んだものは,実は,ひも/M理論における三次元の実体なのではないだろうか?相対論的に言えば,ミンコフスキーとアインシュタインが開発した四次元時空は,実は,時間とともに展開していく3ブレーンの軌跡である可能性はないのだろうか?つまり,私たちの知るこの宇宙は,一枚のブレーンなのではないだろうか?
著者も,「重力は幻想である」といったのは,「わたしたちが暮らしているこの空間そのものが,ある種の『幻想』」だと言えるからだ」と言っている。
私たちは縦・横・高さという三つの情報で位置の決まる三次元空間を現実のものだと感じていますが,ホログラフィー原理の立場から見れば,それはホログラムを「立体」だと感じるのと同じことに過ぎません。空間の果てにある二次元の平面上で起きていることを,三次元空間で起きているように幻想しているのです。
重力に押しつぶされて,二次元空間のようなところにいる小惑星の生命体が,地球からの知識を急速に吸収して,高度な文明へと発展を遂げていくSF小説を読んだ記憶があるが,タイトルを忘れた。
それは,ともかく,ホログラフィー原理によって,重力を含まない量子力学に翻訳できるだけではなく,量子力学だけでは解決困難な問題を,重力理論に翻訳して,アインシュタインの幾何学的な方法で解くことができるようになった。しかし,超弦理論が目指しているのは,究極の統一理論,宇宙の玉ねぎの「芯」を説明する,最終的な基本法則である。しかしまだ,道は,途上にある。
そのとき,残された大きな問題がある。
その基本法則には,理論的な必然があるのか,偶然なのか。
もし偶然だとすると,宇宙は一つだけではなく無数にあって,超弦理論で可能な選択肢は全てどこかの宇宙で実現しているのではないか。ブライアン・グリーンは,『エレガントな宇宙』でこう言っている。
インフレーション的膨張の条件は宇宙全体に散らばった孤立した領域でくり返し現れるかもしれない。そうなると,インフレーション的膨張が起こり,そうした領域は新たな個別の宇宙に発展する。こうした宇宙のそれぞれでこのプロセスがつづき,古い宇宙の遠く離れた領域で新たな宇宙が生まれ,膨張する宇宙の広がりの網が果てしなく成長する。……この大きく広がった宇宙の概念を多宇宙,その構成部分のそれぞれを宇宙と呼ぼう。……私たちが知っていることすべてが,この宇宙全体を通じて一貫した一様な物理が成り立っている…と述べた。しかし,他のもろもろの宇宙がこの宇宙から切り離されているか,あるいは,少なくともあちらのひかりがこちらに届くだけの時間がこれまでになかったほど遠く離れているのであれば,このことは他のもろもろの宇宙の物理特性には何の関係もないかもしれない。そうであれば,物理は宇宙ごとに異なると想像できる。
しかし,逆に,私たちの世界をつくっている素粒子模型は,いくつかある選択肢の中から,どうして選ばれたのか。それを「人間原理」と呼ぶようだが,
自然界の基本法則には,宇宙に人間=知的生命体がうまれるよう絶妙に調節されているように見えるものが少なくありません。
その極端なのが,ガイア理論の,ジェームズ・ラブロックの考えだが,不思議な調節は,たとえば,
太陽と地球とのちょうどいい距離。太陽から,150億メートル離れている。
陽子は正の電荷をもつので,陽子同士は反発しあう。しかし電磁気力がいまより2パーセント弱かったら,陽子同士が直接結合し,太陽は爆発的に燃え尽きる。
陽子は電子の約2000倍の重さだが,この質量比が大きすぎるとDNAのような構造をつくれない。
暗黒エネルギーは10の120乗分の一という値だが,これより大きければ,宇宙の膨張速度が速くなりすぎて,銀河は生成できない。逆に負の値だと宇宙は潰れてしまう。
空間は三次元だが,仮に四次元だと,ニュートンの法則の逆二乗ではなく,逆三乗になり,太陽系は不安定になり,惑星は太陽に落ち込んでしまう。
等々,こう基本法則を並べると,あまりにも人間に都合がよすぎる。これを神様に頼らず説明しようとするのが,人間原理だと,著者は言う。
私たちが太陽に近すぎる水星や遠すぎる海王星ではなく,知的生命体への進化に適した地球の上にいるように,私たちのこの宇宙が,たまたま私たちにとって「ちょうどよい基本法則」を持っていた…。
こう考える「人間原理」は,科学にとって最終兵器だと,著者は警鐘を鳴らす。
説得力のある仮説なのは確かですし,実際そうである可能性はありますが,安易にこの考えに頼るべきではない。最初から人間原理で考えていると,実は理論から演繹できる現象を見逃して「偶然」で片づけてしまうおそれがあるからです。
物理学の歴史においては,偶然に決まっていると思われていたことの多くが,より基本的な法則が発見されることで,理論の必然として説明できるようになりました。
そしてこういう例を挙げている。
私たちの宇宙は,三次元方向にはほとんど平坦であることがわかっています。これは宇宙の膨張のエネルギーと物質のエネルギーが絶妙につりあっているからです。もしもビックバンの一秒後に,このふたつのエネルギーがわずか100兆分の一でもズレていたら,宇宙の膨張がそのズレを増幅するので,宇宙はすぐに収縮して潰れてしまうか,急激に膨張して冷え切ってしまっていたでしょう。
この絶妙なつりあいは,人間原理でなくても,説明できる。著者は,言う。
インフレーション理論によると初期宇宙は加速的膨張によって宇宙がアイロンをかけられたように真っ平になるので,100兆分の一の精度の微調節も自然におきます。
と。そして,こう締めくくります。
科学とは,自然を理解するたる目に新しい理論を構築していく作業です。実証的検証がその重要なステップであることは言うまでもありませんが,科学の進歩とは,…ある分野から生まれた新しいアイデアが科学者のコミュニティの中でどのように受け入れられていくか,それがどれだけ新しい研究を触発しているかということも,その分野の進歩を測る重要な目安だと思います。
いま物理の最前線は,その意味で沸騰していると言っていいのかもしれない。ガイア理論のジェームズ・ラブロックがガイアシンフォニーの第4番で,こういっていた。
答えは直観的にわかり,自分を納得させるのに2年かかり,仲間をわからせるのに3年かかる。
ひとつの斬新なアイデアがパラダイムを崩し,新しいパースペクティブを開く。その醍醐味を十分知らしめる本になっている。
僕などは,宇宙が膨張している,と初めて聞いた時,その外はどうなっている?という疑問を持ったものだ。本書はそれに,間接的だがひとつの答えを出してくれていた。それが僕には拾いものであった。
ビッグバン=大爆発というと,空間の一点から,爆発物が外向きに広がっていく様子をイメージするかもしれません。そうすると,爆発物がまだ届いていないところはどうなっているのか疑問になります。しかし,宇宙のビッグバンでは,空間自身が膨張するのです。空間の膨張とは「二点間の距離が広がる」ことですから,必ずしもその空間の「外側」は必要ありません。箱が外側に向かって拡張しなくても,箱の内部の縮尺が変化すれば,二点間の距離は広がったり狭まったりします。(中略)
例えば,あなたの目の前に左から右に無限に伸びているゴムひもがあると思ってください。無限なので両端はありませんが,それでも,ゴムが伸びれば,二点間の距離は広がるし,縮めば二点間の距離は狭まります。つまり,無限の空間でも,膨張や収縮はできます。
きっとよくある質問なのでしょう。手慣れた答えです。そして思ったのは,たぶん大きさのイメージが理解を超えているのだろう。宇宙誌膨張しているという時,ゴム風船をイメージする。どうもそうではない。しかも距離に比例する速さで遠ざかっている。
距離が遠いほど遠ざかるのなら,あるところから先の銀河が地球から遠ざかる速度は,光速を超えてしまうでしょう。拘束を宇宙の制限速度としたアインシュタイン理論に反すると思うでしょうが,あの理論は宇宙の中での移動速度に関するものですから,宇宙そのものが超光速で膨張することまでは禁止していません。
では,超光速で遠ざかっている銀河は,地球から観測できるでしょうか。答えはノーです。膨張が続いている限り,その光は地球に届きません。実際,最新の観測結果によると,宇宙の膨張は止まるどころか,100億年ごとに二点間の距離が倍になる勢いで加速しています。
46億年の地球の歴史よりはるかに遠い昔が,仮に光が届いたとしても,今地球に届くのだと考えると,途方もない感覚にとらわれてくる。とても人間の間尺では測りきれないのはやむを得ないだろう。
参考文献;
ブライアン・グリーン『宇宙を織りなすもの』(草思社)
ブライアン・グリーン『エレガントな宇宙』(草思社)
市村弘正『「名づけ」の精神史』(みすず書房) |
|
朝敵 |
|
水谷憲二『「朝敵」から見た戊辰戦争』を読む。
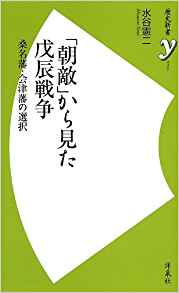
決断とは,覚悟のことだ。覚悟とは,何かを捨てる覚悟だ。その意味で,何かを決断する時,選択肢が浮かんでいる。決定する以上,情勢に流されてとか,事態に追い詰められてということでは受け身だ。追い詰められても,自分にとっての意味を考えながら,主体的に考えていくものでなくてはならない。そこで思い出すのは,勝海舟です。
維新時,最大の危機の徳川宗家を残したのは,勝海舟の政治力です。
鳥羽伏見で敗走してきた慶喜をはじめとする幕閣の面々に,勝はこう言い放ちます。
慶喜公は,洋服で,刀を肩からコウかけて居られた。己はお辞儀もしない。頭から皆に左様言うた,アナタ方,何と云う事だ。此れだから私が言わない事じゃない,もう斯うなってからどうなさる積りだ,とひどく言った,上様の前だからと,人が注意したが,聞かぬ風をして十分言った。刀をコウ,ワキにかかえてたいそう罵った,己を切ってでも仕舞おうかと思ったら,誰も誰も,青菜の様で,少しも勇気はない,かく迄弱って居るかと,己は涙のこぼれるほど嘆息したよ。
松浦玲は,こう書いている。
「失意の将軍と,失意の回収との出会いである。その失意の内容は二人以外にはわからなかったろう。慶喜と海舟とは,お互いの考え方の一致点と相違点とを心得ている。そうしていま,その相違点・一致点を含めて,全部がだめになってしまっているのだ。海舟はここで,すべてを投げ出してしまってもよかった。慶喜の方は,すでになかばなげだしている。」
しかし海舟は投げ出さない。彼が幕府に登用されて以来の流れの中で,「自己の技術と思想をかため,それを人につたえ,そのことによって反幕勢力の中にも人的なつながりをつくってきた」。その中心に,「かつて海舟が,幕府の頼むべからざるゆえんを教えた西郷隆盛がたっている。極端にいえば,元治元年の時点で海舟が一度幕府を見はなし,そのことを西郷に伝えたからこそ,現在の状態が起こっているともいえるのだ。海舟は,この後始末をつけなければならない。」
どうしようとしたか,その嘆願書で,薩長の「私」を非難する。官軍が居留地で外国人と衝突し,諸外国が軍艦を呼び,居留地を兵で固めようとしている。そんな中で,一方で,徹底恭順を貫徹する体制を整え,すでに大政を奉還し,他の大名と横並びである徳川家をただつぶすためだけに兵を動かすのは,「私」だと,勝は非難する。
結果として,徳川家は残った。では,一桑会と呼ばれて,鳥羽伏見の責任を問われた,会津,桑名はどうしたのか。本書は,会津ではなく,桑名藩生き残りを中心に描いている。しかし,一人の勝もいない,一人の慶喜もいない気がする。むしろ行きがかりから,全面戦争に走った会津藩に眼が向きがちだ。
桑名の当主,松平定敬は,慶喜とともに海路江戸へ逃げ,一時恭順の意を示しながら,家臣とともに,仙台,函館と最後まで,反政府側にとどまり続けた。だが,他方,戦闘力のほとんどを出陣させた藩側は,朝敵とされ,地理的にも,真っ先に征討軍の矢面に立たされて,意思決定を迫られる。藩論は,三つに分かれる。
・開城東下論 跡継ぎ万之助(十二歳)を擁して江戸へ向かう
・恭順論 藩主定敬の実兄が藩主の尾張藩による周旋
・守戦論 籠城して末代まで名を残す
結局,藩論がまとまりきらず,というかまとめきれず,神饌で開城東下論と決めたが,それでも異論続出してまとまらず,最終的に恭順に決まったという。戦うと言ったところで,戦闘主力は藩主とともに藩外の大阪ないし江戸におり,籠城のしようも,開城東下論もないのだ。それをまとめきれない状態で,腰砕けになったに近い。
それは,西国諸藩においても同様で,慶応四年一月三日鳥羽伏見で開戦後,僅か三日で新政府の勝利が決定すると,七日には慶喜追討令,11日には諸藩に率兵出京を命じている。事態の急変についていけている藩などない。土佐の山内容堂ですら,鳥羽伏見の戦いを会桑と薩長の私闘と見ていたほどなのだ。わずか一か月で,個々に孤立した諸藩は,横並びに,新政府に服していく。
結局,征討軍への出兵か資金提供かを求められて,それに応ずる形で,西国各藩は,新政府に組み込まれていく。朝敵と名指された藩も,そうでない藩も,結果として雪崩をうって右へならえしていく。個々の気概等々吹き飛ばすほどの時代の奔流を前に,各藩が孤立して意思決定をせざるを得ない時代状況はよくわかる。その意味で,なおのこと,勝の卓越した時勢観,交渉術が目を見張る。
転々と転戦した松平定敬は,函館陥落前に投降し,罪一等が減じられ,津藩へ永預となる。桑名藩は四割位の減封ながら,藩を存続させた。ほぼ壊滅的な戦いをした会津藩とは好対照で,確かに生き残りをはかった留守部隊の責任者の酒井孫八郎の苦労はよくわかるが,言ってみれば,ただ恭順し,嘆願しただけだ。
他の藩が,かようにほとんどがなすすべを知らず,呆然としている中で,東北諸藩は,東日本政権樹立という夢とビジョンを持っていたとされる。ただ武名と意地のみで,東北諸藩の戦争があったのではないし,会津戦争があったのではない。そのあたりは,著者とは見解を異にする。ただ時勢に合わせて,周章狼狽するだけではなく,その中で,大義と名分を立て,大きなビジョンを持って会同した東北諸藩は,会津を中心に,単なる武辺ものの意地で戦ったのではない。そのあたりは,星亮一『奥羽越列藩同盟』に,詳しい。考えてみれば,薩長土肥熊といった西南諸藩を除けば,山川浩,雲井龍雄,河井継之助等々錚々たる顔ぶれなのだ。
では,どうしたらよかったかが,誰が,是非が言えるのだろうか。
会津藩,桑名藩の戊辰戦争の結末を,こういう数値を出している。
会津藩
死者数 約2500名
領地 会津23万石から斗南3万石へ転封
藩主の処罰 松平容保,鳥取藩へ永預
桑名藩
死者数 約100名
領地 桑名11万石から6万石へ減封
藩主の処罰 松平定敬,津藩へ永預
犠牲だけで是非は言えない。まして数だけでは,言えない。ただ,死者については,国内戦をしていない桑名は戦闘員である藩士だけだが,会津は,籠城前,多くの婦女子,老人が自害している人数も含まれている。結果から是非は言えないけれども,そこには大きな差がある。しかしいずれをとっても,いずれにも悔いはある。ただ,選択してか,選択を強いられてか,そこにそれぞれの価値観による判断があるだけだろう。
あえて言えば,強いられてでもなく,なすすべもなくでもなく,いやいやでもなく,横並びしただけでもなく,その場で最善の決断をためらわずになした,勝の決断を取る。
松浦玲はいう。
「むこうが兵を向けてくるかぎり,たとえ官軍の名前をもっていようと,薩長側が『私』だという論法は,海舟の胆の中にこうして確率された。この『公』『私』の論は,彼が十数年鍛えぬいてきたものだけに,きわめて強固な信念となっている。彼はこの論法で,西郷との会談をピークとする幕府瓦解始末を乗り切ろうとするのである。その論法が正当かどうかはここでは問うまい。ひとは状況にしたがって自分の真価をもっともよく発揮できる生き方を確立する権利をもっている。」
この瞬間に真価を発揮した勝海舟は,維新前後の中で,最も輝いている。
参考文献;
水谷憲二『「朝敵」から見た戊辰戦争』(歴史新書y)
松浦玲『勝海舟』(中公新書)
松浦玲『徳川慶喜』(中公新書)
星亮一『奥羽越列藩同盟』(中公新書) |
|
足軽 |
|
早島大祐『足軽の誕生』を読む。
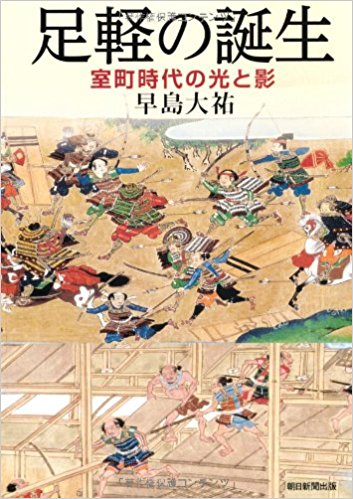
処士横議という言葉があったと思う。本書を読んで思い出した。幕末,藩の覊絆を離れ,士農工商の身分を超えて,下級武士から郷士,豪農までが,国を出て諸国で勝手に国を憂い,議論をして,結果として彼らの多くは薩長から見捨てられていくことになるが,そのエネルギーは混沌と言っていい。幕末,その嚆矢を放ったのは,大阪天満の元与力大塩中斎であった。その彼をはじめとする下級の武士は,近辺豪農たちと血縁を結びながら,身分社会末期の統治機構の機能不全という混迷に立ち向かった。いま日本は,大塩中斎の立ち向かったと同様の混迷の中にある。身分の固定と階級社会に近い格差の固定は,社会を閉塞し,いらだつエネルギーは個人の爆発としてしか発揮できないジレンマの中にある。
本書は,丁度応仁の乱前後,寺社や公家の荘園を管理していた地下の国人たちが,時代の変化,鎌倉と京都という二重権力の時代から,京都で武家が室町幕府として実権を一元的に握る時代へと移った時代の趨勢にのって,荘園の主である公家や寺社から守護である武家へと主を乗り換えていく。それは,単に村や地域の顔役であった荘官層,土豪層だけではなく,その荘園の民の各層までが,武家の被官となり,中間・小者として村々から出ていく,あるいは覊絆を脱する機会として出ていこうとする。
しかし京は今のような街ではない。商品を商えるのは,朝廷や幕府から売買の権利を得ている神人や供御人であり,寺社造営の建築に携われるのは,寺社から大工職という権利を安堵されたものだけだ。残りは,か細い地縁血縁を頼るほかは,乞食か盗賊に落ちるしかない。それでも,諸国から牢籠人と呼ばれる浪人もあふれる。その人たちは,グレーゾーンといわれる五条,六条から九条にかけての洛中洛外の境域的地域などに蟠踞する。あるいは武家宿所,寺社といった治外法権的に場所にもたむろしている。
彼らは何をしていたか。博打である。特に流行ったのが四一半と呼ばれた博打。そこでは,寺僧,武家,荘民,牢人,盗賊が多数寄り合って,博打に興じている。そこでは,「掛け金が喧嘩のもとになった半面,彼らの間に独特の連帯・つながりをもたらしたのではないか」という。
このなんというか,身分を超えたつながり方は,尋常ではない。すでに,時代のマグマが活性化しているといってもいい。まさに幕末,各層を超えてつながったエネルギーとよく似ている。
室町幕府は,威令が届かず,土一揆や徳政一揆の鎮圧に,征伐の軍が編成できず,結局現実的に動員可能なものを優先する。そうして彼らが正規軍の中に編成され,応仁の乱では,かつての暴れ者が足軽大将になって登場する話を紹介している。たとえば,侍所所司代として陣頭に立った多賀出雲は,洛中の浮浪の徒を組織化したという。また骨皮道賢という目付は,河原ものか野伏上りと言われ,かつて都鄙悪党のリーダーであり,部下は中間・小者ばかりなのである。その人たちが,幕府の威令を保つために活躍する。
幕府の機能不全から,各層から,ふさわしい人材が自分の居場所を見つけ,幕府の要職を占め,あるいは勝手に自分の利益のために,平然と将軍の上意を騙って,己の意を通そうとする。すでに下剋上の戦国へと踏み出している。ここにも幕末との類似が見える。幕末の幕府を担う逸材の多くは,勝海舟をはじめ,武家身分の埒外から登場している。
村上一郎は,名著『草莽論』を「草莽とは,草莽の臣とは違う」と書き始めた。草莽とは,孟子の「国に在るを市井の臣といい,野に在るを草莽の臣という。皆庶人なり」とあり,地方にひそむ庶士を草莽の臣と呼ぶ。その封土内に住んでいるから,君主に対しては臣であるが,仕えている臣とは同じではない。草莽は草茅に通じ,草野,草深いあたりに身を潜め,たとえ家に一日の糧がなくとも,心は千古の憂いを懐くという,民間慷慨の処士であり,それこそが維新に噴出してきた草莽の典型だと,村上は言っていた。松蔭の「恐れながら天朝も幕府もわが藩もいらぬ。ただわが六尺の微軀あるのみ」といったときの,草莽崛起とはそんな意味だという。
ただ個人的には,このファナティックなマインドが突破力を持っていることは信ずるが,とてもついてはいけない。むしろ,松蔭の『講孟余話』をたしなめた山県太華の,冷静・理知的な評が好きだ。松蔭の華夷の弁について,こう言っている。
「我が国のひとが,漢土の言葉に倣って,日本を自称して中国といい,すべての海外の国を蛮夷と称するのは,漢土での意味とは違っている。漢土で昔から中国と夷狄の別があるのは,中国は礼儀を尊ぶ国であって,中国の外の国で,世々朝貢して中国の属国となっていながら,遠方のため王化が及ばず,中国の礼儀の礼儀を守ることのできぬ国を号して夷狄といっていやしめた。」
にもかかわらず,漢土の例に倣って,わが国の攘夷論は,自国を中国といい他国を夷狄といい,時刻を尊く,他国をいやしいというべき論拠がないと言っている。しかしこの正しさは,いまも,昔も沸騰した時代の世論に通用しない。確かに,その時正しいことを言う人は,その時代,体制の享受者だから,その正しさを言うことが,自己弁明のにおいをもっている,ということはよくわかる。しかし理非曲直をきちんと正せないものに,時代をつくる資格はない,僕はそう信じている。だから,ファナティックな主張には,聞く耳は持つが,たぶん一緒に行動する友にはならないだろう。
時代の覊絆や格式が融けていく時,その隙間から人材が湧いて出る。いま日本は格差が固定化し,身分とは異なるが,階層が固定化しつつある。その閉塞感を打ち破る変革を日本人が自分の手でやれるかどうかか問われている気がする。
ペリー来航,第二次大戦の敗戦,石油ショック,すべて外圧だ。そこで時代が大きく変わった。考えてみると,応仁の乱から,戦国期は,自分たち自身で国の枠組みを壊し,溶かした時代であった。それが,何をきっかけにできたかといえば,室町幕府という統治機構の機能不全だ。今日,日本は議会制民主主義という統治機構が機能不全に陥っている。その意味で,大きな崩壊と融解の時期が来ているのかもしれない。
ただこのとき,ともすると,我が国は武に走りがちだ,侍大好きの人たちが多いから。しかしそういう場合は多く失敗してきた。これからは,もっと視野広く,全焦点(パンフォーカス)のモノの見方で,次世代を描きたいものだ。横井小楠が,武からの脱皮を懸命に模索したように。
参考文献;
早島大祐『足軽の誕生』(朝日新聞出版) |
|
わかりあえないこと |
|
平田オリザ『わかりあえないことから』を読む。

※
企業の人材担当者は重視する能力のトップにコミュニケーション能力を上げる,という。しかし,そのコミュニケーション能力の内実がはっきりしない。学生は,「きちんと意見が言える」「人の話が聞ける」「空気を読むこと」等々という。しかし,著者は,企業が求めるコミュニケーション能力は,ダブルバインド(二重拘束)に陥っている,と指摘する。たとえば,自主性を重んじる,と常日頃言われ,相談に行くと,「そんなこと自分で判断できないのか,いちいち相談にくるな」と言われる。しかしいったんトラブルが起きると,「なんできちんと上司にホウレンソウしなかった」と叱られる。
これは,創造性や商品開発でもある。「それぞれの創造性を生かす」と言いながら,指示されたこと以外をする余地はあまりない。勝手なことをしても,上司は無視する。有名な例では,大手家電メーカーの技術者がある技術を開発し,上司に提案した。なんとその上司は,「うちのような大手がそんなことをやれるか,ほかにやるところがあるだろう」と拒まれ,挙句,本人は起業し,その技術がいまや家電各社に採用されている,という。
コミュニケーションでも本音と建前がある。たとえば,異文化理解能力,つまり異なる文化,価値観を持った人に対しても,きちんと自分の主張を伝えることができる能力でグローバルな経済環境で力を発揮してもらう。しかし一方では,上司の意思を察して機敏に行動する,会議の空気を読んで反対意見は言わない,輪を乱さない等々が暗黙のうちに求められている。
こんな矛盾した能力が求められているが,求める側がその矛盾に気づいていない,ダブルバインドの典型だ。ベイトソンは,これが統合失調症の原因だという仮説を提起したことがある(今は否定されている)が,例えば,親が「体さえ丈夫ならいい」と一方で言いながら,成績が悪いと怒り出す,こうした例と比べると,異文化理解力と同調圧力のはざまで,コミュニケーションに戸惑う状態が目に見える,と著者はいう。
著者が全国の小中学校でコミュニケーションの授業や国語教材開発を通して,気づいたのは,コミュニケーションの意欲の低下。
特に単語でしゃべる。「ケーキ」「というように。しかし子供が少ないから,優しい母親が,それだけでわかってケーキを出す。子供に限らず,言わなくて済むなら,言わないように言わないように変化する。しゃべれないのではなく,しゃべらない。能力ではなく,意欲の低下。これは学校でも同じだ。少子化で,小1から中3まで30人一クラスというところが結構ある。いくらスピーチの練習をしても,お互いに知り尽くしていて,いまさら話すことはない。少子化が「ボディブロー」のように効いている,と著者はいう。
「伝えたい」という気持ちは,「伝わらない」という経験からしか来ないのではないか。いまの子どもたちには,その経験が不足している,という。
そこで,著者は,現在のコミュニケーション問題を,二つの切り口から提起する。
ひとつは,コミュニケーション問題の顕在化,
もうひとつは,コミュニケーション能力の多様化。
第一の点については,こう言っている。
若者全体のコミュニケーション能力は,どちらかと言えば向上している。「近頃の若者は……」と,したり顔で言うオヤジ評論家たちには,「でも,あなたたちより,いまの子たちの方がダンスはうまいですよ」と言ってあげたいといつも思う。人間の気持ちを表現するのに,言葉ではなく,たとえばダンスをもって最高の表現とする文化体系があれば(中略)日本の中高年の男性は,もっともコミュニケーション能力の低い劣った部族ということになる。
リズム感や音感は,いまの子どもたちの方が明らかに発達しているし,ファッションセンスもいい。異文化コミュニケーションの経験値も高い。けっしていまの若者たちは,表現力もコミュニケーション能力も低下していない。
事態は,じつは逆ではないか。
全体のコミュニケーション能力が上がっているからこそ,どんなときも一定の数いる口下手な人が顕在化したのではないか,と著者はいう。
かつては,そういう人は職人や専門技能者になっていった。「無口な職人」だ。しかしいま日本の製造業はじり貧で,大半は第三次産業,いわばサービス業につかざるを得ない。それは製造業から転職した場合も,同じ問題に出会う。大きな産業構造の変化の中,かつての工業立国のまま,「上司の言うことを聞いて黙々と働く産業戦士を育てる仕組みが続く限り,この問題は,解決しない」という。
必要なのはべらべらしゃべれることではなく,「きちんと自己紹介ができる。必要に応じて大きな声が出せる」その程度のことを楽しく学べるすべはある,と著者はいう。
もうひとつの,コミュニケーションの多様化については,ライフスタイルの多様化によって,ひとりひとりの得意とするコミュニケーションの範疇が多様化している,という。たとえば,一人っ子が2,3割を占める。大学に入るまで親と教師以外の大人と話したことがないという学生が一定数いる。あるいは母親以外の年上の異性と話したことがないものも少なくない。身近な人の死を知らないで医者や看護師になる学生もいる。
いま中堅大学では就職に強い学生は,体育会系と,アルバイト経験の豊かなもの,つまり大人との付き合いになれている学生だ。ここで必要なのはコミュニケーション能力ではなく,慣れの問題ではないか。だから,著者は学生にこういう。
「世間でいうコミュニケーション能力の大半は,たかだか慣れのレベルの問題だ。でもね,二十歳過ぎたら,慣れも実力のうちなんだよ」
ではどう慣れされるコミュニケーション教育をするのか。二つの例を紹介している。
ひとつは,著者が手掛けた中学国語教材の中で,「スキット」を使った劇つくりをさせる。ストーリーは,朝の学校の教室で,子供たちがわいわい騒いでいる。そこへ先生が転校生を連れてくる。転校生の自己紹介と,生徒から転校生へのいくつかの質問。先生は職員室へ戻り,生徒と転校生が残されて,会話していく。
このテキストを,班ごとに配役を決めて,演じる。先生がくるまでワイワイ何の話をするのか,転校生がどこから来たのか,どんな自己紹介をするのか,先生のいなくなった後,どんな話をするか,すべて生徒たちに決めさせ,台本をつくり,それを発表する。
従来のように正解を持っていて,それによって訂正するやり方を取らず,すべてを任せる。
「日常の話し言葉は,無意識に垂れ流されていく。だからその垂れ流されていくところを,どこかでせき止めて意識化させる。できることなら文字化させる。それが確実にできれば,話し言葉の教育の半ばは達成されたといってもいい。」
という。ここに狙いがある。自分たちが使っている言葉を意識する,たとえば「ワイワイ話している」ことを具体的に検討していく中で,話さない子もいる,そこにいない子もいる,遅刻する子もいる,寝ている子もいる等々,そうしたことを意識することを通して,話さないこともいないことも,表現として感ずることになる。
いまひとつは,高校生,大学生,大学院生との演劇ワークショップ。
「わたしの役割は,せいぜい,特に理系の学生にコミュニケーション嫌いを少なくして,余計なコンプレックスを持たせないこと」
と言い切り,コミュニケーションの多様性,多義性に気づいてもらうことだ,という。使っている教材の一例は,列車の中で話しかけるというエクササイズ。
四人掛けのボックス席で,知り合いのAとBが向かい合って座っている。そこにも他人のCがやってきて,「ここ,よろしいですか?」というやり取りで,Aさんが,「旅行ですか?」と声をかけて世間話が始まる,というスキットを使う。
現実の場で,話しかける人が実は少ない。平均的には1割程度という。半分以上が話しかけず,場合による,というのが2,3割。場合によるの大半は相手による,という結果らしい。しかも各国でやってみると,様々。開拓の歴史が浅いアメリカやオーストラリアは話しかける。イギリスの上流階級は,人から紹介されない限り他人に話しかけないマナーがある等々。日本語や韓国語は敬語が発達しているので,相手との関係が決まらないと,どんな言葉で話しかけていいかが決まらないところがある。仮に相手が赤ん坊を抱いたお母さんなら,何か話しかけるかもしれない。
「旅行ですか?」という簡単な言葉をどう投げかけるかを考えることを通して,
自分たちの奥ゆかしいと感じるようなコミュニケーションの特徴が,国際社会では少数派であり,多数派のコミュニケーションをマナーとして学ぶ必要があること
そして,高校生の9割5分は自分からは話しかけないという,だからこの言葉が,その子たちのコンテキスト(その人がどんなつもりでその言葉を使っているかの全体像)の外にあるということ
普段使わない言葉のもつずれが,コミュニケーション不全になりやすい,ということ
を確かめていく作業になる。そして,「他人に話しかけるのは意外にエネルギーのいるものだ」「そのエネルギーのかけ方や方向も人によって違う」ということを実感してもらう。これも慣れる流れにはいるのだろう。
ここまで紹介して,コミュニケーションを考えていくことが,単に個人のコミュニケーション能力の問題に還元できない,社会的,文化的,教育的背景の中で生じていること,それを全体に国としてやる姿勢は見られず,何か方向違いの復古性だけが際立ち,ますます子供たちを追い詰めていく危惧を感じた。
ともすると,コミュニケーションをスキルと考えがちだ。しかし,そのスキルには,シチュエーションがある,バックグラウンドとなる文化的社会的背景がある。コミュニケーションは,その中で浮かんでいる,あぶくと考える。例えば,ヒトと話すときは,こうしましよう。こういうやり方をするといいですわ,等々。そういうあぶくの立て方をどれだけ学んでも,本当に意味があるのか。著者はそう問いかけているように思う。それは,あくまで,コミュニケーションの出来不出来を個人の能力やスキルに還元しているからだ。それができなければ,本人は追い詰められていく,ますます自分がため人間だ,と。コミュニケーションスキルを好意で教えていく人間が,実は追い込む側に加担している。
※※
いま日本人に要求されているコミュニケーション能力の質が,大きく変わりつつある,と著者は言う。かつては同一民族という幻想でくくれたが,いまもう日本人はバラバラなのだ。この新しい時代には,バラバラな人間が,価値観はバラバラなままで,「どうにかうまくやっていく能力」が求められている。著者は,「協調性から社交性へ」とそれを呼んでいる。
わたしたちは「心からわかりあえる関係をつくれ」「心からわかりあえなければコミュニケーションではない」とすりこまれてきたが,「もう日本人はわかりあえないのだ」と,著者は言い切る。それを,たとえば,高校生たちに,次のように伝えているという。
「心からわかりあえないんだよ,すぐには」
「心からわかりあえないんだよ,初めからは」
この点が,いま日本人が直面しているコミュニケーション観の大きな転換の本質,という。つまり,心からわかりあえることを前提にコミュニケーションというものを考えるのか,人間はわかりあえない,わかりあえない同士が,どうにか共有できる部分を見つけ,広げていくということでコミュニケーションを考えるか,国際化の中で生きていくこれからの若者にとってどちらが重要と考えるか,協調性が大事でないとは言わないが,より必要なのは社交性ではないか,という。
金子みすゞの「みんなちがって,みんないい」ではなく,「みんなちがって,たいへんだ」でなくてはならない,とそれを表する。この大変さから目を背けてはならない,と。
ところで,日本語では,対話と会話の区別がついていない。辞書では,
会話=複数の人が互いに話すこと,またその話。
対話=向かい合って話し合うこと,またその話
とする。著者は,こう区別する。
会話=価値観や生活習慣なども近い親しいもの同士のおしゃべり
対話=あまり親しくない人同士の価値観や情報の交換。あるいは親しい人同士でも,価値観が異なるときにおこるそのすりあわせなど
日本社会は,対話の概念が希薄で,ほぼ等質の価値観や生活習慣を持ったもの同士のムラ社会を基本とし,「わかりあう文化」「察しあう文化」を形成してきた。いわば,温室のコミュニケーションである。ヨーロッパは異なる宗教,価値観が陸続きに隣り合わせ,自分が何を愛し,何を憎み,どんな能力を持って社会に貢献できるかを,きちんと他者に言葉で説明できなければ,無能の烙印を押される社会を形成してきた。
たとえば,
柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺
という句を聞いただけで,多くの人々は夕暮れの斑鳩の里の風景を思い浮かべることができる。この均質性,ハイコンテキストな社会が,世界では少数派であると認識し,しかもなお,察しあう,わかりあう日本文化を誇りつつ,他者に対して言葉で説明できる能力を身につけさせてやりたい,それが著者の問題意識であることは,全編を通して伝わってくる。それは若者に限らず,同調するコミュニケーションしか身に着けないまま,転職を余儀なくされている中高年の元製造業技能者も同じ状況にある,という強い危機感でもある。
それは韓国に二十歳で留学し,海外での演劇上演,演劇ワークショップをこなしてきた著者の日本の現状への危機意識でもある。
その中で,コンテキストのずれのもたらすコミュニケーション不全を,強調している。こんな例を挙げている。
ホスピスに,50代の末期癌患者が入院してきた。この患者は,解熱剤を投与するのだが,なかなか効かない。つきっきりの奥さんが,「この薬,効かないようです」と看護師に質問する。看護師は,「これは,これこれこういう薬なんだけれども,他の薬の副作用で,まだ効果があがりません。もう少しがんばりましょう」と丁寧に説明をする。その場では納得するが,また翌日も同じ質問をする。看護師は,親切に答える。それが毎日1週間繰り返される。当然ナースステーションでも「あの人クレーマーではないか」と問題になってくる。そんなある日,ベテラン医師が回診に訪れた時,奥さんは,「どうしてこの薬を使わなきゃならないんです」と,例によって食ってかった。医者は,一言も説明せず,「奥さん,つらいねぇ」といったのだという。奥さんは,その場で泣き崩れたが,翌日から2度と質問をしなかった,という。
コンテキストを理解することは,誰にでも備わっているもので,特殊な能力ではない,と学生に説く,という。その場合,大事なことは,その能力を個人に原因帰属させないことだ。そうではなく,どうすればそういうことが気づきやすい環境をつくれるか,という視点で考えることだ。それをコミュニケーションをデザインする,と表現している。
わたしも,それはいつも感じている。組織内でコミュニケーション齟齬が起きると,個々人の能力に還元する。そのほうが楽だからだ。しかし人はミスをするし,勘違いもする,早飲み込みもする。その齟齬を置きにくい,しくみやルールをつくる。それはすでに当たり前になっている,復唱だが,同じ言葉を繰り返すことではない。自分の理解したことを相手にフィードバックするのだ。大体,しゃべったことではなく,伝わったことがしゃべったことなのだから。何を受け止めたかを必ず返すルールにする。それをたったいまからでもやろうとするかどうかだ。そこには,原因を個人ではなく,仕事の仕組み側にあるという認識がない限り,踏み出せないだろう。フールプルーフと同じ発想ではないだろうか。
最後に著者の言っていることを記しておきたい。
「いい子を演じることに疲れた」という子どもに,「もう演じなくていいんだよ,本当の自分を見つけなさい」ということが多い。しかしいい子を演じさせたのは,学校であり,家庭であり,周囲が,よってたかってそういう子どもを育てようとしてきたのではないのか,と。
第一本当の自分なんてない。私たちは,社会において様々な役割を演じ,その演じている役割の総体が自己を形成している。霊長類学者によれば,ゴリラは,父親になった瞬間,父親という役割を明らかに演じている,という。それが他の霊長類と違うところだという。しかしゴリラも,いくつかの役割を演じ分けることはできない。人間のみが,社会的な役割を演じ分けられる。
私も思う。いい加減,「本当の自分」という言い方をやめるべきだ。いまそこにいる自分がそのまま自分でしかない。いい悪いではなく,自分の価値もまた,何もしないで見つかるはずはない。必至で何かをすることを通してしか見つかるはずはない。まずは歩き出さなくてはならない。そこではじめて,自分の中に動くものがあるはずなのだ。
参考文献;
平田オリザ『わかりあえないことから』(講談社現代新書) |
|
もう一つの地球 |
|
レイ・ジャヤワルダナ『もう一つの地球が見つかる日』を読む。

映画『アバター』をはじめ,SFでは地球外生命体,エイリアンや異星人の住む惑星は,定番になっている。しかし,本書は,プラネットハンターたちの栄光と悪戦苦闘を,描いている。著者は,「アースツイン(地球の双子)の発見もそう遠いことではない」という。すでに,太陽系外惑星の数は,750を超え,2012年中には1000の大台を超える,と言われている。
もちろん,「太陽系外に地球サイズの惑星を発見したり,あるいはその存在を単に想像するのと,生命の存在を発見するのとでは全く次元の異なる話」であるし,かりにバイオマーカー(生命の存在を示す兆候)を発見しても,「単純な細菌によるものなのか高等な宇宙生物によるものなのかは区別がつかない」にしても,「銀河系内で技術文明をもつのはわれわれ人間だけだと考えるのは,思い上がりではないにしても,ばかげているように思われる。銀河系内には2000億個もの恒星があり,惑星もいたるところに存在しているようだし,宇宙には,生命のもととなる物質が豊富にあるから」だ,と著者は言う。だが,「地球外生命体が存在する可能性を考えるのと,その証拠を摑むのは全く別の問題」だ」とも言う。
そのための営々とつづくプラネットハンターの探索の歴史があるからだろう。この探索は,「この世界は一つだけなのか」という問いから始まり,最初に,カントが,「惑星は若い太陽を取り巻いている希薄な粒子雲が合体して生まれた」と提唱し,太陽系の内側にある惑星が高密度なのは,,重い粒子が太陽のそばに集まったためだし,外側にある惑星が巨大になったのは,はるかに大量の物質を集めることができたからだと,論じた。その後さまざまな曲折をへて,「現在考えられている惑星誕生の過程の大筋は,初期のカントの考えに似ている」という。つまり,惑星はありふれた存在だということになる。
だとして,数ある惑星の中で,生命に適した惑星の条件は何なのか。
まずは適度な大きさ。誕生したときの質量の大きさが地球の10倍を超える惑星は,周囲に残っている円盤ガス(恒星の周囲のという意味)を大量に集めて,木星や土星のような巨大ガス惑星になる。その表面に,陸地に相当する個体部分がない。逆に,惑星の質量が小さすぎると,待機を保持できず,水があっても,蒸発してしまう。また気候の安定に必要なプレートの相互運動があることで,大気,海,地殻の間で二酸化炭素などの物質が循環する。プレート運動が生じるには,最低でも,地球の1/3の質量が必要で,火星はそれを下回っている。
第二は軌道がほぼ円形になっていること。円形軌道なら惑星は一年を通じて均一の熱を中心星(恒星,地球にとっての太陽)から受け取ることができる。細長い軌道では,極端な場合,寒暖の差が激しすぎる。
第三は,惑星がどこに位置しているか。「ふさわしい」恒星の近くに位置していることが不可欠の条件になる。どのような恒星が,ふさわしいのか。ひとつは,生命が誕生して進化するのに十分な期間にわたって存続できるように,恒星の寿命が長いこと。大質量だと数億年で燃焼してしまう。質量の小さい赤色矮星は数千億年と長い。太陽は,100億年なので,寿命としては,その中間にある。また惑星の属している恒星の近くにどんな天体があるかも,重要だ。近くに恒星が密集していれば,生命には危険になる。太陽は,銀河系の外縁にあるのが幸いしている。
第四は,水の存在。その意味では恒星に近すぎても遠すぎてもいけない。液体の水が存在するのに適した温度になっている範囲を,「ハビタブル・ゾーン」という。地球は,太陽のハビタブル・ゾーン内に位置しているが,金星は,ハビタブル・ゾーンよりも太陽に近いところにあり,火星は,かろうじてハビタブル・ゾーンにとどまっている。
第四は,二酸化炭素とメタンの存在。初期の地球では,太陽はいまの70%しか明るくなかった。したがって地表は0℃以下であったとされる。そこで水が存在したのは,二酸化炭素とメタンの温室効果による。それは,プレート運動によって,大気中の二酸化炭素と海洋と地殻中の炭酸塩との間での循環によって温室効果が機能してきた。
第五は,酸素とメタンの共存。酸素とメタンは互いに相手を分解してしまうので,化学的には共存できない。したがって共存している場合は,地表の生物によって,絶えず生み出されていることを示している。
こう見ると,惑星の数は無数としいうほどあるかもしれないが,意外と,地球という存在の条件は厳しいのかもしれない。いや踏み込むと,惑星が何千というオーダーであることはあるだろうが,その中で地球になれる条件は隘路なのではないか。素人考えだが,そんな気がする。別に地球の特殊性を強調する気はないが。たとえばねハビタブル・ゾーンにあっても,ちょっと条件が違えば,火星のように,地球になりそこなう。
かつて,宇宙は膨張している,ということを読んだ時,その膨張し続ける宇宙の外は何があるのか,この宇宙を支えている世界とは何なのか,と瞬間に疑問に思ったものだ。ビックバンからこの宇宙が始まったとする。では,その前は何なのか。それは時間と空間について,問いを出していることになる。時間は非可逆であるとされるが,膨張した後,再び収縮するとするなら,その後,またビックバンを繰り返すのか,素人ながら,宇宙を考えていると,わくわくする。これをスピリチュアルに考えようとする向きがあるが,それは宇宙という膨大な広がりを,矮小化しているとしか思えない。人間の不遜さの現れに,僕には見える。いまあるこの人の尺度で測れない世界を,そのまま受け止めるとすると,少なくとも,他の生命体が住む惑星が発見された時,その認識の突破口になるのではないか。
著者はこう断言する。
「どんな形にせよ,地球外生命−たとえそれが原始的な生命であっても−科学の世界を震撼させる劇的な出来事になるはずである。その影響の大きさに匹敵するものと言えば,地球を宇宙の中心から追い出したコペルニクスの太陽中心説,人間も含め,地球上すべての種は共通の祖先の末裔であるとしたダーウィンの進化論くらいしかないだろう。もし生命が二つの惑星でそれぞれ独自に誕生できるなら,地球外の1000,さらには100万の惑星でも誕生するとしていけない理由がどこにあると言うのだろう。地球だけが生命の生息する惑星ではないことがはっきりすれば,その影響は計り知れないほど大きく,科学におけるパラダイム・シフトの引き金になるだけでなく,宗教から芸術にいたる人間のさまざまな営みに大きな変革をもたらすことになるはずだ。そんな劇的な瞬間の訪れは,もはや遠い将来にやってくるかもしれない出来事ではない。今後10年以内とはいかなくても,われわれが生きているうちに『その時』を迎えることになるだろう。」
我々の生きているうちにその日が来る。それを楽しみにしたい。その時何が起きるのかが,目撃できるのだ。わくわくするではないか。
参考文献;
レイ・ジャヤワルダナ『もう一つの地球が見つかる日』(草思社) |
|
脳のクセ |
|
池谷祐二『脳には奇妙なクセがある』を読む。
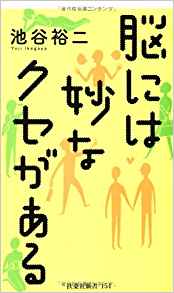
※
正直いって,本書は,『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な私』やアントニオ・R・ダマシオ『生存する脳』に比べると,焦点が一点に収斂していないせいで,読むほどに脳が沸騰するという体験はしなかったが,反面連載したものをまとめたという性格もあり,多様な脳に関する最新研究情報をもらったという印象が強い。
全体の印象として最も興味を惹かれたのは,最新の脳研究の最前線での結論もさることながら,仮説を検証するための様々な実験の工夫だ。仮説か問題意識かを確かめるために,研究者が知恵を絞っていろんな実験を工夫をしている様子が,なかなか興味深い。それは,たぶん成功した例しか出ていないので,死屍累々,様々な失敗の累積の上に,この成果があるのだろうと想像してみると面白い。いかに問題意識が最先鋭でも,それを現実に着地させて,どういう実験をすればそれが確かめられるかの発想がなければ役に立たないというのは,われわれの世界でも,どんな理屈も問題意識も,現実に検証しなくては何の価値もない。その意味ではまったく同じことが言えるのかもしれない。
今回は老化を巡ってそんなことで,自分の関心を惹いたものから拾ってみたい。
運動と学力の相関について,反復シャトル走と科目別の相関を調べた例がある。その運動能力の成績と算数が最も相関し,48%,国語読解力についても,40%もの一致率を示したという。読書の内容を理解するときは,脳の前頭前野や帯状野が活性化し,計算に際しては,頭頂間溝が活性化する。この領域は有酸素運動の時活動する部位なのだという。つまり,脳の老化は,体の老化に付随しているのではないか,というわけである。それはよくわかる。集中力や思考を持続するには猛烈な体力を必要とするのだから,そして,そもそも脳も肉体なのであり,日頃の鍛錬が必要なのは,足腰だけではないのかもしれない。
ところで,加齢はあまりいいイメージはないが,アメリカの調査では,人生に対する幸福感が,U字曲線を描く。4,50代が底で,そこから上昇する,という。そのことは脳の活動パターンからも,20歳前後と55歳以上の対比で,若者がマイナスに強く反応するネガティブバイアスを持つのに対して,年配者は年とともに,ネガティブバイアスが減って,プラス面に強く反応する,という。それも,伴侶を失ったり,重病を患ったりした経験のある人ほど,ネガティブバイアスは弱い,という。
穏やかでにこにこしている年寄りが多いというのは,いいことかもしれない。またいい社会なのかもしれないが,反面歳と共に悪い感情が減っていくということは,リスク管理に難があるということを意味する。振り込め詐欺が,これだけ周囲で厳しい制約を設けても,一向減らないのは,ある意味で,そこにいい面しか見ない,という老人特有の心理傾向が反映しているのかもしれない。とするといま取り組んでいるような社会的な対応では,老人の幸福感を動かす力がない,ということになる。後からもちろん後悔するかもしれないが,その相手にさほどの悪感情をもたないのかもしれない。本当か?
夢を描くことで夢は実現するということをいうが,それは未来を想像するときに活性化する前運動野があり,それは体の運動をプログラミングする部位でもある。体の動きが未来のイメージと関係がある,という。さらに未来をいきいき想像するには,海馬が活動する。だから,海馬が老化すると,生き生き未来を描けなくなる,というわけである。脳がふけると,夢が持てなくなる,のか?
高齢者のうつ病が増えている。うつ病の四割が60歳以上なのだという。確かに年齢とともに,寝ていても,昔ほど夢も見ない。幸せ感かどうか現状に安らげば,未来(そんなに先は長くないが)を夢見る必要性もない。心穏やで安定していれば,脳への刺激が減って,痴呆はともかく,うつというのはイメージしにくい。そのせいか,老人性うつは,薬で治る率が高い。で,池谷さんはこういう。
「心境の変化というよりも,むしろ生物学的変化が引き金になっている可能性が高いのだと思います。神経伝達物質の減少という器質的な変化です。」
さて,そこで,だ。では運動すれば,その伝達物質の減少が止められるのか,だ。アメリカ保険福祉省は,一日30分の運動を勧めている。しかし74%はそれを満たしていないそうだ。
もうひとつは,我々が選択行動をとるとき,損得比較をする眼窩前頭皮質であり,他にどんな可能性があるかを調べようとするのは前頭極皮質。いわば「情報利用」と「情報収集」のバランスを取って選択するように,脳の機能上なっている。しかし老化とともに,収集型であることをやめ,身近な人との会話だけで一日が終わってしまう傾向が強い。その意味で,様々な情報にアクセスするために,人とモノとコトとかかわることで,前頭極皮質を活性化する,ということが必要のようだ。
それは老人に限った話ではない。痴ほう症にならない三条件というのがある。①有酸素運動,②メタボにならない,③コミュニケーション,という。コミュニケーションというのは通信,交流,会話という意味も含める。いつもの人ではなく,いろんな人との会話が,脳を刺激するようだ。やはり,体力が肝心だ。
※※
かつてコミュニケーションを拒絶されたと受け止めると,脳にとっての衝撃は,実際に殴られたのと同じだといわれていると,読んだことがあるが,例えばこんな実験がある。
三人でバレーボールの練習をしている。初めは三人でボールを回しているが,そのうち被験者にボールが回らなくなる。自分以外は目の前で楽しく遊んでいるのをながめている,そんなのけ者状態にされた,心の痛んだ状態のとき,脳はどう反応するのか。仲間外れにされたその時,大脳皮質の一部である,前帯状皮質が活動する。前帯状皮質の活動が強い人ほど,強い孤立感を味わったという。
この部位は身体の痛みの嫌悪感に関係する。手足の痛むときに活動する部位が,心が痛むときにも活動する。このことについて,池谷さんは,こう書いている。
ヒトは社会的動物です。社会から孤立してしまっては,生きていくのがむずかしいでしょう。ですから,自分が除け者にされているかどうかを,敏感にモニターする必要があります。そのための社会監視システムとして,痛みの神経回路を使いまわすとは,見事な発明であったと言ってよいでしょう。
そこからこんなことを仮説として出している。
一見抽象的にも思えるヒトの高度な思考は,体の運動から派生している。
進化をさかのぼれば,動物は身体運動を行い,そのために筋肉と神経系を発明し,高速の電気信号を用いて,素早く運動を行おうとし,この神経系をさらに効率的に発達させた集積回路が脳,だというわけです。しかし,脳はさらに進化して,身体を省略することをする。
脳の構造で言えば,脳幹や小脳,基底核は進化的に古く,身体と深い関係がある。そうした旧脳の上に,大脳新皮質がある。大脳新皮質は,当初は,旧脳を円滑に動かす促進器であったのが,脳が大きくなるにつれて,大脳新皮質が大多数を占めるようになると,機能の逆転が起き,「ヒトの脳では,この臨界点を超え,大脳新皮質による下剋上がおきている」と池谷さんは推測する。
だから,大脳新皮質が主導権をもつヒトの脳では,身体を省略したがる。つまり,身体運動や身体感覚が内面化されることによって,脳は,「身体から感覚を仕入れて,身体へ運動として返す。身体の運動は,ふたたび,身体感覚として脳に返って」くる,そのループを,身体を省略して,「脳内だけで情報ループを済ませる」ようになる。この「演算行為こそが,いわゆる『考える』ということ」だと,推測する。その結果の,上記の心の痛みと体の痛みの共用ということが起きる。
そういうところが,言葉を使う面でもあらわれる。例えば,ひとに対して,「お前は何々だ」とラべリングするのも,相手の身体運動や行動癖を言葉によってラべリングすることで,感覚や身体運動を,脳内だけで完結していることだというのです。「時間にルーズだから遅刻する」というラベルは,よく遅刻する身体運動の頻度から,脳内でラベルづけしただけだ,という。脳内で自己完結して,理解したつもりになる,ということらしい。かつて「あなたは過去に蓋をしている」と言われたことがあるが,それは僕が,相手には何かを隠しているような不思議な印象を持ち,その理解をラベルづけでわかった気になろうとした,いわば脳の自己防衛反応だったと考えれば,なんとなく相手の気持ちもわかる。もっとも「蓋をしている自分」に気づかないだけだと言われれば,仕方がないが…。
言葉というのは,脳が誕生して5億年を1年の暦に置き換えると,大晦日の夜10時以降,というほど最近なのだが,
言語が逆に,我々の感覚を左右している。こんな例を挙げている。
青と緑の中間色を見た時,言葉でどう表現しようかと苦心する。メキシコ北部のタマフマラ語では,これに対応する言語がある。ロシア語圏でも,「明るい青」と「暗い青」に相当する単語を別々に持っていて,両者を素早く区別する。つまり,語彙の有無が認識力を左右している。さらに推し進めて,「自分や他人の感情に気づくことができるのも,言語を持っているから」だと研究結果が出ている。
このことから,敷衍すると,例のウィトゲンシュタインの言う,人は持っている言語によって,見える世界が違うというのは,脳的にもあたっていることになるらしいのだ。
ここで実感を書くと,実は老化とともに,身体が衰える。衰えることで,脳内で自己完結した思考は,貧弱になっていく気がする。なんたって健康な身体があるからこそ,脳内だけでの代用が可能だったからだ。で,ある年齢になると,身体を思い出す。必ずしも,健康管理のためだけではなく,脳の自己防衛のために,だ。何せ,意志する何十ミリ秒前には,意志させるよう脳が働き出しているのだから,意識は健康のためと思っているが,実は脳は自分の自己完結を強化しようとしているだけなのかもしれない。
そのせいか,最近身体や身体の感覚に妙に惹かれる。これも脳の自己防衛と考えるれば,それに従わないと,ぼけてしまうかもしれない。やばい!
※※※
直感とひらめきの違いについて,池谷さんはこんなことを言っている。
ひらめきは思いついた後に,その答えの理由を言語化できる。直感は,本人にも理由がわからない確信。ただなんとなくとしか言いようがないあいまいな感覚。根拠は明確ではないが,その答えの正しさが漠然と確信できる。しかし「直感は意外と正しい」という。ヤマ勘や思い付きではない。そして,ひらめきを,知的な推論,直感を動物的な勘,ひらめきは,陳述的,直感は,非陳述的,と説明する。
直感は,線条体や小脳が関与するが,ひらめきには,脳の働きとして,理詰めで正答が導ける場合と,相手の出方を推測しながら,判断しなければならない場合があり,同じひらめき型では,まったく脳の使い方が異なるようだ。ただ,ひらめいた瞬間,脳の広範囲が活性化すると言われている。それについては,ここでは触れられていないが,直感の時とは,少し違う気がする。直感は,パターンで感じ取る,という気がする。将棋や囲碁のプロが,蓄積した経験の中から,直感する場合,なぜかは説明できないが,それが結論として動かないことに変わりはない。
ではアイデアがひらめくときはどうなのか。
グレアム・ウォーラスによれば,着想の王道は,
① 課題に直面する
② 課題を放置することを決断する
③ 休止期間を置く
④ 解決策をふと思いつく
だそうだが,特に③の熟成期間が重要らしい。ある実験では,課題を長い時間起きて考えていた人より,睡眠をとった人のほうが,成績が良いという結果が出ているらしい。特にREM睡眠と呼ばれる,浅い眠りの多い人ほど好成績だったという。
こうしたステップでは,ジェームズ・ヤングの『アイデアのつくり方』が最近では有名だが,そこでは,
第一段階 資料集め
第二段階 集めた資料の加工 【ここまでが準備】
第三段階 孵化段階 【孵化(あたため)】
第四段階 アイデアの誕生 【啓示(ひらめき)】
第五段階 アイデアの具体化 【検証】
とある。たぶん,②と③が孵化プロセスにあたる。
ヴァン・ファンジェの定義以来,創造性とは既存の要素の新しい組み合わせとされており(川喜多二郎氏は,これを,「本来ばらばらで異質なものを結びつけ,秩序付ける」といった),その組み合わせを見つけた時,脳内の各所とのリンクというかたちで出現するのではないか,とひそかに考えている。そのための準備期間がいる。今まで考えられていたものごとのつながりを崩して,新しいつながりを見つけるには,ある種の視点転換がいるのだから。
これで思い出したのだが,数学者の岡潔さんが,タテヨコナナメ十文字,考えに考えて考えつめて,それでだめなら寝てしまえ,といっていたのと符合するのではないか。ただ,この眼目は,ただ熟成すればいいのではなく,その前の段階で,脳をフルに使いこんで,考えつめたプロセスがあってこそ,寝てしまうことで,その間,トンネルビジョンに陥っていた着想を,違う視点から考えるきっかけになる,というところではないかと思う。
そこで,睡眠ということが,かぎになる。
睡眠中の脳の活動については,まだ決定的な答えは出ていないようだが,睡眠の役割の一つは,「記憶の整序と固定化」にあるといわれる。実際,レミニセンス現象と呼ばれる睡眠効果が実験で確かめられている。たとえば,ある訓練をして,12時間後,やってみると,平均50%に低下するのだが,その後7時間睡眠をとると,前日の訓練直後の成績に戻る,という。
睡眠でも,浅い眠りの時は,海馬がシータ波という脳波を出し,情報の脳内再生を行っている。逆に深い眠りの時は,大脳皮質がデルタ波を出し,記憶として保存する作業を行っている,とされる。ということは,深い眠りの時に,効果的にデルタ波をだせば物覚えが良くなるということが実験で確かめられている。
ここで問題は海馬である。記憶の再生ということは,その前につめに詰めたことを,もう一度違う形で再生していることを意味する。自分の経験では,すごく緊張する,新しい場,たとえばワークショップに初参加したような夜,すさまじく刺激的な夢を見た,という経験をしたことがある。夢は記憶の再整理ともいわれるが,このプロセスで,意識的に眺めていたものを,俯瞰したり,別の文脈(夢は多くそんな,まったく別のシチュエーションで展開されるケースが多いように感じる)に置かれることで,着想につながることがあるのではないか,という気がする。
自分の体験では,脳内の着想や問題意識は,無意識の中で,ずっと続いていく気がしている。そして,ふと,何か関係ないものの中で,たとえば人との会話や読んでいる本の中から,刺激を受けて,ふいに着想することがある。これは,メモをとりつづけていると,同じ傾向の発想が断続的に思いついていく,そしてそれが少しずつ発展しているのに気づく。その意味では,休止とは,そこにのめりこむことから,一旦離れる,ということも含んでいるのかもしれない。
※※※※
自分は神仏の加護は信じたいので,我が家には,荒神様もあるし,神棚もあるし,お札も結構貼ってあるし,小さいながら仏壇もある。年の初めには初詣もする。その程度の習慣に従っているだけだ。ご利益以上のものを得たいとも思わないし,神を近くに感じたこともない。その代り金縛りにもあわず,神秘な体験もまったくない,スノッブそのものの小市民だ。それを不幸と見る人もいるかもしれないが,どうせ死んでしまえば,ハイそれまでなのだから(そうではないと言われたこともあるが,わからないことはわからない),いまの自分には関係ない,という考えの持ち主だから,冒涜と言われればその通りだろう。
ところで,人があるところにほぼ宗教があるということは,ヒトが神なるものに親和性を本能的に持っている,つまり神を感じる脳回路をもっているのではないか,そう考える科学者の問題意識は面白い。
その実験のひとつに,「こめかみよりも少し上,脳で言えば側頭葉に相当する部分を磁気刺激すると,存在しないはずのモノをありありと感じる」のだそうだ。実験すると,40%の人が何らかの知覚体験をしたという結果が出ている。「奇しくも英語でこめかみはtemple,つまり『聖なる殿堂』という意味」だ,と。
この側頭葉が原因で起こすてんかん発作では,1.3%が神秘体験をするといわれている。かつての上司が,その発作を起こしたのを目撃したことがあるが,それで思い出したのは,ドストエフスキーだ。彼も,その病をもち,その体験を語っていたし,小説にもした。
ただ個人的には,宗教ということと神秘体験をすることと結びつけるのはあまり好きではない。アメリカのエプライ博士は,「宗教心が強い人は自己中心的だ」と主張しているという。「神の思し召し」というのは,神の意図なのではなく,無自覚な本人の個人的願望が反映されている,という。
それでふと思い出したのは,「はからい」という親鸞の言葉だ。「はからい」は如来の本願のほうにあり,人間の側にはない。だから絶対他力だ,「最後の親鸞を訪れた幻は,知を放棄し,称名念仏の結果に対する計い(はからい)と成仏への期待を放棄」する。と。これを知ったのは,吉本隆明の『最後の親鸞』だ。そこで,彼は,こんなことを書いていた。
<わたし>たちが宗教を信じないのは,宗教的なもののなかに,相対的な存在にすぎないじぶんに眼をつぶったまま絶対へ跳び超してゆく自己欺瞞をみてしまうからである。
僕はこの言葉に吸い寄せられた記憶がある。いまの自分にとことん付き合うしかない,そういっていると僕は読んだ。自殺を意識したどん底の頃だったと記憶している。何かにすがろうとするおのれの頭を殴られた感じだった。強い意志をそこに感じ取り,かなわないとも感じた。
歎異鈔の中で,唯円が,尋ねる。自分は,念仏をとなえても,湧き上がるような歓喜の心がわかない。いちずに浄土へ行きたいという心が起きない。どうしてなのか,と。親鸞は,自分もそうだという。そして,こう答える。喜べないのは,凡夫のしるしだ。だからこそますますきっと往生できるとおもわなくてはいけない。喜ばせないのは,煩悩に満ちた凡夫ゆうだ。仏はとうにご存じで,他力仏の悲願はそういう凡夫を必ず浄土へ行かせようと結願されたのだ,と説く。
ただ信心が足りないからと,どこかの新興宗教のように何かを買えなどとは,親鸞は説かない。「久遠劫より今まで流転せる苦悩の旧里は棄て難く未だ生まれざる安養の浄土は恋しからず」と受け止める。その言い方は,まず相手に〇をつけて,しかし念仏を唱えれば浄土へ行ける,という考えを否定し,こう言っている。「ひたすら知にたよらない他力の往生心を発起し,方便や計らいの名残を残した門を出て,弥陀の選択された本願に絶対的に帰依する広い海に転入」する,と。
だから最後は,念仏を信ずるも念仏を棄てるも「面々の御計らいなり」となる。
ここには,すべての計らいをすてて絶対的に帰依できるかどうかが,最後に問われている。それで浄土に行けるのか,本当に救われるのか,と考えるのは,人の側の思惑に過ぎない。しかし,たぶん,これはもういわゆる宗教であることを突き抜けている。こういう思想家,宗教家が,日本にいたことを,いまの(徳川時代のキリシタン対策としてつくられた)檀家制度の果てにある,真宗からはなかなかうかがえない。
ちょっと話を矮小化するようだが,わからんことはわからん,と言えるのはすごいことだ。ましてや宗教の教祖が。それだけでも,器の大きさに圧倒される。そこから思い出したが,神田橋條治氏が,
すぐれた人は,わからないという言葉で勝負する,と。要はわからないことはわからない,知らないことはしらない,という。という趣旨のことを言っていた気がする。
管理職だったころ,知ったかぶりするのも嫌だが,知らない,というのにも抵抗があった。しかしフランクに「俺それよく知らない,教えてくれない」と言えばよかったのだ。しかしそうやって開示しながら,どこかで,相手が語ることから,相手の力量を測ろうとするのだろうな,きっと。ああ,器が小さい。
※※※※※
人は学んだとことの1/2から1/3を,8時間後には忘れている,という。成りたい自分をイメージすれば,夢はかなう,という人がいる。そして現実にそうなったという人も一杯いる。だが,たぶん,ただ夢見ただけでも,強く思っただけでも,ないはずで,そのことを実現できた人は意識していない,そんな気がしたいた。
脳は出力することで記憶する。それは経験的にそう思ってきた。使わなければ,脳のニューロン・ネットワークは強化されず,強化されなければ,忘れていく,と。池谷さんは,こう書く。
脳に記憶される情報は,どれだけ頻繁に脳にその情報が入ってきたかではなく,どれほどその情報が必要とされる状況に至ったか,つまりその情報をどれほど使ったかを基準にして選択されます。
前に笑顔をつくるだけで,楽しくなる,という例を挙げた(http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/10981807.html)が,笑顔という表情の出力を通して,その行動結果に見合った心理状態を脳は生み出したと言えるようだ。たとえば,身体を眠くなる状態にしておくから,眠くなる。身体が先で,眠気は後,会議や授業中の睡魔も,「静かに座っている姿勢が休息の姿勢でもあるから」だということになる。
やる気も同じで,やる気が出たからやるというより,やりだしたことで気が乗り始める。「何事も,始めた時点で,もう半分終わったようなもの」ということらしいなのだ。たとえば,掃除の例を挙げている。始める前は億劫で,その気にならないが,えいやっと,動き出すと,とことんきれいにしたくなる,ということがあるように。
デューク大学のクルパ博士は,ネズミのひげがモノに触れた時(受動,入力)と,ネズミがひげを動かしてモノに触れた時(行動,出力)では,大脳皮質の反応が,まったく違い,「身体運動を伴うと,ニューロンが10倍ほど強く活動する。つまり,うだうだ言っているよりは,まずは動き出してしまうと,その結果勝手にニューロンが活性化し,どんどん自分を前へ押し出してくれる,ということのようだ。
だから夢を見た人は,意識的か無意識的かは別にして,すでに何か動き出してしまっている,そのことが,夢を手元に近づけている,と言えるのかもしれない。
ところで,英語には頑張れ元気を出せという気合いにかかわる言葉はないそうだ。「あきらめるな」とか「ベストを尽くせ」といったより具体的な表現しかないらしい。頑張れは,あえて訳せば,「Chip
up」「Cheer
up」であり,顎を上げろとかうつむくな,という具体的な指示になる。顎を上げる,うつ向かない,という行動が心に影響を与えるというのは,笑顔の例と同じだ。身体の構え,恰好を取るから,がんばるマインドを引き出していく…。
同じことは姿勢にも言える。ブリニョール博士らは,学生たちに,「将来仕事をするために,自分のいいところと悪いところを書き出す」というアンケートを,一方は背筋を伸ばして座った姿勢,他方は,猫のように背中を丸めて座った姿勢で,書いてもらった。すると,背筋を伸ばした姿勢で書いた内容のほうが,丸めて書いた姿勢よりも,各進度が高かったそうだ。自分の書いたことについて確かにそう思うとより強く信じたということだ。
ここでも,形や行動,姿勢が,強くマインドを左右する結果が出ている。よく,柔道や剣道,その他の技にかかわる世界,「形」をまねるところから入るのは,守破離の「守」の部分,形から入って形からでる,といわれるのにも似ているだろう。
「形」の模倣とは,各世界における「型」に含まれる要素的な活動(「型」を要素に分解できるわけではないが)の学習といってよい。(『「わざ」から知る』)
ただしここで「形」と「型」を区別しているところに注目しておかなくてはならない。型とは,「技法と集合的個人的な実践理性」という。何のことかわからないが,先代勘三郎が,こういっている。
「先代の源之助のおじさんがお辰をやったとき,いつも後見を勤めてて……,あの焼ゴテに赤く火が見えるのは,丁度いい間合いを計って後見が仕掛けてあるモグサに線香で火をつけるんです。そうやって毎日しているうちに,お辰の呼吸(いき)とか段取りとかが,自然に身につくんですね。
というように,形を習得しただけではなく,学ぶものがその「形」の意味を,模倣を通して自分なりに解釈し,その芝居全体の意味は何か,歌舞伎全体での意味は何か,と文脈全体を取り込むという,より大きな目標に注目を移していくことで,「形」を自然な「型」にしていく。「形」の習得は技の習得の入り口に過ぎない,その意味の「守」ということなのだろう。
そこにも,姿勢や形,恰好から入っていく入り口が見える。
このことは,例のライルのいう「Knowing that」(知識の所有)と「Knowing
how」(遂行的知識)が思い出され,知っていることとできることの違いにも思いがいく。
自分は怠け者で,いつも,「形」のところから引き返してきた気がしてならない。何かを極めたものは,たぶんすべてののが見える見え方が違うのだろう,という気がする。今更遅いが,死ぬまで,型の手前まで,行きたいものだ。
参考文献;
池谷祐二『脳には奇妙なクセがある』(扶桑社)
吉本隆明『最後の親鸞』(春秋社)
生田久美子『「わざ」から知る』(東京大学出版会) |
|
希望 |
|
玄田有史『希望のつくり方』を読む。
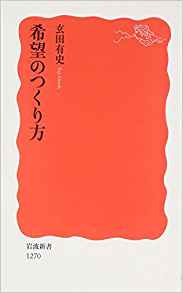
『希望のつくり方』タイトルが「ちょっと」と感じさせるもので,面映ゆくて,外でカバーを付けたまま読むのがためらわれて,積読の憂き目にあっていた。それが,ふと昨日目に留まり,読み終えた。久しぶりに,頭の中が活性化し,脳内の広範囲が点滅しているのがわかる,どういうか,読みながら,いろいろなことを考えさせてくれた本だ。読んでみていただくしか,この興奮は伝えにくい。
村上龍は「この国には何でもある。本当にいろいろなものがあります。だが,希望だけがない。」と小説の中で語らせている。データ的には,将来への希望を持っている人(20歳以上)は,78.3%,そのうち実現できると思っている人は,80.7%。つまり,63,2%の人が実現見通しのある希望をもっている,三人に一人が実現可能な希望を持てない社会,ということになる。
本書では,夢と希望の違い,幸福と夢の違い,安心と希望の違いを,しながら,希望をクローズアップしようとしている。その中で気になったのは,夢との違いだ。本書では,
夢は無意識に見るものであり,あるいは現状に満足しない,飽き足らない気持ちから次々生まれる。
希望は,意識的に見たり,苦しい状況だからこそ,あえて持とうとする。
こう区別している。しかし,キング牧師の有名な,「I have a dream」
というセリフがある。希望が,将来に実現したい「まだない存在」(エルンスト・ブロッホ)だとすれば,夢と希望の差は何なのか。本書には,上記しかないが,僕は仰角(高所にある対象物を見る観察者の視線と水平面のなす角度)の差だと感じた。遠くの何かを見ている時,それが水平線に近いか,大空の上か,夢は,仰角が大きい。中天にあれば,夢は憧れに近い。「夢をもったまま死んでいくのが,夢」。しかし仰角が水平面に近づけば近づくほど,現実性が高まる。希望と夢はある面重なっている。公民権運動の中にいたキング牧師には,叶う夢として,dreamという言葉を使ったのではないか。
著者は,希望の四本柱を次のように言っている。
ひとつは,ウイッシュ(wish),思い,願い。
二つ目は,何か,Something,将来こうなりたい,こうありたいという具体的な何か。
三つ目は,Come True,実現。
つまり,
Hope is a Wish for Something to Come True.
しかし,変化は変わるのを待つのではなく,変えるアクションなくては希望は中空の星にとどまる。で,
Hope is a Wish for Something to Come True by
Action.
となる。しかし希望は個人の中だけにとどめるものなのか,共有できないものなのか。社会の未来への希望という視点から見た時,
Social Hope is a Wish for Something to Come
True by Action with Others.
あるいは,
Social Hope is a Wish for Something to Come
True by Action with Each Other.
となる。他の誰かと,共有する何かを一緒に行動して実現しようとする。「個人の希望は,『誰と一緒にやるか(with
Others)』という要素を加えることによって,社会の希望となります。このとき他者(others)として,お互い(Each
Other)に顔が見えて,一人ひとりの言葉を直接聞きあえる関係を築けるのが,地域の希望の特徴です。」
この本が労働経済学者が書いたという一番のポイントは,希望を共有するところまで視界を広げているところだろう。凡百の夢実現本の軽薄さとの違いがはっきり出ている。
「何が自分に本当は向いているかなど,すぐにわかるものではありません。それこそ,様々な希望や失望を繰り返しながら,一生をかけてみつけていくものです。」
ただ問題は,希望を単なる心の持ちようにしてはいけない,そういう問題意識が著者にはある。その人の置かれた社会や環境によって,希望の有無が左右されているとし,希望の有無を左右する背景を3つ挙げている。
第一は,可能性。選ぶことのできる範囲,もしくは実現できる確率。選択範囲が広かったり,実現確率が高い時,自分の可能性が大きいと感ずる。そういう人ほど,希望を持ちやすい。具体的には,年齢,収入,健康。
第二は,関係性。「希望は個人の内面だけに閉じた問題ではなく,その人を取り巻く社会のありようと深くかかわってい」て,希望があるかどうかも,社会における他者との関係による影響をまぬがれない。これが重要である背景には,「日本に急速に広まっている社会の孤独化現象」だという。その背景から,「人間関係を大事にしよう」「もっとコミュニケーションをうまくしましょう」という最近の風潮にちょっと批判的だ。「日々のコミュニケーションに疲れた人々をもっと追い込む」ことにつながる。「もっとうまく人と交わらなくてはいけないんだ。それができない自分には希望はないんだというプレッシャーがさらに強まる」と。賛成だ。コミュニケーションは大事だが,人生の中ではもっと大事なことがある。
第三は,物語,あるいはストーリー。「最初は希望がないと思い込んでいた人も,丹念に時間をかけて考えていくと,奥底から自分自身の希望に出会うことも多い」「希望を見つけるその過程で」出会うのが,物語だという。そこで思い出すのが,V.E.フランクルが言った,どんな人にも語りたい物語がある,だ。
希望の物語性についての第一の発見は,「希望の多くは失望に変わる。しかし希望の修正を重ねることで,やりがいにであえる」。「希望の多くは短観に実現しません。大事なのは,失望した後に,つらかった経験を踏まえて,次の新しい希望へと,柔軟に修正させていくことです。」統計にも,無やりがい経験の高さは,当初の希望を別の希望にへ得た人だったとう。
希望の物語性についての第二の発見は,「過去の挫折の意味を自分の言葉で語れるひとほど,未来の希望を語ることができる。」統計でも,挫折を経験し,何とか潜り抜けてきたひとほど,希望を持っている。
希望の物語性についての第三の発見は,「無駄」。「希望は,実現することも大切だけど,それ以上に,探し,出会うことにこそ,意味がある。」「希望とは探し続けるものであり,模索のプロセスそのものです。そしてみつけたはずの希望も,多くは失望に終わり,また新しい希望を求めた旅がはじまる。」
つまり「希望は,不安な未来へ立ち向かうため必要な物語です。希望のあるところには,なにがしかの物語が存在します。物語の主役は,必ず紆余曲折を経験します。挫折や失敗の一切ない物語は」ないのだ。「挫折を乗り越えるという体験があって,初めて未来を語る言葉に彩りは増します。」自分の中に自分を動かしていく,物語を持てるかどうか。もちろん未来はわからないが,「人生に無駄なものなどひとつもない。」その通りだ。悪戦苦闘して自分の希望を彫琢していく生き方でいいのだ。それこそが人生ではないか。きれいに語るものの側ではなく,汗みどろの側に物語がある。
希望だけを真正面から,学問として語るだけで,これだけの奥行きがある,つまりは人の生き方を語ることは,社会的人間としての人のつながり,社会のありようまで,視界を広げなくては語れない,その重層的な追及らまずは脱帽。久しぶりに,脳の広範囲が活性化する,読書の楽しみを味わった。
ちなみに,この本が出たのは,2010年なのに全然古さを感じない。釜石の例が出るが,新日鉄釜石の廃炉後の復興が,ちょうど震災からの復興ともダブり,いま読むことにも意味を感じた。
参考文献;
玄田有史『希望のつくり方』(岩波新書) |
|
他者 |
|
柄谷行人『探求Ⅰ』を読む。
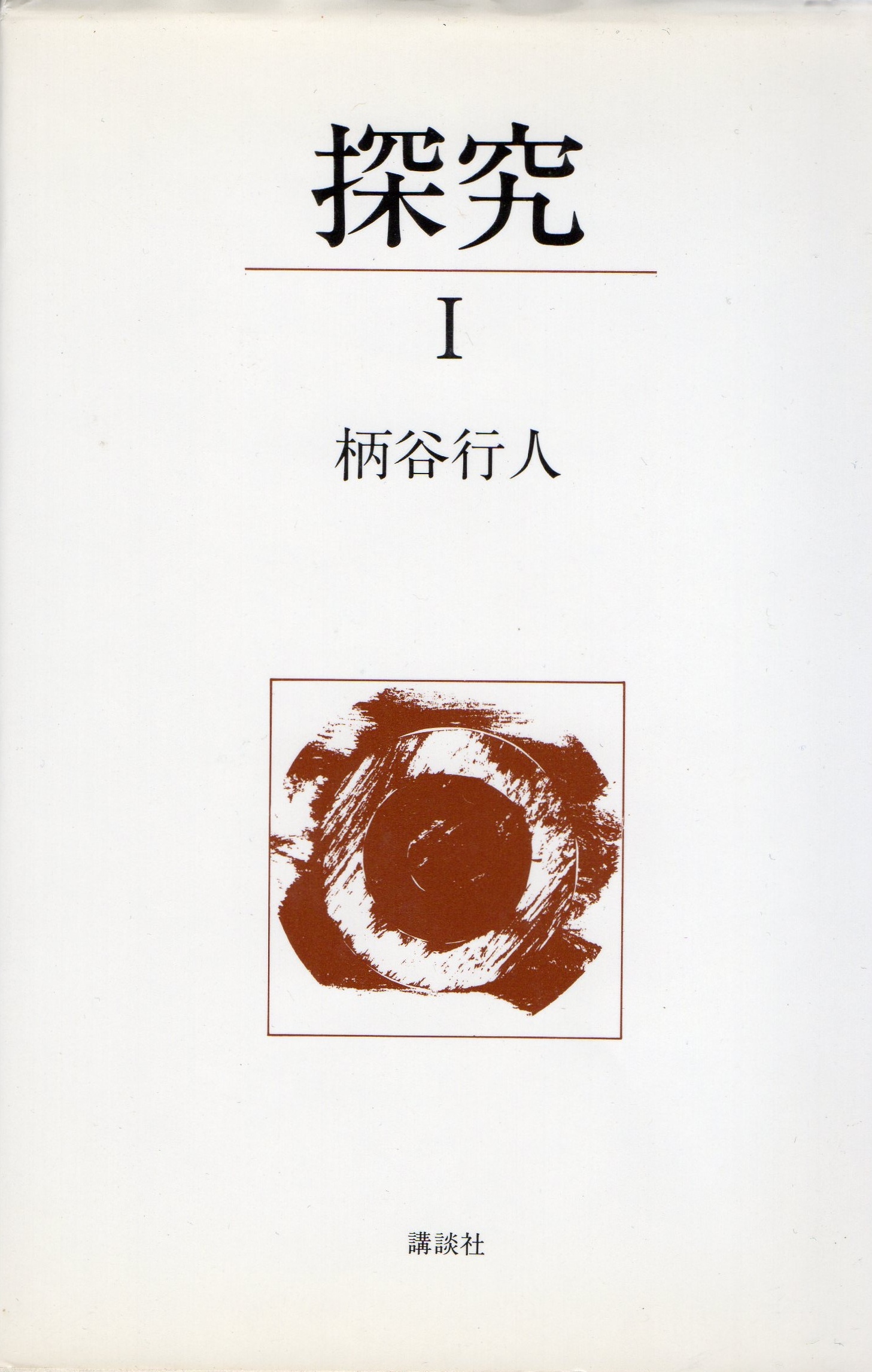
本書は,1986年上梓である。もとになった連載は,1985年である。30年余前である。しかし,色褪せていない,と僕は思う。
「本書は,《他者》或は《外部》に関する研究である。」
と「あとがき」で書くが,「他者」とは,ウィトゲンシュタインの言う,
「言語ゲームを共有しない者」
の謂いである。それを,ウィトゲンシュタインは,
「われわれの言葉を理解しない者,たとえば外国人」(『哲学探究』)
と例示した。著者は,
「たんに説明のために選ばれた多くの例の一つではない。それは,言語を『語る−聞く』というレベルで考えている哲学・理論を無効にするために,不可欠な他者をあらわしている。言語を『教える−学ぶ』というレベルあるいは関係においてとらえるとき,はじめてそのような他者があらわれるのだ。」
と。
語る−聞く,
と
教える−学ぶ,
を終始対比しつつ語る。だから,
「対話は,言語ゲームを共有しない者との間でのみある。そして他者とは,自分と言語ゲームを共有しない者のことでなければならない。」
と。「言語ゲーム」とは,ウィトゲンシュタインが,
「われわれは,ひとびとが野原でボール遊びに打ち興じ,現存するさまざまなゲームを始めるが,その多くを終りまで行わず,その間にボールをあてもなく空へ投げ上げたり,たわむれにボールをもって追いかけっこをしたり,ボールを投げつけ合ったりしているのを,きわめて容易に想像することができる。そして,このとき誰かが言う。この全時間を通じて,ひとびとはボールゲームを行っているのであり,それゆえボールを投げるたびに一定の規則を準備していることになるのだ,と。
でも,われわれがゲームをするとき,―〈やりながら規則をでっち上げる〉ような場合もあるのではないか。また,やりながら―規則を変えてしまう場合もあるのではないか。」(『哲学探究』)
といったことに由来する。つまり,コミュニケーションにおいて,「規則(コード)によっている」のではなく,
「そのような規則とは,我々が理解したとたんに見出される“結果”でしかない」
のであり,その結果を,著者は,
「『意味している』ことが,そのような《他者》にとって成立するとき,まさにそのかぎりにおいてのみ,“文脈”があり,また“言語ゲーム”が成立する。なぜいかにして『意味している』ことが成立するかは,ついにわからない。だが,成立したあとでは,なぜいかにしてかを説明することができる―規則,コード,差異体系などによって。」
その懸隔を,著者は,
「命がけの飛躍」(マルクス)
という。この他者は,サルトルの言う「対自存在」も,ヘーゲルの言う「主人と奴隷」も,他者ではない。それは,
「自己意識ともう一つの自己意識の,互いの置き換え」
にすぎない。それは,自分の声にすぎない。この他者との関係を,
「なんら通訳可能なものをもたない二つの異なるものがいかにして等置されるのか」
という価値形態と重ね合わせている。その関係を,
社会的,
と呼ぶ。共通性があるのではなく,結果として共通性が生み出される。
著者は末尾で,一つの結論に至る。
「われわれは,ここで対話を二つに分けるべきである。一つは,一般関係(著者は『隣り合わせ』の関係という)における他者との対話である。これは弁証法と呼ばれる。それは内なる対話(内省)によって,事後の根拠・本質に向かって行く。そこに,哲学あるいは形而上学がある。もうひとつは,対関係(著者は,他者が他者性としてある『向かい合わせ』の関係という)における“他者”との対話であって,私はこれをイロニーと呼ぶ」
イロニーとは,ソクラテスのそれである。ヘーゲルの説明ではこうある。
「彼はそのことを知らない。そこで彼は人々をして語らしめるために無邪気さを装って問いかける。そして彼に教えてくれるように人々に懇願する。」
と。それによって,
「彼らが何も知ってはいないということを知ることを教えた」
のである。まさに,
教える−学ぶ関係
である。このイロニーは,
「弁証法が排除した“他者性”の回復に他ならない」
と著者は締めくくる。僕に興味深いのは,独我論を抜け出たとする西田幾太郎の,
「自己が自己自身の底に自己の根底として絶対の他を見るといふことによつて自己が他の内に没し去る,即ち私が他に於いて私人を失ふ,之と共に汝も亦この他において汝自身を失はなければならない。私はこの他に於いて汝の呼声を汝はこの他に於いて私の呼声を聴くといふことができる」(『私と汝』)
について,「いささかも他者性をもたない」と一蹴し,
「独我論を出ようとする独我論」
と呼んだ。著者の言うように,これは,
「神(一般者)と私」
の関係に過ぎず,こう言い切っている。
「“他者性”としての他者との関係,“他者性”としての神との関係を排除している。…私と一般者しかないような世界,あるいは独我論的世界は,他者との対関係を排除して真理(実在)を強制する共同体の権力に転化する。西田幾太郎やハイデッガーがファシズムに加担することになったのは,偶然(事故)ではない。」
ウィトゲンシュタインの言葉に,
人は持っている言葉によって見える世界が違う,
というのがある。それは,言葉を交わしていても,何かを共有していることとはならないのだと思う。今日,実は言葉の意味の強制がすさまじい。それは,他の排除どころか,異質そのものの排除に見える。しかし,そのことに対峙するべき知は,無力さを増しているように見える。西田的な,
「自己の根底として絶対の他を見るといふことによつて自己が他の内に没し去る,即ち私が他に於いて私人を失ふ,之と共に汝も亦この他において汝自身を失はなければならない。」
世界が近づいている気がしてならない。
参考文献;
柄谷行人『探求Ⅰ』(講談社) |
|
外部 |
|
柄谷行人『探求Ⅱ』を読む。

『探求Ⅰ』では,他者を問題にした。
「この私と他の私とが同一ではなく,また同一の規則体系にも属さないような条件を考察し,それを『売る−買う』や『教える−学ぶ』といった非対称的なコミュニケーションの関係に求めた」
つまり,「言語ゲーム」を共有しない他者である。本書では,実は,そういう他者との関係に視点を当てる。「あとがき」で,
「問いつづけてきたのは。『間』あるいは『外部』において生きることの条件と根拠」
と書く。それは,
「理論の問題ではなく生きることの問題」
とし,本書では,それを,
超越論的,
という言葉で表現する。
「超越論的主観とは,外部的であろうとする“態度” そのものなのだ」
と。
「《超越論的》ということは,…外部的であることだが,しかし,それは実際に共同体の外にあったりそれを超越していることを意味するのではない。共同体を超越して世界一般について考えることが,まさに共同体の内部に在ることなのだ。
超越論的自己は,したがって自己意識ではない。自己意識は,たしかに自分の属している世界をこえる。しかし,それは反省にすぎず,つまり鏡像の中にあるにすぎない。したがって,《超越論的》であることは,たんに自己関係(自己言及)的であるのではなく,共同的なシステムに対して自己関係的であるのでなければならない。」
「あるシステムに対して自己関係的であり,そのかぎりで外部的であることを意味している。」
だから,もちろん「自らをメタ(超越的)レベルにおくのではない」。
「私は,超越論的ということを,自己意識の構造や自我の統一などといった問題に限定しないで,われわれが経験的に自明且つ自然であると思っていることをカッコにいれ,そのような思い込みを可能にしている諸条件を吟味(批判)することだという意味で考える。」
「さらに重要なことは,私という主体はないと言うこと,ランボー流にいえば,『私とは他者だ』と言うことが,それ自体超越論的な主体によって可能だということである。
そのような主体が在るというならば,それはただちに経験的な主体になってしまう。あるいは超越的な主体になってしまう。超越論的主体は,世界を構成する主体=主観ではなく,そのような世界の外部に立とうとする実践的な主体性においてしかないのである。」
その出発点は,
単独性,
である。「この私」「この物」の「この」である。それは,
個体の特殊性,
とは異なる。
「主観は『この私』ではない。主観とは誰にでも妥当するものだ。事実,『私』という主体(主観)は,言語の習得のなかで形成されるものであり,それはもともと『共同主観的』である。いいかえれば,『私』という類の特殊でしかない。しかし,単独性としての『この私』は,そのような主観ではない。(中略)この私は,この物やこの他者との関係においてしかあり得ないのである。私も他者も物もあるが,この私・この他者・この世界が存在しないような世界は分裂病的である。」
それは,
固有名,
にも通じる。
「固有名は外国語のみならず自国語においても翻訳されない。つまり,それは一つの差異体系(ラング)のなかに吸収されないのである。その意味で,固有名は言語のなかでの外部性としてある。」
そこで,デカルトの「コギト」が改めて問い直される。
「『コギト』がたんに『思惟』することではなく,それまでの“慣習”(システム)のなかでの思惟をすべてカッコにいれることを意味するからであり,(中略)『私が考える』が“慣習”にすぎないのではないかと疑うことにしかない。つまり,この疑うことそれ自体が“精神”の証明なのである。
デカルトによる“精神”の論証は,読者に“精神”を要求する。彼は,自分の論証は,『先入見からまったく解放せられたる精神を,自分自身を感覚との交わりから容易にたち切ることのできる精神を要求する』といっている(『省察』)。デカルトがいいたいのは,われわれが心をもち意識をもつといったことは“精神”の証明にはならないということだ。そのような意識または自己意識は,いわば“身体”なのだ。」
その「精神」は,システムの外に立つことを要求する。このデカルトの方法が,
超越論的,
なのである。ただし,それは,
「上方や下方に向かうことではない。それはいわば横に出ることだ。…デカルトの『方法的懐疑』が,もはやどんな立場でもありえない立場,《外部性》としての立場においてのみ可能である」
その意とすることは,内省(自己対象化)やメタ化(超越的)ではない。
「われわれが『思惟』とよんだり『内面』とよんでいるものは,社会的な“慣習(言語ゲーム)”にすぎない。『私は考える』は,少しも私的ではない。内的なものは,徹頭徹尾社会的(制度的)である。それはデカルトのいう“身体”であって,“精神”ではない。」
このデカルトのコギトが「一般的な私(主観)ではなく」外部性,単独性,言い換えると,超越論的な立場に立つ。そこで,『探求Ⅰ』のソクラテスの対話に,戻ってくる。
「ソクラテスが提出したのは,世界や自己に理性が内在するという考え方ではなく,『対話』を通過したものだけが理性的だという考え方である。」
それは外部,他者との対話である。フロイトの精神分析に,著者は同じ対話を見る。
「精神分析は『対話』でなければならない。(中略)フロイトは,いわばソクラテス…の斥けた他者を,『対話』の場に連れこんだ。(中略)しかし,そのとき,彼はけっして対話に入らない者たちを見出したのである。(中略)分裂病者は,感情転移してこない。彼らは《他者》である。そのとき,彼らを『ナルシズム神経症』とよぶのは,本来感情転移(同一化)するはずの者がそれを拒否して背を向けたというのにひとしい。それは,他者の超越性(外部性)を,内在化することである。他者の外部性をみとめるかわりに,それを内部からの脱落者(退行者)とみなすのである。(中略)リビドーし,感情転移関係においてのみ根拠をもつ概念であり,しかるに分裂病者が感情転移してこないとすれば,フロイトはどちらかを選択しなければならない。つまり,リビドー理論を貫徹すれば,分裂病を退行とみなければならず,分裂病者を他者と見れば,リビドー理論を放棄しなければならないのである。だが,フロイトはこの選択を強いる『境界』に立ちつづけたようにみえる。ユング派も,反精神医学も,それぞれ違った意味においてだが,フロイトを批判すると同時に,彼が見出した『境界』そのものを洗い流してしまったのである。」
こういう姿勢を,
超越論的,
というのであろう。
「理論の問題ではなく生きることの問題」
とはこのことであろう。それは,是非はともかく,ある意味で,本書は,予言になっている。今日のわれわれほど,超越論的であることが必要なのである。
「特に日本において支配的なデカルト的な主体への批判は,一つには,主−客分離をこえて主−客合一の境地へ至るというような類のものである。そして,西洋における『主体』批判の言説がそこに援用される。しかし,それは個としての私を,たえず共同体の中に回帰させようとする支配的な言説(文法)に強制されているのではないか,と疑ってみることができる。そのように疑う私が,いわば超越論的なった自己である。それは個としての私ではなく,外部性・単独性としての私である。」
そういう超越論的なった立場こそが,今日こそ求められる。知的退廃とは,主−客合一の圧力である。類(一般性)に呑みこまれる個(特殊性)ではなく,その外に立ち,超越論的なった立場に立つ「この私」という単独性なのである。
参考文献;
柄谷行人『探求Ⅱ』(講談社) |