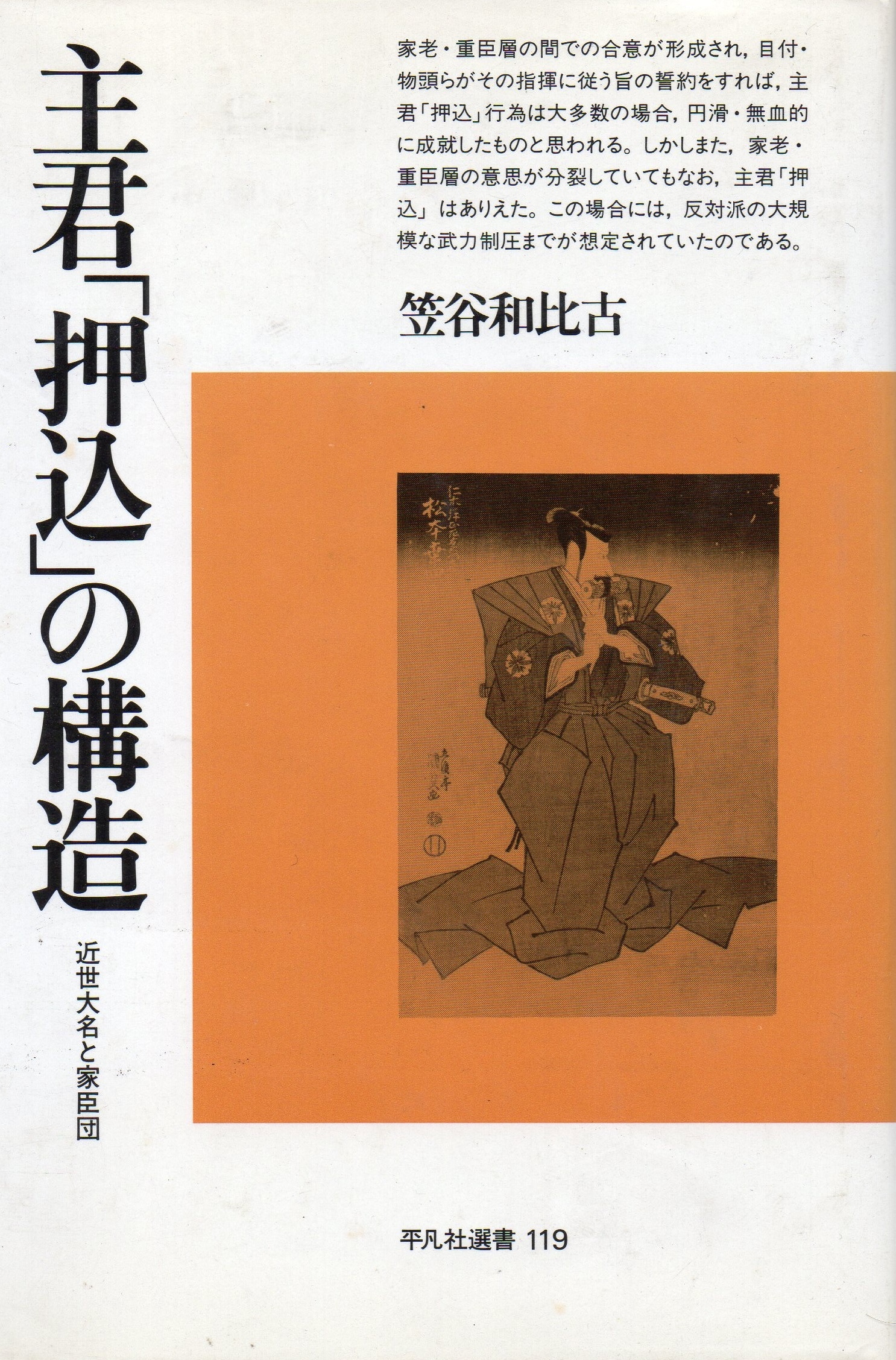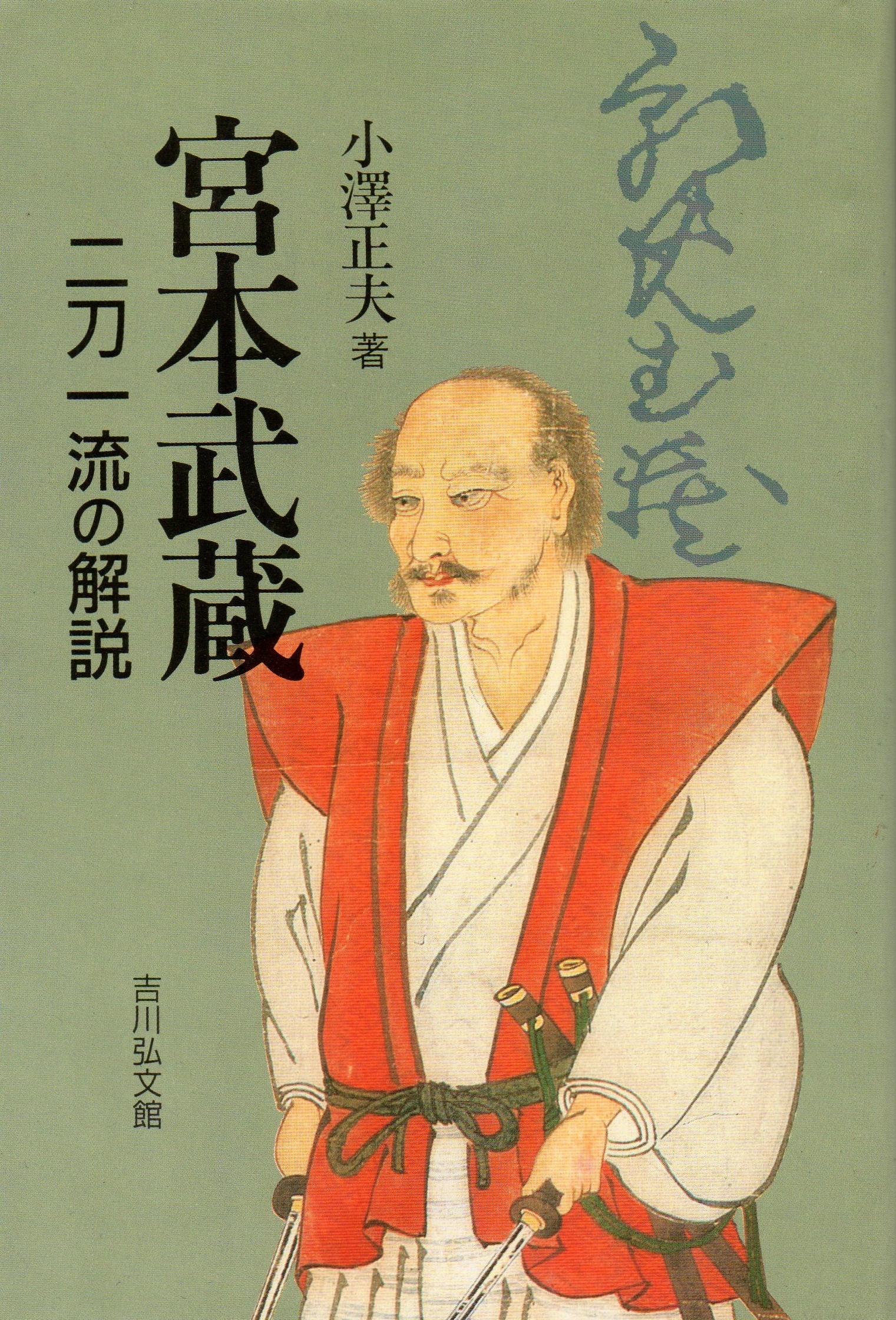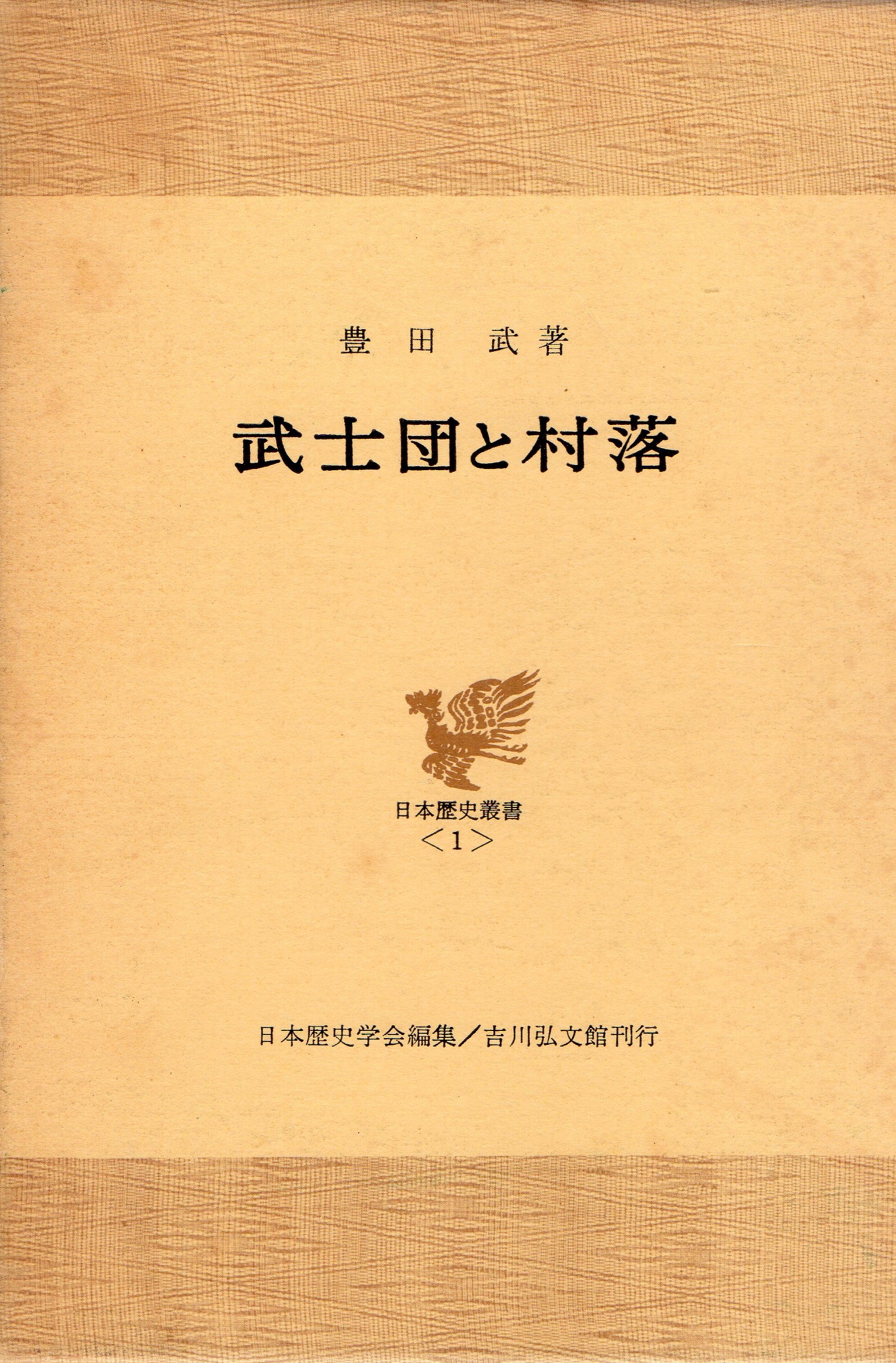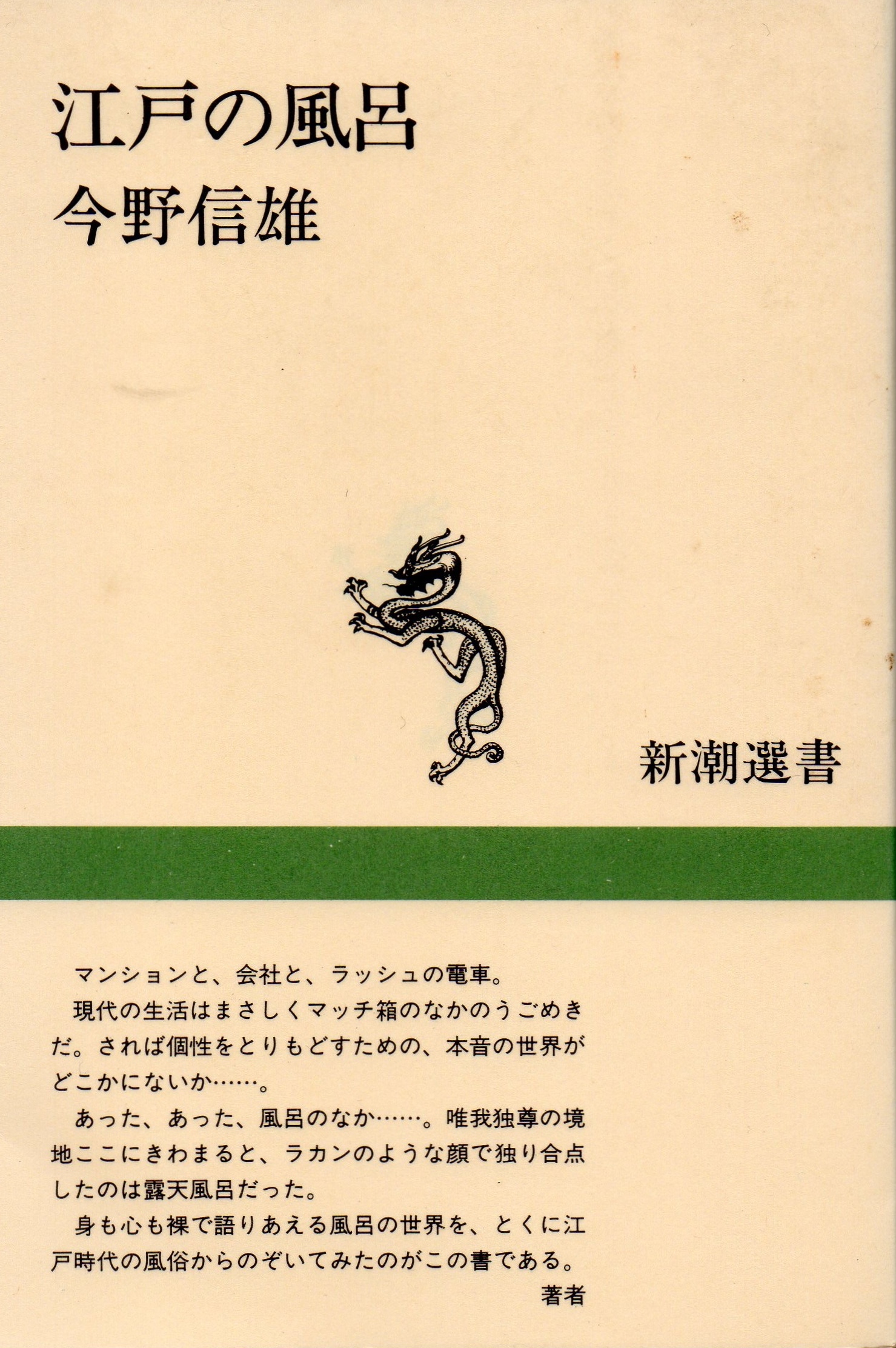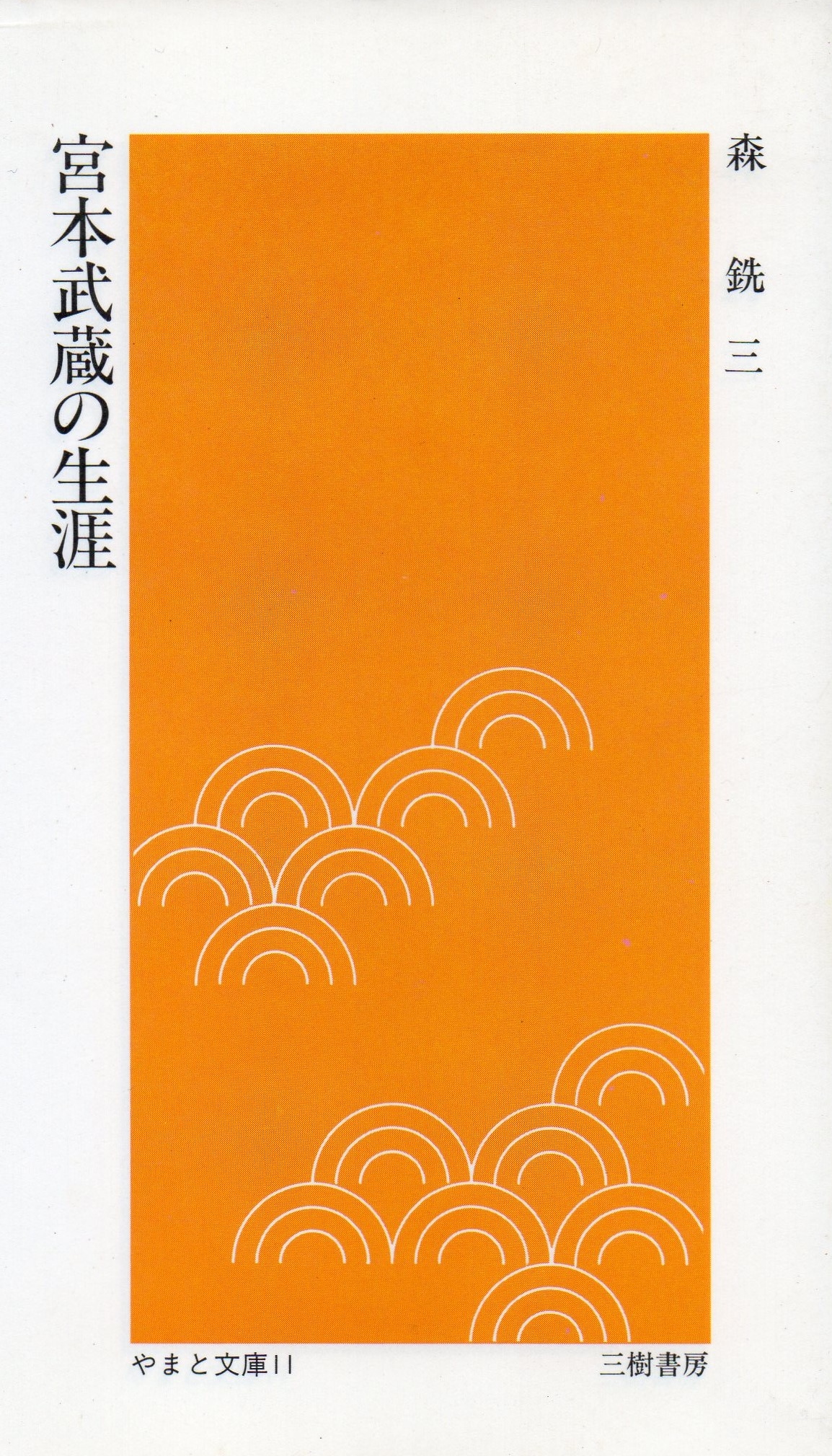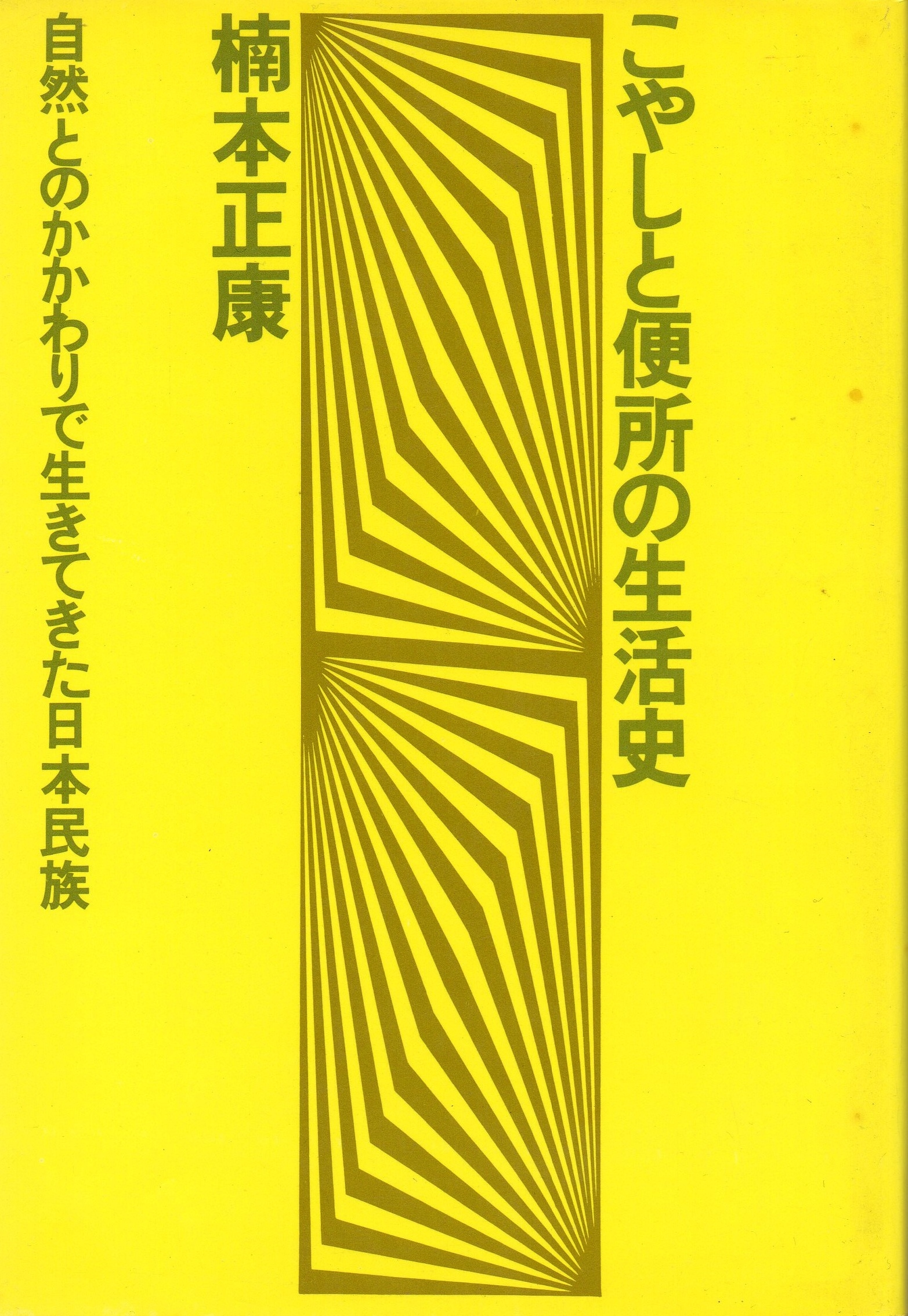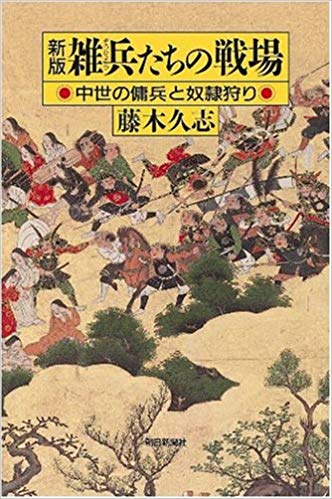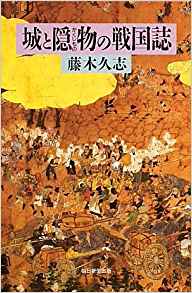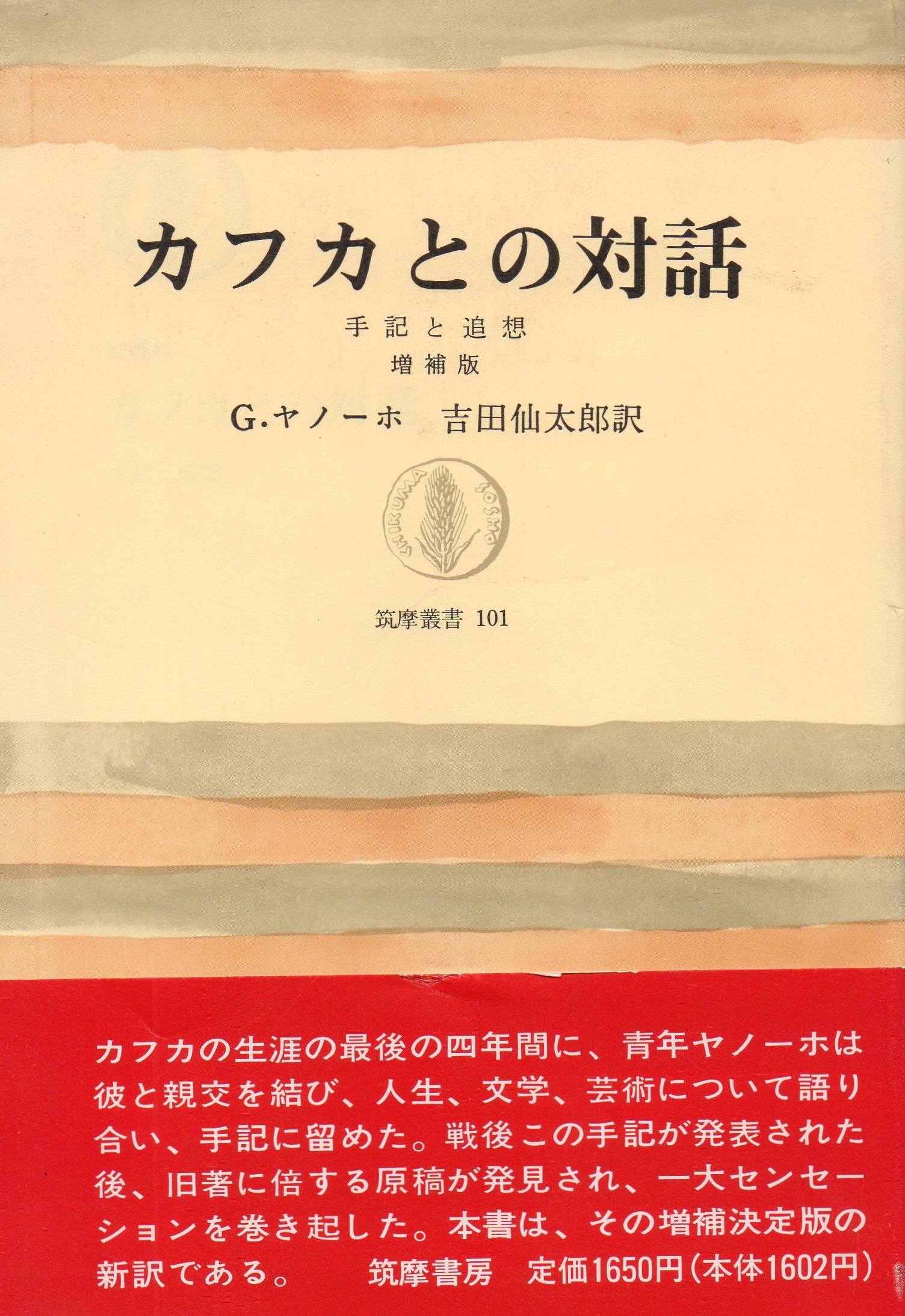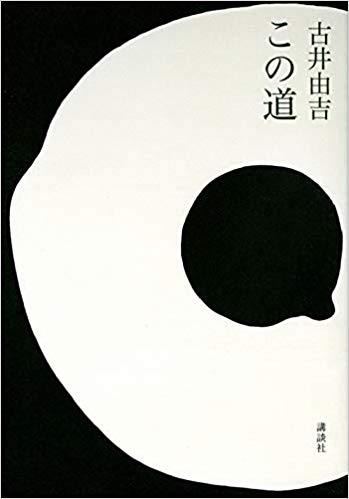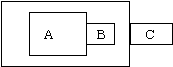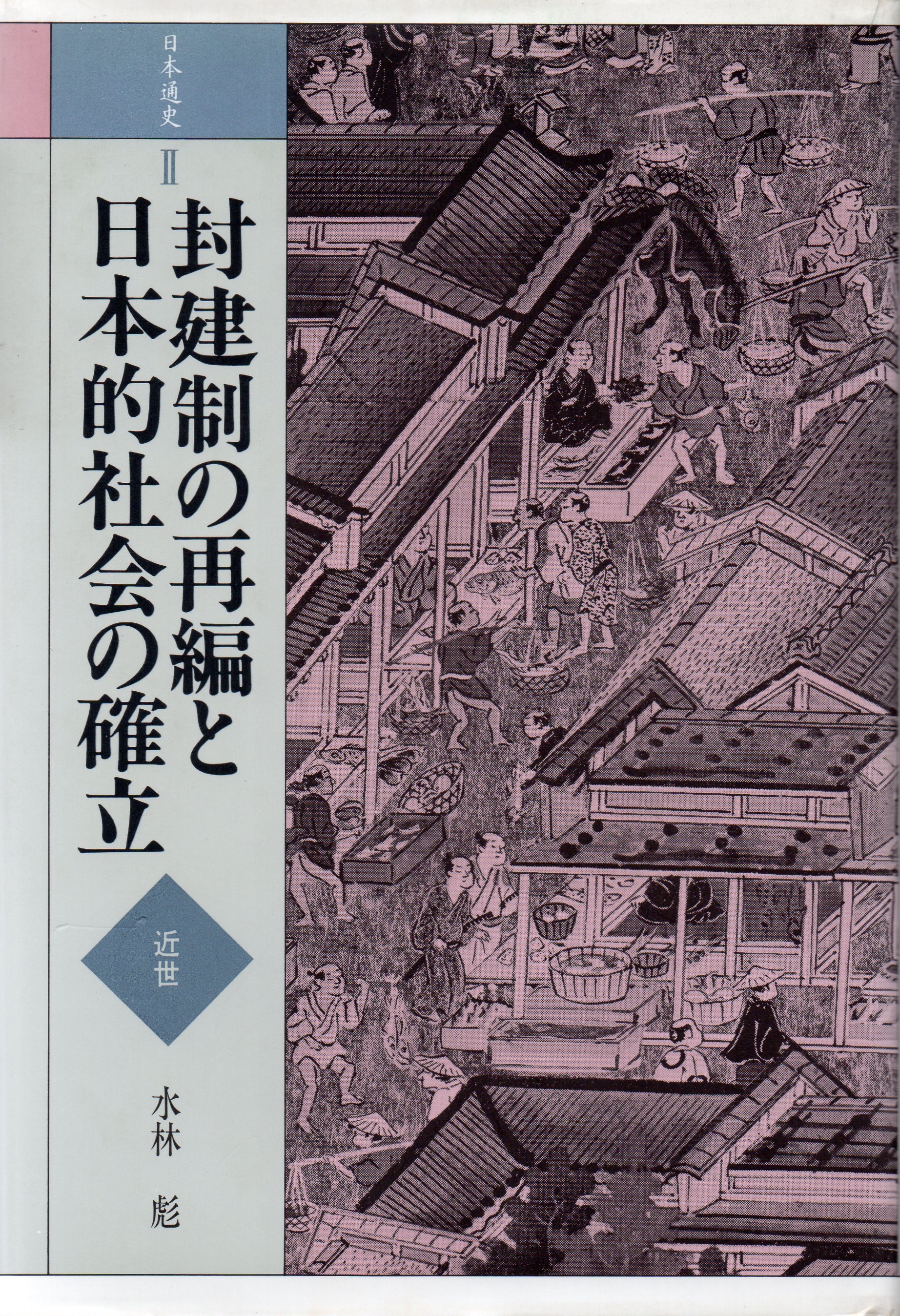|
主君「押込」 |
|
笠谷和比古『主君「押込」の構造―近世大名と家臣団』を読む。
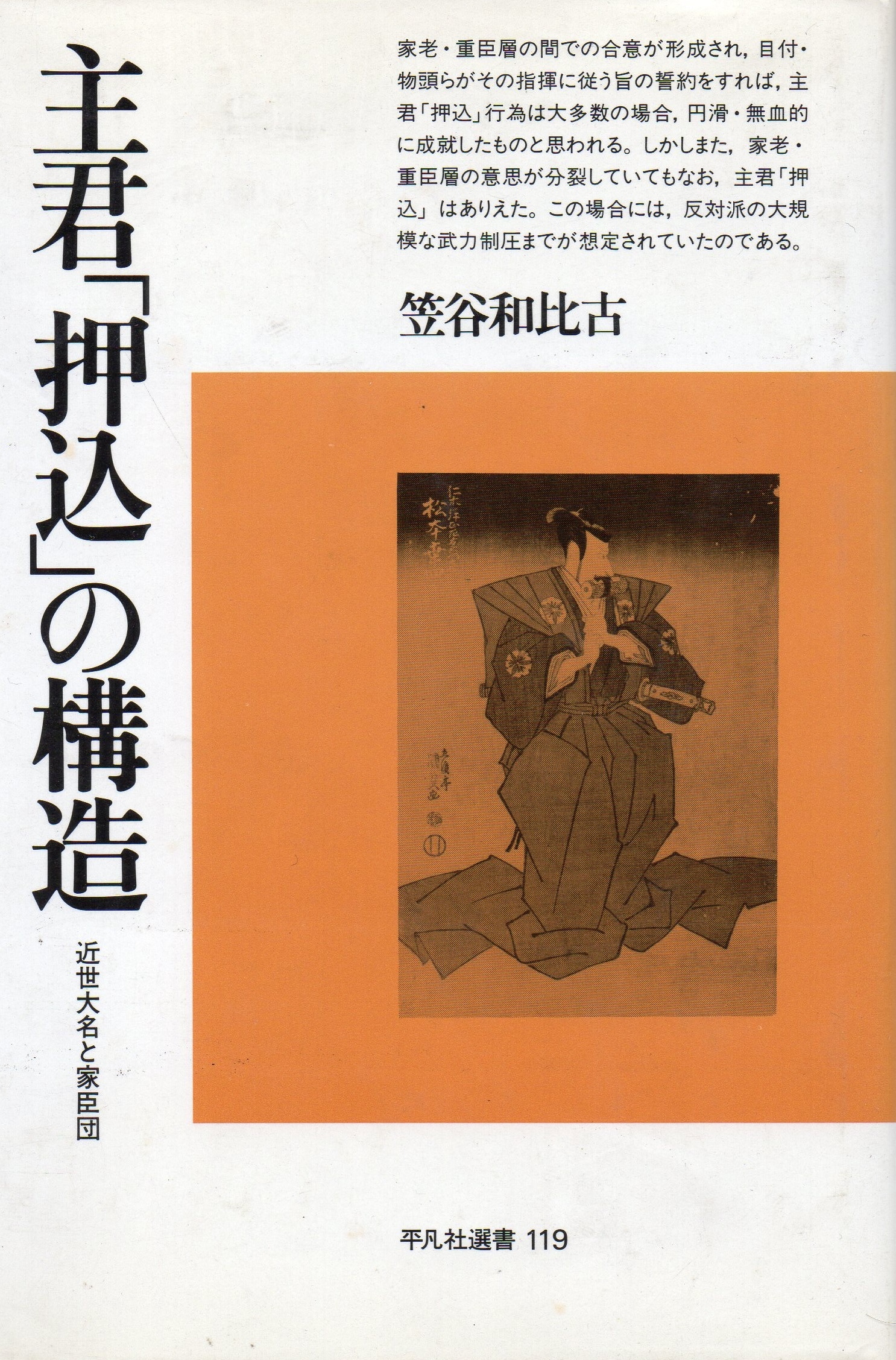
本書のテーマは,
「近世の大名諸家でおきた主君『押込』の問題である。」
主君「押込」は,例外的な行為ではなく,慣行として行われてきたことを,本書は明らかにしていく。
歌舞伎の「伽羅先代萩」ではないが,時代劇の伊達騒動や黒田騒動といったお家騒動は,大概,主君と対立する重臣層は,悪役と相場は決まっている。しかし,本書は,そうして培われてきたわれわれのイメージを一新したことで,有名である。それどころか,家臣団による,主君「押込」は,
「悪逆行為などではなく,それ自体は正当な行為としてこの社会(つまり江戸期の武家社会)では広く認知されていた事実」
を,本書は明らかにしている。しかし,問題の性格上,
「主君『押込』問題なるものは,それが発生したにしても,大名家の公式記録にその次第が明記されることはまずない」
ので,あくまで一次史料をもとに検討を加えていくが,
「もとより事件のアウトラインをつかむためには第二次的な史料,即ち後の時代に,第三者の手で,単なる風聞に基づいて,記されたようなタイプの史料にもよらねばならないであろう。しかしその場合でも,それが第一次史料によって裏付けられる,ないし強い示唆を与えられている場合にはじめて,その記述を信憑性のあるものとして受け入れていくことにしよう。」
との方針で,本書では,
宝暦・明和の蜂須賀家の事件,
宝暦元年の岡崎水野家事件,
宝暦四年旗本嶋田家事件,
宝暦五年加納安藤家事件,
正保三年古田騒動,
万治三年伊達綱宗隠居騒動,
元禄八年丸岡本多騒動,
宝暦七年秋田騒動,
安永九年上山松平家の内訌,
文久元年黒羽大関家事件,
等々を取り上げている。しかし,あるいは,表面化しないものの,前藩主隠居,家督相続されている事例の中にも,家臣団による「主君『押込』」が隠されているかもしれないと思わせるところがある。
さて,蜂須賀十代当主重喜を廻る案件は,末後養子として佐竹家から迎えられた重喜が,
「根本的に旧例や家格秩序に拘束されない,合理的な役職制度」
を目指とた新法「役席役高の制」を導入し,
「家格基準の秩序体系を役職を中心とするものに組み替え,同時に少録下位家格の者に,高級役職への就任機会を与えようとする」
ことを目指し,仕置家老を失脚させ,自分を「押込隠居」させようとした三家老を閉門に追い込み,ついに,
「主君の意のままに任免可能な自由な官僚制」
を実現し,
「旧例にも家格秩序にも身分特権を有する勢力の意向にも制約されず,主君の意思がそのまま藩という政治機構の意思に転化しうるような政治体制,すなわち,『専制』」
形成するに至る。一方で,倹約令,備荒貯穀倉の設立,放鷹地の開墾,藍玉専売等々を実施し,自らは,領内に豪奢な別荘を造営する。しかし,その時点で幕府が介入し,隠居命令を出す。そこに,
「養子之事ニ茂候得ば,養家江対し旁不慎成儀ニ思召候,依之隠居被仰付之」
とある。ここにあるのは,
「家老層の勢力が安定的に存在する一般的な状態の下では,主君はその権威と権力をもってしても容易には専制的権力行使がなしえない」
主君「専制」を暴政と見做して容認しない姿勢である。
藩内の家老を中心とする政治体制には,それを必然とする背景がある。ひとつには,
「近世初期の主君親裁ないし主君独裁体制なるものは,その仕置きの内容が,後の時代に見られるような全体としての藩政の内実をもたず,精々主君の蔵入地の差配と,それに基づく財政運営を対象とするような段階の政治形態であった…。それがいわゆる藩政の確立と共に,家臣団の給地も一元的に統合されて藩領の全体性の中に包摂され,年貢収取・治水・開発・勧農・救恤・治安・裁判等の全般滝なった行政が,この藩全体に押し及ばされ,他方では家臣団の封禄支給も実質的に藩財政の一環に組み込まれていくような段階に至ると,(知行地の多い)外様大身の重臣を含む家臣団の総体が藩政の運営・決定に参与していくことになるのである。
だから家老政治とは,このような一元的な藩政の必然的な産物だと見ることができる…。」
しかも,第二に,この大身の家臣たちは,たとえば,黒田長政が遺言で,
「武功有ル家来共ヲモソコナヒ不申」
と言い残しているように,家禄とは,
「単なる封禄ではなく先祖の武功に基礎をぐ封禄であるとされる。即ち,勲功ある家臣の家にとっては知行・家禄は当然の権利」
なのである。今日の藩を作り上げたのは,藩主のみではなく,家臣の武功に依っているからである。だから,長政は,遺言で,
「子孫ニ至リ,不義放逸ヲ専トシテ,諌ヲ聞入ズ,自由ヲ働キ掟ヲ守ラズ,ミダリニ財宝ヲ費スモノアラバ,家老中申合セ,其者ヲ退ケ,子孫ノ中ヨリ人柄ヲ撰ビテ主君トシ,国家ヲ相続セシムベシ」
と書かしめている。この考え方は,君主ではなく,「御家」に忠誠の対象としていくことを反映している。幕府の『東照宮御遺訓』には,
「将軍の政道その理にかなはず,億兆の民艱困することもあらんには,誰にてもその任にかはるべし,天下は一人の天下にあらず,天下の天下なり」
ということを「家康が語ったと信じられていた」という時代的な背景がある。
こうしたことを背景として,主君「押込」行為が,
「規範的な意味においても正当ものとしての地位を獲得し,近世秩序の一方の柱をなすものとして成長していく過程」
で,手続き,型式が明確になって,制度的に安定していく。それは,
家老・重臣層の合意形成,
親類大名の諒承取り付け,
幕府の内意,
であり,それを以て「押込」が執行される。その限りでないと,例えば,安藤家事件で,家老に死罪を申し渡した書面で,幕府は,
「其方儀,主人對馬守不身持に候はば幾度も諫言を可加之処,等閑に取計,心底を不尽蟄居致させ,」
と,重ねての諫言もせぬことを咎めている。「主君『押込』」は,諫言の延長線上の行為とみなされているのである。
参考文献;
笠谷和比古『主君「押込」の構造―近世大名と家臣団』(平凡社選書) |
|
二刀一流 |
|
小澤正夫『宮本武蔵―二刀一流の解説』を読む。
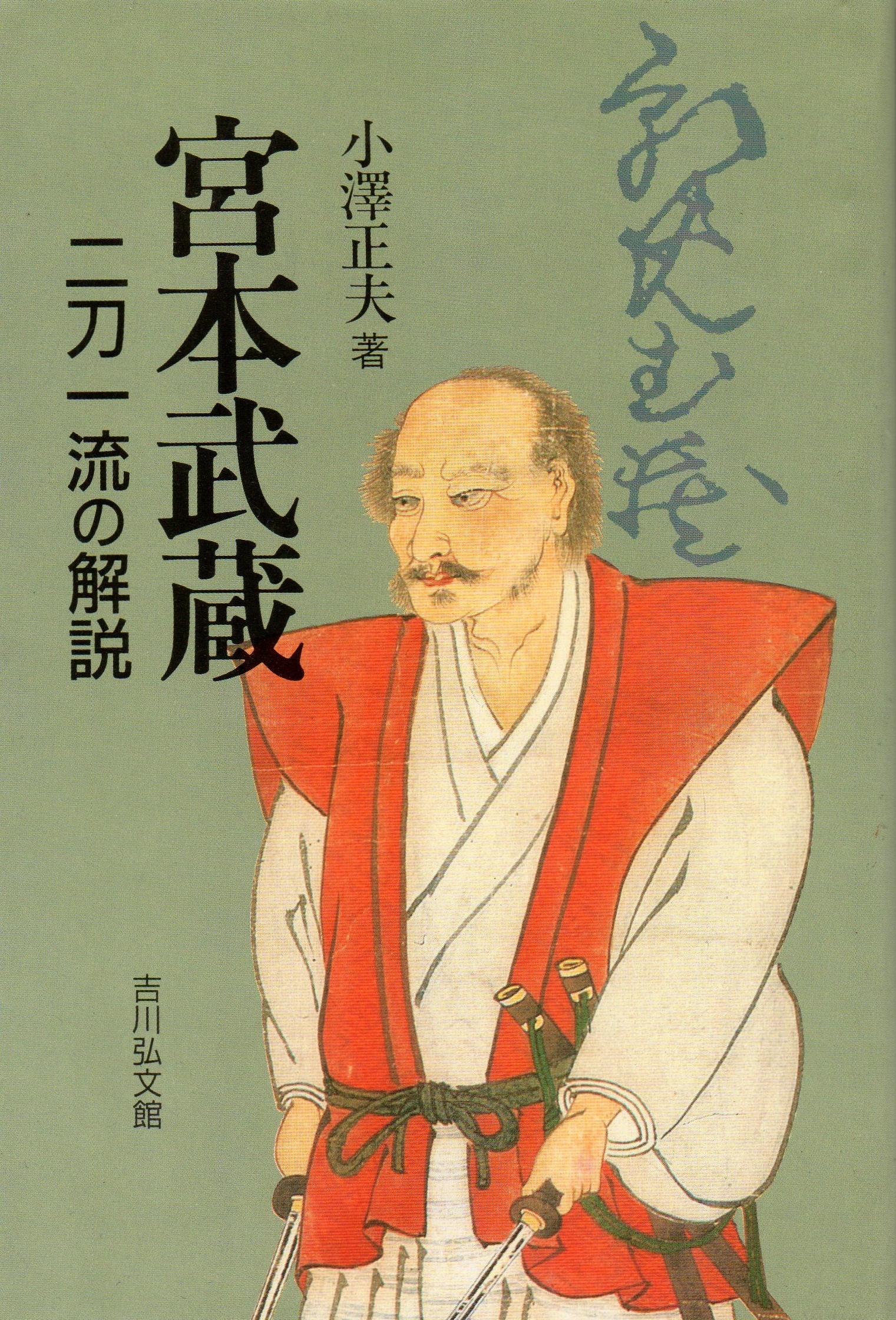
本書は,兵法家宮本武蔵,正確には,
新免武蔵藤原玄信,
の事蹟と,その兵法,
二刀一流,
を詳説したものである。二刀一流は,初期には,
円明流,
といい,最晩年に,
二天一流,
と名づけた。
僕は,剣には疎いので,素人判断で,かつて『五輪書』を読んだとき,間合いと拍子ということに要があるという点に強い印象を受けた。たとえば,「秋猴の身」というのが水の巻にある。
敵が打つ前に,身を早く寄せていく呼吸,
あるいは,「膝膠の身」というのは,
相手に身を密着させて離れない,
という。立ち合っている最中のことである。この間合いの一気の詰め方は,「敵を打つに一拍子の打ち」にある,
彼我ともに太刀の届くほどの位置をとり,敵の心組みができない前に,自分の身も動かさず,心も動かさず,すばやく一気に打つ拍子,
と通底するものだと思う。武蔵は,「間合い」を,
間積り,
と呼ぶ。
本書に,「間積り」について,こうある。
「進んで敵を打つには太刀を何尺突き入れれば届くかという正確に見積もりが『間積り』である。円明流では『立ち合い積り』と呼んで太刀の寸を例に説明している。切先から約五寸の物打の部分を『過去』と呼び,鍔元から五寸ばかり先を『未来』と呼び,残りの中央部分を『現在』と名づける。
『過去』で敵の現在へ寄った瞬間に敵の太刀に乗って攻撃するか,もし現在までに接近できないうちに,敵の動きが早ければ退って次の機会を狙う。『過去』から敵の『未来』を打っても届かないから二歩踏み込み,手の伸び一尺を加えると,辛くも敵の小手を切り付けることができる。」
あるいは,
「切先五寸の空間を越して二歩踏み込んでも七寸,つまり現在にわずか二寸しか交わっていない。敵が太刀をあげて始動すれば良くて合打ち,悪くすれば踏み込むと同時に切られる。できれば現在と未来の境目,つまり鍔元五寸まで接近して打ち込めば失敗しない。過去から現在に近寄って,打ち込むか退ろうかなどと思案するのは禁物である。過去から未来を打てば打ち外すから,現在へかかれば素早く未来を越して打たねばならない。切先五寸のうち,その一,二寸が届くか否かで勝負が決る。
したがって敵の切先が交わらない前に,何歩踏み込めば切り付けることができるかを素早く見積もるのが,『間積り』と呼ばれ,身長,太刀の長さを比べて,一瞬のうちに判断しなければならないから,多くの経験が要る。昔は『間積り』や,防ぎ技を変じて攻め技への返しは目録以上の者でなければ教えなかった。基本技に習熟しなければ『間積り』ができず,できない者に秘伝を伝えても理解できないと見たからである。」
と。武蔵やその弟子の事蹟を見ると,相手は手も無く追いつめられる。たとえば,熊本に入り,柳生の高弟氏井孫四郎と立ち合ったとき,庭の隅に追い詰められたし,それを見て自ら立ち合った細川忠利は,武蔵から木刀を面上に突きつけられたまま追い詰められる。間合いの負けである。
あるいは,明石滞在時,夢想権之助に立ち合いを迫られた折,
「武蔵は,わが兵法は打太刀を慥えて使うような型剣法ではない,何処から打ち込んできても即座に打ち込める兵法である,と答えると,権之助は四尺の棒で不意に打ち掛かった。武蔵は楊弓細工をしていて手にした割木で立ち向かい隅に追い詰め,眉間を打って,その場に倒した。」
というのも同じである。
武蔵の兵法は,剣術を指さない。剣術を,
一分の兵法,
と言い,用兵作戦術を,
大分の兵法,
と呼び,一分の兵法の達人にならなければ,大分の兵法はわからない,とした。あくまで,戦国時代を生きたものの実践の書である。だから,「二刀」についても,地の巻で,
「一命を捨てる程の時は道具を残さず役に立てたきもの也。道具を役に立てず腰に納めて死する事本意に有るべからず。然れども両手に物を持つ事左右共に自由には叶い難し。太刀を片手にて取習はせんため也。」
と実践的な理由である。
「太刀は広き所にて振り脇差は狭き所にて振る事先ず道の本意なり。此の一流に於いて長きにても勝ち短きにても勝つ。故によつて太刀の寸を定めず何れにても勝つ事を得る心一流の通也。太刀一つ持ちたるよりも二つ持つてよき所,大勢を一人で戦ふ時,又取籠り者などの時によき事あり」
大勢を相手にする「多敵の位」では,
「我刀脇差を抜いて左右へ広く太刀を横に捨て構へる也。敵は四方より懸るとも一方へ追廻す心也。敵懸る位前後を見分けて先へ進む者には早く行逢ひ,大きに目を付けて敵打ち出す位を得て,右の太刀も左の太刀も一度に振り違へて,行く太刀にて其敵を切り戻る太刀にて脇に進む敵を切る心也」
とし,
「如何にしても敵を一重に魚つなぎに追ひ廻す心に仕掛け」
とは,なかなか面白い表現である。
個々の剣法にその魅力があるのではない。武蔵はその極意を,
乾坤をそのまま庭にみる時は,我は天地の外にこそ住め,
と詠んだ。これが,
二天,
の意味である。これは,目付について,
観見二つの見様,
というのと通じる。風の巻に,
「観の目強くして敵の心を見,其場の位を見,大きに目を付けて其戦の景気を見折ふしの強弱を見て,正しく勝つ事を得る」
とし,
小さく目を付くる事なし,
と。武蔵に柳生一門はほぼ歯が立たなかった。それは,道場剣術ではないからに違いない。
身に楽を巧まず,
身ひとつに美食を好まず,
心常に兵法の道を離れず,
等々と「独行道」に書いた武蔵は,「たるみ」「ゆるみ」を厭い,入浴を嫌って「濡れた手拭いで汗を拭く程度」だっという。弟子の黒田家家臣小河露心は,関ヶ原で手柄を立て,戦場で生死をかけて戦ってきた者にとって,武蔵の兵法なんぞ何程かと思ったが,ついに打ち込めず,門人になった後も,隙あらばと思ったが,
「武蔵が木刀を取ってクワッと開いて立ち出ると,身が縮まるような気がして思わず知らず後へ下がり,ついに一本も打つことができなかった。」(兵法先師伝記)
という。どこにも隙がないのである。
武蔵の兵法も,独学だが,絵も,彫刻も独学である。それもまた,
兵法の境地,
を描いている。僕は個人的には,「枯木鳴鵙図」が好きである。
参考文献;
小澤正夫『宮本武蔵―二刀一流の解説』(吉川弘文館) |
|
武士団 |
|
豊田武『武士団と村落』を読む。
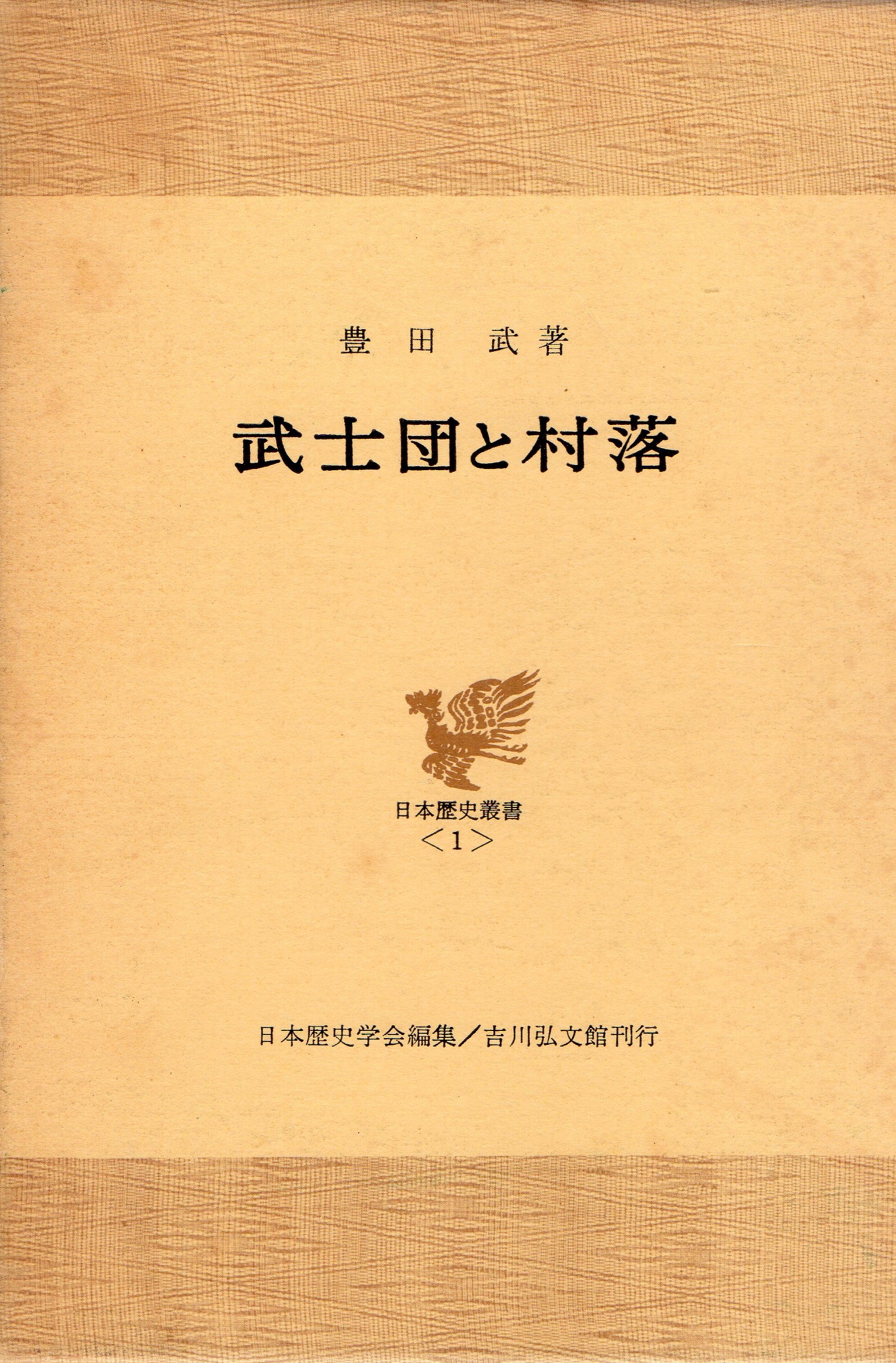
随分旧い本なので,今日の学説との乖離があるかもしれないが,土地に土着し,土地を開墾・開発していく武士の先祖たちの力強い姿が浮び上がってくる。基本かれらは大地につながっていた。
著者は,「はしがき」で,
「ここに武士団とは,平安末期から鎌倉時代を通じて,族的団結によって特徴づけられた武士の集団をいう。この時期の武士は,村落に深く根をはり,農耕生活を営みながら,戦闘に従事する点において,後期の武士とは著しく生活を異にする。」
と,在村し農業に携わる人たちであった。その類型は,
荘園領主級武士,
荘官級武士,
郎党所従武士,
といったり,
豪族的領主層,
地頭的領主層,
田堵(たとみ)名主層,
と分けたり,何らかの形で農事と切れていない。
「武士ともなる名主は,他に独立の小名主を従えて,それから所当・加地子を徴収していた領主的な名主ではなかったかと思う。またどんな大きな領主であっても,平安末期から鎌倉にかけて活躍していた武士は,農業からまったく遊離することなく,農村に土着し,直接経営の土地を,自己の下人や所従に耕作そせる名田(みょうでん)の持主であった。」
で,著者は,
「武士に共通する性格は,荘園領主とちがって,農村に居をかまえていた在地領主であるといいたい。彼らは他から侵害を受けない私領をもち,それ自身名主でありながら,他の名主を支配するという領主的な性格をもっていたのである。」
という。かれらの成長の背景には,平安後期以降,
「国衙や荘園領主による直接の開墾がすくなくなり,反対に地方に住む富農層が積極的に開墾をすすめてきたという事実である。国家としても,彼らが大規模なった開墾をおこない,百姓名(みょう)を買得・集積し,空閑地を囲い込んだりすることをそのまま黙認した。黙認どころか,荒廃した公田の復旧や加作を奨励し,官物の一分免除・雑事・雑役の免除の特典をあたえた。」
ということがある。それを積極的に担ったのは,国衙の在庁官人や郡司・郷司などの地方官であった。
「彼らが私領を拡大した方法の一つは,国衙から特別の便宜を得て,開発の地を別符とか,別符名(別名)とか称してこれを私領化した方法である。在庁官人たちは,これを通じて自らその保司職や名(領)主職をもつに至ったのである。」
こうした連中,つまり,
「在庁官人や郡司・郷司等の資格をもった在地領主はまたいっぽうにおいて公家や社寺の設置した荘園の荘官であった。その中にはその在地勢力を利用するため,荘園領主がこれを,下司や公文に任命したものもあるが,その多くは自己の開発した私領をこれに中央の公家や社寺に名目的に寄進して,自らは下司や公文となりながら,実質的には在地領主としての地位を確保したのであった。その目的は,私領に対する国衙権力の追求を合法的にまぬがれようとするところにあった。」
こうして,在地領主には,
国衙の機構を利用した在庁や郡司層,
荘園領主に私領を寄進してその荘官となった開発領主,
があるが,
「その多くは同一人にしてその二つを兼ねていた。この場合,これらの領主は。もはや従来のようにただ下人や所従を使役して直接経営をなすことはなかった。彼らはこの時期に相当に現れはじめた中小名主にその経営の大半を預け,随時その労力の提供を受けて,直営地の経営をおこなっていたのである。」
こうした在地領主から,武家の棟梁と呼ばれるものになっていく。
「在地領主の開発した私領,とくに本領は,『名字地』と呼ばれ,領主の『本宅』が置かれ,『本宅』を安堵された惣領が一族の中核となって,武力をもち,武士団を形成した。中小名主層の中には,領主の郎等となり,領主の一族とともにその戦力を構成した。武士の中に,荘官・官人級の大領主と名主出身の中小領主の二階層が生まれたのも,このころからである。武門の棟梁と呼ばれるような豪族は,荘官や在庁官人の中でもっとも勢を振るったものであった。」
要は,武士もまた,国土を私的に簒奪したものたちということになる。その多くが,官人,荘官というのも,なにやら,今日の官人の振舞を思い起こさせ,暗澹としてくる。
この武士団の中核をなすのが,一族・一門であり,広義の同族をさす。実態は,
「移住・開発した地方に蔓延した同族を中心として形成されている。この場合,苗(名)字は,公家が本第の屋号,もしくは一族の祭祀所である山荘を名字源とするのに対し,武士は,開発の本宅または本宅の地名をそのまま苗字とした。そして開発に功績のあった先祖を,根元的な本源と仰いでこれを祭り,それ以前の先祖を祭祀の対象としなかった。」
この「名字」族を一族・一門という。こうした在地領主の屋敷は,重要な河川や交通路を支配し得るような要衝の地にあり,やがて大領主へと発展していく。
「南北朝以後,地頭をはじめとする在地領主の直接経営はしだいに減少をはじめた。しかし小規模な在地領主は依然として耕作地を残し,下人・所従をかかえて,これを耕作させていた。戦国大名の支配下にあった給人は,みなこのような手作地をもっている。」
と,室町時代,戦国期の戦国大名へと発展していく兆しがすでに見えている。
参考文献;
豊田武『武士団と村落』(吉川弘文館) |
|
幽霊 |
|
今野円輔『日本怪談集 幽霊篇』を読む。

まさに,本書は「志怪小説」である。志怪とは,
「怪を志(しる)す」
中国の旧小説の一類,不思議な出来事を短い文に綴ったもの。また創作の意図はなく,小説の原初的段階を示す。六朝東晋の頃より起こった。「捜神記」など,
と『広辞苑』にある。ここで言う,「小説」は,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
であり,
「昔、中国で稗官(はいかん)が民間から集めて記録した小説風の歴史書。また、正史に対して、民間の歴史書。転じて、作り物語。転じて,広く,小説。」
その意味で,いま言う小説のはしり,ということになるが,
「志怪小説、志人小説は、面白い話ではあるが作者の主張は含まれないことが多い。志怪小説や伝奇小説は文語で書かれた文言小説であるが、宋から明の時代にかけてはこれらを元にした語り物も発展し、やがて俗語で書かれた『水滸伝』『金瓶梅』などの通俗小説へと続いていく。」
と,一応フィクションではない。本書は,その志怪小説の「幽霊」篇である。
「このような体験を,超心理,深層心理の発現と解するのも,あるいは単なるナンセンスと眺めるのも,それは読者のご自由だが,何はともあれ,なるべく,どんな先入観にもとらわれずに,その実態を見極める作業からはじめることが,もっとも科学的態度ではないかと思う。多くの例話を読み,比較,総合を試みることによって,わが同胞の霊魂現象が果たしていかなるものであるかを考える素材としていただけるならば,この,日本初の“幽霊体験資料集”編纂目的のなかばはたっせられたわけである。」
と,著者は「はじめに」にしるす。
すがたなきマボロシ,
人魂考,
生霊の遊離,
たましいの別れ,
魂の寄集地,
浮かばれざる靈,
死霊の働きかけ,
船幽霊,
タクシーに乗る幽霊,
親しき幽霊,
子育て幽霊,
と言った章別に,体験談が載る。おなじみの『遠野物語』をはじめとする史料からの転載もあるが,
「編者の直接採取以外の資料については,資料的価値のある部分だけの再録にとどめ,できるだけ原文を尊重した。」
など,柴田錬三郎『日本幽霊譚』,小泉八雲『怪談』,田中貢太郎『怪談全集』などからは採ってないと,あくまで,「志怪」に限定している,とみていい。
「幽霊譚」に奥行が見えてくるのは,「お菊虫」や「皿屋敷」を廻って,折口信夫の,
「キクという名の女性について,折口信夫先生は,(慶応大学の御霊信仰についての講義で)…『佐倉宗五郎の話は実感人形(稲の害虫を追う虫送りの)から出た話にすぎない。宗五郎も,死んで稲虫になったと言われている。そのことから出発して,宗五郎の靈が祀られるにいたる史実らしいものが考え出されもしているのだ。だから同じような伝説のある人なら直ぐそんな話がくつついてくる。伝説が事実を変造する』と説いたあと,『播州皿屋敷の話も同じだ。キクという女は,井戸に投げこまれてオキク虫というものになっているが,これは早乙女虐殺の話で,きっと井戸に関係がある。地下水はどこへでも通じているからだ。不思議に日本の虐殺される女の名には,お菊というのが多い。私は正確には三つ知っている。(イ)毛谷村六助妻園の妹,おきく,(ロ)累解脱物語,与右衛門の子,(ハ)播州皿屋敷,ひとつの見当はついている。加賀の白山に関係がある。自由のククリヒメだが,これはヒントに止める。ともかくオキクと水とは関係がある。水の中で虐殺された女の霊魂とオキクとの関係がある。』」
という話を糸口に,民俗の深部に辿り着ける。
著者が,三田村鳶魚の,
「幽霊を,あるとして無い証拠を挙げるのも,無いとしてあるという現実を打破しようとするのもコケの行き止まり」
という詞を引用しつつ,
「鳶魚翁が指定しなかった第三の立場があろうかと思う。簡単にいうならば,いわゆる幽霊なるものは物理的には実在しないことはいうまでもないから問題にはしないが,実在しないモノを,どんな条件のもとで,どんなふうにその姿を見たり,その声を聞いたりするのか,そこには日本人の特質らしい現象が認められるかどうか,歴史的な変遷がありそうか,など調べてみようというたちばである。」
とし,幽霊を相手にせず,
「幽霊を見聞するわれわれ自身の生活史の一部分−隠されていた未解決の精神史,民間信仰史の一面」
を相手にする,と。
そして,最後に,
「ともかく,真実らしい体験記を整理してみると,われわれが幽霊について持っていた常識は大部分間違っていたらしい。…じっさいの幽霊の中には『恨めしや−』といって出たモノはほとんどない。女性も出るが,男性もしきりに出るばかりか子供,老人の靈にも男女の別はなさそう。血みどろとか,吹出物などで醜悪な顔付きといった陰惨な姿もほとんど体験されていない。ちゃんと足があった。ミシミシと歩く音をたてながらという例が多く,足が無かったというのはむしろ少ない。服装では三角の額烏帽子といった死装束も少なく,ふだん着,外出着が多い…。タクシーを利用する幽霊が急増した。恨めしいどころか,肉親がなつかしくて会いに来ただけというのが多く,圧倒的に多いのはウナ電や電話より早く来る死亡通知の幻。明治このかたの新傾向らしいのは,何の目的で出たのかさっぱりわからないというタイプ。」
とまとめる。いまから60年近く前の編纂だが,現代もあまり変わるまい。
参考文献;
今野円輔『日本怪談集 幽霊篇』(現代教養文庫) |
|
江戸の風呂 |
|
今野信雄『江戸の風呂』を読む。
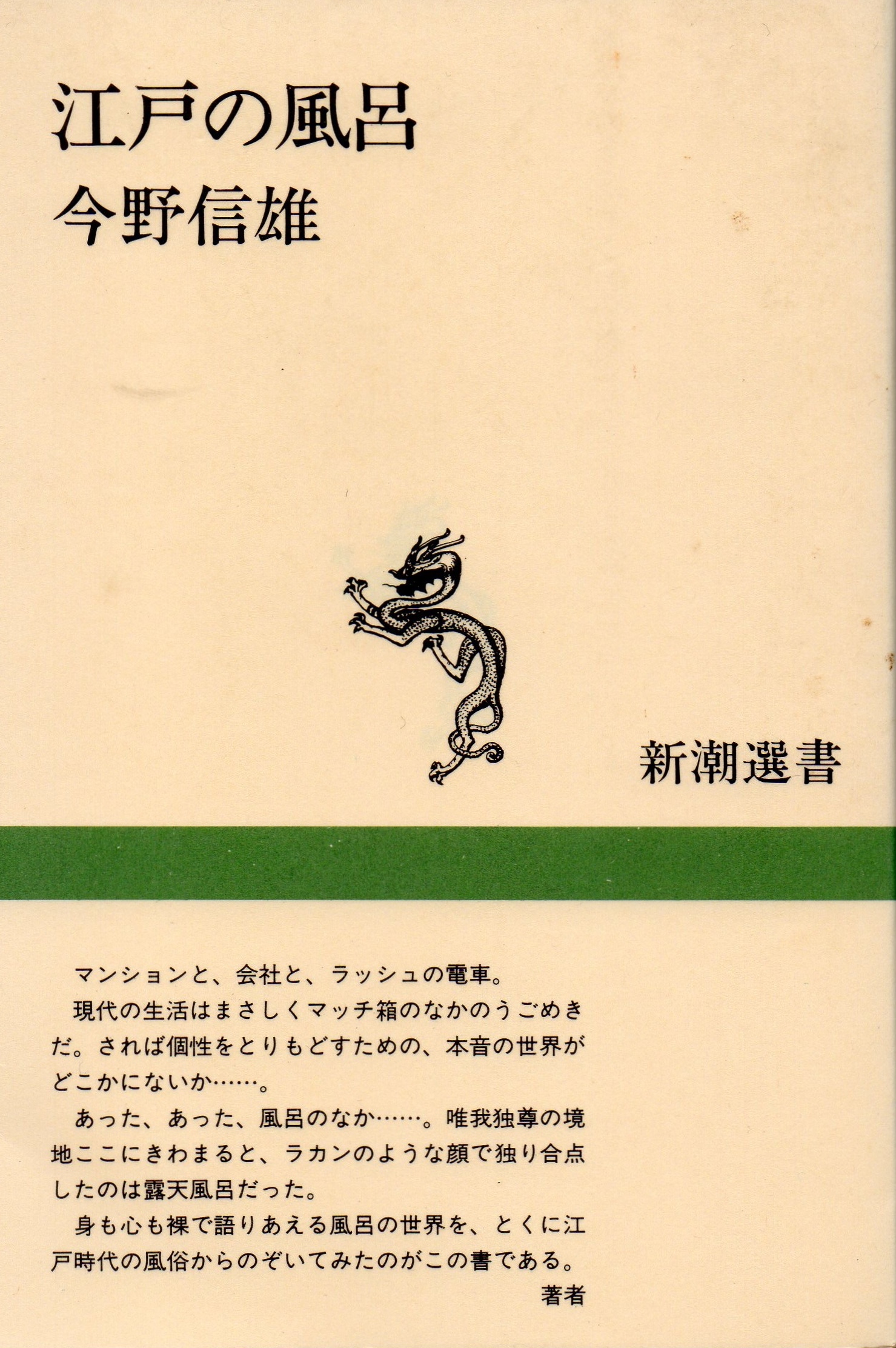
いわゆる銭湯(湯屋)の嚆矢は,家康が江戸入りした天正十九年(1591)とされる。場所は,
「常盤橋と呉服橋の中間にあった錢瓶橋のたもと」
とか。これは蒸風呂である。この蒸風呂が洗湯になったのは江戸も後期になってからである。
本書の引く『慶長見聞録』には,
「風呂銭は永楽一銭(永楽通宝一枚)なり。みな人めずらしきものかなとて入りたまいぬ。されどもその頃は風呂ふたんれんの人あまたありて,あらあつの湯の雫や,息がつまりて物もいわれず,煙にて目もあかれぬなどと云ひて,小風呂(むし風呂につきものの湯をたくわえた湯槽)の口にたちふさがり,ぬる湯を好みしが…」
とあるとある。江戸の建設ラッシュで人が集まってくる。それを当て込んでの開業らしい。その二十数年後の慶長十九年(1614)には,既に湯屋が軒を並べる。同じ書には,
「今は町ごとに風呂あり。びた銭五文廿銭ずつにて入る也。湯女(ゆな)といいて,なまめける女ども廿人,三十人並びいて垢をかき,髪をそそぐ。そてまた,その他に容色よく類なく,心ざま優にやさしき女房ども,湯よ茶よと云ひて持ち来り類むれ,浮世がたりをなす。こうべを回らし一たび笑めば,百の媚をなして男の心を迷わす」
と,もはやフウゾクである。寛永十三年(1636)になると,
「銭湯は午後四時頃で閉店し,以後はにわか座敷にして金屏風をめぐらし,遊女スタイルになった湯女が,客の席にはべった」
とある。この影響で吉原が衰微し,ついに,
「遊女を湯女風呂に派遣」
するに至る。さすがに幕府も放置できず,寛永十四年(1637)
「湯女は一軒に三人かぎりとし,違反者は大門外で刑に処することとなった。このときお仕置処分になった湯女風呂は三十七軒にもなる。」
とある。そこは「蛇の道は蛇」で,
「表に見えるところでは三人でも,屏風のかげにまわれば,なまめかしく着飾った女たちが何人も待っていた」
とか。今も昔も変わらない。
湯屋を本書では次のように紹介する。
「銭湯の外には,まず目印になる看板がある。この看板,『ゆ』とか『男女ゆ』と書いた布を竹の先に吊り下げてすたり,矢をつがえた弓を目印にしている店が多かった」
という。
「ゆいいるという謎也。『射入る』『湯に入る』と言近きを以て也」(『守貞漫稿』)
との洒落らしい。
入ると,まず土間があり,ここで履き物を脱いで下足版に預け板の間に上がる。そこで番台に湯錢を払う。板の間が脱衣場である。
「客は衣服戸棚に脱衣を入れるか,…かごに入れるが,別に自分だけの衣服を包んでおくための,大きな布を用意してくるときもある。これが風呂敷だ。…湯からあがった時には足を拭うのに用いた…」
洗い場(流し場)は,
「中央に溝があり,汚水が外へ流れ出るしくみになっている。汚い話だが,多くの男たちや子供が恥じらいもなく,ここで堂々と小便をする」
とか。当然,中も推して知るべしで,
「肝心な風呂の湯が予想以上に不潔なのである。そこで,入浴がすむと清潔な湯をもう一度全体に浴びることになる。これを上り湯とも岡湯とも浄湯とも書くが,岡湯とは,湯槽を湯舟ともいうところからもじった言葉である。この岡湯を浴客が勝手に汲みだすことはできない。小桶を出して番頭に汲んでもらうのである。というのも,浴客のなかには不潔なまま洗い桶を使用する不心得者がいたからだ。カラン(蛇口)式になったのは昭和の初期まことである。」
とある。
江戸初期,蒸風呂と洗湯を兼ねた湯槽の,戸棚風呂というのが一次流行った。
「洗い場で引き戸をあけて中へ入り,また引戸を閉める。つまり戸棚に隠れるような感じで,中の湯は一尺(約三十センチ)ほどしかない。だから腰だけ下が湯につかるだけだ。これを戸棚風呂といったが,引戸が板だから別名を板風呂といった。しかし引戸が閉めてあるから,内部は蒸気でむんむんする」
これは,燃料不足と水不足からきたものだ。引戸を開けたてする度に蒸気が逃げるので,引戸に代わって,引戸を固定し,下一メートルほどを開け放った柘榴口の風呂が登場する。
この柘榴口は破風造りの屋根か鳥居が付いており,この名残りが,今日の銭湯の破風造りである。
それにしても,銭湯は安く据え置かれ,寛永元年(1624)から明和九年(1772)まで,六文のままなのである。寛永の頃を百とすると,明和では三百,三倍の物価という。
一日に薪一本除けて焚けば,三百六十本虚(むだ)に焚く,
一本疏(おろそ)かにせざれば数日を助く,況や一生数年の損をや,
等々と「湯語教」という湯屋経営の教科書に載る。
「『弱いかな弱いかな』とか,『安いかな安いかな』と愚痴をこぼしながら,…心がけ一つでやはり相応に利益のある堅実な商売だった」
と,茶者は想像する。
風呂という世俗の坩堝に,江戸時代の庶民の風俗(フウゾクかも),風習が象徴的にみえ,なかなか面白いが,紙数が足りないのか,温泉や湯立神事の章は,余分な気がする。
参考文献;
今野信雄『江戸の風呂』(新潮選書) |
|
妖怪 |
|
今野円輔『日本怪談集 妖怪篇』を読む。

本書は,今野円輔『日本怪談集 幽霊篇』の続編になる。
妖怪は,
「タソガレの逢魔が刻からカワタレの暁闇,夜明けまで,あるいは一番鶏の鳴くまでの間の夜は,人間の支配外,つまりは人外の魔物の時間であった。生活圏のもっとも狭い空間は軒下の雨垂れ落の内であり,人魂が川を越したら生き返らないというなど,川のこちらであったし,山のあなたはも知らぬ他国であった。また,墓地からの帰りは,後を振り返ってはいけないなどのタブー,さては後を振り返らずに肩越しに物を投げる呪法などを考え合わせると,前代日本人が確認できるのは躰の前方であって背後にはいつも不安を感じていたらしい」(「はじめに」)
という時代の日本人の心性のありようと深くかかわっている。それは,アニミズムということばだけでは代替できない,深い奥行がある。
妖怪の大部分は,
御靈信仰系,
と
祖霊信仰系,
に大別できるという。つまり
神々が妖怪化,
したものらしい。狐やタヌキ,カワウソ,イタチ等々妖怪化する動物も多く,
神霊,
神使い,
霊獣,
であった可能性が高く,植物でも,
神樹,
靈木,
が祟る。つまりは,
神霊から妖怪へ,
の大ざっぱな流れがある。だから,
「妖怪の特徴のひとつは,もともと人間を恫喝し,ワッと叫ばせるにすぎなかったとは柳田翁の説であった。妖怪出現の目的は,人間に対する恨みをはらそうとか,とり殺すというような悪意があってのことではなくして,もとは神霊の威力を示し,それを認めさせるためであったから,人間の側が畏怖すれば即ち目的は達せられたという。その威力に伏し,承認すれば,それ以上は追求しないという形式は,…よほど妖怪しつつある小正月の定期的な訪問神であるナマハゲの行事などにも如実に示されている。」
というのが,本来形なのであろうか。後は,昔話によって変化していく。
本書では,
路上に出没する妖怪(股くぐり,ノブスマ,ツチノコ,見越し入道等々),
家の中の化け物(ザシキワラシ,マクラガエシ等々),
河童,
山童,
ぶきみな化け物(ロクロッ首,一つ目小僧,大入道,海坊主,牛鬼等々),
ユーモラスなケモノたち(キツネ,タヌキ,ムジナ,イタチ,カワウソ),
鬼と天狗,
山姥,
磯女,
雪女,
器物の怪,
化鳥,
樹木の靈,
主,
といったものが並ぶ。水木しげるではないが,今日のデジタル世界の方がよほど薄っペラに思えるほど,奥行のある世界である。
「妖怪の基盤を形成しているのは,日本人の民間信仰であり,神霊に対する強烈な畏怖に他ならない」
のは確かで,
「ヘングェ(変化)といい,バケモノというのは,正体は別にあって,他の現象を示現し,わが身ならぬ他の姿を現すもののことである。」
「オニ」の項
http://ppnetwork.seesaa.net/article/461493230.html?1536090582
で触れたように,もともとは,
もの,
と総称していた。モノノケの「モノ」である。顕現しているものの向こうに何かがあると感じるから,それを,モノとしか呼びようがなかったのである。
参考文献;
今野円輔『日本怪談集 妖怪篇』(現代教養文庫)
鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫) |
|
極致 |
|
森銑三『宮本武蔵の生涯』を読む。
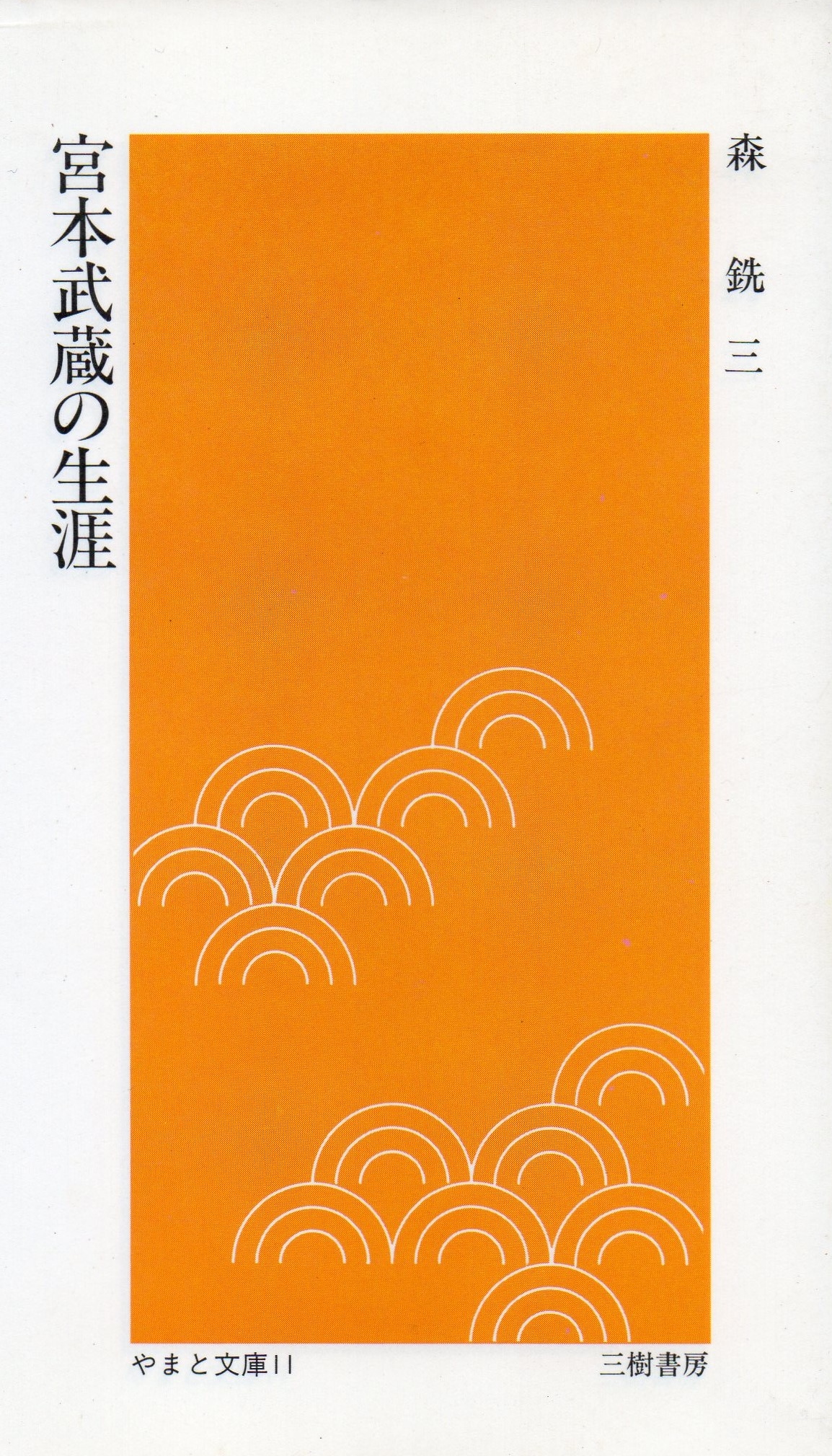
「序文」に,尽きている。
「心常に兵法を離れず。
独行道と題する宮本武蔵の自戒十九条の最後に,かやうにいってある。
武蔵の生涯は,剣を以て一貫する。剣といふわが國特有の武芸に一命を託して,あらゆる物慾に目もくれず,つひにその道を極め尽くした。然もそれを極め尽くした時,忽然として広い世界へ出た。剣法に於て,既にその敵がなくなってゐたばかりか,剣の一芸に通ずることに依って,武蔵は己を大成し,兼ねて人事の百般に通ずることを得た。芸術に遊べば画が成り,彫刻が成り,その他が成った。絵画その他は,武蔵に於てはもとより余技であった。然もこれを簡単に余技といひ去るのは当らない。それらは,武蔵の生命とする剣と一つに結ばれてゐた。剣道と芸術と,武蔵に於ては二にして一であり,一にして二であった。武蔵は剣道を極めることに依って自己を完成した。道を求めて通を得た。武蔵は剣の人にして,兼ねて道の人だった。武蔵の武蔵たるの所以はそこに存する。武芸家として,また人として,武蔵は正に古今に独歩する。」
戦前,まさに対米戦の始まる直前に書かれ,戦時中に上梓された。そんな雰囲気があるかもしれないが,簡にして要を得る,とはこのことである。
本書の中の,「宮本武蔵の生涯」の中に特段特異なことがあるのではないが,二つのエピソードが面白い。後世宮本伊織として,小笠原家の重臣になり,武蔵の彰徳碑を建てる養子伊織は,いわゆる寛永の御前試合で,
「荒木又右衛門と試合して相打ちとなった」
とある。伊織(八五郎)二十三歳,荒木又右衛門三十八歳。
「又右衛門が伊賀國上野で,渡辺数馬に助太刀して河合又五郎を打ち取って,大いに部名を挙げたのは,その年十一月七日のことである。」
と。養子にするだけの才を,少年に見つけたにしても,優れたる育成力である。その武蔵の人を見る目を窺わせるのが,ただひとり奥義をさずけた弟子,寺尾求馬のエピソードである。武蔵の兵法三十五カ条の,「巌の身」という一条に,「動くことなくして,強く大いなる心なり」というのがある。細川光尚にその意をたずねられた武蔵は,
「事に臨んで申し上げなくては,これを顕し難うござる。寺尾求馬を召し出されまたしならば,即座に御覧にいれませう」
と答え,召された求馬に,武蔵は,傍らから,
「求馬,思召の筋あり,唯今切腹仰付くる。さやう心得て支度致せ」
と申し渡した。求馬は,「謹んで御請申上げまする。御次を拝借致しまする。」
と言った立った。その自若とした,平素と変らない態度を,
「只今ご覧遊ばされました求馬の体が,即ち巌の身でござりまする」
と武蔵は言った,というエピソードである。武士道は死ぬことではなく,ただ死の覚悟を指す,ということと関連し,武蔵がひとを見る目を示すエピソードがある。森鷗外が『都甲太兵衛』という小説にもした,都甲太兵衛の件だろう。
細川忠利に謁見した折,忠利に,「当家の侍で,御身の目に触れた者はいなかったか」と尋ねられて,武蔵は,「只一人を見受けました」と答えた。名前を知らないので,忠利は,武芸に名のある者を召したが,そこにはおらず,捜し出してこいとの命で,武蔵は間もなく,諸士の控え所にいた,都甲太兵衛を連れてくる。ただ都甲太兵衛は,式台に着座して武蔵が御殿へ通るのを目迎目送しただけである。
忠利は,どういうところが目に留まったかと問われて,武蔵は,「本人の不断の覚悟をお尋ねなされたら分かります」
と答える。都甲は,「別にこれと申すこともない」と言うのを,武蔵は,「拙者は貴殿の武道に見込みがあって申し上げた。只平生の心掛けを腹蔵なく申し上げたら宜しうござろう」と促されて,都甲が答えたのが,
「私は据物の心得と申すことに,ふと心附きまして,その工夫を致しました。人は据物で,いつでも討たれるものぢゃと思うてゐるのでござります。平気で討たれる心持になるのでござります。最初は,ともすれば,据物ぢやといふことを忘れてなりませなんだ。それから据物ぢやといふことを不断に心得て居りまして,それが恐ろしうてなりませなんだ。だんだんと工夫致します内に,据物ぢやと存じてゐて,それがなんともなうなりました。まことにたわいもないことを申し上げました。」
と,これである。据物とは,「罪人の死体などを土壇に据えること」である。この答えを,武蔵は,
「あれが武士道でございます」
と言った。都甲太兵衛の覚悟の程については,森鷗外『都甲太兵衛』を見ていただけばいい。
『五輪書』に,
「道理を得ては道理を離れ,兵法の道に己と自由ありて,己を奇特とす。ときに逢ひては拍子を知り,自ら打ち水から当る。これ皆空の道なり」
とある。その極致に達したとき,何が見えるのか。
本書の中で出色は,『宮本武蔵』という小説を書いた吉川英治の随筆『随筆宮本武蔵』をこてんぱんに批判しているところだろう。贋作の宮本武蔵の絵を口絵にしているだの,『五輪書』もわかっていないだの,結局問題の多い,宮本武蔵遺蹟顕彰会『宮本武蔵』のみによって書いただの,まあ悪口雑言である。しかし,その程度の理解と鑑識眼で,あの小説を書いたということは,小説家に必要なのは,知識や鑑識眼ではないということの証明みたいなものである。
第二部として,本書に,一書にまとめるのに不足だったのか,
「正忍記」
という忍術の伝書が載っている。これがまた面白い。如何に人に疑われないか,人に紛れるか,に心を砕き,いわゆる忍術書とは縁の遠い,ちょっと変わった伝書である。
参考文献;
森銑三『宮本武蔵の生涯』(三樹書房) |
|
こやし |
|
楠本正康『こやしと便所の生活史』を読む
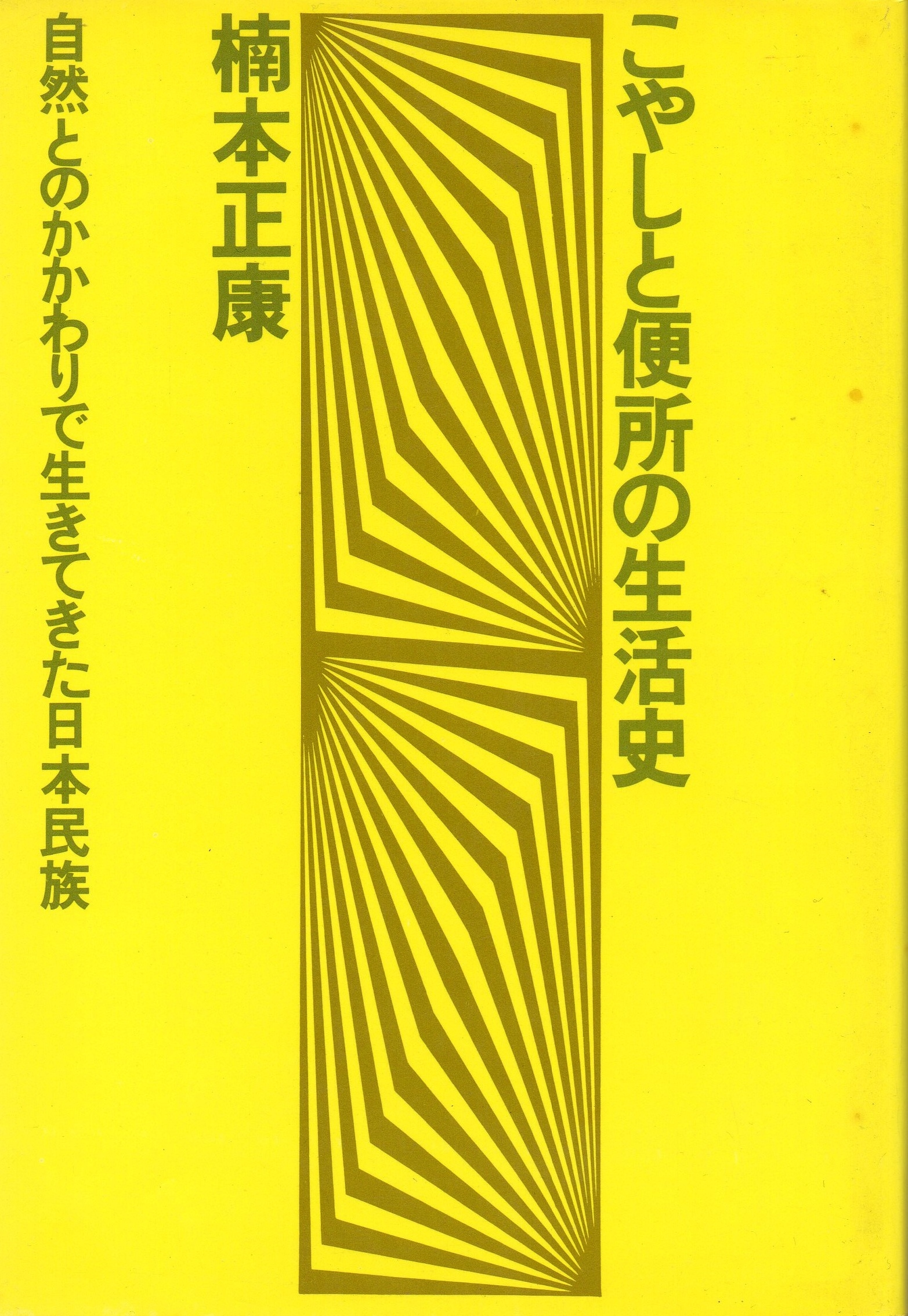
本書は,文字通り,日本における,
こやしと便所の歴史,
である。そして,「肥料」という言葉は明治以降に使われた言葉で,それ以前は,
こやし,
であり,室町時代以降,
糞,
糞培,
糞苴,
を当て,「こやし」と訓ませた。実に分かりやすい。人糞が主要な「こやし」だったからである。
稲作は,早く縄文時代に始まっているが,施肥は弥生時代から始まっている。稲は,
「根刈りではなく,穂刈りだったため,稲わらはそのまま水田に残って,施肥資源になった。」
刈草や稲わらなどの有機物質には,化学肥料では,まったくみられない特徴として,地力の保持増進の働きかある,という。
「稲わら,刈草,木の若草などを水の中に溶かした形にすると,自然状態表現では溶けにくい鉄分が,キレート鉄となり,分子構造が変わって,還元状態で水に溶けやすい二価の鉄となって,有機物から分離され,分解されやすくなる。そして,グルコースのような還元性の糖分が,鉄を見ずに溶けにくい三価の形から二価の形に変えて水溶性とし,植物が鉄を吸収しやすくする。」
ということが現代ではわかっているが,そういう合理的な施肥を,弥生時代にしていたことになる。
いわゆる「便所」は,「かわや」と言われた。これは,
「川の上に架した排便場所」
から来たもののようであるが,事実弥生時代の竪穴住居には「便所」は見当たらない。それが,平城京(750年頃)にはじめて,
共同便所,
らしいものが造られ,延喜式(927年)にはじめて,
「人糞の施用」
があらわれる。「生食用の瓜類」に使われた。これが,
「人糞尿を肥料として用いた文献上の最初の例」
という。
「この人糞尿は,播種前の踏み込み用として使用しているので土壌微生物のはたらきにより,たとえ病原菌等による汚染があったとしても,捕食されて衛生上は安全であり,また糞部分が遅行性であっても,播種前の施用であるため,分解されるまで十分な時間的余裕がある。したがって,現代の科学からみても合理的な施肥方法であったといえる」
とか。この施肥に用いたのと,共同便所とはつながりがあるようである。
二毛作が始まる鎌倉時代,
「灌漑による水田耕作と灌漑を排し,乾田として畑作を繰り返すので,とくに多量の施肥を必要とする。しかも,多収穫をはかるためには,畑作に対する追肥や稲作に対する稲ごえ(追肥)が欠かせない。この場合は,速効性でしかも十分な栄養素をもっていることが何よりも必要なので,この条件を満たしているのは腐熟した人糞尿が最も効果的なのだ」
という。特に,
「長期間貯留して分解された人糞尿が速効性がある」
ことが明らかになるにつれて,
「これを一ヵ所に貯えておかなければならない。そのために。直接耕作にあたる農民も,耕作を受け持たせている地頭や名主たちも,やがて住居の外側などに大きな便池を備えた便所を設けるようになった」
と想像されるという。最古の農業技術書『清良記』に,
「農家に入ってみて,牛馬の厩がきれいに清掃され,雪隠もきれいでたくさん糞尿を貯えてあるうえ,敷地内に菜園が見事に作られて駙あおと育っており,外の田畑が格別素晴らしいような場合は立派な百姓である。これに反し,家の垣根や壁がくずれ,菜園は方ぼうに散らばり,厩には垣も壁もなく,あちこちに厩肥や糞をばらまいておくような者は,どこかの奉公人のように見え,百姓とはいえない」
とあるように,既に肥料としての人糞の重要性が認識され,『洛中洛外図』にも,生育した水田に,柄杓で稲ごえをする頭が描かれているが,
「米の多収穫のためには,この稲ごえが欠かせないのだ。しかし,稲ごえは速効性であることが何より必要で,同時に肥効成分を兼ね備えているものでなくてはならない。…当時としては液状でこのような条件を備えているものは,十分に腐熟した青みがかった人糞尿か,または混じりもののない尿だけだった」
ところから,柄杓で撒いているものの正体は明らかである。こうした施肥の頂点は,江戸時代である。多くの農業専門書が上梓されたが,例えば,佐藤信淵は,
「人糞尿は温熱滋潤の脂膏と揮発透さんの塩気を含んでいるので,田畑に培養すれば,作物の生育にこれほど役立つものはない。しかし,新しいものは効果がないので,腐熟醸化してから使う。糞は溶けて青味をおびた液状となったものを施用しなさい」
こうした篤農家たちの主張は,明治になって,科学的に立証されることになる。注意深い観察から得た経験則が,ここでも生きていることがわかる。
江戸時代,都市の町割りに当たっては,あらかじめ組み取りを考慮して便所が設けられた。たとえば,
「当初から家の裏の方に設けられた」
し,裏店では,
共同便所,
が設けられた。組み取りの対価が決まっており,五段階に分けて価格設定していた,というのが笑える。
最上等品 勤番(大名屋敷勤番者のもの),
上等品 辻肥(市中公衆便所),
中等品 町肥(ふつうの町屋のもの),
下等品 タレコミ(尿の多いもの),
最下等品 (囚獄,留置所のもの),
しかし,そのそうした総額は,年間,四万九千両余,という。このランキングは,明治期,軍人のそれが最上級だというのと,対比すると,ただ笑ってはいられない。
こうした施肥との関係は,トイレのスタイルにも反映するが,戦後化学肥料にシフトするに連れて,糞尿はいらないゴミに化していく。僕の記憶では,少年時代,農地には肥溜めが点在していた。いつごろ無くなったものだったか。今日,トイレは,もはやただ孤立した排泄場所に過ぎなくなったが,それは肥溜めの消滅と関わるに違いない。
本書は,なかなか面白い着眼だが,遺構が残っていないせいもあるが,トイレのありようと施肥の関係だけでなく,排泄そのもの変化(室町期人々は路上でも用を足していた)との関係にも広げて,深掘りしていくと,裏面の文化史になったと思えるのだが。
参考文献;
楠本正康『こやしと便所の生活史―自然とのかかわりで生きてきた日本民族』(ドメス出版) |
|
飢饉 |
|
菊池勇夫『近世の飢饉』を読む。

本書は,江戸時代の飢饉を,
寛永の飢饉,
元禄の飢饉,
享保の飢饉,
宝暦の飢饉,
天明の飢饉,
天保の飢饉,
と順次追っていく。しかし,その前の元和にも飢饉があり,実は,戦国時代もまた飢饉の時代であった。というより,
七度の飢饉に遇うとも,一度の戦いに遇うな,
という言い伝えがあるほど,飢饉は常態であった。慶応にも,明治になっても飢饉がある。さらに,
「近代に入っても明治二(1869)年,同十七年,同三〇年,同三五年,同三八年,大正二(1913)年,昭和六(1931)年,同九年と東北地方を中心に凶作が繰り返された。」
と,近代になっても続くのである。例えば,本書の年表を見ると,
元和元年(1615)奥羽冷害による大凶作,
寛永元年(1624)陸奥飢饉,
寛永三年(1626)旱魃により諸国飢饉,
寛永一六年(1639)西日本で牛疫病(翌年がピーク),
寛永一八年(1641)旱魃・洪水・冷害などで全国的に大凶作,
寛永一九年(1642)大凶作,
と,飢饉が続く。特に江戸時代始め,一七世紀は,一大水田開発時代で,中世までは水田中心ではなかった地域まで,開発が進む。
「大河川の乱流する沖積平野が幕藩領主の大土木事業によって美田に作りかえられ,(中略)全国の高知面積および実収石高は,1600年段階においておよそ206万5000町歩・1973万1000石であったものが,100年後には284万1000町歩・3063万石に増え,これに伴い人口も1200万人から2769万人に急増した。」
東北各藩でも,事情は同じで,
「十七世紀の大開発時代を通して東北農村は一部山間地帯を除き,水田稲作を基調とする田園地帯に変貌を遂げた」
のである。しかしこの時期稲作の北限であるこの地域にとって,冷害に強い赤米ではなく冷害に弱いとされる「岩が稲」というような「商品として売れる多収量」の晩稲を作付けせざるをえない。それは,「市場経済の論理が米づくりの現場に」入り込んみ,
「年貢米にせよ農民手元米にせよ,全国市場に販売するための商品に基本性格が大きく変えられてしまったからである。」
たとえば,仙台藩では,
「販売を目的として江戸回米は『武江年表』などによると,寛永九(1632)年に始まるとされ,後々には江戸の米消費量の三分の一ないし三分の二を仙台米が占めたとまでいわれ,…1650年代,すでに蔵米七〜八万石,家中米・商人米七〜八万石の合わせて一五〜一六万石もの米が回米されていた。年貢米のほか藩による買米もすでに一七世紀段階に始まっていた。」
つまり,
「東北各藩の活発な江戸・上方回米をみれば,一七世紀後半の新田開発は,おもに大消費地たる上方や江戸への年貢米売却を目当てに,藩権力によって積極的に取り組まれた」
のである。これが,冷害・凶作時に悲劇を倍化させる。例えば,弘前藩では,寛永飢饉に際し,
「米価の高騰する端境期に,前年度米を売り急いで儲けようとする藩当局の判断が領内の米払底をもたらし,はやくも八月末に餓死者が出るような飢餓状態を招く」
のである。この背景にあるのは,
「参勤交代制によって江戸に藩邸が設けられ,そこに居住する大名妻子の生活費や家臣団の俸給はむろん,幕府への奉仕や諸藩との交際など『江戸入用』がかさみ,それへの送金を必要とした。年貢米の三分の一以上が『江戸入用』に当てられ,…そうした増大傾向の江戸での出費を賄うためには,年貢米を上方や江戸に売却して貨幣を獲得するほかなかったのである。」
しかも,
「農民たちは,年貢米を上納した残りの手元米を在町や城下の商人に売却して現金を手にし,それで農具や生活用品を購入する生活・消費サイクルのなかにまきこまれるよになっており,凶作の備えはあとにしても,少しでも米相場があがれば売りたくなる衝動に駆られる時代に突入していた。」
農民自身もまた,先を争って高値で売りさばこうとする。
江戸期の飢饉の中で,享保の飢饉に際してのみ特徴的なのは,他の飢饉では見られない,幕府の積極的な介入である。そのため,「飢饉状態からの脱却が比較的はやかった」とされる。
行政がなすべきことをなせば,ある程度の救済ができるのである。飢饉に対して,各藩の対応で死者に格段の差が付くのも,同じである。天明の飢饉の教訓から,「社倉」という,
「民間の人々がそれぞれ穀物を出し合って自治的に共同管理する備荒倉」
があるが,例えば秋田藩では,
「藩側による統制力の強い郡方備米が設置されていたが。しかし。天明の飢饉の経験が遠くなると,備米嫁し付けの金融利殖の方に関心が傾き,現物を貯える備荒の本来の機能がないがしろにされてしまい」
「天保三(1832)年は六〜七分の作柄にとどまり,そのため貸方分を回収することができず,帳面上はともかく空き蔵状態となった。また,天保三年七,八月ごろ米値段がにわかに高くなり,自分用に『凶作の備籾』をもっていたものたちもこの時とばかり売り払ってしまった」
ために,翌四年の大凶作に無防備となった。
江戸時代,あるいは戦前まで,不純な天候に襲われ,定期的に飢饉に見舞われた。二二六事件は,そのさなかで起きている。それは過去の話ではない。戦後1993年には大凶作が再来し,急遽外米が緊急輸入される事態となった。
今日,耕作地が放棄され,高齢化が進む中,飢饉は,別の形で來る。しかし,その備えは,いまの政府にあるのだろうか。今度は,国際的な大凶作になったとき,江戸時代に国内で起こったことが,世界規模で起こる。穀物自給率30%と低いわが国に,その備えがあるとは思えない。飢饉は,必ずしも過去のことではないのである。
参考文献;
菊池勇夫『近世の飢饉』(日本歴史叢書) |
|
戦場の暴力 |
|
藤木久志『飢餓と戦争の戦国を行く』を読む。

『雑兵たちの戦場』で,中世の戦場の実像に迫った著者の,それに関連する著作である。著者は,
「戦争・飢饉・疫病の三つが本書の主題」
としている。「はしがき」に引かれている,
七度の餓死に遇うとも,一度の戦いに遇うな,
という諺が象徴的である。
三度の飢餓に遇うとも,一度の戦さに遇うな,
とも言うという。同じことは,幕末福島の百姓一揆の指導者・菅野八郎が,
世話にも,七年の飢饉に逢うとも,壱年の乱に逢うべからずとは,むべなる哉,
と引用しているという。中世の戦乱が重く人々の言い伝えに沈殿してきた証といっていい。
著者は,中世のはじまりの戦争「保元・平次の乱」直前(1150年)から,中世の終わる「関ヶ原合戦」(1600年)までの450年間記録や古文書の災害情報をデータベース化し,
「日本中世の旱魃・長雨・飢饉・疫病年表」
として巻末に整理している。
「できるだけ生生しい原文のまま,コンパクトな形でとりだして」
年表風にまとめている。たとえば,冒頭の久安六(1150)年は,
諸国大風雨洪水の難(京都),咳病放棄,民庶死亡(京都),
翌年仁平元(1151)年は,
去年暴風の難・洪水の困(改元),大雨洪水(京都),
とあり,久安六(1150)年から慶長五(1600)年まで,ほぼ毎年,水害,洪水,暴風,旱魃,飢饉が訪れている。今日の毎年の災害を見れば,日本列島に住む限り,災害は日常茶飯である。それは,当時も今も,同時に飢饉の危険をはらんでいた。しかし,その餓死の危険よりも,戦争を恐れていたのである。
「十一世紀末から十六世紀末まで,五〇〇年間の改元(年号を変える)回数を数えますと,一五二回ほどにのぼるのですが,そのうち凶事つまり天変地異(飢饉など)や兵革(戦争)を原因とするものだけでも,九六回(約63%)にのぼります。中世の改元の過半には,なんとか飢饉をはじめ災害や戦争から抜け出したいという,『世直し』の願いがこめられていた」
とあるように,ほぼ五年に一回,改元で祈らねばならないほどの「兵革・飢饉・疫疾
」に見舞われていた,ということになる。
例えば,世に源平合戦といわれる戦いは,
「天下の騒動と呼ばれる大がかりな内戦となり,折からの飢饉災害とあいまって,田畠を荒廃させ,百姓を逃散させ,人々を何年も続く餓死に追い込んでいた」
のであり,飢饉は戦争と深くつながっている。この間,
飢饉は169件(二・七年に一回),
疫病は182件(二・五年に一回),
そして,戦争は,
源平合戦〜応仁の乱までは,三〜五年に一回,
戦国時代は,二年に一回,
起きており,それは,そのまま飢饉と疫病の発生をもたらす危険を帯びており,
前者で,十〜五〇年に一回,
大飢饉に見舞われ,後者では,
「ほとんど慢性化した飢饉と疫病のさなかに,戦われていた」
という。特に戦国時代後半百年は,
「飢饉と疫病がそれぞれほぼ五十件ずつという惨状」
が見えるという。武将や大名レベルでの歴史を見ているかぎり決して顕在化しない,歴史の惨状が明らかになってくる。
その戦場では,フロイスが『日本史』で,薩摩島津と豊後大友との戦いについて書いているように,
「(薩摩勢)が実におびただしい数の人質,とりわけ婦人・少年・少女たちを拉致…これらの人質に対して。彼らは異常なばかりの残虐行為を…した」
「薩摩軍が豊後で捕虜にした人々は,肥後の国に連行されて,売却された。…肥後の住民は…彼らをまるで家畜のように,騠来(たかく)に連れて行って,売り渡した。…彼らは豊後の婦人や男女の子供を(貧困から)免れようと,二束三文で売却した。」
「ポルトガル人・シャム人・カンボジア人らが,多数の日本人を購入し,…奴隷として彼らの諸国へ連行している」
これは,なにも九州だけのことではない。大航海時代の「世界的な奴隷貿易の時代」に組み込まれていたのである。
「戦国の中ごろ,日本人の『女奴隷』はポルトガル商人の重要な商品とされ,大きな利潤を生んでいた」
ともいう。そして,マニラには,日本人の奴隷がマニラの治安を脅かすほど多くいた,と言うほどになっている。
戦争を嫌うのは,その結果の飢えや疫病よりも,
濫妨,
乱取り,
という兵士たちの略奪・暴行を恐れていたのである。果ては,人身売買によって,遠く異国に送られることなのである。
戦国の英雄たちの視点では決して見えない,日本中世の残酷で悲惨な実情を,また本書で改めて知らされるのである。
参考文献;
藤木久志『飢餓と戦争の戦国を行く』(朝日選書) |
|
サバイバル |
|
藤木久志『戦国の村を行く』を読む。

戦国時代,農民は,ただ逃げ惑っていたわけではない。濫妨狼藉の被害者であっただけではない。彼らもまた武装し,時に落人狩もした。さらに,
「戦国の世には村も城をもっていた」(はしがき)
のである。本書は,村の,
自力の生き残り策,
を探る。これまで欠けていた
村から領主をみる
視点での「領主・農民関係」を探ることと,飢餓と乱取りの中での,
村の地力生き残り策,
を見ること,これが本書のテーマである。乱取りは,
人間の略奪,
あるいはぶっちゃけ,
奴隷狩り,
であった。それは,上杉謙信(景虎)は常陸小田城を攻め落とした際の,
「小田開城,景虎より,御意をもって,春中,人を売買事,二十銭,三十二(銭)程致し候」
というような人買いによって売り買いされるだけではなく,武田信玄軍の大がかりな人取りのように,
「男女生取りされ候て,ことごとく甲州へ引越し申し候,さるほどに,二貫,三貫,五貫,十貫にても,身類(親類)ある人は承け申し候」
と,身代金目的でもあった。
秀吉が,戦場での「濫妨取りの男女」の人返し(返還・解放)と「人の売買一切相止むべく候」と指示し,「人を売り買う義,一切これを停止すべし」と再三命じ,バテレン追放を命じた背景に,ポルトガル船による奴隷売買が絡んでいたと見なされる所以である。
そんな中,村も自衛する。その一つは,
「敵軍におくの米や錢を支払って『濫妨狼藉停止(ちょうじ)』の禁制や制札」
を買い取ることであり,さらに,境目の村々が,
「敵対する双方の軍に,年貢を半分ずつ払って両属(半手・半納)の関係」
を結ぶことで,
「村の平和」
を買い取っていた。しかし,制札は,
もし当郷の者,手柄に及ばざれば,旗本へ来たりて申上ぐべし,
見逢いに搦め取り,申上ぐべし,
との付記があり,要は,軍兵が濫妨を働いたら,
村の自力で逮捕し,連行せよ,
というのであり,保障された平和は,
当事者の村が自力=手柄(濫妨狼藉の実力排除)によって実現すべきもの,
であった。あくまで,禁制は,
「それを手にした村がその大名から『味方の地』として認定され(もし制札なしに山の城に避難すれば,敵対とみなされ激しい追及にさらされました),禁制に背く濫妨狼藉に公然と実力で防御・抵抗しても,敵対とはみなされなかった」
というところに効力があった。では,にもかかわらず村が戦場になったらどうするのか。戦禍を避けるために,
領主の城の近くの村々は城に籠り,
遠くの村々は山籠り,
をしたという。
山上り,
小屋上り,
とも言い,この「山小屋」が,
村人の籠る自前の城,
つまり,
村の城,
であると,著者はいう。それは,時に,
「幅が七,八間(14メートル前後)もある大きな堀を掘って大名軍に抵抗した」
という例もあるほどで,文献でも,
百姓ら要害をかたく構え,
一味同心して要害をこしらえ,
という「村の城」が知られており,
「中世の社会は,武装権築城権が,領主だけでなく,村や町を含む諸集団にも,広く分有された『自力社会』だった」
ことがよくわかる。中世の終りに,
刀狩り,
や
城破(わ)り,
が秀吉によって打ち出された背景がよく見えてくる。
参考文献;
藤木久志『戦国の村を行く』(朝日選書) |
|
城郭 |
|
西ケ谷恭弘『城郭』を読む。

「城」の由来は,「城」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/463204819.html)で触れたように,本書の主張する,
「城は,貯蔵機能をもち垣檣(えんしょう)で区画した空間であった。すなわち憑(より)シロ(招代)・ヤシロ(家シロ・屋シロ・社)・苗シロ・松シロ・杉シロなどにみられるようにシロは,場所・区画であり,宿り,集まり,集置の粮所の区域をいう。シロはシルシスナワチ標(しるし)が語源であるとされる」
という説が, 『岩波古語辞典』が,
「シリ(領)の古い名詞形か。領有して他人に立ち入らせない一定の区域」
や, 『日本語源広辞典』の,
「知る・領るの名詞形のシロ(国見をする場所)」
であり,
「シロは,場所で,まつたけのシロ,ナワシロ,ヤシロなどのシロと同源」
と重なる。その「シロ」について,『日本書紀』の
葛城,
稲城,
から,幕末の,
五稜郭,
までを辿る。「はしがき」で,
「城のイメージである天空に聳える天守・櫓や石垣・堀が,いかにも近世に忽然と出現したかのような」
従来の城郭史の点と線を繋ぐ,具体的な,感状山城,一乗谷,山中城などの壮大な城郭群によって,
「中世から近世への空白を埋める城郭形態の変遷(編年)」
を描けた,とするように,本書は,城郭の歴史である。
弥生期の,高地性山城,大和王権下の神籠石式山城(こうごいししきやまじろ),朝鮮式山城,蝦夷対策の城柵,武士の登場から,悪党の山城,守護大名,国人領主の築城から戦国時代の城郭への大きな流れを辿りつつ,安土城が,城郭史のエポックとなる。そのプロセスの変化を細かく辿る。
正確な数ははっきりしないが,元和一国一城令で,城割り(城の破壊)が進んだとはいえ,なお残った城もあり,
260以上の城郭が明治維新時に存在した,
とされる。しかし,廃城令,その後のずさんな管理によって,破壊されたもの,荒廃したもの等々によって,存置城郭は58となり,結局,20城のみ残り,その後,戦災などによって,現在天主のみ残るものを含めて,松本城,犬山城,姫路城,等々12城しかない(その写真は,http://heiwa-ga-ichiban.jp/oshiro/index.htmlに詳しい)。明治期,興福寺の国宝級の仏像が路傍に放りだされていたという作為の廃仏毀釈にしろ,この貴重な城々を廃棄した廃城令にしろ,文化というものにほとんど斟酌しなかった,明治政権の作為・不作為の暴虐ぶりがよくうかがえる。
参考文献;
西ケ谷恭弘『城郭』(近藤出版社) |
|
雑兵 |
|
藤木久志『【新版】雑兵たちの戦場−中世の傭兵と奴隷狩り』を読む。
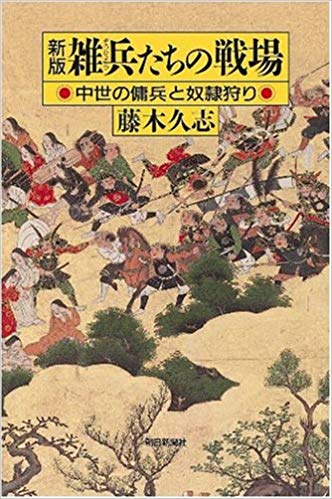
何度目になるだろうか。読むたびに,戦国日本の風景が変わるのを実感する。信長,秀吉や,信玄や謙信といった戦国大名や武将を中心としてみる風景では,戦国期の実像は決して見えない。本書が与えた衝撃は,はかり知れない。
乱取り,
人買い,
奴隷狩り,
奴隷の輸出,
等々,戦国の戦場がもたらした惨状の射程は広く遠く,
山田長政,
にまで及ぶ。山田長政は,大久保忠佐の下僕だったとされる。まさに,雑兵である。それが本書の主役であるが,実は戦国大名の後押しあっての,
乱取り,
なのである。それは,上杉謙信(景虎)は常陸小田城を攻め落とした際,
「小田開城,景虎より,御意をもって,春中,人を売買事,二十銭,三十二(銭)程致し候」
というような人買いによって売り買いされるだけではなく,信玄軍の大がかりな人取りのように,
「男女生取りされ候て,ことごとく甲州へ引越し申し候,さるほどに,二貫,三貫,五貫,十貫にても,身類(親類)ある人は承けもし候」
と,身代金目的でもあり,ともにまぎれもなく,戦国武将そのものが行なっていたことである。天正元年(一五七三)四月、上洛した信長軍でも,雑兵の乱取りは、
「京中辺にて、乱妨の取物共、宝の山のごとくなり」(三河物語)
というありさまである。この雑兵を,著者はこう定義する。
「身分の低い兵卒をいう。戦国大名の軍隊は、かりに百人の兵士がいても、騎馬姿の武士はせいぜい十人足らずであった。あとの九十人余りは雑兵(ぞうひょう)と呼んで、次の三種類の人々からなっていた。
①武士に奉公して、悴者(かせもの)とか若党(わかとう)・足軽などと呼ばれる、主人と共に戦う侍。
②武士の下で、中間(ちゅうげん)・小者(こもの)・荒子(あらしこ)などと呼ばれる、戦場で主人を補(たす)けて馬を引き槍を持つ下人(げにん)。
③夫(ぶ)・夫丸(ぶまる)などと呼ばれる、村々から駆り出されて物を運ぶ百姓(人夫)たちである。」
雑兵の中には,侍(若党,悴者は名字を持つ)と武家の奉公人(下人),動員された百姓が混在している。さらに,
「草・夜わざ,かようの義は,悪党その外,はしり立つもの」
といわれる,いわゆる,
スッパ,ラッパ,
と言うところの,まあ今日の表現で忍者もまた雑兵に入る。このものたちは,
「端境期を戦場でどうにか食いつないでいた」
者たちである。こうした戦場で食いつないでいたものたちは,秀吉によって国内が統一され,戦争が消えたとき行き場を失う。朝鮮侵略は,国内で行なわれてきた,
乱取り,
奴隷狩り,
の輸出であった。一説に,掠奪連行された朝鮮人の数は,
島津だけで三万七千余,
という。出兵した各藩が連行した数は,何十万になるのか?
国外へ出た日本人は,人身売買で,外国商人に売られた人ばかりではなく,傭兵として流出した数は,馬鹿にならない。
「十六世紀末から海を渡った日本人の総数は,とても特定できないが,おそらく十万以上」
といわれる。しかも,
「海外に流れた日本の若者は,鉄砲や槍をもってする戦争に奉仕する『軍役に堪える奴隷』『軍事に従う奴隷』として珍重された」
といい,たとえば,
「1621年(慶長十七),オランダ船のブラウエル司令官が平戸に入港した。目的は幕府の許可を得て,日本人傭兵を海外に連れ出すことであった」
という。
「その多くはごく低賃金で雇われた,奴隷的な兵士であった」
とされる。こうした傭兵は,
「東南アジアの植民地奪い合い戦争や植民地の内乱の抑圧に,手先となって大きな役割を果たした」
こうした流れは,元和七年(1621)に,幕府の
「異国へ人売買ならびに武器類いっさい差し渡すまじ」
という禁令によって終止符がうたれる。このことの与えた衝撃,たとえば,オランダの,
「日本人傭兵なしでとうていアジアの戦争はたたかえぬ」
という反応を見るだけで,いかに日本人傭兵・奴隷がそれに寄与してきたかが想像される。
「切り取り強盗は武士の習い」
「押し借り強盗は武士の慣い」
という諺が,文字通りであったことを知らされるのである。
参考文献;
藤木久志『【新版】【新版】雑兵たちの戦場−中世の傭兵と奴隷狩り』(朝日選書) |
|
二天一流 |
|
岡田一男・加藤寛編『宮本武蔵のすべて』を読む。

本書は,
宮本武蔵とその時代,
五輪書について,
二天一流と武蔵の剣技,
宮本武蔵の書画,
映像のなかの宮本武蔵,
小説に描かれた武蔵,
武蔵の家系と年譜,
宮本武蔵の全試合,
に分けて,分筆されているものである。これで「すべて」なのかどうかはいささか疑問である。今も残る,古流派の人に,剣術(剣道ではない)の基本的技術について,詳述する箇所が抜けているのが気になるが,それでも,本書の中で,
武蔵の家系と年譜,
という経歴部分をのぞくと,読むに堪えうるのは,僅かに,
武蔵の家系と年譜,
のみである。書いているのは,剣道家である。しかし,謙虚に書かれている分,説得力はある。結局,失礼ながら,人を語れば,その語る人そのものの器量がわかる。西郷について,
「釣り鐘に例えると、小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響く。もし、バカなら大きなバカで、利口なら大きな利口だろうと思います。ただ、その鐘をつく撞木が小さかったのが残念で」
と語った龍馬の言は,すべての人物評に当てはまる。
「浮足立つ」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/463499097.html)で触れたように,剣道では,
「現代剣道の足運びは、主に右足を前に出して踏み込み、引き、防ぎます。後ろ足はつま先立ってます。踏み換えて稽古することはまずありません。却って滑稽に見えるかも知れません。」
という。しかし,宮本武蔵は,全く反対のことをいう。
「足の運びは,つま先を少し浮かせて,かかとを強く踏むようにする。足使いは場合によって大小遅速の違いはあるが,自然に歩むようにする。とび足,浮き足,固く踏みつける足,はいずれも嫌う足である。」
この違いは決定的である。
有名な武蔵像の,二剣を下げた姿勢は,ある意味武蔵の剣の姿勢そのものを象徴的に表しているといっていい。
「惣而兵法の身におゐて,常の身を兵法の身となし,兵法の身をつねの身とする事肝要なり」
とある通りである。ただ,この常の身とあるのは,
兵法の身をつねの身とする,
ところを前提にしているのだが,
足におゐて替わる事なし,常の道を歩むが如し,
とする。この歩むが,どういう歩みだったのかが問題になる。
ぼくは本書を読んで,改めて,剣術と剣道とは別物ということを改めて感じさせられた。古武術研究家の甲野善紀氏が言いだした,
ナンバ(走り),
に代表されるように,かつて日本人は,いまのような走り方,歩き方ではなく,
右手と右脚、左手と左脚を同時に出す,
足さばきである,とする説がある。この説の是非はともかく,少なくとも,武蔵は,
爪先立つ,
ことを嫌い,
爪先を少し浮かせて,かかとを強く踏むこと,
を強調した。素人だが,「多敵のくらい」において,
両刀を抜いて,左右に広く,太刀を横に広げて構える,
という太刀捌きは,ナンバの足さばきでこそ,生きるという気がしてならない。
参考文献;
岡田一男・加藤寛編『宮本武蔵のすべて』(新人物往来社) |
|
真説 |
|
原田夢果史『真説宮本武蔵』を読む。

本書を読むと,ほぼ武蔵のイメージが変わる。
著者は「はしがき」で,本書を要約して,こう書いている。
「吉川英治さんは,…剣豪武蔵を求道者武蔵として取り上げたが,その功績は大きい。実像の武蔵は,殺人剣を活人剣へと脱皮するために修業した,類い希な人物であったからである。武蔵は,『二天記』や『吉川武蔵』の虚像よりも,はるかに偉大であったのである。小説や伝記の虚像が,実像の偉大さに及ばないというのは,通説では舟島の決闘が,完成された武蔵の終着駅と解釈したからで,それ以後の武蔵は生ける屍であった。これが虚像である。
実像の武蔵は,二十九歳のこの試合で始めて殺人剣の愚を悟り,禅に,水墨画に,彫刻に,造園に,そして活人剣―五輪書―へと至る,長い遍歴の途を辿るのである。一族の大家長として子弟の面倒を見,九州探題小笠原藩にける,宮本家の地位を不動のものとしたのである。」
これが本書の梗概でもある。その象徴が,小倉碑文の,
天仰實相圓滿
兵法逝去不絶
とみている。著者は,これを,
天を仰げば実相円満,
兵法逝去して絶えず,
と訓み,舟島の決闘以後の武蔵の生き方を象徴すると読み取る。
確かに武蔵の死後百二十年後に書かれた『二天記』やそれに依る吉川英治の『宮本武蔵』の創りだした武蔵像は虚実あわせて,大きい。そこから抜け出ることはなかなか難しいのはたしかだ。
しかし,少なくとも,伊織自身については,自身が再建した泊大明神社や米田天神社の棟札(「泊神社棟札」)記載「田原家傳記」で,
播磨国印南郡米堕邑、田原久光の次男,
であることで,その出自ははっきりしており,『二天記』や吉川英治『宮本武蔵』の,
泥鰌捕りの童,
という伊織像は,もはや改められるほかはない。
本書は,小倉宮本家系図に基づき,伊織を,
武蔵の甥,
としている。つまり,
田原久光,武蔵の兄の次男,
とする。武蔵は甥のうしろだてとなった,とみるのである。僕には,この説の方が,説得力があると思う。少なくとも,武蔵の伊織への肩入れは尋常ではないのだから。
武蔵については諸説入り乱れるが,不思議なのは,少なくとも,武蔵の死後九年目に造られた小倉碑文を,
他の史料と比べて事実誤認や武蔵顕彰の為の脚色も多く見られる,
と一蹴する(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E8%94%B5)ことだ。ほぼ同時代に記されたものを無視するのは如何なものだろか。まずこれを前提に検討すべきであろう。例えば,舟島での佐々木小次郎との対決を,
両雄同時に相会し岩流三尺の白刃を手にし来たり,…武蔵木刃の一撃を以てこれを殺す,
と記す。この一文を無視してはいけないだろう。「同時」とあるのは,同時なのであって,あえて遅れて相手を焦らすなどという『二天記』の創作された姑息な武蔵のイメージは,ここにはない。顕彰碑ということを差し引いても,同時代の記録を創作と捨て去るのは,ちょっと解せない。
本書の武蔵像は,ただ真面目で実直に,甥の後だてとなり,それを支えていいる姿で,孤高のイメージとは離れている。そのイメージが,
天を仰げば実相円満,
兵法逝去して絶えず,
なのである。著者は,
「剣技の世界に見切りをつけ,活人剣,治国の剣の世界へと大勢が変わりつつあることを,直感的に悟っていた」
と,その意図を読む。その後の武蔵とは,
「尚も深き道理を得んと朝鍛夕練して,兵法の道にかなうように思われた」(『五輪書』)
時までを指す。そのとき五十を超えている。
天を仰げば実相円満,
とは,
「若干二十歳で二千五百石,島原の陣で千五百石の加増で計四千石である。小笠原十五万石…一門衆でも筆頭が千五百石から二千石止まり」
の中で,宮本家は,異例の出世である。しかもその名は将軍家の耳にも達した。治国の役を,伊織が果たしたのである。宮本家は,以来幕末まで続く。本書の巻末には,十三世伊織宮本信夫氏が,
「小倉藩では,宮本家代々の当主を本名の如何にかかわらず『宮本伊織殿』と知行状を出してい.る。私の手許に,五通,諸先代の知行状があるが,それぞれ本名があるにもかかわらず公文書の時は『宮本伊織』と呼んだ。初代伊織が傑物だったからと思われるが,それにしても奇妙な慣行である。」
と書いている。伊織が(というより,その後ろ立ての武蔵が)小笠原藩にとって大きな存在であったという一例は,七代貞則のとき,
「宮本家に小笠原家から養子が入った」
という。
「小倉分藩一万石篠崎公の弟が七代伊織貞則であり,以来宮本家は小笠原庶家の待遇」
となることにもみられる,という。
参考文献;
原田夢果史『真説宮本武蔵』(葦書房) |
|
隠物・預物 |
|
藤木久志『城と隠物の戦国誌』を読む。
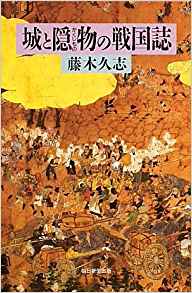
本書は,戦国時代,戦国武将目線ではない,その惨状を暴いてきた著者の連作の一つである。本書のテーマは,
「人びとは,どうやって家族を守り,家財を守ったか」
に焦点を当てる。先ず,身を守る手段としての,
戦国の城,
の,村人の避難所として,
地域の危機管理センター,
としての役割である。いまひとつは,
「戦場から逃げるとき,運びきれない大切な家具・家財や,農具・家畜,様々な食糧,あるいは米作の作に欠かせない大切な種籾」
等々をどうやって保全したか,その,
「村の隠物・預物」
に焦点を当てる。前者は,『戦国の村を行く』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/463189273.html)などでも取り上げたが,ただ人が逃げ込むだげではなく,
「戦争が来ると,俵物(食糧)ばかりか,牛や馬まで連れて,領主の館や大寺などに避難していた。持ちこまれたものは『隠物』とか『預物』などと呼ばれていた。」
というように,家財もまた避難させていた。神社もその対象である。たとえば,
「織田信長か尾張(愛知県)の熱田神宮(熱田八ヶ村)に,『俵物』を神社の中に運ぶのを認める,と保障していた。また神社の中に避難している,他国や当国の敵味方や,奉公人・足弱(老人・女性・子ども)や,彼らの『預ヶ物』も,先例の通り,暗線を保障する,といっていた」
しかし,そした神社・城郭だけではなく,村々も互いに預け合っていた。
「山間の村々は里の村々との間に,村と村との契約として,無料で道具預かりをするのが,日常の習俗となっていた」
という。寺側も同じらしく,多聞院英俊は,日記に,
「こんど道具を預けたまわるにつき,一瓶・両種,送り給わり…」
「道具取りに来る…大根二十八給わり…」
等々,引き換えにさまざまな礼物が繰られているが,金銭による謝礼はない。
「関白(秀吉)殿より,当(春日)社へ奉加(寄付)米の代銀の皮袋二つ,預かり申し候,両三人符(ふだ 封)を付けられ候,(皮袋の)中の物躰は見ず,請け候」
とあり(多聞院日記),預けた側は封をし,請取証文を出す。それは民衆にとどまらず,たとえば,信長も,安土城に近い近江蒲生郡長命寺に米十石を預け,それについての指示が,
「その方へ預ヶ申し候,米十石,西川三郎左衛門二郎方へ,御うたがいなく,お渡しあるべく候,その方の預かり城は,尾張にござ候あいだ,まいらせず候,もし何方わり出し素とも,反故たるべく候」
とある。
しかし,そうして預けた家財も,
「そこが戦場になり,味方の軍が敗北し,敵軍が乗り込んでくると,せっかくの家財の保全や緊急避難の苦労も,たちまち水の泡となった。
戦いに勝った占領軍は,戦場地帯にある敵方の預物・隠物を狙って,徹底した追及を行い,『預物帳』という台帳まで作らせて,すべてを没収した」
その追及・捜査は,
道具改め,
道具糺し,
道具尋ね,
等々と呼ばれた。
「原田(直政)が大阪の本願寺との合戦(石山合戦)で戦死すると,大和の筒井順慶は,奈良中の寺と町に『触れ』を回して,もし原田同類の『預かり物』があれば,『紙一枚,残さず出さるべし』と厳しく命じた。徹底した預物狩りであった。
これを聞いた多聞院の英俊も,原田同類の塙小一郎から預かっていた米を,慌てて出し,『いまさら不便(不憫)の次第なり』と同情し,自分の非力を嘆いていた」
秀吉は,柴田勝家の越前に侵攻すると,三カ条の指令を出し,その冒頭に,
「兵粮ならびに,あづけ物」
の提出を命じ,
「秀吉,条数(三カ条)をもって申し出し候こと,みかえし候においては,その一町残らず,妻子以下,ともに成敗」
と恫喝していた。
戦国の必死の隠物,預物も,敗戦すると,敵にすべて没収されるリスクがあった。この中世の習俗は,中世に限ったことではなく,戊辰戦争に際しても,更に,先の大戦下,
防空壕への人びとの非常持ち出しの物の退避,
もそうした習俗の延長線上にある,と著者は推測する。
参考文献;
藤木久志『城と隠物の戦国誌』(朝日選書) |
|
高持百姓 |
| 渡邊忠司『近世社会と百姓成立―構造論的研究 』を読む。

「近世では一人前の男が一年に消費する米の量は一石(玄米で一五〇キロキグラム)から二石、また夫婦と子供・親の五人から六人の家族が自らを自力で維持していくことのできる標準的な規模は、裏作も可能な田畑を合わせて五反五畝程度、石高にして八石前後の所持であった。表作の米は年貢・諸役(貢租)として徴収され、裏作の麦を主食としながら。である。麦は米とほぼ同じ収量を期待できるから、五反以上の高持百姓は再生産が可能で、上手くやれば、いくらかの蓄積も可能なる。但し、これは裏作の不可能な地域では通用しない。それに反して、五反(約八石)以下の百姓はかなり苦しい。」
と,大石久敬が『地方(じかた)凡例録・下』で試算したように,
五反,
八石,
程度の田畑所有がないとやっていけない。にもかかわらず,
「近世の土地台帳である検地帳や名寄帳,あるいは免割帳などに記載された高持百姓あるいは本百姓のち所持石高や田畑の反別が一石未満,また一反未満を中心に零細な百姓が圧倒的に多い」
本書の問題意識は,こうした
自立できない零細な階層,
一石・いったん未満の高持百姓,
の再生産を可能とした条件は何か,
である。高持百姓とは,名請百姓。高請地(たかうけち)(検地帳に登録され年貢賦課の対象とされた耕地 (田畑)
および屋敷地)を所持し、年貢・諸役を負担し、村の一人前の構成員としての権利・義務を持つ農民,つまり「天下の根本」とされる徳川時代の幕藩体制を支える基礎が,この高持百姓と呼ばれる人々である。その多くが,零細農家であるということである。
いま一つ,本書本書の問題意識は,「百姓」という概念について,
「少なくとも領主側の法令や記録には,百姓は当たり前のように出てきても『農民』という用語はほとんどでてこない」
ので,「百姓と農民をなんら検討もなしに同義」とは出来ない,ここの解明である。「百姓成立」と本書のタイトルが鳴っている所以でもある。
「あらゆる姓氏を有する公民」の意,あるいは,凡下,地下人であった「百姓」は,凡下,地下が侍以外を指したのと同様,侍以外を指した。そこでは,農民とイコールではない。百姓を農民と重ねることになった端緒は,秀吉の「定」(天正十四年),「条々(刀狩令)」(天正十六年)によって,「領主と百姓の基本関係が年貢の賦課と徴収関係にあることを規定した」が,その前提になっているのは,「『百姓』の社会的役割が年貢米の生産と納入」という秀吉の百姓像である。この条例で,
「農民という用語が用いられておらず,年貢米納入者が(百姓),給人(領主)と対峙する者が『百姓』であり『百姓』の社会的責務が年貢・夫役の納入であると規定されていることである。」
ここにあるのが,近世に踏襲される百姓像の原型である。そして,刀狩は,
「兵と農との完全な分離によって中世以来の在地領主制の解体を完全なものとし,在地には侍を住まわせない」
のが主眼であった。結果,「百姓」とは,
「検地名請人(高持百姓)だけとなった」
が,そのため,
「一つは,兵農分離後の村の居住者すべてを『百姓』と見なしたために,農を業とする者以外も百姓概念に含ませたことである。これによって,実際の居住者には商人・職人などがいながら百姓と位置づけられ覆い隠される事態をもたらした」
「もひとつは,村居住者の多様性が隠された結果,領主も他の諸階層も一様に村には農耕に専念するものしか居住しないという予断と錯覚を産み出す事態をもたらした」
とする。この百姓像は,徳川時代にも引き継がれていく。
これは,地ばえの国人,土豪,地侍を,鉢植化し,移封,転封していくことと裏腹に,村落に残ったものを,侍以外を凡下といったように,百姓といったと言い直してもいい。しかし,そうして,検地を通して,それまでの中小の領主から解き放たれて,領主と向き合う「百姓」は,
「名請高が一石以下,名請反別が一反以下の名請人が圧倒的であること,また家屋敷だけの名請人や田だけ・畑だけの名請人」
となり,
「それぞれの名請高・反別だけでは生活も農業経営の維持も不可能」
な小農民が沢山いることになる。彼らも含めて農業を可能にし,生活を支えてきたのは,独特の村ごとのシステムであったことを,本書は,
第一に,分付主と分付百姓で編成される生産と年貢納入の構造が,単に中世以来の支配・隷属関係ではなく,相互の再生産の扶助構造になっていること,
第二に,用役牛の共同保有(これをベースに五人組が形成されている)によって扶助構造となっていること,
第三に,質入れを利用した融通の仕組み,
を挙げていく。しかし,最後の質入れは,一年の決算に質屋を利用して,
「不勝手之百姓ハ例年質物ヲ置諸色廻仕候」
というように,それは,
「春には冬の衣類・家財を質に置いて借金をして稲や綿の植え付けをし,秋の収穫で補填して質からだし,年貢納入やその他の不足分や生活費用の補填は再度夏の衣類から,種籾まで質に入れて年越しをして,また春になればその逆をするという状態にあった」
ことの反映で,
「零細小高持百姓の経営は危機的であった」
ことを記している。これは摂津国を例にしているが,寒冷地では,もっと厳しい状態で,近世慢性的に飢饉が頻発した背景が窺い知れるのある。近世の飢饉(http://ppnetwork.seesaa.net/article/462848761.html)についてはすでに触れた。
参考文献;
渡邊忠司『近世社会と百姓成立―構造論的研究 』(佛教大学研究叢書) |
|
奇跡 |
|
G・ヤノーホ『カフカとの対話』を読む。
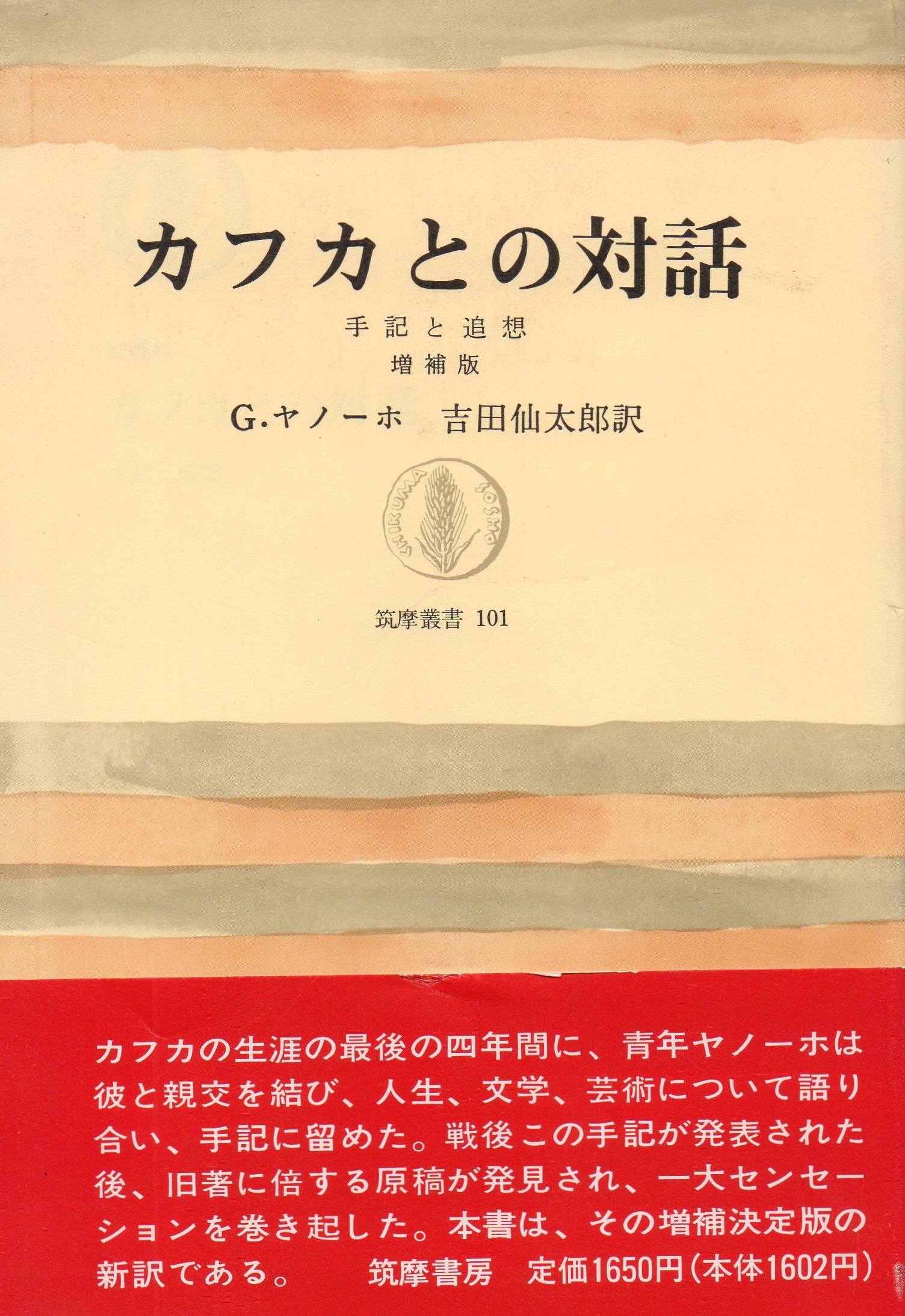
この本は,奇跡のように思える。当時17歳だった青年が,父親の労働者障害保健局の同僚だったカフカにあったのは,カフカの死の四年前,僅か二年ちょっとの期間である。しかしもただそれだけではこの本はなり立たない。17歳ながら,ちょっと文学の才気のある青年であったこと,カフカが彼をいつくしみ,真正面から応答していること,そしてなにより彼自身が抜群の記憶力と,記録癖があったことがなければ,成り立たない。しかも,この本が上梓されるにも,数々の苦難を経て,ほとんど諦める程の状況にあった。この本が出版されたこと自体もまた,奇跡であった。
著者は,第二次大戦と戦後の動乱のチェコスロバキアで,しかし,何とかこの本を上梓はすることが出来た。それにわれわれは感謝しなくてはならない。カフカの肉声が,しかも若い後輩との真摯な会話の中に,写し出されているのである。
カフカの遺構を出版したマックス・ブロートと,カフカ晩年を支えたドーラ・ディマントも,この対話を讀むと,
「フランツ・カフカが目の前にいて話しているような印象を受ける」
と語っているように,その体験を文字に写した著者の筆力のたまものでもある。ブロートは,さらに,初めて手記を見た時の印象を,
「あの手記は,私の忘れ難い友の本質的な相貌を―一部私の知らなかった委細をも含めて―感動的に甦らせてくれました」
と書き,その上梓に尽力する。
著者は,「日本語版によせて」で,こう書いている。
「私は今日,私に対する運命の厚意というものを自覚しています。私は困難な青春の暗澹たる一時期に,フランツ・カフカの知遇を得たのであり,私がただ一人で―よきにつけ悪しきにつけ―この時代のなかをよろめきつづけて来たそのすべての年月を通じて,彼の善意と生への献身とを私の伴侶としてきたし,単なる意志の力で我がものとすることの叶うものでもない。フランツ・カフカの言葉は,私にとって,時代の混乱を切りぬけるよすがでもあり,困難きわまる状況にあって私の力となる,友愛の手でありました。私はだから,この私のカフカとの対話を文学とはみなさない。それは信仰告白であり,内なる光の遺産であり,はたすべき課題なのです」
17歳の青年が,晩年のカフカと遭遇した奇跡は,彼自身にとっても巨大な財産であったようである。記録をうしない,ほぼ出版を諦めた時も,恐らく彼を支えたものはカフカとの体験であった。カフカは,彼の両親の離婚をめぐる難局で,彼に,
「忍耐は,すべての状況に対する特効薬です。われわれは,すべてのものと共振し,すべてに身を捧げ,しかも落着いて忍耐強くなければなりません。(中略)曲げたり,折ったりということはあり得ない。自己克服に始まる,克服という行為があるのみです。これは避けるわけにはいかない。この道を逃れるならば,必ず破滅が待っています。忍耐強くすべてを受入れ,成長しなければなりません。不安な自我の限界は,愛によってのみ打ち破られる。私たちの足もとにかさこそ音をたてる枯葉の向こうに,すでに若い新鮮な春の緑を見,そして忍耐し,待たねばなりません。忍耐こそ,すべての夢を実現させる真の,唯一の基盤です」
と語る。この真摯な語りかけを書き残されたこともまた奇跡である。彼自身は,この言葉を,こう受けとめたのである。
「これが,ドクトル・カフカが私に撓まぬ思いやりをもって植付けようとした,彼の生活信条であった。そしてその信条の正しさを彼は私に,あらゆる言葉,あらゆる手振り,あらゆる微笑とその大きな眼の輝き,そして労働者傷害保険局における永年の勤務によって確信させたのである。」
その後の父親の自殺,カフカの死,第二次大戦後の未決監への無実の収監という難局の中でも,その遺産は生きつづけたのだろう。それにしても思う。若くして,巨大な精神と遭遇することは,彼の人生にどんな巨大な翳を落したものか,と。
彼にとっては,カフカは,
「私という人間の掛替えのない本質を庇護する防壁なのである。彼は,その善意と思いやりと気取りのない誠意をもって,氷に閉ざされた私の自我の展開を促し,見守ってくれた当の人である」
という。だから,
「死後出版された作品」
を知らないし,読まないのである。
「わたしには,作家フランツ・カフカの小説や日記を読むことはできない。彼が私に疎遠であるためではない。彼があまりにも身近に思えるからである。青春の混迷とそれに続く内的外的な苦難,経験によって余すところなく打砕かれた幸福の観念,突然に襲い来った公権剥奪とそのため日増しに増大する内的外的の孤独化,こうした私の灰色の,心労と不安に破れ果てた日常そのものが,私を,忍耐と苦悩の人ドクトル・フランツ・カフカに固く結びつけていた。彼は私にとっては文学現象などというものではなかったし,今もその事情は変わらない」
フランツ・カフカを直に知り,頻繁に語り,その語り,振舞いに接してきた彼にとって,
「彼の書物より偉大」
な影響を,しみとおるように受けとったのである。彼は,ただ書く。
「わたしにはフランツ・カフカの書物を読むことはできない。彼の死後はじめて出版された遺稿を学ぶことに依って,私の内部に響いているその人となりの魅惑の余韻が弱まり,疎遠となり,ことによると失われてしまうことを怖れるからである。(中略)遺稿を讀むことによって,私のドクトル・カフカに対して取返しのつかない距離が生じはしまいか,私はそれを怖れるのである。何故なら,…フランツ・カフカは私にとって,抽象的で超個人的な文学現象ではないからである」
彼のカフカ像は,
「『変身』『死刑宣告』『村医者』『流刑地』,そして―私の知っている『ミレナ―への手紙』の作家は,すべて生けるものに対する首尾一貫した倫理的責任の告知者であり,プラーハの労働者傷害保険局の勤務に縛られた一役人の,一見平凡な役所生活において,最も偉大なユダヤの預言者たちの地上を蔽いつくす底の神と真実への憧憬とも紛う,あくなき灼熱の焰を降らせた一人の人間なのである。」
あるいは,彼は,わずか二年の間に,この世得るべきすべてを得てしまったのかもしれない。それもまた,奇跡に等しい。
参考文献;
G・ヤノーホ『カフカとの対話』(筑摩書房) |
|
奥行 |
|
古井由吉『この道』を読む。
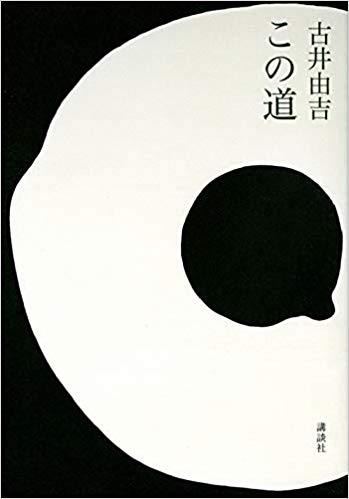
好きな作家の近作である。八十路を超えてなお,この旺盛な筆力はただ事ではない。二歳年長の健三郎は新作を書かなくなって久しいのに比べると,その筆力は際立つ。
古井由吉については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/423068214.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/395877879.html
で近作については触れたが,その作品構造については,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm#%E8%AA%9E%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
で分析したことがある。その特徴は,文体そのものが,皺のように,いくつもの現代過去未来が重なった言葉の奥行,
と,
作品そのものの語りの構造が,次々と入子のように次元を重ねていく作品世界の奥行,
と,二つの奥行にある,と思っている。
二つがこの作品集も僅かに残っている。処女作『木曜日に』で,
「私」は、宿の人々への礼状を書きあぐねていたある夜更け、「私の眼に何かがありありと見えてきた」ものを現前化する。
それは木目だった。山の風雨に曝されて灰色になった板戸の木目だった。私はその戸をいましがた、まだ朝日の届かない森の中で閉じたところだった。そして、なぜかそれをまじまじと眺めている。と、木目が動きはじめた。木質の中に固く封じこめられて、もう生命のなごりもない乾からびた節の中から、奇妙なリズムにのって、ふくよかな木目がつぎつぎと生まれてくる。数かぎりない同心円が若々しくひしめきあって輪をひろげ、やがて成長しきると、うっとりと身をくねらせて板戸の表面を流れ、見つめる私の目を眠気の中に誘いこんだ。
厳密に言うと、木目を見ていたのは、手紙を書きあぐねている〃とき〃の「私」ではなく、森の山小屋にいた〃そのとき〃〃そこ〃にいた「私」であり、その「私」が見ていたものを「私」が語っている。つまり、
①「私」について語っている〃いま〃
②「私」が礼状を書きあぐねていた夜更けの〃とき〃
③山小屋の中で木目を見ていた〃とき〃
④木目になって感じている〃とき〃
の四層が語られている。しかし、木目を見ていた〃とき〃に立つうちに、それを見ていたはずの「私」が背後に隠れ、「私」は木目そのものの中に入り込み、木目そのもののに〃成って〃、木目が語っているように「うっとり」と語る。見ていたはずの「私」は、木目と浸透しあっている。動き出した木目の感覚に共感して、「私」自身の体感が「うっとり」と誘い出され、その体感でまた木目の体感を感じ取っている。
こういう時間の折り畳まれた文章は,この作品集にはない。もう一つの作品構造の入子も,この作品集には,「たなごころ」にしか見られなくなっている。
僕は文体の,いくつもの次元を折り畳んだような複雑な語りもいいが,この作家の最大の特色は,語りの次元が次々と入れ替わり,入子のように複雑に語りの空間を折り重ねていく,語りの奥行が好きだ。それは,「哀原」で,典型的に見られた。
語り手の「私」は、死期の近い友人が七日間転がり込んでいた女性から、その間の友人について話を聞く。その女性の語りの中に、語りの〃とき〃が二重に入子となっている。
一つは、友人(文中では「彼」)と一緒にいた〃とき〃についての女性の語り。
お前、死んではいなかったんだな、こんなところで暮らしていたのか、俺は十何年間苦しみにくるしんだぞ、と彼は彼女の肩を掴んで泣き出した。実際にもう一人の女がすっと入って来たような、そんな戦慄が部屋中にみなぎった。彼女は十幾つも年上の男の広い背中を夢中でさすりながら、この人は狂っている、と底なしの不安の中へ吸いこまれかけたが、狂って来たからにはあたしのものだ、とはじめて湧き上がってきた独占欲に支えられた。
これを語る女性の語りの向う側に、彼女が「私」に語っていた〃とき〃ではなく、その語りの中の〃とき〃が現前する。「私」の視線は〃そこ〃まで届いている。「私」がいるのは、彼女の話を聞いている〃そのとき〃でしかないのに、「私」は、その話の語り手となって、友人が彼女のアパートにやってきた〃そのとき〃に滑り込み、彼女の視線になって、彼女のパースペクティブで、〃そのとき〃を現前させている。「私」の語りのパースペクティブは、彼女の視点で見る〃そのとき〃を入子にしている。
もう一つは、女性の語りの中で、男が女性に語ったもうひとつの語り。
或る日、兄は妹をいきなり川へ突き落とした。妹はさすがに恨めしげな目で兄を見つめた。しかしやはり声は立てず、すこしもがけば岸に届くのに、立てば胸ぐらいの深さなのに、流れに仰向けに身をゆだねたまま、なにやらぶつぶつ唇を動かす顔がやがて波に浮き沈みしはじめた。兄は仰天して岸を二、三間も走り、足場の良いところへ先回りして、流れてくる身体を引っぱりあげた。
と、そこは、「私」のいる場所でも、女性が友人に耳を傾けていた場所でもない。まして「私」が女性のパースペクティブの中へ滑り込んで、その眼差しに添って語っているのでもない。彼女に語った友人の追憶話の中の〃そのとき〃を現前させ、友人の視線に沿って眺め、友人に〃成って〃、その感情に即して妹を見ているのである。
時間の層としてみれば、「私」の語る〃とき〃、彼女の話を聞いている〃とき〃、彼女が友人の話を聞いている〃とき〃、更に友人が妹を川へ突き落とした〃とき〃が、一瞬の中に現前していることになる。
また、語りの構造から見ると、「私」の語りのパースペクティブの中に、女性の語りがあり、その中に、更に友人の語りがあり、その中にさらに友人の過去が入子になっている、ということになる。しかも「私」は、女性のいた〃そのとき〃に立ち会い、友人の追憶に寄り添って、「友人」のいた〃そのとき〃をも見ている。〃そのとき〃「私」は、女性のいるそこにも、友人の語りのそこにもいない。「私」は、眼差しそのものになって、重層化した入子のパースペクティブ全てを貫いている。
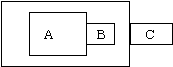
いってみれば,語り手は,C,B,Aのそれぞれの語りの時間を,自在に行き来言する。この「哀原」を彷彿とさせたのが,「たなごころ」であった。
あの石を,とうとう拾って来なかったな,と病人は悔やむように言った。
とはじまる文章は,語り手は病人の譫言を聴いていたはずである。しかし,いつの間にか,その病人自身になって(いるかのように),
さきのほうを行く人の姿が樹間に遠くなったり近くなったりする。
と,山を登る若者の視点に移り,
ひとりになった。老人の腰をおろしていた石の上をあらためて眺めると,左の脇のほうに,掌の内におさまるほどの小石がある。そこに置かれたように見えた。黒く脂光りするまるい石だった。手に取れば温みが残っている。(中略)
この日のささやかな記念に持って帰ろうかと考えたが,間違いもあることだろうからと思いなおして,石を元のところにそっともどし,腹もまだすいていないので,もうひとつ先の峠を目あてに,尾根づたいの道を取ることにした。
と,冒頭の取ってこなかった「石」の話で締めくくる。かつてのような意識的な視点の移動というよりは,その思いを代弁しているような軽みがある。作品集全体に,語られているのが,死や病でありながら,どこか軽みがあるのも,同じかも知れない。どちらかというと,かつての文体の方が好きなのだが。
参考文献;
古井由吉『この道』(講談社) |
|
日本社会の祖型 |
|
水林彪『封建制の再編と日本的社会の確立』を読む。
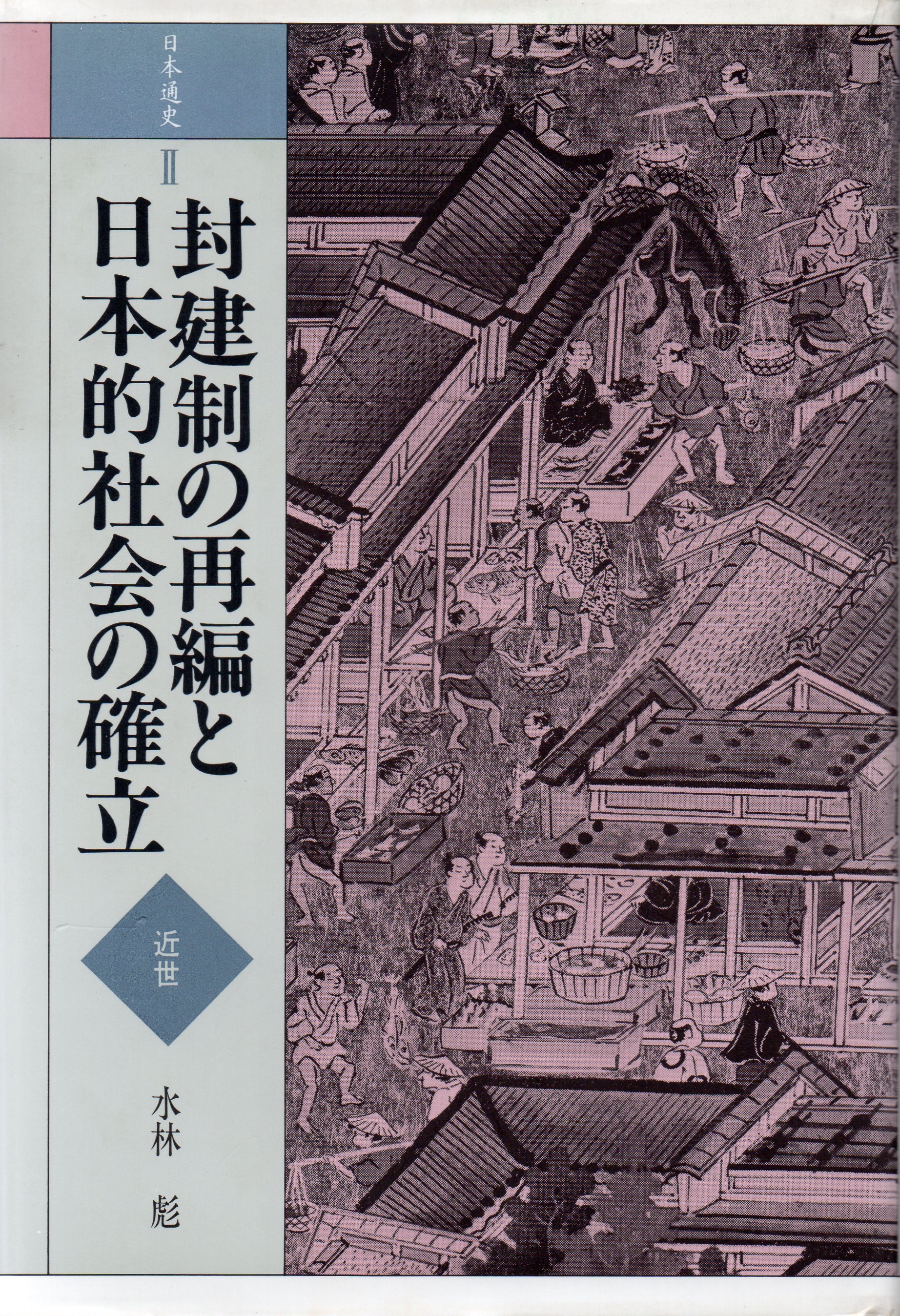
本書は日本通史の中の一巻で,戦国時代(十六世紀)から江戸末期(十九世紀半ば)までの四百年間を扱う。そのテーマは,表題,
封建制の再編と日本社会の確立,
である。二つのテーマが語られている。一つは,
封建制の再編,
である。その意味は,第一に,
「戦国大名権力の形成に始まり,,統一権力と其の下での幕藩制的大名権力の成立に至る歴史が,中世封建制を再編成し,封建制をよりいっそう強固に再構築する過程であった」
こと,具体的には,
「畿内近国の戦国大名織田信長の権力が成長・発展し,後継の豊臣権力において,戦国大名権力が幕藩制的大名権力へ,さらには他の戦国大名を幕藩制的大名権力へと強制的に鋳直すところの統一権力へと飛躍するという形で現出した」
その意味の第二は,
「織田・豊臣権力,その跡を継いだ徳川権力の全国統一権力が,戦国大名権力を含む戦国社会全体を再編成し,戦国大名権力とは質的に区別される幕藩制的な質をもって封建制を再構築した」
それは,端的には,
兵農分離,
を基礎とする封建制を打ち立てた,ということである。それは,すべての武士が,大名から下々の武士までが,
鉢植化,
し,本領を喪失したことだ。その嚆矢は,後北條滅亡後の関東六カ国へ国替えされた徳川家康に見ることが出来る。
「国替えは,豊臣権力の徳川大名権力に対する介入であり,秀吉の家康に対する支配を強化する措置であったが,このことは,徳川氏が家臣団に対して支配を強めてゆく重要な画期」
でもあった。具体的には,
「家臣団の本領の喪失と新領国での上からの知行割…によって土着の領主・土豪層は,いわば鉢植えの武士となった」
のである。同時に,太閤検地によって測り直された知行地の石高は,その武士が,
「負担する軍役量は宛行われた石高を基準として決せられる」
ことになる(たとえば,知行石高百石について五人の動員という比率で軍役を課された)。つまり,封建制の再編とは,
「全国土はいったんは秀吉(後には徳川)のものとなり,それがあらためて諸大名に恩給される」
という形を取り,
「父祖伝来の本領地の否定を意味し,さらに,領主と領民との個別的な人的支配従属関係(被官主−被官関係)の禁止を意味する」
のである。鉢植化とは,もはやすべての武士がその土地への所有権を失っているということである。それなのに,落下傘のように転封された大名が,その土地の主である農民から当然の如く年貢を徴収する仕組みということである。
本書のもう一つのテーマ,
日本的社会の確立,
の第一の意味は,
「戦国期から統一権力の形成期にかけての封建制の再編成・再構築が,例えば,西欧の封建制の歴史と比較して独特であり,その結果としてできあがった幕藩体制が特殊日本的な性格を有しているということである。」
さらに,幕藩体制は,
「同時代の中国とも根本的に異なるものであった」
ことである。
第二の意味は,
「近現代の日本社会の祖型が,近世社会,特にその後半期の幕藩体制社会のうちに見いだされる」
ことである。たとえば,
「人々が,家族・村・企業などの諸団体に強く組み込まれていること,それらの諸団体が緊密に統合される形で国家が成り立っていることが挙げられるが,このような秩序の形式的特徴,すなわち人々の中間諸団体への強い組み込まれ現象と中間団体を介しての緊密な国家的統合は,実はすでに幕藩体制において確立していた」
ことであり,さらに,国家,そして,これと関連する法についての観念に関しても,
「今日の日本人には,法といえば,人の権利を守るもの斗りも,国家が人々の自由を束縛するための命令と観念する人が多く,それでいて,国家を拘束する法よりも,自由に行政活動を行う国家に対して信頼を寄せるという現象が強くみられるが,そのような国家や法についての観念は,幕藩体制において,それ以前の中世的法観念を否定することによって確立したものである」
という。戦国期にあったのは,
非理法権大,
という観念であった。
非は非道,理は道理,法は法度,権は権力,天は天道,
権力は天道に反すれば滅ぶ,
というものであり,中世には,ムラは,
自力救済,
という,
「ムラどうしが領主権力を排して紛争を解決する」
秩序を有していた。幕藩体制はその否定の上に成立している。今日,まだ,
お上意識,
が根強く,お上に逆らうことに抵抗する心性,いわば,
奴隷心性,
は,豊臣,徳川と続き,その土壌の上に成り立った明治にも引き継がれた体制の「蒙古斑」に思えてならない。
参考文献;
水林彪『封建制の再編と日本的社会の確立』(山川出版社) |