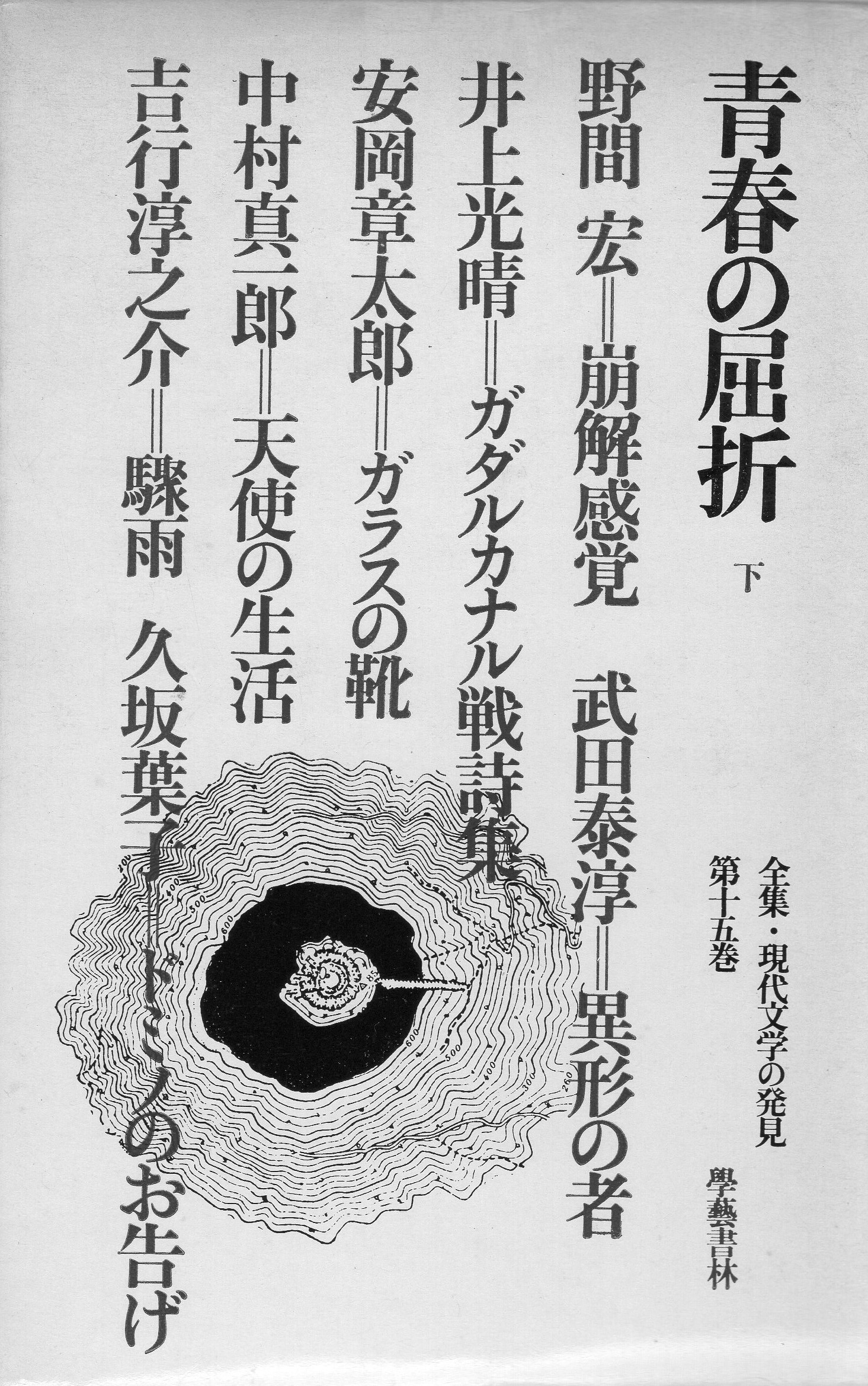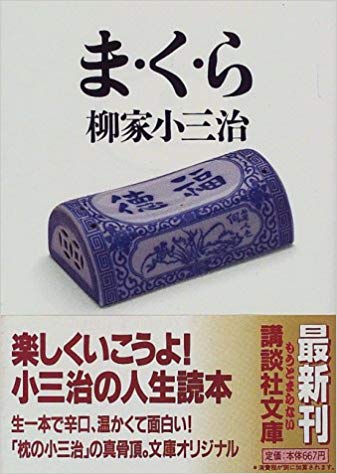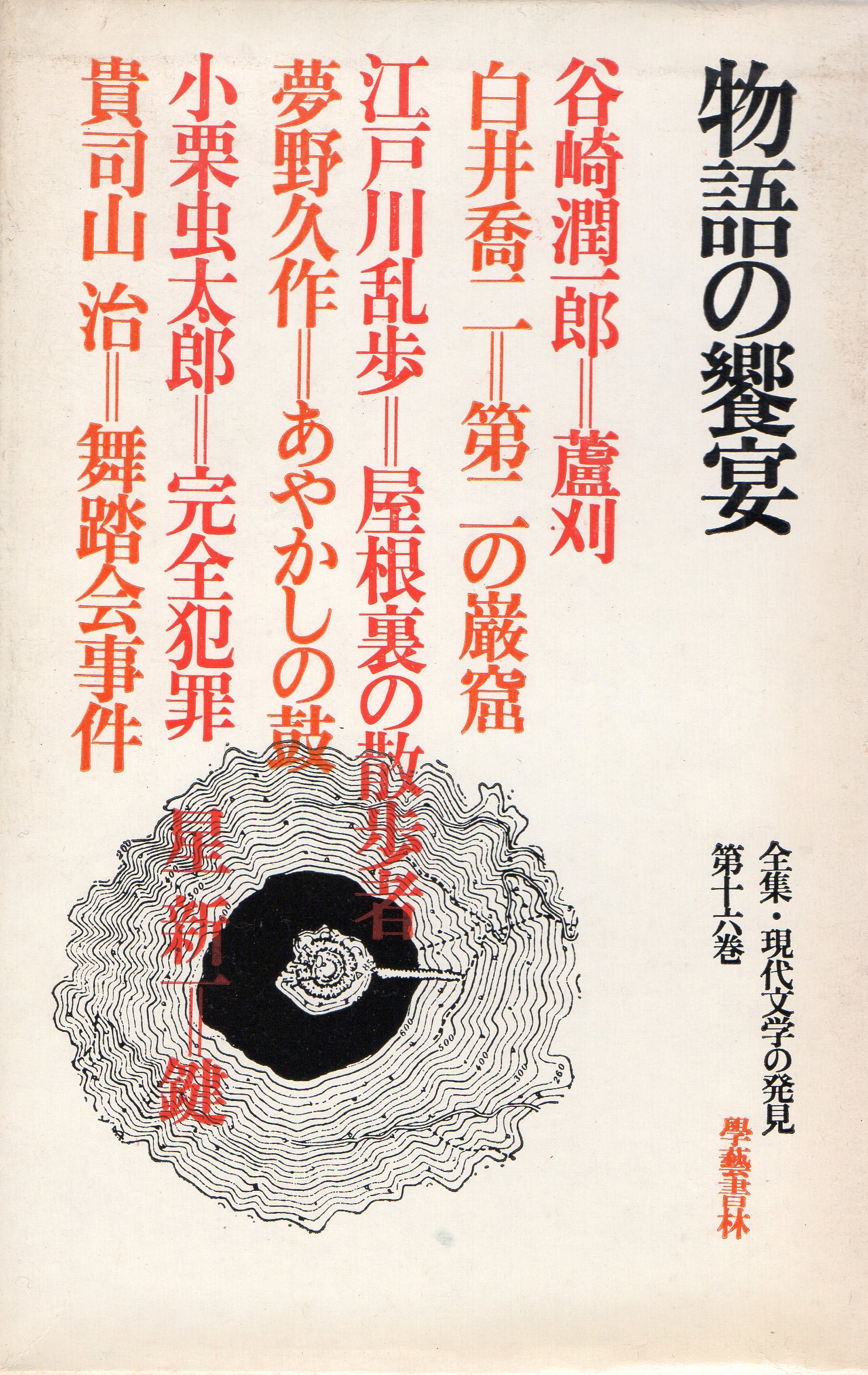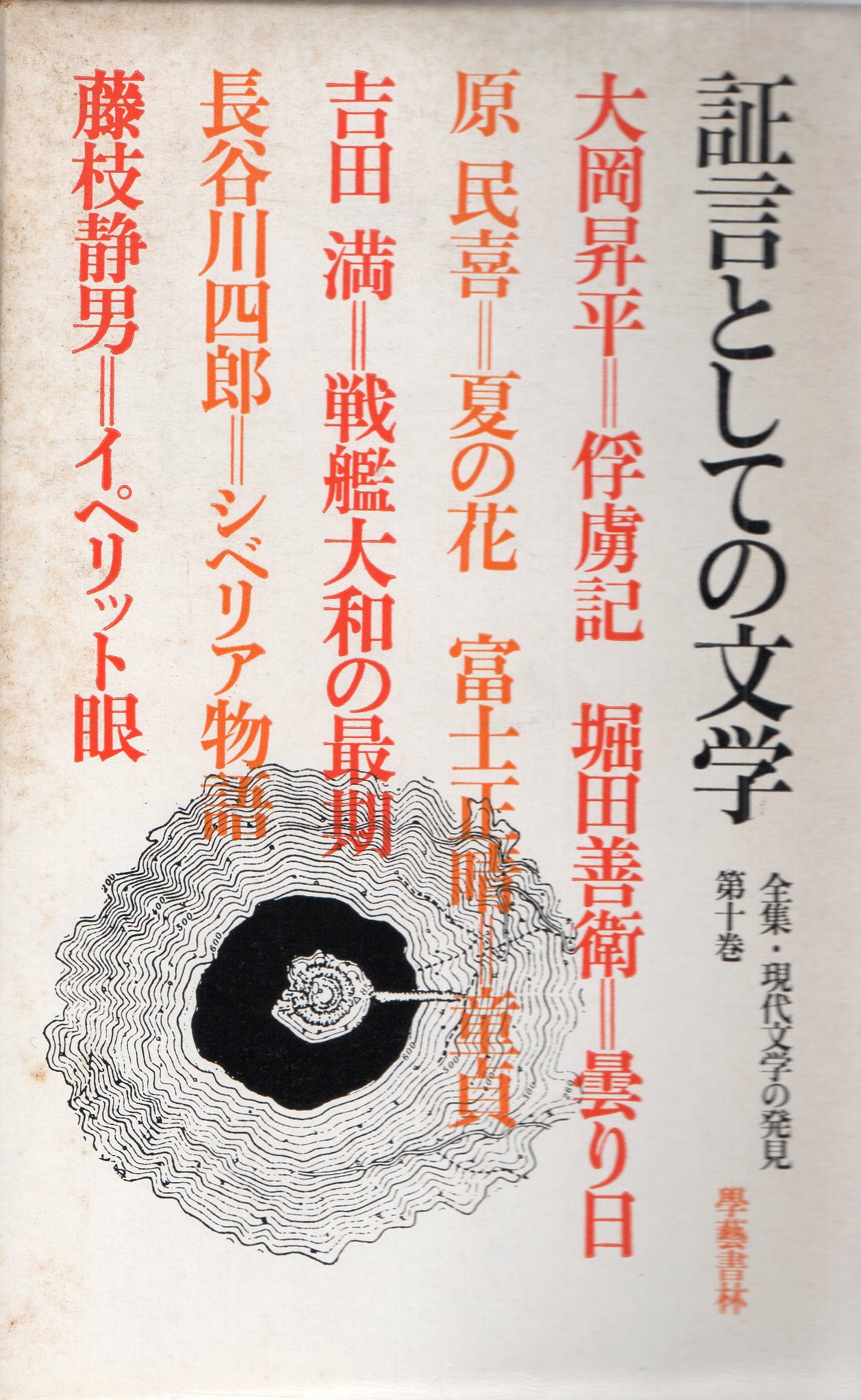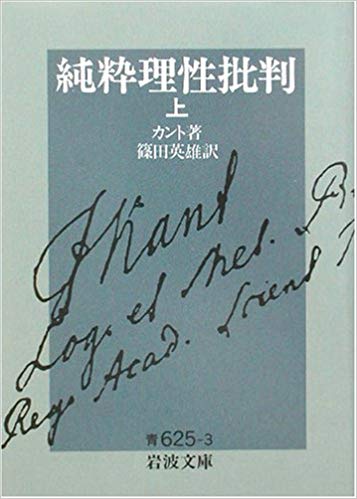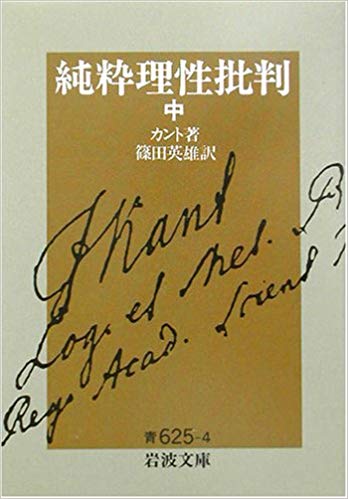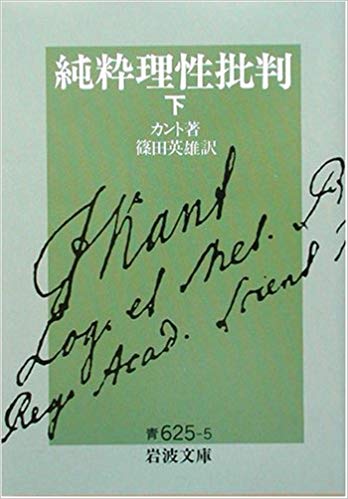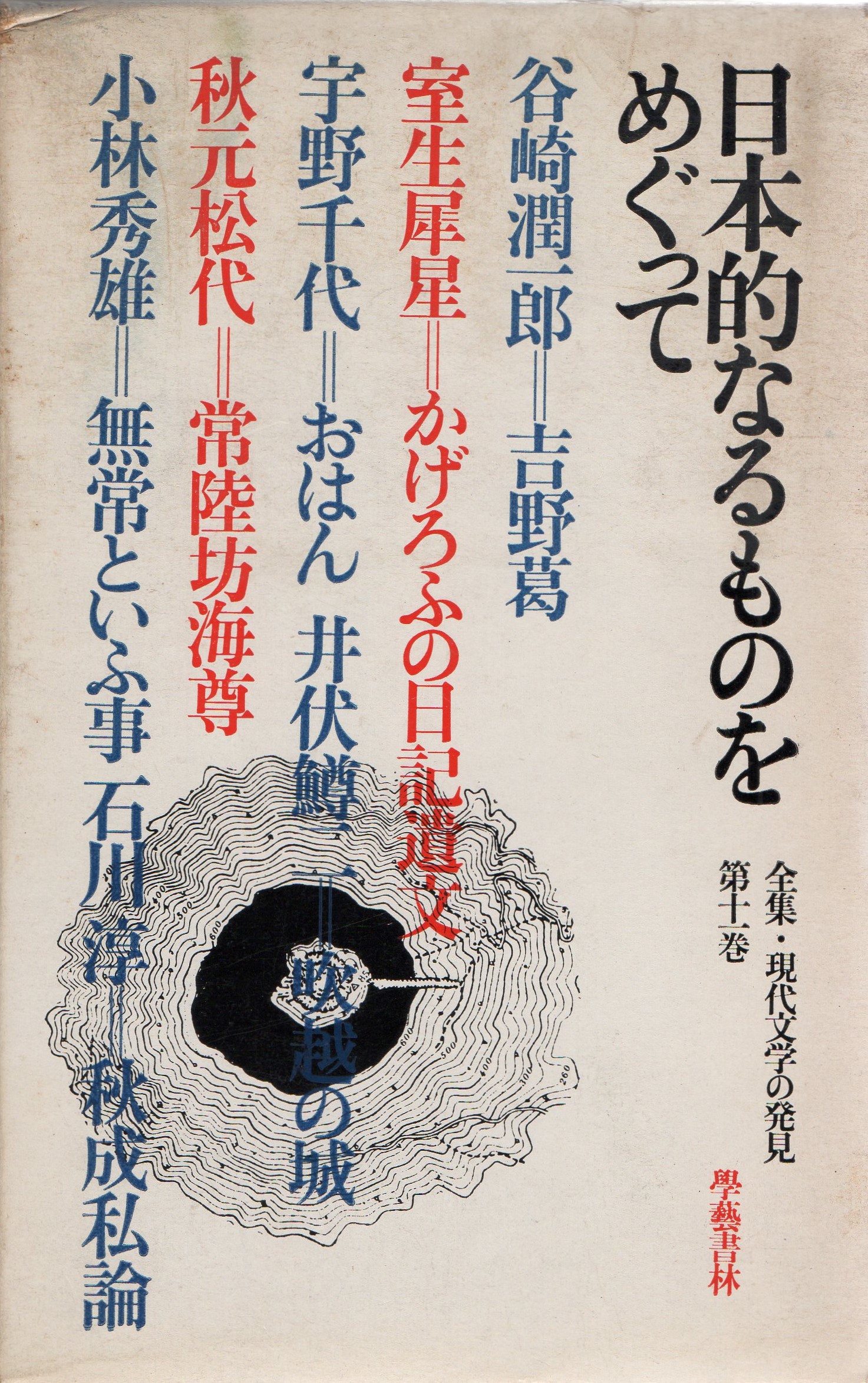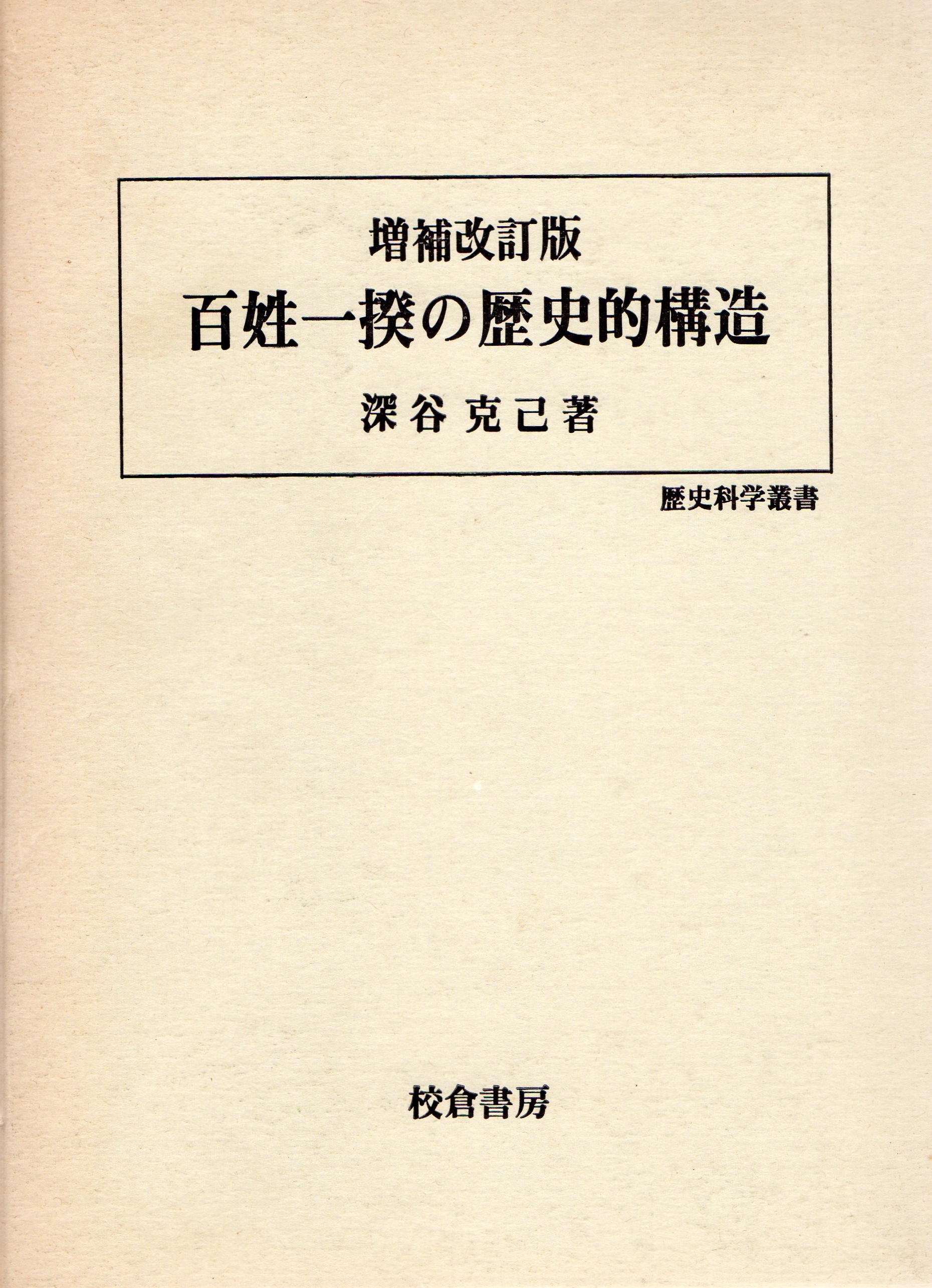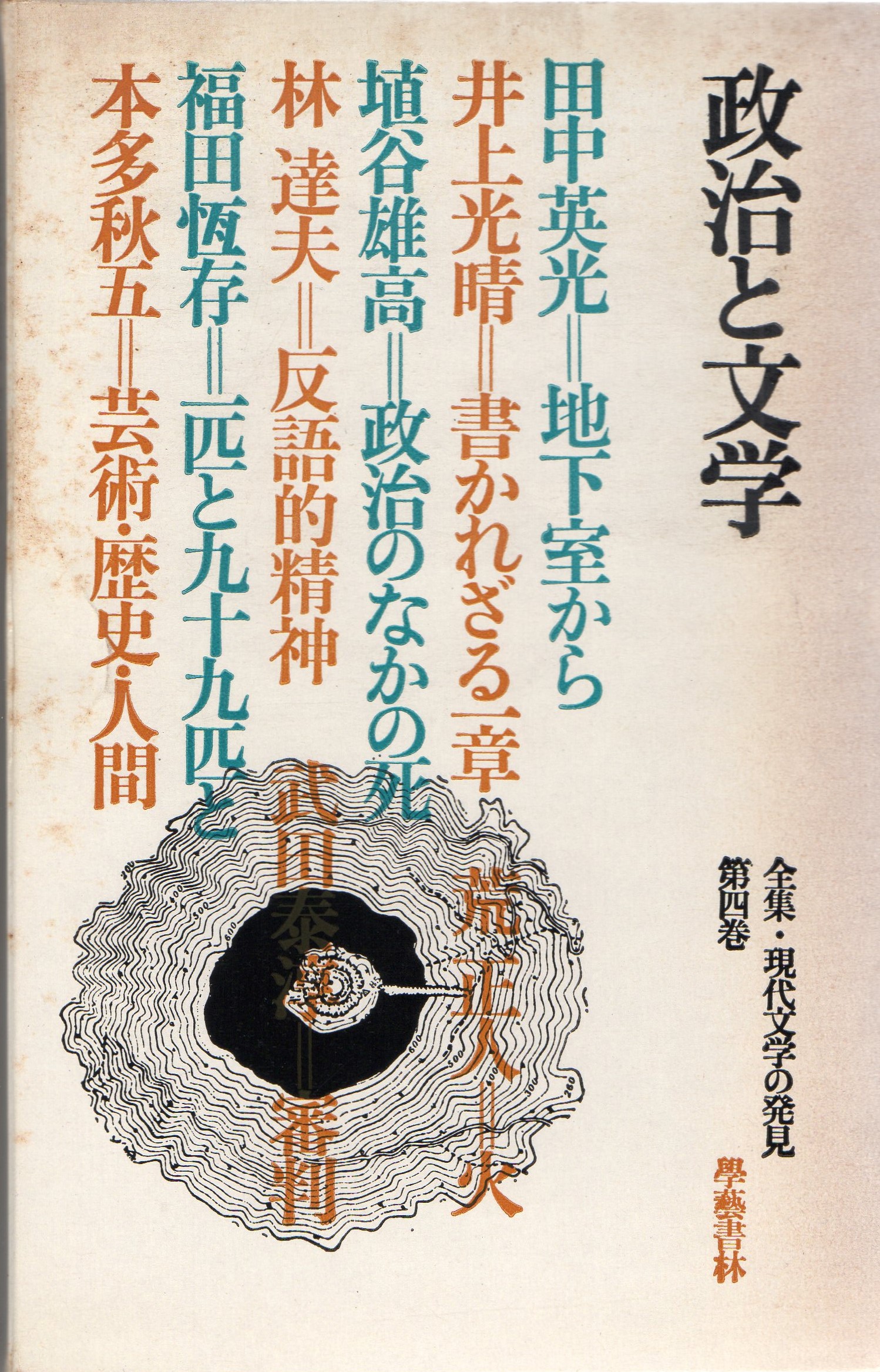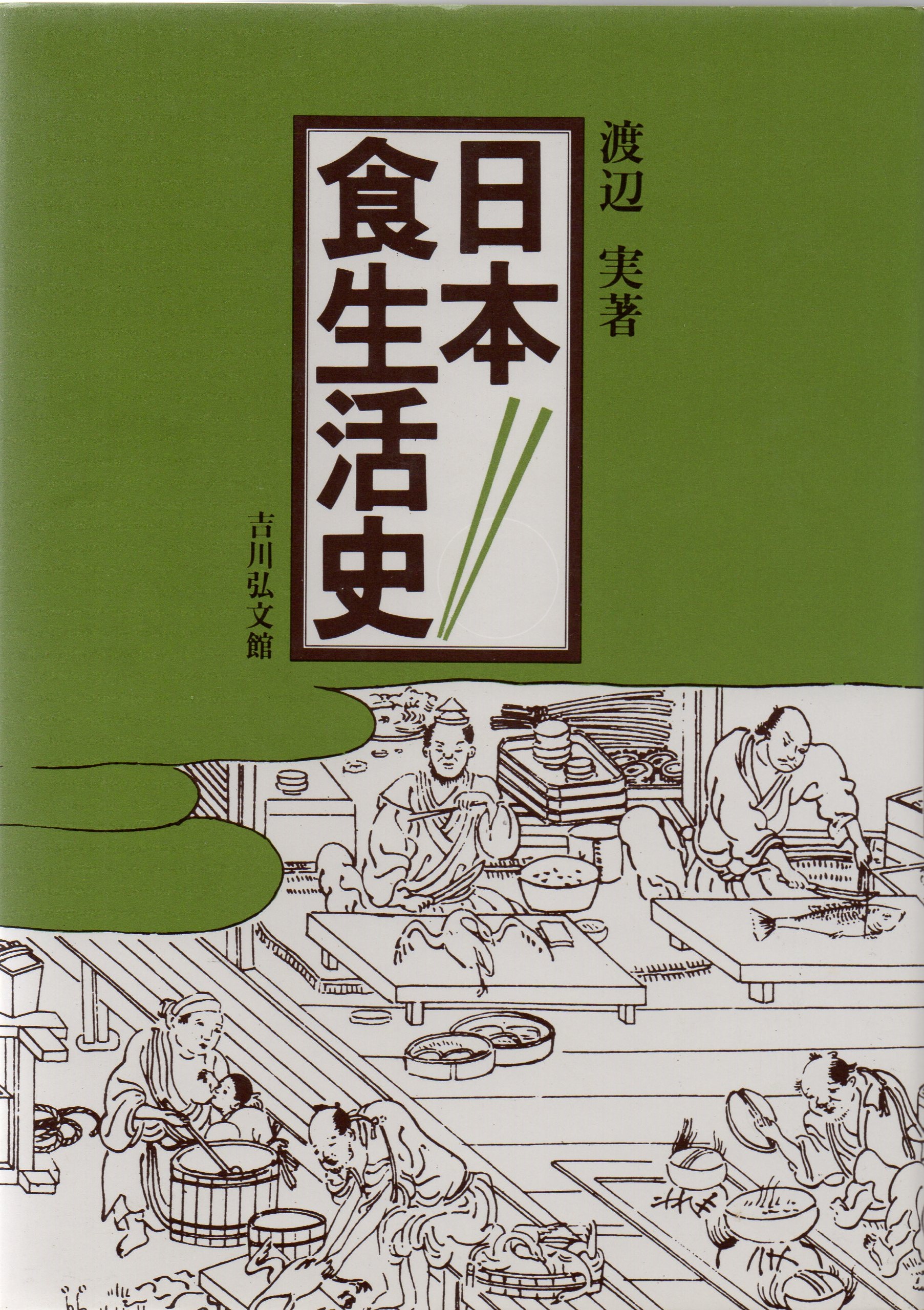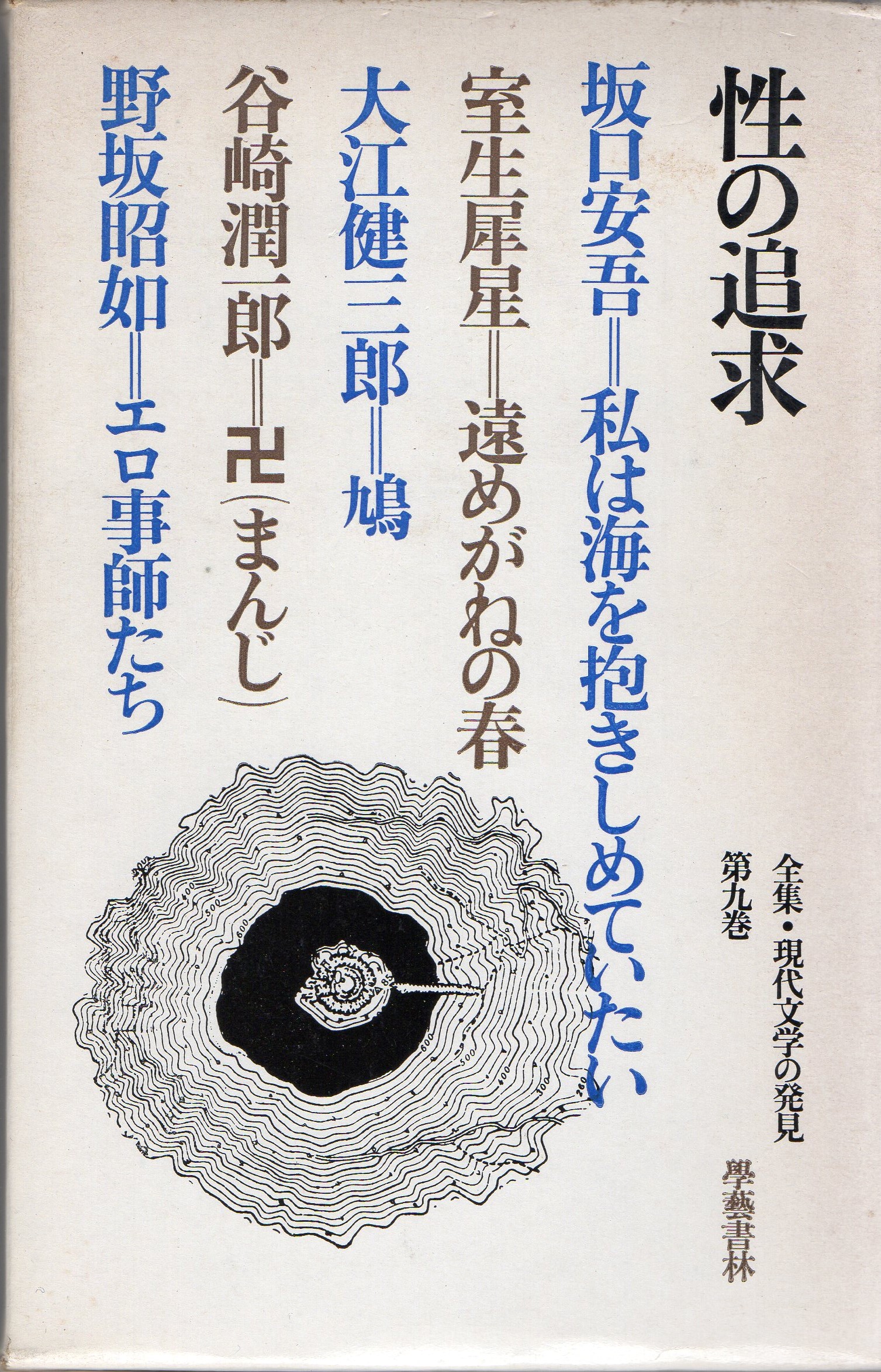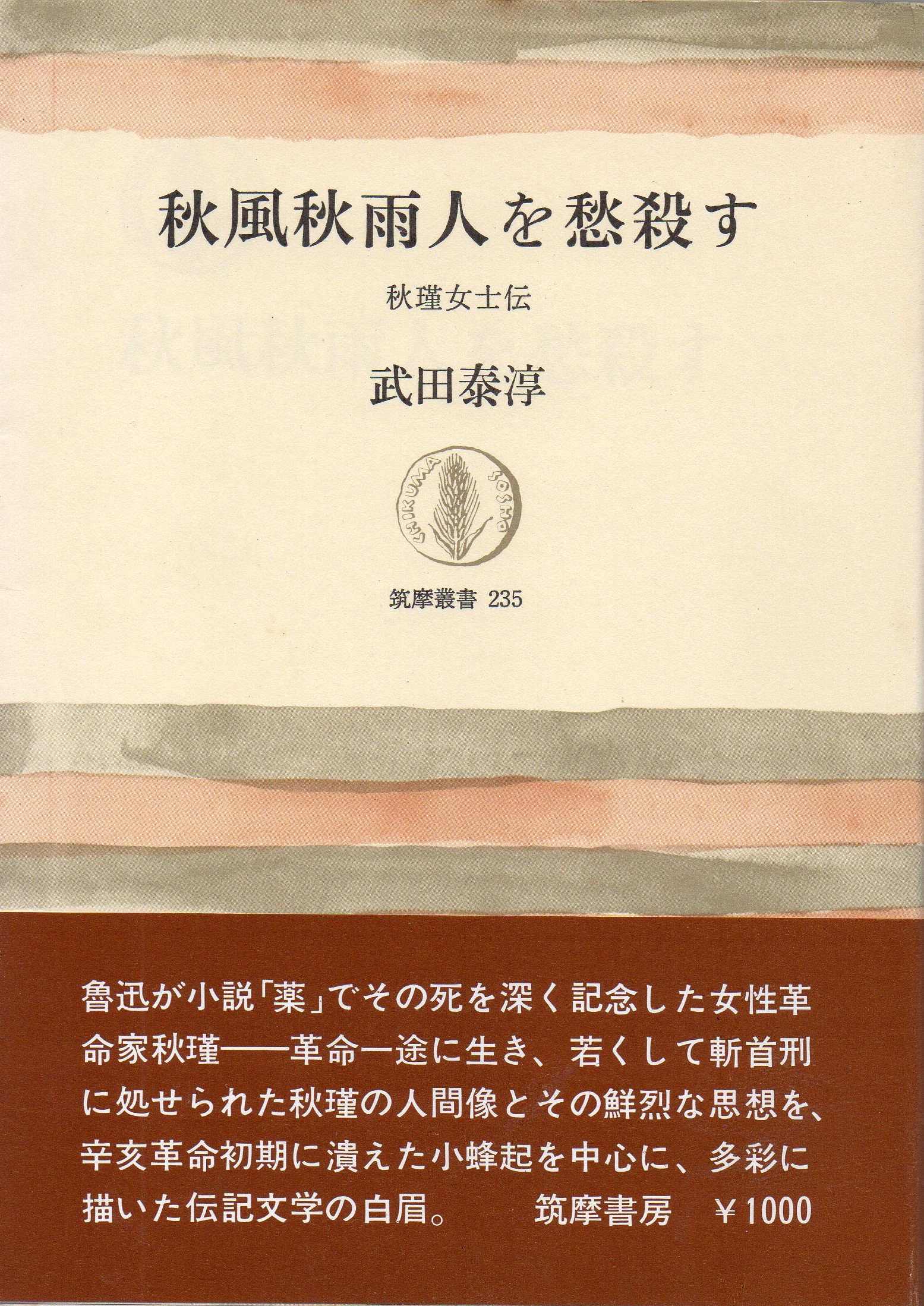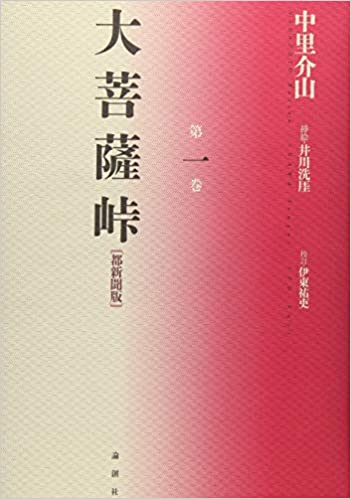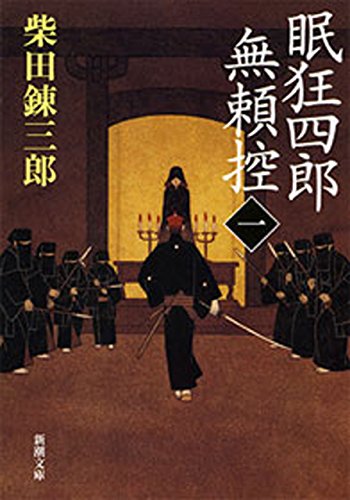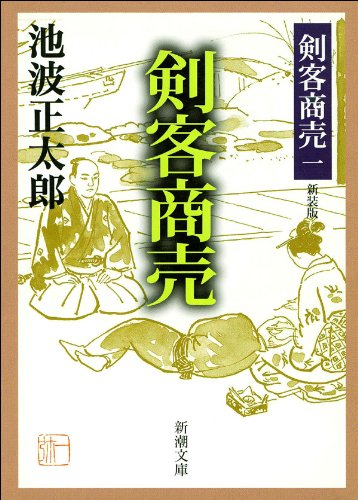|
大岡昇平他編『青春の屈折下(全集現代文学の発見第15巻)』を読む。
現代文学の発見、 |
|
柳家小三治『ま・く・ら』『もひとつま・く・ら』を読む。
柳家小三治は、噺の導入部である「マクラ」が抜群に面白いことでも知られ、「マクラの小三治」との異名も持つ。全編がマクラの高座もあるとか。 「まくら」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/421083802.html)、 「気っ風」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473027032.html?1578515555)、 で触れたことと重なるが、 まくら、 は、その演目に合ったものをするが、基本的には、 演じる落語の演目に関連した話をする、 現代ではほとんど使われなくなった人、物、様子などの解説をする、 2種類が骨格で、それにいろいろまぶす結果、いろいろな話が加えられるらしい。小三治のように、 まくらだけで高座が終わる、 ということもあるが、そこまで行くと、本題に入らなくて(そこで終わらないで)、このまま続けてほしい、と(観客側が)いうほどの、まくら自体が、 エンターテイメント、 になっているからかもしれない。しかし、それは、噺家としての力量が前提で、個人的には、まくらでその力量が見える気がする。 「マクラは、噺の本題とセットになって伝承されてきているものが少なくない」 という。しかし、素人ながら、マクラの果たす役割は、ただ、 現実(この会場のこの時、この場)と噺の世界、 をつなぐ、 回路 というか、 異次元を開くまじない(「開けゴマ」みたいな)、 というだけではない気がする。もちろん、そういう意図があるにはあるが、僕は、いま、噺をしようとしている噺家その人が、その導き手で、その人の口先に乗って、一緒に噺の世界へ入って行くための、 協約関係、 というか、 共同作業関係、 というか、 同盟関係、 というか、 違う言い方をすると、 この(噺の)船頭の船に乗ってついて行っても大丈夫、 という見立ての位置づけにあるのではないか、という気がする。独演会が多いので、初めから、その噺家を目当てに出かける場合、それは不必要に見えるかもしれないが、寄席で、次々と噺家がとっかえひっかえ(失礼、入れ代わり立ち代り)登壇する場面を想定すると、 まくら、 は、ある意味、リアルに噺家の人柄と力量とを見極める手がかりになっているのではないか、という気がする。 「マクラはお客さんが本編に入りやすい状態にほぐす役割を兼ねているのです。このマクラは落語にとって前フリなのです。また、マクラは『話す』のではなく、『振る』といいます。なぜなら、まずはこのマクラでお客さんを『振り向かせる』ということでしょう。」 とある。しかし、当たり前だが、まくらにその噺家の技量と力量と器量が反映している。これも、前にで書いたが、 まくら、 に個性があり、人柄が出る、というよりも、噺そのものに人柄が出るというか、極端に言うと、噺が、 人柄で変る、 という意味では、「まくら」は、その人柄のリトマス試験紙なのかもしれない。しかし、活字で読むのは、「まくら」の内容で、本来、 その場、 その時、 その雰囲気、 を共有するその時その場の観客と共に、聞かなければ、口調も、テンポも、声音もわからない。それでも本書は可笑しい。著者自身が、「あとがき」で、 「たしかに自分で高座でしゃべったものには違いないのだけれど。聞いて下さっているお客さんは興味を持って眼を輝かせたり、わらってくれてはいましたよ。その反応に乗せられてついつい長い枕話になったり、だけどそれは、その時その時空間に消えてしまう私とお客さんとの瞬間瞬間の共有時間であり、お互いのその場限りの楽しい時間、としてのおしゃべりだったのです」 と本人自身が語っている通り、本来活字化されるはずのないものが活字化された。それでも、 「読んでみると自分ながら面白ぇこというヤツだなァコイツァ。と笑っちゃったりして。とてもみっともない」 と書いているほどではあるのだが。 読み通してみて感じたのは、たぶん、その場では、この何十倍もおかしかったであろうことは、たしか、 めりけん留学奮闘記、 を当時NHKで観たときの、捧腹絶倒をよく記憶しているので、想像がつく。 ニューヨークひとりある記、 玉子かけ御飯、 駐車場物語、 ミツバチの話、 熊の胆の話、 小さんにも事務員さんにもなる名前、 笑子の墓、 パソコンはバカだ!! 等々、別に作り話ではなく、 「ここに載ってるのは全部自分が実際に出会ったり感じたことばかり、そのまんま。第一、枕としてしゃべっているということは、『このあとは落語をおしゃべりさせていただきますよ』という前提があっての枕ですから」 とある通り(あとがき)自身の体験を話しているだけだが、なぜが可笑しい。句会の仲間でもある故小沢昭一は、 「ある一つの材料を語るのに、もう根ほり葉ほり、いろんな角度から、しつこくイジル。腰をすえて、ああもこうも、オモシロイことを見つけてこだわっていく。そういうネバッコイ話運び」 が真骨頂と、評する。オーディオ、オートバイ、塩、熊の胆、ハチミツ等々、それがそのまま話になっていく。 ふと、僕は、 お伽衆、 のことを思い出した。御伽衆(おとぎしゅう)は、 「室町時代後期から江戸時代初期にかけて、将軍や大名の側近に侍して相手をする職名である。雑談に応じたり、自己の経験談、書物の講釈などをした人。御迦衆とも書き、御咄衆(おはなししゆう)、相伴衆(そうばんしゅう)などの別称もあるが、江戸時代になると談判衆(だんぱんしゅう)、安西衆(あんざいしゅう)とも呼ばれた。」 とある(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%BC%BD%E8%A1%86#cite_note-ko-1)。 咄(はなし)相手を主としたから御咄衆とも言うが、正確には御伽衆の中に御咄衆が含まれる。御伽衆は、語って聞かせる特殊な技術のほか、武辺談や政談の必要から相応の豊富な体験や博学多識、話術の巧みさが要求されたため、昔のことをよく知っている年老いた浪人が起用されることが多かった、ともある(仝上)。 慶長年間(1596年‐1615年)に御伽衆の笑話を編集した『戯言養気集』(ぎげんようきしゆう)には、 「御伽衆の講釈話が庶民に広がって江戸時代以降の講談や落語の源流となったとも言われるので、御伽衆は落語家の祖でもある」 と、まさに、落語の先祖である。豊臣秀吉の御伽衆の一人、 曽呂利新左衛門、 は、実在を疑われているが、 「落語家の始祖とも言われ、ユーモラスな頓知で人を笑わせる数々の逸話を残した。元々、堺で刀の鞘を作っていて、その鞘には刀がそろりと合うのでこの名がついたという(『堺鑑』)。架空の人物と言う説や、実在したが逸話は後世の創作という説がある。また、茶人で落語家の祖とされる安楽庵策伝と同一人物とも言われる。」 とある(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BD%E5%91%82%E5%88%A9%E6%96%B0%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80)。こんな逸話がある、とか。 秀吉が、猿に顔が似ている事を嘆くと、「猿の方が殿下を慕って似せたのです」と言って笑わせた。 秀吉から褒美を下される際、何を希望するか尋ねられた新左衛門は、今日は米1粒、翌日には倍の2粒、その翌日には更に倍の4粒と、日ごとに倍の量の米を100日間もらう事を希望した。米粒なら大した事はないと思った秀吉は簡単に承諾したが、日ごとに倍ずつ増やして行くと100日後には膨大な量になる事に途中で気づき、他の褒美に変えてもらった。 御前でおならをして秀吉に笏で叩かれて、とっさに「おならして国二ヶ国を得たりけり頭はりまに尻はびっちう(びっちゅう)」という歌を詠んだ。 ある時、秀吉が望みのものをやろうというと、口を秀吉の耳に寄せた。諸侯は陰口をきかれたかと心落ち着かず、新左衛門に山のような贈物を届けたという。 等々(仝上)。この曽呂利に擬されているのは、落語の祖とされる、 安楽庵策伝、 で、安楽庵策伝が京都所司代の板倉重宗に語った話をもとに作られたのが、元和9年(1623年)の、 『醒睡笑』 である。収載された話は約1、000話に及び、 「収載された話は最後に落ち(サゲ)がついており、策伝はこの形式で説教をしていたと考えられている。『醒睡笑』には現在の小咄(短い笑い話)もみられ、また、この本に収載された話を元にして『子ほめ』『牛ほめ』『唐茄子屋政談』『たらちね』など現在でも演じられるはなしが生まれているところから、策伝は『落語の祖』といわれる」 のである(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BD%E8%AA%9E)。 なにやら、小三治の「まくら」を読むと、軽口・頓智に富み、狂歌の達人として人気者だったという、 曽呂利新左衛門、 のことを思い出す。本書所収の、 めりけん留学奮闘記、 ニューヨークひとりある記、 玉子かけ御飯、 駐車場物語、 は、まさに御伽衆の笑話を思い出させる。 参考文献; 柳家小三治『ま・く・ら』(講談社文庫) 柳家小三治『もひとつま・く・ら』(講談社文庫) 野村雅昭『落語の言語学』(平凡社選書) |
|
大岡昇平他編『物語の饗宴(全集現代文学の発見第16巻)』を読む。
本書は、 |
|
大岡昇平他編『証言としての文学(全集現代文学の発見第10巻)』を読む。
と題された全16巻の一冊としてまとめられたものだ。この全集は過去の文学作品を発掘・位置づけ直し、テーマごとに作品を配置するという意欲的なアンソロジーになっている。本書は、 証言としての文学、 と題された巻である。収録されているのは、 大岡昇平『俘虜記』 原民喜『夏の花』 吉田満『戦艦大和の最期』 長谷川四郎『シベリヤ物語』 藤枝静男『イペリット眼』 富士正晴『童貞』 堀田善衛『曇り日』 石上玄一郎『発作』 西野辰吉『C町でのノート』 木下順二『暗い火花』 開高健『裁きは終わりぬ』 梅崎春生『私はみた』 広津和郎『松川裁判について』 秋山駿『想像する自由』 李珍宇『手紙』 である。 開高健『裁きは終わりぬ』は、アイヒマン裁判、梅崎春生『私はみた』はメーデー事件、広津和郎『松川裁判について』は松川裁判の、それぞれ傍聴記録、証言、論証である。しかし、ノンフィクションであれ、フィクションであれ、日記であれ、見聞録であれ、いずれ、カメラで言うなら、フレームを決めた画像でしかない。フレームを決めた瞬間画像は客観的ではない。その瞬間、大なり小なり、私的パースペクティブを免れないのである。その意味で、 証言としての文学、 などというものは成り立たない。文学が、 思想の伝達手段、 でないように(プロレタリア文学をめぐる茶番で実証済み)、 事実の証言手段、 でもあり得ない。文学は、 虚実皮膜、 の時空にある。意識的に虚構を立てるのと、意識的に事実を語ろうとするのとは、程度の差でしかない。 ぼくは、どんな情報も、大なり小なりフェイク、であると思っていて、そのことは、 「言葉の構造と情報の構造」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0924.htm) で触れた。つまり、 それがフィクションであれノンフィクションであれ、 証言であれ偽証であれ、 事実の報告であれ虚報であれ、 発信者が、事実と思っていることを、自分の観点から言語化しているにすぎない。それは、意識的に嘘を報告することと、程度の差でしかない。 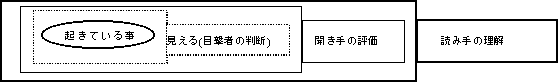 事実そのものは、情報にはなり得ない。ユカタン半島に巨大隕石が落ちても、それを人が情報化するまで、それは人に伝わることはない。だが、それが情報化(フィクション化であれノンフィクション化であれ、科学レポートであれ娯楽情報であれ)されたとき、 「情報は発信者のパースペクティブ(私的視点からのものの見方)をもっている。発信された『事実』は,私的パースペクティブに包装されている(事実は判断という覆いの入子になっている)」 のである(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod092.htm)。だから、 証言としての文学、 などというタイトルは、 自家撞着、 以外の何物でもない。そのことを、本作品群が、例証している。 あとは、文学として、 虚実の皮膜、 で自立しているかどうかだけだ。事件や現実に依拠している限り、作品世界は自立していない。その意味では、 李珍宇『手紙』 は作品ではない。 収録されたものの中で、作品として、自立できているのは、 大岡昇平『俘虜記』 原民喜『夏の花』 吉田満『戦艦大和の最期』 長谷川四郎『シベリヤ物語』 藤枝静男『イペリット眼』 富士正晴『童貞』 堀田善衛『曇り日』 石上玄一郎『発作』 西野辰吉『C町でのノート』 木下順二『暗い火花』 である。突出しているのは、 大岡昇平『俘虜記』 である。ある意味で、私的フレームの中で、ひとつの作品世界を自立せしめている。戦後の出発点にふさわしい、といっていい。 石上玄一郎『発作』 も、この作家らしい構造化された作品だが、僕にはこの人がいつも作りすぎる虚構に、嘘を感じてしまう。その意味では、自立が状況に依存している、と思わせる。 長谷川四郎『シベリヤ物語』 は、独特の雰囲気を醸しだしている。シベリア抑留中の俘虜生活を描きながら、どこかメルヘンのようにふんわりした雰囲気を作りだしている。それは、作家の視点にあると思う。たしか、チャップリンが、 人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ、 といったことを思い出す。別に描写の視点が俯瞰にあるのではなく、作家の登場人物に対する距離の置き方が、ロングショットであることによる。あるいは、変な言い方だが、作家の感情は遠くにおいて、ひとごとのように、書いている。 昔々あるところに、 と同じ語り口である。悲惨さは、その距離で漉されている。 吉田満『戦艦大和の最期』 は、日記の体裁をとりながら、 片仮名表記、 と、 文語体表記、 で、一定の距離感をもち、多少情緒過多ながら、一応の日録の体裁を保ち、自立する世界を保ち続けている。しかし、『戦艦大和の最期』の、 「初霜」救助艇ニヒロワレタル砲術士、左ノゴトク洩ラス、 として、最後に追加した文章、 救助艇タチマチニ漂流者ヲ満載、ナオモ追加スル一方ニテ、スデニ危険状態ニ陥ル 更ニ収拾セバ転覆避ケ難ク(中略)シカモ舩ベリニカカル手ハイヨイヨ多ク、ソノ力激シク、艇ノ傾斜、放置ヲ許サザル状況ニ至ル ココニ艇指揮オヨビ乗組下士官、用意ノ日本刀ノ鞘ヲ払イ、犇ク腕ヲ、手首ヨリバッサ、バッサト斬リ捨テ、マタハ足蹴ニカケテ突キ落トス…… について、 初霜短艇指揮官・松井一彦の反論や、吉田に削除を求める書簡、 があり(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E8%89%A6%E5%A4%A7%E5%92%8C%E3%83%8E%E6%9C%80%E6%9C%9F)、また、大和乗組員の生き残り八杉康夫が、 内火艇は船縁が高くて海面に顔を出している様な漂流者の手は届かないから基本的にありえないことで、羅針儀がある内火艇に磁気狂いの原因となる軍刀を持ち込むこともありえないという。また艇にはロープが多く積まれ、引き揚げなくてもロープにつかまらせて引っ張ればいい。それに駆逐艦に救助された大和の乗組員たちは皆横瀬に軟禁され、お互いが体験したことを話し合っていたから、酷い行為があれば一遍に話題になっていたはずだが、そんな話は全くなかった、 と答えている(仝上、https://news.nifty.com/article/domestic/society/12280-535250/)し、八杉に詰問されて、吉田は「私はノンフィクションだと言ったことはない」と弁明したとされる(仝上)とか、さまざまに異論が出ている。あくまで、作家の体験に終始している限り、実名を出しているからと言って、誤解や勘違いで済む。しかし、伝聞を載せたことで、いろいろ異論が出た。ま、大なり小なり、フェイクなのは仕方がないが、この部分は、本論とは関係ない部分で、ちょっと欲を出したとしか言いようのない、蛇足である。これで、全体の印象が変わるのは、残念な気がする。 秋山駿『想像する自由』 は、李珍宇『手紙』によって、 内部の人間、 という概念の演繹をしているだけで、僕には、自閉された空間を堂々巡りしているようにしか読めなかった。始めに、「内部の人間」ありきで展開する論旨の外に、李珍宇『手紙』は、秋山の手を逃れて自立している、と見えた。 参考文献; 大岡昇平他編『証言としての文学(全集現代文学の発見第10巻)』(學藝書林) |
| I・カント(篠田英雄訳)『純粋理性批判』』を読む。
たしか、ゲーテが、 われわれは知っている物しか目に入らない、 といった。この、知覚したものを、 表象、 といい、これを現実ではなく、 現象、 と、カントは言った。 「つまり我々が認識し得るのは、物自体としての対象ではなくて、感性的直観の対象としての物――換言すれば、現象としての物だけである」 ここから、人の認識プロセスの、 感性→悟性→理性、 の奥行きを徹底的に点検していく。 「感性によって我々に対象が与えられ、また悟性によってこの対象が考えられ」 「理性によって対象とその概念とを規定する」 あくまで、 実在、 ではなく、心の中の認識プロセスに徹頭徹尾貫徹していくところは、呆然、唖然、慄然とするしかないほどである。 「私がここに言う(純粋理性批判の)批判は、書物や体系の批判ではなく、理性が一切の経験にかかわりなく達得しようとするあらゆる認識に対して、理性能力一般を批判することである。」 と「序文」で述べている。批判とは、 純粋理性批判の法廷、 である、と。 ゲーテの言う、 知っている物しか目に入らない、 あるいは、さらに、誤解を恐れずに言うなら、 知っている物しか目に入らないことを知っている、 ことをも、カントは、 ア・プリオリ、 という。 「経験そのものが認識の一つの仕方であり、この認識の仕方は悟性を要求するが、悟性の規則は、対象がまだ私に与えられない前に、私が自分自身のうちにこれをア・プリオリに前提していなければならない。そしてかかる悟性規則はア・プリオリな悟性概念によって表現せられるものであるから、経験の一切の対象は、必然的にかかる悟性概念に従って規制せられ、またこれらの概念と一致せねばならない」 「つまり、我々が物をア・プリオリに認識するのは、我々がこれらの物のなかへ、自分で入れるものだけである」 からである。もちろん、 「私の感官に関係するような物が私のそとにあるということの意識は、私自身が時間において規定されたものとして存在しているという意識と同様に確実だということである」 が。 では、そうした内的プロセスで、 「悟性および理性は、一切経験にかかわりなしに何を認識し得るか、またどれだけのことを認識できるか」 が、本書の主要な問題であると、カントは述べる。ちなみに、カントの言う、 経験、 は、 「対象は我々の感覚を触発し或いはみずから表象を作り出し或いは我々の悟性をはたらかせてこれらの表象を比較し結合しまた分離して感覚的印象という生の材料に手を加えて対象の認識にする、そしてこの認識が経験といわれるのである」 と、つまり、 「認識は、すべて経験をもって始まる」 のである。 そして、対象を認識するというのには、 直観によって対象が与えられ、 悟性概念によって対象が、考えられる、 「即ち認識には、二つの要素が必要なのである」 と、そして、 「我々は、カテゴリーがなければ、対象を思惟することができない。またこの概念即ちカテゴリーに対応する直観によるのでなければ、思惟された対象を認識することができない」 と。ちなみに、ア・プリオリなカテゴリーとして、「分量」(単一性・数多性・総体性)、性質(実在性・否定性・制限性)、関係(付属性と自存性・原因性と依存性・相互性)、様態(可能・不可能、現実的存在・非存在、必然性・偶然性)を、アリストテレスに倣って、名付け、 かかる概念が経験を可能にする、 としている。ただし、 「純粋悟性概念は、常に経験的にのみ使用せられ得るものであり、決して先験的には使用せられ得ない」 とある。この場合、「先験的使用」とは、「この概念が物一般即ち物自体に適用されること」であり、「経験的使用」とは、「この概念が現象だけに適用されること」であり、 「悟性がア・プリオリになし得るのは、可能的経験一般の形式を先取的に認識することだけである――また現象でないものは経験の対象になり得ないから、悟性は感性の限界、つまりそのなかでのみ我々に対象が与えられるところの限界を踏み越えることはできない、ということである。悟性の諸原則は、現象を解明する原理にすぎない」 と。そして、規則を用いて現象を統一する、 「悟性の諸規則を原理のもとに統一する能力」 が、理性になる。理性は、 直截に経験やまたなんらかの規則を原理をもとに統一する能力、 である。当然対象ではなく、悟性と関わる。理性は、 推理の能力、 なのである。 「およそ推理には、理由となる一個の命題(大前提或いは大命題)と、これから引き出されるいま一個の命題(小前提或いは小命題)即ち推論があり、最後にこの推論の結果(理由と帰結との関係、結論)がある、そしてこれによって第二の命題(小命題)の真が第一の命題(大命題)の真と必然的にむすびつくのである。」 悟性の推理の場合、 「推論された判断が、第一の命題にすでに含まれていて、この判断が第三の概念(媒概念)によって媒介されなくても、第一の命題から導出される」 のに対して、理性推理の場合、 「結論を出すために、理由となる認識(大前提)のほかに、なお別の判断(小前提)を必要とする」 つまり、 三段論法、 を要する。つまり理性概念は、 推理によって得られた概念、 であるために、 正しい推論らしく見せかけて忍び込んだ、 詭弁的概念、 に陥る危険がある。 「理性の固有な原則は、一般に、悟性の制約された認識に対して無制約的なものを見出し、これらによってその統一を完成することである。だから、理性は無制約的なもの、すなわち原理の能力ではあるが、しかし対象と直接関係せず、悟性とその諸判断とのみ関係するから、その活動はあくまで内在的でなければならない。もし……認識の現実的な対象にまで高めようとするならば、それは悟性の概念を無制約的なものの認識に適用することによって。超越的となる」(シュヴェーグラー) のであり、カントは、無制約的な推理には、論理学の、 定言的推理、 仮言的推理、 選言的推理、 から導き出して、 心理学的、 宇宙論的、 神学的、 と三つの理念に分ける。これは、「我々の表象のもち得る」関係が、 主観に対する関係、 現象における多様な客観に対する関係、 あらゆる物一般に対する関係、 であるが、この表象の綜合的統一をこととする理念は、 思惟する主観の絶対的(無条件的)統一を含み、思惟する主観(「私」)は心理学の対象、 現象の条件の系列の絶対的統一を含み、現象の総括(世界)は宇宙論の対象、 思惟一般の一切の対象の条件の絶対的統一を含み、物(一切の存在者中の存在者)は神学の対象、 とする理性推理に分野分けする。そして、その誤謬を、心理学の、 「私は多様なものをいささかも含んでいないような主観という先験的概念からこの主観そのものの絶対的統一を推論する。しかしこのような仕方では、私はかかる主観に関して如何なる概念も持ち得ない」 ので、この種の推理を、 先験的誤謬推理、 といい、宇宙論の、 「与えられた現象一般に対する条件の絶対的全体という先験的概念の設定を旨とするものである。そして私は、一方の側の系列の無条件的、綜合的統一について自己矛盾する概念を持つところから、これに対立する統一のほうが正当であるという推論をする。しかしそれにも拘らず私は、この統一についてなんら知るところがなく、従ってなんの概念ももち得ない」 という推理を、 アンチノミー、 といい、神学の、 「私に与えられ得る限りの対象一般を考えるための条件全体から、物一般を可能ならしめるための一切の条件の絶対的、綜合的統一を推論する、――換言すれば、単なる先験的概念によっては知り得ないような物から、一切の存在者中の存在者というようなものを推論する。しかし私は、超越的概念によってはかかる存在者を尚さら知り得ないし、またその無条件的必然にいたっては、それについてまったく知りようがない」 という推理を、 理想、 と名づける。その詳細をここで展開しても意味がないが、この「理性」の広大な広がりに魅せられ、埴谷雄高が『死霊』を着想したのは、有名である(『死霊』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/471454118.html)については触れた)。 「恐らく、思考の訓練の場としてこれほど広大な場所はないのである。勿論、この領域は吾々を果てなき迷妄に誘う仮象の論理学としてカント自身から否定的な判決を受け、そこに拡げられる形而上学をこれも駄目、それも駄目、あれも駄目と冷厳に容赦なく論破するカントの論証法は、殆ど絶望的に抗しがたいほど決定的な力強さをもっている。けれども、自我の誤謬推理、宇宙論の二律背反、最高存在の証明不可能の課題は、カントが過酷に論証し得た以上の苛酷な重味をもつて吾々にのしかかるが故に、まさしくそれ故に、課題的なのである。少なくとも私は、殆んど解き得ざる課題に直面したが故にまさしく真の課題に直面したごとき凄まじい戦慄をおぼえた」 と書いている(あまりに近代文学的な)。 僕は、誤謬推理の中で、コギト批判の部分に強く惹かれた。 我思う、ゆえに我あり、 である。ここに、 実体化、 単純化、 同一化、 物体と相互的、 の罠がある、と。 「私は、単に思惟するだけではいかなる対象も認識しない、対象の認識は、与えられた直観を意識の統一に関して想定することによってのみ可能である。そしてまたおよそ思惟は、かかる意識の統一によって成立する。それだから私は、思惟する私を直接に意識することによって、私自身を認識するのではない。私は、直観において与えられた私を、思惟の機能に関して規定されているものとして意識するときに、私を認識するのである。従って思惟における自己意識の様態は、いずれもそれ自体まだ対象に関する悟性概念ではなくて、単なる論理的機能にすぎない。しかしかかる論理的機能は、思惟に認識の対象をあたえるものではない、従ってまた私自身をも認識の対象として与えるわけにはいかない」 「われわれが思惟だけにとどまっている限り、我々は実体即ちそれ自身だけで自存する主観という概念を、思惟する存在者の自分自身に適用する必然的条件をもたない」 「『私は考える』という命題は経験的命題であり、この命題はまた『私は実在する』という命題を含んでいる。しかし私は、『思惟する一切のもの(存在者)は実在する』と言うことはできない、もしそうだとしたら。『思惟する』という特性が、この特性をもつ一切の存在者を必然的存在者にすることになるからである。従って私は私の実在を、『私は考える』という命題から推論されたものとみなすことはできない、ところがデカルトはそれができるとおもったのである」 「それだから私が思惟によって表象するところの『私』は、あるがままの私でもなければ、私に現れるままの私でもない、この場合の私は、客観を直観する仕方を度外視して、自分自身を客観一般としてのみ考えるのである」 と。「われ思う」は、自己意識である。そのことで、実体としての私の存在の証明にはならない。あくまでデカルトは、 そのように意識している我だけはその存在を疑い得ない、 ところに力点を置き、自我の自立を想定していたのかもしれないが。しかし、この心の作用の実体化は、今日も根強い。「我思う」は、 「単なる意識、すなわちあらゆる表象および概念に伴ってそれらを統合し担っているところの心の作用である。この思考作用が今や誤って物と考えられ、主観としての自我が客観、魂としての自我の存在とすりかえられ、前者について分析的に妥当することが後者へ綜合的に移されるのである」 と(仝上)。この綜合的と、分析的も、カント独特の用語である。 「述語Bが主語の概念の内にすでに(隠れて)含まれているものとして主語Aに属する」 ものを、 分析的、 といい、 「述語Bは主語Aと結びついているが、しかしまったくAという概念の外にある」 ものを、 綜合的、 という。主語Aから演繹できるものを分析的、主語Aを相対化し、俯瞰(帰納)しなくては、綜合的ではない。そこから、「我思う故に我あり」の、「我思う」に、分析的に「我あり」が含まれていなければ、「我思う」自体を相対化し、「我」の外から俯瞰しなくては、明らかにできない、というふうにも言えるのである。 参考文献; I・カント(篠田英雄訳)『純粋理性批判』(岩波文庫) A・シュヴェークラー『西洋哲学史』(岩波文庫) |
| 大岡昇平他編大岡昇平他編『日本的なるものをめぐって(全集現代文学の発見第11巻)』を読む。
現代文学の発見、 |
| 深谷克己『百姓一揆の歴史的構造』を読む。
本書は、著者の、 |
| 大岡昇平他編『政治と文学(全集現代文学の発見第4巻)』を読む。
現代文学の発見、 |
| 渡辺実『日本食生活史』を読む。
類書が少ないせいか、随分前(1964年)に上梓された本だが、新装版が出ている。本書は、「我が国の食生活史の時代変遷」を、以下のように、「便宜上区分して」、 |
| 大岡昇平他編『性の追求(全集現代文学の発見第9巻)』を読む。
現代文学の発見、 |
| 武田泰淳『秋風秋雨人を愁殺す:秋瑾女士伝』を読む。
秋風秋雨人を愁殺す(秋風秋雨愁殺人)、 は、彼女の絶命詞と伝えられる。しかし、本書によると、「秋瑾集」では、 秋雨秋風、 となっており、当時の新聞紙上でも、みな、 秋雨秋風、 となっているし、西湖畔に建てられている記念碑も、 秋雨秋風、 となっている。彼女の親友呉燦芝のみが、 秋風秋雨、 としている、とか。 日本留学中に光復会に入り、浙江で武装蜂起を計画したが、発覚して捕縛された。 取り調べに際して、 秋風秋雨愁殺人、 とのみ書き記しただけで、何の発言もせず、 秋女士は「革命党人は死なぞおそれやしない。殺したければ殺すがいい」と豪語して、歯をくいしばり目をつぶり、酷刑(ごうもん)にたえているので、革命側の秘密をさぐり出せぬ幕友(書記とか秘書の役で政治家につきそう知識人)は、仕方なくなり、ニセの供述書をこしらえ、それに無理やり指の印をおさせた。 という。翌日六月六日午前四時に、斬首された。
本書には、秋瑾だけではなく、それと連携し、僅か前の五月二十八日蜂起した、徐錫麟についても、詳しく触れている。 |
| A・シュヴェークラー『西洋哲学史』を読む。
哲学史をタレスからはじめる、 とし、 古代哲学(ギリシャ、ローマの哲学)、 (中世の哲学)、 近世哲学、 の区分に従い、デカルト、スピノザ、ライプニッツ、カント、フィヒテ、ヘーゲルへと至る哲学史である。 特に、第一の古代哲学は、 ソクラテス以前の哲学(タレスからソフィストまでを含む)、 ソクラテス、プラトン、アリストテレス、 アリストテレス以後の哲学(新プラトン主義までを含む)、 と詳細である。 本書は、まず哲学の定義から始まる。 哲学するとは考えること、事物を思考によって考察することである、 と。では、実際的な活動においての思考、あるいはその他の諸科学の思考と、哲学のそれとはどう違うのか。 哲学を経験的な諸科学から区別するものは哲学の素材ではなくて、その形式、方法、認識の仕方である。個別的な経験科学はその素材を経験から直接にとりあげる。それを眼の前に見出し、見たままにとりあげる。哲学はこれに反して、与えられたものを与えられたままにとりあげるということは決してしない。それは与えられたものをその最後の諸根拠にまで追求し、あらゆる個別的なものを究極原理に関係させ、知識の総体のうちにおける制約された一分肢として考察する。まさにこのようにすることによって哲学は、個別的なもの、経験のうちに与えられたものから。直接性、個別性、および偶然性という性格を除去するのであり、経験的な個別性の大洋から普遍的なものを、無数の秩序のない偶然事から必然的なもの、一般的な法則をとりだすのである。要するに哲学は、経験的なものの総体を思想的に組織された体系という形で考察するのである。 これだとわかりにくいが、これを私的に注釈するなら、 経験や具体的な諸科学のメタ科学、 ということなのではないか。あるいは、 科学のメタ科学、 と言ってもいい。 形而上学(metephysic)、 とは、ギリシャ語で、 Meta+physika(自然学)、 である。ある意味、 思考することを思考する、 思想することを思想する、 つまり、 考えることを考えること、 なのではあるまいか。だから、 経験的諸科学と交互作用をなしていること、 その意味で、 哲学は一方には経験的諸科学を制約するとともに、他方にはまた哲学自身がそれらによって制約されるということである、 のであり、その意味で、 完成された哲学、 はあり得ず、 さまざまに相継いであらわれる時代哲学という形でのみ存在する、 のである。だから、哲学史は、 これらのさまざまの時代哲学の内容、順序、および内的連関、 ということになる。結果、上述の区分で哲学の流れを俯瞰していくのが、本書である。 哲学に無縁なぼんくらな人間には、なかなか前後の道筋をたどりきれないが、その都度の、シュヴェークラーのコメントがなかなかワサビがきいていて楽しめる。たとえば、 ソクラテス以前の哲学に共通な傾向は、自然を説明する原理を見出すことである、 と、その中のエレアのゼノンの逆説(アキレウスと亀、飛ぶ矢は動かず)について、 物質と空間と時間の無限分割性という概念のうちにある困難と二律背反を、はじめて少なくとも部分的には正しく指摘したものであるが、アリストテレスはゼノンをこれらの議論のために弁証法の創始者と呼んでいる。ゼノンはまたプラトンにも根本的な影響を与えた。 プラトンとソクラテス、アリストテレスへの流れについて、 プラトンによってギリシャ哲学は、その発展の頂点に達した。プラトンの体系は、自然的および精神的宇宙の全体を一つの哲学的原理から最初に完全に構成したものである。それはすべての高い思弁の原型であり、形而上学的および倫理的観念論の原型である。ソクラテスによっておかれた単純な土台に立って、哲学の理念は、ここではじめて包括的に実現された。ここで哲学は完全な自己意識に達した……、しかしそれと同時にプラトンは、哲学を与えられた現実に観念的に対立させた。(中略)これはより実在論的な物の見方によって補われなければならなかった。そしてそれはアリストテレスに始まるのである。 結局古代哲学は、 プラトン=アリストテレス的哲学の二元論(中略)を克服しようとして挫折したのである。キリスト教はこの問題を再びとりあげたのである。それは、古代の思考が実現しえなかった理念、神の彼岸性の廃棄、神的なものと人間的なものとの本質的統一を自己の原理とした。神が人となったということ……がキリスト教の思弁上の根本理念であって、(中略)この時からずっと一元論が近世哲学全体の特徴となり根本傾向となっている。 そして近世哲学は、 古代哲学が立ちどまっていたその点から出発したのである。思考、自己意識が自分のうちへしりぞいたのがアリストテレス以後の哲学の立場であったが、これはデカルトにあって近世哲学の出発点をなしており、近世哲学はここから出発して、古代哲学が脱却しえなかったあの対立を思考によって媒介し融和させるにいたったのである。 さて、そのデカルトは、 第一に、まったくの無前提という要求を出したことによって、哲学の新しい時代の創始者である。すなわちデカルトは、思考によって措定されていないすべてのもの、あらゆるあたえられた真理に対して絶対の抗議を要求したのであるが、これはそれ以後ずっと近世の根本原理となっている。第二に、デカルトは、自己意識の原理、純粋に自立的な自我の原理を提示したが(デカルトは、精神すなわち思考する実体を個人的自己、個々の自我と考えた)、これは古代の知らなかった新しい原理である。第三に、デカルトは存在と思考、存在と意識との対立を提示して、この対立の媒介を哲学的課題として宣言したが、これは近世哲学全体の問題となっている。 デカルトの切り離した精神と物体、意識と存在を解決する一つの方法は、 二つの実体と見ないで、一つの実体の現象形態とみること、 である。それを、 神のみが実体で古物はすべて偶有的である、 と、整合的に言い表したのがスピノザである。スピノザの体系が、 デカルトの体系の完成であり真理である、 とされる所以である。 スピノザの体系は、考えうるかぎりもっとも抽象的な一神論(むしろ一元論)である。 しかしそれは、 人々の普通の観念には実在と見えるすべてのものをその視野からしりぞけ……、その欠陥は実体のこの否定的な深淵を存在と生成の肯定的な根拠に変えることを知らない点にある。 デカルトの二元論を克服する道には、 物質の側に立つか、 観念の側に立つか、 である。 一面的な観念論、 と 一面的な実在論(経験論、感覚論、唯物論)、 の、二つの試みは同時に始まる。実在論的発展系列の創始者は、ジョン・ロックである。 経験論が精神的なものを物質的なものの下位におき、精神的なものを物質化しようとする努力によって導かれていたとすれば、観念論は逆に、物質的な物を精神化すること、すなわち物質的な物がその下に包摂されるように精神の概念を理解することに努める。(中略)後者のそれは(ライプニッツやバークレでは)…すなわち精神(心)と表象(観念)のみが存在するという命題である。……観念論の立場は精神的な存在、自我を実体とする。 実在論と観念論を、カントは、次のように統一する。 自我は実践的な自我としては自由であり自律的であって、自分自身の無制約的な立法者であるが、理論的な自我としては受容的であり経験の世界によって制約されている。しかしそれはまた理論的な自我としてもそれ自身に二つの側面をもっている。なぜなら、一方、我々のあらゆる認識の素材が経験に由来し、経験こそわれわれの認識の唯一の領域であるかぎりにおいて、経験論が正しいとすれば、他方、経験するためには、経験によっては与えられずア・プリオリにわれわれの悟性のうちにふくまれている概念が必要であるから、合理主義が認識のア・プリオリな要因および素地を強調するのは正しいのである、 と。なお、カントの『純粋理性批判』については触れた(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473549212.html)。 カントのアンチテーゼであり、フィヒテがカントの直接の帰結である。 カントはなお二元論的であって、それによれば、自我は一方では理論的自我として外界に隷属し、他方では実践的自我として外界の主人である。言いかえれば、自我は客観に対してあるいは受容的にあるいは自発的にふるまう。フィヒテは、実践理性の優位を強調することによってこの二元論をとりのぞいた。すなわち、フィヒテは、理性をひたすら実践的なもの、意志、自発性と考え、客観にたいする理性の理論的、受容的な態度をさえ、ただ活動の減少、理性そのものによって定立された正言と考えるのである。 フィヒテから出て、フィヒテと対立したシェリングの根本欠陥は、 絶対者を抽象的に客観的なものと理解したことであった。絶対者はまったくの無差別、同一性であった。このような無差別からは、第一に、規定されたもの、実在的なものへ移っていくことは不可能で、したがってシェリングは後になると絶対者と実在する世界との二元論におちいった。第二に、このような無差別のうちでは自然的なものにたいする精神的なものの優位性がなくなり、両者は同等のものとされて、観念的なものと実在的なものとのまったく客観的な無差別こそ両者よりも高次のもの、したがって観念的なものより高次のものとして定立されていた。このような一面性を反省するところからヘーゲル哲学は現れたのである。 で、ヘーゲルは、その方法によってその先行者と根本的にちがっている。 絶対者はヘーゲルによれば、存在ではなく発展である。すなわち、それはさまざまな区別と対立とを定立するが、これらは独立であったり絶対者に対立したりするものではなく、個別的なもの各々もその全体も絶対者の自己発展の内部にある諸契機にすぎない。したがって絶対者が自分自身のうちに、区別―といっても絶対者内の諸契機をなしているにすぎないような区別―へ進む原理をもっていることが示されなければならない。この区別は、おのれが絶対者へ付加するのではなく、絶対者が自ら定立するのでなければならず、そしてそれはふたたび全体のうちへ消失して、絶対者の単なる契機であることを示さなければならない。 つまり、ヘーゲルの方法は、 各々の概念はそれに固有な対立、固有な否定を自分自身のうちにもっている。それは一面的であり、その対立をなしている第二の概念へ進んでいくが、この第二の概念もそれだけでは第一の概念と同様に一面的である。かくしてこれらが第三の概念の契機にすぎないこと、そして第三の概念ははじめの二つの概念のより高い統一であり、両者の統一へと媒介するより高い形態のうちで両者を自分に含んでいることがわかる。この新しい概念が定立されると、それはふたたび一面的な契機であることがわかり、この一面的なものは否定へ、そしてそれとともにより高い統一へ進んでいく。概念のこの自己否定が、ヘーゲルによれば、すべての区別と対立の発生である。 だから、ヘーゲルの方法とは、 絶対的なものは単純なものではなく、最初の普遍者のこのような自己否定によって生まれる諸契機の体系である。この諸概念の体系もまたそれ自身抽象的なものであって、たんなる概念的な(観念的な)存在の否定、実在性、(自然における)諸区別の独立的実在へと進んでいく。しかしこれもまた同様に一面的であって、全体ではなく一契機にすぎない。このようにして独立的に存在する実在もふたたび自己を止揚して、自己意識、思考する精神のうちで概念の普遍性へ復帰する。思考する精神は、そのうちに概念的存在と観念的存在とを包括して、それらを普遍と特殊のより高い観念的統一としている。このような概念の内在的な自己運動、 なのである。 本書は、ヘーゲルまでしか語られない。しかしヘーゲルの、この観念の巨像はある意味、逆立ちしている。たとえば、 キリスト教がはじめて神と世界とを積極的に融和させる。それはキリストという人格のうちに、神的なものと人間的なものとの統一の実現である神人を見るからであり、神を、自分自身が外化(人間化)しそしてこの外化から永遠に自分のうちへ帰る理念として、すなわち三位一体の神としてとらえるからである。 というヘーゲルの絶対精神の考えは、やがて、フォイエルバッハによって、こう転倒されることになる。 神的本質(存在者)とは人間的本質以外の何物でもない。またはいっそうよくいえば、神的本質(存在者)とは人間の本質が個々の人間―すなわち現実的肉体的な人間―の制限から引き離されて対象化されたものである。いいかえれば神的本質(存在者)とは、人間の本質が個人から区別されて他の独自の本質(存在者)として直観され尊敬されたものである。 ここから、マルクスの唯物史観が始まるが、同じく人間へと取り戻そうとしたキルケゴールは、 人間は精神である。しかし、精神とは何であるか? 精神とは自己である。しかし、自己とは何であるか? 自己とはひとつの関係、その関係それ自身に関係する関係である。あるいはその関係がそれ自身に関係するということ、そのことである。自己とは関係そのものではなくして、関係がそれ自身に関係するということなのである。 と書いた。それが実存主義へとつながっていく。 ヘーゲルは、逆立ちした観念の巨像、総合体系である。いわば、哲学のギリシャ以来の到達点であると同時に、ある意味でコペルニクス的な転換点でもあることがよくわかるのである。 参考文献; A・シュヴェークラー『西洋哲学史』(岩波文庫) フォイエルバッハ『キリスト教の本質』(岩波文庫) キルケゴール『死にいたる病』(中央公論社) |
| 武田泰淳『司馬遷―史記の世界』を読む。
『春秋』のような編年体ではなく、紀年体(きでんたい)のスタイルを編み出した「史記」の構造は、 十二本紀(ほんぎ) ↓ 三十世家(せいか) ↓ 七十列記(れつでん)、 という構造になっている。花田清輝が、「司馬遷が、権力のピラミッドの頂点に注目し、それからしだいにかれの視線を底辺にむけていったのは―すなわち、かれの『史記』を、まず『十二本紀』、つぎに、『三十世家』、おわりに『七十列伝』といった構成で書きすすめていったのは理由のないことではありますますい」と評したのは、武田の着眼に基づいてのものであった。 本紀は、 帝王一代の事跡、 を記したものであり、世家は、 諸侯など、世襲の家柄の記録、 列伝は、 人臣の伝記を並べた記録、 である。 史記が、ピラミッド型の階級構造にしたのは、ひとつは、その世界が頂点に立つ帝王からピラミッド構造を成していたからではあるが、いまひとつは、司馬遷が、歴史を動かすものは人間とみた、からである。 世界の歴史は政治の歴史である。政治だけが世界をかたちづくる。政治をになうものが世界をになう。「史記」の意味する政治とは「動かすもの」のことである。世界を動かすものの意味である。歴史の原動力となるもの、世界の動力となるもの、それが政治的人間である。政治的人間こそは「史記」の主体をなす存在である。政治的人間は、世界の中心となる。そのために「十二本紀」がつくられた。政治的集団は分裂する集団となる。そのために「三十世家」がつくられた。政治的人間は独立する個人となる。そのために「七十列伝」がつくられた。「本紀」についても、「世家」に於いても、また「列伝」に於いても、司馬遷は人間を政治的人間としてとりあつかうことを忘れなかった。人間が世界の中心となり、分裂する集団となり、独立する個人となるためには、政治的人間にならなければならない。政治的人間としてとりあつかわれた人間だけが、歴史の舞台に於いて、一つの役目をもつことができる。そして役目をもたされた人物として、歴史劇に出場することが許される。かくして、この人物は、あの人物と関係をもち、この役は、あの役と連絡し、そして「史記」全体ができあがるのである。 と武田は記す。そして、 「人間」の歴史が司馬遷の書こうとするところである。「人間」の姿を描くことによって、「世界」の姿は描き出される。(中略)根気よくあせらずに、あたえられた記録により、自分の眼や耳のはたらくかぎり、「人間」の姿を追い求め、「人間」の動きを見失うまいとつとめているうちに、司馬遷の世界構想はおのずと出来上がって来る。 と。だから、出来事の編年体では描き切れないので、 世界の中心となった者の本紀 ↓ それを支えた者たちの世家 ↓ 個々の歴史に登場した個人としての列伝、 という、人の連鎖による「空間的構造」という「史記」世界像は、 世界の『史記』学者の誰も言わなかった、 卓見である(山本健吉)、らしい。 当然ながら、 「本紀」は時間的に継続し、かつ交替したが、各「世家」は空間的に並立し、一世界を形成している。しかもその並立はやはり、周囲から「本紀」を支える並立である。 という「本紀」と「世家」の複雑な関係を示す例として、武田は「陳杞(ちんき)世家」を挙げている。 舜の子孫は、周の武王がこれを陳に封じた。その陳を楚の惠王が滅ぼした。陳については「世家」に記載してある。禹(ウ)の子孫は、同じく武王がこれを杞に封じた。この杞を楚の恵王が滅ぼした。杞については「世家」に記載してある。契(セツ)の子孫は殷となった。殷については「本紀」に記載してある。殷が滅亡して後、周はその子孫を宋に封じた。その宋を斉(セイ)の湣(ビン)王が滅ぼした。その宋については「世家」に記載してある。后稷(コウショク)の子孫は周となった。その周を秦の昭王が滅ぼした。周については「本紀」に記載してある。皐陶(コウヨウ)の子孫の或る者は、英と六(リク)とに封ぜられた。その英と六を楚の穆(ボク)王が滅ぼした。これらについては系譜がない。伯夷(ハクイ)の子孫は、周の武王に至って再び斉に封ぜられた。封ぜられた人は太公望と曰う。この斉を陳氏が滅ぼした。斉については「世家」に記載してある。伯翳(ハクエイ)の子孫は、周の平王の時に至り封ぜられて秦となった。その秦を項羽が滅ぼした。秦については「本紀」に記載してある。垂・益・虁(キ)・龍(リョウ)はその子孫が何処に封ぜられたか不明である。手がかりがない。 右舜から龍まで十一人は、いずれも唐虞(トウグ)の際に功積徳行で有名な臣である。そのうち五人の子孫は皆帝王となった。その余の者の子孫も立派な諸侯になった。 「唐虞の際」とは、中国の伝説上の聖天子である陶唐氏(尭)と有虞氏(舜)二人の治めた時代を指す。ということは、その後の、 呉・斉・魯・燕・管・蔡・陳・杞・衛・宋・晉・楚・越・鄭・趙・魏・韓、 等々は、すべて、尭舜の時代の人々の枝葉であるが、それは「本紀」から出て、面白いことに、「功積徳行」のあった十一人のうち五人は「本紀」に載り、他のものが「世家」扱い、ということである。「本紀」と「世家」の関係がよくわかる記述である。それを、武田は、こう記す。 「本紀」継続がすでに、人間闘争を縦に貫くものであったが、「世家」並立はこれを横につらねたものと言える。「世家」分裂の出発点が、呉、斉、周型であろうと、趙、魏、韓型であろうと、分裂した以上、排他相剋の運命は免れぬ。「本紀」のみが史記世界を充たすのではないことは、「本紀」を読むだけでよく呑み込めた事実であるが、いよいよ「世家」に入ると、世界並立現象の物凄さが、身にしみてわかるのである。 「列伝」は、伯夷列伝からはじまる。その最後に、 天道は公平で、いつも善人の味方をするという者がいる。しかし伯夷、叔斉の如きは、善人と謂えないであろうか。仁をつみ行いを清くし、しかもかくの如くに餓死したではないか。孔子の弟子七十人のうち、孔子はただ顔淵だけを薦めて、學を好む者とした。それだのに顔淵は屡々貧乏で、糟糠さえ充分に食べられず、そのまま若死をしている。天の善人に報ゆるやり方とは何であるか。盗跖は毎日無辜の民を殺し、人の内臓を膾にし、暴戻無残、徒党数千人を聚めて天下を横行したが、ついに天寿をもって終わっている。これは一体何の徳があってのことか?これらはハッキリ誰にでもわかる例である。近世に至っては、素行が治まらず、悪事を犯して、しかも終身逸楽し、富貴が親子代々つづいている者がある。また、行動をつつしみ、言語をつつしみ、邪道をふまず、公明正大なことでなければ憤発しないでいて、しかも禍に遇うものが数え切れない。ここに於いてか余は惑わざるをえない。天道、是か非か、とは真実ではないか。 とある。これが、「史記」を貫く思想とされる所以である。 天道すら信じられないならば、人は何を信じたら良いのか? 司馬遷は何を信じたら良いのか? 自分である。自分の歴史である。「史記」である。天すら棄てたもの、天のあらわさなかったもの。それらの人物をとりあげ、あらわすのは、我司馬遷である。我を信ぜよ。我が歴史を信ぜよ。極端な絶望の淵に沈みながら、もりあがってくる自信力で、「伯夷列伝」は私達をおどろかすのである。伯夷の絶対否定が、かえって司馬遷の勇気を増すのである。「こころに鬱結するところがあって、その道を通ずることが出来ず、往事をのべて来者を想うのである」(太史公自序)。自ら、読者のために「天道」をつくる。自ら「天道」となって、歴史を照明する、不敵な決意である。 これは、腐刑という屈辱を被った司馬遷の心を読んだ著者の心でもある。天ではなく、往事に、天道があり、未来がある、と。 なお、「史記・列伝」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/447234854.html)については、触れた。 参考文献; 武田泰淳『武田泰淳全集第十一巻』(筑摩書房) |
| 吉川英治『宮本武蔵』・五味康祐『喪神』・中里介山『大菩薩峠』・柴田錬三郎『眠狂四郎無頼控』・池波正太郎『剣客商売』他を比較する。
「歴史小説」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/470502694.html)で触れたように、世情、歴史小説と時代小説とは区別されている。 歴史小説は、 主として歴史上に実在した人物を用い、ほぼ史実に即したストーリー、またはその時代を設定して、その中での空想上の物語が書かれたものが展開される小説、 である(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%B0%8F%E8%AA%AC)。たとえば、司馬遼太郎の作品のほとんどは歴史小説の範疇に入る。一時凝って、ほぼ全作品を読んだが、時に、小説を歴史そのものの如く振舞うのに、辟易した。小説は小説であって、歴史にはなれない。この歴史小説に対して、 時代小説は、 架空の人物(例えば銭形平次)を登場させるか、実在の人物を使っても史実と違った展開をし(例えば水戸黄門)、史実と照らし合わせるとかなり荒唐無稽、 とされる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%B0%8F%E8%AA%AC)。その時代小説の一ジャンルとして、 剣豪小説、 なる分野がある(仝上)、らしい。最近のものはわからないが、かつて読んだものとしては、吉川英治『宮本武蔵』、五味康祐『喪神』、中里介山『大菩薩峠』、柴田錬三郎『眠狂四郎無頼控』、池波正太郎『剣客商売』等々が代表的だ。 そんなに熱心な剣豪小説ファンではない。最初に読んだのは、 中里介山『大菩薩峠』 である。その後、何冊か間にあったかもしれないが、御多分に漏れず、 吉川英治『宮本武蔵』 である。 しばらくは藤沢周平に凝って、ほぼ全作品を読んだ。剣豪小説の部類に入るのは、隠し剣シリーズの、 『隠し剣孤影抄』 『隠し剣秋風抄』 『たそがれ清兵衛』 ではないかと思う。「たそがれ清兵衛」「隠し剣鬼ノ爪」「盲目剣谺返し」「必死剣鳥刺し」は映画化された。 「神業」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163234.html)で触れたことだが、昔読んだ剣豪小説の中で、決闘のシーンというか、果たし合いのシーンで、印象に残っているのは、 第一は、中里介山の『大菩薩峠』で、詳しいことは覚えていないが、土方歳三率いる新徴組の手練れが、清川八郎を襲撃しようとして、襲うべき駕籠を間違え、乗っていた島田虎之助に襲いかかり、結局島田一人に十数人の使い手全員が倒され、土方も翻弄される、すさまじい戦いシーンがあった。その迫力は、ずっと記憶に残っている。襲撃の一隊に加わった主人公、机龍之介は呆然、手をつかねて立ち尽くしていた、と記憶している。 第二に、指を折るのは、吉川英治の『宮本武蔵』で、確か武蔵が、柳生石州斎の屋敷に紛れ込み、柳生の四天王と、刃を交えるシーンがあった。その気迫と、立ち会う面々との間合いは、一瞬で決着する吉岡兄弟との立ち会いも、一条下がり松のシーンも、般若坂の決闘も、巌流島の決闘も、かすむほどの緊迫したものだと記憶している。 その他は、以上の作品ほどには印象深くないが、 五味康祐の『柳生連也斎』 での連也斎と武蔵の弟子鈴木綱四郎との立ち会いシーンも記憶に残る。 しかし、事実は小説より奇なり、実際の剣豪は、こんなものではなかったらしい。甲野善紀氏は、江戸時代の剣客で、夢想願流の松林左馬助無雲のエピソードを紹介している。 ある夏の夕方、蛍見物に川べりを門弟とともに散歩していた無雲を、門人の一人が川へいきなり突き飛ばした。無雲は突き飛ばされたなりフワリと川を飛び越え、しかも、突き飛ばした門人も気づかぬ間に、その門人の佩刀を抜き取っていた…。 それは遠い江戸時代の話ではなく、現代の武道家にもいる、という。たとえば、柔術家の黒田泰治師範は、警察の道場で、寝転んだまま力士五人に体中を押さえさせ、よもやと思っていたら、あっという間に、いとも簡単に起き上ってみせた…。 あるいは、親戚男谷信友の弟子の島田虎之助の元で修業した勝海舟が、幕末の剣豪白井亨についてこんなことを語っている。 此人の剣法は、大袈裟に云えば一種の神通力を具えていたよ。彼が白刃を揮うて武場にたつや、凛然たるあり、神然たるあり、迚も犯す可からざるの神気、刀尖より迸りて、真に不可思議なものであったよ。己れらは迚も真正面には立てなかった。己れも是非此境に達せんと欲して、一所懸命になって修行したけれども、惜乎、到底其奥には達しなかったよ。己れは不審に堪えず、此事を白井に話すと、白井は聞流して笑いながら、それは御身が多少剣法の心得があるから、私の刃先を恐ろしく感ずるのだ。無我無心の人には平気なものだ。其処が所詮剣法の極意の存在する処だと言われた。己れは其ことを聞いて、そぞろ恐れ心が生じて、中々及ばぬと悟ったよ。 その白井は、平和時の武術を晴天の雨具にたとえ、なるべく目立たぬことを心掛けるように説いたという。 雨でもないのに、これみよがしに剣術家然として歩くのは、晴れているのに雨具をつけて歩くようなもので、人々の顰蹙をかうだけだ、と。 そういう実態をみると、どうも小説は、少し立ち合いが派手だ。机竜之介は、音無しの構えだ。とは、 相手が討ってくるまで動かずに、相手がしびれをきらして斬りかかってきたところを討つ技である。相手の刀と一度も刃を合わさないので音が鳴らないので音無しという、 とある(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%BA%E7%AB%9C%E4%B9%8B%E5%8A%A9)。眠狂四郎の「円月殺法」に似ていなくもないが、むしろ、竜之介の粗野で粗暴なところは、その静かに待つ剣法とは合っていないように思えてならない。 「円月殺法」は、 陽刀の変化の妙である。したがって、その鋒がおそろしいのであって、刃はおそるるに足りない。ということは、上段や青眼で、これを防ぐには魔神にひとしい迅速の術をそなえていなければならぬ。陰刀をもって、おのれの目から円月をはばむのこそ、最も適切というほかはない。陰刀の場合、刃が威力を含み、鋒は大した役に立たないからである。 右近の無眼唯心流は、実に、狂四郎の円月殺法に勝つために編まれたかとさえ思いなされる奇怪の構えであった。 やむなく、狂四郎は、円月殺法をすてて、刀を下段から青眼に移した。陰刀を制するには、気根を青眼に罩めるのみである。 全身に満たした鋭気を、太刀の鍔もとより、刀身の髄 を通して、鋒までつらぬかせ、技を超えた石火応変の風心刀法を使うが肝要となる。 狂四郎は、敵の攻撃を誘うべく、ゆっくりと、右へ右へとまわりはじめた(「眠狂四郎無頼控」)。 こう見ると、ただ受動ではない。 坂本龍馬を斬ったという今井信郎は、北辰一刀流の皆伝、榊原健吉から直心影流を学んだが、片手打ちという我流の実践剣法で、ひと打ちで相手を倒したらしいが、その彼が、こう言っている。 免許とか、目録とかという人達を斬るのは素人を斬るよりははるかに容易、剣術なぞ習わない方が安全、と。 追い込まれた人が、窮鼠猫を噛む状態の予想外の膂力とスピードの方が、対応できないということらしい。言ってみると、剣術というのは、一定の枠組みの中で、双方想定した枠内でやっているということなのかもしれない。 そういう通常の剣法に対して、いわゆる「相ぬけ」を究極の形として目指した異色の剣法に、「無住心剣術」がある。頂点は、相打ちではなく、相ぬけという。 剣術の勝負は、勝か負けるか、相打ちになるか、そうでなければ意識的に引き分けるか以外ない武術の鉄則を超え、お互いが打てない、打たれない状態で、たとえば、一雲と巨雲の師匠と弟子では、一方は太刀を頭上に、一方は太刀を肩の上にかざして、互いにすらすらと歩み寄り、いよいよの間合いに入ってから、互いに見合って、「ニコッ」とわらってやめた、という。しかし他流には負けたことはない、という。 「他流を畜生心によるもの」 と開祖・針ヶ谷夕雲(はりがやせきうん)がいう。 「無住心剣術」の稽古法は、片手打ちで、特有の絹布や木綿でくるんだ竹刀で、ひたすら相手に向かって真っすぐ入り、相手の眉間へ引き上げて落とす、相打ちから入る。 よく当たるものはよくはずれ、よくはずるるものはよく当たる、 という言葉があり、相手はこっちの姿をみて打ち込んでくるが、こちらは敵を敵として認識せず、敵の気からはずれて出ていくため、意識的に打ち込むものほどはずれてしまい、こちらは相手の気筋を外してでるため、相手には不意に目の前にあらわれるように感ずるらしい。 心にとかくの作為があって勝負に臨めば、勝負にとらわれて、足がなかなか進まず、立ちが相手に届かない、 ともいう。 いわば、「常の気のまま」を尊重する流儀のようで、相手を打つも自分が相手を打つというよりも、自然の法則(天理の自然)が自分の体を通して行われた、という理法のようだが、その太刀の威力は、すさまじく、竹刀打ちを兜で受けたものが、吐血したというほどのものだ。従って、無敗の剣とも言われる。 双方に戦う気があれば、相抜けにはならず、相打ちになる。「相抜け」とは夕雲が用いた用語で、「無住心剣」による立ち合いの理想を説いたものとされる。 双方が傷を負う相打ちとは異なり、相抜けは互いに空を打たせて、無傷の分かれとなる。むしろ高い境地に至った者同士であれば、互いに剣を交える前に相手の力量を感じ取り、戦わずして剣を納めるというもの、 である(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E3%83%B6%E8%B0%B7%E5%A4%95%E9%9B%B2)。 「兵法を離れて勝理は明らかに人性天理の自然に安坐するところに存する」 と、刀の勝負より心の勝負を説いたものとされる。ここまで行くと、もはや剣法というよりは悟達に近い。しかし、それはすべての流派に通じるものらしい。 「眠狂四郎独歩行」にこんなシーンがある。 池泉に浮いた沢渡り石の上で、 一間をへだてて、眠狂四郎と樋口十郎兵衛は、剣を把って、対峙していた。 対峙してから、すでに、半刻が過ぎていた。 流れのはやい雲を縫う下弦の月が、東側の水面から、西側の水面に移っていた。 狂四郎は、地摺り下段。 十郎兵衛は、上段。 その半刻の間に、狂四郎は、一回、円月殺法を、月光の満ちた宙に、描いていた。 十郎兵衛は、その妖しい誘いに乗って来ず、不動であった。 馬庭念流の剛剣は、先の太刀である。それが、円月殺法を能くふみこたえて、斬り込もうとしないのであった。 これは、狂四郎としても、はじめての経験であった。これから、さらに、半刻、いや一刻を費やしても、この対峙は崩れまい、と思われた。 ふっと──。 狂四郎は、自嘲をおぼえた。 十郎兵衛が、構えたまま、半眼で、睡っているのを、さとったのである。 真剣の試合をし乍ら、睡るとは! まさに、未だ曽てあり得ない不敵の振舞いといわなければならぬ。 狂四郎は、いきなり、右足の草履を、対手の顔面めがけて、蹴りとばした。 刹那──かっと、双眼をひき剝いた十郎兵衛は、颶風のような熱気を噴かせて、 「ええいっ!」 と、沢渡り石を蹴って、躍った。 狂四郎は、幻影のように、音もなく、後方の石へ、跳び退った。 剛剣は、狂四郎が跳び退りつつ、ぬぎとばした左足の草履を、両断した。 再び、円月殺法の地摺り下段と、馬庭念流の上段が、対立した。しかし、こんどは、ものの五秒とつづかなかった。 「眠狂四郎氏、止そうか」 十郎兵衛は、おちつきはらった声音で、言った。 「わしは、睡気が去った。睡らずに居れば、お主の殺法をふせぐことはできぬ。……まだ、死にたくはない」 まるで、この立ち合いは、「相ぬけ」のパロディのようになっているのが面白い。 柴田錬三郎のいう、 剣の道は、流派の如何を問わず、必ず「それ兵形は水に法る」という意味の教義を立てる。心形一致の水の妙形をもって「流」の極意とするところに、何々流「法形」が成る。この法形の神秘を悟った兵法者の眼光は、仏語的にいえば、所観の理に能観の知を対照会通して、微塵のくもりがない。すなわち、鏡のように全く澄みきって、対手の心を写しとる(「眠狂四郎無頼控」)、 とは、 奥に達するに三路、一は心形刀、一は形刀心、一は刀形心、 という言葉(常静子剣談)に通じる。 心(気)を磨くこと、 姿や動きを磨くこと、 刀法を磨くこと、 である(http://yamazakinomen.mizutadojo.com/joseishikendan.html)。島田虎之助も、 「其れ剣は心なり。心正しからざれば、剣又正しからず。すべからく剣を学ばんと欲する者は、まず心より学ぶべし」 と言っている(仝上)、とか。 最近のものをほとんど読んでいないので軽々に言うのは、はばかられるが、柴田錬三郎の文章に比べると、池波正太郎の『剣客商売』のそれは、いささか荒っぽい気がしてならない。場合によっては、脚本化されたテレビドラマの方が数段奥深くなっていたりするのは皮肉である。たとえば、 肉薄したが、こちらが動じなかったのを見るや、平助は飛び退って下段につけた。それを見て、 (突いて来る……) と、感じた瞬間、(秋山)大治郎が、わずかに左足を引き、腰を沈めた。 その大治郎の動きに乗じて、 「鋭!!」 気合声を発した鷲巣見平助が、木刀を下段につけたまま突進しつつ、 「たあっ!!」 一気に剣尖を垂直に伸ばし、大治郎の喉元を目がけて突き入れた。 猛烈きわまる突きの一手であった。 大治 郎の体がくるりとまわった。 一瞬、 (突かれた……?) と、見ている人びとの目には映ったやも知れぬ。 二人の体が、もつれ合ったようになり、道場の床板を踏み鳴らしつつ、見所の前まで移行し、そこで左右に飛びはなれたとき、 「う……」 鷲巣見平助が片ひざをつき、頭をたれた。 大治郎は腰を沈め、木刀を正眼半身に構えている。 と(「剣客商売」)。 なお、五味康祐『喪神』は、「物語」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/473489712.html)で触れたように、 瀬名波幻雲斎信伴が多武峰山中に隠棲したのは、文禄三年甲午の歳八月である。この時、幻雲斎は五十一歳―。 翌る乙未の歳七月、関白秀次が高野山に出家、自殺した。すると、これは幻雲斎の隠棲を結びつける兎角の噂が諸国の武芸者の間に起こった。秀次は、曾て、幻雲斎に就き剣を修めたためからである。 とはじまる「語り手」は、当初物語空間に登場してくる、という結構を採る。いささか重厚な文章は、後の作品にもつながっている気がする。 前出の、松浦静山『常静子剣談』に、 曰く「勝に不思議の勝あり。負に不思議の負なし」 問「如何なれば不思議の勝というや?」 曰く「道に遵い術を守る時は、その心必ずしも勇まずと雖も勝を得る。この心を顧る時は、則ち不思議とす」 問「如何なれば不思議の負なしというや?」 曰く「道に背き術を違う時は、敗れること疑いなし、故に爾に云」 とある(眠狂四郎無頼控、http://yamazakinomen.mizutadojo.com/joseishikendan.html)。 道に背き術を違う、 とは、どこかに原理・原則の王道を踏み外し失敗をしているということなのだろうか、なかなか難しい。相手のある中、相手との間の臨機応変の中で、踏み外さないためには、何か別のものが要る気がする。静山は言っている。 仕合をするには、高慢らしく有るは宜しからず。夫とて遜恭なるは宜しからず。唯平心にして勝負の處を得と胸に思て為すべし、 と。思うに、「平心」、 平常心、 とは、「無住心剣術」の、 心にとかくの作為があって勝負に臨めば、勝負にとらわれて、足がなかなか進まず、立ちが相手に届かない、 と通ずるが、素人の憶説が許されるなら、ある種の、 俯瞰する眼、 ではあるまいか。サッカーの優秀な選手は、試合中グランドを俯瞰している、という。それは、おのれから離れて、両者全体の動きの中で、おのれを動かせる、ということなのではないか、とは浅薄な我流の解釈である。 僕には、「眠狂四郎」の作品には、作家がそこを意識している眼があるように感じられた。たとえば、 一歩すさって、(白鳥)主膳は、大上段にふりかぶった。 とみた(男谷)精一郎は、ひたと、丸橋の構えをとった。右旋刀左転刀の刀法に変えたのである。 心形刀流の口伝秘書にいう。「右旋刀左転刀二カ条は、馬上にて敵に向う太刀打ちなり。敵、我が右へ来るときは、丸橋を用う。敵、我が左へ来るときは、青眼を用う」 とあって、元来これは、馬上剣である。 この技法を、地上相対峙のたたかいにおいて、敵の迅業を防ぎつつ、斬りかえす術に変化せしめたところに、妙があった。敵が、自分の左に馳せちがいざまに撃って来たら、丸橋にして之を受け、太刀を右に旋して敵の左を反撃する。敵が自分の右に来たら、青眼にとって、左転する。 ちょうど、精一郎の右側には、古樹を伐った巨株が、草の中にのぞいていた。 当然──主膳が、左側へ奔ると見たので、精一郎は丸橋の構えをとったのである。 ところが ──。 主膳は、両足を、右八字に開いて、綿でも踏むがごとく、すっすっと、精一郎の右側をのぞんで、間隔をちぢめはじめたのである。 ──しまった! 精一郎は、背すじに、氷柱をあてられたような戦慄をおぼえた。 もはや、丸橋から青眼へ、構え直すことは不可能である。構え直せば、隙が生じる。 精一郎は、蜘蛛の糸にたぐりよせられる昆虫と化したおのれを感じた。 ──どうのがれるか? 石火の間に、事理一体の心刀を魔神のごとく発しなければ、主膳の必殺の一撃をかわすことは叶うまい。 おそろしく長い秒刻が移った。 ──くるぞっ! その直感で、精一郎の肉体のいっさいの器官が、それへ備えて、動員された。 と(「眠狂四郎無頼控」)。 因みに、松浦(まつら)静山は、松浦清(まつら きよし)、肥前国平戸藩の第九代藩主。号は静山。随筆集『甲子夜話』が有名だが、心形刀流剣術の達人でもあった。『常静子剣談』(『剣談』とも)は剣術書である。「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」は野村克也の座右の銘として有名だ。静山は、明治天皇の曽祖父にあたるとか。 参考文献; 池波正太郎『剣客商売』(Kindle版) 柴田錬三郎『眠狂四郎無頼控』『眠狂四郎独歩行』(Kindle版) 甲野善紀『古武術の発見』(光文社文庫) 甲野善紀『剣の精神誌』(新曜社) |
-
関連ページ
-
リーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
管理者のリーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
目標達成のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
-
リーダーシップに必要な5つのことについては,【1】【2】をご覧ください。
-
リーダーシップチェックリストについては,ここをご覧ください。
-
発想技法の活用については,ここをご覧下さい。
-
管理者の意味については,「中堅と管理者の違いは何か」をご覧下さい。
-
管理者は何を問題にすべきかについては,ここをご覧下さい。
-
「管理者にとっての問題」については,ここをご覧下さい。
-
-
管理者の役割行動4つのチェックポイントについては,ここをご覧下さい。
-
OJTのスキルについては,ここをご覧下さい。各論は,それぞれ下ページをご覧下さい。
-
OJTプランのプロセス管理【1・2・3】
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションスキルは,コミュニケーションスキル①とコミュニケーションスキル②をご覧下さい。
-
コミュニケーション力チェックリストは,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションタブーについては,ここをご覧下さい。
-
職場のコミュニケーションは,ここをご覧ください。
-
マネジメントに求められるコミュニケーションスキルについては,ここをご覧下さい。
-
-
自己点検チェックリストは,ここをご覧下さい。
-
-
アイデアづくりは,日々 1つずつを実践している。それについては,ここを見てほしい。