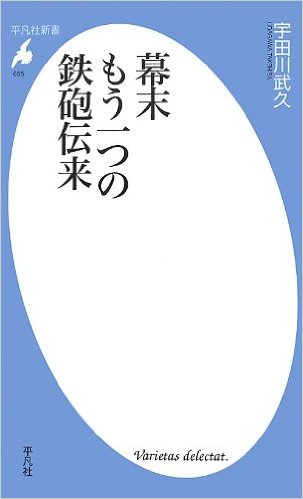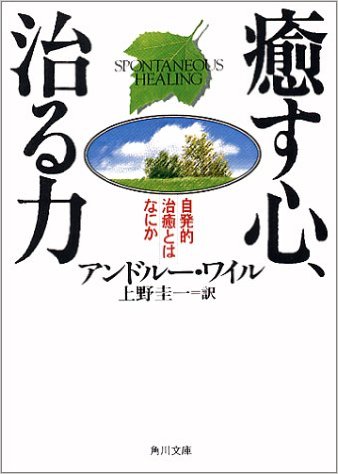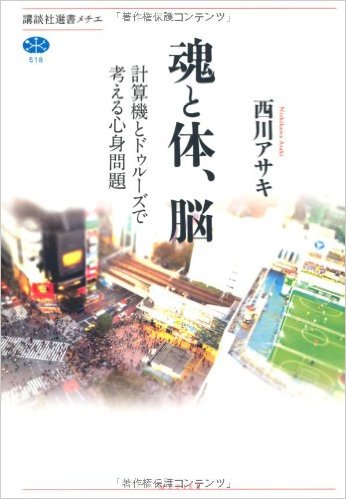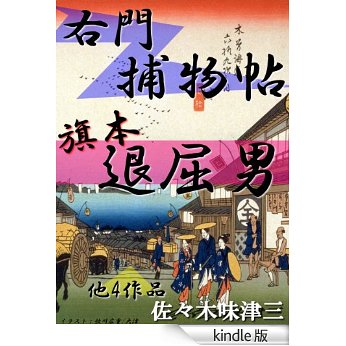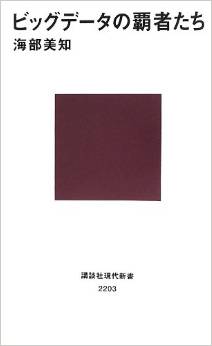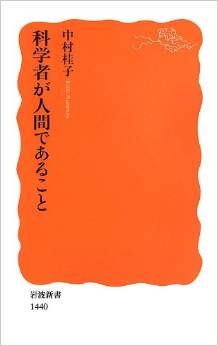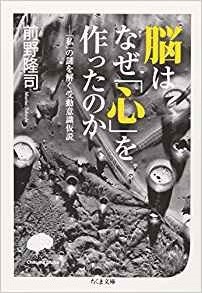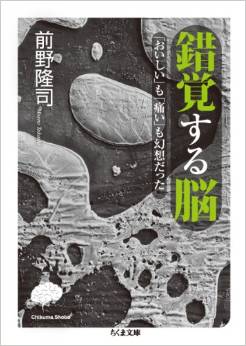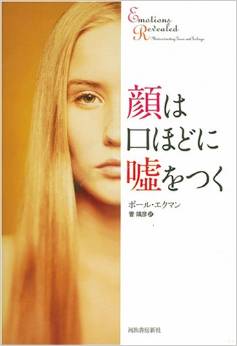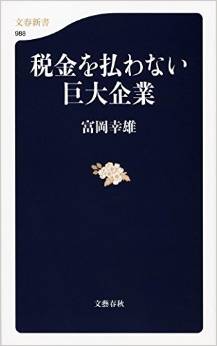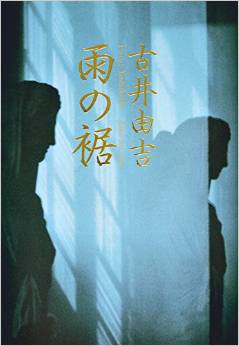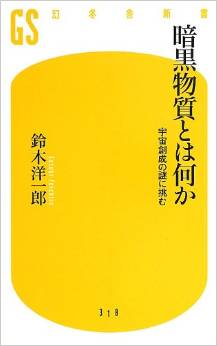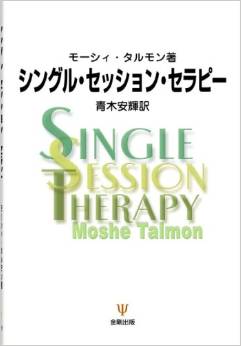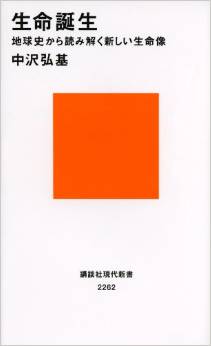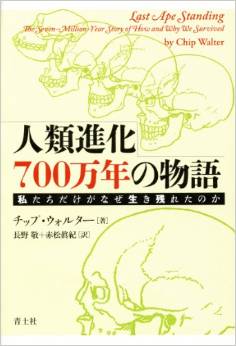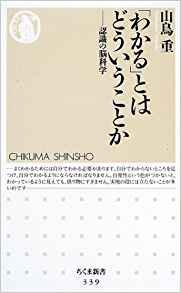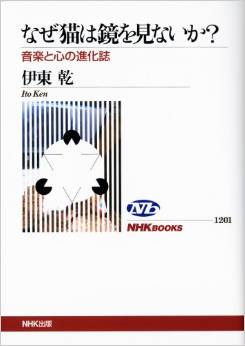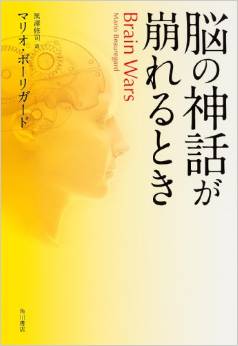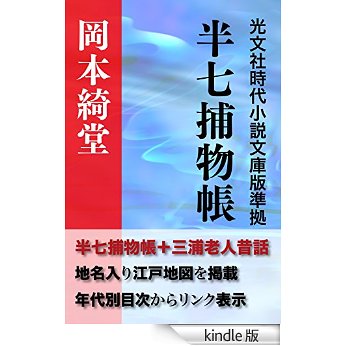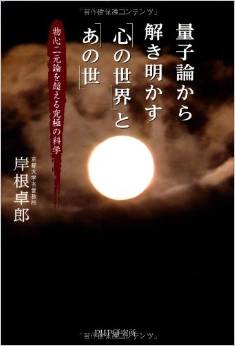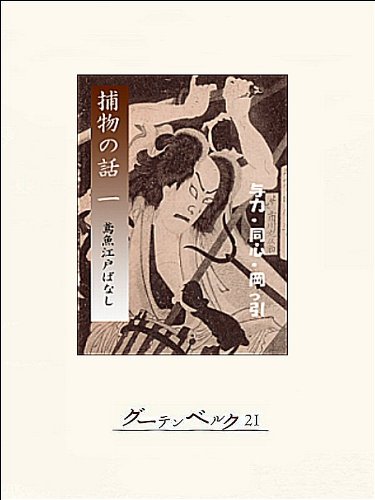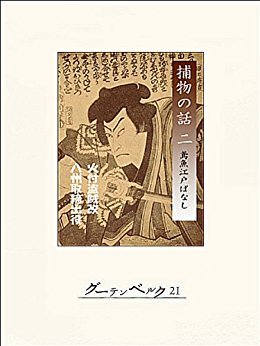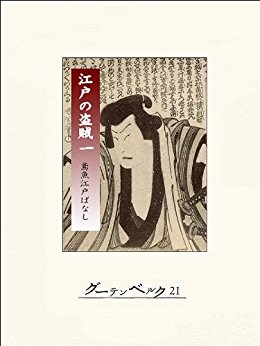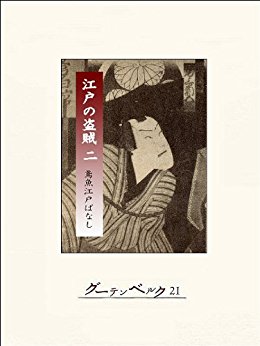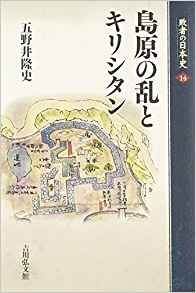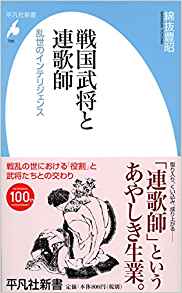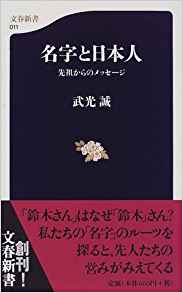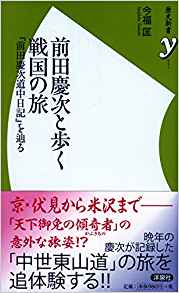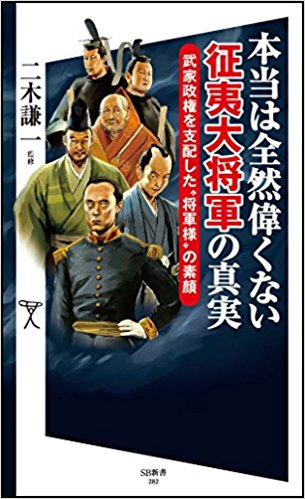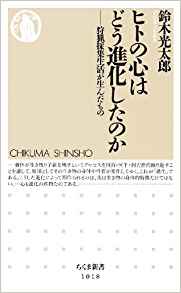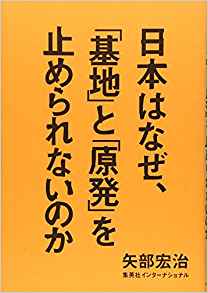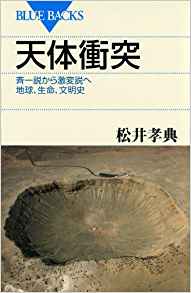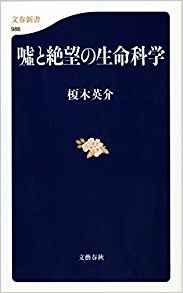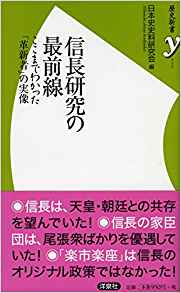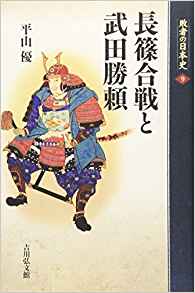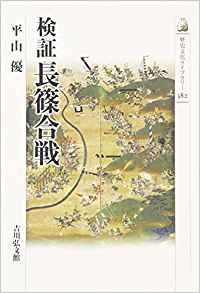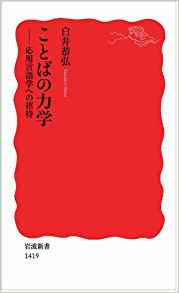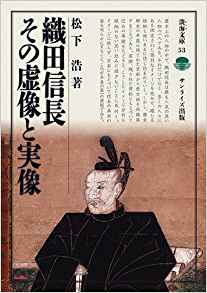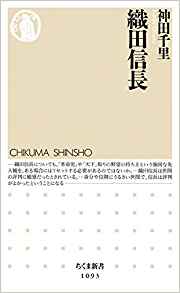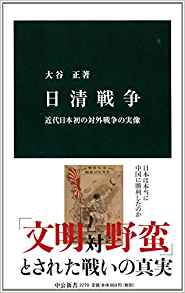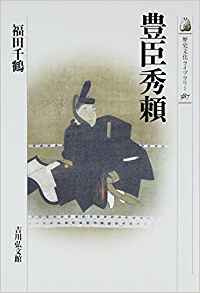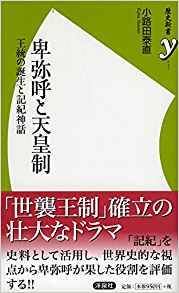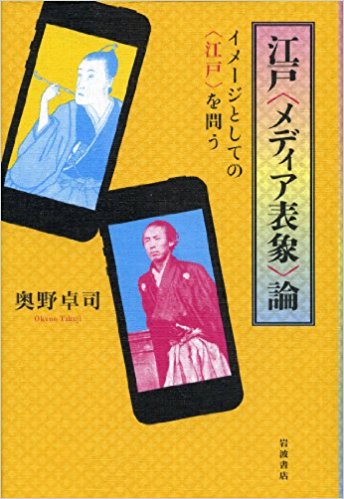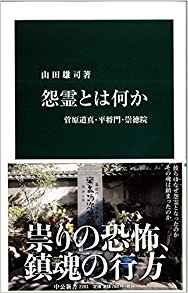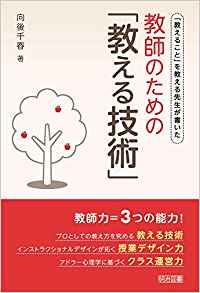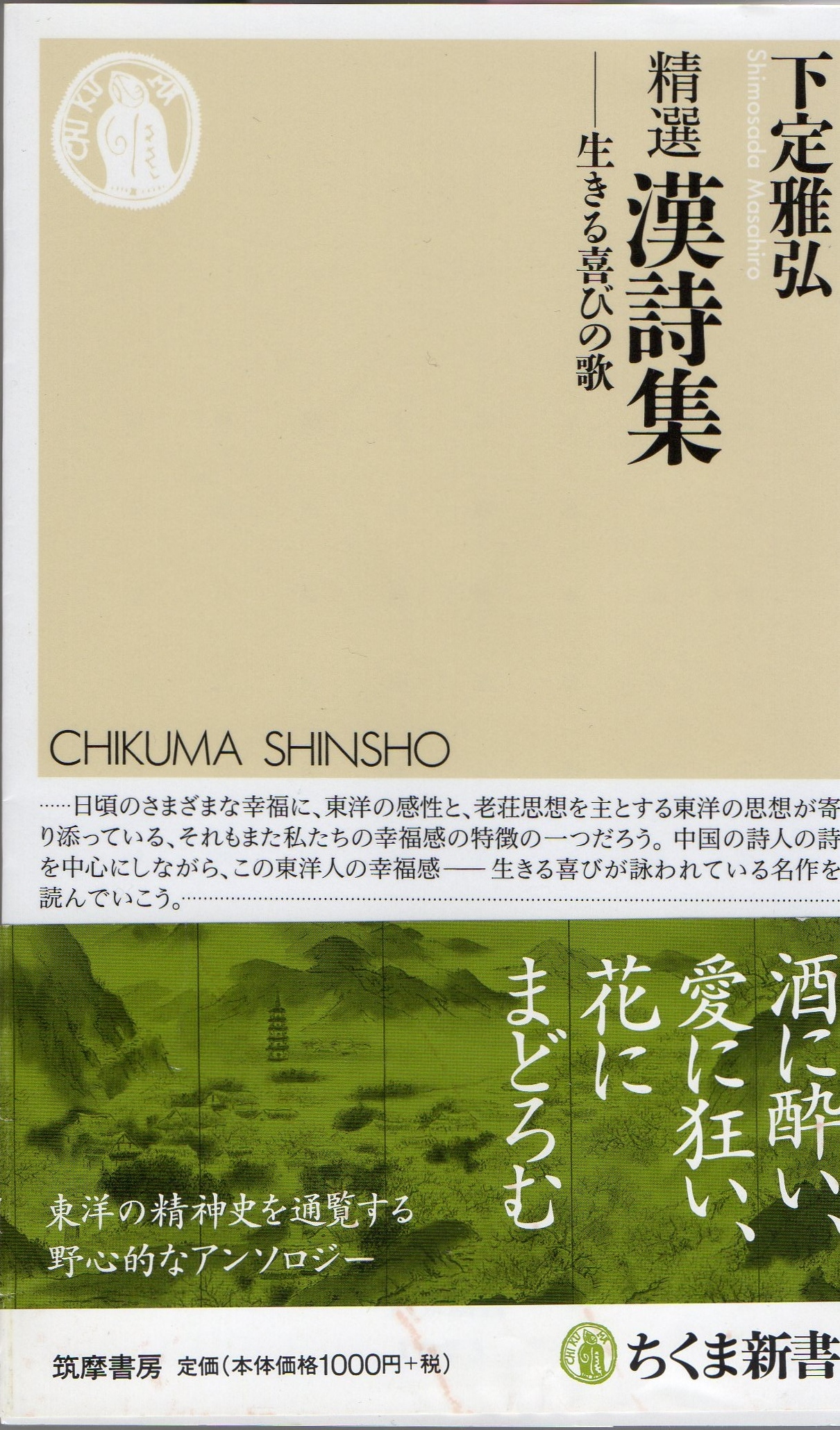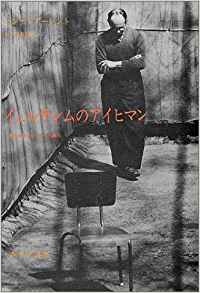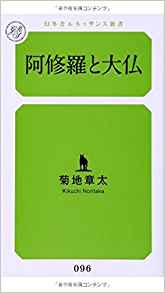|
砲術 |
|
宇田川武久『幕末 もう一つの鉄砲伝来』を読む。
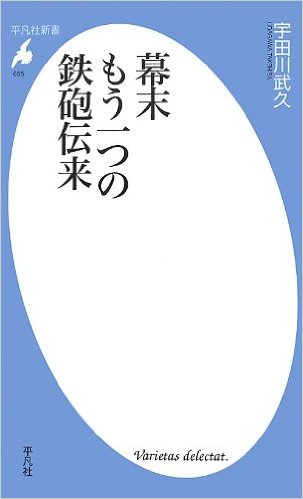
たかが大砲ながら,わが国では砲術と言われ,剣術と同じく,弟子入りして免許皆伝を得なければならない。日本で初めて西洋流砲術を取り入れた高島秋帆は,「兵制砲術書を通詞に翻訳させ,オランダ製の鉄砲を買い入れ,出島のオランダ人から教えを受けながら」,「砲術」を弟子をとって指南した。ただ,秋帆のすぐれたところは,幕府に招かれて江戸に入ると,
「一〇〇名近くの門人を演武の陣容に編成し…火砲と歩,騎馬によるモルチールの榴弾の仕掛打と焼夷弾,ホーウィッスルによる小形の榴弾の仕掛打と数打,馬上筒(燧石式拳銃)の射撃,鉄炮備打,カノン三連と燧石式小銃射撃」
と,曲がりなりにも,個人技ではなく,軍制としての射撃を見せたところだ。しかし,登用した水野忠邦が失脚すると,秋帆は獄に繋がれ,九年後のペリー来航まで西洋式は和式の個人技の後塵を拝することとなる。
本書は,幕末まで日本各地で営々と受け継がれてきた和流砲術を,その一家関家を中心に,
「幕末の砲術社会の全体像を知るためには,西洋流との競合を視野に入れながら和流の顛末」
を語ろうと意図している。いわゆる種子島の鉄炮伝来を,
第一次鉄炮伝来,
とするなら,
第二次鉄砲伝来,
と目すべきは,嘉永六(1853)年六月,アメリカのペリー艦隊の浦賀来航,翌年の日米和親条約締結等々を経て,祖法の鎖国が瓦解して,
「外国勢力の火砲船艦を眼前にして衝撃を受けた幕府は,海防のために西洋の軍事制度を模倣する軍制改革に着手した。幕府と諸藩の軍制改革の進行によって,わが国に西洋の鉄砲や軍事知識が大量に流入した。」
いわば,これが幕末第二次鉄砲伝来の衝撃である,と著者は書く。
鉄炮伝来以来,武芸としての砲術が誕生し,幕末には,西洋式も含めて,400近くの流派が流行したと言われている。しかし,明治政府による古流武芸の停止令によって,その多くの砲術資料が廃棄されてしまった。その中で,土浦の砲術家関家の資料が発見され,本書は,多くそれによりつつ書かれている。
「関流の祖は文禄四(1595)年生まれの関八左衛門之信であり,最後の宗家は文政十一(1828)年に生まれ,明治二十二年に病死した信順である。」
本書は,幕末を生きた,関流宗家の信威・知信・信順と三代の事績を西洋流の台頭と関連させながら編年的に追っている。
「関家は砲術を私の家業として継承したが,土浦藩家臣としての公務があった。」
とあるように,砲術は,稼業であり,「私」なのだ。それにしてもどうして,わが国では,スキルを私の秘伝・秘事として,一子相伝したがるのか。それが,スキルを社会の文化として共有化するという姿勢を欠く。茶道しかり,華道しかり,それは結局,私の金儲けの仕組みとしてしか考えられていなかった,というのは言いすぎであろうか。
砲術も,秘事化される。
「鉄炮が伝来すると,各地に鉄炮の取り扱いを教えることを生業とする砲術家が現れたが,その中から弟子に秘事を授ける流祖が誕生した。火薬は炭・硫黄・硝石を調合して作るが,その際,調合の比率,四季の温湿度を知ることが秘事とされた。通常,発射薬は玉の重さに比例し,一分玉だと一分で同量とし,三匁は玉の重さより幾分少ない。一〇匁で七匁,弾が大きくなると三分の一程度の割合になった。これを『薬積(くすりづもり)』の秘事という。」
鉄砲の仕様,撃つ姿勢にまで秘事はわたる。たとえば,
「鉄炮は銃身と銃床とカラクリ(機関部)からなり,銃身の筒元と先口には照準具の目当を取り付けたが,鉄炮の仕様は流派によって異なった。(中略)
鉄炮は姿勢と呼吸と引金の一致が重視され,膝台・立放頬付・伏せ構え・腰だめなどの射法があり,構え方,手足や顔の位置,距離の取り方を『目当定』の秘事といった。」
思えば,それは職人技と称賛される。しかし,ゼロ戦を製造するのにも,それを操縦するパイロットにまでそれが要求されるところに,日本の悲劇がある。あるいは,日々ビジネスマンにも,そういう個人技の変種を求めている。日本がソフトを汎用化できない,つまり,個人技に留める伝統から,未だに抜け出せていない。ゼロ戦については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163418.html
に書いた。
さて,では,弟子入りするとどういう手順で,皆伝に至るのか。
「弟子は大小の鉄砲を自由に扱えたわけではなく,一定の期間の修行を要した。関流の場合,入門の都市は一〇目玉(一〇目(匁)の玉の意味)正打(しょううち),二年目で二〇目玉正打,四年目で五〇目玉正打,六年目で目録,七年目で二〇〇目玉正打,八年目で小赦(こゆるし),九年目で三〇〇目玉正打,一〇年目で免許,最上級は九〇〇目玉の皆伝とした。」
十年掛けて,皆伝である。その間時代がどんどん変わる。とても,対応できるはずはない。さらに,
「秘事の伝授には内打(ないうち)と正打があり,内打は正打の前の非公式の伝授,正打は宗家や師範の所属藩の役人の立ち会う正式な伝授をいった。門弟は入門や伝授のたびに師匠に謝礼を届け,所属藩主からの謝礼もあった。これが宗家や師範の経済的基盤となった。」
当然弟子には,大名家もあり,江戸時代を通じて,
「丹波福知山・肥後島原・陸奥相馬・磐城・日向延岡,下総生実などの諸藩においては,関流が流行した」
とある。
しかし,威力の彼我の差は一目瞭然,ペリー来航の幕府は嘉永六(1853)年,
「鉄炮師胝(あかがり)市十郎に在来の鉄炮を西洋ゲーベル銃に改造」
させる。ベリー再来航には間に合わなかったが,個人技の各砲術指南家の背後には,それぞれ鉄炮鍛冶がおり,製造技術が背後にあることをうかがわせる。後年になるが,幕府は,安政二年から六年までの間に,6040挺のゲーベル銃を製作している。
「安政三(1856)年の春,ゲーベル銃製作のテキスト『銃工便覧』が版行された。…全国各地の鍛冶たちは,同書を片手にゲーベル銃の製作に挑戦し,洋式化を助けたが,その一方で,和銃を雷管式に改造することも全国規模でおこなわれた。」
この辺りの,キャッチアップする時のわが国の強みがいかんなく発揮されている。
この少し前,幕府はアメリカと条約締結した嘉永七(1854)年,軍事制度を洋式化する軍制改革に着手する。
「(秋帆の弟子江川英竜の子)江川英敏に湯島の鉄砲製作場で西洋小銃一万挺の製作を命じ,…オランダからゲーベル銃六〇〇〇挺を買い入れた。」
このゲーベル銃がモデルとして,全国の鍛冶が政策にいそしむことになるのである。こうした軍制の前に,個人技は,立つ瀬はなく,関流の関利喜助も,「西洋流の修行を拝命」するに至る。
個人技をどう全体のスキルとして共有化するかは,野中郁次郎氏の研究にも見られる如く,わが国組織・社会の宿痾に見える。
なお,幕末の鉄砲については,
http://www.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp/archives/4946
http://www.geocities.jp/irisio/bakumatu/arms.htm
http://portal.dl.saga-u.ac.jp/bitstream/123456789/120368/1/honda_201210.pdf
等々に詳しい。
参考文献;
宇田川武久『幕末 もう一つの鉄砲伝来』(平凡社新書) |
|
治癒力 |
|
アンドルー・ワイル『癒す心、治る力―自発的治癒とはなにか 』を読む。
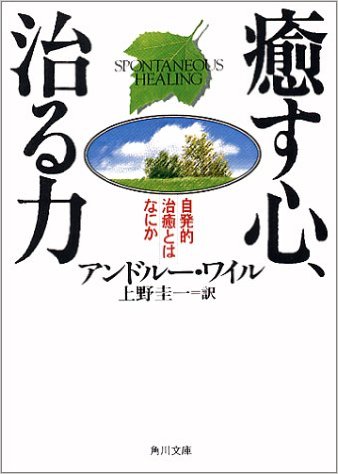
本書は,「自然的治癒」あるいは「治癒力」に焦点を当てて,「治療」ではなく(治癒力を高める)「健康」志向に,その具体的な処方箋にまで及んで懇切な解説がされている。その意図を,著者は,
「わたしは本書に『自然的治癒(Spontaneous
Healing)』というタイトルをつけた。治癒というプロセスの内在的・内因的な特性に読者の注意をうながしたかったからだ。治療が好結果をもたらしたときでさえ,その結果とは,別の条件下ではなんらの外部からの刺激なしに作動したかもしれないような,元々内部に備わった治癒機構の活性化そのもののことなのだ。本書のテーマはとても単純だ。からだには治る力がある。なぜなら,からだには治癒系(ヒーリング・システム)が備わっているからだ。健康な人でも治癒系について知りたいと思うにちがいない。いま健康でいられるのは治癒系のはたらきのおかげであり,治癒系にかんする知識があればより健康になることも可能だからだ。もし不幸にしてあなたが,またはあなたの愛する人がいま病気であれば,やはり治癒系について知りたいと思うだろう。なぜなら,治癒系にかんする知識こそが回復への最良の希望になるからだ。」
と述べている。その発想スタイルは,癌について,
「それは,たとえ初期のがんであっても,体内にがんができていること自体,すでに治癒系の相当の機能不全をあらわしているということである。」
という記述にみることができる。
「とはいえ,細胞が変異することと,がん性の成長をつづけ,宿主を死にいたらしめる力を得ることとのあいだには,根本的な相違がある。細胞が悪性に変異するとき,その細胞は表面の膜に異常な抗原を出現させて,あらたな自己証明を行なう。すると,その細胞の変異を,常時監視している免疫系が自己のからだに帰属していない『非自己』として認識し,それを排除する。無数の細胞分裂がたえまなく行なわれる一方,悪性変異を起こす可能性は常に存在する。がんのタネはたえずつくられ,免疫系がそれを確実に除去している。つまり,進化の途上でわれわれのからだが発達させてきた,がんにたいする防衛機構である治癒系の主要機能は,悪性細胞を除去する免疫監視機構なのである。」
と。しかし,自然治癒に委ねよ,などとは著者は言わない。
「病気になったときは,健康を回復するためにどうすべきか,どんな行動をとるべきかをきめなければならない。その一連の行動をきめるのは自分の責任である。その責任を回避すれば,自分にかわってだれかがきめることになるが,それが自分にとって必ずしも最良の選択になるとはかぎらない。もっとも重要な判断のポイントは,医師などの専門家に診てもらうことが心身の治癒系を助けることになるか,それともさまたげることになるかの一点である。」
として,こう忠告する。
「たとえば現代医学は,外傷の治療に非常に有効である。もしわたしが交通事故で重傷を負ったら,迷わず現代医学の救急救命センターに駆けこみ,シャーマンやイメージ療法家,鍼灸師のところにはいかないだろう。(中略)
現代医学はまた,診断と,あらゆる危機の対処にひじょうにすぐれている。出血・心発症・心臓麻痺・肺水腫・急性うっ血性心臓疾患・急性細菌感染・糖尿病性昏睡・急性腸閉塞・急性虫垂炎などは現代医学にかぎる。(中略)一般的にいって,きわめて深刻かつ執拗な症状,または通常の経験の範囲をこえていて,早急な手当てが必要だと思われる症状の場合は,現代医学を選ぶべきである。」
本書は,三部に分かれている。
第一部は,
「治癒系というものの存在をあきらかにし,こころとの相互作用をもふくんだ治癒系のはたらきをしめす証拠の提示にあてたい。DNAにはじまる生物学的組織のすべてのレベルにおいて,我々の内部には自己診断・自己修復・再生のメカニズムが存在し,必要があればいつでも活動をはじめる体制にある。この内在的な治癒メカニズムを活用する医学は,ただ症状をおさえるだけの医学よりもはるかに効果的である。」
というだけでなく,多くの経験談が挿入されていて,それは,
「自発的治癒はけっして稀なことではなく,しょっちゅう起こっている」
ということを,教えてくれる。しかし,それには,患者自身が,
「これ以上できることはない」
「病気と共存するしかない」
「あと半年のいのちだ」
等々という医師のペシミズムにめげす,回復した一人が証言するように,
「治癒への道のりは人によってちがうかもしれない。でも,道は必ずあるわ。探し続けることよ!」
と,諦めず,捜し続け,たずね続けることでもあるらしい。そのために著者は,こんな知恵を授けてくれる。
からだは健康になりたがっている。
治癒は自然のちからである
からだはひとつの全体であり,すべての部分はひとつにつながっている。
こころとからだは分離できない。
治癒の信念が患者の治癒力に大きく影響する。
そして,こう付け加える。
「治癒は内部から起こる。治癒の原動力は,生きものとしてのわれわれの,本然の力そのものから生じるのである。」
と。
第二部は,
「治癒系をうまくはたらかせるための方法が記されている。ライフスタイルを変え,眠っている治癒力を目覚めさせるための情報」
が満載である。そして,「ただひとこと,歩け!」として,
「からだの適度の運動とじゅうぶんな休息の機会をあたえることによって,自発的治癒が起こる機会をふやすことができる。
からだの運動はじつにさまざまな方法で治癒系のはたらきを活発にする。血液の循環をよくし,心臓のポンプ作用を強化し,動脈の弾力性を高める。と同時に,呼吸器系のはたらきを円滑にし,酸素と二酸化炭素の交換を促進して,からだが代謝産物を排出するのを助ける。代謝産物の排出はまた,呼気のいきおいと腸の運動によっても助けられる。さらに脳からのエンドルフィン分泌を促進し,抑うつ状態を改善して,気分を爽快にする。代謝とからだ全体のエネルギー効率を高める。ストレスを緩和し,深いリラクセーションと眠りをもたらす。そして,免疫機能そのものをも高める。(中略)
人間は歩くようにできている。からだが直立二足歩行で移動するようにできているのである。歩行は複雑な行動であり,歩行のためには感覚経験と運動経験との高度な機能的統合が要求される。歩行は筋骨格系のみならず,脳の訓練にもなる。歩行にともなう一要素でしかないバランスのことを考えてみればいい。凹凸のある重力場の表面で姿勢を変え,移動しながら,楽々と無意識のうちにバランスをたもつために,脳は膨大な情報処理を必要とする。その脳がたよりにしているメカニズムのひとつが,たとえば三次元空間で定位を感知する内耳の機関である。…脳はからだのバランスをたもつために,耳からの情報に加えて,視覚情報にも,それ以外の情報にもたよっている。皮膚の触覚受容体は脳に,からだのどの部分が地面に接しているかを知らせ,筋肉・腱・関節の自己受容体は脳に,空間におけるからだの各部分の正確な位置をたえず知らせている。」
等々。二か月で治癒力を高める,という具体的なプログラムまである。
第三部は,
「病気の対処法に関するアドバイスである。ここでは現代医学と各種代替療法それぞれの長所と短所をあきらかにし,治療に成功した患者が用いた戦略の数々を紹介する。わたしが提供するのは,現代によくみられる多くの病気の症状を改善するための自然療法である。」
しかし,著者は,こう付け加えるのを忘れない。
「自然療法には忍耐力が必要であることも覚えておいてほしい。現代医学の抑圧的なくすりにくらべて,自然療法の方法は効果が出るまでに時間がかかるのがふつうだからだ」
参考文献;
アンドルー・ワイル『癒す心、治る力―自発的治癒とはなにか 』(角川文庫) |
|
ゆらぎ |
|
吉田たかよし『世界は「ゆらぎ」でできている―宇宙、素粒子、人体の本質』を読む。

「この世にあるすべての物質は,常に揺らいでいる」
という文章で始まる本書は,「ゆらぎ」様々にわたって紹介していく。
ひとつは,量子力学の「粒子と波動の二重性」。しかし,
「では,物質がミクロの世界で波になっているというのは,具体的には何がゆらいでいるのでしょうか。…方程式を完成させたシュレディンガー自身でさえ,よく分かりませんでした。」
というしろもの。その答は,マックス・ボルンの,
「物質がその場に存在する確立」
が揺らいでいる,というもの。それに対して,アインシュタインが,
「神はサイコロを振らない」
という名言を残して,受け入れなかったのは有名な話。しかし,今日は,ボーア研究所の提案した,
コペンハーゲン解釈,
が大勢派になっている。つまり,「観測するまでは粒子がどこにあるか確率でしかわからないのに,観測した瞬間に位置が確定する」という考え方である。それを,アインシュタインは,
「私が見るまでは,月はあそこになかったのか」
と,コペンハーゲン解釈を皮肉っている。コペンハーゲン解釈に異をとなえる立場については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/421586313.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416694519.html
で,触れたところだ。
こうした「ゆらぎ」の究極は,「超ひも理論」であろう。物質を構成する最小単位の素粒子,10の−35乗という極小の世界には,34から36の素粒子がある,と想定されている(重力相互作用を生みだすグラヴィトンだけは輪になっているが,それ以外はひも)。この違いは,
「ひもの揺らぎ方が異なるために,別々の素粒子として観測される」
とされる。この説によれば,
「物質の存在自体も,その本質は揺らぎにある」
ということになる。この素粒子を構成するミクロのひもは,
「そもそも太さはないので,構成している材質もありません。ただ長さのみを持っていて,それが揺らいでいるだけです。(中略)ただ,揺らいでいるものは,点でもなければ面でもなく,短いながらも間違いなく線状のものです。点は0次元,面は2次元ですが,素粒子はどちらでもなく,1次元の線状のものが揺らいでいるのです。」
この証明は,現在の観測技術では難しいとされているが,宇宙の観測にわずかな期待がもたれている。
「長い宇宙の歴史の中で,最もエネルギーの水準の高かったのは,間違いなくビックバンの直後です。最新の研究では,現在,ビックバンから138億年が経過していると考えられていますが,宇宙のどこかに宇宙ひもと呼ばれる当時の痕跡が残っている可能性があり,これを発見すれば,超ひも理論が正しいと証明できるかもしれないのです。」
宇宙生命学については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/423899201.html
で触れたが,
「このミクロの揺らぎがもとになり,現在の宇宙全体の構造ができあがったということがわかってきた」
と,著者は続ける。銀河の配置には,その存在の粗密に揺らぎがある。それを,
泡構造,
と呼ぶが,つまり,
「何も存在しない,空洞のような部分を取り囲むように銀河が存在し,さらにまた隣の空洞のような部分を取り囲むように銀河が存在し,さらにその隣も同じような構造になっている」
という。それは,
「少なくとも宇宙が誕生してから38万年後には,物質の密度にほんのすこしだけ場所によって濃淡の差があったということです。いわば,こうした空間的な密度の揺らぎが種となって,宇宙の泡構造が育ったと考えられています。」
しかも,ビックバンを証明するマイクロ波背景放射には,周波数に揺らぎがあったことが発見される。それは,
「温度に換算すると,わずか10万分の一程度の不均衡さ」
である。
「火の玉のような状態だった誕生まもないころの宇宙は,物質がまったく均衡に存在していたというわけではなく,ごくごくわずかではありますが,濃いところと薄いところがあった」
しかし,その揺らぎが大きければ,今のような宇宙にはなっていない。
揺らぎとは,ある意味,不均衡ということである。たとえば,心臓は,揺らいでいる。
「心臓の鼓動がまったく揺らがず,完全に一定のリズムを刻み続けている」
としたら,脳死か重度の心不全,と言われる。生きているということは,振幅がある,ということだ。当たり前だが,妙にほっとさせられる。固定するということは,死んでいる,に等しいのかもしれない。
人は,
概日リズム
サブ概日リズム
概潮汐リズム
概8時間リズム
概2日リズム
概月リズム
と様々な周期リズムで,周囲の環境に適応するあそびを持っている。だから,人は,1日を,24時間ではなく,25時間で設定しているのも,そのせいらしいのである。
参考文献;
吉田たかよし『世界は「ゆらぎ」でできている―宇宙、素粒子、人体の本質』(光文社新書)
吉田たかよし『宇宙生物学で読み解く「人体」の不思議』 (講談社現代新書) |
|
二人称 |
|
西川アサキ『魂と体、脳 計算機とドゥルーズで考える心身問題』を読む。
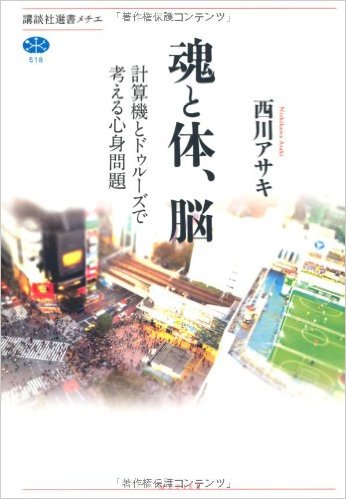
冒頭にこう書く。
「本当に存在するものは何だろうか?
私の『今・ここでの体験』だろうか? それとも,他人から見た『物質としての脳』だろうか? もちろん,両方だろう。ところが,そういった瞬間,『私』の体験と『他人からみた』脳を結ぶメカニズムが知りたくなる。しかし,他人からみた世界,三人称で語られる客観的物理的世界では,脳は複雑な回路にすぎない。そこに一人称の世界,『私』に体験できる質(クオリア)を『生み出す』機構は今のところ見つからず,今後もわからない。」
いわゆる心身問題が,この「三人称的世界=脳」と「一人称的世界=クオリア」の間の問題として現れる。で,
「一人称での心身問題の問いは,『この体験=クオリアから,どのように世界を構成するか?』という形をしている。一方,三人称の場合は,『脳はどのようにクオリアを生みだすのか?』という形になるだろう。」
と整理し,こう問う。
「では,『二人称』の心身問題の問いはどのようなものになるのだろうか?二人称の世界には『私』と『あなた』が存在する。だから問いも二つの方向性をもつ。つまり,(私からあなたへ)「あなたには,心はあるのか?」という方向,そして,(あなたから私へ)「私の体験が,分かるか?」の二とおりだ。」
その意味をさらに続ける。
「この問いかけ方は,きわめて個別的な存在,つまり『私』の前にいる『あなた』や,『あなた』の前にいる『私』が入っている点で,三人称の問い方と異なる。一方,『この私』以外の他者が,『世界にある事物一般の中に吸収され埋没してしまいがちな一人称とも異なる。もちろん二人称を,通常の心身問題に近いバージョンにすることもできる。」
そのニュアンスを,続けて,こう書く。
「たとえば『「この」脳に「あなたはいるか?』という形はどうだろうか? しかし,このときも『脳(一般)にクオリア(というもの)がどのように宿るか?』とは,少し異なるニュアンスが残存する。三人称には個別性がないし,一人称には個別性しかない。一方二人称というのは,その両者を結ぶ。そのとき,対面であることから生じる不確実性,緊張感が生じる。」
と,そして,この問題意識を前提に次の意図を読むと,本書の目指すものが見えてくる。
「ここで一歩引いた視点から,『心身問題』を一種の『ゲーム』だと考えてみよう。つまり,出発点として,『本当に存在するもの=実体』を選び,『選ばれなかったもの=非実体=錯覚』の出発点を説明するロジックを探すゲームだ。たとえば『実体』として脳をとれば,『非実体=錯覚』は『クオリア』だから,『脳がいかにしてクオリアを生みだすのか?』を説明するロジックを探すことが『心身問題』を解くことになる。逆に『実体』を『クオリア』にして同じゲームをはじめることもできる。」
「あるいは,『実体』として『何か新しいX』を持ち出し,『脳』と『クオリア』がともにそのXからくる『錯覚』だと視点を変えることもできる。」
ここで,著者は,その実体とするXを,ライプニッツの考えた「モナドロジー」という世界観を取り上げる。それは,
「まず『実体』としての『モナド』がある。(中略)『モナド』は,基本的には,我々の意識の特徴,つまり『単一で分割できないが,内部に表象=知覚=クオリアをたくさん抱え,変化する』という特徴を一般化したものだ。」
で,「クオリアを実体とする立場で『心身問題』を解く方法の,極端な形」だから,うってつけである。
そして,著者はもう一つ仕掛ける。ライプニッツのモナドロジーそのものを扱うに,それを論じるドゥルーズの『襞』をもってくる。モナドロジーの「あなた」を配することで,ある意味,実体化したクオリアに対比する「あなた」を配した格好に,二重に仕掛ける。それは,ライプニッツが,「モナドロジー」を文通という常に具体的相手を想定して展開したこととも重ねあわされている。それを,キルケゴールの『死にいたる病』にある(ある著作家の作品に知らぬまに誤字がまぎれこんだ)「誤字」の,
「この語字は自分が誤字であることを意識して作者に反抗しようとする。『いやだ。おれは抹消されるのを欲しない。おれはおまえをやり込めるための証人として,…ここに立っているのだ』」
この対話になぞらえる。この場合,どちらが実体でもいいのだ。で,
「実は本書では,冒頭で述べた『心身問題ゲーム』でのXとして,この形の不確実性,二人称の緊張感を持ってきて議論を展開しようとしている」
と。そして,ライプニッツのいう「支配的モナド」と著者の本書で使う「中枢」がキー概念となる。
「(中枢は)もともと著者がコンピュータ・シミュレーション用に考えた概念で,…次の条件を満たすシステム内の特殊な要素が『中枢』である。つまり,[1]それは,自分の属するシステム(身体)に対する縮図=概要を持ち,[2]それは,システムの他の要素に命令を下し,[3]それが失われると,システム全体の協調が破壊され,[オプション]多くの場合,それは唯一(の存在)である。」
という。しかし,集合知のように,「『中枢』的な命令者がいないにもかかわらず,全体として協調した機能…が出現=創発する」ことがある。にもかかわらず,多く,「中枢」が採用されている。
「だとするなら,その必要性はどこから来るのか? そこで,中枢なき集合知の出現=創発ではなく,『中枢それ自体の出現=創発に関するシミュレーションがあれば,『支配的モナド』や『実体的紐帯』(ライプニッツの持ち出した概念)を,より展開するための道具として使えるのではないかと考えた。」
その結果として,本書で最終的に「二人称としての心身問題」に行き着くことになった,と,著者は言う。当然これは,予想がつくように,「私」というものの発生,ということのシミュレーションになる。
著者自身も,「本書は飛ばし読みできない」と書いているように,前の章で展開した概念に依拠して次に進むというようになっているので,(手に余るが,仮にしようとしても)要約するのも難しい。上記の問題意識から,出された結論部分をまとめて,締めくくりとしたい。しかし,実は,本書は,ウロボロスのように,巻末が,巻頭へと戻るような仕掛けにもなっているのだが。
著者は,暫定的と断ってこうまとめる。
「中枢は恐らく二つのモードで体験されうる。一つは,他人の脳,それは体験にとっての不確実性が集中する場所である。これはいわば,三人称の中枢体験であり,または『図』としての中枢である。一方,もう一つのモードがある。それはさまざまな体験を位置づける場,安定した『地=フレーム』としての中枢だ。三人称としての中枢体験に対して,これを一人称の中枢体験と呼ぼう。一人称の中枢は,不確実性が集中する三人称としての中枢と相補的な,安定した背景として体験される。(中略)
別の言葉で言えば,一人称の中枢体験=地の安定性が,『空間』の原基であり,この構造が安定な時に限り,『脳に集中した不確実性=普通の心身問題』が出現できる。しかし,地としてのフレームが不安定になる=一人称としての中枢が不安定になるとき,不確実性は,他者の内部や,脳といった三人称の中枢にも,閉じ込められなくなる=集中しなくなる。すると,陰翳と窪みの間にある『ズレ』のように,異なるクオリア間の協調の不確実性が露呈する。」
この一人称と三人称の中枢が崩れるとき,「二人称の心身問題」,「エージェント間の協調可能性の吟味プロセスが露呈する」という。ここで「わたし」というもののことを言っている。最後に,その「わたし」について,こう締めくくる。
本書で再三取り上げられているシミュレーションは,「ロボットに組み込むプログラムを抽象化したもの」だという。それをロボットに戻した場合,
「ロボット内に自己組織化する『中枢=主体』と,その機能の研究の焦点が向かう。『わたし』は,『なぜ』必要なのだろうか? それを研究者がプログラムするのと,自己組織化させた場合の違いは何だろうか? 直感的には,そこで鍵になるのは,中枢の入れ子構造だと思う。たとえば,脳の場合,身体に脳という『中枢』があるように,脳内にはさらにワーキングメモリー実行系という『中枢内中枢』もあるとも解釈できる。もし,このような入れ子及びその動的な階層変更が,機能的な意味を持つなら,中枢を自己組織化させる場合にのみ生ずる機能があるかもしれない。プログラムを直接書いてしまうと,何レベル入れ子を作るかを先に決定する必要があるが,自己組織化の場合,それをダイナミックに解決してもらうことが可能だからだ。」
とすると,「わたし」と「あなた」の対話は,構造化され,中枢を生みだす,というように見える。いまのところ「わたし」をそう見ていいのか,とふと疑問に思う。いずれ,「X」を実体と仮定したものから始まったのであって,その対話もまた,脳のホログラフのようなものなのではないか。それは,心身問題のとば口を一歩もはいっていないのではないか,と。
参考文献;
西川アサキ『魂と体、脳 計算機とドゥルーズで考える心身問題』(講談社選書メチエ) |
|
分人 |
|
平野啓一郎『私とは何か――「個人」から「分人」へ 』を読む。

私事ながら,昔から,
本当の自分,
とか
自分らしく,
とか
ありのままの自分,
という言葉が大嫌いであった。それは,いまある自分への言い訳でしかない。いま,ここにいる自分以外には,自分はいない,その自分が,
ありのままの自分,
であり,
本当の自分,
であり,
自分らしさ,
そのものだと思ってきた。その自分から逃げられないのである。逃げないことが,自分の人生だからである。何度か自殺しそうになり,その都度思いとどまってきたのは,
自分以外自分の人生を生きていくものはいない,
からだ。著者は,
「個人から分人へ」
と題し,こう「まえがき」で書く,
「全ての間違いの元は,唯一無二の『本当の自分』という神話である。
そこでこう考えてみよう。たったひとつの『本当の自分など存在しない。裏返して言うならば,対人関係ごとに見せる複数の顔が,すべて『本当の自分』である。』
で,「個人(individual)」ではなく,inを取った「分人(dividual)」という言葉を,著者は導入する。
「分人とは,対人関係ごとの様々な自分のことである。恋人との分人,両親との分人,職場での分人,趣味仲間との分人,…それらは,必ずしも同じではない。
分人は,相手との反復的なコミュニケーションを通じて,自分の中に形成されてゆく,パターンとしての人格である。」
つまり,
「一人の人間は『わけられないindividual』な存在ではなく,複数に『わけられるdividual』存在である。」
というわけである。で,
「個人を整数の1とするなら,分人は,分数だとひとまずはイメージしてもらいたい。私という人間は,対人関係毎のいくつかの分人によって構成されている。そして,その人らしさ(個性)というものは,その複数の分人の構成比率によってけっていされる。」
人は,社会的存在である。確か,僕の記憶に間違いがなければ,人の存在は,人と人との関係の,
ノッド(結び目knot),
である。その意味でネットワークの結節点なのである。
「私という存在は,ポツンと孤独に存在しているわけではない。つねに他者との相互作用の中にある。というより,他者との相互作用の中にしかない。」
その意味では,その人がつながる人との側面,
「分人はすべて,『本当の自分』である。」
ということになる。だから,逆に言えば
「本当の自分は,ひとつではない。」
ということになる。その人の個性というのは,
「誰とどうつきあっているかで,あなたの中の分人の構成比率は変化する。その総体があなたの個性となる。」
という意味では,
「分人のネットワークには,中心が存在しない。なぜか?分人は,自分で勝手に生み出す人格ではなく,常に,環境や対人関係の中で形成されるからだ。私たちの生きている世界に,唯一絶対の場所がないように,分人も,一人一人の人間が独自に構成比率で抱えている。」
著者に言わせると,分人には,その対人関係の親疎に合わせて,
「不特定多数の人とコミュニケーション可能な,汎用性の高い分人」(社会的な分人)
「特定のグループ,社会的な分人がより狭いカテゴリーに限定されたもの」(グループ向けの分人)
「特定の相手に向けた分人」
の3レベルがあるが,
「社会的な分人が,特定の人に向けて更に調整されるかどうかは,必ずしも付き合った時間の長さには比例しない」
らしい。この,
多種多様な分人の集合体,
として,われわれは存在していいる,というわけだ。
「誰に対しても,首尾一貫した自分でいようとすると,ひたすら愛想の良い,没個性的な,当たり障りのない時分でいるしかない。まさしく八方美人だ。しかし,対人関係ごとに思いきって分人化できるなら,私たちは,一度の人生で,複数のエッジの利いた自分を生きることができる。」
あるいは,相手の対応しているさまざまな分人の振幅そのものが,
私,
という人間なのである。その意味で,確かに,
「私たちの人格そのものの半分は他者のお蔭なのである。」
だから,
「あなたの存在は,他者の分人を通じて,あなたの死後もこの世界に残り続ける。」
とは,例の,人は二度死ぬ,という意味の,別の側面から見た意味になる。そうして,「私」の死後も,相手の分人の中に「私」は生き続ける。
余談だが,f-MRI(機能的核磁気共鳴画像)で,脳の働きのマッピングが可能となり,一人の人間の中の,慎重な行動の「私」と衝動的な行動の「私」が共存することが,観察され,個人内葛藤と呼ばれている。「分人」が,f-MRIで確かめられる日が来るかもしれない。
参考文献;
平野啓一郎『私とは何か――「個人」から「分人」へ 』(講談社現代新書) |
|
職場学習 |
|
中原淳『職場学習論―仕事の学びを科学する』を読む。

著者は,本書の意図を,
「『人は,どういった支援を受けて成長するのか』,はたまた『どういう特徴を持った職場であったら,人々は助け合い,かかわりあいを持とうとするのか』…本書で筆者が探求したいことは,まさに,これである」
と述べる。つまり,「これまで,いわば『ブラック・ボックス』と化していた『職場における人々の学習』を,具体的には,
「人は,職場で,どのように他者とかかわり,どのような成長を遂げるのか」
また,
「人が成長する職場というものは,どのような組織的特徴を持っているのか」
について実証的に探究するのを意図している。
このベースになったのは,二つの調査である。ひとつは,「他者支援調査」,いまひとつは,「ワークプレイスラーニング調査」である。詳しくは本書を見ていただくことにして,本書のキーワードを著者は,次のように定義している。
他者は,仕事を達成する中で関与のある人」として,上司,上位者,先輩,同僚・同期,部下,である。
学習は,「経験によって,比較的永続的な認知変化・行動変化・情動変化が起こること」として非常に広範囲に捉える。
支援は,「何らかの意図をもった他者の行為に対する働きかけであり,その意図を理解しつつ,好意の質を維持・改善する一連のアクションのことを言い,最終的な他者のエンパワーメントをはかること」とする。
職場は,「責任・目標・方針を共有し,仕事を達成する中で実質的な相互作用を行っている課・部・支店などの集団」。
支援としては,
業務支援(仕事に必要な情報を提供してくれる,仕事の相談に乗ってくれるなどの業務に密接に関連する支援)
内省支援(客観的な意見を与えたり,振り返りをさせたりといった経験にメタ化の機会を与える支援)
精神支援(他者から与えられる,仕事の息抜きになる,精神的安息をえられるなどの支援)
がある,とする。さらに,向上する能力を,
業務能力向上,
他部門理解向上,
他部門調整能力向上,
視野拡大,
自己理解促進,
タフネス向上,
と挙げている。僕は,この能力の上げ方で,引いた。仕事ができる,あるいは,業務遂行能力が向上するとはどういうことか,について,基本的な齟齬を僕は感じた。ありていに言えば,職場で,
成長するとはどういうことか,
あるいは
成長するとは何ができることか,
あるいは,
成長するとはどうあることか,
という核の認識を欠いている,という気がしたのである。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/417632824.html
でも述べたが,アージリスは,能力を,
アビリティ
と
コンピタンス
をあげた。コンピタンスとは,
それぞれの人がおかれた状況において,期待される役割を把握して,それを遂行してその期待に応えていける能力,
であり,ある意味,役割期待を自覚して,そのために何をしたらいいかを考え実行していける力であり,その先に,いわゆるコンピテンシーが形成される。つまり,それは,
自分がそこで“何をすべきか”を自覚し,その状況の中で,求められる要請や目的達成への意図を主体的に受け止め,自らの果たすべきことをどうすれば実行できるかを実施して,アウトプットとしての成果につなげていける総合的な実行力,
である。アビリティとは,
英語ができる,文章力がある等々といった個別の単位能力,
を指す。どうも,多く,本書で言っている能力には,肝心の,
コンピタンス
が含まれていないのである。コンピタンスとは,
自分は何をするためにそこにいて(目的意識),
そのために何をするのか(役割意識),
である。これを,自己の,
ポジショニング,
あるいは,
立ち位置,
という。これなしの能力は,背骨のない付け焼刃でしかない。つまり,実践の場でチームの,職場の実践力にはならない。その意味で,本書の支援が,ただ,そこで与えられた役割をこなすのに必要な知識・スキル程度だとするなら,そんな人が何人集まっても,組織は生きないし生き残れない。主体的に動ける能力が育てられていないからである。
実は,本書を読みながら,かつて,たしか,若林満氏らが,
入社直後配属された上司次第で,伸びしろ(成長と置き換えてもいい)が決まる,
といった,十数年に渡る調査結果を,随分前に出されていたのを思い出していた。調べたが,多分該当するだろうと思われる引用文しか見つからなかった。
http://sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/BKK0000686.pdf?file_id=18084
には,こうある。
「若林ら(若林・南・中島・佐野,1980)は,初期キャリアにおける LMX(垂直交換関係)とキャリア発達との関係を明らかにするために,流通業の大卒男子新入社員
85 名を対象として 3年間にわたる追跡研究を行った.その結果,『入社後 1
年間の直属上司との垂直的交換関係』は,直属上司による『職務遂行』の評価や,人事記録から得られた『給与』や『ボーナス』などの『ハードな側面』と新入社員本人による『職務欲求』『職務充実』『職務満足』『組織コミットメント』など『ソフトな側面』の両面にわたって強く一貫した予測効果を見せた.ここでいう,『直属上司との垂直的交換関係』は,『自分が上司に理解されている度合い』『上司の期待が自分に明示される度合い』『上司が自分の意見や提案を受け入れる度合い』『仕事を離れたつきあいの度合い」などで測定されている.結果を見ると新入社員本人の高い潜在能力が,直属上司との良好な交換関係を通じて開花し,キャリア発達過程は『高い目標と挑戦→直属上司の理解と援助→目標達成→心理的成功体験→成長欲求の強化→より高い目標と挑戦」という好循環を形成していた.一方,『入社時に評価された潜在能力』は高かったが,『直属上司との垂直的交換関係』が低かったグループでは,本人の成長へのモチベーションが『抑圧』されてしまい,それはより深刻な『幻滅感』を生み出してキャリア発達が阻害される結果となっていた.これら入社後
3 年間のデータは,当該新入社員が係長に昇格する時点(入社 7 年目)と課長に昇格する時点(入社 13
年目)の人事データと関連づけてフォローアップがなされた.」
管理監督職昇進時まで追跡されて,その結果をフォローし,確かめているものであった。
ある意味で,そのコアとなるものは,
アビリティ
ではない,と思う。今でいう,(上司をモデルとした)コンピテンシーの育成ではあるまいか。
役割意識と目的意識は,
役割意識なくして目的意識はない
が
目的意識なくして役割意識はない
という関係にある。それが成長の軸で,どのポジション,どの職種についても,ついて回る。
その点では,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/prod062100.htm
でも書いたが,まずは,コンピタンスの確認こそが大事なのではないか。
自分は何のためにここにいるのか,
そのためにどういう役割を担うのか,
そのために何が必要なのか,
ここで初めて,必要なアビリティが明確になる。
その意味で,本書の職場学習には,本人がその組織で生きていくためのコアな軸を欠いているように思える。
ただ,第五章「職場コミュニケーションと『能力向上』」は,ある意味現実的には暗黙の裡にわかっていることだが,職場でどれだけざっくばらんな会話ができるか,が能力向上に資するというところは,その風土づくりは上司次第という意味も含めて,納得できる。しかし,かつて,
上司はその職場風土そのもの,
という常識があったが,筆者らは,ご存知なかったように思えてならない。
参考文献;
中原淳『職場学習論―仕事の学びを科学する』(東京大学出版会) |
|
山形有朋の靴 |
|
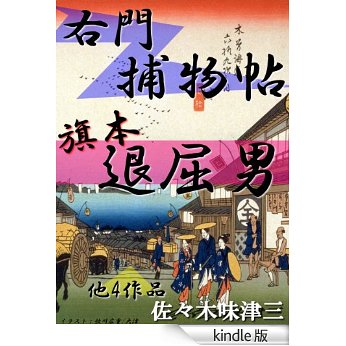
最近,ずっとニッチ時間を見つけては,Kindle版で,昔の大衆小説をぱらぱらと読んでいる。岡本綺堂や野村胡堂,佐々木味津三,林不忘と言ったところに辿り着いた。岡本綺堂については,何度か触れたことがある。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/418326441.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/418161213.html
等々,何度か触れたことがある。僕は個人的に言うと,岡本綺堂は,野村胡堂よりはるかに,文章も構成もまさると思うが,佐々木味津三,
http://www.aichi-c.ed.jp/contents/syakai/syakai/tousan/106/106.htm
というと,『右門捕物帳』や『旗本退屈男』は思い浮かんでも,東映の時代劇映画で,大友柳太郎の『右門捕物帳』や市川右太衛門の『旗本退屈男』しか知らず,原作を読む機会もなかったし,かつては,そんなに簡単に読もうにも手に入らなかった。だから,興味を惹かれて,原作を始めて読むと,映画の主人公のキャラクターとは随分イメージが違うことには驚かされる。しかし,あくまで小説の結構ということだけを考えても,またエンターテインメントとしての出来栄えとしても,現在から見ると(現時点の視点から振り返ると),まあ,映画の原案程度のレベルに見える。いまなら,どの賞にもかすりもしない気がする(失礼…!)。ただ,話自体は,面白いつくりになっていて,それだけに,映画作りには,格好の原作になった,という気がしてならない。
しかし,表題作についてきた四作品,どうやら佐々木味津三の晩年(といっても,37歳でなくなっているのだが)の作品群,「老中の眼鏡」「山県有朋の靴」「流行暗殺節」「十万石の怪談」はいい。「流行暗殺節」
http://www.aozora.gr.jp/cards/000111/files/1485_16865.html
もいいし,「老中の眼鏡」も,
http://www.aozora.gr.jp/cards/000111/files/1483_16864.html
悪くないが,特に,「山県有朋の靴」
http://www.aozora.gr.jp/cards/000111/files/1486_16867.html
には感心した。いまはどこででも,簡単に読めるが,こういう作品が,埋もれていたのか(僕が知らないだけだが),と妙に印象深い。
維新という時代の転換で,取り残された元旗本が,徳川幕府を倒した側の山県有朋の下男に落ちぶれ,有朋の靴を磨いている,という境遇にある。感情を失い,というか殺して,ただ無気力無感動に,淡々と過ごしている。しかし仮面のその表情の下にある,鬱屈がほんの些細なことで吹き出す,その悲しみが,僕にはよく沁みた。
よく考えると,映画のイメージで,作家を投影していたのかもしれない。他にも読めていないものがあるので,たまたまをそもそもとしているかもしれないが,
「佐々木の『右門捕物帖』は、嵐寛寿郎と山中貞雄によって「和製シャルロック・ホルムス」と銘打ち、
『むっつり右門』シリーズとして映画連作された。主人公の「むっつり右門」というあだ名、バスター
・キートンを手本にした無口なキャラクター、人差し指を立ててアゴに手を持っていく癖、これらはすべ てアラカンが創作したものである。
また登場人物の『あば敬(アバタの敬四郎)』、『ちょんぎれの松』も、アラカンや山中が創ったもの
で、映画に合わせて佐々木が原作小説に逆輸入したキャラクターである。『あば敬』の『村上』という姓も、映画でこれを演じた尾上紋弥の本名が『村上』だったことに因んでアラカンが思いつきでつけた。
『右門捕物帖』の設定は、このように嵐寛寿郎プロダクションで先行して創作され、佐々木の原作に採
り入れられていったのだが、当の佐々木は怒りもせず、『こんどの映画どうなる?』とアラカンに聞いてき
て、あべこべに映画の内容を小説のネタにしていた。」
「佐々木の代名詞ともなった作品『旗本退屈男』は、昭和5年にこれを読んだ市川右太衛門が気に入っ
て映画化。以後右太衛門の主演代表作となり、計31本の大ヒットシリーズとなった。」
等々,とあるから,映画のイメージが強いのは当たり前かもしれない。ある意味,映画を意識して,小説を書き,いまで言うと,テレビドラマの小説化のような,先駆けをやっていたことになる。その意味では,『旗本退屈男』のほうは,
「無役ながら1200石の大身。本所割下水の屋敷に住む。独身で家族は妹の菊路。他に使用人が7名同居。身長五尺六寸(約170cm)というから当時としては容貌魁偉な大男」
という原作とは,イメージが違うか,僕の年代だと右太衛門のイメージが鮮烈で,若さをあまり感じない。そのイメージのまま読むと,文章は,確かに,若い,眉目秀麗とあっても,それをスルーしてしまう。視覚で作られたイメージは強い。
「旧制愛知一中(現:愛知県立旭丘高等学校)を中退した後、明治大学政経科を卒業。雑誌記者の
かたわら小説を書き、1919年『大観』に載せた「馬を殴り殺した少年」で菊池寛に見出される。文壇
に姿を現した当初は純文学を志していたものの、父親が遺した借金の為に経済的環境が厳しく、長兄を早くに亡くした事で家族を養い、また家の負債を返す必要が生じたために大衆小説に転向。当時は
格下と言われていた大衆向け小説を書くことに抵抗を感じたが、芥川龍之介から激励を受け感激し、そのことが後々まで影響したと自著に記している。」
とあるので,その筆力を現実化するのに暫し猶予が要ったということか。しかし,
「しかし、自らの体力を削って無理な執筆を重ね、それが為に健康を害してしまい、若くしてこの世
を去った。その死は、現在でいうところの過労死であると言われている。37歳没。 また、小説家とし
て成功した後は弟や妹一家を東京に呼び寄せ、家計の面倒も見たという。」
とあるように,「有朋の靴」が,絶筆という。絶筆と聞くと,また感慨も少し動く。
参考文献;
佐々木味津三『右門捕物帳・旗本退屈男』(Kindle版) |
|
ビッグデータ |
|
海部美知『ビッグデータの覇者たち』を読む。
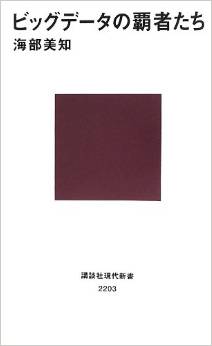
著者は,シリコンバレーに10年以上住んでいるが,エンジニアではない。むしろ,
「技術の話になると,実はエンジニアの話についていくだけで必死」
なのだという。その著者が,
「ビックデータという現象が,企業経営や消費者の日常生活にどのような影響を与えるのかという点から非常に興味を持っており,この本もその観点から書き進めていきたい」
と「はじめに」で述べる。ある意味在米体験を通して,利用者の目線で追っている,と言っていい。
で,著者は,ビックデータを,大まかに,
「人間の頭脳で扱える範囲を超えた膨大なデータを,処理・分析して活用する仕組み」
「『予測』『絞り込み』『見える化』がピッデータの得意技…集計や分析をくわえて何らかの意味を引き出す」
と説明する。いまのところ,「膨大なデータ」とは,
「数十テラバイト(テラ=2の40乗倍)からペタバイト(ペタ=2の50乗倍)といった単位のデータ量」
を想定するらしい。これは時々刻々膨れ上がっていくに違いない。われわれは,天気予報,グーグル,クレジットカードの不正防止,アマゾン等々で日々その恩恵を受けている。
そして,データは(ビックデータ業界では),
新しい石油,
に喩えられる。つまり,
「次世代の産業のコメになるかもしれない」
というわけである。2011年と,少し前だが,マッキンゼーのレポートでは,世界の地域ごとのデータ蓄積量が比較されている。それによると,
「2011年の推計新規データ蓄積量(累積ではなく,1年間に新たに蓄積される量)はアメリカが3500ペタバイト,ヨーロッパが,2000ペタバイト」
と,他の地域を圧倒している。日本は,世界で3番目ながら,400ペタバイトと,250ペタバイトの中国より少し大きい程度。著者は言う。
「ネットの自由度が低い中国と比べてもこの程度しか多くないのかと少々驚きました。」
考えてみれば,もちろん無機的データもさることながら,ツイッターのつぶやきやフェイスブックへの投稿有機的データでも,欧米に圧倒されているのである。これが,
「原料となる資源」
次世代産業のコメということを考えると,情報に対する,日本の為政者,企業経営者の感度の鈍さは,致命的ではないのだろうか(平気で公文書を廃棄し,改竄し,隠蔽する人々だからなぁ)。
「有機的データを使ったビックデータの手法は,…『従来の何かの代替』ではなく,『ネットでしかできないこと』をユーザーに提供する,新しいネット産業のサービスの屋台骨であり,激烈な競争を勝ち抜くための大きな差別化要因となっています。」
しかし,有機的データには,「プライバシー侵害」という陥穽がある。しかしネット企業は,敢えて火中の栗を拾おうとする。なぜか。著者は,その理由を,
「究極的には,『ビッグテータの活用がユーザーのためになる』,さらにそれゆえに『コストを下げ,利益を上げることができる』からです。」
と説明する。さらに,
「シリコンバレーの人々は,『世界を良くする』としいうスローガンをさらりと口にしますが,ビッグデータの分野でも,これをどう役立てるかという『志』は常に底流として持っています。」
という。目的意識と言い換えてもいい。それに比べて,日本の企業には『グローバル化』というお題目はあっても,
「根底に多くの人が共感するような志を持っていなければ,各国のユーザーや業界コミュニティに賛同してもらえません。」
と,日本の企業の志の無さに,巻末で危惧を述べている。そう言えば,たとえば,かつてソニーが会社設立趣意書で,
一、真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設
一、日本再建、文化向上に対する技術面、生産面よりの活発なる活動
一、戦時中、各方面に非常に進歩したる技術の国民生活内への即事応用
一、諸大学、研究所等の研究成果のうち、最も国民生活に応用価値を有する優秀なるものの迅速なる製品、商品化
と述べていたように,かつて製造業にはあった気がする。
閑話休題。
グーグル,アマゾン,フェイスブックといったウエブ企業を中心に,ビックデータの活用例を紹介しているが,いずれも,
「ビックデータ技術の力を自前でもっていなければ,ネットの世界ではもはや大きく成功はできないといってしまってもいいのかもしれません。」
というが,その展開は,ヒッグス粒子の発見といった科学の分野でもビックデータの活用は不可欠で,たとえば,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/421758173.html
で取り上げた,東京大学宇宙線研究所の低バックグラウンド多目的宇宙素粒子検出器XMASS(Xenon
detector for weakly interacting MASSive particles)実験のプロジェクトが,
「闇黒物質に蹴飛ばされたキセノンの原子核は,周囲のキセノンを電離させるなどの影響を与えながらエネルギーを放出して,最終的に止まります。蹴飛ばされたキセノンからエネルギーを得た,周りのキセノンは,紫外線を出して蛍光が発生します。その光が,642本の光電子増倍管が捕まえる信号」を,「長い時間をかけてデータを蓄積し,それを精密に解析することによって,初めて『発見』となるのです。」
と言っていたのも,また同じ例であるようだ。
ビックデータというのは,どこかにあるのではなく,日々の投稿,ツイッターをはじめとした個々のデータそのものが,資源になっていく。たとえば,2013年,アメリカ議会図書館で,ツイッター上の公開ツイートがアーカイブ化され,すべて閲覧できるようになった,という。
「06年の創業以来,これまでのツイートというと,その数1700億本,データ量にして133テラバイトだそうです。」
あほらしいようなツィートも,罵詈雑言も,すべて議会図書館に収蔵されたのである。この姿勢が,そもそも違う。これからは,こういう有機的データをどう使うかの時代になっている。著者は言う。
「もしかとたらビッグデータの技術は,今のグーグル検索やアメリカ議会図書館のツイッター・アーカイブのような形で,社会科学的な『知のプラットフォーム』を作る,という役割までで止まるかもしれません。(中略)それでも先進国で『モノを作る過程でマージンを生みだす』という富の創出の仕組みが終わった現在,『サービス業で富を生みだす』『社会的な難問を解決する』という次の反映を切り開くには,ビッグデータ技術などを使って,『知識を集めて増幅させる』という仕組み以外に,有効なやり方を私は知りません。」
人文科学系を潰そうとし,平気で文書を廃棄するわが国は,ひょっとすると戦後レジームの前へと先祖返りしようとしている分,既に世界の最先端から,遠く置いてきぼりを食っているような,気がしてならない。ツイッターをアーカイブにする,それが次世代の産業のコメという発想は,今の経団連のトップ経営者はおろか,わが国の為政者のどこにも無いに違いないのだから。
参考文献;
海部美知『ビッグデータの覇者たち』 (講談社現代新書) |
|
世界観 |
|
中村桂子『科学者が人間であること』を読む。
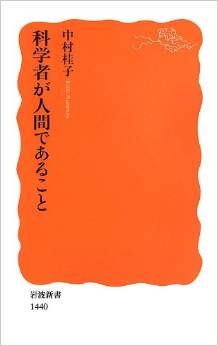
本書が描かれたのが,2013年。わずか二年で,日本国内のの風向きがガラリと変わってしまったことがよくわかる。その意味で,「おわりに」で,
「筆を進めながら常に思っていたのは,あたりまえのことばかり書いているということでした。特段新しいことはありません。けれどもあの大きな災害から二年半を経過した今,科学者が変ったようには見えません。震災直後は,原発事故のこともあり,科学者・技術者の中にある種の緊張が生まれ,変ろうという意識が見られたのですが,今や元通り,いやいぜんより先鋭化し,日常や思想などどこ見吹く風という雰囲気になっています。
それどころか今,『経済成長が重要でありそれを支ええる科学技術を振興する』という亡霊のような言葉が飛び交っています。ここには人間はいません。経済成長とは具体的にどのようなことで,誰の暮らしがどのように豊かに豊かになるのか,幸せになるのかという問いも答もありません。したがって科学技術についても,イノベーションという言葉だけしかないところに大きな予算をつけることが『振興』とされ,その研究や技術開発によって人々の日常がどのようになるかということは考えられていません。私達って人間なんですというあたりまえのことに眼を向けない専門家によって動かされていく社会がまた始まっているとしたら,やはり『科学者が人間であること』という,あたりまえすぎることを言わなければならないと思います。」
と書く言葉が,見事に今日への予言になっている。フクイチはまだ汚染を垂れ流し続け,到底コントロール不可能と見せつけているのに,早くも,原発の再稼働が,科学者のお墨付きではじめられている。そのことに対する,(真の)科学者自身からの,日本の科学あるいは科学者はどうあるべきか,の提言の書である。しかし,著者自身の予言した通り,元の木阿弥,たぶん,また同じ轍を踏むであろうことも,予想される。
本書は,
「50年近く,生命科学の研究に関与しながら,常に本当にこれでよいのだろうかと考え続けてきました。『人間は生き物である。自然の中にある』ということを,最新の生命科学研究の知識を踏まえて,『生命誌(バイオヒストリー,Biohistory)』という新しい知として提案し,近代を問い直して」
きた,著者の,震災を経験しての,(大森荘蔵,南方熊楠等々を参照しつつ)科学者としての在り方を問い直した本,となっている。その考え方は,
「西欧で生まれた科学そのものを否定するのではない方法で,科学という呪縛から解かれることが必要」
とするもので,たとえば,ゲノムを例にして,こう書いている。
「(ゲノムは)一つの細胞の中にあるDNA全体をさします。その性質を一言で表現するなら関係性でしょう。遺伝子と遺伝子,細胞間,さらにはある生物と他の生物との『関係性』『ネットワーク』を内に持つものと捉えることができます。そこで,地球上の全生物の基本物質であるDNAを個々の遺伝子とのみ捉え,個別に分析を進めていくだけでなく,一つの細胞の中にあるDNAのすべてをゲノムとして捉え『全体』を見ようと考えました。さらには生きものを38億年という長い歴史の産物と考える視点から生きものの本質を見るという知を進めることで,世界観の転換につなげたいと思ってきました。」
それは原発に関わった専門家の「狭い視野の価値観で動いていること」への批判となっている(またぞろ,懲りもせず復活してきているが)。著者は,そこに,
「自らもまた社会の中に生きる一人の『生活者』であるという感覚を失い,閉じられた集団の価値観だけを指針に行動している」
のを見る。それは過去のことではなく,今現在も,またぞろ大手を振って闊歩している。それは原発だけではない。たとえば,ヒトゲノム開発をめぐっても,
「日本の大型プロジェクトは…『ゲノムの解析が終わったのだから次はタンパク質でしょう』という単純な発想で,しかも3000億円のたんぱく質の構造をきめるという,量で勝負をするプロジェクトを巨額の資金を投入して始めました。ここには,ゲノム解析に到る研究の歴史や生命現象を考える姿勢,医療という応用へ向けての研究戦略などがまったくありません。これは,基礎研究としても,社会に役立つための研究として評価のできない進め方です。」
と,同様に,「狭い視野の価値観で動いている」,そう言い方は妥当ではないが,まるで金鉱を探す山師そのもののような専門家集団である,と僕には見える。著者は,アニメの『鉄腕アトム』の主題歌,
空を超えて ラララ 星の彼方
ゆくぞ アトム ジェットのかぎり
心やさしい ラララ 科学の子
十万馬力だ 鉄腕アトム
と,『きかんしゃトーマス』の主題歌,
じこがほら おきるよ
いいきになっていると
そうさ,よそみしているそのときに
じこしは おきるものさ
を対比しながら,科学に対する(日本と欧米の)見方の差を例示しつつ(「安全神話」自体があり得ない),
「専門家への信頼がなくなっている理由は,現在の科学そして科学者のありようそのものが間違ってからなのです。」
と,言い切る。そして,その突破口を,大森の,
「日常描写と科学描写の重ね描き」
に見出す。大森は,その意図を,
「私が富士山を見ながら立っている。それは乃ち,光波が私の眼に達し,わたしの脳細胞が興奮しているそのことに他ならないのである。物理学者や化学者はもとより,生理学者もまた,彼らの実験室の中での実際の研究ではこの『すなわち』の『重ね描き』にしたがっているのである。」
と説く。それは,
「科学をする者は科学と日常と思想とを自らの中に取り入れていなければならない」という,著者の思いと重なった瞬間である。それを,
機械論的世界観から抜け出す手がかり,
とし,それを,
「略画的世界観」(自分の眼で見,感じているときの世界像)と「密画的世界観」(近代科学の分解していく世界像)
の「重ね描き」という。それは,
「『科学的』だからといって,密画のほうが略画より『上』なわけでも,密画さえ描ければ自然の真の姿が描けるわけでもないということです。密画を描こうとする時に,略画的世界観を忘れないことが大事なのです。」
という。これは,著者の言う「あたりまえ」のことなのかもしれない。しかし,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163312.html
で触れたように,
サムシング・グレート
という,西欧の科学者には,信仰心と両立させるマインドがある,それを別の言い方で言っているように見える。それ抜きなら,試験管で子供すら創り出すことを,心に何のこだわりもなく,やってのけてしまう。それは,
すべてがわかるわけではない,
という謙虚さに通じる。熊楠は,
「科学哲学は仏意を賛するものとでも見て」
と,自分流に表現している。著者は,大腸菌の遺伝子4100個から,「重要な代謝経路の遺伝子」を欠いても大腸菌は生き延びる,という例を挙げて,
「生きものはその場その場に応じて適当に対処するのです。生物医学では,このような性質をもつものを全体像はまだわからないままに技術に用いるわけですから,『わかっていない』ということを忘れずにいることが大事です。」
と,述懐する。しかし,我が国では,隅々まで,科学神話に陥る余地がある。「きかんしゃトーマス」と「鉄腕アトム」の差は,意外と大きいのかもしれない,と思い知らされるのである。しかし,国立大から,文系を消そうという方向の行き着く先は,金になり,役に立つなら,人体実験でも,戦争でもなんでもする,といういつか来た道に通じるような気がしてならない。
参考文献;
中村桂子『科学者が人間であること』 (岩波新書) |
|
人体 |
|
吉田たかよし『宇宙生物学で読み解く「人体」の不思議』 を読む。

http://ppnetwork.seesaa.net/article/420205932.html
で取り上げたのが,地球史の中で生命起源を探ろうとするものであった。しかし,本書は,端から,生命由来を宇宙と決めてかかっている。そういう成りたちの学問のせいか。
宇宙生物学とは,
「地球に限定せず,宇宙全体の広い視野で生命の成り立ちや起源を解明する学問で,アストロバイオロジーと呼ばれています。」
という。たとえば,その宇宙生物学が挑んでいる最大のテーマの一つが,
「生物を生みだすアミノ酸が宇宙のどこからきたのかを解明すること」
とあるのがいい例だ。そして,暗黒星雲にアミノ酸を発見すべく,壮大なプロジェクトがスタートしている,という。なぜアミノ酸か。
「生命とは,アミノ酸を組み合わせて作られた精密機械」
だからである。いま,
「アミノ酸は,地球上ではなく宇宙空間で合成されたものだという説」
が浮上しつつある,と著者は言う。なぜなら,
「地球上の大半の生命は,ある特徴を持ったアミノ酸しか使用していない」
という「生命の七不思議」があるのだという。
「アミノ酸には右型と左型の2種類のタイプがあります。(中略)鏡像対象になっている2種類のものが存在し,それぞれ右型と左型といいます。試験管の中で普通に化学反応を指せてアミノ酸を合成すると,右型と左型は,ちょうど50%ずつ出来上がります。(中略)ところが,不思議なことに,この地球上で生きている生命は,大半が左型のアミノ酸だけしか利用していないのです。」
その不可思議さも,
「宇宙で誕生したアミノ酸から地球上の生命が誕生したと考えれば,都合の良いストーリーが組み立てられます。実は,もともと太陽系には,左型のアミノ酸のほうが多かったと考えられるのです。実際,現在でも,宇宙からやってくる隕石を分析すると,左型のアミノ酸が多いことが確認されています。」
なぜならば,円偏光と呼ばれる紫外線の性質が関わっている,という説があるらしいのである。
「電磁波の中には,波が伝わっていくときに振動する向きが円を描きながら回転するという特殊タイプがあり,これを円偏光と言います。波が回転する方向が右向きなら右円偏光,左向きなら左円偏光というのですが,右円偏光の紫外線が当たれば右型のアミノ酸が壊され,左円偏光の紫外線が当たれば左型のアミノ酸が壊されることが確認されています。どうやら太陽や太陽系ができる前には,宇宙の中のこの領域では,右円偏光の紫外線多く放射されていたようなのです。これにより右型のアミノ酸だけが壊れたため,比較すると左型が多くなり,それが現在の生命にも受け継がれていると考えれば,矛盾なく説明が可能です。」
その宇宙由来のアミノ酸同士を結合させ生命活動を担うタンパク質に成長させるゆりかごとして,
「注目を集めているのが,熱水鉱床と呼ばれる場所です。(中略)この熱水鉱床では,アミノ酸同士が自動的に結合することがわかっています。海底の熱水鉱床では,高温高圧のため,水は超臨界という特殊な状態になっています。これにより,脱水縮合反応と呼ばれる反応が起き,アミノ酸がつながるのです。」
と,このストーリーが可能であるなら,
「地球外生命が存在する場所として,がぜん,期待が高まるのが,木星の衛星のエウロパです。エウロパには広大な海があり,しかも海底には熱水鉱床が広がっている可能性が高いからです。」
と,宇宙へと視野を広げていく。
もともと生命の源となった海水の大量の水分は,「彗星」に由来している,と考えられている。
「42億年前から38億年前にかけて,彗星が次から次へと大量に地球に衝突しました。彗星は,別名『汚れた雪だるま』と呼ばれています。その名のとおり,彗星を構成している成分は,ほとんどが水の凍ったもので,その中に少量の有機物などが混ざっています。(中略)人間の構成要素のうち,地球に由来した物質はわずか30%に過ぎず,人体の70%は本を正せば彗星だったということになります。」
しかも,もともとその水分にはナトリウムはほとんど含まれていない。海を塩水に変えるのに月が果たした役割が大きいとされている。いまでも,月は年々3.6㎝ずつ地球から遠ざかっているが,それは時代を遡るほど地球に近かったということを意味する。
「ジャイアント・インパクト」説によると,45億年前,火星サイズの惑星が地球に衝突し,その破片が集まったのが月とされている。その時点で,現在の1/12位の距離に月があった。引力は12乗,つまり144倍,「誕生当初の海では現在の100倍以上のエネルギーで潮の満ち引きが行われていた」ことになる。
「月は今の4倍の速さで地球の廻りを回っていたのですが,地球の自転も早く,6時間で一周していました。…つまり,当時は干潮と満潮が1時間半ごとに繰り返しおとずれていたわけです。」
その結果,地殻は潮の流れで削られ,ナトリウムが一気に融け出した,と考えられている。
「体内の細胞は,ほとんどすべてが何らかの形でナトリウムを利用して活動していますが,その中でもとりわけ大きく依存しているのが神経細胞と筋肉細胞です。神経も筋肉も,細胞膜にナトリウムイオンを通す穴が空いており,ここを通ってナトリウムイオンが細胞内に入ってくると,神経細胞は興奮状態になり,筋肉細胞は収縮を始めます。」
つまり,ナトリウムを媒介にしなければ機能を果たせない,ということになる。だから,
「人体では,血液もリンパ液も,ナトリウムイオンの濃度が135〜145mEq/Lの範囲内に収まるよう,厳密にコントロールされている」
特に,濃度が110mEq/Lを下回っただけで,全身の筋肉が痙攣し,脳内の神経細胞が異常をきたし昏睡状態に陥る,という。
少なくとも,宇宙由来かどうかは別として,いまの地球の誕生以来の経緯が,わずかでも狂っただけで,われわれが存在するにしても,よほど今とは変わったものになっていた可能性は高い。
生命誕生の環境という意味で,この広い宇宙の在りようが,いまをもたらしていて,それが,身体の細部に大きな影響を与えている,ということは,癌を考えただけでも奥が深い,ということが見えてくる。本来(地球上に酸素はなかったため)嫌気性であった生物が酸素を利用することで,爆発的な進化を手に入れたが,それは,(ウラン236の不安定さを使う)原子力の利用に似ている,と著者は書く。
「人体は有機化合物と酸素分子を反応させ,二酸化炭素と水に変えることでエネルギーを取り出しています。2つの酸素原子が結合した酸素分子の状態に比べると,酸素原子が炭素原子と結合している二酸化炭素や,酸素原子が水素原子と結合している水の状態のほうがはるかに安定的です。この大きな落差が人体活動を支えるエネルギーの根源となっているのです。」
しかし,そのおかげで,
「その巨大なエネルギーを使って細胞を爆発的なスピードで増殖できる能力を手にしてしまいました。実際条件さえ整えば,人間の細胞はわずか20時間で分裂できるので,細胞の数は20時間ごとに2倍に増え続けることが可能なのです。」
その結果,
「たった1個の癌細胞でも倍々ゲームで増殖することで,1ヵ月が経過すると700億個に増殖することになります。」
著者曰く,
「酸素の利用は,生命が高等生物に発達するうえで不可欠なことでしたが,同時に癌というパンドラの箱を開けることにもなったのです。」
と。しかも,癌で死亡る割合は,チンパンジーでも2%,人間は,日本人で30%の死亡率で,これは,脳の巨大化と関わる,と最近見なされるようになった,という。脳は,6割が脂肪でできており,そのため,
「人間が脳を急激に発達させるためには,死亡を作る能力を高める必要があり…,実際ブドウ糖から脂肪を合成する能力を比較すると,人間は哺乳類の中で傑出して高いのです。」
それが,癌を宿痾とすることにつながった,ということになる。
参考文献;
吉田たかよし『宇宙生物学で読み解く「人体」の不思議』 (講談社現代新書) |
|
ニューラルネットワーク |
|
前野隆司『脳はなぜ「心」を作ったのか』を読む。
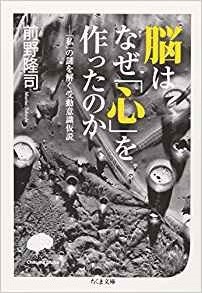
著者は,冒頭でこう言い切る。
「ある日,『心』と『からだ』の成り立ち方はだいたいおなじではないか,と考えているときに,急に心の謎を解く手がかりがひらめいた。私は,生物の脳が,なぜ,なんのために心を作ったのか,そして心はどんなふうに運営されているのか,という心の原理を理解したつもりだ。」
と。そして,
「心が実に単純なメカニズムでできていて,作ることすら簡単であることを,誰にもわかる形で明示できる。これまで心の謎だと言われていた事柄にもほぼ堪えられる。だから,近い将来,心を盛ったロボットを簡単に作れるようになるだろう。」
とも。それが,サブタイトルの,「『私』の謎を解く受動意識仮説」である。著者は,「意識」の主要な謎,
〈私〉の不思議
バインディング問題
クオリア問題
を順次,著者流に解き明かしていく。その際,著者は,「自分」「私」〈私〉を,
「自分」とは,自分のからだと脳を含めた,個体としての,あるいはハードウェアとしての自分,
「私」とは,前野隆司(それぞれ一人一人)の「意識」のことだ。前野隆司の現象的な意識を指す。
〈私〉とは,ものやことに注意を向ける働き(awareness)を除いた自己意識について感じる部分,
と,区別する。
「〈私〉とは,自己意識の感覚―生まれてからこれまで,そして死ぬまで,自らが生き生きと自分の意識のことを振り返って,ああ,これが自分の意識だ,と実感し続けることのできる,個人的な主体そのもの―のことだ。」
これを,
自己意識のクオリア,
と呼ぶが,それは,
錯覚にすぎない,
といい,「心を盛ったロボットは簡単に作れる」とまで言うのである。触覚を専門とする著者は,たとえば,
「私たちは指先で何かに触ったとき,熱いか冷たいか,つるつるかザラザラかを瞬時に,しかも指先で感じるような気がする。しかし指先にはマイスナー小体やメルケル小体といった触角のセンサがあるだけでせ,脳はない。だから,当然,熱いか冷たいかとかつるつるかざらざらかといった情報を皮膚は計算することは決してできない。なのに,どうして触角のクオリアを指先でかんじるのだろうか。」
それは,脳で計算されたあとに,「あたかも感覚器のある場所で感じたかのように見せてくれている」ということになる。例のリベットの,何かを取ろうとする動作を,
意図したよりも350ミリ秒(0.35秒)早く,無意識下の運動準備電位が生じ,実際に指が動いたのは意図した200ミリ秒(0.2秒)後であった,
という実験が示しているのは,
「人が『意識』下でなにか行動を『意図』するとき,それはすべてのはじまりではない。『私』が『意識』するよりも少し前に,小びとたちは既に活動を開始しているのだ。」
ここで小びとと著者が準えているのは,
何らかの機能をこなすニューラルネットワーク(脳の神経回路網)のモジュールの比喩,
である。言い方は変だが,何かを意図したのは,そう意図するように脳が働きかけているからだ,ということになるる。たとえば,脳はこういうこともする。
「感覚受容器から大脳新皮質の感覚野まで信号が伝達するのに要する時間は,感覚ごとにに違う。目の網膜で光を受け取ってから,その信号が脳の第一次視覚野に到着するには0.05秒かかるのに対して,鼓膜から第一次聴覚野までは0.02秒しかかからない。なのに,光と音が同時に目と耳に到着したとき,人は,同時か,または,むしろ光の方が早いように感じる。これは,信号の届いた時刻を,脳が都合のいいようにずらしている結果だ。」
たとえば,
「大脳皮質を刺激したときには,指に刺激を与えたときよりも,『意識』されるタイミングが0.5秒もおくれるのだ。これも奇妙な結果だ。体性感覚が活動し始めてから,脳の『意識』をつかさどる部分が触感覚を『意識』するまでに0.5秒もかかるのだとしたら,実際に指が何かにさわった時に瞬時に触感覚を『意識』できることを説明できない。」
として,著者は,
「『意識』するタイミングは,錯覚」
だと考える。
「いまというタイミングが,実は今だと思っている瞬間よりも,本当は少し遅いのに,それが(脳に)ごまかされている…。」
ということになる。で,
「小びとたち(無意識)は『私』(意識)にしたがっているのか,それとも,『私』(意識)は小びとたち(無意識)にしたがっているのか」
を,著者は,
心の天動説(「私」中心の世界観)
と
心の地動説(「私」は受動的)
と呼ぶ。もちろん,「受動意識仮説」の由来は,ここにある。
「つまり,『私』や〈私〉は世界の端っこにいて,無意識の小びとたちの『知情意』の結果を受け取るだけの脇役」
なのだ,ということだ。たしか,エリクソンは,放れ馬を例に,馬が帰り道を知っていると,無意識に喩えた。その意味ともつながる気がする。
著者は,心を昆虫の反射行動に準えて,「それと大差ない」という。進化の流れから考えたとき,
「進化というのは,真っ白な設計図にゼロから新しい生物のデザインをするような,華麗で創造的なものではない。」
のであり,それは体だけではなく,脳の神経系もそのはずではないか,という著者の指摘に,僕は賛成である。
「もともと下等な生物がもっていたニューラルネットワークを,…新しい情報処理ができるように設計変更しているのだ。このように考えると,受動的な『意識』という考え方は,実は下等な生物のやり方と似ていて,理にかなっている。
能動的な『意識』が存在すると考えようとすると,『意識』をもたない動物から『意識』をもつ動物への進化は,あまりにも不連続に思える。」
で,自説をこう説明する。
「私が述べてきた『無意識』の小びとたちとは,実は,昆虫の反射行動と同じように,…複雑なフィードバック結合が巧みに組み合わされていることに他ならない。」
それは,
「自動的な『私』は,前肢が羽になり手になったように,既存の神経系の構造を少し設計変更することによってつくりだされたということだ。進化の理にかなっている。」
と。そして,
「昆虫の反射の拡張として,小びとたちや『私』や〈私〉をつかさどるたくさんのニューラルネットワークに接続すれば,心全体を作ることができる。」
との著者の発言に期待したい。
参考文献;
前野隆司『脳はなぜ「心」を作ったのか』(ちくま文庫) |
|
イリュージョン |
|
前野隆司『錯覚する脳』を読む。
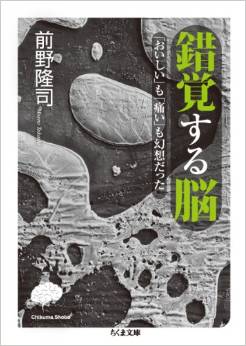
同じ著者の『脳はなぜ「心」を作ったのか』と一緒に買ったのたが,前後逆に読み始めてしまった。『脳はなぜ「心」を作ったのか』については,別途触れるとして,本書である。
サブタイトルに,「『おいしい』も『痛い』も幻想だった」とあるので,おおよそ,著者の主張は予想できる。心身二元論でも,心一元論でもなく,心も,知覚も,表象も,
「すべてはイリュージョンである。」
が,「お伝えしたいこと」である,と冒頭で言いきっている。つまり,
脳も肉体である,
ということである。著者は,本書で,その脳の作り出す意識とは,
「あたかも心というものがリアルに存在するかのように脳が私たちに思わせている」
が,しかし,「意識は幻想のようなもの」ではなく,
錯覚,
だという。つまり,「知覚が客観的性質と一致しない」のである。で,著者は,
「意識はイリュージョンのようなものだ」
という。本書は,それを述べるためのものだ,とも言う。意識には,
覚醒しているという意味,
と
〜について向ける意識,
という意味のそれとがある。後者には,脳の機能に着目する機能的意識(これは定量的に表せるようになるはずである)のほかに,
現象的意識,
と言われるものがある。何かを見ている時の質感や,何かを意識したときの感覚のような,いわゆる,
クオリア,
と呼ばれるものがこれである。イリュージョンと著者がいうのは,このクオリアを指している。
で,心身二元論の立場の,チャ―マーズ『意識する心』をだしに,それに対比しつつ徹底して,脳一元論(心身一元論)を展開していく。著者の立場は,
「心身一元論に立脚し,脳のニューラルネットワークによって,意識の現象的な側面が(あくまでイリュージョンとして)作られている…」
と考えるところにいる。
ペンフィールドの描いた,脳の,運動・感覚中枢の位置に,それが司る身体部位を対応させた図,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Homunculus-ja.png
があるが,しかし(触覚が専門の)著者は言う,
「痛みを感じるのは皮膚の表面だ。皮膚の表面は,角質層という,死んだ皮膚で覆われている。つまり,新しい皮膚は,真皮と表皮の境目で作られ,約一ヵ月かけてだんだん上昇し,表面に角質層として堆積するころには既に死んでいる。角質層は,皮膚を保護する層であり,表面の摩擦によって垢となり剥がれ落ちる運命にある。
そして,痛覚受容器は,角質層のある皮膚の表面ではなく,皮膚内部に配置されている。真皮と表皮の境目あたりか,あるいはもっと深いところにある。それなのに,痛みを感じるのは皮膚の表面なのだ。」
手がないのに手が痛いと感じる,(僕も昔読んだが)V・S・ラマチャンドランの『脳のなかの幽霊』の幻肢の例が,本書でも挙げられているが,それと同じではないか,と著者は言う。記憶で書くが,鏡で脳に,失った手があるように錯覚させると,痛みが消えた,とあったように思う。そのことと,子供が,母親に,
「痛いの痛いの飛んでけ」
と言われて,痛い部分をさすったりしてもらっただけで,痛みが和らぐ(さするだけで痛みの数十%が和らぐと言われている)のとは関係があるのかもしれない。もっと面白いのは,
触角の把持力の制御,
である。重さのわからないコップや,肩さのわからない豆腐を,ちょうどいい力で持つように,把持する力を調節する機能だが,人間は,
「必要最小限の把持力の1.2倍から1.4倍という,ちょうど強すぎず弱すぎない力を加えてものを持つ事ができる。」
のだが,実は,それは意識に上らない,サブリミナル(閾下)で行われている。
「つまり,把持力を制御する際に,人は,指の表面と物体との間にどのくらいの局所的な滑りが生じているのかを意識できない。意識できないにもかかわらず,明らかに把持力制御のために使われているという点がおもしろい。」
と。そして,そのことは,例の意志の問題と絡んでくる。リベットの実験である。
「人が指を動かそうとするとき,『動かそう』と意図する自由意志と,筋肉を動かそうと指令する脳のニューロンの運動準備電位が,どんなタイミングで活動するかを計測した」
実験である。結果は,
「筋肉を動かすための運動準備電位は,意識下の自由意志が『動かそう』と意図する瞬間よりも0.35秒も先だ」
というものだ。そして,著者は,こう言う。
「すべての認知はそうなのだ。見た瞬間にリンゴだとわかるはずがないのと同様に,聴いた瞬間に恋人の声だとわかるはずはない。読んだり聴いた瞬間に,言葉の意味がわかるはずはない。触った瞬間に,熱いと感じるはずはないし,ものの形がわかるはずがない。(中略)ニューラルネットワークによる『知』の情報処理にかかる時間分だけ,本来は遅れるはずなのだ。それを,脳が補正して,タイミングを合わせてくれているとしか考えられない。」
たとえば,
「視覚情報処理にかかる時間はざっと0.2秒から0.5秒だといわれる。刺激が複雑になると,その意味を意識するまでの時間は長くなる。」
しかしそんなタイムラグはあまりない。
「私達は本当は遅れて意識しているのに,時間をさかのぼって意識したかのように感じるようにできているのだ。」
と。その意味では,
脳は,自分が知っている以上を知っている,
と,ミルトン・エリクソンなどが言うことは,ある意味当たっている。
「意識は,たまたま子びとたち(ホムンクルスのこと)の決めた結果を感じているにすぎない」
と,著者は揶揄交じりに言う。
「でも,どちらも自分なのだから,いいじゃないか」
と。確かに。そう考えれば,心安らかではある。
参考文献;
前野隆司『錯覚する脳』(ちくま文庫) |
|
表情 |
|
P.エクマン・W.V.フリーセン『表情分析入門―表情に隠された意味をさぐる』を読む。
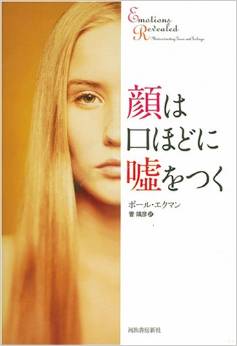
十年近く前,エクマンの『顔は口ほどに嘘をつく』を読んだ記憶があるが,詳細はほとんど忘れている。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/409638012.html
に参加した折,思い出しように本書を購入したまま,積読になっていた。どうやらこの本の方が,先に上梓されたもののようである。
本書も,顔の表情について書かれている。
「驚き,恐怖,怒り,嫌悪,悲しみ,幸福の感情が,ひたい,眉,瞼,頬,鼻,唇,顎,の変り具合に応じてどのように表情として示されるのか」
をスチール写真で提示され,
「感情表出の近くを妨害し混乱させる共通項は,驚きと恐怖,怒りと嫌悪,悲しみと恐怖の間にみられるちがいを際立たせる写真からあきらかになる」
として,その微妙な違いは,
「感情表出の族(family)を示す写真の中に示されている。たとえば,驚きは大きな族(big
family)を持つ感情である。驚きを示す顔はひとつだけではない。不可解による驚き,唖然としたときの驚き,幻惑による驚き,ちょっとした驚き,中程度の驚き,そして極度の驚きなど,たくさんの驚きの表情がある。悲しみと怒りの表情,怒りと恐怖の表情,驚きと恐怖の表情などを示すのに,どのようにして種々の感情がまじりあってひとつの顔の表情になるのか,それを表示する写真から顔の表情の複雑さがつまびらかにされる。」
既に明らかにされているように,顔の感情表現は万国共通である。本書では,
「6つの感情,すなわち,幸福,悲しみ,驚き,恐怖,怒り,嫌悪」
がどのように顔に現れるだけではなく,
「6つの感情が混じりった33種類の感情がどのように顔に表されるか」も呈示している。当然,顔の感情を詳らかにすることで,同時に,「それぞれの感情経験」をも詳細に知ることになる。僕自身は,この感情の複雑な表れが,興味深かった。
実は,顔に現れるメッセージは,感情メッセージだけではない。しかし,本書は,
「素早い信号による感情メッセージ」
に焦点を当てる。そして,それは,
「恐怖,怒り,驚きなどの一時的な気持ち」を指している表情が本物か偽装されたものかということをどのようにすれば識別できるのか」
に焦点を当てる,ということでもある。当然,長い時間つづく「気分(ムード)」とは違う。あるいは,表象的メッセージ,たとえば,同意を求めるときに眼でシグナルを送るといったようなものや,コンマや句読点代わりに,会話の句読法として,顔に現れる渋面,歪みとも違う。
「感情を表す顔の表情のほとんどはごく短時間」
で,素早いもので一秒の何分の一,と言われる「微表情(micro-expressions)」と名付けられるものから,ごくありふれた巨視表情(macro-
expressions)でも数秒しか続かない。
「感情をあらわす顔の表情が5秒ないし10秒も続くことはむしろ稀」
なのであるらしい。逆に言えば,
「かなり長時間示される顔の表情が,実は感情をあらわす純粋の表情ではなく,誇張した形で面白半分に感情を示すにせの表情であることがよくある」
のである。ほんの一瞬しか現れないから,見落とされるのである。本書では,沢山練習課題が示されているのも,トレーニングを要するからにほかならない。途中で,僕自身は,練習問題をスルーした。著者は,顔面統御を認知することの意味を問う。
あなたは,本当に人の顔を見るのをいといませんか?
あなたは,ある人の本当の気持ちを実際に知りたいですか?それとも,その人があなたに知ってほしいとのぞむものだけで十分ですか?
等々,人の顔面統御を認知するということは,知らなくてもいいことを知る,ということを意味する。相手は,僕のことをひょっとすると好きなのかもしれない,という幻想の中で付き合っている方が,相手の僅かな微表情から,相手の嫌悪や軽蔑やらを感じ取ってしまうことが,日常に置いて,幸せかどうかはわからない。
てな負け惜しみを言いつつ,前著『顔は口ほどに嘘をつく』につづいて,敬遠しつつ,本を閉じた。
しかし,
感情の意図的な表出と自然に生ずる表出の区別,
抑制された感情表出,調整された感情表出,隠蔽された感情表出,そして混合した感情表出それぞれの区別,
句読法や例示の形で言葉とともに使われる顔のパターンの区別,
言葉の形成に必要な筋肉活動の区別,
等々を必要とする人には,著者らの開発したFACS(Facial Action Coding
System)がある。
参考文献;
P.エクマン&W.V.フリーセン『表情分析入門―表情に隠された意味をさぐる』(誠信書房) |
|
節税 |
|
富岡幸雄『税金を払わない巨大企業』を読む。
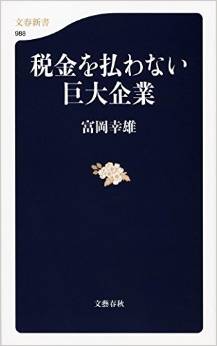
著者は,ご自分のことをこう紹介する。
「戦後,国税庁の職員として,徴税の現場や税務行政の管理を経験しました。…毎年のように,脱税摘発件数と摘発額の双方で第一位。『節税』という言葉を初めて発表したのは,大蔵事務官時代の私でした。…また私は,第一回公認会計士試験,および第一回税理士試験の第一号合格者でもあります。退官後は中央大学の教授として税務会計学を創始し,…多くの会社の顧問も担当して参りました。」
その動機を,あとがきで,徴兵後無事復員したとき,
「日本を戦争に駆り立てた原因のひとつに,国家財政のもろさや経済の脆弱さが挙げられます。日本の財政や経済の弱さを補うために,他国に侵出を企んだのです。―こんな悲惨な戦争を二度と起こさないためにも,日本を内側から強くしなければならない。そうしなれば,戦争で亡くなった人たちに申し訳ない。」
という決意にあるとしています。それだけに,
「現在の日本の財政が著しく弱いのは,税の不公平さに起因することに気づきました。特に,大企業を優遇し,その財政面での“帳尻合わせ”をさせられているのが,一般国民や中小企業だった…。」
と語る言葉には説得力がある。
「法人税と法人住民税,法人事業税を合計した法定税率」(マスコミの使う実効税率)
は,35.64%に下げられ,さらに,2015年度から数年以内に20%台に引き下げた。しかし,著者は言う,
「大企業は,課税ベースである課税所得が,実際にはタックス・イロ―ジョン(課税の浸蝕化)やタックス・シェルター(税の隠れ場)によって縮小され,実際の納税額は大きく軽減されている」
と。たとえば,法定税率が38.01%だった2013年,負担の低い企業を例示している。
三井フィナンシャルグループ0.002%
ソフトバンク0.006%
みずほフィナンシャルグループ0.09%
三菱UFJフィナンシャルグループ0.31%
みずほコーポレート銀行2.60%
みずほ銀行3.41%
ファーストりてーリング6.92%
オリックス12.17%
三菱UFJ銀行12.46%
キリンホールディングス12.60%
等々。その他,住友商事13.52%,三菱重工業16.76%,小松製作所18.76%,日産自動車20.45%,サントリーホールディング21.16%,本田技研工業25.72%,トヨタ自動車27.97%…と続く(トヨタにいたっては,法人税を五年間も払っていなかった)。詳しくは本書を見ていただければいい。にもかかわらず,
「早急に25%まで引き下げる」
よう,経団連は申し入れている。しかし,
「納税額は『課税所得×税率』で算出されます。…たとえ税率が高くても,課税ベースである課税所得を低くおさえることができれば,実際の納税額を少なくすることが可能です。実際に,大企業の納税額が少なく,実効税負担率が低いのは,課税所得を少なくできるからです。」
その仕組みとして,著者は,
①企業の会計操作
②企業の経営情報の不透明さ
③受取配当金を課税対象外に
④租税特別措置法による優遇税制
⑤内部留保の増加策
⑥タックス・イロージョンとタックス・シェルターの悪用
⑦移転価格操作
⑧ゼロ・タックスなどの節税スキーム
⑨多国籍企業に対する税制の不備と対応の遅れ,
を具体的に挙げている。その他,税制上,分離課税などによって,税負担の不公平も加わり,
「日本社会は,現在,税を逃れる手段をもつ1%足らずの富裕層と,その尻拭いをするように重税に苦しむ99%を超える貧困層とに二極化しつつあります」
と,著者は憂う。結果として,
「所得税と法人税の空洞化により,日本の富と税源が失われて,財政赤字の増大を招いている」
ことになる。法人税を,1%下げるごとに4700億円の税収減になる。20%台となると,2兆6508億円以上の税収減になる。その代替に,
配偶者控除の撤廃,
パチンコの換金に課税,
果ては,カジノ構想と,本命を攻めず,明後日の方向に,それも多く国民負担の方向に舵を切ろうとしている。
「企業は法人税を法定正味税率どおりに納税し,受取配当にも一定の税率を課し,優遇税制を見直すことです。現状での消費増税や再増税は,法人税を引き下げるためのバーターではなかったのでしょうか。
私がこのように日本の大企業優遇を憂うのは,借金まみれの日本の財政を健全化させ,活力と競争力のある企業社会に改造し,強い経済を創出して,国民経済を繁栄させたいがゆえです。」
という,まっとうな意見の通る見込みはない。庶民にできることは,まっとうに税金を払わない企業の世界規模の不買運動をすることかもしれない。
参考文献;
富岡 幸雄『税金を払わない巨大企業』 (文春新書) |
|
生理 |
|
古井由吉『雨の裾』を読む。
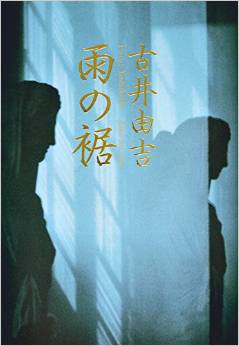
古井由吉の文体は,
生理,
だと思う。皮膚感覚というか,内臓感覚というか,吉本隆明の詩に,
風はとつぜんせいりのやうにおちていった(「固有時との対話」)
というのがあったが,その生理の感覚そのものを描く,と僕は思っている。
古井由吉については,もう何度か書いた。吉本隆明 が言っていたと思うが,
「文句なしにいい作品というのは,そこに表現されている心の動きや人間関係というのが,俺だけにしか分からない,と読者に思わせる作品です,この人の書く,こういうことは俺だけにしかわからない,と思わせたら,それは第一級の作家だと思います。」
僕にとっては,古井由吉こそが,そういう作家だ。前作『鐘の渡り』については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/395877879.html
で書いた。そこでも触れたが,随分昔,古井の文体について,
http://www.d7.dion.ne.jp/‾linkpin/critique102.htm
で,自分なりに書き尽くしたので,後は,大体,楽しんで読んでいるつもりなのだが,今回,あれっと,思ったのは,
「躁がしい徒然」
「死者の眠りに」
あたりの文体が,少しく硬い,というこなれない印象があった。しかし,他の作品には,そういう印象はないので,ただの感覚だが,使われている言葉が,ちょっと違う,ということだ。たとえばだが,
「しかし老年がきわまれば,住み馴れた家を外からあやしみのぞくどころか,家の内にあっても夜中に,手洗いに立って迷うことがあるとか,かねてからそんな話を耳にするたびに,どういう惑わしなのだろうか,と我身の行く末を思って暗い気持ちにもなり,そして何日もしてから,未明に寝覚めして手洗いに立つ途中で,こんなことでもあろうか,とかすかに思いあたるようで,家の内をあらためて見まわすこともあるが,かりに寝惚けて床から起きあがる時に方向を取り違えたとしても,迷うにはなにぶん家が狭すぎる。そのうちに読んだ医学記事の,老化のすすんだ視覚のありようの分析によれば,眼の空間識の変調によって空間が展開図のように,前面にあるのも側面にあるのもひとしく平らたく,一面にひらいてしまう,と考えられるという。なるほど,それなら遠近も方角も失われて,家の内でも迷うはずだ。さらに,空間というものは視覚ばかりでなく聴覚によっても形造られているはずであり,この空間識の変調は視覚の狂いにつれての聴覚の狂いであり,老年の難聴もあるだろうが,戸外のさやぎやそよぎの,人心地のつく音をあらかた遮断した今の世の住まいのせいかとも思われた。」(「躁がしい徒然」)
この感覚は,まぎれもなく古井由吉のものだが,文体が,気のせいかちょっと違う気がした。
夢とうつつの狭間,
いまとそのときとの狭間,
こことあそことの狭間,
等々。狭間というか,ないまぜになったという感覚は,ちょうどベン図ふうに言うと,現と夢,自分と他人の円が,境界詮無く,重なっている,いや,その円が,一つ二つどころか,いくつも重なりあっている,古井そのものの世界だ。
おのれと他人との狭間(綯い交ぜ)
というのもある。それは,
自分というもののゆらぎ,
うつつと言うものの曖昧さ,
あると無いとの不確かさ,
という,日常感覚を,生理のようにたじろがせる,その感覚は,読むほどに,おのれ自身に食い込んでくる。たとえば,前回も触れたが,
それは木目だった。山の風雨に曝されて灰色になった板戸の木目だった。私はその戸をいましがた、まだ朝日の届かない森の中で閉じたところだった。そして、なぜかそれをまじまじと眺めている。と、木目が動きはじめた。木質の中に固く封じこめられて、もう生命のなごりもない乾からびた節の中から、奇妙なリズムにのって、ふくよかな木目がつぎつぎと生まれてくる。数かぎりない同心円が若々しくひしめきあって輪をひろげ、やがて成長しきると、うっとりと身をくねらせて板戸の表面を流れ、見つめる私の目を眠気の中に誘いこんだ。ところがそのうちに無数の木目のひとつがふと細かく波立つと,後からつづく木目たちがつきつぎに躓いて波立ち,波頭に波頭が重なりあい,全体がひとつのうねりとなって段々に傾き,やがて不気味な触手のように板戸の中をくねり上がり,柔らかな木質をぎりぎりと締めつけた。錆びついた釘が木質の中から浮き上がりそうだった。板戸がまだ板戸の姿を保っていることが,ほとんど奇跡のように思えた。四方からがっしりとはめこまれた木枠の中で,いまや木目たちはたがいに息をひそめあい,微妙な均衡を保っていた。密集をようやく抜けて,いよいよのびのびと流れひろがろうとして動かなくなった木目たちがある。密集の真只中で苦しげにたわんだまま,そのまま封じこめられた木目たちがある。しかし節の中心からは、新しい木目がつぎつぎに生まれ出てくる。何という苦しみだろう。その時、板戸の一隅でひとすじのかすかな罅がふと眠りから爽やかに覚めた赤児の眼のように生まれて,恐ろしい密集のほうへ伸びてゆくのを,私は見た。永遠の苦しみの真只中へ,身のほど知らぬ無邪気な侵入だった。しかしよく見ると,その先端は針のように鋭く,蛇の舌のように割れてわずかに密集の中へ喰いこみ、そのまま永遠に向かって息をこらしている……。私も白い便箋の前で長い間、息をこらしていた。(「木曜日に」)
その感覚の時間の流れそのものに沿って書く。しかし,先の引用は,「作家」とおぼしい書き手そのものが,曖昧になることはない。そのせいかもしれない。あるいは,たとえば,
「……私は、徒労感に圧倒されないように、足もとばかりを見つめて歩いた。そしてやがて一歩一歩急斜面を登って行く苦しみそのものになりきった。すると混り気のない肉体の苦痛の底から、ストーヴを囲んでうつらうつらと思いに耽る男たちの顔が浮んできた。顔はストーヴの炎のゆらめきを浴びて、困りはてたように笑っていた。ときどきその笑いの中にかすかな苦悶の翳のようなものが走って、たるんだ頬をひきつらせた。しかしそれもたちまち柔かな衰弱感の中に融けてしまう。そしてきれぎれな思いがストーヴの火に温まってふくらみ、半透明の水母のように自堕落にふくれ上がり、ふいに輪郭を失ってまどろみの中に消える。どうしようもない憂鬱な心地良さだった。だがその心地良さの中をすうっと横切って、二つの影が冷たい湿気の中を一歩一歩、頑に小屋に背を向けて登って行く……。その姿をまどろみの中からゆっくりと目で追う男たちの顔を思い浮べながら、私はしばらくの間、樹林の中を登って行く自分自身を忘れた。
だがそれから私はいきなり足を取られて,前のめりに倒れそうになって我に返った。」(「男たちの円居」)
たぶん,作品の結構も違うし,語り手の位置も違うのだが,なんとなく,難く感じるのは,説明になっているからなのだろう。若い頃の作品と八十代の作品を比較するのも,何だが,自分の気になったところに焦点を当てると,もうひとつ,同じように,
「記憶の時間の流れには幾僧かがあって,それぞれ遅速を異にするように思われる。その速い遅いの時間が,めぐりめぐって,ときたま一点で交わると,人は額へ手をやって,いつのことになるか,と迷ううちにこうして思い出しているいまがさらにあやしくなる。年を収るにつれて,頻繁というほどではないが,よく起こるようだ。朝の目覚めの際にもう一度思わず深くなった眠りから起き出してくると家の内の,見馴れたものが見馴れぬものに映る。いや,そうではない。あまりにも見馴れた様子をことさらに,まやかしのように,際立たせる。しかもいつだか格別の心境から眺めたことがあるように,遠いところから張りつめて,息をこらして,物の表情が浮かびあがる。見つめ返せば,物それぞれの,てんでに主張する鮮明さがかえってみる眼から識別の力を失わせる。つれて自分の立ちどころも知れぬようになり,ささやかながら昏迷の危機ではあるが,それでも何知らぬ顔でいつもと変わらぬ起きがけの言葉を家の者と交わしてのそのそと歩きまわっている。さすがにここまで生きた者のしぶとさと言うべきか。」(「死者の眠りに」)
たぶん,書き手は,感覚の外に立っているせいだ。そのせいで,説明に感じ,違いを感じた。木の目を見ている,「木曜日に」と好対照だ。
「雨の裾」
「夜明けの枕」
「踏切り」
がいい。しかし,文体は,やはり微妙に変わっているのに気づく。
「それきり雨は来なかった。だいぶして刻々の緊張の抜けた気持ちから,こうしていれば夜明けも近いなと男がつぶやくと,まだまだ明けはしないわ,と女は答えて立ち上がり,手提げから取り出してきてひらいたのを見れば,握り飯がふたつきっちりと包まれていた。すっかり忘れていたわ,でも,梅干しを入れてきたので,と女はちょっと鼻を寄せてから一つを男に渡し,もうひとつを自分に取った。さすがに病床から椅子を壁際へ引いて,顔を向かいあわせて食べることになった。女はひっそりとたべながら大きくひらいた目を男の目へ,見つめるでもなく,ただあずけていた。男は逸らすのも支えをはずすようで受け止めるままにしていると,口にした握り飯から女の手のにおいがふくらんでくる。肌を触れ合う以上のことではないか,と男は呆れた。」(「雨の裾」)
たぶん,書き手の位置のせいだ,と気づく。しかし,この,書き手が,誰か他人(ここでは友人)のことを書く,という入り方は,古井作品では,珍しくない。たとえば,友人の話を語る書き手の,
「原っぱにいたよ、風に吹かれていた、年甲斐もない、と友人はおかしそうに言う。見渡すかぎり、膝ほどの高さの草が繁り、交互に長いうねりを打っていた。風下へ向って友人はゆっくり歩いていた。夜だった。いや、夜ではなく、日没の始まる時刻で、低く覆う暗雲に紫色の熱がこもり、天と地の間には蒼白い沼のような明るさしか漂っていないのに、手の甲がうっすらと赤く染まり、血管を太く浮き立たせていた。凶器、のようなものを死物狂いに握りしめていた感触が、ゆるく開いて脇へ垂らした右の掌のこわばりに残っていた。いましがた草の中へふと投げ棄てたのを境に、すべてが静かになった。」(「哀原」)
に比べても,外から眺めている感覚が大きい。それを距離の取り方の違いと取るか,現実感覚からの隔たりと取るか,今のところ答はない。しかし,この距離の取り方も,僕は悪くない気がする。粘りより,淡々とした気味が,一つのリズムになっているように思えるのだ。
参考文献;
古井由吉『雨の裾』(講談社) |
|
同期 |
|
蔵本由紀『非線形科学 同期する世界』を読む。

著者の蔵本由紀氏は,
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%B5%E6%9C%AC%E7%94%B1%E7%B4%80
日本の非線形科学の先駆者。
「著書の"Chemical Oscillations, Waves, and
Turbulence"は非線形動力学の分野でもっとも引用される文献の1つで、『出版部数より引用件数のほうが多い』」
などと言われている。
著者は,劈頭で,
「胸の鼓動,呼吸,体内時計,歩行…,私たちは四六時中『リズム』とともに生きています。鳥のはばたき,蛍の明滅,虫の鳴き声…,命の在る所にリズムがあるとさえ言えます。」
と書く。考えれば,大は,銀河の回転から,地球の公転,自転,小は胸の鼓動まで,我々は,リズムの中に生きている。あるいは,生きていること自体がリズムなのかもしれない。ところが,
「リズムとリズムは出会います。すると,不思議なことが起こります。互いに相手を認識したかのように,完全に歩調を合わせてリズムを刻み始めるのです。これが『同期現象』と呼ばれるもので,『シンクロ現象』とも呼ばれます。」
と,本書は,振り子時計から始まって,蛍の集団発光,吊り橋を歩く群集によってもたらされた橋等々,その同期現象の例示をさまざまに紹介していく。
この同期現象が科学の表舞台に登場することが少ないのは,
「数学的に記述することがなかなか難しい」
からだ,という。なぜなら,
「同期現象は『全体が部分の総和としては理解できない』いわゆる非線形現象の典型なので,『全体が部分の総和として理解できる』線形現象を扱うために磨きをかけられてきた数々の手法では,容易に歯が立たないのです。」
ただ,過去数十年の成果として,「一般的に記述できる数理の言葉を,扱えるようになった」として,著者自身の,
蔵本モデル,
も,本書中で,紹介している。詳細は,
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%B5%E6%9C%AC%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB
に譲るとして,同期現象が注目される理由は,
第一に,生命現象自体が,同期しつつ,意味のあるリズムを生みだしている,という点に着目されているところにある。たとえば,心拍や体内時計,あるいは脊髄の神経ネットワークがリズムを生成し,同期してくれることによって,人や動物が走ったりできるし,魚は泳ぎ,虫も移動できる。
第二には,同期現象を人工システムとして応用できるという期待があるからで,送電システムや信号機のシステムなどに広く応用がはかられてきている。
等々として,著者は,同期現象は,
「広く解釈すれば,同期現象はモノとモノ,人とモノ,人と人との協調した動きを意味します。同期現象の立場から自然や人間社会に光を当てると,今まで見えなかったいろんなことがみえてくる」
という。
個々の同期現象を紹介している箇所の面白さもあるが,それ以上に,非線形著者のものの見方が,なかなか面白い。たとえば,メトロノームや振り子時計を並べておくと,リズムを揃える同期現象がみられるが,その説明を,こう切り出す。
「(具体的な現象からいったん離れて)現象を抽象化して見ることは,とても重要です。そうすることで,いろいろな状況下で現れるリズム現象や同期現象を共通の言葉で言い表すことができるからです。」
その上で,
「『位相』という言葉はリズム現象一般に適用可能な共通語として,特に有用です。リズムの集団が生み出す多くの現象は,位相だけで言い表すことさえできます。位相とはリズムの進み具合のことです。」
として,こういう説明をする。
「ある周期的なくりかえし現象に対応して,円周上を一つの粒子が一定の速さでぐるぐる周回しているようすを思い浮かべると便利です。つまり,振動子を『円運動する仮想的な粒子』と見なすのです。運動方向は左回り,即ち角度が増大する方向で,早さは一定としておきます。すると,振動子がある瞬間にどのような状態にあるかは円周上の粒子の位置で示すことができ,それは角度で表されます。角度ゼロの基準点は適当に定めておきます。円運動のイメージを用いますと,リズムの進み具合を表す位相はまさに角度によってあらわされることがわかるでしょう。」
これは,科学の発見が多く,アナロジーを使うことでなされる,というのと似た,思考スタイルだということができる。
さらに,中枢神経系のうち脳幹と脊髄とを併せた部分を脳の他の部分の切り離した,いわゆる「除脳ネコ」の実験で,中枢と切り離されていても,脳幹を刺激されると,歩きはじめる,という。これは,脊髄にある神経ネットワークがリズミックに動き始めるからだとされる。この神経ネットワークを,
中枢パターン生成器
と呼ぶそうだが,これは,「脊髄の損傷で麻痺した人でも,意図しないのにひとりでに下肢の屈筋と伸筋がリズミックに交替する」という現象がみられるように,
一種の振動子ネットワーク
と見なすことができる。そして,
「それぞれの振動子は活動状態と非活動状態とが交互に現れるようなリズムを示します。このリズムがしっかりした強いものであるためには,この振動子はただ一個のニューロンではなく,ニューロンのグループが作るマクロな振動子でなければなりません。
これらのマクロな振動子はたがいに適当にタイミングをずらしながら,つまり適当な位相差を保ちながら同期して活動しています。それぞれの振動子の活動が,運動ニューロンを介して筋肉のそれぞれの部分にはたらきかけます。」
これは,脳から切り離された「除脳ネコ」が,トレーニングで歩けるようになり,つまり脳無しで,脊髄だけで学習する,ということを意味する。しかも,
「トレッドミル(リハビリ用ウォーキングマシン)のベルトのスピードを変化させた時,ネコはそれに合わせて歩調を変化させる」
ということから,脊髄は環境適応能力さえ持っている,ということになる。このことが,集中制御方式から,
自律分散制御システム,
の応用として,
交通信号機ネットワークへの応用へとつながっていく。たかがリズムではあるが,その非線形は,予定調和ではない,その都度の変化対応の機能を考えていくモデルになっていく。なかなか奥は深い。
参考文献;
蔵本由紀『非線形科学 同期する世界』 (集英社新書)
高沢公信『発想力の冒険』(産能大出版部) |
|
暗黒物質 |
|
鈴木洋一郎『暗黒物質とは何か』を読む。
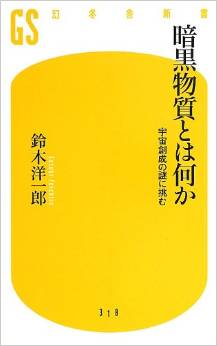
著者は,東京大学宇宙線研究所の低バックグラウンド多目的宇宙素粒子検出器XMASS(Xenon
detector for weakly interacting MASSive particles)実験のプロジェクトリーダーである。
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/xmass/index.html
には,
「XMASS(エックスマス)実験は、液体キセノン(約-100℃)を用いてダークマターを直接探索することを目的としています。」
とある。ダークマターとは,
暗黒物質,
である。
「暗黒物質は,それが私たちの知っている通常の物質(星や空気や私たちの体などを構成する原子や分子)とはまったく性質の異なる物質であることはわかっています。まったく光を発しないので見ることはできず,通常の物質とはほとんど反応しないので,あらゆるものをスルスル通り抜けてしまうのです。」
しかし,宇宙にある物質はすべて原子や分子でできているが,質量をエネルギーに換算した場合,宇宙全体のエネルギーの,
約4.9%,
でしかない。最も多いのが暗黒エネルギーで,
約68.3%,
残りの,
約26.8%,
が暗黒物質である。しかも,
「この暗黒物質がなければ星は生まれず,宇宙は今のような構造を持たない,ただ原子,分子が飛び交うだけの空間だったかもしれません。」
だから,地球もなければ,われわれ人類も存在し得なかったことになる。最初に「ダークマター」と名付けたのは,ツビッキーだが,彼は,「1000個以上の銀河の集まる『かみのけ座銀河団』の質量を推測していて,誤差範囲では説明できない『質量欠損』」に気づき,
「銀河団の領域に『光(電磁波)をまったく発しない重力源』があるのではないか」
と仮定した。たとえば,地球は太陽の周りを秒速30キロメートルの速さで回り,太陽系は,秒速230キロメートルで回転している。しかし,本来,
「銀河系の質量のほとんどが集中しているので,中心部に近づくほど星が受ける重力が強い。ニュートン力学によれば,重力の強さは距離の2乗に反比例するので,重力源から離れるほど受ける重力は弱まります。だとすれば,強い重力を受ける中心部ほど回転速度は速くなります。(中略)ところが,…その回転速度は内側でも外側でもほぼ一定であることがわかりました。」
もしニュートンの法則が間違っていないとすれば,
「そこには目に見える物質以外の重力源があるとしか考えられません。銀河の外側ほどその重力源が多いことになります。」
当然,太陽系の周辺にも暗黒物質がまとわりついていることになる。
また,138億年前,宇宙は,10−36秒後から10−34秒後というわずかな時間に堆積が指数関数的に急膨張を起こし,10−34センチメートルから1034倍以上に膨れ上がった。それから38万年後,宇宙の晴れあがり期に,3000度でしたが,温度分布は一様ではなく,「ゆらぎ」があったとされる。しかし,この宇宙を形成するには,
「ゆらぎが足りない」
と言われる。現在観測されるそのなごりの「宇宙背景輻射」のゆらぎでは,現在のような星や銀河が存在する宇宙はできない,とされる。
「『宇宙の晴れ上がり』のときの物質分布にはもっと大きな濃淡さがなければ銀河は形成されません。(中略)現実におびただしい数の銀河が生まれている以上,ビックバンの38万年後には,観測地の1000倍に相当する物質の濃淡があったはずです。それが『宇宙背景輻射』に反映されていないのは,その『物質』が通常の物質と違う性質を持っており,光を素通しするからと考えられます。」
現在,暗黒物質の質量は,
陽子の100倍から1000倍
と見積もられている。
「仮に100倍だとすると,その個数は1.58の100分の1。つまり100立方メートルあたり1.58個」
となる。「砂漠のゴマ粒」を探す以上の難題である。各国の研究グループが暗黒物質検出にしのぎを削っているが,XMASSでは,
キセノンをシンチレーター(蛍光物質)
として使っている。キセノンを使って,光を検出しようとしている。
「闇黒物質に蹴飛ばされたキセノンの原子核は,周囲のキセノンを電離させるなどの影響を与えながらエネルギーを放出して,最終的に止まります。蹴飛ばされたキセノンからエネルギーを得た,周りのキセノンは,紫外線を出して蛍光が発生します。その光が,642本の光電子増倍管が捕まえる信号なのです。」
しかしすぐにあるかないかがわかるわけではない。
「新種の昆虫を発見するのとは違います。長い時間をかけてデータを蓄積し,それを精密に解析することによって,初めて『発見』となるのです。」
あるかないかではなく,
確率の問題,
であり,
「40〜50日に一例程度の反応しかない」
中でのデータ蓄積が続くのである。今現在も,その地道な作業が続けられている。
宇宙=自然理解の一歩,
のために。
参考文献;
鈴木洋一郎『暗黒物質とは何か』(幻冬舎新書) |
|
絶望 |
|
瀬木比呂志『絶望の裁判所』を読む。

三十三年間裁判官として勤務してきた元裁判官の,今日の裁判所の実態報告である。正直,読むほどに,タイトルのもつ意味が,心の奥底に沁みてくる。
裁判所内部の官僚機構については,本書を読んでいただくしかないが,今日,裁判官にとって「裁判」とはどういう意味を持っているかは,次の記述に現れている。
「現在マジョリティーの裁判官が行っているのは,裁判というよりは,『事件』の『処理』である。また,彼ら自身,裁判官というよりは,むしろ『裁判を行っている官僚,役人』,『法服を着た役人』というほうがその本質にずっと近い。
『先月は和解で十二件も落とした』,『今月の新件の最低三割は和解で落とさないときつい』などといった裁判官の日常的な言動に端的に現れているように,当事者の名前も顔も個性も,その願いも思いも悲しみも,彼らの念頭にはない。…訴訟記録や手控えの片隅に記された一つの『記号』に過ぎず,問題なのは,事件処理の数とスピードだけなのである。」
当然それは,裁判所内部の統制というか,管理体制の反映でもある。
「異論を許さない一種の全体主義体制であり,私のような単なるリベラル,自由主義者に過ぎないものにとってさえ,もしも公式見解と異なった意見を何ごとについてであるにせよ抱いているならば,もはや居場所がないような体制ということになる。」
それは,今の立法,行政とも軌を一にしている。上の覚えをめでたくしようとすると,
「たとえば名誉棄損やプライヴァシーと表現の自由が衝突する訴訟のように,あるいは労働訴訟のように,広い意味での『価値』に関わる事案,行政訴訟や国家賠償請求を始めとする権力のチェックに関わる事案,大企業に対する消費者の請求や医療過誤損害賠償請求等の,当事者双方の有する情報に大きな差のある事案,原告によって新たな法的判断が強く求められている事案」
等々について,基本的に日本の裁判官は,
「及び腰,おっかなびっくりであり,難しい判断を避けようとする,あるいは単に先例に追随しようとする」
傾向が強い,という。それは,おおよそ,裁判の結果をみると予想できるし,市民が勝訴する事案について,政治家が平気で裁判官の個人的思想・信条のせいにする言動を,何度も見てきたのだから。そして判決文も,
「長くてこまかいがわかりにくく,しかも,肝心の重要な争点に関する記述がおざなりであったり,形式論理で木で鼻をくくったように処理されていたりすることが多い。認定事実と法理の結び付きがあいまいで,判断のメルクマールが明らかでないことも多い。要するに,のっぺりした官僚の作文という傾向が強い。これは,…根本的には,裁判官が真摯に事案にコミットしようという心構えが乏しく,また当事者のためにではなく,上級審にみせるために,あるいは,自己満足のために判決を書いているという側面がおおきいことによる。」
と断定してはばからない。それは,
「裁判官が困難な法律問題にみずからが主体的に取り組むことを避けたがる」
傾向があるが,その理由を,和解を強要,押しつけする傾向から推測することができる。昨今,「裁判迅速化の要請を背景に,和解」を迫る,しかも,
「裁判官が当事者の一方ずつと和解の話をする」
のであるが,これは,国際的にいえば,「手続保証違背」である。相手方は,その内容を知り得ないのだから。しかし,にもかかわらず,和解を強要するには,二つの理由がある,と著者は言う。
「一つは要するに早く事件を『処理』したい,終わらせたいからである。裁判官の事件処理については毎月統計が取られており,新受件数が既済件数を上回り,いわゆる未済事件が増加すれば『赤字』となって,『事件処理能力』が問われるし,手持ち件数も増えるから,みずからの手元,訴訟運営も苦しくなってくる。」
そして驚くべきことに,
「もう一つの理由は,判決を書きたくないからである。これには,…困難な判断を行うことを回避したいという場合もあるが,それはまだいいほうで,単に,判決を書くのが面倒である,そのために訴訟記録をていねいに読み直すのも面倒である,また,判決を書けばそれがうるさい所長や高裁の裁判長によって評価され,場合により失点にもつながるので,そのような事態を避けたいなどの,より卑近な動機に基づく場合のほうが一般的である。」
これは,司法の劣化,というより司法の崩壊である。その結果は,
「新しい判断をきらう」
「有力な傾向に追随する」
「争点に関連する範例群の批判的検討を行わず,事大主義に大勢に従う」
という傾向になって現れる。それは,裁判所機構全体の劣化の結果(成果なのか?)と言っていい。著者は,
「時代や社会の流れが悪い方向に向かっていったときにその歯止めになって国民,市民の自由と権利を守ってくれるといった司法の基本的な役割の一つについて,日本の裁判所,裁判官はほとんど期待できないことを意味する。」
と警鐘を鳴らす。
「追随,事大主義を旨とする裁判官が,時代の雰囲気,『空気』に追随し,判例の大勢にしたがって流されていってしまうことは,明らかだからである。」
それは,いつか来た道である。
「太平洋戦争になだれ込んでいったときの日本について,数年のうちにリベラルな人々が何となく姿を消していき,全体としてみるみるうちに腐っていたという話」
は,もはや過去のことではない。当然裁判所の機構の締めつけ,統制は,個々の裁判官に影響を与える。著者は,トルストイの『イヴァン・イリイチの死』の主人公イヴァン・イリイチを再三,例に挙げる。まさに今日の日本の裁判官の官僚性と内面の空虚さを,よくあらわし,
「私は,裁判官時代に,何人ものイヴァン・イリイチや多数の潜在的なイヴァン・イリイチをみてきたように思う。」
と。しかし,著者は,絶望し,ただ批判しているのではない。
「俺は常に個人的見解を持った一個人として生きてきた。もし,自分が存在している意味があるとすれば,みんなに不可能が可能になるっておしえてやることだ」
というボブ・ディランの言葉を引きながら,
「あなたも,私も,およそ人間というものは,不可能を可能にするためにあまれてきたのではないかと,私は,考えている」
と,あとがきで締めくくっている。
三法(三権)分立どころか,政治に一元支配され,いまや,日本は岐路に立っている。というか,既に,ティッピングポイントを越えてしまったのかもしれない。しかし,まだ,戻れると希望を持たなかったら,ただ,地滑り的に地獄へ堕ちるだけである。
参考文献;
瀬木比呂志『絶望の裁判所』(講談社現代新書) |
|
SST |
|
モーシィ・タルトン『シングル・セッション・セラピー』を読む。
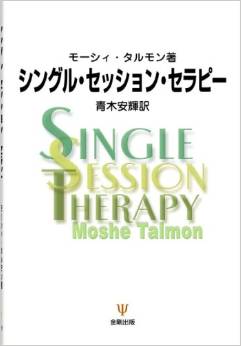
シングル・セッションについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/414952506.html
で,その実践については触れた。本書は,そのバックボーンなる著書である。積読になっていたのをようやく読んだ。
本書では,シングル・セッション・セラピーは,
SSTと略される。本書では,シングル・セッション・セラピーを,
「前後一年間にセッションをもたずにセラピストとクライアントが一回の対面面接を行うこと」
と定義する。多く,セラピストは,
「一回しか面接しないクライアントは計画通りいかなかったケースであり,ドロップアウト」
と見なす傾向があり,たとえば,著者が1985年に調べたケースでは,
セラピストの最も多い面接回数は一回,
全患者の30%は一年に一回しか面接を選択していない(無料ないし低料金にも拘らず)
であり,後に10万人の外来予約患者で追跡したときも,シングル・セッションの傾向は一貫していた。しかも,著者自身が,200人を追跡調査した結果,78%は,
「一回の面接で欲しかったものは手に入ったので当該の問題に対しては以前より良い感じあるいはかなり良い感じを持つようになった」
との答えで,セラピストが気にいらなかったのを理由としたのは,10%であった。つまり,
「ドロップアウトはクライアントあるいは介入システムの失敗を意味する」
と,セラピストが考えるのは,根拠が薄い,としている。著者は,フォローの電話の中で,変化があったと話すクライアントに,こう言う。
「セラピストとして感じるんですけど,今回の変化の主役を務めたのはあなたですね。」
と。それを,
変化の自然なプロセス,
と名付ける。エリック・バーンの,
「患者が回復したときには,『治療が自然の働きを助けた』とセラピストは言うべきであろう。」
という言葉を,エビグラフに使った章で,こう書く。
「私は『変化の自然なプロセス』という用語を使うことによって,既にそこに存在する(自然な)ものの役割と,時間と動き(プロセス)の治療的な役割と,それにセラピストが最初に患者に出会った時点ですでに進行中の不可避な変化を強調しようとしている。患者が同じ場所で行き詰まったままの膠着状態でいるとは考えていない。これらのプロセスの中に,信じられないくらいの治癒力が秘められている。セラピストがそれを患者の内なる力強さや知識と結合させるとき,たった一回のセラピーにおいても,それは強力に活用される。一つ一つのセッションがその時と場所を超えて,より大きな文脈の中で考察されるとき,あなたの期待を大きく上回ることが起こり得る。」
著者は,シングル・セッション・セラピーのセラピストを,
構成的最少主義者
とも名づける。そこでは,関係づけの段階を大事にする,として,
(長い治療プロセスの一部として見るのではなく)「各セッションを,そしてあらゆるセッションを,全体的なそれ自体で完成しているもの」としてとらえること,
(問題を大きくて深く解決には長い年月がかかるとみなすのではなく)「小さいことはすばらしい,ということである。私たちは,物事を一度に一つずつ扱い,ある瞬間を捕えて,現在あるがままに力づけたいのである。知覚や感情,あるいは行動における小さな変化は,クライアントやその家族による新しい変化を引き起こして,新しい生活環境に身を置くことになっていくかもしれない。」
(科学や専門の治療のモダリティに当てはめ,正しいかどうかではなく,クライアントに役に立つために)「小さな変化を一つ期待し,良いところを引き出し,問題を拡大させるのではなく焦点を絞るということであれば,セラピストは,希望を引き出し,取り組み可能な解決策に導く可能性が高くなる。」
等々を挙げる。ここにあるのは,クライアントの力を信じ,みずからが,それを解決していく力がある,と見なす視点である。エリクソンが,
みずから考えを変える力があることを,相手自身が気づけるような状況を作っていく,
のがセラピストの役割である,といっていたのに通じる。
巻頭で,「日本語版の刊行によせて」で,宮田敬一さんが,
「まず,クライエントの問題に対して共感します。次に,焦点づけです。クライエントの否定的な物語にもっと良い意味づけをします。さらに,実際にやれる可能性のある解決法を示します。そして,タルモンさんはセラピストの資質として,人間的な暖かみを持つ人,複雑な問題の中から大事なところに焦点を当てる能力を有すること,楽天的であることを挙げています。」
と,紹介しているが,SSTのチェックリストは,そのことを,如実に示している。
1.このセッションこそが大事なセッションだ
2.各々のセッションを,そしてすべてのセッションを全体的なそれ自体で完結しているものとして考察する。
3.自分の持っているものは,今である
4.すべてここにある
5.セラピーは最初のセッションの前に始まり,その後もずっと続く
6.一回に一歩ずつ進むこと
7.運命の輪を急いで回したり,作り直す必要はない
8.力は患者の中にある
9.患者の力を過小評価するな
10.役に立つためにすべてを知っている必要はない
11.人生は驚きに満ちている
12.人生はセラピーよりずっと偉大な教師である
13.時間,自然,そして人生は偉大な治療者である
14.変化を期待しよう,それはすでに始まっている
ソリューション・フォーカスト・アプローチでいう,「ワンダウンポジション」であり,
変化はたえず起こっており,必然である,
というスタンスを思い起こす。
参考文献;
モーシィ・タルトン『シングル・セッション・セラピー』(金剛出版) |
|
陰伏的(implicit) |
|
デヴィッド ボーム『全体性と内蔵秩序』を読む。

デヴィッド・ボーム『ダイアローグ
対立から共生へ、議論から対話へ』を読んだ折,併せて買ったまま長い間積読になっていたのを,意を決して読み始めた。
専門的,数学的部分は,「本書の理解に全面的に不可欠なわけではなく,専門外の読者にも大部分は理解できるはずである」という著者の言葉に背中を押された。
ただ,正直言って,恥ずかしながら,デヴィッド・ジョーゼフ・ボーム(David Joseph
Bohm)の物理学の位置づけ,その業績についてほとんど知らないままに読んでいるので,まあまったくの自己完結した読みかたになっている。
しかし,ボーム解釈,
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%A7%A3%E9%87%88
と呼ばれるものを見ると,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416694519.html
で触れた,コペンハーゲン解釈とは対立する,「因果律的解釈、のちには存在論的解釈」で,
「隠れた変数理論に基づいており、その源流は1927年のルイ・ド・ブロイによるパイロット波理論である。このことから、ボーム解釈はド・ブロイ=ボーム解釈」
とも呼ばれる,と。確かに,隠れた(いまはまだ見つけられていない)因果を想定しているところがあり,こう布置し直してみると,よく分かるところがある。特に,
Ⅳ 量子論における隠れた変数理論
の章は,「コペンハーゲン解釈に対する真正面からの徹底した批判」になっているようである。
ボームの考え方の典型は,断片化への批判である。たとえば,
「わたしが言いたいのは総体についての考えかた,つまり全体的な世界観がほかならぬ人間の心の秩序全体に決定的重要性をもつことである。ひとがもしその総体を独立した断片から成ると考えるなら,かれの心はまさにそのようなしかたで働いているのである。だがかれがあらゆるものごとを,分割も分断も境界付けも許さぬ(じっさいあらゆる境界は一種の分離・分断である)全体の内に矛盾なく調和的に包摂できるなら,かれの心はそれと同様なしかたで運動するようになり,その全体内部での秩序的行動が生まれてくるだろう。」
とか,あるいは,
「断片的世界観に支配された人間は,世界や人間自身をその世界観にふさわしいように破壊することになり,すべてのものが自分の考え方に一致するように見えはじめてくる。かくして人びとは,自らと世界を断片化して見ることの正当性があたかも証拠立てられたかのように思い込むことができる。」
と。ポームは結構言葉にこだわり,言葉を独自に表現する。たとえば,「陰伏的(implicit)」という表現がある。こういう言い方である。
「一つの理論は,ある対象に対する特定の見方になぞらえられる。それぞれの見方は,対象の一側面の現れを与えるにすぎない。対象全体は,これらのうちの一つの見方で認識しつくされるようなものではない。全体としての対象は,これらすべての見方のなかに示される単一の実在として陰伏的に把握されているのである。われわれが理論を『実在のありのままの記述』と考えるとき,実在は断片的なものとしてわれわれの思考と想像の中に現れる。そしてそれに応じ,われわれは実在があたかもバラバラに存在する諸断片から成るかのように見ることになり,そして,そのようふるまう習慣を身に付けてしまうようになる。」
この「陰伏的」を訳者は,わかりやすく,implicitとexplicitとして対比しているボームの主張を,陽関数(explicit
function)が,ある変数を他の変数の式で表現し,変数同士が互いに独立しているのに対して,陰(伏)関数(implicit
function)は,変数間の関係のみが提示されるとし,
「これらの関数では,変数を独立自存するものとして立て,それらを定義するようなかたちで関数を表現することはあまり意味がない。…しかしそれでも(x,y)の値をすべてグラフ上に取っていけば,その式が全体として何をあらわすかはきわめて明らかになる。」
と注記する。つまり,この「全体に言及してはじめて明瞭に姿をあらわすもの」を,陰伏的と,呼んだということを,ボームの断片化批判の基調と併せて考えると,象徴的な表現になっている。全体に位置づけなければ,というか,全体を想定しなければ,個々の断片の意味は見えない。素人が言うのも変だが,すごく意味にこだわっているように見える。一つ一つには(全体から俯瞰したときに初めて)意味がある(見える),というように。だから,
「相対論と量子論はこのように問題にたいする接近方法は異なるが,次の点で一致している。つまり,それらはともに世界を分割不可能な全体としてみなければならぬことを,すなわちこの全体のなかでは,観測者や観測機器まで含めたあらゆる部分を浸透しあい結びあってひとつの総体をなしているということをしめしている。」
という。その考え方に基づいて,解釈を展開する,
Ⅴ 量子論は物理学における新たな秩序を示唆する―物理法則における内蔵秩序と顕前秩序
が圧倒的に面白い。
「『陰伏的(implicit)』という語は,「内蔵する(implicate)」という動詞から出ている。後者の意味は,『内側に包む』(乗法 mutiplicationtが何重にも包むを意味するように)ことである。それゆえ何らかの意味で,全体の構造が各領域のうちに『包み込まれenfolded』て含まれる,ということを表現する」
として,その内蔵秩序を,こう例示する。
「糖蜜のように高い粘性を持つ液体を詰めた透明の円筒を用いる。そしてその円筒に回転装置をとりつけ円筒中の液体をきわめて徐々に,しかも完全に撹拌できるようにする。この液体中に不溶性のインクを一滴入れて撹拌装置を作動させると,インク滴は徐々に糸状に変形し,やがて液全体に拡散する。そうなったときのインク滴は,ほとんど『でたらめに』分布しているようであり,視覚的には灰色がかって見える。しかしそこで装置を逆向きに回転させるとそれまでの変形は逆行し,染料の滴が突然出現する。つまり,インク滴が再構成されるのである。…
『でたらめ』と思える状態に分布したときでも,その染料はある種の秩序を持っている。しかもその秩序は,例えば,最初異なる位置に置かれた滴ごとに異なる。だがこの秩序は液体中に見える『灰色の塊』の中に包み込まれ,ないし内蔵されている。滴だけでなく,一つの絵全体をこのように『包み込む』こともできる。そのように包み込んでしまえば,異なる絵も見たところ区別できなくなるだろう。」
これを,ホログラムになぞらえているが,この例示は,量子の,
位置と運動量の両方を同時に正確に確定することができない,
とか,
粒子としての特徴をもつと同時に波としての特徴をもつ,
といった特徴を,先のインク滴の例になぞらえながら,
「どちらの場合も直接知覚の中に一つの顕前秩序が現れるのだが,それじしんを一貫して自律的なものと考えることができないのである。染料の例では,その顕前秩序は二つの内蔵秩序の交点として定められた。つまりそれは粘液の『運動全体』の内蔵秩序と,感覚知覚中に引き上げられる染料密度という特徴の内蔵秩序の交点として定められた。同様に『量子』の文脈でも,われわれが『電子』と呼んで来たものに対応する『全運動』の内蔵秩序と,計測機器によって引き上げられ(かつ記録され)る諸特性の内蔵秩序の交点が存在するとかんがえてよかろう。」
として,「分割されぬ全体性という秩序」のもとで,「全てが全てを内蔵する」という構想に到達する。それは,「電子の新しい理論模型」として,
「一個の電子は包み込まれた集団全体(からなる集合)によって理解されねばならず,しかもそれらの集団は一般に空間中の一定の場所に局所化できないということである。ある瞬間を取ると,それらの集団の一つが抜き出されてそれゆえ局所化されるが,次の瞬間その集団は包み込まれ,それに続く別の集団が抜き出される。…粒子というものはわれわれの感覚に顕前する一つの抽象物に過ぎないのである。存在するものはつねに集団の総体である。そしてそれらの集団は原則的に全空間にまじりあい浸透し合っている。」
結果として,宇宙から脳まで,この考え方を敷衍していく。
彼の考えが,今日どんな位置づけかは,たとえば,ド・ブロイ=ボーム解釈は,
「『パイロット波』なる未知の波が粒子の運動に影響を与えているとして、量子力学を古典力学の枠内で説明しようとする試みであり、シュレーディンガーの猫の問題は完全に解決できる。一時は成功したかのように見えたが、二個以上の粒子の運動を想定すると古典力学にない非局所的長距離相関が強く現れることが分かり、現在では完全に下火となっている。」
という説明が出ていたり,
「ボーム解釈はコペンハーゲン解釈などその他の量子力学解釈と同様、あくまで『解釈』に過ぎない。ボーム解釈の予測する結果は全て、ほかの量子力学解釈と全く同等であり、すなわち理論的には同等のものである。量子力学そのものが否定されない限り、ボーム解釈は反証されることもない。」
と言われたりしている。
ある意味,19世紀的な完結した世界像のにほひがないでもない。これをいま読むことの意味は,僕は,その構想力ではないか,と思う。言語の語源から始めて,自分の言葉や説明を,一貫した世界としてまとめ上げていく,あるいはそれ自体が,古典物理学的世界像なのかもしれないが,そういう構想の描き出すものに惹かれる。
ボームの内蔵秩序論はしばしばホログラフィック・パラダイムとよばれたが,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416793184.html
でふれた,ホログラフィック多宇宙と,どうつながるのか,別の関心がわく。
参考文献;
デヴィッド ボーム『全体性と内蔵秩序』(青土社) |
|
世界視点 |
|
河野至恩『世界の読者に伝えるということ』を読む。

著者は,序章で,日本からの文化の発信について,
「アメリカに長年住んで,また,最近ドイツに一年滞在して,そのような日本からの『発信』を外から見ていると,その情熱や努力にもかかわらず,期待したほどに成果があがっていないのではないか,と感じることがしばしばあった。」
と述べる。日本では大々的にメディアで報じられることが,現地の視点ではそれほどのインパクトがないのに,他方,日本で知られていなくても,現地で受け入れられているプログラムに出会うというということがある。それを,
「発信したい気持ち」と「知りたい気持ち」のミスマッチ,
と著者は言う。送り手側が,「自分たちの発信したいこと」にこだわり,日本の事情を海外に持ち込み,日本のやり方でものごとを進める,その結果受け手の知りたいこと,見たいことに応えられない。
「〈正しい〉日本文化を発信する」という発想自体を,大きな視野から見直すことも,必要なのではないか。」
という著者の言葉が,重い。なぜなら,
コミュニケーションというのは,相手の反応で,何が伝わったかが決まる,
あるいは,
こちらの伝えたいことではなく,伝わったことが伝えたことなのである,
という原則が,ここでも生きているからだ。いい例は,
正しい寿司の味を世界に伝えたい,
という海外レストランの認証制度を農水省が始めようとしたところ,海外メディアは,
「日本人は自分たちの食文化を海外に押し付けるな」
という論調で批判し,ワシントン・ポスト紙は,
「気をつけろ,スシポリスがやって来る」
と表現して,反発し,結局,日本食の認証制度は取りやめられた。当然,すでに,アメリカ発祥の
カリフォルニアロール
は,寿司をメジャー料理にした。いま,それが逆輸入されている。
「日本文化を日本の外で楽しみ,日本文学を日本語以外で,日本の外で読む,そんな時代が始まりつつある。このような時代に,世界の読者の側に立って,文化を見て語る文化論が必要とされている。」
その趣旨で,本書は,
「『クールジャパン』をめぐる議論を含め,最近の日本発の文化についての議論で一番欠けているのは,『あえて世界の読者の視点から見る』ということではないだろうか。」
という視点から,
「『世界の中の日本文化』を,日本国内の視点からではなく『世界の読者』の視点から見ること。」
に置いている。著者自身,比較文学・日本近代文学が専門で,大学・大学院での,研究者としてのトレーニングを,アメリカで受け,現在は,「英語で文学を教えている」という立場から,
「北米やヨーロッパの大学という場所から日本文化はどのように見えるか」
から,実例を紹介していく。「世界の読者の視点」を,
ふたつのレンズ
から,見ようと試みる。それは,その視点を,
「世界」の文化として見る,
か,
「日本」(のような,ある国・地域の文化)としてみるか,
のふたつである。それは,最近はアニメやゲームから入るケースもあるようだが,
「日本の文学に興味を持った若者がアメリカの大学に入学したとしよう。その学生が日本文学について学ぶのは,『比較文学』か『地域研究』(日本研究または東アジア研究)のどちらかの学部での授業である」
というような二つの視点でもある。
「日本から見ると,自分のよく知っている作品が世界で楽しまれているということは,それを『日本』の『日本』文化が世界に広がっていると感じる。しかし,世界の人々は,それを,『日本』のイメージを通して見ることもあれば,『どこかの外国の作品』とか『世界のさまざまな作品のひとつ』という広い視野から見ることもある。」
この視点の切り替えである。これに慣れれば,
「世界の人々が日本発の文化をどう見,どう読み,どう評価しているか,整理して理解できるようになるだろう。」
本書は,そんな指針になっている。
たとえば,「世界文学」という視点でみたとき,
「日本文学が日本を離れてどれだけの価値をもつか,という本質的な問いを含んでいる。」
という。そのとき,「日本の」という形容詞は,いらない。ゲーテについて,カフカについて,カミュについて,国名を付けることはないはずだ。
「文学史を,ひとつの言葉や国(たとえば『日本文学』の歴史)の文脈で見るのではなく,国境や言葉の違いを越えて横断的に見てみると,いままで見えてこなかったパターンや共通点が見えてきたり,それぞれの言葉や国ではマイナーだった動きが,世界の大きな流れだと気づいたりする。このような読みかたが『世界文学』的な読みかたなのだ。」
もうひとつの「日本研究」という視点では,「日本らしさ」「日本らしいもの」という切り口は避けられている,という。「日本らしい」は,簡単に「日本人にしかわからない」に転換されやすいし,「ソフトなナショナリズムの顕れ」とも解釈される。昨今のテレビ・マスコミの日本誉め,日本は素晴らしい,の論調は,ある意味その敷居を越えてしまっているかもしれないが,
「最近は,欧米の日本文学研究でも,少なくとも研究者の間では『日本文学を研究すること』と『日本文化を知ること』『日本人(のよう)になる』ことはすべて別のこととして認識されている。」
という。当然,
「日本文化の『日本らしさ』を語るのではなく,世界のなかの日本文化として,他国との比較研究をしたり,現代思想や批評理論,社会学の理論を使って文化を説明したり,ということが主流になってくる。」
だから,
「日本国内の『クールジャパン』の語りかたと,欧米の日本研究の『ポピュラーカルチャー研究』では,同じ材料を扱っても,その方法も文脈も異なる。…日本国内では『海外でうけている』と思われていることでも,欧米の日本研究では批判の対象になることもある。」
それにしても,比較文学と地域研究は,接近してきている。それは,
世界での価値,
ということではないか。日本的であることは,ある意味エスニックとしての価値でしかない。世界の中にあることで,世界に意味と価値があるかどうか,が問われている。日本を正しく発信する,ということではなく,その発信が,
世界全体のために役立つかどうか,
が問われている。そういう視点が,われわれひとりひとりに,あるのだろうか。
参考文献;
河野至恩『世界の読者に伝えるということ』(講談社現代新書) |
|
晩節 |
|
杉晴夫『天才たちの科学史』を読む。

「本書では,現代科学の根底をなす発見をなしとげた巨人たちの業績を,できるだけ平易に解説するとともに,彼らの素顔,つまり赤裸々な人間像を浮き彫りにすることを試みた。」
とし,わざわざ,著者は,
「どんな人間の生涯にも性格的な欠点が露呈する影の部分がある。しかしこのような影の部分は,巨人たちがなしとげた偉業の価値を減ずるものではない。」
と断っている。ことほどさように,人間としては,いささか,いかがかと思う部分が多々あるからであろう。
取り上げたのは,ケプラーから始まって,
ガリレオ,
ニュートン,
ラボアジェ,
ラマルク,
ダーウィン,
メンデル,
フーコー,
パスツール
である。アインシュタインが入っていないが,
「ノーベル賞の受賞対象となった発見・発明は,科学の細分化によりスケールが小さくなり,,さらに科学者の社会的地位が確立し,劇的要素が乏しくなったので取り上げなかった。」
のだそうだ。
眼の悪かったケプラーは,師ティコ・ブラーエの死後,ティコの詳細かつ緻密な天体観測データを,遺族の意に反してでも,持ち出し,それをついに返却せぬまま,占有し,自分の発見のよすがとした。ために,突然死んだティコについて,遺髪から水銀が高濃度で検出されたため,
「師を殺害してまで観測データを手に入れた」
とまで,センセーショナルな言われ方をしているところもある。しかし,ニュートンの体内にも水銀が検出された例があり,当時錬金術に熱中した科学者は多く,ために,
「金属化合物を舌で舐めて確認していたためだという。ティコも同じことをやっていたのではあるまいか。」
というのが妥当な見方なのだろう。そのケプラーの名声にすがって,ガリレオは,
「私が製作した望遠鏡による天体の観測を報告する著書『星界の報告』は,イタリアの同業者の学者たちに反発され,望遠鏡で彼らに転貸を見せても何も見えないと言われ,私の立場は著しく悪くなっています。あなたの神聖ローマ帝国数学者としての権威で,私をこの窮状から救っていただきたい」
と,懇願する手紙を書き,
「人のよいケプラーは,彼自身,望遠鏡をまだ見たこともないのに,ガリレオの願いを聞き入れ,文書でガリレオの『星界の報告』を称賛してやった。」
おかげて,ガリレオは,この本を種にメディチ家に取り入っていくことになるが,ケプラーには感謝することもなく,
「忘恩,不信義のかぎりをつく」
したという。「ケプラーは,晩年窮乏し,行路病者として共同墓地に葬られた。ガリレオは,
「究極の庇護者であると考えたローマ教皇の逆鱗に触れて罪人にされ,その人生も残り少なくなったとき,突如自分の天職に目覚め,その足跡を歴史に残すことを決心したのであった。この著書(『新科学対話』)でガリレオは次の印象的な言葉を述べる。『神の摂理は,我々の前に開かれている最も巨大な書物,即ち大自然のなかに書かれています。その書物は数字の言葉で書かれているのです。』」
しかし,ドイツでもイタリアでもローマ教皇を憚って出版できず,オランダで出版された。ガリレオは既に失明していて,それを見ることはできなかった。
「ガリレオも,そしてケプラーも,〈万有引力の法則〉の発見にいま一歩まで迫っていた」
が,それを成し遂げたのは,二十歳そこそこのニュートンであった。すでに,時代は,
「容易に〈微分積分法〉を発見しうる段階に達していた」
のであり,
「フランスのデカルトによる解析幾何学は,ケプラーとガリレオの諸法則への〈微分積分法〉の適用を容易にした。要するに,青年ニュートンが…偉業をなしとげるための機が熟していたのである。」
にしても,二十歳そこそこで万有引力の法則と微分積分法を発見したニュートンは,以降85歳で亡くなるまで,六十年も生きた。
「この期間に明瞭になるのは,率直に言って彼の実験科学者としての凡庸さ,さらにその性格の執念深さと残忍性である。」
と著者は書き,フックの痕跡を悉く消し去るなど,競争相手の抹殺であり,ライプニッツと争い,
「彼の晩年の30年は前半生の抜け殻にすぎなかった」
と手厳しい見方である。そればかりか,
「彼を恐れるあまり英国の学問は停滞した。」
とさえ言われている,と。
ラボアジェは,徴税官であったが故に,断頭台の露と消えたが,助命を求める要請に,国民公会の返事は,
「共和国に科学者はいらない」
であった。しかし,ラボアジェ処刑の翌日,数学者ラグランジェは言った。
「彼らがこの頭を落とすのは一瞬で足りる。しかしこのような頭が再び現れるには一世紀あってもたりないだろう。」
と。これに関連して,著者が,ガリレオが裁判の判決がおりてから,
「それでも地球はまわっている。」
に関連して,天動説に転向したのは卑怯未練,と批判する声に,著者は,珍しく,語気鋭く,こう言っている。
「宗教者の殉教とラボアジェのような科学者の殉教とを,同じように崇高な精神の表れとして賛美してはならないことである。これは,結局,科学者を言われなく神さまあつかいすることにつながるのではなかろうか。宗教者は信仰を貫き,殉教する光栄を喜びながら処刑されるのである。つまり,信仰こそが彼らの天職であり,彼らの生涯は殉教によって美しく完結するのである。」
が,科学者は,科学の研究によって発見をすることなのだ,という。別に宗教家だから殉死が目的とは思わないので,余り論旨に賛成はできないが,科学者が主張を曲げても,それでも発見は発見である。それでも事実は残る,というのは,そのままをつぶやいただけに過ぎない。
巨人ラマルクに対して,ダーウィンの凡庸さ,せこさは,いまやある意味常識だが,学歴がない故に,学会で相手にされないフーコーを引き上げた,ナポレオン三世を,著者は,
「独裁者であったにもかかわらず,終生科学に対する尊敬心を持ちつづけ,科学者の活動を擁護した」
として,称賛しているが,どこかの偽ヒトラーもどきにも,爪の垢でも煎じて飲ましたいものである。
参考文献;
杉晴夫『天才たちの科学史』(平凡社新書) |
|
プライド |
|
奥井智之『プライドの社会学』を読む。

サブタイトルが,「自己をデザインする夢 」とある。
冒頭,ジェーン・オースティンのPride
and Prejuiceの訳を問題にする。
高慢と偏見
や
自負と偏見
と訳される。著者は,小説中のエリザベスの台詞を,エビグラフに,自身の訳で,
「あちらがプライドをもつのは勝手です。しかしこちらのプライドを傷つけるのは許せません」
と掲げる。あるいは,prideを「誇り」と訳す例もある。著者は,「おわりに」で,これを巻頭におにいた理由を,
「それが『プライドの何であるか』をよく表しているからである。」
と,そして,この(エリザベスの)言葉は,
「Aがプライドをもつように,Bもプライドをもっている。それゆえにAは,Bのプライドを安易に傷つけてはならない,と。もう一歩踏み込んで言えば,彼女は,こう言っている。人間はだれしも(AもBもCも…),他者のプライドを傷つけやすい,と。」
とも付け加える。そして,
「本書は,プライドに関する社会学的考察を試みるものである。一般にプライドは,心理的な事象と理解されている。実際ブライトは,もっぱら心理学者によって論じられてきた。しかしそれは,一個の社会的な事象ではないかというのが本書の出発点である。」
と,問題意識を述べる。僕は,それに強く惹かれる。人は,自己完結して生きていない。人との関係の中で,心理がある。そのことは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/418428694.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/413639823.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/397281789.html
等々でも触れた。関係の物象化(人間と人間の関係が,物と物の関係として表れてくる)という概念がわかりやすい。ときに,帰属するものにプライドを置く。で,本書では,
自己,家族,地域,階級,容姿,学歴,教養,宗教,職業,国家,
と章立て,プライドの依拠するものを順次追っていく。それを,ジンメルを引用しつつ,
「一般に秘密は,何かを隠蔽することをさす。しかし,秘密は,一個の矛盾を孕む。というのも隠蔽することで,かえって他者の注目をあつめるから,と(『社会学』)。その意味では秘密は,装身具と同等の機能を持つ。
その装身具についてもジンメルは,面白い考察を行っている。装身具は本来,自己の優越性を示すためのものである。しかし装身具は,一個の矛盾を孕む。というのも他者の羨望なしには,自己の優越性はしめせないから,と。いったいここで,ジンメルが言わんとすることは何か。それは人間存在が,個別性と社会性の矛盾のなかにいるということであろう。そういう矛盾を孕むというのは,本書の主題であるプライドのばあいも同じである。」
と書き,プライドを位置づけ,こう定義する。
「プライドとは『自分や自分の属する集団を肯定的に評価すること』である。と,当然これとは逆に,『自分や自分の属する集団を否定的に評価すること』もありうる。」
だから,プライドは,
「自己準拠的(self-referential)なシステムである。これは,プライドの基準が,自分自身の中にあることさす。したがってプライドをもつ/もたないは,最終的には本人次第ということになる。」
自己準拠は,一般には自己言及という言い方をする。著者は,しかし,プライドを自己完結させない。
「各人がプライドを自由に操作できることを意味しない。たとえば心理学的に,『どうすればプライドをもてるか』を論じることは勝手である。しかし実際には,プライドの操作はそう簡単ではない。というのもプライドの基準は,個人的なものであると同時に社会的なものであるから,その意味ではプライドもまた,個人性と社会性の矛盾を孕んでいるのである。」
これを読んで,僕の中のもやもやが言語化された気がする。プライドは,他人の存在,他人との関係,はっきり言って他者の承認や認知抜きには,プライドとして機能しない。だから,ある意味,
「わたしたちがプライドをもつのは,私たちが集団のメンバーであるからである。」
と,著者が言うのにつながる。コミュニティの認知がいるのである。それを,
「『わたしたち』は『かれら』と異なることで,『わたしたち』たりうる。そして『わたしたち』こそが,わたしたちにとってのプライドの源泉たりうる,と。」
と,公式化してみせる。で,
「コミュニティこそがプライドの源泉である」
という仮説を表現する。このコミュニティとは,「私たちという意識で結ばれた集団」をさす。
著者は,フロイトを借りて,
「人間は現実の自我とは別に,理想の自我=理想化された自己像をもっている。それは人間に,自分の『あるべき姿』を提示する…。…そこでは人間がプライドをもつ=自己自身を価値的に評価することの心的機制が解明されている」
と説明し,さらに,エリクソンのアイデンティティという概念を借りて,こう付け加える。
「アイデンティティ(自分が何であるのか)概念はそれ自体,『理想の自己』の表明にあたると私は思う。したがってそれは,『現実の自己』との間で軋轢を生じずにはすまない,と。エリクソンはアイデンティティが,社会的な文脈のなかで形成されると捉えている。すなわちアイデンティティは,(自己完結的なものではなく)他者による承認を必要とするとしいうわけである。」
しかし皮肉なことに,
「まさにコミュニティが壊れたときに,アイデンティティが生まれた」
のであり,「アイデンティティはコミュニティの代用品」(Z・バウマン)なのである。それゆえに,プライドをもつこと,
「すなわた自分自身に誇りをもつことが,わたしたちの生存の条件」
なのである。本書の面白いところは,プライド,つまり自己準拠的(self-referential)なシステムは,
「『予言の自己成就』や『ピぐマリオン効果』(教師のきたいによって,生徒の学力が向上する)と同じく,『トマスの公理』(ある状況を現実と規定すれば,結果としてそれが現実になりがちである)と同系列の心理的・社会的機制(メカニズム)ではないか。つまりはプライドのありようで,わたしたちの生のありようが変っていくのではないか。その意味ではプライドは,私たちの生の原動力になっているのではないか。」
という記述である。しかし,現実は,地域社会だけでなく,家族も含めて,社会解体ないし個別化が進行し,コミュニティは日増しに見つけにくくなる。
「はたしてコミュニティのない状況で,私たちはプライドをもつことができるであろうか。」
だから,現実のコミュニティに代わって,「理想のコミュニティ」を希求し,待望していく。いまや,SNSのようなネット上の仲間も,ほんの小さな教室や学習仲間も,その代替品になっている。
「たとえばグローバリゼーションの時代に,ナショナリズムが勃興するという逆説がある。同様に,理想の自己,家族,地域…についてのイメージは,わたしたちの周囲に満ち溢れている。よくも悪くもそれは,人々のプライド回復のための方策なのである。今日『理想のコミュニティ』の果てに人々が見出すものは,いったいなんであろうか。」
本書は,自己,家族,地域,階級,容姿,学歴,教養,宗教,職業,国家と,各章で,それを順次追っていく。
正直言うと,最初の「はじめに」に比べ,だんだん散漫になっていって,焦点が合わなくなっていく。「さいごに」で,著者はこう明かす。
「本書は,十の主題×六つの素材=六十の小話から構成されている。その六十がそれぞれ一定の独立性をもっている(極端に言えば本書が,六十のまとまりのない話から構成されている)」
のは,結果として,
「『プライド』(という得体のしれないもの)にあちらこちらからスポットライトをあてるという体裁になった。」
という。「はじめに」の意気込みに反して,
自己準拠的(self-referential)なシステム
の社会的文脈での構造を分析するというよりは,社会的文脈のなかでのプライドの現れ方を書いてしまった,ということになる。「はじめに」との落差が大きいのが,ちょっと残念な気がしてならない。
参考文献;
奥井智之『プライドの社会学: 自己をデザインする夢 』(筑摩選書) |
|
分子進化 |
|
中沢弘基『生命誕生』を読む。
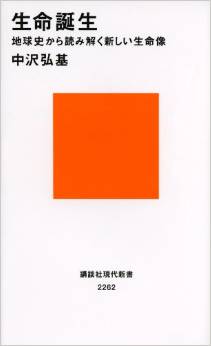
サブタイトルが「地球史から読み解く新しい生命像」となっているのは理由がある。著者は,
「本書は,生命の発生と進化の『壮大なドラマ』を,物理的必然と全地球46億年の時空を見渡す21世紀の新しい自然観をふまえて解き明かします。」
と述べている。なぜなら,
「生命誕生に不可欠な分枝ができて生命の発生に至るまでの『分子進化』(一般には“化学進化”あるいは“前生物的分子進化”と表現されています)と,生命が発生した後の『生物進化』は同じ地球上で切れ目なくつながっていると考えるのが自然ですから,生命誕生以前の『分子進化』のメカニズムも当然,地球環境の変化と自然選択の原理に支配されてきたとみるべきです。こうした視点がないと,『生命の起源』という壮大なドラマを解き明かすことは難しいでしょう。」
その考えを象徴するのが,
(地上しかない,つまり根のない)「ヘッケル系統樹」(ダーウィンの『種の起源』に共鳴して,E・H・ヘッケルがまとめた)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Haeckel_arbol_bn.png
と対比して,著者の考える系統樹は,根がある「地球軽元素進化系統樹」である(本書に添付)。
「同図では,生命進化が地球史的必然であることを表すために,“原始地球史上の事件”
(中央)と,そのとき有機分子が受け取る“環境圧力”(左端),そして“自然選択”の結果,すなわち“環境適者”(右端)を重ねて表現」
している。当然ヘッケルの有名な,
「個体発生は系統発生の短縮された反復である」
では,受精前が想定されていない。本書の問題意識は,その前へと遡る。しかし,分子系統学の知見を加えても,
「現代の生物分子系統学でも,タンパク質(酵素)のアミノ酸配列や遺伝子(DNA,RNA)の塩基配列の類縁から,“近縁種の共通の祖先”→“より遠縁種の共通の祖先”→とたどる系統樹が用いられています」
が,ヘッケルの系統樹と概念は同じで,この考え方で,遺伝子を辿れば,究極の祖先に辿り着けるのか,というと,そうでもないらしいのである。その理由は,系統樹の考え方自体が,
「もともと,ダーウィンの自然選択説によって生物多様性を説明するために考案されたものですから,共通の祖先→その先の共通の祖先→さらにその先の…とたどれるのは,親から子に遺伝子が引き継がれる
“ダーウィン的進化”しか想定されていないからです。しかしバクテリア(原核生物)には生物進化の初期だけにある『細胞内共生』という進化の別の機構があって,遺伝子分析の方法ではその先が辿れなくなるのです。」
著者は,「はじめに」で,
「生命の起源を探る研究を進めていくと,物理や化学の論理だけでは説明できない,さまざまな謎に直面します。なぜ岩石や鉱物ばかりの原始地球に炭素や水素でできた有機分子が出現したか? しかも,アミノ酸や糖など生物をつくる基本的な有機分子はみんな,なぜ水溶性で粘土鉱物と親和的なのか? なぜ,それらがタンパク質やDNAなど高分子に進化したのか? いずれもよく知られた事実ですが,『なぜそうなのか?』
は今の物理や化学では説明できていません。生命の起源や進化に関する“なぜ?”には,生物学,物理学,化学など個々の専門分野の常識では答えられない謎がたくさんあるのです。
その最たるものは『なぜ,生命が誕生して,生物には進化という現象があるのか?』という根源的な命題です。」
と書き,それに応えるには,
「生物は,物質的には地球の一部であり,バクテリアからヒトまでの進化を考える場合には,全地球の物質の変化を地球史46億年の時空で考えなければならない」
として,本書の,ある意味壮大な仮説が生まれてくる背景になっている(上記の進化系統樹は,仮説の集大成になっている)。
当然,宇宙から来たの,火星から来たの,隕石からだの,という地球外生命由来は,一顧だにされない。それは,科学ではなく,妄想でしかないからだ。化学は,検証できなくてはならない。
鍵のひとつは,シュレディンガーの,
「遺伝子は古典物理学で記述される物質の集団ではなく,量子力学の支配する分子でなければならない」
と喝破した言葉にある。つまり,
「何十代も,親の性質を間違いなく子に伝えることのできる遺伝子は,環境の変化で変わることのない“安定な物質”でなければなりません。そうだとすると遺伝子は,ほんの一部が変化するのにも大きなエネルギーを要する『一個の分子』であるはずだ」
というのが,シュレディンガーの洞察の背景にある,
「有機分子は,H,C,N,O,P,Sなどの軽元素が数個から数百,数万個も強固に“共有結合”したものです。“共有結合”とは,原子Aと原子Bが電子を出し合って,それらの電子が両原子をつなぐ軌道を高速でまわり続けることでA−Bが一体化される結合の仕方」
であり,だから,最後に,この高分子の一部の分子基,あるいは原子一個の位置を変えるだけでも,大きなエネルギーが必要になる。そういう変化しにくい,高分子をどう作ったかが,生命起源に迫るキーになる。
もう一つの鍵は,やはりシュレディンガーの,
「生命をもっているものは崩壊して平衡状態になることを免れている」
という,「『生きる』という生命現象そのものが,『宇宙のエントロピーはつねに極大に向かって増加する』という熱力学第二法則に矛盾する」という指摘である。この矛盾を,シュレディンガーは,
「生物体は“負のエントロピー”を食べて生きている」
と表現した。しかし,著者は,
「“矛盾” や“異常”が理解できたところに新しい世界が開けます。」
と言い切る。そして,この矛盾を,「生物の進化を考えるときに,有機分子や生物だけを考える」ことによって勝手に落ち込んだ,「幻のトリック」と言う。つまり,全地球規模で考えれば,
「地球は創生期から46億年,熱を出し続けてきた結果,マグマオーシャンの状態から海ができて,今の穏やかな地球になった」
のであり,いまもまだ,地球が膨大な熱エネルギーを放出し続け,冷却しつづけている。そこから,
「地球にあるH,C,N,Oなどの軽元素,“地球軽元素”もエントロピーの減少によって秩序化します。その結果が有機分子の生成であり,生命の発生,さらには素の進化」
なのだという考えにつながっていく。
著者の生命誕生の仮説とその検証の,詳細な経緯は,本書に譲るとして,本書の最後に,「生命誕生」のプロセスが,たどり直されている。
「43億年前:微惑星の集積が終焉すると,地球は熱を宇宙に放射し,温度が下がって水蒸気が凝集し,全地球を覆う海洋が出現しました。エントロピーの低減による地球秩序化の一環です。」
から始まって,
「40〜38億年前:太陽系の軌道に乱れが生じ,軌道を外れた小惑星やその被破砕物が隕石となって頻繁に地球に衝突しました。…地球にはまだ大陸がなく,表面はほとんど海洋で覆われていましたので,それら隕石は海洋に衝突し,地球の水および大気と激しい化学反応を起こしました。
隕石の海洋衝突で生じた超高温の衝突後蒸気流が冷却する中で,多種多様の“有機分子”が創生されました。」
を経て,
「40〜38億年前頃:海洋堆積層はプレートテクトニクスによって移動し,プレート端にいたって一部は褶曲・断層などを生じつつ島弧の付加体となり,ほかはサブダクション帯…を経て,再びマントル内部に沈み込みます。
その堆積層に含まれていた高分子は,大量に発生した海水起源の熱水やマグマ起源の熱水に遭遇して加水分解する危機に直面します。そのまま熱水中にあれば分解消失してしまいますが,小胞を形成して内部退避した高分子はサバイバルできました。」
と,このストーリーは,想像ではなく,実験室での実験検証を重ねながら,仮説として固められていく経緯も,丁寧に説明されている。科学というものの,仮説づくりと,その検証実験というものが,いかにクリエイティブかを,よく教えてくれるプロセスにもなっている,と思う。
あとがきで,
「“人生は志と運”を信じていながら,取り掛かるのが遅きに失した」
との著者の述懐は,重く切実だ。そのせいか,本書の末尾は,
「本書に納得した読者が,あるいは逆に本書に異議を感じた読者が,さらに一歩,生命起源の未知領域に踏み込むであろうことを信じて,筆を置きます。」
と締めくくられている。ふと思う,野中郁次郎氏は,
知識とは思いの客観化プロセス,
と言っていた。だから,思いは,つなげていけるものなのだろう。
参考文献;
中沢弘基『生命誕生』(講談社現代新書) |
|
ヒト族 |
|
チップ・ウォルター『人類進化700万年の物語』を読む。
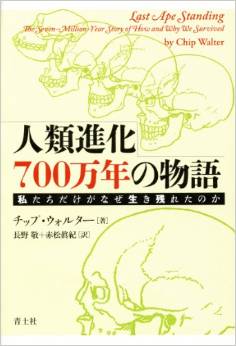
ヒト族は,
動物界 Animalia,脊索動物門 Chordata,脊椎動物亜門
Vertebrata,哺乳綱 Mammalia,霊長目 Primates,真猿亜目 Haplorhini,ヒト上科 Hominoidea,ヒト科
Hominidae,ヒト亜科 Homininae,ヒト族 Hominini,
である。その下にさらに続く。
ヒト亜族 Hominina,ヒト属 Homo,
と。
ヒト科は,ヒト亜科(ヒト属、チンパンジー属、ゴリラ属を含む)とオランウータン亜科で構成される。
ヒト亜科は,ヒト族(ヒト属及びチンパンジー属)とゴリラ族からなる。
ヒト族
はヒト亜族、チンパンジー亜族とそれらの絶滅した祖先のみが属するヒト亜科の族である。現生はヒト、チンパンジー、ボノボの三種のみ。
ヒト亜族は,チンパンジー亜族と分かれ,直立二足歩行をする方向へ進化したグループである。
ヒト属は,ヒト亜族のうち,大脳が大きく増大進化したグループ。現代人ホモ・サピエンスと,ホモ・サピエンスにつながる種を含む。約2万数千年前に絶滅したホモ・ネアンデルターレンシスを最後に,ホモ・サピエンス以外の全ての種は既に絶滅している。
因みに,ヒト属 Homoは,
ホモ・ハビリス H. habilis
ホモ・ルドルフエンシス H. rudolfensis
ホモ・エルガステル H. ergaster
ホモ・エレクトス H. erectus
ホモ・エレクトス・エレクトス(ジャワ原人) H. e. erectus
ホモ・エレクトス・ペキネンシス(北京原人)H. e. pekinensis
ホモ・マウリタニクス(ホモ・エレクトス・マウリタニクス)H. mauritanicus
ホモ・エレクトス・ユァンモウエンシス (元謀原人) H. e. yuanmouensis
ホモ・アンテセッサー H. antecessor
ホモ・ハイデルベルゲンシス(ハイデルベルグ人)H. heidelbergensis
ホモ・ローデシエンシス H. rhodesiensis
ホモ・ケプラネンシス H. cepranensis
ホモ・ゲオルギクス(ドマニシ原人)H. georgicus
ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)H. neanderthalensis
ホモ・フローレシエンシス(フローレス人)H. floresiensis
ホモ・サピエンス(ヒト)H. sapiens
ホモ・サピエンス・イダルトゥ(ヘルト人)H. s. idaltu
ホモ・サピエンス・サピエンス(現代人、現生人類)H. s. sapiens
等々過去700万年の間にいたが,現生人類以外,すべて絶滅した。本書『人類進化700万年の物語』は,訳のタイトルだと,のどかな話に見えるが,原題は,
Last Ape Standing
である。サブタイトルは,ずばりとその意図を示している。
The Seven-Million-Year Story of How and Why We
Survived
ヒト族が他の人類をどう蹴落としてきたか,という話である。27種類(と現時点ではわかっている)他の人類は滅んでしまったのである。
本書は,ヒト族について,注で,
「ヒト科は,ゴリラやチンパンジーを含むすべての大型類人猿を指すが,ヒト族は特に700万年前,あるいはその近辺で共通のチンパンジーの祖先から分枝した古代人と現代人を表す。この中には全てのホモ属(たとえばホモ・サピエンス,ホモ・エルガステル,ホモ・ルドルフェンシス),アウストラピテクス属(アウストラロピテクス・アフリカヌス,アウストラピテクス・ボイセイ等),パラントロプスやアルディピテクスのような古い人類が含まれている。重要なのは私たちが最後に生き残っているヒト科だということだ。」
と書いている(本書の訳では,ヒト族で統一されているが,改めて考えると,ヒト属を指すのかヒト族を指すのかが,混乱するところがあったが,まあこちらの浅学のせいだろう)。
いまのところ(まだもっと多くが発見される可能性があるが),27種類の人類(というか,この場合,ヒト属か)がいたらしいが,なぜか,他は滅びて,
「人間はたった一種類しかいない。なぜか。」
と,著者は問う。それが本書のテーマである。「1万1000年前に最後のホモ・サピエンス以外のDNA系統を廃れさせた」が,
「進化した全人類の中で,なぜ私たちだけがまだ生き残っているのだろう。」
に応えようとするのが,タイトルになっている。
「科学者は地球上に初めて人類が出現した時期を約700万年前と考える。それは主として,わずかしかないその頃の化石証拠が,今日チンパンジーと共通だった最後の祖先から私たちが分離してきたことを示すことによる。」
それ以降の700万年の物語である。しかし,読み終わって,その問いへの明確な答えは,ない。まあ,考えてみれば,当たり前かもしれない。
サヘラントロプス・チャデンシス,
と名付けられたのが,人類の始原となる化石である。彼(彼女)の頭部が,
「前肢の拳を地面につけて歩くゴリラのように45度の角度で胴体についているのではなくて,私たちのように胴体に沿ってついている」
ことを示唆していてた,として直立歩行をしていたと推測する古人類学者もいるそうだ。いずれにしても,
直立歩行,
という移動手段をとる哺乳類,というか全生物の中でも,
「これが類を見ない移動方法であった」
というか,一風変わった方法である,ということに着目しなくてはならない。少なくとも,
「それが一連の進化の出来事を始動させて,あなたや私の存在が可能になった」
のである。それと同時に,
「脳がますます大きくなってきた」。
チンパンジーの脳が約350ccであるのに対して,草地に住む霊長類の脳は,450〜500cc,なぜそうなったか。著者は,飢餓説を紹介している。
「食欲を満たすのが慢性的に困難な場合に,動物の体内では分子レベルで興味深いことが起きてくる。老化速度が遅くなり,十分な食物がある場合と比べて細胞は死ににくくなる。…身体は欠乏を感じると総動員でエネルギーの節約を行なって,最悪の事態に備える。(中略)栄養の極端な欠乏は動物の寿命を延ばすだけでなく,子孫の数が減ることによって進化の競争のもとで種全体が生き残る可能性を高める。…細胞の成長はあらゆるレベルで速度を落とすのだが,そこに…重要で驚くべき例外がある。脳細胞の成長は増大するのだ。(中略)少なくとも,新たな脳細胞の前駆体である視床下部が作り出すニューロトロフィンの場合はそうなっている。そればかりではなく,食料が欠乏すると食欲を増進するグレリンというペプチドが増加する…。グレリンは…シナプスを皮質ニューロンに変形する。…新しいニューロンの活発な成長を補うために体の他の部分は断食によつて乏しい栄養源をやりくりしてそれを脳に送る。言い換えると,体は加齢の速度を遅らせるが,知能は増大させる。」
350万年前,ちょうどあの有名なルーシー(アウストラピテクス・アファレンシス)や同時代の類人猿が,慢性的な食糧不足が脳の成長を加速させていた,ということになる。
直立歩行による移動性,
と
脳の成長による適応力,
が,生き残りに寄与した。しかし,効率よく二足歩行するためには,
骨盤の構造
を変える必要があり,しかしその代りに細くなった腰によって,産道が細くなり,それが大きくなった脳と頭によって,ますますお産を難しいものにした。その解決が,
テオニー,
である。つまり,未成熟(早産)で生れ出ることである。
「ゴリラの新生児のように肉体的に成熟して世の中ですぐに生きていける状態で生まれるとしたら,子宮の中で九か月ではなく二〇か月すごさなければならない。」
われわれの脳は,大人の23%で生まれ,三年間で三倍になり,二〇歳になるまで発達し続ける。これを,
「脳のルビコン」
と呼ぶそうだ。これを渡ると,
長い幼少期
が必要になる。おおよそ,180〜200万年前,ホモ・ルドルフェンシスやホモ・エルガステルがその候補とされている。
「解剖学的現代人」といえるものの出現は,16〜20万年前,エチオピア付近に出現した。しかし7万年前の氷河期,
一万人,
にまで減少する。ほぼ絶滅の危機に陥った。五万年後,気候の反転で,一気に地球上のあらゆるところへ移動していく(実は,その前,170万年前にも,アフリカを出ているが,今日では,それは,絶滅したと考えられている)。
ネアンデルタール人は,ホモ・サピエンスと共通の祖・ホモ・ハイデルベルクスから出ているが,現生人類よりはるかに長い,50万年,氷河期にも生き延びて,ヨーロッパに広がっていた。二万五千年前,ホモ・サピエンスとネアンデルタール人は遭遇し,2万数千年前に絶滅する。
なぜネアンデルタール人は絶滅したのか。いくつかの説があるが,最近有力なのは,ヨーロッパ各地で,クロマニヨン人(ヨーロッパにおける化石現生人類)と,長いもので,1000年も共存していた遺跡が見つかっており,DNAの分析から,1〜4%のネアンデルタールのDNAが現生人類に含まれており,
「ヨーロッパから東南アジアの島々に至る地域の人類の大部分は部分的にネアンデルタール人」
という。7万人に達することがなかったと言われるネアンデルタール人は,ある意味膨張する現生人類に呑みこまれた,というのが今の有力な見方のようだ。
著者は皮肉交じりでこう書く。
「なにしろ人間は他の霊長類や,その他の動物とさえセックスをすることが知られているのだから。」
と。
参考文献;
チップ・ウォルター『人類進化700万年の物語』(青土社) |
|
わかる |
|
山鳥重『「わかる」とはどういうことか』を読む。
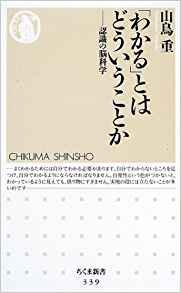
正直に言うと,群盲象を撫ぜるではないが,さまざまな切り口を枚挙してもらったわりに,
分かる,
ということが,なかなか分かった気にならなかった。というのも,わかる,ということには,知情意,というか,
知覚する,
感じる,
考える,
等々という領域と,「わかる」という領域とが,ベン図を例に言うなら,「わかる」という円と,その他の円がさまざまな重なり具合をしていて,たとえば,そもそも感受しなければ,わかるに至らないし,考えなければ,わかるということが必要ない,というように,きっちり境界を区分けできないせいかもしれない。さらに,
記憶する,
覚える,
学ぶ,
理解する,
経験する,
コトバにする,
等々の円とも,微妙に重なりあっている。
だが,僕のイメージするわかると,著者のそれとは,微かなずれがあった気がする。たとえば,著者は,「『わかる』の第一歩」として,
「単純なことですが,記憶にないことはわからないのです。言葉(記号音)の内容(記憶心像)を形成しておかないと,相手の言葉を受け取っても,心には何も喚起されません。(中略)「わかる」は言葉の記憶から始まります。そして言葉の記憶とは…名前の『意味の記憶』です。」
と述べる。不遜ながら,ああ,著者の「わかる」とは,そういうレベルのことを言っているのか,という幻滅がまず生じた。僕の知りたいのは,
腑に落ちる
とか,
納得する,
とか,
理解する,
という「わかる」であり,言葉の意味が了解できるということは,蚊帳の外にあった。本書の最後で,「わかる」のパターンを,
重ね合わせ的理解
と
発見的理解
の二つがあり,前者は,自分の頭にあるもの(モデル,知識,経験,感情,感覚等々)と重ねあわせること,であり,もうひとつは,答えが自分の外にあるもので,既知の答はなく,「自分で新しく発見していく」ものという。
僭越だが,間違っているのではないか。そもそも理解を,学習を,考えたとき,この二分法にしてしまうと,答えが外であろうと中であろうと,自分の中で考えて,
一つの答をひねり出し,
ああこうだったのだ,と納得するシチュエーションは,想定からはずされてしまう。答えが,外にあろうと,自分で考える操作は,常に,
新しい発見,
なのであって,それがアインシュタインの発見であろうと,幼児の発見であろうと,レベル差はあっても,
わかる,
ということの構造は同じである。あるいは,アルキメデスが,「Eureka」(「ユーリカ!」「分かったぞ!」)と叫びながら裸で通りに飛び出したというのもそれである。それを構造化するのが,
「わかるとはどういうことか」
の答でなくてはならない。著者は,「わかる」の土俵を,取り違えているようにしか,ぼくには見えない。たとえば,
「わかる」のわかり方を,
全体像がわかる,
整理するとわかる,
筋が通るとわかる,
空間関係がわかる,
仕組みがわかる,
規則に合えばわかる,
を類別しているが,その「わかった」というときを,
直感的に「わかる」
まとまることで「わかる」
ルールを発見することで「わかる」
置き換えることで「わかる」
と整理する。しかし,それは「わかる」ということの衣装が整理されているのであって,「わかる」ということ自体には踏み込めていない気がしてならない。この類別に当てはめる「わかる」は,
わかったのではなく知識をえた,
だけだ。では,なぜ,知識を得ると,
わかる,
のかが,踏み込めなければ,「わかる」という巨象の皮膚を撫ぜたにすぎない。吉本隆明は,
知ることは,超えることの前提である。
という言い方をした。だから,わかることの手段として,知をえることは,大事には違いないが,なぜ,知を得ると,わかるのか。
僕の億説に過ぎないが,わかる,ということは,
新しいパースペクティブ,
を得ることなのだと思う。
新しい視界,
と言い換えてもいい。メタ・ポジションを手にする,ということだ。それは,
新たな地平に立つ。
ということになる。だから,視界が開ける。よく,わかった瞬間,
頭にランプがともる,
というイラストが描かれるのは,
そのサーチライトで照らす
ことで,いままで照らされていなかったところに光が当たり,新たに見えてくることがあるだ。そこを詳らかにしてほしかった。
参考文献;
山鳥重『「わかる」とはどういうことか』(ちくま新書) |
|
問い |
|
伊東乾『なぜ猫は鏡を見ないか?』を読む。
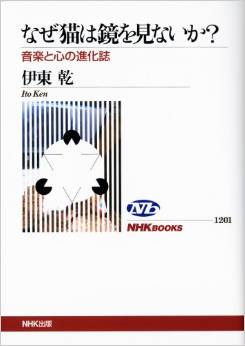
「仕事の全体像がわかる主著を」という依頼を受けた著者は,本書の意図を,最終章で,
「音楽人としての私の根本的な動機,松村(禎三),橘(常定)の二人の師との出会いから出発して(一章・二章),いくつかの大切な契機と初期の仕事(三章・四章),リゲティの示唆とめまいの経験による変化(五章・六章),博士としての仕事(七章)とそれによる新しい作曲・演奏(七章・八章),大学に研究室を構えて以降の展開,解剖,脳機能可視化,ブーレーズとの指揮メソッド作り,オーム裁判と豊田亨君のことなど「多方面の仕事」をコンパクトにまとめ(九章),開高健賞以降のドイツ,シュトックハウゼンと果たせなかった仕事やバイロイトでの展開(十章)などを時系列に沿って記しつつ,…最後に三・一一以降の現状と,ひとまずのまとめを一一章に記した。」
と,語っているように,物理学の博士であり,作曲家・指揮者である,自分の全体像を,
「私個人に修練すべき仕事(作曲・演奏)」
と
「私個人に限局されない仕事(演奏・基礎の探求)」
として描いている。そして,
「この本を私は,単に読み物として書いていない。ここから共に演奏し,また本質的な探究を共に考える,未来の仲間への呼びかけとして記している。」
と書くように,現代音楽の最前線の問題意識と成果が,惜しげもなく,披露されている。僕のような素人が読むべき本ではないのかもしれない。
それにしても,松村禎三,橘常定から始まって,ジョン・ケージ,ルイジ・ノーノ,見田宗介,三善晃,村上陽一郎,武満徹,ジョン・ピアーズ,マックス・マシューズ,レナード・バーンスタイン,磯崎新,井上道義,山田一雄,黛敏郎,若杉弘,ジェルジ・リゲティ,高橋悠治,観世栄夫,ブーレーズ,團藤重光,ホセ・ヨンバルト,カールハインツ,シュトックハウゼン,安藤四一等々,数え切れないほどに,現代音楽の最先端ばかりではなく,最先端の知性との知の格闘は,実に読み応えがある。
それも,
「音楽にとって本質的な問いとは何か?まずそこから自問自答が始まった。あれから30年が経つ。様々な問いを立てて,それに応える形をとって,私は私なりの音楽を作り,また私なりの演奏をしてきた。そんな動機の問いと,おのおのの答から導かれた実際の音楽によって具体的なバリエーションをお話していこう。」
と冒頭にあるように,常に「問い」があるからこそなのではないか。清水博氏の言う,
「創造の始りは自己が解くべき問題を自己が発見することであって,何かの答を発見することではない。」
そのものである。著者の問いは,
「人はいつ『歌』を獲得したのだろう?」
というような,「本質的な」問いが多い。リゲティに言われた厳しい指摘から始まっているが,いま,
「リゲティあたりに『模倣』と腐されない仕事をしよう,またそれを国内外に通じる言葉でも発信し,演奏し,基礎から音楽を積み上げる仕事をしよう。」
という決意に基づいている。誰かのやったことでないことをするには,誰も立てていない問いを立て,それに基礎の基礎から探求し直して,明らかな答えを探す必要がある。東大物理学部に,「作曲指揮研究室」を立ち上げたのも,またそういう問いの連続の中にある。
問いは,本書の各章のタイトルを見ただけでも納得できる(括弧内はサブタイトル)。
なぜ猫は鏡を見ないか(音の鏡と再帰的自己意識)
なぜ聴覚が生まれたのか(自己定位器と聴覚の起源)
なぜ魚群は一斉に翻るか(体の外部に開かれた聴覚)
なぜ音は調和して聞こえるか(物理的音波と認知的音像)
なぜ楽器で言葉を話せるのか(二足歩行と柔軟な調声器)
なぜ猫の仔とトラの区別がつくのか(両耳で聴く差異と反復)
なぜ歌は言葉より記憶に残るか(シェーンベルク=ブーレーズ・パルスの解決)
なぜ異なる歌を同時に歌いはじめたのか(長短と強弱の音声リズム)
なぜ理屈をこねても人の心は動かないのか(悟性が情動に遅れる理由)
なぜ落語家は左右に話す向きを変えるのか(潜水艦から空港騒音対策へ)
等々。そして,その問いは,作曲へとほとんどがつながっている。それは,民謡を採取したバルトークについて,
「バルトークはこれを『学説』として発表したわけではない。あくまで『楽案』として変奏を労作し,『楽曲』にまとめた…」
と語っているが,それは,そのまま,
「本質的な仕事をしたい。」
という著者自身について語っているに等しい。たとえば,「なぜ楽器で言葉を話せるのか(二足歩行と柔軟な調声器)」の章で,金属楽器に弱音器を挿入するというくだりで,
「弱音器をつけた金属楽器は『非現実話法』で語っている,という立場に立てば,複雑極まりないマーラーの総譜に従来とあきらかに別の視点から,系統だった解釈が可能になる。それが正解か誤解かを芸術音楽の指揮者は問わない。重要なのは,仮に誤読であっても一本の強い筋,響きの実体が伴った筋金入りの解釈の芯棒が通れば,そこから新しい音楽を読みだすことができる事だ。(中略)
さらに作曲の立場からは,こうした仮説を楽曲の構築原理に採用することで,新たな音楽言語のグラデーションを設けることができる。(中略)弱音器なしの奏法,金管楽器より変音が穏やかな弦楽器の弱音装着,金管の各種弱音器による異なる変音度合いを一種の『音階』のように見立てて,完全に『リアル』な世界から段階的に仮想性を増し,最後にはどう聞いてもウソっぽい,うさんくさくいかがわしい響きまで,弱音器を系統だって使い分けることができる。」
と書いている通りである。「音楽」を脳の問題として捉える,というのは,そういう先に来ている。
ひとつ例を出しておくと,たとえば,ルドンの「一つ目の巨人」を,初め両目で,次に,右目を閉じて見る。次に左目を閉じて見る。
ほとんどの人が最初に両目で見たときの巨人の位置が「左目だけ」あるいは「右目だけ」とどちらかが単眼でみたときと同じで,もう一方の目だけで見たときには,ひとつめの巨人の位置が動く。
「視野の動かない方の目が『利き目』」
である。これは,目だけではなく,耳でも言える。電話がステレオでないのは,片耳で聴けば十分音声がつながるからではなく,
「人間は音声言語を『両耳で聞いてしまうと』理解力が下がってしまうからだ。『両耳マスキング』と呼ばれる」
ことが起きている,からだと言う。なぜなら,
「目や耳など末梢から入力された情報は,中枢神経系の複雑な処理を経て,言語の高度な意味を持って意識にそれと認識される。そうした処理には時間もかかるしエネルギーも食う。…二つの目や耳から入ってくる情報の片側については,早い段階で処理しなくなる。つまりスイッチオフして,余計な情報処理のエネルギーを節約していると考えられる。」
しかし,二つあることで,環境内の自己定位に,ステレオ視・ステレオ聴が有効で,視覚もそうだが,聴覚も,
「誰かが自分の名前を呼ぶようなとき,私たちは反射的に声のする方向を振り返る。両耳聴=バイノーラル・ヒアリングに注意が向くとき私たちの耳は反射的にステレオモードにスイッチがかわっている。」
このことを,意識して作曲や演奏している人は90年代までは皆無だったが,その目で見ると,ヴァーグナーは,総譜に「演出ト書き」の形で,声と楽器の空間配置と分布を詳細に記しているのである。つまり,
歌手の立ち位置,歌う方向による「両耳相関の違い」
が出ることを知っていたからである。音の空間を意識していた,と伺えるらしいのである。このことは,落語の語りにもつながるらしい。
「『熊さん』と「八っっさん」の会話を,噺家は姿勢を左右に変えて演じ分ける。…寄席で名人の落語を聞くと,左右の側壁に反射する声をコントロールして,小屋の響き全体から『熊さん』と『八っつあん』の違いを創り出している。…名人が適切に側壁をかつようすれば,二人の人物の声を聴き手の左右の耳に,交互にアクセントをつけてとどけることができる…。」
と。脳のことを知らなくても,名人たちは,研ぎ澄まされた感覚で,それを活用していた,ということである。
参考文献;
伊東乾『なぜ猫は鏡を見ないか?』(NHKブックス)
清水博『正命知としての場の論理』(中公新書) |
|
心脳問題 |
|
マリオ・ボーリガード『脳の神話が崩れるとき』を読む。
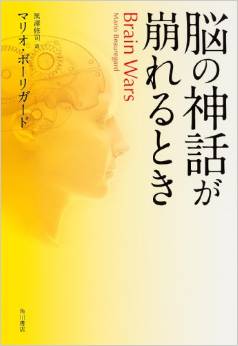
「脳の神話」と言うか,原題は,
Brain Wars
サブタイトルが,
Scientific battle over the Existence of mind
and the proof that will change the way we live our lives
いわゆる「心脳問題」を,著者は終始,唯物論に反対する立場から書いている。
つまり,すべての精神活動は,脳の機能に過ぎないという,古くは,デモクリトスの原子論,ヒポクラテスの,
「脳が損傷を受けると精神の働きも損なわれるのだから,脳は意識,思考力,そして感情の座するところなのである。」
に対する,たとえば,ウイリアム・ジェームズの,
「科学で測ることができるのは,『脳の状態に変化が起これば,精神状態にもそれにともなった変化が起こる』と言う相互関係だけである。」
という指摘にある,「脳が損傷を受けたことにより人の精神機能に変化が起こったからといって,精神や意識が脳から生まれているという証明にはならない。」
という考えや,脳の働きをマップ化した,ペンフィールドの,
「意識,論理思考,想像力そして意思力といった高次の精神機能は脳が生み出したものではない。精神とは脳と相互に作用する,非物質的な現象である。」
という立場の側にいる。
脳もまた肉体の一つである,
等々と言う考え方とは違う。だからと言って,いたずらに,神秘主義であったりスピリチュアリティであるわけではない。マインドの驚異的な力を明らかにしようとはしている。確かに,
プラシーボ効果,
ニューロフィードバック,
神経可塑性,
催眠,
辺りは,脳のもつ機能の凄さを実証する実験や実例を挙げていくのたが,臨死体験に関わる,
超能力,
臨死体験,
神秘体験,
辺りからいささか,科学の常識を外れていく。しかし,著者は,
「量子宇宙には,心脳問題など存在しない。精神世界と物質世界の間に,明確な境界がないからである。」
といい,
「どれだけ科学コミュニティの中で唯物論の学説が根強かろうと,それでは心脳問題の答を見つけ出すことはできない。私たちは,宇宙における精神の力とその中心的役割とを見つけるために新たなモデルをみいださなくてはならないのだ。」
として,「人の精神がもつ普遍的な,そして驚異的な可能性を示す根拠」をたくさん示すのが,本書の目指すことであり,
「心的現象の存在,そして心的現象が人間の脳や肉体に及ぼす影響を示す確かな証拠は数多くある。その証拠はまた,人の精神とは肉体の外で起こる現象にまで作用するのだということ,そして脳が機能していないように見えたとしても人は意識的に常識を超えられるのだということをも物語っている。」
と述べる。精神活動や意識を,実体化して語っておられるのが聊か気になるが,この辺りは,「あの世」と言われる,分岐していく多次元世界の話,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416694519.html?1428004473
と,多次元宇宙の話,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416793184.html?1428175950
ともつながる,量子論に関わってくる。
本書で,主張の色調が変るのは,臨死体験からである。その流れて,幽体離脱の例を挙げておく。
巨大な脳底動脈瘤のバム・レイノルズは,低体温循環停止法(体温を極端に下げて肉体を冬眠状態にし,血管を取り換える手術)を受ける。バムは,麻酔を受けて,意識を失った。ところが,執刀医が,歯科ドリルのような音を立てるのこぎりで頭蓋骨を切開される頃,
「彼女は,体から飛び出して手術室の天井へと舞い上がり,自分に手術を施す石たちの姿を見下していた…。」
そして,意識を失っているはずなのに,医師たちの,予定の右太ももの大腿動脈が細すぎるため,急遽左に切り替えるやり取りを聞いており,冷却されて臨床死状態に成っている頃,本人は,
「ふわふわと手術室から抜け出し,光のトンネルに入って行ったというのだ。彼女はそこで,トンネルの終点で彼女を待っている,…祖母をはじめ,もう死んでしまった家族や友人の姿を見たという。やがて安らぎと温もりとに溢れた無常の光に包まれたかと思うと,自分の魂が神の一部に,すべてを創造した光の一部になってゆくのを彼女は感じていた。だが,この超常体験は突然終りを迎える。亡くなったはずの叔父が,彼女を肉体へと連れ戻したのだ。そのときの感覚を彼女は『まるで氷水のプールに飛び込むようだった』と語っている。」
こうした臨死体験は,アメリカ,ドイツの調査で,人口の4.2%が持っている,と言う。そして,大まかなところ体験は似ている。多く,この体験を通して,「自らの人生を理解し,どう生きるべきだったかに気付く」という。大体,この臨死体験中,バムの例では,医師の会話,別の例では,病院の屋上まで上がっていき,干してある運動靴を見た(後で確かめると,正しかった),と言う例もある。
多くの臨死体験を調べたリングとクーパーは,
「通常の感覚とは異なる別の感覚を通して現実を認知することができる」
と言う。しかし,僭越ながら,似た体験ということは,人間の脳の機能として,そういうものが,『ガンダム』のニュータイプのように,未開拓のままある,ということではないか,と考えた方が,精神を実体化するよりは,まっとうだと思うのだが。
著者は,「たったひとつの事例でしかない」と,多少の蔑みを込めて紹介するが,
「前頭葉にある角回(視覚,言語,認知などに関連するさまざまな処理を行うと考えられている)という部位に電気刺激を与えると,患者は『ベットに横たわる自分を上から見ているようだったが,見えたのは脚を含む下半身だけだった』とはなした。」
という例がある。これは,池谷裕一氏も紹介していたはずである。一つの事例があれば,それを確かめるのが科学者ではないか。神秘体験や幻覚を起こす,側頭葉の部位もある。
僭越ながら,実体化した精神を検証するすべはないが,脳の機能として,超人的な感覚をもたらすと考える方が,精神が脳とは別に実体化してあると考えるよりも,検証のしようがあるように思えてならないのである。それこそが科学のはずだと思えるのだが。
参考文献;
マリオ・ボーリガード『脳の神話が崩れるとき』(角川書店)
池谷裕二『脳には妙なクセがある』(扶桑社) |
|
記憶力 |
|
高橋雅延『記憶力の正体』を読む。

サブタイトルに,「人はなぜ忘れるのか」とある。
冒頭,ウイリアム・ジェームズの,
「もし私たちがあらゆることを忘れないとすれば,ほとんどの場合,何も覚えていないのと同様に困ったことになる。ある一定の時間を要した出来事を思い出すためには,もとの出来事と同じだけの時間が必要になり,新しいことを考えることができなくなってしまう。」
を引きながら,忘却力のお蔭で,われわれは,
「次々と新しいことがらを覚えたり,自分の考えを先に進めていくことができる」
と指摘している。さらに,バルザックの,
「多くの忘却なくしては人生を暮らしていけない」
を引きつつ,辛い出来事も,時間の経過とともに忘れ,辛さが軽減していくことも,忘却の効果をあげている。
ただ,忘れると一言で言っても,二つの意味がある。
「その一つは,長い年月がたってしまうことで,記憶が消滅してしまうケースです。…もう一つは,どこかに記憶としては残っているけれども,それをうまく引き出せないケースです。」
忘却といえば,ヘルマン・エビングハウスの「忘却曲線」が有名だが,その彼が,記憶の現れ方を,三つに区分している。
第一の記憶は,「我々がその目的で意志を働かせれば,失われたかと思われた意識の状態を,ふたたび意識のなかに呼びもどすことができるもの」。それで元の状態を再現できないことを,忘れた,ということになる。
第二の記憶は,「かつて一度意識のなかに存在した精神状態が,なん年もたったあとで,まったく意志の働きなしに,明らかに自発的に,ふたたび現れてくる」,自然に再現される記憶。無意図的記憶と呼ばれる。
この二つは,現在,「意識的記憶ないしは顕在記憶」と呼ばれる。
第三の記憶は,無意識的記憶ないしは潜在記憶,と呼ばれ,それが再現されても,「過去のことを思い出している」と意識されない記憶。
これは,スキルに関わるもので,手続き記憶と言われるものになる。一旦覚えた自転車の乗り方やスキーは,体が覚えている,といってもいい。
エビングハウスの記憶は,ある意味学習の忘却曲線だが,いわゆる自伝的記憶と呼ばれる記憶は,それとはまったく異なって,
「最初の一年間は,ほとんど忘却が起こらず,それ以降は,きわめてわずかずつ忘却される」
というのが,思いでの忘却曲線の特徴とされる。
本書は,「自伝的記憶を中心に忘却や記憶をめぐるトピックス」を扱っている。
たとえば,フラッシュバルブ記憶というのがある。ケネディ暗殺や3.11のようなショッキングな出来事を知った時の自分の状況に関する鮮明な記憶のことである。
フラッシュバルブつまり,「フラッシュライトのように,非常に詳細に記憶されている」ということだが,
「出来事そのものの鮮明な記憶ではなく,自分がいつどこでどのような状況のもと,その出来事を知ったかという自分自身に関する記憶が鮮明であるというものです。」
その出来事を知ったときの「驚き」によって,脳内に生理的な変化が起こり,記憶として焼き付けられる,と著者は言い,
「『驚き』という感情的ストレスが強ければ強いほど,生理的な変化が強く起こり,それだけ記憶が鮮明に焼き付けられる…。」
それは長期間にわたって細部まで保存されているが,しかし,写真のように細部まで正確に記憶されているわけではない。多くの記憶間違いが起こる。
「だれもが経験的に知っているように,何かを覚えるためには,繰り返すことが重要です。だとすれば,繰り返し思い返されるフラッシュバルブ記憶がいつまでも鮮明であるのは,ある意味,何も不思議なことではなくなってしまいます。逆に言えば,私たちがふだんの何気ない出来事を忘れていくのは,それを思い返すことがないからなのです。」
その意味では,感情的ストレスに関与した場面の記憶は良く,それ以外の記憶は悪化する,というのは,
「一つは注意の集中」
であり,
「もう一つは,感情ストレスの関与した出来事が起こった後の反すう,思い返し」
という,まあ,当たり前のことが,記憶を左右する。しかし,
「感情ストレスの強さは,ある適度レベルまでは記憶をよくするのですが,その最適レベルを超えると,今度は逆に記憶が悪化してしまうのです。」
PTSD(心的外傷後ストレス障害)の場合,フラッシュバックのようなつきまといとともに,記憶の欠落をも生む。これは,感覚的記憶ないしは身体記憶といわれる,無意識的記憶の特徴らしい。
無意識的記憶には,
快不快といった感情の関与するもの,
視覚的パターン,
身体の記憶,
というものがある。
身体の記憶は,スキルのような手続き記憶に当たるが,単純接触効果によって,接触頻度が増えるにつれて,意識していないが好印象を持ってしまう,というのが感情の関与するものだ。視覚的パターンは,健忘者に隠し絵を見せる。一日立つと,それを見た記憶を健忘者は持たないのに,隠し絵のパターンは,無意識で覚えていて,素早く再認する,という例がある。所謂勘といわれるものも,パターン認識だが,無意識記憶に入れられるだろう。
言ってみると,知識も含め,我々の頭にある記憶は,主に,
エピソード記憶(自伝的記憶に重なる),
意味記憶,
手続き記憶,
になるが,
「私たちの記憶は,さまざまな記憶が無味乾燥に並んでいるのではなく,それぞれのテーマにまつわる『物語』として,関連した複数の出来事があつめられて(意味づけられて)いるのです。」
だから,
「『過去から未来へ向かって生き続ける一人一人の人間の存在』との関係から記憶を考えたとき,当人自身やまわりの状況が変ることによって,想起される記憶が変り得る可能性が常に存在するのです。」
ということを忘れてはならない。つまり,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416479966.html
でふれたジャネが言うように,
「愉快なときには,何でも薔薇色に見え,哀しいときには,何でも黒色に見える」
のであり,そのときの気分にかなう記憶が思い出される。ナラティブ・セラピーで言うように,いまの生き方が,
自分のドミナント・ストーリーを決める,
別の気分の自分には,
オルタナティブ・ストーリー,
が語れる。記憶もまた,いまの自分の生き方が,語らせる,一つの物語なのだ,という気がする。
参考文献;
高橋雅延『記憶力の正体』(ちくま新書) |
|
感情 |
|
清水真木『感情とは何か』を読む。

著者は,感情について,冒頭で,こう書く。
「私たちは,言語を手がかりにして感情を獲得し,感情を理解し,感情を共有します。感情は,私たち一人ひとりが何者であるかを告げるものであるとともに,私たちが身を置く世界の真相を普遍的な仕方で明らかにするものでもあります。具体的な感情をそのつど正しく受け止めることは,,自立的な自足的な生存への通路なのです。みずからの心に姿を現す感情の一つひとつを丁寧に吟味し,これを言葉に置き換える努力は,誰にとっても必要であり,価値あるものであるにちがいありません。」
これは,「やばい」ひとことで,さまざまな感情の彩りを表現することへの警鐘として語られているが,著者の感情の捉え方を象徴しているようである。
だから,
「感情とは何か」
という問いの意味を,こう書く。
「感情という現象には,一つの特殊な性質があり,この性質によって気分や知覚から区別されます。すなわち,感情を惹き起こす原因となるものが何であるにしても,感情が心に生まれるためには,感情の原因となる事柄が『私』のあり方との関連においてそのつどあらかじめ把握されていなければなりません。これは,感情を知覚や気分から区別する標識です。感情とは,『私とは何者なのか』を教えてくれるものであり,『私とは何者なのか』という問に対する答えは,感情として与えられます。」
さらに,
「気分や知覚は,物の見方や価値評価とは関係なく成立するものであり,この限りにおいて,自然現象に分類されるべきものです。…これに反し,感情は,各人の個性を反映します。」
とも。そして,
「感情の経験とは,自己了解の経験,『私とは何者なのか』を知る経験として受け止められるべきものです。なぜなら,感情の本質は,私と世界の関係をめぐる真理(=真相)の表現である点にあるからです。」
だから,
「『感情とはなにか』という問は,私と世界の関係を存在論的な仕方で問うものであると言うことができます。」
本書の大半は,プラトン,アリストテレス,からデカルト,スピノザ,ヒューム,アーレントまでの,哲学史の中での「感情」の取り扱われ方にページが割かれる。正直言って,西洋哲学に関心のない向きには,些事に渉る議論は,退屈で,迷惑このうえない。
しかし,本書は,「感情の哲学史」を目指し,
「感情の哲学史とは,情動主義との対決の歴史として,そして,感情の快楽の意味を明らかにする試みの歴史として記述されねばならない」
とし,古来以来の,「理性と感情の対立」というテーマを取り上げず,
「『感情とはなにか』を問うことにより本当に問われているものは何か,このような点が明らかになることにより初めて,哲学史に照明を当てる確度が定められ,哲学者たちのテクストに陰翳が生まれ,見解の『幹』と『枝葉』がおのずと区別されて行きます。」
という進め方を取る。それでも細部は,結構煩雑だが,著者が前提にしている考え方は,昨今流行の「アンガー・コントロール」というものとの違いを説くところによく表れている。「アンガー・コントロール」は,
「『怒り』(anger)の名を与えられた感情のコントロールではなく,怒りの表現として普通には受け取られている発言や行動と怒りの感情を結びつけることを容易にするような『気分』のコントロールにすぎません。むしろ,ほんとうの意味に置ける怒りのコントロールが可能であるなら,それは,怒りを変化させ,別の感情を産みだす操作でなければならないでしょう。」
つまり,怒りの代わりに,「憐み」や「悦び」「妬み」「敬意」を覚えさせるのでなければ,それはアンガー・コントロールではなく,怒りにともなう行動のコントロールを言っているだけだ,と言うのである。
それで思い出したが,前にも,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163273.html
で取り上げたが,ジル・ボルト・テイラーは,こう言っている。
「わたしは,反応能力を,『感覚系を通って入ってくるあらゆる刺激に対してどう反応するかを選ぶ能力』と定義します。自発的に引き起こされる(感情を司る)大脳辺縁系のプログラムが存在しますが,このプログラムの一つが誘発されて,化学物質が体内に満ちわたり,そして血液からその痕跡が消えるまで,すべてが90秒以内に終わります。」
生理的な反応の怒りは90秒まで,それ以降は,それはそれが機能するよう自分が選択し続けている,ということである。つまり,思いの偏りで,視野が狭窄しており,怒りつづけなければ,思いの秤のバランスが取れなくなっている,というように,である
著者の言うように,
「コントロール可能なのは,気分だけであり,気分から区別された感情というものは,外部からの一切のコントロールを受けつけないものなのです。」
では,感情とは何か。
「感情の本質は自己了解である。」
と,マルブランシュ(1674〜5の『真理の探求』)を例にとって,
「情念の役割は,さしあたり,身体と心を含む一つの全体としての私の自己保存を支える点に求めることが出来ます。情念の体験を手がかりに,私は,好ましいものを選びとり,好ましくないものを斥けるからです。つまり,情念を情念として受け取ることを可能にするのは,体に対する私の『愛』であることになります。」
と述べる。そして,
「私の正体は,放っておいてもどこかから自然に涌いてくる身ではありません。(中略)フランシス・ベーコンが…用いた…表現を借用するなら,特別な道具を用いて自分を哲学的な『拷問』にかけ,自分の『秘密』を自分に対して『自白』させるくるしいプロセスでしょう。自己了解を目標とする拷問とは,『私は何者なのか』という問に対する答として不知不識に到来する感情から目を逸らすことなく,これを吟味し,説明するよう自らを強いることにほかなりません。」
と集約する。それは,終り近くで,アーレントを借りて,こう述べるところにつながる。
「感情は,『伝達可能』であるかぎりにおいて,公的であるかぎりにおいて感情として受け止めることが可能となります。感情は,単なる内面的,個人的,私的な現象なのではなく,むしろ,これが有意味な経験となるためには,なによりもまず,他人からの承認を想定して何らかの仕方で言葉へと置き換えられるプロセスが必要なのです。このかぎりにおいて,私の感情は,その都度あらかじめある特別な仕方で普遍性を具えていると考えなければならないことになります。」
それは,感情を自分が自分の感情として受け止めるには,言語に置き換える作業が必要であり,言葉に置き換える作業が,他人による承認,他人との共有を想定して遂行されるものであること,そして,その
「他人による承認の基準が『共通感覚』あるいは『趣味』と呼ばれるものであること,さらに,このような基準の正体が『共同体感覚』であり,公的領域に由来するものであること」
を教えてくれるのである。それは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163222.html
で触れた「嫌悪感」のように,社会的に形成される感情もある,ということにつながる。だからこそ,最後の,
「感情は,意見を異にする者たちのあいだのオープンな討議と合意形成の場としての公的領域を形成し維持する意欲,『公共性への意志』と呼ぶことのできるような意欲を基礎とするものであること,したがって,反対に,このような意欲を持たない者には,本当の意味における感情に与る可能性が閉ざされていると考えることが許されるに違いありません。」
という言葉がが生きる。
そう言う指摘に鑑みるなら,今日の,ヘイトスピーチを底辺とし,憎悪と嫌悪感のみでつながる為政者をトップとして,その嫌悪感と憎しみを言語化しようとしない(あるいは言語化するのを避けている,逃げていると言うべきか),いまの日本の今日のありようは,世界から,決して理解されないであろう。
かつて,憎しみ合うアイルランド紛争の最中,ロジャーズが試みた,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/410724005.html
での,エンカウンター・グループにおける,「感情の言語化」による,相互の(相手に対して閉ざされた)「鋼鉄のシャッター」の開扉を目の当たりに見たものにとっては,なお一層,各々を自己完結した閉鎖されたところに押込めていく,今日の為政者の悪意を思うとき,いずれ自分の死後の日本のことにしろ,絶望に駆られる。恐らく,このまま日本は,再度孤立し,絶望的などん底を味わわされる羽目に陥るだろう。
一体何度同じ轍(すべては明治以降のことなのだが)を踏めば,我々は,覚醒するのだろう。いや,覚醒は来ないかもしれない,それほど,絶望している。
参考文献;
ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』(新潮文庫)
清水真木『感情とは何か』(ちくま新書) |
|
三つの声 |
|
岡本綺堂『半七捕物帳 三浦老人昔話 全82話完全版』を読む。
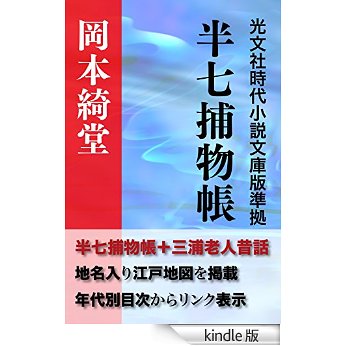
「駒塚由衣江戸人情噺」を伺った折,作者の藤浦敦さんの話で,江戸ものなら,三田村鳶魚か岡本綺堂の随筆,と言われた。半七捕物帳は,推理がない,と散々であった。しかし,(いままで無視していたので)読み始めて見たら,たしかに,江戸風俗を知るにはいいが,推理物としては,少しプロセスが省かれていて,半七の頭の中で完結している具合であった。しかし,僭越ながら,「三つの声」はいい。
これは,今読んでも,読み応えがある。三つの声とは,
明け方,表戸越しに掛けられた声である。
一つ目は,
「庄さん、庄さん」
これに夢を破られて、お国は寝床のなかから寝ぼけた声で答えた。
「内の人はもう出ましたよ」
外ではそれぎり何も云わなかった。
二つ目は,
再び表の戸をたたく音がきこえた。
「おい、おい」
今度はお国は眼をさまさなかった。二、三度もつづけて叩く音に、小僧の次八がようやく起きたが、かれも夢と現うつつの境にあるような寝ぼけ声で寝床の中から訊きいた。
「誰ですえ」
「おれだ、おれだ。平公は来なかったか」
それが親方の庄五郎の声であると知って、次八はすぐに答えた。
「平さんは来ませんよ」
外では、そうかと小声で云ったらしかったが、それぎりで黙ってしまった。
三つ目は,
間もなく、又もや戸をたたく音がきこえた。今度は叩き方がやや強かったので、お国も次八も同時に眼を醒ました。
「おかみさん。おかみさん」と、外では呼んだ。
「誰……。藤さんですかえ」と、お国は訊きいた。
「庄さんはどうしました」
「もうさっき出ましたよ」
この三つの声の表現の中に,すべてを含ませているところは,なかなかの妙手である。詳しくは,上記を読んでいただければいい。
『半七捕物帳』は、岡本綺堂による時代小説で,捕物帳連作の嚆矢とされる。というより,日本の推理小説の嚆矢といってもいい。
「1917年(大正6年)に博文館の雑誌『文芸倶楽部』で連載が始まり、大正年間は同誌を中心に、中断を経て1934年(昭和9年)から1937年(昭和12年)までは講談社の雑誌『講談倶楽部』を中心に、短編68作が発表された。」
とされている。
「綺堂は『シャーロック・ホームズ』を初めとする西洋の探偵小説についての造詣も深かったが、『半七捕物帳』は探偵小説としては推理を偶然に頼りすぎたり、事件そのものが誤解によるものだったりして、謎解きとしての面白さは左程ではないと言われる。しかし何作かは本格性の高い作品である。国産推理小説がほとんど存在しなかった時期に先駆的役割をつとめたことは確かである。」
という中での,「三つの声」である。
因みに,作中で『捕物帳』と言っているのは,
「町奉行所の御用部屋にある当座帳のようなもので,同心や与力の報告を書役が筆記した捜査記録をさしている。」
ので,後年の「右門捕物帳」等々,続く作家たちが使った「捕物帳」とは意味が違う。本来の「捕物帳」の意味を弁えていた,ということである。野村胡堂が『銭形平次捕物控』と,「捕物控」という言い方を使ったのには,たぶん意味がある。
推理小説で言う,「推理」は,野暮を言うようだが,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/prod0951.htm
で書いたように,筋の通り方には,
・意味の論理の筋
・事実の論理の筋
のふたつがある。前者を演繹,後者を推測(推測には,帰納,仮説,といった思考法がある),と呼ぶが,必ずしも,この「推理」の範疇にはおさまらない。ときに演繹的に,相手の論旨のほつれから解きほぐすときもある。
世界初の推理小説は,一般的にはエドガー・アラン・ポーの短編小説「モルグ街の殺人」(1841年)であるといわれるから,ほぼ半世紀遅れての登場ということになる。
僕は,ミステリーファンでも通でもないが,薦められて何冊か読んだなかでは,
アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』,
ウィリアム・アイリッシュ『幻の女』,
エラリー・クイーン『Yの悲劇』,
F・W・クロフツ『樽』
等々が印象に残るが,僕は,中井英夫の,
『虚無への供物』
が一番である。ひねくれ者には,「反推理小説(アンチ・ミステリー)の傑作」と言われ,「推理小説でありながら推理小説であることを拒否する」という世評よりは,
メタ・ミステリー
であるというところがいい。ミステリーを俯瞰しつつ,ミステリーは,現実のなぞに較べたら,箱庭だ,と嘲笑うところがいい。
閑話休題。
話を綺堂にもどすと,『半七捕物帳』だけではないが,随所に,面白い言い回しが出てくる。特徴的なのは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/418053269.html?1430165639
http://ppnetwork.seesaa.net/article/418161213.html?1430333078
等々でも書いたが,たとえば,泥道で難渋したとき,
粟津の木曾殿,
という表現をする。こんな具合である。
「『粟津の木曽殿で、大変でしたろう。なにしろここらは躑躅の咲くまでは、江戸の人の足踏みするところじゃありませんよ。』
まったく其頃の大久保は、霜解と雪解とで往来難渋の里であった。」
言わずと知れた,粟津で泥田に馬の足を取られて,討たれた木曽義仲を指している。平家物語には,
「木曾殿はただ一騎、粟津の松原へぞ駆け給ふ。頃は正月二十一日、入相ばかりの事なるに、薄氷張りたりけり。深田ありとも知らずして、馬をさつとうち入れたれば、馬の頭も見えざりけり。」
とある。その他,滑って転んで,
「とんだ孫右衛門よ」
と,『梅川忠兵衛』の実父の名が,ひょいと出る。切りがないが,
「小利口な五右衛門も定九郎も,みんな攘夷家に早変わり」
といったいい方が,さりげなく出る。芝居や古典の素養などというよりは,当時の読者には,それだけで,メタファーとして通じた(常識)ということに,いちいち躓き,調べているおのれが恥ずかしくなる。
最後に,個人的な印象だが,野村胡堂の「銭形平次」物に比べると,「半七捕物帳」の良さ,というか品と心映えがよくわかる。小説としても,「半七捕物帳」のほうがはるかに,上だと思う。前者は,横溝正史的で,言ってしまえば,けれんみたっぷりというか,嘘っぽい。半七は,確かに地味だが,江戸時代という現実に密着した,さりげない仕草,振る舞いにリアリティがある。それは,時代の制度,身分関係,風俗・文化の細部がよくわかっている,ということなのかもしれない。
参考文献;
岡本綺堂『半七捕物帳 三浦老人昔話 全82話完全版』(Kindle版) |
|
あの世 |
|
岸根卓郎『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」 』を読む。
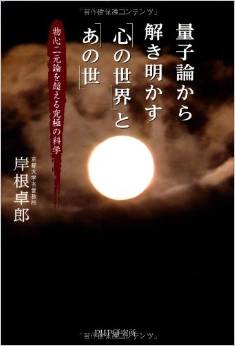
本書は,いわゆる宇宙論の中で,「人間原理」と言われる立場に立っている。著者は,それを,
「私たち〈人間〉は単なる宇宙の観察者であるばかりか,〈宇宙の創造者〉でもあり,しかもその〈宇宙〉はまた私たち〈人間〉に依存している」
とし,こう説明する。
「宇宙の〈万物〉や宇宙で起こるさまざまな〈出来事〉は,すべて〈潜在的に存在〉していて,私たち〈人間〉がそれを観察しないうちは実質的な存在(実在)ではないが,〈観察〉すると突然〈実質的な存在〉(実在)になる。」
と,それを象徴的に,
「月は人間(その心)が見たときはじめて存在する。人間(その心)が見ていない月は存在しない」
という言い方をする。それを解くための背景が,量子論なのである。一件,スピリチュアリティに堕しそうで,しかし量子論の論拠を外さない。そこが,説得力を持つゆえんであろう。
人間原理については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163436.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/394437227.html
で触れたように,現代宇宙科学の一大潮流ではある。
「〈宇宙〉は,〈人間による認知〉を待っている」という,その人間原理を例証していく,第一が,「光と同様,粒子と見なされていた電子などの物質粒子にも,波としての性質,物質波がある」という「物質波理論」である。
マックス・ボルンやニールス・ボーアらは,「〈物質粒子の波〉は,その〈粒子の発見確率〉を表している」とし,
「電子を波と考えると,電子の発見確率は,その電子の波の振幅が最大の場所で最大となり,幅がゼロの場所では最小となる。」
というのである。そして,
「〈電子の波〉もまた〈確率波〉である」
こと,そして,
「〈電子の波〉は,〈観察〉すると一瞬にしとて〈一点に収縮〉するという電子の波の収縮,いわゆる〈波束の収縮〉」
をも明らかにした。別名,「波動関数の収縮」とも「量子飛躍」とも呼ばれるが,この解釈は,「コペンハーゲン解釈」と呼ばれる。
たとえば,電子が一個入った箱を二つに分断して,京都とパリに置いたとする,箱を開けるまでは,両方の箱の中には「電子の波」が共存している。しかし,どちらか一方で,箱を人間が開けた瞬間,「波束は収縮」して,開けた方の箱だけに,「一個の電子」が見つかることになる。
注目すべきは,箱を開けた瞬間に,瞬時にその情報が伝わる,ということである。波束の収縮における情報伝達のスピードは,アインシュタインの特殊相対性理論で言う拘束を超える,ということである。
有名な光の波動性と粒子性を確かめるヤングの「光の干渉縞の実験」があるが,ジョン・ホイーラは,「二枚の半透明鏡を用いる実験」で,光の粒子と波動性の二面性の解明の他に,光と人間の意志の関係についても解明しようとした。そこでは,
光のパルスが第一の半透明の鏡を通過する〈事前〉に,検出器の前方に第二の半透明の鏡を置くか,通過した〈事後〉に,遅れて置くかを選択することによって,光がに波として行動するか,粒子として行動するかを確かめる,
というところにあった。結果は,人間が光が第一の鏡を通過する前に,検出器を第二の鏡の前に置かないことを選択するか,通過した後に置くことを選択するか,で,前者だと光は粒子となり,後者だと光は波動となる,のである。
「光自身は,(第一の鏡)を通過したばかりの時点では,自分が〈後〉で〈粒子〉になるか〈波動〉になるかは知らない」
のである。人間の意志による,事前か事後かの選択で左右される,ということである。これを「遅延選択の実験」と言う。その実験の重要性は,
「〈人間〉は,光が検出器に到達する〈前〉に,光が〈粒子〉として振舞っていたのか,〈波動〉として振舞っていたのかを,〈過去〉にまで遡って知ることができる」
ということであり,さらに,
「〈人間の心〉は,〈光の未来〉に対してはもちろんのこと,〈光の過去〉に対しても,〈影響〉を与えることができる」
という点である。それは,当然光だけでなく,電子についても,
「電子の波のエネルギーになっているのが光子」
であり,電子もまた,波動性と粒子性を持っている。さらに,一つの電子は,複数の状態を同時に取ることができる。それを,「電子の状態の共存性」というが,
「〈電子の状態の共存性〉とは,〈一つの電子〉が〈同時〉に〈複数の場所に共存〉できる」
という。これを,「状態の重ね合わせ」ともいう。
たとえば,箱の真ん中に衝立を立てて箱を二つに区切ったとする。このとき,一つの電子は,左右に同時に存在することが出来る(状態の共存性)。この場合も,〈粒子〉であると同時に〈波〉でもある。この場合,複数の電子があるのではなく,〈波であった〉一つの電子が同時に共存している。
しかし,観測者が箱の片方を開けると,瞬間に,複数個共存していた電子が,
ただの一個の電子
になって,電子がどちらにあったかが確定する。つまり,人の観測によって,開けた場所に存在する状態に,瞬間に変化した(波束の収縮性)のである。
波として共存していたものが,一点に収縮して,粒子,
にしか見えなくなる。著者は,
「電子の波は〈発見確率〉に関係しているから,その波を〈人間が観測〉した〈瞬間〉に,波は〈発見確率100%〉の幅のない〈針状の波〉となって〈一点〉のみでしか発見(観測)されない」
と説明する。見えないものが人間と接触すること(相互作用)で,「観測された状態以外の状態が〈消えて〉なくなる」のである。これが,冒頭で言った,「月は人が見ている時にしか存在しない」ということの意味である。これが,有名なシュレディンガーの「猫のパラドックス」につながる。ノイマンは,「人間の観察によって,猫の生死がどちらかひとつに決まる」とし,その,
「波束の収縮性は数学的には証明できない」
と言い,数学的には導けない,「波束の収縮は,観測装置を準備した人間の意識の中で起こる」と結論づけた。著者も,それを肯って,
「万物を構成するミクロの世界の電子は,私たちの体の外だけではなく,私たちの体の中にもあるから(電子の非局在性),私たち〈人間の心〉はそのような非局在的な〈電子の心〉を通じて〈万物の心〉にも影響を与えるからであり,しかもミクロの世界の電子の行動は,マクロの世界の人間が〈観察するまで〉は,〈確率的〉であるが,人間が〈観測〉すればその〈瞬間〉に〈確定〉する(波動の収縮性)」
と説明する。そして,これは,身近な世界だけのことではなく,敷衍すれば,
「個々の電子が持つ〈量子性〉〈粒子性や波動性や状態の共存性や波束の収縮性〉は,〈空間的〉には宇宙全体へ,〈時間的〉には何十億年もの過去未来へと〈双方向〉に広がっており〈非局在性〉を有している」
ことであり,この原理は宇宙にも広がり,
波動性の宇宙(見えない宇宙)と粒子性の宇宙(見える宇宙)
という二重性,多重性からなっている(多元宇宙)という考えにつながる。著者は,波動性の宇宙(見えない宇宙)を「あの世」と言い,粒子性の宇宙(見える宇宙)を「この世」と言っている。
これを象徴するのが,「シュレディンガーの猫のパラドックス」である。放射性物質と猫を入れて,一定時間後に蓋を開けて中を見る,
「人が蓋を開ける前に猫の生死が決まっているのか(決定論),箱を開けた瞬間に決まるのか(確率論),そのいずれが正しいのかを問う」
ものである。シュレディンガーは,量子論への反対の立場からこの思考実験を提示した。
ここでは,生きているか死んでいるかは,観測されるまでは確率的であり,観測されて初めて確定する,という実証派,人間が観測する前に確定しているとする実在派のことは,ここでは端折って,ヒュー・エベレットの「並行世界説」,多重宇宙論からの解釈を紹介しておく。
「〈生きている猫の宇宙〉と〈死んでいる猫の宇宙〉が〈共存している宇宙〉を考え,その宇宙が観察を繰り返すごとに〈生きている猫の宇宙〉と〈死んでいる猫の宇宙〉に〈分岐〉し,〈生きている猫〉と〈死んでいる猫〉とがそれぞれ〈別の宇宙〉に〈重ね合わせ〉の状態で並存している」
というのである。つまり,人間が観察するまでは,〈生きている猫の宇宙〉と〈死んでいる猫の宇宙〉が共存していたのに,観察によって,分岐した,ということになる。しかも,
「観察によって分岐した複数の並行多重宇宙は,互いに関係が断ち切られ影響し合うことがなくなるので,それらの宇宙を観察する人間もまた分岐して複数存在する。」
つまり,量子の世界が,開く新しい視界である。すでに,アインシュタインの世界像は,崩れかけている。この先はどうなるのか,その意味で,補論の「タイムトラベルは可能か」は,現時点での量子論の最先端を示していて,興味深い。過去へのトラベルは,なかなか難しそうだ。
最後に,
「エネルギーが十分あるときには粒子(物質)と反粒子(反物質)が生成されるが,その粒子(物質)と反粒子(反物質)が消滅すると純粋なエネルギーに還る」
「粒子(物質)は,純粋なエネルギーから生成され,純粋なエネルギーとなって消滅する」
という,この世界がエネルギーの変形ということが,
「万物は気の凝集によってできたものであり,その気は宇宙合そのものを形成している。」
「生とは気の集結であり,死とは気の気の解散」
と,易でいう,「気」そのもののように見え,改めて,『易経』に感嘆した次第である。
ここで紹介された並行宇宙論は,ブライアン・グリーン『隠れていた宇宙』を紹介する折,改めて,マルチバース論(多宇宙あるいは並行宇宙あるいは多元宇宙と言われる宇宙論)を総覧する際,また関わってくる。それは,後日。
参考文献;
岸根卓郎『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」 』(PHP)
高田真治・後藤基巳訳注『易経』(岩波文庫) |
|
取締り |
|
三田村鳶魚『捕物の話 鳶魚江戸ばなし』 を読む。
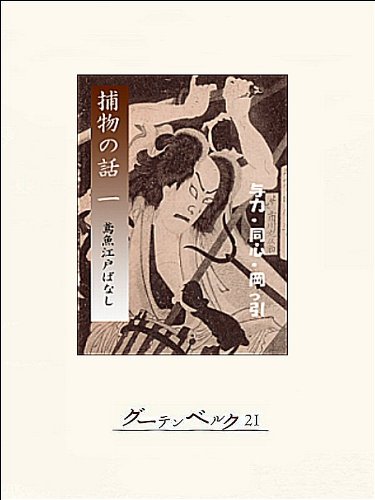
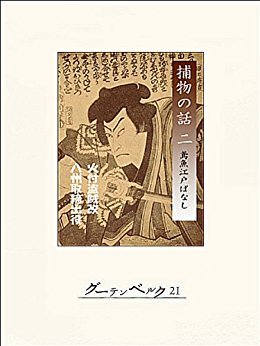
奉行所は,南北二ヶ所(元禄期,短い間中町奉行所)があった。奉行所は,裁判だけでなく,捕物出役に出かけていく。老中の下知で,例えば慶安の変での丸橋忠弥捕縛のような例の他に,取籠り者があるとの訴えによっても出役する場合がある。
その場合,当番与力一人が,同心一人を連れて出役する。継上下(つぎかみしも)で出勤している(のちには,羽織袴に変るが)与力は,着流しに着かえ,帯の上に胴締めをし,両刀をさし,手拭いで後ろ鉢巻をし,白木綿の襷にジンジン端折り(着物の背縫いの裾の少し上をつまんで,帯の後ろの結び目の下に挟み込む)する。槍を中間に持たせ,若党二人に草履取り一人を従えている(本来一騎二騎と数えるが,いつのころからか馬に乗らず槍一本持たせるだけになった)。
「供に出る槍持は,共襟の半纏に結びっきり帯で,草履取は,勝色(かちいろ)無地の法被に,綿を心にした梵天帯を締める。供の法被は勝色で,背中に大きな紋の一つ就いたのを着ている。」
与力は,御目見え以下でも,一応御家人という身分である。ひとりで歩くということはない,ということである。
「同心は羽織袴ででておりますが,麻の裏のついた鎖帷子を着込み,その上へ芝居の四天(歌舞伎の捕手)の着るような半纏を着ます。それから股引,これもずっと引き上げて穿けるようになっています。」
という身なりである。さらに,小手・脛当,長脇差一本(普段は両刀だが,捕物時は刃引きの刀一本),鎖の入った鉢巻きに,白木綿の襷,足拵え,という格好になる。供に,物持ちがつき,紺無地の法被に,めくら縞(紺無地)か,千草(緑がかった淡い青)の股引きを穿く。
刃引きの刀に差し替える,ところが味噌なのだろう。その辺りをリアルにやっていたのは,『八丁堀の七人』というテレビドラマであった。
で,町奉行所の前に呼び出されると,奉行から,与力に「検使に行け」と命じられ,同心には,「十分働け」と言い付ける。さらに,桐の実を三方に載せて,各々水杯をする。与力は,一番手,二番手と捕物にかかる順序を定め,町奉行自身,表門を,八文字に開かせて,出役一同を表玄関まで見送る。
与力と同心の,この身なりの差は,
「与力は…,決して捕物に手を下さない。槍を持たせていくのは,同心の手に余った場合,その槍で敵を弱らせて逮捕の便利をはかるためで,傷つけたり殺したりすることはありません。まったく同心援助のためであります。」
という。
町奉行所は,月番で勤務につく。同心は,三廻りといって,廻り場をきめて巡回させる。三廻りは,
隠密廻り
定廻り
臨時廻り
月番だと,新しい仕事を引き受け,非番は,前の月に受け付けた事件を片づける,ということになる。
まあ,例の仕事人の中村主水の,定町廻りは,月番でも非番でも,毎日出る。江戸市中をおおよそ四筋にわけ,代わりあって巡回する。
「廻り方は竜紋の裏のついた三つ紋付の黒羽織,夏なら紗か絽です。暑い時分には菅の一文字笠,寒天とか風烈とかには頭巾を用いるが,概して冠り物のない方が多い。そうして,御用箱を背負わせた供と,紺看板,梵天帯に,股引,草鞋で,木刀一本さした中間が一人,そのほか手先が二三人ついております。」
こういう一行が巡回しているのである。テレビや映画のように,一人でうろうろするわけではない。
江戸には,自身番と辻番というのがある。辻番は,武家地にある。自身番は,町家に江戸中で三百位ある。自身番は,大道に面したところに,九尺二間の建物で,巡回の度に,同心が声を掛けていく。
自身番は,書役が雇われて通っていて,多いところで三人,夜も人が詰めている。
その意味で,江戸は,木戸番がおり,自身番があり,辻番がある,という防犯の仕組みにはなっていた。発祥はともかく,交番が,日本になじめたのは,この辺りに原因があるのかもしれない。江戸の町々には,木戸があり,木戸番がいて,夜の四ツ(午後10時)に締めてしまう。後は,潜りから出入りさせ,怪しい者が通ると,木戸番が拍子木で次の木戸番に知らせた。
八丁堀の同心には,「背中に胼(ひび)をきらせた」という言葉があったという。まあ,いまの刑事だと,靴を履きつぶすというのに近いか。多く,十二歳から見習いに出て,二十年,三十年の功を積まなければ,廻り方までになれない。
「炎天,寒夜の嫌いなく,雨風に吹きさらされて苦労する。廻り方と言って威張る頃までには,背中に胼(ひび)もきれましたろう。そういう苦労をして,大勢の囚人を取り扱っておりますから,廻り方にぼんくらな奴はいない。自分の仕事にかけては,随分功名を急いだところもありましたが,滅多に捕り違いとか,調べ損ないとかということはありませんでした。」
という。そこが,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416204136.html?1427227894
で述べた火付盗賊改との違いなのかもしれない。
「牢へ入れるというのは軽いことではない。いかに相手が町人どもでも,容易ならぬことでありましたし,また,牢屋の方にしましたところで,いかに定廻りが召し捕ったものであるにしても,入牢証文というものがなければ,伝馬町では受け取りません。入牢証文は,同心が調べて,すぐに同心の手でこしらえる,というような造作のないものではない。……廻り方は,囚人を大番屋に預けおいて,夜分になりましても,すぐに奉行所へ取って返して,一件書類を出して,入牢証文を請求するのであります。…町奉行の御用部屋…手附の同心…へ一件書類を出しますと,それが吟味方へ回る。吟味方のほうでは,その書類を見ました上で,御用部屋から出た入牢証文を当番方へ渡す。それから,その入牢証文が伝馬町…に渡される。」
という次第で,ほぼ一日を要する。大番屋に預けられていた囚人は,町役人に付き添われて,牢に入れるのだが,そのとき,吟味方の与力がひと調べして,入牢と決まれば,嫌疑から刑事被告人に変る,のだという。
吟味を受けると,出来上がった調書に拇印を押す。口書・爪印がすむと,奉行の申し渡しになる。
「御奉行様の御白洲というものは,一つの事件について二度か三度のもので,大概三度目は申渡しになる。それは吟味方の方で十分吟味をととのえて,口書・爪印を済ませまして,御用部屋手付の同心が擬律(ぎりつ)までして,申渡しの文句も整えてある。御奉行様は駄目を押せばいいのです…。」
というわけだ。それにしても,整った官僚組織という印象がある。その中で,前回,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/416204136.html?1427227894
で触れたように,冤罪を発見して,それを覆せるというのは,組織の柔軟性というか,トップの裁量の余地が大きいという気がしてならない。もちろん,そうではないケースも多くあったようではあるが,同じ官僚機構ではあっても,今日裁判制度が硬直しているのが,かえって鮮明に見えてくる。
元来が御先手組という,戦時の先方をつとめるという軍役の名残りで,荒っぽいことで悪名高い火付盗賊改も,制度が整うにつれて,少しやり方が変わる。宝永二年(1705)から五年までこの役にあって,勘定奉行に栄転した平岩若狭守という人は,懇意だった所司代松平紀伊守に,「まず三奉行に相談を遂げる」と語り,死刑と決まった者にも,
「その前日に呼び出して,今度おまえの犯した罪は,どうしても死罪を免れ難いものであるが,今まで申し述べたほかに,まだ何か申し開く筋がありはせぬか,その辺りのことを十分考えて申し立てるようにしろ,百に一つも申し開くことがあれば,また取りはからい方もあるから,と言って聞かせます。」
と。さてさて,結局制度を生かすも殺すも,人だということがよくわかる。
加役(火付盗賊改の)は述べ135人,そのうち三人罰せられているが,多くその処断に瑕疵があった場合だが,冤罪以外に,闕所処分にしたケースで,所有財産を売り払って幕府の御金蔵におさめる決まりだが,中根主税という加役は,遊女まで売り払った。それが科条になり,八丈島へ遠島処分になっている。
いろいろ毀誉褒貶はあっても,この辺りの仕置きをみると,いまの為政者に比べて,遥かに骨がある。
参考文献;
三田村鳶魚『捕物の話 鳶魚江戸ばなし』(Kindle版) |
|
冤罪 |
|
三田村鳶魚『江戸の盗賊 鳶魚江戸ばなし』を読む。
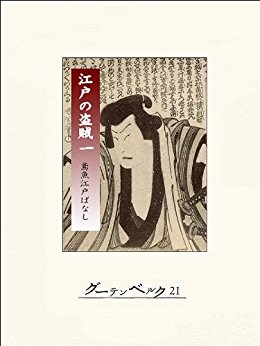 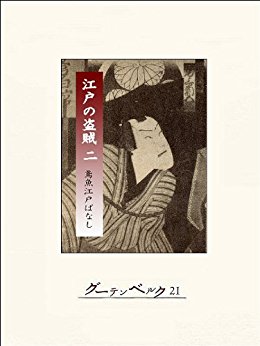
江戸時代初期,江戸が繁華になるに従って,「大草履組」「小草履組」と名のる泥棒が集団で,跋扈したらしい。それが無くなったに当たっては,慶長十三年(1608)にできた,本丸,二ノ丸,三ノ丸,西丸といった内曲輪に加えて,寛永十三年(1636)に,外曲輪ができ(これが総曲輪),それとともに,山下門,幸橋門,虎ノ門,赤坂,四谷,市谷,牛込,小石川,筋違,浅草,に郭(かく)門ができたことが大きいらしい。
「江戸の警備の上には,なかなか大きな事柄だった…。」
と鳶魚は語っている。いまは,「赤坂見附」という名前が残っているが,見附というのは,
「城の外郭に位置し,外敵の侵攻,侵入を発見するために設けられた警備のための城門」
のことで,江戸城には外濠および内濠に沿って36の見附があったとされている。しかし,「江戸の見附は,そんなに多いものではない」らしい。延享期(1744〜47)にできた『江戸惣鹿子』などでも,31しかない,というが,ともかく,これによって,外敵への備えができた。さらに,寛永八年(1631)からは,町奉行所ができ,
「これ以後は,おおきな泥坊になると,江戸回りを舞台にする。江戸の中を舞台にして踊ることはできなくなった。」
ということだ。しかし,なかなかそうはいかないのは,江戸の町が,どんどん人口を吸収して拡大していったからで,元文期(1736〜40)になると,どこまでが江戸で,どこからが田舎であるかがわからなくなった。
で,明暦の大火(いわゆる振袖火事)以後、放火犯に加えて盗賊が江戸に多く現れたため,寛文期(1661〜72)に,初めて火付盗賊改を置く。そして天和三年(1683)に,加役というものができ,御先手組のものが兼務するようになる(で,加役というと火付盗賊改のこととなった)。その最初の者が,中山勘解由である。
「火付盗賊改の方は,町奉行の方の与力・同心と競争の心持があって,手柄を奪い合うことは,後々まであった。後のことですけれども,町奉行所の方の吟味を『檜の木の舞台』といい,加役の方の調べを『オデデコ(御出木偶)芝居』といっている。そこで功をあせるから,早く白状させようともすると,どうしてもこうしても罪にしなければならぬという気持ちもある。うまくゆくこともあるし,また失敗もある。」
と言っているが,当時の人も,かなり酷評しているらしく,
「怪しむべきでもないものを縛っているのも多いようである。調べが厳しいので,言わないうちは死ぬまで責める,というやり方だから,どのみち助からぬというので,目前の苦を逃れるために,罪を認めてしまう者がある,通り者とか,博打打ちとかいう者が,勘解由のために押さえられて,島流しになったものがたくさんいる」
という状態である。そんな逸話の一つが,無宿の伝兵衛が,火付けをしたというので,市中引き回しの上,一日晒し,火あぶりの刑になることが決まっていた。しかしその高札にある犯行時に,「数珠屋にまだ弟子奉公をしていて,火事の当日は,主人方にいた」という噂が広まった。
それを南町奉行所の大岡越前守の手附同心中山五右衛門・小川久兵衛が聞き出し,大岡越前守に上申し,それに基づいて,月番の北町奉行所へ通達したところ,北町奉行の諏訪肥後守は,早速刑の執行を中止し,改めて詮議をし直した,という。
現在の冤罪事件と構造がよく似ている。
きっかけは,火付盗賊改方の目明しが,夜見回りの最中に,土蔵のところで寝ていた胡乱な男をつかまえ,いろいろ脅し,言わなければ拷問してでも言わせる,と脅されて,ちょっと「たわけ者」のところがある伝兵衛は,やってもいない罪を認めたということになる。
現在の裁判よりすごいのは,そうして詮議し直した結果,目明しが死罪,掛りの火付盗賊改方の同心は,役を召し放されて,閉門の処分となった。きっかけを作った二人の同心は恩賞を置けた,という。実は,この後がある。
「(この件に)一番驚いたのは幕閣でありまして,罪もない者を極刑に行うようなことがあっては大変だというので,
老中の松平左近将監は,…命を両町奉行所へ伝えました。それは,無実の罪で極刑に行われようとした顛末を触れに書いて,町の辻々へ貼らせた。その末に,今後重罪の者はもちろん,小さい罪の者であっても,科なき者が科に行われるような場合には,親類身寄りの者から,御仕置以前に遠慮なく再吟味を願い出るように,ということであります。」
DNAで明らかに冤罪とわかっていても,死刑に処せられたものが,名誉回復さえされない現代と比較しても,為政者の姿勢の格差に,愕然とする。どちらが近代的なのであろうか。
結構成物 日光の彫物と大岡越前守
という当時の「物揃」にあり,「頭尽」に,
役人の頭 大岡越前守
と,越前守の評判が高いのも,『大岡政談』という講談が,必ずしも,見てきたような噓でない証である。しかし,それ以降,他の名がないのは,際立た例なのかもしれない。
ただ,「親族身寄」まで広げて再審を願い出られるようになったのは,
「随分思いきった拡げ方だと思います。親類だけでなしに縁類を加えたのが,なかなか目立って見える。それですから,てきめんに再審事件が出てきてもおります。」
という次第で,実際に冤罪が晴らされた例がある。
どうも犯罪というのには,時代を映しているところがあるらしく,享保期(1716〜35)になると,武家も町家も,奉公人に,渡り奉公人が増え,一季半季で,次々と奉公先を変えていく。その間に,
「取り逃げするとか,前の主人のところへ忍び込んで泥坊するということが多かった。」
という。その当時から,「請宿及び戸籍制度」をしっかり立てていないのがいけない,という議論があった,という。身許というのは,人別の確かだったらしい江戸時代ですら,江戸というのが,東京と同じく,大都会でということが分かる。なにより,人で不足なのである。
そんな使用人の犯罪で締めておく。ある商家に縁付いて,お産で亡くなった女性の弔いもすんだ雨の夜,
「あたりも静かになった時分に,亭主のおります座敷の窓から,死んだ女房が覗き込んで,私のもっていた小袖の中に,何々の模様のがある,あれは平生から気に入って秘蔵していたものだが,死んでみると,それを娑婆に置いてゆかなければならぬ,そのことが忘れられないために,冥路の妨げになり,六道の辻にも迷うわけである,どうかあの小袖を渡してもらいたい,と言った。亭主もそれを聞いて,なんだか不憫になってきた。」
幽霊が出たのを不審とは思ったが,小袖を渡した。すると,また少しして,同じように幽霊が出てきて,今度は箪笥の中に真金一両を使い残しておいた,それをくれ,というに及んで,亭主もおかしいと思い,小判を持ってでて,女が窓越しに手を伸ばしたところをつかまえて,押さえつけた,という。よくみると,それは,死んだ女房が嫁に来るとき,里付に来ていた女であった,という。
「都合のいいことには,昔の幽霊は足があったので,幽霊の足が無くなったのは,尾上松緑以来の話です。」
とは,オチである。文化年間,尾上松緑が『東海道四谷怪談』を演じるにあたって,凄味のある演出として,幽霊の足を隠して,人魂といっしょに登場するという手法はないものかと考えた,という。それまでの日本の幽霊には足があったそうである。
参考文献;
三田村鳶魚『江戸の盗賊 鳶魚江戸ばなし』(Kindle版) |
|
おのずからとみずから |
|
竹内整一『「おのずから」と「みずから」』を読む。

語源的には,「おのずから」は,
「オノ(己)+ヅ(の)+カラ(原因,由来)」
で,ひとりでに,という意味になる。「みずから」は,
「身+つ(助詞)」
で,それ自体,つまり,自分から,の意となる。
しかし,日本語では,
みずから
も
おのずから
も,「自ずから」を当てる。そこには,
「『おのずから』成ったことと,「みずから」為したことが別事ではないという理解がどこかで働いている。」
と,著者は述べる。その例として,
「われわれは,しばしば,『今度結婚することになりました』とか『就職することになりました』という言い方をするが,そうした表現には,いかに当人「みずから」の意志や努力で決断・実行したことであっても,それはある『おのずから』の働きでそう“成ったのだ”と受けとめるような受けとめ方があることを示しているだろう。」
もちろん,婉曲的な言い回しで,敢えて「結婚します。」ではなく,「結婚することになりました。」という言い方をしたがる,ということはあるにしても,「そうなるなりゆきで,こうなりました」ということを言外に含んでいる。そう言えば,「さようなら」も,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/402221188.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163568.html
等々で触れたが,「そういうことなので,おわかれします」という言い方は,再見,Good
by(神の身許にあれかし),Auf Wiederserhen(再び会いましょう),Au revoir(またあいましょう)等々にくらべると,「そういうことなので」と,おのずからのニュアンスがある。
似た例で,「出来る」も,
「『出来る』とは,もともとという意味であり,ものごとが実現するのは『みずから』の主体的な努力や作為のみならず,『おのずから』の結果や成果の成立・出現において実現するのだという受けとめ方があったゆえに,『出(い)で来る』という言葉が,『出来る』という可能性の意味を持つようになった」
と,言う。当然それは,諸々の出来事は,
「『おのずから』の働きで成って行くのであって,『みずから』はついに担いきれない」
という,責任が取りきれない,という考え方に通じていく。それを,
「『みずから』は『おのずから』に解消されてしまっている」
と,著者は言う。当然それは,ただ主体の責任を溶かしこむだけではなく,
「『みずから』が『おのずから』の働きに不可避に与りつつもなお,かけがえのない『みずから』を生きているという受けとめ方がそこにある」
というのも事実である。お蔭様という言い方と通底する考え方である。お蔭様については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/415123076.html
で触れた。そこに,「なるべくしてなった」という力を強く感じとっている,ということである。
著者は,本書で,
「『おのずから』と『みずから』とを,ともに『自(か)ら』という一語で語りうるような基本発想において,日本人は,繊細でゆたかな情感を持った独自の思想文化を育ててきたのであるが,しかし同時にそれは,自立的・合理的な思考を欠く不徹底で曖昧な思想文化でもあるという批判をも生みだしている」
として,「おのずから」と「みずから」の「あわい」を,様々な例で,問い直している。それは,
「日本人の自然認識,自己認識のあり方をあらためて相関として問い直すことであり,また,その問いにほぼ重なる問いである,超越と倫理との関わりへの問いをも問うことになるだろう。」
と。たしかに,
自然(おのずから)
「どうせ」の発想(無常感)とおのずから
よしなやと面白や
空即是色
等々と並んで,伊藤仁斎,国木田独歩,柳田國男,夏目漱石,森鴎外,清沢満之,正宗白鳥等々を通して,探っていく試みは,ちょっとっ面白い切り口に違いない。なにせ,無意識に,
「〜することになりました。」
と使っている言葉に,言外に逃げがあることを,意識している人はいないであろう。成り行きで結婚したのだから,成り行きで,「別れることになりました」と,しれっとして言えるのである。それは,「戦争することになりました。」とも「人を殺すことになりました。」とも言い替えていけるのである。
http://ppnetwork.seesaa.net/article/402142102.html
でも触れたが,「仕儀」は,「おのずから」を言外に含んだ,重宝な言葉だ。「戦争する仕儀になりました」は,言外に何か理由がありげに,ただ成り行きでそうなったと言っているだけのことだ。
「おのずから」を,自然のルビに使うことがある。自然は,natureの訳語に当てられる前は,「じねん」とも呼び,
おのずからそうなっているさま
あるがまま,
人の力では予測できないこと
「殊更らしいことを嫌っておのづからなところを尊ぶ」
という言い方,あるいは西田幾太郎の,
「無心とか自然法爾(じねんほうに)とか云ふことが,我々日本人の強い憧憬の境地」
という言い方をしてきた。しかし,それは,親鸞においては,
「こちら側の『みずから』のはからいは,決して阿弥陀の『おのずから』の働きと重なるものとしては受けとめられていない…。」
それを,著者は,こう,読み解く。
「『己を尽す』べく『みずから』の『無限の努力』が要請され,しかもそれ自体が『自己のものではない』『おのずから然らしめるもの』なのだ,という異様な論理がここにはあるだろう。(中略)親鸞において厳密にしかも繰り返し注意されている。つまり,『現実』はどこまでも『絶対』と区別されながら,かつ『相即』するものとして捉えられているのである。『即』とは,そうしたきわめて微妙な『あわい』としての『即』なのである。『おのずから』は,『そとから自己を動かいのではなく内から動かすのでもなく自己を包むもの』なのである。」
自分が信ずることは,おのずからのしわざである。しかし,おのずからのせいにゆだねるわけでもなく,だからこそ,祈るべく尽力する,という感じであろうか。
それは,清沢満之の,
「我等は絶対的に他力の掌中に在る」
という言い方と重なる。そこには,自分の意志で結婚するのだが,大いなる何かに動かされての縁としての結婚だというニュアンスが,ある。もしそこに,自分の努力や意志を前提にしなければ,ただの成り行きにまかせになる。
道元は,「生死即涅槃」「煩悩即菩提」という言い方をしたが,
「道元の説く,その『即』は,決して無媒介な連続性・同一性をいみするそれではない…。座禅という修行を介さないかぎり,その『即』は現成しない。しかしかといってそれは,修行を経て覚証に至ればそうであるという意味の『即』に限定されるものではない。証は修行を経てその結果として到達するものではなく,端的に修行の実践そのものの,瞬間,瞬間においてのみ証せられるものなのである。」
と。この,「即」が「あわい」である。一元論の思い込みでも,二元論でもない。しかし,これは,堕すれば,無責任に陥ることは,必然である。修行,尽力抜きで,
「〜になりました」
という時代に,いま,いよいよシフトが甚だしい。
清沢満之のように,
如来がいるから信ずることができるのか,人間が信ずるから如来がいるのか,
という問いをもつことの重要性は,そこに在るような気がする。
参考文献;
竹内整一『「おのずから」と「みずから」』(春秋社)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房) |
|
術 |
|
甲野善紀・前田英樹『剣の思想』を読む。

前田英樹氏については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/396988408.html
で触れたことがある。甲野善紀氏については,直接ではないが,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163234.html
で触れた。
前田氏が,あとがきで,
「スポーツ式の,つまり西洋式の身の置き方,動き方は,老熟ということを知らない。老熟を知らない世界に名人が生まれるはずはないのだ。」
と述べている。若い者のスポーツと武術との違い,つまりこの本の趣旨を,この一言で言い尽くしている。甲野氏は,それを受けて,
「武術においては,術を身につけた者が老人になっても,術を知らぬ血気の若者などを手もなくあしらったというのは,その身体の運用方法に無理がなく,単なる慣れで体を動かしていた人々とは動きの原理が根本的に違っていたからだと思うのです。」
と述べている。しかし,そんな名人芸も,単なるほら話と受け取られるのが今日の状況です。
「スポーツ選手の頂点は,残酷なほど若い時にやってきます。酷使して,あちこち壊れかかった体を残して現役を退いた時には,かれらは後進の指導とかいうもの以外,スポーツに対して何をしたらいいのかわからない。」
それは,
「スポーツの技術は,体を摩耗させ,ごく短期間で限度に達してしまうことと切り離せない。それは,この技術が,たとえば,職人の手先技などと違って,体全体を激しく使って成り立つものだからでしょうか。決してそうではないと,私は思う。原因は,スポーツの動作体系そのもののなかにこそある。この体系が根ざしている運動の一般法則が,多量に行えば身を損じるという,あきらかな条件のなかに置かれていることに因っているのです。」
と前田氏は言う。そして,
「私が誉めそやしたい技術は,もっと別なところで,おそらくは黙々と生きている奇術です。年齢の積み重なりと強くかかわり,それによってのみ少しずつ可能となってくるような技術なのです。」
という,前田氏は新陰流,甲野氏は,井桁崩しの考案者である武術研究家,ともに,剣術を念頭に置いている。両氏とも,武道という言葉を嫌う。甲野氏は,
「武道という名称が世に広く用いられるようなになったのは明治の始め,武術一般がおちぶれ,蔑視された後に隆盛となった講道館柔道の創始者加納治五郎の『術の小乗を脱して,道の大乗に』という名言がなにより大きな原動力になっていると思います。この一言で,剣術は剣道に,空手道,合気道,杖道,居合道と現在広く行なわれている武道は,皆,『〜道』というようになり,単に武の世界のみならず,茶の湯や生け花も,『茶道』『華道』と」
言うようになった,と言っている。それはそのまま,スポーツへと地続きとなっていく。剣術という呼び方は江戸時代からで,それ以前は,宮本武蔵も,兵法といい,上泉伊勢守も新陰流兵法と名のっている。それについて,
「江戸期を通じて『術』はすでにその中身をなくして広まっていき,遂に柔道式の乱取り稽古を生んでいく…。…剣術,柔術の呼び名が一般化して行った江戸期は,剣術であれ柔術であれ,『術』と呼ばれるに足る中身を根本からなくしていった時代でした。反対に,兵法の呼び名が一般的であった時代には,数々の恐るべき術があり,我が術の成否に日々の命を託して生きるほかない人間が限りなくいた。兵法が生み出されたのは,このような『術』からです。言い換えれば,『法』は,『術』が『術』に克たんとする激しい願いから念じられていた。…日本の戦国期とはこういう時代です。上泉伊勢守の兵法や千利休の茶の湯は,この時代が抱き続けた或る願いの突如とした結実のように起こってきたに違いない。」
と,前田氏は言う。では,その身体使いとはどんなものか。たとえば,
「フィギュアスケートの選手が取る腰のかたちは,新陰流剣術で言う『吊り腰』の形に時としてまったく一致していることがある。腰の背骨のところを垂直に吊り上げられているような姿勢です。この姿勢によって,むしろ体重は上に吊り上がるのではない。体重は,下腹内部のほぼ中央ないしやや前方よりのところから真下に降りるようになる。このような立ち方を一貫して保った歩行が,上泉伊勢守以来の新陰流のものです。こうした歩行では,足が『浮く』と言われる。浮いた足は,地を蹴りません。膝はやや折ったカタチ。進行方向に顔が向いている時は,額と前脚の膝と足指の付け根あたりとは,床に対して垂直のほぼ一線で並んで移動する。」
と言う。これは,まさしく能の「仕舞」の所作である。柳生家は金春流と深いつながりがあり,
「現在の能役者の進退こそ,新陰流の足法を最もよく継承,具現している」
と言う。こうした所作は,その時代の,
歩行文化
の反映であるから,
「能と新陰流剣術とが,発生当時,同一の歩行文化を土壌とし,その土壌から或る共通の純粋な動作体系を,はっきり自覚して引き出すことに成功した」
ということになる。当然,その時代の歩行文化を反映するのだから,今日それが失われているのは,当然のことになる。
「新陰流の移動においては,移動する際に生じる体の軸を何より重んじます。四足獣が歩行する時の移動軸は,言うまでもなく,その脊椎と一致している。軸と脊椎とは,ここでは同義語です。直立歩行する人間では,この二つは直角の方向に分裂している。従って,人間はそのままでは,どうしたって四足獣の運動の一貫性,適切性には敵わないでしょう。靭帯の移動軸は,脊椎の軸から切り離されたために,まことにバラバラな,曖昧なものになっている。」
それをスポーツでは,
「移動軸がバラバラになった靭帯を,そのまま運動の一般法則に従わせ,徹底して酷使する。酷使に耐えられる体力さえ作っておけばそれでよいというわけです。」
対して,新陰流では,
「移動軸は,足法との緊密な連関を通してまったく新しく立て直されなくてはならない」
という考えで,そのために,
「脊椎の曲げによる上体の捻り屈みを禁じる必要がある。(中略)たとえば,刀を縦に真直ぐ振り下ろす場合には,上体を後ろに反らし,横に振る場合には,振る方向の反対側に状態を捻る。あるいは,斬り込む直前にいったん状態をたわめて引く。こういった種類の動きは,すべて日常動作がもたらす基本的な弊害として,消し去らなくてはなりません。どのようにして消し去るのか。
吊り腰による浮き足の足法を身に付けた場合には,ただ真直ぐ正面向きに歩くだけなら,上体はぶれません。反動動作は自然に消える。この時,移動軸は体を左右対称に割った真ん中の線におのずと決まる。」
とする。これを,甲野氏は,「武の技の世界には,『居付く』ということを嫌う伝承が古来から受け継がれて」いるとして,こう述べている。
「この言い伝えに従うならば,床に対して足を踏ん張らないのは勿論のこと,下体に視点を置いて上体を捻ったり頑張ったりしないこと,また腕を動かす時,腕や肩や胸を蹴る形で,つまり固定的支点を肩の関節に作らないようにすることが大事で,そのために,体各部をたえず流れるように使うことが重要なわけです。足や腰を固定して身体をまわすから捻れる…。」
武術では,老人が膂力のまさる若者を手もなくあしらったのは,
「その身体の運用方法に無理がなく,単なる慣れで体を動かした人々とは動きの原理が根本的に違ってきたからだ…」
というものである。今日の「なんば走り」等々が見直されているのは,甲野氏の発見が大きい。このことは,日本の太刀が世界でも珍しい両手保持となったことと深くつながっている。
「片手保持の『太刀打』では,太刀は振られる腕の延長としてあり,それ以上ではありえない。その使い方は,刀剣を単なる道具として手首や肘関節でこねるようにして使う剣技より,はるかによく運動の一般法則を脱することができます。けれども,この時,太刀といったいになって振られる腕は,体全体の動きから見れば,やはりひとつの道具のように機能している。肩先から太刀の切っ先までが一本の武器となって旋回するわけです。
両手保持の刀法ではそうではない。…刀は決して腕で振ってはならない。体全体の軸移動のなかに斬り筋の一貫した体系が成立するのです。」
として,こういう例を挙げる。吊り腰で,移動するのに,斬りの動作を重ねることについて,
「移動軸が身体の中心線にある場合には,斬りはその中心線に沿った真直ぐの太刀路しか使えません。斬りが斜め袈裟に入るのなら,移動軸はその太刀路に合わせ,体の中心線をはずれた別の位置に正確に立てられなければなりません。」
として,少し細部にわたるが,こう分析してみせる。
「大ざっぱに言って三つある。すなわち,体を左右に分ける中心の軸と,左右の肩から両膝を縦に通って地に達する二本の軸とがそうです。八方に開かれた吊り腰の足法は,これら三本の移動軸によって統括され,言わば積分される必要がある。なぜか。その移動が八方に開かれた二つの身体の攻防は,それ自体が無際限に続くほかない性質のものだからです。八方に開かれた移動の関数は,積分されて三つの移動軸に収まる。敵手に対して体が真正面を向いて移動する時には,中央の軸が活きて働いています。右肩,右腰が前方に出た『右偏身(みぎひとえみ)』の移動では右軸が活きて働き,左肩,左腰が前に出た『左偏身』の移動では左軸が活きて働いている。一つの軸が働く時には,他の二つは潜在的状態であり,潜在して一本の軸を支えていると言えます。」
新陰流では,「敵手を斬るとは,自分と敵手との間に」接点を創り出すことであり,「敵手の移動をそれとの接点で瞬時に崩す」ことが,敵を倒すことだ,と言う。それが間合いと拍子ということになる。
最後に,昨今,名人,名人芸が減ってきたのについて,思い当ることがある。前田氏が,上達下達,について触れたところがある。これは,『論語』にある,
君子は上達し,小人は下達す,
から来ている。
「凡人は,とかつつまらぬことに悪達者になる。励めば励むほど,反ってそういう方向に突き進んでしまう。やがて手に負えない厄介者になり,俺はこんなにすごいと言って回りを睥睨する。実は並み以下の者でしかないのに。これが『下達』という意味でしょう。この裏には,『上達』とは何と難しいことか,という孔子の嘆きと,また驚きがあるに違いない。」
まさに,自戒をこめて,今日の毀誉褒貶のハードルの低さとも関わり,汗が出た。
参考文献;
甲野善紀・前田英樹『剣の思想』(青土社) |
|
島原の乱 |
|
五野井隆史『島原の乱とキリシタン』を読む。
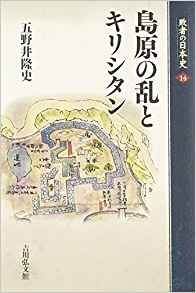
神田千里『島原の乱』(中公新書)
に,かつて強い感銘を受けた。それまでにも,個人的に,マリオ
バルガス=リョサ『世界終末戦争』に触発されて,島原の乱を連想し,
鶴田倉造編『原史料で綴る天草島原の乱』,西村貞『日本初期洋画の研究』,石井進・服部英雄編『原城発掘』,助野健太郎『島原の乱』,鶴田倉造『天草島原の乱とその前後』,戸田敏夫『細川藩資料による天草・島原の乱』,煎本増夫『島原の乱』
等々を読み,さらに,村井早苗『幕藩体制とキリシタン禁制』,姉崎正治『切支丹宗門の迫害と潜伏』,海老沢有道『増補切支丹史の研究』,海老沢有道『キリシタンの弾圧と抵抗』等々も追いかけた上で出会った,神田千里『島原の乱』のもつ,複眼的な記述に強い印象を受けた記憶がある。
だから,期待も大きかったが,少し切り込みが単線に過ぎる気がしてならない。たとえば,
乱側に,松倉家の旧家臣がおり,幕府側に陣借りする形で,松倉旧家臣がいる,
乱側に,無理なりの形でキリシタンになり,加わったものがいる一方で,神仏を信ずるものにとってはキリシタンは悪夢の再来であるとして,藩側で戦ったものもいる,
唯ひとり生き残った絵描き右衛門作が,四郎にかわって指揮を取っていたという目撃談と,軟弱な裏切り者の絵師とていうギャップに,絵師に韜晦する,一筋縄ではいかない複雑な右衛門作像がある,
一旗揚げる最後の機会と幕府軍の各藩に陣借りする牢人もいれば,そのために一揆に加わった牢人もいる,
等々,と言う複雑さ一つとっても,この乱のもつ,構造の複雑さは,変り行く社会構造を背景にして,
(移封した有馬家と共に同行せず)土着した(土着というより,多くは兵農分化していなかった)旧有馬家臣,
(関ヶ原以来この地に土着ないし浪々した)旧小西家家臣,
廃絶された加藤家等々,潰れた各藩のあふれている牢人,
松倉家を致仕した旧家臣,
棄教させられたキリシタンの立ち返り,
キリシタンに無理なりさせられた農民,
戦国の習いに従って,村ごと城に逃げ込んだ一般農民,
一揆勢と藩側の勝敗の帰趨を見ながら,藩から一揆側へ,一揆側から藩側へと右顧左眄して生き残りを図る村々,
等々,という様々な要因が絡み合っていて,確かに農民一揆だが,当初各藩,幕府が,
たかが百姓一揆,
と侮るような戦力ではなかった背景だけからも,この乱のもつ複雑な構造が見えてくる。
乱の見方でも,当初から,
幕府,諸藩から,キリシタン立ち上がりの一揆として位置づけられていた,
のに対して,ガレオン船の船長として長崎に来たポルトガル人コレアは,
「彼らは領主に抵抗して起ち上がって反乱を起こした。キリスト教のために起こしたのではない。ところが殿の役人たちの目的は,彼らの暴虐を隠蔽するためまた日本の領主と皇帝(将軍)の名誉を失わないために,キリスト教のために蜂起した,と発言することにあった。」
と,書いた。彼は,宣教師援助の廉で逮捕され,乱後処刑された。ここには,宣教師側の言い訳があるかもしれないが,といって,もちろん,キリシタン信仰のために,立ち上がったというのは,少し単純化しすぎるであろう。
著者は,
「一度転んだキリシタンたちを糾合して蜂起に駆り立てることになった背景には苛酷な年貢徴収があり,…苛政が一揆発生の要因であったであろう。」
と書く。
勿論,飢饉の続く中,松倉側の重税と未進への過酷な苛政があったということは,多く上層農民層,つまり旧有馬家家臣たちにとっても,それは過酷な状況であった。
そうした絶望的な状況について,神田氏は,かつてこう書いた。
「飢饉という非常事態に際して,今や禁断の果実となったかつての信仰を回復することがこの危機を打開する,困難にして唯一の方法として考えたとしても不思議ではない。こう考えて初めて『キリシタンの葬礼』をしないことによる『「天竺」の怒り』が飢饉を招いたとする,人々の終末観を理解することができるように思われる。『天候不順・凶作・飢饉・領主の苛政や重税』を『棄教したことに対する天罰』と考え,これを『バネとしてキリシタンへの復宗運動が起こった』という鶴田倉造氏の指摘は,大きな説得力を持っていると思われる。」
そう考えると,それを悪夢と考える人もいるのである。キリシタン領主の下,キリシタンが力を持った時代の負の問題,例えば,非キリシタンの迫害,寺の焼き討ち,墓の破壊,人身売買等々が,非キリシタンにとっては,まさかの悪夢の再来なのである。当然,その反発もある。
そうした領民層の複雑な構造への目配りが少し足りないと同時に,反乱側の構想についても,
原城立籠りが当初から計画されていたものではない,
と,捕えられた渡辺小左衛門の口書だけから判断するのは,どうであろうか。著者自身も,
「領民による蜂起は一度キリシタン宗に立ち戻ることによって幕府の検使下向を促し,その際に恨み言を申し述べようとするためであった。」
とする当時の見方を述べているし,乱首謀者たちには,マニラへの移住という策をたて,そのために人を沖縄まで送り出そうとした気配もある,とされるなど,さまざまに構想があったのではないか,という気がする。
確かに,島原藩居城・島原城,唐津藩の富岡城,ともに一揆勢は,あと一歩で攻め落とし切れず,やむを得ず,原城に籠城に至ったけれども,両城攻略の目的は,そこに籠城することであったとすれば,それによって,何かを果たそうとしたのではないか,という推測も成り立つ。
一揆勢と幕府方とは,何回か矢文のやり取りをしているが,そこから読み取れるのは,
①籠城したのは,国家に背いたり,松倉に不満があるのではないこと,
②後生の救いを失わないために,信仰の容認を求めて蜂起したこと,
③現世のことについては将軍や藩主に忠誠を尽くすが,来世のことについては,天使,天草四郎の下知に従う,
という主張が共通してみられる,と神田氏はまとめ,
「『上様』への怨恨か,『地頭』即ち松倉勝家への怨恨かという幕府上使衆の問いに,『誰に対しての恨みでもない。(殺された)キリシタンの数だけ殺す』と原城内から答えた」
ものもいる,と加えている。
こう見ると,単純にキリシタンの乱とも,苛政に反発した一揆とも,一概に言えない複雑な土地柄を反映しているように見える。飢饉は,この土地だけではないし,重税も,飢饉なればこそ,どこでもありえた。それが,この地だけに,有馬の過半の農地が無人の野となるほどの一揆が起きたのか,そのための,
俯瞰の視点
と
虫瞰の視点
の両方がいるし,内と外,東アジア全体を見渡す視点もいる。その意味では,僕には物足りない思いが残った。
僕は,記憶で書くが,幕府がオランダを頼んで,海上から砲撃したように,一揆側にも,スペインを頼んで,キリシタンの移住を画策していたという話を読んだことがある。その両方があって初めて,島原の乱の規模の大きさがわかる気がするのだ。
参考文献;
五野井隆史『島原の乱とキリシタン』(吉川弘文館)
神田千里『島原の乱』(中公新書) |
|
変える |
|
小熊栄二『社会を変えるには』を読む。

新書500ページを超える,新書としては,大作である。しかし,読むのに難渋するところはなく,改めて,世界の,その中の日本の,そしてその中のわれわれのポジションを,ちょうどグーグルの地図を,地球規模から,拡大して,ピンポイントで,いま,ここの自分に辿り着くような,そんな社会運動の地図の役割を果たしている。
ノウハウについも若干触れてはある。著者自身が,いくつかの運動に関わり,デモにも参加した体験からの方法論だが,むしろそこではなく,改めて,「社会を変えるとはどういうことか」を,民主主義の原点,社会,政治思想の歴史を辿り直しながら,現時点を再確認して見せているところにこそ,見るべきものがある。あくまで,著者の「現状認識」の拠ってきたる背景と見ていい。
だから,著者は,あとがきで,こう書く。
「そこで読者にお願いしたいのは,この本を『教科書』にしないでほしい,ということです。私は権威になって,説経する気はありません。自分の書いたことが正しくてほかはまちがっているとか,西洋の思想は立派で日本はだめだ,などということを主張する気はありませんし,その逆もありません。『説教』の材料を『最新のもの』に変えているだけでは,『説教と実感』の対立という構造を変えることはできません。
ましてや,あなたの説教はすばらしい,どうぞ正しい答えを教えてください,私たちは何も考えずにあなたに従います,等々という姿勢をとられたら,この本で書いたことが何もつたわらなかったことになります。」
新しい正解を待っているだけでは何も始まらない。
「そのために,自国の歴史や他国の思想から,違った発想のしかたを知り,それによって従来の自分たちの発想の狭さを知る。その後,従来の発想をどう変えるか,どう維持するかは,あらためて考える。そのたるめに,歴史や他国のこと,社会科学の視点などが,必要になるのです。本書で私は,そういう視点を提供することを考えました」
と。しかし,それでは,今までの,著者の言う,
「政府だ,市場だ,NPOだ,と『正解』の材料をつぎつぎとかえたり」したのとどう違うのか,そうではないのではないか。もうそういう流れは,大なり小なりわかっている,いま必要なのは,著者自身が,今どうすべきかを,主張する思想なのではないのか。この本が実践論のノウハウを語る本ならいざ知らず,ここまででは,あくまで序論にすぎないのではないか。
思想の,社会運動の布置は見えた,
として,本論は,その現状認識の先を,自分の言葉と思想で,どう考えるか,にあるのではないか。その意味で,
思想史はあるが思想がない,
という気がしてならない。哲学概論はあるがおのれの哲学がない,という従来とどこが違うのだろう。
著者は,ここまで材料を提供したのだから,後は自分で考えろ,実践しろ,と言う。一体いままでとどこが違うのか,ただ,俯瞰し,整理して見せただけではないのか,それもほとんど西欧の思想を。たとえば,
「本書で紹介した視点,たとえば,『ポスト工業化』や『再帰性の増大』にしても,社会を見るための視点のひとつです。」
というが,それ自体が,著者の言う,
「政府や帝国大学卒業生が,西洋の文物をよくわからないまま輸入して近代化を進めた」
過去とどこが違うのか。「よく理解している」分違うというのか。それなら,自分の言葉で語るべきだ。(ヴィトゲンシュタインの言うように,)
持っている言葉によって見える世界が違う,
のであれば,輸入の言葉では,輸入の風景しか見えない。最低限,それを咀嚼して,自分の言葉にしなければ,自分の現実から生まれた言葉ではないのではないのか。
僕は,別に正解を求めて,あるいは,実践の後ろ盾を得たくて,本を読むのではない,自分の言葉で,自分の思想を語り,それを実践する思想に出会いたいのである。そこで初めて,対話がある。
上から目線ではないと言いつつ,自分の思想は語っていないのである。現状認識などは,百人いれば,百語るだろう。そうではない,自分の現状認識に基づいて,社会を変える思想を提供しなくては,結局,今までの横書きを縦書きに買えただけの著作とどう違うのか。
たとえば,著者は言う。
「運動とは,広い意味での,人間の表現行為です。仕事も,政治も,芸術も,言論も,言論も,研究も,家事も,恋愛も,人間の表現行為であり,社会を作る行為です。…。
『デモをやって何が変るのか』という問いに,「デモができる社会が作れる」と答えた人がいましたが,それはある意味で至言です。『対話して何が変るのか』といえば,対話ができる社会,対話ができる関係が作れます。『参加して何が変るのか』といえば,参加できる社会,参加できる自分が生まれます。」
と。正論だと思う。しかし,「デモをテロ」といい,対話をした後も,「見解の相異」と嘯く為政者の政権下では,まったくそれは牧歌的な手法にしか見えない。
すでに,日本の現状,民主主義国家の体を装いつつ,実は,政府も議会も,政治家も,国をコントロールできていないということについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/411281361.html
で触れた。それを背景に考えるとき,著者の実践論も,少し甘さを感じる。空(航空)も,米軍基地も,原子力発電も,さらに電波すらも,日米合同委員会マターだと言われる。これは,独立国の形態なのか,そういう現状認識から見ると,結局教養人のいう,正攻法でしかない。しかし,でも,ここにしか突破口がない,としいうなら,それなりの現実認識に基づく思想を立てないと,いつまでも,他国の思想を紹介して,現状認識をするだけでは,突破口はない。
ただ,個人的には,関係の物象化を,
人間と人間の関係が,物と物の関係として表れてくる,
を復習し,吉本隆明の,
関係の絶対性
の意味を別の角度で考えるきっかけにはなった。それについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/397281789.html
で触れたが,著者はこう書く,
「これを応用すると,『人間の能力』も,関係が物象化したものです。たとえば,家族がそろってニュース番組や芸術番組を見ながら夕食をとり,時事問題や芸術について会話があるような家庭で育った子どもは,お笑い番組をみながら夕食をとる過程で育った子どもより,自然と『能力』が高くなります。意識的な教育投資をしたかということではなく,長いあいだの過程の人間関係という目に見えないものが蓄積されて,『能力』となってこの世に現れる…。」
因みに著者は,これを,(ピエール・ブルデューの)「文化資本」という概念で見ている(著者自身による,この光景の帰納としてこの言葉があるのではなく,この(ピエール・ブルデューの)言葉の演繹としてこの風景がある)。この言葉で世の中を見ている。すでにこれ自体が,(著者自身の)関係の絶対性を顕現していることに,著者は無自覚である。
話を元へ戻す。さらに,こう言っている。
「市場経済の中ではみんな平等の人間だと言われますが,実際にこの世に現れるのは,『資本家』と『労働者』という,生産関係の両端でしかありません。『文化資本』のもとになる親の資産や学歴だって,もとはといえば,生産関係のなかで得られたものです。」
「こういう考え方によれば,『個人』とか『自由意志』というものは成りたちません。『個人』といっても,関係が物象化しているものだ。」
ということになる。対立は,個人対個人のそれではないのだ,ということになる。この物象化を,絶対性と見た,ということが,ようやく腑に落ちた,という個人的な感想だが。
参考文献;
小熊栄二『社会を変えるには』(講談社現代新書) |
|
連歌師 |
|
綿抜豊昭『戦国武将と連歌師』を読む。
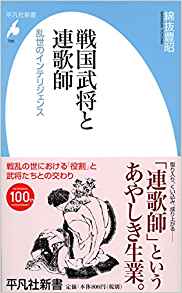
連歌というと,例の,
ときは今天が下しる五月かな
という明智光秀の,本能寺直前の「愛宕百韻」の発句が思い浮かぶ。戦勝祈願の連歌会は,よく催されたようだが,ことが本能寺の変とつながるだけに,それと絡めた解釈がなされてきた。
それにしても連歌は,今日すっかり忘れられた存在である。しかし,南北時代以降,戦国期は,武士,貴族挙げて,文化の華であった。
著者は,
「『連歌』が知られなくなる契機になったのは,明治維新による社会状況の変化がまず第一に挙げられる。それまでは将軍家や仙台藩伊達家では,年頭に連歌会が催されてきたが,幕藩体制ではなくなった明治時代になると,それらは行われなくなった。
また,『連歌』に代わって,『俳諧の連歌』がよく詠まれるようになり,それが『俳諧』と称され,さらにその一部にしかすぎなかった最初の部分『発句』が独立して,一つの作品として盛んに詠まれ,『俳諧の句』となり,それをちじめて『俳句』と称するようになると,『連歌』はわすれられていく。」
と述べている。俳句の芭蕉は,
「世にふるもさらに宗祇の時雨かな」
と詠んだが,それは連歌師。宗祇の,
「世にふるもさらに時雨のやどりかな」
を受けている。江戸時代には,芭蕉の句で,宗祇の句が背景にあることが分かるほどに,まだ連歌は親しまれ,知識となっていたということがわかる。あるいは,俳書『おくれ草紙』に,
花近し髭に伽羅たく初連歌
と載っているが,これだけで連歌師宗祇のことだとイメージできるほどに,身近であった。芭蕉は,『笈の小文』で,
「西行の和歌における,宗祇の連歌における,雪舟の絵における,利休が茶における,其貫道する物一なり。」
と書くほど,連歌(師)の位置は高かった。著者は,和歌・連歌を詠むという表の文学的活動以外に,裏稼業として,情報伝達がある,と言っている。
「関ヶ原の合戦のおり,石田三成から徳川家康弾劾状が諸大名に送られた。常陸の大名佐竹義宣にそれを届けたのが連歌師・猪苗代兼如とされる。」
と,あるいは,駿河の今川氏親に抱えられていた宗長は,甲斐の武田信虎の包囲に合った今川二千の兵を救出するため,和議の使者として,みごとその任を果たしたと言われる。連歌師・宗長にみる,戦国武将に抱えられた連歌師の役割を,お抱え連歌師以外に,
文化人の接待
今川家の記録者
京都との連絡役,交渉役,
他の大名との連絡役,交渉役
を果たしていたとされる。連歌が,武士にとっても公家にとっても教養として高い位置を占めていたことが背景にある。
宗砌という連歌師の書いた『宗砌袖内』には,
「歌一首を分けて,連歌の上下に成す」
とあるように,連歌は,和歌の五・七・五・七・七を,二つに分けて,上句(五・七・五)と下句(七・七)から成る。この連歌を多くの武士が嗜んだ。足利義輝は,
歌連歌ぬるきものぞといふ人の あづさ弓矢をとりたるものなし
とまで言い,「本当の武士というものは,和歌や連歌を詠むことができる者をいう」と言い切っている。昨今の無教養,野卑で,下品なトップに聞かせてやりたいものだ。サムライ心とは,「暴虎馮河」の輩ではないのだ。著者は,
「連歌は,変化に富んださまざまな人生の局面における心情を詠むとともに,自然界の四季折々の変化も詠む。そうしたことが書かれたものを単に『読む』のではなく,そうしたことを自らが『詠む』のが連歌である。……連歌で自然現象や人間の本質などについて表現するという行為を重ねて,『〈自然〉と〈人間〉の理解力を高める』ことができる。戦術ならともかく,戦略を立てる立場の者にとって,それは生き残るために必要な能力であろう。」
と。連歌は,上句と下句を詠みあわせていくため,コミュニケーション・ツールになり得る。たとえば,初の準勅撰連歌集『菟玖波集』に,
我ひとり今日のいくさに名取川 前右近大将源頼朝
君もろともにかちわたりせん 平(梶原)景時
というやり取りが載っている。著者は,
「自分がひとりで今日の合戦で名をあげる,という頼朝の気負いに対して,景時…は家来として,一緒に名をあげる,という忠節心を詠んだところか。頼朝の句は『名取川』に『名をあげる』を掛け,それに付けた景時の句は『徒歩』と『勝ち』を掛けたところが技巧,さらに『我ひとり』に『君もろとも』,『いくさ』に『かち』を付けて応じたところが機知に富み,即興にもかかわらずうまい。」
と述べている。このコミュニケーションである。
さらに,連歌は場を共有する。共に過ごす時間が長い。つまり,連歌は,
「和歌に比して,話をする機会,時間を多くとることができる」
というメリットがある。連歌には,
そもそも連歌とは,上句(五・七・五)と下句(七・七)で詠むだけでなく,さらに,五・七・五と七・七をつけて,長く連ねて続けていく「長連歌」というのがある。戦乱の時代,「百韻連歌」という百句つづけるものが多く行なわれたという。そうなると,「大体,十人くらい」が,一座をなす。その意味で,集団の「結束を図る」のにも利用された。千句連歌というのもあり,そうなると,百とまではいかないまでも,かなりの人数になる。そこを仕切るのに,専門の連歌師が必要になる。
五百年ほど前に成立した和歌の本に『七十一番職人歌合』というのがある。そこの百四十二の職人が,「連歌師」である。連歌師は,ある意味ディレクターでもある。百韻で,十人くらい,順番に句を続けていくが,どうしても,その場を仕切る人が必要になる。
ただ順番に読めばいいのではない。たとえば,
「共同作業ですることであり,たとえば,自分の句を押しつけたりする者がいたり,本来なら初心者が詠むことを控えて,重きをなす人に譲ったほうがよい『月』や『花』を詠んだ句を出したりするので,誰かがしきったほうが,全体のまとまりがよくなる。」
だけではなく,「百韻連歌」は,百韻全体で,一つのまとまった作品となる。その意味では,
「全体を意識していないと,一つの作品として完成度の高いものにならない。各句を見るとともに全体を見通す人が必要とされたのである。」
連歌会での連歌師の仕事で大切なことは,
「連歌が作品として完成し,会の運営がうまくいくよう,全体の流れを整えていくことである。具体的には,全体を意識して,ここではこういう句が欲しいといったアドバイスや,ここでこういう句をいれるとうまく流れていかないからこうしたほうがいいとか,こういう視座で付けるとよいとかいうアドバイスとともに,必要に応じて流れの要所で句を自らが詠むなどし,進めていくのが仕事」
なのだという。そういう連歌と連歌会という者を,戦国武将は,競って嗜んだ。その理由を,著者は,
連歌そのものの享楽
連歌会での家臣や同輩との連帯感の形成
連歌師から中央や他国の情報収集
連歌師を通じた情報の伝達
戦勝祈願といった祈祷
古典教養の学習
等々を挙げた。
「連歌は他人の詠む句に深く関わるという点で,『つながり感』の度合いが異なる。公家以外の連歌会では,現存する絵画資料を見る限り,同じ連衆であるお隣さんとの距離がかなり近い。」
という実際的なメリットが確かにあったのだろう。
「連歌には省略表現や『表の意』だけでなく,『裏の意』を持つ表現などが多い。それでも不都合を生じさせないためには,価値判断の共有が必要である。連歌会は,価値観を共有しているかをお互いが検査する場であると同時に,同じ価値観を共有する集団に属することを認識・確認しあう場でもあった。」
それは,ある意味,「教養を戦わせる場」でもある。戦国期,武士はおのれの教養を高めることにも競い合っていた。それが,トップになっていくための条件であった。茶の湯も,能もまたそうである。
今日,とりわけ戦後のトップ層は,欧米に比べて,知性と教養に見劣りがする,と言われて久しい。ダボス会議でもそうだが,一対一になったとき,すぐに,その無教養さは露呈する。ただ売り上げを誇っただけでは,一員にはなれない。政治家も企業人も,サムライというものの,「文」にもっと着目すべきだ。そんなことをつくづく感じた。トップの恥は,個人ではなく,そういう人物を選んでいる国民の民度を反映している。
参考文献;
綿抜豊昭『戦国武将と連歌師』(平凡社新書) |
|
名字 |
|
武光誠『名字と日本人』を読む。
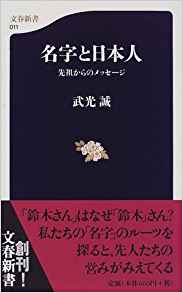
もうずいぶん昔のことだが,いっとき,自分の過去を探ろうとしたことがある。しかし,菩提寺の過去帳も,区役所の戸籍も空襲で焼け,曾祖父より先へはたどれなかった。本書では,「先祖さがしと名字」の章を設けているが,この二つのない場合,手掛かりが薄く,探るのは難しいようだ。尾張藩士だから,藩関係からたどれば,本家もあるし,そこから別れた二分家の一つでもあるから,探りようはあったが,別に由緒正しき家系でもない。その事実を知っただけで,やめた。過去に,おのれの出自に意味があるのではなく,出自は,おのれ一代でつくるべきもの,ということだなのだろうと,受け止めたからだ。
しかし,名字ということへの関心だけは残った。だからか,この本が,「姓(かばね)」の記事の中で紹介されていて,取り寄せた。肝心の元の記事を読んだ本が何だったかがわからなくなっているのだが。
天皇家が姓がないことについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/407928557.html
で触れたが,
日本では,二十九万余の名字があるらしい。ただその中には,斎藤と斉藤,島田と嶋田と嶌田,中田と仲田のような,「同じ概念から起こったとみられる名字」があるので,それらを一つと見なすと,9〜10万通りになる。
名字は,武家身分の者だけが名字を公称することが許されていたので,江戸時代明治の戸籍制度ができたときに,適当に付けたものだろう,という先入観が強いが,著者は,
「江戸時代の農民や町人の多くが,名字を私称したり屋号をや通称を代々つたえていた。」
という。
「長野県坂北村の碩水寺の,天明三年(1783)と文化一三年(1816)の二度の本堂債権のさいの寄進帳…。二度の寄進帳に出てくる,何百と言う寄進者のひとりひとりが,すべて名字をなのっていた。」
あるいは,
「文化一三年(1830)に,富士山の御師で大蔵景政という者が作成した富士講…の名簿がある。それは,信濃国南安曇郡の南半分三三か村…の二三四五人中で,名字のないものはわずか一六人である。」
公的な五人組帳には名字を書かないで,同じ村の寄進帳には名字を書くと言う使い分けをしている例もあるようである。つまり,
「江戸時代の農村では名字を私称することがふつうで,名字をもたない農民が例外的なものであった…。とくに中部地方以東では『水呑百姓』とよばれた小作人まで名字を名乗っていたことを示す文献が多く残っている。」
という。地域的に領主や上層農民が名字を許さなかった例を除くと,ほぼ名字を私称していた,というのである。この「私称」と言うところが,名字の特徴なのである。
名前の言い方に,氏名,姓名,名字,苗字等々があるが,姓,氏,名字(苗字),それぞれが全く由来と歴史が違うのである。
まずは,名字と苗字。文部省が,「名字」。学校教育上は,「名字」が正解。法務省は,「氏」を正式名称としているので,「氏名」が使われる。
「氏」は,「藤原氏」「大伴氏」等々のように,もとは古代の支配層を構成した豪族を指した。「氏」の構成員は,朝廷の定めた氏上(うじのかみ)に統率されていた。地方の中小豪族や庶民は「氏」の組織をもたない。
「姓」は,天皇の支配を受けるすべてのものが名乗る呼称とされた。古代の豪族層と一部上流農民は,「臣(おみ)」「連(むらじ)」「造(みやつこ)」「直(あたい)」「公(きみ)」「首(おびと)」「史(ふひと)」「村主(すくり)」「勝(すくり)」などの「かばね」を与えられ,庶民の多くは,「山部」「馬飼」などの「かばね」を含まない姓で呼ばれた。
天武天皇が684年(天武13)に,八色の姓(やくさのかばね)が制定され,「真人(まひと),朝臣(あそみ・あそん),宿禰(すくね),忌寸(いみき),道師(みちのし),臣(おみ),連(むらじ),稲置(いなぎ)」の八つの姓が定められ,さらに,一般の公民は,670年(天智天皇9年)の庚午年籍,690年(持統天皇4年)の庚寅年籍によって,すべて戸籍に登載されることとなり,そこでも漏れたものは,757年(天平宝字元年),無姓のままの者,新しい帰化人等々にも氏姓が与えられるようになった。
つまり,姓は,朝廷に与えられるものであった。それに対して,名字は,平安時代末に武士の間で生まれた通称である。
「たとえば,北条時政の名字が『北条』であり,彼の姓は「平朝臣」である。」
ただ,氏姓制度は平安中期に崩れたので,「かばね」はすたれて省略され,「平」が姓となる。
「平素は『北条時政』と名のっているが,朝廷の公式行事の場では『平良孫時政』と称した。」これは,江戸時代末まで朝廷支配に関する場面では,「姓」が用いられ,「徳川家康に位階や官職を与える文書には『源朝臣家康』と書かれる。」ことになる。因みに,
毛利輝元は,「大江朝臣輝元」
前田利家は,「菅原朝臣利家」
となる。その意味で,羽柴秀吉が「源でもなく平でもなく『豊臣』の姓」を賜った意味が,よりよく見えてくる。
さて,通称である名字が広まると,ということは,
各地の在地の武士たちの力が強まると,
と言い換えてもいいが,「菅原」「藤原」は,姓をもとにしたものになのに,「名字」と受け取るようになっていく。
「名字」の名は,領地をあらわしている。しかしやがて,中世になると,「出自をあらわす名」を意味する「苗字」と書かれるようになる。江戸幕府は「苗字」を正式表記とした。「苗字帯刀」の苗字である。
本来,姓と苗字は,別のもので,姓は朝廷から与えられるもの,苗字は私称するもの,である。朝廷から与えられる必要がない,「勝手に自称した通称」であり,そういう自立というか,矜持を背景にしているように思える。事実,鎌倉武家が,私称を事実上公称を上回るものにしていく。
名字の十大姓と呼ばれているのが,鈴木,佐藤,田中,山本,渡辺,高橋,小林,中村,伊藤,斎藤,であるが,人口の10%は,この名字と言われ,上位100位の苗字を持つものが,人口の22%と言われているそうだ。
因みに,佐久間ランキング(佐久間英『日本人の姓』〈六芸出版〉による)は,
http://www11.ocn.ne.jp/‾dekoboko/hobby/myouji/sakuma/index.html
に出ている(自分の名字は,183位。70万人いるらしい)。その中で一位なのは,鈴木姓で,人口の1.3%,この背景には,
「熊野信仰を持つ全国の有力農民の間でこの名字が好まれたことを抜きには説明できない」
と,著者は次のように,説明する。
「熊野大社の神官は,古代豪族物部氏の同族の穂積氏であったが,かれらは中世に『穂積』が主に『すすき』とよばれるようになると『鈴木』を苗字にした。そして,中世に熊野大社は各地に山伏を送って意欲的に布教した。熊野大社を祀るようになった武士は,自分の名字を鈴木に改め支配下の農民に自分と同じ苗字を与えた。ゆえに,『鈴木』の苗字は熊野大社の末社の分布が濃い東海地方や関東地方に多い。」
では,次に多い佐藤姓については,
「藤原秀郷の子孫にあたる藤原系の武士が名のった名字である。秀郷の五代目の子孫にあたる藤原公清,公脩の兄弟が,祖先の秀郷が下野国佐野庄…の領主であったことにちなんで『佐野』の『佐』と『藤原』の『藤』とをあわせた『佐藤』を名字にした。」
と言う。では三位の「田中」は,と言うと,
「人びとが新たに土地をひらいて集落をつくったときに,そこの有力者が村落の中心部分に住んで『田中』と名のった。そして,その名字がしだいにそこの中流以上の農民のあいだにおよんでいったのだろう。ゆえに,『田中』の苗字は,『鈴木』や『佐藤』の苗字の広まらなかった近畿地方から北九州にかけての地域に比較的多い。」
と言う。それは,中村性,山本性,小林姓も,田中に似た性格をもつ,と言う。
「『山』や『林』は,村落をまもる神社が作られた神聖な場所をあらわす。集落の指導者で,代々神社のそばに住んでまつりを行なっていた家が,『山本』や『小林』の名字を名のった。」
日本の名字で「貴少姓」は,一,二万位とされる。名字は,多く,地名と深いつながりを持っている。「貴少姓」も,地名に基づくことが多い。著者は,
「苗字は地名からつくられる。」
と言う。地名発祥は,全体の70%と言う。古代豪族の姓は地名や職名に由来するが,その70%は住んでいた地名に由来する,という。
考えれば,私称したのは,在地の有力農民,そこから力をもった武士である。地名には,意味があるのである。
ひとつひとつの名前には,おそらくいろいろな由来がある。著者は,先祖さがしは,日本史につながり,日本の特徴が見えてくるという。確かに,わずかいくつかの例をあげただけで,遠く開けていく視界がある。
なかなか名字の来歴は,奥が深い。
参考文献;
武光誠『名字と日本人』(文春新書) |
|
慶次 |
|
今福匡『前田慶次と歩く戦国の旅』を読む。
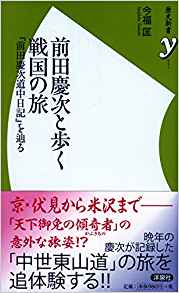
正直,歴史好きに世評高いという,「前田慶次」については,ほとんど知らない。したがって,慶次に関わる本を読んだのは,これが最初である。
前書きに言う。
「本書は,後世,傾奇者として有名になった前田慶次が著したとされる『前田慶次道中日記』の行程を辿りながら,慶長六年という無視されがちな年の列島の光景をすくいあげていこうとするものである。」
若い頃ならいざ知らず,六十九歳の慶次には,傾奇者の欠片も見えない。
傾奇者として有名な,佐々木道誉もそうだが,個人的な趣味であって,本人自身がどんな生きざまであるかとは,関わりがない,と思っている。多くは,後世の人間が,おのれを仮託した思いを背負わされているだけではないのか。
むしろ,慶次は,本来,前田家を継ぐべき人間であったという経歴の方に惹かれる。
慶次,すなわち前田宗兵衛は,
前田家の当主,つまり利家(又左衛門)の長兄利久(蔵人)は実子がなく,滝川一益の甥(と言われている)の慶次を養子に迎え,同じく利家の兄五郎兵衛の娘を利久の養女として娶せられた。
当然,前田家の当主となるべく迎えられたのである。しかし,織田信長が,荒子城主前田利久に対して,弟利家に家督を譲るように命じた。その理由は,
内子縁により,異姓を以て宗を継がしめる故
という。つまり,慶次を養子に迎えていることを指している。まあ,はっきり言って,犬千代時代から信長につかえ,赤母衣衆でもあり,信長と肉体関係もあった利家への贔屓と言っていい。
この理不尽さが,彼を傾奇者にしたと言っていい。世をすねなくてはやっていけないのである。前田家家臣として,関東御陣(小田原攻め)まではあった,とされる。
前田家出奔に当たっては,利家が,世を憚らざる行状を叱りつけたのに対して,
「万戸候の封といふ共,心に叶はずば浪人に同じ。只心に叶ふをもって万戸候といふべし。去るも止まるも所を得るを楽と思ふなり。」
と嘯いたと言う。五千石位を知行していたはずの慶次にとって,「心に叶わない主人にいやいや仕えていても,幾ら知行が多くても浪人と同じ」と出奔したという。普通は,後藤又兵衛が,黒田家を出奔して,「奉公構」と,諸家に触れられて,ついに大坂城に入場するしかなかったように,他家に仕えることは叶わなかったはずである。しかし,秀吉の口利きなのか,上杉の客将として迎えられることになった。
この背景にあるのは,豊臣秀吉が前田利家の甥の名を聞きつけ,召出すように命じた。その折,「大層変わった姿形で伺候するように」という注文がついた。
「前田慶次は髪を頭の片方に寄せて結い,虎の皮の肩衣,異様な袴を着して登場した。衆目が集まる中,慶次は秀吉の面前で拝礼する際,わざと頭を横に向けて畳につけたため,頭は下げても顔はそっぽを向いている格好になった。その時に髷の部分がまっすぐ上を向くように,横に結っていたのである。秀吉はすっかり面白がって,
『さてもさても変りたる男かな。もっと趣向があるであろう。そのほうに馬一頭をとらせる。直々に受けるがよい』と声を掛けた。秀吉の面前で褒美を受けるには,それなりの礼儀が必要である。慶次は,…いったん退出した。間もなく慶次は普通の衣服に改め,神も結い直し,礼法にかなった装束・所作で再登馬した。」
というエピソードで,秀吉から,
「今後はどこなりとても,思うがままに傾いてみせるがよい。」
と,「天下御免」を許されたというのである。しかも,武功は数え切れず,
「学問歌道乱舞にも才能を発揮し,とりわけ『源氏物語』の講釈,『伊勢物語』の秘伝を受けており,まさに文武の士」
であるという。
本日記は,その慶次の,上杉の減封・移封された米沢までの二十六日間の旅なのである。しかも,前年の慶長五年に,関ヶ原の合戦があった翌年のことである。その意味では,まだ徳川時代の街道整備がなされる以前の,変わりゆく街道の様子を伝えているが,慶次らしさは,ほとんど見受けられない。傾奇者どころか,ところどころさしはさむ歌にも,僕にはほとんど見るべきものがなかった。
みどころは,時代の転換期,織豊から徳川治世へと整っていく前の,中世の名残りをとどめたところくらい,と言うと言いすぎであろうか。
関ヶ原合戦直後というのに,そういうことについての言及はほぼなく,徳川については「と」の字も触れていない。一か所,浅香山で,塚を見つけて,「いかなる塚ぞ」と,村人に問う。
「石田治部少とかいう人が,今年の秋のはじめ頃京より送られてきた」
と答える。関ヶ原合戦の翌年である。早くも,
「京よ共り送られてきたという『石田治部少』を村の境へ送り出す」
いわゆる「虫送り」「神送り」の変形である。
「とかいう『石田治部少』を送る一行の中心は,六体(治部少,治部少の母,治部少の妻等々)の人形,青草・柳の葉で編んだ『ふねと』であり,五色の幣を立てている。五色の幣も五行思想にちなんだものである。
先頭には松明百丁をともし,鉄炮二百丁,弓百丁,竹鑓,旗指物にいたるまで取り揃え,赤い地に蘇芳で染め,紙でこしらえた袋の上書きに,「治部少」と書き付けてあった。武具を用意できない者たちは,紙や木の柴を用いて武具らしく作り,大きな杖,刀などをさして行列に加わり,馬乗りは馬乗り,徒歩だちは徒歩だちとわけて進んでいる。
人形を載せた輿の周囲には,称名念仏を唱え,かね,太鼓をたたき,笛を吹く一団がある…。」
在所では巫女が祈祷し,憑依して,
「今年慶長六年,田畠の荒れたるは,わが技にはあらずや」
と叫ぶ,という。慶次は,書く。
「死んだ後までも,人々を畏怖させる,石田三成という人物も,ただの人物ではなかった」
と。
しかし,この本を読んで思い出したが,小田原攻めで,周囲から目立つ美麗な鎧兜と旗印で,先駆けをし,討死した武者がいた,と記憶している。名前を探したが見つからなかった。傾奇者というなら,こう言うタイプの武者こそそうなのではないか。老いた前田慶次には,そういう気概も意気も,この日記からは感じとれなかった。
参考文献;
今福匡『前田慶次と歩く戦国の旅』(歴史新書y) |
|
征夷大将軍 |
|
二木謙一監修『征夷大将軍の真実』を読む。
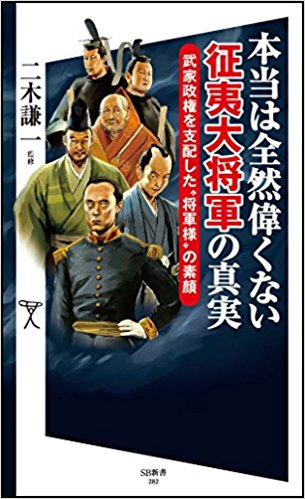
源頼朝の鎌倉幕府の九代から,足利幕府の十五代を経て,徳川幕府の第十五代徳川慶喜までの,全将軍を描く。
征夷大将軍は,東国蝦夷制服を目的に,延暦十三年(794)桓武天皇が平安遷都と同時に,大伴弟麻呂(おとまろ)を征夷大将軍に任じ,蝦夷討伐を命じたのが,嚆矢とされる。従来,坂上田村麻呂を最初の征夷代将軍としてきたが,このとき田村麻呂は,副将軍であった,という。
しかし,その以前から蝦夷征伐軍を派遣しており,和銅二年(709)には,巨勢麻呂が,「陸奥鎮東将軍」に,養老四年(720)には多治比県守が「持節征夷将軍」に任ぜられ,延暦七年(788)に紀古佐美が「征討大将軍」に任じられたことがある。
しかし,一貫して蝦夷征伐がその役割であり,延暦十三年の征討では,実質,坂上田村麻呂が指揮を執り成果を上げ,翌年征夷代将軍に任命された。田村麻呂の活躍で,征夷大将軍の称号が,武臣第一の栄職,との伝統が生まれた。
以上が,征夷大将軍の前史である。
その後も東国に兵乱が起きるたびに,臨時に征夷大将軍が任命されたが,この称号の転機は,
「寿永三年(1184)正月,木曽義仲の征夷大将軍任命である。」
という。ここで意味が,征夷ではなく,「内乱に対して」任命され,
「『東国の兵馬の権』を握る武将としての職」
に変わる。「源頼朝の征夷大将軍は,義仲の前例にならった」ものであった。
この征夷大将軍というのは,
「中国で皇帝に代わって東方に遠征した将軍」
をまねたものだが,日本では,台頭してきた武士たちの間では,朝廷から大権を与えられる征夷大将軍を,
「天下第一の武将」
を指すものと認識するようになり,特に,
「源頼朝以降の征夷大将軍は臨時の閑職ではなくなって常設の官職となり,700年物長期にわたった武家政権の,頂点に立つ者の呼称となった。」
という。なお,征夷大将軍を,大樹公と呼ぶのも,中国出典で,『後漢書』「馮異伝」によると,
諸将が手柄話をしているときに馮異はその功を誇らず,大樹の下に退いた,
という逸話によるらしい。ついでに,幕府というのも,中国出典で,
皇帝に代わって遠征した征夷大将軍の幕舎
を指す。
ところで,本書によると,そういう歴史の始まりである源頼朝は,上洛した折,征夷大将軍を望んだが,
「後白河法皇は,…権大納言兼右近衛大将を頼朝に与えた。この役職は朝廷の公事に参加する義務があり,後白河は頼朝を京に留め置けば,位の頂点に君臨する自身を尊崇するしかなく,やがては頼朝を籠絡できると考えた…」
ようだが,頼朝は鎌倉へ帰る前に,それらを辞任し,「前右近衛大将」という肩書で,「前右近衛大将家政所を開設した」。幕府を開くのに,征夷大将軍の肩書はいらなかった,ということらしい。二年後の建久三年,後白河法皇崩御後,朝廷は,頼朝に,征夷大将軍に任じた。しかし,建久五年(1194),その征夷大将軍を辞任している。
「征夷大将軍はもともと令外官で朝官の職としては低く,近衛大将のほうがはるかに上位で,武家政権の首長としては『鎌倉殿』の地位で十分だった」
と,著者は書く。事実,源氏三代では,「鎌倉殿」が重視されていたようである。
鎌倉,室町,江戸幕府の全39人の将軍を見ていて,おもしろいのは,鎌倉幕府は,結局執権北条家が実権を握り,四代目からは,たんなる傀儡将軍を,京から親王を迎い入れてきた。室町時代も将軍は,名ばかりの時代が長い。徳川家康は,
「徳川氏が征夷大将軍として永遠の政権掌握者とするために,鎌倉幕府や室町幕府の在り方を研究」
したようで,強固な幕府組織を構築したため,幼少な将軍や病弱な将軍でも老中を中心とした幕閣が支える体制を作り上げ,結果として,傀儡と同じ形になっていった。ただ一度,延宝八年(1680),三代将軍家綱が危篤に陥った折,後継問題で,
「幕政を専断する大老酒井忠清は,鎌倉幕府の親王将軍に倣って有栖川宮幸仁親王を次期将軍に推し,北条氏のように執権政治を目論んだ。」
ということがあった。だが,弟がおり,
「忠清が押し切る形で決まりかけたが,春日局の義理の孫の老中堀田正俊は,徳川家の正当な血統として綱吉を強く推して反対した」
結果,綱吉が五代将軍になった,という。
この武家政権の歴史の中で,平氏と,織豊時代だけは,異質である。
織田信長が最終的に何を考えていたかははっきりわからないが,安土城に残された遺構や最近の研究から考えると,幕府を設立するという意思はなかったのではないか,という色合いが強い。秀吉の場合は,明らかに,その身分や経緯から,征夷大将軍にはなれなかったという説もあるが,大阪城という立地から考えると,別の見方も成り立つ。この二人だけが,ひょっとすると,武家政権の700年の中では,平氏とともに,武門の棟梁としては,異質な政権,という気がする。
ともに,政権基盤を確立できない間に,崩壊したので,ただ独裁制のみが際立つが,その色合いだけでも,他の政権とは異質である気がしてならない。
参考文献;
二木謙一監修『ほんとうは全然偉くない 征夷大将軍の真実』(SB新書) |
|
心の進化 |
|
鈴木光太郎『ヒトの心はどう進化したのか』を読む。
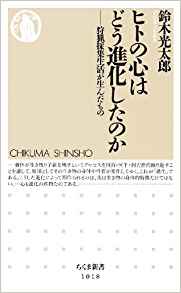
心の進化をたどることは,いまの我々が,ヒトたるにたるとはどういうことか,を照らし出すものになっている気がする。
ヒトをヒト足らしめているものは何か,「ヒトと近縁であるチンパンジーとはどこが違うのか」についての一つの目安は,いわゆる6大特徴といわれているものである。つまり,
大きな脳
直立二足歩行
言語と言語能力
道具の製作と使用
火の使用
文化
である。ホモ・サピエンスというのは,知恵あるヒトである。名付け親は,系統分類をおこなった,リンネである。しかし,その他にも,
ホモ・ファーベル(ものを作るヒト)
ホモ・ロクエンス(しゃべるヒト)
ホモ・モビリタス(移動するヒト)
ホモ・ソシアリスト(社会的なヒト)
ホモ・レリギオスス(神や超自然的な存在を信じるヒト)
ホモ・ルーデンス(遊ぶヒト)
等々ヒトの特徴を表した命名がたくさんある。
本書では,
「カタカナ書きの『ヒト』は生物学的な人間を指す。」
として,他の動物との比較を意識して使われている。ここでもそれに倣ってみよう。
さて,360万年前,アフリカのサヴァンナで,我々の祖先は,二足歩行をしていた。その足跡が残っている。それによって手が使えるようになったが,
「まずその筆頭はといえば,移動能力が格段に高まったことだ。」
と,著者は言う。瞬発力はピューマやガゼルにはかなわないが,
「霊長類のなかでは,地上をもっとも速く走ることができるようになり,しかも長距離を走ることもよくできるようになった。」
このヒトの持久力が,ほかの動物の四足走行よりも格段に優れているらしいのである。
「ヒトは走るために生まれついている」
とさえ言われる。その理由は,
「私たちの脳のなかには,持久走などの長時間の有酸素運動を…快く感じさせるシステムがある(「脳内報酬系」と呼ばれるシステムがこれに関わっている)。」
のだそうだ。狩猟生活を営んできた遺産らしいのである。
さて,移動能力を得ることで,出アフリカといわれる現象が何度かある。一度は,180万年前,北京原人やジャワ原人となる。その後,10〜5万年前にかけて,何度も出アフリカし,一部はクロマニョン人,ネアンデルタール人に,そして,1万4千年前までには,未踏のアメリカ大陸へまで進出する。いまや,70億人である。チンパンジーは,15万頭ほどでしかない。しかし,
「現代人は,数万年前のホモ・サピエンスから基本的なところは変化していない。つまり,ホモ・サピエンスとしての解剖学的特徴はほとんど変化していない。」
だから3万年前のクロマニヨン人の赤ちゃんを現代に連れてきてこの社会と文化の中で育てれば,普通の現代人の生活を送るし,逆に,現代の赤ちゃんをクロマニヨン人に預けても,立派なハンターに育つ,と著者は言う。
「5万年前頃には,…人の特徴の大部分は…すでに存在していた」
と。
さて,ヒトは,「手の動物」なのだそうだ。
「手の指を頻繁に使うことは,左右の手の分業を生じさせた。」
例のペンフィールドのホムンクルスにあるように,脳のどこが身体のどこを司っているかは,詳しくわかっている。で,我々の運動神経は,左右で交差しているが,利き手である右を担当するのは左脳であり,左脳はまた言語脳でもある。
「これはおそらく偶然ではない。手で細かな操作を行う,すなわち順序だった手や指の動きを制御することと,音声や単語を並べ,その順序を規則にしたがって入れ替えることには多くの共通点があるからだ。」
火の痕跡は,80万年前の遺跡から見つかっているが,火には,明かりや暖の他に,道具の製作や加工に利用でき,石は,熱すると,剥離しやすくなるものがある。そして,調理である。火を通すことで,消化しやすくなり,栄養価の高い食べ物を食べられ,摂取できるカロリーも格段に増す。
「ヒトの脳は,実はエネルギーを驚くほど多量に消費する。身体の2%しかないのに,身体全体が消費するエネルギーのうち20%から25%を食う。」
加熱処理は,脳を大きくし,「600ccから900cc」に増えた。それは,エネルギー摂取と相まって,
「(堅い生肉を食べるために)重装備だった歯,あごや咀嚼筋が,華奢なものに変化している…。咀嚼筋が弱くなったことによって頭蓋全体をきつく縛っていた筋肉の拘束は弱まり,これによって,脳は大きくなることができた…」
という可能性がある。この火の管理,たとえば火の勢いを調節するために火吹き筒を吹く,という行為が,
「息の調節が,言語の発生の制御―専門的には「調音」と呼ばれる―のもとにある。」
と著者は推測する。
25万年前には,脳は,現在と同じ1350ccになっていた,と言われる。300万年で,三倍になった。
「新生児の頭は,この大きさでも妥協の産物だ。産道を通れるぎりぎりの大きさで生まれてきて,その後脳はさらに成長し,4倍の大きさになる。」
その拡大の中でも大きくなったのは,前頭前皮質,小脳,側頭葉,前頭葉である。
この前頭前皮質が,自分がいましていることを意識的にモニタリング(「ワーキング・メモリー」と呼ばれる)や,未来のことを順序立てて考えること(プランニング)に関わっている…。さらに,社会的な行動のコントロールにも,道徳的判断やリスクの判断,他者への共感にも関わる。
「小脳…のニューロンの推定数は1000億個だ。大脳皮質のニューロンの数140億個と比較すると,小脳の方が格段にニューロン数が多い…。大脳皮質と小脳の間にはきわめて密な連絡がある…。この小脳こそ,身体の微妙で精密な動きに欠かせない。身体の動きの指令は前頭葉後部から出されるが…,その指令にしたがって,実際に個々の筋肉の動きの調節や順序やタイミングを調節するのは小脳であり,そうした動きが記憶されているのも小脳だ。」
いわゆる手続き記憶に関わっている,とみなすことができるのだろう。そして,側頭葉から前頭葉にかけての白質と呼ばれる部分で,ここが大きく膨らんで,神経線維で満たされている。他の領野との連絡が密に張り巡らされている。この構造は,
「言語機能と関係している。…言語の理解を担当しているのが,ウェルニッケ野…,言語の理解をもとに表出(発話)を担当しているのは,前頭葉のブローカー…である(このブローカー野は,大脳基底核と小脳と協働することで,発話をもたらす)。ブローカーとウェルニッケ野は,弓状束という神経線維の太い束で結ばれている。つまり,側頭葉の内部の部分がふくらんだことは,ひとつには,言語の理解と表出の緊密な連携を反映している。」
いつから話していたかは,言語能力に関わる遺伝子FOXP2が,ネアンデルタール人の化石のDNAから解読され,50万年前に,ホモ・サピエンスの祖先とネアンデルタール人の祖先とが分岐するので,この時代に,話す能力を持っていた可能性がある,とされている。
ヘッケルの反復説,つまり「個体発生は系統発生を繰り返す」という。動物胚のかたちが受精卵から成体のかたちへと複雑化することと,自然史における動物の複雑化との間に並行関係,つまり人類進化の痕は,個の成長のなかに見ることができるとすれば,心の進化もまた,個の心の成長の中に見ることができる。昔読み漁ったピアジェが自分の子供の成長の軌跡に発見したのは,それであった。
脳のシナプス結合が最高になる一歳以降,子供は能動的にさまざまな知識や能力を身につけていく。ひとつは,ことば,いまひとつは心の理論。
「私たちは,相手の心の状態を読んで次の行動をとる。相手がなにをどう思っているかをつねに気にかけながら(場合によっては意図的に気にかけないようにして),自分の対処法を決めている。(中略)私たちが目にすることができるのは相手の行為やしぐさや表情だけであり,耳にすることができるのは相手が発することばと声だけである。しかしふつうは,私たちは,それら外に現れたものを通して,相手がなにを意図しているか,いまどんな感情をもっているか,なにを躊躇しているか,なにを思い悩んでいるかを,すなわち相手の心がどんな状態にあるかを推測する。」
これを「心の理論」と呼ぶ。これがなければ,カウンセリングもコーチングも成り立たない。この発達は,4〜5歳ころに獲得される。ここではじめて,「他者の視点に立つ」ことが可能になる。
「他者の視点に立つことができるというこの能力は,自分がどういう人間かを自覚し始めること(「認知的自己」の出現)とも無関係ではない。というのも認知的自己は,他者と自分の違いがわかり,他者から自分がどう見えるかを意識することから始まるからである。」
これは,鏡の中の自分がわかることとも対応している。だから,
ホモ・イミタトゥス(まねするヒト)
がヒトの特徴でもある。指差し行為は,ヒトしかしない。なぜなら,
「指差しで指示されている方向とは,指差した人間からの方向である。見ている側は,その指差した人間の位置に身をおかないかぎり(あるいはそれを想像しないかぎり),指されている方向を特定できない。」
それは,注意の共有でもある。すでに,ヒトの社会がある。さらに,ヒトは,モノにも心を見る。天変地異や自然現象にも「心の理論」を当てはめる。その先に神や超自然現象を見る。
ホモ・レリギオスス(神や超自然現象を信じるヒト)
でもある。
結びの,収容所の中で仲間に言ったフランクルの言葉は,ヒトとは何であるかを示して,印象深い。
「自分たちのことを思いながら待っていてくれている人たちのことを思うように言う。『どんな苦境にあっても,だれか―友,妻,生きているだれか,亡くなっただれか,あるいは神―が僕たちのそれぞれを見守っていて,ぼくたちがその人や神を失望させないことを願っているのだ』。…人間は待っていてくれる人がいるからこそ生きられるのかもしれない。」
参考文献;
鈴木光太郎『ヒトの心はどう進化したのか』(ちくま新書) |
|
官僚 |
|
矢部宏治『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』を読む。
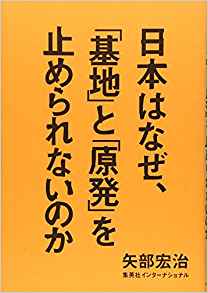
沖縄の地上面積の18%が米軍基地であるが,上空は,100%支配されている,
という。しかし,それを沖縄だけのことと思っては大間違いである。実は,日米地位協定によれば,
「日本国の当局は,…所在地のいかんを問わず合衆国の財産について,捜索,差し押さえ,または検証を行なう権利を行使しない。」
つまり,場所がどこでも,米軍基地の内外を問わず,日本中,「アメリカ政府の財産がある場所」は,一瞬にして治外法権エリアになる,ということを意味している。墜落した飛行機の機体,破片,総てはアメリカ政府の財産と見なされ,警察も消防も手出しできない。
これは,独立を回復し,安保条約が改定された以降も,引き続き維持され,
「占領軍」が「在日米軍」と看板を掛け替えただけ,
の状態が続いている。そもそも,日米地位協定と国連軍地位協定の実施にともなう航空法の特例に関する法律第三項には,
「前項の航空機(米軍機と国連軍機)およびその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については,航空法第六章の規定は,政令で定めるものをのぞき,適用しない」
とある。「最低高度」や「制限速度」「飛行禁止区域」を定めた航空機の運航に関わる規定が,まるごと適用除外になっている。つまり,米軍機は,日本国中どこをどう飛んでもいいのである。
しかも,最高裁は,砂川事件判決で,
「米軍は日本政府が直接指揮をとることのできない『第三者』だから,日本政府に対してその飛行差し止めを求めることは出来ない。」
「日米安保条約のような高度な政治的問題については,最高裁は憲法判断をしない。」
という(いわゆる「統治行為論」という)判決を出し,日本国内では,憲法よりも,安保法が,つまり米軍の行動が優先される,つまり,憲法の適用除外とされたに等しいのである。これ以降,総ての騒音訴訟は,
「米軍機の飛行差し止めは出来ない」
という判決が続くことになる。日本国憲法第八一条には,
「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」
という規定がある。最高裁自体が,憲法違反を平然としている,ということである。基地問題に手を付けた,鳩山前首相は,
「官僚たちは,正統な選挙で選ばれた首相・鳩山ではない『別のなにか』に対して忠誠を誓っていた」
と語っているそうだが,ウィキリークスで暴露された通り,日本のトップクラスの官僚,高見澤防衛省・防衛政策局長,斎木外務省・アジア政策局長が,堂々と,アメリカ側に,鳩山元首相を批判していたという事実が,鳩山元首相の印象を明確に裏付けている。
では彼らは何に忠誠を誓っているのか。結論を先に言えば,
日米合同委員会
に対してである。そこは,
外務省北米局長を代表とする,各省庁から選ばれたトップ官僚と,在日米軍のトップによる月二回の会議,
である。憲法学者の長谷川正安名大名誉教授は,されを,
安保法体系
と名づけた。これが,砂川判決によって,
日本国内法はもとより,日本国憲法の上位に位置する,
ことが確定してしまっているのである。著者は言う。
「官僚というのは法律が存在基盤ですから,下位の法体系(国内法)より上位の法体系(安保法体系)を優先して動くのは当然です」
という。本当にそうなのか,それでは,件のアイヒマンと同じではないのか。ただ,指示された職務を忠実に果たすだけで,国を滅ぼすことも平然とする。そこには,人はいかにいくべきか,という倫理そのものが欠けている。すでに,ずいぶん前から,モラルハザードが起きている。
これと同じことが,原発でも起きている。原発訴訟で,例外を除いて,
「とりわけ児童の生命・身体・健康について,ゆゆしい事態の進行が懸念される」
と言いつつ,しかし,結論は,
「しかし行政措置を取る必要はない」
と無理に接ぎ木したような判決が多く出されている。ここにも,同じ背景を疑いたくなる。
放射能汚染がひどく営業停止に追い込まれたゴルフ場が東電を訴えた裁判がある。そこで,「除染方法や廃棄物処理の在り方が確立していない」という理由で,東京電力に放射性物質の除去を命じることは出来ないという判決が下された。著者は言う,
「おかしな判決が出るときは,その裏に必ず何か別のロジックが隠されているのです。…砂川裁判における『統治行為論』,伊方現原発訴訟における『裁量行為論』,米軍機騒音訴訟における『第三者行為論』など」
として,ここでも,基地問題と同じ適用除外がある,と指摘する。
「日本には汚染を防止するための立派な法律があるのに,なんと放射性物質はその適用除外となっていたのです!」
大気汚染防止法第二七条一項,土壌汚染対策法第二条一項,水質汚濁防止法第二三条一項,いずれも,「放射性物質による汚染,汚濁は適用除外となっている。そして,環境基本法第一三条のなかで,放射性物質による各種汚染の防止については,
「原子力基本法その他の関連法律で定める」
とし,「実は何も定めていない」のだという。だから,汚染被害を訴える農民に,環境省担当者は,
「当省としましては,このたびの放射性物質の放出に違法性はないと認識しております。」
と言い切る。つまり,法的に放射能汚染は,
「法的には汚染ではないから除染も賠償もする義務がない」
ということになる。裁判で門前払いされるわけである。そして最悪なのは,2012年の法改正で,この一三条が削除され,同時に,適用除外とされた条文も削除され,結果として,他の汚染と同じく,
政府が基準を定め(一六条)
国が防止のために必要な措置をとる(二一条)
で規制することになったが,その基準は決められていない。だから,幾ら訴訟を起こしても,「絶対に勝てない」だけではない。環境基本法と同時に改訂された原子力基本法の第二条二項に,
「(原子力に関する安全性の確保については)わが国の安全保障に資することを目的として,おこなうものとする」
とあり,原子力の問題も,基地問題と同様,安保法体系のなかに組み込まれたことを意味する。つまり,裁判の判断の埒外に追いやられたのである。つまり,官僚のさじ加減にゆだねられたのである。
議員立法で「原発事故 子ども・被災者支援法」が可決されても,政府はたなざらしにし,動かないことに対して,法案作成者の議員の一人が,被災者への意見聴取を求めたのに対し,復興庁の水野靖久参事官は,こう言い放った。
「政府は必要な措置を講じる。なにが必要かは政府が決める。そう法律に書いてあるでしょう」
と。これほど,いまの日本の実情を如実に示すものはない。議員立法に対しても,官僚は動かない。こうした背景にあるのが,
日米原子力協定
である。「廃炉」も「脱原発」も,日本側には何一つ決められない。しかも,日米原子力協定第一六条三項には,
「いかなる理由こによるこの協定またはそのもとでの協力の停止または終了の後においても,第一条,第二条四項,第三条から第九条まで,第一一条,第一二条および第一四条の規定は,適用可能なかぎり引きつづき効力を有する」
とあり,協定の終了後も効力がつづく。しかしも日本側からは,
「ひっくり返す武器が何もない」
と著者のいう状況なのである。これは,基地をめぐる地位協定よりも最悪である。つまり,選挙で選ばれた首相が,脱原発を表明しても,官僚が無理といえば,撤回せざるを得なくなる。この日米原子力協定が,憲法の上位にあることになるのである。
いずれも,「原発村」「安保村」といわれる。しかし,原発の規模は年間二兆円円,安保は年間五三〇兆円,
「なぜなら占領が終わって新たに独立を回復したとき,日本は日米安保体制を中心に国をつくった。安保村とは,戦後の日本社会そのものだから」
と,著者は言う。その日本のありようを示す,象徴的な発言は,キッシンジャーが周恩来に,なぜ米軍は他国(日本)に駐留し続けるのか,という問いに,
「もしわれわれが撤退するとなると,原子力の平和利用計画によって日本は十分なプルトニウムを保有していますから,非常に簡単に核兵器をつくることができます。ですから,われわれの撤退にとってかわるのは,決して望ましくない日本の核計画なのであり,われわれはそれに反対なのです。」
「日本が大規模な再軍備に乗り出すのであれば,中国とアメリカの伝統的な関係(第二次大戦時の対ファシズム同盟関係など)が復活するでしょう。…要するに,われわれは日本の軍備を日本の主要四島防衛の範囲に押しとどめることに最善を尽くすつもりです。しかし,もしそれに失敗すれば,他の国とともに日本の力の膨張を阻止するでしょう。」
と述べているとされるところに現れている。その意味で,日米安保条約は,
「『日本という国』の平和と安全のためではなく,『日本という地域』の平和と安全のために結ばれたものだ」
ということを思い起こさなくてはならない。国連(連合国)の「敵国条項」が,まだ日本にだけ(ドイツは事実上脱した)適用されていることを忘れてはならない。その延長線上に(占領軍としての),在日米軍がいる。その根拠法は,国連憲章第一〇七条と講和条約六条に基づいていて,「敵であった国」ということが続いている(イラク占領を「イラクの日本化」といったブッシュ大統領の発言はこの文脈で見ると,アメリカの本音が透けて見える。しかしそのイラクは,日本と異なり,米軍を撤退させたのである)。
中国の,
「日本政府による尖閣諸島の購入は,世界反ファシズム戦争における勝利という結果への公然たる否定で,戦後の国際秩序と国連憲章への挑戦でもある」
という発言は,その文脈から見るとき,敵国条項が生きている前提に立っての非難なのである。
では,我々は,どうすればいいのか。少なくとも,本書にはいくつかの提案があるが,現状では,国内有事とアメリカが判断した際,自衛隊は米軍の指揮下に入ると,密約で合意されている。しかも集団的自衛権自衛権行使を容認したいま,自衛隊が米軍世界戦略の先兵と化すことを意味する。
時間はそれほどない。しかし,少なくとも,基地問題については,今日の事態は,
日本側が,駐留を希望した,
ということに起因する。その拒絶の動きから始めなくてはならない。先例はある。フィリピンであり,ドイツである。いずれも,基地を撤去させた。周辺諸国との和解,関係改善を果たし敵国条項を実質的になくすことに成功したドイツのシュミット首相は,かつてこう言った。
「日本は周囲に友人がいない。東アジアに仲のいい国がない。それが問題です。」
と。その重要性が,30数年たってもなお有効であるばかりか,実は政府は今日,それとまったく正反対の行為を繰り返し,むしろ悪化させているということは,何という状況であろうか。
参考文献;
矢部宏治『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』(集英社インターナショナル) |
|
生態学 |
|
江崎保男『自然を捉えなおす』を読む。

本書は,サブタイトルに「競争とつながりの生態学」とあるように,生態学の立場からの自然の捉え方なのだが,しかし,「序」で,視点を変えるのは人だけで,その視点の差は,「立ち位置」に左右される,と書いているところから見ると,本書が,さまざまな学問的な立ち位置によって,自然の切り取り方が,こうも変わるのだということを,書こうとする,意図があるのだと思う。
で,のっけから,生物学,生理学,生態学の違いから。
生物学は,生物はどのように生きているのか,生きてきたのか,その仕組み,メカニズムは何か
生理学は,生物個体がどのように生命を維持しているのか,そのメカニズムは何か
生態学は,集団レベルの生物学であり,静物に関する社会学であり,経済学であり,「生命」ではなく「生活」の科学
と区分けされる。この違いは,たとえば,「なぜ鳥は渡りをするのか」という問いに,至近要因と究極要因があり,
究極要因は,進化の産物と考えられるものであり,至近要因は,学問分野ごとに変わる。生理学なら,「鳥に渡りの衝動を起させる日長の変化」であり,生態学なら,「渡っていく先にある,繁殖に十分な量の餌」となる。
「現代の生物学者のアタマの引き出し構造は,タンスの引き出しのような,すべてが一つの面を向いたものではなく,『樹木の枝のように四方八方の斜め上にむかって伸びており,枝=各引き出しを引き出すと,そのなかには至近要因群が収納されており,そのはるか奥にはいつも,究極要因群を収納した貯蔵庫そのものである幹の内部が,うっすらと影をまとって見えており,引き出しを戻すと枝が幹に接し,つながるようになっている』といったイメージ…
という。進化を背景にして,各枝先に,生物学の各分野がある,ということになる。
生態学,つまりエコロジーは,もともと,
Ecology=oikos+logos
で,オイコスとは,「家」を意味し,原義から,「生活の科学」なのだという。
さて,そこで地球の自然を研究対象とする生態学の「自然の切り出し方」は,たとえば,日本列島の場合,
「森林・河川・海域・湖沼・草原・水田農耕地・都市」
という七区分になる(「湿地」を入れると,8区分)。それぞれには,特有の生物集団が生息し,その地域生物集団を,
群集
あるいは
生物群集
と呼び,その機能を説明するには,よく知られている食物連鎖が分かりやすい。それは,
「動物は他の生物を食わないと生きていけない(=動物の定義,動物とは他の生物を食う生物である)。たとえば森の住人であるハイタカは多種多様な小鳥を食って生きている,小鳥たちは虫を食って生きている,虫たちは植物の葉っぱを食って生きている」
というものだが,現在の食物連鎖概念は,「植物の光合成による,有機物生産を起点とする生食連鎖のみならず,動植物の死体や死物(デトリタス)を起点とする腐食連鎖にも広がってい」るらしい。
「腐食連鎖とは,たとえば森林土壌中には樹木の落ち葉や動物の死体・排泄物といったデトリタスが大量に蓄積されているが,デトリタスは有機物であり,生物が必要とする(化学)エネルギーが炭素結合として含んでいるので,これを食う多様な動物たち=デトリタス食者や,これらを無機物にまで分解してしまう多様な菌類・バクテリアといった分解者,さらにこれを食う菌食者が生息しており,それらがさらに消費者たる動物たちに食われる連鎖・つながりである」
と。つまり,「食物連鎖が人を頂点とする消費者たちの食料生産機能を担っているのに対し,腐食連鎖は地球全体の廃物処理の機能を担っている」ということになる。それは,
「植物を起点とする『生食連鎖網』とデトリタスを起点とする『腐食連鎖網』という2つの閉鎖的なネットワークが,いきものと死物の二つの回廊(コリドー)を介してボトルネック状につながっており,有機物は群集内を循環することになる」
ということなのである。ここで,ジョージ・タンズリーが発明した概念,
生態系(エコシステム)
が,意味を持ってくる。上記の循環システムは,
「有機物つまり生物体とデトリタスを構成する炭水化合物は群集のなかを循環するのですが,菌類やバクリテリアがデトリタスを最終的に無機物に分解・還元してしまうと,それらは二酸化炭素と水とアンモニアであり(生物体を構成しするタンパク質を完全分解するとこうなる),これらはもはや有機物ではなく生物体を構成しないので,定義上生物体の枠外にでてしまい,狭義の物質(炭素[C],窒素[N],酸素[O],リン[P])は群集の中を循環しないのです。」
タンズリーは,しかし,「群集を抱え込んでいる『無機環境を含めて生態系』と定義」したので,
「生態系内の無機環境にとどまっている無機栄養塩を,植物が光合成で体内に取り込むことになり,生態系のなかを物質が循環することになる。」
この循環を支えているのは太陽エネルギーであり,エネルギーは,生態系内を一巡する間に,生物たちが使いつくし,宇宙に放散してしまうので,
「生態系は太陽をバッテリーとする物質循環装置」
という言い方になる。しかし,これは,地球全体で起きているのであって,上記の区分での生態系では,真の循環は起きていない。たとえば,一方向に流れる河川では,循環が起きるはずはない。で,
「各種生態系には宇宙から光エネルギーが注ぎ込まれていると同時に,広義の物質である無機物と有機物が,有機物に同居する化学エネルギーとともに,隣接する系から流入する。そして,元から存在する物質とともに系内の食物連鎖という循環的な物質移動過程において,群集の食物生産機能と廃棄物処理機能に活用された後,系から流出していく」
として,「流入+系内での循環(的移動)+流出」という物質の動きを,生態系と見なしているらしい。その視点(生活の視点・エコロジカルな視点)からみると,
生物群集は一般的に形態上安定している
ものなのだという。特別な理由がない限り,「絶滅しない」という。では,そのメカニズムは,どうなっているか。
「捕食―被食の関係が織りなす食物連鎖網ネットワーク……たとえば,末広がりの投網のイメージです。最上位に人間がいます。(中略)いっぽうこの食物連鎖とつながりながらも,概念的には別物として,地表あるいは土壌中のデトリタスを基盤とする腐食連鎖の投網ネットワークが存在しているはずです。ただし,腐食連鎖を上にたどっていくと次第に地上の捕食者が登場するので(たとえば,落ち葉を食ったカタツムリをマイマイカブリが捕食する),現実にはこの投網ネットワークは途中から生食連鎖に乗り入れしていることになります。…また,ある種は複数種の餌をとり,同じ種が複数種に食われるので,これらのネットワークの上下のつながりを構成する一本一本の連鎖は,三次元に複雑に互いに交差しており,さらにこれに,競争と利用を動機とする複雑きわまりない捕食以外の生物間相互作用が,縦ではなく横あるいは斜めにつながり繊維として各種個体群をつなげているので,結果として複雑な三次元網目構造が形成されています。」
それぞれの関係は,大きさ(個体数)と太さ(関係の強さ)を時間的に変動させているので,実体は,「四次元網目構造」で,変動幅をもったバランスがある,という。
しかし,それが,隕石衝突による恐竜絶滅のようなリセットがなかったにもかかわらず,なぜ簡単に,地球各地で崩れているのか,について,著者は明確な答えを出していないように見える。そして,
「(恐竜に代わってヒトが頂点捕食者になって)この世は安定の方向に向かった。」
と言う。
「人は,その社会があくまでも他の生物たちがつくるつながり構造の存在を前提として成立している事実に気づくのにかなりの時を要した。」
という。少しぬるくないか,と,思う。
「このことに気づいた今,私たちは人という知性をもった動物として,自らが自然のなかで最上位頂点捕食者のニッチを占めているのであり,群集という地域生物共同体のなかで,そのメンテナンスという共通目標にむかって,『意識的に』貢献することができる唯一の役割であることを自覚しなければなりません。」
とくると,もはや,地団駄ふみたいくらいピンボケである。これが生態学の尖端にいるものの発言なのだ,というのが現実である。
それにしても,本書を読了して,
「生活する空間スケールも種によって大きく異なっています。一般的な植物個体が一生,芽生えたその地(大樹の根際の直径でもせいぜい数メートルの範囲)から離れられないのに対し,動物個体は原則,かなりの範囲を動き回ります。そして人という,すでに月に達した個体がいる特殊例を除いても,翼をもつ鳥たちの一生の行動半径がいかに大きいかはよく知られていることです。なかでも,キョクアジサシという鳥は夏の北極圏で繁殖し,非繁殖期は南極で過ごすので,わたる距離は往復三万2000キロにもなるのです。」
という奥行のある自然を,さまざまな視点から,具体的に見せてくれるのかという期待を,見事に裏切られた感があるる。その要因の多くは,学問としての,自然の切り取り方の異同の細部に力を注ぎ過ぎて,「自然の見え方」の奥行が,ときにまったくわからなくなることがあったせいだと思う。
読みながら,ときに投げ出したくなった。それは,その些末なこだわりが,随所で,話の腰を折り,せっかくの興味を削ぎ取られたせいだ。行動学と生態学の違いだの,動物社会学と行動生態学の違いだの,生態学の中の,群集生態学だの生態系生態学だの個体群生態学だの機能生態学だの等々の区分けへのこだわりが,煩雑すぎ,見方の違いが自然の見え方をこれだけ変える,という具体的に変ったものの描写を後背へ追いやってしまい,興味が切れてしまう。そのために,
「自然を捉えなおす」
というより
「とらえ直そうとする視点の違い」
の方に力点があるようにしか見えなかった。
おそらく,視点の違いで,これだけ自然の見え方が変わる,と言いたかったのだろうが,見え方の違いではなく,見方,つまり学問側の自然の切り取り方の細部に拘泥しすきて,肝心の見え方の違い,ひいては,自然の奥行の深さの方が,地に沈んでしまった感がある。一体何を書きたかったのだろう,と何度も首をひねった。
参考文献;
江崎保男『自然を捉えなおす』(中公新書) |
|
天体衝突 |
|
松井孝典『天体衝突』を読む。
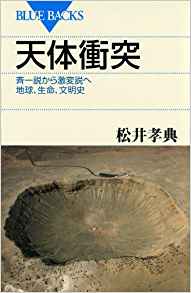
2013年ロシア南部のチェリャビンスクに落ちた隕石は,
「これまで潜在的に指摘され,あるいは実際に,地球史や生命史においては,それが本質的な役割を果たしてきたことが近年明らかにされた天体衝突という現象が,人類あるいは社会に,実際に大きな被害をもたらすことを実証した天体衝突」
であったらしい。天体衝突は,小惑星か彗星ということになる。
「素性的にいえば小惑星は岩石的物資で,彗星は,氷を主成分とする『汚れた雪だるま』と形容される物質である。……彗星はもろいので,それが衝突すると,普通は,大気上空(50㎞以上の上空)で爆発してしまう。。隕石のように破片が地表で回収されるということはない。」
「衝突した天体の破片が地上で回収されると,その物質は隕石と呼ばれる。」
チェリャビンスクで回収された最大のものは,600㎏といわれる。回収された隕石の総量は,4〜6tとされるが,それは小惑星の質量の0.03〜0.05%に過ぎない。その3/4が,アブレーション(熔発)によって蒸発し,残りが塵になったと考えられている。
「小惑星の大気圏通過時は,前面の大気が圧縮され,超高温(場合によっては1万度を超えるほど)になる。小惑星の表面はこの熱で加熱され,温度が上昇し,気化し,発光する。これをアブレーション(熔発)という。」
らしい。このため通過する小惑星は明るく輝く「火球」に見える。チェリャビンスクの場合,太陽より明るかったという。被害は,広範囲に及び,建物だけで,3613棟,その大半は,「大気中で生じた衝撃波による」という。
「衝突が人口密集地の近くで起こり,したがってその被害が広範囲にわたったため,天体衝突が文明にどのような影響をもたらすか,その影響を推定することができる,初めてのケースになった。」
人類が初めて天体衝突による天変地異を経験したというケースということらしい。しかしもちろん天体衝突が稀というわけではない。しかし,わずか20m弱の大きさで,その爆発エネルギーが500㏏,爆発高度が25㎞と高かったにもかかわらず,この被害である。この100年前,ツングースカ爆発では,爆発エネルギー5〜1.5Mt(メガトン:TNTt7h 100万tと同程度のエネルギーを表す)と,一桁大きく,爆発高度が6〜8㎞と低かったため,チャリャビンスクとは比較にならない大きさだったが,人跡未踏の地だったのが幸いした。
高速で地球に衝突した場合,何が起きるのか。
「天体が超高速で大気圏に突入すると,……天体先端部の大気中の生じたこの高圧部分は,パルスとして,大気圏中にも伝播する。その伝播速度は,大気中を伝わる音波(縦波)よりもずっと速く,これが衝撃波と呼ばれる密度の高い高圧波である。(中略)天体の前面に当たる大気は圧縮され,高圧を発生するが,側面や後端部では,そのような圧力は発生しない。そのため天体は,先端部と後端部,あるいは側面とで,異なる圧力を受け,結果として,全体として押しつぶされるような,あるいは引き裂かれるような力を受けるようになる。
前面で発生する圧力は,大気の密度と,天体の運動速度の2乗に比例する。…大気の濃い部分に達するに従い,圧力は急速に大きくなる。そのため圧縮する力も大きくなり,それが天体の強度を超えると,破壊が起きる。破壊が起こると,衝撃波が各破片の前面で発生するようになり,衝撃波は全体として強くなる。破片は破壊以前に比べて軽いため,減速も大きくなり,衝撃波は進行方向にも伝播するようになる。これが爆発による衝撃波である。」
衝突天体の大きさが1㎞になると,大気圏通過中の爆発は起きず,地表に激突する。
「天体が地表に超高速(標的物質を伝わる縦波速度以上という意味)で衝突すると,地殻との接触部で,衝撃波が発生する。衝撃波は,地殻,マントル内部,それから衝突天体とそれぞれの内部に伝わる。…衝突天体は,接触後すぐには減速されないから,衝突後は地殻にもぐりこむ。その間,衝突天体内部に伝わる衝撃波は後端に向かって進行し,例えば,10㎞の直径とすれば,数秒もしないうちに後端に達する。そこで反射すると,衝撃波は,今度は圧力を開放する波(爆発のように,それが通過すると,その通過した部分を破壊し,吹き飛ばす波)として逆方向に伝わっていく。それが,衝突本体から地殻,マントルへと伝わり,先を行く衝撃波に追いつくと,その相互作用により方向が変わる。結果として,その軌跡が放物線を描くように,破片が放出される。」
単純に,衝突の掘削による一時的なお椀型の穴のクレーターと,この穴が大きい場合,すぐに変形し始め,内部からその穴の空白を埋めるような力が働いて,そこが押し上げられ,中央が山のように盛り上がったり,その壁が崩れたれたり,その外側にひび割れが同心円に広がったりと,さまざまな衝突のクレーターのバリエーションは,月面に見ることができる。
そもそも地球に対して月(地球の直径の1/4)のような大きな存在そのものが,実は珍しい存在らしい(冥王星の衛星カロンくらいしかない)のだが,アポロ計画で,
「月の岩石は基本的には,地球のマントルと似ていること」
が明らかにらなり,月と地球は,「兄弟の関係」にあり,
「地球形成の最終段階で,原始地球に火星サイズの原始惑星が衝突し,周囲にまき散らされた破片の集積により,月が生まれた」
という「ジャイアント・インパクト仮説」という考え方があるくらい,地球にとって,天体衝突は,その地球史上頻繁に起こっている。ではどのくらいの頻度で起きるているのか。
100㎞サイズの天体で,数十億年に一回,
10㎞サイズの天体で,数千万年から1億年に一回,
1㎞サイズの天体は,100万年に一回,
100mサイズの天体なら,1000年に一回,
50m(ツングースカ程度の)サイズの天体は,100年に一回,
と推定されている。しかし,数㎞以下でも,文明に影響する。
「その理由の一つは,人類が生物として,衝突による地球環境の影響を受けやすいことがあげられる。そしてもう一つは,文明が沿岸域や大きな川沿いに生まれ,衝突の直接的影響を受けやすいからである。」
と,著者は警告する。今日では,恐竜の絶滅は,天体衝突によるものと,ほぼ考えられるようになっている。メキシコ・ユカタン半島地下にある,6500万年前の白亜紀末の巨大なクレーターは,その衝撃の大きさを推定させている。
衝突したのは,小惑星。地表に対して,約30度で,南南東の方面から衝突した。その大きさは,直径10〜15㎞,衝突速度は秒速約20㎞。この衝突によるエネルギーは,10の23〜24乗J,広島型原爆の10億倍。
その結果起きたのは,
「衝突直後には,衝突地点周辺は,時速1000㎞を超える爆風に襲われる。衝突の瞬間に発生する蒸気雲の温度は1万度を超え,北米方面に広がっていく。周辺では森林火災が発生する。クレーターの形成に伴って,破片が放出され,宇宙空間にまでとばされる。それが再び大気中に突入し,大気を加熱する。再突入した破片の温度は,260度にも達し,その影響は数時間続く。」
この熱で,「大気の主成分窒素が酸化され,大量の一酸化窒素が発生する。…長期的な変動としては,オゾン層も消滅した」とされる。ユカタン半島は浅い海に覆われていたらしいが,クレーターに向かって海水が浸入し,300m超えの津波が発生したと推測されている。深刻なのは,中・長期的な変動で,
「衝突に伴い大量の塵が巻き上げられる。森林火災により大量の煤が発生し,大気中を漂う。衝突地点に厚く堆積していた硫酸岩は蒸発し,硫黄を大気中に放出する。」
数ヵ月から数年大気中に滞留して,太陽光を遮り,地球を寒冷化し,衝突後10年くらいで最大10度の寒冷化が起きる,と予測されている。しかも,大気中の硫黄は,酸素と反応して,硫酸となり,地球に降り注ぐ。海は酸性化することになる。
これまで地球上に生きていた種の99.9%は絶滅している,と言われる。つまり,「種が生まれた総数は絶滅した種の総数とほぼ同じ」なのである。こうした種の死滅も,あるいは進化も,天体衝突という「激変」と無縁ではない,のではないか,という説が大勢になっている。ということは,我々にとって,天体衝突は,大きな天変地異どころか,文明そのもの,人類そのものの存続を左右するほどの影響がある。プラトンの書いた,アトランティスは,そういう意味では,象徴的な意味をもつ。
「宇宙からの天体衝突を監視し,衝突する可能性がある場合にはそれに対処する方策を,世界で考えようという機運が高まっている。」
というのも,至極もっともな話である。
参考文献;
松井孝典『天体衝突』(ブルーバックス) |
|
不正 |
|
榎木英介『嘘と絶望の生命科学』を読む。
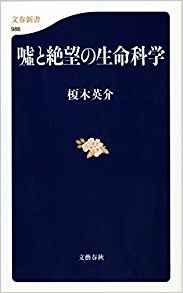
著者は,あとがきで書く。
「告白しよう。STAP細胞の論文が最初にメディアに取り上げられた夜,私は興奮していた。理由は二つある。一つはSTAP細胞が発生学上の大発見だったからだ。もう一つは,小保方氏が『後輩』だと知ったからだ。」
と,しかし,現在進行形なのでと断りながら,
「STAP細胞が明らかにした様々な問題は,理研特有の問題ではなく,日本特有の問題でもないということだ。30年以上前のアメリカの研究不正を扱った『背信の科学者たち』…を20年ぶりに読んでみたが,STAP細胞の問題が決して特殊な事例ではないことを改めて思い知らされた。」
と。そして,こう言うのである。
「実は小保方氏のSTAP細胞論文が騒動になりはじめたとき,バイオの科学者たちは,それほど驚かなかった。もちろん,画像の切り貼り,画像の流用,文章のコピーペーストなど次々と明らかになる疑惑を目の当たりし,多くの研究者はさすがに絶句したが,実はバイオ研究の論文が結構適当で,ときにウソが交じっていることは,バイオ研究者のあいだでは広く知られたことだったのだ。」
だから,「バイオ研究の一部は,虚構の上にそびえたつ」と。では,研究不正とは,何か。
研究不正には,
捏造(Fabrication)
改竄(Falsification)
盗用(Plagiarism)
の3つがあり,頭文字をとって,FFPと呼ばれる。
「ねつ造とは,存在しないデータを都合よく作成すること」
「改ざんとは,データの変更や偽造をすること。都合の良いデータだけをピックアップすることや,逆に都合の悪いデータを削ることも含まれる」
「盗用とは,他人のアイデアやデータ,研究成果を適切に引用せずに使用すること」
「このほかに,研究に関わっていないのに論文の著者になるといったような『不適切なオーサーシップ』や,個人情報の不適切な取り扱い,プライバシーの侵害,研究資金の不正使用,論文の多重投稿等も研究不正に含まれる。」
と。そして,
「東邦大学医学部の准教授だった藤井善隆氏は,なんと172本の論文にねつ造を行ったことが発覚し,不名誉な世界記録をつくった」
という。だからといって,
「バイオ研究に不正が多く発生している印象ではあるが,必ずしもそうではない,というデータもある。…松澤孝明氏によると,バイオ系の研究不正の割合は,37.7%。自然科学系ら限れば,74.1%にも達するが,研究者人口も多いので,必ずしもバイオ系で突出して研究不正が発生しているわけではない…。」
にしても,不正があまりにも多い気がするのは,僕だけだろうか。しかしである。
「アメリカの国立衛生研究所(NIH)から助成を受けていたバイオ研究者の3人に1人が,過去3年間に上位10位までの悪質な行為に関与していた」
というネイチャー誌の記事もある。では,まっとうに研究している研究者はいないのか。捏造,改竄,盗用の対極にあるのは,
「責任ある研究活動」(RCR:Responsible Conduct of
Research)
という。それは,
「研究者のプロフェッショナルとしての責任をまっとうするやり方で研究を遂行すること」
とされる。しかし,ステネック氏らによると,
「『ねつ造,改ざん,盗用』と『責任ある研究活動』との間には『QRP』(QRP:Questionable Research
Practice)があるとしている。」
ここには,
論文の多重投稿
先行研究の不十分な調査
自説に有利な実験結果の選択的な発表や誇張
自説に不利な実験結果の非公開や発表遅れ
等々。つまり,
「ねつ造,改ざん,盗用」と「責任降る研究活動」とは,連続している,
ということなのだ。その間には,
データはあるのに切り貼りしてしまった,
再現性があるのに,データの見栄えをよくしてしまった,
等々,必ずしも不正とは言えないルール違反がある。では,
「不正とそうでないものの境界はどこにあるのか…これが意外に難しい。」
と,著者は言う。たとえば,
「ある論文では,たった一つの画像に,ちょっとだけいじったあとがあった。ある論文では,二つの画像に。ある論文では三つの画像に。その先に,総ての画像やグラフがどこか別のところから持ってきた,完全なニセ論文がある。どこに線を引くのか。そして,誰がその線を引くのか。」
そもそも,研究というのは,
「研究者は,まず“真実”はこうだろうと想像し,『最初はあいまいな仮説』を立てるところからはじまる。つまりこの段階では『ねつ造』であるといえる。そして,人間が未知のことを理解するのは,パトリック・ヒーランが『科学のラセン的解釈』説で述べているように,『最初はあいまいな仮説(つまり『ねつ造』)→試す→都合のいい部分を残し,不都合な部分を変える(拡大・分化,つまり『改ざん』)→試す,のラセン的上昇で,〈知〉が生産される』ので,ある発見のプロセスがこのようだから,発見にはある種の『ねつ造→改ざん』作業が必然なのである。」
というところがあるのだから。そのせいかどうか,いまバイオ研究者で,
「胸を張って自分は一切の不正,あるいは不正と疑わしい行為にかかわっていない,と宣言できる研究者はもしかして少ないのかもしれない。病巣は想像以上に深い。」
と著者は推測する。。そんな馬鹿な,と思いたいが,「実験を行う分野で不正が発生しやすい」。例えば,こんな例を挙げられれば,頷かざるを得まい。
「実験を何回もすれば,ときに変なデータが出てくる。実験のウデの問題なのか,それとも,試薬がおかしかったのか。では,そんな『異常値』が出たときにどうするのか。異常値だけ集めるか,異常値を分析の対象から外してしまうか……異常値だけ集めたデータと,異常値を外したデータは全然異なるものになるかもしれない。つまり,自分の主張にあうデータだけを集めることができてしまうのだ。」
そう考えると,「異常値の一個くらいは消した経験がある研究者」は多いだろう。さらに,
「(画像の)加工しなくても,ウソはつける。何十回も何百回も実験を行って,たまたま自分のたてた仮説にピッタンコの写真がとれた。そういう写真を「チャンピオンデータ」と呼ぶ。いわば,『奇跡の一枚』みたいなものだ。……しかし,たまたま出たチャンピオンデータだけを貼り合わせると,あたかもその仮説が証明されたかのようにみえてしまう。」
確かに,これは,捏造,改竄,盗用には当たらないが。だが,これを研究者個人の倫理のみに押しつけるのは,どうだろう。
「松澤氏によれば,『研究不正等の推定発生件数はの変動傾向が,わが国の科学技術政策の変遷に比較的よく一致している』という。」
つまり,STAP細胞問題も,理研の独立行政法人化を背景に考えないと,浅いものになってしまう。そう考えれば,独立行政法人化された国公立大学でも,同じことが起きているということを暗示している。深い底は,見えてこない。
参考文献;
榎木英介『嘘と絶望の生命科学』(文春新書) |
|
幕臣の維新 |
|
門松秀樹『明治維新と幕臣』を読む。

本書は,戊辰戦争の混乱期,全国統治の空白が生じかねない状況下,明治新政府は,その危機的状況に対応するため,
「幕臣の継続登用」
をはかり,
「各奉行所などの幕府機関を,所属する人員も含めて継承」
することで乗り切った。その多くは,
「ほぼ無名といってよい小身の旗本や御家人であった。彼らは著名な幕臣たちとは異なり,政府の政策形成に関与できるような上級ポストではなく,行政実務に当たる中・下級のポストに登用された。(中略)実際の予算や政策の形成過程では,長年の経験を積み,実務に精通したいわゆる『ノンキャリア』の存在」
である。本書は,そうした「『ノンキャリア』の幕臣たちに光を当てることを試みた」ものである。
旗本御家人については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/410162722.html?1417810594
http://ppnetwork.seesaa.net/article/410218701.html?1417897473
で,その体たらくぶりを散々挙げたが,逆に,その職務に忠実な気質が,明治新政府の立ち上がり期の行政を支えた。
幕臣の気質について,本書でも,
「太平の世が続くことで,武士の『家』の固定化も進み,武士の主従関係の根本である『御恩』と『奉公』の関係についての意識が薄れていくことで,知行・封禄は『御恩』,すなわち主君に対する『奉公』の対価ではなく,『家』が代々相続すべき固有の財産という意識が強まっていく。その結果,(中略)『役料』や『足高』のみが職務に対する対価であり,職務を遂行する以上は当然えられるべき俸給であると解されるようになる。その結果,…幕臣,ひいては武士は,『御恩』と『奉公』の関係に基づく臣下ではなく,役職に就いて働くことで『役料』『足高』という『俸給』を得るサラリーマンに転じていった…。」
と,その気質を述べている。これを前提にすると,本書の主題である,幕臣がそのまま新政府の行政を担うという流れが,理解しやすい気がする。
江戸開城後,徳川家は700万石から70万石に減封,静岡へ移封される。そのとき勝海舟が,幕臣の身の振り方の概算をまとめている。それによると,
旧徳川氏家臣 凡そ三万三千四百戸
朝臣 五千人
静岡行 一万五千人
帰農 六百人 後大抵帰参
大蔵省附渡 百三,四十人
外務省同断 百人
金川(神奈川奉行所を接収・改組) 同断
田安・一橋家へ従属
諸侯の末家は其本家に附する者
静岡・在職人数 四千九百二十四人
私事ながら,母方の実家は,幕臣で,鳥羽・伏見以降の混乱で一家離散,遺児は下僕に背負われて,彼の実家だか親戚だかにかくまわれ,維新後はその姓を名乗って生き延びた,という伝承がある。ここに載らない幕臣の人数も少なくないはずである。
新政府は,鳥羽・伏見で幕府軍を破った後,慶喜以下を朝敵として追討令を発すると同時に,
「幕臣に対して帰順を呼びかけている。そしてこの呼びかけに応じた幕臣に与えられたのが『朝臣』という身分であった。」
「朝臣」は,「あそん」ではなく,「ちょうしん」と訓む。「朝廷の臣」を意味し,
「陸続徳川の家臣,朝臣となり候願い候者有之,皆上京せり。実に千を以て数ふ也」
と,松平慶永が回想している。「朝臣」の身分の要件は,「旧禄高の書上(調書)の提出」と「天皇に対して忠誠を尽くすという誓約書の提出」が求められていた。全員がその身分を得られるわけではないが,
「『朝臣』に関する審査基準は,家長もしくは嫡男など,一家の主もしくはそれに準ずる立場にあること,反政府活動に関与していないこと,明治元年(1868)九月二十五日(慶応四年九月八日に改元)の『朝臣願』の提出期限を守っていること,そしてそれに加えて,…禄高を得られる身分であること,」
である。「朝臣」の待遇は,
「家禄として一定の収入が保証された」
が,規準があり,旧録五千石以上は,家禄を千俵,三千石以上は,五百俵,千石以上は三百俵,五百石以上は二百俵,三百石以上は百五十俵,二百石以上は百俵,百石以上は五十俵,四十石以上は四十俵,四十俵未満は従来通り,とするというものである。
その狙いは,一方で戊辰戦争が継続する中で,数千の幕臣が政府側に留まり,反政府活動を抑止する効果があったが,同時に,行政の継続,連続性を保った効果も大きい。
「戊辰戦争において戦地となった場所は例外として,全国津々浦々が混乱を極め,略奪や暴行が横行したという事態に至っていないということは,少なくとも社会生活を維持できるような秩序が保たれていたということになる。行政が機能しない状態にはほとんどならなかったということになろう。」
たとえば,江戸城開城と同時に,東征総督府は,
「江戸町奉行に対して江戸市中の取締りに引き続きあたるように命じた。さらに,徳川宗家の静岡移封を決定した五月二十七日には,奉行以下,与力・同心を継続登用するものとして,『禄高扶持米等是迄通被下置候事』,すなわち待遇を改善せずに従前どおりとすることを達している。」
この他,開港地となった函館,神奈川,兵庫や長崎,大阪,京都など遠国奉行をおいて幕府が直接支配していた各地でも,奉行所の接収と,その人員の継続登用を行っている。これによって,
「400万石に及ぶ幕領の統治を,幕府が整備した行政組織をそのまま活用することで実現しようとした」
のである。では,そういう風潮を幕臣はどう見ていたのか。旧幕臣である渋沢栄一は,「武士は二君に仕えず」というのは少数派で,十中八,九は明治政府における出世を望んでいた,と振り返っている。著者は,
「忠誠心の問題に悩むことができたのは比較的高禄の旧幕臣にかぎられているかもしれない。江戸町奉行所が接収され,奉行以下,与力・同心に至るまでの全員が継続登用された…が,同心の禄高は三〇俵二人扶持,手取りの俵数に直しても四〇俵程度である。この収入を現代の現代の貨幣価値に…,あえて換算すると,100万円から200万円前後の年収に相当する。(中略)江戸町奉行所をはじめ,さまざまな奉行所で行政実務の最前線にあった同心クラスの旧幕臣は,忠誠心の問題に悩むよりは,日々の生活を支えていくことをそもそも悩まなければならなかったであろう。」
と。しかしその継続登用も,明治十年(1877)前後を画期として,行政機能の維持を目的として登用された幕臣たちは減少していく。
明治5年(1872)には,勅任官に占める旧幕臣は7%,判任官で35%を占めていた。しかし,
「明治政府が求める人材の要件が,行政機能の維持を優先することから近代化政策の推進に代わっていくことで,旧幕臣の入れ替え」
が生じていく。そして,最終的には,明治二十六年(1893)の文官任用令によって官僚の試験任用制度が確立するまで続く。
「明治政府の草創期に政府を支え,また維新の改革が軌道に乗るまで支え続けたのは,無名に近い,行政の現場にあった旧幕臣たちであった。」
ということは,改めて再認識するのは悪くはないとつくづく思う。
参考文献;
門松秀樹『明治維新と幕臣』(中公新書) |
|
幕臣 |
|
氏家幹人『幕臣伝説』を読む。

旧旗本の大木醇堂が,明治になって綴った『醇堂叢稿』に,主として,よっているので,前作『旗本御家人』の続編と言えなくもない。前作については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/410162722.html?1417810594
で,書いた。
冒頭に,幕臣の鳥谷部春汀『旧幕の遺臣』によって,幕臣気質について,こう触れている。
「徳川武士共通の短所は,余りに個人的にして共同団結の精神に乏しきにあり。故に旧幕の遺臣に人材少なからずと雖も,彼等の協力によりて成りたる何等の事実を見ず,また彼等はかつて偉大の計画をなしたることなし。」
と辛辣である。春汀によれば,旧幕臣は個人としては様々な長所を備えているが,協同団結して事を成し遂げるという点では,人材に乏しい,というわけである。
春汀は,勝海舟を評して,
「一代の巨人なりしと雖も,その性格は個人的にして,首領の器に非ざりき」と,手厳しい。海舟にして然りとすれば,後は推して知るべし,
「才能抜群であっても,なぜかリーダーシップとしての資質をかいている」幕臣たちの生き方は,春汀によれば,
「かくの如く個人的にして共同団結の精神に乏しきがゆえに,また概して野心少なく平和の生活を好む。見よ幕府の遺臣にして,権力の争奪,利益の取り遣りの為に,他人を排してまで進むの行動に出づるものありや。自家の功名富貴を求るがためには,如何なる危険をも冒し,如何なる面倒をも忍ぶ意力を有するものありや。余はこれを見ざるなり。」
という体たらくになる。では幕臣醇堂は,どんな生き方を求めていたのか。
「照り降りなく,平均して,吉も無ければ,凶もなく,いつも同様と謂ふが人間世の最上策にて,富まず貧しからず,楽しみもなく苦しみもなく,笑ふことはなく泣くことなく,喜ばず憂へず,伸ず屈せずして生を全ふし,おはりたきものなり。」
かような安穏無事が一番という処世術も,
「ここまで徹底すると驚愕を覚える。」
と,著者。維新後の貧困にあえぐ,落ちぶれた旧幕臣の開き直りか,と思いきや,醇堂は,れっきとした旗本の嫡男でありながら,
「両番士の俸禄は,その並高と称するものは三百俵を以て例とす,これより身を起こして要路の顕職に昇るもあれども,一代限りの立身出世は,予これを欲せざる也」
と書き,
「それよりも結局三百俵を代々維持して,其子其子と部屋住より召出されて,御小姓組・御書院とかはるがはるに勤続相承くることこそ無上の幸福にて,そのうへに亦幸慶とすべきは与頭・組頭に昇りて,又其れより御手先・御持頭を経て,御槍奉行か西丸御留守居に上れば,これこそ至大の幸福也」
とまで書く。「御槍奉行」か「西丸御留守居」かとは,老齢の旗本の閑職で,勘定奉行や町奉行のような要路につくのではなく,名誉の閑職がいい,というのである。
ここから浮かぶのは,
「英雄的気質や企業家精神とは相容れない幕臣たちの寡欲で現状に甘んじる気質」
である。どうやら,しかし,これは,幕臣だけではなく,多くの日本人の気質に重なる気がするが,どうだろうか。
本書は,そんな幕臣の中から,奇人・変人と,余り日の目を見ない役職を拾っている。刃傷沙汰あり,御庭番あり,吉原遊女との心中あり,奇人学者あり,狂歌の蜀山人あり,三味線名人ありと,多士済済だが,変わり種を,いくつかピックアップしてみると,
大奥の御伽坊主
という坊主頭の年配女中がいた。常時四人ほどいたと言われる。何をするのか,というと,大奥の広敷添番を勤めた山中共古が語っている(三村竹清『本之話』)。
「大奥の坊主といふは,女にて髪を剃りたる坊主なり,将軍の閨房の世話をするものにて,御手つき中臈二人並びて,中に将軍休む,其時いろいろのことを将軍にいふといけぬ故,坊主は次の間にうつふして悉く聞き取り,御年寄へ申上るなりといふ」
と。著者は,こんなふうに推測する。
「将軍や世子が何月何日に誰と交接したかは,将軍家の血統を維持するためにもっとも重大な事項であり,正確な記録が残されなかったはずはない。おそらく御伽坊主が記録を作成し,その記録は老女たちによって厳重に管理されていたのだろう。
御伽坊主が次の間で聞き耳を立てたのも,中臈がおねだりなどせぬように監視するためだけでなく,将軍と中臈との間で,子づくりの行為がなされたかどうかを確かめるためだったのではないだろうか。」
当然,若君姫君を取り上げる,お産婆さんもいる。「『恩賜例』という,幕府から「御褒美」や「下され物」が下賜された事例を期したものがある。その中に,「さつま婆」「いつみ」「きん」等々といった,お産婆さんの名がある」。これは,江戸幕府の役職の沿革を記した『明良帯録』にも,載っているという。彼女たちは,代々,
「大奥では中臈と同格で,四谷坂町に拝借地があり,…五人扶持を給され」
ている。しかも,『恩賜例』に出るくらいだから,将軍夫妻から,「折々多額の褒美を頂戴」し,「暮らしぶりは裕福だった」らしいのである。『校合雑記』によると,吉宗の時代,
「長福丸(家重)を取り上げた『御祝儀』として,薩摩姥に白銀五十枚と樽肴,巻物が下され,小次郎様(田安宗武)のときは銀二十枚と樽肴,巻物だった。不審に思った吉宗公が役人に尋ねると,先代のときから御嫡子を取り上げた産婆には銀五十枚,御次男様以下は二十枚と決まっておりますと答えた。
すると,吉宗公,『樽肴と巻物が減少するのは理解できるが,銀は御産御用を務めた者の労をねぎらって下賜するものである。長男であろうと次男であろうと,産婆の苦労に違いがあるとは思えない,長男のとき同様五十枚を与えるように』と仰せられ,薩摩姥は長福様のときと同様,銀五十枚を頂戴した。」
というエピソードがある。しかしも彼女たちは,将軍家御用達のお産婆として,大名家にも出入りしていたという。なかなかの収入と言っていい。
もう一つ下ネタで,「公人朝夕人(コウニンジョウシャクニンと読んだらしい)」という役職の幕臣がいる。定員は,一名。代々世襲という。役目は,
「君辺に侍して御装束の節,御轅の跡に御筒を持也。便竹といふ。君御用道具の第一なり。俗に装束筒と云う。」
とある。将軍が礼服(束帯)を着て参内(内裏に参上)し,装束が邪魔で小用ができないときに,小便を受ける筒状の尿瓶を差し出すのである。しかし,参内は,寛永十一年(1634)の家光以降なく,二百三十年後の家茂のときは,公人朝夕人を従えていない。つまり,この役目は,江戸初期にその役目を終えているのに,代々上田家が世襲されていたのである。
役人の仕事には,今も昔も,目的をとうに終えていても続いているものがあるに違いない,と思わせる役目である。
参考文献;
氏家幹人『幕臣伝説』(歴史新書y) |
|
旗本御家人 |
|
氏家幹人『旗本御家人』を読む。

巻末で,この本が書かれたころ話題になった,例の「死亡届を出さす,年金を受け取っていた」ことに絡んで,「憤まんやるかたない気持ちになった」かもしれないが,として,著者はこう書く。
「ところで,この国は昔はそれほどご立派だったのだろうか。たとえば将軍以下の武士が支配していた江戸時代はどうか。『武士は今の役人よりずっと誇り高く責任感が強かったし,なにより恥を知っていた。だから年金詐取のような破廉恥な行為はありえない。庶民だって,人情に富み親や高齢者を大切にしたから,老人の孤独死なんて皆無だったのでは。』…はたしてそうか。確かに武士のなかには,高潔で優れた人物もすくなからずいただろう。それは否定しない。しかし一般的に言えば,当時の武士たちの多くは,欺瞞と甘えに満ちた慣習にどっぷりつかっていたと言わざるをえない。」
と,だから,「家の当主が死亡しても,その事実を隠ぺいし病気療養中と偽って俸給を頂戴し続けた者がいた」という。武士の中の武士,旗本御家人が,である。そして,
「問題は,このような行為が一部の悪質な幕臣によって行われたのではなく,ほとんどの幕臣が当然のように行っていたことだ。」
という。たとえば,永年勤続表彰として下賜される「老衰御褒美」というのが,あった。
「実は既に死んでいるのに,高齢や病を理由に退職届を出し,『老衰御褒美』の金銀を受け取るケースが少なくなかった…。」
しかし,こんなとんでもない詐欺が習慣化したのは,
「幕府が見ぬふりをしてきたから,将軍の寛大な措置として俸給の不正受給を許してきたからにほかならない。…老中から小役人まで,組織全体が馴れ合い甘え合って,不正を慣例化させるに至ったのだろう。…隠蔽と癒着にまみれた薄汚い世界は,一方で,寛大な優渥(恩恵)に包まれた安穏な世界でもあった。死者の俸給の不正受給の黙認が,『武士は相身互い』あるいは『武士の情け』といった言葉で表現される互助精神の具体化だったことも事実である。」
さて,そんなもたれ合いの幕府の職制を通した,幕臣列伝に,本書はなっている。
まずは,幕府役人の用語。「おさそい」と「おたく」,
「『おさそい』とは『不首尾にて免ぜらるヽ也。何も子細あらされども,病気と称してこれを辞退する事なり』。要するに職務上の過失等を犯した幕府の役人が,罷免されたり病気と称して辞任することを意味していた…。」
「『御宅』とは,『余程おもき事件にて御とがめ』をこうむること。幕臣が重大な過失を犯した場合,夜になって名代の者が若年寄の御宅に呼び出され(だから御宅か),監察官である目付立会いの下,役職の剥奪(『御役御免御番御免』)と厳重な謹慎を申し渡された…。」
そんな結末もあるにしても,いささか風変わりな事例だけをピックアブしてみる。
幕臣の異動願いは,「場所替願」と呼ばれたが,高齢の幕臣のためのポストに,「老衰場」というのがあった。それは,
御旗奉行
御槍奉行
がそれで,太平の世になると,いくさの時代の誉れの役職も,高齢者のポストに化す。そこは,「臨終場」ともなった。
前述の「老衰御褒美」とは,
「幕臣は,死ぬまで将軍に御奉公が原則だったが,七十歳に達し,体力,気力ともに衰えたとき,老衰御褒美を頂戴して役職を辞することができた。」
という,その記録を観ると,「幕府が高齢の幕臣のためにいかに多くの『閑職』を用意したかがわかる」という。驚くべきは,幕末,西洋式の「歩兵(撒兵)」「騎兵」「砲兵」からなる将軍直属の常備軍を設けたが,「撒兵渡辺恒蔵の小普請入りと老衰御褒美を願い出た文書」がある。渡辺は,七十九歳。著者は言う。
「最大の課題であった近代的軍備の確立より,高齢の幕臣たちの処遇が優先された奇怪さ。幕府と幕臣の組織的な緊張感の欠落」
が見て取れる,という。
「十七歳原則」というのがある。「大名や旗本の当主が十七歳未満で亡くなると,養子が許されず,家は断絶とする相続の法」があり,このために,「官年」という,大名や旗本が幕府に届け出る年齢が,実際よりも,五,六歳サバを読んでいた,という。十七歳以上であれば,若年で没しても,養子を取って家を存続させることが出来るのである。
「官年(幕府に届けた年齢)が私齢(本当の年齢)より高いのは,年齢の詐称ではなく,幕府の制度のひとつで,お蔭で,たとえ赤ちゃん(嬰児)であっても,十七歳だと称して家を相続できるようになっていた。家の存続のためには,極端な年齢詐称も半ば,合法とみとめられていた」
というわけである。
就活は,今も昔も大変で,「対客登城前」と呼ばれた。「百俵七人泣き暮らし」という諺があり,封禄米だけでは食べていけないことを諷している。役職に付ければ,「家禄が役高に不足する場合は,不足分が足高として支給」される。
「加えて,年三回に分けて俸給米(蔵米)を支給される際にも,役職(とりわけ激職)を務める者には上等な米が支給されるが,役職についていない幕臣には下等米が回されるのが原則だった」
というから,「非役の小普請」から脱するべく,小普請支配(小普請の旗本御家人を支配,監督する役職)のもとへ請願に出かけるか,早朝,老中や若年寄ほか幕府上層部が江戸城へ登城する前に邸に参上する。これを,「対客登城前」あるいは「対客」と呼んだ。これを幕臣は,「出勤」「勤めに出る」と称していたという。まあ,就活である。
勝小吉は,七歳で勝家の養子になり,十六歳から「勤め」はじめ,出奔したりといろいろあったが,結局番入り(武官への採用)はならず,三十七歳で,海舟に家督を譲る。
幕臣の就職難が始まったのは,舘林藩の綱吉と,甲府藩の綱豊(家宣)が将軍となり,多くの藩士が幕臣になってから,という。
それでも,成功した者はいる。筆頭の一人は,根岸肥前守。小身の旗本から,勘定奉行,町奉行などの要職にまで昇進した。しかし,根岸は,幕臣安生家の三男として,根岸家に養子に入ったということになっている。しかし,出自については,前身は「臥煙(火消人足)」で,蓄えた金で御徒の株(いわゆる御家人株)を手に入れ,幕臣の末端から出世を遂げた,と,生前からささやかれている。しかも,「一パイの文繍(体中の入れ墨)ありたり」とさえも。
しかし,そこに垣間見えるのは,
「与力や御徒等々御家人の地位は『株』として実質的に売買が許されていたから,百姓町人でも,金さえ出せば,御家人すなわち御目見え以下の幕臣になることができた。いや,それだけではない。ひとたび御家人になれば,御目見え以上の旗本に昇格し,さらには幕府の要職に就くことだって可能だった」
という,制度の柔軟性ではなかろうか。
「われわれが今日想像する以上に,幕臣社会とりわけ御家人社会には,庶民出身者がおおかったのである」
と。本書が拠っている,大谷木醇堂『醇堂叢稿』には,こうある。
「所謂非格御取立(俗に成上り立身と云)の人にハ筋目正しきものは少なく,その家をおこしたるものは,或いは前栽売の太郎兵衛,魚商の次郎兵衛,豆腐屋の三朗兵衛など多き事也」
と。幕末の,
勝海舟,
小野友五郎,
大鳥圭介,
平山敬忠,
榎本武揚,
もそうだし,
川路聖謨,
井上清直,
もこれに加えてもいい。
まあ,これは,武士がどうの町人がどうの,ということではない,人としてどうか,ということに結局行き着く過ぎないのかもしれない。
参考文献;
氏家幹人『旗本御家人』(歴史新書y) |
|
外交交渉 |
|
加藤祐三『幕末外交と開国』を読む。

1853年7月8日(嘉永六年六月六日),浦賀沖に巨大な蒸気船二隻に,帆船二隻のペリー率いるアメリカ東インド艦隊が現れた。その船に向かって,浦賀奉行所の役人二人が小さな番船で近づいた。
「幕府は『ウィンブルという旗を掲げた船が旗艦であることをよく知っていた。』と記録している。」
旗艦サスケハナ号に近寄ってきた二人の役人が,「I can speak
Dutch!(自分はオランダ語が話せる)」と叫んだ。ペリー艦隊は,たったひとりのオランダ語通訳ポートマンを応対に出す。
「この出会いは,きわめて象徴的である。最初の対話で発砲交戦を避けることが出来た。それには日米双方の事情があった。見えざる糸が『戦争』を回避させ,『交渉』へと導いた。やがて接触を重ねるうちに,双方ともに『交渉』の重要性を認識し,それに伴う行動を優先させていく。」
両者の事情とは,
幕府は,海軍力を持たないため,彼我の戦力を分析し,戦争を回避する方針,「避戦」を基軸にすえて,「外交に最大の力点を置き,情報を収集し,分析し,それを政策に生かしてきた。」
たとえば,
第一に,アヘン戦争における清敗北の情報を「自国の戒め」と捉え,文政の強硬策を撤回して,穏健な天保薪水令に切り替えた,
第二に,ペリー艦隊来航の予告情報を,前年の内にオランダから入手,準備した。
第三に,ペリー来航の地を,長崎か浦賀と想定して,オランダ通詞の配置を変え,浦賀奉行所の体制を強化した。
他方,アメリカのペリー艦隊側は,
第一に,巨大な蒸気軍艦の石炭や千人近い乗組員の食料などに必要な,独自の補給線を持たず,イギリスに頼らざるを得ず,日本と交戦状態になれば,イギリスは中立宣言をし,イギリス支配下のアジア諸港に寄港できず,補給できなくなる。
第二に,ペリーは「発砲厳禁」の大統領令を背負って来日した。アメリカ憲法では宣戦布告権をもつのは大統領ではなく,議会であり,議会の多数派は,民主党であり,「発砲厳禁」は,何としても交戦をさけなくてはならないということが,大前提であった。
10日間の第一回来航以降,十二代将軍家慶の死去,十三代将軍家定即位などの中で,幕府は,「来春」の再来航に備えなくてはならない。
その論点は,
①鎖国という「祖法」を破棄して平和裏に条約を結び開国するか,それとも「祖法」を死守して戦争をも辞さないのか。
②開国して海外の新たな政治・文化・技術などを導入すべきか,それとも旧来の方策に徹して体制を維持すべきか。
③条約の持つ意味をどう考えるか。とくにアヘン戦争の結果である南京条約の締結以降,急速に国際法にのしあがった最恵国待遇(条項)をどう理解するか。言い換えれば,最初にどの国と条約を結ぶのが有利か。
である。幕府は,大きく政策を変え,
①アメリカ大統領国書を回覧,各界からの意見をもとめるよう老中が決断し,
②ロシア使節プチャーチンを長崎で応接し,ペリーの再来航時期まで,交渉引き延ばしを図る。
③大型船の所有・建造の禁止を説くかどうか,老中諮問し,解禁を決める。
④海からの攻撃に備える「海防」策に着手。
等々を決断する。ところが,
「この大型船解禁に関する老中諮問よりも二か月も早い7月24日に阿部(老中首座)は解禁の決意と,それに伴うオランダ商館長への蒸気船購入をきめていた」
という史料があり,老中首座の阿部正弘(伊勢守)は,「諮問の形式をととのえ,解禁に踏み切った」と考えられる,と著者は見る。
そうして,第二回来航に備えた幕府は,四ヶ月に及ぶ日米交渉を行い,日米和親条約締結に至ることになる。その詳細は,本書を読んでいただくに如くはないが,ペリーによる幕府側の応接掛評が残されている。
林大学頭 五十五歳くらい,中背で身だしなみがよく,厳粛でしかも控え目である。高名なレヴァーディ・ジョンソン(上院議員)に似ている。
井戸対馬守 五十歳くらい。背が高く,かなり肥っているが,感じのよい相貌。わがロンドン駐在ブキャナン(のちの大十五代大統領)にどこか似ている。
伊澤美作守 自称四十一歳,五人の中で一番の好男子である。陽気で,冗談や洒落が好き。道楽者との評判。通詞たちによれば,彼は外交交渉については一番自由な考えをもっており,我々にもそうであったが,日本人にも人気があるようだ。我が国の音楽が大好きだと身振りで伝えた。
著者は,最後にこの交渉経過をこうまとめる。
「ペリー艦隊の来航により幕府は大統領国書を受理し,状況を見つつ対応を考え,徐々に体制をととのえていった。1854年2月8日の横浜応接から本格的な交渉に入り,争点が対立する一方で,互いに贈答と招宴を重ね,相互理解を深めた。条約交渉では,幕府がアメリカ側主張の欠陥を見出し,そこを突破口として双務性の主張を行い,最終的に新しい条約を生み出した。
これが可能であったのは,なぜか。老中や応接掛の国際情勢の理解力,対応力,語学力,さらには交渉力などが重要な要点である。」
と,この時期,植民地になるか,戦争に敗れ不平等条約を強いられるか,であった。日本は,交渉を通して,領土割譲も,賠償金もない,条約締結に漕ぎ着けた。
「この幕府の高い外交能力は特筆されてよい」と,著者は言う。今日の日本の外交官が,議論の最中に「シャラップ」と口走る程度の悪さを露呈しているのと比べると,その知性と教養は,群を抜く。そしてこう続ける。
「老中・阿部正弘をはじめ,交渉にあたった林大学頭ほか奉行・与力・同心にいたるまで,交渉相手のペリー一行にたいして格別の偏見も劣等感も抱かず,熟慮し積極的に行動した。外交に不可欠な情報の収集・分析,政策化の三拍子を組織的に駆使し,条約に多くの対等性をもたせることができた。」
と,ところが,わが国ではこれを正しく評価しないまま,百五十年が経過している。その原因は,
「歴史の一国主義的理解が世界史の理解をゆかめたこと」
「ペリーの行動や片言隻句を針小棒大に誤解・曲解し,…資料の収集・批判を軽視してきたこと」
を挙げ,
「あらためて正しい歴史認識の重要性を痛感する。」
と。慰安婦問題一つとっても,都合のいいことのみを取り上げ,不都合なことには耳を閉ざす,議論に負けると,シャラップと,言ってはならない言葉を平気で吐く。一方では,世界中が苛立っているのに,フクシマについて,頬かむりして,あたかもすべて片が付いたかのようにふるまう。日本が,世界からつまはじきにされるのも遠くはない。
参考文献;
加藤祐三『幕末外交と開国』(講談社学術文庫) |
|
最前線 |
|
日本史史料研究会編『信長研究の最前線』を読む。
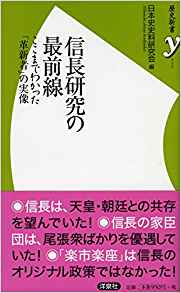
副題に,「ここまでわかった『革命児』の実像」となっているが,14人の競作のせいか,必ずしも理論的な背景が一致していない憾みがあり,旧態依然のイメージから書いている人もあって,結果としては,印象が散漫になった。
「本書は一般の歴史愛好家の方を対象にして,ほかりやすく『現在の信長研究の到達点』を示すべく刊行をけいかくした。」
という。そこで,「第一部 政治権力者としての実像」で,義昭,天皇,官位を扱い,「第二部 信長の軍事的カリスマ」で,桶狭間,長篠,四国政策を扱い,「第三部 信長の経済・文化政策」で,流通・都市政策,宗教を扱う,という流れになっている。
ただ,明智謀反の原因を,あたかも四国政策の変更に起因すると考えているらしい,
「明智光秀は,なぜ本能寺の変を起こしたのか」
のあとに,
「信長は,なぜ四国政策を変更したのか」
を入れることは,この本自体がすでに,それを原因と想定していることを露呈していて,いい感じは持てない。変更していない,とする論文も著書もあり,すこし偏りがすぎ,公平な編集ではない。
しかも,帯にある,「尾張衆ばかりを優遇していた」は,ない。これは,もっともニュートラルで戦国大名研究家の見る信長で,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/390004444.html
で挙げた,池上裕子『織田信長』で強調されていた。そのことは,荒木村重謀叛ともからむ,信長家臣団の構造にも起因することなのに,一本も論文がないばかりか,本文中でも,
「信長家臣団における『勝ち組』『負け組』とは」
でも佐久間信盛にしか言及がない。いささか偏りが過ぎる。
多くは,既に各書で取り上げられている以上の突っ込みはないので,各論文が短いせいもあるかもしれないが,なんとなく上っ面をなぜた感がなくもない。
その中で,気になったのは,
「織田・徳川同盟は強固だったのか」
「信長は,秀吉をどのように重用したのか」
「信長を見限った者たちは,なにを考えていたのか」
の三本だ。
「織田・徳川同盟は強固だったのか」で面白いのは,書札礼から,両者の関係変化を見ていて,三方が原の戦い時点では,既に信長は,家康を家臣と捉え,長篠の合戦では,家康を国衆に位置づけている。そして,
「家康は,武田氏滅亡後,駿河国を信長から与えられ,知行宛行をうけている。それは主従関係になったことを示している。家康にとって信長は,『上様』だったのである。」
それは,同じ信長家臣団に組み込まれたとすれば,家康は,あきらかに,宿老クラスの秀吉より格下ということになる。そういう位置づけを考えてみることで,小牧・長久手の戦での両者の関係も,また別の視界が開けてくるはずである。つまり,家臣団第一位の柴田勝家を倒した後の秀吉の前では,家康が生き残るための手段は,限られていたはずなのである。局地戦の帰趨は,高く自分を売るのにしか使えはしなかった,ということである。
「信長は,秀吉をどのように重用したのか」で,気になったのは,天下統一を信長が考えていなかったのだとすると,どこで,秀吉がそれを意識したのか,ということだ。僕は,四国派兵の段階前後で,信長の思考が変わったのであり,家臣,少なくとも宿老クラスの,秀吉,明智光秀,柴田勝家らは,その変化に気づいていたはずだし,そのことは,家臣団の知行宛行にも大幅な変更をもたらすはずだ。それが,光秀に影響を与えたと,僕は想定している。
ここでは,そうしたことは論旨の埒外なのだが,面白いのは,二つである。ひとつは,秀吉分国である中国地方において,
「分国を統治するうえで,権限の分掌をやこなっており,但馬国では弟の長秀(秀長)を竹田城代,因幡国では与力の宮部継潤を鳥取城代に配置し,それぞれに一国の支配を担当させた。」
さらに,「分国形成にともない,秀吉の『軍団』は『家中』に改編されていった。秀吉の軍事力は,蜂須賀正勝・竹中重治・黒田孝高など,信長から付属された与力によって支えられていたが,天正八年(1580)に秀吉が黒田孝高に宛行状を発給したように,秀吉と与力の関係は封建的主従制に転じようとしていた。」
つまり,家康が信長に対して家臣化したように,信長から秀吉に付属された各与力が,秀吉の家臣化していった,ということである。中国方面の秀吉の力が増すにつれて,摂津茨木の中川清秀,池田恒興も,秀吉の与党化していく。このことが,後の山崎の合戦で,摂津勢が,秀吉側の先方をつとめる伏線にもなっている。
もうひとつは,こうした秀吉の権勢は,信長五男秀勝を養子にしたということも効いている,という。
「秀勝は信長の五男であり,羽柴氏は次代以降に織田一門として遇されうる立場も確保したのである。」
天正九年以降,「長浜領で,秀勝単独による判物・掟書・安堵状も発給されるようになった。まず前線から離れた長浜領において,秀吉から秀勝への権力移譲が先行的に進められた」。
それは,さらに秀勝の成長に合わせ,「軍事行動の指揮権,さらに中国地方の分国の支配権も,秀吉から秀勝に順次委譲していく構想」だったのではないか,と想定している。
その是非は別として,信長葬儀の主催にしても,秀勝がいればこそ,名目が立った。改めて,養子秀勝の存在の持つ意味に焦点を当てたところは,興味深い。
「信長を見限った者たちは,なにを考えていたのか」では,信長から切り捨てられた家臣,見限った家臣が,他の戦国大名に比べて,異様に多いことに着目し,前述の池上裕子氏の,「信長から離反した者はいわゆる外様であった」を挙げているが,これ以上に,尾張閥については,掘り下げられていない。そして,別所長治,荒木村重,松永久秀を例にとって,
「松永久秀・別所長治・荒木村重は,信長の上洛や西国への進出に置いて功績があった。しかし,信長はそれらを無視し,彼らと対立する筒井順慶や浦上宗景,傲慢な羽柴秀吉を登用した。そのため,長治や村重は家臣や与力関係にある国人に対する面目を潰された。そのうえ,信長の目指した政策は,在地の国人や百姓との関係を損なうものであった。」
だから,この三人は,「与力や国人や家臣,百姓に対する支配を信長に脅かされるなかで,自らの将来が見えたからこそ,信長を見限らざるを得なかった」。しかし,外様ではない,「一益・勝家・秀吉は最初から信長の影響下で家臣団を形成し,信長より付けられた与力によって成り立っていたため,信長を見限ることはできなかった」とする。
確かに,その面はあるが,家臣団内部の権力争いでもある。見方を変えれば,家臣団が固定し,既得権化していなかった,というふうにも取れる。それに慣れないものにとっては,結構厳しい自他との戦いを強いられるはずである。
ハンデキャップが大きかったはずの秀吉が,自分ほど家中で,寝る間も惜しんで奉公したものはない,と言っていたことに較べると,この分析は,少し甘い,という気がしてならない。
参考文献;
日本史史料研究会編『信長研究の最前線』(歴史新書y) |
|
勝頼 |
|
平山優『長篠合戦と武田勝頼』を読む。
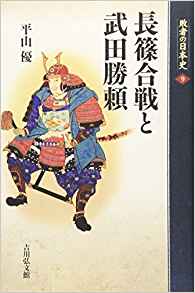
平山優『検証 長篠合戦』の姉妹篇になる。同書については,昨日,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/409358085.html?1416602810
で触れた。本書は,勝頼の出自にかなりのペースを割く。それは,勝頼が背負っているものが,長篠合戦に踏み切る勝頼の決断にかなりの影響を与えているからだと,僕は思う。
従来,長篠合戦は,
旧戦法の武田勝頼対新戦法の織田信長
と評され,それは,
信長軍の三千挺の鉄炮の三段撃ち対武田軍の騎馬戦法
と言われたきた。しかし,そもそも,その「三千挺の鉄炮の三段撃ち」や「騎馬戦法」に疑問だ投げかけられ,近年それが否定されつつある。
一方の武田勝頼評は,変らず散々である。それは,長篠合戦の大敗が,その契機である。で,本書で検討しなければならないのは,
「武田勝頼という人物の生い立ちや政治動向と,長篠合戦の背景を探ること,加えて巷間膾炙される長篠合戦像の成否」
であると,著者は書く。
勝頼は,同時代にどう評価されていたのか。
まずは,武田遺臣が編纂した『甲陽軍鑑』では,
「強すぎたる大将」
と称されている。因みに,「馬鹿なる大将」は今川氏眞,「利口すぎたる大将」は武田義信,「臆病なる大将」は上杉憲政,とされている。それは,
心強く,機転がきき,弁舌明らかで智恵がある,
と称する。しかし,そのために,
心強いために弱気を嫌い,慎重な行動を求める家臣をとうざけ,主君の意を汲むものばかりになる,
という。武田遺臣たちにとって,勝頼は,そういう人物だったということであり,決して「暗愚」ではなかったのである。
また,織田信長は,
「勝頼は信玄の掟を守り,表裏を心得たる恐るべき敵である」
と書状で書いているし,勝頼滅亡後,その首級と対面した際,
「日本にかくれなき弓取りなれ共,運がつきさせ給ひて,かくならせ給ふ物かな」
と,述べたと言われる。上杉謙信も,
「勝頼は片手間であしらえるような対手ではない。信長は,畿内の戦略を一時中断してでもその鋭鋒を防がなくては,ゆゆしき事態を招く」
と,信長に認めている。しかし,
「勝頼が家督を担った十年間は,讒人を登用し,親族の諫言には耳を貸さなかった」
との,穴山梅雪(勝頼の従兄弟)の評もある。で,著者は書く。
「だとすれば,そうした資質の持ち主であった勝頼を後継者に指名した武田信玄の政治判断にこそ,問題の萌芽があった」
し,それが,勝頼の出生以来背負っていた宿命である,と。本書では,
「勝頼が信玄の家督を相続したことが,彼自身に如何なる影響を与え,その思考や行動を規定したか」
を追求しなくてはならない。それが,長篠合戦で,「会戦を回避する選択肢」を選ばす,「あえて決戦を決断した」判断の背景を探ろうと意図している。
武田勝頼,この名に,一つの歴史的背景がある。
「勝頼だけがその諱に武田氏の通字『信』ではなく,諏訪氏の通字『頼』が冠せられている。」
ここに,勝頼の背負っているものが現れている。つまり,
「勝頼は,信玄の息子ではあるが,生まれながらにして諏訪氏を継ぐべき人物とみなされていた…。」
のである。本来継ぐべき義信が信玄との対立で,自害に追い込まれた結果に過ぎない。それだけに,
「武田家当主の地位を,諏訪氏の勝頼が継いだことに対し,複雑な心情をとりわけ甲斐衆がもっていた」
と推測させる逸話が,『甲陽軍鑑』にある。信玄の寄合衆をつためたものが,勝頼の武運長久を祈願して,百日間籠ったところ,霊夢を見て,
「諏方明神 たへる武田の子と生レ 世をつぎてこそ 家をうしなふ」
という歌を聞かされたという。
こうした家中の雰囲気の中で,信玄の死によって,勝頼は家督を継ぐが,信玄の遺言が重い足かせになる。それは,
①勝頼は嫡男武王丸信勝が成人したら,速やかに家督を譲ること(勝頼はそれまでの陣代である),
②勝頼が武田軍を率いるときは,「武田家代々ノ旗」「孫氏ノ旗」など武田家当主を象徴する一切の事物の使用を禁ずる。
③諏訪方法性の兜の着用は認める
というものである。信玄にどんな慮りがあったにせよ,
「この遺言は勝頼に政治的に大きな打撃を与えることになったといえるであろう。それは信玄の意図を超えて,一族,家臣たちの中に,勝頼はあくまで信勝家督までの陣代(中継ぎ)にすぎないという認識を不動の物にしてしまった可能性が高いからである。」
この足枷が,勝頼に,避けられたにもかかわらず決戦へと長篠合戦を決断させたことに影響があったはずである。
「武田家中における権威を名実ともに確立させること,これが勝頼の真意であり,信長,家康を撃破して,父信玄の『3ヶ年の鬱憤』を晴らすことが,自身の『本意』達成でもあり,諏訪勝頼を,武田勝頼に昇格させるもっとも確実な方法だったのであろう。」
と,著者は推測し,
「長篠合戦の敗因は,勝頼と信長・家康との間にだけでなく,勝頼と武田家中の中にも伏在していた」
と,結論づけている。
少し先を急いだ,長篠合戦の争点の中,2つだけ,著者の論点を紹介しておきたい。
まずは騎馬隊について。
結論だけ書くが,軍役定書などをみると,武田,上杉,北条といった東国の軍隊に共通してみられることだが,
「騎馬武者は,『貴賤』(身分)に関わりなく,鎧兜や手蓋,脛楯,指物などを着用した完全武装の出で立ちであった。このことは,騎馬武者だけを一見しただけでは,武田軍では彼らの身分が判然としなかった。」
その他に,
「武田・上杉・北条氏の軍隊には,『一騎相』『一騎合』『一揆相』という身分の低い武士が多数おり,彼らは文字通り騎馬にて参陣した」
さらに,
「『(甲陽)軍鑑』などにしばしば登場する『馬足軽』『馬上足軽』」があり,これは,「家臣たちが軍役定書によって引き連れた家来たちのうち,騎馬の『被官』『忰者』を『馬足軽』と読んだことが想定される。」
だから,
「武田軍では,騎馬武者は侍身分や一騎合衆のような小身の侍などのみで構成されていたわけではなく,被官,忰者,傭兵,軍役衆など,実に多様な身分の人々によって構成されていた」
したがって,
「武田軍には物主指揮下の騎馬武者が多数存在していた」と著者は考える。その例として,岩村衆を挙げる。
「岩村衆は総人数千五百八十余を数え,…鑓六百余本,鉄炮五十余挺,弓四十余張,歩者二百五十余人,馬上五百余騎…,以上のことから,岩村衆は,…騎馬衆は…五百余騎が統括されており,その兵力は岩村衆では,鑓六百余人に次ぐ…。」
つまり,騎馬隊は存在するのであり,だからこそ,
「信長が柵を構築させたのは,単に武田の軍勢を警戒してというだけでなく,騎馬衆にとりわけ注意を払っていたからにほかならない。」
のである。では,待ち構える敵陣への突撃は愚策であったのか。著者は言う。
「(信長の例などをも挙げながら)以上の事例を見ると,鉄炮や弓矢などを装備して待ち構える敵陣に対して,突撃を仕掛ける攻撃法は,当時としては正攻法であった可能性がある。鉄炮があるのに,それをものともしないで突撃を仕掛けたという記録は,意外に多くみられる。武田勝頼が軍勢に攻撃を命じ,武田軍将兵がそれを実行に移したのも,当時としてはごく当然の戦法だったからであろう。武田軍が敗れ去ったのは,織田・徳川の鉄炮装備が,東国戦国大名間で実施された合戦では経験したことのないほどの数量であったことや,敵陣に接近するまでに多くの将兵が戦闘不能に陥り,肉薄して織田・徳川方の鉄炮を沈黙させるに至らなかったことにある。」
そして,だからこそ,「長篠合戦の戦法そのものを批判する記録は一切ない」のだろう,と。
「長篠合戦での武田勝頼の戦法を無謀と捉える一般の考え方は,戦国合戦の正攻法を理解していないことに由来する」
と,著者は言い切る。
次は,三段撃ちである。これも,詳細な論証は省いて,結論だけ取り上げる。
三段撃ちの傍証になるのは,朝鮮の役で,日本軍の鉄炮に苦戦した明軍が,捕虜や投降兵を通じて,導入した,
三段の鉄炮射撃法
を図示している明の『軍器図説』である。では,三列が動いて移動しつつ射撃をしたのか。
「『(長篠合戦図)屏風』には,銃兵が二列に配列されている様子が描かれていた。ところがそれをみると,銃兵の先頭は折り敷き,後列は立射であり,彼らが動いて互いに発射場所を譲り合うような描き方をしていない。これはすなわち,移動を前提とする輪番射撃は,やはり実践では不向きで,採用されていなかったからであろう。実際の輪番射撃とは,三列に配置された銃兵はその場を動かぬことが原則であり,まず最前列だけが折り敷き,戦闘中は決して立ち上がらぬよう指示され,後の二列は交互にずれて立ち位置を決め,同じく動かぬよう命じられていたのではなかろうか。」
と結論づける。火縄銃の連続射撃では不可避の,鉄炮の不発,次弾装填遅れ,銃身内部の残滓の除去,火の再点火などの火縄銃の不備を補うために,信長は,直属の御弓衆によって,脇を固めたのではないか,と著者は推測する。これが,従来の三段撃ちの批判への再批判になっている。。
結局勝頼は,敗退し,多数の重臣を失った。しかし,武田遺臣にとって,これが武田家滅亡の原因とは考えていないらしいのである。
「武田家滅亡の直接の要因となったのは,上杉景勝との甲越同盟締結による北条氏政との甲相同盟破綻と,北条・織田・徳川同盟の成立にあった」
との見方が根強い。しかし,それも,勝頼の政治センスの問題なのかもしれない。かつて,上杉謙信は,
「信玄は,織田・徳川両氏と敵対したということは,あたかも蜂の巣に手を突っ込んだようなもので,せずともよいことを始めてしまった」
と。それは,
「如何に老獪で百戦錬磨の武田信玄であっても,これを収拾するのは容易ではない」
と謙信が認識していたことになる。信玄においてそうなら,ましてや勝頼においておや,であったのかもしれない。しかし,それもまた勝頼にとって,負の遺産であった。
参考文献;
平山優『長篠合戦と武田勝頼』(吉川弘文館) |
|
検証 |
|
平山優『検証 長篠合戦』を読む。
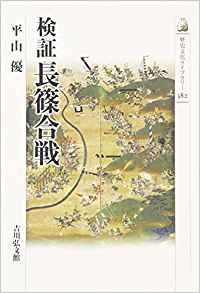
本書は,同じ著者の『長篠合戦と武田勝頼』の姉妹編,というより,同書で漏れた,史料の検証と合戦における両軍の戦力,物量の比較検討部分を独立させている,という。
従来の信長・徳川の三千挺の鉄炮が三段撃ちで,武田騎馬隊を撃破したという通説に対し,三千挺への疑問,三段撃ちへの疑問,騎乗しての戦闘への疑問等々の批判が相次ぎ,通説が揺らいでいる。
本書は,
両軍の鉄炮装備
武田騎馬衆の運用
を詳細に検証し,通説及び通説批判をも,正していく。
まず史料について,
『甫庵信長記』が,慶長十六,七年の初版から寛永元年晩に至るまで,徳川方武士,武田遺臣などの指摘を受けて,記述の改訂,増補を繰り返していた,という事実,つまり同時代人の目の検証を経ている,という意味で,
「あまりにも『甫庵信長記』を貶めてきたのではないか。」
と著者は言う。その意味で,『信長公記』の太田牛一,『甫庵信長記』の小瀬甫庵,それに『三河物語』の大久保忠教も,
「戦国合戦を知る生粋の戦国人である。」
として,同時代の三人の史料は,利用しなくてはならない,といい。「三千挺の鉄炮と三段撃ち」を頭から否定する姿勢ではない。思えば,卓見ではないだろうか。あわせて,いわくつきの,
『甲陽軍鑑』
も,「山本菅助」が実在していたように,またその言葉遣いが,室町時代の古語がふんだんに使われていること,甲斐・信濃の方言が多用されていること等々から,史料として,再評価されていい,と見なす。
こうした史料を背景に,検証を進めていく。
まずは鉄炮及び鉄炮運用について。
「織田信長といえば,鉄炮の大量装備と,その天才的な戦術公案により天下統一へ向けて急成長を遂げたというイメージ」が強いが,ところが,信長と鉄炮についての研究は,少ないし,史料も希少なのだという。それどころか,
「信長自身が発給した文書を調べてみると,鉄炮に関する記載は意外なほど少なく,管見のかぎり,それはわずか一五点を数えるのみで,ここからは信長が大量の鉄炮を装備していた形跡を読み取ることは難しい。むしろ,発給文書における鉄炮関係の記事にかぎっていえば,信長と比較して後進性ばかりが取りざたされる武田氏のほうが,鉄炮の保有を示す記事が登場する時期や文書数も,遥かに彼を凌ぐ。」
という。しかし,『信長公記』を中心に丹念に調べて,いわゆる三段撃ちについて,すでに,天文二十三年(1554)に,今川方の村木城攻めで,信長は敵城の狭間に鉄炮の射撃を集中させたが,そのときに,
鉄炮取りかへ
射撃したという記事が,『信長公記』にある。著者は,
「鉄炮を取り換えながら射撃するのは単なる交代ではなく,銃手はそのままで,後方に控える数人が弾込めをして手渡すという,いわゆる「鳥打ち」「取次」とされる方法」
ではないかとし,この射撃は当時の常識であり,弾込めの時間ロスを補う工夫として早い時期からあった,と見なす。ここに,交代射撃の嚆矢を見ようとする説をたしなめている。
鉄炮隊の編成は,信長の直属の旗本鉄炮衆五百の他,各武将の保持する鉄炮とはわけられており,
「諸手之鉄炮」
という言い方に見られるように,随時各武将から鉄炮放(銃兵)を提出させ,臨時編成する。長篠合戦でも,『信長公記』には,細川藤孝から鉄炮足軽100人,筒井順慶から鉄炮衆50人と,長篠に出陣しなかった武将から強力鉄炮を,参陣している諸将の部隊から鉄炮を引き抜き,臨時に鉄炮衆を編成した。
「織田領国全域(まだ敵勢力が存在したため,必ずしも必ずしも全域を支配下に置いていないところもあるが,それは尾張・美濃・伊勢・近江・越前・若狭・大和・和泉・摂津・河内などに及ぶ)に動員をかけたとすれば,たちまち数多くの鉄炮があつまったことであろう。信長が大量に鉄炮を集めることが可能であった秘密は,武田氏を凌ぐ領国の規模に合ったともいえるだろう。」
として,『甫庵信長記』の,
「兼ねて定め置かれし諸手のぬき鉄炮三千挺」
は,「事実を正確に伝えている」と著者は見る。さらにおもしろいことに,長篠の古戦場で出土した「鉄炮玉の玉目(銃弾の重さを匁で表記したものをいい,大きいほど口径が大きくなる)」から,
「信長が使用した鉄炮の大きさは,実に様々で,決して統一されたものではなかったことがわかる(このことは,信長による大量注文生産にもとづく旗本鉄炮衆や鉄炮衆編成という大方のイメージに再考を迫る事実といえよう)。」
とする。つまり,「諸手抜」の鉄炮,
「つまり,信長の家臣たちが個々に所持していたものを寄せ集めた事情を反映している」
ということを意味する。その鉄砲玉の原産地は,70%が国内,30%が輸入という。戦争激化に伴い,国内だけでは賄いきれなかったことの反映である。
では武田氏はどうかというと,弘治元年(1555)の川中島合戦で,300挺の鉄炮衆の編成をするなど,重要な戦線では重点配備されていた。また陣立て表などをみるかぎり,旗本鉄炮衆があり,加勢の鉄炮衆がありで,基本は,織田と同じく,「諸手抜」で編成されていたことが分かる。
それでは,武田氏と織田・徳川とでは,鉄炮運用において何が違っていたのか。
「それは,鉄炮・魂薬・弾丸の入手,確保の問題に尽きるだろう。」
と著者は見る。
「(武田方が)深刻であったのは,家臣に鉄炮と玉薬を多く準備させようとしても,それが困難であったことが大きい。」
鉄炮を重視しても,畿内やその近国を掌握している信長に比して,入手するのが難しく,敵国である駿河商人を頼ったり,猟師を動員したり村々の所有する鉄炮を召出させたりしていることが,文書などから伺えるという。はては,鉛不足から,
「悪銭を鋳つぶし鉄砲玉への転用に踏み切った」
ことが,文書及び弾の成分分析から,読めるという。つまり,
「武田氏は,玉薬と弾丸の補充に苦慮しつつも,懸命にその不足を克服しようとしていたことは十分に窺い知ることができる。」
だから,上田原の合戦で,武田信玄と戦った村上義清は,鉄炮50挺を投入したものの,一挺につき玉薬と弾丸が三包しかなく,それを撃ち尽くしたら,鉄炮を捨てて斬りこむことになっていた,と『甲陽軍鑑』に出ているそうだが,武田も似た状況ではないか,と著者は見る。
物量の圧倒的差が,武田敗戦の遠因に違いないが,その他に,馬防柵で待ち構える織田・徳川に,無謀に勝頼は突入させた,と通説は言う。
「武田軍の重臣層は,土屋昌続を除き,馬防柵際で戦死した者はほとんどおらず,敗北が決定的となり勝頼が退却を命令した後に戦死している」
という事実から,撤退戦の難しさを示していても,敗戦の結果であって原因ではない。
「武田軍が総崩れになった合戦は,長篠合戦だけである。そして,総崩れになったが故に,武田軍は追撃戦を受け甚大な被害を受けた。」
しかし,著者は,
「不利な条件が重なったにもかかわらず,武田軍の攻勢が早朝より午後二時までの長時間に及んでいたことや,三重の馬防柵をすべて打ち破った場所もあったこと(主力攻撃が実施された徳川軍陣前),鉄炮の弾幕をかいくぐり生き残った武田軍将兵が,少数ながらも徳川軍の陣地に切りこんだとされること,最初の攻撃局面では武田軍が相手を押していた場面もあったことなどを勘案すれば,武田軍は,攻撃目標の徳川軍撃破を目指したが,それを援護する織田軍鉄炮・弓隊を沈黙させられず,もともと寡兵であったがゆえ組織的戦闘の継続が困難となり敗退したわけである。当時の武田氏にとって,織田・徳川軍に匹敵する軍勢召集は,領国規模からいって不可能であった。」
とまとめている。これが彼我の国力差による冷静な分析なのだろう。ただ,特筆すべきは,
「武田軍の将兵は,長篠合戦で織田軍の鉄炮衆に数多くの味方を討たれ,危機的状況に立たされていたにもかかわらず,馬場信春らの指揮官を捨てて決して逃げなかった」
と記録されていることだ。そこには,
「矢玉飛び交うただ中で敵と渡り合うことを『場中の勝負』として称賛し,さらに敵を討ち取ることが出来れば,それを『場中の高名』と呼称し,一番鑓,二番鑓に次ぐ戦功」
とする,勇敢さを誇りとする気風があった,とする。そして,「武田勝頼だけに敗戦彼の責任を負わせること」について,
「そもそもこうした高名の基準と名誉の在り方を確立し,将兵達に浸透させた」
武田信玄その人にまで遡るしかない。領国の限界,領国の貧しさ,将兵の質も含めた,総てを背負った武田氏の負の遺産そのものなのかもしれない,と著者は見ているのである。
最後に,合戦をこう総括する。
「①織田・徳川と武田軍には『兵農分離』と『未分離』という明確な質的差異はなく,ほぼ同質の戦国大名の軍隊であり,
②合戦では,緒戦は双方の鉄炮競合と矢軍が行われ,やがて接近した敵味方は打物戦に移行し,鑓の競合と『鑓脇』の援護による戦闘が続く,
③打物戦では敵が崩れ始めると,騎馬衆が敵陣に突入(『懸入』『乗込』)し,敵陣を混乱させ,最終的に敵を攻め崩す,
④戦国合戦では,柵の構築による野陣・陣城づくりは一般的に行われており,それ自体は特異な作戦ではなかった,
⑤合戦において,柵が敷設されていたり,多勢や優勢な弓・鉄炮が待ち受けていたりしていても,敵陣に突撃するという戦法は,当時はごく当たり前の正攻法であった,」
だから,
「武田勝頼が長篠合戦で採用した作戦は,ごく普通の正攻法であり,鉄炮や弓を制圧し,敵を混乱させて勝利を目指すものであったと考えられる。しかしそれが成功しなかったのは,勝頼や武田軍将兵が経験してきた東国大名との合戦と,織田信長のそれとの違いであったと思われる。それは,織田・徳川軍が装備した鉄炮数と,用意されていた玉薬の分量,さらには軍勢の兵力の圧倒的差という形で表れたと考えられる。」
それがすべてであろう。
なお,姉妹編『長篠合戦と武田勝頼』については,別途紹介したい。
参考文献;
平山優『検証 長篠合戦』(吉川弘文館) |
|
ことば |
|
白井恭弘『ことばの力学』を読む。
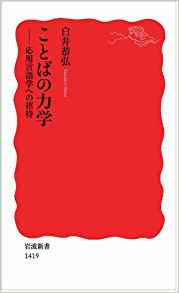
サブタイトルに「応用言語学への招待」とある。応用言語学は,主たる対象が外国語教育であったものが,現実社会のあらゆる場面で重要な役割を果たしている言語についての,「現実社会の問題解決に直接貢献するような言語学」なのだという。
その意味では,実践的なもののはずだが,
「本書で扱われる多くの現象の背後にあるのは,言語とパワー(権力)の関係です。『ことばの力学』というタイトルはその状況を端的に表そうとしたものです。昔から,言語はしばしば,権力を持つ側によって,自分の権力を保持するために使われてきました。たとえば,『美しい英語』というイデオロギーを使って,権力者はそれを話せない者を差別し,自分の正当性を強め,支配してきたわけです。」
だから,たとえば,
「言語が無意識のうちに,私たちの思考や判断に影響を与えるということも,本書の重要なテーマです。同じ現象でもどのようなことばを使って話すかによって,人に与える印象は大きく変わってきます。また私たちは,人がどのようなことばを使うかによって,その話し手に対して知らず知らずにさまざまな印象を持ち,それが私たちの判断に微妙な影響を与え,時には,差別につながることもあります。知らず知らずのうちに無意識の思考に支配されていることを『意識』しておけば,その支配から遁れることができるかもしれません。」
その意味では,本書は,言語についての既成概念や偏見を一つ一つ解きほぐしていく。
たとえば,「科学技術の議論ができない言語がある」という偏見。
「これは『言語そのもの』に問題があるのではなく,科学技術の語彙がその言語にはまだ導入されていないので,英語などの教科書を使った方が(短期的には)早い,というだけのことです。日本でも,江戸時代に初めて西洋の学問が入ってきたときには,同じ問題がありました。オランダ語の医学書を訳した蘭学者の苦心はよく知られています。今では日本語で科学技術を扱うことは出来ない,などと考える人は誰もいません。」
と,そして,「世界の言語はすべて平等」と,言う。
次は,方言。否定的なニュアンスがついてしまっている」が,
「言語学においては,言語のすべての変種が方言と呼ばれます。方言には地域による変種にかぎらず,社会階層や民族集団などによる変種もあります。たとえば,アメリカのアフリカ系アメリカ人(黒人)が話す英語の亜種AAE(African-American
English)は,地域を超えた広がりをみせています。」
で,方言と言語の線引きは難しいのだという。たとえば,
セルビア語とクロアチア語
ノルウェー語とデンマーク語とスウェーデン語
インドネシア語とマレーシア語
は,お互いに意思疎通できるが,別の言語とされている。しかし,津軽弁と薩摩弁では,意思疎通ができないのに,方言とされる。つまり,
「方言も言語も,言語のある種の変種であることに変わりはな」いと考えることが,バイリンガルの問題とつながる。」
もうひとつの偏見に,
「バイリンガルの人は頭が混乱していて,モノリンガルの人のほうが認知的に優れている」
というのがある。だからフィリピンから来た花嫁に,子供とタガログ語で話すことを禁じたりする。しかしこの偏見は,既に覆されている。
「認知心理学の分野では,バイリンガル児のほうがモノリンガル児よりも認知的に優れている,ということが定説になっている。」
「人間の脳は非常に柔軟にできているため,必要な訓練をすれば,それに耐えられるように変化していく…。バイリンガルがモノリンガルに比較して,特に注意をどこにむけるかをコントロールするタスク(課題)に置いて優れていることがわかっています。これは,日常的に二つの言語を処理しなければならないという,いわば脳のトレーニングの帰結だとも言えるでしょう。」
ではなぜ両言語を母国語に近い使いこなしの出来るバイリンガルが育つのか。バイリンガルには,言語知識の容量に限界はないのか。
「ひとつは,『資源の共有』ということです。日本語と英語がまったく別々に習得されるのならば,英語の知識が増えると,日本語の知識が減ってしまうということがあるかもしれませんが,実はかなりの部分で,言語知識は共有されます。ただし,どこがどう共有されるかは,まだはっきりしていません。たとえば,『名詞』という概念は,多少の違いがあっても,ほとんどの言語にあるので,ひとつの言語で『名詞』という概念を習得すれば,もう一つの言語でも容易です。また日本語と韓国語は似ているので,両言語を使うときの脳活動の部位は,日本語との違いが大きい英語や中国語に比べて共通する部分が比較的多いという研究もあります。これは,似ている言語の場合,この『資源の共有』が行われやすい可能性を示唆しています。(中略)脳がふたつの言語を別々に記憶,処理しているのではなく,二つの言語に共通する部分は共有しているため,と考えるのが(ジム)カミンズの二重言語共有説(もしくは,二言語相互依存説)です。主として共有されるのは,日常会話能力(BICS=Basic
Interpersonal Communicative Skills)ではなく,教科など,複雑な内容を扱う学習言語能力(CALP=Congnitive
Academic Language
Proficiency)のほうです。バイリンガルといっても,ただ日常会話ができるレベルと,複雑な内容を議論したり掻いたりというレベルとでは,話が違うのです。これはある意味で納得のいく話で,たとえば,片方の言語で教科書を読む能力を身につければ,もう一つの言語でもかなりの程度その能力が転移するからです。」
「もう一つの理由は,言語習得の方法です。言語習得は,『インプットを理解すること』によっておこると考えられています。インプットとは,言葉を聞いたり読んだりして理解することです。ですから,日本など,外国語によるコミュニケーションの機会の少ないところで勉強すると,言語習得の重要な機会が失われます。」
このことは,方言についても言える。AAE(African-American
English)を,
「英語の方言と見なすのではなく,英語とは別の言語だと考えるエボニクス(Ebonics)という呼び方も使われるようになりました」
というような考え方からすれば,
二言語(方言)併用
ということも,考え方としてありうる。つまり,標準語と方言を並行して学ぶ,という考え方につながる。
「自分の母語(または母方言)に誇りを持ち,時と場合に応じて,使い分けていくことが理想てきです。」
と。それはそのまま手話に通じるのである。手話も,
「立派な自然言語,つまりコミュニケーションの手段として自然に出来上がった言語」
だからである。ただし,「日本語対応手話は,ある意味では日本語をもとに人工的につくられたシステム」なので,ここでいう言語には該当しない。
たとえば,「耳がほとんど聞こえない,音声言語の習得が困難な子ども」の場合,
「まず手話言語(日本手話)で母語を確立することが大切です。そして,さらに幼児期から文字によって日本語に接触させ,手話言語と書き言葉のバイリンガルを目ざせばよいでしょう。」
最後に,認知症だからと言って,言語能力が衰えているのではないということ。このことは,言語能力とは何らを考える例になる。
「知識には,『宣言的知識』と『手続き的知識』があります。前者は何かを事実として知っていて,それについて説明できるような知識(Knowing
what)を指し,後者は,何かのやり方を知っているという知識(Knowing how)を指します。」
だから,意味内容は忘れても,手を動かすことは出来る,ということが起こる。
「言語能力は基本的には,手続き的知識だと言っていいでしょう。……認知的に能力の低下がおこっても,言語能力そのものは変わらない,特に発音,文法などはしっかりしているというケースがふつうです。」
こうした言語知識の二重構造,いつものライルにならえば,
Knowing that
と
Knowing how
となるが,喋れるからと言って,誰もが日本語教師にはなれない,ということである。逆に言えば,
「日本の英語教育では,文法訳読を重視して,宣言的知識ばかり教えているので,使うために必要な手続き的知識が身につかない」
ということになる。応用言語学が,語学教育ににすら,未だ充分適用されていない日本の現状に絶望的になる。教育勅語的な道徳や国家への忠誠心にばかり血道を挙げ,先進国中最下位の教育投資しかしていない日本の未来に,一体誰が責任をとれるのか,と恐ろしくなる。
参考文献;
白井恭弘『ことばの力学』(岩波新書) |
|
天下 |
|
松下浩『織田信長 その虚像と実像』を読む。
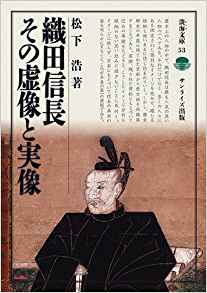
著者は,史実にもとづいて信長の真実の姿を明らかにする,という課題の他に,「近江の中世から近世への過程をたどる」のを第二の課題としている。思えば,元亀の浅井・朝倉との死闘は,近江が舞台であったし,安土城も近江にある。
さて,本書の意図は別にしても,一番の特徴は,信長の目指したものをどう明確にしたかだろう。
まずは「天下」。
既にいろいろ指摘があるように,「天下布武」の天下は,その印文を推した相手,例えば,信玄や謙信や,輝元が「宣戦布告」とは受け取らない意味,つまり,
「天下布武という言葉は,信長の独善的な解釈ではなく,当時の共通した理解の上に成り立っているもの」
とする指摘は当を得ている。
たとえば,越前出陣に際しての手紙で,「今度之儀天下之為,信長為」と使っていたり,上洛出仕命令に,「禁中御修理,武家御用,其外為天下弥静謐」と使っていたり等々,
「当時の用例から,天下とは天皇あるいは将軍を中心とする伝統的社会秩序を内包する社会領域を指す言葉」
であり,
「具体的には京都を中心とする地域を指すと考えられる。」
当然,転化し,全国制覇ではなく,「京都を中心とした朝廷・幕府などの中央政治の再建」といった意味になる。つまり,義輝暗殺後の混迷した状況を,
「信長は義昭を奉じて上洛し,義昭を十五代将軍にすることによって幕府を再興し,中央正字の安定を図ることを目指ししていた」
と考えられるし,そう手紙の相手の戦国大名も受け止めていた,と見なすのが妥当である。だから,
「全国制覇などという荒唐無稽な夢物語」
ではあり得ない。それでは,手紙を見た対手に喧嘩を売っていくことしかならないのだから。
では義昭を追放して以降も,「天下布武」を使い続けるが,その意味はどう変わったのか。
それには,
「いまだ足利義昭が京都にいる段階では天皇−将軍というラインで『天下』成敗の権限が信長に委任されているが,元亀四年(1573)に足利義昭が京都を逐われてからも信長は『天下』という言葉を使用しており,将軍義昭の存在を欠いても信長が『天下』を成敗するという立場をとっている。この場合の論理については,…毛利輝元宛書状案に,『天下被棄置上者,信長令上洛取静候』との文言が見られ,将軍が天下を捨て置くからには,代わって,信長が上洛し,天下静謐を果たすと述べているのである。あくまで将軍の代わりに『天下』を成敗するという姿勢」
である,というところに見ることが出来る。
たとえば,長篠の合戦については,「今度三州敵悉討果,弥天下為静謐候」と述べ,荒木村重征伐に協力するよう指示した中川清秀宛ての朱印状では,「荒木事非我々一人,為天下無道族候」等々の文言に見られる。
著者は,こう書く。
「『天下』とは,あくまで天皇を中心とする世界であり,その平和を乱すものに対する成敗を,信長は自身の戦争の大義名分としているのである。かかる論理は上洛当初から一貫している。変化しているのは,上洛当初は将軍義昭を媒介とし,将軍より委任を受けるという形をとっているのに対し,将軍が京都を逐われてからは,それを自身の果たすべき責務と主張している点であろう。」
そして,その転機は,
「天正三年一一月に右近衛大将に任ぜられた」
ことと推定する。
「右近衛大将は常置の武官の最上位の官職であり,王朝の守護者としての地位にあたる。かかる官職を得たことが,将軍を媒介としない,天下委任の論理を制度上保証したのではないだろうか。」
この論理が,そのまま秀吉に使われていくことを思うと,結構有効な視点なのかもしれない。そうみたとき,同じ年の一一月に,織田家の家督を信忠に譲り,尾張,美濃の領国を譲ったこと,翌天正四年から築城が開始された安土城が,合戦の拠点ではなく,政治シンボルとして,天下人信長の城として,天下を統治する城として築かれ,さらに,直線の大手門,天皇の行幸を想定したこと等々と,つながっていくのである。
それは,逆に言うと,それまでの「天下」とは「天下」の意味が変った,ということなのであり,
「信長が天下統一を具体的に意識し始めるのは自身が天皇との直接結びつきを追求し始める足利義昭を追放して以降であり,さらにいうと天正四年の安土築城開始前後と考えられよう。」
と。その視点から見れば,
「信長の戦いの論理は一貫して天下静謐,すなわち天皇の平和を実現すること」
という名目であったと言っていい。これなら,秀吉の全国制覇,,九州征伐や小田原征伐の大義名分となった惣無事令ともつながる。
最後に近江について,著者は面白い指摘をしている。
「信長は近江の在地社会を温存しつつ,上級支配を展開したのであり,近江の中世を根本的に解体したわけではない。」として,こう述べる。
「近江の中世的在地社会が解体されるのは豊臣政権期,天正十三年の国割を契機としてのことである。豊臣政権のもとで大名権力が国替えを強制されるなか,在地領主たちも主君とともに在地を離れるか,武士を捨てて農民として土着するかの選択をせまられるのである。」
と。しかしである。
「それでも中世近江の自立性が完全に失われることはなかった。江戸時代において,地域支配の末端を担ったのは村落共同体であるが,それは中世の村落自治の伝統を受け継ぐものといえよう。近代においても明治初年の地方支配の再編の中で,大区小区政が採用されず,旧村の系譜を引き継いだ区制が施行された。そして現代において,滋賀県では地方文書が家文書ではなく区有文書として伝わっている地域が多い。地域の『おとな衆』が文書を年番で管理するこういう所有形態は,まさに中世近江の惣村における共有財産の管理システムを想起させる。」
その是非は,置いても,この在地社会のしぶとさには,脱帽である。
参考文献;
松下浩『織田信長 その虚像と実像』(淡海文庫) |
|
信長像 |
|
神田千里『織田信長』を読む。
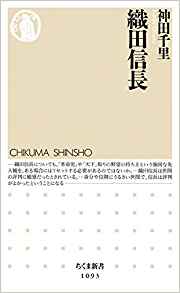
この著者の『島原の乱』には大変お世話になった記憶がある。そんなことで思わず手にした。それと,いくつかの信長本に,神田説の引用もあったことを覚えている。
既に信長については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/406501271.html
http://ppnetwork.seesaa.net/archives/20140828-1.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/400155705.html
等々,何度も触れた。上記の,
金子拓『織田信長〈天下人〉の実像』
にも引用された,神田氏の信長論である。
革命児,
天下統一の野望
等々を,
織田信長観の『箱』
と,著者は呼ぶ。
「様々な学問上の成果の登場にもかかわらず,信長の『箱』は牢固として健在なのが現状である。」
とし,それを,「リセットする」必要がある,とする。で,本書は,
「いままでひろく知られてきた信長像を再検討してみたい。」
として,
第一に,本当に『革命児』であったか,を考えるために当時最大の伝統的権威である将軍や天皇に,どう対処したか,まずは,足利義昭擁立は,「天下を平らげんとする目的でなされたのか,また義昭は傀儡だったのか等々。ついで,天皇や朝廷にどう関わったのか。利用すべき単なるシンボルでしかなかったのかどうか。
第三に,「天下取り」の野望の持ち主であったのかどうか。
第四に,諸宗教勢力にどう対処したのか。
第五に,信長観の「箱」からでてみると,「従来注目されてこなかった」信長の一面を提示したい。
と狙いを挙げ,こう言う。
「歴史上の人物について考えることは,その時代について考えることでもある。この新たな信長像の可能性を通して,これまで注目されてこなかった,この時代の一側面を書きらかにすることが出来れば,望外の幸せである。」
と。将軍との関係については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/406501271.html
で触れたが,要点を触れておくと,
「流浪の身であり,軍事力の上では取るに足りない義昭が,当時の人々の間で…権威を保持していることは,現代人には理解しがたい。しかしそれがこの時代の,否応ない現実であった」
ということを前提にするなら,
「実質的な軍事力は信長側にあることが明白であるにもかかわらず,信長の行為はあくまで,,義昭への『参陣』なのであり,供奉であると,信長も義昭も認識していた」
ということ。
入京の主役は,「公方様の御上洛にただちに供奉する」と信長が書いているように,あくまで足利義昭である。「少なくとも世間への建前として,信長はあくまで,自分は足利義昭の上洛に従うお付の者であると公言」していた立場である。信長,義昭以外の第三者からみても,「この軍事行動の主役が足利義昭その人であった」ということ。
三好三人衆に,義昭が急襲されたとき,信長は,わずか十人前後の騎馬武者だけで,岐阜から駆け付けたが,「この人数では戦力として物の数ではない。独力で三人衆の攻撃を撃退した義昭の軍勢に比べて,ほとんど軍事的な意味はないといってよいであろう。にもかかわらず,信長は,一目散に義昭の許に馳せ参じたのだとすれば,信長の行動は将軍義昭への,命を捨てての忠義を自ら実践し,周囲へもアピールするという意味しかないといってよい。」このとき,尾張,美濃,伊勢,近江,若狭,丹波,摂津,河内,山城,和泉などの諸国から,八万人の武士が,信長上洛の知らせを聞いて上洛した,という。将軍にアピールしたのである。
信長と義昭が不和となったとき,五カ条の規定が作成されたが,一般には,信長が義昭に迫って将軍の実権を獲得し,傀儡化したとする証拠とみられているが,それでは,「なぜ,義昭の天皇や朝廷に対する業務の怠慢を信長はチェックできないのか,諸国の武将らに馬をねだるような御内書を,信長は検閲できなかったのか,信長の許可なしに不適切な論功行賞が成し得たのか,が説明できない」。
越前朝倉討伐は,「上意」による若狭国武藤討伐のためであり,それを背後で操っていたのが朝倉氏と判明したための越前侵攻というのが,「信長の言い分」であり,「姉川合戦も,戦場に足利義昭を迎えて,その上覧の下に行われるはずであった。」また「三好三人衆を討伐すべく行った出陣も,信長,公家衆と奉公衆,美濃衆らがまず出陣し,…足利義昭が出陣している。要するに,信長軍は将軍の軍隊として行動していた。」
朝倉・浅井氏と延暦寺とが和睦をしているが,ほぼ敗勢のなかで信長が和睦できたのは,「足利義昭の力が大きかったことは否めない。当初から義昭と信長との対抗関係を想定して,義昭が朝倉,浅井の蜂起の背後で糸を引いていた,という穿った見方もなくはないが,勘ぐり過ぎだとおもわれる。義昭は信長の後ろ盾として大きな力をもっており,信長にとっては,そうした意味で大事な主君だった。」
信長・義昭が決定的に決裂したのを示すが,「十七条の諫言」であるが,ここで述べているのは,当時の将軍に求められる資格である。「第一に天皇や朝廷に厚く奉仕すること。第二に首都である京都の領主として,家臣や京都住民の信頼にたる存在であること,配下の者への恩賞も処罰も公正なものであるべきこと,そして世間から芳しくない評判を受けるような真似はしないこと,である。」信長は,「義昭に,あなたは家臣や京都住民の尊敬に値する将軍ではない,と宣言したのである。」
信長は,義昭の離反を「御謀反」と表現しているが,その後も何度も,「公方様のなされようは言語道断であるが,君臣の間のことなので」と繰り返し,再三和睦をはかろうとした。「やはり織田信長は将軍の力を必要としていたのだろう。足利義昭に復帰の希望があれば,受け入れてよいとの意向を表明し,さらに義昭復帰が無くなった時点でも,その子供を代役に考えていたことが分かる。言い換えれば可能性のある限り,信長は将軍の臣下として振舞うという立場を追求していたと考えられる。」
そして,こうまとめる。
「実質的には実力で足利義昭を圧倒しているのに,主君を立てると主張しても欺瞞ではないか,と現代人には思えるところである。しかし中世には家来が実力行使により,自分の主張を主君に認めさせることが公然と行われていた。将軍に譲歩を迫るために,幕臣たちが軍勢を率いて将軍御所を包囲する『御所巻』が室町時代には存在した。織田信長が実力で足利義昭を圧倒したとしても,主君を重んじなかったとは必ずしもいえない。むしろ信長は,将軍をあくまで主君として立てる,というカタチで収めかった」
と。この将軍との関係性から伺えるのは,既存の権威をないがしろにしたり,傀儡として利用するというだけではない姿勢である。それは,天皇・朝廷との関係にもうかがえるはずである。
正親町天皇に,譲位を迫ったという言い方をされてきたが,「室町時代にあって,天皇の譲位の儀式は『室町殿』すなわち室町将軍家によってとり行われていた」のであり,応仁の乱以降,幕府の衰微に伴い,将軍家にはそれを行うことが出来ず,後土御門天皇以降,生存中に譲位できず,正親町天皇も,譲位が叶うとは思っていなかったのだろう。信長の申し出で,「後土御門天皇以来,望んではいたが実現しなかったのに,奇特なことであり,朝廷再興の時がきた」と喜んでいた,という。「信長は,足利義昭が将軍の役割を放棄した後に,その代役を買って出たのだと考えられる」。
軍事的威圧と解釈された馬揃えについても,当時の公家には,「お祭り騒ぎ」と受け止められていたし,正親町天皇自身が,「馬揃えの最中に一二人の使者を信長のもとに派遣して,『これほど面白い遊興をみたことはなく,喜びも一方出なかった』との言葉」を伝えており,そうみると,その後,左大臣に任命するとの申し入れに,「織田信長は,譲位の儀をとり行ってから,左大臣を受けたい」と回答したことの意味も,変わってくる。
伝統的権威を重んじる姿勢に鑑みるとき,「天下」の意味が,あらためて問われてくる。これも,すでに明らかにされているが,天下は,全国の意味ではない。
一つは,将軍それ自身,あるいは将軍の管轄する政治などか『天下』の語で表現されている。
二には,京都を含む五畿内(山城,大和,摂津,河内,和泉の諸国)を「日本の君主国」と呼び,その君主を「天下の君主」と呼んだ。
したがって,「天下布武」とは,「正統な将軍の足利義昭の威令が『天下』すなわち五畿内にいきわたること」であり,信長自身,「足利義昭が京都を回復してから『天下』は平和になった」と認識していた。
「天下布武」が,五畿内ということならば,それを越えた,対武田,対毛利,という戦いは,天下統一でないとすれば,何のための戦いなのか。
本書では,対毛利は,織田と毛利の境目戦争であり,対武田は,徳川と武田の境目戦争,と位置づける。
国郡境目相論
という藤木久志氏の説の援用である。境目については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/396352544.html
で取り上げたが,毛利との関係で言うなら,交渉相手であった安国寺恵瓊自身が,
「当毛利家と和睦すれば,平和になるのですから,天下を握っておられる方にとっては上分別というものでしょう」
と評価していた,という点から,毛利を打倒して中国制圧を考えてはいなかった,と著者は見る。ただ,少し疑問なのは,美濃にしろ,伊勢にしろ,近江にしろ,若狭にしろ,丹波にしろ,加賀にしろ,越前にしろ,いずれも以前の戦国大名は,ほぼ壊滅させられている。革命児のイメージから,今度は,余りにも逆に振れ過ぎているのではないか,仮に天下は,当初はそういう意図であったにしろ,どこかで変わったのではないか。でなければ,信長死後,秀吉の全国制覇に,地続きですんなりつながっていかない気がしてならない。
では,結果として,著者は,どんな信長像を提示しているのか。
「我こそ天下人,という野望を前提とする」見方から変えたのは,次のような信長像だ。
義昭が京都出奔後の毛利への手紙に,「将軍家のことは,総ての事について広く評議をおこない」とあるところから,「信長が諸大名との共存をめざし,合議の許天下のありようを決める」と宣言しているとみる。そして,甲斐平定後の天正10年に,関東諸大名に対して,「惣無事令」を発したことをもって,天下人としての将軍の役割である「和睦勧告」を果たそうとしていたとみる。後年,家康が,「信長御在世の時に候ごとく,各々惣無事尤もに候」という,北条に申し入れたのを傍証としている。
世間の慣習を省みず,自由闊達な天才児というよりは,「信長ほど世間の評判に細やかに気を使った人物は滅多にいない」というイメージである。
この点は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/406501271.html
で谷口克広氏も強調していた点だ。例の,十七箇条の諫言にみられる「足利義昭への非難は,恩賞が不適切なために,あるいはその裁定が不当であるために評判を落としている,元号が不吉だとの評判に耳を貸さない,この時節に兵粮米を売り,評判を落としている,宿直の若衆などに依怙贔屓すれば天下の評判はさんざんである,他人の評判をきにしないから『悪い御所』とよばれるのだ,と総て世間の評判を顧ない…!に集中している。」
勝頼が天神城の支援をしないで信濃国の評判を落とし,離反を招くと想定していた信長にとって,世間の不審を招いたのが佐久間信盛らの追放の原因ともしている。
さて,しかし,
「臣下に馬をねだるとは,主君としてみっともないからおやめください」と義昭に諫言した信長の脳裏に,若年の折,平手政秀の諌死を思い描いていた,
とまでいくと,少し,革命児から,逆方向に触れ過ぎの,あまりにも当たり前の信長像に見えてならない。
参考文献;
神田千里『織田信長』(ちくま新書) |
|
日清戦争 |
|
大谷正『日清戦争』を読む。
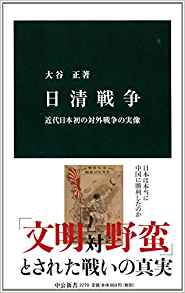
これを読んでいて,不意に頭をよぎったのは,
「そろそろどこかで戦争でも起きてくれないことには,日本経済も立ちゆかなくなってきますなあ。さすがに日本の国土でどんぱちやられたのではたまらないから,私はインドあたりで戦争が起きてくれれば,我が国としては一番有り難い展開になると思ってますよ。」
という発言をしたという,葛西敬之JR東海代表取締役名誉会長のことだ。そういう発想がどこから来るかというと,経営者としての努力ではなく,風が吹けば,といった他力を頼むやり方だ。それを,日清戦争をしたがっていた,軍部と政治家,実業家,ジャーナリストに当てはめるのは,正しいかどうかは知らないが,当初から,清国と戦争をしたがっていた,ということが不思議でならない。少なくとも,
「無理を重ねて開戦に踏み切った」
というのは事実なのだ。当初消極的だった伊藤博文首相も,煽る野党とジャーナリズム,世論に押されて,開戦に踏み切ることになる。この構図は,実は,対米開戦の構図にすごく似ている。似ているのは,
戦闘行為が始まってから宣戦布告した(対米戦は意図的に遅らせたが),
ということと言い,少なくとも,日本の政治,野党,ジャーナリズム,世論が,日清戦争の時を嚆矢として,夜郎自大な国になっていった気がしてならない。
そもそも他国の朝鮮を挟んで,あたかも自国の権益の対象であるように,(朝鮮の宗主国である)清国と競い合い,戦争の火種を捜していたように感じる。この挑戦に対する日本の姿勢は,
琉球
に対する姿勢と近似していたように感じる。強引に,琉球処分をし,(宗主国)清との朝貢関係を断ち切らせたのと同じ論法を,朝鮮に対して使おうとしていたように思える。
開国後,日清の貿易競争によって,外国産綿布の輸入,金地金や米穀・大豆の輸出急増で貧窮化した民衆による,東学農民の蜂起に,朝鮮政府が清への出兵要請したのを受けて,日本もそれに対抗して,(求められてもいないのに)出兵を決定する。しかし,この段階では,
「公使館及び在留邦人保護」
と,目的が限定されたいた。伊藤首相は,
「日清強調を維持しつつ清と交渉を行って朝鮮の内政改革に着手し,朝鮮を清と日本の共通の勢力圏にしようとし,清軍との衝突回避方針」
を取った。しかし,その出兵決定の閣議で,強硬派の陸奥外相は,
「日本も清国に対抗して出兵し,『朝鮮に対する権力の平均を維持する』必要がある」
と述べ,タテマエとは別に,
「閣僚のだれもが出兵の真の目的は朝鮮での清国との覇権抗争にあると理解していた」
のである。したがって,
「陸奥は日清開戦論者として行動し,川上操六参謀次長も開戦準備を進める。」
という状態で,それを煽るように,
「朝鮮への出兵が報道されると,新聞紙上に対清強硬論が掲載され,義勇兵送出の運動も始まった。国民の間で対清強硬論・開戦論が力を増し,開戦論者の背中を押す」
ことになった,という。一方の,清国の対朝鮮政策の責任,李鴻章は,開戦回避を図ったが,国内の主戦論の反対にあって,開戦も回避も,はっきりと意思決定できないまま
「一挙に大軍を送って日本軍を圧倒することで,あるいはまったく派兵しないことで,開戦を回避するという思い切った高等政策をとることができず,政治的・戦略的に拙劣な,小出しに増援部隊を送るという選択肢をとらざるを得なくなる。」
この援軍増派を,日本側は,
「清の対日開戦意図を示したもの」
と受け止め,開戦への扉を開くことになる。そして,豊島沖で,清国海軍と遭遇した日本の巡洋艦群は,発砲し,
豊島沖海戦
が始まることになる。日本側記録では,清国側が発砲して,戦闘が始まったときしているが,著者は,
「イギリスやロシアから,清に対する先制攻撃を控えるようにとの警告があったので,日本側は資料を改竄し,清の先制攻撃による開戦だと強弁した可能性がある」
と述べる。この戦闘は,「宣戦布告あるいは開戦通告以前に」攻撃したのである。これが7月25日。これより前,朝鮮では,「開戦理由を探せ」という陸奥の指示に従い,大鳥公使は,朝鮮政府に,「内政改革の具体的提案」を行っていた。しかし,朝鮮政府は,
「内政改革着手は日本軍撤兵後である,と撤兵を要求した。」
朝鮮の当然の要求に,
「改革の意思がないと判断した大島は,日本軍で応急を包囲して軍事的威嚇によつて要求実現を図る計画を立てた。」
陸奥は,それを容認したが,閣議では異論が出たため,陸奥は,
「正当と認むる手段を執らるべし」
と,曖昧に指示した。現地では,「外相の中止命令を無視して大鳥とすでに漢城にいた大島義昌混成第九旅団長が動」
き始めていた。そして,23日,
「歩兵第二十一連隊長武山秀山中佐が率いた第二大隊と工兵一小隊が,御前五時頃に応急の迎秋門から侵入,警備の挑戦軍と交戦のうえ占領し,国王を拘束した。」
翌二十四日,大院君の下で,新内閣が組閣される。著者は言う,
「後日,不都合な事実は隠され,ここでも歴史の書き換えが行われる。」
と。戦闘が,朝鮮国内と,海上で始まっている。未だ,宣戦布告はなされていない。そして,その宣戦詔書めぐって,紛糾する。
開戦対手国はどの国なのか,
である。
清国一国と戦争するのか,
清および朝鮮と戦争するのか,
しかし,清が先に宣戦上論を出したため,対抗して,
「戦争相手国を『清国』」
とする宣戦詔書が交付される。一体,何のための戦争なのか,誰のための戦争なのか,なぜ,ああも戦争をしたがっていたのか,実のところわからない。そして,結果として,徴兵された国民と,軍夫として徴用された国民が,多く死傷することになる。
当初の作戦方針は,
「黄海・渤海の制海権を掌握し,秋までに陸軍主力を渤海湾北岸に輸送して,首都である北京周辺一帯での直隷決戦を清軍と行う」
という短期決戦であった。しかし艦隊決戦の機はなく,結果として,年をまたぐ長期戦へと変わる。これに似た,甘い見通しの計画が齟齬をきたし,ずるずると現地の状況に引きはずられていくというシチュエーションも,のちに,日中戦争を通して,何度も目撃させられるのと同じことが起きた。
この間,朝鮮では,清国軍の敗走で,日本軍と清国軍との戦いの帰趨が,決しようとしていたが,親日派政権への抵抗が根強く,反日・反開国の第二次農民戦争が起きている。ここで日本軍は,
「できるだけ多くの東学農民を殺す方針」
をとり,川上参謀次長は,
「悉く殺戮せよ」
と命じている。一体何の権限で他国の国民を殺せと命じることができるのか。どういっていいか,その傲慢さは,この後敗戦まで続く。その心性が,またぞろ復活し始めているのは,ひょっとして,国民性なのか?
第二次農民戦争への(日本軍主導の)ジェノサイドによる犠牲者は,3万を優に超え,負傷後の死亡などを加えると,五万に迫る,と言われる。この正確な犠牲者すら分かっていないのである。
中国国内に侵攻した日本軍は,旅順攻撃で,さらに虐殺事件を起こす。ここでは従軍した欧米のジャーナリストと観戦武官が,それを目撃しており,
「11月21日の市街戦と翌日以降の市街の掃討で,日本兵が敗残兵を捕虜にせず無差別に殺害したり,捕虜と民間人を殺害したことを目撃して驚き,これを日本軍による虐殺として非難」
し,さらに開戦詔書で,
「戦争を戦時国際法を遵守して行うことを宣言」
し,世を挙げて,(たとえば,福沢諭吉が)
「文明国である日本と野蛮国である清の戦争」
といい,「文野の戦争」と言っていた日本側の宣伝に,疑問を呈した。
その後,講和全権大使として来日した李鴻章を襲撃したり,割譲された台湾で,それに反対して,独立を期した「台湾民主国」を殲滅していく過程といい,その後の朝鮮での閔妃暗殺といい,総てのやり方が,野蛮で,卑劣で,非人間的で,読み進のが苦痛であった。しかも,平然とその事実を改竄していくことと言い,これ以降,敗戦まで(いや,いまも続いているか)の日本の政治と軍の在り方を,日清戦争の前後で,あからさまに,象徴的に示している。
この事実を,われわれ日本人は,ほとんど知らない。
「大学の歴史学科一年生向け授業で,『第二次農民戦争』『旅順虐殺事件』『台湾民主国』についてアンケートを実施すると,予想した通り正解率は低かった。これらの歴史用語は,韓国や中国の日清戦争に関する歴史教育では必須であるにもかかわらずである。」
このことも,いまの日中韓との歴史認識に深くかかわる。単に,点としての事案(慰安婦とか南京虐殺とかといった)個々の「事件」の認識の差ではない。まさに,この明治以降の日本の東アジアでの在り方,関わり方という,「歴史」の認識の問題なのだ。中韓が「歴史認識」と言っている,この言葉の本当の意味を,僕も含めて,われわれは勘違いしているのではないか,と思い知らされる本である。しかも,これは本当は,単に「歴史」の認識の問題ではなく,「歴史」の事実の是非の問題ではないのか。われわれは,余りにも多くの事実を知らなさすぎる。
参考文献;
大谷正『日清戦争』(中公新書) |
|
パフォーマンス |
|
佐藤綾子『非言語表現の威力』を読む。

どうも,一読の印象は,「パフォーマンス」「パフォーマンス学」という言葉で受けるイメージとは異なって,本書のほとんどは,表現力,つまりは,プレゼンテーションや,スピーチ,コミュニケーションといったところに矮小化されてしまっている気がしてならない。
もともとパフォーマンス学というものが何たるか知らないくせにと言われそうだが,それなら単にコミュニケーション学というはずである。
さて,まあ,閑話休題。
本書の目的は,「最高の自己表現力」を身につけていただくために,
「人間の自己表現の基本的仕組みについて」
「私たちの言葉が相手にどのような構造によって伝わるか」
「『非言語表現』のメッセージ伝達における『自分をどう見せるか』の方法」
「『自分の気持ちをどう言葉で話すか』という『言語表現』の仕組みと技術について」
「好感的対話を続ける方法」
という構成で語られていく。やっぱり,パフォーマンスではなく,あくまで,自己表現らしい。
しかし「パフォーマンスの概念」図を見ると,人生の,
オンステージ
と
バックステージ
にわけ,日常生活を,
舞台
と言い,そこで社会の中での役割を演じる
パフォーマー
として生きている,その背景に,
自己分析のための心理学
言語訓練のためのスピーチ・コミュニケーション学,
自己の演技力養成のための演劇学
が必要といい,さらに,世阿弥の,
我見(自分の目)
離見(観衆の目)
離見の見(最高の自分を見せていく見せる目)
まで持ち出す。しかし,ここで言うパフォーマンスは,結局,
スピーチ
や
プレゼンテーション
や
演説
といった,設えられた(というか特化された)舞台での,魅(見)せる自分の演出ということに尽きるらしいのである。
それはそれでプレゼンテーションやスピーチのスキルとして有効には違いないが,そこに焦点をあてるために,そこでどんなに魅力的なスピーカーでも,その舞台を降りた人生という舞台で,化けの皮が剥がれれば,それは所詮化粧に過ぎないのではないか,という疑問は終始つきまとう。
筆者は,安倍首相のスピーチや五輪のプレゼンを絶賛する。それ自体は否定はしないが,そこで演じられたものが,結局噓であっても,演じたもの勝ちなのであろうか。
どう自分を見せるか,伝えるか,
の重要性を強調し,そのスキルを具体的に説明すればするほど,反面教師として,
安倍首相のスピーチという舞台から降りた,議会での答弁,弁舌,さらにその弁舌の背景にある現実,
を重ねてみるとき,それに欺かれている人もいるだろうが,ここで言うパフォーマンスが,その程度の,
その場でとにかく聴衆を魅了すればいい,
という程度のことだとすれば,それはパフォーマンスではなく,
弁論術
に過ぎない。孔子の言う,
言は必ず信,行は必ず果,
と言っているのは,そんな見せかけのパフォーマンス(悪い意味で「パフォーマンス」というときのニュアンスを思い浮かべればいい)ではないはずだ。本当のパフォーマンスというのは,
人生という舞台で,
担っている役割をどう演じているか,
ということなのではないか。著者が挙げる,
安倍首相のプレゼンテーション,スピーチ,
オバマ大統領のスピーチ,
ヒトラーの演説,
どれをとっても,その場でのパフォーマンスに限定すれば,確かに優れているかもしれない。しかし,その人が,演じている,あるいは演じなくてはならない,
社会的役割
というパフォーマンスと対比しなければ,本当には,その是非,可否の評価は,不十分なのではないか。それがなければ,かつてギリシャの,
議会,法廷,公衆の面前などにおいて,聴衆を魅了・説得する,あるいは押し切るための,実践的な「雄弁術」「弁論術」「説得術」としての,
レトリック,
であり,悪い意味の,
詭弁家
ソフィスト
と同じことを薦めているようにしか見えない。
もし,その程度のパフォーマンスが,「パフォーマンス学」の領域なら,弁論術と言い替えたほうがいい。
ふと思い出すのは,『孟子』の,
恭者は人を侮らず,儉者は人より奪わず,…悪んぞ恭儉と為すを得んや。恭儉は豈声音笑貌を以て為すべけんや。
を思い出す。恭敬でつつましい人という人柄が,見せかけの言葉つきや笑い顔でつくろえるものか,と。しかし,繕えるのだろう。プレゼンで,明らかな噓を真実として押し通したのだから。そう考えて,パフォーマンス学を学びたいと思うか,胡散臭いと,遠ざかるかは,人それぞれ,生き方,価値観次第だろう。その言に勝敗が短期でついても,所詮,と思うのは,僕の選択に過ぎないのだろう。
ところで,著者の言う意味のパフォーマンスの延長で,第一印象を決めるものとして,
アルバート・マレービアン(おなじみの表記だと,アルバート・メラビアンになる)
の,
ヴォーカル38%
ヴィジュアル(著者は,正確には,「フェイシャル」だと訂正している)55%
ヴァーバル7%
を,日本人対象に,自分の新たな集計で,
コトバ8%
声(周辺言語)32%
顔の表情60%
とし,
「人柄は,二秒でわかる」
といい,そのこつを,ズレを見るのだとして,
第一は,表情。表情が表している感情と声の調子のズレ。
第二は,顔の上下が表している感情のズレ。目元と口の周りのギャップ。
第三は,顔の上半分と下半分の筋肉のズレ。
を挙げる。名人芸にはかなわないが,しかし,人は,一瞬で生きているのではない。
パフォーマンス
を,その場,そのときの,スピーチに限定することで,作りあげられるものと,人生という舞台での素とのギャップの方が,僕には大事に見える。焦点を当てている部分が違う,と言われそうだが。
最後に苦言。「パフォーマンス」と「パフォーマンス学」を商標登録しているという。僕は,かつて,「ロジカル・コミュニケーション」という言葉が商標登録されているとして,厳重抗議を受けたことがある。当たり前に使っている「パフォーマンス」という言葉を,商標登録するという神経というか図々しさということ自体に異和感を懐く。自分が造語した言葉でもないのに,登録したもの勝ちののような所業は,この著者の品性を疑わせる。それを,おのれのパフォーマンスで糊塗できるのかどうか,失った人格的信用の前には,感情も理論も効かないというのが,(プレゼンテーションの)LEP(Logos
Pathos Ethos)理論ではなかったのか。
参考文献;
佐藤綾子『非言語表現の威力』(講談社現代新書)
小林勝人訳注『孟子』(岩波文庫) |
|
秀頼 |
|
福田千鶴『豊臣秀頼』を読む。
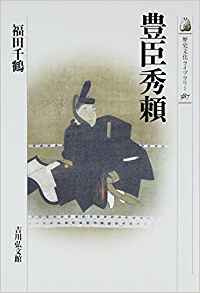
「天下人の血筋を誇りながら,凡庸な性格が豊臣家を滅亡させた」
と言われることが多い,豊臣秀頼に焦点を当てた。
「父は天下人豊臣秀吉。母は戦国大名浅井家に生まれた茶々(淀)。ゆえに,祖母は天下人織田信長の妹市であり,信長は大伯父にあたる。」
血筋から言えば,貴公子である。しかし,過去,彼は,あまり好意的には受け止められてこなかった。
「秀頼の死から四百年となる現在でも,秀頼や生母茶々に対する人々の視線は陰湿で悪意に満ちており,徳川贔屓の江戸っ子でなくとも,凡庸な秀頼と淫乱な悪女茶々の所業によって豊臣氏は自ら滅亡したのであり,自業自得である,というような評価が根強く残っている。」
という著者の,秀頼復権の書である。
大坂夏の陣で,細川忠興は,
「秀頼は大阪小人町近辺まで出陣し,先手は『伊藤丹後・青木民部組中』であった」
と書状で伝えている。この地は,
「徳川方の小笠原秀政・忠脩父子が討死し,弟の忠政…も瀕死の深手を負った激戦区である。物語を辛口で評することで知られる忠興が,激戦区への秀頼の出陣を疑わなかった点は,秀頼が大阪城本丸の奥に隠れて何もしなかった軟弱者であるかのようなイメージを否定する…」
と著者は書く。『大坂御陣覚書』によれば,
「秀頼は,梨子地緋縅の甲冑を着し,天王寺へ出張するため桜御門を出て,父秀吉から相伝した金の切割(縁を切り裂いた幟)二十本,茜の吹貫(吹き流し)十本,玳瑁(鼈甲亀)の千本槍を押し立てて。太平楽と名づけた七寸(約二百十二センチ)の黒馬に梨子地の蔵を置き,引き立てていた。」
という。秀頼は,六尺五寸(百九十七センチ)という大兵だった(『明良洪範』)というので,さぞや見栄えがしたであろう。小柄であった秀吉の,初期の合戦,宇留間(現在の各務ヶ原鵜沼)攻めの時の様子を,『武功夜話』ではこう書く,
木下藤吉郎様の出立は,黒かわの尾張胴,黒鹿毛の馬に跨り,御馬印は麻一枚,薄萌黄,御印は無し。」
と。天下人の御曹司の姿は,天と地と程違う。
「秀頼の教養は,当代一流の学者を招聘して習得し,高められた。慶長二年(1597)五歳の折に早くも『南無天満大自在天神,住吉大明神』の神号を墨書して残しているが,それ以後も『豊国大明神』をはじめ,『龍虎』そのほか多数の筆跡があり,神号仏号・古歌・漢詩だけでも相当な達筆が現存している。和歌・連歌・詩歌・漢詩等をはじめ,貞永式目・憲法・二十二代集・職原抄・禁秘抄・徳失鏡・貞観政要・三略・呉子・四書五経等,法制・文学・儀式・故実・兵学・儒学等に及んだ…。」
もちろん武芸に関しても,
「肥満のために馬にも乗れなかったかのように伝えるものもあるが,天下人を狙う者として,そのような育てられ方はしなかっただろう。事実,弓術の六角義弼,槍術の渡辺内蔵助糺,薙刀・棒・長刀を使う穴沢盛秀,居合術の片山久安が秀頼のそばに仕えており,彼らから『武』に対する教育をうけていたと考えられる。ほかにも,鷹狩・茶道にも親しんでいたことがわかっている。」
そして,十四歳の時,『帝鑑図説』を復刻出版した。
「慶長十一年三月に西笑承兌が寄せた『帝鑑図説』跋文には,『秀頼公が朝夕にこの書を手にして読み,本書の出版を命じたもの』と出版の経緯を説明し,『妙年に及ばずして学に志し,老成人の風規がある』と秀頼の人となりを称賛している。」
これは,家康が,同じ時期に,家康が「伏見版」「駿河版」といわれる政治学の書籍を古活字本として出版していたから,「秀頼版」の出版で,家康に抵抗するという秀頼の意思と同様,『帝鑑図説』が,明王朝で十歳で即位した万暦帝の帝王学教育のために編纂された例になぞらえて,
「為政者として秀頼を立てていく」
ということを表明する秀頼周囲の人々の思惑もあったと,著者は推定する。
こうした秀頼の真骨頂が発揮されるのは,「勢いのある堂々とした書風」と「格調高い気品を感じさせる」家康への書状である。
原文は,
今度若鷹兄鷹
一連弟鷹二聯拜
受被思召寄御懇
意之至難 申尽
別而自愛無比類
存候猶尊顔之時
御礼可令申候
卯月六日 秀頼
大御所御方にて
誰にてもご披露
読み下し分は,
今度,若鷹,兄鷹一連・弟鷹二連を拝受,
思し召し寄せられ,御懇意の至り,
申し尽くし難し,別けて自愛比類なく存じ候
猶尊顔の時,御礼申せしむべく候
恐々謹言
著者は,これは,お礼にかこつけた秀頼の挑戦状と見る。
「書状の形式は,家康の側近に披露を依頼する形式の披露状という丁寧なものだが,子細に見ると,さまざまな書札礼上の工夫がなされているようにみえる。」
として,次のように分析する。
「まず,敬意を示すべき相手の行為を表す用語の前には,一字程度の空白をあける闕字という方法が用いられる。この場合は,家康の好意を示すのは,三行目の『被思召寄』の箇所である。ここに闕字を用いるならば,「被 思召寄」というように,『思』の地の前に一字程度の空白がなければならないが,それがこの書状にはないどころか,意識して詰めて書かれたようにみえる。」
他方,
「秀頼の行為を示す四行目『難申尽』は,『難
申尽』となっていて,心持ち『難』と『申』との間に,闕字があるともないともいえないような微妙な空白がある。さらに六行目には秀頼の行為を示す『存候』があるが,これも五行目の字配りを整えて改行し,自らの行為を示す用語が行頭にくるように工夫されている。行の途中で改行すれば平出という書式になるが,それでは目立ちすぎるので,自然な形で『存候』が行頭に来るように字間を整えたものと考えられる。」
と。表向きは披露という厚礼の形式をとりながらも,
「秀頼自らの行為には敬意を表し,家康の行為には敬意を表さないという書札礼である。…これを一瞥したときの家康の表情はいかばかりだったろうか。」
と,著者は想像する。この文書の意図を詳らかにするには,
「七行目の『御礼可令申候』を『御礼を述べます』と訳したのでは,秀頼の意図を十分に伝えるものとはならない。」
として,
「ここは,『御礼を述べます』ではなく,『御礼します』という,少し広い意味で訳す必要がある。加えて丁寧語の『令』があるので,『御礼をします』を丁寧に訳せば,『御礼を致しましょう』になる。」
とこだわる。それは,
「秀頼と家康の間では,贈答を詳しくみると,そこには互酬関係が成立していないことに気づくからである…。贈答儀礼に関しては,進物を贈られたら相応なものを贈り返すという互酬の関係(両敬)が成立しているかどうかが重要なカギになる。返礼がない場合は片敬であり,返礼をしない側が上位,進物をしただの側が下位に置かれる。」
両者の関係を見ると,たとえば,二条城では両者の互酬関係が成り立つのに,
「大坂城では,家康が派遣した名代に対する互酬の関係は成立しているが,家康が贈った銀子千枚に対する秀頼の返礼が確認できない。」
つまり,大坂城における贈答儀礼には,秀頼は,家康への返礼をしない片敬で対応したのである。この大坂でのやり取りの四日後が,上記の手紙である。
「本来ならば,大坂城への名代派遣や家康の進物に対する礼を述べるべきところだが,そのことには一切触れずに,次回お会いしたときにこちらの御礼を致しましょう,とやり返したのである。」
つまり,
「家康に直接会ったときに返礼すると伝えることで,近く第二戦をいたしましょうとの宣戦布告である。再度の会見で秀頼が家康のもとに出向く可能性がないとはいえないが,返礼をしない秀頼の態度をみる限り,家康が大坂城に挨拶に出向くように求めているようにみえる。」
と。会見を終えた家康は,腹心の本多正純に,
秀頼は賢き人なり
と言ったと言われる。しかし,著者はこう書く。
「ここで秀頼が家康に本気で詰めの勝負に挑む決意をさせてしまい,三年後の大阪冬の陣の引き金を大きく引いてしまったことは,若気の至りとはいえ,爪を隠し通せなかった秀頼の勇み足だったといえなくもない。」
しかし,考えてみれば,家康の裔,徳川慶喜は,鳥羽伏見の敗退を知ると,おのれひとり側近とともに,部下を見捨てて江戸へ逃げ帰った。それに比べれば,秀吉の子,わずか二十一歳の若武者は,父とおのれの名誉は守っているのである。
参考文献;
福田千鶴『豊臣秀頼』(吉川弘文館) |
|
敗者 |
|
渡邊大門『東北の関ヶ原』を読む。

関ヶ原の合戦は,関ヶ原での戦いに焦点が当たり,それ以外の地域での戦いには関心が払われていない。しかし,本書では,主人は,
上杉景勝
そして,
「『直江状』『小山評定』等々の検討を含め,『東北版 関ヶ原合戦』の全貌を明らかにすることにしたい。」
という。圧巻は,直江状の真贋検証である。
越後から会津120万石に移封され,領国整備に余念のない中,上洛をしない景勝は,謀反を疑われる。そんな中での,直江兼続の手紙,いわゆる直江状である。
家康の意向を受けた,西笑承兌(直江兼続とは旧知であり,それ故兼続宛てに手紙を出した)からの手紙への返書である。
西笑承兌の手紙は,景勝の上洛が遅れていることについて,家康が不審に思っており,上方では不穏なうわさが流れている,景勝の神指原の築城,越後河口への箸の構築などを咎め,それについて(兼続が)意見しないのは間違っている,と嗜めた上,以下のとを問うた。
①景勝に謀反のことがなければ,霊社の起請文で申し開きすることが家康の内意である。
②景勝が律儀であることは,家康も承知しているので,釈明が認められれば問題はない。
③近国(上杉に代わって越後に移封された)堀監物が景勝謀叛について報告しているので,きちんと陳謝しなければ釈明は認められない。誠意を見せること。
④この春,加賀の前田利長も謀反を疑われたが,家康の道理によりおさまった。これを教訓にすること。
⑤京都で,増田長盛,大谷吉継がすべてを取次いでいるので,釈明は両氏に伝えること。榊原康政にも伝えるとよい。
⑥景勝上洛が遅いためこのようになったので,一刻も早く上洛すること。
⑦上方で取沙汰されているのは,会津で武器を集めていること,道や橋を造っていることだ。家康が上洛を待っているのは,高麗へ降伏を促す使者を遣わしているからで,降伏しなければ再出兵もありうる,その相談もあるので早く上洛してほしい。
⑧愚僧と貴殿とは数年来親しく付き合ってきましたから,今回のことは笑止と考えています。会津存亡のとき,思案を巡らせることです。
原本はないが,その写しが残っている。直江状は,これへの返書なのである。この直江状が有名なのは,手紙本文の追而書きである。
急いでいるので,一度に申し上げます。家康様または景勝様が下向するとのことですので,すべては下向したときに決着いたしましょう。
とある。これは,
そのときは闘って雌雄を決しましょう
という意味として,家康への挑戦状として受け取られ,家康を挑発している感じであり,これが,
直江状
を世に知らしめた。しかし,
「ただ,追而書は一部の軍記物語や書籍に見られるもので,現在では実際に書かれていたか疑問視されている。」
ものの,肝心の直江状をどうとらえるかは,論争が続いている。その中で,著者は,白峰旬氏に拠りつつ,次のように結論づけた。
①もっとも成立年の早い下郷共済会所蔵文書中の「直江状」(寛永十七年)を用いるべきで,それより新しい写しは,字句の異同や修飾語が付加されている。
②本来の「直江状」は,語調の整わない箇所がある荒削りなものであったが,のちに転写をかさねるうちに美文調に変化していった。
③「直江状」は,西笑承兌書状への返書であり,内容的に照応している。
ということで,信憑性が高い,と見る。そして,
「結論から言えば,『直江状』とは『兼続の家康への大胆不敵な挑戦状』ではなく,『上杉家と堀家の係争の事案に関するものであった』ということになる。」
「つまり,堀氏が上杉氏の動きを報告し,それを一方的に受け入れた家康に対して,上杉氏は釈明をしている」ということになる。そして,「兼続が求めているのは公正な裁定であり,それが受けいれられないならば上洛できないという趣旨」となる。
直江状の時代は,
「書札礼つまり書状の形式・文字などについて規定した書札礼が徹底していた。たとえば,相手の身分(官位や家格など)によって用いる文書を変えるなどである。…当時の人々は,相手の身分を頭に入れながら,礼を失しないように書状を描いた。逆に,書状で用いられる字句や文書がふさわしくないと,偽書(あるいは捏造・改竄)と疑われても致し方ないといえる。」
その意味からみると,直江状に後年手が加えられていることは確かである。
「西笑承兌書状を確認すると,理路整然と順序立てて,兼続に必要な情報を的確に伝達している」のに対して,「直江状」は,何度も同じ釈明を繰り返している。「普通の感覚であれば,相手方の質問に対して,一つひとつ順番に対応する形で応答することだろう。」と疑わしい点は,多々あるが,しかし,
「筆者は原『直江状』なるものが存在し,それにさまざまな文言の修飾や付加がなされ(改竄・捏造というべきか),今に伝わる『直江状』が存在したと考える」。
ただ,
「改竄・捏造という類のものであるのは確かであり,『直江状』…(は)歴史史料としては一次史料同等の価値があるとは考えられず,用いない方が無難なのではないだろうか。」
と結論づけている。
結局景勝は上洛できなかった。家中への手紙で,景勝は,こう言っている。
「今度上洛が実現しなかったのは,第一に家中が無力であったことである。第二に,国の支配のため,秋まで上洛を延期してほしいと奉行衆に回答したところ,重ねて逆心の讒言を信じて,若し上洛のことがなければ,会津を攻撃するとの回答があった。こちらには考えがあるとはいえ,もともと逆心の気持ちはないので,すべてを擲って上洛する気持ちを固めた。あわせて讒人(堀直政)究明のことを申し入れたところ,ただ上洛せよとのことで,それさえ期限を区切って催促するばかりである。上洛はどうしてもできないのである。何通かの起請文は反故にされ,讒人究明もかなわなかった。」
と。結果として,家康は,五万五千を率いて会津攻めに踏み切る。後は,御承知の通り,その期に,石田三成が,上方で挙兵し,急遽西へ戻ることになる。
直江状が話題になるのは,三成との事前密約があることを前提にしている。しかし密約はなかった。そのしるしが,三成の真田昌幸宛ての書状である。
「私(三成)から使者を三人遣わしました。そのうち一人は昌幸が返事を書き次第,案内者を添えて私の方に下してください。残りの二人は,会津(上杉景勝・直江兼続)への書状とともに遣わしているので,昌幸の方から確かな人物を添えて,沼田を越えて会津に向かわせてください。昌幸のところに返事を持って帰ってきたら,案内者を添えて,私まで遣わしてください。」
この冒頭で,挙兵に当たって事前に知らせなかったことを詫びている。
「このような事情を看取すると,この時点で昌幸にさえ西軍決起の情報が届いていなかった様子がうかがえる。」
更に翌月,昌幸宛ての三成の手紙。
「とにかく早々に(昌幸・信繁から)会津に使者を送り,公儀(秀頼)が手ぬかりなく三成と相談していることをお伝えいただきたい。言うまでもないことですが,お国柄もあり,景勝は何かと気になさる方です。しかし,このように昵懇の間柄になれば,さほど気にすることはないので,物腰柔らかく景勝に気にいられるよう申し入れ,成し遂げることです。」
結局関ヶ原での敗北をうけて,景勝は,120万石から30万石に減封され,幕末まで加増されることはなかった。
敗者は,すべての責任を押し付けられる。石田三成,安国寺恵瓊,そして直江兼続もまたしかり。兼続の「直江状」の挑戦的な文面への書き換えは,
「兼続が家康に反抗的でなければ上杉家は没落しなかった」
という恨みが籠っているのかもしれない。
それにしても,敗者には,松浦静山の名言(野村克也氏のというほうが有名かも),
勝ちに不思議の勝ちあり,負けに不思議の負けなし。
が的を射ている。
参考文献;
渡邊大門『東北の関ヶ原』(光文社新書) |
|
思想 |
|
佐藤正英『日本の思想とは何か』を読む。

著者は,冒頭でこう書いた。
「日本の思想は,のっぺらぼうの布筒のようなもので,ときどき流行する思想が,構造化されないままに,雑然と同居している。欧米諸国におけるキリスト教(ヘブライズム+ヘレニズム)に対応する座標軸が見出せない。日本の思想を通底している持続低音は『つぎつぎになりゆくイキホヒ』であって,祭祀の究極の対象は標榜とした時・空の彼方に見失われている,と丸山眞男は説いている(『中世と反逆』)。優れた洞察であるが,日本の思想の一面に過ぎないのではなかろうか。」
と。では,何をここで提示されたのか。
「日本の思想は,否みようのない私たちの思想である。日本の思想を対象化するとは,私たち自身の思想を捉えることでなければならないであろう。」
その通りである。そして,書き手自身の思想が,そこで問われる。
「日本の思想は奥が深い。『古事記』や『古今集』,説経節,小林秀雄などにおいて語られ明かされている日本の思想を捉えかえす」
という。そして,
「本書は,日本の思想に身を置き,日本の思想を基軸にして倫理学を構築することによって,日本の思想を内から捉えることをめざしている。」
と。そして,
「倫理学とは,ひとである生きものであるところの私たちが,ただ生きているのではなく,よくいきようとする衝迫に駆られて,事物や事象,またもう一人の己である他者に出会うありようを,総体として明かし,対象化する」
という。まあ,
いかにいくべきか
を突き詰めて考える,ということに,つづめてしまえばなる。しかし,自己完結させるのではなく,おのれの生きている文脈の中で,それを考えようとすれば,
人はいかにいくべきか,
だけではなく,
この世の中はいかにあるべきか,
この世界はいかにあるべきか,
そのために,
おのれはいかにあるべきか,
に至るほかはない。日本は,周縁の後進国であり,常に,中国の文化圏の中で,そして明治以降は,西欧文明との格闘の中で生きていかざるを得ない。
そのとき,日本の思想という限り,その最先端で,闘ってきた思想が例示されなければならない。しかし,本書にあるのは,
神話から始まって,和歌,仏法,儒学,
と,ただ流れを追っているとしか思えない。そして,その流れを辿るだけでは,
のっぺらぼう
としか印象に残らない。個人的に言えば,尖った思想家はいたはずだ。それを,ただ思想の流れを著述する文脈の中に埋もらせて,顕現させるのを怠っている。思想という限り,しかも『日本の思想』という限り,世界に伍する尖りがいるはずだ。しかし,
伝承としての倫理思想
として,
〈もの〉神の祀り
花鳥風月
仏の絶対知
武士
天
文明
と並べたトピックを見る限り,どこにも尖りがない。たとえば,仏法に絡めて,聖徳太子を挙げているが,十七条の憲法そのものが剽窃の寄せ集めであり,有名な,「和を以て尊しとなす」は,『論語』『礼記』から持ってきているのであり,これを思想の中に取り入れること自体が,いささか,著者の見識を疑う。
逆に,それなら,たとえば,
紫式部
親鸞
荻生徂徠
本居宣長
夏目漱石
と並べてみれば,思想の尖り度が違うはずである。所詮,思想は,個のものである。おのれの,
いかにいくべきか
を突き詰めた果てにしか,思想としての昇華はこない。この著者は,そのぎりぎりと追い詰めていく思想のエッジ,というか断崖の縁が見えていない。
むしろ,こう問うべきだ。我が国に,
世界と拮抗できる思想はどこにあるか,
と。ぼくなら,
親鸞
にまず指を折る。大乗の他力を極限まで突き詰め,ついに,往生のために祈ることを計らいとし,
すべての計らいをてばなし,
「善人なほもて往生をとぐ,いはんや悪人をや。しかるを世の人つねにいはく,『悪人なほ往生す,いかにいはんや善人をや』。この条,一旦そのいはれあるに似たれども,本願他力の意趣にそむけり。」
とまで言い切る,宗教そのものの放棄に至る極限に至りついた。これ程の宗教家は,世界にはいない。
参考文献;
佐藤正英『日本の思想とは何か』(筑摩選書) |
|
妄想 |
|
小路田泰直『卑弥呼と天皇制』を読む。
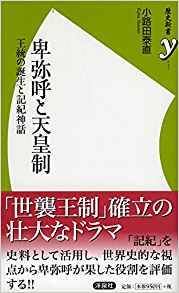
タイトルからして,嫌な予感がした。大和王朝は,卑弥呼の存在を知らない。中国史書からその存在を知って,帳尻を合わせようとして見事に破たんしている。にもかかわらず,両者を地続きとして,構想しているのではないか,と。その予感が,そのまま当たって,どういったらいいか。これだけ妄想を積み重ねると,まあ,一つの物語としても,笑うに笑えない。
著者は,はじめに,こんなエピソードを紹介している。
名だたる考古学者,古代史家のシンポジュームで,素人ながら,一つの質問をしてみた,という。
「なぜ古代日本のの中心(王権の所在地)は奈良にやってきたのか。しかも盆地の南部にと。」
すると会場の空気が一変し,「そんなことわかるわけがない」と嘲笑された,という。しかし,笑った方も笑った方だが,問う方も問う方だ。黄河文明は,なぜ黄河なのか,と問うのに似ているからだ。理由はつけられても,それを確かめようはない。そこにある意味をいくら考えても,その時代の意味には届かない,それだけのことだ。
で,反撥した著者は,その理由らしいことを語っているが,それは興味のある方が,読んでいただけばいい。しかし,それは検証できない。検証できないことは,妄想に過ぎない。
しかし,著者は,冒頭から,妄想(仮説と呼び換えても同じだ。仮説も検証されなければ妄想に過ぎない)を積み重ねる。
『魏志倭人伝』でいう,卑弥呼は,
「鬼道に事え,能く衆を惑わす」
という,その「鬼道」とは,
「一般にはシャーマンとして神に仕える能力のことだとされているが,それは間違いである。祖先に仕える能力のことであった。」
と書く。しかし,「間違い」とする根拠はどこにも示されない。示されないまま,この仮説(妄想)を前提に話を進めてしまう。
「『鬼』とは神のことではなく,祖先のことだからである」
と。その言を証明するつもりなのか,『日本書記』の,倭迹迹日百襲姫(やまとととびももそひめ)を持ち出す。その根拠がよくわからないが,こう説明する。
「『やまとととびももそひめ』を一音だけ改めれば『やまとほととびももそひめ』となる。漢字で書けば,『倭火所火百襲姫』といったところか,天皇の代替わりのことを日嗣というが,そのことを前提にすれば,この名は大和(倭)の王家の火を百台受け継いでいく最初の女王ぐらいの意味になる。血統でつながっていく王家の初代といえば,まさに祖先に仕える能力を手にした最初の王ということになる。」
ここに見られるのは,明らかに,卑弥呼と倭迹迹日百襲姫を同一人としているという,暗黙の前提に立っているとしか見えない。しかし,どこで,それは論証されたのか。
倭迹迹日百襲姫のエピソードを,『日本書紀』から拾ったうえで,
「ということは倭迹迹日百襲姫も,祖先に仕える能力において人並み優れた女性であったということになる。『鬼道に事え,よく衆を惑わ』せた卑弥呼像は,倭迹迹日百襲姫と重なり,それによってより鮮明になるのである。」
と書くが,それは,倭迹迹日百襲姫のことであって,卑弥呼のことではない。にもかかわらず,
「記紀でいうところの崇神天皇の時代(倭迹迹日百襲姫の時代でもある)は,まさに大和王権の国家祭祀の対象が,自然神から祖先神へと移り行く過渡期の時代であったと思われる。その時代の移行を担ったのが,多分,倭迹迹日百襲姫であり,卑弥呼だったのである。
卑弥呼は祖先崇拝の時代を切り開いた最初の王だったのである。」
となり,いつの間にか,倭迹迹日百襲姫について論証したことが,そのまま卑弥呼に当てはめられている。え,卑弥呼は崇神天皇の時代の人なの,と絶句する。
そして,さらに読み進むと,
「社会が身分化すれば,まつるべき神も自然神から祖先神に変更されなければならなかった。自然数しいから祖先崇拝への転換はかくて起こり,卑弥呼=倭迹迹日百襲姫は生まれたのである。」
と,とうとう,卑弥呼=倭迹迹日百襲姫になってしまう。
どうやら,先に結論ありきで,卑弥呼=倭迹迹日百襲姫を前提にして,記紀を読むから,そう見えてくる,ということに他ならない。
記紀を歴史書として読むのはかまわない。しかし,卑弥呼=倭迹迹日百襲姫を前提にして読んだとすれば,それは,史料の読解ではない。論点先取りというか,初めに結論ありきでしかない。
たとえば,倭迹迹日百襲姫の墓と想定される箸墓も,ここでは,そう断定し,しかも,イコール卑弥呼の墓として,話が進められる。
たとえば,倭迹迹日百襲姫は大物主神と結婚したが,神が夜しか現れず,姿を見せないので,朝にも姿を見せ欲しいとせがむ。すると,神は,「吾形にな驚きましぞ」といって,翌朝姫の「櫛笥」のなかに「美麗しき小蛇」となって現れた。それを見て,つい神の戒めも忘れて叫んでしまい,神は,恥じて御諸山に登ってしまった。姫は自分のしたことを恥じて,「箸」で自らの「陰」を突いて死んだ,というエピソードを,
「卑弥呼の行ったことは,結局彼女自身が死ぬことだったのである。自然死ではなく,悲劇的な死を遂げるということだったのである。」
とまとめる。意識的か無意識的か知らないが,倭迹迹日百襲姫を卑弥呼にすりかえている。そして,
「そのために彼女の行ったのが,死後自らのために巨大な前方後円墳を造らせるということだったのである。」
と,箸墓の主は,卑弥呼にすり替わる。まず,箸墓,倭迹迹日百襲姫の墓も推定である。まして,卑弥呼の墓とはまだ到底確定できない。しかし,それをあっさり,すり替えを通して,確定し,いつの間にか,卑弥呼=倭迹迹日百襲姫であるかのように導いていく。そしていう。
「『卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百余歩,徇葬する者,奴婢百余人』…の『径百余歩』の巨大な『冢』は,ほぼ間違いなしに箸墓のことであった。」
と。まあ,ここまで行けば,後は,何を言っても許される。たとえば,こうだ。
「ちなみに,だから箸墓は前方後円墳というあの独特の形をしていたのである。人形をしたあの形は,箸墓建設の目的が亡き卑弥呼の可視化,偶像化であったことの一つの証拠であった。箸墓が,前方後円墳とは言いながら,前方部が末広がりのバチ型をしているのは,卑弥呼が女性だったから,その裳姿を象ったものと思われる。」
妄想もここまでいくと,面白いと言えば,面白いが,これでは嘲笑への反証どころか,嘲笑を重ねられるだけである。
この先にあるのは,記紀を歴史書として見よ,という戦前の復活である。著者はこう書く。
「『古事記』『日本書紀』をもとに,三世紀よりもさらに遡る歴史を描くことも可能なはずである。」
どうやらここが,隠れた狙いらしいのである。その延長にあるのは,紀元節の歴史化である。だから,
「日本は最初から世界文明の形成に参画している。」
と豪語する。いやはや,ここまでいくと,笑ってはいられない。こんなところにまで,夜郎自大が浸透しているのである。
参考文献;
小路田泰直『卑弥呼と天皇制』(歴史新書y) |
|
革命 |
|
松本健一『「孟子」の革命思想と日本』を読む。

冒頭,象徴的な言葉から入る。
「天皇家に姓がいつからなくなったのか。名字がいつからなくなったのか。ひと言でいえば,天皇家は姓を持たないで,姓をあたえる役なのです。」
その姓がないことと,『孟子』の「易姓革命」つまり,王朝の姓が変わり,国が変わる,との関連をみ,さらに日本には,「革命」と言う言葉でなく,「維新」が使われることとの関連につながる。それは,国のありよう自体を左右する。
『孟子』の思想的核心は,「湯武放伐論」にある。
(斉の宣王問いて曰く)「臣にしてその君を弑す,可ならんや。曰く,仁を賊(そこな)う者之を賊と謂い,義を賊う者之を残と謂う,残の人は,之を一夫と謂う,一夫紂を誅せるを聞けるも,未だ君を弑せるを聞かざるなり。」
つまり,「仁義」の徳のない君主は,「一夫」にすぎず,これを討っても,「君を弑する」ことには当たらない,とするのである。だから,孔子の核心が「仁」なら,『孟子』の核心は,「義」である。その考え方の基本は,
「民を貴しとなし,社稷之に次ぎ,君を軽しとなす。是の故に民に得られて天子となり,天子に得られて諸侯となり,諸侯に得られて大夫となる。諸侯社稷を危うくすれば,則ち[其の君を]変(あらた)めて置(た)つ。犠牲既に成(こ)え,粢盛既に潔(きよ)く,祭祀時を以てす。然くにして旱乾水溢あれば,則ち社稷を変(あらた)めて置(た)つ。」
である。民を第一位に置くから,社稷を危うくするなら,天子をも廃す。社稷も,いけにえを供えても旱魃洪水があれば,社稷すら作り変える,と。
因みに,孔子には,
「子路,君に事えんことを問う。子曰く,欺くこと勿れ,而してこれを犯せ。」
とはある。つまり諌めるところまでである。となると,「易姓革命」を避けるには,
「革命を起こさず,王権の秩序を半永久的に維持するためには,どうしたらよいか。王朝が革命の対象とならないためには,王から姓をなくしていく。」
という発想になる,著者は,天武期の藤原不比等のなしたことではないか,と想定している。
「日本では天皇家,それと同時に,支配者であるところの,大君から天皇になった皇室の人々は姓を持たないけれども,その人々というのは姓を与える役割になる。なぜそういう役割になりうるのかというと,これは天つ神の御子だからだという,神格の位置づけにしていく。日本神話により即していえば,高天原から降ってきた,天つ神の子孫であるという定義になる。」
その意味を担っているのが,
天皇
という名づけである。中国では,天子と皇帝とは分けている。
「天子とは天の声を聞く人(多く女),皇帝とはその声を受け取って地上に政治を行う人ですから,本当は二つの,別の存在なのですね。これを一人にしてしまったのが日本で,天子の天と皇帝の皇の地を合わせて,天皇という字,称号をつくったのです。」
『雨月物語』にも出てくるが,『五雑俎』という本に,
「凡そ中国の経書は皆重価を以て之を購う。独り孟子無しと云う。其の書を携へて往く者有れば,舟輒(すなわ)ち覆溺す。此亦一奇事なり。」
と出ていて,『孟子』だけが,日本に伝わらないという伝説が出来上がっている。というよりも,四書五経という以上,伝わっていたが,排除されてきた。しかし,徳川家康が,自分の天下取りを合理化するのに使ったりしているのを見ると,都合が悪いものは巧みに排除してきたということになる。
この辺りに日本という風土文化の,良くも悪くも,特徴がある。しかし,幕末変動期になると,『孟子』は,吉田松陰をはじめとして,蘇ってくる。松蔭は,『孟子』が,君子が,仁と徳とを持たなかったら,王位を奪ってもいい,諌死もいい,国を去ってもいい,と言ったことに対して,「我ガ国今日ニアリテ論ずベキニハ非ザレドモ」と断って,
「易ト去ルト死スルト此ノ三臣アラバ国家亦信ムベシ」
と全面肯定している。でなければ,
「恐れ乍ら,天朝も幕府・吾藩もいらぬ。只六尺の微軀が入用。」
という心映えにはならない。それは,西郷隆盛の山岡鉄舟を評したという,
「命もいらず,名もいらず,官位も金も入らぬ人は,仕末に困るもの也。此の仕末に困る人ならでは,艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。」
という言葉につながる。それは,至誠や義の心映えにつながる。この言葉に続けで,西郷の文章は,『孟子』を引用する。
「孟子に,『天下の廣居に居り,天下の正位に立ち,天下の大道を行ふ。志を得れば民と之に因り,志を得ざれば,独り其道を行ふ。富貴も淫すること能わず,貧賤も移すこと能わず,威武も屈すること能わず』と云ひしは,今仰せられし如きの人物にやと問ひしかば,いかにも其の通り,道に立ちたる人ならでは彼の気象は出ぬなり」
と言っているという。
この「精神(エートス)」は,北一輝へと引き継がれている。
「革命」という言葉を日本は使わず,「維新」と称する。これは,『詩経』に,
「旧邦の周が長くつづしいたのは,その命を『維(こ)れ新た』にしたという言葉が出てくる。」
ところによる。つまり,「古いものや制度を,新たにしていく」,坂本龍馬が,
「今一度せんたくいたし申し候」
と姉に送った手紙の意味になる。しかし,革命(レボリューション)とは言わず,「維新(レストレーション)」というのが,われわれの特徴だが,北一輝は,
「維新革命」
と言い切る。
「維新革命以後の日本は天皇を政治的中心としたる近代的民主国なり」
と。その北が「自分は支那に生まれたら,天子になれたと思うよ」と言ったという。
著者はこう北一輝を評する。
「北の独創性とは,『孟子』の革命思想を利用しながら,『万世一系』神話を形づくった日本も実は中国と同じように朝廷内で宮廷クーデターや王権をめぐっての権力闘争が行われていた,と看破したところでしょう。ただ,日本のばあいは,まず天皇家が姓をなくすことによって易姓革命の可能性を封じたのです。それゆえ,後の覇権者たちは王朝を倒すのではなく,天皇=朝廷をみずからの「権威」として利用するために残しつづけたのです。その,易姓革命を不可能にした日本の支配原理をふまえると,北のばあいも,「天皇ヲ奉ジテ」の軍事クーデターによる『民主革命』方式にならざるをえない,と考えたところに『日本改造法案大綱』の独創性が生まれたわけです。」
今日の中国でも,『孟子』は軽んじられている。しかし,著者は言う。
「欧米や日本から中国には民主主義がないと批判されています。しかし,私の考えでは,民主主義制度がないだけであって,民主思想というのは,二千年前からある。孟子のなかに見事にある。そう考えると,もしかしたら,中国で現体制が倒されるとか,あるいは革命が発動されるときには,また孟子が持ち出されるかもしれないという気がします。」
それは,革命のない国にしてきた日本の尺度では測れない,という気がする。記憶で書くが,確か竹内好(だと思う)が,中国と日本では,時間の感覚が全く違う,と。つまり,あの国は,十年や二十年の単位では測れない,ということだ。多くの日本人が,その点を見誤っている。
参考文献;
松本健一『「孟子」の革命思想と日本』
小林勝人訳注『孟子』(岩波文庫)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫) |
|
江戸イメージ |
|
奥野卓司『江戸〈メディア表象〉論』を読む。
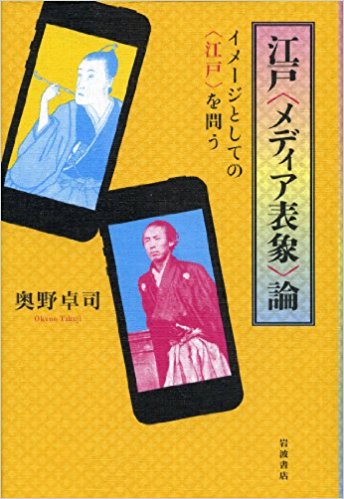
江戸文化ないし江戸ブームについて,著者はこう書く。
(テレビ,映画,芝居,漫画,小説,或いは歌舞伎等々)「これらメディア表象に見られる『発明された伝統』と『編集された歴史』(とここではいったん呼んでおこう)によって,今日のイメージとしての『江戸時代』『江戸文化』はつくられ,人々の間にひろがっているのではないだろうか。」
と。そして,
「これらの〈メディア表象〉によってつくられた『現代の日本人の江戸文化イメージ』を,国内外でのフィールドワークやインタビュー調査によって検証するとともに,その時代時代で江戸時代の文書・図絵・史料が意図的に行われてきた変化のありようを比較することによって解読していこうとするものだ。つまり江戸時代の『史料』の検証ではなく,現代社会における文化行為としての『江戸メディア表象』の変化と,それが現代のわれわれの『江戸時代観』にどのように影響しているかを検討してみたいと思っている。」
と,はじめにで述べる。しかし,結論を先にすると,結論ありきで,書き始められており,論証というよりは,繰り返し,同じタームが繰り返され,いささか辟易した。別に学術論文ではないにしろ,まずメディアの種類ごとに,映画,小説,歌舞伎等々の表現する江戸イメージをきちんと示してほしいし,その比較の中から,どう変わったかを,系統だって示してほしい。でなければ,雑駁なエッセイと変わらない。その意味では,前書きの意気込みに比して,少し肩透かしを食らった感じではある。
よく出るタームで言うと,まずは,
「江戸文化」という物語,
である。人生で過去の見え方は,いまの生き方を反映するのと同様,過去の歴史の見方も,いまの日本のありようを反映する。そんなことは当たり前ではないか。しかし,
「江戸文化ブームを語ることは,江戸時代を語ることではなく,現代社会,とくにそのサブカルチャーを語ることに他ならない。」
「時代の『江戸時代』『近世文化』イメージが,その時代のメディアによる部分的な協調やみたくない部分の削除,つまり『伝統の発明』と『歴史の編集』によってつくられてきたためである。」
と語る時,何をそんなに大袈裟に,と言いたくなる。かつての立川文庫の猿飛佐助や真田十勇士,水戸黄門,あるいは時代劇映画の,いや講談のというほうがいいか,遠山の金さんや,大岡越前,清水次郎長を出すまでもなく,あるいは吉川英治の『宮本武蔵』等々,そのときどきの時代が必要とするところから,作り出されたものに過ぎない。それを,ことごとしく,
「それぞれの時代の語り手が,その時代,時代の価値観で,近世の事柄を語っているのだ。」
と言われても,別に当たり前すぎて,何の感慨も浮かばない。
次のタームは,「鎖国」というものへの疑義。そもそも「鎖国」という言葉は,
「江戸時代に存在したわけではなく,日本を訪れた船医のエンゲルベルト・ケンペルが記述した『日本誌』が後に翻訳されて,その中の表現が誤訳されたものである。ケンペル自身は,むしろ日本の外交政策の巧妙さとして肯定的にドイツ語で記述したのだが,それが後(1727年)に英語に訳されたとき『keep
it
shut』と誤訳された。さらにそれがオランダ語に再度翻訳され,1770年代に日本に入り,1801年(享和元年)になって,元長崎オランダ通詞の志筑忠雄が「鎖国」と誤訳したのである。この誤訳がなされたのが1801年であることからわかるように,江戸時代初期ではない。むしろ日本に対する外国の諸要求が強まってきたとき,それへの防御を正当化するために政治的に誤訳されたものである。」
という。この是非はともかく,本書の趣旨は,鎖国の実態は「海禁政策でしかなく」,長崎,津島,琉球,エゾを通して,大航海時代の世界の情報が入ってきた。したがって,
鎖国が文化を熟成させた
というのは成り立つのか,ということなのである。その狙いは,孤立した「日本」だけが独自に文化を成熟させたというよりは,入ってくる同時代の情報を利用しつつ,作り上げたのではないか,というところに行きつく。
たとえば,京劇と歌舞伎の共通性に着眼し,
「当時の中国本土,琉球,台湾,インドネシア,ベトナム他と,日本との文化伝播・融合の流れを考えれば,歌舞伎と京劇の成立過程において,それらが相互に影響しあいながら,それぞれのスタイルを確立していったと考える方がむしろ自然であろう。さらにこの過程において,歌舞伎では人形浄瑠璃の大きな影響もあった。とすれば,演劇だけではなく,歌舞伎,人形浄瑠璃とアジア各地における人形芝居の流れや民族音楽との絡みも当然考えなければならないはずである。」
それは,次のターム,
当時は大航海時代というグローバリズム
の時代であったということにつながる。たとえば,時計。
「西欧の機械時計は,一日を24時間,一時間を60分と定め,通年で不変なものとして時を刻んでいたが,江戸時代の日本では,昼の長い夏期と短い冬期で時間を調整し,季節に合わせて昼と夜をそれぞれ六等分する不定時法を採用していた。西欧の機械時計が日本に持ち込まれたところ,上方や江戸,名古屋のからくり師たちがこぞってそれを日本の不定時法に利用できるように,さまざまな工夫を凝らし,和時計として改良し実用化した。」
あるいは,カイコの改良の例がある。
「当時農民たちも,稲やカイコがよく育つように,経験的に多様な個体の掛け合わせを繰り返し,新たな品種を数多く生み出していた。そしてその過程で,『養蚕秘録』…などの文書に残されているように,生き物の遺伝に一定の法則性があることを農民が見つけ出していた(当時,西欧においても,メンデルの遺伝法則はまだ確立されていなかった)。」
そういう例があると,「江戸時代の日本は,西欧科学とは異なる,独自の科学技術の発達の道をとっていた」と考えたくなるが,幕府が長崎貿易を統制し,銀の輸出を制約した。銀輸出の対価としての絹糸が日本に入ってこなくなった。その結果,
「絹糸を自国で生産せざるをえなくなった。」
という背景がある。つまり,「閉じてはいなかった」からこそと言いたいようなのである。
しかし,どこに焦点を当てるかで,一つの事実も,違ったように見えてくる。その意味では,江戸時代の何かに焦点を当てるということ自体が,現代の何かを象徴しているのではないか。
「最近では日本の技術の巧みさは,江戸時代の職人から連綿と続く伝統にもとづいているといったことが強引に『論理づけ』られている。その典型が日本の伝統的な技術を応用して建築されたとされる東京スカイツリーの喧伝である。たとえば,伝統的木造建築物である『五重塔』に使われている『心柱』が応用されていると言われる。それは,たしかに当時では優れた技術であったには違いないが,現在の技術からすれば,わざわざ江戸時代の技術に頼らなくても十分高層における風の影響を少なくする構造を設計できたはずだ。」
といい,こう指摘する。
「にもかかわらず,江戸時代の大工の巧みな技をとり入れたということが,さまざまなメディアで一定の説得力をもって語られている。これは,現代の日本の技術が国内外で信頼性を失っていることの逆説的なあらわれである。」
と。これはなかなか卓見ではある。
その意味では,本書の趣旨を,江戸時代のイメージの変遷に,現在のありようを垣間見る,という切り口にしてみた方が,はるかに面白いと,読み終えて初めて気づく。
結論として,著者は,こう書く。
「歴史は『ヒストリー』である以上,人間のつくったストーリー,つまり『物語』である。何が正確な『江戸文化』なのかを延々と論じていても(そうした論争は日常的に行われているが),意味のないことである。つまり,現代社会に生きる私たちの近未来にとって,意味のある『江戸文化』であるかどうかが大切なのだ。今,私たちに課せられているのは,一七世紀,一八世紀のグローバルな『世界』の中での江戸自体の文化を,日本を含む東アジアの観点から相対化していくことだろう。そしてそこから自分の『江戸時代』見出し,自分たちの社会の近未来のあるべき姿を考えることだろう。」
確かに正しい。しかし,ちょっと待って,と言いたくなる。それが本書の最初に,
「現代社会における文化行為としての『江戸メディア表象』の変化と,それが現代のわれわれの『江戸時代観』にどのように影響しているかを検討してみたいと思っている。」
と,狙いを提示していたのではなかったのか。揚げ足取りかもしれないが,一回りして,当初の目的が,これからの課題にすり替わってしまった,という感じである。肩すかしとは,この意味である。
参考文献;
奥野卓司『江戸〈メディア表象〉論』(岩波書店) |
|
怨霊 |
|
山田雄司『怨霊とは何か』を読む。
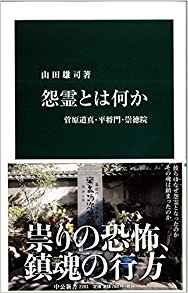
将門の怨霊だの,道真の怨霊だのというのは,過去のことと言いたいが,さに非ず,今日も,我々の心性の中に生きている。大手町の一角の「将門の首塚」は,関東大震災後,その上に大蔵省の仮庁舎が建てられたが,
「しばらくすると大蔵官僚の中で病気となる者が続出し,工事関係者にもけが人や死亡者が相次ぎ,早速整爾大蔵大臣をはじめ二年間に十四人が相次いで死亡し,けが人も多く,特にアキレス腱が切れる者が多かったという。これは将門が足の病のために敗戦の憂き目を見たという故事に関係があるのではないかという噂が広がり,塚の上の庁舎は取り壊されて,昭和三年(1928)三月二十七日に盛大に将門鎮魂祭が行われた…。」
ということでなだめたはずが,その後も「将門の祟り」はつづき,
「昭和十五年六月二十日には都内二十ヶ所あまりで落雷があり,大手町の逓信省航空局をはじめ,付近一帯が延焼した。この年は将門没後千年にあたったことから,庁舎はただちに移転され,一千年祭が挙行され,河田烈大蔵大臣自ら筆をとって古跡保存碑が建立された。」
空襲で焼け野原になった後も,
「GHQのモータープール建設用地として接収され,米軍のブルドーザーによって焼け跡の整地が行われていたところ,ブルドーザーが地表面に突出していた石にぶつかったのが原因で横転し,日本人運転手と作業員の二人がブルドーザーの下敷きになり一名が即死し一名が大けがをした。また,労務者のけが人も絶えなかったこともあり,施行者が調べてみると,ここは将門塚のあった場所で,ブルドーザーがぶつかった石は,塚の石標であったことがわかった。」
そこで町内会長が司令部に塚の由来を説明し,壊さないよう陳情し,塚は残されることになった。
他にも,四谷怪談を歌舞伎や芝居等で上演する前には,お岩様ゆかりの寺や神社にお参りをしないと祟りがあると言われている,という話など,我々の中に生きていることはある。
では怨霊とは何か。著者は,
「怨霊とは死後に落ち着くところのない霊魂であり,それが憑依することにより個人的に祟ることから始まって,疫病・災害などの社会全体にまで被害を及ぼす存在」
と考えられているとし,
「本書では,日本三大怨霊といわれる菅原道真(845〜903),平将門(916〜40),崇徳院(1119〜64)がどのようにして怨霊となって人々を恐怖におとしいれ,さらにはいかなる鎮魂がなされたのか,そして,近世を経てどのように受け継がれて現代に至っているのか,を具体的にあきらかにしていく。」
と,述べている。細部はともかくとして,面白いのは,道真にしろ,崇徳院にしろ,本人は,たとえば,菅原道真は,
「望郷の思いを抱き寂しい生活を嘆きながらも,決して醍醐天皇を怨んだりするようなことはなく,仏教に帰依していた」
し,崇徳院にしろ,
「思ひやれや都はるかにおきつ波立ちへだてたるこころぼそさを,と詠っていても怨念と化す姿勢は窺われない」
という。にもかかわらず,『保元物語』で言うように,筆写した五部大乗経に,舌を噛み切ってその血で大乗経の奥に誓状を書き,諸仏に制約して経を海底に沈めた,というような姿を描き,怨念を煽り立てたのは,陥れた側の後ろめたさもあるが,疫病,天変地異などによる社会の不安定化を反映した不安の投影という面もある。さらに,崇徳院の側に組した側の,つまり敗者の側の,
「崇徳院の復権,さらには自らの復権を行うために,怨霊の存在を語っていった」
という,生臭い理由があり,社会的な不安が,その原因を見つけたがっている心性と重なった,という面もあるに違いない。
こうした怨霊を意識する背景には,
「生命体は肉体の中に霊魂がとどまっていることにより生きている」
という霊魂観がある。
「魂は気のようなものだと考えられていたことから,睡眠中や失神したときには鼻や口から抜け出すことがあった。」
と考えられていて,そのカタチは,『和漢三才図絵』によると,
「人魂はオタマジャクシのような形をしていて,色は青白くてほのかに赤く,静かに空を飛び,落ちたところには小さくて黒い虫がたくさんいる」
という。だから,魂は,ときに生きていても,抜け出す。「生霊」という。では,なぜ怨霊と化すのか。慈円の『愚管抄』には,
「怨霊とは,現実世界において果たせなかった復讐を,冥界において果たすために登場する存在であって,相手を攻撃するだけでなく世の乱れをも引き起こす存在」
と記す。怨霊という言葉自体は,漢訳経典にはなく,中国仏教にはない言葉,つまり日本の仏教者が創り出した言葉であろう,と著者は言う。初見は,『日本後記』に,延暦二十四年(805),廃太子された早良親王の怨霊という言葉がでる。
このとき,これを鎮めたのが興福寺僧善珠。
「善珠は早良の怨霊を調伏したのではなく,仏法を説いて聞かせることによって鎮めたのである。『怨をもって怨に報い』るのでは怨念の連鎖がとどまることがないため,そこからの解脱を説くことによって怨霊をなだめた」,
この善珠の,「呪術的力による調伏」ではなく仏法を説く流れは,最澄・空海を経て,
「怨霊に対して説いて聞かせ,成仏することを願う」
というスタイルが確立した,と著者は言う。しかし,
「室町時代までは,怨霊の存在が信じられて,災異の原因を怨霊に帰結させて国家的対応がとられることも少なくなかった。それと同様に,神社などで発生する『フシギ』な現象すなわち怪異が発生すると,神意を読み解くために朝廷に報告されて,先例が調べられたり,卜占が行われたりして,その対処のために神社で祈祷・奉幣などが行われた。しかし,こうした怪異のシステムも戦国時代にはなくなっていく。
戦国時代を境に神観念は大きく転換した。さまざまな現象の背後に神意の存在を感じ,さらなる災異が起きないように神をなだめるという国家による神々への対応は行われなくなった。それと対照的に,豊臣秀吉,徳川家康といった国家の主導者に神号をあたえて神として祀り,以後傑出した人物が神として祀られる先鞭となった。この現象は,相対的に神の地位が下がることにより人が神になることができるようになるとともに,神に対する崇敬心が希薄になったことを意味しよう。」
と。しかし,我々の中に,いまも,非業な死を遂げた人のために,
「その霊を慰めるために慰霊施設が必ずと言っていいほど建立される。交通事故で亡くなったひとのために,事故のあった場所に仏像が安置されるし,天変地異のために命を落とした人のために,石碑などが建立される。」
ここには,
「外的要因により自らの意思に反して命を奪われた人の慰霊は当然行われなければならない」
という考えが,我々の中にあるということを反映している。それはかつての慰霊がそうであったように,
「関係者の心を整理して慰める行為」
には違いないが,そうしなければ「祟る」という深層心理が根強く残っているともいえる気がする。それは,非命に倒れたものへの慰霊でもあると同時に,残されたものの立命でもあるようだ。
参考文献;
山田雄司『怨霊とは何か』(中公新書) |
|
教える |
|
向後千春『教師のための「教える技術」』を読む。
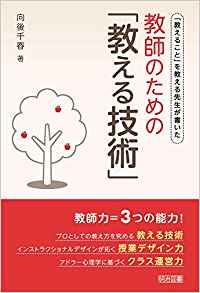
この本は,
「学校の先生や,塾の講師,家庭教師,研修講師といった教えることを仕事にしている人たちのための本」
だそうである。著者の言う通り,確かに,
「『教え方』について真っ向から教えを受けたということがない」
のだ。それでも教職について何とかできるのは,
「学校や塾という枠組みの中で,学ぶ人たちがあなたを『先生』として見ているので,あなたが何をしても,それを『先生からの教え』として捉えている」
おかげであり,それがいったん崩れて,逆回転すると,「教える技術」がないと回復できない,と著者は考え,「教師」つまりプロとしての教える仕事をしている人を想定し,
●教師という役割と立場,つまりプロの仕事して一定水準の品質が期待されていること(失敗が許されないこと)
●大人数を扱うため,クラス運営の技術が必要である
を前提にし,教師力に必要な,
①教える技術
②授業デザイン力
③クラス運営力
三つの能力を身につけていく方法を,本書では展開しようとしている。
と,ここまで書いて,少し気になることがある。閑話休題。
どうでもいいことだが,「能力」という言い方が引っ掛かる。スキルではないのか,ということだ。僕は,能力は,
知識(知っている)×技能(できる)×意欲(その気になる)×発想(何とかする)
だと思っているので,能力は,本で伝えることはできない。なぜなら,やってみようと思うところまでは,伝えられないし,何とかしようと思うところまでは,引っ張ることはできないというか,書き手にはわからない。その意味では,こうやればできる,と思わせる「スキル」の提案なのに,能力と看板を書き換えるのは,羊頭狗肉ではないのか,とちょっと疑問を呈しておく。
ついでながら,Gライルではないが,知識には,
Knowing that(そのことについて知っている)
と
Knowing how(どうやるかを知っている)
の二つがあり,スキルについての知識は,やってみる経験を積まなければKnowing
howは手に入らない。その意味で,上記の能力の要素には,
体験(やったことがある)
や
気力(がんばれる)
や
体力(やり切れる)
も必要なのかもしれない。
さて,ちょっと横道に入りすぎた,本書の紹介に戻る。
まず「教える技術」については,
①運動技能
②知識獲得技能(宣言的知識)
③問題解決能力(手続き的知識)
④学習法略技能
⑤態度技能
を順次具体的に提示されている。それぞれには深入りしないが,これはOJTにも通ずるところが多々ある。必要なのは,教える側が,教える側の土俵(知っているという教壇)に立つのではなく,教わる側の土俵(知らない,やる気がない,わからないという土俵)に一緒に立つということだと感じた。それは,教わる者との協働作業だからにほかならない。その視点で言えば,相手が学ばないのは,共同責任なのである。
「授業デザイン力」は,授業の構想力といっていい。これは,ロバート・ガニエの,
①学習者の注意をひく
②学習の目標を知らせる
③すでに学んだことを思い出させる
④新しい学習内容を提示する
⑤学習のやり方を説明する
⑥練習をさせる
⑦フィードバックを与える
⑧学習成果を評価する
⑨学習したことを他の場面にも活かせるようにうながす
という「9教授事象」をモデルに,使うことを薦めている。さらに,授業に魅力という付加価値をくわえるために,「ARCS動機づけモデル」を提案している。これは,
A(Attention)
R(Relevance)
C(Confidence)
S(Satisfaction)
つまり,引きつけ,自分に関連づけ,自身を持たせ,やってよかったと思わせる,ということになる。
なんとなく,例の,山本五十六の,
やってみせて,言って聞かせて,やらせてみて, ほめてやらねば人は動かじ。
話し合い,耳を傾け,承認し,任せてやらねば,人は育たず。
やっている,姿を感謝で見守って,信頼せねば,人は実らず。
と,マインドとして重なる部分がある。ただ,いまは,山本の上から目線では,だめだと思う。
「わかった?」
とか
「大丈夫?」
とか
という問いかけが,イエスという答えしか実は求めていない(としか相手に受け取られない)のと同じく,相手の土俵の上に一緒に立つことだ,同じ土俵に立てば,こういう問いはしようがないはずである。
クラス運営については,アドラー心理学に拠って,
①タイプ 自分がどういうタイプの教師であるか
②プロセス クラス崩壊は一人の子供の荒れから進展するので,そのプロセスを知ること
③クラス会議をして,相互尊敬と相互信頼の雰囲気を創り出すこと
を提案する。これについては,信頼という土俵が成り立たなければ,すべてのスキルは無効化すると思っているので,日々のおのれの振る舞い,ありようには留意がいるが,しかし,それは,その人の生き方を反映するという気がしてならない。つまり小手先では無理である。
さて,こうして読み通すと,昔,認知心理学や学習心理学を学んだときのことを思い出させてくれる。しかし,あえて苦言を呈したい。
本書には,著者自身が,
「一冊の本の中で扱う内容としては,分量が多すぎたかもしれません。」
というほど,「教える技術」の総覧は提示されている。しかし,提案された「教える技術」を学ぶための手順と,そのためのスモールステップはどこにも提示されていない。さらに言うと,「教える技術」を学ぶための「学習法略」が示されていない。ゴールが高みにあるだけに,「教える技術」を学ぶためのの絶対条件は何か,逆に言うと,それを身につけていなければ,本末転倒となるような,骨格は何かの優先順位,つまり,学習ステップが示されていない。それは,まず何を学び,次に何を学び,そうして,最終的にどうなるのか,の全体ステップの提示でもある。本書のいう「教える技術」に即して,そのガイドラインが欲しいところだ。
参考文献;
向後千春『教師のための「教える技術」』(明治図書)
G・ライル『心の概念』(みすず書房) |
|
捏造 |
|
原田実『江戸しぐさの正体』を読む。

江戸しぐさというのが,社員教育やマナー教育で跋扈している,という。その真偽は知らないが,地下鉄か何かの広告で,こぶしうかせというのを,イラスト入りで見た記憶はある。そのときは,気にも留めなかったが,考えてみたら,椅子などに腰を下ろす,「座る」ではなく,
坐る
のが常態で,あぐらにせよ,正座(これも明治以降生まれたという説がある)にせよ,たとえば,車座になって坐っているところで,こぶしうかせは意味があるとは思えない。
坐
は,
人+人+土
で,人が地上に尻を付けて坐ることを示す。身の丈を縮める意味があるらしい。
座
は,「人+人+土」+广(いえ)
で,本来は,家の中の坐る場所を指す。
さて,本書は,文科省までが,その配布した道徳教材に,
「『江戸しぐさ』が江戸時代に実在した商いの心得」
と明記していることや,それを公民教科書で扱っていることに,危機感を覚え,その正体を暴こうというのが動機のようだ。
最初の提唱者,芝三光の頃は,200位とされた「江戸しぐさ」が,いつの間にか8000とされ,まだまだ増える気配である。それ自体が,すでに胡散臭い。
著者は代表的なものを,いくつか取り上げて,丁寧に反証しているが,たとえば,「傘かしげ」について,疑問を呈している。
ひとつは,傘の普及は,江戸自体後期,傘を差したもの同士がすれちがうシチュエーション自体が,頻繁であったとは思えない。
和傘は,スプリングの入った洋傘に比べ,すぼめたまま手で固定するのが楽な構造になっている。
なにも強引にすれちがわず,一方がすぼめてよければすむ。
江戸の商家や職人の家は,道に面したところに開け広げの土間をつくり,そこを店頭や作業場にしている。そこで「傘かしげ」をやられては,店先がずぶぬれになる。
等々である。現に,傘が普及する以前の庶民の雨具といえば菅笠と簑であり,安藤広重の描いた「大橋あたりの夕立」(「名所江戸百景」)には激しく降る夕立に傘をすぼめて急ぐ町人の姿が生き生きと描かれている。他に,笠と蓑か茣蓙をかぶっている人もいる。
それに,和傘は,
数十本の骨が用いられる。これは洋傘と違い,傘の開き方が,竹の力により骨と張られた和紙を支える仕組みとなっているため,すぼめた際に和紙の部分が自動的に内側に畳み込まれる。その上,自然素材を多用した結果,洋傘に比べて重い。
という。どうも,洋傘をイメージした「しぐさ」ではないか。あるいは,電車にも広告の出ていた,「こぶし腰うかせ」については,「江戸しぐさ」には,こうある。
「川の渡し場で,乗合舟の客たちが船の出るのをまっているとき,後から乗ってきた新しい客のために,腰かけている先客の2〜3人は,腰の両側にこぶしをついて,軽く腰をうかせ,少しずつ幅を詰めながら,一人分の空間をつくる…。」
しかし,しかし狭い渡し船でそんなことをするよりは,いったん腰を上げたほうが早い。だから,茶店のイラストが使われる。どう見ても,市電かなにかのに長いシートでの席の譲り合いのイメージであり,江戸という時代の生活臭がしない。だから,
「『江戸しぐさ』は盛んに江戸時代を称揚するが,それらはいずれも現代的な常識に彩られたもの」
と著者が言うのはもっともだ。生前,提案者の芝は,「江戸しぐさ」は,
「芝の造語」
と言っていたらしいが,いつのまにか,横浜生まれの芝が,
「私の子供の頃,『江戸しぐさ』という言葉は年中耳にしたものでございます。半世紀前までは『江戸しぐさ』が生きておりました」
と言ったことになる。その詐術が,単なるマナー運動にとどまるうちはいいが,安倍政権の後ろだてを得て,学校教育に浸透し始め,「江戸しぐさ」が権威を持ち(イデオロギー化するということだ),禁止されているものとして,
「戸閉め言葉」
「ちょうな(手斧)言葉」
「水掛け言葉」
などを「逆(さか)らいしぐさ」として挙げはじめたとき,すでにそれは,「敵性用語」的になる危険が,確かにある。
「戸閉め言葉」とは,でも,だって,しかし,そんなこと言っても,と相手の言葉を遮る言葉,
「ちょうな言葉」とは,手斧で叩き斬るような乱暴な言葉,
「水かけ言葉」とは,それがどうしたの,と相手の気分に水をかける言葉,
という。それは,相手への反論をしたり疑問を呈することを封じるものである。そのまま,今日の政府の問答無用の振る舞いに近い。単なるマナー運動と見過ごすには,ちょっときな臭さを覚える。
そもそも「しぐさ」という言葉が,いつからあったのか,と調べてみたが,
「シ(為・サ変動詞スルの連用形)+クサ(物事の種)
と,語源はあるが,来歴がわからない。で,手持ちの古語辞典には,しぐさはなかった。『大言海』は,
しぐさ 「仕種」をあて,テダテ,シカタ,シウチ
しぐさ 「科」をあて,所作,ミブリ
と区別してあげる。それ以上はわからなかったから,ここからは,妄想に近いが,
しぐさ
という言葉を使ったこと自体で,既に馬脚を現している気がする。たぶん,「仕種」が古い。そこにあるのは,テダテ,
の意である。身振りには,古くは,所作という言葉を使ったのではないか。
それに,商人というなら,ナニワではないのか。なぜ,「ナニワしぐさ」ではないのか。なぜ「江戸」にこだわったのか。たとえば,奥野卓司氏は,
「『江戸文化』は江戸時代という期間のなかでの,日本各地の文化のことであるはずだが,いつの間にか江戸という一都市の文化にすりかえられてしまっている。少なくともその前半は,上方,西日本のほうが,江戸よりも先進的で高度な文化的成熟がみられたはずなのだが,…『江戸文化』に関する本でも,『江戸文化』は『江戸の文化』という先入観を与えるように書かれている場合が多い。」
という。「江戸しぐさ」もその系列であるというより,意識的にそうしている。
「彼が生きた時代の歴史観から『江戸文化』を記述して」いる,と著者は想定している。この辺りは,もう少し掘り下げる必要があるだろう。本書が,その端緒となってくれるといいのだが,なにせ,
噓も繰り返せば真実になる,
というナチのやり口をまねると公言してはばからぬ為政者の下なので,気味が悪いというより,恐怖が先に立つ。
参考文献;
原田実『江戸しぐさの正体』(星海社新書)
大槻文彦編『大言海』(冨山房)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
奥野卓司『江戸〈メディア表象〉論』(岩波書店) |
|
起源 |
|
岡谷公二『神社の起源と古代朝鮮』を読む。

神社を訪ね歩きながら,新羅の影を探るという趣旨の本だけに,直截,論究するのを期待すると,ちょっとまだるっこしい。しかし,状況証拠を積み上げていくうちに,新羅の影が,色濃いものになっていくところがある。
著者は,谷川健一氏の強い影響を受けているらしいことは,かつて,谷川氏の『青銅の神の足跡』などの本を読んだことのあるものには,蹈鞴,鞴,といった製鉄の跡を追いかけていた影と重なるものがあり,あれもまた渡来系の足跡をたどるものだったことを思い出させてくれた。
著者は,本書の動機を,金達寿氏の,
「神社も神宮も新羅から入ってきたのです」
の言葉に対し,
「神社を日本固有のものと信じている多くの日本人は,驚きや,強い反発,異和感を覚えるであろう。金氏は韓国人だから,そこに我田引水の匂いをかぐ人もいるだろう。しかし私は今,この言葉は多くの真実を含んでいると思っている。神社の成り立ちに,古代朝鮮,とりわけ新羅−伽那の地域が或る役割を果たしたことだけは断言できる。私たちにとってもっとも身近な神社であるお稲荷さんや八幡様が,最初渡来人の祀った神であったことは,すでに多くの人によって論じられている。…本書は,金氏の言葉を内側から検証しようとしたこころみである。」
と述べている。司馬遼太郎も,かつて,
「新羅人は,…日本の原始神道と相通じる神を持っています」
という言い方をしていたが,本書は,
「日本の原神道と朝鮮の古代の信仰との間の密接な関係」
を探るための,旅となっている。
ただ,「日本の原神道と朝鮮の古代の信仰との間の密接な関係」を朝鮮側にたずねるのは,なかなか難しい。
「日本の神社に相当する聖地は,朝鮮半島では,山神堂,ソナン堂,コルメギ堂,堂山などともよばれる堂(タン)だが,仏教,儒教をそれぞれ国教とした高麗,李氏朝鮮の下で弾圧,或いは排除されて消滅するか,儒教化してしまって,日本の『延喜式』に当たるような文献も皆無にひとしく,その古代でのありようは把握できない。」
のだから,という。さらに,国内も,「古代の一時期からはじまった新羅蕃国視,明治以降の朝鮮蔑視から,白木,白城,白井,白国,白鬚などと名前を変えたところが多かった」という。しかし,それでも,「新羅神社と名乗る神社は全国に数多く」,
「日本で最も数の多い神社のそれぞれの一つである八幡神社,稲荷神社が,元来は新羅系の秦氏が祀った神社」
であり,新羅の影響は広く,深く,大きい。新羅の痕跡を尋ねるには,
渡来系の氏族を尋ねる方法
製鉄の軌跡を訪ねる方法
記紀などの神話から尋ねる方法
神社の由来・名前から尋ねる方法
等々が,素人なりに,思い浮かぶが,本書でも,それをいくつか試みている。そして,それが重なっていくのが,印象深い。
たとえば,天日槍(あめのひぼこ)。
天日槍は,記紀などに登場するが,例えば,『日本書紀』では,
「新羅の王の子天日槍来帰り。将(も)て来る物は,羽太の玉一箇・足高の玉一箇・鵜鹿鹿の赤石の玉一箇・出石の小刀一口・出石の矛一枝・日鏡一面・熊の神籬一具,幷せて七物あり。即ち但馬国に蔵めて,常に神の物とす。一に曰く,初め天日槍,艇に乗りて播磨国に泊まりて,宍粟邑に在り,時に天皇,三輪君が祖大友主と,倭直の祖長尾市とを播磨に遣わして,天日槍を問わしめて曰く,『汝は誰人ぞ,且,何れの国の人ぞ』とのたまふ。天日槍対へて曰さく,『僕は新羅国の王の子なり。然れども日本国に聖皇有すと聞りて,即ち己が国を以て弟知古に授けて化帰り』とまうす。仍りて貢献る物は,葉細の珠・足高の珠・鵜鹿鹿の赤石の珠・出石の刀子・出石の槍・日鏡・熊神籬(ひもろぎ)・膽狭浅の大刀,幷せて八物なり。仍りて天日槍に詔して曰はく,『播磨国の宍粟邑と,淡路島の出浅邑と,是二の邑は,汝任意のままに居れ』とのたまふ。時に天日槍,啓して曰さく,『臣が住まむ処は,若し天恩を垂れて,臣が情の願しき地を聴したまはば,臣親ら諸国を歴り視て,則臣が心に合へるを給はらむと欲ふ』とまうす。乃ち聴したまふ。是に天日槍,兎道河より沂りて,北近江国の吾名邑に入りて暫く住む。復更近江より若狭国を経て,西但馬国に到りて,則ち住処を定む。是を以て,近江国の鏡村の谷の陶人は,天日槍の従人なり。故,天日槍の出嶋の人太耳が女麻多鳥を娶りて,但馬諸助を生む。諸助,但馬日楢杵を生む。日楢杵,清彦を生む。清彦,田道間守を生むといふ。」
とある。『古事記』では,「昔,新羅の国主の子有りき。名は天之日矛と謂いき。」として,不思議な逸話を載せている。
新羅の阿具奴摩という沼野ほとりであるいやしい女が昼寝していると,日が虹のように輝いて,その陰上をさし,このときから妊んで赤玉を生んだ。それをうかがっていた男は,その赤玉を女から乞いうけ,腰につけていた。この男が谷の田を作っている人々の食料を牛の背に乗せて谷に入ってきたところ天之日矛にあった。天之日矛は,男が牛を殺して食べるのではないかと疑って,捉えようとしたので,男は,赤玉を贈って,許してもらった。天之日矛は,玉を持ち帰って床のあたりに置くと,美しい女と化したので,婚して妻とした。妻は種々の美味佳肴を作ってもてなしたが,男は奢って,妻に罵言を吐いたところ,女は,「凡そ吾は,汝の妻なるべき女に非ず。吾が祖の国にいかむ」といって,小舟に乗って逃げて難波に留まった。それを追った天之日矛は,難波で渡しの神にとどめられ,やむなく但馬に住んだ。
天之日矛の子孫を,田道間守らを挙げた後,天之日矛が持ってきた宝を,「珠二貫,又浪振る比礼…浪切る比礼,風振る比礼,風切る比礼,又奥津鏡,辺津鏡」の八種を挙げる。
この『古事記』の逸話と同じ話が,書記では,天日槍渡来の生地の直前に,「意富加羅(おほから)の王の子,名は都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)。…伝に日本国に聖皇有すと聞りて,帰化く」とある。
『日本書記』と『古事記』では,天日槍の渡来の時期も,動機も異なるが,天日槍に関連することは,『筑前風土記』『摂津風土記』『新撰姓氏録』『古語拾遺』等々にも出てくる。著者は,
「それゆえ彼の渡来は,古代にあって広く知られた伝承であり,決して無稽な作り話ではなく,なんらかの事実を反映している…」
し,天日槍が,「個人ではなく,集団であろう」というのが,大方の見方と指摘する。『新撰姓氏録』には,
「『新羅国王子天日矛命之後也』として三宅連,糸井連,橘守が挙げられているのに対し,『出自任那国人都怒我阿羅斯止也』として,大市首,道田連,辟田首の三つの氏族があげられている」
という,といったところから考えれば,「弥生時代以降,朝鮮半島から人々が波状をなして渡ってきた」記憶の名残りとして考えられる。
この天日槍から,いくつかの説がある。
天日槍の逸話は,新羅の創世神話に似ている。
「アメは,…朝鮮の意味であり,…立派な武器と宝物を持って行った人々を指す」(金錫亨)
天は「海」であり,挙げる八種は,航海の安全を期するための呪物であり,天日槍の裔とされる三宅連が公海に関連した氏族であり,天日槍の集団は海と深いつながりがある。(上田正昭)
現に,新羅人は航海を好み,その造船技術は優れていて遣唐使として唐に渡った人は,帰途新羅の船に乗りたがったという。
天日槍が巡歴したコースに残る地名とそれにまつわる伝承,その周辺の鉱山や砂鉄の採取場の遺跡などから,天日槍の集団が,金属精錬の集団である。(谷川健一)
「此の御世に,始めて弓・矢・刀を以て神祇を祭る。更に神地・神戸を定む。又,新羅の王子,海檜檜来帰り,今但馬国出石郡に在りて大きな社と為れり。」(『古語拾遺』)
この記事の後に,倭姫命をして初めて伊勢に神を祀らせたとの記事があり,これについて,
「天日槍の渡来が,神社の成り立ちやその祭祀に在る役割を果たしたことを,(『古語拾遺』の編者斎部)広成自身が認めていた」
のではないか,著者は推測する。さらに,天日槍の持ってきたものの中の,「熊の神籬(ひもろぎ)」について,
「朝鮮半島の人にとっては,クマは,熊ではなく,神聖,首長の意味」(金錫亨),「朝鮮語のコムでして,『聖なるもの』という意味」(金達寿)であり,これは,江戸時代の日本の藤貞幹,金沢庄三郎も唱えており,「神籬にかぎらず,古代神道関係の用語には日韓同源語が少なからず見出される。…ヒは霊,モロは三諸山のモロである。古代韓語では宗などの字を当て,神を祀る聖所をマルと呼んでいるが,それと同系語であろう。キは古代韓語では支・城などの字を当てている」(三品彰英)。
そして,著者は,持ってきた以上,大きなものではなく,柳田國男の,「たとえば能登の飯田でなどで榊みこしといふもの,是は白木造りの台の上に,ただ榊の枝を挿したてたもので,これを神籬だと神官はいって居る」の,榊みこしに比定している。
そして,熊が聖なるものというなら,「熊の神籬」が「天津神籬」と同じ意味かも知れない,もしそうなら,と,『日本書紀』の,天忍穂耳尊を降臨させようとした高皇産霊尊が,
「吾は天津神籬及び天津盤境をお越し樹てて,当に吾孫の為に斎ひ奉らむ」
と言ったのを想起する。
大挙して渡来した先進地帯の人が,ただ人だけが来たのではないはずで,文化,祭式をもってきたことは十分想定できる。それを詳らかにする手掛かりは,朝鮮半島にはほとんど残っていない。しかし,
「神社が日本独自のものだという考えは,そろそろ改めねばならない」
という発言は,今日の日韓を見るとき,なおのこと深く同意したい。
参考文献;
岡谷公二『神社の起源と古代朝鮮』(平凡社新書) |
|
葛藤 |
|
谷口克広『信長と将軍義昭』を読む。

冒頭で,昨今の研究の進展で,信長に関して,
http://ppnetwork.seesaa.net/archives/20140828-1.html
でも触れたが,
①『信長公記』の研究,城及び城下町の研究などで,信長の政権についての研究が目立つようになった,
②信長の革新性や強権性ばかり強調するのではなく,人間的弱点や現実的な面が知られるようになった,
ということを挙げて,「特に注目されるのが」
信長の権力と将軍の権力との関係
である,という。従来は,
信長の傀儡政権
とみなされてきた義昭の,将軍としての実権
が見直されてきた,という。で,本書は,信長が,義昭を奉じて,
「上洛前後から将軍追放までの約五年間を中心として,二人の関係」
を描こうとした。
信長政権と義昭政権の関係について,従来の,義昭政権は,
「『傀儡政権』論はもう通用しない」
という立場をとり,
「義昭政権と信長政権とは『相互補完関係』にあった,したがって,『二重権力』もしくは『連合政権』」
論にもとづいて,信長・義昭による政権を語っていく,という方向を著者は選ぶ。その例として,最近の論考を基に,
「上洛後のおよそ一年間に幕府が発給した文書は多数あるが,その中で目立つのは,禁制と安堵状である。久野(雅司)氏の2009年論文には,『足利義昭政権奉行人奉書・関係文書目録』が掲げられており,百五十二通の文書が記録されている。これによると,その期間には禁制十三通,安堵状五十五通を数える。そのすべてが畿内宛て,そして山城におけるものが大部分を占めている。幕府が畿内政権としての力を振るっていることを示す手がかりになるであろう。久野氏は,義昭のもとで実務に長けた奉行人などが,このような政務をきちんとこなしていたと評価し,結論として,義昭政権は決して『傀儡政権』ではなく,畿内における最大の政権として厳然として機能していた」
という考えに同意している。しかし,
備後鞆に移ってからも「鞆幕府」が存在したとか,幕府の終了は,義昭が豊臣秀吉に参礼した天正十五年(1587)である,という説はとらない。
「やはり義昭政権は,いかなる形にせよ元亀四年(天正元年)(1573)七月の追放をもって終わったと見なすべきだと思う。」
というのは穏当ではないか。発給すべき禁制も安堵状も,追放され毛利に頼っている状態では,出しようはない。
「その後の義昭の打倒信長の執念は延々九年間も続く。しかし,日本中の大名を総動員した大信長包囲網構想は,しょせん実現性のない義昭の妄想にすぎなかったと片づけてよかろう。」
と。そもそも,天下とは,後でも触れるが,
畿内及び京
京都の政権
世間
といった意味があるが,著者は,
「『天下』を政権の意味とするにせよ,人間社会の意味でとらえるにせよ,『京都』という地域をはずしては成り立たないことだけは間違いない…」。
だからこそ,義昭は,
「ひたすら京都帰還を思い描いて」
いたからこそ,御内書を乱発して,画策したのだ。しかし,上洛直後は,信長を,
御父,織田弾正忠殿
とまで呼び,『言継卿記』に,信長が京都を離れる折,
「おのおの落涙どもなり,御門外まで送らるる。」
とまで記された関係が,信長打倒の御内書を乱発するまでになったのか。決定的になったのは,有名な,
十七カ条の意見書
である。著者は言う。これは,
「この意見書内での信長の対義昭批判は,政策上などという次元に基づいたものではない。義昭という人物への不信,つまりもっと人間的な尺度から将軍としての品格を問うたものといえるだろう。」
という類のものなのだ。この中で,著者は二点に注目する。
ひとつは,「天下」「外聞」という言葉を何度も使っていること。天下には
①京都のこと,京都を中心とする畿内
②京都におかれた政権。幕府を指すこともあるが,将軍が在京することが条件
③漠然と世間,あるいは世の中。そこで起こる輿論。
といった意味があるが,信長は,
天下の為
天下の沙汰
天下の褒貶
天下の面目
天下の嘲弄
天下の覚え
という使い方を頻繁にし,天下を世間の噂,評判の意味として使い,
「信長はこの『天下』を足場にして,意見書において将軍義昭を批判している」
という。それは,義昭の失政を糺すのではなく,
「義昭の人間性に対するもの」
であり,
「世間は人間的に優れた将軍を望んでいる」
という主張になっていることである。
第二は,信長は,この意見書の写しをあちこちにばらまき,ついには,武田信玄の目にも触れて,
「信玄が信長は『ただの人間ではない』と唸ったという」
ほど,信長が流布させた。狙いは,
「いかにも『外聞』を重視した信長らしい」
宣伝活動になっている。この後,信長は,何度も決裂,講和を繰り返し,槙島城明け渡しでは,義昭の息子義尋まで取ったが,ついに殺すことはなかった。その信長の心理を,細川藤孝宛の書簡にある,
「公方様の御所行,是非に及ばざる次第に候,然りといえども君臣の間の儀に候条,深長に愁訴申し候のところ,聞こしめし直され候間,実子を進上申し候」
と,「君臣の間」という言葉を使い,自分の実子を人質にしてもいいとまで述べている。著者は,述べる。
「『将軍』の地位には,信長をもってしても越えがたい権威があった,としか言いようがない。この『権威』を背景にした『御逆心』に対しては,対処法が大変むずかしかったのだろう。」
と。結局義昭を追放にとどめたのは,だから,
「『外聞』に気を遣ったためである。『天下』の支配を目標とする信長にとって,『外聞』を無視することにより,『天下の執り沙汰』(世論)を悪化させてしまうことは,是非とも避けなければならないことなのである。」
だから,槙島開城,追放後も,再度堺で,義昭帰洛の交渉をもつ。しかし,この期に及んでも,帰洛の条件に,信長が人質を出すことに固執し,交渉相手の秀吉が,あきれはてて,
「いくら上意とはいえ,そんな難題を認めると大変なことになる。将軍は行方知れずになったようだ,と信長様に報告しておく。さっさとどこへなりと行かれるがよかろう」
と言い捨てて帰ってしまった,という。著者も,
「これほど落ちぶれていながらも,将軍位を保持しているだけで,いまだに優位に立っていると思っているのであろう。」
と書く。義昭は,二十人ほどの供と紀伊へ向かい,二年後,鞆へ移る。
「義昭は最後まで信長に負けたことを認めなかった。その意地は,ある意味で敬服に値するだろう。彼のこの意地を支えたものは,ひとえに『自分は将軍である』というプライドであった。彼の場合,将軍である自分が御内書の形で命令すれば,大名以下がその命令を奉戴して動くのは当たり前,と信じているのである。」
義昭が帰郷するのは,天正十五年(1587)のこと,翌年には出家して「昌山」と号す。そのときまで将軍であり続けた。
参考文献;
谷口克広『信長と将軍義昭』(中公新書) |
|
漢語 |
|
高橋睦郎『漢詩百首』を読む。

前にも漢詩については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/406252031.html?1412021752
で取り上げた。漢詩の訓読については,いささかの疑問を持っていたが,本書で,少し,意味を理解したような気がする。
著者は言う。
「日本語は,固有の大和言葉と外来の漢語・欧米語から成っている。とくに漢語の来歴は古く,大和言葉と分かちがたく,外来語と意識することがないまでに日本語の血肉となっている。」
と述べ,例えば,敗戦時に多くの日本人の脳裏に浮かんだのは,
国破れて山河在り
という杜甫の漢詩の一行だったのではないか,という。この,
国破山河在
城春草木深
を,千数百年前のわれわれの祖先が,送り仮名や返り点を付けることで,日本語で読もうとした。そして,
国破れて山河在り
城春にして草木深し
と読んだ。だから,
「この驚異的な,あえていえばアクロバティックナ発明によって,漢詩という外国の詩はなかば日本の歌に,いや,ほとんど日本の歌になった。」
と。さらに,
「私たちの祖先は漢詩を日本語として読む工夫をしただけでなく,自分でも漢詩を作ることを試みた。」
本書には,中国の詩人60人に対して,日本人の詩人40人が載せられている。
中国人は,『詩経』は詠み人知らずのため,『論語』の孔子,
逝く者は斯夫の如きか,昼夜を舎かず
から始める。次は,荘子の,
知らず,周の夢に胡蝶と為るか,胡蝶の夢に周となるか
を採り,
「後世の詩人はほとんど孔子型と荘子型にわけられるのではないか。たとえば,中国の詩の歴史上,最高峰と目される二人のうち,杜甫が孔子型,李白は荘子型といえよう。」
と,冒頭に二人を持ってきた所以である。中国詩人の最後は,毛沢東で,
九嶷山の上 白い雲は飛び
帝子は風に乗って翠微に下る
を採る。一方日本人は,聖徳太子,憲法十七条から,
春従り秋に至るまでは,農桑之節なり
民を使う可からず 其れ農せずは何をか食わん
桑せずは何をか服ん
を採り,詩人,鷲巣繁男の,
地崖 白雪を呼び
青夜 孤狼を発す
幻化 星暦を司り
詩魂老いて 八荒
で締める。ちょうど百人の詩人列伝になっている。こうして,我々の祖先は,漢語を自家薬籠中のものとすることで,
「自分たち固有の文芸や詩歌を豊かにしていったわけです。…たとえば明治維新に欧米の文明を受け入れて自分のものにしたのも,かつて漢字を通して中国の文明を受け入れて血肉化した経験があったからでしょう。ついでにいえば,現在中国で使われている漢字熟語60パーセントが明治維新に欧米語を受け入れるに当たって日本人が作った和製漢語だとききました。」
というところへ至る。漢字へのそういう意識が,真名としての漢字に対して,漢字を借りることで作り出したかなを,
仮名
と呼ぶところに現れている。
「日本人は中国から文字の読み書きを教わると同時に,花鳥風月を賞でることも学んだ。花に関してはとくに梅を愛することを学んだが,そのうち自前の花が欲しくなり桜を賞でるようになった。梅に較べて桜は花期が短いので,いきおいはかなさの感覚が養われる。その成果が漢詩にも現れた典型」
として,
宿昔は猶し枯木のごとかりしに
迎晨一半紅
国香異けこと有るを知り
凡樹同じきことなきを見たり
を挙げる。これは,同時代の,
世のなかにたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし
と歌う在原業平と同じ感性・心性の表現になっている,と。
しかし,もはや漢詩を作れる人はいなくなった。これは,
「日本人全体の漢語力の低下であり,漢語力の低下は漢語を日本語化した日本語力の低下をもたらしかねない。」
と著者は言う。著者の次の言葉は,僕は大きく頷きたい。
「グローバル時代の今日,必要なのは英語力で日本語力ではない,という極論もある。しかし,グローバル時代に適応する底力は国語力であり,国語による教養にあることは,グローバル時代の走りともいえる明治開国期の先人たちの漢語力を含む国語力の豊かさが,力強く証明している。」
持っている言葉によって,見える世界が違う。狭く貧弱な言葉しか持たない者には,狭く貧弱な英語理解しかできない,と僕は思う。
『詩経』序には,
「詩は志の之く所なり。心に在るを志と為し,言に発するを詩と為す」
とある。僕は,それを敷衍して,
文もまた志の赴くところ
と言いたい。陸游の
汝果たして詩を学ばんと欲せば
工夫は詩の外に在り
と。どこか,小楠を思わせる。
参考文献;
高橋睦郎『漢詩百首』(中公新書) |
|
発見 |
|
下定雅弘『精選 漢詩集』を読む。
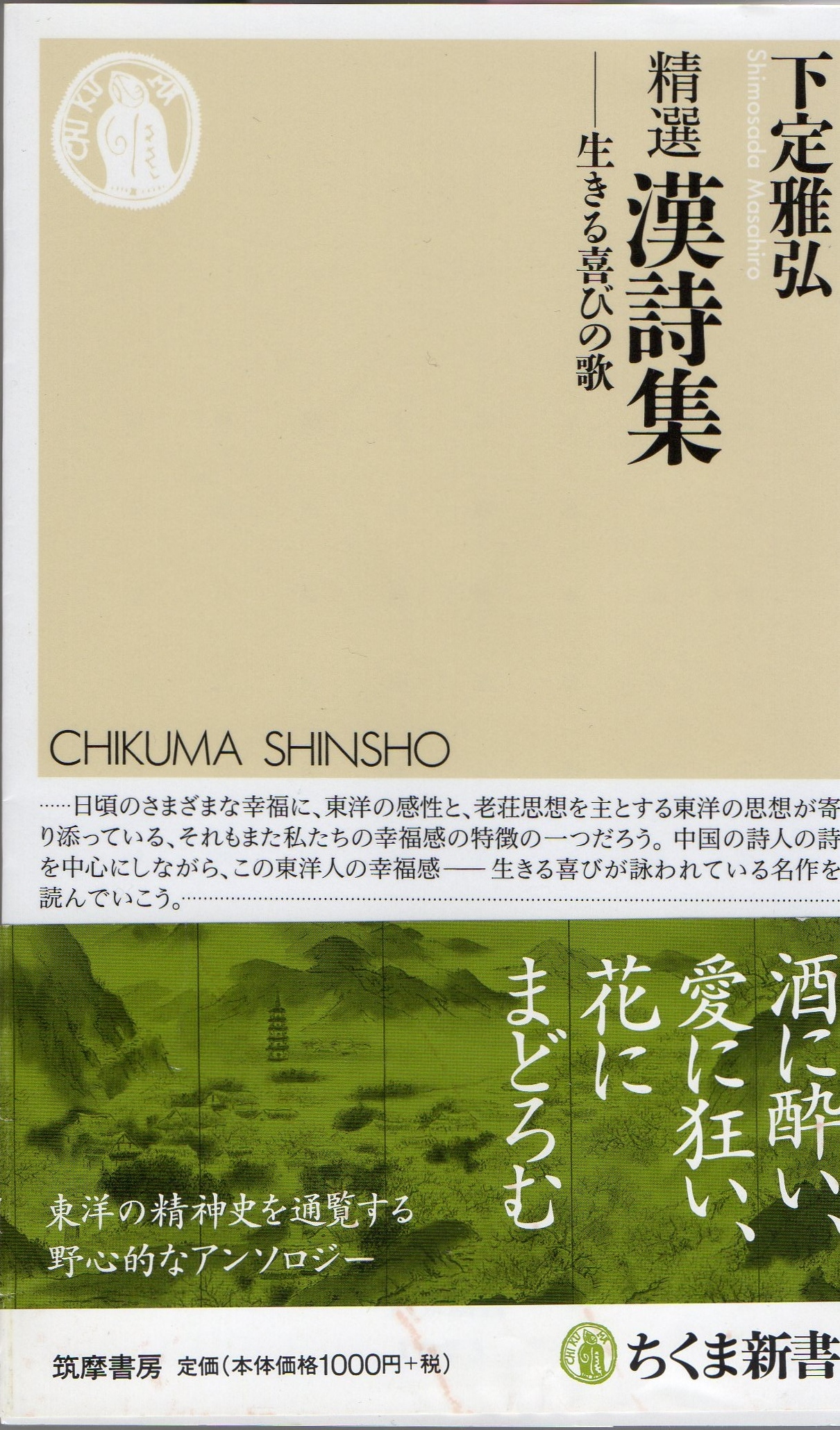
著者は,本書の意図を,
「自然への隋順と融和を含む日頃のさまざまな幸福に,東洋の感性と,老荘思想を主とする東洋の思想が何気なく寄り添っている,…中国詩人の詩を中心にしながら,この東洋人の幸福感―生きる喜びが詠われている名作を読んでいこう。」
と述べる。その例に挙げたのが,陶淵明の詩である。
「『菊を採る東籬の下,悠然として南山を見る。山の気は日夕に佳し,飛ぶ鳥は相い与に還る。此の中に真意有り,弁ぜんと欲して已に言を忘る。』(『飲酒』其の五)とあるのは,『荘子』の中に出てくる話が下敷きになっている。…私たちは,『荘子』のどんな話か知らなくても,此処に何となく東洋的な味わいがあることを感じる。」
僕自身は,こう言う言い方が嫌いである。「東洋的」と丸めた瞬間,思い出すのは,右翼の大物に,書籍についてクレームを付けられ,肩に手を置いて,
「同じ日本人じゃないか」
と言われたと書いた作家の感じたと同じ,寒気である。こういう言い方は,詩人のそれではない。詩人は,何を下敷きにしようと,その言葉の向こうに,
自分にしか見えない視界
を見ている。いや,逆かもしれない。自分が見たものに,
言葉
をつける。その瞬間,その詩人の見た光景が,以降の人の見える世界を決める。それは,
風景(あるいは光景)
の発見であると同時に,
言葉
の発見である。人は,持っている言葉によって,見えている世界が違う,という。しかし,詩人が発見した風景が,以降,共有財産になる。そういう目で見ると,漢詩の発見した風景が,いかに,根強く,日本人の感性に影響を与えているかが,わかる。しかし,それは,たぶん,洋の東西を問わない。ひとしなみに,人間だからである。
そんな例をいくつか拾ってみる。
風は白浪を翻して花千片,雁は晴天に点じて字一行(白居易)
ここで,浪が白く泡立つのを「白い花」に見立てて,波の花に見る,和歌の言い方は,白居易の発見した風声である。波の泡立ちを「浪の花」に見える心情を詩人は作り出した。
あるいは,同じ白居易,
慈恩の春色 今朝尽く
尽日徘徊して寺門に倚る
惆悵す春は帰りて留め得ず
紫藤花の下 漸く黄昏
『和漢朗詠集』に収められたせいもあり,春の心情に決定的な影響を与えた,という。たとえば,
待てといふに留まらぬものと知りながら強ひてぞ惜しき春の別れは(詠み人知らず)
君にだに尋はれてふれば藤の花たそがれ時も知らずそありける(紀貫之)
草臥て宿かる比や藤の花(芭蕉)
春,黄昏,藤の花,に同じ光景を見,同じ心情を懐く。詩人見せる言葉の力である。その言葉が描く光景の力である。
やはり,同じ白居易,
駙苔 地上 残雨を銷し
緑樹 陰前 晩涼を逐う
は,「雨後の清涼」「納涼」というテーマとして,
夕立のなごりの露をそめすてて苔のみどりに募る山蔭(定家)
に生きる。そもそも,雨上がりの涼しさが,光景として,初めて描き出され,それが心情として,共有化されたのだ。
冒頭の陶淵明の詩,
廬を結んで人境在り,而も車馬の喧しき無し
君に問う何ぞ能く爾ると,心遠ければ地もまた自ら偏なり
菊を採る東籬の下,悠然として南山を見る
山の気は日夕に佳し,飛ぶ鳥は相い与に還る
此の中に真意有り,弁ぜんと欲して已に言を忘る
日本には,空を悲しむ感情はなかったという。この詩をはじめ,中国の詩人にとっては,「悲秋」の感情である。いま,われわれは秋にもの悲しさを感じるのは,詩人の見せた光景から端を発している。
しかし,本書を読みながら,結局,読み下した詩を読むことは,本当の意味で,漢詩を楽しんだことになるのか,という危惧を感じ続けた。訳詩ともちがう,独特の日本語になっている。
昔から,素読というと,
子曰く,
である。しかし,それは訳ではない,微妙な日本語を読んでいるのではないかという気がしてならない。たとえば,
上よ
我は欲す 君と相い知りて
長えに絶え衰うること無から命めんことを
山に陵無く,江水為に竭き
冬に雷 震震 夏に雪雨り
天と地との合するとき 乃ち敢えて君と絶えなん
とは恋の歌である。「子曰く」なら,おごそかさが必要かもしれないが,この訓読は,明らかに,詩を歪める。
天よ
私は願います,あの人と愛し合って,とこしえにこの愛が絶えることがありませんように
山の峰々が崩れ,河の水が枯れはて,冬に雷が鳴り響き夏に雪が降り,天と地が合わさって
この世に最後が訪れるとき,その時にあの人と別れましょう
がその訳である。いわゆる素読が,基本的に原語そのものを歪めていることに気づくはずである。こういう読みは,いかがなものだろうか,とそんなことを考えさせられた。で,思い出すのは,井伏鱒二の訳詩である。
勤君金屈
満酌不須辞
花発多風雨
人生足別離(于武陵「勤酒」)
を,
コノサカズキヲ受ケテクレ
ドウゾナミナミツガシテオクレ
ハナニアラシノタトエモアルゾ
「サヨナラ」ダケガ人生ダ
この軽身が,読み下しでは消えてしまうのである。
最後に陶淵明の詩。
慵(ものう)しと雖も興猶お在り
老いたりと雖も心猶お健やか
我が意を得たり。
参考文献;
下定雅弘『精選 漢詩集』(ちくま新書) |
|
アイヒマン |
|
ハンナ・アーレント『イェルサレムのアイヒマン』を読む。
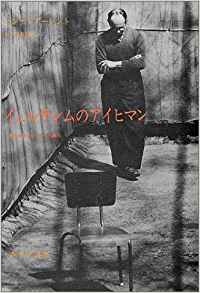
本書は英語で書かれたらしいが,英語で言う,
Crime against humanity
は,独語では,
人道に対する罪
と
人類に対する罪
の二つの言葉がある,と訳者は言う。当該語には,二つの意味が込められている。それは,単なる戦時の犯罪という以上の意味を,アーレントは込めているといっていい。
しかし,英文の(翻訳である)本文中では,アーレントは,こう書く。
「追放(例えば,在日韓国人を迫害したり国外へ追い出すことと言っていい)とジェノサイドとは,ふたつとも国際犯罪ではあるが,はっきりと区別されなければならない。前者は隣国国民に対する罪であるのに対して,後者は,人類の多様性,すなわちそれなしには〈人類〉もしくは〈人間性〉ということばそのものが意味を失うような〈人間の地位〉の特徴に対する攻撃なのだ」
しかしやっかいなのは,アイヒマンを単なる極悪人,人非人ということでは片づかないことなのだ。
「アイヒマンという人物の厄介なところはまさに,実に多くの人が彼に似ていたし,しかもその多くの者が倒錯してもいずサディストでもなく,おそろしいほどノーマルだったし,いまでもノーマルであるということなのだ。我々の法律制度と我々の道徳的判断基準から見れば,この正常さはすべての残虐行為を一緒にしたよりもわれわれをはるかに慄然とさせる。」
その意図は,本書の副題が,「悪の陳腐さについての報告」とあるところからも推測される。
アイヒマンは,粛々と任務を果たし,初めは,
移送,
続いて,
強制収容
続いて,
殺戮
へと至る,ユダヤ人,ジプシーの輸送を担当し,結果として,六百万の人間の殺戮に加担した。殺戮されることを承知の上で,大量の人間をいかに輸送するか,関係部署との折衝,貨車の手配,運行スケジュールの調整等々を果たした。
もちろん,殺戮を指示したのは,ヒトラーだし,その移送と行先を指示したのは,上位者に違いない。しかし,殺戮されることを承知の上で,いかに効率的に大量の人間を輸送するかを考え,実行したことに違いはない。
アイヒマンは,しきりに言う。自分はユダヤ人を憎んでもいなかったし,殺そうとも思わなかった,と。
それに対して,アーレントは,最後に締めくくる。
「アイヒマン裁判で問題になったより広汎な論点のなかでも最大のものは,悪を行う意図が犯罪の遂行には必要であるという,近代の法体系に共通する仮説だった。おそらくこの主観的要因を顧慮するという以上に文明国の法律が誇とするものはなかったろう。この意図がない場合,精神異常をも含めてどんな理由によるにせよ善悪の弁別能力が損なわれている場合には,われわれには犯罪は行われていないと感じる。『大きな犯罪は自然を害い,そのため地球全体が報復を叫ぶ。悪は自然の調和を乱し,罰のみがその調和を回復することができる。不正を蒙った集団が罪人を罰するのは道徳的秩序に対する義務である』(ヨサル・ロガド)という命題をわれわれは拒否し,そのような主張を野蛮とみなす。にもかかわらず私は,アイヒマンがそもそも裁判に附されたのはまさにこの長いあいだ忘られていた命題に基づいてであるということ,そしてこの命題こそ実は死刑を正当化する究極の理由であるということは否定できないと思う。ある種の〈人種〉を地球上から永遠に抹殺することを公然たる目的とする事業にまきこまれ,そのなかで中心的な役割を演じたから,彼は抹殺されねばならなかったのである。」
しかし,これは,そのまま今日のベンヤミン・ネタニヤフをはじめとするイスラエル政権とその中枢の人々へも適用される,ということを,ユダヤ人であるアーレント自身が照らし返している。パレスチナ人には,裁く権利がある,と。
本書を読みつつ,僕は,いくつかのことを思い出していた。
第一は,スタンレー・ミルグラムの実験である。これは,いつも言われていることなので,他に譲る。しかし,人は,その立場になると,その役割を遂行しようと,平然と冷酷になれる。
第二は,いまは潰れた雪印食品の,ミートセンターの出来事だ。センター長は,会社の売り上げ不振をカバーする方法として,輸入牛肉に国産牛のラベルを貼ることを,三人の課長に提案する。一人は反対したが,二人は,黙っていた。後日新聞記者に「なぜ黙っていたのですか」と聞かれた二人の一人は,「サラリーマンだから,わかるでしょ」と答えた。ここにアイヒマンを見る。アイヒマンは,どこにでもいる,それをさせるのは,何か。
アーレントは,アイヒマンについて,
「彼は愚かではなかった。完全な無思想性―これは愚かさとは決して同じではない―,それが彼があの時代の最大の犯罪者の一人になる素因だったのだ。」
と書く。愚かではなかったが,無思想だった。思想とは,イデオロギーの謂いではない。しかし,このアーレントの概念に,ほとんどの日本人,僕も含めた,ほとんどのわれわれに該当するのではないかと,僕は感じている。自分の頭で考える,という程度のことではない。そこで,思い出したのが,吉本隆明の『マチュウ書私論』での,
「人間の意志はなるほど,選択する自由をもっている。選択のなかに,自由の意識がよみがえるのを感ずることができる。だが,この自由な選択にかけられた人間の意志も,人間と人間との関係が強いる絶対性のまえでは,相対的なものにすぎない。」
という言葉である。それについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/397281789.html
に書いた。吉本は,
「秩序にたいする反逆,それへの加担というものを,倫理に結びつけ得るのは,ただ関係の絶対性という視点を導入することによってのみ可能である」
とも言う。この場合の,「秩序に対する反逆」を,「ラベルの張り替えへのNo」と置き換えればいい。それが言えるのは何によってか。それを,
倫理
に結びつける,というのは,個人としての倫理,別の言い方をすると,
ひととしてどうあるべきか,
ではないか,と思っている。そして,それをおのれの生きている文脈に鑑み,
(ここで)自分はいかにあるべきか,
とつなげ,さらに,それを,
自分の生きているこの世の中はいかにあるべきか,
へとつながっていく。それを考えることを,僕は思想性と呼びたい。いま流行の,
いかに生きるべきか,
を自己完結して考えているだけでは,思想性とは言わない。それは倫理を自己完結させているだけだ。だから,
「関係性の強いる絶対性」
とは,客観的にあるのではなく,自分の中に,意識的無意識的に,絶対性として強いるものを感じる,という意味だとすると,吉本の言っているより,もっと広げている(和らげている)かもしれないが,
人は知らず,おのれにとっては,
と,考えて初めて,
人間と人間との関係が強いる絶対的な情況,
というもの(このとき,人も状況も個別,固有化されているが)から,思想も,発想も,意識的か無意識的かは別に,逃げられない,ということに気づく。そのことを考えているかどうか,だといっていい。
誰もが,加害者になりうるのである。それを,自分の意志ではない,命令だから,上司が,国が命ずるから,という理屈は,アイヒマンの場合,許されなかった。ことが重大だったから,ということはない。そういう言い訳は,通用しない。
例は悪いが,エゴグラムで言う,
http://www.d1.dion.ne.jp/‾ppnet/prod06423.htm
CPの強さが,ある程度その社会的役割や立場からもくるというのは,ひどく暗示的に思う。
それは,無思想である,つまり,いかにいくべきか,いかにあるべきかについて,無自覚である場合,陥る陥穽なのである。それは,また,誰もがアイヒマンになりうるということでもある。それは,今日のイスラエルを見ればわかる。
参考文献;
ハンナ・アーレント『イェルサレムのアイヒマン』(みすず書房)
スタンレー・ミルグラム『服従の心理』 (河出文庫) |
|
視野 |
|
菊池章太『阿修羅と大仏』を読む。
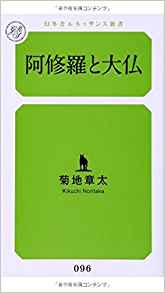
菊池章太『阿修羅と大仏』を読む。
「インドで生まれた仏教は,広大なユーラシア大陸でさまざまな文化と混ざりあい,変質をかさねながら,東のはての島国にたどりついた。日本の仏教文化のはじまりとなった大和の地は,そうした長い道のりの終着駅でもあった。」
と前書きで書き,
「仏像や仏画にこめられた信仰の軌跡をユーラシア・スケールでたどってみたい。」
それをコンセプトに書く,と。それは,日本の仏教の来歴をたどる何千年もの旅でもある。たとえば,中宮寺の半跏思惟像は,著者によれば,三十年以上前には,「菩薩像」と表示され,その後十年して行くと,「弥勒像」と表示が変わり,現在は,中宮寺のホームページには,「如意輪観音像」と表示されている,という。
では,広隆寺の半跏思惟像は,「弥勒像」とされているが,それでいいのか。
ユーラシアからみると,半跏思惟像を,弥勒と呼ぶ例は,皆無という。多く,弥勒像は,X字に脚を交差させた交脚像である。雲崗石窟には,交脚の弥勒像が数多くつくられているが,その交脚像の左右に,
「片脚を膝の上にのせ,手を頬にあてて考え込んでいる人の像がしばしばみられる」
という。この半跏像は,
釈迦が考え込んでいるときの姿
をあらわすという。
「釈迦がまだ悉達多太子と呼ばれていたときの」「樹下で思惟する」
思いにふけっている姿を表す,と言う。なぜ太子思惟像が弥勒の脇にいるのかと言うと,両者には接点がある,という。
「弥勒はまだこの世にあらわれていない。世にあらわれていないから,当然まだ真理にめざめていない。つまり悟りを開いていない。その準備段階である。弥勒は兜率天人たちのもとにいてこの世にあらわれる日を待っている。それまで思惟をめぐらしている。
かたや悉達多太子もまだ真理にめざめていない。家にあってもやもやしている。考えごとの最中である。思惟のまっただなかにいる。つまり,どちらも真理にめざめるまえに考えにひたっているすがたということになる。」
半跏思惟像は,朝鮮半島にも伝わったが,弥勒と呼んだ例は見つかっていない。
「広隆寺の半跏思惟像…は,…(韓国の)徳寿宮旧蔵の半跏思惟像とほとんど瓜二つである。広隆寺の像は日本製ではないであろう。そして弥勒像でもない。」
では何の像か。
「推古天皇の十一年(603)十一月のことである。聖徳太子のもとにある仏像をまつる者を大夫らに求めた。そのとき秦造河勝が進み出てこれをたまわり,蜂岡寺を建てておさめたという。これは『日本書紀』にきされている。」
蜂岡寺,いまの広隆寺である。平安時代の寛平五年(893)までにまとめられた寺の財産目録によると,
「金色弥勒菩薩像一躯」とあり,割注に,「居高二尺八寸」「所謂太子本願御形」と記されている,という。さらに,中宮寺も,太子ゆかりの寺であり,
「中宮寺の半跏思惟像は太子思惟像と呼ばれるのがふさわしくないか。この場合悉達多太子に聖徳太子の姿がかさねられている。」
と推定する。
「ユーラシアにおける長い伝統のむなかでは太子思惟像が本来の呼び名だったのだから。」
と。そしてこう言う。
「私たちは広隆寺の半跏思惟像を弥勒と呼んできた習慣にひきずられすぎてはいないか。日本だけで考えるとそうなってしまう。しかしユーラシアに目を転じるとそれがはっきりする。そこでは,弥勒像は交脚像であり,あるいは巨大立像であった。かたや半跏思惟像は太子思惟像をあらわしている。これが仏教の伝統にほかならない。」
その半跏思惟像は,
「考えあぐねている若い悉達多太子のすがたである。…日本ではそれが聖徳太子にかさねあわされている。。さらに聖徳太子を観音の生まれ変わりとする信仰がシンクロナイズしている。」
と。広い視界の中でものを見ることの重要性を,改めて考えさせられる。特に,今日,自閉し,自画自賛の罠にはまっている潮流を見るとき,さらに広くユーラシアの端っこのわが国への重なり合わさった時間の軌跡が,そのまま古層のように堆積しているのに思い至るとき,それを広げて,辿る視点の重要性を考えさせられる。
例えば,六世紀の,北魏で始まった巨大な廬舎那仏づくりは,唐代までつづき,龍門に高さ17メートルの廬舎那仏がつくられた。ここから東アジアの大仏ブームが始まる。奈良の大仏は,その東漸の結果なのだと見るとき,まったく違った様相が見えてくる。
「廬舎那仏は大宇宙に君臨し,世界のすべてのブッダを統括する存在である。唐王朝の皇帝もまた世界の中心である中国に君臨し,周辺世界の国々を統括する存在と意識されている。こうして廬舎那仏の宗教的意味に政治的意味がオーバーラップしてくる。」
「聖武天皇が全国に国分寺を建立させ,その諸国国分寺を統括する総国分寺としたのが東大寺」である。その開眼法会は,
「聖武太上天皇と光明皇太后と孝謙天皇が臨席した。百官百寮が参列し,内外から一万人あまりの僧侶が招かれた」空前絶後の大法会であったという。
「開眼の導師はボディセナである。南天竺国つまりインドから日本へ帰化した人で,漢字をあてて菩提僊那とよばれた。」
「開眼供養では舞楽が奉納されている。…倭舞とならんで,唐古楽や高麗楽や林邑楽も披露された」が,中国,朝鮮,ベトナムと,「まさしくユーラシア・スケールの祭典だった。八世紀の日本はすでにインターナショナルだった」という,そういうスケールの中に奈良の大仏をおいて見ると,政治的意味と宗教的意味を重ねあわせる思想まで,唐にまねたという流れが見えてくる。
ユーラシアの果てだからこそ,時間軸が,層として堆積している。それを自己完結して考えているだけでは,決して視界は開けない。
興福寺の阿修羅像についても,
「フェスタのためにつくられた。」
と結論づける。「フェスタにつかうために造像された。それがユーラシアにおける長い伝統であった」と。フェスタは,日本で言う花会式である。
「ユーラシアではもっと盛大な祭りだった。誕生釈迦像を山車に載せて町中を練り歩く。これを行像と呼んでいる。」これに随行したのが十大弟子と阿修羅を含めた八部衆の像である。
そう考えたとき,興福寺の像が乾漆でつくられている理由が見えてくる。
乾漆像は,粘度の上に麻布をかぶせ,漆を塗り,それに麻布をかぶせて漆を塗るを繰り返し,漆が乾いたところで中の粘土をかきだす。だから,
「木の心棒のほかに中味ははいっていない。張り子の虎とおなじである。この技法は中国で行像のために考案された。それが中央アジアや日本に伝わったのである。」
度々火災にあった興福寺の仏像がそのたびに運び出されたのは,乾漆像で軽量であったのが幸いした。
確かに,帯にあったように,本書を読むと,「仏像の見方が変わ」る気がした。
参考文献;
菊池章太『阿修羅と大仏』(幻冬舎ルネッサンス新書) |