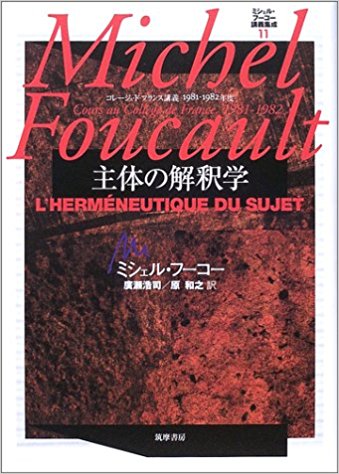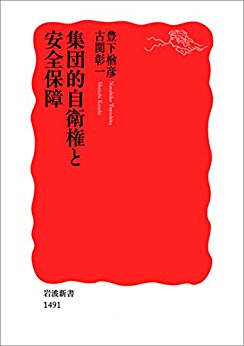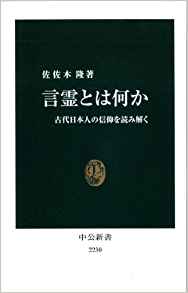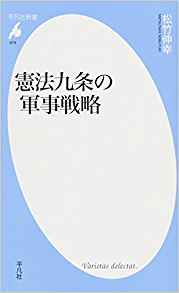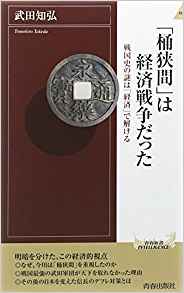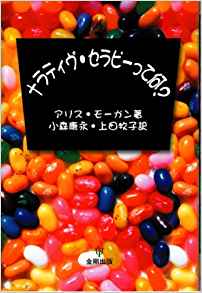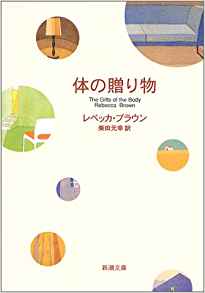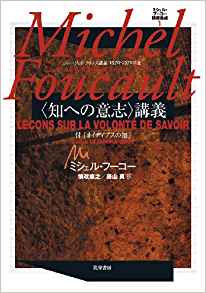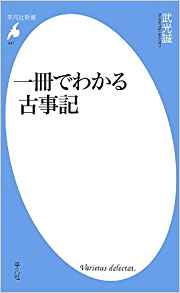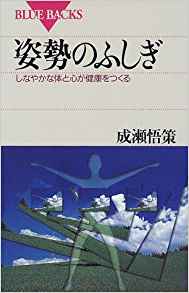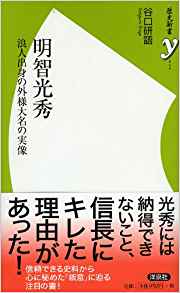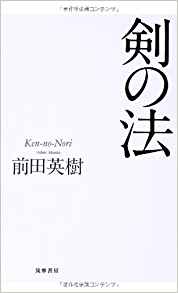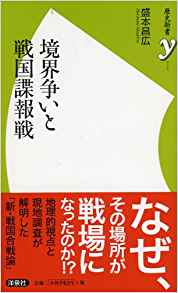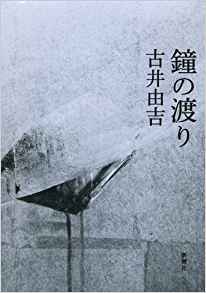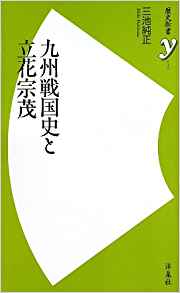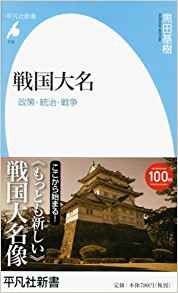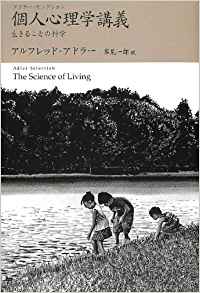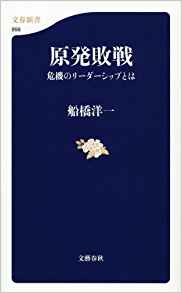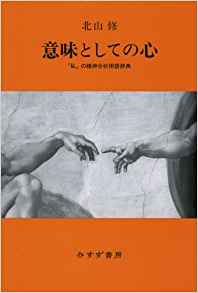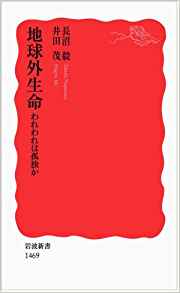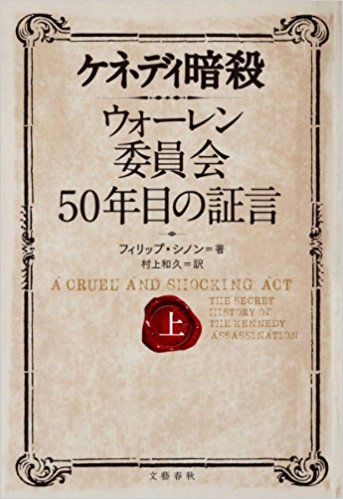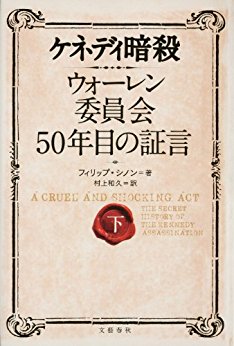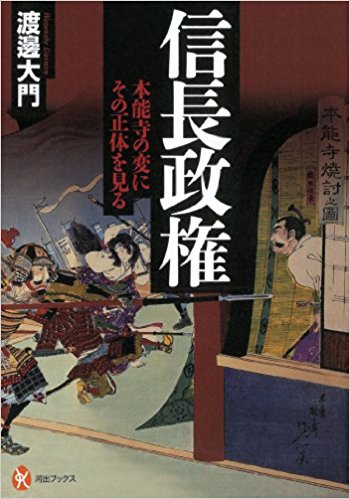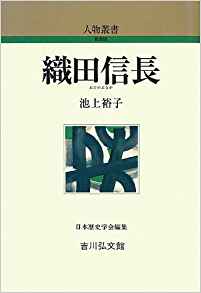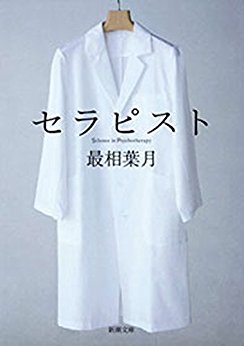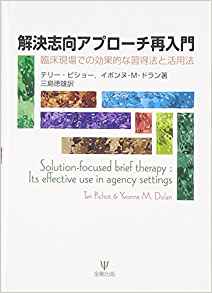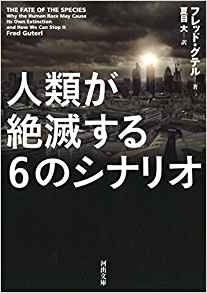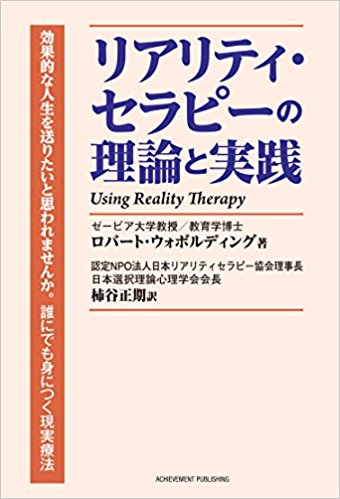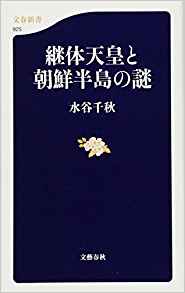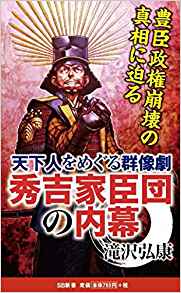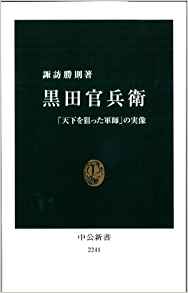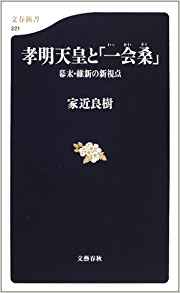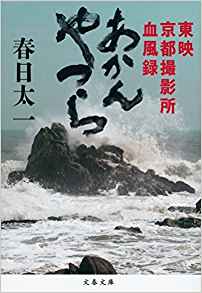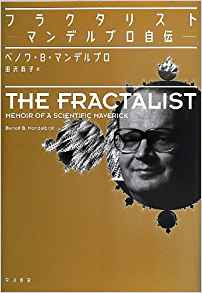|
終焉 |
|
服部茂幸『アベノミクスの終焉』を読む。

素人としての感想に過ぎないが,アベノミクスの印象は,じゃぶじゃぶの公共投資,でもって土建屋が活況で,人手不足。その余波で,いろんなところ(特に3K職場)が人手が足りない。一見好況のようだが,大企業が好調の割に,賃金は下がりっぱなし,非正規雇用のみ増え,円の価値は下がり,といって輸出が増えているわけではなく,貿易収支の赤字が続く,で,何番目の矢か知らないが,結局武器輸出頼みとカジノ誘致って,そんなのに日本の将来はあるのか,というものだ。
この数年のうちに,精神と文化も含めて,大事な日本の岩盤が壊されていくような不安がある。こちらは,どうせ老い先短いが,若い人の無関心が気になる……というところだ。
ほんとうはどうなのか。筆者は,
「アベノミクスが始まる前からその批判者であった。」
という。その意味で,経済学者の論拠を知りたいと思って,読み始めた。ただ,あとがきで,
「2013年10月,第三・四半期のGDP速報がでた。そこでは経済成長率が1%程度だったことが告げられた。14年四月には消費増税があり,第二・四半期には経済が落ち込むことはほぼ確実である。」
とあるように,それ以前に書かれていることを念頭に置かなくてはならない。
まえがきで,
「アベノミクスは異次元緩和という第一の矢,公共事業拡大による国土強靭化という第二の矢,成長戦略という第三の矢からなるとされる。(中略)アベノミクスの主役は第一の矢,脇役が第二の矢であり,第三の矢はまだ登場していない…。」
主役の矢については,
「安倍が無制限の金融緩和を訴えてから,株価上昇と円安が急速に進行した。(中略)しかし,黒田東彦が日銀総裁,岩田規久男が日銀副総裁に就任するのは13年三月であり,異次元緩和が始まるのは四月である。三月までの出来事はいわば『前史』である。
株価上昇も円安も異次元緩和が始まってしばらくするとストップした…。13年の上半期には高かった経済成長率も,下半期には低迷している。」
金融緩和の目的の一つは,円安による輸出拡大であった。しかし,
「12年末に円安が始まると,輸出は再び増加し始めた。円安効果を発揮していたようにみえた。ただし,増加したといっても,…12年のピークにも達しなかった。さらに円安が止まった時から少し遅れて,輸出も減少に転じた。円安が輸出を拡大させたとすれば,円安が止まれば,輸出増大が止まるのも当然であろう。他方,円安にもかかわらず,輸入の伸びは著しい。」
しかも,14年第一・四半期の経常収支は1兆4000億円の赤字である。
「日本の長期停滞の原因はデフレであり,そのデフレの原因は日銀が金融を緩和しないためだ」とする,いわゆるリフレ派の黒田,岩田両氏が日銀の総裁,副総裁に就任して始まった異次元緩和は,しかし,輸出拡大による経済復活に失敗し,
「輸出の拡大が,貿易収支,経常収支を悪化させるとともに,日本の経済回復を妨げている。」
つまり安倍とリフレ派の主張とは真反対のことが生じている。しかも,目論見に反して,
「賃金と可処分所得は名目においても低下が続いている。その結果,実質賃金と実質可処分所得は急減することとなった。」
実は,このいわゆる,失われた20年と言われている金融危機以降,日本の実質賃金も,実質可処分所得も低落傾向にあったが,
「11年以降では,実質賃金はせいぜい微減である。家計実質可処分所得は増加している時期さえみられた。ところが,異次元緩和導入以降,両者は大きく低下した。」
のである。その結果,消費が落ち込むことになる。実は,
「2013年第一・四半期の経済成長率は年率で5%近い。第二・四半期の経済成長率も高かった。このように,アベノミクスが始まってからの半年間の経済成長率はきわめて高かった。しかし,安倍政権が誕生したのは12年12月であり,異次元緩和が始まるのは,13年4月である。13年前半の高成長は異次元緩和の成果ではあり得ない。」
のである。そう,安倍政権に政権が代わって以降,
「皮肉にも,異次元緩和が始まると,経済成長率は低迷する」
のである。
「第三・四半期の経済成長率は年率で1%,第四・四半期にはほとんどゼロである。14年第一・四半期の成長率は6%と極めて高いが,消費増税前の駆け込み需要によるところが大きい。」
リフレ派の目標はデフレ脱却のはずである。現在日銀は,消費者物価上昇率を年率で2%へと引き上げ,それを安定化させることを目標としている。それはどうか。
「13年6月,消費者物価上昇率が前年同月比でプラスとなり,11月には1.6%にまで引き上げられた。13年10月以降,内閣府が調査した1年後の物価見通しの指標も3%を超えている。」
当然現在のインフレは,コストプッシュ型,つまり円安が原因である。
「12年には国内企業物価の低下は消費者物価よりも大きかった。それが13年後半には,国内企業物価の上昇率は2%を超え,消費者物価の上昇率を大きく超えるようになった。」
しかし輸入物価の上昇が止まれば,輸入インフレは止まる。
「13年5月から円安は止まっている。13年末から,輸入物価の上昇も止まった。それと期を同じくして,消費者物価も国内企業物価も上昇が止まっている。」
当然消費増税の影響は別とすると,
「これまでの消費者物価の上昇が輸入インフレの結果でないことが明らかになるまでは,本当にデフレから脱却できたかどうかの判断を行うことはできないはず…」
ということになる。この点でも,アベノミクスの成果は,まだ出ていない。
第二の矢については,
「耐久消費財と民間住宅投資は,経済の回復が始まった09年から急増している。この急増の一部分は,エコカー減税,エコ・ポイントなどの政策によるものであろう。アベノミクスが始まると,再び耐久消費財と民間住宅投資は急増する。この急増も14年4月の消費増税を無視しては考えられないであろう。政府支出の増加も大きい。」
という意味で,第二の矢の効果が上がっているといっていい。耐久消費財,民間住宅投資,政府支出でGDPの四割を占める。これが,アベノミクスの経済成長を支えた,と著者も認める。ただ,
「公共事業に代表される政府固定資本投資はGDPの5%を占めるにすぎない。建設業の就業者も全体の数%程度である。政府固定資本投資を現在のように年率二割で急増させても,それは日本のGDPを1%増加させるにすぎない。」
しかしそうして増加させることで,建設会社の設備能力と人手不足とで,需要には対応しきれない。震災復興事業も拡大している。民間の住宅,工場建設も増え,現実には,業界のキャパを超えており,自治体の公共事業への応札がない事態も起きている。バブルである。しかし,それは人手不足だけを波及させていくようにしか見えない。
さて,こうしたアベノミクスのバッボーンになっている,日本のリフレ派は,アメリカのバーナンキの,
「90年代以降の日本の長期停滞……の原因は日銀が金融を緩和させずに,デフレを放置していることにある」
という主張を受け継いでいる。その意味では,著者の,バーナンキ,グリーンスパンの
「アメリカの住宅バブルの最中に,家計はバブルの中で返済できない負債を蓄積させている」
という警告を知りながら,それに反論し,逆に,「低金利政策と金融の規制緩和によって,金融不安定性を拡大」させ,結果として,08年の危機を招来させた,経済学への手厳しい指摘は,翻って,それをまねて踏襲するアベノミクスへの批判と警告になっている。著者はこういう。
「08年の危機はバーナンキに代表される経済学が何重にも間違っていたことを示している…。」
と。それをクイギンにならって,ゾンビ経済学というが,しかし,「08年の危機はゾンビ経済学を死滅させたかにみえた」が,アベノミクスによってそれが復活した。その復活の理由を,四つ挙げる。
①危機が本当に明らかになるまで危機を否定した。
②経済現象は多面的であり,失敗の唯一の原因というものはおそらくないであろう。それを利用して,成果を自分の手柄とし,失敗の責任を他に押しつけた。
③多数派の力によつて,失敗を犯しても,自らの責任を免責している。
④政治的に有力な集団と結びつき,その利益を擁護した。
これは今,既に我々の目の前で起きつつある。
参考文献;
服部茂幸『アベノミクスの終焉』(岩波新書) |
|
天下 |
|
金子拓『織田信長〈天下人〉の実像』を読む。

信長については,何度か触れた。もっともニュートラルで戦国大名研究家の見る信長は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/390004444.html
で挙げた,池上裕子『織田信長』である。
一方,革命性を強調した信長像は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/400155705.html
藤田達生『天下統一』である。
本書は,信長像を等身大の戦国大名として描く。
「はじめに」で,著者は,自分の問題意識を,こう書く。
「織田信長は本当に全国統一をめざしていたのだろうか。」
それを説明するための本書なのだ,という。そのために,
「信長が義昭を擁して上洛した永禄11年(1568)以降を対象に,とりわけ義昭が京都から追放された元亀四(天正元)年から本能寺にて信長が斃れる天正10年までの期間を中心として,信長と朝廷・天皇とのあいだに起きた事件・できごとを,一つ一つ丁寧に,史料にそくして考えてその歴史的意義をとらえ直し,最後にそれらを総合したうえでの信長の統治者(天下人)としての姿勢をうかがうという構成をとる。」
という。すでに,岐阜城・安土城の発掘がすすみ,その意図を推測する成果がでており,
岐阜城の庭園の室町将軍帝都の類似
安土城の正面の真っ直ぐな大手道に,当初から天皇行幸を構想した城造り
等々が指摘され,専売特許のように言われた,
楽市楽座
も,信長の創意というよりは,戦国大名領国で実施されている政策の継承という見方がされつつあり,さらには,領国支配のやり方も,他の大名と比較して先進性がなく,むしろ遅れていたとする考え方が,戦国大名研究の中で形成されつつある,という。
そこで,「天下統一を目指したのか」という問いについては,
天下布武
という信長の印章にも使われた,
天下
という言葉の意味が問題になる。
天下の意味には,(神田千里氏の整理によると)
①地理的空間においては京都を中核とする世界
②足利義昭や信長などの特定の個人を離れた存在
③大名の管轄する「国」とは区別される将軍の管轄領域を指す
④広く注目を集め「輿論」を形成する公的な場
の四つがあるが,「天下」の領域は,五畿内であるとするのが通常らしい。ただ,
戦国時代は,③の「将軍の管轄領域はほとんど京都を中核とする世界に限定されていた」という意味では,③と①は同義になる。で,
「信長の時代における『天下』の認識はここから出発しなければならない。」
とすると,天下布武の「天下」は何を意味していたのか。もしそれが,従来いわれているように「全国統一」なら,他の戦国大名に喧嘩を売るというか,宣戦布告しているようなものだ。
だから,(神田千里説に従えば)
「『天下布武』とは,足利義昭を連れて入京し,畿内を平定して凱旋するという一連の戦争を遂行した結果,将軍を中心とする畿内の秩序が回復することを勤める。」
という永禄11年に実現した状況を指す,のだという。そして,上洛後の信長の政治理念は,
天下静謐
だと,著者は考える。それは,
「室町将軍が維持すべき『天下』の平和状態を,のちに義昭や信長自身が発給文書のなかで用いる言葉」
でもある。そして,
「信長は天下静謐(を維持すること)を自らの使命とした。」
と見る。
「当初はその責任をもつ義昭のために協力し,義昭が之を怠ると強く叱責した。また対立の結果として義昭を『天下』から追放したあとは,自分自身がそれを担う存在であることを自覚し,その大義名分を掲げ,天下静謐を乱すと判断した敵対勢力の掃討に力を注いだ。」
太田牛一の『信長公記』の,「足利義昭を擁して上洛した永禄11年(1568)から没する天正10年(1582)まで,一年を一巻(一冊)で記した15巻本の自筆本のひとつ…池田家文庫本…の巻一(永禄11年)に」,
信長公天下十五年仰せ付けられ候。愚案を顧ず十五帖に認め置くなり。」
という奥書がある。別の自筆本では,
「信長京師鎮護十五年,十五帖の如くに記し置き候なり。」
ともある。つまり,「天下を十五年にわたりお治めになったといった意味」となる。側近くにいた,太田牛一からみれば,
「十五年間の信長の役割は,信長の死から二〇年ないし三〇年後の牛一にとって,『京師警護』,『天下を仰せ付けた』と認識されているのである。」
ということになる。その時代のうち,
「義昭を『天下』から追放した天正元年以降の十年間,信長と天皇・朝廷とのあいだでおきたむさまざまなできごと」を,具体的には,
天正改元
正親町天皇の譲位問題
蘭麝待切り取り
右大臣任官
絹衣相論
興福寺別当職相論
左大臣推認
三職推認
を丹念にたどりながら,信長の行動基準は,あくまでも天下静謐の維持という点にあった」ことを,描き出している。その点から見ると,秀吉の全国統一は,諸大名を鉢植化したところからも,
「信長と秀吉の間にはおおきな断絶がある」
と著者は見る。この面から,秀吉の事跡は別の証明があてられる必要があるのかもしれない。
ただ,著者は,本能寺の変が,用意なく,大童で遂行されたことに着目し,五月に,朝廷がというより,正親町天皇が,
「征夷大将軍に推認」
しようとした事実に注目する。信長がそれにどう返事したかは,どこにも記録がない。しかし,四国攻めが「天下静謐」とは関係ないところから発せられているということに疑問を呈し,将軍を意識した行動ではないか,と推測する。
あくまで,「天下静謐」という仮説を前提にすれば,ということだが,信長の中で,
天下
がいつの時点かで,全国に変わったという境界線があるのではないか,という受け止め方をすると,興味がわく。まだ,これについては,明確な答えは出されていない。
天下の意味が,五畿内から,途中で,全国統一に変わったとする説は,他でもあった,その変化を,信長がどこで,麾下の武将たちに明言したのか,それが秀吉にどう受け継がれたのか,と問題意識の立て方を変えると,本書は,その端緒に立っている気がする。その視点で見ると,本能寺の変にも別の光が当たるのではないか。
参考文献;
金子拓『織田信長〈天下人〉の実像』(講談社現代新書) |
|
自己認識 |
|
ミシェル・フーコー『主体の解釈学』を読む。
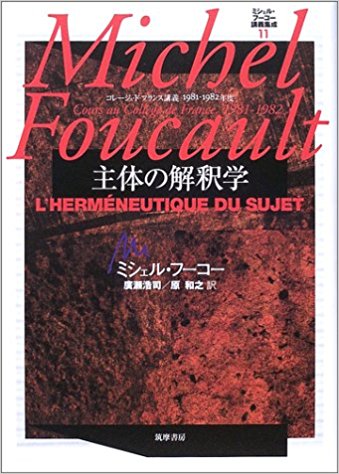
本書は,1982年,コレージュ・ド・フランスで行った講義録である。編纂者の,フレデリック・グロは,
「フーコーは,獲得された研究成果について話すというよりは,ほとんど手探りするようにして,探求の進行を一歩一歩伝えようとするのである。講義の大部分の時間は,彼が選んだ文献の粘り強い読解と,その逐字的な注釈に充てられる。講義ではいわば『仕事中』のフーコーがみられるのだ。」
と,この年の講義の特異性を伝えている。そのせいか,たびたび,フーコー自身,
今日も少し立ち止まってみたいと思います。
ちょっと枝葉末節にこだわり過ぎて申し訳ありません。
みなさんにはあまりにも細かすぎて,足踏みしているような印象を与えるかもしれませんね。
等々と断りを入れている。確かに,あまりにも微に入り細に渉って,ギリシャも,ヘレニズム・ローマも,キリスト教にも,まったく学識のない自分がついていくのは大変だったが,そうか,ここまで綿密に,細心に文献を読みこんでいくのか,という,フーコーの学者としての読みの深さと視野の広さに同時進行で立ち会った気分ではあった。
本講義は,フーコー自身,まだ未完のまま,
自己への配慮
という観念を取り上げるところから,始まる。そして,ギリシャの
汝自身を知れ
との関係へと踏み込んでいく。通常考えている,「汝自身を知れ」は,デカルト以来というべき,
自分を見つめ,
自己の中に自己を見つめ,
そこに主体の真理を解釈する,
といった,「反省の病」(訳者)ともいうべき,自己との関係にある,自己認識,自己解釈とは別の,
自己との関係を結ぶことができるのか,
という問いへのフーコーなりの解答なのだといってもいい。
それは,キルケゴールの,
人間は精神である。しかし,精神とは何であるか?精神とは自己である。しかし,自己とは何であるか?自己とは,ひとつの関係,その関係それ自身に関係する関係である。あるいは,その関係に関係すること,そのことである。自己とは関係そのものではなくして,関係がそれ自身に関係するということである。
という,自己の中に自己完結して,入子のように入り込んでいく,自己との関係とは別のありよう,という意味と言ってもいいのかもしれない
しかし,それを,細部にわたって解釈したり咀嚼していくことは,到底僕の力の及ぶところではない。そこで,フーコー自体が,最終講義で,こうまとめているところから始めたい。
「本年度の授業で私が特に示そうとしたことは,次のことです。フランスの歴史的伝統や哲学的伝統においては―このことは西欧一般に妥当すると思われますが―,主体や反省性や自己認識などの問題の分析全体の導きの糸として特に重視されていたのは,〈汝自身を知れ〉という自己認識でした。しかしこの〈汝自身を知れ〉ということだけを独立して考えてしまうと,偽の連続性が打ち立てられ,うわべだけの歴史が作られてしまいます。つまり,自己認識の連続的な発展のようなものが考えられてしまうのです。この連続的発展は二つの方向で復元されます。第一に,プラトンからデカルトを経てフッサールに至る,根源性という方向,第二に,プラトンから聖アウグスチヌスを経てフロイトに至る経験的拡張の方向での連続的な歴史です。このどちらの場合も,〈汝自身を知れ〉を導きの糸としており,そこから根源性ないし拡張へと連続的に展開されるのです。しかしどちらの場合も,明示的にであれ,暗黙の内にであれ,主体の理論が練り上げられずに背後に残されてしまいます。」
つまり,「汝自身を知」ろうとすることではなく,「汝自身を知」るとはどういうことかが,取り残されている,といいうのである。そのために,フーコーがここでしようとしたのは,
「この〈汝自身を知れ〉を,ギリシャ人が〈自己への配慮〉と呼んだものの傍らにおくこと,さらに自己への配慮という文脈や土台の上に置くことなのです。」
そして,
プラトン主義的モデル(想起のモデル)
キリスト教モデル(自己の釈義と自己放棄モデル)
ヘレニズムモデル(自己の関係の自己目的化モデル)
の三つ(の仮説)を立てて,自己と自己との関係性の在り方を掘り下げていくことになる。
プラトン『アルキビアデス』で言っている〈汝自身を知れ〉は,
「魂が自分の本性そのものを知ること,そしてそれによって魂と本性を等しくするものに到達することであることに気づかされます。魂は自分自身を認識します。そしてこの自己認識の運動において魂は,記憶の底ですでに知っていたことを再認するのです。魂は自分自身を認識します。したがって〈汝自身を知れ〉という様態においては,次のような自己認識が問題になっているのではないことは強調しておきたいと思います。つまり,自己の自己への関係,自分自身に向けられた視線が,内的な客観性の領域を開き,そこから魂の本性とは何かを推論する,ということではないのです。そうではなく,魂とはその固有な本質において,そして固有な実在性において何であるのかということを認識すること以上のことではなく,またそれ以下でもないのです。そしてこの魂の固有な本質の把握が真理を開示してくれる。この真理は,魂を認識対象とするような真理ではなく,魂が知っていた真理なのです。」
として,
「人が自己を知るのは,すでに知っていたことを再認するためなのです。」
そして
「自分自身を認識しなければならないのは,自己に専心しなければならないからです。」
と言う。で,(プラトン主義的モデルでは)
「第一に,自己に配慮しなければならないのは,人が無知だからです。人は無知であり,自分が無知であることを知らないのですが,(出会いや出来事や問いかけの結集として)自分が無知であること,無知であることに無知であることを発見するのです。……そこで自分に専心することによって,この無知に対抗しなければならないこと,あるいは無知に終止符を打たなければならないことさえ発見するのです。これが第一点です。自己への配慮という命法を生じさせるのは,無知の発見,無知の無知の発見なのです。」
そして,第二点は,
「自己への配慮が肯定され,誰かが実際に自己を気づかおうと企てた瞬間に,自己への配慮は『自分自身を知る』という点に集約されます。自己を知れという命法が自己への配慮に覆い被さるのです。自己の認識は,魂が自分自身の存在を把握するというかたちをとります。魂は叡智界の鏡の中で自分を見ることによって自己を認知し,自分の存在を把握するのです。」
そして第三点。
「自己への配慮と自己の認識の接点にあるのが,ほかならぬ想起なのです。魂が自分の存在を発見するのは,自分が見たものを思い出すことによってです。プラトン主義的な想起においては,自己の認識と真実を知ること,自己への配慮と存在への回帰が,魂の一つの運動の中で合流し,まとめられている…。」
これに対して,キリスト教的(修徳的・修道院的)モデルが,三,四世紀につくられる。その特徴は,
「聖書」に書かれ神の言葉や,啓示によって与えられた真理を知るために,心の浄化をする,ということが自己認識の前提となっており,その特徴は,第一に,
「自己を知ることと真理を知ることと自己への配慮の関係は循環的になっています。」
つまり,
「天獄で救われようと思うのなら,〈聖書〉に書かれていたり,〈啓示〉によつて現れたりする真理を受け入れなければなりません。しかしこの真理を知るためには,心を浄化するような知というかたちで自分自身を気づかっておかなければならない。反対に,こうした自分自身による自分自身の浄化的な知が可能になるためには,〈聖書〉や〈啓示〉の真理とすでに根源的な関係を持っていることが条件になっているのです。キリスト教においては,この循環こそが,自己への配慮と自己認識の関係についての根本的な点であるとおもわれます。」
第二点は,
「キリスト教では,自己の認識はさまざまな技法を通して実践されます。この技法の持つ本質的な機能は,内的な幻想を吹き払うこと,魂と心の内部に作られる誘惑を認めること,そしてひとが陥りかねない誘惑を失敗させることにあります。そのためには,魂の中に広がるプロセスや動きを解読するための方法が必要になります。この解読によって,こうしたプロセスや動きの起源や目的や形式を把握するわけです。」
つまり,自己の釈義が必要になる,ということである。第三は,
「キリスト教では,自分自身に返るのは,本質的かつ根源的には自己を放棄するためです。」
プラトン主義とキリスト教の間にかくされていたモデルが,ヘレニズム的モデルである。その特徴は,「自己を到達すべき目標としてたてようとした」というところにある。セネカやマルクス・アウレリウスを例にすると,
哲学には,「人間にかかわる,人間に関係する,人間を見る部分がある。哲学のこの部分は,地上で行うべきことを教える。」もうひとつは,「人間を見るのではなく,神の方を見る。哲学のこの部分は,天上で起きていることを教える。」
この両者の議論の順番は,
「まず自分自身を吟味し,考察すること,そして次に世界を吟味し,考察すること,」
なのである。「人間に関する哲学と神々に関する哲学」の順番の理由は,
「第二のももの(神々に関する哲学)だけが,第一の哲学(人間に関して何を為すべきかを問う哲学)を完成できるのです。…第一の哲学は…人生の中で不明確なさまざまな道を見極めるための光明をもたらしてくれる。…第二の哲学は,闇から私たちを引き離し,光源にまでみちびいてくれるのです。」
ここで言っていることは,
「主体の現実的な運動,魂の現実的な運動です。この運動が,この世界を形づくる闇から引き離し,世界を越えたところに上昇させてくれるのです。」
これは,言ってみると,主体自身の運動,メタ・ポジションづくりといっていい。この運動は,
「第一に,自分自身から逃れ,自分自身から身を引き離す運動であり,こうして欠点や悪徳からの離脱」
を果たすことになる。第二は,
「光がそこからやってくる地点への運動は,神へ私たちを導いてくれるのですが,だからといって,神において自分自身を喪失してしまったり,神においてみずからを滅ぼしてしまったりすることもない。そうではなく,私たちは神との本性の共有,神と共同して働くことへといたるのである。…つまり人間理性は神の理性と本性を同じくしているのです。…神が世界に対してなしていることを,人間理性は人間に対してなさねばなりません。」
第三に,
「このように光まで連れて行き,私たち自身から引き離し,神との本性の共有にまで導いてくれる運動において,私たちは最も高い地点まで昇ることになります。しかし同時に…その瞬間にこそ私たちは,まさに自然の最も奥深い秘密に分け入ることができるのです。」
僕には,すべてが理解できているわけではないが,フーコーが,セネカに代表されるヘレニズムモデルに,あらたな主体のありようを見ている,というように見えた。この運動は,
「この世界から離れて,どこか別の世界へ行こうとしているのではありません。現実から身を引き離して,なにか別の現実であるようなものに到達することではないのです。…世界の中でおこなわれ,世界の中で実現される主体の運動なのです。…この運動は,神と本性を共有する私たちを,頂上まで,この世界の最も高い地点に連れて行きます。この世界の頂上にいるとき,まさにそのことによって,自然の内奥が,秘密が,懐が,私たちに明らかにされるのですが,その瞬間にも私たちはこの世界を離れることはないのです。(中略)私たちは神が世界を見ている視点に到達しますが,この世界に対して本当には背を向けることなはしに,私たちが属している世界を見るのであり,したがって私たちは,この世界における私たち自身をみることができるのです。」
だから,視点の運動なのだと思う。自分対して,自分のいる世界に対して。だから,
「自分を知るためには,自然に対する視点を持っているという条件が必要」
であり,ここで言う自己認識は,自己分析とは無縁なものであり,
「自然についての知が解放的な効果を持つ」
のである。つまり,
「自然についての知,世界を踏破する大いなる視線,また私たちがいる場所から退き,ついには自然全体を把握するに至る視線…」
のことを指している。間違いなく,自己完結した自己対話を指していないことは確かであり,セネカの目指していることは,
「世界から離脱して,そこから目をそらし,別の現実を見ようという努力ではないのです。そうではなくて,中心的であると同時にひじょうに高い一点に身を置き,世界の全体的な秩序,私たち自身がその一部をなしているような全体的な秩序を見下ろすことなのです。…すなわち,世界認識そのものの努力,できるだけ高く身を引き上げ,そこから全体的な秩序としての世界を,…見下ろそうとする努力なのです。すなわち俯瞰的な視点であり,…この自己の自己への俯瞰的視点は,私たちが一部をなすこの世界を包み込み,そうしてこの世界そのものにおける主体の自由を保障してくれるのです。」
この主体における視点の運動は,そのまま認識の運動でもあり,それが単なる閉塞した自己認識でないことは,よく見える。その流れというか,そこに力を入れるフーコーが,この講義自体で,ハイデガーと対決をはかり,講義最後で,
「西洋哲学の問題がこのようなもの―すなわち,世界はいったいどのようにして認識の対象であると同時に主体の試練の場ともなりうるのかという問題,テクネー(技法)を通して世界を対象として自分に与えるような認識の主体があり,また,この同じ世界を,試練の場という全く異なった形式で自分に与えるような自己経験の主体があるということはどういうことなのか,という問題―だとしましょう。もし西洋哲学への挑戦がこのようなものだとするならば,なぜ(ヘーゲルの)『精神現象学』がこの哲学の頂点にあるかがよくおわかりでしょう。」
と述べて,ヘーゲル『精神現象学』を復権させた,その背景が,よく見えてくるような気がする。『精神現象学』を若いころ,ひとりで,逐語的に読んだときの,その朧な記憶から見ると,そこにある自己というものの,あるいは,自己と自己との関係の深さと奥行きというものは,現象学的な自己完結の世界に比して,圧倒的な広がりがあることだけは確かに思える。と同時に,昨今はやりの「自己」「自己対話」「自己発見」が,いかにうすっぺらで,何周もの周回遅れの気がしてならない,日本の精神風土の貧弱さを思わざるを得ない。
まあそれはさておき,セネカの運動のためには,様々な訓練が必要で,その一例として〈死の省察という訓練〉というのがある。この訓練は,
「ある一日に一月,一年,さらには人生全体が流れてしまうかのようにその一日を生きる,という訓練です。そして生きつつある一日の各時間は,人生の年齢のようなものであるのだから,夕べに至ったとき,ひとはいわば人生の夕べ,まさに死ぬ時に至っている。これが最後の日という訓練です。この訓練は,…一日の各時間が人生という長い一日の瞬間であるかのように,一日の最後の瞬間が人生の瞬間であるかのようにして自分の一日を組織し経験することなのです。このようなモデルにしたがって一日を生きることがてきたならば,一日が終わって眠ろうとする瞬間に,『私は生き終えた』と,喜びとともに笑顔で言うことができるのです。」
これに倣ったマルクス・アウレリウスは,
「最高の人格とは,日々をおのが終焉の日のごとく暮らすことだ」
と書いている。ここには,瞬間に対する俯瞰的視点と,生全体に対する回顧の視点がある。視点の運動とは,こう言うことを言うのだろうと,思う。
大事なことは,この三つのモデルは,いずれも,
自己自身による自己自身の変容
ということである。それは,
いかにして真理を語る主体
たりえるかという,実践的な真摯な問いである。こういう問いは,和辻哲郎が羨望を込めて言った,西欧の,
視圏
に関わるように思える。そういう視点は,日本人には,持てるのか,いや,持ったことがあるのか,読むにつれて,おのれの薄弱な自己基盤(コーチングでいうファウンデーションのことではない,この世界を俯瞰するに足る知の不足のことだ)に,身震いした。それは,自己認識する自己の視点のことであり,見られる自己のことでもある。
参考文献;
ミシェル・フーコー『主体の解釈学』(筑摩書房) |
|
家臣 |
|
谷口克広『信長・秀吉と家臣たち』を読む。

谷口克広氏の近刊『信長と将軍義昭 -
提携から追放,包囲網へ』を予約購入する際,つい間違えて,一緒に購入してしまった。
実は数年前,新書版で読んでいるはずで,それを失念して,タイトルだけで,Kindle版でまた購入してしまった。こう言うことは,恥ずかしながら,結構ある。読んだことを忘れている。購入してから書棚にあることに気づく場合もあるが,読みだしても気づかない場合もある。どこかで読んだような,と思って初めて気づくこともある。読んでいないで,積読だと,同じ本を何冊も購入したこともある。
こんなレベルの読み方なので,右から左へ,読み飛ばしているから,身になってはいない。
今度は,秀吉,信長からすこし外して,家臣という側面に焦点を当てて,読み直してみた。
信長と秀吉の関係をみるとき,いつも思い出すのは,信長の,秀吉正妻おねへの手紙である(というよりは,返事である。ということは,おねが秀吉の浮気を訴えた手紙が存在するということになるが)。
「藤吉郎れんれん不足の旨申すのよし,言語道断曲事候か。いず方を相尋ね候とも,それさまほどのは,又再びかのはげねずみ相求め難き間…これより以後は,身持ちようかいになし,いかにもかみさまなりに重々しく,悋気などに立ち入り候ては,然るべからず候」
おねをなだめつつ,やきもちをたしなめている手紙である。よく,信長の気遣いの例として出されるが,それ以上に,秀吉及びおねへの(ただならぬ)厚意を感じる。他に,こうした,個人的な家臣の妻にあてた手紙があるのかどうか知らないが,おねがそういう手紙を直々,信長に出して個人的なことを訴えられる関係が面白い。そこには,おねと信長の関係以上に,「はげねずみ」と呼ぶ秀吉への信長の親しみを,ここから感じる。
では家臣としての,秀吉はどういう家臣だったのか。
秀吉が,確実な史料に登場するのは,永禄八年(1565)で,
「尾張と美濃の境目に本拠地を構えている坪内氏に宛てた証文で,信長が坪内氏に発給した宛行状の副状である。当時秀吉は二十九歳だが,もう信長の奉行人ないし武将格にまで出世している。」
微賤の身から小者として仕えた秀吉は,後に小早川隆景に手紙で書いたように,「家中のものの真似のできない」ような「寝る間も惜しむ」働きぶりを示す。著者はこう書く。
「宣教師ルイス・フロイスも言っているが,信長は早起きである。それに,突然たった一人で駈け出すこともある。側近にしてみれば,常に目を離せない主君なのである。秀吉は小者ながらも,まず直接信長に知ってもらい,次には目を懸けられるよう一生懸命に努めたものと思う。おそらく睡眠時間を大幅に削って頑張ったのだろう。」
と。ついに,天正元年(1573),小谷攻めの功で,北近江三郡を与えられる。十二万石の一国一城の主となる。さらに,天正八年,播磨,但馬を与えられ,五十万石大大名になる。その動員兵力は,備前・美作の宇喜多直家の軍と合わせると,三万になる。
著者は言う。
「信長は能力至上主義者だから,低い地位の者を抜擢した例はたくさんある。それにしても,秀吉ほどの出世は類がない。出発点が小者の身分で,最後は(中国)方面軍司令官にまで登り詰めるのだから,これ以上ありえない出世である。小者なら小者の仕事,奉行なら奉行の仕事を常に全うするし,部隊指揮官に出世したなら,戦いの中で自分の指揮する部隊を最大限に生かそうとする。天賦の才に恵まれていたのは確かだが,それ以上に,現実を直視しながら他人の何倍も努力を心掛けていたというのが,秀吉の出世の秘訣であろう。」
と。あの信長が,秀吉のおべっかなんぞに欺かれはしない。そうではない,陰日向のない勤勉さと努力を,よく分かっていたのだと思う。
「例えば,元亀元年から天正元年までの三年間,秀吉は浅井攻めの最前線である横山城に置かれる。何度も敵の逆襲をしのぎ,見事にその地を守り抜く。その多忙の間,秀吉が畿内の地に発した文書が二十点近くも見られるのである。度々京都に上っていたことがわかる。」
あるいは,こんなエピソードがある。播磨攻めの最中のことである。
「秀吉の猛烈な働きを見て,信長は,……いつになく優しい手紙を秀吉宛に送る。
『よく働いた。戻ってきて一服せよ。』
しかし,秀吉はきかない。
『いえ,このぐらいでは,たいした働きではありません。』
とせっかくの慰労を断って,隣国の但馬まで攻め込み,いくつかの城を落とすのである。
秀吉が安土に報告に上がるのは,十二月になってからだった。ちょうど信長は三河に鷹狩りに行っていたが,出発する前,秀吉が来たら褒美として渡すように,と天下の名物『乙御前釜』を用意していた。信長がこれほど家臣に気を遣うことは珍しいことである。」
この主従の関係は,阿吽の呼吸に見える。
「秀吉は,信長の家臣としての務めについてよく知っていた。思い切り働いて成果を上げさえすれば,信長は必ず認めてくれるということを心得ていたのである。」
だから,
「三木城攻めの時も秀吉は,ずっと不眠不休の努力を続けた。二年近くの攻囲の末ようやく攻略した後,彼は有馬温泉に行き,二日二晩眠りつづけたという。」
では,秀吉の家臣は,どうか。例の高松を撤退した秀吉は,一日一夜で姫路城まで戻る。そこで交わされた会話が,『川角太閤記』に出ている。
「風呂からあがった秀吉は,城に蓄えていた金銀や米をすべて家臣に分け与え,籠城の覚悟のないことを示す。そして,(信長馬廻りで,監察として派遣されていた堀)秀政に向かって次のように宣言する。
『此の度,大博奕を打ち,御目に懸くべき候』
それに対する秀政の弁,
『御意の如く,世間の為体(ていたらく),博奕も成目に来たり,風も順風と見え申し候。帆を御上げなさるべく候。こなたなどの御身上からは,か様の時,二つ物懸の御分別御尤もかと存じ奉り候』
この秀政の言葉の後,側にいた(祐筆の)大村由己が,『名花の桜,唯今,花盛りと見え申し候,御花見御尤もかと存じ奉り候」,さらに黒田孝高が『殿様には御愁嘆の様には相見え候得ども,御そこ心をば推量仕り候。目出度き事出で来るよ』と…」
秀吉をあおったという。問題は順序である。秀政は,信長のトップクラスの側近である。黒田は,秀吉の与力に過ぎない。秀政の発言こそが,この場では意味がある。そして,この両者の関係こそが,のちのち,天下取りに大きく寄与する。山崎では,秀政は,一手の指揮を執り,中川瀬兵衛,高山右近を指揮する。清州会議の結果,信長家家督が三法師となると,秀政は,その傅役となり,秀吉を支えることになる。
ついでながら,秀吉の家臣のように扱われているが,黒田官兵衛も,竹中半兵衛も,蜂須賀小六も,直臣ではない。あくまで,秀吉与力として信長から派遣されている。弟小一郎もまた,あくまで与力である。秀吉ではなく,信長の家臣である。その意味で,いわでもがなだが,半兵衛は軍師ではない。半兵衛の子,重門の書いた,『豊鑑』にもそんなことは書かれていない。『信長公記』には,半兵衛死後,
「六月廿二日,羽柴筑前与力に付けられ候竹中半兵衛,播磨御陣にて病死候。其名代として,御馬廻りに候つる舎弟竹中久作播磨へ遣わされ候」
という記述がある。竹中家の家臣を統率させるという意味である。半兵衛が,軍師でなければ,官兵衛が軍師であるはずもない。
参考文献;
谷口克広『信長・秀吉と家臣たち』(学研新書) |
|
自己目的 |
|
豊下樽彦・古関彰一『集団的自衛権と安全保障』を読む。
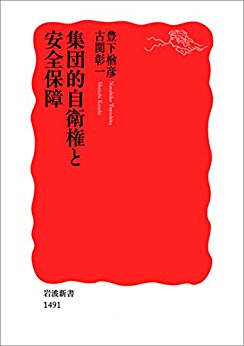
豊下樽彦・古関彰一『集団的自衛権と安全保障』を読む。
冒頭で著者は,憲法解釈の変更についての,記者会見で,具体的な例を挙げたとを取り上げた。それは,
「事実上朝鮮半島有事を想定しつつ,避難する邦人を救助,輸送する米艦船が攻撃を受けた場合」
であった。そして,
「このような場合でも日本自身が攻撃を受けていなければ,日本人が乗っているこの米国の船を日本の自衛隊は守ることができない」
と述べて,集団的自衛権行使ができない現状では,国民を守れない例とした。しかし,基本的に,これは,嘘である。いろんな意見がすでに出されているが,著者は,
「実はこうした事例は,現実には起こりえない。なぜなら在韓米軍が毎年訓練を行っている『非戦闘員避難救出作戦』で避難させるべき対象となっているのは,在韓米国市民14万人,『友好国』の市民八万人の計二二万人であり,この『友好国』とは,英国,カナダ,オーストラリア,ニュージーランドというアングロ・サクソン系諸国なのである。」
つまり,
「朝鮮半島有事において米軍が邦人を救出することも,ましてや艦船で避難させることも,絶対ありえないシナリオなのである。」
にもかかわらず,平然と,
「お父さんやお母さんや,おじいさんやおばあさん,子供たちかもしれない」という情緒で,訴えたのである。著者は,
「こうしたトリックまがいの手法をとらざるを得ないところに,安倍首相が主導する集団的自衛権をめぐる議論の“支離滅裂さ”が象徴的に示されている」
という。僕はそうは思わない。論理が破綻しようが,支離滅裂だろうが,説明した実績だけが残る。ある意味,国民を馬鹿にし,見下し,いずれついてくる,と思っている節が見え,そちらの方が,半ば事実になりつつある現状を見ると,空恐ろしい。
あるいは,「安倍首相が“執念”をもやす」機雷掃海についても,同じことが見て取れる。著者は言う。
(想定されているらしい)「ホルムズ海峡は,オマーンあるいはイランの領海によって占められ公海は存在しないのである。とすれば,安倍首相の公約(海外派兵は致しません,を指す)に従えば,海上自衛隊の掃海艇はホルムズ海峡の手前で引き返してこなければならず,そもそも掃海活動など行えないのである。」
と。しかし,論理的矛盾,奇奇怪怪の「ためにする議論」であろうと,蟻の一穴という既成事実を積み重ねるための詐術といっていい。著者は,
「公海の存在しないホルムズ海峡での機雷掃海というシナリオの立て方それ自体のなかに,自ら宣言した公約を簡単に破棄してしまう意図が当初より孕まれているのである。」
という。というより,その意図を実現するための詐術としての論理でしかない。いや,論理というより,こじつけである。
著者は,こう嘆息する。
「なぜ集団的自衛権をめぐる議論は,これほどリアリティを欠いているのであろうか。それは,本来であれば何らかの具体的な問題を解決するための手段であるはずの集団的自衛権が,自己目的となってしまっているからである。」
そして,こう付け加える。
「それはつまるところ,集団的自衛権の問題が,安倍首相の信念,あるいは情念から発しているからである。」
それはまさに,国家の私物化である。おのれの実現したいことが,国民の望まないことであっても,何が何でも,実現してしまおうというのは,北朝鮮同様の独裁国家になりつつあることを示している。
集団的自衛権を足掛かりに,目指していることは,
戦後レジームからの脱却
である。著者は言い切る。
「最大の眼目は,青年が誇りをもって『血を流す』ことのできるような国家体制を作り上げていくところにある」
と。そこには,現象的には,靖国参拝,「村山談話」「河野談話」の見直しとして現れ,そこから仄見えてくるのは,
東京裁判史観からの脱却
という課題の具体化なのである。自民党憲法改正草案,国家安全保証基本法などにみられるのは,
「サンフランシスコ講和条約を基礎として米国が作り上げてきた戦後秩序そのものへの挑戦」
であり,だからこそ,
「米国主導の戦後秩序を否定する信条と論理を孕み,それに共鳴する広範な支持基盤を有した政権が初めて登場し,いまや日本を担っているのである。」
と著者は危惧を示している。
「これこそ,日本の孤立化が危惧される所以であり,日本をめぐる安保環境の悪化をもたらしている」
と。その危惧は,ジャパンハンドラーの一人として,アーミテージらとともに,集団的自衛権行使できるよう,介錯改憲を求めてきたはずの,元国防次官補・ジョセフ・ナイの,
「集団的自衛権が『ナショナリズムのパッケージで包装』される,つまりは,『好い政策が悪い包装』で包まれるならば近隣諸国との関係を不安定にさせるので反対である,との立場を表明した」
発言に見ることができる。著者は,
「ジャパンハンドラーの最大の誤算は,日本が集団的自衛権を解釈変更して海外での武力行使に踏み出すことを強く主張する政治勢力が,実は,『東京裁判史観』からの脱却というイデオロギーによって色濃く染められていることであった。」
と。それは,アメリカが築き上げた戦後秩序への挑戦なのである。だから,日本に続いて韓国を訪れたオバマ大統領は,日本に明確な警告を発した。
「従軍慰安婦問題について『恐るべき言語道断の人権侵害』と断じ,その上で,突如として安倍首相の名前を上げ,『(首相は)過去というものは誠実かつ公正に認識されなければならないことを分かっている,と考える』と,異例の形で厳重に
“釘をさした”のである。これは,安倍の「歴史修正主義は断じて許さない」というオバマの宣言とみることができる。」
そして,安倍の進める集団的自衛権に対して,「歓迎する」と言いつつ,
①「日米同盟の枠内」であること
②近隣諸国との対話
という厳重な二条件を課した。
「要するに,集団的自衛権の行使は米軍の指揮下で行われねばならないこと,しかしその前提として,中国や韓国との『対話』が不可欠の条件である」
ということである。結局,
「米国の政権は,中国や北朝鮮の脅威を煽りたて日本を米国の軍事指揮下に“動員”しながら,現実には,日米同盟の枠を越えたレベルから自らの国益に沿って行動」
するということである。これのどこが,誇れる国なのか。めざす戦後レジームからの脱却とはこういうことなのか?
在日米軍のために辺野古で着々と進めている工事と言い,どうも言っていることとやっていることが,支離滅裂。ただ国の岩盤を砕いている気がしてならない。
参考文献;
豊下樽彦・古関彰一『集団的自衛権と安全保障』(岩波新書) |
|
奥行 |
|
今野真二『日本語の考古学』を読む。

著者は,
「『考古学』は……「(具体的な)モノを通して」過去の文化を考える学問だ…。本書ではこれから,日本語という言語を対象に『考古学』的なアプローチをしてみようと思う。ここで扱う『モノ』とは,写本や印刷物などの文献である。
過去の日本語を分析するためには,残された文献に就くことになる。…本書が扱うのは,かつて誰かが手で書き写した,あるいは活字を用いて印刷した,具体的なモノとしての書物である。
と「はじめに」で書く。つまり,電子化されたテキストではない,ということだ。なぜなら,
「例えば,同じ『土左日記』の写本であっても,写した人が違えば,漢字や平仮名の使い方が違っていることがある。もっと細かいことを言えば,同じ漢字でも書き方が違ったり,同じ文を書いていても改行箇所が違ったりする。あるいは書き間違えが含まれていたり,注釈のようなメモが書き加えられていたりする。使われている紙も異なる。このように,一つ一つの情報はささいなものだったとしても,そこには,過ぎた「時間」を復元するためのなんらかのヒントがあるのではないだろうか。」
と。だから,言葉としてのまとまりをどう意識していたかとか,どこを文章を区切るか(文のまとまりをどう意識していたか)とか,一つの行をどう意識するか(改行はどこで何を持って意識されたか)とか,等々細かな日本語の過去を洗い出す。そして,それは,
現在につながっている,
という。
たとえば,われわれにとっては,「楷書以外で書かれた漢字」に出会うことはないが,
「書体の歴史を考えたとき,楷書体はむしろ新しい書体である。中国において楷書体が成立したのは初唐だと考えられている。秦の始皇帝(中略)が統一してできた書体が『小篆』である。始皇帝が統一する以前の篆書から派生したものが『隷書』である。(中略)隷書を簡捷化した草隷…をさらに省略化した『草書体』がうまれ…,後漢に入ると盛行していたことがわかっている。隷書から草書が発生する過程で,現在の行楷書に当たる書体が派生し…楷書が完成するのが…初唐…と考えられている。」
朝鮮半島を経て伝わる中国文化は,中国と日本とでは,百年位のタイムラグがある。だからほぼ百年後,平城宮から出土した木簡は,楷書で書かれている。そう考えると,たとえば,現在残されている『万葉集』の西本願寺本(鎌倉時代後期に書写された)は,楷書体で書かれている。
「わたしたちが手にしている最古の写本と,『原万葉集』との間には,失われた時間が横たわっている,ということである。ほぼ楷書体しか知らない現代のわたしたちには想像もつかないような大きな『質的変化』がそこに秘められているかもしれない。」
と,さらに,
「今から一万年あまり前から縄文時代が始まったというみかたがある。社会生活をしているのだから,おそらくは日本語(につながるような言語)が使われていたと考えてよいと思うが,そうだとすれば,日本列島上で日本語は一万年以上使われていることになる。その中で,文献に日本語が足跡を刻むのは,七世紀以降で,現代までたかだか千五百年ぐらいということになる。その千五百年の中で,明治…以降はまだ百五十年にもみたない。局所的といっていもよい。しかしその明治期の日本語でさえ,…現代の日本語とは異なっている。わたしたちが思うほど,現代は絶対のものではない。」
たとえば,漱石の文庫本を,例にとると,まずは,表記が換えられている。
仮名遣いや用いている漢字など
が違うだけではない。著者は,「仰向」と言う表記を例に挙げる。最初の刊行(大正三年 岩波書店)では,
あふむけ
とルビがふられている。この時代の「あふむく」は,発音は,
アウムク
である。しかし,文庫本では,
あおむけ
とルビをふる。つまり,現代日本語としての発音を示したことになる。あるいは,
蒼い
は,
青い
に表記が換えられている。あるいは,
さうして
を
そして
に換えている例もある。印刷されたものについてですら,このような表記の転換が行われている。
「厳密に言えば『本文』を変えたことになるであろう。『作者』を,テキストの改変ができる唯一の人と定義するならば,このテキストの作者はだれということになるのだろうか。」
という著者は,夏目漱石ですらこれである。書き写しを繰り返した,たとえば,紫式部『源氏物語』,紀貫之『土左日記』(紀貫之は左の字を使っている)の作家となると,はなはだ覚束ないのではないか,と言っているのである。
そもそも書写原本とまったくおなじテキストを作ろうとして書写したとしても,不注意から写し損なうことも考えられる。あるいはちょっとした箇所について,原本に何らかの「錯誤」があるのではないかと考えて,書写者の判断で「本文」を変える可能性はつねにある。
藤原定家は,紀貫之の自筆本を,
もとのまま書いた
という。たとえば,
いひ/つかふものにあらすなり
いま/はとても見えすなるを
という文章について,為家筆者本では,
「『さ』には,漢字『散』を字源とする異体仮名(散)が使われているが,定家はこの〈散〉を『す』と判読している。(中略)定家にとって,仮名『さ』にあたる〈散〉はすでになじみのうすいものであった可能性がたかい。」
つまり,どんなにそのまま写そうとしても,
書く時に使用する仮名字体そのものも,変化している可能性がある
という制約があるということらしい。
こうやって一枚一枚薄皮を剥がすようにして,日本語の原風景を探っていく仕事は,実は,過去のことではなく,いまにつながっている気がしてならない。たとえば,繰り返しを示す,
「〱」
があるが,これを行の頭に持ってこないようにするという意識が,16世紀の鎌倉時代に書写された『竹取物語』に見える。いまだと,禁則処理として扱われることにつながる,意識である。
最後にもうひとつ,椿は,
ツ婆木
や
豆波木
と表記される。「木」は,
「『ツバキ』の『キ』という音ではなく,その『意味』において『椿』という樹木と関連づけられており,『万葉仮名』つまり仮名としてではなく,漢字として使われている…」
というのである。
都婆伎
とか
都婆吉
の表記の場合は,音を利用して書いている。つまり,
古代においてすでに,漢字「木」が樹木を指す日本語「キ」と強く結びついていた
わけである。その意味で,
エノキ
ヒノキ
のそれも,「木」が意識されなくなっている例と言えるらしいのである。
『新撰字鏡』をみると,漢字の和訓に万葉仮名が当てられている。
村 牟久乃木(ムクノキ)
槙 万木(マキ)
樟 久須乃木(クスノキ)
桐 支利乃木(キリノキ)
こうした背景にあるのは,その時代の語構成の感覚である。しかしその特徴は,
「『ミナト』に単漢字『港・湊』をあてるようになると,もともとは,『ミ(水)+ナ(助詞のノ)+ト(戸)』という語構成をなしていたことがわからなくなり,『まつげ』に単漢字『睫』をあてるようになると,もともと『マ(目)+ツ「助詞ノ+ケ(毛)」であることがわからなくなる。同じように,〈燃料にする木〉という語義の『タキギ』はよく考えれば,『タキ+キ』という語構成をしていることがわかる。動詞『タク』の連用形『タキ』に『キ=木』が複合している。現在では,単漢字『薪』をあてることがほとんどなので,『よく考え』ないと,そのことに気づきにくい。しかし『万葉集』には『燎木伐(たきぎこる)』…とある。『燎』字には〈やきはらう〉という字義がある。また,『多伎木許流(かきぎこる)』ではやはり,『タキギ』の『ギ』に『木』字が使われている。』
日本語の考古学は,このように丹念に,砂を払い,いわば,日本語の根っこ探っていく試みと言える。その奥行きの中に,いまの日本語がある,ということがよく伝わってくる。
語源が気になっている僕には,語源すら,日本語と表記として使った感じとの「音」を使ったり,「意味」で使ったりというその使い分けまで踏み込んでいくと,書くことと話すことの言葉の乖離にことばの深い奥行が見えてくる気がする。
参考文献;
今野真二『日本語の考古学』(岩波新書) |
|
家と血と藝 |
|
中川右介『歌舞伎 家と血と藝』を読む。

昨年の五代目歌舞伎座の杮葺落興業では21演目が上演され,演目ごとの配役表のトップ,つまり主役に据えられた役者は,十人。
坂田藤十郎,尾上菊五郎,片岡仁左衛門,松本幸四郎,中村吉右衛門,中村梅玉,坂東玉三郎,坂東三津五郎,中村橋之助,市川海老蔵,
である。しかし,この十人は,家としては,七家となる。
市川團十郎家(海老蔵)
尾上菊五郎家(菊五郎)
中村歌右衛門家(梅玉,橋之助,坂田藤十郎)
片岡仁左衛門家(仁左衛門)
松本幸四郎家(幸四郎)
中村吉右衛門家(吉右衛門)
守田勘彌家(坂東玉三郎,坂東三津五郎)
本書は,「この七家の家と血と藝の継承の歴史を描く」が,
「全体としては,明治以降現在までの歌舞伎座の座頭をめぐる権力闘争の歴史でもある。」
しかし,どういう権力闘争なのか,というと,
「『歌舞伎座の舞台で主役を演じること』を求めての闘争である。他の劇場で主役を演じることができても,歌舞伎座の舞台に立てなければ意味がないのだ。それは歌舞伎座が劇界で最高位の劇場だからである。そうなったのは明治以降でしかないのだが,逆に言うと,明治以降の歌舞伎の世界は歌舞伎座を頂点とした構造となっている。さらに,その歌舞伎座で主役を勤めることができるのも,いま挙げた七つの家が中心という構造になってしまった。」
何が主役を張る決め手になるかと言うと,「藝」ではあるが,「人気」も必要であるし,「政治力」も必要になる。
「歌舞伎の場合は,役者個人の『藝』や『人気』もさることながら,その『家』の歴史や格式といった要素が大きく左右する。……門閥で成立している世界といったほうがいい。そして,門閥を支えているのが『世襲』制度である。」
だから,七家は,親子関係だけでなく,「複雑きわまりない姻戚関係」によって,
「ひとつの巨大ファミリーを形成している。『歌舞伎役者の八割は親戚』である。」
という。しかし,
「この『世襲』『門閥』による七家寡占体制は,しかし,四百年続く歌舞伎史の最初期から続いているものではなく,この百年ほどの間に確立したものに過ぎない。」
本書は,まさに,この体制の形成史そのものになっている。
「戦国武将列伝の歌舞伎役者版を描つもり」
で,語られていく。その複雑な関係は,たぶん,振り返らないとよくわからない。たとえば,
「いまや歌舞伎界は七代目松本幸四郎の子孫なくしては成り立たない」
ほどと言われるが,その七代目は,三重県の土木業を営む家の子として生まれ,藤間流家元,二代目勘右衛門の養子となり,九代目團十郎の家に住み込むようになり,高麗蔵襲名,幸四郎襲名を果たした人物だ。著者は言う。
「七代目松本幸四郎の最大の功績は三人の息子を戦後を代表する幹部役者に育て上げたことだと言われる。ただ育て上げただけではない。三人を,市川宗家,中村吉右衛門,尾上菊五郎それぞれの後継者にまでしたのだ。すなわち,息子たちが十一代目市川團十郎,八代目松本幸四郎(白鷗),二代目尾上松緑であり,他に娘婿が四代目中村雀右衛門だ。そして孫が十二代目團十郎,九代目幸四郎,二代目吉右衛門,三代目松緑,八代目大谷友右衛門,七代目中村枝雀,曾孫が十一代目海老蔵,七代目染五郎,四代目松緑となる。」
と。これだけで,四家が関わることになる…。
さて,話を戻すと,本書は,「宗家」と呼ばれる團十郎家の,十二代團十郎の死から,語られていく。そして,最後は,中村勘九郎の息子・七緒八の,歌舞伎座での初舞台で締めくくられる。
「この勘九郎の子・七緒八は,初代中村歌六の六世代目の男系の男子にあたる。さらにこの子は尾上菊五郎家の血も引いており,三代目菊五郎から数えて八世代目,その父の初代尾上松助からだと九世代にわたり血脈が確認できる。五代目菊五郎は中村羽左衛門家に生まれているので,この子は十一代羽左衛門から数えると八世代目になる。さらに,祖母(十八代勘三郎の妻)が中村歌右衛門家の出なので,こちらをみると,五代目福助から五世代目になる。…これに横や斜めの関係もあるので,歌舞伎の幹部役者のほとんどが,彼の親戚である。」
しかし,
「歌舞伎の世界は世襲といえども,必ずしも実子が継いでいるわけではない。そして名家に生まれただけでは主役は務められない。名家だからと言って,いつまでも続くわけではない。」
という。たとえば,明治以降劇界で天下を取った役者,
「九代目團十郎,五代目歌右衛門,六代目歌右衛門に共通するのは,その名が自動的に与えられたのではなかったということだ。自分の力で獲得した名跡である。六代目菊五郎にしても,五代目の実子だが,義兄・梅幸を押し退けての襲名であり,その後に苦労があった。初代吉右衛門は父がいたとしても傍系の人で,彼が創業者に近い。みな,『役者の子』(養子を含む)ではあったが,エスカレーターに乗るようにして,出世したわけではない。」
坂東玉三郎は,「現在の幹部クラスのなかで数少ない『大幹部』の『実子』ではない役者」だ。
「このことは幹部の血縁でなくても才能と運があれば主役を勤められることの証拠ともいえる。しかし彼が今日のポジションに到達できたのは,徳川時代からの名門家の養子になったからでもある。その手続きを踏んでいなかったら,彼の今日のポジションはない。」
つまり,
「坂東玉三郎という当代随一の女形は,歌舞伎の可能性と限界と矛盾の象徴」
でもある。著者はこういう。
「二十一世紀になってもなお,歌舞伎の舞台では血統による世襲と門閥主義により,幹部役者の家に生まれた者でなければ主役を演じられない。逆に言えば,幹部の子として生まれれとりあえずチャンスが与えられ,誰の眼にも『あれはダメだ』と映らない限りは主役あるいは準主役としてでることができる。」
こんな箱庭の芝居に,いまを生きているものの息吹はない。いま一種の演劇ブームである。ものすごい数の小さな劇場に,若い人が押しかけている。その熱気とエネルギーは,歌舞伎座にはない。僕は,顰蹙を買うかも知れないが,税金で守らなくてはならないような伝統芸能は,いらないという主義だ。それはもはや死んだものだ。死んだものは,いま必要ではないということだ。囲われた「伝統芸能」は,いまという時代と格闘しない。そんなものは文化ではない。文化は過去にはない。いま,われわれ自身が,あらたな伝統の担い手なのであって,もしあるとするなら,そこにこそ,金を投入すべきだと考えている。亡くなった勘三郎は,そのことに敏感であった。コクーンで彼を観たとき,その熱意を感じた。しかし,それを継ぐ者はいない。歌舞伎が,そういう古典芸能に陥るかどうかの,いま瀬戸際にあるように思える。
参考文献;
中川右介『歌舞伎 家と血と藝』(講談社現代新書) |
|
言霊 |
|
佐佐木隆『言霊とは何か』を読む。
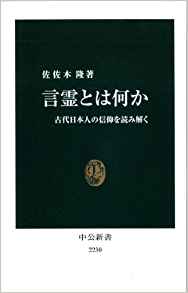
著者は,言霊の,一般的な理解の例として,『広辞苑』を引く。
「言葉に宿っている不思議な霊威。古代,その力が働いて言葉通りの事象がもたらされると信じられた。」
と。しかし,一見して,異和感がある。言と事をイコールと感じるからといって,誰の言葉でも,その言葉通り実現すると,信じられたのか,と。
著者は,
「古代日本人にとって『言霊』とはどんなものだったのかを具体的に検討」
するのを目的として,
「言葉の威力が現実を大きく左右したり,現実に対して何らかの影響を与えたりしたと読める材料のみを取り上げ」
て,
「言葉の威力がどのようなかたちで個々の例に反映しているのかを,『古事記』『日本書紀』『風土記』に載っている神話・伝説や『万葉集』に見える歌などを読みながら,一つ一つ確認していくことにしたい」
とまえがきで述べる。それは,結果として,言葉が一般的に霊力をもつという辞書的通念への批判の例証になっていく。
まず,「言霊」の「こと」は,一般的に,「事」と「言」は同じ語だったというのが通説である。あるいは,正確な言い方をすると,
こと
というやまとことばには,
言
と
事
が,使い分けてあてはめられていた,というべきである。ただ,
「古代の文献に見える『こと』の用例には,『言』と『事』のどちらにも解釈できるものが少なくなく,それらは両義が未分化の状態のものだとみることができる。
という。ただ,まず「こと」ということばがあったと,みるべきで,「言」と「事」は,その「こと」に当てはめられただけだということを前提にしなくてはならない。その当てはめが,未分化だったと後世から見ると,見えるということにすぎない。
「『言霊』の『霊(たま)』は,『魂』の『たま』と同じ語であり,
霊魂,精霊
のことだと,一般には説明されている。
で,「言霊」使用例(「言霊」を読みこんだ例は『万葉集』には三首しかない)の分析に入る。たとえば,
①神代より 言ひ伝て来らく そらみつ倭国は 皇神の 厳しき国 言霊の幸はふ国と 語り継ぎ 言ひ継がひけり 今の世の 人もことごと 目の前に 見たり知りたり…(山上憶良)
②志貴島の 倭国は 言霊の 佐くる国ぞ ま福くありこそ(柿本人麻呂)
③言霊の 八十の衢に 夕占問ふ 占正に告る 妹相寄らむと(柿本人麻呂)
これ以外に,『古事記』『日本書紀』『風土記』を含めて,「言霊」の確かな用例はないのだという。で,ここから,その意味をくみ取っていく。
③の「夕占問ふ」とは,「夕占」である。
「夕方,道の交差点になっている辻に立ち,そこを通行する人が発することばを聞いて事の吉兆・成否を占う,」
という意味である。おみくじを引いて,神意を知るのと同じというと,言いすぎか。
②は,その前の長歌をうけている。そこには,
「葦原の 瑞穂の国は 神ながら 事挙げせぬ国 然れども 辞挙げぞ吾がする 言幸く ま福いませと 恙無く ま福くいまさば 荒磯波 ありても見むと 百重波 千重浪しきに 言上げす 吾は 言上げす吾は」
とあり,①も②も,
「皇神(すめかみ)」「神(かむ)ながら」を承けたかたちで「言霊」という語が用いられている,ということである。
として,著者は,ここで用いられた
「『言霊』が神に対する意識と密接な関係があったことを物語る,」
として,こう説く。
「人間の口から発せられたことばが,その独自の威力を発揮し,現実に対して何らかの影響を及ぼす,といった単純な機構ではない。神がその霊力を発揮することによって,『言霊の幸はふ国』を実現し『言霊の佐くる国』を実現するのだというのが,(①と②の)『言霊』に反映する考え方なのである。」
当然,③の占いも,
「行為が向けられた相手は神であり,『占正の告る』の主体も神だということになる。つまり,人間が『占』を行って,神に『問ふ』のであり,神がそれに応じて『占に告る(占いの結果にその意思を表す)』のである。」
と述べ,『広辞苑』に代表される通説の説明は不十分で,
「(三例の)「言霊」は神を意識して用いられたものであるのに,…神とのかかわりが視野にはいっていない,」
と言う。そして,
「三例の『言霊』は,神がもつ霊力の一つをさすもの,」
と考えると,ことばに対する当時の日本人の考え方は,原始的なアニミズムを脱し,
「『言霊』については,早い段階で,人間には具わっておらず神だけがもつ霊力だと考えられるようになっていたのではないか」
と推測する。そして,以降,ことばの威力を,文献にあたりながら,
いかに神の霊力
を意識していたか,を検証していく。
呪文
祝詞
国見・国讃め
国産み
夢あわせ
等々を検討したうえで,
「本書では,ことばがその威力を発揮して現実に何らかの影響を与えた,と読める材料だけを古代の文献から集め,その内容を具体的に分析した。『古事記』『日本書紀』『風土記』の神話・伝説や『万葉集』の歌を見る限り,ことばの威力が発揮され,それが現実に影響を与えるのは,神がその霊力を用いる場合である。人間の発したことばを聞き入れた神がその霊力を発揮して現実に影響を与える,というかたちになっているのが普通である。」
とまとめる。つまり,
「人間の発することば自体に威力があって事が実現するのではなく,人間の発することばを聞き入れた神が事を実現してくれる…,」
というわけである。
「ことばに霊力がやどると信じたのは,人々の間で日常的に何気なく交わされることばではな(く)…儀礼の場で事の成就を願う非日常的な状況において,特別な意識をともなって口から発せられることばに霊力がこもる…」
ということである。上記の万葉三首以降,「言霊」をもちいた歌は,数えるほどしかない。そこでも,強く神対する意識がある。では,どこで,
「人間の発することばにまで拡大され,さらにまた,ことばそのものに霊力がやどるという解釈にまでかくだいされることになった,」
のか。著者は,江戸時代の『万葉集』で,上記三首の解説を調べる。
江戸時代前期,契沖の『万葉代匠記』
江戸時代中期,賀茂真淵『万葉考』
では,神との関係を明確に意識している。しかし,
江戸時代後期,橘千蔭『万葉集略解』
では,
この歌に神霊がやどって,
と,神意抜きの解釈に変わる。師の真淵が「神の御霊まして」という説明の神意をはき違えてしまったらしいのである。
これ以降,
言霊とは,ことばの神霊のことであり,発することばにおのずから不思議な霊力がある
というように変わっていく。それは,とりもなおさず,
自然や神への畏れ
をなくしてしまった現れなのではないか,と思う。だから,
ことばをもちいた祝詞や和歌や諺にも言霊が宿る,
と際限なく拡大していく。それは,人の不遜さ,思い上がりに通じるものがあるような気がしてならない。人というより,日本人の,と言った方がいい。その不遜さは,またぞろ,妖怪のように復活してきた気配である。夜郎自大とはよく言ったものである。
参考文献;
佐佐木隆『言霊とは何か』(中公新書) |
|
世界観 |
|
千田稔『古事記の宇宙(コスモス)』を読む。

著者は,あとがきで,こう書く。
「本書では,『古事記』の底流をなしている自然をぬきだして,日本人の自然観と,そこから見えてくる,カミ意識に主たる焦点を定めた。古来,この国のカミ意識は,万物に神霊が宿っているというアニミズムであった。欧米などの一神教からは,見えない世界であって,原始宗教とさげすまれた位置づけをされてきた。だが,地球のいわゆる「環境問題」が深刻化の様相を呈しつつある昨今,自然界のすべてに神霊が宿り,人間も自然界に属しているというアニミズム的認識こそが,『環境』論を考えるとき,『共生』よりも,強い倫理性を発信できると思い,そのようなことが『古事記』によって示唆されているのではないかという思いで,本書を綴ってみた。」
と,しかし,序では,
「『古事記』は史書である。史書に登場する神々のすべてを,単純にアニミズムという枠内に収めることはできない。なぜならば,純粋な自然の霊への信仰だけでなく,『古事記』という政治的色合いをもった史書に収められている自然と神の関係からは,創作性をぬぐいさることができない場面もあるからである。そのために,本書では,無垢の自然に宿る神と,政治性をおびた人格神的なものとを交錯させながら述べることになる。」
と,『古事記』の性格のむずかしさを言い当てている。で,構成としては,
「ある種博物誌のような体裁をとっているが,それは,『古事記』という一つの宇宙論的記述を,腑分けして,解き明かそうとした試み…,」
として,
「史書としての『古事記』をいっぽうに意識しながら,『古事記』の中に見出される自然に目を注ぎ,この国の自然観の源流をたどってみたい,」
と,天と地そして高天の原,ムスヒとアマテラス,海,山,植物,鳥,身体,
と,章分けされている。しかし,一番面白いのは,
序
である。まず,言う,
カミ
の語源が分からないのである。
上
が語源ではないか,とあたりをつけていたらしいが,
そうではないのだという。で,いくつかの説が載せられている。
大野晋は,
「カミの語源としてこれまで上げられた,『上(カミ)』,鏡(カガミ),畏(カシコミ),カミの『ミ』は『ヒ』の転化で太陽のことであるという諸説は,いずれも古代の音のうえで『カミ(神)』の語源とはいえないとして,しりぞけた。そして南インドのタミル語との比較研究によれば,カミ(神)の古形カムは『カ』と『ム』との複合によつて成りたった語で『カ』は光線・雷光で『ム』は王・領主であると判明した。」
という。
本居宣長は,「まだ思いつかない」としたうえで,
「すべてカミ(迦微)というのは,…天地の諸々の神をはじめ,それをまつる神社に坐す御霊をも指し,また人は言うまでもなく,鳥・獣・木草の類,海・山などその他何であっても,尋常でないほどすぐれたるところがあって,かしこきものをカミと言う。」
谷川健一は,
「神(カミ)はクマと音が通じていて,クマシネは神に捧げる稲のことでその稲を作る田をクマシロというとして,…『和名抄』の岩見国邑知郡と淡路国三原郡に神稲(くましろ)郷…もそれに準ずるとする。」
もうひとつ谷川は,
「『クマ』は山の籠ったところを指す形容語という説があるが,『カミ』も幽暗なところに在すものという意味であると説く。」
さらに,古代朝鮮語のcomあるいはkumaは,どちらも暗い空間という意味である,ということから,著者は,
熊野
のことを想起する。そして,
「牟婁(むろ)という地名が熊野にあること,『むろ』は『もり(杜)』に由来するならば,大和の三輪山,すなわち『古事記』の御諸山の『みもろ』に通じることから,『熊野』という地名と『カミ』とのつながり」
は検討に値すると,留保しつつ,著者自身は,『カミ』の由来を,
「本来『カミ』は荒ぶる存在であったため,白いイノシシも黒いクマも『カミ』として認識されたが,黒いクマがより獰猛であったために『カミ』のシンボル性を強く表現した」
と考えるに至る。それは,本居宣長の,あらぶるものすべてが「カミ」とするものの延長線上にあるが,そういうものとして,カミを見ていく,と言う仮説の上に立って書いている,と表明のと同様である。
もうひとつ著者が注目するのは,道教の影響である。『古事記』の撰録と献上を太安万侶に命じたのは元明天皇であるが,諡が,
天淳中原瀛真人天皇(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと)
である。
天淳中原
とは,天の瓊(たま)を敷きつめた原,瀛は瀛州(中国の東の海に浮かぶ不老長寿の薬のある三神山の一つ)という意味で,真人とは,道教で高い位の千人をいう。
その元明天皇に強い影響を与えた斉明(皇極)天皇も,宮の近くにある多武峰の山頂に,両槻(ふたつきの)宮あるいは天宮(あまつみや)と呼ばれる観,つまり道教寺院をつくった。
ということは,『古事記』を作った人々には,道教の世界観で,見えていたものがある,そうして見えた景色がある,ということなのだ。
その意味で,『古事記』の冒頭,
「天地初めて発けし時,高天の原に成れる神の名は,アメノミナカヌシ(天之御中主)の神。次にタカミムスヒ(高御産巣日)の神。次にカミムスヒ(神産巣日)の神。この三柱の神は,みな独神と成りまして,身を隠したまひき。」
でいう,「高天」に神が住むという信仰は,道教由来ではないか,と言う。
「おそらく,高天の原は,…中国の経典を参考にしてつくられた言葉であると思われる,」
と,著者は推測する。その意味するところは,
「『古事記』は稗田阿礼の口誦によったとする素朴な成立事情だけからは説明できない,」
ということになる。そして,この『古事記』の冒頭は,『日本書紀』にはなく,一書第四の諸説の一つとして載せているだけである。このことを,著者はこう推測する。
「これは,天武天皇の命によってつくられた『古事記』の高天の原の記述には,政治的宗教的意図があることを明示していると読みとれるのである。『日本書紀』の編纂者たちは,それを過小評価しようとしたのである。」
実は,その言葉が,その言葉を使っている人の見ている世界を示す。その言葉の意味に,大袈裟に言えば,世界観がある。人は,世界を,おのれの世界観で見ている。というより,おのれの世界観しか,そこに見ない。別に現象学的な意味だけではなく,そういうものの見方なのだ。とすると,その言葉が,どう意味で使われたのか,はその世界を共有するためには必須になる。
世界観と言う言い方が大袈裟なら,景色といってもいい。たとえば,
ササギ
という鳥の名がある。仁徳天皇を,
大雀命(おおさざきのみこと)
とよぶ,このサザキである。これには,
雀
の字を当てて,
スズメ
であったり,
ササギ
であったりし,『日本書紀』では,鷦鷯の字で,ササギ,と訓ませている。これは,今日,
みそさざい
を意味する。雀かミソサザイかでは,見えているものが違うのである。
『古事記』の宇宙を見るのは,一筋縄にはいかないのである。
参考文献;
千田稔『古事記の宇宙(コスモス)』(中公新書) |
|
劣化 |
|
佐伯啓思『正義の偽装』を読む。

帯には,
稀代の社会思想家
とある。しかし,読んで,異和感のみが残った。福田恆存はまだしも,件の長谷川三千子を麗々しく引用するあたり,そのレベルの人かと,ひどく幻滅した。
著者は,本書について,
「時々の時事的な出来事や論点をとりあげつつ,それをできるだけ掘り下げて,使嗾的に論じるというのが連載の趣旨なのです。」
という。そのうえで,
「私には今日の日本の政治の動揺は,『民主主義』や『国民主権』や『個人の自由』なる言葉を差したる吟味もなく『正義』と祭り上げ,この『正義』の観点からもっぱら『改革』が唱えられた点に在ると思われます。われわれは,本当に信じてもいないことを『正義』として『偽装』してきたのではないでしょうか。」
と書く。この文章に,詐術がある。自分は,
「この世の中に対する私の態度はかなりシニカルなものです。」
といって,まず部外者に置く。そうすることで,上記の「偽装」については,責任を逃れている。そして,
さしたる吟味もなく,
「正義」と祭り上げ
もっぱら「改革」が唱えられた
本当に信じてもいないことを「正義」と「偽装」
しているのは,著者ではない,「愚かな日本人」ということになる。著者の論拠は,保守だから,主として,
サヨク
や
野党
がその批判の対象になる。しかし,かくおっしゃる世の中で,ご自分はのうのうと大学教授を享受している,この社会の当事者である点を,置き去りにしている。かつて,吉本隆明が,丸山眞男の当事者意識を痛烈に批判していたのをふと思い出す。当然,僕は,この著者の言うところの,
サヨク
に該当するらしいのだが,しかしいまどき左翼だの右翼だのというふるい分けというか,レッテル張りに意味があるのだろうか。せいぜい石破氏のデモを「テロ」と名付けたり,安倍氏が批判者を「左翼」というラベル貼りする以上の実態はないと思うが,未だラベル貼りすることで,自分をその埒外に置きたい人がいるらしい。けれども,自分を埒外におこうと,どの立場に立とうと,時事に対して,批判することはもちろん自由だ。しかし,評論家であることは許されない。この日本において,自分だけ埒外にいることはできない。自分または自分の家族も巻き込むことを意識しない当事者意識の欠けた意見は,基本,聴くに値しない。
しかし,本書へのいらだちは,それだけではない(当事者意識のないどころか,高みから見下ろしているのは,この手の論客のお得意技なので,そのことはさて置いても)。
たとえば,
「『自由』や『民主』『富の獲得』『平和主義』といった戦後の『公式的な価値』は,実は,一皮むけば,すべて自己利益の全面肯定になっている」
と書く。「公式的な価値」って,誰にとって,誰が,と言う茶々は入れない。そういう言い回しで,皮肉たっぷりに言うのが,ご自分の存在基盤になっているらしいので,言ったところで,痛痒を感じまい。問題は,これは,著者の仮定にすぎないということだ。そう著者が仮に仮説として言った,ということだ。ところがである。つづいて,
「すると人はいうでしょう。人間とはそういうものだ。どうして利己心をもって悪いのか。そうです。別に悪くありません。誰もが自分の生命や生活を第一に考え,自己利益を目指し,富が欲しい。これは当然と言えば当然です。しかし,戦後の『公式的な価値』は,この本質的にさもしい自己利益,利己心を『正しいもの』として正義にしてしまったのです。それに『自由』や『民主』や『経済成長』や『平和主義』という『錦の御旗』を与え,『政治的正しさ』を偽装してしまったのです。」
こういうのをマッチポンプと言う。ご自分で問い,それに「さもしい」という問いにはなかった価値判断までも加え,「(自分ではないアホな国民が)正しいものにしてしまった」と言っている。この論旨は,詐欺である。
そもそも仮定は,著者がした。この仮定を受け入れなければ,たとえば,「自己利益」という前提を外せば,別の結論になる。こういうのを,前提に結論を入れている詐術という。
決められない政治,責任を取らない云々と批判のある風潮に対して,こう言う。
「『決断をする』にせよ,『責任をとる』にせよ,これは指導者に求められる責務なのです。そして,『決断』も『責任』も,それなりの力量や先見性をもった『主体』でなければできません。『決断』はいうまでもなくまったく未知で不確定な未来へ向けてひとつの事柄を選び取ることで,そこには先見性と強い意志がなければなりませんし,『責任』の方も,選択の結果がいかなる事態を引き起こすかというある程度の因果関係の推論がなければ意味を持ちません。」
ここまでは,まあ,いい。しかし,ここからがお得意の論旨の展開である。
「こうしたことを予見できるのは,人並み外れた能力なのです。ということは,われわれは,人並み外れた力量を指導者に求めているのです。(中略)ところが他方で,われわれの理解する『民主主義』とは,『民意を反映する政治』であり,われわれの常日頃の思いや感情や不満が正字に反映されるべきだ,という。指導者とは,われわれのいうことをよく聞き,われわれの不満を代弁してそれを解消してくれるはずの者なのです。端的に言えば,民主主義のもとでの政治家とは,『庶民感覚』をもった者で,できる限り我々に近い人であるべきなのです。
こうなると矛盾は覆い隠すべくもないでしよう。われわれは,一方で,指導者に対してわれわれにはない卓越性とたぐいまれな力量を求め,他方では,指導者はわれわれとチョボチョボであるべきだといっているのです。」
こうやって,単純化して,あえて,論点を明確にするというやり方はある。しかし,この矛盾は,著者が立てた仮説に基づく。その仮説が違っていれば,話はかみ合わない。
たとえば,「無責任」で問題にしていることは,こういう抽象的なことではない。もっと具体的な,あのこと,このことである。ひとつひとつの具体的なことについて,責任を取っていない,と言っているのである。
最近の例で言えば,原子力規制委員会の田中委員長は,合格を認定したが,
「再稼働の判断には関与しない。安全だとは私は申し上げません」
と言い,菅官房長官は,
「規制委が安全性をチェック。その判断にゆだねる」
と言い,岩切薩摩川内市長は,
「国が責任を持って再稼働を判断すべき」
と言う。そして,
「もし事故が起きたら、その時の責任は?」
と質問されて,岩切薩摩川内市長は,
「これは国策だから、国が責任を取るべきだと思う」
と言う。責任とは,たとえば,この一連のなすり合いのような,具体的な言動,事案について言っている。
あるいは,メルトダウンしたフクイチは,いまだコントロールできず,全太平洋を汚染つつあるのに,
コントロールロー出来ている,
という平然とウソを言い,ウソがまことの如く頬かむりしているという,個々の具体的な言動を指している。それを一般論に置き換えて,それは,
ないものねだりだ,
ということで,無責任を容認しようとする,この論旨こそが無責任な,論旨のすりかえである。たとえば,政治も,国家→県→市町村という政治レベルのクラスを意識的にぼかし,一般論として,ひとしなみに捉えて,政治家は,
われわれの不満を代弁してそれを解消してくれるはずの者
と言い替えてしまう。まさに,巧妙かつ卑劣である。この手の論旨に満ち溢れていて,もういちいち指摘するのも辟易する。
G・ライルは,知性は,
Knowing that
だけではなく,
Knowing how
がなければだめだという。著者は,シニカルに逃げて,
Knowing how
を一切示さない。自分なりにどうするかを示さなければ,所詮知識のひけらかしか,批判への評論でしかない。自分は安全なところで,時代を享受しながら,時代をシニカルに皮肉る。知性的なふりをした,巧妙なプロパガンダ以外の何ものでもない,
社会思想
の「偽装」である。しかし,ご自分が当事者意識を持とうが持つまいが,ご自分の子息,縁者の子息は巻き込まれる。あるいは,黒澤明がこずるく兵役を免れたように,この手の人には,抜け道があるのかもしれない。でなければ,ご自分を対岸においてものを言う神経が理解不能だ。
たしか,ミルトン・エリクソンをベースにする,NLP(神経言語学的プログラミング Neuro-Linguistic
Programming)には,ミルトンモデル(その反対はメタ・モデル)というのがあり,物事をあいまいに糊塗する言葉遣いというのを列挙している。たとえば,
一般化
省略
歪曲
とあるが,とくに気になるのは,省略の一種(だと思う),
遂行部の欠落(あるいは遂行主体の曖昧化)
といわれるものだ。
誰が,
誰にとって,
という主体が,対象が,意識的にぼかされる。NLPのテキストは言う,
「話し手は,自分に当てはまるルールや自分の世界モデルを,他人にも押し付けようとする時に,遂行部の欠落を使います。」
あたかも,
すべて,
みんな,
ということで,何かを手に入れようとする子どものよく使う手のように。
「みんなそうだよ」。
参考文献;
佐伯啓思『正義の偽装』(新潮新書)
G・ライル『心の概念』(みすず書房) |
|
知性 |
|
田坂広志『知性を磨く』を読む。

律儀なファンではないが,以前に,何冊か強い印象を懐かされた本を読んでいる。基本的に,その知性に惹かれていることが,普段は読まない「ノウハウ」チックな本書を手にした動機である。
著者は問う。
「学歴は一流,偏差値の高い有名大学の卒業。
頭脳明晰で,論理思考に優れている。
頭の回転は速く,弁もたつ。
データにも強く,本もよく読む。
しかし,残念ながら,
思考に深みがない。(中略)
端的に言えば,「高学歴」であるにもかかわらず,深い「知性」を感じさせない…,
ではなぜ,こうした不思議な人物がいるのか?」
と。著者は,
知能
と
知性
をこう区別する。
「知能」とは,「答の有る問い」に対して,早く正しい答えを見出す能力
「知性」とは,「答の無い問い」に対して,その問いを,問い続ける能力
と。さらに,
知識
と
知恵
と
知性
をこう整理する。
「知識」とは,「言葉で表せるもの」であり,「書物」から学べるもの
「智恵」とは,「言葉で表せないもの」であり,「経験」からしか摑めないもの
「知性」の本質は,「知識」ではなく,「智恵」である
と。そして,いまひとつ,「専門性」について,
「我々は,『高度な専門性』を持った人物を『高度な知性』を持った人物と考える傾向にある」
しかし,
「『高度な専門性』を持った人物が無数にいながら,肝心の問題が解決できない」
と。
フクイチの放射汚染はまだ続いており,太平洋全体に汚染が広がりつつある。しかし,少なくとも,汚染を止める手立てを,専門家は何一つ構築できていないどころか,めどさえ立っていない。
ふと思い出すのは,アーサー・C・クラークが言っている言葉である。
「権威ある科学者が何かが可能と言うとき,それはほとんど正しい。しかし,何かが不可能と言うとき,それは多分間違っている」
と。著者は,サンタフェ研究所で,
「この研究所には,専門家(スペシャリスト)は,もう十分いる。われわれが本当に必要としているのは,それらさまざまな分野の研究を『統合』する『スーパージェネラリスト』だ」
という発言に触発されて,これからは,
「垂直統合の知性」を持ったスーパージェネラリスト
が必要と説く。それは,
さまざまな専門分野を,その境界を超えて水平的に統合する「水平統合の知性」
ではない。その例を,アポロ13号の事故の時,NASAの主席飛行管理官を務めていたジェーン・クランツに,そのモデルを見る。そこでは,混乱し絶望的状況の中で,
「我々のミッションは,この三人の乗組員を,生きて還すことだ!」
と明確な方向性を示し,次々に発生する難問を,専門家たちの知恵を総動員して,次々とクリアし,無事に帰還させた。そして,ここに,知性のモデル(「スーパージェネラリスト」)を見つける。
「まさに『知性』とは,容易に答の見つからない問いに対して,決して諦めず,その問いを問い続ける能力のこと。」
として,「七つのレベルの思考」を提示する。
第一は,明確なビジョン
第二は,基本的な戦略
第三は,具体的な戦術
第四は,個別の「技術」
第五は, 優れた人間力
第六は,すばらしい「志」
第七は,深い思想
この字面だけを見ていると,常識的に見えるかもしれないが,たとえば,
戦略とは,「戦い」を「略(はぶ)く」こと
技術の本質は,知識ではなく,「智恵である」
というように,ひとつひとつに,著者なりの「知略」が込められている。
このすべてに僕は賛成ではないが,すくなくとも,自分なりの体験と知恵から「知性」を描き出そうとする,オリジナルな思考のプロセスがよく見える。
智恵をつかむための智恵とは,
「メタレベルの知性」
という著者の「知性」のメタ・ポジションには,深く同意するところがある。
ライルは,知性について,
Knowing how(ある事柄を遂行する仕方を知っている)
と
Knowing that(何かについて知っている)
に分けた。そして,こう書く。
「ある人の知識の卓越や知的欠陥を問題にしている場合においてさえも,すでに獲得し所有している真理の貯蔵量の多寡は問題ではない」
と。ただ,このKnowing howとKnowing
thatは,同じクラスと考えず,クラスが別と考えると,
Knowing howについてのKnowing that
というメタレベルの「知」であることも含意していることになる。
僕は,必要なのは,智恵とか知識とか知能というレベルではなく(それがあることを前提にしないと話は進まないが),
メタ・ポジション
での思考力なのだと思う。自分の経験を智恵にすることが必要だとは思うが,著者の言うように不可欠とは思わない。むしろ,
目利き
出来るメタ化の力なのだと,感じた。
参考文献;
田坂広志『知性を磨く』(光文社新書)
G・ライル『心の概念』(みすず書房) |
|
九条 |
|
松竹伸幸『憲法九条の軍事戦略』を読む。
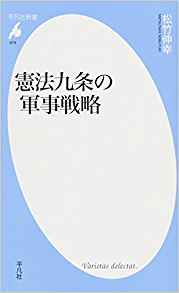
昨年刊行されたものだ。もはや時機を失したか,と悔いつつ,失いつつあるものの大きさに思い至る。
はじめにで,著者はこう書く。
「九条と軍事力の関係が相容れないという点では,護憲派と改憲派は共通している…。だが私は,この既成事実に挑戦することにした。護憲派にも軍事戦略が必要であると考えるにいたった。」
と。その意味では,本書の主張は,堂々の議論と,国民全体のコンセンサスを経るという,改憲プロセスを念頭に置いての論旨というふうに考えられる。しかし,議論も討議もないまま,泥棒猫のようにこそこそと既成事実を積み重ねて,実質改憲を果たし,集団的自衛権の行使を可能とし,武器輸出三原則を放棄し,あろうことか,イスラエルと共同開発まで踏み込むとは,著者の予想を超えている。
おそらく,今後,いままでの対米従属の政治路線からは,アメリカの戦争に従属従軍し,いまそうであるように,イスラエル側に加担し,アラブを敵に回すことになるだろう。ついこの間,3.11のために祈ってくれたガザの子供たちのことは報じられないまま,その子供たちが戦車に蹂躙されているのを,黙認している日本政府の行動は,世界に,日本のポジションを明確に語っている。
では,われわれは,一体何を喪おうとしているのだろうか。
九条のもと,専守防衛を旨としたきたが,それは,
「専守防衛とは相手からの武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し,その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限度にとどめ,また保持する防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど,憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略をいう…」(大村防衛庁長官 参議院予算委員会 81.3.19)
つまり,
日本側が反撃を開始するのは相手から武力攻撃を受けたときであり,
その反撃の態様は,自衛のための必要最小限度の範囲にとどめ,
その反撃をする装備も自衛のための必要最小限度
というものである。これに合わせて,自衛権発動の三要件というのがある。
「憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については,政府は,従来からいわゆる自衛権発動の三要件(我が国に対する急迫不正の侵害があること,この場合に他に適当な手段のないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られると解している」(参議院決算委員会提出資料 72.10.14)
「他に適当な手段がない場合」を除くと,専守防衛の要件と重なっている。この趣旨は,
「外交交渉とか経済制裁などで相手国の侵略をやめさせることができるならそうすべきであって,武力で自衛するのはそういう手段ではダメな場合に限る」
という意味である。
こういう専守防衛の考え方を,
九条にしばられている
故,と考えるのは,的外れである,と著者は言う。
「そもそも自衛権という概念は,憲法九条で発生したわけではない。武力行使を禁止する国際法が発展するなかで,その例外措置のようなかたちで生まれたものである。武力行使は違法だが,自衛の場合は違法性が阻却されるという考え方である。」
それは,アメリカ独立戦争時を嚆矢とし,当時のアメリカのウェブスター国務長官のイギリス側への書簡がある。
「英国政府としては,差し迫って圧倒的な自衛の必要があり,手段の選択の余地がなく熟考の時間もなかったことを示す必要があろう。加えて,…非合理的もしくは行き過ぎたことは一切行っていないことを示す必要があろう。自衛の必要によって正当化される行為は,かかる必要性によって限界づけられ,明白にその範囲内のものでなければならない…」
これは今では「慣習法として定着したといわれている」として,著者は,
「国際法上の自衛権とは,憲法九条のもとにおける自衛権の三要件とほぼ同じなのである。日本は憲法九条があるから自衛権さえ制約されているというひとがいるが,自衛権発動の要件は,日本も外国も変わらないのだ。」
と言う。この慣習法とは別に,国連憲章第五十一条が,自衛権発動について,
第一,各国が自衛権を発動できるのは,(国連安保理が)必要な措置を取るまでの間に限定されること
第二,各国が自衛措置を取った場合,安保理に報告しなければならないこと
第三,自衛権が発動できるのは,武力攻撃が発生した場合に限定したこと
の三つの制限を設けている。第三項は,英語だと,現在完了形ではなく,現在形である。つまり,
「自衛権の要件を厳守することは,九条のある日本だけの制約ではない」
ということを,著者は強調する。
そして,むしろ,いままでの日本の姿勢が,世界的には武器になってきたのだと,次の二点を象徴として挙げる。
第一は,武器輸出三原則
第二は,集団的自衛権行使の制約
武器輸出は,かなり緩和されてはきたが,それが功を奏したのは,
国連軍備登録制度
制定である。
「その資格を持った国がひとつ存在した。武器を輸出してこなかった日本である。日本はこの制度を創設するために,『軍備の透明性』と題する国連総会決議の案をもって各国を説得し,調整し,最終的に決議の採択にまで持ち込んだのである。」
これが果たせたのは,武器輸出三原則があったからである。武器規制に関しては,
世界的に注目されている
のは,もはや過去のことだ。三原則は,
防衛装備移転三原則
に変え,武器見本市に初参加し,防衛副大臣が,ライフルを構えていた写真が配信された。もはや,政府は武器商人の露払いになっている。
いまひとつは,言うまでもなく,集団的自衛権である。日本が海外で殺傷行為をしていないというイメージは,世界的には確立していた。そのことではたせる役割はあったし,ある。しかし,もはや,その意味で,「普通の国」と成り果てた。これについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/401642428.html
で触れたので繰り返さない。
このつけは,集団的自衛権を行使した瞬間,日本が攻撃の対象となる,ということを意味する。それは,対アラブならば,日本国内のどこかが無差別テロの標的になる,ということにほかならない。
まだ間に合うのかどうかは,もはや微妙であるが,本書の掲げた「九条をバックとした軍事戦略」は,実質的に,不可能になりつつあることだけは確かである。
参考文献;
松竹伸幸『憲法九条の軍事戦略』(平凡社新書) |
|
気 |
|
宇佐美文理『中国絵画入門』を読む。

よく考えると,例えば,山水画,水墨画,というように,結構中国絵画の影響を受けているのに,
中国絵画について,ほとんど知らないことに気づく。
著者は,
気と形を主題にした中国絵画史
というイメージで本書を書いたと説明する。そして,
中国絵画について何かを知りたいと思われた方,そこで知りたいと思うことはなんなのか。それを知ることがなければ読んだ意味がないと思うことは何なのか。
それをまず書くという。
中国絵画の流れを何か一本スジを通して記述できないか,
という問題意識で俎上に上ったのが,
気
である。では,気とは,何か。
最初は,孫悟空の觔斗雲のような形
で表現されていた(後漢時代の石堂の祠堂のレリーフにある),霊妙な気を発する存在としての西王母の肩から湧くように表現されていた気が,
逆境にもめげず高潔を保つ精神性を古木と竹で表現した(金の王庭筠の「幽竹枯槎図」の),
われわれが精神や心と呼んでいるものも,
気の働きと考えるようになり,そういう
画家の精神性が表現されたということは,画家のもっている気が表現された,あるいは形象化された,
という気まで,いずれも,気を表現したと見なす。
簡単に言えば,中国絵画における気の表現は,気を直接形象化した表現から,実物の形象を使いつつ気を表現するという
ところまで変換していく。そこから,
どのようにすれば気そのものを形象化することなく,気を表現できるか,という問題が,常に中国絵画の中心課題として存在していた,
と著者は見る。この転換点になったのは,(「帝王図鑑」の)
気韻生動
と言われる,
(皇帝を描いた場合)皇帝が,皇帝たる風格(精神性も含めて)を感じさせるものでなければならない。それが人物画の肝要な点だと考えられた
ところだという。つまり,
絵画にとって重要なことは,形を写し取ることではなく,形を超えたもの,人物画では気韻あるいは人物の精神性であると考えたのである。
それは,たとえば,静物では,(李迪「紅白芙蓉図」)の,
芙蓉の気,それは,読者の方がこの絵を見て感じる,その匂い立つ美しさそのものが芙蓉の気なのである。
と著者は言う。
ともかくこの絵から感じとられたこと,それがまさにこの絵のもっている気にほかならない,
ということが重要なのだと言う。
その気には,いまひとつ,
筆墨の気
がある。いわゆる,
筆気
である。これは,
筆意ともよばれ,線の流れに作者の心の流れを読み取ろうという発想である
という。気の表現は,
直截的形象化,描かれた対象のもつ気の表現,作者自身の気の表現,線のもつ気,墨の気など,
様々な形を使ってなされてきたが,この,
形をもたない気が形をとって現れること
を,
気象,
と呼ぶ。これが,
中国芸術全般を支配する思想
といっていい,と著者は断言する。気は,
万事万物を構成する「もと」
であり,物質はもとより,
我々の「精神」も気のはたらき
であり,陰陽の気の交代が昼と夜であり,
世界のすべては気を原理として生成変化し,……気でできた世界は形をめざして動いている。簡単に言うと,世界とは造形力そのものなのだ。
しかし,と著者は言う。気が画家自身の気の表現であるとしても,
画家がもっている気がそのまま画面の形象になるという気の思想だけですべては片づかない。いかめしい顔をしていても心は優しいというのはきわよめてよくある話である。
で,著者は,
外見と内面が一致しないとする発想を,「箱モデル」と呼ぶ。箱の外見からは箱の中身が分からないからである。対して,気象の発想によるものを「角砂糖モデル」と呼ぶ。角砂糖全体は中心部分も含めてその性質は同じである…から,外見と中身は一致し,中身は外見から推知できるのである。
後者のそれが,
作者の持っている気がそのまま作品に現れるもので,それは生得のものだ,
という考え方に通じ,人格主義につながる。
中国の芸術は,しばしば作品ではなく,作者によって価値を判断する。…絵が上手いとか下手とかという問題をわきにおいて,絵を描いた人物自体の価値を基準としようとする,
考えへとつながり,さらに,蘇東坡の,
形が似ているかどうかで絵を論じてはいけない
につながる。形をこえたものを求める形象無視の頂点に来たのは,
文人画
である。
絵画も文人が描けば芸術だが,画工が描けばそうではない,
というように。その頂点に,
牧谿
がくる。牧谿は光の画家と言われるが,それは,レンブラントの,光と影とは全く違う。
牧谿のひかりは,…「気そのものが輝いている」光である。光が三次元空間に充満している。我々の言葉で言う「空気」が光っているのである。それが照らされた光ではない,
から影がない。ここにあるのは,
透徹した精神性
である。それは,
絵画がまるで言葉によって語りかけ,それに絵を見ている人間がこたえているようなもの,
である,と著者は言う。
書もそうだが,作者の精神性というものが,最後に,作品を凌駕する。
個々の作品ではない,
らしいのである。
数千年を,一冊で読み切るのは無理には違いないが,読み終えて,そこかしこで,老荘,孔孟の気配を感じた気がしたのは,錯覚だろうか。
参考文献;
宇佐美文理『中国絵画入門』(岩波新書) |
|
クーデター |
|
半田滋『日本は戦争をするのか』を読む。

解釈改憲をはじめとする現政権の進めている憲法空洞化は,
クーデターである,
そう本書は断罪する。
本書は,
安倍政権が憲法九条を空文化して「戦争ができる国づくり」を進める様子を具体的に分析している。法律の素人を集めて懇談会を立ち上げ,提出される報告書をもとに内閣が憲法解釈を変えるという「立憲主義の破壊」もわかりやすく解説した。
と「はじめに」に書くように,解釈改憲が閣議決定される前までの,安倍政権の言動を,つぶさに分析している。
はじめに憲法空洞化ありきだから,理屈と膏薬は,どこにでもつく。ほとんど,ウソと屁理屈で,本当は理由などいらないのだろう。
集団的自衛権の行使容認に踏み切ること自体に目的があり,踏み切る理由はどうでもよい…,
と言わしめる所以である。空念仏のように,「我が国を取り巻く安全保障環境が一層悪化している」と言いつつ,それを緩和するための政治家として為すべき外交努力を一切しないのも,その伝なのだろう。
だから著者は,こう言う。
なぜ,事実をねじまげるのだろうか。憲法を変えさえすれば日本はよくなるという半ば信仰に似た思い込みがあるのだろうか。
近隣諸国との緊張を高めてナショナリズムをあおり続ける背景には「占領期に米国から押し付けられた日本国憲法を否定し,自主憲法を制定する」との強い意思を示す狙いがあるのだろう。
と。しかし,その自民党憲法改正草案は,
驚くべき内容である。現行憲法の特徴である「国民の権利や自由を守るための国家や為政者を縛るための憲法」は,「国民を縛るための国家や為政者のための憲法」に主客転倒している。近代憲法の本質が権力者が暴走しないように縛る「立憲主義」をとっているのに対し,自民党草案は権力者の側から国民を縛る逆転の論理に貫かれている。
そういう時代錯誤の為政者を生んだのが,国民だとすると,国民の中にある,ドストエフスキーのいう「大審問官」を求める,そう水戸黄門の印籠を求める心性が反映している,としかいいようはない。そう考えると,絶望感に駆られる。
しかし,そういう改憲手続きの手間さえ,安倍政権は省こうとしている。つまり,現内閣の閣議決定による,
解釈改憲
である。そのための道筋は,
①安保法制懇からの報告書を受け取る
②報告書を受けて,あらたな憲法解釈を打ち出し,閣議決定する。
③その解釈にもとづき,自衛隊法を改正したり,必要な新法を制定したりする
で,すでに②まで経た。ここには,国民は不在であり,議会も全く不在である。そして,ロードマップを兼ねる国家安全保障法の制定を目指す。
武器の輸出の緩和
武器輸出三原則の見直し,
秘密保護法
教育基本法の改正
こうして,実質憲法は骨抜きにされていく。ついには,徴兵制を口にされるところまで来ている。自民党憲法草案の現実化である。
国会論議を経ないで閣議決定だけで憲法の読み方を変えてよいとする首相の考え方は,行政府である内閣の権限を万能であるかのように解釈する一方,立法府である国会の存在を無視するのに等しい。憲法が定めた三権分立の原則に反している。(中略)
首相の政策実現のためには,これまでの憲法解釈ではクロだったものを,シロと言い替える必要がある。歴代の自民党政権の憲法解釈を否定し,独自のトンデモ解釈を閣議決定する行為は立憲主義の否定であり,法治国家の放棄宣言に等しい,
為政者が「法の支配」を無視して,やりたい放題にやるのだとすれば,その国はもはや「法治国家」ではない。「人治国家」(ありていに言えば独裁国家であるのだ=引用者)ということになる。ならず者が街を支配して,「俺が法律だ」と言い放っているのと何ら変わらない。
「人治国家」とは,ありていに言えば独裁国家であるのだ(そのせいか,中韓とは敵対しつつ,妙に独裁国家・北朝鮮とはパイプが強まっている,ように見えるのは,勘ぐりすぎか?),そして,著者は,
首相のクーデター
と呼ぶほかはない,と言い切る。麻生の言う,
ナチのやり口をまねる,
まさにそのままである。それが,たんなる糊塗やごまかしではなく,確信犯であるのは,安倍氏の発言からも見て取れる。
安倍氏は,国会答弁でこう言い切った。
「最高の責任者は私です。政府答弁に私が責任を持って,その上で私たちは選挙で国民の審判を受けるんですよ。」
著者は,こう解説する。
意味するところは,「国会で憲法解釈を示すのは内閣法制局長官ではなく,首相である私だ。自民党が選挙で勝てば,その憲法解釈は受け入れられたことになる」ということだろう。
と。選挙で大勝し,内閣支持率が高い,
思い通りにやって,何がわるい,
ということなのだろう。そして,憲法とは何かの質問に対して,
(憲法が)国家権力を縛るものだ,という考え方は絶対掌王権時代の主流な考え方
憲法は日本という国の形,理想と未来をかたるもの
と述べた。ここには,
国民の権利
も
自由の保障
もない。この延長線上に,自民党の憲法草案がある。
憲法を普通の政策と同じように捉えている
立憲主義の考え方が分かっていない
といっても,たぶん聞く耳というか,そういう考え方は視野にないだろう。まして,国民の自由などは。
さて,安倍氏がただひたすら求めている集団的自衛権は,何をもたらすのだろう。
僕の理解では,集団的自衛権とは,
他の国家(アメリカを想定していい)が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国(日本である)が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。
その本質は,
直接に攻撃を受けている他国を援助し,これと共同で武力攻撃に対処する
ところにある。なお,
第三国が集団的自衛権を行使するには,宣戦布告を行い中立国の地位を捨てる必要があり,宣戦布告を行わないまま集団的自衛権を行使することは,戦時国際法上の中立義務違反になる。
そして,著者は言う。
集団的自衛権は東西冷戦のゆりかごの中で成長した。驚くべきことに第二次世界大戦後に起きた戦争の多くは,集団的自衛権行使を大義名分にしている。
ベトナム戦争は,南ベトナム政府からの要請があったとして,集団的自衛権行使を理由に参戦した。
このときの集団的自衛権行使の仕方には,
アメリカのように攻撃を受けた外国(南ベトナム)を支援するケース
と
韓国のように,参戦した同盟国・友好国を支援するケース
の二つがある。そして,著者は言う。
集団的自衛権を行使して戦争に介入した国々は,「勝利」していない
と。
自国が攻撃を受けているわけでもないのに自ら戦争に飛び込む集団的自衛権の行使は,きわめて高度な政治判断である。一方,大国から攻撃を受ける相手国にとっての敗北は政治体制の転換を意味するから文字通り,命懸けで応戦する。大義なき戦いに駆り出された兵士と大国の侵略から時刻を守る兵士との士気の違いは明らかだろう。
こういう説明のないまま,集団的自衛権行使を,内閣の閣議決定のみで,事実上,
憲法九条
の解釈を変えて,改憲した。集団的自衛権の必要性を説明するために政府の挙げた事例は,個別自衛権,つまり,現状のままで対応可能なのに,である。その説明もない。
しかし,ほとんどその境界線をあいまいのまま,対外的な国際公約としてようしている。
この違いを分かりやすく解説しているのは,
http://www.asahi.com/articles/DA3S11221914.html
である。あいまいのまま,いかにも,自衛の延長戦上に,集団的自衛権があるように思わせたいのであろう。
手続き上と言い,
国民への説明の内容と言い,
ほとんど詐欺同然,泥棒猫の仕業である。
しかし,いままで,アメリカの
ブーツ・オン・ザ・グラウンド(陸上自衛隊を派遣せよ)
の要請を,歴代政権が,九条を楯に拒んできたが,もはや,後方支援ではなく,前線に,戦闘力として参加ができる。つまり,アメリカ兵に代わって,あるいは一緒に血を流してくれる。アメリカ政府が歓迎するわけである。
そしてたぶん,日本が独自に集団的自衛権を行使することはない。恐らく。ほとんどアメリカの集団的自衛権行使に参加することになる。しかもアメリカの(そしてイスラエルの)同盟軍として。それは,アラブを敵にするということになる蓋然性が高い。同時に,それは,スペインやイギリスで起きた無差別テロの標的にもなるだろうリスクをはらんでいる。その言の説明は一切ない。突然,銀座で自爆テロが起きるかもしれない。
ここまですることは,誰かの利益になるからするのであろうと推測はつく。現政権がそのお先棒をかついているのだとして,われわれ国民にとっての利益でないことだけは確かである。
参考文献;
半田滋『日本は戦争をするのか』(岩波新書) |
|
経済視点 |
|
武田知弘『「桶狭間」は経済戦争だった』を読む。
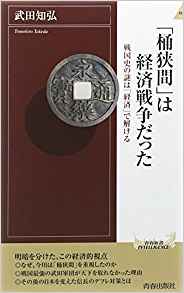
信長の政策を経済面に焦点を当てている。その面で,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/400155705.html
の,戦国大名の鉢植化の背景を理解するのには好都合ではある。表題は,桶狭間となっているが,それだけを掘り下げたわけではなく,ただの入口,後は,武田,上杉,毛利などの戦国大名との対比。少し突っ込み不足は,新書の限界として諦めるとして,
桶狭間の戦いが知多半島をめぐる戦い,
という仮説は,面白い着眼には違いなすが,まだ論証が足りない気がする。
知多半島とその周辺地域というのは,実は商工業において重要な地域だった…,
とする根拠が,
知多半島の窯業,
つまり常滑焼の生産地だった。常滑焼というのは,当時の全国的な陶器ブランド,
というのは,どの程度確かなことなのか。日用雑器としての土器にブランドがあったのかどうか,その他の窯業地との比較,他地域の例示等々がないまま,
知多半島の窯業は,12世紀ごろからさかんになったとされ,本州,九州,四国の多くの中世の古墳群から土器が発見されている。(中略)中世の遺跡から知多半島の土器が発見されていないのは,本州,九州,四国の中ではわずか二,三県である。つまり,中世から知多半島の土器は日本全国に流通していたのである。知多半島は,中世から日本最大の土器生産地域であり,もっといえば中世ではにほん有数の工業地帯だったわけだ。
と言われても,にわかには信じられない。いや,経済視点を除いて,地政学的にこの地域に意味があったのではないか,という他の視点の検討抜きでは,どうもいまひとつ説得力が欠ける。
ところで,信長が,津島を抑え,経済力を持っていたことは,通説である。謙信が直江津,柏崎の関税収入だけで,
年間四万貫,
だいたい三十万石の収入に匹敵する,ということから,その二つの港よりはるかに栄えていた津島からは,
三十万石
以上の収入があり,遠江,駿河,三河,終りの一部を支配する,百万石の今川義元と,尾張一国約六十万石と,津島の収入を合わせると,ほぼそれに匹敵し,動員兵力は,
ほぼ互角
だったのではないか,という話は,説得力がある。その証拠に,最近発掘されつつある清州城は,
南北2.7キロ,東西1.4キロもの惣構えをもつ巨大な城下町だった。あの大阪城にも匹敵するものだった,
という。そう考えると,織田対今川の軍勢,
二千対二万四千
というが,実勢は,織田方は一万近く,しかも,義元本陣は,四,五千,別に奇襲しなくても,十分勝てる計算になる,という理屈である。
さて,その信長の経済政策の画期を,整理しているところが分かりやすい。
一つは税制,
本年貢以外の過分な税を徴収してはいけない,
関所の税を課してはならない,
という信長の指示が残されている。それも,収穫高の三分の一と,江戸時代に比しても低い。それに対して,武田は,土地の貧しい甲斐のせいもあるが,度重なる重税,棟別税,後家役まで課したのと好対照である。
第二は,貨幣納税の貫高制から,米での納税の石高制に変えたこと,
これも換金のための農民の負担を減らしている。
第三は,金銀を貨幣として設定したこと。ここでは,
金と銀,銅銭の交換価値が明確に定めてあり,史上初めての試み。
という。
第四は,検地。それも,かなり細かな歩の単位まで,実測していたと言われる。このことが,大名を鉢植化することになるのだが。
第五は,楽市楽座。多く寺社が座の後ろ盾になり,冥加金をとるという既得権益になっていた。それは一種の価格破壊につながる,と著者は言う。
安土に楽市楽座をつくれば,畿内にある「座」は大きな影響を受ける。安土に売り上げを奪われないために,価格競争をせざるを得なくなる。
結果として,京都の座は消滅していく。
第六は,枡や単位の統一。このことは,関所の撤廃と同時に,物流の革命をもたらす。
第七は,インフラ整備。関所の撤廃と同時に,道路をつくる。『信長公記』には,
入り江や川には,船橋を造り,石を取り除いて悪路をならす
道幅は三間半(6m)とし,街路樹として両側に松と柳を植える
等々を指示したとある。
傑作は,安土城を一般公開したことだ。これは,以前も以後もあり得ない。しかも,大勢が押し寄せたため,百文を徴収したという。
こうした信長の視界に,全国があったことが分かると同時に,自分を遥か高みにおいて,戦国武将どころか,天皇も,自分の眼下においていたように思えてならない。
最後に苦言をひとつ,
足利義昭を,「義輝」と誤植するのは,まあ勘違いとして許されるとしても,その後,今度は,武田義信が出てきて以降,再三,義昭を「義信」と誤植するのは,いくらなんでもいかがかと思う。誤植の多寡は,出版社の格をしめす,とはよく言うが,そういうものだと思う。昔,先輩が,一冊の単行本を上梓して,
ひとつ誤植があった,
とひどく悔やんでいたのを思い出す。それは,編集者の矜持でもある。
参考文献;
武田知弘『「桶狭間」は経済戦争だった』(青春出版社) |
|
ナラティヴ |
|
アリス・モーガン『ナラティヴ・セラピーって何?』を再読。
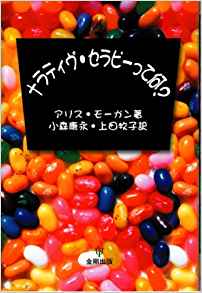
「ナラティヴ・アプローチ入門」を受講するのを契機に,かなり前に読んだ,本書を再度読み直してみた。
基本中の基本の再確認だが,結構大事なことを忘れていた気がする。その基本を,おさらいしておきたい。
著者は,イントロダクションで,
ナラティヴ・セラピーは,カウンセリングとコミュニティー・ワークにおいて,相手に敬意を払いつつ非難することのないアプローチとなることを自らに課しています。人々をその人の人生における専門家として位置づけるわけです。問題は人々から離れたものとして捉えられ,人々は本人の人生における問題の影響を減らすのに役立つようなスキル,遂行能力,信念,価値感,取り組み,一般的能力を豊富に備えていると考えられています。
多用な原理がナラティヴな仕事の仕方を支えていますが,私の意見としては,次の二つが特に重要です。ひとつは,絶えず好奇心をもっていること,もうひとつは,あなたが本当に答を知らない質問をすることです。
このことを,この本を読むときに念頭に置いておいてほしい,と勧めている。
さらに著者は,ナラティヴ・セラピーにおいて,
私はも相談者に合うとき,会話の方向性に対する可能性をまるで旅路のように考えることがあります。選択可能な分かれ道や交差点,小道,行路が数多くあるのです。一歩踏み出す度に,前後左右,斜めにと,いろいろな種類の新しい別の分かれ道や交差点が現れます。相談者と共に見出すたびに,私たちは可能性を広げていくのです。どこへ行くか,そして途中で何を捨てていくのかは,私たちに選ぶことができます。いつも違った道に行くことができます。
と。そして,
ナラティヴ・セラピストが相談者にたずねるひとつひとつの質問は,旅路の中の一歩なのです。
と。いわば,共同作業なのである。しかしそのために,
セラピストは,相談者の興味が何か,そして,旅がいかに相談者の好みと一致しているか理解したいと考えます。
例えば,こんな質問をしながら。
この会話は,あなたにとってどんな感じがしますか?
このことについて続けて話をしましょうか?それとも……について話した方がいいですか?
あなたはこのことに興味を感じますか?このことは,時間を割いて話した方がいいでしょうか?
等々。
ナラティヴ・セラピーは,「再著述」の会話または「リ・ストーリング」の会話,
である。ストーリーとは,
出来事が
(過去・現在・未来の)時間軸上で,
連続してつなげられて
プロット(筋)になったもの
である。実は,人は,いくつものエピソードをもっているのに,ひとつの意味でつなげた自分の物語をもっていて,その意味から外れた多くのエピソードは,筋からはずされている。本当は,
すべてのストーリーは同時に存在し得,なにか出来事が起こると,そのときにドミナントである意味(プロット)によって解釈される。
その限りで,
出来事に対して…与えている意味は,自分自身の人生に対する影響力において中立的ではない…,
のである。しかも,
自分の人生を理解する仕方は,自分たちが生きている文化というより広範なストーリーによって影響を受けている。
それには,
ジェンダー,階級,人種,文化,そして性的指向性,
等々がストーリーのプロットを大きく左右する。そのことに,必ずしも自覚的,意識的とは限らない。
では,見つけるべきドミナント・ストーリーに代わるオルタナティヴ・ストーリーは,
代わりのストーリーであれば何でもよいわけではなく,相談者自身によって同定され,相談者自身が生きたいと考える人生に沿ったストーリーでなければなりません。
しかし,
問題をはらんだストーリーの影響から自由になるためには,オルタナティヴ・ストーリーを再著述するだけでは十分ではありません。ナラティヴ・セラピストは,オルタナティヴ・ストーリーが「豊かに記述」される方法を探る…
ことが必要になる。そのために,問題を外在化し(例えば擬人化し),名付け,問題の歴史をたどり,その影響を明らかにすることを通して,
問題に対しいかに対処し,処理したかについての気づきの可能性を広げ,それによって引き出された一般能力と遂行能力に光を当てることになる…,
と同時に,それを通して,
問題と問題のストーリーを支持している幅広い文化の信念やアイデア,それに実践を発見し,認識し,「分解すること」(脱構築)
をしようとする。たとえば,
このストーリーのつじつまを合わせるためには,どのような前提がその背後にあるのだろうか?
このストーリーは,まだ名前も付けていないどんな前提を背景にして成り立っているのだろうか?
問題の生命を支えている,当たりまえと思われている生き方や在り方は,何だろうか?
等々の質問をしながら,
当たり前とされている
ことを分解し,検討する。さらに,
それらの考えは,どのようにして発展してきたのでしょう?
あなたは,これらの考えに納得できますか?
性的・親密な関係における人々の役割について,あなたの信念をいくつか聞かせてくれませんか?
等々。こうした会話を通して,
ドミナント・ストーリーの「荷解き」を助け,異なる視点からそれらを捉えるように援助します。
脱構築の会話で重要なことは,セラピストが「当人の考えを変えよう」としてセラピストのアイデアや思想を押し付けないことです。……セラピストは,答えがわからないがゆえに質問をしているわけですから,好奇心を持ちつづけることになります。
問題を支えている価値観や考え方について,
それが役に立つものか否か,
を明らかにしていく。
役に立たないものだと判断されて初めて,
問題の影響を受けていない期間やユニークな結果(ソリューション・フォーカスト・アプローチで言う例外)
が,クライエントにとっても意味が出てくる。しかし,重要なのは,
ユニークな結果を探るのを急がないことです。人がセラピストに相談に来た以上,問題のストーリーは大きな影響力を持っていて,その人の人生に多大な影響を与えてきたと考えるのが妥当です。セラピストがこれらの影響を探求し,その中で,影響を認識すること…
なのである。だからこそ,
ユニークな結果は,オルタナティヴ・ストーリーの窓口
なのであり,それだけに,
ユニークな結果(ドミナント・ストーリーないし問題の外に位置する出来事)は,セラピストが気をつけて耳を傾けない限り,気づかれないことがしばしばです。人々はこれらの出来事はさして重要ではないと見なす傾向があり,そのことについて早口で話したり,さらっと流してしまうことが多いものです。
ただし,
相談者が注目に値すると認めない限りドミナント・ストーリーにはなり得ない,
ということを忘れてはならない。だからこそ(ここがソリューション・フォーカスト・アプローチとは決定的に異なることだが),
セラピストは,出来事が特別でユニークなものか当人に確かめてもらう必要があります。相談者がそのできごとをいつもとは異なる重要なことだと捉え,ドミナント・ストーリーと矛盾していると考えた場合にのみ,ユニークな結果とみなされる。
そのためにも,
(ドミナント・ストーリーから外れた)……は,あなたにとってどんな意味がありますか?
あなたは,問題が悪化していくのをどうやって止めたんですか?
問題がそれほど支配的ではなく,いばっていないときはありましたか?
問題があなたを止めたり邪魔しようと試みたのに,問題の思い通りにはならなかったときのことを思い出せますか?何が起きたのですか?
あなたが問題に抵抗して,思い通りにやり通したときのことについて話してくれませんか?
といった質問が不可欠になる。
このユニークな結果が後づけられ,地固めされればされるほど,そして新しいストーリーと結びつけられ,意味が与えられるほど,新しいプロットが生み出され,オルタナティヴ・ストーリーがより豊かに記述され…
ていくことになる。
参考文献;
アリス・モーガン『ナラティヴ・セラピーって何?』(金剛出版) |
|
虚点 |
|
レペッカ・ブラウン『体の贈り物』を読む。
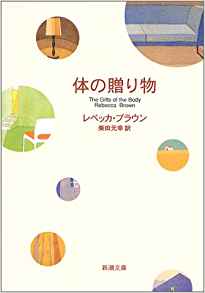
これは僕の意志ではなく,「ナラティヴ・アプローチ入門』の第三回目用の事前課題として出されたもの(肝心のセミナーには不参加にしだのだが)。まず,僕の手にすることのない類の本,というか小説だ。僕の関心領域の外にあるので,視野に入ることはない。いわゆるベストセラーではないらしいのだが。
推測するに,第三回は,「パラレルチャート」がテーマなので,それに絡めると,ここから,「私」及び登場人物の人生の物語を理解し,描き出そうということなのではないか,と思うが,ま,そこは,セミナーに参加しないのでわからない。
「私」は,USCという組織から,PWA(エイズウイルス感染者の)ホームヘルスケア・エイドとして,ホスピスへ入居す(でき)る前の患者の自宅に,このサービスは,医療行為は行えないらしいので,その他のハウスキーピングも含めた患者のサポートをするために,戸別訪問を行っている。どうやら,USCの創設間近い頃から活動に参加しているらしい。
全体のタイトルもそうだが,各章も,
The gift of 〜
で始まり,
汗の贈り物
充足の贈り物
涙の贈り物
(略)
希望の贈り物
悼みの贈り物
と続く。面白いことに,「私」については,ほとんど語られない。患者とのやり取り,患者とのサービス,組織とのやりとりだけが,淡々と語られる。例外は,
今度の人は見た目に一番不気味だった。本当に病そのものに見えた。マーガレットからは,特別に必要なのは体に軟膏を塗ってあげることだけだと言われていた。軟膏はどろっとして不透明で,黄色っぽいゼリー状だった。大きなプラスチックの広口壜に入っている。何の匂いもしなかった。はじめて行って,壜のふたを開けたとき,誰か他人の指が軟膏をすくい取った跡が残っていた。なぜかそれ見てあんなに怯えたのか,自分でもわかない。でもとにかく私は怯えた。私はその人に触るのが怖かった。その人を見るのも怖かった。
腫れ物はどれも黒っぽい紫色で,二十五セント貨くらいの大きさだった。縁は黄色く,その人の肌は黒っぽ茶色だった。腫れ物から液や膿は出ていたりはせず,かさぶたもできてはいなかった。年じゅう軟膏を塗っていたからだ。
というところに(はじめて)感情が出ているくらいに思う。この章が,「姿の贈り物」だ。因みに,マーガレットとは,組織のマネジャーの一人だ。他は,患者を,抱き起したり,食べさせたり,風呂に疲らせたりのサポートを淡々とこなす。
たとえば,上記の軟膏を塗ってあげた患者に,ジュースを飲ませるところがある。
私はスプーンでジュースをすくった。すごく少量だ。澄んだピンク色のジュースの,ほんの一口。スプーンを口の方へ動かしていきながら,片手を彼の手首近くに当てたまま私は言った。「これからこのジュースを口元に持っていきますよ。もう唇のすぐそばにあります。オーケー。さあどうぞ」
かちん,とスプーンの底が下側の歯に当たるのが聞こえた。私は彼の口のなかでスプーンを傾けた。彼は唇を閉じ,飲み込んだ。
「ようし」と私は言った。「いい感じですね。もっと飲みます?」
彼はまばたきした。
「オーケー」と私は言った。もう一杯スプーンにジュースを入れて,口に持っていった。「さ,またジュース,来ましたよ」。彼の唇が,吸いこもうとするかのように動いた。私はスプーンを口に入れて,裏返した。彼は飲み込んだ。
「いいですねえ」と私は言った。「すごくいいですよ」
彼はまばたきした。
結局スプーン六杯分,ジュースを飲ませた。でも,六杯目で,喉がゴロゴロと音を立て,ジュースが一部飛び出してしまった。彼は口を大きく,怯えたようにO字型に開け,クーンと甲高い声を上げた。息が詰まってしまうのでは,と私は慌てた。
という調子である。「私」の感情を表現することはほとんどない。ここにあるのは,自分の感情を押し隠して,淡々と仕事をしかし,丁寧にこなす姿だけがある。いわば,淡々と,
前捌きする援助職のベテラン,
という感じである。
そういうとき,ある意味「私」は,虚点(という言葉があるかどうか知らないが)というか,ここに「虚」として,しかい(存在し)ない,ように見える。だから,「私」の生活も,私の背景も,まったく語られない。性別も,本当はよくわからない。
患者と,すでに死んだ,「私」も世話をしたカーロスの話を,こんなふうに会話する。
マーティは大きく息を吸って,顔にある種の表情を浮かべた。自分が本当に答を知りたいのか,よくわからないまま訊ねるみたいな表情だった。
「死ぬのって,救いになりうると思う?」とマーティは訊ねた。
「思う」と私は答えた。
マーティは息を止めていた。それから,ふうっと吐き出した。口元が柔らかくなった。そして,切なそうに私を見た。マーティは私に知ってほしかったのだ。
「僕,手伝ったんだ」とマーティは言った。
「カーロスのいい友だちだったんだね」と私は言った。
「うん,そうだった」とマーティは言った。「僕は思いやりある行いをしたんだ。僕はあいつに死の贈り物をあげたんだ」
この章は,「死の贈り物」と題されている。
「私」は,病気に感染したマネジャーのマーガレットの送別のミーティングに参加して,マーガレットと,古くから参加しているという話題の後,マーガレットに問われる。
「あなたこれ,永久につづける気じゃないでしょ?」と言った。
「実は,辞めようかと思ってるんだよね」と私は口にした。口にしたのも,そもそもはっきり意識して考えたのも,そのときがはじめてだった。
「それがいいね」とマーガレットは,私が言い訳を並べる暇もなく言った。わたしのことをよくわかっていてくれているのだ。「何かほかのことをするのもいいよね。またやりたくなったら,いつでも戻ってきてペレニアルになればいいし」
ペレニアルとは,UCSでしばらく働いて,それから何か別のことをやり,またしばらく戻ってきて,それからまた何か別のことを,と出入りを繰り返す人のことだ。
「私」が虚点というのをよく表しているのは,マーガレットと会話していて,背後で,夫のディヴィッドが話しているのが聞こえるところだ
次の次の夏に,上の子が小学校を卒業したら彼とマーガレットとで子供たちをディズニーランドに連れて行くんだと言っていた。「次の次の夏」と言ったのを聞いて,私の目がきっとディヴィットの方を向いた。ほんの一瞬だったけれど,マーガレットは見逃さなかった。あとどれぐらい生きられるのだろう,と私が考えているのを彼女は見てとった。
私はマーガレットに謝りたかった。でも何も言えなかった。
マーガレットはまだ私を見るのをやめていなかった。「あなたにやってもらえることがあるわよ」と彼女は言った。
彼女は私の頬に片手を当てた。二たりでリックを車に乗せたあのとき,彼女に触れた手触りを私は思い出した。彼女の手が私の肌にくっつくのを感じた。彼女は言った―「もう一度希望を持ってちょうだい」
この最終章は,「希望の贈り物」と題されている。
「私」は周囲をひたすら反照する。「私」側から,働きかけるのは,患者のサポート,ハウスキーピングについてだけだ。「私」自身については,まったく語られない。
ただ一か所,ミーティングへ出る前,
五時ごろだった。私は家に帰って,猫に餌をやり,しばらく一緒に遊んでいた。ミーティングではピザが出るから,何も食べなかった。しばらくして,気を取り直し,無理して湖畔へ散歩に出た。しばらく歩きまわった。
ここでだけ,私生活が語られる。
「私」が虚点になっている分だけ,絶望的な患者の状況が,感情抜きで無表情に映し出される。その分,状況の絶望が伝わる,しかし,各章では,必ず,ギフトを見つけ出す。まるで,エレナ・ポーター『少女ポリアンナ』の,
どれだけ苦しい状況でも、牧師である父親の遺言の「よかった探し」をする,
ポリアンナ(パレアナ)のように。それも,「私」が虚点で,ただ患者を淡々と映し出しているだけであることによって,際立ち,フォーカシングされることになる。
そして,思うに,この虚点という位置こそが,この種の
サービス
の,あるいは,
サポート
そのものの,あるいは,
それを担う人の,
ポジショニングそのものの象徴なのではないか,という気がする。そう気づいて,思い出したことがある。
旅先でのったタクシーの女性ドライバーが,それまで長年勤めていた介護施設で,あるとき,ふいに糞尿の匂いに耐えられなくなり,辞めた,と。
淡々と,虚点でサポートしていたのに,嫌悪というか,マイナス感情が起こった途端,虚点には立てなくなった,と言うふうに考えられる。前捌きだけでは対応できなくなった,というか破綻をきたしたのだ。
その分岐点が,腫物への不気味さ
である。感情が,虚点を踏み出してしまった,のかもしれない。
参考文献;
レべッカ・ブラウン『体の贈り物』(新潮文庫)
エレナ・ポーター『新訳 少女ポリアンナ 』(角川文庫) |
|
知への意志 |
|
ミシェル・フーコー『〈知への意志〉講義』を読む。
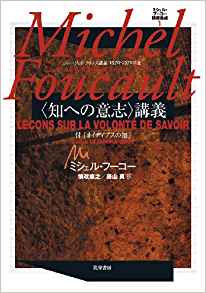
「ミシェル・フーコー講義集成1」である。「コレージ・ド・フランス講義 1970‐1971年度」。フーコーの講義録である。実際の講義の録音を基にすることになっているが,この年度には,それがないため,フーコーが講義のために残した草稿にもとづいている。
こんな知の巨人について。何か論評できるはずもなく,ただその精緻な論理と奥行きの深さに,昨今の日本の知のレベルの劣化というか,痴呆化に思いが至る。
しかも,これがコレージュ・ド・フランスの講義だということだ。出席者は,大学生,教職員,研究者,その他の興味本位の人たちに,毎週行われている。この知的レベルの高さに,まず驚嘆するしかない。それに比して…,もはや言葉もない。
「知への意志」と題したのこ講義は,
真理への意志が,言説に対して排除の役割を果たすのではないかどうか,すなわち,真理への意志が,狂気と理性の対立が果たしうる役割,もしくは禁忌のシステムが果たしうる役割に―一部において,そしてもちろん一部においてのみ―類似した役割を果たすのではないかどうか知ることである。
と始まる。そしてこう問う。
真理への意志は,他のあらゆる排除のシステムと同様,根底において歴史的なものではあるまいか。真理への意志は,その根底において,他の排除のシステムと同様,恣意的なものではあるまいか。真理への意志は,他の排除のシステムと同様,歴史のなかで変容を被りうるものではあるまいか。真理への意志は,他の排除システムと同様,制度的なネットワーク全体によって支えられ,絶えず再開されるものではあるまいか。真理への意志は,他の緒言説にたいしてのみならず他の一連の実践に対してなされる拘束のシステムを形成するのではあるまいか。要するに,問題は,真理への意志のなかに,いかなる現実の闘いといかなる支配の介入が入り込んでいるかを知ることなのだ。
問いは,それが新しく,鋭ければ鋭いほど,あらたな答えを秘めている。そこには,
真理は権力の外にあるのでもなければ,権力なしにあるのでもない,
というフーコーの立場が含意されているらしい。つまり,
知は,無私無欲でも,正義でも,まして,自由でもない,
ということを,フーコーは暴き続けている流れの中において見なくてはならない。別のところで,フーコーは,次のように語っている,という。
知識人の役割は,他の人々に対して何を為すべきかを語ることではありません。いかなる権利があって知識人はそんなことをしようというのでしょう。……知識人の仕事,それは,他の人々の政治的なのかたちを定めることではありません。そうではなくて,それは,自分自身の領域において行う分析の数々によって,自明性や公準を問い直し,慣習および思考や行動の仕方に揺さぶりをかけ,一般に認められている馴染み深さを一掃し,規則や制度の重要性を測り直し,そして,そうした再問題化から出発しつつ,一つの政治的な意志の形成に参加することなのです。
おのれの専門領域で,既成概念を崩し,そこから政治的な意志形成に参加しろ,ということだ。いまなら,各々の立場で,いまの日本の方向性を正すべく,深掘りし,知の再形成に挑め,ということなのだろう。しかし,怠惰と惰眠のせいで,いま,もう時間は限られているが。
さて,そこで,フーコーは,さらに,問う。
真理への意志という言葉を口にするとき,……問題となっているのは,真理への意志なのか,それとも知への意志なのか。そして,真理と知という二つの概念のうちの一方あるいは他方を分析する場合には必ず出会うことになる概念―つまり認識という概念―についてはどのようなことが言えるだろうか。
そして,さらにフーコーは,問う。この問いの連鎖の中で,ふと思い出すが,清水博が,
創造の始まりは自分が解くべき問題を自分が発見することであって,何かの答えを発見することではない,
と書いていた。そのフーコーの問い。。。
意志という語を,どのような意味で理解すべきであろうか。この意志という語の意味と,認識への欲望ないし知への欲望といった表現のなかで使用されている欲望という語の意味とのあいだに,いかなる差異をみいだせばいいのか。「知への意志」という,ここで他と切り離して考えられている表現と,「認識への欲望」という,より馴染み深い表現とのあいだに,いかなる関係を打ち立てればよいのか。
と。そして,この例題として,アリストテレスの『形而上学』の冒頭が引かれる。こうある。
すべての人間は,その自然本性によって,認識への欲望を持っている。諸感覚によって引き起こされる快楽がそのことの証拠である。実際,諸感覚は,その有用性を抜きにしても,それら地震によつて我々に好まれるものである。そして,あらゆる感覚のなかでも最も我々に好まれるのが,視覚である。
フーコーは,ここの三つのテーゼを読み取る。
①知にかかわる欲望が存在する
②この欲望は普遍的であり,あらゆる人間のうちに見いだされる
③この欲望は自然によって与えられている
そして,アリストテレスの論証を推測しつつ,また問う。
第一の問い。感覚および感覚に固有の快楽は,いかなる点において,認識への自然的欲望のしかるべき例であるのか。
第二の問い。もし,あらゆる感覚が,それぞれの感覚が行う認識活動に応じてなにがしかの快楽を与えるのであるとするなら,動物たちはなぜ,感覚を持つにもかかわらず認識することを欲望しないのか。アリストテレスが,認識への欲望を,すべての人間に備わるもの,ただし人間のみに備わるものとみなしているように思われるのは,いったいなぜだろうか。
そして,フーコーは,こう答える。
アリストテレスは,一方では,認識への欲望を自然のうちに組み入れ,その欲望を感覚と身体に結びつけて,ある種の形態の喜びをその欲望の相関物とすることに成功する。しかし他方,それと同時に彼は,認識への欲望に対し,人間の類的自然本性のなかで,つまり,知恵の境域,自己のみを目的としており,そこでは快楽が幸福であるような一つの認識の境域のなかで,その地位と基礎を与えるのである。
そしてその結果,身体,欲望が省略される。感覚すれすれのところで諸原因の大いなる平静かつ非身体的な認識へと向かう運動,この運動は,すでにそれ自身,知恵に到達しようとする漠とした意志である。この運動は,すでに哲学なのである。
そこから, こうまとめる。
アリストテレスのモデルが…含意しているのは,知への意志が好奇心以外のなにものでもないということ,認識が感覚のかたちで常にすでにしるしづけられているということ,認識と生とのあいだには根源的な関係があるということである。
ここまでの,わずか数行のアリストテレスの文章を掘り下げ,拡大し,敷衍化していく思考のダイナミズムは,とてもひとつひとつの背景と根拠をフォローしきれない。しかしその奥行きと問いの深さのもつ知の巨きさには,感嘆するほかはない。
このアリストテレスに対比して,フーコーは,ニーチェを取り上げる。
ニーチェのモデルが主張しているのは,逆に,知への意志が認識とは全く別のものに送り返されるということ,知への意志の背後にあるのは感覚のような一種まえもっての認識ではなく,本能,闘い,力への意志であるということだ。
さらに,
ニーチェのモデルは,知への意志が,もともと真理と結びついていたというわけではないことも主張している。知への意志は,錯覚を作り上げ,虚偽をこしらえ,誤謬を繰り返し,真理がそれ自身一つの効果でしかないような虚構の空間において自らを繰り広げるものなのだ,と。
さらに,
ニーチェにとって,知への意志はすでにそこにある認識の前提条件を想定するものではない。真理は前もって与えられるものではなく,一つの出来事として産出されるものであること。
ニーチェは,こう言い切っている。
認識それ自体などない,と言うこと,それは,主体と客体の関係が(そして,アプリオリ,客観性,純粋認識,構成的主体といったその他派生物のすべてが),実は認識の基礎として役立つものではなく,逆に認識によって産出されたものである,
そして,ニーチェは,
コギトのような認識の核心のようなものを拒絶し,
主体と客体との関係は,認識を構成するものではない。それどころか認識によってもたらされる第一の主要な錯覚,
と言い切る。むしろ,
主体と客体との関係から解放された認識,それが知なのである。さらに,哲学的伝統で,
意志と真理との関係の核心に見出されるもの,それは自由である,
というものを,ニーチェは根底から,覆す。
真理と意志との連接は,自由ではなく,暴力
である,と。で,フーコーは問う。
真理が認識以後のものであり,認識から出発しつつ暴力として不意に出現するものであることが本当であるとすれば,真理は認識に対して加えられた暴力であることになる。真理は,真なる認識ではない。真理は,変形され,捻じ曲げられ,支配された認識である。真理は,偽なる認識なのだ。真なる認識との関係において,真理は,誤謬のシステムなのである。
そこを,さらに,フーコーは詰める。
更に一歩先へと進めねばならない。もし真理が,認識することの錯覚を破壊するものであるとすれば,そして,もしその破壊が,認識に逆行して,認識そのものの破壊としてなされるとすれば,そのとき,真理は虚偽であることになる。…真理は,認識することへの報いとして言表されるまさにそのとき,真理を語ってはいない,
と。そして,こうフーコーはまとめる。
このようにして明るみに出された力への意志とはいったい何か。それは,存在(不動で永遠の真なる存在)から解放された一つの現実,すなわち生成である。そしてその生成を暴露する認識は,存在を暴露するのではなく,真理なき真理を暴露するのである。
したがって,二つの「真理なき真理」があるということだ。
―誤謬,虚偽,錯覚としての真理,すなわち,真ならざる真理。
―そうした虚偽としての真理から解放された真理。すなわち,真理を語る真理,存在と相互性を持ちえない真理。
真理の絶対性から解放されたとき,真理は相対化され,その地平の延長戦上に,社会構成主義がある,と見なせば,ここまでの論考に,一つの光明が見える。認識は,生成され,真理もまた生成される。飛躍かもしれない…が。
ところで,付録の「オイディプスの知」は,知の問題を分析した,象徴的な論考で,読み応えがある。その最後に,フーコーは,こう締めくくっている。
我々は,知を,意識=良心という観点から思考しているのだ。それゆえに,我々はオイディプスとその寓話をネガティブなものとしてしまったのである。無知と有罪性という言い方がされるにせよ,無意識と欲望という言い方がされるにせよ,いずれにしても我々は,オイディプスを知の欠如の側に置いており,知に結びついた権力を持つ人物をそこに認めようとはしない。神託と都市の証言が,それらの種別的な手続きおよびそれらによって産出される知の形態に従って,過剰と侵犯の人として追い立てる人物。そうした人物を,我々は底に認めようとはしないのだ。
そこにも,知があるとは,ニーチェの結論から必然的につながっていくように思われる。そして,それは,権力とつながってもいる,と。
参考文献;
ミシェル・フーコー『〈知への意志〉講義』(筑摩書房)
清水博『生命知としての場の論理』(中公新書) |
|
物語 |
|
武光誠『一冊でわかる古事記』を読む。
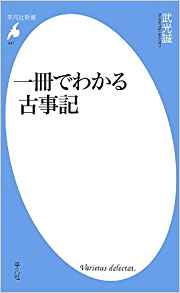
『古事記』の世界全体が,新書の解説本でわかるわけでもないが,
分かりやすい形で,読者に『古事記』の世界を紹介する,
意図で,著者の眼鏡を通した古事記世界像である。その意味で,かつて読んだきり読み直していない『古事記』を,他人の解説という目を通すと,どう見えてくるのかが,僕にとってのひとつの面白さだ。
古事記も物語であり(日本書紀が官製の物語なのに比し),太安万呂がまとめた,
全体で一つの流れをもつ物語である。
しかも,『古事記』は,
「帝記」「旧辞」と呼ばれる文献をもとにしてつくられた『古事記』の作製のときに,「帝記」にも「旧辞」にも,異なる内容を期したいくつもの異本があった。
それを一本にまとめるにあたって,
「旧辞」にもとづく物語の部分と,「帝記」を写した王家の系譜を帰す部分とを組み合わせてつくられている。
こう著者は解説する。もちろん,これも,著者の説に過ぎない。
物語というのは,一貫した世界を描く。そのために,その物語にそぐわない素材は,カットされる。歴史もまた物語とされるのは,著者が取捨選択して,世界を描き出すためだ。でなければ,ただ事実をつなげても,世界は見えてこない。
そこでは一貫した視界を造るために,外されるものがある,ということだ。と同時に推測されることは,一貫するために,不足を足す,ということがある。極端なことを言えば,その時代でないものを別の次代の事実から持ってきて,自分の描くジグソーパズルの全体像のためのピースにしてしまうということもある。
いまひとつ,物語は,書くということに伴い,言葉自体の連続性に拘束される,つまり,言葉にした瞬間,事実とは別に文章という文脈の拘束力に規制される。たとえば,同じ日の出でも,
朝日,
と書くのと,
日の出,
と書くのでは,次につなぐ言葉の規制力が異なる。つまり,言葉は,言葉によって,文脈を強制される。従って,否応なく,事実からは隔てられる。
そう思って,古事記を見ると,結構面白いところが多々ある。
たとえば,著者はこう言う。
古代人は「言葉には物事を動かす力がある」とする,言霊信仰をもっていた。そのために,個々の神の名はそれぞれの役割を示す重要な名称と考えられていた。天之御中主神の名前をもつ神さまは,世界の中心で万事をとりしきる能力をもつ。高御産巣日神と神産巣日神は,人間や動物が楽しい生活を送れるように見守り,かれらを繁殖させる力をもつ。
しかし,逆の言い方もできる。世界の万物をとりしきる神がいるとして,それに名をつけた瞬間,世界は,その神の御業に見えてくる,それは今日もそうである。われわれは,言葉を持つ(あるいは名づける)瞬間,そのように世界が見える。それを言霊と呼ぶなら,いまも言霊はある。
あるいは,建御名方神が建御雷之男神に打ち負かされ,諏訪湖まで逃げて降伏したという逸話について,
建御名方神の名前は,『古事記』の大国主神関連系譜にはみえない。諏訪側にも,大国主神を建御名方神の父神として重んじた様子はない。
こういったことからみて,建御名方神の話は後に加えられた可能性が高い。
と言う。その背景にあるのは,
六,七世紀に朝廷は,神話の整備や祭祀の統制に力を入れた。これによって,全国の神々を皇祖天照大御神を頂点とした秩序のなかに組み込もうとした…。
という政治的事情である。これまた物語に丸める動機になる。
あるいは,五世紀,南朝の宋朝に,倭の五王,讃,珍,済,興,武が使者を派遣したと,史書にある。それに合わせて,武が,
雄略天皇の実名,「ワカタケ」の「タケ」を漢字にしたもの,
として,雄略天皇に比定されるところから,残りを,
興を,安康天皇,
済を,允恭天皇,
珍を,反正天皇,
讃を,履中天皇もしくは仁徳天皇
にあてようとする。しかし,安康天皇,反正天皇は,中国史書にあわせて,後に系譜に加えられたのではないか,と見られる,と著者は言う。
つまり,中国側にある事実に合わせて,空白を補ったのである。たとえば,讃を,仁徳天皇とする説は,
仁徳天皇の実名の「オオササギ」の「ササ」を「讃」と表記したとする,
のである。もうここまで行くと,歴史も,確かに(創作)物語でしかない。
さらに,著者は,
五世紀はじめに本拠地を河内に遷した王家は,六世紀後半の570年代に最盛期をむかえたと考えられる。この時期に,日本最大の古墳である仁徳天皇陵古墳が築かれた…。
古墳の年代から見て,仁徳天皇陵古墳が五世紀はじめの仁徳天皇を葬ったものでないことは明らかである。(中略)仁徳天皇陵古墳は,有力な大王であった雄略天皇のためにつくられたものとみても誤りではあるまい。仁徳天皇陵ができたあとの河内の古墳は,次第に縮小していった。
さらに,こう付け加える
朝廷で漢字が用いられなかった時代には,「正確な系図を伝える」という発想は見られなかった。(中略)渡来人の知識層が朝廷での活躍が始まる五世紀なかばにようやく,王家の系図づくりがはじめられた。その頃の系図は,次のようなものではなかったかと思われる。
(いわれびこ)……みまきいりひこ(崇神天皇)――
いくめいりひこ(垂仁天皇)――ほむたわけ(いささわけ,応神天皇)――大王の祖父――大王の父――大王
このなかのほむたわけ(いささわけ)は,「七支刀銘文」にみえる倭王旨(ささ)に対応する実在が確実な大王である。……次の三人が五世紀実在した大王である可能性が高い。
おおさざき(仁徳天皇)――わくご(允恭天皇)――わかたけ(雄略天皇)
これに名前が不明な大王を二人加えたものが,倭の五王である。「おしは」が,倭の五王の一人であった可能性もある。
不足をつないで,一貫性を保たなければ,ひとつの自己完結した世界はまとまらない。歴史も,また,「史記」を含めて,物語であるのだろう。
参考文献;
武光誠『一冊でわかる古事記』(平凡社新書) |
|
マインドサイト |
|
ダニエル・J・シーゲル『脳をみる心・心をみる脳』を読む。

キーワードは,マインドサイトである。
マインドサイトについて,こう書く。
マインドサイトとは,自分の心と脳の働きを意識することができる注意集中の形である。マインドサイトをもつことで,心のなかの暗く激しい渦に巻き込まれるのではなく,「いま自分はどんな気持ちでどんな状態にあるか,これからどうなりそうか」に気づくことができます。すると,これまでの決まりきったパターンから抜け出します。いつもと同じような気持ちになり,感情に押し流されていつもと同じ行動をとるという悪循環から抜け出すことができるのです。マインドサイトによって,自分のそのときの感情に「名前をつけて,手なづける」ことができるようになります。
マインドサイトそのものの語義的な定義がないので,憶測になるが,
心を見る眼
という意味と,
心を見るポイント
という意味と,
心のさまざまな側面
というような意味がある,と僕は受け止めた。ただ対自やメタ・ポジションというだけではなく,見方の意味が含まれているように思う。
マインドサイトは特別なレンズのようなものです。
という言い方もあるし,
気づきの車輪,
といって,自転車の車輪のイメージで,中心軸からスポークが外輪へ向かって伸び,外輪の思考,感情,知覚,身体感覚に注意を向けている,その中心軸で気づきを感じる,その中心軸を前頭前野と考えていい,という言い方もしており,マインドサイトの持つ意味の多重性がある。
さらに,手法として,
フォーカシング(自分の心の状態に注意を向ける)
や
マインドフルネス(瞑想)
が紹介されているので,更に
注意を向ける向け方
という側面でもある。
そして心の表象を,著者は,
自分の心のイメージをつくる「私マップ(me-maps)」
他者の心についてイメージする「あなたマップ(you-maps)」
私とあなたの関係性をあらわす「私たちマップ(we-maps)」
があるとし,
これらがなければ,自分自身の気持ちや他者の気持ちを感じ取ることはできません。
という。この前提としてあるのは,
自分の心をよく知らなければ,他者の心を知ることはできません。自己理解するための力が高まることによって,相手の気持ちを理解して受け入れることができるようになります。脳のミラーニューロンが「わたしたち」という視点を獲得することにより,自己感覚もまた新たな視点を獲得します。心と身体の状態に気づき共感すること,自己を強化して他者とつながり合うこと,個でありながら集団としていられること―これこそが,社会的脳の共鳴回路がつくり出すハーモニーの源なのです。
という考え方なのである。
背景には,最新の脳科学の成果があるが,脳をイメージする時の,
脳ハンドモデル
は出色である。
手の親指を他の指と手のひらのなかに包み込むようにすると,「手ごろ」な脳のモデルができます…。握りこぶしの手のひら側のほうが人間の顔にあたり,手の甲が後頭部にあたります。手首は背骨から脳の根元まで伸びた脊髄と考えてください。親指をピンと立て,他の指をまっすぐに伸ばすと,ちょうど手のひらが脳の内部にある脳幹にあたります。親指を手のひらに折り曲げると,そこが大脳辺縁系のだいたいの位置を示します(両手を同じようにしてもらえば,右脳と左脳の対照的な様子を右手と左手で造ることができます)。その後人差し指から小指をくるっとまるめて元に戻すと,それが大脳皮質となります。
前述の車輪モデルで言う,中心軸,つまり前頭前野の持つ機能が,マインドサイトの機能と重なることに気づく。それには,9つある。
①身体機能の調節 心拍,呼吸,将かなどの私立神経の調節。交感神経というアクセルと副交感神経というブレーキのバランス調節である。
②情動調律 自分の心の状態を変化させて,相手の心の状態に共鳴するよう波長を合わせる。だからこそ相手に思われている,と感じられる。
③感情のバランス調整 感情のバランスを保つ
④柔軟に反応する力 入力と行動の間に「間」を置く力をもち,それが柔軟な反応をつくりだす。
⑤恐怖を和らげる力 前頭前野には大脳辺縁系と直接つながる線維連絡があり,恐怖をつくり出す扁桃体の発火を抑制し,調整する
⑥共感 あなたマップを作る能力。相手の心の状態に波長を合わせるだけでなく,心の中でどんなことが起こっているかを感じ取る力がある
⑦洞察 私マップをつくり,自分の心を知覚する。過去と現在をつなげて,この先何が起こるかを予測する,タイムトラベル装置
⑧倫理観 何が社会のためにいいか,そのためにどんな行動をすべきか,の概念をもつ。ここが破壊されると道徳観念が喪失する
⑨直感 体の知恵へのアクセス。心臓や腸などの内臓を含むからだ内部の隅々から情報を受け取り,「こうしろといっている」「これがただしいとわかる」という直感をつくり出す
要は,マインドサイトとは,脳の,とりわけ前頭前野のもつ能力をどう生かすか,ということだと言い換えてもいい。そのために,
①オープンさ 見聞きした者や心に浮かんだものすべてをありのままに受け容れる
②観察力 経験の中にあってなお自分を観察する力。自己観察によって,自分の生きている瞬間を全体としての文脈からみることができる
③客観性 思考,感情,記憶,信念,意図などの,ある瞬間心にあるものが一時的なものにすぎず,それが自分の全人格をあらわすものではなく,ほんの一面に過ぎないと気づかせてくれるのが,客観性
が,マインドサイトによる心のコントロールのための三要素としている。だから,
心とは関係性のプロセスであり,身体とつながり合うプロセスである。それによってエネルギーと情報の流れを調節するものである,
という定義は,心を実体化しないという意味で,キルケゴールの有名な一節が,瞬時に浮かぶ。
人間は精神である。しかし,精神とは何であるか?精神とは自己である。しかし,自己とは何であるか?自己とは,ひとつの関係,その関係それ自身に関係する関係である。あるいは,その関係に関係すること,そのことである。自己とは関係そのものではなくして,関係がそれ自身に関係するということである。
だから,マインドサイトは,
エネルギーと情報の流れをチェックし,整える,
ためのものと言い換えてもいい。そこで得るのは,
一つ目は,心臓の動きを感じ,お腹の具合に耳を傾け,呼吸のリズムに心を合わせる…身体の状態に耳を澄ますことによって,たくさんの大切なことが伝わってくるということ…。
二つ目は,関係性と心の世界は一枚の布の経糸と横糸だということです。私たちは他者との相互作用を通じて,自分の心をみています。
ということになる。最終的には,マインドサイトで,8つの統合を目指す,とする。
①意識の統合 注意集中する気づきの中心軸をつくりだす
②水平統合 全体思考の右脳と論理,言語の左脳の統合
③垂直統合 あたまのてっぺんからつま先まで,個々の部位の機能を統合し,一つのシステムとして機能させる
④記憶の統合 潜在意識に光を当て意識化する
⑤ナラティブの統合 左脳の論理的物語と右脳の自伝的記憶の統合による,「私の人生はこうだ」と理解する
⑥自己状態の統合 異なった基本的欲求と衝動を抱えた自己を,健全で多層な自己の一面として受け入れる
⑦対人関係の統合 私たちとしての健やかな幸せの状態。共鳴回路によって相手の心の世界を感じ,ともにいる,心の中にいる感覚
⑧時間的統合 未来が読めない,不確かな世界のなかでも,つながりを感じ,心穏やかに生きられる
それぞれが,臨床事例を通して,どう実践的に身に着けていくかが,具体的に紹介されている。いってみると,偏ったり,喪った自分を取り戻し,自分の再生の実践報告である。もちろん読んだだけで,マインドサイトが身に付くわけではないが,自分のボスとしての自分というものを取り戻すとはどういうことなのかが,よく伝わる物語になっている。
自分を取り戻すとは,
自分の一貫したライフストーリーが語れる,
ということなのだということがよくわかるのである。
ただ,最後に,ちょっと気になったことがある。
著者は,自分の核について,
すべての自己の状態の根底には,なんでもありのまま受け容れる核たる無垢の自己(receptive
self)があるのではないかと私は考えている。研究者のなかにはこれを,itselfを意味するラテン語の単語ipseにちなんでipseityとよぶ人もいます。Ipseityとは,複数の自己の状態の根底に共通して流れる「自分らしさ」である。
なんとなく,心の中に,
純粋の自分がいる
まっさらな自分がある
という言い方をすることで,世俗的な「自分探し」の「自分」と同じように,自己を実体化してしまったのではないか。あくまで,関係性の中での自分であるからこそ生きる,
マインドマップ
ではないのか。関係性の統合とは,あくまで,メタないしメタ・ポジションを指すのであって,実体ではないはずではなかったか。
もしマインドマップを喩えではなく,実体としてのレンズであったり,実体としての中心軸の自分,としてしまったのでは,それまでのせっかくの議論が胡散臭くなる。自己を関係性の中に徹底して納めなければ,
脳の中の小人,
ホムンクルス(Homunculus)
と同じことだ。自分の中の自分の中の自分の中の自分……。
どこまでもキリはない。
それはともかく,本書が,ナラティヴ・アプローチの参考図書として,セミナーのレジュメに記載されていた意味がよくわかる。それは,ポジショニング次第で,どんな物語を語ることもできる,という意味でもある。自分という世界の多様性と豊かさ,と言ってもいい。
良くも悪くも,本書もまた,著者自身の,
物語
であるのだろう。
参考文献;
ダニエル・J・シーゲル『脳をみる心・心をみる脳』(星和書店) |
|
姿勢 |
|
成瀬悟策『姿勢のふしぎ』を読む。
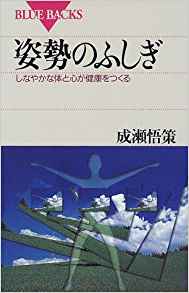
脳性マヒで動かないはずの腕が,催眠中に挙がったという事実に直面したのがことの始まりで,それ以来三十数年を経て今なお,人の「動作」というものの面白さに取り付かれっぱなしの状態,
という著者の,
肢体不自由者の「動作訓練」と並んで,動作による心理療法を「動作療法」とし,両者を合わせて「臨床動作法」と呼ぶ,
独自の治療効果のある療法の臨床実験の報告になっている。脳性まひから始まった対象は,いまや,脳卒中のリハビリ,四重肩,五十肩,自閉症,筋ジスからスポーツまで,幅広く応用範囲が広がっている。
その基本は,脳性マヒでの実証が背景になっている。
催眠暗示でリラックスできてもそれだけなら醒めれば元に戻りやすいということもあって,催眠に頼らずに同様の効果がえられないか…,
という課題から出発し,ジェイコブソンの「漸進弛緩法」を手掛かりに,
筋緊張のみられる肩や腕,腰や膝,足首などの関節をまず他動的に抑えて緊張させてから,押さえている力を弱めて筋弛緩をはかりながら,緊張感から弛緩感への体験変化を感じ取らせることで,リラックスしていこう,
というやり方に辿り着き,その効果に気づく。(ジェイコブソンについては,著者の別の本『リラクセーション』でも触れた。)
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163475.html
その効果は,
脳性マヒの子の手足が動くか動かないかというとき,ただ単に「動く」というだけでなく「動きすぎるほど動く」…,それこそ本当の話なのです。例えば手足を動かしたりしゃべつたり,からだで何かをしようとするとき,きまって腕や脚が突っ張ったり,その腕が後ろへ跳ね上がるように動いたり,肘を強く屈げて胸へ抱え込む,頸が緊張して頭が俯いたり前後に動く,そっぽをむく,などの動きや緊張はごくふつうにみられることです。
それを,
こうして動きすぎるほどよく動くにもかかわらず,そのからだは本人の気持ちや意思とは関係なく勝手に動いてしまい,どう努力しても自分の思うようには自分のからだを動かせないというのがこの子たちの本当の特徴なのです。
ととらえ,それまでの
動かない,動かせないなどととして捉え,「動かない」ことを基礎にしてこの子たちの特徴,
として考えた,いままでの理論や訓練への明確な反論となっている。そして,こう捉える。
脳の病変で肢体を不自由にしているのは,その病変が脳・神経系や,筋・骨格系のような生理的な機能に影響するというよりも,そのからだの持ち主である主体の自分のからだを動かすためのキーの押し方に影響して,それを未熟,不適切または不全にし,あるいは誤らせたりするため,主体の思うようには動かせなくなると考えるのが最も事実に合っているように思われます。すなわち,肢不自由をもたらした脳の病変は,生理的な過程に直接影響するというよりも,主体が自体を動かす心理的な活動を歪めるのが原因なので,たとえ脳の動きに関わる部分から,脳・神経系,筋・骨格系への生理的,物理的過程に異常がなくても,結果として不自由になるということになるわけです。
つまり,
この子たちのからだは病理学的に動かないのではなく,生理的には動く自分のからだを,その主体者が自分の思うようには動かせないだけ,
なのだから,
適切に動かせば動くようになるものなのです。
ということになる。もちろん,
何もこの子たちを健常者に近づけようなどとしているわけではけっしてありません。その子がもって生まれた体の機能,心の可能性を無駄なく,無理なく,なるべく充分に伸ばし,できるだけ生きがいのある豊かな人生を送れるように援助しようとしている…,
のである。では具体的にどうするのか。
動作のための努力は,まず「動かそう」として自分のからだへ働きかけることから始まります。例えば,握手を意としてそれを実現しようとするとき,まず握手するために必要な力を入れて腕を伸ばし,手を出し,握ろうとします。そうなるように主体は自分のからだに働きかけます。それは……腕に力を入れる感じ,伸ばしていく腕の感じ,手を出す感じ,相手の手を握るために入れる力の感じなどの実感を確かめながら,自分が実際にからだへ働きかけの努力をしていることをからだで実感することです。
動かそうと努力した結果,自分のからだのどこが,どのように動いているのか,現実のからだの動きを冷静かつ客観的に把握し確認するという努力は,動作において欠かすことができません。例えば,握手のとき,腕に力が入っている,腕は適切に伸びている,相手に向かってちょうどいいところまで手は出ている,手は相手の手を確かに握っている,相手の握り返す手を確かに感じている,などというような確かめる努力をしなければなりません。しかもそれは,……握手という動きの進行につれて,一コマ一コマにそのつど意図通り,ないし働きかけ通りに動いているか否かを現在進行形で確かめながら,動きの過程を進めることになります。
このプロセスは,ひょっとすると,スキーを覚えたり,自転車に乗ったりと何か新しいことを身体で覚えていく時と,変わらないのかもしれない。思い出すのは,このプロセスを細密にたどって,ポリオで動けない自分のからだを動けるように再学習したミルトン・エリクソンのエピソードであったが,
このように,自分の主体的な努力によって自分の意図通りの動きを実現した時,それをめざして活動している自分自身の努力活動の状況を自らのものとして実感することを「主動感」と呼んでいます。意図通りの動きが出来れば成功したと満足し,うまくいかなければ失敗したと反省するにせよ,いずれもそれは自分自身の責任によるものとして捉えるのは,それが自分がやったものという「主動感」の裏付けがあるからほかなりません。
この普通の人にとって意識もしない動作を,意識してたどっていく「動作体験」について,こんなことを書いています。
最近は脳性マヒも重度になり,しかも,ほかの傷害が重複して寝たきりの子が(対象として)増えてきました。こんな子たちの教育や訓練には,言葉が役立たないので動作が最も主要な手段になります。それまで寝たきりだった子が,独りでお坐り(あぐら坐り)できたときの独特の動作はまことに感動的です。補助の手を放したとき,全身にグッと緊張がはしって倒れずに坐位で踏ん張れた瞬間,眼がパッチリと見開き,右から左へ,さらに左から右へとゆっくり顔を動かして見回すのです。しかも,その直後からその子が大変化をします。それまで稚く弱弱しかった表情や仕草がしっかりと生き生きしたものに変わってくるのです。その後の心身の成長もまた驚くほど急速になっていくものです。
これを,
タテ系動作訓練法
と名付けていますが,ヨコからタテになることが人にとっていかに大事なのか,という視点から,立つ,について,
人が自分で立てるためには,重力にそって大地の上へ自体をタテにまっすぐ立てられるように彼自身が適切な力を全身に入れなければならないことが分かります。その力は,全身の筋群すべてを統合してからだに基軸をつくり,それをタテ直に立てようとするものですから,これを体軸ないし身体軸として捉えることができます。
として,次のような効果を挙げている。
この体軸は,……自分のからだの全筋群を統合して,初めて形成される彼自身の努力の結晶です。
また,「タテ直一本に通る心棒」として,
自分のからだをタテに立てられるようになると,表情や市靴などの自分自身に対する主体の対応が大変化するだけでなく,身体軸を外界の環境を受け容れて認知し,理解するための手掛かりにしようとします。
そして,
体軸が立てられるようになって外界の認知と対応がしっかりしてくるのは,彼がそれを原点として前後,上下,左右という三次元の座標軸において外界空間を捉え,自分の体軸を基準にして,その枠組みの中にそれを位置づけられるようになったことを意味します。
さらに,
時間の経過に伴って,この体軸が自分自身のよりどころとしての自体軸となって,外界が自分の中でそれぞれのものとして位置づけられてくるにしたがい,彼の心の中で,自分の置かれている外界全体が四次元世界として構成されてきます。その世界を自分と関係づけて認知し,対応し,あるいは活きかけ,活きかけられる基軸が考えられます。それは自分のからだという単なる身体軸にとどまらない主体的活動の中軸ですから,それを「自己軸」と呼ぶことができるでしょう。
こう見ると,ただの姿勢というより,立つ,ということの人間にとっての重要性が際立つ。著者は,よい姿勢とは,と,こうまとめる。
まず頸から肩,および背中から腰までの軀幹部が屈にも反にもならすぜ,自体軸がしっかり直に立てられていること,そしてお尻が引けず,股関節と膝が反らず屈がらず,まっすぐであること…。それらの節の部位がカタチの上でタテ直になっていればよいというのではなく,その形で全体重がかかとにかかるように,体軸にそってしっかり踏み締めができており,全体重が足の裏で確実に支えられるように,自体軸がやや前傾して重心が踵よりもすこし前,土踏まずのあたりにあり,足指のつけ根あたりに踏みつけの力が適切に入っていること。そのため,自体軸のどの部位にも主体によって柔軟ながら強くて確実な力の入っている状態が,もっともよい姿勢と言ってよいでしょう。
と。姿勢とは,構えであり,
物理的および社会的な外界の環境での事象やできごとに対応する仕方ないし態度…,
とするなら,こういう自体軸,あるいは自己軸を意識することで,眼の見え方が変わってくるということなのだろう。確かに,ヨコになっていたり,くつろいでいては,パースペクティブは開かない。姿勢は,そのまま,この世界への対処の仕方,もっと言えば,
対峙の仕方,
なのだから。
参考文献;
成瀬悟策『姿勢のふしぎ』(講談社ブルーバックス) |
|
革命 |
|
藤田達生『天下統一』を読む。

サブタイトルに,「信長と秀吉が成し遂げた『革命』」とある。何が革命なのか。
著者は冒頭でこう言う。
私たちは,戦国大名領国制の深化,すなわち分権化の延長線上に天下人による統一,即ち集権化があることを,何の矛盾もなく当然のように考えてきたのではないか。近年においても,天下人信長と秀吉や光秀らの数ヵ国を預かる国主級重臣との関係を,戦国大名と支城主の関係と同質ととらえ,戦国大名領国制の延長と見る研究が発表されている。
例えば,『戦国大名』では,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/395650739.html
のように,延長と見ている。その中間にあるのは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/390004444.html?1393535997
の信長論かもしれない。
本書では,
天下統一戦とは,極端に言えば,織田信長以外の武将は誰も考えなかった「非常識」な戦争だった。
集権化とは,戦国時代末期になってはじめて信長が意識的に推進した政策だったことが重要なのだ。天下統一とは,天下人率いる武士団の精神構造も含めた価値観の転換があってなしえたもので,信長や秀吉の改革については奇跡的とさえ言えるのではないか。
という問題意識で展開されている。その意味で,真正面から,
天下統一,
というもののもたらしたものを洗い出している,と言えそうである。
集権化を支えた信長の軍事力の秘密を解く鍵は,実は戦闘者集団である武士と生産者集団である百姓との身分と居住区の截然たる分離,即ち兵農分離にある。これに関連して信長と他の戦国大名との際だった違いとして本拠地移転に着目した。
尾張統一以後,清州(愛知県清須市)→小牧山(愛知県小牧市)→岐阜(岐阜市)→安土(滋賀県近江八幡市)へと本城を移動させるたびに,信長は家臣団に引っ越しを強制させた。長年住み慣れた本領を捨てて,主君と運命を共有する軍団を目指したのである。
こういう兵農分離は,信長の直属軍に,その端緒がある。
近習と足軽隊に重きを置く戦術は,尾張時代の信長の特徴だった。千人に満たない規模の直属軍が,軍事カリスマ信長の意志にもっとも忠実に従う軍団の中核を形成した…,
とされる。その例証で,
信長の軍団の兵農分離は,直属軍からはじまった。
とする。たとえば,有名な,斎藤道三との会談の時,「三間中柄の朱やり五百本」ときされているように,主力の長槍隊は三間柄,あるいは三間半柄を揃えさせていた,というのは,
信長が長さばかりか色も含めて同じ規格の者を大量に準備し,足軽たちに装備したものである。これは,もはや従来のような自前の武装ではなくなっていたことを物語っている。
長槍は長いほど重くしなることから統一的な操作が難しく,日常的に足軽たちに軍事訓練を課さねば,大規模な槍衾を組織的に編成することはできなかった。
そしてさらにこう断言する。
長槍隊に属した足軽たちはサラリーマン的にリクルートされていたことになる。そうすると,信長の軍事的成功は莫大な銭貨蓄積に支えられていたとの見通しが立つ。
事実,信長家臣の中には,商人的家臣の存在があり,津島,熱田,清州という領内拠点都市の有力者を家臣として従え,その商業的特権を保護し,必要な物資や莫大な銭貨を獲得した。それが,
軍団の兵農分離を促進した,
と,著者は見る。
その信長の新たな秩序作りの嚆矢を,天正八年,信長から大和・摂津・河内における一国全域規模の城割(城館の破却)を命ぜられたことに見る。
大和おいては,郡山城を除いて,国中すべてが破却され,これには一国の人夫が動員され,監督のための上使も派遣され,かなり徹底的になされた。この意味は,
城主だった国人・土豪層で在村を選択したものはやがて帰農したのである。要するに,城割によって兵農の地域的分離が進展する
ことになる。さらに,信長は,
重臣と与力大名が協力して領国支配をおこなうよう指導し,城割や築城そして検地に関わる最終決定もおこなっていることが判明する。光秀は,与力大名の細川氏や一色氏に対する軍事指揮権は預けられているが,最終的なそれは,信長が握っている。
そして,戦国大名の延長線上にあるのではない信長像を,こう言う。
織田領の全知行権は信長に属し,勝家クラスの重臣だったとしても,あくまでもそれを預かっている代官に過ぎないと,その本質を理解すべきである。たとえば重臣層は,正面きって信長からの転封命令を拒めたのだろうか。
いまや,信長の一声で,
縁もゆかりもない他国へと,転封によって占領支配をおこなう時代,つまり鉢植大名の時代になったのである。
それが可能になったのは,
中世武士の所領は交換不可能であったが,検地による所領の石高表示…により,それが初めて可能になったことは革命的といってよい。
つまり,城割,検地はセットであり,それが鉢植大名化をもたらすと同時に,軍役に大きな変化をもたらす。
石高制による領主所領の把握は,彼らに対する軍事奉公即ち軍役の賦課基準の確定
をも目的としたものであり,例えば,現存する明智軍法では,百石が最低単位で,
主人が六人の家来を引き連れることを規定している。そして百石以上の所領をもつ家臣については,動員すべき侍・軍馬・旗指物持・槍持・幟持・鉄砲衆の具体的数が示されている…。
この信長の到達したのは,
家臣団に本領を安堵したり新恩を給与したりする伝統的な主従関係のありかたを否定し,大名クラスの家臣個人の実力を査定し,能力に応じて領地・領民・城郭を預ける預治思想
だった,と著者は主張する。それは,
父祖伝来の領地すなわち本領を守り抜く中世武士の価値観が,将軍を頂点とする伝統的な権威構造を再生産し,戦国動乱を長期化し泥沼化させた原因であると判断した。(中略)信長とその後継者秀吉による天下統一戦は,全国の領主から本主権を奪って収公し,あらためて有能な人物を国主大名以下の領主として任命し,領土・領民・城郭を預ける「革命」だった。
当然,この延長戦の上に,秀吉が来る。この分岐点を小牧・長久手の戦いと,著者は見る。これは,
織田体制を継承しようとする信雄と,独自の政権構想を掲げて天下人をめざす秀吉との,「天下分け目の戦い」といっていい,
と。この直後,全国規模の国替を強制し,
それまで同輩的な関係にあった諸大名を命令ひとつで転封可能な鉢植大名にして,彼らに対する絶対的な主従関係を確立した。
最終的には,
天下統一戦を通じて家康をはじめ伊達政宗・上杉景勝などの大大名まで転封させたことである。旧主で織田氏家督であり秀吉に次ぐ正二位内大臣という高位高官にあった織田信雄でさえ,転封命令に服さねば改易に処され…
るところまでの権力を掌握したのである。
信長や秀吉の新領地に対する統治を「仕置」とよび,秀吉の段階で城割・検地・刀狩などの統一策が占領マニュアルとして盛り込まれ(仕置令),一大名によって一国単位で強制された。…これらを性急に強行しようとした国々では,牢人衆―かつての大名家臣だった国人や土豪たち―をリーダーとする激烈な仕置反対一揆が頻発した。
天下人たちは,それを公儀に対する反逆と位置づけて,麾下の大名に命じて徹底的に虐殺した。
その結果,
天下統一戦を通じて,秀吉は麾下の大名領主に対して本領を収公し他所への知行替を強行して鉢植化し,民衆からは武装蜂起すなわち一揆の自由と居留の自由を刀狩令と土地緊縛策によって奪った。秀吉は天下統一によって,中世における領主と民衆の根本的な権利を剥奪したといえよう。
この先に江戸時代の幕藩体制が来るが,このとき,大名は,
将軍から「大事な御国を預」かっている
という認識に変わる。もはや,自らの武力で領国を切り取る戦国大名の面影も消えている。その時代になって初めて,武士道という作法が,逆に,必要になってくるということなのだろう。
参考文献;
藤田達生『天下統一』(中公新書) |
|
謀反 |
|
谷口研語『明智光秀』を読む。
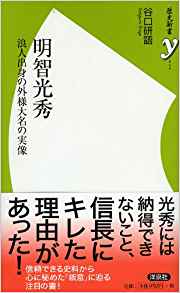
本能寺の変で一躍歴史に名を残したが,さて,では事跡はというと,ほとんどが残っていない。歴史に登場したのは,彼の生涯五十数年のうち,
後期の足かけ十四年,
である。
その十四年間で光秀は,一介の浪人から,当時の日本でベストテン入りするだろうほどの権勢者へと成り上がった。
と著者は言う。しかし,
これはまったく信長の十四年間と重なるのであり,光秀の伝記を書くはずが,信長外伝になってしまう可能性がある。
とまえがきで書いた著者は,彼についてのほとんどが本能寺の変に関わるもので,本書執筆にあたって,
一つは,「本能寺の変の原因をさぐる」という視点を意識的に避けたこと,
もう一つは,江戸時代の著作物をできるだけ排除したこと,
の二点を留意した,という。結果として,実は,信長抜きでは,ほとんどその人生のない,という伝記になっていることは否めない。
唯一歴史に残った,本能寺の変の前年に光秀の制定した,
家中軍法
も著者に言わせると,
こんなことで戦争ができるのか,
と言わしめる代物らしいが,その後書きで,
瓦礫沈淪の輩を召出され,あまつさえ莫太の御人数を預け下さる,
と書いた。その本人が,「預け下さ」つた主を,翌年弑するのだから,人生は分からない。
その光秀の「瓦礫沈淪」の前半生については,ほとんど分からない。確かなのは,
「永禄六年諸役人附」
の足軽衆の末尾にある「明智」が,光秀と推測される,という程度である。だから,土岐の流れとかと言われる光秀だが,正体は,
光秀と室町幕府との関係は,義昭以前にさかのぼるものではなかったと結論するのが妥当だろう,
ということになる。明智を名乗っているが,
どこの馬の骨か分からない,
ものが,兄義輝の暗殺で担ぎ出され,あちこち転々とする義昭の,まあどさくさに紛れて足軽衆に潜り込んだ,というのが実態ではないのか,と勘繰りたくなる。光秀は,
細川の兵部太夫が中間にてありしを引き立て,中国の名誉に信長厚恩にて召遣わさる,
と多聞院日記にある,というし,ルイス=フロイスは,
彼はもとより高貴の出ではなく,信長の治世の初期には公方様の邸の一貴人兵部大輔と称する人に奉仕していたが,その才略・深慮・狡猾さにより,信長の寵愛を受けることになり,主君とその恩恵を利することをわきまえていた,
と『日本史』に書いた。
まずは,幕臣細川藤孝の知遇を得,信長との交渉役を経て,世に出て行ったということになる。
光秀が『信長公記』に登場するのは,上洛した義昭が,撤退したはずの三好三人衆らに,宿所の本圀寺を襲撃された折,その防戦に当たった人数の中に,
明智十兵衛
として,である。その一年後の,元亀元年の浅井・朝倉勢三万が南下した志賀の陣では,二,三百を抱えるほどになっている。さらに山門焼き討ち後,近江志賀郡を与えられ,坂本に城を築城するに至る。城持ち大名になったのである。
翌年元亀二年,摂津高槻へ出陣した折には,一千人をひきており,四年後の天正三年には,すでに二千人を率いるまでになっている。そして丹波・丹後平定を経て,丹波一国を拝領した後の,天正八年以降は,一万を超える軍勢を擁するのである。
例の佐久間信盛折檻状では,
日向守は丹波国を平定して天下の面目をほどこした,
と,外様にもかかわらず,織田家中第一の働きをしていると,名指され,ひるがえって宿老の信盛の怠慢を責めるだしに使われるほどになっていくのである。
にもかかわらず,備中出陣のため,わずかな人数で上洛した信長の虚をつくかたちでも謀反を起こしたのである。著者は言う。
光秀の心の葛藤をとやかく詮索しても所詮わかろうはずがないが,積極的にせよ消極的にせよ,信長に取ってかわろうという意志はあったとしなければならない。変後の行動,すなわち近江の平定,安土城の接収,朝廷・五山への配慮,細川・筒井両氏の勧誘,そして山崎の合戦,この流れをみれば否定できないだろう。そして,軍事的な背景についていえば,光秀にとって千載一遇,またとないチャンスであったことははっきりしている。
その背景について,与力の筒井のあわただしい動きから,筒井順慶,光秀に,信長から,何らかの指示があったのではないか,と推測する。
「謀反」があまりにも突然のことであり,しかも何の準備もなかったらしいから,光秀をして決断させた(信長から指示された)何事かがあったはずである。
と推測する。それを,著者は,光秀を中心に,細川藤孝,筒井順慶を与力とする体制の解体にある,とみている。
前にも書いたが,フロイスの言う通り,光秀評を,
裏切りや密会を好み,刑を科するに残酷で,独裁的でもあったが,己を偽装するのに抜け目がなく,戦争においては謀略を得意とし,忍耐力に富み,計略と策略の達人であった。また築城のことに造詣が深く,優れた建築手腕の持ち主で,選び抜かれた戦いに熟練の士を使いこなしていた,
という,
一筋縄ではいかない,したたかで有能な戦国武将,
というイメージで見るとき,光秀も,
そういうことなら,おのれが,
と,信長にとって代わりたい,と思うに至ることはありうる,とは思う。しかし,そこまで追い詰めたのが,信長の何がしかの指示だとすると,結局,光秀は,
信長に振り回された,
というか,信長の光に照らし出された一人だということができる。しかし,変後の処理を見ると,どうもちょっと,器が小さかったのではないか,という気がしないでもない。変後の秀吉の周到な手際に比べると,光秀は,
おのれを見誤った,
ような気がしてならない。
参考文献;
谷口研語『明智光秀』(洋泉社歴史y新書) |
|
手抜き |
|
釘原直樹『人はなぜ集団になると怠けるのか』を読む。

副題に,「社会的手抜き」の心理学とある。要は,手抜き,著者はこう定義する。
個人が単独で作業を行った場合にくらべて,集団で作業を行う場合のほうが一人当たりの努力の量(動機づけ)が低下する現象を社会的手抜きという。
この例に,フランスのリンゲルマンの行った実験結果を上げ,一人の力を100%とした場合,集団作業時の一人あたりの力の量は,
2人の場合93%,3人85%,4人77%,5人70%,6人63%,7人56%,8人49%,
となったという。それは,
集団の中では責任感が希薄になる,
のが一因と,著者は推測し,そういう例を,見て見ぬふりから,カンニング,ブレインストーミング,スポーツの八百長,集団浅慮まで,幅広く例を挙げつつ紹介していく。
その原因として,
外的条件(環境要因)としては,
評価可能性 個々人の集団への貢献度がきちんと評価できるかどうか
努力の不要性 自分の努力が集団全体にほとんど影響せず,しかも他の人と同等の報酬が得られる場合
手抜きの同調 他の人が努力していなければ,自分だけ努力するきになれない。強い仲間意識や暗黙の集団規範
内的条件(心理的・生理的要因)としては,
緊張感の低下
注意の拡散
を挙げた。結果として内的条件は,外的条件の結果として発生するので,
どのような条件,とくに外的条件がどのように連結して社会的手抜きにつながるか,
の切り口から,
①期待
個人の努力が個人のパフォーマンス向上につながるという予期。勉強しても成績が上がることが予期できなければ,期待は低くなり,自己効力感(自分の努力と成果が結びつく可能性が高いと認識している感覚)も低い。
②道具性
パフォーマンスが何らかの報酬や罰に結びつくと思っている度合(信念)。業績が挙がれば給与が増えたり,賞賛されたり,名誉を得ることができる程度が強ければ,「道具性」が高いことになる。
③報酬(価値)
その人の主観的価値として,仕事や報酬に意味がある
の3要素が個人の動機づけとして高い,とまとめた。
では,どんな人が手抜きするのか。
評価可能性が低く,自分のパフォーマンス(業績)が必ずしも自分の報酬とはならない場合や,自分が努力しても集団のパフォーマンスの向上にはほとんど役に立たない(道具性が低い)場合には社会的手抜きが生じやすい。そのために評価可能性や道具性の認識に敏感なパーソナリティ(気質,正確,能力を含めたもの)の持ち主は社会的手抜きをしやすいと考えられる。
そこで,パーソナリティを,
外交性
情緒安定性
勤勉性
協調性
開放性
の5因子の組み合わせでパーソナリティを測ると,
強調性と勤勉性は手抜きと,負の関係,という実験があるようである。そのほかに,
達成動機(個人的な目標や基準を達成しようと努力する傾向)の高い場合,(中略)どのような時にも手抜きしなかった,
という。それはわかる気がするが,しかし,その動機と,や(らされ)ることのギャップが大きい場合はどうなのかと,ちょっと疑問が残る。
結論として,パーソナリティと社会的関係を見た場合,その人の認知として,
評価可能性(自分の努力が公けに認められる),
努力の不要性(自分の努力が集団全体に役に立つ)
道具性(自分の努力や報酬や罰と直接結びつく),
報酬価値(仕事事態や報酬に価値がある),
すべてに正の反応なのは,
勤勉性
と
達成動機
であるようだ。突っ込んだ言い方をすると,外的な条件がどうであろうと,自分の,
価値基準が明確である,
と手抜きがしにくい,ということになる。すべてのパーソナリティに効くのは,
評価可能性,
のようである。手抜きを左右する,重要な要因,ということになる。
気になるのは,
腐ったリンゴ効果
である。
自分の利益を優先して集団の利益をないがしろにするような利己的振る舞いをする者が集団の中にいた場合,
その利己的な人一人を認識していないと非協力は50%
その利己的な人一人を認識していると非協力は80%
と,たった一人の林檎でも,集団全体を腐らせる,と。
さて,では社会的手抜きにどう対応するのか,ありきたりだが,
目標の明確化,
正確なフィードバック
個人の役割の明確化
ということが挙げられていた。結局,
個々人のその仕事への意味づけ,
をはっきりさせる,という意味では,やる気をどう高めるか,ということと軌を一にする話に落ち着く。
しかし読み終わって,手抜きを,
本来やれる(はずの)こと,やるべきことをサボること,
と言い換えると,難しいのは,それが,そのひとの「本来できるレベル」と,どう決めるのか,その日その日で,その「本来」というのは変わるのに,ロボットのような機械的な対応を求めていいのだろうか,という疑問だ。
ある組織で,組織改革があった時,その当人が,これは,
スーパーマンを求めている,
とぽつりと言った。孔子ではないが,
人に備わらんことをもとむるなられ,
である。僕は社会心理学者が書いた本を読んだとき,いつも現実とは違う実験結果で現実を推し量ろうとしている,という気がしてならない。今回も,ずっと違和感をぬぐえなかった。
人は,一人一人違う,どの立場から,それを見るかによっても変わる。そもそも手抜きか手抜きでないかは,なんではかるのだろう。
その一瞬,手抜きしているように見えて,その手抜きが,次のパフォーマンスに寄与する,ということは,ありうる。だから,どの視点から見ているかで変わる,と思うのだ。
それと,集団になっている時と,ひとりでやっている時と,出す力が違うのは当たり前ではないかという思いがある。その余力が,次へのステップというか,バネになる。そこで次の手を考える。余力なく,全力でやっていて,組織が回転するとは思えない。同じ作業を永遠に繰り返していては,集団というか,組織自体が生き残れないのだから。
その意味でタイトル『人はなぜ集団になると怠けるのか』は,逆に,人は集団の中にいると怠けるもの,という著者側の先入観でものを見ているのではないか,そしてそれにふさわしい結果が出るように実験している,としか見えないところがある感じが拭えない。勘ぐりかもしれない。しかし著者の想定している程度の仕事観,労働観では,今日の組織は生き残れない気がしてならない。
参考文献;
釘原直樹『人はなぜ集団になると怠けるのか』(中公新書) |
|
快戦 |
|
中村彰彦『ある幕臣の戊辰戦争』を読む。

幕末,「四八郎」という言葉があったそうだ。
攘夷論者の清川八郎(庄内藩郷士),
北辰一刀流の達人,井上八郎(幕臣),
彰義隊副頭取の天野八郎(幕臣),
心形刀流の伊庭八郎(幕臣),
の四人である。本書の主人公,伊庭八郎は,旧幕府遊撃隊を脱走し,函館で死ぬ。
伊庭家歴代当主は,ただの幕臣ではなく,下谷御徒町にある心形刀流道場主で,神田お玉ヶ池の北辰一刀流玄武館,九段坂上三番町の神道無念流の練兵館,南八丁堀浅蜊河岸の鏡新明智流の士学館,と並ぶ,江戸の四大道場の一つであった。
伊庭八郎は,心形刀流の創始者伊庭是水軒から数えて,八代目,軍兵衛の嫡男であった。軍兵衛が急死した後は,一番弟子を宗家とし,養父のもと八郎は,道場経営に当たり,22歳で幕府に召出されるまでつづく。
道場は,当時門人数一千名以上。門人帳を綴じるのに,八寸の錐をあつらえたと言われるほどの盛況であった。
伊庭八郎は,身長五尺二寸,158㎝と小柄,しかし,
眉目秀麗,俳優の如き好男子,
伊庭の麒麟児,
伊庭の小天狗,
等々と称された。得意技は,諸手突き,同時代,突きを得意とした,鬼鉄こと,
山岡鉄舟,
と立ち会い,鉄舟を道場の羽目板まで追い詰めた,といわれる。この時分のエピソードに,牛込の天然理心流の試衛館の隠居(道場主が養子の近藤勇)周斎に,土方歳三とともに,小遣いをねだった,というのがある。八郎,歳三の両者が,ともに,五稜郭で戦死するのも,因縁である。
幕府に召出された八郎は,すぐに講武所剣術教授方に出役を仰せつかり,奥詰衆,つまり将軍親衛隊となり,将軍家茂上洛の際には,道中警護に当たる。第二次幕長戦の最中,家茂が死去し,多くの幕臣は,遺体を守り,東帰したが,八郎は大阪に残る。
幕府は,奥詰衆を遊撃隊へと編成替えし,銃隊編成とされ,小姓組,書院番組,新御番組を加えた,総勢590人に及ぶ部隊となった。
鳥羽伏見の戦いでは,上京を仰せ付けられた130人とともに,鳥羽街道の四ツ塚で,薩軍の銃砲にさらされる。幕府に勝る火器に圧倒される。
遊撃隊は「剣槍二術」と「銃術」を「兼習」する部隊だったはずだが,初めて実戦を経験するうちに剣客としての原点に立ちもどり,「剣槍二術」で戦うことを選択
する。それは遊撃隊だけでなく,会津藩も,新選組も,
抜刀斬りこみ,
を選ぶ。成果はともかく,伊庭八郎は,
薩将野津七左衛門(後の野津鎮雄陸軍中将)をして幕軍流石に伊庭八郎在りと嘆称せしめたと伝えられた
が,抜刀斬りこみ中,砲弾を胸に受け,卒倒する。ただ当時の砲弾は貫通力が弱く,鎧の胸甲にはじき返されたものの,その衝撃で血を吐き,昏倒するにとどまった。
海路江戸へ向かう途中脱走した遊撃隊三十人とともにあった伊庭八郎は,上総で,請西藩一万石の藩主林忠崇を巻き込み,徳川家再興を期して,上総義軍を立ち上げ,榎本武揚の軍艦「大江丸」の助力を得て,真鶴に上陸する。
この間,帰趨を見守る各藩,陣屋からの金穀,武器の教室を受けつつ,脱走遊撃隊は,270人に膨れ上がり,ミニエー銃470挺,大砲二門を備えた,洋式銃隊に変貌を遂げていく。
しかし期待した上野彰義隊も一日で,潰れ,新政府軍は,長州,鳥取,津,岡山四藩兵一千を派遣,箱根で激突することになる。
ここで,伊庭八郎は片腕を失う。
包囲された中で,腰に被弾,三人を斬ったものの,左腕手首近くを斬られ,結局左腕を失うことになる。負傷後,骨が突き出た状態になったため,肘下から,切り直しの必要が出たが,八郎は,
人,吾が骨を削る。昏睡して知らざるべきか,
といって麻酔を拒んで,手術を受けたが,
神色不変,
だったという。隻腕となった伊庭は,しばらく,江戸(東京に改称)でかくまわれ,左の片肘に銃を架して球を撃つ練習をしつつ,元年11月に,五稜郭の榎本軍に合流する。
今一度快戦をしたい,という思い,
言い換えると,死に場所を求めて,伊庭八郎は,函館に向かった。
土方歳三は,三分の一の兵力と,能力の劣るミニエー銃で敵を後退させ,
疾風の花を散らすに似たり,
と称された,戦死を遂げる。
著者は言う,
かつて近藤勇の養父周斎老人に小遣いをねだった伊庭八郎,土方歳三のふたりが,ともに快戦の夢を果たしてから死んでいった,
と。伊庭八郎26歳。土方歳三34歳。
戊辰戦争に当たって,というか,そこをおのれの切所としなければ,別にこだわりなく時代を乗り越えていくことができる。しかし,その状況を潔しとしなければ,それと戦うことになる。その切所は,一回とは限らない。最期は,たぶん,切所で戦うこと自体が,目的化していたかもしれない。しかし,そこで死したもの,生き残ったもの,いずれもその人の人生を使ったのであって,他人の人生ではない。
僕は,こういう人の生き方を見ると,これは武士だから,剣客だから,というのではなく,その人の生き方なのだとつくづく思う。
甘いと言われるかもしれないが,いったんその状況を引き受けた以上,それに(伊庭八郎,土方歳三のように)殉ずるのも,そこから(榎本武揚のように)離脱するのも,それなりに自分の選択だ。
会津戦争で生き残った,佐川官兵衛,山川大蔵は,西南戦争で官軍に参加し,佐川は戦死,山川は生き残った。
参考文献;
中村彰彦『ある幕臣の戊辰戦争』(中公新書) |
|
攻城 |
|
伊東潤『城を攻める 城を守る』を読む。

城には人格がある。信玄のいう,
人は石垣,人は城,
の意味ではない。建造物としての城自体に,縄張りした人物の人品骨柄,器量が出る。それが,攻城戦において,もろに出る。本書の面白さは,そこにある。
ただ連載物の単行本化のため,著者が断るように,
上田城,
がなかったのは,個人的には少しがっかりしたが,白河城から,熊本城まで,時代は異なっても,城ごとの人格は,攻め手側の人格との勝負でもある。
籠城は,後詰の援軍がなければ,ほとんど勝ち目はない。松平容保の会津城,豊臣秀頼の大阪城,荒木村重の有岡城,浅井長政の小谷城,島原一揆の原城等々,そうならざるを得ない仕儀にて,孤城の籠城になる。追い詰められてか,やむを得ずかはともかく,その瞬間,勝負は決している。その前に,切所はあった。そこに,将の器量の差が出る。
武田勝頼のように,長篠城を攻囲しつつ,織田・徳川連合軍を誘い出した。これは,信玄が二俣城を落とさず,家康を三方ヶ原におびき出したのと同様の,武田流の戦法だと著者は見る。
長篠城を囮にして信長と家康をおびき出し,「無二の一戦」に及ぼうとしたのではないか。むろん連合軍が後詰に来ないと分かれば,長篠城を落とせばいい。
と。しかし,結果は,設楽ヶ原で惨敗する。勝頼は,数年後,高天神城が徳川軍に包囲されたとき,後詰をせず,
これにより,勝頼の威信は地に落ちた,
という。攻めるだけではなく,味方の城が包囲されたとき,どういう姿勢を取るかは,味方は見ている。
秀吉の備中高松城包囲の際の,毛利の後詰,勝家の織田軍に包囲された越中魚津城への景勝の後詰等々。
直接的には,勝頼は,味方の後詰を怠ったことにより,離反が相次ぎ,自滅していった。
攻める側,守る側,ともにわずかな判断ミスが,致命的になる。
大阪城は,第四期の工事が,秀吉死後も続き,最終的には,八キロメートルにも及ぶ惣構堀に囲まれた,総面積四百万平方メートル,
という巨大な城で,難攻不落といっていい。二十万で包囲した家康軍も攻めあぐね,講和に持ち込むと,惣構掘,二之丸堀を埋め尽くし,本丸を囲む内堀だけの裸城にして,ようやく落とした。
攻め手と守り手の側の器量の差が,これほどはっきり出た攻城戦はない。いかな秀吉の器量をもってした築城した城といえども,守将の器量以上の働きはしない。
逆に,廃城となっていた原城にこもった島原一揆勢三万七千は,攻囲する幕府軍十二万四千を翻弄し,功を焦る,指揮官板倉重昌の強引な総攻撃を撃退し,板倉を始め四千四百もの死傷者を出し,一揆方はわずか十七名の死傷者にとどまるという,幕府側は完敗を喫した。
もちろん,その瞬間だけではなく,それまでの経緯抜きでは評価できないが,追い詰められて余裕のないはずの一揆勢に比し,後任の上使派遣を知らされて,功を焦らざるを得ない状況にあった板倉と,どこかにたかが百姓一揆と侮る気持ちがあった,その油断と隙は,攻撃側の乱れとなり,一揆側に衝かれた。それは,そのまま家格の低い板倉を上使として派遣した,家光の油断と隙,といっていい。実際,柳生宗矩が,その人事の危うさをたしなめたが,時すでに遅し,だったと言われている。
ほんのわずかな油断が,ぎりぎり対峙している両者の中に,隙間をつくる。
肥後半国十九万石を秀吉から拝領した加藤清正は,熊本城を築く。
城の周囲五・三キロメートル,本丸は総石垣,本丸に至る道は複雑に屈曲し,幾度となく櫓門をくぐらせ…築城当時,櫓四十九,櫓門十八,その他の城門二十九を数え,井戸に至っては,百二十余に達したという。
しかし築城されたのは,二百七十年前,銃砲主体の近代戦用の城ではない。しかも守り手は三千三百の鎮台兵,つまり農民兵である。攻め手は一万三千の,強兵薩摩軍。しかし,一か月の攻城も,抜けなかった。
大義ないまま,「暗殺の真偽を質す」という名目でたった薩軍は,十分の準備もないまま,
ただ剽悍な薩摩隼人を恃み,「軍を進め一挙に敵城を粉砕戦」という…,
無為無策での攻撃は,ただ無謀に千三百もの戦死者の屍を累々と積み上げただけだ。
攻め手の西郷隆盛の覚悟と守将谷干城の覚悟の差といっていい。私学校の暴発により,やむを得ず立たざるをえなかったにしても,その状況を主体的に変える立場に,西郷はいた。それを桐野にゆだね,状況に流されていった西郷に比し,谷は,持てる力をフルに使って,不利な状況を主体的に乗り切った。
将の差とは,状況の有利不利ではなく,もちろん守る堅城の可否でもなく,兵の強弱でもない。それを戦力にするかしないか,無駄な死にするかしないかは,かかって将の器量による,それは状況をどう主体的に乗り切るかどうかという,まさに将の才覚の問われる機会はない,そしてこれほど優劣のはっきりした戦力を,逆転した攻城戦はない。
それは,原城攻撃の板倉重昌にも言える。
参考文献;
伊東潤『城を攻める 城を守る』(講談社現代新書) |
|
間合い |
|
前田英樹『剣の法』を読む。
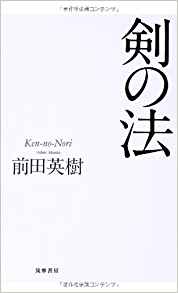
この本は,何のために書かれたのかが,読んでいて分からない。著者は,
この本は,新陰流の刀法を実技面からかなり詳しく書いたものである。けれども,技の解説書といったものではなく,この刀法が成り立つ根本原理を,誰が読んでもわかるように書いたつもりである。このような原理をつかんでいれば,流祖以来四百数十年にわたって続くこの刀法の中心は崩れないと思う。
と言われる。ならば,
ただ新陰流の原理を伝えるために書いたのか,
それとも,
その精神のもつ普遍性を描きたかったのか,
それとも,
刀身一如という刀と身体の捌きを伝えたかったのか,
いずれとも,読んで判然とせず,ときに苛立った。
いま新陰流を学んでいるものにとっては,あるいは学びたいと思っているものには,さらには武道を心得ている方々には,役に立つかも知れない。しかし,いまどき刀そのものをもっている人間も少ない。まして,刀で立ち会うなどということは,試合ですらない。刀なしでは役に立たない兵法について,詳細に語られる意図が,僕には遂にわからなかった。刀あっての兵法だろうと思うし,それなしならば,単なる作法と同じになるから。
僕はもともと,
士
と,
剣術家(兵法家)
とは別のものだと思っている。兵法家(剣術家)が士とは限らないのである。僕にとっては,士道とは,ここにある,胸を叩く,
横井小楠
をこそ士と思っているので(剣を嗜む,あるいは剣を究めることがないとは言わないが,あくまで嗜みの一つ。事実小楠は皆伝の腕ではある),
剣客,
剣士,
兵法家,
剣術家,
は,士とは思っていない。せいぜい,
剣術に特化した士,
でしかない。この著者を僕はよく知らないので,そのどちらなのかは知らない。しかし,いま,この兵法が,役に立つ,とは,読んだかぎりでは(剣も知らぬ愚鈍な自分には)少しも感じられなかった。最後を読んで,兵法に耽溺しているご自身の自己弁護のために,縷々書き連ねたのだと,あやうく思い違いしそうになった。
もしあえて言うなら,本書から学んだことは,
間合い,
だと思う。人との間合いだ。著者が,身勢,拍子,間積り,太刀筋,と言っている,
間積り
と間合いが同じものなのかどうかは知らないが。
その面から見ると,結構面白さが見えてくる。僕が読み取ったかぎりでは,相手の構え,目付,拍子,間積りを,いかに崩すか,いかに破るか,に真髄がある,と見た。たとえば,上泉伊勢守が,愛洲移香斎の陰流によって開眼したいきさつについて,著者はこう書いている。
まず,型の始めに取る脇構え(中略)…から敵は,脇構えのままの姿勢で太刀を頭の右横に持ち上げ,前の左足を踏み込んで,こちらの左肩を斜めに切りこんできます。こちらはどうするか。敵と全く同じように,太刀を頭の右横に持ち上げ…,これまた敵とまったく同じ動きで,左足をわずかに踏み込み,斜め切りに相手の左掌を切り落とす…。二人の動きは,相似形を描き,ただわずかな時間のずれで勝敗がわかれるのです。
この動きから,伊勢守が開眼したのは,
まっすぐな体の軸がわずかに前へ移動する,その移動のふわりとした力によって,敵を切り崩す原理です。敵の切り筋を,自分の切り筋で塞ぎながら勝つ,
と。しかし,
相手のほうが先に切るのに,なぜ,あとから出す,こちらの切りが,勝ってしまうのでしょう。…相手は,こちらの左肩を切ろうとしています。こちらは,その相手の,すでに打ち出されている左掌を切ればいいわけですから,それだけ相手よりも動く距離が少なくなる。この間合いの差によって,こちらの切りが先になるのです。
しかし,ここでの勝敗の在り方は,ただ動く距離の大小だけで説明のつく事がらではありません。相手が動く,その動きに対して,こちらの移動が作るわずかな〈拍子のずれ〉が,崩しを生むのです。
と。ここに新陰流の流祖の見た真髄がある,と著者は言っている。
この勝ち口には,限りない自由と有無をいわせない必然とが,完全に,同時にあります。
それをこう説明します。
ここでの自由は,ただ任意に動き回る自由とは違う。「車」の構え(脇構え)から,わずかに踏み込む時,こちらが踏み込む線は,相手が踏み込んでくる線と,まったく同じ線上にるのでなくてはなりません。つまり,双方の四つの脚が,一線上にある。この踏み込みによる軸の移動が,ふわりと相手の軸の移動に乗るわけです。この時に,連動して一挙に為される軸の移動,間合いの読み,拍子の置き方,太刀の切り筋には,原理として言うなら,毛一筋程の狂いがあってもいけません。この一挙によってだけ,勝敗は天地の理のように,必然のものになるのです。
この必然は,彼我の関係性のなかに,
ただ自分だけの考えで,強引に創るのではない。敵と自分との〈間〉にある関係,即ち間合い,拍子,太刀筋の関係から,おのずと創り出されてくる…,
と。そして,ここに,陰流の「陰」の意味も隠されている,著者は言う。
陰流の剣法において,陽は対手です。陰は自分です。この関係の置き方に,陰流の極意がある。……「猿廻」(えんかい。上述の立ち合いを指す)…の型では,打立ち(敵)と使太刀(自分)は,ほとんど同じ動きをします。勝敗が生まれるのは,,二つの動きの間にわずかなずれを作ることによってです。陽の打立ちは先に動き,陰の使太刀はそれに応じて遅れて動く。陰は,始めから陽のなかに潜んでおり,陽の動きに従って外に現れる。現れてひとつの太刀筋になる。
突っ込んだ言い方をするならば,そもそも相手が,そう繰り出すように仕組んでいる,と言ってもいい。著者は,
始めに動くのは相手です。が,それは対手の動きを待っているのではない。相手を「陽」として動かし,動く相手のなかに「陰」として入り込むためです。入り込めば,打太刀の「陽」は,おのずから使太刀の「陰」を自分の影のように引き出し,その「影」によって覆われ,崩されることになります。
ありていに言えば,脇構えが,左肩を打つように,誘っている,と言ってもいいのである。この,
敵に随って己を顕わし,敵がまさに切ろうとするところを切り崩す勝ち方,
を
随敵
というそうである。上泉伊勢守が求めているのは,
ただ勝つことではありません。勝つことをはるかに超えて,彼我のすぐれた関係を厳密に創造すること,
あるいは,
相手の動きに協力するかのように入り込み,そのまま相手が崩れてしまう位置に身を占め,重く,しかもふわりと居座ってしまう感覚が必要です。
と著者が言うとき,その閉ざされた関係には,誰ひとり入り込む余地はない。例えは,悪いかもしれないが,ダンスに似ている。両者が同じ土俵の上で,緊張した糸を手繰りあいつつ,ひとつの完結した世界を作っている。それは,余人の入り込むことのできぬ,閉鎖空間なのである。
例えば,三代将軍家光の御前で,江戸柳生の柳生宗冬(宗矩の子息)と尾張柳生の連也が立ち会った光景をこう描く。
宗冬は,三尺三寸の枇杷太刀を中断に取っている。その宗冬から四,五間隔てたところに立った連也は,右偏身で小太刀を下段に堤げ,その切っ先は左斜め下に向けている。つまり,右移動軸の線に切っ先を置いた(あるいは,切っ先を左斜め下向させたままの真正面向きか)。その位取りのまま,連也はスルスルと滞りなく間を詰め,たちまち大山が圧するように宗冬の眼前に迫った。この時,宗冬は,真っ直ぐの中断から左手を放し「思わず知らず」右片手打ちに,連也の左首筋から右肋骨にかけて切り下げてきた。連也は,右偏身から正面向きに変化しつつ小太刀をまっすぐ頭上に取り上げ,己の人中路(中心軸)を帯の位置まで切り通すひと振りによって,宗冬の右親指を打ち砕いた。
右偏身(みぎひとえみ。右半身)とは,
右足を前に,左足を後ろにして立ち,左腰だけを四十五度開いて立ちます。この時,右足は真っ直ぐ前を向き,左足は左に四十五度開いて
いる状態で,スルスルと間を詰めて,左肩を(打つように)誘っている,と言えなくもない。
こちらからスルスルと間を詰めていき,その結果,相手は先に打ち出さざるを得なくなる,
新陰流の「目付」では,相手の切りを,自分の左側か右側かの二つに分けて観るのですが,さらに進んで言えば,相手の切りが自分の左側へ来るように誘い込むことが大切…,
このように迎えた時,振られる相手の拳が自分の型の高さにくる瞬間が必ずある。切っ先より一瞬前に拳が降りてくる。。その瞬間を捉えて,こぶしを打つ…,
という。そのように切り下げた,と見ることができる。
この一瞬の見切りは,体が覚えている,その差はほんのわずかなのだろうと,推測するしかない。たしかに,剣術家は専門職には違いないが,
できないことは,決してわからず,わかる,ということは,稽古のなかで積み重なる〈新しい経験〉としてしかできません。
自分の体でできないことは,わからない,というのが芸事一般の決まりです…。
と言われると,そのただなかにあるものにしか見えない,体感覚があるのだろうと,羨望深く,ただため息をつくほかはない。
参考文献;
前田英樹『剣の法』(筑摩書房) |
|
境目 |
|
盛本昌広『境界争いと戦国諜報戦』を読む。
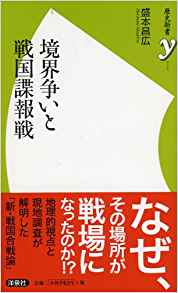
「戦国諜報戦」は,いささかオーバーというか,境界線での陣取り合戦には情報のやり取りも含まれるので,ここから想定される忍者と早合点すると,少し当てが外れる。
本書は,
信長や秀吉が現れる戦国時代の最終段階に,島津・長宗我部・伊達などの大名が複数の領国を支配するようになる前は,国衆が分立している国の方が多数であり,大きな戦国大名がいる国の方が少数だった,
その時代の,一国全体を統一する側ではなく,言ってみれば,地元での地場の人たちの戦いに,焦点を当てている。
(そうした)多数派を無視して,少数派を戦国時代の代表として記述する従来の戦国像,
への新たな像の提示を目指している。
その焦点を,
境目
におく。こう述べている。
戦国時代の合戦のほとんどは,隣り合う戦国大名間で起きたものである。力がある戦国大名は隣接する大名を攻撃して,所領の拡大を目指していた。一方,攻撃される大名は,侵入を阻止するために,境界を防衛する。そのために必然的に,戦国大名の支配領域の境界付近で合戦が起きる…,
こうした境界をめぐる争いを,研究者は,近年,「境目相論」と呼んでいる。本書は,まさに,それを描こうとしている。
戦国大名は,一般に,武田氏は甲斐,上杉氏は越後のように,一国または複数の国を支配しているものと,一郡または複数の郡を支配領域とする小さな戦国大名があるが,後者を国衆と呼ぶ。その境目が,国境になる。
その視点で見ると,有名な合戦も,
川中島の戦いは,北信濃支配をめぐって,南下する上杉と北上する武田の間の境目での合戦であり,
桶狭間の戦いは,鳴海・大高という,今川・織田の境目をめぐる攻防であり,
長篠の戦いは,武田勝頼の三河・信濃の境目への出撃に呼応した戦いであり,
山崎の戦いは,摂津の高山右近,茨木の中川清秀,伊丹の池田恒興による山城との境目の攻防であり,
賤ヶ岳の戦いは,近江と越前の境目,柳ヶ瀬での対決であり,
関ヶ原の戦いは,畿内と東国の境,不破の関という境目での攻防であり,
と,ある種の境界線で戦われたというふうに見ることができる。
この境目,多くは,地形・水系に由来する。
例えば,山。
一般的な境目になるのが山。山城と近江の国境は逢坂山。古来「逢坂の関」が設けられていた。峠は,多く,分水嶺を分ける。三国峠は,関東側が利根川水系,越後川が信濃水系。その水系が多く,一つの郡を形成する。
例えば川。
川はしばしば境目となる。大井川は駿河と遠江を分け,木曽川は尾張と美濃を分ける。
そうした境目の攻防で,橋頭堡として,城が築かれる。それを,
新地,
もしくは,
地利,
と呼ぶ。新しく得た領地と言った意味だが,そこに城が築かれる。付城とも呼ばれる。したがって,新地は,城のことをも指すようになる。
境目に作られた城は,境目の防衛を担うと同時に,敵方の城への攻撃拠点となる…,
その意味で,敵の城を攻撃するために,周囲に付城を築くが,攻撃拠点であると同時に,橋頭堡の意味も持つことになる。
この攻防の先兵になるのが,その国を追われた牢人衆ということになる。そこには,国を奪われた国衆も含まれる。
牢人については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/396273414.html
で触れた。本貫地を奪われたという意味では,本貫地を取り戻す戦いにもなる。
また,境目の地域は,危険が高いため,村内に散らばって住めず,城の近くに,すぐに城に逃げ込めるように住む,当然他国へ逃散するのを防ぐ意図もある。これを,
寄居,
という。。
また,この境目は,両者の情報戦の主人公は,
草,
と呼ばれる。時代劇で出る,「草」とは,少しニュアンスが違う。『政宗記』にこういうことが書かれている。
奥州の軍(いくさ)言葉に草調儀などがある。草調儀とは,自分の領地から他領に忍びに軍勢を派遣することをいう。その軍勢の多少により,一の草,二の草,三の草がある。一の草である歩兵を,敵城の近所に夜のうちに忍ばせることを「草を入れる」という。それから良い場所を見つけて,隠れていることを「草に臥す」という。夜が明けたら,往来に出る者を一の草で討ち取ることを「草を起こす」という。敵地の者が草の侵入を知り,一の草を討とうとして,逃げるところを追いかけたならば,二,三の草が立ち上がって戦う。また,自分の領地に草が入ったことを知ったならば,人数を遣わして,二,三の草がいるところを遮り,残った人数で一の草を捜して討ち取る。
当然駆け引きが行われる。その主人公は,身分的には,
足軽,
として,足軽衆に組み入れられているが,その実態は,
乱波
あるいは
透波(素波),
と呼ばれる。折口信夫は,こう書いている。
透波・乱波は諸国を遍歴した盗人で,一部は戦国大名や豪族の傭兵となり,腕貸しを行った。透波・乱波は団体的なもので,親分・子分の関係がある。一方,それから落伍して,単独となった者を,すりと呼んだ。山伏も法力によって,戦国大名などに仕えることもあった。山伏の中には逃亡者・落伍者・亡命者などが交じり,武力を持つ者もいて,この点でも,透波・乱波と近い存在である。
草の異称として,
かまり,
しのび,
あるいは
伏,
があるが,
一人前の武士がすることではない活動の象徴として,大久保彦左衛門の『三河物語』には挙げられており,まさに,境目的な,人たちだったということができる。
信長,秀吉,家康という人物を視点に戦国を描くのが鳥瞰的とするなら,ここで描いた地場での戦いは,虫瞰的といえるもので,確かに華々しさはないが,もう一つの戦国史といっていい。
盛本昌広『境界争いと戦国諜報戦』(洋泉社歴史新書y) |
|
牢人 |
|
渡邊大門『牢人たちの戦国時代』を読む。

いわゆる牢人が歴史上現れるのは,源平争乱期からである。牢人には,
①郷土をはなれて,諸国を流浪する人
②主家を去り,封禄を失った人。
があり,前者は,律令国家で本貫地での税負担に窮乏化し,本貫地から逃げて浮浪人になっものを指す。国家の根柢を揺るがす問題であった。後者は,近世仕官していない武士を差した。江戸時代,浪人が定着する。
元来は,牢人と浪人は使い分けられており,『吾妻鑑』などでは,
浪人は,土地を離れた農民たちを,牢人は主のない本来武士身分にあったものを意味する,
ようである。
南北朝・室町期になると,守護がほろびると,牢人が生み出され,大きな問題となる。例えば,嘉吉の乱で滅ぼされた播磨・備前・美作の守護赤松氏の旧領に,山名氏が入部してくると,赤松氏被官の所領は闕所とされ,赤松支配下のものたちは,居場所を失い,牢人となっていく。かれらは,他国浪々を余儀なくされる。
こうした牢人たちが大量に出現するのが,戦国争乱期である。無数の主家を失った牢人を,例を挙げて紹介しているが,この時期有名なのは,尼子氏再興を懸けた,山中鹿之介である。
こうした主家再興は,そのまま,失った自分の所領や権益を取り戻す戦いでもある。その意味で,牢人は,あらたに入部したり,領有した支配者及びその被官人にとっては,自分たちの所領を脅かす,危険な爆弾といってもいい。
そのために,牢人規制が,その都度の支配者から発令される。古くは,室町幕府の,
浪人に家を貸してはいけない,
というものから,足利幕府の実権を握った三好長慶による,
浪人衆を許容するものは,聞きつけ次第成敗する,
というものまで,そして秀吉政権による,牢人停止令にとどめを刺す。
①主人を持たず,田畑を耕さないような士は村から追放せよ,
②もともと職人・承認の経験がある士なら,田畑を耕さなくても追放としない,
③主人のある奉公人は別にして,百姓は武具類の諸事を調査し,これを没収する,
百姓と武士の身分の厳格な区分を意図し,著者はこう書く,
主人持ちの奉公人身分でもなく,百姓,商人,職人にも属さない牢人は,村から追放されるか,武具を取り上げられる(実質的に武士身分を失う)かの,苦境に立たされた,
のであり,主取りの侍か,帰農するかの二者択一ということになる。
ここで言う奉公人とは,戦いの主力を担ったものであり,
①名字を持ち武士に寄子・被官として奉公する士・足軽
②名字をもたない中間・小者
を指す。主家を失った瞬間,身分を喪失し,社会の邪魔者となる。しかし,彼らが活躍の場を見つけるのは,
関ヶ原の合戦であり,大阪の陣であり,最期に島原の乱である(一説には,文禄・慶長の役も,あふれかえった牢人対策の側面があるとされる)。
この三回に,名が出てくるのが,宮本武蔵である。関ヶ原では,西軍についたという説があったが,近年,黒田家に属す新免家に組していたとされている。大阪の陣では,福山藩・水野家の客将として出陣している。そして,島原では,55歳で,中津城主・小笠原長次の後見として出陣し,一揆側の投石で負傷している。いずれも,仕官せず,最期は,細川家の客分のまま,五輪書を書き上げる。
しかし,大阪の陣後,
①落人を隠し置く者は,厳罰に処す,
②得体の知れない旅人の宿泊の禁止,
と,落人探索は,厳しく,多くの牢人は,失った所領の回復を果たすどころか,仕官の道も,当初は,
古参のもの,つまり,秀吉の代から仕えていたもののみ,
召し抱えてよいとされ,新参のもの,つまり大阪の陣で豊臣方についたものは,召し抱えてはならないという禁止がなされ,それが解かれるのは,十年後であった。
今も昔も,牢人は,あらたな仕官先を見つけるのは至難の業であったらしい。平和の時代に入ると,その困難は一層厳しいものになる。
これは,本書の対象ではないが,島原後,十数年,家光死後の,慶安の変,いわゆる由比正雪の乱も,大阪の陣以降の,改易,減封の中であふれた牢人問題が,背景にあった。
関ヶ原合戦後,牢人となった真田昌幸,信繁(いわゆる幸村)の父子は,配流先の九度山での生活は困窮をきわめ,信之への金の無心の手紙が多く残っている。いま和歌山の名産になっている「真田紐」は,生活を支えるために作製された。後世の講談のように,
来るべき日に備えて,虎視眈々と打倒徳川をうかがっていた,
生活とは程遠く,昌幸は,何度も郷里への帰国を規模していた,という。
秀忠軍三万八千を,わずか二千で上田城で翻弄し,関ヶ原に遅参させた,稀代の武将,真田昌幸も,
所領や軍勢を奪われ…,羽をもがれた鳥に等しい存在であった,
と,著者は言う。真田父子にして,これである。後は,推して知るべし,というところか。
参考文献;
渡邊大門『牢人たちの戦国時代』(平凡社新書) |
|
文体 |
|
古井由吉『鐘の渡り』を読む。
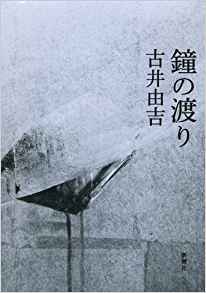
文章と文体は違う。古井由吉の文章は,文体としか言いようはない。今日の作家で,文体と呼べる文章を書くものは,大江健三郎と古井由吉しかいない。後の作家は,なべて,ただの物書きに過ぎない。
つくづく,またそう実感した。
文体とは,(日本語で言うなら)他国語に翻訳不能な文章といっていい。意味は伝わっても,それは,もはや文章でしかない。そこに,その作家の日本語がある。
まったく久しぶりに古井由吉を読んだ。もう,ん十年まえに,古井由吉論をまとめた。
http://www31.ocn.ne.jp/‾netbs/critique102.htm
たぶん,そこですべてを言い尽くしたと,勘違いしていた。そこでは,古井由吉の作品の構造分析をしたつもりであった。しかし,久しぶりに最新作を読んでみて,気づいたことがある。
夢と現の境目,
が彼の描いてきた世界だということに,改めて,というかいまさらながら,何か大事なことを見落としていたような,忘れ物をしたような感覚に,気づいた。
原っぱにいたよ、風に吹かれていた、年甲斐もない、と友人はおかしそうに言う。見渡すかぎり、膝ほどの高さの草が繁り、交互に長いうねりを打っていた。風下へ向って友人はゆっくり歩いていた。夜だった。いや、夜ではなく、日没の始まる時刻で、低く覆う暗雲に紫色の熱がこもり、天と地の間には蒼白い沼のような明るさしか漂っていないのに、手の甲がうっすらと赤く染まり、血管を太く浮き立たせていた。凶器、のようなものを死物狂いに握りしめていた感触が、ゆるく開いて脇へ垂らした右の掌のこわばりに残っていた。いましがた草の中へふと投げ棄てたのを境に、すべてが静かになった。
雨はまだ落ちていなかったが,服は内側からしっとり濡れていた。地面は空よりも暗く,草の下に転がる得体のしれぬ物がたえず足に触れたが,足はもう躓きも立ち止まりもせず,陰気な感触を無造作に踏みしめて乗り越えていく。そのたびに身体が重くなる。しかし風が背後でふくらんで、衰えかけてもうひと息ふくらむとき、草は手前から順々に伏しながら白く光り、身体も白く透けて、無数の草となって流れ出し、もう親もなく子もなく、人もなく我もなく、はるばるとひろがって野をわたって行きかける。野狐が人間の姿を棄て、人間の思いを棄て、草の中に躍りこむのも、こんなものなのだろうか、とそんなことを友人は考えたという(「哀原」)
これは,僕の好きな作品の書き出しだ。このまま七日間失踪する。あるいは,
それは木目だった。山の風雨に曝されて灰色になった板戸の木目だった。私はその戸をいましがた、まだ朝日の届かない森の中で閉じたところだった。そして、なぜかそれをまじまじと眺めている。と、木目が動きはじめた。木質の中に固く封じこめられて、もう生命のなごりもない乾からびた節の中から、奇妙なリズムにのって、ふくよかな木目がつぎつぎと生まれてくる。数かぎりない同心円が若々しくひしめきあって輪をひろげ、やがて成長しきると、うっとりと身をくねらせて板戸の表面を流れ、見つめる私の目を眠気の中に誘いこんだ。ところがそのうちに無数の木目のひとつがふと細かく波立つと,後からつづく木目たちがつきつぎに躓いて波立ち,波頭に波頭が重なりあい,全体がひとつのうねりとなって段々に傾き,やがて不気味な触手のように板戸の中をくねり上がり,柔らかな木質をぎりぎりと締めつけた。錆びついた釘が木質の中から浮き上がりそうだった。板戸がまだ板戸の姿を保っていることが,ほとんど奇跡のように思えた。四方からがっしりとはめこまれた木枠の中で,いまや木目たちはたがいに息をひそめあい,微妙な均衡を保っていた。密集をようやく抜けて,いよいよのびのびと流れひろがろうとして動かなくなった木目たちがある。密集の真只中で苦しげにたわんだまま,そのまま封じこめられた木目たちがある。しかし節の中心からは、新しい木目がつぎつぎに生まれ出てくる。何という苦しみだろう。その時、板戸の一隅でひとすじのかすかな罅がふと眠りから爽やかに覚めた赤児の眼のように生まれて,恐ろしい密集のほうへ伸びてゆくのを,私は見た。永遠の苦しみの真只中へ,身のほど知らぬ無邪気な侵入だった。しかしよく見ると,その先端は針のように鋭く,蛇の舌のように割れてわずかに密集の中へ喰いこみ、そのまま永遠に向かって息をこらしている……。私も白い便箋の前で長い間、息をこらしていた。(「木曜日に」)
これは処女作である。このころから,この現と夢,幻想と現の境を描ききっている。
日常の中の,こんな夢と現の境が,底流するテーマなのだ。そんな危うさを,本短編集にもずっと通奏低音のように響く。それは,ほんのわずかなずれから始まる。
梅雨時の夜の更けかかる頃に,同年の旧友と待ち合わせた酒場へだいぶ遅れて急ぐ途中,表通りから裏路へ入って三つ目の角を見込むあたりで,蒼い靄のまつわりつく街灯の下に立ちつくす半白の男がいる。近づけばその友人で,やがて私の顔を認めて目を瞠ったなり,妙にゆっくりと手招きして,地獄に仏とはこのことだ,と取りとめもなく笑い出した。
また何の冗談だとたずねると,道に迷ったと言う。知った足に任せて歩くうちに路の雰囲気がどうも違うようなので,さては角をひとつはずしたかと見当をつけなおして,しばらく行くと見覚えももどったようで,ようやく店までまっすぐのところまで来たかと思ったら,初めの角にいる,三度まわって三度同じところに出た時には小便洩らしそうになった,ワタシハイマ,ドコデスカと泣き出さんばかりだった,と笑いづけた。
あんた,もう何年,あの店に通っているんだ,と呆れて顔をあらためて見れば,手放しで笑いながらも憔悴の影がある。(「明日の空」)
僅かなずれに,足を取られれば,そのまま失踪ということもある。そんな危うさが,さりげない日常に口をあけている。見ないつもりなら見ないですむ。しかし,いったん見てしまうと,目がそらせなくなる。
母親は壁ぎわにしゃがみこんで泣き出した時にはまだ,ただもう途方に暮れきっていた,とやがて思った。泣くだけ泣けば心が空になり,子たちの手を引いて長い階段を降り,夜更けの街をあてどもなくさまよった末に,気を取り留めて,先の望みもない日々の苦にもどっていたかもしれない。しかし女の子におずおずと顔をのぞきこまれて,どうして泣いているのとたずねられた時,子たちへの不愍さのあまり,母親の心は一度に振れた。
切符をなくしてかなしくて,という言葉を女の子は,いましがた切符を出して改札口を通り抜けたのを見ているので,まだ分別の外ながら,引き返しのきかぬ声と聞いた。立ちあがると母親の面相は一変していた。
最短区間の切符を買いなおして連絡通路をまっすぐに行く母親の,周囲からきっぱりと切り離された後姿が見える。女の子はその脇で,力を貸すようにひたりと寄り添い,乱れもない足を運んでいる。母親の鬼気は吸いこまれるままになったか。もう片側に男の子は手を引かれて,遅れがちの短い足をちょこちょこと送っている。ときどき,脇見をしている。
人は追い詰められて,姿ばかりになることがある。外からそう見えるだけでなく,内からしてそうなるようだ,と二十歳ばかりの男がそんなことを思ったものだ。若年の間にいっとき挿まる,老いのような境だったからか。(「地蔵丸」)
母子心中を,そう想像しているのである。その一瞬,二十歳の若者も,現と夢の境にいる。
この短編集の中では,表題にもなっている,「鐘の渡り」と「八ツ山」がいい。
「鐘の渡り」は,最近では珍しく,三十代の男の話だが,『杳子』に比べると,淡泊だが,捨てがたい魅力がある。
……暮れた道を走ったこともあるけれど,人の道は夜目にもかすかに光ったものだと話を逸らすと,人のからだには燐がふくまれているからな,息に吐いて,汗に滲んで,道にこぼして行くんだ,と朝倉は答えて,
――ひとりきりになって考え込む人間も,雨の暮れ方などには部屋の内に居ながらうっすらと光る。境を越えかけたのを悟った病人を見たことがあるか。
そう言ってこちらへ向き直った。そのとたんにあたりの林が一斉に燃えあがり,頭上には雨霧が立ちこめているのに西のほうの空の一郭で雲が割れたらしく,斜めに射しこむ陽の光を受けて木々の枯葉が狂ったように輝きながら,八方でまっすぐに揺らぎもせずに降りかかり,足もとの朽葉も照るようで,朝倉の顔も紅く染まり,それでいていきなり闇につつまれて遠い火をのぞくような眼を瞠った。ほんのわずかな,十と数えぬ間のことで,あたりが雨もよいの暗さにもどると,見たか,と朝倉は言って,何をと問い返す閑もあたえず,背を向けて歩き出した。
追って雨が降りかかってきた。(「鐘の渡り」)
参考文献;
古井由吉『鐘の渡り』(新潮社) |
|
復活 |
|
三池純正『九州戦国史と立花宗茂』を読む。
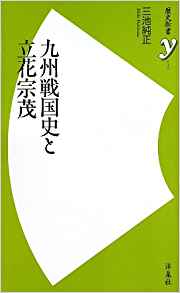
凋落する大友宗麟の旗下で,島津,毛利,竜造寺と戦い続け,秀吉の力で,大友家の面目を保った後,秀吉による九州再編の中で,立花宗茂は,大友配下から,初めて,秀吉直属の,柳川九万石大名に取り立てられる。
著者は,奥州盛岡城の南部盛直の言葉を引用して,
上方では奉公をよくする者は,たとえ小者でもサムライに取り立てられるため,誰もが我劣らじと奉公に励んでいる。それが秀吉の軍隊のからくりに違いない,
という。それは,新たに取り立てた大名に対する天下人の意図を言い当てていて,
秀吉は中世名主たちを小者から侍へ,そして大名へと取り立てていったが,それはそのまま「唐入り」という大陸侵略への道と結びつく「からくり」であった,
という。
しかし,考えてみれば,これは秀吉の旧主織田信長のやり方そのものではないか。秀吉自身が,卑賤の身から,大名へと取り立てられたし,信長旗下には,そうして取り立てられた者たちが,競って先陣を争い,関東へ,中国へ,四国へと,怒涛のように進出していった「からくり」でもあった。
だから,旧臣であっても,その働きが悪ければ,佐久間信盛,林通勝のように追放される憂き目にあう。それが他の者に,「我劣らじと」働かせる原動力にもなる。
ある意味そういう人材の登用と使い捨ても,秀吉は信長から学んだのではないか。
さて,そうして見込まれた宗茂は,大陸侵略の前線を担わせる目的があったということになる。
では秀吉のもくろみは何か。こういう説を紹介する。
(全国)統一の過程でみずからを朝廷権力のなかに位置づけた秀吉は,朝権の及ぶ範囲を拡充する方途をとって政権のフロンティアを拡大し,大陸侵攻と国内統一は朝権の拡大として並行的に進められた。
秀吉は後陽成天皇を北京に移し,養子の秀次を中国の関白にし,天皇家や公家に北京周辺の百カ国を与えるとし,従来の冊封という中国への朝貢を前提とした外交関係から,秀吉か覇権を拡大して東アジアの頂点に立とうとした。
事実秀吉は,現在のフィリピンに使者を派遣して服属を要求し,拒否すれば派兵するとまで言っている。これはかつて鎌倉時代にモンゴルが日本に伝えてきた内容と同じで,秀吉自身が東アジアの頂点に立とうとしていたことがうかがえる。
そんな中で,宗茂も二度にわたり朝鮮出兵の先兵として,文禄には,軍役として,戦闘員,水主,水夫,職人,雑役人夫を含めて,二千五百人を率いて渡鮮,慶長には五千人を率いて,まさに先兵役をはたした。
その後,秀吉後の政権交代期,宗茂は,関ヶ原の合戦では,小早川,島津とともに,西軍についたものの,本戦の関ヶ原に間に合わず,手前の大津城攻城に足止めされたまま敗戦に立ち至る。結果として,改易となり,流浪することになる。
この間,家臣に支えられ,あるいは加藤清正の厚誼に与りつつ,家康,秀忠との交渉を粘り強く続ける。そして六年後,一万石を持って,秀忠に召しだされる。宗茂四十歳。
その後秀忠に近侍しつつ,江戸御留守番となり,四年後三万石に加増となり,御咄衆を経て,柳川藩主田中家の改易を機に,奇跡的に,旧柳川領十一万石の大名に返り咲く。宗茂五十四歳である。
家臣宛に,
我ら事,柳川・三潴郡・山門郡・三池郡拝領致し,まかり下り候,本領と申し過分の御知行下され,外聞実儀これに過ぎず候,
と喜びを伝えている。
豊臣も滅んで元和偃武以降,もはや武功でおのれを誇示できない時代,武で名を成した宗茂が,文で権力者にすり寄る様子は,何かちょっと哀れに見えるが,本人は必死であろう。
御咄衆というのは,宗茂のほか,丹羽長重,細川興元,佐久間安政で,四人ずつ二組に分かれて,隔日に秀忠御前に伺候する。宗茂が選ばれたのは,
宗茂公は生得の気風正直を宗として,時めく人に諂い給うこともなく,武家の古風を失い給わざれば,
という。事実,この席で,
大津城攻めの時は,まず大津城を攻め崩し,東国大名たちの首を一つ一つ取る覚悟であった,
と,そのときの大津城主京極家のものがいても,豪胆に話したと,話題になっている。
しかし,そんな話をせざるを得ない宗茂の胸のうちは,本音のところどうだったのか,と思う。わずかの戦いの帰趨次第で,この立場は逆転していたかもしれない。
武門というものが生き残るのは,結局「武」ではなく,「略」の時代になっていたということのあかしであり,そうして復活した立花宗茂は,そういう時代のひとつの象徴なのかもしれない。
参考文献;
三池純正『九州戦国史と立花宗茂』(歴史新書y) |
|
戦国大名 |
|
黒田基樹『戦国大名』を読む。
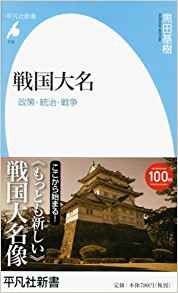
昨今の研究の蓄積で,
戦国大名と織豊大名・近世大名とは,領域権力ということで,基本的な性格を同じくし,社会状況の変化に応じて,その様相を変化させていった…,
と捉える見方が有力になっているとし,
中世と近世を分かつキーワードとなっていた,「太閤検地」「兵農分離」「石高制」などの問題は,実は研究の世界だけにおける,ある種の幻想であったことがはっきりしてきている…,
ということから,改めて,
戦後大名は総体として,どのような存在で,どのう特質をもつものと考えらるのか。
を示したのが本書ということになる。
相模の北条氏,甲斐の武田氏,駿河の今川氏,越後の上杉氏,安芸の毛利氏,豊後の大友氏,薩摩の島津氏等々が,代表的な戦国大名だが,
大名家当主を頂点に,その家族,家臣などの構成員を含めた組織であり,いわば経営体ととらえるのが適当,
と著者は定義する。
一定地域を支配する,領域権力を持ち,支配が及ぶ地域が面的に展開し,「国」と称され,戦国大名が支配する領域を領国と呼んでいる。それは,
線引きできるような,いわゆる国境で囲われた面として存在していた。その領国では,戦国大名が最高権力者として存在した。領国は,他者の支配権が一切及ばない,排他的・一円的なものであった。そこには天皇や室町幕府将軍の支配も及ばなかった。
だから,「国家」と称されていたのである。その権力構造は,
支配基盤としての「村」と,権力基盤としての「家中」の存在に特質付けられ,…その構造とは,領国支配を主導し,「家中」に対し主人として存在する大名家当主とそれを支える執行部,それらの指揮をうけ奉公する「家中」,両者かに支配を受ける「村」の三者関係,
となっている。羽柴秀吉が,
給人(家来)も百姓も成り立ち候様に,
といったように,戦国大名の権力が成り立つには,
軍事・行政の実務を行う家来と,納税する村の両方が,それらの負担が可能な程度に存続していることが前提になっていたのである。
したがって村に対して,一方的な収奪を行うということはありえないことになる。村々を潰せば,大名の存立基盤そのものが危機に陥る。戦国大名の支配基盤は,
政治団体としての「村」にあった。村が当時における社会主体であり,大名への納税主体であったことによる。村は一定領域を占有し(村領域),そこから得られる,用水や燃料などの資源をもとに,生産・生活を行っていた。時に,それらの生産資源をめぐって,隣接する村との間で,武力を用いて激しい紛争を行うこともあり,まさに「政治団体」として存在していた。その村の構成員が百姓であった。…戦国大名の支配基盤は,個々の百姓家ではなく,それらを構成員とした政治団体である村であった,
と捉えられる,としている。そして,戦国大名同士の,存亡をかけた戦争になると,
例えば北条氏では,永禄十二年(1569)からの武田氏との戦争のなかで,村に対し,奉公すべき対象として「御国(おくに)」をあげるようになり,「御国」のためになることは,村自身のためでもある,あるいはそうした奉公は「御国」にいる者の務めである,
と主張するようになる。だから著者は,
こうした戦国大名と村との関係は,現代の私たちが認識する国民国家と国民との関係に相似するところがある。このことから戦国大名の国家は,いわば現在に連なる領域国家の起源に当たる,
と指摘している。思えば,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/390004444.html?1393535997
にあるように,信長の全国制覇は,分国支配の延長線上にある。
そう考えると,,戦国大名の家臣団構造,税制,流通政策,行政機構などを分析したうえで,戦国大名と織豊・近世大名の画期とされた,
兵農分離,太閤検地,石高制,楽市・楽座,貨幣政策
等々は両者の異質さよりは,両者の連続性に目を向けるべきだと主張するのはよくわかる。
ただである,確かに,領域権力としてはそうだろうが,各戦国大名レベルで見ると,
豊臣政権に服属した時点で,戦国大名ではなくなり,豊臣大名と定義される。戦国大名は「惣国」における最高支配権者という存在ではあったが,豊臣政権に服属したことによって,自力救済機能が抑制されるからである。
もちろん領国内の支配は独立的に展開できるし,豊臣政権から領国内の民衆に対して公事賦課があるわけではない。しかし,江戸時代の学者・萩生徂徠が「武士を鉢植えにする」と云い方をしたように,豊臣政権は,専制的に,大名を移封・転封させることができた。いわゆる「鉢植え大名」である。
その意味では,戦国大名は,天下が統一されて以降,独自に兵を動かすことも,陳情することもできなくなっており,豊臣政権,徳川幕府下では,戦国大名は,明らかに自律性,支配権限が制約されていることは間違いない。
かつて,戦国大名に服属した大小名が,領国としては独立していながら,戦国大名の支配下にあった「国衆」と言われた存在と,戦国大名自身が同じになったといっていい。
参考文献;
黒田基樹『戦国大名』(平凡社新書) |
|
アドラー |
|
アルフレッド・アドラー『個人心理学講義』を読む。
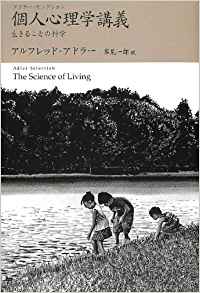
最近,あちこちでアドラーが云々と言われ,読んだかと聞かれる。ずっと,どこかでせせら笑って,スルーしていた。どこかで,僭越ながら,フロイトの幅と深みにかなうはずはないと思っていたからだ。
あまり喧しいので,一応目を通すつもりでWebの紀伊國屋,アマゾンを捜したが,本人の書いた(速記起こしも含め)モノが品切れか,廃刊で,やっと,この本だけが手に入った。入門書や解説書は山のようにあるようだが,そういうのは読む気がしない。生意気だが,他人の目や理解,評価の色眼鏡を通してではなく,自分の目でチャレンジしなくては,話を聞いただけで読んだ気になるのと一緒だ,と思っているところがあるからだ。
そんな経緯で,この本を手にしたが,正直言って,時間を無駄にしたと思っている。少なくとも,この本からは,皆が大騒ぎする理由が皆目読み取れない。頭の悪い僕自身の理解不足を棚に上げて,あえて言い切るが,中井久夫を読んだときの強烈なインパクトやミルトン・エリクソンの衝撃には及びもつかない。
少なくともこの本では,フロイトを批判して別れたが,別の因果論を立ててそれによってものを見ようとしているとしか見えない。フロイトの性欲シフトを批判して,ただ別にフォーカスする色眼鏡を拵えただけだ。今日,フロイトが批判されている因果論を,通俗にしたとしか,頭の悪い僕には受け取れなかった。
たとえば,
サディズムと子どもに対する虐待で告発された男性のケースがある。彼の成長を調べると,いつも彼のことを批判していた支配的な母親がいたことがわかる。それにもかかわらず,彼は学校では優秀で知的なこどもになっていった。しかし,母親は彼の(学校での)成功には満足しなかった。そのため,彼は家族への愛から母親を排除したいと思った。母親には関心を持たず,父親に献身し強く結びついた。
このような子どもが,女性は過酷で酷評するものであり,女性との関わりは,どうしても必要な時でなければ,進んでは持ちたくないと考えるようになったことは理解できる。このようにして,彼は,異性を排除するようになった。その上,不安な時にはいつも興奮するので,このようなタイプの人は,いつも不安を感じずにすむ状況を求めている。後には,自分自身を罰したり拷問を加えたい,あるいは,子どもが拷問されるのを見たいと思うかもしれない。さらには,自分自身や他の人が拷問を加えられるのを想像するのを好むようになるかもしれない。彼は,いま述べたようなタイプなので,このような現実の,あるいは,空想上の拷問の間に,性的な興奮と満足を得るようになるだろう。
この男性のケースは,誤った訓練の結果を示している。彼は自分の習慣との関連を理解していなかったし,もしも理解いたとしても気づいた時には遅すぎたのである。無論,二十五歳や三十歳の人をで適切に訓練することはきわめて困難なことである。適切な時期は,早期の子供時代である。
一読してわかるのは,アドラーの側に人の生き方についての正解がある,と思っているとしか見えないところだ。だから,
子どもの指導に関しては,主たる目的は,有益で健康な目標を具体化することができる適切な共同体感覚を育成することである…。普遍的な劣等感が,適切に活用され,劣等コンプレックス,あるいは,優越コンプレックスを生じないようにするためには,子どもたちを社会の秩序に調和するように訓練することによってしかない。
時代の制約があるにしても,今日の社会構成主義とは,ちょっと異質な考え方といっていい。この背景にあるのは,アドラー独自の劣等感についての考えがある。
優越性と劣等性に結びついたコンプレックスという言葉は,劣等感と優越感の追求の過度な状態に他ならないということを忘れてはならない。そのように見ていくと,二つの矛盾した傾向,即ち,劣等コンプレックスと優越コンプレックスが同じ個人の中に存在するという見かけ上のパラドックスを回避することができる。というのは,優越性の追求と劣等感は,普通の感情として,当然のことながら,相補的なものであることは明らかだからである。もしも現在の状態に,何らかの欠如を感じないのであれば,優越し成功することを求めるはずはない。
劣等感は病気ではない。むしろ,健康で正常な努力と成長への刺激である。無能感が個人を圧倒し,有益な活動を刺激するどころか,人を落ち込ませ,成長できないようにするとき初めて,劣等感は病的な状態となるのである。優越コンプレックスは,劣等コンプレックスを持った人が,困難から遁れる方法として使う方法の一つである。そのような人は,自分が実際には優れていないのに,優れているふりをする。そして,この偽りの成功が,耐えることのできない劣等である状態を補填する。普通の人は優越コンプレックスを持っていない。優越感すら持たない。われわれは,皆成功しようという野心を持っているという意味で優越性を追求する。しかし,このような努力が仕事の中に表現されている限り,精神病の根源にある誤った価値観へと導くことにはならない。
だから,
劣等コンプレックスを見出すケースにおいて,優越コンプレックスが,多かれ少なかれ,隠されているのを見出したとしても驚くにはあたらない。
社会適応は,劣等感と優越感の追求の社会的な結果から引き起こされている。劣等コンプレックスと優越コンプレックスという言葉は,不適応が生じた後の結果を表している。これらのコンプレックスは,胚珠の中にも血流の中にもない。ただ,個人と,その社会環境の間の相互作用のなかでのみ起こるものである。なぜあらゆる人にコンプレックスが起こらないのであろう。すべての人は劣等感を持ち,成功と優越性を追求する。このことがまさに精神生活を構成する。しかし,あらゆる人がコンプレックスを持っていないのは,劣等感と優越感が共同体感覚,,勇気,そしてコンプレックスの論理によって,社会的に有用なものになるよう利用されているからである。
いまひとつ前述の引用からみられる,アドラーの特徴は,原型とライフスタイルである。
原型,即ち,目標を具体的なものにする初期のパーソナリティが形成されるとき,(目標に向かう)方向線が確立され,個人ははっきりと方向づけられる。まさにこの事実によって,後の人生で何が起こるかを予言できるのである。個人の統覚は,それ以後,必ずこの方向線によって確立された型にはまっていくことになる。子どもは,任意の状況をあるがままに見ようとはせず,個人的な統覚の枠組みに従って見る。状況を自分自身への関心という先入観にもとづいてみるのである。
そして,
原型がまさしく現れるのは,困難な,あるいは新しい状況においてである。
われわれは,ある環境の条件の下で,ライフスタイルを見る。(中略)好ましくない,あるいは,困難な状況に置かれたら,誰の目にもその人のライフスタイルは明らかになる。……ライフスタイルは,幼い頃の困難と目標追求から育ってきたものなので,統一されたものである。
例として,ある男性(三十歳)のケースを挙げている。
彼は,いつも最後の最後になって,人生の課題の解決から逃れている。彼には友人がいたのだが,その友人のことを強く疑っていたので,その結果,この友情はうまくいかなかった。友情は,このような条件の下では育たない。なぜなら,このような関係においては,相手が緊張するからである。言葉を交わすくらいの友人はたくさんたにもかかわらず,本当の友人がいなかったのは容易に想像がつく。(中略)
その上,彼は内気だった。赤い顔をしており,話す時には時々いっそう赤くなる時があった。この内気さを克服できれば,よく話せるようになるだろうと考えていた。……このような状態のときには,人にいい印象を与えることができなかったので,知人の間で好かれることはなかった。彼はこのことを感じており,結果としてますます話すのが嫌いになった。彼のライフスタイルは,他の人に近づくと自分自身にだけ注意を向けるというものであるといえよう。
で,アドラーは,こう診断する。
劣等感を減じることである。劣等感をすっかり取り除くことできない。実際私たちはそうすることを望んではいない。なぜなら,劣等感は,パーソナリティ形成の有用な基礎となるからである。しなければならないことは目標を変えることである。…ケース…の目標は,他の人が自分より愛されるということを理由に逃避するというものである…。私たちが取り組まなければならないのは,このような考えである。
アドラーは,自分の心理学を個人心理学と名付けたが,それは,
個人の生を全体としてみようとし,単一の反応,運動,刺激のそれぞれを,個人の生に対する態度の明確に表された部分とみなしている。
重要なことは,行為の個々の文脈,,即ち,個人の人生におけるあらゆる行為と動きの方向を示す目標を理解することである。この目標をみれば,様々なばらばらな行為の背後にある隠された意味を理解することができる。それらは全体の部分として見ることができる。逆に,部分を考察する時,それを全体の部分として考察すれば,全体についてよりよく理解することができる…。
精神の運動は器官の運動に似ている。どの心のうちにも現在の状況を超えていき,将来に対する具体的な夢を仮定することで,現在の欠陥と困難を克服しようとする目標,あるいは理想という概念がある。この具体的な目的,あるいは,目標によって,人は自分が現在の困難に打ち勝っていると考えたり感じることができる。将来,成功すると心のうちで考えているからである。この目標という観念がなければ,個人の活動はどんな意味も持たなくなる…。
この目標を定め,それに具体的な形を与えることは,人生の早期,即ち,子ども時代の形成期の間に起こる…。成熟したパーソナリティの一種の原型,あるいは,モデルが,この時期に発達しはじめる…。
たぶん,このあたりの考え方が,アドラー信者の魅力の根拠なのだろうとは推測がつくが,僕には,「…で,それがどうした?」という感覚で,スルーしがちだ。まあ,権力というか,成功志向の人にとって意味のある言葉なのだとは思うが,僕には…。
で,個人心理学が目指すのは,
「社会」適応である,
とアドラーへは言い切る。それが,目的である。それが,すでに社会構成主義とは相いれない。正解がありき,だからである。
個人は,ただ社会的な文脈の中においてだけ,個人となる。
誤った原型を持った少年が,後の人生,例えば,十七歳か十八歳という成熟しかけている年齢になったときどうなるか…。
社会適応の欠如は,原型において始まっている…。
どんな思想家も,おのれの中に,一般化原則を見つけ,それを一般化する。フロイトにもそれがある。だから,同意できるところがなくもない。しかし,どんな生き方が,有用で,無用なのかを,切り分けられる思想を,僕は好まない。それは,俺の勝手だからだ。
どこに正解がある,という思想は,現代にはなじまい,改めてそう確信した。
まあ,僕ひとりの妄想かもしれないが…!
参考文献;
アルフレッド・アドラー『個人心理学講義』(アルテ) |
|
第二の敗戦 |
|
船橋洋一『原発敗戦』を読む。
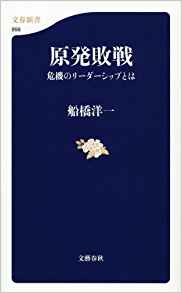
著者は,原発事故の当時の当事者に取材してまとめた『カウントダウン・メルトダウン』の後,大宅壮一賞受賞の折り,「恐るべき『戦史』」との選評を得たことから,改めて取材した「フクシマ戦史」。著者自身,
事故に取り組んだ東電の現場の人々や本店の幹部の人々にできるだけ直接,話を聞いて,危機の現場はどうだったのか,危機の司令塔は何をしていたのか,危機のリーダーシップはどこにあったのか,その感覚を共有したいと思った,
と語るように,再度の取材の中で本書はまとめられた。本書の後半は,
チャールズ・カストー(元米NRC日本サイト支援部長)
増田尚宏(福島第二原発前所長)
折木良一(前防衛省統合幕僚長)
野中郁次郎(一橋大学名誉教授)
半藤一利(作家)
との対談が組まれているが,対談相手,半藤一利氏は,
日米の危機対応,組織構造,リーダーシップのあり方の違いなど,あの頃(第二次大戦中のこと)と全く変わっていないことに驚かされます。
と述べているように,第二次大戦での敗戦になぞらえて,それとの類比・類推のなかで,日本人の,日本文化の,日本組織の,日本のリーダーの宿痾を剔抉している。
半藤とのやりとりに,こんなくだりがある。
半藤 じつは私,アメリカの技術力に改めて恐れ入ったのですが…。
船橋 まさに今回,「第二の敗戦」だと思うのはそこなんです。技術,物量,ロジスティクス,それからインテリジェンス。日本は底が弱かった。
半藤 日本はロボット大国と言われておりました…。
船橋 活躍したのはアメリカの,アイロボット社のパックボットという軍用ロボットでした。もっともアメリカの強さを見せつけられたのは,モニタリング力です。炉のなかの状況は日米,東電いずれもわからない。しかしアメリカは空からのモニタリングという技術をもっていました。あの炉は何度で放射線量はどれほどかと,それを1万8000m上空から無人偵察機グローバルホークで撮っちゃう…。
(中略)
船橋 日本のインテリジェンスの特色は3つあります。「(情報が)上がらない,回らない,漏れる」です。(中略)日本では,まず下から上に上がらない。上も上で,吸い上げる力が弱い。それは政策トップが戦略目標とゲームプランを明確に持っていないためです。各省全部バラバラ,そしてタコ壺。だから回らない。特に,防衛省と警察庁,それから外務省の間は回りません。従って統合的アプローチ,つまり「政府一丸になって」取り組むのが苦手。それから情報が漏れやすい…。
その弊害が,もろに今回出た。そして,「はじめに」で,こう書く。
危機の時,その人の本当の器量がわかる。
危機の時,リーダーシップが否応なしに問われる。
危機の時,その国と国民の本当の力が試されるし,本当の姿が現れる。
日常漠と思っていたそのようなことを今回,私たちは痛感した。
しかし,それもこれも,どこかで聞いたようなことばかりではないか。
戦後70年になろうというのに,いったい,いまの日本はあの敗戦に至った戦前の日本とどこがどう違うのだろう。
日本は,再び,負けたのではないか。
著者のこの深い敗北感は,第二次大戦になぞらえる心情は,実は,危機の当事者たちにも,共有されている,と言うことに深刻に驚かされる。
福島第一原発の現場は,過酷事故対処に必要なものは何もなかった。水もガソリンも,バッテリーも。
なかでも人員が決定的に不足していた。しかも補充は少なかった。人員の不足は単に頭数の問題ではなかい。作業に必要な知識,技量を有する人材が不足していたし,交代して対応する態勢ができなかった。
同じ半藤との対談で,
半藤 …吉田所長という指揮官以下の50人あまりの現場の方たち,いわゆるフクシマ・フィフティは頑張った。しかし事故の規模からいって,アメリカなら50人とか70人なんてことはあり得ませんよね。
船橋 あり得ないです。なにしろ原子炉が6つもあるわけですから,国務省の幹部もカストーも,1000人以上の規模で当たるべきだったとはっきりそう言ってました。
と指摘している。これを,
まるでガダルカナルではないか,
と思ったと,対策統合本部に詰めた外務省幹部が証言している,と言う。それは,大岡昇平の『レイテ戦記』にもあったと思うが,
ここでは戦力の逐次投入による戦力消耗と戦闘敗北の典型的例,
とみなされている。要は,一気に戦力を投入せず,現場の様子を見ながら,ちびちびと投入したという現実を,そうなぞらえているのである。
日本サイト支援支部長のチャールズ・カストーが,フクシマ第一原発の吉田昌郎所長に初めて会ったときの最初の質問が,「作業員たちはちゃんと寝ていますか?」でした。
と,半藤との対談で,著者は紹介しているが,この発想にあるのは,
長期戦を前提にした,危機への対応,
であり,そのために大量の人的投入が不可避なのだと分かる。同時に,思い出すのは,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163418.html
でも書いたが,
ゼロ戦の搭乗員の生命無視の軽量化
と
ゼロ戦に対抗して設計製作されたF6F (Grumman F6F Hellcat)
との対比だ
F6Fは,頑丈であること,単純化されて生産性が高いこと,防弾フロントガラス,コクピットを張り巡らした部厚い装甲,装甲されたエンジンとタンク,等々パイロットを守るために,ゼロ戦相手とわかっていても,機動性すら犠牲にしている。それは,人命尊重というより,ベテランパイロットの操縦を前提にしない,徴兵された普通の兵士が操縦することを前提にした設計思想だ。
それに対して,ゼロ戦は,軽量化と機動性を確保するために,防弾燃料タンク,防弾板,防弾ガラス,自動消火装置等々の防御部分がカットされ,被弾するとあっという間に火を噴く。それを回避するために,パイロットの個人技に依存した。
昭和天皇は1945年9月,…日光の湯元のホテルに疎開していた皇太子明仁親王にペン書きの手紙を出した。その中で,「敗因について一言いわしてくれ」として,「我が国人が,あまりに皇国を信じ過ぎて,英米をあなどったことである」と「我が軍人は,精神に重きをおいきすぎて,科学を忘れたこと」を敗因として挙げた,
と言われる。というより,人命を大事にするためにどうしたらいいかを考えるのに対して,人命よりも軽量化と機動性を大事にする,どちらが科学にとってハードルが高いか,だ。
著者は,それと同一の発想を,
炉心溶融
を
炉心損傷
に言い換えたところに見る。
東電も,保安院も,メルトダウンには病的なほど神経質になった,
という。
あくまでも真実を探求する科学的精神の欠如と異論を排除するムラ意識があるのではないか。
「原子力ムラ」などといういびつで同質的な既得権益層が跋扈し,研究者の科学的かつ独立精神を蚕食した。
それは科学の敗北ではないか,
と。いまなお,現場では戦いが続いているのに,国を挙げて,何千の単位の態勢を取っているとは聞こえてこない。
思えば,STAP細胞騒動でも,科学者も,研究者も,科学的に細胞の有無を検証しようとするよりは,論文の欠点をあげつらい,あまつさえ,最後は一人の責任に押し付けて,知らぬ存ぜぬとは,とうてい科学的対応とは言えない。ここにも,何か象徴的な騒動を見る。
遅まきながら,本書を読んで,改めて,『カウントダウン・メルトダウン』を読みたいと思った次第。
参考文献;
船橋洋一『原発敗戦』(文春新書) |
|
言葉 |
|
北山修『意味としての心』を読む。
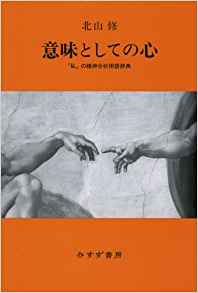
ヴィトゲンシュタインの言葉に,
もっている言葉によって,見える世界が違う,
と言った趣旨のものがあった(と記憶している)。
ここにあるのは,精神科医で精神分析家である北山修の言葉集(辞典)といっていい。凡例では,
さまざまな機会にあらわしてきた,精神分析的観点からみた臨床語を集め編集した,
とある。たとえば,「あい」からはじまり,
「あふ」はその語源説のひとつに上下の唇が相寄るときの音から出たという連想があるように,二つが互いに寄り合ってぴったり一致する,調和する,一つになる,という意味で,ものともの,人と人との間の基本的意識を示しています。特に「合う」の場合は,「出会い」がさらに進んで,受け入れる,矛盾しない,ぴったり当てはまるという適合,合致,調和のニュアンスが強調されます。(中略)「医者に会う」「先生に会う」とは言っても,「通行人に会う」とは言わないように,対人関係にいつて,「会う」が使われる場合は会う意味があるときで,無意味に会うことは会うではなくて,むしろ会っていないことになります。よって通常は,会うこと,合わせること自体に大きな意味や高い価値があり,…このような意識を伴う「あふ」という言葉は,面接と対話を価値ある形式とする日本語臨床の基本語となります。
という具合である。この「日本語臨床」という言い方には,特別な意味がある。著者はこういう。
日本人は普段より「滅多なことは言わない方がいい」と考え,饒舌や雄弁をそれほど好まないなど,言葉にあまり期待しない傾向があるため,精神医学や臨床心理の領域でもむしろ非言語コミュニケーションの重要性が説かれ,その視点から多数の心の理論が翻訳を通して輸入され,外国製の概念や理論で臨床の現象が割り切られることが正しいとされる風潮も見られます。心を描写するための言葉が日本語に豊富にあるにもかかわらず,研究者たちが日本語を生かすことが稀という傾向も強くありました。
その問題意識の中に,土居健郎の「甘え」論がある,と考える。そして,
もともと解釈や言語化という精神分析の技法論に見られるごとく,言葉と精神分析臨床は切っても切り離せないものであり,フロイトは夢,機知,言い間違いの精神病理などの分析で,言葉と意識・無意識に関して様々な相から検討を試みています。
として,
言語を主たる治療媒体とする精神分析理論の発展に向けて言語学者,文化人類学者,精神病理学者,言語心理学者などの知見から学ぶことは多く,日本語の中での精神病理の特徴や治療のための言語の機能について明確にしていく作業も必要です。言語論とともに重要なのは意味論的視点であり…,
とする,言葉の意味と機能に着目する著者の姿勢そのものの蓄積が,本書ということになるのではないか。
精神分析療法は,「心の台本を読む」ことを仕事とする,という言い回しが,何度か出るが,それを,「劇」になぞらえて,こういう言い方をしている。
「筋書きを読む」という仕事には,最初に劇の展開があり,問題が劇化され,その劇が繰り返され,やがて筋書きが読まれて,そしてその洞察を通し筋書きを考え直して書き替え,協力して新たな劇を創造するなどの作業が,段階的なものとして含まれるでしょう。そして,劇的な関係を引き受けてこれを分析する分析的治療者の仕事とは,劇の比喩で言うなら,出演しながら筋書きや心の台本を読むことになります。
あるいはこうも言う。
精神療法の言語的な仕事が「人生物語を紡ぐこと」,そして「人生を語り,語り直すこと」と説明されることが多くなってきましたが,これは古典的精神分析で言うところの過去の再構成という仕事です。
更に,
人生を物語として言葉で語って,それを二人で考えていこうとする分析的臨床的態度は,日本においても臨床心理学の基本となっている,
あるいは,また,
頼まれてもいないのに生きがいの動機づけや構造を指摘して,他人の生きがいによけいな解釈で水をさすことは,分析家の「野暮」と「愚の骨頂」「いらないお世話」となるでしょう。そして抱えられた空虚を埋めようとして何かがなされる場合,内側からの自己表現や創造としての何ものかが,たとえ野暮ったくて不器用なものでも,まずは貴重な意味ある生成となることがあります。精神分析とは,症状から,夢から,些細な言動から,そういう意味を取捨選択して発見し共有することに徹底的に貢献し「意味ある人生」にしようとする仕事なのです。
と。
精神分析では,言葉が媒介になる。
自由連想法の設定(セッティング)では分析者と後ろ向きの被分析者の二人はほとんど顔を合わせることがありません。それで,治療的に検討され取り扱われる素材は,被分析者により言葉で報告されるものがほとんどとなります。被分析者の無意識的反応を把握し,これを言葉で描き出すという営みの中で,そこに織り込まれてゆく分析的セラピスト側からの応答を「解釈」と呼びます。
そうして,
それまで無意識であった台本が読み出され,それが人生として生きられながら語られて,心の表と裏を織り込んだ人生物語を紡ぎ出すことになるのです。
と。そこで言葉が,他の療法に比して,格段に重要になる。そのことについて,フロイトの「言葉の橋」という言葉を手掛かりに,こう言っている。
両義的な言葉は,人々に共有されやすい意識的な意味と,個人が個別の内面に抱いている個性的な意味との間の橋渡し機能を果たしているのであり,私は,この議論を,心の内面と外面,内界と外界の間に橋をかけ,その内と外を結び付けているという言葉の機能の,精神分析研究の歴史的出発点としたいのです。
と,それを分析的な言い方で表現すると,
すでに意識されている意味と抑圧されて意識されにくい意味との間に橋をかける,
となるはずである。そのことの効果を,こうまとめている。
私は,「話す(ハナス)」には,対象を外界へ放す(ハナス)機能と,対象を自己から離す(ハナス)機能があると考えて,内的体験を外界へ伝えながら内外を分離させる言葉の機能を,総合的に「橋渡し機能」と呼びたいと考えています。
さて,精神分析家の北山修の言葉から見えるのは,こんな風景として,では,作詞家,
北山修,
あの,フォーククルセダーズのメンバーであり,提供したのも含めるレコーディングされたのが400曲,作りっぱなしのも含めると700曲に上るという,作詞家としての言葉から見えるものは別なのかどうか。
たとえば,橋田宣彦と旅の宿で嵐が通り過ぎる間に作ったという,
人は誰もただ一人旅に出て
人は誰もふるさとを振り返る
ちょっぴり寂しくて振り返っても
そこにはただ風がふいているだけ(「風」)
の向こうには,何が見えているのか。例えば,こんなことを,あとがき代わりの,「私の歌はどこで生まれるのか」に書いている。
「かける兎」の如き私が,昼間は跳びはねて遊び,あるいは懸命に働き,夜になり「疲れた兎」が横たわり目を瞑ると,あるいは勝って酔った気分で横になると,眠り始めた兎の背後から亀がゆっくりと立ち現れるのです。夜な夜な出現するこの亀は,歩みはのろいし,目を閉じ夢と眠りの中に生きているようなのです。
この夜から朝の間にある「考える亀」という,移行の領域において考える「私」は,自分に正直な「素の自分」です。亀でも兎でもない,そして亀でもあり兎でもあり,その真ん中で「本来的」とでもいうべき状態であり,「私は私」なのです。そこで朝起きたら患者に何を言うか考えたり,よいイデアを思いつきながら眠りにまた落ちたりしています。…そして外からは寝ているように見えますが,実は泣いていたり,誰かを罵っていたり,吠えたり,読んだり,そして歌ったりして,ここに歌詞の元がたくさん生まれているように思うのです。
そして私個人の場合,覚醒の手前で時に「なき」ながら考えているので,そこでこそ再び旅の歌も生まれ,そこが人生のクリエイティヴィティの原点です。また,分析のセッション中で精神分析家の「私」が何も見ずに目を瞑り暗闇の中でぼんやりと考えていますと,この状態が度々発生します。気持ちの上で揺れながらも,その旅の途中で,本来の自分として,考えはまとまっているなあと感じます。
そして外向けの歌作執筆活動では,亀から兎への間で引継ぎがあって,例えば朝型の亀の「歌」を日中兎が選択的に書き移し,「私」が修正加工し歌として書き直すところが外向きの創作の核心です。
この個人の自己対話を見ていると,著者自身が,創造性の項で,
フロイトは,子どもの遊びの中に創造性の発露を発見し,それが大人になると空想や劇に姿を変えると考えました。願望充足を特徴とする空想や白日夢は通常個性的すぎる内容であり,他者に伝えたとしても不快感をもたらすことが多いのに対して,詩人は個人的な空想を受容される形で伝えることで他者にもたらします。このことに注目したフロイトは,神経症者と比較して,創造的行為とは,抑圧のゆるさと,空想や白日夢を公共性の高いものにする強い昇華の能力とを同時に有するものと考えました。
と述べていることと照合してみると,まさに,
言葉によって見えているものは,
作詞家のそれも,
精神分析家のそれも,
北山修というひとりの人の見えているものに違いない。と感じるのである。
参考文献;
北山修『意味としての心』(みすず書房) |
|
多宇宙 |
|
青木薫『宇宙はなぜこのような宇宙なのか』を読む。

人間原理については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163436.html
宇宙のあり方については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163082.html
でそれぞれ触れたが,ここでは,「人間原理」をキーワードに,最新の宇宙論の最前線を紹介している。
人間原理とは,
宇宙がなぜこのような宇宙であるのかを理解するためには,われわれ人間が現に存在しているという事実を考慮に入れなければならない,
つまり,人間が存在するべく宇宙がつくられている,という目的論的な考え方である。「はじめに」で,著者が言うように,
たしかに,もし宇宙がこのような宇宙でなかったとしたら,われわれ人間は存在しなかったろう。地球も太陽も存在しなかっただろうし,銀河系も存在しなかっただろう。
しかし,なぜそういう考えが出てきたのか,著者は,本書の目的を,
人間原理とはどんな考え方なのか,
なぜそんな考え方が生まれたのか,
その原理から何が出てきたのか,
を考えることだとしている。
この考えが出てくる背景には,アインシュタインの,
神が宇宙を作ったとき,ほかの選択肢はあったのだろうか,
という問いである。もちろん,神は,言葉の綾である。言い換えると,
あれこれの物理定数は,なぜいまのような値になったのか,
となる。そこで,著者は,基本的な四つの力(重力,電磁力,強い力,弱い力,)に関わる,二つの例を挙げる。
ひとつは,重力である。
もし重力が今より強かったら,太陽やその他の恒星は,押しつぶされて今より小さくなるだろう。強い重力で圧縮された中心部の核融合反応は急速に進み,星はすみやかに燃え尽きてしまうだろう。地球やその他の惑星も,いまよりサイズは小さくなり,表面での重力は強くなるため,われわれは自重で潰れてしまうだろう。逆に,もし重力が今より弱かったなら,天体のサイズは大きくなり,中心部の核融合反応はゆっくりと進み,星の寿命は延びるだろう。
いずれにしても,地球上にわれわれは存在しない。
二つ目は,強い力と電磁力との強さの比である。
もしも強い力が今よりも弱かったなら,電気的な反発力が相対的に強くなり,陽子はそもそも原子核の内部に入ることはできなかっただろう。その場合,初期宇宙の元素合成の時期に,水素原子核(陽子)よりも大きな原子核は生じなかっただろう。この宇宙は水素ばかりの,ひどく退屈な世界になっていたはずだ。逆に,もし強い力が今よりも強かったなら,陽子同士が結びついてしまい,水素(つまり単独の陽子)は早々に枯渇しただろう。水素の存在しない宇宙は,この宇宙とは似ても似つかないものになっていたはずである。
つまり,物理定数が今の値でなかったとしたら,宇宙の姿は,いまの宇宙ではなかった,ということである。
では,なぜ今の値なのか。その問いに,ハーマン・ボンディは,コインシデス(偶然の一致)を示して,議論を提起した。本書では,3つを紹介している。
①電子と陽子の間に働く電磁力と重力の比が,1040
②宇宙の膨張速度の目安であるハッブル常数から導かれた「長さ」(大雑把な宇宙の半径)と電子の半径(核力の到達距離)の比が,1040
③宇宙の質量(宇宙の質量密度×半径の三乗)を,陽子の質量で割った,宇宙に存在する陽子(あるいは中性子のような,電子と比べて思い粒子)の個数が,1040
これに対して,人間原理を打ち出してきたのが,ブランドン・カーターなのである。そして,
コペルニクスの原理,
つまり,人間が宇宙の中心にいる,
ことを否定した考え方に,過度に拡張しすぎている,として,
a.われわれが存在するためには,特別な好都合な条件が必要であること,
b.宇宙は進化しており,局所的なスケールでは決して空間的に均質ではないこと,
を理由に挙げた。そして,ボンディの挙げたコインシデンスを,「コンベンショナル(普通)」な理論で説明するには,
人間原理,
を受け入れなければならない,といったのである。ボンディのコインシデンスの①,②については,すでに説明がつく。問題は,③である。カーターは,こう言う。
宇宙は(それゆえ宇宙の性質を決めている物理定数は),ある時点で観測者を創造することを見込むような性質を持っていなければならない。デカルトをもじって言えば,「我思う。故に世界はかくの如く存在する」のである…,
と。これは,著者が言うように,
「この宇宙の中で,存在可能な条件を満たされた時期と場所に」存在しているという話ではすまず,「そもそも宇宙はなぜこのような宇宙だったのか」という問題と関わっている,
のである。しかし,カーターは,話をこう展開する。
物理定数の値や初期条件が異なるような,無数の宇宙を考えてみることには,原理的には何の問題もない。
もし,宇宙が無数にあるなら,「知的な観測者が存在できるような宇宙は,世界アンサンブルの部分集合に過ぎない,
とするなら,
われわれは無数にある宇宙の中で,たまたま我々の存在を許すような宇宙に存在している,
というだけのことになる。このカーターの提起の,
世界アンサンブル,
という考え方は,宇宙のインフレーション理論,
宇宙誕生の10−36秒後に始まり,10−36秒後には終わった(中略)。その一瞬の間に1030倍にも膨張した,
とされる。そして,
宇宙誕生は一度きりの出来事ではない,
というのが,物理学者の考え方なのだ。とすると,そこから,自然に,
宇宙はわれわれの宇宙だけではない,
という,多宇宙ヴィジョン,
が生まれ,膨張する宇宙の中に,
海に浮かぶ泡のような領域…を,泡宇宙か島宇宙,
と呼ぶ。そして,
われわれの宇宙は,無数にある泡宇宙のひとつに過ぎない。いわゆる「地平線宇宙」―どれだけ高性能の望遠鏡が開発されようとも,そこから先は未来永劫決して見ることができないという意味での「地平線」の内側―
にいる,ということになる。宇宙の理論の,
多宇宙ヴィジョンは,ほとんどデフォルト,
と著者は言いきる。人間原理は,この時点で,反転し,人間による,観測選択効果になった,と。
いま,アインシュタインが言った,
宇宙は,ある必然性があってこのような宇宙になっている,
さまざまな定数の値が,他のどの値でもなく,この値でなければならぬ,
という理論を目指して,科学者は様々な仮説にチャレンジしている。
参考文献;
青木薫『宇宙はなぜこのような宇宙なのか』(講談社現代新書) |
|
眠り |
|
内山真『睡眠の話』を読む。

実験的に,徹夜をすると,簡単な判断を要する時間がビール大ビン一本飲んだ状態に匹敵する…,
ということを聞くと,確かに,眠りは人間にとって大切なのだが,五人に一人が不眠に悩んでいるという。
本書は,睡眠に悩む人との対話を踏まえて,
睡眠と私たちの生活,睡眠と心や身体の健康,睡眠と脳の働き…
について,睡眠学の立場から解き明かしていく。では,睡眠とは何か。
眠っている時には,私たちは人間ではなく霊長目に属するただの哺乳類になる。
のだそうだ。爬虫類などの変温動物から恒温動物になることで,環境に対する適応力を飛躍的にのばしたが,その分,
体温を保つために常にエネルギーを燃やし続けなければならず,変温動物に比べると大量の食物が必要となった。
さらに,
内外からの情報を処理し,身体をよりうまく働かせるための大脳を発達させた。(中略)発達した大脳は,体温を一定に保つ恒温動物としての限界をさらに超えて,膨大なエネルギーを消費する。そして活性酸素のような有害な老廃物も産生するし,機能変調が起こりやすいという脆弱性を持つ。長時間働かせていると身体が供給できるエネルギー量では足りなくなる。これを防ぎ,大脳をうまく働かせるために上手に管理する,
これが睡眠であり,
身体が休む時間帯に大脳をうまく沈静化して休息・回復させ,必要な時に高い機能状態の覚醒を保証する機能をもつに至った,
ということであり,
身体が休む時に,脳の活動をしっかり低下させ休養させるシステム,
これが,睡眠ということになる。当然不足すれば,機能不全に陥る。このシステムは,
意外にシンプルな仕組みでできている。体内の温度を積極的に下げることで,まるで変温動物のようになって脳と身体をしっかり休息させるのだ。皮膚から熱を積極的に逃すシステムが働くと,身体の内部の温度が下がると同時に,頭の内部にある脳の温度が下がっていく。体内の温度が下がると,生命を支えている体内の化学反応が不活発化する。つまり,代謝が下がり,休息状態になる。
すると,眠くなるらしいのである。眠らないでいると,
起きていた時間に比例して脳脊髄液の中にプロスタグランジンD2が増えてくる。(中略)長く起きていたという時間に関する情報が脳脊髄液中の睡眠物質の量に転換され,この睡眠物質の増加という情報が神経情報となって,脳の眠りを引き起こす部位,視床下部に伝達されるのだ。そして,視床下部の眠りを引き起こすGABA神経系が働き出す。GABA神経系は,より奥にある目を覚ましておく神経活動を支える部位,結核乳頭体のヒスタミン覚醒系を抑制し,
われわれは眠くなる。では,よく知られた,レム睡眠,ノンレム睡眠は,どういう機能があるのか。一晩の睡眠の80%位がノンレム睡眠と言われているが,
健康人が夜七時間の睡眠をとる時,まず浅いノンレム睡眠から次第に深くなり,深い睡眠がしばらく続く。そして,寝返りの後,浅いノンレム睡眠が出現し最初のレム睡眠に移行する。入眠から最初のレム睡眠までの時間は平均すると90分くらいである。レム睡眠が5〜40分続いた後,再びノンレム睡眠に入っていく。その後,レム睡眠はノンレム睡眠と交代しながら90〜120分程度の周期で出現する。
レム睡眠時は,夢を見ることが知られているが,
夢はレム睡眠というごく浅い眠りに随伴する内的体験だ。本当に完全に脳が休んでいる状態では意識が途切れるわけで,夢体験が起こることは考えにくい。脳がある程度の活動状態に保たれているために夢見を体験することができる。
というのも,
レム睡眠中には,外界からの情報が遮断されているからだ。
音や光だけでなく,身体の感覚も脳に伝わらないように遮断されている。なぜなら,
まどろんだ状態での夢体験に応じて身体が動いてしまうと,…瞬く間に眼が覚めてしまう。筋肉が動いたというフィードバック信号は強力に眼を覚ましてしまうからだ。
で,この間は,
脳からの運動指令が,脊髄のあたりで遮断された状態にある。
この時金縛りが起きる。「睡眠麻痺」と呼ばれる。夢を見ている時,外界の刺激はないのだから,当然素材は,脳の内部情報になる。
脳の奥のほうにある記憶に関連した大脳辺縁系と呼ばれる部分が活発に活動し…,同時に大脳辺縁系で情動的反応に関連した部位も活発に活動している…。一方で,記憶の照合をしている,より理性的な判断機能と関連する前頭葉の機能は抑制されている。
フランスの脳生理学者ミッシェル・ジュヴェの発言がいい。
レム睡眠中には,動物も人間も危機に対処する行動をリハーサルし,いつでも行動できるよう練習している,
と。つまりは,イメージ・トレーニングである。
では,ノンレム睡眠は,どういう機能なのか。
ノンレム睡眠には,まどろみ期,軽睡眠期,深睡眠期とあり,軽睡眠期がノンレム睡眠の80%を占める。
まどろみは電車の座席できちんと坐っていられ,乗り越さない睡眠。軽睡眠は,誰でも自分が眠っていると感じられ,だらんと首が保てなくなる。降りる駅でどあが閉まる直前に目が覚める。深睡眠は,自分が熟睡していると感じる。多少の音では目が覚めない。電車を乗り越すのはこの状態。
ノンレム睡眠は,脳を休めるためだが,軽睡眠が多いのは,完全に働きを停止してしまっては生物にとって危険だからと考えられる。
長い間覚醒していればいるほど,その後の深いノンレム睡眠である徐波睡眠が増加する。一種のホメオスタシス維持機能ということになる。
深いノンレム睡眠中は,子どもの成長や身体の修復に関係する成長ホルモンが活発につくられる。
細菌やウィルスなどの外敵が身体に侵入すると,防御機能が働き,白血球がこれらを排除する。こうした時,つくられる免疫関連物質,インターロイキンなどの免疫物質の中には体内の免疫機構を活性化するとともに,深いノンレム睡眠を誘発する作用を持つものがある。感染時に眠たくなるのはこうした物質が働いている証拠と考えてよい。
これも体に備わった防御機構なのだといっていい。睡眠効果のもっと面白いのは,新しい技能を身に着ける時,練習による向上度もあるが,十分睡眠することで,手続き記憶が強化され,練習した以上に技能が向上する,という。
睡眠中の技能向上は苦手な動作ほど大きい,
というのは,脳の機能としてもちょっとわかる気がする。寝ている間に定着する,ということなのかもしれないが,ノンレム睡眠の方がより効果的ということらしく,夢のリハーサル効果ではないのが意外だと言えば,言える。
ところで,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388163590.html
でも書いたように,フェイスブック上のコミュニティ「早起き賊」に加わっているが,朝型夜型は,体質というか,
体内時計の周期が24時間より長めだと夜型になりやすく,この周期が24時間より短い,ないし24時間に近い場合には,朝型になる,
という。
体内時計の細胞では,時計遺伝子というタンパク質の設計図に基づいて時計機能を担うたんぱく質が製造される。この細胞内での一種の化学反応が24時間周期でゆっくり変動し,直接一日という時間をとらえる。
ま,遺伝子で決まる,ということか。しかし,習慣化で,変えることもできる,そんな気がする。そこが,人間の人間たる所以なのだ。
睡眠障害対処12の指針の四に,こうある。
早寝早起きではなく,早起きが早寝に通じる,
と。まさに早起き賊が,常々言っていることだ。
参考文献;
内山真『睡眠の話』(中公新書) |
|
地球外生命 |
|
長沼毅・井田茂『地球外生命』を読む。
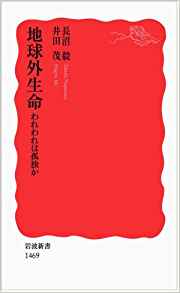
銀河系の恒星の数はおおよそ数千億個,だとすると一千億個以上の地球型惑星が存在し,生命を宿しうる「ハビタブル惑星」も100億個以上ある,と考えられている。ただ,系外惑星系は,太陽系とは似ても似つかぬ惑星系が多く,…中心星の近傍の灼熱領域(太陽系での最内縁の水星の軌道のはるか内側)に,スーパー・アースと呼ばれる大型地球型惑星をもっていて,何個ものスーパー・アースがひしめき合っている…,
にもかかわらず,氷を主成分としたスーパー・アースが複数見つかっている,という。
地球外生命の発見もそんなに遠くないと思われる中で,本書は,地球の生命を掘り下げ,
地球生命にとって良かった条件を洗い出し,…どの程度普遍化できるか,
を探っている。なぜなら,
わたしたちは,地球に住んでいる,共通の祖先から枝分かれした単一の生物しか知りません。この生物を手がかりにして,宇宙の環境にどのような生命が存在しうるかを考えるしかありません。手始めに,地球の生物が生きていける限界を押さえておきます。
地球上の生物を生き方で分けると,
動物(多細胞) 陸上と海に数十億トン
植物(多細胞) 陸上と海に1兆〜2兆トン
微生物(多細胞,単細胞) 陸上と海に2000億トン〜3000億トン,地下に400億トン
動物の中の3.6億トンが人である。しかし,普通,生物は,
バクテリア(細菌)
アーキア(古細菌)
真核生物
と分けられる。
真核生物の細胞膜はバクテリアに似ており,遺伝子のはたらきなどはアーキアに似ていることから,バクテリアがアーキアを食べて,食べられたアーキアが核になって,真核生物になったとされるが,地球上のすべての生物は,単一の系統,共通の祖先から発している。
ではそもそも生命はどう誕生したのか。
ひとつの説が,アレクサンドル・オパーリンの原始スープ説。
まず無機質から有機物が生成され,その有機物が海の中で結合して,アミノ酸,塩基,リン酸などができ,それらが長くつながってタンパク質やDNA,RNAなどの核酸ができ,生命に至った…。
いまひとつは,ギュンター・ヴェヒタースホイザーのバイライト仮説。
パイライト(黄鉄鉱)ができるときにはエネルギーが生じ,このエネルギーで二酸化炭素を取り込んで糖質などの有機物が作れる。
いまひとつは,外来説。そのひとつがか,ジョセフ・カーシュビングの火星起源説。
生命誕生は40億年前,当時地球には陸地がなく,陸地がないと,生命活動に重要なミネラルが海に供給されない。しかし40億年前の火星には陸も海もあり,生命誕生に都合がよい環境だった。また火星からの隕石の飛来は,13000年前に南極に落下した例があり,隕石の中に入っていると,摩擦を受ける大気圏通過は,10秒くらいで,中心部は40℃までしか上がらない,とされている。
では知的生命体への進化は,どのように行われたのか。
実は地球上では,大酸化事件が数回起きている。生命誕生期には,酸素はほとんどなく,当時の生物は嫌気型であった。しかしシアノバクテリアという海中の光剛性バクテリアが,30億年前から,酸素を発生させ,20〜24億年前,酸素の蓄積量がティッピングポイントを超え,地球表面が一変する。
酸素呼吸は無酸素呼吸に比べエネルギーの発生量が10倍以上大きく,酸素呼吸の第一世代微生物が地球生態系で1人勝ちしていく。
その酸素呼吸のトップランナーが,私たちの祖先細胞に食べられたか,あるいは侵入したかして,そのまま細胞内に居座ったオルガネラがミトコンドリア,
というわけである。著者は言う,
もし私たちの祖先の細胞にミトコンドリアの前身のバクテリアが侵入せず,細胞内小器官になってくれなかったら,多細胞化,ひいては大型生物の出現はなかったでしょう。ミトコンドリアとなったバクテリアが現れたのは,シアノバクテリアが光合成の廃棄物として酸素を吐き出すという,地球規模の環境汚染をしてくれたおかげです。地球に限らず,いったん酸素が大気や海洋に放出されたら,やがて酸素を消費する生物が出現するでしょう。それは宇宙においても普遍的なシナリオだと思います。
この生物は,酸素呼吸により大量のエネルギーを得る半面,酸素呼吸で生じたラジカルが遺伝子を傷つけるので,遺伝子を安全に収納する細胞を特殊化させるでしょう。つまり,卵子と精子による有性生殖もまた普遍的と思われます。多細胞化して生物種が増え,生態系が複雑になると,…センサーとその情報処理系,すなわち感覚器官と脳が発達するでしょう。
つまり,生命が誕生し,酸素がある環境なら,多細胞で神経系を持ち,有性生殖を行う生物が生まれるチャンスは十分にあると思われます。
ワクワクするのか,ぞくぞくするのか。探査計画は目白押しである。
参考文献;
長沼毅・井田茂『地球外生命』(岩波新書) |
|
奇襲 |
|
一ノ瀬俊也『日本軍と日本兵』を読む。

一ノ瀬俊也『日本軍と日本兵』を読む。
本書は,
米陸軍軍事情報部が1942〜1946年まで部内向けに毎月出していた戦訓広報誌に掲載された日本軍とその将兵,装備,士気に関する多数の解説記事などを使って,戦闘組織としての日本陸軍の姿や能力を明らかにしてゆく,
ものである。戦死者数については,
日本陸軍:戦死1,450,000、戦傷53,028
日本海軍:戦死437,934、戦傷13,342
アメリカ陸軍:戦死41,322、戦傷129,724
アメリカ海軍:戦死31,484、戦傷31,701
アメリカ海兵隊:戦死19,733、戦傷67,207
アメリカ軍の太平洋戦線での戦死は107,903、負傷171,898、その他(事故などで)死亡48,380
という数値がある。
日本兵の戦死者の六割が餓死とも言われる。病気になっても後送されることはなく,
戦争末期に至るまで,退却の際に味方重傷病者を捕虜とされぬよう殺害していた,
から,実際の戦闘で死んだ者は,もっと少ないかもしれない。しかしも後退を続ける戦線では,飛行機の特攻機だけではなく,陸戦でも,それと似た自殺攻撃が数々ある。たとえば,
木に縛り付けられた狙撃兵。
米兵はこう証言する。
日本軍が狙撃兵を木に縛り付けておくのは我が方の弾薬を浪費させるためだと思っている。(中略)三日経った日本兵の死体を木から切り降ろしたことがある。78発の弾痕があり…,
と。さらには,敵戦車に手を焼いて,
対戦車肉攻兵
を考え出す。その攻撃手順は,
①待ち伏せた一人が対戦車地雷などの爆雷を手で投げるか,竿の先に付けて戦車のキャタピラの下へ置く,②二人目が火炎瓶などの発火物を,乗員を追い出すために投げつける。③これに失敗すれば戦車に飛び乗り,手榴弾や小火器で展視孔を潰す,
というものだが,著者も言う通り,戦車には常に援護の歩兵がおり,そううまくいかない。で,こういうことになる。
日本兵が戦車正面の道路に横たわっていたのが見つかり,撃たれると体に結び付けられた対戦車地雷が爆発した。
こういう人命軽視の作戦を,軍中枢では,机上の空論で立てていた。犠牲は,一人一人の国民の人生を丸投げすることで支払われる。この種の作戦は,卑怯すれすれだから,
丘の頂上で日本兵が白旗を降りだした。(中略)彼はこっちへ来いと言った。兵が立ち上がると丘の麓に隠れていた敵が発砲した。
とか,
降伏するかのように泣きわめきながら近づいてきた。十分近づいたところで立ち止まり,手榴弾を投げてきた。
等々,「卑怯な日本軍」(戦訓広報誌)を演じることになる。これでは,ゲリラ兵と同じである。ついには,沖縄戦では,
蜘蛛の穴陣地
という人間地雷原を作り,
戦車の接近が予測されると蜘蛛の穴に入る。各自が肩掛け箱形地雷などをもっている,
という作戦を立てる。しかも,
手首に引き紐を結びつけるよう命じられているので,投げてから一秒後に爆雷は爆発する。
もちろん兵は爆発に巻き込まれる。
戦死者の中には,こういう人の命を虫けらのように扱われた兵が含まれる。その他に,撤退の命令がないための,ばんざい突撃などの自暴自棄の夜襲攻撃を加えれば,無意味な死者の数は,もっと増えるだろう。
しかもこういう作戦を考えた参謀たちは,八原博通大佐,後宮淳大将は,のうのうと生き残り,対戦車必勝法として,誇らしげに戦後語っている。しかも,八原は米軍に投降している。
戦訓広報誌は,日本兵の短所を,こう書いている。
予想していないことに直面するとパニックに陥る,戦闘のあいだ決然としているわけではない,多くは射撃が下手である,時に自分で物を考えず,「自分で」となると何も考えられなくなる,
将校を倒すと,部下は自分で考えられなくなるようで,ちりじりになって逃げてしまう,
と。著者はこう締めくくる。
米陸軍広報誌の描いた日本兵たちの多くは,「ファナティック」な「超人」などではなく,アメリカ文化が好きで,中には怠け者もいて,宣伝の工夫次第では投降させることもできるごく平凡な人々である。上下一緒に酒を飲み,行き詰ると全員で「ヤルゾー!」と絶叫することで一体感を保っていた。兵たちは将校の命令通り目標に発砲するのは上手だが,負けが込んで指揮官を失うと狼狽し四散した。それは米軍のプロパガンダに過ぎないという見方もできようが,私は多分多くの日本兵は本当にそういう人たちだったのだろうと,と思っている。その理由は,彼らの直系たる我々もまた,同じ立場におかれれば同じように行動するだろうと考えるからだ。
また嫌な時代の足音が聞こえ始めていることが気になる。徴兵,集団的自衛権,他国への兆発(多く自己肥大の結果)等々。挙句の果てに,命を使い捨てにされる。こういう太平洋戦争中の悲惨さを,もっともっと周知されるべきだろう,とつくづく思う。
参考文献;
一ノ瀬俊也『日本軍と日本兵』(講談社現代新書) |
|
真相 |
|
フリップ・シノン『ケネディ暗殺(上・下)』を読む。
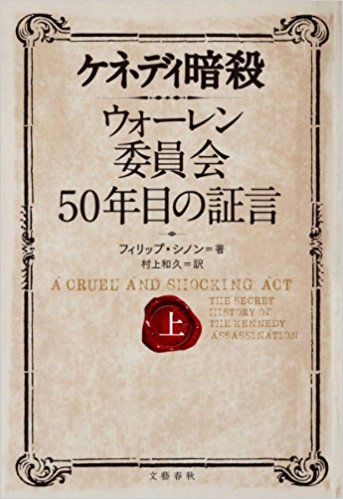 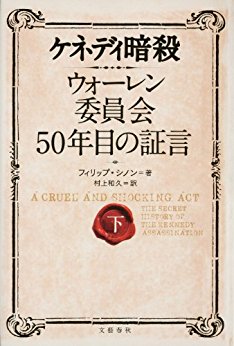
サブタイトルに「ウォーレン委員会50年目の証言」とある。ウォーレン委員会の全委員(この中には,後のフォード大統領も含まれる),その下で,調査に当たった若い調査員(ほとんどが若いバリバリの弁護士)の,委員会での活動を追っている。そこで,何が明らかになり,意図したかどうかは別に,何が明らかにされないままに残ったかを,つぶさに追う。
そして,報告書発表後の陰謀説ただならない中で,明らかにされたこと,開封された秘密にも言及し,委員会のスタッフたちが,CIAとFBIに,意識的に妨げられ,調査の方向を歪められ,隠されてきた一つの真実に,著者は辿り着く。
著者は,『9・11委員会』の調査報告書が,なぜ真実にたどり着けなかったか,本来責任を負うべき人間が免責されたかを追い詰めた『委員会9・11委員会調査の本当の歴史』を出版しているが,本書は,まさに,「ウォーレン委員会の真実の歴史」を描いている。
誰が何を妨げたか,誰が,どう消極的だったのか,何か明らかにされ,何が隠されたのか,何百という人間に会い,ほかのどの作家にも見せられてない秘密扱いの文書や私信,法廷筆記録,写真,フィルム,そしてその他多くの各種の資料に目を通すことを許された。本書内の発現や引用はすべて,側注巻末のソースノートが詳細に示すように,出典が明示されている。
と言い,こう指摘している。
わたしの目にあきらかなのは,この50年間―実際には,アメリカ政府の上層部の役人たちが,暗殺と,それにいたる出来事について,嘘をついてきたということである―とくに,誰よりCIAの高官たちが。
と,だから,当時のフーヴァーの後任のFBI長官ケリーは,
もしFBIダラス支局があのとき,FBIとCIAの他の部署でわかっていたことを知っていたら,「疑いなくJFKは1963年11月22日にダラスで死んでいなかっただろう」
と,言っている。防げる程度の情報を持っていた。もっていたのに,防げなかったことも,隠蔽の動機になっている。
本書は,当時メキシコのアメリカ大使館にいた,外交官の,国務省のロジャーズ長官にあてた,オズワルドのメキシコ滞在期間での行状に関するメモ(1969年)から,始まる。そして,それを50年後,著者が確かめることで終わる。
そのメモは,重大な方向を示していたが,それを送られたCIAはそれを,「さらなる措置は必要ない」と,CIAの防諜活動の責任者アングルトンの署名付きで,国務省へ返答した。その時点なら,まだより真実に迫れた可能性があったにもかかわらず,である。
著者は,責任者のリストとして,次の人々を挙げる。
第一に,CIAの元長官である,リチャード・ヘルムズを挙げる。ウォーレン委員会に,カストロを標的とした暗殺計画(これに,ケネディ大統領も,弟のロバート・ケネディも関わっている)を話さないという決定を下した。そして,アングルトンとメキシコ支部の責任者スコットが,フーヴァーのウォーレン委員会への手紙,「オズワルドがメキシコシティーのキューバ大使館にずかずか入っていって,ケネディ大統領を殺すつもりだと断言したことを報告する手紙,を行方不明にさせた,と著者は推測している。
アングルトンが隠そうとしたのは,CIAメキシコ支部がオズワルドについて知っていたすべて,さらには,CIAが,暗殺の四年前にさかのぼって,オズワルドを非合法に監視していた(なぜオズワルドをターゲットにしたのかはわからいまま)こと等々がある。
第二に,FBI。FBIは,暗殺日の数時間から,オズワルドに共犯者がいたという発見につながりそうな証拠を追うことを,わざと避けていた。著者は推測する。
フーヴァー(FBI長官)にとって,暗殺を暴行歴のない不安定な若いはみだし者のせいにするほうが,FBIが防げたかもしれない大統領殺害の陰謀が存在した可能性を認めるより,楽だった。(中略)もしFBIが1963年11月にすでにそのファイルに存在していた情報にもとづいてただ行動していればケネディ大統領は死ななかっただろうと断言したのは,フーヴァー自身の後継者のクラレンス・ケリーだった。
暴行歴のないどころか,オズワルドは,七ヶ月前,退役将軍ウォーカーを狙撃し,ニクソンも狙撃すると,公言していた。さらに,ケネディ射殺後,逃亡中に,職務質問した巡査を,射殺している。
第三は,委員会のトップ,ウォーレン最高裁首席判事。ケネディ家との個人的関係から,委員会に,大統領の司法解剖の写真とエックス線写真を,再検討することを拒んだ。それは,
医学的証拠が今日も手のほどこしようがないほど混乱したままになることを保証した,
と,著者は言う。さらに,スタッフに,メキシコでつながる,シルビア・ドゥランの事情聴取をさせなかった不可解な命令も含まれる。
著者は,断言する。
もし…ケネディの司法解剖の写真とエックス線写真を再検討することをゆるされていたなら,医学的証拠と一発の銃弾説についての議論の多くはとうの昔に片が付いていたかもしれない。
第四は,ロバート・ケネディ。著者は,(ウォーレンより)
もっと大きな責任を負っている。
と言い,こう説明する。
ロバート・ケネディ以上に真実を要求すべき立場にいたものはいなかった(中略)。それなのに,ロバート・ケネディは,兄と自身の非業の死のあいだのほぼ五年間,ウォーレン委員会の答申を完全に支持しているとおおやけに主張し続け,そのあいだずっと家族と友人には委員会は勘違いをしていると確信しているといっていた。
ロバート・ジュニアは,その理由を,
兄の暗殺における陰謀の疑念をおおやけに生じさせることで,差し迫った国民的問題,とくに公民権運動から注意をそらすかもしれないと恐れていた,
と言う。
著者の辿り着いた真実は,
カストロ支持者だけでなくキューバの外交官もスパイも参加するダンスパーティにオズワルドが参加していたという事実だけだ。
しかしそこでは,おおっぴらに,
来客の一部が,誰かジョン・F・ケネディを暗殺してくれないか,
と口にしていたのだ。ケネディが必死で叩き潰そうとしていたキューバ革命の生き残りのために。
著者は言う。
事実は,われわれがパーティでオズワルドを見たということだ,
とその目撃者は,50年目に再度それを確認した。その大事な情報が,その当時,ウォーレン委員会に届くことはなかった。
ケネディ暗殺の陰謀説の一部は,とくに陰謀の法的定義を考えれば,それほど強引なものではない。それにはふたりの人間が悪事をたくらむことしか必要ではないからだ。ほかの人間がひとりでもオズワルドにケネディ暗殺を焚きつけていれば,定義上,陰謀は存在したことになる。
と著者の言うように,
使嗾の機会があったという事実は,大きい。
ところで,本書は,陰謀説の根拠となっているらしいことが,いかにいかがわしいデータから出ているか,を示している例がいくつか出ている。暗殺本で著名になったマーク・レインについても,レインからもらった電話で腹を立てた,地元新聞記者エインズワースがかけたいたずらが,大騒ぎになっていくエピソードを紹介している。
この記者は,現場にいて,三発の銃声と,その場にいた人が,教科書倉庫の上部を指差しているのを確認し,走り出して,警官射殺と逃げ込んだ映画館での逮捕を,そのとき目撃している。
著者は,ウォーレン委員会のスタッフたちの地道な,ひとつひとつ洗い出していく手際もきちんと紹介している。たとえば,オズワルドの収入と,支出を,きちんと洗い出している,オズワルドが遮蔽のために積み上げた段ボールについた指紋を特定する,オズワルドは,どこへ逃走しようとしていたのか。手にしていたバスの乗り継ぎ切符から何が推測されるか等々。
著者は,
わたしは委員会の当時若かったスタッフ法律家の大半には賞賛の念しかいだいていない。彼らは明らかに暗殺についての真実にたどりつこうと奮闘していた。
と付言している。
因みに,オリバー・ストーン監督,ケビン・コスナー主演の『JFK』のギャリソン検事を,上記の新聞記者エインズワースは,ギャリソンから電話を受けて,
イカれていると同時に,選挙でえらばれた高位の公務員が,ギャリソンが信じていると明言するばかばかしい話を信じられるという事実に不安を覚える,
と一蹴している。
参考文献;
フィリップ・シノン『ケネディ暗殺』(文藝春秋) |
|
機 |
|
渡邊大門『信長政権』を読む。
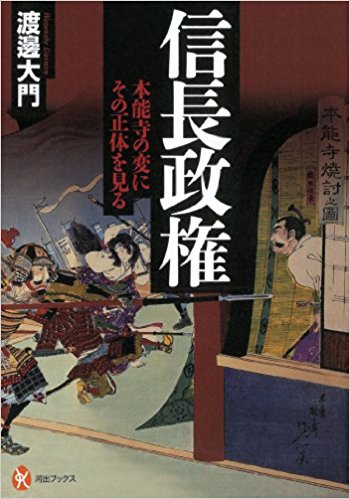
このところ連続して,読み逃していたのを拾い出して読んでいる。これもその一冊。
本能寺の変に焦点を当て,信長政権というものに迫っている。
著者の結論は,
信長の「天下一統」(あるいは戦争)の根幹には自己の権力欲と言う,極めてパーソナルなものがあった。「天下一統」後における展望や構想などがはっきりと見えてこない。…際限なき勢力拡大欲である。
信長の政権はパーソナルなものから出発したが,領土拡大とともに分国支配を配下の者に任せざるを得なくなった。そして,統治を任された配下の大名たちは,一定程度の自立性を保ち,領国支配などを行った。一見して信長独裁ではあるが,実体は多くの配下の大名たちに支えられていたのである。しかし,譜代や一門が優遇されたのに反して,外様は危機感を抱いていた。…荒木村重,別所長治はその代表であり,謀反の危険性は絶えず内包していたのである。意外と政権の基盤は,脆弱であったと言えるかもしれない。
と言う。そして,信長の対室町幕府,朝廷に対しても,それを潰そうとか,変えようとかとする姿勢はなく,
温存しながら自らの権力を伸長しようとしていた,
とみる。たとえば,義昭と交わした五カ条にわたる条書には,第五条に,
天下静謐のため,禁中への奉仕を怠らぬこと
を,義昭に求めている。著者は言う,
信長にとっての天下とは,少なくとも朝廷と幕府との関係を抜きにしては語ることができなかった。しかもその政策は意外なほど保守的である。
その意味で,本能寺の変の朝廷黒幕説はほとんど意味をなさないし,変後の光秀の行動を見る限り,突発的に決断したとみるのが妥当だ。
与力であるはずの,しかも娘婿でもあり舅でもある細川藤孝・忠興,筒井順慶が加担しなかったばかりではなく,摂津の,高山高友,中川清秀,池田恒興といった有力武将は誰一人積極的に加わらなかった。
光秀は,髷を切って出家した細川藤孝・忠興親子にあてた手紙が残っているが,そこでは,
摂津の国を与えようと考えているが,若狭がいいならそう扱う,
私が不慮の儀(本能寺の変)を行ったのは,忠興などを取り立てるためである,
等々と哀願に近い文面である。ここに計画性を見るのは難しく,著者が,
光秀が本能寺の変を起こしたのは,むろん信長がわずかな手勢で本能寺に滞在したこともあったが,他にも有力な諸将が遠隔地で戦っている点にも理由があった。彼らが押し寄せるまでには時間がかかると予測し,その間に畿内を固めれば何とかなると思ったであろう。こうした判断を下したのも,変の結構直前であったと考えられる。
と言うとおりである。しかし,
周囲の大名が積極的に光秀に加担しなかったところを見ると,光秀の謀反には無理があり,秀吉のほうに利があると考えたと推測される。
状況を見る限り,もともと無理筋の計画だったというほかはない。ところで,その光秀であるが,著者は,
これまで光秀は(室町幕府の)外様衆・明智氏を出自とすると考えられてきたが,それとは程遠い存在と言える,
のではないか,と名門の出自に疑問符を投げかけている。
つまり,幕府外様衆の系譜を引く明智氏ではなく,全く傍系の明智氏である可能性や,土岐氏配下の某氏が明智氏の名跡を継いだ可能性も否定できない。
と。つまりは,どこの馬の骨かははっきりしないということだ。だから,
いずれにしても当時の明智氏は,全くの無名の存在であった,
ということになる。だからこそ,変の直前の家中軍法で,
既にがれきのごとく沈んでいた私を(信長が)召し出され,さらに多くの軍勢を預けてくださった,
と,光秀自身が書いているのは,重みのある言葉なのだ。
光秀どころか,秀吉,滝川一益等々,信長家臣の多くは,氏素性のはっきりしないものが多い。著者は,高柳光壽氏の,
光秀の性格は信長に似ている,
を引き,こう付け加えている。
ちなみに秀吉も庶民派的な明るい性格のイメージがあるものの,実際は真逆であった。秀吉は戦場において磔刑を行い,抵抗するものには厳しい罰を科した。(中略)高柳氏が指摘するように,信長がこうした「アクの強い人物」を好んだことには注意を払うべきである。
主人は凶暴だが,部下もまた,それに似た凶暴な人物が集められている。つまり,世上言われるほど,光秀が,名門土岐氏出身の知識人というわけではないということだ。そういう先入観を取ってみれば,目の前の天下(ここでは中央すなわち畿内と意味)取りの千載一遇のチャンスを逃すはずはない,のではあるまいか。
参考文献;
渡邊大門『信長政権』(河出ブックス) |
|
総括 |
|
谷口克広『信長の政略』を読む。

著者は,労作『織田信長家臣人名辞典』をまとめた,市井の歴史研究家である。僕は昔から,結構ファンで,『秀吉戦記』『信長の親衛隊』『織田信長合戦全録』『信長軍の司令官』『検証本能寺の変』『信長と消えた家臣たち』『信長の天下所司代』『信長と家康』等々,ほとんど読んでいる。
本書の動機について,
『織田信長家臣人名辞典』という本が,私の実質上のデビュー作である。出されたのが1995年…その18年間に単著だけで20冊近くも信長関係の本を書かせていただいた。(中略)ただそれら20冊近い著作を振り返ってみて気が付いたのだが,信長について総括した概説書が一冊もない,
という「信長の政治の総括」,いわば,政策全体の概説というか評価というのが本書である。
で,
外交と縁組政策
室町幕府と信長,
朝廷と信長,
宗教勢力と信長,
という周囲との政略と,
信長の家臣団統制
信長の居城とその移転政策
信長の戦略と戦術
という統一選へ向けた政略と,
土地に関する政策
商工業・交通に関する政策
町に関する政策
という民衆統治に関する政策とで最後に総括につなげていく。
朝廷との関係にしても,室町幕府との関係でも,それを破壊するという革命性は薄い,と著者は言う。
信長にとって,律令制の官位というのは,名誉栄典として利用する以上のものではなかったと思う。天正三年十一月の権大納言兼右大将任官は,追放した足利義昭(権大納言兼征夷大将軍)を意識したものだったと思われるが,その後…拒否の姿勢もない代わりに,猟官運動の跡などまったくない。…信長自身の政治的地位は,官位体系とは別次元に存在していた…と(いうのが)正鵠を得た表現といえよう。
そして,足利義昭との関係も信長には義昭を排斥するつもりはなかったようで,人質の子息義尋も殺していない。
著者は,吉田兼和の『兼見日記』にある兼和との対話で,自分の天皇や公家の評判を聞いている信長の様子から,
将軍と対決しようとしながらも,その正義の拠りどころを天皇に求めようとしている信長の姿,また京都にいる貴族や庶民の中に形成された世論をも気にしている信長の姿が浮かび上がるであろう。
そして,
信長ぐらい世間の思惑=世論を気にした為政者はいない,
と言う。
いわゆる,楽市楽座も,別に信長が嚆矢とするわけでもないし,信長が座を安堵しなかったわけでもない。いわゆる兵農分離は,直属の馬廻衆ですら,安土城下での出火騒ぎで,家族を尾張の領地に残したままであることが露見したくらいで,意図とは別に,徹底できていたとは言えないようである。
当然検地も,太閤検地と比べようもなく,
荘園制の特性である重層的で複雑な収取権を否定しきっていない,つまり,中間搾取の形を残してしまっている,荘園領主と妥協した政策を展開した,
と。また,安土城をみるように,近世の城郭の端緒をなすものとの位置づけがなされてきたが,
防御機能はほとんど顧みられず,政治・経済の中心としての役割を置いた白とみなされてきた。だが,惣構えの土手の発見により,
少し様相が変わってきた。近世の城に惣構えなど存在しない。いわゆる戦国自体特有の惣構えのある城,ということになると,安土城の位置づけも変わってくるのである。
しかし,にもかかわらず,著者は,革命児には当たらないが,こう総評する。
信長は現実家なのであり,その基調は合理性にある。だから,「合理的改革」と呼ぶのが最も相応しいのではあるまいか。仮に本能寺の変で倒れず,いよいよ信長の下で統一政権が発足したならば,その改革は次々と成就していったものと思われる。(中略)信長は,途中で倒れるけれども,その成果は時代の豊臣政権,更に徳川幕府へと受け継がれていく,
と。そして,「たら」「れば」で,もし本能寺の変がなければ,四国,九州,東北が,軍門に降るのは,
おそらく三年ほど。五年とかかることはなかった,
と著者は推測する。
参考文献;
谷口克広『信長の政略』(学研パブリッシング) |
|
精神治療 |
|
中井久夫『[新版]精神治療の覚書』を読む。

あとがきで,精神科医の中里均氏が,
中井久夫氏はわが国の精神医療を変えてしまった。それまでは,精神医学に限らず内科学にせよ眼科学にせよ,すべての科目の教科書は,国内外を問わず疾患の成因病理の記述に厚く,治療については付け足しのように書かれているに過ぎなかった。
中井氏は常々それを嘆いておられた。だから氏の記述の最重要論点は常に治療論であり,成因論や精神病理的論考は,治療論を導くための助走に過ぎない。
と書いておられるように,実に,視野の広い,患者への治療姿勢が,細やかに書かれている。その一端は,中井氏と話をしながら,中里均氏が,
「精神治療とは美に入り細を穿って患者をサポートするものだ」と思い込んだ。幸せなインプリンティングだったかもしれない。氏の言行一致の態度が説得力を増幅した。中井氏以前の精神科治療の多くがもっと大雑把なものだと知ったのは,後になってからである。
そう中井氏の治療姿勢からの影響を,語っている。たとえば,その一端は,
一般に,患者は問題をいっぱいかかえており,急性精神病状態のおいては,問題に目を蔽うことができなくなっている。そのことは万々承知ではあるが,同時に急性精神病状態においては,一つ問題を解決している間に――解決できるとしての話だが――三つくらいはあたらしく問題が生まれている。「いま,あなたのかかえている問題を解決しようとすると,その間に問題がふえていないか。問題の中にはこちらが無理に解決しなくても問題のほうから消えてくれるものがあると思う。消えるものは消えてしまってよいのだし,それから残る問題を解決してもおそくないものが多いのではなかろうか。それに,よく休めた頭で考えることと,眠れない時の考えとは,ちがっているのを経験しないだろうか」という意味の助言はしてもよい…。患者と語ることばは,短い文章で,なるべく漢語が少なく,低声で,しかも平板でない音調のほうがよいと思う。ことばは途切れ途切れであってよい。錯乱状態でも,ちょうど台風が息をしているように,緩急はあるもので,この緩急のリズムをつかみ,それに合わせて語ると,意外に多くを語れるものである。時にはまったく押し黙っている患者の耳元で,「ほんとうは大丈夫なのだ。君はいまとうていそう思えないだろうけどね,ほんとうは大丈夫なのだ」とささやきつづけるよりほかにないこともある。この場合も決して馬の耳に念仏ではない。むしろ,患者は全身を耳にして聞いている,といっていいであろう。完全な緘黙不動不眠患者の隣室に泊まり込んで私は小さく壁をノックし続けたことがあったが,あとで患者は,私がずっと醒めていて,そのしるしを送りつづけていたことが判っていた,と話した。
と著者が語っている(「平板云々」は,後で触れる)が,前述の言行一致とは,これを指す。僕は,プロの覚悟と見た。中井は,これに続いて,
患者は決して堅い鎧をまとっているのではなくて,むしろ外部からの過剰な影響にさらされ続けている…。患者は粘土のごとく,無抵抗に相手の刻印を受け容れる…,
として,こんなことを書く。
精神科医の多くは思い当るふはしがあると思うが,再発を繰り返したり,長期に不安定な精神状態で治療を受けた歴史を持つ患者を新しく受け持つと,患者と話しているのか,過去に患者を診た精神科医たちのおぼろな影と対話しているのか分からなくなる。これは一種の,精神科医の憑依現象といってもよいかも知れない。…憑依しているものとされている人との仲は決してよいものではない。時には,自分の中に取り込まれてしまった精神科医と苦しい暗闘をつづけている人もある。(中略)患者と社会との接点は,ほとんと治療者一人に絞られていることを忘れてはならない。
と。この目配りは,具体的に治療行為になると,もっと広く,厚く,微細にわたり,なおかつ柔らかく優しい。
とにかく治療者は,“山頂”で患者と出会う。そうでないことは例外である。治療者は家族とともに下山の同行者である。(中略)重要なことは,本人と家族と治療者の三者の呼吸が合うかどうかである。この呼吸合わせのための労力はいくら払っても払い過ぎということはない。それが予後の最大決定要因であり,それを怠ると,最初の外泊時に両親がマラソンを強いたり,本人が職をさがしに出たりして,もっとわるいことに治療者がそれを知らないということが起こりうる。
この呼吸合わせに治療者はイニシャティヴをとらなければならない。本人も家族もあまりに深く病気という事態に巻き込まれているからである。(中略)医師はスペシャリストとして依頼をうけて事に当たるのであるが,必要なのは,絶対に加速してはならない過程と加速可能な過程とを見分けることである。加速してはならない過程を加速しようとして,本人を焦らせ,家族を焦らせ,そして医師当人が焦りの中に巻き込まれて,結局焦りの塊りが三つ渦を巻いて回っているだけという場合は皆無ではない。
で,必要なのは治療的合意であり,それには,
「本人と家族の呼吸が合わなければ治るものも治らない」という表裏のない事実を述べるべきだろう。実際この“呼吸合わせ”が成功し持続するかどうかで治療の九割は決まるといって差支えないだろう。「何か月で治りますか」と家族や本人がたずねても,医師はこの前提をくり返したのちに,もし見通しを述べるほうが望ましければ,述べるがよい。そして「この呼吸が合わない限り何回でも仕切り直しになりかねません」と告げるべきだろう。
と付け加える。専門外なので,あまり深入りはできないが,「聴く」について,書かれたくだりが,結構面白い。いくつか拾ってみる。
医学の力で治せる病気はすくない。医学は依然きわめて限られた力なのだ。しかし,いかなる重病人でも看護できない病人はほとんどない。(中略)急性精神病状態においては,医師の行為の大部分も看護と同じ質のものであろう。患者の側にだまって30分すわることのほうが,患者の語りを三時間聴き取るよりも耐えることがむつかしいことは,経験した者は誰でも知っていよう。しかし,おそらく,このことは精神科医の基本的訓練の一つとなるべきものだろうと思う。
「聴く」ということは,聞くことと少し違う。病的な体験を聞き出すということに私は積極的ではない。聞き方次第では,医者と共同で妄想をつくりあげ,精密化してゆくことになりかねない。
「聴く」ということは,その訴えに関しては中立的な,というか「開かれた」態度を維持することである。「開かれた」ということはハムレットがホレイショにいうせりふ「天と地との間には……どんなことでもありうる」という態度といってよいであろう。
「分かる,分かる」という応対は,ただ安易なだけではない。(患者は)「分かってたまるか」という感じとともに「すべてが見通しであり,すでに分かられてしまっている」という感じを…抱いている。(中略)この「言い当て」は患者の不安を増大する。(中略)時には患者がいわんとして表現がみつからず,ほとんどもがくように苦しむこともあるもので,その時は「あなたのお話をずっときいていると,ひょっとしたら,こんな風に感じているのではないかという気がするのだが」という前置きで,あくまで,他人の心中を憶測する際の慎みを忘れない態度で話すことは,一般に患者を楽にし,「分かられた」という受け身感がなく,やはり通じるのだという疎通感を生む…。
なぜ患者のそばに沈黙して坐ることがむつかしいのだろう。むつかしいことは,やってみればすぐわかる。(中略)患者の側に坐っていると,名状しがたい焦りが伝わってくる。…この焦りは,何に対する焦りという,特定の対象がはっきりしない。いや,そもそもないのかも知れない。患者はしばしば自分を「あせりの塊り」であると表現する。(中略)焦りは患者から伝わるようにみえるが,むろん治療者自身の中に眠っているものが喚起されるといっても一般にいいだろう。この二つはほとんど同じことかもしれない。沈黙思念のそばで治療者は一方では患者に目に見えないリズムの波長を合わせつつ他方では自分の持っている(そう豊かでもない)余裕感が患者に伝わるのをかすかに期待しようとする。そのほかに方法はなく,しかもこの時点で,治療者は―とにもかくにも―患者と社会のほとんど唯一の接点であろうからである。
傍らにいて,治療者が焦りを感じなくなることは,急性期が終わりを告げた,かなり確かな証拠である。
もうひとつ面白いのは,声で,聞き分けようとする姿勢だ。これも,聴くにかかわる(ここに,前述の平板云々への答がある)。
アメリカの精神科医,H・S・サリヴァンは,
訓練(トレーニング)の声
と
希み(デザイア)の声
というのを分けていたという。
「訓練の声」とは,音域の狭い,平板な声だろう,私は,妄想を語る時,音調がそのように変わること,逆に,そのような音調は,妄想を語っていることを教えてくれる…。一般弁論になる時,人間の声はそうなりがちである。数学の証明を読み上げる時,上司に問われて答える時,等々。それは防衛の声であり,緊張の声である。これに対して,
「希みの声」は音域の幅のひろい,ふくらみのある声だろう。患者にせよ,患者でないにせよ,自分の心の動きを自然に表現する時はそうなるものであろう。
と著者は書いている。そして,作曲家の神津善行氏の書いていた,
音域の広い人と狭い人とでは,同じことを語っていても,相手に受容される程度が大幅に違う,
を紹介して,音域が狭い人は人に反発を受けやすいのだ,という。
精神病患者の声は,ふだん後者であることが多い。切り口上や紋切型に属する声である。
という。それが普段から,対人関係の妨げになっていたのではないか,と想像している。そして,
時に患者から,音域の深々とした,あるいはしみじみとした,感情の籠った声が聞かれうることを聞き逃してはならないだろう。…まさに,そのような声を聞く時が急性期が終末に近づいたか,少なくとも,急性期からの脱出可能性が高まった一つのしるしである。
という。こうした目配りの細やかさには,驚かされる。
たぶん,精神科医にとってバイブルに他ならないということが,門外漢の僕にも伝わる。著者も,
学会に行くと,精神科医になった時に最初に読んだ本だと私に挨拶する人が結構いた,
というのはよくわかる。
出発がウィルス研究にある中井にとって,
病気のはじまりとか回復というのはどういう順序を追っていくかという研究に興味があった,
のは当然ながら,家族や患者への目配りも,ただごとではない。
その謦咳は,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/391584184.html
で触れた,最相葉月が『セラピスト』で詳しく書いているとおりだ。
参考文献;
中井久夫『[新版]精神治療の覚書』(日本評論社)
最相葉月『セラピスト』(新潮社) |
|
信長 |
|
池上裕子『織田信長』を読む。
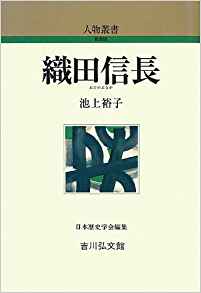
戦国大名の研究家である著者の「信長」伝である。いわば,最新の信長研究の成果といっていい。
著者は,先ず,
「信長許すまじ」と,平成のいまも眉をつりあげ,言葉を激する人びとが少なくなかった。(中略)北陸,東海,近畿,中国地方など,殊にその傾向がつよかったように思う。
瀬戸内の島々の人びとのなかには,信長勢と戦う一向衆の応援に水軍としてはせ参じた船の民の末裔があちこちにいて,ご先祖の船乗りたちがいかに水上戦で信長軍をほんろうしたかを,きのうのことのように唾をとばして語ってくれる人たちがいた…。
と,五木寛之が新聞に寄せた文を引用し,こう言う。
私はこの文章に深く共鳴し安堵の思いをもった。近年は,平和が勝者=権力者も含めて多数の希求していた絶対的な価値であるようにみなして,平和のために統一をめざし実現したから民衆に支持されたという権力象を描く立場もある。そうなると,信長や統一政権に抵抗した人々の立つ瀬がないのである。
それで思い出したのは,花田清輝が,
戦国時代をあつかう段になると,わたしには,歴史家ばかりではなく,作家まで,時代をみる眼が,不意に武士的になってしまうような気がするのであるが,まちがっているであろうか。時代の波にのった織田信長,豊臣秀吉,徳川家康といったような武士たちよりも,時代の波にさからった―いや,さからうことさえできずに,波のまにまにただよいつづけた,三条西実隆,冷泉為和,山科言継といったような公家たちのほうが,もしかすると,はるかにわれわれに近い存在だったのかもしれないのである。
そう皮肉っていたのを思い出す。
では信長は何をしたのか。
楽市楽座,
検地,
兵農分離
等々,信長が古い時代を打ち壊したというイメージが喧伝されるか,実は,楽市楽座も,検地も,北条氏を始め,他の戦国大名がすでに行っている。では,信長は何をしたのか。
信長の人物像を示すものとしては,ルイス・フロイスが『日本史』で言う,
きわめて戦を好み,軍事的修練にいそしみ,名誉心に富み,正義においては厳格であった。彼はみずからに加えられた侮辱に対しては懲罰せずにはおかなかった。…彼はわずかしか,またはほとんどまったく家臣の忠言に従わず,一堂からきわめて畏敬されていた。…彼は日本のすべての王侯を軽蔑し,下僚に対するように肩の上から彼らに話をした。そして人々は彼に絶対君主に対するように服従した。
著者は,信長の言動に合致するところが多い,と評する。
では信長は何をしようとしたのか。
天下布武
が有名だが,この段階,つまり美濃攻略後,岐阜城に移った時点での,
天下
は,当時の用法にならって,京都・畿内支配,を指していた。しかし,本願寺との和睦がなった頃,
天下一統
を使い始めたときから,天下は,全国に拡大する。そこで目指していたのは,
分国,
つまり自分の領国の拡大戦である。それは,家臣構成を見るとわかる。
領国が拡大するにつれて,数郡・一国の領域支配を,家臣にゆだねていく。たとえば,秀吉には,
江北浅井跡一職進退
出来るようにゆだねる。こうして拡大した織田の分国の,分国を家臣にゆだねていく。しかし,その大半は,織田一門か譜代の尾張出身者が占めている。わずかに美濃出身者がいる程度だ。そして,領国支配をゆだねられた家臣のうち,
尾張・美濃出身者で信長に離反したものはいない。信長との強い絆が形成されていたからであろう。
そう著者は言う。離反者は,
松永久秀,荒木村重,明智光秀,
だけである。その理由を,
信長の戦争は現地の武士を利用し,彼らを家臣に組織しつつ進められたのではあるが,結局のところ,戦国大名はもちろん,有力な国人・武将の多くを討ち滅ぼしたり,追放したりして命脈を絶っていく戦争であった。領国支配者=大名に取り立てられたのはほとんどが譜代家臣であり,現地の中小武士はその給人に編成されることによってのみ生き残ることができた。
だから,こう言い切る。
その意味では信長は旧い秩序の破壊者であったかもしれない。(中略)しかし,もっとも大きな破壊は人的破壊だったのではないだろうか。容赦のない殺戮戦を展開し,その後の信長譜代の直臣を大名にすえる。信長の分国とは信長と譜代直臣の領域支配体制であった。
その意味では,家臣の官位叙任に当たって,
羽柴秀吉が,羽柴筑前守,
明智光秀が,惟任日向守,
等々としたのは,譜代をその地域の(この場合は九州の)大名とする布石と考えれば,納得がいく。
戦国大名らの地域権力は信長のもとで生き残ることはできないから必死の抵抗を試みる。荒木村重や光秀のように信長に取り立てられても,譜代重用のなかでいつまでその地位が保てるかわからない不安がつきまとう。かすかな勝算に賭けて謀反に走るしかなくなる。謀反と頑強な抵抗は,信長の戦争,分国支配のあり方が生みだしたものである。
したがって,明智光秀の謀反も,村重の謀反の延長線上で,著者は捉えている。
本能寺の変の背景や原因を考える時,光秀が村重と似たような立場にいたことに思い至る,
と。村重は,播磨攻略の中心にいて,黒田孝高の活躍も村重が信長に伝えていた。それを突如秀吉にとって替えられた。
光秀は,四国の長宗我部の取次として,強いパイプを保ってきた。然し突如として四国攻略戦略が,三男信孝のもとで遂行されることになっていくのである。
戦功を積み重ねても,謀反の心をもたなくても,信長の心一つでいつ失脚するか抹殺されるかわからない不安定な状態に,家臣たちは置かれていた。一門と譜代重視のもと,譜代でない家臣にはより強い不安感があった。独断専行で,合議の仕組みもなく,弁明,弁護の場も与えられず,家臣に連帯感がなく孤立的で,信長への絶対服従で成り立っている体制が,家臣の将来への不安感を強め,謀反を生むのである。
と,著者が言う通り,これほど家臣の裏切り,謀反の多い戦国大名は珍しい。
最後に,著者は言う。
光秀の謀反は,村重らのように城に立て籠もるのではなく,信長を直接襲撃するという手段に出て成功できた。単独で極秘に策を練り,機を逃さなかったことが成功へ導いた。だが,それゆえに連携がなく,次への確かな展望と策を持つことができなかった。
この一語で,世にかまびすしい謀略説のすべてを粉砕している。上質な研究者の確信といっていい。
あとがきで述べている言葉も,なかなか含蓄がある。
信長の発給文書をみて気づくことは,信長自身は百姓や村と正面から向き合おうとしなかった権力なのではないかということである。郷村宛の禁制以外に村や百姓支配に関わって発給した文書はほとんどないのである。
あくまで,領主にのみ目が注がれ,そのために,
信長には農政・民政がない,
と。これもなかなか含蓄がある。家臣に丸投げしているのである。
基本的には命じられた本人が,戦術を練り,調略・攻撃を駆使して自己の責任で平定の成果をなるべく短期間であげることが求められた。そのために必要な兵力・兵粮・武器弾薬の調達は本人の責任である。
だから,築城,道路整備,,兵粮もふくめた百姓の陣夫,夫役は,家臣たちがしている,ということになる。信長は,
百姓らの負担がどれだけ過重かは関知しない。
その意味で,極めて危い土台の上に成り立っていることがよく分かる。
恵瓊の有名な予言,
信長の代五年・三年は持たるべく候,明年辺りは公家などに成らるべく候かと見及び候,左候て後,高ころびにあをのけにころばれ候ずると見え申し候,
とは,そんな信長体制の危うさを見抜いたものと言えそうだ。
参考文献;
池上裕子『織田信長』(吉川弘文館)
花田清輝『鳥獣戯話』(講談社文芸文庫) |
|
セラピスト |
|
最相葉月『セラピスト』を読む。
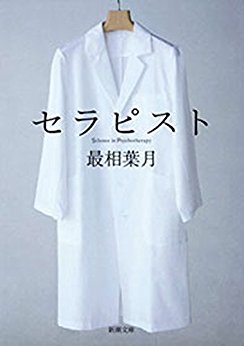
経糸に精神科医・中井久夫の絵画療法とユング派分析家・河合隼雄の箱庭療法を,緯糸に,戦後ロジャーズが持ち込まれて以降のカウンセリング史,彩りに,ご自身のセラピー体験を織り交ぜた,言ってみると,日本のセラピーの現状を,見事なタペストリーに織り上げている。
『絶対音感』の著者による,セラピーそのものへの肉薄である。そのために,著者は,取材を続けながら,
臨床家を目指す人々が通う大学院に通い,週末は,臨床心理士を始め対人援助職に就く人々が通う専門の研修機関で共に学びながら,臨床家になるための,またプロフェッショナルの臨床家であり続けるための訓練の一端を知ろうと考えた…。
この動機を,こう語る。
自分のことって本当にわからない―。そう。自分のことって本当にわからない。
そもそも私はなぜ専門機関に通ってまでこの世界を知りたいと思ったのだろう。私の内面にどんな動機や衝動があったのだろう。
守秘義務に守られたカウンセリングの世界で起きていることを知りたい。人はなぜ病むかではなく,なぜ回復するかを知りたい。回復への道のりを知り,人が潜在的にもつ力のすばらしさを伝えたい。箱庭療法と風景構成法を窓とし,心理療法の歴史をたどりたい。セラピストとクライエントが々時間を過ごした結果,あらわれる景色を見たい…。
まさにそのようにまとめられた著作になっている。
この問題意識にぴったりだったのが中井久夫である。中井は,河合に刺激を受けて,独自の絵画療法を工夫していく。
中井は当時,精神科医になって四年目。…患者が寡黙になる回復過程に絵画が使用できないものかと試行錯誤していた。(中略)中井が病棟を歩きながら思い描いていたのは,個別研究を通して(回復過程の)モデルを作ることだった。
その成果である「精神分裂病者の精神療法における描画の使用―特に技法の開発によって作られた知見について」で,精神医学における二つの問題を指摘している。
第一に,臨床では,なによりも徹底した研究が不足し,一般化への指向性が希薄であること,
第二に,分裂者の言語が歪められていること,
精神病理学の歴史はこれまで,患者の言語の歪みを切り取って妄想と名付け,これがいかに歪み異質であるかばかりに着目してきたけれど,臨床においてはむしろ,言語的であれ,非言語的であれ,治療者と患者がいかにして交流を可能にするかのほうが重要である。描画もこれと同じではないか。精神科医は患者の描画の異質さや特殊性にばかり注目してきたが,本当に重要なのは,意志と患者がいかにして描画で交流することができるか。
中井はそう考え,
治療者として患者にどう向き合うか,
を心掛ける。そして,箱庭療法からヒントを得て創案した「風景構成法」を,この論文で発表する。
箱庭は統合失調症の患者に使うには慎重でなければならない,という河合の紹介を受けて,
患者に箱庭療法をしてもらってよいかどうか,その安全性をテストする方法として,また,紙の上に箱庭を造るに,三次元の箱庭を手っ取り早く二次元で表現する方法として編み出した,
のが風景構成法である。この研究を踏まえて,
精神分裂病状態からの寛解過程―描画を併用した精神療法をとおしてみた縦断的監察
という,通称「寛解仮定論」をまとめる。
従来,統合失調症の精神病理学では発病の過程は多く観察されて記述されているのに,寛解(回復)の過程にはあまり関心が向いていない。中井は,統合失調症の患者に向き合って判明した事実を解説したのである。
そこでは,中井は,
沈黙に耐えられない医者は,心理療法家としてダメだと思います(山中康裕は10分間の沈黙を中井に陪席して体験している)
患者さんは,沈黙が許容されるかどうかが,医師を選ぶ際の一つの目安だと思っている…。
という姿勢であり,山中は,
中井の診察風景はまるで「二人の世界」だったとして,
こう言っている。
絵を描いてくださいというのではなく,流れの中にある。道具もわざわざ別の所からだしてくるのではなく,手元にあるものをさっと出して,ちょっと描いてみない,と誘う。とても自然です。患者が描いている間は,ほほ−,ほ,ほ,といって鑑賞する。上手下手の評価はせず,二人の世界で遊んでいるという感じでした。
この雰囲気を,著者は,一度は,クライエントとして,二度目は,中井をクライエントとして体験する。それが,逐語として載っている。著者は,
中井と行った絵画療法の逐語録を配置したのは,ふだんなら削除してしまう間や沈黙,メタファーで語り合う場の空気を感じとっていただきたいと思ったから…,
というが,読む限り,その雰囲気は,独特で柔らかである。
中井は,こう書いている。
絵を媒介にすると,治療関係が安定するのです。言葉の調子,音調が生かせるのです。ナチュラルな音調を交わすことができて,自然に気持ちが伝わる。
言葉はどうしても建前に傾きやすいですよね。善悪とか,正誤とか,因果関係の是非を問おうとする。絵は,因果から解放してくれます。メタファー,比喩が使える。それは面接のとき,クライエントの中で自然に生まれるものです。絵は,クライエントのメッセージなのです。
でも,それが一番わかるのは,不眠に悩む外来患者を見送る際,こう声を掛けるのだというエピソードだ。
「今晩眠れなかったら明日おいで。眠れたらせっかくの眠りがもったいないから明後日でもよいけれど」
こういう中井の姿勢というか態度に,いままでになかった精神療法の先達を見る。
著者の言う通り,箱庭療法や風景構成法は,数ある心理療法の一つでしかない。しかも,増大する心の病に対応するには,昨今はやりの認知行動療法やブリーフ・セラピーに比べて,時間がかかりすぎるかもしれない。
しかし,箱庭療法と絵画療法は,患者に向き合う中から日本独自に完成された療法である。そこには,第一級の河合隼雄と中井久夫という巨人の,真髄がある。
そう言えば,神田橋條治さんが,よく中井久夫のことを,尊敬をこめて言及していたのを思い出す。
読んでいて,確かにブリーフ系というかミルトン・エリクソン系譜に言及がないが,精神科医に焦点を当てたのだからやむを得ないという以上に,噂には聞いていたが,巨人,中井久夫の謦咳に接した気がして,アマゾンで,予約中の『新版・精神科治療の覚書』(中井久夫著)を,思わす速攻で購入予約してしまった。
参考文献;
最相葉月『セラピスト』(新潮社) |
|
謀略 |
|
鈴木眞哉・藤本正行『信長は謀略で殺されたのか』を読む。

鈴木眞哉,藤本正行両氏が,本能寺の変を巡る,百家争鳴ただならぬ中で,謀略説をまとめて撫で斬りにしている。まあ,気持ちいいくらい,一刀両断である。因みに,藤本正行は,桶狭間の奇襲説を,『信長公記』を読み込んで,正面突破と初めて主張した人だ。いまそれが定説になりつつある。
もともと戦前は,明智光秀の単独犯,
を,あまりにも自明の事実として,
ほとんど謀略説はなかった。そこへ,例えば,
足利義昭黒幕説
イエズス会黒幕説
朝廷黒幕説
を代表に,
明智光秀無罪説,羽柴秀吉黒幕説,徳川家康黒幕説,毛利輝元黒幕説,長宗我部元親黒幕説,本願寺黒幕説,高野山黒幕説,酒井証人黒幕説等々,
まあ後を絶たないというか,こんなに日本人は,謀略だの黒幕だのが好きなのかと思うほどだ。
そこで著者らは,
本能寺の変の実態を再検討する,
ことから始め,それを踏まえて,
個々の「謀略説」が成立するものかどうかをチェック
し,そのポイントに,
実証性があるかどうか,
をおいた。そして,
それぞれの説が論理的な整合性をもっているかどうかも重要だが,単に表面上,理屈があっているかどうかでは足りない。常識的にみて納得できるかどうかが問題あある,
とする。しごく当たり前で,オーソドックスなアプローチだといっていい。素材は,『信長公記』だけでなく,本能寺襲撃に加わった明智の下級武士の覚書,「本城惣右衛門覚書」,ルイス・フロイスの『日本史』等々。
そして,「謀略説に共通する五つの特徴」として,こうまとめる。
①事件を起こした動機には触れても,黒幕とされる人物や集団が,どのように光秀と接触したかの説明がない,
②実行時期の見通しと,機密漏えい防止策への説明がないこと,
③光秀が謀反に同意しても,重臣たちへの説得をどうしたのかの説明がないこと,
④黒幕たちが,事件の前も後も,光秀の謀反を具体的に支援していないことへの説明がないこと,
⑤決定的な裏付け資料がまったくないこと,
そして,こう問う。
この事件が,あの時点,あの場所,あの形でなぜ起きたのか,
と。そして,
結論を言えば,光秀の謀反が成功したのは,信長が少人数で本能寺に泊まったからだ。そういう機会はめったにない。また,光秀が疑われることなく大軍を集め,襲撃の場所まで動かせる機会もめったになかった。光秀にとってこれらの好条件が重なったとき,初めて本能寺の変は成功したのである。すなわち本能寺の変は,極めて特異な〈環境〉の下でしか発生しなかった事件なのである。
そのことを予想して謀略をめぐらすことはできない,と著者は言うのである。その絶好の条件は,
光秀自身が作ったものではないということ,
さらに,
彼以外の特定の誰かが作ったものでもない。光秀が中国出陣を命ぜられたのは,その直前に秀吉から信長への援助要請が届いたからだ。また,他の武将たちがすべて京都周辺から離れていたことも,織田家の内部事情によるものであり,光秀を含めて特定の誰かが工作した結果でもない。
つまりこの好機は,天正十年五月の後半に突然飛び込んできたものなのだ。当然謀反の準備はこの時から始まったと見なければならない。こうした事実は,謀反を計画した真犯人が別にいたとする謀略説に,決定的なダメージを与えるものである。
と述べ,むしろ,光秀という人物像を,改めるべきだと指摘する。ルイス・フロイスは,『日本史』で,
裏切りや密会を好み,刑を科するに残酷で,独裁的でもあったが,己を偽装するのに抜け目がなく,戦争においては謀略を得意とし,忍耐力に富み,計略と策略の達人であった。また築城のことに造詣が深く,優れた建築手腕の持ち主で,選び抜かれた戦いに熟練の士を使いこなしていた,
と評している。光秀を,
古典的教養に富んではいるが,どこか線の細い常識家で,几帳面ではあるが,融通のきかない人物,
とするイメージを払拭すべきだと,主張する。フロイスの示す,
一筋縄ではいかない,したたかで有能な戦国武将,
というイメージで見るとき,光秀が,実質「近畿管領」(高柳光寿)というべき地位にあり,畿内の重要地域を任されていたという意味で,
光秀と信長は馬が合う人間だった,
とする高柳氏の指摘を注目すべきだ,指摘している。そして,こういう言葉には,説得力があるように思う。
光秀が絶対に失敗を許されない立場にいたことを忘れてはなるまい。フロイスの『日本史』に,光秀が重臣たちに謀反を打ち明けたあとの行動について,「明智はきわめて注意深く,聡明だったので,もし彼らの中の誰かが先手を打って信長に密告するようなことがあれば,自分の企てが失敗するばかりか,いかなる場合でも死を免れないことを承知していたので」直ちに陣容を整えて行動を開始したとある。
これこそ,常識的な見方といっていい。そして,朱子学的な順逆の価値観を捨ててみれば,光秀の決断は,下剋上の戦国時代において,別段特異な現象ではないことがわかるはずである。
目の前に天下(この場合,日本全国ではなく,中央部分,すなわち畿内を指す)を取れる機会があるのを,むざむざ見逃す手はない,ということなのではないか。
参考文献;
鈴木眞哉・藤本正行『信長は謀略で殺されたのか』(歴史y新書) |
|
向き合う |
|
柴山哲也『日本はなぜ世界で認められないのか』を読む。

答は,ここにある,と思った。
著者は冒頭で書く,
…世界企業ランクと大学ランクの低迷ぶりを比較するだけで,日本の「失われた20年」の内容がはっきり見えるようだ。
日本はもう世界に冠たる経済大国でも技術大国でもない。下手をすると衰亡するに任せた国家ということになってしまいかねない。これこそ日本人の多くが直面せざるを得ない淋しい現実だということを,深く認識すべきなのである。
未だにモノづくり大国という。世界のどこへ行っても家電製品は,棚の隅に追いやられ,シェアは微々たるものになっている。そういう現実をきちんと見るところからしか未来はない。しかし,いまやられているのは,公共事業へのじゃぶじゃぶの税金の投入であり,円安誘導による企業の業績支援であり,武器三原則を放棄しての武器輸出である。それは,裏を返すと,日本は,重厚長大の,そんな武器にしか輸出の活路はないのか,ということなのかと疑いたくなる。
どうしてこんな体たらくになったのか。
著者は,さまざまな現実に向き合わず,糊塗してきた結果だと言いたいらしいのである。
福島の原発事故(ドイツでは汚染水漏れは事故と呼ばず原発スキャンダルと呼んでいるらしい)二度被曝した日本は,安全神話にすがったというが,実はそれだけではない。
…敗戦で植民地を失ったイタリア,ドイツが脱原発が進行した最大の理由は廃棄する処理場がないことだった。
と著者が指摘するように,小泉元総理の言う最終処分場がないままでは,原発は限界が来る,という現実を,政治家も,ジャーナリズムも,国民も,見ないふりをしてきた。本来,すでに行き詰っている,にもかかわらず,再稼働,新設へと舵を切ろうとしている。
米国第三代大統領のジェファーソンは,「新聞の批判の前に立つことのできない政府は崩壊しても仕方がない」といった。
しかし,日本では,沖縄密約事件もそうだが,新聞自体が,政府の矢面に立たない(立ちかけた毎日は,週刊新潮と世論によって倒産の憂き目にあった)。まして,政府は批判など,馬の面にションベン,解釈改憲で,人を戦場へ赴かせ,人を殺し,殺されるという状況を,実現しようとしている。そして,その事実に多くの国民は,目をそらしている。
すでに,津波前に地震で原発が破損していたという情報が出始めているが,かつて東電内部で,津波と原発への影響を分析し,国際会議に英文レポートとして報告されていたと言われる。それも,東電も政府も握りつぶしてきた。
著者は言う。
日本も民主主義を標榜しているのだから,たとえ政府や東電が嘘をつき間違ったことをしていても,メディアがしっかり監視していれば,国民へのダメージは最小限度に食い止めることができる…,
と。しかし日本のメディアは,記者クラブの囲い込みを出ない。記者クラブは,戦時下の,国家総動員法に基づいて
国家統合されたときにできた戦時体制の持続だ。いわば,大本営発表をそのまま報道する,というのに近い。いま,その悪癖から脱しているとは到底言えない。
著者は,自分の体験で,米国人も,中国人も,韓国人も,
いくら金持ちになっても,過去の罪から逃げている日本人を心の底のどこかで軽蔑している,
と。たとえば,
そうしないと,広島,長崎の被爆の歴史も相手にはなかなか通じなくなる。原爆投下は自業自得ではなかったか,という反論に出会っても,沈黙せざるを得なくなることがある。
真珠湾奇襲は,アメリカ人にとって,パールハーバー・シンドロームとして,何かあると,湧き上がってくる。9.11では,「第二のパールハーバー」と,ニュースキャスターが叫んだ。ことほど左様に,
普段の米国人は日本人に対して,…敵愾心は持っていない。…しかし自動車摩擦や経済摩擦がこじれたときや日本製品がアメリカ市場を席巻して米国の労働者の雇用などにつながったりすると,,米国のパールハーバー・シンドロームは突如,再燃する。
しかしわれわれ日本人は,ほとんど奇襲やパールハーバーでの戦死者のことを思い出しもしない。ただの手違い程度だと思っている。
本当にそうか。誰も真摯にそのことを突き止めようとはしてきていない。真珠湾奇襲についてさえ,これである,他は推して知るべしだ。
本当にそれでいいのか。著者は問う。
それにしても日本はなぜ大東亜戦争を始め,なぜあのような無残な敗北を喫するに至るまで戦争をストップさせることができなかったのだろうか。その根本を問うことが,今こそ必要になってきた。
実は,日本の戦争責任は連合国による東京裁判で裁かれてはいるが,日本自身の手によって総括したことはない。このことは,日本が国際的に認められない最大の原因になっている。
と指摘する。最近ドイツでは,収容所の看守が逮捕された,というニュースが流れた。90歳を超えている。その姿勢である。かたや,日本では,A級戦犯が首相になっいる。この違いは大きい。
90年代の「失われた十年」は,二十一世紀にはいると,「失われた二十年」へと延長され,2010年代になると,「失われた三十年」が取りざたされるようになった。
しかし,政府も企業も,非正規雇用を増やし,人件費削減にただ走り,結果として,人材を枯渇させ,あらたな事業開発が鈍化し,さらなるリストラに走り…と,ただ貧困を増幅しただけだ。
海外諸国の目に対して鈍感で,海外からの批判にも耳を傾けず,自画自賛をくり返し,内部改革を拒否し続けた日本が,近隣の中国や韓国に追い抜かれるのは,当然の帰結だった。
著者の言は,耳に痛いが,今の現状を直視する王道以外,失われた何年を克服する手立てはない。しかし,いま政府がやっているのは,過去踏襲の公共事業による景気浮揚であり,お札の増刷によるデフレ脱却だ。
そうやって生き残るのは,もはや競争力のない古い体質の企業だけだ。本来体質改善すべきこの機に,先延ばさせているだけだ。企業の自己革新と体質改善を促すには,今のように,企業を甘やかす円安政策は,逆効果でしかない。
結局,明治維新以来,一度も自主的に自己変革したことのない体質は,今回もまた続くのではないか。しかし,それは,国の衰亡しか意味しない。
参考文献;
柴山哲也『日本はなぜ世界で認められないのか』(平凡社新書) |
|
社会構成主義 |
|
ケネス・J・ガーゲン『あなたへの社会構成主義』を読む。

冒頭著者は宣言する。
今,世界中で,さまざまな学問の壁を越えた刺激的な対話が始まっています。それがいったいどのようなものかを,ぜひ,読者のみなさんに伝えたいというのが私の願いです。……それは,16世紀から17世紀に起こった,思想や実践の大きな転換…にも匹敵します。なぜならば,その対話は,私たちが「これは事実である」「これは善い」と考えているすべてのものの基盤を根底から揺さぶるだけではなく,クリエイティヴな考えや行為を生み出すまたとない機会を提供するものだからです。
ここで言う対話,こそが,キーワードである。事実も,価値も,我々の外にあるのではなく,我々自身の対話のなかで生み出している,これが,僕の理解した社会構成主義の肝である。それは,どこかに正解があるのではなく,正解はわれわれ自身が創り出している,ということになる。その意味では,専門性や科学性の権威性そのものを,民主化する,というような意味がなくもない。
この画期を,ポストモダンから,説き始め,それを三つに整理するところからスタートする。
第一は,言葉は現実をありのままに写しとるものではない。
第二は,価値中立的な言明はない。
第三は,記号論から脱構築へ。
第三は説明がいるでしょう。これは,ソシュールの,「意味するもの(シニフィアン)」と「意味されるもの(シニフィエ)」の関係は恣意的であり,「降っている雪」を「雪」とよぶのは,たまたま偶然にすぎない。とすると,
あらゆることばがいかなるシニフィエ―対象,人,できごと―でも意味しうる…,
ということになる。そして,もうひとつ,
記号のシステムはその内的な論理に支配されている,
ということをソシュールは言った。ということは,
言語の使用が内なる論理によって決められているということは,「意味」が言語の外の世界から独立したものである,ということを意味する,
ということになる。言語の脱構築を理論化したデリダは,
第一に,すべての有意味な行為は―合理的な決定をする,人生における重大な問題に対してよい答えを出す―はすべて,あり得たかもしれない多様な意味を抑圧することによって成り立っている,
第二は,私たちが行うすべての決定は,たとえいかに合理的に見えても,合理性の根拠を突き詰めてていけば必ず崩壊する可能性をはらんでいる,
と,その不確かさを説明している。それへの一つの答えを,ヴィトゲンシュタインは,
言語ゲーム
というメタファーで示した。どんなゲームにも(自己完結した)ルールがあるように,言葉の意味もそれと同じだと,ヴィトゲンシュタインは,言う。
言葉の意味とは,言語の中でその言葉がいかに使用されているかということ,
である。つまり,言葉は,言語ゲームのなかで用いられることによって,その意味を獲得していく。
それは,言語が事実や心を写す道具ではなく,
言葉を用いてものごとを行っている,
のであり,
相手と一緒に何かを行っている(パフォーマンスに加わっている),
のであり,その中で意味が生まれてくる。つまり,
状況を超えた事実というものは存在しない,
事実はある,ただし,常にある特定の限られたゲームの中に,事実はある,
ということになる。
こう言うことを前提に,社会構成主義は四つのテーゼをもつ。
第一は,私たちが世界や自己を理解するために用いる言葉は,「事実」によって規定されない。
第二は,記述や説明,そしてあらゆる表現の形式は,人々の関係から意味を与えられる。
第三は,私たちは,何かを記述したり説明したり,あるいは別の方法で表現したりする時,同時に,自分たちの未来をも創造している。
第四は,自分たちの理解のあり方について反省することが,明るい未来にとって不可欠である。
第三は,我々の未来が過去ではなく,
人と話したり,何かを書いたりしているまさにその瞬間にも,私たちは確かに未来を創造している
のであり,そのためには,
与えられた意味を拒否する―例えば,性差別者や人種差別者の言葉を無視する―だけではだめで…,それに代わる新しい言葉や,新しい解釈や,新しい表現を生み出さなければなりません,
と言い,それを生成的言説,と呼ぶ。結局社会構成主義は,
事実や全を,社会的なプロセスの中に位置づけ,我々の知識は,人々の関係の中で育まれるものであり,個人の心の中ではなく,共同的な伝統の中に埋め込まれていると考えている。したがって,社会構成主義は,個人よりも関係を,孤立よりは絆を,対立よりも共同を重視する,
という。その点から見ると,二つのポイントが特筆される。
第一に,心理的な言説は,内的な性格な記述ではなく,パフォーマティヴなものである。が,「愛している」ということで,ある関係を,他ではない特定の関係として形づくっている。
例えば,「愛している」を「気になる」「敬愛している」「夢中だ」と言い換えると,関係が微妙に変わる。だから,こうした発話は,単なる言葉ではなく,パフォーマティヴな働きをしているのである。
第二は,パフォーマンスは関係性の中に埋め込まれている。このパフォーマンスには,文化的・歴史的な背景を取り入れなければ何の意味も持たない。つまり,私があるパフォーマンスをするとき,さまざまな歴史を引きずり,それを表現している。言い換えると,文脈に依存している,ということになる。
ある人のパフォーマンスは,必ずある関係の構成要素である,
ということになる。
しかし,ここから疑問がわく。
関係性の中で,自分が依存している限り,確かに,
記憶やその他の心のプロセスが集合的なものであることは,いいかえれば,それらが共同体の中に配分されている,
ということは認めるし,感情も価値も,そうかもしれない。ヴィトゲンシュタインの言うように,
理解(や判断もそうかもしれない)を,心のプロセスとして理解しようとしてはいけない。……その代り,自分自身にこう問いかけてみなさい。私たちは,どんな時に,あるいはどのような状況において,「どうすればいいか,わかったよ」と言うのか,と。
意味を個人の心に閉じ込めるのではなく,人々の相互関係の中に位置づける,
と。それを,僕流に,
関係性の反映,
と呼ぶとすると,しかし,一人一人の脳のなかでの,
関係性の記憶,
というか思考のプロセスは,イコールではない。一人一人が考えていることは,文脈とイコールではない。人によって,異なる。
たしかに,
私はたった一人では,何も意味することはできません。他者の補完的な行為を通してはじめて,「私は何かを意味する」力を得る,
というのはわかる。しかし,社会構成主義の四つのテーゼの言う,第四の,
理解のあり方について反省する,
という,その反省の主体は,誰なのか。結局,この主体なくしては,対話も,反省もない。
この「私」
を「我思うゆえにわれあり」の「われ」を主客二分として,葬り去ったところから,社会構成主義はスタートしたと強調するが,しかし,反省する主体,会話する主体なくして,ゲームが成立するのか。その主体は,ゲームの単なる駒なのか。とすれば,関係性が紡ぎ出す中で,ただ紡がれていればいいのか。
関係性の他者は,主体あってこそ,他者ではないのか。
例えば,こう言っている。
私たちの現実が,他の人々に耳を傾けられ,肯定されて,会話がますます調和したものになった時,変化力をもつ対話へ向けてのさらなる動き―「自己内省」―が生じる可能性が生まれます。モダニズムの伝統として,私たちは常に「統合された自我(ego)」として会話の中に位置づけられています。つまり,私たちは,単独の首尾一貫した自己として構成されています。そのため,論理的あるいは道徳的な一貫性がない人は,人々の軽蔑の対象になりますし,私たちは自分と立場を異にする人々に対して,自らの意見を,ほころびのない織物のように作り上げようとします。したがって,私たちがいったん対立関係に入り込んでしまうと,私たちの距離は決して縮まることがありません。
その関係性に対して,
自らの立場を疑問視する試み―つまり「自己内省」への会話によって,異なる声を受け入れて,多声性を取り入れる会話がいる,と述べる,
その内省する主体である。たった一人のときでさえ,特定の文化に根差した話し方をしているにしても,その主体は,何なのか。統合された自我を否定しながら,そこは,スルーしている。いまある現状をそのままにしていくのか。普通の日常で,人と接している自分を,そのまま前提にするのか。
個人主義的な自己に変わって,関係性の中の自己,
という,その自己のことである。これについては,僕の読んだかぎり答えが見えなかった。
それを無批判に使っている,というところが気になった。それなら,例えば,
自己は,相手から認知されることで存在する,
と徹底的に置き換えてみる。しかし,それでも,そを認知し,受け止める「自己」とは何か,
答が先のばしというか,スルーされたままのような気がする。
僕は,自己について,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388611661.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/389704147.html
書いた。しかし…!
参考文献;
ケネス・J・ガーゲン『あなたへの社会構成主義』(ナカニシヤ出版) |
|
原発 |
|
内藤克人『日本の原発,どこで間違えたか』を読む。

本書は,1984年刊の『日本エネルギー戦争の現場』その文庫版『原発への警鐘』(1986年)の部分復刻である。
ある意味安全神話という塗装メッキがすでに,30年も前に剥がされていたのである。
序で,著者はこう書く。
巨大複合災害に打たれてそのとき,私たちの社会はなおも「原発122基構想」(2030年時点の達成計画)へ向けて疾駆する途次にあったのである。
安倍政権は,その構想の復活を図っている,と言ってもいい。また中断した構想を継続しようとしている。
一度決定すると,容易に変更できない体質は,戦前と変わっていないと著者は言う。そう,もはや大鑑巨砲時代が終了したのがわかっていたのに,戦艦大和を作り続け,特攻としてしか使い道のないしろものでしかなかった。著者は,戦史研究家の,戦争突入についての,
意思決定が遅く,一度決定すると容易に変更できない。なんとなれば,変更にはまた(決定までと)同じプロセスを必要とするからだ。つまり状況の変化が万人の目に明らかになって,初めて決定を変更する…,
を引用するが,僕はそうは思わない。それは,そうすることで利益を得,得をするものがいる利権構造だからではないのか。万人の目に変化が明らかになっていても,その変化を見ず,再稼働,新規建設に邁進するのは,そういうこととしか思えない。
著者は,冒頭で,三点を指摘する。
第一は,「この国においては,人びとの未来を決める致命的な国家命題に関してさえも,『国民的合意』の形成に努めようとする試みも,政治的意思さえもほとんど見受けられることはなかった。国の存亡にかかわるエネルギー政策が,原発一辺倒に激しく傾斜していった過程をどれだけの国民が認知し同意していたであろうか」。
第二に,これまで原発一極傾斜大政を推し進めてきた原動力のひとつに,あくなき利益追求の経済構造が存在していたことだ。原発は建設は重電から造船,エレクトロニクス,鉄鋼,土木建築,セメント…ありとあらゆる産業にとって大きなビックチャンスであった。
第三に,これは著者の個人的感想にすぎないにしても,…ひとたび原発が立地した地域社会には特有の「暗さ」が感じられたことだ。そうした地域では原発が立地するまでは活発であった賛否の声は消え,地方議会においても反対派はほぼ淘汰の憂き目に逢っていた。地域の住民たちは雇用の機会を得たことの代償に,あるいは迷惑施設料(「電源三法交付金」)など「原発マネーフロー」の僅かな余恵と引き換えに,原発については「黙して語らない」を信条と強いているかのようであった。
原著の序で,著者はこう警告していた。
音もなく,臭いもなく,色もなく,そして何よりも,人の死に関してもたらされるものが“スローデス(緩やかな晩発性の死)”である。十年,二十年かけてゆっくりとやってくる。“見えざる死”にたいして,ひとは無防備で,弱い,
と。それはいま福島で,日々人体実験が行われつつある。
原発の絶対安全神話は,仮定で成り立っている。T65Dと呼ばれる推定値である(1986年に
DS86に,2003年新しい線量推定方式としてDS02になっているが)。これは,広島長崎での被爆者の発病率から推定された暫定値だが,その十分の一以下でも人定に影響がある,という説が出ていたが,このT65Dが独り歩きをして権威性を帯びていく。ICRP(国際放射線防護委員会)勧告の年間5レムという数値は,この推定値から割り出されたものだ。これが間違っていれば,すべてが崩れる。いずれにしても,仮説にすぎない。仮説にすぎないものにすがって,安全が神話化されている。
マンクーゾ博士は,闇に葬られた「マンクーゾ報告」で,
原子力発電所で働く作業者の被爆線量は年間,0.1レム以下に抑えるべき,
と。実にICRPの50分の一と指摘していたのだ。彼は言う,
放射線被ばくというのは,時間をかけて徐々に表れてくるものです。(中略)二十年も三十年も結果が出るまで時間がかかるんです。
そしていう。
スローデスを招くんです。死は徐々にゆっくりやってくるんです,
と。そういえば,第五福竜丸に乗っていたマグロはガイガー計数管でも測れるほど高い放射能をもっていたのに,サンプルの海水は低い数値して示さなかった。
自然にある放射能と人口のそれとの違いは,生体内に蓄積されていく,ということなのだ。そして,その体内被曝は物理的には測れない。
つまり結果が異常となって体に現れるまでわからない,ということなのだ。しかも,それは,十年,二十年とかかる。
いま福島,だけではない,日本全体が生体実験の真っ最中なのだ。これだけの危機を,国民的な合意もないまま,招きながら,そして,いま福島第一原発で,正確に何が起きているかもわからないまま,汚染がまき散らし続けられ,再度原発を稼働させようとしている。
これはエネルギー問題ではない。国のあるいは,国民のあり方,将来にかかわる問題なのである,とつくづく思う。
参考文献;
内藤克人『日本の原発,どこで間違えたか』(朝日新聞出版) |
|
違い |
|
テリー・ピショー&イボンヌ・M・ドラン『解決志向アプローチ再入門』を読む。
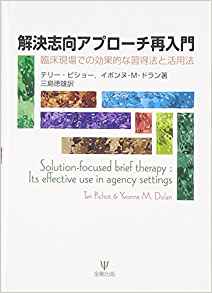
ソリューション・フォーカスト・アプローチ(SFA)については,何度も触れたが,最近では,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/388984031.html
http://ppnetwork.seesaa.net/article/391885947.html
で,触れた。そこで上がった参考文献を,改めて,読み直してみた。
復習という意味合いが強かったが,いくつか,改めて,気づいたこともある。
裁判所,保護観察部等々の紹介機関からやってくる,薬物中毒,アルコール中毒,DV等のクライエントをセラピーするという条件の中で,いかにソリューション・フォーカスト・アプローチが有効かを,実践的に確かめ,自分のものにしていった著者たちの,問題志向からの転換の悪戦苦闘が,反映されているという意味では,アメリカの事情に詳しくないものには,多少煩雑で,読みにくいところもあるが,創始者の,インスー・キム・バーグやスティーブ・ディ・シェイザーという第一世代の薫陶を受けた,第二世代のセラピストが,
臨床現場で習得していったプロセス,
が具体化されており,より噛み砕かれた内容になっている。その意味で,振り返るのに,丁度いい。特に,
第一章 解決志向の基本
第二章 個人セッションの流れ
第四章 たくさんのミラクル
は,振り返りと整理には,丁度良かった。たとえば,解決志向の原則は,
1.壊れていないならば,治すな
2.何かがうまくいっているならば,もっとそれをせよ
3.うまくいっていないならば,何かちがうことをせよ
4.小さな歩みの積み重ねが大きな変化につながる
5.解決は必ずしも直接的に問題と関連するとは限らない
6.解決を創り出すための言語に必要なものは,問題を記述するために必要なものとは異なる
7.どんな問題も常に起こっているわけではない。利用可能な例外が常にある
8.未来は,創り出されるし,努力して変えることもできる
ミラクル・クエスチョンについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/391885947.html
で触れたので,それ以外をすこし拾い出してみる。
例外については,スティーブの,
「不規則」な例外が不規則ではなく,実は,まだ記述されていないが,ある文脈のパターンの中に埋め込まれているのである。そして,これがもし記述されれば,例外を予測し,その結果,それを処方することもできるだろう,
を引用し,
例外は,変化が足元にあり現実である可能性があるという,かすかな望みを提供する場合が多い。例外が明るみに出ると,クライエントは希望を得る。というのは,自分の奇跡の一部が今起こっていると彼らにわかり始めるからである。
そう,例外は,「既に起こっている奇跡」だということの再確認である。
実は今回再度気づき直したのは,
違いの質問
である。著者は,こう言う,
違いの質問は,クライエントの変化の効果や変化の可能性を確認して目立たせ,その結果,提案された変化が確実に,現実的で,実現可能で,やりがいがあるものとなるための「エコロジーチェック」を提供する,
と。そして,
違いの質問は,クライエントの中に火をともすために必要な,拡大された状態を提供する。
典型的には,クライエントが現在,過去,または将来可能性のある具体的な変化を認識した後で,この質問はなされる。
第一に,
過去の変化の影響を探求する違いの質問は,同様の変化が現在の状況において有益と思われるかどうかを,クライエントが決定するのを援助する点で有益である。
この場合,忘れていたスキルや成功体験を認識し直すことが多い,という。たとえば,
「あなたが以前,毎晩一緒に夕食をとるようにしていたとき,そのことでご両親との関係でどんなことが違っていたのですか」
第二に,
可能性のある変化(例えば,奇跡の日に起こる変化や,一たび問題が解決された後のこと)を探求する質問は,クライエントの奇跡が,関係する人々にとって長期的に持続する利益を結果的に生み出す様子を明確にする点で役立つ。
変化が,どう周囲の人に影響し,それがどう自分に反照してくるかの確認だが,たとえば,
セラピスト「(クライエントに起こった変化)で,あなたにとってどんなことが違ってきたのですか」
クライエント「初めて実現しそうに思えたんです。…実際私は興奮しているの!」
セラピスト「そんなに興奮すると,どんなことが違ってきますか?」
クライエント「元気が出ます。…初めて力が湧いてきます。これが上手くいくようにしたいと思っています」
セラピスト「これらの変化で,息子さんにとってどんなことが違ってくるでしょうか?」
この周囲への影響の質問は,
関係性の質問
として著者が設定している介入と関係が強い。つまり,関係性の質問は,
自分の目標を達成することが自分の人生における重要な人々に与える影響を,クライエントが評価する,
よう援助する。それは,そのまま,可能性の実現がどういう違いをもたらすか,ということにつながる。たとえば,ミラクル・クエスチョンのあと,
「御主人に,夜中に奇跡が起こって,あなたの飲酒問題が解決したことがわかるでしょうか?」
とつながる。その意味で,著者は,「違いの質問」に,二つの切り口があるとして,
ひとつは,クライエント自身の変化の気づき,
いまひとつは,周囲の人,家族,友人の変化の気づき,
と言っている感じがする。ここからは,僕の勝手な理解になるが,この二つの切り口も,もう少し細かく,例示できそうな気がする。たとえば,
①変化の前と後
「ここに治療に着た結果として,どんなことが違ってくれたらいいと思いますか?」
「これを修了し,やり終えたことがケースワーカーにわかると,どんなことが違ってくるでしょうか?」
②変化そのものによる変化
「この奇跡で,あなたと息子さんにとってどんなことが違ってくるでしょうか?」
「もしケースワーカーがあなたのそんな側面を見ることができたとしたら,どんなことが違ってくるでしょうか?」
③変化の発生
「そういった行動でどういった違いがうまれると,あなたは思われますか?」
「あなたが(セラピーに)現れたことがケースワーカーにわかったら,あなたにとってどんなことが違ってくるでしょうか?」
④レベルアップの変化
「(スケーリング・クエスチョンで)あなたが6にいるとき,どんなことが違っていているでしょうか?」
「そうなったら,どんなことが違ってくるでしょうか?」
⑤変化の予測
「ここへ来た結果として,どんなことが違っていたらいいと思っていますか?」
「あなたのご両親は,あなたがここへ来た結果として,どんなことが違ってくればいいなと思っているでしょう?」
⑥変化の差異
「それはいつもと違うのでしょうか?」
「あなたにとって,どんなことが違ってくるでしょう?」
「そんなふうにすると,とても違ってくることを知っていたのですか?」
「どんな行動が違ってくるのが,見える必要があるのでしょうか?」
「それでどんなことが違ってくるのでしょう?」
等々,多少重複するところがあるが,
変化の差,違い,
変化の状態から見えるものの違い,
相手から見える違い,
といったものだが,細かく言うと,
違う,
違っている,
違ってくる,
違って見える,
と言い替えただけで,微妙に変わる。ここでは,クライエントに,
どういう立場で,
どの位置に立って,
どの条件のもとで,
どういう立場で,
どういう背景で,
どういう文脈で,
等々ビューポイントを設定してもらうことで,いまとの違いに気づき,そこに,自分の持っているリソース,あるいは,引き起こした変化に着目してもらうことが重要なのだ,と改めて再確認させられた次第。
参考文献;
テリー・ピショー&イボンヌ・M・ドラン『解決志向アプローチ再入門』(金剛出版) |
|
絶滅 |
|
フレッド・グテル『人類が滅亡する6つのシナリオ』を読む。
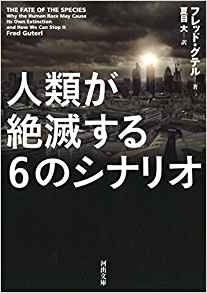
正直言って,大変読みにくい。自分で,いくつかの学説を整理して,シミュレーションした世界を,それぞれについて描いてもらった方が,危機感は,イメージしやすい。正確を期すためか,個々の学者の考えをいくつも,フォローしていくために,肝心の危機が,伝わりにくいのが難点。よほど科学の個々の学説の違いに興味ある人以外は,ついていくのが大変だろうと感じる。
人類の滅亡と地球の滅亡とは別なので,本書はあくまで,地球が存続するが,人類が滅亡の危機に瀕するシナリオということになる。
著者は言う。
私は以前,プリンストン大学教授のスティーヴン・バカラに「カナダやアラスカ,シベリアの永久凍土が解け,地中に閉じ込められていたメタンや炭素が大気中に放出されたらどういうことになるか」と尋ねたことがある。彼の答えは「あらゆる種類の怪物が姿を現す」だった。
この本は,その「怪物」について書いた本だ。
切り口は,6つ。
スーパーウイルス
大量絶滅
気候変動
生態系
バイオテロ
コンピュータ(サイバーテロ)
これですべてかどうかはわからない。ただ,いずれも,人類に起因する。一番重要なのは,
気候変動,
と著者は言う。
そして,大量絶滅と気候変動と生態系は,リンクしている。そのキーワードは,
ティッピングポイント,
つまり,ゆっくりと予測可能な変化をしていたシステムが,突如急激な予測外の変化を始める時点のこと。たとえば,
すでに思い荷物を背負ったラクダは,ワラを一歩乗せただけで背骨が折れる,
という,その瞬間のことらしい。そして,その瞬間を過ぎてしまったら,
最早戻す方法は全くない,
というのである。まるで,経営や組織について言われる,湯でカエル現象,
カエルを熱湯に入れるとすぐに飛び出すが,冷たい水にいれて徐々に水温を上げていくと,温度の変化に気づかず,やがて暑い湯の中で死んでいく。緩やかな変化に気づかず,いつしか手遅れなることのたとえ,
そのもののようだ。しかも,地球規模の変化には,何十年,何百年,何千年とかかるはず,というのが常識だとすると,もっと短いという説がある。
恐竜の絶滅などの大きな出来事も,数日や数週間といった,…短い期間で起きていた可能性がある,
と。ティッピングポイントの目安は,氷河である。例えば,
グリーンランドには,もしすべて解けて海に放出されれば海水面を6メートル以上押し上げる,
(南極大陸の氷床がすべて解けると)海水面を約80メートル押し上げる,
と言われる。いまのままのペースで解けていくとすると,300年という。しかし,ティッピングポイントを超えたとすると,もはや取り返しがつかないのである。
24億年前,藻類が放出した大量の酸素によって,当時繁栄していた嫌気性バクテリアが一気に滅びた,
とされる。そして,
酸素濃度の変化自体はゆっくりと進行したのだが,状態移行は急激だったのではないか…。ブレーカーが落ちるのに似ている。酸素が少しずつ増えても,ある時点までは何も変化がないように見えるが,突然スイッチが入ったように様相が激変するのだ。
そのスピードが速すぎれば,変化に対応するいとまがない。いま,そのティッピングポイントに近づいていないという保証はない。では我々はどうすればいいのか。
ティッピングポイントへの到達を未然に察知し,防止できるようにする,
しかない,のである。それにしても,国家にもそれはある。いま,わが国は,その,
ティッピングポイント,
に差し掛かりつつある気がしてならない。これは,自分たちでコントロールできるはずなのだが…!
参考文献;
フレッド・グテル『人類が滅亡する6つのシナリオ』(河出書房新社) |
|
芸術の脳 |
|
酒井邦嘉編『芸術を創る脳』を読む。

編者の酒井邦嘉氏については,『言語の脳科学』について,
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/11237688.html
で触れたことがある。言語脳科学の専門家である。その著者が,本書の意図を,
ふたつの意図を込めた。それは,芸術家一人一人が持つ独自の頭脳」と「芸術を生み出す人間一般の脳機能」を明らかにすること,
と述べる。そのための手法として,各分野で活躍中の,
曽我大介(指揮者,作曲家)
羽生善治(棋士)
前田知洋(クロースアップ・マジシャン)
千住博(日本画家)
との対談という方法を取り,
芸術を創っていく過程や創造的能力の秘密
を探ろうとしている。それを,
人間が芸術を生み出す能力は,より基本的な言語能力と密接に関係していると思われる。そこで,芸術に関する興味深い問題を,私の専門である「言語脳科学」を手がかりに考えることにした,
というわけである。是非の判断は,読んでいただくほかないが, 読んでみての私的印象では,
ひとつは,言語の専門家である小説家あるいは詩人が対象にいないこと,
いまひとつは,どうしても対談の散漫さ(会話は受け手に左右される)を免れず,掘り下げは不十分であること,
二つの憾みを残す。それと,ないものねだりかもしれないが,たった一人を相手にした方がよかったという印象をぬぐえない。
ただ,「言語を芸術と置き換えても整合性が取れる」と,上記の『言語の脳科学』について,千住氏が言及していることと,「言語は人間の言語機能を基礎にする」という著者の仮説からいうと,あえて文学者を設定する必要はなかった,ということかもしれないが。
さて,対談者ごとに共通項を拾い上げていくのは,素人には手に余るので,各対談者について,ちょっと引っかかったところを取り上げて,読んでみたいと思ってもらえれば「よし」としたい。
「(間宮芳生先生から伺ったところでは)作曲中にインスピレーションが沸きだしてくる瞬間というのがあって,その瞬間はあらゆることが理路整然と素晴らしく順序立てて頭の中に湧き出してくるそれが止まらなくなって書き続けるのです。それなのに,例えば,ベートーヴェンの時代だったら,女中が「だんな様,ご飯ができましたよ!」とやってくる。そうすると集中力がプチッと途切れてしまいます。(中略)その瞬間に途切れてしまったものを,後からつなぎ合わせる必要が出てきます。そのつなぎ目がどの作品にもあるというのです。
そのとき私はよくわからなかったのですが,いざ自分が作曲をするようになったら,その意味がとてもよくわかるようになりました。そうしたら,ほとんどの曲に継ぎ目がみえてくるわけで,そこに何らかの無理が残っているのです。」(曽我大介)
これは,ある意味,意識の流れを言語化(コード化)しているまさにその瞬間のことに他ならない。言語は,意識の1/20から1/30のスピードしかない。その集中している最中に途切れると,意識の流れは,遠ざかり,消えてしまう。後からは再現不能の,瞬間の,今しかない。そのことは,拙い経験でもわかる。思っていることを言語化しようとしている時に,他に気を取られると,その思いの方が消えて行く。
「将棋でもたくさんの手が読める,よく考えて計算できるという能力はもちろん大事なのですが,もっと大切なことがあります。それは,『この手はダメだ』と瞬間的にわかることです。(中略)プロ棋士は,アマチュアの高段者より10倍も100倍もたくさんの手が読めるわけではなくて,読んでいる手の数はほとんど同じくらいでしょう。それでも,バッと見たときに選んでいる手がたぶん違う。」(羽生善治)
その能力は,目利きだが,それは理屈ではない。たぶん手続き記憶による。10歳くらいまでに「体内時計」のように体に組み込まれた,将棋のセンスのようなものらしい。だからといって英才教育が成功するとは限らない。「好き」で「面白い」「やりたい」が必要なのかもしれない。
棋士は,対戦した全体を再現できるが,それについて,羽生さんは,こう言っている。
「それは歌や音楽を覚えるのとまったく同じでしょう。最初の数小節を聞いたら,誰の歌かとか何の音楽家がわかるのと同じで,将棋も慣れてくると『あっ,この局面は矢倉の一つの展開だな』とか,「これは振り飛車の将棋だな」とわかってきますよ。
音楽でも一つ一つの音符をバラバラに覚えているわけではなく,メロディーやリズムのまとまりを聴いて認識しますね。それと同じで,ひとつひとつの駒の配置を覚えているのではなくて,駒組みのまとまった形や指し手の連続性から捉えているのです。」
これって,どこかの研修で教わった,記憶術と似ている。つながりに意味があれば,全体の時系列が一気に蘇る。
「マジックを創作するときに,…複雑怪奇なものになってしまうことがあります。でも明確な言語化できない限りは,たとえ自分がとても気に入ったものであっても,あまり良いマジックではない。(中略)第二に,私にとってマジックとは『対話(ダイアローグ)』です。マジックの台詞を考えるとき,お客さんとキャッチボールするように構成していきます。…私はこのようなスタイルを『呼吸型』と呼んでいます。」(前田知洋)
だからこそ,前田さんは,ロベール・ウーダンを引いて,「人はただ騙されたいのではなく,紳士に騙されたいと思っている」と,言う。そしてこんな逸話を紹介する。
二人の絵描きが腕を競う話です。…それぞれの絵が宮殿に持ち込まれます。一人目がキャンバスを覆う布を取ると,見事な葡萄が描かれてましたすると,窓から鳥が入って来て,その絵の葡萄をつたのです。その絵を描いた画家は意気揚々として,「どうだ,鳥の目も騙すような葡萄を描いた自分は,この国一番の絵描きだ」と言って,もう一人の絵描きに「どんな絵を描いたのか,その布を取って見せろ」と迫りました。迫れた絵描きは何もしようとしません。その絵は,なんとキャンバスを覆う布を描いたものだったのです。「動物を騙す絵描き」と「絵描きさえも騙す絵描きという発想がおもろいでしょう。
落語の「抜け雀」を思わせるエピソードだ。もちろん,前田氏は,内輪受けのあざとさを自覚したうえで,あえて紹介している。マジシャンの矜持と受け止めていい。
「芸術は,何も人がびっくりするようなことではなくて,皆が忘れてしまっていること,忘れているけれども人々が必要とすることを提案できるかどうかで真価が問われるのです。」(千住博)
それを「切り口の独創性」と呼ぶ。そこが,その人とのオリジナルなものの見方だからだ。あるいは,認知の仕方といってもいい。いわば,自分の方法を見つけるとは,ものごとへの切り込み方を見つけることだといっていい。それが,各主題ごとに様々に横展開していくことになる。だからこそ,
「実は芸術は,とても簡単なことをやっているのです。『私はこう思う。みなさん,どうですか』と問いかけているのです。」
と。だから答えではなく,「わからない」という感想もまた一つのメッセージなのだ。ということは,すべての生き方,がそこに反映する。いや反映しなくてはならない。
「私たち絵描きは,アトリエに入ったときには,もう勝負がついているのですよ。アトリエに入って,『さあ,何を描こうか』というのでは手遅れなのです。」
ジムで運動しているとき,散歩しているとき,食事しているとき,常住坐臥,すべてが準備と予習であり,すべてが,無駄ではない,
人生に無駄なし(大阿闍梨 酒井雄哉)
なのであり,
「人生そのものが製作のプロセスでもあって,毎日何を食べて,誰と話をして,どんな本を読むかということが大切なのです。」
美しい絵を描きたかったら,美しい人生を過ごせ,
ということに尽きる,と。自分の人生,生き方,が自分のリソースなのだということだ。
ところで,最後に,脳と芸術に関わるエピソードを二つ。
認知症の人と羽生さんが将棋を指したとき,盤面が理解できていた,という。そして,次の指し手をちゃんと考えていたのだ,という。
もうひとつ,認知症の人にマジックを見せたところ,健常者と変わらぬ反応を示した,という。
人間的な脳の高機能が保たれているのだ,という。僕は,ふと思い出したが,脳溢血で倒れた人が,意識しして笑うことはできなくなった。しかし,確かV.S.ラマチャンドランの本で読んだ記憶があるが,おかしい漫才のようなものを聞くと,自然に笑みがこぼれたのだ,というエピソードを。
人の脳の奥深さは,まだまだ分かっていない。失われた意識レベルの奥に,まだ知られぬ機能が生きているということらしい。
参考文献;
酒井邦嘉編『芸術を創る脳』(東京大学出版会) |
|
リアリティを支えるもの |
|
ロバート・ウォボルディング『リアリティ・セラピー』を読む。
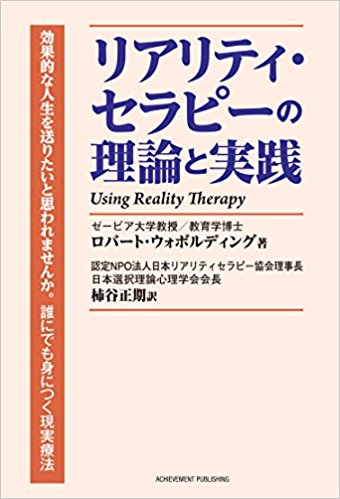
ロバート・ウォボルディング『リアリティ・セラピー』を読む。
グラッサーの『選択理論』を読んだ流れから,ここに遡っている。リアリティ・セラピーについては,訳者の柿谷正期氏が,こう要約している。
他のカウンセリングと違う点は,過去の出来事が現在の状況に直接関係していなければ,クライアントの過去についてあまり話をさせないようにすることである。また,「感情」は「全行動」の構成要素のひとつに過ぎないので,コントロールしやすい「行為」と「思考」に関連づけ,いつまでも「感情」に焦点をあて続けることをしない。変化をもたらす具体的な方法では,クライアントが現在欲しているものを尋ねる。そしてここからクライアントが自分の人生を展開していきたいと思っている方向に広げていく。
だから,クライアントの今していること(全行動)に焦点を合わせ,現在の方向は自分で選択したものであることを理解させる。
リアリティ・セラピーの中心点は評価の質問にある。「現在の行動を続けていて,自分の求めているものが手に入る可能性があるか。また自分が行きたいと思っている方向に行くことができると思うか」と尋ねる。
過去を重視しないのは,ブリーフ・セラピーは,過去を問題にしないので,リアリティ・セラピーの専売特許ではないが,「行為」に着目するところは結構面白いと思う。ソリューション・フォーカスト・アプローチのミラクルクエスチョンでは,奇跡の起きた朝を,詳細に聞いていくが,必ずしも行為ではなく,その場,そのシチュエーションを詳細に描写する方に力点がある。そうすることで,奇跡のリアリティが高まり,それだけで気づきが起きる。
リアリティ・セラピーの前提になっているのは,次の二つである。
ひとつは,人間を動かしている基本的な欲求は,4つである。
①所属の欲求 人と親しくなり,かかわりをもちたいという欲求
②力への欲求 人との競争の中,あるいは何かを達成したいという欲求
③楽しみの欲求 遊びや笑いの欲求
④自由の欲求 選択肢場所を移動する自由,内面の自由の欲求
いまひとつは,人の行動は,行為,思考,感情,生理反応の4要素から成り立っている。
そこから,リアリティ・セラピーの原則が生まれる。
第一原則 人は欲求(ニーズ)と願望(ウォンツ)を充たすことに駆り立てられている。
第二原則 自分の求めているものと,置かれた状況で自分の得たものとの差(フラストレーション)が具体的な行動を生み出す
第三原則 人間の行動は,行為,思考,感情,生理反応で構成されており,目的がある。すなわち行動は,自分の求めているものと,自分が得ているとおもうもののあいだにあるギャップを埋めようとするものである。
第四原則 行為,思考,感情,生理反応は,分離できない行動で,内側から生じる。そのほとんどは選択である。
第五原則 知覚を通してこの世を見るが,知覚には,出来事や状況を知識として取り入れる低いレベルと,それについて評価を加える高いレベルがある。
ある意味で,望んでいること(目標)と現状とのギャップを明確にして,その目標実現をサポートしていく,問題解決プロセスに近似しているように見える。
だから,まず「何を欲しているか?」「何を望んでいるか?」という質問が重要である。そこで自分の欲求をどう満たしたいかを明確にしていく。しかし,それが,本当に望んでいるものかどうかが,クライアント自身にだってはっきりしているとは限らない。一見,試験に通ることを望んでいるようでいて,実は,その先の,「自由」を目指していることだってある。で,こんな質問になる。
「もし欲しているものが得られたら,何を手に入れることになりますか?人生はどうなると思いますか?」
だとして,
「いまあなたのしていることは,そのために役に立っていると思うか?現在の方向は満足のいくものになっていると思うか?」
そして,
「人生をよりよいものに変えるために,今晩どんなことをしてみたいですか?」
つまり,自分の人生の支配権は自分にあり,人生そのものが自分の選択にかかっている,ということを質問を通して,クライアントに提案している,あるいはリクエストしていることになる。
人生の大まかな方向について明確にした後,具体的に何をするかを詰めていく時,有効なのが,「行為」についての質問だ,というところが,リアリティ・セラピーの要になることのように思う。
「あなたは何をしているか?」
という問いである。
何が出来事に遭遇してばたついたときや欲求不満に陥ったとき,われわれは自分の感情には気づいても,その時の「行為」には気づいていない。リアリティ・セラピーでは,他のセラピーがするように,「感情をみきわめ,感情に触れ,何年もさかのぼって,原因と思われる過去の出来事に対して洞察を得る」ようなことはしない。感情は,あくまで,クライアントの選び取った行動から自然に出てきたものと考える。あくまで,行為の結果とみなす。だから,行為に着目する。
確かに,落ち込んだり動揺しているとき,心の状態に意識が向いているので,そのとき自分が何をしていたか,そのときの振る舞いや行為には無自覚だ。そこで,
自分の行動の「行為」の部分を変えれば―ということは,よりよい選択をすれば―感情も必ず変わる…
と考える。そこで,クライアントが一番気づいていない「行為」に焦点をあてる。特定の日に,何をしたかを,テレビカメラで記録するように,詳細に,描写する。
その上で,クライアント自身に自分を評価させる。
「あなたのしていることは,役立っていますか?」
「いましていることをつづけて,自分の求めているものを手に入れられますか?」
「あなたの欲しているものは現実的ですか?達成可能なものですか?」
「そのような見方をして役に立ちますか?」
「あなたは此のカウンセリングで自分の人生を変えることに,どれほど本気で取り組む決意ですか?」
「それは役に立つ計画ですか?」
そして,行為を変える,行動計画を立てるが,リアリティ・セラピーの計画は,些細な「行為」にある。
「今晩何をしますか?」
は,大それたことである必要はない。たとえば,いつも喧嘩している妻に,「笑顔になる」という行為であるかもしれない。鬱の女性は,車で送迎してくれる娘に,「川がきれいだね」と一言言うのかもしれない。
小さなものの積み重ねがあって完成があるが,何かを完成させることは小さなことではない。
大事なのは,結果(目標)中心ではなく,過程中心の計画なのだと,リアリティ・セラピーは考えている。小さな行為を積み重ねる(選択する)ことで,行動が変わる。行動が変わることで感情が変わる。
楽しいから笑うのではなく,笑うから楽しい。
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/11165966.html
で触れたように,怖いから鳥肌立つのではなく,鳥肌立つから怖い,つまり,笑うからうれしいし,泣くから悲しい。これが今の脳科学の常識らしい。その意味では,小さな行為を通して,行動を変え,感情を変えていくことは理にかなっている。
参考文献;
ウイリアム・グラッサー『選択理論』(アチーブメント出版)
ロバート・ウォボルディング『リアリティ・セラピー』(アチーブメント出版) |
|
異議 |
|
清水昭三『西郷と横山安武』を読む。

著者は,あとがきで書く。
対朝鮮とのかかわりの中で,今なお正視すべきはあの国是の如きかつての「征韓論」である。またこれを行動として実現してしまった「韓国併合」とその消えぬ波紋のことである。けれども,こうした日本人としてまことに恥ずべき思想や行動を可とせず,抗議の諌死を遂げた人物が,たった一人存在していたのは,なんという救いであったろう。その人物こそ草莽の士で,西郷隆盛と生き方としては対照の関係にあった横山安武である。彼はわが国最初の内閣総理大臣伊藤博文の初代文相森有礼の兄でもあった。
横山安武は,唯一,日本人の良識である。彼こそ幕末維新を生きた真の知識人だったのである。
いまもなお,薩摩藩士,横山安武の抗議の建白書は,現代日本をも鋭く刺し突く槍である。いまなお,嫌韓,ヘイトの対象にして,言われなく他国を侮蔑する者への,無言の刃である。
読めばわかるが,建白書は,維新政府そのものへの痛烈な批判になっている。五箇条の御誓文に反する,政府の施策,政治家の生きざまへの,真摯な怒りである。これもまた,今に通ずる。150年たっても,未だに,維新はなっていない。
五箇条の御誓文はいう,
広く会議を興おこし,万機公論に決すべし
上下心を一にして,盛に経綸を行ふべし
官武一庶民に至る迄,各の其の志を遂げ,人心をして倦ざらしめん事を要す
旧来の陋習を破り,天地の公道に基づくべし
知識を世界に求め,大おおいに皇基を振起すべし
と。
これと比較しながら読めば,彼が何に絶望していたかが,見えてくる。
では安武はどんな建白書を書いたのか。明治3年である。
方今一新の期,四方着目の時,府藩の大綱に依遵し,各々新たに徳政を敷くべきに,あにはからんや旧幕の悪弊,暗に新政に遷り,昨日非とせしもの,今日却って是となるに至る。細かにその目を挙げて言わんに,第一,輔相の大任を始め,侈糜驕奢,上,朝廷を暗誘し,下,飢餓を察せざるなり。
第二に,大小官員ども,外には虚飾を張り,内には名利を事とする,少なからず。
第三に,朝礼夕替,万民古儀を抱き,方に迷う。畢竟牽強付会,心を着実に用いざる故なり。
第四,道中人馬賃銭を増し,かつ五分の一の献金等,すべて人情情実を察せず,人心の帰不帰に拘わらず,刻薄の処置なり。
第五,直を尊ばずして,能者を尊び,廉恥,上に立たざる故に,日に軽薄の風に向かう。
第六,官のために人を求るに非ずして,人のために官を求む。故に毎局,己が任に心を尽くさず,職事を陳取,仕事の様に心得るものり。
第七,酒食の交わり勝ちて,義理上の交わり薄し。
第八,外国人に対し,条約の立方軽率なるより,物議沸騰を生ずること多し。
第九,黜陟の大典立たず,多くは愛憎を以て進退す。春日某(潜庵のこと)の如き,廉直の者は,反って私恨を以て冤罪に陥る数度なり。これ岩倉(具視)や徳大寺(実則)の意中に出ずと聞く。
第十,上下交々利を征りて国危うし。今日在朝の君子,公平正大の実これありたく存じ奉り候。
そして,別紙を添える。ここに安武の満腔の思いがある。全文を載せる。
朝鮮征伐の議,草莽の間,盛んに主張する由,畢竟,皇国の委糜不振を慷慨するの余,斯く憤慨論を発すと見えたり,然れ共兵を起すに名あり,議り,殊に海外に対し,一度名義を失するに至っては,大勝利を得るとも天下萬世の誹謗を免るべからず,兵法に己を知り彼を知ると言ふことあり,今朝鮮の事は姑らく我国の情実を察するに諸民は飢渇困窮に迫り,政令は鎖細の枝葉のみにて根本は今に不定,何事も名目虚飾のみにて実効の立所甚だ薄く,一新とは口に称すれど,一新の徳化は毫も見えず,萬民汲々として隠に土崩の兆しあり,若し我国勢,充実盛大ならば区々の朝鮮豈能く非礼を我に加へんや慮此に出でず,只朝鮮を小国と見侮り,妄りに無名の師を興し,萬一蹉跌あらば,天下億兆何と言わん,蝦夷の開拓さへも土民の怨みを受くること多し。
且朝鮮近年屡々外国と接戦し,顧る兵事に慣るると聞く,然らば文禄の時勢とは同日の論にあらず,秀吉の威力を以てすら尚数年の力を費やす,今佐田某(白茅のこと)輩所言の如き,朝鮮を掌中に運さんとす,欺己,欺人,国事を以て戯とするは,此等の言を言ふなるべし,今日の急務は,先づ,綱紀を建て政令を一にし,信を天下に示し,万民を安堵せしむるにあり,姑く蕭墻以外の変を図るべし,豈朝鮮の罪を問ふ暇あらんや。
震災の復興,福島のコントロールがいまだしなのに,と考えると,そのまま今日に当てはまる。
信を天下に示し,万民を安堵せしむるにあり,姑く蕭墻以外の変を図るべし,豈朝鮮の罪を問ふ暇あらんや,
は,今のわれわれを突く刃である。
ふと思い出したが,マザー・テレサの講演を聞いて感動した日本の女子大生が,マザーに「私もインドに行き貧しい人の為に働きたい」と伝えたそうです。マザー・テレサの返事は,「日本にも貧しい人,苦しんでいる人はいます。目の前で苦しんでいる人を助けてあげてください」というエピソードが,胸に迫る。隗より始めよ,である。
明治5年,西郷隆盛は,安武の碑文を書いた。
朝廷の百官遊蕩驕奢して事を誤る者多し。時論囂囂たり。安武乃ち慨然として自ら奮って謂う。王家衰頽の機此に兆す。臣子為る者,千思万慮以て之を救わざるべからず。然して尋常諌疏百口之を陳ずと雖も,力矯正する能わざれば,則ち寸益無きのみ。一死以て之を諌めんに如かず,
しかし,淡々としたのこ文は,他人ごとに見える。西郷は当事者であったにもかかわらず,である。
その西郷隆盛自身が,翌年征韓論に敗れ,7年後城山で自害するのは,皮肉である。
それにしても,いつから,義を重んじなくなったのか。義を見てせざるが士なら,義を失ったものに,士という言を使うこと自体がおこがましい。横井小楠の理想はどこに消えたのか。
堯舜孔子の道を明らかにし,
西洋器械の術を尽くさば,
なんぞ富国に止まらん,
なんぞ強兵に止まらん,
大義を四海に布かんのみ,
といった気概と希望が満ち満ちている横井の夢を泥まみれにして,大義なき国に貶め,他国を塗炭の苦しみに陥れても,少しも惻隠の情すらなく,他国を侮って悔いなきものどもの国にしてしまい,またしつつある,この国に,
どんな,「天地の公道」があるのか。
どんな,振起すべき「皇基」があるのか。
今上天皇の心に,少なくとも,それがあることが,わずかな救いでしかないとは,情けなく,恥ずかしい。
参考文献;
清水昭三『西郷と横山安武』(彩流社) |
|
いのち |
|
清水博『〈いのち〉の普遍学』を読む。

本書は,
仏教と科学の視点から「〈いのち〉を問う」ことを目的にして,竹村牧男さんと私の間で…始まった往復書簡が,本多弘之さん,竹内整一さんと,対論の相手を変えて引き継がれ
たものを中心において,第一部で,「〈いのち〉の科学」,第三部「〈いのち〉の普遍学からの構想」を配置して,
〈いのち〉の居場所としての地球の危機を考える…共通の精神が…貫いて流れている…
ものとなっている。
著者は,「はじめに」で,こう書く,
往復書簡の主題が「〈いのち〉への問い」であるように,人間が生きていくことは,「未来に向かって問いかけ」,そしてその答えを自分なりに見つけては,また「問いかけていく」ことの繰り返しであり,答えはすでに問いかけのうちに隠れているのです。
したがって生きていくために必要なことは,「正解」を探すことではなく,自分を包んでいる新しい状況に対する問いかけ方を知ることです,
と。そして,これから必要なのは,自分一人を主役として際立たせることに生きがいを求めることではなく,
皆が主役となって役割を分担しながら共に生きていく「生活共創」の時代,
だとも。それには,
多くの人びとがそれぞれの貴重な〈いのち〉を与贈し,共に主役となって,時代を越えて愛されるものごとを,ドラマの共演のように一緒につくり出していく創造的な活動です,
とも。
ところで,〈いのち〉という表現について,なぜ生命ではなく,〈いのち〉なのか。
〈いのち〉とは,それ自身を継続していくように地球の上ではたらいている能動的な活き(はたらき)のことです。
だから,
生きものをモノという面から捉えるために使われてきた「生命」という概念だけでは不十分であり,現実に不足しているコト(関係性)の面からも生きものを具体的に捉える方法が必要,
として,〈いのち〉という概念を使う,という。これは,
日本人が昔から使ってきた「命」に近いのではないか,
と。そして,〈いのち〉を語るとき,生きものが生きている居場所抜きでは語れない。
生きものの〈いのち〉とそこに生きている生きものとは,たんなる全体と部分以上の関係にあります。またそればかりではなく,生きものの〈いのち〉が存在している場所でなければ,居場所とは言いません。その意味から,居場所には居場所としての〈いのち〉があります。その〈いのち〉は,生きものの〈いのち〉を加えあわせたものではなく,居場所に広がって遍在する「全体的な〈いのち〉」です。さらに居場所から取り出した生きものの性質は,居場所にあるときの性質とは一般的に全く異なってしまいます。
この関係を,こう説明します。
居場所の部分である生きものたちの内部には,それぞれ居場所全体の〈いのち〉の活き…を映す活き「コペルニクスの鏡」(と仮称します)があり…,その「コペルニクスの鏡」に映っている全体の〈いのち〉の活きが個々の生きものの性質を内部から変える…,
として,人間の身体と約60兆個の細胞との関係で例示します。
人間の身体は…約60兆個と言われる非常に多くの多様な細胞たちの居場所です。また,それらの細胞は,それぞれの〈いのち〉をもって自律的にいきています。その身体が一つの生命体として統一された活きをもっているのは,細胞たちがそれぞれ共存在原理にしたがって共創的な活動をしているからですが,…人間の身体の〈いのち〉という全体とこれらの細胞たちの〈いのち〉という部分を,全体と部分に分離することなく,一つのものとしてつないで「生きていく複雑系」としている活きがあるから,
その統一性が生まれてくる。この全体と部分がわけられないことを,
居場所の〈いのち〉の二重性
と著者は呼びます。つまり,
その居場所の〈いのち〉の活きと,その居場所で生活している生きものの〈いのち〉の活きを機械的に全体と個に分けることは原理的にてきません。(中略)生きものの〈いのち〉が居場所の〈いのち〉に包まれると,生きもののうちにある「コペルニクスの鏡」がその居場所の〈いのち〉の活きを映し,居場所の「逆さ鏡」が生きものの〈いのち〉の活きを映して,互いに他に整合的になるように変わる〈いのち〉のつながりが居場所と生きものの間に生まれるからです,
と。それを量子力学の粒子と場になぞらえ,
粒としての〈いのち〉と場としての〈いのち〉,
あるいは,
局在的な存在の形と遍在的な存在の形,
と,その二重性を表現しています。それをサッカーを例に,こう説明しています。
場の〈いのち〉の活きであるチームの活きは,個々の粒としての〈いのち〉の活きである選手の活きを単純に足し合わせたものものではないということです。それは,居場所に場として広がった「一つに統合された活き」,すなわち一つの「全体的な〈いのち〉」の活きです。
こうして広がった場こそが,
居場所に広がった〈いのち〉の遍在的な形態,
なのだ,と。
考えてみれば,人は,さまざまな場で生きている。家庭であり,企業であり,地域社会であり,国家であり,…の中で,継続して生きていくためには,その場所が,
居場所,
にならなくてはならない。そのためには,
粒の〈いのち〉と場の〈いのち〉の活きが,互いに整合的になることが必要
なのだという。そして,
ある場所に場所的問題が存在するということは,自己の〈いのち〉をそこへ投入してみると,〈いのち〉の二重性の形をつくれないことがわかるということです。それは,その場所が自分の居場所にならないからです。したがって,自分の〈いのち〉が相互誘導合致の活きによつて〈いのち〉の二重性をつくることができたと感じることができるまで,―その場所が自分にとって居場所になったと感じることができるまで―場所の環境条件を変更したり,自分の〈いのち〉の活き方を変えたりする努力をしてみるのです。
そこに,自分のポジションと役割が見つかることで,自分がそこにいることで場そのものが動き変化していく,そういう場と自分の関係をつくっていく,ということは,一人ではできない。いじめを考えたとき,
個々の〈いのち〉と場の〈いのち〉,
だけではない,もうひとつ必要な気がする。そのヒントは,場所的世界を劇場に見立てた,「場の即興劇理論」にあるように思える。すなわち,
場としての舞台,
舞台上の役者,
見えない形で参加しいてる観客,
の三者のうち,観客ではないか,という気がしている。それを,西田幾多郎を借りて,
「どこまでも超越的なるとともにどこまでも内在的なる(存在)」としてしかとらえられない「他者」(=「絶対の他者),
であり,それは,自己の無意識の深層に存在している,と同時に,
それが自己(役者)が存在している場所的世界(劇場)を超えて自己が関係するどのようなる劇場をも大きく包む存在,
とも呼びます。それを,著者は,「観客の声なき声」とも呼ぶ。
観客を,こう説明すれば,イメージがわくはずです。
関係子(役者)は重層構造をした〈いのち〉の居場所(劇場)に存在して,そしてそれぞれの居場所で〈いのち〉のドラマを同時並行的に演じていると考えます。たとえば,一人の人間の場合,簡単に見ても,家庭と,企業と,地域社会と,日本と,アジアと,世界と,地球というように,重層的な居場所で同時に即興劇を演じるように生きています。役者がそのうちの一つの居場所における即興劇を意識しているときに,それより大きな居場所において進行している〈いのち〉のドラマの影響が即興劇の観客の活きに相当します。
役者と舞台が整合的になるのは,その居場所よりも。重層構造の上でより大きな居場所の相互誘導合致の活きから,対応して考える,ということなのだと言える。
それは,狭く限定した「島宇宙」だけで問題解決しないというふうに言いかえると,なんだかありふれてしまうか。しかし〈いのち〉は,その小さく限定した中だけで,自己完結してはいけない。またそういう視野で見ている限り土壺にはまる。
つまりより上位の視界の中で,その視野の中において見ることで,一見相互誘導合致の活きが損なわれているように見える〈いのち〉も,その活きが生き返る解決が見える,ということなのではないか。
とりあえず,そういう「問いかけ方」をすることで,その場で生きる道が見えてくる。居場所が未来からくる,とはそういうことではないか。
浄土が未来から呼びかけてくると,心から信受するところに,「正衆聚」が与えられる,そこで現生は安心して未来からのはたらきをいただく「いま」になる,という。そのことに通ずる,ような気がする。
それは,親鸞の「如来の回向」とつながり,清澤満之の「天命を安んじて,人事を尽くす」の意欲へとつながる,と思える。
参考文献;
清水博『〈いのち〉の普遍学』(春秋社) |
|
素朴信念 |
|
高橋惠子『絆の構造』を読む。

われわれは,人との関係,家族との関係について,多くの常識というか,先入観を刷り込まれ,それに縛られて自縄自縛に陥っているところがある。本書は,それを改めて解きほぐしていこうとしている。
著者は言う。
本書では,それぞれの人が現在持っている「人間関係」,ひととの「絆」の「仕組み」を検討することを提案している。その「仕組み」が実は興味深い「構造」をなしていることを明らかにすることで,それぞれの人が自分の人間関係の内容を知り,ユニークなオーダーメイドの絆の再構築をするヒントになればうれしい
と述べる。それは,逆にいえば,多くの人が,オーダーメイドではなく,お仕着せの人間関係観,家族観に拘束されている,ということでもある。そして,
人は,誰とでも同じように,無差別につながれるわけではないのである。…一生涯にわたって,人は周りの人びとの自分にとっての意味,つまり,安心・安全をもたらす人,行動を共にしたい人,困っていたら助けてあげたい人などを区別しながら,自分にとって好きで有効な数人を選択しているのである。(中略)注目すべきは,表現された対人行動ではなく,各人が持っている頭の中のプログラムなのである。このプログラムは,複数の重要だと選択されたメンバーで構成されているが,彼らは雑然とそこに入れられているのではなく,各メンバーにはそれぞれ心的役割が振られ,整理されているとするのが妥当である。そして,あるメンバーの役割は別のメンバーの役割と関連し,ネットワークをなす構造を持つと考えるとよさそうなのである。
大事なことは,人間関係に,こうあるべきだ,こうでなければならないという価値や常識,イデオロギーにあるのではない,人は,自分が生きるために,人との関係を選択し,自分の関係を創っていくことができる。あるいは現にそうやってつくっている現実の関係を認めることだ。でなければ,強制でしかないし,拘束でしかない。
たとえば,「絆」はいいものだという神話について,
「絆はよいものだ」「人は絆を持つのが当たり前だ」とし,さらに,「もっと親密で,しかも,自然な絆は親子・家族間のものだ」「母子の絆が絆の原型だ」
という常識や思い込み(「素朴信念」と著者は言う)に苦しめられている人が多いのではないか,と著者は問う。マストになった瞬間,そうでない人を異常にする,あるいは異常ではないかと悩まされる。それでは,
オーダーメイドの人間関係をつくるうえでの障がいになるのはなにか。
まずは家族について。311の後,絆の大合唱が起こったが,朝日新聞の調査では,
危機に瀕して,実際に(家族との)関係が深まった,
というひとは三割に満たない。
家族が困ったときに助けてくれる愛ある共同体であるというのは根拠のない思い込み,つまり,神話なのだと思い知らされる,
と著者は言う。しかし,国のすべての制度は,「標準家族」というものをベースにしている,世界でも例がない仕組みを取り続けている。つまり,社会的なリスクを担う,最小単位のセーフティネットとされているのである。
それは,
夫が主たる稼ぎ手で,妻が専業主婦で家事・育児を受け持つ
という生別役割分担を前提とした「男性稼ぎ主型」で,それが,家族のあたりまえの生活,子どもの育児・教育,老人の介護などの生活・福祉をスムーズに実行する社会の単位とみなされている。だから,
すべての人は標準家族に属するという前提に立ち,市民ひとりひとりが社会の単位,
とはみなされていない。税制,健康保険,介護保険,企業の賃金体系まで様々な風習に至るまでが,それで貫徹されている。
しかし,標準家族は三割に満たず,一番多いのは,単身世帯で35%程度,夫婦のみの世帯が二割,一人親世帯が一割,二世帯は,微々たる数でしかない。しかも生涯結婚しない人も,増え続けている。
標準家族ではない人が,七割を占めているのに,家族主義を前提にして施策が進められ,多くが不利益だけではなく,
幼い子供は母親の手で育てるべきである,
という素朴信念が,逆に女性に生むことをためらわせ,自分の人生を諦めさせられたくない,
という事態を生み,少子化の遠因になっている,と著者は言う。では女性を拘束する,
幼児期にしっかり育てなれば取り返しがつかない,
乳幼児の経験が後の人生を決定する,
というのは,本当なのか。著者は言う。
人間の発達には柔軟性があり,取り返しがきき,その人がやる気になった時が,発達の適時なのである。親に虐待されて不幸な乳幼児期を贈らざるを得なかった子どもがその後に十分な養育・教育を受けて回復したという事例
が増えてきたという。つまり,
乳幼児期の発達から将来を予測することは難しいこともわかったきた
のである。どう考えていも,90年に及ぶ人生の中で,わずか三年間が決定する,というのは納得できない,という著者の言葉に賛成である。
では母子関係は特別なのか。その根拠に使われているのが,イギリスのジョン・ボウルビィの「愛着理論」である。ボウルビィは,
人類には生存を確保するために,強い他者に庇護を求めるというプログラムが遺伝子にくみこまれるようになった,
とした。愛着とは,
「無能で無力な人間」が「有能で賢明な他者」に生存,安全を確保するために擁護や援助を求めること,
と定義される。ボウビィルは,その「他者」に母親を重視した。しかし,著者は,最晩年ボウビィルが,「母親が働きに出るのは反対だ」と発言したことを例に,
家父長制イデオロギーがボウルビィルの科学者としての者を狭めた,
と言い切る。そして,サラ・ハーディの研究結果に基づいて,
人類を含め類人猿では母親になっても育児をするとはかぎらない。母性本能は疑わしい…。母親になることには学習が必要である,母親以外が養育する事例が類人猿に広く見られる…,そして類人猿の雌も幾次と生産活動を両立させている…。
と指摘する。そして,
母子関係は大切ではあるが偏重する必要はない。
とも。つまり,母性本能というのは,社会的文化的に刷り込まれた結果である,ということである。
著者が最後に紹介する,カーンとアントヌッチの,
コンボイ
という,サポートネットワークの測定法がなかなか面白い。
面接調査によって,
同心円に,中央が自分,その外に,最も大切な人,その人なしに人生が想像できない位親密に感じている人,その外に,親しさの程度は減るがなお重要なな人,一番外の円に,それほど親しくはないが重要な人を,挙げてもらう。
次に,それぞれの人を上げた理由,どう重要なのか,を聞く。
著者は,8歳から93歳までの1800人余りの面接調査を試みている。三つのうん平均で七〜八人,そこに出るのは,
他者に助けられつつ,自分らしくあるという自立を手に入れるうまい仕組みだといえる。なぜなら,誰か一人に全面的に左右されずにすむ。つまり,誰かにすべて依存することはない。その上,誰がどのように有効なサポーターであるかがわかっていれば,あるサポートが必要になった時にあわてなくてすむ。
という自分で選んだネットワークなのである。重要なのは人数ではない。
自分が選んだ大切な役割・意味を持つ人々を構成メンバーとする人間関係の中で暮らしている,
ということなのだ。それを更新しながら生きている。大事なことは,母親が重要な存在ではあっても,子どもたちにとって,
重要な他者の一人であるというのが正しい,
ということなのだ。父親や祖母が愛着の一番手として挙がることものである。
気づくのは,日本の根強い素朴信念が,多くの呪縛や心の病をもたらすということだ。そのほとんどは,家族を主体とする政策やイデオロギーによる拘束でもある。そして,いま,その家父長制イデオロギーというか,家族主義が復権されようとしている。「おひとりさま」(上野千鶴子)が大勢なのに,である。
現実と政治家のイデオロギーのギャップの中で,子どもの貧困率は16%になろうとし,実に子供の,6〜7人に一人が貧困状態にあるという,先進国の中でも政治の貧困が際立つ。それは標準家族という幻想(イデオロギー)の上に立つ政策が,そこからこぼれていく一人親家族の貧困を放置している(見捨てている)結果でもある。
アンシャン・レジュームというイデオロギーの妄想の中,いまも子供が貧困の中死んで行く,こんな「美しい国」が何處にあるのか。激しい怒りを感じつつ,ドストエフスキーがカラマーゾフの兄弟の中で子供の悲劇を指摘していたことを思い出す。あれは,19世紀の話なのだ。21世紀になってもこの体たらくなのだ。
そう思うとき,絆自体が,イデオロギーとして使われたのだと思い至る。
参考文献;
高橋惠子『絆の構造』(講談社現代新書) |
|
王統 |
|
水谷千秋『継体天皇と朝鮮半島の謎』を読む。
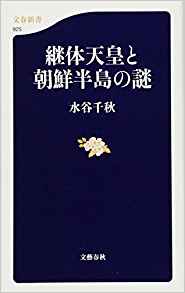
武烈天皇崩御の後,王位継承者が絶え,応神天皇から数えて五代目に当たる,越前三国に住む,普通なら天皇になれそうもない遠い傍系の王族が,五十七歳で,それまでの王統の血が絶えて,白羽の矢が立った。父も祖父も曾祖父も天皇ではない。
大和から越前まで派遣された使者は,一目見てこの人こそ天皇にふさわしい,
と感じたというが,即位して二十年間,大和盆地の外に都を置き続け,大和の磐余玉穂宮を都としたのは,亡くなる前五年から八年とされている。
それだけに,
実は王統の血は断絶しているのではないか,実は応神天皇五世孫などではなく,近江か越前の地方豪族で,王位を簒奪したのではないか,
等々と謎の大王とされている。
著者は,記紀と考古学の成果から,
地方に土着した傍系王族,
の一人と見る。たとえば,
播磨に土着した顕宗・仁賢兄弟は,履中天皇の孫,
継体の前に王位継承者候補となった倭彦王は,丹波にいた,
等々の例を挙げ,後年のような臣籍降下という制度がない時代には,どんな傍系でも王と名乗り,地方に土着していた,とする。継体は,そういう一人ということだ。
しかしほとんど晩年にいたるまで,大和に入れず,樟葉宮(枚方市),筒城宮(田辺市),弟国宮(長岡京市)と,大和盆地の外縁を転々としていく。
継体支援勢力は,大伴氏,物部氏,和邇氏等々だが,この豪族たちの本拠地は,大和盆地の東側であり,西側,つまり葛城氏の支配地域に,なかなか入れなかった,と著者は見ている。
ただ,継体天皇の背景に,渡来人が深くかかわっている,と著者は見る。その一例として,和歌山県の隅田八幡宮の人物画鏡の銘文に,
癸未年八月曰十大王年男(孚)弟王在意柴沙加宮時斯麻念長奉遣開中費直穢人今州利二人尊所白上同二百桿所此竟
とあり,
曰十(おそ)大王の年,男(孚)弟(おふと)王,意柴沙加(おしさかの)宮にいますとき,斯麻,長く奉(つか)えんと念(おも)い,開中費直(かいちゅうのあたえ),穢人今州利(えひといますり)の二人の尊を遣わして白(もう)すところなり。同二百桿を上め,此の竟(かがみ)を作るところなり,
と読める。503年,継体の即位する四年前,斯麻王則百済の武寧王が,意柴沙加宮(忍坂宮)にいたとき,この鏡を送ったと解釈されている。
そのつながりは,武寧王の棺は,日本にしか生息しない高野槇でつくられていたことからも,知れる。しかも,訃報をきいてから送ったのでは間に合わない。生前から,調達する手はずが整っていたのではないか,と見られている。
五経博士の倭国への派遣,
百済の軍事的応援,
等々,継体期の百済との深い関係を考えると,渡来人を介した,深い関係が推測されるのは間違いない。
しかし,この継体天皇即位の経緯を見ると,邪馬台国の卑弥呼の死後,国が乱れた後,宗女壹與(台与)を立てて修めたことを思い出す。倭人伝に言う。
卑弥呼の死後,男の王が立つが,国が混乱し互いに誅殺しあい千人余が死んだ。
卑弥呼の宗女「壹與」を13歳で王に立てると国中が遂に鎮定した。
と。つくづく,邪馬台国,倭国,ヤマトと,つづく王権の流れが,シャーマニズムというか,宗教的権威というか,血統というシンボルというか,がないと収まらないらしいことを,思い知らされる。
ただの馬の骨が天下を制しても誰もついて行かない,というか,いつも自分たちのオーソライズに利用することをし続けてきた,ということなのかもしれない。
いまもそれは続いている。
横井小楠の,
人君なんすれぞ天職なる
天に代わりて百姓を治ればなり
天徳の人に非らざるよりは
何を以って天命に愜(かなわ)ん
堯の舜を巽(えら)ぶ所以
是れ真に大聖たり
迂儒此の理に暗く
之を以って聖人病めりとなす
嗟乎血統論
是れ豈天理に順ならんや
という詩がいまも意味があるのはそのせいだろう。いつになったら,この呪縛から解かれるのか,あるいは,永遠に続くのか,気になるところだ。
参考文献;
水谷千秋『継体堪能と朝鮮半島の謎』(文春新書) |
|
ラマルク説 |
|
杉晴夫『人類はなぜ短期間で進化できたのか』を読む。

サブタイトルに,「ラマルク説」で読み解く,とある。本書のベースは,ラマルク説なのである。
本書は,
入門書としては類例のない,人類の進化だけでなく,人類の進化の延長として捉えた人類文明社会の進化を考察するところまでを扱っている。その意図を,はじめにで,こんなエピソードを紹介して,説明している。
1981年にアフリカ大陸南部で,何億年も前に絶滅したと思われていた原始的な魚類シーラカンスが初めて生きた状態で発見され,大きな話題となった。当時,末広恭雄東京大学教授が,生きたシーラカンスの標本を入手する探検隊を組織したとき,「なぜこんなことをやるんですか」との新聞記者の質問に対して「われわれ自身を知りたいからです」と答え,われわれ人類の進化のルーツを生物学的にたどることの意義を強調した。
この考えがただしいなら,原始人類が家族,社会を形成していった跡をたどり,現代の人類の文明社会の成立につなげて考察する本があってもよいであろう。
で,ラマルク説である。ラマルクの
用不用説は,動物が一代で発達させた器官がその子孫に伝わること,つまり獲得形質の遺伝を前提としている。進化論の入門書によると,このラマルクの考えは,ワイスマンという学者の研究によって否定されたことになっている。しかしこの実験は,マウスの尾を20代以上にわたって切り続けても,尾の短いマウスはうまれてこなかったという無意味極まるものであった。
尾を切るという所業は単に動物に被害を加えるのみで,動物が環境に適応しようとする努力による器官の用,不用とは何の関係もない,
と切り捨てる。そして,ラマルク説は,誤解されているという。
ラマルクという人は,人(動物)が一代で獲得した能力がその子孫に伝わると主張しました。つまり英会話の得意な人の子は,はじめから英語がしゃべれるというのです。何とばかばかしい説でしょう。
と紹介されている現状に対して,改めて,ラマルクの説を,こう説明する。
ラマルクは,進化は生体に内在する力によって起こる,
と考える。それは,
(1)循環系における血液,体液の運動と,
(2)神経系における電気信号の伝わり,である。これらの働きによって,環境に対する適応力の増大,
つまり合目的性と,単純なものから複雑なものへの変化が徐々に起こるとする。
それに,現代の知見を加えて補足すると,
(1)は,身体の内分泌系のホルモンなどの働きを指しており,
(2)は環境の変化を感知する感覚神経,身体運動を起こす運動神経,体内の器官の活動を支配する自律神経の働きが含まれる。これらの神経系の働きや内分泌系の活動は大脳の脳幹部で統御されている。さらに子孫に遺伝子を伝える男女の生殖腺における精子,卵子の形成は内分泌系のホルモンによって調節されている,
と。だから,
ラマルクが洞察したように,生体がその生存を賭けて周囲の環境に適応しようとする結果が,神経系から内分泌系に伝わり,更に内分泌系から生殖腺における精子,卵子の核酸の遺伝子や卵細胞の細胞質に影響を与えている,
と。そして,進化論と対比して,こう言う。
ダーウィンの進化論の中核をなす自然淘汰は,その当否の検証に地質学的時間を要するので原理的に検証不能である…のに対して,ラマルクの生体に内在する力,つまり現代の言葉でいえば生体の神経系,内分泌系,生殖腺の環境に適応しようとする働きは,現在は困難としても,理論的には将来,検証が可能,
である,と。さらに,
ダーウィンの進化論とラマルクの進化論の違いは,前者が進化の原因をもっぱら自然の選択に帰するのに対して,後者は生体に内在する力を仮定することである。しかしダーウィンの進化論も,生存に適した形質が子孫に伝わるとする以上,ラマルクと同様に獲得形質を仮定せざるをえない,
という。たとえば,
地中生活をするモグラや暗黒生活をする洞穴の生物などの眼が退化して消失する現象は,ラマルクの用不用説では使用しない器官は退化すると明快に説明される。しかしダーウィンの自然淘汰説では,そもそも生存に有利な形質のみを考え,器官の退化の説明は考慮されていない。ダーウィンはこの現象を自然淘汰で説明できないことを大変気に病んでいたという。
つまり,ダーウィンの進化論は,実質破綻していた。では,なぜ生き延びたのか。それは,
メンデルによる遺伝子の法則の大発見と,これに続く遺伝子の突然変異の発見,
による。しかし,
実はこの時点で,ダーウィンの考えた生物形質の変異は,現在では単なる形質の個体差による彷徨変位と呼ばれる現象で,遺伝しないことがわかっている。したがって形質の変異を獲得形質の遺伝と考えたダーウィンの説は実質的に滅びていたのであり,彼の名が消えても不思議ではなかった。
その後,遺伝子の突然変異を進化と考える研究者よって,ネオ・ダーウィニズムとして引き継がれているのが,現状ということになる。
しかしその進化論では,なぜ生物は下等なものから高等なものへと変化していったのかという定方向性進化が説明できない。遺伝子のランダムな突然変異では,有利不利は半々であり,
ひたすら「気の遠くなるような長い年月」をかければ,アメーバ―が進化して人類になる,と単純に考えているのだろうか,
と疑問を呈する。そして,ほとんどの説明が,用不用のラマルクを使って説明していると,随所で例を挙げている。たとえば,人類の祖先が樹上生活を選んだことは,
後の人類の発展にとって根本的に重要であった。樹上を棲息域とすれば,当時としては身体が小さく,牙や角のような武器もなく無力であったものが,外敵に襲われる機会も少なくなる。したがって平地で暮らしているウマのように外敵の襲撃から遁れるために蹄を進化させる必要もなく,ウシやゾウのように角で武装する必要もなく,……これが霊長類が他の動物に比べて特殊化の度合いが少なかった理由である。生物の進化を調べると,いったん特殊化した動物はもはや元の状態に戻ることはできない。
と説明する。こういう説明の仕方,つまり,
原因が結果を生む因果律が働いて起こる歴史的事実を,遺伝子という志向性をもたない物質に怒る突然変異の積み重ねで説明できるとは思われない。ネオ・ダーウィニズムは人類の進化に対し,納得のいく説明を与えられないと考える。現に人類進化の歴史を解説する人々は,皆筆者と同様な説明をしている。つまり,無意識のうちに「生体に内在する力」すなわち神経系などの働きを考えるラマルキニズムの説明を行っている,
のである。あるいは,野生のオオカミから犬(シェパードからチワワまで)への変化は,ネオ・ダーウィニズムの突然変異では説明できない。個々の遺伝子のランダムな突然変異の確率からは,オオカミからチワワへの変化には,数億年がかかる。しかし,
人類がイヌなどの家畜を飼育しはじめたのは,現在から約一万年前に過ぎない。
ここでも,動物の進化におけるラマルクの先見性が見える,と著者は言う。
また,たとえば,人類の基本的特徴は,直立二足歩行,大きな脳容積,歯の退化,であるとされるが,
この人類化石の判定法すべてが,ラマルク流の考えによるものである,
と著者は言う。
こうみてくると,結局,突然変異説も,自然淘汰説も,用不用説も,未だ同列の仮説なのだ,ということを改めて再確認し,頭に刷り込まれる理論でモノを見ることの危うさを点検するには,ある意味格好の本なのかもしれない。
ところで,印象深いのは,上記人類化石の特徴である,直立二足歩行,歯の退化を具えたのは,アウストラピテクス(猿人。現在は440万年前とされるアルディピテクス・ラミダスが最古の霊長類)が長く,霊長類の最古とされてきたが,この時代から,仲間同士の殺人がなされている。
この殺人は人類が原人からホモ属に進化するとますます頻繁に,しかも大量になってくる。人類学者のバイネルトは,「霊長類の化石に殺された痕跡があれば,それはサルではなく,人類と断定してよい」とまで言い切っている,
という。
今も続く,地球上で,ホモ・サピエンスのみが,仲間同士の殺し合いをしているのである。憂鬱になる記述である。
参考文献;
杉晴夫『人類はなぜ短期間で進化できたのか』(平凡社新書) |
|
俯瞰 |
|
滝沢弘康『秀吉家臣団の内幕』を読む。
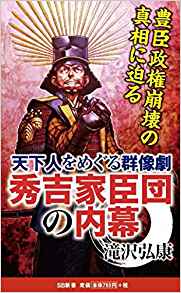
このところ立て続けに読んでみて,所詮歴史も物語とはいえ,官兵衛を図にすると,こうも官兵衛が巨大になるのかということを実感させられた。まあ,眉に唾つけつつ読んだと言っても,官兵衛の秀吉旗下での位置づけがはっきりしない。そんなところに,本書が出た。まあ,泥鰌本と言えば言えるだろうが,官兵衛の配置図というか,ポジションをうかがわせるものになっている。
貧農の出から出発した秀吉は,一門,譜代の家臣を持たぬ,それこそ,今どきははやらぬのかもしれぬが,裸一貫から,天下人に駆け上がった。他の戦国武将が,小豪族から成り上がったにしろ,それなりに一門眷属をもっているのに,本当に眷属自体が少ない。
まず出発は,糟糠の妻,おねを得たところから,始まる。頼ったのは,おねの実家筋からである。
おねの父である杉原定利,おねの叔父にあたる杉原家次,おねの兄である木下家定,おねの姉ややの夫,浅野長政である。
木下姓自体が,おねのははの実家木下から貰い受けたと想定されているのである。
美濃攻めの功績で,歴史上,知行宛行状の添え書きに,
木下藤吉郎秀吉
の名が始めて登場する。この時期が創業期の家臣団になる。
一門衆として,杉原定次,木下家定,浅野長政,姉ともの夫,三好吉房,母なかの親戚,小出秀政
家臣として,蜂須賀正勝,前野長康,山内一豊,堀尾吉晴といった尾張衆,
となっていく。右腕になったのは,蜂須賀正勝である。ただこの時期は,信長から与力として,付属している状態なので,必ずしも秀吉の直臣ではない。
美濃攻略後,加わったのが,
生駒親正,加藤光泰,仙石秀久,竹中半兵衛といった美濃衆,である。同時にこの時期,秀吉は,幼若より身近に使えさせて,ひとかどの武将になっていくものを,育てようとしている。
第一世代が,神子田正治,尾藤知宣,戸田勝隆,宮田光次,
である。その後,第二世代に,福島正則,加藤清正,加藤嘉明ら,いわゆる賤ヶ岳の七本槍が登場する。
浅井長政を倒した後,秀吉は,初めて,北近江三郡の一国一城の主となる。そこで,浅井旧臣を取り込んで,急増していく。例えば,こんなふうだ。
一門衆 羽柴秀長,羽柴於次秀勝,杉原家次,浅野長政,木下家定,三好吉房
近江衆 宮部継潤,脇坂安治,寺沢広政,田中吉政,増田長盛,石田正継,石田三成,大谷吉継,片桐且元,中村一氏
尾張衆 蜂須賀正勝,前野長康,山内一豊,堀尾吉晴,桑山重晴,加藤清正,福島正則,加藤嘉明
美濃衆 竹中半兵衛,生駒親正,加藤光泰,仙石秀久,坪内利定,石川光政,佐藤秀方
播磨・摂津衆 黒田官兵衛,明石則実,別所重宗,小西行長,
腰母衣衆 古田重則,佐藤直清
黄母衣衆 尾藤知宣,神子田正治,大塩正貞,一柳直末,中西守之,一柳弥三右衛門,小野木重勝
大母衣衆 戸田勝隆,宮田光次,津田信任
初めて官兵衛が出てくる。中国攻めにおいて,官兵衛が活躍したことは間違いないが,本能寺の変後の大返し,賤ヶ岳の合戦では,『黒田家譜』や『太閤記』を除くと,官兵衛の活躍ははっきりしない。
歴史史料上は,秀吉が,秀長宛てに出した書状に,
砦周辺の小屋の撤去を,官兵衛や前野長康,木下定重に命じるように指示している,
というところがある。一方,三成は,近江衆の一員として,吏僚として活躍している。著者は言う。
賤ヶ岳の戦いにおける秀吉軍の勝利の背景には,陣城や防衛網の構築と,超スピードの大返しが大きな要因であった。情報の収集・分析能力,全体のプランニング,用意周到な準備と遂行能力が勝敗を決したという点では,賤ヶ岳の戦いは,高松城の攻城戦や中国大返しと同様の新しい合戦と言える。そして,それらを準備し実行したのが,三成や大谷吉継,増田長盛ら,近江衆を中心とした吏僚たちであり,中国戦線で鍛えられたかれらは,秀吉軍に不可欠な存在となっていたのだ。賤ヶ岳の戦いではどうやら帷幄の中心には官兵衛ではなく,三成がいたようなのである。
と。戦いの中心を,動員から,兵站までの全体像を描いたとき,重要なのは,後方活動や机上の仕事を受け持つ吏僚の役割であり,兵站の確保が大切になる。
敵軍を圧倒するために,秀吉軍の動員兵力は合戦を経るごとに,加速度的に増大していく。三木城・鳥取城・高松城の攻城戦では,2万〜2万5000人だったのが,賤ヶ岳の戦いでは5万人,小牧・長久手の戦いでは7万人,四国攻めや越中攻めでは10万人,九州攻めや小田原攻めでは,20万人,文禄・慶長の役では30万人が動員されている。
兵数が増大するほど,兵站が難しくなるのは言うまでもない。兵站を担ったのは,一貫して吏僚派奉行であり,
三成・吉継が中心をになった。合戦の場で,吏僚の存在感が増して言った,と著者は想像する。このあたりに,武断派と文治派の対立の根を,著者は見ている。
そして,著者はこう最後で締めくくっている。
秀吉家臣団は,秀吉が一代で築きあげたものである。しかもその主なファクターは,信長の与力,新しい領地での在地武将,旧信長家臣,外様大名といった外部から加わった新戦力であった。彼らの忠誠は強烈なカリスマ性をもつ「秀吉」個人に向かっていたのであり,それが「豊臣家」への忠義となるには,時間が足りなかった。
要は,秀吉の個性によって,つないできた統一のタガは,彼の死によって,信長が急死ししたとき,秀吉がそうしたように,次の天下取りに近いものへと,靡いていくのは,当たり前といえば当たり前だ。
それが徳川家康であったということだ。
家臣団全体を俯瞰してみるとき,大友宗麟が国元に送った手紙に,
内々の儀は宗易(千利休),公儀の事は宰相(秀長)
と言われており,政権内の実権は,この二人と,各大名との取次と呼ばれた役職との二重構造になっていて,取次として上杉,佐竹など有力大名との折衝を担ったのは,三成であった。
その意味で,中国戦線,九州攻め以降は,実質官兵衛は蚊帳の外にいたとみた方がいいようなのである。
家臣団肥大の中で,吏僚が政権内で力をつけていくのは,どの武家政権でもある。それが制度として政権維持にまで高度化される前に,秀吉の死去で,政権は瓦解していく。その中に官兵衛を置いてみたほうが,官兵衛が徳川へとシフトしていく理由も背景もよく見える。
泥鰌本の官兵衛ものに欠けている,家臣団の中での俯瞰とその位置づけは,ものをみるときの鉄則のように思えてならない。
参考文献;
滝沢弘康『秀吉家臣団の内幕』(ソフトバンク新書) |
|
数字 |
|
佐藤朋彦『数字を追うな 統計を読め』を読む。

かつてマッカーサーが,日本政府の発表する数字が杜撰であることを厳しく指摘したのに対して,当時の吉田茂首相は,「もしも戦前にわが国の統計が完備していたならば,あんな無謀な戦争はやらなかったろう」と言い返したという。
著者は言う,
客観性を持たない統計に基づいて国家を運営すれば,その国は滅びることになるでしょう。
と,その意味では,わが国の統計は戦後本当に,始まったといっていい。統計法が制定され,そこにはこうある,と著者は言う。
統計の作成に従事する者が統計を歪めるような(真実に反するものたらしめる)行為をした場合には,6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定している。
だから,
正しい統計が完備され,それを国民の誰しもが自由に利用できる環境にある,
ことが必要だと。
本書の狙いを,現役の統計局職員である著者はこうまとめる。
①統計のつくり手側からみた内容であること
②どのような点に目をつけながら統計を読めば,見えないものが見えてくるかの秘訣の伝授
③統計学の解説ではなく,数字の読み解き方を解説する
と。たとえば,労働力調査(2003年データ)について,
(15歳以上25歳未満の)就業者数は,573万人で,この年齢層の人口に占める割合は38.3%です。…残りが非労働力で853万人(56.9%)です。内訳をみると,在学者が750万人で,非労働力人口の約9割を占めています。また,学校基本調査結果から推計された人数ですが,進学のために浪人している者が14万人,そしてこれ以外の者が89万人となっています。さらにその中で,就業の希望のない者が40万人います。
この数値に注目し,「ニート」に着眼したのがたのが,『孤立無業』を表わした玄田有史東大教授である。これが,いわば仮説といっていい。これが数字を読むということの意味なのだろう。
あるいは,餃子の年間消費量が,宇都宮市が長くトップにあったが,著者はこういう。
単に家計調査の結果を眺めただけでは,簡単には見つからなかったと思います。家計調査の収支項目は550項目近くもあります。食料に絞っても200項目以上と,かなりの数です。この餃子の支出を見つけた宇都宮市の担当者は,家計調査による統計数字を丁寧に,そして大事に見ていき,地域振興のヒントになるのではと思いついたのではないかと思います。
その意味で,
①数字を丁寧に扱うこと,
②現場を見て歩くこと,
が数字理解には欠かせない,と著者は強調する。現場感覚があるから,数字に疑問が出る。その疑問が,数字の読みを深める。
そこで,統計リテラシー(統計を読む力)を身に着ける方法を,
①我が国の基本的で身近な統計を頭に入れておく。例えば,人口,就業者数や失業者数,物価動向,国内総生産額等々,
②基本統計数値が頭にあると,新聞などの調査結果について,気になったり,疑問を持ったりすることが可能になる,
③発表された数値の解釈やコメントはも一つの見方なので,別の見方もあると考える,
と,挙げた。
僕は,それよりも,自分の現場感覚,現実感覚と対照し,それとの違和やズレを大事にしてみたい。それが,数字の読みを深め,自分の仮説につながる,と思っている。仮説については,
http://blogs.dion.ne.jp/ppnet/archives/11372364.html
で触れた。
因みに,明治に,statisticsを最初に訳したのは,柳河春三ではないかと言われているが,それを福地源一郎が,アメリカのBureau
of Statistics を統計寮と訳したのが嚆矢とされている。この「統計」という訳語は,中国でも,韓国でも使われている,という。
参考文献;
佐藤朋彦『数字を追うな 統計を読め』(日本経済新聞出版) |
|
プロパガンダ |
|
跡部蛮『秀吉ではなく家康を「天下人」にした黒田官兵衛』を読む。

泥鰌本の4冊目。もうこれで打ち止めにする。新書版とはいえ,いい加減な物語を語るのはやめてほしい。確かに,どこに焦点をあてるかによって,図は変わるとはいえ,こうそれぞれが勝手読みをするのを歴史と言ったら,カーが嗤うに違いない。
こう言うのは,版元を見て判断する,というのが僕の基準だが,それは当たっている,といっていい。
さて,本書は,小和田哲男『黒田如水』から学んだということばが,プロローグに載せられているが,その小和田氏とは,真逆の結論からスタートしている。といっても,中身は,それに近いのが笑えるが。著者はこう書く,
「豊臣秀吉を天下人にした稀代の軍師」という通説的理解に疑問を抱く一人だが,秀吉死後,官兵衛とその嫡男・長政の父子は,家康の天下取りに大きく貢献し,関ヶ原の合戦後,家康から,「御粉骨御手柄ともに比類なく候。いま天下平均の儀,誠に御忠節ゆえと存じ候」という賛辞をたまわる。
と。しかし,これは,社長が功労者に言うセリフであって,だからといって,
豊臣秀吉を天下人にした稀代の軍師,
から,
家康を「天下人」にした黒田官兵衛,
と入れ替わる根拠とも思えない。ただ仕える主人を変えただけだ。どこに焦点をあてるかで,変わることには,著者自身が気づいているらしく,さんざん官兵衛を持ち上げた挙句,あとがきではこう書く。
秀吉の天下がほぼ定まった同(天正)十三年頃,官兵衛はキリスト教に入信するが,このころ宣教師ルイス・フロイスが『日本史』に書き残した言葉が,世間が官兵衛をどう評していたか如実に表しているように思う。
「関白の顧問を務める一人の貴人がいた。彼は優れた才能の持ち主であり,それがために万人の尊敬を集めていた。関白と山口の国主(毛利輝元)との間の和平は,この人物を通して成立した…」
このことから,こう逆に推測する。
官兵衛の事績として知られるのは毛利との交渉だけという見方もできる。実際に福岡藩の正史である『黒田家譜』を除くと,一級史料で彼が秀吉の天下統一に獅子奮迅の活躍をしたという事実や評価は見られない。
つまり,後世の彼の評価と当時の現実とは大きな落差がある。これを,著者は,こう言う。
官兵衛を実像以上の存在に見せようとしたプロデューサーがいたと考える。ほかならぬ秀吉である。
そして,こう説明を加えていく。
秀吉の官兵衛評については『家譜』に掲載される次の話が有名だ。あるとき秀吉はふざけて近臣の者に,自分が死んだら誰が天下を給ったらよいかを問い質してみた。誰もが家康や前田利家,毛利輝元ら大身の大名の名前ばかり挙げた。そこで秀吉は,「汝ら知らずや」,つまりおまえたち誰もわからないのかといい,「黒田如水なり」として,官兵衛の名を挙げたという。『家譜』は,だからこそ秀吉は官兵衛に大国を与えなかったのだといい,一般的にもそう理解される場合が多い。しかし,この手の話が後世まで語り継がれる要因のひとつは,秀吉得意のプロパガンダの結果であったと考えた方が理解しやすい。
なぜなら,
下層階級出身の秀吉には譜代の臣はおらず,世に名前の通った家臣もいない。だからこそ秀吉は,彼自身がプロデューサーになって自分の配下の者を世に売り出そうとした。
と。そういえば,賤ヶ岳の七本槍(本当は,『柴田退治記』では9人だったようだが)でいう,
福島正則
加藤清正
加藤嘉明
脇坂安治
平野長泰
糟屋武則
片桐且元
等々もその例だし,
中国大返し
美濃大返し
という命名もまた,その例だろう。
事実,秀吉は,祐筆となり,側近だった大村由己に,
『天正記』
『播磨別所記』
『惟任退治記』
『柴田退治記』
『関白任官記』
『聚楽行幸記』
『金賦之記』
と次々に,ほぼ同時進行で,軍記を書かせているが,それにも目を通し,口も出している。あの『信長公記』の太田牛一にも,『大かうさまくんきのうち』『太閤軍記』を書かせている。
当時の軍記物は,皆の前で詠み聞かせる。直後にこうやって物語を読み聞かせ,宣伝していくのである。戰さの直後に,こう読み聞かされれば,そこに載りたいという動機が生まれてもおかしくない。現実と,同時進行で歴史を創り出そうとしていた,と言えなくもない。信じたかどうかは別に,自分の出自についても,
御落胤説
まで物語にしようとする,秀吉である。
こう考えると,実は,あとがきの,この焦点の当て方の方が,本文よりはるかに面白い。が,この説を図として,展開すると,実は官兵衛を主役とする本書には都合が悪く,秀吉の類い稀なプロデュース能力だけが際立ってしまう。
だから,著者が,
官兵衛は秀吉を恐れ,その官兵衛を家康が恐れた。
等々というのは,たわごとにしか見えない。官兵衛は,絶えずその時の仕えるべき相手である秀吉や家康に,疑われないよう,慎重に連絡し,許可を得て動いている。所詮,
秀吉あっての官兵衛であり,家康あっての官兵衛である。
そこを見間違えては,官兵衛像は虚像に過ぎない。
参考文献;
跡部蛮『秀吉ではなく家康を「天下人」にした黒田官兵衛』(双葉新書) |
|
通説 |
|
小和田哲男『黒田官兵衛』を読む。

泥鰌本の三冊目。
正直これが歴史学者の本か,と思うほど,通説べったり,失礼ながら,ほとんど,突っ込んだ研究を(いまは)していないということを,証するような著作だ。
はじめに,でこうある。
「黒田官兵衛の魅力は何か,一言で説明してほしい」といわれれば,私は,「戦国自体の最も軍師らしい軍師」と答える。
軍師が存在していないことは,日本史家の基本的な考えだ(とはお考えになっていないらしい)。講談や小説ならいざ知らず,到底ありえない。しかも,本書中に,どこも,軍師の定義もない。
さらに,こう言うのである。
さらにそれに一言加えれば,「トップに馴れる力をもちながら,補佐役に徹したその生き方」と答えることにしている。
何をどう考えようと,所詮歴史も物語だから,その人の自由だが,
秀吉の帷幄に官兵衛がいなければ,秀吉がはたして天下を取ることができたか疑問である。仮に天下が取れたとしても,織田信長時代の凄惨な戦いが繰り返され,もっと多くの血が流されたものと思われる。
歴史に,たら,れば,はない。この説は,仮説,つまり官兵衛=軍師に依拠してしか言えない。しかし,それなら,なぜ,無謀な文禄の役を止められなかったのか,という茶々はいれずにおこう。歴史が示しているのは,秀吉がいなければ,官兵衛はおらず,官兵衛がいなくても,秀吉は天下を取った,ということだ。
こういう著者の論法は,随所にみられる。
たとえば,信長と謁見した時のことについて,
このときの越権の模様は『信長公記』にも記されておらず,『黒田家譜』にしか出てこないので,以下,同書によりながら,
と書き進める。『黒田家譜』の記述については,かなり慎重を要するのに,第一次史料である『信長公記』をさておいて,話を展開している。『信長公記』に記述がなければ,疑わなければならないのに,である。
あるいは,こういうのもある。
『武功夜話』については,「偽書だ」といって頭から否定する人もいるが,秀吉の家臣だった前野将右衛門長康の子孫が,家に伝わる古記録などをもとに,幕末になって著わしたもので,部分によっては信用できる箇所もあり,…,
といいつつ,検証抜き(信用できる箇所だという証明がないまま)に使っている。大体『武功夜話』の本体自体が公表されていない古記録を,疑ってかかるのが当たり前だ。しかも,幕末とは,300年もたってから書かれたものなのだ。疑うのが常識ではないか。
なのに,『武功夜話』によると,として,他の史料を示さず,『武功夜話』だけで,官兵衛の活躍を追うところが随所にある。さらには,『黒田家譜』の記述(官兵衛の功績を示そうとするのが当たり前)に,『本能寺の変を聞いて,呆然とする秀吉に,
さても此世中ハ畢竟貴公天下の権柄を取給ふべきとこそ存じ候へ,
と励ました記述を,『川角太閤記』(これも第一次史料ではない)まで持ち出して,
呆然自失の状態から,官兵衛の一言で秀吉が我に返ったのは確かである。官兵衛がそばにいなければ,秀吉の対応が遅れた可能性があり,
と,見てきたような嘘を受け合う。講談師か?とつっこみを入れたくなる。
だから敗北した小牧・長久手の戦いについても,
その場に官兵衛がいたら,反対し,この作戦は実行されなかったと思われる。
ここまで言い切られると,呆れるより,そういう本なのだと思うしかない。しかし,最後に著者の入れた,官兵衛の遺訓は,創ろうとした官兵衛像を見事に裏切っている。
1.神の罰より主君の罰おそるべし。主君の罰より臣下百姓の罰おそるべし。其故は,神の罰は祈りもまぬかるべし。主君の罰は詫言して謝すべし。只臣下百姓にうとまれては,必国家を失ふ故,云々
2.大将たる人は,威といふものなくしては万人の押へ成りがたし。去りながら悪しく心得て,態と我身に威を拵てつけんとするは,却って大なる害となるものなり。其故は,只諸人におぢらるる様に身を持なすを威と心得,家老と逢いても威高く事もなく目をいからし,詞をあらくし,人諌めを聞き入れず,我に非有る時もかさ押しに言いまぎらし,我意を振舞によって,家老も諌を言ず,おのづから身を引様に成行くものなり。家老さえ如斯なれば,まして諸士末々に至迄,只おぢおそれたる迄にて,忠義のおもひなす者なく,我身構をのみにして奉公を実によく勤る事なし。かく高慢に人をないがしろにする故,臣下万民うとみて必家を失ひ,国亡ぶるものなれば,能々心得可き事なり。云々,
まさに,後年の黒田騒動を予見したような遺訓だが,ここにはただ,二代目の我が子(長政)に藩を守るように言い聞かせている,功に成り遂げた父親の心配するイメージしかない。
秀吉の,子ども(秀頼)のことを,涙を流して頼んでいたイメージと重なるだけだ。そして,この託しているもののスケールの差は,そのまま,秀吉と,官兵衛の差といっていい。
参考文献;
小和田哲男『黒田官兵衛』(平凡社新書)
渡邊大門『黒田官兵衛』(講談社現代新書) |
|
実像 |
|
諏訪勝則『黒田官兵衛』を読む。
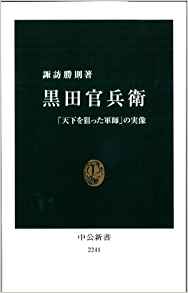
官兵衛本が相次いで出されている。順次見ていくが,これが二冊目。どこに焦点をあてるかで,結構差が出る。本書は,武人としての官兵衛以外に,
キリシタンであり,
茶人であり,
歌人である,
官兵衛の姿に焦点をあてているのが特色かもしれない。
一般には,太閤記などのせいもあり,軍師というイメージが強く,その線で,司馬遼太郎『播磨灘物語』も,吉川英治『黒田如水』も描かれている。その典型は,江戸時代の『常山紀談』のある,官兵衛が,息子長政に語った,こういうエピソードだろう。
我は無双の博打の上手なり。関ヶ原にて,石田今しばらく支へたらば,筑紫より攻登り下部のいふ勝相撲に入りて,日本を掌のなかに握んと思ひたりき。其時は,子たる汝をもすてて一ばくちうたんとおもひぞかし。
しかし実際には家康の許可を取り,逐次自分の動きを家康に明確に示し疑われる行動は巧みに避けている。このあたりが実像だ。だから,江戸時代の『故郷物語』で,長政が凱旋して,中津城で手柄話をした折,家康は私の手を握り,三度抱擁してくれたと官兵衛に話した。その時,官兵衛は,冷ややかに,
左の手か,それとも右の手かと尋ねた。長政は右の手であると答えた。官兵衛は,左の手は何をしていたのか,と再び質問した。左手で家康を刺し殺すこともできたものを,との含意だ…
というのだが,この辺りは,「作り話」に過ぎない。著者は言う。
数々の武功からすると,官兵衛は非常に細心で堅実で,秀吉への連絡を怠らなかった。戦況を逐次報告し,秀吉の意向を確認し,判断を仰いだ。秀吉の没後は,家康を始めとする徳川陣営の人々と緊密に連絡を取った。これにより徳川方であることを明確に示し,三成陣営にも通じているのではないかと疑われるのを防いでいる。
と。そして,むしろ,
官兵衛はきわめて誠実な人物であった。
そのことは,小田原合戦で北条方との交渉役をつとめ,北条氏直に開城を決意させる。その折,氏直から,『吾妻鑑』と日光一文字の刀など三点を贈られている。また関ヶ原合戦後,吉川広家との盟約を着実に履行し,最後の最後まで毛利一族を見捨てなかった。さらに,さかのぼれば,荒木村重の籠る有岡城に幽閉された際,家臣たちが起請文を作成した事例等々が示すように,家臣からも大変慕われていた。
だから,著者は,
官兵衛なくして秀吉の天下統一は完遂できなかったといっても過言ではない。ただし,ここで注意しなくてはならないのは,官兵衛は秀吉の家臣団の中では随一といってよい名将だが,政権の中枢にあったわけではないことである。…「内々の儀」は千利休が,「公儀の事」は豊臣秀長が取り仕切っていた。秀長・利休の没後は,石田三成らが台頭した。官兵衛の存在をあまり過大評価するのは間違いである。
と。文化人としての官兵衛に焦点をあてているのが,本書の特徴だが,まずは,
官兵衛は高山右近・蒲生氏郷の勧めにより入信し,…秀吉の家臣たちに改宗を促したことが知られている。
洗礼名はシメオン。ルイス・フロイスの年報では,
小寺官兵衛殿Comdera Cambioyedono
とあり,官兵衛の読みが,「かんべえ」ではなく「かんびょうえ」であるとわかる。官兵衛は,死ぬまでキリシタンであり,葬儀も,自領の博多の教会で,キリスト教式で行われた。
茶の湯については,秀吉が重視していて,秀吉家臣団の多くも親しんだ。はじめ,官兵衛は武将が好む者ではないと,考えていたようだが,小田原合戦時,陣中で秀吉に招かれて,渋々茶室に入った逸話が残っている。
秀吉は茶を点てる様子もなく,もっぱら戦の密談を続け,数刻が過ぎた。秀吉が官兵衛に語るには「これが茶の湯の一徳というものだ。もし茶室以外の場所で密談をかわしたならば,人から疑いをかけられる。茶室で話せば剣技が生ずることはない」。
これを聞いて感服して,官兵衛は茶の道に入った,という。
茶席では様々な教養が要求されることはいうまでもない。たとえば,床の間に墨跡がかかっていた場合,その書を読むことができ,その内容を理解することが必要である。官兵衛は幼少の頃から培ってきた学問的な素養を十分に生かして茶席に臨んで行ったのである。
連歌については,連歌会の歌がいくつも残っているが,挑戦出陣に際して,細川幽斎から,歌学に関する書籍を贈られている。
中央歌壇の最高権威者である細川幽斎から,
『堀河院百首』(幽斎が書写したもの)
『新古今集聞書』(幽斎が書写。巻末に,今如水此の道に執心を感じ,之を進呈する,と記されている。)
『連歌新式』
書籍を贈られたのは,官兵衛が本格的に連歌に取り組んでいることを示している。この三年後には,官兵衛は,一人で連歌百韻を詠じている。
こうみると官兵衛は,武将として確かに優れているが,世に言われる野心家というよりは篤実な性格なのではないか。文禄の役で,朝鮮にて,死を覚悟して,長政に遺した家訓がある。
1.官兵衛の所領が上様(秀吉)に没収されなかったならば,現在仕えている家臣たちに,書面に記したように渡すように。
2.もしその方(長政)に子供ができなかった場合,松寿(官兵衛の甥)を跡取りとするように。もし,器量がない場合,松寿は申すに及ばず実子であっても不適格である
3.家臣たちに対しては,前々から仕えているものをしっかり取り立ててゆくことが大切である
4.諸事,自分の想い描いた通に事が運ぶとは限らない。堪忍の心がけが必要である
5.親類・被官には慈悲の心を持ち,母には孝行するように
6.上様・関白様(秀次)のことを大事にしていれば神に祈ることもない
どうだろう,戦国時代を誠実に戦いきった人間の,一種の透明な心映えが見える。
官兵衛も結構失敗し,秀吉の勘気を蒙っている。しかし,肥後の領国支配に失敗した佐々成政は切腹,戸次川合戦で敗戦した仙石秀久は改易された。しかし官兵衛は,同時期領国支配でも佐々と同じ一揆をおこされ,島津攻めでも失敗しているが,不思議と,秀吉から見逃されている。それは,誠実に,粘り強く対処して,貢献してきた官兵衛の力量を,秀吉は必要としていたからではないか。
参考文献;
諏訪勝則『黒田官兵衛』(中公新書) |
|
物語 |
|
家近良樹『孝明天皇と「一会桑」』を読む。
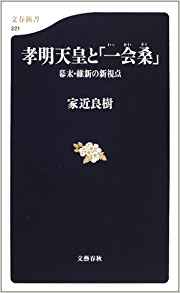
同じ著者の,『西郷隆盛と幕末維新の政局』について取り上げたことがあるが,切り口を変えると,また別の「地」が浮かび上がる。ただ,いままで当たり前としてきたことに異を唱えようとする,問題意識は似ている。
一会桑とは,一橋慶喜であり,会津藩(松平容保)であり,桑名藩(松平定敬)を指す。副題に,「幕末・維新の新視点」とあるように,孝明天皇と一会桑にウエイトを置きながら,いままでの維新史の常識に風穴を開けようとしている。
その維新史観を,西南雄藩討幕派史観と,著者は呼ぶが,その問題を二つ挙げている。
ひとつは,西南雄藩を特別視することと引き換えに,二重の抹殺がなされ,幕末史がひどく偏った内容のものになったことである。二重の抹殺とは,幕府・朝敵諸藩の抹殺と,薩長両藩内にも多数存在した対幕強硬路線反対派の無視である。
いまひとつは,明治以降の日本人が,その実態以上に幕末期の政治過程を英雄的なものとして受け取ったため,他国ことにわが国周辺諸国に対して,変な優越感を持つにいたったことである。
特に二点目は,征韓論,対外雄飛論,そして大東亜共栄圏という発想へとつながる原因になったとまで,著者は見る。
基本的に,維新史の常識とは,勝者の歴史である。あえて言えば,勝者に拠った造られた物語である。それに対してもオルタナティブな物語を紡ぎ出そうというのである。その象徴が,敗者である,「一会桑」(と孝明天皇)からの切り口なのである。
歴史も物語であり,視点を変えると,パースペクティブも変わる,ということなのである。
さて,まず孝明天皇について,著者はこう言う。
はっきり言えば,孝明天皇が攘夷にあそこまでこだわらなかったら,日本の幕末史はまったく違ったものになったと考えられる,
と。孝明天皇は,それまでのような,「宮中の奥深くに鎮座まします,もの言わぬ,いままでのような伝統的な天皇」ではなかったのである。
だから,老中堀田正睦が,通商条約締結不可避を,理路整然と情理をもって説得しても,「理屈も何も差し置き,ただひたすら落涙」して,「頑なに受けない」まま,根を上げた堀田は,ついに朝廷側に押し切られてしまう云々。
そして,「一会桑」については,著者は,
孝明天皇が自己の代弁者とみた政治勢力,
であるとみなす。「一会桑」は,孝明天皇という強烈な攘夷思想を持つ天皇と出会い,接触を深めることで,
孝明天皇と一会桑三者は,やがて互いを必要不可欠の存在として認め合い,深く依存する関係に入る。すなわち,一会桑の三者は,孝明天皇の攘夷思想を尊重し,他方天皇は,一会桑の三者に自己の代弁者としての役割を積極的に見いだしていく。最初から攘夷志向が強かった会津関係者はともかく,一橋慶喜なども京都に定住するようになると,当初の開国論はどこへやら,天皇(朝廷)の上位実行の要請に同調するようになる。
たとえば,禁門の変直前絶望的に孤立無援に陥っていた会津藩を,孝明天皇は,会津藩を擁護する叡慮(宸翰)が下され,更に,長州藩士が京都から退去せよとの説諭に服さない場合は,直ちに追討せよとの綸旨を出す。
だから容保は,「御所向きの御都合は,一橋様・御家(会津藩)・桑名様にて悉皆御引き請け,御整遊ばされ候(松平容保の)思し召し」という,満々たる自信を持っていたと言われる。
大政奉還の意味についても,「大政奉還前と後では,徳川慶喜の置かれた状況が決定的に違う」として,著者は,こう言っている。
大政奉還前の慶喜は,いうまでもなく,反幕勢力によって激しく揺さぶられるようになっていたとはいえ,日本全国にまたがる政治を主宰(諸大名を統括)する十五代将軍の職にあった。しかし,大政奉還後の彼は,もはや将軍ではない徳川家の当主に過ぎない。(中略)
ということは,慶喜自身が,仮に大政奉還後もひき続き新しく誕生する諸侯会議(諸大名の合議制によって運営される)のリーダーとして,徳川氏中心の政治体制を保持もしくは創出していくつもりであった,つまり実権を掌握していくつもりであったとしても,それは彼個人一代でのみかのうであったということである。
さらに,
より大事なことは,慶喜が「天下の大政を議定する全権は朝廷にある。すなはち,わが皇国の制度法則,一切万機,必ず京師の議政より出つべし」とする土佐藩の大政奉還建白書を受け入れたことである。ここに大政奉還のもっとも根本的な意義が存したといえる。
という。さらに,
慶喜が王政復古(それは幕府制の廃止と徳川家の一大名家への降下を意味する)と長州藩の赦免に同意したことで,「倒幕の密勅」をもってしてまで打倒しようとした対象が消滅し,慶喜と対幕強硬派の諸藩・宮・公家との対立関係が基本的には解消されることになった…,
といい,両者の対立点を消し去る効果があったのである。そのために,対幕強硬派の挙兵へ向けての戦略が一気に崩れ,王政復古クーデターに参加した,尾張藩,越前藩,土佐藩,芸州藩が,「扶幕の徒」(大久保利通)になり,
事態をこのまま放っておけば,徳川氏および場合によっては会桑両藩を含むを雄藩連合政府が成立し,王政復古クーデターが,旧来の封建支配体制の修正・再編にとどまる危険がでてきた。
大久保らは,それを何としても,くいとめようとしたが,
かつて王政復古クーデターを決断したときよりも,遥かに大久保らに冒険主義的な選択(文字とおり「イチかバチかの大バクチ」)を迫ることになった。
鳥羽伏見の戦い前夜は,これほど紙一重の中にあり,従来のように,
薩長両藩によって展開された粘り強い,しかも一貫した武力討幕運動のもたらした成果というよりも,ワンチャンスを確実に生かした在京薩藩指導者の起死回生の策がものの見事に決まった結果といったほうが,より適切であった…。
と。
まさに視点を変えることで,異なるパースペクティブが見えてくる。そのすべてが同時に,よじれる糸のように起こったのだとみなした方が歴史の幅と奥行きが広がるように思う。
参考文献;
家近良樹『孝明天皇と「一会桑」』(文春新書)
家近良樹『家近良樹『孝明天皇と「一会桑」』』(ミネルヴァ書房) |
|
祭り |
|
春日太一『あかんやつら』(文藝春秋)を読む。
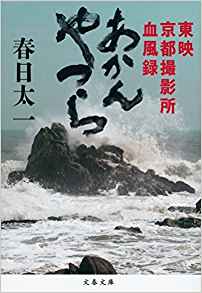
副題に,「東映京都撮影所血風録」とある。著者曰く,
京都撮影所の群像劇,
だそうだ。要は,東映京都撮影所自体が舞台である。そこに,経営者,撮影所長,プロデューサー,監督,脚本家が,どんちゃん騒ぎをしながら,走り抜けていく。まるでお祭りである。こう言う時の主役である,俳優は,この本では脇役に過ぎない。
日本映画の父,マキノ省三の二男,光雄が父意の遺産である,マキノプロダクションのスタッフとともに,創立したばかりのおんぼろ会社東横映画に,乗り込むところから,話は始まる。
大陸から引き揚げてくる映画人の救済,
という願いを,東横映画製作開始の方針となる。それにともなって,みずからの映画人生で培った人脈をフルに使って,体制固めをしていく。光雄の呼び掛けに,光雄の実兄,マキノ雅弘,異母兄,松田定次,稲垣浩,脚本家も,八尋不二,比佐芳武,小国秀雄らが呼応する。
光雄は,
右翼も共産党も関係ない!映画の好きな奴が映画を作る。ここは大日本映画党や!
という方針で,東宝争議やGHQのレッドパージで追われた人にも,活躍の場を与える。
今井正や家城巳代治にも映画を撮らせている。
夢はあっても金はなかった。そんな中で,量産こそが儲かる製作体制である,というマキノ省三から受け継いだ考えで,
少々の予算はオーバーしても,月九本作るところを更に十本作れば,一本当たりの間接費がそれだけ安くつくではないか,
の考えのもとに,ムチャクチャ作り続ける。著者はこう言う。
(東映京都で)量産された時代劇は,ほとんど通俗的なものばかりだった。そのため批評や他社のインテリ系の映画人からは「ジャリ掬い」「薄っぺらな紙芝居」と蔑まれてもいた。が,貧しい中を必死の思いで潜り抜けてきた男たちには,そんなことは全く気にならなかった。どんなことをしても映画をあてなければ,彼らはすべてを失う状況にあり,そこから必死の想いで這いあがってきた。
通俗で何が悪い。
むしろ,それこそが彼らにとっての大義であり,正義でもある。
光雄は言う,
脚本には泣く・笑う・(手に汗)握るの三要素を入れろ。それさえできていれば,あとは,頭とケツさえしっかりしておけばエエ,
物語のベースは,痛快,明朗,スピーディや,
と。そう,どこか大衆演劇一座のような,必死さと,過酷さがある。
どうしたら観客に受けるのか,
どうすれば客を呼べるのか,
それだけに血道を上げていく。そして究極の量産体制に突入していく。
年間八十本の時代劇を製作する,
という。それは,
週単位ででは二本弱。いまの連続テレビドラマの倍近いペースで映画,しかも準備や撮影に手間暇のかかる時代劇をつくっていたということになる。そのため,当時の東映京都は殺人的なスケジュールに追われていた。
という。例えばこんなふうだ。
スタッフたちの時間外労働は多い時で月に300時間近いこともあり,月給の倍近くをそれで稼ぐことになる。そして,一本クランクアップするとほとんど休みはなく,すぐに次の現場に入る。休みらしい休みは正月と盆の二日くらいしかなかった。もちろん,家に帰る暇はなかなかない。大部屋俳優たちは家に帰らずに控室で雑魚寝して,早朝からの撮影に備えたという。
まるで高度成長期の企業のようだ。ハイテンションな高揚感がつづいていく。しかし,当然映画は斜陽になり,
90年代,気づいたら東映京都の作りだす作品は「古臭さ」の代名詞になっていた。
と。死の直前,長く京都撮影所長をつとめ,社長,会長を歴任した岡田茂は,相談役高岩淡に,
京都は楽しかったなあ。特にあの貧乏だった頃,あのころが一番良かった…
と述懐する。まるで,青春時代のお祭りを振り返るようだ。
昔,早稲田祭前のクラブの出し物三つ四つが並行して,大わらわで走り回っていたときの昂揚感を思い出す。もっとそれ以上の,興奮とハイテンションがあったに違いない。カツドウヤとしてのプライドと使命がある以上。
ここでもまれて,排出された監督,脚本家は数知れないが,当然,片岡千恵蔵,市川右太衛門,中村錦之助,東千代之介,大友柳太郎,美空ひばり等々の,黄金の時代劇時代を支えたスターも,舞台に登場しては消えて行く。
その時代,スクリーンを観ていた自分にとって懐かしいのは,スターではなく,脇役だった。思い出すままに挙げていけば,原建策,阿部九州男,加賀邦男,尾上鯉之助,田中春男,吉田義男,安倍徹,汐路章,進藤英太郎,山形勲等々。
その華やかなスクリーンの背後の修羅場とお祭りを知ってみると,スクリーンのあの通俗性が,輝いて見える。
著者はこう締めくくる。
東映京都にとって,本当の戦いはこれからになる。戦いには一人でも多くの味方が必要だ。本書の最大の目的は,一人でも多くの方に「共に戦う見方」になつてもらうことにある。そこになみだはいらない。 |
|
フラクタル |
|
ベノワ・B・マンデルブロ『フラクタリスト』を読む。
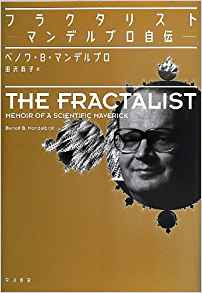
マンデルブロ集合の発明者(マンデルブロ自身は,発明ではなく,昔から存在したものの発見と言っているが),フラクタルの命名者である,ベノワ・B・マンデルブロの自伝である。本人は,最終校正直前に亡くなったが。
何しろその幅広い分野を渡り歩いた好奇心に驚かされ,そして,数学,言語,経済,フィナンシャルから物理学,天文学,数学まで多岐に渡る成果を残しているのも,また脅威だ。しかも,大学にではなく,IBM研究所に在籍したまま。
本人は,こう言う,
ケプラー的夢,
を追い続けたと。ケプラー的夢とは,次のようなものだ。
ケプラーは二つのものを結びつけたのだ。古代ギリシャの幾何学者が発見した楕円を,惑星運動には常に,変則が存在するという古代ギリシャの天文学者の誤解と結びつけたのだ。ケプラーは数学と天文学としいう二つの分野で自らの持つ知識を利用して,この惑星運動が変則ではないことを確かめた。変則と思われていたものは,じつは楕円軌道だった。このような発見をすることが,子ども時代の私の夢となった。
その夢を,マンデブロウは実現したことになる。その初めは,
語の出現頻度
であり,続いては,フィナンシャルでの,
相場価格変動,
であり,いずれも,著者の「ラフネス」と呼ぶ,「変則」の数学的解析である。結果として,それが,著者が,
フラクタル,
と名づけた領域にたどりつく。フラクタルとは部分と全体が互いに相似な図形である。で,昔読んだ,稲垣足穂が,星雲の渦巻きと蝸牛の渦巻きを対比させていたのを思い出す。
著者は言う。
二種類のフラクタルの区別に辿り着いた。フラクタルには,自己相似(海岸線のように,どの方向についても同じ割合で縮尺される図形)と自己アフィン(乱流のように,方向によって縮尺の割合が異なる図形)の二種類があるのだ。
と。そのフラクタル,とは,1975年に,著者が命名した。ラテン語の,
Fractus(割れた,砕けた)
から考え出した。面白いのは,
私の刺激を受けてあとに続く人たちを,言い表す言葉が必要になった場合には「フラクタリスト」という言葉の響きがよさそうだということもあらかじめ確認しておいた。
という発想だ。すでに,その重要性を,そのように予見できていたのだ。
有名な,マンデルブロ集合は,
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AD%E9%9B%86%E5%90%88
にあるように,さまざまな図形が見られるが,これを描くために使われるのは,
zn+1 = z2/n + c
z0 = 0
というシンプルな式だ。コンピュータで何度も繰り返して結果を平面上に表示すると,マンデルブロ集合が出現する。若い頃,数式を幾何学図形に置き換えて理解していた著者の才能の,見事な顕現と言えなくもない。
この図形の例として引き合いに出されるのが,カリフラワー。一株のカリフラワーをいくつかにわけると,小房は元のブロッコリーとそうじだが,小房は,更に小さな小房の集まりであることに気づく。さらにその小房は…と続く。
このマンデルブロ図形は,自然界だけではなく,絵画にも多く見られる。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%A6&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-P6OUorWBMjKlAXP_IHwBQ&ved=0CEYQsAQ&biw=1366&bih=666
マンデルブロの発想を見ていると,
既存の要素の組み合わせ,
という創造性の原則,もっというと,川喜多二郎が言う,
本来ばらばらで異質なものを意味あるように結びつける,
ということを思い出させる。彼は最後に,バーナード・ショーの言葉で自伝を締めくくった。
理性的な人間は,自分を世界に合わせる,
理性を欠く人間は,世界を自分に合わせる努力を続ける。
したがって,すべての進歩は理性を欠く人間にかかっているのだ。
と。
参考文献;
ベノワ・B・マンデルブロ『フラクタリスト』(早川書房) |