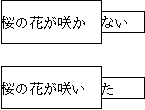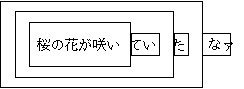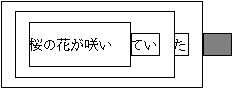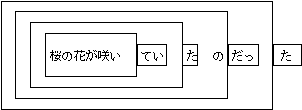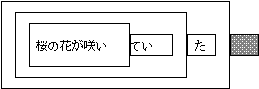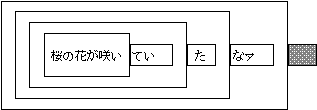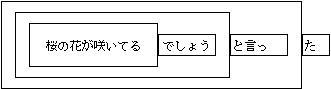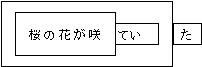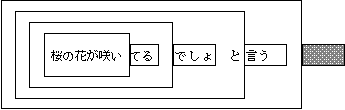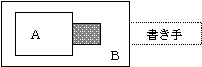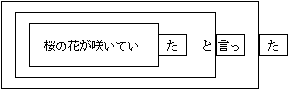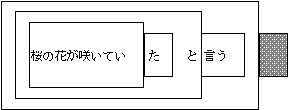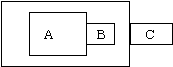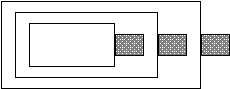文学の眺めはすべて一つの眺めである。あたかも記述者が描写する前に窓際に立つのは,よく見るためではなく,みるものを窓枠そのものによって作り上げるためであるようだ。窓枠が景色を作るのだ。(ロラン・バルト『S/Z』)
語りのパースペクティブとは、語るものがどこから、どこまでを視野に入れて、語られるものについて語っているのか、ということにほかならない。ここで必要なのは、「誰がしゃべっているのか。」
(R・バルト、前掲書)を明確化することではない。書き手であれ、語り手であれ、主人公等作中人物であれ、ここでは関係ない。語っている〃とき〃(ところ)から語られている〃とき〃(ところ)までの奥行、つまり語りがどこまで届いていくかという深度のみが問題なのだ。
1.語りの位置
周知の通り、時枝誠記氏は、日本語では、
における、「た」や「ない」は、「表現される事柄に対する話手の立場の表現」(時枝誠記『日本文法口語篇』)、つまり話者の立場からの表現であることを示す「辞」とし、「桜の花が咲く」の部分を、「表現される事物、事柄の客体的概念的表現」
(時枝、前掲書)である「詞」とした。つまり、(詞)は、話し手が対象を概念としてとらえて表現した語です。「山」「川」「犬」「走る」などがそれであり、また主観的な感情や意志などであっても、それが話し手の対象として与えられたものであれば「悲しみ」「よろこび」「要求」「懇願」などと表現します。これに対して、(辞)は、話し手のもっている主観的な感情や意志そのものを、客体として扱うことなく直接に表現した語です。
(三浦つとむ『日本語はどういう言語か』)
そして、終止形等のように、「認識としては存在するが表現において省略されている」
(三浦、前掲書)場合の、「
」部分は、「言語形式零という意味」(三浦、前掲書)で、ゼロ記号と呼んでいる。いずれにおいても、が、日本語の表現構造になっており、辞において初めて、そこで語られていることと話者との関係が明示されることになる。即ち、
第一に、辞によって、話者の主体的表現が明示される。語られていることとどういう関係にあるのか、それにどういう感慨をもっているのか、賛成なのか、否定なのか等々。
第二に、辞によって、語っている場所が示される。目の前にしてなのか、想い出か、どこで語っているのかが示される。それによって、〃いつ〃語っているのかという、語っているものの〃とき〃と同時に、語られているものの〃とき〃も示すことになる。
さらに第三に重要なことは、辞の〃とき〃にある話者は、詞を語るとき、一旦詞の〃とき〃〃ところ〃に観念的に移動して、それを現前化させ、それを入子として辞によって包みこんでいる、という点である。
三浦つとむ氏の的確な指摘によれば、
われわれは、生活の必要から、直接与えられている対象を問題にするだけでなく、想像によって、直接与えられていない視野のかなたの世界をとりあげたり、過去の世界や未来の世界について考えたりしています。直接与えられている対象に対するわれわれの位置や置かれている立場と同じような状態が、やはりそれらの想像の世界にあっても存在するわけです。観念的に二重化し、あるいは二重化した世界がさらに二重化するといった入子型の世界の中を、われわれは観念的な自己分裂によって分裂した自分になり、現実の自分としては動かなくてもあちらこちらに行ったり帰ったりしているのです。昨日私が「雨がふる」という予測を立てたのに、今朝はふらなかつたとすれば、現在の私は
予想の否定 過去
雨がふら なくあっ たというかたちで、予想が否定されたという過去の事実を回想します。言語に表現すれば簡単な、いくつかの語のつながりのうしろに、実は……三重の世界(昨日予想した雨のふっている〃とき〃と今朝のそれを否定する天候を確認した〃とき〃とそれを語っている〃いま〃=引用者)と、その世界の中へ観念的に行ったり帰ったりする分裂した自分の主体的な動きとがかくれています。 (三浦、前掲書)
つまり、話者にとって、語っている〃いま〃からみた過去の〃とき〃も、それを語っている瞬間には、その〃とき〃を現前化し、その上で、それを語っている〃いま〃に立ち戻って、否定しているということを意味している。入子になっているのは、語られている事態であると同時に、語っている〃とき〃の中にある語られている〃とき〃に他ならない。
これを、別の表現をすれば、次のように言えるだろう。
日本語は、話し手の内部に生起するイメージを、次々に繋げていく。そういうイメージは、それが現実のイメージであれ、想像の世界のものであれ、話し手の内部では常に発話の時点で実在感をもっている。話し手が過去の体験を語るときも、このイメージは話し手の内部では発話の時点で蘇っている。
(
熊倉千之『日本人の表現力と個性』)
重要なことは、主体的表現、客体的な表現といっても、いずれも、「話し手の認識」
(三浦、前掲書)を示しているということだ。例えば、という表現の示しているのは、「桜の花が咲いてい」る状態は過去のことであり(〃いま〃は咲いていない)、それが「てい」(る)のは「た」(過去であった)で示され、語っている〃とき〃とは別の〃とき〃であることが表現されている。そして「なァ」で、語っている〃いま〃、そのことを懐かしむか惜しむか、ともかく感慨をもって思い出している、ということである。この表現のプロセスは、①「桜の花が咲いてい」ない状態である〃いま〃にあって、②話者は、「桜の花の咲いてい」る〃とき〃を思い出し、〃そのとき〃にいるかのように現前化し、③「た」によって時間的隔たりを〃いま〃へと戻して、④「なァ」と、〃いま〃そのことを慨嘆している、という構造になる。
ここで大事なことは、辞において、語られていることとの時間的隔たりが示されるが、語られている〃とき〃においては、〃そのとき〃ではなく、〃いま〃としてそれを見ていることを、〃いま〃語っているということである。だから、語っている〃いま〃からみると、語られている〃いま〃を入子としているということになる。しかし、これが、
と、辞( )がゼロ記号となっている場合は、外側の辞による覆いがない状態、つまり入子の語りの部分が剥き出しになった状態と言っていい。辞としての、〃いま〃での話者の感嘆を取っただけなのに、こうしてみると、前者と比べて、明らかに〃とき〃の感じが重大な変化を受けていることがわかるはずである。つまり、前者では明らかに〃いま〃から話者が語っているということがはっきりしているのに、後者ではそれがはっきりしなくなっている。
そのため第一に、〃いま〃という辞を取ることで、〃いま〃の中に入子となっていた〃とき〃が剥き出しとなる(〃いま〃の直前、つまり完了を表すということもあるが、「なァ」の〃とき〃よりは過去)。そのことによって、「なァ」でははっきりしていた〃いま〃からの時間的距離
(つまり時制)が曖昧化する。前出の例で言えば、「咲いていた」のが、〃そのとき〃であったのに、(〃いま〃からみた〃そのとき〃ではなく)〃いま〃であるかのように受け取れる。だから、「咲いていた」のが、過去というよりは、完了状態を現しているニュアンスが強まっている。それは、①「た」が辞の位置にあることになる。つまり、「た」という主体的表現は、話者の語っている〃いま〃となる。②そのため「花が咲いてい」る〃とき〃とそれを語っている〃とき〃との関係が新たなものになっているからにほかならない。
その結果、第二には、そのことによって、「なァ」では、「なァ」と慨嘆していた話者の主体的表現であったものが、その表現を囲んでいた辞(つまり、□)が取られることで、あたかも客観的(事実)の表現(客観的に起こっている(ある)ことの表現)であるかのように変わってしまう。だから、「咲いている」のが、〃いま〃「既に(もう)」咲いている現実を表現しているように変わっていく。
しかし、「た」は過去ないし完了を示す辞ではなかったか?そうならば、「た」に立って語るとは、「なァ」の有無に関わらず、その語っている〃とき〃からの過去であることを示しているはずではないのか。
だが、日本語の過去あるいは完了の助動詞「た」は、
(時枝、前掲書)起源的には接續助詞「て」に、動詞「あり」の結合した「たり」であるから、意味の上から云つても、助動詞ではなく、存在或は状態を表はす詞である。……このやうな「てあり」の「あり」が、次第に辭に轉成して用ゐられるやうになると、存在、状態の表現から、事柄に對する話手の確認判斷を表はすやうになる。
とあるように、「過去及び完了と云へば、客觀的な事柄の状態の表現のやうに受取られるが、この助動詞の本質は右のやうな話手の立場の表現」(同)であり、むしろ、判断を示していると見たほうがよく、その場合、問題なのは、それが〃そのとき〃の判断なのか、〃いま〃の判断なのか、が混然としている点なのだ。なぜなら、〃いま〃からみて〃そのとき〃「咲いて」いたという過去についての表現なのか、それとも〃そのとき〃見たとき、既に「咲いて」いたという状態の完結(完了)を示すものなのか、は判然と区別はできないからだ。
この「た」の意味は、次のように変えてみると一層はっきりする。
つまり「た」という判断が、〃いま〃からみた過去だったということを敢えて表現するためには、こうしなくてはならないということだ。ということは、「桜の花が咲いて」いる状態を指摘しているのを語っているのが、〃いつ〃のことなのかを示す機能を「た」はもっていないということにほかならない。つまり、「た」は、語っている〃とき〃を隠されている。終止形のゼロ記号の状態にあるのと同じなのである。だから、「なァ」という〃いま〃を示す辞を失うことで、「た」は過去としてのニュアンスを失い、「(〃いま〃の)判断」なのか「(〃そのとき〃)既に」なのかの区別が曖昧化してしまっている、ということができるだろう。
しかし、同じゼロ記号でも、前述の、
と、
では、異なっている。後者は、主体的判断そのものがゼロ記号化されているのに対して、前者は、判断の〃とき〃がゼロ記号化され、「た」という判断が〃いま〃であるかのように語られている。
つまり、後者では、「桜の花が咲く」とは、主体的な時間に関わった表現ではなく、一般的に「桜の花
(というものは)咲く(ものだ)」という概念的意味か、あるいは桜の花が咲いている(事実の)状態を客観的に表現しているかの意味に変わる。それに対して、前者では、「た」が残ることによって、主体的表現は残されており、ただそれが〃いま〃なのか〃そのとき〃なのかが曖昧化され、〃そのとき〃=〃いま〃として表現されている、ということになる。
このことから、敷衍すれば、ゼロ記号化によって、話者のいる〃とき〃を隠し、全く客観的表現を装うこともできるし、起きている出来事(あるいはそれへの主体的表現=辞)を同時進行にドキュメントしている擬制もとれるという、二つの機能をもつことになる、といえるのである。
だが、問題はここからである。これが話し言葉であるならこれで問題は終わる。しかし、そう書かれているのだとするとどうなるのか。そう書いたのはいつなのか?
もし、書いたのが〃いま〃だとすれば、図のように書き改められることになる。
つまり、①「桜の花が咲いてい」ない状態である〃いま〃にあって、②話者は、「桜の花の咲いてい」る〃とき〃を思い出し、〃そのとき〃にいるかのように現前化し、③「た」によって時間的隔たりを〃いま〃へと戻して、④「なァ」と、〃いま〃そのことを慨嘆している、⑤というように、書き手が書いている〃いま〃にいて、語っているということになる。これがこの語りを語っている本人であれば語り手となるが、それが別の誰かの語りを〃いま〃写したのだとすれば、ゼロ記号の箇所は「と、言う」ということになる。それが語っている〃いま〃より前となれば、「と言う+た(言った)」となる。
ここに明らかになっているのは、語られていることの入子の奥行と、語るものの視点の奥行、つまり認識構造の奥行にほかならないということだ。そしてこのことは、入子の深度に応じた認識の深度になっているというように、入子の奥行が、語るものの認識構造の奥行と対になっているということだ。多くの場合、書かれたものの外郭の□がゼロ記号化していることを意識しないでいる。しかしそれでは、「話し手の認識」の構造をつかんだことにはならない。
以下、特別に指摘しない限り、「語る」〃いま〃とは、そう語り手が書かれた〃とき〃にいて語っていることだとみなしている。
さて、次の場合はどう考えたらいいか。
「と言った」とあることが、語る=書く〃とき〃を示していると考えると、本来の構文から考えれば、話者の辞は、入子になった話者の「〜でしょう」と「言っ」たことを現前化している。しかし、話者はここまで語ったとき、入子となった話者の語っている「桜の花が咲いてる」という事態自体をも現前化しているのである。
つまり、話者が「た」という辞で括ったとき、まず「〜でしょう」と推測した時点での語りを入子として、「桜の花が咲」く状態を想定し(”そのとき〃の発話の状態に〃なり〃)、その上で、それが〃いま〃からみた過去(完了なら直前)だったとまとめていることになる。
更にそこから敷衍すれば、入子になった話者は、「桜の花が咲いている」事態を現前化した上で、それを推測している。その推測を〃そのとき〃聞いたことを、〃いま〃示すことで、話者は、その推測によって縛られていることを示している。〃そのとき〃推測したが今は違うのか、その推測通りになったのか、それともその推測で違う事態がもたらされたのか、いずれにしても、入子の話者の見たものに〃いま〃見られている。だからこそ、それを語った話者は、「でしょう」という推測を「言っ」たことを語ることで、実は、入子の話者の見ているものをも見ている、といえるのである。
例えば、
を例に取って考えれば、もっとわかりやすいはずである。ここで、語っている「た」に立った語るものは、その桜を現前化しつつ、その桜にも見られているのにほかならない。語っている〃いま〃から〃そのとき〃を見るとき、その過去の〃とき〃が〃いま〃を照らしている(「た」を完了とみなせば、完了前つまり「咲く」前の〃とき〃が〃いま〃を照らす)。〃そのとき〃は咲いていたが、〃いま〃は咲いていない(完了なら、〃そのとき〃は咲いていなかったが、〃いま〃は咲いている)、というように。そしてそのことによって、〃いま〃は〃そのとき〃に比較して語られている。でなければ、桜の咲いていたことを〃いま〃思い出して語る必要は語り手にはなかったはずなのだ。
だから重要なことは、こうした日本語の語りの構造を考えたとき、実は、語る→語られるは、入子構造になることで、語るものの一方通行ではないということなのだ。
このことは同様に、次のようにゼロ記号化されていても事態は変わらないはずである。
ところが、ゼロ記号化されることで、「でしょう」と推測しているのは、〃いま〃である擬制をとる(前述の入子の部分が剥き出しになった状態)。「でしょう」と推測する相手の「言う」のを語っている話者は、その場で、「『〜でしょう』」と言う」のを見ている形になる。表現上は、現前化されているのは相手の「言う」事態でしかない。つまり話者は、「と『言う』」のを見ているだけで、「桜の花が咲いてる」のは語られたのをそのまま語っているだけだ。
その場での感慨にしろ、過去の想い出にしろ、あるいは推測にしろ、そうした主観の表現を省略したとき、一見表現されたものは、そのとき話者がそれを同時的に見ているという擬制的な客観描写にみえることによって、話者のパースペクティブは、「言う」ことにしかとどかなくなるということである。ゼロ記号によって、しかし、話者の〃いま〃は消えても、むろん話者の存在までが消えてしまう訳ではない。
つまり辞は、いわば、「観念的に二重化し、あるいは二重化した世界がさらに二重化するといった入子型の世界の中を、われわれは観念的な自己分裂によって分裂した自分になり、現実の自分としては動かなくてもあちらこちらに行ったり帰ったりしている」
(三浦、前掲書)自由を保証しているということができる。それは、詞を主体的な表現で包むとは、観念的世界であるということを表示していることでもあるということを意味する。たとえば、
語っているもの |
というように、詞と辞の境界を空間的に示してみれば、話者の位置は、線を境にして、時間的空間的に隔てられている。しかし観念的には、時間的隔たりにすぎない。過去について思い出すとき、語られているもの
(こと)の〃とき〃と〃ところ〃にいるような実感をもっても、語られているのは時間的に前のことだ。また、推測ないし想像によって、〃いま〃の別のところにいる誰かについて、そこにいるつもりになることもできる。それが「観念的な自己分裂」にほかならない。しかし辞があるかぎり、それとの隔たりは明示される。ところが、ゼロ記号のときは、辞が消え、語られている の〃とき〃が剥き出しとなることで、〃とき〃も〃ところ〃も明示なく変わってしまう。〃そのとき〃であったものが、〃いま〃であるかの擬制をとる。
それは、辞が表記されていないだけ、話者(話者のいる〃とき〃)を隠して、いかにも客観的事実(同時的現実)を表現しているように見えるというのにすぎない。話者そのものが消えることではなく、 の背後に、確かに話者がいるのに違いはない。
こうした事情は、文学作品における語りにおいても同断のはずである。ただし、作品においては、語ることと語られることとは共に虚構であるということに注意しなくてはならない。
言述の作者として、語り手は実際に、現在−物語行為の現在−を決定するが、その現在は、物語言表行為を構成する言述の現前化行為と同様に虚構である。
(
P・リクール、久米博訳『時間と物語』)ということを前提とすれば、辞とは、ここでは(虚構の)語り手の語っている〃とき〃ということになる。辞をはっきりさせ、そこから、〃あるとき〃を語っている、
物語的言表行為がもつ……特性とは、言述そのものの中で、言表行為と、物語られる事がらの言表とを区別する特徴を言表行為が提示すること
(リクール、前掲書)にほかならない。これを、先の日本語構文の分解に倣って、図示すれば、次のようになるだろう。
|
↓ |
|
語っている時点 |
で、ゼロ記号化とは、「語り手のいる時点」が消されていることにほかならない。それをどう呼ぶかは別にして、それは、「物語られている時間の流れそのもの」が剥き出しにされていることにほかならない。
しかし、辞のゼロ記号化の場合と同様、
語り手がいなければ「物語」の存在はありえない。「話」の見かけ上の「非人称」も結局は必ず「人称」なのであり、結局は「言説」である。
(
ウォー、結城英雄訳『メタフィクション』)こと、あくまで擬制的であることを忘れてはならない。
この間の消息について、古井由吉氏は、書き手の状況から、次のように言っている。
とにかくある人物ができかかって、それが何者であるかを表さなくてはならないところにくると、いつも嫌な気がしてやめてしまう。そんなことばかりやつていたんです。で、なぜ書けるようになったかというと、本当に単純なばかばかしいことなんです。「私」という人称を使い出したんです。……そうしたらなぜだか書けるんです。今から考えてみると、この「私」というのはこのわたしじゃないんです。この現実のわたしは、ふだんでは「私」という人称は使いません。「ぼく」という人称を選びます。この現実のわたしは、ふだんでは「私」という人称は使いません。「ぼく」という人称を選びます。だけど「ぼく」という人称を作品中で使う場合、かえってしらじらと自分から離れていくんです。(中略)
……この場合の「わたし」というのは、わたし個人というよりも、一般の「私」ですね。わたし個人の観念でもない。わたし個人というよりも、もっと強いものです。だから自分に密着するということをいったんあきらめたわけです。「私」という人称を使ったら、自分からやや離れたところで、とにもかくにも表現できる。で、書いているとどこかでこの「わたし」がでる。この按配を見つけて物が書けるようになったわけです。
(
『「私」という白道』)この虚構の「私」とは、むろん虚構の辞であり、虚構の現在に語っている〃いま〃をおいているのにほかならない。
この意味するところは、
(R・バルト、沢崎浩平訳『S/Z』)私と称することは確実に記号内容を自分に引き受けることである。それはまた、伝記的な時間を自分のものにすることであり、想像の中で、知覚し得る《進化》に従うことであり、自分を運命の対象として意味づけることであり、時間に意味を与えることである。
と考えて間違いはない。ここでの文脈で言えば、語りの「私」を明示することは、辞を明確化することであり、このことは、先の例でいえば、ゼロ記号化による擬制的語りを拒否していることに他ならない。それについて、少し前で、
……小説であれば一応人物がでますよね。主人公。それを何と呼ぶか。私小説を書く了見はなかったんです。ならば山田でも林でも何でもいい、勝手に人物をつくり出すことにそう良心もとがめないんだけれど、名前をつけるとなると何となくやましい、自己嫌悪も強い。一方では何だかリアリティを失っていくようで、……。
(
古井由吉、前掲書)と語り、ともかく出発点では、ゼロ記号としての語りへの拒絶反応を示しているようなのである。
ところで、ヴァインリヒ氏は、語りの時制について次のように指摘している。
われわれは多くの場合、話者や聞き手に直接関与し、すでに周知であるか当面念頭にある事柄を説明することが多い。……それには時間的規定がさほど必要ではない。
しかしわれわれが語るときには、その発話の場から出て、別の世界、過去ないし虚構の世界へ移る。それが過去のことであれば、何時のことであるかを示すのが望ましく、そのため物語の時制と一緒に……正確な時の表示が見られる。
(
ヴァインリヒ、脇阪豊他訳『時制論』)つまり、「語り」とは、語っている〃とき〃とは別の〃とき〃について語ることに他ならない。そして語り手が語っている〃とき〃との関わりで、どういう〃とき〃のことかを示さなくてはならない。だから、語りの時制とは、語り手が〃いま〃とは別の〃とき〃について語っているということの指標にほかならない。
それに対して、「説明」とは、語られることが語っている〃いま〃であることを意味する。だから、語られることが〃そのとき〃であっても、語っているものの感慨は〃いま〃であるということもありうる。語られたことが過去であるとか、それに対する感慨を示すとかによって、語っている〃いま〃を示すのは、日本語の例で言えば、辞に該当することになる。
過去の事柄を「語る」のではなく「説明する」とすれば、それはまさに完結した事柄ではなく、現在あるいは未来の事柄と同様、まさに自分の世界に属し、それへの配慮から説明するものだからである。それは一種の過去ではあるが、自ら行為する時と同じ言葉で表現するのだから、自ら関与する過去である。そして過去を説明しながら表現することによって、同時に自分の現在と未来を変えるのである。それは……語られた世界をそのままにしておく語り手の落ち着いた冷静さとはおよそかけ離れている。(中略)……われわれが現在完了で過去の事柄を説明するというのは、いわば過去を「語る」ことによって、われわれの存在と行動から切り離して閉じ込めてしまうのではなく、「説明する」ことによって、過去をわれわれの存在と行動のために開いたままにしておくことなのである。
(
ヴァインリヒ、前掲書)それは、「説明」が、「話者や聞き手に直接関与し、すでに周知であるか当面念頭にある事柄を説明することが多い」のに対して、「語る」ときは、「その発話の場から出て、別の世界、過去ないし虚構の世界へ移る。それが過去の世界であれば、何時のことであるかを示すのが望まし」いのは当然で、そこに時制の必要性が生ずる、というわけである。
その意味で、ヴァインリヒ氏の言う時制は、語り手が語っている〃とき〃にいて語っているのか、語られている〃とき〃を語っているのかを示す指標であり、それによって、語り手からの距離を示し、語りに入ったとき、語りから戻ったとき、特有の時制に変わる、ということを言っているのである。
しかし、日本語の場合は事情が異なる。
(き+あり)」に含まれる存在詞「あり」の力だ。「今は(昔〔男あり〕き)あり」というふうに分解できるような表現で、「男あり」という事象が、「昔……き」というように、時間の副詞「昔」と助動詞「き」によって、過去のイメージとして物語の語り手の意識のうちに回想され、それを「今は……あり」と聞き手の前に、「今ある」ように表出する。(中略)古い日本の物語は「今は昔……」と始まる。典型的な例は『今昔物語』などにみるように、「今は昔男ありけり」だ。……この「今」は、語りの現在であり、語り手の意図は、「昔いた男」というイメージを、語りの場に蘇らせることだ。それを可能にするのは、助動詞「けれ
そこで、日本語には、過去・現在・未来という時間の線上に客観的に提出される、西欧語の時制がない。しかし、これは日本語が過去や未来を弁別しないということではなく、過去も未来も話し手
(語り手)の現在に持ち込まれて表現されるのだ。(中略)西欧の物語が、物語の出来事は語られる以前に起きていなければならないという理由から、過去が基本的な物語の時制となるのに対し、日本語の物語のそれは、語り手の意識に蘇る心理的な現在なのだ。
(
熊倉、前掲書)このことは、日本語の構造から容易に想像できる。つまり、詞、すなわち語られていることは、語っている〃いま〃ではなく、いったん語られているものの〃とき〃を現前化し、時間的隔たりを下りながら、再び語っている〃いま〃へと戻ってくる。
だから日本語では「説明」「語り」といった区別される時制的表現をもたないが、時制がないのではない。全体として辞が語られるものを(詞)を包み、語っている〃いま〃へと戻す。その戻すプロセスに時間的隔たりはきちんと表現されている。「過去も未来も話し手(語り手
)の現在に持ち込まれて表現される」(熊倉)というのは、入子になって〃そのとき〃を〃いま〃として語りながら、時間的隔たりを飛ぶことを示す辞によって、語っている〃いま〃に戻り、それが話者の主体的表現でしかなかったことを示すという意味でなら、誤ってはいない。しかし〃そのとき〃がいつも語っている〃いま〃に持ち込まれて、現在として語られているというのなら、正確ではない。語られたことが、〃いま〃とされるのは、まさに眼前のことを語っているのでなければ、語られることの〃とき〃と〃ところ〃を現在として、現前化している入子の語りであるか、語っている〃とき〃がゼロ記号化されている語りであるか、の二つに限られる。それはいずれにおいても、語り手が擬制的にゼロ化されているからにすぎない。その限りで、〃そのとき〃はあたかも〃いま〃として現前化されるが、それは語っている〃いま〃に辷り込むから現在的に語るのではない、逆である。語られている〃そのとき〃を〃いま〃として現前化するから、そのとき語りは現在形になるにすぎない。
そして話者の辞へと戻るとき、一気に語られる〃とき〃と語っている〃とき〃との時間的隔たりが顕在化し、現前化(現在として表現)されていた入子になった部分が、〃いま〃ではなく、〃そのとき〃でしかなかったことを明らかにすることなのだ。ゼロ記号でも構造的には、その部分が隠されているにすぎない。
逆に言えば、入子の表現をどこまで遡っても、〃そのとき〃は現在として現前化される。その意味で、日本語では、一方で、辞を通して、話者の主体的表現の声が消えないのと同時に、どれだけ複雑に時間を遡っても、あるいは時間を下っても、またどれだれ入子の重なった表現でも、その遡及先は現前化されている、ということが重要なのだ。「それが現実のイメージであれ、想像の世界のものであれ、話し手の内部では常に発話の時点で実在感をもっている。話し手が過去の体験を語るときも、このイメージは話し手の内部では発話の時点で蘇っている」
(熊倉、前掲書)とは、その意味でなければならない。また熊倉が言う、「西欧の物語が、物語の出来事は語られる以前に起きていなければならないという理由から、過去が基本的な物語の時制となる」かはあくまで言語の構造上の差異にすぎず、問題が時制の有無にないことは明らかである。
(リクール、前掲書)物語は作家が書きはじめるところで止まる。
のは日本の作家でも同じであって、
小説というのは原則として過去形で書くべきものなんですよね。過去に起こった出来事を人に伝えるわけだから。
(
古井『「私」という白道』)と、意識としての姿勢に変わりはない。同一の姿勢をもっている。もっていても、それは日本語の構造から制約されるというべきである。むしろ、ヴァインリヒ氏の措定した、「語り」と「説明」の指標としての時制に代わる機能として、辞と辞のゼロ記号化を考えみるべきではないかと思う。
日本語では、辞において、語られていることとの時間的隔たりが明示される。そして入子となっている語られていることの語り(あるいはゼロ記号化した語りも)においては、その時間的隔たりがゼロ化され、〃いま〃語っているように語られることによって、「言表される事がらと、言述の現前化行為との同時性を示す」
(リクール、前掲書)〃とき〃(現在)にあることとなる。そして、辞の時制によって、語っている〃いま〃へと復帰する。この意味で、日本語はヴァインリヒ氏が例にした印欧語とは逆に、語られることを語っている〃とき〃は〃いま〃として、「説明」の時制である、現在形や完了形で表現される。そしてむしろ辞へと戻ったとき、辞を表す助詞、助動詞等によって、語られたことが、語っている〃とき〃とどういう関わりがあるかが表現される。過去だとか判断だとか否定だとかを示す辞において、結果として語られたことが、「説明」か「語り」かが表現される。これは膠着語としての日本語の特徴にほかならない。同時に、現在形や完了形の表現は、ゼロ記号化の場合があり、その場合、それが「語り」なのか事実を表現している「説明」なのかの区別がつかないことになる。
それは、日本語が、「語り」と「説明」の区別をつけていない言語なのだというふうに考えるべきなのではあるまいか。つまり、語られている〃とき〃に立っている限り、そこで語られていることが、入子の語りとして現在形で語られているのか、ゼロ記号化した語りなのか、語っている〃いま〃客観的事実を述べているのか(この三者はいずれもゼロ記号化した語りと区別つかない)を区別することはできない。区別する時制もそれに代わる指標ももっていない。あるのは、その語りが辞へと戻るかどうかだけだ。そこで初めて、過去か〃いま〃の判断かが示される。そこで、ヴァインリヒ氏の「説明」と「語り」の区別がつくだけである。むしろその意味で言えば、敢えてヴァインリヒ氏に準れるならば、「詞」が客体的表現でありながら、むしろ〃いま〃から観念的に「自己分裂」した「語り」であり、「辞」が主体的表現として〃いま〃語られていることを明示する「説明」に当たると言えなくもないのだ。
とすると、こういうことが言えるのである。入子の語りにしろ、ゼロ記号化された語りにしろ、語られていることは、観念性の表示が消え、〃いま〃の客観的現実を表現しているように擬制的に言表される。その限りで、それが事実か想像か物語かは区別されない。それは〃いつ〃〃どこから〃〃誰か〃を特定できない語り手が、語られている〃いま〃すすんでいる事態をそのまま映しているかのような位置にあることを、括弧つきでながら、あらわにしているのである。
ところで、辞の〃とき〃とは、「物語は作家が書きはじめるところで止まる。」
(リクール、前掲書)、その〃とき〃にほかならない。その〃とき〃から照射されることによって、語られたことは、たちまち主体的に彩られたものへと変わってしまう。それに対して、ゼロ記号では、〃いま〃起きつつあるかのように語っている擬制のまま戻る〃とき〃はもたない。一体〃いま〃起きていることを、どこで見ているのか?いつどこでそれを語っているのか?それをいつどこで書いているのか?は、隠蔽される。それは、次のように分解できる。
つまり、本来語り手の「辞」(語っている〃とき〃)がゼロ記号化することで、語り手の後ろに隠れていられた書き手が、語り手への〃自己分裂〃が擬制的に消され、直接語られている〃とき〃(A)に直面することになる。それは、語り手のいる〃とき〃( )を消して、書き手の現実と虚構の「現実」との疑似的なドッキングをもたらすことになる。
〃いま起きつつある〃ことを〃いま〃書いているという擬制は、語っている〃とき〃と書いている〃とき〃とを共に消す(隔たりがないふりをする)ことが必要だ。あたかも〃いま〃〃ここ〃にいるかのような、ということがもたらすのは、劃き割りの視野にほかならない。ちょうど映画のセットが剥き出しに、現に連続した状態に譬えることができるかもしれない。しかし、見えないものを語るためには、観念の入子を必要とする。とすれば、語りの光源を生み出し、ゼロ記号化を脱するしかない。
古井氏の言う「私」を語り手にするとは、そういう擬制がとりにくくなることを意味する。常に「私」の見たものであり、「私」の時間の流れの中であり、そして自分の意味の中での時間である、ということなのである。
それは、〃いま〃起きつつあることを写すという擬制が、時空の客観的制約の中に押え込まれる(科学論文を極北とする)のに対して、「私」あるいは語り手の時空(というより、私的な時間のなかで時間化された空間)の中で、自由な主観的奥行をもつことができるという結果にほかならない。
さらに、辞がそのように入子にする語りを抱え込む(奥行をもつ)ことが、単に語るものからの一方通行だけにはならないのも当然の帰結なのである。というのも、あくまで辞という私的な表現の中に包まれた自己分裂にすぎないからであって、次のような図で考えてみれば、
|
(書き手) |
作中人物にとって、語り手は、語るものであり、「 」にとっては、作中人物が語るものである。そして逆に言えば、「 」を語ることで、実は作中人物は「 」に語られている。同様に、作中人物を語ることで語り手は作中人物に語られていることなのである。なぜなら、辞とは私的な、主体的表現なのであって、それを語ることは自らを語ることになるからであるのにほかならない。そして、いうまでもなく、外郭が、書いている〃とき〃にほかならない。その〃とき〃は、語られた〃とき〃を問題にする限り、一切視野の外の〃とき〃にほかならない。
とすれば、問題は、
(リクール、前掲書)物語られる世界は人物の世界であり、それは語り手によって物語られるのである。(中略)人物が自分の経験について語る言説を物語世界に合体させるとき、言表行為=言表……を人物化させる用語によって再定式化することができる。すなわち、言表行為は語り手の言説となり、言表は人物の言説となる。とすると、問題は、どのような物語の手法によって物語は人物の言説を物語る語り手の言説として構成されるかを知ることだけである。
むろん作家自身が、である。しかし、辞と辞のゼロ記号化と、どちらの語りが実り多いかは比較することはできない。それは方法上の問題にすぎないからだ。
2.語りの奥行
さて、愈々古井由吉氏の語りについて検討するときである。いままで、蜒々日本語の構造を取り上げてきたのも、故のないことではないのである。
まず、古井氏の語りの、典型的な一例を取り上げてみる。
腹をくだして朝顔の花を眺めた。十歳を越した頃だった。
(『槿』)「腹をくだして朝顔の花を眺めた」とあれば、読み手は、話者が朝顔を眺めている場面を想定する。しかし続いて、「十歳を越した頃だった」とくると、なんだ、想い出の中のことだったかと思い知らされる、ということになる。しかし、ここに古井氏の語り構造の特徴がある。こういう次第を普通の(?)表現にしてみれば、
十歳を越した頃、腹をくだして朝顔の花を眺めていたことがあった。
となるだろう。両者のどこが違うのか。前節で取り上げたように、構造上は、「腹を下して朝顔の花を眺めてい」る場面が「た」によって客観化され、現前化されて、その上で、それが「十歳を越した頃」で「あった」と、過去のこととして時間的に特定され、語っている〃いま〃へと戻ってくるという構造になることはいずれもかわりない。
つまり、そう語る心象においては、一旦現前化された「朝顔の花を眺めてい」る場面が想定されており、その上で、〃いま〃へと戻って来ることで、時間的隔たりが表現されることとなる。
この日本語的表現からみた場合、
腹をくだして朝顔の花を眺めた。十歳を越した頃だった。
(『槿』)は、その心象の構造を語りに写し取ったものだということができるはずである。「辞」によって主体的表現が完結するとは、こういう構造にほかならない。これが古井氏の語りの第一の特色ということができる。
更に、『槿』の例を分析してみると、注意すべきなのは、この「腹をくだして朝顔の花を眺め」ていたのを想い出していたということをただ語っているだけではないということだ。それなら、
十歳を越した頃、腹をくだして朝顔の花を眺めていたことがあった。
と語ればすむ。こう語るのとの違いは、思い出されている場面を思い出しているのを語っているということにある。そこには、想い出の場面と思い出している場面の二つが現前しているのである。実は、これも、日本語の構造に根差している。
「詞」で客体的表現(これは客観的という意味だけではない。客観化した表現)であり、「辞」は主体的表現(主観的な感情や意志の表現)であり、〃そのとき〃について〃いま〃感じているという場合が一番分かりやすい。それを具体的に表現するとすれば、〃そのとき〃見えたものを描き、それを〃いま〃どう受け止めているかを描けば、正確に構造を写したことになるだろう。このとき、〃そのとき〃と〃いま〃は二重に描き出される。
もう少し突っ込んだ言い方をすれば、主人公を語っている〃いま〃と、主人公が朝顔を眺めている〃とき〃とは一致しているわけではないから、
①主人公を語っている〃とき〃
②主人公が朝顔を眺めている〃とき〃
③主人公に語られている、「十歳を越した」〃そのとき〃
と、三重構造になっているというべきである。同時に、思い出されている〃そのとき〃の場面と、それを思い出している〃いま〃の場面とが、それを語る語り手のいる〃とき〃から、二重に対象化して、語り手は、それぞれを〃いま〃として、現前させているということにほかならない。
前出の日本語の例で言えば、
①「桜の花が咲いて」いる〃とき〃
②「桜の花が咲いていた」と「言っ」た〃とき〃
③「桜の花が咲いていた」と「言った」と語っている〃いま〃
の三つの〃とき〃があり(むろん、前述の通り、この語りを囲んで、④「と言った」と書いている〃とき〃があることは言うまでもない)、それぞれを現前化させていると言ったらわかりやすいはずである。そして現前化するとき、〃そのとき〃は〃いま〃として、それぞれがゼロ記号化した語りとなっているはずである。そうすることで、実は入子の語りは完結し、そこまで語りのパースペクティブは到達しているということを意味する。
そして、ここには、古井氏の語りを考えるとき、重大な意味が隠されている。
すなわち、③の語りの時点から見たとき、②の〃とき〃も①の〃とき〃も入子になっているが、単純な入子ではない。③から①を現前化するとき、話者は、②の発話者に〃なって〃それを現前化しているのである。もし、①が自分の回想だとしたら、〃そのとき〃の自分になっているし、もし他人(相手)の発話だとしたら、〃そのとき〃の他人(相手)の発話になって、それを現前化しているのである。だから、ここで語りのパースペクティブの奥行というとき、入子になっているのは、語られたこと自体だけではなく、語るもの自体をも入子にし、しかもその発話を入子の発話者に転換して入子にしているということを見逃してはならない。
だから、前節で触れたように、これがゼロ記号となっているときは、
前述の①の時間を欠き、その分語りが奥行を欠いていることになるというのは見易いし、また「と言」う〃とき〃を〃いま〃としたとき、話者には相手が目の前にいることになり、その言う「桜の花が咲いていた」という言葉が〃いま〃発せられたことを写しているために、その発話だけが対象として見えるだけになるというのも見易いはずだ。
前者のような語りの構造は、語りのパースペクティブという面で考えるなら、語り出される〃そのとき〃が、前へ前へ(あるいは過去へ過去へ)と、発話者も含め、入子になって重ねられていくということでもある。これが、古井氏の語りの第二の特色ということができる。
これは『槿』だけではなく、処女作『木曜日に』以来のものなのだ。『木曜日に』の冒頭は、次のように語り始められている。
鈍色にけぶる西の中空から、ひとすじの山稜が遠い入江のように浮び上がり、御越山の頂きを雷が越しきったと山麓の人々が眺めあう時、まだ雨雲の濃くわだかまる山ぶところの奥深く、幾重もの山ひだにつつまれて眠るあの渓間でも、夕立はそれと知られた。まだ暗さはほとんど変わりがなかったが、まだ流れの上にのしかかっていた雨雲が険しい岩壁にそってほの明るく動き出し、岩肌に荒々しく根づいた痩木に裾を絡み取られて、真綿のような優しいものをところどころに残しながら、ゆっくりゆっくり引きずり上げられてゆく。そして雨音が静まり、渓川は息を吹きかえしたように賑わいはじめる。
ちょうどその頃、渓間の温泉宿の一部屋で、宿の主人が思わず長くなった午睡の重苦しさから目覚めて冷い汗を額から拭いながら、不気味な表情で滑り落ちる渓川の、百メートルほど下手に静かにかかる小さな吊橋をまだ夢心地に眺めていた。すると向こう岸に、まるで地から湧き上がったように登山服の男がひとり姿を現し、いかにも重そうな足を引きずって吊橋に近づいた。
と、まるで〃いま〃起きつつあることを、同時進行に語るような語り口が、実は、
《あの時は、あんたの前だが、すこしばかりぞっとさせられたよ》と、主人は後になって私に語ったものである。
と、「私」が、過去において宿の主人から聞いた話を再現して語っているのだということが、種明しされる。つまり、ここでまるでゼロ記号の羅列のような、終止形止めが目立つのも、それを思い出している〃いま〃ではなく、〃そのとき〃を〃いま〃とした語りを入子にしている(剥き出しにしている)からにほかならない。
だからむろん、この場合の「た」と「る」の不統一な使用は、語っている〃いま〃からの過去形と、〃そのとき〃を〃いま〃とする現在形の混同でないのは先にも述べた通り、「た」が判断のそれとして、「物語の現在に結びついて」(熊倉、前掲書)、語っている〃そのとき〃において、〃いま〃のように現前化されているからにほかなない。このままならば、ゼロ記号化にほかならない。
だからこそ、冒頭、「長くなった午睡」から目覚めた宿屋の主人の視線で、自分を客観化した「男」、つまり〃そのとき〃の「私」について、〃そのとき〃を現在として現前させた語りをとっている。
しかし、古井氏は、そこから〃いま〃の語りへと戻す「辞」を明示している。すなわち、ゼロ記号化へは流れることはない。そのため、一見ゼロ記号化と見える入子の語りが、実は、語っている〃いま〃から、〃そのとき〃を見ていたもの(ここでは宿の主人など)になって(語りの視点を辷り込ませて)、語っているにすぎないことを明らかにするのである。
古井氏の語りの第三の特色は、このようにゼロ記号化に落ち込まないことによって、〃そのとき〃を現前化するだけでなく、それぞれ入子とした語りの〃いま〃との距離を、つまり「辞」としての〃いま〃からの隔たりのすべてを語りのなかに持ち込んでくることに自覚的な点なのだ。これを語りのパースペクティブの奥行と言わなくてはなるまい。
こうした古井氏の語りの特色を考える対照として、山川方夫氏『愛のごとく』を引き合いに出してみる。
(中略)−結局、私はそんな感覚が好きだったのかもしれない。自己の二重性をそのときどきに使いわけて、相手が私の表皮だけで興奮し分泌しているのを、暗い内部のもう一方で、無責任にじっと眺め、味わっているのが好きだったのかもしれない。
そのとき、私はいわば女を一つの「物」としてしか扱っていなかったのだ、と思う。私は自分の暗い激情の奔出を感じながら、相手に人間を失格させ、自分もまた人間を失格して、一つの粗暴な凶器そのものに化しているのに恍惚を感じていたのか。とにかく、私のいちばん燃えたのはそんなときだ。
「『物』としてしか扱っていなかったのだ、と思う」のは、この物語の中の〃とき〃ではなく、これを語っている〃とき〃にいる「私」だ。そこから、語られている〃とき〃が、入子になっているようにみえる。
(中略)私は何気なく女の目に笑いかけた。女も私を見て笑い、その目と目とのごく自然な、幸福な結びつきに、突然、私は自分がいま、狂人の幸福を彼女とわかちもっているのをみた。 (山川、前掲書)ある夜、あんまり女がうるさく邪魔をするので、私は彼女をおさえつけ馬乗りになって、ありあわせのシャツやネクタイやで女の手脚をかなり強く縛った。女はそれに異常なほどの興奮で反応した。……丸太棒のように蒲団をころげながら、女はシーツにおどろくほどのしみをつくったのだ。それからは、……私も習慣のようにほどけないように背中でその手首を縛り、抱きかかえるようにして蒲団に寝かせてやる。
(中略)
……煙草をつけて背後の女を振りかえった。……「ほどく?」と私は訊ねた。が、女は目で微笑するとゆっくりと首を振った。
だが、〃そのとき〃の「私」の視線は、女の外面から跳ね返されている。いや、そうではない。〃そのとき〃の「私」の気持や関心しか語られてはいない。むしろ、ここにあるのは、〃そのとき〃にもなお、語っている〃いま〃の「私」の辞によって左右されている視野だ。いや、〃そのとき〃の「私」しか見ようとしない「私」だ。〃いま〃の「私」は、〃そのとき〃の自分に〃見えていたもの〃よりは、そういうものを見ていた〃そのとき〃の自分を語ろうとしているようにみえる。それには理由がある。
(山川、前掲書)私はいつも自分にだけ関心をもって生きてきたのだ。自分にとって、その他に確実なものがなにもなかったので、それを自分なりの正義だと思っていた。私はいつも自分を規定し、説明し、自分の不可解さを追いかけ、自分をあざけり軽蔑してくすくす笑いながら、でも仕方なく諦めたみたいに、その自分自身とだけつきあってきたのだった。
「私」は〃そのとき〃の自分の「関心」にしか、自分の視野に映っていたものではなく、そういう視野を見ようとした自分しか語らない。その自意識がどういう変化を蒙るかに語りの関心が向けられている。
Cの〃とき〃にいる「私」にとって、A、つまりBの〃そのとき〃の「私」の見ているものではなく、Bの辞そのもの、Aをどう見ているかに関心がある。入子にしたのは、語られているAではなく、それを語っている〃そのとき〃の「私」自身にほかならない。
しかし、AもまたBの辞に彩られた視野でしかないとすれば、Bを入子にすることと、Aを入子にすることとに差があるとするのは、単なる言葉の綾にすぎないではないか、と見えるかもしれない。
それなら、古井氏は、どういう語り方をするのか。例えば『杳子』では、
肌の感覚を澄ませていると、彼は杳子の病んだ感覚へ一本の線となってつながっていくような気がした。道の途中で立ちつくす杳子の孤立と恍惚を、彼はつかのま感じ当てたように思う。
……杳子は道をやって来て、ふっと異った感じの中に踏み入る。立ち止まると、あたりの空気が澄みかえって、彼女を取り囲む物のひとつひとつが、まわりで動く人間たちの顔つきや身振りのひとつひとつが、自然の姿のまま鮮明になってゆき、不自然なほど鮮明になってゆき、まるで深い根もとからたえずじわじわと顕われてくるみたいに、たえず鋭さをあらわにして彼女の感覚を惹きつける。杳子はほとんど肉体的な孤独を覚える。ひとつひとつの物のあまりにも鮮明な顕われに惹きつけられて、彼女の感覚は無数に分かれて冴えかえってしまって、漠とした全体の懐かしい感じをつかみとれない。自分自身のありかさえひとつに押えられない。それでも杳子はかろうじてひとつに保った自分の存在感の中から、周囲の鮮明さにしみじみと見入っている。
これは、「彼」の思い描いた、杳子にほかならない。しかし、『愛のごとく』の「私」と異なり、語り手はただ「彼」が見た杳子を語るだけではなく、杳子の目で、杳子の見るものを語っていく。それは語られている〃とき〃を踏み越えて、「彼」に語られている杳子の見ている〃とき〃をも、語ろうとしているということにほかならない。それは、別の言い方をすれば、「彼」の心象から更に踏み込んで、「つかのま感じ当てたように思う」〃そのとき〃の「彼」の心象の中の杳子の〃とき〃を現前化しているのにほかならない。
つまり古井氏が入子にしているのは、〃そのとき〃見ている「私」でもなく、また〃そのとき〃「私」の見ていたものでもなく、もう一歩踏み込んで、見られている「杳子」の〃とき〃そのものにほかならない。それは、前節の日本語の構文例で示したように、そう語ることは、「彼」の辞に彩られるだけの杳子ではなく、杳子に拘束され、杳子の視野を、更にその中で見られている自分をも見たいという自分の心情を現実化していることになるはずなのだ。
だが、『愛のごとく』で、女が何を見ていたかを語らせようと思えば語らせられたはずだ。そうしていないのは、「私」にそうとしか語らせないことが必要だったからである。そして『杳子』では、「彼」の見た杳子から踏み込んで、杳子の見るものを語らせるのも、次節で述べるように、そうする必要があったからにほかならない。
このこと自体は、バルト氏が、
(バルト、前掲書)文学の描写はすべて一つの眺めである。あたかも記述者が描写する前に窓際に立つのは、よくみるためではなく、みるものを窓枠そのものによって作り上げるためであるようだ。
と言う〃窓枠〃の取り方の違いに過ぎない。確かなことは、山川氏は、『愛のごとく』で「私」の自意識、あるいは自我の奥行を語る必要があり、古井氏は『杳子』で、見られるものを見るという、描写の奥行を語る必要があった、ということだ。
ところで古井氏は、徳田秋聲氏を出しにして、こういうことを言っている。
まず意志からみる、意志から聞く、性格の事ではなかった、と私は見る。意志が最初の力として働いていれば、視野はおのずと自我を中心としてしぼられるだろう。時間もまた自我の方向性をもつ。ところが秋聲の小説においては、主人公が他者との葛藤の只中にあり、情念に揺すぶられている時でさえも、その姿は場面の中にあって、描写される。手法のことを言っているのではない。本質的に、描写される存在として、作者の目に映っているのである。これをたとえば漱石の、たとえば『道草』の同様の場面とくらべれば、差違は歴然とするはずだ。漱石の場合は、主人公の情念が場面に溢れ、場面を呑みこむ。つまり自我の空間となる。(中略)
……自我を立てる。捩れていようと歪んでいようと、折れていようと曲がっていようと、とにかく自我を立てることによって成り立つ。それによって現実を得、現実を失う。そういう態の私小説にたいして、自我を抱えながら身上話の客観性へ身を臥せる、水平へひろがり深くなる態の私小説があり、秋聲文学は後者の第一人者ではないか。
(
「私小説を求めて」)「あんがい秋聲の文学の本質に深く触れる」(同)と指摘している点は、むしろ古井氏自身の「文学の本質」とみなして構わない。実際、「私」を立てることについて、前述とは別の場所で、次のようなことを言っている。
(「翻訳から創作へ」)私の場合、小説の中で「私」という素っ気ない一人称を思い切りよく多用することを覚えてから、表現の腰がひとまず定まった。この一人称は自我を引寄せるよりも、ひとまず他者の近くまで遠ざける働きをする。それとひきかえに、私は表現といういとなみの中で以前よりもよほどしぶとく自我に付くことができるようになった。描写においてである。見たままを写す、記憶に残るままを写す、そこまではまさに描写だが、描写によって心象が呼び起され、その心象がさらに細部まで描写で満たすことを要請することがある。その時、人は物に向うようにして心象に向いながら、おのずと自我を描写することになる。……そして小説は全体として、いくつかの描写による自我の構図となる。
山川氏の『愛のごとく』の語りは、まさに、「意志が最初の力として働いていれば、視野はおのずと自我を中心としてしぼられるだろう。時間もまた自我の方向性をもつ」ものであることは明らかである。
ここに、『愛のごとく』と『杳子』との方法
(あるいは資質)の差がみられる。山川氏が語られている〃とき〃を語ろうとして、一見入子となった〃そのとき〃が語られていくのに、その実、語っている「私」の光源が強いため、「私」は絶えず背後に語る自分を尚語ろうとする自分の影を、そう語る自分を語る自分を語る自分……というように、無限後退的に、自我の奥行を抱え込んでいる。「私」が入子にしているのは、通底する自意識にすぎない。語っている〃いま〃の自意識を光源として、入子の語りの中にも通底し、前へも後ろへも重なる自意識だけだ。だから、語っている〃いま〃のそれなのか、語られている〃そのとき〃のそれなのかは区別がつかない。あるのは、〃いま〃にも〃そのとき〃にも、満ち溢れている自意識のパースペクティブだけだ。それに対して古井氏は、語っている〃とき〃にいて、心象を描写として投影(入子に)する。「他者の近くまで遠ざけ」られ、〃いま〃として現前化(入子に)された描写は、更にその向こうに、その「描写によって呼び起こされ」た心象を現前化した描写として、また入子の〃いま〃を抱え込む。それは、入子にした〃そのとき〃に強く拘束され、〃そのとき〃に強く惹かれているからであり、それを知りたいと思うからであり、……という強い心象が生み出した(投影した)からこその現前化(描写)なのであり、その「要請」が自意識ではなく、それが〃いま〃のごとく表象している〃そのとき〃を現前化しようとする。入子となった〃そのとき〃が、「描写」の奥行として描き出される。結果として自我の奥行はついてくる。前述の『杳子』で、結局杳子が見るように語ったことで明らかになったのは、だから杳子の心ではなく「彼」の「自我」でしかなかった、ということができよう。
実は、語られる〃とき〃を入子にするとき、古井氏も、「〜を見ていた私を語っている私を語っている……」と、無限に語るものの〃とき〃を抱え込むことに変わりはないはずである。その意味では、どこまでも己れの自意識の影に振り回されている山川氏の『愛のごとく』の「私」との差は、本当は少ないのかもしれない。だが、その自意識の入子を、自意識のパースペクティブで表現するか、見られたもののパースペクティブで表現するかの差は大きい(「〜を見ていた私を語っている私を語っている……」で言えば、「見ていた」「私」を語るか、「〜」を語るかの違いだ
)。自意識でみるとき、同じように〃とき〃を入子にしながら、絶えず自意識のタイムトンネルをくぐって、いつもどこでも自分しか見てはいない。自分の感情、自分の知覚、自分の理屈……。どこにいても、いつも変わることはない。しかし、その自分を「他者の近くまで遠ざける」とき、自分もまた風景となる。他者も自分も、見られるもの(「描写される存在」)という意味では同列に並ぶ。そのとき、その向こう側(自分に見えない側)に、相手の見ているものを見ることは、こっちからそれを説明すること(それこそ自意識にほかならない)ではなく、向う側に立って見ることにほかならない。それは、自意識の堂々巡りの地獄を、自意識としてでなく(それは「説明」)、それが表出しているものを語るという形で、逆手に取っているとみなすことができる。
『愛のごとく』の「私」にとって、せいぜい「私」が女をどう見ているか、どう見えるかにのみ関心がある。「私」の視線は「女」が何を見ているかまでは届かない。足を引っ張っているのは自意識にほかならない。「私」は自己欺瞞、自己韜晦を語りたいのだ、誰に?ほかならない「私」自身に、だ。それを自意識の地獄という。だから「私」はひたすら「説明」するだけだ。何を?自分自身について。誰に?自分自身に。そして懸命に言訳の理由を見つけようとする。
私は、自分が誰も愛さず、したがって誰からも愛される資格のない人間だ、という考えを変えたわけではなかった。私はときたま仕方のない情慾の他は、なにひとつ女に強制したのでもなく、その情慾すら、ほとんどは女への過剰なおつきあいの精神、目の前にいる相手への弱さから、いわば「強制」させられているのだ。いつ女が消えても、だから、なんの不自由もない。−
あるいは、こう「説明」する。
……たしかに「愛」はない。「資格」もない。が、いったい、それがなんだろうか。それはいわば私だけの部分、人びとがすべてかくしもっている隠微な秘密の部分への幼い拘泥ではないのか。女がはじめて泊まった朝、そして昨夜、自分がいやでもこの女といっしょに、その中にいるのを感じざるをえなかったある日常、おれの異常、おれの狂気、おれという一つの恐怖さえ平然と咀嚼し、石を投げ入れた沼ほどの動揺もみせない女。もしかしたら、おれはこの女とならいっしょにやっていけるかもしれない。
こうした「私」の「説明」があるから、突然の女の死亡通知を前にした「私」の動揺に意味がある。語るべきものがある、ということになる。
突然、胸がふるえてきた。大きく呼吸を吸うと、涙がふいにあふれだした。考えられないことだったが、涙は止りそうにもなかった。私はあわてて部屋に帰り、蒲団にうつぶして泣きはじめた。涙は頬をつたい、声をあげて泣きながら、私は物心ついてから自分がこうして泣くのははじめてだと気づいた。いまにもノックの音が聞こえ、女がやってくるかもしれない。見られてもいい。いや、おれは女に見てもらいたいのだと思った。
こういう自意識の傷は、結局自分に見えたものしか見ない結果なのだ。それに対する自分の心の動きを語るしかない。しかしその心の動きを見ているのは〃いつ〃の「私」なのか、〃そのとき〃の「私」を見て〃いま〃感じているのか、それとも〃そのとき〃の自分の感慨を〃いま〃語っているのか?こうした語っているものを語っているものを語っているものを……語る、というように、書き割りの自我とでも言うべき〃いま〃も続いている感慨が、全体を覆っていく。
しかし繰り返すが、もしここで自意識の奥行でなく描写の奥行として語れば、「私」は女を見ていること、女の見ているものを見たいという自分の心象の描出にほかならず、それはそのまま『愛のごとく』の作品そのものを成り立たせなくしてしまうのは間違いない。だから、それを古井氏が転倒するのは、逆にそのことによって成り立たせたいものがあるということを意味しよう。
「私」という語りの〃とき〃を明示することで、その「私」が語る〃そのとき〃は「私」の辞に包まれたものでしかない。しかし〃そのとき〃「私」は語られるものに〃成る〃。それは、語られものを語るとき、風呂敷としての「私」は、包まれるものそのものになっている。そのことによって、初めて「私」は描写の奥行を現前化している。
『木曜日に』では、「私」は、失われた自分の記憶を思い出そうとする。しかし、決して語っている〃とき〃で自問しない。失われた〃そのとき〃の周囲を現前させる語りによって、それを蘇らせようとする。そうすることでかえって鮮やかに、〃いま〃と〃そのとき〃の己れの差異が現れる。
ビルの間にはたまたま人影が絶えていた。こんな瞬間が真昼の街にもあるものだ。人気のない石切場のような静けさが細長く走るその突当りでは、黄金色の日溜りの中を人間たちの姿が小さく横切っては消えていく。(中略)それから私は、ふと気味が悪くなって立ち止まった。見上げると、両側には二枚のコンクリート壁が無数の窓を貼りつけて、私のほうへ倒れかかりそうに立っていた。(中略)私は谷底をまた歩き初めた……。
谷底を歩みながら、私は《また立ち止まったらたまらないな》とくりかえしつぶやいていた。それと同時に私は、すでに立ち止まってしまった自分の姿を、呆然と細い首を伸ばして頭上を見上げている自分の姿を、思い浮べた。幾度となく私は立ち止まったような気がした。しかしそのたびに私は立ち止まった私のそばを、自分自身の幽霊のように通り過ぎた。そしてとうとう私は立ち止まった。実際に立ち止まって空を仰いだのだ。それから、私は憂鬱の虫にとり憑かれてビルの間を抜け出た……。
「私」の記憶ではこうだ。しかし、それを目撃した女友達が見たのは違っていた。
その時、彼女は自分の中で凝っていたものがほぐれるのを感じた。彼女は思わず足どり軽く私のそばへ飛んで行こうとした。ところが、私の体は張りを失って泥のようにずるずると崩れ出した。私は膝を折って不安な中腰となり、腕を両側にだらりとたれ、首を奇妙な具合に低く突き出し、厚い唇を鈍重にふるわせて、何だか吐気をこらえているような様子だった。それから風にあおられたように私はふたたび体を起し、まだ定まらない腰つきでふらりふらり彼女のほうに向かってきた。そして彼女にまともから突き当って、彼女をコンクリートの上に倒した。書類が二人のまわりに散った。私は彼女を突き倒したままの姿勢で立ちつくし、彼女は私を見まもった。一枚の紙が私の足もとに落ちた。それを私は一心に見つめていた。拾ってくれるのかしら、彼女は私の横顔を見つめた。すると私はその白い紙をまるで恐ろしいもののようにまたいで、それから後もふりかえらずに立ち去った。(略)という……。
このとき、自分の過去を、「私」は、彼女の過去の〃そのとき〃〃そこ〃へ滑り込み、〃そのとき〃の彼女のパースペクティブの中にある、見られている「私」を、彼女の目で語っている。「私」は、自分のパースペクティブの入子として、彼女のパースペクティブを重ねている。〃そのとき〃の彼女の見た自分を、彼女の視線で、体験し直すように見ることで、頽れかけた自分の輪郭をなぞり直し、〃いま〃の「私」のパースペクティブの中に、整序し直し、あったはずの自分の記憶を取り戻そうとしている。
こういう語りは、語っている〃とき〃にウエイトはなく、語られている〃とき〃(あるいは〃もの〃)に比重がかかっているように見えて、実は逆なのだということが重要な点だ。それは、主体的表現(辞)によって包まれた語りは本当にあったことかどうか、確かめようはない、ということでもある。こうした入子の語りは、妄想や夢を語るのにこそふさわしいのかもしれない。たとえば『男たちの円居』で、それが効果的に使われる。
……私は、徒労感に圧倒されないように、足もとばかりを見つめて歩いた。そしてやがて一歩一歩急斜面を登って行く苦しみそのものになりきった。すると混り気のない肉体の苦痛の底から、ストーヴを囲んでうつらうつらと思いに耽る男たちの顔が浮んできた。顔はストーヴの炎のゆらめきを浴びて、困りはてたように笑っていた。ときどきその笑いの中にかすかな苦悶の翳のようなものが走って、たるんだ頬をひきつらせた。しかしそれもたちまち柔かな衰弱感の中に融けてしまう。そしてきれぎれな思いがストーヴの火に温まってふくらみ、半透明の水母のように自堕落にふくれ上がり、ふいに輪郭を失ってまどろみの中に消える。どうしようもない憂鬱な心地良さだった。だがその心地良さの中をすうっと横切って、二つの影が冷たい湿気の中を一歩一歩、頑に小屋に背を向けて登って行く……。その姿をまどろみの中からゆっくりと目で追う男たちの顔を思い浮べながら、私はしばらくの間、樹林の中を登って行く自分自身を忘れた。
と、まず「私」は、自分の苦しみに沿い、それから小屋に残っている男たちの、飢えでぼんやりしている姿を思い描き、うつらうつらする衰弱感に一緒になって浸り込み、その水膨れしてぼんやりした想念の中で一緒になって遠ざかる「私」たちの影を一瞥し、その背中を思いやる、その視線を、「私」は次には一転して自分の背中に感じながら、樹林の中を登っている「私」のところへと、視線は返ってくる。
つまり、「私」は相手の思いの中の「私」を、相手と一緒になって思いなし、一緒になって視線を送り、それからその視線を感じながら歩く「私」へと返ってきている、というわけである。
「私」は男たちに〃成り〃、男の視線で自分を眺める。男を見ていた「私」は、男に〃成る〃ことで、男の視線で自分を見、しかもその視線を背中に感じている自分に戻ってくる。その視線の転換すべてがここに語られている。それは、夢を見ているときに等しい。夢を見ているとき、夢の中にいる自分と、その自分を見ている自分、そのすべてを夢に見ている。夢を見ながら夢に見られているのを夢に見ている。
断っておくと、この「私」の語りは、ゼロ記号化した語りではなく、「私」が語っている〃いま〃から、入子にした語りなのだ。ということは、ここには、辞としての語りの中に、歩いている「私」の〃いま〃、その「私」が男たちになって「うつらうつら」している〃いま〃があり、そしてその男たちが見遣っている「私」の〃いま〃がある。
この同じ意識は、小屋の中で空腹で「うつらうつら」しながら夢想している〃とき〃にもある。
はるばると風の吹き渡る森の中で、おそらくここよりも風下のほうで、針金のワッカに首を突っこんで、野ウサギが悶えている。濡れた黒土の上で足掻きに足掻きまくったそのあげく、ふくよかな首筋の毛皮に深く、赤い素肌に至るまで針金に喰いこまれて、今ではもう窒息の苦しみも引き、内側から静かにひろがってくる生命の充足感につつまれて、ただ後足をヒクリヒクリと恥ずかしそうにひきつらせながら、心地よさのあまりうっとりと白眼を剥いて息絶えていく。が、まだ生きている、まだ生きている、死の前で時間が停っている……。
「私」は、「うつらうつら」しながら、夢想の中で、「針金のワッカに首を突っこんで、野ウサギが悶えている」のを見ていながら、同時に、「今ではもう窒息の苦しみも引き、内側から静かにひろがってくる生命の充足感につつまれて、ただ後足をヒクリヒクリと恥ずかしそうにひきつらせながら、心地よさのあまりうっとりと白眼を剥いて」いる兎に〃成り〃、その苦痛を自分のものとして感受し、その果ての恍惚を感じ取っている。
《見ている》うちに《見られている》ものに〃成り〃、そのパースペクティブを見、しかもその視線を受けている《見るもの》でもある。そのとき、距りが消えるのは、《見るもの》と《見られるもの》の間ではなく、それを語っている視点にとってにほかならない。「私」は見ていると同時に、見られている。見られている自分に〃成って〃いる。そして意味があるのは、それを見届けている視線である。その視線にとって、《見るもの》と《見られるもの》は距りがない。
見るものが見られるものに〃成る〃とは、そのパースペクティブをおのれのものにするということにほかならない。それを見るものにとっては、それが《見るもの》の夢か、《見られるもの》の現か、には差はない。いずれにとっても、それを現前化して〃いま〃見ているのだからだ。それは、
観念的に二重化し、あるいは二重化した世界がさらに二重化するといった入子型の世界の中を、われわれは観念的な自己分裂によって分裂した自分になり、現実の自分としては動かなくてもあちらこちらに行ったり帰ったりしているのです。
(
三浦、前掲書)という日本語の言語表現の特色そのものに根差しているからにほかならない。
だからこそ、『男たちの円居』で、「私」が、自分が外へと歩き出したのを語ることと、自分が外へと歩き出したのを夢想の中に見ているのを語ることが見分けがたく、
だが、しばらくして、私は頭を起した。風が止んで、雨が静かに降りはじめた。もう一人の人間が闇の中でふっと体を起したのを、私は感じた。
私は椅子から立ち上って戸口のところへ行き、扉を一杯に明け放った。そして暗闇の中に小屋の明りを流して待った。やがて私の足もとから濡れた地面をそって細長く伸びる薄い光の尖端を、すうっと横切って森の闇のほうへ消えて行く人影があった。私は後手に扉を閉じて闇の中へ踏み出した。衰弱感の中で、不思議な力が私を支えてくれた。
と、見ているのが、「私」がストーブの前でうつらうつらしながら、閉じ込められた中で、救いを求める気持が外に描き出した幻だとしても、あるいは現実に〃そのとき〃現とも夢とも境界の朧気なまま、外へと彷徨い出た、霧の中のように夢うつつの情景だとしても、それを〃いま〃語る「私」にとって、それほどの差があるのではなく、むしろ、〃そのとき〃を見届けている(語っている)〃いま〃の「私」からの視線が、そこまでの射程をもって、現前化した描写として語られている、ということこそが重要なのだ。
だから古井氏にあっては、語っている〃とき〃の自意識の後退し続ける自問には意味を見いださないというべきなのだ。それはヴァインリヒのいう「説明」にすぎない。なぜなら、それは結局語ることではなく、語ることを語ることでしかないからだ。そこが、『愛のごとく』の語りとの差に違いない。
自意識の「説明」を語るのではなく、自意識の見るものを見せる、そこに現前化した入子の〃とき〃の奥行は、『哀原』に鮮やかに描き切られている。その重ねられた描写には、それぞれの自我が炙り出されてくる。
語り手の「私」は、死期の近い友人が七日間転がり込んでいた女性から、その間の友人について話を聞く。その女性の語りの中に、語りの〃とき〃が二重に入子となっている。
一つは、友人(文中では「彼」)と一緒にいた〃とき〃についての女性の語り。
お前、死んではいなかったんだな、こんなところで暮らしていたのか、俺は十何年間苦しみにくるしんだぞ、と彼は彼女の肩を掴んで泣き出した。実際にもう一人の女がすっと入って来たような、そんな戦慄が部屋中にみなぎった。彼女は十幾つも年上の男の広い背中を夢中でさすりながら、この人は狂っている、と底なしの不安の中へ吸いこまれかけたが、狂って来たからにはあたしのものだ、とはじめて湧き上がってきた独占欲に支えられた。
これを語る女性の語りの向う側に、彼女が「私」に語っていた〃とき〃ではなく、その語りの中の〃とき〃が現前する。「私」の視線は〃そこ〃まで届いている。「私」がいるのは、彼女の話を聞いている〃そのとき〃でしかないのに、「私」は、その話の語り手となって、友人が彼女のアパートにやってきた〃そのとき〃に滑り込み、彼女の視線になって、彼女のパースペクティブで、〃そのとき〃を現前させている。「私」の語りのパースペクティブは、彼女の視点で見る〃そのとき〃を入子にしている。
もう一つは、女性の語りの中で、男が女性に語ったもうひとつの語り。
或る日、兄は妹をいきなり川へ突き落とした。妹はさすがに恨めしげな目で兄を見つめた。しかしやはり声は立てず、すこしもがけば岸に届くのに、立てば胸ぐらいの深さなのに、流れに仰向けに身をゆだねたまま、なにやらぶつぶつ唇を動かす顔がやがて波に浮き沈みしはじめた。兄は仰天して岸を二、三間も走り、足場の良いところへ先回りして、流れてくる身体を引っぱりあげた。
と、そこは、「私」のいる場所でも、女性が友人に耳を傾けていた場所でもない。まして「私」が女性のパースペクティブの中へ滑り込んで、その眼差しに添って語っているのでもない。彼女に語った友人の追憶話の中の〃そのとき〃を現前させ、友人の視線に沿って眺め、友人に〃成って〃、その感情に即して妹を見ているのである。
時間の層としてみれば、「私」の語る〃とき〃、彼女の話を聞いている〃とき〃、彼女が友人の話を聞いている〃とき〃、更に友人が妹を川へ突き落とした〃とき〃が、一瞬の中に現前していることになる。
また、語りの構造から見ると、「私」の語りのパースペクティブの中に、女性の語りがあり、その中に、更に友人の語りがあり、その中にさらに友人の過去が入子になっている、ということになる。
しかも「私」は、女性のいた〃そのとき〃に立ち会い、友人の追憶に寄り添って、「友人」のいた〃そのとき〃をも見ている。〃そのとき〃「私」は、女性のいるそこにも、友人の語りのそこにもいない。「私」は、眼差しそのものになって、重層化した入子のパースペクティブ全てを貫いている。
こうした古井氏の語りのパースペクティブの深度が、日本語の構造の奥行と深く結びついていることを見逃すべきではない。
3.見るものと見られるもの
見える、と語ることと、見えるものを語ることとの差は、知覚、想像、夢を問わず、認識の問題ではない。表現の問題にほかならない。だが、自己意識の奥行から言えば、第一節で述べたように、語っている〃いま〃について自覚的かどうかからみて、あるいは認識の奥行の問題といえるのかもしれない。
さてそこで、見るものが見られるものに〃成る〃のを語る、という語りの特徴をよりはっきりさせるために、更に『杳子』を取り上げてみる必要がある。
『愛のごとく』のように、見る自分に固執し、「自我を立てている」(古井、前掲書)のでないとは、
(『「私」という白道』)自分が見る、自分を見る、見られた自分は見られることによって変わるわけです。見た自分は、見たことによって、また変わるわけですよ。
ということにほかならない。他人についても同様だ。見ることによって、見られるものが変わる。見られるものが変わることによって、見るもの自身もまた変わる。
山川氏の『愛のごとく』で、「私」は確かに変わったが、それはいわば一方通行でしか語られない。しかし変わったことを語る(これは「説明」だ)のと、相手の〃そのとき〃を自分のものとして見る、見られる立場から見ていたはずの自分を見返す、そうすることで見る自分にインパクトを与える、という変えられ変わっていく〃そのとき〃を「語る」のとは違う。『杳子』は、まさにそういうふうにして、変え変えられ変わる〃そのとき〃が語られる。
杳子は深い谷底に一人で坐っていた。 十月もなかば近く、峰には明日にでも雪の来ようという時期だった。
彼は、午後の一時頃、K岳の頂上から西の空に黒雲のひろがりを認めて、追い立てられるような気持で尾根を下り、尾根の途中から谷に入ってきた。道はまずO沢にむかってまっすぐに下り、それから沢にそって陰気な潅木の間を下るともなく続き、一時間半ほどしてようやく谷底に降り着いた。ちょうどN沢の出会いが近くて、谷は沢音に重く轟いていた。
(中略)河原には岩屑が流れにそって累々と横たわって静まりかえり、重くのしかかる暗さの底に、灰色の明るさを漂わせていた。その明るさの中で、杳子は平たい岩の上に躯を小さくこごめて坐り、すぐ目の前の、誰かが戯れに積んでいった低いケルンを見つめていた。
こう書き出された『杳子』もまた、「後になって、お互いに途方に暮れると、二人はしばしばこの時のことを思い返しあった。」と、『木曜日に』と同様、二人が出会いを振り返っているのだということが明らかにされる。『木曜日に』が、失われた自分自身をを見付け出す、「私」の自分自身との関係そのものの確認の物語であったとみなせば、『杳子』は、「彼」による、杳子との関係そのものの確認の物語であるとみなすことができる。だからこそ、ここで見るものが見られるものと〃成る〃語りを必要とする理由もまたあるのである。
「彼」のパースペクティブの中で見られるものである杳子は、杳子のパースペクティブの中では「彼」を見るものでもある。二人が出会いについて「思い返す」ことは、相互に、そのパースペクティブを確かめ合い、交換することによって、〃一方通行のパースペクティブ〃が、〃双方通行のパースペクティブ〃にされ、それによって、ただ見られるものであるはずの杳子によって、「彼」のパースペクティブが質されるだけでなく、「彼」のパースペクティブに依存した語り手のパースペクティブそのものが、修正されていく。それは語りだけのことではなく、物語そのものもまた修正されていく。
杳子は、「足音が近づいてきて、彼女のすぐ上あたりで止んだ」のに気づいて、我に返る。
その時はじめて、杳子はハッとした。だれかが上のほうに立って、彼女の横顔をじっと見おろしている。そんな感じが目の隅にある。たしかにあるのだけれど、それが灰色のひろがりの、いったいどの辺に立っているのか、見当がつかない、見当がつかないから頭の動かしようもわからない。
同じことを、「彼」は、別様にとらえる。見詰めている「彼」の山靴に触れた小石が転がりだし、
女が顔をわずかにこっちに向けて、彼の立っているすこし左のあたりをぼんやりと眺め、何も見えなかったようにもとの凝視にもどった。それから、彼の影がふっと目の隅に残ったのか、女は今度はまともに彼のほうを仰ぎ、見つめるともなく、鈍いまなざしを彼の胸もとに注いだ。気がつくと、彼の足はいつのまにか女をよけて右のほうへ右のほうへと動いていた。彼の動きにつれて、女は胸の前に腕を組みかわしたまま、上半身を段々によじり起して、彼女の背後のほうへ背後のほうへと消えようとする彼の姿を目で追った。
ここには、まず「彼」の視線で見た杳子があり、つぎに杳子のパースペクティブを借りた(思い入れた)「彼」の視線が、杳子の心の動きを追い、逃げる彼の動きと、追う杳子の視線の、見るものと見られるものの、緊張が見届けられている。これを、杳子は次のように、見ていた。
《いるな》と杳子は思った。しかしいくら見つめても、男の姿は岩原に突き立った棒杭のように無表情で、どうしても彼女の視野の中心にいきいきと浮び上がってこない。《いるな》という思いは何の感情も呼び起さずに、彼女の心をすりぬけていった。杳子は疲れて目をそむけた。それから、視線がまだこちらに注がれているのを感じて、また見上げた。すると、漠としてひろがる視野の中で……男は、二、三歩彼女にむかってまっすぐに近づきかけて、彼女の視線を受けてたじろぎ、段々に左のほうへ逸れていった。男は、杳子から遠ざかるでもなく、杳子に近づくでもなく、大小さまざまな岩のひしめく河原におかしな弧を描いて、ときどき目の隅でちらりちらりと彼女を見やりながら歩いていく。
この時「彼」は、杳子に語り出された〃そのとき〃を、彼女の視線になって、それに映っていた自分を見ている。ちょうど『木曜日に』の「私」が、女ともだちの見たものを語っていたのと同じ構造だ。「彼」は〃そのとき〃の自分を、自分のパースペクティブの中で再現することで、彼女のパースペクティブだけでなく、自分のパースペクティブをも語り、その二つのパースペクティブの差異を現してみせている。それが、「確認」という意味にほかならない。だから、
歩むにつれて、形さまざまな岩屑の灰色のひろがりの中、その姿は女のまなざしに捉えられずに段々に傾いて溺れていく。漠とした哀しみから、彼も彼女を見つめかえした。すると女の姿も彼のまなざしにつなぎとめられずに表情をまた失い、はっきりと目に見えていながら、まわりの岩の姿ほどに訴えてこない。彼はすでに女を背後に打ち捨てて歩み去るこころになった。
と、「彼」が見たものは、次に杳子のパースペクティブで語り直される。杳子は、「男が歩いていくにつれて、灰色のひろがりが、男を中心にして、なんとなく人間くさい風景へと集まっていく」のを、見守っている。
わが身をいとおしく思って、そのために不安に苦しめられて、その不安をまたいとおしく思って、岩屑のひしめきにたちまち押し流されてしまいそうなちっぽけな存在のくせに、戦々恐々と彼女をよけていく。それでも、そうやって男が歩いていくと、彼女にたいしては険しい岩々が、彼のまわりに柔らかに集まって、なま温かい不安のにおいを帯びはじめる。杳子は……、《立ち止まって。もし、あなた》と胸の中で叫んでしまった。
掠め過ぎる影と影の擦れ違いざま重なり合う、その束の間の互いのパースペクティブの吻合を、「彼」は語っている。
足音が跡絶えたとたんに、ふいに夢から覚めたように、彼は岩のひろがりの中にほっそりとたっている自分を見出し、そうしてまっすぐに立っていることにつらさを覚えた。それと同時に、彼は女のまなざしを鮮やかに躯に感じ取った。見ると、……女は、……不思議に柔軟な生き物のように腰をきゅうっとひねって彼のほうを向き、首をかしげて彼の目を一心に見つめていた。その目を彼は見つめかえした。まなざしとまなざしがひとつにつながった。その力に惹かれて、彼は女にむかってまっすぐ歩き出した。
《見るもの》が《見られるもの》の見ているものを見る、《見られるもの》に見られている自分を見る、それを「彼」のパースペクティブの中に見る。その一瞬の錯覚は、しかし、《見るもの》と《見られるもの》との距りを縮めることを意味しない。むしろ後ずさりし、遠ざかるから、手繰り寄せようとする視線にほかならない。それが、接近したかと思うとたちまち離反していく二人の心の関係を象徴している。
見たと思ったことは、見られたという意識とともにある。だが、それは手に入れた瞬間から不確かなものになっていく。この出会いの印象は、「あの女の目にときどき宿った、なにか彼を憐むような、彼の善意に困惑するような表情」に思い当たって崩れる。
《あの女は、あそこで、自殺するつもりだったのではないか》という疑いが浮かびかけた。すると記憶が全体として裏返しになり、彼は女の澄んだ目で、幼い山男のガサツな、自信満々な振舞いを静かに見まもる気持になった。
それは、「彼」のつかんだパースペクティブ全体の転倒にほかならない。その転倒は、駅のホームにおける再会でまた転倒される。
少女はかれの右側を一歩ほど遅れて歩いていた。先の尖った靴がときどき彼の目の隅に入り、あたりのざわめきの中で冴えた音を規則正しく立てていた。輪郭たしかな足音とでも言ったらよいのだろうか、それが自分の鮮明さに自分で苦しむように、ときどき苛立たしげにステップを踏んだ。そのたびに彼は振り向いた。すると、切れ長の目が彼に見つめられてすこしたじろぎ、それから、視線が小枝のように弾ね返ってきて彼の目を見つめて微笑んだ。あの日、谷底に坐っていた女の、目と鼻と唇と、細い頤にやわらかく流れ集まる線を、彼はまたひとつずつ見出した。
『杳子』の語りは、「彼」による、こうした確認・修正・再確認の繰り返しだ。だが、確認とは、見るものと見られるものの交換である。確認は一方的ではない。《見るもの》が、《見られるもの》のパースペクティブを見ようとすれば、《見られるもの》が侵食されるだけでなく、《見るもの》も《見られるもの》に侵食され、《見られるもの》に変わっていく。二人の関係が深まるにつれて、このことが微妙に浸透しあい、影響を与える。
神経の病は、関係の中でしか顕在化することはない。いや関係が神経の病を創り出す。神経の病とは関係の病そのものにほかならない。それは《見ること》と《見られること》の病でもある。あるいは「彼」が意識しているように、「彼」が《見ること》によって、「彼」に《見られる》という関係の中で、杳子に顕われてきたというべきかもしれない。
ところで、厳密に言えば、この二人の確認は、「後になって、お互いに途方に暮れると、二人はしばしばこの時のことを思い返しあった」とあるように、語り手が「彼」について語っている〃とき〃でなく、「彼」が語られている〃とき〃でもなく、その〃とき〃の中の〃あるとき〃を〃いま〃として、現前化されている。その意味で、これ自体が「彼」についての語りの入子となっている。
だから、これを見届ける語りにとっては、「彼」について語っている〃とき〃から、
①「彼」が語られている〃とき〃
②「彼」等が振り返っている〃とき〃
③「彼」と杳子が出会った〃そのとき〃
の三層を重層化し、それぞれを〃いま〃として現前化しており、見るもののパースペクティブでも見られるもののパースペクティブでも、差をもっていない。夢も現も差はない。未来も過去も違いはない。古井氏にとって、語るとは、そもそも語られるものに〃成る〃ことにほかならないからだ。しかし、それで距離がなくなったのではない。隔たりをゼロ化しようとしているのにすぎない。それが語りの入子のもつ意味だ。
なぜなら、語りの入子を重ねるのは、辞としての「私」(ここでは語り手が視点を重ねた「彼」)が〃いま〃、「確実に記号内容を自分に引き受け」「時間に意味を与え」
(バルト、前掲書)たからにほかならない。そしてそれは、「観念的に二重化し、あるいは二重化した世界がさらに二重化するといった入子型の世界の中を、われわれは観念的な自己分裂によって分裂した自分になり、現実の自分としては動かなくてもあちらこちらに行ったり帰ったりしている」(三浦、前掲書)からなのだ。こうした語りの構造は、既に処女作『木曜日に』にみることができる。
「私」は、宿の人々への礼状を書きあぐねていたある夜更け、「私の眼に何かがありありと見えてきた」ものを現前化する。
それは木目だった。山の風雨に曝されて灰色になった板戸の木目だった。私はその戸をいましがた、まだ朝日の届かない森の中で閉じたところだった。そして、なぜかそれをまじまじと眺めている。と、木目が動きはじめた。木質の中に固く封じこめられて、もう生命のなごりもない乾からびた節の中から、奇妙なリズムにのって、ふくよかな木目がつぎつぎと生まれてくる。数かぎりない同心円が若々しくひしめきあって輪をひろげ、やがて成長しきると、うっとりと身をくねらせて板戸の表面を流れ、見つめる私の目を眠気の中に誘いこんだ。
厳密に言うと、木目を見ていたのは、手紙を書きあぐねている〃とき〃の「私」ではなく、森の山小屋にいた〃そのとき〃〃そこ〃にいた「私」であり、その「私」が見ていたものを「私」が語っている。つまり、
①「私」について語っている〃いま〃
②「私」が礼状を書きあぐねていた夜更けの〃とき〃
③山小屋の中で木目を見ていた〃とき〃
④木目になって感じている〃とき〃
の四層が語られている。しかし、木目を見ていた〃とき〃に立つうちに、それを見ていたはずの「私」が背後に隠れ、「私」は木目そのものの中に入り込み、木目そのもののに〃成って〃、木目が語っているように「うっとり」と語る。見ていたはずの「私」は、木目と浸透しあっている。動き出した木目の感覚に共感して、「私」自身の体感が「うっとり」と誘い出され、その体感でまた木目の体感を感じ取っている。
節の中心からは、新しい木目がつぎつぎに生まれ出てくる。何という苦しみだろう。その時、板戸の一隅でひとすじのかすかな罅がふと眠りから爽やかに覚めた赤児の眼のように割れてわずかに密集の中へ喰いこみ、そのまま永遠に向かって息をこらしている……。私も白い便箋の前で長い間、息をこらしていた。
最後に、視線は、〃いま〃語っている「私」へと戻ってくる。そして、その「私」のパースペクティブの入子になって書きあぐねていた〃そのとき〃の「私」の視線があり、その入子となって、小屋の中で木目を見ていた〃そのとき〃があり、更に木目に滑り込んで、木目に感応していた〃そのとき〃がある。と同時に、浸潤しあっていたのは、〃そのとき〃見ていた「私」だけでなく、それを〃いま〃として、眼前に思い出している語っている「私」もなのだということである。
そのとき、《見るもの》は《見られるもの》に見られており、《見られるもの》は《見るもの》を見ている。《見るもの》は、《見られるもの》のパースペクティブの中では《見られるもの》になり、《見られるもの》は、《見るもの》に変わっていく。あるいは《見るもの》は《見られるもの》のパースペクティブを自分のものとすることで、《見られるもの》は《見るもの》になっていく。その中で《見るもの》が微妙に変わっていく。
だが、その語りは、語っている「私」が、〃いま〃見たのにすぎない。〃いま〃そのときを思い出して語っている「私」も、その入子になっている「私」も、木目も、その距離を埋めることはない。いやもともと隔たりも一体感も「私」が生み出したものなのだ。ただ、「私」はそれに〃なって〃語ることで、三者はどこまでいっても同心円の「私」であると同時に、それはまた「私」ではないものになっていく。それが「私」自身をも変える。変えた自分自身を語り出していく。そういう語りの可能性が、古井氏の達成した語りの構造にほかならない。
しかし、この入子のパースペクティブは、ただ見られるものの奥行を広げるだけには留まらないはずである。見られるものの奥行は、見るものの見る視点そのものの後退をも伴っているはずだ。ちょうど消失点を無限大にすることが、認識の深度に等しいように、〃いま〃語ろうとしている語りの奥行は、消失点を前へ前へと遠ざけていくとき、語りの視点を後ろへ後ろへと後退させていけるのに釣り合っているはずである。
なぜなら、語っている〃いま〃と〃ここ〃を失わないからこそ、その語りの奥行を可能にする。しかし、それは同時に、前へと繰り越される自意識(あるいは後退する自意識と言っても同じだ)を伴わざるをえないという両刃性をもっている。とすれば、後退する自意識に語りを切り拓くものが期待できないと同様に、入子を重ねていく語りも、表現技術的な彫琢としてならともかく、語りのパースペクティブの可能性を、これ以上拓くと予感させるものは見当たりそうにもない、と言えるかもしれない。
それならば、たとえば、次のような、
辞をもたない語り、ゼロ記号化した語りの入子を重ねた語りならどうか。そこには語っている〃いま〃も〃ここ〃もない、幻想も現実も区別する指標はない。しかし、そういう語りとは、「誰がしゃべっているのか。(中略)ディスクールが、というよりも、言語活動が語っている」(バルト、前掲書)ことになるのだろうか?その疑問に対して、少なくとも、古井氏は、既に『眉雨』において、ひとつの答えを出しているようにみえる。
しかし、これはまた別途に論じなくてはならない課題のようである。