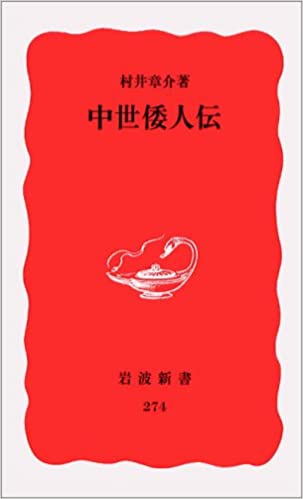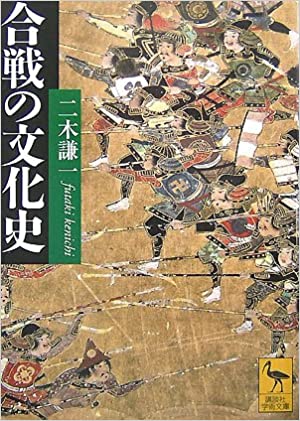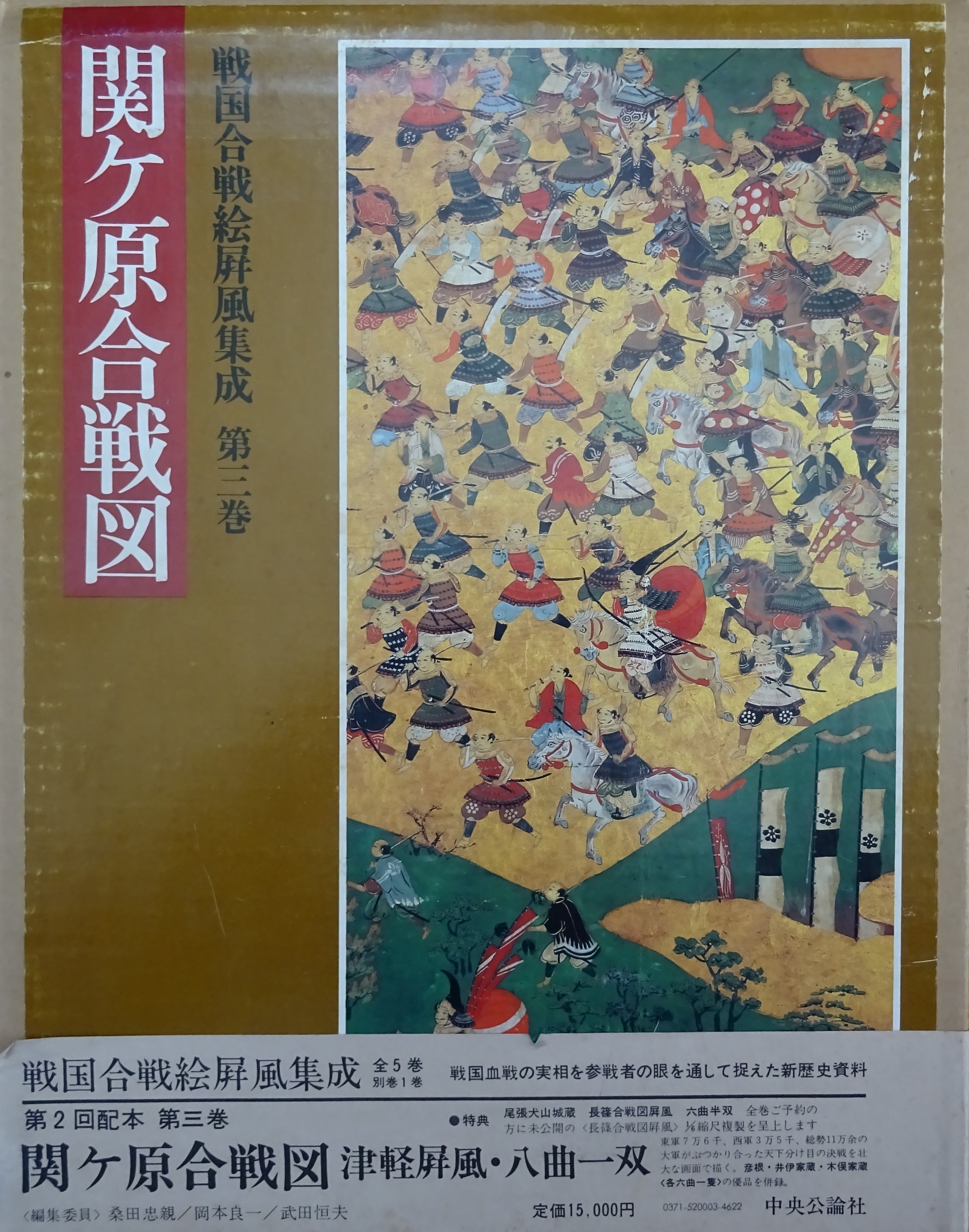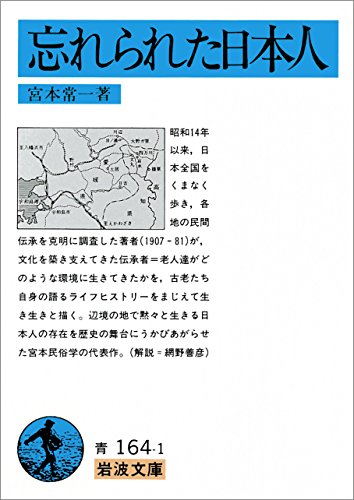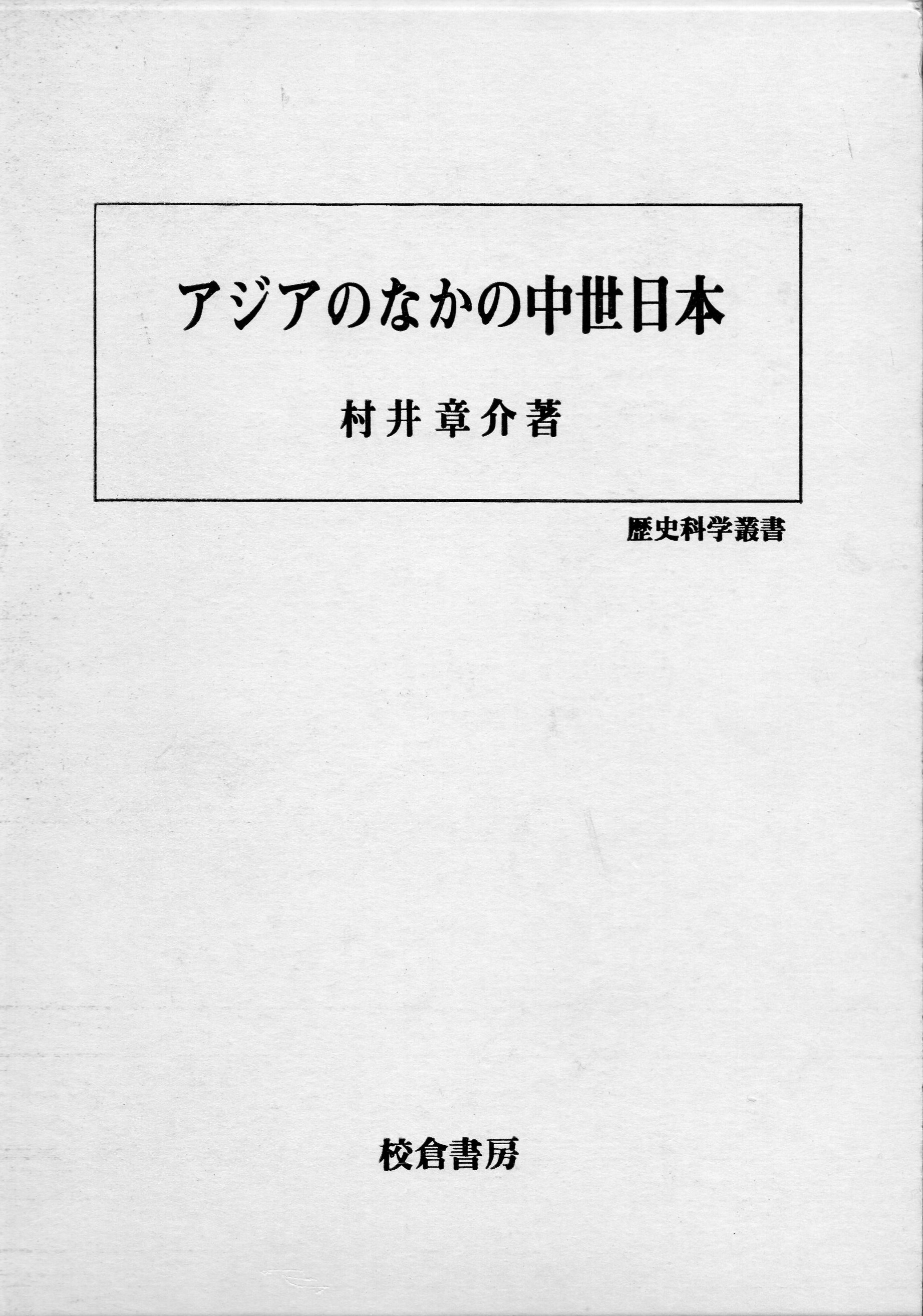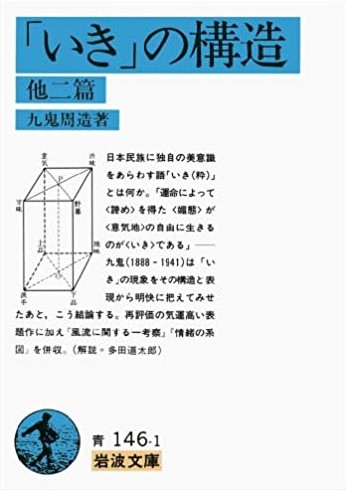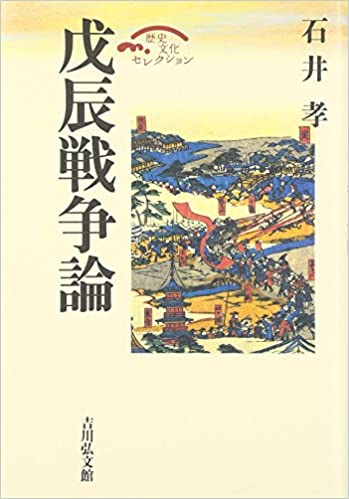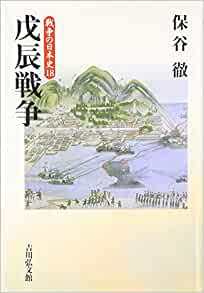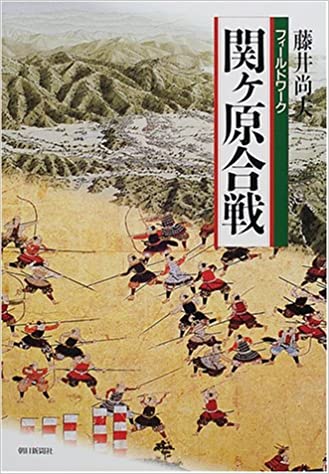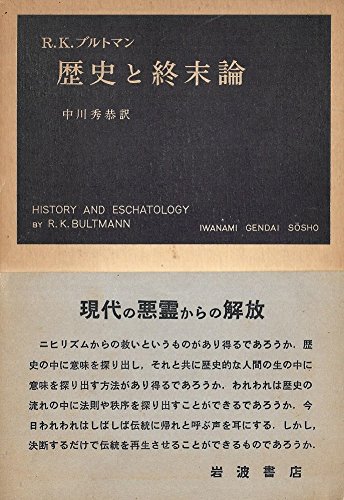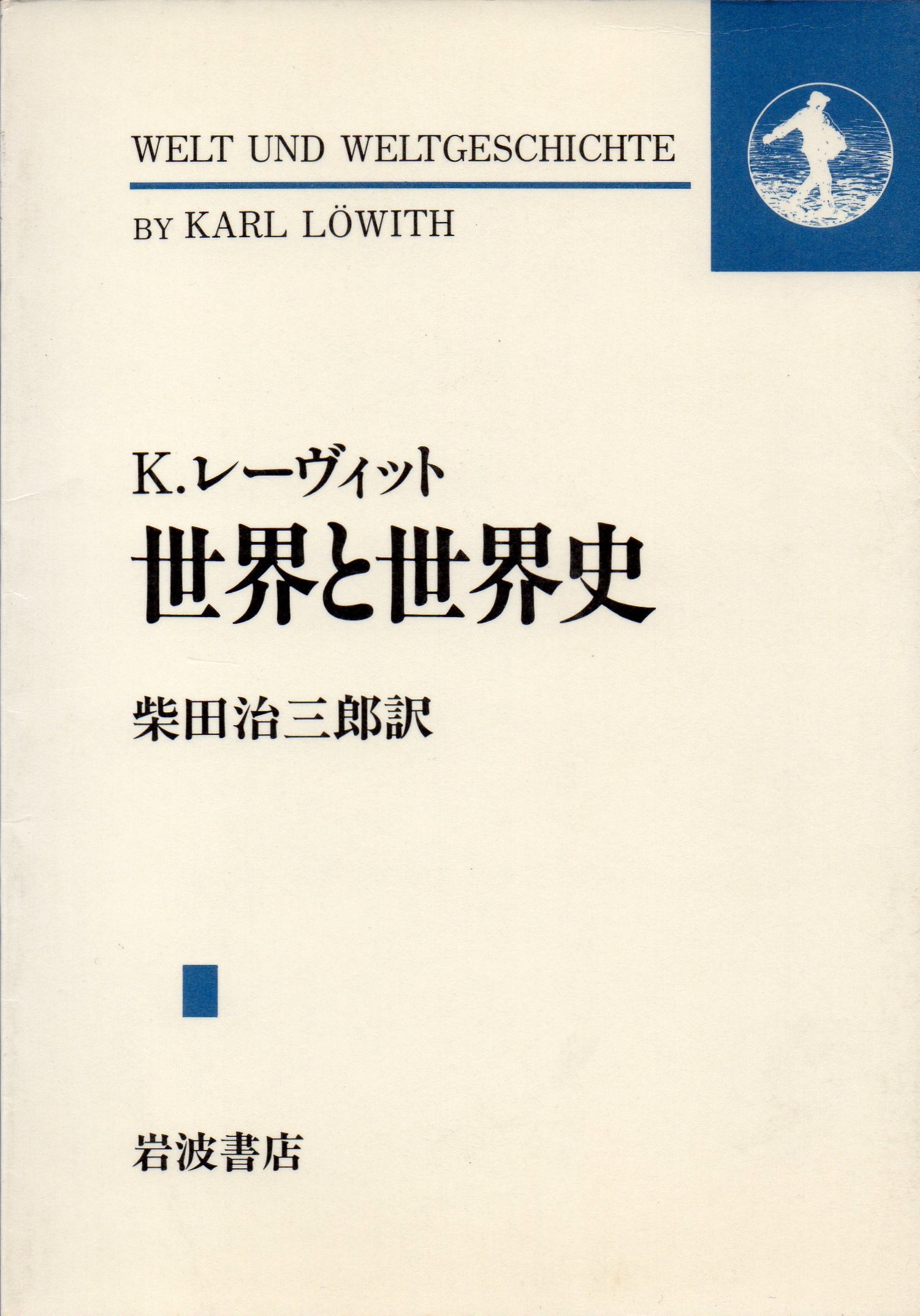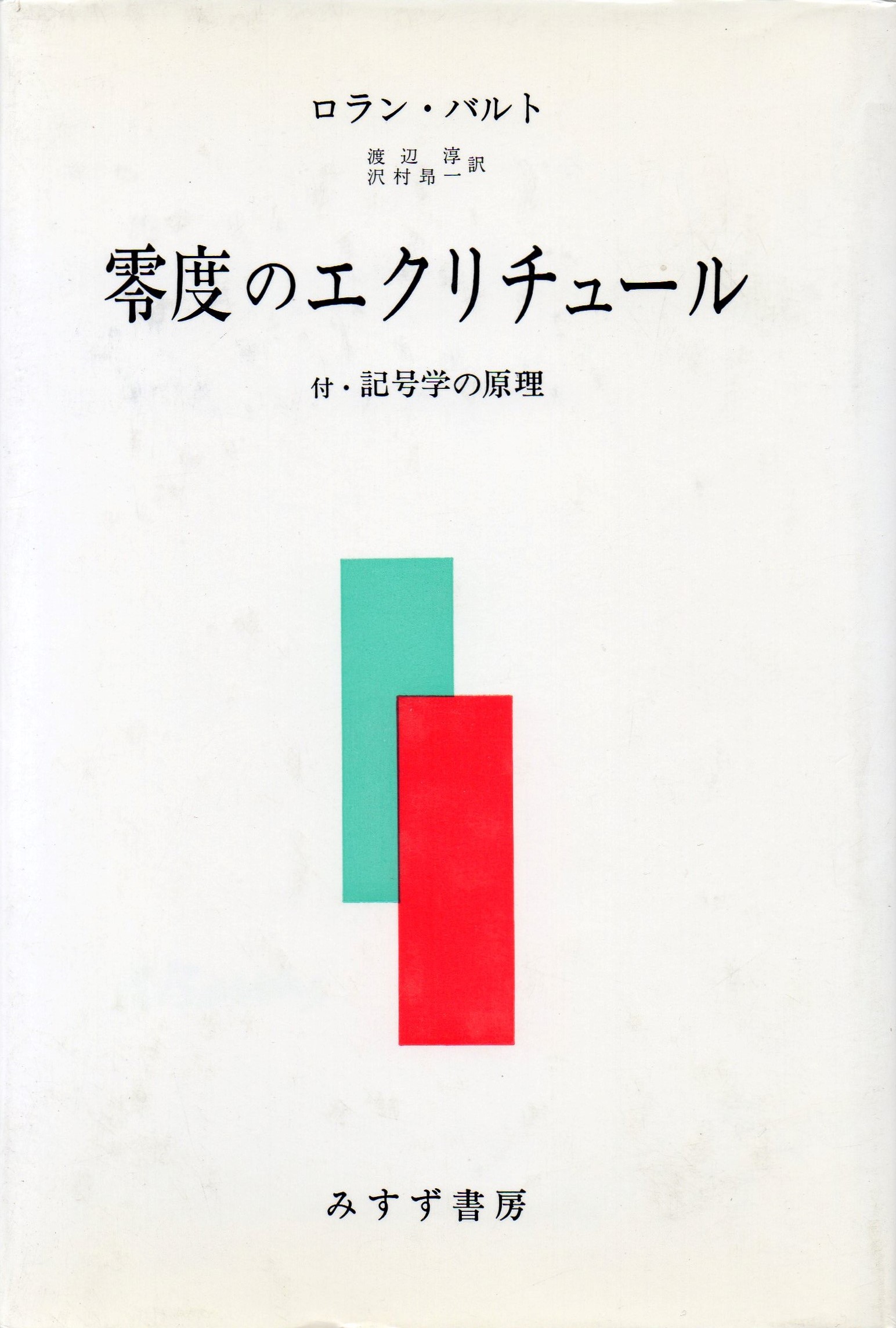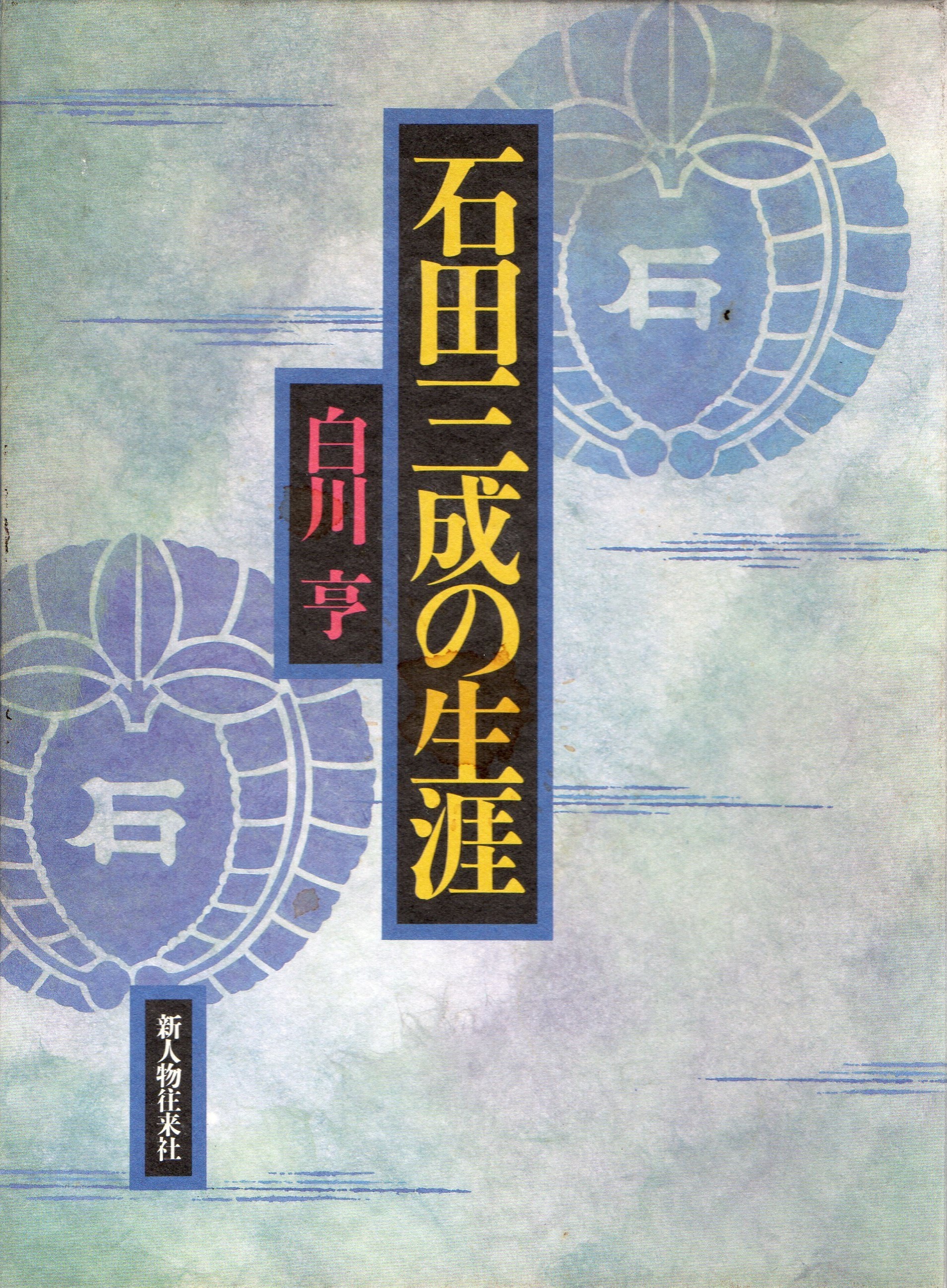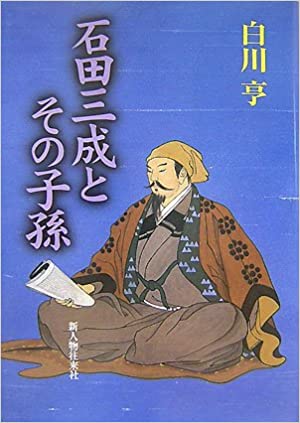| 村井章介『中世倭人伝』を読む。
|
| 二木謙一『合戦の文化史』を読む。
本書は、もともとは、「合戦の舞台裏」というタイトルであったらしい。「舞台裏」には違いないが、どちらかというと、 武具、 兵器、 の推移を辿っているので、「文化史」という雰囲気はない。むしろ、軍事技術史、といった感じではあるまいか。 本書を読んで、面白いことに気づいた。ひとつは、 日本の技術革新、 の特徴である。それは、ほとんど伝来技術によってスタートする。例えば、武器は、日本は世界史レベルからかなり遅く、 「ふつうはまず木・石製にはじまり、ついで銅・青銅製に移り、そして鉄器という順序に発達している。しかも多くの国では千年または千五百年という長い青銅器時代がある。ところが日本では、このいわゆる青銅器時代はなく、木・石器時代から、いきなり青銅・鉄器がほとんど同時にもたらされ、その後も超スピードで鉄器時代に進んでいるのである」 と、いわば文明国ではない故の、おくれてのスタートなのだが、 「弥生式時代から古墳時代にかけての数百年の間に、武器の製造や使用法も急速な発達をとげ」 て、 「四世紀のころには種々の武器を製造する鍛冶部があらわれ、七世紀ごろになると、逆に中国や朝鮮に対して日本製の武器が多量に輸出されるまでになっていた」 という、 「またたく間に外来文化を模倣し、さらに独自のものまでを創造する」 という特徴が武器でも表れていることである。 「中世倭人伝」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-11.htm#%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB)によると、16世紀半ば、 灰吹き法、 という画期的な銀精錬技術を密かに伝習して、それまで輸入品であった銀を、大量の密輸品として朝鮮に輸出するに至り、朝鮮側は、 「倭国の銀を造ること、未だ十年に及ばざるに、我国に流布し、已に賎物(ありふれた物)となる」と述べせしめた。正当な伝来ではなく、そのために朝鮮人が罪に問われたほどなのに、日本は、この技術によって、17世紀には、世界の銀生産量の三分の一を占めるに至るのである。ここにも、技術革新のコアを模倣する力を見ることが出来る。しかし、銀の精製法の革新である、電解精錬を、日本が開発したということはない。 さらに、種子島経由で伝来した火縄銃でも同じことが起きている。 鉄砲伝来は天文十二(1543)年であるが、 「日本の戦国大名らは、またたく間に鉄炮と火薬の製法を学んで、新兵器として活用することに成功したのである。信長が長篠合戦ではじめて鉄炮の組織的活用をおこなったのは天正三(1575)年だが、それから二十五年後の関ケ原合戦のころには鉄炮は主力兵器となっていた」 のであり、戦国時代末期には、 日本は50万丁以上を所持していたともいわれ、当時世界最大の銃保有国、 であった、とされる。しかし、その後三百年、江戸末期に、ゲーベル銃がもたらされるまで、 火縄式、 が改められることはなく、結局外国製の、 ゲーベル銃、 メニエー銃、 が輸入されるまで、 燧石式、 も、 雷管式、 も、 まして、 後装施条銃(ライフル)、 も開発できなかったのである。 こうした日本の軍事技術開発の桎梏には、もうひとつ大きな敗因がある。それは、 兵法、 の無いことである。兵法學は、 甲州流、 越後流、 北條流、 等々あるが、 甲陽軍鑑、 を代表とする、その著作は、 「孫呉の兵法や『平家物語』『太平記』など戦陣の物語をもとに、陰陽五行や天象方位をまじえて適宜につくりあげたものであり、…しょせんは泰平の世の軍学者が考えだしたもので、現実味に乏しい」 つまりは、 虚構の兵法、 にすぎず、一人の孫子(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-1.htm#%E5%AD%AB%E5%AD%90)も、ひとりのクラウゼヴィッ(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-1.htm#%E6%88%A6%E4%BA%89%E8%AB%96)も生み出さなかった。戦術レベルではなく、戦略レベルの戦争論は、以後今日まで、日本では、論じられたことはないし、広くそうしたソフトウエア全般については、日本には一つも世界基準となるものを生み出せていない。旧軍部の参謀本部自体が、甫庵信長記の創作をもとに、桶狭間等々の戦術を研究していたのであるから、噴飯物で、とてもアメリカ相手に勝てるはずはないのである。『甫庵信長記』の捏造については、「信長の戦争」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-10.htm#%E9%80%9A%E8%AA%AC%E3%82%92%E8%A6%86%E3%81%99)で触れた。 参考文献; 二木謙一『合戦の文化史』(講談社学術文庫) |
| 内村鑑三『代表的日本人』を読む。
|
| 桑田忠親,武田恒夫他『関ケ原合戦図(戦国合戦絵屏風集成第三巻)』を読む。
第一類 旧津軽家本関ヶ原合戦図屏風(大阪歴史博物館蔵) 八曲一双(各隻194×590センチ) 第二類 井伊家本関ヶ原合戦図屏風(彦根博物館蔵) 六曲一隻(156.7×361.2センチ) 木俣家本関ヶ原合戦図屏風(同) 六曲一隻(159.1×364.6センチ) 関ヶ原町教育委員会蔵本関ヶ原合戦図屏風 六曲一隻(175×380センチ) 第三類 徳川美術館本関ヶ原合戦図屏風 二曲二双(72.4×55.4センチ) 東京国立博物館蔵本関ヶ原合戦図屏風絵 紙本二巻(縦79センチ) 第四類 国会図書館蔵本関ヶ原合戦絵巻 二巻 静嘉堂文庫蔵本関ヶ原合戦絵巻物 一巻 大東急記念文庫蔵本関ヶ原合戦絵巻 二巻 である(仝上)。このうち、第四類は、絵巻物なので、本書は扱っていない。本書は、 旧津軽家本関ヶ原合戦図屏風(大阪歴史博物館蔵) 八曲一双 井伊家本関ヶ原合戦図屏風(彦根博物館蔵) 六曲一隻 木俣家本関ヶ原合戦図屏風(同) 六曲一隻 を扱っているが、 井伊家本関ヶ原合戦図屏風(彦根博物館蔵) 六曲一隻 木俣家本関ヶ原合戦図屏風(同) 六曲一隻 関ヶ原町教育委員会蔵本関ヶ原合戦図屏風 六曲一隻 は、 同じ大きさの画面とほぼ同じ構図である、 合戦の布陣人物の配置、旗指物の有様は全く同一、 等々から、原本を同じくする模写本とみなされている(仝上)。特に、 赤い旗指物を誇張して描くことから井伊直政を中心として木俣右京・向山内記といった井伊藩の猛将たちの関ヶ原合戦での奮闘ぶりを顕彰することが主目的、 であったとみられ(仝上)、いずれも、落款から幕末期の制作とみなされており(岡本良一「関ケ原合戦図屏風」)、旧津軽家本の関ケ原合戦図屏風が、 合戦の起きた慶長五年(1600)以後十年余の間に制作された、 と、実戦から隔たっていない時期に制作された、 実戦の記録性と迫真力をもった生々しい戦況の現実観とを具備した歴史画として高く評価されている、 のと、比較すると、大きさからいってもスケールからいっても、落差がある。 普通、屏風といえば六曲一双で、その大きさも縦横およそ150センチ×370〜380センチが通り相場であるが、この屏風は194センチ×590センチという大型で、さすがに家康が命じて制作させたもの、 とされている(仝上)だけの特別のものである。これが、 津軽屏風、 といわれるのは、旧津軽家に長く襲蔵されてきたからである。津軽家の史料(津軽藩旧記伝類)には、家康の異母弟松平康元の娘満天姫(まてひめ)が、家康の養女として津軽二代藩主信枚(のぶひら)に嫁いだ際の輿入れ道具の一つとして持参したことが知られている。満天姫は、 嫁入りに際し家康の所持していた「関ヶ原合戦図屏風二双の内一双」を拝借したい旨申し出たところ、家康は一度は外の品ならば何なりと許すと断ったが、満天姫の熱意に折れて、「遠国のなぐさみにもせよ」と所望を許した、 という。その経緯を、『津軽藩旧記伝類』の「藤田氏旧記」に、 満天姫君或年家康公へ御願被成候は、子孫へ長く宝に仕度候間、関ヶ原御屏風二双の内、一双拝借仕度旨申上ければ、家康公仰に其義は迚も望に叶ひがたし、外品なれば何なりと望に叶ふべしと申ければ、姫、余の御品は少も望無御座候、何にも頂戴被仰付度旨、泪を流して無余儀御願被遊ける故、家康公にも左程のことならば暫く預け置の間、少しく遠国のなぐさみにもせよと御預被遊けるとなり、 とある(仝上)。津軽屏風の特徴は、 右隻は、大垣城、杭瀬川の戦いが描かれ、 左隻は、勝敗の帰趨の決まった後の、石田・島津・小西・宇喜多・大谷陣営の敗走する様子と、これを追う東軍が描かれる、 が、他の合戦図と比較して、 2026人、 も描かれているのに、家康すら、右隻に、 大勢の馬上の鎧武者に囲まれるように疾駆する、鉢巻頭の鎧武者が家康と判定されるのであるが、この家康以外、左右両隻を通じて誰一人としてその名を指摘できる人物はいない、 ばかりか、部隊も、判然としない。この種の合戦図では、「異例」のこととされる。通常、 馬印・幟・指物などの旌旗によって、部隊名はもちろん、個人名までがはっきりと指摘できる、 のであるが、その中で、例外的に、 左隻の合戦の画面には西軍陣地を突破する福島正則らの先鋒隊が奮戦する有様だけが描写、 されているのである。満天姫の前夫は、福島正則の子正之であり、その死後家康の元に戻っていた。満天姫のこだわりは、ここにあったのではないか、とされている。で、 家康としては全部手放してしまう気になれず、八曲の二双の内の半分、つまり、第一隻(右隻)と第三隻(左隻)とを対にして一双にして与えたのではないか、 と(小和田哲男「関ヶ原合戦図屏風」)し、そう考えると、普通、 一つの大きなテーマを扱い、その図様を画面構成する場合、必ず図様は連続した形式で構成されるのが常套的表現法、 なのに、現存の津軽屏風が不自然に切れていて、左隻と右隻の図様がうまく連繋できていない画面構成(神山)である理由が、たとえば、 満天姫は福島隊にこだわった。前夫のおもかげのありそうな部分、第一隻(右隻)と第三隻(左隻)をピックアップした、 と考える(小和田)と説明できる、と。つまり、 本来二双ということになると、右から第一隻・第二隻・第三隻・第四隻とあったわけで、場面から見ると、その第一隻と第三隻が現存し、第一隻を右隻、第三隻を左隻とよんでいる、 ことになる(仝上)。第四隻には、 佐和山攻略の状況が描かれていた、 と(岡本)考えれば、大垣城からはじまった関ヶ原合戦の時間経過が、完結するということになる。 なお、津軽屏風に描かれている家康は、 神格化された後世の家康像、 とは異なる現実味があり、合戦直後に描かせたと考えられる傍証となる。 屏風絵は、現物を目の前に見るのが一番だが、ガラス越しでは細部は見えず、画集の良さは、ある面細部をくまなく見ることが出来ることだが、全体の流れが一覧しにくいことが、当然ある。 絵巻物、 から派生した屏風絵だけに、時間軸が、右から左へ、同時に、 東から西へ移動していく、 形になっている。そうみると、津軽屏風の断続が、一層際立って見えてくる。特に、「津軽屏風」は、各軍の旗幟も明らかでなく、家康を除くと、殆ど個人を識別するのも難しいが、合戦後近い時期に描かれただけではない、 記録映画的価値、 があるのは、 小荷駄(輜重)隊の物資運搬状況、 野陣の状況、 穀竿をふるって稲こきをしたり、杵で脱穀したりする様子、 等々、他の合戦図屏風にはない描写が豊富であり(岡本)、それは、俯瞰してでは気づけない、画集ならではの特典である。 参考文献; 桑田忠親、武田恒夫他『関ケ原合戦図(戦国合戦絵屏風集成第三巻)』(中央公論社) 藤本正行「入門戦国合戦図屏風」(別冊歴史読本『戦国合戦図屏風』)(新人物往来社) 小和田哲男「関ケ原合戦図屏風」(仝上) |
| 宮本常一『忘れられた日本人』を読む。
著者は「あとがき」で、 無名にひとしい人たちへの紙碑(しひ)のできるのはうれしい、 と書く。まさに、 無名の人々の紙の碑、 である。特に、 名倉談義、 土佐源氏、 梶田富五郎翁、 が印象深いが、とりわけ、 土佐源氏、 は、創作かと思わんばかりの、その人の一生が、語られている。多くは、語りによって表現されているが、ふと、V・E・フランクルの、 人は誰もが語るべき物語を持っている、 という言葉を思い出す。その物語を聞き出す、著者の聴く力に敬服する。博労であったが、盲目となり、乞食になって、橋の下に住む語り手は、最後にこう締めくくる。 「婆さんはなァ、晩めしがすむと、百姓家へあまりものをもらいに行くのじゃ。雨が降っても風がふいても、それが仕事じゃ、わしはただ、ここにこうしてすわったまま。あるくといえば川原まで便所におりるか、水あびに行く位のことじゃ……。ああ、目の見えぬ三十年は長うもあり、みじこうもあった。かまうた女のことを思い出してのう。どの女もみなやさしいええ女じゃった。」 これを創作と疑った人に対し、「宮本氏は……採訪ノートを示して墳った」(解説・網野善彦)という。もっともだろう。ここまで赤裸々に語らせるには、並の人の聞き取り力では不可能なはずだからである。 橋の下の乞食の物語は宮本氏というすぐれた伝承者を得て、はじめてこうした形をとりえた、 のである(仝上・網野)。 著者は山村調査の方法について、こう書いている。 「……私の方法はまず目的の村へいくと、その村を一通りまわって、どういう村であるかを見る。つぎに役場へいって倉庫の中をさがして明治以来の資料をしらべる。つぎにそれをもとにして役場の人たちから疑問の点をたしかめる。同様に森林組合や農協をたずねていってしらべる。その間に古文書があることがわかれば、旧家をたずねて必要なものを書きうつす。一方何戸かの農家を選定して個別調査をする。私の場合は大てい一軒に半日かける。午前・午後・夜と一日に三軒すませば上乗の方。(中略) 古文書の疑問、役場資料の中の疑問などを心の中において、次には古老にあう。はじめはそういう疑問をなげかけるが、あとはできるだけ自由にはなしてもらう。そこでは相手が何を問題にしているかがよくわかる。と同時に実にいろいろなことをおしえられる。「名倉談義」はそうした機会での聞取である。 その間に主婦たちや若い者の仲間にあう機会をつくって、この方は多人数の座談会形式ではなしもきき、こちらもはなすことにしている。」 そして、 「私のいちばん知りたいことは今日の文化をきずきあげてきた生産者のエネルギーというものが、どういう人間関係や環境の中から生れ出てきたかということである。」 と。だからこそ、その一人に語りを深追いしていく。調査に反対している人のところへも行く。しかし、 「どうにもならなくて手をあげたという場合はすくない。これは私が前時代的な古風な人間であるからだと思う。そして相手の人が私の調子にあわせるのでなく、自分自身の調子ではなしてくれるのをたいへんありがたいと思うし、その言葉をまたできるだけこわさないように皆さんに伝えるのが私の仕事の一つかと思っている」 と。 まさに、「はなす」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba7.htm#%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%99)は、 放す(心の中を放出する) である(大言海)。「かたる」との差は、 筋のある、 事柄や考えを言葉で順序立て、 というところになる。その中に、 庶民の「生活誌」(仝上・網野)、 がおのずと浮かび上がってくる。 「村の寄り合い」にある、村里内の話し合いは、 「今日のように論理づくめでは収拾のつかぬことになっていく場合が多かったと想像される。そういうところではたとえ話、すなわち自分たちのあるいて来、体験したことにこと寄せて話すのが、他人にも理解してもらいやすかったし、話す方もはなしやすかったに違いない。そして話の中にも冷却の時間をおいて、反対の意見が出れば出たで、しばらくそのままにしておき、そのうち賛成意見が出ると、また出たままにしておき、それについてみんな考えあい、最後に最高責任者に決をとらせるのである。これならせまい村の中で毎日顔をつきあわせていても気まずい思いをすることはすくないであろう。と同時に寄りあいというものに権威のあったことがよくわかる。 対馬ではどの村にも帳箱があり、その中に申し合せ覚えが入っていた。こうして村の伝承に支えられながら自治が成り立っていたのである。」 とあり、そのゆったりとした時間の流れは、危機に際してもきちんと働くことは、中世、近江の「小さな共和国」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-8.htm#%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD)で触れた、琵琶湖畔の、 「集落が、乙名を指導者とする行政組織を持ち、在家を単位とする村の税を徴収し、若衆という軍事・警察組織を持ち、裁判も行い、村の運営を寄合という話し合いで進め、そのため構成員は平等な議決権を持つ、自治の村落」 であったことと通底する気がする。史料の言葉で、これを、 惣村、 と呼び、 「惣の目的は住民の家を保護することで、平等観念は一揆の原理」 と同じである。 参考文献;宮本常一『忘れられた日本人』(岩波文庫) |
| 松浦玲『検証・龍馬伝説』を読む。
|
| 松浦玲『明治の海舟とアジア』を読む。
明治維新の時数え四十六歳の海舟は、七十七歳まで生きた。その海舟は、 |
| 和辻哲郎『日本精神史研究』を読む。
通読して、僕には、 |
| 村井章介『アジアのなかの中世日本』を読む。
「マージナル」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-11.htm#%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB)で触れた村井章介『中世倭人伝』の背景になる時期と重なり、「海の民」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-10.htm#%E6%B5%B7%E3%81%AE%E6%B0%91)で触れた田中健夫『倭寇―海の歴史』や、「倭寇」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-10.htm#%E5%80%AD%E5%AF%87)で触れた竹腰輿三郎『倭寇記』でいう、前期倭寇と言われる時期を中心に、中世日本の、本土の中心から離れた、辺境地域の倭人たちの世界を、「アジア」という広がりの中で、多角的に洗い出している。 「ここでわたしがしつらえた《アジア》というステージに登場する役者は、けっして国家だけではない。たとえば倭寇のように、国際関係を背景から規定するとともに、国家のわくを超えた地域の担い手となり、一面では国家の規制力によってゆがめられる、そういった人間集団も、主役に名をつらねている。またアイヌや琉球人のように、独自の国家を所有した有無はあるにせよ、結果的には日本の国家に呑みこまれてしまった民族集団が、自己を形成する過程も、重要なだしものだ。このように日本の中世は、国家のわくぐみを相対化し、《可能性としての歴史》を構想するのに好適な素材に恵まれている。 そしてこの素材にとりくんだ背景には、現代に生きるわれわれが、国家利害をすべてのうえにおく思考からいかに脱却し、アジア諸民族や国内の少数民族との関係をどう自覚的に創造しうるか、という問題関心があった。」 と著者は、全体の編集意図を整理している。 面白いのは、南北朝から、室町、戦国時代と、国内政権が分散的、拡散的で、中央集権的な国家ができるまでの間、周辺は、倭寇に代表されるような人々が、朝鮮半島や中国沿海部、フィリピン、インドシナ半島と、広い領域に、他国に強い影響を与え続けていたことだ。その人々は、「倭人」とされるが、その、 「《倭》とは本来日本の同義語ではなく、《倭種》とは西日本のみならず、江南から山東半島、朝鮮半島南部にかけての大陸沿海部にも分布する、海洋民的な性格の人びとのこと」 なのである。 その一つのモデルを、著者は、 「列島内の一部分が、内海を通じて列島外の一定地域と結ばれ、こうして国境を超えたひとつの地域、たとえば私が『環シナ海地域』とよぶような地域が登場します。こうなりますと地域の登場は、列島中央の国家権力から発する求心力に抗して、国家的統合を相対化する遠心力として作用するでしょう。ここで措定された『地域』とは、伝統的な海外交渉史の主要概念である『国交』や『貿易』が線で表象されるとすれば、面で表象される点に特徴があります。そして地域を面たらしめているものは、それ自体多彩な要素からなるところの交渉の担い手たちであり、かれらが展開する多様で多面的な活動そのものだといえます。具体的に申しますと、中国人海商、倭寇、琉球人などがこの担い手でありまして、かれらは、それぞれの出身の国家に対しては相対的に『自由』にふるまい、自由な分だけ『地域』への帰属意識をもっていた、と考えられます。」 と書く、その《面としての地域》は、倭寇の、あるいは倭寇を装う集団の活動地域と重なっていく。そして、この問題意識は、ともすると中世を、武士の世界と見る見方への反論になりえるのである。たとえば、 「従来日本の中世を前進させたものとイメージされてきたのは、武士=在地領主、およびかれらが結集した権力である幕府であったが、これら《武》の勢力が力をふるいえたのは、《文》に対して先進的だったからではなく、むしろ中国文明を中心とする東アジア世界のなかで、日本のおかれた辺境性にもとづいている。『自力救済』や『寄せ沙汰』にみられるように、暴力とコネが一貫して紛争解決の手段だったのが日本の中世の特徴であって、この未開性にくらべれば、『武人より文人、武勇よりは安穏に価値を見出す東アジアの世界観』にそれなりに従うべきところがあったのではないか」 と。それは、「脱亜入欧」という今日までつづく考え方に通底するアジア蔑視への痛撃となり、それは何処か、 や 横井小楠(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-6.htm#%E5%B0%8F%E6%A5%A0%E8%AB%96) の描いていた世界観と通底するものがある。 さて、その意味で中央の「日本」から離れた周辺での、幅広い世界像を描いている点で、 Ⅲ 中世日本列島の地域空間と国家、 が出色である。「周辺」とは、中央から見た場合、 異域、 であり、 化外、 であり、 ケガレの地、 であり、 鬼の住処、 であり、中央から、 「皇都→畿内→外国(げこく)は浄から穢へと段階的に移行する同心円構造をなしていた」 のであるが、しかし、 「周縁の人びと境界の往来者にとって、異域はもはや鬼のすみかではなく、あらたなもうひとつの《文明》であった。異域に人力のおよばざる鬼ではなく、自己と種々のちがいはあるにせよ人間を発見するとき、それはもはや異域ではなくなり、それと自己とをへだてる境界の性格も変わってくる。」 それを著者は、 海上の境界という観念の出現、 と特徴づける。著者はそのモデルを、 環日本海地域、 東シナ海地域、 に見出す。前者は、 十三湊を中心に、北海道のアイヌ、沿海州、高麗までの日本海地域、 になる。後者は、 倭寇活動地域、 と重なる。しかし、その時代は、十六世紀後半の秀吉の統一で終わりを迎える。その決算が、 文禄・慶長の役、 であるが、 「国内戦争の論理をそのまま延長したものであり、朝鮮の自主性を徹底的に無視し朝鮮人民に甚大な損害をもたらした暴挙であった……。そこには、中世を通じて温存されてきた、朝鮮を日本に服属すべき国とみなす観念の反映をみてとることができる。」 それは、そのまま、武の政権の明治政府の行動へとつながり、今日までその禍根は尾を引いている。
参考文献; |
| 九鬼周造『「いき」の構造』を読む。
著者は、「いき」を、 内包的構造、 に分けて、その構造を鮮明にした。「内包的構造」では、 媚態、 の三つの表徴に分解した。 「媚態」とは、異性に対する「媚態」である。 「異性との関係が『いき』の原本的存在を形成していることは、『いきごと』が『いろごと』を意味するのでもわかる。『いきな話』といえば、異性との交渉に関する話を意味している。」 「媚態」とは、 「一元的の自己が自己に対して異性を措定し、自己と異性との間に可能的関係を構成する二元的態度である。そうして『いき』のうちに見られる『なまめかしさ』『つやっぽさ』『色気』などは、すべてこの二次元的可能性を基礎とする緊張にほかならない。」 と。 「意気」すなわち、「意気地」とは、 「意識現象としての存在様態である『いき』のうちには、江戸文化の道徳的理想が鮮やかに反映されている。江戸児(えどっこ)の気概が契機として含まれている。(中略)『江戸の花』には、命をも惜しまない町火消、鳶者(とびのもの)は寒中でも白足袋はだし、法被一枚の『男伊達』を尚(とうと)んだ。『いき』には、『江戸の意地張り』『辰巳の侠骨』が無ければならない。『いなせ』『いさみ』『伝法』など共通な犯すべからざる気品・気骨がなければならない。『野暮は垣根の外がまへ、三千楼の色競べ、意気地くらべや張競べ』というように、『いき』は媚態でありながらなお異性に対して一種の反抗を示す強みをもった意識である。(中略)『いき』のうちには溌剌として武士道の理想が生きている。」 であり、 「理想主義の生んだ『意気地』によって媚態が霊化されていること」 が「いき」の特色であると、する。「諦め」は、 「運命に対する知見に基づいて執着(しゅうじゃく)を離脱した無関心である。『いき』は垢抜けがしていなくてはならぬ。あっさり、すっきり、瀟洒たる心持でなくてはならぬ。」 とし、 解脱、 とする。 「『いき』は『浮かみもやらぬ、流れのうき身』という『苦界(くがい)』にその起源をもっている。(中略)『諦め』したがって『無関心』は、世智辛い、つれない浮世の洗練を経てすっきりと垢抜けした心、現実に対する独断的な執着を離れた瀟洒として未練のない恬淡無碍のこころである。」 と。そして、この三者を、 「第一の『媚態』はその基調を構成し、(中略)媚態の原本的存在規定は二元的可能性である。しかるに第二の徴表たる『意気地』は理想主義の齎した心の強みで、媚態の二元的可能性に一層の緊張と一層の持久力を呈供し、可能性を可能性として終始せしめようとする。(中略)媚態の二元的可能性を『意気地』によって限定することは、畢竟、事由の擁護を高唱するにほかならない。(中略)媚態はその仮想的目的を達せざる点において、自己に忠実なるものである。それ故に、媚態が目的に対して『諦め』を有することは……、かえって媚態そのものの原本的存在性を開示せしむることである。媚態と『諦め』の結合は、自由への帰依が運命によって強要され、可能性の措定が必然性によって規定されたことを意味している。」 とまとめ、要するに、 「『いき』という存在様態において、『媚態』は、武士道の理想主義に基づく『意気地』と、仏教の非現実性を背景とする『諦め』とによって、存在完成にまで限定されるのである。」 と。さらに、「意気」の外延的構造では、「上品−下品」、「派手−地味」、「意気−野暮」、「渋み−甘味」の中で、位置づけなおしてみせる。しかし、著者自身が、「結論」で、 「『いき』を分析して得られた抽象的概念契機は、具体的な『いき』の或る幾つかの方面を指示するに過ぎない。『いき』は個々の概念契機を分析することはできるが、逆に、分析された個々の概念契機をもって『いき』の存在を構成することはできない。」 と言っているように、分解された要素を束ねても、「いき」とはどこかに乖離がある。読みながら感じた違和感は、それだけではなく、少しく「武士道」や「江戸ッ子気質」について、理想化され過ぎている感があった。 「いき」は、 意気、 と当て、 明和頃、深川の岡場所に流行し、のちに一般化した語。粋であること、あかぬけしていること、洗練された美があること、しゃれていること(江戸語大辞典)、 近世中期頃からの江戸の町人に主に発達した美意識の一。嫌味なくさっぱりした態度、垢抜けした色気、洗練された媚態などを意味した(古語大辞典)、 (心映えの「意気」とは区別し、「清爽」を当て)意気ある人の、風采(ふり)、瀟洒(さっぱり)したるより出づ、さっぱりとして、いやみなきこと、婀娜たること、粋なること(大言海)、 とある。「いなせ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba2.htm#%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%9B)で触れたことがあるが、「いき」は、 心意気の略、 ではないか。その意味は、 気持ちや身なりのさっぱりして垢抜けしていて、しかも色気をもっていること、 あるいは、 人情の機微に通じ、特に遊里や遊興に精通していること、 ということらしい。類語に「伊達」というのがある。語源は、 ひとつは、「取り立てる」の「タテ」で、目立つという意味。実際以上に誇示する。 いまひとつは、「タテダテシイ」の「ダテ」で、意地っ張りという意味だ。伊達の薄着、というように、言ってみると依怙地を張っている、というニュアンスである。だから、 ことさら侠気を示そうとすること、 とか 派手にふるまうこと、 とか 人目につくこと、 とあって、そこから、 あか抜けていきであること とか さばけていること となっていく。しかし、どこかに、「見栄をはる」とか「外見を飾る」というニュアンスが抜けない。似たものに、「伝法」もある。「伝法な」は、 浅草伝法院の下男が、寺の威光を借りて、悪ずれした荒っぽい男であったのが、「デンポウ」なの由来、 とされる。転じて、無法な人、勇み肌という意になっていく。「鉄火肌」というのもその流れだろう。「鉄火」というのは、鉄火場、つまり博奕場である。しかし、「鉄火肌」の「鉄火」は、 鉄火(鉄が焼かれて火のようになったもの)、 という意味から来ているので、気性の激しさを言っている。 また「いさみ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba5.htm#%E5%8B%87%E3%81%BF)は、 市人の、気概(いきはり)を衒(てら)ふ者。其の気立てを、いさみ肌、きほいはだ、と云ふ(大言海)、 気概を、 いきはり、 と訓ませ、意気地を張る、というニュアンスにし、それを衒う、つまり、 見せびらかす、ひけらかす、 という含意である。そういうのを喝采するひとがいるから、ますますいきがる、ということになる。 どうも、いきがっている本人ほど、周囲は、認めていず、だからいっそう伊達風を張る。その辺りの瘦せ我慢というか、依怙地さは、嫌いではないが、所詮、 堅気ではない、 のである。まっとうではなく、そういう男伊達というか侠気というのは、 戦国武将の気風の成れの果て、 らしく、そのことは、「サムライとヤクザ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-6.htm#%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%A4%E3%82%AF%E3%82%B6)で触れた。 僕は、「いなせ」や「いき」は、気骨とは違うと思う。「気骨」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba2.htm#%E6%B0%97%E9%AA%A8)は、 「気(気概ある)+骨(人柄)」 である。これこそが、サムライである。 容易に人に従わない意気、自負、 こそが、「いき」ではないのか。それは、「心映え」だから、見栄を張って、外に着飾るものでも、言い募るものでもないのである。 三田村鳶魚は、 「武士が単なる偶像化されたる『人間の見本』であったり、あるいは、『人間の理想化』であっては、『武士道』甚だ愚なるものである。」 と言っている。著者の「武士道」が理想化され過ぎているように感じるのは僻目だろうか。「武士道」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-2.htm#%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93)については触れたが、武士道の謂れについて、鳶魚は、 「戦国末期の『武辺吟味』というのは、弓馬・剣槍、あるいは鉄砲等の武器に関することで、主として戦場における働き、すなわち、軍事上における働きの場合に用いられたものであって、今日いうところの武士道ではなく、むしろ、兵書・兵学に属するものであった。吟味は今でいう研究という言葉に相応するものだ。それよりも、『男の道』の方が『武士道』には近い。『そうしては男の道が立たない』というようなことは、『武士道が立たない』というのと同一の意味で用いられた言葉だ。故に、もし『武士道』なるものの語原的詮索をするとしたならば、武士道の母胎は『男の道』であって、これから、武士道なる言葉が転化し発生したものだ、ということが出来る。」 とし、武士道とは、 義理、 すなわち、 善悪の心の道筋、 である、とする。もう少し突っ込めば、 倫理、 である。倫理とは、 いかに生きるか、 である。だから、 「武士が切腹をするということには、二通りの意味がある。その一つは、自分の犯した罪科とか過失とかに対して、自ら悔い償うためには、屠腹するということであり、今一つは、申し付けられて、その罪を償うということである。そして、そのいずれにしても、切腹は自滅を意味する。(中略)切腹は、…武士に対する処決の一特典にしか過ぎない のである。ただ自らその罪に対する自責上、切腹して相果てるというその精神だけは武士道に咲いた一つの華と言っ てもよいが、武士道の真髄ではあり得ない。」 したがって、他人の忖度とは無縁である。前に、 心映え、 といったのはその意味である「心映え」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E5%BF%83%E3%81%B0%E3%81%88)で触れたように、その真髄は、周りへの影響のニュアンスの、 心延え、 というではなく、何か一人輝きだしている、 心映え、 がいいのである。 ついでながら、著者の「江戸児」は、鳶魚に言わせると、現実とは異なるようである。「江戸ッ子」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/436936674.html)で触れたことだが、「江戸ッ子」は、 「表通りには住んでいない。皆裏通りに住んでいた」 つまりは、 裏店(うらだな)、 に棲む。では、裏店とは何か。鳶魚曰く、 長屋と裏店とは違う、 という。 「長屋というのは建てつらねた家ですから、どんな場所にもあった。水戸様の百間長屋などというのは、今の砲兵工廠の所にあったので、その他大名衆の本邸には、囲いのようにお長屋というものがあって、そこに、勤番士もおれば、定府の者もおりました。長屋の方は、建て方からきている名称ですが、裏店の方は、位置からきている名称」 で、位置とは、場所を指す。 「裏店というのは、商売の出来ない場所」 で、ここに住んでいるのは、 「日雇取・土方・大工・左官などの手間取・棒手振、そんな 手合で、大工・左官でも棟梁といわれるような人、鳶の者でも頭になった人は、小商人のいる横町とか、新道とかいうところに住んでおりますから、裏店住居ではない。」 では、裏店に対して、表店とは何か。そのためには、町人とは何かが、はっきりしなくてはならない。 「町人という言葉から考えますと、武家の住っている屋敷地に居らぬ人、市街地に住んでいる人を、すべて言いそうなものなのに、町人といえば商人に限るようになっている」 のであって、そこには、裏店の人間は入らない。「江戸ッ子」の風体は、 半纏着、 で、 「明らかに江戸ッ子を語っているものは、半纏着という言葉です。半纏着では、吉原へ行っても上げない。 江戸ッ子というと、意気で気前がよくって、どこへ行ってももてそうに思われるが、半纏着だと銭を持っていても女郎さえ買えないんだから、ひどいものです。この連中は、普通の人の着物を長着という。羽織は見たこともない手合だから、長着は持っていない。持っているのは、半纏・股引だけだ。もし長着があるとすれば、単物に三尺くらいのものでしょう。」 と。いったいこの「江戸ッ子」は何人いるのか。 「大概 江戸の人口の一割くらい」 で、五万人、と鳶魚は見積もる。我々のイメージしている「江戸ッ子」は、町人かその使用人であったが、それを鳶魚は、「江戸ッ子」に入れないらしい。 なお、「野暮」については、「野暮天」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E9%87%8E%E6%9A%AE%E5%A4%A9)で触れた。 参考文献; |
| 石井孝『戊辰戦争論』を読む。
戊辰戦争については、ぼくは不案内なのだが、様々の論争があるらしい。著者は、 |
|
保谷徹『戊辰戦争(戦争の日本史18)』を読む。
本書は、 |
|
藤井尚夫『フィールドワーク関ヶ原合戦』を読む。
著者は、 |
| R・K・ブルトマン『歴史と終末論』を読む。
大学一年の時、確か一般教養の哲学で勧められて読んだのだが、何に感動したのか、すごく影響を受けたと思い込んでいた。しかし改めて読み直してみても、その感動が甦ってくることはなかった。多分、末尾の、 |
| K.・レーヴィット『世界と世界史』)を読む。
著者の、次のことばは印象的である。 |
| ロラン・バルト『零度のエクリチュール』を読む。
本書は、
という(「語りのパースペクティブ(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic1-1.htm)」)、何重にもわたる語りの入子構造は、ソシュールの言語構造論からは、ほとんど立ち入り不可能だろう。その意味で、ぼくには、僭越ながら、 |
| 白川亨『石田三成の生涯』を読む。
本書は、津軽藩(三成辰姫の子が三代津軽信義)の、三成の裔する三家(杉山、山田、岡家)に連なる著者が、 |
| 白川亨『石田三成とその一族』を読む。
津軽に現存する、 |
|
白川亨『石田三成とその子孫』を読む。
|
-
関連ページ
-
リーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
管理者のリーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
目標達成のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
-
リーダーシップに必要な5つのことについては,【1】【2】をご覧ください。
-
リーダーシップチェックリストについては,ここをご覧ください。
-
発想技法の活用については,ここをご覧下さい。
-
管理者の意味については,「中堅と管理者の違いは何か」をご覧下さい。
-
管理者は何を問題にすべきかについては,ここをご覧下さい。
-
「管理者にとっての問題」については,ここをご覧下さい。
-
-
管理者の役割行動4つのチェックポイントについては,ここをご覧下さい。
-
OJTのスキルについては,ここをご覧下さい。各論は,それぞれ下ページをご覧下さい。
-
OJTプランのプロセス管理【1・2・3】
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションスキルは,コミュニケーションスキル①とコミュニケーションスキル②をご覧下さい。
-
コミュニケーション力チェックリストは,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションタブーについては,ここをご覧下さい。
-
職場のコミュニケーションは,ここをご覧ください。
-
マネジメントに求められるコミュニケーションスキルについては,ここをご覧下さい。
-
-
自己点検チェックリストは,ここをご覧下さい。
-
-
アイデアづくりは,日々 1つずつを実践している。それについては,ここを見てほしい。