言葉を覚えるということは,ある種俯瞰する視点を手に入れたことを意味する。それは,ユンギアンが言うように,そのときから,空を飛ぶ夢を見るというのは,その象徴といってもいい。
例えば,目の前の石くれを,石という言葉で置き換えることで,多くの石のひとつに,それはなった。
しかし,そのことで,石と目の前の石とは,ギャップが生まれる。置き換えて失ったのは,自分にとってのかけがえのないニュアンスといってもいい。
表現にそんなものはいらないという考え方もあるだろうが,そぎ落としてはいけないものをそぎしか落としてしまっているかもしれないのだ。
言葉のスピードの20~30倍で,意識は流れている,といわれる。それは,言語化できるのは,意識の1/20~30ということだ。そのとき自分が考えていたこと,思っていたことの1/20~30しか拾い上げられない。その余は,落ちていく。
書くということを考えると,
ひとつは,自分の思いを言葉にしようとする,
いまひとつは,言葉が次の言葉をつなげていく,
の二面がある。もちろん,何か書きたい思いがあって書きはじめる。しかし,言語化した瞬間,言語の意味の範囲から,思考が流れ始める。その時,すでに,ずれがはじまっている。
虚実皮膜
というのは,何も虚構を作っている時だけとは限らない。
日記を書いたことのある人ならお分かりのはずだが,自分の出来事を書いているはずなのに,その出来事自体は変わらないのに,そのニュアンスが書き方によって,変わっていくことがある。それは,言葉の作用に他ならない。
もちろん嘘ではない。嘘ではないが,そのときのコトを正確に写しているのとは少しずれる。
ひとつは,言葉の持つ俯瞰性から,視点が変わる,
ということはもちろんある。しかし,言葉に感情が籠ると,それほどの感情でなかったはずなのに,感情が煽られてしまうことがある。
つまり,いまひとつは,言葉が,勝手に言葉を紡ぎ出す。
つまりは,どっちにしろ,言葉が,見える世界を変える,ということになる。このことを,虚実皮膜というのではないか。
虚実皮膜については,近松門左衛門は,
http://www.kotono8.com/2004/06/27chikamatsu.html
によると,こう言っている。
芸というものは,実と虚との皮膜(ひにく)の間にあるものだ。
なるほど,今の世では事実をよく写しているのを好むため,家老は実際の家老の身振りや口調を写すけれども,だからといって実際の大名の家老などが立役者のように顔に紅おしろいを塗ることがあるだろうか。また,実際の家老は顔を飾らないからといって,立役者がむしゃむしゃとひげの生えたまま,頭ははげたまま舞台へ出て芸をすれば,楽しいものになるだろうか。
皮膜の間というのはここにある。虚にして虚にあらず,実にして実にあらず。この間になぐさみがあるものなのだ。
と。これは,真実らしく見せるために,黒澤明が,『七人の侍』のラストシーンで,墨汁の雨を降らしたことと似ているが,どうも不遜ながら,そこに,虚実の皮膜があるのではなく,
コトを写そうとすると,
言葉であれば,すでに,丸めるほかなく,映像であれば,自然光ではなく反射板や照明を使わなくてはきちんと撮れないように,表現自体が,現実ではなくなる,ということの方が大きい。
それは,自分の想いを語っていても,その思いは,言語のレベルで,言語に連なって,語られていく。語られていくにつれて,思いの原形質の質感ともニュアンスとも,ずれていく。
そのずれの感覚がないと,描いたものだけで,すべてを判断する。
書くというのは,いわば,すべての情報がそうであるように,フレームワークの中に入れることだと言ってもいい。
そのことは,「言葉の構造と情報の構造」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0924.htm#%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0%E3%81%A8%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0)で触れたが,書くということの持つ,宿命といっていい。しかし,そのことに自覚的な人は少ないかもしれない。
書くということは,書いた瞬間から,現実から乖離する。しかし,書いたものからしか,視界は拓けないのも事実なのだ。
私の言語の限界が私の世界の限界を意味する,
とヴィトゲンシュタインが言ったように,書かなければ始まらないのだから。
「異和」と書いたが,普通は,「違和」と書く。ただ,なぜか,この言葉が気になる。
僕の記憶に間違いがなければ,吉本隆明は,『初期ノート』から,「異和」を使っていて,編者の川上春雄が,それに「まま」とルビを振っていた記憶がある。
吉本は,若い頃から,癖なのか,意識してなのか,「違和」ではなく,「異和」を使い,最後まで使いとおした。その意図は,もう確かめようはないが,
異和
と
違和
では,ニュアンスが違うのではないか。
「違」は,違う,悖る,背く,去る,遠ざかる,といった意味で,
違法,違憲,違反,違背,等々,
といったように,基準や定め,掟に背くというニュアンスが強い。
「異」は,異なる,違う,他と異なる,といった意味で,
異常,異心,異形,異郷,異見,異才,異能,異性,異名,異物,異腹,異邦,異変等々,
異質さというか,他から際立つというニュアンスがある。
「違う」は,平面的なのに,
「異う」は,立体的な感じがする。
あえて推測すれば,「違和」は,波立ちなのに,「異和」は,屹立,巍巍とした山並みの感じである。突出しているといってもいい。だから,「異和」の方が,違和の感覚が際立つ。
まあこれだけの話なのだが,自分の感覚を言語に置き換えるとき,ありきたりの言葉では,うまく言い尽くせない感じがすることがある。なにせ,思いの方が,言語の20~30倍のスピードで走り去っていくのだ。そのときその感覚を捉えそこなうと,すぐ思いと言葉がずれていく。
類語辞典を引いても,それは平面的な連想だから,ただ言い換えているだけで,言いたいことを,的確に表現する言葉を探すときには,あまり役に立たない。
それなら,いっそのこと,アナロジーかメタファーか,の方がなんとなくニュアンスが伝わる。
情報(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0924.htm#%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0%E3%81%A8%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0)には,
コード変換できる言語化可能なコード情報
と
コード変換できない雰囲気とか文脈といったモード情報
とがあるというが,まさにその通りで,デジタルとアナログと置き換えてもいい。アナログとは,まさにアナロジーといってもいいので,メタファーやアナロジーが伝えやすいのは当然だろう。
それは思いを絵にしたり,ビジュアルにしたりするのに近いかもしれない。
ところがビジュアルにすると,そこで,また少しずれる。
ヴィトゲンシュタインではないが,
およそ言いうることは言い得語りえないことについては沈黙しなければならない,
のか。それには,少し異和がある。
諦めるは,
思いきる,
仕方がないと断念したり,悪い状態を受け入れたりする,
それまで続いていたものを終わりにすること,
といった意味が辞書にある。しかし,この「諦める」は,「明らむ」の,「明るくなる」という意味以外の,
物事を見きわめる,
物事が明らかになる,
確かめられる,
という意味からきているという。
ということは,諦めると決めたとき,どっちにしろ,(それが正確かどうかは別にして)自分なりに見積もっている,ということになる。
多く,諦めるとき,
自分を小さく見積もり,相手(対象)を大きく見積もる,
諦めないときは,
自分の力量を大きく見積もり,相手(対象)を小さく見積もる,
と言えそうだが,実は,相手がどうあろうと,自分がどうあろうと,自分の続けたい意志,思いを捨て兼ねたというのが近い。
いい例かどうかわからないが,二年ほど前,初マラソンで,青梅マラソンにチャレンジしたことがある。始めてたぶん三ヵ月か四ヵ月で,正直無謀とは思ったが,とにかく走り出した。ただ,後ろからなので,スタート地点に立つまでに,15分か20分を要した。で,まあうしろのほうから,のろのろ走ったのだが,15キロ手前で,あと10分と言われたのだが,折り返しが目前のところで,右手に15キロの関門が見え,折り返しから,そこまで,2,300mくらい,その時点で鐘が鳴っていて,無理と諦めてしまった。足が痛いのが,その後押しをした。
しかし,だ。途中でリタイアしたことより,15キロまで走って,そこで時間切れと言われたのならまだしも,その手前で,断念したことを,今もずっと悔いている。
つまり,そこで諦めたのだが,その見積もりは,残りの距離に比して,脚を引きずるようにしていた,自分の残り体力を対比して断念したことが,早まった諦めだと,ずっと尾を引いている。
潔さというのは,ある意味,自分を捨てることなのではないか,という気がしてならない。
あるところで,池田屋で新選組に襲撃され,割腹した宮部鼎蔵を,
池田屋で逃れられるものを逃れず,あっさり諦めるような潔さを,士道と呼ばぬ,
といった人がいる。僕も同感である。そこで逃げずに割腹するのは潔いかもしれぬ,しかし,それは,おのれを安く見積もりすぎではないか。おのれの志と,思いは,それほど安っぽいものなのか,と思う。
多く士道を,
暴虎馮河し死して悔いなき者,
と勘違いしている向きがある。僕は士道とは,腕(ぷし)ではなく,心だと思う。思いだと思う。志だと思う。
そこであっさり投げ出す程度の志なのか,
ということだ。あるいは,西郷の言ったとされる,
命もいらず,名もいらず,官位も金もいらぬ人は,始末に困るものなり。この始末に困る人ならでは,艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり,
も,『論語』の孔子の言葉とは微妙にずれる。子曰く,
暴虎馮河し,死して悔いなき者は,吾与にせざるなり。必ずや事に臨みて懼れ,謀を好みて成さん者なり,
と。必ずや事に臨みて懼れ,
その実現のために,おのれの命を安売りしないもののことだ。臥薪嘗胆といってもいい。
僕のマラソンはさほどの志ではないが,
諦めてはいけないことを諦めた,
諦めるべきでないところで諦めた,
という悔いがある。志があるなら,地を這っても,赤恥をかいても,生きのびねばならない。
死生,命あり,
である。おのれの天命を自ら断つのは,非命である。
おのれの命を安く見積もってはいけない,それはおのれの想いを貶め,おのれ自身を卑しめることだ,まして,それを士道とは呼んではならない。
思い込みと,思い入れとは微妙に違う。
思い入れは,よほどのことがないと,自分に思い入れすることはない。相手か,言葉が,考えか,ともかくそれに思いを致す。芝居で言う,「思い入れたっぷり」というのは,役柄に入れ込むのであって,自分ではない。
しかし思い込みは,思いの力点が,自分側にある。自分の信念,自分の観察,自分の思いを,信じて疑わない。
思い入れは,仮託,託すといっていい。思い込みは,固執,あるいはこだわりといっていい。
だから,思い入れは,代理なのかもしれない。自分でできない思いを,誰かに託す,誰かに事寄せて,その実現を期待する。その分,自分への執着はすくないかもしれない。
思い込みは,逆だ。誰かに託すなどということは真逆だ。あくまで我執,あるいは自分の思いへの執着だ。その分,自分を過大に信じている,と言えるのかもしれない。
恋に思い入れはない。あるのは思い込みだ。
是非善悪は,ここで入れていない。
思い込みのない仕事はない。そのとき,その仕事に思いが託されている。その仕事に強い思い入れがなければ,自分の動機づけにはならない。しかし,そこに,思い込みがなければ,執念がなければ,単なる憧れに終わる。
一念岩をも通す,
の一念とは,思い込みでしかない。
よく言えば,思い入れは,信頼やファンとかになるし,思い込みは,確信や信念になる。
悪く言えば,思い入れは,執心となり,思い込みは,執念になる。
たとえば,
思いが入らない,
思いが込もらない,
と,否定形にしてみると,もう少し違いがはっきり見える。
思いが入らない,あるいは,思いが入れられない,は信じられないことを指す。仮託する相手(もの)への拠りどころが自分の中にない,ということを意味する。あるいは,自分の中に,そのことへの思いが薄い,力が入らない,というふうにも言える。
思いが込もらない,あるいは,思いが込められない,は相手や何かに,というふうに言えなくもないが,自分の,とつけると,自分の中に,そのことへの強い思いがない,というふうに見える。
あるいは,時間軸で見ると,未来にあるのが,思い入れで,過去からいまにあるのが,思い込みという言い方もできる。
いずれにしたって,自分の中の思いだ。外へ託すか,自分に託すか,その境界線はそんなにはっきりしているわけではない。
僕は人への思い入れはない。むしろ,思い込みがある。人に対しても,自分の思いのこもり方が強すぎる。それは,仮託ではない。
だから,自分の思うに任せないと,
投げ出すか,
腹を立てる,
厄介な思い込みよりは,思い入れの方がいい。はじめから,託しているのだから,叶わぬのは,別におのれのせいではない。
しかしそれでは人生はおのれの人生ではない。
自分(の思い)に執着し,自分(の思い)に執心する。それでいい。なにも,遠慮はいらない。ひとさまが,代わりに,僕に人生を担ってくれるわけではないのだから。
仮説と言えば聞こえはいいが,予想,予測,期待,先入観,言ってしまえば,まあ,妄想に近い。どんな立派な仮説でも,検証されるまでは妄想。他は推して知るべし…。
アインシュタインの仮説も,一時光より早いものがあると大騒ぎになった。まあ,観察誤差ということで落ち着いたと記憶しているが,ことほど左様に,アインシュタインの相対性理論すら,まだ仮説だと聞くと,まあ確かなものは,それほどこの世にはないと,安心する。
脳科学者に,「仮説脳」だか「予測脳」だか「予想脳」ということを言っておられた方がいらっしゃったが,あけすけに言えば,「先入観」とも言える。われわれは日常的に仮説あるいは予測しては検証する,を繰り返している。
多く,
こうかもしれない,
こうなったらいい,
こうなってほしい,
という願望だか期待をもって生きる。それは,仮説ではない。といって,
こうすれば,こうなる,
こうなっているのだから,こういうことだ,
というのは,筋というか,蓋然的な流れというか,あくまで事実(の動き)の予測に過ぎない。
仮説は,固く言えば,
仮の説明概念,
ぶっちゃけ,
仮にそう言っておこう,そう考えておこう,そう見ておこう,
ということだ。そういう眼鏡で見ると,そう見える,というだけのことだ。
これを,
事実
としてしまうと,本当の妄想,もう病気になる。
しかし,ストーカーもそうだが,ある意味,期待と仮説は,混同されやすい。そうした方が安らかになれるからだ。
期待というのは,「そうなってほしい」という自分のイメージを現実にかぶせる(と凹凸は見えにくくなる)。
仮説というのは,「そう考える」といまとは別の未来がストップモーションのように映し出される(気がする)。
微妙だが,事実が裏切るかどうかで,どちらも,検証されるというか,結果を突きつけられる。
期待は,自分のトンネルビジョンだから,かぶせ直しは効かない。しかし仮説は,「そう」を別に置き換えればいい。
思うに,どうせ仮説をたてるなら,妄想なのだから,とがっているほうがいい。尖っている方が,現実との葛藤が大きく,読み直し自体が面白くなる。尖っていないと,現実の重みに圧倒されて,すり減り,丸まって,当たり前の読解になっていく。
いまどき少子化などというのは仮説でも何でもない。
しかし何十年後日本人が絶滅する,と言えば,とまあ少しは尖っている。どうせ現実の鑢ですり減らされる尖りなら,もっと尖った方がいい。たとえば,少子化が徹底すれば,
労働力を大々的に受け入れるほかない。そうなれば,いまの看護師受け入れのように,日本語条件なんぞ言っていられない。なんせ,介護を必要とする老人があふれかえるのだから。となると,英語,中国語,朝鮮語,ベトナム語等々が飛び交うだろう。
それって,徹底すると,どうなるのだろう。
ときに,妄想は,悲観的に見えるかもしれない。しかし,悲観の裏には楽観が張り付いている。
それば,ひょっとすると昔大陸から大挙渡来人が来たのに匹敵する巨大な変革のエネルギーになるかもしれない。
まあ,自分はこの世にはいないが…。
参考文献;
仮説づくり;http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0926.htm#%E4%BB%AE%E8%AA%AC%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B
あの野村克也氏が,
女を取るか野球を取るか
と迫られて,女を取ったと,ご自分の逸話を語っていたのを覚えている。それが,あのサッチーなのだが,その是非はともかく,そういう決断をするというのが,僕にはわかる。両方という選択肢はない。それほどの岐路が,確かに人生になくはない。
恋は思案の外
という言い方をするが,いろいろ経緯はあったろうが。結果としてシンプソン夫人を取って国王の位を捨てたエドワード八世の例もある。
棄てても悔いのない決断というのがあるのかどうかは知らない。
もともと決断とは,何かを捨てることだ。そう決定した瞬間,捨ててよかったと自分で思うほかないが,しかし,それは決断のその一瞬で決まるのではなく,その後の生き方で決まるのではないか。
しかし一瞬,ロジックも理性も消えるときがある。それが右脳か左脳かというのは意味がなく,ジル・ボルト・テイラーも言っているように(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-6.htm#%E5%8F%B3%E8%84%B3%E5%B7%A6%E8%84%B3),
わたしはたしかに,右脳マインドが生命を包みこむ際の態度,柔軟さ,熱意が大好きですが,左脳マインドも実は驚きに満ちていることを知っています。なにしろわたしは,10年に近い歳月をかけて,左脳の性格を回復させようと努力したのですから。左脳の仕事は,右脳がもっている全エネルギーを受け取り,右脳がもっている現在の全情報を受け取り,右脳が感じているすばらしい可能性のすべてを受け取る責任を担い,それを実行可能な形にすること…。
なので,それをコントロールすることはできる。それをするかしないかも,脳が選択している。
ジル・ボルト・テイラーは,コントロールのコツをこう言っている。
わたしは,反応能力を,「感覚系を通って入ってくるあらゆる刺激に対してどう反応するかを選ぶ能力」と定義します。自発的に引き起こされる(感情を司る)大脳辺縁系のプログラムが存在しますが,このプログラムの一つが誘発されて,化学物質が体内に満ちわたり,そして血液からその痕跡が消えるまで,すべてが90秒以内に終わります。
通常無意識で反応しているのを意識的に,90秒を目安に,自分で選択できる。例えば,90秒過ぎても怒りが続いていたとしたら,それはそれが機能するよう自分数が選択し続けているだけのことだ,というわけだ。
それは,好きとか嫌いという感情についても言えることで,それを選択している。あるいは,理性もまた,それをよしとコントロールしないことを選択している,ということになる。
というかその感情の奔流に流されるのを,よしとした,流されていいと思った,ということだ。
そういえば,映画『卒業』のベンジャミンとエレインは,どうなったのだろうか。それぞれは,どういう生き方をしたのか。その決断を,後から悔いることはなかったのか。いやずっとそれを悔いるような生き方をしたのか,それともそれを忘れてしまうような生き方をしたのか。
一瞬の感情で決断するということは,考えて考えた末決断することと,僕には,それほど差があるとは思えない。結果として,見えない未来は,最後は直感で決めるしかないからだ。
だから,たぶん決断の可否は,その一瞬ではなく,その結果どう生きたかなのではないか。あるいは,逆に,それを機に生き方を劇的に切り替えたかどうか,というべきかもしれない。
思えば,どんな決断も,一つの契機なので,その一瞬に見えた(はずの)シーンというかステージに乗り切れたかどうかなのかもしれない。
そのためにこそ決断したはずなのだから。
僕自身も,それに近い選択をした。しかし,悔いとか振り返るとかはほとんどない。なぜなら,その一瞬がなければスタートしない人生のステージに乗ったからこそ,いまの自分があるからだ。いまの自分は,よかれあしかれ,それがあるから,ある。
参考文献;
ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』(新潮文庫)
かつて,神田橋條治さんが,
ボクは,精神療法の目標は自己実現であり自己実現とは遺伝子の開花である,と考えています。「鵜は鵜のように,烏は烏のように」がボクの治療方針のセントラル・ドグマです。
と書いていた。遺伝子学の堀田さんは,
遺伝子で決めている範囲を逸脱することはできない。それは厳然たる真理だと思います。ただし,遺伝子が決めている範囲をすべて使っているかというと,実はほとんど使っていないとおもうんですよ。僕だって,もし優れた指導者に出会えれば,全然違う才能を発揮して,…いたかもしれません。そういう才能を発揮するような環境にいなければ,その才能が有ることも知らずに死んでいくわけです。(中略)自分が遺伝的にもらった才能というのは,自分が思っているよりはるかに広い。それを開拓するのが,学習するということです。
というふうに語っている。つまりは,遺伝子で決定論的に決まるのではなく,非決定論的な柔軟性がある,それは少し丸めた言い方をすると,どんな生き方をするかでその開花は変わる,といってもいい。
ところで,ハエのゲノム(一組の染色体)には,約一万五千の遺伝子があり,ヒトの遺伝子は三万程度で,その差が小さいように感じるが,一個の遺伝子を変えただけで大きなことが起きるのだから,数千個も変われば,全然違うものになる。しかし,
ひとつの幹に沿って生物が進化していって,最後に無脊椎と脊椎の二つの枝に分かれたんです。それもたかだか四億~五億年前のことで,四〇億年近い生命の歴史を考えれば,別れてからの時間が全体の10パーセントなら,90パーセントは同じだということになります。
その意味では,ヒトとヒトの間の差は,平均0.1%,ゲノムとして0.1%の変動,チンパンジーとは1%の違い。10倍違う。わずか1%の差でも,
ヒトとヒトの間の距離の10倍くらいのところにチンパンジーがいるというようなイメージです。
こう空間的に示されると,不思議とイメージが鮮明になる。それもそのはずで,
脳の視角野といわれる部分は,実際に物体を見たときに働いている領域なんですが,イメージしただけでも同じように活動する…。
ことに起因している。
言語については,小さい時にある段階までに一番適応しやすい年齢があり,自然に言語を学んでいくが,
脳は,聞こえているものが言語なのか雑音なのかわかっています。赤ん坊がちゃんと言葉がわかるようになるということは,たくさんの聞こえている音の中から言葉を抽出して取り入れている…。
という。ここで不思議なのは,手話もそれと同じ自然言語なのだということだ。
アメリカの研究では,手話を第一言語として使っていたろうあ者が左脳のトラブルで手話失語になることを報告しています。
つまり,手話も赤ちゃんが自然に第一言語として覚え,手話を使っているときの脳を調べると,完全に左脳優位であるという。
ここから想像できることは,言語化する方法が何であれ,抽象化する作業は左脳が担う。必然的に,脳の機能としては同じだということだ。
では,そういう人間の脳とコンピュータを比較して,何がわかるのか。人がコンピュータをつくるので,コンピュータは人を超えられない,そういう常識は正しいのか。
たとえば,将棋のコンピュータでは,従来の,手をしらみつぶしに計算して,最も良い手を残すというやり方から,
最初に可能な手を絞り込んでしまうのです。つまり,手持ちのデータを使って,いくつかの手はありえないということで,落としてしまう。絞った手に関して深く読んで見込があるかどうかを判定して,その中で一番良いのを残すという方法を取っています。
という。「将棋のコンピュータは,捨て方を人間が教えてやった時点で,創造性に一歩近づいた」のだという。
この背後にあるのは,堀田さんの,
天才とは,ものを捨てる能力の高いひとじゃないか,…いろいろな可能性を考えるスピードが速くて,しかも,その可能性の中で,適切なものだけ残して,不適切なものを捨てる。
という考え方と照らしてみるとき,一歩人に近づいている。たとえば,
コンピュータが意志をもてるか,というのは本質的な問題です。「意志」とは,自分が自分に対して命令を出すことでしょう。…それら簡単にできます。つまり,コンピュータがある命令を別の命令で呼べばいいわけです。それは「サブルーチン」というプログラムの基本としてよく知られています。(中略)人間の脳もまさにそうなっているのでしょう。下位の命令は,脚を動かしなさい,…という「運動野」の命令なんですが,その上位の前頭葉のニューロンは,その命令に対してさらに命令を出す役割をしているのです。
本書でも言っているが,人間と同じものをつくっても仕方がない。何をするためのものなのか,というツールとして徹底するのか,人の代替をつくろうとするのか,そういう選択が現実的になってきた時代にいる,ということが実感である。
参考文献;
堀田凱樹・酒井邦嘉『遺伝子・脳・言語』(中公新書)
神田橋條治『技を育む』(中山書店)
いってみると,「言っていること」と「やっていること」とに落差がある,ということだ。リスポンシビリティというのは,有言実行だと訳した人がいるが,単なる結果責任ではない。それを言うことをやる,しかも日常的に実践できるということの積み重ねでなくてはならない。
これは,
言語コミュニケーションと非言語コミュニケーションの乖離かもしれないし,
本音と建て前の隙間かもしれないし,
マニュアルの理想と現実かもしれないし,
ビジョンと現場の乖離かもしれないし,
方針と現状とのギャップかもしれないし,
命令期待と遂行実態の差かもしれないし,
さまざまのところで現れるが,そのギャップがあることが問題なのではなく,それをギャップと感じないこと,そのギャップに気づかないことが問題なのだ。
先日,ドトールのある店に入ったところで,後ろの席で,コーヒーカップだか,トレイだかを落としてしまったらしく,店内にけたたましい音が響き渡った。すぐ店員が駆けつけて,「お怪我はなかったですか?」と声を掛けた。そこまではどの店でもやると思われるかもしれない。しかし,僕はスタバで,自分が粗相をし,コーヒーを落としてしまった。幸い割れなかったが,テーブルと床が汚れてしまった。店員が駆けつけてきて,何か声を掛けてくれたが,それはドトールのそれではなかった。で,仏頂面をして,モップで床を拭いた。その間,僕はそばで,立ち尽くし,なんだか立たされた生徒のように,居場所をなくし,早々に店を出た。言葉と態度が全く乖離している見本のようなものだ。明らかに,ドトールの勝ちである。このことを,僕はあちこちで吹聴している。
どんなに丁寧に,マニュアル通りに声掛けしてもらっても,それでこちらの体がほぐれるのではない。相手の態度だということだ。
「たまたま」を「そもそも」としている,と言われるかもしれない。それは,視点が違う。一度不快な思いをさせられたら,たぶん二度とその店にはいかない。客の心とはそういうものだ。かつて松屋で不快な思いをし,そのことに抗議の手紙も出したが,以来,決して松屋には行かない。
客が粗相をしたら,普通それだけで委縮し,居場所がなくなる,という客の心理がわかっていない。その時,いつもの馬鹿丁寧で,サービス満点の対応らしいものが,どんな実態なのかの化けの皮がはがれる。
あるいは,宅急便で,キャリーバックを送った。旅先のホテルでそれを開こうとしたら,キャリーの脚がもげていることに気づいた。しかし,当日ではなく,荷造りし直す時なので,三日後であった。まあ,仕方ないと諦めて,その状態のまま家へ送り返した。それが届いた時,担当の配達の人が,そのことを指摘した。それは,往復便だったこともあり,宅急便の責任というニュアンスであった。こちらは,脚が見つかるとも思えないので,いいですと断ってしまったが,これが言行一致というものだ(後日サムソナイトは保証があると後で,買い直すときに聞かされたが,「遅いよ」捨ててしまった後だ)。
それを,センゲ氏は,信奉理論と使用理論という表現で説明する(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-6.htm#%E8%87%AA%E5%B7%B1%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC)。
口で言っていることと実際の行動との乖離をとらえることだ。たとえば,私が人は基本的に信頼できるという見解(信奉)理論を公言しているとしよう。ところが,絶対に友人にお金を貸さず,油断なく全財産を守っていたらどうだろうか。これはどう見ても,使用理論,つまり深層にあるメンタル・モデルと信奉理論が食い違っている。
そして,こう付言する。
だから,信奉理論と使用理論との乖離に直面したとき発すべき第一の問いは,「私は信奉理論を本当に大切にしているのか?」「それは本当に自分のビジョンの一部なのか?」である。信奉理論に対する揺るぎない決意がないのなら,その乖離は現実ビジョンの間の緊張を表しているのではなく,現実と(おそらく人の眼を気にして)推進する考え方との間の緊張なのだ。
もちろんここで問題にしているのは,当該の店員ではない。その人にそういう振る舞いをさせているスタバそのもののビジョンと現実との乖離であり,その現実化に問題があるということだ。それは,ビジョンの敗北である。どんな立派な看板も,一瞬で潰える。
僕の知り合いで,弁当屋の社長がいた。一旦食中毒を出して廃業に追い込まれた。いったん失敗したら,後は,会社を畳むところまで行くしかない,そういう厳しいぎりぎりの修羅場にいる,という緊張感がない。
サービスとは,それを受ける側にとって,一回限りの一期一会で,そこで得た印象がすべてなのだ。言い訳無用,モノのように修復できない。
まあ,センゲ流に言うと,たまたまの事例から一般化する「抽象化の飛躍」を犯しているかもしれないが。
参考文献;
ピーター・M・センゲ『学習する組織』(英治出版)
修羅場は,ふつう「しゅらば」と読むが,辞書によると,「しゅらじょう」とある。そして,「阿修羅王が帝釈天と闘う場所」とある。そこから転じて,血なまぐさい戦乱,激しい闘争の場所の意味になる。
しかしここで言う意味は,自分自身の限界との戦いの意味だ。
最近自分のキーワードになっていて,それを切り口にして,いろいろ考える傾向がある。
僕のイメージでは,自分の限界を超えないと対処できない事態にどれだけ,意識的に対応し,クリアしてきたかということだ。自分の知識と経験,スキルでは到底切り抜けられないような事態に,正面からぶつかって,それを潜り抜けたか,ということだ。そういうシチュエーションを経ていない人は,どこかに,
事態を甘く見るというか,
自分のキャパを甘く見るというか,
人の苦労がわからないというか,
自分の役割が見えないというか,
そこで自分のなすべき何かがみえないというか,
一緒にやるには何かが足りないというか,
人として信の置けない感じがある。
修羅場というシチュエーションで起きているのは,自分というものの限界線,境界線,あるいは閾値を超えていく,というか超えない突破できないところに置かれているということだ。あるいは,それは自分の伸び白一杯一杯まで引っ張りに引っ張って,なんとかかんとか自分を拡大しきらなければ,その事態を乗り切れない。出来るとか,出来ないなどを,口にもできないし,そんなことを言い訳にもできない事態という意味でもある。言い方は大袈裟だが,不安と恐怖で,悪夢にうなされ,はっと目覚める。そんなことを繰り返し,長いトンネルの向こうに,自力で抜けられる,光明が見える。その時,一つステージが上がっているはずだ。
必死で自分の容量以上のタスクをこなすためには,自分の知らないことを必死でインプットしなくてはならない。知らない,出来ないことを,人に聞きながら,教えを乞いながらでも,やらなくてはならない。だってそれが自分のやらなくてはならないことだからだ。それを天命と呼ぶか,役割と呼ぶか,使命と呼ぶか,タスクと呼ぶか,役目と呼ぶかはどうでもいい。それを逃げられない自分の仕事と思い定めたら,やりきるしかない。それを,責任を取るというのだと思う。
そこでは,
自分との格闘がある。
自分の心との格闘がある。
自分の技量との格闘がある。
自分の器量との格闘がある。
自分の技術との格闘がある。
自分の無知との格闘がある。
自分の生き方との格闘がある。
自分の思想との格闘がある。
自分の弱さとの格闘がある。
自分の根性との格闘がある。
自分の気力との格闘がある。
アップアップ状態でも,そこから逃げ出せず,そこに踏みとどまり,為すべきことを必死でする,そういうことだ。
その経験を経ていないと,自分の資質のままにこなしてきたので,自分の限界というものがわからない。だから,
それが自分の能力の限界なのか
それが自分の経験不足なのか,
それが自分のスキル不足なのか,
それが自分の知識不足なのか,
という見方をする。そうではない。自分自身のトータルの限界なのだ。だが,そこで耐えてそれを何とかしようとはしないで,やり直します,出直します,という。そうではない,いま,そのできない状態の自分のまま,限界までやりきってしまわなければ,同じことを繰り返すということが,わからない。
だから,他責(これはおれには合わない)となるか自責(おれはだめだ)になる。そのどっちでもない。言い方は酷だが,今まで何も自分を酷使しなかった「つけ」だということだ。
大口をただけるほど,修羅場をくぐったと言えるかどうかわからないが,そのつど必死で自分の限界を超えてきたことは事実だ。その瞬間の格闘を過ぎると,いつの間にか次のステージに立っている。その時見える世界が変わる,そういう体験を何度かした。
振り返ると,そのプロセスは,フロー体験に近い。気づくと何時間もたっている,ということが何度もあった。それは決して楽しいばかりの時間ではない。修羅場体験にとっては,楽しいかどうかは,どうでもいい価値観に思える。
人は一人では生きていけない。人とのかかわりの中で生きる。人との結節点として生きる。しかし,ひととの関係とは,場に他ならない。
清水博さんは,「『生きている』ことと『生きていく』こととは,まったく異なることです。…〈いのち〉の居場所がなければ,生きるものは,「生きている」ことはできても,「生きていく」ことはできません。」という。
ではいのちの居場所とは何か。サッカーの例を挙げている。
サッカーの選手たちが,サッカー場という居場所に自分で自分の役割を位置づけることができるようになると,はじめて立派にチームプレーをすることができる。これと同じように,いきものも自分なりの役割を自分で〈いのち〉の居場所に位置づけることができて,はじめて〈いのちの〉与贈循環をうまく実行できる。
与贈循環とは,生きものがまず〈いのち〉を,〈いのち〉の居場所に贈って,次に今度は逆に,その居場所から〈いのち〉を贈られる。これが繰り返されるのが,〈いのち〉の循環,という。
これを生命と考えず,チームに入った状態を考える。その場に入って,自分の居場所を見つけるまでに,チームから学んだり教えられたりしながら,チーム自体の居場所を知り,その目的を知り,その意味を知り,そこでの自分のいる意味を知って,はじめて自分がそこで何をするかが見えてくる。そう考えれば,我々はいつもこれを繰り返している。それを僕は,「ポジショニング」と呼んできた。
場に位置づけられていることが存在existenceを獲得しているという事であり,これと活(はたら)きや意味に結びつかない物理的存在presenceとは違う。
自分の「ポジショニング」がわからない人は,自分の役割どころか,何をするためにそこにいるのかが,わからないので,チーム内で主体的に仕事に関わり,仕事を創り出していくことができない。それではチームの石ころ,つまり邪魔者にしかなれない。
これを細胞レベルで,説明すると,こうなるようだ。
人間でも,他の動物でも,胞胚の細胞たちは,胞胚という〈いのち〉の居場所全体のなかのどのような位置(ポジション)に自分がいるかを知っていて,その位置にしたがって,たとえば,自分が将来,手になるか,心臓になるか,脳になるかというように自分の役割を決めて,その位置にふさわしい細胞に変わっていく。…胞胚の手術をして細胞の位置を取り替えっこすると,取り替えられた細胞は,それぞれ新しい位置にふさわしい役割を発見して変わっていく。
細胞は,その働く場を得なければ,居場所がなく,居場所があってはじめて,どうなるかが決まっていく。清水さんは,これを,「生命の二重存在性」と呼び,次の様に説明する。
その第一は,生命という活(はたら)きは自己の存在を自己表現,あるいは自己創出する活(はたら)きであるために,場に位置づけられなければ生き物は一つの決まった形(表現形)を取れないということである。そしてその表現形は,局在的生命と遍在的生命のあいだの創出的循環のために,一定の状態に留まることができない…。生命の自己表現性とは,生命は場に位置づけられた存在をその場へ表現するかたちで活(はたら)いているということである。生命はそれ自身をそれの上へ表現する「場的界面現象」(場的境界の生成現象)であるといえる。生きものは,その存在を場に表現するから場においてコミュニケーションができるのである。
これを清水さんは,ふたつのモデルで説明されている。
ひとつは「自己の卵モデル」
①自己は卵のように局在的性質をもつ「黄身」(局在的自己)と遍在的性質をもつ「白身」(遍在的自己)の二領域構造をもっている。黄身の働きは大脳新皮質,白身の働きは身体の活(はたら)きに相当する。
②黄身には中核があり,そこには自己表現のルールが存在している。もって生まれた性格に加えて,人生のなかで獲得した体験がルール化されている。黄身と白身は決して混ざらないが,両者の相互誘導合致によって,黄身の活(はたら)きが白身に移る。逆もあり,白身が黄身を変えることもある。
③場所における人間は「器」に割って入れられた卵に相当する。白身はできる限り空間的に広がろうとする。器に広がった白身が「場」に相当する。他方,黄身は場のどこかに適切な位置に広がらず局在しようとする。
④人間の集まりの状態は,一つの「器」に多くの卵を割って入れた状態に相当する。器の中では,黄身は互いに分かれて局在するが,白身は空間的に広がって互いに接触する。そして互いに混じり合って,一つの全体的な秩序状態(コヒーレント状態)を生成(自己組織)する。このコヒーレント状態の生成によって,複数の黄身のあいだでの場の共有(空間的な場の共有も含む)がおきる。そして集団には,多くの「我」(独立した卵)という意志器に代わって,「われわれ」(白身を共有した卵)という意識が生まれる。
⑤白身が広がった範囲が場である。したがって器は,白身の広がりである場の活(はたら)きを通して。黄身(狭義の自己=自分)に「自己全体の存在範囲」(自分が今存在している生活世界の範囲)を示す活(はたら)きをする。そして黄身は,示された生活世界に存在するための適切な位置を発見する。
⑥個(黄身)の合計が全体ではない。器が,その内部に広がるコヒーレントな白身の場を通じて,黄身に全体性を与える役割をしている。現実の生活世界では,いつもはじめから器が用意されているとは限らない。実際は,器はそのつど生成され,またその器の形態は器における人間の活(はたら)きによって変化していく(実際,空間的に広がった白身の境界が器の形であるという考え方もある)全体は,卵が広がろうとする活(はたら)きと,器を外から限定しようとするちからとがある。
⑦内側からの力は自己拡張の本能的欲望から生まれるが,外側からの力は遍在的な生命が様々な生命を包摂しようとする活(はたら)きによって生まれる。両者のバランスが場の形成作用となる。
場そのものの変化を動態的に考えるために提唱されたのが,もう一つのモデル,即興劇モデル。
卵モデルの黄身に相当するものが,「役者」であり,器が「舞台」の境界で,その器の中に広がる白身に相当するのが,「舞台」であり,「観客」として遍在する生命がある,という関係性で見ることができる。即興モデルでは場は即興的に演じられるドラマの舞台ということになる。そして場所(卵の入った器が置かれているところ)が役者,舞台,観客が存在する「劇場」に相当する。役者は観客の共感を呼ぶドラマ(活(はたら)き)を演じることが必要になる。
場の変化をドラマ的時間に位置づける自己(局在的自己,自己中心的領域,黄身)とその自己(黄身)の演技をドラマ的空間に位置づける場としての自己(遍在的自己,場的領域,白身)の二つが相互誘導合致の過程で交互に循環的に活動することによってドラマが進行する。
舞台とは,意識の野であり,観客の活(はたら)きは意識の野を含めて,その外に広がる無意識の活(はたら)きでもある。それは,
局在的自己(黄身)は遍在的自己としての場(白身)に対してつぎの変化を繰り返しながら自己表現を(循環的に)つくりだしている。すなわち,場を受け入れる,自己を場に位置づける,場における自己の存在を自己表現をする。この時場の束縛から踏み出して新しい自己表現を創出しようとする。他方,場がおこなう変化は,局在的自己の自己表現(部分的表現)を包み込む全体的表現を生成し,局在的自己の新しい自己表現を待つ,の繰り返しである。
局在的自己(黄身)の重要な性質として,それが場(白身)に位置づけられて存在しているときには,その自己の存在を身体によって場に自己表現するという性質がある。場に位置づけられた自己は,「顔のある個」であり,その存在は個物的である。場において自己表現がなされる結果,場が変化する。場が変化すると,新しい位置づけが必要となる。そのことによって新しい自己表現がなされ,場がさらに変化することになる。
この時必要なのは,現在存在していない未来の舞台(場)を創造することだ,と清水さんは言う。場の外に立ってどのように見るかを考えなければ,未来は見えない。
場は人間の意識がつくり出す空間であり,要素サイクルに伴って絶えず生成と消滅を繰り返している。場の大きな変化は意識の野の変化であり,場(意識)の外からやってくる。場の未来は観客の活(はたら)きを至って外側から訪れるのである。
場には,三種類ある,と清水さんは言う。
ひとつは,生活の場。リアルタイムにドラマを演じている場だ。その場で,どんな選択肢を取るかを日々決断し,選択している。それをさせているのが,人生の場。自己(局在的自己,黄身)は,その内部に様々な生活の舞台における体験を記憶し,その体験を人生の場で編纂し,自己の歴史ドラマの中に位置づけている。だから,人間は自分が作った人生という歴史ドラマの筋に基づいて容易に判断を下すことができる。もうひとつが生死の場。個としての生命が確実に死ぬことを前提としている場である。それは,局在的な生命の生と死で一つの状態になっている場であり,局在的な生と死が生と死で一つの状態になっている場でもある。
石原吉郎の詩がある。
死はそれほどにも出発である
死は全ての主題のはじまりであり
生は私には逆向きにしかはじまらない
死を<背後>にするとき
生ははじめて私にはじまる
死を背後にすることによって
私は永遠に生きる
私が生をさかのぼることによって
死ははじめて
生き生きと死になるのだ(「死」)
未来から見るとはこういうことなのかもしれない。
ともかく,いくつかの卵の白身が互いに混じり合って,コヒーレントな状態状態(共時的な状態)をつくっているとき,黄身の相互関係も,「我と汝」(個が互いに向き合う関係)となったり,「我々」(互いに同じ側に立つ関係)となったりする。それは,黄身の自己中心的な活(はたら)きが白身による吸引力(同一化力)より大きいか小さいかで決まる。
白身と黄身の関係には,慣れが起きる。そこに閉塞状況が生まれる,と清水さんは指摘する。マンネリ状態である。それには,次のどれかが起きている。
①舞台の上に自分の現在の現在の状態を位置づけられない
②最初に設定した目標の位置が誤っている
③自分の位置と目標の位置との間の空間が複雑であるために,目標に近づけない
どうだろう。いささか狭い気がする。目標というより,目的や意味が見いだせないか,見誤っているか,ではないのか。目的が見えないから,目標が位置づけられず,自分の位置が見えない。
でもいずれにしろ,その瞬間,
もしこの位置づけができないときには,即興劇の舞台の上には存在していないことになるから,舞台から外れて個人になっていることを意味している。
これを機に,舞台を外から見る,という視点の転換がいるのかもしれない。
舞台づくりとは,出会いの場づくりのことであり,舞台では,様々な役者が演じる多様な演技を受け入れて一つに統合し,それを一つの即興劇としてイメージする想像力が必要になる。この即興劇を舞台設計から考えていく知的な活(はたら)き,つまり構想力が必要である,という。それには,
パトス(情)を共有すること,即ち共感の場づくりから始めることが必要である。と同時に,それを一時的な昂揚にとどめないために,ロゴスを共有することが必要である,と。
その意味と目的の共有であり,そのための道筋を描くことができていなくてはならない。つまり,
実践の論理には,まず実現したい夢が必要である。…夢を具体化しようとし続けることから未来に関するイメージが次第に明確になり,やがて具体的な目的として共有できるようになる。夢のある明確な目標を共有し,それを実現するための舞台を想定することから変革のイメージが生まれ,そのイメージをビジョンにすることから戦略が生まれてくる。戦略が生まれてくるためには,イメージに具体的な携帯電話を与えなくてはならない。
だから情と論理がいる,ということである。
しかし,実際に場づくりをしようとしてみると,人と人との袖振り合う感覚で接点ができ,お互いが場を意識しあうというところまでは割と広がる。しかし詰めてみると,実はそれぞれの「夢」自体が,微妙な齟齬があり,その差は意識すればするほど大きくなっていく。結果として共通の夢を具体化するところまでいけないことが多い。場づくりは,そうたやすくはないことに気づく。そこまでの処方箋はどこにもない。
ただ人との接点の中で,白身が接することで場ができ,そこで黄身にも影響が出る。だから,その場を永久と考えるよりは,あっては別かれ,別れてはまた会うのの中で,自分の居場所となる場所がつれていくのではないか,と考えることもできる。そういう場をいくつも,多層に,多面に持つことが,その人の黄身を豊かにしていく。命のポジショニングは,その人にしか見えない。それでいいのかもしれない。そんな気がし始めている。
参考文献;
清水博『コペルニクスの鏡』(平凡社)
清水博『場の思想』(東京大学出版会)
昨今どういうわけか,「しなくてはならないこと」を口にすると,「したいこと」を言えと言われることがある。それがよくわからない。バランスの問題ではない。
人には,「やらねばならぬこと」「やりたいこと」「やれること」の三つがある。しかし,やらねばならぬことをしないものに,やりたいことは実現できるかもしれないが,人として,全く信をおかない。そういう人をいっぱい見てきた。
僕は「しなくてはならないこと」が,たとえちっぽけな雑用でも,それをするのが自分の役割だと思ったら全力でやる。そうしない人間を腹の底から軽蔑する。それを僕がしなければ,他の人がしなくてはならない。「しなくてはならないこと」は,誰にとっても「しなくてはならないこと」だからだ。
もう一つ思っているのは,「したいこと」を言う人は,多く修羅場をくぐっていないように見える(失礼!)。自分の伸び白いっぱいにやっても,まだとても届かない中,でも逃げ出さず,やり遂げるという意味だ。それは他人にとっては修羅場ではない。当人にとってのみ,修羅場だ。そんなことで迷っているのか,そんなところで手間取っているのか,そういう目で見る先輩は少なくない。それだけの仕事をこなせる人から見たら,出来の悪い人間のもたつきは,いらだつだろう。ましてチームなら,レベルの落ちているところがチーム全体の足を引っ張っている。
そういう中で,自分が「しなくてはならないこと」を,なんなくこなしていける人間にしていく。「こなしていける」ところが重要で,そこで立ち止まれば,単なるベテランで終わる。そこで自足せず,さらに自分の伸び白を引っ張り,広げていく。それがなければ,こなしに自足したただのベテランだ。
ときに,「したいこと」を言う人が,「しなければならないこと」を逃げている逃げ口上に聞こえることがある。あるいは,「しなければならないこと」を回避するための言い訳にしているように聞こえることがある。僕の僻目かもしれない。しかし,そう聞こえる状況にいて,そう聞き取ったのだということは確かだ。人の忖度など知ったことではない,という言い方もある。しかし,いったん信頼を失ったら,それを取り戻すには数百倍いることを骨身にしみて知っている。
閑話休題。
ところで,人の能力は,知識(知っている)×技能(できる)×意欲(その気になる)×発想(何とかする)の総量だと思っている(これに体力だの感力だのがいるかもしれないが)。ここで発想が重要で,これは未知の,未経験の事態を,文字通り「何とかする」ことによって,自分の伸び白を広げていく。そういう修羅場の経験も必要だという意味で,能力を伸ばすには,きっかけとしては一番重要だと思っている。
もし「したいこと」というなら,「しなければならないこと」を潜り抜けていなければ,単なる願望以上にはそれはならない。それだけの度量と器量と技量と力量は,黙って勉強するだけではつかないからだ。
イチロー語録は,なかなかイチローが端倪すべからざる人物だということを示しているが,たとえば,
小さいことを積み重ねるのが,とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。
今自分にできること。頑張ればできそうなこと。そういうことを積み重ねていかないと遠くの目標は近づいてこない。
練習で100%自分を作らないと,打席に立つことは出来ません。自分の形を見付けておかないと,どん底まで突き落とされます。
「たのしんでやれ」とよく言われますが,ぼくにはその意味がわかりません。
毎日,力は振り絞っていますよ。余力を残そうとしていたら問題。
どんな難しいプレーも当然にやってのける。これがプロであり,僕はそれに伴う努力を人に見せるつもりはありません。
努力せずに何かできるようになる人のことを天才というのなら,僕はそうじゃない。努力した結果,何かができるようになる人のことを天才というのなら,僕はそうだと思う。努力できるのも才能という。
等々をみると,テレビの番組で,「好きなことをやっているが,ちっとも楽しくない。」というイチローの言葉を思い出す。「したいこと」を忘れてはいけない。しかし,それを実現するためには,そのために日々しなくてはならないことを,歯を食いしばってやらなければ,「小さな積み重ね」ひとつクリアできないだろう。
僕は,古いタイプの人間なので,「やりたいこと」のために,いま目の前で,人として「やらなければならないこと」を見逃したり,その立場でやらねばならぬことを放置したり,否でも応でも「やらなくてはならないこと」を全力でやり遂げようとしない人を信じない。
そして,なお,したいことを選ぶのなら,その自分の「しなくてはならないこと」を放棄してもなお,それは「する」に値するのか,を考えに考えた末にしか,「したいこと」は現実味を帯びない。仮に,現実に見えても,まだふわついた仮のものでしかない,と信じている。当然すべての責は,それを選択した自分にのしかかる。毀誉褒貶などという話ではない。その世界で二度と生きていけないというくらいのこともあり得る。そういう覚悟があるのなら,贅言は無用だ。
それは資格を取ったり,お勉強で得られるものではない。
苦しいことの先に,新しいなにかが見つかると信じています。
自分自身が何をしたいのかを,忘れてはいけません。
というイチローの言葉は,それを前提に見るとき一層輝く。
選択理論によれば,「前に出ること」を選択したから,ポジティブな感情と思考になる。ポジティブになったら,前向きになるのではない。過去にとらわれず,立ち止まらず,前へ進もうとする選択肢を取ったから,ポジティブな思考になる。
「やりたいこと」の方を選択するから,やりたいことが図に見え,やらねばならぬことが地になる。逆に,(その立場と役割にあるのに)「やらねばならぬこと」に向き合わず,「やりたいこと」を選択したとき,やらねばならぬことには二度と出会うことはないだろう。そういう人とは,一緒に何かをしたくはない。
だからと言って,地が消えるわけではない。考えようでは,「したいこと」と「しなくてはならないこと」は,地と図の関係なのかもしれない。「したいこと」を実現しようとすれば,いずれ,そのためにクリアしなくてはならない「しなくてはならないこと」にぶつかることになる。しかし自分にとって「したく」もない「しなければならないこと」に比べれば,それに立ち向かうのは容易だという言い方もできる。
しかし,だ。僕はそうは思わない。
「したくないこと」であろうが,
「できないこと」であろうが,
「したこともないこと」であろうが,
しなければならないとなった,そのときに,それを自分のキャパと技量を超えてチャレンジし,それをなんとかかんとかクリアした経験がなければ,自分の伸び白を極限まで引っ張り,拡大しなければならない「そのとき」の経験が,その伸び切った自分のキャパの感覚がないから,たぶんできる範囲のキャパが狭い。いや,ぎりぎりまで拡大するというその感覚自体がない。
なぜなら,「やらなければならないこと」は,逃げ道なくやらなくとはならないが,「やりたいこと」は,所詮自分の裁量内,その狭い範囲でしか,精一杯やらないという,気ままが許される。いや,許す。それをしない意志は,イチローレベルでないとない。
年寄りのたわごとだが,やりたくなくても,やったことがなくても,しゃにむにやらなければならないことを,必死でやりとおした経験がなければ,その経験の持つ意味は分からない,ということだ。
昨日ある場で,「こつこつ習慣化のすすめ」を聴く機会があったが,まさに「やりたいこと」をやるために,「やらなくてはならないこと」というハードルが出てくる。それをどう日常的にクリアするかだ。これは,また別途ブログでまとめたい。
参考文献;
ウイリアム・グラッサー『選択理論』(アチーブメント出版)
グラッサーは,ある日妻に突然去られて,落ち込むクライアントに,
奥さんが家を出てから,あなたは家にいて座ったままで,仕事に行かないという選択をしているわけですね
そして,
今日ここにくる選択をしましたよね。
と。ここに選択理論の中核がある(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-6.htm#%E9%81%B8%E6%8A%9E)。
彼は,自分の感じているみじめさを選んでいる。
すべては,自分が選択したということ,そしてその選択には意味がある,ということである。こういう場合,多くの古臭いセラピストは,感情を問題にするだろう。もっと古臭いセラピストは,過去に原因を探ろうとするだろう。しかしすでにE・F・ロフタフたちが明らかにしたように,記憶はうそをつく。書き換えられる。おおくの幼児虐待の記憶,性的虐待の記憶は,セラピストの問いによって,つくられた物語であることは明らかにされた。
過去はいまの状況がつくる物語に過ぎない。生い立ちや母子関係に原因を探っても,現状は動かせない。今落ち込んでいるのは,過去のせいではなく,いまの自分だからだ。感情を探ることも,あまり意味がない。感情は,たとえば,脳卒中で倒れた脳科学者テイラーが,
わたしは,反応能力を,「感覚系を通って入ってくるあらゆる刺激に対してどう反応するかを選ぶ能力」と定義します。自発的に引き起こされる(感情を司る)大脳辺縁系のプログラムが存在しますが,このプログラムの一つが誘発されて,化学物質が体内に満ちわたり,そして血液からその痕跡が消えるまで,すべてが90秒以内に終わります。
脳の化学的・生理的反応は90秒で終わるのである。
通常無意識で反応しているのを意識的に,90秒を目安に,自分で選択できるということです。例えば,90秒過ぎても怒りが続いていたとしたら,それはそれが機能するよう自分が選択し続けているだけのことだ,というわけです。
つまり,その感情を選択しているのである。なのに,その感情を取り出し注目すれば,ますますその感情にのめり込むことを選択し続けるだけだ。あるいはその感情と自慰しているに等しい。
そこから抜け出すには,3つの選択肢しかない,とグラッサーは言う。
①自分の求めているものを変える
②自分のしていることを変える
③両方を変える
上記のクライアントの例に即せば,
①妻への要求を変える
②妻に対して行っていることを変える
となる。そして,グラッサーは,
落ち込みを選択するということは,落ち込みがどれほど長引いても,精神病ではない。すべての行動と同様,これも選択なのだ。歩いたり,話したりするような直接の選択ではないが,全行動の概念を理解すれば,全ての感情は,快感であれ,苦痛であれ,間接的な選択であることがわかってくる。
として,全行動をこう説明する。
私の辞書によると,行動とは,体を動かし,何かをすることである。…選択理論の観点から言うと,体の動かし方が重要である。体を動かす方法には四つの不可分の要素がある。第一に行為。行動について考えるときに,ほとんどの人が歩く,話す,食べる,などの行為を考える。第二に思考。私たちはいつも何かを考えている。第三の要素は感情。私たちが行動するとき,いつも何かを感じている。第四は生理反応。何かをしているときにいつも生理反応が伴っている。例えば,心臓の鼓動,肺の呼吸,脳の働きに関係のある神経化学物質の変化。
行動するときこの四つが同時に機能している。そして,
あなたが全行動を選択するとき,常に四つの構成要素すべてが関与しているが,直接コントロールできるのは行為と思考だけである。
先のクライアントが選択したのは,落ち込の行為と思考なのである。そして,これを選択することで,他の選択肢を無意識で抑圧していることになる。
第一は,怒りである。落ち込むことで,相手への怒りが抑制されている。
第二は,人にお願いせずに,援助を求める方法になっている。
第三は,したいこと,恐れていることをしない言い訳にしている。
落ち込み,引き籠らせることで,激しい怒りに駆られて,妻を探し出し,強引に連れ戻そうとしたり,自暴自棄の行動を取ったりという他の選択肢をしないようにさせたということができる。
このバックボーにあるのは,人をコントロールすることではなく,自分をコントロールするという視点,自分の責任のとれることを自分でする,という視点だ。
何事でも自分にしてもらいことは,ほかの人にもそのようにしなさい。(マタイ伝)
孔子も同じことを言っている。
子貢問いて曰く,一言にして以って身を終うるまでこれを行うべき者ありや。子曰く,それ恕か。己の欲せざる所を人に施す勿れ。
記憶が不確かだが,ミルトン・エリクソンが,オネショの子に,あえて「今日はオネショをする日」と決めさせたことがあったと思う。それは,オネショが外的なものではなく,自分でコントロールできるものだということを,体得させていくことだったように思うが,それと同じことだ。
だとすると,まずは落ち込むことで,より悪い事態になるのを防ごうとする選択をしたのだ,とみなすと,次にすることは,自分自身の中で,
次に何をするつもりですか,
と問いかける。そこには,
①自分の求めているものを変える
②自分のしていることを変える
③両方を変える
の選択肢がある。何かをする,いつものやり方を変える,いつもと違う肯定的なことをする等々。ソリューションフォーカスト・アプローチの,
もしうまくいっていないのであれば,何でもいいから,(いつもと)違うことをせよ,
という原則が生きるかもしれない。グラッサーは言う。
私たちは,相と所属,力,自由,そして楽しみという四つの心理的欲求を満足させるように遺伝子によってプログラムされていると,私は信じている。すべての行動は選択時点では最善の選択であり,四つの欲求を満たすためのものである。
参考文献;
ウイリアム・グラッサー『選択理論』(アチーブメント出版)
ロバート・ウォボルディング『リアリティ・セラピー』(アチーブメント出版)
E・F・ロフタフ&K・ケッチャム『抑圧された記憶の神話』(誠信書房)
E・F・ロフタフ『目撃者の証言』(誠信書房)
ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』(新潮文庫)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)
昔読んだ時代小説(というか剣豪小説というべきか)の世界で,決闘のシーンというか,果たし合いのシーンというので,印象に残っているのは,第一は,中里介山の『大菩薩峠』で,詳しいことは覚えていないが,土方歳三率いる新徴組の手練れが,清川八郎を襲撃しようとして,襲うべき駕籠を間違え,乗っていた島田虎之助に襲いかかり,結局島田一人に十数人の使い手全員が倒され,土方も翻弄される,すさまじい戦いシーンがあった。そのやりとりの迫力は,ずっと記憶に残っている。襲撃の一隊に加わった主人公,机龍之介は呆然,手をつかねて立ち尽くしていた,と記憶している。
ついでながら,第二に,指を折るのは,吉川英治の『宮本武蔵』で,確か武蔵が,柳生石州斎の屋敷に紛れ込み,柳生の四天王と,刃を交えるシーンであった。その気迫と,立ち会う面々との間合いは,一瞬で決着する吉岡兄弟との立ち会いも,一条下がり松のシーンも,般若坂の決闘も,かすむほどの緊迫したものだと記憶している。
ついでに思い出したのは,何の映画だったか覚えていないが,果たし合いの後,相手が,「急所を外した」というセリフを言った時,会場から失笑が漏れたことがあった。そういう神業を,ほとんどの人が知らないというか,小説の中のことと思っているらしい,とその時感じたものだ。
僕自身も,別にそういう神業に出会った経験はないが,技量を極めたときに,どんな状態になるかぐらいの想像力はある。難波走りと同様,かつての日本人の体の使い方は,明治以降の体育教育及び軍隊教練で,正座も含めて,創り出されてしまい,それが普通のように思ってしまっている。日本人本来の体の使い方,及びそんな日本人の知っていた身体を見失ってしまっているので,それを探るよすがもない。
甲野善紀氏は,江戸時代の剣客で,夢想願流の松林左馬助無雲のエピソードを紹介している。
ある夏の夕方,蛍見物に川べりを門弟とともに散歩していた無雲を,門人の一人が川へいきなり突き飛ばした。無雲は突き飛ばされたなりフワリと川を飛び越え,しかも,突き飛ばした門人も気づかぬ間に,その門人の佩刀を抜き取っていた…。
それは遠い江戸時代の話ではなく,現代の武道家にもいる,という。たとえば,柔術家の黒田泰治師範は,警察の道場で,寝転んだまま力士五人に体中を押さえさせ,よもやと思っていたら,あっという間に,いとも簡単に起き上ってみせた…。
あるいは,親戚男谷信友の弟子筋の島田虎之助の元で修業した勝海舟が,幕末の剣豪白井亨についてこんなことを語っている。
此人の剣法は,大袈裟に云えば一種の神通力を具えていたよ。彼が白刃を揮うて武場にたつや,凛然たるあり,神然たるあり,迚も犯す可からざるの神気,刀尖より迸りて,真に不可思議なものであったよ。己れらは迚も真正面には立てなかった。己れも是非此境に達せんと欲して,一所懸命になって修行したけれども,惜乎,到底其奥には達しなかったよ。己れは不審に堪えず,此事を白井に話すと,白井は聞流して笑いながら,それは御身が多少剣法の心得があるから,私の刃先を恐ろしく感ずるのだ。無我無心の人には平気なものだ。其処が所詮剣法の極意の存在する処だと言われた。己れは其ことを聞いて,そぞろ恐れ心が生じて,中々及ばぬと悟ったよ。
その白井は,平和時の武術を晴天の雨具にたとえ,なるべく目立たぬことを心掛けるように説いたという。
雨でもないのに,これみよがしに剣術家然として歩くのは,晴れているのに雨具をつけて歩くようなもので,人々の顰蹙をかうだけだ,と。
また坂本龍馬を斬ったという今井信郎は,北辰一刀流の皆伝,榊原健吉から直心影流を学んだが,片手打ちという我流の実践剣法で,ひと打ちで相手を倒したらしいが,その彼が,こう言っている。
免許とか,目録とかという人達を斬るのは素人を斬るよりははるかに容易,剣術なぞ習わない方が安全,と。
追い込まれた人が,窮鼠猫を噛む状態の予想外の膂力とスピードの方が,対応できないということらしい。つまり,並みのプロと格段のプロとの違いは,そんな心構えにあるらしい。
言ってみると,剣術というのは,一定の枠組みの中で想定された枠内でやっているということなのかもしれない。そういう通常の剣法に対して,いわゆる「相ぬけ」を究極の形として目指した異色の剣法が,「無住心剣術」という。頂点は,相打ちではなく,相ぬけという。
剣術の勝負は,勝か負けるか,相打ちになるか,そうでなければ意識的に引き分けるか以外ない武術の鉄則を超え,お互いが打てない,打たれない状態で,たとえば,一雲と巨雲の師匠と弟子では,一方は太刀を頭上に,一方は太刀を肩の上にかざして,互いにすらすらと歩み寄り,いよいよの間合いに入ってから,互いに見合って,「ニコッ」とわらってやめた,という。しかし他流には負けたことがない,という。
「他流を畜生心によるもの」と開祖夕雲がいう,
「無住心剣術」の稽古法は,片手打ちで,特有の絹布や木綿でくるんだ竹刀で,ひたすら相手に向かって真っすぐ入り,相手の眉間へ引き上げて落とす,相打ちから入る。
よく当たるものはよくはずれ,よくはずるるものはよく当たる,
という言葉があり,相手はこっちの姿をみて打ち込んでくるが,こちらは敵を敵として認識せず,敵の気からはずれて出ていくため,意識的に打ち込むものほどはずれてしまい,こちらは相手の気筋を外してでるため,相手には不意に目の前にあらわれるように感ずるらしい。
心にとかくの作為があって勝負に臨めば,勝負にとらわれて,足がなかなか進まず,立ちが相手に届かない,
ともいう。いわば,「常の気のまま」を尊重する流儀のようで,相手を打つも自分が相手を打つというよりも,自然の法則(天理の自然)が自分の体を通して行われた,という理法のようだが,その太刀の威力は,すさまじく,竹刀打ちを兜で受けたものが,吐血したというほどのものだ。従って,無敗の剣とも言われる。
双方に戦う気があれば,相抜けにはならず,相打ちになる。
それで思い出したのが,69連勝でストップした横綱の双葉山が「未だ木鶏たりえず」といったとされる「木鶏」である。「荘子」にこういう逸話がある。
紀子という鶏を育てる名人に鶏の要請を依頼する。王は,10日ほど経過した時点で仕上がり具合について下問する。すると紀渻子は,「まだ空威張りして闘争心があるからいけません」と答える。更に10日ほど経過して再度王が下問すると「まだいけません。他の闘鶏の声や姿を見ただけでいきり立ってしまいます」と答える。更に10日経過したが「目を怒らせて己の強さを誇示しているから話になりません」と答える。さらに10日経過して王が下問すると「もう良いでしょう。他の闘鶏が鳴いても,全く相手にしません。まるで木鶏のように泰然自若としています。その徳の前に,かなう闘鶏はいないでしょう」と答えた。
いわば,この心境である。これを,こういっている。
当流に奇妙不思議な教えや修行法があるのではなく,人々がほんらいもっている天心を日々常に養い育て,私心を払い,意識を洗い捨てるからである。人々がみな,幼児の頃にはもっていながら,成長するにつれて,いつの間にかなくしてしまった一物(本来の天心)が,次第に立ち戻ってきて,肉体に再び宿ってくるそうなれば,命がけの場でも自然と霊妙な働きが生まれて,自由に敵をあしらう。
老子の
知る者は言わず,
言うものは知らず
をふと思い出す。この剣法は,江戸中期門人一万人と言われながら,ついに,いまに伝わらない。
ところで,小林秀雄は,武蔵について言及し,
彼(武蔵)は,青年期の六十余回の決闘を顧み,三十歳を過ぎて,次の様に悟ったと言っている。「兵法至極にして勝にはあらず,おのずから道の器用ありて,天理を離れざる故か」と。ここに現れている二つの考え,勝つという事と,器用という事,これが武蔵の思想の精髄をなしているので,彼はこの二つの考えを極めて,遂に尋常の意味からは遥かに遠いものを摑んだ様に思われます。器用とは,無論,器用不器用の器用であり,当時だって決して高級な言葉ではない,器用は小手先の事であって,物の道理は心にある。太刀は器用に使うが,兵法の理を知らぬ。そういう通念の馬鹿馬鹿しさを,彼は自分の経験によって悟った。相手が切られたのは,まさしく自分の小手先によってである。目的を遂行したものは,自分の心ではない。自分の腕の驚くべき器用である。自分の心は遂に子の器用を追う事が出来なかった。器用が元である。目的の遂行からものを考えないから,全てが転倒してしまうのだ。兵法は,観念のうちにはない。有効な行為の中にある。(中略)必要なのは,子の器用という侮辱された考えの解放だ。器用というものに含まれた理外の理を極める事が,武蔵の所謂「実の道」であったと思う。
そしてこうまとめている。
思想の道も,諸職諸芸の一つであり,従って未知の器用というものがある,という事です。兵法至極にして勝つにはあらず,というのは思想至極にして勝にはあらずという事だ。精神の状態に関していかに精しくても,それは思想とはいえぬ,思想とは一つの行為である。勝つ行為だ,という事です。一人に勝つとは,千人万人に勝つという事であり,それは要するに,己に勝つという事である。武蔵は,そういう考えを次のような特色ある語法で言っています。「善人をもつ事に勝ち,人数をつかうことに勝ち,身を正しく行うことに勝ち,民を養う事に勝ち,世に例法を行う事に勝つ」,即ち人生観を持つ事に勝つ,という事になりましょう。
「未知の器用」とは神業といっていい。そこまで,技量を極限まで極める。「相ぬけ」もまたそれだ。技は,結局身体が覚える。しかし,それは伝わらない。その人に体現されたものだからだ。五輪書を百回読んでも,技にはならぬ。
僕は,これを修羅場をくぐるという。つまり,技量の極北へ行くために,血みどろの努力がいる。イチローは,それを,
小さいことを積み重ねるのが,とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています,
という。結局,
知る者は言わず,
言うものは知らず
なのだ。
参考文献;
甲野善紀『古武術の発見』(光文社文庫)
甲野善紀『剣の精神誌』(新曜社)
かつてもいまも,僕は,サムライを美化する連中を嫌いである。侍は,基本,社会の寄生虫である。穀つぶしである。ヤクザも同様だ。自閉し自己完結した世界に閉じこもり,それを完結させるために独自のしきたりと風儀を必要とする。
昔,博徒に仮託して,こう語らせたことがある。
「あっしはね,こう申し上げては失礼ながら,お武家様なんぞは,あっしら博徒同様,この世には必要のない,無職渡世ではないかと思いやすね,百姓衆にとっても,職人にとっても,ましてや商人にとっては,お武家さまなんぞは無用のものですよ,何かを生み出すわけではなし,ただ何の因果か上にたって威張ってお指図される。でも,その無用の方々がいなかったら,どれだけお百姓衆の肩の荷が軽くなることか,
お侍方は,仁とか義とか,仰ってますが,それは上に乗っかっておられる言い訳に聞こえます。理をこねくっておられる。いい迷惑です。いっそ,そこをのいてくれっていいたいですよ。あっしらにも,あるんですよ,仲間内の仁義ってやつが,杯かわした親分への忠,お互いの島への義ってやつですよ。でも,こんなのは,住んでいる人を無視して,勝手にあっしらが囲っただけですよ,これも似てるでしょ,お武家様のやり口に,まあ,真似たんでしょうがね。無職渡世は無職渡世なりに理屈がいるんですよ」
その通りなのだ。新渡戸稲造は,『武士道』で,こう書いた。
武士道精神がいかにすべての社会階級に浸透したかは,男達として知られたる特定階級の人物,平民主義の天成の頭領の発達によっても知られる。彼らは剛毅の男子であって,その頭の頂より足の爪先に至るまで豪快なる男児の力をもって力強くあった。平民の権利の代言者かつ保護者として,彼らはおのおの数百千の乾児(こぶん)を有し,これらの乾児は武士が大名に対したると同じ流儀に,喜んで「肢体と生命,身体,財産および地上の名誉」を捧げて,彼らに奉仕した。過激短気の市井の徒たるべき阻止力を構成した。
この愚かな文を読むだけで,『武士道』を読む気をなくすだろう。この「男達」を「暴力団」「ヤクザ」と置き換えればよい。第一,大正時代から,警察は,ヤクザを「暴力団」と措定し,その取締りを計っていることは,国立公文書館に当たれば,わかる。暴力団が男達(おとこだて)なんぞといわれたら,みかじめ料を拒んだがために殺されかけた人は何と言うか。
暴力団は勝手に,お互いの間で縄張りという自己の勢力範囲を設定し,縄張り内で風俗営業等の営業を行いあるいは行おうとしている者に対し,その営業を認める対価あるいはその用心棒代的な意味で,挨拶料,ショバ代,守料など様々な名目で金品を要求する。この要求に応じた者にこれを月々支払わせるが,これをみかじめ料と呼ぶらしい。
ともすれば,任侠道を表看板にし,暴力を武器としたアウトサイダーたちの反社会的行動であり,利権争いに過ぎない。任侠道などは,武士道同様,ないからこそ,あるいはすたれたからこそ,言挙げしなくてはならなかったまでだ。それが自己防衛というか,自分存在証明に他ならない。でなければ,存在する必要がないのだから。
ところで,明治期,『武士道』の英文が出た直後,こういう書評が出た。新渡戸が薩摩藩の若者が薩摩琵琶を奏でるのを「優美」と称賛したのに対して,
薩摩琵琶と関係の親密な『賤のおだまき』は之を何とか評せん。元禄文学などに一つの題目となれる最も忌まわしき武士の猥褻は,余りに詩的に武士道を謳歌する者をして調子に乗らざらしむる車の歯止めなるべし。
薩摩藩でとりわけ男色の習俗が顕著で,その事実を伝えず,美化するだけでは表面的だ,と言っている。ことほどさように,実は,実体としての武士とは別の世界を,虚構の世界を描いている,そう考えるほかない代物なのだ。
氏家幹人は,こうまとめている。
戦乱の世が終わり,武将が大名に昇華して,徳川体制に組み込まれた。その過程で,戦士の作法であった男道はすたれ,治者あるいは役人の心得である武士道へと様変わりする。爾来,武士は総じて非武闘化し,代わって,武家屋敷側が傭兵のように雇った,供回り,駕籠かきに委託した。次第に彼らは武士を軽視し,武家も彼らの命知らずの行動に危機感を抱きながら,ある種賞嘆の感情を抱くようになる。
結局平和ボケし,堕落した武士に変わって,馬鹿な男伊達を競う連中が出てきて,それがヤクザの精神の(いわゆる任侠の)淵源になっているだけだ。
幕末の開明的官僚,川路左衛門尉聖謨は,その一人。こう日記に書いている。
上かたの盗賊は,死するといふことはしりながら網のかかるまで先甘美軽暖の事によを過ごすか,百年生て乞人たらむよりは盗人と成てわかくして被殺かましといふかこときもの共にて,入墨後の盗なと少しもおしつつますみないふ也,死をみる如帰に人とは不思議也。
この畏怖の念に,すでに武士と盗人,ヤクザと区分けすることの無意味さが現れている。
結局大事なことは,もっともらしい看板や二本差しではなく,人としてどうなのか,ということが問われているだけだ。それに,任侠だの侍だの男だてなどの限定をする必要はない。
子曰く,暴虎憑河し,死して悔いなき者は,吾与(とも)にせざるなり,
である。
これでも三河武士の末裔だが,それでも,サムライであることを野放図に賛美する輩が信じられない。
参考文献;
氏家幹人『サムライとヤクザ』(ちくま文庫)
ジョセフ・ジャウォースキーは,こう言う。
数年にわたるリーダーシップ・フォーラムでの経験から,私は,人々の中には一体感を経験したい,自分より大きなものの役に立ちたいという強い欲求があることがわかってきた。そんなふうに役立つことが人間である意味だということも理解し始めた。だからこそ,個々のメンバーよりももっと大きなものと結びつき,一つの意識として行動するチームの一員であるという経験は,人々の人生においてたぐいまれな瞬間として光彩を放つことになるのだ。
それを場ができると呼んでもいい。その時,リーダーシップのあり方も変化している。ジャウォースキーは,リーダーシップを,四段階に分けた。
第一段階 自分が中心になるリーダー
この段階では,メンバーを大切にすることができない,信念がなく,自分の意思のほかは何にも左右されない未熟な段階。その時その時で変わる可能性があり,誠実さに欠ける。
第二段階 一定の水準に達しつつあるリーダー
メンバーを大切にする程度にまで成熟している。この段階にあるリーダーにとっては,安定性が大きな価値を持つ。彼らは公正さと礼儀とメンバーに対する敬意を大切にし,必ず組織の目標を達成する。この段階になると,性向は,メンバーとともに,そしてメンバーを通して成し遂げられる。
第三段階 サーバント・リーダー
帰属意識の範囲を広げ,あらゆる人を受け入れる。第三段階のリーダーは自分の権力を使ってメンバーの役に立ったり,メンバーを成長させたりする。この段階のリーダーは「強い達成欲求」を示すが,組織のメンバーや社会の誰かを犠牲にすることはない。
第四段階 新生のリーダー
昨今の山積する課題に対しては,サーバント・リーダーシップだけでは十分ではなく,サーバント・リーダーの特徴と価値観を持っているが,全体的なレベルが一段上がる。そして目を見張るような働きをし,業績を上げるその中心には,暗黙知を使う力がある。第四段階のリーダーは,宇宙には目に見えない知性があって,私たちを導き,創り出すべき未来に対して準備させてくれると確信している。
いまの場を,いまのチームを,より大きな広がりの中で,全体の中で,位置づけなおす,ということは,意味を変えることかもしれない。意味が変わると,現実の見え方が変わり,行動の意味も変わる。
ジャウォースキーは,最終的に4つの原理にまとめる。
①宇宙には開かれた,出現する性質がある。
一連のシンプルな構成要素が,新しい性質を持った新しい統一体として,自己組織化という,より高いレベルで突然ふたたび現れることがある。そうした出現する性質について原因も理由も見つけることはできないが,何度も経験するうちに,宇宙が無限の可能性を提供してくれることがわかる。
②宇宙は,分割されていない全体性の世界である。物質世界も意識も両方ともが,分割されていない同じ全体の部分なのだ。
存在の全体は,空間と時間それぞれの断片―一つの物であれ,考えであれ,出来事であれ―の中に包まれている。そのため,宇宙にあるあらゆるものは,人間の意思やあり方を含め,ほかのあらゆるものに影響を及ぼす。なぜなら,あらゆるものは同じ完全なる全体の部分だからである。
③宇宙には,無限の可能性を持つ創造的な源泉がある。
この源泉と結びつくと,新たな現実―発見,創造,再生,変革―が出現する。私たちと源泉は宇宙が徐々に明らかになる中でパートナーになるのである。
④自己実現と愛(すなわち宇宙で最も強力なエネルギー)への規律ある道を歩むという選択をすることによって,その道では,数千年にわたって育まれてきた,いにしえの考えや,瞑想の実践や,豊かな自然の営みに直接触れる事から,さまざまな教えを受けることになる。
本物のリーダーシップとは,出現する場をうまく使って,新たな現実を生み出す技術だという。そして,あらわれることになっているものは,何を成し遂げるかを決めたときに初めて現れる。だから,自分の中から現れようとするものに,この世界の存在の過程に,耳を傾ける。世界によって支持してもらうためでなく,世界が望むとおりに世界を実現するために。
では,どうすればいいのか。マイケル・ポラニーは,そのプロセスをこうまとめている,という。
①ふとした折に,それとなく示される
発見のプロセスは,見出されるべき問題がふとした折にそれとなく示されて,おぼろげに始まる。それは心の奥から沸き起こるぼんやりした声,すなわち「明確に言い表すことのできない衝動」であり,その衝動の中で,ほかの人が存在していることに気づきさえしない問題を感じ取ることになる。
②宇宙の意思によってヒューリスティックな情熱が引き起こされる
最初に起きるぼんやりした暗示は,発見者によって,探究しようという固い決意へと変わる。これは使命,すなわち宇宙の意思によって突き動かされるヒューリスティックな情熱,自分自身より大きなものに身をゆだねるという行為へと進化する。
③身をゆだねること,奉仕する気持ち
発見者は,現れようとしているものにいっそう近づくために,自分の現在の知から離れようとする。
④精力的に理解を深める人として内在する
発見者は労苦を重ねることによって,心が整い,自分ではコントロールできない源泉から真実を受け取れるようになると信じて行動する。
⑤一歩下がることと突然のひらめき―恩寵
探求は静かに時が流れたのちに終わりを迎える。ふいに恵治がって問題の解決策がもたらされる。
⑥試してみることと確認
こうした勝利の閃光によってもたらされるものは,普通の解決策ではなく,まだ試していない方法に思い当ったにすぎない。
まさに,U理論のステップの,Uの谷の底の,「内在ひらめき」プロセスで,源泉とどう意思疎通するか,だ。
①全体を見渡す力 他の視点からの見方に,つまり別の現実があり得ることに心が開く。
②メタファーの魔法 目の前の課題について認識される状況を,不可能と思われる状況から無可能な状況に変える。
③共鳴の役割 もともと別々だった二人の私が,共有される私になり,現実に対する認識や解釈を変えられるようになる。
④不確かさに身をゆだねる 不確定性とともに流れる。現実が望むように現実に現れさせる。
⑤概念的相補性についての論証 原子スケールでの波動・粒子の二重性が相補的であるように,その現実をその現実が望むように明らかにしなくてはならない。意識と源泉も相補的,相互重なりあって経験を生む。
⑥心のセルフマネジメント 心を鍛えるツールを使う。
ボームは,その人がたゆまぬ個人的鍛錬をするならば,人の肉体は,予期せぬ大量の情報の入り口になる,といっている。
ここでは,三つを挙げている。
ひとつは,世界はひらかれ,可能性にあふれていると考えることで,心のあり方が可能性へシフトする
いまひとつは,内面を鍛える。瞑想,観想,自然の中で過ごす等々
そして,即座に行動する勇気
結局,神秘的な「啓示」や個人的な瞑想的なものに丸められてしまっているのが気にいらない。それが大事だということは認めるにしても。
監訳者金井壽宏は,こうまとめる。
出現する未来を感じて,それを現実のものにしていく。そのような力が,ビジョンに向かって,人々を巻き込み,そのビジョンを実際に現実のものにしていくというリーダーシップの基盤にある。こうしたジャウォースキーのリーダーシップ論が通常のリーダーシップ論と大きく異なる点は,その一種の神秘的な性質にある。つながり合う人々の「出現する未来」への想いが強ければ,偶然も味方となり,いろいろな流れが絶妙のタイミングと組み合わせで合流する局面がある,とジャウォースキーは示唆している。
「源泉(ソース)」とは,ボームの言葉では,「内蔵秩序」である。リーダーシップ,チームワークがうまくいくとき,ひとつの意識として行動しているという感覚をもたらすものであり,個々のメンバーよりももっと「大きなもの」に結びついているという感覚をもたらすもの,と言えよう。
ボームの言う内蔵秩序というのは,境界や単独の存在を離れ,全体論や相互のつながりを指す。「非分離の分離」という。たとえば,音楽に夢中になっているとき,それを直接経験している。フロー状態もそれだ。バラバラでありながら,一つの感覚を同時に持つというのは,確かにまれだがある。
結局リーダーシップを,また特殊なものに還元しているとしか思えない。こんなことをしているうちに社会は動く。人は飢え死にする。リーダーシップをどこかカリスマ性へ戻そうとしているようにしか見えない。だとすれば,矛盾と腹立ちを覚えるだけだ。
参考文献;
ジョセフ・ジャウォースキー『源泉』(金井壽宏監訳 英治出版)
デヴィッド・ボーム『ダイアローグ』(金井真弓訳 英治出版)
マイケル・ポラニー『暗黙知の次元』(佐藤 敬三訳 紀伊國屋書店)
コミュニケーションにおけるわかりやすさとは,教科書風に言えば,次のようになる,らしい。
わかりやすさとは,相手に,賛成反対は別として,話し手が何をいっているかがいかに明確に伝わるかを意味している。それには,ふたつの切り口で整理する必要がある,とされる。
●必要なマインド,態度
・相手の立場を配慮する姿勢があること
・自分の理念,ポリシーが明確であること
・礼儀あるいは誠意があること
・情熱,熱意があること
・わかりやすい言葉遣いであること
・視野狭窄ではない広い視点をもっていること
・これしかないという思い込みがなく,選択肢のある,柔軟なものの考えができること
・情報収集,論拠がきちんとしていること
・自分のリズムだけでなく,相手との間合い,リズムにも配慮できること
・オープンマインとで,質問,疑問にも即応できること
・自己コントロールできていること
●内容と表現の工夫
・前後関係あるいは文脈を確認する 話の前後関係,背景,文脈の共有化がはかられている
・メッセージの主旨明快 5W1Hで,内容が筋道の通り,すっきりしていること
・一貫性 シーケンシャルな話の流れが,一筋明確で,たどりなおせる
・簡潔性 盛りだくさんにならず,負荷のかからない簡単明晰な短い言葉遣い。箇条書き,要約がある
・論理性 ロジカルであることの利点は,再現性,なぞることによる共有のしやすさにある
で,さらに,コミュニケーションにおけるわかりやすさの4要素とされるものがある。
①明快さあるいは簡潔さ~伝わりやすさの工夫は,ポイントを最初に示す。言いたいことは3つ。
②共有性あるいはたどり直せる~ロジカルである、筋がとおっている。後から検証できる
③理解しやすいあるいは把握しやすい~構造として示す。図解して全体像を示す。
④言葉のやさしさあるいは独特の言い回しがない~組織内や自分しか使わない言葉を使っていないか。
しかしこんな理想的なマインドと姿勢で,教科書通り表現できるなら,誰も,世の中これ程悩んだりはしまい。もうすこし自分流儀で,簡便なやり方を,実践的に考えてみたい。
そもそもコミュニケーションは自分の伝えたことではなく,相手に伝わったことが,伝えたことである,といわれる。まずは,相手に聞く姿勢になってもらうための準備作業がいる。それをセットアップというが,それを土俵をつくるというが,それが出来た上で,ではどうするか。
たとえば,何かを伝えたいのだとする。その場合,原則は三つだと思っている。
①自分が何を言おうとしているかが明確であること《指示内容の明確さ》(指示内容の明確性)
②わたしはそう考える,わたしはそう思う,《発言主体を明確にする》(「私」の発言であることの表現)
③相手はどう受け止めているのか,《フィードバックをえる》(相手の「着信状態」を確認する)
まずは,雑談の場でなければ,誰かに言葉を発するのは,みずからの意思をキチンと伝えるためであることが多い。いくら内容が明確でも,意思のない言葉に力はない。意思の力とは,自己確信である。そしてそれが相手にどう伝わっているかを確かめつつ発信することができる必要がある。
そのためには,最低限,考えながら話さないこと。できれば,「言いたいことは,3つ」というように,最初に言いたいことを言い切ってしまって話し始める。ということは,事前に何を言いたいかが自分の中で整理できていなくてはならない。特に重要なことを伝えようとする時は。
信頼のバックボーンは,言葉である。といって怒りも腹立ちもなくすことはできない。なまじ「バカヤロー」と言いたい気持ちを隠すよりも,「ぼくは,バカヤローといいたい気分だ」「そう大声で怒鳴られると萎縮してしまいます」と,感情を言葉にするのも悪くない。これは前に触れた。感情的になるのと,感情を表現するのとは違う。
少なくとも,感情を言葉として表現することで,①自分の感情との間合いが取れる,②相手の感情とも距離を取れる。感情のやり取りを感情のぶつかりあいでなく,言葉によるコミュニケーションの土俵ができるような気がする。それがとっさの反応で怒ってしまうと,まあ身も蓋もなくなるのだが。
世の中に正解があると思うから,誰かの名を借りたりしたくなる。しかし正解はないとなれば,「僕は~と思う」と言うことで,仮に「~」が間違っていても,主観の器に乗っている以上,僕の意見に過ぎない。そういう責任の取り方はしなくてはいけない。リスボンシビリティとは「有言実行」と訳すと言った人がいたが,言ったことに責任を取るとはそういうことだ。
それでも,言えばいいというものではない。大事なのは,内容や「私」の主観的な発信が,独りよがりにならず,相手に伝わっているかどうかを確かめられるのがいい。自分の言うことに対して,相手がどんな身振り,手振り,感情,言葉等々から,相手がどう受け止め,どう感じ,どう理解してくれているかを推し量ることができることである。
とはいえ,こういうところに名人芸はいらない。出来るなら,フィードバックを,言葉でもらうのが一番いい。伝わったことをストレートに返してもらいにくければ,「どう思った?」「どう感じた?」と,感想でも,印象でもいい。それで初めて,同じ土俵で,そのことについて語れるだろう。
口頭のメッセージは歩留り25%と言われる。どっちにしたって歩留りは悪い。それなら,それが30%になったら御の字ではないか。
ミーティングとか話し合いというのが,大事には違いないが,別の視点からそれを考えてみたい。
たとえば,チームのコミュニケーションといった場合,それには,いくつかのレベルがある。
たとえば,他部門や上位部門を含めた組織内のタテ,ヨコのコミュニケーションのレベルや仕組みがあることが前提になるが,チーム内には3つのコミュニケーションのレベルがあると思う。
①チーム全体としてのコミュニケーション
チームは何をするためにあるのか,そのために何をするのかという,目的や方向性を確認し,そのために,ひとりひとりが何をするのかを確認し,すりあわせ,フォローしていくレベルである。
②業務遂行レベルでのコミュニケーション
仕事を現実に遂行していく上で,上司とメンバー,メンバー同士,場合によっては,他チームや上位者とのコミュニケーションを,日々,年度を通してしていくレベルである。たとえば,チームのおかれている状況認識の刷り合わせ,正確な情報の共有,問題意識の共有,ノウハウ,知識・経験の共有化。そのために報連相,ミーティング,打ち合わせ等々。
③個々のメンバー同士の一対一のコミュニケーション
必ずしもインフォーマルだけではなく,仕事の上でも,私的に問題意識を交換したり,雑談したりするコミュニケーションのレベルである。たとえば,日頃からキャッチボールの機会を確保し,問題意識をすりあわせられる。懇親,親睦の他,何気ない会話のできる職場の雰囲気づくり等々。
チームのリーダーにとって,チーム全体のコミュニケーションと業務遂行レベルのコミュニケーションがなくては,チームとして機能しない。もちろん,雑談や喫煙ケージでの会話というのは重要ではあるが,チームとしてのコミュニケーションの土俵があってこそ意味がある。
その意味で,リーダーと部下全体,リーダーと部下ひとりひとり,部下同士のコミュニケーションをするための,お互いが何について話しているかを共有できている場,それを土俵と呼ぶとすると,それにはふたつある。
●上司と部下,先輩と後輩,同僚同士といった,役割に基づくコミュニケーションの状況(機会)づくり。
●そのつど,その場その場の,私的コミュニケーションの場づくり。
コミュニケーションのレベルと関連づけると,前者が,チームレベルや業務遂行レベル,後者が一対一レベルにあたる。チームレベルや業務遂行レベルでのコミュニケーションがなければチームとならない。しかしチームメンバーひとりひとりが何をしているのか,何を考えているのか,何を思っているのかを知らなくては,ひとりひとりの仕事をただ足しただけの集団になる。もちろん,ふたつの土俵が別々に必要というわけではない。一緒に役割を果たすこともあるし,別々に設定しなくてはならないこともある。ただ,チームには,この両輪のコミュニケーションが必要なのである。
つまり,コミュニケーションの機会はさまざまあるが,そのつど何のためにそれをするのかという目的意識を明確にもち,それを相手にも伝えなければ,単なる情報のやり取りで終わる。当然ミーティングの目的と立ち話の目的は違う。
しかし,一番効果のあるのは,意図のない会話を,意図を持ってやることだと思う。
それは,日々何気ない立ち話をすること,それをどう意識的なコミュニケーションの手段にするかだ。
例えば,上司が,日に何度も,「どう?うまくいってる?」とか,「必要があったらいってね?」などと声をかける,とする。そうすれば,初めはうるさく感じても,少なくとも,上司が自分を気にかけてくれていることだけは伝わる。ある調査では,部下との接触頻度が3回以上接触あると,親しみを感じるというデータもある。
それを,いわば,相手との土俵づくりのきっかけにするのである。後は,日に何度か,立ち話で,情報交換ができるようになればいい。形式ばった報連相とは別に,私的に報連相を重ねられるようになるだろう。信号待ちの30秒程度の立ち話でも,積み重ねることで,十分相手とジョハリの窓でいうパブリックを広げることはできるのである。
立ち話のいいところは,相手が身構えをするいとまがないうちに,話をするところだ。この場合,土俵を考える必要がない,というところだ。一緒に話をするためのセットアップのようなものがないと,話したけど聞いていないということが起きる。しかし立ち話というか,すれ違いざまの会話は,そもそもそういうことを必要としない,ある意味,世間話程度,声掛けの延長だと思っていればいい。だから,相手も,身構えを捨ててくれる(かもしれない)。
ザイアンスの法則ではないが,単純接触効果というのも,馬鹿にはならない。その意味で,すれ違いざまに,「どう?」と声をかける。信号待ちの30秒でも相当の会話はできるのではないか。
そんなことを考えていたら,グラッサーがこんなことを書いていた。
余りにも多くの教師や上司は,生徒や部下に対して,温かく,友好的に,そして支援的に接することがどれほど必要であるか分かっていない。これは手間のかかることではない。一日に数分,相手を注目するだけで,すばらしい効果があらわれる。
まさにそれを行動で示すだけだ。
参考文献;
ウイリアム・グラッサー『選択理論』(アチーブメント出版)
人は文脈に依存して生きている。またさまざまな役割を使い分けて生きている。軸とは何かがよく分かっていないが,ぶれないということをよしとする考え方には賛成できない。返って,生きにくいというか,適応性のなさを露呈しそうな気がする。
そう思っていたら,西垣さんが,小説家の平野敬一郎の『私とは何か』を引用しながら,こんなことを書いていた。
個人とは「西洋文化に独特のもの」であり,それをもたらしたのは「キリスト教(一神教)の信仰」と「論理学」だと平野はいう。一たる神に対しては,終始,一貫性のある「本当の自分」が向きあわなくてはならない。また,論理的にカテゴリーをわけていくと,動物があり,人間があり,国民があり,男女があり,ついに最小単位として一つの肉体をもつ「個人」ということになる。(中略)
個人のかわりに平野が主張するのは「分人」だ。「一人の人間は『わけられないindividual』存在ではなく,複数に『わけられるdividual』存在である。だからこそ,たった一つの『本当の自分』,首尾一貫した『ブレない』本来の自己などというものは存在しない」と,平野は言い切る。
人との関係の中で人は生きている。人とのリンクの結節点として生きる。とすれば,相手に応じて,親になり,子になり,友になり,部下になり,上司になり,客になり,サプライヤーになり,と変わっていく。その中でいる自分でしかありえない。頭で考えた自分ではなく,そういう生きた関係の中にいる自分こそが自分であり,その振れ幅分だけ,自分の多様性と柔軟性がある。
クライアントの前のコーチとしての自分と,子の前の親としての自分が,軸がぶれなかったとしたら,その人は人間ではない。そのぶれる幅が自分でわかっていること,意識できていることは大事かもしれないが,終始一貫,変わらないとしたら,たぶん適応障害を起こしているはずだ。
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)価値観
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)姿勢
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)自信
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)ものの見方
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)愛情
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)コミュニケーションスタイル
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)夢一直線
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)目的
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)ゴール
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)確信
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)生き方
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)好み
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)生活スタイル
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)生活基盤
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)生活環境
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)人間関係
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)友情
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)体形
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)自己認識
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)エネルギー
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)熱意
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)方向性
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)リーダーシップ
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)ミッション
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)戦略
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)強み
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)性格
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)目利き
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)感性
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)眼力
ぶれない(なんなら「ゆるぎない」と言い換えてもいい)批判力
等々と挙げてみると,変わらないのがいいとされるものもあるかもしれない。しかし,あえて言うと,人は変化し,成長する。成長したステージにいてもなお,まだ,前のミッションに拘泥するとしたら,それはそれで自分の使命を見失っているということになりかねない。
また自分のシチュエーションも,おかれる位置も,時々刻々変化し続けているはずである。
人は成長し,変化する。変化とは,
前の自分より大きくなること,
自分を脱ぎ捨てて脱皮すること,
以前の自分を置き残して前へ行くこと,
つまり,以前の自分の軸とは変わっていなくてはおかしい。軸がぶれないとは,成長していないということの証,頑迷固陋の証,固定観念に執着する証なのかもしれないのだ。
あるいは,ぶれるから人間なのではないか。様々な人と会い,様々なシチュエーションにもまれ,ああでもないこうでもないと迷う。ぶれる,振れる。だから人間で,その振れる幅の分だけその人の経験が大きく,閾値が高いと言えるのではないか。軸がぶれないという喩えは,機械にはいいが,人には適さない。
参考文献;
西垣通『集合知とは何か』(中公新書)
平野敬一郎『私とは何か』(講談社現代新書)
期待は,自分で望めない。相手が勝手に期待し,無期待外れを起こす。これが困る。
ネットを見たら,期待をこう整理していた。
●「将来・理想などにかかわる期待」として,希望・願い・願望・希望的観測・予感・与望(を担う)・心待ち(にする) ・心づもり等々
●「儲け・利得などにかかわる期待」として,思惑・甘いユメ・そら頼み・目算・夢想・見込み・当て・予期する・取らぬタヌキの皮算用・思い入れ 等々
●「(良好な進展・好都合の返事などが)期待できる」として,手ごたえ・脈がある・望みがある・楽観できる・成算がある・(効果が)見込める・現実味を帯びる・確かな感触を得る・霧が晴れる
等々
●「(成長・活躍などが)期待できる」として,見どころのある・(末)頼もしい・成長株・有望株・新進気鋭・前途洋々・大器晩成の~等々
●「期待を持たせる」として,気を持たせる・相手の気持ちを)くすぐる・思わせぶりな態度・空手形を振り出す・リップサービス等々
と上げていた。ここにあるには,こうあるべきだ,こうなるはずと,思い込んでいることを指す。まあ,それが自分に関わることなら,自分がそのつけを払い,めげたり,自己嫌悪に陥るだけなので実害は,他には及ばない。
しかしよく言うのは,ひとに,(多くは,子供や部下や,といった目下の者に)「期待しているよ!」と,まあ本人は,励ましのつもりか,本心で信じているかは別として,そういわれた側は,相手が親や上司だった場合,プレッシャーを感じる。
よく言われるように,本人の望まないアドバイスは,説得(あるいは陰に命令)という。つまりは,「こうしろ」といっているようにしか聞こえない,と。
それをもじれば,本人の求めていない期待は,単なる負担であり,プレッシャーでしかない。つまりは,「当然できるものと思っているよ」「当然やるはずだよな」「やってくれなくてはな」「やれ」と言っているようにしか聞こえない。
なぜこんなことが起きるのか。
もともと期待は,期待する側が,勝手に自分の思いを相手に託して,相手の像を作り上げているからだ。その像は,期待される側とすりあわされてはいない。期待する以上,
自分が相手に何を求めていて,
そして相手にはそれをする力がある(あるいは,ここでそれにチャレンジするには,いい機会だ)
同じ状況に自分もある(あるいは,ぼくも同じチャレンジの場だ)
等々と,期待している側が,自分の思っていることを伝えなくては,その期待されている側には,相手の思い入れに反駁したり,反論したり,軌道修正を加える機会が持たれないまま,期待の負荷を背負わされて,挙句の果てに,結果だけで,勝手に期待外れを起こされても困るのだ。
期待というのは,両者の立場の相違が最も出るものだと思っている。上司と部下,親と子,いずれも,心底相手ができると思っている場合も,そう思っていることをきちんと伝えなければ,「できない」「でるはずない」(と思い込んでいる)自分にとっては,期待はただの重荷でしかない。肝心のことを言わないで,期待の空手形を振り出されると,それだけで,不渡りにしそうで,相手への信頼や尊敬や敬愛の気持ちがあればあるほど,その期待を重荷に感じ,「何とかしなくては」「何かとか応えなくては」と,プレッシャーに押しつぶされる。
この時,相手に,自分が心の底から信じていて,「仮に今回できなくても,次への大きなステップになるはずだと信じている」とまで,言葉にして伝えていれば,プレッシャーではなく,自尊感情と自分への自信が,期待に応える力を発揮させるかもしれない。そこで必要なのは,コーチングでいう承認であり,認知なのではないか
(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06431.htm#%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB)。
確かに,事実としての「できていること」を承認することも大事だが,特に,その人の持っている可能性や潜在力を強く指摘し顕在化させる認知も重要になる。
そういう両者のコミュニケーションの場として(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06461.htm#%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%A7%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%E2%85%A0),
ジョハリの窓を念頭に置くといいと,いつも思っている。自分の認めていることと相手の認めていることをすりあわせた「パブリック」づくりを日々意識していれば,期待へのプレッシャーも期待外れも起きないですむはずだ。
期待は所詮,一方的な思い入れで,期待されている側はコントロールできない。
「こうあるべきだ」
「するべきだ」
「せねばならぬ」
「こうならなければ」
「こうなるはずだ」
「するのが当然だ」
「する必要がある」
と思っていても,それが自分にとって当たり前でも,相手にとっては寝耳に水かもしれない。それを忘れると,期待外れから,両者の齟齬は拡大する一方になる。
ずっと何かを待っている,ということはないか。ゴドーを待ちながら,というのを観た時,自分が待っているのが,神でも人でもなく,単なる僥倖のような気がして,待つのをやめようと思った記憶がある。
爾来,というかもともとというべきか,待つのが嫌いである。並ぶことも嫌いである。むしろ,並んでいるような店は避ける。評判や世評に乗せられるのを潔しとしない。それは,自分の判断の放棄である。そういう好奇心は,他力の好奇心である。自分の感覚と感性で,失敗しながら,探っていく。
意味なく行列をつくる。意味なく,待つ。診察を待つ,ラーメン屋で待つ。入場を待つ。有名店で並ぶ。死ぬのを待つ。その間も時間は過ぎていく。
確か秋元康は,人生は,電話に差し込んだままのテレフォンカードと同じだと言った。話をしようとしまいと,度数はどんどん減っていく。定められた寿命がどのくらいなのか,確か落語の『死神』で,自分のろうそくを見るというのがあった。ネットで見ると,こう紹介されている。
何かにつけて金に縁が無く、子供に名前をつける費用すら事欠いている主人公がふと「俺についてるのは貧乏神じゃなくて死神だ」と言うと、何と本物の死神が現れてしまう。仰天する男に死神は「お前に死神の姿が見えるようになる呪いをかけてやる。もし、死神が病人の枕元に座っていたらそいつは駄目。反対に足元に座っていたら助かるから、呪文を唱えて追い払え」と言い、医者になるようアドバイスを与えて消えた。
ある良家の跡取り娘の病を治したことで、医者として有名になった男だが『悪銭身に付かず』ですぐ貧乏に逆戻り。おまけに病人を見れば死神はいつも枕元に・・・とあっという間に以前と変わらぬ状況になってしまう。困っているとさる大店からご隠居の治療を頼まれた。行ってみると死神は枕元にいるが、三千両の現金に目がくらんだ男は死神が居眠りしている間に布団を半回転させ、死神が足元に来たところで呪文を唱えてたたき出してしまう。
大金をもらい、大喜びで家路を急ぐ男は途中で死神に捕まり大量のロウソクが揺らめく洞窟へと案内された。訊くとみんな人間の寿命だという。「じゃあ俺は?」と訊く男に、死神は今にも消えそうなろうそくを指差した。曰く「お前は金に目がくらみ、自分の寿命をご隠居に売り渡したんだ」。ろうそくが消えればその人は死ぬ、パニックになった男は死神から渡されたロウソクを寿命に継ぎ足そうとするが……。
ろうそくの火は,燃え続けている。休む間もなく,限界まで燃え続けて,いずれ消える。その間,無駄に何かを待つなら,それはテレフォンカードと同じことだ。まずは,自分から迎えに行かなくてはならない。何を?未来の自分を,だろう。あるいは,ジョセフ・ジャウォースキーの「出現する未来」に倣うなら,出現する自分と言ってもいい。
いまの自分を,いま,ここに置き残して,一刻一刻と前へ出る。自分を時に刻み付けて,ひとつらなりに流れとなって,次の自分にたどり着く。あるいは,ヤドカリが自分の将来の住み処を,大きめの貝殻に託すように,大きめの自分にたどり着く。
一期にして
ついに会わず
膝を置き
手を置き
目礼して ついに
会わざるもの(「一期」)
とは,ひょっとすると,相手との邂逅ではなく,自分との邂逅なのかもしれない。自分に出会い,そこから,また別れて,新たな自分に出会う。エンカウンターとは,自分と仮設の時間と空間で出会う。しかし,その場を難れると,元の木阿弥になるのは,それが自分の姿勢にまで,マインドセット化されていないからだ。
私は私に耐えない
それゆえ私を置き去りに
する
私は 私に耐えない それゆえ
瞬間へ私を置き去りにする
だが私を置きすてる
その背後で
ひっそりと面をあげる
その面を(「置き去り」)
これは,逃げただけだ。その自分も含めて,自分として受け入れなければ,たぶん背後霊のように付きまとわれるだろう。そこには前進はなく,一歩前進二歩後退が続くだけだ。
生きるとは,そうやって,自分の位置を変えていくことだ。
生きるとは 位置を見つけること あるいは 位置を踏み出すこと そして 位置をつくりだすこと 出なくてはならない。
だからこそ,最後にどういう位置にいて,どこに立つかが問われる。
かぎりなく
はこびつづけてきた
位置のようなものを
ふかい吐息のように
そこへおろした
石が 当然
置かれねばならぬ(「墓」)
最後にどういう位置にいるのかも,自分で決めなくてはならない。自分の物語のエンディングをどうするか,それがHappy ending にしろ,Sad endingかBad
endingかは知らないが,それは自分で決められる。そこから,また新しい物語が始まる。
私はほとんどうかつであった
生の終わりがそのままに
死のはじまりであることに
死もまた持続する
過程であることに
死もまた
未来をもつことに(「はじまる」)
だから,待つのはやめる。並ぶのもやめる。それは他力にゆだねることだ。自分の時間をいつも自分のコントロールできるところに置いておこう!
参考文献;
石原吉郎『石原吉郎全詩集』(花神社)
ジョセフ・ジャウォースキー『源泉』(英治出版)
横井小楠については,概略は,
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E4%BA%95%E5%B0%8F%E6%A5%A0
で知っていただくとして,「今までに恐ろしいものを二人見た。それは横井小楠と西郷南洲とだ」と勝海舟は「氷川清話」で述べていることから紹介しておきたい。さらに「横井の思想を西郷の手で行われたら敵うものはあるまい」とも述べている。妹婿の佐久間象山ではなく,小楠を挙げているところが海舟らしい。
坂本龍馬の船中八策も由利公正(三岡八郎)の五箇条の御誓文も,元は横井小楠にある。坂本の師匠勝海舟とは,肝胆相照らす間柄で,坂本も勝の使いで何度も,熊本に蟄居中の小楠をたずねている。由利は,小楠が越前に招聘された折,立てた殖産興業策に触発され,横井から財政学を学び,藩札発行と専売制を結合した殖産興業政策で窮乏した藩財政を再建する。
その由利と龍馬は気が合い,2度目の福井来訪時,早朝から深夜まで延々日本の将来を語り合ったという。背後の小楠の思想が,生かされている。明治新政府に召されたのも故なしとしないが,ために暗殺されることになった。
ついでながら,横井小楠については,松浦玲『横井小楠』(筑摩学芸文庫)を読んでほしい。本文の倍の注が,この本自体のもつ,通常の伝記ものとは異なる破格の熱が伝わってくる。因みに,松浦の『勝海舟』もいい。海舟全集を編集しただけに,細部がよく見えている。それに『坂本龍馬』もある。
小楠は実践家なので,学問も,政治としての実践論になっている。ここでは,小楠の思想をふれるには力量不足なので,その講義の一端と,自分の好きな詩を紹介してお茶を濁す。一回でまとめようと思ったが,長くなりすぎたので,二回にわける。
学問の学び方が,実にユニーク。実学と称されただけのことはある。
学の義如何,我が心上に就いて理解すべし。朱註に委細備われとも其の註によりて理解すればすなわち,朱子の奴隷にして,学の真意を知らず。後世学者と言えば,書を読み文を作る者を指していうようなれども,古えを考えれば,決して左様な義にてはなし。堯舜以来孔夫子の時にも何ぞ曾て当節のごとき幾多の書あらんや。且つまた古来の聖賢読書にのみ精を励みたまうことも曾て聞かず。すなわち古人の所謂学なるもの果たして如何と見れば,全く吾が方寸の修行なり。良心を拡充し,日用事物の上にて功を用いれば,総て学に非ざるはなし。父子兄弟夫婦の間より,君に事え友に交わり,賢に親づき衆を愛するなり。百工伎芸農商の者と話しあい,山河草木鳥獣に至るまで其の事に即して其の理を解し,其の上に書を読みて古人の事歴成法を考え,義理の究まりなきを知り,孜々として止まず,吾が心をして日々霊活ならしむる,是れ則ち学問にして修行なり。堯舜も一生修行したまいしなり。古来聖賢の学なるもの是れをすてて何にあらんや。後世の学者日用の上に学なくして唯書について理会す,是れ古人の学ぶところを学ぶに非らずして,所謂古人の奴隷という者なり。いま朱子を学ばんと思いなば,朱子の学ぶところ如何と思うべし。左なくして朱子の書につくときは全く朱子の奴隷なり。たとえば,詩を作るもの杜甫を学ばんと思いなば,杜甫の学ぶところ如何と考え,漢魏六朝までさかのぼって可なり。且つまた尋常の人にて一通り道理を聞きては合点すれども,唯一場の説話となり践履の実なきは口耳三寸の学とやいわん。学者の通患なり。故に学に志すものは至極の道理と思いなば,尺進あって寸退すべからず。是れ眞の修行なり。
「朱註に委細備われとも其の註によりて理解すればすなわち,朱子の奴隷にして,学の真意を知らず」とは厳しい。誰それの解釈や解説を読んだのでは,その奴隷と言い切っている。
「後世の学者日用の上に学なくして唯書について理会す,是れ古人の学ぶところを学ぶに非らずして,所謂古人の奴隷という者なり。いま朱子を学ばんと思いなば,朱子の学ぶところ如何と思うべし。左なくして朱子の書につくときは全く朱子の奴隷なり」とも言う。これと同じことを,王陽明も『伝習禄』の中で触れていた。つながるのかもしれない。
彼は講義中にメモを取ることを禁じた。それは,小楠の言うことをそのまま書き取ったのでは,小楠の奴隷になるだけだ。その都度,自問自答しつつ,考えることを求める。
学ぶとは,書物や講学の上だけで修行することではない。書物の上ばかりで物事を会得しょうとしていては,その奴隷になるだけだ。日用の事物の上で心を活用し,どう工夫すれば実現できるのかを考える,そのまま書きとめるのではなく,おのれの中で,なるほどこのことか,と合点するよう心がけるが肝要だ。合点が得られたときは,世間窮通得失栄辱などの外欲の一切を度外視し,舜何人か,沼山何人かの思いが脱然としておこる,この学問にはまりこみ,日用実用の上でどう力行するかを工夫する,その修行なのだ,という。小楠の奴隷になのではなく,おのれの合点を得て,世の中に,おのれの工夫を実現せよ,それには日々,一刻一刻が,そのときだと心得よ,という趣旨であった。
「且つまた古来の聖賢読書にのみ精を励みたまうことも曾て聞かず。すなわち古人の所謂学なるもの果たして如何と見れば,全く吾が方寸の修行なり。良心を拡充し,日用事物の上にて功を用いれば,総て学に非ざるはなし」とは,実践家らしい。
朋有り(これは論語の「朋有り,遠方より来る」云々を指す),この義は学問の味を覚え,修行の心盛んなれば,吾がほうより有徳の人と聞かば,遠近親疎の差別なく,親しみ近づきて話し合えば,自然と彼方よりも打ち解けて親しむ,是れ感応の理なり。此の朋の字は学者に限らず,誰にてもあれ其の長を取りて学ぶときは世人皆吾が朋友なり。憧々として往来するの謂いにあらず今一際広めていえば,幕府より米利堅に遣わされし使節を米人厚くあしらいし其の交情の深さにても考え思うべし。是れ感応の理なり。此の義を推せば,日本に限らず世界中皆吾が朋友なり。
日本に限らず世界中皆吾が朋友なり。この言,二人の甥を龍馬に託して洋行させる折送った,有名な送別の詩
堯舜孔子の道を明らかにし
西洋器械の術を尽くさば
なんぞ富国に止まらん
なんぞ強兵に止まらん
大義を四海に布かんのみ
の満々たる楽観主義を思わせる。和魂洋才などという縮んだ諭吉の思想とは全く違う。「大義」と言っているところがポイントだ。「大義」を第二次大戦下のおためごかしのスローガンと同じにしてはならない。堯瞬の理想主義を高々と掲げてはばからない。彼には,国権主義とは無縁なのだ。だから楽観主義という。この高らかな楽観主義は,暗殺で,ついに政策に反映されることはなかった。この精神は,五箇条の御誓文の精神と通底している。因みに,五箇条とは,以下のものだ。
一,広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
一,上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一,官武一途庶民ニ至ルマデ各其ノ志ヲ遂ゲ,人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
一,知識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
長所短所についても,面白いことを言っている。
長所短所といっても,右と左というようにはっきり区別されたものならば,そういうやり方もあろうが,長所短所はつながりあっていて,しっかり区別はつかない。たとえば,火は燃えるが故に種々利用されるが,その長に任せて制するところがなければ,家も宝も焼き尽くしてときには人の命もそこなうことになる。水も物を潤す性あるものの溢れるときは害をなす。これ長に短あるところ,物みなそうである。人にありても進取的な人は退き守るに短なるがために,手前に過を取ることがあり,退守的な人は進み取るに短なるために機を失することが多い。
横井の「堯舜孔子の道を明らかにし」という楽天主義について,渡辺京二は,神風連の生みの親,林櫻園と対比して,こう批判している。
国民攘夷戦争(幕末の攘夷熱のときに決戦を唱えた)の主張から全人間界の出来事の放棄(晩年厭世的になり神事に専念するようになる)にいたる櫻園の思想的道すじは,彼がヨーロッパ文明の圧倒的な侵蝕力を鋭く感知し,この異種文明との出会いがわが国の伝統的文明を運命的に脅かさずにはいないことを見抜いていたところから,生まれたもののように見える。たとえば開国論者横井小楠には,「堯舜孔子の道を明らかにし/西洋器械の術を尽くさば/なんぞ富国に止まらん/なんぞ強兵に止まらん/大義を四海に布かんのみ」という有名な詩があるが,櫻園にいわせればこれはとほうもない誇大妄想というものであったろう。ヨーロッパ文明との接触はそれから「器械の術」だけをいただけばいいようなものではなく,小楠にとっての「大義」すなわち「堯舜孔子の道」を必然的に崩壊させずにすまぬことであることを,彼はおそら洞察していた。
しかしこれは本人の言うように,「深読み」に過ぎない。楽天家とは,小楠へのほめ言葉に過ぎない。
所詮シニカルな現実主義者は,神の世界に逃避し,途方もない楽天家は,最後まで現実的であった。シニカルな評論家が,自分の血を流すことは,決してない。櫻園は畳の上で往生し,小楠は,京都の寺町丸太町の路上で襲撃され,小刀の刃が刃こぼれするほど敵と戦い,首を刈られた。
僕はシニカルな現実主義者を信じない。恐らく評論家でしかない。それを擁護するものもまた評論家でしかないのだ,と経験則から学んでいる。
参考文献;
野口宗親『横井小楠漢詩文全釈』(熊本出版文化会館)
山崎正董『横井小楠』(明治書院)
松浦玲『横井小楠』(ちくま学芸文庫)
渡辺京二『神風連とその時代』(洋泉社)
僕の好きな小楠の言葉は,これだ。
本当の小人,姦人というのは百人にひとりもいない。その他は皆人としてたりないところがあるにすぎない。それをすぐ小人,姦人とけなし,よいところをみてやらず,欠点のみ責めるのは,その責めているほうこそが小人なのだと思い知らねばならぬ。小人をもって小人を責むるということです。
「小人をもって小人を責むる」とは,痛い。子曰く,君子は諸(これ)を己に求め,小人は諸(これ)を人に求む,と。おのれを知らないのと,相手を知らないのとは,丁度裏表ということか。そして,こう言う。
人材には、上中下とある。高い節操、篤行があり、才智が深く、道理を外さず臨機応変に対処できるものが上材、才識が秀で英邁豪俊ではあるが、行いを慎んだり、大事を取れぬものは中材、諄諄としてしきたり墨守し、智力で臨機応変に対応できぬものは下材、下材ではものの役に立てぬ。上材は、百世に一人現れるもので、中材の異能のものこそが役に立てるものだ。いまはその中材の抜擢すら慣例にとらわれていて、登用される道が閉ざされているが、この混迷の時代、中材こそが有用な人材になりうる,と。
こうした人材観の背景にあるのは,
人は三段階あると知るべし。天は太古から今日に至るまで不易の一天である。人は天中の一小天で、我より以上の前人、我以後の後人とこの三段の人を合わせて一天の全体をなす。故に我より前人は我前生の天工を享けて我に譲れり。我これを継いで我後人に譲る。後人これを継いでそのまた後人に譲る。前生今生後生の三段あれども皆我天中の子にしてこの三人あって天帝の命を果たすものだ。孔子は堯舜を祖述し、周公などの前聖を継いで、後世のための学を開く。しかしこれを孔子のみにとどめてはならない。人と生まれては、人々皆天に事(つか)える職分である。身形は我一生の仮託、身形は変々生々してこの道は往古以来今日まで一致している。故に天に事えるよりのほか何ぞ利害禍福栄辱死生の欲に迷ふことあろうか,
という,天を意識し,連綿と続く歴史の一端を担っているという自覚だ。先人の背に乗って,後世へとつないでいく。その眼から見れば,異国を「夷狄」と呼ぶ攘夷の風潮が,小楠には相対化される。
中国にとって我国が東夷とよばれたように、みずからを中華とみなさねば、そうは呼べない。では、彼らにとって、われらはどう見えるのか、大洋を押し渡ってきた彼らにとって、われらはちっぽけな島国でしかない。彼らにとって、われらこそが夷狄かもしれない。では、なぜ国を開くのか、国を開くことで、一国の中で堅持された仕組みは崩れる。いま起きていることは、いままでこの国を動かしてきた偉い人たちが、この事態に対処できない周章狼狽ぶりをさらけ出し、国の政事を果たしていけぬことを世間に知らしめたにすぎない。
道は天地の道なり。わが国の、外国のということはないのだ。道のある所は外夷といえども中国なり。無道になるならば、我国支那といえどもすなわち夷なり。初めより中国といい夷ということはない。国学者流の見識は大いに狂っている。だから、支那と我国とは愚かな国になってしまった。亜墨利加などはよく日本のことを熟視し、決して無理非道なことをなさず、ただわれらを諭して漸漸に国を開くの了簡と見えた。猖獗なるものは下人どもだけだ。ここで日本に仁義の大道を起さなくてはならない、強国になるのであってはならない。強あれば必ず弱あり、この道を明らかにして世界の世話やきにならにはならねばならぬ。一発で一万も二万も戦死するというようになることは必ずとめさせねばならぬ。そこで我日本は印度になるか、世界第一等の仁義の国になるか、この二筋のうちしか選択肢はない。
そして異国との対応のあり方を,こう説く。常に,天が意識されている。
天地仁義の大道を貫く条理に基づかねばならぬ。すなわち、有道の国は通信を許し、無道の国は拒絶するのふたつだ。天地には道理がある。この道理をもって説諭すれば、夷狄禽獣も従う。
応接の最下等は、彼の威権に屈して和議を唱えるもの。これは話にならない。結局幕府はこれを取った。次策は、理非を分かたず一切異国を拒否して戦争をしようとするもの。これが攘夷派の主張だ。長州が通告なく通過する艦船を砲撃したのはこれだ。これは天地自然の道理を知らないから、長州がそうなったように、必ず破れる。第三策は、しばらく屈して和し、士気を張ってから戦おうというもの。水戸派の主張だ。これは彼我の国情をよく知っているようだが、実は天下の大義に暗い。一旦和してしまえば、天下の人心怠惰にながれ、士気がふるいたつことなど覚束ない。最上の策は、必戦の覚悟を固め、国を挙げて材傑の人を集め政体を改革することである。天下の人心に大義のあることを知らせ、士気を一新することである。我は戦闘必死を旨とし、天地の大義を奉じて彼に応接する道こそが、義にかなうはずだ。
この第三策は,勝海舟の考えでもあった。家茂も慶喜も,幕閣もこ,徳川幕府という体制の維持に汲々として,国としての覚悟を決断しなかった。小楠は大政奉還を聞いて,松平春嶽に,こう建策している。
第一に、議事院を建てられるべきこと。上院は公武御一席、下院は広く天下の人材を御挙用のこと。第二に、皇国政府相立った上は、金穀の用度一日もなくてはすまぬ。勘定局を建てられ、五百万両くらいの紙幣をつくり、皇国政府の官印を押し通用するようにすべきこと。第三に、一万石につき百石の拠出を求め、新政府の収入とすること。第四に、刑法局を建てられるべきこと。第五に、海軍局を兵庫に建てられるべきこと。関東諸侯の軍艦を集め、十万石以上の大名から高に応じて人数を定めて兵士を出さしめ、西洋より航海師ならびに指揮官を乞い、伝習させる。第六に、兵庫開港期限が迫っている。国体名分改正の第一歩なれば、旧来の条約中適中せざるを一々改正し公共正大百年不易の条約を正むべし。第七に、外国は交易、商法の学があり、世界物産の有無を調べ、物価の高低を明らかにして広く万国に通商している。そうした熟練に対して、我国は拙劣であり、大人と子供のようなものだ。彼らが大奸をなす所以である。十余年来交易において我国大損たるは明らかである。これより外国に乗り出すにあたっては、まず魯、英、佛、墨、蘭に日本商館を建て、内治においては、商社を建て、兵庫港であれば、五畿内、四国、南海道は、大名ばかりでなく、小人百姓も共望によってその社に容れ、同心して共に舟を仕立てて乗り出し交易すべし。
小楠の中の,ありうべき国家像は,この後,さらにブラッシュアップし,実践される機会が与えられないまま,潰えた。しかしここにあるのは,清潔感だ。義であり,天であり,という言い方を今風に変えれば,絶対に譲れぬ価値を見据えているといっていい。それは徹底している。
その小楠に,こういう詩がある。小楠の判断の一端を知ることができる。
彼を是とし又此を非とすれば
是非一方に偏す
姑(しばら)く是非の心を置け
心虚なれば即ち天を見る
心虚なれば即ち天を見る
天理万物和す
紛々たる閑是非
一笑逝波に付さん
衆言は正義を恐れ
正義は衆言を憎む
之を要するに名と利
別に天理の存する在り
是非の二者択一ではない視点をいつも持つ,小楠はしたたかな政治顧問であった。小楠が,松平春嶽のブレーンであった時,最も松平春嶽が輝いていた。その間,藩レベルで,こうすれば民が肥え,結果として藩が豊かになるという殖産政策を実施した。なかなか端倪すべからざるコンサルタントでもある。ついに国レベルで,実践する機会に恵まれないまま殺された。
酒席に,肥後勤王派の襲撃を受けた折,士道に悖る行為があったとして,知行召し上げ士席剥奪の処分を受け,熊本郊外の沼山津に逼塞していた時,こう読んだ。
心事分明にして疑う所無く
四時佳(か)興(きょう)坐(そぞろ)に卮(さかずき)を傾く
此の生一局既に収め了(おわ)り
忘却す人間(じんかん)の喜と悲とを
なかなかどうして,こんな達観した御仁ではない。この間,井上毅と対話した(というより喧嘩別れした対談)で,こういっていた。「凡そ我が心の理は六合に亘りて通ぜざることはなく,我が惻怛の誠は宇宙間のこと皆是れにひびかざるはなき者」と,昂揚した言い方をしていた。まだまだ意気軒昂であった。
人君なんすれぞ天職なる
天に代わりて百姓を治ればなり
天徳の人に非らざるよりは
何を以って天命に愜(かなわ)ん
堯の舜を巽(えら)ぶ所以
是れ真に大聖たり
迂儒此の理に暗く
之を以って聖人病めりとなす
嗟乎血統論
是れ豈天理に順ならんや
と,あの時代に言い切れる人はそうはいまい。いまでも,なかなか難しい。だから「廃帝論」を論じたとして,暗殺者をかばう論調が高まり,危うく暗殺者が英雄になるところだった。これは将軍継嗣問題で,一橋慶喜か紀州の慶福かで対立している時に読んだとされている。
あえて深読みすれば,血統による世襲は天下を私物化することだ。天命をうけた天徳の人が天下のために政事をするのではなく,君主の血統を維持するために国天下があるかのごとくになる。開幕以来天下のためにする政事これなく,ことごとく徳川氏のため,また諸侯はおのが国のためになされている。これを逆転しなくてはならない。君子のために国があるのではなく,国を治めるために君主がある。政事の役に立たないなら,君主は取り替えなければならない,そう読める。
嗟乎血統論/是れ豈天理に順ならんや,こう言い切れる人こそ,真の民主主義者に他ならない。いまの日本は,二代目三代目だらけ,またそれをよしとする風潮がある。その踏襲主義で,自由闊達な風土の国々に太刀打ちできようか。
二人の甥を坂本龍馬に託して洋行させる折,送ったもうひとつの送別の詩,
心に逆らうこと有るも
人を尤(とが)むること勿れ
人を尤むれば徳を損ず
為さんと欲する処るも
心に正(あて)にする勿れ
心に正にすれば事を破る
君子の道は身を脩むるに在り
に彼の心意気がある。おのれを律することなきは,彼の眼中にはない。
参考文献;
野口宗親『横井小楠漢詩文全釈』(熊本出版文化会館)
山崎正董『横井小楠』(明治書院)
松浦玲『横井小楠』(ちくま学芸文庫)
松浦玲編『佐久間象山・横井小楠』(中央公論社)
自分はこうはありたくない,こうは見られたくない,という自分イメージというのは,いわば自分の価値の映し鏡なのかもしれない。僕だったら,こうなる。
自分が下品だと思いたくない
自分が愚かだとは思いたくない
自分が間抜けとは思いたくない
自分が下劣だとは思いたくない
自分が卑しいとは思いたくない
自分が嫌らしいとは思いたくない
自分が愚図とは思いたくない
自分が下卑ているとは思いたくない
自分が汚いとは思いたくない
自分が野卑だと思いたくない
自分が夜郎自大とは思いたくない
自分がみすぼらしいとは思いたくない
自分が無様だと思いたくない
自分がうざいと思いたくない
自分が不細工と思いたくない
自分が野暮とは思いたくない
自分がめめしいと思いたくない
自分が浅ましいと思いたくない
自分が痛ましいとは思いたくない
自分が老耄と思いたくない
自分がぼけとは思いたくない
自分がみっともないと思いたくない
自分がじたばたしてると思いたくない
自分を軽躁と思いたくない
自分が狼狽していると思いたくない
自分が悄然としていると思いたくない
自分が傲岸不遜と思いたくない
自分が弱腰と思いたくない
自分が軟弱とは思いたくない
自分がいい加減と思いたくない
自分が場当たり的と思いたくない
自分が無為無策とは思いたくない
自分が手ぬるいとは思いたくない
自分が粗忽とは思いたくない
自分が投げやりとは思いたくない
自分が疎漏とは思いたくない
自分がお調子者とは思いたくない
自分が軽率とは思いたくない
自分が無分別とは思いたくない
自分が軽薄とは思いたくない
自分が無責任とは思いたくない
自分が不謹慎とは思いたくない
自分がこせこせしているとは思いたくない
自分が不実とは思いたくない
自分が不埒とは思いたくない
自分がだらしないとは思いたくない
自分が放逸とは思いたくない
自分が自分勝手とは思いたくない
自分が出放題とは思いたくない
自分がちゃらんぽらんとは思いたくない
自分が気まぐれとは思いたくない
自分が卑怯とは思いたくない
自分が卑屈とは思いたくない
自分が因循姑息とは思いたくない
自分が風馬牛とは思いたくない
自分が無愛想とは思いたくない
自分がそっけないと思いたくない
自分が意地悪とは思いたくない
自分がこころないとは思いたくない
自分が薄情とは思いたくない
自分が残忍とは思いたくない
自分が因業とは思いたくない
自分が傲慢無礼とは思いたくない
自分が狭量とは思いたくない
自分が横柄とは思いたくない
自分が尊大とは思いたくない
自分が高慢とは思いたくない
自分が居丈高とは思いたくない
自分が不遜とは思いたくない
自分が高飛車とは思いたくない
自分が官僚的とは思いたくない
自分が権柄づくとは思いたくない
自分が気障とは思いたくない
自分が猪口才とは思いたくない
自分が見栄っ張りとは思いたくない
自分がぶしつけとは思いたくない
自分が非礼とは思いたくない
自分が傍若無人とは思いたくない
自分が不作法とは思いたくない
自分が偏頗だとは思いたくない
自分が陰湿とは思いたくない
自分が粗暴とは思いたくない
自分が狡猾とは思いたくない
自分が厚顔無恥とは思いたくない
自分が陋劣とは思いたくない
自分がしみったれとは思いたくない
自分が破廉恥とは思いたくない
自分が悪辣とは思いたくない
自分がみみっちいとは思いたくない
自分が吝嗇とは思いたくない
自分が強欲とは思いたくない
自分が固陋とは思いたくない
自分が依怙地とは思いたくない
自分が優柔不断とは思いたくない
自分が意気地なしとは思いたくない
自分が癇癖とは思いたくない
自分が無粋とは思いたくない
自分が無能とは思いたくない
自分があざといとは思いたくない
自分が猿知恵とは思いたくない
自分が浅薄とは思いたくない
自分が短慮とは思いたくない
自分が鈍感とは思いたくない
自分が付け焼刃とは思いたくない
自分が半可通とは思いたくない
自分が非常識とは思いたくない
自分が拙劣とは思いたくない
自分は胡散臭いとは思いたくない
正確にいえば,直観は事後に正しい。したがってわれわれはやすやすと自らを騙して,自分は知っている以上に知り,知っている以上に知っていたと思い込む,という。つまり,
ほとんどの人は,自分自身を実際よりは高く評価している,
そうだ。さてどうか。
まあ,しかし,どのみち自分でしかない。その振り幅が大きいほど,自分ののりしろが大きいと考えることだ。
参考文献;
デヴィッド・G・マイヤーズ『直観を科学する』(麗澤大学出版会)
ありたくたくない自分リストについては,取り上げた。では,ありたい自分,なりたい自分,望ましい自分のリストを挙げてみるとどうなるか。はじめは,認めたくない自分リストの裏返しになるだけではないかと思ったが,必ずしもそうではない。ちょっと違う。その微妙に違うところが面白い。
認めたくないのは,自分の嫌な部分,そういう部分が自分に少しでもあるのではないか,そういうのは嫌だと,他山の石で,人のふるまい,ありようからリストを挙げている。
しかし,ありたい自分,なりたい自分,望ましい自分,あったらいい自分は,理想ではないが,そうはなれないだろうという諦めがある。だから,第一級とか上品とか,偉大といった,トップクラスのことを望まない。ちょっとつましく,もう少し背伸びすればなれそうなところを挙げる。
そう考えると,微妙にすれ違っている。そこがまた意外であった。
しかもリストは,相互に微妙に矛盾する。勇敢さと臆病さを共存させる。それは,そうなりたい自分と,そんなことはどうでもいいと反理想に開き直る自分とに割れる。その幅が自分なのだろう。
さて,そこで,ランダムに,思いつくままに…,ありたい自分,なりたい自分,望ましい自分,そうなればいいだろう自分を,リストアップしてみた。ありたい自分,なりたい自分,望ましい自分,そうなれればいいだろう自分は,また,そう認めてほしい,そう思われたい自分でもあるようだ。さっそくながら……。
自分は剛直な人でありたい
自分は果断な人でありたい
自分は勇敢な人でありたい
自分繊細な人でありたい
自分は本物の人でありたい
自分は清潔な人でありたい
自分は風格ある人でありたい
自分は渋い人でありたい
自分は気韻ある人でありたい
自分は切れ味ある人でありたい
自分は詩趣ある人でありたい
自分は枯淡な人でありたい
自分は孤高の人でありたい
自分は独特の人でありたい
自分はユニークな人でありたい
自分はオリジナルな人でありたい
自分は傍系の人でありたい
自分は異端の人でありたい
自分は飄逸な人でありたい
自分は平々凡々な人でありたい
自分は勇往邁進の人でありたい
自分は尖る人でありたい
自分は透徹した人でありたい
自分はお洒落な人でありたい
自分は洒脱な人でありたい
自分は創造する人でありたい
自分はクリエイティブな人でありたい
自分は貫く人でありたい
自分は漸進,漸進,ひたすら漸進の人でありたい
自分は独立不羈の人でありたい
自分は偏倚の人でありたい
自分は左派の人でありたい
自分は長躯の人でありたい
自分は温容の人でありたい
自分は活眼の人でありたい
自分は俯瞰の人でありたい
自分は遠望の人でありたい
自分は表現する人でありたい
自分は発想豊かな人でありたい
自分は直言の人でありたい
自分は寡黙の人でありたい
自分は力行の人でありたい
自分は直感(直観)の人でありたい
自分は思慮深い人でありたい
自分は卓見の士でありたい
自分は忖度の人でありたい
自分は速断の人でありたい
自分は決断の人でありたい
自分は洞見の人でありたい
自分は目利きの人でありたい
自分は迷妄の人でありたい
自分は切磋琢磨の人でありたい
自分は創意の人でありたい
自分は初心の人でありたい
自分は士心の人でありたい
自分は義の人でありたい
自分は執着する人でありたい
自分は親しまれる人でありたい
自分はへそ曲りでありたい
自分は克己の人でありたい
自分は一徹でありたい
自分は土性骨のある人でありたい
自分は辛抱強い人でありたい
自分は敬意を払われる人でありたい
自分は謙遜の人でありたい
自分は好感される人でありたい
自分は恩寵の人でありたい
自分は冷静な人でありたい
自分は楽しむ人でありたい
自分は悲憤慷慨の人でありたい
自分は表現者でありたい
自分は大人でありたい
自分は士人でありたい
自分は天邪鬼でありたい
自分は理想家でありたい
自分は志士でありたい
自分は不器用な人でありたい
自分は立ち尽くす人でありたい
自分は呑み込みの悪い人でありたい
自分は物分りが悪い人でありたい
自分は目端の利かない人でありたい
自分は上品な人でありたい
自分は下品を厭わぬ人でありたい
自分は軽佻浮薄でありたい
自分は野暮天でありたい
自分は臆病な人でありたい
自分は冷静沈着な人でありたい
自分は緩やかな人でありたい
自分は潔い人でありたい
自分は執着しない人でありたい
自分は自由な人でありたい
自分は穏やかな人でありたい
自分は時流に逆らう人でありたい
自分は流行に背を向ける人でありたい
自分は無粋な人でありたい
自分は武骨な人でありたい
自分は剛毅朴訥な人でありたい
自分は物静かな人でありたい
自分は悠揚な人でありたい
自分は泰然自若とした人でありたい
自分は飄々とした人でありたい
自分は率直な人でありたい
自分は真率な人でありたい
自分は真摯な人でありたい
自分は闊達な人でありたい
自分は柔軟な人でありたい
自分は虚心の人でありたい
自分は悠悠閑閑な人でありたい
自分は凛とした人でありたい
自分は大量の人でありたい
自分は謙虚な人でありたい
自分は律儀な人でありたい
自分は廉直な人でありたい
自分はざっくばらんな人でありたい
自分は柔和な人でありたい
自分は反骨の人でありたい
自分は硬骨の士でありたい
自分はおおらか人でありたい
自分は剽軽な人でありたい
自分はユーモアの人でありたい
自分は才知の人でありたい
自分は怜悧の人でありたい
自分は具眼の士でありたい
自分は篤学の士でありたい
自分は酔狂の人でありたい
自分は浩然の人でありたい
自分は恐れない人でありたい
自分はゆるぎない人でありたい
自分は自恃の人でありたい
自分は自立(自律)の人でありたい
自分は持久力の人でありたい
自分は持続する人でありたい
自分は挫けない人でありたい
自分は折れない人でありたい
自分は揺るがぬ人でありたい
自分は登りつづける人でありたい
自分は諦めの悪い人でありたい
自分は温情の人でありたい
自分は恩義の人でありたい
自分は真っ直ぐ前を見つめる人でありたい
自分は凹まぬ人でありたい
自分は大度の人でありたい
自分は覚悟の人でありたい
自分は楽観の人でありたい
自分は夢を追い続ける人でありたい
自分は志を貫く人でありたい
自分は恋する人でありたい
自分は愛の人でありたい
自分は問い続ける人でありたい
自分は信念の人でありたい
自分は物分りの悪い人でありたい
自分は成長し続ける人でありたい
自分は見抜く人でありたい
自分は眼力の人でありたい
自分は自ら発光する人でありたい
自分は心眼の人でありたい
自分はオープンマインドの人でありたい
自分は心豊かな人でありたい
自分は手放す人でありたい
自分は気概のある人でありたい
自分は気骨のある人でありたい
自分は颯爽とした人でありたい
自分は屈せぬ人でありたい
自分は泰然自若の人でありたい
自分は春風駘蕩の人でありたい
自分は義憤の人でありたい
自分は天空の人でありたい
自分は空を泳ぐ人でありたい
ありたい自分,なりたい自分,望ましい自分は,振幅があり,相互抵触し,矛盾する。その振れ幅は,自分には軸がないという捉え方もあるが(事実そう言われたこともあるが),それだけの多様性を自分が持っている,と考えたほうが,自分の伸びしろの広さと思えて,まあ都合がいい。
考えようによれば,人はその時,その人,そのシチュエーションに応じて,多様な自分で向きあう。その意味では,一面的ではない。それは自分の多様性と柔軟性と受け止めておけばいい。人は人色ではない。人は様々な可能性を持つ。それを,成否,是非,可否の自分としてリストアップすることで,見えてくると言えるのかもしれない。
この作業は,あるいは自己承認なのかもしれない。この一つつひとつが,ではなく,そのすべての振れ幅そのものの自分を,である。
かつて上司であった編集長は,部下の書く文章について,箇条書きにすることを徹底させた。おかげで,習い性になり,『語りのパースペクティブ』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06461.htm#%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%A7%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%E2%85%A0)
を書いた時,最終選考で,選者の一人後藤明生氏から,文学的ではないと評されて,落ち込んだことがある。しかし,やはり,箇条書きにすることは,読み手にわかりやすい,とは思う。
たとえば,何々について言えることは,
①
②
③
という具合である。そして,重宝なことに,いくつという枠を決めると,その数だけ,ひねり出してしまうことができる。言うべきことが,見えてくる。
たとえば,文章に欠かせないことは,五つである,と言い切ったとすると,
①一文のセンテンスで,輻輳させず,言いたいことをシンプルに言い切る
②カンマをある程度多めに入れる。
③「です調」か「である調」か「だ調」か,レベルを統一する
④主語を明確にする
⑤過去形か現在形かの区別は意識的にする
等々である。別にここで言い切ったことが正しいかどうかではない。そう言い切ることで,伝えたいことの枠が決まる。人は枠なしで,ぼんやりものを考えない。同様に,読み手に取っても,書き手の枠組み,いわば窓枠がはっきりした方が,そこから見ている視界がはっきりする。
たとえば,大事なことは,三つです。と先に宣言されると,頭に入りやすいという。口頭のメッセージは25%の歩留りと言われる。しかし,こうやって堰を作ってもらうと,シーケンシャルに流れていく話題が,区切れ,分節化することで,記憶にとどめやすくなる。これも箇条書きの一種といっていい。
当然枠を替えれば見える世界が変わる。たとえば,いまの文章に欠かせない五箇条を別の切り口で書けば,
①語り手は誰か
②語られている世界は何処か
③語られているひと(びと)は誰か
④語られている時間はいつか
⑤語り手はどこにいるのか
という風にも書ける。
ただこういうことで得られるわかりやすさは,決めつけと近似で,わかりやすくするために,何かを犠牲にしていることがある。そこを考え始めると,そう簡単に箇条書きが「わかりやすい」とのみは言い切れない。
別の視点で考えると,箇条書きにするということは,ある次元を網羅することになる。それは,次のサイトにあるような,ロジカル・シンキング(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0951.htm#%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%92)でいう, ロジカルツリーには,縦につながる筋を通すことと横のつながりのもれなくすることの二つがあるが,箇条書きで書いているのは,横のつながりだけなので,縦の筋から次元を変えれば,別の箇条書きの項目が生まれてくる。この延長線上に,チェックリストがある,といってもいい。
たとえば,コミュニケーション力を,「チェックリスト」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06394.htm#%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%8A%9B%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88)
として,まとめた場合,
聞く力/伝える力/自己開示力/感情コントロール力/人と関わる力/モニタリング力,
とわけるのが,ロジカルツリーで言う縦の筋の第一段階とすると,この各項目が決まれば,その下へブレークダウンした具体的項目を考えることになる。これが横のつながりになる。
だから,箇条書きで書くということは,次元を設定しさえすれば,それを次元を上へあげていくことも,下へ下げていくことも,次元さえ分かっていれば,レベルを変えて書くことができる,ということになる。もっとも,人の脳は,丸めるのが得意なので,上へ丸めるのに比べると,ブレークダウンはずいぶん不得手ではあるが。
茂木健一郎さんは,
表現として高度の洗練と達成を求めるほど,言語圏の奥へと入り込んでいき,他の言語圏の人には不可視な場所に取り込まれていってしまう。そのような言語の仕掛ける罠を思うとき,私は他のどのような事態からも受けないたぐいの打撃を受け,深い絶望を感じる。
では勝ち馬の英語に乗ればいいのか。そうは茂木さんは考えない。
もちろん異なる言語の間には,ある程度の「翻訳」が可能である。日本語圏の住人にとっての志ん生の味わいを,英語圏の言語で表現することが全く不可能であると決めつけられるわけではない。(中略)しかし,複数の言語の壁を超えて普遍性を立てることを志向するとき,そこにはおのずから原理的な困難がある。(中略)厳密にいえば,ある概念の普遍性は,その概念の翻訳可能性と一致するとは限らない。たとえば,世界の中のある言語圏だけが到達し,把握している普遍性が存在することはありうる。
そう述べた上で,村上春樹に言及した。
双方向の行き来が盛んになるにつれて,翻訳可能なものだけが事実上の普遍性を帯びていくということは実際的な意味で不可避のダイナミクスだといってよい。村上春樹の作品が,最初から翻訳可能な文体で書かれていることは,意識されたものであるかどうかは別として高度に戦略的である。
自分が村上春樹を好きになれない理由が分かった気がした。イスラエルへひょこひょこ出かけて何とか賞を受賞する,政治センス(意志的だとしたらなおさら)の能天気さだけではなく,その書く姿勢そのものが相容れない。
同じ翻訳家として,ムジールの翻訳から出発し,ついに日本語の極限にまで到達した古井由吉と,同じく戦後,翻訳文章などと揶揄されながら,日本語の新たな表現を獲得した大江健三郎とは,全く対極にある。親鸞が,折口信夫が,あるいは吉本隆明が,翻訳不能なのは,普遍性がないからではなく,掘り下げた「共同幻想」の根っこが,翻訳不能なのだ。そこにのみ,日本のコアがある。それを「文化的遺伝子」と,茂木さんは言う。
和辻哲郎が,『鎖国』の中で,世界的視圏という言葉を使っていたことを思い出す。世界的視圏を仰望した和辻は,考えれば,楽天的だったということができる。自分を捨て,日本語を捨てても,日本人は残る。その重みを見落とすものに,日本を語る資格はない。
例えば,古井由吉の傑作『眉雨』の一文。
空には雲が垂れて東からさらに押し出し、雨も近い風の中で、人の胸から頭の高さに薄明りが漂っていた。顔ばかりが浮いて、足もとも暗いような。何人かが寄れば顔が一様の白さを付けて、いちいち事ありげな物腰がまつわり、声は抑えぎみに、眉は思わしげに遠くをうかがう、そんな刻限だ。何事もない。ただ、雲が刻々地へ傾きかかり、熱っぽい色が天にふくらんで、頭がかすかに痛む。奥歯が、腹が疼きかける。たがいに、悪い噂を引き寄せあう。毒々しい言葉を尽したあげくに、どの話にも禍々しさが足らず、もどかしい息の下で声も詰まり、何事もないとつぶやいて目は殺気立ち、あらぬ方を睨み据える。結局はだらけた声を掛けあって散り、雨もまもなく軒を叩き、宵の残りを家の者たちと過して、為ることもなくなり寝床に入るわけだが。
夜中に、天井へ目をひらく。雨は止んでいる。とうに止んでいた。風の走る音もない。しかし空気が肌に粘り、奥歯から後頭部のほうへまた、降りだし前の雲の動きを思わせる、疼きがある。わずかに赤味が差す。
これを翻訳したら,たぶん意味は通るかもしれない。しかし文体のコアは消える。文章を伝達の手段と考えるなら,それでもいい。それなら文学は成立しない。小説世界が既にあるものとして,それを前提に書かれる小説はいざ知らず,いまだかってない文学という世界を切り開こうとする作家にとって,文体はその単なる表現手段ではない。そのリズム,その語彙の選択,そのつなぎ,その流れ,句読点の打ち方一つ,その醸し出す雰囲気,そのすべてが文学作品を支える大事な世界の構成要素だ。そもそもそこまでわかって翻訳している人間がどれだけいるのか。
翻訳した時,何かが壊れる。翻訳とは,翻訳者が書き直しているに等しい。その翻訳で,実は原作は解体され,翻訳者の知識と理解度に応じて再構成されている。原作とは似ても似つかぬものになっているのは,詩を読むとはっきりわかる。
たとえば,
巷に雨の降る如く
我が心に雨の降る
これって,ベルレーヌのではなく,堀口大学の情緒だ。
それでもなお翻訳可能性とは何なのか。僕にはわからない。そこまで通訳可能性に楽天的にはなれない。
参考文献;
茂木健一郎『思考の補助線』(ちくま新書)
たとえば,以下の図を見て,何に見えるかをやってみる。もちろん正解はない。
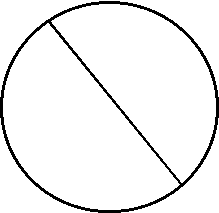
人の想像力は,たいしたもので,円に直径が描かれているだけなのに,球に見たり,円筒に見たり,半分開きかけたカップ麺にみたりと様々だが,同じものを見ていても,同じように見えているとは限らない。その見え方に,その人のオリジナリティがある。たとえば,中に,円ではなく,直径の方に眼を向ける。すると,スイカといったときに,その線が気になる。皿といった時も,その線が気になる。別に正解はないので,なんと見てもいいが,人は,全体に丸める癖があるが,丸めることに抵抗する人がいる。この場合,人より,少しだけ,細かいところが気になるわけだ。
つまり,人は誰でも,自分独自の具体性のレベルを持っている。つまり,
人は同じものを見ていても,同じように見えているとは限らない。
それは,人のリソースからきている。それを意識すると,他人との具体性の差を発想の違いとして使うことができる。それぞれのレベルを左右するものにはいくつかあるが,一例を挙げると,
●記憶というリソースを考えると,一般に,人の記憶は,
・意味記憶(知っている Knowには,Knowing ThatとKnowing Howがある)
・エピソード記憶(覚えている rememberは,いつ,どこでが記憶された個人的経験)
・手続き記憶(できる skillは,認知的なもの,感覚・運動的なもの,生活上の慣習等々の処理プロセスの記憶)
といわれる(この他,記憶には感覚記憶,無意識的記憶,短期記憶,ワーキングメモリー等々がある)が,なかでもその人の独自性を示すのは,エピソード記憶である。これは自伝的記憶と重なるが,その人の生きてきた軌跡そのものである。発想の独自性は,これに負うことが多い。アナロジーは,ほぼエピソード記憶に起因する。
意味レベルでは同じでも,一つの言葉にまったく別の光景を見ている場合もある。コミュニケーション・ギャップが生ずるのは,こういう場合が多い。言葉の意味を理解することと,自分なりに腑に落ちることとはギャップがある。その人の生きてきた自伝的部分が,他の人とは異なっている,ということだ。しかし発想という面で言えば,人と違う,おのれだけの独自の何かがそこにあると言えるのかもしれない。
以前メールで,「思惑」という言葉を使ったら,知人が激怒した。その言葉自体に,文脈を離れて反応したのは,意味レベルではなく,その人の体験,まあエピソード記憶から出来した何らかの感情反応に違いない。履歴を張り付けて,返信したら,本人は落ち着きを取り戻したが。これも,そういう例だ。
感覚というリソースで言うと,感覚面でも,その人特有のリアリティの差があらわれる。NLP(Neuro-Linguistic Programming
神経言語プログラミング)では,ひとは,特有の優位感覚をもっているという。
・視覚優位(Visual ビジュアル) 外部に向って見る場合にも,内部の心象を描く場合にも用いる。
・聴覚優位(Auditory オーディトリー) 外の音にも,内の音にも用いる。
・触運動覚優位(Kinesthetic キネステティック) 体感覚(触覚・味覚・嗅覚)。外側にも内側にも向く。
たとえば,ビジュアル感覚に優れている人には,同じものを見ていても,詳細な部分に目が向いたりする。円に直径の,直径に眼が向いた人は,そうなのかもしれない。しかし,それは,人のもっている感覚の中にあえて優劣をつけてみただけで,ものに応じて,シチュエーションによって,あるいは一緒にいる人によって,その強弱が違うので,僕はあまり信じていない。すべての感覚を持っていて,たまにそれの強弱が出るだけだと考えていい。優位を大げさに言うと,勘違いを起こす。
時々思うが,「具体性」というのは,人によって違う。それぞれ自分にとっての当たり前をもっている。たとえば,上司が「具体的に言え」と言うとき,上司が,とんでもない「くそリアリスト」だと,詳細なディテールを求めている。部下が,超アバウトだと,本人がどれだけ具体的に語っても,上司の具体性には届かないだろう。
あるいは,一言で,「上から」といったときも,上は,二階からなのか,木の上からなのか,屋上からなのか,高層ビルの上からなのか,人によって一瞬思い浮かぶレベルは違っている。それがその人の当り前だから。
しかしその当たり前は,意識的に動かすことができる。ただし,それに気づけば,の話だ。たとえば,東京タワーの上から,飛行機の上から,人工衛星の上から,月から等々。そのことによって,具体性のレベルを変えていける。
因みに,具体的かどうかの原則は,次の3点。
・他にないたったひとつの「もの」や「こと」であるかどうか
・心の中に,気持ちや感情を動かすイメージが浮ぶかどうか
・特定の何かをそこから連想させる力があるかどうか
具体的にするための4つのアプローチは, 具体例で考えることである。
●具体例で考える~具体のレベルを下げる
●強制,あるいは見たいように見る~見える側を変える
●シリーズ化する~連想による横展開
●5W1H、あるいはストーリーを描く~ピンポイントにする
であり,これで,自分のリアリティ感のレベルを確かめることができる。
しかし,それは自分自身で自己完結して閉ざしている限り,それはなかなか気づけない。人との違いに気づいて初めて,自分の独自性に気づく。
リソースといわれているものを,ちょっと自分なりに,整理してみると,こんな感じになる。
たとえば,問題と接するときの,インターフェースにあたるのが,その人の感度である。どんな問題にアプローチするのか,何を拾い,何を捨てるのか,どこに注意を払うのか,何に気をとめるのか,のポイントとなるものだ。それは,内のリソースと外のリソースに分けて,大まかに,仮説的にわけてみる。
●内的リソース
問題への感度には,その人のもつアンテナとその人のフィルターのふたつの側面から考えなくてはならない。それを内的リソース(資源)とよぶなら,その感度を上げるには,アンテナの感度をあげることと,フィルターを活用することだ。フィルターはよく固定観念とか先入観と呼び習わされている。それはその人の知識と経験と気質のすべて,その人のもつ内的リソースそのものである。
・アンテナ アンテナは,問題意識と呼んでおく。これは,いまその人のいる状況,たとえば,どんな仕事をしているか,チームとしてどんな課題やテーマを追っているか,どんなことに興味や関心をもっているか,どんなニーズや動機をもっているか,といった,その人のいる文脈によって規制されている。
・フィルター フィルターは,そのひとが培ってきた内的なものの特質,これまでの経験,知識,技能,あるいはもう少し体質的な気質や性格といった,いわばその人のパーソナルな特質にかかわるものだ。
大きく分けると,
・知性フィルター
・感性フィルター
・感覚フィルター
にわけられる。知性フィルターは,その人の知識,経験であり,自分のもつ意味や価値を通してものを見る。しかしその関心を選んだのは,その人の感性か感覚かに起因しているかもしれない。誰かに影響を受けたとしても,その影響を受け止める感性,感覚が作用する。感性,感覚は生得的ではあるが,感性の多くは生きる中で身につけてきた。喜怒哀楽や好悪を通して見ることとなる。多くはマイナス的に受け止められるが,むしろそれを自分の特徴として受け止める姿勢がいる。感覚は遺伝子に起因するので,自分の特徴がわかりやすいが,自分にとって当たり前だから,気づきにくい。しかしそれが,外部リソースを生かす鍵になる。
●外的リソース
内的にもっているものだけでは,どうしても限界がある。そんなときに,外部の頭脳を使うことになる。有識者の見解を求めたりするのはその一つだが,チーム内,組織内での情報交換や意見交換,つまりはキャッチボールを通して,別のリソースを手に入れるということが重要になる。たとえばブレーンストーミングのように,人とのキャッチボールを通して,相手のリソースを借りて,自分にないアンテナやフィルターを手に入れる。キャッチボールをする効果は,異なるリソースに出会うことで,自分にとって当たり前すぎて,自分の中で気づかなかった,あるいは埋もれていた新たな独特さを発見することにある。
人との違いは,ほんのわずかだと僕は思っている。そのわずかな差異を広げ,深堀りして初めて,その違いが人の目に明らかになる。思い込みでも,思い上がりでも構わない。まず,人との違いに着目してみることだ。そこからしかオリジナリティは生まれない。いつまでも,ひと様のやっていることを探す,外へ答えを探すだけでは,それは見つからない。まず,違いを大袈裟に言葉にして,外に出したみることだ,と信じている。
人はすべてオリジナルであり,人はすべて個性的だ。自分にとって当たり前は,人にとって当たり前ではない。それに気づければいい。
久しぶりに,吹き出すような怒りを感じた。人との間である程度の齟齬があるのはやむを得ない。多少の行き違いもある。それが積み重なると,相手が,自分の何々が気にいらないせいなのだ,と勝手にその原因を邪推する。その瞬間に,激しい怒りを覚える。勝手な思い込み,そしてこっちが考えてもいない理由で齟齬が起きていると勘ぐるな,といういら立ちが,噴出して,激怒に変わる。
それで一瞬で空気が一変するのを,何度も経験してきた。
もっとも最近怒りやすくなっている気がする。喜怒哀楽が少し尖っている。これは治療のためステロイド剤を飲んでいることに起因しているのかもしれない。どうしても,テンションが通常より上がるため,感覚センサー,感情センサーの感度が尖る。そのせいもあるのではないか,という気がしている。最近ずっと穏やかな人間になってきていると,思い込んでいたのだが。
しかし,思えば,社会人としては,稀有なくらい,激怒することが多い人間であった。余り周囲の権威を慮ったり,損得勘定をしないせいなのかもしれない。いや,怒りが沸騰したら,損得なんて念頭から消えてしまう。その位激しく怒る。ま,人間が小さいせいに過ぎないが。
平生は,自分で言うのもなんだが,穏やかな人間だと思っている。時には,普通なら怒ることにもあまり目くじらを立てないほど,鈍感なこともある。
それが,怒りが爆発するのは,たぶん,いくつかのパターンがある。
ひとつは,くだくだと,自分の落ち度をつかれたり,もうそんなことを忘れているのに,腹を立てているのではないか,と邪推して,そのことをねちねちと繰り返されると,面倒くささと,いい加減にしろ,という思いで,両者の間の隙間を一気に広げるように,怒りを爆発させる。今日のは,それだ。もうそのことをこちらは何とも思っていないのに,まだこちらはそれを根に持っているのではないか,と勘繰られ,そこをつついて広げようとする。こちらとのギャップが,大きすぎて,「そんなことを思っていない」と言えば言うほど,何かかえって言い訳をしているようで,こちらの思いとは齟齬を大きく,その微妙な食い違いが説明しようがない。で,進退両難,主観的にはにっちもさっちもいかない気がして,切れてしまう。
いまひとつは,理不尽な言いがかりだ。これは,会社人生活最大の爆発だ。三十代,その会社の実力者に,進行途上の仕事について,自分の意見として言うのではなく,誰それが言っていたというような形で,理不尽な言いがかりをつけられた。もし,その人が,自分の意見として言ったとしたら,反論はしたかもしれないし,議論にはなったかもしれないが,そこまで激しい怒りを感じなかったのかもしれない。まだ完成していないのだから,それを修正する余地があり,自分の中でも,結論がでず,どうするか迷っている部分についての,言いがかりであった。しかも,その言い方が,「だから,全てだめ」というような言い方であった。しかし,ここには,上位者や責任あるものも取るべき態度についてのこちらの価値観なり期待像があり,その他人事のような言い振りに,カチンときたのが,発火点なのかもしれない。
またもうひとつは,これもよくあることなのだが,怒りというより,切れる,というのに近い。たとえば,何かを提案し,それで通った後に,追加でいくつか要請が来る。で,それに応える。それを何度が繰り返すうちに,あるとき,それはいいんだ,こちらで解決できる。それがお願いしたいことではない,と何というのか,いつの間にか,向こうの要請に応えようとしていたはずなのに,こちらからのお願いのようにすり替わって,主客が転倒してしまうケースがよくある。はっきり言うと,面倒になる,あるいは,邪魔くさくなる,うるさくなる,という感じで,「わかりました。では降ります」と言ってしまうことがある。積み上げた積み木を,こちらで蹴散らしてしまう感じだ。相手はたぶんびっくりしているだろうが,知ったことか,という感じになる。
この頃はあまりなくなったが,もうひとつあるパターンは,世の中の理不尽さや非道への激しい怒りを感ずることがあった。例えば,契約社員が理不尽に首を切られたり,言われない理由で上司が言いがかりをつけている場合,あるいは,不当な人事異動に対して,一種の正義感で,口を出すケースがあった。その役割でも立場でもないのに,のこのこしゃしゃり出て言って,一言口を出す。言ってみると,茶碗に手を突っ込んで引っ掻き回すみたいな感じだから,事態をこじらしてしまう。この場合の怒りは,静かな怒りで,場違いなところに,立っている,ということをわかっていて,あえてそこに立っている。言ってみると,蛮勇に近い。ただ本人は,別にそう思っていないので,冷静に理非曲直を口にしている。
義憤という言葉が近いのかもしれない。「義を見てせざるは勇無きなり」という類だ。例えば,リクルートスーツを強いている癖に,最近の若い奴は創造力がないとほざく人事担当者がいる。ないのはお前だ!と怒鳴りたくなる。個性をふんだんに振るっていいと言われたら,いまの若い人の多くは,そこらのサラリーマンのオヤジよりはるかに個性的な感性をもっている。ダンスのセンス,音楽のセンス,ファッションのセンス等々。それを発揮させる機会も与えず,非個性化リクルートスーツだからかえって個性が掘り出しやすいなとど理屈を捏ねて,見抜けぬ自分を棚に上げ,創造性がないなどという。こんなファッションを強い,意味ないお辞儀やもてなしを強要する会社に未来はない。もはやそれ自体がガラパゴスなのだと気づいていない。あきれるより何より,そんな会社はダメだとつくづく思う。個性のないところに創造性はない。個性のない会社に未来はない…とまあこんな具合だ。
だいたい自分の怒りのパターンは,こんな感じだ。もちろん,どの怒りも,REBTではないが,自分が起こしていて,相手のせいではない。自分のイラショナルビリーフのせいだと,REBTなら言うだろうが,必ずしもそうではない。ラショナルかイラショナルかという区分自体が,イラショナルなのだ。
ただ,いずれのパターンの場合も,その場を凍りつかせることが多い。その位激しい怒りを爆発させる。しかし自分では,それを望んでいるのではない。主観的には,やむを得ざる仕儀にて,そうなったという感じで,怒りの後,立っている自分の立ち位置に戸惑うことが多い。怒りに任せて,こぶしを振り上げたのだが,別に冷静に思案し,作戦を立てているわけでもないので,一の矢の次がない。二の矢,三の矢の用意がない。
その意味で,怒った後は,間抜け面をして棒立ちになっている。その一瞬で,醒めているということかもしれない。「人間の器量はどの程度のことを怒ったかによって測れる」「何に怒るかで,その人の器量がわかる」ともいう。おのが器量の小ささに,その瞬間気づくというべきか。「怒る時に怒らなければ,人間の甲斐がありません」とも言うが,しかしどんな怒りも,徒労感を伴う。
ならぬ堪忍するが堪忍
とはよく言ったものだ。
一朝に忿(いきどお)りにその身を忘れて以てその親に及ぼすは惑いに非ずや
ま,そこまでの激しい怒りは,まだ一度しかないが,しかし怒らぬ如くはない。
過ちて改めざる,是を過ちと謂う,と。
参考文献;
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)
人によっては,親友が何十人といると誇らしげに言う。しかし統計的に見て,記憶ではアメリカのデータだったが,親友というのは,せいぜい一人か二人,ゼロも結構いた。ネットで見ると,親友の数ランキングは,
1位 2人 25%
2位 0人 23%
3位 3人 19%
4位 1人 18%
5位 4人 6%
とあった。まあ常識の線だろう。「親友」を「親しい友」ととるか「信頼できる友」ととるかによって差はあるが,「親友」と「友人」と「知人」の境界線はそう明確ではない。
その境界は別として,「親友」という言葉から,瞬間に浮かぶのは,ベン図の円の重なり具合で表現し,たとえば,二つの円が重なっていたら,信頼度や親密度が高いというイメージになる。そこで親疎をしめしている,と。
しかしそうだろうか。どうもそれは,両者の関係性を示しているのではなく,両者の似たもの度を示していたり,関心や趣味の重なり具合を示している程度にしか思えない。
親友というのをどう定義するのは難しいが,いくつかの例を挙げると,
●親友とは、とても仲がいい友人を差す。心から理解し合える友人のことを心友ということもある。
●互いに心を許し合っている友。特に親しい友
●一生、失いたくない人。
●心の支えになってくれる人。居てくれるだけでホッとする人。
●いつでも気兼ねなく相談することができ、自分のことを一生懸命に考えてくれる友達のこと。
等々となる。どうも,気兼ねなく何でも言いあえる,いいことも悪いことも率直に言える,といった関係性の親密度,関係の深さを指している感じがする。
しかしそれでは,友人,知人,悪友,幼友達,学友との境界線はあいまいなのではないか。むしろ,親友とは,自分の側が相手にどういう関係を求めているかの反映で,その自分のニーズや希求に合わせて,そういう友が寄ってくる,という印象を受ける。悪い言い方を見すると,フェロモンに引き寄せられたという感じだから,多く似たもの同士という感じがする。
とすると,親友をどう定義するかが,その人の親友像を示すというふうに言ってもいい。
ハリー・スタック・サリヴァンは,
人間にとり、8歳半から始まる前思春期が非常に重要であるとし、そこでの友情から物事や世界の意味を確認できる、貴重な時期だとした。そこでの関係は、いわゆるchumshipと呼ばれる。もし、それまでの母子関係(乳幼児期~前思春期まで)に何かしらの問題があった場合でも、ここでの重要な他者との出会いが、その人の人生を支える可能性がある,
としている。そして,児童期(4,5~14,15歳)における親友(chum)というものは「癒し」の効果があると説いている,そうだ。
「癒し」ということをサリヴァンは言っている。それはサリヴァンの希求,思い入れと受け止めたほうが無難だろう。フロイト派流に,転移とは言わないが。正直,僕は,過去の母子関係を持ってくる考え方には辟易している。そう見れば見るほど,そういう縛りにおのれ自身を縛っていくだけだ。おそらく,サリヴァンそのものが縛られていたのだ,と疑いたくなる。
過去がいまを創っているのではなく,いまが過去を創っている。人の記憶は捏造する。エリザベス・F・ロフタフが,セラピストによって促された子供の親による性的虐待記憶の多くが,子供の想像によってつくられた偽記憶であることを暴いたように。記憶は平気で嘘をつく。
僕は,親友像について,全く別に考えている(もちろんそこに僕の親友像が反映している)。まずは,ラベルとしての親友かどうかはどうでもいい。ただの親しい友でも,通りすがりでも,フェイスブックでつながっただけの知り合いでも,両者が,ひとつの土俵の上に一緒に立てるかどうかが鍵だ。
土俵というか,ベン図ふうにいうと,二つの円が離れていようと,くっついていようと,その二つの円の外に,二つの円を囲む土俵というか,舞台をしつらえて,その土俵の上で,一緒に何かが創れるかどうか,一緒に何かクリエイティブな何かをし始めようとできるかどうかにかかっている。
そこで一緒に何かをはじめ,何かができれば,そこで二人は同士(fellow)から同志(comrade)に変わる。その段階で,もう親友とか友人というラベルなんか不要なのだ。
たぶんそのプロセスで,次の新しい円に乗り換えるかもしれないし,円が広がるかもしれない。
ただだべっているだけの関係性よりは,何かを創り出していく仲間であることの方が,いまは大事だと思っている。その意味で,何かを一緒につくった仲間は,その関係の中で創り出した紐帯は,たぶん,いまは全くその土俵を共有していなくても,あるいはいまや生死を別っても,いつまでも続く。そんな関係が,いまも断続的に,いくつか続いている。
そういう関係を人生の中にいっぱい残していきたいと思っている。それを何と呼ぶにしても。
確か,NHKの特別番組で,高倉健が,「その人の生き方が出る」と,演技について語っていたのを覚えている。その時,高倉健は,亡くなった大滝秀治との僅か一言三言のやり取りに,感動して涙ぐんでいた。そこで大滝秀治という人物を,丸ごと受け止め,そのわずかなセリフに,大滝のすべてを注ぎ込んだ,人生を見た,というと大袈裟か。
では,翻って,役者でも,著名人でもない,平凡な自分にとって,おのれの生き方が出る場面とは何か。
ものを食べているときの居ずまいか,
歩いている姿勢か,
ひととしゃべっている格好か,
人を口説いているのめりこんだ口吻か,
些細なことで口論している顔つきか,
肩が触れた程度でいらついている狭量な身構えか,
いやいや,その人の平生の行儀や居ずまいではないし,その人の人品骨柄,出自のことでもない。どんな生まれであろうと,どんなにお行儀が悪かろうと,その人自身の生き方なのだ。あるいは生きざまと呼ぼうか。どんな覚悟で生きているか,その生きざまがあらわに出るのはどういうときか。
たぶん,ひとつ思いつくのは,危機の一瞬だ。非日常になった時,どんな身構えが取れるか,周章狼狽するか,人を押しのけてでも前へ出ようとするか,見かねてわが身を顧みず誰かを背負い込むか,いずれが正しいとか間違っているとかを言うつもりはない。そこに,その人の生きざまが出る,というまでだ。そこで,道徳的なもの言いをする,安全なところから人をけしかけたりけなしたりするタイプの人間が大嫌いだ。戦争を煽る政治家が,真っ先に逃げ出すわけにはいかないことも,特攻隊に涙する政治家は,政治自身が(おのれ自身が)あたら若い者を無理や死地に赴かせるかもしれないことを顧みもしない。映画監督の黒澤明は,戦争中,コネを使って徴兵を逃れた。いわばずるく立ち回って生きのびた。そのことを戦後隠し通した。是非はともかく,そこに生きざまが出ている。どんな傑作を書こうと,どこかにその生きざまの卑しさが出る。
もうひとつは,本音で対面し,対話するときだ。コーチングしかり,カウンセリングしかり,討論しかり,インタヴューしかり,告白しかり,本気で叱るときしかり…。そのとき,おのれがさらけ出される。何も転移・逆転移だけが,おのれがさらけ出されるシチュエーションとは限らない。自分だけが,クライアントの何かに,たとえば,一言,一場面,ある感情等々に反応する。しかし,僕は反応することを悪いこととは思わない。それが,ほかならぬ自分自にちがいないのだから。だから,ファウンデーションを整えたり,自分軸を強化したりする化粧が嫌いなのだ。それは,反応する自分を隠そうとする姿勢だ。自分は隠そうとするのに,クライアントにそれに向きあえなどと,どの口が言うのか。むしろ,クライアントに反応する自分を,その場でさらけ出し,僕は,それに反応してしまいました,といえることの方が大事だ。そう口にしたり,さらけ出していることを自覚することで,その自分の振れや揺れは,自分の振り幅(揺れ幅ではない!)になる。自分のキャパシティになる。のりしろになる。
しかし,それを隠した瞬間,自分は縮んでいく。ますます隠す。あるいは逆に自分を大きく見せようとする。黒澤明が『トラトラトラ!』で躓いたように。その歪みはいずれ,自分に返ってくる。
僕は,いま絶えず,凛としていたい,凛とありたいと思っている。思っているだけだから,生きざまにはなってはいない。あまり好きではないが,松蔭が,草莽崛起といった,草莽の心根に近い。草莽とは草茅,草むら,雑草である。しかし心は千古の憂いを懐く慷慨の処士。威武も屈する能わず,貧賤も移すこと能わぬ,士でなくてはならない。ただし士は,二本差しを意味しない。どんなやくざな奴も,だらしないやつも,士道は「胸」にある,でなくてはならない。やたら勇ましい,大言壮語の猪武者が大嫌いである。それは侍ごっこという。勇ましいことを言うやつに限って真っ先に逃げる。どこかの元都知事が典型だ。暴虎憑河し,死して悔いなき者は,吾ともにせざるなり,である。
それは,人に左右されず,揺るがず,立っている。その位置を保ち続けている。
空海の詩に,
一身独り生歿す
電影是れ無常なり
というのがある,しかもなお,そこには,
遮那阿誰が号(な)ぞ
本是れ我が心王なり
と言い切る自負がある。わが身は一人ぼっちで生まれては死んでいく,まさに稲光のように一瞬のうちに,と言いながら,大日如来とは,元はと言えば,自分の心のことだ。ここにある,と言い切れる自負がいい。士道とは,ここにあり,と胸をたたく気概である。
まあ,空海になぞらえるのは,不遜のきわみで,口幅ったいが,
乾坤に独り
凛として
起つ
こんな心境でありたい。そして,そういう生きざまでありたいし,死にざまでありたい,と念じている。
あるいは,杜甫の,
飄然
思いは群れならず
でもいい。
参考文献;
篠原資明『空海と日本思想』(岩波新書)
村上一郎『草莽論』(大和書房)
四方田 犬彦『「七人の侍」と現代』(岩波新書)
「まどか」は,
円か,
とあて,
「古くはマトカとも」
と,辞書(『広辞苑』)にはある。意味は,
まるいさま。まんまるなさま,
満ちたりてやすらかなさま,穏やかなさま,
で,『日葡辞典』には,
マトカナヒト,
という用例があり,円満なさま,円満具足,という意味もあるようだ。
語源は,『古語辞典』には,
「ものの輪郭が真円であるさま。欠けたところなく円いさま」
とあり,『大言海』は,
「全(まったき)と通ずと云ふ」
とする。『語源由来辞典』によると,
円か
あるいは,
団か,
を当て,
「マド(円)+カ(状態)」
で,円満な状態の意,まるい,おだやかという意味,とする。
「円(圓)」という字の,
「員」は,「〇印+鼎」の会意文字で,丸い形の容器を示す,圓は,「囗(かこい)」を加えて,丸い囲い,
で,円形,まるい,欠けた所のない,という意味を持つ。「員」をみると,
「円(圓)の原字」
とあり,転じて,丸い形のもの,また広くものを数える単位に用い,さらに人数をかぞえるようになった,
とある。和語で「まとか」と言っていた言葉の意味と,「円」の意味とを重ねて,「円か」と当てたということだが,その知識と読みの深さには驚く。「団(團)」を当てている場合があるようだが,「団(團)」という字は,
「專」の原字は,円形の石をひもでつるした紡錘の重りを描いた象形文字で,甎や磚(円形の石やかわら)の原字。圓は,「□(かこみ)」を加えて,円形に囲んだ物の意,
で,やはり,まるい,という意味になるが,円形のかたまり,円形に集まったひとかたまりになった人や物,といった意味で,円より,丸いのメタファ色が強い。そのせいか,あまり,まどかに,団かと表記はしないようである。
ところで,「円」というと,通貨の「円」が類推される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
によると,
「『円(圓)』という単位名は中国に由来する。中国では、銀は鋳造せずに塊で秤量貨幣として扱われたが(銀錠)、18世紀頃からスペインと、それ以上にその植民地であったメキシコから銀の鋳造貨幣が流入した(洋銀)。これらはその形から、『銀円』と呼ばれた。後にイギリス香港造幣局は『香港壱圓』と刻印したドル銀貨を発行したのはこの流れからである。『銀円』は、その名と共に日本にも流入し、日本もこれを真似て通貨単位を『円』と改めた。」
とあるが,
http://www.kuniomi.gr.jp/geki/iwai/enyurai.html
によると,
「18世紀頃の中国では、銀塊を中国銀貨としていたんです。この頃は中国にも日本にもメキシコの銀貨が入って来ている時代で、中国ではメキシコ銀貨の円形を指して、『銀円』と呼ぶようになったのです。その後、中国でも円形の銀貨を作るようになったのですが、円の正字である「圓(げん)」は画数が多めなので、同じ読みの「元」を貨幣の総称と決めて「銀元」としたんです。日本は多くのことを大陸(中国など)から倣っていますが、これも倣うことにして、「円」にしたのです。」
とあり,元も円も同源か,と思ったが,しかし,
元は,ゲン(漢音でガン,呉音でゴン)
圓は,エン(漢音,呉音も同じ)
で,漢和辞典で見る限り,わからない。で,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%83
をみると,
「中国語では、貨幣の単位を話し言葉と書き言葉とで使い分ける。『块』は専ら話し言葉で使う単位であり、書き言葉では、『圆』を用いる。紙幣に書かれた文字は当然書き言葉であるから『圆』と表記されている。ただし、『圆』には、発音が同じで『yuán』で画数の少ない『元』をあてるのが日常的な習慣となっている」
とあり,「圆」は,圓(繁体字)であり,円(新字体)とあるから,「圓」が「元」になったというのが,やはり正しい。それにしても,
そのカタチが円い,
ところから,「円」と読んだとは,なかなか面白い。因みに,「元」の字は,
「兀(人体)の上にまるい,印(あたま)を描いた象形文字で,人間の丸い頭のこと。頭は上部の端にあるので,転じて先端,はじめの意となる」
とある。初め,とか,元のもの,という含意を込めて,「元」を当てているというふうに見えなくもない。
参考文献;
簡野道明『字源』(角川書店)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
落語で,『胴乱の幸助』というのをきていて,
胴乱(どうらん)
という言葉に反応した。僕のイメージでは,小さいころ,植物採集の際に,ぶら下げていた記憶があり,それをぶら下げている,というのが,ピンとこなかったのだ。
辞書(『広辞苑』)には,胴乱について,
革または羅紗布などで作った方形の袋。薬,印,たばこ,銭などを入れて腰に下げる。もとは,銃丸を入れる袋だったという。銃卵,筒卵,佩嚢
植物採集に用いる円筒状・長方形の携帯具
菓子「ごまどうらん」の略
とある。「銃卵」「筒卵」については,
「革製の方形をした小袋。古くは筒卵,銃卵とも書いた。語源は定かでないが,《日葡辞書》(1603)に〈火薬や弾丸などを入れるのに用いる皮製の袋〉と記され,《雑兵物語》にも〈胴乱の早合(はやごう)〉とあり,元来は鉄砲の弾丸入れで腰にさげていた。」
とあり,胴乱と同じとわかる。「佩嚢」は,通常「背嚢」と書く。
「軍人・学生などが物品を入れて背に負う方形のカバン。革・ズックなどでつくる」
とあり,どちらかというと,リュックサックと呼んだ方が近い。リュクサックについては,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AF
に,
「ドイツ語本来の発音は『ルックザック (Rucksack)』、オランダ語では『リュッフザック』で、『背中袋』の意味である。英語にも『ラックサック
(rucksack)』という語があるが、登山の専門用語であり、一般には通じにくい。英語の『バックパック』や日本語の『背嚢』は、いずれもドイツ語のなぞりである。
日本語が『ルック』でなく『リュック』であるのは標準ドイツ語で背中を『Rücken』(リュッケン)と言うことに影響されたものである。日本語で単にザックと呼ぶこともあるが、ドイツ語の『ザック
(Sack)』は単に『袋』という意味であり、文脈上明らかな場合を除き、リュックサックの意味では使わない。」
とあり,要は,リュックサックの直訳が背嚢,つまりは軍事用語から来ている。しかし,胴乱に較べると,少し大きすぎる。
「薬や印などを入れて腰に下げる長方形の袋。江戸時代初期に鉄砲の弾丸入れとして用いられたのが始り」
との記述があるが,少し間違っているかもしれない。
本来は,「早合」は「早盒(はやごう)」と書き,火縄銃の改良に起因している。
火縄銃は,まず銃の筒先から,火薬を詰めて突き固め,それから弾丸をいれて火薬に接するように突き固める。それから火皿に口火薬を入れて蓋をし,火縄挟みを上げて火縄を装着し,火蓋を開いて据銃してねらいを定め,,引鉄を引いて発射する。一発目は用意しているからいいが,二発目以降はこれを繰り返す。このため,火縄銃には,銃の他,
火縄,
火薬及び火薬入
口火薬入
玉及び烏口(玉入れ)
が必要になる。
銃の装填操作を短縮するためにできたのが,原始的薬莢の,「早盒」である。胴乱は,早盒入れなのである。
早盒は,
「木を刳りぬいて銃の口径に合わせた筒や竹筒にあらかじめ火薬と玉を詰めたもの」
で,それを銃口にあててカルカ(弾薬を筒口から押し込むための鉄の棒)で突き,火薬と玉を一度に詰め込める。この普及で,火薬入,玉入が要らなくなり,胴乱を肩から吊ったりした。
http://www.pref.nagasaki.jp/bunkadb/index.php/view/304
を見ると,この早盒,明治初めごろ,捕鯨銃に生きていたようだ。
ところで,『胴乱の幸助』のは,腰に下げて,お金も入れていたようだから,いまで言うと,
ウエストバック
か
ヒップバック,
か
ウエストポーチ
ということになる。要は,腰カバンとして使っていたのだろう。その意味では,印籠の大きい奴,といったイメージか。
『胴乱の幸助』は上方落語の演目のひとつ。
http://homepage2.nifty.com/8tagarasu/dourannkousuke.html
にあるように,
「阿波の徳島から出てきて、一代で身代を築いた働き者の割り木屋の親父の幸助さん。いつも腰にどうらんをぶらさげて歩いている。喧嘩の仲裁をするのが道楽で、喧嘩なら子供の喧嘩、犬の喧嘩でも割って入るという。往来で喧嘩を見つけると中に割って入り、必ず近くの料理屋で説教し仲直りさせご馳走するのを楽しんでいる。」
で,浄瑠璃「桂川連理柵」(かつらがわれんりのしがらみ)お半長右衛門帯屋の段の嫁いじめの所を稽古している声を聞きつけ,喧嘩と勘違いして,仲裁しようとし,無趣味で浄瑠璃も「お半長」(心中するお半長右衛門を略して)も知らず,実話と勘違いして,京都と聞いて,三十石船に乗って京都へ出かける。柳の馬場押小路虎石町の呉服屋に入って,仲裁しようと,お半と長右衛門をここへ出せと迫ると,
番頭 「お半も、長右衛門もとうの昔に桂川で心中しました」
幸助 「え、死んだか、汽車で来たらよかった」
という下げである。
それにしても,こういうタイトルはよくあるが,胴乱は本題とは何の関係もない。
参考文献;
笠間良彦『日本合戦武具辞典』(柏書房)
内省は,左脳がする。左脳は意味づけたり,物語を創ったりするのが得意である。しかしそれは大概,自分への批判である。正直,右脳・左脳と区別するのは好きではないが,あくまで脳内の対立軸(自己対話相手)のアナロジーとみなして以下,考えてみる。
僕は18歳で上京して以来,初めての一人暮らしということもあって,自己対話のつもりで,日記をはじめ,以来30数年毎日,日々の感想,意見,読後感,読んだ本からの抜書きを続けていた。それは文章の訓練のつもりでもあった。感情の表現,意見の表現,おのれの思いの文章化を通して,どういう表現スタイルを創っていくかが,底流の動機でもあった。しかし,文学への志を捨てて,しばらくしたある時,疑問に思った。日記で内省し,自己批判し,反省することに何の意味があるのか。書くこと自体,内省すること自体が目的化していた。
そこで,一切思いを文章化するのをやめた。数年後,何十冊もあったB5版の日記もすべて破棄した。
左脳というか自分を批判する視点(自己批判杉浦A)は,そのまま,ありのまま,そのとき,その場所の自分を超えた「自分」のありようを認めない。いまそこで何をするか,その時何ができなかったか,そこで為すべきことは果たせたのか,と時間と場所を限定して,責める。そこでは,ずっといる「自分」を見るのではなく,その振る舞いの成否,可否,是非のみを見る。その判断基準は,僕のではなく,自分を批判する視点(自己批判杉浦A)のものだ。
マイケル・ガザニガは,左脳は,我々の行動を正当化する理屈を即座に創り上げる解説者である。意味を瞬時に創り上げる。だから,ある詩人曰く。「自己内省は忌むべきである。それはこれまでの混乱を一層ひどくする」と。なぜなら,責め立てるのは,左脳だからである。
自身が38歳で脳卒中で倒れ,左脳の機能を失いつつ,そこから回復した経験をもつ脳科学者J・B・テイラーは,「する」(doing)機能の脳(左脳)を「ある」(being)機能の脳(右脳)より重視する傾向にある,という。しかし,
右脳はとにかく,現在の瞬間の豊かさしか気にしません。それは,人生と,自分に関わる全ての人たち,そしてあらゆることへの感謝の気持ちでいっぱい。右脳は満ち足りて情け深く,慈しみ深い上,いつまでも楽天的。右脳の人格にとっては,良い・悪い,正しい・間違いといった判断はない。
それを右脳マインド彼女は呼び,
冒険好きで,豊かさを喜び,とても社交的。言葉のないコミュニケーションに敏感で,感情移入し,感情を正確に読み取ります。宇宙とひとつになる永遠の流れを気持ちよく受け入れます。それは聖なる心,智者,賢人,そして観察者の居場所なのです。直観と高度な意識の源泉です。右脳マインドは常にその時を生きていて,時間を見失います。
しかしわれわれは,左脳で決断し,右脳へ踏み込もうとしない。
もちろん左脳は,ないがしろにしていいはずはない。彼女は言う。
わたしはたしかに,右脳マインドが生命を包みこむ際の態度,柔軟さ,熱意が大好きですが,左脳マインドも実は驚きに満ちていることを知っています。なにしろわたしは,10年に近い歳月をかけて,左脳の性格を回復させようと努力したのですから。左脳の仕事は,右脳がもっている全エネルギーを受け取り,右脳がもっている現在の全情報を受け取り,右脳が感じているすばらしい可能性のすべてを受け取る責任を担い,それを実行可能な形にすること。
左脳マインドは,外の世界と意思を通じ合うための道具。ちょうど右脳マインドがイメージのコラージュで考えるように,左脳マインドは言語で考えてわたしに話しかける。左脳の言語中枢の「わたしである」ことを示す能力によって,わたしたちは永遠の流れから切り離された,ひとつの独立した存在になります。
問題なのは,左脳が物語を創り上げてしまうことだ,と彼女は言う。その物語がドラマやトラウマを引き起こす。特に,身体か疲れていたり,精神的に参った状態にあるとき,否定的な思考回路が傷つけようと頭をもたげる。そのとき,
脳が言っていることに注意し,その考えが身体のどのような感覚をもたらすかに気づけば,自分が本当は何を考えたり感じたりしたいのか,意のままに選べるようになります。
その根拠を,彼女はこう説明する。
わたしは,反応能力を,「感覚系を通って入ってくるあらゆる刺激に対してどう反応するかを選ぶ能力」と定義します。自発的に引き起こされる(感情を司る)大脳辺縁系のプログラムが存在しますが,このプログラムの一つが誘発されて,化学物質が体内に満ちわたり,そして血液からその痕跡が消えるまで,すべてが90秒以内に終わります。
通常無意識で反応しているのを意識的に,90秒を目安に,自分で選択できるということです。例えば,90秒過ぎても怒りが続いていたとしたら,それはそれが機能するよう自分数が選択し続けているだけのことだ,というわけです。
90秒たったら,切り替えられる。そういう選択ができる,という。それを選ぶかどうかだ,というわけだ。
だから,内省というのは,左脳に主導権を握らせ,自分の右脳の平安を騒がせるだけなのだ,ということになる。騒ぎ立てている感情を,反復し,さらに波立てているだけなのだ。彼女は自分の脳卒中からの発見をこう言い切った。
「頭の中でほんの一歩踏み出せば,そこには心の平和がある。そこに近づくためには,いつも人を支配している左脳の声を黙らせるだけでいい」と。
自分を批判する声,怒りや悲しみ,あるいは嫉妬は,90秒でその化学的根拠を失う。そこで,捨てることを意識すれば,捨てられる。内省で,二度とかえらない過去を振り返るよりは,これから得られる自分の未来を思い描く方が建設的だ。それが自分のいつも押さえつけている右脳的機能の発揮させる機会なのだ,とテイラーはいう。
僕自身は日記をやめてから,悩みや鬱屈を長く引きずらなくなった。鬱屈を表面化することで,それを形として固定してしまう懸念がある。内省は,無駄なエネルギーだ。内省し続けて得たものより,内省をやめて,得たものの方が多い。
内省は平板な,並列な批判・反批判。あるいは集中砲火のいわゆる総括。しかし多くの内省は同心円の,堂々巡り,その思考の積み重ねの矢印を,どう生きるのか,実現したい夢は何か,今やろうとしていることの自分の意味は何か等々,なんでもいいが,外へ向けた瞬間,結果として,時間軸が伸び,空間が広がり,3D,4Dになっていく。そういった思想や思考を練り上げていく方にエネルギーを使う方が,未来に役に立つ。
もしどうしても,自分を振り返りたいなら,人と話すか,人からのフィードバックをもらう方がいい。例えば,コーチングはそれに役に立つだろう。堂々巡りには決してならない。
だから,僕は過去を振り返らない。一時間前も,昨日も,10年前も,もう取り返せないことに代わりはない。では明日どうするのか,を考える方がはるかに楽しく,建設的だ。
参考文献;
ジル・ボルト・テイラー『奇跡の脳』(新潮文庫)
デヴィッド・G・マイヤーズ『直観を科学する』(麗澤大学出版会)
「赤ちゃん~脳の成長の神秘」(NHKの再放送)の中で,こんなセリフがあった。
返事をしないからと言って,
赤ちゃんの中で何事も起きていない
と考えるのは間違っている(パトリシア・クール ワシントン大学教授)
耳の背後の言語野が活性化するという。言葉が変わると,それにも反応する。ならば,大人の場合の沈黙は,脳内活性化度は,赤ん坊の比ではあるまい。
コミュニケーションは自分の伝えたことではなく,相手に伝わったことが,伝えたことである,ということをよくいう。その意味では,言葉によるコミュニケーションだけではない,相手に伝わったことが,こちらが意図しようがしまいが,伝えてしまったことなのだ。あるいはこういう言い方もできる。僕のしゃべったことがどう伝わったかは,相手が何を返すかでわかる,と。
たとえば,
黙っていても
考えているのだ
俺が物言わぬからといって
壁と間違えるな(壺井繁治)
という詩から,相手が,黙っている壺井をシカとしたのだとも受け取れるが,ふてくされていると無視されたともいえる。そのメッセージを正確に受け止めているとは限らない。しかし,黙るということには,ひとつのメッセージが込められている。
沈黙には,文脈がある。
たとえば,
先生 どうして何も言わないんだ。
生徒 (無言)
先生 黙ったままでは,わからん。いったい何を考えているんだ。
生徒 (やはり無言)
という会話で,生徒は一見何も伝えていないように見えるが,この沈黙をどうとらえるか,だ。
吉川悟先生は,こう書いている。
たしかに,生徒は表面的に何も伝えていないのですから,従来の考え方では「コミュニケーションが成立していない」と考えがちです。こうした≪ものの見方≫は,会話の中にある言葉によって伝わる情報だけに目を向けているといえます。
しかし,別の面からも考えられるはずです。それは,「生徒が無言でいるという行動がコミュニケーションの一形態である」と考えることです。つまり,生徒が何もしないという行動は,先生から見れば生徒からのメッセージとして伝わるということです。生徒は「何もしていない」のではなく,返事をすべき時にはっきりと「無言でいる」という行動をとっているのです。この「無言でいる」という行動は,「返事をしない」という意志伝達の意味があると考えられます。つまり,無言で何も話さないという行動であっても,それが会話の前後関係によって異なる意味を持つと考えるのです。
情報には,コード化できるコード情報と,コードでは表しにくい,その雰囲気,身ぶり,態度,薫り,ニュアンス等々より複雑に装飾された情報である,モード情報があると言われている。
つまり,文脈によって言葉の意味はがらりと変わる。たとえば上記の例でいえば,死にたいと言って泣いていた生徒との会話とするか,万引きして問い詰められてふてくされている生徒との会話とするかで,ニュアンスはがらりと変わる。
吉川先生は,
コミュニケーションの前後関係や流れの違いによって伝達される情報は,会話の前後関係・脈絡・場面の状況などから伝えられている情報を含むものであり,表面に表れない意味が含まれています。この考えにしたがえば,(中略)コそのミュニケーションの文脈(前後関係・脈絡・場面の状況など)に関する情報を把握するためには,出来る限りコミュニケーションの全体の流れを理解しなければならないのです。
として,コミュニケーションによって伝達される意味の種類を,僕なりにまとめて,整理すると,こうなる。
①コミュニケーションに用いられているすでに共有されているという前提に立った単語で伝えていることの意味。ただこの場合も意味レベルでは一致しても,そこに描いているイメージが人それぞれのエピソード記憶によって,異なっていて,そこでずれを生ずることはあり得る。犬といっても,マルチーズなのか,シェパードなのか。
②コミュニケーションに用いられている単語の並び方,文法的な規則によって,生まれる意味。平田オリザが言うように,「その,竿,立てろ」というのと,「竿,竿,竿,その竿立てて」というのと,「立てて,立てて,その竿」というので,ニュアンスが違う。
③コミュニケーションによって用いられている文同士のつながりによって生まれる意味。結論を先に出して,経過を説明するのと,経過説明して,結論を言うのと,伝わり方が違うだろう。判決文で,主文を最後にするのと,最初にするのを使い分けているのは,裁判官の意図を伝えようとしているからだ。
④身ぶりや表情など,非言語レベルで伝えられる意味。言葉は明るくても,表情や手が別のことを伝えていることはある。
⑤コミュニケーションを行っている人の声の強弱やトーン,特殊なニュアンスなどによって伝えられる意味。ひそひそ声になることで,それ自体で秘密を伝えようとしていることが,伝わる。メラビアンの法則の言うとおり目に見えているものの,伝達力の方が強い。
⑥その場の状況や会話の前後関係など,文脈によって規定されている意味。会議で順番に発言させられるのと,手を挙げるのとでは意味が変わる。
文脈抜きの情報の危険性は,日々の新聞報道でも,ネット情報でも,いやというほど思い知らされている。情報の裏を取るとは,ある意味で,その具体的な場面について,確かめることを含んでいる。
コーチングでも同じで,文脈を共有できているかどうかは,絶えず確認し続けなくてはいけない気がする。なぜなら,文脈は,言葉出来なく,言葉の背景にあるエピソード記憶(自伝的記憶に重なる)に依存しており,言葉に張り付くモード情報だから,体験を共有していないと,ニュアンスが伝わりにくいからだ。
参考文献;
吉川悟『家族療法―システムズアプローチの「ものの見方」』(ミネルヴァ書房)
金子郁容『ネットワーキングへの招待』(中公新書)
平田オリザ『わかりあえないことから』(講談社現代新書)
子曰く,これを知る者はこれを好む者に如かず,これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。
知る者よりも,好む者よりも,楽しむ者というのは,実感としてよくわかる。どんな博学も,所詮外的知識で,それを自分のものとしているとは言えない。好学もまた,外にあるものを取り入れているだけだ。楽しむ者だけが,それを自分のものとして,一体になって,体現している。
どうも僕はこの楽しむが苦手だ。まず,(人でもものでも本でも)相手と会うと,相手との距離をはかる。そして相手の枠組みを知ろうとする。そのとき自分との親疎の価値をはかっている。だから食わず嫌いというのが多い。それが「やりたくない」ことにチャレンジする気になった原因の一つかもしれない。しかし,好むに変わると,いっぺんに距離を消して相手の土俵に乗ってしまう。一も二もなく,相手を全面是認に変わる。別におのれを消しているわけではないので,相手の土俵に乗っている妄想に近いから,自分の土俵を拡大しているのだともいえる。いわば,いずれも独り相撲。この極端な距離感覚が,ずっと自分を悩ませてきた。楽しむは,彼我の対立や対峙を消さなくてはできない。それは,まず自分をその場に溶け込ませなくてはできない。主役が場になる。その時になる。そういう開放性が苦手であった。
しかし今,その時,その場で自分をどれだけ開放し,解放できるかを,自分でチャレンジさせようとしている。楽しむ,というところまでは行けていないかもしれない。しかしおのれにこだわり,おのれの立ち位置にこだわり,相手との距離にこだわり,おのれの見かけや外見への執着を手放そうとしている。
ところでCTI系では,傾聴には二側面があるとして,
①注意を払う 感覚を通して受け取ったものへの気づき。コーチが受け取っているすべての情報に対して注意を傾ける。息遣い,話し方のペース,声の調子等々。
②インパクトに気づく 傾聴したことへの対処。コーチの対処がクライアントに影響を与える。
それを,次の3レベルに分けている。
①レベル1・内的傾聴 意識の矛先が自分に向いている。自分の考えや意見・判断,感情,身体感覚に意識が向いている。
②レベル2・集中的傾聴 意識はクライアントに向いており,全ての注意がクライアントに注がれている。相手の発するすべての言葉に一心に耳を傾け,声の調子,ペース,ニュアンスを逃さず聴こうとしている。
③レベル3・全方位的傾聴 一つのことに焦点を当てるのではなく,周囲に広く意識を向けている状態。自分と周囲のエネルギーに気づく。そのエネルギーの変化に敏感になる。
しかし,このくそまじめなコーチングは,卒業すべきだと感じている。コーチングでコーチがリラックスして,その場そのものを楽しんでいたら,その感覚は全開になり,全てに広く関心が向くはずだ。
遊びに夢中になっている時,遊びの世界の外には関心が向かないけれども,遊びの世界の中で起きていることには,敏感で,感覚が研ぎ澄まされている。それと同じだ。その時,場そのものと一体になっている。
これを知る者はこれを好む者に如かず,これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。
をあえてこれに当てはめてみる,とどうなるか。
知るというのは,レベル1,好むというのはレベル2,楽しむというのは,レベル3,と置き換えてみることができる。
知るとは,自分の知的好奇心に基づく対象化だ。内部の問題意識,関心から相手を見ている。しかし好むというのは,相手との距離を埋めるため,相手に接近していく。自分を離れて,相手そのものに寄り添う。好きになるとはそういうことだ。だから,焦点は相手にあっている。楽しむというのは,自我や我執が消える。あるいは自分をかなぐり捨てる。そこでは,彼我の差が消え,彼我一体のその場そのものになって,全体に浮遊する。あるいは場そのもの,空気そのものになって,相手と共に,一緒になってわくわくする。あるいは風のように自在な眼になっている。
その時,コーチはいない。コーチングそのものになっているというと言いすぎだが,リアル世界の何某というコーチではない。そこに我執も,経験も,知識も,価値も,置き去りにされている。在るのは,クライアントの様々な自己を,開示し,展開し,たとえば絵巻物か,無限に折りたたまれた手紙のように,次々と延ばされ,広げられていく世界に,一緒になってついていく。
それは,過去であるより,未来であることの方が楽しいだろう。まだ来ていないが,きっと来るだろう未来,いやこうすれば来るだろうとはかっている未来を,白紙の巻物の中に,描き出していく。
楽しむには,こだわりや拘泥や足枷や執着や是非や可否を一切合財手放さなくてはならない。楽しさは自分の開放なのだし,解放なのだから。そして結果の予想もないし,どこへ行くかもわからない。目標や,できるできないや,アクションプランも捨てなくてはならない。大体,アクションプランの立つようなことが,コーチングの対象になること自体,コーチングへの侮辱である。そんなものは,目標達成計画書を書くように,自分で描けることだ。
かつてある大きな装置産業で仕事をさせていただいたとき,担当者は,「うちの社員はやる気がない,昨日本社の健康管理室の人が話しをしにきてくれたが,あまりの態度の悪さに怒って帰ってしまった」というのである。何で外部の人間にそんなこと言うのかも変だが,「やる気がない」と決め付けられたものは,もっとやるせないに違いない。
確かに,言われる通り,態度はよろしくない,しかし,一応聞いてはいる。そこで,ちょっといつもとより早く,「自分のやっていること振り返って,自分にキャッチフレーズつけてみよう」といった。
オーソドックスな旗の意味と手順は,
である。
やり方は簡単なのにした。ただ自分のやっている仕事を洗い出して,それにキャッチフレーズをつけるだけ。でもけっこう面白がって,こんなのありかと聞いてくる。詳しいことは忘れたが,「番長」とか「囃子役」というのがあったと思う。なかなかかわいいものだ。
これは,改めて自分の誇りに名づけ,ラベルつける作業なのだ。
そして,ふと思った。自分の仕事に誇りもつ機会など与えられていないのだ。ただ日々,やらなくてはならないことに追いまくられ,それが出来るか出来ないかしか問われない。それをやることの意味やそれを自分がすることの意味は考える機会もない。一体何が自分にしか出来ないことなのか,自分だから出来ることなのか,立ち止まる機会もない。
いや,多分機会は一杯あるし,キャリアについて考える場も与えられている。しかし生身の誰それに引き寄せた,自分の誇りを考える機会とは受け止められなかったのかもしれない。なぜなら,出来ることリストをいかに早く積み上げるかに関心を向けざるえない,強いプレッシャーがあったに違いない。
大体,やる気という言葉のイメージは,一般には,「何にでもばりばりやる」「積極的に何でも取り組む」「困難なことでも根気よくやり遂げる」「何にでも進取の気持がある」のようだが,ある調査では,「静かに熟考する」「納得しないことはやらない」「感受性が強い」「生き生きしている」「仕事を楽しんでいる」「何かを達成しようとする意志が強い」「ユーモアがある」「心に余裕がある」「人中では目立たない」「やさしい配慮がある」と,それぞれのキャラや個性によってかなり幅広いのだ。
だから,やる気があるとかないとかということ,たとえば親や会社の上司がいうときは,自分のイメージに基づいていっている恐れがある。そのとき,どういう期待をしているかによっては,それ自体が本人のやる気殺ぐことだってありうる。たとえば,
「バリバリ動き回る」とか「根性がない」といった肉体的な表現,「あんまり会議でも発言しない」「自分の主張がない」「チャレンジする気持がない」「言われたことしかしない」「高めの目標を与えてもそれをクリアしようと努力しない」「すぐできません,わかりませんと音を上げる」「自分でとことん考えようとしない」「仕事を掘り下げようとしない」「仕事の幅が狭く,積極的に努力したり勉強したりしない」等々。前出の多様なやる気とのギャップは大きい。
それなら,それぞれのやる気を表現してもらう,それぞれがやる気のある状態になっているとどなっているのかを語ってもらうほうが,手っ取り早い。それを仕事上の役割や立場にひも付けするのは上司の役割なのだ。
自分の仕事に旗を立てるいうことについては,ふれたことがある。
仕事というのは,自己表現なので,そこに自己が表現される。いやいや仕事をやらされている自己はそういう仕事しかできない。迂闊な自己は迂闊な仕事をする。他責にする自己は他責の仕事しかしない。所詮,全て自己が表出される。自己が対象化される。外在化される。
自分の旗を持たず仕事をしている人は,自分の目的を持たないで働いている人だ。それは,たぶん組織やチームの目的を自分のそれと勘違いしている人だ。自分のいる意味と組織にとっての意味は違う。そういう時,チームや組織のそれを失うと,自分の人生の意味まで一緒に失う。旗こそ,自分の目的だ。
その自己のいる意味づけ,何をするためにそこにいるかの旗印が,どう人に働きかけ,巻き込むかのリーダーシップの質を決める。リーダーシップとは,いわば,自分の実現したい夢や目的のために周りの人を動かすことだ,特に上位のものを動かすことだ(上位を動かせなければ基本的にリーダーシップは機能しない,というかそんなものはリーダーシップごっこだと思っている)。その時,自分の旗が,その大義名分になる。名分もなく,人に助力を求めるものは,単なる甘ったれで,たぶん,その人に助力を求めた時も好き嫌いか,虫の居所で是非を決める人だ。そういう人は避けるに如くはない。
ところで,旗印あるいは,旗指物というのは,永禄から大阪の陣くらいまで大盛況だった。以降下火になる。以前は,源氏が白旗,平家が赤旗と,私の旗幟を許されなかったが,戦国時代に入ると,盛んになり,関ヶ原がピークという。自分を売り出し,自分を際立たせるのに,旗印は,恰好で,紋所から奇想天外な絵柄まで様々個性を競った。
しかし,ひとかどの武将でなくてはおのれの指物を許されず,番指物といって,一隊一隊の相じるしに,その形,色を一様にするものしか使えない。比類なき働きのものにのみ番指物の代わりに,自分の指物を許される。加藤清正が秀吉に指物ご免を願ったところ,「なんじまだ前髪の身分なのに,歴々の将をさしおいて指物を願うとは粗忽の至り」と相手にしない。そこで,勝手に陣幕で作ったらしい。
指物がないのは,これといって武功のない端武者とみられる。
武将にとっては,自分の存在を高らかに敵味方に示す目印であり,敵にとっては標的であり,味方にとってはライバルだ。しかし同時に,その旗印に何を持ってくるかが,自分という侍の出自であり,自分の侍として目指すべきものであり,自分のよって立つところを明示する。まあ,けれんみたっぷりでいいし,見えやはったりもいい。どうせすぐ化けの皮ははがれる。
有名なのは,謙信の「白地に黒の文字で昆の一字」の四半,石田三成の「大吉大一大万」は後世の捏造と言われるがなかなか面白い,信玄は,「其疾如風 其徐如林 侵掠如火 不動如山」が有名,家康の「厭離穢土 欣求浄土」は,若いころ部下も含めた一向門徒と闘った記憶にもとづく,秀吉は瓢箪に金のきりさき,黄金である。法華信者の加藤清正は,南無妙法蓮華経,キリシタンの小西行長は「紙袋に朱の丸」をつけた旗で日の丸の意だったらしい等々。
人生という戦場において,自分がどんな旗を掲げるのか。いやそもそもそんなこと自体を普通の人は考えない。しかし,仕事で自分の旗を掲げる以上に,自分という存在を明確な印として,はためかすことほど重要なことはない,と信じている。
その時の考え方は,自分について,
自分のリソース
自分の夢
自分の使命(天命でもいい)
で考える。やりたいこととできることとやらなくてはならないことのもじりだ。
ここでいう天命とは,別に神に示されたものではない。運命でもない,キリスト教徒の言うミッションでもない。あえて言えば,天運,寿命といっていい。
死生,命あり,富貴,天にあり
の「天」だ。そこに勝手の思い入れを入れるのは自由だが,それは,人の「はからい」に過ぎず,天は関知しない。天とおのれの資源と夢とを考え併せて,
おのれは何をするために,ここに居るのか,
を自分なりに答えを出す。それが人が,この世に生きる意味だ。意味は,人から与えられるのでもなく,天から与えられるのでもない。ましてや神が与えるものではない。あるいは天は,道は示すが,それを歩くかどうか,どう歩くかを決めるのは自分自身だ。
それが,フランクルの言う,自分の人生にどう応えるか,ということのもう一つの答え方だ。
そして,「人のおのれを知らざるを患(うれ)えず,人を知らざるを患(うれ)うる」とき,
敬して失う無く,人と与(まじ)わるに恭しくして礼有らば,四海の内,皆兄弟也
という。つまりは自己完結して,孤をかこつことがなければ,おのれのリソースは必ず開花する場がある。そういう人と出会う。それなら,おのれの旗印をいつも掲げていなくてはならない。
それで思い出したが,自分が髭・鬚をはやしたのは,独立した時で,世話になった先輩がはやしたのをまねたが,汚らしかった(失礼!)ので,きれいにしようとだけは思った。それは,自分なりの矜持を示したつもりだった。以来ずっと目印になっている。
もちろん,旗は見えなくてもいい。心に掲げているだけでいい。
参考文献:
高橋賢一『旗指物』(人物往来社)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)
自分を表現するということは,自分の中にあるものを表出するという個人に自己完結したものもあるが,そうではないものもある気がしてならない。
元来,文学青年であった自分にとっては,自分の内面の外在化という,個人としての自己表現こそがすべてであった。そのために,どう言語化するか,については悪戦苦闘もしたし,好きな古井由吉の『杳子』等々をほぼ全文を書き写して,その文章のリズムと生理を体得しようとしたこともあった。「風はとつぜん生理のようにおちていった」という「固有時との対話」の一節が,いつも頭をよぎっていたものだ。あるいは,Ô
saisons ô châteaux,おお、季節よ、城よ,も頭をよぎる,そうしてフレーズが蓄積していく。
結局,いつの間にか,自分の文章のリズムはできた,というかどう工夫してもその先行かない,自分の書き方が固まってしまった。ま,日常的に文章にするのを業にしてしまったせいで,書き上げなくてはならないから,とにかくまとめきってしまおうとする。そうすると,表現の工夫は遠のいた。
流儀は,ロジカルではなく,噴出するように描き切ってしまう。書き方も,アバウトな全体が見えると,部分を書き連ね,最後に一気に流れに変える。しかし,ついに生理としての文体は自分のものになっていない。
それは,何と言おう,自分のありようと一体化した文章,呼吸するように,息遣いがそのまま文章になって起伏していく文章がそうなのだろうとは,あては衝く。しかしそれを自分のものにするのとはちょっと違う。
しかしここで言いたいのは,文章論ではない。それだけが自己表現ではない。そんな当たり前のことに,最近気づいた。いまある方と,セミナーになるか,ワークショップになるかわからないが,一緒に何かをやろうということで,いろんな話をする機会がある。それは生き方の話であったり,コーチングの話であったり,夢であったり,コーチのあり方についてであったりする。
そんな中で,ふと気づいたのだが,僕はセミナー講師をしたり,研修講師をしたりするが,自分でそれを企画して売り込んだことが一度もない。元来が怠け者で無精だから,せいぜいホームページを98購入と同時にでっち上げたくらいだ。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/
初めに,プログラム集のような冊子に企画をでっち上げたが,その時も,特に売り込む意識があったわけではない。だから,人をどう集めるとか,どうやったら人の関心を呼ぶのかとかに,強い意識がなく,自分の言いたいこと,手渡したいスキルは何か,そういう自分のコンテンツの表現に意識向きがち。だから,テキストは,膨大に厚い。基本的にプロジェクターを使わず,パワポも使わない。
つまり自己完結した自己表現の延長線上にずっといる,ということなのだ。
しかし,別の自己表現がある,という当たり前のことに気づいた。つまり,自分を素材にする,ということだ。自分は,自分の表現ではなく,人の表現の素材になる,という自己表現の仕方である。
自分のコンテンツを表現するのではなく,そこにいる相手とともに表現する。例えば,
相手を語ることで自分を表現する
相手に語られることで自分を表現する
相手と語り合うことで自分を表現する
相手と共にいることで自分を表現する
相手と共に何かをすることで自分を表現する
相手と共にいるだけで自分を表現する
相手との関係性そのもので自分を表現する
そのとき,表現は自己完結していない。その時,表現は,
その場そのもの
その雰囲気そのもの
その空気そのもの
その空間そのもの
その関係性そのもの
そのフィールドそのもの
その磁場そのもの
が自分を表現している。その時,自己は,そこで表現しようとするものの要因というか要素というものになっている。表現の自己完結性が崩れている。ここらに,いま表現としての新しい意味を自分として発掘,発見,創造しようとしている気になっている。そこでは,
自分の個を生かす場である,
と同時に,
自分の個が,そこに融解していく場である,
と同時に,
別の個が,そこで現実化する場でもある。
あるいは,その場そのものの中で化学変化を起こしていく。そのプロセスそのものが自己表現と置き換えてもいい。
そういう止揚の場,そういう変質の場,そういう昇華の場でありたいと思っている。いままでのコンテンツは,そこで脱皮するに違いない。その脱皮自体もまた新たな自己表現になる。
夢についてあまりに楽天的に語る人にも,思考は現実化すると,手放しで喜ぶ人にも,僕はちょっとだけ身を引く。夢をかなえた人は何人いるのか,努力の問題ではない。人一倍努力しょうと届かぬ夢はある。でなければ夢ではない。
ある映画で,タイトルは忘れたが,35歳で,入団テストにチャレンジし,150キロ超えのスピードを出して,メジャー再デビューした男の物語だった。その男が,ある人に是非を尋ねに行く。その人曰く。
自分の夢を持つのはいいが,
それは,
自分がやるべきことを見つけるまでだ。
やるべきことを,目の前のタスクや課題や生活のための問題処理ととらえるか,天命ととらえるかで意味が変わる。映画の男は,「それを俺に聞くのか?」と反問しつつ,そう言ったのだ。その意味は,その夢は,やるべきことを放り出すに値するのか?と問いかけている。
夢は,実はいまの現状とかけ離れているものとは限らない。いま実現していることで,近似に達成できていることがある。それに自分で気づいていない。
もともと夢は,金剛般若経に,一切の有為法は,夢・幻・泡・影の如く,露の如く,また,電の如し,というように泡や露と対比される,はかないものだ。
秀吉の有名な辞世,「露と落ち 露と消えにし わが身かな
浪速のことも夢のまた夢」でいう夢も,一瞬間の幻の意味だ。よく夢幻という意味で使う。夢の持っている,はかなさ,幻さのニュアンスが昨今ひどく弱くなり,実現させたい願いのほうシフトしている。それだけ,為せば為せる環境が整っているということもあるが,夢が過大評価されすぎているせいかもしれない。
夢を実現できるかどうかは,それを目標化することだという御説がある。それは間違いだ,所詮目標化できるような夢なら,ただ行動目標を立てるだけで実現できる。大金持ちになりたい→10億円→…これは,可否かどうかは別に実現できる。これは夢ではないからだ。
そんな程度のしょぼいものを夢と言われては困る。コーチになりたい,カウンセラーになりたい等々も同様だ。誰でも資格を取れば,まあなれる。夢はその先にある。何をしようとしているのか,ほかならぬ,自分がそれになることの意味と価値は何か。
たぶんそう簡単ではない。成りたいものになる。それは簡単だ。総理大臣だって,今どきの値打ちの下がった総理大臣なら,大概そのための筋道は見える。
こういうのは夢とは言わない。少なくとも,僕の中では,夢ではない。問題は,なった後なのだ。その先に何もないなら,それは単なる野心や野望の近似値に過ぎない。
夢とは,今までないものだ。自分の出番ではじめて世の中に存在する類のものだ。私というコーチという存在ではない。私というコーチが何を実現するのか,でもない。人の夢をサポートするなどというのは,夢ではない。単なる実現可能な役割,というよりコーチ一般の役割そのものではないか。そんなものを夢とは呼ばない。
人の後追いではない,二番煎じでもない,この世にまだないものだ。それは自分の思いを言語化してみることでしか見えてこない。言葉にした時,自分を,自分の思いをメタ化する。その言葉が,自分の思いとの微妙な差に気づき,より近いものへと導いてくれる。
実現できる夢もどきはさっさと達成され,実現されぬ真正の夢は,はるかな遠い頂に見える。以前にも引用したが,中島みゆきの「ヘッドライト・テールライト」にある。
行先を照らすのは
まだ咲かぬ
見果てぬ夢
はるかうしろを
照らすのは
あどけない夢
照らし出されている先には,まだカタチはない。なぜなら誰も実現していないのだから,後方にある夢も,まだカタチはない,まだ淡い思いだけだから。
ある人から,相談を受けた。自分の契約を継続せず,前から望んでいたある職場の面接を受け,内諾を得たのだという。しかし,契約更新をしないとの意思表示が,契約書にある一か月前を過ぎていたため,それを楯に,後任者がきちんと仕事をできるまで留まって,ちゃんと引き継げ,それをするのが常識ある社会人だ,と脅してくる,という。
法的なことは,僕が知人に聞いて,確かめたのだが,いざ経営陣と面と向かうと,本人は,弱腰になるのか,出来る限り遺漏のないようにすると誓約書を書かされてしまった。たぶん,一人で数人の経営陣に囲まれればそうなる。またそういう状況で書いたものは,争えば,効力がないことを確定するのはそう難しくもないし,知人に頼んで,強力な弁護士も立てられるだろう。
しかし問題は,法律問題ではなく,心の問題だ。心の弱気だ。相手はそんな慮りはないのに,相手への善意や好意を勝手に受け止めて,相手に悪いので,とか,後足で砂をかけられないとか,どうでもいい心配り,気配りをしてしまう。いまそんなことが問題ではない。自分がやりたいことがやれるかどうかの瀬戸際なのに,だ。
よく日本人はおもてなしの心がある,なとどとつまらぬことを言う人がいるが,そういう人はこういう修羅場にあったことのない人だ。時に,経営者は平気で人の人権を踏みにじる,上司も平気で部下の人生をぶち壊す。そのことを非難する気はない,そういう立場になれば,人は非情になりうるし,ならなければ,自分自身が生きのびられないだけだ。もちろんそうでない選択肢を取ることはできるが,それはそれで別の修羅場になる。
だから,僕に言わせれば,おもてなしとは,上から目線なのだ。お情け,ないし温情目線と言い換えてもいい。あるいはゆとりと余裕のあるときの,特殊にしつられたシチュエーションのことだ。人を切る時,人から切られる時,そんなことを言っている余裕は自分から消えているだろう。でなければ,自分が切られる。
茶の湯で,初めて「一期一会」を言った井伊直弼は,一体何人の若い逸材を無残に殺戮したか。ただ徳川幕府という権威を守るためだけに。人は,場合によっては,そうなるということだ。「茶室」という特殊な状況のそれを一般化する議論を僕はほとんど信じないのはこのためだ。しかも,「茶室」内は,あれはあれで,裏面で,実は様々な思惑が入り混じっている。表面的なおもてなしなどに騙されているお人よしには見えないだけだ。「茶室」もまた,丁々発止の,緊張した修羅場なのだ。
結局おもてなしとは,おためごかしであり,親切とは,相手を出汁することであり,心配りとは,ためにするものだと,そう割り切らなければ,おのれを縛る束縛を脱することはできない。自由を得るためには覚悟がいる。何が何でも自由になる,という覚悟ではない。自由のためにはすべてをかなぐり捨てる覚悟だ。すべての慮りも忖度も無駄な配慮と思わなければならない。そういう心配りは,相手からは隙に見える。その隙を相手は衝いてくる。
相手がおのれを貶めようと嵩にかかっている時,優しい気持ちを持つのは,人間としては悪くはないが,ますます自分が追いつめられるだろう。対峙すべき時に,きちんと立ち切っていなければ,相手にとっては隙に見える。腰を引くことは,それはそのままおのれでおのれを貶めているのと同じだ。
ある作家が,右翼についてだか天皇制についただか書いた時,有名右翼に呼び出された。そして,最後こう言われた。「同じ日本人じゃないか」と肩に手を置かれたという。それを読んだ瞬間,背筋が寒くなった。丸めたところで事態は変わっていない。しかし,丸めてしまうことで,差異を消そうとする。しかし,情報の価値は差異にしかない。丸めた情報はただの一般論だ。一般論に丸めることで事態を収めようとしたのだろう。こういうのを清濁合わせ呑むという言い方をする人がいる。いわば,合わせ呑まれた側に立ったことがない人のセリフだ。修羅場とは,合わせ呑まれそうになったものの状況を言っている。
今回,本人は敗北感にまみれている。つまり,相手を信じたが,あるいは相手の好意を信じたが,それは相手にとっては衝くべき隙にしか見えなかったということだ。鮮やかにその隙を衝かれてしまった。自分の心が押し込まれた分だけ,敗北感が募る。
こういう修羅場をくぐっていないで,表面的で,きれいごとを言う人間を,僕は信じない。
この修羅場をくぐるときには,一切の妥協も配慮もかなぐり捨てなくてはならない。しかしそれができる人は本当に少ない。人は,皆人が好いのだ。人の好さは,こういう場合,隙そのものだ。
ひとは,自分のことしか考えていない。自分の利益を守るためにしか相手に向き合わない。修羅場で同情心や心配りは,おのれを衝く致命傷になりかねない。
そして結局思うのは,それが自分にとって,生涯を賭けるに値すると思ったら,修羅にならなくてはならない。人間性を棄てても構わない。その覚悟がなくて,得たいものが,のほほんとして得られるなんてことはない。
決断とは,捨てることだ。覚悟とは,斬ることだ。自由とは断念することだ。
かつて,僕は,「君は,うちの社風にあわない」と言われて,辞職に追い込まれた。上司やトップに逆らうことをそう呼んだらしい。そのとき,僕の内側で,どんな葛藤があり,どんな断念があり,どんな悲壮感があったかなんかは,関係ない。それは,隙でしかない。
何も捨てず,何も断念しないで,えられるものはない。自由には自由の代償がいる。
自由でいるつもりだが,本当にしたいことをしようとした時,初めて桎梏が,足枷が,見えてくる。それを断ち切らなければ,あるいはそれを断ち切る勇気を持てなければ,いまのままの奴隷の状態でいる方が安寧というものだ。
自由が戦わないで得られるなどと思ってはならない。断固とした決意なしに,自由になることなんて難しい。
もちろん,付言しておくが,しがらみを断ち切るのをよしとしているのではない。断ち切れる人と断ち切れない人の差は,覚悟の問題だと言っているだけだ。どっちにしたって,同じ人生。いい悪いはない。どの道死ぬまでの一生だから。
所詮おためごかしに聞こえるかもしれないが,最近心底そう思えるようになった。言うまでもないが,「人生はすべて意味がある」ではない(そんなのは当り前)。「すべての人生に意味がある」の意味だ。
どんな人生にも意味がある。
偉い学者はもちろん,
成功した大金持ちも,
貧乏の中でのた打ち回り野垂れ死にした人も,
有り余る金で贅沢に一生を過ごした人も,
凶悪な殺人者も,
その犯人に殺された人も,
自殺するまで追い詰めたいじめっ子も,
追い詰められた校舎から飛び降り自殺した人も,
コインロッカーに遺棄された赤子も,
ロッカーにへその緒を附けたまま我が子を見捨てた母親も,
居眠り運転して人身事故を起こしたドライバーも,
暴走した乗用車に跳ね飛ばされた幼稚園児も,
すべての人の人生に意味がある。是非善悪は神の視座でなくては下せない。しかし僕は神の存在を信じない(まあ創造主の意味の神で,可愛げのある八百万の神は,信じているが)。いま宇宙は膨張し続けている。しかし一転収縮に転じ,ビックバン以前になった時,宇宙は極小の粒に圧縮される。神がいようといまいと,すべては消える。そんなものに,是非をゆだねるべきではない。もし神が,その圧縮された点の外にいるなら,無傷でそんなところにいるようなものに,傷つき歎く人間のことなど分かるはずはない。もはや神ではない。世界と,すべての人間と丸ごと一心同体,一緒に世界とともに消滅する神でなくては,神として信ずるには足りぬ。なら,神は,宇宙とともに圧縮され潰れる。
しかも,意味の有無も,価値の是非も,所詮その人単体で,自己完結して下そうとすると,それも,そもそも間違っている。人は,社会的動物であり,人と人とのつながりの結節点としてしか存在しえない。なら,その人が意味も価値もないのなら,それに連なる人々も意味も価値もなくなる。
そんなことはありえない。
その人の意味も価値も,その人と連なる人ごととのリンクの中でしか浮かび上がってはこない。
僕の弟は,10か月で,誤診のため急死した。10か月では戒名もない。死ぬ前,母がしきりに悔いていたのを耳にした。しかしその弟も意味があると信じている。いま,思い出を兄弟に残した。母の悔いを残した。ぼくに記憶を残した。
意味を見つけられないのは,是非の眼で曇っているか,こちらの知恵と見識の不足のせいだけだ。
どんな人生にも意味がある。
家中の襖という襖をバットの先で破りまくった高校生も,
リストカットを繰り返して,手首に何本もの筋を創ってしまった娘も,
追い回した果てに憎さ百倍でその両親を殺してしまったストーカーも,
毎日ガード下でただ飲むために飲んでいる酔っ払いも,
脳溢血で半身不随になり,自暴自棄になっている独居老人も,
家賃が払えずほおり出されてコンビニの賞味期限切れをあさっている男も,
何かをしようとしていても,
何もしなくても,
ただそこにいるだけでも,
何かを成し遂げても,
何も成し遂げなくても,
ただ立っているだけでも,
すべての人の人生に意味がある。是非を抜き,前提抜きで,掛け値なく,すべての人の人生に意味がある。
すべての人の人生に物語があり,物語のない人生はない。である以上,その物語に,たった一人で登場する人は一人もいない。一人もいないということは,その人一人に自己完結させて意味を見つけようとすることはできないということだ。
天の視点も,神の視点も,宇宙の法則もいらない。ただのおのれの人生をよく見ているひとには,すべての人の人生に意味が見える。
意味に価値を入れてはいけない。
成功したかどうか,
幸せだったかどうか,
楽しかったかどうか,
面白かったかどうか,
その行為の可否ではなく,
その行動の是非ではなく,
ただ,その存在とその人生に意味がある。それがクライアントに丸印を附けるということの,真の意味でなくてはならない。
しかしだ,自己完結した人生そのものの中にいる本人は,その意味には気づけない。どっぷりつかり,絶望し,やけくそになり,自暴自棄になっている本人には気づけない。
それに気づくには対象化がいる。メタ化がいる。自分自身と,自分のありようとを対象化しなくてはならない。方法は二つしかない。
一つは,人の眼だ。評価ではなく,ありのままに,その人自身と,その人のありようと,人生をフィードバックすること。
いまひとつは,自分が自分を,自分のありようを,自分の人生を,言葉にして語ること。
それを一人でできる人もいるが,聞き手がいて,それをフィードバックすることの効果は大きい。鏡効果によって,自分で自分を認知できる。
ここにこそ,シャインのいう,プロセス・コンサルテーションに携わる,援助職の出番がある。
是非の色眼鏡,可否の色眼鏡,善悪の色眼鏡は,自分の人生を見るときにいらない。ましてや援助職には,それが有る無しが,その人の技量のメルクマールだ。眼鏡なしで,相手を見られない人は,プロセス・コンサルテーション,いわゆる援助職についてはいけない。まして,色眼鏡で相手を峻別している自分に気づいていないような人に,支援をされたくはない。
遠くから名前を呼ばれている気がして,ふっと目覚めた。その直前夢を見ていた気がするが,はっきりしない。目の前で,執刀の女医さんが,終わりましたよ,と声をかけてくれた。
ありがとうという意志表示で出たのか,
単に(ちょっとかっこいい)女医さんの手を握りたかったのか,
なんとなくうつつの何かに触れたかったのか,
どういうわけだか,思わず手を出したら,握手を返してくれた。間合いというのはこういうことなのだろう。
痛みはひどかったけれども,まあ何とか食事はとれたが,翌日位から身体が弱り,気力が萎えていった。無自覚に萎えていく,無意識ではない,萎えていくことを意識しているのに,それを自覚していない。そのまま無気力になっていく。まあ,こんな程度いいのではないか,そう諦めかけた時に,自分は,まだまだ終わっていない,ということを感じた。
思い出したのは,フランクルの問いだ。人は人生に何かを求めるのではなく,自分の人生が自分に求めているものにどう応えるか,それを天命と呼ぶんだと,僕は思った。
天命という言葉は,別に使命とか役割とかとは関係ないと思っている。そういう意味に使っている人は,思い上がっているか,うぬぼれているか,無自覚に自己欺瞞に陥っている。人には,天寿を全うすべき天から定められた寿命がある。だから,途中でそれを全うできなかったことを,非命という。すべての人に天命がある。生きることそれ自体が,天命であって,何か目的があるなどと思い上がってはいけない。
人生には目的などない。自分が目的を定めるだけのことだ。それを神から託されたと思い上がるのも自由,誰かのために尽くそうとするのも自由。ただおのれの欲のためにだけ生き切るのも自由。死ねば死に切りと思うのも自由。だから人間だけが,自らの生を絶つ自由がある。
しかし僕は,まだ生かされているなら,生かされているうちに自分にできることをしたいと思う。そこで人生を諦めるのも,そこで人生を投げ出すのも,別におのれの人生だから,ひと様にとやかく言われる筋合いはない。しかし,自分がそれでは納得できない,と感じている。
天命を信じて人事を尽くす,とはそんな時に自分に問いを出す。
おのれの存在を賭してでもすべきことがあるのか,という問いが,現実味を帯びる。その問いを絵空事にしない。
王陽明は,『伝習禄』で,聖人の「生知安行」,賢人の「学知利行」に対して,普通に学ぶものを,「困知勉行」とし,天命と一体の聖人,天に事える賢人に対して,天命が何たるかを知らないから,「天命を俟つ」(人事を尽くして天命を俟つ)以外ないのだと言った。だから,「殀(わかじに)か寿(ながいき)を全うするかによってその心を弐(たが)えず,身を修めて天命を俟つ」といった。その伝で言えば,与えられた寿命を生き切るほかはない。後は,天命を俟つのみ。
だから,余生というのはない。余りの人生なんぞあるはずはない。ふと,もうのんびりしてもいいのではないか,ゆったり過ごすか,等々と思ったりする。しかしそれは与えられた限りある人生の無駄遣いだ。
確か秋元康が,人生は電話口にテレホンカードを差し込んだ状態に譬えた。しゃべってもしゃべらなくても,度数は減っていく,と。
生きている限り,のんびりするのは,僕には人生の放棄に見える。
生きている限り,というか生かされている限り,しなくてはいけない何かが見える。人のためであれ,自分のためであれ,それが自分のすべきことというのが見える。
よく,すべきことではなく,したいことを言え,という言い方をする。僕はナンセンスだと思っている。したいことは,所詮したいこと。優先順位は低い。好きなことをしているイチローが,ちっとも楽しくなんかないです,と言っていたのが印象的だ。したいことよりも,自分でなくてはできないこと,自分こそがやるべきだと信じたことをやる,それを大事にしたい。それが福嶋さんの言う,「出番」とはそういうものだろう。
それが天命からか,役割からか,義務からかはどうでもいいのではないか。いま「自分が」やらなくてはならないと感じたことをやるべきだ。それが僕は人生への問いに答えることだと信ずる。所詮したいということも,すべきということも,自分の思い込みや思い違いにすぎないのかも知れないのだ。
だとしても,いま「自分が」やらなくてはならないと感じ,やらないですませば,きっと後から後悔するに違いないと感じるのなら,いますべきなのだ。楽しくないとか,したくない,したいことではない等々いうことは,所詮やるべきことをしない逃げに過ぎない。
楽しいか,やりたいかの選択肢は,本当はどうでもいいあいまいなものに過ぎない。楽しくしたいことだけをしている人生など,所詮楽しさしかないだけのつまらぬ人生だ。
いま,ほかならぬ,自分がしなくてはならないと感じることこそから,逃げず,やらなくてはならない。それをしなくては,きっと後悔するに違いないと思ったら,なおしなくてはならない。それが天命というもののように思える。
たとえ,心情告白でも,独立宣言でも,終活開始でも,戦闘開始でも,闘争宣言でも,限界突破でも,何であれ,それがし残したことなら,それが天命だ。天命に軽重も是非もありはしない。その人の一生分の価値だけがある。
CTPのテキスト(僕の受けた2004年当時)には,提案について,
提案とは,新しい視点を提起要することです。提案と,「指示・命令」は違います。「提案」は,あくまで彼ら(クライアントを指す)が自分の責任で行動を選択することを促します。言い換えれば,「YESかNO」の選択権は常に相手にあるという立場に立って伝えるのが,「提案」です。
とある。CTI流だと,「YES,NO,逆提案」となる。逆提案が入っている分だけ,対等という感覚が強まると言ってもいい。
提案というのは,指示命令とは違う,という。しかし,望まれていないアドバイスは,命令に聞こえる。「俺の言うことをきけ」と。だから,提案も同じだ。望まれていない「提案」は,YESと言えというふうにしか聞こえないかもしれない。
人は,自分が選択したと思えなければ,強制されたと感じる。ではどうすれば,強制と感じないで,自分の選択と感じられるのか。
第一は,その選択肢の選定プロセスに,相手も一緒に加わり,そのどちらかに選ぶのがベストと感じることができている場合だ。つまり,一緒に提案の中身を,つくりかあげていくプロセスがあることだ。
第二は,選択できる,ということだ。提案が,ひとつではなく,いくつかあり,その中から,自分が自主的に選んだと感じられることだ。
その場合,二者択一では選択と言わない。「YESかNO」を迫っているのと変わらない。選択できる,という意識が持てるのは,最低限3つがいる。あまり多くなると,選べなくなる,ということをよく言うが,せめて3つの中から選べるのがいい。
その理由は,
①当然第一に述べたように,これっきゃないところから,諾否のみを求められるのは,押し付けられているという感覚が強い。特に,心理的に上位と感じている人からのそれは,強制のニュアンスがどうしても出る。コーチングではそれはないと思われるかもしれないが,そう思っているコーチは思い上がっている。クライアントには,潜在的に,「コーチに嫌われたくない」「コーチによく思われたい」という心理があり,それが強迫性をもつ。
②二つだと,二者択一,つまりあれかこれか,から選ぶことになる。これだと実際やってみるとわかるが,心理状態は諾否に近い。
③三つの良いところは,二つある。少なくとも選んだ感はある。いま一つは,人は上中下とあった場合,大概真ん中を選ぶ傾向がある。従って,相手に選んでほしいものがある時,本命をそこに置くと,割と選ぶ傾向が高まる。
その意味で,提案者にとっても,選択者にとっても,3つの選択肢は,好感度が高い。できるなら,提案する以上,相手に選んでほしいし,また相手に選んだと思ってもらいたい。
ソリューション・フォーカスト・アプローチでは,クライアントに提案(Suggestion)を行う。その場合,
行動提案(クライアントに何かするように求める)
と
観察提案(生活の中で解決作りに役立ちそうな部分に注意を払うように求める)
とがある。いずれを出すかは,面接中に集められた情報を基にするが,その場合注目すべきは,
「初回面接の終了時までに,ほとんど例外なく,臨床家とクライアントは共同作業によって,クライアントの望みを明確にできる。…提案を決めるために最も重要なことは,クライアントが何か違いを求めているかどうかに注目することである。」
とし,解決したい問題があり,自分が何とかしなくてはいけないと考えている状況では行動提案,問題に気づきながらも自分を解決の一部であると考えていない場合は,観察提案,といった選択基準を提起している
どうやら,提案は,協働作業として,おのずとそれをすることが自分にとって不可欠と思える状況というか,文脈をつくって,一緒にそこへたどり着くのがいいのではないか,と思えてくる。
ただ,さらに付け加えると,僕は提案は,受ける,受けない,逆提案という選択肢の中で,ただ並べるのではなく,クライアントの想定外の提案がいいと思っている。しかもそれがコーチとクライアントの協働関係の中で,必然的に飛躍が起こりうる,というようなものでなくてはならない。
ただ価値に合うとか,大きな主題に合うというコーチの理屈ではなく,それをやってみることが,いまの自分にとって必要なんだと思わせるものだ。
僕はその流れは忘れたが,絶対やりたくないものを列挙し,その中から,何かにチャレンジするという提案を,コーチから受けた記憶があるが,それは自分が変化とかチャレンジということを言ってきた文脈から出た提案であった。その文脈に納得し,その文脈に乗って,コーチとともに,やりたくないことを列挙し,その中から,選択していく。それも自分でも想定外のことを選び,チャレンジする。
それを断ったら,チャレンジという自分のやろうとすること自体が口先三寸になる。そういう文脈であった。
そう,だから,提案は,それだけが突出しても,提案ではなく,指示命令にしかクライアントには聞こえない。一連のコーチングという協働関係の中から,コーチもクライアントも,ともにそういうことだよな,と納得できる提案が,ぽろりと落ちる,しかも想定外に,そういうものなのだと思う。
参考文献;
インスー・キム・バーグ他『解決のための面接技法【第三版】』(金剛出版)
ずいぶん昔,ランボーの『地獄の季節』という岩波文庫の薄いのを読んではメモし,メモしては読んでいた記憶があるが,いつの間にか紛失してしまった。改めて買ったが,もう昔の熱は冷めていた。
それが,大量の書籍と日記を処分した時に,ポロリと出てきた。すべての記録とか日記とか文書類を廃棄してしまったので,いまは,かつて自分の書いたものは,この文庫に走り書きした,詩片らしきものしか残っていない。
そして,最近思うのだが,この世の中の基準では,その人が,何を考え(てき)たかではなく,何を(果)したかにのみ意味があるのではないか。だから行動に移されなかった思いや,言葉にされなかった思い,活字にならなかった文章は,なかったも同然なのだ,と。まあ,確かに,その通りだ。一篇も書かぬ詩人は,詩人ではない。
そうであるかもしれない。だが,だ。結局考えて,考えて,考え抜いた末,何もしないという決心も,ある,とこの頃は思う。あるいは,書き込んで,書き込んで,書き込んでも,結局ものにならないものも,あるいはものにしないと決めることも,あるかもしれない。その時,人生には,人の眼から見れば,何の軌跡も残さぬことになるだろう。そうかもしれぬ。しかしそれでも,いいのではないか。そう思うようになった。
何度も同じ引用で(口癖のようになってしまったので)恐縮だがガイアシンフォニー第三番で,
人生とは,なにかを計画している時に起こってしまう別の出来事のことをいう。結果が最初の思惑通りにならなくても,…最後に意味をもつのは,結果ではなく,過ごしてしまったかけがえのないその時間である。
とある。それが「過ごしてしまったかけがえのない時間」なのかどうかはわからない。しかし,そこで思い詰め,考え込んだ時間があったことだけは確かだ。その圧縮された時間感覚だけが,いまの自分の中にある。確かに,底流としてあるし,土台としてある,そんな気がする。
「思い群ならず」という,杜甫の言葉がある。李白をほめたたえた詩の中で,「白や詩敵無し,飄然として思い群ならず」とある。ここでそれを言うのは,負け惜しみというか,強がりかもしれない。しかし,一人一人が,自分の言葉を口にしても,雑踏の中では,ひとまとまりの雑音となってしまう。それと同じで,ずっと視点を遠ざければ,同じことだ。
だからと言って,声高の声に同調したり,流行っている者に乗ったり,誰かのお先棒を担ぐ,というのは嫌だ,誰かの真似や,誰かの弟子や,誰かの後塵を拝するのはもっと嫌だ,とまあそんなことを言っているから,所詮我流からしか抜け出せない。我流でも,宮本武蔵までいけば,一派が立つ。そこまでの気概も器量もない。
自分の思いに拘泥していると言えば,言えるのかもしれない。しかし,そこにコアがあるのなら,それを簡単に手放していいはずはない。まあ,一種の開き直りに近い。
フロムは,こういう。
私たちは自分自身を「信じる」。私たちは,自分のなかに,ひとつの自己,いわば芯のようなものがあることを確信する。境遇がどんなに変わろうとも,また意見や感情が変わろうとも,その芯は生涯を通じて消えることなく,変わることもない。この芯こそが,「私」という言葉の背後にある現実であり,「私は私だ」という確信を支えているのはこの芯である。
自分自身を「信じている」者だけが,他人に対して誠実になれる。なぜなら,自分に信念をもっている者だけが,「自分は将来も現在と同じだろう,したがって自分が予想しているとおりに感じ,行動するだろう」という確信をもてるからだ。自分自身に対する信念は,他人にたいして約束ができるための必須条件である。
他人を「信じる」ことのもうひとつの意味は,他人の可能性を「信じる」ことである。
このコアがあるからこそ,世界に自分を開ける。ブーバーは言う。
他の人間そのものに自己を向け,自らを開くものののみが,自己の中に世界を受けとる。
いまは,だから,我執というシャッターを開いて,外に向かって,おのれを全開するときなのだろう。それがどういうコアであろうと,それを信ずることで人を信じ,世界を信ずる。
参考文献;
マルティン・ブーバー『我と汝・対話』(岩波文庫)
エーリッヒ・フロム『愛するということ』(紀伊國屋書店)
最近,「かりもの」ということが気になる。自分が,ということもあるが,人を見ていて,そう思うこともある。口幅ったいし,まあそんな偉そうな口をきける立場でもないが(だからこそ言い得るということもある),上は,外国人(特に欧米)の著者や考え方のお先棒担ぎから,下は,ひと様の考えの真似まで,自覚なく自分のもののごとくしゃべっていると,キリではあっても,キリにはキリの虚仮の一念というのがあっていい,そんなことを考えてしまう。福沢諭吉以来,そういうのが当たり前になっている。しかしいずれは,化けの皮ははがれる,と信じている。これも所詮は虚仮の一念かもしれない。閑話休題。
ところで,「かりもの」というのを,辞書的に言うと,
亜流の ・ 形式だけ(似ている) ・ (外形を)なぞっただけの ・ (~の)コピー ・ (単なる)引き写し ・ (真に)身についたものでない ・
便宜的な(振る舞い) ・ (~を)真似る ・ 本物でない~ ・ 咀嚼されていない~ ・ しっくりしない
等々となる。では,そのうちの「亜流」を辞書的には,
二流 ・ 借り物 ・ 薄っぺら ・ なぞる ・ 次 ・ 型通り ・ 陳腐 ・ えせ ・ 真似る ・ 副
となる。その流れで,言うと,自分のものでもないのに,自分のもののごとく語る,ということか。
では,プロとアマの違いは何か。これは,別のところで書いた気がするが,
プロであるとは,その能力と成果物で“金”が取れることには違いがないが,最大の特色は,自分独自の(オリジナルな)“方法論”をもっていることだ。どんなに経験したことのない,未知の(領域の)問題にぶつかっても,瞬時に(といかないこともあるが),自分なりにどうすればいいか,どういうやり方をすればいいかの判断と決断ができることだ。それは,また,自分のやり方に対する批評力があることをも意味する。つまり,自分の方法の方法をもっていることであり,自分のコトバで自分のやり方(の新しさ,独特さ)と内容(の独自性と共通性)を語れる(コトバをもっている)ということである。
こう考えている。でも,「かりもの」であっても,プロとして存在しうる。別の概念かもしれないが,お金はとれても,結局人の褌で相撲を取っているような,居心地の悪さを感じる。それは僕だけの倫理なのかもしれない。はじめ「かりもの」であっても,それを自分の言葉で語っていくうちに,自分のオリジナルな世界へと突き抜けていくということはある。しかし,その場合,おのずと,とは思えない。意識的に,守破離ではないが,それを自分の衣とし,次には,それを脱ぎ捨てて脱皮していく,ということはあるだろう。その場合は,「かりもの」を意識していなくてはならない。
人の能力を,僕は,
能力=知識(知っている)×技能(できる)×意欲(その気になる)×発想(何とかする)
と分解している。「知っていて」「できる」ことだけを,「その気になって」取り組んでも,いままでやったことをなぞるだけのことだ。いままでやったことがない,いまのスキルではちょっと荷が重い,といったことに取り組んで,「何とかする」経験をどれだけ積んだか,でその人の能力のキャパシティは決まる,と言っても過言ではない。
そうして積み上げた知識と経験を,ただそのまま体験として蓄積するだけでは,プロにはなれない。それを,批評するパースペクティブを持っていること,つまり,自分の方法の方法,プロフェッショナルのプロフェッショナル,つまりプロフェッショナルであるとは,メタプロフェッショナルであることなのである。それは,自分が何の,どんなプロフェッショナルであるかを,コトバにできることでもある。人に伝えられるコトバをもっているかどうか,がプロとアマの本質的な差のように思う。
言ってみれば,人は生きてきた分だけ,量や質はともかく,知識と経験は蓄積される。人の能力はそこにしかない。それをどう生かすかにしか,自分を生かす途はないのである。それをどうコトバにするか,そこに自分の“方法論”を明確化する筋がある。
ほかのところでも書いたが,元来,僕は,
世の中には,一流と二流がある。しかし,二流があれば,三流もある。三流があれば四流がある。しかし,それ以下はない,
と思っている。
「一流の人」とは,常に時代や社会の常識(当たり前とされていること)とは異なる発想で,先陣を切って新たな地平に飛び出し,自分なりの思い(問題意識)をテーマに徹底した追求をし,新しい分野やものを切り開き,カタチにしていく力のある人。しかも,自分のしているテーマ,仕事の(世の中的な)レベルと意味の重要性がわかっている。
「二流の人」とは,自らは新しいものを切り開く創造的力はないが,「新しいもの」を発見し,その新しさの意義を認める力は備えており,その新しさを現実化,具体化していくためのスキルには優れたものがある。したがって,二番手ながら,現実化のプロセスでは,一番手の問題点を改善していく創意工夫をもち,ある面では,創案者よりも現実化の難しさをよくわきまえている。だから,「二流の人」は,自分が二流であることを十分自覚した,謙虚さが,強みである。謙虚さがなかったら,四流になる。
「三流の人」とは,それがもっている新しさを,「二流の人」の現実化の努力の後を知り,それをまねて,使いこなしていく人である。「使いこなし」は,一種の習熟であるが,そのことを,単に「まね」(したこと)の自己化(換骨奪胎)にすぎないことを十分自覚できている人が「三流の人」である。その限りでは,自分の力量と才能のレベルを承知している人である。
自分の仕事や成果がまねでしかないこと,しかもそれは既に誰かがどこかで試みた二番煎じ,三番煎じでしかないこと,しかもそのレベルは世の中的にはさほどのものではないことについての自覚がなく,あたかも,自分オリジナルであるかのごとく思い上がり,自惚れる人は,「四流以下の人」であり,世の中的には“夜郎自大”(自分の力量を知らず仲間内や小さな世界で大きな顔をしている)と呼ぶ。
僕はせめて,四流ではありたい,おのれを知っている謙虚な人間でありたい,と思っている。つい思い上がって,うぬぼれがちなだけに,おのれを戒めておきたい。
どんな仕事も,先人の肩の上に載っている,といったのは,確かフロイトだったような記憶があるが,そういう謙虚さはいつもいる。iPS細胞の山中先生が,「私の受賞は便乗受賞で,50年前の,ジョン・ガードン先生が,カエルの腸細胞の核を別のカエルの卵子の核と入れ替えただけで,受精せずにオタマジャクシが生まれることを実証されることで,受精卵と生殖細胞だけが,完全な遺伝子の設計図を持つという,100年前以来の常識を覆したことが,私のiPS細胞につながった」と言っておられるのが,心に響くのはそのせいだ。
少なくとも,自分自身と自分の仕事と成果に誇りをもっていること,あるいは誇りをもてるようにするにはどうすればいいかをたえず考えていることが,四流かそうでないかの分かれ道であるように思う。
そのために,こんな問いを切りぬいたことがあった(今も手帳に貼ってある,自戒でもある)。
そもそも自分の職業は何か?
これまで実際にやりとげたことは何か?
顧客の中で誰かそのことを証明してくれるか?
自分の技能(スキル)が最高水準にあることを示すどんな証拠があるか?
競争社会を乗り切っていくのを助けてくれるような新しい知人を,会社をこえて何人得たか?
今年度末の(職務)履歴には昨年と違った内容のものになるか?
自分一人である程度の領域がカバーできる力があればあるほど,期待する水準が高いので,自分一人で何でもできるなどと思い上がらず,(いまは組織にはいないので)チームや仲間で推進していく(達成度を高める)にはどうしたらいいかを考えている。一人で得られる(世の中の水準から見た)成果や情報力は,チームや仲間で得られるものに比べれば格段の時間とコストがかかるのだから。それに,もう自分を過信できるほど若くはない。過信は40代で卒業できなければ,ただの能天気!
参考文献;
ピーター・センゲ他『学習する組織「5つの能力」』(日本経済新聞社)
創造性とは何か,といったとき,ヴァン・ファンジェの定義,
①創造者とは,既存の要素から,彼にとっては新しい組み合わせを達成する人である
②創造とは,この新しい組み合わせである
③創造するとは,既存の要素を新しく組み合わせる(組み替える)ことにすぎない
が有名だが,いまいちピントこなかった。あるとき,川喜田二郎が,
創造性とは,本来ばらばらで異質なものを意味あるように結びつけ,秩序付けること。
と書いているのを見つけて,ようやく腑に落ちた記憶がある。つまり,意味あるように組み替える,あるいは新しい意味が見つかるような組み合わせを見つける,ということだ,と。自動的に見つかるわけではなく,エジソンではないが,普通の人はもうこれだけやったんだ,と思うところに来て,やっとそのわずか先に光明が見える,そういう努力の中からしか生まれてこない,という意味なのだろう。それは,永遠に見つからないということも含めている。
しかし,
窮すれば即ち変じ,変ずれば即ち通ず,
という易経にある言葉もある。窮しているということは,ひとつの壁だ。壁があるということは,多くの人がそこで投げ出す一つにハードルだと思えればいい。そうすると,選択肢が見える。引き下がるのも,そうだが,横へずれてもいい。ここで,しばらく立ち止まってもいい。岡潔さんは,
タテヨコナナメ十文字考えぬいて,それでもだめなら寝てしまえ,
といった趣旨のことを言っていた記憶がある。それもその一つだ。ひらめく一瞬は,0.1秒脳の広範囲が活性化する。いつもと同じ筋道で見ている限り,いつもの答えしか出ない。脳の,いつもと違うリソースとリンクさせなくては,あるいはリンクするまでのタイムラグが,いわゆる孵化の時間ということになる。脳は,問題意識を掲げると,勝手に考えていく。答えは,脳から出てくる。
「アイデアいっぱいの人は決して深刻にならない」というのは,フランスの詩人ポール・ヴァレリーが言った,僕が大好きな言葉だが,広角な視界は,いつもたくさんの選択肢が出せるとところからくる。そういうゆとり,自分への間合いが必要な気がする。
キルケゴールはいう。人間は精神である。しかし,精神とは何であるか?精神とは自己である。自己とは何であるか?自己とはひとつの関係,その関係それ自身に関係する関係である。あるいはその関係において,その関係がそれ自身に関係するということ,のことである。
結局人は,自分と会話している。あるいは,自分と,自分A,自分B,自分C,自分D…自分nと対話している。田中ひな子さんは,カウンセラーは,
その人自身が自分としている会話(「自分を巡る自分との対話)であり,セラピストは,クライアントのしている「自分との会話」に入っていく。
といった。その自分との対話の間合いを自分で測る,それが選択肢を出すカギだと思う。心の余裕が必要な所以なのだ。
サルトルは,こんな言い方をしていた。
自己とは,それ自身との一致であらぬ一つのありかたであり,「同」を「一」として立てることによって「同」から脱れ出る一つのありかたであり,要するに,いささかの差別もない絶対的凝集としての「同」と,多様の綜合としての「一」とのあいだの,つねに安定することのない平衡状態にあるひとつのありかたである。
こんな不安定の中での自分との間合いが,ゆとりなくしては生まれないというのも,ちょっと常識的で嫌だが。
ところで,ハイデガーは,人は死ぬまで可能性の中にある,と言ったが,サルトルは,私は,まさに私の行為が可能でしかないがゆえに,不安なのである,と言っていた。
「可能性」とは,「その約束の場所で私自身に会えないかもしれない」という恐れであり,「もうそこへ行こうとしないかもしれないおそれ」である,とも。記憶違いかもしれないが,「握った手は握ることができない」といったのもサルトルだったように思う。学生の時の授業で聞いたそのことはだけが妙に印象に残っている。そうだよな,握った手は握った手だ,と。
神田橋條治は,いう。ボクは精神療法の目標は自己実現であり自己実現とは遺伝子の開花である,と考えています。「鵜は鵜のように,烏は烏のように」がボクの治療方針のセントラル・ドグマです。
鵜は鷹にはならず,鷹は家鴨にはなれない。おのれ自身の可能性とは,そういうことだ。後は,そのための努力だ。確か,論語にあった。一人に備わらんことを求るなかれ,と。一人の完全性には限度がある。
そういえば,論語曰く,
己れを知ること莫きを患えず,知らるべきを為さんことを求む。
かつては,自惚れが強かったので,この意識が強かった。しかしいまは,
人のおのれを知ること莫きを患えず,人を知らざるを患えよ
が,強く響く。たぶん,「人を知る」ということの重要さを,ようやくこの歳で知った。すべておのれ一個の力でできると,過信していた。しかしそういう過信が,人の後を金魚のうんこのようについて歩くのを,よしとはしなかった。そういう若気の至りがあってもいい,と今はおのれを許す。
カーネギーはいう。議論に負けてもその人の意見は変わらない。よく落ち込んだものだが,議論ではなく,対話だと考えると,正しいか間違っているかではない。ガチの対立になるのは,N・R・ハンソンの言う,人が,それぞれ知識でものを見ていることを失念しているからだ。
N・R・ハンソンは,こう書く。20世紀の天文学者が,宇宙空間の適当な位置から眺めれば,地球が太陽のまわりに軌道を描くように見え,その逆ではないことを見るように,13世紀の天文学者は,宇宙空間の適当な位置から眺めれば,太陽が地球の周りに軌道を描くように見え,その逆ではないことを見たのである。ゲーテがわれわれは知っていることだけを見る,といった。ウィトゲンシュタインが「~として見る」といったことを,そうハンソンはたとえた。
おのれを知るとは,おのれの限界を知る,ということでもある。しかしそれは,謙虚さからしか生まれない。つくづくそう思う。
自分が生かせる,とはどういうことか,ひとつはいまの自分のありのままで,生き生きと心身ともに活動できることだが,同時に,自分のキャパ一杯に活動することで,新たな自分を日々つくりだしていける,そういう成長性もなくてはならない。
自分を受容することが,ともすると,そのままの自分でいい,という自足を勧めるように聞こえて,どこか納得いかない。それでは,自分の気づいていない,自分の可能性を伸ばす機会を自分で棄ててしまうことになる気がしている。
自分の限界は,自分で「もうこれまで」と思うもう一つ先まで,自分を出し切らなくては見えてこない。そうすると,そのギリギリが当たり前の常態になるような努力をする。すると,さらに自分の限界線が広がる。閾値を決めてしまって,それを限度とするのは,自分を貶めることだ。
確かに,自分はかって,自己肥大で,自己を過大評価していた。しかしだからこそ,取り組めたこともあった気がする。それが自分の領域をはるかに超えたところだと,やってみて気づくこともある。そこが一つの目標になる。いつの間にか,それができている日が来る。そういうことの繰り返しの中で,自分のキャパを少しずつ超えていく。
場とは,
そこで自分が生き生きするためには,自己完結した自分を手放すこと,
それは,逆に言うと,自分のためではなく,大事な誰かのために,その人が生き生きできるような場を設え,そこでその人が生き生きし,限界にまで,楽しんでチャレンジできるように,サポートしきる,そういう場を作ることが,ひとつの方法なのではないか,そんなことに気づいている。
それをどう伝えたらいいのか。いやいや,それがどうしたら可能なのか,そのことがまだ見えていない。おのれを捨てることが,そして,そこで大事な人がおのれのパフォーマンスを最大限発揮し,実現しきれること,それを支え,実現することが,自分自身の新たな可能性を広げることになる,そういう場を創りたいと思っている。
つくづく自分の我執にこだわる自分が本当に卑小でちっぽけな存在に思えてくる。おのれの限界が見えてしまったいま,その努力はまだまだ続けるけれども,それが見えなかったときに比べて,やはりモチベーションが違う。その目的は,少しずつ遠ざかっているように見える。
フロムはいう。
集中できるということは,一人きりでいられるということであり,一人でいられるようになることは,愛することができるようになるための一つの必須条件である。もし,自分の足で立てないという理由で,誰か他人にしがみつくとしたら,…二人の関係は愛の関係ではない。逆説的ではあるが,一人でいられる能力こそ,愛する能力の前提条件なのだ。
ならば,少しは資格はある。さらにフロムは言う。
愛とは,特定の人間に対する関係ではない。愛の一つの「対象」にたいしてではなく,世界全体にたいして人がどう関わるかを決定する態度,性格の方向性のことである。
しかし,フロムが引用する,マイスター・エックハルトの言う,
もし自分を愛するならば,すべての人間を自分と同じように愛している。他人を自分自身よりも愛さないならば,本当の意味で自分自身を愛することはできない。
をもじるなら,たった一人を愛することができないなら,それ以外の人を愛する力量は知れているともいえる。
だから,視点を変えた時,自分自身を生かすという我執を手放すなら,それを自分ではなく,人が生きる場,人が自分を生き生きと成長させていく場と考えれば,その場は,自分自身が人を生かすべき舞台となる,新しい場ができる気がしている。
まだまだ模索なのだが,自分だけでなく,その場の人が,共に生き生きするというにはどうすればいいのか。
フロムの言葉にヒントがあるかもしれない。
二人の関係がそれぞれの存在の本質において自分自身を経験し,自分自身か逃避するのではなく,自分自身と一体化することによって,相手と一体化するということである。愛があることを証明するものはただ一つ,すなわち二人の結びつきの深さ,それぞれの生命力と強さである。
自分から逃げないこと,自分がしようとすること,自分のしたいことと一体化すること,そこからしか出発点はない,当たり前だが,そんな確認からはじめよう。
ふと気づくのだが,これって,究極のコーチングの場そのものなのではないのか。
参考文献;
エーリッヒ・フロム『愛するということ』(紀伊國屋書店)
共同・共働・協同・協働は,微妙に意味が違うようだ。手元の辞書(広辞苑第五版)では,
共同;commonの訳語。二人以上が力を合わせること。協同と同義に用いることがある。
共働;coaction,相互作用。共生的,敵対的・中立的な関係に大別できる。たとえば,捕食者・被捕食者関係。
協同;【後漢書】ともに心と力を合わせて助け合って仕事をすること。協心。
協働;cooperation,collaborationの訳。協力して働くこと。
とある。ネットで見た三省堂の国語辞典では,次のような見解を出している。
「共同」「協同」「協働」は,音が同じで,意味も似ているので,まぎれやすいことばです。このうち,最もしばしば目に触れるのが「共同」,次に「協同」です。「協働」も戦前からあったことばですが,近年,「官民協働」などの形でよく使われるようになったので,『三省堂国語辞典』でも今回の第六版から採用しました。
「協働」の意味は〈同じ目的のために,力をあわせて働くこと〉です。したがって,「官民協働」は行政と民間が力を合わせて働くこと,「協働契約」はメーカーと原材料の生産者などが力を合わせて働く契約,と解釈されます。
ただ,それならば,「共同」や「協同」でもかまわないのではないか,と考える読者もあるでしょう。「協働」を辞書に載せる以上は,「共同」「協同」との違いをはっきり説明しておく必要があります。そこで,両者の語の説明を改めて見直しました。
従来の第五版では,「共同」は〈ふたり以上の人が力をあわせてすること〉,「協同」は〈力を
あわせること〉となっていました。それぞれ違うようでもあり,同じようでもあります。「協働」を含め,どれも結局「力を合わせる」点で共通するようにも読めます。
しかし,「協同」はこれでいいとして,「共同」には「力を合わせる」という要素は必ずしもありません。「共同浴場」「共同受信アンテナ」は,べつに力を合わせて風呂に入ったり,電波を受信したりするわけではありません。施設をいっしょに使っているだけのことです。そこで,第六版では「共同」の語釈を以下のようにしました。
〈ふたり以上の人が いっしょに・する(使う)こと。「―研究・―浴場」〉
「共同研究」は,力を合わせなければ完成しませんが,それは結果としてそうなるものです。ことばの意味そのものは,「力を合わせてする研究」ではなく,「ふたり以上の人がいっしょにする研究」ということです。
ここでは,協働する,と言うところに,単に協力して働くのではなく,目的を共有するということがある。「協」という字には,「合わす」「叶う」「和らぐ」「つきしたがう」という意味がある。だから,やわらぎあうという「協合」,話し合いの「協議」,心を合わす「協心」,あわせてかなでる「協奏」,力を合わせる「協力」がある。
思うに,その時,場ができているかどうかなのだと思う。一人一人の力が消えて,場としての力が主体として動き出す。場をチームと置き換えてもいい。誰かがとか誰々のチームと言っているとき,チームも場もまた自立していない。
ネットで,こんな言葉を見つけた。(http://hetagasaki.blogspot.jp/2012/01/blog-post_29.html)
わたしたちが,最終的に目指しているのは「協働」であろう。「共同」や「協同」は,作業の均一な配分とか成員の均質性を前提とするが,「協働」は,成員間の異質性,活動の多様性を前提とし,異質な他者との相互作用によって成立する。英訳するとイメージがぴたりとくる。協働学習は「collaborative
leaning」である。
思うに,大事なのは,互いの異質さを前提にして,場として昇華できることだ。そのためには,本気の衝突が必要かもしれない。本気の中に,その人の価値と譲れないものが見えてくる。それをどう生かして場にあげていくか。場の中に乗せていくか。その丁々発止こそが,場を場として立たせるカギのような気がする。
昔「踊る仔馬亭」という喫茶店をやっていたことがある。すぐにぴんときた方もあるだろうが,『指輪物語』でホビットたちが逃げ込んだ宿の名だ。あの当時,それに凝っていた友人が訳者にわざわざ断って,名前を使わせてもらった。しかし惨憺たる結果であった。ほぼ二年,お互いの本音をぶつけ合って,どうしていくかを話し合った。言ってみると,場を作り上げるのではなく,どう場を終焉させるかの話だったが,振り返ると,あの話をし続けた三人が,いまもときどき旅に出る仲間だ。あれは,逆向きだったかもしれないが,その前の夢を語る日々は,上っ面の話だったことが,どん底になってみて,初めてわかる。
いまぼくは,この協働について,ひとつのポリシーがある。自分を突っ支い棒とすることだ。いくつもの場がなくなるのを見てきた。大きくは会社,小さくは自分たちのチーム,仲間の場,自分が意思決定に関われなかった場合もあるが,なくなってみて初めてその持つ意味の大きさに気づくこともある。自分にとって大切な場や人には突っ支い棒の役を果たそうと思っている。自分は主役を張るタイプではない。かつては自分を過大評価していたが,今はそう思っている。従って,どう場を支えられるか,小さなことから大きなことまで,自分なりにやってみよう。
「では,また」という言葉を何気なく口にする。しかしもう二度と会えないかもしれない,そういう思いが頭をよぎると,ちょっと気楽には使えなくなる。
一期一会という言葉がある。千利休の弟子の山上宗二『山上宗二記』に「茶湯者覚悟十躰」として,「路地へ入ルヨリ出ヅルマデ,一期ニ一度ノ会ノヤウニ,亭主ヲ敬ヒ畏ルベシ」とあるそうだ。
それを,井伊直弼が自著『茶湯一会集』巻頭で「一期一会」という言葉にして世の中に広めた。あなたとこうして出会っているこの時間は,二度とないたった一度きりのものだから,この一瞬一瞬を大事に,今出来る最高のおもてなしをする,という趣旨であるそうだ。
ところで,さようなら,と言う言葉について,田中英光は,『さようなら』の冒頭,
さようならなくてはならぬ故,お別れしますというだけの,敗北的な無常感に貫かれた,いかにもあっさり死の世界を選ぶ,いままでの日本人らしい決別の言葉だ。
こう書いた。それに続いて,井伏鱒二が,于武陵の「勧酒」という詩の一節,「花発多風雨 人生足別離」を「ハナニアラシノタトヘモアルゾ 『サヨナラ』ダケガ人生ダ」と訳しているのを紹介し,それを太宰が「グッドバイ」の解題に引用している,と述べていた。そして,他の言語のように,神の祝福をとかまた会いましょうと言うニュアンスがないと嘆いていた。
「左様ならば,お別れします」「そういうことならばお別れします」でいう「さようならば」「そういうことなら」というのは,田中の言うようなニュアンスもなくはないが,文脈依存の日本語らしく,その場の二人,あるいはその場に居合わせた人にしか,「左様」の中身はわからない,そういう次第を共有している者同士が,「そういうこと」で,と別れていくニュアンスではないか,と感じる。
かつて会議の後,上司が,「じゃ,そういうことで」と会議を閉めようとしたら,部下の女性が,「そういうことってどういうことですか」と,気色ばんで食って掛かったことがあった。ある意味,「そういうこと」で丸められては困る状況を無理やり閉じようとした上司への強烈なしっぺ返しだったのだが,文脈依存の「そういうこと」だからは,「そういうこと」が共有できていなければ,こういう裂け目がのぞくことになる。
僕自身は,さよらな,という語感には,ちょっとした悲哀とセンチメンタルな心情があって,嫌いではない。
「左様ならなくてはならない運命だからお別れします」と言うと深刻だが,
「そういう次第なのでお別れします」
「そういうわけなら,お別れします」
「そういうわけで,お別れしましょう」
「そういうことでお別れしましょう」
「そういうことなら,(ここで)お別れしましょう」
というふうに,並べてみると,いまの言い方も,その簡略版で,
「…てなことで,お別れします」
「ていうか,じゃあここで」
「それなら,ここで」
「(それ)じゃあ,ここで」
「(そういうこと)では,ここで」
「そんじゃあ,また」
等々と言うが,結局その場にいるものにしか伝わらない,共有した時間と空間の中での,「そういうことで」と言うニュアンスが,言外に含まれている。
しかし,「さようなら」という言葉には,死別は含まれてしない気がする。死別に際して,「さようなら」とはなかなか言いにくい。第一,相手とは共有できないというか,共有したくないというか,そういう思いが強いので,文脈は,こちらとあちらでは「そういうことなので」とは了解しがたい。でも,そのためか,最近,「では」とか「それじゃあ」と言って別れる時,一期一会が強く意識されるようになった。
ユングは40歳を「人生の正午」にたとえていた。その意図は,「午前の太陽の昇る勢いはすさまじいが,その勢いゆえに背後に追いやられたもの,影に隠れてしまったものがたくさんある。それらを統合していくのが40歳以降の課題だ」というところにあるのだそうだ。
それが統合できたかどうかは,自分ではわからない。ただ,40代以降の方が,生き生きとしていたという思いはある。いやいや,必死だったというほうが近い。そしていま,日没が近づき,その先が見えるようになると,一日一日,時々刻々が大事だと,我に返ると,気づく。「過ごしてしまった時間」がどういうものだったかが,ふと頭をよぎる。
そう気づくと,「じゃあ,また」「またね」「では」「バイバイ」というふうには簡単に言えなくなる。そんなとき,「さようなら」という言葉が,結構役立つ。「そういうわけなので,お別れします」「それならばここでお別れします」という言葉に,いっぱいの思いがあっても,さりげなく言える。
さようなら,はその都度,そういう次第で,ここまでご一緒に過ごさせていただいたが,いよいよお別れのときが来ました,では元気でお過ごしください,との思いを込めて,言わなければならない。それは去っていく側には言えるが,残される側には言いにくいものかもしれない。
自分を開く以上,そのことで,人と深くつながりたい,そのことを少し深めてみたい。そして,その究極,人との対話をどうしていくのかに話をつなげていければ一応成功。
こんな文章を書きとったメモがあった。出典もあるが,記憶にあまりない。
他の人間そのものに自己を向け,自己の中に世界を受け取る。わたしの存在によって受け入れられ,全実存の圧縮の中に,わたしと向かい合って生きる存在の他者性のみが,わたしに永遠の輝きをもたらすのである。存在のすべてをあげて,相互に語り合い,<なんじはそれなり>というときのみ,彼らの間に現存の住み家が存在するのである。(ブーバー『対話』)
これから,
一人の人をほんとうに愛するとは,すべての人を愛することであり,世界を愛し,生命を愛することである。誰かに「あなたを愛している」と言うことができるなら,「あなたを通して,すべての人を,世界を,私自信を愛している」と言えるはずだ。(フロム『愛するということ』)
が,ちょうと裏返しのように対になっている。「そこにいるあなた」を,他にかけがえのないものとして意識することを通して,そのひとのいる世界を受け取る。それは,裏返せば,その人を愛することを通して,その人がここにいること,あるいはその人がこうして,いま,ここにいる世界をまるごと受け入れることに通じる。その人とともにその人のいる世界を受け入れることだ。
もちろん,これは「愛」について言っている。しかし「愛する」もの同士の関係は,実は相互に相手をどう受け入れるか,という関係性の典型的なあり方を示しているが,特殊な関係ではないような気がする。
アダム・カヘンはこう言っている。
私たちは,すべてのステークホルダーの人間性と自分自身の人間性に目を向け,耳を傾け,心を開き,受け入れない限り,人間の複雑な問題に対する創造的な解決策を生み出すことはできません。創造性を発揮するには,私たちの自己のすべてを必要とします。私たちの思考,感情,人格,経歴,欲望,そして魂を必要とするのです。固定された事実や考えを理性的に聞くのでは十分ではありません。相手が自分の可能性や彼らの置かれている状況の中に存在する可能性に気づくことを促すような聴き方をする必要があります。この種の聴き方は相手の横で感情を共有する,いわゆる「同情」ではありません。彼らの内側から分かち合う「共感」なのです。このような聴き方は,既存の異なる考えに目を向けることを可能にするだけでなく,新しい考えを生み出すことを可能にしてくれます。
そしてこのとき,聴き方について,オットー・シャーマーの4つの聴き方を紹介している。
①ダウンローディング(Downloading) これは,『U理論』で紹介されていたものだが,自分のストーリーの中から聞いているというもので,いつもの自分の言い方,聴き方から離れないやり方である。自分の言っていることや聞いていることが単なるストーリーでしかないことに気づいていず,他人のストーリーには耳を貸さない。自分のストーリーを支持するストーリーだけを聞き取る。
②ディベーティング(debating) 討論という聴き方。このとき,討論会や法廷の審判のように,外側から互いの話や考えを聞いている。
ダウンローディングやディベーティングをしているときは,既存の考えや現実を提示し,再生しているだけで,何も新しいものを生まない,と,アダム・カヘンはいっている。
③リフレクティング・ダイアローグ(reflective dialogue)
内省的な対話。自分自身の声を内省的に聴き,他の人の話を共感的に聴く。主観的に「内側から」聴く。
④ジェネレーティブ・ダイアローグ(generative dialogue) 自分や他人の話を内側から聴くばかりではなく,「システム全体」から聴く。
③④が,世界の紛争当事者との間で,どんな対話をしたのかは,著書を見てもらうことにして,コーチングとの類比を感じました。当然聴くというテーマなのだから,当たり前といえば当たり前だが。
コーアクティブ・コーチングでは,傾聴を3レベルに分けている。
レベル1 内的傾聴 意識の矛先は自分自身。つまり自分の内側の声。自分の考えや意見,判断,感情,身体感覚に意識が向く状態で,クライアントにふさわしい傾聴レベルとする。
レベル2 集中的傾聴 コーチの意識は,レーザー光線のように,クライアントに向いており,すべての注意がクライアントに注がれている。恋人同士の関係性をアナロジーとして使っている。
レベル3 一つのことに焦点を当てるのではなく,自分の周りのあらゆるものごとに意識の焦点を向ける。
つまり,傾聴のレベルでは,少なくとも,自分が「開かれ」ており,「愛」の関係に近く,自分だけではなく,相手および相手の世界に対しても開かれていなくてはならない。
では,それがどう対話につながるかは,次回に。
参考文献;
マルティン・ブーバー『我と汝・対話』(岩波文庫)
アダム・カヘン『手ごわい問題は対話で解決する』(ヒューマンバリュー)
エーリッヒ・フロム『愛するということ』(紀伊國屋書店)
開・聞・愛に続いて,対話への途を考えてみる。
対話について,物理学者デヴィッド・ボームは,こう書いている。
対話では,人を納得させることや説得することは要求されない。「納得させる(convince)」という言葉は,勝つことを意味している。「説得する(persuade)」という語も同様である。それは「口当たりのいい(suave)」や「甘い(sweet)」と語源が同じだ。時として,人は甘い言葉を用いて説得しようとしたり,強い言葉を使って相手を納得させようとしたりする。だが,どちらも同じことであり,両方とも適切とは言えない。相手を説得したり,納得させたりすることには何の意味もないのだ。そうした行動はコヒーレントな(一貫性のある)ものでも,筋の通ったものでもない。もし,何かが正しいのであれば,それについて説得する必要はないだろう。
そして,こういう。
概して,自分の意見を正当化している人は,深刻になっていないと言っていい。自分にとって不愉快な何かをひそかに避けようとする場合も,同様である。(中略)
だが,対話では深刻にならねばならない。さもなければ対話ではない-私がこの言葉を使っている意味での対話とは言えないのだ。フロイトが口蓋の癌に侵されたときの話をしよう。フロイトのもとへやってきて,心理学におけるある点について話したがった人がいた。そのひとはこう言った。「たぶん,話などしないほうがいいのでしょうね。あなたはこれほど深刻な癌に侵されているのですから。こんなことについてはお話したくないかもしれませんね」。フロイトは答えた。「この癌は命にかかわるかもしれないが,深刻ではないよ」。言うまでもなく,フロイトにとっては単に多数の細胞が増殖しているだけのことだったのだ。社会で起きていることの大半はこんな表現で言い表せるだろう-それは命にかかわるかもしれないが,深刻なものではない,と。
自分の問題を脇に置いて,いいのかどうかはわからない。対話は,そのように,相手に対して,自分を開くことなのだ。その時,自分が開いた分,相手も開く。
平田オリザは,対話と会話を,
会話とは,複数の人が互いに話すこと。またその話。
対話とは,向かい合って話し合うこと。またその話。
とし,
会話は,価値観や生活習慣の近い親しいもの同士のおしゃべり
対話は,あまり親しくないもの同士の,価値観や情報の交換
とした。この区別を,中原淳・長岡健は,雑談,議論と対比して,
雑談とは,自由なムードの中で,戯れのおしゃべり
対話とは,自由なムードの中で,真剣な話し合い
議論とは,緊迫したムードの中で,真剣な話し合い
とした。この「真剣」が,ボームの言うように,おのれの身を削るような,深刻さをもっている,という意味で受け止めていい。ただし議論と違うのは,納得や説得ではない,ということだ。雑談には,たとえば,喫煙ゲージの中が濃密な会話になっているように,結構重要なことは雑談で話される。それは別にまた触れてみたい。立ち話の効果というのを結構重視しているので。閑話休題。
ところで,カーネギーの『人を動かす』に,
議論に負けてもその人の意見は変わらない。
とある。対話のイメージは,ブレインストーミングでのアイデアを出していくのと同じだ。批判せず,自由に,相乗りして,たくさん。意見は,仮説と考えて,共通の認識を作っていくプロセスは,ブレストのマインドだと考えていい。たとえば,会話だって,こういわれる。
(自分の)発話の意味は受け手の反応によって明らかになる。
後続する会話によって先行する会話の意味が組み替えられていく。
ここに,対話の面白さがあるはずなのだ。話すことで,その話の中身が,相手の当てる光によって,少し意味を変える。それは,発話したことの中身が,自分が意識しない,幅と奥行きを持っているということなのだ。だから,自分の意味だけに固執すれば,その豊かな意味の世界は閉ざされてしまう。
ボームは,ある深刻な対話のことを,こう書いている。
彼らは互いに説得したかどうかよりも,話し合えたことの方が重要だ。何か違うものを生み出すためには,それぞれの見解を捨てなければならないと,きづいたのかもしれない。愛を好む人がいれば憎しみを好む人がいたとか,疑り深くて慎重でいささか皮肉屋であることを好む人がいたとかといった事実は重要ではない。実のところ,一皮むけば,誰もがみな同じだったのである。どちらの側も頑なに自分の見解にしがみついていたからだ。したがって,その見解に妥協の余地を見出すことが,鍵となる返歌だった。
「開く」の重要性がここにある。閉じていた方が安心というのは,自足しそのままにとどまることを望んでいることになる。
対話で理解が深まるのは,他者のことだけではありません。他者を理解すると同時に,自分自身についての理解を深めることができるのです。「対話」の効果とは何かを考える時,これはとても大切なことですが,「対話」の中で自己の理解を語り,他者の理解と対比することで,自分自身の考え方や立場を振り返るのです。つまり,「対話」は,自己内省の機会ともなるのです。(中原淳・長岡健『ダイアローグ』)
さらに,ミードの例を引いて,こういう。
ミードによれば,自己とは「本質的に社会構造であり,社会経験の中から生じる」存在と理解することができます。もし,世の中に自分一人しか存在しないなら,そもそも「自分らしさ」なんて意識する必要がありません。自分以外の他者がいるから,「他者の目」には自分がどう映っているかを考え始めるのです。つまり,「自分らしさに気づく」とは,他者の目に映る自己イメージ―自己に関する首尾一貫した物語―を自分自身でつくり上げていくということです。人は「自分のイメージ」「自分の物語」を自分だけでつくることができるわけではありません。他者への語りかけ,他者のまなざし,他者の言葉を通して「自分の物語」をつくり,ときには編み直すのが人間なのです。
人とのやりとりを通して,自分が耳にしたこと,人との対比の中で気づいたことを通して,気づきが生まれる。
気づきを積み重ねていくことが,「自己像を紡ぎ出す」=「自己理解を深める」ということです。だから,自己理解を深めるには,ひとりであれこれと思い巡らすだけでなく,「対話」を通じて,自分の考え方や価値観を他者に語ることが効果的なのです。
対話は,結果として,自分の物語を語ることを通して,それぞれが自己理解を深めると同時に,二人,ないし三人,その場の対話相手と一緒に,きったく新しいストーリーを作り出していく場でもある。つまり,
人は「対話」の中で,物事を意味づけ,自分たちの生きている世界を理解可能なものとしています。人が物事を意味づけるときに,独りでそれに向かっているのではありません。相互理解を深めていくには,単に「客観的事実(知識・情報・データ等々)そのもの」を知っているだけでなく,「客観的事実に対する意味」を創造・共有していくことも重要となるのです。特に,個々人の経験や思いについてストーリーモードで積極的に語り合うことで,自己理解と他者理解が相乗的に深められ,新たな視点や気づきが生まれてくる…
そういえば,ドラッカーは,情報とは,データに意味と目的を加えたものである,と言っていたが,一人ひとりが,「客観的事実に対する意味」を語る,それをどう受け止めて,それからどうなったかと,「自分の考え方や価値観を他者に語る」ということは,客観的な何某の知識・事実ではなく,自分の側で起きている主観的な世界を語ることになる。「語る」ということ,それを「ストーリーモード」と呼んでいるが,それは自分を対象として,自分の物語を語ることになる。
参考文献;
アダム・カヘン『手ごわい問題は対話で解決する』(ヒューマンバリュー)
中原淳・長岡健『ダイアローグ』(ダイヤモンド社)
デヴィッド・ボーム『ダイアローグ』(英治出版)
平田オリザ『わかりあえないことから』(講談社現代新書)
対話ということを考えていくうちに,「自分の物語を語る」へと行きついた。
フランクルが,人は誰も自分の語りたい物語をもっている,と言っていたが,というのも,物語るエピソードそのものが,かけがえのないその人の人生の時間そのものだからと思えてならない。それは,その人と,それを共体験した人とでしか共有できない。
いや,一緒に体験したところで,それはその人の体験で,自分の体験ではない。所詮,人の見ている現実は,その人だけのもので,その色合いも,肌合いも,心映えも,光景も,一緒に居ても,同じではない。人は,同じものを見ていても,同じように見えているとは限らない。にもかかわらず,共体験したものでしか,思い出は共有できない。まあ,そこに,写真だの,コトバだのがあり,物語もまたその一つなのかもしれない。
人の認知形式,思考形式には,「論理・実証モード(Paradigmatic Mode)」と「ストーリーモード(Narrative
Mode)」がある(ジェロム・ブルナー)があるとされている。前者はロジカル・シンキングのように,物事の是非を論証していく。後者は,出来事と出来事の意味とつながりを見ようとする。
ドナルド・A・ノーマンは,これについて,こう言っている。
「物語には,形式的な解決手段が置き去りにしてしまう要素を的確に捉えてくれる素晴らしい能力がある。論理は一般化しようとする。結論を特定の文脈から切り離したり,主観的な感情に左右されないようにしようとするのである。物語は文脈を捉え,感情を捉える。論理は一般化し,物語は特殊化する。論理を使えば,文脈に依存しない凡庸な結論を導き出すことができる。物語を使えば,個人的な視点でその結論が関係者にどんなインパクトを与えるか理解できるのである。物語が論理より優れているわけではない。また,論理が物語りより優れているわけでもない。二つは別のものなのだ。各々が別の観点を採用しているだけである。」(『人を賢くする道具』)
要は,ストーリーモードは,論理モードで一般化され,文脈を切り離してしまう思考パターンを補完し,具象で裏打ちすることになる。
エドワード・ソーンダイクは,人間が物語を記述するための抽象的ルール体系を頭の中に持っていると仮定し,それを物語文法と呼んだ。たとえば,
設定
テーマ
プロット
解決
の項目に従って,
誰が,いつ,どこで,どのような事件に巻き込まれて,どんなトライアルを行い,どういう結果が生まれたのか,
を把握しようとする。そして,実験の結果,物語の提示が,物語文法の順序と一致しているほうが,文章の記憶や理解が促進されることを発見した。この辺りは,記憶術とリンクする問題かもしれない。つまり,物語性を持たせた方が,記憶する事項のつながりが記憶にとどまりやすい。それは,もう一か月前の,ランダムな言葉を,思い出せるところからも証されている,といってもいい。
さらに,ロジャー・C・シャンクと,ロバート・P・エイベルソンは,人の会話を理解するコンピュータシステムを開発する中で,人間の知識は,ステレオタイプ化された状況とそれに伴う習慣化された行動とのセットからなる「劇の台本のような物語」として表現されているとして,それを「スクリプト」と呼んだ。
面白いことだが,ひとつの物語を記憶から引き出すと,別の物語(あるいはエピソードといった方がいいかもしれない)が,例えば,たった一つのシーンから,別のシーンにリンクして,思い出の連なりが思い起こされてくる。そうやって,自分の中にある,メインのストーリーは別に,様々なスピンアウトした物語が,紡ぎ出せる。
その意味で,自分の物語を語り直す,あるいは語ることで,自分の人生に違う光が当たり,そこから,未来に別の岐路が開く。語ることで,その道とつながる,という気がしてならない。
ナラティブセラピーで悲嘆の起因を延々とした物語で紡ぎ出し,いまの自分を貶めているドミナントストーリーに対して,別のオルタナティブストーリーを導き出すことで,自分への信頼を取り戻そうとするというのは,だから,故なきことではない。
その意味で,コーチングには,その人の過去の物語ではなく,新しい未来の物語を一緒に紡いでいくという意味で,セラピーとは違う光の当て方で,ナラティブコーチングと言うのはありうるし,現にやっていることはそういうことなのだと思う。
参考文献;
中原淳・長岡健『ダイアローグ』(ダイヤモンド社)
年甲斐もない,と言われそうだが,また「好き」のことを考えてみたい。
どうしたら好きになるか,については,好意の互恵性だの,相手の自己開示だの,接触頻度だのとあるが,一瞬の胸の鼓動の高まりのような(と書きつつ,もう心臓にもカビが生えて,感受性も鈍ってしまっているので,はるかな昔のことを思い出すしかないが),その一瞬というのは何なのだろう(と,書けること自体が,そういう心理状態からは距離がある証拠か?)。
で,結局自分を好きになっているのだ,と考えたが,それはそれとしてあるかもしれないが,そこだけには納まらないものがある気がしてならない。
好きという感じを表現すると,
同じ空気を吸いたい
同じステージに居たい
同じ場所を占めたい
同じ時間を生きたい
といった感じのような気がするが,もっと踏み込むと,人は生きている限り,ひとつの場を占めている。その「場」には,時間と空間はあるが,ハイパーなので,一定の場所に固定されているわけではない。もちろんその人がそこにいるという物理的な場だけを意味しているのではなく,その時代の,その社会の,大袈裟に言うと,この地球に,一定の空間(時空という方がぴったりする)を占めている。その「場」を共有したい,という思いなのかもしれない。
あるいは,共有することで,その「場」がもっと豊かになる,もっと楽しくなる,もっとわくわくする等々の期待が膨らむのかもしれない。
どちらか一方に倣うとか,どちらかに一方に従うとか,どちらかと一体になるといことではない。それでは,誰かの人生と一緒になることであり,自分人生の「場」を捨てることだ。そういうのは,僕のイメージしているものには入らない。それなら,二つの「場」がぶつかり合い,丁々発止するわくわく感はない。それぞれがそれぞれの「場」を,自分の努力と好奇心と興味で膨らませ続ける。そうすることが,二つの場が,出会うたびに,新しい出会いの昂奮を生み出す。そこから,何かが生まれるかもしれない。そうやって成長する「場」同士が,ぶつかり合う,機会がほしいのかもしれない。
それって,協同作業とよく似ているし,ブレインストーミングの自由なキャッチボールにも似ている。本来,コーチングも,そういう場であれば,コーチもクライアントも,ともに,そのコーチングという場での出会いが,数倍数十倍わくわくするものになるはずだ,と思う。そこで生まれるのは,是非,可否の二者択一ではない,足して二で割るような妥協でもない。それぞれの人生の「場」が面からぶつかりあうことで,生まれてくる新たな別の何かだ。でなければ,ブレインストーミングをする意味はない。
だから,どちらの場も,それ自体で生き生きし続けなくてはならない。そして,出会う時,その二つの場のぶつかり合い,あるいはダンスの中から,全く別の場を,それぞれが掴み取る,そういう出会いであり,そういう機会が,両者を成長させ,それぞれの「場」がさらに豊かになっていく。
それが勘違い,思い込み,錯覚ということを後で気づくことはある。同じ場として成立しないことに気づくからだ。でも,それも,ひとつの出会いであり,それぞれの場が豊かになって行くプロセスと思えば,無駄でも消耗でもない。何せ,それも,おのれが生きていく場の,消長なのだ。いずれ,その場はなくなる。なくなっても,いつまでもそこに,名残りのような隙間を残す,隙間があるような思いを残す,そんな場でありたい。そういう生き方でありたい,と思う。そのために,何かができるのではないか,そういう出会いへのわくわくする期待なのではないか,と思う。
歳のせいか,最近自分が時代おくれになった,もう時代の流れにいないということを実感するようになった。先日のあるトークライブで,
50~60代ではなく,30~40代でなくてはだめだというニュアンスの話を聞いたせいばかりでもない。実感としては,ひどく寂しさを感じている。
まずはそこを認めるところから始めたい。
では時代おくれとはどういうことなのだろう。
河島英五の歌に「時代おくれ」というのがある。「時代おくれ」というタイトルが気になって,改めて歌詞を読んでみた。でもこれは時代おくれというよりは,つつましやかなお父さんの自恃の歌,あるいは自戒の歌ではないか,という気がする。
一日二杯の酒を飲み
さかなは特にこだわらず
マイクが来たなら 微笑んで
十八番を一つ 歌うだけ
妻には涙を見せないで
子供に愚痴をきかせずに
男の嘆きは ほろ酔いで
酒場の隅に置いて行く
目立たぬように はしゃがぬように
似合わぬことは 無理をせず
人の心を見つめつづける
時代おくれの男になりたい
不器用だけれど しらけずに
純粋だけど 野暮じゃなく
上手なお酒を飲みながら
一年一度 酔っぱらう
昔の友には やさしくて
変わらぬ友と信じ込み
あれこれ仕事もあるくせに
自分のことは後にする
ねたまぬように あせらぬように
飾った世界に流されず
好きな誰かを思いつづける
時代おくれの男になりたい
目立たぬように はしゃがぬように
似合わぬことは 無理をせず
人の心を見つめるつづける
時代おくれの男になりたい
これは僕の時代おくれのイメージではない。時代おくれとは,感傷的に,さみしさを開き直るのでも,もちろん世の中をすねることでもない。時代おくれという以上,おくれる前がなくてはならない。その時,時代と同時に走っていて,置いて行かれたというなら,単なる落伍になる。そこで開き直ったところで,見苦しいだけだ。時代おくれを矜持ととらえたり,美学ととらえたりするのは,開き直りの一種でしかなく,みっともない。
では,何が時代おくれなのか。いまも懸命に走っている。もちろん若いころのスピードはないが,気づくと,息切れしたり,妥協したり,粘りが失せて,少しずつ時代とずれ,おくれを取り始めている。だが,ここでリタイアしたり,離脱するのは,時代おくれとは言わない。それは道からのいたというだけだ。まだ時代の中で,戦い続けていなくては,時代おくれとは言えない。たとえば,周りから見れば,ドンキホーテでも,本人は恐竜と戦っているつもりでなくてはならない。たとえば,
●時代のスピードについていけない(というか,ついていけなくてもすんでしまう)
●新しい技術についていけない(というか,ついていかなくてもすましてしまう)
●新しい流行・トレンドを知らない(というか,知らなくてもすんでしまう)
●時代への批判力を失う(というか,まあいいか,とすませてしまう)
●時代と格闘しようとしない(というか,しないですむところにいる)
●過去の延長線上から離れられない(というか,それしか知らない)
●若い人とキャッチボールができない(というか,相手にされていない)
●時代への苦情や文句しか言わない(というか,ほとんど自己完結した独り言)
等々の現象が起こっていても,戦線離脱をしてはいない。あくまで,主観的かもしれないが,最前線に立ち止まって,戦場に踏みとどまっている。しかし,主観に反して,戦場の主力とはみなされず,遅れていく。そういう場合だけを「時代おくれ」と呼ぶ。でなければ意味がない。
確かに,時代の最先端を作っているのは,働き盛りの30~40代に違いはない。時代おくれどころか,最先端にいるつもりなのに,悲しいかな,仲間の足を引っ張りかねない自分に,ある時,ふっと気づく。
では,時代おくれにならない指標は何か。リストアップしてみると,こうなる。
①たえず新しいものを創り出す思考力があるか
②おのれ自身の頭と感性でアウトプットを出し続けているか
③時代の先を読み,次に何をすべきかの先手を打っているか
④過去の延長線上ではなく,フラクタルに,あるいは非線形的に,新しい未来を作り直せているか
⑤自分の旗を立て,人を引っ張って,先頭を走る力があるか
⑥新たな業を創り起こす構想力があるか
⑦まだ先達の教えを乞い学び続ける成長への意欲があるか
⑧新たなコラボレーションの場を作っていくリーダーシップがあるか
⑨新しいことへの好奇心と関心に引っ張られて探索し続ける探究心があるか
⑩最先端に立ちはだかる壁を突き破る突破力があるか
⑪あらゆる情報にアンテナを立てその意味を再構成していく判断力があるか
⑫協働する仲間を絶えず維持・強化していける魅力があるか
⑬政治へコミットメントをするパワーがあるか
⑭既成の利権や権威に対する批判力はあるか
⑮人を目利きし,育てるエネルギーはあるか
⑯時代の潮流に棹さしおのれを生かし切る行動力があるか
⑰時代の潮目を見切り大胆な方向転換する勇気はあるか
⑱長老,功労者,権威者におもねらずおのれを律するプライドはあるか
⑲作り上げたものをリセットして作り直すクリエイティブな情熱があるか
⑳妥協や中庸を拒み,あくまで尖がって走り続ける気概はあるか
丸まらず,物分りよくならず,訳知り顔にはならず,絶えず尖がって走り続け,時代の真ん中に居続ける。そういう気骨あるつもりでも,時代からずるずると,置き去りにされていく,その不安こそが,時代おくれという精神でなくてはならない。その心意気だけは失ってはならない。歎いたり,すねたり,ましてや苦情や文句だけを言うようになったらおしまいだ。老人かどうかというより,人間としておしまいだ。まして,安全なところから,人を煽るだけだったり,評論家になっていては,もう論外。
不遇時代の美空ひばりが,焦らず,怒らず,諦めず,を自戒していた。いつも,それを,こう言い換えている。腐らず,驕らず,諦めず,と。
尻切れ蜻蛉
あるいは
尻切り蜻蛉
は,辞書(『広辞苑』)によると,
仕事が完結せず,中途で途切れて後が続かないこと,
とある。
完結しないことのたとえ,
ともあるから,まあ,
未完了,
というわけだ。で,「尻切れ」を引くと,
うしろの方が切れていること,中途で終わっていること,
「尻切れ草履」の略。
「尻切れ半纏 (ばんてん) 」
とある。ということは,「尻切れ」自体で,
中途で終わっている,
という意味がある。それに,「蜻蛉」をつけたのはどういう意味なのだろう。
『大言海』には,「しりきりとんぼ」として出ている。
「物事をなすに,断断(きれぎれ)となりて,永続せぬ人を罵り云ふ語」
と,極めて限定した使い方だと言っている。で,「尻きれ」を見ると,
「藁草履の類。」
としかない。つまり,尻切れは,藁草履を指し,その類比から,中途半端ということに意味が広がったのではないか,と推測されるのである。
藁草履を引くと,
藁を編んで作った草履,
とある。では草鞋とどう違うのか。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E9%9E%8B
に,両者の違いについて,こうある。
「草鞋または鞋(わらじ)は、稲藁で作られる日本の伝統的な履物の一つである。同様に稲藁で作られる藁草履(わらぞうり)と混同され易いが、形状が若干異なる。草履が現在のサンダルに近い形状であるのに対し、草鞋は前部から長い「緒(お)」が出ており、これを側面の「乳(ち)」と呼ばれる小さな輪およびかかとから出る「かえし」と呼ばれる長い輪に通して足首に巻き、足の後部(アキレス腱)若しくは外側で縛るものである。鼻緒だけの草履に比べ足に密着するため、山歩きや長距離の歩行の際に非常に歩きやすく、昔は旅行や登山の必需品であった。また蹄鉄のない江戸時代には、馬にも馬用のわらじを履かせてヒズメを保護していた。」
いま藁草履は,オシャレや健康グッズとして売られているが,これを見る限り,「尻切れ蜻蛉」にはつながらない。実は,
尻切れ草履,
というものがあるらしい。現在の感覚だと,
はき古して、かかとの部分が切れてしまっている草履,
という意味に受け取るが,もうひとつ,
かかとに当たる部分がなく、後ろのほうが切れたように見える短い草履。足半(あしなか)。しりきれ,
というのがある。
http://members3.jcom.home.ne.jp/pehota02/equipment/foots/ashinaka.htm
によると,
見た目以上に便利な履物で、今ではその名前すら忘れ去られつつある足半であるが、中世の武家にはポピュラーな履物であったし、半世紀前くらいの農村では、立派な現役の履物であった。
現在でも鵜師の足下に見る事が出来る。」
しかし,なぜ,蜻蛉なのか,
http://www.lance2.net/gogen/z415.html
に,面白い説明があった。
「『尻切れトンボ』の『トンボ』っていうのは昆虫の『トンボ』じゃなくて『トンボ草履』っていう昔ながらの履物からきているんだよ。『トンボ草履』にはかかとがないんだけど、その様子から『尻切れトンボ』という言葉が生まれて段々と一般化していったと考えられているんだ。」
と,つまり「足半」を,「蜻蛉草履」と呼んだ,という。辞書(『広辞苑』)には,
「鼻緒の先を蜻蛉の翅のような形に結んだ草履。田野,会場で働くときに用いる。足半という地方もある。」
とある。先の足半の別の写真を見ると,結び目がある。
調べていくと,何ということもないが,生活の中から消えてしまうと,言葉が宙に浮く。かつては,
尻切れ蜻蛉
というとき,足半がイメージとして明確に浮かんでいたに違いない。
しかし,尻切れ蜻蛉,という言葉は,単なる中途半端,未完了,道半ば,とは違うニュアンスなのではないか。足半は,草履から見れば,尻切れだが,それはそれで,完了したものだ。どうも,
尻切れ蜻蛉,
というとき,世の基準から見たら,まだ未完了だと,咎めている,という含意がある。しかし本人にとっては,必ずしもそうではないかもしれないのである。ここが,
未完了
と
尻切れ蜻蛉
の違いのように見える。
ちなみに,「尻切れ半纏」というのは,腰の辺りまでしかない、たけの短い半纏,これも「しりきれ」と略すらしい。
それにしても,
極楽蜻蛉,
だの
蜻蛉返り,
だの,蜻蛉にまつわる言葉が多い。蜻蛉返り(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba2.htm#%E8%9C%BB%E8%9B%89%E8%BF%94%E3%82%8A)については触れた。
人を嫌う場合,相手の中にある自分を嫌うという言い方がある。それを否定はしないが,どうも自分で引き受ける,というか自己内省という,そういう姿勢は悪くはないにしろ,そういうことで,本来は別のはずのモノが,結局自分の側に嫌う原因がある,だから,自分を正せという方向に行く。しかしそういう説明だけでは納得しきれないものがあるような気がしてならない。たとえば,逆に「好き」というのは,自分の中に似たものがいっぱいあるからといえるのか,というと,どうもそうでもない気がする。
僕自身について言えば,最近気づいたのは,人を嫌うということは,あまりないようで,うん十万貸したままドロンされても,その人を嫌いにはなれない。人に振られた程度では嫌いにはならないし,相手によほど敬遠されても,それでも好きではなくても,嫌いにはなれない。まあ,自分に返ってくると言えば,その通りで,結局自分を責めて,まあおしまい,となることが多い。ただ,あえて言えば,相手が自分を嫌っていれば,そうなるかもしれないが,人間関係が薄いせいか,そう手ひどく憎まれも嫌われもしていない(と勝手に思っているから,そう感じるだけかもしれないが)。
嫌いという時,食べ物はどうか,蛇やゴキブリはどうか,やくざはどうか,性犯罪者はどうか,家庭内別居している相手はどうか,と考えていくと,そう一概には,自分の中にあるとばかりは,言えそうもない気がしてくる。
たとえば,「嫌い」にあるのは,思いつく限りで(学問的なことは別として),その反応パターンをあげてみると,
①生理的反応
②生得的反応(本能的反応)
③価値的反応(感情的反応も含まれる)
④社会的反応(慣習的反応)
⑤文化的反応(地域性や日本性による)
⑥関係性的反応
がある気がする。
生理的反応は,生理的に受け付けないものなので,忌避感や嫌悪感を催すものは,ある意味で共通している。たまにゲテモノ趣味はあるが。これは,自分の中にあるなしはどうも関係ない。
生得的というのは,成育歴を通して感じてきたもので,たとえば,父を憎んでいれば,父に似たものを嫌うという傾向はある。しかしこれは第一印象のようなもので,そのうちに消えて行くことがある。食べ物もそうだが,ピーマンはいつの間にか,好きではないが,嫌いでもなくなっている。
価値については後に回すとして,社会的反応は,社会的差別や忌避とつながる。社会的に忌避するもの,乱暴者,犯罪者等々を嫌うということはある。だが,かつて(もうふた昔前のことだが),留置所で(何でそこにいたかは内緒だが)一緒になったやくざは,個人的に知り合うと,嫌な奴ではなかった。というよりも,池袋をしまにしているらしいのだが,一度遊びに来いかなどと言われた。これは,その相手との距離感の問題だ。
かつて,父親が地方新聞のコラムに書いていたのだが,映画館で,後ろの席にいるやつが,映画の中の悪人を罵倒していた。よほどの正義感かと思って振り向くと,かつて自分が取り調べた小悪人だった,という。一定の距離感の中にいると,個人的親密さとか認知が高まり,相手を知れば,社会的な反応としての,やくざだからという「嫌い」度は,その距離から離れれば離れるほど,高まるのではないか。
これは,いわゆる単純接触効果(ザイアンスの法則)といわれるものと関係があり,接触頻度が高いほど,好意をいだきやすい。これは,関係性的反応とも関係してくるかもしれない。
文化的反応としては,その人の価値にも関わるところがあるし,社会的な反応に関わるところもある。例えば,AVやDVなどへの反応には,個人としての価値に反するという「嫌い」もあるが,社会的な意味で,「嫌い」という反応もある。ここは,価値に絡んで,是非は言えない部分で,犯罪すれすれのところだってありうる。
関係性的というのは,相互の関係性からもたらされるものという意味だ。たとえば,好意の互恵性,ということがあるので,相手が自分に好意を持っていれば,こちらも好意を懐きやすい,当然,「嫌い」も互恵性がある。また自分の所属集団に好意を抱きがちなので,身びいきや愛国心も,自分の所属する集団への好意から敵対相手への「嫌い」が増すことになる。
価値という部分について,例えば,人が人を殴るシーンを目撃した時,「嫌悪」が起きるのは,自分の中にもそういう暴力性があるからだ,という説明がされ,この場合がもっとも,もっともらしく聞こえる。
確かにそういう部分も少なくないかもしれないが,それは価値に関わっているからだと僕は考える。暴力が好きな人もいるかもしれないが,基本は人は暴力を嫌う。これは,扁桃体の反応でもある気がするが,それよりは,その人が生きていくうちに,コアにしている倫理(人としての生き方)に関わるのだと思っている。恐らくは,多くは親や環境から身に着けてきた,その意味ではコヒーレントな(一貫した)何か,なのだ。それを軸と呼んでしまうと,身も蓋もない。
ただ,最近の研究では,「好き」と「嫌い」は別のもので,「好き」の上昇は,「嫌い」を減少させない,という。「好き」でもあるし「嫌い」でもあるという両価性,アンビヴァレンツもあり得る,ということなのだが,言葉に,
「好悪」はあるが「好嫌」はない。言葉の世界では,「好き」の反対は,「悪む」なのだ。
ちょうどいま『あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか』(レイチェル・ハーツ)を読んでいる。その感想を含めて,次はもう少し展開してみたい。
場が主役といった場合,その場をどう枠づけるかがカギになるのだろうか。もう一度前回のまとめを繰り返すと,
場という時,次の3つを考えてみる必要があるのではないか。
ひとつは,その場の構成員相互の関係性と言い換えてもいい。別の人とだったらそうはならなかったかもしれない。
ふたつは,その場の構成員相互の行動・反応である。ある行動(非言語も含め)にどうリアクションがあるのか等々。
みっつは,その時の状況(文脈)である。明るい日だったのか,寒い日だったのか,うるさい環境だったのか等々。
その時の全体の雰囲気である。前項と関係があるが,フィーリングと言ったものである。
これが場の構成要素だとすると,B=f(P, E)は,場(field)=Fを中心に,
F=f(P, E,B)
となるのではないか,ということであった。数学的に正しい表現なのかどうかわからない。しかし場があるからこそ,相互の関係も,その場の雰囲気も変わっていく。その意味で場を地ではなく,図として考えてみる。
これについて思いつくのは,金井壽宏と中原淳の対談(『リフレクティブ・マネジャー』)で中原がこういっていることだ。
ジーン・レイヴとエティエンヌ・ウェンガーは,人材育成と組織行動の関係を理解するのに役立つ革新的な枠組みを提唱した。「正統的周辺参加」(Legitimate
Peripheral
Participation)と呼ばれるそのモデルは,「個人としての学習効果をいかに組織としての仕事に結び付けるか」という問題提起を否定し,この問題の前提にあった「学習-仕事」「個人-組織」といった二項対立的な認識に変更を迫った。
といい,そのモデル「リベリアの仕立屋」をこう説明する。
西アフリカのリベリアの仕立屋では,徒弟は衣服製造の仕上げ,つまりボタンをつけたりする工程から仕事をおぼえ,それができるようになると,生地を縫うこと,さらに生地の裁断というふうに,製造ステップとはちょうど逆の順番で学習していく。これにより,最初に徒弟は衣服の全体像を把握でき,前工程がどのように次の工程に役だっているかを理解しやすくなる。その上,店としては失敗がない。服を作るうえで,一番難しいのは裁断であり,次が縫製で,一番ミスが許されるのはボタン付けだからだ。
こうした正統的周辺参加モデルにおいては,新人(学習者)にとって学習は,仕事の中の日常的行為に埋め込まれたものであり,「学習-仕事」という対立概念は存在しない。(中略)共同体の実践活動に参加するときに,学習者が意識しているのは,知識やスキルの習得などシステマティックに細分化された目的ではなく,トータルな意味での実践活動における行為の熟練だ。傍目には「新人が知識を身に着けた」とか「新人が重要な問題点に気づいた」というふうに見えても,学習する本人は「いい仕事をしよう」と思っているだけで,「今,自分は学習している」とは考えていない。
そんなのは職人の世界やブルーカラーのだけだと言われるかもしれない。しかし,中原はこう言っている。
正統的周辺参加モデルはホワイトカラーの職場にも見られる。人がよく育つと言われる職場では,一人の課長がぐいぐい引っ張るというよりは,メンバーそれぞれの成長度合いに合うように仕事をうまく配列されていて,相互に助け合いの関係がある。そういう職場や職場内の関係をつくることも,「教育者」としてのマネジャーのお役割ではないかと私は思う。
ここから,二つのことを連想する。
ひとつは,職場長は,その職場の風土そのものだ,ということだ。風土が変わると職場が変わる。
ふたつは,かつて,ある百貨店の,全新人の10年後をフォローした調査で,入社3年間についた上司で,その新人の成長度(伸び白)というか,出世が決まる,と言われたことがあった。その職場の上司が,新人に何を教えたかだ。
ジーン・レイヴ,エティエンヌ・ウェンガーは,言う。
学習を正統的周辺参加と見ることは,学習がたんに成員性の条件であるだけでなく,それ自体,成員性の発展的形態であることを意味する。私たちはアイデンティティというものを,人間と,実践共同体における場所およびそれへの参加との,長期にわたる関係であると考える。
そこで得られる知識も大切だが,「共同体と学習者にとっての参加の価値のもっと深い意味は,共同体の一部になるということにある」のだ。
訳者の佐伯胖さん,全ての学習がいわば「何者かになっていく」という,自分づくりなのであ」る,と言っている。とすると,「場」が,そういう人を作り出していくのでなくてはならない。
そういう機会はいっぱいある。たとえば,すぐれたコーチやカウンセラーを見ていると,自分の勉強会を自分がやっていたのが,そこで学んだ人が,今度は自分が代わってその場を運営したり,外へ新たな会を横展開させたりしている。それも,「リベリアの仕立屋」バージョンといっていい。
自分はいま,本当に学びたいことがいっぱいある。しかし,しなくてはならないと感じていることも一杯あってなかなか全てには出つくせないが,そういう「場」を見つけることだけでなく,(いまさらめくが)そういう「場」づくりを手伝うことにも,目を向けてみたいし,それをやってみたいと思っている。それがまた自分の成長につながる,という気がしている。
参考文献;
ジーン・レイヴ&エティエンヌ・ウェンガー『状況に埋め込まれた学習』(産業図書)
中原淳・金井壽宏『リフレクティブ・マネジャー』(光文社新書)
コミュニケーションで言えば,良寛には,「戒語」といわれる戒めがいくつかあるが,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod065.htm#%E8%89%AF%E5%AF%9B%E6%88%92%E8%AA%9E
これは,いわばしゃべり方や振る舞いを言う。つまりコミュニケーション・タブー集だ。ここでは,それよりは,コミュニケーション齟齬をなくすためにどうしたらいいか,そのためのちょっとした工夫に触れたい。言ってみれば,できている人にとっては,ありきたりで,当たり前のことなのかもしれないが。
例えば,職場やチームで,コミュニケーションがとれているとは,どうなっていたらコミュニケーションがとれていることなのだろうか。
コミュニケーションが必要なのは,役割を割り振って,あとは蛸壺にはいってひとりひとりが背負い込んで黙々と仕事をする職場にしないためだろう。そういう職場は,チームにはなっていない。単なる個人商店の集まりにすぎない。あるいは組織として仕事をしていない。
仮に組織やチームの目指すものをどう分担するかがわかっていたとしても,チームではないのではないか。チームで仕事をするとは,一人で仕事を抱え込まず,他人にも仕事をかかえこまさない仕事の仕方のことだと考えている。そこではどんな仕事も,自分一人でやっているのではないという了解がとれている,些細な問題もチームに上げ,チームで解決すべきことはチームで解決しようとし,上位部署もまきこんで解決すべきことは上司を介してより上位にあげていく。そのときもし自分のやるべきことをチームにあげたとすれば,「それは君の仕事だ」と,本人につき返すことができるのが,チームなのではないか。そういうコミュニケーションがとれていてはじめて,チームの要件としてのコミュニケーションがとれているといえるのではないか。と,まあ考えている。
いきなりそこまでは無理として,とりあえず,ぎくしゃくしたコミュニケーションではない,あるいはせめてコミュニケーションの齟齬がない,言った・聞いてない,頼んだ,頼まれてない,という消耗なやり取りを減らすにはどうしたらいいのか。
まず,第一は,コミュニケーションの開始に手続きがいるのではないか。あるいは手続きがわかれば,せめて歩留りはよくなるのではないか。
コミュニケーションは自分の話したことではなく,相手に伝わったことが,自分の話したことである,と言われる。仮に自分が10話したとしても,相手に2しか届いていなければ,私の話したことは,2だということだ。そうなれば,相手にできるだけ届くようにする必要がある。
そのために,まずは,相手に聞く姿勢になってもらう必要がある。何かをしながら,聞くのではなく,こちらを向いて,自分の話を聞く身構えになってもらわなくてはならない。
そのためには準備作業がいるはずである。話し手と聞き手の両者が,共通の何かについて話す・聞く関係をとっているという,仮にそれを土俵と呼ぶとすると,同じ土俵に立っていることを意識してもらわなくてはならない。同じ,話す・聞く関係性を意識して初めて,聞くのが始まると考えなくてはならない。
たとえば,一対一の対話なら,
「いまちょっといい?」
「いま,5分いい?」
「ちょっと話がしたいのだが,いい?」
「いま手が離せる?」
等々と,聞くところからはじまるだろう。
相手が都合が悪いと言えば,
「何分後ならいい?」
「後でまた声かけてみるから,その時よろしくお願いします」
等々とやり取りするかもしれない。ミーティングなら,事前の日程調整からはじまるだろう。
なぜこんなことにこだわるかというと,人は仕事しながら,聞いているときは,こちらが話している途中から,意識しだすかもしれない。あるいはうわの空で聞き流すかもしれない。だって,何かしているときは,そちらに意識が向いている,聞こえる声に意識が向くまでは,タイムラグがある。
仮に,いいと言っても,こちらに向き直ってくれるまでは,意識は,途中の作業の方に向いているかもしれないのだ。
そこで第二に,共通の土俵にのっていなければ,歩留りは悪いはずである。口頭のメッセージの歩留まりは25%という説がある。ましてや,何かをしながらでは,もっと歩留りが悪いはずだ。
どのレベルのコミュニケーションでも,相互の間で,お互いに「どういうテーマ(話題)」を話しているかについて共通認識ができていなければ,すれ違いざまの挨拶にすぎない。共通に何について話しているという土俵がないところでは,コミュニケーションは成立しないとかんがえるべきだろう。仮にコミュニケーションしても,「言った,言わない」が必ず起きる。あるいは頼みごとなら,とんでもないことが実行されたりする。
一対一なら,「ちょっといい」といい,相手が向き直ったら,「何々について話したい」のだが,いいかと,確認することになるし。ミーティングなら,アジェンダの周知になるだろう。ミーティングでやることが,一対一のコミュニケーションでもひつようなのだろう。
そこで,少なくとも,何かについて,一緒に話している認識はできる。しかしそれでOKかというと,そうでもない。人は,聞きながら,勝手な解釈をする癖がある。例えば,前にもふれたが,記憶には,
・意味記憶(知っている Knowには,Knowing ThatとKnowing Howがある)
・エピソード記憶(覚えている rememberは,いつ,どこでが,記憶された個人的経験,自伝的記憶と重なる)
・手続き記憶(できる skillは,認知的なもの,感覚・運動的なもの,生活上の慣習等々の処理プロセスの記憶)
がある。意味は同じでも,まったく違うイメージを各自が自分のエピソード記憶から当てはめているかもしれない。
そのために,伝え方にも工夫がいるかもしれない。たとえば,
・一時にたくさんのことを伝えない,
・簡潔に,言いたいことは三つ,1つは何々,2つは何々,3つは何々,と明確にする,
・簡潔な刷り物(メモ)を一緒にする。そうすると,歩留りが50%を超えるという説がある,
・大事なことを繰り返す,
・できるだけ,誤解を生まないような具体的な表現で,具体例を添える,
等々が考えられる。
第三は,伝わったことが話したことなのだから,相手に何が伝わったかの確認がなくては会話は終了していない。
相手にどう受けとめられたかを確認するためにも,相手からのフィードバックなくては,会話は終わらない。どう受け止めたか,復唱,再現,リピート,感想,意見等々,相手に応じたフィードバックをもらうことで,伝わったことが確認できる。
第四は,指示や依頼についても,終わった後のフィードバックがいる。
「終わったら,声をかけてね」
「終わったら,連絡ください」
「終わったら,どうなったか知りたいので,面倒でしょうが,一報ください」
ということを一言加える。あるいは,これをルールや慣習にしてしまえれば,楽になるのだが。
当たり前のことなのだが,日々のやり取りでは結構手順を飛ばす。家族や親しい間だと,余計そうなる。日々の気遣いは,当たり前のことを当たり前にきちんとできることなのだろう。それが,両者のパイプを太くし,信頼を深める。近い人間にすら信頼が得られないようでは……。自戒。
岡山市内の郷土文学館で,見つけた,
おじさんと
人に呼ばれる齢になっても
じっきに
かっとなる癖はやまぬ
思慮分別もたらぬ
金も力もないが
名誉も地位もほしくない(吉塚勤治「自己紹介」)
という詩が気にいっている。「自己紹介」という題なのも,いい。もう,おじさんどころか,爺だが。
歳をとると,視野が狭くなる。行動範囲も限られてくる。必然的に,いつもの場所で,いつもの人と,いつもの会話しかしなくなる。
認知症にならない3条件というのを,ずいぶん昔,「ためしてがってん」でやっていたと記憶している。それは,
①メタボにならないこと
②有酸素運動をすること
③コミュニケーション
③のコミュニケーションというのが,みそだ。コミュニケーションというのは,家族やいつもの知り合いと,あいさつしたり,「風呂,めし」というのとは違う。ましてや,テレビを観て,ぶつぶつと文句を言うことではない。それは,一般に独り言という。しかし,上記の近親者との会話も,自己完結している。自己完結している,ということは,脳をとりたてて酷使しなくても,なんとなく流れていく,そういう状態を機能的固着という。
何がひらめいた時,0.1秒,脳の広範囲が活性化するという。それは,いつもの使い慣れた部分ではなく,自分の脳に蓄えたリソースと,広範囲にネットワークがつながる,ということだ。これがなくては,脳は,どんどんしぼんでいく。
その意味で,脳を酷使しなくてはならない。そのために,
①まずは,ウォーキング
②いろんな人と出会う機会を逃さない
③積極的に自己表現する
を心掛ける。人と出会えば,人は自分とは違う。違う人と会話するためには,いつもと違うところを使わざるを得ない。そのことによって,今までアクセスせず,断線していた脳のネットワークが再接続するかもしれない,新たな,接点をつくりだすかもしれない。そのことが,まずは脳にとって刺激だ。
自己表現とは,自分を語ることでもいい。新しい機会,新しい場所,新しい時間,新しい人と出会うこと自体が,すでに,自分に何らかの表現を強いるはずだ。
そして,
④広範囲の読書
少なくとも,若い時と同じスピードで本を買うと,どんどん積読になっていく。読書スピードはどんどん落ちていく。
だからといって,速読をしようとは思わない。読書のスピードはその人の思考のスピードなので,無理に速度を上げても,思考が研ぎ澄まされ,シャープになるとは思えない。速読者で,ノーベル賞,芥川賞,仁科賞等々をもらったという話を寡聞にして聞かない(いたらごめんなさい。話の都合上いないことにします)。ここで言いたいのは,頭がいいかどうかではない,人真似ではない,独自のものを考えている人を見たことがない,という意味だ。まして,速読を宣伝している人は,自分オリジナルの技術でも考え方でもない人がほとんどだ。
人の真似をしたり,人のお先棒を担ぐ人は,好きになれない。たとえ,ピンでなくても,キリであっても,自分で必死に考え,必死につかんだ結論でなくては,意味がない。そういう人でなければ,権力者の周りにうろつく手合いと同じ人種だと思っている(かつて選挙を手伝ったとき,蜜に群がる蟻のような手合いをいっぱい見た。こういうのを泥棒という)。自分で,血を流して,考えろよ,安易に,人の正解をもらうな!が自分のせめてもの意地だ。それも,おじさん予防対策の一つだ。言ってみると,意地というか,虚仮の一念,意地をなくしたら人間おしまいだ。
読書は読むことに主眼があるのではなく,ましてやいかに早くたくさんの本を読むかではない。一行ずつ,書き手と対話することのほうが大事だ。
それに,いかに速読が瞬間は,脳の酷使でも,速読に馴れれば,脳にとっては何の刺激にもならず,速読という機能的固着を一つ増やすだけだろう。閑話休題。
だから,まだ前へ進もうとしている。いくつになっても,前へ進む。新しい何かをする。
生きるとは
位置を見つけることだ
あるいは
位置を踏み出すことだ
そして
位置をつくりだすことだ
位置は一生分だ
長い呻吟の果てに
たどりついた位置だ
その位置を
さらにずらすことは
生涯を賭すことだ
それでもなおその賭けに
釣り合う
未来はあるか
それに踏み切る
余力はあるか
まだ
死んだ後,おのれの位置が定まる。棺を蓋いて事定まる,という。しかし,人は生き方通りの死に方をする,ともいう。出処進退を過たず,の気概でいこう。
クライアントになった瞬間,その人がコーチであれカウンセラーであれ,大学者であれただの人であれ,コーチの前でクライアントになった瞬間,クライアントでしかない。でなければ,そこでクライアントになる意味がない。
そこで向きあっているのは,自分自身であり,属性も経歴も関係ない。そこに一人の人として,いる。
にもかかわらず,時にコーチは,おのれの仮説を,あるいは自分の直感をぶつけてくる。
「あなたは過去に蓋をしている」
「あなたは自分を偽っている」
「軸がない」
「自分に気づこうとしていない」
「抱えた問題でバランスを取っている」
「目指すものがはっきりしていない」
「問いをそらす」
「目を合わさない」
「幸福感がない」
「自分に向き合っていない」
わずか30分のコーチングで,これだけ指摘されて,よほどのマゾか,自分自身に悩んでいる人でなければ,コーチングを嫌いになるだろう。これに似た言い方は,ほかにもある。
「本当の自分を知らない」(今ここに居る自分以外に自分はいない。こういう言い方は,ここに居る自分を貶めている)
「箱に入っている」(それはあんたの眼だろう。自分がそうとしか見えない認知の歪みだ)
「自分を偽っている」(だから入信しろといいそうだ!)
等々。まったく,ここまで貶められて喜ぶ自己卑下の持ち合わせは,少なくとも,自分にはない。仮に,直観でそう感じるのは,コーチの自由だ。そう感じさせる何かがあったのだろう。しかし,その直観を捨てずに,強化し,それを合理化するように持っていくコーチングとは,一体何か!こう書いて,自分がはっきり,怒っていることに気づいている。それはなまじいのものではない。憤怒に近い。人をそこまでコケにして,フォローもせず,最後まで,「気の毒に,自分に気づけていないとは」という口吻を続けられたら,ほんと,マジに落ち込まない方がおかしい。まして,相手は,結構著名なコーチなのだ。一瞬,オレッテ,そうなのか?考え込まされてしまう。事実,まだ落ち込んでいる余波が続いている(から,こんなことを書いている)。
コーチングとは何か,について改めて言いたくはないが,たとえば,コーチとは,
クライアントをゴールに運ぶ人
クライアントの鏡
クライアントと一緒にクライアントの真っ白なキャンバスに向かう人
だとしよう。そのためにコーチングがある。そのために,ここまで言われたら,まずは,そのコーチとは一緒に語りたくないのが心情だろう。しかし,だからこそ,冒頭の言葉が効いてくる。コーチングのクライアントになった瞬間,クライアントの立場として,コーチを上に見る傾向はある。そういうポジショニングにある。このことを,最近のブリーフ・セラピー系では,強く意識することを求める。入院したら,患者になり,コーチングの場なると,クライアントになる。
だから,ここまでだめだしされたらどうしたらいいのか,ますますダウンしていくに決まっている。それを意図していたのだとしたら,このコーチは,コーチというよりは,新興宗教の勧誘者に似ている。
あなたには××がついている(悪霊だったり,方位だったり,何でもいい。いまの不幸の原因らしいものを言う)
あなたはしあわせになりたいですか?
だったらまず引っ越しなさい。
もっとしあわせになりたいですか?
だったら,この○○(花瓶であったり,仏像であったりする)を買いなさい!
もっとしあわせになりたいですか?
では,これに入信なさい…
まあ,これと似たり寄ったりだ。もはや,コーチというよりは,悪霊払いに似ている。
コーチの資格がないとは言わないが(そんな資格は僕にはない),明らかに何かに憑りつかれている。偏見なのか,固定観念なのか,知識なのか,直観という悪意なのか,自分を相手に対して,そういうポジションを取らなくては,いいコーチングができないと思い込んでいる。
だから,客観的に見れば,それは,あなたがそう見たのであって,それはあなたの仮説にすぎない。それを自覚せず,その眼鏡が真実という前提でセッションを進めていくと,クライアント像は,ますます歪んでいくだろう。
ミルトン・エリクソンの原則は生きている。
①相手について仮定しない。
②緩やかな変化
③相手の枠組みであること
④みずからの考えを変える力があることを,相手自身が気づけるような状況をつくりだす
⑤そのために使えるリソースとなるものを相手の中に見つけだし利用する
まずは,ダメ出しの連発の前に,自分が気づいていないリソースを見つけさせてくれ,と言いたくなる。そのコーチングが,自分にとっていいかどうかの目安は,僕の私見では,
●コーチングを受ければ受けるほど苦しくなるかどうか
●自分のマイナス,欠点,問題,患部,瑕だけが暴かれていないかどうか
●コーチが自分を遠くから(上から)見ているような感覚にならないかどうか
つまり,コーチが自分の味方なのか,敵なのかだ。それでなくても,まっとうな人なら,ひとつやふたつ,自分を責める材料は持っている。それを誠実な人という。だから,自分を責めている,その自分をけしかけ,煽って,その傷口に塩を塗りたくるようなのは,そもそも金をとってコーチングすべきではない。
その逆でなくてはならない。
●一緒の土俵,あるいは自分の枠組みを尊重してくれているかどうか
●同じ方向を見てくれているかどうか
●どんなことがあっても,自分を承認し,認知してくれているかどうか
同じ土俵で,同じものを見ることについては,
で触れた。もし,土俵ができていて,一緒に同じ方向を見てくれていることが分かったなら,前述のダメだしすべては,コーチからの提案と受け取ったかもしれない。しかし,自分について,自分の存在について一切の承認なしの,ダメ出しを人は聞く耳を持っているのだろうか。これって,セールスの基本中の基本なのではないか?
承認については,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06431.htm#%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB
で触れている。
いまは,コーチングを受けていて,コーチングのプロセスを楽しんでいる。今までで一番楽しいコーチングかもしれない。すぐこういう声が聞こえそうだ。クライアントが楽しいということは,大事な問題から目をそらしているからだ,と。そういうやり方をするコーチングもあるかもしれない。コーチングについての解釈はいっぱいあるし,実践家によって,いろんなことを言うだろう。しかし,これも人生の一コマなのだ。楽しい人生であっていけないはずはない。
チェックリストには,いろんなタイプがある。学問的なものでないという前提だが,いいままで,いろいろ試しに作ってみたのが,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod063.htm#%E7%9B%AE%E6%AC%A1
ここにある。この程度のものは,そんなにつくることは難しくない。というか,こういうものをコツコツ作り上げていくのが大好きなのだ。管見によればだが,チェックリストは,おおよそ4つのタイプに分かれるように思う。
第一は,いわゆる,チェックして総数を数えて,全体の傾向や,自分の特徴をつかんでいくタイプ。これが一番多いし,バリエーションが出しやすい。
例えば,コミュニケーション力では,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06394.htm#%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%8A%9B%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
リーダーシップでは,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0630.htm#%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
アイデア力では,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0639.htm#%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E5%BD%A2%E6%88%90%E5%8A%9B%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
というようなものが作れる。要は,気になる項目をリストアップしていけばいい。思いつくままでもいいし,そういうたぐいの本を取り出して,必要なチェック項目になりそうなものをリストアップしていけばいい。
例えば,良寛に,「戒語」というのがある。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod065.htm#%E8%89%AF%E5%AF%9B%E6%88%92%E8%AA%9E
これは,何種類もある戒語を集めて,整理しただけだ。それでも,人との付き合いでの嫌なコトリストになっている。これなどは,良寛が,ただ無作為に,思いつくまま嫌われるリスト(嫌いな振る舞いリスト)を列挙しただけのものだ。これも,全体の過不足を見ながら,洗練すれば,きちんとした「人に嫌われない付き合い方リスト」にできる。
第二は,傾向や必要項目をリストアップするもの。
コミュニケーションタブーをリストアップするか,
前に挙げたが,コミュニケーション力として必要なものを,俯瞰して,聞く力,伝える力,自己開示力,感情コントロール力,人と関わる力,モニタリング力といったように整理してみると,もっともらしくなる。
あるいは,オズボーンのチェックリストに代表される,いわゆる発想チェックリストもこれにはいる。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0831.htm#%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
この場合は,ただリストを上げただけではなく,発想に寄与する項目をリストしなくてはならないので,何でもいいというわけにはいかないが,5W1Hのように通常使われているものなども,経験則から絞られたとみることができる。
第三は,専門の心理テストほどにトライや結果を厳選していないが,ある程度の傾向値が出せるもの。エゴグラムも,正式なものではないが,つくろうと思えば作れる。ただし,学問的ではないので,目安程度のものだ。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06422.htm#%E3%82%A8%E3%82%B4%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%87%AA%E6%88%91%E5%88%86%E6%9E%90
第四は,マネジメント力とか管理能力のような,もう少し全体像を見ようとするもの。
例えば,管理能力全体を行動レベルに落として,チェックリスト化したものとしては,
管理者の行動分析例を取れば,「チーム方針策定」「メンバーの目標統合」「仕事の進捗管理」「リーダーシップ強化」「活力ある職場づくりのマネジメント」「業務を通しての部下指導」と,管理場面に応じて作っていくことになる。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06220.htm#%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E5%BC%B7%E5%8C%96%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06221.htm#%E6%B4%BB%E5%8A%9B%E3%81%82%E3%82%8B%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
あるいは,管理者の部下指導力に特化してチェックリスト化しようとすると,管理者の日常行動,マネジメントスタイルそのものが,部下への仕事の価値観,業務遂行で何を重視するかを教えていくことになる。その面から,管理行動をチェックしてみると,あらゆる機会が部下指導につながるはずである,という仮説のものとに,チェックリスト化を試みている。管理者の行動分析例の部下育成側面だけにピンポイント化したいると言える。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/view56.htm#%E6%96%B0%E4%BB%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E3%81%AE%E9%83%A8%E4%B8%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%8A%9B%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
こういうと,口幅ったいが,どんなものでも,とりあえずチェックリストはできるが,
① まずは,目的を限定すること。たとえば,コーチングスキルというように。
②
次は,それに必要なアクション,あるいはマインド,あるいは姿勢,身構え等々をブレークダウンする。この場合,たとえば,何か目安になるものがあると,漏れを見つけやすい。5W1H,ヒトモノカネ,あるいはPDCA等々。
③ 最後は,それを整理して必要なものにし,仕えるかどうかは,試してみる期間がいるだろう。
以下は,発想力アップのためのマイ・チェックリストづくりの手順を書いたものだが,これは他にも応用できるはずである。
本当は,目的によって違うが,発想という観点なら,2つか3つが使いやすいチェックリストだと思う。そのあたりも,目的から最小限のものをつくることがベストだ。
自分は,対,ということと,目的対比を念頭に置く。どつぼにはまっているときは,選択肢を失っている。その時の救いの「藁しべ」のつもりだ。
いつも思っていることは,リーダーシップをリーダーとは切り分けて考える必要があるということだ。そのあたりを,実感的に(論理的ではないが)整理しておきたい。
まず,Leadershipの意味だが,語源的に正しいかどうかはわからないけれども,辞書を見る限り,
Leadership のshipは,Friendshipのような状態を示す意味
と,
Leadershipのようなスキルを示す意味
をもっているのではないか,と推測している。そこから,少しばかり飛躍するようだが,勝手に,Leadershipとは,リーダーである(状態を保つ)ためのスキル(技量)と考えている。自ら何を(達成)するためにリーダーであるのかに答えを出し,それを実現していく力量である。
もちろんLeadershipは,保有能力ではない。
環境変化,組織の内部変化に対応して,何のために何をなすべきかの旗幟(目的)を明確に立て,そのためにメンバーを組織し実現していく実行能力である。当然,リーダーシップもそれ自体をもったり,発揮することが目的ではない。リーダーだからといって,やたらとリーダーシップを振り回されてはかなわない。メンバーに徹底できない(徹底しきれない)まま目的や方針を振りかざし,報告がない情報が上がってこないと嘆いても,それはおのがリーダーシップのつけでしかない。
しかし,リーダーとリーダーシップは分けて考えるべきではないかと思っている。
あえて区別すれば,リーダーは,役割行動であり,リーダーシップはポジションに関係なく,その問題やタスクを解決するために必要と考えたら,自らが買って出る,あるいは誰かの委託を受けて,その解決に必要な周囲の人々を巻き込み,引っ張っていくこと(つまり,リーダー的役割をしょっていくこと)である。その意味では,トップにはトップの,平には平のリーダーシップが求められるはずなのである。
つまり,リーダーシップはその人の役割遂行に応じて,必要な手段なのではないか。職位が上のほうに行けばいくほど,リーダーシップがないことが目立ち,下へ行くほど,リーダーシップがあることが目立つ。上に行けばいくほど,リーダーシップを発揮しやすい条件と裁量を与えられているから,それがあるのが当たり前だから,ないことが目立つのである。そのことは,またあとで触れる。
では,まず,リーダーであるとはどういうことなのか。
「リーダーである」とは,組織(大は国,小は企業組織やその構成チームまで幅広く組織という形態を取っているものすべてを指す。集団はここでは外しておく)の目的を達成するための指導者(指揮官)であり,目的達成の責任者として存在する。自薦他薦で「リーダーになる」ことは可能だが,メンバーにリーダーと認知されない限りリーダーではありえない。リーダーと認められなければ,仮に旗を掲げても,振りかえると誰もいないという体たらくになりかねない。
またいま現在リーダーであるからといって,いつまでもリーダーでありつづけられるわけでもない。常にメンバーから問われるのは,(あなたは)「何のために(何を実現するために)リーダーとして存在しているのか」である。その答は,リーダーである限り,自分で出さなくてはならない。その答が出せなくなったとき,リーダー失格になるのでである。
もちろん「リーダーである」ことは目的ではない。あくまで組織やチームの目的を達成することが目的である。それにはたえず「組織(チーム)の目的は何か」を明確にさせなくてはならないだろう。目的にかなわない「何か」を,自分もしくはメンバーがしたとすれば,第一義的にリーダーの責任である。もちろん,時代の変化とスピードの中で,組織(やチーム)の目的は変わる。変わらざるをえない。だから,常にメンバーと共に“目指すに足る目的”を掲げ直さなくてはならない。それが今日「リーダーである」ことの最も重要な使命かもしれない。
リーダーは,一方では,
自分は「何のために(何を達成するために),リーダーとしているのか」
「(目的を達成するために)リーダーとして,何をしなくてはならないのか」
「(目標を達成するために)リーダーとして,どういうやり方をすべきなのか」
等々と絶えず自問しつづけなくてはならない。しかしそれだけに自己完結させれば組織維持そのものが目的化してしまうだろう。だから他方では,
果してこの組織(やチーム)は存在する理由を,この世の中に,かつて持っていたようにいまもまだ持ちつづけているのかどうか,
組織の使命,組織の存在理由,そのものへの問い直しもまたリーダーにしかできないことである。
そのとき,リーダーシップとは,リーダーである(状態を保つ)ためのスキルであり,
組織は何のために存在するのか,
その目的からみて目標・手段は適切か,
あるいはその目的はいまも重要か,
もっと別の目的を創れないか,
等々と,問いを続ける姿勢である。その答えがビジョンであり,旗幟である。旗幟を鮮明に掲げ続けられるかどうかは,リーダーが組織の目的とどれだけ格闘したかの結果であり,そこにこそリーダーシップが必要なのである。戦術・戦略を語るのはその後である。
誰がその立場に立っても与えられた役割しか果たさないなら,誰がリーダーになっても同じである。一人一人が,自分に与えられた役割と格闘し,目的達成のために,何をすべきか,何にウエイトを置くべきかを主体的に考えようとしなければ,組織(やチーム)は硬直化する。
リーダーは,リーダーとしての立場と役割とは何かを自問しながら,何を目指すことが組織(やチーム)の未来を決することになるのかと,組織(やチーム)の目的と格闘し,その方向と行く末を描き出していく。
下位者(や構成メンバー)一人一人もまた順次,それを実現するために何をしたらいいか,それぞれの役割の目的と格闘しながら,主体的に考えていく。そういう組織(やチーム)が硬直化するはずはない。
こうした各層,各レベルで自問する組織(やチーム)なっているかどうかの責は,ひとえにリーダーの硬直化そのものにある。ビジョンを掲げぬリーダーには説明責任どころか結果責任も果たせないだろう。リーダーに弁解はない。掲げたビジョンそのものがすべてを語るからだ。そのビジョンは,それを実現するために何をすべきかを,メンバー一人一人に考えさせ値打ちのあるものなのかどうか。リーダーはその是非で,おのれにリーダーシップを問われるだろう。
だが,リーダーシップは組織やチームのリーダーのものと考えるのを前提にしていいものなのか。
たとえば,リーダーシップにこんな常識はないか。
①リーダーシップはトップのものである,
②リーダーシップはパーソナリティである,
③リーダーシップは対人影響力である,
これを点検してみる必要があるのではないか。
僕は,リーダーシップとは,トップに限らず組織成員すべてが,いま自分が何かをしなければならないと思ったとき(これを覚悟という),みずからの旗を掲げ,周囲に働きかけていく。その旗が上位者を含めた組織成員に共有化され,組織全体を動かしたとき,その旗は組織の旗になる。リーダーシップにふさわしいパーソナリティがあるのではない。何とかしなくてはならないという思いがひとり自分だけのものではないと確信し,それが組織成員のものとなりさえすれば,リーダーシップなのである。
そこに必要なのは,自分自身への確信である。それが自分を動かすものだ。それが人を動かす。リーダーシップは他人への影響力である前に,自分への影響力である。「お前がやらなくて誰がやるのか」「自分がやるしかない」と,みずからを当事者として動かせるものが,自分の中になければ,人は動かない。それが旗の意味であり,旗の実現効果であり,そこに共に夢を見られることだ。
だから,リーダーシップには,新たな常識が必要となる。
①周囲を巻き込める夢の旗を掲げられること,
②夢の実現プランニングを設計できること,
③現実と夢とを秤にかけるクリティカルさがあること,
である。
「こうすべきだ」だけでは人は乗らない。それが単なる夢物語でも人は乗らない。夢と現実味をかね合わせて,絶えず点検していける精神こそが,求められるリーダーシップである。それは,パーソナリティでも地位でもパワーでもなく,スキルであることを意味している。
それは,実は仕事の仕方そのもののことであるのではないか。要は,一人で抱え込まず,いかに人を使うか,人のサポートをつかむかが必要とて言ったが,それは言ってみれば,リーダーシップの端緒を意味している。つまり,こうだ。
その人が自分の役割を責任持って達成しようとするとき,自分の裁量内でやっている限り,その仕事は完結しない。ときに自分の裁量を超えて,人に働きかけ,巻き込んででも,それを達成しなくてはならないときがくる。それがリーダーシップを自分が必要になるときである。
必要なのは,自分は何をするためにそこにいるのか,そのために何をしなくてはならないのかを,自分の頭で考えられるかどうかだ。それを仕事の旗と呼ぶ。それは平のときから自ら考え続けていなくては,リーダーシップがあって当然という立場になったとき,リーダーシップがないことが目立つだけなのである。
で,最後に,リーダーシップが自分に必要となるシチュエーションをまとめてみると,次のようになるだろう。
①自分の仕事を自己完結しないで,その完成を目指すとき,より上位(上司という意味で限定していない)を巻きこんでいかざるを得ない
必要なのは,その仕事を真に完結するのはどういうことか,その目的達成にはなにをしなければならないか,を考えていることだ。自分の裁量を超えても完結を目指すとき,上位者や周囲を巻き込まざるを得ない。そのとき,明確な旗が不可欠となる。それは上位者の指示を正そうとすることも含まれる。
②かかえている問題が大きく深いとき,より上位者を巻き込まざるを得ない
その解決すべき問題が,自分を超え,部署をまたぎ,広がるほど,より幅広く巻きこんでいかざるを得ない。
③自分の仕事にリーダーシップを発揮しようとしないものに,リーダーシップは担えない
組織の中で,自分のしたいことを実現しようとかするなら,上位者を動かさざるを得ないはずである。
④組織やチーム内に,自分以外にチームをまとめていけるものが見当たらないとき,その役を引き受けざるを得ない
別に勝手に「しょっている」のとは違う。自分が経験と知識,キャリアから見て,リーダー役を買わなくてはならないと自覚し,チームをまとめて,チームの目標達成のために何をしたらいいかをチームメンバーと一緒になって考えていこうとするとき,そのとき,役割としてのリーダーを担い,チームをリーダーとなってまとめ,引っ張っていこうとしていることになる。この場合,メンバーがそれを受け入れ,それを支えようとしてくれている限り,独りよがりではなく,チームメンバーは彼(女)にリーダーシップがあるというだろう。
⑤だからといってすべてをひとりでしょいこむことではない
メンバーをその共通の土俵に乗ってもらえば,協働してやっていくことになる。その時自分は触媒役である。
だから,要するに,リーダーシップとは,リーダーシップは,自分(ひとり)では(裁量を超えていて)解決できないこと,あるいは解決してはいけないことを解決するために,解決できる(権限のある,スキルのある)人を動かして,一緒に,その解決をはかっていこうとすることである。
とくに,リーダーシップの真価が問われるのは,自分のポジションより上や横を動かそうとするときだ。そのとき必要になるのは,
●「何のために」「何を目指して」という,意味づけ(組織全体にとっての,その仕事にとっての,各自にとっての,その問題にとっての等々)が明示でき,
●必要な人々に,その意味をきちんと伝えていく力があり,
●めざすことを一緒にやっていくための土俵(協働関係)をつくれ,
●協力してくれた相手,サポートしてくれた人への感謝と承認を怠らないこと,
ではないか,と考えている。まさにどこまで自分が考えて,考えて,考え詰めているかが問われている。自問自答し,自分で答えを出す力が問われている。
自分の知っている範囲なので,あるいはとんでもない間違いをしているかもしれないが,恋には対立語がない。たとえば愛なら愛憎,好なら好悪がある。その意味では,「恋」に憎しみや悪意は似合わない。
辞書的に言うと,日本語には,本来「愛」はない。漢語からきた。だからか,本来の意味とは別に抽象度が高い印象を受ける。古語辞典では(といっても自分の持っている岩波版の古いタイプだが),「恋う(ふ)」には,「思い慕う」か,「異性を思い慕って悩む」という意味しかない。
「愛す」は,①大切に扱う,大事にする,②手心を加える,遠慮して扱う,③あやす,機嫌を取る,の意味しかない。恋とか恋愛はない。
「好む」には,①好く,愛する,②選ぶ,という意味だが,この場合の①の意味は,例で,「いまめかしき事をこのみたるわたりにて…」とあり,「恋」のニュアンスはない。
このあたりからは,憶測と独断になるが,まずは,「恋」・「愛」・「好」の矢印の方向性を考えると,「恋」は,水面に映る自分に恋をしたナルキッソスの話があるにはあるが,「愛」に自己愛があり,「好」にも自己を好むという言い方があるのに,自己恋や「自分を恋う」というのはあまり聞かない。しかも,矢印は,誰でもいいというわけではなく,基本は,一点にピンポイントで向かう。恋のキューピッドの矢が,意味があるのは,そのためだ。「恋」の漢和辞典での意味も,「こふ」に一点張り。ただ,恋々という言葉あるように,「恋」には軟弱さが付きまとう。だから,恋着とか恋泣になってしまうようだ。
「好」は,嗜好とか愛好とか愛玩いう言葉があるので,本来の「愛」の「めでる」「いつくしむ」ということとつながって,かなり狭い範囲に限定された矢印のような気がする。人とも物とも時とも相性のいい言葉らしい。漢和辞典的(といっても角川の『字源』だが)には,「よし(善)」か「うつくし」のニュアンスがあり,もちろん好色の「好」でもあるが,好意の「好」であり,好漢の「好」であり,好事者の「好」であり,好人物の「好」であり,好都合の「好」であり,好評の「好」であり,好機の「好」でもある。
「愛」は,漢和辞典的には,「いつくしむ」「親しむ」「めでる」「したう」とあり,幅が広い。仁愛の「愛」でもあり,愛育の「愛」でもあり,愛児の「愛」でもあり,愛詠(好んで歌う歌)の「愛」であり,愛惜の「愛」でもあり,愛着の「愛」でもあり,愛嬌の「愛」でもあり,愛妾の「愛」でもある。さらに,自愛の「愛」もある。
現代は,「愛」ですべてが代替できるくらい幅広いが,漢字としての「愛」も元来そんな感じになっている。矢印は全方向と言っていい。
恋と愛の違いにはいろいろ説もあるようだが,三島由紀夫が,ことを書いていたそうだ(ネットで知ったので保証はしない)。
思うに、「好く」というのは、個人資質的な扇形した感情移入を云うのであろう。対極は「嫌い」であり、人はそれぞれ多少なりともその嗜好性向が異なっているので塩梅良くなっているように思われる。「恋」というのは、「好く」の扇形をかなり狭めた極力一対一のかなり濃度の高い「好く」感情移入なのではなかろうか。
それに対して、「愛」というのは、一対一の「恋」の扇形を開く方向への感情転移なのではなかろうか。「愛」は広がれば広がるほど良いが、いずれ「止まり」がやってくる。なぜなら、「愛」は強めれば強めるほど逆に「憎」を呼び込むからである。こうなると、それまでの「愛」を「第一次愛」と呼び、「憎」と絡みながら織り成していく「愛」感情を「第二次愛」として区別すべきであろう。その上で、「第二次愛」も又広げていけば行くほど良い。
三島らしい屁理屈だが,どうもしっくりこない。僕はベン図で関係性を考えてみた。例の円を重ねたり,つなげたりする,ジョン・ベンの考案した,複数の集合の関係や、集合の範囲を視覚的に図式化したものである。
「恋」は,どちらかというと二つの円が離れている。だから知恵の輪のように接点だけで絡みつく。
「愛」は,二つの円が一部重なっているか,全体が重なっているかだろうが,しかし思うに,重なっている場合は,どちらかの円の方がはるかに大きくて,自分側が大きい方なのか相手側が大きい方なのかは別として,大きな円の中に包み込まれているのではないか。
「好」は,ほんのわずか,相手の円が接している。その接している部分,ないし重なり合っている部分が大きくなるほど,マニアックになるというか,執着が強まる。この場合円の大小は「好」には影響しない。
ただ,「恋」の円は,円ではなく,輪。知恵の輪が絡みつくように,別々のまま。言い様を変えると,まあ一方通行。絡んではいるが,重なることはない。だから,「恋」。だから,「恋」が「愛」になることはない。慈愛という言葉があるが,その時,「恋」ではない。なぜなら,目線がもう「恋」の一方通行の目線ではないからだ。それは「恋」の終焉の果てに,ひょっとしたらありうる境地だ。「愛」の場合も,確かに,特に大きいほうが小さいほうを飲み込んでいる場合,やはり一方通行に違いないのだが,一方通行で自足する傾向がある。自足というかそこで充足している。「恋」は終始,一方通行にじれている。しかし,「恋」には「憎」も「悪」もない。「恨」もないと思う(ここらは異論があるかもしれない)。
「恋」からの連想で,ちょっと古いが,与謝野鉄幹の「人を恋うる歌」を思い出した。ネットで歌詞を調べてみたが,どうも人を「恋ふ」という感じではない。壮士の勇ましげな空元気っぽくて,好きではない。この中で,有名なのは,一番だが,
妻をめとらば 才たけて
みめ美わしく 情けある
友を選ばば 書を読みて
六分の侠気 四分の熱
二番は,
恋の命を たずぬれば
名を惜しむかな 男(おのこ)ゆえ
友の情けを たずぬれば
義のあるところ 火をも踏む
恋とは言っているが,単なるだしに使われているだけだ。とてもいただけない。与謝野鉄幹という人間の程度の悪さを想像させてしまう(正直のところよく知らないし,こんな歌ではよく知りたくもない)。
全歌詞は,ネットでみるといろいろあるので見てほしいが,あえて好意的に受け止めれば,よく読むと,一方通行で,人への憧憬に満ちている。その意味で,人を「恋うる」というのはあたっていなくもない。
どのみち,自分には無縁で,他にないものかと,いろいろあたってみたが,短歌ならたくさんあるのだろうが,結局この詩に落ち着いた。
他人を励ますことはできても
自分を励ますことは難しい
だから-というべきか
しかし-というべきか
自分がまだひらく花田と
思える間はそう思うがいい
すこしの気恥ずかしさに耐え
すこしの無理をしてでも
淡い賑やかさのなかに
自分を遊ばせておくがいい(吉野弘「自分自身に」)
僕は,まあ,愛とか恋とかには縁のない人間なので,つまるところ,「好」に落ち着いてしまったようだ。こういう含羞の気色が「好」みのようだ。
コーチングでも視点を大事にします。いわばものの見方だからです。
たとえば,CTIの基礎コースのテキストには,「視点転換のスキル」について,こうある。
「視点転換のスキル」とは,クライアントが自ら置かれている状況を別の視点からとらえることで,異なる選択肢が見つけられるようにサポートするためのスキルです。ちなみに,視点を変えるということは,コーチがクライアントから得たデータに異なる解釈を与えることを意味し,通常は否定的にそのデータを解釈している相手に対し,肯定的な解釈を提示することで,相手は新たな可能性を見出すことができるのです。たとえば,あるクライアントが,非常に激しいマーケットで権限の強いポジションの候補者になりながら一歩及ばず,そのポジションを逃したとしましょう。そのクライアントは落ち込み,自分の仕事能力に自信を失っています。この状況に視点転換を使うならば,「それほど競争の激しいマーケットで候補にあがったということは,あなたの経験と知識がそれだけ素晴らしいということなのです」となります。
しかしこの例では,視点の転換というより,ものの見方を示唆してしまっている。これは視点をクライアント自身に変えさせるための質問を使う方が効果的に思える。たとえば,「それほど競争の激しいマーケットで候補にあがったということについて,同僚や部下はどう見ているでしょう」という方が,クライアントの視点そのものを変えることになる。視点転換を,その結果えられるものではなく,転換そのもので得られるものに,力点を置くべきだと思うが,これは別の視点。閑話休題。
ところで,CTPのテキスト(自分が学んだ2004年当時のもの)では,こうあります。
コートには,クライアントが,今の状態は自分が起こしたものであり,これから望む未来も自分でつくっていくことが可能だという立場に立つよう促すスキルが求められます。そして,そのためには相手に多面的な視点を与えることが役に立ちます。
多面的という言い方は,視点そのものというより,視点から見えるものに力点を移している。しかし,視点がクライアントのものの見方を変えるのだとすれば,「選択肢」という言い方のほうが妥当な気がする。
それはともかく,続いて,そのために,
①責任を引き寄せる たとえそれが望ましくないようなものであっても,今ある状況や起こっている問題は自分が作り出したものであるということを,クライアントに自覚させることです。(コーチング大好きな人からは顰蹙を買うだろうが,あえて言えば,大きなお世話,こういう上から目線が,ときどき鼻につく。もしそれに敏感でなければ,鼻につくコーチになるはずだ。いまの多くのセラピストは,こういう言い方をしない。もう少しセンシティビティが必要だろう。)
②枠を替える クライアントは,ときに,自分の置かれている状況を,ある特定の枠組みに当てはめ,身動きができなくなってしまうことがあります。その状況を,飛躍へのチャンスという捉え方に変換できたとしたら,その後の行動は大きく変わってきます。「枠を替える」とは,クライアントがゴールに向かうことを妨げている,物事に対する見方(枠)を取り替え,相手に新しい視点を与え,行動への動機づけを行うことです。
③支柱を外す クライアントの基本的な考え方や解釈,仮説,コミュニケーション・スタイル,優先順位について,それが機能していないことを指摘し,取り除く手伝いをすることです。
④バージョンアップする クライアントの行動を決めている基本的な考え方や解釈を点検し,その幅を広げたり,新しいものに変えたりする機会とする。
⑤自分の体験を伝える コーチはすでにそれを試していることが必要です(これは変!クライアントから何が出てくるのかわからないのに,何をためすの?こういうおこがまし差が,時に鼻につく)
⑥提案する 相手に新しい視点を提案する。イエス・ノーの選択権は相手にある。CTIでは,イエス・ノー・逆提案の三択を提案する。この方が選択肢として正しい。
⑦リクエストする コーチが望んでいることをストレートに相手に伝えることです。その人がまだ試していない,その人の可能性を引き出す,その人が無意識につくっている枠の外へ連れ出す狙いがある。
さて,こう見てくると,視点そのものについては,あまり深入りしていないように思えます。それは,自分の視点について考えるよりは,「~という視点で見たらどう見えます」「それをあえて好きだと思ったら,どうなります」のように,別の視点をコーチ側から提起することで,別の視界を開かせることで,おのずと気づきを得られるようにするところに,力点があるからだと思われます。
ここでは,視点そのものについて,もう少し突っ込んで,私見をまとめてみました。
人は意識していないが,自分の見方を持っていると思っています。それは価値観であったり,生まれつきの見る位置であったり,こだわりであったり,暗黙の前提であったり,慣れであったり,なんとなく制約を考慮していたり,気づかず固定した位置でみていたりしています。それを自分でチェックすることで,変えることができます。ただし,見方だけは,意識しないと変えられない。特定の見方をとっていることを気づかない限り,変えることはできないのです。
つまり,こうです。「変える」とは,それを意識してみるという意味なのです。例えば,「価値を変える」とは,「~と見た」とき,「いま自分は,どういう価値観・感情から見たのか」と振り返ってみるということです。そのとき,善悪なのか美醜なのか喜怒なのかをチェックし,それ以外の,価値観で見たらどうなるか,無意識の見方を意識し,「では,別の見方ならどうなるか」と,改めて別の見方を取ってみる“きっかけ”にするのです。
①[みる」をみる-見る自分の対象化
視点を変えるというのは,視界(パースペクティブ)を変えるためにそうするのです。それを「見え方を変える」ということができます。見え方を変えることで,見ているものの印象が変わります。視点,たとえば具体的には,見る位置の移動することで,見え方が変わるからです。
その意味で考えると,われわれの想像力は,見る位置を動かせるのです。頭の中で,モデルを回転させたり,拡大縮小したりできますが,たとえば,現実的に,見る位置を近づければ,対象は大きくなりますし,遠ざければ小さくなるはずですし,ひっくり返せば,逆さまに見ることになります。見えているものを変えてみることで,見え方を変えることができます。見え方を変えることで,いままでの自分の見方が動くはずです。
しかしそれをするためには,対象を見ている自分の位置にいる限り,それに気づきにくいのです。なぜなら,見ているもの,対象の方に意識の焦点があっているからです。
それが可能になるのは,「見ている自分」を「見る」ことによってだけです。つまり,見る自分を突き放して,ものと自分に固着した視点を相対化することです。そうしなければ,他の視点があることには気づきにくいのです。だから,コーチングの質問で,「ほかの視点は?」と聞いたり,「○○の視点で見たらどう見えますか?」というのが効果的になるのです。
これをメタ化と呼びましょう。自分自身を含め,自分の見方,考え方,感じ方,経験,知識・スキル等々を対象化することです。それは,「『見る』を見る」ことだ,といえましょう。「見る自分」を意識しない限り,何を見ているかに意識の焦点が向かっており,どう「み(てい)る」か,どこから「み(てい)る」かは,「見る自分」自身は気づけないからです。
何かを対象化するためには,いったん立ち止まって,自分を,自分の位置を,自分のしていることを,自分のやり方を振り返らなくてはなりません。たとえば,言葉にする,言語化する,図解する,というのもその方法のひとつになるでしょう。それをするためには,対象化する必要があるからです。つまり,象徴的な言い方をすれば,「『見る』を見る」ということになる,というのはその意味です。
たとえば,「どつぼ」にはまって,トンネルビジョンに陥っているとき,視野狭窄の自分には気づけません。自分がトンネルに入り込んでいること自体を気づけない。それに気づけるのは,その自分を別の視点から,見ることができたときだけです。そのとき,初めて,止まる,前進し続ける,戻る,横へ行く等々の選択肢が見えてきます。つまり,視点を意識するとは,他の選択肢を意識できるようになる,ということなのです。なぜなら,見ているものではなく,見ている「見る」が対象になっているからです。
もう一つ,「どつぼ」を脱出する方法があります。あえて,自分の視点(視野狭窄に陥っている)を捨てて,意識的に,他人に仮託してみることです,たとえば,上司,トップ,先輩,家族等々,具体的なイメージのわく視点を想定して立ってみる。それ以外に自分の視点の狭窄に気づきにくいのです。これしかないと思いこんでいる自分の状態では,それ以外にあることには気づきにくい。だから,それを,「みる」をみると呼んでいる。「他には」の視点バージョンといってもいい。コーチングが意味が出てくるのは,ここなのです。これも,コーチングでよくやる質問です。「○○さんなら,どういうでしょう?」等々。
②「『見る』を見る」ための4原則~メタ化によってものの見方を相対化する
では,② 「『見る』を見る」ための視点として,どんなものがあるのか。4つほど例示をしてみました。
①「問い」(問題)の設定を変える-その「問い」(問題)の立て方がものを見えにくくしていないか
●問いの立て方を変える 問題そのものを設定し直す,別の問いはないか,問題そのものが間違っていないか,新たな疑問はないか,見逃した疑問はないか
●目的を変える 別の意味に変える,別の意義はないか,別の目的にする,意味づけを変える,意図を変える
●制約をゼロにする 時間と金を無制限にする,別の制約に変える,人の制約を無視する
●根拠を見直す その前提は正しいか,前提を見直す,前提を捨てる,こだわりを捨てる,価値を見直す,大切としてきたことを見直す
②視点(位置)を変える-その視点(立脚点)が見え方を制約していないか
●位置(立場)を変える 立場を変える,他人の視点・子供の視点・外国人の視点・過去からの視点・未来からの視点になってみる,機能を変える,一体になる・分離する,目のつけどころを変える,情報を変える等々
●見かけ(外観)を変える 形・大きさ・構造・性質を変える,状態・あり方を変える,動きを変える,順序・配置を変える,仕組みを変える,関係・リンクを変える,似たものに変える,現れ方・消え方を変える等々
●意味(価値)を変える まとめる(一般化する),具体化する,言い替える,対比する別,価値を逆転する,区切りを変える,連想する,喩える,感情を変える等々
●条件(状況)を変える 理由・目的を変える,目標・主題を変える,対象を変える,主体を変える,場所を変える,時(代)を変える,手順を変える,水準を変える,前提を変える,未来から見る,過去から見る等々
③枠組み(窓枠)を変える-その視界が見える世界を限定していないか
●全体像から見直す 全体像を変える 広がりを変える,別の世界のなかに置き直す,位置づけ直す
●設計変更する 出発点を変える,ゴールを変える,要員を変える,仕様を変える,組成を変える
●準拠を変える 別の準拠枠を設定してみる,よりどころを見直す,前提を変える,制約を消す(変える)
●リセットする すべてをやり直す,リソースを見直す,ゼロにする,チャラにする,なかったことにする
④やり方(方法)を変える-その経験とノウハウ(経験のメタ化)が方法を狭めていないか
●本当に可能性は残っていないか まだやれるというには何が必要か,何があれば可能になるか,どういうやり方ができれば可能になるか,何がわかれば可能になるか,
●まだやり残していることはないか 他にやっていないことはないか,まだ試していないことはないか,まだやって見たいことはないか,ばかげていると捨てたことはないか,限界を決めつけていないか,
●プロセスを変える まだたどりなおしていないことはないか,別の選択肢はないか,分岐点の見逃しはないか,捨てていいプロセスはないか,経過を無視する,逆にたどる,資源の再点検,見落としはないか
●手段を変える 試していないことはないか,異業種で使えるものはないか,捨てた手段に再チャレンジする
実は,初めは視点については,視点の位置をどう変えるかのみを念頭に置いていましたので,②だけしか考えていませんでした。しかしあるメーカーで,こんなことを言われたことがあります。「問題」はわかっている。しかし解き方がわからない,と。
しかし,思ったのです。もし問題がわかっていて,どうしても解き方がわからないのだとしたら,自分が「どつぼ」にはまっていると思うべきです。とすると,わかっていると思い込んでいる「問題」の設定そのものを見直す必要があるのではないか。本当にそれがもんだいなのか,と。そこから,考えを進めて,上記の4つの視点を整理してみました。ポイントは,見ることを制約すると思われるものを,少し広げて検討しようとしたところだと思います。
しかし,まだ仮説です。仮説ということは,僕自身の機能的固着(固定観念)から脱していないところがあるのではないか,ということです。絶えずそういう問題意識を持ち続ける必要があります。すべては仮説ですから,正解ではないということです。
昨今捨てるが流行っているらしい(ちょっと遅れてる?)。それを何たら,というらしい。へそ曲がり流に言うと,物に執着する心を捨てるのだとすれば,物を捨ててもだめで,自分の中の何かの執着を捨てなくてはならない。しかし執着を捨てるということは,人生への自分の固執を捨てることだ。自分のこだわりを捨てることだ。そこを悪者のように言うのがよくわからない。なぜそこまで自分を貶めるのか,理解できない。
こだわっているのは,自分の何かだ。その何かには,意味がある。そのままにしろとは言わないが,その執着がエンジンになっているのか,ブレーキになっているのか,アクセルになっているのか,で意味が変わる。超えるべきものは自分が超える。他人の力を借りなくても,必要な時に必要なものに出会い,必要な決断をする。きちんと生きている限り,必ずそうする。
その程度に自分を信じられない人が,右顧左眄して,人の生き方に左右されるのはどうなんだろう。その提唱者は自分のためにやったのだ。それは成功した,しかしそれを取り入れるには,慎重でなくてはならない。自分の人生なのだ。自分の人生には自分の流儀があるはずだ。そんな無駄なことをやっている間に,生きることに執心した方がいい。
それに,一度捨てたら,二度と戻ってこないものがある。その時,価値がないと思ったとしても,人間のいまなど,ほんの数秒しかないと言われている。
老婆に見えたり若い娘に見えたりする,漫画家ヒルのだまし絵が有名だが,立方体の二つの見え方がする,ネッカーの立方体というのもある。どちらが見えるとしても,「その瞬間にはいつもひとつしか認識できない」と,エルンスト・ヘッペルは言う。両方が同時に見えることはない。
これは,意識の中に一つの対象しか存在していないことを示している。一つの対象が注意の中心にあるとき,別の見え方も含めて他のすべては背景に引っ込んでしまい,そして背景になる。……一つの意識内容はいつも数秒しか留まらず,それもまた沈下して他のものと交代してしまうのである。
こんな危うい今の決断は,今の背後のさまざまな思いを地に押し込んで,図として表面化しているだけだ。そしてこういっている。
現在すなわち私たちの意識は,鞍の背のように時間の上にあり,そこに私たちがまたがっている。そしてそこから時間の二方向,つまり過去と未来を眺めている。
過去のすべては自分の中にある。捨てるべき対象ではない。どんな恥ずかしい過去も身を隠したくなる過去も,すべては自分のリソースなのだ。そんな経験をしたことのない人は,その分失敗も過誤も犯さない経験しかしていないのだ。それをリソースと呼ばなくてどうするのだろう。僕は自死を含めて,三度死に損なった。それを恥ずかしいとは思わない。そのすべてを含めて自分のリソースだ。自分というものの人生だ。
第一,もし捨てるというのなら,徹底的にやらなくてはならない。ものを捨てる。金を捨てる。家を捨てる。職を捨てる。家族を捨てる。欲を捨てる。名誉も誇りも捨てる。そこまでいけば出家だ。自分の執心を捨てる一番いい方法は,自分を捨てることだ。そこまで徹底的に考えた末の廃棄なのだろうか?
僕には,どうも捨てることに執心する気持ちがわからない。わざわざ棄てなくても,僕は棄てるべき時が来れば,普通の人は棄てられると思う。棄てることで人生が変わるような人は,今まで何もしなかった証でしかない,と思っている。
そういう人は,身を切るような(まさに何かを捨てるような)決断も気なかったし,決意もしなかったし,というかもしれない。
しかし僕は,そういうふうに自分を貶める人を信じない。その人は謙遜しているか,自分を観ていないだけだ。人生で,何も捨てなかった人などいない。親を捨てなくては結婚できない。親の戸籍を捨てることではないか,結婚とは。就職は,それしかなかったというかもしれないが,それを選択したのだ。そこに決断がなかったとは言わせない。決断とは捨てることだ。その瞬間,あり得る可能性を,捨てて選んだのだ。
僕は,引っ越しするにあたって,3年ほど前,30年以上書き綴ってきた日記をすべて捨てた。それは後悔していない。過去を捨てるとは,この程度でなくては棄てたことにはならない。僕の執着は本だ。それも同じ時期1/3捨てた。しかし,これだけは後悔している。なぜなら,本はものではない。自分の知的好奇心そのものだ。知的好奇心がやまない限り,また必要になる本がある。その時は必要ないと思っても,また螺旋のように知的好奇心,問題意識は戻ってくる。だから,何冊かを買い戻した。しかし,もう二度と買い戻せないものもある。本に引いた線だ。その時の自分の関心は,今も同じ関心になる。そこを確かめるだけで,その本のエッセンスがわかる。そういう読み方をしてきた。それだけは,戻ってこない。
捨てた瞬間戻らないものがある。それでも捨てたいなら,捨てればいい。自分の人生だから。ただし,その行為が人真似でない証をするべきだ。捨てる基準は自分で作る。僕なら,四段階の捨て方をする。
速攻で棄てていいもの,
判断猶予しておくもの,
絶対捨てないもの,
そして絶対捨てる対象にしないもの。
それも,少し間を置く。本当に速攻で棄てていいのか。その判断は今という時だけか,将来の自分も見据えているのか,明日の自分の方向は見えているのか等々。
ひとの記憶には,大きいもので,3つあると言われている。
①意味記憶(知っている Knowには,Knowing ThatとKnowing Howがある)
②エピソード記憶(覚えている rememberは,いつ,どこでが記憶された個人的経験)
③手続き記憶(できる skillは,認知的なもの,感覚・運動的なもの,生活上の慣習等々の処理プロセスの記憶)
この他,記憶には感覚記憶,無意識的記憶,ワーキングメモリー等々があるが,なかでもその人の独自性を示すのは,エピソード記憶である。これは自伝的記憶と重なるとされているが,その人の生きてきた軌跡そのものである。すべてものには,人生が絡む。それを捨てるには,よほどの慎重さがいる,と思っている。
デカルトは,問題分析の時に従うべき4つの原則を書いているそうだ。
①真であると明証的に認識できないものを決して真であると承認しないこと
②調べようとする問題をもっと簡単に解決するためには,適切で必要なだけ多くの部分に問題を分けること
③適切な順序で思考すること。すなわちもっとも単純で見抜かれるべくことからはじめて,それから次第にいわば階段を上るように,複雑なものの理解へ進むこと。さらにいうと,普通は連続しないものにすら順序をもちこむこと。
④何も忘れていないと確信できるほど何もかも完全に列挙して,一般的な見解を打ち立てること。
性急さはもちろん,これがいいと思い込む先入観を避け,疑う余地がないほどはっきりと自分で確証できないことに従わない。これが原則だ。
参考文献;
エルンスト・ヘッペル『意識のなかの時間』(岩波書店)
評判を聞いて,C・オットー・シャーマー『U理論』を読んだ。そこで,直感したのは,「開く」という言葉であった。それを,あるセミナーで公言したら,たまたまそこに,版権を持っている会社の社員の方がいらして,名刺交換した時,「恥ずかしながら,ザックリと開くことだと受け止めた」と申し上げたら,笑いながら,肯定的な反応をいただいた記憶がある(勝手読みか?)。
翌年早々のある勉強会で,「今年のテーマは『開く』だ」と,また公言したところ,何人かから好意的な反応をもらい,その後の懇親会で,それまで,つかず離れず,長い付き合いのあるカウンセラーに,付き合ってくれと言われて,驚いたのをよく覚えている。自分を開く,という言葉に,それほどの反応があるとは予期せずに,動揺したのを覚えている。残念なことに,3月に3.11が来て,しばらくそれどころではなくなったが,気持ちとしては,続いていた。ただ,あまりそれを公言しないでいた。ただ,「自分を開く」と公言することに,自分の予想を超えて,(すべての方ではないが)強く反応される方々がいらっしゃることに,少し戸惑っているのは確かだ。
自分のイメージでは,この「開く」は,いわゆる自己開示とはちょっと違う。自己開示は,心理学辞典では,
他者に対して,言語を介して伝達される自分自身の情報,およびその伝達行為をいう。狭義には,聞き手に対して何ら意図を持たず,誠実に自分自身に関する情報を伝えること,およびその内容をさす。広義には自己に関する事項の伝達やその内容を示す。自己開示の中でも,非常に内面性の高いものを開示することを告白という。
として,自己開示と自己呈示をこう分けている。
自己開示は言語的な伝達のみを対象としているのに対し,自己呈示は非言語的な伝達も含む。自己開示は意図的であるか否かはかかわりないが,自己呈示は意図的であることを前提にしている。他者が好むような行為をあえて見せたりすることを含む。
しかし,自分のイメージでは,ちょっとこれとは違う。単にドアを開けている,というのでも,シャッターを下ろさないというのでもない。もう一歩踏み出して,自分の考えていること,自分の感じていること,自分の思いを,必要な時に,いつでもオープンにできるし,そのことにこだわらず,いつでも手放せられるというニュアンスがある。
いってみると,自分についての執着を捨て,こだわりを捨て,とらわれを放ち,頓着しない,という感じが強い。あまり自己限定しないという意味では,ブレインストーミングでアイデアをまとめていくときのあの感覚に近いかもしれない。
その時,二人であれ,三人であれ,もっと多くの人がいるのであれ,その場に溶け込める,というニュアンスもある。
それまでは,いい意味でも,悪い意味でも,どこか肩肘張って,おれがおれがという感じが付きまとい,浮いている感じがあった。いや,もうちょっというと,浮いている自分を,むしろ,よしとしていたきらいがあった。それを自恃と称していた。いまも,それがなくはないし,完全溶け込んだのでは,情けない。ここでの意味は,その場とひとつになり,その場そのものが独自に動き出すのに,主体的にコミットできるようにする,という感じだ。いつもそれがうまくできているわけではないが,姿勢としてはそのつもりだ。
それとの関連で言うと,もうひとつ「自分を開く」にニュアンスがあるとすれば,人との接し方というか,人とのかかわり方である。これは自分特有の問題かもしれないが,育成歴もあって,人との接触の範囲が狭く,それを広げることに消極的だったということがある。だから,人見知りをする。初めての場には行きにくい。大体初めての場に行かなければ,ますます自己閉鎖していくことになる。悪循環だ。
ある日突然,というか,これは,「開く」と公言する十年位年前,あるコーチングの勉強会で,講師から「鎧を着ているみたいだ」と言われ,その人に,カウンセリングでも学んだら,と言われたのがきっかけで,以来,カウンセリング,セラピー,コーチング,心理学等々,好奇心の赴くまま,積極的にいろんな集まりに出るようにしてきた。だから,開くには人との接触への馴れというのもある,という気がする。馴れれば,おのずと開いていく。「自分を開く」と公言した前後から,この傾向がますます増幅してきた。その意味で,自分の中では,「開く」のニュアンスには,もっともっともっと広く人と接するというのがある。
ところで,『U理論』では,直接的に「開く」にかかわることを,そんなに言及していないが,まずは,3つの「私たちが生まれついて持っている」能力について,
①開かれた思考(マインド) 理性的な,IQタイプの知性にかかわる能力。ここでは,物事を,事実も数字も先入観なく,新鮮な眼で客観的に見る。「思考はパラシュートのようなもの-開いて初めて機能する。」
②開かれた心(ハート) これは感情指数,EQを働かせる能力だ。他者と共感し,異なるコンテキストに適応し,他者の立場になって物事を考える力。
③開かれた意思 真の目的と真の自己を知る能力。このタイプの知性は意図やSQ(スピリチュアル指数)と呼ばれることもある。この能力は,手放す,迎え入れるという行為にかかわっている。
この能力は個人レベル(主観性)だけではなく,集団のレベル(間主観性)のどちらにも備わっている,とシャーマーさんはいう。
そのためにしなくてはならないことは,いっぱいあるのだろうが,まずは,
・評価・判断の声(VOJ:Voice of Judgment)を保留し,
・その時,その場,相手への皮肉・諦めの声(VOC:Voice of Cynicism)を棚に上げて,
・古い自分を手放して,恐れの声(VOF:Voice of Fear)を克服する,
必要があると,シャーマーさんは言っている。しかし,こう考えれば,難しいことではないと感じる。
評価・判断の声(VOJ:Voice of Judgment)を保留し,
その時,その場,相手への皮肉・諦めの声(VOC:Voice of Cynicism)を棚に上げて,
は,いわば,おなじみの,ブレインストーミングのマインドだ。つまり,「批判禁止」。相手を批判するということは,自分の価値・評価からしているので,批判をやめた瞬間,こころのシャツターが開くことを意味する。相手の意見を閉ざすことは,自己完結して意見をまとめているのと同じだ。自分一人の価値と評価でまとめるくらいなら,人と話さなければいい。
そして,そうやってこころのシャッターを開けた瞬間,自己完結した,閉じた世界を開いたことなので,すでに古い自分を手放すことを始めているといっていいのではないか,と思う。
そのための自分の習慣として,シャーマーさんが,こんなことを提案しているのが,気に入っている。
①朝早く起きて,自分にとって一番効果のある,静かな場所へ行き,内なる叡智を出現させる
②自分なりの習慣となっている方法で自分を自分の源につなげる。瞑想でもいいし祈りでもいい。
③人生の中で,今自分がいる場所へ自分を連れてきたものが何であるかを思い出す。すなわち,真正の自己とは何か,自分のなすべき真の仕事は何か,何のために自分はここにいるのかと問うことを忘れない。
④自分が奉仕したいものに対してコミットする。自分が仕えたい目的に集中する。
⑤今はじめようとしている今日という日に達成したいことに集中する。
⑥今ある人生を生きる機会を与えられたことに感謝する。自分が今いる場に自分を導いてくれたような機会を持ったことのないすべての人の気持ちになってみる。自分に与えられた機会に伴う責任を認識する。
⑦道に迷わないように,あるいは道をそれないように,助けを求める。自分が進むべき道は自分だけが発見できる旅だ。その旅の本質は,自分,自分のプレゼンス,最高の未来の自己を通してのみ世の中にもたらされる贈り物だ。しかし,それは一人ではできない。
このすべてがわかっているわけではないが,自分を取り戻する時間が必要だということはわかる。しかし,この前提に,あらゆるところで,自分を開けていなければ,この習慣は意味がない。
開くというのは,ある意味,平田オリザのいう,「協調性から社交性」に通ずるとも思っている。協調とは,周りとの関係性に主眼がある,しかし社交性は,こちら側からのアプローチだ。それは,開くことで効果をアップする,と信じている。
そして,「自分を開く」は,開けば開くほど,ますます深く開ける。そう確信している。
参考文献;
C・オットー・シャーマー『U理論』(英治出版)
平田オリザ『わかりあえないことから』(講談社現代新書)
人に好きといったことが何度あるだろうか。その一瞬のことを思い出してみると,どうも,相手に対してというよりは,自分の影に向かって言っているのではないか,という気がする。自分自身を見ている。つまり,好きというのは,自己完結して,自己循環しているような気がするのだ。自分というプロジェクターが写したように,自分の幻影の膜の中で見ている相手のような気がする。
キルケゴールは,自己とはひとつの関係,その関係それ自身に関係する関係である。あるいはその関係においてその関係がそれ自身に関係するということである。自己とは関係そのものではなく関係がそれ自身に関係することである,といっていた。つまりは,自分との関係を関係するのである。
それは,丁度透明な風船の中に入って,影の自分と対話している。絶望する自分とそれほどでもないと思う自分との対話であったり,希望を照らし出す自分と踏みとどまろうとする自分との対話であったり等々,似たように,好きな人を前にして,その人自身ではなく,自分の描いた自分を見ている。
二人が向き合っていても,自分は,自分自身の中の自分と向き合っているとする。相手も,相手自身の中の自分と向き合っているとするなら,お互いが会話していても,相手の言っていることを,自分の影を通してしか耳に入れていないかもしれない。あばたもえくぼとは,よく言ったものだ。
それでは,自分と相手が,その自分という真の意味で向き合うには,どうすればいいのか。
ここは,妄想だが,啐啄同時ではないが,自分と相手が同時に,自分という自己幻影の膜を抜け出さなくてはならない。
「啐啄同時」が,鶏の雛が卵から産まれ出ようとするとき,殻の中から卵の殻をつついて音をたてる。これを「啐」と言い,その一瞬,すかさず親鳥が外から殻をついばんで破る,これを「啄」と言う。この「啐」と「啄」が同時であってはじめて,殻が破れて雛が産まれる。お互いが,同時に,相手の自己幻影の膜を,啐啄同時に破る。
そうやって,自己幻影の膜を破るとすると,それは,どういう一瞬なのか。自己充足とも,自己満足とも違う,相互が厳しい自己確認をしなければ,自己幻想の膜からは出られない。一人ではなく,相互だからできる気がするのだが,お互いが,相手をただ一人のその人として認め合うことなのではないか。それは,霧の向こうに,一瞬見える。立った一瞬。その時を逃すと,またおのれの影しかそこに見なくなる。
ブーバーは,一人の人に対し,私の<なんじ>として向き合う,という。僭越だが,僕は,丁度さかさまから,ブーバーと出会っているらしい。
ブーバーは,われわれが何かを経験するとき,世界には関与していないという。経験とはわれわれの内部におこることであって,われわれと世界の「あいだ」におきることとはなっていない,と。だから,まず,私という我の中に汝を見出すべきなのだ,経験とは,だから,「我からの遠ざかり」である,と。
でも,それでは,結局自分の影を見ているだけなのではないか,という懸念がある。間違っているかもしれないが,その自分の影を,破らなくてはならない。
フロムはいう。「愛とは,特定の人間にたいする関係ではない。愛の一つの『対象』にたいしてではなく,世界全体にたいして人がどう関わるかを決定する態度,性格の方向性のことである」という。だから,「一人の人をほんとうに愛するとは,すべての人を愛することであり,世界を愛し,生命を愛することである。誰かに『あなたを愛している』と言うことができるなら,『あなたを通して,すべての人を,世界を,私自身を愛している』と言えるはずだ。」と。
確かに,人は人を相手しいるとき,心が広く大きくなり,世界を祝福したい気分になる。でも,それは,まだ自分が自分の幻想に惹かれ,その時,その場に自己満足しているからではないのか。そういう態度になるために何が必要なのか。
更に,フロムは言う。「二人の人間が自分たちの存在の中心で意志を通じ合うとき,すなわちそれぞれが自分の存在の中心において自分自身を経験するとき,はじめて愛が生まれる。この『中心における経験』のなかにしか,人間の現実はない。人間の生はそこにしかなく,したがって愛の基盤もそこにしかない。」と。そしてこう言う。
二人の人間がそれぞれの存在の本質において自分自身を経験し,自分自身から逃避するのではなく,自分自身と一体化することによって,相手と一体化するということである。
自分自身を「信じている」者だけが,他人にたいして誠実になれる。なぜなら,自分に信念をもっている者だけが,「自分は将来も現在と同じだろう,したがって自分が予想している通りに感じ,行動するだろう」という確信が持てるからだ。自分自身にたいする信念は,他人にたいして約束ができるための必須条件である。
そして,こう言う。
愛するということは,なんの保証もないのに行動を起こすことであり,こちらが愛せばきっと相手の心にも愛が生まれるだろうという希望に,全面的に自分をゆだねることである。愛とは信念の行為であり,わずかな信念しかもっていない人は,わずかしか愛することができない。
もしお互いが,相手の「なかの芯のようなもの」を信じあえれば,たとえ「環境がどんなに変わろうとも,また意見や感情が多少変わろうとも,その芯は生涯を通じて消えることなく,変わることもない」自己の中にある確信を,しっかり確認できれば,あるいは自己完結の膜は破れていくかもしれない。
コミュニケーションは,「何かを共有する」ことでもある。言葉は,少なくとも,膜を濾してでていく。その言葉を介してしか,それを破り,見つける方法はないのなら,もっともっと,自分を語り,自分をさらけ出していくしかないのかもしれない。
その果てで,自分というプロジェクターが映しているような自己幻想の「好き」から,リアルなおのれを認知してもらうことを通して,相手のリアルな認知をつかみ,そこから,互いの<芯>を認め合うことが,ひょっとすると,本当の意味での自己完結の幻を破れるのかもしれない。仮に幻が破れなくても,まあ,それはそれでいいのかもしれないが,それでは自己満足をついに脱することはできまい。
まずは自分の物語を,もっともっと語らなくてはならない。
参考文献;
エーリッヒ・フロム『愛するということ』(紀伊國屋書店)
デヴィッド・ボーム『ダイアローグ』(英治出版)
人との距離がうまく測れないというときはないだろうか。それは,たぶん家族との間でも,間々あるが,それはたぶんこちらの心の側に隔てを意識すること(ありていに言えば,後ろめたいことやこだわりのあること)であって,ここでの場合には当てはまらない(こともないか?)。
僕自身は,対一人に対しても,対グループや場にしても,いつも,どこかに隔てを感じている。どういうといいだろう。踏み込めない障壁を感じている。それは,相手にあるのではなく,たぶん自分にある。たとえば,好きな人と帰り道が一緒になったとする,確かにしめたと思うのだが,さしさわりのない話をしているうちに,だんだん気分が重くなって,そこから逃げ出したくなる。そこから先へ踏み込むのに,たぶん氷が解けるように,少し時間がかかる。そんな気持ちがあるせいか,分かれ道でサヨナラを言うと,ほっとする思いが半分くらいある。しかし後から,こういえばよかった,ああいえばよかった,と悔いがくる。
C・オットー・シャーマーが,意識の在り方と対話について,こんな整理をしていた。
①私の中の私([I-in-me]境界内部にある中心から行動する) 当たり障りのない会話
ここでの会話は,
過去のパターンや蓄積したデータをダウンロードするような会話で,既存の態度や考えのパターンを再生産している。相手の受け入れやすいことしか言わず,自分の考えていることを言わない自閉的なシステム。
②それの中の私([I-in-it]境界の内側の周辺から行動する) ディベート(討論)
ここでの会話で,自分の考えていることに基づいて話す。互いに異なる考え方を言い合う。あなたはあなたの考え,私は私の考えを言う。それぞれのシステムは閉鎖したままの,適応的システム。
③あなたの中の私([I-in-you]境界の周縁(向こう) から行動する) ダイアローグ(対話)
ここでの会話は,初めて習慣と決まりきったやり方の世界の内側から,その周辺部へ,境界で囲まれた領域の外周へとシフトしていく。ここでは内からの視点ではなく,全体(両者双方)の一部としての自分を観るところから話をする。互いの異なる考え方の中で,私には私の考えがあるが,と自分の考えを外から見て,内省することが始まる,自己内省システム。
④いまの中の私([I-in-now]開かれた境界を超えて出現している領域から行動する) 生成的な流れ
ここでの会話は,自分の内側の視点から,外を眺めていたものが,自分(の内側)から外(の領域)へ出て,外の領域
から物を見始める。自分と他者の境界を超えて,流れているものから話す。その時のその場,その文脈に立って,自分を観,相手を観る。これを,プレゼンシング(Presencing)と呼んでいる。Sensing(感じ取る)とPresence(存在)の混成語。最高の未来の可能性のリソースとつながり,それを今に持ち込むことという,生成的システム。
こうしてみる,結果として,自分自身が自分の境界をつくっていて,おずおずと声を出している。そこでは,相手も,おずおずと私か自分を開示しない。自分の意見を出すと,相手は,それに合わせてたぶん自分の意見を出す。自分の自己開示に合わせてしか,相手も自己開示しないとみえる。
確かに,社会的浸透理論(アルトマン&テイラー)によると,自己開示を通してお互いに相手のことを知ることにより,相互の信頼が増し,好意的な関係が形成される,という。さらに,開示が表面的か内面的かでは,明らかに,内面的な開示の方が,話し手への行為が高まるし,さらには,相手が開示したことが,自分への信頼によるものとみなせたことが,より満足度を与えることになるとされている。
で,開示について,
①関係の初期より,関係が継続するにしたがって,開示と好意の関係が大きくなる。
②女性同士の方が,開示と好意の関係が大きいが,男女間ではあまり見られない。
③特定の人だけに自己開示を行った方が,誰にでも開示するより,好意のとの関係が大きい。
④自己開示の幅と深さほど,好意度との関係が大きい。
とされている。だから,自己開示,それも,内面的な開示をする,そういう場や機会を自分でつくっていかなくてはならない。これは,慣れもある。ザイアンスの法則ではないが,単純接触効果というのがある。何回かあっているうちに,相手の好意度も増すし,こちらもそれによって慣れていく。
しかし,その先にあるのは,心理的障壁だ。ただ開示するのではなく,心と感情と知がオープンにならなくては難しい。ここで,思い浮かんだのは,ブレインストーミングだ。ここで大事なのは,すべてのアイデア(考え方,考えも)是非や可否ではなく,異質さとみなすということだ。良し悪しではなく,違いとみなす。情報とは差異であるとは,ベイトソンの言葉だが,そうみなした瞬間,すべてはイーブンに,どう組み合わせるか,どうそれをクリアしていく別のアイデア(考え,考え方も)に行くかを考える。その心理的効果は,共感性に通じるものがある。自分の枠を出て,自分の意見ではなく,そこにある意見そのものの海の中にいる。そのとき,その場にいて,その場の方向を考えている。かっこよく言うと,(アイデアのまとまった)未来から今を見ている。先の④の今の中の私になれる。
そのとき,いまを作り出していくのは,たぶん,自分が,内面から自己開示できる程度にまで,自己の境界を超えて出て,心を開く,つまり,
・評価・判断の声(VOJ:Voice of Judgment)
・皮肉・諦めの声(VOC:Voice of Cynicism)
・恐れの声(VOF:Voice of Fear)
という心の中の抵抗(サボ)をかき分けていかなくてはならない。まずは,自分ができない理由(原因,たとえば自分の生い立ちや成長プロセスの外因(佐世保,富山,多治見,岡崎,高山,大垣,一宮と転々として,小学校を4回変わったから,その場所へ入るのに,様子見からはいる云々)に被けることを辞めるところから始めなくてはならない。
参考文献;
C・オットー・シャーマー『U理論』(英治出版)
奥田秀宇『人をひきつける心』(サイエンス社)
人を好きになったり,嫌いになったりは,恋は思案の外,という言葉があるくらい,理屈では分からない。だから,その思いを伝えようとすると,なかなか難しい。しかし,それは自分の視点からしか見ていないからかもしれない。
今昔物語に,有名な話がある。
(といっても,恋い焦がれた男が,相手を嫌いになるつもりで,便器を見たら,香木があったという,さんざんこけにされたという印象程度しかなかったので,ためしにグーグルで「うんこ 香木」で引くと,今昔物語の巻3
0とわかった。『宇治拾遺物語』第3巻には「平貞文本院侍従の事」にも似た話があり,谷崎純一郎の『少将滋幹の母』にも同じような場面が出てくるし,また芥川龍之介はこれをもとに『好色』を書いているようだ。以下にそれを要約してみた)。
兵衛佐の平定文が,通称は平中という人がいた。上品で,容姿は美しく,立ち居振る舞いや言葉もあか抜けしていて,当時,この平中にまさる色男は世の中にいなかった。だからもてる。プレイボーイである。その平中が,藤原時平に使える侍従の君と呼ばれる若い女性に夢中になる。
しかし歌を送っても,返事もくれず,せめて「見た」と二文字でいいから返事がほしい,と書き送ると,自分が書き送った手紙の<見た>の部分を破って,薄紙に貼りつけて返す。平中は,哀しさと情けなさで,ふさぎこんでしまった。
しかし長雨の続くある日,こんな夜に訪ねていったら,鬼のように非情な心の持主でも,哀れに思ってくれるのではないか,そう思って,暗い雨の夜,その家に仕える女性たちの住む部屋のあたりへ行き,以前より取り次ぎをしていた小娘を呼んで「思いつめた末にやってまいりました」と伝言させると,やがて小娘が帰ってきて,「今はまだ他の人も寝ていないので,御前を下がるわけにはいきません。しばらく待っていてください」との返事,散々雨の中待たされた末,人々が寝る気配があり,やがて内側に誰か来る音がして,引き戸の掛金をそっと外した。喜んで戸を引くとなんなく開く。もう夢心地で,心を静めて部屋に入ると,そこには香のかおりが満ちている。寝床とおぼしいところをさぐると,柔らかい衣ひとかさねを身につけて,女が横たわっている。頭から肩にかけてほっそりと,髪は凍っているように冷ややかである。嬉しさのあまり語りかける言葉も思いつかなかったところ,女が,「たいへんなことを忘れていました。障子の掛金を掛けていません。行って掛けてきますからね」といって,上にはおっていた衣を脱ぎおき,単衣と袴ばかりを着て行った。障子の掛金を掛ける音が聞こえ,もう来ると思ったのに,足音は奥の方に去っていき,戻ってくる音もしないまま長い時間がたった。おかしいと思って,起きて障子のところへ行って調べると,掛金が向こう側から掛けられているのがわかった。また,平中はコケにされた。
その後平中は,なんとか彼女の欠点を耳にして,嫌いになってしまおうと考えたのだが,まったく悪い噂がない。ふと,あんなにすばらしい女だけれど,便器にするものを見たら,百年の恋もさめるんじゃないかと思いついた。
そこで,便器を洗いに行くところを奪い取って,中身を見てやろうと,女の部屋のあたりをうろついていたところ,小娘が,香染の布に便器を包み,赤地に絵のある扇で隠しつつ部屋から出てくるのを見つけた。それをひったくって,中をみると,金漆を塗った便器であった。肝心の中身はともかくとして,包んでいた布といいその便器といい,ありきたりのものとはかけ離れたすばらしさ。おそるおそる蓋をとると,たちまち丁子のよい香りが匂う。その意外さに驚いて中を覗きこむと,薄黄色い液体が半分ばかりあって,親指くらいの大きさの黄黒い物体が三切れほど,丸まっている。香りがあまりにかぐわしいので,鼻にあてて嗅ぐと,黒方(くろぼう)という,数種の香を練り合わせた薫物のかおりであった。便器の液体は,丁子の香りが深くしみている。ちょっと嘗めてみたら,苦くて甘く,かぐわしいこと限りない。尿に見せかけた液体は,丁子を煮てその汁を入れたのであり,ウンコのようなのは,野老(トコロ)と黒方にあまづらを混ぜて捏ね,大きな筆の軸に入れて押し出して作ったのだとわかった。
それにつけても思うのは,こんな細工自体は,ほかにも思いつく者がいるかもしれない。しかし,便器を奪って覗くやつがいるかもしれないなどと,そもそも誰に予想できるだろうか。彼女は常人の心を超えているのだ。この人間界の人ではない。それからというもの,平中は,ただただ思い惑って,そのあげく病気になり,とうとう死んでしまったという。
平中は,今風に言えば,ストーカーなのだろう。しかし相手に完全に遊ばれている。逆に言うと,平中の思う土俵とは別のところで,侍従の君はゲームをしている,と言えなくもない。平中は,自分の土俵で相手にしてもらえない,と嘆き,落ち込むが,侍従の君の遊びの土俵の上で,相手の仕掛ける罠を,こちらも予想しながら,楽しんだら,別の土俵かもしれないが,何かを一緒にしていることになったのかもしれない。
ここまでコケにされてもなお,好きでありつづけるのはかまわない。しかし自分の土俵に相手が乗ってくれることを期待し続ければ,ストーカーになるしかない。しかし普通はありえないが,侍従の君のように,多少変態的に見えるが,相手をおちょくり,痛めつける遊び(?)の土俵に乗ってみるという,土俵の共有化もあるのかもしれない。
対人魅力の研究では,「好意の返報性」が指摘されている。自分を好きとか素晴らしいと思ってくれる人を,好ましいと思いやすい,という。しかし侍従の君にはそれは当てはまらない。ストーカーにも当てはまらない。
対人認知の類別というのがある。相手との相互作用の有無で親疎を分けている。相互作用というのは,自分(相手)の反応で,相手(自分)が懐く印象が変わったり,相手(自分)が示す振る舞いが変わったりする関係である。結果依存性という言い方もされる。それには一方的な影響を与える非対称性と相互に影響しあう対称性の二つがあるとされる。
①レベルゼロのひとたち たまたま,すれ違っただけ,行きあわせただで,再び会うことのない,将来のかかわり(相互関係)のない,人物として意味づけられることのない他者。
・注目するだけ その人の存在に気づいて,その人に注意を向ける。電車に乗っている時の向かい側の席の人。
・速射判断するだけ その人の外見や振る舞いを見て,その人がどんなタイプかを判断する。美人だな等々。
②レベル1 人物として認識されているが,相手との何らかのやりとり(相互作用)が行われていない他者。
・グループA タレントや有名人など,テレビに映る人たち。こちらが一方的に知っているだけの人たち。
・グループB 友人の友人で,その人と付き合うことには関心を持てない人たち。フェイスブックでつながっているだけというのも含まれるかもしれない。
・グループC 相互作用をしたいと思っているのではなく,お店の店員に声を掛けたり,バス待ちの人に声を掛けたりと,その場だけのかかわりとなるひとたち。
③レベル2 相手から一方的にコントロールされたり,支配されたりする関係。教祖との関係もこれに近い。この場合,結果依存性が,一方的な影響を与える側と,それを受ける側の二つがあることになる。
④レベル3 対等に相手に影響を与え合っている関係。共同作業をしている場合には,テニスの試合のような競争関係も含まれる。相手を正確に認知しようとし,評価に敏感に反応する傾向がある。
⑤レベル4 ここでは単なる関心ではなく,相手からの好意が気になる相手。その相手への思い,関心の高さは,他のレベルとは比較にならない。好意を示すものを好むという,好意の返報性と同時に,好ましさに目が向きがちというポジティブ・バイアスがあるとされる。
で,われわれは,相手から何らかの好意的反応を得ると,それが本当かどうかを,確証をえようとし,相手が自分をどう見ているか,自分を受け入れようとしているのか,自分をどのような人物だと判断しているかに,関心をよせる,と言われています。
遠くからあこがれているだけでは,「心の中の島」は,はるかに離れた「心の中だけの夢」にとどまる。鏡越しに垣間見るだけでは,現実の距離は縮まらない。そこへ近づくには,どんなに遠くても現実に第一歩を踏み出すことから始めるしかない。しかし,自分の思いと,相手の思いとは,同じスタートラインにはいない。そのスタートラインの違いを気づかなければ,ボタンのかけ違いが起こる。
どうも,平中は,レベル4を期待し,侍従の君は,レベル3の段階で,相手を試していたと見える。ここで,平中は,土俵から降りてしまった。諦めたというのは,自分の土俵に相手が乗ってくれないと,見極めたということだ。でも,侍従の君は,別の土俵にいる。もともと何の関係もない二人なら,ボタンが掛け違っているのは当たり前。それなら,どこかで,こちらが調整するしかない。調整は,相手はしてくれない。好意を示した側が,土俵をしつらえ直すほかはない。そう見える。
確かに,ちょっと男性から見ると,切ないが,しかし相手が自分に合わせてくれることを,一方的に期待し続けるのは身勝手というものだ。そこを踏み越えると,ストーカーに陥っていく。
たとえば「好きだ」と一方的に言うだけでは,相手から見れば,何も伝えていないに等しい。伝えているのは,ただ,自分の感情だ。情念だ。しかし,それを受け止める必要が相手になければ,その思いは,宙に舞うだけだ。まして,相手には,相手の事情がある。
かつて先輩に,「魚のいない池で釣糸を垂れている」と言われたことがあるが,それに近い。言ってみれば,空しい独り相撲に過ぎない。
たぶん,どこかの歌会で一緒にいられる場を見つけるとか,何かそういう迂遠でも,ともかく土俵を同じくするところから,スタートを揃え直すというのも一つの方法だが,思うに,仕掛けられたゲームという土俵で,すでに競争関係(レベル3)に入っている,それをまずは一緒に楽しむという余裕があったら,それで同じスタートラインに立てていたのではないか。むろんそれでは嫌なのかもしれないが,でも,遠くから眺めて憧れているだけよりはましではないか。そういう視点の切り替えが必要だったのだろう。
自分の土俵,つまり自分の求める相互関係だけにこだわるのは,コミュニケーションの扉を閉ざすことになるらしい。
参考文献;
山本眞理子・原奈津子『他者を知る』(サイエンス社)
芭蕉の最後の句に,
旅に病んで夢は枯野をかけ廻る
此の道や行人なしに秋の暮
がある。病んだり,落ち込んだりした時,ふと頭をよぎる。別に芭蕉の心境と重ねているわけではなく,勝手に,自分の凹んだ気持ちを思い入れているだけだ。とかく病むと気弱になる。
ずいぶん昔,あまり休んだことがなかった学校を休んだ夕方,友達がプリントを届けがてら見舞いによってくれたことを今でも思い出すことがある。あの時,気持ちとしては,休むほどでもないのに,休んだという感覚があり,友達の見舞いに面映ゆさを感じたのをよく覚えている。会社勤めの頃も,病気を口実に休んだことはあるが,あまり病欠をした記憶は多くはない。しかし,休んでひとり部屋で寝ているときの感覚は,奇妙なものだ。
人が元気でいる日常から,一人取り残されたような,一人だけ穴に落ち込んだような感覚で,同僚が立ち働いているオフィスの様子がイメージとして浮かんだりする。この感覚は自分だけのものなのかどうかはわからないが,狭いながら,自分のいる世界から,一瞬はじき出された感覚をもつ。
天命という言葉がある。天から与えられた寿命という意味もあるが,天によって定められた宿命という意味もある。それに対して反対は,非命。非命は,天命を全うしない,横死を意味する。
その一瞬には気づかないが,振り返ると,あのときがそうだったと思い当たる,歴史の転換点に,偶然立ち会うことが,ほんの限られた幸運な人間に訪れる。誰もが,おのれ一個の力のみを頼りに,それに立ち向かう。
そのとき,二種類の人間にわかれる。一人は,その流れを,おのがものとして,馬乗りに乗りこなす。いま一人は,その流れに翻弄され,押し流され,やがて力尽きて呑まれる。あるいは逃げ惑うか,ただ横切るので精一杯か,そもそも傍観者で終わるか,いずれにしても,多くは,その流れとの,束の間の交差を果たしながら,ついに足跡すら残せず,翻弄されたまま,一瞬の光芒として消えていく。その束の間の,ひとりひとりと歴史の奔流との交差点だけが,累々とつづいていく。それもまた,別の意味で,もうひとつの歴史なのかもしれない。
あるいは,束の間,歴史の馬を乗りこなしたつもりでも,結局振り落とされ,はかない一閃に終わるのかもしれない。織田信長も,明智光秀も,結局そうした光芒の一つでしかなかった。いま馬乗りにのっているものが,そうではないかどうかは,いまはまだわからない。
だとすると,非命が天命でもありうるし,横死というには当たらないのかもしれない。自分は野垂れ死にという言葉が似合っている,と思っているが,二度だろうか,そういう歴史の変わり目に,当事者の一員として加わったのは。一度は,大学で,二度目は羽田で。しかし,ただ驥尾に伏したまでで,見事に振り落とされた。
最近,維新という言葉が,いろんな意味でつかわれている。しかし,村上一郎はこんなことを書いていた。
影山(正治)は,革命者ないし改革者に対立するものとして,維新者という名称を用いている。維新者は,本質的に,涙もろい詩人なのである。維新者は,また本質的に浪人であり,廟堂に出仕して改革の青写真を引くよりは,人間が人間に成るというとき,そのような設計図は役に立たぬことを知っているのである。維新者は,若々しい情熱を政治にそそぐこと,人後に落ちなかった。が,とど時務・情勢論の非人間性を知る者でもあった。だから,岩倉具視や大久保利通のようにはあり得なかった。
そして,
文化・文政以来の明治維新の精神過程をたどると,それは永久革命というに近い変革のプロセスであると同時に,竹内好もいうように,革命であり反革命である。この矛盾は,けっして単純ではない。開国が革命的で攘夷が反革命でもなければ,その反対でもない。
と続けている。
たぶんあれかこれかの二分ではなく,四つも五つも交錯し,自身反革命の徒と思われようとなお信ずる志のもとに生死した。だから,維新者なのだという。まあ,いまふうにいうと,右も左も関係なく,突破していく力強さといった感じか。松浦玲さんは,坂本龍馬を,「突破力」と称したが,そういう感じか。
だから維新者には,どこか死者のにおいがする。昨今のためにする議論とはどうも違う。死を賭したというべきか。後ろの方の安全なところから,人をけしかけるのとは違う。自分が最前線に立つ気概がないところに,死のにおいはない。空元気のように,粋がることでもない。猪武者は武者ではないから,そう呼ばれる。暴虎憑河し死して悔いなき者は吾与にせざるなり,と孔子の言われる通りだ。
孔子つながりで言うと,村上一郎は,こう書いた。
「友あり遠方より来る,また楽しからずや」とは,友人が九州か東北からやって来た,さあ上がりたまえ,いっぱいやろうなぞというくだらぬことではなく,百年の後に知己あるを信ずる志だと,太宰治の小説にもいっているのである。
と,この連想で言うと,
温故知新
も,貝塚茂樹は,「煮詰めてとっておいたスープを,もう一度あたためて飲むように,過去の伝統を,もう一度考え直して新しい意味を知る」と解釈していた。知識ではなく,時代の中で読み直さなくては,実践知にはならない。
そういえば,石原吉郎は,あるあとがきで,こんなことを書いていた。
「もしもあなたが人間であるなら,私は人間ではない。/もし私が人間であるなら,あなたは人間ではない。」
これは,私の友人が強制収容所で取調べを受けたさいの,取調官に対する彼の最後の発言である。その後彼は死に,その言葉だけが重苦しく私のなかに残った。この言葉は兆発でも,抗議でもない。ありのままの事実の承認である。
ついでに言うと,神田橋條治さんは,「人事を尽くして天命を待つ」をこう言い換えた。「天命を信じて人事を尽くす」と。その方がしっくりくる。
参考文献;
村上一郎『非命の維新者』(角川新書)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)
企画の「企」の字は,「人」と「止」と分解されます。「止」は,踵を意味し,「企」は,「足をつま先立て,遠くを望む」の意味とされます。いわば「くわだて」です。「画」は,はかりごと,あるいは「うまくいくよう前もってたくらむ」の意味です。いってみれば,プランニングです。企画とは,「現状より少し先の完成状態」を実現するためのプランを立てることになります。この「現状より少し先の完成状態」が,いわば企画で実現したい理想やアイデアといわれるものに当たるでしょう。
ここから大事なことがふたつ言えます。
①アイデアだけでは企画にはならない,それをどうすれば実現できるかの具体策,つまり「画」を伴ってはじめて企画になる,ということです。
②現にいま起きている,何をすべきかが明確なことは,企画の対象ではなく,いますぐ対応のアクションをとるべき事柄だ,ということです。いま起きていることは,企画の対象ではないとは,こういうことです。たとえば,いま窓ガラスが割れたとします。すると,誰なら,いつまでに,いくらでやるか,とすぐに動き出します。割れたガラスを見ながら,このガラスを修繕するためにどういう企画をたてるかなどと考える人はいません。「何をすべきか」がわかっているとはこういうことです。しかし,このときの対応にはわかれるはずです。
第1は,その当該の問題を解決するだけで,「よかった,よかった」と終えてしまうタイプ。次にガラスが割れるまで,何も考えないでしょう。ここからは,発生する問題の処理に追われるだけで,企画は生まれません。
第2は,「何で,こう簡単に割れてしまったのか。確か2ヵ月前にも割れた」と考え,「割れにくいガラスにするにはどうしたらいいか」,「割れる前にその前兆をわかるようにするにはどうしたらいいか」「割れても罅ですむようなものにするにはどうしたらいいか」等々と考え始めるタイプ。このとき,企画の端緒にたっています。ただ,それが自分の裁量でできることなら,企画をたてるまでもなく,すぐに自分が着手すればいいことです。もし自分の裁量を超えているなら,相手が上司かお客さんかは別として,その人を動かすために,あるいは説得するために,企画が必要になります。時間もコストも,相手に権限があるからです。その人に動いてもいいと思わすためには,説得できるだけの意味と成果が示せなくてはなりません。これが,現実に企画というものを必要とする一瞬です。ここでいうのは企画書ではなく企画です。口頭で説明するだけでも,相手を動かせるからです。
そうすると,相手からみた場合,企画には,次の3点が不可欠となるはずです。
①何のためにそれを解決(実現)しようとしているのか。企画は目的ではない。何のためにそれをたてようとしているか,それを実現することにどんな意味があるのか。意味のないことに手を貸す人はいないのです。
②企画にどんな新しさがあるのか。わざわざ金と手間をかけてやる以上,いままでさんざんやったことではいみがない。何か新しいこと,何か新しい切り口が必要だ。それは,やることの意味にも通ずることでしょう。
③企画を実現するプランは具体化されているか。どんなリソースを使って,どういう手順で,いつまでに達成できるのか,実現するためのシナリオは明確か。「画」がなければ企画ではないのです。「画」は,「それは無理だ」への,企画するものの説得材料なのです。「画」がなければ,単なる思いつきにすぎないのです。
しかし企画力と企画を立てる力とはイコールでしょうか。確かに②と③は企画を立てる力といえるでしょう。解決プランニング力である。けれども「これを何とかすべきだ」「こういうことを実現したい」と感じなければ,そもそも企画はスタートしないのではないでしょうか。それが①の背景にあるものになるはずです。これを問題意識と呼ぶとしましょう。
このままでいいのか,何とかならないか,という思いである。この強さは,明確な目標(こうしたいという期待値)と目的(それをするのは何のためか)が明確であることと比例する。だからこそ,この思いを企画にする必要がある,企画にすべきだ,と感じる。これは,問う力といっていいはずです。これこそが多分企画力でしょう。
こう考えると,企画力は特別なスキルではないのではないかという気がします。仕事をするとき,常にいまのままでいいのか,どうしたらより新たなものにしていくか,を考えていく姿勢が求められています。その問題意識が自分の裁量内でできることなら,やるかやらないかが問題となります。しかしそれが裁量を超えたとき,その問題意識を実現するために企画が必要になる。周囲を巻き込まなくては実現できないからです。これは別の言葉で言うと,リーダーシップの問題でもあるはずです。リーダーシップとは,己の裁量を超えたとき,そのおのれの仕事への思いを実現しようとするために,周囲を,上位を巻き込もうとするスキルである。そのとき,企画は,おのれの思いを明示する旗となります。この旗がなくては,リーダーシップが自分のものになりません。これを実現するために,人を巻き込むのであって,旗なしのリーダーシップは,単なる役割行動に過ぎません。
企画の「企」は,「人」と「止」であり,人が爪先立って遠くを見ることだという意味は,企画力とは,仕事をするものにとって,その仕事にどれだけ未来を見ているかを測る基準でもあるということです。実は企画を立てる力は,それを実現するための手段スキルに過ぎないのです。
ところで,問う力は,近似の言葉に置き換えるとクリティカル・シンキングに該当します。問う力を考えるとき,『知覚と発見』(N・R・ハンソン,紀伊國屋書店)を挙げないわけにはいきません。新科学哲学派のクーンと並ぶハンソンの遺稿ですが,問う力とは何かを考えるための必読書であると信じて疑いません。とりわけ,上巻は,何が当たり前として見逃させるのか,どう先入観を崩すか,ものの見方を変えにくくさせるのは何か,等々が丹念に分析されているのです。
清水博さんは,「創造の始まりは自己が解くべき問題を自己が発見すること」と言っていますが,それは,「これまで(自分のいる場所で)その見方をすることに大きな意義があることに誰も気づいていなかったところに,初めて意義を発見すること」といっています。まさに,だから新しく,だからそれを解決することに意味があるのだということになるはずです。
参考文献;
N・R・ハンソン『知覚と発見』(紀伊國屋書店)
清水博『生命知としての場の論理』(中公新書)
もう独立して20年以上になり,組織で働いた期間より,はるかに長くなった。長くなったことで,その当時気づけなかったことに気づけるようになった。
別に正しいとは思わないが,こういう自己認識を持っていれば,たぶん独立してもうまくいくような気がしている。わかっている人にとってはばかばかしい常識かもしれないし,できる人にはたわごとかもしれない。またこういう言い方は,聞きようでは,上から目線なのかもしれないが(それが一番嫌なので),率直にいま思っていることなので,さらりと読み流してもらえればうれしい。
第一は,抱え込まない。自己完結した仕事をしないということだ。多くの場合,気づかずに,おれが何とかしなくては,と抱え込んでいるケースが目立つ。当たり前のことだが,仕事はチームでする。チームのタッグを組んでいることを忘れるくらい,人はたこつぼに入って仕事をしている。この状態を抱え込みというが,抱え込んでいることの最大の問題は,それが本人が抱え込んではならない,あるいは抱え込んでもどうにもならないレベルの問題なのかもしれないのに,本人が抱え込んでいるために,周りに見えないことだ。
チームの原則は,言うまでもなく,目的の共有化,役割分担,コミュニケーションだが,お題目のようにそんなことを言っていればいいというわけではない。チームとして機能するには,では,具体的には,それはどうなっていることなのか。たとえば,
①目的を共有するという。では,どうなったら共有したことになるのか,ただお題目のように目的を復唱することではない。それぞれの日々の仕事ひとつひとつが,チームの仕事につながっていることを,そのチームの仕事が上位部署の仕事につながっていることを,ひとりひとりが,ひとつひとつの仕事で了解できていることだ。そのためのコミュニケーションをリーダーがしたのかどうか。
②役割分担とは,どうなったら役割分担していることになるのか。単に自分の担当に責任をもつことなのか,それだけではない。自分の担当業務を介して,自分が解決できない事案にぶつかったとき,それを自分でかかえず,上司やチームに投げかけられることだ。チームで仕事をし,そのための自分の役割がわかっているとは,自分の役割を超えた案件で,自分がやるべきことなのか,チームでやるべきことなのか,チームを超えた部署や組織でやるべきことなのかが見極められることでなくてはならない。そのためには,日々上司やチームメンバーとの間で,お互いの仕事について,率直にコミュニケーションをとれる土俵ができていなければ,「それはうちの仕事ではない」「どうせ言ったって仕方ない」「どうせどうにもなるまい」ですましてしまうことになる。
③コミュニケーションがとれているとは,どうなっていたらコミュニケーションがとれていることなのか。コミュニケーションが必要なのは,役割を割り振って,あとは蛸壺にはいってひとりひとりが背負い込んで黙々と仕事をする職場にしないためだ。そういう職場は,チームになっていない。仮にチームの目指すものをどう分担するかがわかっていたとしても,チームではない。チームで仕事をするとは,一人で仕事を抱え込まず,他人にも仕事をかかえこまさない仕事の仕方のことだ。そこではどんな仕事も,自分一人でやっているのではないという了解がとれている,些細な問題もチームに上げ,チームで解決すべきことはチームで解決しようとし,上位部署もまきこんで解決すべきことは上司を介してより上位にあげていく。そのときもし自分のやるべきことをチームにあげたとすれば,「それは君の仕事だ」と,本人につき返すことができるチームだ。そういうコミュニケーションがとれていてはじめて,チームの要件としてのコミュニケーションがとれているといえるのである。
第二は,いま現場で起きていることは,いま現場で,そのことに携わっている人間にしかわからない。しかし,現場の人間にも,そのおきている意味はつかめていないかもしれない。そのためにこそ,報連相がある。報連相は,問題状況を共有するためにする。それができていなければ,あるいはそれができない状況であれば,現場のことがつかめぬまま,指示することになる。あるいは抱え込むほかはなくなる。
第三は,何をするために自分がそこにいるのかの答えを自分なりに見つけておくこと。それを自分の仕事に旗を立てるという。それは自分の仕事の意味づけであり,自分の意味づけであり,チームの意味づけでもある。
それを簡便に分解してみたのは,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0653.htm#%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AB%E6%97%97%E3%82%92%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%82%8B
である。
旗をたてるとは,自分自身の意味づけ,自分の仕事の意味づけ,自分のチームの意味づけを考えることであり,それが,チームとの関わり,上司との関わり,他のチームとの関わり,組織全体とのかかわりを考え,自分の役割を主体的に考えることになる。それが,旗を立てることの効果になる。たとえば,目的や目標を共有化するということは,自分の立場,役割としてそれをどういう形で受け止めていくかを考えることになる。それが,自分の旗を上司の旗とリンクさせ,組織の旗とつなげていくことになる。
大事なことは,自分や自分のチームの目標ではなく,その目標を達成することで,自分や自分のチームの所属する上位チームの目標(自分の目標にとっては目的)にどういう形でリンクしているのかを意識することである。それが自分の目標の意味づけであり,仕事の意味づけとなる。
そして組織成員全員が,自分の旗を持つということは,旗の連なりを見れば,組織の方向性と,そのためにそれぞれ果たしている意味が見えてくる,そんな夢のような妄想を,最近いつも描いている。
本当かウソかは知らないが,人が死ぬとき,身体から離脱して魂だけが,その部屋を俯瞰する位置にいて,死にかけている自分を眺め,その周りにいる家族や知人をながめるのだと,聞いたことがある。
まあ,そんな経験はしたことはないが,三度死にかけた。
一度はたぶん多治見で,幼稚園の時,自分の記憶では,友達とふざけながら,石段を下りてきて,振り向いてか,後ろ向きに降りたか,下のところでダンプに引きずり込まれた,と覚えていた。自分で記憶していたか,母からそういわれたかはともかく,長くそう信じていた。
ところが,母が亡くなった後,その幼稚園の園長さんから葉書が来て(ということは,母はずっと交信していたということだが),「タクシーにひかれた」とあった。たぶん,若いころ,園児が交通事故にあうという,結構ショッキングな事件で,はっきり記憶に残っておられたのだろう,母の死を知って,いただいた葉書にその件がかいてあった。記憶は,園長先生の記憶が正しいのか,母の記憶なのか,自分の記憶なのかは別にして,ダンプとタクシーではずいぶん違う。確かに,車の真下の,道路に横たわって,車の底を見上げていたという記憶もあるような気がする。しかしそこで見ていたのが,ダンプかタクシーかまでははっきりしない。
幸い,軽症で,というか脚はヒビが入った程度であったが,目じりと額には大きな傷跡がいまも残っている。そのせいでずいぶん頭が悪くなっている,本当はもっといい頭になるはずだったと勝手に思い込んでいる。
二度目は,確か,小学校の4年か5年か6年,そのあたり,たぶん4年生のころ。高山にいたのがそのころで,確か北山といったと思うが,その方向の谷川で,真夏になると泳ぎに行っていた。記憶ははっきりしていないが,誰かと一緒に行ったはずだ。で,そこで,まだ平泳ぎもまともにできない頃で,足が届いているところを,時々足先で,川底を確かめながら,立ち泳ぎのようにして,そろそろと泳いでいて,不意に足先から川底の感触が消え,それでばたばたとあわてたのか
(でないと誰も気づかないし,気づかないと誰も助けてくれなかったはず)
,しかし泳げない悲しさ,どんどん流されて,気づいたら,川底に沈んでいくところだった。その時,幻か,幻想か,本当に見たのかわからないが,川の水を通して,真っ青な空が見え,白い雲が浮かんでいるのも見えた。丁度厚い牛乳瓶の底から見たような感じであった。それはほんの一瞬だった気がするのだが,ずいぶん長い間,川底に横たわって,青空を見上げていたように記憶している。
助けられた記憶ははっきりしていない。たぶん泳ぎの達者な上級生が助けてくれたのだろう。腕を抱えあげられて引き上げられたのだろうが,そこはおぼろにしか覚えていない。ただ,川岸の岩の上で,腹這いになって,冷えた腹を温めていた記憶が残っている。礼を言ったのか,何人が助けてくれたのかも覚えていない。仲間の上級生だったのかもしれない。その後,そのことが話題になったことも覚えていないので,仲間内では,日常茶飯だったのかもしれない。
しかし,よく「溺れかかるとうまくなる」と,言うように,その経験で確かに泳げるようになった。
三度目は,ちょっと恥ずかしいが,大学生の時,失恋して,ちょっと死にたくなった。本気で死ぬ気だったかどうかはわからないが,死のうとしたことだけは覚えている。しかしたいしたことにもならず(というかまだ死にたくなかったのだろう,あっちへは行かず,現へ戻ってきた),誰にも知られず,コトは未遂ということで終わった。トホホな経験だ。
この程度の死の体験だが,残念ながら,臨死体験はない。身体から離脱した経験もないし,自分を真上から見下ろしている経験もない。しかしこの視点を人工的に設える工夫を,神田橋條治先生が書いている。
「面接している自分は,今ここに居て,患者の話に聴き入り,うなずいたりしている。ところが,その意識の一部,主として観察する自己が,一種の離魂現象を起こして空中にまいあがり,面接室の天井近く,自分の斜め上方から見下ろしている」
こうイメージしろ,と言っている。そして,「馴れるにしたがって,長時間そのイメージを保つことができるようになり,ついで,空中の眼という意識が,次第に薄くなりながら広がってくる。そしてついには,面接している自分にまで届いて,両者が融合してしまうことがある。そのときおそらく,『関与しながらの面接』が成就した」という。
これは,清水博先生が,『生命知としての場の論理』で,宮本武蔵の『兵法三十五箇条』にある,真剣勝負に臨むときの心構えを例に出されているが,「相手を対象化して正確に捉える『見の目』と,場所の中に置いて超越的に捉える『観の目』をもって敵を見る」という,その感覚とよく似ている。
そしてこれは,CTIでいう,傾聴のレベルが,レベル1(自分の考えや意見,感情,身体感覚に意識が向く状態),レベル2(すべての注意がクライアントに向けられている状態),レベル3(一つコトに意識を向けるのではなく,自分の周りにあらゆる物事に対して意識の焦点を傾けている状態)にあるとするが,丁度レベル3と似ていると言えるだろう。
ところで,幽体離脱には脳に根拠があるらしいのだ。ブランケ博士は,右側頭頂葉の「角回」を刺激すると,被験者の意識は,2メートルほど舞い上がり,天井付近からベッドに寝ている自分が見える,のだという。幽体離脱は健康な人でも,30%ほどが経験する,と言われているそうだが,実は,これは日常生活でも,結構経験するそうだ。
たとえば,有能なサッカー選手には,プレイ中に上空からフィールドが見え,有効なパスのルートが読める,といわれている。こうした俯瞰力は,宮本武蔵の例と似ている。それは,自己を客観的に評価するために,自分を他者の視点で見る,ということが必要とされているが,そのための脳の回路は,備わっているのではないか,池谷裕二先生はそう言っている。神田橋先生が,トレーニングでそれができたというのは,その回路をオープンにし,仕えるように強化したということなのではないか。
では自分にもできるのか???
参考文献;
清水博『生命知としての場の論理』(中公新書)
神田橋條治『精神科診断面接のコツ』(岩崎学術出版社)
池谷裕二『脳には妙なクセがある』(扶桑社)
ただ相互にキャッチボールしているだけでは場が場として動き出さない。どんな瞬間なのか,と言われると,どうも場と一体になったり,場と距離を感じたりしながら,その場が目指しているものを,なんとなく感じ取って,それに沿っていく。あるいは場の方向を先取りしたり,導いたりする感覚のあることもある。
例えば,研修などで,あるいはワークショップという場で,そこにいる自分になじめない,その場になじめない自分から,やがてその場の中にいる自分を認め,その場にどうかかわるかを考え,さらに,その場を動かそう,あるいはその場の動きに寄与するようにかかわるようになり,やがて,一瞬だが,場の動きと一体になった感じがする。それを一人一人が体験していく中で,それぞれなりに,場の中での自分の居場所を見つけていく。
僕の中ではこんな感じです。自分がうまくかかわれなかったり,なんとなくはじき出された感じを持った時は,違和感が残ります。
清水博先生は,こんなことを言っていました。
「自己は二重構造をもっていることがわかります。一つは自己中心的に(自他分離的に)ものを見たり,決定をしたりしている自己(自己中心的自己),もう一つはその自己を場所の中に置いて,場所と自他分離しない状態で超越的に見ている自己(場所中心的自己)です。私はこの構造のことを,自己の二活動領域とか活動中心と呼んできました。即興劇では,場所中心的自己がドラマのシナリオをつくり,自己中心的自己がそのシナリオに沿った演技(自己表現)をしていくと考えられます。
わかりやすく言うと,自己中心的自己は場所の中に存在している個物(ストーリーの中で守護として表現されるさまざまな個物,名詞)を対象として,自他分離的に捉えたり,表現したりする働きをもつています。また場所中心的自己はその主語の場所の中における状況を述語するのです。その結果ドラマのシナリオの中では,自己の二活動領域が一緒に働いて,『個物的な主語について述語する』という形式が与えられるのです。」(『生命知としての場の論理』)
宮本武蔵の真剣勝負に臨むときの心構えが例に出されていますが,「相手を対象化して正確に捉える『見の目』と,場所の中に置いて超越的に捉える『観の目』をもって敵を見る」といいます。そこまでいかなくても,グループの中に入った時,似たようなことをしていることに気づきます。
それでまた思い出しましたが,C・オットー・シャーマー氏は,「グループが針の穴を抜ける」という言い方をしていました。その瞬間は,「いつでも時間の流れがゆるやかになり,周囲を取り巻く空間が開かれていくように思う。我々は自分たちの言葉やしぐさ,思考を通して微細な存在の力が輝くのを感じた。未来の存在が見守っていて,我々に注意を向けているようだった。」「グループや組織の関係者が,異なる場から見たり感じたりするようになるのは,この地点」なのだ,という。「未来の領域と直接つながり,その未来の領域が伝える(触発)するやり方で行動できるようになる。」これを,プレゼンシングという。未来の可能性からものを見,出現する未来から自己にかかわっていく動きのことだ,という。
(『U理論』)
そこでは,
まずグループのメンバー間に強いつながりが感じられる。
次に,人々の間に真の存在の力が感じられる。
このレベルのつながりを経験すると,いつまでも続く微細な深い絆ができる。
という。しかし,そのグループへ入るには,それなりの覚悟と手放す作業がいる。「そのたびに敷居を超える」感じだという。
「サークルへ入るときは,まるで死んでしまいそうな感じになります。だから,その感じに気づいたら受け入れることにしています。境界を超えるときは,死ぬときはこういう風に感じるに違いない,というような感覚です。」
「全員が境界を超えると,私たちの状態は変わり,集合的な存在を得ます。私たちは新しい存在,『サークルという生命体』の存在を得ます。私の経験では,境界を超えないことには『サークルという生命体』は経験できません。そのあと,その『サークルとしての生命体』は一個人としての私を超えます。もはや個人としての私はほとんど問題にならないのです。けれど,逆説的ですが,同時に個人としての私もはっきりしてくるのです。」
まさに,自己中心的自己と場所中心的自己が,その場で一体化している感じです。なかなかそういう機会をえられないのは,ひとつは,そこへ入る覚悟をする時に,自分が何か手放すことを拒んでいるためだし,
その場でも,自分を場の中に立たせず,分離したままでいようとしていたせいではないか,と気づかせられます。
『場を保持する』ために,その場で必要なのは,場を保持するための,三つの聞く力だという。
第一は,無条件に立ち会うこと。
「立ち会うこと,つまりここで話している保持することの特質は,個人がサークルの源(ソース)と同一化することです。」
「一人ひとりの何かを見る目,感じる心,聴く耳が,もう個人のものではなくなるのです。ですから,予測を状況に重ねてみることはほとんどありません。生命がその瞬間に起こすことに対して自分たちを開くこと以外の意図はほとんどありません。ただ感受性があるだけで,何の企てやもくろみもありません。判断をせず,ありのままを祝福して受け入れる精神だけです。」
第二は,無条件の愛で水平に開くこと。
「部屋のエネルギーの焦点は頭から心臓のあたりに降りてきます。というのは,ふつうその入り口は誰かの心が本当に開いたときに,そしてもちろん領域の存在が感じとられたときに生じるからです。エネルギーの場は降りていくほかないのです。」
「個人的ではない愛には祝福があります。その愛は個人を超越しているということです。個人の人格は関係ありません。私たちは集団としてこの個人を超越した場のレベルを,ただ保持できているだけだと私は思っています。」
第三は,どこ注意を向けるか。
「私たちには真の自己を見るという合意があります。私たちの中の誰かがどんなことをしようと,ほかのひとはその人がしくじったとは考えません。そういう風には考えないと決めているのです。その行為の意図は本来の自己にあるのです。人のためにしてあげられるもっとも素晴らしいことの一つは,その人の本来の自己を見つめることです。私がそれを見ることを通して,その人はもっとも自分自身を生きられるようになる。」
そのとき,「私は大きな人物になったようなに感じます。私自身の存在が充実していく感じがします。」と。
これはあるいはコーチングという場の目指すもののような気がします。そういう場で,「たくさんのことが見えるようになり,もっと多くの自分を経験する」のであり,その場でなければ出会えない,何かがある,というような。
そういえば,そういった場の中の自己なしには,人間は存在しえない,社会的な存在であり,場所的状況を切り離して,自分を語るのは,「自己言及の病理」と清水先生は言っておられました。
僕はどんな場所も自分の居場所ではないという感じを持ち続けていますが,それは,自分が自己完結した自己中心的自己を手放せないせいなのかもしれない,と感じます。病理的かどうかは別として,そういう場に,まだ出会えていないのかもしれない,そう思うことにしています。しかし場は出会うもの,待つものではなく,つくるものであり,つくるのにかかわるものだということを,自分が置き去りにしている,ということにも気づかされています。
参考文献;
清水博『生命知としての場の論理』(中公新書)
C・オットー・シャーマー『U理論』(英知出版)
市民講座「iPS細胞こんにちは!~臍帯血はいのちのお母さん~に参加した。ただ山中伸弥先生の講演予定だったのを期待してのことだった。ノーベル賞授賞の報道直後もあり,思わずミーハーで応募した。しかし受賞式準備で多忙のため,山中伸弥先生が来演できなくなったとのメールを受け取ったが,やはり行く気になった。代わりに,iPS細胞研究所の副所長(所長は山中先生)で,山中先生とタッグを組んでiPS細胞を発見された中畑龍俊先生が見えると聞いたからだ。
正直iPS細胞については,素人で,実のところそんなにわかっているわけではない。ただ,iPS細胞によってすべての細胞へと分化でき,再生医療を現実的なものにした程度しか知識はない。
で,ネットで調べたウィキペディアによれば,
人工多能性幹細胞とは,体細胞へ数種類の遺伝子を導入することにより,ES細胞(胚性幹細胞)のように非常に多くの細胞に分化できる分化万能性
と,分裂増殖を経てもそれを維持できる自己複製能を持たせた細胞のことである。
元来,生物を構成する種々の細胞に分化し得る分化万能性は,胚盤胞期の胚の一部である内部細胞塊や,そこから培養されたES細胞(胚性幹細胞),および,ES細胞と体細胞の融合細胞,一部の生殖細胞由来の培養細胞のみに見られる特殊能力であったが,iPS細胞の開発により,受精卵やES細胞を全く使用せずに分化万能細胞を単離培養することが可能となった。
分化万能性を持った細胞は理論上,体を構成するすべての組織や臓器に分化誘導することが可能であり,ヒトの患者自身からiPS細胞を樹立する技術が確立されれば,拒絶反応の無い移植用組織や臓器の作製が可能になると期待されている。ヒトES細胞の使用において懸案であった,胚盤胞を滅失することに対する倫理的問題の抜本的解決に繋がることから,再生医療の実現に向けて,世界中の注目が集まっている。
また,再生医療への応用のみならず,患者自身の細胞からiPS細胞を作り出し,そのiPS細胞を特定の細胞へ分化誘導することで,従来は採取が困難であった組織の細胞を得ることができ,今まで治療法のなかった難病に対して,その病因・発症メカニズムを研究したり,患者自身の細胞を用いて,薬剤の効果・毒性を評価することが可能となることから,今までにない全く新しい医学分野を開拓する可能性をも秘めていると言える。
ということだ。で,元へ戻ると,はじめに,山中先生のビデオメッセージがあり,そこで,「私の受賞は便乗受賞で,50年前の,ジョン・ガードン先生が,カエルの腸細胞の核を別のカエルの卵子の核と入れ替えただけで,受精せずにオタマジャクシが生まれることを実証されることで,受精卵と生殖細胞だけが,完全な遺伝子の設計図を持つという,100年前以来の常識を覆したことが,私のiPS細胞につながった」という趣旨のことを発言されたのが印象深かった。普通の細胞からでも,遺伝子操作ができるという,大きなパラダイムの変更があってはじめて,研究の道筋が作られた,という意味で,共同受賞者のイメージがかなりクリアになった。
そして,iPS細胞研究所の今後10年の目標として,
① iPS細胞研究の基盤強化としての,知的財産の確立
② 再生医療のためのiPS細胞のストックをつくり,国内外に提供
③ iPS細胞を使った臨床研究を始める
④ 患者からiPS細胞をつくり,病気の原因を解明し,創薬していく
を掲げ,①はすでにほぼできつつあり,③と④がこれからの課題なっている,ということであった。そこで,②にかかわって,臍帯血バンクとの関連が生じてきたことがよくわかる。
中畑先生は,臍帯血(へその緒から摂取する赤ちゃん血液)の中に,医療に有効な造血幹細胞があることを世界で最初に発見された方で,いまiPS細胞を作るためにさい帯血がもっとも有効であることなどをお話していただいた。
実はiPS細胞も拒絶反応が起きる。それは白血球の型,HLAが,血液型違い数万あり,第三者の提供する体細胞では拒絶反応が起きる。しかし母親と父親から同じHLAという型を引き継いだ人(HLAホモドナー)の体細胞では,血液型O型と同じように,多くの人に移植できる。実は,1名のドナーで日本人の80%がカバーできることが予測されている。そのために,京都大学ではiPS細胞のストックづくりに,臍帯血縛の協力を得ようとしている。
日本臍帯血バンクネットワークは,それぞれ独立した8つ(平成24年4月1日現在)の地域バンクの集合体であり,臍帯血移植に必要なHLA(白血球の血液型)情報等の全国一元管理および公開適合検索,より安全なさい帯血の保存と提供のための検討など,移植が公平かつ安全に行われるための事業を行っている。
臍帯血移植は,白血病などの重い血液疾患に対して骨髄移植という治療が有効であり,病気になって正常な造血ができなくなっている患者さんの骨髄を健康なドナーの方からいただいた骨髄でおきかえて病気を治すという方法である。
あくまで,臍帯血移植のためのネットワークだが,そこで,HLAドナー登録をしているために,そのタイプの蓄積がiPS細胞のストックにとって,凄く有効になる。で,こうある,臍帯血からのiPS細胞ストックには,「HLAホモドナーを対象に,臍帯血移植に使用できないものを対象とする」と。
体細胞からiPS細胞をつくれば,①ほぼ無限に増殖し,②すべての細胞へ分化できる,という特色を,最大限に生かし,しかも,多くの人の再生医療に備えて,HLAタイプごとのストックを増やしていく,今回の市民講座の背景にはこんな連携があり,さらには,そのための資金支援が期待されている。
実は政府資金の支援では,多くの人材を長期に賄えず,190人の職員中,実に169人が非正規職員で,その人たちが,知的財産の確立や広報活動にかかわっている。そのひとたちをどう正規の人としていくか,欧米に立ち遅れている,研究のバックアップ組織の在り方についても,強いアピールがなされた。
研究者本人に焦点が当たりがちだが,その研究を支援するための,知財確立,法規制との調整・交渉,広報等々,幅広い人的なバックアップがなければ,そのすべてが研究者個人の負担にかかってくる。いってみると,正規軍と孤立したゲリラが科学の第一線で戦っているようで,圧倒的に不利だ。その上,そういう研究者を支援する,私的基金はアメリカと比較しても少ない。どうも日本の大金持ちは,社会への還元の仕方を知らないようで(といって金のない自分がそういう言い方をするのもなんだが),基金作りまで研究者がやらなくてはならない。恐らくそういうことも含めて,臍帯血バンクとの連携なのだろう。
それにしても,そうした研究のファウンデーション,バックアップ体制のない中で,日本の科学者,研究者はよくやっているなあ,と感心した日でもあった。
日本臍帯血バンクネットワーク
http://www.j-cord.gr.jp/ja/qa/index.html;jsessionid=0385ADF0CB103B9D323FEC9EC9DE6010
京都大学iPS細胞研究所
http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/index.html
この間,ある人と話をしていて,ふと,今更のように気づいたことがあるので,ブレインストーミングの続きで,もう少し考えてみたい。
ブレインストーミングストーミングは,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod083.htm#%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0
にあるように,4原則があるが,その中の第一条に,「メンバーの発言への批判禁止」というのがある。
「批判」は,既存の価値や知見での評価である。アーサー・C・クラークも言っている。「権威ある科学者が何かが可能と言うとき,それはほとんど正しい。しかし,何かが不可能と言うとき,それは多分間違っている」と。批判しないということは,自分の価値判断や感情,準拠枠を脇に置くことだ。そのことで,相手の声や意見が入りやすくなる。
こちらの枠組みを外すことで,シャッターが開く,そのことで相手の話が入りやすくなり,共通点見つけやすくなる。さらに相手の土俵で受けとめられれば,共感につながるのではないか。
ロジャースは,共感について,
「クライアントの私的世界をそれが自分自身の世界であるかのように感じとり,しかも『あたかも……のごとく』という性質(“as if”quality)を決して失わない-これが共感なのであって,これこそがセラピーの本質的なものであると思われる。クライアントの怒り,恐れ,あるいは混乱を,あたかも自分自身のものであるかのように感じ,しかもその中に自分自身の怒り,恐れ,混乱を巻き込ませていないということ」
が条件であると書いている。あたかも,自分のそれであるように受け取る。しかも自分の感情を混乱させるような巻き込まれのない状態で,ということです。それには訓練がいる,と書いている。
ここでは,日常的に,あるいは生活面で共感「的」であるとはどういうことなのか,を考えてみたい。
カーネギーは,「議論に負けても意見を変えない」と名言を吐いている。勝ち負けになるのは,どちらかが正しいと思っているからだ。所詮どちらも,自分の知識と経験からきた『仮説』に過ぎないと思えるかどうかだ。
この背景にあるのは,どこかに正解や正しい答えがあり,それが自説だと思い込むからだ。アインシュタインの理論ですら,仮説にすぎない。ついこの間,敗れたの破れないのと,大騒ぎになっていた。
では,仮説だとすれば,どうすればいいのか。どちらもが,自分の土俵から相手を見るのではなく,共通のテーマを,両者の頭上に置いて,それを見ている構図,を取ることではないか。これを神田橋條治さんは,二者関係から,三項関係へと呼んでいた。
こういうことだ。話し相手が部下や後輩だとして,どうしても部下のしたこと,部下の発言,部下の失敗,部下の報連相等々となると,「どうして君はそうしたの」と,上位者や先輩として,部下に話を聞く姿勢となる。それでは,どうしても部下側は,聞いてもらう立場であり,言い訳する立場になる。そういう会話のスタイルをしている限り,話をしにくいし,聞きにくい。そこで,部下の「したこと」,「発言」「報連相」「成果」そのものを,ちょうど提出された企画書を前にして,一緒に企画そのものを検討するように,部下と一緒に「したこと」,「発言」「報連相」「成果」「テーマ」を,上位者と下位者が一緒になって眺めている関係がほしい。二者関係から,そういう三角形の関係にすること。そうすることで,聞く側も,部下という属人性を話して検討しやすくなる。その位置関係は,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod064301.htm#%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0
で触れておいたので,その構図を見てほしい。コーチング的な質問で,それを表示すると,次のようになる。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod06432.htm#%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%881
いわば,お互いがそれぞれの土俵から見るか,相手の土俵で一緒に考えるか,土俵を頭上に描くか,の違いになる。そのとき,マインドとしては,ブレインストーミングをするのと同じだ。つまり,批判しない,ということだ。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/view51.htm#Critique%20Back%20Number%2049
アイデアを考えるときも,事情は同じだ。結局,自分の土俵,つまり立場,考え方,価値観からものを言うということは,相手にそれに従えと言っているのと同じことだ。そうでないなら,両者イーブンで,そこから共通の答えを探していく作業ができる。それなら,あたかも同じとみなすことはなく,同じものを見つけ出していけるのではないか。
もっと行けば,相手に○を付けてしまう。フェイスブックで,「いいね!」するつもりで,相手にOKをだす。OKした以上,話を聞かざるを得ない。自分にそう課すのも一つの手かもしれない。
カーネギーは,「議論したり反駁したりしているうちには相手に勝つようなこともあるだろう。しかそれはし空しい勝利だ。相手の好意は絶対にかちえないのだから。」と言っていた。といって意見の対立はある。そんなときは,
意見の不一致を歓迎せよ-二人の人がいていつも意見が一致するなら,そのうちの一人はいなくてもいい人間だ。
を忘れないことだ。
発想をスキルから考えるのもいいし,人とのキャッチボールから考えるのもいい。例のブレインストーミングストーミングは,いわば,アイデアや発想を自己完結しないためのいい仕組みだ。ブレストについては,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod083.htm#%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0
を見ておいてほしいが,そのほか,コミュニケーションにかかわるチェックリストは,次のように結構ある。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod0831.htm#%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
基本的に,アイデアや発想に,否定やネガティブはないのだから,このブレスト4条件は,マインドセットの基本中の基本だろう。確か,カーネギーも『人を動かす』で言っていた気がする。
「二人の人がいて,いつも意見が一致するなら,ひとりはいらない」
と。人はそれぞれ違う。しかしその違いは,微細かもしれない。アイデアで大事なのは,その微細にこだわることでもある。アイデアを考えるのは,議論するのではない。勝ち負けでもない。正否でもない。カーネギーの言う,「議論に負けても意見を変えない」というその個を大事にしつつ,しかし,人は一方で,使い慣れた脳しか使わない,機能的固着に陥っている。自己完結は,絶対タブーなのだ。
そのほかに,考えられるのは,3つあるように思う。
第一は,どうしても外に答えを探そうとすることだ。答えは自分たちの中にある。というより,徹頭徹尾自分たちの中で考えなくては,発想とは言わない。自分たちのリソースを使い尽くす。たとえば,「正方形がいくつあるか」という設問がある。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod021.htm
この出典では,正解が巻末にあった。こういうのをパズルという。たとえば,
ためらわず,こういう人がいる。
「ラインの交差したところは正方形ではないか」
それに,どう反応されるだろうか。「そんなばかな」「それは禁じ手だ」「そんなことがOKなら……」
こういう自由に考える人が必ずいる。こういう意表をつく発想は,大概はそれを押しつぶすか,面白いジョークとして聞き流されて,まともに相手にされない。こういう発想があるから,自己完結してはいけないのだ。キャッチボールする意味がある。
第二は,アイデアに正しい間違いはないということだ。こういう質問がある。「部下に,何かいいアイデアはないか,あったらどんどん出してくれ,というのだが,なかなか出てこない,出てきてもありきたりでつまらないものばかりだ,部下の発想力をアップするいい方法はないか」と。
これに,二つの疑問が浮かぶ。まず,アイデアは完成型でなくてはいけないという誤解がある。アイデアづくりとは,端緒の思いつきをキャッチボールで深めていくものであり,完成品が出てくるものではない。一緒にまとめ上げていく共同作業のおもしろさを管理職は気づいていない。いまひとつは「ありきたり」と思っているのはトップだけかもしれない,ということだ。自己完結している限り,それに気づけない。
むしろ,こう考えるべきだ。くだらないアイデアはない。くだらないといった瞬間,そのアイデアは生かされることなく,消えていく。例えば,くだらないと思ったら,こう聞いてみる。「わかった,もしこのアイデアが実現できたら,何が起こる,あるいはどういうことができるようになる」と。部下は何か言うだろう。そしたら,「その目的を実現するのに,ほかにどんなアイデアが考えるだろう」と,一緒に洗い出していく。どんなアイデアも,完結品ではない。一緒に完成していくプロセスが大事なのではないか。
第三は,まずできるかどうかを考えない。どうなったらベストかを考える。われわれは大体できることを少しずつ積み上げていく。その意味で失敗はないが,突出もできない。ダイソンがあの掃除機を提案した時,どの家電メーカーも見向きもしなかった。我々は扇風機を五枚羽,十枚羽と積み上げて,そよ風を作り出す。しかしダイソンは羽根のない扇風機をつくる。失敗しないために,「できること」を積み上げていっても,「こうなったらいい」「こういうのがあればいい」という発想から,どこまで実現可能か,どうやったら実現できるかを考えるタイプには永遠に追いつけない。
そもそも発想とは,どうしたら実現できるかを考えることであって,できることを積み上げることではない。むしろ,できない(と思われている)ことを,できる (と思える)
ようにすることだと信じている。
だから,個人的には,多機能は発想とは言わない,と思っている。組み合わせることは多機能で代替してはならない。なぜなら機能をつけたして働かせるのではなく,機能を加えないで同等の働きをさせるにはどうしたらいいかを考えることが,発想だと思うからである。
川喜田二郎氏の「本来ばらばらで異質なものを意味あるようにむすびつけ,秩序づける」という創造性の定義をかみしめなくてはならない。つなぎ合わせただけではだめなのだ(それは多機能)。つなぎ合わせた時,まったく別の意味が見える。その時,機能は足したのではなく,一つになってしまう,あるいはなくなってしまう,そういうことを考えるのが,発想の面白さなのではないか。
参考文献;
エドガー・ハーディ『「2+2」を5にする発想』(上出洋介訳 講談社)
いま日本人に要求されているコミュニケーション能力の質が,大きく変わりつつある,と著者は言う。かつては同一民族という幻想でくくれたが,いまもう日本人はバラバラなのだ。この新しい時代には,バラバラな人間が,価値観はバラバラなままで,「どうにかうまくやっていく能力」が求められている。著者は,「協調性から社交性へ」とそれを呼んでいる。
わたしたちは「心からわかりあえる関係をつくれ」「心からわかりあえなければコミュニケーションではない」とすりこまれてきたが,「もう日本人はわかりあえないのだ」と,著者は言い切る。それを,たとえば,高校生たちに,次のように伝えているという。
「心からわかりあえないんだよ,すぐには」
「心からわかりあえないんだよ,初めからは」
この点が,いま日本人が直面しているコミュニケーション観の大きな転換の本質,という。つまり,心からわかりあえることを前提にコミュニケーションというものを考えるのか,人間はわかりあえない,わかりあえない同士が,どうにか共有できる部分を見つけ,広げていくということでコミュニケーションを考えるか,国際化の中で生きていくこれからの若者にとってどちらが重要と考えるか,協調性が大事でないとは言わないが,より必要なのは社交性ではないか,という。
金子みすゞの「みんなちがって,みんないい」ではなく,「みんなちがって,たいへんだ」でなくてはならない,とそれを表する。この大変さから目を背けてはならない,と。
ところで,日本語では,対話と会話の区別がついていない。辞書では,
会話=複数の人が互いに話すこと,またその話。
対話=向かい合って話し合うこと,またその話
とする。著者は,こう区別する。
会話=価値観や生活習慣なども近い親しいもの同士のおしゃべり
対話=あまり親しくない人同士の価値観や情報の交換。あるいは親しい人同士でも,価値観が異なるときにおこるそのすりあわせなど
日本社会は,対話の概念が希薄で,ほぼ等質の価値観や生活習慣を持ったもの同士のムラ社会を基本とし,「わかりあう文化」「察しあう文化」を形成してきた。いわば,温室のコミュニケーションである。ヨーロッパは異なる宗教,価値観が陸続きに隣り合わせ,自分が何を愛し,何を憎み,どんな能力を持って社会に貢献できるかを,きちんと他者に言葉で説明できなければ,無能の烙印を押される社会を形成してきた。
たとえば,
柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺
という句を聞いただけで,多くの人々は夕暮れの斑鳩の里の風景を思い浮かべることができる。この均質性,ハイコンテキストな社会が,世界では少数派であると認識し,しかもなお,察しあう,わかりあう日本文化を誇りつつ,他者に対して言葉で説明できる能力を身につけさせてやりたい,それが著者の問題意識であることは,全編を通して伝わってくる。それは若者に限らず,同調するコミュニケーションしか身に着けないまま,転職を余儀なくされている中高年の元製造業技能者も同じ状況にある,という強い危機感でもある。
それは韓国に二十歳で留学し,海外での演劇上演,演劇ワークショップをこなしてきた著者の日本の現状への危機意識でもある。
その中で,コンテキストのずれのもたらすコミュニケーション不全を,強調している。こんな例を挙げている。
ホスピスに,50代の末期癌患者が入院してきた。この患者は,解熱剤を投与するのだが,なかなか効かない。つきっきりの奥さんが,「この薬,効かないようです」と看護師に質問する。看護師は,「これは,これこれこういう薬なんだけれども,他の薬の副作用で,まだ効果があがりません。もう少しがんばりましょう」と丁寧に説明をする。その場では納得するが,また翌日も同じ質問をする。看護師は,親切に答える。それが毎日1週間繰り返される。当然ナースステーションでも「あの人クレーマーではないか」と問題になってくる。そんなある日,ベテラン医師が回診に訪れた時,奥さんは,「どうしてこの薬を使わなきゃならないんです」と,例によって食ってかった。医者は,一言も説明せず,「奥さん,つらいねぇ」といったのだという。奥さんは,その場で泣き崩れたが,翌日から2度と質問をしなかった,という。
コンテキストを理解することは,誰にでも備わっているもので,特殊な能力ではない,と学生に説く,という。その場合,大事なことは,その能力を個人に原因帰属させないことだ。そうではなく,どうすればそういうことが気づきやすい環境をつくれるか,という視点で考えることだ。それをコミュニケーションをデザインする,と表現している。
わたしも,それはいつも感じている。組織内でコミュニケーション齟齬が起きると,個々人の能力に還元する。そのほうが楽だからだ。しかし人はミスをするし,勘違いもする,早飲み込みもする。その齟齬を置きにくい,しくみやルールをつくる。それはすでに当たり前になっている,復唱だが,同じ言葉を繰り返すことではない。自分の理解したことを相手にフィードバックするのだ。大体,しゃべったことではなく,伝わったことがしゃべったことなのだから。何を受け止めたかを必ず返すルールにする。それをたったいまからでもやろうとするかどうかだ。そこには,原因を個人ではなく,仕事の仕組み側にあるという認識がない限り,踏み出せないだろう。フールプルーフと同じ発想ではないだろうか。
最後に著者の言っていることを記しておきたい。
「いい子を演じることに疲れた」という子どもに,「もう演じなくていいんだよ,本当の自分を見つけなさい」ということが多い。しかしいい子を演じさせたのは,学校であり,家庭であり,周囲が,よってたかってそういう子どもを育てようとしてきたのではないのか,と。
第一本当の自分なんてない。私たちは,社会において様々な役割を演じ,その演じている役割の総体が自己を形成している。霊長類学者によれば,ゴリラは,父親になった瞬間,父親という役割を明らかに演じている,という。それが他の霊長類と違うところだという。しかしゴリラも,いくつかの役割を演じ分けることはできない。人間のみが,社会的な役割を演じ分けられる。
私も思う。いい加減,「本当の自分」という言い方をやめるべきだ。いまそこにいる自分がそのまま自分でしかない。いい悪いではなく,自分の価値もまた,何もしないで見つかるはずはない。必至で何かをすることを通してしか見つかるはずはない。まずは歩き出さなくてはならない。そこではじめて,自分の中に動くものがあるはずなのだ。
参考文献;
平田オリザ『わかりあえないことから』(講談社現代新書)
いつから無口が貶められるようになったのだろう。会話の中の沈黙が,いつから無視されるようになったのだろう。
沈黙もまた主張であり,発言だということを,いつから忘れられてしまったのだろう。いつから,黙り続ける自由まで,失ったのだろう。あるいは人がしゃべりたい時まで待つだけの間をいつからうしなったのだろう。緘黙という言葉がある。黙る,ということだ。そこには強烈な意志がある。もっとも,妻から問い詰められて,完全黙秘という完黙というのもあるが。
一体いつから我々はこんなに言葉を雑音のように吐き出すようになったのか。昔の,というと笑われそうだが,父親は必要な時しかしゃべらなかった。ここぞという時にだけしゃべった。それがいつの間にかそういう父親は,父親失格の烙印を押されかけている。しゃべるというのは,ハミングのように言葉をまき散らすことなのか。
もちろん,僕は,「口に出さないことは伝わらない」という主義なので,黙っているだけで感じ取るとか,見ただけで相手を目利きするとかということのできないせいもあるので,しゃべるということをなおざりにする気がないが,何が大事で何が大事でないかの区別もつかないくらい,オンオフなしに,ずっとしゃべり続けていれば,耳は自動的に半開きになり,聞かなくなるのではないか。
さんまに代表されるような吉本芸人が,軽快にしかし薄っぺらにしゃべりつづけるだけのテレビ番組がいつから,ゴールデンタイムを占領するようになったのだろう。芸人だけが楽しんでいるのを,こちらはあほ面をして眺めている(ということは自分も観ているのだが)。軽薄にしゃべり続けることが,どうして価値あるとみなされるようになったのだろう。電車の車内放送から始まって,家庭,警察,みな喋り捲っている。子供に教え諭すように,おせっかいなおばさんのように。もっとも,おせっかいなおばさんも少なくなったが。
例が悪いが,オバマの演説は確かにうまい。しかし,四年たって,あの熱気を引き起こした演説がもたらした効果が,どれだけ本気だったのか,どれだけ実現されたのか,それぞれの希望に灯がついたのか,そろそろ検証されるだろう。演説のうまさだけを云々することに,いまもかつても疑問だった。この間の大統領選が,うってかわって熱気がうせている(伯仲という別の熱気だった)のも,そのせいかもしれない。どうもつい,巧言令色鮮なし仁,を思い浮かべてしまう。わが国にも,演説のうまさは比べようもないけれど,そういう政治家が多い。覚悟がなさすぎる。リスポシビリティとは,有言実行のことだ,と訳した人がいるが,つまりは言ったことに覚悟するということだ。言い訳も,説明も無用ではないか。やったか,やらなかったか,だけなのだから。
その意味では,壺井繁治の詩が好きだ。そこには,饒舌にも,沈黙にも無用な意味を与えていない。しゃべることも黙ることも,同格のコミュニケーションなのだ。
黙っていても
考えているのだ
俺が物言わぬからといって
壁と間違えるな
かつて沈黙は,寡黙に通じ,寡黙は黙考に通じた。しかし無口は嫌われる。自分を主張しろ,という。しかし主張することだけがいつも正しいわけではない。緘黙という言葉がある。意志として黙ることだ。沈黙しがちなことを,しゃべれないとおせっかいに言うようになったのは,なぜなのだろう。なんにでも,病名というレッテルを貼り,そうすることで,相手を理解したつもりになり,無遠慮に,土足で人の中へ踏み込んでくるのとよく似ている。
黙って
暮らしつづけた
その間に
空は
晴れたり
曇ったりした
と壺井繁治は詩に書いた。かつて職人は寡黙であった。静かな毎日がそうして過ぎていった。
黙り虫壁を通す
あるいは
言葉寡なきを求めて子の師たらしむ
とも言う。もちろん,昔から,
木像物言わず
とか,
黙り者の屁は臭い
と,諺にも無口への悪口はある。韻を外すときは,外すことを意識していた。そこに格調があった。しかし誰もがしゃべり続け,韻を外しっぱなしになると,ただ無秩序に,エントロピーが増大し,ノイズが漂うだけだ。底の浅さだけが目立つ。
だからと言って,誤解されたくないので,付け加えるが,昔の日本人は格調が高かったなどとは口が裂けても言わぬ。日中戦争での上海上陸作戦で,上陸に加わった部隊のほとんどが全滅し,わずかに生き残った数十名の中にいた父が,左腕を負傷し帰国した(だから僕が生まれた)が,あるとき,ぽつりと,「(中国では)ひどいことをしてきたからな」といったことがある。その時の表情を忘れない。何か苦いものを飲みこむ感じだった。そんな人でなしのことをしたのも,かつての日本人だ。しかし,こんなに意味なく,むやみにしゃべりはしなかったのではないか。ただそれをかみしめるやつも,かみしめないやつも,黙って受け止める度量があった気がする。器量があった。いまは黙って受け止めるだけの器がない。もちろん僕自身も含めて,器が小さくなった。
平均身長は,何十センチも伸びて,倭人ではなくなったのに,倭人であった頃のほうが,はるかに器が大きかった。それは幻想かもしれないが。
歳を食った人間の繰り言かもしれないが……。
質問については,コーチング的な意味と位置づけについては,例えば,次のようなことが言えるし,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod021.htm
またコーチング的対応とそうでないやり取りとの違いは,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/prod064301.htm#%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0
とまとめることができる。
でも,もう少し先を考えてみたい。
たとえば,「コーチングのスキルは,注意を向けることに尽きる」(ジョセフ・オコナー&アンドレア・ラゲス『NLPでコーチング』)という言い方もあるし,「注意を向けるだけで,心はつながる。それが欠けていては,共感は生まれようがない」(ダニエル・ゴールマン『SQ
生きかたの知能指数』)ともいう。
ゴールマンは,注意を向けるということについて,さらに,
「相手に注意力を集中するほど,相手の内面を鋭敏に感じ取ることができる。より迅速に,より微妙な信号まで,より曖昧な状況においても,感じ取ることができる。逆に,ストレスが大きければ,それだけ相手に対する共感力は落ちる」
「このような特別の結びつきにはつねに3つの要素が伴うことを,ローゼンタール(ハーバード大学教授)は発見した。お互いに対する心の傾注,肯定的な感情の共有,そして非言語的動作の同調性,である。この三要素がそろったとき,ラポールが生まれる。お互いに対する心の傾注は,第一の重要な要素だ。2人の人間が互いに相手の言動にきちんと注意を向けるとき,そこには互いに対する関心が生まれ,2人の集中力がひとつになって知覚が結びつく。お互いが注意を向け合う状態になると,感情を共有しやすくなる」
ともいう。それを,私は,共通の土俵という言い方をする。土俵というと,「戦う場」のイメージが強いので,共通の場でも,フィールドでも,舞台でも構わないが,ともかく,一緒の地平に立っているということが大事なのだ。
「流行のハウツー本に書かれている内容とは反対で,意図的に腕の組み方や姿勢を真似て相手に調子を合わせても,それ自体でラポールが高まるわけではないのだ」という。これは,その通りだと思う。この背後には,
「ドイツ語の『Einfühlung』は,1909年に初めて英語に訳され,「empathy(共感)」という新造語として伝わったが,このドイツ語を文字通りに訳すならば,『~の中へ感じる』であって,他者の感情を内的に模倣することを示している。『empathy』という訳語を作ったセオドア・リップスは,『サーカスで綱渡りをする芸人を見ているとき,私は自分が彼の内側に入ったような気持ちになる』と述べている。他者の感情を自分自身の身体で経験するような感覚だ。そして,そういうことは確かに起こる。神経科学者たちは,ミラーニューロンの働きが活発な人ほど共感も強い,と指摘している。」
なのだと,例のミラーニューロンまで挙げている。しかし,こんなことよりなにより,土俵にのるようにすればいい。一番いいのは,相手の土俵にのることだ。
たとえば,部下に,「バカヤロー」と,その失策やミスを頭ごなしに叱るのは,正解を自分が持っているところから,自分の土俵で言っている。これを,
「自分で振り返って,俺はなんて馬鹿なことをやってるんだって,思うことない?」
と問いかければ,部下は自分自身の中で,答えを見つけなくてはならないだろう。質問は,質問されたものが,自分の中に答えを見つけようとすることなら,問う側から,相こ手に考えてほしいことを,命ずることなく,探させることになる。
「お前は,あほか!」
というよりは,
「お前さんは,自分で振り返って,おれはあほか,と思うことない?」
と問いかけたほうがいい。ただし,その問いに答えられないようなタイプもいる。正真正銘の考えないタイプの場合は,噛んで含めるように,小さなステップを,ひとつひとつ,叱りながら導くしかない。しかしその場合でも,相手に,なぜ自分が相手を叱っているか,の思いをきちんと伝えなくてはいけない。基本的に,
口に出さないことは伝わらない。
と私は思っているので,たとえば,「今ここで,これをきちんと覚えておかないと,ここで働く戦力とはみなされないぞ。」というように。
で,このことは,単に,叱るとか指導といったことだけではなく,アイデアや発想のおいても,必要だと思っている。これについては,
http://ppnetwork.c.ooco.jp/view51.htm#Critique%20Back%20Number%2049
でもふれたが,一緒につくりあげていく,というのは,一緒の土俵に乗らない限りできないことなのだ。
【注】ミラーニューロンは,相手の動作を見ただけで活性化する。ミラーニューロンの多くは,運動前野にある。実際の会話や動作,運動を起こそうとする意図まで含めて,運動にかかわる神経を支配する部分のそばにあることで,他人の動作を見ただけで,自分の脳内で同じ動作を起こす部分が即座に活性化する。人間のミラーニューロンには,物まね以外にも,意図を読み取る,相手の行動から社会的願意を推論する,感情を読み取るなどの働きがあり,共感性の神経科学的な根拠となっている。
発話の意味は,受け手の反応によって明らかになる,という。
それは,自分が喋ったことがどう受け取られたかという意味でもあるが,そうシャツチョコばらなくても,その受け取られ方で,話し始められた会話の意味が変わっていく,と考えてもいい。それが,実は会話の楽しみなのかもしれない。受け手は,話し手の会話の中から,自分が刺激を受けた部分に焦点を当てるから,当然少しずつ話の焦点がずれるが,極端な場合は,受け手の体験や記憶の中の話に移行してしまうかもしれない。
伝達という意味で言えば,口頭のメッセージは歩留り25%という説があるくらいで,基本的には,全部を聞くようにはできていないのだろう。だからもともと会話では,意識しないと,自然と自分に引き寄せてしか,相手の話を聞けない。というより,それが聞くことの常態なのだろう。だから,あえて,傾聴といわないと,丸ごと相手の話が入ってこないのだろう。
脳は活発に働き続けている。会話してもしなくても,関係なく想念は走り回っている。そこにちょっとした刺激が,外部から入ると,一瞬でひらめくが,それは,その前に,意識的無意識的に考え続けていた結果に過ぎない。その意味で,人は自分で話しながら,自分で発見したり気づいたりする。よくコーチングではオートクラインなどというが,発話する時,発話の2~30倍のスピードの想念から,言葉にして,口から言語として語りだす。それまでのプロセスは,自分の思いをどう言葉にするかの方に注意が向いている。しかし発話した瞬間,こんどは自分の喋った言葉を耳から,情報として聞く。それが,外からの人の言葉と同様に,脳への刺激となり,気づきをもたらす。ブレインストーミングが効果があるのは,相手の発言の意味内容全体よりは,そこから受け止めた刺激としての情報に,たぶん意味がある。その門前で,批判してしまったら,ゲートを入る情報が少なくなる,そんな意味だ。
会話の微妙なずれ,ということで井上光晴を思い出して,探してみたが,うまく例題になるものが見つからない。
適当に拾い出してみた。
「酔ったな」彼はいった。
「酔ってなんかいないわ。事実をいっているだけよ」
「何が事実だ。森次のことを,いつおれが一枚看板にした。森次のことを,いつおれが売り物にした。森次のことをいうのは,あいつが可哀そうだからだ。いつ,おれが自分の性根をうしなった」
「森次さんが可哀そうなのは,いまはじまったことじゃないじゃないの,はじめからだ」
「ごまかすなよ」
「私が何をごまかしてるの」
「ごまかしてるよ。君は自分のことは何もいわないじゃないか」
「変ないいがかりはよしてよ。私が何をいわないっていうの,何を隠しているっていうの」
「君は隠しているよ」
「ほら,それがあなたの得意の論法よ。自分が危くなると,逆に相手に短刀をつきつけるんだから」
「短刀をつきつけられるようなことがあるのか」
「なにをいってるの。言葉だけのりくつはやめてよ」(『地の群れ』)
ただ単純にページからランダムに引き出しただけだが,普通の会話のずれと微妙な乖離が見事に出ている。会話の名手という気がしている。人は,自分のことを考えている,だから自分の引っかかったところに食いつく。そしてそこで会話が変わっていく,ということが如実にわかる。
この会話のずれは,お互いの思いのずれになり,思いのずれは,少しずつ行き違い,隔絶を広げていく。こんな時,話せば話すほど,ずれは大きくなる。
相手のずれに気づければ,その人の関心か,あるいはその人としての注意の向きがみえる,かもしれない。たぶん受け止めるということが必要なのは,そのことを拾い上げることなのではないか,という気がしてくる。そこに,意識していないかもしれない,関心や価値があるはずだから。
昔から怒りっぽく,怒りで散々な目にあっていたとしよう。
そのとき,どう怒りをコントロールするかという話になるのだろうか。たとえば,論理療法でいうように,イラショナルビリーフがあるからだと。たしかにそれもあるかもしれない。だが,怒りがその人の価値にかかわることだとしたら,それをコントロールすることは,その人の何かを矯めることになる。
確かに激昂した状態で,冷静な判断は下せないし、瞬間のさらにその一瞬の一瞬に集約されたような尖がった状態になっていて,すさまじい視野狭窄に陥っている。トンネルビジョンの状態になっているときの,そこからの抜け出し方は,一瞬立ち止まれるかどうかにかかっている。その瞬間,選択肢が生れる。このまま行くか,立ち止まり続けるか,戻るか,選択肢が絶えず3つ以上生まれるとき,すでに発想に余裕が出る。
頭の中の,意識の流れは言語化のスピードの20倍から30倍なのだという。さまざまな思いや妄想が次々と流れそれを言語にしようとするとき,その思いに適合する言葉を瞬時に探し当てて,コトバにして口から出す。ところが,怒りの瞬間は,感情が最優先で流れるので,言葉も短絡化する。しかし,思い出すと,言葉を口に出す寸前,必ず,コンマ何秒かの間がある。ほんの一瞬どうするかを迷う束の間がある。その間が,たぶん,立ち止まる最後の機会になる。
何度も怒りで失敗してきたので,この間合いはよくわかる。長く,自分の怒りを恥じてきた。あるいは,そのたびに悔いる自分を蔑んできた。
怒りを前にして,相手の反応は3つに分かれる。同じ土俵で,怒りの度合いを張り合う。この場合,よく野生のオス同士が負けじと張り合うのに似ている。いまひとつは,すさまじい鎧を着飾って,それで対抗する。手段は,いろいろあるが,まあ馬耳東風と流されるのが、ますます怒りを煽る。最後は,土俵を下りて去る。とりあえずは頭を下げても,心の中で舌を出しているのが、よく見える。
最近はめったに怒らなくなった。怒るには相当のエネルギーがいるからだ。叔父の口癖は,怒ったら負け,というのだ。成らぬ堪忍するが堪忍,とはよく言ったものだ。
ただ,このごろ必ずしも怒りを悪いこととは思わなくなった。怒りを抑えることも大事だが,怒るべきときに怒らないことのほうが,人間的ではない,と感ずる。そのときに怒らなくてどうすると思うことも多い。自分にしろ,誰か身近な人にしろ,あるいは赤の他人でも,理不尽なことに出会ったとき,それに屈することなく,怒りを挙げることは必要ではないか。怒っている,ということは大事なのだ。
ただし,怒ることと怒っていることを伝えることは別だ。なんと成長したものだ。そう思えるようになっている。ではどう伝えるのか、もちろん,アサーティブなアプローチも悪くない。ただ,せっかちな自分の性には合わない。
で考えた。怒っているとしよう。その時,「俺は怒っている」と伝えても,その怒りの大きさは,伝わらないだろう。その瞬間の冷静さが相手に伝わるだけだから,多少日頃の人間関係を意識させることにはなるかもしれないが,怒っているインパクトと,その怒りの大きさは伝わらない。で,
「おれは,いま,
馬鹿野郎!(ここは,怒りの大きさに合わせて大声を出してもいい)
と,言いたい気分なんだ」
と言ってみる。相手の瞬間の驚愕の表情と,そのあとのほっとした表情の落差をひそかに楽しむ。これなら、まだコミュニケーションの土俵に乗っている。
器用でもない,気もきかない,やることなすことうまくいかない,仮にそうだとしよう。
それをどう受け止めるのだろう。まずは,そのことを率直に語った真率さを,まずはポジティブにとらえるだろう。相手が問題といったことは,単なる言いかえではなく,真のリフレーミングにするには,それを心底プラスと受け止めなければ,単なるおためごかしに過ぎない。その率直さに,自分を何とかしたいと真実思っている姿勢と,だからこそ,あえて自分のマイナスを強調した,とみなせば,それは自分の負の部分と向き合える勇気なのかもしれない,あるいはいまの自分を何とかしたいという前向きの姿勢なのかもしれない。さらにその口ぶりの中に,不器用だけれども,粘り強さがあることをかすかに誇りに思っているにおいが感じられるかもしれない。あるいは気が利かない自分のなかに,頑固で,梃子でも動かない,軸があるのかもしれない。そして,やることなすこと,と総括しているなかに,実はもれてしまった,小さな成功が隠れているのかもしれない。
言葉で語っているのは,本人がいま意識しているネガティブ光線に照らし出されている部分だけなのだ。ではそこからもれた,別の機会,別の場所では,何があったのか,それは別のポジティブ光線で意識的に照らし出して見なければ,浮き上がっては来ないだろう。そこが,リソースをみつけるためのポイントなのではないか。
人はみな可能性がある,という。神田橋條治先生は,生来付与されている遺伝子の可能性を開花させる,という言い方をされていたが,それこそがポジティブ光線というものだ。
器用でないことで,得したことがあるかもしれない。その視点で見ていくと,器用でないことで,努力する必要があり,結果として,別のものが開花しているかもしれない。しかし本人は器用・不器用で振り分けているから,そのことは視野に入ってこないだろう。
われわれは(いや,ぼくはというべきだろう),一つの視点をとると,それから,なかなか離れられなくなる傾向がある。それを固定観念ともいうが,正確には機能的固着,つまり脳の働きが固まっている,あるいは脳のいつもの場所しか使っていないということである。それを習熟,という習性と呼んでもいい。
ネガティブになずむと,それによって,すべての過去が一色に染まる。ナラティブセラピー風にいえば,それが自分の観念を支配するドミナントストーリーとなる。それと異なる視点で見れば,ひょっとすると,数多のオルタナティブストーリーがあるはずなのだ。
神田橋條治先生は,それを能力と名づけた。悲観的というのは,悲観できる能力。極楽トンボよりはいい。怒りっぽいというのは,何についてもアグレッシブになれる能力等々。先ずは相手のネガティブに○をつければ,それはリソースなのだから。
エリクソンは,有名な,すきっ歯に悩む女性に,すきっ歯から水を飛ばす練習させた。あるいは人前でおならをして引きこもってしまった女性に,大鍋一杯の豆料理(海軍では口笛豆というそうだ)を作って食べさせ,大きいおなら,小さいおなら,うるさいおなら,やさしいおならの練習をすることを課題として出した等々。オハンロンによると,エリクソンは,患者の行動や体験のパターンを無批判に受け入れるだけでなく,パターンを積極的に発見し,変化を起こすために利用した,という。
N.R.ハンソンにならえば,なぜ,同じ空を見ていて,ケプラーは,地球が回っていると見て,ティコ・ブラーエは,太陽が回っていると見るのか。あるいは,同じく木から林檎が落ちるのを見て,ニュートンは万有引力を見,他人にはそうは見えないのか,ということになる。ハンソンは,それを「~として見る」と呼んだ。結局,われわれは対象に自分の知識・経験を見る。ゲーテは,「われわれは知っているものだけをみる」と言った。その延長線上で考えればいい。行動理論風にいえば,そういう見方を学習したのだ。ネガティブでおのれを見たほうが,生きやすいか,自己弁護しやすいか,防衛しやすいか等々。
能力に置き換えるのも,リフレームするのも,別の視点,別のものの見方,つまりオルタナティブなポジティブ光線で,照らし出すことで,別の自分が見えてくる,ということなのだ,と思う。
参考文献;ノーウッド・R・ハンソン『知覚と発見』(紀伊国屋書店)
http://ppnetwork.c.ooco.jp/view04.htm#%E2%80%9CCritique%20Back%20Number%202
「大丈夫?」というと,苦しそうに急き込んでいた母が,「大丈夫じゃない!」と苦しそうに返してきたのを初めて聞いたときは,びっくりした。そういうこと言う人ではなかったからだ。あわててナースコールを押すと,ちょっと見ただけで,医師を呼びに走った。それからは,何回か,同じ問いかけし,同じ応えが返ってくる,それもそのうち出来なくなった。そんな思い出が蘇る。
正直,見かねて,だれもが,ついつい「大丈夫?」と声を掛けがちである。
これが,親しい仲なら,ただの気遣いですむが,これが上下関係,上位者と下位者だと,そうはいかない。内心は,困っていて,悩んでいても,「大丈夫?」と上司に声掛けられて,「ハイ,困ってます,実は…」と返事できるには,それこそ,両者に信頼関係がないと難しい。たとえば,ジョハリの窓でいう,「パブリック」ができているのなら,こころ安く打ち明けられるが,そうでなければ,「ハイ,大丈夫です」といいがちである。いや,そういわなくてはならないような,暗黙のプレッシャーを上司のその言葉に受け取りがちである。意識しているかいないかは別に,その言い方には上から目線を感じてしまい,「大丈夫」としか答えようがないのかもしれない。
だから,分担しているパートを担っている,各部下に,「うまくいっている?
」「大丈夫?」と声を掛けて,部下から,「大丈夫です」と返事がきたからといって,安心してはならない。ここは,大丈夫といっておくしかない。困っていることがある,といいそびれてしまったから,いまさら聞けない,そんなことをしたら,なんでもっと早くいわない,と叱られるのがおちだ,等々。その結果,蓋を開けたら,その部分が遅れており,全体の足を引っ張ることになる,なんてことになる。
ではどういう声掛けをしたらいいのか。ベストの答えは,個々ばらばらだろうが,せめて「ちょっと心配そうに見えたが,困ったことがあったら,いつでも声をかけてね」とか「サポートがいるなら,遠慮しないで言ってね」というように,具体的な声掛けでないと,実はとは言いづらいのかもしれない。
「大丈夫?」という言い方には,念のため声をかけるが,たぶん大丈夫だという返事が来ると,どこかで期待してるというニュアンスが,みえみえで,とても何が打ち明けたり,相談できる雰囲気感じさせないのに,違いない。本来,日頃から,そういう気安い関係がつくれればいいが,それが難しければ,せめて,声掛けの言葉に,こちらの思いや心が開かれているのでなくてはならない。そこに,声を掛ける側の心が開いている状態が,相手にみえなくてはならないのだろう。
「アドバイスしていい?
」という声掛けでは,多く相手に優位性を感じ取り,体が固まるのだという。そこには,暗に「俺の言うことを聞け」というニュアンスを嗅ぎとるからだ,といわれている。親切心も,気遣いも,自分の立ち位置を意識して,相手にどう受けとられるかを考える必要があることが多い。なかなか人の心理は難しい。
●ジョハリの窓
ジョハリの窓については,
のコミュニケーション・チャンネルを確立できる~常にパブリックをつくる
をご覧ください。
“ジョハリの窓”は,ジョセフ・ラフトとハリー・インガムのファーストネームからつけられた。自己理解の仕方として,
・自分にわかっている自分/自分にわかっていない自分
・他人にわかっている部分/他人にわかっていない部分
の4つの窓に分けてみようとするものである。
共通のコミュニケーションの土俵づくりという面で“ジョハリの窓”を考えたとき,重要なのがパブリックづくりである。自分(上司)が知っている自分を,自分が果たしている役割,自分のしている仕事の仕方,進め方,何を重視し,何に価値をおいているか,を他人(部下ひとりひとり)が,理解してくれている部分とすると,パブリックのできている部分だけで,部下ひとりひとりとのコミュニケーションの土俵ができていることになる。これを相手との間で形成するのが,コミュニケーションの土俵づくりをする意味である。
パブリックを広げる方法はふたつである。
第一に,自分が何を考え,どう思っているかを語ることである。自分が何を目指し,何をしようとしているかを明確にすることによって,プライベイトな部分を小さくできる。
第二は,相手からのフィードバックを聞くことである。自分の行動がメンバーからどう受け止められているかをフィードバックしてもらい,自分の知らない部分,気づいていない部分を受けいれることによって,ブラインドの部分を減らせるのである。
われわれは,まず相手に先入観をもつ。
強持てだ,不潔だ。愛想が悪い。目が怖い等々。自分には,それと,こちらの持つ仮説とどこが違うのかがわかっていないようだ。たとえば,コーチAでは,タイプ別けということをいう。私はコントローラーというタイプが強く。それと並んで,プロモーターがある。それがわかると,私の振る舞いのすべてがコントローラーにふりわけらけられる。やることなすことが,コントローラーの枠にはまって見えられることで,いらだつかしょげるか,相手にしないかしか選択肢がない気がしてくる。それで納得している相手の当てはめを聞かされていると,自分が自分でなくなっていく印象がある。セラピストが,DSM-Ⅳの分類基準に当てはめて病名診断をするのも,それとよく似ているのかもしれない。
今更めくが,ロジャースは,「人間的成長の促進に関するいくつかの仮説」の中で,こういっている。
「私がある種の関係を提供できるなら,相手は自分が成長するために,その関係を用いる力が自分の中にあることを見出すであろうし,そこで変化と人間的な成長が生じるであろう」
そして,有名な3つの要点を取り上げている。
「私は自分自身が関係の中で純粋であるほど,その関係は援助的なものになることを見出してきた。このことは,私が出来る限り,自分自身の感情に気づいている必要がある,ということを意味している。つまり表面的には,ある態度を表しながら,より深層の無意識的な水準では,別の態度を持っているのでは,純粋であるとは言えない。」
「第二の条件として,私は次のことを見出している。すなわち,私がその人に対して受容と好意を持てば持つほど,その人自身の成長のために用いることができるような関係を創りだすことが出来る。受容という言葉の意味は,私にとって,無条件に自己の尊厳を持つ人間―つまりどんな状態や行動や感情であろうと,価値ある人間―として,その人に暖かい配慮を寄せるということである。」
「私はまた,私がクライアントを理解したいと思い続けていると感じている度合いに応じて,つまり,その瞬間の相手の感情とコミュニケーションのどちらについても,その人が見ているままに,感受性豊かに共感することによって,関係が重要なものになるということ見出している。」
ここにすべてが尽きているような気がする。だから,こころある人は,仮説を立てて人に向きあわない。あるいはすぐに自分の仮説てばなすことができる。
でも,自分でもたぶん無意識でやることがあるだろう。その仮説から見れば,すべてが,そう見えてくる,というように。それで相手がわかった気になる。
その意味では,コミュニケーションについていった,エリクソンの原則を,自分は大切にしたいといつも思っている。
ひとつ,相手について仮定しないこと
ひとつ,緩やかな変化
ひとつ,相手の枠組みであること
ひとつ,自らの考えを変える力があることを,相手自身が気づけるような状況つくること
ひとつ,そのために使える相手のリソースとなるもの相手の中に見つけて利用する
そこにあるのは,眼鏡や仮説ではなく,逃げることなく,相手と向き合うことだ。
同じことを,ブリーフセラピーの若島礼文先生は,
まずは相手に○をつける。
自然な変化の語り(どう良くなっているか,良くなっているところに焦点あてる)
Do something different
の三原則挙げる。
またCTI系のコーアクティブ会話術では,
先ずは受け止める
いいところを見つける(①とにかく「いいね!」という。②その考えのいいところは,といい点にフォーカスする,③さらに加えると,とそれを発展させる )
感謝を見つける
の三原則を挙げる。
先ずは相手に○印つけなくて,どうするのか,自分にまず言い聞かさなくてはならない。わたし自身が,人以上に,好き嫌いの先入観が強いから。
参考文献;『ロジャースが語る自己実現の道』(岩崎学術出版)
明治維新後,四半世紀経て執筆され,更に10年後にやっと上梓された,福沢諭吉が『痩我慢の説』で,勝海舟の幕末の政権運営を,「予め必敗を期し,その未だ実際に敗れざるに先んじて自ら自家の大権を投棄し,只管平和を買わんとて勉めた」と痛罵したのに対し,福沢から送られたその本へ,勝はこう返事したといわれています。「行蔵は我に存す,毀誉は他人の主張,我に与からず我に関せずと存じ候」。簡潔な,しかし痛烈な返答の後背にあるのは,リーダーを語ることとリーダーたることとは違います。リーダーシップを論じることとリーダーシップとも違います,という勝の矜持です。『痩我慢の説』は,維新後四半世紀経て後執筆され,更に10年も後に上梓されています。そのときが終わってから,何を言おうと所詮評論でしかない。勝の口癖,「機があるのだもの」という声が聞こえてきそうだ。
リーダーを論ずることとリーダーシップを論ずることとは,微妙な違いがある。確かにリーダーはポジションを指し,そのポジションを機能せしめる働きとして,リーダーシップは重要になる。だからといってリーダー論ずることが,リーダーシップを論ずることの代用にはならない。なぜなら,リーダーシップはポジションに関係なく,すべてのものに必要なものだからだ。すくなくとも,組織で動くものにとっては,それなしでは仕事することは,蛸壺の中で自己完結して仕事することを意味し,それは真に仕事するということにはならないからだ。
たとえば,仕事を問題解決と置き換えて考えてみる。問題を解決していくというのは,次々起こる問題に対処するという意味ではない。目標立て,そこのある障害(問題)をクリアして,目標を達成していくことと置き換えれば,仕事のイメージが明確になる。単に原状回復ではなく,目指すべき水準(期待値と置き換えてもいい)を実現していく,ということである。その場合,問題のハードルが高ければ高いほど,つまり目指す達成水準が高いほど,自己完結していて実現できるはずはない。そのとき,問題解決とは,それ解決できるモノやコトを動かせる人を動かさなければ,一人で出来るはずはないのだ。
では幕末,海舟と諭吉にとって,目指すべき目標は何か。それは,徳川家を存続させることでしかない。なぜなら,既に大政奉還し,幕府機能は朝廷に返上しており,幕府はないからだ。そのとき,勝がつかった論法は,薩摩,長州という藩を残したまま,徳川家のみを潰そうとするのは,「薩長の私だ」という理屈だ。西郷は,「我国を捨て皇国を興す」(ここでいう国は薩摩藩を意味する)と書いていた。慶喜に辞官納地を求めるなら,薩摩も長州も領地を返納しなくてはならない。徳川だけにそれを求めるのは,「私」であり,それを強いるのは「私」だ。大政奉還した慶喜のほうが「公」である,という論法だ。
鳥羽伏見の敗戦で戦線離脱し,逃げ帰ってきて,しおれている徳川慶喜と幕閣に,「だから言わんことじゃない,どうするつもりか」と,面罵した。さんざん慶喜に煮え湯を飲まされた海舟は,ここで既に慶喜が投げ出してしまっているのだ,海舟も投げ出しても良かった。「何をいまさら,俺は知らぬ」という選択肢もあったはずだ。しかし,勝はすべてを引き受ける。松浦は,「ひとは状況にしたがって自分の価値を最も発揮できる生き方を確立する権利がある」と書く。
ここから勝のリーダーシップが発揮されていく。まずは,徹底恭順するよう上司(慶喜)を動かし,そうやって「私」を捨てた徳川が「公」を貫くことで,相手にも「公」で応じさせようとする。相手にも「私」を捨てさせようとする。「我今至柔示して,之に報ゆるに誠意以ってし,城渡す可し,土地納む可し,天下の公道に処して,其興廃を天に任せんには,彼また如何せむや」と。見事に徳川家を残したのだ。
諭吉のような外部の人間には,その瞬間の勝の立ち位置は見えない。このとき最もおのれの真価を発揮できる,そういう生き方を,このとき勝は選択している。リーダーシップとはそういうものだ,と勝は言っている。だから後から何をいわれても,毀誉は他人の主張,我に与からず我に関せず,なのだ。その一瞬,その人の生き方の価値にかかわる,選択肢が目の前に現れる。それを選んだとき,そのリーダーシップは,そういう個性,個の輝きをもっている。それはほんの些細な問題解決でも同じである。
組織にいる人間にとって,リーダーシップとは,トップに限らず組織成員すべてが,いま自分が何かをしなければならないと思ったとき(それを覚悟という),みずからの旗を掲げ,周囲に働きかけていく。その旗が上位者を含めた組織成員に共有化され,組織全体を動かしたとき,その旗は組織の旗になる。リーダーシップにふさわしいパーソナリティがあるわけではない。何とかしなくてはならないという思いがひとり自分だけのものではないと確信し,それが組織成員のものとなれば,リーダーシップなのである。
参考文献;松浦玲『勝海舟』(中公新書)
ミルトン・エリクソンは,若い頃の自分の体験で,迷い馬に出会ったとき,ただその馬に跨って,馬の行きたいところにしたがい,馬の歩くにまかせ,やがて,飼い主の牧場にたどりつき,戻ってきた馬に飼い主が驚いた,という逸話を,無意識を信ずるという例として,紹介していた。
最近の脳研究では,人が自分の意思する意図を意識の上るのが,実際に運動が生ずる150ミリ秒前,さらにそれよりも400ミリ秒も前に,脳の運動神経系の活動電位が変化している,という。つまり,手を伸ばして,コップを取ろうと意思する150ミリ秒前に,無意識は動いており,それより400ミリ秒も前に,脳は動かそうという活動開始している,というわけだ。
脳が損傷し,意識的な笑い顔が作れなくなっても,脳は自然に笑い顔つくれる,ともいう。よく,脳は,自分が知っている以上のことを知っている,というが,脳という自分のリソースのもつ奥深さから考えると,人が意識している部分はほんの一部で,その一部でおのれ全体左右しようとするのではなく,無意識というより,おのれの脳の志向を確かめて動いてみる方が先かもしれない。
その意味で,自分のリソースというのは,自分で意識的に探索しようとするよりは,無意識の志向をどう引き出すか,という視点で考えた方がいい。精神科医の神田橋條治は,精神療法の目指すのは,その人の遺伝子を開花させることであり,それがその人の自己実現だ,という趣旨のことを書いていたが,それはこの文脈で考えると,よくわかる。
それは,必ずしも,本人が意識している「なりたい自分」,口に出している「ありたい自分」ではないかもしれない。それ探し出すために,対話療法をするともいえる。コーチングもまたその一翼を担っているとすれば,本人の語る言葉ではなく,その人のリソースの語りだすもの,とりあえずは言葉にならない感情,思いを導きださなくてはならないのかもしれない。「クライアントの可能性を信ずる」というのは,単にその人の伸び白を信ずることではない。まだ本人も知らないリソースの可能性現前化させること,それこそが遺伝子開花させることでなくてはならない。結構奥深く,重い。(敬称略)
アイデアは,いわば脳内のリンクをどう多岐に張るかにかかっている。はっとひらめいたとき,0.1秒脳内の広範囲が活性化するという。つまり,いつもとは違うところがつながって,ひらめきにいたったことになる。
それを前提にすると,アイデア出しは自己完結させてはならない。ブレインストーミングが有効のなは,それによって,自分の脳が刺激を受け,思わぬところとリンクさせることが出来るからだ。
また一つは,その意味では,いつものように見ている限り,同じようにしか見えない。そこで,見え方を変える工夫がいる。
たとえば,ひっくり返す,裏返す,遠ざける,近づける,分解する,解体する等々。そうやって見え方を変えることで,いつもと違う見方を強制的にする,というのもひとつ。
おいおいお伝えするとして,大事なことは,脳内リンクが多様化,多岐化するのを常態にすること。それには,脳内リンクの筋力トレーニングしかない。
ばかばかしくても,日々考え続ける。いま一日一個を実践している。ぶっちゃけると,実は今年にって,一日一個にしたが,従来は一日二個であった。歳とともに,二個目が出なくなって,とうとう諦めた。二個にチャレンジするのもいい。
その成果は,次のページを見てほしい。実にくだらないことに着目してほしい。
http://ppnetwork.c.ooco.jp/idea00.htm#Idea%20Memo
アイデアは,完成品が出るのではなく,くだらないものから,揉んでいく。その意味で,アイデアにくだらないものはない。くだらないと一蹴した瞬間,大事な獲物を逃す。出発点にすぎないことを肝に銘じなくてはならない。
極楽蜻蛉とは,最近あまり使わないが,
うわついたのんき者を罵って言う語,
とある。手元の辞書には,載っていないので,ネットの,日本語俗語辞典
http://zokugo-dict.com/10ko/gokurakutonbo.htm
には,
「極楽とんぼとはどんな場面でも呑気に過ごす楽天家のことで、そういった人を嘲う言葉として江戸時代から使われている。池や水田の上空を優雅に飛ぶトンボの姿は、見ようによっては何も考えず、呑気に飛んでいるようにも見える。」
とてある。同じく,『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ko/gokurakutonbo.html
には,
「極楽とんぼの『極楽』は安楽で何の心配もない場所や境遇。『とんぼ』は昆虫のとんぼのことで,のんきに生活しているもののことを,極楽を飛ぶとんぼのようなものとたとえた言葉である。…同じ意味の言葉に『極楽とんび』もある。『とんぼ』や『とんび』がこのような喩えに使われるようになった由来は,上空を舞うように飛ぶ姿からである。とんぼの中には,極楽とんぼの喩えには向かない素早く飛ぶ種も多いが,ここでのとんぼはアキアカネのことと思われる。」
とある。アキアカネは,
「普通の赤とんぼ」
のことである。これに関して,こんな記述もあった。
「日本の古名に『あきつしま』というものがあります。『あきつ』とはトンボの古名ですから、日本のことをトンボの島と呼んでいたことになります。それほどトンボは重要な虫だったわけです。
さて、この『あきつ』は赤とんぼのことだと思われます。赤とんぼは夏の間は山の上で暮らし、秋になると大群となって麓におりてきます。現在では余り見かけなくなりましたが、昔は稲刈りの頃に空が赤く見えるほどの大群でやってきて、害虫を食べてくれました。赤とんぼは豊作を象徴する虫だったのだと思います。
『あきつ』は『秋の(虫)』という意味かと想像します。トンボは『飛ぶ棒』が語源だろうと言われています。」
あきつは,
秋津
あるいは
蜻蛉
とあて,古くは,「あきづ」と訓み,平安以降「あきつ」と訓むようになった。とんぼの語源は,
「飛ン坊」で,飛び回る昆虫,
という説と,
「飛羽,トビハの音便」で,飛ぶ羽をもつ昆虫,
で,必ずしも蜻蛉を指していない。『古語辞典』には,
とんばう(蜻蛉),
として,こういう例が引用されている。
「此の国の形とんぼうに似たり。故に此の虫の形になぞらへて,蜻蛉国と云へり。蜻蛉とは東方といふ虫也。此の虫は,あづまの方より出で来る故に,東方と云ふなり」(古今序注)
『大言海』には,「とんばう」として,
蜻蛉
蜻蜒
を当て,こう注記する。
「飛羽(とびは)の音便延。(縫物(ヌイモノ),ぬんもの。追物射(オヒモノイ),おんものい。布衣(ホイ),ほうい。牡丹(ボタン),ぼうたんと同趣)。今トンボと云ふは,却って本語に近きなり。昔蜻蜒をゑばと云ひき(これがゑんばとなり,やんまとなる。)」
極楽は,言わずもがなだが,
「阿弥陀仏の居所である浄土。西方十万億土を経たところにあり,まったく苦患(くげん)のない安楽な世界で,阿弥陀仏がつねに説法している。極楽浄土。安養浄土。西方浄土」
で,これが転じて,
「きわめて安楽な場所や境遇」
を指すようになる。それにしても,
極楽蜻蛉
と書くか,
極楽とんぼ
と書くか,
極楽トンボ
と書くか,
で,ずいぶん印象が変わる。お気楽という意味では,
極楽トンボ,
が合う気がする。類語は,
楽観的な
のんきな
楽天的な
呑気な
希望的観測
とあるが,僕は,
能天気・能転気(脳天気)
が一番近い気がする。辞書(『広辞苑』)には,
軽薄で向う見ずなさま,
生意気なさま,
物事を深く考えないさま,
とある。ずいぶん幅がある。能天気にしているのが,向う見ずに見えたり,生意気に見えたりするということか。
類語は,極楽蜻蛉と重なるが,
http://zokugo-dict.com/25no/noutenki.htm
に,こんな記述があった。
「能天気とは呑気で軽薄なことや安直なこと。またはそのような人をさす。更にそれが転じ、生意気な人を指しても使われる。能天気が普及したのは古く、江戸時代の書物には既に使われている。のうてんきには実に様々な表記があるが、一番多く使われるのは能天気。以下、脳天気、能転気、のーてんきがある。更に最近ではノー天気という表記もあるが、どれも意味は同様。脳天気という表記は昭和時代後期から使われるようになったもので、小説家の平井和正が広めたといわれている。」
そう,「ノー天気」という表記がぴたりかもしれない。能天気の類語は,極楽蜻蛉と重なるが,
お気楽
安直
が加わるところが,違うが,極楽とんぼにそれがない理由がむしろわからない。
尻馬に乗る,というのは,辞書(『広辞苑』)には,
ヒトの後ろについて無批判に物事をする,
他人の言説に付和雷同する,
とある。もっとひどいのは,
分別もなく他人の言動に同調して,軽はずみなことをする
人のあとについて,調子に乗ってそのまねをする,
と,かなり手厳しい。まあしかし,
鉄棒曳き,
や
廊下とんび,
ましてや,
虎の威を借る狐,
よりはましと思うが,しかし他人の言説にただ乗りすると,少なくとも,付けはこっちへ来る。
尻馬に乗る,
という言い回しは,『日葡辞典』にも,
「ヒトノコトバノシリウマニノル」
と出ているようだから,中世から使われていたようだ。
そもそも,尻馬
というのは,
人の乗った馬の後ろに乗ること,
また,
前を行く馬の後ろを行くこと,
とある。だから,
重騎
累騎
という言葉を,『大言海』は,「尻馬」の意味に,載せ,『平家物語』の,「土佐房夜討事」の,
「馬に乗せて(土佐房を),我身(弁慶)は尻馬に乗りて」
というくだりを引用している。要は,
同じ馬の後ろに相乗りするか,先行する馬にしたがって後ろからついていく,
という,馬の乗り(方),騎馬の進め方の話に過ぎない。そこから,
人の言動に便乗,
とか,
便乗して事を行うこと,
と言ったふうに意味が,便乗という意味に(悪い方へ)拡げられたが,
「
うしろ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E3%81%86%E3%81%97%E3%82%8D)
に書いたように,かつては,
まへ⇔しりへ,
のちには,
まへ⇔うしろ,
と対で使われるようになったが,どうも,「しり」も,
尻から抜け,尻に敷く,尻に帆掛ける,尻も溜めず,尻も結ばぬ糸,尻を割る,尻がかるい,尻が重い,尻馬,尻ごみ,退く,尻目,尻が据わる,尻が長い,尻上がり,尻足,尻押し,尻が来る,尻こそばゆい,尻から焼けてくる,尻切れトンボ,尻毛を抜く,尻声,尻ごみ,尻下がり,尻すぼみ,尻叩き,尻に火がつく,尻ぬぐい,尻抜け,尻早,尻引き,尻舞い,尻目,尻目遣い,尻もや,尻を落ち着ける,尻を食らえ,尻を拭う,尻を引く,尻を捲る,尻を持ち込む,
等々,「後(うしろ)」も,
後ろ足(逃げ足),後ろ明かり,後ろ歩み(あとじさり),後ろいぶせ(将来への不安),後馬(尻馬),後ろ押し,後ろ髪,後ろ影,後ろ軽し,後傷(向う傷の逆,逃げた証),後ろ暗い,後袈裟,後ろ言(陰口,愚痴),後詰(うしろづめ,後詰(ごづめ)),後ろ攻め,後ろ千両,後ろ盾,後ろ手,後ろ付き,後ろ違い,後ろ礫,後ろ飛び,後巻,後ろの目,後弁天,後ろ前,後ろめたい,後ろを見ず,後ろ向き,後見,後見る,後ろ矢(敵に内応して味方を射る),後安し,後ろ指,後を切る,後を見せる,
等々,どうもいい語感はない。しかし,「うしろ」と「しり」は,使い分けていて,
しりうごと,で後言,とあて,
しりえ,で後方とあて,
しりえで,で後手とあて,
しりさき,で後前とあて,
しりざま,で後方とあて,
しりざら,で後盤とあて,
しりつき,で後付とあて,
しりっぱね,で後つ跳ねとあて,
しりぶり,で後振りとあて,
等々,しかし,「うしろ」と訓ませるときは,
後ろ暗いが尻ぐらいとも,
後ろめたいが尻めたいとも,
後ろ指が尻指とも,
後を見せるが尻を見せるとも,
「尻」を当てることはない。そこから,
「尻」は,
物事の付けのように,一つ一つの振る舞い(しくじり),
を指し,「後」は,
それ自体がその人の在りよう(の落ち度)を示す振る舞いに敷衍される,
使い方が多い気がする。「尻」の字と「後」の字が与える印象から来ているのかもしれない。
という推測を勝手にしておいた。その意味では,
尻馬,
というのは,その人のありようが,あるいは目指すものが,主体的でない,というニュアンスが強くなったのではなかろうか。
「尻馬」とは、人が乗った馬の尻のこと。自分は後ろに乗るだけで、前で手綱を握る人にただ従うことからたとえていうもの,
との説明もあり,相乗りの場合も,先行するのについていく場合も,相手任せ,というニュアンスがあるせいだろう。
参考文献;
語源由来辞典
http://gogen-allguide.com/si/shiriumaninoru.html
紅葉狩りというのは,
山野に紅葉を尋ねて鑑賞すること,観楓,
と,辞書(『広辞苑』)にはある。狩りは,『古語辞典』には,
「駆りと同根」
とあるので,「追い立てる」という意味があり,本来は,
鳥獣を追い立てて獲る,
で,『大言海』では,転じて,
魚・貝をとること,
という意味となり,さらに転じて,
草木を探し求める,
という意味がある。辞書(『広辞苑』)には,
薬草・松茸・蛍・桜・紅葉などを尋ね捜し,採集,または鑑賞すること
と,載る。いまは,紅葉狩りの他は,
ぶどう狩り
だの
いちご狩り
だの,
蛍狩り
だの,
茸狩り
だの,
と言った言葉に残っているが,
狩猟採集,
と対で言っていたのには意味があるらしい。
かつては,桜にも,
桜狩り,
と言ったようで,『方丈記』に,
「桜を狩り,もみじをもとめ」
という一説がある,と『古語辞典』に例文が載る。また,藤原定家の和歌に,
桜狩り 霞の下に今日くれぬ 一夜宿かせ 春お山もり
という歌があるらしく,春の『花見』ことを『桜狩り』といっていたこともあるようだ。
今では「紅葉狩り」以外に,「眺める意味」としてはあまり使われない。桜を狩る(折る)ことは,いつの間にか風習として禁止されたのも大きいかもしれない。ただ,「狩り」というのは,
「平安時代には実際に紅葉した木の枝を手折り(狩り)、手のひらにのせて鑑賞する、という鑑賞方法。」
だったとされ,その意味では,紅葉だけは,「狩り」を可能にしたのが大きいのかもしれない。
梅にも,現在でも,梅狩りという言葉があるようだが,これは,梅の実を狩ることで,文字通り収穫である。梅(うめ)は,
中国音(呉音)を写したもので,平安時代にmumeと発音したので,古写本には「むめ」と書くものが多い,
と,『古語辞典』にはある。中国から渡来したもので,平安以降特に香をめでていた。だから,「狩らない」のではないか,と想像する。
「漢語」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-4.htm#%E6%BC%A2%E8%AA%9E)
「発見」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-4.htm#%E7%99%BA%E8%A6%8B)
でも書いたように,われわれ日本人は,ものの見方や感じ方を様々,中国由来から学んできた。まるで日本人の心性と言われるものも,たどると,中国由来だったりする。詩人の高橋睦郎氏は,
「日本人は中国から文字の読み書きを教わると同時に,花鳥風月を賞でることも学んだ。花に関してはとくに梅を愛することを学んだが,そのうち自前の花が欲しくなり桜を賞でるようになった。梅に較べて桜は花期が短いので,いきおいはかなさの感覚が養われる。」
とその機微を語っている。あるいは,陶淵明の詩,
廬を結んで人境在り,而も車馬の喧しき無し
君に問う何ぞ能く爾ると,心遠ければ地もまた自ら偏なり
菊を採る東籬の下,悠然として南山を見る
山の気は日夕に佳し,飛ぶ鳥は相い与に還る
此の中に真意有り,弁ぜんと欲して已に言を忘る
は有名だが,元来,日本には,秋を悲しむ感情はなかったという。この詩をはじめ,中国の詩人にとっては,「悲秋」の感情である。いま,われわれは秋にもの悲しさを感じるのは,彼ら中国詩人の見せた光景から端を発している。あるいは,その言葉を知ることによって,その悲しみを見る。だから,
「奥山に 紅葉(もみぢ)踏みわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ 秋は悲しき」(古今和歌集)
という感性は,輸入品なのだ,ということができる。しかし,その感性と,
紅葉狩り,
は少し違う。どうやら,秋の美しさをさまざまに歌っている日本人の本来の感性の流れの中に位置づけられる,気がする。その行き着く先は,たとえば,
「江戸時代中期ころ、富裕な商人が生まれ町民文化が華やかになるのとともに、紅葉狩りは行楽として爆発的な人気になりました。その火付け役となったのが『都名勝図会』などの名所案内本です。紅葉の名所を紹介すると、たちまちそこに人が押し寄せました。同じ版元が出した『友禅雛(ひいな)形』と呼ばれる小袖(着物)のデザイン本も女性の間で引っ張りだことなり、「竜田川の紅葉」や「紅葉の名所」をデザインした最先端の小袖を着て紅葉狩りに出掛けるのがステータスだったのです。平安時代の歴史物語『大鏡』に、藤原道長が大堰川に漢詩の舟、和歌の舟、管弦の舟を浮かべて紅葉を楽しんだという記述がありますが、そのころは紅葉の山を遠目に見ていました。それに対して、江戸時代になると紅葉の木の下に幕を張り、お弁当やお酒を持ち込んで花見同様どんちゃん騒ぎをしました。現代とまったく同じです。そこに宗教観はなく、遊興の楽しい気分だけがありました。」
というところになる。
参考文献;
http://souda-kyoto.jp/knowledge/kyoto_person/vol3.html
「半七捕物帳」で,「阿漕の平次を決め込む」
という言い回しを見て,
阿漕は,
あこぎ
と訓むが,その音感の印象から,よく時代劇などで,
「阿漕な奴」
という言い回しの記憶があり,
強欲でやり方が義理人情に欠けあくどい,
とか
無慈悲に金品をむさぼる,
といったニュアンスで受け取っていた。だから,辞書(『広辞苑』)にある,
際限なくむさぼる,また,あつかましいさま,
酷く扱うさま,
という意味の方は(なんとなく)知っていたが,
地名「阿漕の浦」の略。古今六帖「遭ふことを阿漕の島に引く網のたびかさならば人もしりなむ」の歌による,
とあって,意味として,
度重なること,
とあり,転じて,上記の意味になる,とあるのは,浅学にして知らなかった。『古語辞典』では,
古歌「伊勢の海の阿漕が浦に挽く網も度重なれば人もこそ知れ」を踏まえた言葉。『阿漕が浦』は伊勢神宮に供える神饌を捕るための禁漁地だった」
として,まず,
隠れて行うことも,度重なれば危うい意,
があり,次に,
(禁を犯して漁をする意から)限りなくむさぼること,飽くを知らないこと,
とある。だから,禁漁地であるのを隠れて漁をする,という含意から,あまり外していない使い方だ。それが,辞書(『広辞苑』)では,前提や枠を外した意に転じている,とみえる。『大言海』は,
事を度々すること
俗に,際限なく貪ること,
としていて,すでに,転じた位置にあるように見える。
で「阿漕の浦」をひくと,
津市の海浜。伊勢神宮に供する神饌の漁場で,殺生禁断の地とされ,また謡曲・浄瑠璃によって有名,
とあり,上記の歌から,
「隠しごとも度重なれば広く知れ渡る意」
とある。さらに,「阿漕の平次」も載っていて,辞書(『広辞苑』)には,
「阿漕ヶ浦で禁断を犯し,魚を得ようとして簀巻きにされたという伝説の漁夫。古浄瑠璃『あこぎの平次』,人形浄瑠璃『田村麻呂鈴鹿合戦』(『勢州阿漕浦』)などに作られる。能『阿漕』や御伽草子『阿漕の草子』が先行するが,この人名はでない。」
とある。
推測するに,禁漁区で,密漁も度重なれば,ばれる,といったニュアンスの意味だったのが,
「母の病のために禁断を破って魚をとり、簀巻 (すま) きにされたという伝説」
に作り上げられた,と見えなくもない。「阿漕(あこぎ)」の言葉の由来
https://church.ne.jp/akogi/akogi.htm
によると,
「『御伽草子』に『阿漕の鰯売り』という話があります。平安時代以後の阿漕は、伊勢神宮の御厨となって、漁獲物を神宮へ奉納していました。
・伊勢の海の阿漕か浦に引網の度かさならはあらはれにけり。
・いかにせん阿漕ケ浦のうらみても度重られはかわる契りを。
などの和歌が残されているように、伊勢神宮と阿漕の漁民の間に、いざこざが絶えなかったことを伝えています。これはある期間の漁獲を献納であったのですが、阿漕の人々には、生活上、死活問題であり、
『度かさならは あらはれにけり』で、 処罰をうけたらしいのです。
こういうことから、『阿漕平治物語』が江戸時代にできたようです。室町時代末期にも「謡曲・阿漕」があったようですが、まだ、「阿漕平治」という特定の人物をさしていません。江戸時代中期になって浄瑠璃(義大夫)の『勢州阿漕浦・鈴鹿合戦、平治住家の段』ができ、それを『芝居』に仕組み、ここに『阿漕平治』の名を登場させたのです。」
とあり,漁民にとっては大いなる迷惑で,こっそり獲っていたというわけなのだろう。しかし,
「度かさならは あらはれにけり」
と,処罰された,という謂れを見ると,やはり,「こっそり何度も重ねてばれる」という含意があった,と見ることができる。その意味で,おおっぴらに,
無慈悲な業突く張り,
というのは阿漕というよりは,
非情
とか
無慈悲
というべきものだろう。因みに,「阿漕の平次」は,
「阿漕平治は母が病気で寝込んでいるため、伊勢神宮へ奉納するための漁場と知りつつ、病によく効くという「矢柄」という魚を密漁してしまいます。これで母の病気を癒せると嬉しがってわが家に帰ったのですが、あまりの嬉しさに浜辺へ笠を忘れてきてしまいます。そこへ、役人が来てその笠を見つけ、「笠に平治と書いてあるのが証拠だぞ」、と平治を引き立てて処刑をしてしまいました。母の病を思っての孝行も水の泡。平治は簀巻きにせられて、海へ投げ込まれてしまった」
という話らしい。
それにしても,「阿漕の平次を決め込む」というのは,
「しかしいつの代にも横着者は絶えないもので、その禁断を承知しながら時々に阿漕の平次をきめる奴がある。この話もそれから起ったのです。」
というくだりなので,
欲深い平次
でも,
親孝行の息子
でもなく,
横着ものの平次,
のようである。
「大宅太郎を気取って」というフレーズが野暮天の僕には(現代それが通じる人は稀有かもしれないが)通じない。で,調べる破目に。
こんな一文がある。
「大宅太郎光国、と聞いてピンときた方はハッキリ言ってかなりの妖怪通。実はこの男、あの『がしゃどくろ』のモデルとなったとされる国芳の絵、『相馬の古内裏』に描かれている人物である。」
歌川国芳の「相馬の古内裏(ふるだいり)」の,相馬の古内裏とは,
「平安時代の武将、平将門が下総国相馬に京都の御所を模して建てた屋敷のこと。」
国芳の『相馬の古内裏(ふるだいり)』の元になったのは,江戸時代後半の山東京伝によって書かれた『善知鳥安方忠義伝(うとうやすかたちゅうぎでん)』。『善知烏安方忠義伝』のあらすじは,
承平天慶の乱(935年-941年)で朝廷に反抗して新皇を称した平将門が討ち取られた後、相馬の古内裏も焼かれて廃屋となっていた。ところが、将門の娘の滝夜叉姫(たきやしゃひめ)が父の遺志を果たそうと妖術を使って仲間を募り、古内裏に夜な夜な妖怪が出没するようになった。大宅太郎光国(おおやたろうみつくに)という勇士がこれを討伐しようとして、滝夜叉姫の繰り出す妖術に苦しめられながらもついに勝利する,
というもの。国芳の『相馬の古内裏』は,
「滝夜叉姫が呼び出した骸骨の妖怪が大宅太郎光国に襲い掛かる場面で、原作では等身大のたくさんの骸骨が現われるところを、歌川国芳は1体の巨大な骸骨として描いている。ヨーロッパの医学書の骨格図に基づいた非常に写実的な骸骨はそれまでの浮世絵には無い凄みを画面に与え本作品を国芳の傑作の一つたらしめている。がしゃどくろと直接の関係はないが、現代におけるがしゃどくろのイメージを方向付けた絵であると言える。」
とある。国芳の絵の,
「左にいるのが姫、中央が大宅太郎光圀、右は姫を守ろうとする荒井丸。」
原作では無数の骸骨に襲われるのを,国芳が巨大な骸骨を一体登場させたことになる。
ここでいわれる,「がしゃどくろ」は,
「巨大な骸骨の妖怪。妖怪通の間では有名な話だが、このがしゃどくろは近年(1970年代)になって創作された妖怪であり、古い時代にそんな妖怪はいなかった。」
と説明がある。ウィキペディアは,こう説明する。
「戦死者や野垂れ死にした者など、埋葬されなかった死者達の骸骨や怨念が集まって巨大な骸骨の姿になったとされる。夜中にガチガチという音をたててさまよい歩き、生きている人を見つけると襲いかかり、握りつぶして食べると言われる。近年になってから創作された妖怪であり、各地の民間伝承などから採取された伝統的な妖怪とは出自が異なっている。漢字で「餓者髑髏」と書く。」
確かに,『古語辞典』にも載っていない。
「1970年前後に刊行された通俗的な妖怪事典の類の中で、その著者らによって創作された妖怪で、柳田國男の著書でも言及されておらず、各地の伝承にも現われていない。」
とかで,
「『世界怪奇スリラー全集2 世界のモンスター』(秋田書店、1968年)での斎藤守弘による記述が初出とされる。後に水木しげるが『妖怪事典』や『日本妖怪大全』で取り上げ、広く知られるようになった。水木が描いたがしゃどくろの姿も、国芳の「相馬の古内裏」が基になっている。」
という。国芳は,べつにがしゃどくろとは名づけていない。水木のがしゃどくろのブロンズ像は,境港市水木しげるロードに設置されている。
前置きが長くなったが,大宅太郎は,妖怪を退治した豪傑,ということで,まあ,素戔嗚尊,桃太郎から始まって,岩見重太郎,渡辺綱,源頼光等々と並ぶ,鬼やら妖怪退治の列伝に入る。そういう豪傑を気取った,ということだろう。
因みに,源頼光と坂田金時,渡辺綱らの四天王が退治したとされるのが,大江山の酒呑童子。
「酒呑童子(しゅてんどうじ)は、丹波国の大江山、または山城国京都と丹波国の国境にある大枝(老の坂)に住んでいたと伝わる鬼の頭領、あるいは盗賊の頭目。酒が好きだったことから、手下たちからこの名で呼ばれていた」
とされる。しかし,鬼とか,妖怪は,
化外
つまり,
王化の及ばない所。国家の統治の及ばない所,
であり,みちのくといった空間的距離だけを指していない。
「酒呑童子や羅生門の鬼に代表されるように、京の都に出没する鬼は、王権を脅かす政治的な色合いの強い鬼である。天皇が勅命を下し、武将に鬼を退治させる物語―それは、王権が自らの権力を誇示し、その物語を通して王権を称掲する手段にしようとして、つくり出したものではなかったのか。」
という説もある。鬼は,心の影である。それは,亡霊,怨霊とよく似ている。「怨霊」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-4.htm#%E6%80%A8%E9%9C%8A)については書いた。
要は,大宅太郎を気取る,とは,英雄・豪傑を気取る,ということか。
参考文献;
http://www.youkaiwiki.com/entry/2013/07/14/235613
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%A9%E3%81%8F%E3%82%8D
https://nohmask21.com/oni/densetsu01.html
鬼とは,辞書(『広辞苑』)には,
「隠(おに)で,姿が見えない,意という。」
とあり,
天つ神に対して,地上などの悪神,邪神,
伝説上の山男,巨人ゃ異種族の者,
死者や霊魂,亡霊,
恐ろしい形をして人にたたりをする怪物。物の怪,
想像上の怪物,仏教の影響で,餓鬼,地獄の青鬼,赤鬼があり,美男・美女に化け,音楽・双六・詩歌などにすぐれたものとして人間界に現れる。後に,陰陽道の影響で,人身に牛の角や虎の牙をもち,裸で虎の皮や褌を締めた形をとる。怪力で,性質は荒いも
鬼のような人で,非常に勇猛な人,無慈悲な人,借金取り,或ることに,精根かたむける人,鬼ごっこなどで人をつかまえる人,
奇人の飲食物の毒見訳。鬼役。
と幅が広い。メタファで使われる部分を省いても,一筋縄ではいかない。
語源は,『古語辞典』に,
「隠の古い字音onに,母音iを添えた語。ボニ(盆),ラニ(蘭)に同じ」
とある。『大言海』は,もっと詳しい。「和名抄」に云う,として,こう書く。
「鬼(キ),於爾,或説云,穏(オスノ)字,音於爾(オニノ)訛也,鬼物隠而不欲顕形,故俗呼曰隠也,人死魂神也」トアリ,是レ支那ニテ,鬼(キ)ト云フモノノ釋ニテ,人ノ幽霊(和名抄ニ「鬼火 於邇比」トアル,是レナリ)即チ,古語ニ,みたま,又ハ,ものト云フモノナリ,然ルニ又,易経,下経,睽卦ニ,「戴鬼一車」疏「鬼魅盈車,怪異之甚也」史記,五帝紀ニ,「魑魅」註「人面,獣身,四足,好感人」論衡,訂鬼編ニ,「鬼者,老物之精者」ナドアルヨリ,恐ルベキモノノ意ニ移シタルナラム。おにハ,中古ニ出来シ語トオボシ。神代記ナドニ,鬼(オニ)ト訓ジタルハ,追記ナリ」
どうやら,我々のイメージする,鬼が島の鬼や,桃太郎の鬼は,後世のもので,そもそも「オニ」と訓んでいなかったようなのだ。『古語辞典』の意味を拾っておくと,
恐ろしい形をした怪物。オニということばが文献にあらわれるのは平安時代に入ってからで,奈良時代の万葉集では,「鬼」の字をモノと読ませている。モノは直接いうことを避けなければならない超自然的な存在であるのに対して,オニは本来形を見せないものであったが,後に異類異形の恐ろしい怪物として想像された。それには,仏教・陰陽道における獄卒鬼・邪鬼の像が強く影響していると思われる。
という意味がまず載り,ついで,
飲み物の毒見をする役
(接頭)名詞に冠して,勇猛・無慈悲・形の異様なことを表す
が載る。漢字「鬼」の字は,
大きなまるい頭をして足元の定かでない亡霊を描いた象形文字,
で,中国語では,
おぼろげなかたちをしてこの世に現れる亡霊,
つまりは,
亡霊,
を指す。『漢字源』には,
「中国では,魂がからだを離れてさまようと考え,三国・六朝以降は泰山の地に鬼の世界(冥界)があると信じられた。」
とあり,やはり,仏教の影響で,餓鬼のイメージになっていった,と見られる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC
にあるように,我々の鬼のイメージは,
「頭に角(二本角と一本角のものに大別される)と巻き毛の頭髪を具え、口に牙を有し、指に鋭い爪が生え、虎の毛皮の褌を腰に纏い、表面に突起のある金棒を持った大男である。また、肌の色によって『赤鬼』『青鬼』『緑鬼』などと呼称される。このように、鬼が牛の角と体、虎の牙と爪を持ち、虎の毛皮を身に付けているには、丑の方と寅の方の間の方角(艮:うしとら)を鬼門と呼ぶことによるもので、平安時代に確立したものである。」
当然,現在の鬼の姿は仏教の羅刹が混入したものである,とされる。ちなみに,羅刹(天)とは,
「(仏教の天部の一つ十二天に属する西南の護法善神)鬼神の総称であり、羅刹鬼(らせつき)・速疾鬼(そくしつき)・可畏(かい)とも訳される。また羅刹天は別名涅哩底王(Nirrti-rajaの音写、ラージャは王で、ねいりちおう、にりちおう)ともいわれる。破壊と滅亡を司る神。また、地獄の獄卒(地獄卒)のことを指すときもある。四天王の一である多聞天(毘沙門天)に夜叉と共に仕える。」
とある。このイメージが強い。しかし,そもそも鬼というのは,
「日本書紀にはまつろわぬ『邪しき神』を『邪しき鬼(もの)』としており得体の知れぬ『カミ』や『モノ』が鬼として観念されている。」
というところに典型的に見られ,基本,
化外の民,
つまり,
「鬼とは安定したこちらの世界を侵犯する異界の存在だという。鬼のイメージが多様なのは、社会やその時代によって異界のイメージが多様であるからで、まつろわぬ反逆者であったり法を犯す反逆者であり、山に住む異界の住人であれば鍛冶屋のような職能者も鬼と呼ばれ、異界を幻想とたとえれば人の怨霊、地獄の羅刹、夜叉、山の妖怪など際限なく鬼のイメージは広がるとしている」
ということになる。今日でも,市民社会を侵す部外者,権力に逆らうものは,
鬼
の代わりに,異名を名づけるはずである。酒呑童子に代表されるような鬼や悪鬼羅刹は,
「戦乱や災害、飢饉などの社会不安の中で頻出する人の死や行方不明を、異界がこの世に現出する現象として解釈したものであり、人の体が消えていくことのリアルな実演であり、この世に現れた鬼が演じてしまうものと推測している。」
この世の外は,異界であり,そこの住民として鬼を想定した。考えれば,鬼が島も,退治する側の視点からしか見られていない。鬼は退治すべきものとするのは,
こちら側=善
を前提にする。そう言えば,
鬼畜米英,
はその延長線上にある。自分の理解できぬもの,自分にまつろわぬもの,を鬼と呼ぶ。なんだか,反日という言葉にも,そういう自分たちの世界以外は,悪とする古来以来の自閉した世界観を反映しているように見えて,滑稽である。
それにしても,
http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%AC%BC
にある,鬼の入る言葉の多いこと。
参考文献;
http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%AC%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC
女形は,
お山
とも書き(『古語辞典』は,「お山」の字を当てている。),
おやま,
と訓むものだと思っていた。実際辞書(『広辞苑』)を引くと,
「近世,仮名書きでは『をやま』とも」
とあって,
女形人形,またはその人形遣い手
歌舞伎で,女の役をする男役者,おんな形,またはその略
(上方語)色茶屋の娼妓,後に遊女の総称。
美女
等々の意味を載せる。『語源由来辞典』には,
「人形浄瑠璃の,美人の人形名,ミノノオヤマ」に由来する,
とある。要は,僕の常識では,
「歌舞伎において若い女性の役を演じる役者、職掌、またその演技の様式そのものを指す」
と思ってきた。
しかし,これはなかなか奥が深い。小谷野敦氏は,遊女の由来から,女形の呼び方について,
「『遊女』というのは平安朝以来の名称で,むしろ中世の,江口・神崎で,水辺に棲んで舟に乗り,淀川を下ってくる男たちに声をかけるのが遊女,地上を旅して春を鬻ぐのを傀儡女(くぐつめ),男装したものを白拍子などといった。中世には前の二つはあわせて遊女とされ,遊女の宿といったものが宿駅に出来たりしたし,京の街中には,地獄などと呼ばれる遊女宿があり,遊君(ゆうくん),辻君(つじきみ),厨子君(ずしきみ)といった娼婦が現れた。…近世以来,上方では娼婦を『おやま』と呼んだ。歌舞伎の女形が『おやま』と言われるのは,人形浄瑠璃で,遊女の人形を『おやま人形』と訓んだことから来ている。だから,女形の人は,『おやま』と言われるのを嫌い,『おんながた』としてもらうことが多い。」
とある。女形を,
おんながた,
と呼ばせる謂れはここにあるらしい。辞書(『広辞苑』)は,「おんながた」を別項として立て,
「演劇で,女役に扮するおとこの役者,またはその訳柄,おやま,おんなやく」
とある。「男が女を演ずる」という意味が,「おんながた」とすると,際立つということもあるのかもしれない。
『大言海』は,「をやま」について
「承応の頃,江戸の人形遣,小山次郎三郎,巧みに処女の姿をつかひて,小山人形の名起こりしより出づ」
と,異説を書く。で,
あやつり人形の女形,
歌舞伎の女形(おんながた)の称,その大立者(おおだてもの)なるを立をやま,少女なるを,わかをやまと云ふ,
遊女の異名,
と,「おんながた」と「をやま」を区別している。女形(おんながた)と呼ぶときの,「がた」は,
接尾語で,ガタと濁る,
と,『古語辞典』にあり,
~役,
という意味になる。囃子方などと同じとある。だから,
「ガタは『方』つまり、能におけるシテ方、ワキ方などと同様、職掌、職責、職分の意を持つものであるから、原義からすれば『女方』との表記がふさわしい。歌舞伎では通常『おんながた』と読み、立女形(たておやま)、若女形(わかおやま)のような特殊な連語の場合にのみ『おやま』とする。『おやま』は一説には女郎、花魁の古名であるともされ、歌舞伎女形の最高の役は花魁であることから、これが転用されたとも考えられる。」
という説明になる。
さらに,
「通説によれば、1629年(寛永6年)に江戸幕府が歌舞伎などに女性を使うことを禁じたために、その代わりとして歌舞伎の世界に登場したとされ、江戸では糸縷権三郎、大坂では村山左近がその祖であったと伝えられている。江戸時代の女方は芸道修業のため、常に女装の姿で女性のような日常生活を送るものとされていた。
なお、中国の京劇においても女形(『旦』と言う)が存在したが、現在ではその役を女優が行っている。」
と,なぜ,男性が女性役をするかの謂れが載る。因みに,「旦」の字は,
「日+一印(地平線)」
で,太陽が地上に現れることを示す。目だったものが外に現れ出ること。意味は,
あした,日の出,
を指し,
外に現れ出ること,
とともに,
中国の劇で,女に扮する役者,
で,「花旦」で,
若い美人を演じる女形,
とある。外に現れ出る,とは,
秘すれば花,
を連想するのは突飛だろうか。
「ただ珍しさが花ぞと皆人知るならば、さては珍しきことあるべしと思ひ設けたらん見物衆の前にては、たとひ珍しきことをするとも、見手の心に珍しき感はあるべからず。見る人のため花ぞとも知らでこそ、為手の花にはなるべけれ。されば見る人は、ただ思ひのほかに面白き上手とばかり見て、これは花ぞとも知らぬが、為手の花なり。さるほどに人の心に思ひも寄らぬ感を催す手だて、これ花なり。」
参考文献;
小谷野敦『日本恋愛思想史 - 記紀万葉から現代まで』 (中公新書)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%BD%A2
心中は,
しんちゅう,
と訓むと,
こころのうち,胸中,内心,
という意味になるが,
しんじゅう,
と訓むと,いまだと,情死,つまり,
相愛の男女が,一緒に自殺すること,
更には転じて,親子心中,無理心中のように,
二人以上のものが死を遂げること,
と,受け取ることが多い。しかし,辞書(『広辞苑』)をみると,心中(しんじゅう)には,その他に,
人に対して義理を立てること,
相愛の男女がその真実を相手に示す証拠,放爪,入墨,断髪,切指等々。
ひゆ的に,打ちこんでいる仕事や組織などと運命を共にすること,
といった意味があり,「しんじゅう」が「しんちゅう」と重なってくる。語源的には,
中国語の,「心中」は,
心の中の誠実,
の意味とあり,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E4%B8%AD
には,
「『心中』は本来『しんちゅう』と読み、『まことの心意、まごころ』を意味する言葉だが、それが転じて『他人に対して義理立てをする』意味から、『心中立』(しんじゅうだて)とされ、特に男女が愛情を守り通すこと、男女の相愛をいうようになった。また、相愛の男女がその愛の変わらぬ証として、髪を切ったり、切指や爪を抜いたり、誓紙を交わす等、の行為もいうようになる。そして、究極の形として相愛の男女の相対死(あいたいじに)を指すようになり、それが現代にいたり、家族や友人までの範囲をも指すようになった。」
とあり,過不足なく,言葉の謂れが書かれている。
小谷野敦『日本恋愛思想史』には,
「近松門左衛門が描く娼婦は,大阪のしかも下層の女郎である。『曽根崎心中』『冥途の飛脚』などでは,その女郎が,恋人である男の境遇に同情して,心中し,ともに逃亡するのだが,これらによって心中が流行し,幕府では心中を『相対死(あいたいじに)』と呼び,これを創作に組むことを禁じた。『心中』というのは,がんらい『心中立て』つまり恋人に愛を誓うという意味だった。しかし実際の心中というのは,男も女も金につまってするもので,近松が描いたような美しいものではなかった。…明治期のものながら,落語に描かれた『品川心中』は,品川の岡場所女郎の実態をリアリズムで描いている。」
とある。『品川心中』のあらすじは,
http://senjiyose.cocolog-nifty.com/fullface/2005/06/post_3922.html
にあるとおりだが,リアリズムはともかく,欲得づくであるところは,漫画チックに描かれてはいる。
因みに,「心中」には,
心中立て,
心中尽くし,
といった言葉があり,『大言海』には,「心中(しんぢゅう)」を,
互いに心中立てする意,
と書き,「心中立て」については,
心中を立てとほす意,忠義立て,男だて,同趣,
とある。つまり,ほんらい,「心中」は,「しんじゅう」と訓もうと,「しんちゅう」と訓もうと,
心中立て,
つまり,こころの誠実,要は真心を通す,という意味なのであり,その結果としての,
相愛の男女がその真実を相手に示す証拠立て,
や
情死
に過ぎない,という意味となる。辞書(『広辞苑』)に,「心中立て」を,
人との約束を守りとおすこと,
とあり,それに注記して,
特に,相愛の男女が誓いを守り通すこと,またその証拠を示すこと,
とあり,「心中尽(しんじゅうずく)」も,
相手への信義・愛情をつらぬくこと,
とある。愛情は,信義の一つの象徴とみなせば,「心中」の意味がよく見える。
『古語辞典』には,「心中(しんぢう)」は,
心,考え,
が最初に意味として載る。この辺りの機微をよくつかんでいる。因みに,「心」という字は,心臓を描いた象形文字。それは,そのまま,
こころ,精神,
を意味し,「中」という字は,
旗竿を枠の真ん中に,貫き通したもので,真ん中の意,
または,
真ん中を突き通す意,
をもつ。まさに,心の真ん中を貫く,とは,佳い字を当てている。
参考文献;
小谷野敦『日本恋愛思想史 - 記紀万葉から現代まで』 (中公新書)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E4%B8%AD
落語の,『片棒』を聴いていて,
http://ginjo.fc2web.com/81katabou/katabou.htm
「けち」の言い回しで,
しみったれ,あかにしや,六日知らず,
等々と出た。で,六日知らず,を調べると,
「朔日、二日、・・、五日と指を折るのは良いが、六日から指を開いていくのはせっかく得たものを手放すようでいやだ」
という意味,と出ている。
握りっぱなし,
の洒落,とある。
「指を折って日数を勘定していって、六日からは指を開かねばならないが、それを惜しむほどのケチ。『だすことならば、袖から手をだすのもいやだ、口から舌をだすのもいやだという、これを俗に六日知らずと申します。』」
とか,
「日を勘定するのに一日二日三日四日五日と指を折る。六日てぇとこれを開けなくちゃァなりませんで、一旦握ったものはもう絶対離さないと言うので、吝嗇屋の事を『六日知らず』と言う悪口がございます。」
とか,
「1日.2日.・・、と指折り数えて「5日」までは指を折り曲げ握っていくが、『6日』からは指を開いていきます。握ったものは離さないと言うので「6日」から上は数えない。また数えられなかったので、知らないと言うケチです。」
等々と,噺の枕に使われる。落語には,『片棒』以外にも,『位牌屋』『味噌蔵』『吝嗇(しわい)屋』等々がある。
その他に,「あかにしや」というのは,落語の『片棒』『位牌屋』『味噌蔵』『死ぬなら今』等々に登場する,
主人公の商人・赤螺屋(あかにしや)ケチ兵衛,
だが,この,
「赤螺屋」は吝嗇家(ケチな人)の異称,
で,これは,
巻き貝のアカニシが、一度フタを閉じたらなかなか開かない,
という形容からきたらしい。赤螺(あかにし)を調べると,辞書(『広辞苑』)には,
アッキガイ科の巻貝。殻高は約15cm、殻口の内面が赤いのでこの名がある。表面は淡褐色で、3列の大小の突起列がある。日本各地の暖かい浅海の砂泥底にすむ。卵嚢を「なぎなたほおずき」という。肉は食用。紅螺。辛螺。
という貝の説明の他に,
(財布の口を開かないことを,赤螺が殻を閉じて開かないのにたとえる)ケチな人をあざけって言う語,
とあり,
「サザエに似た巻き貝で、サザエの貝殻にこの貝を入れて食卓に出すと解らなかったと言われます。”あかにし”は焼くとツボの蓋を堅く閉じて取り出す事が出来なかった。そこで何も出さない事、ケチの代名詞として”あかにし”と言った。それに名前がケチ兵衛と付いていれば、 もう、これ以上のケチは無かった。」
とある。赤螺屋ケチ兵衛は,むろんそこからとられている。
それにしても,どうして「けち」が悪口の代表になるかというと,語源からみえてくる。「けち」は,
吝
の字を当てるが,
囲碁用語の「結」「闕」(けち),
で,
「終盤で,一目,一目半とつめる」
から来ている。「けちる」という動詞も,ここから来ている。「結(けち)」は,呉音で,
「囲碁で,終局に近づき,駄目を詰めて寄せること,またその目」
とあり,「闕」(けち)とも当てる。そこから,賭け弓で勝負を決めること,に意味が広がっている。囲碁をやらぬものにはわかりにくいが,『大言海』には,
「碁を打ち終ふるを,結局と云ふ,結なり,弓に云ふも,勝負の最後の決定の意なるべし」
として,こう説明する。
「囲碁の終はりがたに,隅々などの,決まらぬ目を詰め寄すること。これをケチをさすと云ふ。今,よせと云ふ,是なり。ケチを先手にさすを,結鼻(けちばな)をとると云ふ。先手にさせば,一目づつの得となるなり」
とし,さらに,
「今,駄目をさすをケチさすと云ふは,闕の音にて,闕(欠)目すなはち,駄目なり」
とある。辞書(『広辞苑』)で,「けち」をひくと,「けちがつく」の「けち」と並んで意味が載るが,この「けち」は,「怪事」とあてる。この「けち」は,また別の由来なので,改めて,考える。
それにしても,一目,半目の差で勝負が決まるとき,一つ一つを慎重に詰めざるを得ない。そこから「吝嗇」の意が出て来ているとすれば,それは,無駄にしない,というか,慎重という意味で,悪いことには思えない。「一円をなおざりにするもの一円に泣く」である。
吝嗇の「吝」の字は,
「文+口」
で,「文」は,
「土器につけた縄文の模様のひとこまを描いたもので,こまごまと飾り立てた模様のこと」
で,
「口先を飾って言い訳をし,金品を手ばなさない意」
を示す。「嗇」の字は,
「上部は『麥(麦)』の略体。下部は囲んだ倉の形で,畑の収穫物を倉庫にしまい込むこと」
という意味になり,抱え込んで離さない,といった意味になる。「けち」に「吝しむ」の「吝」を当てるのは,なかなか含意がある。「吝」には,惜しむ以外に,くよくよして思い切りが悪い,という出し惜しみのニュアンスがある。
しみったれというのも,
「しみ+たれ」
で,
シミが垂れたように,少しずつ垂れる,
ということだろうか,みすぼらしいという意味も,意気地がない,という意味もあるようだが,一般には,
けち,
と同義と取られる。
しわ(吝)いは,
「皺+い」で,金を出すのに顔に皺を寄せて渋い顔をする
あるいは,
「締まる」「渋る」の形容詞,渋るの変化,
の二説がある。やはり出し惜しみ,である。
僕は,小心のせいか,けちが,悪いことには思えない。そのせいか,けちの反対語は,
太っ腹,
気前がいい,
ではなく,
浪費,
らしいのである。けちとは,
しまり屋
始末屋
節約家
なのである。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%87%E6%A3%92
http://ginjo.fc2web.com/81katabou/katabou.htm
因業おやじ,
という罵り言葉かある。因業は,語感からも,仏教用語から来ているらしいとわかるが,辞書(『広辞苑』)には,
因と業,または果報をまねく因となる業,
頑固で無常なこと,むごいこと,
と意味が載る。これだと分かりにくいが,別の辞書をみると,
何らかの結果を生む原因になる行為。また、因と業。
《前世の悪業が原因で招いた性格や運命の意から》
・頑固で思いやりのないこと。また、そのさま。
・宿命的に不幸なこと。また、そのさま。
と載る。善悪いずれにしても, 因があって業がある,
前世の悪業が原因となって招いた,
という意味で,その性格やいまのありようがある,ということらしい。『大言海』は,
因と業と
頑なにして苛(から)きこと,心ねじけて情けのなきこと(悪業によりて然りとする意)
とあり,因縁を見よ,とある。因縁(いんねん・いんえん)の説明がふるっている。
「譬えば,穀を地に植うれば,稲を生ず,穀は因なり,地は縁なり,稲は果なり,然して,これをおこなふことを業と云ふ。因りて,因縁,因果,因業など,人事の成立(なりゆき)は,皆因(ちなみ)あり,縁(よ)る処ありて,果(はて)に至ること,予め定まれりとす。」
つまり,
何らかの結果を生む原因となる行為,
があって今がある,ということらしい。
因果はめぐる風車
というか
因果応報
ということなのだろう。どうも,この考えは,我々の奥底に根深くあるらしい。過去の付け,というのもそういうことだ。辞書(『広辞苑』)には,
物事の生ずる原因,因は直截的原因,縁は間接的条件,
とでる。すぐに原因・結果を想定する傾向が人間にはあるので,生についても,そういうことを想定する。そういう発想と思えば,世代を超えていくスケールの因果論とも言える。
因縁,
因果,
因業,
は,セットということになる。
穀は因なり,地は縁なり,稲は果なり,
がこの間の関係を言い尽くしている。因みに,「業」は,梵語karman,羯磨(かつま)のこと,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD
には,
「『行為』を意味する。業そのものは、善悪に応じて果報を生じ、死によっても失われず、輪廻転生に伴って、アートマンに代々伝えられると考えられた。アートマンを認めない無我の立場をとる思想では、心の流れ(心相続)に付随するものとされた。中国、日本の思想にも影響を与える。『ウパニシャッド』にもその思想は現れ、のちに一種の運命論となった。今日、一般的にこの語を使う場合は、(因縁・因果による)行為で生じる罪悪を意味したり(例えば『業が深い』)、不合理だと思ってもやってしまう宿命的な行為という意味で使ったりすることが多い。」
とある。辞書(『広辞苑』)は,「行為」を,
身(身体)・口(言語)・意(心)の三つの行為(三業)
とし,その行為が,未来の苦楽の結果を導き出す,という。前行が,後のおのれにつけが回る,と言うことだ。だから,いま,因業おやじと呼ばれている輩は,過去(あるいは前世)の悪業の報いを受けている(あるいはそのお返しをしている)ということになる。
どこか,そこには,因果を見ることで納得するという悲哀が感じられなくもない。
「因」の字は,
「□(ふとん)+∧印(乗せたもの),または大(ひと)」
で,布団を下に敷いて,その上に大の字に乗ることを示す,という。で,
下地を踏まえて,その上に乗ること,
を意味する。だから,何かを踏まえる,とか,重ねる,という意味になる。「業」の字は,
ぎざきざの止め木のついた台を描いたもの
で,でこぼこがあってつかえる意を含み,
すらりとはいかない仕事の意,
という。本来,ぎざぎざの歯止めのついた台の意から,それをメタファにして,
ぎざぎざとつかえて苦労する仕事,
という意味に広がっている。「縁」の字は,
彖(たん)は,豕(し ぶた)の字の上に特に頭を描いた象形文字で,腹の垂れ下がった豚,の意。豚と同系。「縁」は,糸をつけて,布の端に垂れ下がったふち,
の意。なんとなく,それをメタファに,ふち,てづる,つながり,といった意味に広がっていくのがわかる気がする。「果」の字は,
木の上に丸い実がなった様を描いた象形文字,
で,文字通り,果実,であり,物事の結果である。
梵語に当て字をしたにしても,その語の含意をよく込めている。その意味で言うと,因業の類語,
意地張り
頑冥
あこぎ
無慈悲
非道
等々という言葉は,いま・ここしか指していない。しかし,
因業,
と名づけられると,それはもっと謂れと由来の深い,悪業であるというニュアンスが出る。
人気は,
ニンキ
とも
ジンキ
とも
ヒトケ
とも
訓むが,それによって意味が変わる。
ニンキ,
と訓むのが,今日の一般的な読みかただが,辞書(『広辞苑』)では,
人間の意気
世間一般の気うけ
となり,
その地方の気風
という意味になると,
ジンキ,
と訓みが変わる。更に,
ジンキ,
と訓むと,
人いきれ,また,その場の人々の気配,
という意味が加わり,併せて,
世間の評判,
という,「にんき」と訓むのと同じ意味が加わる。どうも,「ジンキ」という訓み方が先だったのではないか,という気がする。『大言海』をみると,「ニンキ」の項には,「ジンキ(人気)に同じ」とあり,「ジンキ」には,
世上の人の思い入れ,人々の気受け,群集心理,人心,ニンキ,
とある。『古語辞典』には,
ジンキ
として,ただひとつ,
体熱,
の意味しかなく,「多い群集には人気がでるぞ」という用例が載る。
ヒトケ,
と訓むと,
人のいる気配,人の気(け),
という意味になる。『大言海』には,「ヒトゲ」で載る。
人の居る気配,人の居る様子,
人らしくあること,人がましきこと,
とある。前者はともかく,いまは,後者の意味で使うことはあまりない。『古語辞典』には,やはり「ヒトゲ」で載る。
人の気配,人の存在を感じさせるもの,
世間並みの人らしい雰囲気,
(多く「~なし」の形で使われる)まともな人らしく見えるさま,
とある。「まともな人らしく見えるさま」ではないときに,「人気(ヒトゲ)なし」と使ったもののようで,逆に言うと,人らしいという使い方をしたのではないという推測がつく。だから,「人がましい」の意味は,薄らいだのではあるまいか。
語源ははっきりしないが,漢字を見ると,「人」は,
人のたった姿を描いた象形文字,
で,「もっと身近な同族や隣人,仲間を意味した」とある。「気(氣)」の字の,
「气」は,息が屈曲しながら出てくるさまで,「气+米」は,米をふかすときに出る蒸気,
を意味する。で,
息であったり,
ガス状のものであったり,
人の心身の活力であったり,
人の感情や衝動のもとであったり,
天候や四時の変化を起こすもとになるものであったり,
偉人のいる所に立ち昇る雲気であったり,
理気二元論のいう生きている現象であったり,
を意味する。で,
「形はないが,何となく感じられる勢いや動き」
といった含意になる。ある意味,エネルギーというと言いすぎか。そう考えると,
人気(にんき)
も
人気(じんき)
も,
人のエネルギーの動きの様やありようの変化を表す。となれば,どう訓んでも,すべてそこに,眼に見えない人の気のカタチがあることでは一貫している。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
とぼけなのかぼけなのか,
といった川柳があったような気がするが,「とぼける」は,
恍ける,
惚ける,
と当てる。意味は,辞書(『広辞苑』)には,
老いて頭の働きが鈍くなる,ぼける,
聞かれたことに対して,わざと知らないふりをする。しらばくれる
ぼんやりする,
わざと滑稽な言動をする,
といった意味が載る。『古語辞典』には,
老いぼれる,耄碌する,ぼける,
しらばっくれる,知らぬふりをする,
の意味が載る。語源的には,
「と(接頭語)+ぼける」
で,わざと知らないふりをする,という意味である,とある。『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/to/tobokeru.html
も,
「とぼけるは『ぼけ』は、『ばか(馬鹿)』など痴愚を表す語と同源で、それに接頭語の『と』が ついたのが『とぼける』といわれる。
しかし、頭の働きが鈍くなることを『ぼける』と言い、 漫才などのボケのようにわざとすることもあるから、『ぼける』に接頭語『と』がついた言葉
と考える方が自然であろう。 」
とある。しかし「と」という接頭語に当たる説明は,どの辞書にもない。
『大言海』は,
「言惚(ことほく)るの略訛か」
として,
恍(ほ)く,しれじれしくなる,ぼんやりする,
恍けたる風をして戯れる,おどける,どうける,
知らぬさまを装う,しらばっくれる,
という意味を載せる。どうやら,
ぼける,
という意味が,本来の耄碌から,メタファとしてのそれに,つまり,
ぼけたふりをするに,
なり,ボケとツッコミの「ボケ」意味にと,拡大していったように見える。どっちかというと,いまは,
しらばっくれる,
という意味が強いが,どう見ても,本来は,
とぼける,
と
ぼける,
は,ほぼ同義だったように見受けられる。「と」の有無で,ニュアンスが変わるが,例えば,
~「と」ぼける,
あるいは,
~と,ぼける,
と,してみると,何がしかのわけがあって,「ぼける」というふうに変る。「と」は,副詞なら,
とにもかくにも,
ともかくも,
ふと,
といったようになるが,それと同根らしく,助詞でも,「とにもかくにも」を,
「話し手と相手が共通に知っていることを意識的に取りたてて指示して,『かく』という既知の自分の領域にあるものと対比させる意味を持つ」
と説明され,「見ると」とか「聞くと」といった使い方の場合,それを意識的に指示しているニュアンスがある。あるいは,
~と言って
~と思って,
等々だと,理由や動機を表す。どうやら,「と」と使うことで,その思ったり,感じたりすることが,
「常に意識的・意図的であり,時には作為的」
を示すらしいのである。だから,億説だが,
~「と」ぼける,
~と,ぼける,
は,
~とぼけてみた,
という感じなのではないか,と勝手に想像する。「と」のもつニュアンスが,ただのボケから,意識的,作為的ボケへと,転じていったのではないか,と思ってみる。そう考えると,意味のシフトが見える気がする。妄説だが。
「惚」の字は,
「忽(こつ)は『心+勿(よく見えない)』で,ぼんやりすること。のちに『たちまち』の意の副詞になったため,惚は忽の原義を表すようになった。」
とあり,気を取られて,ぼんやりすること,という意味である。
「恍」の字は,
「『心+光』で,荒(むなしい)の意を含む。何かに気を取られて,心の中がむなしくなること」
とあり,うっとりする,とか,ぼんやりしてよくみえない,という意味になる。当てた漢字からも,
呆ける,
という意味はあるが,とぼけるのもつ,
意識的な,
しらばっくれる,
という意味はない。現代の「とぼける」の同義語も,
シラを切る,
しらっぱくれる,
知らんぷりを決め込む,
という意味がほとんどである。やはり,「と」の有無で,意味の変化が生じたようだ。
~とぼける,
と見なしておくのが,まあわかりやすいのではないか。因みに,呆の字は,
「子(こども)+∪印(おむつ)」
で,「幼児をおむつに包んだ姿。何も知らない幼児と同様にぼんやりしている者の意に転じる。また褓(おむつ)の源氏でもある」とある。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
あながちは,
強ち
とあてる。辞書には,
あまり強引であるさま,
身勝手であるさま,
しいて,必要以上に,異常なまでに,
(下に打消しの語を伴って)断定しきれない気持ちを表す。必ずしも。一概に,
強い否定の意を表す。決して。
とある。語源は,
「アナ(オノレの変化)+勝ち」
で,
自分勝手にしたいままをやっていく,
という意味で,古語は,「強引で身勝手」の意味。しかし,現代語では,
「古語の意味は完全に消えて,下に打消しを伴って,必ずしも,の意でもちいます」
とある。現代の辞書にある名詞的な使い方は,辞書にのみ残っている,ということだろう。
『古語辞典』の注記には,語源辞典と同じ説を取り,
「アナは自己,カチは勝ちか,自分の内部的な衝動を止め得ず,やむにやまれないさま,相手の迷惑や他人の批評などに,かまうゆとりを持ちないさまをいうのが原義。自分勝手の意から,むやみに程度をはずれての意。→せめて,しいて」
と説明する。
『大言海』は,
「アナガチは,嗟勝(あながち)の義。又,孔穿(あなうがち)などと云ふ説あれど,共にいかがか。尚考ふべし」
としている。そして,意味は,
強いて,おして,無理に,
しか載せていない。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/a/anagachi.html
は,「あな(己)+勝ち」をとる。「あな」は,『古語辞典』には,
「オノ(己)の母音交換形。アナガチのアナに同じ」
とある。ただ,別の『古語辞典』には出ていない。
身勝手→衝動を止め得ぬさま→やむにやまれぬさま→一途,ひたむき→必ずしも,→決して,
『古語辞典』の意味を,ただ並べて見ると,自儘な振る舞いが,やむにやられぬ,一途になり,それが否定的な意味合いから,変化していくのが見える気がする。億説に過ぎないが,勝手気ままが,自由に見え,ひたむきにも見える。傍からは,それが必ずしも悪くない,と変じていく,と勝手に流れを作ってみると,それはそれで意味ありげに見えてくる。
ところで,「強(彊)」の字の説明を見ると,
「彊は,がっちりとかたく丈夫な弓。〇印は丸い虫の姿。強は,『〇印の下に虫+音符彊の略字体』」
と載る。もともとは,
「がっしりした体をかぶった甲虫のこと。強は彊に通じて,かたくじょぶな意に用いる」
とある。そのため,強い,という意味だけでなく,彊にあてて,
しいて,
とか
無理やり人にやらせる
といった意味を持つ。
だから,
強いて
とか
強いる
という用い方をする。「強いる」は,語源は,
「古語シ+フ」
で,「サ変の連用形のシ+フ(継続・反復)」が語源。従って,
「し続ける」
という意味で,
「自分でも,他人にとっても,し続けるのは嫌なことです。そういう意味から,強いる,強制する意へと転じたとするのが自然」
とする。し続けることが,「強制」に転じる意味づけは,少し無理がないだろうか。本来和語には,
強制する,
というニュアンスはない。それに,「強」の字を当てたことで,
無理やりやらせる,
という「強」の字のもつ意味が意味をシフトさせていったとみる方が,普通ではなかろうか。
参考文献;
大野晋・佐竹 昭広・ 前田金五郎編『古語辞典 補訂版』(岩波書店)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
貧相は,
いかにも貧乏そうな人相,(反対が,福相),
貧弱でみすぼらしく見えること。またそのさま,
という意味だから,貧しい相という漢字そのものということになる。
『大言海』には,
貧しき状の容貌,
又貧乏の運命を具へたる人相,
窮相,
とある。で,『沙石集』から,
「さて,彼佛,御うなじの貧相に御坐すを,上人,仏師を呼びて直さしめんとする」
の例示が出ていて,案の定,仏相を指しているらしいことをうかがわせる。しかし,最近の用例を見ると,
貧相で空疎な内容,
貧相な朝食,
等々,容貌よりは,
貧弱とか,
みすぼらしい,
という(貧しさよりメタファとしての貧弱さに)意味にシフトして使われているような気がする。豪華とか華麗とか横溢といったニュアンスの反対語として使われている。だから,たとえば,類語を見ると,
風采の上がらない,
野暮ったい,
不恰好な,
貧弱な,
体格の良くない,
華奢な,
侘しい,
哀れな
惨めな,
等々を挙げる。「貧相な」というと,こういう含意で言われている,ということになる。そのせいか,「貧相に見える人の5つの理由」というのが
http://otonaninareru.net/poor/
に,載っている。それは,
家族や親族に文句ばかり言う
ニュースや政治について不満を言う
身なりが貧相
お金の使い方が偏っている
テレビで見た事ばかりを話す
だそうである。申し訳ないが,これを挙げている人自体が,貧相そのもののモデルである。その人に見えている世界そのものが痩せて,みすぼらしい,ということを無意識のうちに露呈している。こういうことを貧相と言っているレベルこそが貧相なのではないか。むしろ,
他人を貧相と評する,
こと自体が貧相そのものといっていい。因みに,福相というのは,
裕福な運命を具えた人相,福々しい人相,
とある。『大言海』も,
福々したる状の容貌,
有福なるべき運命を具へたる人相,
とある。肝心なのは,「貧相」が「貧乏」とイコールではないように,「福相」も「裕福」とイコールではない。そういう相に過ぎない。人相は,
人の顔つきに,その人の性格・性情・運命などが現れていること,
という意味で,人相占いは,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E7%9B%B8%E5%8D%A0%E3%81%84
にあるように,「顔相、骨相、体相など、人体のつくりから性格や生涯の運勢を割り出す占い」とされる。個人的には,骨相学
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AA%A8%E7%9B%B8%E5%AD%A6
や,クレッチマーの
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%BC
体系説,つまり体系で性格がわかるとした説等々,いずれもどこかいかがわしい,と思っている。ある面,人間の内面を安く見積もりすぎていて,その説自体を,そういう説を。主張する人が貧相に見えてしまう。
「相」という字は,
「木+目」
の会意文字で,木を対象において目で見ること,AとBが向き合う関係を表す。とすると,相手を貧と見るのは,自身の貧を投影し,自分の貧が相手に見えているにすぎない。
「貧」の字は,
「分(分散)+貝(金銭財貨)」
で,「分」は,「八印(わける)+刀」で,二つに分けること,「貧」は,家から金が分散する,という状態を示す。「福」の字は,
「畐は,とくりに酒を豊かに満たしたさまを描いた象形文字。福は,…それに示(祭壇)を加えた字で,神の恵みが豊かなこと」
を表す。こう見ると,貧しさは,財貨の散逸ではなく,神の恵みへの感謝を示す,心の充実の欠如を示している,とも取れる。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
ひっぱりだこは,
引っ張り凧
とか,
引っ張り蛸
と当てられる。意味は,辞書(『広辞苑』)には,
多くの人から所望されること,
「はりつけ」の異称,
とある。もう,いまは,
「人気があって、多くの人から争って求められること。また、その人やその物」
という意味で使われることが多いだろう。
語源は,
「蛸の乾物を作るのに,その足を引っ張り拡げる」
から来ていて,
「あちこちの多くの人から,争って求められること」
となる。古くからの言葉のようで,『古語辞典』にも,
「蛸の足を竹串で四方に引き拡げて干すこと。またその干蛸」
とある。
はりつけの刑のこと
を指したのは,
「蛸の干物を作るときに、8本の足を広げて干していた姿が似ていることから、はりつけの刑の様子やその刑をまっている罪人のこと」
を指したらしい。
『語源由来辞典』には,
http://gogen-allguide.com/hi/hipparidako.html
「タコの干物を作る際,足を四方八方に広げて干された形に由来する。昔はその形から,はりつけの刑やその罪人を表す言葉として『ひっぱりだこ』は使われていたが,いつしかいまの意味に変化していった。本来は『引っ張り蛸』が正しく,『引っ張り凧』は誤りであるが,特に漢字で表記する言葉でなかったことや,凧の語源も蛸に通じることから,正しい表記として扱われるようになったと考えられる。」
とあるが,「凧」の字を当てたせいか,
「一説には、空に上がった凧(たこ)を大勢で引き合うこと」
ともいわれているようだが,やはり蛸を干している姿から来たというのが順当のようだ。
「蛸」の語源は,
「タ(手)+コ(接尾語)」
とされる。「蛸」の字は,
「虫+肖(細い,小さい)」
で,「卵からかえったばかりの小さく細い虫の子」だから,「くもやかまきりのたまごを表す熟語につかう」ので,「たこ」の意で使うのは,国字。「章魚」とも書く。「たこ」に,「蛸」の字を当てたのは,「たこ」を虫と見たのだろうか。
「凧」の語源は,
「イカノボリ,タコノボリ」
と言われるところから,
「干した蛸の形から」
来ているとされる。「凧の尻尾」は,タコやイカのアシとみている,と見られる。因みに,「凧」は,国字。
「風+布」
で,風に舞う布切れ,の意。
だから,『語源由来辞典』が言うように,元々,「凧」も「干蛸」から来ているのだから,「引っ張り凧」とあてても不思議はない。
因みに,「干し蛸のつくり方」というのがあった。
http://hyogo-nourinsuisangc.jp/6-mame/img/suisan/6.pdf
この連想で,『キングダム』の最新巻で「嫪毐(ろうあい)」が,車裂きの刑になるところがあった。車裂きの刑は,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E8%A3%82%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%88%91
に詳しい。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
霧雨というか,細かにまとわりつくような雨が降っている日があって,
小糠雨,
という言葉を思い出した。しかし,日本語は,季節ごとで表現が変わる。たとえば,
「春のものを『ぼたもち』、秋のものを『おはぎ』とする」
というように。もっとも,これも異説があり,
「もち米を主とするものが『ぼたもち』、うるち米を主とするものが『おはぎ』である」とする説,
「餡(小豆餡)を用いたものが『ぼたもち』、きな粉を用いたものが『おはぎ』である」とする説,
等々。この辺りは,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%A1
に詳しいので譲るとして,で,「小糠雨」である。辞書(『広辞苑』)には,ただ,
細かい雨,糠雨,
とあり(『大言海』は,微雨,細雨(さいう)を加えている),「糠雨」は,
極めて細かい雨,霧雨,小糠雨,
と,循環する。まあ,ここからは季節がないように見える。しかし,
「小ぬか雨は非常に細かい雨のことですが、春に降るこのような雨のことを小ぬか雨、秋に降るものを霧雨と呼ぶようです。牡丹餅とおはぎは同じものでも春は牡丹餅、秋はおはぎと呼ぶように、雨にも季節で呼び方が変わるようです。」
とあり,季節によって使い分けられているらしいのである。そもそも,「こぬか」というのは,
小糠,
粉糠,
糠,
と当て,
「米を舂(つ)くとき,表皮の細かく砕けて生ずる粉末」
のこと。だから,「小糠雨」の語源は,
「こぬか(粉のような糠)+雨」
で,音もしないで降る細かい雨,の意とある。因みに,「ぬか」の語源は,
「ヌケカワがヌカワ,ヌカと音韻変化したもの」
とある。「ヌ」は,脱穀の意の「ヌ」だが,「カ」を皮とみるか,離ルのカと見るか,二説ある,という。
ひとつは,「ヌ(脱ぐ)+カ(皮)」で,脱穀した後のヌケカワ説,
いまひとつは,「ヌ(脱ぐ)+カ(離る)」で,籾のうち穀類と離されたものというヌカ説,
がある。ただ,農民は,「コヌカ(粉+糠) 玄米の皮,外胚乳などが砕けて粉になった」と,「コメヌカ(米+糠)」と,「モミヌカ(籾+糠)」,「モミガラ(籾+殻)」とを区別している,と説明がある。
辞書だけでは,コトバのもつ季節感がよくわからない。小糠雨が,春で,霧雨が秋だとすると,季節ごとの雨の呼び名が気になって,ちょっと挙げてみる。
春だと,春雨,桜雨,春時雨,菜種梅雨,春霖,梅若の涙,雨木の芽雨,花の雨,桜ながし,催花雨(さいかう),春驟雨(はるしゅうう),花時雨,春時雨(はるしぐれ),走り梅雨,迎え梅雨等々。
夏だと,卯の花腐し(うのはなくたし),ながし,筍梅雨,走り梅雨・梅雨・梅霖(ばいりん),青梅雨,五月雨,送り梅雨,戻り梅雨,虎が雨,白雨(はくう),村雨(むらさめ),群雨,にわか雨,夕立,白雨,喜雨,青葉雨,翠雨(すいう),緑雨,瑞雨(ずいう)、穀雨(こくう)、甘雨(かんう),洒涙雨(さいるいう)等々。
秋だと,秋雨,秋霖しゅうりん),洗車雨,御山洗,秋時雨,秋霖,時雨(しぐれ),
冬だと,冬雨(とうう),寒雨(かんう),凍雨(とうう),時雨(朝時雨・夕時雨・小夜時雨・木の葉時雨・村時雨・横時雨・月時雨),氷雨(ひさめ)等々。
季節の区分けは難しく,卯の花腐し(うのはなくたし)は季語は夏らしいが,春に入れてもおかしくない。
なお,雨粒の大きさで呼び名が変わるらしく,
小糠雨,霧雨は,0.5mm
靄は,0.02mm
とあった。小糠雨は,「そぼ降る」,霧雨は,「煙る」のだそうだ。
季節を問わない雨の呼び名も多く,
驟雨(しゅうう) 突然降り出す雨。俄雨(にわかあめ)。
地雨(じあめ) しとしとと振りつづく雨。纏わり付くようなうっとおしい雨。
篠突く雨(しのつくあめ) 篠とは群生する細い竹、篠を束ねて突きおろすように激しく降る雨です。
村雨(むらさめ) 群雨/叢雨とも。群になって降る雨。玉が散っているような雨のことです。
天泣(てんきゅう) 空に雲が無いのに細かい雨が降ってくることです。狐の嫁入りとも。
怪雨(あやしあめ) 花粉、黄砂、火山灰などいろいろな塵が混じって降る雨のことです。
等々。いやはや,雨の名の多いこと。因みに,「雨」の字は,象形文字で,
「天から雨の降るさまを描いたもので,上から地表を覆って降る雨のこと」
とある。
雨については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8
に詳しい。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
http://www.i-nekko.jp/sahou/word/ame/
http://www.k-pole.co.jp/zatugaku_30.html
http://fritha.cocolog-nifty.com/wordsworth/2007/02/post_7b50.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8
「士気」
と書くと,
兵士の戦いに対する意気込み。また転じて,集団で事を行うときの意気ごみ,
という意味になる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AB%E6%B0%97
の説明では,
「(しき、英: morale)は、一般に部隊の任務を遂行する上で有用な兵員の心理的な積極性や耐久性を指す。
その他、軍事関係以外にも集団組織行動全般での関係者の行動意欲に関わる心理的高揚のバロメーターを表す。」
とあり,まあ,
士気が上がる,
士気が高い,
という言い方をする。一方,「志気」は,
もの事をなそうとする意気込み
という意味になる。『大言海』だと,それに,
こころざし,気性,
が加わるが,しかし,結果として,両者とも,
やる気,
を指しているように見える。「士」と「志」の字は,「士」は,前にも書いたが,
男の陰茎の突き立ったさまを描いた象形文字で,牡の字の右側にも含まれる,
成人して自立するおとこ,
を意味する。「士気」の語源は,
「士(兵士)+気(元気)」
で,それが一般に転じたとされる。「志」は,
「士印は,進み行く足の形が変形したもので,之(し)と同じ。士女の士(おとこ)ではない。『心+士』は,心が目標を目指して進み行くこと」
と説明されている。で,
「ある目標の達成を目指して心を向ける」
という意味になる。「大志」「とか「立志」の「志」は,目的と訳されることもある。
こうみると,英語に訳すと,共にmoraleになってしまうのだが,「士気」と「志気」の差は,意気込みには違いないが,目的意識の向かう先の差であるように見える。
士気の類語は,
(団体の構成員にその団体が成功を収めたいと思わせる精神)団の精神,モラール, 団結心,
であり,志気の類語は,
(集団における積極的な意志や心意気)意気込み,やる気 ,やるぞという心意気,戦意,モチベーション
となり,両語は置き換わるようで微妙に違う。
「士気」は,所属する集団(の目標)に向かうのに対して,「志気」は,個々の目指す目標を介して集団の目標に向かう,という気がする。
あるいは,同じ集団の意気込みでも,士気は集団に焦点が当たるが,志気は個々人の内側に焦点が当たる。たとえば,「士気が上がる」「士気が高い」(志気が高い,志気が上がるとは言わない)は,
やる気が高い,
やる気が上がる,
と言い替えられるが,集団を指して言うことが多い。個人なら,「やる気がある」「やる気になる」というだろう。
「
やる気」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E3%82%84%E3%82%8B%E6%B0%97)は触れたことがあるが,
やる気は,
遣る気
と当てられる。遣る気は,辞書(『広辞苑』)には,
「ものごとを積極的に進めようとする目的意識」
とある。他の辞書だと,
進んで物事をなしとげようとする気持ち,
というニュアンスだが,「目的意識」とあるのがみそだと思う。
遣る気の「遣る」は,語源的には,
「自分の身から遠くへ動かす行動」
という意味で,送る,遣わす,与える,進ませる,はかどらせる等々の意味,とある。辞書(『広辞苑』)には,大きく分けて,
その場の勢い,成り行きに任せて他方へ行かせる,
(身分が同等以下の者に)与える,
自ら物事を行う,
(他の動詞の連用形について)動作が完了する意,動作を遠くから行われる意(晴れやらぬ,見遣る),
等々といった使い分けがあるが,どうも「遣る気」は,
「自らが物事を行う」気,
という使い方で,そこに,漫然とというよりは,目的がある,つまり,
その気になる,
というニュアンスがあるような気がする。その意味で,「志気」に重なるのである。
『ワーク・モチベーション』(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-3.htm#%E3%83%A2%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)で触れたが,類語の,モチベーションという言葉は,
動機づけ,
つまりは,辞書的には,
「人や動物の行動を引き起こし,一定の方向に向かわせる一連の行動」
とあり,まあ,パヴロフやスキナーの無条件であれ,オペラント条件付けであれ,犬や鳩じゃああるまいし,餌づけするように意欲を引き出そうとする,モチベーション理論には,忌避感がある。内発的だの外発的だのというのは,働かせようとする者が,働く意欲を引き出そうとする発想に見えてならない。そこには,
「士気を高めよう」
というのと同じ上から(あるいは部外からの)目線を感じてならない。それに比べて,
やる気を起こす,
とか
やる気を引き出す,
という言葉には,そもそも内にあるやる気スイッチをどうやって点火できるかという視点があるように思える。
つまり,やる気があるとは,それをするための「何か」(目的)が自分の中にあることなのである。それをするためならその気になれる,たとえば,それをする意味や価値や魅力(大切さや値打ち,面白さや楽しさ),興味や関心,自己表現(目立つ,存在感,賞賛)等々が必要なのである。そのうちからの視点が,
やる気,
だとすると,「志気」とは重なるが,「士気」には重ならない。視点の位置が違うのである。
「はかどる」の
「はか」
である。
はかが行く,
という言い方もする。
はかどるは,
捗る
果取る
と当てる。
はかが行くは,
果が行く
と当てる。いずれも,
仕事が順調に仕上がっていく,
進捗する,
という意味である。語源は,「はかどる」で言うと,
「ハカ(進度・進み具合)+とる(積み重ねる)」
で,仕事が進という意味になる。『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ha/hakadoru.html
には,
「はかどるの『はか』は、『はかる』『はかばかしい』などの『はか』と同源で、漢字では『捗』『
果』『計』『量』などと書き、仕事の分担や目標・進み具合などを意味する語。 『はかが行く
(はかがゆく)』の形では平安時代から見られ、『はかどる』の形は江戸時代から見られる。」
とある。で,「はか」を調べると,辞書(『広辞苑』)には,
計,
量,
の字を当て,
稲を植えたり刈ったり,まくた茅を刈るときなどの範囲や量,また稲を植えた列と列の間を言う。
目あて,あてど。
(「捗」とも書く)仕事の進み具合,
の意味が載る。で,『古語辞典』を調べると,
計,
量,
捗,
の字を当て,
「ハカリ・ハカドリ・ハカナシなどのハカ」
とあり,上記の辞書(『広辞苑』)と同じ意味が載る。『大言海』は,「計」と「量」を別項を立てる。それぞれの由来が異なることがはっきりわかる。さすがに,『大言海』である。
「計」は,
「稻を植え,又は刈り,或いは茅を刈るなどに,其地を分かつに云ふ語。田なれば,一面の田を,数区に分ち,一はか,二(ふた)はか,三(み)はかなどと立てて,男女打雑り,一はかより植え始め,又刈り始めて,二はか,三はか,と終はる。又稲を植えたる列と列との間をも云ふ。即ち,稲株と稲株との間を,一はか,二はかと称す。」
と,ある。こういう説明が,文字面ではなく,現実をわかっている説明という。辞書(『広辞苑』)は,意味レベルではなく。その実態,エピソードレベルまで降ろさなくては,芯の意味は分からない。
「量」は,
「量(はかり)の略。田を割りて,一はか二はかと云ふ。農業の進むより一般の事に転ず。かりばかの条をみよ。」
とあり,「仕事の捗る」という意味を載せる。因みに,「かりばか」を見ると,
刈婆加,
の字を当て,
「稲刈りに,田に区分を分割して,刈り取ることを云ふ。刈量(かりはか)の義ならむ。…功程(はか)のゆく,ゆかぬという語,是なるべし。然して,それがやがて,稻,茅の刈取という意となりしとおぼし」
とある。初めは,「量」で,その意味が広がって,「計」になり,ついには,
捗る,
とあて,「捗」を当てるようになった,と考えられる。この「はか」が,
はかない,
の「はか」に通じる,というのである。『大言海』は,
無果敢,
儚,
の字を当て,
「あとはかなし(無痕迹)の略,としているが,辞書(『広辞苑』)には,
果無い,
果敢無い,
儚い,
の字を当て,
「ハカは,仕上げようと予定した作業の目標量。それが手に入れられない,所期の結実のない意」
として,
これといった内容がない,とりとめがない,
てごたえがない,
物事の進捗などがわずかである,
うっけない,むなしい,特に人の死についていう,
等の意味が載る。「はか」がいかない,という意味の,果てに,
とりとめがない,
むなしい,
と行きついたということになる。「はかない」には,「いたずらに」という意味がある。はかか行かないことはたしかに,むなしい。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
序の口というのは,
物事の始ったばかりのところ,発端,
相撲の番付の最下段に記名される地位,
の意味だが,当然,謂れは,相撲から来ていると想像される。語源は,
「序(順序の始め)+口(物事の始め)」
で,物事の発端,という意味になる。「序」の字は,
「予は,機織りの杼(ひ)を描いた象形文字。杼は,糸を押し伸ばす働きをする。抒(のばす),舒(のびのびする)と同系。序は,「广(いえ)+予(よ)」。おもやの脇にのび出た脇屋。また,心の中の思いを押し延ばして展開する意」
とある。で,意味は,脇屋の意味の他に,
ある基準による決まった並べ方,順序,
とある。「口」は,
「人の口や穴を描いたもの。その音がつづまれば谷(穴の開いた谷),語尾が伸びれば孔(あな)や空(筒抜けのあな)となる。いずれも中空に穴の開いた意」
とあり,口の連想からか,
入り口,
という意味をもつ。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/si/jyonokuchi.html
には,
「序ノ口は番付に初めて記されるくらいなので,『上り口』という意味から古くは『上ノ口』と表記されていた。『上ノ口』が『序ノ口』と表記されるようになったのは,『序』には『序盤』などのように物事の初めや最初の意味があるからだが,一番下の位であるのに,『上』と書かれる意味がわかりづらかったのも理由のひとつであろう。物事が始まったばかりを意味する『序の口』は相撲の序ノ口に由来する。」
とあり,相撲では,
序ノ口
と表記される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%8F%E3%83%8E%E5%8F%A3
にもあるように,
「元々は、番付の上り口という意味で『上ノ口』と表記したが、『上』は上位と紛らわしくなるため、『序ノ口』が用いられるようになった。」
ということらしい。ところで,「すもう」は,
相撲
とも
角力
とも
書く。語源は,
「すま(争)ひ」
から来ている。「すまひ」は,
拒ひ,
と当て,
相手の働きかけを力で拒否する意,
で,
「相手の力に負けまいとして抵抗すること,手向かうこと」
とある。従って,相撲,角力は当て字。
「古くは,武術で,打つ,殴るなどの技もありました。用例として,スマイナヤム(争い悩む,断りかねてどうしたらよいか困る),スマイ牛(前に進もうとしない牛)」
と載る。『大言海』には,「すまひ」の項に,相撲が載る。
「争(すま)ふの名詞形。争(すま)ひの義。戦場の組打ちの慣習(ならはし)なり。源平時代の武士の習いしスマフもそれなり」
とある。相撲の謂れの詳細については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%92%B2
に詳しいが,『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/su/sumou.html
には,
「『争う』『負けまいと貼り合う』を意味する動詞『すまふ(争ふ)』が名詞化して『すもう』になったか,『すまふ』の連用形『すまひ』がウ音便化したと考えられる。平安時代の辞書『和名抄』に『相撲
須末比』とあるように,古くは『すまひ』と呼ばれていたが,ウ音便化されたという確定的な文献がないため,『すまふ』と『すまひ』のどちらであるかは断定できない。古代の『すまひ』は蹴りなども行われる力比べで,細かなルールはなかった。『日本書記』の垂仁紀七年にる野見宿禰(のみのすくね)と當麻蹶速(たいまけはや)の対決記事があり,これが相撲の始まりとされる。現代の相撲の基本様式は,平安時代に宮中で行われた『節会相撲(せちゑすまひ)』が恒例化したものであり,室町時代末期に娯楽観覧のための職業相撲が発達」
とある。序ノ口は相撲用語から来ているが,相撲用語
http://deliciousway.sakura.ne.jp/sumo/shiryou7.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%92%B2%E7%94%A8%E8%AA%9E%E4%B8%80%E8%A6%A7
は,一杯あるが,一般化している言葉は,意外に少ない気がする。将棋や囲碁から来ている言葉の方が圧倒的に多いのは,一般の人が,それをする機会が多いせいかもしれない。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
小谷野敦『日本恋愛思想史』(中公新書)
「やろう」というのは,いまだと,
「この野郎!」
と,罵るとき位にしか使わない。辞書(『広辞苑』)には,
田舎者(日葡辞典),
前髪を剃った若者,
野郎頭の略,
初期歌舞伎の俳優の称,
男色を売る者,陰間,
男を罵っていう語,
が意味として載る(この他に,「野郎帽子」の略,というのもあるらしい)。
野郎の語源は,
「ワラワ(童)変化,和郎」
と,
「ヤ(野)+ロウ(郎)」
の混淆した語,とされる。
「和郎(若者・若僧)と野郎(田舎者)は,どちらも男を罵る語」
とあるところを見ると,罵る言葉は,原義らしい。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E9%83%8E
には,
「野郎(やろう)とは、成人男性を指す言葉。江戸時代では前髪を落として月代を剃った男性を指した。のちにこの言葉は男性を罵る場合に使用されるようになる(対語は「女郎(めろう)」
とあり,
「月代を剃った頭を『野郎頭』と言い、その『野郎頭』の役者のみで興業される歌舞伎は『野郎歌舞伎』と呼ばれた。 女形を演じる男性役者は、そり落とした月代を手ぬぐいなど隠したが、やがて『野郎帽子』と呼ばれる被り物を用いるようになった。 野郎歌舞伎の役者(『野郎』)が得意客に呼ばれて遊興の場に連なることもあり、『野郎遊び』、『野郎買ひ』という言い回しが使用された。」
『大言海』は,
野郎
野良
の字を当て,「野郎」の意味の変遷を詳述する。まず,
「薩摩にて,人を罵り呼ぶに和郎(わろう)と云ふ。此語,童(わらわ)の音便なるべし,(童は,古へは,冠を放ちて,わらは形なるを,痛く卑しむる世なれば,云ひしなり)其の和郎の野郎に転じたるなり。さやぐのさわぐ,わやくのわわくの類なり」
と注記する。したがって,
薩摩詞にて,男子を卑しめ呼ぶ語と云ふ。又,貴人にむかへて,下郎を賤めて云ふ,
が意味の最初に来る。次に,
「承応元年,若衆歌舞伎の男色を売る甚だしきによりて,令して前髪を剃り落さしめ,成人の如くならしめし者の称(歌舞伎子(かぶきこ)の条を見よ)。紫の帽子を被りて,成人の姿を隠す。これに因りて,野郎頭,野郎帽子の名起こる。」
とある。因みに,歌舞伎子を見ると,若衆歌舞伎に同じとあり,少年の歌舞伎役者,とある。
これが転じて,直に孌童(かげま)の称。陰間の条の(二)をみよ,
とある。で,陰間を見ると,
「舞台に出ず,陰に居る間の意と云う。蔭子と云ふも同じ」
とあり,こう説明がある。
「少男を抱え起き,若衆歌舞伎にしたてむとて,芸を仕込み居るものの称。蔭子とも云ふ。芝居に出でて歌舞するを,舞台子と云ふに対す(女の踊子をかげま女などとも云へりと云ふ)。蔭子をして男色を売らしむるを色子と云ふ。」
そして,二の条には,
「かげまは,後に全く,男色を売るを専業とする者の称となり,常に女装して客を迎ふ。かげま茶屋とて,娼家の如きものありき。」
とある。
更に,それが転じて,
「泛(ひろ)く前髪なき男子,または,若き男子を罵り呼ぶ語,奴。」
と,何やら一巡して元の「罵る言葉」に戻った感じである。
それにしても,阿国歌舞伎から若衆歌舞伎に,そして野郎歌舞伎に,ずっと色を売るニュアンスが付きまとっている。若衆は,ずばり,
「上略して衆道,下略して若道(にゃくどう)と云ふ」
とあり,男色を指す。
野郎帽子については,
http://www.honnet.jp/metro/rekisi/r192/rekisi27.htm
に,
「歌舞伎役者が頭に紫の布を付けているのを見られたことがあるでしょう。鬘のない時代ですから、女形(おやま)が月代(さかやき)の髪型で登場すれば、それはあまりにも滑稽なことです。そこで剃った月代を隠す為に布を被せたのですが、お洒落な感じがしてこれを『野郎帽子』と呼んだのでした。それで女形はみんなこのようにしたのでした。」
とある。なるほど,あれを帽子と呼んだのか。
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/2/2_02.html
には,
「阿国が創始した『かぶき踊り』が人気を博すと、それをまねた遊女や女性芸人の一座が次々と現れました。このような女性たちによって演じられた『かぶき踊り』を『女歌舞伎』といい、京だけではなく江戸やその他の地方でも興行され流行しました。図は京の四条河原の仮設の舞台で行われた『女歌舞伎』で、そろいの衣裳に身を包んで輪になった遊女たちが、当時最新の楽器だった三味線に合わせて踊る様子を描いています。」
それが衆道歌舞伎に,さらに野郎歌舞伎に変っていく。
http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/kabuki_dic/entry.php?entryid=1293
には,
「成人前の前髪立【まえがみだ】ちの少年による若衆歌舞伎【わかしゅかぶき】が禁止されると、少年たちは前髪を剃り落として歌舞伎を演じました。前髪を落とした頭を野郎頭【やろうあたま】と呼ぶため、野郎頭で演じられた歌舞伎を野郎歌舞伎といいました。それまでの歌舞伎は歌と踊りが中心でしたが、野郎歌舞伎は時間の経過とともに場面が変わる複雑なストーリーをもつ演劇に発展しました。」
とある。
いやはや,たかが「野郎」という言葉の奥行に圧倒される。
参考文献;
http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/kabuki_dic/entry.php?entryid=1293
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/2/2_02.html
http://www.honnet.jp/metro/rekisi/r192/rekisi27.htm
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
五衰というと,三島由紀夫の『天人五衰』を連想するが(そうでもないか),
五衰三熱,
という言葉があり,そこから調べ出した。五衰は,
天人が命尽きんとするときに示す五種の衰亡の相,
で,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BA%BA%E4%BA%94%E8%A1%B0
では,
「六道最高位の天界にいる天人が、長寿の末に迎える死の直前に現れる5つの兆しのこと。」
と説明される。(経によって諸説あるが)涅槃経では,
衣裳垢膩(えしょうこうじ):衣服が垢で油染みる
頭上華萎(ずじょうかい):頭上の華鬘が萎える
身体臭穢(しんたいしゅうわい):身体が汚れて臭い出す
腋下汗出(えきげかんしゅつ):腋の下から汗が流れ出る
不楽本座(ふらくほんざ):自分の席に戻るのを嫌がる
とされ,さらに,異説が多い「身体臭穢」の代わりに
『法句譬喩経』1や『仏本行集経』5では「身上の光滅す」
『摩訶摩耶経』下では「頂中の光滅す」
『六波羅蜜経』3では「両眼しばしば瞬眩(またたき、くるめく)」」
とされる,とある。長寿の天人にも,死がある,というのも面白いが,「三熱」は,やはり仏語から来ていて,
「竜・蛇などの承ける三つの苦悩,熱風・熱沙に身を焼かれること,悪風が吹いて住居・衣服を奪われること,金翅鳥 (こんじちょう) に(『子が』と加えるのもある)捕食されること。三患」
とある。因みに,金翅鳥は,
「迦楼羅(かるら)」に同じ,
とあり,迦楼羅は,梵語garuḍaの音写。
「インド神話における巨鳥で,龍を常食するという。仏教に入って,天竜八部衆の一として,仏法の守護神とされる。翼は金色,頭には如意珠がおり,常に口から火焔を吐くという。日本で言う天狗箱の変形を伝えたものとも言う。」
とある。金翅鳥は,
「インド神話・仏典に見える想像上の鳥。八部衆の一つ迦楼羅(かるら)とは別のものであったが,同一視されるようになった。」
とも言われる。金翅鳥については,
http://makasatsu.web.fc2.com/bird.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%80
に詳しい。ついでながら,迦楼羅炎(かるらえん)というと,
不動明王の光背の名称,迦楼羅の羽を広げた形に似るから,
という,そうだ。
さて,「五衰」に「三熱」が加わった,「五衰三熱」は,『故事ことわざ辞典』によると,
五衰三熱の苦,
とあり(「五衰」は,天人が死ぬ前に現れるという五種の衰相。「三熱」は,畜生道で竜や蛇などが受ける三つの苦しみ),
「逃れられない苦しみをいう」
とある。この言葉が,神道史の中に出てくる。かつて,神祇信仰においては,女性が中心的な役割を果たしてきたが,仏教の「女性罪業観」つまり,
「仏教では,インド仏教以来,『五障」といって,女性は,梵天・帝釈・魔王・転輪聖王(てんりんじょうおう)・仏になれず,成仏するには『変成男子(へんにょうなんし)』(いったん男性に転生すること)が必要とされた。また戒においても,比丘尼に対して,比丘尼戒はその数倍の数がある」
によって,「穢れ」観が増大した。
しかしそれにしても,マホメッドにしても,釈迦にしても(キリストは良くわからないが),どうしてこう女性や,性を怖れるのだろう。不謹慎ながら,「まんじゅう怖い」の一種か,と思ってしまう。
閑話休題。
で,神仏習合というか,本地垂迹というか,日本の神々,特に女神が困ったことになった。そのため,謡曲『葛城』『三輪』等々には,
「弁才天,三輪神といった女神が,女性の身からの救済を願う話が載せらる」
ということになる。そこに,「五衰三熱の苦しみから免れんとする」という言葉が出てくる。『三輪』には,三輪神(女神)が,玄賓僧都(げんぴんそうず)に衣を求めて,
「まづ当社は女体にてござ候。また承り候へば,神も五衰三熱の苦しみがござあると申し候へば,さやうのおんことに御衣をご所望ありたると推量仕りそうろう。」
とある。女神が,高僧に帰依して五衰三熱の苦しみから救済を請う物語がパターン化される,という。
「三熱」の含意で,龍・蛇があり,龍蛇神につながるが,弁才天は,本地垂迹で,市杵嶋姫命(いちきしまひめ)と同一視され,水の神とされる。その意味で,「三熱」の意味を汲んでいるところがあるが,本来男神である,葛城神,三輪神まで,女神に置き換えて,「抜苦請願」する役割を振られている。これが,中世,天照大神が男神とする例が,神道側にもあったというから,神仏混淆が,行きつくところまで行った,という感じなのであろうか。
五衰から,少し遠くへ来過ぎた。
参考文献;
伊藤聡『神道とはなにか』(中公新書)
一時しのぎ(一時凌ぎ)
と
一時のがれ(一時逃れ・遁れ)
はどう違うのだろう,というのが端緒。
「しのぎ」は,辞書(『広辞苑』)で引くと,
「しのぎ」で,
茶道で,風炉の灰をよせるとき,山の灰角(はいかど)の名,
柄杓の名所(などころ)柄のけらくびにつづくところ,
とある。「けらくび」とは,
柄と合 (ごう) (水や湯を入れる部分)の合わせ目,
で,「けらくび」は,
槍の穂と柄とが接する部分。,
だから,そこから来ているのかと思うが,刀剣では,鎬は,辞書(『広辞苑』)にはこうある。
「刀剣の名所(などころ)。投信の刃と棟との間を縦に走り,稜線をなして高くなったところ。また,両刃の剣の中間的にある稜線。ある種の鏃にもある。」
つまり,鎬の字を当てると,鑓でも刀でも,
「刀の刃と峰(背の部分)の間で稜線を高くした所」
あるいは
「刃と背(みね)との間の稜(かど)立って高い部分」
を指す。図で見ると,鎬の位置は,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Katana_%28ja%29.png/300px-Katana_%28ja%29.png
でよく分かる。「鎬を削る」としいう言い回しがあるが,
『 語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/si/shinogiwokezuru.html
には,
「しのぎ(鎬)」とは、刀の刃と峰(背の部分)の間で稜線を高くした所。 その鎬が削れ
落ちるほど激しく刀で斬り合うさまを「しのぎを削る」と言うようになり、後に、刀を用いた争い以外にも熱戦を指して言うようになった。
苦しみに耐えて何とか切り抜ける意味の『凌ぎ』を用いて,『凌ぎを削る』と誤表記されることがある。『鎬』の語源が『凌ぎ』と関係ないとは言えないが,『しのぎを削る』という慣用表現において『凌ぎ』は関係ない…」
とあり,「しのぎ」が「けらくび」の位置なら,「つばぜり合い」と間違えているのではないか。「つばぜりあい」は,「鍔迫り合い」と当てるが,
「互いに打ち込んだ刀を鍔で受け止めたまま押し合うこと」
だから,「けらくび」のあたりで,もみ合うことになる。しかし,「鎬を削る」は,
「切り合うとき,鎬が互いに強く擦れて削り落ちるように感ずるからいう」
とあり,刀身をぶつけ合うことを指すので,「けらくび」でいう「しのぎ」と「鎬」は位置が違うような気がする。
しかし,『語源由来辞典』とは異説だが,「鎬」と「凌ぎ」は,語源的には関係がある。「鎬」について,
「語源は『しのぎ(凌ぎ)です。刀の衝撃を凌ぐ(耐える)部分のことを指します。」
とあり,本来,「凌ぐ」ために「鎬」がある,ということになる。因みに,ヤクザの言う,
シノギ,
も,そこから来ていて,
「シノギとはヤクザ・暴力団の収入や収入を得るための手段のことをいう。『糊口をしのぐ(飯をのり状の粥にして食いつなぐこと)』または『鎬(しのぎ)を削る(両者の刀の鎬が削れるほどの激しい戦いのこと)』からきたとされているが詳しいことはわかっていない。暴力団の主なシノギとして用心棒、麻薬の密売、ノミ行為、高利貸しといったものから、最近ではオレオレ詐欺・ワンクリック詐欺の元締めなど手の込んだものまで、違法性のあるものが多い。」
とある。
「しのぎ」も「鎬」も,結局,
凌ぎ,
から来ているが,『大言海』には,
しぬぐの転,
とあり,「しぬぐ」をみると,
忍ぶの他動の意,
とある。『古語辞典』では,
踏みつけ,抑える意が原義,
とある。辞書(『広辞苑』)には,
堪えること,しのぐこと,
一時をしのぐ意,
とあり,いまは,逆転しているが,本来は,『古語辞典』にある,
押さえ伏せる,
山・波などを押し分けのりこえる,
侮る,さげすむ,
で,それが,主客逆転して,
辛抱して困難・障害などを乗り切る,
という意に転じたとみることができる。「凌」の字は,
「夌(りょう)は『陸(おか)の略体+夂(あし)』の会意文字で,力をこめて丘の稜線を越えること。力むの力と同系で,その語尾が伸びた語。筋骨を筋張らせて頑張る意を含む。凌は,それを音符として,冫(こおり)を加えた文字。氷の筋目の意味」
とあり,
力をこめて相手の上に出る,
といった,「力づく」の感覚がある。そう考えると,
「一時凌ぎ」
は,逃げ身というよりも,力づくで拮抗するというニュアンスがある。因みに,「鎬」の字は,
「硬い金属のこと」
を意味する。一方,
一時逃れ,
は,似た意味には違いないが,
「その場だけつくろって、困難や責任を逃れようとすること」
というか,
「間に合わせ」
のニュアンスがあり,似た意味ながら,どこか身をかわそうという逃げの姿勢が見える。「のがれ」は,
逃れ,
か
遁れ,
いずれにしても,「回避」のニュアンスがある。「逃」の字は,
「兆は,骨を焼いて占う時に,左右に離れた罅が生じたさま,『逃』は,『辶(足の動作)+音符兆』で,右と左に離れ去るさま」
とあり,「遁」の字は,
「盾(とん)は『目+頭を隠す楯』の会意文字。遁は,『辶(すすむ)+音符盾』で,何かをたてとしてそれに隠れつつ進む,つまり隠れて姿を消すこと」
とあり,一時逃れ(遁れ)は,まともに向き合うのを避けていることに変りはない。
それなら,今はほぼ同じニュアンスで使われるが,やはり,
一時逃れ,
よりは,
一時凌ぎ,
の方が,ましということになる。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%88%80
笠間良彦『日本の甲冑武具辞典』(柏書房)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
うざいは,ときに,
ウザい,
とも表記したりする。辞書(『広辞苑』)には載らない。
『日本俗語辞典』
http://zokugo-dict.com/03u/uzai.htm
には,
「うざいとは『うざったい』の略で、『鬱陶しい』『わずらわしい』『うるさい』『面倒臭い』『気持ち悪い』『邪魔』といった意味を持つ。うざいは1980年代のツッパリブームから関東圏を中心に使われるようになり、1990年代には不良以外にも使われ、全国的に普及する。うざいが更に簡略化された『うざ』や、うざいの語感が荒くなった『うぜー(うぜえ)』という言い方もある。2006年、学生の相次ぐ自殺が社会問題となるが、うざいと言われたことが原因になったり、うざいの一言が発端で殺傷事件になるほど荒い言葉なので使用には注意が必要である。」
とある。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/u/uzai.html
は,意味を,
「うざいとは、主に若者言葉で面倒だ。鬱陶しい。うぜえ。うぜぇ。 うざったいとは、ごちゃごちゃ・細々して煩わしい。うざっこい。」
として,『語源由来辞典』を,
「うざいは1980年代頃から使われ始めた言葉で、『うざったい』の略。
うざったいは俗に『鬱陶しい』を略した言葉で,元は東京多摩地区の方言であったものが,東京の若者の間で広く使われるようになり全国に広まったといわれる。その語源は,江戸時代に広く使われていた『うざぅざ』という擬態語を形容詞化したものと考えられる。『うざぅざ』は,『うじゃうじゃ』や『うじょうじょ』と同じく,似た種類の物が沢山集まっている様子や,つまらないことをくどくど言うことを意味する。」
とする。どうやら,関東圏で使われ出したものらしい。辞書(『広辞苑』)には,「うざったい」は,
「まごまごしていて,うっとうしい,わずらわしい,めんどくさい」
という意味を上げる。確かに,そういう手合いがいないとは言わないが,それは,こっち側が,単なる,
短気,
というか,
気が短い,
というだけで,結局自分の気性を相手に投影しているだけのことではないのか,と感じてしまう。関東ではやりだしたのがわかる気がする。(いまは全国的だとしても)関西弁では,元々こういうのを,何と言ったのだろう。
いまは,何でもかんでも,
うざい,
の一言で片づけてしまうようだ。多く自分の側の気分や気質を反映しているだけなのに,あたかも,相手のせいであるかの如くに貶めるのが,
うざい,
という言い回しであるように感ずる。たとえば,
http://shuchi.php.co.jp/article/1760
で,心理カウンセラーともあろう輩が,
「【ウザい話し方】話していて「疲れる人」「面倒くさい人」の口ぐせとは」などと題して,
「『ウザい話し方』50のパターン ~ あなたも知らずにやってませんか?」
等々とリストアップする。うざいと感じるのは,聴き手の問題であって,話し手の問題とは限らない。少なくとも,どんなにうざいと客観的に見えようと,好きな相手の話はうざいとは感じない。問題なのは,聴き手の状態であり,さらには,両者の関係性(をどう感じているかという聴き手の)認識の問題でしかない,と僕は思う。
しかも,うざい項目を,
相手を疲れさせる話し方
「面倒くさい!」話し方
食事&飲み会
仕事
口ぐせ・言いまわし
と分けている。可笑しいのは,
「何かの会に誘うとやたらと質問してくる」
「すぐに質問を挟んで話の腰を折る」
のがうざいといいながら,
「話が曖昧で、ちっとも具体化していかない」
と挙げる。曖昧なら,質問すればいいのであって,そんなことがなぜうざいのかわからないが,前項で質問をうざいといった手前,そうできないのだろうと勘繰りたくなる。要は,おのれの聴き癖を挙げているにすぎない。
蟹はおのれの甲羅に合わせて穴を掘る,
とはよく言ったものだ。
閑話休題。
「うざい」の源流が江戸時代というが,『大言海』には,
「うざっこい」
が載る。そこには,
「うざっこし,うざっこきと云ふべき口語」
と,注記して,
「うざうざする状なり。多く群がりて厭ふべし。うじゃっこい(小虫などに云ふ)」
とある。これで,「うざっこい」が「うざったい」に転じたものと想像がつく。
うじゃうじゃ,
というのは,辞書(『広辞苑』)には,
「多数の小さい虫などが絡み合ったり重なりあったりして蠢くさま」
「小声でくどくどものを言うさま」
とあり,「うじゃうじゃ」の意味に,転じていく「くどくどしたものの言い方」の意味があることがわかる。『大言海』は,
「うざうざの転」
としている。つまり,どちらも,状態を,表現しているだけの,
うじゃうじゃ,
うざうざ,
が,
うざっこい,
うざっったい,
と転じたとき,状態への評価,厭う感情が入っている,ということになる。それにしたって,その感情は,相手ではなく,感じる側の問題に過ぎない。
「別に,おまえさんに,うざいなどと言われる筋合いはない。」
と言い返せば済むだけのことだ。相手の勝手な感情まで知ったことではない。
ださいは,
ダサい,
と表記したり,
「ダッセー!」
と言ったりする。辞書(『広辞苑』)には,
野暮ったい,洗練されていない意を表す,
とある。『日本語俗語辞典』
http://zokugo-dict.com/16ta/dasai.htm
は,「ダサい」と表記し,
時代遅れ、野暮ったい、田舎臭いこと,
として,
「ダサいとは古臭い(時代遅れ)、野暮ったい、田舎臭い、かっこ悪いといった意味の形容詞で、1970年代から関東の若者を中心に普及した言葉である(一説には1950年代から一部の若者の間で隠語的に使われており、1970年代に広く浸透したともいわれる)。1980年代後半に入ると対語の『ナウい』が死語となるが、ダサいはそのまま使われ続け、現代に至っている。田舎を「たしゃ」と読み、ダサいになったとの説もあるが正確な語源は不明。」
と説明する。
『語源辞典』には,「ださい」の語源として,
「~ダサ(田舎者の語尾)+イ(形容詞化)」で,田舎者らしく洗練されていない,
と
「ダってサイ玉だもん」で,都心から離れていて垢抜けしていない,
の二説が載る。『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ta/dasai.html
には,別の説を載せる。
「『田舎』を『だしゃ』と読み,形容詞化した『だしゃい』もしくは『だしゃ臭い』が転じて『ダサい』となったとする説が有力とされるが,方言で『だしゃー』ということはあっても,『田舎』を『だしゃ』と読む例が見当たらないことや,『ダサい』が使われ始めた1970年代には『間抜け』などの意味で使われていたため,不自然と考えられている。ただし『間抜け』や『格好悪い』と罵る際,『田舎』を持ち出すことはあるため,この部分においては不自然ではない。『だ埼玉(ださいたま)』が略され『ダサい』となったとする説もある。名前の前について粗末な意を表す『駄』があるため一見関連がありそうだが,『ださいたま』の説は,タレントのタモリが埼玉県民をからかい洒落で言ったものが広まったものである。」
と。しかし,田舎者だから洗練されていない,というのは,いずれ田舎者でしかない東京在住者の,ささやかな優先意識に過ぎない。一年前に住んだか,十年前に住んでか,百年前に住んだか,程度の差に過ぎないことを差異をつけているにすぎない。そもそも江戸っ子だって,京都に較べれば田舎でしかなく,あっちこっちから寄せ集められた田舎者の矜持に過ぎない。江戸っ子を誇る輩が大した輩でないのと同様,人を田舎者よばわりする輩は,どうせ目くそ鼻くそ,と思っていい。どこに住んでいたかなど,どこで生まれたかと同様,多く,他律的に過ぎない。だから,「ださい」という人間は,自分自分を相手にを投影している。おそらく,エスタブリッシュメントは,そういうたわごとを言わない。下々の人間の,わずかな矜持と思えば,可愛げがある。事実,
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/35713.html
には,
「今の40代半ば以上の方々が、使い出した言葉と記憶しております。俗に言う、暴走族の方々ですが、(カミナリ族までは古くないと思います)その頃殆どがマニュアルシフトですから、バイクや車を運転している時に、妙にカッコつけてダブルクラッチや速いギアチェンジをしようとして、たまに、ギアを入れそこなったり、ギア抜けしたりして、『惰性』で走ってしまう事があります。とてもカッコ悪いです。それを面白おかしく「ダッセー!」と言い出したのが、切っ掛けだったようです。まとめますと、
ギア抜け=惰性で走る
カッコ悪い=『ダッセー!』=『ダサい』となります。」
と,こんなところが本当ではないか。さらに,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%B5%E3%81%84
には,
「1970年代前半から関東地方の若者の間で広まり、1980年代にタレントのタモリが埼玉県民を嘲笑する意味で『ダサい』と『埼玉』を掛け合わせた『ダ埼玉』という造語を生み出して流行させた。」
とあり,
「『ダサい』の類義語としては『いも』『いも臭い』『いもっぽい』『ださださ』『へこい』『へぼい』『ポテトチック』などがあり、対義語として『ナウい』という言葉があった。1980年代後半に入るとこれらの言葉の多くは死語となった。『ダサい』という言葉も廃れたが、2000年代においても使用されることがある。」
として,
「こうした言葉が関東地方で広まった背景には、人々が持つ『見栄っ張り』の要素がある。周囲と同調する傾向の強い関東地方の人々は、東京から配信される『都会的』『洗練された』とされる情報に追随し、そうした価値観を反映した人間像を演じることで、都会から配信される文化を自分たちが支えているのだと認識していた。一方でこうした人々は、他者から『ダサい』と評されることを嫌う代わりに、埼玉県や千葉県出身者を嘲笑の対象と見なし、彼らを否定的に捉えることで自らの存在意義を確認していたという。」
と解説している。けだし,そんなところにしか自恃の念が持てない,ということに過ぎない。人を,
田舎もの,
だの,
ダサい,
だの,
と評する言葉は,所詮おのが身の投影でしかない。
ただ,興味深いのは,
http://thesaurus.weblio.jp/content/%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
では,類語を,「ださい」と「ダサい」と区別している。
「ださい」は,土くさい ・ 野暮 ・ 土気 ・ 土臭い
と,そのままだが,
「ダサい」は,
魅力が欠けているさま,
物事の外見や内容が洗練されていないさま,
身のこなしなどが洗練されていないさま,
時代遅れでかっこうが悪い,
味わい深さがないさま,
容姿などが洗練されておらず見劣りするさま
能力や風貌が劣っているさま ,
でそれぞれ挙げている。「ダサい」が,語源は別として,その風貌(つまりは状態,外観の表現)だけではなく,内実,センス,魅力などを評する言葉(つまりは,価値の表現)へと拡散していった,ということなのだろう。しかし,「ダサい」としいう評は,それしか評するべき言葉を持たない,という意味で,かえって,おのれの「ダサ」さを顕在化させるように思える。その程度の言葉でしかものの見えない人に,「ダサい」などと言われたくないものである。
人は,持っている言葉によって見える世界が違う,
のだから。
「そそる」は,辞書(『広辞苑』)には,自動詞と他動詞が載る。それぞれ意味が違う。
前者は,そそりたつ,の「そそる」で,『古語辞典』では,
聳る,
と当てる。意味は,
高くそびえる,
心がうき立つ,
遊里をひやかして歩く,
早口そそり(早口言葉に同じ)をする,
とあり,後者は,
揺する,
心を浮き立たせる,
箕であおって(揺すって)えり分ける,
(感情・欲望などを)起こせる,煽る,
とあり,自動的か他動的か(つまり,他に作用を及ぼす目的語があるかどうか)とは,別に意味は重なる。
『大言海』も,両者を分け,前者を,
進み昇る,
心浮き立ち,進む,浮かれ騒ぐ,そぞろぐ,すずろぐ,そそめく,いすすく,ぞめく,
と載り,後者は,
揺り動かす,進み上げる,心浮き立たする,
ぞめく,冷やかす,
と載る。
そぞろぐ,すずろぐ,そそめく,いすすく,ぞめく,
という言葉は,あまり聞きなれない。「そぞろぐ」を調べると,「すずろぐ」に同じとある。「すずろぐ」は,
「ススは,進むの語幹,ロクは,同様の義,進むに通ず,かびろぐ,同趣」
とある。で,
心すずろに進む,気進む,そぞろぐ,そそく,そそる,
と載る。すずろ歩き(漫歩),つまり,
どことも当てなく歩くこと,
つまり「そぞろ歩き」,散歩である。しかし,「ぞめく」は,「そめく」の転で,「そめく」は,「さめく」の転。「そめく」は,
「サは,颯(さ)と吹く風,サと笑う,などのサ」
とあり,さっと吹く風の意の他に,
さざと流れる,
さざめく,騒がしく音たつ(濁りて,ざめく,転じて,ぞめく,)
とある。で,「ぞめき」は,
騒き,
とあて,
ぞめくこと,そそること,サワギ遊び歩くこと,さざめくこと,ざんざめくこと,
ひやかし,素見,
とある。どうやら,二系統で,
漫然と歩くこと,あるいは歩き騒ぐこと,
と,
心を浮き立たせること,
の意味が重なって,ひやかし,につながったものらしい,と推測される。
『古語辞典』は,「そそり」で載るが,ひとつは,「聳り」と当て,
「丈高いさまの意のソソロカと同根」
として,
高くそびえたつ,
高くする,
とし(「そそろか」は,背丈がすらりとして高いさまの意),いまひとつの「そそり」は,
「ソソは,そそき(噪)・ソソノカシ(唆)のソソと同根。そわそわ,せかせか,ざわざわさせる意。また人の気持ち・興味などを掻き立てる意」
として,
さらいあつめる,
箕で穀物・茶などをあおってえり分ける,
あおる,そそのかす,
浮かれ騒ぐ,
遊里をひやかして歩く,
と載る。どうも,「聳る」と「そそる」は別系統なのではないか。しかし,語源は,「そそる」は,
「高く上がる」
で,山がそそり立つの,ソソルとする。気持ち,気分が高く上がる,つまり,「起こさせる」のソソルも同源,という。
『古語辞典』を信ずるなら,本来,別系統だった「そそる」が,心が浮き立つと山が立つと,アナロジカルに重なって,混ざり合ってしまったようだ。本来そこにはなかったようにみえる,
ぞめく,
という騒ぎ立つ含意は,もともとの「そそる」に含まれていたものが,ちょっとニュアンスを変えて際だったと推測される。それにしても,言葉は生きているが,そもそも担っていた意味を,外れることなく,外延を広げ,深度をふかめて,続く,というのは面白い。それによって,「そそる」という言葉に陰翳を与えている。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
「そそぐ」は,
注ぐ(灌ぐ),
と当てるのと,
雪ぐ(濯ぐ)
と当てるのと意味が違う。ただ,いずれも,共通して「灌ぐ」の字も当てるところに,何か意味がありそうだ。
「注ぐ」は,室町時代までは,「そそく」だったらしいが,
水が激しく流れる,
雨または雪が降る(降りかかる),
名もだがしきりに落ちる,
流れ入る,流れ込む,
風が吹きいる,
まき散らす,流しかける,
注ぎ込む,
もっぱらその方向へ向ける,
等々といった意味になり,「雪ぐ」だと,「すすぐ」に同じとあり,「すすく」は,
漱ぐ,
濯ぐ,
雪ぐ,
洒ぐ,
滌ぐ,
と当てて,
水で洗い清める,
口をゆすぐ(漱ぐ),
穢れを清める,
汚名を晴らす(雪ぐ),
といった意味になる。いずれも,水に関わる。語源を見ると,
「雪ぐ」は,「すすぐ」とも訓ませ,
「『ソソ・スス(擬音)+ぐ』です。水で洗い清める,汚名をソソグ,ススグに雪の文字を使うのは,中国語の訓読みから来たもの」
とする。
「注ぐ」は,つぐ,さす,とも言い,
「『ソソ(水を注ぐ擬音)」+ぐ』です。水などを流しかける意です。流れ入れるソソグ,光がソソグ,も同源です。ツグは,継ぐと同源です。液体が切れないようにツグで,注ぐを,ソソグとも,ツグとも,訓読するのは同源だからです。サスは,差すで,手を出して注ぐです。」
とある。ちなみに,「濯ぐ」は,
「『スス(擬音)+ぐ』です。水で洗い清める意です。ケガレ(汚れ),汚名をススグにも使います。中世はソソグが主流でした。関西ではいまでも,そそぐを使う人が多いようです。」
とある。『古語辞典』にも,
「ソソは,擬音語・擬態語。水の流れる音,かかる音,散る音など」
とあり,江戸時代初期から濁音化した,とある。
思うに,ソソもススも,水にまつわる擬音語・擬態語であり,それだけでは,
水が流れる
のか,
水がかかる,
のか,
水が散る,
のかさっぱり区別がつかない。それに漢字を当てることで,いつも感じることながら,その意味が格段に広がった。「そそぐ」が,
水を流す,
水で清める,
含意をもつことから,から,「そそぐ(すすぐ)」が「雪ぐ」になったのは,わかりやすい。
それにしても,昨今,「やばい」「わわいい」ですべてを済まそうという傾向は,いってみると貧弱な和語への先祖がえりに見える。また,元の貧弱な言語系に落ちぶれていくのであろうか。それは,貧弱な視界になる,ということに等しい。
人は持っている言葉によって見える世界が変る,
いわば,貧相な言葉は,貧相な世界しかもて(見え)ないことになる。
さて,その意味で,漢字を当たっておく。
「注」は,
「水+主(灯火)」で,燃えている灯火に水を掛ける,が語源。」
で,「濯」は,
「翟(テキ)は,『羽+隹(とり)』の会意文字で,キジが尾羽を高く抜き立てたさま。濯はそれを音符とし,水を加えた字で,水中に付けたものをさっと抜きあげて洗うこと」
とある。「漱」の字は,
「欶は,せかせかと動かす意。漱はそれを音符とし,水を加えた字で,せかせかと口を動かす動作から,口で嗽をする意となる。」
とある。「洒」の字は,
「西は,めのあらいざるを描いた象形文字。栖(ざるのような鳥の巣)にその原義が残る。ざるに水を入れるとさらさらと流れ去ってざるが後に残ることから,陽の光や昼間の容器が,ざるの目から抜けるように流れ去る方向,つまり「にし」を意味するようになった。ざるの間から細かく水が分散して出ていく,という含意から,洒は『水+音符西』で,さらさらと分散して水を流すこと」
とある。「滌」の字は,
「攸(ゆう)は,『人の背に細かく長く水をそそぎかけるさま+攴(動詞の記号)』の会意文字。條(=条)は細かく長い木の枝。滌は『水+音符條』で,細く長いの意味を含み,攸の原義を表す」
とある。「雪」の字は,
「もと『雨+彗(すすきなどの穂で作ったほうき,はく)』の会意文字で,万物を掃き清めるゆき」
の意とある。因みに,「雪辱」は,
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/se/setsujyoku.html
によると,
「『辱』は『辱められる(はずかしめられる)』を意味し、『雪』は『雪ぐ(そそぐ)』『すすぐ』『洗い 清める』を意味する。
そこから、恥をそそぐことを意味するようになり、前回負けた相手に 勝ち、受けた恥をそそぐことを『雪辱する』『雪辱を果たす」と言うようになった。』
とある。 擬態語には,ここまでの含意はない。漢字さまさまで,それをないがしろにする気風に,未来はない。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
御の字は,辞書(『広辞苑』)には,
最上のもの,
ありがたい,しめたなどの意,
とあり,少なくとも,最上のものというより,
ありがたい,
程度のニュアンス,あるいは,
「ないよりまし」
とか,
「余沢」
というニュアンスで使うことが多い気がする。
『大言海』には,
「尊称の連体詞なる御を,名詞に用いたるもの。キチガヒをきの字などと云ふ類」
とある。で,
「容姿の好きを褒めて云ふ語」
と簡潔である。『古語辞典』には,
「『御』という文字」
という説明があり,「貴人の名のただ代わりに御の字ばかり書くべし」
との用例が載る。その他に,「特に,遊里の太夫をいう」とも載る。
『デジタル大辞泉』
http://dictionary.goo.ne.jp/jn/34706/meaning/m0u/
には,
「江戸初期の遊里語から出た語。『御』の字を付けて呼ぶべきほどのもの、の意から」
とあるので,本来は,
非常に結構なこと,望んだことがかなって十分満足できること,
最上のもの,
というニュアンスを,「御」という字に込めたものと思える。
「御大(おんたい)や御身(おんみ)など、『御』という字は特に優れたものの頭につく最上級の尊敬語。『御』という字をつけたくなるほどの尊いもの」
という意味の説明もあった。語源的にも,
「御の字をつけたいほどありがたいの意」
ということになる。『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/o/onnoji.html
でも,
「 御の字の『御』は尊敬の意を表したり、名詞の頭に付けて丁寧に言うときに用いる。 その『御』の字を付けたくなるほどありがたいという意味で、『御の字』
という言葉が生まれた。 もとは遊里から出た言葉で、江戸時代初期から見られる。」
とある。しかし,『デジタル大辞泉』は,補足として,
「文化庁が発表した平成20年度「国語に関する世論調査」では、『70点取れれば御の字だ』を、本来の意味とされる『大いにありがたい』で使う人が38.5パーセント、本来の意味ではない『一応、納得できる』で使う人が51.4パーセントという逆転した結果が出ている。」
とある。「そこそこ」「まずまず」といった意味合いで使う,ということだろうか。
「そこそこ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba2.htm#%E3%81%9D%E3%81%93%E3%81%9D%E3%81%93)
で書いたように,
ぎりぎりセーフ,
という含意だし,「まずまず」も,
どうにかこうにか,
といった含意である。そんなニュアンスで使っているというのである。つまり,
「『御の字』という言葉に、100点満点中の60点くらいの合格点というイメージを持つ人」
が多いということである。辛うじて合格点,ABC評価で,Dランク,Fにならない,不可にならないというニュアンスである。たしかに,正確に言えば,
「大いに有り難く、非常に満足である」
が正しくて,
「満足というほどではないが、納得できるレベル」
というのは不正確だというわけである。たとえば,
「どの程度を満足と思うかは人それぞれですが、たとえば60点を目標として臨んだテストで70点であれば満足のいく結果だったと言えるでしょう。この場合は自分の想像以上の結果が出ていますので『とても有り難いなあ、御の字だよ』という表現を用いることができます。一方、70点くらいは取れると思っていたテストで、60点しか取ることができなかった。60点が合格点だとしても、取り組んできた勉強に対して本人は不本意な結果であったと感じるのではないでしょうか。『それでも合格したのだから、まあいいか。御の字だね』と表現してしまうと、これは誤りになります。」
という文章もあった。しかし,言葉は生き物。意味の変った言葉は,多い,というかほとんど。今後,意味がそっちへシフトしていくはずだ。それを正否でただすのは,言葉のもつ意味が分かっていないと言われても仕方あるまい。
「大工調べ」という落語に
「あのな一両二分と八百の所へ八百もってってグズグズ言おうてんじゃねえんだ。一両二分、親方の方を持って行くんじゃねえか。八百ばかりはおんの字だい」
という啖呵を切るところがあるそうだ。
「大家に店賃(たなちん)のかたに道具箱をとられてしまって仕事ができないという与太郎に、大工の棟梁が店賃の一両二分八百のうち持ち合わせの一両二分を渡して払わせようとすると、大家は八百足りないからと道具箱を返そうとしない。大家のあまりにも因業な態度に棟梁は腹を立て、大家にぽんぽんと威勢よく罵詈(ばり)雑言を浴びせるという場面」
でのことで,「極めて満足なこと」という意味で使われている。しかしいま,
「いちおう、納得できる」で使う人
が51.4%という逆転した結果が出ているということは,いま,意味が変った,ということだ。そういう言葉の意味が変る,そのティッピングポイントに立ち会っていると思えば,面白いではないか。
参考文献;
平成20年度の「国語に関する世論調査」
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/h20/
まずまず,
というときは,
まあ,満足いく,
というニュアンスであろうか。
辞書(『広辞苑』)には,
先ず先ず,
と当て,
何はさておき,
どうやら,まあまあ,
という意味が載る。「まず」の語源は,
「軽い感動のマア」
で,
何とマア,
マア何より,
マア何よりも先に,
まず初めに,
このような過程で,「マズ(先ず)」が成立した,とする。
「先ず(先づ)」は,『古語辞典』には,
まっさきに,第一に,
他のことよりも先に,とりあえず,
(否定の表現を伴って)どうにもこうにも,いっこうに,
といった意味が載る。『大言海』は,
「前に通ず」
と注記して,
先に,かねて,先立ちて,
しばらく,まあ,とりあえず,
と出る。たとえば,
「先ずは,一献」
とか,
「先ずは,ビール」
という使い方に鑑みると,
さしあたり,
とか,
当座,
といった場つなぎの含意がある。
語源から考えると,
まあまあ,
と,ほぼ重なるのかもしれない。まあまあは,しかし,辞書(『広辞苑』)には,
かなりの程度に,
まずまず,
あるいは,
(相手をなだめるときなどに)さしあたりこの場は,しばらくは,ともかく,
という意味がある。
そう考えると,
まずまず,
も
まあまあ,
も,
とりあえずの合格点,
十分ではないがある水準は超えた,
完全ではないが一応許容できる,
という含意で,そこには,
今のところは,これでいいが,将来は,これではだめ,
という意味合いが含まれている気がする。しかし,
まあまあだな,
と言われるのと,
まずまずだな,
と言われるのと,言われた側の印象はどうだろう。どうも,個人的には,
まずまず,
の方が,高い評価に聞こえる。まあまあには,
君の実力からみると,
という含意があり,まずまずには,
これからの期待を込めて,
という含意があるように感じる。それは,「先ず」の「先」の字のイメージからくるのかもしれない。
「先」は,
「足+人の形」
で,跣(はだしの足先)の原字。足先は,人体の先端に当たるので,先後の先の意となった,とある。そうみると,「まずまず」には,
その人のなかでは,いい方,
というニュアンスも含まれているかもしれない。
そこそこ,まあまあ,まずまず,の比較は,「そこそこ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba2.htm#%E3%81%9D%E3%81%93%E3%81%9D%E3%81%93)
で触れたので,それと一部重複するかもしれない。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
阿魔
と書くと事々しいが,よく,
「このあま,」
と,映画やドラマで,女性を罵倒する時に使う。もちろん,僕は,女性にそんな言葉を使ったことはない(ないはず,ないと思う,ないような気がする)が。
手持ちの辞書には出ていない。俗語らしい。
『隠語大辞典』
http://www.weblio.jp/content/%E9%98%BF%E9%AD%94
によると,
女ノ事ヲ云フ。〔第六類 人身之部・北海道庁〕
女性を詈る語。尼の意、男性の坊主に対す
女を罵つていふ詞。
〔俗〕女中のこと。主として在支、在日外人間に使はれてゐる。
〔俗〕女を罵つていふ言葉。「あまつこ」と同じ。
女人夫。
印度語から出た語、女を罵つて云ふ語、又在支、在日の外人等が女中を云ふ
とある。これが正しいかどうかはわからないが,これからに見るかぎり,あきらかに差別語だが,
「ばかチ〇ンカメラ」
などと,平然と使ったりするのと同様,これが明らかな差別語であることを意識していない人の方が多いのではないか。
「チ〇〇コロ」
などという,蔑視の言葉と類同である。こういう言葉を平然と使うようになったのは,維新後の近代日本以降であると思っている。西洋と並んだと自惚れ,アジア諸国に対し優越感を持ち,「名誉白人」などと言われて喜んで,南アの黒人差別に加担していた日本人の気質と重なるような気がする。
阿魔
の語源はわからないが,『日本語語感の辞典』には,
「女性を卑しめて言う古い俗語。特に,若い女性に対して用いることが多い。…男性版の『野郎』と違って親しみをこめて用いる例はほとんどない。海にもぐる『海女』ではなく,仏に仕える『尼』の系統の語というが,読経をするような殊勝な女とは無縁なので,『阿魔』という感じを使って区別する例が多かった。もはや女性に対しておおっぴらに言える時代ではないので,近年はめったに使われない。」
とある。「尼」は,
「尼の語源は、サンスクリット語の「善良な女性」を意味するambaaの俗語形の音写ではないか」
等々といわれ,母の意ともあるが,他の辞書には出ていないがけれど,『大言海』の「尼」の項を見ると,
「女の義。梵語に,僧を比丘と云ひ,女僧を比丘尼(女僧)と云ふ。これを尼(に)とのみにも云ふ。…此尼に女の意なる阿摩をあてたるなり(善女,信女)。康煕字典『尼,女僧也,釋典有比丘尼』敏達紀,十三年九月,『令度,司馬達等女島曰善信似尼』とあり,是れ,我が邦の女僧の始なり。或は,翻訳名義集に,『阿摩,此云母』とあり,女の僧となるは,多く,老女なれば,母の義に取りて,尊称したるが,普通の女僧の称となれるなるべしと云ふ説もあり,今,沖縄にて,下層民の母をあま,又あんまと云う」
との注記がある。しかし,ここでいう「阿摩」と「阿魔」は同じであろうか。
「阿摩」と書くとと,「阿摩羅識(あまらしき)」のことを指し,阿摩羅識については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%91%A9%E7%BE%85%E8%AD%98
に詳しい。
「天台宗では、阿摩羅識をけがれが無い無垢識・清浄識、また真如である真我、如来蔵、心王であるとし、すべての現象はこの阿摩羅識から生れると位置づけた。」
とあるから,この「阿摩」が「「阿魔」になったというのはどうかと思うが,逆に,だから,「摩」を「魔」に変えたのだとも邪推できなくもない。
とちあま,
ということばがあるらしく,
とち阿魔,
とあてる。意味は,
ばかな女。女性をののしるときに用いる。
とある。この場合も,阿魔である。
「阿」の字は,もともとは,「阿諛」のように阿る意味もあるが,
阿兄(あけい)
とか
阿母(あぼ)
といった親しみの気持ちを表して人を呼ぶ言葉につく,接頭語,でもある。
「魔」の字は,
「麻は,摩擦してもみとるあさ。擦ってしびれさせるという意を含む。魔は『鬼+音符麻(しびれさす)』あるいは梵語の音訳字か」
とあってはっきりしない。「摩」の字は,
「麻は,すりもんで線維をとるあさ。摩は『手+音符麻』で,手で擦り揉むこと」
とある。
ただ,「摩」の字はそのまますること,磨くことといった意味だが,「魔」は,まものとか,怪しい術といった意味になる(ただ,人の善事を妨げる欲界第六天の王,転じて悟りの妨げとなる煩悩には,魔羅とも摩羅とも当てるらしいが)。
『大言海』を信ずるなら,ほんらい,「阿摩羅識」の「阿摩」で,女性,それも,けがれのないというニュアンスであったものが,悪罵の表現として使われるとき,「阿魔」に変った,と見るのが,できる推測だが,どうだろうか。
参考文献;
中村明『日本語語感の辞典』(岩波書店)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
「あほ」は,
阿呆
とも
阿房
とも,
あてる。
辞書(『広辞苑』)には,
愚かであるさま,またそのような人,
とあるが,『日葡辞典』にも,
「アハウヲイウ」
とあるらしく,中世末期には既にあったらしい。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/a/ahou.html
には,
「あほ. 【意味】 あほとは、愚かなさまや行動、愚かな人。馬鹿と同じ意味で、人を罵る言葉 であるが、関西方面では、馬鹿よりも軽い意味や親しみをこめて使われる。
【語源・由来】.
あほの語源は、秦の始皇帝が異常に大きな宮殿『阿房宮』を建てたことからとする説が多い。この説にも,二通りの話があり,『阿房宮』は項羽に焼かれたが,あきれるほど馬鹿でかく,全焼するのに3ヵ月もかかったことから,馬鹿げたことを『阿房』というようになり,『あほ』と呼ぶようになったとする説と,大きな宮殿を建てたが,財政が困難になり,国が滅びてしまったことからとする説がある。しかし,『阿房』の表記はこの語源から充てられたとする見方が強く,当て字とされている。その他,『おこがましい』の語源となる『をこ』が変化して,『あほう』になったとする説で,『馬鹿』の語源説のなかにも『をこ』の音韻変化とする説があり,共通はしているが,共に苦しい音変化である。あほの有力な説として,中国江南地方で,『おばかさん』を意味する方言『阿房(アータイ)』を禅僧が伝え,日本語読みで『あはう』となり『あほう』になったとする説がある。ただしこの説も文献上に出てくるものではなく,この方言によって『阿房』という漢字が充てられたとも考えられ,阿呆の正確な語源は未詳である。また,あほうを,『アホ』や『あほ』と,『う』を省略するようになったのは近世以降のことである。」
とあるが,「あほ」の語源については,「アホ・バカ分布図」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%AB%E5%88%86%E5%B8%83%E5%9B%B3)
で触れた。そこで,「あほ(う)」である。語源には,他にも,
五山の禅僧が阿呆(アータイ)の漢語をアハウと読んだという説
関西方言の「アア,ホウカ」の音韻変化した説,応答が「アア,ホウカ(ケ)」としか言えないことを揶揄している。
始皇帝の阿房宮(項羽に妬かれたが,あきれたほど馬鹿でかく全焼するのに三か月かかった)説。
等々があるようだが,はっきりしていない。ただ,『大言海』は,
「元来,あわう,若しくは,あばうなるべし。あわは,狼狽(あわ)つの語幹(狼狽(あわ)を食ふ)あわ坊の約。小狼狽(あわて)を擬人化したる語。とちめんぼう,同趣なり。新竹斎物語に『くだらぬ理窟,あわう口』,続松の葉に『恥を知らぬは,あほう坊』,またあわわの三太郎などもあり,但馬にて,あはあ,駿河にて,あっぱあと云ふ。あわて者は,まぬけ者なり。常に阿房と書くは,秦の始皇帝の阿房宮を,当字にするなり。あほは,約(つづめ)て云ふなり(山椒(さんしょお)をさんしょ,愛相(あいそう)をあいそがつきる)。」
と書き,さすがにその見識を示している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%91%86
によると,「阿呆(あほう、あほ)」は,
「日本語で愚かであることを指摘する罵倒語、侮蔑語、俗語。近畿地方を中心とした地域でみられる表現で、関東地方などの『馬鹿』、愛知県などの『タワケ』に相当する。」
とある。また,「をこ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E3%82%92%E3%81%93%EF%BC%88%E3%81%8A%E3%81%93%EF%BC%89)
でも触れた。
「あほ(う)」は,阿房とも当てるが,阿呆とも当てる。「阿」の字は,
阿兄(アケイ),
阿母(アボ),
等々と,親しみの気持ちを表して人を呼ぶ言葉につく接頭語。
「魏・晋からのち,多く使用された。もと,江南地方の方言」
とある。「呆」の字は,
「子(こども)+∪印(おむつ)」
で,
「幼児をおむつで包んだ姿。何も知らない幼児と同様にぼんやりしている者の意に転じる褓(おむつ)の原字。」
とある。「房」の字は,
「『方』とは,両側に柄の張り出た犂を描いた象形文字。『房』は,『戸(いえ)+音符方』で,おもやの両側に張り出た小部屋のこと。」
とある。そう考えると,「阿房」の当て字は,阿房宮になぞらえてこじつけで,どうせ当てるなら,
阿呆,
がふさわしく,そこには,
「ばかの大足,小足のあほう,ちょうどいい加減がくそだわけ」
というときの,ばかに比べると,どこか,親しみがこもっているように思える(関西圏では違うらしいが)。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
火車とは,
かしゃ,
と訓むが,宮部みゆきの小説のタイトルのことではない。
火車とは,辞書(『広辞苑』)によると,
火が燃えている車。生前に悪事をした亡者を乗せて地獄に運ぶという,
という意味である。その他に,火車には,
火車婆の略,
中国語における蒸気機関車もしくは列車のこと,
太古中国で火薬の発明から発展して作られたといわれるロケット兵器,
葬送の時にわかに風雨が起こって棺を着とばすこと,
といった意味もある。最後のそれは,ここで言おうとしている,いわゆる「火車」と関係がある。『大言海』に,「くわしぁ」として,
「仏説に,生前に悪事をせし亡者,地獄に堕ちむとする時,これを迎ふる車なりと云ふ」
の意味の他に,
「葬送の時,俄かに風雨起こりて,棺を吹き飛ばすことあるを,くわしぁと云ふ。妖ありて,屍を取らむとするにて,即ち,地獄の火車の,迎へに来たりしなりとて,大いに恐れ恥ずことなりと云ふ。」
とある。火車婆も,
(来世は火車に乗せられて地獄に落ちるからという)悪心の老婆,おにばば,
を指し,まあ,(地獄に堕ちそうな業突く張りという)悪口である。
「火の車」と訓むと,当然,「火車」の意味もあり,
(火車の訓読)地獄にあるといわれる火の燃えている車,獄卒が罪ある死者を乗せて地獄に送る,
という意味もあるが,
生計の極めて苦しいすこと,
という,よく知っている意味になる。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/hi/hinokuruma.html
には,火の車(ひのくるま)について,
「火の車は,仏教語『火車(かしゃ)』の訓読みした語。火車は火の燃え盛った車で、極卒の 鬼が生前に悪行を働いた者を乗せて地獄へ運び、責め苦しめるといわれる。
火の車に乗せられた者は、ひどい苦しみを味わうことから、苦しい経済状態を表すようになった。また苦に満ちた世界(娑婆)を,火事にあった家に喩えた仏教語『火宅』と関連づけられ,火の車が家計が苦しいことを意味するようになったともいわれる。」
とある。火車については,
http://dic.pixiv.net/a/%E7%81%AB%E8%BB%8A
に詳しいが,火車と火の車について,
「前者は、僧侶が仏教の死生観を民衆にわかりやすく伝えるために生まれた法話『地獄縁起』(じごくえんぎ)に源を発しており、『生前に重い罪を犯した亡者が地獄へ送られる際に押し込められる獄卒が曳く獄炎の車』という本来の意味が時代と共に『悪人の魂を地獄に送る死神』へ形を変えたものである。
なお、貧窮に喘ぐ様子を表す例えの1つ『火の車』はこの獄炎の曳車が語源であり、車に入れられた亡者が地獄に着くまで業火に焼かれながら責められ続ける苦況を余裕の無い台所事情に置き換えたものである。また、別説によると『火車は死んだ悪人を、火の車は生きたままの悪人を地獄へ連れ去る別個の存在である』とされている。
後者は、人間の死没との因果関係について怖れを抱く日本特有の怨霊信仰と密接に結び付いた慣習から生まれた民話に源を発しており、『悪人が死ぬと葬列を襲って死体を奪い去り、五臓を引きずり出して食い荒らす』という悪鬼の類として描かれている。」
と,懇切である。堤氏は,
「源信『往生要集』によれば,人はこの世での善行悪行の報いにより,死して極楽に迎えられる者もあれば,地獄に堕ちてさまざまな責め苦を受ける者もる。そのありさまを眼前に見るがごとくに具象化した六道絵,十王図などの仏教絵画が平安・中世から江戸期を通して数多く製作され,絵解きに用いられたり,寺院本堂の余間に懸けられたりして俗徒の信仰心を喚起した。また,近世には『往生要集』の絵入版本が量産されることによって,冥府の具体的な様相を大衆の心象に根付かせることになった。」
と言い,その地獄絵の一隅に,しばしば描かれたのが,
「牛頭馬頭の鬼卒の引く火の車であり,堕獄した亡者が乗せられ身を焼かれてられる…。さらに悪行ある者は命おわるとき必ず火車が飛来して冥苦の世界に連れ去る」
図なのであり,そのイメージか強かったのではないか,説く。それは,仏法の因果応報を解きつつ,一方で布教のため,高僧の法力を示す場として,時に,渡辺綱のような,妖怪退治の話として,語られることになる。
前者の例としては,
「(益子の鶏足寺を開いた)天海禅師は大罪人の葬儀を敢えて引き受け,自分の舌根を血みどろの戦いにより亡者の遺骸を火車妖鬼から守りぬいた」
という法力咄があり,後者の例としては,
「武勇の誉れ高い松平五左衛門近政という侍……(は)友人の妻が死に,野辺送りに参列した折のこと,葬列が村はずれにさしかかったところで突然空が暗くなり,雷電風雨とともに一群の黒雲が棺桶を目指して襲いかかる。見ると妖鬼が雲中から手を出して遺体を奪おうとしているではないか。人々の屍をつかみさる『火車』の怪事とは,まさにこのことであった。人々は恐れ逃げまどうが,抜刀奮戦する近政の活躍で,片手を斬り落とされた妖鬼は,黒毛を生じた三本爪の腕を残して退散する。」
という。
昨今,火車の妖鬼はない。火の車も,言葉としていつの間にか,あまり使われなくなった。しかし,悪行がなくなったのでも,貧困がなくなったのでもない。どうやら,見て見ぬふりをしているだけだ。というか,おのれの内しか見ていない。だから,現実のおのれのことも,他人のことも,見ようとしていない。それは,おのれが地獄に堕ちても気づかぬということだ。そういう恐れすら消えてしまったのかもしれない。それは,人間としての劣化ではないだろうか。
参考文献;
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
http://dic.pixiv.net/a/%E7%81%AB%E8%BB%8A
http://www.youkaiwiki.com/entry/2013/01/20/%E7%81%AB%E8%BB%8A(%E3%81%8B%E3%81%97%E3%82%83)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E8%BB%8A_(%E5%A6%96%E6%80%AA)
娑婆は,
しゃば,
とも
さば,
とも訓む。辞書(『広辞苑』)には,
「梵語sahā,忍土,忍界と訳す。」
と注記して,
苦しみが多く,忍耐すべき世界の意。人間が現実に住んでいるこの世界。釈迦牟尼が強化する,
自由を束縛されている軍隊,牢獄または遊郭などに対して,外の自由な世界,俗世間,
とある。しかし,これでは,実はよく意味が分からない。『古語辞典』では,
「釈迦出現のこの世界,または釈迦の教化がおよぶ世界」
とあり,ただの俗世をいうわけではない。
『生活の中の仏教用語』には,
http://www.otani.ac.jp/yomu_page/b_yougo/nab3mq000001r30o.html
「『サハー』には、その意味を表す『忍土(にんど)』という意訳語もある。忍土とは、『苦しみを耐え忍ぶ場所』という意味である。そのあまりに露骨で身も蓋もない意味が人々に嫌われたのであろうか、こちらの方はあまり使われてこなかった。いずれにしても、私たちが生活しているこの世の中は、本質的に苦しみを耐え忍ぶ場所であるというのが、仏教の世界観なのである。(中略)
『娑婆』には、もう一つの意味がある。それは、ブッダ釈尊が人間を教化する場所という意味である。つまり、私たちの苦しみに満ちた生活の中に、苦しみを生み出す根元を教えて、与えられた生活を肯く生き方を教えようというのである。眼前の苦しみは、そのよって来たる所を明らかに知って、人間であることを完成していくための糸口であると言うのである。』
と書いている。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/si/syaba.html
は,
「娑婆は仏教から出た言葉で、『忍耐』を意味するサンスクリット語『saha』の音写。
この世は内に煩悩があり、外は苦しみを耐え忍ばなければならない俗世であることから『忍土』と漢訳され、自由のない世界は『娑婆世界』や『娑界』と呼ばれた。
そこから、江戸時代の遊郭では吉原を『極楽』に見立てて,吉原の外を『娑婆』と言うようになった。しかし拘束されている女郎達の立場からすれば,『娑婆(吉原の外)』は自由な世界にあたるため,本来の意味とは正反対の意味として使われるようになった。」
ウィキペディアも,
「江戸時代になり、吉原などの遊郭では、金さえ出せば身分に関係なく、自由に心ゆくまで遊べるということから、遊郭を『浄土』に見立て、郭(くるわ)の外の世界を娑婆と呼んだ。しかし一方、『籠の鳥』になっている遊女の視点から見ると、郭の中は地獄で、外の世界である『娑婆』こそ、自由に過ごせる人間的な世界である。この『遊女の視点』の意味合いのほうがだんだん一般的になっていき、軍隊や刑務所、隔離病棟などの拘束を受ける場所と外の世界を対比して、自由に過ごせる外の世界という肯定的な意味合いで娑婆と表現するようになった。」
とあり,確かに,娑婆は苦の世界というよりは,俗世そのものの意味に変っている。
『日本語俗語辞典』
http://zokugo-dict.com/12si/syaba.htm
では,
「娑婆とは、刑務所にいる人からみた外の自由な世界。」
と言い切っている。
「娑婆とは仏法では人が生きる世界を指し、世界四苦八苦の苦しみに耐える自由のない世界としている。しかし、俗語的に娑婆は刑務所に入っている人にとっての外の自由な世界を意味する。これは江戸時代、遊郭を娑婆に対する極楽安堵の地と例えていたが、遊郭で働く女郎からは『娑婆(外の世界)こそ自由の世界』になるためで、意味は逆だがどちらも人が普通に暮らす世界をさす意味では変わっていない。
俗語的意味で娑婆がよく聞かれるのはドラマなどの出所シーンにおける『シャバの空気はうめえ』というセリフで,また、日常生活でも合宿中の生徒や新入社員、人里離れた地で勤務する人など自由のきかない生活をしている人が『早くシャバに戻りたい』といった形で使用する。」
とあるが,昨今は,そんな大仰に言い方をする人は減ったのではないか。下手をすると,通じない。しかし,娑婆がらみの言葉は多い。
娑婆以来は,
「久しぶりに会ったときに使うあいさつの語」
という意味には違いないが,正確には,
「江戸時代,遊郭内で知人に会ったときの挨拶の言葉」
という前提がある。
娑婆気は,「しゃばき」「しゃばけ」と訓むが,促音化した,
娑婆っ気,
の方が,なじみがある。
現世に執着する心。世俗的な名誉や利益を求める心,
という意味だが,そんなに重くはないニュアンスではないか。
娑婆で見た弥三郎は,
「知っている人なのに、知らないふりをすること。弥三郎は、弥次郎・弥十郎などともいう。」
とも言う。いずれも,江戸時代の言い回しだが,昨今は,廃れた。
娑婆塞ぎ(しゃばふさぎ,しゃばふさげ)となると,
生きているというだけで、なんの役にも立たないこと。また、その人,
という意味だが,。完全に死語になっている。その言葉で見える世界がなくなったのだということだろう。それは,この世界が,苦しみでなくなった,自由になったという意味なら,いいのだが,ただそれが見えなく(気づかなく)なったのだとすれば,最悪である。
参考文献;
http://www.otani.ac.jp/yomu_page/b_yougo/nab3mq000001r30o.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%91%E5%A9%86
のだいこは,
野太鼓
とか
野幇間
とあてる。例の夏目漱石『坊っちゃん』の,赤シャツにくっついていた画学の先生の仇名についていたのが,
野だいこ,
どある。
無芸な幇間(ほうかん)を卑しめていう語,
らしいが,辞書(『広辞苑』)には,
内職に幇間(たいこもち)をする者,素人の幇間,転じて芸もなく,ただ客の座をとりもつだけの幇間を卑しんでいう称,
とある。幇間の「幇」は,
助けるの意,
と,辞書(『広辞苑』)にある。
「客の宴席に侍し,座を取り持つなどして遊興を助ける男」
のことだが,男芸者,太古持ち,とも言う。語源は,
「太鼓をうまくたたいて調子を取る」
の意で,転じて,人の機嫌を取る者の意で用いる,とある。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ho/houkan.html
では,
「幇間の『幇』は、助けるの意味、『間』は人と人の間、つまり人間関係のことで、『幇間』は
客と客、客と芸者の間を助ける、酒宴の雰囲気が途切れた際に興を助けるという意味となる。 幇間の俗称が『太鼓持ち』であることから、『幇間』と書いて『たいこ』や『
たいこもち』と呼ぶこともある。また,正式の師匠につかず,見よう見まねで行うものは『野幇間』という。」
とある。しかし,『大言海』をみると,
太鼓持,
の字を当て,
「六斎念仏の鉦持太鼓持より起こりて,金持ちに陪する意なりと云ふ」
とある。そして,
「吉原にて客人に従い一座の取持ち伽になるを業とするもの。をとこげいしゃ(男芸者)の異名。」
とあり,こう追加してある。
「太鼓持に対して,放蕩者を鉦打と云ひたり。芸なくして伽となるを,野太鼓と云ふ。…金を持つ者は太鼓を持たず。」
因みに,六斎念仏(ろくさいねんぶつ)は,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E6%96%8E%E5%BF%B5%E4%BB%8F
に詳しいが,
「古く六斎日に行われた念仏であるとされる。」
もので,六斎日(ろくさいび)とは,
「仏教の思想に基づく斎日のひとつ。この斎日は1ヶ月のうち8日・14日・15日・23日・29日・30日の6日で、前半の3日と後半の3日に分け、それぞれの3日を三斎日と称した。
六斎日の歴史は古く、律令制における令にもこの日は殺生を禁じる規定があり、出家したものは布薩説戒を行い、在家のものは八斎戒を守ることとなっていた。」
とある。これに起因しているらしいが,まあ,幇間は,昔の大人の遊びにセットだ。
落語に『鰻の幇間』というのがある。
「夏の盛りの真っ昼間。野だいこの一八は、知り合いの姐さんたちのところを回って食事にありつこうとするがみんな留守。焦った彼は、通りかかった『どこかで見たような男』を取り巻いて、必死で昼飯にありつこうとする。首尾よく(汚い)鰻屋に連れて行ってもらうが、この男、とんでもなくしたたかな性格で、のらりくらりと探りをかわし、一八を残して食い逃げする。その上お土産を二人前(話によっては十人前)も持って帰っていたために、一八は全部自腹を切らされてしまう。おまけに、芸人自慢の下駄までもっていかれていた」
という噺だが,相手にたかろうとする一八に,確か「ダニみたいだ」と言われても食い下がった挙句の,やらずぶったくられた顛末である。まさに,野幇間である。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
http://white1.seatears66.com/6_4.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E6%96%8E%E5%BF%B5%E4%BB%8F
伽は,
とぎ
と訓むが,辞書(『広辞苑』)には,
相手をつとめること,つれづれを慰めること,
夜のつれづれなど,そばにいて話の相手をすること,またそのひと,
寝所にはべること,またその人,
看病すること,またそのひと,
御伽衆,
とある。「伽」の字は,本来は,
「梵語のガの音を音訳するために作られた字」
で,伽藍とか伽羅に使われる。「トギ」に「伽」を当て,退屈を慰める意に用いるのは,我が国だけのことらしい。
この「伽」に「お」をつけるのも,別に項目としてあり,似ているが,
お相手をすること,特に戦国・江戸時代,主君のそばにいて話し相手をつとめること,また,その人,
寝室に侍ること,またその人,
「おとぎばなし」の略,
とある。どちらかというと,いまは,寝室云々の方の意味が強いが,相手をすること,ということが本来の意味なのだろう。『古語辞典』には,
「トギは,相手をする意の動詞トギの名詞形」
とある。従って,「おとしばなし」は,
御伽話
あるいは
御伽噺
と書く。いまや,桃太郎やかちかち山のように,
子供にきかせる昔話や童話,
の意となっているが,本来は,
伽の際に人のつれづれを慰めるために語りあう話,
であり,織豊期の秀吉や秀次などの大名の,
御伽衆,
というのは,
室町時代以降,主君に近侍して話し相手を務めた役,
を指す。別名,
御咄衆,
御迦衆,
相伴衆,
談判衆,
とも呼ばれる。あるいは,
話伽,
咄の衆,
という言い方もある。秀吉の御伽衆には,一説には800人とも言われ,
曾呂利新左衛門,
織田有楽斎,
足利義昭,
織田信雄,
佐々成政,
千利休,
今井宗薫,
大村由己,
古田織部,
金森長近,
等々,それに,信長に謀反し,家臣,家族を見捨てて(ために一族皆殺しになった)有岡城を脱出した荒木村重も,確か御伽衆に加わっていたと記憶する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%BC%BD%E8%A1%86
には,
「戦国時代は参謀としての側面が強く、僧侶や隠居して第一線から退いた重臣、没落した大名、武将が僧形となり務めることが多かった。戦乱の世が治まってからは、主君の無聊を慰める役割も重視され、豊臣秀吉の頃には勃興した新勢力である町人らも召し出され新たな文化の担い手となった。江戸時代以降も将軍や諸大名は御伽衆を召し抱えたが、政治の実権が重臣に移るにつれ、次第に勢力は衰えた。」
とある。だから,単に,
「退屈をなぐさめるために話し相手をすること」
というわけでもない。因みに,「はなし」(話・咄・噺)は,
「放す(心の中を放出する)」
が語源。
「物語とか,物をカタルとかのカタル(語)が,ダマス(騙・瞞)に使われるようになってきたので,近世になってハナスに,漢字の『話』を当てて生まれた語」
と説明がある。漢字の「話」は,
「舌(カツ)は,舌(ゼツ)とは別の字で,もと丸くえぐる刃物の形(厥刀[けっとう]という)の下に口印を添えた字で,口に丸くゆとりをあけて,勢いよくものを言うこと。話は『言+音符舌(かつ)』で,すらすらと勢いづいてはなすこと」
と,説明がある。物語の意味もあり,この字を当てた人の見識が伺える。
因みに,「咄」は,
「突然,沈黙を破って舌打ちする擬声語」
で,昔話や小話に当てたのにはどんな意味があったのか。さらに,「噺」は,
「口+新」
で,耳新しい噺の意を込めた日本製の漢字。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%BC%BD%E8%A1%86
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
「うぶめ」と聞いてすぐに,ピント来る人は少ないだろう。よほどの妖怪通である。
産女,
あるいは,
姑獲鳥,
と当て,
うぶめどり,
と訓む場合も,
姑獲鳥,
と当てる。
「うぶめ」は,辞書(『広辞苑』)には,
産褥にある女,
(「姑獲鳥」と書く)出産のため死んだ女がなるという想像上の鳥,または幽霊。その声は,子供の鳴声に似,夜中に飛行して子供を害するという。うぶめどり,うぐめ,
と,その意味を載せる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%A5%B3
には,
「産女、姑獲鳥(うぶめ)は日本の妊婦の妖怪である。憂婦女鳥とも表記する。死んだ妊婦をそのまま埋葬すると、『産女』になるという概念は古くから存在し、多くの地方で子供が産まれないまま妊婦が産褥で死亡した際は、腹を裂いて胎児を取り出し、母親に抱かせたり負わせたりして葬るべきと伝えられている。胎児を取り出せない場合には、人形を添えて棺に入れる地方もある。」
とある。出産が,今でもそうだが,難事だったことを窺わせる。産女は,
http://www.candychild.com/fantasy/u/
によると,
「赤子を抱いて現れる。下半身は血まみれで、子供を抱いてくれと頼む。抱いていると、赤子はだんだん重くなり、地面に下ろそうと思っても、身動きができない状態になる。その重さに耐えることができれば、彼女は成仏することができるという。抱いていた赤子が、木の葉に変わっていたという話もある。姑獲鳥(うぶめどり)は青鷺に似た鳥のような生き物で、青白い炎に包まれて空を飛ぶ。地上に降りると、産女になるとされる。」
とあるが,
http://www.zb.em-net.ne.jp/~kiokunomori/html/mukashi/kaisetsu/ubume.html
によると,
「産女とは、産死した女の霊が化した化物(妖怪・幽霊)の事をいいます。産女の登場する話は沢山の種類がありますが多くは、晩方に道の畔(川の畔など)に現れ、通る人に赤子を抱いてくれと
頼むというものです。そしてその先の話は三種に分かれます。
第一は、名僧の法力によって母子の亡魂が救われるというもので、『和漢三才図会』『新編鎌倉志』などの産女塔の由来譚による
と、昔この寺の第五世日棟上人が、ある夜妙本寺の祖師堂へ詣る道すがら、夷堂橋の脇から産女の幽霊が現れるのに出会った。
冥途の苦難を免れたいと乞うので回向すると、一包の金を捧げて消えたというものです。
第二は、抱いた赤子が次第に重く腕がぬけるほどになり、それに耐えると金銀をくれるというもので、上総山式郡大和村法光寺の
宝物『産の玉』の由来として説かれている話のごときものです。
昔、寺の日行という上人が、道の途中で女が憔悴した赤子を抱いているのに出会い、頼みに応じて抱き取ってやると、
重さは石のようで、冷たさは氷のようであった。上人はさわがずにお経をよんでいると、女はお陰で救われたと礼を言い、 礼物として安産の玉をくれたと伝えられています。
そして第三は、授かった礼物が金品ではなく大力(怪力)であるというものです。
島原半島に伝わる話の一つに、ある女が産女の子を預かって大力を授けられ、後代々の女の子にそれが 伝わったという例があります。」
とある。ところが,姑獲鳥を,
こかくちょう,
と訓むと,中国の別の妖怪になる。これが,日本に伝わって,混同されたものとされている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%91%E7%8D%B2%E9%B3%A5
によると,姑獲鳥(こかくちょう)は,
「中国の伝承上の鳥。西晋代の博物誌『玄中記』、明代の本草書『本草綱目』などの古書に記述があり、日本でも江戸時代の百科事典『和漢三才図会』に記述されている」
「『夜行遊女』『天帝少女』『乳母鳥』『鬼鳥』ともいう。鬼神の一種であって、よく人間の生命を奪うとある。夜間に飛行して幼児を害する怪鳥で、鳴く声は幼児のよう。中国の荊州に多く棲息し、毛を着ると鳥に変身し、毛を脱ぐと女性の姿になるという。他人の子供を奪って自分の子とする習性があり、子供や夜干しされた子供の着物を発見すると血で印をつける。付けられた子供はたちまち魂を奪われ、ひきつけの一種である無辜疳(むこかん)という病気になるという。」
とある。そして,
「江戸時代初頭の日本では、日本の伝承上の妖怪『産女』が中国の妖怪である姑獲鳥と同一視され、『姑獲鳥』と書いて『うぶめ』と読むようになったが、これは産婦にまつわる伝承において、産女が姑獲鳥と混同され、同一視されたためと見られている」
らしいが,「鳴く声は幼児のよう」というから,確かに紛らわしい。
これが,遠い昔のことかというと,
「1984年(昭和59年)5月15日の午前7時25分、静岡市(現・静岡市葵区)産女(うぶめ)の県道で女性が運転する乗用車が集団登校中の児童の行列に突っ込み、児童数人を跳ね飛ばしてガードレールに激突した。加害者の証言によると、三つ辻の道路の左側に変な老婆が立っており、避けようとして事故になったと答えた。だがこの事故を目撃した児童はオートバイを追い越そうとして事故になったと証言し、老婆のことには言及していない。その土地は古来から産女新田と呼ばれていて、地名の由来は江戸時代に牧野喜藤兵衛という漂泊の者の妻が妊娠中に死に、その霊が何度も現れたため、その怨念を鎮めるため村人が産女明神として祀ったという縁起である。」
という例が載る。
そのことを信じる,というかそういう文化的文脈の中にある人にしか見えないものなのだろう。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%A5%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%91%E7%8D%B2%E9%B3%A5
http://www.zb.em-net.ne.jp/~kiokunomori/html/mukashi/kaisetsu/ubume.html
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
けちという意味の,「六日知らず」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E5%85%AD%E6%97%A5%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A)につ
いては触れたが,けちには,「ドけち」の「けち」以外に,
けちがつく,
の「けち」がある。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ke/kechi.html
は,「けち」を,
「金品を惜しがってださないこと。卑しいこと。またその人」
とし,その語源を,
「ケチは、『けちをつける』『けちがつく』の語源と同じく、不吉なことを 意味する『怪事(けじ)』が訛って『ケチ』になった。 江戸時代以降、ケチは『粗末で貧弱な
さま』『いやしい』などの意味を持つようになり、現在の意味に転じていった。 」
とする。しかし,「けちくさい」の「けち」は,「六日知らず」で書いたように,
囲碁用語の「結」「闕」(けち),
が語源で,
「終盤で,一目,一目半とつめる」
から来ている。「けちる」という動詞も,ここから来ている。
「結(けち)」は,呉音で,
「囲碁で,終局に近づき,駄目を詰めて寄せること,またその目」
とあり,「闕」(けち)とも当てる。そこから,賭け弓で勝負を決めること,に意味が広がっている。囲碁をやらぬものにはわかりにくいが,『大言海』には,
「碁を打ち終ふるを,結局と云ふ,結なり,弓に云ふも,勝負の最後の決定の意なるべし」
として,こう説明する。
「囲碁の終はりがたに,隅々などの,決まらぬ目を詰め寄すること。これをケチをさすと云ふ。今,よせと云ふ,是なり。ケチを先手にさすを,結鼻(けちばな)をとると云ふ。先手にさせば,一目づつの得となるなり」
とし,さらに,
「今,駄目をさすをケチさすと云ふは,闕の音にて,闕(欠)目すなはち,駄目なり」
とある。「けちがつく」の「けち」は,語源が,『語源由来辞典』が言うのに似て,
「ケシ(怪し)(怪事)」
で,不吉,ないし,縁起が悪い,という意味になる。語源的にも,
「怪チ・恠チ(縁起が悪い,不吉)」
で,
縁起が悪くなるようなことを言う
欠点を挙げてけなす,
という意とする。『古語辞典』も,
「ケシ(怪事)の転か」
とあり,
不吉事,不吉な兆し,縁起が悪いこと,
とあるが,同時に,
しわいこと,
そまつ,貧弱,
ばからしいこと,つまらないこと,
と意味が並ぶ。「怪事」と「闕・結」と,由来が違うのに,「けち」で,意味が重なったのだろうか。『大言海』は,「闕」「結」「怪事」と,「けち」を,それぞれ別の項を立てている。「怪事」の「けち」については,
「倭訓栞けち『アヤシキ事ニ云フハ,恠事(かいじ)ノ音転也』(屐子(けいし),けいち。皀角子(さいかし),さいかち。うるしね,うるち。弟子,丁稚。私(わたし),わっち。)」
とあり,
怪しきこと,不吉,
といった意味と並んで,
怪事(けち)を恐るるよりして,臆病,卑怯,
転じて,吝(しわ)いこと,けちんばう,
とあり,吝嗇の意味と重なっていることがわかる。辞書(『広辞苑』)で,「けち」をひくと,「結」「闕」とは別に,「けち」として,
縁起が悪いこと,不吉の前兆,
不敬気,金品を必要以上に惜しむこと,
ある語に付けて,いまいましい意を表す。「けちふとい二才野郎じゃ」。
と載る。「けし」を見ると,『古語辞典』には,
異し,
怪し,
と当てて,
「ケ(異)の形容詞形平安女流文学では,『けしうはあらず』『けしからず』など否定形で使うことが多い」
として,
いつもと違う,ふだんと違って宜しくない,別人に愛情をもつ,病気が悪いなどの場合に使う,
劣っている,悪い,
下手である,
不美人だ,
非常である,甚だしい,
(連用形「けしう」の形で副詞的に)ひどく,
と意味が載る。こう見ると,億説だが,「怪し」は,普通と違うことを示す。それが,
吝い,
に転じていくのが,普通の人の視線では,わかる気がするが,(普通と思っている)自分と違うものを貶める,というのは,今も昔も,自己完結した世界観の反映でしかなく,島国的な,差別の始まりである。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
「月がこうこうと輝く」という場合,
煌々
と
耿々
と
皓々
と,
どちらがいいのか,と迷った。
「煌々」は,「晃々」とも当てるようだが,辞書(『広辞苑』)には,
きらきらひかるさま,ひかりかがやくさま,
という意味が載る。
「耿々」は,辞書(『広辞苑』)には,
光の明るいさま,ひらきらとひかるさま,
という意味と,
心を安んぜぬさま,うれえるさま,思うことがあって,忘れられないさま,
という意味がある。「耿々」は,「煌々」に比べて,陰翳がある,という含意であろうか。
「皓々」は,「皎々」とも当てるが,辞書(『広辞苑』)には,
白いさま,潔白なさま,
月のひかりなどの明るいさま,
むなしく広いさま,
という意味で,「月こうこうとして」は,「皓々」を当てる,ということなのだろう。似た意味で,
浩々,
というのがあるが,これは,辞書(『広辞苑』)によると,
(書経)水の広々と広がっているさま,
(中庸)こうだいなさま,
とあり,「皓々」の広さの「むなしさ」の含意はないようだ。
http://www.weblio.jp/content/
http://hyogen.info/word
等々によると,「耿々」は,
明かりが耿々とついている
耿々として眠れない
という使い方をする。「煌々」は,
煌々たる星の輝き
電球が煌々と輝く
と言った使い方になる。「皓々」は,
皓々たる白壁,
皓々冽々たる空霊の気
皓々たる月
と言った使い方となる。『大言海』は,
「皓々」を,「白く光りてある状,又潔く白き状を云ふ語」
「耿々」を,「光かがやく状に云ふ語。気澄みて寝られぬ状に云ふ語」
とのみ,区別する。
この区別は,漢字に当たるしかない。
「煌」の字は,
「皇は,『自(はな)+音符王』からなり,偉大な鼻祖(開祖)のこと。大きく広がる意を含む。煌は『火+音符皇』で,光が大きく広がること」
と説明され,輝く意だが,「光が大きく司法に広がる」という意味になる。
「晃」の字は,「晄」とも書く。
「光は『火+人』の会意文字で。晃は,『日+音符光』で,光が四方に輝くこと」
と説明され,光るという意で,「光が四方に広がり出る,またそのさま」という意味で,「煌」とほぼ重なる。
「耿」の字は,
「会意文字。『耳+火』。もと,耳から光が出るほど叩く意。転じて,ちかちかと火花が光ること」
と説明され,「ちいさくぽっとあかるいさま」「目の奥がちかちかして不安なさま」という意味をもつ。これは,伝統の明かりに使うのにふさわしい。
「皓」の字は,
「もとは,『日+音符告(こく)』の形声文字で,日が出て空が白むさまをあらわす。皓は,『日』を白に変えたもの」
と説明され,「白く輝くさま」という意味になり,語源は別として,やはり,月について,
月出でて皓たり,
と使う。白く輝くのは,やはり月だろう。
「皎」の字は,やはり,白く輝くさま,清らかなさま,という意味になる。「皓」と同じように,
月出でて皎たり,
とも使うようなので,「皓」と「皎」の字は代替されるようだ。
日本語に当てると,同じ訓みになってしまうが,中国語では,発音が明らかに違うのだろうと,想像しながら,漢字を入れた我が国祖先の苦労がしのばれる。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
「こんな晩」
とは,殺されたモノの怨霊が死後数年たって殺したものの子供に憑りうつるという因縁咄風の民談で,昔話として伝わるが,
六部殺し,
と重なることが多い。それは江戸の戯作にも引き継がれ,堤邦彦氏は,
こんな晩型説話,
と呼ぶ。たとえば,こんな話だ(山東京伝『安積沼後日仇討』)。
「高野参詣の旅僧を嵐に紛れて斬り殺して金を奪った過去をもつ大日九郎,いまは与九郎と名を変えて女房との間に男児をもうけている。ある雷雨の夜,四歳になるまで言葉を発しなかった息子が,父親に抱かれながら,『とと様,旅の僧を殺した晩はこんな晩であったのふ』とつぶやく。」
典型的な,「こんな晩」だが,多くは,,
怨魂の転生した子供が放蕩,犯罪などの乱行を繰り返して親の財産や親の命までおびやかして破滅に至らしめる,
という内容になる。夏目漱石の「夢十夜」にも,
「昔、或る満月の晩、一夜を頼んだ六部を,夫婦は金を目当てに殺した。数年後、夫婦の間に一人の男の子が生れた。ところが、いつまで経っても息子が口を利けない。そんな或る日、男がもう寝ようとしているところへ息子が来て、
『おっとお、おらおしっこへいきてえ』
と言った。今まで一言も喋らなかった自分の息子が、とうとう話したのである。男は嬉しくて、息子を負ぶって外にある雪隠へと連れて行った。丸い月の綺麗な夜だった。雪隠まで歩く男の背中には、先程生れて初めて喋った自分の息子がいる。男が未だ尽きぬ笑顔の儘に、満月を見上げると、
『・・・こんな晩だったなあ』
再び息子が喋った。
『お前が俺を殺したのも、丁度こんな晩だったなあ』」
と,似た話がある。六部と僧の違いだけである。
「
六部」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E5%85%AD%E9%83%A8)について触れたときに,
六部殺し(ろくぶごろし)についても書いた。
「日本各地に伝わる民話・怪談の一つ。ある農家が旅の六部を殺して金品を奪い、それを元手にして財を成したが、生まれた子供が六部の生まれ変わりでかつての犯行を断罪する、というのが基本的な流れである。最後の子供のセリフから、『こんな晩』とも呼ばれる。」
とある。この話には,大体こんな感じらしい。
「ある村の貧しい百姓家に六部がやって来て一夜の宿を請う。その家の夫婦は親切に六部を迎え入れ、もてなした。その夜、六部の荷物の中に大金の路銀が入っているのを目撃した百姓は、どうしてもその金が欲しくてたまらなくなる。そして、とうとう六部を謀殺して亡骸を処分し、金を奪った。
その後、百姓は奪った金を元手に商売を始める。田畑を担保に取って高利貸しをする等、何らかの方法で急速に裕福になる。夫婦の間に子供も生まれた。ところが、生まれた子供はいくつになっても口が利けなかった。そんなある日、夜中に子供が目を覚まし、むずがっていた。小便がしたいのかと思った父親は便所へ連れて行く。きれいな月夜、もしくは月の出ない晩、あるいは雨降りの夜など、ちょうどかつて六部を殺した時と同じような天候だった。すると突然、子供が初めて口を開き、『お前に殺されたのもこんな晩だったな』と言ってあの六部の顔つきに変わっていた。」
これも書いたことだが,六部とは,六十六部が正式で,
「法華経を66回書写して、一部ずつを66か所の霊場に納めて歩いた巡礼者。室町時代に始まるという。また、江戸時代に、仏像を入れた厨子(ずし)を背負って鉦(かね)や鈴を鳴らして米銭を請い歩いた者。」
を指す。略して,六部(ろくぶ)と呼ぶ。辞書(『広辞苑』)には,六十六部について,
「廻国巡礼の一つ。書写した法華経を全国66ヵ所の霊場に一部ずつ納める目的で,諸国の社寺を遍歴する行脚僧。鎌倉末期にはじまる。江戸時代には俗人も行い,鼠木綿の着物を着て鉦を叩き,鈴を振り,あるいは厨子を負い,家ごとに銭を乞いて歩いた。」
「こんな晩」型の話は,落語の『もう半分』につながっていく気がする。『もう半分』は,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%82%E3%81%86%E5%8D%8A%E5%88%86
に,
「夫婦で営む江戸の居酒屋に、馴染みの棒手振り八百屋の老爺の客がやって来た。老爺は,いつものように『もう半分』『もう半分』と,半杯ずつ何度も注文してちびちびと飲み、金包みを置き忘れて帰って行った。夫婦が中を確かめると、貧しい身なりに不釣合いな大金が入っている。しばらくすると老爺が慌てて引き返し、娘を売って作った大事な金だから返してくれと泣きついた。しかし、夫婦は知らぬ存ぜぬを通して追い出した。老爺は川へ身投げして死んだ。その後、奪った金を元手に店は繁盛し、夫婦には子供も生まれた。だが、子供は生まれながらに老爺のような不気味な顔で、しかも何かに怯えたように乳母が次々と辞めていく。不審に思った亭主が確かめると、子供は夜中に起き出して行灯の油を舐めている。『おのれ迷ったか!』と亭主が声を掛けると、子供は振り返って油皿を差し出し『もう半分』」
と,概略が載る。因縁話はほぼ重なる。
おおく殺されるのが,僧であったり,六部であるところから,この咄自体が,
「仏者の立場から提唱されたのではないか」
と想定される。
「経文の説く不偸盗・戒殺の教えに背く罪深い行為として民衆教化の法席に語られたはずである。」
とされるのも,唐由来の仏教説話や勧化本にしるされた僧殺し,もしくは僧物奪取の悪報譚から来ているらしいこととも関係があるのだろう。堤氏は,
「噺のルーツをさかのぼれば,中国の鬼索債譚(金を貸した者の死霊が不返済の借り主の子に転生して家財を食いつぶす)に行きあたる」
と。しかし,それが,説話から,江戸時代の戯作,漱石へと沁みとおっているのは,
「説話環境として,『こんな晩』の伝承世界に対する民衆の共通理解が不可欠である…。非道に命を奪われた者の再生を因果応報の当然の結果として捉える共同幻想の素地がなければ,この話の怪談としての生命力は半減してしまうのではないか。」
と,堤氏は言う。さてしかし,今日,因果応報は,生きているのであろうか,我々のこころに。
参考文献;
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
小説というのは,
「英: fiction(総称)、novel(長編)、story(短編)、仏:
roman(長編)、nouvelle(中編)、conte(短編))とは、文学の形式の一つである。小説とは、散文で作成された虚構の物語として定義される。
内容では、随筆、評論、伝記、史書などと対立するものであり、形式としては詩や戯曲と対立するものである。」
というのが定義だが,そもそも,「小説」という言葉が,日本語ではない。で,辞書(『広辞苑』)をみると,
「漢書(芸文志)『小説家者流,蓋出於稗官,街談巷語,道聴塗説者之所造也』」
とあって,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
とある。それを前提に,明治期,坪内逍遥が,
novel
の訳語として,当てた。稗史とは,
「昔、中国で稗官(はいかん)が民間から集めて記録した小説風の歴史書。また、正史に対して、民間の歴史書。転じて、作り物語。転じて,広く,小説。」
を言う。語源を見ると,こうある。
「中国の『稗史』からでたものです。『小(とるに足りぬ)+説(議論)』が語源です。市井の出来事や話題を,書き記したものです。」
ウィキペディアは,
「小説という言葉は、君主が国家や政治に対する志を書いた大説や、君主の命などを受けて編纂された国史に分類される伝統的な物語や説話に対して、個人が持つ哲学的概念や人生観などの主張を、一般大衆により具体的に分かりやすく表現して示す、小編の言説という意味を持たされて、坪内逍遙らによって作られて定着していったものとも言われている。」
と要領よくまとめている。そのせいか,『大言海』には,「小説」は載らない。
日本語では,
物語
咄(囃)
という言葉があったが,両者の違いを,近世の俳人高田幸佐は,例話を挙げて区別しているそうだ。
「首を斬られた盗人が自分の首を懐に入れて逃げ去った話」
は,「世に噂にもまことしからぬ儀」は,「咄とこそいうなれ」と定義する。一方,
「朱雀院の御宇に起きた平将門の乱の折,将門の獄門首が歯がみをなして声をあげた怪異談」
は,「出書正しき物語」の典型としている。堤邦彦氏は,
「ここにいう『物語』とは,史実と認められる出来事や,原拠の明らかな故事をもとに創り出された話」
を指す。従って,
「それらは時・人・所を明示しえる内容でなければならない」
ということになる。逆に言うと,それを明示して見せることで,「噂」ではないかのごとく見せることができる。
辞書(『広辞苑』)に,「物語」を,
「作者の見聞または想像を基礎とし,人物・事件について叙述した散文の文学作品。狭義には平安時代から室町時代までのものをいう。大別して伝奇物語・写実物語または歌物語・歴史物語・説話物語・軍記物語・擬古物語などの種類があり,『日記』と称するものの中にはこれと区別しがたいものもある。」
と,説明する。「物語」は,
「モノガタル(世間話をする)の名詞化」
が語源とされ,語り伝えたこと,世間話,を言うとある。要は,
「特定の事柄の一部始終を語ること、あるいは古くから語り伝えられた話をすること」
ということになる。あくまで,事実らしさ,という現実のへその緒抜きでは,噺も物語も受け入れられなかったのかもしれない。
それが,仮名草子や浮世草子等々に繋がり,江戸の戯作へと,「物語」自体が,独立した世界として成立していく鍵は,なんだったのだろう,と想像する。
怪異譚
が,
怪奇物語,
になっていくのは,その世界自体を,楽しむ精神が必要だ。
怪談噺の名手,三遊亭円朝は,
「幽霊など神経病による妄想に過ぎない」
と,自嘲しつつ,怪談を語り続けた姿勢は,江戸文化の残照を固守した,
「戯作者魂の発露」(堤邦彦)
というところに,物語のもつ力を,確信するマインドを見る。自分がそれを怖れている人には,それは,現実の話なのであって,物語にはならない。
小説は,原義は,稗史であったが,いまや,この言葉は,
別の視界を開いている,
つまり,現実とのへその緒を断って,小説は,ノベルになっている,ということだろう。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%AA%AC
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
悶着は,
悶著
あるいは
捫着
あるいは
捫著
とも当てる。「もんじゃく」とも訓む。辞書(『広辞苑』)には,
乱れもつれること,もめごと,
かかりあうこと,関係のたえないこと,
という意味が載る。『デジタル大辞泉』には,
感情や意見の食い違いから起こるもめごと。いさかい,
好ましくないものとかかわり合うこと,
と載る。こちらの方が,意味のニュアンスというか,陰翳がある。中世末期の『日葡辞典』には,
「モンヂャク,モミツク,即ち,モノヲイロイロニトリアツカウ」
とあるらしい。語源は,
「悶(もだえ苦しむ)+着(接尾語 著しい)」
とあり,
心のもだえる争い,もめごと,
となる。たんなる「いさかい」ではなく,心をもみくちゃにされるようないさかい,というニュアンスであろうか。
『由来・語源辞典』
http://yain.jp/i/%E6%82%B6%E7%9D%80
は,
「考えなどが合わず。物事がもつれてもめること。多くは『一悶着』の形で使われる。」
として,『語源由来辞典』を,
「『悶』は気がふさぐこと、『着』はくっついて離れない
の意で、中国では『悶着』は『不愉快な気分が続く』意を表す。それが日本では、『嫌な感じ』の意が、互いの感情のもつれや意見の食い違いから起こる争いやもめごとの意に意に転じた。」
として,「悶着」の含意が,はっきりする。
「悶」の字は,
「門とは,入口を閉じる門,塞ぐ意を含む。悶は『心+音符門』で,胸が塞がって外へ発散せず,むかむかすること」
とある。悶々とか苦悶という使い方を見ると,その含意はわかる。漢和辞典(『字源』)を見る限り(「悶著」の字を当てていたが),「揉めて争う」という意味が載る。
「捫」の字は,
「門は,綴じて中を隠す,隠れた物を探る意を含む。『捫』は,『手+音符門』で,手探りすること」
とある。どうも,「捫」からは,「悶」の意は出ない。謂れはわからないが,漢和辞典(『字源』)によると,「悶着」に,「捫着(著)」と当てる表現は,我が国だけの使い方のようだ。
「着」の字は,
「著(ちゃく,ちょ)」が本字,
とある。で,
「『艸(くさ)かんむり+音符者(つまる,集まる)』で,ひとところにくっつくこと。着は俗字」
とある。「著」の字を調べると,
「者は,柴をもやして,火熱をひとところに集中するさま。著は,『艸+音符者』で,ひとところにくっつくの意を含む。箸(ちょ 物をくっつけてもつはし)の原字。チャクの音の場合は,俗字の着で代用する。」
とあり,さらに,
「著はのちに,著者の著の意味に専用され,チャクの意に使うときは,着を使うようになった」
とある。因みに,「者」の字に当たると,
「者は,柴がこんろの上で燃えているさまを描いたもの(象形文字)で,煮(火力を集中して煮る)の原字。ただ古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ,諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を,『~するそれ』ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また,転じて『~するそのもの』の意となる。唐・宋代には『者箇(これ)』をまた『適箇』『遮箇』とも書き,近世には適の草書を誤って,『這箇』と書くようになった」
とある。
それにしても,悶着に,
悶著,
と当てる時,我が背国の先人は,「著」と「着」の関係を熟知していたことになる。いつもながら,先人の中国語理解の深さに感嘆する。
こう見ると,悶着は,
いさかい,
いざこざ,
よりは,
葛藤,
確執,
という言葉が,近い気がする。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
「がらんどう」は,
伽藍堂
と,当てるケースもあるが,本来別ではないか。辞書(『広辞苑』)には,
がらんどう,
は,中に人や物が何もないこと,
という意味であり,
伽藍堂,
は,
寺院の中で,伽藍神を祀ってある堂,
とある。因みに,伽藍とは,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%BD%E8%97%8D
によると,
「伽藍は、僧侶が集まり修行する清浄な場所の意味であり、後には寺院または寺院の主要建物群を意味するようになった。サンスクリット語のsaṁghārāma (सँघाराम)
の音写で、『僧伽藍摩(そうぎゃらんま)』『僧伽藍』が略されて『伽藍』と言われた。漢訳の場合は『衆園(しゅおん)』『僧園(そうおん)』などと訳された例があるが、通常『伽藍』とのみ呼ばれる。」
それが,後に,
寺院の建築物の称,
に広がって使われるようになった。宗派によって異なるが,
「伽藍を構成する主な建物として、俗世間との境界を示す山門、本尊を祀る本堂、仏塔、学習の場である講堂、僧の住居である庫裏、食堂(じきどう)、鐘楼、東司などがある。」
ということになる。伽藍神(がらんじん)は,
「寺院を守護する神。護伽藍神(ごがらんじん)・守護伽藍神・寺神ともいう。」
で,伽藍神を祀る堂を伽藍堂という,ということになる。
「通例『伽藍神』といえば、禅宗寺院の仏殿等に祀られる、道教神の姿をした像をいう。日本では、この種の像は中国宋代仏教の影響を受け、鎌倉時代中頃から制作・安置されるようになった。」
とあり,
「高野山の四社明神,延暦寺の山王七社,興福寺の春日神社などが著名」
と。「がらんどう」の語源については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%89%E3%82%93%E3%81%A9%E3%81%86
では,
「もともと伽藍神を祭る『伽藍堂』が語源といわれる。『伽藍堂のように何も無い』部屋などといわれた事から、そのように言われるようになった。」
とするし,『日本語俗語辞典』
http://zokugo-dict.com/06ka/garandou.htm
も,
「がらんどうとは建物の中に人がおらず、物もあまりない閑散としたさまを表す。がらんどうとはもともと寺院にある伽藍堂のことである。寺院のお堂は広く、人もあまりいないことからきた言葉であり、本来は寺院のように広い建物に人や物がないさまを指したが、最近では狭い部屋であってもがらんどうと言う。(『がらんとしている』の『がらん』も伽藍堂からきたものである)またこれが転じ、財布の中に何も入っていない状態、つまり無一文のこともがらんどうという。」
を「がらんどう」「伽藍堂」をとる。手元の『日本語源広辞典』は,
「ガラン(空虚のカラの撥音化)+ドウ(空洞)」
としている。『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ka/garandou.html
は,
「がらんどうの語源には、寺院の中で伽藍神を祭ってある堂を『伽藍堂(がらんどう)』と いい、伽藍堂の中は何も無くて広々としていることからとする説がある。
また、『がらん』『 からん』『からっ』『からから』などの擬態語からや、『から(空・殻)』が転じたとする説もあり、がらんどうの語源は未詳である。」
と,未詳とする。『大言海』は,「がらんと」と「がらんどう」を別項を立て,
「がらんと」は,
ガランは,空(から)の音便転」
とし,「がらんどう」は,
「がらんとの語を,伽藍堂と移して,寺堂の広きに寄せて云ふ語にもあらんか」
とする。たぶん,これが正解だろう。がらんと広い感覚を,伽藍堂に当てはめることで,視覚的イメージが鮮明になった。浄土宗の,
http://jodo.or.jp/knowledge/word/19.html
をみると,
「中に何も入っていなかったり、また、だれもいず、ガランとして広かったりするありさまに使う。広い建物、例えば講堂や体育館などは、人が使っていない時、とかくがらんどうの感じが強い。これに漢字を当てると『伽藍堂』となる。つまり、伽藍というのはお寺、堂は神仏を祀るとか、多くの人を入れるための建物のことをいう。殿堂、廟堂、公会堂その他、大きくて広く立派な建物のことは、とかく『堂』をつけ、『正々堂々』などのように、小細工のない、貫録があることを形容するにも使う。ここから、学問や技芸などが深奥に達するのを『堂に入る』というようになった。いずれにせよ、寺院というものは、古来から、広く大きい建築物で、ふだんはほとんど人気がなく、堂々と静かなたたずまいを誇ったものである。そこから『伽藍堂』という形容句が生まれたものであろう、と思われる。」
「がらんどう」に,「伽藍堂」の字を当てた効果が,こう言う文章,感覚を生む,といういい見本だ。言葉で視界が開くが,漢字のもつ視覚効果は格段に大きいと実感させられる。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
天狗は,
てんぐ,
と思いきや,
あまぎつね,
とも呼び,
流星(よばいぼし),
でもある,という。『日本書記』に,
「(欽明天皇の九年(637年)春二月)大きなる星東より西に流る。僧旻僧(ほふしみんほふし)曰へらく,流星(よばいぼし)に非ず,是は天狗(あまぎつね)なり。其の吠ゆる声雷に似たるのみと」
とある。阿部正路氏は,
「大きな音を立てて東から西へと流れる流星は,時の人たちにとって,地雷の音とみえたが,中国で学問をした旻は,根元にたちかえってそれはアマキツネ,すなわち天狗なのだと教えた」
と説明し,天狗が日本の文献に最初に現れたもの,という。これは,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8B%97
によると,
「元々天狗とは中国において凶事を知らせる流星を意味するものだった。大気圏を突入し、地表近くまで落下した火球(-3~-4等級以上の非常に明るい流星)はしばしば空中で爆発し、大音響を発する。この天体現象を咆哮を上げて天を駆け降りる犬の姿に見立てている。中国の『史記』をはじめ『漢書』『晋書』には天狗の記事が載せられている。天狗は天から地上へと災禍をもたらす凶星として恐れられた。」
という知識を,旻が持っていたということになる。
「今日、一般的に伝えられる、鼻が高く(長く)赤ら顔、山伏の装束に身を包み、一本歯の高下駄を履き、葉団扇を持って自在に空を飛び悪巧みをするといった性質は、中世以降に解釈されるようになったものである。」
とされているが,天狗は,今日では,例えば,辞書(『広辞苑』)には,
「深山に棲息するという想像上の怪物。人のかたちをし,顔赤く,鼻高く,翼があって神通力をもち,飛行自在で,羽団扇をもつという。」
それが,どういうわけか,高慢なこと,そういう人を指すように変る。それについて,
「天狗は、慢心の権化とされ、鼻が高いのはその象徴である。これから転じて『天狗になる』と言えば自慢が高じている様を表す。彼等は総じて教えたがり魔である。中世には、仏教の六道のほかに天狗道があり、仏道を学んでいるため地獄に堕ちず、邪法を扱うため極楽にも行けない無間(むげん)地獄と想定、解釈された。」
とある。
その形状は,
「天狗の形状姿は一定せず、多くは僧侶形で、時として童子姿や鬼形をとることもあった。また、空中を飛翔することから、鳶のイメージで捉えられることも多かった。」
「平安末期成立の『今昔物語集』には、空を駆け、人に憑く『鷹』と呼ばれる魔物や、顔は天狗、体は人間で、一対の羽を持つ魔物など、これらの天狗の説話が多く記載された。」
「『平家物語』では、『人にて人ならず、鳥にて鳥ならず、犬にて犬ならず、足手は人、かしらは犬、左右に羽根はえ、飛び歩くもの』」
等々様々,前記の阿部氏は,鳥は天狗の特質の一部であり,
「そのかたち鶴の如くで,色くろく,目はともしびのように光って羽ふるえ,鳴く声高いところの,新たなる屍の気変じた〈陰摩羅鬼(おんまらき)〉に近い。天狗の特質はあくまでも二本の足が確かで,一枚歯の足駄をはいているところにあるといえるだろう。天狗は人間でありながら他界にも現実にも徹することができず,しかも永遠に死ぬことができないことを怒っているものなのである。二本の確固とした足は他界に踏み込みながらなおこの世につれもどされている人間そのものを示し,一本の足駄の歯は,他界にも現実にも半ば足を踏みいれながら,常に,他界からも現実からも疎外され続けていることを意味する。」
と,その悲哀を書く。『古語辞典』を見ると,
中国で,古くは流星の一種,落下の際,音響を発するもの。天狗星
(山海経には「陰山に獣あり,其の状狸の如くして白首,名づけて天狗といふ」とある)空を自由に飛び回る想像上の山獣。後に,深山で宗教的生活を営む行者,特に山伏に擬せられ,大男で顔赤く,鼻高く,翼あって神通力を持つ者と考えられた。高慢なもの,または,この世に恨みを残して死んだ人がなるともいわれる,
と,経緯がわかりやすい。
天狗は,麒麟と同じく,想像上の獣だったものが,いつの間にやら,妖怪変化,怪物に変じてしまった。
『大言海』は,その経緯を順次あげていく。
流星の一種,天狗星と云ふもの(史記「天狗,状如大奔星有声,其下止地殻狗」),
一種の山獣なりと云ふ(山海経「其状如狸而白首,名曰天狗,其音如榴榴」),
(一種の魔物空中を飛行してじざいなるものと云ふ。魑魅魍魎,変化,こだま)後に図するところは,人の如くにして,両翼あり,手足の爪長く,頭巾を戴き,篠掛けを着て,金剛杖,太刀,羽団扇などを携帯し,一見修験者の装の如く,其の鼻突出したるを,大天狗と云ひ,又其の小さきを烏天狗,木の葉天狗などと云ひ,深山に棲むと云ふ。鞍馬山の僧正坊,愛宕山の太郎坊,比叡山の次郎坊,飯縄山の三郎,大山の伯耆坊,彦山の豊前坊,白峰の相模坊,大峯の前鬼など,大天狗なり。而して天狗を讃岐の金毘羅の使いとす」
と,想像が膨らんでいくさまが,可笑しい。
参考文献;
阿部正路『日本の妖怪たち』 (東書選書 )
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8B%97
つるは,
鶴
のことだが,和語で「つる」というのと「鶴」とは,同じなのだろうか。
落語に「つる」という噺がある。八五郎が,ご隠居に「鶴の謂れ」を聞く。
「昔は『首長鳥(くびながどり)』と呼んでいたが,鶴と言われるようになったのは,鶴が唐土(もろこし)から飛んで来た際、『雄が「つー」っと』、『雌が「るー」っと」飛んで来たために『つる』という名前になったと教えられる。それを外で吹聴しようとしたが,、『雄が「つるー」っと』と言ってしまったために困り果てる。
一旦ご隠居のところへ戻って再び教えてもらうが, 今度は『雄が「つー」っと来て「る」と止まった』と言ってしまったため、苦し紛れに『雌は黙って飛んで来た』と言う。」
まあ,これは根多だが,「つる」の語源は,
「連ル」
とされる。「連れだって飛来する鳥の意」で,鶴の古名は「タヅ」だが,これも,連れの意,とし,
「蔓を語源とし,蔓のように伸びた首だという説もありますが,疑問」
とする。『古語辞典』には,
「万葉集には,助動詞ツルという箇所に『鶴』の字を宛てた例があるから,当時ツルという語はあったと思われるが,歌の中ではすべてタヅと詠んで,ツルと詠んだ例はない。タヅが歌語であったからだとされている。古今集以後は,歌の中にもツルを用いるが,やはりタヅの方がずっと多く使われている。朝鮮語(turumi
鶴)と同源。」
とある。因みに,「タヅ」は,
田鶴,
とも
鶴,
とも,当てる。しかし『大言海』には,
「声を以て名とす。古今集注(顯昭)に,鶯,郭公,雁,鶴は我名をなくなりとあり。朝鮮語つり」
とあり,語源は鳴声らしい,と分かる。ここでも,「つる」という呼び名は,朝鮮語由来で,本来の和語は,
たづ,
らしいと推測できる。『大言海』は,やはり,
「鳴く声かと云ふ」
とする。朝鮮では,「つる」と聞こえ,われわれには,「たづ」と聞こえたということか。
「歌詞に多く用ゐらる。ツルよりは,古き語なるが如し。又,古へには,鵠(くくひ)をも,鶴(おほとり)をも云へり」
とある。辞書(『広辞苑』)にも,
「鳴声を写したもの」
とあるので,語源は,どうやら鳴声だが,
ツル
とも
タヅ
とも聞こえる,ものらしい,と思えるが,念のため,
蔓
の語源を調べると,
「ツ(連・銃)+ル」
で,二説あるらしい。
ひとつは,「他の植物に巻きつくもの(連ル)
いまひとつは,「長く連なったひとまとまりのもの(銃ル)
である。しかし,この語源説でいけば,「蔓」も「鶴」も,
「連ル」
で,同源となる。『大言海』は,「蔓」について,
「古言,ツラの転,連の意,朝鮮語つる」
とある。『古語辞典』は,
「ツラ(弦・蔓・列)・ツリ(釣)・ツレ(連)と同根」
とある。鳴声節よりは,「連ル」の方が,言葉的な意味がある気がする。
http://www.nihonjiten.com/data/45825.html
には,
「鶴。鳴声に由来する説、群れて飛ぶ様子から『連(ツラ)なる』からとする説、朝鮮語で鶴を指す『ツルミ』から転じた説、首が長いことから『ツツラ(蔓)』が転じた説などがある。なお、連なる様から『蔓』と『鶴』は同語源ともされる。漢字表記『鶴』の音符「隺(カク)」は、高く至るの意で、鶴が天まで至るように高く飛ぶ様を表したとされる。」
とある。で「鶴」の字を調べると,
「隺(カク)は,鳥が高く飛ぶこと,ツルそれを音符とし,鳥を加えた字。確(堅くて白い石)と同系なので,むしろ白い鳥と解するのがよろしい」
とある。そうしてみると,中国人の見る「鶴」と,朝鮮人の見る「つる」と,古代の和人の見る「タヅ」は,同じだったのだろうか。
因みに,「蔓」の字は,
「艸+音符曼(おおいかぶさってのびる)」
「弦」の字は,
「玄は,『幺+‐印』で,幺(細い糸)の先端がわずかに一線の上にのぞいて,よくみえないさまで,糸の細いこと。弦は,『弓+音符玄』で,弓の細いいと。のちに楽器につけた細いいとは,絃とも書いた。
「釣」の字は,
「『金+音符勺(液体のなかの一部を高く取り上げる)』で,水の中の魚を金ばりでつって,高く水面上に抜き出すこと」
とある。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
きつね,
は,
狐,
と書く。辞書(『広辞苑』)には,
「日本では人をだますとされ,ずるい物の象徴とされてきたが,稲荷神の使いでもある。」
とある。そのせいか,そのメタファから,
たくみに人をだます,
とか
(男を誑かすところから)娼妓を罵って言う語,
という意味で使われる,らしい。しかし,日本最古の説話集『日本国現報善悪霊異記』には,
「欽明天皇(540-571年)の御代に美濃の国大野の出の男と結婚した女が子供までもうけるが,実は野干(きつね)であって,その家の犬に吠えたてられて籬(まがき)の上にのがれていたのを,その夫が,やさしく『汝と我との中に子供生まる。故に,吾忘れじ。毎(つね)に来たりて相寝よ』と招きよせ,それに従ったので,以来,〈來つ寝〉(きつね)と呼ぶようになった…。」
という話が載る。語源を見ると,
「キツ・クツ(鳴き声)+ネ(接尾語 犬inu>nu>ne)」
とある。『大言海』には,
「本名キツ,またクツにて(キツの條を見よ),ネは意なく添えたる語(羽(は)ね,杵(き)ね,眉(まゆ)ね)。又,或は,稲荷の神の使いとして,尊称のネを添えたるか」
とある。で,「きつ」の項を見ると,
「又,クツと云ふ。共に鳴く声を名とせしならむ。其の声,コウコウとも云ひ,狂言記に釣狐を,吼噦(こんくわい)と云ひ,クワイクワイと云ひ,今コンコン」
とあり,鳴き声が語源のようだ。きつねは,古名,
きつ,
くつ,
別名,
いがたうめ,たうめ,野干(やかん),たうか,けつね,
と,『大言海』は書く。
『由来・語源辞典』
http://yain.jp/i/%E7%8B%90
によると,
「語源は諸説あり、その一つは、『きつ』は鳴き声から、『ね』は接尾語的に添えられたものとされる。また、『き』は『臭』、『つ』は助詞、『ね』は『ゑぬ(犬)』が転じたもので、臭い犬の意とする説、『きつね(黄猫)』の意とする説、体が黄色いことから「きつね(黄恒)」とする説などがある。」
『日本辞典』
http://www.nihonjiten.com/data/45902.html
によると,
「『キ』は臭、『ツ』は小詞、『ネ』は犬(エヌ)からで、臭気のある犬の意・『キツエヌ』が転じた説、好んで人家に来て寝るから、またキツネが妻に化けて子を産んだという伝説の中の「なんじ我を忘れたか・・・来つ寝(キツネ)よ」に由来し、『来寝(キツネ)』の意とする説、色が黄色いことから『黄恒(キツネ)』、『黄ツ猫(キツネ)』の意とする説、鳴声に由来し、キツイ鳴く音(ネ)、またはキツの鳴声にネを添えた説などがあり、他にも多説ある。」
と,それぞれ載せる。
しかし,まあ,「きつ」「くつ」と呼んでいたのだから,鳴声説が,妥当なのだろう。なぜ,人をだますということになったのか,その謂われは,よく分からないが,『古今著聞集』には,
ある男が,朱雀大路で,美しい女と逢う。女は狐なのだが,男は女に迫る。女は,『交合(まぐわい)をすると必ず死んでしまうから』と断るのだが,男がさらに迫ると,『あなたの仰せに従うけれども,結局あなたの身代わりになって死ぬのだから,若し私の心を合われて思われるのなら法華経をかいて供養してください』と言い,夜明け方,女は男に扇を乞い,あした武徳院にいってごらんなさいと言い置く。男が武徳院に行ってみると,一匹の狐が扇で顔を覆って死んでいた。男は哀れに思い,七日ごとに法華経をかいて供養したところ,七七,四十九日の日の夢に,女は天女たちに囲まれて『我一乗の力によって,今忉利天(とうりてん)に生まるなり』と告げて去った。
という話が載っている。
どうも,
恋しくば尋ね来て見よ 和泉なる信太の森のうらみ葛の葉
の葛の葉の白狐にしろ,狐の方が情が深い。
「王子の狐」という噺がある。
http://ginjo.fc2web.com/34oujinokitune/oujinokitune.htm
「王子稲荷(東京都北区王子)の狐は、昔から人を化かすことで有名だった。
ある男、王子稲荷に参詣した帰り道、一匹の狐が美女に化けるところを見かける。どうやらこれから人を化かそうという腹らしい。そこで男、『ここはひとつ、化かされた振りをしてやれ』と、大胆にも狐に声をかけた。『お玉ちゃん、俺だよ、熊だ。よければ、そこの店で食事でも』と知り合いのふりをすると、『あら熊さん、お久しぶり』とカモを見付けたと思った狐も合わせてくる。かくして近くの料理屋・扇屋に上がり込んだ二人、差しつ差されつやっていると、狐のお玉ちゃんはすっかり酔いつぶれ、すやすやと眠ってしまった。そこで男、土産に卵焼きまで包ませ、『勘定は女が払う』と言い残してさっさと帰ってしまう。店の者に起こされたお玉ちゃん、男が帰ってしまったと聞いて驚いた。びっくりしたあまり、耳がピンと立ち、尻尾がにゅっと生える始末。正体露見に今度は店の者が驚いて狐を追いかけ回し、狐はほうほうの体で逃げ出した。
狐を化かした男、友人に吹聴するが『ひどいことをしたもんだ。狐は執念深いぞ』と脅かされ、青くなって翌日、王子まで詫びにやってくる。巣穴とおぼしきあたりで遊んでいた子狐に『昨日は悪いことをした。謝っといてくれ』と手土産を言付けた。穴の中では痛い目にあった母狐がうんうん唸っている。子狐、『今、人間がきて、謝りながらこれを置いていった』と母狐に手土産を渡す。警戒しながら開けてみると、中身は美味そうなぼた餅。子狐「母ちゃん、美味しそうだよ。食べてもいいかい?」母狐『いけないよ!馬の糞かもしれない』」
どっちがだますのやら。「狐」という字は,
「犬+音符瓜」
で,やはりクワクワと鳴く声を真似た擬声語らしい。
参考文献;
阿部正路『日本の妖怪たち』 (東書選書 )
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%84%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E5%AD%90%E3%81%AE%E7%8B%90
粟散辺地は,
ぞくさんへんじ,
と訓み,辞書(『広辞苑』)では,
辺鄙な知にある小さい国,
とある。
粟散辺土,
粟散辺州,
粟散国,
とも言う。我が国を指している。
わが朝は粟散辺地の境,
と言った言い回しをする。
粟粒を散らしたような小さい国,
という意味で,インドや中国のような大国に対して,日本のことを,へりくだって言った。
「『粟散』は粟散国(粟のように散在する小国)のこと。『辺地』は最果ての地。特に日本人自身が、日本のことを中国やインドと対照させて、このように表現するときがある。」
と説明する。
辺地粟散,
という言い方もした。僕は,こう謙虚に,というよりは事実として自国をそう意識していた時代の日本人がまっとうだと思う。明治維新後,
世界に冠たる日本,
世界の中の日本,
という言い方をするようになった。列強に伍して,肩怒らせなくてはならない時代という意味が分からなくもないが,
夜郎自大,
に近く,気持ちが悪い。
粟散辺地という言い方は,仏法との絡みで,意識されたようだ。
「空間的にも時間的にも仏法より疎外された国」
という意識を,
粟散辺土,
という言葉に表現した。自己意識である。この言葉によって見えている世界は,
「『仁王経』などによれば,我らの住む南閻浮提(なんえんぶだい 須弥山を取り巻く四大陸のひとつ)は五天竺を中心に,十六の大国,五百の中国,一千の小国,さらにその周囲には無数の『粟散国』があるという。『粟散国』とは粟のごとく散らばった取るに足らぬ国という意味で,日本はそのような辺境群小国のひとつ」
という自己意識である。事実文明発祥のインド,中国の巨大な影響下にあった,周辺国の一つであることは確かだ。中国由来でないものを探すのは,文字一つとっても,箸ひとつとっても,漆ひとつとっても,至難といっていい。そういう冷静な自己意識であった時代が,我が国では,長かったといっていい。
粟散
の初見は,延暦十七年(917)の『聖徳太子伝略』らしく,以後こういう言い方が定着し,『平家物語』にも,
「この国は粟散辺地とて,心うきさかひにてさぶらへば,極楽浄土とて,めでたき処へ具しまゐらせさぶらふとぞ。」
という言い方が載る。それと前後して,中国を大国として,
小国辺土,
とも言ったようだ。こんな言い方がいいというつもりはないが,列強に伍して,大国意識を引きずり,自画像が露出した時代よりは,はるかに冷静だと思う。このことで思い出すのは,吉田松陰である。
「崛起」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E5%B4%9B%E8%B5%B7)に書いたが,吉田松陰の『講孟余話』で過激な攘夷論を,大儒・山県太華は,理論だって,冷静な正論を吐いている。
漢土の例にならって,自国を中国といい,他国を夷狄といい,我は尊く,彼はいやしいというべきわけがない。海外の諸国も,皆人間の国であり,禽獣虫魚とは違う。天がこれら外国の人々に倫理・道徳の根本を与えること,皆同じである,
あるいは,
アメリカ・ロシアは海外の別国であり,その使節が主命を奉じてわが国に来たのである。両国とも,もともとわが属国ではない。だからかならずしも一々わがいうところに従うことがあろうか。彼らは利害を解いて,自分らの請うところを求めるのである。何で深くこれを怒ることがあろう。かつ,向こうは大国であるのに,対等の礼をもって,やってきているのである。彼らに少しく不遜の形があっても,事情により寛恕してもよくはないか。どうしてかならずしも兵をもって彼らを撃つにいたることがあろう。
等々。同じ儒者である横井小楠も,
「道は天地の道なり。わが国の、外国のということはないのだ。道のある所は外夷といえども中国なり。無道になるならば、我国支那といへどもすなわち夷なり。初めより中国といい夷ということはない。国学者流の見識は大いに狂っている。だから、支那と我国とは愚かな国になってしまった。これで亜墨利加などはよく日本のことを熟視し、決して無理非道なことをなさず、ただわれらを諭して漸漸に国を開くの了簡と見えた。猖獗なるものは下人どもだけだ。ここで日本に仁義の大道を起さなくてはならない、強国になるのであってはならない。強あれば必ず弱あり、この道を明らかにして世界の世話やきにならにはならねばならぬ。一発で一万も二万も戦死するというようになることは必ずとめさせねばならぬ。そこで我日本は印度になるか、世界第一等の仁義の国になるか、この二筋のうちしか選択肢はない。」
と言っていた。その道は,維新では断たれ,夜郎自大の道に進んでいってしまった(その結果の敗戦であるにもかかわらず,懲りもせず,またぞろ夜郎自大な空気が蔓延し始めている)。
天下は一人の天下である,
という松陰に対して,山県太華は,
天下は一人の天下に非ず,天下の天下である,
と,まあただっこに対して冷静な論理で突っぱねるのに似ている。しかし,今日,駄々っ子のような為政者をたしなめる大儒は,いない。
参考文献;
伊藤聡『神道とはなにか』(中公新書)
村上一郎『草莽論』(大和書房)
松浦玲編『佐久間象山・横井小楠』(中央公論社)
鬼の霍乱(かくらん)という言い回しは,昨今あまり使わなくなった。かつては,いつも月月火水木金金(この言い方もあまり伝わりにくいか),と休みなく働く上司が不意に病欠したりしたのを指して,そう陰口していたが(「目上の人に対して直接使うのは失礼にあたる」とされているが,感覚的にそれはわかって使っていたらしい),辞書(『広辞苑』)にある意味は,
いつも極めて壮健なひとが病気になることのたとえ,
とある。まあ,諺の一種で,「ことわざ辞典』にも載り,
鎧のままで鬼の霍乱,
という句が載っている。「鬼」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E9%AC%BC)については触れたが,ここで言う鬼は,中国語の亡霊の意味ではなく,角のある件のオニのイメージなのだろう。『語源辞典』には,
「鬼(平素丈夫な人)+霍乱(日射病)」
とある。鬼のイメージは,そういうものなのだろう。
「オニということばが文献にあらわれるのは平安時代に入ってからで,奈良時代の万葉集では,『鬼』の字をモノと読ませている。」
とあるので,恐ろしい怪物のイメージが定着した以降のことばということになる。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/o/oninokakuran.html
によると,
「霍乱は、もがいて手を振り回す意味の『揮霍撩乱(きかくりょう らん)』の略で、日射病や暑気あたり、江戸時代には夏に起こる激しい吐き気や下痢を
伴う急性の病気をいった。
いつもは健康な人を強くて丈夫な人を『鬼』、珍しく病気になることを『霍乱(急性かつ苦しむ病気)』にたとえ,『鬼の霍乱』というようになった。」
とある。『由来・語源辞典』
http://yain.jp/i/%E9%AC%BC%E3%81%AE%E9%9C%8D%E4%B9%B1
には,
「『鬼』は強くて、丈夫な者の象徴。『霍乱』は漢方の用語で、日射病や夏に激しい下痢を起こす急性の病気のこと。つまり、鬼が病気になるれば誰でもびっくりするところから、いつも丈夫で健康な人が病気になったときに使われるようになった。」
とある。どうも,「霍乱」ということばに,この諺の鍵がありそうだ。辞書(『広辞苑』)には,
暑気あたりの病。普通は,日射病を指すが,古くは吐瀉病も含めて用いた,
とある。季語は夏なので,今風に言うと,
夏バテ,
となるが,重ければ,
熱中症
ということになる。暑気あたりは,『日本大百科全書(ニッポニカ)』
https://kotobank.jp/word/%E6%9A%91%E6%B0%97%E3%81%82%E3%81%9F%E3%82%8A-1545933
には,
「夏の暑さのために病気になることをいうが、医学では、一般に暑熱障害と総称される。臨床的には、熱疲労、熱けいれん、熱射病・日射病に分けられる。熱疲労は、もっとも普通にみられる病型で、高温環境下での労働、炎天下のスポーツなどでおこりやすく、体温は正常であるが、水分や塩分の欠乏をきたし、ショック状態となる。熱けいれんは、発汗で塩化ナトリウムの喪失が著しいときにおこり、有痛性の四肢あるいは躯幹(くかん)の筋肉群にけいれんをきたす。熱射病・日射病は、とくに夏の強い直射日光にさらされ、前夜の睡眠不足や疲労が重なると発症しやすく、体温調節中枢の機能が障害され、発汗が止まり、体温の異常な上昇をきたすのが特徴である。暑熱障害では、体温(直腸温)が41℃を超すと脳に非可逆性変化をおこし、死の転帰をとることが多い。」
とある。熱中症は,
「暑熱環境下においての身体適応の障害によっておこる状態の総称である。本質的には、脱水による体温上昇と、体温上昇に伴う臓器血流低下と多臓器不全で、表面的な症状として主なものは、めまい、失神、頭痛、吐き気、強い眠気、気分が悪くなる、体温の異常な上昇、異常な発汗(または汗が出なくなる)などがある。また、熱中症が原因で死亡する事もある。特にIII度の熱中症においては致死率は30%に至るという統計もあり、発症した場合は程度によらず適切な措置を取る必要があるとされている。また死亡しなかったとしても、特に重症例では脳機能障害や腎臓障害の後遺症を残す場合がある。」
とある。医学的な区別は別にして,暑熱に対応できない肉体的な反応らしく,どうやら,(前兆はあるが自覚しないまま)突然起きるらしい。
「霍」の字は,
「会意文字。もと『雨+隹二つ(並んで飛ぶ鳥)』。雨に降られて,パッと羽を広げて飛び立つ鳥の羽音のあわただしさをあらわす。『霍』はその略字」
で,
はやいさま,
ぱっとひろがるさま,
ぱっときえるさま,
と,すばやいさまを指す。「乱(亂)」は,
「(亂の)左の部分は,糸を上と下からてで引っぱるさま。右の部分は,乙印で押さえるの意を示す。あわせてもつれた糸を両手であしらうさまを示す。もつれ,もつれに手を加えるなどの意をあらわす」
とある。まあ,突然,突発の乱心に,周りが慌てたのだろう。
『大言海』には,「霍乱」は,
「(霍は直音,カク,揮霍,繚乱の義。身を悶え,手足を振り回す態を示すと云ふ)烈しく吐瀉する病,多く夏日の飲食に起こるに云ふ」
とある。『古語辞典』には,
急性胃腸炎または吐瀉病の漢方名,
とある。暑気あたり,などという生易しいものではないようだ。
参考文献;
尚学図書編『故事ことわざの辞典』(小学館)
「やらずぶったくり」は,
遣らずぶったくり,
と当てる。意味は,
人に与えることをせず,人から取り上げるばかりであること,
とある。面白いのは,
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445569384
には,
「『ぶったくり』という言葉は本来ありません。『ぼったくり』の『bo』が訛って『bu』になっただけです。」
とある。真偽は確かめようがないが,「ぶったくり」を辞書(『広辞苑』)で引くと,
打った繰り
と当てて,
ぶったくること,特に,他人のものを強奪すること,
とある。「やらずぶったくり」のニュアンスは,少し弱く,打った繰りのニュアンスからは,強奪ということになる。むしり取るでもまだ弱い。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1252881932
にも,
「『ぼりたくる』から音便化した言葉です。『ぼり』は『暴利』のことで
これを動詞化して『ぼる』の連用形ということです。これは『米騒動』の時に出た言葉のようです。暴利をむさぼること、法外な値段を吹っかけることの意味で使われます。」
とある。しかし,辞書(『広辞苑』)に,
ぼったくり
は載らない。『語源辞典』には,
「ブツ(接頭語)+タクル(手繰る)」
とある。『大言海』には,
「ぶったくる」
で載る。
無理に奪い取る,
商売に,価格以上の値を貪る,
とある。「ぼったくる」は載らない。が,
「ぼったてる」
は載る。
追立てる
と当てる。
「おひたてる(追ひ立てる)の訛。追(ぼ)ふの條をも参見せよ」
とある。「追(ぼ)ふ」は,
「追(お)ふの訛」
とある。だから,「ぼったくる」と「ぶったくる」が転訛することはある。ただ,「暴利」の「ぼう」とか,「米騒動云々」はいかがなものか,と思ったが,辞書(『広辞苑』)で,「ぼる」を引くと,
(米騒動の際の暴利取締令に出た語で「暴利」を活用させたもの)
と載り,
法外な代価,賃銭をとる,不当な利益をむさぼる,
と出ている。これで落着か,というとそうはならない。『語源辞典』には,
「むさぼる」の「ぼる」,
と載る。そして,
「『暴利+る(動詞化)』説は疑問です。」
と書く。『大言海』も,
「むさぼる(貪)の上略」
として,『日本新永代蔵』から,
「江戸の大阪屋のボラれし年」
との例文を載せる。どうやら,「貪る」の「ぼる」から,「ぼったくり」となり,「ぶったくり」となったということのようだ。関西は知らず,一般には,
やらずぶったくり,
というようだ。この「遣らず」を引くと,
遣らずの雨
遣らずもがな
が出る。「遣らずの雨」とは,
人を帰さないためでるかのように降ってくる雨,
という。なかなか,粋な言い方ではないか。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
縄墨は,
じょうぼく
と訓む。
守るべき規準。規則。また,標準
の意味である。
墨縄,
とすると,
すみなわ,
と訓む。意味は同じ。
墨糸,
と同じである。辞書(『広辞苑』)には,墨壺を参照と出る。墨壺は,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%A8%E5%A3%BA
に詳しいが,
墨汁を淹れた壺,
だが,
「大工や石工などが直線を引くのに用いる道具。一方に墨肉を入れ,他方に糸(墨糸)を巻き付けた車をつけ,糸は墨池の中を通し,端に仮子(かりこ)という小錐(こきり)をつける。墨糸を加工材に真直ぐに張って,垂直に軽く弾くと,黒線が材面に印される。」
という使い方をする。昔は,建築現場で見かけたことがある。しかし,今は,アマゾンや楽天を見ると,原理は同じなのだろうが,オシャレになっている。
同じ,標準とか規律という意味でも,
縄矩,
というのがある。
じょうく
と訓む。意味は,
墨縄(すみなわ)と差し金,
を指す。
縄規,
と同じ意味だが,
すみなわとぶんまわし,
の意になる。ぶんまわしとは,
縁を書くのに用いる具。いまで言う,コンパスのことである。
縄尺(じょうじゃく)は,
墨縄と物差し,
と,意味は同じだが,墨から,墨糸,コンパス,物差しまで,セットで,規準という意味のメタファとして使っていたということになる。
由来は多分同じだから,意味も同じだが,
規矩準縄(きくじゅんじょう)
規矩縄墨(きくじょうぼく)
規矩標準(きくひょうじゅん)
鉤縄規矩(こうじょうきく)
といった四文字熟語もある。
「規」は円を描くときに使うコンパス。
「矩」は長さを測るための指矩(さしがね)のこと。
「準」は水平を測るための水準器。
「縄」は直線を引くための墨縄(すみなわ)のこと。
「鉤」は曲線を引く時に使う道具。
と,それぞれの道具を元にしているのも同じである。しかし,大工や石工の現場が判っていてこそのメタファだ。その道具が,プレハブ住宅が増え,人の目に触れにくくなったせいか,言葉から意味が受け取りにくくなった。それに代わる豊かな現実がなければ,言葉軽く,浮遊することになるような気がする。いま,メタファと現実が逆転していはしまいか。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
簡野道明『字源』(角川書店)
こだまは,
木霊
とか
木魂
とか
木魅
とか
谺
と当てる。辞書(『広辞苑』)には,
樹木の精霊,
やまびこ,反響,
歌舞伎囃子の一つ。深山または谷底のやまびこに擬す,
とある。語源は,
「木+タマ(魂・霊)」
とある。
「木の精霊,やまびこのこと。反響を。タマシイの仕業と見ている言葉」
と載る。「やまびこ」は,
山彦,
と当て,辞書(『広辞苑』)には,
山の神,山霊,
山や谷などで,声,音の反響すること,
と,ある。語源は,
「山+ヒコ(精霊・彦・日子)」
で,山間での音の反響を指す。しかし,『語源由来辞典』を見る限り,
樹木の精霊
と
山霊
とは同じなのだろうか,と引っかかる。
例の,鳥山石燕『画図百鬼夜行』には,「こだま」を「木魅」と当て,老松と翁と嫗とが描かれていて,
「百年の樹には神ありてかたちをあらはすといふ」
とある。阿部正路氏は,
「老いた樹木は,樹木たることを超えて,神そのものとしての,本来の姿をあらわすという思想がある。百年とは,要するに並の人間の生命を越えたものの,長い月日を意味するものであり,『百鬼夜行』における『百』も,数字として限定された〈百〉を意味するものではなく,無限に存在しつづけるものの数の〈総体〉として意識されてきたものであった。」
と書く。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E9%9C%8A
には,
「木霊は山神信仰に通じるものとも見られており、古くは『古事記』にある木の神・ククノチノカミが木霊と解釈されており、平安時代の辞書『和名類聚抄』には木の神の和名として『古多万(コダマ)』の記述がある。『源氏物語』に「鬼か神か狐か木魂(こだま)か」「木魂の鬼や」などの記述があることから、当時にはすでに木霊を妖怪に近いものと見なす考えがあったと見られている。怪火、獣、人の姿になるともいい、人間に恋をした木霊が人の姿をとって会いに行ったという話もある。」
と説明する。
『古語辞典』をみると,「中世末まで,コタマと清音」とあり,例外はあるが,濁らなかったようだ。
「鬼か神か狐か木魂か」(『源氏手習い』)
「樹神,古太万(こたま)」(『和名抄』)
「木魅(こたま)」(名義抄)
と例が載る。樹木の精霊として,
「古びた木に宿って,人気の少ないときに形をあらわし,害をすることがあると信じられた」
という意味とともに,
「山中・谷間などで起こる音の反響現象を,樹神の応答と想像したもの。やまびこ」
とあり,どうやら,老木に宿る精霊のいたずらの一つが,やまびこ,ということになる。しかし,『古語辞典』の「やまびこ」の項には,音の反響の他に,
山の神に同じとあり,そこを引くと,
「山に住み,山をつかさどる神」
とある。樹木の精霊と山の神は違うのではないか。『大言海』も,やまびこは,
天彦(あまひこ)と同趣,
とあり,
山の神,山霊,
とある。「やまひこ」と訓ませると,やはり,山の神のニュアンスになる。因みに,天彦(あまびこ)とは,
天上の人
という意味になる。どうやら,辞書レベルで見る限り,
木魂
と
山彦
は由来が違うのではないか。しかし現象は同じ,反響を指すようになり,重なりあったということになろうか。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
阿部正路『日本の妖怪たち』(東書選書)
大野晋・佐竹 昭広・ 前田金五郎編『古語辞典 補訂版』(岩波書店)
弁慶読みは,
ぎなた読み,
とも言う。
「文章の区切り方を間違えて、文の意味を取り違えること。または区切り方で意味が分かれるような文章をつくる言葉遊び。『弁慶が、なぎなたを持って・・・』というのを『弁慶がな、ぎなたを持って・・・』と読んだという故事より『ぎなた読み』とも呼ばれる。」
という説明で意は通じる。
http://dic.pixiv.net/a/%E3%81%8E%E3%81%AA%E3%81%9F%E8%AA%AD%E3%81%BF
http://homepage2.nifty.com/maru777/naginata.htm
等々に「ぎなた読み」の例が出ている。たとえば,
それが「世界(ワールド)」かッ!来いーーっ!→それが「世界(ワールド)」!カッコいーーっ!
ウスバカゲロウ(薄羽蜉蝣〔昆虫〕)→薄馬鹿下郎〔罵言〕)
ハーモニー奏でておくれ→ハーモニカ撫でておくれ
あの丘まで、駆けていくわよ→あのオカマ、出かけていくわよ
等々。つまり,
句読点,
ひとつで微妙に意味が変わる。句読点とは,
「句読点(くとうてん、英:punctuation)とは、句点と読点の総称である。最も狭義には終止符とカンマのみを指すが、より広く疑問符や感嘆符、省略符を含む場合、さらに広義には括弧、カギ括弧、その他文章に使う様々な記号を含む場合がある。」
とあり,辞書(『広辞苑』)には,
現在は句点には「。」,読点には「、」を用いる,
とある。
「句読点は、その置き方により構文上重大な変化を起こしうる」
のは,英語にもあるらしい。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A5%E8%AA%AD%E7%82%B9
によると,
"eats, shoots and leaves"(食って撃って逃げる)
と
"eats shoots and leaves"(芽と葉を食べる)
と,
「カンマを入れることによって意味が変化する。日本語では分かち書きの習慣がないためにさらに誤解が起きやすく、誤解を防ぐために読点を多く打つことがある。」
その最近の例では,
アフガン航空相撲,
というのがある。
アフガン航空相,撲殺される,
が,つなげるとこうなる,という例だ。しかし,これは,言葉を文脈から切り離すことで生まれる多義性なのではないか。文脈というのには,文字通り,
文章の流れ,
と,いまひとつ,その発話のなされた,
状況の中,
の二つの意味がある。どんなフレーズも,
文脈から切り離さなければ,
誤解を生みようはない。上記の,
アフガン航空相撲殺される
も,文脈のなかで聞けば,誤解の仕様はない。多く,特に日本語は,文脈に依存した言葉が多いから,一見主語が隠されているが,そんなことはない。たとえば,
さようなら,
は,他国のことばと違って,
左様なる次第ですからお別れします,
という次第を共有している前提で,発せられる。これについては,「さようなら」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba2.htm#%E3%81%95%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%89)
で触れた。しかし,その文脈を意識してぼかすことが,我が国の為政者にはある。
敗戦(戦争に敗れた),
を
終戦(戦争は終わった),
と,置き換えることで,文脈とは別に,当事者意識から離れた,他人事のような意味だけが独り歩きし始める。それは,戦争責任者を免罪させる効果がある。だから,また,
平和,
の名目で,
戦争をオブラートに包むことが平然となされる。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%B3%E8%88%AA%E7%A9%BA%E7%9B%B8%E6%92%B2
売り家と唐様で書く三代目,
という。
江戸時代中期にできた川柳,
という。
「初代は苦労して家や財産を築く。
二代目はそれを受け継いで手堅く維持する。初代が苦労したのを知っているので、金持ちになったからといって浮わついた暮らしはしない。しかし、三代目になると、生まれたときから金持ちで苦労を知らないので、遊芸などで身を持ち崩し没落して、ついに自分の家を売り家に出すようになる。その売家札の字が唐様(からよう)で、しゃれている。遊芸におぼれて商売をるすにした生活がしのばれる、という意味です。」
とある。「売り家」と書いた札の文字が,
「中国風の書体でしゃれており,商売を留守に遊び暮らした生活ぶりがしのばれる」
という含意である。
「昔、貸家は『かしや』と仮名で、売家は漢字で書く習慣があった。」
というから,その「売家」という文字の意味が深くなる。
唐様,
とは,
「和風ではなく中国風であること。唐風と同義。」
とある。あるいは,
「唐様とは中国の書風のことで、禅僧による唐様を特に墨跡と呼ぶ。」
とあり,
「日本の書流(しょりゅう)とは、和様書の流派の総称である。平安時代中期の世尊寺流から分派した和様の流派が、江戸時代中期、御家流一系に収束するまでを…範囲とし、それ以外の著名な書流はその他の書流…。唐様は含めない。」
とある。まず,和流は,
「奈良時代から平安時代にかけて盛行した王羲之の書風を根底として、平安時代中期に三跡(小野道風・藤原佐理・藤原行成)らによって日本人らしい感覚の一つのスタイルが完成した。これを出発点として、平安時代末期に法性寺流、鎌倉時代末期に青蓮院流、江戸時代には御家流と書流が変化してきたが、この系列に生まれた書を総称して和様という。」
とある。
では,唐様は,というと,
「墨跡の中国書法が北島雪山・細井広沢らに伝わり唐様として発展していく。唐様は儒者・文人などに用いられ、寂厳・池大雅らが継承し、江戸時代末期には幕末の三筆と呼ばれる市河米庵・巻菱湖・貫名菘翁の3人へと展開していった。この3人は武家や儒者に信奉者が多く、特に江戸の市河米庵は諸大名にも門弟があり、その数5000人ともいわれた。江戸時代中期ごろから書法の研究が進み、これまでの元・明の書風から晋唐の書風を提唱する者があらわれ、巻菱湖・貫名菘翁らは晋唐派であり、市河米庵などは明清派であった。」
と説明される。
「江戸時代中期ごろから書法の研究が進み、これまでの元・明の書風から晋唐の書風を提唱する者があらわれ、巻菱湖・貫名菘翁らは晋唐派であり、市河米庵などは明清派であった。」
とあるから,ひとくくりに唐様と言ってしまえないが,素人には,違いがよく分からない。しかし,つくづく思うが,
売り家と唐様で書く三代目,
と川柳に詠い,それを聞く側も,聞きはとる力が,あったということになる。当然それは,唐様と,和様の区別もついたということになる。現代よりはるかに,素養のレベルが高いのである。
と同時に,この川柳が多くに共感され,諺の如くにして伝えられてきた背景には,豪商,豪農であっても,
「努めざれば三代にして滅ぶ」
という危機意識を反映している,江戸期町人・農民のまっとうな共通意識をも表している,と言えなくもない。
それに比して,今や三代目,四代目ばかりの政治家どもには,危機感の欠片もなく,売り家どころか,売り国の札を,金釘流で描きそうな連中ばかりだ。こんな連中と心中するつもりなのだろうか。
参考文献;
尚学図書編『故事ことわざの辞典』(小学館)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1281310572
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%9B%B8%E6%B5%81#.E5.94.90.E6.A7.98
僭上は,
古くは「せんしょう」とも,
と言われ,『古語辞典』には,確かに,
せんしゃう,
で載る。
身分・分際を超えて上のものの真似をすること,
身分・分際を超えて,驕り高ぶること,
という意味になる。辞書(『広辞苑 第五版』)には載らないが,古い『広辞苑』には,
身分を超えて驕り高ぶること,
長上をしのぐこと,
と載る。最近は使われなくなった,ということだろう。因みに,長上とは,
年長,目上,
を指す。『デジタル大辞泉』には,僭上は,
1 身分を越えて出過ぎた行いをすること。また、そのさま。「―な振る舞い」
2 分を過ぎたぜいたくをすること。また、そのさま。
3 大言壮語すること。また、そのさま。
の意味が載る。
僭上の沙汰,
とか,
僭上振り,
と言った使い方をする。『大言海』には,
身分を超えて物事をすること,ほしいままに,分際を犯すこと,臣として妄りに君の真似ををすること,
自分のことを誇張して云ふこと,
と載る。分際とは,辞書(『広辞苑』)には,
その者に応じた程度・限界,
身の程,分限,身分,
と載るが,『大言海』がそのニュアンスを的確に伝える。
かぎり,ほど,分限,
身の分に応ずるほど,身分,
を指す。とっさに浮かぶのは,
僭越,
という言葉だが,僭越は,
身分・地位を超えて出過ぎたことをする,
つまりは,
でしゃばり,
ということになる。
違いは,僭上は,
真似,
だが,
僭越は,
出過ぎ,
というところか。いずれも,身分の上のものからの視点で,癪に障るというか,いまいましい,と思うということだ。その振る舞いを,前提なく見たら,つまり,身分低きものが,分際を弁えず,
しゃしゃり出ているように見える,
というところがみそだ。だから,類語は,価値を味付けすると,
厚顔,厚かましさ,ずうずうしい,たけだけしい,
という意味になる。しかし,価値の眼鏡を剥ぎ取ると,そこにあるのは,
身分は低いがすぐれた才能,
ということを,暗に言っていることが多い。それは,身分や長幼で押さえつけなければ,
逸材,
であることが,少なくないのではないか。それを,
逸足,
と言う。逸足とは,
足の速いこと。また、そのもの。駿足 ,
すぐれた能力をもっていること。また、その人。逸材,
という意味である。
先日,写真家の大野純一氏が,ツイッターで,
「欧米のビジネスでは、互いのモチベーションを高め合うことで結果を出し、日本のビジネスでは、飛び抜けた結果を出す人間の足を嫉妬で引きずり下ろし合う。この二つの違いでは、生産性が3倍。実質的な金額では700倍の差が出ると言われています。研究や芸術、政治なども全く同じ構造だと思います。」
と発言されていたことを思い出す。
逢魔が時とは,辞書(『広辞苑』)には,
おおまがとき(大禍時)の転。禍いの起きる時刻の意,
とあり,
夕暮れの薄暗い時,黄昏,
の意とあり,
おまんがとき,
おうまどき,
とも言うらしい。『大言海』は,
おほまがとき(大禍時),
で載る。
黄昏の薄暗き時の称。大魔が時などと云ひて,怪ありとす。訛りて,おまんがとき,
と意味を載せる。薄暮れ時を指している。
黄昏,
というのは,語源的には,
「タ(誰)+そ+カレ(彼)」
で,「誰だ,彼は」の意とある。夕方人影が見分けにくくなる,という意味である。『大言海』は,
「誰そ,彼かと見分け難き義。たそがれ時の下略」
とある。『古語辞典』に,
たそ,
の項があり,
誰そ,
と当て,
「タは代名詞,ソは,指定する意の助詞」
とあり,こんな万葉集の歌が,例に載る。
「たそかれと問はば答むすべを無み君が使いを帰しつるかも」
夕方の薄暗くなる,昼と夜の移り変わる,と物の輪郭が,うす闇にまぎれてはっきりしなくなる時分である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A2%E9%AD%94%E6%99%82
には,
「読んで字の如く、逢魔時は「何やら妖怪、幽霊など怪しいものに出会いそうな時間」、大禍時は「著しく不吉な時間」を表していて、昼間の妖怪が出難い時間から、いよいよ彼らの本領発揮といった時間となることを表すとする。逢魔時の風情を描いたものとして、鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』があり、夕暮れ時に実体化しようとしている魑魅魍魎を表している。」
とある。
http://abcd08.biz/usimitudokioumagatokikimon/
には,おおよその時刻が,
「暮六つと言われる酉の刻(17時~19時)は逢魔が時といわれ、魔物と遭遇してしまう時間とされています。
人間の時間である昼間と魔物の時間である夜の切り替わる時間帯です。大禍刻とも呼ばれていて、たそがれ時(黄昏時)も同じ意味です。たそがれ時は、(誰、彼?)から来ていて、顔も良く判別できない暗い状態を表しています。」
とある。日の落ち方にもよるので,夜と昼の狭間,ということだろう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1323106583
に,
「それは恐らく日が沈み、それまで明らかだったものの輪郭がぼやけて見えなくなっていく、その覚束なさから生まれる不安なのだ。そして、ぼんやりとした物の陰から、何か異界の者がそっとはみ出るように現れてくるのだ。」
とある。陰と闇とがまぎれ,物の形がとける,という感覚は,ちょっと気味は悪い。さらに,
「だから、普通には魔物に逢っても意識されることは殆んどない。夕暮れ時の忙しさの中で、それは薄暗闇に紛れてしまう。ただ、感受性の強い、幼い子供を除いて……。
夕食の支度やら何やらで、忙しく立ち働かなくてはならないこの時間帯は、不思議なことに、赤ん坊は必ずぐずり、幼子は聞き分けがなくなって、母親にまとわり付くものだ。その多くの理由は、純な魂が、魔物を感じ取って不安になるためだと私は考えている。しかし、当然彼らにはその不安を説明することはできない。で、大人はいらいらと叱ったり、よしよしと宥めたりするだけなのだ。」
とあり,だからか,
「世俗、小児を外にいだすことを禁(いまし)む。」
という。
また,逢魔が時は,
王莽(おうもう)の故事に付会して「王莽時」とも書く,
とある。「おうまがとき」を「おうもうがとき」と掛けたのだろうか。
「これは王莽前漢の代を簒ひしかど. 程なく後漢の代になりし故. 昼夜のさかひを両漢の間に. 比してかくいふならん。」
と,鳥山石燕は言っているそうだが。
王莽については,
http://www.y-history.net/appendix/wh0203-108.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E8%8E%BD
に詳しい。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A2%E9%AD%94%E6%99%82
へびの語源は,
「『ヘ(這・延)+ミ(虫)』の湯音韻変化」
とある。
くちなわ,
とも呼ぶ。「くちなわ」の語源は,
「朽ち(罵り語)+ナワ(青大将)」
とあり,「朽ち+縄」は俗解と退ける。『大言海』によると,ヘビは,ほかにも,
やまとのかみ,
ながむし,
たるらむし,
たるなむし,
等々の異称があり,「へみ」について,
「延蟲(はえむし)の約(白蟲(しらむし)しらみの類),転じてヘビとなる(黍(きみ)きび,夷(えみし)えびすと同趣)」
とある。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/he/hebi.html
には,
「ヘビの語源には、『ハヒムシ(這虫)』の略など這うように動く様子からとする説や、脱皮を することから『ヘンミ(変身)』の転とする説、小動物を丸のみするところから,『ハム(食む)』の転といった説がある。 ヘビが体をくねらせて前進する姿は特徴的であるし、脱皮の『ヘンミ』が『ヘミ』『ヘビ』へと変化する過程で、「ビ(尾)」の意味が加わったとも考えられる。また『ハブ』や『ハミ(マムシ)』は,『食む』からと考えられているため,『食む』を語源とする説も十分考えられる。
古く『へび』は,『へみ』と呼ばれており,『ヘミ』が変化して『ヘビ』になったと考えられているが,『ヘビ』の方言には,『ヘム』『ヘブ』『ヘベ』『ハビ』『ハベ』『ハム』『ハメ』『バフ』『ヒビ』などのほかに,これら二音の中間に『ン』を挟んだ『ヘンビ』『ヘンミ』など数多くの呼称があり,どの語が元で多くの方言が生じたか定かでないため,語源もどの説が正しいとは言い切れない。」
としている。同じ,『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ku/kuchinawa.html
は,「くちなわ」については,
「ヘビを『くちなわ』というのは、ヘビの形が朽ち た縄(腐った縄)に似ていることから。 口が付いた縄の意味ではない。」
としている。念のため,漢字の「蛇」の字は,
「它(た)は,頭の大きいヘビを描いた象形文字。蛇は,『虫+音符它』で,うねうねとのびる意を含む。它が三人称の代名詞(かれ,それ)に転用されたため,蛇の字で它の元の意味をあらわした」
とある。もともとの「へび」は,
這う虫,
ながむし,
くちなわ,
には,価値表現も感情表現もない。「蛇」の字そのものにも,状態表現しかない。いつから,畏怖や怪しいものに変ったのだろう。
阿部正路氏は,
「蛇の古語はナビ=奈備である。それを鎮めて神奈備とし,日本の神の基本に据えたのも所詮蛇への畏怖である。」
とある。妖怪の「濡れ女」にしても,「ろくろく首」にしても,蛇を根底においた妖怪,とする。
『俵藤太物語』には,大蛇に頼まれて近江国三上山の巨大な百足を退治する話が出ているが,
「蛇と水と龍はひとつながりの存在であり,蛇が人間の力を借りて百足を退治するのは,足のない妖怪の足を持つ者への限りない恐れを暗示する」
という。しかし,思うに,
「竜蛇の力こそ人間にとって理想の怪力をもたらすもの」
と思われているのに,
最後は,八俣の大蛇のように,最後は退治される。恐れとは退治の対象そのものなのかもしれない。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
阿部正路『日本の妖怪たち』(東京書籍)
鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫)
おきゃんは,
御侠
と当てて,辞書(『広辞苑』)には,
「キャンは唐音。『侠』を女の名のように用いたもの」
とあり,
「(若い)女の行動や態度が,活発で軽はずみなところがあること,たそのような女。おてんば」
と意味が載る。『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/o/okyan.html
に,
「現在はあまり使われず、死語となっている。」
とあるように,ほとんど耳にしない。男側ないし社会通念として,女らしくないという観念で女性を見るところからのことばだから,まだまだにしても,男女差が,我々の意識の中で,消えてきたためだろう。語源は,
「おきゃんは、漢字
で『御侠』と書かれ、接頭語の『御』と『任侠(にんきょう)』などの『侠』の字を唐音読み『侠(きゃん)』からなる。元々は,接頭語の『お』をつけない『きゃん』の形で使われ,勇肌で粋なことや人を意味した。そのような性格であれば,男女問わず使われていたが,明治時代に入ってから『お』を付け,若い女性のみを指す言葉になった。」
とあり,明治以降,女性の活発さが目につくようになったということなのだろうか。『古語辞典』には,
きゃん(侠)
として,
「任侠の気概に富み,言動の威勢がいいこと,またその人。女にも言う」
とある。これを見る限り,価値表現はない。つまり,その状態を指して,
気概のある,威勢の良さ,
を指している。しかし,『大言海』には,同じく,
きゃん(侠)
で載り,
「きんぴら娘の略転したる語か,倭訓栞,きゃん『侠の唐音なるべし』」
と注記して,
「きんぴらむすめ,はすはむすめ,おきゃん,おてんば」
と意味が載る。どうも,「侠」を男女に,
状態表現,
として使っていたはずなのに,女性を指すようになると,とたんに,
価値表現,
感情表現,
となり,『大言海』は露骨に,というか時代を反映してか,あけすけになる。因みに,「侠」の字は,
「右側の元の字は,夾で,両脇に子分を抱え,両側から守られて大の字型に立つ親分を示す会意文字。侠は,『人+音符夾』で,夾の後出の字」
とあり,
「子分をかかえて仲間同士で協力する人たち。男だて」
と意味が載る。いわゆる「任侠」「侠客」の「侠」である。
「おきゃん」の類語を調べると,
おてんば,
はすっぱ,
尻軽,
と散々である。まずは,『大言海』の,
きんぴらむすめ,はすはむすめ,おてんば,
に当たってみると,「きんぴらむすめ」は,
金平娘
と当て,
荒々しい振る舞いをする少女,伝法肌,
という意味になる。ここまでは,「おきゃん」の状態表現を維持しているように見える。「おてんば」は,
オテンバ,
と載り,「於轉婆」と,明らかな当て字で,
「蘭語 otembaar」
が語源とする。
「女の出過ぎたるたるもの。たしなみなき女。あばずれもの等々」
とあり,「てんばの條をみよ」とある。「てんば」には,
「此語,古来,仏蘭西語なりと云ひ,又,顚婆なりと云ひ,又,天馬なりと云ひ,又傳播の意義の変転したるものなりと云ふが,皆あらず,蘭語にぞある」
と注記する。しかし,語源辞典を見ると,二説あるらしい。
ひとつは,オランダ語のotembaar説。英語のuntamable(飼い馴らし得ない)の意,
もうひとつは,傳馬(将軍家御用品を運ぶ馬)説。威勢よく元気に跳ね回る馬の比喩から元気よく跳ね回る意,
とあるらしい。どちらとも決めかねるが,後者は,少し無理があるような気がする。しかし,辞書(『広辞苑』)で。「転婆」をみると,
騒々しくてつつしみのない女,出しゃばり女,
という意味(だんだん意味が本来の状態表現から,価値表現がえげつなくなる気がするが)の他に,
そそっかしいこと,軽はずみ,男女ともにいう,
親不孝なこと,
という意味が載り,「転婆」もまた,本来,その軽はずみさを,男女に使っていたことが判る。
「はすは」は,
蓮葉,
と当て,『大言海』は,
「はすは」
「はすはめ(蓮葉女)」
「はすはむすめ(蓮葉娘)」
と分けているが,「はすは」について,
「斜端(はすは)の意か,あるいは云ふ,蓮葉の義か」
とあり,「蓮葉」は,
「蓮葉の水をはじくに,ひらしゃらするより,女の其状をなすに,喩へて云ふ語」
とある。辞書(『広辞苑』)にも,「斜端(はすは)」と「蓮の葉が水をはじく時の形状に喩えた語」と同じ説を載せる。ただ,「蓮葉商」という言葉があり,
際物師,
を指し,『語源辞典』は,「蓮つ葉」について,
「蓮の葉商い」
と説明し,際物商売の粗悪な品を指す,とある。それが転じて,
「はでで,下品で軽はずみなこと」
を指す,と。それにしても,「おきゃん」の類語の幅の広いこと,
元気さ
と
たしなみのなさ
の裏腹は,まあわかるとしても,それと,
軽はずみ,
と
下品,
とはつながらない。いまもそうかもしれないが,女性を貶めるのは,男側の心の反映と考えると,それと違うものを勝手に求めているのだということがよくわかる。しかし,そこに価値表現を加えるのは,いかがなものか。その意味で,おきゃんも,おてんばも,はすっぱも,皆死語になっているのは,いいことに違いない。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
人事は,
ひとごと
とも,
じんじ,
とも訓ませるが,まずは,
ひとごと,
のほうである。
「ひとごと」は,
他人事
と当てるのと,
人事
と当てるのでは少し意味が違う。前者は,
自分には無関係な他人に関すること,また,世間一般の事,
となるが,辞書(『広辞苑』)には,
「俗に『他人事』の表記にひかれて,『たにんごと』ともいう」
とある。そういう理由もあるかもしれないが,前者の意味でも,
人事,
とも当てるので,紛らわしいから,市立と私立を区別して,「いちりつ」と読んだり,「わたくしりつ」と読んだりして,口頭での区別をするという意味がないわけではない。
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/152.html
には,放送用語として,
「まず、「他人事」「たにんごと」という表記(書き方)と言い方・読み方は、どちらも放送では原則として用いないことにしています。「自分に関係ないこと」などを意味する場合の伝統的な言い方は「ひとごと(人事)」[ヒトゴト]とされ、放送でもこの語法を採っています。」
と述べ,
「もともと『他人(たにん)のこと』を意味する語・ことばには『ひとごと』という言い方しかなく、この語に戦前の辞書は『人事』という漢字を主にあてていた。ところが『人事』は『じんじ』と区別できないので『他人事』という書き方が支持されるようになり、これを誤って読んだものが『たにんごと』である。」
としている。そう考えると,もともと,
人事,
と書いて,
他人事の意,
と
他人のことば(評判)
という二重の意味をもっていた。
後者の「人事」は,
他人の言葉,世人の言葉,評判,世のうわさ,
という意味になる。
人事(ひとごと)言わば,筵敷け,
という諺がある。
人事(ひとごと)言えば影が差す,
とも言うが,
人の噂をすると,きっとその人がやってくるものだ,噂をするならそのつもりでせよ,
という意味らしい。
因みに,「じんじ」と訓ませる「人事」は,
人間に関する事柄,人間社会にあらわれる事件,
個人の身分・能力に関する事項,人の一心上に関する事柄,
人の為し得る事柄,人間わざ,
社会・機構・組織などの中で,個人の身分・地位・能力の決定などに関する事柄,
俳句の季語の分類の一。天文・地理などに対し人間に関する題材,
という意味で,いわば,
その人に関すること,
であり,「にんじ」と訓むと,『正法眼蔵』などに,
「諸方の雲水の人事の産を受けず」
とあり,『徒然草』に,
「人事多かる中に,道を楽しむより気味ふかきはなし」
とあったりして,お経でよくあるが,仏教系は,鼻音化するのであろうか。
だから,
人生の諸事。人としてすることや人との付き合いなど,
も,「じんじ」とも「にんじ」とも訓む。
『語源辞典』には,
「中国語の『人+事』が語源,人のすること,人としてなすこと」
という意味と言う。たとえば,
人事蓋棺定,
つまり,人の行事の是非善悪は棺の蓋をして定まる,という意味の「人事」と,
人事を尽くして天命を待つ,
つまり,人として為し得ることを尽くして,結果は天命に委ねる,という意味の「人事」と,
人事不省,
つまり,地殻を失い,意識不明になること,という意味の「人事」と,
人事の意味の幅は広い。因みに,漢字で,
「人言」
と書くと,
人の噂,
人の口,
の意味になる。これを訓むと,
ひとごと,
と訓める。『古語辞典』も,『大言海』も,
「ひとごと」
で,
人事
と
人言
で項を分けている。ここからは,億説だが,「人事」は,あくまで,
人に関わること,
あるいは,
人の為すこと,
であり,それに,和語の,うわさや,ひとごとという意味のニュアンスはない。しかし,「人事」という表現を手に入れ(「じんじ」という言い方は,和語にはない),「ひとごと」に当てはめたことで,「人言」と紛れたのではないか。
「古代(日本)社会では,口に出したコト(言)は,そのままコト(事実・事柄)を意味したし,またコト(出来事・行為)は,そのままコト(言)として表現されると信じられていたそれで,言と事は未分化で,両方ともコトという一つの単語で把握された。従って奈良・平安時代のコトの中にも,言の意か事の意か,よく区別できないものがある。しかし言と事とが観念の中で次第に分離される奈良時代以後に至ると,コト(言)はコトバ・コトノハと言われることが多くなり,コト(事)と別になった。コト(事)は,人と人,人と物とのかかわりあいによって,時間的に展開・進行する出来事,事件などを言う。時間的に不変の存在をモノと言う。」
と,古語辞典にもあるように,「言」と「事」は,同一視されてもいたのだから。
「ひとごと」
と,和語で話す限り,「ひとごと」は「ひとごと」以外なく,紛れることはないが,言葉の陰翳の薄い,貧弱な会話に,漢字が混じることで,表現に奥行が増した。
「人事」
と当てた場合は,文脈のなかで,そのニュアンスを読み取るほかはない。「人事」に,「他人事」の意と,「他人の噂」の意味が,滲み出た。その陰翳効果は,漢字をもってしか手に入れられなかった。
他人事の意味の「ひとごと」については,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/405159096.html
で触れた。
参考文献;
大野晋・佐竹 昭広・ 前田金五郎編『古語辞典 補訂版』(岩波書店)
ぬえは,
鵺
とも
鵼
とも
恠鳥
とも
奴延鳥
とも当てるようだ。辞書(『広辞苑』)には,
トラツグミの異称,
源頼政が紫宸殿上で射取ったという伝説時用の怪獣。頭は猿,胴は狸,尾は蛇,手足は虎に,声はトラツグミに似ていたという。平家物語などに見え,世阿弥作の能(鬼能)にも脚色,
転じて正体不明の人物や大度にいう,
とある。『大言海』には,
「和(ナエ)にて,なびく声に云ふ。即ち,恨むる如く,うらぶる如く,しなふる如くなれば云ふと」
と注記して,
「又,ぬえどり。ぬえこどり。梟の類。世に怪鳥として,其鳴くを凶兆とす。吉野山等の深山に棲む。大きさ鳩の如く,黄赤にして,黒班あり。嘴の上は黒く,下は黄にして,脚は黄赤なり。昼伏し,夜出でて,木の梢に鳴く,聊,小児の叫ぶが如し。鬼つぐみ。関東に,虎つぐみ。」
と,あわせて,
「近衛天皇の時,源頼政が射て獲たりと云ふ想像上の怪獣の名。猴首,虎身,蛇尾にて,声は鵺の如し(『平家物語』)と云へるより移りて,世に誤りて,その名とす。」
とあり,あくまで,鳴き声が「鵺」,つまりトラツグミだったのを,誤って,怪獣の名にしたのだ,というわけである。
漢字「鵺」「鵼」は,あくまで,鳥の名を指し,それに,怪獣を当てたのは,我が国のみである。
「ひさかたの天の河原にぬえどりの うら嘆げましつ為方(すべ)なきまでに」
という万葉の歌にあるように,
「鵼鳥の」といえば「裏歎」の枕詞,
だとされる。それほどに,ぬえの鳴声は,哀しげなのだろう。しかし,多く,『徒然草』に,
「喚子鳥なく時,招魂の法をばおこなふ次第あり。これは鵺なり。」
とあるように,霊魂を呼び戻す,不吉の鳥とされたらしい。だから,
「空中で鵼鳥が鳴いたので,幣を奉る」
ということをする。そういう前提で,『太平記』には,隠岐次郎左衛門が射落としたのは,
「頭は人の如くにして,身は蛇の形也,嘴の前曲て歯,鋸の如く生違ふ。両の足に長き距(けづめ)有て,利(と)きこと剱の如し。羽崎を延べて之を見れば,長さ一丈六尺也」
というものであった。ところが,前出のように,源三位頼政が射落としたのは,
頭は猿,軀は狸,尾は蛇,手足は虎」
と『平家物語』に記す。『源平盛衰記』は,同じ源三位頼政の話で,
「頭は猿,背は虎,尾は狐,足は狸」
と変る。まさに,「ぬえ」的ではある。
かの鳥山石燕は,
「鵼は深山にすめる化鳥なり。源三位頼政、頭は猿、足手は虎、尾はくちなはのごとき異物を射おとせしに、なく声の鵼に似たればとて、ぬえと名づけしならん。」
と書く。
しかし,阿部氏は,高松塚古墳に描かれた,東に青竜,西に白虎,北に玄武,南に朱雀,の四神の,
「零落して,妖怪になったものの総体」
ではないか,と言う。
参考文献;
http://www.youkaiwiki.com/entry/2013/07/03/173020
阿部正路『日本の妖怪たち』(東京書籍)
鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫)
真偽は知らないが,豊臣秀吉は,六本指であった,という説がある。
前田利家の伝記『国祖遺言』に,
「太閤様は,右手の親指が一つ多く六つもあった。あるとき,蒲生氏郷,肥前,金森長近ら三人が聚楽第で,太閤様がいらっしゃる今の側の四畳半の間で夜半まで話をしていた。そのとき秀吉さまほどの方が,六つの指を切り捨てなかったことをなんと思っていらっしゃらなかったようだった。信長さまは秀吉さまの異名として『六ツめ』と呼んでいたことをお話された。」
とある,という。いまでもそうだが,先天性多指症というのがあり,
「指(足の場合は趾)が分離形成される段階で、1本の指(趾)が2本以上に分かれて形成される疾患のことである。結果として手足の指の数が6本以上となる。反対に、指の数が少ないのを欠指(趾)症という。」
何かの本で,出産というのが,いかに奇跡的か,ということを書いてあったのを読んだ記憶がある。
「日本人では手指の場合は拇指(親指)に、足趾の場合は第V趾に多く見られる。」
という。ルイス・フロイス『日本史』にも,秀吉を,
「優秀な武将で戦闘に熟練していたが、気品に欠けていた。身長が低く、醜悪な容貌の持ち主だった。片手には六本の指があった。眼がとび出ており、支那人のように鬚が少なかった。極度に淫蕩で、悪徳に汚れ、獣欲に耽溺していた。抜け目なき策略家であった。」
と書く。姜沆『看羊録』にも,秀吉は,
「生まれたとき,右手が六本指であった。成長するに及び,…刀で截里落としてしまった。」
との記述がある。多指症は,二千人から三千人に一人の発生頻度らしいし,男が三に対して女性が二と言われる。当時の医療技術から考えると,切るのはリスクが大きい。渡邊大門氏は,
「非常に面倒なのは,大小の二つの指には本来は一つになるべく組織などが分化していることで,単に動かしにくい小さい指を切ればよいという問題ではないことである。要するに不要な指を切るというものではなく,指を再生する手術になるということだ。これはかなり複雑なものであり,大手術になるといわれている。」
と述べ,前近代日本では,指を切ったという例はあまりなく,秀吉も切らなかった可能性が高い,という。
なぜ,五本指なのか。
http://matome.naver.jp/odai/2143030879212163801
によると,
「生物は環境によって、長い時間をかけて姿を変化させてきました。より種を存続させられるよう環境に適合し、進化の過程で不要な部分は退化させてきたのです。魚から両生類が進化したばかりの時代には、6本や8本の指を持つ生物もいましたが、進化の過程で不要な指が退化していくことで、5本指のものが登場し、これが現在の、陸上脊椎動物全ての祖先になったと考えられています。」
とし,
「いろいろな本数の種の中から、なぜか5本指のものだけが生き残り、両生類の子孫である爬虫類や哺乳類も5本指となった。」
と,理由はわからないが,
「クジラやゾウからコウモリやヒトにいたるまでの多くの脊椎動物の手足は同じ設計図をもっている。つまり、5本の指は、手首にある関節の集まりに結びついている。」
ので,
「馬も牛もその祖先は5本指で、進化するごとに指の数を減らして、今の姿になったということです。陸上をすばやく駆けて、天敵である肉食動物から早く逃げるためには、たくさん指があるよりも、蹄のついた1本指のほうが適していたのでしょう。人間はというと、祖先と同じ指の数を“偶然”維持し続けているだけなのです。地球の誕生に比べると、人間の誕生は、ほんの最近の出来事です。もしかしたら、人間はまだ進化の途中なのかも知れません。」
とする。五本指は,進化プロセスの偶然としても,
「両手の指が10本なので10進法が普及した」
など,それが基本発想を左右していることに変りはない。
阿部正路氏は,
「人間の五本の指は,知恵と慈悲と瞋恚と貧貪と愚痴を示すという。」
と書く,
「二つの美徳と三つの悪戸を同時にかねそなえているのが人間であり,人間は二つの美徳で三つの悪を必死でこらえている危ない存在であるからこそ人間なのであって,その二つの美徳を失えば,もはや鬼であり,妖怪である。」
とする。
「瞋恚と貧貪と愚痴」
とは,所謂三毒である。
「仏教において克服すべきものとされる最も根本的な三つの煩悩、すなわち貪・瞋・癡(とん・じん・ち)」
を指す。即ち,
むさぼり,
いかり,
おろか,
である。これのみになった妖怪が,泥田坊である。
鳥山石燕は,『今昔百鬼拾遺』で,
「むかし北国(ほくこく)に翁あり子孫のためにいささかの田地をかひ置て寒暑風雨をさけず時々の耕作おこたらざりしに この翁死してよりその子
酒にふけりて農業を事とせずはてにはこの田地を他人にうりあたへれば夜な々々目の一つあるくろきものいでて 田をかへせ々々とののしりけり これを泥田坊といふとぞ」
と,泥田坊を説明する。
「智恵も慈悲も失って,鬼と化しつつおのれの失われた田地を求めつづける」
まさに,貪る鬼である。阿部氏はこう説明する。
「〈悪〉は『泥田坊』ではない。『泥田坊』を鬼にまでおいやったものなのだ。ここでは酒にふけったわが子に仮託されているが,実はわが子をそこまで追いやったものこそ妖怪なのだ。それは,『泥田坊』の前に決して姿をあらわさず,ために『泥田坊』の三本の指は爪そのものと化しつつ,虚空をあがき,おのれの胸をかきむしる。見開かれた目は,怒りのあまり頭の中心に集まって一つとなる。叫ぶ声は聞こえないが,その身開かれた一つの目は,永遠に閉ざされることなく不気味に光っている。」
参考文献;
阿部正路『日本の妖怪たち』(東京書籍)
http://matome.naver.jp/odai/2143030879212163801
渡邊大門『秀吉の出自と出世伝説』(歴史新書y)
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-15-2-5-0-0-0-0-0-0.html
「あく」は,
悪(惡)
と当てるが,『語源辞典』には,こうある。
「アク(悪)は,中国語をそのまま使っています。中国語源の悪は,『亜(先祖の墓)+心』です。『先祖の墓の前に立っている忌まわしい心』の意です。転じて,醜い心,胴テクニカルスキル的によくない意です。日本語でワルイ名詞形はワルですが,イタズラッ子に使うくらいで,一般的な善悪の悪は,中国語を使っているのです。」
とある。因みに,「ワルイ」については,
「語源は,『ワル(割る・破る)で,割れた物は』は『悪』です。…つまり『壊れた物ハ,ヨクナイ』というのがワルイの語源です。」
とある。漢字の「悪(惡)」の字は,こう説明する。
「亜(亞)の字は,象形文字。建物や墓をつくるために地下に四角く掘った土台を描いたもので,表に出ない下の支えの意から,転じて,つぐことを意味する。堊(建物の土台となる粘土)の原字。また,下でつかえるの意を派生し,唖(のどがつかえてしゃべることができない)・惡(胸がつかえて嫌な気持ち)に含まれる。惡は,『心+音符亞』で,下に押し下げられてくぼんだ気持ち,下積みでむかむかする気持ちや,欲求不満」
と。ここからは,悪(にく)むは出るが,善悪の悪の意味は,出にくい。で,意味を見ると,
いやな行い,
むかつくような状態,
が,
悪いこと,
という意味が並んで出る。好悪は出やすいが,直接には,善悪の悪の意は出にくい。対象に対する価値判断というより,主体の悪感情,マイナス判断から,善悪が出たように見える。
漢字の悪・醜・慝・凶の区別を見ると,
悪は,善の反なり。美惡・醜悪と用ふ。またにくむと訓むときは,音ヲなり,
醜は,形の見苦しき義。好または美の反なり,
慝(とく)は,心のあしきなり。淑の反なり,姦慝,邪慝と連用す,
凶は,吉の反なり,いまいましきなり,
とあり,主体の反応に中心があり,どうやら,西欧で言う,悪とは少しニュアンスが違う。だから,
「儒教と道教には西洋思想にみられるような善悪の対立構造がないが、中国の民間信仰では何か悪い物の影響についてよく言及される。儒教の主要な関心事は知識人や貴人にふさわしい正しい社会的関係・行動にあった。それゆえ「悪」という概念は悪い行動ということになる。道教では、二元論がその中心に据えられているにもかかわらず、道教の中心的な徳に対立する思いやり、節度、謙虚は道教において悪の相似物だと推測できる。」
とする。中国語の「悪」を借りた日本では,
「日本語における『悪』という言葉は、もともと剽悍さや力強さを表す言葉としても使われ、否定的な意味しかないわけではない。例えば、源義朝の長男・義平はその勇猛さから『悪源太』と、左大臣藤原頼長はその妥協を知らない性格から『悪左府』と呼ばれた。鎌倉時代末期における悪党もその典型例であり、力の強い勢力という意味である。」
と,やはり善悪は,こちらの受けとめ次第である。例えば,鎌倉幕府にとって,楠正成が悪党である,というように。
「『古事記』において、『悪事』は『マカゴト』と読ませる(古代の解釈では、悪の訓読みは『マカ・マガ』となる)。対して、『善事』は『ヨゴト』と読む。現代では、マガゴトの漢字は『禍事』を当て、ヨゴトは『吉事』の字を当てていることからも、古代の感性では、禍(か)=災い=悪という図式ということになる。」
というわけで,「割る・破る」を「ワル」とする心性と重なってくる。それは,客観的な価値観というよりは,主体にとっての凶事をさすのであろうか。
『大言海』は,
あしき事,ワロキ事(善に対す)
よこしまなること,人の道に外れたること,無動,悪逆,
木の強き,猛き,荒々しき意として接頭語の如く用いらる,
と説明し,「悪」のニュアンスをよく伝えているのではないか。
阿部正路氏は,
「秦の呂不韋撰の『呂氏春秋』によれば,『妖,悪也』という。また,『妖,怪也』ともいう。〈悪〉とは,人並み秀れた力をもつ者に冠せされたものであること,悪源太義平や悪七兵衛景清にその例をみる。〈悪〉とはまた,怨死者の悪霊を示すなであること,悪七兵衛景清にまつわる説話がおのずから伝えているが,この悪七兵衛景清は,謡曲『景清』や古浄瑠璃『日向景清』においては,目をえぐりとって盲目となり,なおこの世に生き長らえたと伝える。」
と書く。「悪」は,禍々しさを指していることがよくわかる。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA
http://www.youkaiwiki.com/entry/2013/05/12/150634
阿部正路『日本の妖怪たち』(東京書籍)
「つうかあ」は,辞書(『広辞苑』)には,
「『つうと言えばかあ』の約」
と載り,
お互いに気心が知れていて,ちょっと言うだけで,相手にその内容がわかること,
気持ちが通じ合って仲の良いこと,
という意味が載る。
「つうと言えばかあと答える」
の約,というのが正確なのかもしれない。かつてあった携帯電話(僕が最初に手にしたのはこの会社のソニー製であった)の「ツーカーセルラー」の会社名も,この「つーかーの仲」に由来していたそうだが,この言葉,手元の辞書を見る限り,語源がはっきりしない。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/tu/tsuukaa.html
には,
「近世から見られる語で,略した『つうかあ(ツーカー)』,その間柄をいう『つうかあの仲(ツーカーの仲)』は,昭和40年代頃から使用が見られる。『つう』と『かあ』の語源は諸説あり,正確なことは解かっていないが,「つぅことだ」と言った相手に対し『そうかぁ』と答え,内容を言わなくても伝わる関係をあらわしているという説が有力である。
情報が筒抜けであることや滑らかな様子を表す擬態語『つーつー』,事情に通じていることをいう『つう(通)』など,『つう』に関しては他に考えられるものもあり,語呂合わせに『かあ』が添えられたとも考えられる。
その他『通過の仲』の『通過』がくだけた語とする説は,漢語が流行した明治末期から大正にかけて生まれた言葉で,物事が通過するように相手に伝わることを『通過の仲』といったとするものだが,『つうかあ』が略された語であることを考慮されておらず,成立する時代も異なることから考えがたい。
ツルが『ツー』と鳴いて,カラスが『カー』と応えるところからという説は,先に『かあ』をカラスの鳴声に見立て,『つう』に意味を持たせるため『鶴の一声』に関連づけたもので,ツルとカラスの関係は定かではなく,ツルは『ツー』とは鳴かない。」
と,諸説を挙げる。
http://homepage2.nifty.com/osiete/s506.htm
には,その諸説が載っているが,一部挙げてみると,
「話の前置きも無いまま江戸っ子が突然『◯◯つぅことだ』と言ったことに対して相方が『そおかぁ』と答えるだけで互いに理解し合う様子を見た人々が『つうかあの仲』と呼んだ事に由来する」(「これは、江戸っ子同士の会話で、気心知れた仲なら話の前置きも無いまま『○○っつうことだ』と話しかけ、相方が『そうかぁ』と答えるだけで互いに理解し合う様子を見た人々が、『つーかーの仲』と呼んだことに由来するとか。」という言い方の方が伝わるか。)
「『江戸語の辞典/講談社学術文庫』の『つうかあ』の項目では、『つう』『かあ』共に助詞『つ』『か』の長呼『ツー』『カー』と解釈され、『つ』は複合助詞『とさ』の訛『つさ』の『さ』を略したもので、今は多く『と』を用い、『か』は疑問の助詞より転じ、『つ』『か』は鼻唄をうたう時など詩の末尾に付ける一種の詠嘆助詞とされています。用例として、十返舎一九の『六あみだ詣』文化8(1811)年から『潮来うたへばとて文句のしまいにツウだのカアだのというもの向ふ見ずはしかたがねへ』を掲げています。」
「明治末期から大正にかけて、漢語が大流行し、一般の庶民もやたらに漢語を振り回した時期があり、そんな時代に誕生したのが『通過の仲』、すなわち『ツーカーの仲』で、物事が通過するように、こちらの意思が相手に伝わるというような意味で使われた。」
「つうといえばかあ、という意味でのつうは『通』という漢字が当てはまり、『食通』とかのように、何かに特に優れていたり、良く知っていることを言ったもので、『ツーカーの仲』とは本来的に多少意味がずれた使い方をされていたように思います。ですから、『あの人に聞いたらパソコンのことは、つうと言えば、かあで分かっちゃうよ」というような表現で使われていたようです。」
「ツルの『ツウ』という鳴き声と、カラスの『カア』という鳴き声のことです。
ツルのように白く、カラスのように黒い、見かけは相反するようであっても、ツウと鳴き、カアと応える姿は実に仲が良いわけで、『ツーカーの仲』と言います。」
等々。ただ,上記の,「『江戸語の辞典』(前田勇、講談社学術文庫)にある,
「つう-かあ(助)
共に助詞「つ」と「か」の長呼。「か」は疑問の助詞より転じ、鼻唄をうたう時など、詞の末尾に付ける一種の詠嘆助詞。」
と,助詞の「つ」「か」が伸びたもの,という説は,『語源を知れば日本語がわかる』(柚木利博、ふたばらいふ新書)にも,
「『ツー』は助詞の『つ』、『カー』は助詞の「か」がそれぞれ伸びたもので、唄の合いの手などに用いられたという話もあります。」
とある由で,これが,まっとうのように思える。つまりは,
唄の合いの手,
ということだ。その呼吸というか,間合い,を「つうかあ」というのは,現実味がある。
合いの手,
は,
「間(アイ)+手」
で,『大言海』は,
間の手事(てごと)の略,
とする。
「音曲にて,唱の間(あひ)に,琴,三味線の楽器のみにて奏する手事。」
とある。『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/a/ainote.html
には,
「元は邦楽用語で,『あい』は『間』を意味し,『て』は,『メロディー』『楽曲』『調べ』などを意味する。そこから唄や踊りの間に入れる演奏を『合いの手』というようになった。さらに,会話などの進行を促すために,相手の話の合間に挟む言葉も言うようになり,漫才のボケに対するツッコミや,インタビューの聴き手のことばも言うようになった。」
とある。そう考えると,類語は,ウマが合う,肌が合う,気が合う,というのとは少しニュアンスが違う。
息が合う,
とか
阿吽の呼吸
とか
以心伝心
が,近いのだろう。
開眼は,
かいげん,
と訓むのと,
かいがん,
と訓むのとでは,少し意味が違う。
「かいがん」
は,読んで字の如く,「眼」を「開く」で,
目が見えるようになること。また,見えるようにすること,
だが,
「かいげん」
と,訓むと,意味が特定される。辞書(『広辞苑』)には,
新たに出来た仏像・仏画像の眼を入れ,仏の魂を迎い入れること,また,その法会,開眼光,解明,入眼(じゅがん),
とある。「大仏開眼」「開眼供養」という言い方をする。
そのメタファで,
慧眼を開くこと,仏道の心理を悟ること,一般に芸道などで悟りを開くこと,
となり,さらに,世阿弥が,
演者の演技によって,見物人を感激させることのできる一曲の山,三道,
という意味で使う。
「一番の眼を開く妙所なれば,開眼と名付く」
と。因みに,開聞とも言うらしく,
文句と節がぴったり融合して見物人に感動を起こさせる一曲のやま,三道,
で,
「理曲二聞を一音の感に現す境を開聞と名付く」
と。
「かいがん」「かいげん」両者違いはあるが,それを敷衍させていくと,共に,
物事の道理や真理がはっきりわかるようになること。また,物事のこつをつかむこと,
という意味になり,
俳優開眼,
を,「かいがん」とも訓ませるとするようだが,しかし,
二刀流開眼,
は,「かいげん」と訓ませるのが,妥当とすれば,やはり,本来の趣旨からすれば,「かいげん」が正しいのではないか。
語源は,中国語で,
「仏像仏画を供養して,仏の霊を迎える儀式」
とされる,それが転じて,芸道の心理を悟る,に広がったので,「かいがん」と訓ませるのは,
文字通り眼が開く,
眼が見えるようにする,
の意味に限定されるのだろう。『大言海』には,
「天智記,十年十月『開百佛眼』とあり,筆にて點眼することなりと云ふ」
とある。因みに,「眼」と「目」の違いは,「眼」の字は,
「艮(こん)は,『目+匕首(ひしゅ)の匕(小刀)』の会意文字で,小刀で句まどっため。または,小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は,『目+艮』で,艮の原義をあらわす」
とある。で,「艮」の字を調べると,
「会意文字。『目+匕(小刀)』で,小刀で目の周りにいつまでも取れない入墨をすること。あるいは視線を,小刀で突き刺すようにひと所にとめることをあらわす。一定の所にとまっていつまでもとれない,の意を含む。」
とある。一方,「目」の字は,
「象形文字で,めをえがいたもので,瞼に覆われているめのこと」
とある。
「開」の字は,
「会意文字。門のかんぬきを両手ではずして,門をあけるさま,または,『門+幵(平等に並んだ姿)』で,とびらを左右に平等に開くことを示す」
で,どうやら,心を啓く,という意味の場合,
かいげん
でなくてはならず,開いている限り,「目」ではなく,「眼」でなくてはならない。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
何やら引導を渡されたような気分で,目の前が真っ暗というか,頭の中が真っ白になる,ということがある。
引導とは,辞書(『広辞苑』)には,
仏教用語,迷っている衆生を導いて,仏道に入らせること,また,死者を済度するため,葬儀の時導師が棺前でに立ち,転迷開悟の法話を解くこと,
導くこと,手引き,
と載る。「引導を渡す」と言う言い方をするが,上記の仏教用語から転じて,
最後の決意を宣告してあきらめさせる,
とある。
http://www.shorinzenji.com/%E4%BD%8F%E8%81%B7%E3%81%AE%E8%A9%B1/%E5%BC%95%E5%B0%8E%E3%82%92%E6%B8%A1%E3%81%99/
では,
「私の場合、葬儀の開式から25分から30分で引導です。
故人の生前での生き方や功績などを讃えます。
その後、死の事実を認識させ、現世の執着を棄て、悟りの道(仏道)へ進むよう説き、この世から悟りの世界へお導きさせて頂きます。
最後の方では、「喝(カツ)」「露(ロ)」などと目が覚めるように激しく悟りを促したり、「咦(いぃ~)」など優しく説いたりします。
事実(真実)を語り、故人様が自らの死に向き合うための儀式でもあります。」
と,具体的な「引導の渡し方」の例示がある。つまりは,
「死んだことをわからせる儀式であることから,相手が諦めるための最終的な宣告のいみでつかわれるようになった」
と,『語源由来辞典』には載る。『語源辞典』には,
「中国語の『引(手引き)+導(導く)』が語源です。仏教で,衆生を導き善道に入らせること,をいいます。」
とあるところからも,ほぼ仏教語なのだろうとは思う。しかし,
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/287629.html
には,
「『引導』というのは、元々中国で古くから使われていた言葉で、特に『道教』では、一種の気息術か、呼吸法で、大気を吸い込むことを言いました。しかし、普通の言葉として、『手引きする』『案内する』というような意味があります。
仏典を漢訳するとき、サンスクリット語 parikarsana
の訳語に、この『引導』を選んだのです。『法華経』では、人々を導いて仏道に入らせる意味で使われています。また、死者を済度する意味でも使います。
後に、死者の葬儀の時、導師が、棺の前で、法語や仏教の教えの詩(ガーター)を語って、死者を、迷界から浄土へと導くよう試みる儀式のことになります。
これを、『引導を渡す』と言います。『迷界から浄土へ導く』とは何かと言うと、これは、死者に、『死んだ事実』を確実に認識させ、現世への執着を棄て、悟りの仏道へと進むよう説くことだとも言えます。つまり、『お前は間違いなく死んだ』ということを、死者に宣言する儀式にもなります。こういう『引導を渡す』という形の儀式をしたのは、中国黄檗集の祖、黄檗希運で、彼は9世紀頃の人です。」
とあり,本来は,日常的にも使われていた,「引導」を,転訳したというのが,正確にようだ。
その意味で,『大言海』は,最初に,
ひき,導くこと,てびき,
という意味を最初に載せ,見識を示す。例示として,
「有羣(ぐ)魚躍水飛空引導」
と,南史を引き,
「右大臣殿,此事引導口入,可進名簿歟」
と,明月記の例も引く。その意味では,始まりはともかく,「引導」が,
手引き,
という意味を持っていたために,転用されたことをよく示す。
因みに,「引」という字は,会意文字で,
「弓+|印」で,|印は,直線状に↓と引くさまをしめす,
と言う。「導」という字は,
「道は,『辶(足の動作)+音符首』の会意兼形声文字で,頭を一定の方向に向けて進むこと。また,その道。導は,『寸(て)+音符道』で,道の動詞としての意味を示す。」
で,一定の方向に引っ張っていく,と言う意味になるが,
「古くは,道で代用した。訓の『みちびく』は,『みち(道)+引く』から」
と,注記がある。因みに,「寸」が「て」というのは,「寸」の字が,
「『手のかたち+一印』だ,手の指一本の幅のこと。一尺は,手尺の一幅で,方向に22.5㎝。指十本の幅が丁度一尺をあらわす」
という謂れから。
「引導を渡す」の類語はあまりないが,「とどめを刺す」と対比して,
「(引導を渡すは)仏教用語から転じて、『最終的な宣告をして、諦めさせる』という意味があるようですが、これは『最終的な宣告をする』にウェイトがあります。引導を渡しても、相手が納得するとか、諦めるとは限らないからです。
仏教なら、『お前は死んだのだ、そのことを知り、成仏せよ』と引導を渡しても、死者が納得せず、この世への未練から、亡霊などになったり、輪廻に落ちるということは、別に珍しいことでもないからです。
他方、『止めを刺す』というのは、殺したはずの相手を、生き返る余地などないように、念を押して、首を突くとか心臓を刺して、死を確実にすることです。ここから転じて、念を入れて、終わらせるという意味になります。」
.
とあった。引導は,メッセージだが,とどめは,アクションというわけである。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
「ぬし」は,
主,
と当てて,辞書(『広辞苑』)には,
土地や家などを領有し,支配する人,また一般に,ある事を主宰する人,首長,君主,
主人の尊称(後世は尊敬の意を失う),
人・相手の尊称,
所有者,持ち主,
ある行為をした人,ある事柄の中心となる人,当人,
おっと,良人,
山または河などにふるくから住んでいる霊力があるといわれている動物。転じてある場所に長く住んでいる人,
という多様な意味があるが,ほぼ「あるじ(主)」と同義で使われているようだ。『古語辞典』を見ると,
「『…の主人(うし)』のつづまった『…ぬし』が独立して名詞となったものか」
とあり,最初に,
主人,主君の尊称,
(自分に対して主人の位置にあるものとして扱う意から)人・相手の尊称,
とある。それが,だんだん下へ落ち,終には,「この部屋のぬし」の位置まで下落する。
代名詞としての「ぬし」も,『古語辞典』にあるように,従って,
(敬意をこめていう)二人称あなた,
からやがて,
三人称,あのかた,
となるが,これは近世遊女が用いたという。現代だと,これが,辞書(『広辞苑』)には,
あなた,女性から親密な男を呼ぶ語,
という使い方になる。まだ,親愛が残っているだけましかもしれない。しかし,わざわざ,「おぬし(御主)」と,「御」をつけるところからみると,代名詞としては,敬意を込めるには,「ぬし」では足りないと感じるところまで,「ぬし」のイメージが下がっているのかもしれない。
『大言海』には,
「之大人(のうし)の約という。後,誤りて,ノシと云ふ。沖縄にてヌウジ,朝鮮古語,君長の義に,ニシコムと云へり。又,アイヌ語に,ニシバ(殿の意)と云ふ語あり。」
と注記して,
「相手を敬ひ,又人を尊称するに添ふる語。大人(ウシ)と云ふに同じ。」
とある。『語源由来辞典』をみると,
「ウシ(大人)に接尾語ノ(n)が加わった語」
とあるが,大人(うし)の語源を見ると,
ぬしの変化説,
「ウ(大)+シ(人)」の二音節説,
があるが,『大言海』は,
「ウは,おほの約,う(大)の條を見よ。シは,人の意。某(それ)がし,とじ(刀自),みやじ(宮司),沖縄にて,王,又は,地方の頭を,ううぬし(大主)と云ふ」
とあり,「ウ(大)+シ(人)」に軍配が上がる。
それにしても,代名詞として使うとき,
お前
にしろ,
貴様
にしろ,
かつては,「おまえ」が,
御前
で,神仏や貴人の前,
という意味だったり,「貴様」が,
中国語の貴兄などを真似て,「アナタ+サマ」,
の意で,貴信,貴殿,貴君,貴官等々と同じく造語した和製漢語だったりしたのと同様,相手を敬う意であったものが,いまでは,貴様も,『日本語語感の辞典』には,
「同等以下の相手を見下したりして言うときのぞんざいな表現」
とあり,例の「貴様と俺とは同期の桜」というよりも,言われた側の印象が落ちている。
「お前」も,『『日本語語感の辞典』では,
「主に男性が目下かごく親しい相手に使うぞんざいな二人称」
で,確か,女性は,「お前」と会社で呼ばれるのに抵抗があると,記事で見たことがあるほどに,格が下がっている。
手前,
というのは,本来,一人称で,
自分のことをへりくだって言う語,
であったはずなのに,いまでは,
「てめえ」
という言い方で,
相手を見下す二人称
に変っているのとつながるのかもしれない。それは,身分差が,表面上無くなっているようになっていくのに,リンクしているような気がする。しかし,言葉は,
相手がどう受け止めたか,で自分の発話の意味が決まる,
という文脈依存性が高い,それは,時代に合う言葉を使わないと,誤解を招く,ということでもある。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
「かっぱ」は,
河童
と当てる。辞書(『広辞苑』)には,
カワワッパの約,
とあるが,『大言海』には,
「河童(かわわらわ)の約なる,カワワッパを,再び,約めたる語」
とある。これが正確だろう。
辞書(『広辞苑』)にある意味の多さに驚く。
想像上の動物。水陸両生,形は四五歳の子供のようで,顔は虎に似,くちばしはとがり,身にうろこや甲羅があり,毛髪は少なく,頭上に凹みがあって,少量の水を容れる。その水のある間は陸上でも力強く,他の動物を水中に引き入れて血を吸う。河郎,河伯(かはく),河太郎,旅の人,かわっぱ。
とまずは,河童の説明がある。しかし,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E7%AB%A5
には,
「川や沼の中に住む。ただし例外に地行浜(現在、福岡ドームが建っている辺り)の酒飲み河童は、海に住む。泳ぎが得意。悪戯好きだが悪さをしない妖怪として伝えられる場合もあるが、多くは水辺を通りかかったり、泳いだりしている人を水中に引き込み、おぼれさせたり、「尻子玉」(しりこだま。尻小玉とも書く)を抜いて殺すなどの悪事を働く。抜いた尻子玉は食べたり竜王に税金として納めたりする。尻子玉とはヒトの肛門内にあると想像された架空の臓器で、これを抜かれるとふぬけになると言われている。この伝承は溺死者の肛門括約筋が弛緩した様子があたかも尻からなにかを抜かれたように見えたことに由来するようである(尻子玉は胃や腸などの内臓を意味するという説もある)。」
とあって,多少異説はある。この河童の泳ぎや形態,河がらみからのメタファから,
泳ぎの上手な人
頭髪を真ん中を剃り,まわりをのこしたもの(おかっぱ)
見世物などの小屋にいて,観客を呼び込む者。合羽
(川に船を浮かべて客を呼ぶところから)江戸の柳原や本所などにいた私娼,船饅頭
河童の鉱物であるからというキュウリの異称
と意味が続く。しかし,キュウリの異称というのは,少し行き過ぎで,正確には,
キュウリを芯にして巻いた海苔巻,
をカッパ巻,といい,略してカッパというのが正確のようだ。ちなみに,キュウリは,
「黄+瓜」
で,熟した色から命名したのが語源で,「胡瓜」の字は,中国語表記を借用している。ついでに,合羽(哈叭)は,
ポルトガル語capaで,ラテン語cappa(頭巾)から来た言葉,
で,マント型の雨着のこと,合羽は当て字らしい。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/ka/kappamaki.html
には,かっぱ巻について,
「かっぱ巻は、河童の好物が『キュウリ』だからといわれる。 その他、河童の総本家『水天宮』の紋章と、キュウリの切り口が似ていることから、キュウリを『かっぱ』と呼ぶようになったとする説もある。」
としている。この点について,
http://okwave.jp/qa/q1676566.html
では,
「キュウリが夏祭りの神へのお供え物で、かっぱの起源が水の神であったことの名残だということです。そうしたことから、キュウリの異称に『かっぱ』があります。
もうひとつ。
昔、かっぱは水神が妖怪化したものと考えられていたそうです。きゅうりは水神信仰とむすびついていたので、夏が近づくと、疫病や水難をさけるため、きゅうりを川に流す風習が全国的にあったそうです。ここからかっぱ=きゅうりになったと言われています。」
とあり,河童が水の神と近いことを思わせる。因みに水天宮の本宮は,
http://www.suitengu.net/saizin.html
にあるように,久留米にある。謂れは,ともかく,
「当宮は古来農業、漁業、航海業者間に信仰が篤い」
とされ,それを,
「留米の水天宮は久留米藩歴代藩主(有馬家)により崇敬されていたが、文政元年(1818年)9月、9代藩主有馬頼徳が江戸・三田の久留米藩江戸上屋敷に分霊を勧請した。これが江戸の水天宮の始まりである。」
とあるように,分社したのが,東京の水天宮らしい。
一概に水だけにつなげられないのは,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E7%AB%A5
に,
「河童の由来は大まかに西日本と東日本に分けられ、西日本では大陸からの渡来とされるが(河伯信仰)、東日本では安倍晴明の式神、役小角の護法童子、飛騨の匠(左甚五郎とも)が仕事を手伝わせるために作った人形が変じたものとされる。両腕が体内で繋がっている(腕を抜くと反対側の腕も抜けたという話がある)のは人形であったからともされる。大陸渡来の河童は猿猴と呼ばれ、その性質も中国の猴(中国ではニホンザルなど在来種より大きな猿を猴と表記する)に類似する。
河神が秋に山神となるように、河童も一部地域では冬になると山童(やまわろ)になると言われる。大分県では、秋に河童が山に入ってセコとなり、和歌山県では、ケシャンボになる。いずれも山童、即ち山の神の使いである。また、河童は龍などと同じ水神ともいわれる。山の精霊とも言われる座敷童子などと同様に、河童も一部の子供にしか見えなかったという談がある。」
とあり,どうやら,日本の通例で,神ないし,信仰の対象は,尊崇を失うと,妖怪化するらしい。言葉が,御前が,おめえ,と罵り言葉に変るのと,通底しているような気がする。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』(角川ソフィア文庫)
大根役者は,約めて,
大根,
とも言う。
芸の拙い役者や俳優を見下す言葉,
という意味である。三文役者とも言う。因みに,「三文」とは,「三文判」という言い方をするように,
銭三文,
とは,価値が低い,という意味らしい。最近は言わないが,三文オペラ,三文文士,と言った使い方をする。しかし,なぜ,
一文,
ではなく,三文なのだろうか。
早起きは三文の徳,
という言い方をしたり,
二束三文,
という言い方をするところを見ると,「三文」に意味があったのかもしれない。「二束三文」の意に,
二束でも三文しかならないわずかな価値,
と
二束にするとわずかな価値が見出せる意,
とあるところを見ると,一文銭では,意味をなさず,三文,というところに意味があったのだろうか。
一文無し,
は,文無し,の意味だが。「ときそば」では,二八そばが十六文,しかしもとになった,笑話本「軽口初笑」の「他人は喰より」では、そばきりの価格は六文。三文ではそばも食べられないが。
話を大根役者に戻すと,『日本語語感の辞典』に,こうしいう逸話が載っている。
「小津安二郎監督は撮影中にスタジオが暑過ぎて,これじゃ映画じゃなくて納豆をつくるところだとぼやいた後で,『君たちはいいよなあ大根で,芋ならとっくにふけている』とからかったという。」
語源は,諸説ある。たとえば,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%A0%B9%E5%BD%B9%E8%80%85
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E6%A0%B9%E5%BD%B9%E8%80%85-162214
等々には,
「大根は食材として利用範囲が広く、どのような調理を行ってもめったなことでは食中り(しょくあたり)せず、大量に食べても消化を促進する成分を含み殺菌作用があり漢方薬としても用いられることから腹をこわすことがない。食中りすることを食べ物に中たると表現することから大根はあたることがない。役者が何かの演目や配役でヒットし、人気が出て成功することをあたると表現することから、役者として当たらない、または当たりのとれないことをかけたとする説。」
「何かしらの理由で役者が演目の配役を外されることを舞台が観客席よりも高い位置にあったことから下ろすと表現する。演技の下手な役者は観客動員数を左右することで演目の興行成績にも影響し、早々に舞台から下ろされることが通例である。このことから役者を下ろすことと大根の簡単な調理法として卸金(おろしがね)を用いてすり砕く大根おろしの卸すをかけたとする説。」
「演技が下手なために人の役まで至らず、馬の前足・後ろ足を演じ、馬の脚が大根を連想させた、とする説。」
「役者の付き人や予備の役者を『ダイコウ』と呼び、訛ってダイコンとなったとする説。」
「大抵の大根の品種は中身が白いことから、技量が乏しく表現力に欠けた役者や俳優の演技は素人同然である。このことから白いのしろと素人のしろをかけたとする説」
「演技の下手な役者は白粉(おしろい)を多用することから白をかけたとする説。」
「演技の下手な役者が舞台に出ると場が白けるとする説。」
「大根の根の白いことを素人(しろうと)に寄せていった説」
等々が諸説出ている。『語源辞典』には,
下手な役者ほど白粉をぬりたくるから,
白いだけの下手な素人役者,というシロい大根の役者という洒落,
大根に食中毒がないところから,当たらない役者,つまり下手な役者を意味する,
と,出ている。『大言海』は,
「大根の根は白き故,しろうと(素人)のシロに寄せて云ふとぞ」
と,大根の白さから来たという説を取る。『大辞林』は,食あたりしない説を取っているらしい。まあ,通説はないのだが,文化文政時代,
沢庵大根は,1本=15文,
だったらしいから,少なくとも,
大根役者,
と呼ばれる方が,
三文役者,
といわれるよりはまし,ということになるのかもしれない。
因みに,
英語圏では大根役者を,
ham actor,
ham
と呼ぶらしい辞書では,
演技過剰の大根役者,
とあった。ほかに,
しろうと(amateur)
とある。大根役者とは,洋の東西,
演技がオーバーなへぼ役者(な素人),
を指すことに変りはないようだ。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
掣肘は,
せいちゅう
と訓むが,辞書には,
「《『呂氏春秋』審応覧・具備にある、宓子賤が二吏に字を書かせ、その肘を掣(ひ)いて妨げたという故事から》わきから干渉して人の自由な行動を妨げること。」
という意味になる。この『呂氏春秋』とは,漫画『キングダム』の,嬴政(えいせい),後の始皇帝の政敵,相国・呂不韋が食客を集めて共同編纂させた書物,である。
『呂氏春秋』「審応覧・具備」については,
http://www.kokin.rr-livelife.net/classic/classic_oriental/classic_oriental_156.html
に詳しいが,原文の当該箇所は,
「宓子賤(ふくしせん)、亶父(たんぽ)を治むるに、魯君の讒人(ざんじん)を聴きて、而して己をして其の術を行うを得ざらしむるを恐る。
将に辞して行くに、近吏二人を魯君に請ひて、之と倶ともに亶父に至る。
邑吏(ゆうり)の皆な朝するに、宓子賤、吏二人をして書せしむ。
吏の方(まさ)に将(まさ)に書せんとするに、宓子賤、旁(かたはら)従(よ)り時に其の肘を掣搖(せいよう)す。」
である。哀公への宓子賤の諫言,という落ちである。子賤は,孔子の弟子である。
「掣」の字は,
「制の左側は,『木+/印』の会意文字で,木材の必要な部分を斜めに断ち切るさまを示す。制はそれに刂(刀)を加えた字で,刀で必要なだけ切り取り,他を切り捨てること。掣は,『手+音符制』で,相手の行動を途中で切ってとめること」
である。おさえる,とか,相手の行動をおさえて勝手に行動させない,といった意味になる。「制」にも,勝手な振る舞いを抑える意味があり, 「制肘」とも書く。
「肘」の字は,
「『肉+寸(手)』。もと丑が腕を曲げたさまを示す字であったが,十二支の名に転用されたため,『肉+丑』の字がつくられた。それと肘とはまったく同じ」
とある。因みに,漢字では,一口に「ひじ」といっても,
肘(腕の関節,臂は中部の湾曲せるところ,肘はその外側)
肱(臂の第二節,肘より腕に至るまで)
臂(肘より腕に至る間,手の上部)
臑(かいな,肩より肘に至る間。)
と書き分けている。和語「ひじ」は,「ひざ」に対して,
「ヒジ(曲げる)」
で,腕の関節の曲がる部分を指す。『古語辞典』には,朝鮮語と同源,とある。『大言海』は,
「引縮(ひきちぢ)みの意にもあるか」
として,動作からの言語化を取る。
「ひざ」は,
「ヒジ(曲げる)」の転,
「ヒ(引く)+ザ(いざる)」で,肢をひきいざる部分,
の二説ある。『大言海』は,ここでも,
「ひき,ゐざるの意。坐儀に進退するより云ふか」
と,動作から来ているとみる。どうもその方が,理にかなう気がする。
さて,掣肘であるが,多くは,
掣肘を加える,
といった使い方をする。
牽制する,
という意味だが,語源から考えると,
横槍を入れる,
水を差す,
容喙する,
介入する,
ちょっかいを出す,
というのもあるが,直截的には,
邪魔をする,
というのが近い。因みに,横槍を入れるというのは,
横を入れる,
とも言い,
攻撃の最中に,別の軍が敵の側面から攻撃すること,
を言い,室町時代以降,突撃の主力は槍なので,「横槍を入れる」というようになった,とある。それが,矢による場合,
横矢,
というらしい。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
笹間良彦『図説日本戦陣作法事典』(柏書房)
本分は,辞書(『広辞苑』)によると,
その人の守るべき本来の分限,
ひとやものの本来備わっているもの,本来の性質,
とある。その二つをつなげると,神田橋條治氏の言う,
自己実現とは遺伝子の開花である,
という言葉が意味を持つ。その言葉は,
「鵜は鵜のように,烏は烏のように」
と続く。鳶は鳶であり,鷹は鷹である,鳶は鷹にはならない。だから,前にも書いたが,
「自分が鵜なのか,鷹なのか」を見極めること
こそが,修行となる。その「分」については,「分」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E5%88%86)
で書いたが,意味は,
各人にわけ与えられたもの。性質・身分・責任など,
の意味で,分限・分際・応分・過分・士分・自分・性分・職分・随分・天分・本分・身分・名分等々という使われ方をする。そこでも書いたが,「分」の字は,
「八印(左右にわける)+刀」
で,二つに切り分ける意を示す。とすると,分け与えられた,
天分
であり,
性分
であり,
職分
であり,
名分,
を尽くす,ということになる。名分とは,孔子の言う,
名正しからざれば,則言順(したが)わず,言言順(したが)わざれば,則事成らず,
を思い出す。いろんな解釈があるが,僕は,
持っていることばによって見える世界が違う,
というヴィトゲンシュタインの言葉を思い出す。つまり,その言葉はその人の思いを示す。
先の文に続いて,孔子は,
君子これに名づくれば必ず言うべきなり,これを言えば必ず行うべきなり,
という。
綸言汗の如し,
に通ずる。まさに,これこそ,
本分
である。語源は,
「本(もともと)+分(つくすべき義務)」
で,尽くすべきつとめ,であるとして,しかし,本分は,
天分,
だとして,天命と重なるものなのか,天については,「天」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E5%A4%A9)
に書いた。
天命を具体的に自分の課題としようとするとき,
おのが分,
に突き当たる。鵜は鷹にはなれない。それを,つとめで表現すれば,
本務
になる。
その中身が,
職務,
任務,
責務,
義務,
と,なるのだろう。
職務は,担当する任務。任務を役割分担した具体的な分担業務。
任務は,自分の責任として課せられたつとめ,であるから,本分の具体的な課業になる。責務について,それをおのれの任務として自覚し直せば,責務になる。自分が全うすべき(とは当事者としてすべての責任を負うべき)つとめ,という自覚ということになる。
義務は,辞書(『広辞苑』)的には,「自分の立場に応じてしなければならないこと」とあるが,『論語』に,知とは,
民の義を務め,鬼神を敬して遠ざく,
とある。知とは,実践である,という。
参考文献;
神田橋條治『技を育む』(中山書店)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)
「花に嵐」とは,
花に嵐とは、良いことには、とかく邪魔が入りやすいことのたとえ,
として使われる。
『故事ことわざ辞典』
http://kotowaza-allguide.com/ha/hananiarashi.html
には,
「好事を『花』に見立て、『嵐』はそれを散らして吹く激しい風の意。花がきれいに咲くと、激しい風が吹いて撒き散らしてしまうことから、良いことにはとかく邪魔が入りやすいことをいう。『花に風』とも。」
とある。「花に嵐」と言うと,前にも挙げたが,于武陵の「勧酒」という漢詩,
勧君金屈巵 君に勧(すす)む金屈卮(きんくつし)
満酌不須辞 満酌(まんしゃく)辞するを須(もち)いず
花発多風雨 花発(ひら)けば風雨多し
人生足別離 人生別離足る
を,井伏鱒二が,
コノサカヅキヲ受ケテクレ
ドウゾナミナミツガシテオクレ
ハナニアラシノタトヘモアルゾ
「サヨナラ」ダケガ人生ダ
と訳した。
http://homepage1.nifty.com/yasuki-a/toku-kanshu.html
によると,井伏は,
「講演のため林(芙美子)とともに尾道へ行き、因島(現尾道市)に寄ったが、その帰り、港で船を見送る人との別れを悲しんだ林が『人生は左様ならだけね』と言った。井伏は『勧酒』を訳す際に、この
“せりふ” を意識したという」
とある。僕は,この訳詩を,田中英光の
『さようなら』
で知った。太宰治が,それを,絶筆
『グッドバイ』
に,このフレーズを載せた,といわくつきである。
「花に嵐」に似た言い回しに,
好事魔多し
寸善尺魔
月に叢雲(「花に風」と続く)
花発いて風雨多し
等々がある。しかし,これは視点を変えれば,たとえば,
人間万事塞翁が馬,
という言い方になる。それは,
「人間万事塞翁が馬とは、人生における幸不幸は予測しがたいということ。幸せが不幸に、不幸が幸せにいつ転じるかわからないのだから、安易に喜んだり悲しんだりするべきではないというたとえ。」
という意味であり,
『故事ことわざ辞典』
http://kotowaza-allguide.com/ni/saiougauma.html
によれば,
「昔、中国北方の塞(とりで)近くに住む占いの巧みな老人(塞翁)の馬が、胡の地方に逃げ、人々が気の毒がると、老人は『そのうちに福が来る』と言った。
やがて、その馬は胡の駿馬を連れて戻ってきた。
人々が祝うと、今度は「これは不幸の元になるだろう」と言った。
すると胡の馬に乗った老人の息子は、落馬して足の骨を折ってしまった。
人々がそれを見舞うと、老人は「これが幸福の基になるだろう」と言った。
一年後、胡軍が攻め込んできて戦争となり若者たちはほとんどが戦死した。
しかし足を折った老人の息子は、兵役を免れたため、戦死しなくて済んだという故事に基づく。
単に『塞翁が馬』ともいう。『人間』は『じんかん』とも読む。」
となる。これは,『淮南子(えなんじ)』人間訓にある故事による。似たものに,
禍福は糾える縄の如し,
沈む瀬あれば浮かぶ瀬あり,
楽あれば苦あり,
上り坂あれば下り坂あり,
楽は苦の種、苦は楽の種,
となる。たとえば,「禍福は糾える縄の如し」とは,
幸福と不幸は表裏一体で、かわるがわる来るものだということのたとえ,
であり,
『故事ことわざ辞典』
http://kotowaza-allguide.com/ka/kafukuazanaerunawa.html
によれば,これも,『史記・南越列伝』『漢書』によるらしく,
「『史記・南越列伝』には『禍に因りて福を為す。成敗の転ずるは、たとえば糾える縄の如し』とあり、『漢書』には『それ禍と福とは、何ぞ糾える縄に異ならん』とある。」
という,因みに,
「糾える」は文語動詞「あざなふ」の命令形+完了を表す、文語助動詞「り」の連体形からで、「あざなふ(糾う)」は「糸をより合わせる」「縄をなう」
を意味するそうだ。「花に嵐」と「塞翁が馬」と違いがあるとすると,
月に叢雲
と
禍福
との,時間軸の長さだろう。
参考文献;
井伏鱒二『厄除け詩集』(筑摩書房)
田中英光『さようなら』(現代新書)
「二才野郎」の二才は,
青二才,
というときの,
二才である。青二才については,「若造」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E8%8B%A5%E9%80%A0)
で,「若造」に関連して,触れたが,「青」は,未熟の意。
人柄,技両の未熟なること,
と,『大言海』にはある。二才は,
「アオ(未熟)+ニサイ(幼魚)」
で,ボラなどの幼魚を二才,というのに喩えて,
歳若く経験の乏しい男を罵って言うという。
『語源辞典』には,
「アオ(若く,経験浅く,未熟)+ニサイ(新背,新成人)」
とする説もある,とする。若者組に入る新入りを,「新背(にいせ)」といい,それが訛ったとする。
『語源由来辞典』
http://gogen-allguide.com/a/aonisai.html
には,
「青二才の『青』は、『青臭い』や『青侍』などと用いるように、未熟な者を表す接頭語。 青二才の『二才』には二通りの説があり、正確な語源は未詳。
ひとつは、若者組(現在の青年
団)に入るニューフェイスを『新背(にいせ)』といい、転訛して『にさい』になったとする説。この説では,新来者を馬鹿にする言葉として『青にせー』という語が生まれ,『五才』を『ごせー』『六才』を『ろくせー』と言うことから、『二才』の字が当てられ『青二才』になったとされる。九州南部地方では、若者を『にせー』や『にさい』と言う。もうひとつは,ボラなどの稚魚を『二才魚』『二才子』『二才』などと呼ぶことから喩え、『青二才』となったとする説で,一般的にはこの説が有力とされている。」
と,懇切に説いている。
「二才野郎」
という罵り言葉があるらしいが,二才とは,
若造,
といったニュアンスになるのだろう。『大言海』は,
動物の生まれて二年になるもの,特に,すずき,ぼらなどの二年子,
と載せて,加えて,
若者を卑しめて罵る語,
とあり,
毛二才
とか
小二才
といった言い方もしたらしい。
「野郎」についても,「野郎」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba1.htm#%E8%8B%A5%E9%80%A0)
で触れたが,野郎の語源は,
「ワラワ(童)変化,和郎」
と,
「ヤ(野)+ロウ(郎)」
の混淆した語,とされる。
「和郎(若者・若僧)と野郎(田舎者)は,どちらも男を罵る語」
とあるところを見ると,罵る言葉の原義らしい。つまり,
二才野郎,
というのは,
「青二才」
に加えて,
野郎のもつ言葉の陰翳,
「おかま」
という罵りのニュアンスを込めているように見える。前にも書いたように,『大言海』は,
野郎
野良
の字を当て,まず,
「薩摩にて,人を罵り呼ぶに和郎(わろう)と云ふ。此語,童(わらわ)の音便なるべし,(童は,古へは,冠を放ちて,わらは形なるを,痛く卑しむる世なれば,云ひしなり)其の和郎の野郎に転じたるなり。さやぐのさわぐ,わやくのわわくの類なり」
と注記し,
「薩摩詞にて,男子を卑しめ呼ぶ語と云ふ。又,貴人にむかへて,下郎を賤めて云ふ」
が意味の最初に来る。次に,
「承応元年,若衆歌舞伎の男色を売る甚だしきによりて,令して前髪を剃り落さしめ,成人の如くならしめし者の称。紫の帽子を被りて,成人の姿を隠す。これに因りて,野郎頭,野郎帽子の名起こる。」
とある。これが転じて,
「直に孌童(かげま)の称。」
と変る。しかし,前にも,「野郎」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E9%87%8E%E9%83%8E)
で書いたが,新渡戸稲造が美化した「武士道」への批判として,
「薩摩琵琶と関係の親密な『賤のおだまき』は之を何とか評せん。元禄文学などに一つの題目となれる最も忌まわしき武士の猥褻は,余りに詩的に武士道を謳歌する者をして調子に乗らざらしむる車の歯止めなるべし。
」
とあったように,「薩摩藩でとりわけ男色の習俗が顕著」であったらしいことを思うと,微妙なのだが,だとしても,というか,だからこそ,
二才野郎,
などと表面きって罵られることは,最大の恥辱だったに違いない。
「まじめ」は,
真面目,
と当てるが,辞書(『広辞苑』)によると,
まじめ,
というのは,「まじめ」と書いて,まったく別の意味もあるらしいのである。即ち,こうある。
「(鎮静の意,漁村語)黎明と朝,夕方と黄昏との境目をそれぞれ,朝まじめ,夕まじめ,という。この時刻は深海の魚類も水面近くに浮くので,好漁の潮時。まずめ,まずみ,まさめ。」
一般には,
まずめ,
というらしく,辞書には,
「日の出・日の入りの前後。釣りにもっともよい時間」
とある。「まずめ釣り」という言い回しもあるらしい。「まさめ」というと,木の,
柾目(正目),
で,木の「幹の中心を通って縦断した面」とか,
正眼(正目),
で,「まのあたり」とか「正しい見方」とか,となる。これを「せいがん」と訓むと,
「験の切っ先を相手の目に向ける(刀の)構え方」
になる。閑話休題。
「まじめ」を,
真面目,
と表記する場合のことについては,「まじめ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba2.htm#%E3%81%BE%E3%81%98%E3%82%81)
で触れたことがある。すこし重なるかもしれないが,語源的には,
マジ(擬態・まじまじ)+目
で,真剣な顔つき,誠実な態度,誠意があるなどの意味になる。
まじまじ
は,
「マジマジ(目の擬態語)」
で,「目を据えて一心に見る」
という意味になる。物を凝視しているときは,
真剣なまなざし,
になるには違いない。『語源由来辞典』,
http://gogen-allguide.com/ma/majime.html
には,
「まじめの『まじ』は、『まじろぐ』の『まじ』と同じで、しきりに瞬きするさまのこと。 じっと
見つめるさまを表す『まじまじ」も、元は目をしばたかせるさまを表していた。 まじめの『め』は、『目』の意味である。
まじめは、緊張して目をしばたかせるだけの真剣な顔つきから、本気であることや、誠実なさまを表すようになった。また、近世には真剣な顔つきになることだけでなく,目をしばたたかせる姿から、おびえた堅い表情や白けた顔なども『まじめ』といった。なお、漢字で『真面目』と表記するのは、意味から当てられた当て字である。」
と。しかし,当て字にしても意味があるはずである。
実は,「真面目」は,
しんめんもく,
と訓ませると,
本体そのままのありさま,本来の姿,転じて真価,
まじめ,実直,
という意味になる。『大言海』は,
真実(まこと)の面目,ありてい,実際の所のよく表れたること,真相,
戯れならぬこと,まじめなること,真摯,
とある。では,「面目」は,というと(「めんぼく」「めんもく」と訓む),
かおかたち,
おもただしき人に面向け,目を合すこと,人の世に立てる誉れを保つこと,
面おこし,名誉,
とある。『古語辞典』を見ると,まず,
人にあわす顔,体面,
とあるので,当初は,ただの「顔つき」から,「世間に対して顔を向けられる面」つまりは,名誉や誇り,へとメタフィジカルに広がったことが想像される。それに,「真」がつくと,
まことの,
という意味だけではなく,表面ではなく,その正味が,という意味で,
真骨頂,
というニュアンスになる。
一方,「まじまじ」は,『古語辞典』には,
目をしばたたくさま,またそういう状態で目が冴えて眠れないさま
平気なさま,図々しいさま,しゃあしゃあ,
もじもじするさま,,
という意味が載る。江戸時代をみると,
阿鼻焦熱の苦しみをまじまじと見てゐられうか
という使い方で,
ただなすところなく見ているさま,じっとみつめるさま,
の意と,
さすがの喜多八,しょげ返りて顔を赤らめ,まじまじしてゐるを
という使い方で,
もじもじ
の意,とある。そこからは,
真面目
の意味は見当たらない。むしろ,
ただ手を束ねてこわばっている,
とか,
照れて気後れ(もじもじ)している,
の意の方が強い。
真面目
の字を当てたのがいつの頃かは分からないが,
しんめんもく
と読む「真面目」の字を当てた瞬間,他の意味が,「地」に下がり,誠実さが「図」として浮き上がった,ということなのかもしれない。
漢字「真面目」のもつインパクトが,「まじまじ」の擬態のもつ曖昧な意味を,変えてしまった,ということのようである。ちなみに,
「面目」
は,中国語の「面目」,
名誉,
を示す。因みに,「面」の字は,
「首(あたま)+外側をかこむ線」
で,頭の外側を線で囲んだその平面をあらわす
という。また,
「面は,顔前なり。頁(人間の貌を大きく描き,その下に小さく両足を添えた形を描いたもの。あたまを示す)从(したが)ひ人面の形に象る」
ともある。「目」は,「め」を描いた象形文字。
やはり,顔と眼は,単なる,「かお」や「め」だけではないのである。
なお,「マジ」は,別に
http://zokugo-dict.com/31ma/maji.htm
で,
「マジとは真面目の略で、『真面目』『本気』『真剣』『冗談ではない』といった意味で使われる。マジは江戸時代から芸人の楽屋言葉として使われた言葉だが、1980年代に入り、若者を中心に広く普及。『マジで』『マジに』といった副詞として、また「マジ○○(下記関連語参照)」といった形容詞的にも使われる。
また、『本気』と書いてマジと読ませるマンガなどもある。」
と,あるように,別の分派もあるようだが,昨今は,「マジ」は,また少しニュアンスが変わってきているようだ。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
簡野道明『字源』(角川書店)
「そらごと」は,
空言,
虚言,
と当てるのと,
空事,
虚事,
とあてるのとでは,意味が違う。「言」と「事」の字から,推測はつくが,辞書(『広辞苑』)によれば,
空言
は,
事実でないことば,
うそ,
とあり,
空事
は,
事実にもとづかないこと,
つくりごと,
とある。口に出すか,表現するかは別にして,その表現することを,
空言,
と言い,
表現されているものを,
空事,
と,使い分けていることになる。語源は,空言は,
「空(いつわり,うそ)+言(ことば)」
空事は,
「空(空虚,うそ)+事(事件)」
とある。因みに,漢字「空」の字は,
「会意兼形声。工は,尽きぬくいを含む。『穴+音符工』で,つきぬけて穴が空き,中に何もないこと」
という原義。漢字「事」は,
「会意文字。『計算に用いる竹のくじ+手』で,役人が竹棒を筒の中に立てるさまを示す。のち人の司る所定の仕事や役目の意味に転じた。」
とあり,漢字「言」は,
「会意文字。『辛(切れ目をつける刃物)+口』で,口をふさいでもぐもぐいうことを音・諳といい,はっきりかどめをつけて発音することを言という」
とある。
ところで,空事は,
絵空事,
という言い方があり,辞書(『広辞苑』)には,
絵は画家の作為が加わった実物ではないということ,転じて,物事に虚偽,誇張の多いこと,架空の作りごと,
となる。『デジタル大辞泉』には,
「絵には美化や誇張が加わって、実際とは違っている意から」
と注記が付いて,
大げさで現実にはあり得ないこと。誇張した表現」
とあり,「空事」を更に誇張した言い方になる。『古語辞典』には,「ゑそらごと」として,
「絵に描かれたものが実際とあわないこと」
「物事が虚偽・誇大であること」
とある。これだと意味がよく分からないが,『大言海』は,
「絵は,写生のみにては,見どころなければとて,実形に多く作意,又は,想像を加へて,写するものなるを云ふ。丹青過実」
とある(因みに,「丹青」とは,赤と青の意味から絵の具の意味に広がったが,『日葡辞典』には,「絵画」とあり,「丹青過実」とつながる)。『大言海』は,さらに,『古今著聞集』から,
「その物の寸法は,ぶんにすぎて,おほきに書きて候こと,いかでか實には,さは候べき,ありのままの寸法に書きて候はば,みどころもなきものに候ゆゑに,ゑそらごととは申すことにて候」
を引用してる。この意味ならば,誇大とか,虚事という意味合いは出ず,絵の表現技法を言っているにすぎない。
もともと,『古語辞典』も,『大言海』も,
「虚言」
「空言」
しか載せていない。「言」が「事」だからというよりは,もともと言葉に出すこと自体を,
空言,
と言っているので,口に出した「空言」の中身を,
空事,
と区別する意味があまりないからではないか。辞書を信ずるなら,ここからは,億説になるが,
絵空事,
と
空言
が重なって,
空事
という言い方が,あるいは生まれたのではないか。そのために,
絵空事
の意味が,
空事
にひっぱられたのではないか,と。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
「おそれ」は,
恐れ,
怖れ,
畏れ,
懼れ,
虞れ,
等々,とさまざまな字を当てる。意味は,辞書(『広辞苑』)には,
恐怖,恐れ,
よくないことが起こるのではないかという心配,不安,
かしこまること
で,一般には,「恐」を当て,不安の意味の時は,「虞」,かしこまるには「畏」もあてる,とある。
和語の「おそれ」の語源は,
「おす(押,圧)+る(再動詞化)」
とあり,
「心に圧迫を受け続ける」
という意味になる。『古語辞典』を見ると,「おそれ」は,
「平安中期頃に,上二段活用のオソリから転じて成立した形」
とあり,「おそり」には,
「奈良時代から平安初期にかけて上二段活用,平安中期から一般には下二段活用に移ったが,漢文訓読には伝統的に上二段活用も使われた」
とある。つまりは,
「畏れる所以」ではなく,「畏るる所以」
と使ったということか。和語では,「おそれ」だが,漢字は,「おそれ」を細かく意味を使い分ける。
「恐」は,未来を怖るるなり,助詞に用ひて,大抵此くならんと気づかうに,恐らくは此の如くならん,といふなり,
「懼」は,恐懼,疑懼,震懼と連用す,恐怖するなり,
「畏」は,おそるるの甚だしきなり,敬の字の義を帯ぶ。古は,威の字と通用す。畏敬,畏服と連用す,
「怖」は,おどすとも訓む。わけもなく,怖じおそるるなり,
「惶」は,おそれあわつるなり,恐惶,驚惶と用ふ,
「怯」は,臆病なること,
「慄」は,おそれてぞっとする,
「悸」は,心動くなり,胸騒ぎ,
等々と,同訓異議語を,整理する。同じ,心を圧迫するにしろ,
恐怖
なのか,
不安
なのか,
畏まる
のかでは,意味が違うし,その圧迫で,
慌てる
のか,
怯える
のか,
おどされる
のか,
ぞっとするのか,
で,また微妙にニュアンスが違う。しかし,どうやら,ほとんど「恐」の字を当てて,丸めてしまっているらしい。だから,
恐い
も,
恐れをなす
も,
恐れ多い
も,
恐れ入る
も,
恐れながらも,
ほぼ,「恐」で通用させる。そのくせ,日本人の感性は,微妙で繊細などと,臆面もなく言う。僕は,
ことばによって見える世界が違う,
と思っている。日本人が自己意識で,繊細というほどに,言葉を些事にこだわって使い分けているとは思わない。
やばい,
かわいい,
で,ほとんどが通用するのは,今日に始まったことではないのではないか。言葉を丸めるとは,微細に違う現実を写しだす言葉の細部にこだわらないということであると同時に,その場に,その文脈にいる人との間だけで,ニュアンスが伝わればいいと思っている,というふうにしか思えない。
因みに,「恐」の字は,
「上部の字(音 キョウ)は,『人が両手を出した姿+音符工』からなり,突き通して穴をあける作業をすること。恐はそれを音符とし,心を加えた字で,心の中が突き抜けて,穴のあいたようなうつろな感じがすること」
とある。
「怖」の字は,
「『心+布』で,何かに迫られた感じで怯える」
「畏」の字は,「田(鬼の首)+爪」で,
「象形文字。大きな頭をした鬼が手に武器を以ておどすさまを描いたもので,気味わるい威圧をかんじること」
とある。我が国で,「かしこまる」「おそれいる」意に使うのは,わが国特有で,原義からは外れる。「畏」のもつ「心がすくむようなさま」から転じたものとされる。
「懼」の字は,
「瞿(く)は,『目二つ+隹(とり)』の会意文字で,鳥が目をきょろきょろさせること。懼は,『心+瞿』で,目をおどおどさせる不安な気持ち」
「虞」の字は,
「『虍(とら)+音符呉』で,もと虎のようにすばしっこい動物のこと。ただし普通はあらかじめ心を配る意に用いる。」
とある。
現代の中国は知らず,少なくとも,かつて中国は,物を細部にわたって分化し,名づけていた。そのおかげて,われわれも,ものごとの機微を知ったに違いない。そのことは,
「漢語」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-4.htm#%E6%BC%A2%E8%AA%9E)
で触れた。
参考文献;
簡野道明『字源』(角川書店)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
凡例は,
はんれい,
と訓む。辞書には,
「書物のはじめに掲げる,その書物の編集方針,鑓用の仕方などに関する箇条書き。例言。」
とある。その他に,
図表で使用する記号などの意味を説明するための領域,またそこに描画されている内容,
という意味もある。だから,地図などでも,地図の中で用いる特別な記号や境界線について意味を説明するのを凡例と呼ぶ。たとえば,国土地理院の電子国土ポータルにおける凡例は,
http://map.daitaku1.com/docs/note/
である。語源は,中国語,
「ハン(凡・汎 広い)+例」
で,広くあてはまる例,である。「凡」の字は,
呉音で,「ボン」
漢音で,「はん」
と訓む。象形文字で,
「廣い面積をもって全体を蓋う板,または布を描いたもの」
で,実は,
凡例,
のように,「ハン」と訓ませるケースは少なく,
平凡,
凡人,
凡民,
等々と,「ボン」と訓ませるケースの方が多い。後は,
凡そ(おおよそ),
と訓む場合である。ために,
https://kotobank.jp/word/%E5%87%A1%E4%BE%8B%5B%E3%81%BC%E3%82%93%E3%82%8C%E3%81%84%5D-897689
にあるように,つい,
ぼんれい,
と訓みたくなる。『大言海』には,
「杜預,左傳序『其發凡以言例,皆經國之常制,周公之垂法,史書之舊章,仲尼從而脩之,以成一經之通身体』」
と,例示が載る。古くから,例言として使われてきたものらしい。
それにしても,日本での読みは,
黄海,
黄金,
と,「オウ」(呉音),「こう」(漢音)と,使い分けている。ために,
黄禍論,
は,「おうかろん」「 こうかろん」と,両用にルビを振る。、独語なら,Gelbe Gefahr,英語なら,Yellow periなのに,である。
その辺りの,誤読(これも,「ごよみ」,「ごどく」と訓める)について,
http://homepage2.nifty.com/tei-tagami/newpage5.html
で,いくつか紹介しているが,単に,
呉音,
漢音,
だけでなく,
訓読。
によっても,訓み方が違う,
裏面,
を「りめん」でなく,「うらめん」と呼んでいけないのなら,
重箱,
は,本来,「じゅうばこ」ではなく,
漢音なら,じゅうしょう
呉音なら,ちょうそう
あるいは,まぜこぜにするなら,「じゅうそう」か「じゅうしょう」あるいは,「ちょうそう」か「ちょうしょう」と訓まなくてはならなくなる。訓み方で使い分ける例まである。
競売,
は,「きょうばい」,「けいばい」と訓むが,
オークションなどは「きょうばい」
地方裁判所による不動産の競売は「けいばい」
となるらしい。そうなると,通用すれば,いいということで,言ったもの勝ちということか。
参考文献;
増井金典『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房)
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
文身は,よく,
ほりもの,
とルビを振る場合があるが,辞書(『広辞苑』)によると,
「(『文』は模様の意)身体にほりものをすること,また,そのもの,入墨」
とある。入墨は,他に,
紋身(もんしん)
倶利迦羅紋々(くりからもんもん)
紋々(もんもん)
彫り物(ほりもの)
刺青(いれずみ)
タトゥー
等々と呼ばれる。
確か,『魏志倭人伝』に,
「皆黥面文身」
とあり,男子はみな顔や体に入れ墨し、墨や朱や丹を塗っていた,とされる。
「黥面文身」は,
http://www.geocities.jp/ydna_d2/geimenbunshin.html
に詳しいが,
「『アイスマン』や、世界中で発掘される古代人のミイラからはほぼ例外無く、『刺青』が彫られている」
らしく,倭人伝に,
「夏の王の少康の子が、會稽に封ぜられた時、断髪して入墨をし、蛟(みずち)の害を避けたという。今、倭の漁師も好んで水にもぐって魚や蛤を捕り、身体に入墨をして大魚や水禽を避けていたが、後には飾りになった。」
とあるように,多く
「大魚(サメ)や水禽(ウミヘビ)からの被害を避ける為」
という,一種魔よけというか,まじない,のようなものだが,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/421311554.html
で,「くりからもんもん」について書いたが,男伊達を競う意図と同時に,そこには,
「(梵語krkara黒龍と訳すと云う)岩の上に立てたる剱を,黒龍の,巻きめぐりて,其の切先を呑まんとし,其の背に,火焔の燃えあがる象を図したるもの。剱は不動明王の三摩耶形(さんまやぎょう)にて,右手に持てる降魔の剱,龍は,左手に持てる縛の索(なわ)にて,龍の剱を巻くは,即ち不動の化身の像なりと云う。勇肌の火消,鳶の者などの,その背に,此図を文身(ほりもの)にしたるを,倶利伽羅もんもんと云う。燃え燃えを火焔の勢いに因みて,勇ましくはねて云うなるべし」
と『大言海』で,「倶利伽羅」を説明するように,勇肌の火消,鳶の者にとってのまじない,験担ぎの要素があったに違いない気がする。
文身について,『大言海』は,
「身をもどろくること。身體にほりものをなすこと。いれずみ。ほりもの」
とある。「もどろくる」というのは聞きなれないが,
班・文・紊
の字を当て,
「斑になす,また,身に箚青(ほりもの)をす」
という意味とする。「箚青」とは,「青を箚(さ)す」,まさにに入墨である。『大言海』は,つづいて,
「後漢書,又は三国志に,本朝の伝に,文身被髪の事を記せり,文身は後にも搢紳家に残り,被髪は宮女に残れり」
と付記する。因みに,搢紳(しんしん)家とは,
「《笏(しゃく)を紳(おおおび)に搢(はさ)む意から》官位が高く、身分のある人。」
を意味し,搢紳は,
縉紳,
とも当てる。被髪は,
「髪を結わないで、ばらばらに乱していること。」
とある。浅学にして,わからないが,被髪はわかるが,「文身は後にも搢紳家に残」ったというのは,どういうことなのだろう。
総じて,入墨となるが,どうも,入墨というと,
「古代から中国に存在した五刑のひとつである墨(ぼく)・黥(げい)と呼ばれた刑罰にまで遡るとされる」
など,どうも刑罰の含意が出るが,
文身,
と書くのと,
入墨,
と書くのとでは,由来が違うのではないか,という気がしてならない。倭人伝では,
入れ墨の位置や大小によって社会的身分の差を表示していた,
とされるし,
「2,500年前のアルタイ王女のミイラは、腕の皮膚に施された入れ墨」
があったとされる。「文身は後にも搢紳家に残」ったというのはこのことを指すのかもしれない。
「文」の字は,象形文字で,
「もと,土器につけた縄文のもようのひとこまを描いたもので,こまごまとかざりたてた模様のこと。のち,模様式に描いた文字や生活のかざりである文化の意となる」
とある。「もじ」の意だが,
「象形文字や指事文字のように,事物や模様のように描いたもじのこと」
である,ともある,だから,模様の意でもある。「あや」と訓むわけである。論語に
「小人の過つときは必ず文(かざ)る」
とある。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E3%82%8C%E5%A2%A8
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
三到とは,
さんとう
と訓むが,
朱熹「訓学斎規」
による,とされる。つまり朱子の言葉である。
「読書に必要な三事,心と目と口を十分に働かせて読むこと。心を集中し、目でよく見、口で朗読すれば内容が会得できるということ」
を意味する。ここから,
読書三到,
という言葉が生まれた。
「眼到(がんとう)」 目でよく見ること,
「口到(こうとう)」 声を出して読むこと,
「心到(しんとう)」 心を集中して読むこと,
の三つである。
三到之中,心到最急,心既到矣,眼口豈不到乎,
とあるので,このうちとくに心到が不可欠であり,秘訣だということになる。しかし,
読書亡羊
という言葉もある。『荘子』にある,
「ある二人の男が羊の放牧をしていて、羊に逃げられてしまった。事情を問うと、一人は読書に夢中になっていたからと答え、もう一人は博打に夢中になっていたからと答えた。理由の差こそあれ、二人とも羊を逃がしてしまったという点では同罪である」
という故事に由来し,
「羊の放牧中、本を読んでいて番を怠けたため、羊に逃げられてしまった意。転じて、他のことに気をとられて、肝心な仕事をおろそかにすることのたとえ」
とされる。どんな故事ことわざにも,正逆ならぶのだから,読書も是非があるのは当然か。他にも,
読書に適した三つの時期として,
読書三余,
という言葉もある。
冬(一年の余り),
夜(一日の余り),
降雨(時間の余り),
というのだそうだ。まあ,多くは,
読書百遍義自ずから見(あらわ)る,
といった読書の利点を説くものが多いが。
それにしても,「三」という字のついた言葉は多い。「三」の字は,指事文字で,
「三本の横線で三を示す。参加の参と通じて,いくつもまじること。杉(さん),衫(さん)などの音符彡(さん)の原形で,いくつも並んで紋様をなすの意を含む。日本では,奈良時代に,サムと音訳し,三位(サムミ),三線(サムセン)といった。三郎(サブロウ)のサブはその転訛である。」
とある。そのためか,
三々五々,
のように,「いくつも」「たびたび」といった含意を持っている。
三友(詩・琴・酒),
三道(地獄・餓鬼・畜生),
三宥(不識・過失・遺忘),
三戒(青年の女色・壮年の闘争・老年の利得),
三行(孝)(養・喪・祭)
等々と,三のつく熟語は山のようにあり,三つというのは,何かの要件を挙げる時の選択肢としては最低単位になるらしいが,たとえば,
三顧,
といったとき,確かに,
「蜀の劉備が、諸葛亮を軍師として招くために、その草庵を三度訪れたという、諸葛亮『前出師表』の故事から」
きていて,劉備は三顧だが,「三」というよりは,「たびたび」というニュアンスなのだし,
三致意,
というと,
深く意を用いる,
と,「三」に意味があるのではない。そう考えると,
三昧,
と,Samādhi、サマーディの音写に,「三」を当てた意味も見える。
仏教における禅定(ぜんじょう)、ヒンドゥー教における瞑想において、精神集中が深まりきった状態のこと,
だそうだ。
三,
というのは,あるいは,短期記憶に残りやすい数なのかもしれないが,相手に伝える時,
言いたいのは,三つ,
というほうが,二者択一,選択肢なし,よりは,耳に通りやすいのもあるし,
三国一,
という方が,全国一,というよりは,比較対象があり,耳どおりがいい。因みに,三国とは,
日本と唐と天竺,
を指すそうだ。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
簡野道明『字源』(角川書店)
袖というのは,辞書(『広辞苑』)によると,
衣手(そで)の意。奈良時代には,ソテとも,
と注記がある。『語源辞典』には,
「ソ(衣)手」
とあり,こう注記する。
「上代仮名遣いが,甲乙矛盾するのが難点ですが,他に適した説がみつかりません。」
と。で,
「衣の手の部分」
の意とし,異説として,
「ソ(衣)+出」
で,
「衣のうち手の出る部分の意」
とある。上代仮名遣いの甲乙については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E7%89%B9%E6%AE%8A%E4%BB%AE%E5%90%8D%E9%81%A3
に詳しいが,
「ひらがな・カタカナ成立以前の日本語において、a i u e o の5音ではなく、古い時代にはより多くの母音の別があった」
とされ,「仮名の50音図でいうイ段のキ・ヒ・ミ、エ段のケ・へ・メ、オ段のコ・ソ・ト・ノ・(モ)・ヨ・ロの13字について、奈良時代以前には単語によって2種類に書き分けられ、両者は厳格に区別され」,「片方を甲類、もう片方を乙類と呼ぶ。例えば後世の「き」にあたる万葉仮名は支・吉・岐・来・棄などの漢字が一類をなし、「秋」や「君」「時」「聞く」の「き」を表す。これをキ甲類と呼ぶ。己・紀・記・忌・氣などは別の一類をなし、「霧」「岸」「月」「木」などの「き」を表す。これをキ乙類と呼ぶ。」
とするもの。
で,袖だが,この甲乙に矛盾するということらしい。その意味では,難点というよりは,説として問題というべきなのかもしれない。『大言海』も,衣手(そて),衣出(そで)両説を挙げている。
袖は,本来は,
衣服の見頃(衣服の、襟・袖・衽 (おくみ) などを除いた、からだの前と後ろを覆う部分の総称。前身頃と後ろ身頃)の左右にあって,両腕をおおう部分,
であり,
和服ではたもとの部分を含めていう,
というのが原義だが,それをメタファとして,さまざまに意味の外延が広がっている。たとえば,「肩甲」という,
鎧の肩の上をおおい,矢・刀を防ぐもの,
はまだしも,
牛車(ぎっしゃ)・輿などの前後の出入り口の左右の部分,
巻物,文書の初の端(『大言海』には「文書の初めに白く残したるは,衣の端なる袖に似たれば,云ふ」とある),
門・戸・垣・舞台などの左右の端の部分,
洋装本のカバーや帯の,表紙の内側に折れ込んだ部分,
と,意味が広がる。袖のつく言葉は多い。『大言海』から拾うと,
袖合い月,袖扇,袖移し,袖裏,袖格子,袖香炉,袖書,袖垣,袖笠,袖笠雨,袖貝,袖がらみ,袖几帳,袖包み,袖括り,袖口,袖較べ,袖輿,袖乞い,袖印,袖摺り,袖摺松,袖扇子,袖凧,袖畳,袖築地,袖頭巾,袖付,袖の下,袖判,袖控え,袖屏風,袖縁,袖覆輪,袖枕,袖まくり,
等々,さらに,
袖にする,
といった,袖に絡む諺や熟語はやたらに多いのは驚く。辞書(『広辞苑』)には,
鎧袖一触,
袖行く水,
袖打ち合わす,
袖返す,
袖掻きあわす,
袖に食らう,
袖に時雨(しぐ)る,
袖に縋る,
袖に墨つく,
袖にする,
袖に湊(みなと)の騒ぐ,
袖の上の珠砕く,
袖振り合うも他生の縁,
袖振る,
袖纏き返す,
袖を片敷く,
袖を絞る,
袖を連ねる,
袖を通す,
袖を広ぐ,
袖を濡らす,
袖を引く,
袖を分かつ,
無い袖は振れない,
等々と載る。こう見ると,日常の仕草,振る舞いから,その微妙な含意をくみ取っていくことをしている。
もっている言葉で見える世界が違う,
と言う。それは,その言葉の分だけ,世界を,
分化,
し,見分けている,ということを意味する。いま,われわれは,そうしているだろうか。その言語化力が劣っているということは,世界を認知する力が衰えているということなのではないだろうか。
素は,
ス
とも
モト
とも
シロ
とも,
訓む。仕舞が素舞であることから,素については,「店仕舞い」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-4.htm#%E6%BC%A2%E8%AA%9E)
で,素とは,「しろ」であり「もと」であり,「はじめ」である。意味としては,
撚糸にする前のもとの繊維,蚕から引き出した絹の原糸
とか,
模様や染色を加えない生地のままの,白い布
等々,下地とか地のままとか生地とか元素といった意味合いが強い,と触れたことがある。
「素」の字(呉音は「ス」漢音「ソ」)は,
「『垂(スイ)の略字体+糸』で,ひとすじずつ離れて垂れた原糸」
とある。で意味は,
撚糸にする前のもとの線維。繭から引き出した絹の原糸,
という意味から端を発している(「要素」「元素」)。だから,
手を加える前のもととなるもの,
という意味に広がり,そのメタファから,
生地のまま,
となり(「素質」「素朴」),さらに,染色する前の,
しろい,
と広がる。で,『論語』の,
子夏問曰。巧笑倩兮。美目盼兮。素以為絢兮。何謂也。子曰。繪事後素。曰。禮後乎。子曰。起予者商也。始可輿言詩已矣
にある,
素以為絢兮(素以て絢(あや)となす),
について,子夏が,
繪事後素,
と答えたのについて,古注では,
絵の事は素(しろ)きを後にす
と,絵とは文(あや),つまり模様を刺繍することで,すべて五彩の色糸をぬいとりした最後にその色の境に白糸で縁取ると,五彩の模様がはっきりと浮き出す,
と解すると,貝塚茂樹注にはある。しかし新注では,
絵の事は素(しろ)より後にす,
と読み,絵は白い素地の上に様々の絵の具で彩色する,そのように人間生活も生来の美質の上に礼等の教養を加えることによって完成する,と解する。これをとって,大塩中斎は,諱を後素と言った,ということは,すでに触れた。
話を元へ戻すと,白い,という意味から,
下地,
となり,
ただで,
とか,
地のままで,
とか
生野菜,
と,外を広げる。
日本語だと, 「す(素)」「そ(素)」と訓み方で使い分けている。「す」と訓むと,
ありのまま,
という系統で(「素顔」「素うどん」「素手」),日本特有の使い方は,
「日本の音楽・舞踊・演劇などの演出用語。芝居用の音楽を芝居から離して演奏会風に演奏したり、長唄を囃子(はやし)を入れないで三味線だけの伴奏で演奏したり、舞踊を特別の扮装(ふんそう)をしないで演じたりすること」
と意味を拡大したり,「素」をつけて,
「素寒貧」「素町人」と,軽蔑の意味を込める,
とか,
素早い,すばしっこい,
と,程度のはなはだしいのに使うし,まじりっけなしという意味で,
「 素顔」「 素肌」「 素うどん」「 素泊り」
と使う。しかし,これは,我が国だけでの使い方らしい。
一方,「そ(素)」と訓ませて,
白い,生地のまま,
という系統で,飾りっ気のない(「素服」「素地」「素因」「素質」「簡素」「素行」「平素」「素描」「素朴」しかし「素性」は「す」と訓む)という意味の範囲になる。
漢字の「素」は,「もと」という意味では,本・元・原等々とは,区別されて使われる。
本は,末に対していい,後先をただしていう,
原は,水源の義より,根本を尋ねていう,
旧は,新の反,
故は,今に対して,以前はこうであった,という
素は,白き帛のこと,下地からの意,
基は,土台の意,
と区別する。その意味で,「素」は,「もと」は「もと」だが,上塗りを剥がした,生地,地肌,という意味になる。日本の音楽や舞踊で用いる場合,
「飾り気がなく,それ自身ということで,音楽の面では〈素唄(すうた)〉〈素謡(すうたい)〉〈素浄瑠璃〉〈素語り〉〈素で演奏する〉などと用いられる。長唄に関していえば,芝居から離れた純演奏会様式のものを〈素唄〉といい,また囃子なしで,三味線の伴奏だけで奏することを〈素〉ともいう。能では伴奏なしにうたうことを〈素謡〉と称するし,浄瑠璃では,人形芝居や歌舞伎から離れ,演奏会様式で純粋に音楽を味わうものを〈素浄瑠璃〉,三味線の伴奏なしに浄瑠璃を語ることを〈素語り〉などと呼ぶ。」
仕舞は,
素(装束をつけない)+舞
なのだという。つまり,
仮面や衣装なしの舞い,
ということになる。その意味から考えると,「素」でいうもとは,その人の,
素地,
ということになる。それは,何もない意味ではない。その人が生き方として身に着けてきた,
その人自身,
という意味になる。素顔,とは,そういう意味でなくてはならない。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)
簡野道明『字源』(角川書店)
貝塚茂樹訳注『論語』(中公文庫)
志怪とは,辞書(『広辞苑』)には,
中国の旧小説の一類,不思議な出来事を短い文に綴ったもの。また創作の意図はなく,小説の原初的段階を示す。六朝東晋の頃より起こった。「捜神記」など,
とある。ここで言う,「小説」は,「小説」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E5%B0%8F%E8%AA%AC) で触れたように,
「市中の出来事や話題を記録したもの。稗史(はいし)」
であり,『日本大百科全書(ニッポニカ)』には,
「中国、六朝(りくちょう)時代にもっとも盛んに記録された説話の名称。「怪を志(誌)(しる)したもの」という意味の命名で、この種の話には怪奇な内容をもつものが多いところから、近代中国の文学史家によって名づけられたものである。志怪小説ともよばれ、特異な人物の事跡を記録した志人小説という説話群と相対する説話群の呼称でもある。六朝も早期の三国・晋(しん)のころの志怪には、昔話や伝説など、民間伝承の記録とみられるものが多いが、劉宋(りゅうそう)以降、六朝期後半の志怪書には、仏教や道教の功徳(くどく)を説く宗教説話がしだいに数を増してくる。しかし今日原形をとどめる志怪書は1本もなく、いずれも後人が『太平広記(たいへいこうき)』や『太平御覧(たいへいぎょらん)』などの類書に引かれ残っていた六朝志怪書の断片を拾い集めて作り直したようなものばかりである。また原話の筆録に忠実でなく、話の骨子だけを記したようなものも多い。」
と詳しい。
「昔、中国で稗官(はいかん)が民間から集めて記録した小説風の歴史書。また、正史に対して、民間の歴史書。転じて、作り物語。転じて,広く,小説。」
その意味で,いま言う小説のはしり,ということになる。
「志怪小説、志人小説は、面白い話ではあるが作者の主張は含まれないことが多い。志怪小説や伝奇小説は文語で書かれた文言小説であるが、宋から明の時代にかけてはこれらを元にした語り物も発展し、やがて俗語で書かれた『水滸伝』『金瓶梅』などの通俗小説へと続いていく。」
というわけだ。
そもそも「志怪」とは,
「怪を志(しる)す」
という意味らしい。「志」という字は,
「士印は,進み行く足のかたちが変形したもので,之(いく)と同じ。士女の士(おとこ)ではない。志は『心+音符之』で,心が目標を目指して進み行くこと」
とある。意味には,「しるす」「書き留めた記録」という意味もある。「怪」の字は,
「圣は,『又(て)+土』からなり,手でまるめた土のかたまりのこと。塊と同じ。怪は,それを音符とし,心を添えた字で,丸い頭をして突出したいような感じを与える物のこと」
とある。で,「あやしい」「見馴れない姿をしている」「不思議である」という意味になる。
志怪に関心を持ったのは,三遊亭圓朝の創作した怪談噺「牡丹灯籠」は、中国明代の小説集『剪灯新話』に収録された小説『牡丹燈記』に着想を得ている,というように,中国から着想というか,翻案というか,下手をすればそのまま剽窃したものが結構あるのではないか,ということからだ。
代表的な作品としては,
『列異伝』曹丕の作として伝えられるが、現存するものには後人の作品が混入しており、成立の経緯は不明。
『捜神記』晋の干宝作。
『捜神後記』晋の陶淵明作。「桃花源記」が含まれる。
『述異記』斉の祖冲之作。同題の任昉作の書は地理書的作品。
『異苑』宋の劉敬叔作。劉は江蘇省銅山の人で、東晋の劉毅、劉裕に仕えた。
『漢武故事』作者不詳。班固の作として伝えられて来たが、六朝の作品と見られる志人小説。
『聊斎志異』清の蒲松齢作。
等々と挙げられているが,たとえば,
『捜神記』の『むじな』や『ろくろ首』は,小泉八雲『怪談』の原典
となっていると言われるし,『剪燈新話』の『牡丹燈記』は,
三遊亭円朝の『怪談牡丹燈籠』
の元になっており,上田秋成は『剪燈新話』の構成を借りて,
『雨月物語』の『吉備津の釜』
を著している,という。すでに,江戸時代(寛文年間1660年代)には,
『伽婢子(おとぎぼうこ)』
『狗張子(いぬはりこ)』
が,志怪小説の翻案として,出されている。
こうしたものが受け入れられる,文化的・社会的背景として,
仏教や道教の思想の浸透に伴って、輪廻転生の物語
が受け入れられる土壌がある,ということなのだろうか。日本的な土壌については,「怪異」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-3.htm#%E6%80%AA%E7%95%B0)で触れたように,
中世風の高僧法力譚の定型におさまりきれなくなった江戸怪談の多様な表現,
が可能になった時代背景があるようである。その頂点に,
『雨月物語』
が来る,ということのようである。
日本・中国の古典から脱化した怪異小説9篇,
という表現が,正によく示している。
参考文献;
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E6%80%AA%E5%B0%8F%E8%AA%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E6%9C%88%E7%89%A9%E8%AA%9E
累は,
かさね,
と訓む。「累」を検索すると,
松浦だるま『累 -かさね-』
という漫画が出るが,ここで言う,
累
は,怪談で有名な,
「累ヶ淵」
を指す。
辞書(『広辞苑』)には,こう載る。
「会談の女主人公。下総国羽生村の百姓与右衛門の妻。嫉妬深い醜婦で,夫に鬼怒川で殺害され,その怨念が一族に祟ったが,後に祐天上人の祈念で解脱したという。歌舞伎『伊達競阿国戯場(だてくらべおくにかぶき)』『法懸松田成田利剣(けさかけまつなりたのりけん)』,浄瑠璃『薫樹(めいぼく)累物語』,清元『色彩間苅豆(いろもようちよつとかりまめ)』,三遊亭円朝の『真景累ヶ淵』などで有名」
と。このほかに,宝井馬琴の読本『新累解脱物語』もある。
ちなみに,祐天とは,東横線の「祐天寺」駅のそれを指し,「祐天寺」は,晩年草庵(現在の祐天寺)を結んで隠居し,そこで没した地となる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%90%E5%A4%A9
には,
「祐天は陸奥国(後の磐城国)磐城郡新妻村に生まれ、12歳で増上寺の檀通上人に弟子入りしたが、暗愚のため経文が覚えられず破門され、それを恥じて成田山新勝寺に参篭。不動尊から剣を喉に刺し込まれる夢を見て智慧を授かり、以後力量を発揮。5代将軍徳川綱吉、その生母桂昌院、徳川家宣の帰依を受け、幕命により下総国大巌寺・同国弘経寺・江戸伝通院の住持を歴任し、正徳元年(1711年)増上寺36世法主となり、大僧正に任じられた。晩年は江戸目黒の地に草庵(現在の祐天寺)を結んで隠居し、その地で没した。享保3年(1718年)82歳で入寂するまで、多くの霊験を残した。」
とある。その霊験の一つが,「累」ということになる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E3%83%B6%E6%B7%B5
には,「累」の謂れを,
「下総国岡田郡羽生村に、百姓・与右衛門(よえもん)と、その後妻・お杉の夫婦があった。お杉の連れ子である娘・助(すけ)は生まれつき顔が醜く、足が不自由であったため、与右衛門は助を嫌っていた。そして助が邪魔になった与右衛門は、助を川に投げ捨てて殺してしまう。あくる年に与右衛門とお杉は女児をもうけ、累(るい)と名づけるが、累は助に生き写しであったことから助の祟りと村人は噂し、「助がかさねて生まれてきたのだ」と「るい」ではなく「かさね」と呼ばれた。
両親が相次いで亡くなり独りになった累は、病気で苦しんでいた流れ者の谷五郎(やごろう)を看病し、二代目与右衛門として婿に迎える。しかし谷五郎は容姿の醜い累を疎ましく思うようになり、累を殺して別の女と一緒になる計画を立てる。正保4年8月11日(1647年)、谷五郎は家路を急ぐ累の背後に忍び寄ると、川に突き落とし残忍な方法で殺害した。
その後、谷五郎は幾人もの後妻を娶ったが、尽く死んでしまう。6人目の後妻・きよとの間にようやく菊(きく)という名の娘が生まれた。寛文12年1月(1672年)、菊に累の怨霊がとり憑き、菊の口を借りて谷五郎の非道を語り、供養を求めて菊の体を苦しめた。近隣の飯沼にある弘経寺(ぐぎょうじ)遊獄庵に所化として滞在していた祐天上人はこのことを聞きつけ、累の解脱に成功するが、再び菊に何者かがとり憑いた。祐天上人が問いただしたところ、助という子供の霊であった。古老の話から累と助の経緯が明らかになり、祐天上人は助にも十念を授け戒名を与えて解脱させた。」
と,辞書(『広辞苑』)より,詳しく書く。寛文十二年(1672)のことである。これを最初に取り上げたのは,『古今犬著聞集』(1684年)で,
「祐天和尚がかさねが亡魂をたすくる事」
として採録されたのが始まりで, 「怪異」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3-3.htm#%E6%80%AA%E7%95%B0)で書いたように,もともとは,祐天の法力の霊験を説話として,浄土教(祐天は浄土僧)の布宣のためのものであったもので,他に六話,化益譚の載る,その一つの話が,以降,さまざまに翻案されて広まっていったことになる。
仏教唱導者の近世説教書(勧化(かんげ)本)
の類例といっていい。堤邦彦氏は,その背景を,
「檀家制度をはじめとする幕府の宗教統制のもとで,近世社会に草の根のような浸透を果たした当時の仏教唱導は,通俗平易なるがゆえに,前代にもまして,衆庶の心に教義に基づく生き方や倫理観などの社会通念を定着させていった。とりわけ人間の霊魂が引き起こす妖異については,説教僧の説く死生観,冥府観の強い影響がみてとれる。死者の魂の行方をめぐる宗教観念は,もはやそれと分からぬ程に民衆の心意にすりこまれ,なかば生活化した状態となっていたわけである。成仏できない怨霊の噂咄が,ごく自然なかたちで人々の間をへめぐったことは,仏教と近世社会の日常的な親縁性に起因するといってもよかろう。」
と述べていた。神仏の霊験,利益,寺社の縁起由来,高僧俗伝など,
仏教説話の俗伝化,
のひとつである。その説話の目的と興味が,
「高僧の聖なる験力や幽霊済度といった『仏教説話』の常套表現を脱却して,怨む相手の血筋を根絶やしにするまで繰り返される亡婦の復讐劇に転換するさまを遠望することになるだろう。」
それは,怪異小説に脚色され,虚構文芸の表現形式を創り出すところへとつながっていくことになる。
累の悲劇は,ちょっとした「稗史」(中国で稗官(はいかん)が民間から集めて記録した小説風の歴史書。また、正史に対して、民間の歴史書。転じて、作り物語)が,物語へと昇華されていくプロセスを垣間見させてくれるようである。稗史,つまり 「小説」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba4.htm#%E5%B0%8F%E8%AA%AC)については触れた。
参考文献;
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E3%83%B6%E6%B7%B5
堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』(ぺりかん社)
こういう詩がある。
このかなしみを
よしと うべなうとき
そこに たちまち ひかりがうまれる
ぜつぼうと すくいの
はかないまでの かすかなひとすじ
八木重吉の無題の詩である。『幼き歩み』に収録されているらしい。不勉強で,鈴木三重吉なら知っていたが,八木重吉の名はほとんど記憶になく,まして詩については全く知らなかった。
八木重吉については,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%9C%A8%E9%87%8D%E5%90%89
に詳しい。、1898年に生まれ,1927年に,
「29歳の若さで亡くなった。5年ほどの短い詩作生活の間に書かれた詩篇は、2000を優に超える」
という。どうりで若い写真しかないわけだ。
多分若書きのまま,亡くなったのだろう。詩集が出版されたのは死後のことになる。
勝手な印象でいえば,最後の二行が要らない気がする。
よしと うべなうとき
そこに たちまち ひかりがうまれる
そう書いた時,悲しんでいる自分を突き放している。すでに,悲しむ自分が,一筋の道として見えている。その意味で,悲しみは,超えている。
かなしみ
と題する詩が,谷川俊太郎にもある。
あの青い空の波の音が聞こえるあたりに
何かとんでもないおとし物を
僕はしてきてしまつたらしい
透明な過去の駅で
遺失物係の前に立つたら
僕は余計に悲しくなつてしまつた
このときも,悲しみは,既に超えられている。だから,悲しみの由来を見ている。
しかし,中原中也の,
汚れっちまった悲しみに……
は,少し違う。
汚れっちまった悲しみに
今日も小雪の降りかかる
汚れっちまった悲しみに
今日も風さえ吹きすぎる
汚れっちまった悲しみは
たとえば狐の革裘(かわごろも)
汚れっちまった悲しみは
小雪のかかってちぢこまる
汚れっちまった悲しみは
なにのぞむなくねがうなく
汚れっちまった悲しみは
倦怠(けだい)のうちに死を夢(ゆめ)む
汚れっちまった悲しみに
いたいたしくも怖気(おじけ)づき
汚れっちまった悲しみに
なすところもなく日は暮れる……
この詩の中也のことについては,
http://ppnetwork.seesaa.net/article/414295670.html
で書いた。中也は,悲しみの堂々巡りのどつぼから出られていない。出られていない自分をみている。その分悲しみは深い,という気がする。
藤村操,
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%9D%91%E6%93%8D
と言う旧制一高生が遺書として残した,
「巌頭之感」
がある。
巌頭之感
悠々たる哉天壤、
遼々たる哉古今、
五尺の小躯を以て此大をはからむとす、
ホレーショの哲學竟(つい)に何等のオーソリチィーを價するものぞ、
萬有の眞相は唯だ一言にして悉す、曰く「不可解」。
我この恨を懐いて煩悶、終に死を決するに至る。
既に巌頭に立つに及んで、
胸中何等の不安あるなし。
始めて知る、
大なる悲觀は大なる樂觀に一致するを。
ホレーショとはシェイクスピア『ハムレット』の登場人物を指すらしく,
There are more things in heaven and earth, Horatio. Than are dreamt of in your philosophy
(世界には哲学では思いも寄らないことがある)
らしい。ここに,悲しみは悲しみとして受け止めきれない,悲しみが見える。「悲しみ」(http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba3.htm#%E6%82%B2%E3%81%97%E3%81%BF) で書いたように,「悲」の字は,「哀」の字とともに,いわゆる悲しみで,
悲は,喜の反対。痛なり,
哀は,楽の反対。あわれがりて,深く悲しむ。哀悼と用いる。哀は痛みの声に現れるもの。悼は痛みの心に存する,
とある。「悲」(痛み)の声に現れるのを「哀」というとある。
つまり,悲しみは痛みに通ずるらしいのだ。藤村の遺書にあるのは,悲しみの所以を知らず,傷む心の悲鳴に見える。
参考文献;
藤堂明保他編『漢字源』(学習研究社)