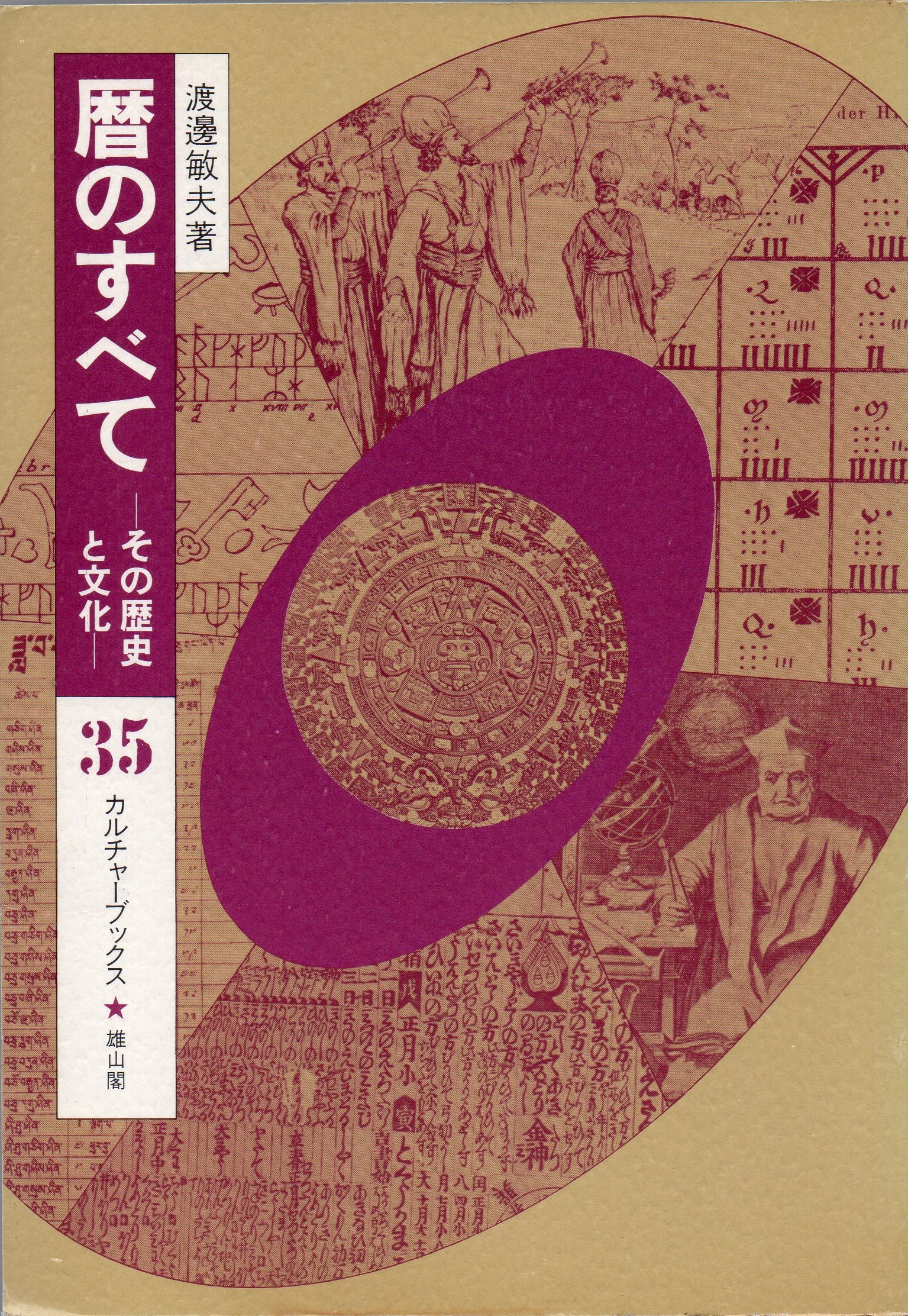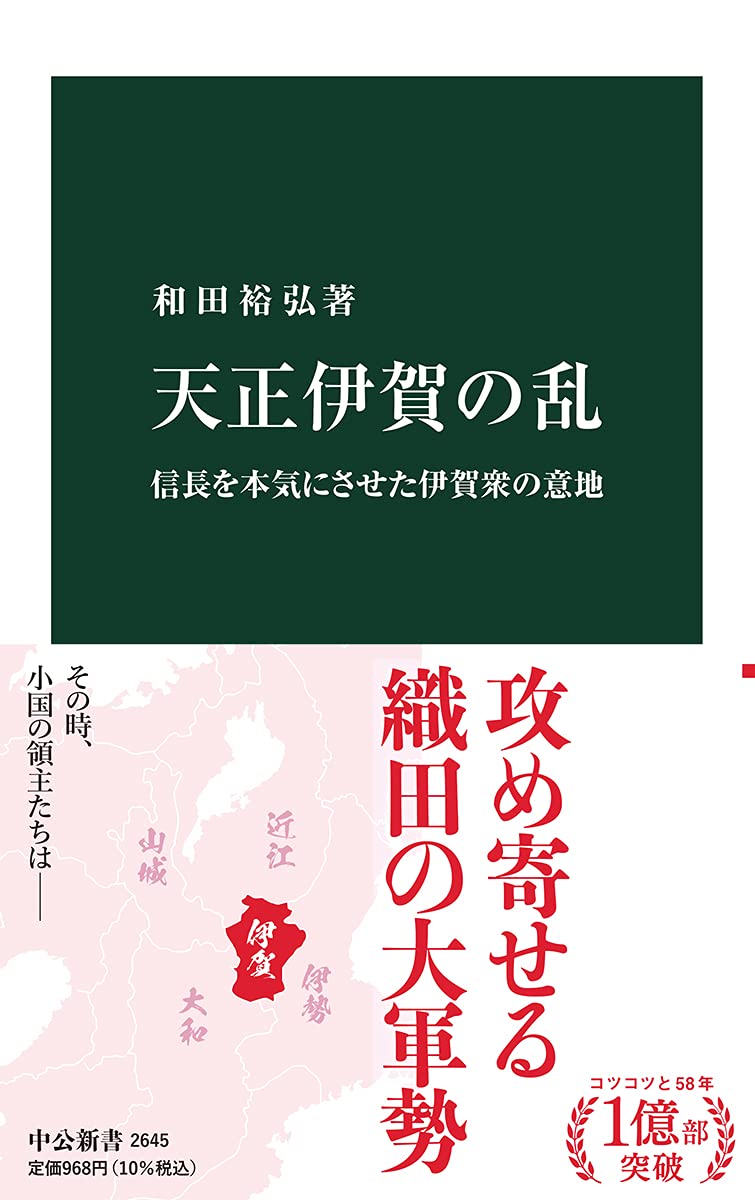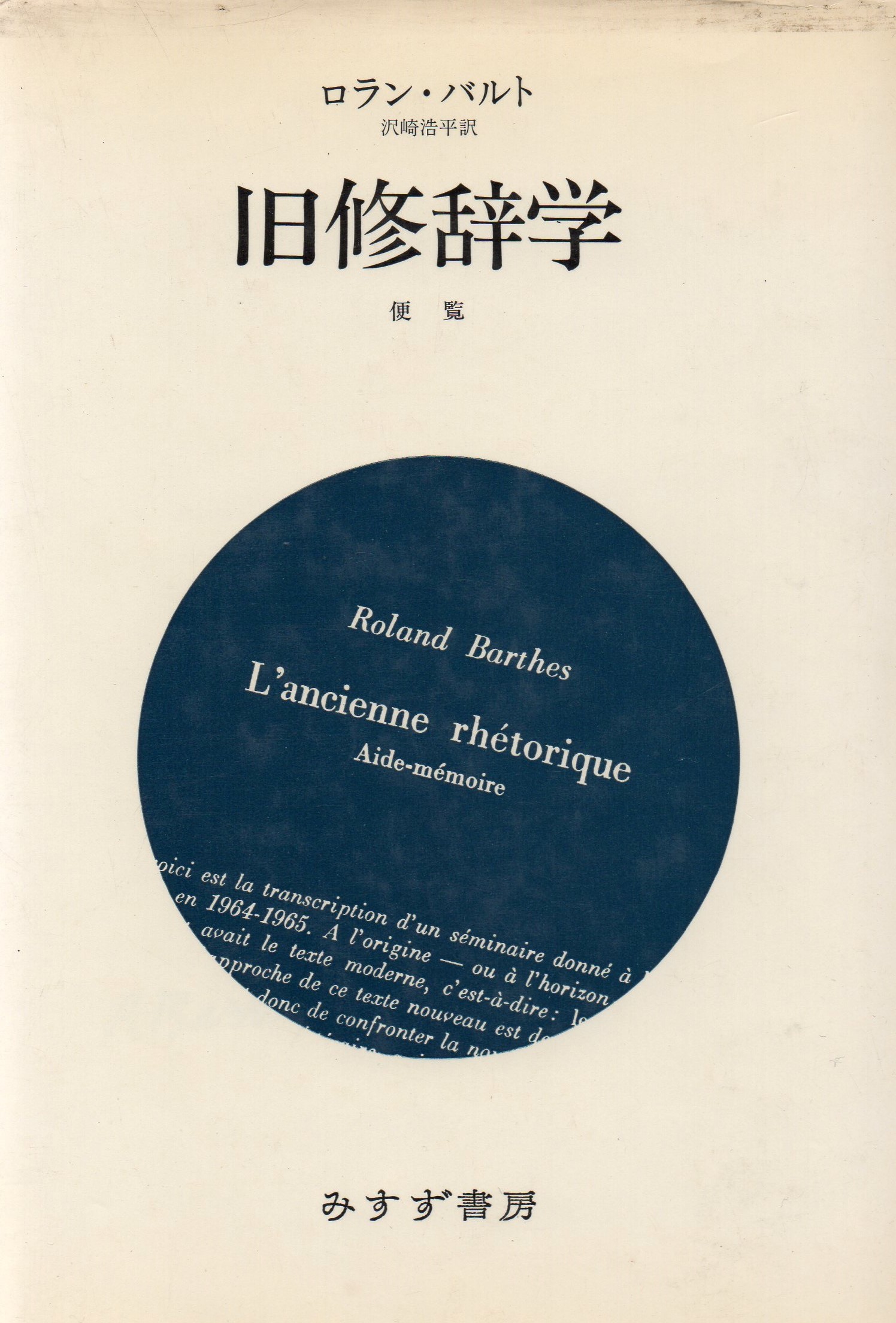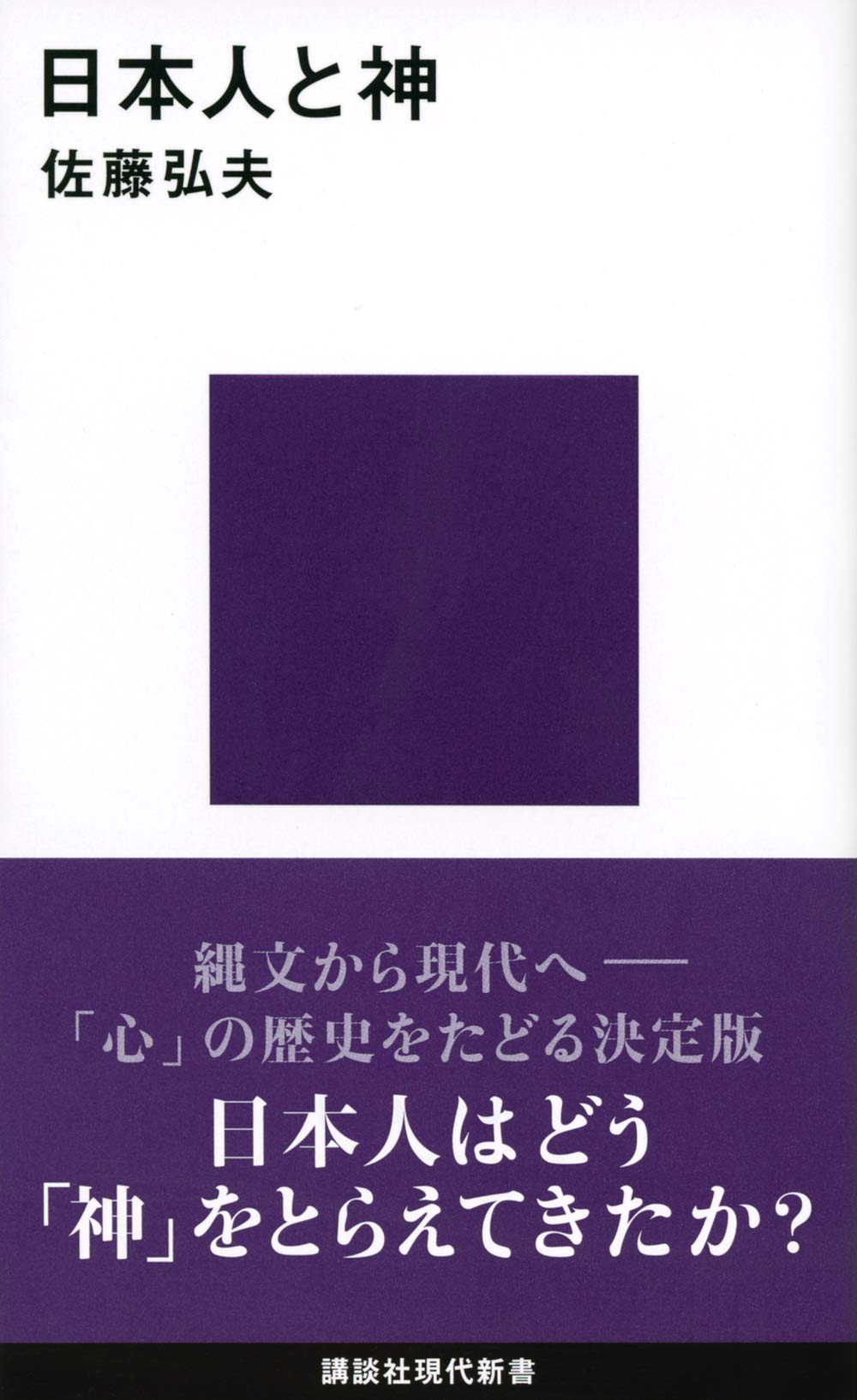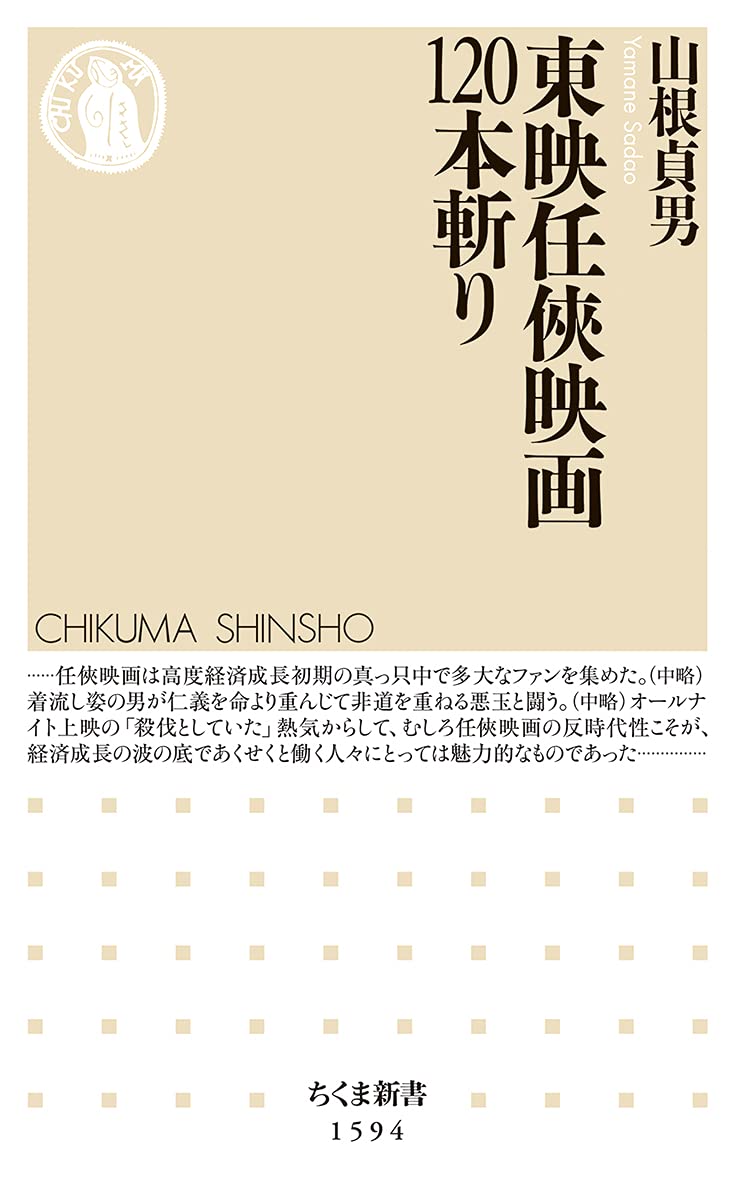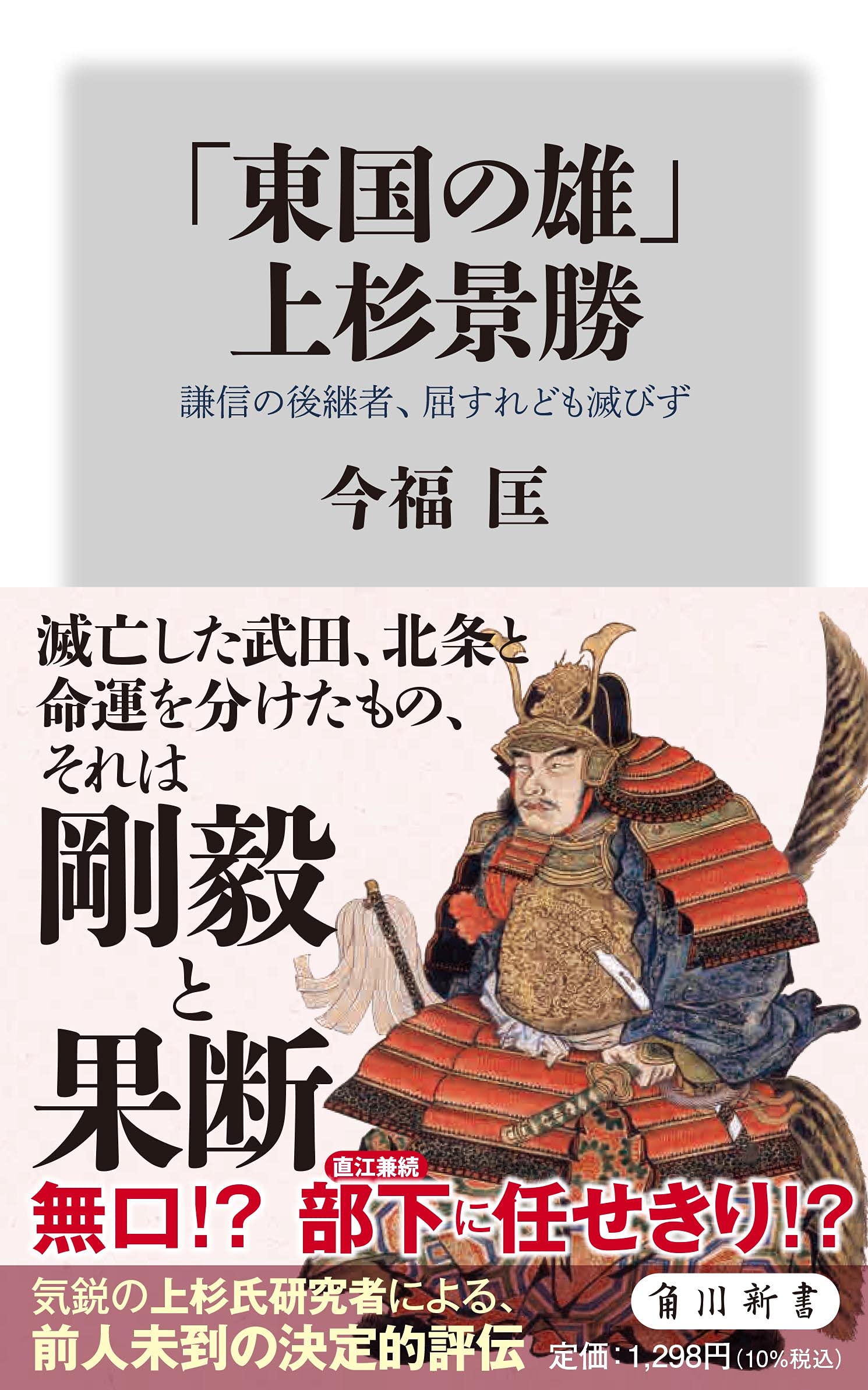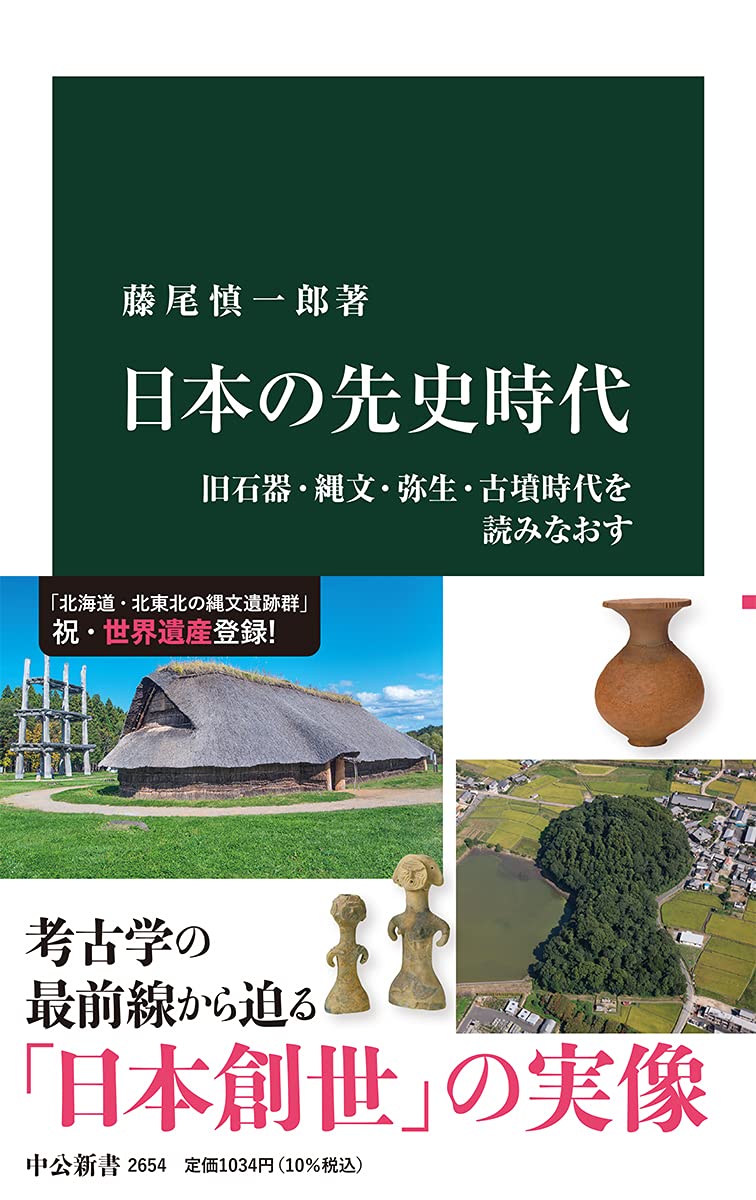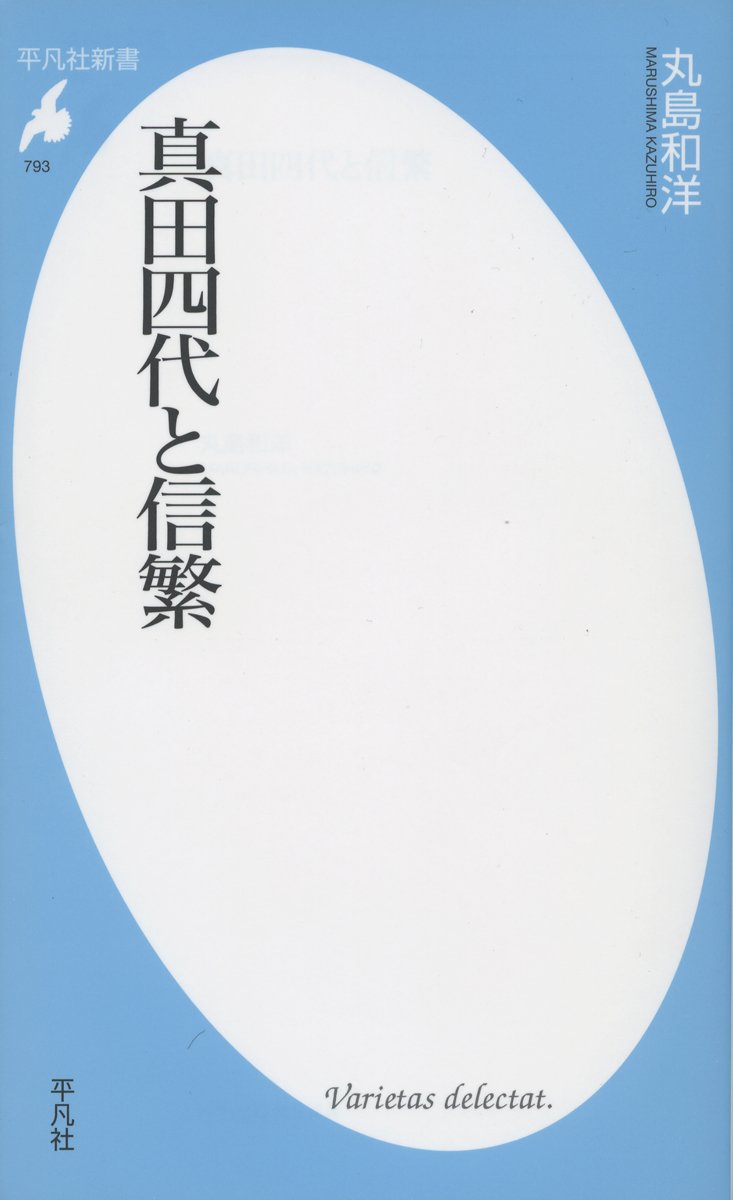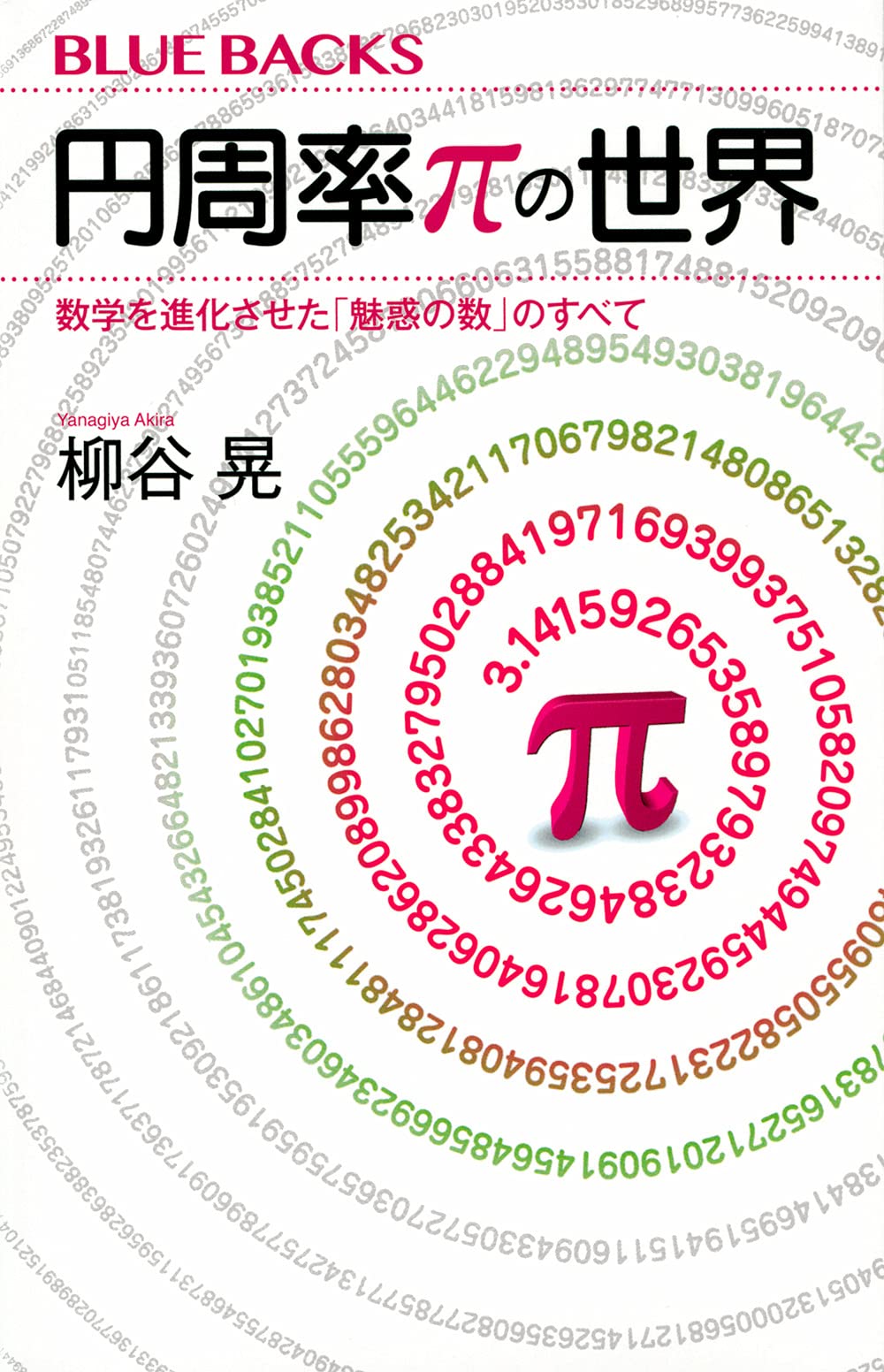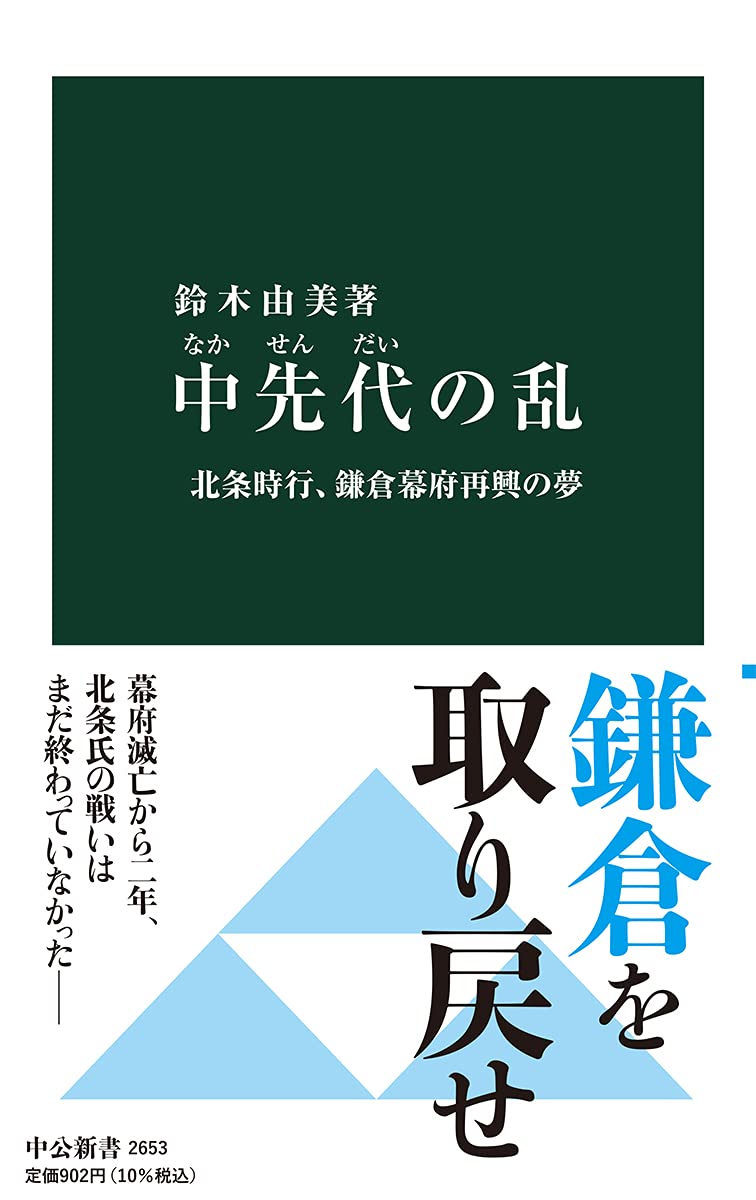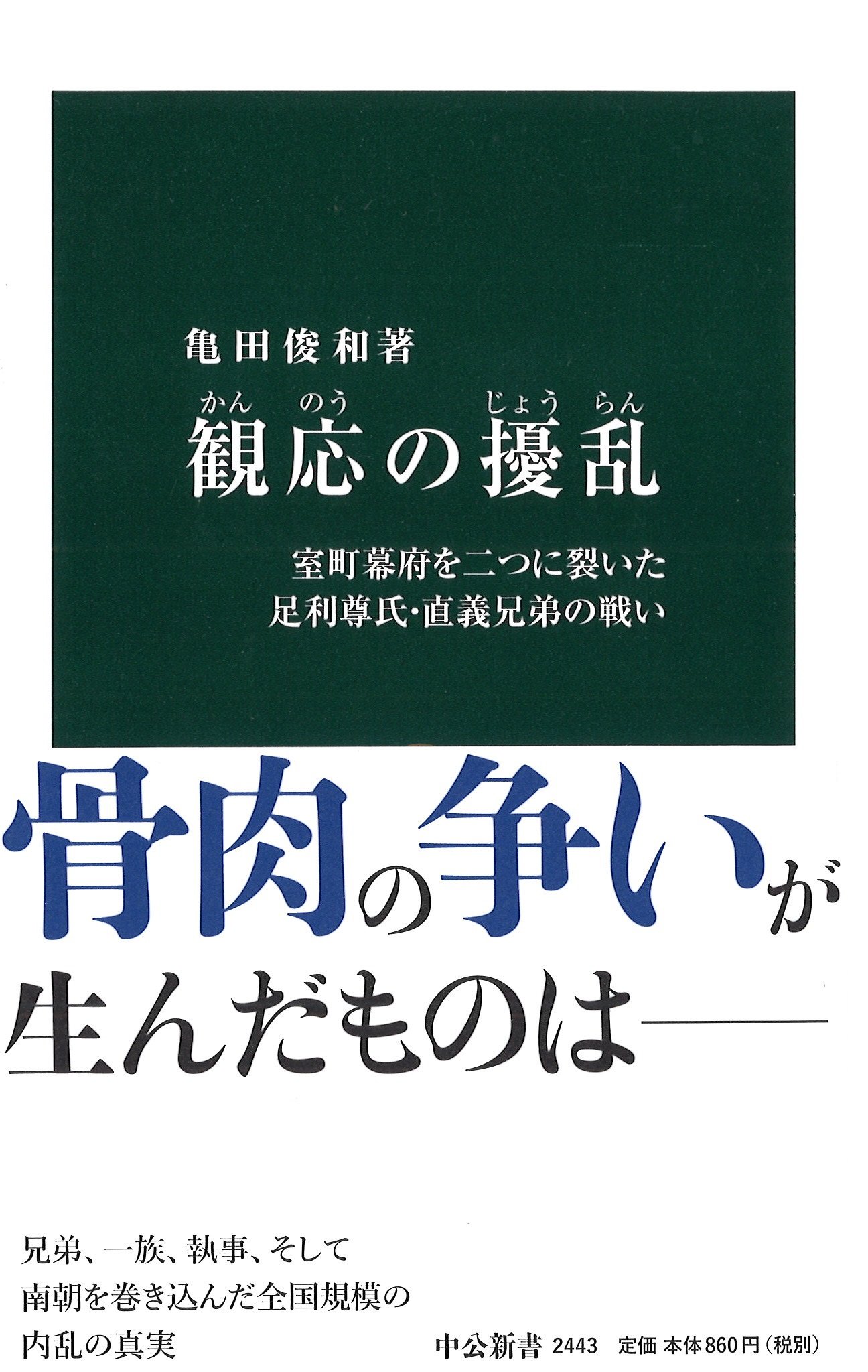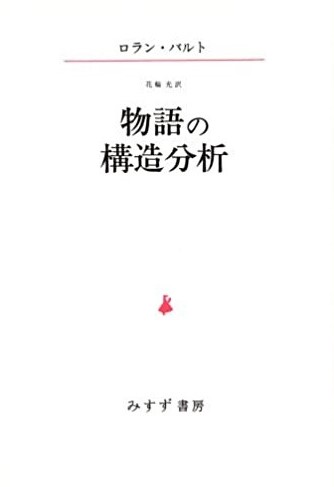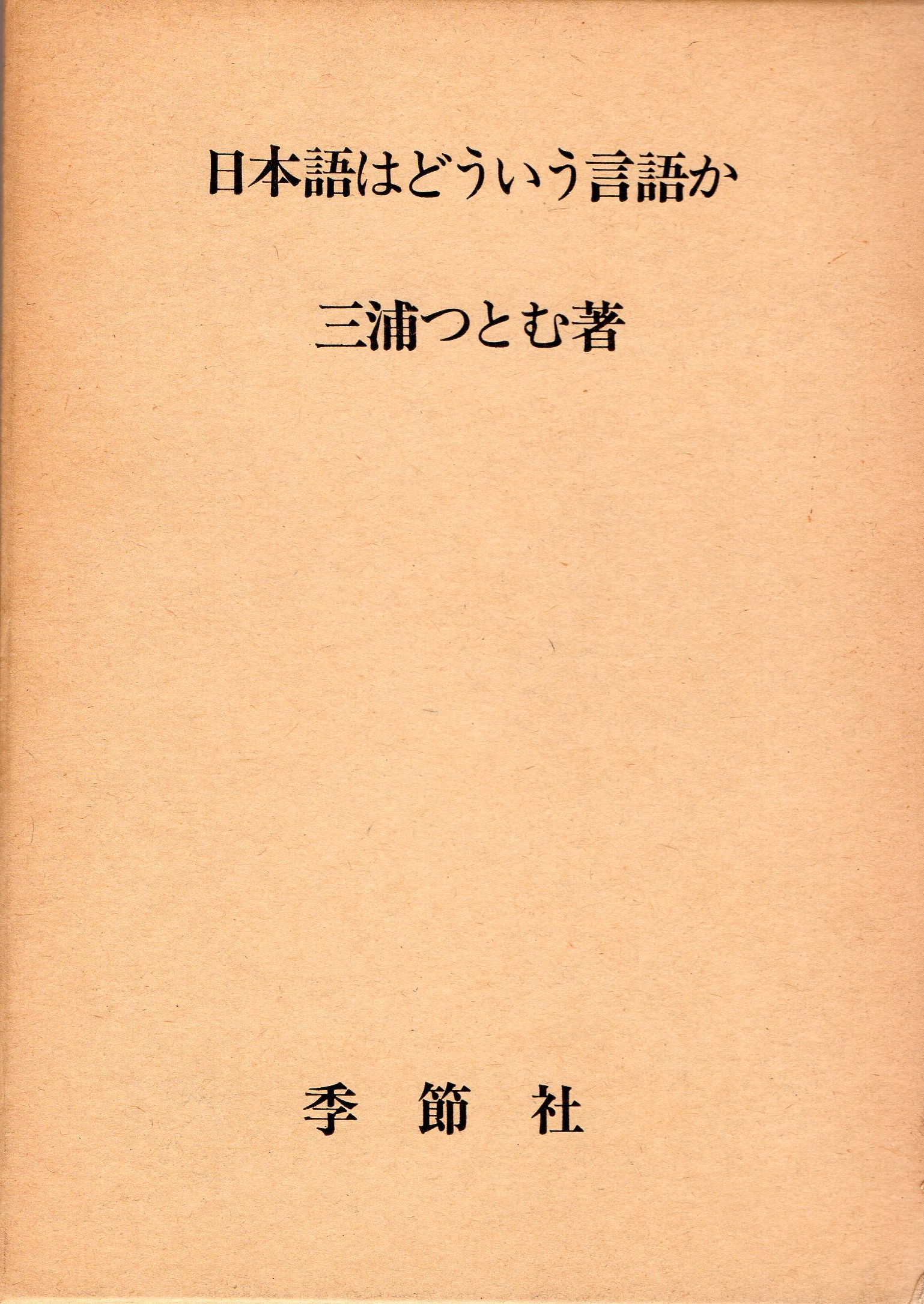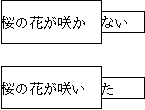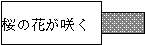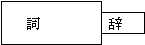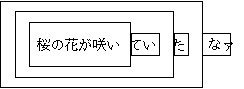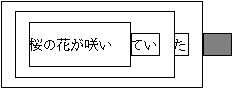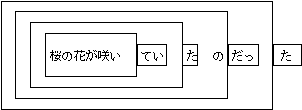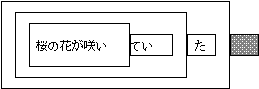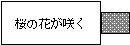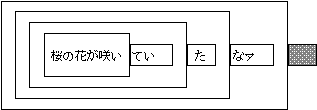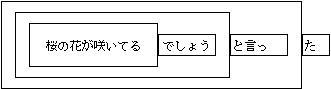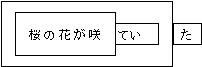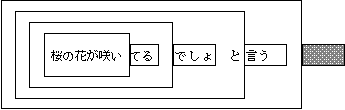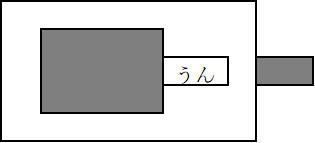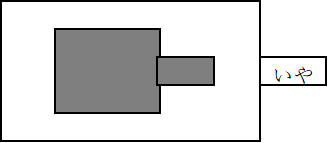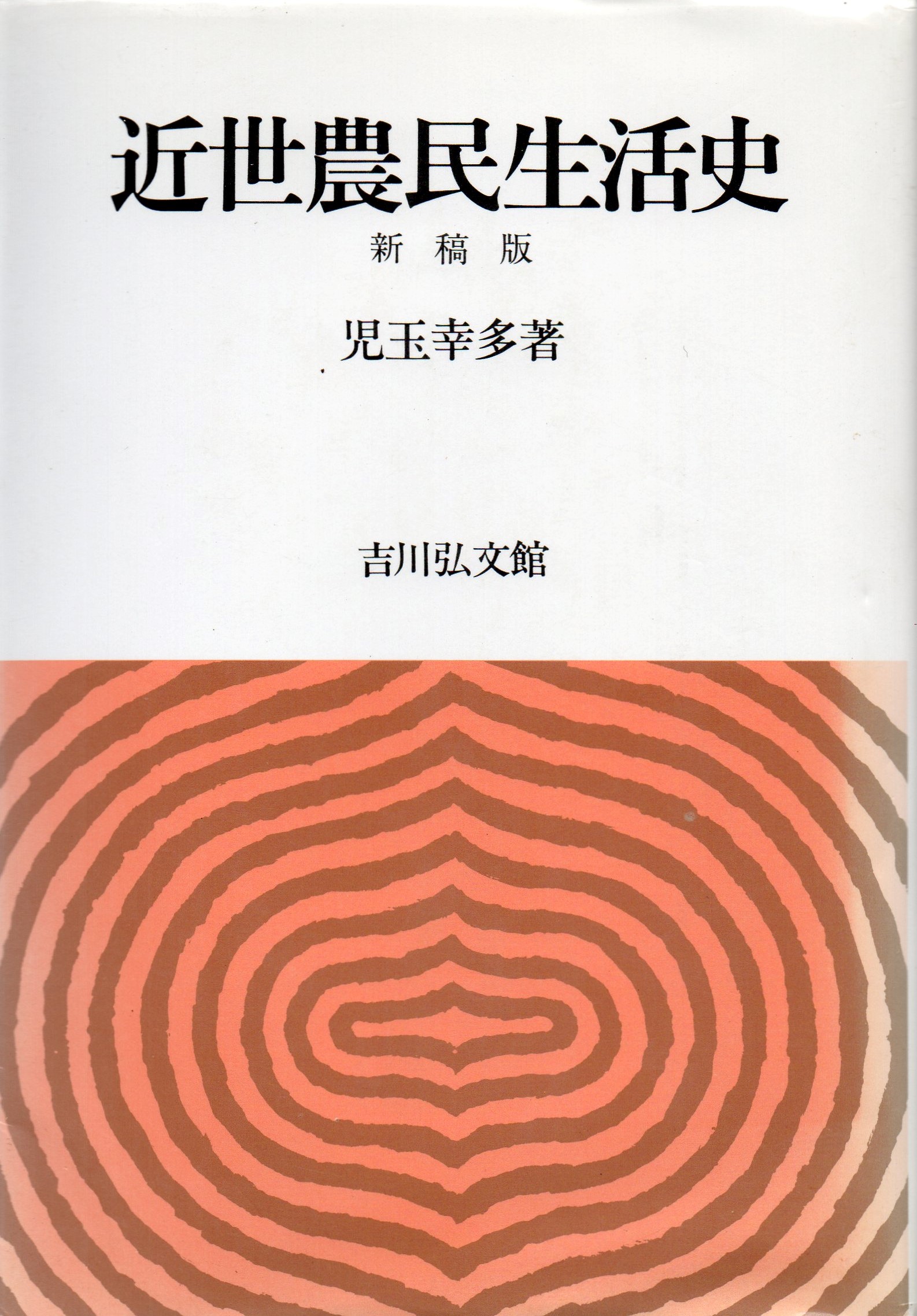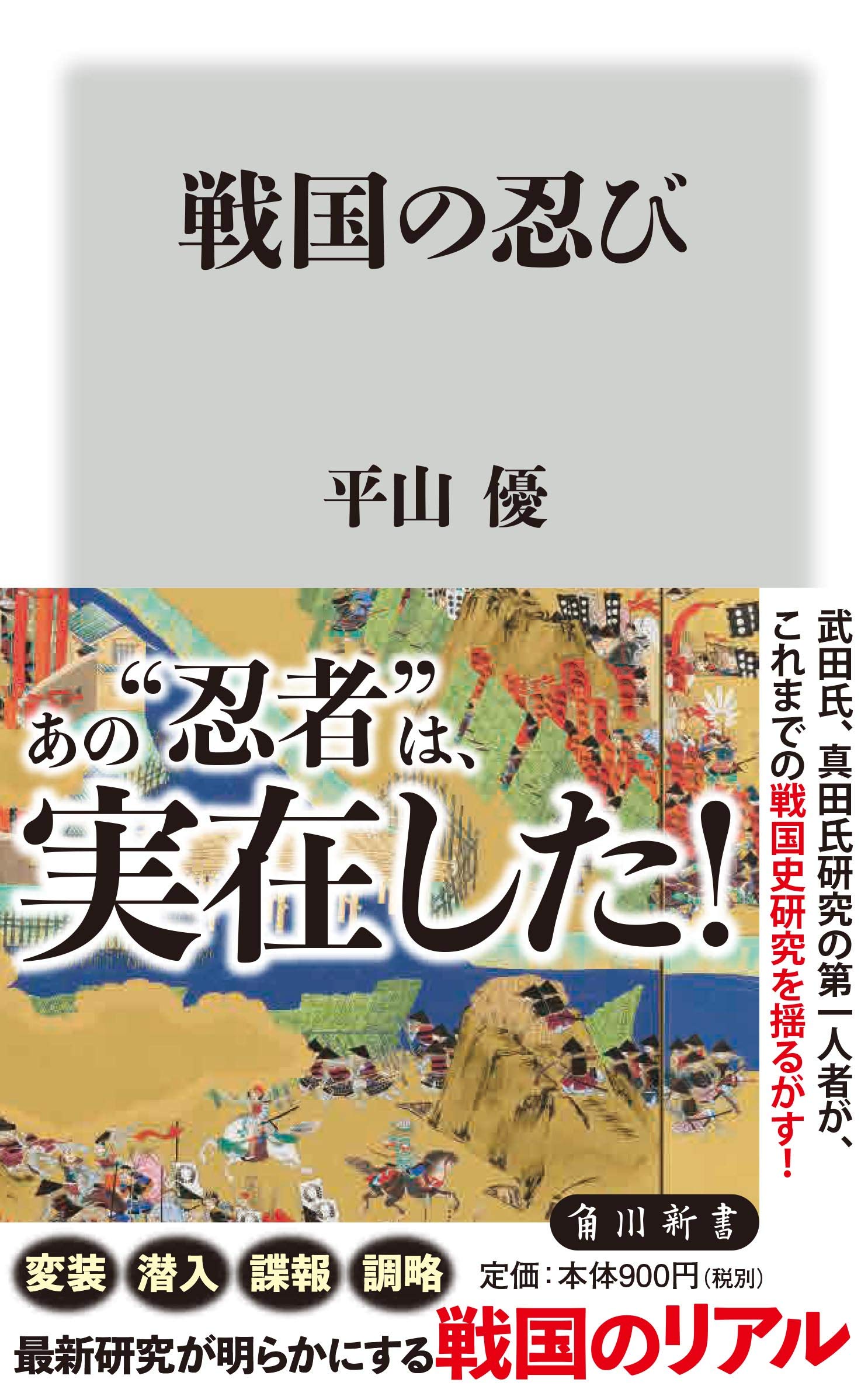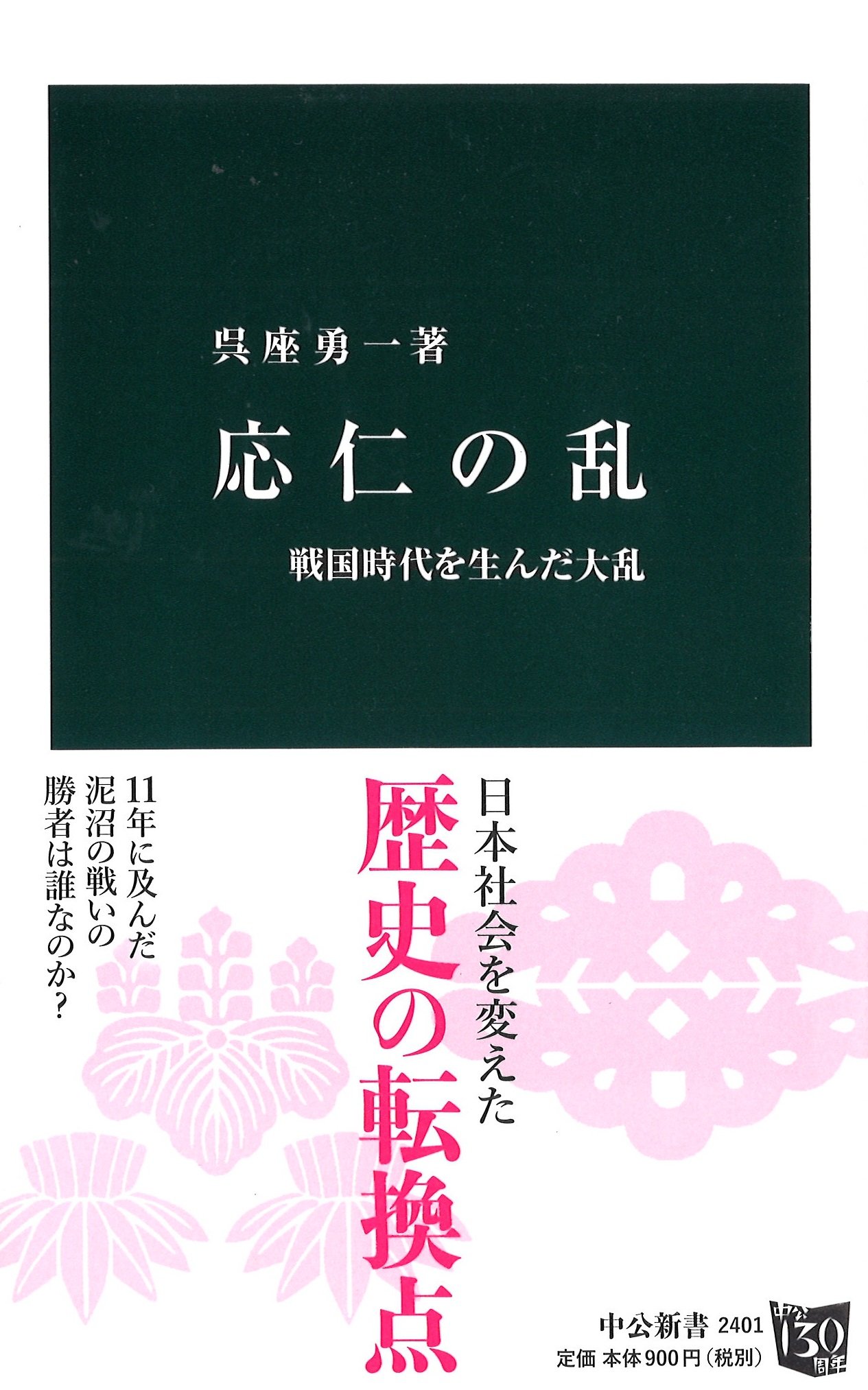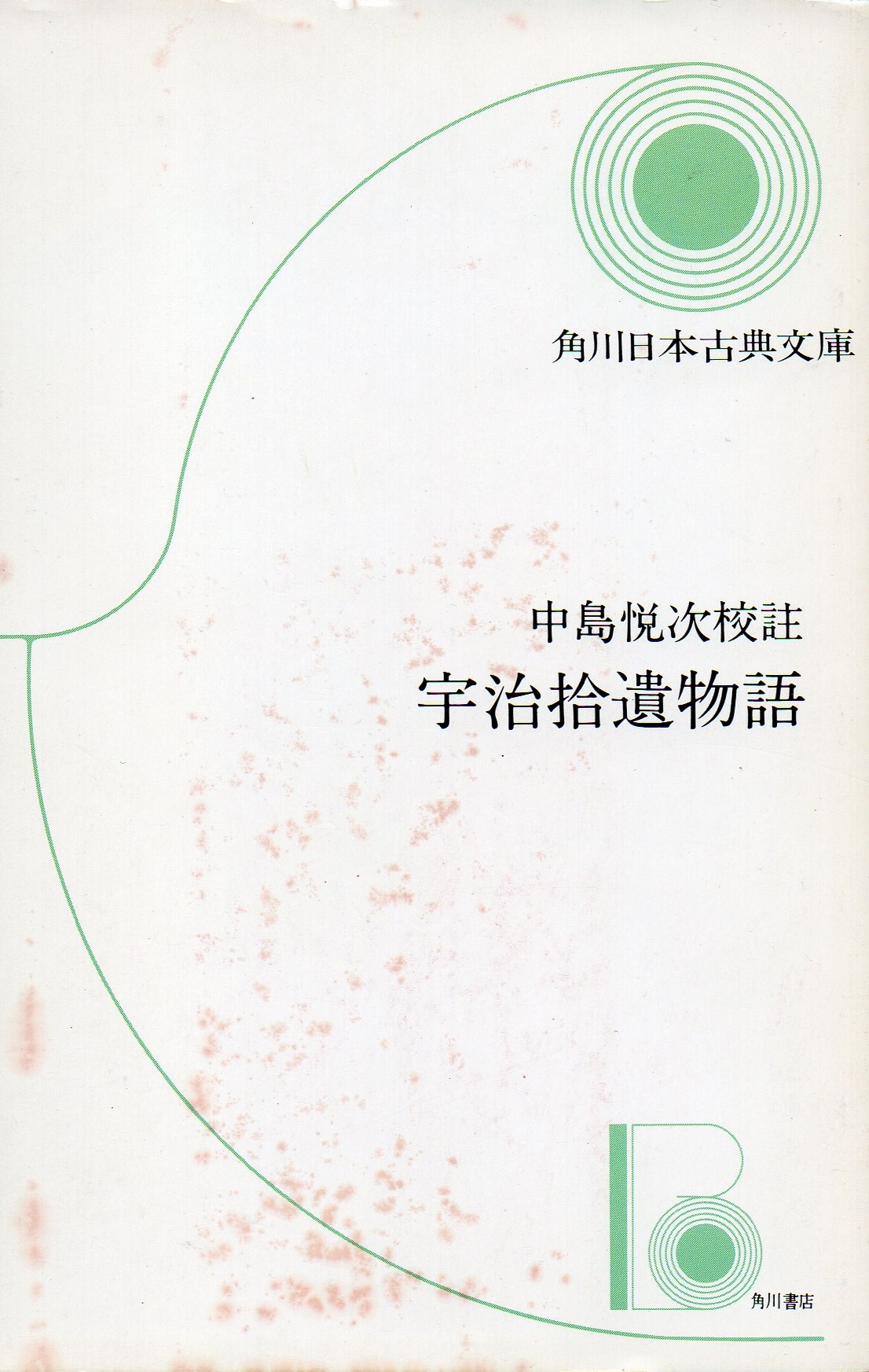| “n粕q•vپw—ï‚ج‚·‚ׂؤپ\‚»‚ج—ًژj‚ئ•¶‰»پx“ا‚قپB
پu—ïپv‚ئ‚حپA |
| کa“c—TچOپw“Vگ³ˆة‰ê‚ج—گپ\گM’·‚ً–{‹C‚ة‚³‚¹‚½ˆة‰êڈO‚جˆس’nپx‚ً“ا‚ق
پ@
|
| ƒچƒ‰ƒ“ ƒoƒ‹ƒgپw‹ŒڈCژ«ٹwپx‚ً“ا‚قپB
–{ڈ‘‚حپAپuڈCژ«ٹwپv‚ج—ًژj‚ة“–‚½‚éپA |
| ƒNپ[ƒٹƒGپEƒWƒƒƒ|ƒ“•زپw•د–e‚·‚é–¢—ˆپ\گ¢ٹEٹé‹ئ14ژذ‚جژںٹْگي—ھپx‚ً“ا‚قپB
–{ڈ‘‚حپAپuƒNپ[ƒٹƒGپEƒWƒƒƒ|ƒ“پv‚ةŒfچع‚³‚ꂽ‹Lژ–‚©‚çپAپuƒrƒbƒOƒeƒbƒN‚ح‚ا‚±‚ةŒü‚©‚¤‚©پv‚ئ‚¢‚¤ƒeپ[ƒ}‚إپA |
| چ²“،چO•vپw“ْ–{گl‚ئگ_پx‚ً“ا‚قپB
–{ڈ‘‚حپA |
|
ژRچھ’ه’jپw“Œ‰f”C‹ ‰f‰و120–{ژa‚èپx“ا‚قپB
|
| چ‚گ…—Tˆêپw‰F’ˆگl‚ئڈo‰ï‚¤‘O‚ة“ا‚ق–{پ\‘S‰F’ˆ‚إ‹¤’ت‚ج‹³—{‚ًگg‚ة‚آ‚¯‚و‚¤پx‚ً“ا‚قپB
–{ڈ‘‚حپA‰¼چ\‚جپA |
| چ،•ں‹§پwپu“Œچ‘‚ج—Yپvڈمگ™Œiڈںپ\ŒھگM‚جŒمŒpژزپA‹ü‚·‚ê‚ا‚à–إ‚ر‚¸پx“ا‚قپB
ڈمگ™Œiڈں‚حپAŒھگM‚ج‰™‚إ‚ ‚éپiژo‚جژqپjپB‚ا‚؟‚ç‚©‚ئ‚¢‚¤‚ئپAٹm‚©‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پw“V’nگlپx‚إ‚àپAژه–ً‚ھ’¼چ]Œ“‘±‚إ‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚ةپA–ع—§‚½‚تپA’n–،‚ب‘¶چف‚إ‚ ‚éپBژi”n—ة‘¾کY‚حپA |
|
“،”ِگTˆêکYپw“ْ–{‚جگوژjژ‘مپ\‹ŒگخٹيپE“ꕶپE–يگ¶پEŒأ•ژ‘م‚ً“ا‚ف‚ب‚¨‚·پx“ا‚قپB
پuگوژjژ‘مپv‚ئ‚حپA |
| ٹغ“‡کa—mپwگ^“cژl‘م‚ئگM”ةپx‚ً“ا‚قپB
چKچjپ\گMچjپ\ڈ¹چKپ\گM”V ‚جگ^“cژl‘م‚ً’ا‚¤پB‚»‚جˆسگ}‚ًپAپu‚ح‚¶‚ك‚ةپv‚إپA پuگ^“c‰ئ‚حپAگM”ة‚ج‘c•ƒچKچj‚ج‘م‚ة•گ“c‰ئ‚ة‘®‚µ‚½چ‘ڈO‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ئ‚±‚ë‚ھپA•گ“c‰ئ‚ھگD“cگM’·‚ة–إ‚ع‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚½‚كپAگM”ة‚ج•ƒڈ¹چK‚حگ^“c‰ئ‚ً•غŒى‚µ‚ؤ‚‚ê‚éگيچ‘‘ه–¼‚ً‹پ‚ك‚ؤڈ”‘ه–¼پi“؟گى‰ئچNپAڈمگ™ŒiڈںپA–kڈًژپ’¼پj‚ج‚à‚ئ‚ً“n‚è•à‚«پAچإڈI“I‚ة–LگbڈG‹g‚ةڈ]‚¤پB پ@“V‰؛گl‚ئ‚ب‚ء‚½–LگbڈG‹g‚حپAچ،‚ـ‚إ‚ئˆظ‚ب‚èپAچ‘ڈO‚ئ‚¢‚¤ژ©ژ،—جژه‚ً”F‚ك‚ب‚¢•ûگj‚ً‚ئ‚ء‚½پB‚¾‚©‚çڈ]—ˆ‚جچ‘ڈO‚حپA‡@ژ©ژ،Œ ‚ً剝’D‚³‚ê‚ؤ‘ه–¼‚ج‰ئگb‚ة‚ب‚é‚©پA‡A‰üˆص‚³‚ê‚é‚©‚ة•ھ‚©‚ꂽپBگ^“c‰ئ‚حچK‰^‚ة‚àپAڈG‹g‚©‚ç“ئ—§‘ه–¼‚ئ‚µ‚ؤ”F‚ك‚ç‚êپAچ]Œثژ‘م‚ً’ت‚¶‚ؤ‘ه–¼‚ئ‚µ‚ؤ‘¶‘±‚µ‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚آ‚ـ‚èچ‘ڈO‚ئ‚حپAگيچ‘ژ‘م“ئژ©‚ج‘¶چف‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB پ@‚¾‚©‚çگ^“cژپ‚ج—ًژj‚ً’ا‚¤‚±‚ئ‚حپAگيچ‘ژ‘م‚»‚ج‚à‚ج‚ًچl‚¦‚邱‚ئ‚ة‚آ‚ب‚ھ‚éپBپv ‚ئڈq‚×پA چ‘ڈO‚ئ‚µ‚ؤ‚جگ^“c‰ئ‚ًٹm—§‚µ‚½چKچjپEگMچjپA ‚©‚çپA ‹كگ¢‘ه–¼‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‘b‚ً’z‚ڈ¹چKپEگM”VپiگMچKپjپA ‚ـ‚إ‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚پA‚ئپB‚»‚ê‚حپA پuچKچj‚جٹˆ“®‚ھ‚ي‚©‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é1540”Nچ ‚©‚çپAڈ¼‘م”ث‘c‚ئ‚ب‚ء‚½گM”V‚ھ–v‚·‚é1658”N‚ـ‚إ‚ج–ٌ100”Nپv ‚ھ‘خڈغ‚ة‚ب‚éپB‚µ‚©‚µپA پuژہ‚ح•گ“cژ‘م‚ج‚±‚ئ‚µ‚©‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢پv ‚ئ‚¢‚¤پB‚و‚¤‚â‚‹ك”NپA پu–LگbڈG‹g‚ةڈ]‚¤‚ـ‚إ‚ج“®Œü‚ھ‚ ‚«‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½پv ‚ھپA پu–Lگb‘ه–¼‚ئ‚ب‚ء‚ؤˆبچ~پAچ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚جگ^“c‰ئ‚آ‚¢‚ؤ‚حپAگ”‚¦‚é‚ظ‚ا‚µ‚©Œ¤‹†‚ھ‚ب‚¢پv ’†‚إ‚جپA–{ڈ‘‚حپAŒ»چفگiچsŒ`‚إ‚جگ¬‰تپA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB ‚µ‚©‚µپwچb—zŒRٹسپx‚إپA پi‘\”Hڈ¹گ¢پEژOژ}ڈ¹’ه‚ئ•ہ‚ٌ‚إپjگMŒ؛‚ج—¼ٹلپA ‚ئڈج‚³‚êپA پuگMŒ؛ژ©گg‚ھ‚»‚جڈê‚ةچs‚©‚ب‚‚ؤ‚àپAژ©•ھ‚إŒ©‚ؤ‚«‚½‚©‚ج‚و‚¤‚ةپAڈَ‹µ•ھگح‚جچق—؟‚ً•ٌچگ‚·‚é‚ئژ]‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپv ˆê•û‚إپAڈG‹g‚©‚ç‚حپA •\— ”ن‹»ژزپi‚ذ‚ه‚¤‚è‚ذ‚«‚ه‚¤‚ج‚à‚جپjپA ‚ئ•]‚³‚êپA — •\‚ج‚ ‚éگM—ٹ‚إ‚«‚ب‚¢گl•¨پA ‚ئŒ©‚ب‚³‚ê‚ؤ‚à‚¢‚½پA گ^“cڈ¹چKپA ‚ھˆê”ش–ت”’‚¢پBگM”Z‚جڈ¬Œ§پi‚؟‚¢‚³‚ھ‚½پjگ^“c‹½‚جچ‘ڈO‚©‚çپA–Lگb‘ه–¼‚ئ‚µ‚ؤ—ٌ‚µپA ڈ¹چK‚جڈم“c—ج3–œ8000گخپA گMچK‚جڈہ“c—ج2–œ7000گخپA ‚ً—ج‚µپA‚³‚ç‚ةپA–LگbڈG‹g‚ج”n‰ô–ً‚ئ‚ب‚ء‚½پA گM”ة‚ج1–œ9000گخپA ‚ھ‰ء‚ي‚é‚ـ‚إ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB “ء‚ة•گ“c‰ئ–إ–SŒم‚جپAگ¶‚«ژc‚è‚ً‚©‚¯‚½پA–kڈًپAڈمگ™پA“؟گى‚ئپA‹A‘®گو‚ً•د‚¦‚آ‚آپA‘خڈمگ™‚ج‹’“_‚ئ‚µ‚ؤپA“؟گى‰ئ‚ةڈم“cڈé‚ً’zڈ邳‚¹پA‘خ“؟گى‚ج‹’“_‚ئ‚µ‚ؤ‚جڈم“cڈé‰üڈC‚ًڈمگ™‚ةچs‚ي‚¹پAژ©‚çپA‚»‚جڈéژه‚ة‚¨‚³‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚Œoˆـ‚حپAڈ¬‚³‚بچ‘ڈO‚ھپA‘ه‚«‚بگيچ‘‘ه–¼‚ًژè‹ت‚ةژو‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إپA’ة‰ُ‚إ‚à‚ ‚éپB‚µ‚©‚à“؟گىپE–kڈًٹش‚جکa–r‚إپA‚à‚ك‚ة‚à‚ك‚½گ^“c‚جڈہ“c—ج–â‘è‚إ‚حپAڈG‹g‚جپuڈہ“cچظŒˆپv‚إپA ڈہ“c—ج‚جژO•ھ‚جˆê‚ھگ^“c—جپA ڈہ“c—ج‚جژO•ھ‚ج“ٌ‚ھپA–kڈً—جپA ‚ئŒˆ‚µ‚½‚ج‚ةپAگ^“c—ج‚ة‘g‚ف“ü‚ê‚ç‚ꂽ–¼Œس“چڈé‚ض‚ج–kڈً‚جڈo•؛‚ھپAڈ¬“cŒ´چU‚ك‚ج‚«‚ء‚©‚¯‚ئ‚ب‚é‚ب‚اپA‚±‚ج’nˆو‚إ‚جڈ¹چK‚حپA‚¢‚ي‚خ‘ن•—‚ج–ع‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB ڈ¹چK‚ة‚آ‚¢‚إ–ت”’‚¢‚ج‚حپA‚â‚ح‚èپA‘‚ةپA چK‘؛پA ‚ئŒؤ‚خ‚ê‚éپA گM”ة‚جپA‘هچâڈéچ‡گي‚إ‚جٹˆ–ô‚¾‚낤پB‚µ‚©‚µپA–¼‚ة‚µ•‰‚¤پA گ^“cٹغپA ‚حپA پuگ^“cٹغ’zڈé‚حپAگM”ة‚ج”ˆؤ‚إ‚ح‚ب‚پAڈ”ڈ«‚ج’kچ‡‚ة‚و‚ء‚ؤ’è‚ك‚ç‚êپAŒ‹‰ت“I‚ةگM”ة‚ھژw–¼‚³‚ꂽپv ‚ئ‚·‚éگà‚ھ‚ ‚èپi–kگىˆâڈ‘‹LپjپA پuگM”ة‚حژèگ¨‚ھڈ‚ب‚·‚¬‚ؤژç‚èگط‚ê‚ب‚¢‚ئ–kگىژںکY•؛‰q‚ة‘ٹ’k‚µپAŒم“،ٹîژں‚©–¾گخ‘S“o‚جژx‰‡‚ً‹آ‚¬‚½‚¢‚ئگ\‚µڈo‚½پB‚µ‚©‚µژںکY•؛‰q‚حپA‚¹‚ء‚©‚پwگ^“c‚ھٹغپx‚ئ–¼•t‚¯‚é‚ج‚¾‚©‚çپAژèگ¨‚ھڈ‚ب‚‚ئ‚àژ©—ح‚إژç‚é‚ׂ«‚¾‚ئ—G‚ك‚½پv ‚ئ‚¢‚¤پB‚»‚ê‚ً— •t‚¯‚ؤپA پuŒم“،ٹîژں‚ھ—VŒR‚ة‚ب‚ء‚½‚½‚ك‚ةگM”ة‚ھ‚ح‚¢‚ء‚½پv ‚ئ‹L‚µپi‘هچمŒنگwٹoڈ‘پjپAگ^“c•û‚جŒR‹L‚إ‚àپA پuڈoٹغ‚ًژَژوپv ‚ئ‚ ‚èپiگ^•گ“à“`پjپA‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‘هچم“~‚جگw—Lگ”‚جچU–hگي‚ئ‚µ‚ؤپA“؟گى•û‚ة‘ٹ“–‚ج‘¹ٹQ‚ً—^‚¦‚½‚ج‚¾‚©‚çپA‚ب‚©‚ب‚©‹»–،گ[‚¢پB ژQچl•¶Œ£پG ٹغ“‡کa—mپwگ^“cژl‘م‚ئگM”ةپxپi•½–}ژذگVڈ‘پj |
| –ِ’JچWپw‰~ژü—¦ƒخ‚جگ¢ٹEپ\گ”ٹw‚ًگi‰»‚³‚¹‚½پu–£کf‚جگ”پv‚ج‚·‚ׂؤپx“ا‚قپB
‰~ژü—¦ƒخ‚ئ‚حپA |
| —é–ط—R”üپw’†گو‘م‚ج—گپ\–kڈًژچsپAٹ™‘q–‹•{چؤ‹»‚ج–²پx‚ً“ا‚قپB
پu’†گو‘مپi‚ب‚©‚¹‚ٌ‚¾‚¢پjپv‚ئ‚حپA |
| ‹T“cڈrکaپwٹد‰‚جڈï—گپ\ژ؛’¬–‹•{‚ً“ٌ‚آ‚ة—ô‚¢‚½‘«—ک‘¸ژپپE’¼‹`ŒZ’ي‚جگي‚¢پx‚ً“ا‚قپB
پuٹد‰‚جڈï—گپi‚©‚ٌ‚ج‚¤‚ج‚¶‚ه‚¤‚ç‚ٌپjپv‚حپA پuژ؛’¬–‹•{ڈ‰‘مڈ«ŒR‘«—ک‘¸ژپ‚¨‚و‚رژ·ژ–چ‚ژt’¼‚ئپA‘¸ژپ’ي‚إ–‹گ‚ًژه“±‚µ‚ؤ‚¢‚½’ي’¼‹`پi‚½‚¾‚و‚µپj‚ھ‘خ—§‚µپAڈ‰ٹْژ؛’¬–‹•{‚ھ•ھ—ô‚µ‚ؤگي‚ء‚½‘Sچ‘‹K–ح‚جگي—گپv ‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج“àگي‚حپA پuٹد‰Œ³”Nپi1350پj10ŒژپA‘¸ژپ‚ھ•s’‡‚إ‚ ‚ء‚½ژہژq‘«ٹ_‚ھ’¼“~پi‚½‚¾‚س‚نپj‚ً“¢”°‚·‚邽‚ك‚ة‹مڈB‚ةŒü‚¯‚ؤڈoگw‚µ‚½Œ„‚ً“ث‚¢‚ؤپA’¼“~‚جڈf•ƒ‚ة‚µ‚ؤ—{•ƒ‚إ‚à‚ ‚ء‚½’¼‹`‚ھ‹“s‚ً’Eڈo‚µ‚½‚±‚ئ‚©‚çژn‚ـ‚éپv ‚ئ‚³‚êپA’¼‹`ŒR‚ھˆ³ڈں‚µپAٹد‰“ٌ”Nپi–k’©گ³•½Œـ”Nپ@1351پj“ٌŒژپAژt’¼ˆê‘°‚ھژSژE‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚إپAپuٹد‰‚جڈï—گپv‚ج ‘وˆê–‹پA ‚ھڈI‚ي‚éپB—¼ژز‚جچuکa‚حپAŒـƒ•Œژ‚إ”j’]پA“¯ژµŒژ––پA’¼‹`‚ھ‹“s‚ً’Eڈo‚µ‚ؤپA–k—¤‚ضŒü‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚إپA ‘و“ٌ–‹پA ‚ھژn‚ـ‚èپA—‚گ³•½ژµ”Nپiٹد‰ژO”Nپ@1352پj“ٌŒژ‚ة’¼‹`‚ھژ€‹ژ‚µ‚½‚±‚ئ‚إپA‹·‹`‚جپuٹد‰‚جڈï—گپv‚حڈWŒ‹‚·‚éپB‚µ‚©‚µپA‚±‚جŒم‚àپA•¶کaژO”Nپi1353پjŒـŒژپA’¼“~‚ھ‹“s‚ً–عژw‚µپA—‚ژl”NژOŒژپA‘¸ژپ‚ح’¼“~‚ًŒ‚‘ق‚µ‚½پB ‚±‚جٹش‚àپAٹد‰“ٌ”Nپi1351پjڈ\Œژ‚جپAگ³•½ˆê“پi‚µ‚ه‚¤‚ض‚¢‚¢‚ء‚ئ‚¤پj‚ئŒؤ‚شپA“ى’©‚ة“ˆê‚³‚ꂽ‹ح‚©ژlƒ–Œژ‚ًڈœ‚«پA“ى–k’©‚ج‘ˆ‚¢‚ح‘±‚¢‚ؤ‚¢‚邵پA’¼“~Œ‚‘قŒم‚àپA‚½‚ئ‚¦‚خپA‘¸ژپژ€ŒمپA پuچNˆہŒ³”Nپi1361پjڈ\“ٌŒژپA“ى’©‚حژl“x–ع‚ج‹“s’Dٹز‚ً‰ت‚½‚·پB‚¾‚ھ‚±‚ج‚ئ‚«‚à“ى’©ŒR‚جژه—ح‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚حژ¸‹r‚µ‚½‘O–‹•{ژ·ژ–چ×گىگ´ژپ‚إ‚ ‚ء‚½‚µپAگè—ج‚à‚²‚’Zٹْٹش‚إڈI‚ي‚ء‚½پB‚»‚µ‚ؤ‚±‚ê‚ھچإŒم‚ج“ü‹‚ئ‚ب‚ء‚½پBٹد‰‚جڈï—گ‚ج‚و‚¤‚بپA–‹•{‚ج‘¶–S‚ً‚©‚¯‚é‹K–ح‚جگي‚¢‚حڈI‘§‚µ‚½پv ‚ئ‚ ‚éپB‚±‚جŒمپA40”N‚à“ى–k’©“à—گ‚ھ‘±‚‚ھپA‚»‚ê‚ظ‚اگي—گ‚ً’·ˆّ‚©‚¹‚½‚ج‚حپA’¼‹`‚ھˆêژ“ى’©•û‚ة‚آ‚¢‚½‚و‚¤‚ةپA پu–‹•{‚إ‚حپAŒ —حچR‘ˆ‚ة”s–k‚·‚é‚ئ“ى’©•û‚ة“]‚¶‚é•گڈ«‚ھ‘±ڈoپv ‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ ‚èپA’¼‹`‚حپA‚»‚جگو—ل‚ة‚ب‚ء‚½پA‚ئ‚جژw“E‚حڈd—v‚¾‚낤پB “ى–k’©‚ج‘خ—§‚حپA‘[‚‚ئ‚µ‚ؤپA‚±‚جپuٹد‰‚جڈï—گپv‚حپAگ³’¼پA ‚ي‚¯‚ھ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢“à—گپA ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ꂼ‚ê’†ٹj‚ئ‚ب‚鑸ژپ”hپA’¼‹`”h‚ج•گڈ«‚ھ‚¢‚é‚ھپA‘½‚‚حپA”ق•û‚ة‚ب‚ر‚«چں•û‚ة‚ب‚ر‚«پA’è‚ـ‚ç‚ب‚¢پB—¼ژز‚ج‘خ—§‚·‚çپA‚»‚ج——R‚ھ‚ح‚ء‚«‚è•ھ‚©‚ç‚ب‚¢پB’کژز‚حپA ژہ‚ةٹï‰ِ‚ب“à—گپA ‚ئŒؤ‚شپB پuژlڈً“ë‚جگي‚¢‚إ“ï“G“ي–طگ³چs‚ةڈں—ک‚µپAژ؛’¬–‹•{‚ج”eŒ ٹm—§‚ةگâ‘ه‚بچvŒ£‚ً‰ت‚½‚µ‚½ژ·ژ–چ‚ژt’¼‚ھپA‚ي‚¸‚©ˆê”N”¼Œم‚ةژ·ژ–‚ً”ë–ئ‚³‚ê‚ؤژ¸‹r‚·‚éپB‚¾‚ھ‚»‚ج’¼Œم‚ةگ”–œ‹R‚جŒRگ¨‚ً—¦‚¢‚ؤژهŒN‚ج‘«—ک‘¸ژپ“@‚ً•ïˆح‚µپA‹t‚ةگ“G‚جژOڈً“a‘«—ک’¼‹`‚ًˆّ‘ق‚ة’ا‚¢چ‚قپB پ@‚ئ‚±‚ë‚ھ‚»‚جˆê”N‚ ‚ـ‚èŒم‚ةپA’¼‹`‚ھڈh“G‚ج“ى’©‚ئژè‚ًŒ‹‚ش‚ئ‚¢‚¤ٹïچô‚ةڈo‚éپBچ،“x‚ح‘¸ژپپ\ژt’¼‚ً— گط‚ء‚ؤ’¼‹`‚ةگQ•ش‚é•گڈ«‚ھ‘±ڈoپA‘¸ژپŒR‚ح”s–k‚µ‚ؤچ‚ˆê‘°‚حوnژE‚³‚ê‚éپB پ@‚¾‚ھ‚»‚ج‚ي‚¸‚©Œـƒ•ŒژŒم‚ة‚ح‰½‚à‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚ة’¼‹`‚ھژ¸‹r‚µ‚ؤ–k—¤‚©‚çٹض“Œ‚ض–v—ژ‚µپAچ،“x‚ح’¼‹`‚ة‘¢”½‚µ‚ؤ‘¸ژپ‚ة‹AژQ‚·‚é•گڈ«‚ھ‘ٹژں‚¢‚إپA‘¸ژپ‚ھڈں—ک‚·‚éپB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚جŒم‚à“ى’©پiژه—ح‚ح‹Œ’¼‹`”hپj‚ئ‚جŒƒگي‚ھ‚µ‚خ‚ç‚‚ح‚ظ‚ع–ˆ”NŒJ‚è•ش‚³‚ê‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB پ@’Zٹْٹش‚إŒ`گ¨‚ھ‹ة’[‚ة•د“®‚µپA’nٹٹ‚è“I‚ب—£چ‡ڈWژU‚ھ‘±‚ˆَڈغ‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بگي—گ‚حپA“ْ–{ژjڈم‚إ‚à—ق‚ًŒ©‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBپv ‚±‚ج—£چ‡ڈWژU‚ح‚ب‚؛‹N‚«‚é‚ج‚©پB—¼ژز‚جژxژ‘w‚ة‚حپA پu–¾ٹm‚بپcپcˆل‚¢‚ب‚ا‘¶چف‚¹‚¸پA—¼”h‚حٹî–{“I‚ة“¯ژ؟‚إ‚ ‚ء‚½پB”غپA‚»‚ٌ‚ب“}”h‘خ—§‚ب‚ا‘¶چف‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB–¾ٹm‚ب”h”´‚ھŒ`گ¬‚³‚ê‚ح‚¶‚ك‚é‚ج‚حپA‚ا‚ٌ‚ب‚ة‘پ‚Œ©گد‚à‚ء‚ؤ‚à’هکaژl”Nپi1348پjگ³Œژ‚جژlڈً“ë‚جگي‚¢ˆبچ~‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚µ‚ؤˆê•”‚ج•گڈ«‚ًڈœ‚¢‚ؤپA‚»‚جچ\گ¬‚àچإŒم‚ـ‚إ—¬“®“I‚إ‚ ‚ء‚½پv ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ’کژز‚جŒ©•û‚إ‚ ‚éپB‚إ‚حپA‰½‚ھŒ´ˆِ‚©پB
پu‚»‚à‚»‚àٹد‰‚جڈï—گ‚ج’¼گع“I‚ح‚¶‚ـ‚è‚حپA‘¸ژپ‚ئژt’¼‚ھ‹مڈB‚ج’¼“~‚ً“¢”°‚·‚邽‚ك‚ةڈoگw‚µ‚½‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پBژj—؟‚ة–R‚µ‚¢“ï“_‚ح‚ ‚é‚ھپA‘¸ژپ‚جژہژq‚إ—L”\‚إ‚ ‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‚ب‚؛‚©ˆظڈي‚ةٹُ‚فŒ™‚ء‚ؤ”rڈœ‚µ‘±‚¯‚鑸ژپ‚ة”½”‚ھڈW‚ـ‚ء‚½ژ–ڈî‚حٹm‚©‚ة‚ ‚ء‚½‚ئژv‚ي‚ê‚éپB”©ژRچ‘گ´‚ھ’¼‹`”h‚ة“]‚¶‚½‚ج‚àپA‚»‚ج—v‘f‚ھ‘ه‚«‚¢‚ئگ„’肵‚ؤ‚¢‚éپcپcپB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ٌ‚ب‘¸ژپ‚جˆس‚ًڈ³‚¯‚ؤپA’„ژq‹`‘Fپi‚و‚µ‚ ‚«‚çپj‚ًژںٹْڈ«ŒR‚ة‚·‚邽‚ك‚ة‘S—ح‚إŒ£گg‚µ‚ؤ‚¢‚½ژt’¼‚ة‘خ‚µ‚ؤ”ل”»‚ھڈW’†‚µ‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBپv |
| ƒچƒ‰ƒ“پEƒoƒ‹ƒgپw•¨Œê‚جچ\‘¢•ھگحپx‚ً“ا‚قپB
–{ڈ‘‚ج–ع‹ت‚حپAٹھ“ھ‚جپA |
| ژO‰Y‚آ‚ئ‚قپw“ْ–{Œê‚ح‚ا‚¤‚¢‚¤Œ¾Œê‚©پx“ا‚قپB
’کژز‚حپA–`“ھ‚إپAژl‚آ‚جگف–â‚ً‚µپA–{ڈ‘‘S‘ج‚ض‚ج–â‘èˆسژ¯‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‚ئگ}ژ¦‚µ‚½پi‚±‚جگ}ژ¦‚جژd•ûژ©‘جپAژO‰Y‚آ‚ئ‚قژپ‚جˆؤڈo‚µ‚½‚à‚ج‚¾پj•\Œ»‚ة‚¨‚¯‚éپAپu‚½پv‚âپu‚ب‚¢پv‚حپAپu•\Œ»‚³‚ê‚éژ–•؟‚ة‘خ‚·‚éکbژè‚ج—§ڈê‚ج•\Œ»پvپiژژ}گ½‹Lپw“ْ–{•¶–@ŒûŒê•رپxپjپA‚آ‚ـ‚èکbژز‚ج—§ڈê‚©‚ç‚ج•\Œ»‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًژ¦‚·پuژ«پv‚ئ‚µپAپuچ÷‚ج‰ش‚ھچç‚پv‚ج•”•ھ‚ًپAپu•\Œ»‚³‚ê‚éژ–•¨پAژ–•؟‚ج‹q‘ج“IٹT”O“I•\Œ»پvپiژژ}¤‘OŒfڈ‘پj‚إ‚ ‚éپuژŒپv‚ئ‚µ‚½پB‚آ‚ـ‚è¤
‚جپu–شگü£•”•ھ‚حپA¢Œ¾ŒêŒ`ژ®—ë‚ئ‚¢‚¤ˆس–،£پiژO‰Y¤‘OŒfڈ‘پj‚إپA—ë‹Lچ†پiƒ[ƒچ‹Lچ†‚ئ•\‹L‚·‚éپj‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚éپB‚¢‚¸‚ê‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپA
‚ھپA“ْ–{Œê‚ج•\Œ»چ\‘¢‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپAژ«‚ة‚¨‚¢‚ؤڈ‰‚ك‚ؤپA‚»‚±‚إŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ئکbژز‚ئ‚جٹضŒW‚ھ–¾ژ¦‚³‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB‘¦‚؟¤
‚ئ‚¢‚¤•\Œ»‚جژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپAپuچ÷‚ج‰ش‚ھچç‚¢‚ؤ‚¢پv‚éڈَ‘ش‚ح‰ك‹ژ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚èپiپV‚¢‚ـپV‚حچç‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚¢پjپA‚»‚ê‚ھپu‚ؤ‚¢پvپi‚éپj‚ج‚حپu‚½پvپi‰ك‹ژ‚إ‚ ‚ء‚½پj‚إژ¦‚³‚êپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚ئ‚«پV‚ئ‚ح•ت‚جپV‚ئ‚«پV‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ•\Œ»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚µ‚ؤپu‚بƒ@پv‚إپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚¢‚ـپVپA‚»‚ج‚±‚ئ‚ً‰ù‚©‚µ‚ق‚©گة‚µ‚ق‚©پA‚ئ‚à‚©‚ٹ´ٹS‚ً‚à‚ء‚ؤژv‚¢ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج•\Œ»‚جƒvƒچƒZƒX‚حپA
‚ئپAژ«‚ھƒ[ƒچ‹Lچ†‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚حپAٹO‘¤‚جژ«‚ة‚و‚é•¢‚¢‚ھ‚ب‚¢ڈَ‘شپA‚آ‚ـ‚è“üژq‚جŒê‚è‚ج•”•ھ‚ھ”چ‚«ڈo‚µ‚ة‚ب‚ء‚½ڈَ‘ش‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚¢پBژ«‚ئ‚µ‚ؤ‚جپAپV‚¢‚ـپV‚إ‚جکbژز‚جٹ´’Q‚ًژو‚ء‚½‚¾‚¯‚ب‚ج‚ةپA‚±‚¤‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‘Oژز‚ئ”ن‚ׂؤپA–¾‚ç‚©‚ةپV‚ئ‚«پV‚جٹ´‚¶‚ھڈd‘ه‚ب•د‰»‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚é‚ح‚¸‚إ‚ ‚éپB‚آ‚ـ‚èپA‘Oژز‚إ‚ح–¾‚ç‚©‚ةپV‚¢‚ـپV‚©‚çکbژز‚ھŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ح‚ء‚«‚肵‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ةپAŒمژز‚إ‚ح‚»‚ê‚ھ‚ح‚ء‚«‚肵‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
‚آ‚ـ‚èپu‚½پv‚ئ‚¢‚¤”»’f‚ھپAپV‚¢‚ـپV‚©‚ç‚ف‚½‰ك‹ژ‚¾‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًٹ¸‚¦‚ؤ•\Œ»‚·‚邽‚ك‚ة‚حپA‚±‚¤‚µ‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾پB‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAپuچ÷‚ج‰ش‚ھچç‚¢‚ؤپv‚¢‚éڈَ‘ش‚ًژw“E‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ًŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھپAپV‚¢‚آپV‚ج‚±‚ئ‚ب‚ج‚©‚ًژ¦‚·‹@”\‚ًپu‚½پv‚ح‚à‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ظ‚©‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚آ‚ـ‚èپAپu‚½پv‚حپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚ئ‚«پV‚ً‰B‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBڈIژ~Œ`‚جƒ[ƒچ‹Lچ†‚جڈَ‘ش‚ة‚ ‚é‚ج‚ئ“¯‚¶‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB‚¾‚©‚çپAپu‚بƒ@پv‚ئ‚¢‚¤پV‚¢‚ـپV‚ًژ¦‚·ژ«‚ًژ¸‚¤‚±‚ئ‚إپAپu‚½پv‚ح‰ك‹ژ‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒjƒ…ƒAƒ“ƒX‚ًژ¸‚¢پAپuپiپV‚¢‚ـپV‚جپj”»’fپv‚ب‚ج‚©پuپiپV‚»‚ج‚ئ‚«پVپjٹù‚ةپv‚ب‚ج‚©‚ج‹و•ت‚ھB–†‰»‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚éپA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邾‚낤پB
‚ئپA
‚إ‚حپAˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپBŒمژز‚حپAژه‘ج“I”»’f‚»‚ج‚à‚ج‚ھƒ[ƒچ‹Lچ†‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤپA‘Oژز‚حپA”»’f‚جپV‚ئ‚«پV‚ھƒ[ƒچ‹Lچ†‰»‚³‚êپAپu‚½پv‚ئ‚¢‚¤”»’f‚ھپV‚¢‚ـپV‚إ‚ ‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
‚آ‚ـ‚èپA‡@پuچ÷‚ج‰ش‚ھچç‚¢‚ؤ‚¢پv‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚ ‚éپV‚¢‚ـپV‚ة‚ ‚ء‚ؤپA‡Aکbژز‚حپAپuچ÷‚ج‰ش‚جچç‚¢‚ؤ‚¢پv‚éپV‚ئ‚«پV‚ًژv‚¢ڈo‚µپAپV‚»‚ج‚ئ‚«پV‚ة‚¢‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةŒ»‘O‰»‚µپA‡Bپu‚½پv‚ة‚و‚ء‚ؤژٹش“Iٹu‚½‚è‚ًپV‚¢‚ـپV‚ض‚ئ–ك‚µ‚ؤپA‡Cپu‚بƒ@پv‚ئپAپV‚¢‚ـپV‚»‚ج‚±‚ئ‚ًٹS’Q‚µ‚ؤ‚¢‚éپA‡D‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةپAڈ‘‚«ژè‚ھڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپV‚¢‚ـپV‚ة‚¢‚ؤپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚±‚ê‚ھ‚±‚جŒê‚è‚ًŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é–{گl‚إ‚ ‚ê‚خŒê‚èژè‚ئ‚ب‚é‚ھپA‚»‚ê‚ھ•ت‚ج’N‚©‚جŒê‚è‚ًپV‚¢‚ـپVژت‚µ‚½‚ج‚¾‚ئ‚·‚ê‚خپAƒ[ƒچ‹Lچ†‚ج‰سڈٹ‚حپu‚ئپAŒ¾‚¤پv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚»‚ê‚ھŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚¢‚ـپV‚و‚è‘O‚ئ‚ب‚ê‚خپAپu‚ئŒ¾‚¤پ{‚½پiŒ¾‚ء‚½پjپv‚ئ‚ب‚éپB
پu‚ئŒ¾‚ء‚½پv‚ئ‚ ‚邱‚ئ‚ھپAŒê‚éپپڈ‘‚پV‚ئ‚«پV‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئچl‚¦‚é‚ئپA–{—ˆ‚جچ\•¶‚©‚çچl‚¦‚ê‚خپAکbژز‚جژ«‚حپA“üژq‚ة‚ب‚ء‚½کbژز‚جپuپ`‚إ‚µ‚ه‚¤پv‚ئپuŒ¾‚ءپv‚½‚±‚ئ‚ًŒ»‘O‰»‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µپAکbژز‚ح‚±‚±‚ـ‚إŒê‚ء‚½‚ئ‚«پA“üژq‚ئ‚ب‚ء‚½کbژز‚جŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپuچ÷‚ج‰ش‚ھچç‚¢‚ؤ‚éپv‚ئ‚¢‚¤ژ–‘شژ©‘ج‚ً‚àŒ»‘O‰»‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚ً—ل‚ةژو‚ء‚ؤچl‚¦‚ê‚خپA‚à‚ء‚ئ‚ي‚©‚è‚â‚·‚¢‚ح‚¸‚إ‚ ‚éپB‚±‚±‚إپAŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپu‚½پv‚ة—§‚ء‚½Œê‚é‚à‚ج‚حپA‚»‚جچ÷‚ًŒ»‘O‰»‚µ‚آ‚آپA‚»‚جچ÷‚ة‚àŒ©‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‚ظ‚©‚ب‚ç‚ب‚¢پBŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éپV‚¢‚ـپV‚©‚çپV‚»‚ج‚ئ‚«پV‚ًŒ©‚é‚ئ‚«پA‚»‚ج‰ك‹ژ‚جپV‚ئ‚«پV‚ھپV‚¢‚ـپV‚ًڈئ‚炵‚ؤ‚¢‚éپiپu‚½پv‚ًٹ®—¹‚ئ‚ف‚ب‚¹‚خپAٹ®—¹‘O‚آ‚ـ‚èپuچç‚پv‘O‚جپV‚ئ‚«پV‚ھپV‚¢‚ـپV‚ًڈئ‚ç‚·پjپBپV‚»‚ج‚ئ‚«پV‚حچç‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ھپAپV‚¢‚ـپV‚حچç‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚¢پiٹ®—¹‚ب‚çپAپV‚»‚ج‚ئ‚«پV‚حچç‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAپV‚¢‚ـپV‚حچç‚¢‚ؤ‚¢‚éپjپA‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةپB‚»‚µ‚ؤ‚»‚ج‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپAپV‚¢‚ـپV‚حپV‚»‚ج‚ئ‚«پV‚ة”نٹr‚µ‚ؤŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚إ‚ب‚¯‚ê‚خپAچ÷‚جچç‚¢‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ًپV‚¢‚ـپVژv‚¢ڈo‚µ‚ؤŒê‚é•K—v‚حŒê‚èژè‚ة‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ح‚¸‚ب‚ج‚¾پB
‚ئ‚±‚ë‚ھپAƒ[ƒچ‹Lچ†‰»‚³‚ê‚邱‚ئ‚إپAپu‚إ‚µ‚ه‚¤پv‚ئگ„‘ھ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپAپV‚¢‚ـپV‚إ‚ ‚é‹[گ§‚ً‚ئ‚éپi‘Oڈq‚ج“üژq‚ج•”•ھ‚ھ”چ‚«ڈo‚µ‚ة‚ب‚ء‚½ڈَ‘شپjپBپu‚إ‚µ‚ه‚¤پv‚ئگ„‘ھ‚·‚é‘ٹژè‚جپuŒ¾‚¤پv‚ج‚ًŒê‚ء‚ؤ‚¢‚éکbژز‚حپA‚»‚جڈê‚إپAپuپwپ`‚إ‚µ‚ه‚¤پxپv‚ئŒ¾‚¤پv‚ج‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚éŒ`‚ة‚ب‚éپB•\Œ»ڈم‚حپAŒ»‘O‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح‘ٹژè‚جپuŒ¾‚¤پvژ–‘ش‚إ‚µ‚©‚ب‚¢پB‚آ‚ـ‚èکbژز‚حپA¢‚ئپwŒ¾‚¤پxپv‚ج‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إپA¢چ÷‚ج‰ش‚ھچç‚¢‚ؤ‚éپv‚ج‚حŒê‚ç‚ꂽ‚ج‚ً‚»‚ج‚ـ‚ـŒê‚ء‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚¾پB
پuٹد”O“I‚ة“ٌڈd‰»‚µپA‚ ‚é‚¢‚ح“ٌڈd‰»‚µ‚½گ¢ٹE‚ھ‚³‚ç‚ة“ٌڈd‰»‚·‚é‚ئ‚¢‚ء‚½“üژqŒ^‚جگ¢ٹE‚ج’†‚ًپA‚ي‚ê‚ي‚ê‚حٹد”O“I‚بژ©Œب•ھ—ô‚ة‚و‚ء‚ؤ•ھ—ô‚µ‚½ژ©•ھ‚ة‚ب‚èپAŒ»ژہ‚جژ©•ھ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح“®‚©‚ب‚‚ؤ‚à‚ ‚؟‚炱‚؟‚ç‚ةچs‚ء‚½‚è‹A‚ء‚½‚肵‚ؤ‚¢‚éپvپiژO‰Y¤‘OŒfڈ‘پj
پu‚¢‚âپv‚ئپA”غ’肵‚½ژ‚حپA
ژه‘ج‚ھپA‘ٹژè‚جŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپu‚±‚ئپvپiژŒپj‚ة“¯ˆس‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©پA‘ٹژè‚جŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئپiژ«پj‚ً”غ’肵‚ؤ‚¢‚é‚©‚جپAژه‘ج‚جٹد”O“I‚ب“®‚«‚جˆل‚¢‚ًپA–¾ٹm‚ةژ¦‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB |
| ژ™‹تچK‘½پw‹كگ¢”_–¯گ¶ٹˆژjپx“ا‚قپB
–{ڈ‘‚حپA“–ڈ‰پA |
| •½ژR—Dپwگيچ‘‚ج”E‚رپx‚ً“ا‚قپB
–{ڈ‘‚حپAژj—؟‚ةڈo‚ؤ‚‚é‚©‚¬‚è‚إپA |
| Œàچہ—Eˆêپw‰گm‚ج—گپ\گيچ‘ژ‘م‚ًگ¶‚ٌ‚¾‘ه—گپx‚ً“ا‚قپB
–{ڈ‘‚حپA‹»•ںژ›‘m‚ة‚و‚éپA |
| ’†“‡‰xژںچZ’چپw‰Fژ،ڈEˆâ•¨Œêپx“ا‚قپB
‚¤’n‚ج‘ه”[Œ¾‚ج•¨ŒêپA ‚ئ‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپA‚ئ‚ ‚éپi–{ڈ‘‰ًگàپjپBڈک‚ةپA گ¢‚ة‰Fژ،‘ه”[Œ¾•¨Œê‚ئ‚¢‚س•¨‚ ‚è‚«پBچں‘ه”[Œ¾‚ح—²چ‘‚ئ‚¢‚¤گl‚ب‚èپA ‚ئ‚ ‚èپA •½“™‰@ˆêگطŒo‘ ‚ج“ى‚جژR‚¬‚ح‚ة“ىگٍ–[‚ئ‚¢‚سڈٹپA ‚ة‚±‚à‚ء‚ؤپA ‰—ˆ‚جژزپAڈم’†‰؛‚ً‚¢‚ح‚¸Œؤ‚رڈW‚كپAگج•¨Œê‚ً‚¹‚³‚¹‚ؤپA‰ن‚ح‚¤‚؟‚ة‚»‚ذ‚س‚µ‚ؤپAŒê‚é‚ة‚µ‚½‚ھ‚ذ‚ؤپA‘ه‚«‚ب‚é‘oژ†‚ةڈ‘‚©‚ꂯ‚èپA ‚ئپA ڈ\ژl’ںپAپiڈ”–{‚ةڈ\Œـ’ں‚ئ‚ ‚éپj ‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚ ‚éپB‚±‚ج—R—ˆ‚ة‹’‚ê‚خپA ڈ‚ب‚‚ئ‚àڈ\“ٌگ¢‹Iچ پA ‚ة‚ح‘¶چف‚µ‚½پA‚ئ–ع‚³‚ê‚éپi‰ًگàپjپB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚ج–{‚حژ¸‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB ڈک‚ة‚حپAŒم’iپA Œم‚ة‚³‚©‚µ‚«گlپX‚©‚«‚¢‚ꂽ‚é‚ ‚ذ‚¾پA•¨Œê‚¨‚ظ‚‚ب‚ê‚èپB‘ه”[Œ¾‚و‚èŒم‚جژ–‚©‚«“ü‚ꂽ‚é–{‚à‚ ‚é‚ة‚±‚»پA ‚ئ‚ ‚èپA ‚±‚ê‚ح‹°‚ç‚پAچ،“ْ‚جچ،گج•¨Œê‚جژ–‚©‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپA ‚ئ‚ ‚éپiپWڈمپjپB پw‰Fژ،ڈEˆâ•¨Œêپx‚حپAŒأ‚پAپwچ،گج•¨Œêپx‚ئ“¯ˆêژ‹‚³‚ꂽ‚èپAچ¬“¯‚³‚ꂽ‚肵‚ؤ‚«‚½پB‚½‚ئ‚¦‚خپA چ،گج•¨Œêڈ\Œـ’ں‘ه–هƒjچف”Vپi‘½•·‰@“ْ‹LپjپA ‚حپA–¾‚ç‚©‚ةپw‰Fژ،ڈEˆâ•¨Œêپx‚ًژw‚µ‚ؤ‚¢‚éپB پw‰Fژ،ڈEˆâ•¨Œêپx‚حپA ‰Fژ،‘ه”[Œ¾•¨Œê‚جڈEˆâپA ‚جˆس‚إپAچىژزژ©گg‚ب‚ج‚©پA‘¼‚جگl‚ب‚ج‚©‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھپA Œڑ—ï“ٌ”Nپi1212پj‚©‚çڈ³‹vژO”Nپi1221پj‚ـ‚إ‚جˆ½‚éژٹْ‚ةچى‚ç‚ꂽ‚ھپAپi’†—ھپj‘ه‘جڈ\“ٌگ¢‹IڈI‚ي‚èچ ‚ةˆêگو‚¸گ¬‚èپAڈ‚ب‚‚ئ‚àŒ’•غژO”Nپi1215پjˆبŒمپEگmژ،ژO”Nپi1242پjˆبŒم‚ج“ٌ‰ٌ‚ح‰ء•MپA ‚³‚ꂽپw‰Fژ،‘ه”[Œ¾•¨Œêپx‚جŒمپA ‚³‚é’ِ‚ةپA‚¢‚ـ‚جگ¢‚ة–”•¨‚©‚½‚è‚©‚«‚¢‚ꂽ‚éپA‚¢‚إ‚«‚½‚ê‚èپB‘ه”[Œ¾‚ج•¨Œê‚ة‚à‚ꂽ‚é‚ً‚ذ‚ë‚ذ‚ ‚آ‚كپA–”‘´Œم‚جژ–‚ب‚اڈ‘‚«‚آ‚ك‚½‚é‚ب‚é‚ׂµپB–¼‚ً‰Fژ،ڈEˆâ‚ج•¨Œê‚ئ‚¢‚سپB‰Fژ،‚ة‚ج‚±‚ê‚é‚ً‚ذ‚ë‚س‚ئ•t‚¯‚½‚é‚ة‚âپA–”پAژکڈ]‚ًڈEˆâپiژکڈ]‚ج“‚–¼پj‚ئ‚¢‚ض‚خپA‰Fژ،ڈEˆâ•¨Œê‚ئ‚¢‚ض‚é‚©پA ‚ئپAŒمگ¢‚جپuڈکپv‚جڈ‘‚«ژè‚حگ„‘ھ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جچىژز‚ح•s–¾‚إ‚ ‚éپB ‚µ‚©‚µپAپw‰Fژ،ڈEˆâ•¨Œêپx‚حپAپwچ،گج•¨Œêپx‚ھپA ٹeکb‚جڈ‘‚«ڈo‚µ‚ًپuچ،ƒnگجپvپAŒ‹‚ر‚ًپuƒgƒiƒ€Œêƒٹ“`ƒwƒ^ƒ‹ƒgƒ„پvپA ‚ئ“ˆê‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة”ن‚ׂؤپAڈ‘‚«ڈo‚µ‚àپA چ،‚حگجپA ‚±‚ê‚àچ،‚حگجپA گجپA ‚±‚ê‚àگجپA ‚±‚ج‹ك‚‚جژ–‚ب‚é‚ׂµپA ‚ـ‚½‚حپA ‚¤‚؟‚آ‚¯‚ةڈ‘‚«ڈo‚·پA “™پX—lپX‚إپAŒ‹‚ر‚à“ˆêگ«‚ح‚ب‚¢پB •د‰»‚ً—^‚¦پA“à—e‚àٹeکb‚ھژ©—R‚بکA‘z‚ج‚ـ‚ـ‚ةگڈ•M•—‚ةè¶ژ[‚³‚êپA’ڑ“x“k‘R‘گ‚ًŒ©‚é‚و‚¤‚ةپAژںپX–ع‚³‚«‚ج•د‰»‚ً’ا‚¤‚ؤˆêچû‚ھ“ا—¹‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ة”z—¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éچىژز‚ج—pˆس‚ھژf‚ي‚ê‚éپA ‚ئ‚µپiچZ’چژز‰ًگàپjپA ’†گ¢‚جگàکb•¶ٹw’†‚ج”’”û ‚ئ•]‚µ‚ؤ‚¢‚éپiپWڈمپjپB•]‰؟‚ح‚ئ‚à‚©‚‚ئ‚µ‚ؤپAٹHگى—´”V‰î‚ھپA ’nچ–•دپA •@پA ˆًٹںپA —³پA ‚ئپA‚±‚ê‚ً‘èچق‚ةڈ¬گà‰»‚µ‚½‚ظ‚ا‚ة‚حپAگl‚ج‹@”÷‚ً“ث‚¢‚½‚à‚ج‚ھ‚ ‚ء‚½‚à‚ج‚ئ‚حژv‚¤پB‚½‚ئ‚¦‚خپA •@’·‚«‘m‚جژ–پA ‚حپA گجپA’r‚ج”ِ‚ة‘P’؟“à‹ںپi‚؛‚ٌ‚؟‚ٌ‚ب‚¢‚®پj‚ئ‚¢‚س‘mڈZ‚ف‚¯‚éپBگ^Œ¾‚ب‚ا‚و‚ڈK‚ذ‚ؤ”N‹v‚µ‚چs‚ذ‚ؤ‹Mپi‚½‚س‚ئپj‚©‚肯‚ê‚خپAگ¢‚جگlپX‚³‚ـ‚´‚ـ‚ج‹F‚è‚ً‚¹‚³‚¹‚¯‚ê‚خپAگg‚ج“؟‚ن‚½‚©‚ة‚ؤپA“°‚à‘m–[‚àڈ‚µ‚àچr‚ꂽ‚éڈٹ‚ب‚µپB•§‹ںپAŒن“”پi‚ف‚ئ‚¤پj‚ب‚ا‚àگ₦‚¸پAگـگكپi‚ً‚è‚س‚µپj‚ج‘m‘Vپi‚»‚¤‚؛‚ٌپjپAژ›‚جچu‰‰‚µ‚°‚چs‚ح‚¹‚¯‚ê‚خپAژ›’†‚ج‘m–[‚ةŒ„پi‚ذ‚ـپj‚ب‚‘m‚àڈZ‚ف“ِ‚ذ‚¯‚èپB“’‰®پi‚ن‚âپj‚ة‚ح“’•¦‚©‚³‚ت“ْ‚ب‚پA—پپi‚ پj‚ف‚ج‚ج‚µ‚肯‚èپB‚ـ‚½‚»‚ج‚ ‚½‚è‚ة‚حڈ¬‰ئپi‚±‚¢‚ضپj‚ب‚ا‚à‘½‚ڈoپi‚¢پj‚إ—ˆپi‚«پj‚ؤپA—¢‚à“ِ‚ذ‚¯‚èپB‚³‚ؤپA‚±‚ج“à‹ںپi‚ب‚¢‚®پj‚ح•@’·‚©‚肯‚èپBŒـکZگ،‚خ‚©‚è‚ب‚肯‚ê‚خپAèَپi‚¨‚ئ‚ھ‚ذپj‚و‚è‰؛‚è‚ؤ‚¼Œ©‚¦‚¯‚éپBگF‚حگشژ‡‚ة‚ؤپA‘هٹ¹ژqپi‚¨‚ظ‚©‚¤‚¶پj‚ج•†پi‚ح‚¾پj‚ج‚₤‚ة—±پi‚آ‚شپj—§‚؟‚ؤ‚س‚‚ꂽ‚èپBلyپi‚©‚نپj‚ھ‚éژ–Œہ‚è‚ب‚µپB ‚ئ‚ح‚¶‚ـ‚èپA ٹں‚ً‚·‚·‚é’ِ‚ةپA‚±‚ج“¶پA•@‚ً‚ذ‚ٌ‚ئ‚ؤ‘¤پi‚»‚خپj‚´‚ـ‚ةŒü‚«‚ؤ•@‚ً‚ذ‚é’ِ‚ةپAژèگk‚ض‚ؤ•@‚à‚½‚°‚ج–ط—hپi‚ن‚éپj‚¬‚ؤپA•@ٹOپi‚ح‚أپj‚ê‚ؤٹں‚ج’†‚ض‚س‚½‚è‚ئ‚¤‚؟“ü‚ê‚آپB“à‹ں‚ھٹç‚ة‚à“¶‚جٹç‚ة‚àٹں‚ئ‚خ‚µ‚è‚ؤپAˆê•¨پi‚ذ‚ئ‚à‚جپj‚©‚©‚è‚تپB“à‹ں‘هپi‚¨‚ظپj‚«‚ة• —§‚؟‚ؤپA“ھپAٹç‚ة‚©‚©‚肽‚éٹں‚ًژ†‚ة‚ؤ‚ج‚²‚ذ‚آ‚آپAپu‚¨‚ج‚ê‚ح‚ـ‚ھ‚ـ‚ھ‚µ‚©‚肯‚éگSژ‚؟‚½‚éژز‚©‚بپBگS‚ب‚µ‚جŒîژ™پi‚©‚½‚îپj‚ئ‚ح‚¨‚ج‚ê‚ھ‚₤‚ب‚éژز‚ً‚¢‚س‚¼‚©‚µپA ‚ئپA•@‚ًٹں‚ة—ژ‚ئ‚·‚ئ‚¢‚¤ڈo—ˆژ–‚ھ’†گS‚ب‚ج‚ةپAٹHگى‚جپA •@ ‚حپA ‘T’q“à‹ں‚ج•@‚ئ‰]‚¦‚خپA’r”ِ‚إ’m‚ç‚ب‚¢ژز‚ح‚ب‚¢پB’·‚³‚حŒـکZگ،‚ ‚ء‚ؤڈمگO‚جڈم‚©‚çèù‚ج‰؛‚ـ‚إ‰؛‚ء‚ؤ‚¢‚éپBŒ`‚حŒ³‚àگو‚à“¯‚¶‚و‚¤‚ة‘¾‚¢پB‰]‚ي‚خچ×’·‚¢’°‹l‚ج‚و‚¤‚ب•¨‚ھپA‚ش‚ç‚è‚ئٹç‚ج‚ـ‚ٌ’†‚©‚ç‚ش‚ç‰؛‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB ‚ئ‚ح‚¶‚ـ‚èپA’·‚¢•@‚ًڈ¬‚³‚‚µ‚½ŒمپAŒ´•¶‚إ‚حپA ’ٌپi‚ذ‚³‚°پj‚ة“’‚ً‚©‚ض‚ç‚©‚µ‚ؤپAگـ•~پi‚ً‚µ‚«پj‚ً•@‚³‚µ“ü‚é‚خ‚©‚è‚ï‚è’ت‚µ‚ؤپA‰خ‚ج‰ٹ‚جٹç‚ة“–‚ç‚ت‚₤‚ة‚µ‚ؤپA‚»‚جگـ•~‚جŒٹ‚و‚è•@‚ً‚³‚µڈo‚إ‚ؤپA’ٌ‚ج“’‚ة‚³‚µ“ü‚ê‚ؤپA‚و‚‚و‚‚ن‚إ‚ؤˆّ‚«ڈم‚°‚½‚ê‚خپAگF‚ح”Z‚«ژ‡گF‚ب‚èپB‚»‚ê‚ً‘¤پi‚»‚خپj‚´‚ـ‚ة‰çپi‚سپj‚¹‚ؤپA‰؛‚ة•¨‚ً‚ ‚ؤ‚ؤگl‚ة“¥‚ـ‚·‚ê‚خپA—±—§‚؟‚½‚éچEپi‚ ‚بپj‚²‚ئ‚ة‰Œ‚ج‚₤‚ب‚镨ڈo‚أپB‚»‚ê‚ً‚¢‚½‚“¥‚ك‚خپA”’‚«’ژ‚جچEپi‚ ‚بپj‚²‚ئ‚ة‚³‚µڈo‚é‚ًپA–ر”²‚«‚ة‚ؤ”²‚¯‚خپAژl•ھ‚خ‚©‚è‚ب‚é”’‚«’ژ‚ًچE‚²‚ئ‚ةژو‚èڈo‚¾‚·پB‚»‚جگص‚حچE‚¾‚ة‚ ‚«‚ؤŒ©‚نپB‚»‚ê‚ً‚ـ‚½“¯‚¶“’‚ة“ü‚ê‚ؤپA‚³‚ç‚ك‚©‚µ•¦‚©‚·‚ةپA‚ن‚أ‚ê‚خ•@ڈ¬‚³‚‚µ‚ع‚ف‚ ‚ھ‚è‚ؤپA‚½‚¾‚جگl‚ج•@‚ج‚₤‚ة‚ب‚è‚تپA ‚ئ‚ ‚éچH’ِ‚ًپA “à‹ں‚ج—p‚ًŒ“‚ث‚ؤپA‹‚ضڈم‚ء‚½’يژq‚ج‘m‚ھپA’mŒبپi‚µ‚é‚×پj‚جˆمژز‚©‚ç’·‚¢•@‚ً’Z‚‚·‚é–@‚ً‹³‚ي‚ء‚ؤ—ˆ‚½پA ‚ئ‚¢‚¤پA “’‚إ•@‚ًن¥‚ن‚إ‚ؤپA‚»‚ج•@‚ًگl‚ة“¥‚ـ‚¹‚é‚ئ‰]‚¤پA ‚»‚جƒvƒچƒZƒX‚ً‰„پX‚ئ–c‚ç‚ـ‚¹‚ؤ•`‚«پA‚³‚ç‚ةپA ‚½‚¾‚جگl‚ج•@‚ج‚₤‚ة‚ب‚è‚تپB‚ـ‚½“ٌژO“ْ‚ة‚ب‚ê‚خپAگو‚ج‚²‚ئ‚‚ة‘ه‚«‚ة‚ب‚è‚تپA ‚ئ‚µ‚©‚ب‚¢‚‚¾‚è‚ًپA‚»‚ج’Z‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éٹش‚جپu“ٌپAژO“ْپv‚ً–c‚ç‚ـ‚¹پA•@‚ھ’Z‚‚ب‚ء‚½ŒمپA–{گl‚حپA ‚»‚ê‚©‚çˆê”سگQ‚ؤ‚ ‚‚é“ْ‘پ‚ٹل‚ھ‚³‚ك‚é‚ئ“à‹ں‚ح‚ـ‚¸پA‘وˆê‚ةپAژ©•ھ‚ج•@‚ً•ڈ‚إ‚ؤŒ©‚½پB•@‚حˆث‘R‚ئ‚µ‚ؤ’Z‚¢پB“à‹ں‚ح‚»‚±‚إپAٹô”N‚ة‚à‚ب‚پA–@‰طŒoڈ‘ژت‚جŒ÷‚ًگد‚ٌ‚¾ژ‚ج‚و‚¤‚بپA‚ج‚ر‚ج‚ر‚µ‚½‹C•ھ‚ة‚ب‚ء‚½پA ‚ج‚¾‚ھپA ڈٹ‚ھ“ٌژO“ْ‚½‚آ’†‚ةپA“à‹ں‚حˆسٹO‚بژ–ژہ‚ً”Œ©‚µ‚½پB‚»‚ê‚حگـ‚©‚çپA—pژ–‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA’r‚ج”ِ‚جژ›‚ً–K‚ꂽژک‚ھپA‘O‚و‚è‚àˆê‘w‰آڈخ‚µ‚»‚¤‚بٹç‚ً‚µ‚ؤپAکb‚àلïپX‚¹‚¸‚ةپA‚¶‚낶‚ë“à‹ں‚ج•@‚خ‚©‚è’‚ك‚ؤ‚¢‚½ژ–‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ج‚ف‚ب‚炸پA‚©‚آ‚ؤپA“à‹ں‚ج•@‚ًٹں‚ج’†‚ض—ژ‚µ‚½ژ–‚ج‚ ‚é’†“¶ژqپi‚؟‚م‚¤‚ا‚¤‚¶پj‚ب‚¼‚حپAچu“°‚جٹO‚إ“à‹ں‚ئچs‚«‚؟‚ھ‚ء‚½ژ‚ةپAژn‚ك‚حپA‰؛‚ًŒü‚¢‚ؤ‰آڈخ‚µ‚³‚ً‚±‚炦‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚ئ‚¤‚ئ‚¤‚±‚炦Œ“‚ث‚½‚ئŒ©‚¦‚ؤپAˆê“x‚ة‚س‚ء‚ئگپ‚«ڈo‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پA “™پXپA‹p‚ء‚ؤڈخ‚¢‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ةپAپuچ،‚ح‚ق‚°‚ة‚¢‚₵‚‚ب‚肳‚ھ‚ê‚éگl‚جپA‚³‚©‚¦‚½‚éگج‚ً‚µ‚ج‚ش‚ھ‚²‚ئ‚پv‚س‚³‚¬‚±‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚إ‚ ‚éپA ‚ئ‚¢‚¤کb‚ة‚س‚‚ç‚ـ‚¹پA•@‚ھ‚à‚ئ‚ض–ك‚ء‚½‚±‚ئ‚ةپA “à‹ں‚حچQ‚ؤ‚ؤ•@‚ضژè‚ً‚â‚ء‚½پBژè‚ة‚³‚ي‚é‚à‚ج‚حپAچً–é‚ن‚¤‚ׂج’Z‚¢•@‚إ‚ح‚ب‚¢پBڈمگO‚جڈم‚©‚çèù‚ج‰؛‚ـ‚إپAŒـکZگ،‚ ‚ـ‚è‚à‚ش‚ç‰؛‚ء‚ؤ‚¢‚éپAگج‚ج’·‚¢•@‚إ‚ ‚éپB“à‹ں‚ح•@‚ھˆê–é‚ج’†‚ةپA‚ـ‚½Œ³‚ج’ت‚è’·‚‚ب‚ء‚½‚ج‚ً’m‚ء‚½پB‚»‚¤‚µ‚ؤ‚»‚ê‚ئ“¯ژ‚ةپA•@‚ھ’Z‚‚ب‚ء‚½ژ‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚بپA‚ح‚ê‚خ‚ꂵ‚½گS‚à‚؟‚ھپA‚ا‚±‚©‚ç‚ئ‚à‚ب‚‹A‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚ج‚ًٹ´‚¶‚½پB پ@پ\پ\‚±‚¤‚ب‚ê‚خپA‚à‚¤’N‚àڑA‚¤‚à‚ج‚ح‚ب‚¢‚ة‚؟‚ھ‚¢‚ب‚¢پB پ@“à‹ں‚حگS‚ج’†‚إ‚±‚¤ژ©•ھ‚ةڑ‘‚¢‚½پB’·‚¢•@‚ً‚ ‚¯•û‚جڈH•—‚ة‚ش‚ç‚آ‚©‚¹‚ب‚ھ‚çپB ‚ئپAˆہ“g‚µپA گlٹش‚جگS‚ة‚حŒف‚ة–µڈ‚‚µ‚½“ٌ‚آ‚جٹ´ڈî‚ھ‚ ‚éپB–ـک_پA’N‚إ‚à‘¼گl‚ج•sچK‚ة“¯ڈ‚ب‚¢ژز‚ح‚ب‚¢پBڈٹ‚ھ‚»‚جگl‚ھ‚»‚ج•sچK‚ًپA‚ا‚¤‚ة‚©‚µ‚ؤگط‚è‚ت‚¯‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚é‚ئپAچ،“x‚ح‚±‚ء‚؟‚إ‰½‚ئ‚ب‚•¨‘«‚è‚ب‚¢‚و‚¤‚بگS‚à‚؟‚ھ‚·‚éپBڈ‚µŒض’£‚µ‚ؤ‰]‚¦‚خپA‚à‚¤ˆê“x‚»‚جگl‚ًپA“¯‚¶•sچK‚ةٹׂ¨‚ئ‚µ‚¢‚ê‚ؤŒ©‚½‚¢‚و‚¤‚ب‹C‚ة‚³‚¦‚ب‚éپB‚»‚¤‚µ‚ؤ‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©پAڈء‹ة“I‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپA‚ ‚é“Gˆس‚ً‚»‚جگl‚ة‘خ‚µ‚ؤ•ّ‚‚و‚¤‚بژ–‚ة‚ب‚éپA ‚ئڈq‰ù‚·‚éگS—“Iٹ‹“،‚ة•د‚¦‚ؤ‚¢‚éپB گ\‚µ–َ‚ب‚¢‚ھپA’P‚ب‚éپA ’·‚¢•@‚ج‘m‚جگU•‘‚¢پA ‚ئ‚¢‚¤ڈَ‘ش•\Œ»‚ًپA‚»‚ج•@Œج‚جٹ‹“،‚ئ‚¢‚¤پA ‰؟’l•\Œ»پA ‚ض•د‚¦‚½پiƒfپ[ƒ^‚ةˆس–،‚ئ–ع“I‚ً‰ء‚¦‚½‚à‚جپA‚آ‚ـ‚è‰؟’l‚ً‰ء‚¦‚½‚à‚ج‚ًڈî•ٌ‰»‚ئ‚¢‚¤پj‚ج‚¾‚ھپA‚»‚جژèکr‚âپAچى•i‚ئ‚µ‚ؤ‚ج•]‰؟‚ح‚ئ‚à‚©‚پA‘m‚جگl•؟‚à•د‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پA‘fچق‚جڈخ‚¢کb‚ًپAگl‚جگS‚ج‚¤‚½‚ؤ‚ب‚锽‰‚ئ‚¢‚¤‰؟’lٹد‚ض‚ئ•د‚¦‚½پB‚»‚جگ¥”ٌ‚ح‚³‚ؤ‚¨‚‚ئ‚µ‚ؤپA–l‚ة‚حپA‘fچق‚ج‘m‚جپAگHژ–‚جژ•@‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پA ٹں‚ً‚·‚·‚é’ِ‚ةپA‚±‚ج“¶پA•@‚ً‚ذ‚ٌ‚ئ‚ؤ‘¤پi‚»‚خپj‚´‚ـ‚ةŒü‚«‚ؤ•@‚ً‚ذ‚é’ِ‚ةپAژèگk‚ض‚ؤ•@‚à‚½‚°‚ج–ط—hپi‚ن‚éپj‚¬‚ؤپA•@ٹOپi‚ح‚أپj‚ê‚ؤٹں‚ج’†‚ض‚س‚½‚è‚ئ‚¤‚؟“ü‚ê‚آپB“à‹ں‚ھٹç‚ة‚à“¶‚جٹç‚ة‚àٹں‚ئ‚خ‚µ‚è‚ؤˆê•¨پi‚ذ‚ئ‚à‚جپj‚©‚©‚è‚تپA ‚ئ‚¢‚¤ژ–‘ش‚ةپA “à‹ں‘هپi‚¨‚ظپj‚«‚ة• —§‚؟‚ؤپA“ھپAٹç‚ة‚©‚©‚肽‚éٹں‚ًژ†‚ة‚ؤ‚ج‚²‚ذ‚آ‚آپAپu‚¨‚ج‚ê‚ح‚ـ‚ھ‚ـ‚ھ‚µ‚©‚肯‚éگSژ‚؟‚½‚éژز‚©‚بپBگS‚ب‚µ‚جŒîژ™پi‚©‚½‚îپj‚ئ‚ح‚¨‚ج‚ê‚ھ‚₤‚ب‚éژز‚ً‚¢‚س‚¼‚©‚µپB‰ن‚ب‚ç‚ت‚₲‚ئ‚ب‚«گl‚جŒن•@‚ة‚à‚±‚»ژQ‚êپA‚»‚ê‚ة‚ح‚â‚‚â‚ح‚¹‚ٌ‚¸‚éپB‚¤‚½‚ؤ‚ب‚肯‚éگS‚ب‚µ‚ج’sژزپi‚µ‚ê‚à‚جپj‚©‚بپB‚¨‚ج‚êپA—§‚ؤ—§‚ؤپA ‚ئ‚ؤپA’ا‚¢—§‚ؤ‚é“à‹ں‚ةپA’†‘ه“¶ژqپi‚؟‚ن‚¤‚¾‚¢‚ا‚¤‚¶پj‚ھپA گ¢‚جگl‚جپA‚©‚©‚é•@ژ‚؟‚½‚é‚ھ‚¨‚ح‚µ‚ـ‚³‚خ‚±‚»•@‚à‚½‚°‚ة‚àژQ‚ç‚كپA‚ً‚±‚جژ–‚ج‚½‚ـ‚ض‚éŒن–V‚©‚بپv‚ئ‚¢‚ذ‚¯‚ê‚خپA’يژq‚ا‚à‚ح•¨‚جŒم‚ë‚ة“¦‚°‘قپi‚جپj‚«‚ؤ‚¼ڈخ‚ذ‚¯‚éپA ‚ئŒ¾‚¢•ش‚µ‚ؤ‚¢‚é—¼ژز‚ج‘خ“™‚ب‚â‚èژو‚è‚ج•û‚ھپA‚و‚ظ‚اچ،•—‚ةژv‚¦‚éپB ژQچl•¶Œ£پG ’†“‡‰xژںچZ’چپw‰Fژ،ڈEˆâ•¨Œêپxپiٹpگى•¶Œةپj |
-
ٹضکAƒyپ[ƒW
-
ƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
ٹا—ژز‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
–ع•Wگف’è‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
–ع•W’Bگ¬‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
-
ƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة•K—v‚ب‚T‚آ‚ج‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپCپy‚Pپzپy‚Qپz‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
ƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒvƒ`ƒFƒbƒNƒٹƒXƒg‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
”‘z‹Z–@‚جٹˆ—p‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
پu–â‘è‚جŒ©•ûپEŒ©‚¦•ûپvپu–â‘èˆسژ¯‚ًˆç‚ؤ‚éپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپCٹe•إ‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
ٹا—ژز‚جˆس–،‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپCپu’†Œک‚ئٹا—ژز‚جˆل‚¢‚ح‰½‚©پv‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
ٹا—ژز‚ح‰½‚ً–â‘è‚ة‚·‚ׂ«‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
پuٹا—ژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ج–â‘èپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
-
ٹا—ژز‚ج–ًٹ„چs“®‚S‚آ‚جƒ`ƒFƒbƒNƒ|ƒCƒ“ƒg‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
ٹا—ژز‚جٹا—چs“®—ل‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
-
‚n‚i‚s‚جƒXƒLƒ‹‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پBٹeک_‚حپC‚»‚ꂼ‚ê‰؛ƒyپ[ƒW‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
–ع•Wگف’è‚جƒٹپ[ƒ_پ[ƒVƒbƒv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
ƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‚حپCƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‡@‚ئƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‡A‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
ƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“—حƒ`ƒFƒbƒNƒٹƒXƒg‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
ƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒ^ƒuپ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
•·‚«•û‚جƒ^ƒuپ[‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
گEڈê‚جƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB
-
ƒ}ƒlƒWƒپƒ“ƒg‚ة‹پ‚ك‚ç‚ê‚éƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“ƒXƒLƒ‹‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
-
ژ©Œب“_Œںƒ`ƒFƒbƒNƒٹƒXƒg‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB
-
-
ƒAƒCƒfƒA‚أ‚‚è‚حپC“ْپX ‚P‚آ‚¸‚آ‚ًژہ‘H‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ًŒ©‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB
-
پu”‘z—ح‚ئ‚ح‰½‚©پv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ئڈd•،‚·‚é‚ھپC‚±‚±‚ًŒ©‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB
-