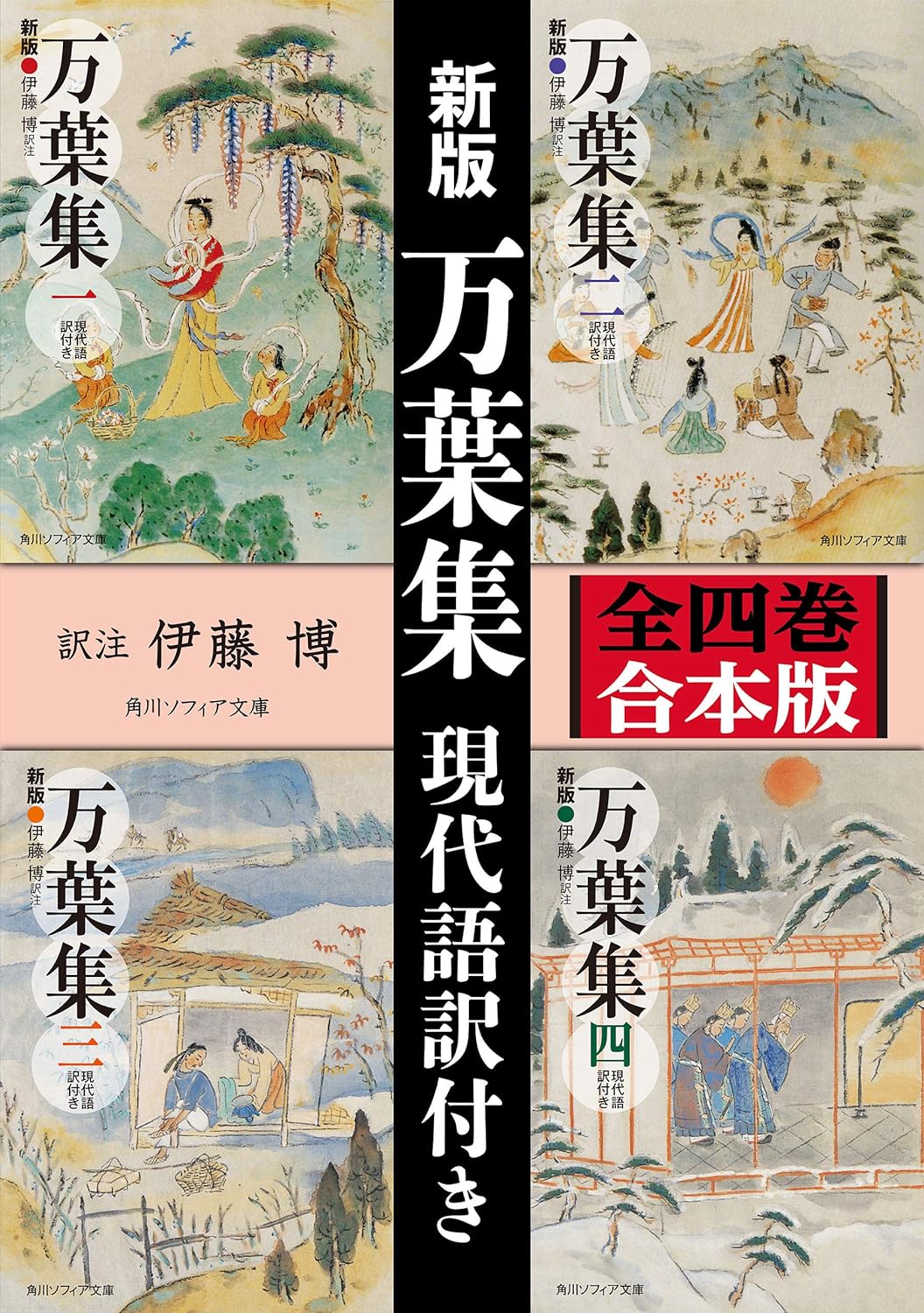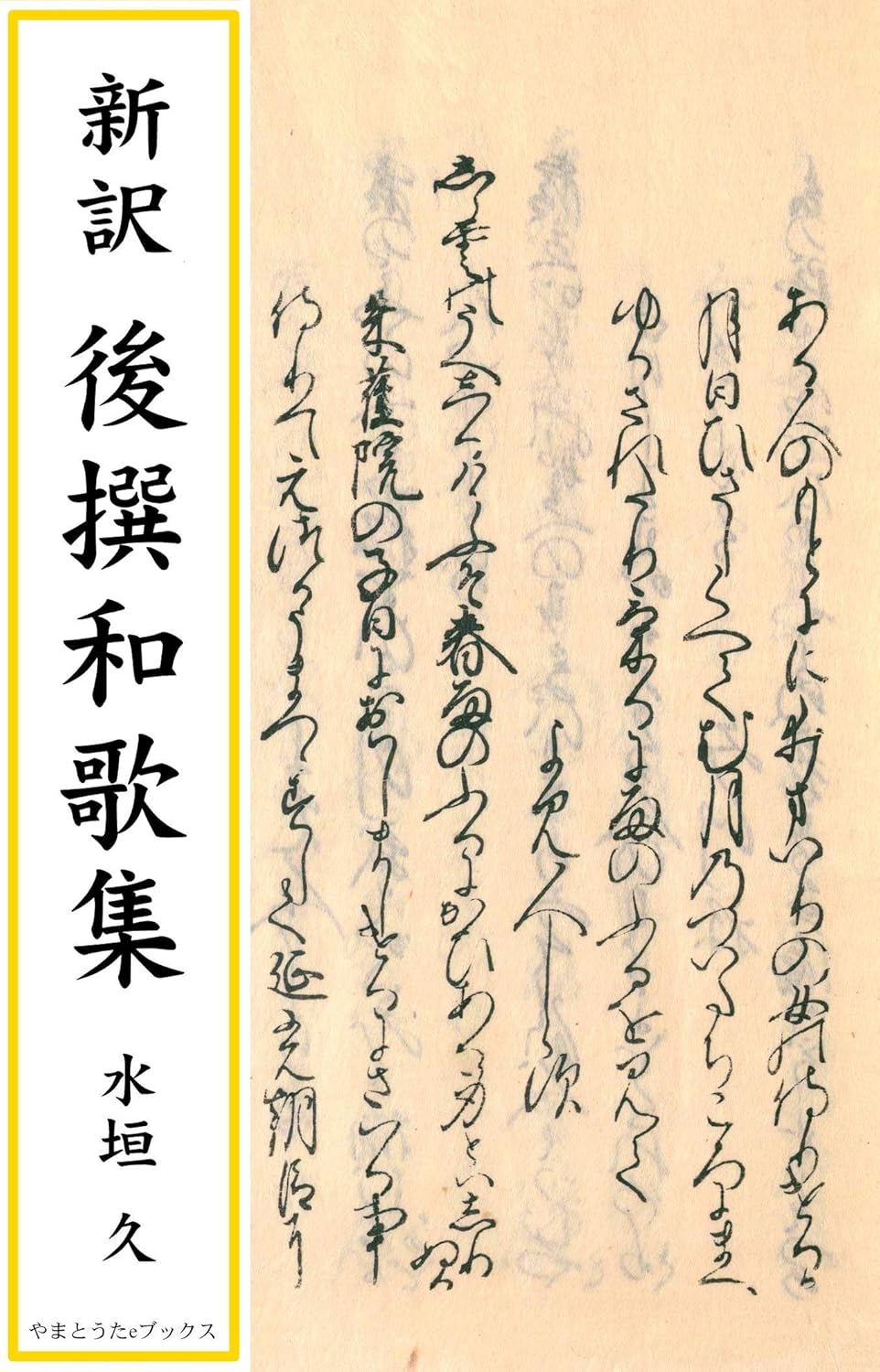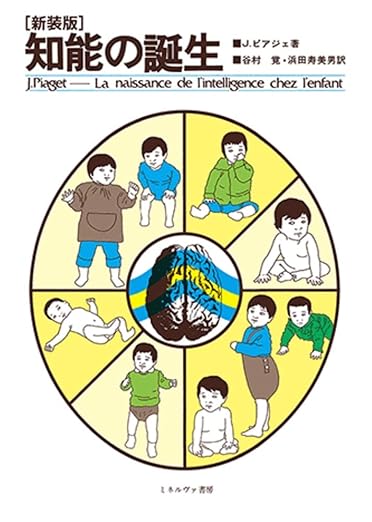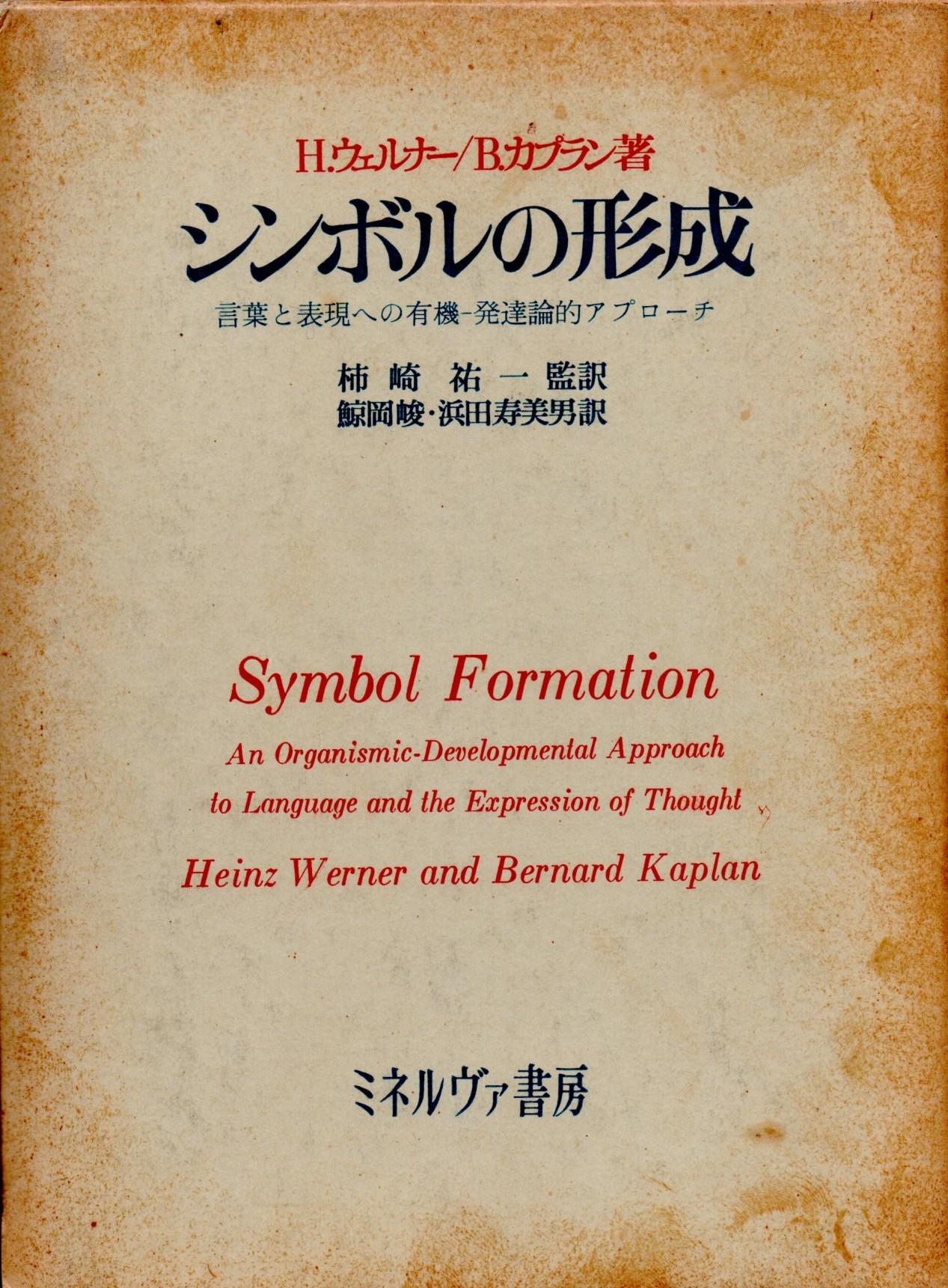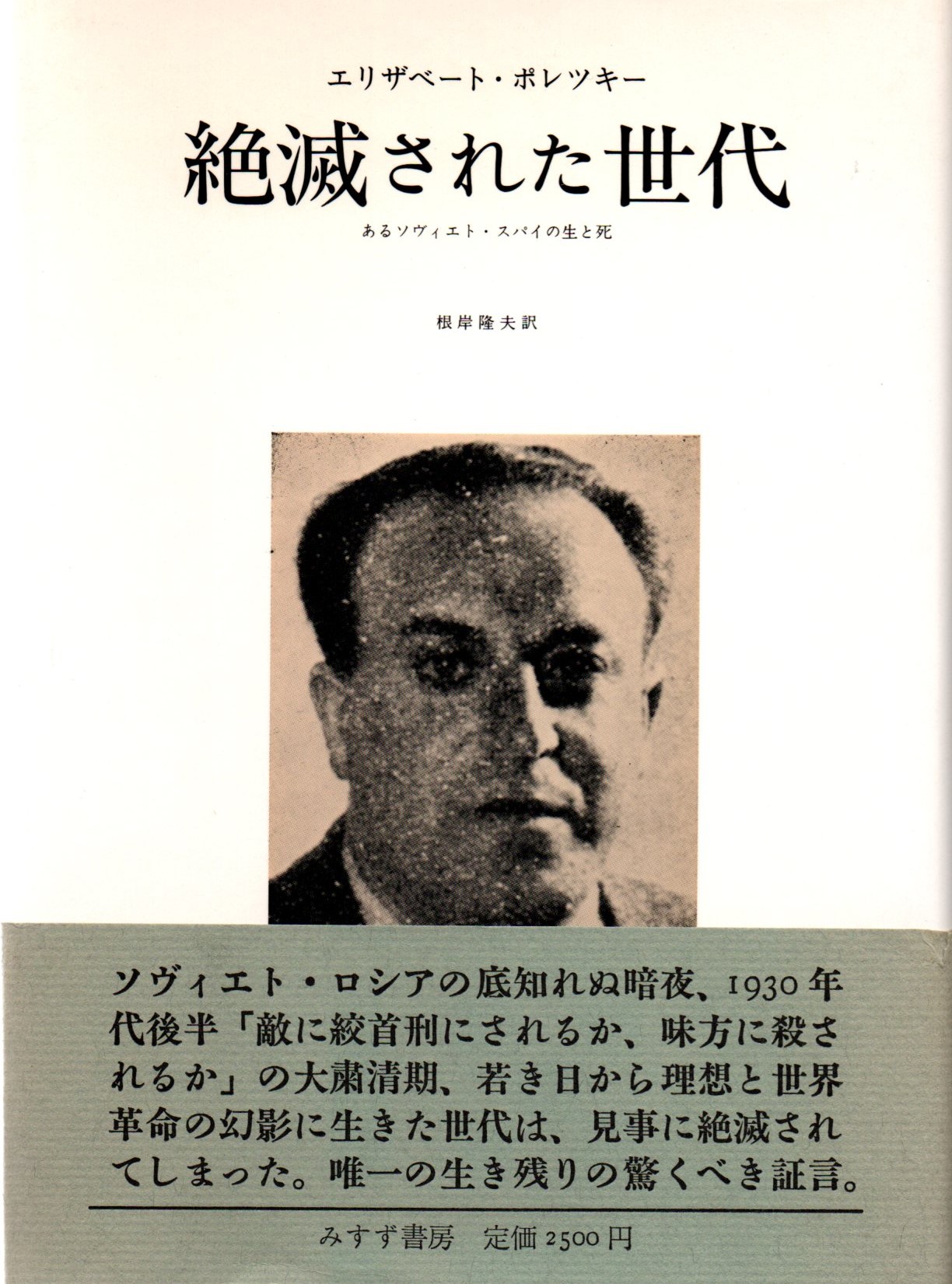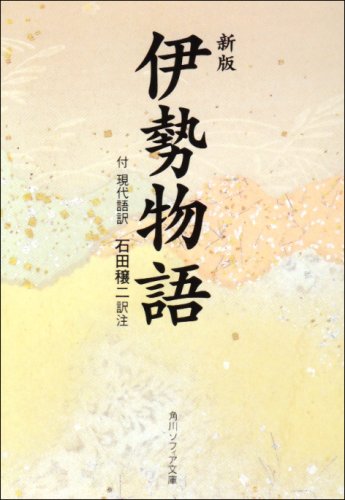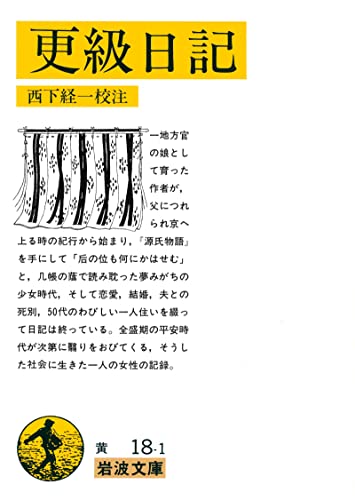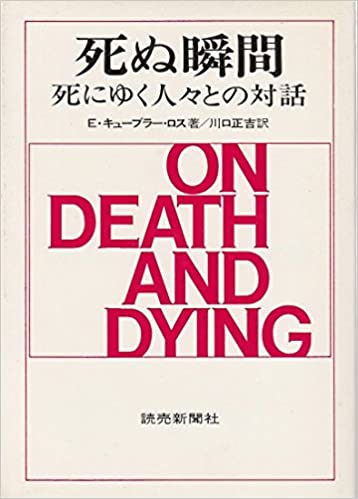| J・J・ギブソン(古崎敬訳)『生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を探る』を読む。
ギブソンは、 |
|
|
|
|
|
J・ピアジェ(谷村覚・浜田寿美男訳)『知能の誕生』を読む。
『子供における知能の誕生』(本書)、 『子供における実在の構成』 『子供における象徴の形成』 の一冊である。ピアジェのいう、 知能、 の、 言語的知能(反省的知能)、 と、 実用的知能(感覚運動的知能)、 のうち、本書は、後者を扱っている。本書には、例によって、自分の子供たちの観察例が、200例ほど、克明で、緻密な行動観察をベースに論旨が展開されている。その是非を云々できるほどの知識はないので、一種の感想記になるが、いくつか気なることを述べておきたい。 本書も、二度目になるが、かつて、 『知能の心理学』(波多野、滝沢訳 みすず書房 1960) 『思考の心理学』(滝沢武久訳 みすず書房 1968) 『知能の誕生』(谷村、浜田訳 ミネルヴァ書房 1978) 『思考の誕生』(滝沢武久訳 朝日出版社 1980) 『模倣の心理学』(大伴茂訳 黎明書房 1988) 『遊びの心理学』(大伴茂訳 黎明書房 1988) 『表象の心理学』(大伴茂訳 黎明書房 1988) と、ピアジェを読み漁ったことがある。その結論は、 考えるとはどういうことか、 でまとめたことがあるが、そのステップを、 感覚運動的知能の段階(0〜2歳) 前操作的思考の段階(2〜6、7歳) 具体的な操作的思考の段階(6、7〜11、2歳) 形式的な操作的思考の段階(11、2歳〜14、5歳で成人に近づく) とみて(これはピアジェの発達理論の第二期にあたるらしいが)、本書も対象となる、 感覚運動的知能、 とは、 五感や動作を通して外部との関係を体得していく時期と考えることができる。ここでは、「対象物の不変性」つまり、そこに見えるものは、布で覆われようと遮られようとある、ということを知っていく段階だということができる。この時期を通して、われわれは自分が動くと見え方が変わること、自分が動けば近くなり遠ざかれば小さくなることを、暗黙のうちに身につけていくのではなかろうか。これによって、乳児のときに喜んだ「いないいない、ばあ」には反応しなくなる。そこにあるものが見えなくなっても、そこにあることがわかっていれば、再び現れたことに面白がったり驚いたりはしないからだ。 この時期の末には、例えば、手の平のコインを乗せ、それを布団の下に入れて隠し、空の手を見せると、子供はそこにコインがないとわかると、すぐに布団を剥がす行動をとる、ということをピアジェは実験している。既に子供は、目に見えないところ(布団のした)でモノが移って(隠され)も、それを追跡していくことができる。このとき、初歩的な推論をしているのである。ただし、子供は言葉ではなく、感覚運動的な活動(行動)によってそれを確認していくのである。 前操作的思考、 とは、表象的思考、つまり実物ではなく実物のイメージを描くことができること、言葉を使ってモノやコトを表現できることを意味する。それは、運動感覚的活動の内面化といっていい(一々行動で示さなくても、前述の例なら、言葉でその推測を説明できるようになっている)。それは、ままごと遊びで、はっぱを札とみなしたり、ごっこ遊びなどで、シンボルを自由に扱えるようになっているところに典型的に見いだすことができる。そこでは、そこに母親がいなくても、母親を表象しながら、母親のつもりになって、その行動をなぞることができる。感覚運動的活動では、その場やそのモノに依存していたのにそれなしで、既に頭の中だけで、活動することができるようになっていることを意味する。それは描画、工作といったことができるようになったり、言葉によっての表現も可能となる段階である。 ただし、まだ言葉は内面化されていないから、遊んでいるとき、誰に話しかけるというのでもなく独り言をしゃべっている。 4歳女の子「この木にはね、おサルが上るのよ。おサルさんかわいいね、すうっと登ってすうっとおりるのよ」 4歳男の子「ハイウェーだぞ。メルセデスベンツが走るんだぞ、大きいんだぞ」 お互いに誰かと話し合っているわけでないし、人に聞かれているというつもりもない。ただ自分で自分が考えていることをどんどんことばにして、それを刺激にしてまたしゃべっている。これを思考プロセスそのものが外面化しているとみることもできるだろう(相良守次編『学習と思考』)。 ここでピアジェが操作的といっているのは、言葉や記号を操作して思考できることを意味する。数を数えるのに指やモノで数えるのではなく、数字を操作することができること、あるいはスズメ>鳥>動物>生物といった類(クラス)の関係を頭の中で概念的に理解できること等々、われわれ成人が難なくこなしている思考における、抽象的概念的な働きを意味している。したがって、この段階では、イメージや表象はまだモノやコトといった具体的なものを媒介にしないと不十分なのであり、まだ知覚イメージ(知覚的図柄)に左右されてしまう。 例えば、同じ量でも、外観に欺かれて、大きい器の方が多いと答える。また一方から他方へ移すと、見かけに左右されて、量が変わったと判断する。高さと全体量の関係といった操作的思考ができていないから、視覚的な同値性が見られないと、同値と認めないのである。 具体的操作思考、 では、 具体的な事物についての概念ができ、モノを見たり扱っている限り、論理的な思考が働かせられるようになる。したがって分類や配列ができ、ここでは操作的思考として、スズメ>鳥>動物>生物といった類(クラス)の関係の分類や前述のコップの見かけに左右されたりせずに、全体量の同一性を理解できるようになる。 しかし、例えば5歳の子に水を入れたコップと穴の開いた50円玉を見せて、 「このお金を入れたら、浮くか、沈むか」 と聞くと、 「沈む」と答えた。その理由を聞くと、しばらく50円玉を見詰めて、 「穴が開いているから」と答えた。で、次に穴の開いていない50円玉を取り出して、同様の質問をすると、 「沈む」 「穴が開いていないから」と答える。奇妙な理屈だが、金属でできたものの沈む知覚経験が強く印象づけられていて、それに左右されているということができる。しかし、理由は説明できないのに、言語的概念を手に入れた8歳の子供になると、同じ質問をされると、「お金=鉄みたいなものは沈む、木の棒=木でできているもの浮く」という反応をする。重い軽いという概念で区別している。ただしまだそれは法則的な整理ができていないから、「鉄でできている船は浮くではないか」と問うと、「船の形にすると皆浮く」という形で答える。それに答えるためには、ものごとを統合的に説明し、仮説から演繹的に推論する論理体系を学ばなくてはならない。 またこの段階になると、通常は独り言は少なくなって、「………ここはうんと………」(ぶつぶつ口の中で言っているけれども、あまり聞き取れない)、というように、独り言が次第に聞き取れなくなっていく。それは、自分のためにしゃべっているのであって、別に文脈が整っている必要がないからであり、それだけ、自分の内的会話と人とのコミュニケーション(社会的会話)とが分離していくということでもある。こうして言語が内面化されていく(相良等・前掲書)。 形式的操作思考、 では、 具体的事物がなくても、頭の中で論理操作ができるようになる。とくに前段階でできなかった、「もし、こうなったらこうなる」といった形で推理できる、仮説演繹的な思考ができるようになる。既に成人の思考の段階にある、ということができる。いわば人間としての思考の枠組ができあがるのである。しかし、こうした論理的思考は、いわばそれまでの感覚運動的知能、表象的思考、形式的思考と、順次、言語だけでなく、動作・行動や知覚イメージ、映像を内面化してきたその積み重ねの結果として形成されている。 操作とは、内面化された活動である、 というのは、そのことであり、われわれの中には、感覚運動的活動がひょいと外面へ現れることがあるのだ。例えば、ゴルフのスイングを想定するとき、肱の恰好や腰の据わり方を、思わず躯を動かしながら、あれこれ考えている。これは、自分の躯の動きが頭の中にしまわれている(内面化されている)ものが顕在化したと考えられる。また、ソロバン上手が暗算に際して、そろばんがなくても、頭にそろばんのイメージをつかまえられる(イメージの内面化)し、同時に思わず右手で空を弾くような仕草をする(動作の内面化)。これらは、内面化された動作が、一瞬外へ滲み出た例ということができる。あくまで、操作的思考は、「内面化された活動」だというのは、そういうことを意味している。 その面で、特に付け加えておく必要があるのは、動作の内面化には重要な問題が含まれているという点である。「いないいない、ばあ」には反応しなくなる時期を通して、われわれは対象への距離と位置を学んでいく。それは、見え方が変わっても対象が存在しつづけること、しかし見え方は見方によって変わりうること、即ち、視点の問題である。そこから、「そもそも立体という考えは、人間が動けるから存在するわけです。もしたとえば私が植物としてこの場所に立っていただけだとしたら、つまり私が生まれてこのかたいままで全然移動していないとすると、私には立体という観念はないわけだ。立体は、自分と立体との間に相対的な運動が可能で、物体を上下、左右、前後から見ることができて、はじめてわかる」(森政弘)と、言えるのである。 感覚運動的知能を手に入れたとき、われわれきは、同時にどこから見たらどう見え方が変わる(見方を変えると見え方が変わる)か、ということをもつかんだということだ。それが、実はイメージを左右する重要な問題であることは、繰り返すまでもないだろう。と同時に、見ることに視点をもつことが、いかに根深くに関わっているかを示してもいるのである。 以上の4段階のステップを、 動作、行為およびそれらの内面化した過程(現実の見え方=視覚) 知覚、経験およびその内面化したイメージ(心象としての見え方=イメージ) 言語およびその内面化した象徴過程 現実の因果関係の内面化した法則的論理 と、整理し直すことができる(相良等・前掲書)。 大人になると、操作的思考つまり言語と論理による思考だけが目につくが、それしか使わないのではない。前述したように、論理的思考は、感覚運動的知能、表象的思考、形式的思考と、順次、言語だけでなく、動作・行動や知覚イメージ、映像を内面化してきたその積み重ねの結果として形成されているのである。このすべての思考が、われわれの中で層となっていると考えなくてはならない。モノを考えるとき、われわれは、以上の4つの軸すべてを組み合わせているのであって、この4軸は思考形成のプロセスであると同時に、思考力の4つの要因でもあるとみなすことができる(丁度、マズローの欲求5段階説で、生理的欲求→安全欲求→所属の欲求→承認の欲求→自己実現の欲求の5つの欲求が、欲求の順位のステップであると同時に併存する欲求のレベルを示すものであるように)。 それは下のように構造化することができるだろう。 現実の関係性の内面化=論理的思考 言語、記号などの内面化=言語的思考 知覚、経験の内面化=表象(イメージ)的思考 動作、行動の内面化=感覚運動的思考 これは、別の言い方をすると、初期には個別具体的であったものが、言葉や理屈を通して、どんどんまとめた抽象化・一般化したものに昇華していくということでもある。それが知識を得るということになるのだろう。 ギルバート・ライル『心の概念』、 で触れたことだが、ライルは、「理知」(intelligence)の概念を、 knowing that(内容を知ること)、 と、 knowing how(方法を知ること)、 に分けた。 ある事柄を遂行する仕方を知っている(knowing how)、 とは、 みずからの真理を見出す能力、さらに真理を見出した後にそれを組織的に利用する能力、 を指している。つまり、 知っている、 だけでなく、 知っていること、 を、 知っている、 ことの積み重ねである。これを、 メタ化、 と一応呼んでおく。ピアジェの理論で気になるのは、 知っていること(knowing that)、 と、 それを使いこなして対応していくこと(knowing how)、 とが地続きになっているところだろう。たしか、ユングが、 ひとは言葉を覚える頃、空を飛ぶ夢を見る、 といった趣旨のことを言っていたと思うが、それはなかなか意味深で、要は、言葉を覚えるとは、 メタ化、 する能力を得るということを象徴的な言い方で表現したのに違いない。 感覚運動的知能の段階(0〜2歳) ↓ 前操作的思考の段階(2〜6、7歳) ↓ 具体的な操作的思考の段階(6、7〜11、2歳) ↓ 形式的な操作的思考の段階(11、2歳〜14、5歳で成人に近づく) というステップは、 感覚運動的知能 ↓ 操作的思考 と言い換えることができる。それは、 知っていいること(knowing that) ↓ どうするかがわかること(knowing how)、 だが、そこには、脳がそうなっているように、 層化、 されており、 知っていること、 見たこと、 感じたこと、 を、 メタ化、 しなくては不可能になる。 メタ化、 のエポックが、 言語化、 とするなら、 空を飛ぶ、 つまり、 上から見る、 あるいは、 対象化、 は、それまでとは地続きではなく、 次元を異にする、 といっていいのである。ちなみに、 メタ化、 を、 対象化、 の意味で使っているが、外山滋比古は、 具体的、即物的なものを一次的、 同種の一次的なものを集め、整理し、相互に関連付ける(抽象化させる)と二次的(メタ化)、 これをさらに同種の二次的なものを集め、昇華させると三次的(メタ・メタ化)、 としている(思考の整理学)。そう考えると、 表象(知覚したイメージを記憶に保ち、再び心のうちに表す作用)、 が、 メタ化、 とするなら、 言語化、 は、 メタ・メタ化、 ということになる。 参考文献; J・ピアジェ(谷村覚・浜田寿美男訳)『知能の誕生』(ミネルヴァ書房) J・ピアジェ(波多野完治、滝沢武久訳)『知能の心理学』(みすず書房) J・ピアジェ(滝沢武久訳)『思考の心理学』(みすず書房) J・ピアジェ(滝沢武久訳)『思考の誕生』(朝日出版社) J・ピアジェ(大伴茂訳)『模倣の心理学』(黎明書房) J・ピアジェ(大伴茂訳)『遊びの心理学』(黎明書房) J・ピアジェ(大伴茂訳)『表象の心理学』(黎明書房) ギルバート・ライル『心の概念』(みすず書房) 森政弘「多角的に観る」(自在研究所 森政弘編『納得の工学』) 相良守次編『学習と思考』(大日本図書) |
|
エルンスト・カッシーラー(生松敬三・木田元訳)『シンボル形式の哲学』を読む。
シンボル形式、 の意味が、最後までよくわからないだけでなく、枝葉が多く、論旨を追うのに、辟易させられる。僕なりに、全体像を整理すると、 認識とはもともとこの本質的な目標――特殊なものを一つの普遍的な法則と秩序にはめこむこと――にむけられている、 そして、 すべての真に厳密で精確な思考は、シンボル論と記号論のうちにはじめて、おのれを支えてくれる足場を見いだいことになる、 ということを前提に、いわば、著者の、 シンボル形式化、 とは、世界を捉える方法としての、 世界のメタ化(客観化)、 の手法なのだと理解した。冒頭の、 哲学的思索の出発点は、存在という概念によってしるしづけられる。存在という概念がまさしく概念として構成された瞬間に、つまり、存在者が多種多様であるのに対して存在するということはひとつであるという意識が目覚めた瞬間に、はじめて哲学固有の世界考察の方向が成立するのである、 ということに象徴されるような、 自立したメタ化世界を作っていく、 という、その手法として、著者は、 言語、 神話(的思考=概念)、 科学(的思考=概念)、 をキイ概念にして展開していく。そして、 シンボル形式、 の代名詞でもある、 記号、 について、 記号の本質的・普遍的利点として、記号が単に表示のためだけでなく、なによりも一定の論理的関係の発見に役立つこと、――それが単に既知のもののシンボルによる略記法を可能にするだけでなく、未知のもの、与えられていないもののもとに赴く新たな道を開くものだということ、 と記してもいる。しかし、世界をメタ化、つまり、著者のいう、 シンボル形式化、 が、 この三者で足りているのかどうかについては、浅学の自分にはわからない。あえて憶説を言うなら、 文学、 詩、 絵画、 といった、メタ化の最たるものについてのウエイトが少なく、より鮮明に、 科学と対立させつつ別に論ずべきもの、 なのではないか、という疑問はある。 あらゆる科学の基礎概念、つまり、科学がそれによってみずからの問題を提起し、その解決を定式化する手段は、もはやある与えられた存在の受動的な写像ではなく、みずからつくり出した知的なシンボルだと考えられるようになる、 と書くように、 現実の写像、 や、 現実の代替、 ではなく、 メタ化された世界そのものの自立した世界、 を目指すとして、少し古臭い、19世紀的なイメージではあるが、 科学的思考、 とりわけ、 数学、 を頂点に置いたところで、21世紀の今日から見ると、時代からの遠い距離を感じざるを得ない。著者は、 数学的記号に固有の意味は、それ自体で〈存在する〉記号のうちにあるのでも、それらの記号が〈模している〉もののうちにあるのでもなく、理念形成作用のある特殊な方向にある、――つまり、それらの記号が目指している外的客観にあるのではなく、ある特定の客観化の仕方にあるのである。数学的諸形式の世界は、秩序化の形式の世界なのであって、事物の形式の世界ではないのだ、 と書き、だから、「シンボル形式の哲学」が主張するのは、 〈記号〉がけっして思考の単に偶然な外被ではなく、記号の使用のなかに思考の特定の方向転換が、思考のある基本的な傾向や形式がはっきり刻印されている……、 のであり、で、 シンボル的思考の本性は、思考内容そのものを操作するのではなく、それぞれの思考内容に特定の記号を対応づけ、この対応づけの力を借りて、複雑な証明の連鎖のすべての項をひとつの形式にまとめあげ、それらを一目で文節された総体として捉えることを可能にしてくれる濃縮化を果たすことにあるからである、 ということなのだとする。そして、象徴的なのは、本書の掉尾である。 自然科学的認識は、おのれ自身の圏内で、精神のある一般的な構成法則を立証し実現してゆく。自然科学的認識は、それがおのれ自身に集中し、おのれの現状と、おのれの望んでいるものを把握すればするほど、世界を把握し理解する他のすべての形式と区別されるおのれ独自の契機――と、おのれをそれら他のすべての形式と結びつける契機と――が、いっそう明確に際立ってくるのである、 と。もちろん、著者自身が、 数学的自然科学の可能性を問題にするとしても、数学的自然科学は……、やはり客観化作用一般の一特殊例としかみなされない……、 とはいっているものの。 参考文献; エルンスト・カッシーラー(生松敬三・木田元訳)『シンボル形式の哲学』(全四冊)(岩波文庫) |
|
|
|
H・ルフェーヴル『パリ・コミューン』、リサガレー『パリ・コミューン』、大佛次郎『バリ燃ゆ』を読む。
確か、マルクスは、『ルイ・ボナパルトのブリュメールの十八日』で、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
関連ページ
-
リーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
管理者のリーダーシップについては,ここをご覧下さい。
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
目標達成のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
-
リーダーシップに必要な5つのことについては,【1】【2】をご覧ください。
-
リーダーシップチェックリストについては,ここをご覧ください。
-
発想技法の活用については,ここをご覧下さい。
-
管理者の意味については,「中堅と管理者の違いは何か」をご覧下さい。
-
管理者は何を問題にすべきかについては,ここをご覧下さい。
-
「管理者にとっての問題」については,ここをご覧下さい。
-
-
管理者の役割行動4つのチェックポイントについては,ここをご覧下さい。
-
OJTのスキルについては,ここをご覧下さい。各論は,それぞれ下ページをご覧下さい。
-
OJTプランのプロセス管理【1・2・3】
-
目標設定のリーダーシップについては,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションスキルは,コミュニケーションスキル①とコミュニケーションスキル②をご覧下さい。
-
コミュニケーション力チェックリストは,ここをご覧ください。
-
コミュニケーションタブーについては,ここをご覧下さい。
-
職場のコミュニケーションは,ここをご覧ください。
-
マネジメントに求められるコミュニケーションスキルについては,ここをご覧下さい。
-
-
自己点検チェックリストは,ここをご覧下さい。
-
-
アイデアづくりは,日々 1つずつを実践している。それについては,ここを見てほしい。