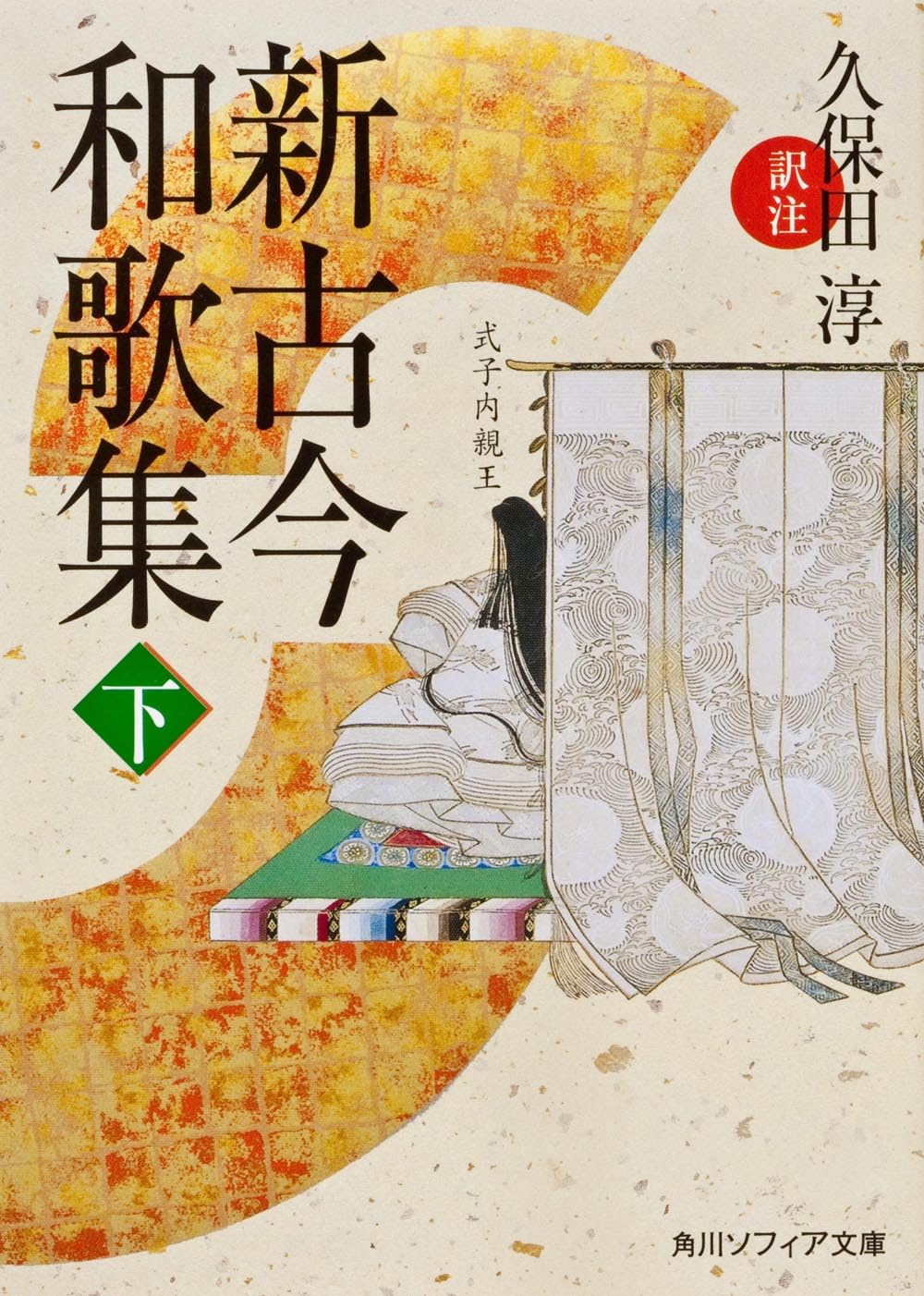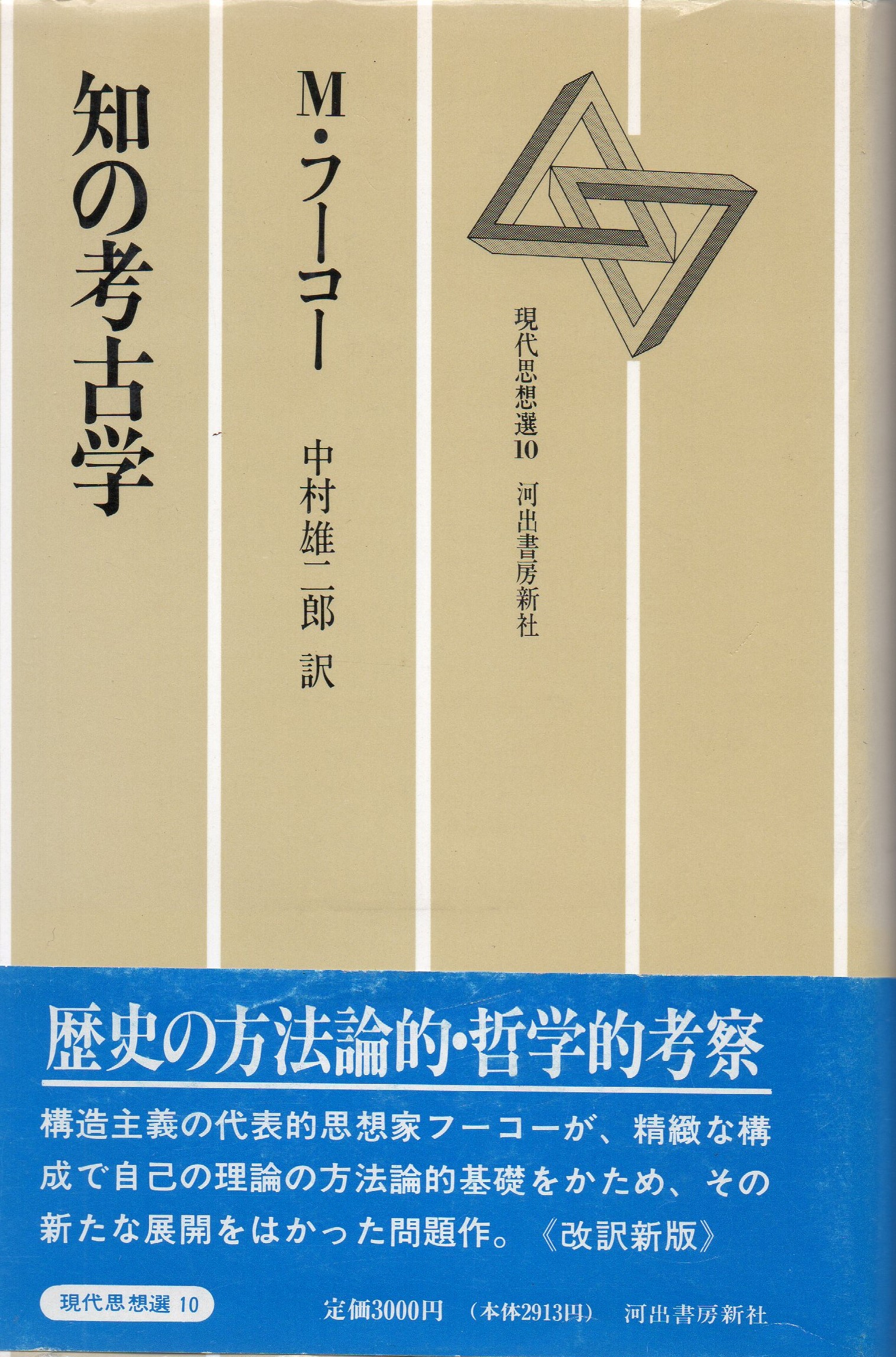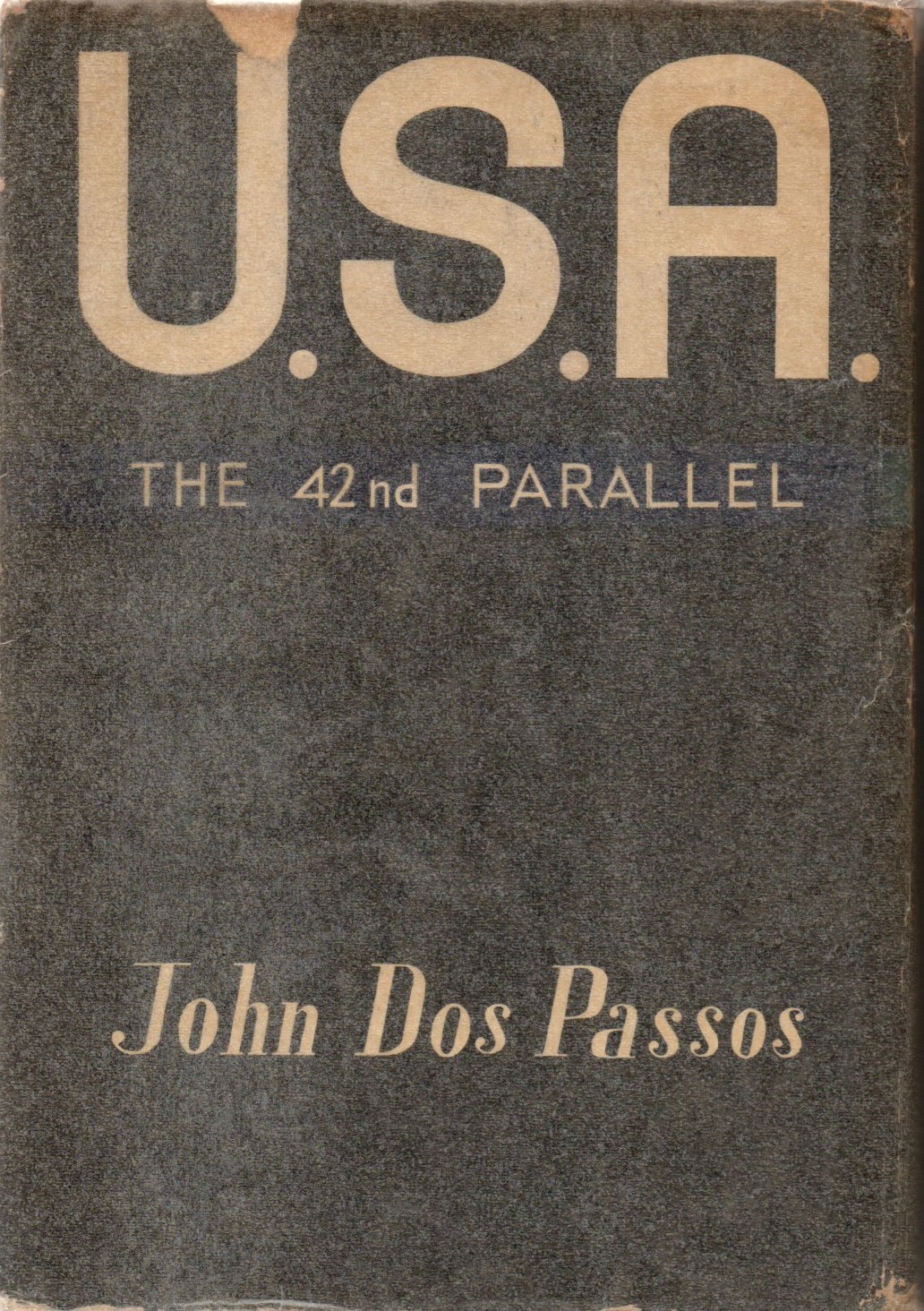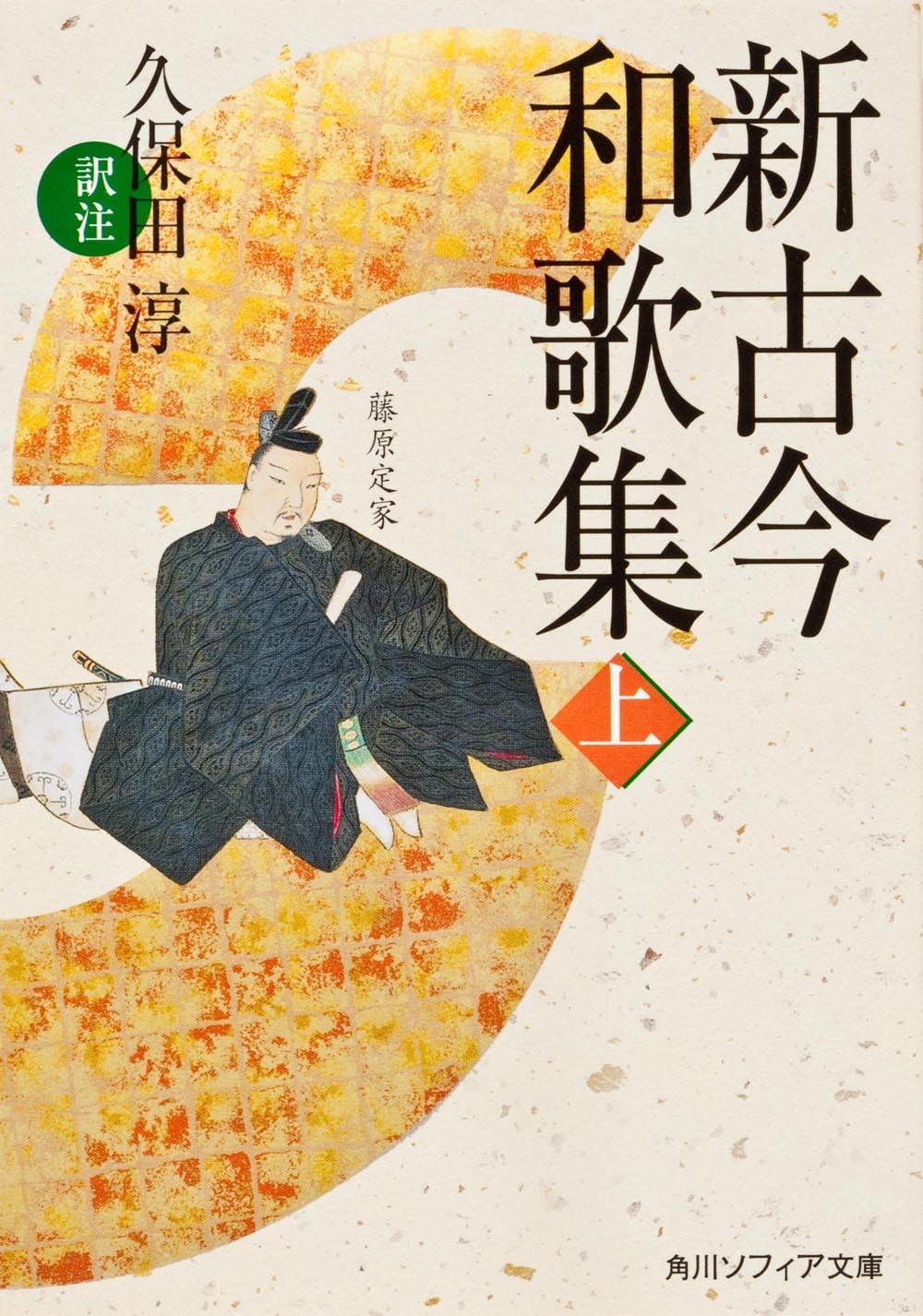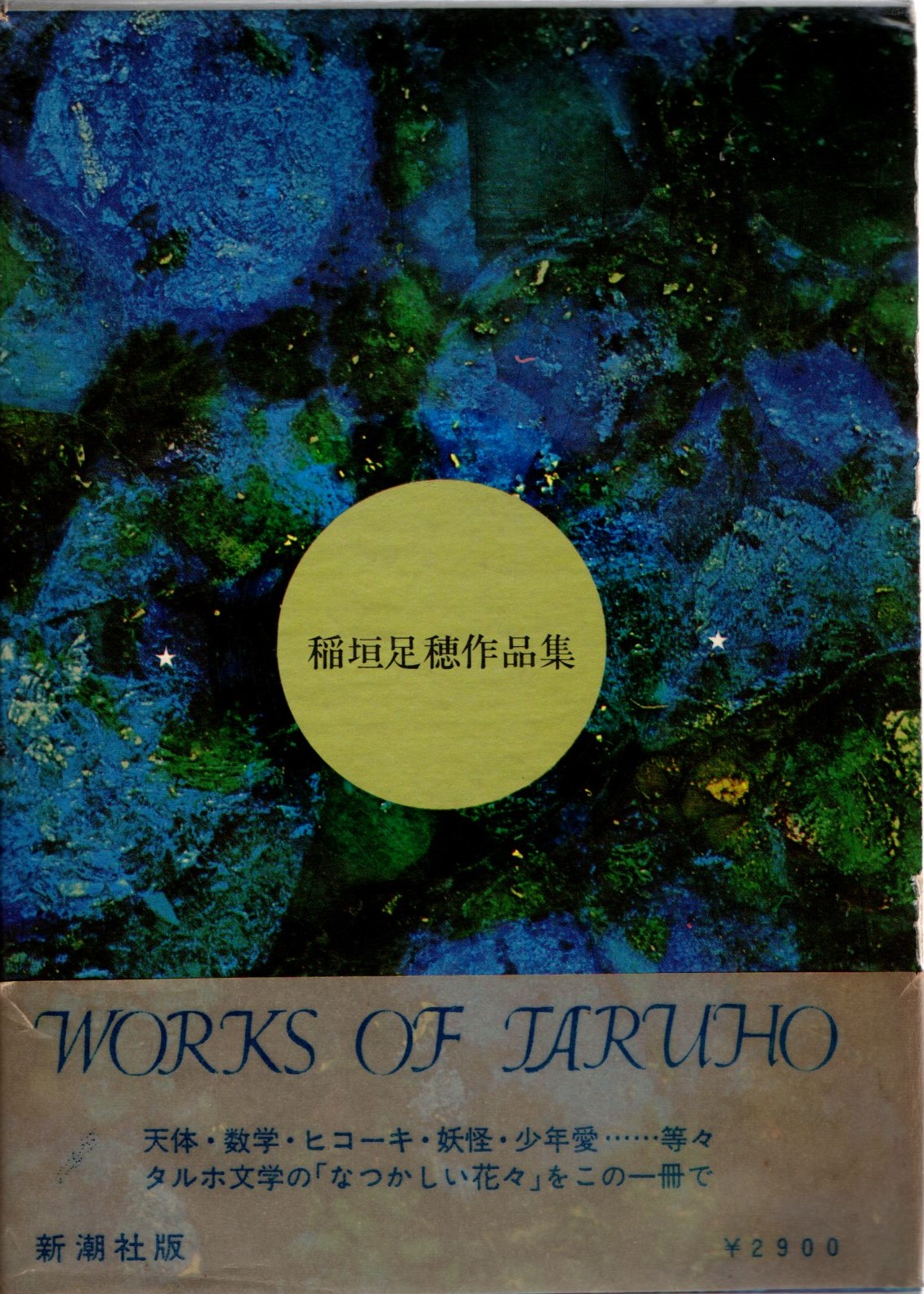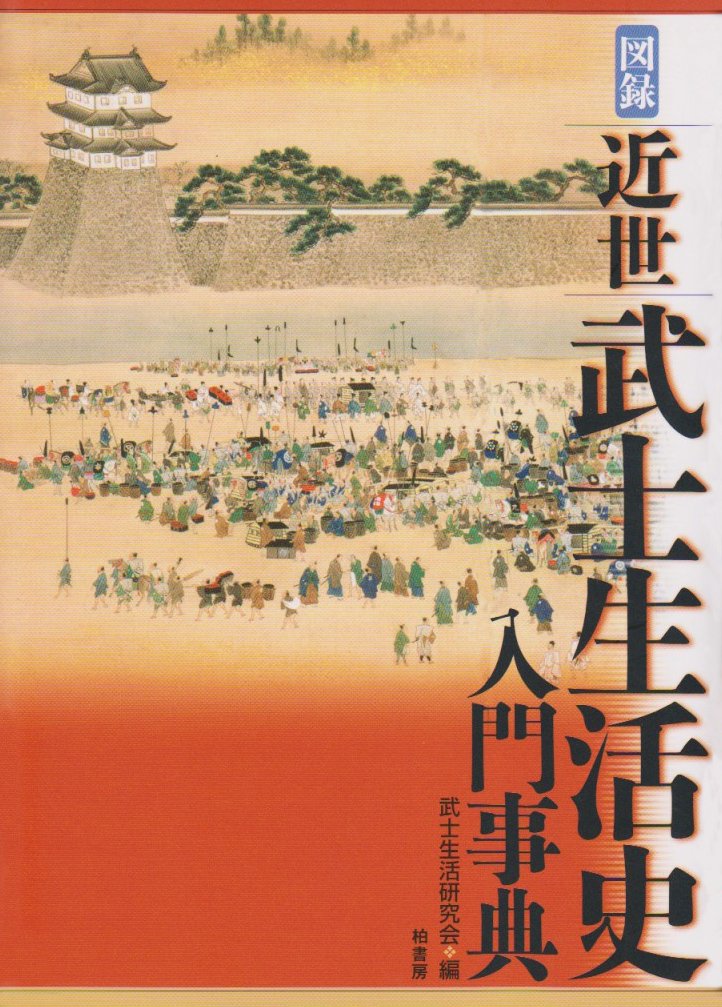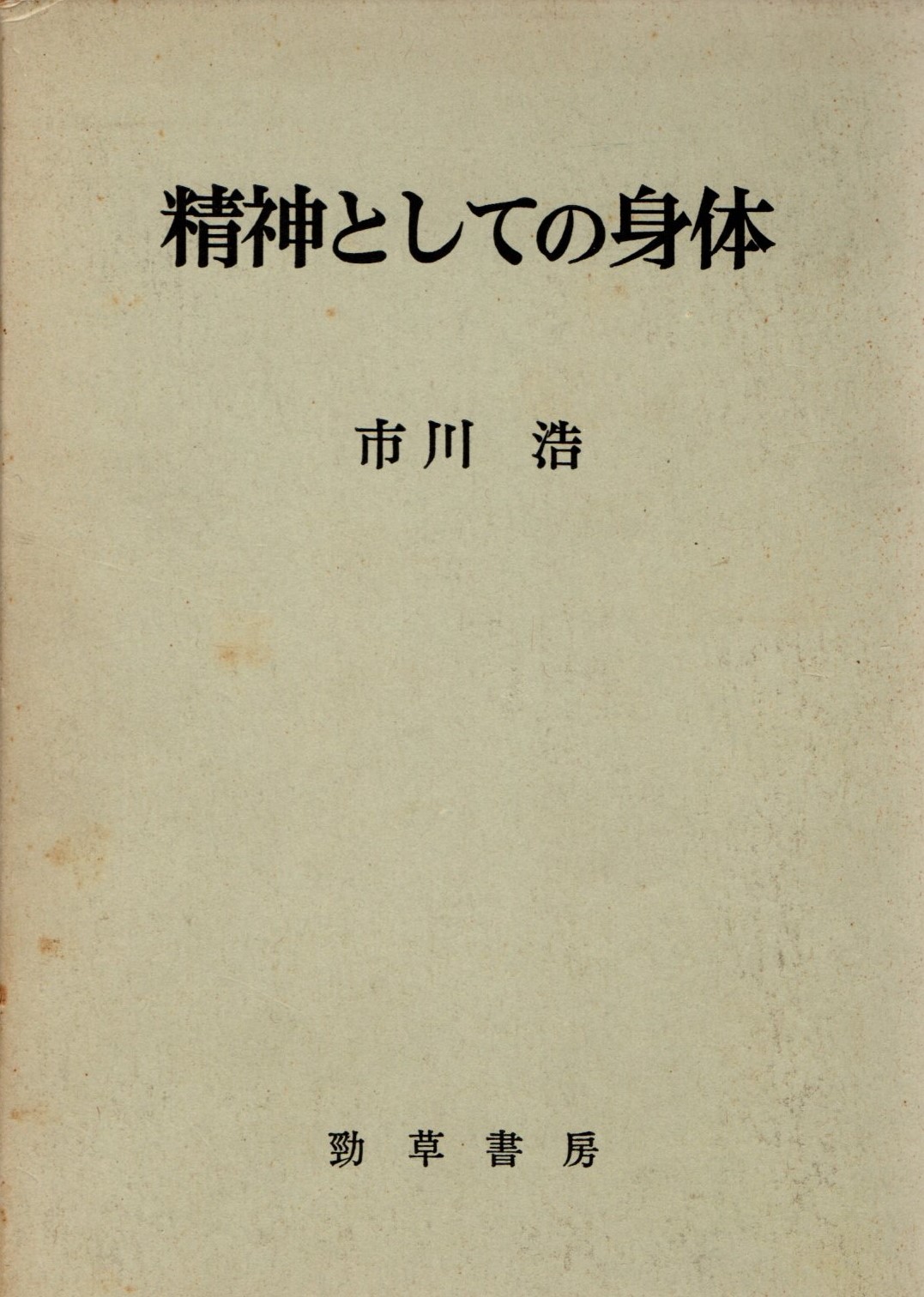|
局外者 |
| M・フーコー( 中村
雄二郎訳)『知の考古学』を読む。
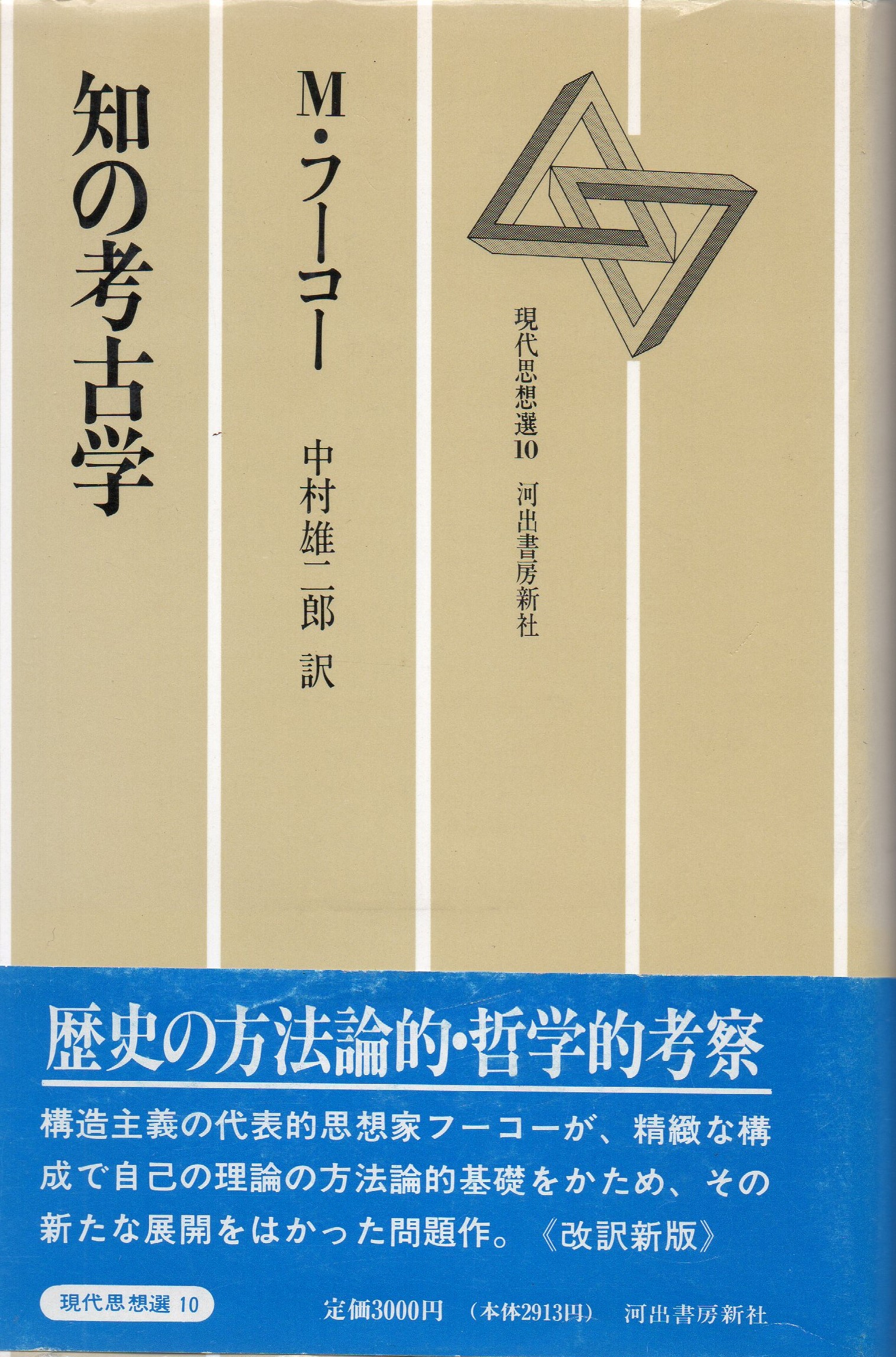
とてもフーコーを論じ、構造主義を云々ずるだけの知識がないので、これを読んで起った自分の中の反応を書き留めておく。あくまで、憶説、妄説である。
『言葉と物』で、フーコーが、
「……自分が自分の言語の総体に、秘かですべてを語り得る神のように、住まってはいないことを学ぶ。自分のかたわらに、語りかける言語、しかも彼がその主人ではないような言語が、あるということを発見するのだ。それは努力し、挫折し、黙ってしまう言語、彼がもはや動かすことのできない言語である。彼自身がかつて語った言語、しかも今では彼から分離して、ますます沈黙する空間の中を自転する言語なのだ。そしてとりわけ、彼は自分が語るまさにその瞬間に、自分がつねに自分の言語の内部に同じような仕方で居を構えているわけではないということを発見するのであり、そして哲学する主体……の占める場所に、一つの空虚が穿たれ、そして無数の語る主体がそこで結び合わされては解きほぐされ、組み合わさっては排斥し合うということを発見するのだ。」(豊崎光一訳『外の思考』)
と書いていることを引用したことがあるが、本書の結論のところの、自己対話の中で、
語る主体をなしですまそうとつとめた、
との指摘に対して、
語る主体への照合を保留したとしても、それは、すべての語る主体によって同一の重要なのは、反対に、さまざまな差異がなにから成り立つのか、一つの同じ言説=実践の内部で、人々が異なった対象について語り、対立する意見をもち、矛盾した選択をすることがどうして起こりえたか、を示すことであった。また、言説=実践のあれこれが相互に区別されるのはどのような点によるのか、示すことでもあった。要するに、私が欲したのは語る主体の問題を排除することではなく、言説の多様性のなかで語る主体がもちえたさまざまな位置と機能を明確にすることであった。
と答えている。構造主義の、
歴史と文化を相対化する、
ということと、
語る主体を相対化する、
こととは、一対のように、僕には見える。
歴史主義、
を否定することと、
非中心化、
とは一対である。
歴史主義、
とは、
救済史、
とつながり(救済史については、K・レーヴィット『世界と世界史』、R・K・ブルトマン『歴史と終末論』、O・クルマン『キリストと時』で触れた)、主体を、
歴史の中において、
歴史の中から見ることではないか。それに対して、
考古学、
というとき、過去の文化、著作、思想を、
遺跡、
遺物、
として、主体としての著者を、
歴史の外から、
あるいは、
歴史の終着点から、
見るということにつながるのではないか。それは、歴史の、
局外者、
となり、
歴史に責任をとらない、
ということでもある。それは、
救済史、
になぞらえるなら、
究極の時点(たとえば、最後の審判)、
から、過去を振り返るに等しくはないか。それは、
神の視点、
に近い、というと、言い過ぎだろうか。確かに、
歴史主義、
は、『世界と世界史』で触れたように、
救済史、
つまり、
神的な始りから神的な終わり、
を、
約束からその実現(最後の審判)への前進、
とみなしたことが、
ヘーゲルの世界精神の現実化、
という、
キリスト教的信仰の世俗化をもたらし(ヘーゲル『精神現象学』については触れた)、それが、マルクスの、
史的唯物論、
という終末論の世俗化を理論化に至らしめた(マルクス『経済学批判』、『資本論』については触れた)。しかし、こうした、
何かを目指している歴史、
という考え方の、
歴史主義、
は根深く、
「人間は歴史的に制約されているのみならず、根本的に歴史的に存在する――つまり人間は徹頭徹尾時間的な存在だからである。歴史的な意識と伝達の可能性は、ハイデッゲルによれば、人間的実存――それの時間性がもっとも決定的に表現されるのは、それが死を予想して実在している、あるいは『終わりに向かう存在』である、という事実においてである――の総体的かつ徹底的な歴史性に存する。」
とするハイデッガーですら、
「存在そのものは『存在の生起』であり、その真理は真理の生起であり、歴史的な出現と隠伏はそれぞれ、そのさどの決定的な瞬間に変化する『現前』と『不在』である」
と(ハイデガーについては『形而上学入門』、『存在と時間』で触れた)、言ってみれば、時間軸を短くし、終末を、「存在の運命」の瞬間に貶めただけのように見える。
確かに、歴史主義は、
「もろもろの理念、神、道徳律、理性の権威、進歩、支配者の幸福、文化、文明などがその建設的な力を失い、無価値」(レーヴィット)
なのかもしれないが、逆に言うなら、
歴史の外から、
ではなく、現在進行形の、
歴史の中から、
歴史に身をゆだねている、
からこそ、その、
歴史の責任を自ら負う、
ということをも意味したはずだ。しかし、
構造主義、
は、少なくとも、フーコーのそれは、
歴史を外から、
言い換えると、
歴史の終着点から、
見ている。だからこそ、
考古学、
というのではないか。それかあらぬか、僕には、構造主義の後、
ポスト構造主義、
は、ぺんぺん草も生えない、不毛の地になっているとしか見えない。なぜなら、
歴史の終着点から総括してしまった跡、
には、何もないからではないか。
こんな感想を懐いた読後である。
なお、ミシェル・フーコーについては、、『〈知への意志〉講義』、『主体の解釈学』、『言葉と物―人文科学の考古学』については触れた。
参考文献;
M・フーコー( 中村 雄二郎訳)『知の考古学』(河出書房新社) |
|
語り口 |
| ガブリエル・ガルシア=マルケス(鼓直訳)『百年の孤独』を読む。

語り手に特徴がある。その語りは、
日常的な現実と非日常的な幻想の混在、
にあり、
幽霊、
も、
幻想、
も、
空想、
も、
奇跡、
も、
現実と地続きに、並列に扱われている。これを、
魔術的リアリズム、
と呼ぶらしいが、この語りの手法自体は、別に新しいことではない。かつての語り物では、
人、
も、
物の怪、
も、
幽霊、
も、
妖怪、
も、
併存しているのが当たり前であった。このことで思い出すのは、中上健次が、『奇蹟』について、その手法を、
「どんなふうに突っ走ったかというと、語りもの文芸を導入するという方向にです。読者は現代人だから当然、語りものに慣れていませんよね。もう忘れてしまっている。それでも強引に、文章をたわめてでも突っ走っていくというのをやってみた。」(渡部直己氏との対談)
と語っている語り物の特徴である。それについては、『古井由吉・その文体と語りの構造』で触れたが、
中上氏の『奇蹟』は、『地の果て至上の時』の〈物語の物語〉である。それは、モンの語りのパースペクティブに収斂した『地の果て至上の時』の語りをさらに相対化させた、語りの「辞」の相対化を徹底させたものとなっている。『地の果て至上の時』では、語りの語りというモンの語り(のパースペクティブ)に一元化することで、語りの奥行(という物語のカタチ)を駆使し、語りを重層化、多層化したのだとすれば、『奇蹟』では、同じように、見かけ上はトモノオジ(の幻覚)の語りに収斂していくような、語りの射程は、しかし、その奥行をどこまでたどっても、いつのまにかはぐらかされ、その代わりに、語りの奥行(という深度)の違う語りのすべてを、洗いざらい棚卸しするようにさらけ出し、そのすべてを横並びにしてみせたのである。(中略)
語り手によって語られることとの奥行のすべてが、語り手のパースペクティブから解き放されることによって、語られることのすべてが同列に展開され、それは一見、語りのパースペクティブそのものの解体に見える。確かに、語りの深度の違いが鞣され、彩りの違う語りが並列にされて、かえって物語に内包する(零記号化したはずの)語り手が解き放たれ、別々の語りが並んだように見える。しかし語り手が向き合う(語る)ものが変われば、語りのパースペクティブは変わる。ここにあるのは、語り手が、入子の語りの深度をひとつの“とき”に収斂する語りではなく、(零記号化した語り手たちの語る)入子の語りすべてが併置される語りに向き合っている、語る“いま”も、語られる“あのとき”“そのとき”も眼前に一斉に店開きする、新たな語りのパースペクティブなのである。
そこにあるのは、ただ、
過去、
も、
現在、
も、
未来、
も、
ひとしなみに、同列に並べられている世界であり、それは、
あのとき、
も、
そのとき、
も、
あそこ、
も、
そこ、
も、
いまここ、
に、
語り手の眼前に現前している語りである。それは、
心の中、
も、
心の外、
も、
また同列であり、当たり前ながら、
うつつ、
も、
ゆめ、
も、
幻想、
も、
空想、
も、
差別なく並ぶ世界であり、当然、
生きている人間、
も、
死者
も、
幽霊、
も、
同列であり、
怪異、
も、
不思議、
も、
自然現象、
も、
同列である。そうみれば、本作の、百年に渡る、
ほぼ同心円のような経時的な流れ、
の中で、全てが同列に語られているのは、その語り口からの当然の帰結である。どこかで読んだ記憶があるが、この語り口(「祖母の語り口」と言っていたような)が、一気に書き上げるきっかけになった、と。その意味で、この語り口にこそ、本作の特徴があるのだろう。
ただ、そうしたことによる、精緻な、全てを並立にするリアリティは、面白いのだが、時に、不思議なことに、眠気を誘う。名前が似たような名前であることだけでなく、同心円でつづく、似たバリエーションの逸話の積み重ねに、既視感があり、本作の中で、ウルスラが、
時間というものはぐるぐる回っている、
と、言っているように、同心円の、いや螺旋状に、似たエピソード(出来事は似ていないが、ブエンディア一族の特徴的なありよう、生き様のバリエーション)が一層眠気を誘う。これは、此方の事情なのかもしれないが、ふと、30年以上前に読んだ、それと対比される、
マリオ バルガス=リョサ『世界終末戦争』、
を思い出した(マリオ
バルガス=リョサは、ガルシア=マルケス、コルタサル、フェンテスと共に、〈マフィア〉として括られる中南米作家のひとり)。これは、ブラジルに実際にあった、
カヌードスの反乱、
を描いたものだが、こちらは、
いくつもの場面を並行させつつ、様々な人間が登場する、
という、『百年の孤独』とは異なり、時間的には経時的だが、
空間的な広がり、
のある、スケールの大きな作品だ。個人的な好みの問題かもしれない。しかし、『サンクチュアリ』で触れたことだが、
「新聞の切り抜き(『ニュース映画』)・作者の意識の流れ(『カメラの目』)・登場人物たちそれぞれのドラマで、20世紀初頭の『アメリカ合衆国』を、虚実織り交ぜて、実験的手法で、眺望したもの」
とされ、ちょうど、1930年代のアメリカを俯瞰したものになっている、
ドス・パソス(ジョン・ロデリーゴ・ドス・パソス(John Roderigo Dos
Passos)『U・S・A』、
や、
フォークナー作品、
のように、
同時進行の中に、様々な場面を並行させて、広く、物語を展開させていく手法、
に魅力を感じているせいかもしれない。日本の作家でいうと、フォークナーの影響を受け、
『虚構のクレーン』
『死者の時』
『地の群れ』
等々の、
井上光晴、
がいる。
『書かれざる一章』(大岡昇平他編『政治と文学(全集現代文学の発見第4巻)』)、
『ガダルカナル戦詩集』(大岡昇平他編『青春の屈折下(全集現代文学の発見第15巻)』)、
については、触れたことがある。

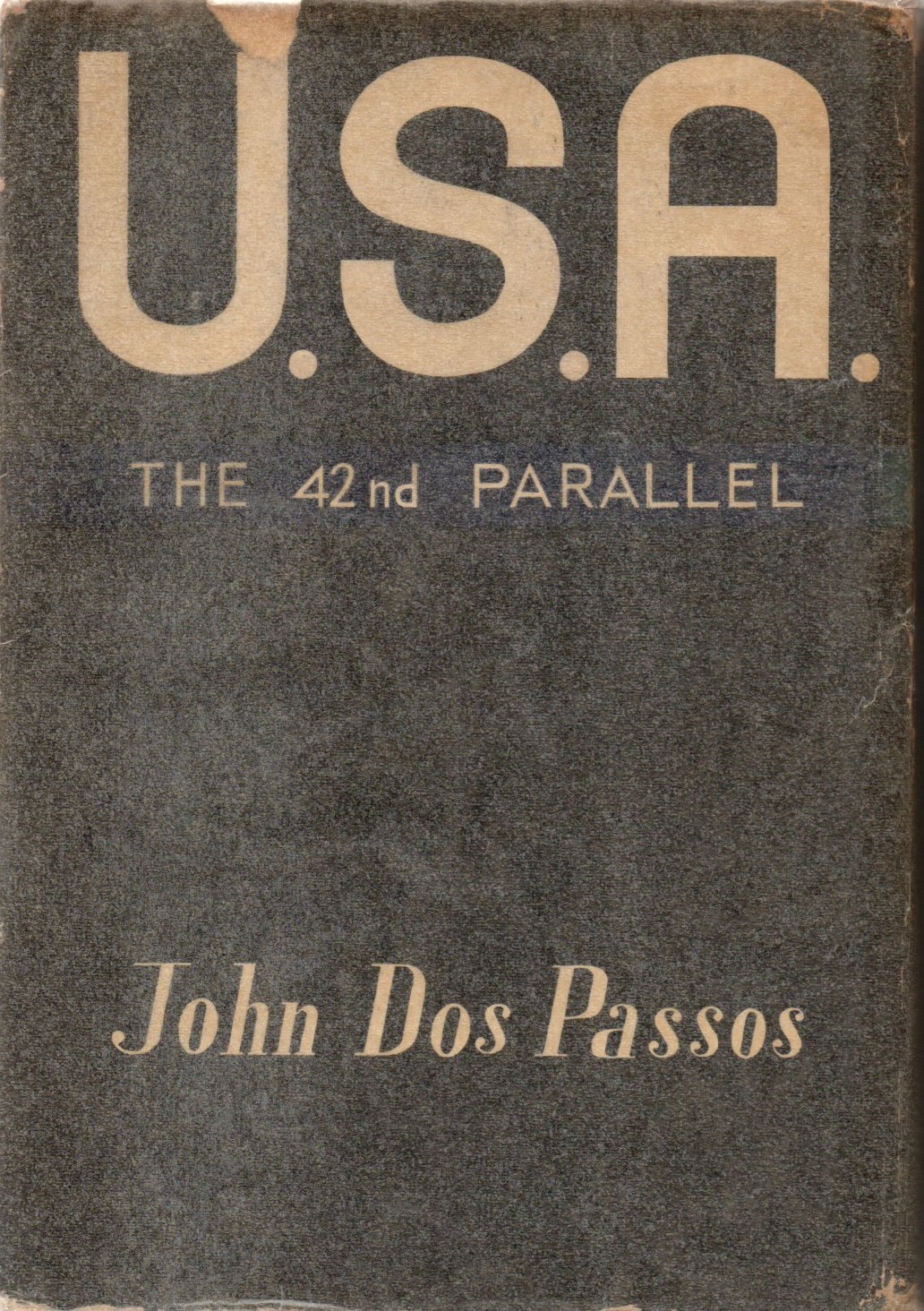
参考文献;
ガブリエル・ガルシア=マルケス(鼓直訳)『百年の孤独』(新潮文庫)
マリオ バルガス=リョサ(旦敬介訳)『世界終末戦争』(新潮社)
ドス・パソス(並河亮訳)『U・S・A』(改造社) |
|
メタ歌 |
| 久保田淳訳注『新古今和歌集』を読む。
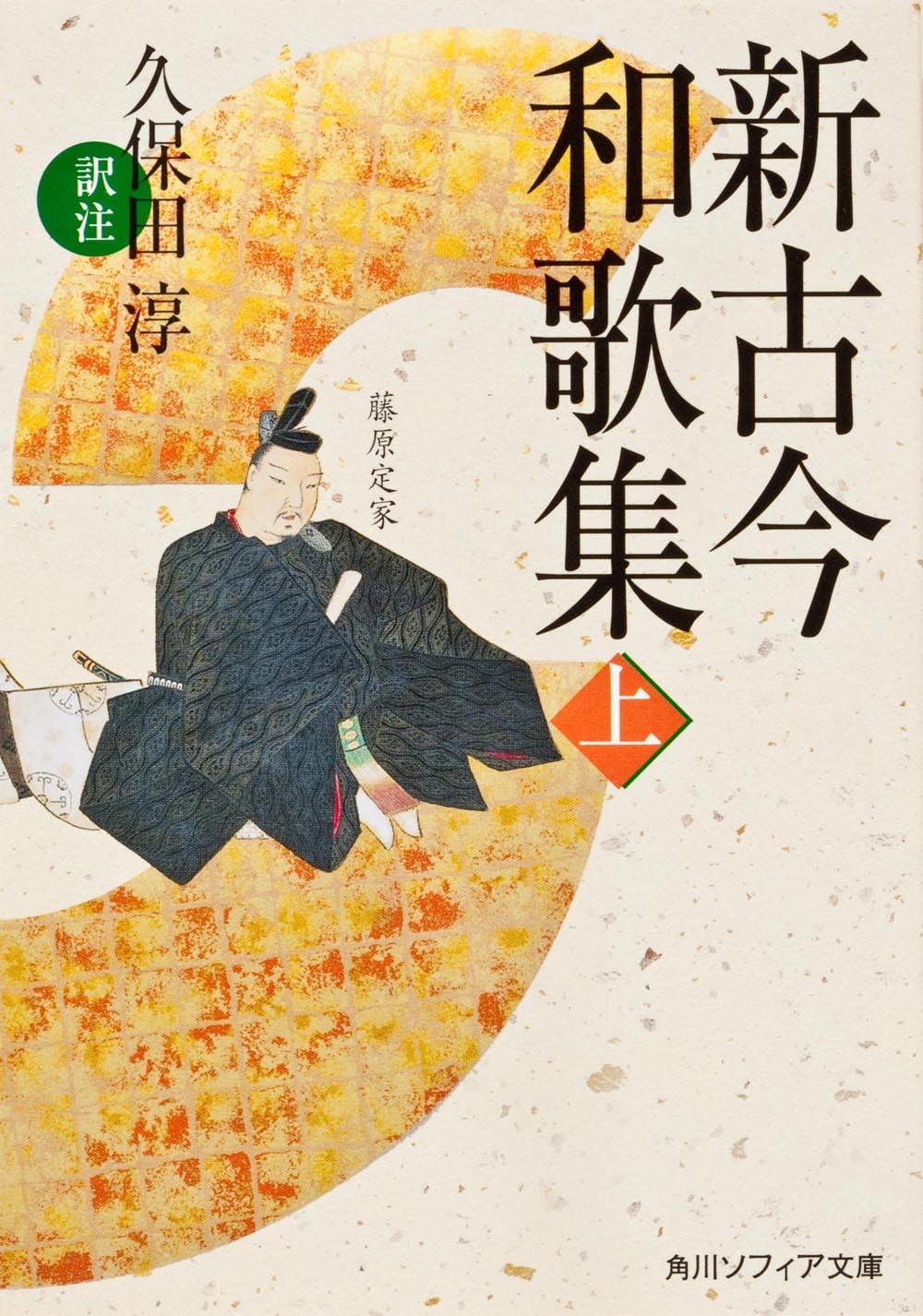
「斯の集の体たるや、先万葉集の中を抽き、更に七代集の外を拾ふ。深く索めて微長も遺すこと無く、広く求めて片善も必ず挙げたり。」
と、「序」で言うとおり、万葉集をはじめ、古今集から千載集までの七勅撰集のすぐれた歌1980句を選んでいる。しかも、
「和歌という形式の枠内で古典の伝統によって洗練された大和言葉の微妙な組み合わせにより、現実をはるかに超えた美の世界を実現しようと努めた」(久保田淳・解説)
という独自の文学観に基づき、その方法も、
「『古今』『後撰』『拾遺』の三代のすぐれた歌の語句を大胆に取り込んだり、『源氏物語』や『狭衣物語』などの作り物語のある場面を利用したり、『白氏文集』や『和漢朗詠集』などの漢詩文の佳句から発想・表現を借りたりした」(仝上)
という独特の物だ。その典型的なものは、
すぐれた古歌や詩の語句、発想、趣向などを意識的に取り入れる表現技巧、
である、後世に、
本歌取り、
というようになり、中世の歌論書では、
本歌とす、
本歌をとる、
本歌にとる、
などの形で見える修辞法で、新古今集の時代に最も隆盛した。たとえば、
苦しくも降りくる雨か三輪が崎佐野のわたりに家もあらなくに(万葉集)、
を本歌として、
駒とめて袖打払ふ蔭もなし佐野のわたりの雪の夕暮(藤原定家)
と詠うのが一例になるが、
古くからある有名な歌や、自分が好きな歌、オマージュしたい歌などを「本歌」として、その中の1句もしくは2句を取り入れて新しく歌を詠む、
という手法(https://tanka-textbook.com/honkadori/)で、定家は、『近代秀歌』、『詠歌之大概(えいがのたいがい)』において、本歌取りの原則的な事柄について、
句の置き所を変えないならば2句まで、句の置き所を変えるならば2句と更に3、4文字まで本歌を下敷きにするのがいい、そして、枕詞や序詞の入った本歌については、あまりに有名な名句という評ではないならば初2句までそのまま本歌取りに用いてもいいが、本歌と主題を合致させるのは避けなくてはいけない、本歌のネタ元として三代集と『伊勢物語』と『三十六人家集』のみを採用し、昨今の詩からは引っぱらないようにするのがいい、
とした(https://jtanka.com/tankadaigaku/archives/23)。その基本は、
〔1〕本歌の字句はできるだけ置き場所を変えて借用し、字数は二句以上3、4字までとする。
〔2〕本歌が四季の歌ならば、新作は恋・雑(ぞう)の歌というふうに主題を変え、また趣向を変えて取ることが望ましい。
〔3〕格別な名句や同時代人の歌は避ける、
などである(日本大百科全書)。ある意味で、
メタ化された歌、
メタ和歌、
といってよく、
現実を詠うのではなく、詠われた世界や感覚・情緒をベースに更に詠う、
という、
作品世界の多重化・多層化、
の狙いがある。それは、言わば、
虚構の歌世界、
である。たとえば、
明けぬるか川瀬の霧の絶え間より遠方(をちかた)人の袖の見ゆるは(後拾遺・源経信母)、
を本歌として、
川霧といふことを、
という詞書で、
あけぼのや川瀬の波の高瀬舟くだすか人の袖の秋霧(左衛門督通光)
という歌は、
曙、浅瀬に立つ波は高く、高瀬舟に棹さして川を下すのだろうか、舟人の袖がちらりと秋霧の絶え間から見えるよ、
と注釈される(久保田淳訳注『新古今和歌集』)が、明らかに、本歌を知っていてこそ、この歌の情景の奥行きが見える。もちろん、『袋草紙』に、
麓をば宇治の川霧立ちこめて雲居に見ゆる朝日山かな(権大納言公実)、
の歌は、公実自身が
川霧の麓をこめて立ちぬれば空にぞ秋の山は見えける(拾遺・清原深養父)、
を盗んだと語ったとあるように、ある意味、本歌取りと盗作とは微妙な差なのだが、それは、言語世界が自立していればこそ生じることだともいえる。『新古今和歌集』は、言語作品が、ここまで自立した世界を目ざしている、というと言い過ぎだろうか。その分、それは嘘だろう、と言いたくなるような、空々しい世界や、情緒が透けて見えてしまうこともある。いくつか上げて見ると、たとえば、面白い工夫と見えるのは、
色見えでうつろふものは世の中の人の心の花にぞありける(古今集・小野小町)、
を本歌とした、
さりともと待ちし月日ぞうつりゆく心の花の色にまかせて(式子内親王)
で、主体的な心の変化に置き換えているところが工夫だが、
黒髪の乱れも知らずうち臥せばまづ掻きやりし人ぞ戀しき(和泉式部)
を本歌とした、
掻きやりしその黒髪の筋ごとにうち臥すほどは面影ぞ立つ(定家)
は、それをおのが心のメタファに置き換えて、本歌の直截的な表現よりも屈折している。
しかし、虚構的であることで、
霜こおる袖にも影は残りけり露よりなれし有明の月(右衛門督通具)
ながめつつ幾度袖に曇るらむ時雨にふくる有明の月(藤原家隆)
晴れ曇る影を都に先立ててしぐると告ぐる山の端の月(源具親)
などは、かなり仮想的というか、作りものめいていると言えるし、
知られじなおなじ袖には通ふともたが夕暮れと頼む秋風(家隆)
物思はでただおほかたの露にだに濡るれば濡るる秋の袂を(有家朝臣)
みるめ刈る潟やいづくぞ棹さしてわれに教へよ海人の釣舟(業平朝臣)
などは、技巧的というよりは作為的に過ぎる気がするし、
難波人いかなる江にか朽ちはてむ逢ふことなみに身をつくしつつ(摂政太政大臣)
梶を絶え由良の湊に寄る舟のたよりも知らぬ沖つ潮風(摂政太政大臣)
しるべせよ跡なき波に漕ぐ舟のゆくへも知らぬ八重の潮風(式子内親王)
まばらなる柴の庵に旅寝して時雨に濡るる小夜衣かな(後白河院)
なびかじな海人の藻塩火たきそめてけぶりは空にくゆりわぶとも(藤原定家朝臣)
等々は、技巧的というよりも、ちょっと嘘っぽい。
といった新古今和歌集の特徴を拾ったというよりは、自分の心に何かさざ波を立てた歌を、勝手に拾ってみたのは、次の130首ほどになる。
風まぜに雪は降りつつしかすがに霞たなびき春は來にけり(読人知らず)
春の夜の夢の浮橋とだえして峰に別るる横雲の空(定家)
大空は梅のにほひに霞みつつ曇りもはてぬ春の夜の月(仝上)
梅の花にほひをうつす袖の上に軒もる月の影ぞあらそふ(仝上)
梅の花たが袖ふれしにほひぞと春や昔の月に問はばや(右衛門督通具)
照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ月夜にしくものぞなき(大江千里)
あさみどり花もひとつに霞みつつおぼろに見ゆる春の夜の月(菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ))
帰る雁今はの心有明に月と花との名こそ惜しけれ(摂政太政大臣(良経))
つくづくと春のながめのさびしきはしのぶに伝ふ軒の玉水(大僧正行慶)
春風の霞吹きとく絶えまより乱れてなびく青柳の糸(殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ))
青柳の糸に玉ぬく白露の知らず幾代の春か経ぬらむ(藤原有家)
花の色にあまぎる霞立ちまよひ空さへにほふ山桜かな(権大納言長家)
ももしきの大宮人はいとまあれや桜かざしてけふも暮らしつ(赤人)
花にあかぬ歎きはいつもせしかどもけふの今宵に似る時はなし(在原業平朝臣)
散り散らずおぼつかなきは春霞たなびく山の桜なりけり(祝部成仲)
山里の春の夕暮れ来て見れば入相の鐘に花ぞ散りける(能因法師)、
花さそふなごりを雲に吹きとめてしばしはにほへ春の山風(藤原雅経)
吉野山花のふるさと跡絶えてむなしき枝に春風ぞ吹く(摂政太政大臣)
たがたにかあすは残さむ山桜こぼれてにほへけふの形見に(清原元輔)
柴の戸にさすや日影のなごりなく春暮れかかる山の端の雲(宮内卿)
春過ぎて夏来にけらし白たへの衣干すてふ天の香具山(持統天皇)
声はして雲路にむせぶほととぎす涙やそそく宵の村雨(式子内親王)
ほととぎす深き峰より出でにけり外山の裾に声の落ち来る(西行法師)
あふち(楝)咲くそともの木蔭露おちてさみだれ晴るる風渡るなり(前大納言忠良)
さみだれの雲間の月の晴れゆくをしばし待ちけるほととぎすかな(二条院讃岐)
帰り来ぬ昔を今と思ひ寝の夢の枕ににほふたちばな(式子内親王)
たちばなの花散る軒のしのぶ草昔をかけて露ぞこぼるる(前大納言忠良)
たちばなのにほふあたりのうたた寝は夢も昔の袖の香ぞする(皇太后宮大夫俊成女)
いさり火の昔の光ほの見えて蘆屋の里に飛ぶ蛍かな(摂政太政大臣)
窓近き竹の葉すさぶ風の音にいとどみじかきうたた寝の夢(式子内親王)
窓近きいささ群竹(むらたけ)風吹けば秋におどろく夏の夜の夢(春宮大夫公継)
むすぶ手に影乱れゆく山の井のあかでも月のかたぶきにける(前大僧正慈円)
夕立の雲もとまらぬ夏の日のかたぶく山にひぐらしの声(式子内親王)
いづちとか夜は蛍ののぼるらむ行く方知らぬ草の枕に(壬生忠見)
白露のなさけ置きける言の葉やほのぼの見えし夕顔の花(前太政大臣)
たそかれの軒端の萩にともすればほに出でぬ秋ぞ下に言問ふ(式子内親王)
この寝(ね)ぬる夜のまに秋は来にけらし朝けの風のきのふにも似ぬ(藤原季通朝臣)
おしなべてものを思はぬ人にさへ心をつくる秋の初風(西行法師)
うたたねの朝けの袖にかはるなりならす扇の秋の初風(式子内親王)
手もたゆくならす扇のおきどころ忘るばかりに秋風ぞ吹く(相模)
薄霧の籬の花の朝じめり秋は夕べとたれかいひけむ(清輔朝臣)
心なき身にもあはれはしられけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ(西行)
見わたせば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ(定家)
深草の里の月影さびしさも住みこしままの野べの秋風(右衛門督通具)
月影の澄みわたるかな天の原雲吹き払ふ夜はのあらしに(大納言経信)
秋風にたなびく雲の絶え間よりもれいづる月の影のさやけさ(左京大夫顕輔)
行く末は空もひとつの武蔵野に草の原より出づる月影(摂政太政大臣)
過ぎてゆく秋の形見にさを鹿のおのが鳴く音もをしくやあるらむ(権大納言長家)
秋来れば朝けの風の手を寒み山田の引板(ひた)をまかせてぞ聞く(前中納言匡房)
ふけにけり山の端近く月さえて十市の里に衣打つ声(式子内親王)
ひとめ見し野辺のけしきはうら枯れて露のよすがに宿る月かな(寂蓮法師)
秋の夜は衣さむしろ重ねても月の光にしくものぞなき(大納言経信)
あけぼのや川瀬の波の高瀬舟くだすか人の袖の秋霧(左衛門督通光)
村雲や雁の羽風に晴れぬらむ声聞く空に澄める月影(朝恵法師)
いつのまにもみぢしぬらむ山桜きのふか花の散るを惜しみし(中務卿具平親王)
柞(ははそ)原しづくも色や変るらむ杜の下草秋ふけにけり(摂政太政大臣)
時わかぬ波さへ色にいづみ川柞(ははそ)の杜(もり)にあらし吹くらし(定家朝臣)
おきあかす秋の別れの袖の露霜こそ結べ冬や来ぬらむ(皇太后宮大夫俊成)
月を待つ高嶺の雲は晴れにけり心あるべき初時雨かな(西行法師)
柴の戸に入日の影はさしながらいかにしぐるる山辺なるらむ(清輔朝臣)
世の中になほもふるかなしぐれつつ雲間の月のいでやと思へど(和泉式部)
秋の色を払ひはててや久方の月の桂にこがらしの風(雅経)
風寒み木の葉晴れゆく夜な夜なに残るくまなき庭の月影(式子(しょくし)内親王)
霜枯れはそことも見えぬ草の原誰に問はまし秋のなごりを(皇太后宮大夫俊成)
津の国の難波の春は夢なれや蘆の枯葉に風渡るなり(西行法師)
さびしさに堪へたる人のまたもあれな庵(いほり)並べむ冬の山里(西行法師)
かつ氷りかつは砕くる山川の岩間にむせぶ暁の声(皇太后宮大夫俊成)
見るままに冬は來にけり鴨のゐる入り江の汀(みぎは)薄ごほりつつ(式子内親王)
白波に羽うちかはし浜千鳥かなしき声は夜の一声(重之)
さ夜千鳥声こそ近く鳴海潟(なるみがた)かたぶく月に潮や満つらむ(正三位季能)
風さゆるとしまが磯の群(むら)千鳥立ちゐは波の心なりけり(正三位季経)
降りそむる今朝だに人の待たれつる深山の里の雪の夕ぐれ(寂連法師)
おのづからいはぬを慕ふ人やあるとやすらふほどに年の暮れぬる(西行法師)
數ふれば年の残りもなかりけり老いぬるばかりかなしきはなし(和泉式部)
けふごとにけふやかぎりと惜しめどもまたも今年に逢ひにけるかな(皇太后宮大夫俊成)
あはれなりわが身のはてやあさ緑つひには野辺の霞と思へば(小野小町)
たれもみな花の都に散りはててひとりしぐるる秋の山里(左京大夫顕輔)
なれし秋のふけし夜床はそれながら心の底の夢ぞかなしき(大納言実家)
朽ちもせぬその名ばかりをとどめおきて枯野のすすき形見とぞ見る(西行法師)
物思へば色なき風もなかりけり身にしむ秋の心ならひに(皇太后宮大夫俊成)
けふ来ずば見でややままし山里のもみぢも人も常ならぬ世に(前大納言公任)
思へ君燃えしけぶりにまがひなでたちおくれたる春の霞を(源三位)
夜もすがら昔のことを見つるかな語るやうつつありし世や夢(大江匡衡朝臣)
あらざらむのち偲べとや袖の香を花橘にとどめおきけむ(祝部成仲)
あるはなくなきは数添ふ世の中にあはれいづれの日まで歎かむ(小野小町)
暮ぬまの身をば思はで人の世のあはれを知るぞかつははかなき(紫式部)
思ひ出でば同じ空とは月を見よほどは雲居にめぐり遭ふまだ(後三条院)
人をなほ恨みつべしや都鳥ありやとだにも問ふを聞かねば(女御徽子女王(きしにょおう))
み山路に今朝や出でつる旅人の笠白妙に雪積もりつつ(大納言経信)
袖にしも月かかれとは契りおかず涙は知るや宇津の山越え(鴨長明)
年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけりさやの中山(西行法師)
年を経て思ふ心のしるしにぞ空もたよりの風は吹きける(藤原高光)
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする(式子内親王)
忘れてはうち歎かるる夕べかなわれのみ知りて過ぐる月日を(式子内親王)
わが恋はいはぬばかりぞ難波なる蘆のしの屋の下にこそ焚け(小弁)
わが恋は荒磯の海の風をいたみしきりに寄する波のまもなし(伊勢)
しるべせよ跡なき波に漕ぐ舟のゆくへも知らぬ八重の潮風(式子内親王)
なびかじな海人の藻塩火たきそめてけぶりは空にくゆりわぶとも(藤原定家朝臣)
数ならぬ心のとがになしはてじ知らせてこそは身をも恨みめ(西行法師)
ながめわびそれとはなしにものぞ思ふ雲のはたての夕暮れの空(左衛門督通光)
くれなゐに涙の色のなりゆくをいくしほ(入)までと君に問はばや(道因法師)
覚めてのち夢なりけりと思ふにも逢ふはなごりのをしくやはあらぬ(後徳大寺左大臣)
身にそへるその面影も消えななむ夢なりけりと忘るばかりに(摂政太政大臣)
なき名のみ立田の山に立つ雲のゆくへも知らぬながめをぞする(権中納言俊忠)
逢ふことのむなしき空の浮雲は身を知る雨のたよりなりけり(惟明親王)
思ふには忍ぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ(業平朝臣)
夕暮れに命かけたるかげろふのありやあらずや問ふもはかなし(読人しらず)
君来(こ)むといひし夜ごとに過ぎぬれば頼まぬものの恋ひつつぞ経(ふ)る(読人しらず)
つらしとは思ふものから伏柴(ふししば)のしばしもこりぬ心なりけり(左衛門督家通)
恋ひ死なむ命はなほも惜しきかなおなじ世にあるかひはなけれど(刑部卿頼輔)
言の葉のうつろふだにもあるものをいとど時雨のふりまさるらむ(伊勢)
くまもなき折しも人を思ひ出でて心と月をやつしつるかな(西行法師)
いくめぐり空ゆく月も隔てきぬ契りし中はよその浮雲(左衛門督通光)
今はただ心のほかに聞くものを知らずがほなる荻の上風(式子内親王)
草枕結び定めむ方(かた)知らずならはぬ野辺の夢の通ひ路(雅経)
さりともと待ちし月日ぞうつりゆく心の花の色にまかせて(式子内親王)
掻きやりしその黒髪の筋ごとにうち臥すほどは面影ぞ立つ(定家)
夢かとよ見し面影も契しも忘れずながらうつつならねば(皇太后宮大夫俊成女)
いかにしていかにこの世にありへ(経)ばかしばしもものを思はざるべき(和泉式部)
梅の花香をのみ袖にとどめおきてわが思ふ人は訪れもせぬ(業平朝臣)
雲居より遠山鳥の鳴きてゆく声ほのかなる恋もするかな(凡河内躬恒)
人ならば思ふ心をいひてましよしやさこそはしづのをだまき(藤原惟成)
見てもまたまたも見まくのほしかりし花の盛りは過ぎやしぬらむ(藤原高光)
思ひきや別れし秋にめぐり逢ひてまたもこの世の月を見むとは(皇太后宮大夫俊成)
ながめして過ぎにし方を思ふまに峰より峰に月は移りぬ(入道親王覚性)
老いぬともまたも逢はむとゆく年に涙の玉を手向けつるかな(皇太后宮大夫俊成)
一筋に馴れなばさてもすぎの庵(いほ)によなよな変る風の音かな(右衛門督通具)
命さへあらば見つべき身のはてを偲ばむひとのなきぞかなしき(和泉式部)
數ならぬ身をも心の持ちがほにうかれてはまた帰り来にけり(西行法師)
おろかなる心の引くにまかせてもさてさはいかにつひの思ひは(西行法師)
憂きながらあればある世にふる里の夢をうつつにさましかねても(読人しらず)
ささがにの空にすがくもおなじことまたき宿にも幾代かは経む(僧正遍照)
数ならぬ身を何ゆゑに恨みけむとてもかくても過ぐしける世を(大僧正行尊)
願はくは花の下にて春死なむそのきさらぎの望月の頃(西行法師)
世の中はとてもかくても同じこと宮も藁屋もはてしなければ(蟬丸)
夢や夢現や夢とわかぬかないかなる世にか覺めむとすらむ(赤染衞門)
闇鉇れて心のそらにすむ月は西の山辺や近くなるらむ(西行法師)
なお『古今和歌集』については触れた。
参考文献;
久保田淳訳注『新古今和歌集』(角川ソフィア文庫Kindle版) |
|
異化 |
| 稲垣足穂『稲垣足穂作品集』を読む。
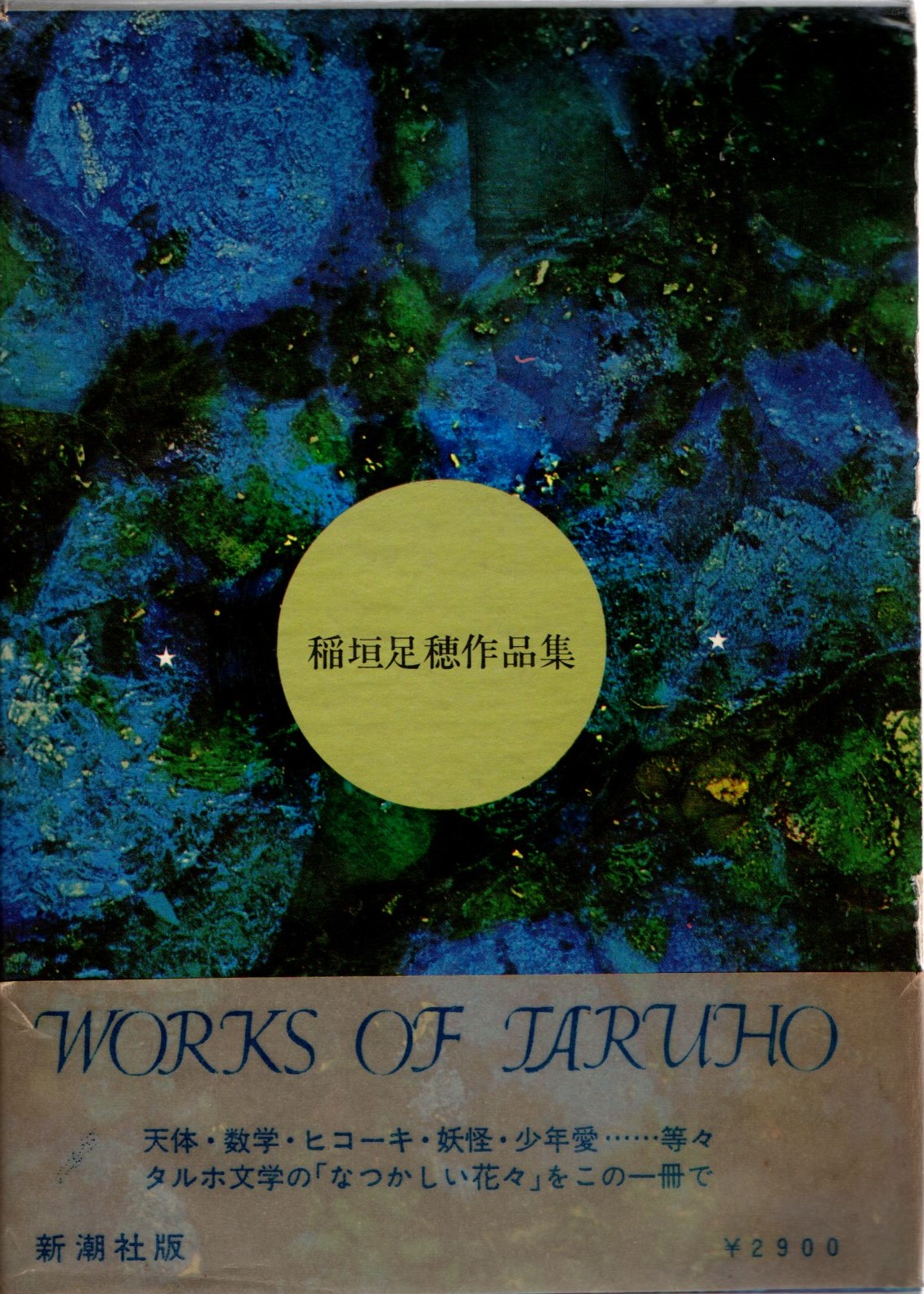
本書に所収されているのは、
チョコレット、
星を造る人、
黄漠奇聞、
星を売る店、
一千一秒物語、
セピア色の村、
煌めける城、
天体嗜好症、
夜の好きな王様の話、
第三半球物語、
きらきら草紙、
死の館にて、
弥勒、
悪魔の魅力、
彼等、
随筆ヰタ・マキニカリス、
紫の宮たちの墓所、
日本の天上界、
澄江堂河童談義、
イカルス、
A感覚とV感覚、
僕の触背美学、
古典物語、
美のはかなさ、
僕の弥勒浄土、
僕の“ユリーカ"、
山ン本五郎左衛門只今退散仕る、
Prostata-Rectum機械学、
少年愛の美学
である。残念ながら、足穂のもう一つの世界、
宇宙、
に関わるものがほとんどない。昔に読んだ記憶では、
松岡正剛編・稲垣 足穂『人間人形時代』(工作舎)
という本があり、本の真中に穴のあけられた、ちょっと変わった装丁の本であった。
閑話休題、
本書では、
黄漠奇聞、
彌勒、
が面白く、世評高い、
一千一秒物語、
のこじゃれた世界は、僕には、いま一つであった。
彌勒、
には、鴎外の『澀江抽斎』が試みた、
(作品を)書くことを書く、
ということが作品になる、という方法を試みているが、石川淳の『普賢』と同様、どこかで、うつつの側の自分の物語の方へシフトしていってしまったというように見える。
彌勒、
については、大岡昇平他編『存在の探求(上)(全集現代文学の発見第7巻)』で、埴谷雄高『死霊』、北條民雄『いのちの初夜』、椎名麟三『深夜の酒宴』を比較して、触れたことがある。
埴谷雄高『死霊』が、存在とのかかわりを、自己意識側から、広げるだけ広げて見せたというところは、他に類を見ない。特に、一〜三章は、文章の緊張度、会話の緊迫度、無駄のない描写等々、のちに書き継がれた四章以降とは格段に違う、と僕は思う。
俺は、
と言って、
俺である、
と言い切ることに「不快」という「自同律の不快」とは、埴谷の造語であるが、少し矮小化するかもしれないが、
自己意識の身もだえ、
と僕は思う。埴谷は、自己意識の妄想を極限まで広げて見せたが、「存在」との関わり方には、
自分存在に限定するか、
世界存在に広げるか、
その世界も、
現実世界なのか、
或いは、
自然世界なのか、
で、方向は三分するように思う。『いのちの初夜』は、自分の癩に病にかかったおのれに絶望して、死のうとして死にきれず、
「ぬるぬると全身にまつわりついてくる生命を感じるのであった。逃れようとしても逃れられない、それはとりもちのような粘り強さ」
の生命を意識する。そして同病の看護人の佐柄木に、
「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです」
と言われる。その生命そのものになった己を受け入れよ、と言われる。
「あなたは人間じゃあないんです。あなたの苦悩や絶望、それがどこからくるか、考えてみて下さい。ひとたび死んだ過去を捜し求めているからではないでしょうか」
似た発想は、稲垣足穂『彌勒』にもある。主人公、
「江美留は悟った。波羅門の子、その名は阿逸多、いまから五十六億七千万年の後、竜華樹下において成道して、さきの釈迦牟尼の説法に漏れた衆生を済度すべき使命を託された者は、まさにこの自分でなければならないと」
ここにあるのは、自己意識の自己救済の妄想である。しかし、それは、椎名麟三『深夜の酒宴』の、叔父の用意した紅白の、輪を作った綱を示されて、
「咄嗟に思いついて、その綱の輪を首にかけた。そしてネクタイでも締めるようにゆるく締めてから二、三度首を振った」
主人公の、現状の悲惨な状況を無感動に受けいれているのと、実は何も変わってはいない。
「そのとき、突然僕は時間の観念を喪失していた。僕は生まれてからずっとこのように歩きつづけているような気分に襲われていた。そして僕の未来もやはりこのようであることがはっきり予感されるのだった。僕はその気分に堪えるために、背の荷物を揺り上げながら立止った。そして何となくあたりを見廻したのだった。すると瞬間、僕は、以前この道をこのような想いに蔽われながら、ここで立止って何となくあたりを見廻したことがあるような気がした。……この瞬間の僕は、自分の人生の象徴的な姿なのだった。しかもその姿は、なんの変化も何の新鮮さもなく、そっくりそのままの絶望的な自分が繰り返されているだけなのである。すべてが僕に決定的であり、すべてが僕に予定的なのだった。……たしかに僕は何かによって、すべて決定的に予定されているのである。何かにって何だ―と僕は自分に尋ねた。そのとき自分の心の隅から、それは神だという誘惑的な甘い囁きを聞いたのだった。だが僕はその誘惑に堪えながら、それは自分の認識だと答えたのだった」
と、「認識」と己に言い切らせる限りで、自己意識は、まだおのが矜持を保っているが、それはそのまま今のありように埋もれ尽くすという意味では、より絶望的である。それは、
絶望を衒う、
といってもいい。
それにしても、しかし、いずれも、『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャのように、
神の作ったこの世界を承認することができない、
という、
「僕は調和なぞほしくない。つまり、人類に対する愛のためにほしくないというのだ。僕はむしろあがなわれざる苦悶をもって終始したい。たとえ僕の考えが間違っていても、あがなわれざる苦悶と癒されざる不満の境に止まるのを潔しとする」
境地から後退してしまうのだろう。埴谷も椎名も、ともに投獄の経験を持ち、そこから後退したところで、身もだえしているように見える。確かに、
戦いの痕跡、
はある。しかしそれで終わっていいのだろうか。そこには、日本的な、余りにも日本的な、
自己意識の自足、
か、
自然への埋没、
か、
しか選択肢はないのだろうか。今日の日本の現状を併せ考えるとき、暗澹たる気持ちになる。
山ン本五郎左衛門只今退散仕る、
については、種村季弘編『日本怪談集』で触れた。この元となったのは、堤邦彦『江戸の怪異譚―地下水脈の系譜』でも触れた、
「江戸時代中期の日本の妖怪物語『稲生物怪録』に登場する妖怪。姓の『山本』は、『稲生物怪録』を描いた古典の絵巻のうち、『稲生物怪録絵巻』を始めとする絵巻7作品によるもので、広島県立歴史民俗資料館所蔵『稲亭物怪録』には『山ン本五郎左衛門』とある。また、『稲生物怪録』の主人公・稲生平太郎自身が遺したとされる『三次実録物語』では『山本太郎左衛門』とされる」
という話が基ネタである。まだ元服前、十六歳の「稲生平太郎」が、我が家に出没する妖怪変化に対応し、大の大人が逃げたり寝込んだりする中、「相手にしなければいい」と決め込んで、ついに一ヶ月堪え切り、相手の妖怪の親玉、山ン本五郎左衛門をして、
「扨々、御身、若年乍ラ殊勝至極」
と言わしめ、自ら名乗りをして、
「驚かせタレド、恐レザル故、思ワズ長逗留、却ッテ当方ノ業ノ妨ゲトナレリ」
と嘆いて、魔よけの鎚を置き土産に、供廻りを従えて、雲の彼方へと消えていく。この、肝競べのような話が、爽快である。
山本五郎左衛門、
については、「山本五郎左衛門」に詳しい。
本書の眼目は、
A感覚とV感覚、
Prostata-Rectum機械学、
少年愛の美学、
だろう。僕自身にはちょっとついていき兼ねるところがあるが、とりわけ、
少年愛の美学、
は、
歴史の異化、
といってもいいものになっていて、言わば、常識で知っている歴史を、その多層の深部から、手セラ氏出して見せたという感じがある。ただ、惜しいかな、初めから、Oと管となっている
A、
優位の結論があり、PもVも添え物であるということを、それこそ、博引傍証の限りを尽くして詳述しているきらいがあり、読むほどに深まるというよりは、並列的な記述になっているところが、難点と言えば難点ではある。
参考文献;
稲垣足穂『稲垣足穂作品集』(新潮社) |
|
武家の実像 |
| 武士生活研究会編『図録近世武士生活史入門事典』を読む。
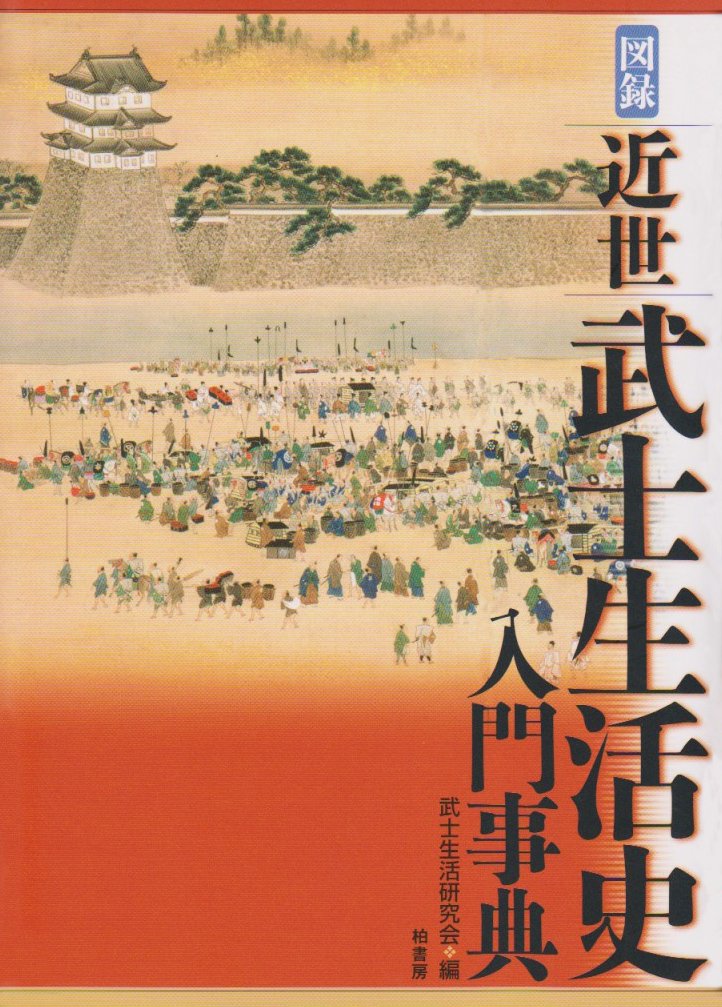
本書は、武家、殊に江戸時代の武家の、
身分、職制、
服装、
儀礼と儀式、
政治、
経済生活、
居住、
食生活、
女性、
教育、
文化、娯楽、
などと、生活全般の、実情を網羅したものになっている。
特に、その収入と生活をみると、
定収入である、
禄、
と、
役職に伴う、
役高、
とがあるが、たとえば、
二百石、
の家禄のものだと、仮に、
四公六民、
として、
八十石、
が取り分になる。これを俵に直すと、四斗俵で、
二百俵、
となる。元和(1615〜24)の頃だと、米一石が銀二十匁、この頃、
銀五十匁を一両、
としたので、
一両で、二百五十斗、
という相場になる。これが、元禄(1688〜1704)だと、
銀六十匁が一両、
で、慶應元年(1865)だと、
一石が七両二分、
に高騰、最下層の武家の、
三両一人半扶持(これが、三一(さんぴん)侍と悪口の謂れ)、
では、江戸初期なら、
米八石、
買えたのが、幕末では、
五斗、
の米がやっと買える状態になる。仮に、中頃の、
一石一両、
と考えても、二百石で、
八十両、
の収入で、これで、
家族・武家奉公人、
を養うのである。
江戸時代、
百石、
の侍は、登下城、公用などの外出時、
槍一筋を供に持たせ、草履取(戦時には主人の必要品を持つ)の二人の供(武家奉公人)、
で、主人は徒(かち)である。これ以下は、
自前の槍ではなく、御貸槍、
で、戦時以外は槍を持てない。
騎乗できるのは、
二百石以上、
で、江戸幕府規定の、
軍役による着到(陣触れにより参陣すること)の軍規、
では、
侍一人、槍持一人、馬の口取一人、甲冑持一人、小荷駄一人、
の五人を連れる。
この収入では、
登城に必要な槍持、草履取の二、三人、
を雇うのが限度であった。
三百石、
となると、かなり上級の収入であるが、軍役では、
侍一人、槍持一人、馬の口取一人、挟箱持一人、甲冑持一人、小荷駄一人、
という規定になり、
七人、
を抱えなくてはならない。一例では、
実収入百二十石、
で、
ほぼ、
百二十両、
主人一家、家来の食費 四十五両、
家来への給金 三十八両、
諸雑費 四十両、
主人一家の衣物代 三十両、
で、
三十三両、
の赤字となる。三百石でこれである。あとは、推して知るべしである。
武家の家計は、いわば、慢性的な赤字になっており、中下級武士は、
屋敷内を畑にするなどして、副食品の自給自足をはかり、
微禄のものは、
内職に精を出す、
ということになる。
身分制なので、
服装、
から、
儀礼、
まで、規定があり、
席、
の位置から、
お辞儀の仕方、
まで定められ、窮屈なものであった。たとえば、
貴人に対する挨拶、
は、
貴人へ拝礼するにはわが付すべき座席のすこし手前にひざまづき左のひざより三足すりより平伏す、両手先左右の饟およそ三寸くびよりひざを凡五寸にして首を畳に附くべし、
とある。
参考文献;
武士生活研究会編『図録近世武士生活史入門事典』(柏書房)
笹間良彦『図説 日本戦陣作法事典』(柏書房) |
|
スペクトラム |
| 小林憲正『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』を読む。

生命を維持するのに欠かせないタンパク質が、偶然にできる確率は、
10の四万乗分の1
と試算され(フレッド・ホイル)、生命誕生には、
「多数のヌクレオチド(核酸を構成する単位)を結合させたリボ核酸、いわゆるRNAが必要とされている」(序章)
が、
「条件を満たすRNAをつくるには、ヌクレオチドを40個、正しい順番でつなぐ必要があります。」
が、それが地球系で偶然できる確率は小さく、そこで宇宙での発生を考えると、
10の40乗個、
ほどの恒星があれば、「何とか偶然にRNAがひとつできる(戸谷友則)というが、銀河系には、
4000垓(4×10の23乗)、
の恒星、惑星も、
數秭(ジョ 10の24乗)、
あり、地球で生命が誕生したのは奇跡とされる(仝上)。そんな中で、本書は、
「生命とは何か、生命はいかに誕生したか」を、古代から近年までの研究の流れを説明し(第1〜4章)、
生命誕生のシナリオとしての「RNAワール」に代わりうるモデルとして、「がらくたワールド」を提案する(第5章)。
さまざまな生命の起源説を調べる手がかりとして、「宇宙」というタイムマシンがあり、生命の誕生、進化のさまざまなステップは、この宇宙のどこかに現在進行形で存在している、その可能性を探しに行き(第6章)、
生命誕生のプロセスについては、「化学進化」概念が主流になっているが、その正しい理解のために「生物進化」を参考にしつつ(第7章)、
最後に、生命と非生命のあいだをどう埋めればよいかを考える(第8章)、
という流れで、
生命と非生命のあいだ、
をつなぎ、
両者はデジタル的に0と1に区分できるものではなく、スペクトラムに、連続的につながっている、
として、
生命スペクトラム、
という結論を述べていく。
地球上の生命の特徴は、
第一に、地球生命は水と有機物に依存したものです。これが大前提です。
第二に、地球生命は外界と区別する「細胞膜」を持っています。細胞膜はおもにリン脂質でつくられています。
第三に、地球生命は細胞膜の中で化学反応を行います。これは「代謝」とよばれます。代謝は、酵素というタンパク質が触媒となって、コントロールされています。
第四に、地球生命は「自己複製」を行うことにより、増殖します。
第五に、地球生命は環境の変動に応じて「進化」(変異)します。
とし、
「最後の2つ(第四と第五)が可能になるのは、核酸のおかげです。」、
とする(第1章)。で、「地球型」生命の誕生には、
リン脂質、
タンパク質、
核酸、
が必要で、
「とりわけタンパク質と核酸は、両者がともにそろわなければ生体内でつくることができないものであり、地球生命
の根源をなす分子と考えられます。」
ので、生命の起源研究では、
タンパク質と核酸の起源が最重要課題、
と考えられてきた。しかし、これは、
あくまでも地球生命の「特徴」であって、「条件」ではない、
ので、
全く異なる生命がないとは言えない。しかし、生命の基本である、
自己複製、
などを考えた時、
「自己触媒により自分自身を作り出す」
という可能性があり、
細胞膜、
も、
「有機体の凝集体(他の分子をすきまにはさんだもの)から、きれいな膜状のもの、さらに現在の細胞膜のように膜外から必要なものを取り込んだり、不要なものを外に出したりできる高性能のものまで」(第8章)、
さまざまなレベルがある。そう考えると、完成体の、
生命、
からではなく、
非生命、
から、
スペクトラムとして連続的に(アナログ的に)存在している状態、
を考えた時、
生命、
の概念も変わるのではないか、そんな気がした。
参考文献;
小林憲正『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックスKindle版)
|
|
身体から精神へ |
|
市川浩『精神としての身体』を読む。
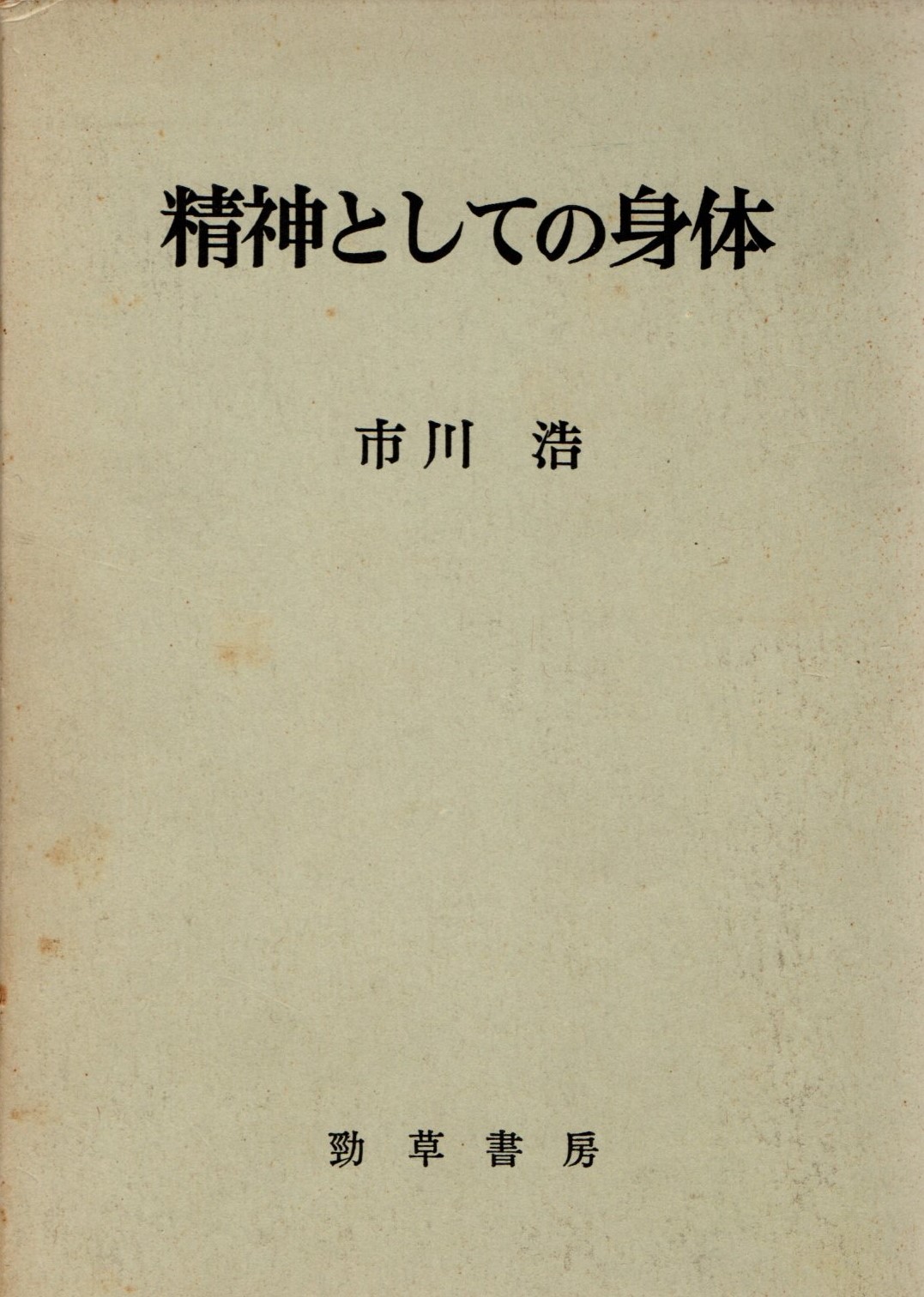
何度目だろう。判型が変わり、文庫になっても読んだ。しかし、読み直してみると、若い頃、なぜ熱中し、何度も読みたいと思ったのかがわからない。1975年初版の、半世紀前ということもあるので、多少の古さを感じることもあるにしても、この論旨のたどり方の、機能的な分解の仕方は、どうも、いま読み直すと、機械的すぎる気がしないでもない。
本書は、コギトではないが、意識や精神から身体を見るのではなく、
身体から精神へ、
と辿っていくところに、新しさがある。
現象としての身体、
で、
主体としての身体、
客体としての身体、
渡しの対他身体、
他者の身体、
と、身体感覚をたどり、
構造としての身体、
で、身体の外部指向の、
向性的構造、
志向的構造、
という、外界への、
はたらきという構造、
を通して、
他者、
と関わる。このとき、
「他者は、私が自分を私として認識するための条件であるとともに、私としての私が存在するための条件である。私は他者を自分の存在条件として発見するのである。このような相互主観性の世界は、私が他者を意識の対象としてとらえ、かつ自分が他者の意識の対象となっていることを自覚することをとおして把握される。前者は他者の対象身体を介して、後者は私にとっての私の対他身体を介して了解されるのであり、両者の背後には、私の主観身体と他者の主観身体の把握が潜在している。それゆえ自己あるいは他者を意識の対象としてとらえることは、自己あるいは他者を主観性としてとらえることと矛盾しない、むしろそれは相互主観性の世界が成立するための条件でさえある。」
こうした身体の側の外界への「はたらき」かけを通して、
共可能性、
地化、
図化、
変換、
中心化、
脱中心化、
同調、
組み込み、
と、現実が構造化される。こうした、
「生成的構造はさまざまのレベルで統合されるから、現実の人間は、抽象的射像としての身体や精神に接近したり、それから離れたりする。……たとえば睡眠や病気(ことに精神障害)の場合、人間は身体的となる。質的および量的に環境がせまくなり、体験の統一性が失われ、自由に態度を転換することがむずかしくなる。逆に統合のレベルが高まり、脱中心化がすすむ場合には、われわれは精神的になる。私は自分を自由の中心と感じ、全人格的に充実した統一体として自己をとらえる。しかしきわめて精神的なはたらきとされている認識にしても、それがわれわれにとって真理をめざすかぎり、世界との身体的かかわりをはなれてはありえない。世界が物体的なものをふくんでいるかぎり、身体と必然的にむすびついていない純粋精神は、世界を認識することができないであろう。」
とし、ここで、タイトルである、
精神としての身体、
に行き着き、
「身体が精神である。精神と身体は、同一の現実につけられた二つの名前にほかならない。それはデカルトが、二元論的な立場からではあるが、精神は身体の一部に(たとえば脳髄に)他の部分をさしおいてやどっているわけではなく、身体と全面的に合一し、あたかも一つの全体をなしているとのべたとき、いいありらわそうとした事態である。〈はたらきとしての身体〉が、あるレヴェルの統合を達成し、『身体が真に人間の身体となった』とき、精神と身体はもはや区別されない。『精神』と『身体』は、人間的現実の具体的活動のある局面を抽象し、固定化することによってあたえられた名前である。」
として、日本語の、
身にしみる、
身を入れる、
身になってみる、
身につまされる、
と使う、
身(み)、
ということばを例に、
「『身』は、単なる身体でもなければ、精神でもなく……精神である身体、あるいは身体である精神としての〈実存〉を意味する」
と集約する。その、
精神としての身体、
のもたらす、
行動としての構造、
として、
道具、
や、
言語、
という、
仲立ち、
を介して、身体の延長として駆使して、世界へ働き掛けていく。その働きを、
癒着的形態の行動、
稼働的形態の行動、
シンボル的形態の行動、
とたどり、
時間、
や、
空間、
を広げていく姿を追う。
「人間は〈仲立ち〉によって、自分の生得的能力を拡大する。人間は自己の身体の感覚器系、運動器系、栄養器系、神経系、内分泌系などをモデルとして、その直接の外化、延長であるにとどまらず、用具としての普遍的機能をもった観測機械、動力機械、伝達機械、計算機械などをつくり、それらを介することによって、感覚し、はたらきかけることのできる世界をいちじるしく拡大してきた」
だけではなく、さらに、
想像の世界、
を、
映画、
テレビ、
で外在化し、さらには、ネットを通して、この世界の先に、
サイバー空間、
という別の世界まで現実化し、
映画『マトリックス』、
の世界では、どちらが原字なのかはわからなくなっているし、
アニメ『攻殻機動隊』、
では、
電脳空間と呼ばれる仮想空間や他者の電脳などの情報源に、自らの意識が入り込むことによって情報を得る、
ことまで可能となり、ついに、主人公、
草薙素子、
は、機械の身体を捨てて、
サイバースペース、
の中へ入ってしまった。
こう見ると、たしかに、本書の世界は古いが、しかし、この、
身体から精神へとアプローチ、
していくスタイルは新しく、このアプローチを現代の尖端までたどっていくと、
精神としての身体、
が意味することが、
サイバー空間、
では、文字通り、
身体としての精神、
が、文字通り、
精神としての身体、
に化していくことまで見通せるのに、改めて驚かされる。再々々々…読による新しい発見であった。
参考文献;
市川浩『精神としての身体』(勁草書房) |
| |
|
|