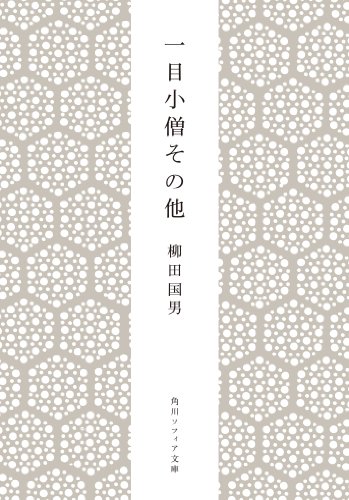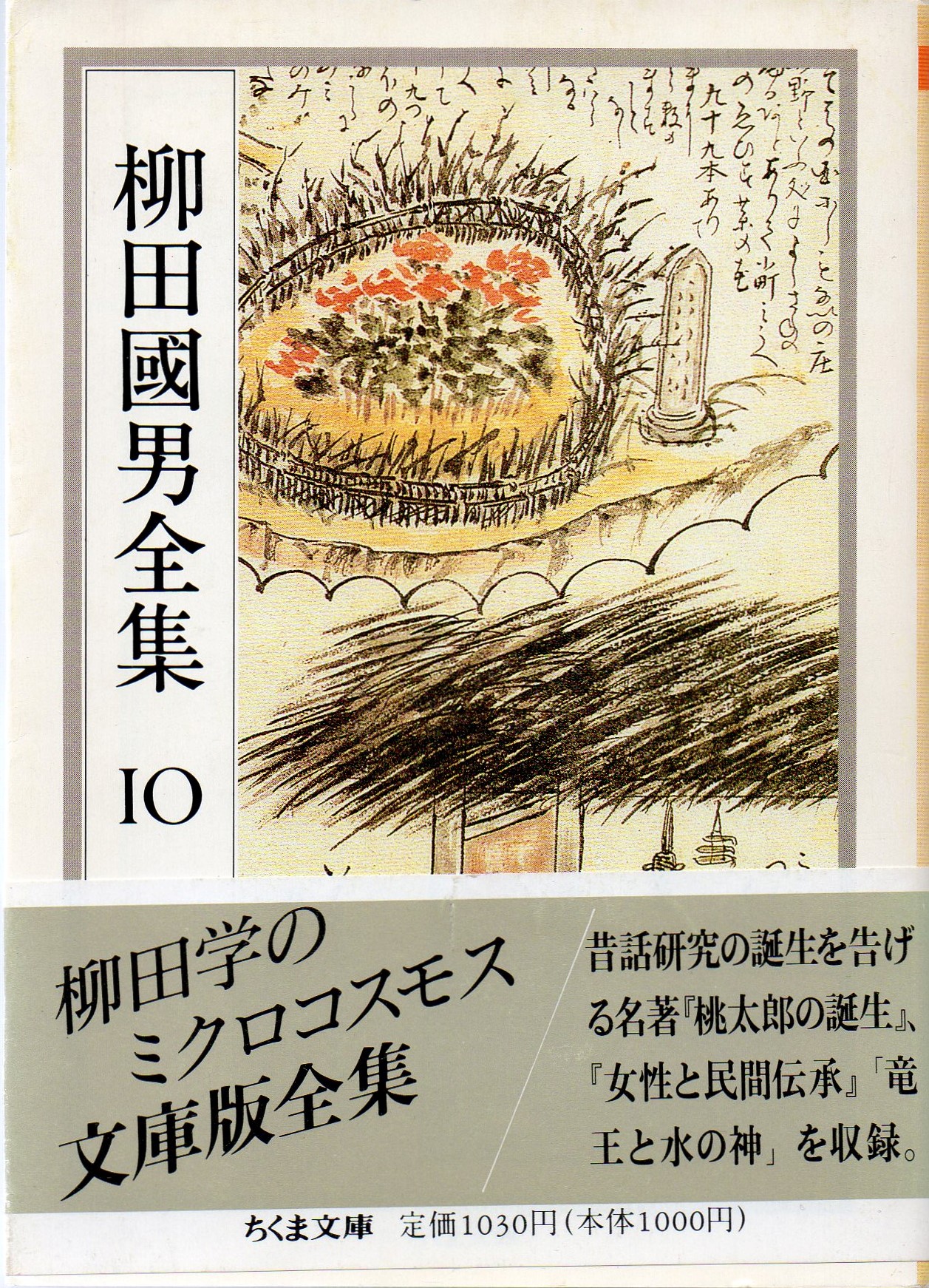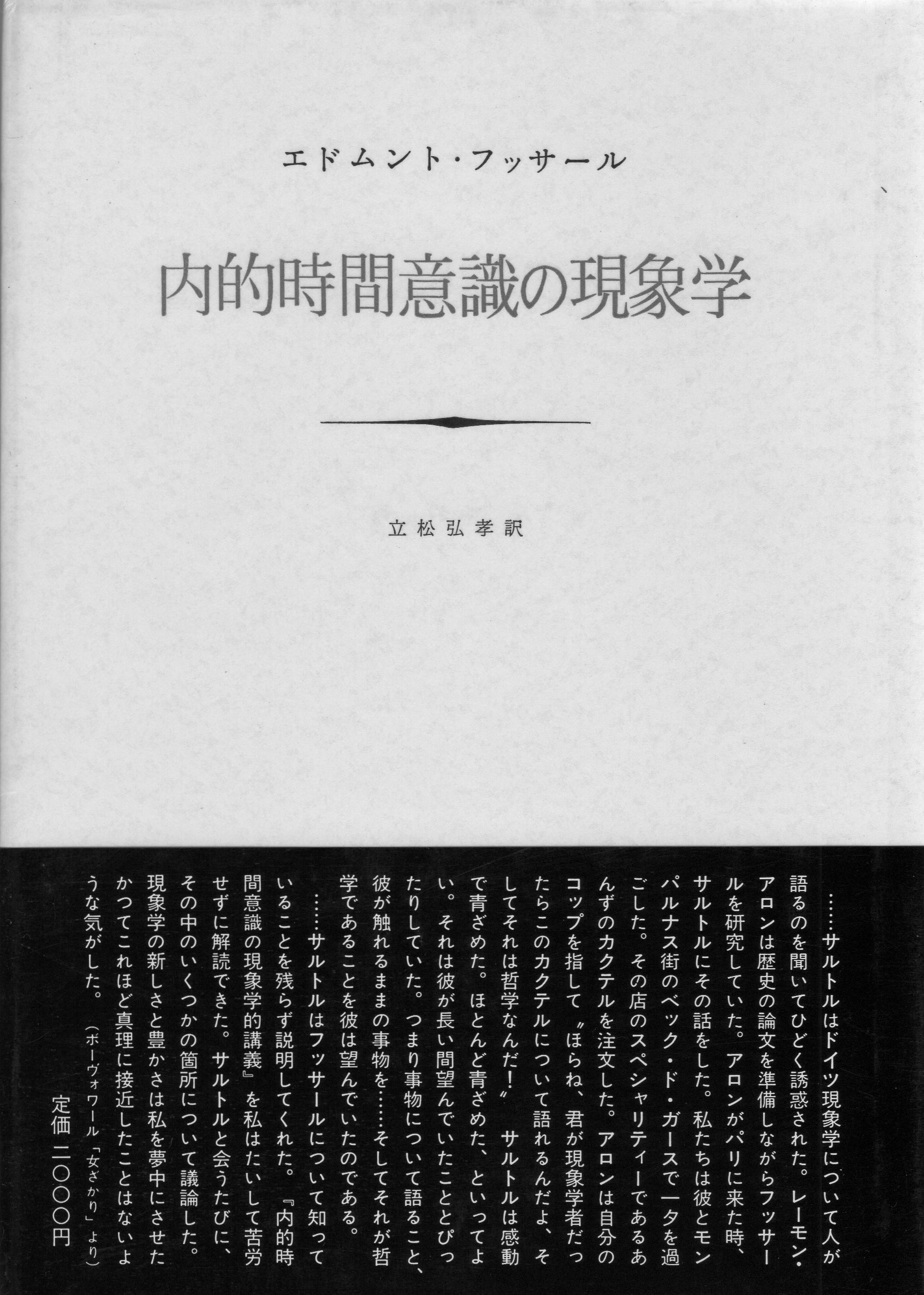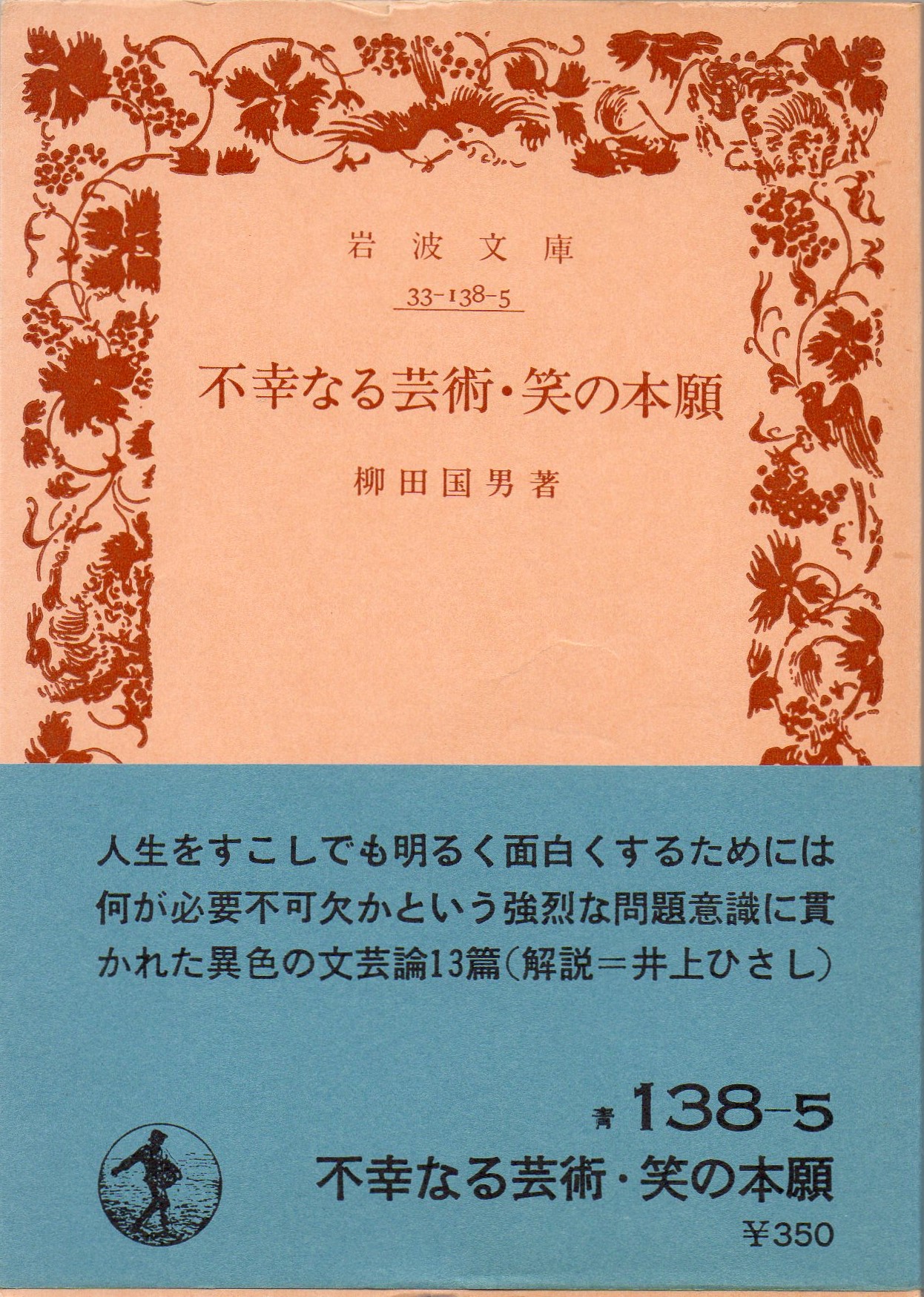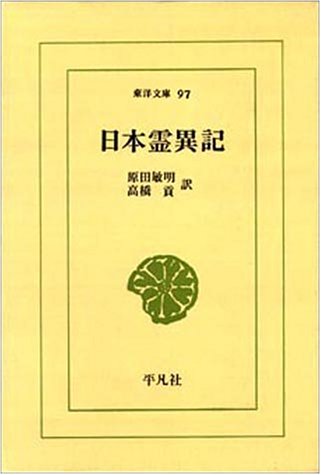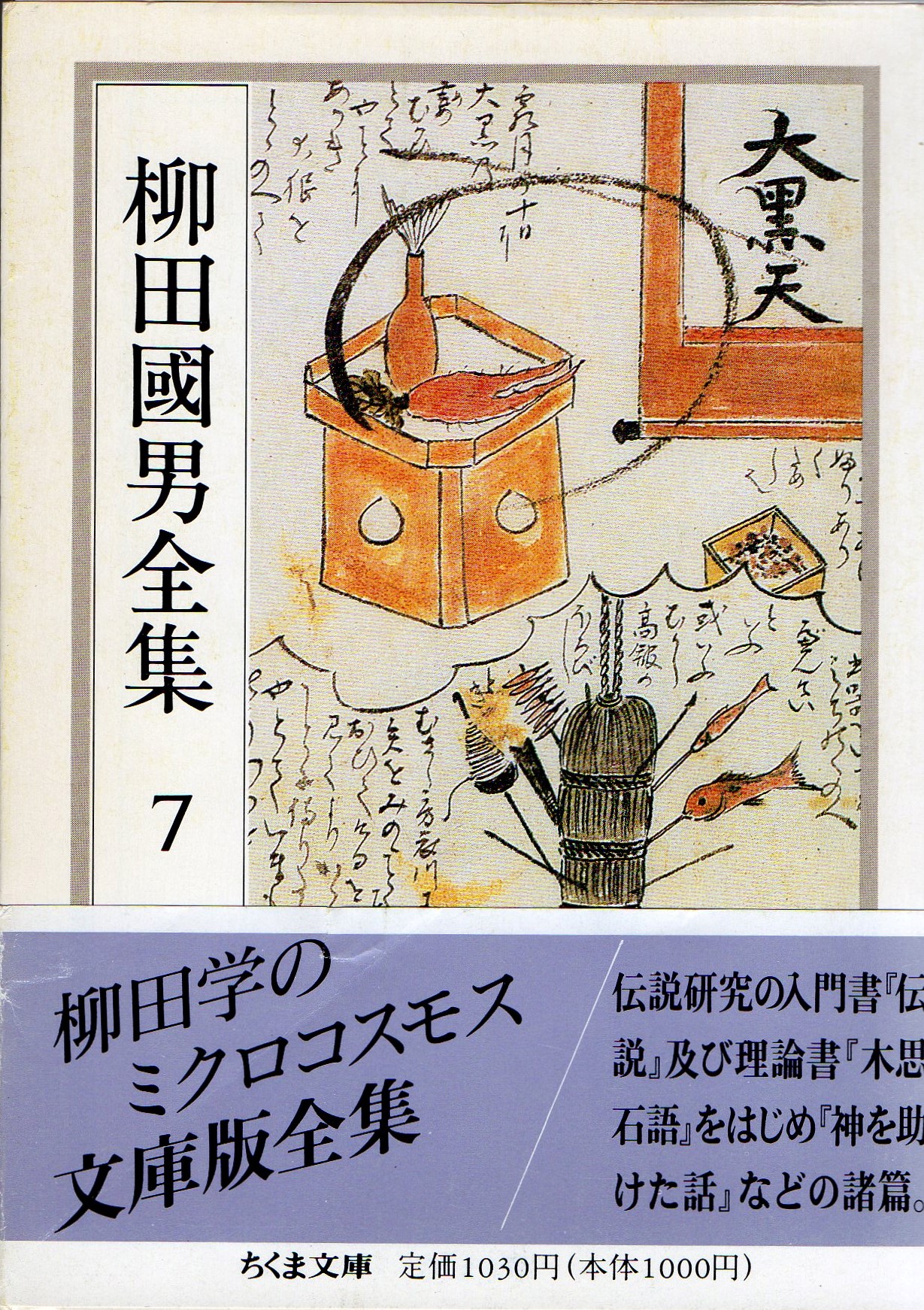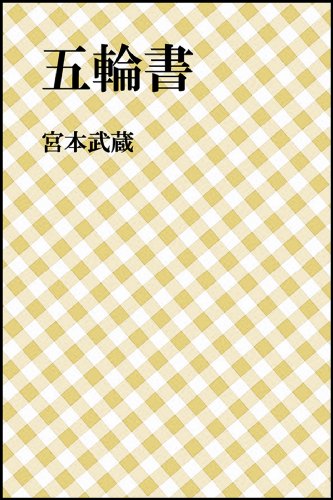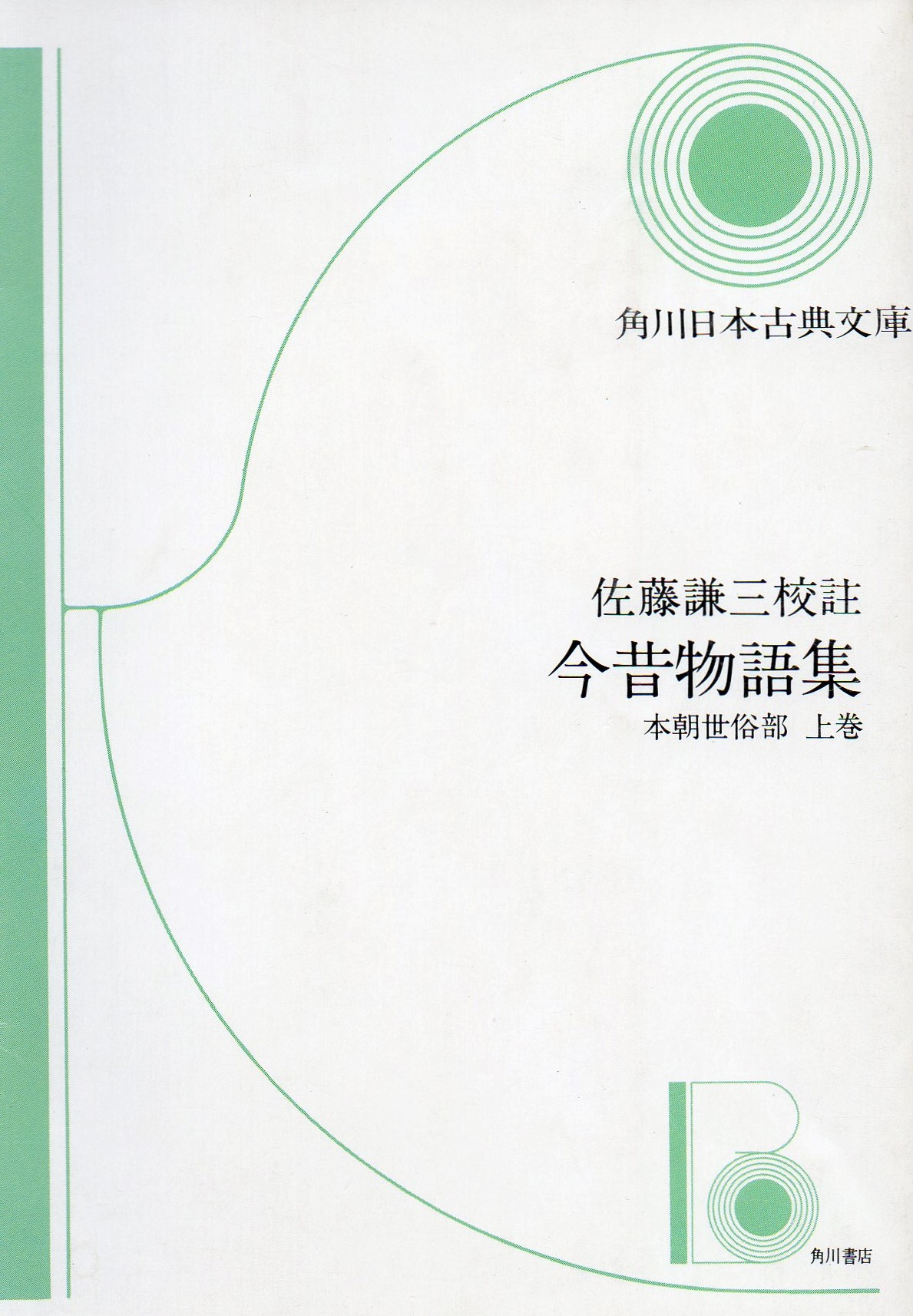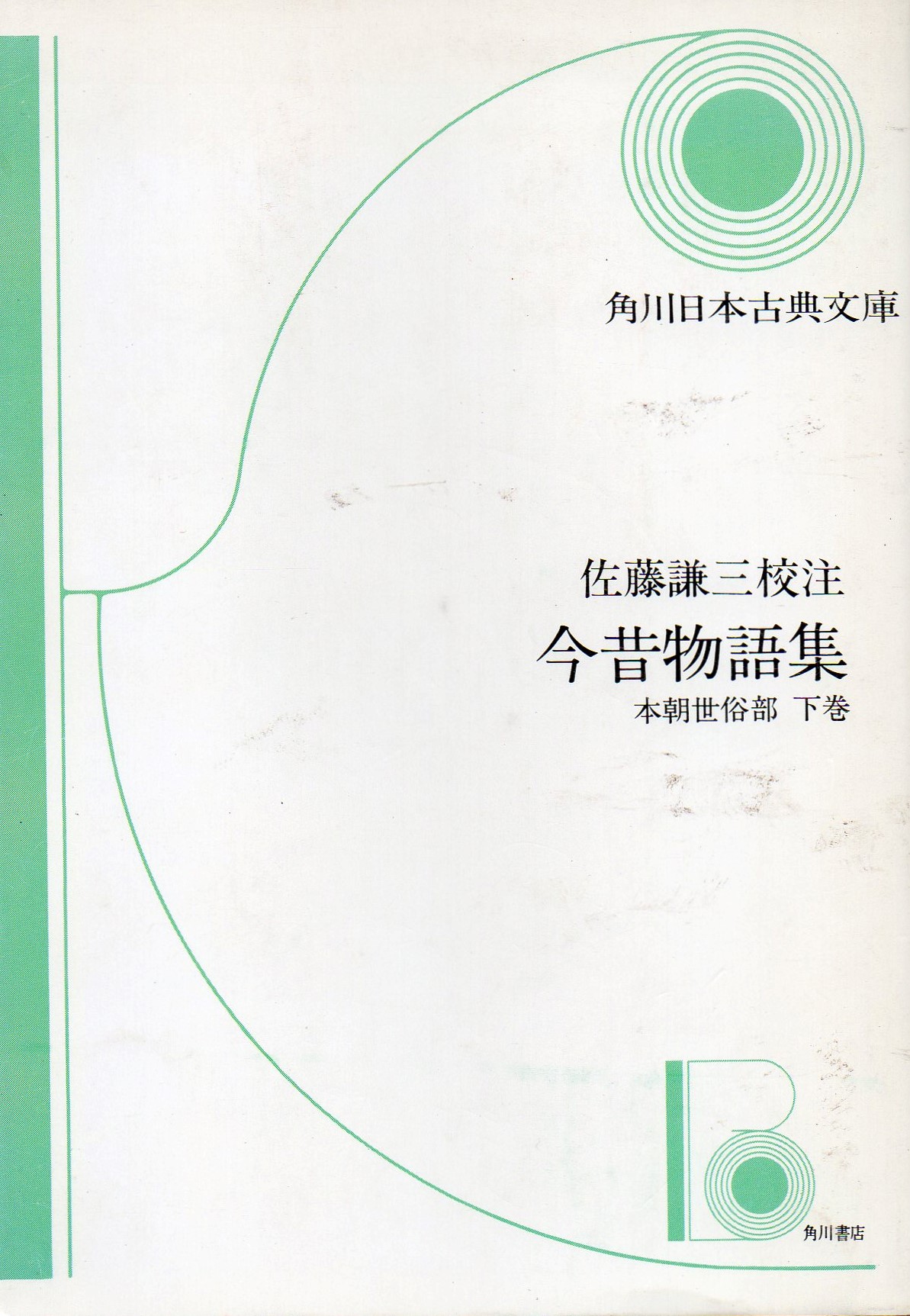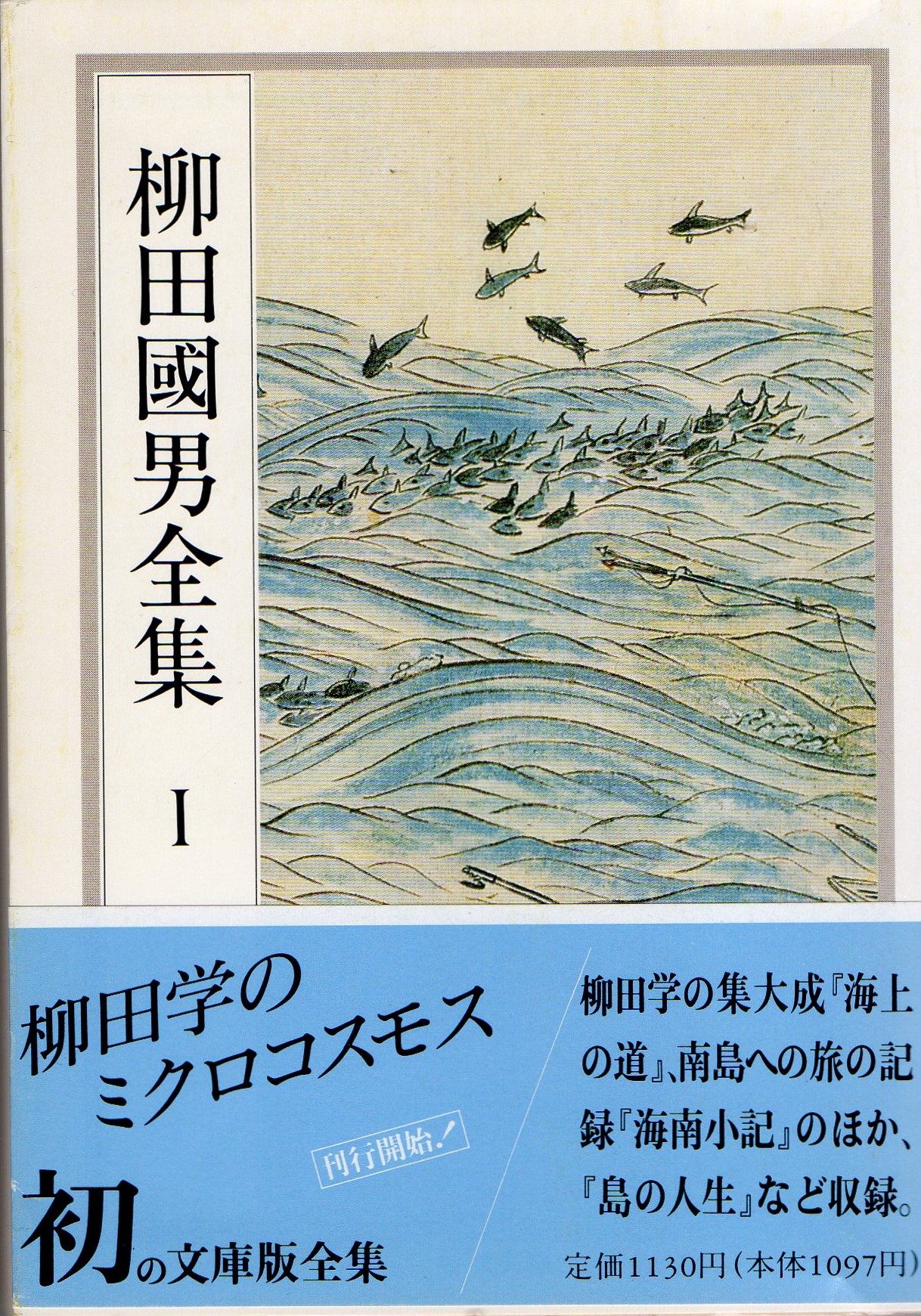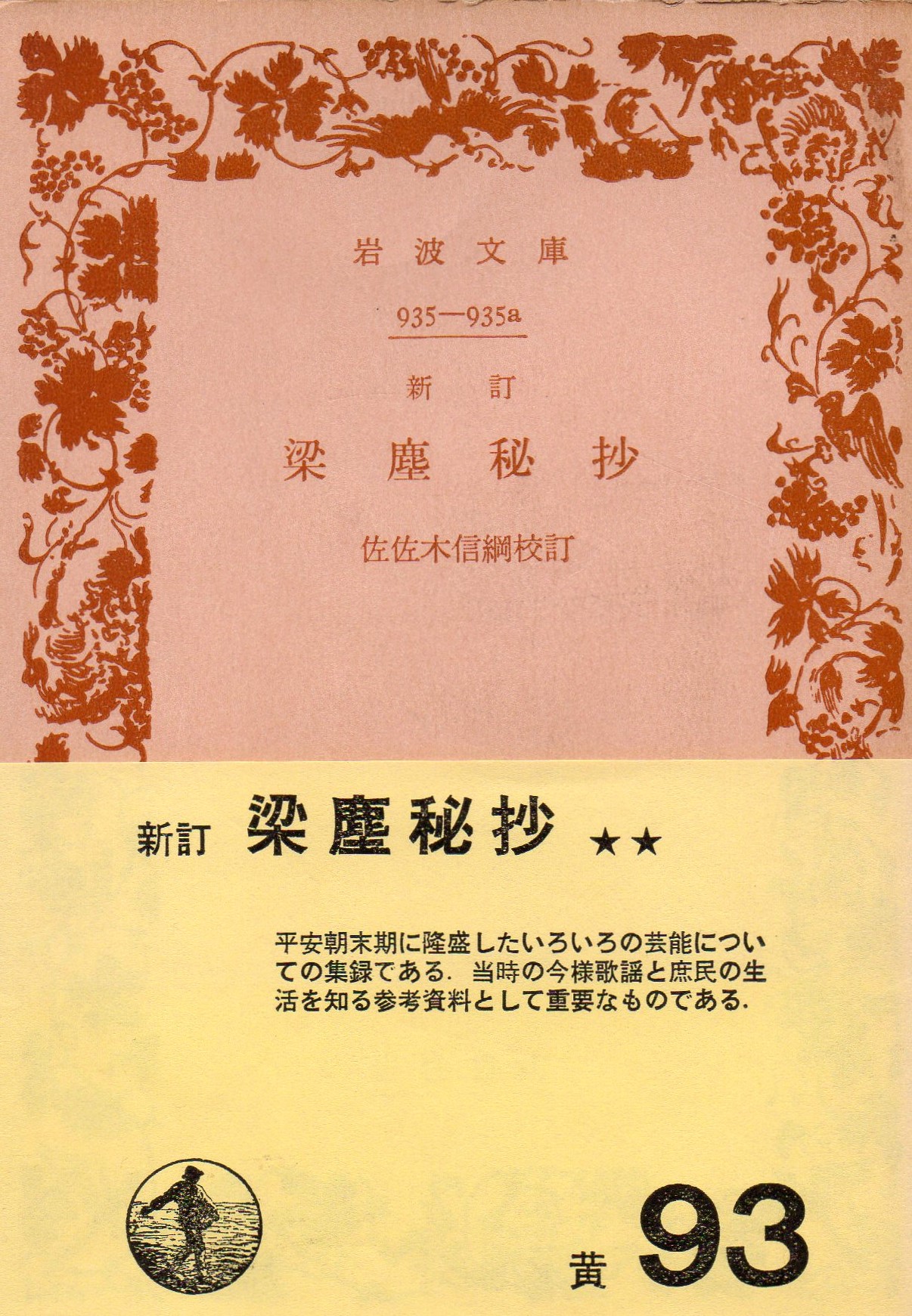|
零落した神 |
| 柳田國男『一目小僧その他』を読む。
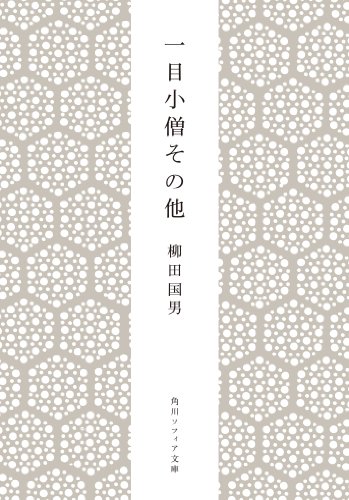
本書には、大まかにわけて、
一目小僧、
目一つ五郎考、
鹿の耳、
の御霊信仰、
橋姫、
の橋姫信仰、
隠れ里、
魚王行乞譚、
物言う魚、
の神霊譚、
流され王、
ダイダラ坊の足跡、
の異種神信仰、
餅白鳥に化する話、
熊谷弥惣左衛門の話、
の霊異信仰、
が掲載されている。一言で言うなら、
「一目小僧は多くの『おばけ』と同じく、本拠を離れ系統を失った昔の小さい神である。」(「一目小僧」)、
「それが次々にさらに畏き神々の出現によって、征服せられ統御せられて、ついに今日のごとく零落するに至ったので、ダイダばかりか見越し入道でも轆轤首でも、かつて一度はそれぞれの黄金時代を、もっていたものとも想像し得られるのである。」(ダイダラ坊の足跡)、
などというように、
信仰の対象であったものが零落し、妖怪と目されるようになっていく事例、
ということになる。その信仰が残っている間は、
伝説、
として語られる。もとは神聖なる神話であったかも知れないが、信仰の零落に伴って、伝説から信仰が失われると、やがて、
語り物、
あるいは、
昔話、
の形式となって語りつがれてゆくことになる(「物言ふ魚」)。
「説話と伝説との分界を、明らかにすることがことに必要である。説話は文芸だから、おもしろければ学びもしまねもしよう。伝説に至ってはとにかくに信仰である。万人がことごとく欺かれ、または強いられて、古きをすてて新しきに移ったとは思えぬ。外国の教法がこの土に根づくために、多くの養分日光をここで摂取したごとく、伝説もまたこれを受け入れて支持する力が、最初から内にあったがゆえに、これだけの発展をとげることが可能であったかも知れぬのである。伝説から信仰が失われると、あるものはやがてそれが語り物、あるいは昔話の形式となって語りつがれてゆく。」(魚王行乞譚)
だから、「日本伝説目録㈠」と名づけて、若き著者が、抜書き、整理したもののメモに、
「明に虚構と認めらるゝは如何におもしろくとも採らずただ迷信によりて伝はれるをのこし外国伝説のつくりかへ又とらず」
とあるという(小松
和彦「新版解説」)のも、その原則が早くから著者の基準にあったという証なのだろう。だから、
たとえば、
江戸本所の七不思議の一つ、足洗いという怪物、
というような、
「昔話にも、何か信仰上の原因があったのではないか」
と思う、とし、
「深夜に天井から足だけが一本ずつ下がる(という足洗という怪物も)。これを主人が裃で盥を採って出て、うやうやしく洗いたてまつるのだというなどは、空想としても必ず基礎がある。洗わなければならなかった足は、遠い路を歩んできた者の足であった。すなわち山を作った旅の大神と、関係がなかったとはいわれぬのである。」(ダイダラ坊の足跡)、
と推測するのである。また、たとえば、
「たいていは雨のしょぼしょぼと降る晩、竹の子笠を被った小さい子供が、一人で道を歩いているので、おうかわいそうに今ごろどこの子かと追いついてふり返ってみると、顔には目がたった一つで、しかも長い舌を出してみせる」(「一目小僧」)、
という、
一目小僧、
も、
「自分は主として一目の怪が、山奥においてその威力を逞しくしている事実に着眼して、実は最初にこれと昔の山の神の信仰との関係を、探ってみたいと思っているところなのである。
かく申せば何か神を軽しめて、一方には妖怪に対し寛大に失するように評する人があるか知らぬが、いずれの民族を問わず、古い信仰が新しい信仰に圧迫せられて敗退する節には、その神はみな零落して妖怪となるものである。妖怪はいわば公認せられざる神である。」(仝上)、
という問題意識から、
「ことによると以前はこれも山神の眷属にして、眇目ということを一つの特徴とした神の、なれの果てではないかと推測し、他の方面にも神の片目という例はないかどうか、あるならどういう様子かということを、参考のために調べてみるだけである。(中略)神様が一方の目を怪我なされたというのは、存外に数多い話である。」(仝上)
といった検索を経て、縷々事例を分析し、
「何か上代の天目一神(あめのまひとつのかみ)神話から筋を引いてるものがあるのではないか」(仝上)
などと勘案しつつ、
「(同じ例は多いが)いずれも水の神が魚のみか人の片目なる者をも愛し選んだという証拠であって、それはもちろん食物としてではなく、たぶんは配偶者、少なくとも眷属の一人に加える場合の、一つの要件のごときものであったのである」(目一つ五郎考)
として、
「一目小僧は多くの『おばけ』と同じく、本拠を離れ系統を失った昔の小さい神である。見た人がしだいに少なくなって、文字通りの一目に絵にかくようにはなったが、実は一方の目をつぶされた神である。大昔いつの代にか、神様の眷属にするつもりで、神様の祭の日に人を殺す風習があった。おそらくは最初は逃げてもすぐつかまるように、その候補者の片目をつぶし足を一本折っておいた。そうして非常にその人を優遇しかつ尊敬した。犠牲者の方でも、死んだら神になるという確信がその心を高尚にし、よく神託予言を宣明することを得たので勢力を生じ、しかもたぶんは本能のしからしむるところ、殺すには及ばぬという託宣もしたかも知れぬ。とにかくいつの間にかそれがやんで、ただ目をつぶす式だけがのこり、栗の毬や松の葉、さては矢に矧(は)いで左の目を射た麻、胡麻その他の草木に忌みが掛かり、これを神聖にして手触るべからざるものと考えた。」(一目小僧)
と推測していくのである。この成れの果てが、全国に散らばる、
片目・片足の怪物・妖怪、
片目の魚、
等々の説話として残ったと見たのである。
この仮説の是非も、その後の検証がなされたかどうかは知らないが、大胆な説である。
この説でふと思い出したが、戦国期、村同士の自力救済による抗争や戦国領主との対抗時、あらかじめ後処理の時の責任を取らせる犠牲者を決めておく、というのを読んだ記憶がある。村の貧しいものか、余所からの流れ者か、いずれにしても、その家族の面倒を後々まで村で見ることを約束して、そういう役につけたという。どこか、この「一目」の生贄に似た、村々の民の発想の底流のような気がしてならない。
なお、柳田國男の『遠野物語・山の人生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488108139.html)、『妖怪談義』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488382412.html)については別に触れた。
参考文献;
柳田國男『一目小僧その他』(Kindle版) |
|
神話への隘路 |
| 柳田國男「桃太郎の誕生」を読む。
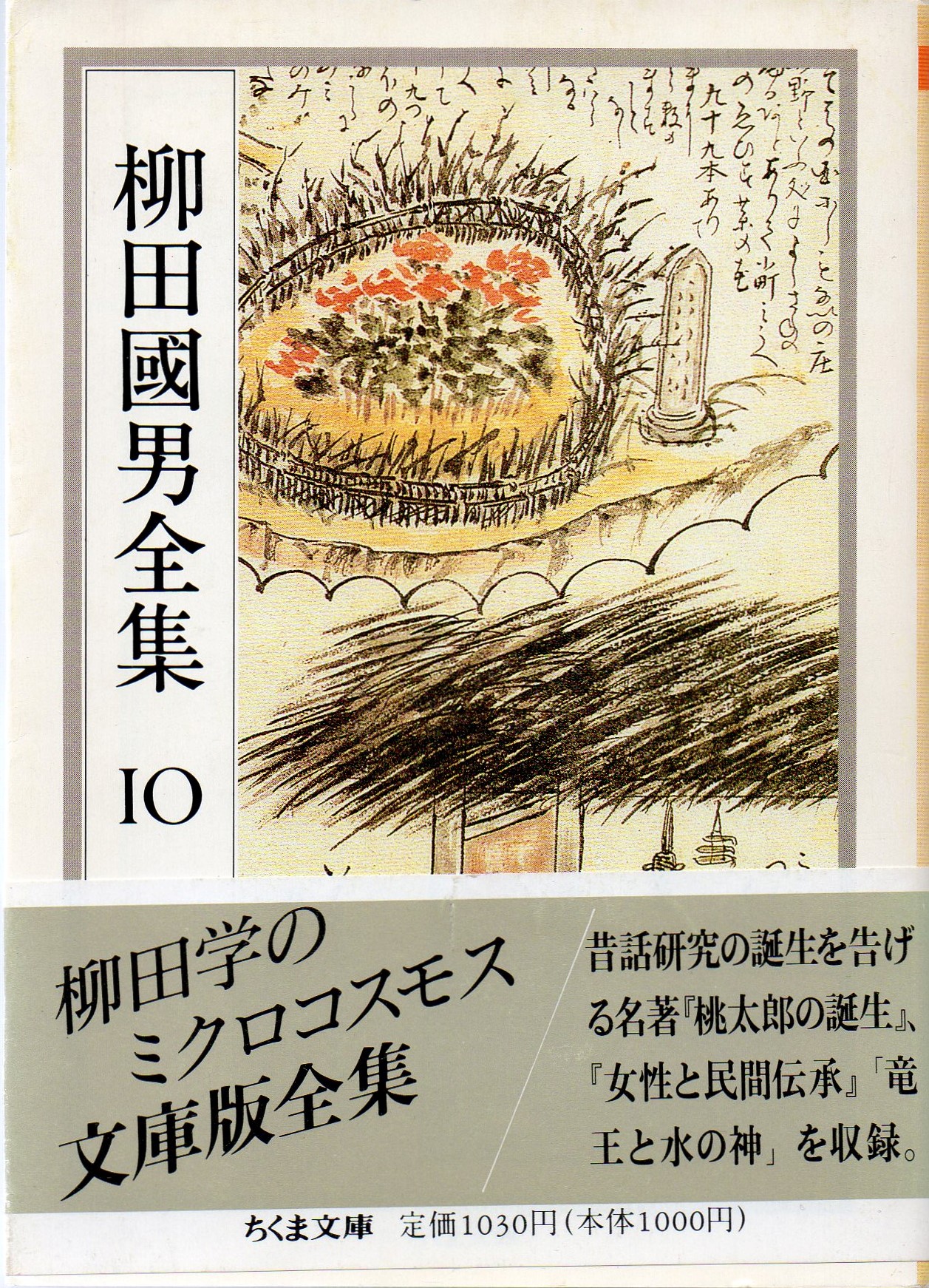
本書は、
桃太郎の誕生、
の他、
女性と民間伝承、
竜王と水の神、
が所収されている。片や、桃太郎という「小さ子」説話から、昔話、伝説を縦横に遡り、古代の水の神信仰へとたどり着き、片や全国にちらばる和泉式部由来という伝承の地の比較検討から、その話を全国に持ち歩いた女性を通して、「歌占人」へと至り着く、という壮大な伝承の空間を再現しようとしている。
その縦横にくり広げられる仮説に裏打ちされている膨大な知識と情報に圧倒されるばかりである。「桃太郎」の「改版にさいして」で、
「この書に説くがごとき昔話の起源論、これと中間の成長発達とを、二つに引き離して見ようとする方法論は、まだ諸外国の通説とはなっていないようである。そうしてやや大雑把な私の検討では、まだ明白にこれらの仮定を、覆えすような資料は発見されていない。」
と、自身の「昔話」を発展段階を通して訴求していく方法に自信を見せている。とくに、日本では、説話と伝説と神話が、
三つ巴になって交錯、
し、「神話」も、
「數も少なく出現の機会も稀であり、また非常に荒れすさみかつ不純になってはいるが、とにかくこれらの伝説と民間説話へ、移り動いて往った足取りだけは見られる。それにはこの異類求婚譚、その中でもことに蛇の婿入りの話などが、かなり豊富に手頃の材料を供するかと思う。」
とし、桃太郎の昔話も、その原型は、蛇婿入譚のように、目に見える形で残されていないにしても、昔話成長の三つの変化、つまり、
一、
説話が上代において夙く芸術化し、そのやや成熟した形において弘く流伝していたもの、たとえば死人感謝譚や紅皿欠皿話、
二、
説話の信仰上の基礎がまったく崩壊せず、従ってこれを支持した伝説はもとより、その正式の語りごとがなお幽かながら残っていたもの、たとえば蛇婿入りのごとき一部の異類求婚譚、
三、
説話が近世に入って急に成長し、元の樹の所在は不明になったが、まだその果実の新鮮味をうしなわぬもの、たとえば桃太郎・瓜子姫説話の類、
の、「二種類三様式の説話が、入りまじってともに行われているということ」は、比較研究にとって便利だとし、江戸時代五大御伽噺(桃太郎・猿蟹合戦・舌切り雀・花咲爺・カチカチ山)に整理選択された中の「桃太郎」も、「少なくとも桃太郎と同時に並び行われ、九州中国にも稀に伝わり、東日本はほとんど到る処に保存せられている」、
瓜子姫、
の説話が童話化の潤色をうけずにあるのを比較しつつ、
桃と瓜、
という、
「元はおそらく桃の中から、または瓜の中から出るほどの小さな姫もしくは男の子」、
であり、
人間のはらからまれず、
しかも、
急速に成長してひととなった、
という、
小さ子(ちいさご)物語、
の骨子が引き出され、それは、
竹取物語、
一寸法師、
とも近く、『諸社根元記』の「倭姫古伝」にある、
姫が玉虫の形をして筥(はこ)の中に姿を現じたまふ、
と繋がっていく。「桃」や「瓜」の流れてくる川上の峰々はそこから下り給う神々の坐す場所であり、
「白蘞(かがみ)の皮で作った舟に乗り、鷦鷯(ささき)の羽衣を着て、潮のまにまに流れ寄った」
という「小男(おぐな)阳」の物語と比べ合わせると、
「最初異常に小さかったということが、その神を尊くまた霊ありとした理由」
ではないか、と推測していく。それは、たとえば、
小犬が川を流れてくる、
とする「犬子噺」ともつながり、その犬が殺されて、その跡から木が生える話は、花咲爺につながり、その犬が「桃」のように川上から流れ着いたというのも、桃太郎と無縁ではなく、さらに流れてきた鳥籠に雀が入っていて、と舌切り雀につながったりと、
五大噺が互いに関係がある、
とまで推測していく。
「昔話の英雄の異常な出現、すなわちただの女の腹から生れなかったということと、同時にその普通でない成長のし方であるが、人が昔話は作り事、どうせありもせぬことをいうのだと思うようになって、かえってこの要件には重きを置かぬ結果を見た。しかも前代の常識においては、これほど人を感動させることはなかったので、ある一人の童子が誰にも予期し得ぬような難事業に成功したとすれば、それは必ず生まれから違っていたろうと思い、もしくはそれと反対に、不思議の誕生をするくらいの人間だから、鬼ヶ島の宝でも取ってこられたのだと解する風が、我々の祖先には行き渡っていた。従うて蟹や雀の大勝利という話が、かつては発端において桃太郎とよく似ていたとしても、必ずしも奇怪でなくまた混乱でもなかったと思う。その上に人が時あって異類に転身し、もしくは鳥獣草木の姿を具えつつも、人と同じく思惟し咏歎し得たということも、きわめてありふれたる上代人の考え方であった。桃や瓜の中からでさえ生まれると認められた者が、しばらくは小蛇・小犬の形をもって我々の間にいたとしても、それだけが特に不可思議というほどでもなかったのである。だからこのいわゆる五大噺の相互の類似なども、事によるとそれがある一つの根幹から、岐れて変化して行った経路を暗示する、偶然の痕跡であるかも知れぬと私などは思っている。」
そして、「小さ子」説話の、
田螺の長者、
一寸法師、
を経て、
「小さ子」説話の背後に水の神の信仰を見出そうとして行く。たとえば、「桃太郎」で、桃を拾い上げるのに直接関係のない、
爺が山へ柴苅りに行く、
と何気なく語られていることが、
柴苅爺の話、
にある、町に柴を売りに行ったが売れず、その柴を水底に向かって投げ込んだところ、その川ないし淵から美しい女性が出てきて、柴の礼を言い、水底へ導かれていくと、投げ込んだ柴がきちんと積み重ねてあった、という説話とつながり、
竜宮、
とつながっていた古い信仰の痕跡ではないか、と推測する。日本人にとっての「竜宮」が、いずれの国とも異なり、
妣(はは)の邦、
であり、
「ひとり蒼海の消息を伝えた者が、ほとんど常に若い女性であったというに止まらず、さらにまた不思議の少童を手に抱いて、来たって人の世の縁を結ぼうとした」、
のである(「竜宮」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488132230.html)については触れた)。ちょうど、
河童、
が、
小さ子たる水神童子の零落した姿、
であるように、かつての信仰の翳がつきまとっていることは間違いない。
こうしたキーワードを手掛かりに深い深層を探っていく方法は、「女性と民間信仰」でも同じで、全国各地に伝わる和泉式部の墓や伝承を対比しつつ、「歌……に相応な解釈を付けて、神々の思召しのごとく説き聴かせる」、
歌占人(うたうらびと)、
の女性にたどり着く。そして、
「少なくとも和泉式部の諸国の伝説の、主要なる特色の一つであった親子再会譚は、舞踏と深い関係があった上に、また歌占とも因縁をもっております。」
と書く。
こうした仮説がどの程度検証されているのかは素人の自分には窺えないが、その視界の幅のひろさと奥行きの深さを、今日どれほどの人が追いかけられるものなのか、とため息が出る。
なお、柳田國男の『遠野物語・山の人生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488108139.html)、柳田國男『海上の道』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488194207.html)、『妖怪談義』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488382412.html)、『一目小僧その他』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488774326.html)については別に触れた。
また、石田英一郎『桃太郎の母―ある文化史的研究』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/456362773.html)についても触れた。
参考文献;
柳田國男「桃太郎の誕生他(柳田国男全集10)」(ちくま文庫) |
|
現象学的分析 |
| エドムント・フッサール(立松弘孝訳)『内的時間意識の現象学』を読む。
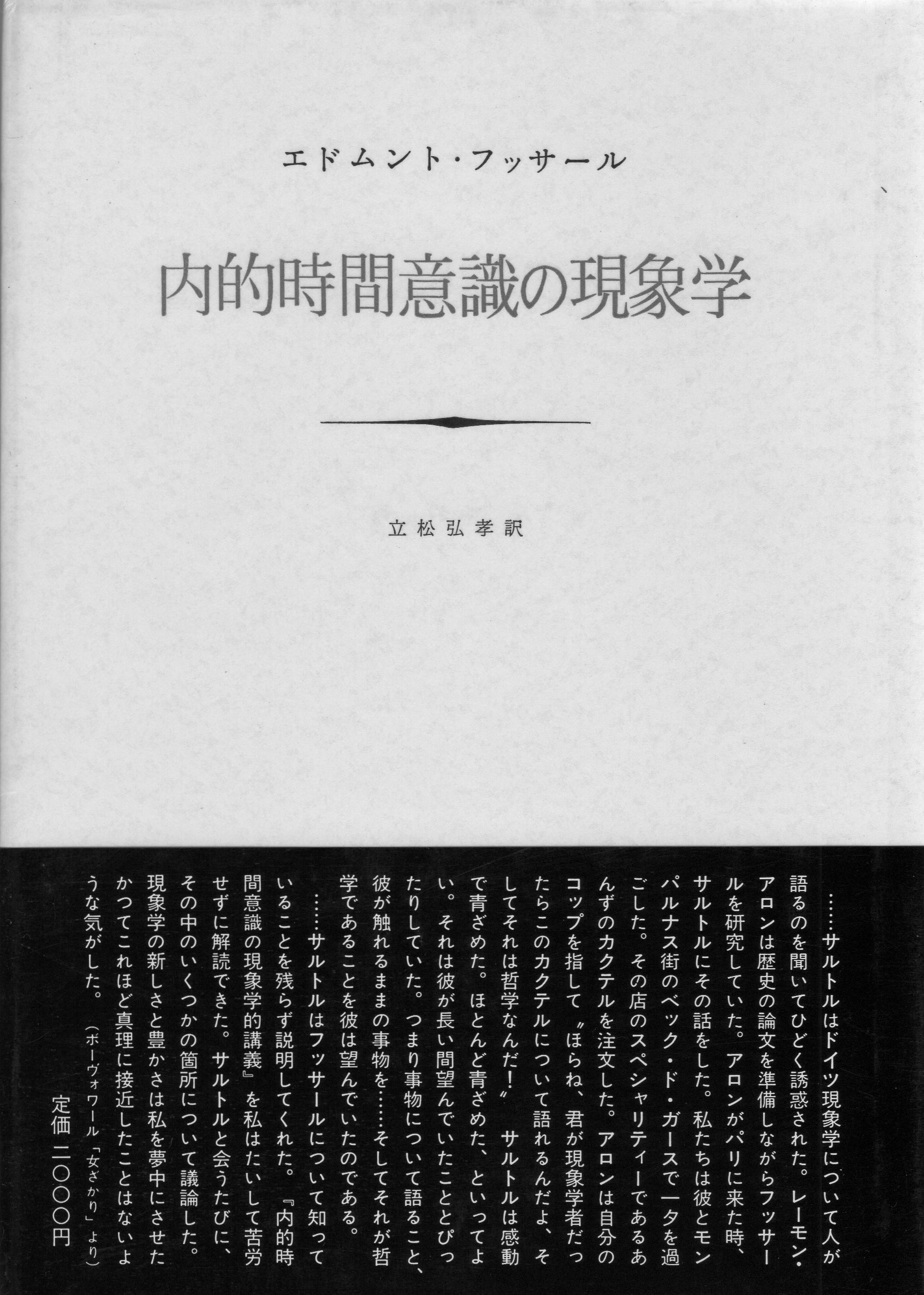
本書は、二部に分かれる。
「第一部は『現象学および認識論の主要部』と題して1904、05年の冬学期にゲッチンゲンで行われた週四時間講義の最後の部分を収録している。(中略)この講義では《もっとも根底的な知的作用、すなわち、知覚、想像、心象意識、記憶、時間直観》が研究されることになっていた。第二部は講義の補遺と1910年までになされた新しい補足的研究から成り立っている。」(編者・序)
本書ではじめて、
時間を主観的に、
つまり、
主観的な時間意識や内在的な意識体験の時間性、
について、
現象学的に、
つまり、
直接与えられた意識(知覚直観、純粋経験・意識)を整理することなく、できるだけ言葉に置き換えて記述していく、
ことで、
意識内部の時間意識、
の道筋を明らかにしようとしているのは。確かだとしても、しかし、それにしても、本書は難解である。
「一般に難解な彼の著作の中でも最も難解を嘆ぜしめるもの」
といわれる(訳者あとがき 高橋里美「フッセルにおける時間と意識流」)。論旨の難解さももちろんあるが、次々と説明抜きで繰り出される「概念」が、とても追尾不能のせいもある。たとえば、
「勿論われわれの誰もが時間とは何であるかを知っている。時間はもっともよく知られたものである。しかしいったんわれわれが自分自身に時間意識について論明し、客観的時間と主観的時間とを正当な相互関係に置いて、そしてどのようにして時間的客観性が、つまり個体的客観性一般が主観的時間意識の内部で構成されるかを意識しようと試みるならば、それどころか、純粋に主観的な時間意識、すなわち時間体験の現象学的内実を分析しようと試みるだけでも、忽ちわれわれは稀有の困難、矛盾、混乱にまきこまれてしまう。」
とある(「序論」)だけでも、「時間」だけで、
時間性格、
客観的時間、
主観的時間、
時間的客観性、
個体的時間性、
主観的時間意識、
時間体験、
等々と繰り出される。文脈で理解できるものもあるが、微妙な含意差は、推測していくほかはない。
たとえば、メロディを聞いている時、
「内在的・時間的客観が恒常的な流れの中でどのように《現出》し、どのように与えられているか」
という、
内的時間意識の現出様式、
を、次のように記述する。
「音が鳴り始め鳴り終わる全過程の統一は、それが鳴り終わったあと次第に遠い過去へ《後退する》。このような沈退の中で私はなおもその音を《把持》し、それを《過去把持》のうちに所持している。そして過去把持が存続する限り、その音はそれ自身の時間性を保持し、同じ音でありつづけるのであり、その持続も変わることがない。私はその音の所与存在の様式に注意を向けることができる。その音とその音が充たしている持続は《諸様式》の連続する中で、《恒常的な流れ》の中で意識されているのである。そしてこの流れの一位相をなす一点が《鳴り始めた音の意識》と言われ、そこでは音の持続の最初の時点が今という様式で意識されている。その音は所与であり、いまとして意識されている。しかしそれがいまとして意識されるのは、その音の諸位相のどれか一つがいまとして意識されている《限り》でのことである。しかし(音の持続の一時点に対応する)時間位相のどれかが顕在的な今であるとすれば(ただし出発点の位相は例外である)、一連の位相は《以前》として意識され、また出発点から今の時点までの時間的持続の広がり全体は経過した持続として意識される。……」
と、明らかに自分の個人的体験とは齟齬のある部分はあるが、フッサール自身が、
「このような記述を行う場合われわれはすでに多少の観念的虚構を用いて操作している。」
と言っているし、
「音が絶対に変わることなく持続するというのは一つの虚構である。」
といっているので、免責されるようだが、そうだろうか。音の持続を前提に立てている構造そのものが、疑わしくなってくるのではないのか。
正直「現象学」による分析の価値を云々する力はないか、少し齧った認知心理学からいうなら、本書が追求する、
知覚、
記憶、
想像、
想起、
心象、
等々は、正に認知心理学の領域であり、たとえば、「記憶」を、「記憶」一言で片づけるのは、いささか問題があり、たとえば、記憶は、
「意味記憶」(知っている Knowには、Knowing ThatとKnowing
Howがある)、
「エピソード記憶」(覚えている rememberは、いつ、どこでが記憶された個人的経験)、
「手続き記憶」(できる
skillは、認知的なもの、感覚・運動的なもの、生活上の慣習等々の処理プロセスの記憶)、
があるとされるが、「メロディ」の記憶を、
意味記憶、
でみるか、
エピソード記憶、
で見るかでは、その主観的時間意識には差があるはずで、主観的な意識記述は、今日、認知心理学の知見と照合さるべきなのではないか。いかに主観とはいえ、「虚構」の記述に意味があるとは思えない。
参考文献;
エドムント・フッサール(立松弘孝訳)『内的時間意識の現象学』(みすず書房)
J・R・アンダーソン『認知心理学概論』(誠信書房) |
|
語源のもつ意味 |
| 柳田國男『不幸なる芸術・笑の本願』を読む。
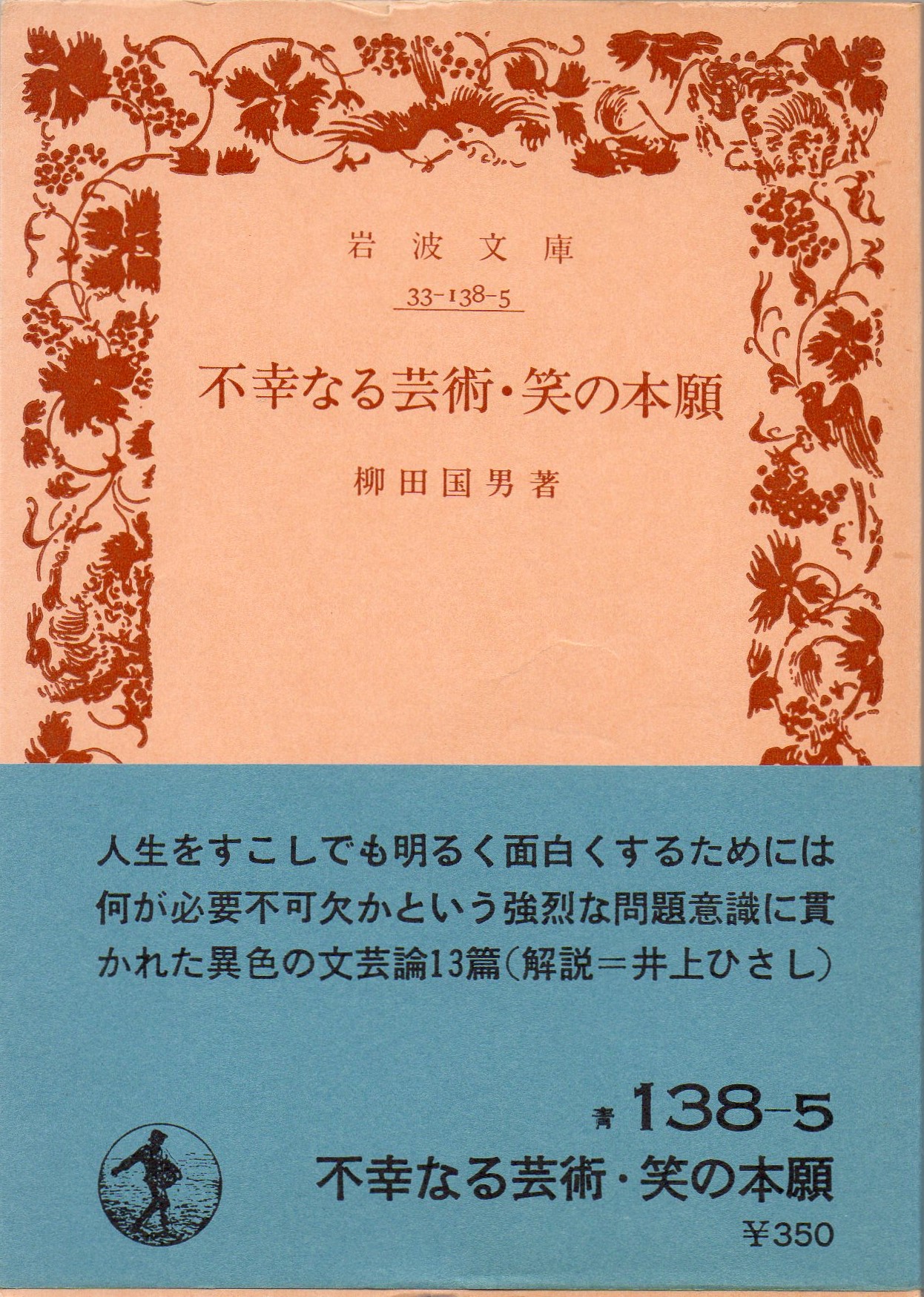
本書には、
笑の本願、
不幸なる芸術、
の二著が収められており、「笑の本願」は、
笑の文学の起源、
笑の本願、
戯作者の伝統、
吉右会記事、
笑の教育、
女の咲顔、
が、「不幸なる芸術」には、
不幸なる芸術、
ウソと子供、
ウソと文学の関係、
たくらた考、
馬鹿考異説、
烏滸の文学、
涕泣史談、
が、収められている。いつも通りの柳田節なのだが、中でも、
へったくれ、
の語源と絡めて、
「神社に従属した小区域の地名に手倉田(たくらだ)というものが諸国に存する。羽後の雄物(おもの)川の岸には『言語道断』と文字に書いて、タクラダという村さえあった。タクラダ・タクラは多く地方の方言で愚か者を意味し、ノンダクレとかヘッタクレとかいう普通語もそれから出ている。或いはまた馬鹿をオタカラモノと呼ぶ土地もある。手倉田・田倉田は即ち彼らに田を給し、神役を勤めさせた名残かと思われる。三河の山村の花祭の囃しの詞に、笛に合わせて一同がターフレタフレと囃すのも、やはり一つの語の変化であって、いわゆるクナタフレが神に仕え、その愚かさを役に立てたこと、今の馬鹿囃しの火男(ひょっとこ)などと、本の趣旨を同じくする者かと思う。」
と、神の前で「笑わせる」職分役という民間習俗に至る「笑の起源」に迫った、
笑の文学の起源、
その「たくらた」を、
「タクラという語は少なくとも方言ではなかった。今も複合語としては標準語の中にも通用している。たとえば泥酔者をノンダクレ、是をもう少し悪い発音にかえて、ドンダクレという語は田舎にあり、関西の方では是をヱヒタクレという者が多く、ヨッタクレという語もまだ東京には少し残っている。それからまたヒョウタクレという語があり、東日本の方言集には多く採録されていて、愚人を意味する。」
とし、その語源を、
「タクラフという動詞が、都にもあったということである。……或いはタクラブ(較)という語と源が一つのもので、二人相対しての動作に限っていたのではないかとも思う。」
と探って、
神前での道化役、
へと遡及させていく、
たくらた考、
の二編が、とりわけ面白い。「へったくれ」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489851160.html?1658081573)で触れたことだが、
へったくれ
愚か者、
の意味が通底していることの意味の奥行きを考えさせられる。この二編と関わるが、
烏滸、
と
馬鹿、
との関係を、
日本語のワ行がバ行に、WがBに移ってくるのは通例、
で、
母音のオ列からア行に移ること、
から、新村説である、
ワカ(若)→バカ(馬鹿)、
つまり、
Waka→Baka、
という転訛を取り上げながら、暗に、ぼくには、
オコ(烏滸)→バカ(馬鹿)、
つまり、
Woko→Baka、
の転訛に読みこめて、「愚か者」のもつ意味が、
烏滸→馬鹿、
と転じることから、
笑が凋落したこと、
の象徴とする、
烏滸の文学、
も、深読みすると、パースペクティブの深い読み物であった。また、
うそ、
と
いつわり、
の違いを探り、
「何処の田舎に行って見ても、今はまだウソとイツハリと、もしくはデタラメとゴマカシと、即ち笑うべき虚言(ソラゴト)と憎むべき虚言(キョゴン)との、二つ別々の名詞の併存を必要としている。」
とする、
ウソと子供、
ウソと文学の関係、
また、生まれた赤児の前に据える、
高盛りの飯、
の風習があるが、女子だと、
高く盛った飯の両側に、指または箸の先で附いて辰の穴をあける、その児の頬にエクボができて、愛嬌がよくなる、
という風習のもつ「えくぼ」の意味から、「えむ」と「わらふ」との違を探った、
女の咲顔(えがお)、
も興味深い。なお、
吉右会記事、
については、「きっちよむ話」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489762390.html?1657822771)で触れた。
なお、柳田國男の『遠野物語・山の人生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488108139.html)、『妖怪談義』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488382412.html)、柳田國男『海上の道』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488194207.html)、『一目小僧その他』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488774326.html)、『桃太郎の誕生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489581643.html)については別に触れた。
参考文献;
柳田國男『不幸なる芸術・笑の本願』(岩波文庫) |
|
説話の原点 |
| 景戒(原田敏明・高橋貢訳)『日本霊異記』を読む。
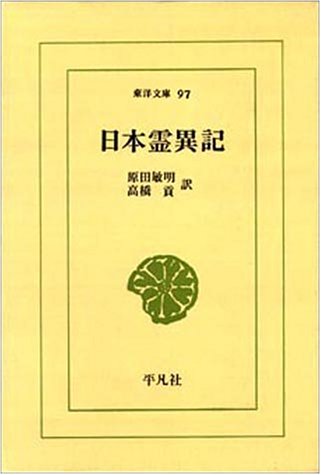
本書『日本霊異記(にほんりょういき・にほんれいいき)』は、正確には、
日本国現報善悪霊異記(にほんこくげんほうぜんあくりょういき)、
で、平安時代初期編纂の、最古の説話集である。
上巻35話、
中巻42話、
下巻39話、
で、
計116話、撰者は、薬師寺の僧、
景戒(きょうかい)、
であり、各巻に序文を記し、唐に、
冥報記(めいほうき)や般若験記(金剛般若集験(こんごうはんにゃしゅうげん)記)、
といった霊験記があり、他国の話ばかりではなく、自国の「不思議な出来事を信じないことがあろうか」と、本書をまとめたと記している。
全文は漢文体で、ほぼ時代順に記述されている。上巻は、
雄略天皇の時代(五世紀後半)から聖武天皇の神龜四年(727)まで、
中巻は、
聖武天皇の天平元年(729)から淳仁天皇の天平宝字七年(763)まで、
下巻は、
称徳天皇の時代(764〜770)から嵯峨天皇の時代(809〜822)まで、
と、所収の話の背景は、
奈良時代及びそれ以前、
と、
現存する日本最初の説話集であるとともに、奈良時代の説話を集大成したもの、
となり(本書解説)、後の、
法華験記(ほっけげんき)、
三宝絵詞(さんぼうえことば)、
今昔(こんじゃく)物語集、
等々に多大な影響を与えた、とされる(仝上)。
現報善悪霊異記、
とある如く、
善悪の応報を説く因果譚、
が過半を占め、
三毒(さんどく 貪・瞋・癡(とん・じん・ち)の煩悩)、
やら、
四重五逆(殺生・偸盗・邪淫・妄語の四重、殺父・殺母・殺阿羅漢(悟りを開いた聖者)、破和合僧(教団破壊)、出仏身血(仏身を傷つけること)の五逆)、
やら、
五戒(不殺生戒、不偸盗戒、不邪婬戒、不妄語戒、不飲酒戒)を破る、
やら、
十悪(殺生・偸盗・邪淫・妄語・綺語(きご 真実に反して言葉を飾りたてる)・悪口(あっく)・両舌(りょうぜつ 二枚舌を使う)・貪欲・瞋恚・邪見)、
やら、仏教での戒めやら、罪の応報を、これでもかこれでもか、と読まされると、ふと我が身を振り返って見ざるを得なくなる。仏教説話集の効能の一端を、我が身で味わう羽目になった。
しかし、後の説話がそうであるように、また昔話や伝説、神話に生きているように、
狐や牛、亀、鳥などの動物、あるいは雷、鬼を人間と同じように扱い、
動物や雷、鬼が人間と同じように話し、考え、行動している、
という特色が見え、たとえば、「野干」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/485021299.html)でも触れた、
女、……成野干……随夫語而來寐、故名為也(上巻第二話)、
とあるように、女となって男と結婚し、子供を産んだが、小犬に吠えられて、狐の正体がばれたときに夫から、
「おまえとわたしの間には子供が生まれたのだからわたしは忘れない。いつでもきてそこにとまりなさい」
と言われ、そのとおりまたきてとまった。そこで、
岐都禰(来つ寝)、
と名づけたとあり、その子にも、
岐都禰(きつね)、
と名づけ、姓を、
狐直(きつねのあたえ)、
とつけた、と「キツネ」の由来を伝えているなど、なかなか興味深い説話も多い。
参考文献;
景戒(原田敏明・高橋貢訳)『日本霊異記』(東洋文庫) |
|
通底する土俗 |
| 柳田國男「伝説・木思石語他(柳田國男全集7)」を読む。
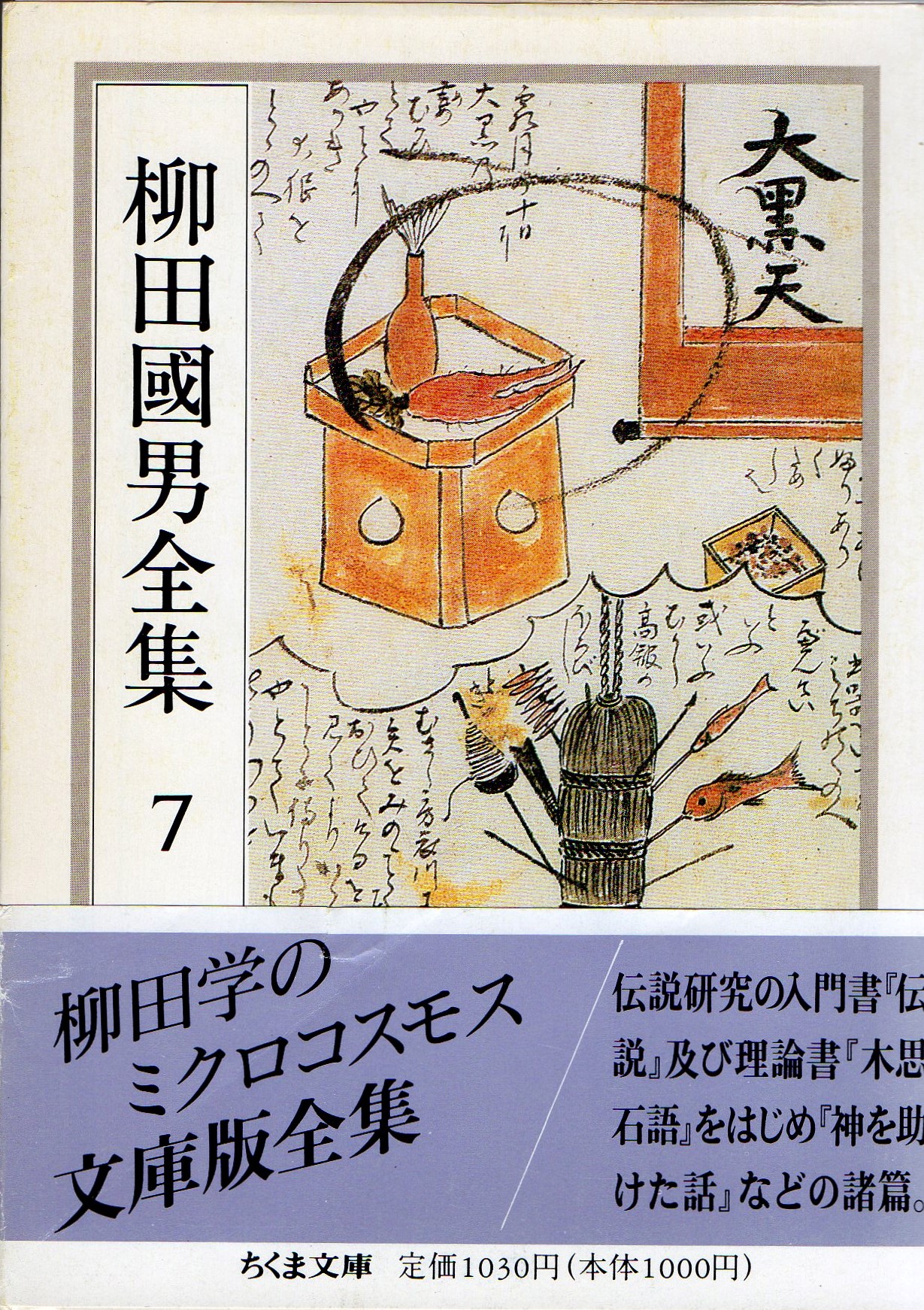
本書には、
伝説、
木思石語、
神を助けた話、
他が収められている。「木思石語」では、伝説の分類を試みている。伝説は、
ハナシではなく、その世に伝わっているのはコトである、
として、
土地に定着し地物と不可分に伝わっているもの、
を中心として、
木の伝説(腰掛松、矢立杉、杖銀杏、逆さ榎等々)、
石の伝説(腰掛石、休石、傾城石、比丘尼石等々)、
塚の伝説(黒塚、行人塚、将門塚、七人塚、赤子塚等々)、
水部伝説(池、淵、滝、温泉等々)、
道の神の威力伝説(坂、辻、橋、渡し場等々)、
森と野の一隅、古い屋敷跡伝説(長者の故跡等々)、
社寺、堂閣、旧家、名門の伝説、
と分類している。伝説は成長し、変化し続けている。ために、モチーフ・内容からでは、そこで語られる中身、ストーリーはどんどん変わっていくのである。その意味で、今日どう整理し直されているのかは分からないが、
「通例は地形・地物について語られる限りは、たいていその目的物が伝説の要旨を名に負うている。それが名木でありまた名石であるのみで、いまだ字(あざ)の名や村の名に応用せられない間は、多くは伝説そのものの忘却とともに、名称も消えてしまうものであるから、名がある以上はその陰につつましく隠れて、まだ伝説も活きているものとみてよいので、すなわち単なる木石の呼名を書き留めることが、やがてはまた伝説の採集ともなるわけである。」
という「対象物」に限定した柳田國男の意図ははっきりしている(木思石語)。
本書で、特に面白かったのは、
神を助けた話、
の、
赤子塚の話、
である。
母の幽霊に育てられた、
という(「子育て幽霊」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/483116941.html)については触れた)、
頭白(ずはく)上人、
の伝説から、
その上人の父の名、
筑波の東北佐谷村の源治、
から、
(佐夜中山)夜泣石、
との関連を見(「夜泣石」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/483101232.html)については触れた)、及び、幽霊が団子を買いに行く婆の小屋の、
後生車、
から、
賽の河原の石積み、
とのつながりを探り出し、さらに、
佐夜の中山の夜泣石、
は、実は、
夜啼きの松、
が枯れた後に流布した伝説であり、
夜啼松、
は、全国に分布し、
その一片に火を点して見せると子どもの夜啼きを止める、
とする、
夜啼松、
は、たとえば、
「大昔仁聞という高僧、行脚して夜この樹(夜泣松)の側を通る時、赤子を抱いて樹蔭に野宿している婦人を見た。その赤子大いに啼いて困り切っているので、すなわち松の樹に向かい経を読んで後、その落葉松毬を集めて火を燃やし、光を赤子に見せるとたちまち啼き止んだ。」
という「夜泣松」のエピソードは、
「通例ウブメの怪と称して、人の説く話とそっくりである。」
とし(「うぶめ」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/432495092.html)については触れた)、この、
夜啼きの願掛け、
は、
「祈禱というよりもむしろ呪術である。ただある一定の地にある松の樹などに限って用いるゆえ、次第にその樹を拝し、またはむ樹下に祠を構えるようになった」
ものであり、その場所は、
佐夜の中山の峠道、
か、
里の境、
河の岸、
橋の袂、
と推測し、
道祖神の祭場、
につながると絞っていく。そして、
賽の河原、
が、
才の河原、
西の河原、
道祖河原、
等々と当てられ、仏教の地獄とは関係なく、
道祖神(サエノカミ)、
とつながり(「道祖神」については「さえの神」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489642973.html)で触れた)、それは、
地蔵、
とつながる(「地蔵」については「六道能化」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/485970447.html)で触れた)。そして、かつての、
棄児(すてご)の儀式、
へと通じていく。それは、
健やかに育つまじないとして、
「大事な若君に棄という名を付けて、生先(おいさき)を祈った」
という例も古くからあり、
「現に江戸でも三代将軍家光生れて二歳の時、健やかに育つまじないとして、侍女これを抱いて辻に出て、通り掛かりの三人目に売った。山田長門守ちょうど三人目に来合わせ、これを買い受けた」
という話もある。その場所が、村の境、
道祖神の祭場、
だと推測していく。この推理の筋道は、壮観である。
「児捨馬場が児拾馬場であったごとく、また子売地蔵がやはり子買いであったごとく、死んだ児の行く処とのみ認められた賽河原が、子なき者子を求め、弱い子を丈夫な子と引き換え、あるいは世に出ようとしてなお彷徨う者に、安々と産声を揚げしめるために、数百千年間凡人の父母が、来ては祈った道祖神の祭場と、根元一つである」
とする推論が是か非かは分からないが、民間俗信に通底する深く、広い土俗が流れていることだけは良く見えてくる。
なお、柳田國男の『遠野物語・山の人生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488108139.html)、『妖怪談義』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488382412.html)、柳田國男『海上の道』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488194207.html)、『一目小僧その他』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488774326.html)、『桃太郎の誕生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489581643.html)、『不幸なる芸術・笑の本願』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489906303.html)については別に触れた。
参考文献;
柳田國男「伝説・木思石語他(柳田國男全集7)」(ちくま文庫) |
|
万里一空 |
| 宮本武蔵『五輪書』を読む。
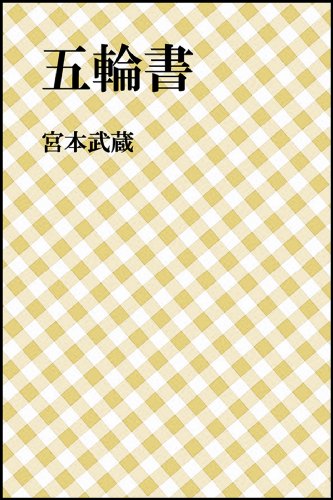
「武士の兵法を行ふ道は、何事に於ても人にすぐるゝ所を本とし、或は一身の切合に勝ち、或は数人の戦に勝ち、主君の為、名をあげ身をたてんと思ふ。是兵法の徳を以てなり。又世の中に、兵法の道をならひても、実の時の役にはたつまじきと思ふ心あるべし。其儀に於ては、何時にても、役にたつやうに稽古し、万事に至り、役にたつやうにおしゆる事、是兵法の実の道也。」
とあるように、武蔵の兵法は、徹頭徹尾相手に勝つこと、端的に言えば、
皆人をきらん爲也、
を目指す。だから、
「剣術一通の理、さだかに見分け、一人の敵に自由に勝つ時は、世界の人に皆勝つ所也。一人に勝つと云い心は千万の敵にも同意也。将たるものの兵法、ちいさきを大きになす事、尺のかたを以て大仏をたつるに同じ。」
と、
一人と一人との戦ひも、万と万とのたたかひも同じ道なり、
と言い切り
一対一の戦い(小分の兵法)、
も
多数の合戦(大分の兵法)、
も同じこととして展開する。この姿勢は、いわゆる、
兵法者、
とは少し異なる気がする。それは、武蔵が、
山水三千世界を万里一空に入れ、満天地とも挈(と)る、
という心を題として、
乾坤を其儘庭に見る時は、我は天地の外にこそ住め、
と、仏者や禅者の謂いとは異なる、
天地を俯瞰する、
かの如き境地と無縁ではない(鎌田茂雄『五輪書』)。本書で、武蔵は、兵法に、
我に師なし、
と言い切るように、本書も、
「今此書を作るといへども、仏法・儒道の古語をもからず、軍記・軍法の古きことをもちひず、此一流の見たて、実の心を顕す事、天道と観世音を鏡として、十月十日の夜寅の一てんに、筆をとって書初るもの也。」
と、自分の言葉で書いたと宣言しているのである。ここにも、武蔵の強い意志がある。
本書は、
五つの道をわかつ、
ため、
地、
水、
火、
風、
空、
の五巻に別つ。地の巻では、
「兵法の道の大躰、我が一流の見立、剣術一通りにしては、誠の道を得がたし。大きなる所よりちいさき所を知り、浅きより深きに至る。直なる道の地形を引きならすによって、初を地の巻と名付く也。」
水の巻では、
「水を本として、心を水になる也。水は方円のうつわものに随ひ、一滴となり、滄海となる。水に碧潭の色あり、清き所をもちひて、一流の事を此巻に書顕す也。剣術一通の理、さだかに見分け、一人の敵に自由に勝つ時は、世界の人に皆勝つ所也。一人に勝つと云い心は千万の敵にも同意也。将たるものの兵法、ちいさきを大きになす事、尺のかたを以て大仏をたつるに同じ。か様の儀、こまやかには書分けがたし。一を以て万と知る事、兵法の利也。一流の事、此水の巻に書記す也。」
火の巻では、
「戦ひの事を書記す也。火は大小となり、けやけき心なるによって、合戦の事を書く也。合戦の道、一人と一人との戦ひも、万と万との戦も、同じ道也。心を大きなる事になし、心をちいさくなして、能く吟味して見るべし。大きなる所は見えやすし、ちいさき所は見えがたし。其仔細、大人数の事は即坐にもとをりがたし。一人の事は心一つにて変る事はやきによつて、ちいさき所しる事得がたし。此火の巻の事、はやき間の事なるによつて、日々に手馴れ、常のごとく思ひ、心のかはらぬ所、兵法の肝要也。然るによつて、戦ひ勝負の所を火の巻に書顕す也。」
風の巻は、
「風の巻としるす事、我一流の事にはあらず、世中の兵法、其流々の事を書のする所也。風といふに於ては、昔の風、今の風、其家々の風などとあれば、世間の兵法、其流々のしわざを、さだかに書顕はす、是風の巻也。他の事を能く知らずしては、自らのわきまへ成りがたし。道々事々をおこなふに、外道と云ふ心あり。日々に其道を勤むるといふとも、心のそむけば、其身はよき道と思ふとも、直ぐ成る所より見れば、実の道にはあらず。実の道を極めざれば、始めし心のゆがみに付けて、後には大きにゆがむもの也。吟味すべし。他の兵法、剣術ばかりと世に思ふ事、尤也。我兵法の利わざに於ても、各別の儀也。世間の兵法を知らしめん為に、風の巻として、他流の事を書顕す也。」
空の巻では、
「空と云出すよりしては、何をか奥と云ひ、何をか口といはん。道理を得ては道理をはなれ、兵法の道に、おのれと自由有りて、おのれと奇特を得、時にあひては拍子を知り、おのづから打ち、おのづからあたる、是皆空の道也。おのれと実の道に入る事を、空の巻にして書きとゞむるもの也。」
吉川英治の『宮本武蔵』の影響で、武蔵にも、
剣禅一如、
のイメージが強いが、実像はちょっと違う。柳生宗矩などに禅の臭みが伴うが、武蔵にはない。たとえば、火の巻、
けんをふむと云ふ事、
に、
「敵の打出す太刀は、足にてふみ付くる心にして、打出す所を勝ち、二度目を敵の打得ざるやうにすべし。踏むと云ふは、足には限るべからず、身にても踏み、心にても踏み、勿論太刀にて踏み付けて、二のめを敵によくさせざるやうに心得べし。是則ち物毎の先の心也。」
という一節がある。ここでは、
身にても踏み、心にても踏み、勿論太刀にて踏み付けて、
とあり、まるで、
身心一如、
と、
心と体と刀が一体化した動きを強調して、相手が、
二度目の打出す、
のを妨げようとしている。ここにあるのは、実利的な考えである。本書でも、随所にあるには、いかにして、
相手との流れを崩すか、
を、徹頭徹尾説く、
先手を取る、
拍子を崩す、
間合いを変ずる、
相手の心を乱す、
変調する、
など、諸々の具体的工夫は、武蔵が、
十三歳にして初而勝負、
をして以来、
廿八、九迄、
「国々所々に至り、諸流の兵法者に行合ひ、六十余度まで勝負をすといへども、一度も其利をうしなはず。」
という命がけの実践の中で、いかにして勝つか、のみに収斂させた結果に見える。
参考文献;
宮本武蔵『五輪書』(Kindle版)
鎌田茂雄『五輪書』(講談社学術文庫) |
|
タブロイド紙も顔負け |
| 佐藤謙三校注『今昔物語集』を読む
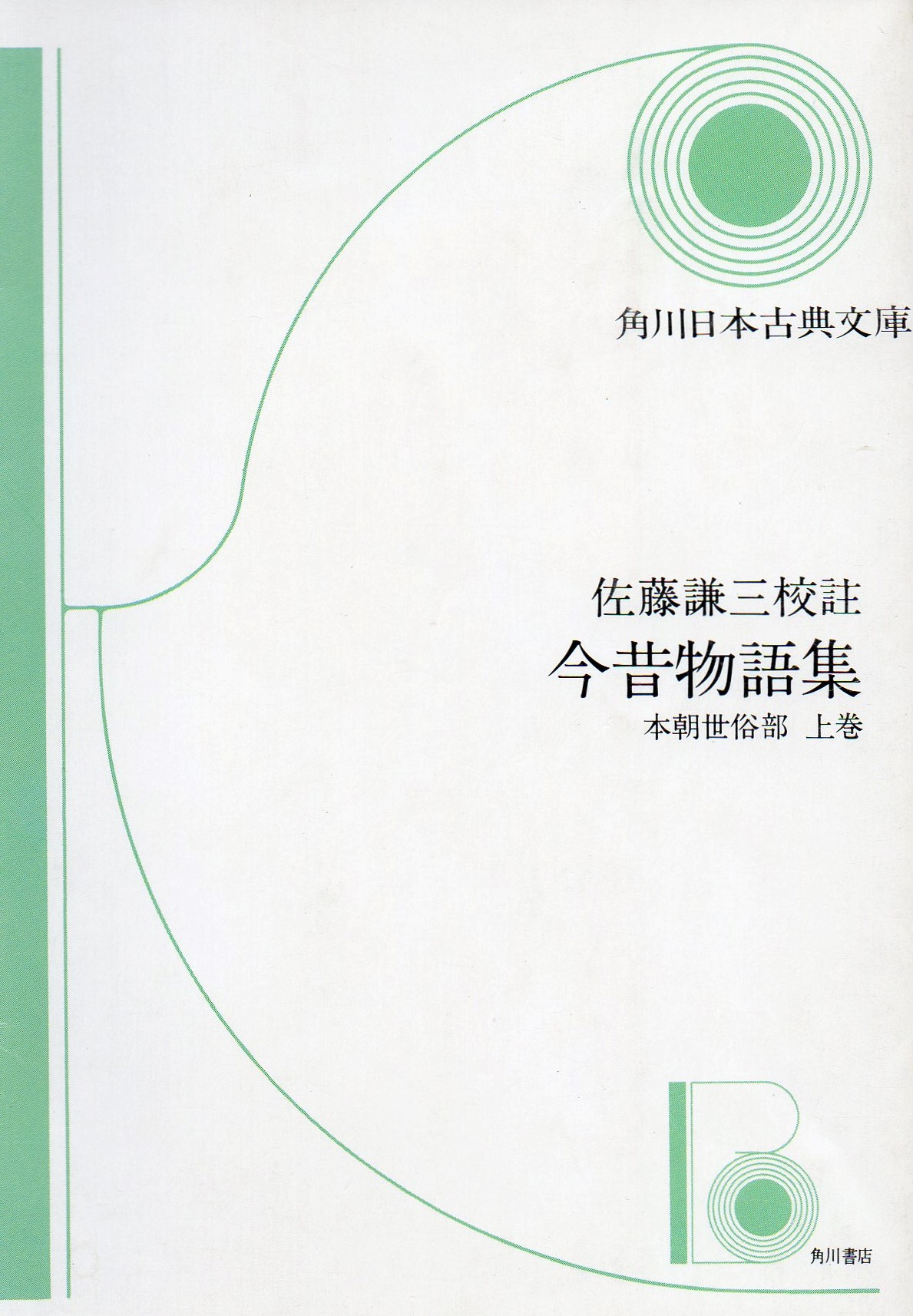 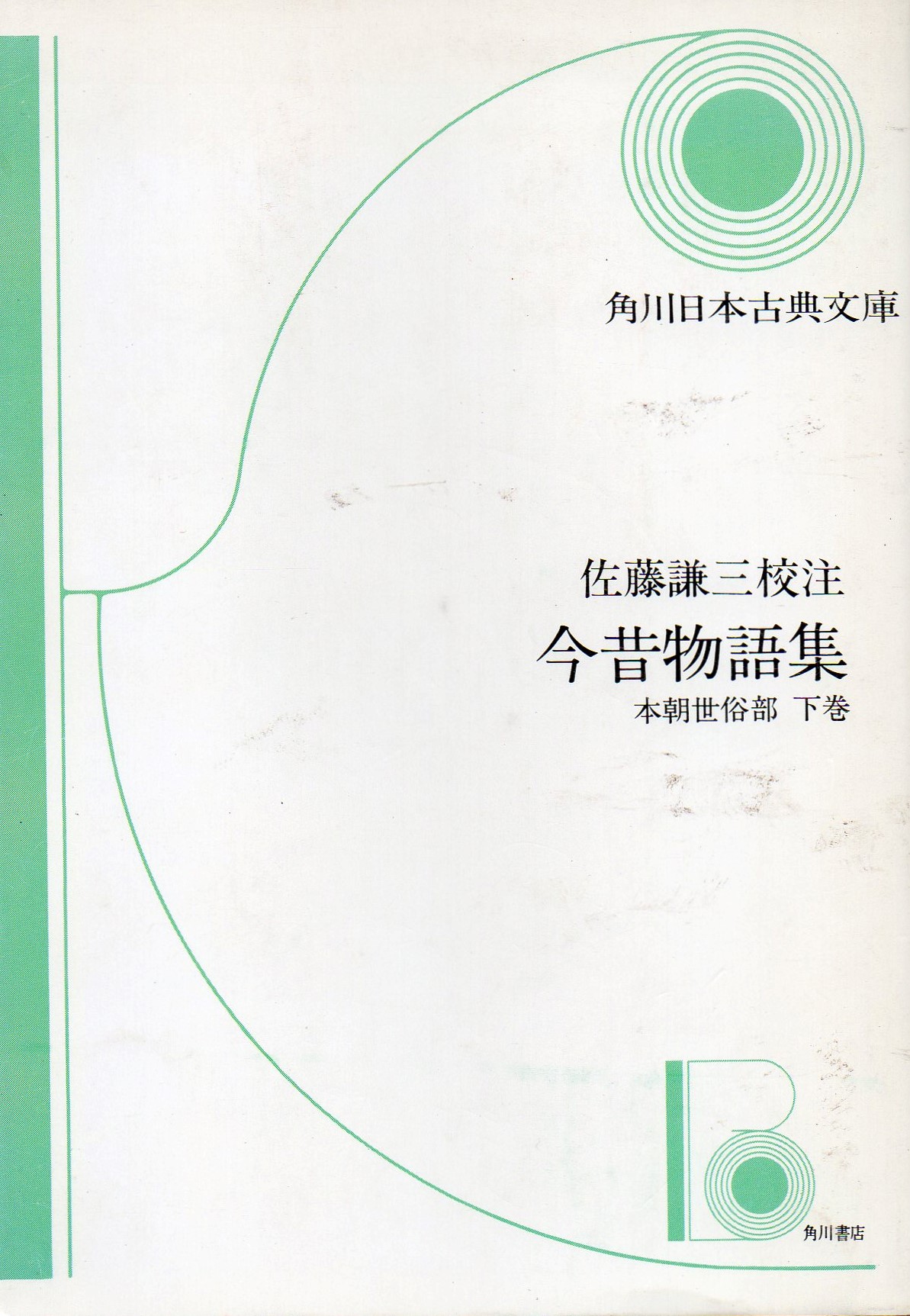
『今昔物語集』は、
平安時代末期の説話集、
であり、この「今昔」というタイトルは、それぞれの物語が、
「今昔」(「今は昔」)という書き出しで始まり、「トナム語リ傳へタルトヤ」(「と、なむ語り伝えたるとや」)という結びの句で終わる、
ことからくる、
便宜的な通称、
とされる、
日本最大の説話集、
である。
全31巻、
1040話、
巻1〜5が天竺(インド)、
巻6〜10が震旦(中国)、
巻11〜31が本朝(巻11〜21が本朝仏法)、
で(巻8・18・21は欠)、各部、
仏法、
世俗、
の2篇に分ける。本書は、
本朝部の仏法の部分を除いた、いわゆる世俗の物語部分、
のみを収録している(巻22〜31)。なお、天竺、震旦部では、仏典や漢籍の翻訳翻案がほとんどで、本朝仏法編は、
『日本霊異記』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/490129996.html)、
に重なる部分が結構あり、
文章を改め、あるいは潤色を加えている、
とされるが、
中国の仏教説話集『三宝感応要略録』『冥報記(めいほうき)』『弘賛法華伝(ぐざんほっけでん)』『孝子伝』、
日本の『日本霊異記(りょういき)』『三宝絵詞(さんぼうえことば)』『日本往生極楽記』『本朝法華験記(ほっけげんき)』『俊頼髄脳(としよりずいのう)』『宇治大納言物語』、
といった、さまざまの系統を集大成する説話集になっている。全体は、
説話の内容によって整然と分類配列、
されている。
この編者を、
宇治大納言と呼ばれた源隆国、
または、
その子の、鳥羽僧正覚猷、
とする説もある(本書解説)が、
未だ定説はない、
とされる(仝上)。ただ、別に、現物は残っていない、
宇治大納言物語、
と称する説話集があり(『宇治拾遺物語』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/484515144.html)では序文に記されている)、
その影響を受けている、
とされ(仝上)、共通する説話の数は、
『今昔物語集』と『宇治拾遺物語』間で81、
とされる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%98%94%E7%89%A9%E8%AA%9E%E9%9B%86)。
ただ、今日の伝本のほとんどが、
江戸時代の書写、
で、それらはすべて、鎌倉時代中期を下らない鈴鹿(すずか)本を祖本とするから、中世にはほとんど流布しなかったらしく、中世文学に直接的な影響を与えた形跡がない(日本大百科全書)、とされる。
芥川龍之介は、この説話集を素材に、『羅生門』『芋粥』などを小説化したためか、
美しい生まなましさ、
今昔物語の芸術的生命であると言っても差し支えない、
とまで評価している(本書・解説)ようだが、その評価の是非とは別に、従来の価値観からの、
霊験譚、
因果応報譚、
に収まりきれない、従来目を向けられることのなかった、
山林修行民間布教の聖(ひじり)、
武士、
盗賊、
漁師、
庶民の女、
小女、
等々を取り上げているところが面白く、まるでタブロイド紙のように盛りだくさん。
大織冠(藤原鎌足)、始めて藤原の姓を賜りし語(ものがたり)、
から始まった「本朝」世俗部は、
平将門、謀叛を發して誅せられる語、
藤原純友、海賊なるによりて誅せられる語、
といった政治ネタから、
内裏の松原において、鬼、人の形となりて女を食ひし語、
狐、人につき、取られたる玉を乞ひ反して、恩を報ぜし語、
人妻、死にて後、本の形となりて舊夫に會ひし語、
寸白(すばこ)、信濃守に任じてとけうせし語、
といったもののけネタ、
金峯山の別當、毒茸を食ひて酔はざりし語、
左大臣の御讀經所の僧、茸に酔ひて死にし語、
安房守文室清忠、冠を落として笑はれし語、
左京大夫、異名を付けられし語、
池の尾の禪珍内供の鼻の語、
といったゴシップネタ、
湛慶阿闍梨、還俗して高向公輔となりし語、
常澄安永、不破の関に於いて京にある妻を夢見し語、
燈火の影に映りて死にし女の語、
といった因縁ネタ、
蛇、女陰を見て欲を發し、穴を出でて刀に當りて死にし語、
蛇、僧の晝寝せるまらを見て、呑みて淫を受けて死にし語、
といった下ネタ、
但馬國に於いて、鷲若子をつかみ取りし語、
土佐國の妹兄、知らざる島に行き住みし語、
夫の死にたる女人、後に他の夫に嫁がざりし語、
といったうわさ話ネタ等々と、そのバリエーションの多さ、豊かさには圧倒される。
ちょっと変わっている「由来譚」は、
信濃國のをばすて山の語、
で、
年老いたるをばを、嫁に強いられて、深き山に捨てに行ったものの、終夜(よもすがら)寝られず翌日迎えに行った、
話なのだが、
さて其の山をば、それよりなむ姨捨山(をばすてやま)と云ひける、
と、
をば→姨、
と、「姨捨山」の由来譚になっている。
なお、『日本霊異記』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/490129996.html)、『宇治拾遺物語』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/484515144.html)については触れた。
参考文献;
佐藤謙三校注『今昔物語集』(角川文庫) |
|
炭焼小五郎伝説 |
| 柳田國男「海南小記(柳田国男全集1)」を読む。
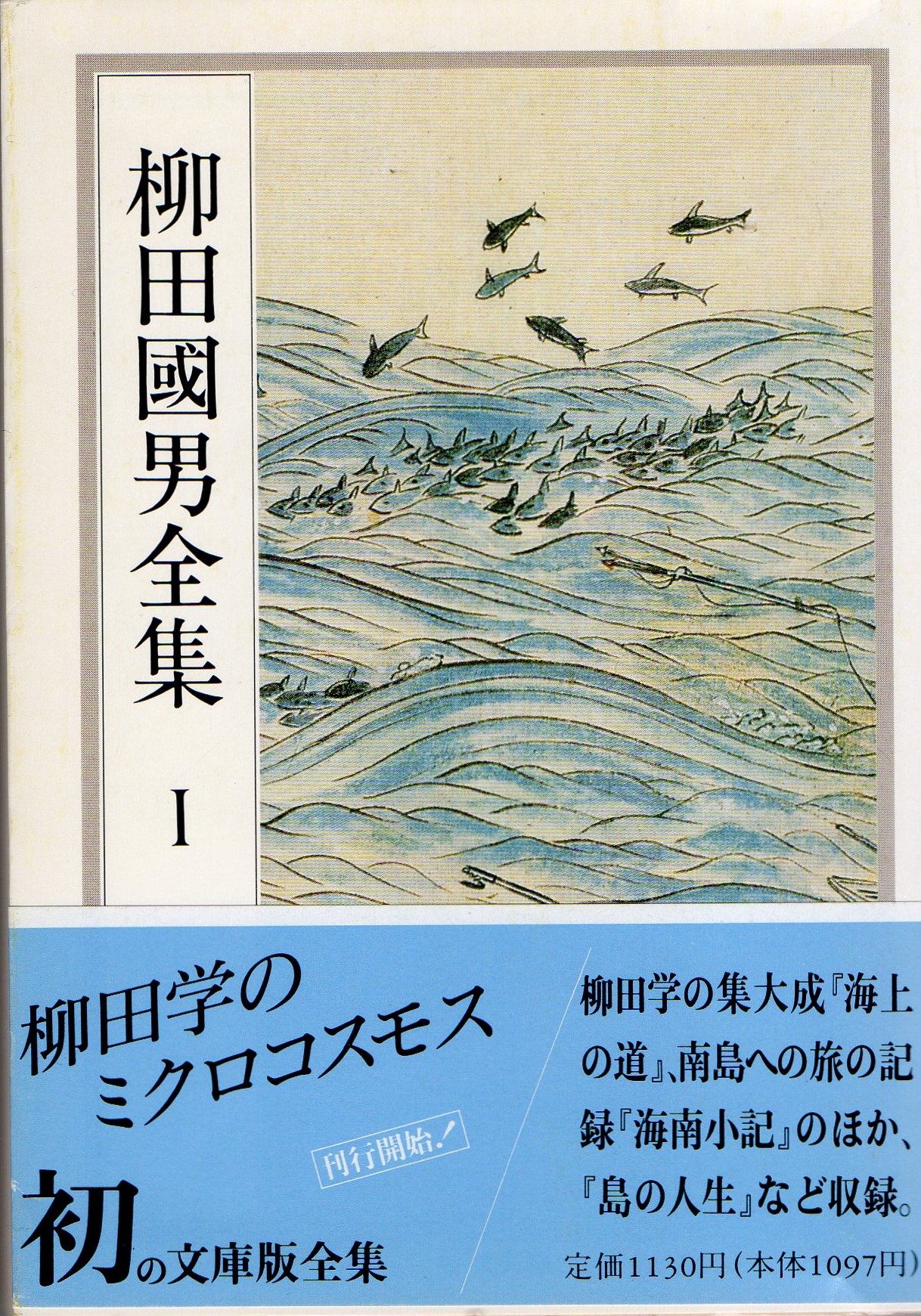
本書には、
海上の海、
海南小記、
島の人生、
が載っているが、『海上の道』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488194207.html)は別に触れた。『海南小記』は、官吏を辞した後、宮崎、鹿児島、沖縄、宮古、八重山を訪れた紀行文である。それだけに気楽に読めそうなものだが、文中随所に出てくる蘊蓄、学識に基づく含意のある意味が、とうてい追い切れず、おそらく筆者が書こうとしたことの半分くらいしか追いきれない気がする。たとえば、
「伊座敷の町からこの島泊まで、元はいちばん高い山の八分まで登って越えるのが、近いゆえに唯一の通路であった。しかるに隣の西方区を通って、最近に一間幅の路を一建立で開いた人がある。それが豊後から来た炭焼だと聞いたときは、何だか古い物語のようで嬉しかった。炭焼は十何年の勤倹でこしらえた家屋敷を売り払い、まだ入費が足らぬのでわざわざ国へ金を取りに行って来た。そうしてできあがった新道の片端に、かの小五郎の小屋のごときものを建てて住んでいる。どうしたこんな志を立てたのか、また末にはいかなる果報が来るものやら、自分などには分からずに終りそうである。」
とある「小五郎」とは、本書で後に出でくる『炭焼小五郎が事』の、豊後の炭焼き小五郎という民話の主人公のことである。地元の人はともかく、このことを知らないと、この一文は、ただ素通りするしかない。こんな文章が頻繁にある。
この紀行は、1919年に行われているので、その当時の風俗がよく描かれているのもまた面白い。例えば、入墨について、
「沖縄県では一般にハチジというようである。慶長の初めにできた『琉球神道記』にも、入墨の風俗を述べて針突(はりつき)と書いているから、ハッツキの転音であることがよく分る。(奄美)大島では釘突(くぎつき)というと『南島雑記』にあるのは、これも針突の誤写ではなかろうか。何にしても二島分立の以前から、弘く行われていた風俗であって、それが時を経るうちにわずかずつの変化を見た。大島の方では、もう珍しいというほどに、針突をした人が少なくなっている。」
といった一文には、入墨禁止の布令のあとの名残がみられている。そうした興味は尽きない紀行だが、やはり僕には柳田國男の真骨頂は、『海南小記』に収められている、
炭焼小五郎が事、
と題された、全国にある、
小五郎長者、
という民話の追跡であると思える。安芸・賀茂郡の盆踊りで、
筑紫豊後は臼杵の城下、
藁で髪ゆた炭焼小ごろ、
と歌われるように、
山中で一人炭を焼いていた男(豊後では小五郎)がいて、
都から貴族の娘が観世音のお告げで押しかけ嫁にやってきて、
炭焼きは花嫁から小判または砂金をもらって市へ買い物に行く途中、水鳥を見つけて、それに黄金を投げつけてしまう、
なぜ大事な黄金を投げつけたかと戒められると、
あんな小石が宝になれば、
わしが炭焼く谷々に、
およそ小笊で山ほど御座る、
と、山にごろごろある金塊を拾ってきて長者になる、
という話である。この話の四つの要点のうち、三つまで具備した話が、
「北は津軽の岩木山の麓から、南は大隅半島の、佐多からさして遠くない鹿屋の大窪村にわたって、自分の知る限りでもすでに十幾つかの例を算え、さらに南に進んでは沖縄の諸島、ことには宮古島の一隅にまで、若干の変化をもって、疑いもなき類話を留めている。」
という。こうした「炭焼」伝承の背景に、
鋳懸(いかけ)、
と称する人たちを想定し、
鋳物師、
あるいは
鍛冶、
つまり、
金屋、
と称する人々がいたと考え、こうひとつの仮説を立てる。
「炭焼小五郎の物語の起源が、もし自分の想像するこどく、宇佐の大神の最も古い神話であったとすれば、ここに始めて小倉の峰の菱形池の畔に、鍛冶の翁が神と顕れた理由もわかり、西に隣した筑前竈門山の姫神が、八幡の御伯母君とまで信じ伝えられた事情が、やや明らかになって來るのである。(中略)播磨の『古風土記』の一例において、父の御神を天目一箇(あめのまひとつ)命と伝えてすなわち鍛冶の祖神の名と同じであったことは、おそらくこの神話を大切に保管していた階級が、昔の金屋であったと認むべき一つの証拠であろう。」
そしてこの炭焼民話は、
竈神の由来、
にまでつなげていくのである。この一連の流れは、いつも見る、柳田手法ではあるが。
本書の中で、もう一つ、八丈島からは南へ約60km程度離れている、
青ヶ島、
が、天明の大噴火で327人のうち八丈島への避難が間に合わなかった130人余りが死亡した噴火から、帰還を果たすまでの約40年間の、
青ヶ島還住記、
の住民の奮闘記は、今日の同島のことを思うと、なかなか感慨深い。以降、噴火はなく、現在、
人口は170人、113世帯、
とある(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E3%83%B6%E5%B3%B6)。
なお、柳田國男の『遠野物語・山の人生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488108139.html)、『妖怪談義』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488382412.html)、柳田國男『海上の道』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488194207.html)、『一目小僧その他』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/488774326.html)、『桃太郎の誕生』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489581643.html)、『不幸なる芸術・笑の本願』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/489906303.html)、『伝説・木思石語』(http://ppnetwork.seesaa.net/article/490961642.html)については別に触れた。
参考文献;
柳田國男『海南小記(柳田国男全集1)』(ちくま文庫) |
|
遊びをせんとや生まれけむ |
| 佐々木信綱校訂『梁塵秘抄』を読む。
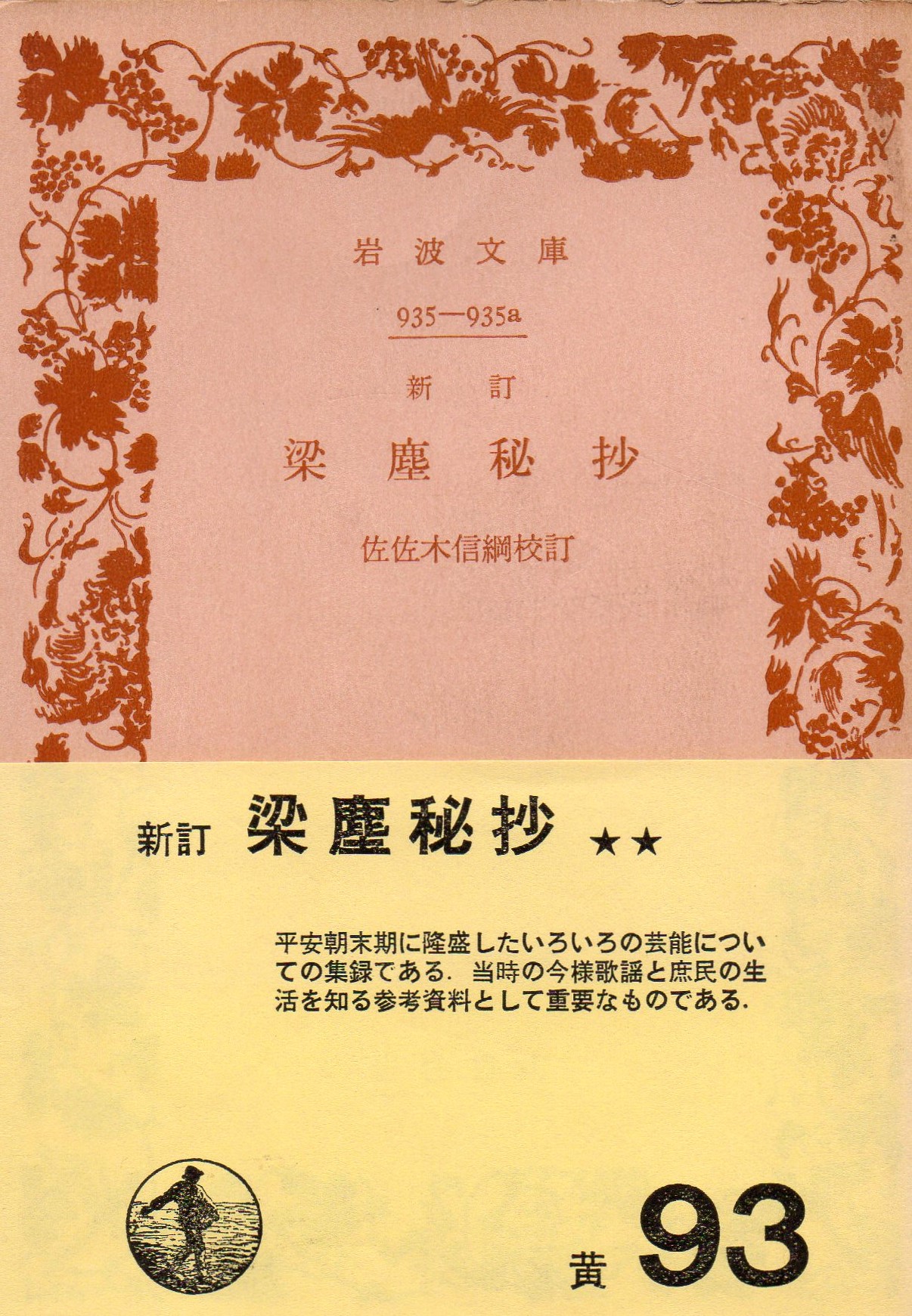
『梁塵秘抄』のタイトルは、「梁塵」(http://ppnetwork.seesaa.net/article/492471821.html)で触れたように、
梁塵、
とは、文字通り、
建物の梁(はり)の上につもっている塵(ちり)、
の意だが、
虞公韓娥といひけり。こゑよく妙にして、他人のこゑおよばざりけり。きく者めで感じて、涙おさへぬばかりなり。うたひける聲のひびきにうつばりの塵たちて、三日ゐざりければ、うつばりのちりの秘抄とはいふなるべし、
と、
梁塵秘抄、
となづけた所以を書いてある(『梁塵秘抄』巻第一)通り、
舞袖留翔鶴、歌声落梁塵(「懐風藻(751)」)、
と、
梁塵を動かす、
梁(うつばり)の塵を動かす、
梁(うつばり)の塵も落ちる、
という故事を生んだ、
歌う声のすぐれていること、
素晴らしい声で歌うこと、
の意、転じて、
音楽にすぐれている、
の意で使われる(広辞苑)。これは、『文選』(もんぜん 南北朝時代の南朝梁の昭明太子蕭統によって編纂された詩文集)の成公綏「嘯賦」の李善注に引く、劉向の「七略別録」に、
劉向別録曰……漢興以来善雅歌者、魯人虞公、発声清哀、遠動梁塵(文選)、
と、みえる故事に由来する(故事ことわざの辞典)。
本書は、
梁塵秘抄巻一(断簡)、
梁塵秘抄巻二(全巻)、
梁塵秘抄口傳集巻一(断簡)、
梁塵秘抄口傳集巻十(全巻)、
梁塵秘抄口傳集巻十一(全巻)、
梁塵秘抄口傳集巻十二(全巻)、
梁塵秘抄口傳集巻十三(全巻)、
梁塵秘抄口傳集巻十四(全巻)、
が収められているが、
梁塵秘抄巻一(断簡)、
梁塵秘抄巻二(全巻)、
梁塵秘抄口傳集巻一(断簡)、
梁塵秘抄口傳集巻十(全巻)、
のみが、巻十に、
大方詩を作り、和哥をよみ、手をかくともがらは、かきとめつれば、末のよ迄もくつる事なし。こゑのわざの悲しき事は、我身かくれぬる後とどまる事のなき也。其故に、なからむあとに人見よとて、未だ世になき今様の口傳をつくりおく所なり、
と、後白河法皇自身が記している通り、
後白河法皇の御撰、
であり、『梁塵秘抄』はもと、
本編10巻、
口伝集10巻、
だったと見られている。もし揃っていれば、
五千首を数えて『万葉集』にも匹敵する大歌謡集であった、
と推測されている(馬場光子『梁塵秘抄口伝集 全訳注』)。しかし現存するのはわずかな部分のみである。本編は、巻第一の断簡と、巻第二しか知られていないが、歌の数は、
巻第一が21首、
巻第二が545首、
の、あわせて、
566首、
であが(ただし重複があるので、もう少し少ない)。巻第一の最初に、
長唄10首、古柳34首、今様265首、
とあるので、完本であれば巻第一に、
309首、
が収められていた(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%81%E5%A1%B5%E7%A7%98%E6%8A%84)ことになる。
また、口伝集の巻第十一以降については謎があり、御撰ではなく、後白河法皇の近辺者によって書かれたものと推測されている。
『梁塵秘抄』というと、
遊びをせんとや生(う)まれけむ、戯(たはぶ)れせんとや生(むま)れけん、遊ぶ子供の聲きけば、我が身さへこそ動(ゆる)がされ、
舞え舞え蝸牛(かたつぶり)、舞はぬものならば、馬(むま)の子や牛の子に蹴(くゑ)させてん、踏破(ふみわら)せてん、真(まこと)に美しく舞うたらば、華の園まで遊ばせん、
といった、
雜八十六首、
に入る歌が有名だが、
広義今様には内容・旋律様式から分類された「部」、
があり、
A 教の流行を反映して経典を歌謡化した法文歌(娑羅林 しゃらりん)をはじめ、これと似た曲節の「只の今様」、 また片下、早歌など、
B 東国をはじめ新たに地方から都に入った祭祀関連歌謡の神歌。中でも足柄十首・黒鳥子・旧河・伊地古は大曲(秘曲)とされた、
C 長歌・旧古柳・権現・御幣・十二所の心の今様・高砂・双六などの様々な旋律様式の「様の歌(物様)」、
D 農耕神事・儀礼を出自とする歌謡(田歌。あるいは臼歌・杵歌なども含まれるか)、
の、四グループに分かれる(馬場光子『梁塵秘抄口伝集 全訳注』)。しかし、今日の我々にとっては、
仏は常にいませども、現(うつつ)ならぬぞあわれなる、人の音せぬ暁に、ほのかに夢に見え給ふ、
四大聲聞(しだいしょうもん)いかばかり、喜(よろこび)身(み)よりも餘るらむ、我等が後生の佛ぞと、たしかに聞きつる今日なれば、
我等は何して老いぬらん、思へばいとこそあはれなれ、、今は西方極楽の、彌陀の誓(ちかひ)を念ずべし、
などといった法文歌よりも、
わが子は二十(はたち)に成りぬらん、博打(ばくち)してこそ歩くなれ、國々の博黨(ばくたう)に、さすが子なれば憎かなし、負(まか)いたまふな、王子の住吉西宮、
媼(をうな)が子供は唯二人、一人の女子(ご)は二位中将殿の厨雜仕(くりやざうし)に召ししかば、奉(たてま)てき、弟(をとと)の男子(をのこ)は、宇佐の大宮司(ぐし)が、早船舟子(ふなこ)に乞ひしかば、奉(また)いてき、神も仏も御覧ぜよ、何に祟りたまふ若宮の御前ぞ、
冠者は妻設(めまうけ)に來んけるは、かまへて二夜(ふたよ)は寝にけるは、三夜(みよ)といふ夜の夜半(よなか)ばかりの暁に、袴取(はかまと)りして逃げけるは、
わが子は十餘に成りぬらん、巫(かうなぎ)してこそ歩くなれ、田子の浦に汐ふむと、いかに海(あま)人集(つど)ふらん、正(まさ)しとて、問いみ問はずみ嬲るらん、いとをしや、
といった、「雑首」にある、庶民の息吹の聞こえる歌が、やはりいいし、
聖(ひじり)の好む物、樹の節(ふし)鹿角(わさづの)鹿(しか)の皮、蓑笠錫杖木欒子(もくれんじ 木槵子)、火打笥(け)岩屋の苔の衣(ころも)、
此の頃京(みやこ)に流行(はや)るもの、肩當(あて)腰當烏帽子止(えぼうしとどめ)、襟の立つかた、錆烏帽子、布打(ぬのうち)の下の袴、四幅(よの)の指貫、
此の頃京(みやこ)にはやるもの、わうたいかみかみゑせかつら、しほゆき近江女(あふみめ)女冠者、長刀(なぎなた)持たぬ尼ぞなき、
遊女(あそび)の好むもの、雜藝鼓(つづみ)小端舟(こはしぶね)、簦(おほがさ)翳(かざし)艫取女(ともとりめ)、男の愛祈る百大夫(ももだゆう、ひゃくだゆう 傀儡師(子)や遊女が信仰する神)、
凄き山伏の好むものは、あぢきないくたかやまかかも、山葵(わさび)こし米(よね)水雫(みづしづく)、澤(さは)には根芹(ねぜり)とか、
聖の好むもの、比良の山をこそ尋(たづ)ぬなれ、弟子遣りて、松茸平茸滑薄(なめすすき)、さては池に宿る蓮(はす)の這根(はいね)、芹根(せりね)蓴菜(ぬなは 蓴菜(じゅんさい))牛蒡(ごんぼう)河骨(かはほね こうほね)うち蕨(わらび)土筆(つくつくし)、
武者(むさ)の好むもの、紺(こむ)よ紅(くれなゐ)山吹濃き蘇芳(すわう)、茜(あかね)寄生樹(ほや)の摺(すり)、良き弓胡簶(やなぐひ)馬(むま)鞍太刀腰刀(こしがたな)、鎧冑(よろひかぶと)に、脇立(わきだて)籠手(こて)具して、
心凄きもの、夜道船道(ふなみち)旅の空、旅の宿、木闇(こぐら)き山寺の経の聲、思ふや仲らひの飽かで退く、
隣の大子(おほいご)のまつる神、頭(かしら)の縮(しじ)け髪、ます髪額髪(ひたひがみ)、指の先なる拙神(てづつがみ)、足の裏なる歩きがみ、
池の澄めばこそ、空なる月影も宿るらめ、沖よりこなみ(前妻)の立て来て打てばこそ、岸も後妻(うはなり)打たんとて崩るらめ、
等々といった、当時の風俗が垣間見える歌がいい。
参考文献;
佐々木信綱校訂『梁塵秘抄』(岩波文庫)
馬場光子『梁塵秘抄口伝集』(講談社学術文庫) |