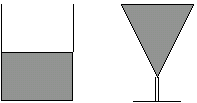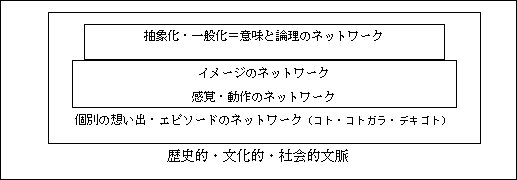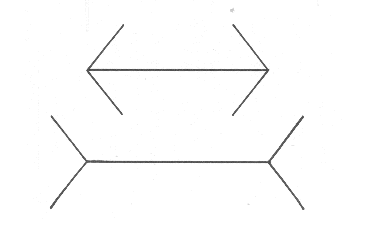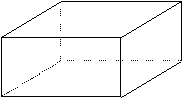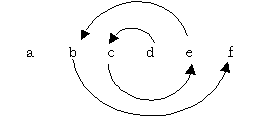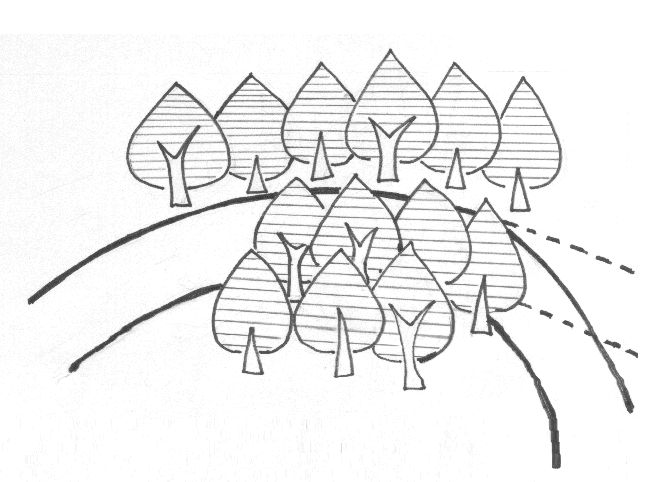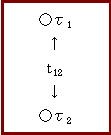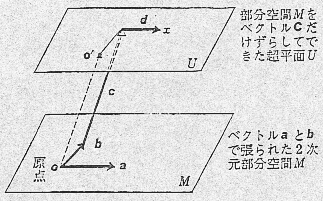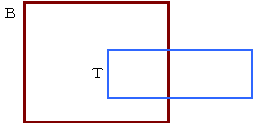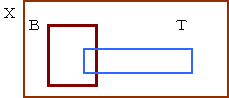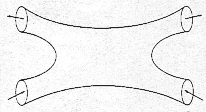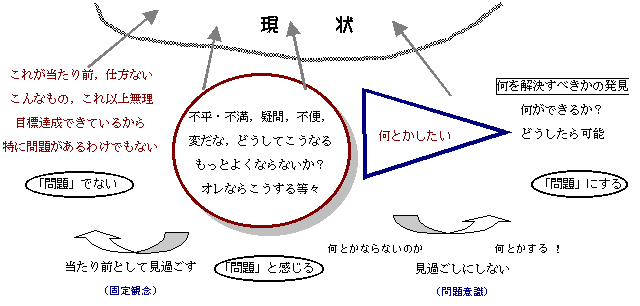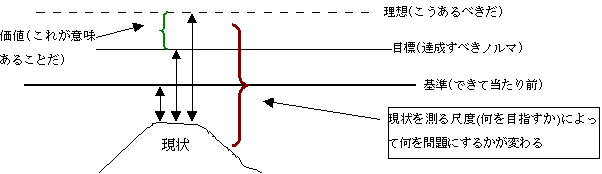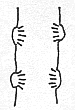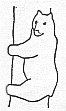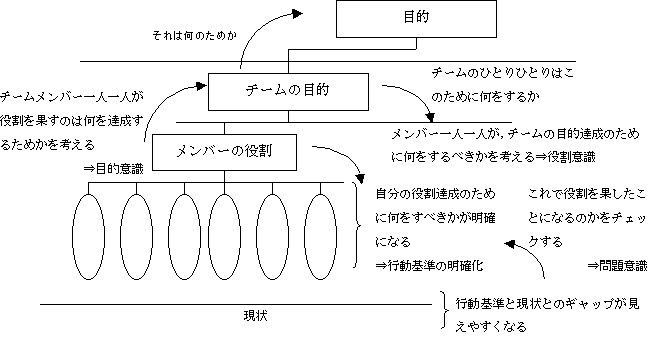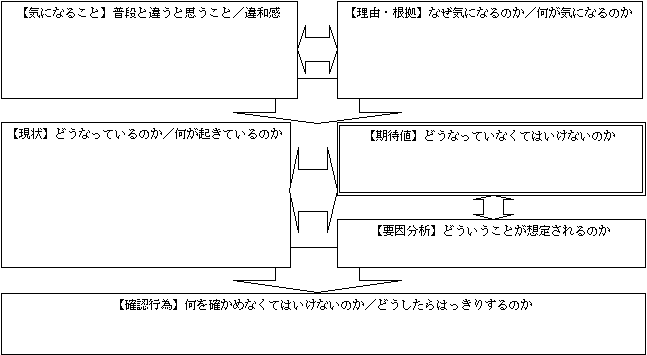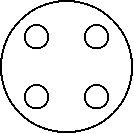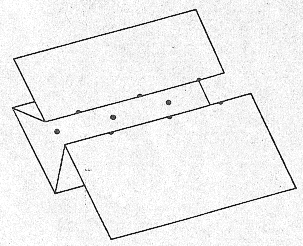-
プロフェッショナルとは何か
プロとアマの違いは何か
プロであるとは,その能力と成果物で“金”が取れることには違いがないが,最大の特色は,自分独自の(オリジナルな)“方法論”をもっ ていることだ。どんなに経験したことのない,未知の(領域の)問題にぶつかっても,瞬時に(といかないこともあるが),自分なりにどうすればいいか,どういうやり方をすればいいかの判断と決断ができることだ。それは,また,自分のやり方に対する批評力があることをもいみする。つまり,自分の方法の方法をもっていることであり,自分のコトバで自分のやり方(の新しさ,独特さ)と内容(の独自性と共通性)を語れる(コトバをもっている)ということである。
人の能力は,
能力=知識(知っている)×技能(できる)×意欲(その気になる)×発想(何とかする)
と分解できる。「知っていて」「できる」ことだけを,「その気になって」取り組んでも,いままでやったことをなぞるだけのことだ。いままでやったことがない,いまのスキルではちょっと荷が重い,といったことに取り組んで,「何とかする」経験をどれだけ積んだか,でその人の能力のキャパシティは決まる,と言っても過言ではない。
そうして積み上げた知識と経験を,ただそのまま体験として蓄積するだけでは,プロにはなれない。それを,批評するパースペクティブを持っていること,つまり,自分の方法の方法,プロフェッショナルのプロフェッショナル,つまりプロフェッショナルであるとは,メタプロフェッショナルであることなのである。それは,自分が何の,どんなプロフェッショナルであるかを,コトバにできることでもある。人に伝えられるコトバをもっているかどうか,がプロとアマの本質的な差のように思う。言ってみれば,人は生きてきた分だけ,量や質はともかく,知識と経験は蓄積される。人の能力はそこにしかない。それをどう生かすかにしか,自分を生かす途はないのである。それをどうコトバにするか,そこに自分の“方法論”を明確化する筋がある。
- 一流と二流の差
世の中には,一流と二流がある。しかし,二流があれば,三流もある。三流があれば四流がある。しかし,それ以下はない。
「一流の人」とは,常に時代や社会の常識(当たり前とされていること)とは異なる発想で,先陣を切って新たな地平に飛び出し,自分なりの思い(問題意識)をテーマに徹底した追求をし,新しい分野やものを切り開き,カタチにしていく力のある人。しかも,自分のしているテーマ,仕事の(世の中的な)レベルと意味の重要性ががわかっている。
「二流の人」とは,自らは新しいものを切り開く創造的力はないが,「新しいもの」を発見し,その新しさの意義を認める力は備えており,その新しさを現実化,具体化していくためのスキルには優れたものがある。したがって,二番手ながら,現実化のプロセスでは,一番手の問題点を改善していく創意工夫をもち,ある面では,創案者よりも現実化の難しさをよくわきまえている。だから,「二流の人」は,自分が二流であることを十分自覚した,謙虚さが,強みである。
「三流の人」とは,それがもっている新しさを,「二流の人」の現実化の努力の後知り,それをまねて,使いこなしていく人である。「使いこなし」は,一種の習熟であるが,そのことを,単に「まね」(したこと)の自己化(換骨奪胎)にすぎないことを十分自覚できている人が「三流の人」である。その限りでは,自分の力量と才能のレベルを承知している人である。
自分の仕事や成果がまねでしかないこと,しかもそれは既に誰かがどこかで試みた二番煎じ,三番煎じでしかないこと,しかもそのレベルは世の中的にはさほどのものではないことについての自覚がなく,あたかも,自分オリジナルであるかのごとく思い上がり,自惚れる人は,「四流以下の人」であり,世の中的には“夜郎自大”(自分の力量を知らず仲間内や小さな世界で大きな顔をしている)と呼ぶ。
少なくとも,自分自身と自分の仕事と成果に誇りをもっていること,あるいは誇りをもてるようにするにはどうすればいいかをたえず考えていることが,四流かそうでないかの分かれ道であるように思う。
せめて三流にとどまりたいもの……
自戒として,せめて三流でありたいし,それは能力の問題ではなく,意識してできる,生き方の問題であるように思う。そのためには,自分の能力と実力の現状に自足せず,世の中の水準,流れと対比しながら,たえずこれでいいのかと自らを振り返り,チェックし,レベルアップする努力を続けていることが必要である。例えば,(ある本から抜き出したものだが)次のような自問をしてみる。
そもそも自分の職業は何か(何屋か?)
これまで実際にやりとげたことは何か?
顧客の中で誰かそのことを証明してくれるか?
自分の技能(スキル)が最高水準にあることを示すどんな証拠があるか?
競争社会を乗り切っていくのを助けてくれるような新しい知人を,会社をこえて何人得たか?
今年度末の(職務)履歴には昨年と違った内容のものになるか?自分一人である程度の領域がカバーできる力があればあるほど,期待する水準が高いので,自分一人で何でもできるなどと思い上がらず,組織やチームで推進していく(達成度を高める)にはどうしたらいいかを考えている。一人で得られる(世の中の水準から見た)成果や情報力はチームや組織で得られるものに比べれば格段の時間とコストがかかるのだから。
- 問題の見方・見え方
問題はすべて私的である
認知心理学の知見では,“いまはこういう状態である”という初期状態を,それとは異なった別の“~したい状態”(目標状態)に転換したいとき,その初期状態が“解決を要する状態”つまり“問題”となる。
言い換えると,眼前の状態を“問題”とするかどうかは,目標状態をもっているかどうかによるということにほかならない。つまり目標がなければ,初期状態に問題は存在しない,ということを意味する。
ここから3つのことが言えるだろう。
第1は,問題とは,所与ではなく,当該の状態を問題と感ずる人にとってのみ存在するという意味で,「私的である」ということである。だから共通な問題が“ある”のではなく,私的な問題が共通な問題に“なる”あるいは共通な問題に“する”にすぎない。
第2は,目標状態の中身を,いわゆる“目標”のほかに,例えば達成すべき課題水準,維持すべき水準,保持すべき正常状態,守るべき基準といったものに敷延して考えていくと,目標状態とは,自分に負荷している目的意識からくるものであり,それがあるからこそ現状に対して“問題”を感じさせるのだと言えるだろう。だから関心や興味があれば問題を感じるというのは誤解にすぎない。関心や興味が目的意識への端緒になるから,そのような錯覚を生むだけで,関心があってもそこから自分の目標を明確化していなければ,現状との“解決すべき”ギャップは鮮明でなく,ぼんやりした不安や不満といった情緒にとどまるだけだろう。
更に第3に,目標と関わる心理状態を,「~したい」(欲求)状態だけでなく,他に「~しなくてはいけない」(使命・役割)「~する必要がある」(役割)「~すべきだ」(義務)「~したほうがよい」(希望)といったものまで想定してみると,それは,初期状態を認知する人が,そこでどういう立場(視点)で状況に向き合っているかが鮮明になってくる。逆に言えば,どういう心理状態が目標を持たせるかがはっきりしてくる。
よく問題意識という便利な言葉を多用するが,問題意識があるから問題が見えるのではない。問題が見える立場と意識があるから問題意識というものがあるように見えるだけだ。肝心なのは,どういう状態だと目標と総称できるものを持てるか,ということにほかならない。これだけが大事なことだ。
以上から言えることは,目標もなく,問題の見方や解決法をいくら仕入れても,多分問題が見えてくることはないだろう,ということだ。大切なのは問題の見え方だ。だが,見え方には無自覚的なことが多く,だから,例えば「問題意識が強い」「弱い」というような言い方をしてしまう。そしてどうやったら問題意識を強化できるか,という逆立ちした発想になってしまう。問題意識とは,問題が見えやすい状態にいるということにすぎない。問題意識は教化できないが,問題の見えやすい状態を強化することはできるのである。それには目標をはっきりさせることなのだ。
問題へのアクセスパターン
「問題を解くとき,ひとりで解くよりも,グループで解くほうが問題をたくさん解くが,このようなグループの経験は,その後のひとりで問題を解く力を向上させない」と言われる。立花隆も,ひとりで解ける作業過程をわざわざ何人かに分割してやらせているにすぎないと,同じような趣旨で問題解決訓練に批判的なことを述べていた。
それは,問題を与えられた(あるいは解くことを強制された)箱庭的状況が,はじめから問題とその解答があることが前提としてしまっていることがあるからにほかならない。現実には何が問題かは自明ではないし,それを問題とすべきかどうかでさえ一義的ではない。現にわれわれは,「問題外」「問題にならない」「問題にする必要もない」と,問題にすることを切り捨てることが多いし,逆に問題にもならないことを問題視して失笑されることも少なからず経験したはずだ。単に知識・経験がなくて未知なだけで,誰にとっても問題にもならないことを問題にしたり,見当違いのところに首を突っ込んでいるだけだったり,錯覚や幻想や勘違いは両手に余る程あるはずだ。まして今や問題がはっきりしないだけではなく,何が解答かさえ,あるいは解答があるかどうかさえわからないことが多いのである。
とすれば何を目標とし,目標とどう関わるから,何が問題となるかという,“問題”へ私的な関わり方を省略したのでは,“問題”そのもののもつ個人的な側面を欠いた奇麗事になってしまうのである。確かに協働することで,自分と違った視点の取り組み方から刺激や気付きを受けることがないとは言えないが,それは各自が自分の問題への関わりについて経験を積んだ後にこそ意味があるのである。
熟達者は,問題の情報に含まれる既知の組み合わせによって,新しい知識を見いだせるような関係式(文脈)を考えて新しい知識を求め,それと既知とを組み合わせていく,という前向きの方法で問題を解くのに対して,素人は,まず問題情報から最終的に求める未知を見いだし,次にその未知を求めるのに適当な関係式を記憶から捜しだし,それに頼って最終的未知を求めるのに必要な何らかの下位目標を見つけだし,それを求めるのに必要な関係式をさがす,という後向きの方法で解く,とされる。その違いは,熟達者は,例えばチェスだと,50,000~100,000のパターン化された知識ユニット(碁でいえば石と石の意味ある関係図式)をもっていて,問題の中から解決への手掛かりとなる意味ある図式(情報)を見付け出しやすいのに,素人はバラバラの断片的知識しかないため,意味のある情報を見付け出しにくいことによる,とされている。
そうした関係づけられた知識が問題を見えやすくするということにほかならない。知識に差があるとしても(それは時間をかけて身につければいい),今の状況を既知の類似パターンに置き換え,状況に合わせて持っている知識を転換したり,組み合わせたりしながら,問題を既知化していくアプローチは学べるはずである。それは集団ではできない個人の認知プロセスなのである。
解く問題だけではない
情報化時代は,問題の解き方がわからないだけではなく,問題の意味そのものがわからない問題が増える。それはコードの解読をするような定量的情報よりは,モードの解説やコードの文脈を読み取る定性的情報の方がより重要化になるからにほかならない。
情報は,一般に「不確実性を減少するもの」という意味で考えられている。そこでは,どこかにそういう価値ある情報があるものだという考え方が前提にされている。どこかにある情報を手に入れれば,正解が解けるというように,だ。しかし,ある価値が前提になっていた時代は終わっている。何が価値か何に意味があるかは不透明であり,正解はどこにもないとなれば,情報そのものから意味や価値を発見することがより重要になってくる。つまり,情報は単に「不確実性を減少する」ためにどこかから収集・集計してくればいいものではなく,「新たに見付け出す(出現してくる)」ものになったのである。
それは,別の言い方をすれば,記号に概念(意味されるもの)を結びつけることにほかならない。記号と意味との出会いは全くの偶然でしかなく,そこで見付けた意味に価値があるのではない。価値は,同時に現れた前後に結びあっている他の記号との間に形成されるにすぎない。その文脈をどう読むかが情報の発見にほかならない。
それは問題についてもいえる。今日目標そのもの(あるいは現状そのものすら)が曖昧で,問題そのものが不明確なことが少なくない。とすれば,問題はただ意味を解けばいいのではなく,意味を創り出さ(発見し)なくてはならないのである。
解く問題にとっては,どう解くかの手続きを発見するにすぎない。例はまずいが,パズルを解くのと似ている。しかし創る問題は,価値と意味を見付けなければならない。それは目標そのものの発見といっていい。何を目標とするか,それにどう関わっているかにこそ,その人にとっての当該問題の意味と価値があるのだから。
だが意味が発見できれば,その曖昧な問題は解く問題に転換する。あるいは3択4択といった選択問題に転換すれば,解く問題に変換する。問題の創出とは,解ける問題にどう転換するかということをも意味している。
それには,事態を次のように組み替えてみることが有効になるだろう。
①特徴の抽出・組み合わせによる知っている型はめ(知覚的な型はめ,関係構造の型はめ,文脈はめ)
②経験的な文脈(状況・雰囲気)による解釈(つじつま)あわせ(文脈の異同比較による新しい文脈にあてはめる)
③同型性の認知(構成要素を知っている世界へ対応させてみる)
④縮小世界の再構成(ミニチュア化して全体の関係をつかむ)
⑤極限への拡大(極端な状態を想定することで状況の境界を想定する)
⑥視点の移動・転換(見る位置を変えることでパースペクティブを変える)
⑦立場の転換(主客を変えることで見えるものを転換してみる)
⑧視野の拡大・拡張(局所のアップ,細部の拡大によって景観を変貌させる)
⑨ストーリーの創造(全く別の時空の中で自由に展開させてみることで,制約条件を解き放す)
視点の移動
問題の発見とは,過去の(既知の)知識の組み替えにほかならない。どうすればそれがしやすくなるかが発想法にほかならない。それは,過去の経験・知識をどうつかえば現状の意味をとらえることができるかの工夫にほかならない。
組み替えという場合,型はめや要素の組み合わせで新しい意味を再構成する場合と,新しい文脈の中に並べることで新しい意味を発見する場合の2つのパターンがあるが,いずれも,現在の自分の視点と視野を変換することによってしか難しい。
そのための方法は,列挙したが,それを整理すると,「視点の移動」「文脈の変換」「発想域(次元)の拡張」「ストーリー(起承転結)の構成」の4つになるだろう。
視点の移動には,
視覚の視点(視点)
観念の視点(観点)
の2つがある。いわば知覚的な視点と思考の視点ということができる。
前者は,視角の変換,視野の転換・転倒などを含めた,まさにものを見る視点の移動・変動であり,接近したり遠ざかったり,分離したり統合したり,逆に見たり反対側から見たり,上下前後左右から見たり,横から見たり縦から見たり,といった視点を移動させていくことで,ものの見え方を変えていこうというものだ。
視点ということから見れば,拡大とは視点の接近であり,縮小とは視点の後退である。分離とは視点の分散であり,統合とは視点の集約ということになる。視点の移動は移動に伴って物理的に見え方を変えてしまおうということにほかならない。
われわれは,通常透視画法(一点を視点としての遠近法でみた画像)のような特定の視点から見た対象像でものをとらえていると考えがちであるが,われわれは一方の視点から見ている対象の別の局面についても,それが見えていないだけでどうなっているかを経験から知っていることが多い。例えば,立方体を描くとき,見えない側面をよく点線で描くように,別の局面の見え方を想像していることが多い。つまり,1つの視点からの対象を見ているときでさえ,その形が全体像の1局面であること,全体を見渡す途中の像であることを承知して見ているのである。
視点の移動は,いろいろな局面に直面させることでそうしたさまざまな視覚像の経験を呼びさますことになるはずである。
観点というのは,対象に意味(あるいは価値=機能)が固定されてしまっている場合が多い。例えば挟みは切るものと固定した結合ができてしまい,それ以外の視点でみなくなっている。それを,対象を変容(質)させるような,伸ばしてみる・縮めてみる,軽くしてみる・重くしてみる,薄くしてみる・厚くしてみる,といった転倒した視点や,代用・応用・転用といった敢えて異なる価値(意味)を見付け出させる視点に移動することで,見え方を転換させようとすることにほかならない。オズーボーンのチェックリストは多く視点の移動の範疇に入るはずである。
また立場の転換も,視点を相手に置くという意味では,視点の移動の中に含めることができる。それは見る視点を移動することで,相手の立場に“なる”,相手の視野が自分のものに“なる”,相手の気持が自分のものに“なる”といった“なる”視点への転換とよぶことができる。
文脈の転換
ものの見え方とは,ものの像の違いではなく,ものを視る視点の違いにほかならない。視点を変えることで,おのずと像が異なって見えてくること,それが視点の移動の意図である。それならば,対象そのものの状況・条件を組み替えてれば,視点を転換させ新たな意味が見えてくるはずである。それが文脈の転換にほかならない。
例えば,「馬鹿やろう」という言葉も,男同士の睨み合った状況と男女の睦言では全く違ってくる。文脈を変えることで,異なった価値と意味が見えてくることを意図しているといっていい。文脈崩しには次のチェックリストが有効になる。
◇主体を変える
これはどの視点から見るかということの転換でもある。相手から見たらどうなるか,例えば売る側でなく買う側(顧客側)からみたらどう意味が変わるかということでもあるし,更に掘り下げれば,何も人間の視点である必要はない。例えば細胞レベルでみたらどうなるのか,原子のレベルでみたらどうなるのか,でもいいし,逆に宇宙規模で考えてもいいし,神の視点で俯瞰してもいい。
◇対象を変える
対象を固定する必要はない。別の相手だと違う状況になるかもしれない。人間の感情が状況を見えにくくすることは多い。また対象を不動のものと見ることで,状況を固定的にしてしまっていることも少なくない。
◇時間軸を変える
これはまず,過去-現在-未来という時間を変えてみること。今でなく明日とすると見えやすくなることも多い。時間軸を直線とみなさなければ,映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の世界は成り立たないように,時間軸の設定が,文脈を変えるのである。
◇空間軸を変える
ここ・そこ・あそこ・どこの転換である。場所だけではない。方向も位置(前後左右上下)も,内外も,遠近も,表裏もある。特にわれわれの対象識知は,上下を固定してみる姿に慣れており,逆さにするととたんに識知力が落ちることが知られている。逆に言えば空間軸を転倒するだけで,馴れた文脈が異質化することを意味する。
◇理由(目的)を変える
前提としている価値・意味・基準・規範・目的・論理・感覚・感情を変えてみる。目的を下げただけで事態が急変することも少なくないはずだ。それにこだわらなくてはならないとしている自分の価値そのものを前提としないだけでも,違った見え方をするはずである。
◇方法(やり方=手段)を変える
機能を変えて代用品を使う,スタイルを変えてみる,拡大したり縮小してみる,統合したり分離してみる,手順を変えて順逆を転倒してみる,人を変えてみる,仲間を変えてみる,担当をかえてみる,不必要な部分を削除してみる,優先順位を変えてみる,下位目標を変えてみる,といったことがある。
◇水準(レベル・ウエイト)を変える
どれだけという評価基準を変えること。手段-目的を転倒することで,最終目標を先送りしたり,逆に前倒ししたりして,手段=下位目標で目標達成としたり,目標=下位目標とすることで目標水準をあげたりすることになる。また全体-部分-要素の構成を変えてみることは,目標を過小化したり逆に目標を過大化したりすることになる。
発想閾(次元)の拡張
視点の移動が見る位置によって見え方を変え,文脈崩しが状況を変容させることで見え方を変えたとすれば,通常だと自分が絶対発想しそうもない領域まで,自分の発想を拡張させてみる機会の設定が,仕事に関係ないとか日常生活に不用ということで,自分の境界外に埋もれていた,あるいは放置されていた発想領域へと発想のキャパシティを拡張することになるはずである。それはただ外に新しい意味を見付けるだけでなく,自分の内にも新しい可能性を見付けることになり,それが一層発想閾を拡大することになるはずである。そこでは,目的-手段の連続性や全体-部分-要素といった既知のつなげ方(既知のパースペクティブ)をいったん括弧に入れることが必要となる。そういう見え方をする自分の視点を括弧に入れることである。
発想領域を拡張していく手近なものは“連想”である。これには,「意味的(論理的)なつながり」を広げていくものと,「イメージ的(感覚的)なつながり」で広げていくものとがある。
意味的なものは,知識や経験で連想していくもので,言葉や概念,社会的通念が仲立ちとなっていく。感覚的なものは,音,香り,形態(図形),手触り,といった五感や知覚,感性が仲立ちとなるが,そこにはものの大小,軽重,長短,拡大・縮小,膨張・収縮,遠近,といったイメージの異同も仲立ちとなる。イメージ的なものには,空間的なものだけでなく,成長・孵化・脱皮といった時間的な変化・変質をも含めていい。
連想はその中に,類似・類比・類推を含めて,ただ同質・同形だけでなく,対比的なものへもつながりを同心円のように広げていくが,それに対して,例えば,比喩はその典型だが,ただ類似性だけでイメージの連環の拡張と意味を膨らませていくことが可能である。比喩の場合,隣接性と相似性(類似性)の二つがある。前者は,「馬」に「走る」をつなげるのに対して,後者は,「馬」に「牛」を連想していく。
確かに連想や類似性の連環によって,発想の枠は拡張していく面はあるが,これだけでは平面的で,同一レベルを尻取りゲームのように広げただけでしかない。それは結局自分のもともともっていた発想閾の限界を超えていないからという面もあるが,それ以上に,その連想のつながり方が,既知の文脈や意味のつながりからみつけたきたのだから,もともとの文脈や意味の脈絡を引きずっているからにほかならない。
だから問題は,発想したものやそういう発想そのものに意味があるのではなく,1つ1つはバラバラで点でしかない発想を全く別のパースペクティブ(一定視点からの遠近法)に入れて整理し直してみることが重要なのである。
その整理の仕方の,ポイントは,関連別やテーマ別,大小別,遠近別,優先度別という既知の意味での整理を排除することである。それはまとめることを前提としているから,どうしても整合性をつけようして,多数決で整理することになる。どうしても入り切らないものを捨てるか無理やり当て嵌めるかする。それではもともとの文脈と違いのない整序になるだけだ。むしろ入り切らないで残るデータの方から文脈を見付け,それに多数派を位置付づけ直してみるべきだ。多数決で見つかる意味では二番煎じにすぎない。
ストーリーの構成
カードに書き散らした発想を整理するとき,大体は系統的な遠近法でまとめようとする。それが時系列であれ,因果系列であれ,親近度であれ,どのみち既存の意味に集約するしかない。それでは意味がない。まとめることが目的化しては,多数決になるだけだ。どうしてもはみ出すデータの方に,既存の系列には収まり切れない新しい意味が出現しているかもしれないのである。
問題の意味が見えなくなるのも,“いま”“ここ”という制約の中で整合性のある説明(つじつま)を考えようとしているからのことが少なくない。思い切ってそういう制約を捨てた状況設定でストーリーを推測・想像してみるというのも有効である。文脈を換えると意味が変わる。異なる文脈に置くことで,別の意味が見えてくることも多い。
場面設定(いつ,どこで)と役柄(誰と誰が)から話の流れをとにかくでっちあげてみる。それはありうる(ありえた)可能性の再構成という意味をもっている。「やりたい(やりたかった)こと」「なりたい(なりたかった)こと」「あのときこうすればよかったこと」の復権である。それは選択肢として気付かず捨ててきたものの復元でもある。そういう目で見直すと,過去の成功例ではなく,失敗例が蘇ってくるかもしれない。
文脈崩しで触れたチェックリストが,ストーリーの切口として使えるはずである。
◇主体を変える 自分がやらなかったらどうなるか,自分が別の人格だったらどうなるか,上司や仲間がもっと助けてくれたらどうなるか,別の人だとどうするだろうか,上司ならどうするだろうか,別の会社だったらどうだろうか,誰ならいいのか
◇対象を変える あの人でなかったらどうか,あの人だったらどうか,別のイメージの客を考えたらどうなるか,誰にしたらいいのか
◇時間軸を変える 昨日だったらうまくいったのではないか,今ならうまくいくのではないか,明日ならどうなるか,1ヵ月後ならどう変わるか,1年後ならどうなるか,3年後ならどうか,いつならいいのか
◇空間軸を変える あそこでなければどうか,どこでもいいのならどうか,別の状況だったらどうか,状況の配置が変わっていたらどうなのか,どこならいいのか
◇理由を変える 全くフリーハンドだとしたらどうか,何の価値もないのだとしたらどうか,目的が違っていたとしたらどうか,どういう理由ならうまくいくのか,このままほっておいたらどうなるか
◇やり方を変えてる いままで捨てられてきたものを再現してみる,問題外としてきたことをやり直してみる,失敗したやり方を再現してみる
過去に捨てたり,過去には有益でなかった発想がいまあるいは明日なら有効であるということは多い。結局人間の発想のキャパシティは限界があり,そうそう突飛なことを思い付くことはない。いつか発想していたことを,別の文脈に刺激されて思い出すということも少なくない。とすれば,自分の過去をどう蘇らせるかということは存外重要である。その意味でも,“いま”という特定の文脈だけに合わせようとすることは,それ以外の可能性を捨てることに等しいというべきだろう。
ノイズからの遠近法
僅かな情報からストーリーを描くということは,結局自分の経験・知識から見えるものを想定してみることにすぎない。そう考えれば,問題の見え方とは,問題を表現してみることにほかならない。既知のものをどう組み合わせて見えやすくするか,その表現力が問題へのアクセス力に差異を生むことになる。だが問題は,それをどういう位置からみているかだ。
図と地,信号(情報)とノイズ,目標と手段,部分と全体,どういう言い方をしても同じだが,われわれは自分のパースペクティブにおいて必ず差異をつけている。それがものを見分ける根拠でもあり,またものを一色でしか見られない発想閾を狭めている理由でもある。図をみわけるのは,その中に自分の既知の図形を見分けるからだ。それを支えているのは,目標であり,知識であり,経験にほかならない。だから,新しい問題に出会ったとき,それを既知化することは,一種矛盾したものを孕んでいる。結局自分の知っているもので類推することは,自分の知っている範囲を出られない,というように。
だから,視点の移動には,視点の位置を変えることだけでなく,焦点の移動(アップにしたり,無限大にしたり)もまた含まれている。図ではなく地に焦点を当てることで,信号がノイズになり,ノイズが信号になる。この転倒は意味だけでなく,価値を転倒する。そこまでいかなくても,信号の識閾を拡張する。情報が,どこかにあるものを探すのでなく,新たな意味を見付けるもの(発見するもの)になるとは,そういうことにほかならない。曖昧さが重要視されるとはそういうことにほかならない。
目標と手段についても同じことがいえる。下位目標が上位目標の手段となる,目標-手段の連鎖は,1ステップずつ解決していけば目標に到達できる,という信念に基づく。それは原因-結果の連鎖と相関している。原因があれば結果がある,というのはすべては曖昧なところなく論理づけられるとする決定論にすぎない。いま情報の意味が変わったというのは,情報の一義的な意味ではなく多義的なものを受け入れなければ意味がつかめないからにほかならない。それは原因は特定できないということだ。とすれば結果も特定できない。目標は曖昧で,下位目標が最終目標の方が問題がよく発見できることもありうるということだ。
これを敷衍してみると,情報は受信するだけのものではないということがいえるはずである。もし信号とノイズの境界が曖昧であるとすれば,発信者にとって多義的でなかったメッセージが受信者には多義的で脈絡の見えないものであること,あるいはその逆が生じえるし,現に生じている。ある定まったコードを受信し,それをコードブックで解読するだけではもはや情報は読めない。それをマイナスと見るかプラスとみるかで,問題が見えるかどうかがきまる。脈絡も意味も曖昧ということは,新たな意味を見付けられるチャンスなのだ。その意味で,第2回に否定した集団的問題解決の効果を再確認すべきだろう。つまり,いま問題の新たな意味を見付けるのが,人と人のコミュニケーションの中においてだ,という意味では重要だ,と。むろんそこでは,人によってパースペクティブが異なり,そこで整序される見え方も違っているということが前提となる。
- 発想のコツ
発想って何?
世の中の発想論ではたいてい,「頭のサビを落とす」「頭を柔らかくする」ということをキャッチフレーズにしている。
まず疑問なのは,そんなに簡単に,頭が柔らかくできるのか,ということだ。それより何より,何十年も生きて来たいい大人に向かって,今までの考え方を捨てろと言う。それにムッとしたことはないだろうか?
「冗談言うな,オレは長年こうやって仕事をしてきたんだぞ」と。
こう感じている自分の反感の方が正しいのではないか,と内心思いながら,そんなことを言っているから「頭が固いのだ」と言われそうで,これまでずっと言い出しそびれてきた,ということはないか。
なぜ「頭の錆」や「柔らかさ」が問題になるのだろうか。サビとか固いとは何のことなのか?錆ついて回らなくなったギア,グリスの固まったベアリング,あるいはショートして堂々めぐりする回路,といったイメージだろうか。しかしクイズやパズルといった「頭の体操」なんかで,頭の滑りがよくなったり思考が柔らかくなったりするものか。問題なのは,創造性ではないのか。パズルを解くことに長ずることで,優れた創造性を発揮したものを寡聞にして知らない。多分,クイズマニアのように,「手慣れたパズルの解き方」に習熟するだけではないか……。
なぜなら,たいていのクイズやパズルには答えがある。そういうのを,発想とは言わない,と信ずるからだ。わたしは,頭にサビなんてないと思っている。断言してもいいが,頭の柔らかさと発想力とは関係ない。少なくとも,パズルやクイズの出来不出来と発想力とは何の関係もない。小器用にクイズをこなす小才よりも,不器用なほどに考え込む物分かりの悪さのほうがずっと大切なのだ。
敢えて言えば,頭のサビこそが,わたしたちの個性にほかならない。その人が生きる中で身につけた知識と経験のもたらす思考の慣性にほかならない。まあ,惰性に近いかもしれない面があるのは認めるとしても。
しかし,それも含めたものが,その人なりのこの時代と社会での生き方なのであり,ものの見方なのである。これを個性と呼ぶほかはないのだ。問題は,個性があるかどうかが大事なのではない(個性は十人いれば十の個性があるのであって、そのこと自体に意味も価値もない)のと同様,サビがあるかどうかが問題なのではないのだ。サビは生きて来た証にすぎない。頭の固さと評されるものも,良かれ悪しかれ,その人らしさにすぎない。大事なのは,そのサビや固さを価値あるものにできるかどうか,つまり自分のもっている知識・経験を使いこなせるかどうかなのだ。その使い方に発想力のある人とない人とに差がでる。問題は,その使いこなし方だ。ここでも従来の発想論に不満がある。「常識は捨てなくてはいけない」「当たり前を疑ってみろ」と強調しながら,それをどうやったらいいのか,についてはどこにも具体化されていなかったことだ。
発想力をどうしてステップ化するか
正直,わたしは,比較的クイズやゲーム感覚の頭の体操が苦手である(決して嫌いではないが)。そのためでもないが,どこかでクイズやゲームをうさん臭く感じてきた。それでいながら,一方では自分が不得手なことをずっと気にかけてもきた。しかし,多くの発想の書は,それをもって発想力診断テストとしているところがある。では,パズル発想が苦手なら,発想力はないのか?
しかし,あるとき気づいたのだ。確かに見かけはパズルは,アクロバットのような頭の回転を要求するが,そこで求めているのは手先の器用さのような頭の使い方の器用さにすぎないのではないのか?それがいわゆる発想力と何の関係があるのか?むしろそういう器用さは,手品と同様,見かけの転換だけで,本当の意味の発想の転換とは関係ないのではないのか?と。そして,人に手品の如き発想を強いるとしたら,その発想の手引の方が間違っているのではないか,と。
そういう“コペルニクス的発想転換”(?)をした以上,別の理屈を立てなくてはならない。そういう場合,わたしのような真面目さだけが取柄の(ということは何の取柄もないに等しい)手合いが言訳とするのは,往々にして,「発明は99%の努力(パースピレーション=汗)と1%のインスピレーション」というエジソンの努力神話しかない,と相場は決まっている。しかし,本当にそれだけで可能なのかどうか。ともかく,そうした思い付きをきっかけに,いわゆる“天才”のひらめきを,自分のような凡才の汗と努力だけを担保に可能にする方法はないか,という,言わば虫のいい願望から始まった,その結論については,「アイデアづくりの基本スキル」をみていただくことにして,その背景となった考え方だけ述べておきたい。
むろん古来,多くの創造性研究の端緒もそうした問題意識にある。
古くは,いわゆるレトリック研究そのものが,能弁家の弁論技術を体系化するところから始まっている。
既に,キケロが「能弁家たちが自然におこなってきた」ものを研究したものについて,「技術から能弁が生まれたのではなく,能弁から技術が生まれた」と皮肉を言っていると,紹介しておられる佐藤信夫氏は,そういうレトリックの技術体系は,「天才が自在におこなう操作とおなじことを,凡人が不器用な努力によっておこなうと仮定すればどうなるか」という問題の立て方をしているが,それは,「天才が巨大な問題を一挙に解決して到達したのとおなじ地点へたどりつくために,律義者は,その一個の問題を大変な数の小階段に分割し,分岐点ごとに考え込む」(まるで,コンピータのモデルと同じ)というものとなる。しかし,その模型は,間違っていると,氏は指摘されている(『レトリックの消息』)。「天才的作業を仮説的凡人のモデルによって説明している装置は,じつは装置のほうが虚構的なのであった。才能ある人間が(人間はみな装置よりも才能がある)飛躍するのではなく,それを飛躍として説明する理論のほうが幻想的に律義なのだ」と。
模型として設計している装置そのものが,虚構の「天才」モデルに対比して普通の人間を現実以上に律義(つまり間抜け,ということだ)に設定している。しかも,その前提に立って,天才の能弁(あるいは美文)を,どうすれば凡人にも可能にできるか,と設問し,虚構の「天才」の一瞬の一またぎをステップに分割して,それを愚直なまでに一歩ずつ辿ることで,それに肉薄できる,とした誤てるモデルにすぎない,というわけである。なぜなら,人間はそのモデルのように間抜けではないからなのだ,というわけである。
前述の「アイデアづくりの基本スキル」も,実はレトリック研究と同じく,凡人の律義さだけを担保に,汗と努力だけで天才の「飛躍」を図ろうとしているが,まさに人間が「モデル」のように間抜けでないからこそ,それを正当化する理由があるのである。
つまり,普通の人でも,「装置よりも才能がある」からこそ,実は発想が問題となるのである。そういう飛躍とは,慣れから来ているといっていい。われわれはレトリックでも,発想でも,愚直なまでに分解されるほどの手順を一々意識しなくても,一瞬のうちに比喩を使うし理解する。しかし,それは慣性として使い理解しているにすぎない。発想にとってはそれこそが桎梏にほかならない。モデルの,律義に分割したステップを辿らせることによって,いつもの自分の手慣れた一またぎそのものを異化すること,それがこのモデルの効果にほかならない。それに,「仮説的凡人のモデル」に問題があったとすれば,そういう愚直なモデルを創ったことにあるのではなく,それを唯一の見習うべき手本,つまり正解と見なしてしまったことにあるのではあるまいか。しかし,正解が1つなら,ただそのままなぞればいいだけであって,そこに一人ひとりの工夫の余地はないし,そんなところに創造性などはない。
ここにあるのは,あくまで,1つのモデルでしかないのだ。それを通して,自分の発想プロセスを異質化すべき装置にすぎない。習字の手習用の手本のように,それをなぞること自体に意味があるのではなく,丁度ストップモーションにかけたゴルフスィングのように,自分が意識せずにしてきた発想プロセスを,1コマずつに分解された動作として客観的に分析してみればいいのだ。そこから自分との類似性を見つけるか異質性を感じるか,それとも自分の長所に気づくか欠点に気づくか,あるいは目指すべき目標を見つけるかは,本人次第だ。何にでも運勢占いのように託宣を戴かなくては気がおさまらないという発想をまず捨てなくてはならない。モデルは,模範解答ではなく,それを通して自分なりに新しい発想のパースペクティブ(視野)を得るべきものであって,それは他人によってではなく,自分自身によって見つけるべきものなのだ。
ちょうど宮本武蔵の『五輪書』は,天才武蔵でなくては会得できないが,千葉周作の奥義は,素人が,確実に身に付けられる教本だというのに似ている。
わたしは,だから,“ブレークスルー”とは,そういう意味でも,自分流の壁の破り方にほかならない,と思っている。ブレークスルーとは,自分の既成の発想の“変成”と考えている。問題解決で言えば,問題形成まで,である(既知を破って未知を創り直すところまで)。目標の発見・形成が目指すべきものなのだ。だから,“発想”のブレークスルーなのだ。
われわれは,爾来とかく突貫工事には慣れている。それは,誤解を恐れずに言えば,問題を解決することに長けている,ということだ。しかしその特技が効くのは,目標が明確なときだけだ。いま,われわれに必要なのは目標そのものの形成なのだ。何をしたらいいのか,何を目指したらいいのか,という最も根本的なことを発見しなくてはならない時代なのだ。だから,同じく“ブレークスルー”とは言いながら,ナドラーの『ブレークスルー思考』とは,全く問題意識を異にする。
といって,美文作成のためのレトリック体系のように,ブーレークスルーの教則本ではないから,ここあるのは,回答例のひとつにすぎない。われわれは,結局既知の枠の中で収まってしまう思考の慣性を,一度スローモーションのようにコマ毎に分割し,自覚的に1つ1つ踏み破ってみなければならない。そのためのモデルにほかならない。それを辿ってみることによって,自分なりにどこをどう直せばいいのか,その工夫のためのツールは用意したつもりである。むろん,これだけが正解では決してないし,正解だと主張もしないが。
確かに,アインシュタインがブレインストーミングをやっている姿を想像できないが,といって彼は独自のブレークスルーの仕方をもっていなかったとか,それに無自覚にやっていたと考えるべきではない。方法論のない研究などありはしない。彼もまた,自覚的にやっていたはずだ。それが何かは,外目には,多くブラックボックスとなっているだけのことだ。それをわれわれなりに,自分で創り上げなくてはならない。
発想転換の発想転換
創造性や発想力を問題にするとき強調されるのは,《視点の転換》とか《発想の転換》である。そのためにどうしたら発想や視点が転換できるか,パズルを使ってみたり,ゲーム感覚の「頭の体操」を試みたりする。しかし,強調したいのは,
視点(見方)を変えるのではなく,見えるもの(見え方)を変えること
である。つまり,見慣れた見方や使い慣れた発想や視点が問題なら,
見慣れた見方
使い慣れた発想や視点
がしにくい条件をつくってしまえばいいではないか,ということである。見ているものをひっくりかえせば,視点は逆立ちせざるをえない。
たとえば,下のような図形があるとする。
見方によっては,これは立方体を一方から見たものにも,正方形の穴が開いているとも見える。しかし,どうやっても,これが正方形に見えてしまって,それ以外の見方がしにくいのだとしよう。
そのとき,そういう固定観念をやめなくてはいけない,既成概念は崩さなくてはいけない,などといくら言ってみたところで仕方ないのだ。
むしろ,この図が正方形には見えないようにしてしまえばいいのではあるまいか。そういう仕掛けがつくれればいいわけだ。その方法としては,第一には,見る位置をいろいろ強制する。一番いいのは,裏側へむりやり引っ張っていくとか,高いところへ連れていくとかだが,その代わりに,これは凸部を上から見たところだとしたらどうか,凹部を上から見たところとしたらどうかなどという別の視角を強制する方法がある。
第二には,この図をやぶったり,伸ばしたり,細かくバラバラにしてしまったりと,正方形には見えないように変形してしまう方法がある。
第三には,これは口という字を拡大したものだ、あるいは日という字を書く途中だ,または四畳半の部屋の間取り図だ,というように,この図の意味を限定したり,変えてしまったりする方法がある。
第四には,これは紙に書いた図ではなく地面に引いた線とか,ゴム膜の上に書いたものだとしたらどうか,昼間ではなく夜見えているのだとしたらどうか,あるいは洞穴で遠くに見えたものだとしたらどうか等々というように,この図から受ける常識的なイメージに,別の条件を設定し直してみる方法がある。
こうして一種強制的に,いつもの見方がしにくくすることによって,見方を変えざるをえなくすることができるのではないか,ということである。
わたしは、まず、こうした見え方を変えるための方法を《バラバラ化》と名付けている。そのためのチェックリストは,「創造的発想とは」に,実例を示した。
見る側の視点を変えさせるためにバラバラにしたものは、それだけでもいろいろな刺激を与えるが、アイデアなり発想としてまとめていくには、そのままでは思いつきにとどまることが多い。それをまとめたのが,前述の,「アイデアづくりの基本スキル」であり,「4つの発想スキルの使い方」である。
-
考えるとはどういうことか
時実利彦氏は,考えるとは,「受けとめた情報に対して,反射的・紋切り型に反応する,いわゆる短絡反応的な精神活動ではない。設定した問題の解決,たてた目標の実現や達成のために,過去のいろいろな経験や現在えた知識をいろいろ組みあわせながら,新しい心の内容にまとめあげてゆく精神活動である。すなわち,思いをめぐらし(連想,想像,推理),考え(思考,工夫),そして決断する(判断)ということである」(『人間であること』)と定義している。
しかし,これだけでは,精神活動の中身を分類して,考えることの中身には,こういう種類のものがあると整理しているだけあって,それぞれの仕組みがどうなっていて,どうしてそのように考えることができるのかまで踏み込んでいないため,考えるとはどういうことをすることなのかが見えてこないように思えるのだ。それをもう少し突っ込んでみなくてはならない。
思考形成のステップ
われわれがモノを考えるという活動は,通常は行動のように外部からは伺えないほどに内面化されているが,初めからそうなのではない。この内面化のプロセスを明らかにすることで,思考の発達のステップを明らにすることができる。こうした点から,思考の仕組みを明らかにしたのが,J.ピアジェである。それによれば,思考発達は,
感覚運動的知能の段階(0~2歳)
前操作的思考の段階(2~6,7歳)
具体的な操作的思考の段階(6,7~11,2歳)
形式的な操作的思考の段階(11,2歳~14,5歳で成人に近づく)
の4段階を取るとした。年齢は個人差も時代差もあるので目安にすぎないが,このステップの順序は,その中間に様々なレベルの移行ゾーンを持ちながらも,変わらないとされている。
感覚運動的知能とは,五感や動作を通して外部との関係を体得していく時期と考えることができる。ここでは,「対象物の不変性」つまり,そこに見えるものは,布で覆われようと遮られようとある,ということを知っていく段階だということができる。この時期を通して,われわれは自分が動くと見え方が変わること,自分が動けば近くなり遠ざかれば小さくなることを,暗黙のうちに身につけていくのではなかろうか。これによって,乳児のときに喜んだ「いないいない,ばあ」には反応しなくなる。そこにあるものが見えなくなっても,そこにあることがわかっていれば,再び現れたことに面白がったり驚いたりはしないからだ。
この時期の末には,例えば,手の平のコインを乗せ,それを布団の下に入れて隠し,空の手を見せると,子供はそこにコインがないとわかると,すぐに布団を剥がす行動をとる,ということをピアジェは実験している。既に子供は,目に見えないところ(布団のした)でモノが移って(隠され)も,それを追跡していくことができる。このとき,初歩的な推論をしているのである。ただし,子供は言葉ではなく,感覚運動的な活動(行動)によってそれを確認していくりのである。
前操作的思考とは,表象的思考,つまり実物ではなく実物のイメージを描くことができること,言葉を使ってモノやコトを表現できることを意味する。それは,運動感覚的活動の内面化といっていい(一々行動で示さなくても,前述の例なら,言葉でその推測を説明できるようになっている)。それは,ままごと遊びで,はっぱを札とみなしたり,ごっこ遊びなどで,シンボルを自由に扱えるようになっているところに典型的に見いだすことができる。そこでは,そこに母親がいなくても,母親を表象しながら,母親のつもりになって,その行動をなぞることができる。感覚運動的活動では,その場やそのモノに依存していたのにそれなしで,既に頭の中だけで,活動することができるようになっていることを意味する。それは描画,工作といったことができるようになったり,言葉によっての表現も可能となる段階である。
ただし,まだ言葉は内面化されていないから,遊んでいるとき,誰に話しかけるというのでもなく独り言をしゃべっている。
4歳女の子「この木にはね,おサルが上るのよ。おサルさんかわいいね,すうっと登ってすうっとおりるのよ」
4歳男の子「ハイウェーだぞ。メルセデスベンツが走るんだぞ,大きいんだぞ」
お互いに誰かと話し合っているわけでないし,人に聞かれているというつもりもない。ただ自分で自分が考えていることをどんどんことばにして,それを刺激にしてまたしゃべっている。これを思考プロセスそのものが外面化しているとみることもできるだろう(相良守次編『学習と思考』)。
ここでピアジェが操作的といっているのは,言葉や記号を操作して思考できることを意味する。数を数えるのに指やモノで数えるのではなく,数字を操作することができること,あるいはスズメ>鳥>動物>生物といった類(クラス)の関係を頭の中で概念的に理解できること等々,われわれ成人が難なくこなしている思考における,抽象的概念的な働きを意味している。したがって,この段階では,イメージや表象はまだモノやコトといった具体的なものを媒介にしないと不十分なのであり,まだ知覚イメージ(知覚的図柄)に左右されてしまう。
例えば,同じ量でも,右の方が多いと答える。また一方から他方へ移すと,見かけに左右されて,量が変わったと判断する。高さと全体量の関係といった操作的思考ができていないから,視覚的な同値性が見られないと,同値と認めないのである。
具体的操作思考の段階では,具体的な事物についての概念ができ,モノを見たり扱っている限り,論理的な思考が働かせられるようになる。したがって分類や配列ができ,ここでは操作的思考として,スズメ>鳥>動物>生物といった類(クラス)の関係の分類や前述のコップの見かけに左右されたりせずに,全体量の同一性を理解できるようになる。
しかし,例えば5歳の子に水を入れたコップと穴の開いた50円玉を見せて,
「このお金を入れたら,浮くか,沈むか」
と聞くと,
「沈む」と答えた。その理由を聞くと,しばらく50円玉を見詰めて,
「穴が開いているから」と答えた。で,次に穴の開いていない50円玉を取り出して,同様の質問をすると,
「沈む」
「穴が開いていないから」と答える。奇妙な理屈だが,金属でできたものの沈む知覚経験が強く印象づけられていて,それに左右されているということができる。しかし,理由は説明できないのに,言語的概念を手に入れた8歳の子供になると,同じ質問をされると,「お金=鉄みたいなものは沈む,木の棒=木でできているもの浮く」という反応をする。重い軽いという概念で区別している。ただしまだそれは法則的な整理ができていないから,「鉄でできている船は浮くではないか」と問うと,「船の形にすると皆浮く」という形で答える。それに答えるためには,ものごとを統合的に説明し,仮説から演繹的に推論する論理体系を学ばなくてはならない。
またこの段階になると,通常は独り言は少なくなって,「………ここはうんと………」(ぶつぶつ口の中で言っているけれども,あまり聞き取れない),というように,独り言が次第に聞き取れなくなっていく。それは,自分のためにしゃべっているのであって,別に文脈が整っている必要がないからであり,それだけ,自分の内的会話と人とのコミュニケーション(社会的会話)とが分離していくということでもある。こうして言語が内面化されていく(相良等・前掲書)。
次いで,形式的操作思考の段階では,具体的事物がなくても,頭の中で論理操作ができるようになる。とくに前段階でできなかった,「もし,こうなったらこうなる」といった形で推理できる,仮説演繹的な思考ができるようになる。既に成人の思考の段階にある,ということができる。いわば人間としての思考の枠組ができあがるのである。
しかし,こうした論理的思考は,いわばそれまでの感覚運動的知能,表象的思考,形式的思考と,順次,言語だけでなく,動作・行動や知覚イメージ,映像を内面化してきたその積み重ねの結果として形成されているということを忘れてはならない。「操作とは,内面化された活動である」というのは,そのことであり,われわれの中には,感覚運動的活動がひょいと外面へ現れることがあるのだ。例えば,ゴルフのスイングを想定するとき,肱の恰好や腰の据わり方を,思わず躯を動かしながら,あれこれ考えている。これは,自分の躯の動きが頭の中にしまわれている(内面化されている)ものが顕在化したと考えられる。また,ソロバン上手が暗算に際して,そろばんがなくても,頭にそろばんのイメージをつかまえられる(イメージの内面化)し,同時に思わず右手で空を弾くような仕草をする(動作の内面化)。これらは,内面化された動作が,一瞬外へ滲み出た例ということができる。あくまで,操作的思考は,「内面化された活動」だというのは,そういうことを意味している。
その面で,特に付け加えておく必要があるのは,動作の内面化には重要な問題が含まれているという点である。「いないいない,ばあ」には反応しなくなる時期を通して,われわれは対象への距離と位置を学んでいく。それは,見え方が変わっても対象が存在しつづけること,しかし見え方は見方によって変わりうること,即ち,視点の問題である。そこから,「そもそも立体という考えは,人間が動けるから存在するわけです。もしたとえば私が植物としてこの場所に立っていただけだとしたら,つまり私が生まれてこのかたいままで全然移動していないとすると,私には立体という観念はないわけだ。立体は,自分と立体との間に相対的な運動が可能で,物体を上下,左右,前後から見ることができて,はじめてわかる」(森政弘)と,言えるのである。
感覚運動的知能を手に入れたとき,われわれきは,同時にどこから見たらどう見え方が変わる(見方を変えると見え方が変わる)か,ということをもつかんだということだ。それが,実はイメージを左右する重要な問題であることは,繰り返すまでもないだろう。と同時に,見ることに視点をもつことが,いかに根深くに関わっているかを示してもいるのである。
思考における個人別の独自の彩り
以上,4段階のステップを踏んで,思考を獲得していくことになるが,それは,
①動作,行為およびそれらの内面化した過程(現実の見え方=視覚)
②知覚,経験およびその内面化したイメージ(心象としての見え方=イメージ)
③言語およびその内面化した象徴過程
④現実の因果関係の内面化した法則的論理
と,整理することができる(相良等・前掲書)。
大人になると,操作的思考つまり言語と論理による思考だけが目につくが,それしか使わないのではない。前述したように,論理的思考は,感覚運動的知能,表象的思考,形式的思考と,順次,言語だけでなく,動作・行動や知覚イメージ,映像を内面化してきたその積み重ねの結果として形成されているのである。このすべての思考が,われわれの中で層となっていると考えなくてはならない。モノを考えるとき,われわれは,以上の4つの軸すべてを組み合わせているのであって,この4軸は思考形成のプロセスであると同時に,思考力の4つの要因でもあるとみなすことができる(丁度,マズローの欲求5段階説で,生理的欲求→安全欲求→所属の欲求→承認の欲求→自己実現の欲求の5つの欲求が,欲求の順位のステップであると同時に併存する欲求のレベルを示すものであるように)。
それは下図のように構造化することができるだろう。
現実の関係性の内面化=論理的思考
言語,記号などの内面化=言語的思考
知覚,経験の内面化=表象(イメージ)的思考
動作,行動の内面化=感覚運動的思考
これは,別の言い方をすると,初期には個別具体的であったものが,言葉や理屈を通して,どんどんまとめた抽象化・一般化したものに昇華していくということでもある。それが知識を得るということになるのだろう。
これをわれわれの日常レベルでの思考の仕方からみると,それらは,どういう形でわれわれの中に蓄積(記憶)され,それを,そのつどどういうふうに取り出しているかという視点から考えてみることができる。ひとつの考え方は,
・エピソード記憶(個人的な過去の出来事,想い出のシーンが,そのときどきの状況と脈絡をもって蓄積されているモノやコトのエピソード)
・意味記憶(いままで学んだ知識や論理の蓄積)
・手続記憶(自転車に乗れる,機械が操作できるといった技能の蓄積)
といった分類となり,手順→意味→エピソードの順に下位システムを形成しているとされている(E.タルビング)が,誤解を恐れずに,この記憶の階層を前述の4層に当て嵌めて,強引に単純な図式にしてしまえば,
といったふうに層をなしているというふうにみることができる。つまり,われわれの感覚運動活動やイメージは,個別の想い出に支えられ,彩られているのである。しかし,各層は多少の交ざり合いはあっても,それぞれがバラバラのネットワークとなっていて,意味を辿っても必ずしもそのエピソードにつながるとはいえない。
エピソード記憶は,特定の時期に限定された独特の時間的な組織化になっていて,何かの薫りからある想い出が浮かんだり,ある感情(悔しさや怒り)によって,ふいに昔の恥ずかしい体験が思い出されたりする(ポップアップ現象)。ある言葉から,一瞬の出来事がイメージされたりということもある。あるいは意識しないで独自の言葉や色への嗜好が現れているということがある。その意味で,エピソード記憶の多くは無意識状態にあるとみなされる。といっても,無意識というのは,ここからここまでというように,絶対的な領域として確定しているものではなく,あるときは意識化されても,別のときには意識の外にあったりする相対的なものであり,固定された場所(フロイトが表現した“潜在意識”や“意識の底”“意識の下”というのはあくまで比喩である)として実体的にとらえるべきではなく,「常にあたかも(as if)」(ユング)としてしか説明できない,そのときどきの意識にのぼらないものを,無意識とみなせばよい。
論理や意味を考えているときには,直接には個別の体験とは接続しにくいが,無意識で独特の意味(ニュアンス)を見ているかもしれない。あるいは,自分では論理的でも,その根拠にしているのは,法則を納得させる個別の体験が強力に作用しているのかもしれない。モノの見方に個別のエピソードからの情緒的歪みがあることに気づかないでいるかもしれない。ある意味で,エピソード記憶は,ネットワーク全体に浸潤していて,エピソード記憶は意味記憶で意味づけられ,意味記憶はエピソード記憶エピソードで感情的に色付けられているが,そのことにわれわれは自覚的でないから,独自の彩りには気づいていないし,またその個別の根茎となっているエピソードを意識していないだけなのだ。エピソード記憶は,知識や意味的なつながりを追いかけている中からは見えてこない。それには自覚していないからだ。にもかわらず,一種キイワード(あるいはキイとなる偏光眼鏡)のようなものに出会うと,一瞬のうちに回路が変わり,独特のエピソード記憶と接続してしまう(ある恰好をしたとたんに,小学校のときの忘れていた光景とつながる,というように),極めて近いところにある。
このように,エピソード記憶のほとんどは,ときとところによって浮かんだり沈んだりしているものであり,無意識のネットワークなのである。しかし,その人としての独自性は,個人としての経験の蓄積であるエピソード記憶の中にこそあるのだから,ここにこそ,良くも悪くも,その人のオリジナリティがあると考えるべきではあるまいか。これこそが,本来の自分の知識・経験(あるいは個人的経験に彩られた知識)であり,たとえ常識や定石にとらわれたものであったにしろ,その独自の彩りの中に,発想のオリジナリティの基盤がある。われわれはこれ以外に独自のものをもっていないのだから,独自のエピソードに彩られた知識や経験,イメージ,感覚を,どう生かすか,どう引き出すかが重要なのだ。
知覚イメージへの過信は禁物
既に述べたように,思考は,
・現実の関係性の内面化=論理的思考
・言語,記号などの内面化=言語的思考
・知覚,経験の内面化=表象(イメージ)的思考
・動作,行動の内面化=感覚運動的思考の4つの軸がある。そのうち,感覚運動的思考や表象思考は,われわれには大きな働きをしている。とりわけ子供では,成人と異なり,モノの名前や意味を知らない分,モノを説明したり考えたりするとき,モノの動きで表現(ブーンと飛んでいる仕草)したり,モノを生き物で,コトガラを別のモノで喩えたり(踏石を亀と見立てたり,湿疹をサイダーの泡と喩えたり)する。これが成人なら,簡潔にモノやコトの名前を言ってしまって終わることになる。しかしその底で,言葉の実体を,そういう具体的な体験が支えているし,イメージも内面化した知覚・経験が支えていることは,成人も変わりはしない。それが,子供に限らず,成人にとっても知覚上の錯覚に満ちている理由である。例えば,下図のようなものを示されると,右の矢の方が長いと感じたり(ミューラーリヤーの錯視),
出典;種村季弘・高柳篤『だまし絵』(河出文庫)
また,前述のように,細いコップに入ったものの方が量が多いと直観的には錯覚したりするのも,成人してからも一瞬の錯覚に陥る。しかし,それは,マイナスとのみ考えるべきではなく,例えば下図のように,
背後を想定できるのも,このイメージの働きのせいである。しかしそのために,下図のような対象では錯覚を生ずることになる(①は,ネッカーの立方体,②は,R.ペンローズの,「考えられない図形」,いわゆる“悪魔のフォーク”)。
①
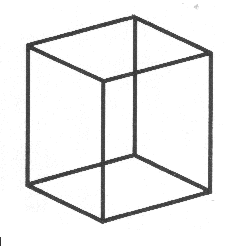
②
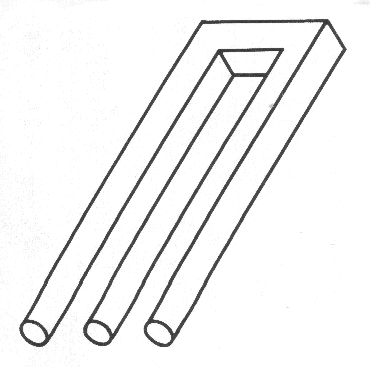
出典;種村季弘・高柳篤『だまし絵』(河出文庫)
①では,奥行を示す稜線が前景となったり,前出の図の点線のように後背に引っ込んで見えたりする。これは,知覚経験から,われわれが背後の状態を既に知っているからにほかならない。しかし,逆に“悪魔のフォーク”で混乱するのは,その知覚経験の当て嵌めが効かないからにほかならない。
左右脳で区分する発想こそが問題
われわれにおいて,こうした知覚経験が,子供のように単なる図柄の差で判断するほど単純ではないが,全体的に把握する上で,非常に大きな力をもっている。例えば,
adgacgaegabga□
という文字系列を解くのに,コンピュータは不得意だが,われわれは,一瞬のうちに,パターンを見つけ,agは繰り返されており,実質的には,
dceb□
の文字系列を解けばいいのだということに気づける。そして,それは,例えば,
の渦巻きのようなイメージを浮かべることで,文字の列の特色をつかむことができるし,cとd,bとeが向き合った反射の関係とイメージしたりもできる(相良・前掲書)。その意味で,この直感とでもいうべきものは,イメージを想定することで全体像をつかまえやすくすることは事実である。
確かにこうした映像的な思考,つまりいわゆる右脳的思考は,コンピュータの最も不得意とするものであり,全体的な判別,認知という経験に即したわれわれにとっては利点というべきものではあるが,それがいわゆる右脳論以来過大評価されすぎているように思われてならない。空間情報の処理を右脳がやっているという常識化した見解に対して,全体をつかむイメージの形成には左脳が大きく関与しているとする実験結果も少ないがあるし,知識の枠組が全体を一括して把握するのを助けるとする,後述のハンソンの指摘もある。こうした視覚イメージを内部記憶によって総合するためには,左脳の機能が大きく作用するというのは,また当然考えられる反論なのである。
むしろ,大事なのは,右左で脳の機能を2分する発想自体が問題なのである。われわれがイメージを浮かべているとき,脳の活動部位は,右左といった単純な区分ではきかないくらい,後頭葉,前頭葉,下部側頭葉,頭頂葉,全体にわたっている,といわれる。しかも,イメージは受動的に画像を思い描くというようなものだけではなく,能動的に(先を読むというように)働かせており,その意味では常識的な左脳の「枠組」や「パラダイム」「予期図式」のようなものをもって,予測的予期的に描いてみせるという面ももっていることを見逃せないのである。「知っているものを見る」「見たいもの(しか)見えない」「見たいものをみようとする」というのは,こうした知覚イメージもまた,われわれにとって習得されたものだからだ。その意味では,直感もまた,一種の思考の慣性といっていいのである。
論理的思考のみが落し穴なのではない
イメージが強調される反面で,われわれの言葉や文脈による表現が敵役とされてきた。それは正しいのだろうか?
確かに,われわれがほとんど言葉,つまり意味や文脈で物事を考えたり,あるいは概念でモノを考えているため,「知っている」というとき,大体「その意味を知っている」「学んだ」「読んだり聞いたり知ったりした」ということである。その意味によってモノを見ている。更に,現実を,学んだ知識・経験(因果関係や法則)によって,ものごとを推理したり,類推したり,演繹したりする(こうすれば,こうなる。こういうときは,こうなるはずだ)。これが知識の力といっていい。こうなるのが当たり前,というわけだ。そしてその多くが,新しい発想の妨げとなってくるとされるのは,こうしたモノの見方がモノの見え方を決めてしまうからにほかならない。だから,そうした知識が問題だ,というのは意味がない。妨げているのは,知識ではなく,知識がこしらえる上げている枠組だからである。
例えば,われわれは言葉の意味と文脈,論理でものを判断することに慣れ過ぎている,というより,それが科学的であるということを身に染みてしまっている,という点である。そのことがモノを別の角度(幻想や情緒で彩られたファンタジー)から見る,つまり別の視野をつかむのに妨げとなってくる,というわけである。
その例として,P.ゴールドバーグ『直観術』(工作舎)におもしろい小話が出ている。
ある心理学者は,ノミに「跳べ」といったら跳べるように訓練した。
試みにノミの足を1本取ってみたが,まだノミは命令に従って跳べた。
2本とっても,3本取っても命令に従って,跳びつづけた。
やがて全部の足をとってしまったら,ノミは跳ばなくなった。
そこで,この学者は,次の結論を出した。
「足を全て失ったノミは聴覚をなくす」
ある意味で論理的に推測していくときの戯画である。陥り易いマイナスを極端にひょうげんすればこうなるだろう。ある情報を理屈だけで考えると自分の手慣れたこじつけ解釈になりがちだ,というわけである。
あるいは,3段論法でこういうばかげた結論を導くことはないか。例えば,
すべてのおもちゃはディスカウントで売れる
すべてのディスカウントは利益が低い
すべてのおもちゃは利益が低い
これをどうみたらいいのだろうか。もののとらえ方として,何が問題だろうか?思いつく限り,アトランダムに挙げてみれば,
①すべてのとか,いくらかのとか,なにも~ないといった言葉で結論づけられると容認しやすくなる。そういう言葉で表現されると,事実と受け止める傾向が強い。例えば,「この例(データ,現象等)では」「もしそうだとすれば」という条件を消してしまう。
②確率として読んでいる。確率はありうる正解の1つにすぎないのに,正解=1つとするために,帰納のもっともらしさの危険性がもっと高くなる。
③結論を否定してみていない(利益率の高いおもちゃはないのか)。逆はないのか,違う例はないのか,と想定してみない。
④すべてのおもちゃ販売=ディスカウント販売(ディスカウントのみ)と変換して読んでしまっている。少数事例(あるいは特筆例)を一般化し,すべてに敷衍してしまっている。“たまたま”を“そもそも”と読み変えてしまう。
⑤特定モデルで納得している。そういえば某に,某にもは当て嵌まると,勝手に当て嵌まるものだけを思い起こして,それだけで小世界を形成してしまう。
⑥意識的にそういうことはありうると考えてしまっている。先入観に合致するとそこから抜け出せない。
⑦仮説形成において,それと矛盾する否定的な情報の獲得と使用が下手。負の情報を探そうとしない。合うものを探そうとして,合わないものを探そうとしない。
等々。言語=論理的思考の陥りやすい傾向を,このように整理できるかもしれない。これは,われわれの思考が,わたしたちが知っていることあるいは知っていると思うことに則して推論しようとする,抜きがたい傾向があるからにほかならない。知識の枠組のもつステレオタイプ性を証拠立ててくれている。こうした過ちを防ぐには,一般には,
①合理化しないこと=それでは既知のつじつまにあわせるだけ
②理屈にあわないことをあわないままにする
③矛盾は矛盾のままにする
④否定的なものはそのまま受け入れてみる
⑤結論を急がない
⑥意味や論理だけでなく,感覚,イメージ,動き,経験も含めて考えてみる
ということを意識的にすることが必要になる,と言われている。むろん,この分析自体にそれほどの誤りはない。実地に当たってみればすぐわかることだ。問題なのは,だから知識ではなく,イメージによる直観を使った方がいいのだ,ということが強調される点だ。実際に自分の経験ではどうなの?自分のイメージはどうなのか?しかし,それは本当だろうか?
思考の枠組みをつくっているもの
例えば,単純な例を出してみる。車の運転で,車幅が自分の躯のように感じて,車の動き=体感になって,自在に動かせるようになる。しかし,その慣れによって形成された枠組によって,われわれは大きな錯誤を犯すこともまた多いのだ。例えば,下図のように,
道路の行方を経験から,点線のように読み込んでしまうことがままある。そのイメージで運転していくと,カーブに差しかかったとたん,ヘヤピンカーブなのに慌ててハンドルを切るという目にあったことも少なくないはずだ。
前述したように,言葉や論理の形成のバックにあるのは,感覚論理的思考であり,イメージの思考であり,「思考を特徴づけている構造は,言語的事実よりも一層深い活動と感覚運動的メカニズムの中に,その根をのばしている」(ピアジェ)のであって,運動感覚的ないしイメージによって形成された思考の構造によって,既に言葉や論理の思考の受け皿が作られている。論理的思考を支えているのは言語的思考であり,それを支えているのが知覚イメージであり,それを左右するのが感覚運動思考なのであって,4つのパターンすべてが層を成していると考えるべきだと前述したのはそういう意味である。ただ,成人になれば意味や理屈の判断という形をとることが多くなるというだけのことなのだ。
だから,イメージや感覚が大人の常識の枠組を外しやすいというのは誤解にすぎない。むしろ,イメージや感覚の枠組があるから,言葉や論理の制約を強化するといったほうがより正確なのである。そのいずれもが,ともかくわれわれの知識と経験の蓄積の上に形成されてきたものであり,モノを見る「枠組」として制約となっている,という意味では,同列だということなのだ。
われわれの知識のネットワークは,基本的には,論理的組織ではなく,世界が私たちの経験の中で総合されるあり方を反映している。記憶は,ほとんどの場合実在の写しではなく,実在をもっともらしく再構成したものであり,典型的な事態に対する強調がつきまとっているのだ,ということが大事であり,その意味では,イメージや感覚こそが最も歪んでいるのかもしれないのだ。感覚やイメージが過大評価されるのと同様,知識を過小評価することに意味があるはずはないのである。
問題なのは,右脳と左脳の機能区分を,効能の区分と同一視したところにある。どちらか一方が錯覚や錯誤に加担しているなどということはないのだ。“あれかこれか”は,脳機能においてもない。両者相俟って,われわれの発想を制約しているということを見失うと,ブレークスルーを,誤った感受性や感覚の強化にのみ走らせることになる。感覚だけを評価したり,知識のみを強化したりすることを,本書で取り上げることはない。よくも悪くも,われわれの発想に窓枠を嵌め,それが一方でパターンを直観させ,他方で発想を制約もするのは,われわれの形成・蓄積してきた思考の4軸そのものの結果なのである。
-
アナロジー的発見による情報編集の効果
グルーピング直したり,再構成した情報から何かを読み取ろうとする場合,その組み合わせから常識的に,あるいは論理的に推測できる範囲で組み立てたのでは,既知の枠組を再現してしまう可能性が大きい。ちょうどプラモデルの場合のように,わかっている輪郭をなぞってしまうからである。それを避けるには,部分の組み合わせからのアナロジーを通して,別の輪郭,構造へと飛躍させていくことが必要である。そのアナロジーから見立てられたものが,初めの常識や理屈を飛躍できればできるほど,新しい構造と輪郭を発見できるはずである。
- 編集の青写真にアナロジーを使う
グルーピングを通して,どういう関係づけが見えたろうか。例えば,グループA,B,C,Dと分けていくことによって,全体の位置関係がわかってくる,AとBとのクラス差(包含関係)が見えてくる,あるいはぼんやりと,全体の輪郭Xらしきものが感じられる,ということがある。いまここで必要なのは,こうしたグループ間の構造,つまり全体としての新しい“つながり"=“新しい関係性の発見”なのである。これが,新しい組み合わせのもたらすパースペクティブにほかならない。その意味で,バラバラ化が“既知のパースペクティブを崩す”ことであり,情報の括り直しが“未知のパースペクティブの発見”であるなら,このプロセスは,“新しいパースペクティブの形成”にほかならない。
この新しい関係を見つける方法として,まず考えられるのが,《しらみ潰しの発見型》である。別に大袈裟なものではなく,われわれが通常試行錯誤しながらやっているやり方であり,グループ化した情報群同士のありうる組み合わせパターンを,逐次検証しながら,組み合わせ1つずつについて,しらみ潰しに,1つ1つ試しては消去して,新しい組み替えを見つけ出していこうとすることだ。この典型例は,チャールズ・ヤン氏が,形態分析法で示した組み合わせ方法がある(『ビジネス思考学』)。
そこでは,ある機能区分別に,そのサブグループ群すべての組み合わせの可能性を探るために,各機能毎にサブグループの(標題)カードを並べ,スライド式に順次ずらして,各組み合わせを検討している例を示している(アイデアづくりのスキル「組み合わせ」を参照)。
当然この組み合わせはその掛け合わせ要因の数が増えれば増えるほど,爆発的になり,場合によっては,とうてい時間的に許容されえない。この爆発的な組み合わせを避けるためには,別の方法が必要となる。それが《アナロジーによる仮説型》なのである。
これは,グルーピングで得た全体の関係性のイメージから,何かになぞらえられる(見立てられる)アナロジーを発見し,それを仮説として,個々の組み合わせパターンを類推して導き出すのである。
情報群の組み合わせからのアナロジーを見つけ,それの構造と輪郭から新たな組み合わせの可能性を見つけ,それを仮説として,個々の要素間の関係を検証していくことになる。しかし重要なことは,与えられた情報の組み合わせパターンを探り出すのではなく,創り出すことなのである。似ているからアナロジーを見るのではなく,アナロジーを見るから似ているものが発見されるのでなければならない。そうでなくては,既知の類似性を当てはめているだけだ。異質な両者にアナロジーを創り出すから,両者に新しい関係性が発見される。関係のあるものを見つけることではなく,両者の間に敢えて関係性を創り出すこと,それが,新しい組み合わせ発見の意味でなくてはならない。
しかし,発見型(ありうる関係のしらみ潰しにする)と仮説型(アナロジーによる新しい関係の発見)は,全く別ものであろうか。例えば,要素間のつながりが見えることで,新しい枠組が見つかることがあると同時に,新しい枠組を創り出すことでも要素間に新しい関係を見つけられる。つまり,両者は別々の作業ではなく,仮説が発見を促進するし(こうだとすれば,こう見えるはずだ),またしらみ潰しの組み合わせが仮説を発見しやすく(こういう組み合わせなら似たものはないか,何か関係したものはないか)もするのである。しらみ潰し式が絶対に非能率とはいえないのである。
先の図式化した関係を使って,この問題を整理すれば,次のようになるだろう。
見え方を変える→とらえ方が変わる→仮説が変わる
↑ ↓ ↓
見え方が変わる←とらえ方を変える←仮説を変える
つまり,見え方の変化は,とらえ方の変化に,そしてわれわれのとらえ方の枠組=図式を変える,という,「見え方を変える→とらえ方が変わる→仮説が変わる」の流れは,いわばしらみ潰しに,新しい組み合わせを試みるという見え方の側からとらえ方を変えるという発見型である。逆に,「仮説を変える(見つける)→とらえ方を変える→見え方が変わる」が,仮説型に当たる。ただ,しらみ潰しの作業を通して,仮説の発見ができれば(丁度天才がそうであるように,図式がひらめけば),新しいパースペクティブを手に入れやすいかもしれない。
- アナロジーを通せば新しい関係が見える
ここで言うグループ間の関係づけという意味には,
第1に,因果関係,対立関係,順序関係,補完関係,位置関係,配置関係,組み合わせ,組成,時間的連鎖,といった《文脈》あるいは《脈絡》といった平面的関係,
第2には,全体・部分関係,包含関係,密度,優劣,優先順位,内外,骨組,階層,システムといった《構造》といった階層的関係,
の2つがある。つまり,われわれは,グループ化によって部分集合に括ることを通して,ただ平面的な分類をしていくのが目的ではないのである。われわれが見つけたい関係は,
《文脈》 水平的な関係
《構造》 垂直的な関係
の2つなのである。建物で喩えるなら,柱,床,壁,窓,屋根,といった部分の相互関係だけではなく,何階建てなのか,位置の上下は,奥行は,前後は,といった,部分間のクラス,役割・機能関係をもつかまなくてはならない。その意味では,むしろ“新しい関係性の発見”というよりは,新しく構成し直すこと,つまり,“新しい構成の発見”というべきものなのである。
この“新しい構成の発見”は,グループ化していく過程で浮かび上がってきた関係の,新しい“文脈"と“構造"をはっきりさせるために,それから見ればより新しい構造が見えてくるような,新しい仮説を形成することなのだ。それによって,より“新しい関係”が見え,かつ新しい文脈が整理できるような,仮説である。それが,グループ間に「習慣的に相互に矛盾しあう」「交錯点」を発見し,1つの脈絡にすることにほかならない。
そうした「特異点」を見つけることが,グループ間に整合性をもたせる“構図の形成”であり,その構図によって,グループ同士をひとつに括れる,あるいはひとつにつなげる枠組を形成することである。これは,“共通性の発見”と変わらない。違いがあるとすれば,共通性の発見では,並べた両者の間に,類似性と関係性を見つければよかったが,ここでは,グループ化のもたらした図式と対比すべきものは隠されている。それと似ている,または関係のある“何か”を見つけ出し,それとの対比によって,図式の構図をよりはっきりさせていこうというところにある。
当然この“何か”は,グループ化の中で大まかにつかまれた構図との(類似性と関係性によって)アナロジーを見つけ,それを媒介として,グループ間の構図,あるいは全体の構成,枠組をつかもうというのである。その意味で,新しい構成(隠された枠組)を発見するとは,“アナロジーの発見”なのである。
つまり,共通性発見作業の中でつかんだ関係を,何かのアナロジーとして見ることができれば,そこから関係の中に新しく(例えば,見つかっていない関係とか全体の輪郭とか)見えてくるもの(仮説)があるはずである。これを仮説として検証することで,関係を新しく構成し直すことができるのである。
新しい構成の発見に導くアナロジーをどうやって手に入れたらいいのか?ゴードンは,『シネクティクス』の中で,アナロジーの手法を,
・擬人的類比(personal analogy)
・直接的類比(direct analogy)
・象徴的類比(symbolic analogy)
・空想的類比(fantasy analogy)
の4つ挙げている。直接的類比は,対象としているモノを見慣れた実例に置き換え,類似点を列挙していこうとするものであり,擬人的類比は,対象としているテーマになりきることで,その機構や働きのアイデアを探るという,いわゆる擬人法であり,象徴的類比は,ゴードンの取り上げている例では,インドの魔術師の使う伸び縮みする綱のもつイメージを手掛かりに連想していこうとするものであり,空想的類比は,潜在的な願望のままに,自由にアイデアをふくらませていこうとするものであるが,いずれも,その区別はわかっても,それをどう使いこなし着想に結びつけるかの方法論は具体化されていない。もちろん,擬人法や空想は,アナロジーの手掛かりとして重要であるのは,後述する通りであるが,こういうアナロジーの分類だけではアナロジー発見の手掛かりとはなりにくい。
むしろ,大事なのは,アナロジーの発想の仕組み(アナロジーの見方)であり,類似性と関係性というアナロジーの構造(アナロジーの見え方)をはっきりさせることだ。
- アナロジーの仕組み
では,アナロジーはどんな構造をしているのか,その共通した仕組みをまずはっきりさせておかなくてはならない。前述したように,アナロジーの中身は,関係性と類似性であるから,その違いから,アナロジーと概括されるものを,以下のように2つにわけることができる。
・類似性に基づくアナロジーを,「類比」
・関係性に基づくアナロジーを,「類推」
既に類似性と関係性で触れたように,前者は,内容の異質なモノやコトの中に形式的な相似(形・性質など),全体的な類似を見つけだすのに対して,後者は,両者の間の関係(因果・部分全体など)を見つけ出す。関係性に基づくアナロジー=類推を整理すると,
・構成要素の関係性からの類推
・関係から見えてくる全体構造の類推
の2つのタイプがある(類似性に基づくアナロジー=類比は,後で触れるように,類推の特殊型なのである)。
- 両者の構成要素のもつ関係性からの類推
第1は,典型的には,独立した2つの対象間の構成要素の対比によって,下図のように,既知のBの要素間(β1β2)の関係(b12)がわかっており,Tの要素(τ1)とBの要素(β1)とが対応し,BとTの要素間の関係(b12とt12)が対応しているとき,それとの類推から,Tにおいてもτ2があるに違いない,と推測していく。
この場合,要素の類推だけでなく,関係そのもの(b12,t12)の類推でもいいし,またこの場合,性質が1つであれば類比となる。この意味からみれば,類似性に基づく類比は,対比する両者の比較項目を1として括ったときに成立する,特殊なアナロジーなのである。
Β T
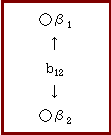
さらに,関係性に基づくアナロジーの場合は,厳密に言えば,B→Tの全体同士,β1→τ1,β2→τ2,……βn→τnの要素間の1対1の対応関係と,Bとその構成要素β1,β2,……βn,Tとその構成要素τ1,τ2,……τnといった関係,とは異なる関係性をもっている。前者を,水平関係,後者を垂直関係,と呼ぶこともできる。例えば,原子と太陽系の比較で言えば,核と太陽,電子と惑星といった1対1の関係とは別に,原子構造→電子・核,太陽系→惑星・太陽の間には,全体・部分乃至因果関係を見ることができる。あるいは,次の例で言えば,
→水平関係
垂直関係↓ 《人間》 《魚》
《鳥》 手 鰭 翼 肺 鰓 肺 毛 鱗 羽毛 出典;M.ヘッセ著『科学・モデル・アナロジー』(培風館)
と,対比した場合,水平関係(の1対1の関係)では類似性が見られ,垂直関係(の全体と構成要素の関係)では全体・部分の関係がみられる。当然,比べる両者の間に,水平関係の対応があれば,ある程度まで垂直関係が類推できることになる。
《類似性による空間の再構成》
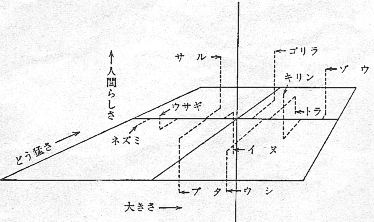
《類推による世界の再構成》
出典;右図は,佐伯胖著『イメージ化による知識と学習』(東洋館出版社),左図は,ルーメルハート著『人間の情報処理』(サイエンス社)
また,ここでは2次元での関係の比較をしているが,これが3次元での関係あってもいいし,コトを考えるとき,時間経過を考えることも当然ありうるのである。
例えば,3次元空間に,部分集合の間の親疎を,距離をもとに位置づけて,各部分集合は「m次元の類似性空間内に,それぞれ一個の点として表現できる」とし,それらの関係は,座標の中に,それぞれの間の方向と距離で表現されるとしてみたり(ルーメルハート),「韓国の産業構造は, 数年前のわが国の産業構造である」といった類推や比喩表現を,「部分空間」との“ずれ”(平行とは限らない)によって形成された「空間」に,元の空間の関係を“転移"(置き換え)することで推測していくものとして,表現しようとする考え方(佐伯胖)等々がある(上図)。
いずれも,各要素間の関係を,座標軸上の距離(奥行や幅)や方向をもってプロットしようとするもので,上述したところに奥行の関係を加えただけで,基本的には同じである。
類似性は,内容の異質なモノやコトの中に形式的な相似(形・性質など),全体的な類似を見つけだすのに対して,関係性は,両者の間の関係(因果・部分全体など)を見つけ出すものであり。その関係性に基づくアナロジー=類推には,,
・構成要素の関係性からの類推
・関係から見えてくる全体構造の類推
の2つのタイプがあり,前者について,前回触れた。引き続き,後者について述べていくこととしたい。
- 両者の関係から見えてくる全体構造の類推
第2は,その要素ではなく,独立しているBとTとの間の関係から,それを図とする地を類推することになる。一つは,両者の位置関係自体から,
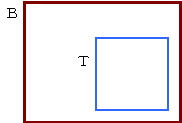
両者が,包含関係だったり,全体・部分関係だったり,一部重なっていたり,という全体としての関係づけの発見であり,いまひとつは,
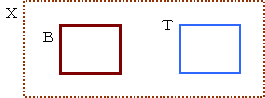
BとT自体が,両者を要素とする別の枠組の内部の組成関係である,という関係づけを見つけ出す場合である。これは,隠されているフレームを,両者間の構造から,類推していくことになる。この場合,BとTの内部の要素間の関係が,第一のような対応関係になっていることがあってもかまわない。こういう両者の関係は,対等とは限らず,例えば,BがTの部分(あるいはその逆)という関係であることも,当然ありうる。
- アナロジーと推理の関係
アナロジーは,類似性→関係性へとより文脈化,構造化していく。これは,次のように,
類比 → 類推 → 推論
《類似性》 →《関係性》 →《論理性》
形 因果 法則性
外観 対立 帰納性
色 位置 演繹性
性質 順序 つじつま
構造 補完 原理
仕組み 配置 原則
組成 全体・部分 理論
配置 類・種 数学
と整理できるだろう。アナロジーは橋渡し役となって,推理という論理的な脈絡へとつなげていくことになるといってもいい。たとえば,
破線の部分は,全体としての□という形がわかれば容易になる。既知の□をアナロジーとすることで,破線の部分を補完するのは,ある意味では推理にほかならない。これが,関係性であっても同様だ。始めに類似性があり,続いて関係性のアナロジーが来るという順序は便宜的なものにすぎない。
メロディーを聞いたとき,われわれが,別に関係性(音符の関係)ではなく,ひと連なりのまとまった節として聞き取っているのと同様,いずれが先ということはない。しかし,いまここで問題にしているのは,組み合わせの《文脈》と《構造》をつかむことである。
その意味では,関係からアナロジーに気づくことも,形からアナロジーに気づくこともあるかもしれないが,前者のときには全体の輪郭を対比するためには全体の類似性を,後者のときには,構成,組成を比較するために関係性を,やはり洗い出さなくてはならない。
- アナロジーをモノで表わせばモデル,コトバで表わせば比喩
類似性を手掛かりに,鳥をアナロジーとすることによって,コウモリを理解しようとするとき,われわれがよくするのは,モデルをつくることだ。あるいは写真や図解もその一種だ。そして,それを言葉で表現しようとすると,「夜飛ぶ鳥,こうもり」といった比喩を使うことになる。
いわば,アナロジーによる発想は,われわれが自分たちの思い描いているものを,一種の~,~を例に取れば,~というように,といった具体像で表そうとするときの方法であり,それは2つの方法で具体化することができる。
1つは,言語による表現である“比喩”(アナロジーのコトバ化)
もう1つは,モノ・コトによる表現である“モデル”(アナロジーのモノ・コト化)
である。
ただ,断っておけば,アナロジー→モデル・比喩という順序を固定的に考えているわけではない。アナロジー思考があるから,比喩やモデルが可能なのではない。確かに,関係にアナロジーの認知がなくては,それを喩えたりモデルとしたりすることはできないが,逆にAをBに喩えるから,その間に類似性を認識できることがあるし,モデル化することで,より類推が深化することもある。逆に類比が的確でなければ,比喩やモデルが間の抜けたものになることもある。
むしろ,3者は相互補完的であって,アナロジーの発見がモデル・比喩を研ぎ澄ましたものにするし,モデル・比喩の発見が新しい類比を形成することになる。
では,アナロジーの表現スタイルであるモデル・比喩はどんな関係をもっているのか。アナロジーの基本的な枠組はどうなっているのかを,以下整理しておきたい。
アナロジーによる発想は,われわれが自分たちの思い描いているものを,一種の~,~を例に取れば,~というように,といった具体像で表そうとするときの方法であり,それは,
1つは,言語による表現である“比喩”(アナロジーのコトバ化)
もう1つは,モノ・コトによる表現である“モデル”(アナロジーのモノ・コト化)
という,2つの方法で具体化することができる,と述べた。以下,それぞれについて,具体的に詳細に考えてみたい。
- モデルの仕組み
アナロジーの流れが,類似→関係→論理であるように,その表現スタイルであるモデルにも,類似→関係→論理の段階がある。モデルの表現レベルに合わせて整理すると,
・スケール(比例尺)モデル
・アナログ(類推)モデル
・理論モデル
と,アナロジーの流れと,対応している。スケール(比例尺)モデルは,類似性であり,アナログ(類推)モデルは関係であり,理論モデルは論理性である。
スケール(比例尺)モデルは,実物モデル,いわゆる,木型(モック・アップ)と呼ばれる,材質や媒体は違うが原寸大のものから,プラモデルや船舶模型,微生物の拡大図,スローモーション撮影,社会過程のシミュレーション等の,現物の縮小・拡大したものまである。これは,大きすぎるもの,小さすぎるものを,われわれに見えやすいレベルに合わせることであり,それによって,いわばどう見えるか,どう働くか,どんな仕組みか,どんな法則で動くか,を“モノ化した類似性”として,つかみやすくできる。当然必ずしも現物そのままではなく,むしろ,その特性の一部との同一性を模倣するかたちになる(その意味では相似的)。木型は形のみを真似て材質や機構は捨てているし,縮小(拡大)模型は大きさを犠牲にして,働きや機構を真似る。
アナログ(類推)モデルは,対象となるモノ・コトの基本構造や仕組みを表現したり,それを理解しやすくするために,“喩え”として創り出すもの。この場合も,サイズや媒体は同一である必要はなく,その仕組みや構造,機能を表現するために,別の関係(構造)を見立てる。例えば,水素原子を太陽系に見立てたり,電気回路を水流に見立てたりする(下図)のが,科学ではよくみられるが,両者の関係性によってアナロジーが立てられ,《構造》を発見するのに最も適している。これは“モノ化した関係性”と呼ぶことができる。
《水素原子のモデル》 《電子回路と水流モデル》
[原子構造] [太陽系システム] [水流モデル] [電子回路]
原子核 太陽 単位時間に流れる水量 電流
電子 惑星 水圧 電圧
電子の公転 惑星の公転 細い管 抵抗
太い管 回線
出典;M.ヘッセ著『科学・モデル・アナロジー』(培風館),山梨正明著『比喩と理解』(東大出版会)
理論モデルは,やはり関係性のモノ化であるが,形あるものとして実在化するよりは,関係性の実体化として,数学的モデルと理論モデルの2つにわけられる。
前者はいうまでもなく,数式や論理式という記号化によって,関係性そのものの機能と構造を表現する。そのいい例が,市川亀久彌氏の等価変換理論の“等価方程式”である。
出典;市川亀久彌『創造性の科学』(日本放送出版協会)
V iという適当な観点によって,Aο,Bτという既知の事象が,共通項сεによって等式が成立する,あるいは,既知であるAοという事象にviという適当な観点を導入することによって,Σaを廃棄し,新たなΣbを加えることで,AοからBτへと等価変換したことを意味している。つまり,両者を同じもとの見なす(同定する)観点によって,異なる両者を等号で結びつけられる新しいパースペクティブが開けることを,表現したのである。
理論モデルは,仮説を単純化した図式で表現する概念モデル(例えば,時空の虫食い穴によるタイムマシンモデル,あるいは素粒子が点ではなく広がりをもつとする,下図の超ひも理論のヒモモデル)やもっとイメージ豊かに構想された仮想的モデル(例えば,今日のコンピュータの出発点となった,記号で作動する装置を想定したチューリング機械モデル)がある。
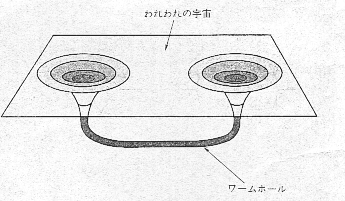
出典;F・D・ピート『超ひも理論入門上下』(講談社),松田・二間瀬『時間の本質』(講談社)
われわれに重要なのは,モデルは,情報ビジュアル化のもっていたと同様に,アナロジーをよりビジュアルにしているだけに,具体的イメージが描け,思考を展開していく「案内人」としては最適であり,これを枠組として,新しい見え方が探りやすいという点なのである。
- 比喩の仕組み
比喩とは,ある対象を別の“何か”に喩えて表現することである。通常言葉の“あや”と言われる。その意味やイメージをそれによってずらしたり,広げたり,重層化させたりすることで,新しい“何か”を発見させることになる(あるいは新しい発見によってそう表現する)。これもアナロジーの構造と同様で,比喩には,直喩,隠喩,換喩,提喩といった種類があるが,直喩,隠喩が《類似性》の言語表現,換喩,提喩が《関係性》の言語表現となる。
1,直喩
直喩は,直接的に類似性を表現する。多くは,「~のように」「みたいな」「まるで」「あたかも」「~そっくり」「たとえば」「~似ている」「~と同じ」「~と違わない」「~そのもの」という言葉を伴う。従って,両者は直接的に対比され,類似性を示される。それによって,比較されたAとBは疑似的にイコールとされる。それは,
対比された両者が重ね合わせられることを意味する。ただし,全体としての類似と部分的な性格とか構造とか状態だけが重ね合わせられる場合もある。ただ,「コウモリは鳥に似ている」「昆虫の羽根は鳥の翼に似ている」等々,既知の類似性を基に「AとBが似ている」と比較しただけでは直喩にならない。「課長は岩みたいだ」「あの頭はやかんのようだ」といった,異質性の中に「特異点」を発見し,新たな「類似」が見い出されていなくてはならない。
2,隠喩
隠喩も,あるものを別の“何か”の類似性で喩えて表現するものだが,直喩と異なり,媒介する「ようだ」といった指標をもたない(そこで,直喩の明喩に対して,隠喩を暗喩と呼ぶ)。したがって,対比するAとBは,直喩のように,類比されるだけではなく,対立する二項は,別の全体の関係の中に包括される,と考えられる。AとBの類似性を並べるとき,
① ② ③

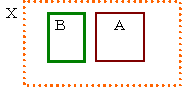
出典;佐藤信夫『レトリックの消息』(白水社)
①のようにAとBが重なる直喩と同じものもある(「雪のような肌」と「雪の肌」)が,②となると,先に挙げたハーヴェイの「心臓のポンプ」を想定すればいい,このとき「心臓」と「ポンプ」は両者を包括する枠組のなかにある。③は,一般的な隠喩であり,「獅子王」とか「狐のこころ」といったとき対比する一部の特徴を取り出して表現している。
この隠喩は,日本的には,「見立て」(あるいは(~として見なす)と言うことができる。こうすることで,ある意味を別の言葉で表現するという隠喩の構造は,単なる言語の意味表現の技術(レトリック)だけでなく,広くわれわれのモノを見る姿勢として,「ある現実を別の現実を通して見る見方」(ラマニシャイン)とみることができる。それは,AとBという別々のものの中に対立を包含する別の視点をもつことと見なすことができる。これが,アナロジーをどう使うかのヒントでもある。即ち,何か別のモノ・コトをもってくることは,問題としている対象(われわれにとっては,グループ化した情報群)を“新たな構成”から見る視点を手に入れることになる。
3,換喩と提喩
換喩と提喩は,あるものを表現するのに,別のものをもってするという点では共通しているが,直喩,隠喩とは異なり,その表現が両者の“関係”を表している(“言葉による関係性”の表現)という共通した性格をもっている。両者の表現する《関係性》は,換喩が表現する《関係性》が,空間的な隣接性・近接性,共存性,時間的な前後関係,因果関係等の距離関係(文脈)であり,提喩が表現する《関係性》が,全体と部分,類と種の包含(クラス)関係(構造)となっているが,この違いは,換喩で一括できるほどの微妙な違いでしかない。
換喩の表す関係は,「王冠」で「王様」,「丼」で丼もの,詰め襟で学生,白バイで交通警察,「黒」「白」で囲碁の対局者,ピカソでピカソの作品等々に代置して,相手との関係を表現することができる。そうした関係を挙げると,
・容器-中身
・材料-製品
・目的-手段
・主体-付属物
・作者-作品
・メーカー-製品
・原料-製品
・産地-産物
・体の部分-感情
等々,がある。いわば,その特徴は,類縁や近接性によって,代理,代用,代置をする,それが表現として《関係》を表すことになる。
一方,提喩となると,その代置関係が,「青い目」で外人,白髪で老人,花で桜,大師で弘法大師,太閤で秀吉,といった代表性が強まる。この関係としては,
・部分と全体
・種と類
・集団-成員
等がある。ただ注意すべきは,全体部分といったとき,
木→幹,枝,葉,根……
木→ポプラ,桜,柏,柳,松,杉……
では,前者は分解であり,後者はクラス(分類)を意味している。前者は換喩,後者が提喩になる。
4,比喩による推論
この《関係性》表現が,われわれに意味があるのは,こうした部分や関連のある一部によって,全体を推測したり,関連のあるものとの間で《文脈》や《構造》を推測したりすることである。対象となっているものとの類縁関係やその包含関係によって,その枠組を推定したり逆に構成部分を予測したりすることで,われわれは,隣接するものとの関係や欠けているものの輪郭や全体像の修復や補完をすることができるのである。これは,すでに推理にほかならない。
こうした比喩の構造をまとめてみれば,
[類似性] [関係性] [推論]
《直喩・隠喩》→《換喩・提喩》→《推理》
となるだろう。われわれは,“まとまり"としての類似性をきっかけに,似た問題を探すことができる。そして更にその中の《文脈》と《構造》の対比を通して,未知のものを既知の枠組の中で整理することができる。しかし,最も重要なことは,ひとつの見方にこだわるのを,比喩を通した発見によって,全く別の《文脈》と《構造》を見つけ出せるという,いわば見え方の転換にあるといっていいのである。
- アナロジー・モデル・比喩は別のものではない
“新しい構成発見”の手掛かりとして,以上のアナロジー・モデル・比喩をどう活用するかを考えるためには,この3者の,補完関係を整理しておかなくてはならない。
[類似性] → [関係性]→[論理性]
直喩・隠喩→換喩・提喩→推理 (比喩)
類比→ 類推 →推論 (アナロジー)
スケールモデル →類推モデル →理論モデル (モデル)
アナロジー・モデル・比喩の関係を,誤解を恐れず,簡略化すれば,上のようになる。「~として見る」がアナロジーであるなら,それを比喩的に言えば,“意味的仮託”あるいは“意味の置き換え”であり,“価値的仮託”あるいは“価値の置き換え”である。モデル的に言えば,“イメージ的仮託”あるいは“イメージの置き換え”であり,“形態的(立体的)仮託”あるいは“形態の置き換え”である。仮託あるいは置き換えること(仮にそれにことよせる,という意味では,代理や代置でもある)で,ある“ずれ”や“飛躍”が生ずる。だから,それを通すことによって,別の見え方を発見しやすくなるということなのだ。なぜなら,前述したように,われわれの意味的ネットワークの底には,無意識のネットワークがあり,意味や知識で分類された整理をはみ出した見え方を誘い出すには,このずれが大きいほどいいのだ。
われわれが,アナロジーを使うのは,自分たちがテーマをもっていて,それをよりうまく表現するためでも,言いたいことをモデルによって新しい関係の中で表現してより的確に伝えるためでもない。大事なことは,われわれは,自分たちの関係づけた情報群に《意味》と《構図》を発見したいのだ。つまり「それがもっているはずの(隠れた)テーマ」を見つけたいのだ。そのために,アナロジーを下絵や隠し絵,あるいは手本にして,それをトレースすることで,隠されていたものを炙り出したいのだ,ということを忘れてはならない。
創造性のステップで言われる“あたため”というものがあるとすれば,この“下絵”の発見のための時間にほかならない。どういう下絵が,新しい見え方をもたらすのか,「そうか,そういう見方をすればいいのか」と気づく発見的認識をもたらす隠し絵を,アナロジーを使って見つけ出さなくてはならない。そのための時間が必要なのだ(アナロジーを通してモノを見ることを図 式化したのが,別図である)。
- アナロジー発見の2つのアプローチ
アナロジーを通じて(媒介にして)別の見え方をつかむという意味では,その媒介が言葉なら別の意味に,モデルなら別のモノ・コト(空間表現)に,似ていれば類似性が,つながれば関係性が,それぞれ見つかるはずである。では,そうしたアナロジーを見つけ出すにはどうしたらいいのか。
その鍵については,前述した通り,ゴードンが幾つかを,類比タイプを分類している。それをもう少し整理し直すと,考え方として,2つになる。
第1は,アナロジー(あるいは比喩表現,モデル表現)着眼点の整理である。どういう視点に立てば(どんな見方をすれば)どんなアナロジーが見えやすい(どんなアナロジーとなる)か,われわれの視点(見方)別にリストアップしておくアプローチである。ゴードンの挙げた擬人的類比,空想的類比はここに含まれる(アナロジーの見方チェックリスト参照)。
第2は,見えているものから想定できる(炙り出せる)アナロジーの基本パターンをチェックリスト化することである。それは,アナロジーの類似性,関係性の構図をできるかぎりリストアップし,それと対比することで,強制的にこちらの目にスクリーンをかけ,アナロジーを発見しやすくしようとするものである(アナロジーのパターンとなる,かくかくの見え方はないか等々)。これによって,見えているものの背後に隠されているアナロジー可能態を次々洗ってみることができる。ゴードンの挙げた直接的類比,象徴的類比は,ありうるアナロジーの構図(パターン)の1つと考えることができる(アナロジーの見え方チェックリスト参照)。
ここまでに,共通性の発見→グループ化→共通性の発見……によって,より上位グループ化し,アナロジーを通して,そのグループ間の関係づけをつかみ,最終的にグループ群の構造を把握し,アナロジーという眼鏡によって,新しい見え方が展け,新しい構成を造形することを可能にすることを述べてきた。新しい構造がつかめることで,情報の編集作業は最終段階になる。
- アナロジーによって全体の構図を見る
例えば,Aを,Bというアナロジーとして見ることで,新たに見えてくる(分かる)コト(X)には,2つのタイプがあるはずである。
即ち,第1は,類似性として見えてくるものには,次のようなものがある。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)を通して,Xの形に見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)を引き合いに出すことで,Xの機能に見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)として見ることで,Xの構造が見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)をスクリーンとすることで,Xの大きさを推定できる。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)をトレースすることで,Xの組成を推定できる,等々。
そして第2は,関係性として見えてくるものには,次のようなものがある。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)を通して,Xの(要素)関係が見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)を通して,Xの全体像(フレーム)が見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)をなぞることで,Xの包含(全体・部分)関係が見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)を写すことで,相互(因果・序列)関係が見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)を通して,隠れて(欠けて)いた関係が見える。
A(の要素関係)は,B(の要素関係)を通して,全体の枠組を補修することができる,等々。
- 構図を下敷に組み立て直す
われわれは,自分の知っているものを通して(なぞって)しか,未知のものを理解できない。例えば,「コウモリ」が未知とすれば,既知の鳥を通して,推し量るしかないのである。そこで,鳥の構造,器官,機能を通して,コウモリのそれを推測していく,これがアナロジーである。この異同を通して,単独でコウモリを見ていたのとは違う見え方を手に入れる。ボーアが太陽系のアナロジーによって原子構造に新しい見方を示した(これはモデル)ことや,田中角栄を太閤秀吉に見立てることで彼の何かがよく見えてくること(これは比喩)も,同じくアナロジー「を通す」ことによって見えたことなのである。
仮に,そこで新しい組み合わせが見えたとすれば,それを新しい構成についての仮説として,細部の組み合わせが説明できるかどうかを,演繹していけばいいのである(もし~と同じ組成で見たらどうか,同じ構造として見たらどう見えてくるか,等々)。それが情報の新しい見え方(解釈)を可能とするとき,アナロジーは,新しい意味と背景を見る,偏光レンズのような役割を果したのである。
アナロジーによって,新しいパースペクティブが見えてくる例は,科学的発見には枚挙しきれないほどあるが,例えば,地球が回っているとしたコペルニクスによって,宇宙の見え方が変わったように,17世紀に心臓をポンプと見立てたW.ハーヴェイによって,機械に喩えられる心臓が発見されている。それまで,静脈弁も発見されていたのに,「静脈は心臓へ向かってのみ流れ,動脈は心臓から出てゆく方向でのみ流れる」ことが見えなかった。ちょうど,宇宙の見方をアリストテレス以来の宇宙像でしか見なかったように(ハーヴェイ『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』岩波文庫)。
ではなぜ,ハーヴェイには,その搏動によって血液循環をさせる心臓が見えたのか。なぜ機械に喩えられる心臓の機能と構造が見えたのか。それは,毎日の無数の解剖によって得た情報の見え方を,その時代の知識の文脈による区分や分類で整理するのではなく,その見え方自身によって,新しく括り直そうとしたところにあった。
無数の生物,心臓をもたないミミズ,カイメンから心臓をもつカタツムリ,貝,ザリガニ,蛙,魚,哺乳類,鳥に至るまで心臓を解剖し,観察し続けて,動脈を切断すれば「半時間以内に全血量が全身」から出てしまうこと,あるいは動脈を心臓近くで「結紮する」と動脈が空になること,こうして「まずはじめに心房が収縮し,その収縮の間に血液が心室へと送り出される」「心室は充満し,心室は収縮して搏動し,血液を動脈に送り出す」と集約し,この心臓の働きが,「他の器官に先んじて発現」し,動物を1つの全体として作り上げる「一種の機械である」と見たのだ。“ポンプ”という言葉を使わないまでも,「収縮によって血液を動脈の中に押し出し」て循環させる心臓の働きを見たとき,比喩としてのポンプを見ているのである(ラマニシャイン)。それによって,その機能と構造に新しい見え方が生まれてくる。
こうしてつかまえた仮説を通して,どういう見え方ができ,新しい構成のし直しができるかを, 繰り返し検証しなくてはならない。そうやって,部分集合間の新しい関係づけを創り出すことによって,最終的に新しいシステムを形成することになる(これを図にしてみると,別図のようになる)。
- 再構成にアナロジーを使う意味
情報を括り直してアイデアを創り出すのに,アナロジーを媒体にしている,構成し直し型の創造性技法の代表的なものとしては,
・アナロジーによる発想の拡散→収束をシステマティックに体系化していくプロセスをモデル化した,NM法
・一見関係ないものを類比によって結びつけていく,類比的発想モデルの代表的なものとして, シネクティクス
が挙げられる。この他,一般にはブレストの変形や発散型に分類されるものに,
・構成要素に分解し,その要素別のコンポーネント(構成要因)を洗い出し,要素間にコンポーネントの最適組み合わせを図っていく,形態分析法
・欠点(希望点)を改善のアイデア集約の鍵としてまとめていくものとして,欠点(希望点)列挙法
・属性(機能・形態・素材,あるいは機能区分)に分解して,それぞれごとに改革・改善・変更のアイデアをまとめていく,属性列挙法
がある。ただ,最終的なアイデア集約を,単に現状の枠組の範囲内ですます(改善)か,それとも枠組そのものを壊すようなものにしていくかを左右するのは,既知の枠の中でまとめるか,それを別にアナロジー等でずらしていくかにある。その点で言えば,後者の3技法は,こういうものだと先入観をもって取り組まないほうがいいだろう。
それに対して,シネクティクスとNM法は,アナロジーを使っている点が,特色である。シネクティクスは,ゴードンの開発した技法であり,この「シネクティクス」は,ギリシャ語の「無関係な要因を1つの意味あるものに統合する」という意味で,その触媒としてアナロジーを活用しようというものである。NM法はこのシネクティクスをヒントに開発された技法である。このいずれもが,誤解を恐れずに言えば,KJ法等によって情報を括り直していくプロセスの先に,そのまま論理的あるいは常識的に共通項を括ったのでは,「異質な組み合わせ」になりにくいので,アナロジーという別の枠組を下敷にすることで,特異な組み合わせを探り,アイデアを発想しようとする。そのアナロジーの使い方の違いでいろいろな技法がありうるということになる。
例えば,NM法をよりわかりやすいステップにしたNM-T法では,①課題設定→②キイワード設定→③アナロジー発想(キイワードから見立てられるアナロジーへと転化する)→④アナロジーのバックグラウンドの洗い出し(アナロジーのイメージを媒介に構造や形態などをビジュアルに表現する)→⑤アイデアの集約(そのビジュアルなイメージを仲介として課題解決のアイデアを洗い出す)→⑥解決策(アイデアの分類整理),といったステップをとる。確かに,一見すると,③のステップでのアナロジー発想が中核のように見えるが,実は,発想プロセス全体で見れば,一番重要なのは,最後に個々のアイデアをどう組み合わせるかであり,その青写真としてどうアナロジーを使うかなのである。
問題は,どちらのアナロジーを重視するにしろ,アナロジーはどうすれば発想できるのか,ただの類比と類推と推理とはどう違うのか,あるいはモデルと比喩とはどう違うのか等々については,どの技法もあまり深入りしていないため,ほとんど前述したゴードンのアナロジー分類やその考え方を踏襲しているようなのである。しかし,そのシネクティクスの場合は,グループ討議でこうやって出てくるアナロジーを使えばいいと例示してはいるが,それ以上にそのアナロジーがどうすれば発想できるかまでは踏み込んでいない。そのため,アナロジーを展開するためには個々の経験的なひらめきに頼るしかない部分が残るのが,難点なのである。
確かにアナロジーは,アイデア着眼や連想の手段として活用するだけならともかく,最適組み合わせの青写真として活用するためには,発想全体の中でアナロジーの位置づけをより明確にし,どういうプロセスがアナロジー発見をもたらすのかをはっきりさせておかないと,アナロジーは単なる発想転換の技術程度の受け止め方しかされなくなってしまう。アナロジーは,最終的な発想の構造と文脈を決定する,発想の要なのに,である。
アナロジーについては,ここを御覧下さい。
アナロジーの見つけ方については,ここをご覧下さい。
アナロジーの見方チェックリスト,アナロジーの見え方チェックリスト参照下さい。
- 自己点検と相互点検の仕掛け
問題意識とは何か
「問題」というものが転がっていることはありません。問題はいつも誰かの目を通してのみ“問題”となります。どこかに「問題がある」のではなく,誰かが「問題にする」ことによって,初めて,「問題になる」ものなのです。
ここには,ふたつの意味があります。
第1は,「問題」は,誰にとっても「問題」とは限らないということです。その人にとって「問題」と思えても,他の人にとっては何でもないこともあります。もし,誰の目から見ても「問題」なら,実行する,つまり誰が,いつ,どういう解決をするかだけが問題です。ここでいう「問題」とは,誰も気づいていないが,いずれ大きな広がりをもつだろう「問題」,まだ誰も気づいていない危機となる「問題」,まだあまり気にとめられていないが,必ず顕在化する「問題」等々です。
第2は,同じく問題とされたとしても,それを解決しようとするとは限らないということです。問題と課題とは違うのです。飲み屋で上司の悪口,会社の批判をしているのは,その人がそれを問題だと思っているということです。でも,多くは酒の肴として,翌朝は忘れてしまうのでしょう。誰もが,それが自分が解決すべき問題だと受け止められるとは限らないのです。
しかし,その問題を,自分が解決すべき問題として,具体的に考え始めたり,行動を起こし始めたとき,その「問題」は,その人にとって,「課題」になるのです。ちょうど毎日風呂に入っていて,いつもお湯だったらいいのにと考えても,大半は風呂から上がった瞬間に忘れるのに,それを忘れず,自分の課題として解決した人がいたから,24時間風呂が世の中に存在するように。
下図は,人が問題と感じたときにとる対応を図解したものです。
「後3ヵ月で異動だから」と問題から逃げることもあります。暇がない,予算がない,人手がないと言訳して,問題を避けることもあります。しかし大半は,他の人も別に気にかけていないじゃないか,別に大したことではないと,「問題」を見過ごすのです。
その一方で,自分の感じた問題と向き合い,何とかならないだろうか,考え始めたとき,始めて問題は解決しなくてはならない事柄として目の前のあるのです。これを,問題意識と呼びます。問題を感じることは,誰にでもできます。しかし,それに向き合わない限り,その問題は,ないのと同然なのです。
ただ,何を解決しなくてはならない「問題」と意識するかは,その人が何を問題と思うかで,違ってきます。問題とは,現状と基準とのギャップですから,何に基準を置くかで,
①理想との乖離を問題だと思う(理想との差を問題にする)
②立てた目標や基準の未達や逸脱を問題と思う (目標未達を問題にする)
③不足や不満を問題と思う(欲求や満足の満たされないことを問題にする)
④価値や判断の基準からの逸脱を問題だと思う(価値や意味との距離を問題にする)
等々に分かれるのです。
言い換えると,眼前の状態を“問題”とするかどうかは,どういう基準を意識しているかによるのです。つまり,基準の明確化が,より問題への感度を高めることになるはずなのです。
なぜ問題意識が妨げられるか~固定観念あるいは先入観とは何か
ハンソンは,“見る”とは,次の図を,
木によじ登っている熊として見ることであり,それは,九十度回転したら,次のような様子が現れるだろうことを見るのである,といいました。そうではないかもしれないのに,です。それが先入観です。
つまり,われわれは対象に自分の知識・経験を見るのです。あるいは知識でつけた文脈を見るのです。ゲーテの言う通り,われわれは知っているものだけをみるのです。
種村・高柳『だまし絵』(河出文庫)
図を見て下さい。この絵は,老婆に見えたり,若い女性に見えたりします。しかし,この絵を描き変えます。まず老婆にしか見えないように描き変えた絵を見たあと,この図を見ると,100%の人が老婆にしか見えなくなるという実験結果があります。また,若い女性にしか見えないように描き変えた絵を先に見せられて,図を見ると,同じように100%の人が,若い女性にしか見えなくなるというのです。
つまり,先に絵を見た経験によって,絵への先入観が作られてしまうのです。
私たちがものを見るということは,外界からの情報がすべてと思いがちです。しかし,実は外から入る情報は20%程度で,残りは脳内の他の部位からの情報を使っていると言われます。すでに知っているものを見たとき,それと意識するより速く,脳内の回路が起動し,すでに見たものとして見てしまう。このように,経験によって強化された脳が,自分の「ものの見方」を決定しているのです。
知識とは,学習を通して手に入れた,モノの見方の枠組みであり,知識を学ぶとは,ものの見方を学ぶことです。人間の心は,モノを見るときのクセで折り目がつき,皺(しわ)がつくものである,といわれるのも,無理はないのです。
もちろん,知識が無用と言うのではありません。知識がなければそもそも見えるものが見えないのですから。しかしそれがときに,新しい事態を見過ごす原因となるということなのです。
どう気づきを高めるか~個人としてのスキル
先入観を崩すには,発想の柔軟性が必要です。これは,別のいい方をすると,ものの見方の多角化です。保育園の保母さんがしゃがんでいるのは,園児と同じ目線を取ろうとするからです。副支店長を公募したスーパーがありましたが,それはお客様の視点から売り場をチェックするということです。われわれは,知らないものを拾ったとき,よくあっちからこっちから眺めます。これを「ためつすがめつ」するといういい方をしますが,多角的とは,それを意識してやることなのです。
左利きの人の不便さは,右利きの人には意識しにくいことです。
子供の立場で使いつらい自販機は大人の視点では気づきません。
若い人には何でもない重さが,年寄りには腰を痛めるほどの重量です。
売り手には扱いやすい商品分類も,買い手には欲しいものが探しずらいだけです。
こうしたことは意識しないと気づけないのです。そうすると,
視点が変われば(モノの)見え方が変わり,
(モノの)見え方が変われば(見る側)の見方が変わる
意識的に視点を動かすことで,いつもの自分の位置や立場からはなれ,別のところから見ることができます。そうすることで,見慣れたものの違った側面に気づくことがあります。
そのためのツールは,ふたつです。ひとつは,チェックリストです。どんなものでも構いません。いわゆる5W1Hでもいいし,自分の犯しやすいミスをリスト化してもいいでしょう。筆者は,下図のようなチェックリストを作っています。
①視点(立場)を変える いまの位置・立場そのままでなく,相手の立場,他人の視点,子供の視点,外国人の視点,過去からの視点,未来からの視点,上下前後左右,表裏等々
②見かけ(外観)を変える 見えている形・大きさ・構造のままに見ない,大きくしたり小さくしたり,分けたり合わせたり,伸ばしたり縮めたり,早くしたり遅くしたり,前後上下を変えたり等々
③意味(価値)を変える 分かっている常識・知識のままに見ない,別の意味,裏の意味,逆の価値,具体化したり抽象化したり,まとめたりわけたり,喩えたり等々
④条件(状況)を変える 「いま」「ここ」だけでのピンポイントでなく,5年後,10年後,100年後,1000年後あるいは5年前,10年前,100年前,1000年前等々ここでいう,「変える」とは,それを意識すると置き換えても同じです。自分が取った視点を意識したときはじめて,では別の視点に何があるかと考え始めることができるからです。たとえば,「視点を変える」の,「視点を意識する」は,「~と見た」とき,「いま自分は,どういう視点・立場からみたのか」と振り返ってみる,ということです。そうすることで,では別の視点ならどう見えるか,と考えていくことができるのです。
第2は,人とのキャッチボールです。
キャッチボールという言葉は,少し説明を要するかもしれません。周知の3Mのポストイット開発をめぐる逸話があります。シルバーという人が,接着剤を開発していて,貼ってもすぐ剥がれてしまうものを創り出しました。彼はそれを「失敗」とはみなさず,社内の技術者同士のミーティングで,自分にはこの使い道が思いつかないが,誰かいい使い道があったら教えてくれないかと,言ったのです。その中に,いつも聖歌隊で,本に挟む付箋に不便を感じていたフライが,その使用方法を思いつき,ポストイット発案につながったのです。
こうした自分の問題意識をぶつけることで,新しい何かを発見することにつながるやりとりを,キャッチボールと呼びたいのです。ブレインストーミングを雑談化したイメージです。カーネギーは,「2人の人間がいて,いつも意見が一致するなら,そのうち1人はいなくてもいい人間だ」(『人を動かす』)と,言っていました。ひとりひとり生まれも来歴も違う人間なら,モノの感じ方も考え方も違って当たり前です。だから,ひとりひとりの発想も違うはずです。チェックリストを使ってひとりでやる発想転換を,人とのキャッチボールを通してしようとするのです。しかし,大事なことは,人に正解を教えてもらうのではありません。自分と違う切り口からの発想に,自分の中で答えに気づくことなのです。したがって,キャッチボールは一方通行であるはずはありません。キャッチボールをしそこなうのは,自分にとってデメリットなのです。それが以下のタブー十ヶ条です。
キャッチボールタブー10ヵ条
①話し手を,どうせろくな話はしない奴だと評価して締め出していないか
「あいつの話はおもしろくない」「どうせたいしたことじゃない」「いつもくだらないことしか言わない」「いつも言い訳ばかりだ」という態度をしていないだろうか。そうなるとほとんど聞いていないし,当方が聞いていないことは相手にわかるものだ。
②そこまで聞けば分かったと早合点で結論づけていないか
「そこまで聞けばわかった」「よっしゃ」「まかせておけ」「みなまで言うな」と勝手に早呑込みしてしまっていないだろうか。相手は別のことをいいたいのかもしれないのに!
③相手の話に自分の期待を読みこんで聞いていないか
「おれのことは,わかってくれるはず」「あそこまで言ったんだ,きちんとやってくれるはず」「あれだけ教えたんだ,できるはず」という,一方的な思い込みはないか。それでは相手のことが見えてはいない。あるいは逆に,「そうだろう,よくわかる」「そうだ,それがおれの言いたいことだ」と,自分の期待や願望だけを聞き取っていることはないか。それでは,相手の本当に聞いて欲しいことは聞こえていない。
④自分の聞きたくない部分には耳をふさいでいないか
「そういうことを言いたいんじゃないでしょ」「そんなことは聞いていない」と,途中で遮ってしまっていないか?言いたいことを決めるのは,相手なのに。
⑤相手の話から自分のイメージを勝手に広げて聞いていないか
相手の話から勝手に自分のイメージを広げて,相手の言うことを聞いていない。勝手に解釈する。片言聞いただけで,勝手に自分の空想やアイデアを肥大させていく。そこには相手の気持も考えも全く入り込む余地はない。
⑥答えの予行演習をして聞いていないか
相手の話の途中から何を言おうかと一生懸命考えていて結局聞いていない。どう叱るかとかどう言い訳するかとか,自分の都合や事情にこだわっているいるだけ。それならコミュニケーションする必要はなくなってしまう。予想しない結論になるから会話がある。
⑦相手の言葉尻や態度に感情のカーテンをおろしてしまっていないか
後輩のくせに,新人のくせに,そういう生意気なことを言うのか。相手の言葉尻にこだわっているのは,結局自分の立場やプライドを傷つけない心地よい言葉を重んじているだけ。中身が自分の意向や趣旨に反すれば聞く耳をもたないのだと,相手は受け取るだけだろう。
⑧相手の話の中身よりは話し方や表現に目を奪われていないか
そういう言い方はあまりいい表現でない,言い方が間違っている,表現にミスがある,と口の利き方を問題にして,自分の価値観でつい説教を垂れる。たまたま表現スタイルで文句をつけているが,結局形式を理由に中身を聞く耳をもたず,自分の価値観を押し付けているだけ。
⑨相手の発言以上の意味を読みこんで聞いていないか
相手が意見や提案をしたとき,「君は何かね,僕のやり方に文句をつけているのか」「僕の考えは間違っているというのか」と悪意に解釈したり,単に私的に賛意を示しただけなのに,公に賛同したと触れまわったりしていないだろうか。相手の言葉の意味は相手のものだ。それを確かめて,自分と同じかどうかは確かめなくてはならない。
⑩聞きたいことや都合のいいことだけしか聞こえていないのではないか
聞きたいこと,おいしいことだけしか聞かない(人を選ぶ,情報を選ぶ)。おいしいことしか聞かない人には,おいしいことしか誰も言わないということにほかならない。とても相手の悩みに聞く耳をもてそうもない。デビッド・アウグスバーガー『聞く』(2)を参考にしている。
気づきを高めるチームとしての取り組み
問題の特性から,次の点が言えるはずです。
第1は,問題が誰かの目を通してのみ“問題”となるのだとしますと,共通な問題が“ある”のではなく,ひとりひとりが問題にしている問題を,共通な問題に“する”というプロセスを経る必要があるということを意味します。
第2は,問題とする“基準”,たとえば達成すべき目標,維持すべき水準,保持すべき正常状態,守るべき基準等々が共有化されていなくては,何を問題とするかがバラバラになってしまう。基準が共有化されてこそ現状に対して“問題”を共有化できるのです。
第3に,基準と関わるひとりひとりの意識には,理想との差,目標の未達,不足や不満,
価値や意味との距離等々ありますから,チームとして目指すもの(目的),期待する成果(目標)をすりあわせる必要があるのです。
そこで,「問題を意識する」ことを高めるには,次の4点が重要になりましょう。
①そのことについての知識・経験があること
②目的や目標が何であるかを知っていること(目的意識)
③それが自分の問題であると感じること(役割意識)
④それを自分が何とかしなくてはならないと感じていること(当事者としての自覚)
つまり問題意識があるから問題が見えるのではないのです。問題が見える立場と意識があるから問題意識が強くなるのです。どういう状態だと問題が見えやすい状態とすることができるか,ということなのです。 それは,こういうことです。チームの目指すものは何かという目的意識があるから,その中で自分は何をすべきかが意識でき,その役割意識があるからこそ,何が問題かに気づきやすい,ということなのです。これをたえず,チーム内で確認し,すり合せることが必要です。
問題意識を高めるために,確かにひとりひとりのレベルアップも不可欠です。チームで仕事をしているときは,それだけでは問題の解決になりません。ひとりひとりのミスや不注意を起こさないようなチームとしての仕組みをどう作るかが課題でなくてはなりません。
たとえば,コミュニケーションでもそうです。職場のコミュニケーションは,仲良しになるために必要なのではありません。コミュニケーションの目的は,共有化した職場の目的・目標を達成するために,それぞれが分担している役割の間での情報交換です。
報告:PDCAの共有化(仕事の進捗状況の擦り合せ)
連絡:業務情報の共有化(保有知識やチエ・ノウハウのレベル合わせ)
相談:問題状況の共有化(事態の現状認識や見通しのキャッチボール)
たとえば,報告・連絡・相談というのが求められます。しかし,それは上位者の職場管理のツールでも部下のアリバイ証明のためにあるのでもありません。それをすることが,共通の目的達成のために不可欠だからです。メンバーがつかんだ情報をチームとして共有化することで,共通認識を持つことができます。ひとりひとりのかかえている問題状況をきちんと共有化してもらうことで,ひとりで抱え込んで追い詰められる事態を避けられるはずです。何のためにチームを組んでいるのか,メンバーの数の和ならチームを組む効果が出ているとはいえません。1+1=2+αをどれだけ出すか,問題意識もまた,個人のスキルとして考えている限り,チームとしての課題解決になることはないはずです。
大事なことは,ひとりひとりの問題意識を,一個人のスキルや能力として自己完結させないことです。ひとりでできることは限度があります。どんなにすぐれた問題意識の持ち主でも,所詮個人の発想の枠から出ることはできません。
それよりは,どんな些細な気がかりでも,どんなつまらなそうな違和感でも,チームメンバーの問題意識にさらすことで,「どうです?」「ひょっとしたら」「前にもこんなときが」「それならこうしたら」等々といった,キャッチボールを通して,掘り下げる場があることです。このとき,ミーティングや会議だけを想定されていたら大間違いです。会議のみで問題意識がかわされることはまれです。何気ない会話,雑談,立ち話,重要なことはこうした中で気づかれます。そういうことがフランクにできる場づくりが必要なのです。ポストイットはそれなしに世にはでていないのです。
- 自己モニタリングのしかけ
エラーやミスを防ぐには,自分の行動や気持ちをモニターする自己モニタリング,自分で自分の行動をチェックし軌道修正するのが不可欠といわれます。しかし,それを個人に押しつけるのでは意味がありません。ここでの「自己」は,チームと置き換えて,自己点検→相互点検→全体点検をまわすことが有効だと考えています。そのツールがキャッチボールです。ひとりひとりの問題への気づきのレベル差を,マイナスと考えるのではなく,プラスとみなすなら,それを活用して,チーム全体としての気づきを高めればいいのです。
気になるシート
一般に,自己モニタリングのプロセスは,Plan(計画)→Do(実行)→Check(確認,軌道修正)→Action(次への対応)によって実現されるといわれています。ひとりひとりが,自分のその日の段取りを確認し,その通りできたかどうかをチェックしながら,軌道修正して,次にアクションを取るという個人の仕事のモニタリングを,チーム全体のものにするとは,ひとりの力量に押しこめないということです。ひとりでは気づけないことがあります。それを全体の耳と目で感知したものを,全体の中でチェックすることが,チーム全体の仕事を完結させることなのです。
たとえば,図のシートを使って,日々の些細な確認をする作業が,チームの目的と目指すレベルの確認となり,その共通の土俵づくりが,メンバーに共有化されていくプロセスとなれば,そのことでひとりひとりの問題意識を高めることになり,それを日々意識せずざっくばらんにすりあわせることができる,という循環を効果的にするには,地道な日々のキャッチボールを積み重ねていくことです。引用・参考文献
1)ノーウッド・R.ハンソン(渡辺博・野家啓一訳):知覚と発見上.P181~185,紀伊国屋書店,1982.
2)デビッド・アウグスバーガー(棚瀬多喜雄訳):聞く.すぐ書房,p50,1985.
3)海保博之,田辺文也:ヒューマンエラー.新曜社p86~93,1996.
-
発想力アップのためのマイチェックリストをつくる
- 発想の原動力タイプをチェックする
チェックしてみる
下記の設問で、強くそう思う個所に、レ印でチェックして下さい。
(注)発想の原動力チェックを参照してください。
問題意識のタイプ
チェック項目
該当の有無
Ⅰ・希望・願望・理想の「ワガママ発想」
ありたい/やりたい/なりたい/ほしい
①やりたいと思っていること(もの)がある ②試したいと思っているもの(こと)がある ③ほしいと思っているもの(こと)がある ④できたらいいなと思っていることがある ⑤あるといいなと思っているもの(こと)がある ⑥なれたらいいなと思っていること(もの)がある ⑦できたら面白いと思っていること(もの) がある ⑧あったら役立つと思っているもの(こと)がある ⑨こうなったらいいと思っているもの(こと)がある ⑩わかるといいと思っているもの(こと)がある ⑪行けたら良いなと思っていることがある ⑫変われたらいいなと思っていること(もの)がある ⑬知りたいと思っていること(もの)がある ⑭持ちたいと思っていること(もの)がある ⑮乗りたいと思っていること(もの)がある Ⅱ・水準(目標)の未達・逸脱の「イライラ発想」
できない/やらない/やれない/及ばない
①やりたいのにできなくてイライラしていること(もの)がある ②あるといいのにないために腹の立っていること(もの) がある ③気にはなっているが当面の仕事と関係ないのでやっていないこと(もの)がある ④やめなくてはいけないと思っているのに誰も気にしていないのでイライラしていること(もの)がある ⑤ずっと放置してきたのでどうってことはないと誰も見向きもしないこと(もの)があるので、気になっている ⑥やらなくちゃいけないのにできないためにモヤモヤしていること(もの)がある ⑦しなくてはいけないと思いながら手付かずになってヤキモキしていること(もの)がある ⑧ああしたいこうしたいと思っているのに何もできずキリキリしていること(もの)がある ⑨ついつい先送りにしてしまっていること(もの)がある ⑩やらなくてはいけないがどうせ駄目と諦めているもの(こと)がある ⑪誰かがやるだろうと手をつけていないこと(もの)はないか ⑫このままではまずいと思いながら放ってあってハラハラしていること(もの)がある ⑬何とかしなくてはと思ってもどうしていいか分からないお手上げのこと(もの)がある ⑭いろいろ手を尽くしてみたがまったく効果のあがらないこと(もの)がある
⑮解決するたびに別のところから新たに問題が出て一向解決しないこと(もの)がある Ⅲ・欠点・不都合・無駄の「マイナス発想」
足りない/まずい/欠けている/
①足りないと思っているもの(こと)がある ②ないことが不満なこと(もの)がある ③欠けていると思っているもの(こと)がある ④不平なもの(こと)がある ⑤使いにくいと思っているもの(こと)がある ⑥すぐ故障してしまうと思っていること(もの)がある ⑦無駄だ(必要ない)と思っていること(もの)がある ⑧無理だと思っていること(もの)がある ⑨不便だと思っているもの(こと)がある ⑩役立たないと思っていること(もの)がある ⑪不安に思っていること(もの)がある ⑫不満に思っていること(もの)がある ⑬不充分だと思っていること(もの)がある ⑭未完だと思っていること(もの)がある ⑮未熟だと思っていること(もの)がある
Ⅳ・自慢・自信・誇りの「プラス発想」
いける/やれる/どこにもない
①自分にはひとに誇れること(もの)がある ②自分にはひとに自慢できること(もの)がある
③ひとより優れていると思っていること(もの)がある ④どこにも(誰にも)ないと思っていること(もの)がある ⑤自分の中で大事にしていること(もの)明確である ⑥自分にとって何が値打ちがあるかいつも明確である ⑦自分には役立つもの(こと)・貢献できるもの(こと)がある ⑧自分には得意の分野(領域)がある ⑨ひとにはない、ちょっと珍しいこと(もの)をもっている ⑩自分には、ひとにない、ちょっと楽しいこと(もの)がある ⑪自分には、ひとにはない、面白いこと(もの)がある ⑫誰も気づいていない、自分が初めてのもの(こと)がある ⑬自分は最近話題になったこと(もの)がある ⑭自分は、新しい(古い)こと(もの)をもっている ⑮自分は、わくわくするようなこと(もの)をもっている
- 評価方法
各タイプ毎に、10以上になるのがあれば、それがあなたの問題意識のタイプと考えられます。10以上のものが2以上あった場合は、暫定的にレ点数多いものを、ご自分のタイプと仮定し、後で、次点のものと対比しながら、修正してみてください。いずれも、10に届かない場合は、その中で、レ点数の多いものを、一応ご自分の傾向値とお考えください。
評価項目の得点
傾向
Ⅰ・希望・願望・理想の「ワガママ発想」が高い 理想を設定ないし強く意識し、現状とのギャップに強く問題意識を感じる傾向 Ⅱ・水準(理想)の未達・逸脱の「イライラ発想」 現状の達成水準や基準に意識が向き、それへの未達・逸脱に問題意識を感じる傾向 Ⅲ・欠点・不都合・無駄の「マイナス発想」が高い 現状の問題点、不便、苛立ちを強く意識するために、日常的に不平や不満をエネルギー源にしている Ⅳ・自慢・自信・誇りの「プラス発想」が高い 自分の内部エネルギーが高く、他者や現状よりも、自分の中から価値や問題意識を発する
- 評価結果をどうみるか
あなたが、どこに強く問題意識をもつかのタイプをチェックしました。
発想は、現状を何とか変えたいと思うところから必要になるのですが、その出発点は、何について何とか変えたいと思うかです。それが、
Ⅰは理想の実現、
Ⅱは未達の回復、
Ⅲは問題点の改善、
Ⅳは内部価値の実現
それぞれに、強い意識があるということです。「問題」は、自分が問題にしない限り、自分にとって解決し、何とかしなくてはならない「課題」になることはありません。発想のスキルやツールが自分にとって不可欠となるのは、その後です。
その意味で、まずご自分の中に、何に問題を感じやすいのか、何を問題視するのか、どこに引っかかるのか、何に目を奪われるのか等々を、傾向として確認しておかなくてはなりません。それが、ご自分の発想のスタートラインだからです。
どれかひとつにならず、バラけた場合は、それぞれに応分の関心を示す傾向があるということです。悪く言うと気が多いと言うことですが、発想の幅が多岐にわたる可能性があるとも言えます。それを長所にするも短所にするのもご自身です。その中でも、相対的に数の多いものに、注目してみてください。
発想するとき使えるのは、自分の頭の中にあるものだけです。発想スキルを自分のものにするとは、自分の体と頭に、いつでも使えるカタチで自分流にしておくということです。
- 自己流チェックリストをつくる準備作業
チェックリストづくりの要件
チェックリストは,ここに既存のチェックリストの大半を紹介していますが,技法は自分の頭の中にはいっているものしか使い物にはなりません。
チェックリストは,自分にスクリーンをかけ,発想を促すことです。そのため,
・発想に必要な視点をあらかじめ設定しておく
・発想の漏れや落ちをなくすことができる
・必要点をある程度カバーすることで,発想を効率化できる
・準備なく発想しようとするときと比べて,発想の手掛かりが与えられる
・チェックすることで,自然に必要な視点や観点の転換をしていける
等々が必要になりますが,既存のものは制作者の必要にあわせて創られていますから,自己流の必要に応じたチェックリストが必要になります。
まず,チェックリストづくりの要件を以下に整理しておきます。
(1)チェックリスト項目の制約
使えるチェックリストは,せいぜい3~7項目が限界です。最大でも,10項目程度にします。ベストは3~4項目です。バラバラ化の切り口でも示したように,更にいくつかを細分化することは可能ですが,現実には使いこなせないように思います。
(2)使用目的から重点項目をリストアップする
その目的達成に不可欠と思われる要件を列挙してみることです。その上で,目的達成に重要と思われるものから順序づけていく。それを図解すると,下図になります。
(3)陥穽を防ぐ
自分がいつもつまづくところ,いつも陥る落とし穴やしくじり,あるいは,いつもこだわる固定観念等々を,予め防ぐために,ポイントをチェックリスト化しておきます。たとえば,「お掃除チェックリスト」や「後始末チェックリスト」のように,「相手のことを考えたか」「見逃しはないか」「見落としはないか」「再チェックしたか」等々の項目が必要になりましょう。それは,次のようなフローや切り口を考えることで,見つけやすくなるはずです。
・PDCA(Plan→Do→Check→Action)
・「案を出す」→「評価する」→「選択する」→「実行する」
・インプット→プロセス→アウトプット
で,たとえば,こんな項目。
・異見は出尽くしたか
・何が確かなことで何が曖昧なことか
・相手からの視点で考える
・相手はどう受けとめているかを考える
(4)5W2Hの洗い出し
目的指向の場合も,陥穽防止のリストも,具体的に考える切り口に5W1Hが使えます。「それはどこにあるのか」「それは誰がもっているのか」「誰がやったのか」「誰にメリットがあるのか」「どのように起こったのか」「いつ必要なのか」等々。たとえば,次のようなバリエーションにもできます。
・主体を変えたら(ヒト,立場,担当者,責任者,視点)
・対象を変えたら(モノ,コト,相手)
・時間軸を変えたら(いま,昨日,明日)
・空間軸を変えたら(場所,位置,内と外,表と裏,前後,上下,遠近,方向,間隔)
・理由を変えたら(価値・意味・基準・規範・目的・論理・感覚・感情)
・やり方を変えたら(方法,手段,優先順位,順序)
・水準を変えたら(レベル)
(5)思考プロセスのどこにポイントを置くか
インプット(素材)→アウトプット(最終状態)のプロセスの中で,どこにウエイトをおくのか,です。たとえば,素材の決め方が甘ければ,そこに焦点を当てるし,プロセスの追求が甘ければ,「まだまだないか」「もっともっとないか」「もう少し」といった項目が,また計画段階が甘ければ,「見通しは十分か」「誰と誰がサポートしてくれるのか」「障害の検討は十分か」等々の項目が,チェックリストとして必要になります。
その他,プロセスを考えるには,以下のような流れや視点を考えることも,ポイントが見えてきます。
・PDCA(Plan→Do→Check→Action),PDS(Plan→Do→See)
・「確認する」→「選択する」→「手に入れる」→「チェックする」
・「案を出す」→「評価する」→「選択する」→「実行する」
・「ヒト」「モノ」「カネ」「トキ」「チエ」
・5W2H
で,たとえば,こんな項目。
・その目的は明確か
・誰にどんな必要性があるのか
・誰がやるのか
・やらなかったらどうなるのか
(6)リストアップの仕方
チェック項目をリストアップしていく場合,留意すべき点は,次のようになります。
・箇条書に書き出すこと。できるだけ短く,①②……と挙げていくこと。
・一項目は一つの意味にすること。曖昧だと感じたら,別の言い方をしてみる。そうすると,元のものが二以上の意味をもっていることがある。
・一項目出したら,そのバリエーション,それに関係あるものを一緒に挙げてみること。
・過去にやったことがある場合は,どこが問題だったのかを挙げてみる。それを避けることがリストアップすべき項目となる。
・失敗しやすいこと,よくやる間違いも必ず挙げておく。
・リストは,関係ありそうなもの毎にグループ化しておく。そうすると,そこから関連したことが思い出されてくる。
・グループ化したリストは,ピラミッド型に序列をつけてみる。すると,同列だと思っていたものが,上のレベルだったり,下のレベルだったりする。
・その場面,その動作をイメージしながら,挙げてみる。
・チェック項目は,絶えず見直しつづけなくてはならない。
以上を目安に,自分流の発想チェックリストにしてみてください。
はじめから完成を目指すのではなく,まず暫定リストを作成し,その上で,トライアンドエラーで,実際に何度も試し,しっくりするものに仕上げればいいのです。
既存チェックリストからチェック項目を拾う
とはいえ,いきなり自分のチェック項目はつくりだしにくいと思います。まず,既存のチェックリストを参考にすることにしましょう。
ここに既存のチェックリストを挙げておきましそこからチェック項目の候補をピックアップしてみましょう。
たとえば,オズボーンのチェックリストは,基本的には4項目群に整理できます。
①モデル,対照,先例のトレース(借用・応用)をしてみる
②いまあるものの代理・代替・代用・転用をしてみる
③大きさ,形,性質といったものの変形・変質をしてみる
④いまあるもの加減乗除をしてみる
この項目の効果は,いまあるアイデアやモノ(商品)と対比しながら,どうやったらそこからアイデアを展開できるか,というところを徹底してリストアップしているところにあります。他のチェックリストでも,同じようにそのねらいや主旨を整理してみると,使いやすい項目に直すことも可能です。
しかし,大事なことは,チェックリスト項目をそのまま受け取るのではなく,「それはどういう意味か」「それを広げるとどういうことになるのか」「ほかに該当することはないのか」等々とキャッチボールしてみる必要があります。自分流のチェックリストに項目を借りる場合も,まずは,チェックリスト項目と,格闘してみることが必要でしょう。それを使いこなす中から,おのずと自分の傾向に合う項目がみつかるはずです。
まずは,チェックリストから,ご自分の,
気にいった項目
気になる項目
引っかかる項目
を抜き出してみてください。2~3項目でいいと思います。これが,まずは,ご自分のチェックリストの出発点です。あとは,以下を読みながら,あるいはお試しになりながら,自分のものにまとめあげていくことになります。
たとえば,こんなものをオズボーンのチェックリストと5W2Hから引っ張ってくるでしょう。
抜き出したチェック項目 その狙い これに似たものはないか 連想や類比が鍵になる 主客を代えたら 前提にしているものを疑う 何のために 目的をついつい忘れる これがまずはご自分のチェックリストの出発点です。あとはお試しになりながら,自分のものにまとめあげていくことになります。
以下,チェックリストをつくるのに必要な実践アドバイスをつづけていきましょう。
-
自己流チェックリストをつくる
~自分の思考特性に合わせたチェックリストづくり
自分の発想タイプ別に,
①希望・願望・理想の「ワガママ発想」が高い「理想の実現」指向タイプ
②水準(理想)の未達・逸脱の「イライラ発想」が高い「未達の回復」指向タイプ
③欠点・不都合・無駄の「マイナス発想」が高い「問題点の改善」指向タイプ
④自慢・自信・誇りの「プラス発想」が高い「内部価値の実現」指向タイプ
の4分類にわかれたと思います。それぞれのスキル化のポイントを整理してみます。
その基本的パターンを図解したものが,上図です。それぞれの「実現したい」ものに,発想が働きやすいわけですから,それを刺激するチェックリストにしなくてはなりません。
ただ,発想タイプというのは,その人のこだわり,固執する個所です。それは他の言い方をするなら,発想のかたよりです。それを強化するのもひとつの考え方ですが,それに基づく発想をしてきたということを考えれば,それを避けるにはどうしたらいいか,にチェックリストのポイントをおくのも有効に思われます。
①希望・願望・理想の「ワガママ発想」が高い「理想の実現」指向タイプ
自分の理想,願望を実現する指向が強い。「こうあるべきだ」「こうでなくてはならない」といった,自分の重視している価値,なりたいもの,やりたいこと,ほしいものに目が向きがちです。「理想の実現」に必要なのは,具体的手段や,現実がどうなっているかに向ける視点です。それを意識したチェックリスト化が必要です。
このタイプは,前述の5W1Hの,「なぜ」を連発する傾向があります。「なぜできないのだ」「なぜ思うようにならないのだ」等々。それは発想を堂々めぐりにさせる可能性があります。したがって問いを,「何がそれをもたらすのか」という,事実を明確にさせる問いが有効です。たとえば,
・何がそうさせているのか
・何によってこうなったのか
・誰が利益をえるのか
・何がそれによってえられるのか
・誰がそれをすればいいのか等々
②水準(理想)の未達・逸脱の「イライラ発想」が高い「未達の回復」指向タイプ
目標達成指向が強烈です。周りを巻きこむ力も強いはずです。それだけに,発想の原点は,目指す目標とのギャップに目が向きますです。どうしてもギャップの原因に目が向きますが,それを目的化する懸念があります。そこでポイントは,ギャップの側ではなく,基準の確認の側にあります。基準の意味や目的を確認するチェック項目が必要になります。たとえば,
・それは何のためなのか
・それができたらどうなるのか
・目指しているものの意味は明確か
・その影響はどのくらいに及ぶか
・誰がやるべきなのか
③欠点・不都合・無駄の「マイナス発想」が高い「問題点の改善」指向タイプ
「不」の字(不便,不満,不都合,不具合など),「悪」の字(調子が悪い,具合が悪い),「欠」の字(欠けている,欠点),「無」の字(無い,無理,無駄)から発想することですが,どうしても自分の利益,自分の立場に視点にかたよりがちです。どれだけいろいろな立場,視点,視野から,通常では見えにくい欠点を出せるかが鍵になります。たとえば,
・からだの不自由な人にとってどうか
・病気の人にとってどうか
・子供にとってどうか
・外国人にとってどうか
・老人にとってどうか
・女性(男性)にとってどうか
④自慢・自信・誇りの「プラス発想」が高い「内部価値の実現」指向タイプ
自分が価値をおいているもの,大切と思っているものを重視していますから,その意味や価値は,自分にとっては明確のはずです。しかし他人とか変わりない自分人の殻の中からものを見がちです。一度相対的な目で見直して,改めてその価値を再点検する視点が必要です。たとえば,
・それは誰に,どんな意味があるのか
・その価値を誰と誰が分ち合ってくれるのか
・他の領域から眺めてみると同じ価値か
・明日も,10年後も,同じ価値が続くのか
・他の世界から見ても値打ちは同じか
-
自分のスキルに整理する
自分の発想タイプを参考に,自分のチェック項目を見直してみてください。ことばを使いやすいものに代えてみるのがいいでしょう。チェック項目の追加や削減はありませんか。それは箇条書きになりましたか?それで発想を試してみていただきます。
自己流チェックリスト項目
その狙い
チェック項目を使いやすく書き直す
たとえば,筆者なら,次のように,表現を変えてみますし,更に1項目追加してみます。これを洗練させたのが「バラバラ化の4原則」になるのです。
自己流チェックリスト項目
その狙い
チェック項目を使いやすく書き直す
これに似たものはないか 連想や類比が鍵になる 似たものを探せ 主客を代えたら 前提にしているものを疑う 別の立場から考える 何のために 目的をついつい忘れる それで何が実現するのか 対で考える 一面にとらわれる 必ず対比して考える しかし,一度作ったら完成ではありません。何度も何度も試しながら,
①質量ともに大量の発想数を出すのに向いているか
②何か不足している感じはないか
③使い勝手の悪いものはないか
④それで,本当に発想を展開するキーになっているかどうか
等々を切り口に点検し,差し替えていっていただきたいものです。これが,ご自分の発想の旗印です。少なくとも,いつでも使える項目があることで,パニックになる時間を短縮できるだけの自信にはなるはずです。
-
自分流のスキルをもう一歩詰める
-
発想技法のブラックボックス部分
“バラバラ化”のスキルとして,
①視点を変える
②カタチを変える
③意味を変える
④条件を変える
の4つを挙げ,その「変える」の意味は,それを意識してみるということだ,と考えています。たとえば,「視点を意識してみる」とは,「~と見た」とき,「いま自分は,どういう視点・立場からみたのか」と振り返ってみる。そのとき,会社の立場で見たのだとすれば,それ以外の,父親として見たらどうなるか,客の立場で見たらどうなるか等々,無意識にとっている視点を意識し,「では,別の視点ならどうなるか」と,改めて別の視点を取ってみることで出発点とすることができる,ということでした。
しかし,ここには,ほんの少し嘘が入っています。嘘というより,正確には,一種の後知恵が入っているのです。
正確な記憶ではありませんが,ある生物学者が,こんなことを言っていたことがあります。彼は,ある高山に生息する蜂の研究をしていました。生態が余り知られていないため,研究室で生育してみることを考えたが,一度目は,冬を越せずに全滅した,次の年,気温が問題だったのではないかと気づき,その高山の温度に近い気温に一定に保ってみたが,やはり全滅してしまいました。翌年も,より厳密な温度管理をしてみましたが,やはり全滅しました。失敗を繰返したあるとき,その学者は,「もしや,と気づいた」そうです。高山の温度に一定にするといっても,捕まえたときの夏の温度を保ったが,「もしかすると,夏は夏の,冬は厳冬の温度が必要なのではないか」というわけです。そこで,一年間の温度変化を調べ,そのサイクルに合わせた気温変化を実現してみたところ,翌年孵化に成功した,というのです。
そこで,問題は,「ハッと気づいた」というところです。まさか,学術論文に,「はっと気づいた」とは書けず,もっともらしい仮説を記述したそうですが,実態はこんなものだった,といった趣旨の話でした。
ここで申し上げたいことは,この「はっと気づいた」瞬間のことではありません。その前段階で,頭はフル回転しているはずです。まず,一定の温度に保ってはどうかと着想しています。いわば,一定温度維持仮説を立てたことになります。
が,それが失敗して,自分たちの行動側の瑕疵ではないかと疑い,温度管理不徹底仮説を試し,それでもだめだったわけです。
そこには暗黙のうちに,その蜂を捕獲したときの気温でなくてはならないという先入観があったことになります。で,想像するに,無意識で,山の気温そのものに目を向けたのではありますまいか。そうすると,山であれ,地上であれ,気温が一定ということはありえません。すごしやすい気温を保つのは人間だけなのです。
生物学者のこの“はっと気づく”体験が,温度を山の一年の変化に合わせればいい,つまり気温の高い夏と寒い冬の両方が必要なのではないかという,通年気温変化仮説とでもいうべきものにたどりつくことになるのです。
-
肝心なプロセスはブラックボックスになっている
-
ここから我田引水するつもりはありません。ただ,大事なことは,この学者の論文の結論からは,その発想の悪戦苦闘のプロセスは見えないということなのです。この結論には,そういう発想にたどりつくプロセスは隠されているのです。
それは,バラバラ化の視点についてもいえるということです。これは,筆者の発想プロセスの方法を知識化したもの(語れるスキル化)には違いありませんが,その結論からだけでは,プロセスがブラックボックス化されているのです。
本当に必要なのは,そのブラックボックスになっている部分そのものなのではないか,ということなのです。
たとえば,発想技法には膨大な種類がありますし,チェックリストも多くのものがあります。どの技法も,その発案者の発想プロセスの方法化,あるいは知識化なのです。
結論部分からは,どうやってそういうものが生まれたのか,どういう必然性で,そういうものにまとまったのかは,決して見えませんし,あるいは作った本人にも分からない部分があるかもしれません。バラバラ化の4つの切り口にしても,いわば,結論に過ぎないのです。それが,後知恵と申し上げた理由なのです。
しかし,自分の発想力を高めようとするとき,最も参考になるのは,そのブラックボックスになっているプロセスそのものなのです。
- 発想のキーワードを見つける
どの発想技法も,その発案プロセスは語られることはありません。エジソンは,99%の汗と1%のインスピレーションと言いましたが,その汗とは,プロセスに流すもののことです。
自分の発想プロセスを目に見えるグラスボックス化するのは,各自それぞれ試みるしかありませんが,筆者は,そのプロセスの鍵を,“対”あるいは“対にして考えること”にあると考えています。
これを合理的に説明しようとすると,うまくいきませんが,バラバラ化の「~を変える」という切り口で,何をしようとしていたのかということを具体的にみてみると,たとえば,
「位置を変える」というのは,どこからどこかへであり,
「まとめる」というのは,何かをなにかにであり,
「カタチを変える」というのは,何かから何かへであり,
「理由を変える」というのは,何かから何かへであり,
等々,すべて前と後,原因と結果というように,何かと何かの対比なのであり,それを一言で表現してみると,何かと何かの“対” あるいは“対にして考える”という言い方がぴったりくるということなのです。
ここで言う“対”は,対概念チェックリストがそのイメージを具体化するのに最適でしょう。たとえば,
多-少/長-短/中空-充満/浅い-深い/拡大-縮小/広-狭/厚-薄/濃-薄/強い-弱い/動-静/加-減/開-閉/重-軽/明-暗/量-質/速-遅/天-地/高-低/左-右/前-後/遠-近/親-疎/頭-尾/最先端-最後尾/最良-最悪
等々。それをたえずチェックするキーワードとするという意味です。たとえば,「前から見てこう見えた,とすると,その反対,後から見たらどうなるか」「オレの視点ではなく,オマエの視点ならどうなるか」等々。
それを,あえて図解してみるなら,下図のようになります。必ずしも,位置関係や物理的なものだけをイメージしているわけではありません。ただ,図にしようとすると,その部分しか描けないだけなのです。
遅れているもの←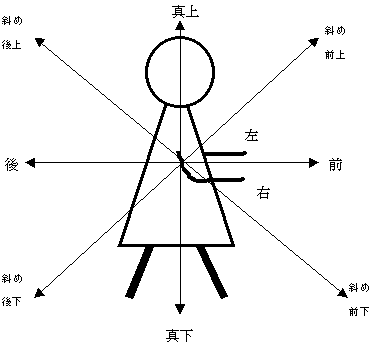 →先行するもの
→先行するもの
前から見る後から見る,右横から見る左横から見る,大人の視点子供の視点,親の視点子供の視点,役所の立場住人の立場,窓口の効率申込者の便利,売上高と利益,止める便利走る効果,外す便利止める効率,開く便利閉める便利等々,対として常識に考えられるものは,当然いくつか浮かびますが,ここで重要なのは,対は「あるものとして」ではなく,対に「してみる」ことです。
だから,既知の対だけをイメージするのではありません。あえて対においてみる,対において対比してみることで,発想してみるということです。
「緑と青」でもいいし,単純に「イエスとノー」ではなく,「ちょっと賛成と大いに賛成」でもいいし,「プリンターとコピー」でもいいし,「スキャナーとカメラ」でもいいのです。
そう置いてみることで,見えてくるものを期待する。だからあえて対として対比してみることが重要なのです
対は,いわば,「ああでもないこうでもない」と考えあぐねる,発想の悪戦苦闘プロセスそのものの筋道を言っているだけなのです。
数学者の岡潔氏は,「タテヨコナナメ十文字に考える」と言い,エジソンが「99%の汗」と言ったのも,このプロセスを差しているのです。
この“対”に似たキーワードになる,発想のコツを,一人一人が見つけることが,その人にとっての,発想スキルづくりの最後の詰めの作業なのだといっていいのです。
発想プロセスのキーワード化
ご自分の発想スキルを,ひとつのキーワードで表現してみてください。そのステップとして,
①箇条書にしたチェック項目を再確認し,
②そこで何をしようとしているのかを具体的に考えて
③そこでの動き,変化を一言で的確に表現できるキーワードを考えてください。
以上のキーワードを,
④それで,本当に発想を展開するキーになっているかどうか
を確かめて,ご自分の発想の旗印として下さい。少なくとも,パニックになる時間を短縮できるだけの自信にはなるはずです。
たとえば,前述した4タイプのチェックリスト例から,一例として,各タイプのキーワード化を試みてみますと,
①の「理想の実現」指向タイプは,「5W2H」
②の「未達の回復」指向タイプは,「目的確認」
③の「問題点の改善」指向タイプは,「もうひとつの視点」
④の「内部価値の実現」指向タイプは,「相対化」
となります。
発想のキーワード化作業の意味
キーワードづくりの作業とは,ちょうどキーワードを創り出す作業と似た作業を逆にたどって,またまとめていく作業になります。
一見無駄なようで,対のキーワードのバックデータとして,バラバラ化の切り口があるように,キーワードの背後に,具体的な切り口があることで,キーワードを本当の意味で,そこから発想を引き出す鍵とすることができるのです。
自己流チェックリストを使いこなす
チェックリストを発想のツールとして使うというのは,既存のチェックリストもそうですが,ただその項目と照らし合わせれば,自動的にアイデアが大量に出るということではありません。
どういうことかといいますと,チェックリストの場合,たとえば「視点を変える」というチェック項目があったとして,それをただ読み流しても,決して発想につながることはありません。必要なのは,そのチェック項目を,自分の発想への刺激として,それと意識的にキャッチボールすることなのです。
たとえば,バラバラ化の4つの切り口,
①視点を変える
②見かけを変える
③意味を変える
④条件を変える
をチェックリストとして活用する場合を例にとって,具体的に考えてみます。
たとえば,身近にあるパソコンをみながら,どれだけのアイデアが出せるかを試みるとします。
「視点を変える」という項目とキャッチボールするとは,「視点」とは何のことか,
立場なのか,位置なのか,こちら側の価値観なのか,機能なのか,感情なのか,着眼するところなのか,先入観なのか,慣れたものの見方なのか,
立場だとしたら,どういう立場なのか,公人としての立場,私人としての立場,会社員としての立場,父親(母親)としての立場,子供としての立場,
位置だとすると,どういう位置なのか,上から,下から,横から,上からだとしたら,どのくらいの上なのか,下だとしたら,どのくらいの下なのか,
価値だとすると,無価値なのか,価値が高いのか,価値が薄いのか,価値が減っていくのか,価値が高まっていくのか,
意味だとすると,意味が同じなのか,意味が変わるのか,意味が読みにくいのか,意味が誰にもわかりやすいのか,
機能だとすると,どういう機能なのか,機能を減らすのか,機能を付加するのか,
感情だとすると,いい感情なのか,悪い感情なのか,怒りなのか,悲しみなのか,喜びなのか,楽しみなのか,うれしさなのか,
等々を,考えること自体で,アイデアにつながるはずなのです。チェックリストは,それ自体がアイデアの元ではなく,自分自身の記憶と知識とのキャッチボールによって,アイデアを誘発する起爆剤,導火線にすぎません。
とすると,公人仕様セキュリティパソコン,会社員のIDカードなしには使えないパソコン,親が子供のパソコンをモニタリングできるパソコン,ゲーム機仕様の使えるキッズパソコン,どこに行っても衛星で探知できるIDパソコン,使い捨て可能な紙かダンボール製の激安パソコン,年々ネットでバージョンアップ可能なパソコン,カバーやボックス部分を着せ替え可能なパソコン,液晶(モニター)部分が取り替え可能なパソコン,不明な部分にポインターを置くだけで解説が(音声でも)出るパソコン,ポインタが一定時間動かないと自動上書きするパソコン,液晶部分のみが剥がれて独立した形態端末になるパソコン,キーボードもマウスもないパソコン(入力手段が音声のみ),携帯電話と同じ大きさのパソコン,仕様機能単一パソコン,必要機能がICチップで自由に追加・削除できるパソコン,使い手の感情に対応してキーボードの圧力が変わるパソコン,感情レベルを感知するセンサーのついたマウスが,パソコンの壁紙を自動的に差し替えるパソコン,等々とキャッチボールのつどアイデアのかけら位は手に入る。
もちろん,キャッチボールすれば,すべての項目で何かが必ず出てくるというわけではありません。が,少なくとも,固まっていた脳のネットワークに新しい回路がよみがえったり,忘れていた回路が行き返ったりする手がかりにはなるはずです。
そうした手がかりになるかどうかは,キャッチボールに耐えられる項目になっているかどうかとも関係があります。この点も自作チェックリスト評価のポイントになるはずです。
-
発想力を高めるためのベースを強化する
- 発想マインドをチェックしてみます
- 発想が必要になるとき
発想が必要になる場面を想像してみてください。それは、
いままでのやり方ではどうもうまくいかない
自分ひとりでは、できそうにもない
このままではうまくない
等々といった、いままでのやり方や考え方では行き詰まっている状態のはずです。そのとき、どういう反応をするかで、その人のタイプが分かれるでしょう。大きくは、
何が何でも、頑張ってみようと走りまわる肉体派
もうだめなのではないかと諦める悲観派
何とかしてみようと、知恵と工夫を試みる前向き派
といったところでしょう。しかし、いままでのやり方ではだめとわかっているのに、むやみに走りまわったところで、無意味です。また諦めるのならいつでもできます。ここで必要なのは、「何とかしてみよう」と考え始めるかどうかです。そうでなければ発想はスタートしないのですから。
このマインドを整理すれば、
だめかもしれない→だから他のやり方を考えてみるのじゃないか
無理かもしれない→いまのままでは無理だが、何か手はあるはずだ
難しい→考えもしないで難しいと言ったところで始まらない
やるだけ無駄→無駄にならない可能性があるのではないか
人がない金がない時間がない→人も金も時間もたっぷりあるところなどどこにもない
という前向きの姿勢です。そこには、
・何とかならないか
・どうすれば可能になるか
と考える姿勢です。そして、考えるだけではなく、結果として何とかしてしまうことです。
たとえば、「明日までしか猶予がない」という切羽詰った状態のとき、「残された時間の中でできること」が見えてしまうために、無理、難しいと考えます。しかし、発想力のある人は、「残された時間でできるには何人必要なのか」「その期限は絶対なのか」「その時間内に、絶対に全部できなくてはならないのか。まずできる範囲をやり、次にどれだけ、その次にどれだけと、作業を分割すれば可能なのではないか」と、次々どうすれば可能になるかというアイデアを思いついていくはずです。
だから、発想とは、何ともならない壁の前でも、「何とかすること」、あるいは何とかして見せる力です。そこに「発想は数」が生きているのです。
ご自分は、発想の必要なときどんな対応をするのでしょうか。それをチェックしてみていただくのが、「発想への引っ込み思案度チェック」です。
- 発想への引っ込み思案度チェック
●下記の設問で、該当する場合は、レ印でチェックを入れてください。
設問項目
該当する
嫌いな人の新しいアイデアや新規企画には、つい色眼鏡で評価してしまう 現状を批判したり、問題をあげつらうより、自分の責任と役割を全うすべきだと思う 未知の分野や不得意分野のことになると、とたんに頭が真っ白になってまう 知らないことややったことのないことにぶつかったとき、つい尻込みしてしまう 人のアイデアのアラや欠点が良く目につき、つい批判的な物言いをしてしまう 疑問や問題を感じても、忙しさに取り紛れて、見過ごしにしてしまうことが多い 自分にすべきことは明確であり、何が何でもそれを完遂するしかないと思っている いつも、人はどうしているのだろうか、どういうやり方をするのか、と気になる 新しいことをするときには、自分のやり方で良いのかと心配になってくる 間違いや失敗を恐れて、新しい取り組みややり方より手馴れた方法を選ぶ ずっと同じ職場で同じ仕事に携わり、自分の得意分野が限定されている 会社関係、職場関係以外の人間関係が少なく、地域とのつきあいも少ない 取引先や業務関連以外に、異分野の人や地域の人と一緒に何かに取り組んだ経験はない 人が変わった行動や目立つ発言をすると、批判的に見てしまう 新しい知識や技術について関心はあるが、勉強する機会がない この何年も展覧会、コンサート、劇場に出かけたことがない 特に瑕疵や支障もないのに、いままでの仕事のやり方を変える必要はないと思う 上司に提言や提案する苦労をするくらいなら、体に汗して駆けずり回るほうがいい いつも社内や上司、周囲の評価や評判を気にかけている 自分なりの考え方や仕事の仕方を、周りや上司に働きかけるのは面倒だと思う マンガや週刊誌、雑誌以外にあまり本を読む機会はない 新たなチャレンジよりも、現在の仕事でやるべきことでできていないことが気になる 目の前の山積みされた仕事に忙殺される日々で、その仕事に疑問を感じるゆとりがない いままでのやり方については、人に負けないスピードと処理能力があると自負する 新しい考えややり方に拒絶反応を示すことがある 自分と合わないと感じると、その人を避けたり話をしない傾向が強い 困難や難しいことに取り組むのはできれば避けたいと思う 自分は人知れずコツコツと地道に努力する縁の下の力持ちが似合っている いまのやり方を改善しなくてはならなくなると負担が増える気がする 権威やお墨付きに弱い
評価方法
チェックの数
傾向
~1
すばらしいチャレンジング精神です 2~5
十分チャレンジングな性向です。更に一歩を踏み出してください 6~10
ちょっと新しいことに臆病ですが、結局チャレンジする方でしょう 11~15
少し新しいことに引っ込み思案です。自分を信じて踏み出すチャンスです 16~20
かなりの殻の強さです。殻は現状への防御でしかありません。 21~24
いまに必死です。でもその裏に新しさへの自己防衛が強く働いています 25~
新しさを歯牙にもかけない現状踏ん張り派です。明日は大丈夫ですか?
評価結果をどう見るか
評価結果はどうだったでしょうか。
結果はあくまで大雑把な傾向です。発想に必要なとき、「何とかなる」と楽観になる傾向がどれだけ少ないかを「引っ込み思案」度としてみたものです。
この傾向から見えますのは、仕事熱心で、明日のことよりいまの目標達成に必死になっている姿が強く浮かび上がってくると思います。
しかし、いまの仕事の意味はどうなのか、いつまでこのままで続くのか、このままで良いのか、新しい事態がきたらどうなるのか、ということを全く考えず、ただひたすら与えられた仕事とタスクをこなそうとするのは、どこか現状に首までどっぷり使ったイメージになります。あまりいいイメージとはいえません。
「何とかなる」と考えればいいというものでもありませんが、危機に瀕したとき、「どうすればいいのか」と考えるか、ダメだと頭を真っ白にさせてお手上げになるのと、どちららが、ご自分の可能性を広げてくれるか、です。
アイデアにあふれた人は深刻にならないとは、バレリーという詩人の言ですが、それは「何とかなる」「何とかする」という自信のせいでしょう。
『夜と霧』で、フランクルは、アウシュビッツという絶望的状況の中でも、「どうやったら生き延びるか」の創意と工夫をしている人を紹介していますが、「もうだめ」と思えば自暴自棄に死ぬだけですが、「どうしたら生き残る可能性があるか」と必死で工夫をし、生き残っていくところには、究極の発想力をみることができます。
こんな話があります。絞首台へ運ばれる馬車に乗っていたある貴族が、到着したところで、読みさしの頁に折り目をつけました。それを見て笑った獄吏に、自分の首が下がるまで何があるか分からないではないか、と言ったといわれます。その精神です。
発想への引っ込み思案に見られる、攻撃も怒りも反感も批判も、実は、自分の心のおそれがもたらす自己防衛です。おそれには、失敗へのおそれ、自分の安定が壊れることへのおそれ、まだ何も踏み出していないのですが、何となく未知へのおそれ、自分の能力へのおそれ、何か試みることでかえって苦難になるのではないかというおそれ等々があります。
それは、数が出せれば、消せるおそれです。本章の終わりまでお付き合いいただいて、「何とかなる」との、発想への自信を取り戻していただきたいと思います。
引っ込み思案度の低かった方は、ご自分の天性や何となくやっていた発想力を意識的な方法にして、スキルとして身につける工夫をしてみていただきたいと思います。そのためのチェックポイントをたくさん用意しています。さあ、はじめてみましょう。
- まず、いくつ思いつくかを試してみます
- 何に見えるか
まず、何に見えるでしょうか?ご自分で、時間を15分と限って、いくつ出せるかを試みてください。
(行宗蒼一氏による)
いかがでしたか?いくつ出せましたか?この結果でけで何かがわかるわけではありませんが、こんな風に自己診断してみてください。
発想数 評価
2個以下 あなたが培ってきた知識と経験が大いに邪魔しています 3~5個 知識と経験に引っ張られ過ぎ、新しいことを考えるのが難しくなっています 6~10個 ちょっとあぶないところ、まだ頭の中は柔軟さが残っています 11~14個 平均以上です。なかなかの柔軟さです 15~19個 まずは立派です。発想に少し自信をもってよさそうです 20以上 恐れ入りました。かなりの頭の柔らかさです 50以上 あっぱれです。抜群の発想力です ここでは、数だけです。良いかどうかの評価は、アイデアを決定する段階です。アイデアを出している段階で、良い悪いを診断することは、自分のいまのあるいは過去の価値に基づくものです。ひょっとしたら、いま悪いと捨てたものこそが、これからよくなるかもしれません。今は、良いアイデアを出す最善策は、できる限り、半端でないくらい膨大な数のアイデアを出すことです。その膨大な数こそが、常識の枠を破る鍵です。
- 何が妨げたか
ご自分の結果はいかがでしたか。何が数を出す妨げになったでしょうか?「何に見えるか」を考えてみたプロセスを思い起こしながら、どんなところでとまってしまったのかを振り返ってみてください。
どんな状態だったでしょうか?1、2個思いついたところで頭が真っ白になったひとつ思いついた形から離れられなくなった似た形がいくつか出たが、後が続かなくなったひとつカタチは思いついたが、名前が浮かばなくて立ち止まってしまった等々いろんな状態があったと思います。では、なぜ、その状態から出られなくなってしまったのでしょうか。どうすれば、その状態を抜け出せたと思いますか?頭が固い、固定観念がある等々と考えた人がいらっしゃると思いますが、それで説明になっているでしょうか。
たとえば、頭が固いとすると、それはどういう状態なのでしょうか。固定観念があるというのは、どういう状態なのでしょうか?固いというのは、ひとつ出したところで固まってしまったからだとしましょう。なぜひとつで固まったのでしょうか?なぜそこから出られなくなったのでしょうか?
たとえば、マイナスネジと思いついたところでとまったとします。なぜとまったのか。そのとき何も考えられない思考停止状態になったはずはありません。何かを考えていたはずなのです。何を考えていたのでしょう。ひょっとして、「マイナスネジ、マイナスネジ」同じ言葉がぐるぐるしていたとしましょう。それはなぜなのでしょうか。
マイナスネジのカタチに似たものを思い出そうとしたが、まったく思いつかなかった、同じ図柄のものがそれしか思いつかなかった、その図が頭の中で固まってしまった等々
それがどうしてなのかは、おいおい解き明かしていくにしましても、ご自分なりに、行き詰まった状態がどの当りかを、きちんと掘り下げておくことが絶対必要です。発想というのは個人的な作業です。詰まったところは、多分、その人の発想の癖です。つまずきやすい傾向です。癖がわかった方が、それを打破しやすいはずです。
- なぜ数が出なかったのか
先ほどの例でいいますと、「マイナスネジのカタチに似たものを思い出そうとしたがまったく思いつかなかった」というのは、どういうことなのでしょうか?
ひとつ考えられるのは、マイナスネジというカタチそのものが、次のものを思いつく前提になってしまっているということです。つまり、マイナスネジに似たものはないかと考えたとき、マイナスネジの大きいのとか小さいのとか、マイナスネジのバリエーションしか思いつかないのは当たり前です。どれもこれも同じマイナスネジでしかないのですから。
もうひとつの原因は、円と直径の平面図そのもののカタチを思い浮かべて、それに似たものを思い浮かべようとしたからということかもしれません。そのとき、たとえば、上から見てそう見えたのだから、横から見て同じように見えるものはと考えれば別の展開になったかもしれません。あるいは、それを面ではなく、球や筒として見たら、というように展開することもできたかもしれません。
どうしてそうできなかったのでしょうか?それは、一つ見えた形や思いついた視点から離れられなくなったからです。
どうしてそうなってしまったのでしょうか?それは、どうやってそれを思いついたかを考えようとしなかったからです。
スキルや方法は、いわばやり方についての知識です。自分がやったやり方を人に語れることです。子供の頃、ゲームでもプラモデルの出来不出来よりは、攻略本やマニュアルにない独特のノウハウを語っていた仲間がいたはずです。彼は、自分が成功した体験を自分なりの方法として完成させていたのです。ご自分で、どうやったかを振り返り、チェックし、人に語れるようにすることが、自分のスキルにするための大事な作業です。これを、自分の知識のメタ化と言います。
「マイナスネジ」にしか見えない状態は、どうやってマイナスネジを思いついたかが語れない状態です。それは無意識で思いついたことを、ぼんやり挙げただけなのです。
数を出すほどいいと言われている以上、「マイナスネジ」にこだわっていても仕方がないのです。
それを切り替えるには、大体次のようなタイプがあると考えていいでしょう。
①マイナスネジ似たカタチのものを、必死で思いつこうとする。
②マイナスネジから離れて、同じ形を幅広く考えて見ようとする。
③平面としての円と直径から、立体や球に探索を広げようとする。
④なぜマイナスネジに見えたのかを考え、それを他に広げて考えようとする
①と②は、大差ありません。③と④は、いずれから入っても、似たようにかなり展開できるはずです。
③の場合なら、円として見ないで、円筒、球、円錐と見たらどうなるかに切り替えることですし、④なら、円として見たのは、上から見てそう見えたのだ、ヨコから見たらどうなるか、下から見たらどうなるか、と切り替えていくことになるでしょう。③は、④の切替を無意識的に済ませてしまったと、言えるかもしれません。
大事なのは、①や②のように、もう行き詰まっていると分かっているのに、そこで無意味に頑張ったり、やみくもうんうんうなるのか、③や④のように、意識して別の見方はないかと、切り替えていけるかどうかの違いです。
もうお気づきの通り、「発想への引っ込み思案チェック」で確かめた発想のタイプがここに出ているのです。
たとえば、錠剤、マイナスねじの頭、駐車禁止の標識等々が浮かんでとまったとします。しかし、そのカタチにこだわっている限り、似たものを思いつくのを待っているだけなのです。数の多少は、そんなに違いはないはずです。似た形のものが並んでいるはずです。
しかし、早めに気づいた人は、いろいろ工夫を始めたはずです。たとえば、平面ではなく立体、球、あるいは凸状態なのか、凹状態なのか等々。いったん、
自分の見たものの形
自分の見ている視点
は何で、どうしてそう思いついたかをチェックすれば、それとは違う形を思いつくのは難しいことではないはずです。多分10個±αまではいくはずです。
しかしそれ以上出そうとすると、もっと別のタブー破りが必要になります。たとえば、
桃
と思いついたとします。普通は、それとは別の似たものへと移るはずですが、続けて、
スイカ
瓜
みかん
オレンジ
メロン
等々とつなげていく人がいたはずです。大体の人は、
「それはまずいだろう」
「それはずるい」
と待ったをかけるところです。そのまますすめるとしても、どこか照れ笑いを浮かべながら、後ろ暗い思いをしながらのはずです。
でも、なぜまずいのでしょう。そこにあるのは、経験から自分で作ったタブーです。それを破るには、これで良いのだという確信犯的な、自覚が必要です。でないと、そうは続けられないからです。
なぜ、そうしたタブーをつくるのでしょうか?この問題を先に解いておきたいと思います。
発想を妨げるもの
固定観念の正体
多くの人が、固定観念や先入観という言葉を発想力の言訳として使うようです。固定観念は、頭の固さとイコールではありませんし、発想を妨げる障害物でもありません。
固定観念とは、その人の培ってきた知識と経験そのものをさします。問題なのは、その使い方が固定してしまっているところです。だから、新しいことに立ち向かうとき、それが邪魔になって、別の見方がしにくくなるだけのことです。
一般の固定観念の使われ方は、その状態になっている知識と経験なのです。だから固定観念があるかどうかが問題なのではないのです。そこに開き直らず、どうそれを価値あるものにできるかどうかです。蓄積され、整理された知識と経験をどう使いこなすかです。
発想とは、その人の知識と経験の函数です。知識と経験を使ってしか生み出しようはないのです。問題なのは、発想を知識と同じように、勉強して蓄えようとする考え方です。
人の脳のニューロンは、100億以上あるといわれていますが、まず胎児のとき、妊娠20週で大量に死滅していく、といわれます。更に20歳を過ぎると、1日何十万個と死んでいくとされています。その原因は、他のニューロンとの間にシナプス(ニューロンとニューロンの接続部分)を形成できなかったためと考えられています。人間の脳のこうした回路網(ニューロンによるネットワーク)は、10の14乗にも及ぶシナプスがあるとされています。入力信号の伝達に使われたシナプスは強化され、使われないシナプスは弱体化し消えていくのです。この回路網は、人間の知識と経験によって形成されるのです。固定観念とは、絶えず使い、いつも使っている入力信号(使い慣れた知識、いつもの仕事の仕方等々)によって強化された回路網に他なりません。
種村・高柳『だまし絵』(河出文庫)
種村・高柳『だまし絵』(河出文庫)
たとえば、図左は、老婆に見えたり、若い女性に見えたりしますが、この際、どっちに見えようと大した問題ではありません。しかし、この絵を、『老婆』にしか見えないように描き換えた絵を先に見せられた後、この図を見ると、100%の人が老婆しか見えなくなるとの実験結果が出ています。
逆に、『若い女性』にしか見えないように描き換えた絵を先に見せられると、その後図表1-3を見ると、100%の人が、若い女性しか見えなくなるのです。
つまり、先に書き換えた絵を見た経験によって、脳のネットワークが強化され、その回路を通してものを見てしまっているのです。
図右も、同じです。二列目の絵を、左から右へ見ていただく。ずっと男の顔です。三列目の絵を、左から右へ見ていただく。女の絵です。一番右の絵は同じであり、一列目の絵がそれです。
最初に、経験され強化された回路で見るとき、自分のものの見方を決定してしまう、という、経験のアナロジーをここで確認していただければいいのです。
だから、人間は固定観念の固まりだと嘆くのはナンセンスです。それが、自分の持っている知識と経験だ、ということに過ぎないのです。それは、発想にとって邪魔でも踏み台でもありません。ただの前提に過ぎないのです。
- 発想を妨げるものを確かめる
・知っていることが妨げになる
繰り返すまでもなく、何が発想妨げるのか、と言えば、「知っていること」が、なのです。いまある(知っている)枠組みが「これ以上は無理」「こんなものだ」「誰も成功していない」と妨げるのです。
たとえば、IBMのワトソン会長は、1943年、コンピュータの世界の需要は5台位だろう」と言いきっています。1958年、ビジネスウイーク誌は、「日本の自動車メーカーが自力で(アメリカ)市場を切り開くことはないだろう」と予言しました。数々のSFで未来を予言したH.G.ウエルズでさえ、「私の創造によれば、潜水艦は乗組員を窒息させ、沈没するだけである」(1929年)と言っているのです。
SF作家のアーサー・C・クラークも、こんなことを言っています。「権威ある科学者が何かが可能と言うとき、それはほとんど正しい。しかし、何かが不可能と言うとき、それは多分間違っている」と。
過去の経験・知識によって、分かっている(知っている)という「思い込み」が、当たり前のこと、疑いもないこと、見慣れたこと「として見」(え)てしまうのです。分かっている(知っている)こと「として(しか)見」(え)なくするのです。
これがものを見る「眼鏡」(先入観や固定観念)になり、「問題」を見えにくくするのです。その人が仕事を通して身につけた、ノウハウや知識そのもの、それによって仕事をこなし、仕事がよくできると評価もされた経験やキャリアそのものが、その人のものの見方を決定づけているのです。
知識とは、学習を通して手に入れた、モノの見方の正解(枠組み)であり、知識を学ぶとは、ものの見方を学ぶことです。人間の心は、モノを見るときの癖で折り目がつき、皺になるものである、といわれるのも無理はないのです。アインシュタインいわく、「常識は、16歳までにわれわれの心に刷り込まれたモノの見方の集合体」なのです。
・「固定観念になる」3つのタイプ
固定観念について、数々の心理実験がありますが、古典的なものとして、ブルーナーとポストマンの次のような実験が有名です。即ち、観察者に数秒間トランプのエース・カードの配列(1列4枚の3列)を見せ、その中に何枚のスペードのエースがあったかをたずねるものです。
ほとんどの観察者は3枚と答えますが、実際には5枚あるのです。ただしそのうちの2枚は“赤い”スペードのエースになっているのです。だれもがスペードは黒と思い込んでいるので、赤いカードはハートかダイヤとの見込み判別してしまうのです。
あるいは、心理学のテキストによく出てくる例では、天井から2本の紐がぶら下がっており、1本をもつともう1本の紐が届かないような位置になっています。周囲におかれている椅子とハンマーを使って、もう1本のロープに手を届かせられるかを考えさせようとします。10分以内に解ける人は39%しかいないといいます。ハンマーは釘を打つものと見なしているために、その機能に関係なく、単なる重みを利用した錘りにして、振子にするという発想が出てきにくいのです。
われわれは知っているということによって、それを知っているものを見てしまう(知識・経験のアテハメ)だけではなく、知っているものとして見てしまう(つじつま合わせ)、知っているものと見てしまう(錯覚)、知っているものに見えてしまう(幻覚)等々、知識・経験がそれ以外に見ることを妨げているのです。これを、
①焦点化
②固定化
③一般化
の3つに整理できます。
焦点化とは、ひとつのことしか見ないということです。自分の見方や考え方にこだわる、ある観念・信念や好き嫌いの感情のある1点、焦点から目が離せなくなる、ということです。
固定化とは、1つのことしか見えないということです。経験的に身につけた機能・価値、区別、分類でしか見られない、ということです。前述の心理学の実験は大半これに属します。たとえば、ハンマーは釘の頭を叩くもの、椅子は座るものとしてしか見えないために、その機能を無視して単なる錘にするということに気づきにくいのです。
一般化とは、1つ見えたことをすべてと見なす、“たまたま”を“そもそも”と思うということです。子供は、意識してか無意識にか、この手を使います。母親に、何かをねだるとき、「何々ちゃんも持っている」と言ってもインパクトが薄いので、「クラスの子はみんなもっている」と。
ある意味で、いずれも自分の正解(多くそれはその時代や世の中のもつ正解)への固執です。われわれは、知っているものを見る、といったのはゲーテですが、「知っていることが見える」からこそ、「知っていることしか見ない」ことが起こるのです。
しかし、それは破れるのです。それを次に考えてみたいと思います。
どうしたら発想量が増やせるのか~具体化の4原則(1)
- 具体的に考える(あるいは具体例を挙げる)
(行宗蒼一氏による)
この図情報だと考えてみてください。とすると、その分析で意味のないのは、「円に直径」という情報です。情報でほしいのは具体性です。そして、具体性こそ、数を出すコツなのです。
では具体性とはどういうことでしょうか?ちょっと考えてみてください。
どんなことを考えたでしょうか?
それが具体的かどうかを見極める鍵は、
①それが、他にないたったひとつのものかどうか
②それが、心の中に、気持ちや感情を動かすイメージが思い浮かぶかどうか
③それによって、特定の何かを、そこから連想させる力があるかどうか
です。たとえば、図表1-6を、
ボール
と言った場合、一般的には、抽象度が高く、具体性とは言いきれません。しかし、ある人にとっては、少年の時の具体的なエピソードや思い出を引き出すキーワードになっている場合があります。そのとき、それは、その人にとって具体的であり、たったひとつのものです。では、
ベースボールの球
と言うとどうでしょうか。それなら、
ピンポン球
サッカーボール
バレーボールの球等々と、似ているものが、次々と連想できます。これは、ひとつの具体性です。でも、他にはないものではありませんし、人によってイメージが浮かぶところまではいきません。他にないものという以上は、
長嶋の400号ホームランの記念ボール
自分が少年チームで初勝利をあげたときのウイニングボール
横浜球場の外野席で、シートの下に転がっていたボール
といった感じでなくてはなりません。これなら、具体性は、特定のここにしかないものということになります。
ここに、アイデアを考えるときのヒントがあります。まず、「具体的であるほどいい」ということです。それは、たとえば、単に、
野球ボール
というよりは、
糸の切れかけた使い古しの野球ボール
と言ったように、それ以上の具体例が出しにくいもののほうが、なおいいということです。それにならえば、ボール種類だけ、次々具体例が出せるはずです。
糸の切れかけた使い古しのサッカーボール
糸の切れかけた使い古しのソフトボール等々。とすると、それとの関連で、具体的に出されたものほど、アイデアを誘発しやすいということが言えるはずです。たとえば、
割れかけたピンポン球
罅の入ったくす球と言えば、具体性の鍵を一応かなえているはずですが、他にないものをそこから考えていくと、
卓球選手権の決勝戦で試合を決めた割れかけたピンポン球
といったふうになりましょう。あるいは、
川上に見えた、止まった野球ボールの縫い目
イチローに見えた、始動しかけた打撃姿勢を変えさせた野茂の落ちかけたフォークボー ルの縫い目と言ったものになるでしょう。具体的、個別的なモノであるほど、それを受け止めて受けるイメージや印象がいろいろに広がりやすいのです。それも、ときの具体性、場所の具体性まで加味して、どこそこで、いま何かが起こった直後、いまにも何かが起ころうとしている直前といった一瞬をつなぎとめられれば、なおさら数は増えるはずです。
図を見ながら、思いつく限り、具体性を意識して、列挙してみてください。
どうでしたか?その感覚を覚えておいてください。
どうしたら発想量が増やせるのか~具体化の4原則(2)
強制、あるいは見たいようにみる
下図を見たとき、大体は、似て見えるものを探したはずです。「見たいように見る」とはどういうことでしょうか?ちょっと考えてみてください。
(行宗蒼一氏による)
いかがでしたか?
見たいように見るとは、「それはあんな角度ではないからだめだ」と、図の直径の角度の違いで捨ててしまうアイデアを、すくいあげる方法です。
たとえば、時計の時刻の3時50分を思いついたとします。「いや、角度からみると、4時50分か」と思い直したりしたことはなかったでしょうか?それをタブーというのです。
こういうカタチに見えるものはないか、という似たものを必死で思いつこうとするアプローチだけでは、受動的です。思いつくのを待っている形です。
ここで「見たいように見る」とは、図を見たいものにあわせるように動かすこと、変えることです。たとえば、
「6時を差している時計が傾いているところ」
「3時55分を差している時計が少し傾いているところ」
等々。実際に図を変えるのではなく、替えたように見てしまうということです。主体的な操作ができれば、数は格段にふやせるはずです。
図見ながら、思いつく限り、「見たいように見て」列挙してみてください。
どうでしたか?だいぶ感じが変わったと思います。
たとえば、手近のノートパソコンから、無理やり考えていくとこうなります。
後ろから見たマウスのセンターの切れ目
前から見たマウスのセンターの切れ目
罅の入ったCD-ROMディスク
罅の入ったDVD-ROMディスク
回転しているCD-ROMディスク
回転しているDVD-ROMディスク
キイボードのRの字
キイボードのSの字
キイボードのBの字
キイボードの「の」の字等々。まだ、どこかカタチの似たものを探しているところがあります。知っている知識を当てはめたてるのでは、まだ、発想と呼ぶには自由度が少な過ぎる気がします。発想とは“何とかする”ことですから、知らない、わからない、どうにもならないという状態が、発想のスタートラインのはずです。そこで、こう考えてみます。
こういうカタチにするにはどうすればいいか
こういうカタチに見えるようになるには、どうなっていればいいのかすると、たとえば、こうなります。
ワードの作図機能の円を描き出したところで間違って斜めラインを引いてしまった
マウスの裏側のボール止めをまわしかけたところ
廃棄処分にしたノートパソコンを両側から圧搾しているところ
プリンターの出力表示の文字化けした文字停止記号
キイボードのOの字についた汚れ
キイボードのDの字についた汚れ
キイボードのEの字についた汚れ
キイボードのUの字についた汚れ
キイボードのQの字についた汚れ
キイボードのかすれて消えかけた@マーク等々。いくらでも出るはずです。具体的にノートパソコンを前にして考えみていただければ、まずは、目の前に似たものが見えますが、ついで、
こうしたらこうなるのではないか
こう見れば、こうなるのではないか等々、といったものが次々に浮かんでくるはずです。いわば、こういうカタチに見えるものはないか、これに似たものはないか、という発想から、
こういうカタチに見えるためにはどうなっていればいいのか
こういうカタチに見たいのだがそのためにはどうすればいいのかという発想に移っていくのです。
見える側、見えるものに合わせるのではなく、見えるもの、見ているものを、自分の見たいように変えてしまう、見たいように、あるいは見えるように変えてしまう、あるいはこうすれば、こう見えるようになる、こういう風になっていれば、こう見えると変えてみるのです。
発想の鍵は、そう見えるように、“強制する”ことです。あるいは見たいように見てしまうことです。
発想は、技法ではありません。技法は他人任せ、他人を当てにすることです。発想は、自分を頼むことです。知識ではありません。知識とは異なり、自分の中に答えを見つけ出すことなのです。
シリーズで考える~点から線へ
図を試みたとき、数がある程度出せた人は、シリーズ化という表現をしたかどうかは別に、「これは何とかシリーズだ」と、発想の連続性を考えたはずです。どんなシリーズを考えましたか?ちょっと考えてみてください。
具体的に、かつ見たいように見るということを意識的にする発想は、発想を展開するという意味では、まだ“点”展開にすぎません。こうしたやり方では、ひとつひとつの発想が単発で次へと有機的につながらず、ひとつ思いついては、また次に発想しなおすという、断続した作業にしかなりません。これを“線”展開にする必要があります。
たとえば、連想というのは、
道路→車→タイヤ→パンク→スペアタイヤ→ホイールキャップ→
といった、いわば、思いつきの連鎖反応といっていいものです。これも、次に何が出てくるか、その日の気分次第で、数を出す保証にはなりません。そこで、これをもう少し意識的にやろうとしますと、線として連続して考えていく、シリーズを意識してみる方法が考えられます。たとえば、物の見方で、
上から見たものか、
下から見たものか、
ヨコから見たものか、
前から見たものか、
後ろから見たものか、
裏から見たものか、
等々と、強制的に視点を変えるだけで、いくつもの見え方ができます。あるいは、モノの形を絞って、丸いものとして連続して考えていくのは、先の果物シリーズといえましょう。その他、
何か似たものはないか
というのも、桃、柿、りんごと果物を思いつくためのシリーズとすると、そこから、次はひびの入った皿、どんぶり、茶碗等々と、食器シリーズにしていくことで、数につながるはずである。その他、
何かと関係するところはないか
分割するとどうなるか
と、他とのつながりや切口でシリーズ化していってみることもできます。特に、「分割する」はモノやコトだけではなく、時間の分断も加えますと、変化も表現できます。
例えば、
小田急百貨店のマークの点が落ちたところ(いまから書き入れるところ)
半分に切ったケーキの残った半分
沈みかけた船の船窓に見えた水(ここまで迫ってきた)
細胞分裂しかけたところ(あるいは細胞融合の直前)
中から生まれかけ、罅の入ったモスラ(その他何でも)の卵
シールを剥がそうとして失敗して半分だけ残った
絹糸がまかれつつある手鞠の一本目
半ば月に隠れた太陽等々、何かが加わる瞬間、何かが分裂する瞬間、何かが加わろうとしている直前、何かが抜け落ちた直後等々。そうすると、知っているもの継起する時間的な変化が見えるようになります。その幅も明日や昨日、1年や十年に広げたり、どこかに場所を移したり、ひとを替えたり、と条件を掛け合わせていくと、もっともっと違った見え方になるはずです。こうすることで、少なくとも、点が線につながるはずです。
図を見ながら、思いつく限り、「シリーズ化」で列挙してみてください。
どうでしたか?だいぶ数がふやせる感触がつかめたのではないでしょうか。
5W1H、あるいはストーリーで考える~線から面へ
点から線へ、更に線から面展開へと、発想につながりとひろがりを持たせるには、いわゆる、5W1Hとか5W2Hといわれるもの有効です。つまり、
・何のために(WHY)
・何を(WHAT)
・誰が(誰に)(WHO)
・いつから(いつまで)(WHEN)
・どこから(どこまで)(WHERE)
・どうやって(HOW)
ですが、これは、具体化を状況や場面にまで広げて考えてみようとすることです。
5W1Hを考えるということは、できるかぎり、ピンポイントの、いま、ここ、あるいはそのとき、どこかに絞り込んでいこうとすることです。たとえば、
松井が打ったホームランが東京ドームの天井にぶつかって、外野席に飛びこんだボール
番町の青山屋敷で腰元が割った小皿の1枚
具体化を徹底するとは、こういうふうにピンポイント化、特定化することになります。たとえば、誰が、何時、何処で、どうしたの?と聞かないと、ものごとがはっきりしないのは、逆にいうと、ものごとを個別化、特定化するには、こういうことをしなくてはいけないということなのです。
それは、一種の物語の一場面を切り取るということに近くなります。たとえば、
ワールドカップ決勝で、へたり込んだカーンの前に転がっていた雨にぬれたボール
三都主のペナルティキックがゴールバーにぶつかってゆがんだボール
といった感じになりますが、これを、単発に終わらせず、ひとつのストーリーの中で連続して考えていくには、もう少し意識的な試みが必要になります。
それをステップ化するなら、次のよう
①具体的場面(シーン)を描いてみます
・どういう場所(場面)で
・どういうとき(機会、時間帯、経過時間の中)に
・何をしているのか
②それにふさわしい登場人物を設定してみます
・誰(と誰)がやっているのか、
・誰(と誰)が見ているのか、
・誰(と誰)がどんな関係にあるのか
③その場面には、どんな仕掛け(舞台装置)がふさわしいかを列挙してみます
④状況設定と登場人物によって、ひとつのストーリーを描いてみます
次で、具体的に試みてみます。
点から線へ、線から面へ
5W1Hでストーリーを描くことで、具体的なシチュエーションの、そのとき、その場所を思い描くことで、面として発想を出しやすくなるはずです。たとえば、下図で一緒に試みてみましょう。思いつくままの、点発想なら、どんなものが出せるでしょうか?「具体的に考える」「見えるようにみる」を意識して、ちょっと考えてみてください。
いかがでしたか?意識的に試みてみましたか?それともあいかわらず、漫然と思いつくのを待っていましたか?
たとえば、安全帽の先端についている会社の社章、工場の受付にある防犯用の監視カメラのレンズ、襟から外れてしまった徽章、カメラのレンズを手で焦点を絞っているところ、ひっくり返したマグカップの底、シャツにボタンをかけたところ、逆にボタンを外そうとしているところ、鐘馗様の目、武者冑の前立て、自分に向けているビデオカメラのレンズ等々といった感じて出てくるでしよう。
次は、シリーズ化を意識して、線発想で考えてみてください。
いかがでしたか?どんなシリーズが思いつきましたか?大事なのは、ひとつにしがみつかず、次々とシリーズを変えてみることです。
たとえば、単発で出た、魚の目を発想連鎖の手がかりとして、シリーズ化すれば、金魚の目、フナの目、黒鯛の目、真鯛の目、めだかの目、鱶の目、金目の目、イカの目、蛸の目、イルカの目、鯨の目、蛙の目等々と、次々に意識的につなげてみることができます。
更にこれを、たとえば、「ローラーで伸ばしている」という状況設定から、連続化していくなら、パン生地、そばの生地、うどんの生地、ピザ生地、ケーキの生地、伸ばした餡、延びた飴といった連続性でもいいですし、あるいは、圧延で伸ばしている粗鉄、銅線、鋼、鍛鉄、塩ビシート、ポリエチレンシート、梳きあがったロール紙とつなげていけますし、あるいは、再生ヘッドと触れている、カセットテープ、VTRテープ、オープンリールテープ、8トラテープ、8ミリテープと、一種連想で、シークエンシャルな記録スタイルに関連するものを枚挙していくこともできます。これでも確かに点から線になっていますが、結局どこまでも、思いつきに頼るところがあり、“連続性の思いつき”にとどまっているのに変わりはありません。
そこで、ストーリーを描いてみるのです。面発想で考えてみてください。
どんなシチュエーションを描きましたか?
たとえば、鯉のぼりのイメージの連続になぞらえて、初節句を迎える子供のために、新しい鯉のぼりを発注した父親 が、じりじりしながら、鯉のぼりの届く日を待ちわびている、というストーリーを描いたとすると、
白い鯉のぼりの生地に初めて目が入ったところを思い描いている
鯉のぼりのウロコが描かれているところ
目に墨が入った鯉のぼりに、これから色づけしていくところ
働いているラインで、ベルトを巻き込むローラーが鯉のぼりに見えてしまった
鯉のぼりを見た我が子が思わず手で目を覆おうとしている竿につけた鯉のぼりを立てようとして、からみついた鯉のぼり
となり、それを鯉のぼりが届いて、子供と一緒に見上げている場面、に想定すると、
棹にからみついたところを棹の先から見たところ
我が子に向けたビデオカメラのレンズキャップをとり忘れて慌てて外そうとしている
棹の前で、行きつ戻りつしている自分の歩いている軌跡
樋の先に去年見失ったボールが引っかかっていた同じことを、たとえば、主人公を代えたり、立場を変えたり、場所を変えたり、時を変えたりすることで、出していくことができるはずです。これでストーリーにシリーズ化を加えたかたちになります。ストーリー化が単発で思いつけるとは思え生ません。まずは、いろいろ単発で思いつく中で、シリーズ化や出来るなら、ストーリーを描いてみればいのです。ストーリーを描かなくてはならない、と思いつめるのは、発想とは無縁のことです。
アイデアの出やすい状況を作り出す
アイデアは、待っていても自分の方へ訪れてはくれないのです。だからこちらからアイデアが出やすい状況を設定してやるだけのことです。アイデアの方から出てこなくてはならない状況を作ることなのです。具体的に考える、見えるように見る、シリーズ化、ストーリーも、そうしたほうが数を出しやすくなるからなのです。
シリーズ化は、ストーリー化の一歩直前まできているのです。上から見たという状況設定を描くことは、それを面に広げ、「誰が」「どこで」を加えるだけでのことで、子供が幼稚園で、子供がテーマパークで、とすることで、シリーズ化の延長線上に、具体的シチュエーションを加えているのです。
発想は具体的であるほどいいと述べましたが、他の3つは、具体化効果の延長線上にあるといってもいいのです。具体化とは特定化です。ストーリー化とは、具体化しやすい発想状況を作り出しているのだと言い替えてもいいのです。
したがって、当然ストーリー展開だけですべてよしとなるはずはありません。シリーズ化で、視点や対象をあれこれ考え、具体的シチュエーションを描いた方が出そうだったら、描いてみるし、だめなら、別の視点を想定してみればいいのです。
たとえば、モノの発想の場合、上から見たり、下から見たり等々と視点を設定した方が、出しやすいかもしれませんが、誰が、どこで、どんな使い方をするのかと、ストーリーを描くことで、より細部を詰めることができます。
たとえば、下図で、
棹にからみついたところを棹の先から見たところ
としたとします。これにシリーズ化で、上から見たところ、下から見たところ、と加えていくことで、厚みが増すはずです。
二階から見て、棹の周囲を行きつ戻りつ揺らいでいる鯉のぼり
竿の先の矢車が風でゆれて軌跡を描く
等々となり、単に点から線、線から面の一方通行ではなく、それを遡ることで、面を層へと、厚みを加えることができるはずです。当たり前ですが、何かひとつだけ、秘密の手法があるということはないのです。
再度別の図でためす
以上のコツを元に、再度同じ図で、15分で考えてみてください。
具体性、見たいように見る、シリーズ化、ストーリーを、意識的に試みていただけたでしょうか?前回とは、出方が確実に違っているはずです。どうやって出したか、どうしいうやり方が出しやすかったか、それぞれを振りかえって、意識化してみることが大事です。
行宗蒼一氏より
次に、下図で、同じように「何に見えるか」を、15分の間で試みて下さい。
いかがでしたか。間違いなく数が増えているはずです。問題は、ご自分がどうやってふやしたのかという自分のやり方を振り返り、自分でチェックして、それをご自分の方法として、人に語れるようにすることです。それがご自分のスキルとするコツです。
著者流に試みると、次のようになります。たとえば、“シリーズ化”を活用して、
皿の上に乗っている果物と思いつくと、皿の上シリーズとして、
「皿の上のリンゴ4つ」
「皿の上のみかん4つ」
「皿の上のカキ4つ」
「皿の上の桃4つ」「皿の上のスモモ4つ」
「皿の上の瓜4つ」
「皿の上のトマト4つ」
「皿の上のオレンジ」
等々と、果物を次々羅列できるし、上に乗っているものを、果物や卵(それも鶉からダチョウまで)からごま、塩粒といった極小化することも、あるいは、巨大化して遊園地の回転カップへと連想していけるはずです。テーブルの上へと転想すれば、
「テーブルの上のコップ」
「テーブルの上の茶碗」
「テーブルの上のタンブラー」
「テーブルの上の湯呑」
「テーブルの上のお椀」
「テーブルの上の丼」
「テーブルの上の皿」「テーブルの上の猪口」
等々と「テーブルシリーズ」として、更に食器をいろいろ置き換え、鍋や釜、更に果物や球、に置き換えられるはずです。
皿やテーブルを、どんぶり、お椀、茶碗、フライパン、なべ等々へとつなげられます。さらに「土管」や「井戸」「池」と変えて、「土管シリーズ」「井戸シリーズ」「池シリーズ」と考えますと、「土管にのぞくケーブル」「土管にのぞく水道管・下水管」や「井戸に浮かんだ果物シリーズ」になりますし、「池に浮いたシリーズ」にすれば、
「池に浮いた空き缶4つ」
「池に浮いたタイヤ4つ」
「池に浮いた竹筒4つ」「池に浮いたゴムボール4つ」
「池に浮いた野球ボール4つ」
「池に浮いたバレーボール4つ」
「池に浮いた空き壜4つ」
等々、そこに浮かんでいるいろいろなモノに変えられますし、井戸や池を湖に海に宇宙へと広げていけば、4つの丸は島や惑星や島宇宙になりまようし、口の中と見立てれば、「口の中シリーズ」として、歯や飴玉とみなすこともできる。更に、中の円を凸部ではなく、凹部と見なせば、ボタン穴や車のホイールへと広がるでしょう。しかも、そこまでの発想が上からの視点と自覚していれば、同じものを下から見る(それは引っくり返したのと同じ)と、「脚シリーズ」として、
「丸テーブルの脚」
「丸椅子の脚」
「豚の脚」
「牛の脚」「鹿の脚」
「豚の脚」
「牛の脚」
等々、机・テーブルから4足動物、更にはUFOといった別のシリーズへ発展させられるでしょう。これに、誰が、どこでと加えてみると、更に数を出しやすくなるはずです。
- 常識を超える数を出すことの意味
出せる数が、尋常でない、常識を超えたとほうもないほど数であれあるほど、その発案者の努力の程度は中途半端ではないことは実感していただけたと思います。
同時に、ある常識的なラインを超えたとき、その人のそれまでの発想の限界点を超えた大爆発が起きるはずです。そこには、いままでにない飛躍的な転換が起きているはずなのです。
たとえば、20個ではなく2、000個とすれば、そこには、尋常一様ではない努力必要です。それが、仮に万を超える数だったとしましょう。もはやそれは単なる努力を超えた、とてつもない飛躍が起きているのではないでしょうか。
ご自分が試みたプロセスを振りかえって、想像してみてください。
たとえば、20~50個の範囲なら、少しの工夫と努力でできるはずです。それには、「こんなことはまずいのではないか」「こういうやり方は意味ないのではないか」「ここまでやっていいのか」等々という自分の心のタブーを破るということが必要だっだはずです。
しかし、2、000個、さらに万を超えるとなると、そういう漸進的な増え方では間に合わないはずです。粘りといったところで、それは並大抵の粘りではないはずです。そこには、ある飛躍、発想転換がいるはずです。
たとえば、一方に大きさ、他方に果物の種類というマトリックスのようなものを、次々と設定するというような、その人がそれまでにしてきた、常識的な発想の仕方を破っていく、飛躍した着眼や着想の転換なくては、そこまでの増大は生まれないはずです。その転換や飛躍が、爆発的な数を出そうとするときに生まれるはずです。この“とほうもない”というところが、ここでの重要なポイントなのです。
- 発想への伸びしろをチェックする
- 発想の遊び度
のりしろは、貼り合わせる部分の余分です。遊びは、ハンドルなどの余裕です。発想にも、そうしたゆとりがほしいのです。
よく、「できない理由はできる証拠だ。出来ない理由を解決すればいい」と言われます。しかし、たとえば、何かを頼まれたとき、
「できません」
ととっさに答えてしまう人がいるのは、何故なのでしょう。その場合、それは、
永遠にできないということなのか、
「このままでは」できないのか、
「いまの自分では」なのか、
「自分一人では」なのか、
「いまのやり方のままでは」なのか、
「いままでのままでは」なのか、
と、自分に問い直す“ゆとり”がほしいのです。それがあれば、少なくとも、
ひとりでは無理だが、頼んだ人のサポートがあればできるかもしれない
と、「できない」と発想することではなく、「どうすれば」「どういう状態になれば」「どういう条件があければ」、「できる」のかと発想をすることが可能になるはずです。
では、そのために何が必要なのでしょうか?
よく自責化ということが問われます。そこには、自分が主体的にやるという意味で、
自己責任でいう、自分で責任を取ると言う意味、
自分が責任を持ってやるという、当事者意識の意味
のふたつの意味が含まれていますが、それ以外に、
自分に解決できるカタチに置き換える
という意味があります。自責化と言う以上、それを引き受けるだけではなく、実現して見せなくてはなりません。実現する目安が立たなければ単なるその場しのぎでしかありません。
そのとき必要なのが、どうすれば可能になるかを考える姿勢です。それを自分がやるという視点で考えたのが、「自分に解決できるカタチに置き換える」です。これはまさに「何とかする」発想そのものです。
どういうふうにすれば自分に、どんな風にできるのか
どこまでの完成度なら自分にできるのか、どん感じでできるのか
どういうやり方なら、どこまでひとりでできるのか
等々が明確になれば、「どうすれば実現可能性が高まるか」は、相手にも自分にも見えてくるはずです。
発想というのは、自分ですべてをしょいこむということではありません。そんなことができるはずはありません。どこをどうサポートしてもらえば、どこまで自分にできるかを明確にできることは、既に「何とかしている」ことです。
「できない」という言葉ですべてを遮るのは、「できない」という発想が、「できる」という発想を妨げているからです。「できない」という発想こそが、固定観念と呼ばれるものなのです。
ここで、第1章の4つのポイントを思い出すのが有益です。「できない」を、ひとまとめにしてしまうのではなく、
何がなのか、
どうできないのか、
どこまでできないのか、
どういう条件でできないのか、
等々と具体的に考えることです。それが、固定観念を崩す方法でした。自分についてもそれは当てはまります。アイデアにあふれた人は深刻にならないとは、バレリーという詩人の言ですが、それは、いつもどうすれば可能性が生まれてくるか、という視点で考えることをやめないからだ、と言い換えてもいいのです。それを発想の遊び度、あるいはのりしろと呼んでおきます。そののりしろが、発想をパワーアップしてくれるという意味では、それを発想の“伸びしろ”と呼んでおきます。
では、ご自分の発想の“伸びしろ”度はどうでしょうか?ご自分の発想の足を引っ張っているところはないでしょうか?「発想の“伸びしろ”チェック」で点検してみてください。
- 発想の“伸びしろ”をチェックする
●下記の設問で、該当する場合は、レ印でチェックを入れてください。
種類
設問項目
該当の有無
A
①正解はひとつしかないと思っている ②仕事の遂行にはルールは重要であり、従うべきだ ③自分に創造性はないと思っている ④考えや主張は論理的で筋道が通っていなくてはならない ⑤現実的な考えがもっとも尊ばれる ⑥遊びや遊び心は仕事には無用である ⑦専門外のことに口を出すべきではない ⑧ばかげたことやふざけたことを考えるべきではない B
①間違えたり、失敗することを恐れている ②秩序を重視し、曖昧さを許さない ③発想より判断することを好む ④緊張を緩め、ゆっくり暖めながら考えることが苦手である ⑤熱中し過ぎ、早く成功しようとやりすぎることがある ⑥興味を引かず、やってみようともしないことがある ⑦想像力やイメージが苦手である ⑧想像力のコントロールがきかなくなり、奔放になることがある C
①初めのアイデアに飛び付き、それに満足してしまう ②早まった結論に飛び付いて、はやとちりしてしまう ③早く結論を出そうと焦る ④意欲過剰での空回りするところがある ⑤入れ込みすぎて堂々巡りに陥る ⑥効率にとらわれて、近視眼的結論に陥る ⑦黒か白か(あれかこれか)割り切りたがる ⑧慣れを引きずる D
①誰からも評価を得ようとする ②自分のアイデアをベストと見なし、次善策を認めない ③リスクにためらい、決断を先延ばしにする ④批判に弱い ⑤採択か否決かの二者択一で考える ⑥ミーティングで結論を得ようとする ⑦他人の意見に耳をかさない ⑧権威やお墨付きを求める このチェックリスト作成に当っては、R.V.イーク、城山三郎訳『頭にガツンと一撃』(新潮文庫)、J.L.アダムス、恩田彰訳『創造的思考の技術』(ダイヤモンド社)、E.ロードセップ、豊田晃訳『発想力を伸ばす』(創元社)を参考にしました。
- 評価方法と評価結果の見方
Aは、発想に対する先入観
Bは、発想プロセスでの苦手意識あるいはおそれ度
Cは、発想プロセスのつまづき度あるいは失敗しやすい傾向
Dは、アイデア実現への制約あるいは非発想的姿勢
をそれぞれチェックしていただきました。いずれも、発想の成功や飛躍の足を引っ張る、制約要因となっています。
ご自分の発想の足枷度はいかがでしたでしょうか?
Aでみていますのは、発想とはこういうものと思いこんでいる決めつけ度です。いわば、発想というものへの固定観念です。この数値が高いほど、発想を評価していないということです。この数値は、第1章の「引っ込み思案度」と関連があります。「発想なんて」と、発想への不信感は、発想へのおそれをも示していますから。このチェック項目の反対が、望ましい発想観となります。
Bでみていますのは、発想プロセスでのおそれ度です。第1章の「引っ込み思案度」が発想全体へのおそれを示しているとしますと、これは発想プロセスで、引いてしまう傾向を示しています。だから、あまり発想が奔放になったり、意図を外れたりすると、それを押さえる方向に働きます。このすべては、発想のアウトプットを枠内に納めようとします。せっかくの発想力の働きを制約してしまいます。
Cでみていますのは、発想プロセスのどこでつまずくかを示しています。焦りや性急さや自己満足は、発想そのものの可能性を自ら閉じるものです。Bが、発想プロセスで、常識の方へと引っ張ろうとする、ためらいやおそれ度という制約を示すとすると、Cは、折角広がった発想を、つまらない評価で台無しにしてしまう、発想評価でのマイナス因子です。
Dでみていますのは、発想結果をどう生かすかというときの現実との折り合いのつけ方です。その正しさを実現するには、自分のアイデアへの自信とそれを保証する検証の確実さです。誰かにすがって、権威付けたり、発想の正しさを保証したりすることでありませんし、ましてや自己過信や自己満足でもありません。
こうしたマイナス因子は、ご自分の中で培われ蓄積されてきたものです。それをどう崩していくか、発想は、過去の自分自身との格闘でもあるのす。そのためのスキルを、次に用意しました。
発想姿勢の基本原則は、次の3つです。
①知っていることをあてはめない
②答えはひとつではない
③キャッチボールしてみる
ひとつずつ説明していきましょう。
知っていることをあてはめない
「知っていること」を当てはめないは、もう説明の必要はないと思います。キャッチフレーズ風に言いいますと、
・疑え、つじつまの合うことだけで結論を急ぐな
・裏を読め、見えていることだけで結論を急ぐな
・先を見ろ、いまという一点 だけで結論を急ぐな
となりましょう。
発想は知識ではありません。知っていることで「わかる」ことがあるかもしれません。しかし、それは、答えのひとつでしかない、と考える姿勢が不可欠です。次の、「答えはひとつではない」と関連しますから、そこで、もう一度触れることにします。
答えはひとつではない
たとえば、下図を示して、「9点を一筆書きで通しなさい」といった課題が、発想の本にはよく出されています。
みなさんもご一緒に考えてみてください。あるいはご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな方は、それ以外に答えがないかを考えてみてください。
いかがでしたか。どんな答えが見つかりましたか?
たとえば、発想の本では、正解は「正解は巻末に」とあり、下図のような考え方が示されます。
しかしもしそれだけが正解なら、それは発想ではなく、知識に過ぎないのではありますまいか。
ラッセル・L・エイコフは、この問題を宿題に出された自分の娘に、図表2-4のように紙を折れば解けることを示しました (ラッセル.L.エイコフ『問題解決のアート』建帛社)。
翌日娘はそれを発表しましたが、担任の教師は「それはできない」と、その回答を拒絶しといいいます。その教師は、生徒が答えを自分で見つけることを求めているではなく、教師の知っている答えを見つけさせているだけなのではないでしょうか。発想の本にある、正解は巻末に、と同じです。それは知識を覚えさせているのと変わらないのです。それを発想とは呼びません。
キャッチボールしてみる
キャッチボールは、説明を要するかもしれません。それには、こういう意味を込めているのです。
例の3Mのポストイット開発をめぐる逸話があります。シルバーという人が、接着剤を開発していて、貼ってもすぐ剥がれてしまうものを創り出しました。彼はそれを「失敗」とはみなさず、社内の技術者同士のミーティングで、自分にはこの使い道が思いつかないが、誰かいい使い道があったら教えてくれないかと、言ったのです。その中に、いつも聖歌隊で、本に挟む付箋に不便を感じていたフライという人が、その使用方法として、ポストイットを発案したのです。
この、いわば自分の問題意識をぶつけることで、新しい何かを発見することにつながるやりとりを、キャッチボールと呼びたいのです。
カーネギーは、「2人の人間がいて、いつも意見が一致するなら、そのうち1人はいなくてもいい人間だ」(『人を動かす』)と、言っていました。ひとりひとり生まれも来歴も違う人間なら、モノの感じ方も考え方も違って当たり前です。それが自己表現できないのは、組織の中で、ひらめ状態のほうが生きやすいとか、下手に目立たないほうがいいとか、別の理由から、同じ意見にしているだけなのです。
こうしたキャッチボールの効果については、後で触れますが、キャッチボールをするために戒めとしたいことは、下表に、タブーとして挙げておきます。自己点検の材料としてみて下さい。
キャッチボールタブー10ヵ条
①話し手を、どうせろくな話はしない奴だと評価して締め出していないか
「あいつの話はおもしろくない」「どうせたいしたことじゃない」「いつもくだらないことしか言わない」「いつも言い訳ばかりだ」という態度をしていないだろうか。そうなるとほとんど聞いていないし、当方が聞いていないことは相手にわかるものだ。
②そこまで聞けば分かったと早合点で結論づけていないか
「そこまで聞けばわかった」「よっしゃ」「まかせておけ」「みなまで言うな」と勝手に早呑込みしてしまっていないだろうか。相手は別のことをいいたいのかもしれないのに!
③相手の話に自分の期待を読みこんで聞いていないか
「おれのことは、わかってくれるはず」「あそこまで言ったんだ、きちんとやってくれるはず」「あれだけ教えたんだ、できるはず」という、一方的な思い込みはないか。それでは相手のことが見えてはいない。あるいは逆に、「そうだろう、よくわかる」「そうだ、それがおれの言いたいことだ」と、自分の期待や願望だけを聞き取っていることはないか。それでは、相手の本当に聞いて欲しいことは聞こえていない。
④自分の聞きたくない部分には耳をふさいでいないか
「そういうことを言いたいんじゃないでしょ」「そんなことは聞いていない」と、途中で遮ってしまっていないか?言いたいことを決めるのは、相手なのに。
⑤相手の話から自分のイメージを勝手に広げて聞いていないか
相手の話から勝手に自分のイメージを広げて、相手の言うことを聞いていない。勝手に解釈する。片言聞いただけで、勝手に自分の空想やアイデアを肥大させていく。そこには相手の気持も考えも全く入り込む余地はない。
⑥答えの予行演習をして聞いていないか
相手の話の途中から何を言おうかと一生懸命考えていて結局聞いていない。どう叱るかとかどう言い訳するかとか、自分の都合や事情にこだわっているいるだけ。それならコミュニケーションする必要はなくなってしまう。予想しない結論になるから会話がある。
⑦相手の言葉尻や態度に感情のカーテンをおろしてしまっていないか
後輩のくせに、新人のくせに、そういう生意気なことを言うのか。相手の言葉尻にこだわっているのは、結局自分の立場やプライドを傷つけない心地よい言葉を重んじているだけ。中身が自分の意向や趣旨に反すれば聞く耳をもたないのだと、相手は受け取るだけだろう。
⑧相手の話の中身よりは話し方や表現に目を奪われていないか
そういう言い方はあまりいい表現でない、言い方が間違っている、表現にミスがある、と口の利き方を問題にして、自分の価値観でつい説教を垂れる。たまたま表現スタイルで文句をつけているが、結局形式を理由に中身を聞く耳をもたず、自分の価値観を押し付けているだけ。
⑨相手の発言以上の意味を読みこんで聞いていないか
相手が意見や提案をしたとき、「君は何かね、僕のやり方に文句をつけているのか」「僕の考えは間違っているというのか」と悪意に解釈したり、単に私的に賛意を示しただけなのに、公に賛同したと触れまわったりしていないだろうか。相手の言葉の意味は相手のものだ。それを確かめて、自分と同じかどうかは確かめなくてはならない。
⑩聞きたいことや都合のいいことだけしか聞こえていないのではないか
聞きたいこと、おいしいことだけしか聞かない(人を選ぶ、情報を選ぶ)。おいしいことしか聞かない人には、おいしいことしか誰も言わないということにほかならない。とても相手の悩みに聞く耳をもてそうもない。デビッド・アウグスバーガー、棚瀬多喜雄訳『聞く』(すぐ書房 1985)に加筆、アレンジしています。
エイコフの例が突破口となって、
上図について、いろいろなアイデアが浮かぶはずです。これも、エイコフ相手のキャッチボール効果とみなすことができるでしょう。
たとえば、縦の3点が互いに接触するほどに紙を折り曲げ、次にその3列の点を、横1列に並ぶように紙を折り曲げていくと1本の線で通ります。
また9点を描いたページを切り取り筒状に丸めれば、それを周回する線は1本ですむはずです。
その9点が地球規模の大きな球面におかれているとすれば、地表の9点など極細の1線で一回りできるでしょう。
逆に、9点を巨大化すれば、ほんの少し、例えば活字の2倍位の大きさにしただけで、縦3点を斜めにかすめさせれば、一筆で引けるはずです。その逆に、9点を点ほどに極小化すれば、一筆で塗り潰せてしまいます。
もっと極小な点なら、ペン先の1滴でも9点を通るでしょう。
もっと原始的に考えるなら、焼鳥の串でも鉛筆でも、1点ずつ順繰りに手繰って貫いても、1本で通せるはずです。
あるいは、太い筆で一筋に9点を塗りつぶせば、一本でとおったことになります。
こうした発想は、キャッチボールをすることで、もっともっとさまざまなアイデアに発展させることができるはずです。
仮に、エイコフのような一人がタブーをやぶると、「なんだ」「それでもいいのか」と、暗黙のうちに自分の中で作っていた制約を解いて、一斉にアイデアが涌き出てくるはずです。キャッチボールの効用は、エイコフのような、平然と常識を乗り越えるアイデアの持ち主とのやりとりがあることで、自分の中の足枷が取れ、発想のが楽しさを味わえることにあるのです。
与えられた課題を解くのは、どこかで習ったことはなかったか、知っていることはないかと、どこかに正解を探すことではないのです。自分なりに、課題を自分に解けるカタチに置き換えてみる工夫なのです。第1章でさんざんやっていただいた「何に見えるか」と、基本的には同じです。それをスキルとして、次に深めてみましょう。
発想力を高めるバラバラ化の4つのスキル
具体化効果のもつ意味
発想するためのポイントを、
①具体的に考える
②強制的に、あるいは見たいように見る
③シリーズ化する
の4つに整理して、実際にいろいろトライしていただきました。なぜ、発想効果につながったのかを、再度確認しておくところからはじめたいと思います。
「具体的」ということに、「具体的であるとはこれである」といった唯一の解答はありません。具体的とは特定することですから、特定化された数だけ具体化できるということです。「どこまでいったら具体的になったことになるのか」に、際限はないのです。それが、発想です。発想は数であるということです。
行宗蒼一氏より
たとえば、いままで再三使った上図が『円に直径』と見えたとします。それを具体的に言ったらどうなるのか、それを更に具体的に言ったらどうなるのか、更にそれを具体的に言ったらどうなるのか等々を、意識的にすすめていくやり方が、上記の4つでした。こうして具体化していくスキルを、バラバラ化と名づけておきたいと思います。
その意味を整理しておきたいと思います。
たとえば、この図を、一種の情報を見た場合、これを見ながら「何に見えるか」を集める場合、発想としてやる場合と、いわゆる情報収集・分析する場合と、どう違うのでしょうか?それとも同じことなのでしょうか?ちょっと考えてみてください。
基本的には同じだと思います。情報の収集・分析の場合も、円と直径であるところから出発して、その意味するものは何かを考えていきます。その場合も、具体的であり、特定されたほうが、情報としての価値があることは間違いありません。たとえば、どこどこの出入り口を横から見たものといったほうが、開閉する出入口という情報より、価値が高いはずです。
しかし大きな違いがひとつあります。
情報の価値は、その目的にかなうかどうかです。情報を収集・分析するのは目的ではなく、それによって何らかの目指していた目的が達成されなければ意味がありません。それは、たとえば暗号の解読であったり、仮説の検証であったり、現実の再現や確認であったり、意味の発見だったりします。ジグソーパズルのピースを集めて、図を完成させるのに似ています。
たとえばある犯罪が起きて、Aという犯人のアリバイを調べようとするときに、Aという人が同じ時間どうしていたかとかのみが重要です。無関係のBがどこで何をしようと、その現場と同じ環境のところは他にどこかとか、そこでのファッションとか購買傾向とか、そこにいる男女比率とか、平均身長とか、平均収入とかは無意味です。徹底した目的指向の、均質な一定レベルの情報が必要なのです。当然売れる商品づくりのマーケティング分析という目的なら、また別の情報分析が必要になるはずです。
しかし、発想では、違います。均質な情報では意味がないのです。たとえば、りんごに見える、桃に見える、という情報は均質ではないかという疑問をいだくかもしれません。でも、同じ図が桃に見えるのとりんごに見えるのとは均質ではありません。むしろ桃に見えたり、りんごに見えたりする、図表2-6の異質性が際立ってくるはずです。
発想で必要なのは、この異質性です。
今まで見えないような現実の見え方、
そうとは気づかなかった現実の一面、
そんなふうにも見えるのかという驚き、
等々こそが必要なのです。行き詰まっている現状を突破するには、いままでとは異なる異質性こそが必要なのです。そして異質性は、個別化の中にこそあるのです。
たとえば、犯人の顔写真を、誰かと特定するためには、顔として認識してもらい、その人が犯人かどうかを同定してもらわなければ、情報としての役には立ちません。
しかし、発想にとっては、それが顔であると同時に、かぼちゃであり、ゴリラであり、マスクであるという多様で、異質な可能性の方が意味があるのです。
それは、通常の情報収集は、現実から自分たちの正解を確かめたり、発見したりしようとしているのに対して、発想では、それが正しいかどうか、現実的かどうかはさておいて、そこに可能性のあるものすべてを洗い出そうとするからなのです。
もちろん、最終的には発想も、見つけ出したアイデアを現実の中で実現しなくてはなりません。その場合、それでいいかどうかを確かめる情報収集の作業は必要になりますが、まず必要なのは、現実性や評価や判断ではなく、現実の多様性・異質性を浮かび上がらせることで、今まで見えなかった新しい答えを見つけることなのです。
バラバラ化の効果を高める
①もっと具体化する
いままでいろいろな図形を使って試みた「何に見えるか」の発想作業は、ひとつの情報から、どれだけ多角的な意味や可能性を引き出すか、という試みなのです。だから、これをバラバラ化と呼びます。
当然対象を、意識のレベルで多角化、多様化するだけではなく、現実にそうしてみることは有効なはずです。たとえば、切り裂く、切り刻む、膨らます、引っ張る、伸ばす、拡大する等々。
カタチをバラバラにすれば見え方が変わる
見え方が変われば見方が変わる
からです。それも発想を促すには悪いことではありませんが、現実的な変化と同じことを、こうしたらどうなるかと、仮定してみるのが、発想の多様性、多角性というものです。
だから、物理的な細分化、逆転、拡大縮小、膨張収縮等々と同じことを、具体的に想定してみる、たとえば、
①元の輪郭、形態、文脈、意味、属性がなくなるくらいできるかぎり細分化する
②誰がいつどうした、何がどうなったと個別化することで、意味をはみ出す
③一方向だけではなく多方向、多角的な見方をすることで、一定の見え方を崩す
④拡大縮小、膨張収縮、伸張収縮などの変形によって、固定したカタチをなくす
⑤もとの条件を変えてしまう
等々を具体的に想定してみることによって、より具体的に発想することができるはずです。だからバラバラ化なのです。
②バラバラ化の効果
大事なことは、このバラバラ化によって知っている意味や輪郭から切り離され、
・いつもの見方がしにくくなるだけでなく、
・自分の中に隠れていた知覚・イメージ・感覚が触発され、
・元の意味や形から切り離され、
・バラバラの素材同士に別のつながりがあぶり出されてくる、
ところなのです。そこに、何かの意味のつながりや、何かの輪郭の断片を見分けることではありません。それ自体独立した素材として、直接に記憶の中のバラバラの知覚、感覚、イメージへの刺激となることなのです。
バラバラな情報が、文脈や意味のネットワークに収まっていた想い出・記憶の断片に直接刺激し、そこで気泡が浮くように切り離されて浮かび上ってくる効果をねらっているのです。
たとえば、何気ない友人との会話の言葉から、不意にとうの昔に忘れていた幼い頃の出来事を思い出したりします。プルーストの『失われた時を求めて』では、一口のマドレーヌの味が過去の一切を呼び戻しました。
ちょうど、脳の一部に電気の刺激を与えられると、きれぎれに記憶のイメージが浮かぶのと同じように、意味のつながり、経験のつながりとは切れた断片が直接引き出されるのです。それが、まったく異質な情報の間の予期せぬつながりを発見させるのです。
われわれが手に入れられる知識は、自分で気づいているよりもはるかに大きいと言われています。脳は意識している以上のことを知ってます。無意識のネットワークは通常、意識的に明らかにできるよりもはるかに多くのことを知っているのです。記憶の中の、思い出、エピソードに代表される個々人の経験、学んだ知識、身につけたスキルの多くは、意識からは埋もれてしまっています。それが、バラバラの情報からの刺激によって、開かれる、あるいは誘い出されるのです。いわゆるハッと思いつく、ひらめく、というのはこういう状態です。これがバラバラ化効果です。
しかも、記憶などの内部情報は、口に出す、文字に書く、図に描く、写真にする、表にすることで、われわれにとって異質なものになるのです。頭の中では、話すスピードの何十倍で言葉やイメージがかけまわっていると言われています。それを文字にする、言葉にすることで、考えがまとまることもありますし、言葉にすることで頭の中で感じたり考えていたことと微妙なギャップが生まれることもあります。それが大事なのです。
バラバラ化のスキル
①4つの具体化との関連
バラバラ化効果をスキル化するヒントは、既に述べたところから明かです。
物理的な細分化、逆転、拡大縮小、膨張収縮等々と同じことを、具体的に想定してみることで、バラバラ化が促進することを述べました。例として、
①元の輪郭、形態、文脈、意味、属性がなくなるくらいできるかぎり細分化する
②誰がいつどうした、何がどうなったと個別化することで、意味をはみ出す
③一方向だけではなく多方向、多角的な見方をすることで、一定の見え方を崩す
④拡大縮小、膨張収縮、伸張収縮などの変形によって、固定したカタチをなくす
⑤もとの条件を変えてしまう
等々を想定するによって、より具体化できると述べました。これがバラバラ化のスキルです。
これを整理したものが、次の4つの切り口です。これが、著者の語れるスキルです。
①視点の異質化
上から見たもの、下から見たもの、横から見たもの、前から見たらもの、後ろから見たもの、等々、多様な視点(位置から)のものの見方であること。
②カタチの異質化
大きさのレベル(細分化、巨大化)、表現レベル(具体的、抽象的)、スタイル(図表、数式、写真)等々、モノやコトがさまざまな形態・様式で表現されていること。
③意味の異質化
人ごとに勝手意味づけ、主観の交じった感情、文脈や意味を共有化しない、意味・価値のバラバラ化。あるいは連想、類比、具体例の列挙等々で、意味の中心から関連あるものへと広げて、意味をずらしていく。
④条件の異質化
過去現在未来、朝昼夜、条件設定がバラバラであること。いつ使うのか、誰が使うのか、どういう場所で使うのか、どんな使い方をするのか等々、条件、状況、つながりを変えてしまう。言い換えると、
①視点を変える
②カタチを変える
③意味を変える
④条件を変える
という4つになります。第1章で挙げた、
①具体的に考える
②強制的に、あるいは見たいように見る
③シリーズ化する
④5W1Hあるいはストーリーを描く
の4つのポイントとの関連を、あえて説明しますと、④がストーリーで、①②③は、具体化する切り口になっていますと同時に、そのままシリーズ化として活用できるはずなのです。
これにいくつか具体化例を加えて整理し直しますと、下表のようになります。
①視点(立場)を変える いまの位置・立場そのままでなく、相手の立場、他人の視点、子供の視点、外国人の視点、過去からの視点、未来からの視点、上下前後左右、表裏等々 ②見かけ(外観)を変える 見えている形・大きさ・構造のままに見ない、大きくしたり小さくしたり、分けたり合わせたり、伸ばしたり縮めたり、早くしたり遅くしたり、前後上下を変えたり等々
③意味(価値)を変える 分かっている常識・知識のままに見ない、別の意味、裏の意味、逆の価値、具体化したり抽象化したり、まとめたりわけたり、喩えたり等々
④条件(状況)を変える 「いま」「ここ」だけでのピンポイントでなく、5年後、10年後、100年後、1000年後あるいは5年前、10年前、100年前、1000年前等々4つのアプローチを、更にその具体例に細分化して、図解したのが、下図です。
多角的な見方をするための4つの切り口 (バラバラ化)
視点を変える
(1)位置を変える
(2)立場を変える
(3)方向を変える
(4)価値(気持)を変える
(5)機能(働き)を変える
(6) 目のつけ所を変える
(7)データ(情報)を変える意味を変える
(1)まとめる(一般化する)
(2)具体例で考える(具体化する)
(3)言い換える
(4)(全体と,他と)対比してみる
(5)区分(区切り)を変える
(6) 連想する
(7)喩(たと)える見かけを変える
(1)カタチを変える
(2)大きさを変える
(3)量を変える
(4)性質を変える
(5)状態(あり方)を変える
(6)動きを変える
(7)位置(順序)を変える
(8)構造(仕組み)を変える
(9)関係(つながり)を変える
(10)似たものに変える
(11)現れ方(消え方)を変える条件を変える
(1)理由(目的)を変える
(2)目標(主題)を変える
(3)対象を変える
(4)主体を変える
(5)場所を変える
(6)時を変える
(7)やり方を変える
(8)水準を変える
(9)前提・制約を変える
②バラバラ化を使いこなす鍵
表でいう、「変える」とは、それを意識するという意味です。
例えば、「視点を変える」の、「視点を意識する」は、「~と見た」とき、「いま自分は、どういう視点・立場からみたのか」と振り返ってみる、ということです。
そのとき、会社の立場で見たのだとすれば、それ以外の、父親として見たらどうなるか、客の立場で見たらどうなるか、子供の視点で見たらどうなるか、老人の視点で見たらどうなるか、身体の不自由な人の視点で見たらどうなるか、車椅子に乗った状態で見たらどうなるか、外国人の立場で見たらどうなるか、未来の人間から見たらどうなるか等々。
無意識にとっていた視点を、ひとつ意識するだけで、それを起点にして、「では、別の視点ならどうなるか」と、それ以外のさまざまな視点が上がってくるはずです。少なくとも、自分の取った視点を振りかえることで、「そうでない別の視点」を、最低限もうひとつ取ることはできるはずです。
自分の取っている視点を意識することで、それとは異なる視点を、意識して探していくことができる、そのきっかけとして、自分の視点を意識してみることが大事なのです。それは、発想というものが、天性でも、感性でも、思いつきでもなく、意識的する作業であるということを意味しているからなのです。
こうしたひとつの情報を異質化することをバラバラ化と名づけた真の意味は、ここにこそあるのです。発想を促進するのも自分であり、つまずくのも自分です。発想は、自動的な作業ではなく、主体的かつ、意識的な作業であり、ほっておけばそれまでですが、意識的にすれば、自分の中に埋もれていた、あるいは眠っていた回線(脳細胞のネットワーク)を復元し、活性化することができるのです。
③バラバラ化実験
たとえば、おなじみの図を例に、バラバラ化スキルを使って、数を出してみましょう。みなさんも試みてください。
いかがでしたか?数が出しやすかったですか?
ちょっと考えてみましよう。まず、センターサークルというのが思いついたとします。その「センターサークル」という着想が、「いま自分は、どういう視点・立場からみたのか」と振り返ってみると、仮想的に、サッカーのピッチを上から見ていたことに気づいたとしましょう。とすると、横から見たら、何に見えるか、と考えていきます。たとえば、
弓の的、ホイールキャップ、スクーターのタイヤ、台車の車輪等々。
それだけではすぐ詰まりますから、的シリーズで考えてみると、射的の的、宝くじの当選番号を決めるダーツの的、射撃の的等々
行き詰まったら、では、下から見たら、何に見えるか、と考えていきます。たとえば、
お尻、福岡ドーム球場の天井、天文台天体望遠鏡の天井等々。で、お尻シリーズで続けていくなら、豚のお尻、赤ちゃんのお尻、牛のお尻、イノシシのお尻、桃のお尻等々というように、シリーズ化して展開して行くことになります。
それに、いつ、どこでという視点を加えれば、面展開にしていくことができます。
バラバラ化のツールとして使えるモノに、2つのツールがあります。1つは、他人の異質性を生かすブレインストーミング。いま1つは、自分の発想にある種のスクリーンを強制的にかけるチェックリスト法です。それぞれを、具体的な使い方を含めて紹介してみます。いずれも、既に有名なスキルですが、そのツールを、バラバラ化という目的のために使いこなすには、それなりの工夫と努力が必要となります。
ブレインストーミングのキャッチボール効果
①ブレインストーミングの効果
キャッチボール効果については、前に触れましたが、ブレインストーミングは、キャッチボール効果を上げるのに有効なスキルです。
出典;エルンスト・マッハ『感覚の分析』(須藤吾之助・廣松渉訳 法大出版局)
図は、マッハの自画像です。寝椅子に横たわるりながら、自分がどう見えるかを図示しています。マッハはこのデッサンを、「自己観察による私」と名づけています。ふさふさした髭が肩の突端になびき、下方にむかって短縮された遠近法で、胴、肢、足と順次つづいていく図は、科学的には多少眉唾ものでも、個人の視界の狭さと発想の限界のアナロジーと見ることができます。
キャッチボールを、こうした個人の限界を破る手段と考えます。ブレインストーミングを、そのツールとして使うことができるのです。
ブレインストーミングは、ブレイン(脳)のストーム(嵐)を意味します。他人のもっている異質性を生かして、自分の中に異質さを掘り起こす効果を上げるのです。この真意は、「発見は、自分の中でする」というところにあります。
人と会話する、人と雑談する、人に相談する、人を教える、人を指導する、人をコーチする、人をカウンセリングする、人をコンサルティングする等々、人との言葉によるやり取りの全てを、人から何か答えを教えてもらう意味だとすれば、間違っています。常に、「答えは自分の中にある」のです。
自分ひとりでは発想が狭いから、自分と違う発想の人からヒントをもらう、自分との違いを借りて、あるいはその違いを鏡として、自分自身の中に、自分の忘れていた記憶の中に、アクセスしないままに枯れかけていた感性の中に、薄れていた体験の中に、自分の気づかない異質さを見つけるのです。しかし気づくのは、自分であり、見つけるのは自分の中に、なのです。
②ブレインストーミングの原則
ブレインストーミングの原則を整理しながら、ブレインストーミングの原則そのものとキャッチボールしてみましょう。
ブレインストーミングの原則
1、メンバーの発言への批判禁止
2、自由奔放な発言
3、自由奔放な発言
4、他人の発言への相乗りOK
5、自己激励と相互激励の雰囲気で①メンバーの発言への批判禁止
出されたアイデアへの批判は最後まで控えることです。批判をしないことで、心の「制約」「妨げ」が排除されます。つまりタブー解除効果です。 会議やミーティングで、もっともらしい批判に頻繁に出会うはずです。
曰く、「その説はおもしろいが、こことここにボトルネックがある」「それは一般的には正しいが、当社の社風にあわない」「そんなものをやっても市場は小さい」云々。
こういうのを、論理的悲観主義というそうですが、「批判」は、往々にして、既存の価値や知見での評価でしかないのです。
ここでは、アイデアへの批判はカッコに入れます。こう自分に言い聞かすことです。「ダメなアイデアだと思うなら、ダメと言う代わりに、自分でダメでないアイデアをぶつけてみること」と。
②自由奔放な発言
これは、突拍子もないもの、奇抜なもの、風変わりなもの、乱暴なものほどよいという意味です。何でもあり、です。自由奔放な雰囲気が各自の「自制」の構えが消えるはずです。自由な雰囲気、自由な発想を保証するといっていいのです。
③質より量
この原則は、なかなか納得しがたいはずです。「質のいいものをたくさん」といいたくなるのが常識です。
しかし、新しい何かを創り出そうとしているのに、何が質が高くて、何が質が低いかがわかっているはずはないはずです。もし質の評価があるとすれば、既存の価値観であり、それはある意味では先入観にすぎません。
いま必要なのは、どんな制約にも、どんな知識にもとらわれずに、自由に、何でも、発想することです。多いほど発想への刺激となり、すぐれたものが見つかるチャンスがふえるはずです。
発言回数の多さは異質な発想のチャンスの出やすい機会をふやすことになるはずです。質より量は、発言機会の保証にもなるはずです。アイデアの量は、多ければ多いほどいい。それがいいアイデアに出会うための王道です。
④他人の発言への相乗りOK
これは、一番重要な原則です。これが、キャッチボール効果を高めるのに一番有効です。ポストイットの例は、いわば、相乗りの例と考えていいのです。
自分の限定された見方を崩すためには、異質な角度からの他人の発想に刺激され、「そういう見方があるのか」「それを、こういうふうにすれば、もっとよくなるのではないか」と、相手の発想を借りながら、あるいはそれ(の一部)と組み合わせながら、よりいいアイデアにつなげようと、ともかくアイデアと遊ぶゆとりが必要です。
聞くこと(聴くと訊くのふたつ)が、ここでは重要になります。ブレインストーミングは目的ではありません。ここで必要なのは、自分の中に、自分の気づかない異質さを見つけることだからです。
⑤自己激励と相互激励の雰囲気で
キャッチボール効果はその場の全員の関わり抜きには成立しません。メンバーは違いに影響しあい刺激しあう。ひとりが何かひらめいたとき、まわりはいいアイデアが出るようアドバイスや励まして、盛り上げていく。
「アイデアは、心の中にあるだけではだめ、表現されてはじめて、誤りも正せるし、新しい意味や可能性がつけ加えられる」。その通りでしょう。
③キャッチボール効果
大事なことは、ブレインストーミングもキャッチボールも目的ではないということです。キャッチボールを通して、自分の中に、発見を促すことです。「そうだった!」「そんなことがあった」「そう見ていいのか。とすれば、こうも考えられる」「自分にもこういうときがあった」「自分にもできる」等々。
自分の中で、当たり前としてきたこと、当たり前として見逃してきたこと、知っているつもりで疑いもしなかったこと、知ってるつもりで知らなかったことに、光を当てて、あるいは光の当て方を変えて、違った側面を見つけることです。そのためにキャッチボールをしているのです。
それは、言い換えれば、自分自身を異質化することといってもいいかもしれません。自分の知識、経験、スキル、ノウハウを異質化することです。自分では気づかなかったその価値を、発見することです。
そのために、人とキャッチボールする。人をコーチする、人とコミュニケーションする、人をカウンセリングする、人をコンサルティングする。異質性の交換は、すべてのキャッチボールの原則です。
相手が異質な、気づきもしなかったことを言ってくれることで、埋もれていた自分の回路を蘇らせることができます。そのとき、キャッチボールは、自分の発想のツールとなるのです。
④キャッチボールが発想の質と量を増大する
発想の本で、下図を見かけたことはないでしょうか。そして、「正方形がいくつあるか」と、設問しています。
エドガー・ハーディ『「2+2」を5にする発想』(講談社)
せっかくですから、「正方形がいくつあるか」。みなさんも考えてみてください。
いかがでしたか?まさか16などという答えで満足されなかったでしょうね。30?ですって?例によって、答は巻末にとありでは、確かに「30」と出ています。
しかし、ここまで読まれた読者なら、こういう発想は、間違っていると気づかれるはずです。答がひとつなら、知識に過ぎないのです。知識なら、学べば手に入れられる、知っている人に聞けば直ぐ手に入る、あるいは、先達が必ずどこかにいる、ということです。
たとえば、図表2-12を見て、ためらわず、こういう人がいるのです。
「ラインの交差したところは正方形ではないか」
それに、どう反応されるでしょうか。
「そんなばかな」
「それは禁じ手だ」
「そんなことがOKなら……」
実は、こういう自由に考える人が、必ずいるのです。
学生時代でも、クラスでよく、こういう意表をつく発想をする仲間がいなかったでしょうか。大概は、それを押しつぶすか、無視してこなかったでしょうか。
こういう発想を、生かすも殺すも、聞き手側の“聞く耳”次第なのです。こういう発想をする人がいるから、キャッチボールに効果があるのです。問題は、それを生かす耳を、聞く側が持っているかどうかだけなのです。
聞く耳があれば、そうかこの枠組みにこだわらなくてもいいのか、それなら、立体と考えればいい、あるいは、シートが重なっているのを上から見ていると考えてもいい、格子状のものと考えてもいい等々、次々と制約を破れるのは、自分の中のタブーを崩せば、それに反応するものを自分の中に必ず持っているからなのです。
いまの例もそうですが、発案ないし問題意識を提供した人のほうが、発想としては、あるいはアイデア力としてはすぐれていたかもしれません。しかし、大事なのは、それだけなら個人の発想から出られないということです。それだけでは、ひとつの面白いアイデアにとどまるところを、拡大し、広げていけるのは、それに聞く耳をもった人とのキャッチボールによってだということなのです。
発想を妨げるのは、人のせいではありません。発想は、自分の中に答を見つけることだとしますと、発想を妨げるものは、自分自身の中にこそあるのです。
- バラバラ化のツール~チェックリスト
- チェックリストを使いこなして発想力アップ
①チェックリストを使ってみる
チェックリストを、具体的に例にあげながら、その使い方に触れておきます。発想の基本スキルにあるチェックリストの中から、オズボーンのチェックリストを取り上げますと、次の通りです。
・他に利用できないか/現在のままで新しい用途はないか/少し変えて他の利用法はないか
・他からアイデアが借りられないか/一部借りたら/これに似たものはないか/他に似たアイデアはないか/過去にこれと似たものはないか/何かマネできるものはないか/他に当て嵌められないか/誰のマネができるか
・変更したらどうか/新しく変えてみたら/曲げたらどうか、形を変えたら/意味、色彩、動作、音、香り、形式、包装、方法を変えてみたら/その他の変更をしてみたら
・大きく(あるいは多く)したら//何か加えたら/もっと時間をかけたら/回数(頻度)を多くしたら/もっと強くしたら/もっと高くしたら/もっと長くしたら/もっと厚くしたら/もっと速くしたら/もっと多くしたら/馬鹿でかくしたら/最大にしたら/誇張したら /他の価値を加えたら/他の成分を加えたら/倍にしたら/掛け合わせたら
・小さくしたらどうか/何か減らしたら/もっと小さくしたら/もっと濃縮(凝縮)したら/小型にしたら/もっと軽くしたら/もっと低くしたら/もっと遅くしたら/やめたら/少なくしたら/分割したら/ひかえめにしたら
・代用したらどうか/誰かほかの人にやらせたら/何かほかのものにしたら/ほかの成分にしたら/ほかの材料にしたら/ ほかの場所にしたら/ほかのやり方にしたら
・入れ替えたらどうか/構成分子を入れ替えたら/タイミングを替えたら/他の型に替えたら/向きを替えたら/上下を替えたら/他のレイアウトにしたら/他の順序にしたら/原因と結果を入れ替えたら/ペースを変えたら/日程を変えたら
・反対にしたらどうか/積極(肯定)と消極(否定)を変えたら/反対にしたら/裏返しにしたら/後ろ向きにしたら/逆さまにしたら/役割を逆にしたら/立場を変えたら/主客を転倒したら/逆に言ったら
・結合したらどうか/混合、合成、詰め合わせ、アンサンブルにしたら/組みにしたら/目的を結合したら/アイデアを結合したら
これを発想のツールとして、下図を例に、みなさんも、実地に考えてみてください。
いかがでしたか?これまで以上にでましたか?それとも出しにくかったですか?
もし、チェックリストがあれば、いくつでもアイデアが出ると期待していた方はがっかりされたことだと思います。ひょっとすると、以前より出なかった可能性があります。
それは、発想技法というイメージに期待して、受動的になったからだと思います。以前のとき、自分で必死に考えようとされたのに比較すると、受身に回ったのではありませんか?
②使い方で変わるチェックリスト効果
チェックリストを発想のツールに使うというのは、その項目と照らし合わせれば、自動的にアイデアがでるというものではありません。そんなところてんを押し出すような便利なツールがあるはずはありません。
チェックリストを使うときも、その他の発想技法を使うときもそうですが、使う側の主体的な姿勢が問われているのです。
どういうことかといいますと、チェックリストの場合、たとえば「他に利用できないか」というチェック項目を何も考えず読み流していっても、決してアイデアにつながることはないのです。必要なのは、そのチェック項目を、自分の狭い発想への刺激として、それとキャッチボールすることなのです。
オズボーンのチェックリストを例にとって、具体的に考えてみます。
たとえば、「変更したらどうか」の項にあります、「曲げたらどうか、形を変えたら」という項目を例にとってみます。これをただ流すのではなく、
曲げてこういうカタチになったというのもある、
ここからいろいろな方向に曲げてみるというのもある、
カタチを曲げて変えるのもある、
カタチを変えてこういうふうに見えるもの、というのもある
等々と、その項目を切り口にして、あれこれと可能性を考えることなのです。それは、チェック項目を刺激に、自分自身の記憶と知識とのキャッチボールをするということなのです。チェック項目をひとつの外部情報として、自分自身を刺激するように、あれこれキャッチボールしてみる素材とするということです。
情報にするとは、その言葉を鵜呑みにするのではなく、その言葉の意味、イメージ、条件等々を様々に問い直して、様々に考える素材にする、という意味です。
そう考えていくと、曲げてこういうカタチになるものとして、
ゴム風船を無理やり折り曲げて重ねたところ
パン生地を丸めて半分のところに切れ目を入れたところ
練ったそば粉を曲げて重ねたところ
針金を曲げて作った知恵の輪
ワッフルのケーキを曲げて重ねたところあるいは、カタチを変えてこうなったものとして、
半分破れた金魚すくいの紙
ハンバーガーのパンに包丁で切れ目を入れたところ
かかとを小さくしたダイエット用のスリッパ
切れ目を入れたスイカ
半分残ったデコレーションケーキ等々と、ひとつの項目から、いくつでも発想の種が出てくるはずです。たとえば、
「何か加えたら」
「もっと多くしたら」
「馬鹿でかくしたら」
「最大にしたら」
「もっと高くしたら」
「もっと長くしたら」
「もっと厚くしたら」といった、大きさに関わる項目については、既に第1章で試みたのと同じことになりますので、この項目とのキャッチボールの仕方だけ例をあげてみますと、たとえば、何か加えるというのは、今から何かをしようとしているところ、し忘れているところ、何かを加えると完成する、何かをし忘れたので追加しようとする等々が考えられるはずです。
たとえば、「馬鹿でかくしたら」という項目とキャッチボールすると、馬鹿でかいとはどのくらいか、ボールと比較して大きいという意味か、ごま粒と比較して大きいという意味かという、これ自体の基準量をあれこれ考えるということがあります。また、それから何処まで大きくするのか、東京ドームか、人工衛星か、地球か、太陽か、星雲か等々といった、大きくする比例度の感覚もあるでしょう。
さらには、馬鹿でかくする、そのいまのものを何処に置くかで、その大きさ比は変わってきます。たとえば、スリッパに見えたのを例にあげたとしますと、
大人のスリッパ
といえば、子供のスリッパを基準においていることになります。
相撲取りのスリッパ
というと、大人のスリッパを基準においていることになります。それを具体化していくと、
小錦のスリッパ
ジャイアント馬場のスリッパというふうに挙げていくことができます。たとえば、
「もっと時間をかけたら」
を例にとってみますと、
ここからスタートして何らかのカタチになるところ、
時間を経てこうなってしまったところ、
もう少し時間があればもっと違ったものになるのに時間がなくてこうなってしまった、
等々が想定できます。とすると。
毛糸を丸く巻き始めたところ
止まりかけているコマあるいは回り始めたコマ
望遠鏡を横切った飛行機雲
割れた皿を合わせて接着しようと試みているところ
もっと模様をつけるつもりが忘れて一本棒の切れ目しかないフランスパン
ひび割れて亀裂の入った鏡餅等々が上げられるはずです。
発想は発想する土俵が具体的であればあるほど、具体的な連想を生み出しやすいのです。その土俵は、何かを思いつく手がかりを、チェック項目が与えてくれていると考えればいいのです。
「他の価値を加えたら」
も、同じように考えると、たとえば、価値を、いい価値悪い価値、新しい意味古い意味、思い出という情緒、不安という情緒等々と広げていけます。また、「他の成分を加えたら」
も、線を加える、色を加える、質を加える、肌あいを加える、臭いを加える、香りを加える等々とキャッチボールすることで、「合併で消された社章」とか「お香をたいているところ」「便器」といったイメージを浮かべやすくなるはずです。
このあたりで、止めますが、すべての項目とキャッチボールすれば、必ず何かが出てくるというわけではありません。が、少なくとも、固まっていた脳のネットワークに新しい回路が浮かんだり、忘れていた回路が再生したりする手がかりにはなるはずです。
ブレインストーミングと同様、チェックリストも、それを刺激として、自分の中に、自分の異質さを発見する条件づけ、として使えるはずなのです。
- バラバラ化ツールを使って発想量のアップを確かめてみよう
以上、バラバラ化の4つの切り口とバラバラ化のツールである、ブレインストーミングとチェックリストによる発想の仕方を、具体的に例示してきました。ここで、それが、どれだけ効果的か、ご自分なりに確かめてください。
左の「円と直径」図は、既に散々試しましたが、それでなおどのくらい出せるかを試してみていただくのも一興でしょう。ツールとスキルを整理した後、五百以上になると豪語した人もいたくらいですから、試してみる価値はあります。
この「円と直径」図をウォームアップとしてさらに、右図で、どれくらい発想数がアップされられるかを試してください。
発想数アップの試みとしては、次のようなことを、順次試してほしいと思います。
①まず、第1章で出した数の確認
②バラバラ化の4つのスキルを意識して、発想してみる
③オズボーンのチェックリストのチェック項目とキャッチボールしながら発想する
④発想技法ハンドブックの他のチェックリストを取り上げ、そのチェック項目と、③と同じように、キャッチボールして発想してみる
⑤ブレインストーミングの要領で、職場の誰か、あるいは友人、家族と一緒に、図を見ながら、フリーに出し合ってみる
このすべてを試みてもなお、以前より、格段に発想数がアップさせられなかったという場合は、まずそんなことはありえませんが、発想数を出すためのスキルを、再度きちんとおさらいし、各項目の意味とあれこれキャッチボールしながら、試み直してほしいと思います。必ず数は出せるはずです。(了)
【右図の発想例】
たとえば、前にも挙げましたが、皿の上シリーズとして、皿の上のリンゴ4つ、皿の上のみかん4つ、皿の上のカキ4つ、皿の上の桃4つ、皿の上の瓜4つ、皿の上のオレンジ等々と羅列できるし、上に乗っているものを、果物や卵(それも鶉からダチョウまで)からごま、塩粒といった極小化することも、あるいは、巨大化して遊園地の回転カップへもつなげていけるはずです。
テーブルの上へと転ずれば、テーブルの上のコップ、テーブルの上の茶碗、テーブルの上のタンブラー、テーブルの上の湯呑、テーブルの上のお椀、テーブルの上の丼、テーブルの上の皿、テーブルの上の猪口等々とテーブルの上シリーズとして、食器を鍋や釜、更に果物や球にも置き換えていけるはずです。
さらに円を土管や井戸、池と置き換えて、土管の中シリーズ、井戸の中シリーズ、池の中シリーズと考えていきますと、土管にのぞくケーブル、土管にのぞく水道管・下水管や、井戸に浮かんだ果物シリーズになりますし、池に浮いたシリーズにすれば、池に浮いた空き缶4つ、池に浮いたタイヤ4つ、池に浮いた竹筒4つ、池に浮いたゴムボール4つ、池に浮いた野球ボール4つ、池に浮いたバレーボール4つ、池に浮いた空き壜4つ等々、そこに浮かんでいるいろいろなモノに変えられます。
井戸や池を湖に海に宇宙へと広げていけば、4つの丸は島や惑星や島宇宙になりますし、口の中と見立てれば、口の中シリーズとして、歯や飴玉とみなせます。中の円を凸部ではなく、凹部と見なせば、ボタン穴や車のホイールへと広がるでしょう。
そこまでの発想が上からの視点と自覚できれば、同じものを下から見て(それは引っくり返したのと同じ)、脚シリーズとして、丸テーブルの脚、丸椅子の脚、豚の脚、牛の脚、鹿の脚等々、机・テーブルから4足動物、更にはUFOといった別のシリーズへ発展させられます。
-
こうすれば企画はカタチになる
企画に何を見るか~企画には何が必要か
まず,あなたは上司か先輩だとしましょう。部下や後輩から企画が上がってきたとします。あなたなら,どんな点をチェックしますか?
どうですか。アイデアのよさでしょうか?企画書の読みやすさでしょうか?それともわかりやすさでしょうか?斬新さでしょうか?ボリュームでしょうか?
少なくとも,企画は,アイデアをひけらかしたり,企画することや企画書を書くことが目的ではありません。それは,
存在しない新しい商品やサービスを実現する,
現状の不都合やトラブルが起きない仕組みや仕掛けをつくる,
誰も到達したことのない目標を達成する,
等々のために立てるもののはずです。企画がそれを実現して見せなければ,企画した意味がありません。
当然,それ以外にも手段はあるはずです。企画は,他の手段よりも優れていることを示さなくてはならないはずです。それを構造化したのが,下図です。企画は,何らかの目的達成のための,一手段なのです。
当然,企画をチェックするのは,次の3点です
①それによって何が達成(実現・解決)されているか(されるか)
②それは,どんな点で新しいのか(いままでないものか,それともいままであるものとどこが違うのか)
③それは,どこまで実現可能なのか(実現できるメドが,きちんと示されているか)
第1は,企画は,それによって「何を解決(実現)しようとしたか」「何が解決(実現)できたか」が明確でなくてはなりません。それが企画を立てる目的だからです。企画は,目的実現(達成)のための手段(のひとつ)に過ぎないのです。その意味では,何のために(何を解決するために)それを立てたかの目的を明確にしていなくてはならないし,である以上,それを実現できる案を示すものでなくてはならないのです。
第2は,企画にするに足る“新しさ”が必要です。
いくら,目的が明確で,実現プランがクリアでも,既に誰かが立てたもの,既にどこかで実行しているものなら,企画には値しません。どんなに目的が明確でも,それがなければ,ひとりよがりに終わるだけなのです。
第3は,こうすれば,実現できるという,実行プランニングを示していなくてはなりません。企画は,立てることが目的でないということは,その目的を実現できなくてはなりません。それがが,空手形でない証拠を,きちんとしたアクションプランのカタチで示さなくてはならないのです。企画の「画」の部分です。実現プランのない企画は,「画」のない,夢倒れの「企」のみということになるのです。
以上の3点から,企画のポイントが,下図のように絞られるはずです。
【企画の結果と企画の立案】
企画のどこを見るか(アウトプットとしての企画)
企画を立てるポイントは何か(インプットとしての企画)
①何が解決(達成)されているか
①何を解決しようとするのか(絞り込み)
②どこが他と違うのか(新しいのか)
②どう(他と違う)解決をしてみせるのか
③どうこまで実現に現実味があるのか
②どう(他と違う)解決をしてみせるのか
企画に当って何をすべきか
では,以上を前提に,実際に企画を立ててみるこどうなるでしょうか?
たとえば,毎年毎年不評続きの「忘年会」の幹事にさせられた若手社員が,「いつもの忘年会はちっとも面白くない」との問題意識で忘年会を企画するという状況設定で,考えてみましょう。
ご自分の職場で忘年会を企画しなければならなくなったとして,あなたなら,まず何から着手しますか? ちょっと考えてみてください。
どうでしたか?去年何をしたかを調べようとしましたか?それとも,去年の参加者に希望ないし不満を情報収集しましたか?あるいは,他の職場の成功例を取材にいきますか?
これは上司や顧客に企画を依頼されたのと同じ状況です。そのとき,まず何をすべきなのでしょうか?これは業務命令を受けたときと同じだと思います。
通常,次の3点確認しなくてはなりません。
第1は,その目的は何か,です。つまり忘年会は何のために開くのかです。
第2は,その期待成果は何か,です。アウトプットとしてどういうものを期待しているか,です。これは目的達成の程度といってもよいでしょう。
第3は,その期限はいつかまでか,です。
企画も同じです。特に依頼された場合,その依頼主が,何のために,何を求めているかを確認しないで企画することは,企画が期待はずれにならないための最低限の前提です。
忘年会のように,年中行事のように実施している場合,ただ何となく引き継がれ,何となく企画し,何となく実施しているというものの企画が一番難しいのは,それをやることが前提になっていることなのです。
しかし,本当にやる必要があるのか,必要がないなら別ですが,必要があるとしたら,その目的を改めて確認しなおさなくてはなりません。でなくては,何時までたっても,本来の目的とは別のカタチで実施されつづけることになるからです。
これは,企画を立てるとき,最も誤りやすいことでもあります。企画を依頼されると,「企画を立てる」ことを前提にものを考えてしまうのです。たとえば,「忘年会」も,それをやめる,一律ではなく個別パーティ方式にする等々,「忘年会」という概念とは全く別のものに変えるという方が,その目的にかなうかもしれないからです。
忘年会の企画を依頼されたとき,どう考えるかを構造化してみたのが,下図です。
「~について企画してくれないか」と言われて,そこからいきなり企画の中身に入っても,それで何を達成しようとするかが明確でなければ,企画の評価のしようがないのです。そういうのを,企画ごっこと呼びます。
だから,まず,その目的を確認するのです。たとえば,「若い人が参加したがるものにしてほしい」と言われたとします。でも,それだけでもだめなのです。
なぜなら,現実には「若い人が参加したがるものにしてほしい」ということを解決するだけで,すべてがクリアになることはめったにありません。それを目的と考えた背景が必ずあるはずなのです。それは,依頼者が向き合っている現状です。それを解決したくて,企画依頼があったと考えるべきなのです。
たとえば,その現状が,下図のようになっていたとしましよう。
とすると,依頼した側が考えた「若い人が参加したがらない」ということを解決すればいいのかどうかは,こうした現状と向き合い,改めて「何が問題なのか」を洗い出し,本当は,何を解決すればいいのかを検討し直すほかはないのです。
忘年会企画の意味を整理し直してみたのが,下図です。
-
企画づくりの基本スタンス~誰のために企画するのか
企画は,通常自分の「こんなものがあればいい」という関心や「こうしたい」という問題意識だけで立ち上げることは少ないと思います。
たとえば,よくあるのは,
①上司や関係者から「~について企画してくれないか」といった指示や要請,要望
②関係部署や出先から「~について企画にならないか」といった依頼や問い合わせ,要望
③部下や後輩から「~について企画したいのだが……」といった相談や申し入れ,依頼
④客先やユーザー等から「~について企画はないのか」といった要求や問い合わせ,要請
⑤顧客からの要望から「~について企画してみてはどうか」といった問題意識
⑥自分自身の仕事上で「~について企画にならないか」といった問題意識や思いつき
上司から,「~について企画してくれないか」という指示があったとき,「何をすればいいか」を考えるため,通常は「よそはどうしている」と,横並びで同業他社,他省庁,他部署,他業界,他国はどうしていると考えるところから,はじめるのではないでしょうか?
しかし,そういう発想は,本コースでは外して考えようと思います。もちろん,そういう企画づくりが無意味とはいいません。
たとえば,温泉饅頭。どの温泉地にもあるお土産ですが,最初の発案者は,自分の温泉地の何かを解決しようとしてはじめたはずなのです。たとえば,いい土産ものがない,名産がない,客を呼べる名物がない等々。しかし,それを真似た温泉地が,うちもと真似ただけなのだが,結果として,自分たちの名産がないという問題を解決していたとすれば,それでも企画であることには変わりがないからです。
しかし,ここでは,オーソドックスに,独自にいいアイデアを考えていくというプロセスを中心に企画づくりを考えてみたいと思います。
その意味では,企画づくりは,
①企画は,立てることが目的ではないはずである
②その企画を立てて,何を実現したいのか(目的)がはっきりしていなければならない
③それがはっきりしなくてはアイデアは面白さや成功例を拾い集めることになる
④目的がはっきりしていなくては,その企画が適切だったかどうかの評価ができない
ということなのです。まず,企画は,「何を実現(達成)するために立てるのか」(目的),現実をどう動かそうとするのか,の確認からはじめなくてはなりません。
自分の企画でなければ,その依頼主のそれによって実現したいことを確認することが,きかく目的のすりあわせになるはずなのです。
「このままでいいのか」という“現状への問い”(これが問題意識)から企画は始まるのですが,その“問い”は自分自身の問いだけとは限りません。上司,顧客・ユーザー,関係者,部下(後輩)等々の“問い”かもしれません。しかし,それを明確な企画(の達成すべき)目的と定めたときから企画は始まるはずなのです。
-
自主企画と依頼企画の違い
では,依頼された場合と自分の問題意識から企画にする場合と,どこがちがうのでしょうか?ちょっと考えてみてください。
依頼された企画も,その趣旨を実現しなくては依頼に答えることになりません。そうすると,その依頼「~について企画して欲しい」の依頼主旨によって,何を達成したいのかを確認せざるを得ません。それをさかのぼることは,依頼主(個人とは限りませんが)の問題意識を明確にすることになるはずです。
依頼企画も自主企画も,そのアプローチの仕方は違っているようにみえますが,何を解決すべく企画を立てるかを明らかにするために,そもそもの問題意識を明確にするところから出発する必要があるのです。
たとえば,依頼企画の場合,図表1-7のように,その目的(その企画によって何を解決しようとするのか)を探ると,依頼主の問題意識,何を問題としているかを明確にしなくてはなりません。更には,忘年会の例と同様,その問題の背景までさかのぼらなくてはならないでしょう。それをすることで,当初の「~について」という企画依頼でも,その目的を実現するためには,依頼とは別の企画の方がふさわしいことに気づくこともあるのです。この掘り下げは,下図の自主企画の掘り下げと同じはずです。
しかし,自主企画でも,具体的な問題からスタートするよりは,何となくぼんやりとした関心や問題意識から企画したいことを考え,それによって実現したいことは何かとさかのぼっていくということのほうが多いのではないでしょうか?そのとき,結局依頼企画を立てる場合と同じことをしているのです。
下図は,前の依頼企画の図を一部手直ししただけです。結局,企画の出発点は,それが自分であれ,他の誰の発案であれ,「~についての企画」という要請を鵜呑みにするのではなく,それは何を実現(解決)するためなのかを絞り込むことからはじまる,ということなのです。
【ぼんやりした企画したいものから問題を絞り込む流れ】
-
企画づくりの流れ
結局,企画づくりは,
①はじめから,現状への問題意識からスタートとして,企画を立てていく場合,
②顧客や上司の「~についての企画」から企画し始めたが,実質まったく別の規格を作らざるをえないことがわかった場合,
③自分がぼんやり「~について企画」と思ってスタートとしたものが,実質その目的にさかのぼったところ,全く別の企画を必要とした場合,
のいずれの場合も,何を本当に解決するのかを確かめようとすると,図表1-9のように,問題意識を洗い出さなくてはならないのです。
それぞれ企画のスタートの仕方は違っても,結果として,図表1-10の点線で囲んだ部分の企画づくりの流れとなっていくことを確認していただきたいと思います。
以下で,順次考えていく企画づくりの流れは,自分のぼんやりした企画から,真の問題を明確にし,それを解決するために何をしていくかを考えていく,下図の赤い破線で囲んだ部分の流れを取ります。
【ぼんやりした企画したいものから問題を絞り込む流れ】
その流れを一覧化すると,下図になります。忘年会を例に,本コースで考える企画づくりの流れに沿って,企画づくりをフロー化したものです。このフローと構造が,ここで考えている“企画づくりの筋”となります。
これをフレームにすれば,下図になります。アイデアの是非や用語,また各細部の不明点はそのままに,どういうふうに企画していくかだけを眺めておいてください。
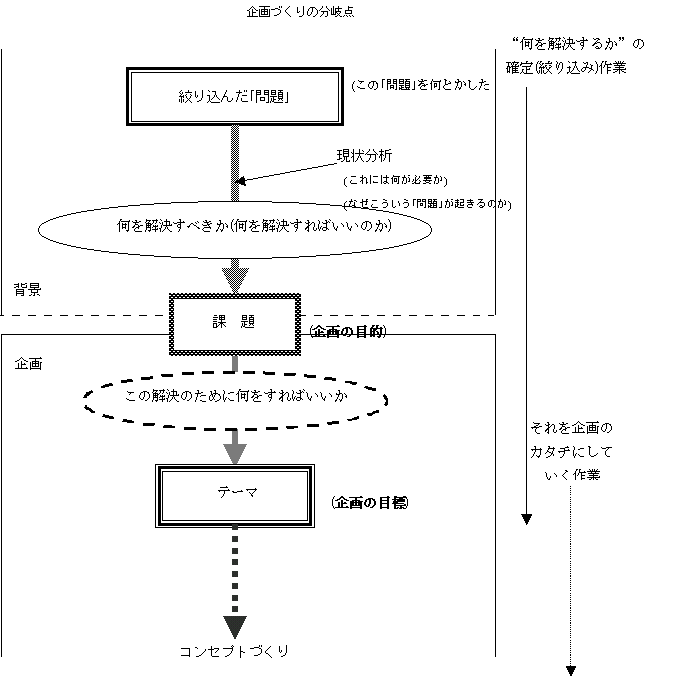
-
企画づくりは仮説の連続です
下図は,一見ひとつながりでしかないように見える,先ほどの企画づくりのフローの流れひとつひとつが,仮説のつながりでしかないことを示しています。
つまり,「若い人が参加したがらない」という問題を選び取ったところから,企画が始まっているのであり,もし別の,「宴会だけの忘年会を嫌っている」「他社はもっと面白い」を取り上げたとしたら,また別の流れになるはずなのです。
企画というものが,結局自分の判断で切り取った一連の流れであること,したがって,別の選択をすれば,全く別の企画の流れになり,異なる案になるのです。
-
コツさえわかれば企画にできる
さて,まず,ご自分が企画してみたいことを考えてみてください。
企画とは何か,とか企画に何か条件があるのか等々と,難しいことをを考える前に,みなさまの心に漠然とある企画イメージのままで結構です。実現したいこと,達成したいこと,解決したいこと,何でも結構です。必ずしもご自分の問題意識でなく,上司から指示されている企画でもかまいません。いくつか,ランダムに挙げてみてください。
いかがでしたか?何か思いつきましたか?たとえば,こういうのを思いついたとしましょう。
「口に入れたら一瞬で溶けるチョコレート」
別に食品メーカーの社員だけが,企画を立てるとはかぎりません。あるいは,
「(昔上司に言われた)必要情報をさっと取り出せる,ファイリング」
というのでもいいでしょう。あるいは,
「自分の恋人を喜ばせる最適プレゼント探しツール」
というのでもいいでしょう。どれかひとつ,ぼんやりと企画したいと思っていることを仮「テーマ」として絞ってください。ここで仮としたのは,あくまで,ぼんやりと企画したいと思っていることに過ぎないからです。これを詰めていく中で,企画テーマを絞っていくことになります。
そこで,下図のフォーマットを参考に,次の点を考えてみてください。
①仮テーマによって「実現できる」のは何か→これが企画の実現すべきこと
②その背景となることにどんなことがあるのか→他に問題とすべきことはないか
③①の問題を実現するための手段は他にないか→これが企画の競争相手
④最初に企画しようと思った仮企画の見直し→テーマや焦点を練り直す
⑤最初に企画しようと思った仮企画より良いものが見つかったか?→これが本企画
さて、どうでしょうか?④⑤に基づいて、決まった企画したいことを具体化するには何をすればよいのか、これが企画テーマになりますが、これはまだ先のことです。
ここで大事なのは、はじめにぼんやりと企画したいと思ったことは、それによって実現したい目的を実現するのにふさわしかったでしょうか?そのままでいけるにしろ、いけないにしろ、目的を考えることで、企画したい仮「テーマ」が少なくとも、奥行きが深まったはずです。
企画は立てることが目的ではないとはこのことです。企画づくりの大事なポイントですので、もう少しここを詰めておきたいと思います。
前に挙げた,
「口に入れたら一瞬で溶けるチョコレート」
という思い付きを企画に絞っていく例を,下図に例示して見ました。
-
企画したいことを構造化する
まずは、ご自分が企画したいと思ったことを、上記で挙げた、
①仮テーマによって「実現できる」のは何か→これが企画の実現すべきこと
②それを実現するための手段は他にないか→これが企画の競争相手
③最初に企画しようと思った仮企画の見直し→テーマや焦点を練り直す
④最初に企画しようと思った仮企画より良いものが見つかったか?→これが本企画
の4点について、下図にのっとって、ご自分が何を企画したいのかを構造化にしてみて下さい。
それを一覧化すると次のように整理できるはずです。これが,今後の企画づくりの骨格です。企画しなおす場合は,ここへ立ち戻る必要があります。
あなたの企画したいことの構造
企画したいと思っていること
それによって解決(実現)したいこと(目的)
その背景となること(現状)
目的から見てふさわしい別の企画はあるか
企画評価のポイントは、そのまま企画づくりのポイントになります。
①それによって何が達成(実現・解決)されているか(されるか)
②それは、どんな点で新しいのか(いままでないものか、それともいままであるものとどこが違うのか)
③それは、どこまで実現可能なのか(実現できるメドが、きちんと示されているか)
このためには、何のために企画を立てるのか、つまり何を実現するために企画を立てるのかを明確にすることからはじめなくてはなりません。
まずは、ご自分がぼんやりと「企画したい」と思ったことを、上表で、再度整理し直していただきたいと思います。
企画づくりの全体像については,『企画の立て方・作り方』をご覧ください。-
企画づくりの基本スタンス
◇企画づくりでは,
①企画は,立てることが目的ではない
②その企画を立てて,何を実現したいのかがはっきりしていなければならない
③それがはっきりしなくてはアイデアは面白さや成功例を拾い集めることになる
④目的がはっきりしていなくては,その企画が適切だったかどうかの評価ができない
のである。まず,企画は,「何を実現(達成)するために立てるのか」の確認からはじめなくてはならない。
◇依頼企画も自主企画も,そのアプローチの仕方(迫り方)は違うが,何を解決するために企画を立てるかを明確にするところから出発することに変わりはない。
依頼されて企画する場合
◇依頼企画の場合,いきなり,その企画のために何をしたら言いかと,企画アイデア(それは企画実現の手段)に走ると,依頼者の要請からずれることがままある。それは,企画者自身も,その意図や意味を十分わかっていないことからきている。その場合,その目的(その企画によって何を解決しようとするのか)を探ることで,その解決には,依頼の考えている「企画」とは別の企画の方がふさわしいことに気づくことがある。その目的→テーマの掘り下げは,自主企画の掘り下げと同じになる。
-
自主的に企画していく場合
◇自主企画は,①上司からの指示や顧客からの要請といったカタチで始まる場合と,②自分で,ぼんやり企画したいと思っていることを,企画のテーマとして確定していく場合と,ふたつある。整理すれば,次のように,
①現状で感じた問題そのものの解決をはかるために,何をすればいいのかを詰めて企画へとまとめ上げていく,【ゼロから企画立をち上げるタイプ】
②自分の企画テーマ(企画したいこと)を企画テーマに絞り込んでいくもの【ぼんやりした企画を明確に絞り直していくタイプ】
のふたつのタイプになる。
-
ゼロから企画を立ち上げるタイプ~企画を問題からまとめ上げていく
これは,現状の中で気づいたり,気になった問題を,どうしたら解決できるか,というカタチで,問題の絞込み→その解決のために何をするか→その解決のために何をするか,と企画をゼロから具体化していくことになる。
【問題意識からスタートしてゼロから企画を立ち上げるタイプの場合の構造】
-
企画テーマを絞り直していくタイプ~企画にしたいものが漠然としてあるものを純化していく
この企画を立てるときは,いつもの手慣れた自分の仕事エリアや専門領域であり,どんなものが企画になるか,どこに企画の種があるか等々,企画づくりに慣れや既視感があり,あらためて目的や背景を考えることがない。しかしどんな企画づくりも,その目的から外れては,企画としての成功はない。これは,改めて,企画づくりの目的や背景を再確認し,いわば初心に立ち返って,企画したいこと→その目的(その企画で何を解決ないし実現したいのか)→その背景となること(時代,ニーズ等々)と,企画の意図を明確にし,その意図実現の方法を新たに検証し直し,企画したいことをピンポイントのテーマに絞り直して明確にしていく。ある意味で,通常当該企画領域の仕事をしている人にとっては,当然これは企画になるという勘が,ベテランであるほど働くはずである。そのとき,あらにためて自分の企画を,いままでの惰性や慣れではなく,改めて自分の問題意識を解決するのに,本当にそれで本当にいいのかを検討し直していく,企画テーマの絞り直し型である。これは依頼企画と明確化していくのと似た作業になる。
【自分がぼんやり「~について企画」と思ってスタートとしたものが,目的をさかのぼったところ,全く別の企画を必要とした場合の構造
】
【ぼんやり企画したいものからテーマを絞り直す型の自主企画の構造】
◇いずれのアプローチも,自分が何を問題にしているかを人に説明できなくては,その企画は人と一緒には企画づくりができない。それは,自分一人の問題意識から始まったときでも,人の依頼から始まったときでも,協働作業として企画づくりを進めようとすると,その大元の現状の確認から始めて,自分が何を問題としているか,その人は何を問題としているか,を一緒になって確認し,その現状を一緒になって向き合うことなしには,誰にとっても,自分の企画とはならない。自分の企画とならないところで,自分の発想が生まれてくることはない。自分の発想が生まれなくて,自分が乗れる企画にはならない。自分の乗れない企画に,いったい誰が乗ってくれるだろうか。
◇要は,自分の企画であれ,上司に依頼された企画であれ,顧客やユーザーに依頼された企画であれ,自分が自分の仕事の現状で,自分の問題に向き合わなくては企画にならないように,上司やユーザーの向き合う現状に一緒に向き合い,同じ問題を問題にし,それを解決しようとしなければ,企画の目的のない企画であり,そう言うプロセスを経て,自分自身の企画とすることができる。
-
ぼんやり企画したいことからテーマを絞る~何を実現したいのかを明確にする
たとえば,ぼんやり企画したいことがある場合,そのテーマの絞り方には3つのタイプがある。
①企画したいと思ったことがそのままテーマとして確定できる場合
②テーマの目的を確認することで,テーマが少し変わる場合
③企画テーマが更に絞れる場合
いずれの場合も,次のをチェックしながら,本当にこの企画で実現したいのは何かを明確にしていく必要がある。
①企画したいと思ったことによって,何が達成されるのか,何が実現できるのか。場合によってはその目的となる問題の背景までさかのぼることで,現実の何を動かせるかを絞ることで,目的が明確になる。
②それは,企画したいことの真の目的になっているか。違っている場合,問題の背景となっている現状に立ち戻らざるをえない。当然問題が別の場合は,企画そのものが変わってくる可能性がある。
③目的がそのままでも,企画したいと思ったことが,その解決になっているかどうか。その目的からみて,当初仮に企画したいと思ったことは,書き直したり,別の企画にしなおさなくてもいいか。
④企画したいと思ったことは,以上の結果から,何をすべきかが明確なものになったかどうか
企画づくりの全体像については,『企画の立て方・作り方』をご覧ください。