![]()
�y�S�̊�{�X�L���z
������
�O���[�s���O
�g�ݍ��킹
�A�i���W�[
![]()
���u������v�̈Ӗ�
���܂���J�^�`�C���܂���Ӗ��C���܂�������C���܂���\���C���܂���ʒu�W�C���܂��闬�ꓙ�X������C���̒�����C�V�����W�Â���������
���u������v�
�c���[�^�̕����@��������(�@�\�����C�ړI�E��i)�C��������(�����敪)
�t���[�^�����@�@����̃p�^�[��(���n��C���ʊW�C�N���]��)
�z�u�^�����@�@�ʒu�W�C�z�u�W���X�p�[�X�y�N�e�B�u(���ߖ@)�̊W
�\���^�����@�@�@�g���W�C���i�\�����X���̓I�W
�^�����@�@�@�T�v�Q�g�C�q�g�E���m�E�J�l
�W�����N�^�����@�V���b�t���C�s�[�X�։��
���u������v�̃p�^�[����
�@�E�n���}�i�c���[�j��ɐݖ���u���[�N�_�E������
�S�̍\��������ɕ�������ƁC�I�������o�閈�ɁC�B�����͌������C
��̉��E������ւƍi���Ă����B
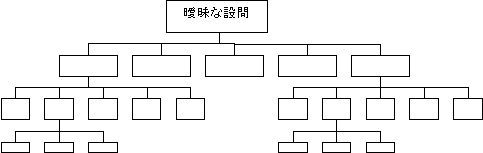
�@�E�ړI����i�A���Őݖ���u���[�N�_�E������
�u�S�̍\��������ɍL���Ă����v���@�́C�ړI�i�ڕW�j�̂��߂̎�i�͉����C���̎�i�i���ʖڕW�j�̂��߂̎�i�͂Ȃ����C�ƖړI����i�̘A���Ƃ��āC�ݖ�̃l�b�g���[�N��g�ݗ��Ă邱�Ƃ��ł���i����́C�g�D�E�V�X�e���̂悤�ȃR�g���邢�͏��i�̂悤�ȃ��m�̓����i�����E�@�\�j�̏ꍇ�͖ړI���@�\�ɒu�������Ă݂�j�B�@
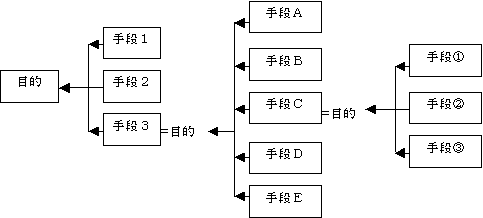
�E���������ʘA���Őݖ���u���C�N�_�E������
�@�ړI����i�A���̐ݖ���C�ړI�����ʂɁC��i�������ɒu��������C���������ʂ̘A���Ƃ��Đݖ��g�ݗ��Ē������Ƃ��ł���
�E��ґ���̑I�����A���Őݖ���u���C�N�_�E������
�@�@�A�B�قǐݖ₪���m�łȂ��C���R�Ƃ����B���Ȗ��̒��ŁC���ӂ���j�S�ւƁC���̏œ_���i���Ă����Ƃ��C��ґ���ɂ���āC�B�������������������Ȃ���C�i�荞��ł����B�Ⴆ�C���E�́������́��ƊE�́��Г��́��E��̏́������o�[�̏́c�c�Ƃ����悤�ɁC�L��������ʂ̏ɁC�����u���C�N�_�E�����Ă����ݖ�̎d��������B�܂��C�Ⴆ�C����l�̐E�Ƃ��������Ă邽�߂ɁC�ݖ�𗧂ĂĂ����ɂ́C���c���ߐl���������������Ԃ������[�J�[���T�[�r�X�����d�����傩�y���Z�������c�c�ƁC�O���珇����ґ��ꎮ�ɍi��������Ă����Ƃ������̂�����B���ăe���r�́u��\�̔��v�Ƃ����ԑg�ŁC�u����͓����ł��v�Ƃ����������C20�̎���œ��ɂ��ǂ���Ƃ������̂�����C����͓����ł����l�ł����H�����������Ă��܂����H�����݂ł����H�c�c�ƁC��ґ���̎����20��J��Ԃ��Ă����B����C�Q�Q�O (1,048,576�j���̂P�ɍו������Ă������Ƃł���(�Ⴆ�C�C�G�X�^�m�[�̑I���P����P�r�b�g�Ƃ���ƁC�T��ŁC�Q�T��32�ʂ�ɂȂ�)�
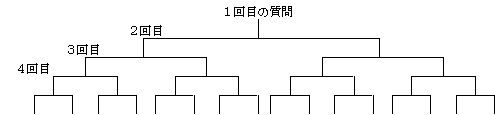
![]()
�@���O���[�s���O�̖ڎw������
�o���o���ɂȂ������̒��ɁC�Ӗ��̂���u�Ȃ���v�i���˒����̊�j�����邱�Ƃɂ���āC�o���o���́u�n�v�Ɂu�}�v�������o���B
�@���O���[�s���O�̊�͋��ʓ_
���ʓ_�̔����|�������C�o���o���̏�狤�ʐ������C�V���ȊW�Â��������o���B
���ʓ_�͌�����̂ł͂Ȃ��n��o���|�u�X���A�q���̎q�̒藝�v�i�n�ӌd�j�B�Q�H�̔����̋��ʓ_�Ɣ����ƃA�q���̋��ʓ_�́C�q��̐��Ŕ�r������蓯���ł���B
�@�����ʓ_�����邽�߂̃`�F�b�N���X�g
�@�܂��ו���������Ȃ��̂�������Ȃ��B
�A�t�ɍו������߂��Ă��܂��Ă���̂�������Ȃ��B���̂��߂ɁC�P�ЂƂ��Ӗ��̒P�ʂ������Ă��邩������Ȃ��B
�B�܂������Ƃ���͂Ȃ����ƍl���Ă݂�B�Ӗ��I�C�`���I�C���I�C�`�ԓI�C�\���I���B
�C�Ⴂ�͂ǂ��ɂ��邩�B�t�ɁC���Ă������Ȃ����̂͂ǂꂩ�C�Ⴂ�͉����C�������邱�Ƃŋ�ʂ��͂����肷��B���Ă��Ȃ����̂Ƃ����łȂ����́C�Ƃ����Q�O���[�v�̋��E���������Ă���B
�D�ʂɌ�������(�u������)���Ȃ����B����͂ǂ��������Ƃ��ƁC�ʂɌ��������Ă݂�C�ʂ̂��̂ɂ��Ƃ��Ă݂�i��g�j�C���̂��̂ɒu�������Ă݂�i�g����߁C���ۉ��C�k���C�t���ɁC���Ԃ��C�L���C�k�߂铙)�B
�E�������̗�ōl���Ă݂�B��̓I�l���C��̓I�����C��̓I�o�����Ŕ�ׂĂ݂�B
�F���҂ɊW�Â�������̂͂Ȃ����i�A�i���W�[�j�B�ꕔ�ł��C��������ԐړI�ł��C�f�������Ȃ���ł��C�͂��ɊW�Â�������̂͂Ȃ����C�������ʁC�\���C�O�ƌ�C����������̕����C����������@�̑S�́C�ڕW�Ǝ�i�C�n�Ɛ}�C���ցC�]���C����C�⊮�C���q�C��q�C�A�z�C���X�B
�G���W�Ȃ��̂͂Ȃ����B�t�ɁC�ǂ�ȈӖ��ł����W�Ȃ��̂ɂ���āC�ŏ��̃O���[�v�����}���
�H�W��ގ�������}��i�G�}�j�͂Ȃ����B�S���W�Ȃ������Ȃ̂ɁC�����ʂ̃��m�⌾�t�ƊW�Â���ƁC�ԐړI�Ɏ��Ă�����C���̊W�Â��ɂ���āC�S�̂̔z�u����������C�����������Ă���
�I���҂����ꂼ��ʂ̃��m�i�������́C�W������́j�ɒu�������Ă݂�B�ʂ̂��̂ɒu��������ƁC���ʁ@���������邩������Ȃ��B
�J��[�E�⊮���Ă݂���ǂ����B���������Ă��Ȃ����C��������������̂͂Ȃ����B�����C����������狤�ʍ��������邩������Ȃ��B
�K�������Ă݂�C���킹�Ă݂�C�d�˂Ă݂�B��̉�����ƁC���ʍ����݂��邩������Ȃ��B
�L���ꂼ��ꂷ��i�����j���̂͂Ȃ����ƍl����B���҂��܂Ƃ߂�Ƃǂ��Ȃ邩�C���ҋ��ʂ̎P�͂Ȃ����C���ʂɊ����g�͂Ȃ����C�ƍl���Ă݂�B
�M���ꂼ���k���Ă݂�B���ꂼ�ꂪ���Ɍ������Ă���i�R�����Ă���j���C���������炵�����̂��ƁC�w�i�E�����E���R�ɑk���Ă݂�B
�N���ꂼ��������Ă݂�B���ꂩ��ǂ��Ȃ邩�C����̕����C������l���Ă݂�ƁC�����ł͈�{�����Ă��邩������Ȃ��B���̂��߂ɁC����ڎw���Ă��邩�ƁC�ړI���l���Ă݂�B
![]()
���g�ݍ��킹�̂߂�������
�َ��̂��̂�g�ݍ��킹�邱�ƂŁC�s�[�X���̂̏o���ɂ������Ȃ��C�S���V�����S�̑��������o��
���g�ݍ��킹�̌�����
|
�@�\�P�@ |
�T�u�P |
�T�u�Q |
�T�u�R |
�T�u�S |
�T�u�T |
�T�u�U |
�@ |
|
�@ |
�@�\�Q |
�T�u�P |
�T�u�Q |
�T�u�R |
�T�u�S |
�T�u�T |
�T�u�U |
|
�@ |
�@�@�\�R |
�T�u�P |
�T�u�Q |
�T�u�R |
�T�u�S |
�@ |
�@�@ ��
�g�ݍ��킹��P�@�������^�g�ݍ��킹
�@ �����_���ɂ��낢��g�ݍ��킹�ė֊s��n��o��
�O���[�v���������Q���m���C�����g�ݍ��킹�āC�V�����\���������Ă����B�Ⴆ�C�@�\�ʋ敪�Ƃ��̃T�u�O���[�v�Q�̑g�ݍ��킹��T�邽�߂ɁC�e�@�\���ɃT�u�O���[�v�̃J�[�h����ׁC�X���C�h���ɏ������炵�đg�ݍ��킹����������B
�@ �������^�g�ݍ��킹
�@ �@�����}����g����(�������̗̂֊s�����)�֊s�̃��f����n��o��
�O���[�s���O�œ����S�̂̊W������C�����ɂȂ��炦����i�����Ă���j�A�i���W�[�����C�X�̑g�ݍ��킹���o���B�܂��S�̘̂g�g������A�i���W�[�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�
���㗝�^�g�ݍ��킹
�����ɏœ_�ĂāC�S���ł͂Ȃ��P�����őg�ݍ��킹�������Ă����i�����ɕ��������^�̕ό^�j
![]()
�@���A�i���W�[�̂߂�������
�َ��ȕ���Ƃ̑Δ��ʂ��āC�܂������V�����Ӗ���s���l�܂�̑ŊJ�ɂȂ���
�@���A�i���W�[�Ƃ�
�A�i���W�[�Ƃ́C���Y�̉������C����Ǝ����i���邢�͊W�̂��肻���ȁj�ʂ̉�����}��Č��邱�ƁC��`��ʂ��ģ����(�l����)���Ƃł���B
�Ⴆ�C�`���C����Ɏ����w��ʂ��Č���(��������)�Ƃ����̂́C
�E�`�̎d�g�݂��w�̎d�g�݂�ʂ��ė�������
�E�`�̍\�����\����ʂ��ė�������
�E�`�̑g�����w�̑g����ʂ��ė�������
�E�`�̋@�\���w�̋@�\��ʂ��ė�������
���X�B�A�i���W�[�Ō������̂́C�����Ȃ��W���C�u�`��ʂ��āv���邱�ƂŌ����邱�Ƃł���B
�@���A�i���W�[�́g�������h
�A�i���W�[�́C���̂Q�ɂ킯�邱�Ƃ��ł���B
�E�ގ����Ɋ�Â��A�i���W�[���C��ޔ�
�E�W���Ɋ�Â��A�i���W�[���C��ސ��
�O�҂́C���e�َ̈��ȃ��m��R�g�̒��Ɍ`���I�ȑ����i�`�E�����Ȃǁj�C�S�̓I�ȗގ������������̂ɑ��āC��҂́C���҂̊Ԃ̊W�������o���B���ɊW�����d�v�Ȃ̂ł��邪�C����ɂ́C���̂Q�̃^�C�v������B
�@�@�@���҂̍\���v�f�̂��W������̗ސ�
�Ɨ������Q�̑ΏۊԂ̍\���v�f�̑Δ�ɂ���āC���m�̂a�̗v�f��(��1��2)�̊W(b12)���킩���Ă���C�s�̗v�f(��1)�Ƃa�̗v�f(��1)�Ƃ��Ή����C�a�Ƃs�̗v�f�Ԃ̊W�ib12��t12�j���Ή����Ă���Ƃ��C����Ƃ̗ސ�����C�s�ɂ����Ă���2������ɈႢ�Ȃ��C�Ɛ������Ă����B�v�f�̗ސ������łȂ��C�W���̂��̗̂ސ��ł��������C�������P�ł���C�ޔ�ƂȂ�B
�a
| �@�@���@��1 �@�@��b12 �@�@���@��2 |
�s
| �@�@���@��1 �@�@��t12 �@�@���@��2 |
�@�@�A���҂̊W���琶�ݏo���S�̍\���̗ސ�
���̗v�f�ł͂Ȃ��C�Ɨ����Ă���a�Ƃs�Ƃ̊Ԃ̊W����C�����}�Ƃ���n��ސ����邱�ƂɂȂ�B
�@���҂̈ʒu�W����C���҂̕�܊W�C�S�́E�����W�C�ꕔ�̏d�Ȃ�C�Ƃ����S�̂Ƃ��Ă̊W�Â��̔����B
�A�a�Ƃs���̂��C���҂�v�f�Ƃ���ʂ̘g�g�̓����̑g���W�ł���C�Ƃ����W�Â��̔����B����́C�B����Ă���t���[���i�w�j���C���ҊԂ̍\������C�ސ����Ă����B
�@�@�O���[�v�Q�ɐV�����S�̂̃��f����������ɂ́C���̂R�p�^�[��������B
�@�@���S�̂ɊW�����Ă�����̂�������
�@�@�@�C���[�W���ہC�����Ȃǂ��猩���Ă�
�@�@����������Ȃ���������C��������t�Z���Ċ֘A������̂��z������
�@�@�@�����f�B�̈�߂���t���[�Y���Ȃ��Ă���
�@�@�������ƕ����̊W�̒f�Ђ���S�̑���������
�@�@�@�����f�B�ƃ����f�B�̂Ȃ��肩��S�̂�ސ����Ă���
�@���A�i���W�[�̃p�^�[����
�@�E�A�z��
�������t�ōl���Ă��邾���ł͂Ȃ�����̂��C�C���[�W����݂����邱�ƂŁC���ł���̂ł���B
�@�@�@�@ �J�b�p�����키�����c�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �n�Q������̂��₶�����]��
�@�@�@ �o�[�R�[�h�����W���c�c
�E�ސ���
�^����ꂽ��������̘g�g�݂��l����Ƃ��C���̂܂܌@�艺����̂ł͂Ȃ��C���̓���̏��C�ʂ̏ݒ�Ɂi���肵�āC���z���āj�u�������āC���̘g�g�݂�ς��čl���Ă݂�B�������邱�ƂŁC�^����ꂽ���̘g�g�݂̒��ł́C�C�Â��Ȃ������ʂ̎��E�i�u���v�j�������Ă���B
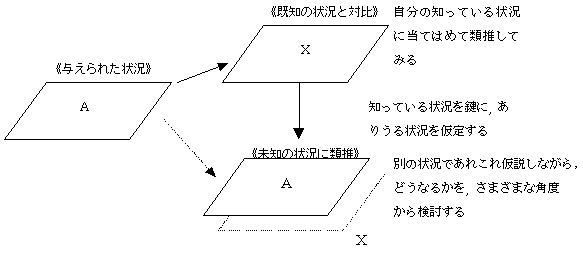
�E�g��i�k���j
�ʏ�̎��_�Ō��Ă������C���̐[�x�╝���[�܂�����L�������肷�邱�Ƃ͕ʂƂ���,���ʂɋ��������ω����邱�Ƃ͂Ȃ����C�ΏۂƂ̋������ӎ��I�ɕς��邱�ƂŁC�߂Â��Ίg�傷�邵�C��������Ώk������B�����ɉ��Η��Ԃ������ƂɂȂ�B�ォ�猩��Θ��Ղ������ƂɂȂ�B
![]()
|
�n�����Ƃ͉����ɂ��ẮC�����������������B
| |||||||||||
|
�A�C�f�A�Â���̊�{�X�L���ɂ��ẮC�����������������B
| |||||||||||
|
���z�Z�@�ɂ��ẮC�����������������B
| |||||||||||
|
���z�g���[�j���O�ɂ��ẮC�����������������B |
�S�̊�{�X�L�����g���Ă̏��T���ւ̉��p�ɂ��ẮC�����������������B
| |||||
| �S�̊�{�X�L�����g�������C�ɂ��ẮC�����������������B | |||||
| �n�����J�����C�v���O�����́C�n�����J�����C�v���O�����E�ڎ��������������B | |||||
| ��楔��z�E�n�����Ɋւ���Q�l�����ꗗ�ɂ��ẮC�����������������B |
![]()
�n�����J�����C���֖߂� |
| �n�����Ƃ͉����� |
| �A�C�f�A�Â���̍\�� |
| ���z�g���[�j���O�� |
| �A�C�f�A�Â���̊�{�X�L���� |
| �A�i���W�[�̌������P�� |
| �n�����J�����C�v���O�����E�ڎ��� |
| ��楔��z�E�n�����֘A�Q�l������ |
![]()