![]()
|
インシデント・プロセスの作業手順 |
インシデント・プロセスは,与えられた課題を,どうクリアするかという「方法課題探求型」の,限定された中での,情報探索プロセスである。つまり,
①課題として与えられた“問題状況の把握”
←状況を俯瞰し,多角的に「問い直す」(“バラバラ化”)=隠れた「問題」を明るみに出す問題意識の掘り下げ。「問い直し」のレベルに応じて,解決のレベルが決まる。
②情報ネットワーク化により,情報探索に連続性・方向性をもたせる(“設問の構想”)
←バラバラ化を通して見つけた“つながり”(分解/グルーピング/組み合わせ/類推)を仮定として,情報へのアクセスを“広角化”し,情報群をゾーンでとらえる。
③集約した情報の“序列化・関係づけ”(新しい“つながり”を見つけること)によるブロック化
←情報群に共通項を見つけて,それを基準に,グルーピングする(グルーピングは既存の分類基準によらず,探索目的に合わせて,必要な“事項”を枚挙する)⇒不足情報の発見
④情報ブロックの“ウエイトづけ”(重要度による序列化)による並べ替え,再配置
←情報の序列づけによる評価(評価基準は,情報探索の目的によって,メリハリがつけられなくてはならない)⇒情報ブロックの序列がパースペクティブ(一定視点からの“情報の遠近法”)になる。
⑤方向づけた情報の“構図(私的パースペクティブ)”の確定
←ウエイトづけられた再配置を通して見えてくる“確からしさ”の構図によって仮説を仮構する。
⑥仮説の描く“パースペクティブの確度”を確かめる←仮説のフィードバックによる“確かさ”の検証の流れであり,的確な情報探索ができるかどうかは「問い」の多角化によるが,集約した「情報」のウエイトづけ(方向づけ)の是非が,課題をクリアできる仮説を立てられるかどうかを左右する。
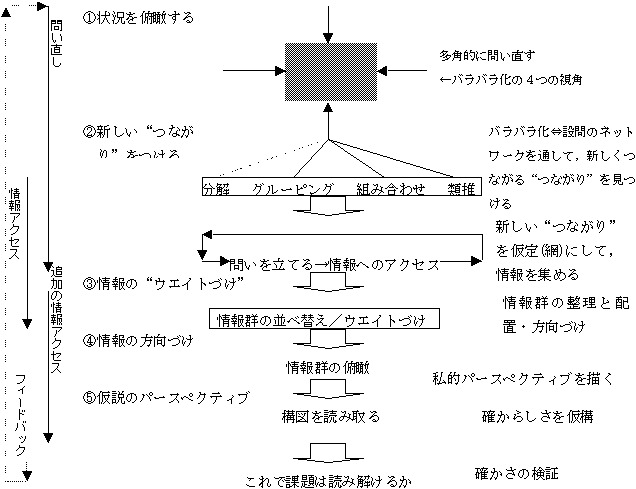
![]()
|
インシデント・プロセスを進めるための5つのポイント |
①必要とされる情報は,インシデントに「何を」見るか(その中の“何"を“どれだけ”「問題」とするか)によって異なってくる。
⇒課題/インシデントの多角的分析
・与えられた課題の状況の把握(何が起きたのか/何が分かっていることか/何が分からないことか)
・与えられた課題は何か(何を解決しなくてはならないのか/どこまで解決する必要があるか)
「何を問題とするか」→与えられている「課題」を,そのままを「問題」とするか,別に「問い直し」て,改めて「問題」を立て直す,のいずれの場合も,自分たちが「解決しなくてはならない“問題”」を明確にしなくてはならない。
②「何を解決するか」は,課題ですべてが与えられているわけではない。
⇒インシデントと課題の“読み"で変わる情報収集の目的
・「インシデント」は状況分析の手掛かりを与える。課題は情報収集に方向性を与える。しかし,課題とインシデントがイコール目的ではない。
・インシデント及び課題に,何を見たか(インシデントと課題に“何"を“どれだけ”「問題」としたか)によって,情報収集の中身,質・量は違う
「何を解決しなくてはいけないか」→②で「問題」としたことは,「どういうことを解決しなくてはいけないのか」「どういうことを明らかにしなくてはいけないのか」「どういうことが確かめられればいいのか」「どういう“答え”を出さなくてはいけないのか」「どういう“答え”なら解答になっているのか」等々,解決する (しなければならない)目標」を明確にする。
③「どういう情報を集めるか」「どういう情報が必要か」(これが情報探索の「目標」)は,「何を解決するか」(これが情報探索の「目的」)によって変わる。
⇒情報探索の目的は,インシデントと課題の“読み込み”(どこまで,何を「問題」としたか)の幅と奥行によって,目的のレベルと方向は変わる。
④「どう情報を集めるか」(これが情報探索の「方法」)は,「どういう情報を集めるか」(どういう情報があれば,「目的(何を解決するか)」を達成できるか)という仮説(こうすればこうなる,という情報探索の読み)の網の掛け方によって変わってくる。
⑤集めた情報に,どんなパースペクティブを見るかは,それをどう並べるか(どうウエイトづけるか)によって異なってくる。それは,始めに何を「問題」としたか(「問題」の見方)によって左右される。
・具体的に情報を収集し,情報のグルーピング,ウエイトづけによって,そこからどんな仮説(解決方法)が,どれだけ読み取れるのかを洗い出す。
・その“仮説”を,「課題」の“解決しなくてはならない目標”にフィードバックし,それでどれだけ的確な“答え”(仮説)となっているかどうかをチェックし,“より確からしい解答”にまとめていく。
・集約情報⇔仮説,仮説⇔情報再集約によって,課題の“答え”としての確からしさをクリアしながら,“仮説”を“検証”していく。
⇒パースペクティブの見え方は,最初の問題意識に左右される。それは,先入観(無意識的なレンズ)に対して,仮説(意識的なレンズ)が,ものの見方の幅と深度を変えるからである。
![]()
|
どう情報をアクセスしたらいいか-「問い」で何をえるべきか
|
◇次の諸点を意識的に「問題」にして,「問い」を組み立てたい。
◎「問い」を通して,情報の枠組みを広げる(インシデントに与えられた「所与の枠組み」を,「問い」を通して,境界線をはみ出し,拡大していく)
◎状況をピンポイント(いま・ここ)に限定しない(時間的,空間的に広げて位置づけ直す)
◎「問い」を立てることで,求める目標領域を埋めていく(未知を埋める)
◎「問い」と得られる情報とのズレが,予想からのズレとなる(「問い」=「答え」ではなく,はみ出す部分が予想を超えた広がりをもたらす)
◎「問い」によって具体化(細分化)されていかなくてはならない(「問い」が選択をもたらし,選択の選択の選択……を通して,分解,ブレークダウンされていく)
◎「問い」によって求めるのはピンポイントではない(「問い」を蛸足式に連鎖させる,連想によって多層化させる,「問い」によって拡大(縮小)させる等によって予期を超えた枠組み拡大をもたらす)
◎「問う」こと自体によって元々の問題の状況が変わる(そこで問うことによって,それが“ありきたり”ではないこと,平常でないことを浮き立たせ,平坦な状況に波風を立てている)
◎「問い」の多角化で異質なディメンジョンが見えてくる(「問い」は,前から,裏から,横から等々,多角化することで見える部分が広がる)
◎二者択一の「問い」とすることで具体化できる(特定化できる「問い」の仕方で,求めるポイントに焦点が絞られる)
◎「問い」によって均質さが崩れる(「問い」の焦点を多角的にすることで,一点が拡大されたり,異質な面に照明が当たったり,ざらざらなものに変わる)
◎「問い」によって,一般性(原理・原則)が見える(それと同じ状況,状態,形態のものとの類推ができる)
◎「問い」ですべての情報は手に入らない「問い」のすべてに「情報」があるとは限らない。手に入る限りの情報と情報で,つながりをつける(推測)するしかない。
◎「問う」側の情報の整理の仕方(設問構想)とアクセス先の情報の整理の仕方(収蔵方法)とは異質である。ほしい情報は,アクセス先の情報がどういう整理の仕方になっているかに合わせて(翻訳し直して),初めて手に当たりをつけることができる。
|
情報をどう仮説にするか-情報はつなげただけではカタチにならない ◇情報を収集・整理することと,そこから仮説(解決案)を発案していくこととの間には,飛躍がある。単に,多角的な「情報」を集約・分類しただけでは「○○情報」の整理に終わる。集約した情報群から,どう飛躍した発想(新しいものの見方)で,全体構図を想定していける(設定していける)かどうかである。 ◇この鍵となるのは,情報の加工・編集による,(情報群への)次の3つの“方向づけ"である。
3つの“方向づけ"が,集めた情報を,どこまで先入観にとらわれず,具体的なシチュエーション(時代背景,場面,登場人物の関係等々)に配置した,具体像として描けるかどうかを左右する。 |
|
仮説を確認する-その“読み”は確かか
|
![]()
|
インシデントの進め方&ケース例については,ここをご覧下さい。 | |||
|
ケースの構造については,ここをご覧下さい。 | |||
|
ケースの種類については,ここをご覧下さい。 |
![]()
![]()