![]()
ƒPپ[ƒXƒ‰ƒCƒeƒBƒ“ƒO‚ة‹پ‚ك‚ç‚ê‚邱‚ئ
–â‘è‚جچ\‘¢‰»‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جچؤٹm”F
ƒPپ[ƒXƒ‰ƒCƒeƒBƒ“ƒO‚ج‘O’ٌ
‚ا‚¤ژ–ژہ‚ًڈW‚ك‚é‚©
‚ا‚¤‚¢‚¤ژ–ژہ‚ھژg‚¦‚é‚©
‚ا‚¤ژ–ژہ‚ً‚آ‚ب‚°‚ؤ‚¢‚‚©
ژ–ژہ‚ً‚ا‚¤ƒPپ[ƒX‚ة‚ـ‚ئ‚ك‚é‚©
‚ا‚¤ڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚¯‚خ‚¢‚¢‚©
![]()
ڈW‚ك‚½ژ–ژہŒQ‚ًپC‚ا‚¤‚آ‚ب‚°‚ؤ‚¢‚‚ج‚©پB‚آ‚ب‚°‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپC
‡@ژ–ژہŒQ‚جٹش‚إپCڈک—ٌ‚ً‚آ‚¯‚é
‡A–ع“I‚©‚ç‚جژوژج‘I‘ً
‡Bژ–ژہŒQ‚جڈ‡ڈک(‹N‚«‚½ڈ‡پC”Œ©‚³‚ꂽڈ‡‚ب‚ا)
‚ؤ‚·‚ھپCƒ|ƒCƒ“ƒg‚حپC‘وˆê‚ةپC’N‚جژ‹“_‚©‚ç‚©‚جپCƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒu‚ًŒˆ‚كپC‘و“ٌ‚ةپCƒEƒGƒCƒg‚أ‚¯‚ً‚·‚邱‚ئ‚ة‚آ‚«‚ـ‚·پB
ƒEƒGƒCƒg‚أ‚¯‚ة‚حپC
-
ژ–ژہ‚ج‹پگS‰»پ@ژ–ژہ‚ًƒeپ[ƒ}‚إٹ‡‚ء‚ؤپCڈ‡ژںپC“–ڈ‰ƒeپ[ƒ}‚ض‚ئڈW–ٌ‚µ‚ؤ‚¢‚
-
ژ–ژہ‚ج‰“گS‰»پ@ژ–ژہ‚ًˆِ‰تٹضŒW‚إپC’†گS–â‘è‚©‚瓯گS‰~‚إٹg‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚
‚ج‚Q‚آ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إپC‚»‚ê‚ً”O“ھ‚ةپCژ–ژہ‚جگ®ڈک‚ة‚حپCژں‚ج‚و‚¤‚بƒJƒ^ƒ`‚ھ‚ ‚肦‚ـ‚·پB
‡@ژ–ژہ‚ًٹ‡‚è‚ب‚ھ‚çپCƒeپ[ƒ}‚جƒuƒŒƒCƒNƒ_ƒEƒ“‚ة‘خ‰‚³‚¹‚ب‚ھ‚çپCƒeپ[ƒ}‚ض‚ئڈW–ٌ‚µ‚ؤ‚¢‚
‡AژŒn—ٌ‚ةڈ]‚¢پC’Pڈƒ‚ةگ¶‹N‚µ‚½ڈ‡‚ة•ہ‚ׂé
‡Bˆِ‰تٹضŒW‚ةڈ]‚¢پC•ہ‚ׂؤ‚¢‚
‡Cٹeژ–ژہ‚ً‹َٹش“I‚ةگ®ڈک‚µپCڈêڈٹ“I‚بٹضکAگ«‚ً‚آ‚¯‚é
‡Dڈo—ˆژ–‚جگV‹Kگ«پC–ت”’‚³‚ً’†گS‚ة‚¨‚¢‚ؤپC”z—ٌ‚µ‚ؤ‚ف‚é
‚±‚جچى‹ئ‚حپC‚ ‚éˆس–،‚إپCژ–ژہ‚جچى‚èڈo‚·‹َٹش‚ًƒCƒپپ[ƒW‚·‚éچى‹ئ‚إ‚·پB‚±‚ج‚ـ‚ـ‚إ‚àپCƒPپ[ƒX‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‚ـ‚ئ‚ـ‚è‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ڈêچ‡‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپCƒPپ[ƒX‚ئ‚µ‚ؤ‚جپgŒ‹چ\پh‚ة‚ـ‚ئ‚ك‚é‚ة‚حپC‚à‚¤‚ذ‚ئچH•v•K—v‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB
‚ذ‚ئ‚آ‚جƒPپ[ƒX‚ةپCپgŒ‹چ\پh‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚é‚ئ‚حپCٹeژ–ژہ‚ًƒPپ[ƒX‚ئ‚¢‚¤‘S‘ج‚ج’nگ}‚ج’†‚ةپC‚ا‚¤–ًٹ„‚أ‚¯پC‚ا‚¤ˆت’u‚أ‚¯‚ؤپC•z’u‚µ‚ؤ‚¢‚‚©‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‚ـ‚ئ‚ك•û‚ج—vŒڈ‚حپCژں‚ج‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
‡@ژٹش‚جگ®ڈکپC‹َٹش(ڈêڈٹ)‚جگف’è‚ھ–¾ٹm‚إ‚ ‚邱‚ئ
‡A‘S‘ج‚جژ–ژہٹضŒWپCˆِ‰تٹضŒW‚ھˆêٹر‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ
‡B‘S‘ج‚ًگ§Œن‚·‚éژ‹“_(Œê‚èŒû)‚ھگ®چ‡گ«‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ
چإ‚àڈd—v‚ب‚ج‚حپC‡B‚إ‚·پB–â‘è‚جƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒu‚ً•`‚‚½‚ك‚ة‚حپC‚»‚ج—v‚ئ‚ب‚é–عŒ‚ژز(“–ژ–ژز‚إ‚à‚¢‚¢‚ھ)‚ھ•s‰آŒ‡‚إ‚·پBژ–ژہ‚ئ‚حپC’N‚©‚ة–عŒ‚‚³‚ê‚ب‚¢Œہ‚èپC‘¶چف‚µ‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB
‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپC‚»‚جژ–ژہ‚ھپC’N‚ج–ع‚©‚çپC‚ا‚ꂾ‚¯‚ج‹——£‚ً‚à‚ء‚ؤ(“–ژ–ژزپC‘ٹژèپCٹضŒWژزپC‘وژOژزپC–³ٹضŒW‚ب–عŒ‚ژز“™پX)پC‚ا‚¤Œ©‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©پC‚إ‚·پBƒPپ[ƒX•ھگح‚جپu–â‘è‚جچ\‘¢‰»پv‚ً—U‚¤‚ة‘«‚éژ–ژہ‚ھ•K—v‚¾پC‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
‚±‚ج¢’N£‚ًپC•ض‹X“I‚ةپCŒê‚èژè‚ئ“ا‚ٌ‚إ‚¨‚«‚ـ‚·‚ھپC‚½‚ئ‚¦‚خپCپu‚f‰غ’·‚ھپC‚rژq‚ً’چˆس‚µ‚½پv‚ئ‚¢‚¤ژ–ژہ‚ًپC‚ا‚¤ژو‚èڈم‚°‚é‚©پC‚ئ‚¢‚¤–â‘è‚ةٹض‚ي‚é‚ج‚إ‚·پBپu‚rژq‚حپC‚f‰غ’·‚ة’چˆس‚³‚ꂽ£‚ئ‚·‚é‚©پCپu‚f‰غ’·‚حپC‚rژq‚ً’چˆس‚µ‚½پv‚ئ‚·‚é‚©‚إپCژ‹“_‚جˆت’u‚ح•د‚ي‚è‚ـ‚·پB‚»‚جڈo—ˆژ–‚ًپC’N‚ھپC’N‚ج—§ڈê‚إپC•ٌچگ‚·‚é‚©‚ئ‚¢‚¤–â‘è‚إ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB
پsƒ‰ƒCƒ^پ[پ„Œê‚èژèپ„“–ژ–ژزپt
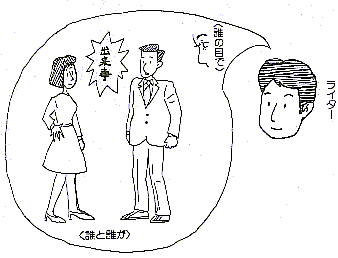
چ±چׂب‚±‚ئ‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ھپCژں‚ج“ٌ‚آ‚ً”ن‚ׂؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پu‚f‰غ’·‚حپC‚rژq‚ً’چˆس‚µ‚½پB‚±‚ꂾ‚¯Œ¾‚¦‚خپC‚ي‚©‚邾‚낤‚ئ‚f‰غ’·‚حژv‚¢پC‚rژq‚حپC‰غ’·‚ح‚¢‚آ‚àŒûگو‚خ‚©‚肾‚©‚çپCŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ئ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھˆل‚¤پC‚ئژv‚ء‚½£
پu‚f‰غ’·‚حپC‚rژq‚ً’چˆس‚µ‚½پB‚±‚ꂾ‚¯Œ¾‚¦‚خپC‚ي‚©‚邾‚낤‚ئ‚f‰غ’·‚حژv‚¢پC‚¤‚آ‚ق‚¢‚ؤ‚¢‚é‚rژq‚ج—lژq‚ً‚¤‚©‚ھ‚ء‚½پv
‘Oژز‚ھپCژ–ژہ‚ًکëلص‚·‚éپgگ_‚جژ‹“_پh‚¾‚ئ‚·‚é‚ئپCŒمژز‚حپC‚f‰غ’·‚ج–عگü‚ةژ‹“_‚ًŒإ’肵‚½پCپg“–ژ–ژز‚جژ‹“_پh‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
ٹm‚©‚ةپC‘Oژز‚حپC‚·‚ׂؤ‚جژ–ژہ‚ئگS‚ج“®‚«‚ً‚‚ـ‚ب‚Œ©‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·‚ھپC‚±‚ê‚حŒ»ژہ‚ج–â‘è‰ًŒˆ“–ژ–ژز‚جژ‹“_‚ئ‚حˆظ‚ب‚è‚ـ‚·پB’N‚جƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒu‚إ–â‘è‚ً‘¨‚¦‚é‚©‚ھپC–â‘è‰ًŒˆ‚ج‘و‚P•àپK‚¾‚ئ‚·‚é‚ئپCŒمژز‚ج•خ‚ء‚½ژ‹“_‚ج•û‚ھپCŒ»ژہ‚ج‚ي‚ê‚ي‚ê‚جڈî•ٌژûڈWپC–عŒ‚‚ج‚ ‚è•û‚ة‹ك‚¢‚ح‚¸‚إ‚·پBŒمژز‚ج•û‚ھپC‚»‚جژ‹“_‚©‚ç‚ج–â‘è‰ًŒˆ‚ض‚ئ‚آ‚ب‚ھ‚è‚â‚·‚¢‚±‚ئ‚حژ–ژہ‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚µ‚©‚µپC“¯ژ‚ةپC‚»‚جژ‹“_‚جŒہٹE‚ًˆسژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئپCŒë‚ء‚½ƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ةٹׂé‰آ”\گ«‚ح‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپB
‚±‚ج‘¼‚جژ‹“_‚ئ‚µ‚ؤ‚حپC
‚rژqپپژ„پC‚f‰غ’·پپژ„‚ئ‚¢‚¤ژ‹“_
‚rژq‚جژ‹“_
‚f‰غ’·‚â‚rژq‚ج“¯—»‚جژ‹“_
“™پX‚à‚ ‚肦‚ـ‚µ‚و‚¤پB—v‚حپC‚»‚جŒê‚èژè‚ھŒˆ‚ـ‚邱‚ئ‚إپCژ–ژہ‚جƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒu(ژ‹ٹE)‚ھŒˆ‚ـ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خپC‚f‰غ’·‚جژ‹“_‚إ•`‚‚ئ‚·‚é‚ئپC‚·‚ׂؤ‚جژ–ژہپCڈî•ٌ‚حپC‚f‰غ’·‚ج–ع‚âژ¨‚ً’ت‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚èپC‚f‰غ’·‚جگ„‘ھ‚âٹ´ڈî‚جƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚ً’ت‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‚f‰غ’·‚جŒ¾“®‚»‚ج‚à‚ج‚àپC‚»‚¤–{گl‚ھŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚é’ت‚è‚©‚ا‚¤‚©‚حپC—¯•غ‚µ‚½ڈم‚إ‚ج‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
‚³‚ç‚ةپCڈW‚ك‚½ژ–ژہ‚àپC‚·‚ׂؤ‚ھپC‚f‰غ’·‚ً’ت‚µ‚½پCٹشگعڈî•ٌ‚ة•د‚ي‚ء‚½Œ`‚إپC”z’u‚³‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
‚³‚ؤپC‚±‚¤‚µ‚½پC—\”ُ“I‚بچى‹ئ‚ج‚ ‚ئپC‘S‘ج‚ً‚ا‚¤‚ـ‚ئ‚ك‚ؤ‚¢‚‚©پC‚إ‚·‚ھپC‚ـ‚ئ‚ك•û‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚حپC‚Q‚آ‚إ‚·پB
‡@‚ـ‚¸‘S‘ج‚ج—¬‚ê‚ًچ\‘z‚·‚éپ¨ژ–ژہ‚ً‚»‚ê‚ة‚ ‚ي‚¹‚ؤ”z’u‚·‚é
‡Aژ–ژہ‚ج‚آ‚ب‚¬•û‚ًچH•v‚·‚éپ¨‘S‘ج‚جچ\‘z‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚‚é
Œمژز‚حپCژ–ژہŒQ‚ج‚قگ®—پCٹضŒW‚أ‚¯‚ج’†‚©‚çپC‘S‘ج‚ًŒ©‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚‚ج‚إ‚·‚ھپC‘Oژز‚حپC”ç‘ـ‚ًگو‚ة—§‚ؤ‚ؤپC‚»‚ê‚ة‚ ‚ي‚¹‚ؤپCژ–ژہ‚ً”z’u‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
‚±‚±‚إ‚حپC‘Oژز‚ً—ل‚ةپCچl‚¦‚ؤ‚ف‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حپCƒPپ[ƒX‚ج–ع“IپCٹْ‘زگ¬‰ت‚©‚çپCƒPپ[ƒX‚جپgŒ‹چ\پh‚ًچl‚¦‚ؤ‚¢‚±‚¤‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚·پB
‚½‚ئ‚¦‚خپC–â‘è‚جƒ^ƒCƒv‚ئ‚µ‚ؤ‚حپC
پE–â‘è‰ًŒˆŒ^
پE‰غ‘è(–ع•W)گف’èŒ^
پE‰غ‘è(–ع•W)’T‹پŒ^
‚ج‚Rƒ^ƒCƒv‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپC‚±‚ê‚ً‚à‚ء‚ئٹڑ‚فچس‚‚ئپCˆب‰؛‚ج‚و‚¤‚ة‚³‚ـ‚´‚ـ‚بƒpƒ^پ[ƒ“‚ًچl‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB
| ‡@“ث”‚ج‹ظ‹}ژ–‘ش‚ً‘O‚ةپC‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚¢‚¢‚ج‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚‚ب‚é—§‚؟‰گ¶Œ^ ‡Aچ¬–ہ‚µ‚½ژ–‘ش‚ةپC‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚¢‚¢‚ج‚©چl‚¦‚ ‚®‚ث‚ؤ‚¢‚éژvˆؤ“ٹ‚°ژٌŒ^ ‡B‚ ‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚·‚é‚ٌ‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پC‚±‚¤‚µ‚ؤ‚¨‚¯‚خ‚و‚©‚ء‚½‚ئژv‚¢”Y‚قŒم‰÷Œ^ ‡C‚ ‚ꂱ‚ê•ذ‚ء’[‚©‚çژژ‚ف‚éژژچsچِŒëŒ^ ‡D‚ ‚ꂱ‚êˆّ‚ء‘~‚«‰ٌ‚µ‚ؤ‚ـ‚·‚ـ‚·ژ–‘ش‚ًˆ«‰»‚³‚¹‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ˆ«‚ ‚ھ‚«Œ^ ‡E‚±‚ꂾ‚¯‚â‚ء‚½‚ٌ‚¾‚©‚çژd•û‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‹ڈ’¼‚èŒ^ ‡F‚±‚ꂾ‚¯‚â‚ء‚½‚ج‚ة‚ئ—ژ‚؟چ‚قژ©گM‘rژ¸Œ^ ‡Gچإˆ«‚جژ–‘ش‚ب‚ج‚ةپC‚ـ‚¾‚ ‚«‚ç‚ك‚¸پC‰½‚ئ‚©‚µ‚و‚¤‚ئپCژں‚جˆêژè‚ًچl‚¦‚آ‚أ‚¯‚é”S‚èچکŒ^ ‡H‚ا‚¤‚·‚ê‚خ‚à‚ء‚ئ‚¤‚ـ‚‚¢‚‚©پC‚ ‚ꂱ‚êچl‚¦‚ؤچl‚¦”²‚¢‚ؤ‚¢‚éژvچُ’T‹پŒ^ ‡IˆسژvŒˆ’è‚ة•K—v‚بڈî•ٌ‚ج•s‘«‚ة”Y‚فپC‚ ‚جژ肱‚جژè‚إڈî•ٌژûڈW‚ً‚ح‚©‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éڈî•ٌ’TچُŒ^ ‡J‚ ‚ئ‚à‚¤ˆê•à‚إ‰½‚ئ‚©‚ب‚éپC‚¢‚¢ƒAƒCƒfƒA‚ح‚ب‚¢‚©‚ئپC‚â‚è•û‚جچH•v‚ً’T‚·ڈ•Œ¾ژx‰‡Œ^ ‡KگV‚µ‚¢‚±‚ئپC–¢ŒoŒ±‚ب‚±‚ئ‚إ‚àپCژ©•ھ‚ج—ح‚ً‰كگM‚µ‚ؤ“ثگi‚·‚é’–“ث–زگiŒ^ ‡LŒب‚ج—ح‚ً‚«‚أ‚©‚¸پC‰°–ت‚à‚ب‚ژ©گM‚ً‚ذ‚¯‚ç‚©‚µ‚ؤŒh‰“‚³‚ê‚éٹ®‘S•‚‚¢‚ؤ‚¢‚éŒ^ ‡Mژ©•ھ‚ح‰½‚ً‚µ‚½‚ç‚¢‚¢‚ج‚©‚ھ‚ـ‚ء‚½‚ژ©ٹo‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ب‚¢–ًٹ„‘rژ¸Œ^ ‡N‚ا‚¤‚µ‚½‚点‚ء‚ئ‚‚إ‚«‚é‚ج‚©‚ھ‚ي‚©‚炸—§‚؟ژ~‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ء‚ؤ‚¢‚«•û’T‹پŒ^ ‡O’mژ¯‚à‚ ‚èپC—‹ü‚ح‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپCژہ‘H‚ھ‚¢‚آ‚à”؛‚ي‚ب‚¢“ھ‚إ‚ء‚©‚؟Œ^ ‡Pژü‚è‚ة‘«‚ًˆّ‚ء’£‚ç‚ê‚ؤپC“Dڈہ‚ةٹׂء‚ؤ‚¢‚éگlٹشٹضŒW•sگMŒ^ ‡Qƒ`پ[ƒ€“à‚جگlٹشٹضŒW‚ھچإˆ«‚إپC–ع•W’Bگ¬‚ة’N‚àˆس—~‚ًژ¦‚³‚ب‚¢ٹ‹“،‹ê“¬Œ^ ‡R•”‰؛‚ھ—DڈG‚إپCژèچj‚ھ‚³‚خ‚«‚«‚ꂸپCگU‚è—ژ‚ئ‚³‚ê‹C–،‚جœ›”n‚ة–|کM‚³‚ê‚é‹RژèŒ^ ‡Sڈمژi‚جژv‚¢‚آ‚«‚ةگU‚è‰ٌ‚³‚êپC•”‰؛‚©‚ç‚àŒ©•ْ‚³‚ê‚ؤںTڈَ‘ش‚جƒXƒgƒŒƒXˆ³”—Œ^ |
–³گ”‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپC‚±‚ج•ûŒüگ«‚ًکg‘g‚ف‚ئ‚µ‚ؤپCژ–ژہ‚ً‚آ‚ب‚°‚ؤ‚¢‚‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚؟‚ه‚¤‚اپCژ–ژہ‚ً‚آ‚ب‚°‚ب‚ھ‚çپC‘S‘ج‚ًƒeپ[ƒ}‚ةڈW–ٌ‚µ‚ؤ‚¢‚‚ج‚ئ‚حپC‹t•ûŒü‚©‚ç‚جƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ب‚ج‚إ‚·پB
‚³‚ؤپC‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپCچإŒم‚ةپCژ–ژہ‚ًڈ‘‚«ڈم‚°‚ؤ‚¢‚‚ة‚حپC
‡@‚ذ‚ئ‚آ‚ج—§ڈê‚©‚ç‚جڈî•ٌپEژ–ژہپEگ„‘ھ‚إپC
‡A(Œê‚èژè‚ج)ژهٹد‚ة‚و‚éپC•خ‚è‚ئ‚ن‚ھ‚ف‚ً‚à‚؟پC
‡B–â‘è‚جƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒu‚ھ•sٹ®‘S‚إ‚ ‚é
‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپCƒPپ[ƒX‚حƒPپ[ƒX‚炵‚‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB‚»‚±‚©‚çپC–â‘è‚جƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒu‚ً•`‚«پC‰ًŒˆ‚ً—û‚ء‚ؤ‚¢‚‚½‚ك‚ة‚حپC
پE•s‘«‚µ‚½ژ–ژہ‚〈‚¦‚ب‚¢ژ–ژہ‚ًپCƒWƒOƒ\پ[ƒpƒYƒ‹•—‚ة‚آ‚ب‚°‚ç‚ê‚é
پEگ„‘ھ‰آ”\‚بڈî•ٌپC“`•·‚ھگ·‚èچ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚é
پE–â‘è‚جƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒu‚ً•`‚‚½‚ك‚جچœٹi‚ئ‚ب‚éژdژ–پEگl‚جŒn‚ةکR‚ê‚ھ‚ب‚¢
‚±‚ئ‚ھٹجگS‚إ‚·پB‚±‚±‚ًچإŒم‚جƒ`ƒFƒbƒNƒ|ƒCƒ“ƒg‚ئ‚µ‚ؤپCƒPپ[ƒX‚ًٹ®گ¬‚³‚¹‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
![]()
|
ƒPپ[ƒXƒ‰ƒCƒeƒBƒ“ƒOŒ¤ڈC‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚±‚ً‚²——‰؛‚³‚¢پB |
![]()
| Œ¤ڈCƒvƒچƒOƒ‰ƒ€ˆê——‚ض |
| ƒPپ[ƒXƒ‰ƒCƒeƒBƒ“ƒO‚جƒXƒLƒ‹‚ض |
| ƒPپ[ƒXƒ‰ƒCƒeƒBƒ“ƒO‚جƒXƒLƒ‹‚P‚ض |
| ƒPپ[ƒXƒXƒ^ƒfƒBŒ¤ڈC‚ض |
| ƒIƒٹƒWƒiƒ‹ƒPپ[ƒX‚أ‚‚è‚ض |
| –â‘è‰ًŒˆٹضکAژQچl•¶Œ£‚ض |
| ƒPپ[ƒXƒXƒ^ƒfƒBٹضکAژQچl•¶Œ£‚ض |
![]()